| 【歌意1823】 |
草木がうちなびく春に、もうなったようだ
家の門の柳の梢で、うぐいすが鳴いている
|
柿本人麻呂歌集の昨日までの「春」は、
かすみの「たなびく」視覚的な感覚で詠われているが
この歌は、鶯の鳴き声を聞き、春の訪れを感じている歌だ
諸注にも、この歌の評価はいろいろで
あまり良く評価していないのは、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕といえる
「嫌味はないが、形だけの美しさが先に立って、力のない歌風と言い得よう」としている
しかし、概ねは「絵画的」、「美的」などと評している
私も、人麻呂歌集歌と比べての評価云々ではなく
うぐいすが、やって来て、春を知らせるかの如く鳴く
そして、柳の細い枝の先端でのその姿を想像すると
とても動的な春らしい「映像」を思い浮かべることができる
山の中で、うぐいすの鳴き声を聞く歌も、よく目にするが
こうした、身近な場での「春」を感じさせる情景もまた、いいものだ
この掲題歌とは離れるが、右頁の歌〔1432〕
その左注に、気にかかる一文をみた
「右一首依作者微不顕名字」
作者の身分が低いので、その名を記さない、という意味だ
これはどういうことなのだろう
もっとも、「作者不詳」歌すべてが、本当に「不詳」だとは限らず
このように、実際は解っていても、名を敢えて記さないことは知られている
作者の立場上のこともあるだろうし...
しかし、その理由として「身分の低い」というのは、私には馴染みがない
それとも、珍しくないことなのだろうか
『万葉集』の真髄は、後の「歌家」のような「歌人の家系」でもなく
幅広く歌を載せ、中には駄作だと評されるものまで、確かに載っている
しかし、それが『万葉集』なのだ、それが魅力なのだ、と私は思っている
もっとも、防人歌の歌群には、地域ごとに防人たちの歌を集め
しかし拙いものは篩い落とした、とする旨まで左注にあるにはあるが
それでも、その「拙い歌」の程度が明らかでない以上、
本当に「歌」としての「質」だけで判断されたのか
あるいは、「表現上」、「技術上」のことだけで落とされたのか
その「レベル」は知る由もない
ただ、この〔1432〕歌が、
身分が低くて歌集に載せられる立場の人ではないが
歌の見事さから、捨てるのは惜しい...そう言っているのだろうか
そんな気持ちで、何度も読み返してみると...
難波を出立して、草香山を越える
「あしからぬ」人に、早く行って逢いたい
これは、何だか...「ならぬ恋」の相手に、覚悟の上で逢いに行く
そんな気持ちの歌のようにも思えてきた
だから、「身分が低い」というのではなく
そんな立場に「落とされてしまった」人の歌なのかもしれない
きっと、元はそこそこの立場のある人なのではないか、と...
当然、この時点での『万葉集』編者も知っていよう
大いに同情をしたのではないだろうか
そして、名は出せないが、その「詠歌」を載せる...
それが、精一杯の「厚意」だと、見せたかった
難波から、明日香へ...あるいは平城へ...急ぎ向う「人」の姿が、切実に思えてならない
|
|
掲載日:2013.12.01.
| 春雑歌 詠鳥 |
| 打霏 春立奴良志 吾門之 柳乃宇礼尓 鴬鳴都 |
| うち靡く春立ちぬらし我が門の柳の末に鴬鳴きつ |
| うちなびく はるたちぬらし わがかどの やなぎのうれに うぐひすなきつ |
| 巻第十 1823 春雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【注記】〔1432・16〕
| 【1823】語義 |
意味・活用・接続 |
| うちなびく[打霏]〔枕詞〕「春」にかかる |
| はるたちぬらし[春立奴良志] |
| たち[立つ] |
[自タ四・連用形](風・霧・霞など)生じる・起こる・立ち込める |
| ぬ[助動詞・ぬ] |
[完了・終止形]~てしまう・~てしまった |
連用形につく |
| らし[助動詞・らし] |
[推量・終止形]~にちがいない |
終止形につく |
| わがかどの[吾門之] 私の家の門 |
| やなぎのうれに[柳乃宇礼尓] |
| うれ[末] |
(「うら」の転)木の枝や草の葉の先端・こずゑ |
| に[格助詞] |
[位置](空間的な場所を表す)~で |
体言につく |
| うぐひすなきつ[鴬鳴都] |
| つ[助動詞・つ] |
[完了・終止形]~た・~てしまった |
連用形につく |
| 掲題歌トップへ |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [枕詞「うちなびく」] |
春は草木が枝葉を伸ばし靡くことから「春」にかかる枕詞になった
もともとは修飾語だったが、この時点では、「枕詞化」しているとされている
「草香山」にかけた枕詞の用例もある 〔8-1432〕
| 春雑歌/草香山歌一首 |
| 忍照 難波乎過而 打靡 草香乃山乎 暮晩尓 吾越来者 山毛世尓 咲有馬酔木乃 不悪 君乎何時 徃而早将見 |
| おしてる 難波を過ぎて うち靡く 草香の山を 夕暮れに 我が越え来れば 山も狭に 咲ける馬酔木の 悪しからぬ 君をいつしか 行きて早見む |
| おしてる なにはをすぎて うちなびく くさかのやまを ゆふぐれに わがこえくれば やまもせに さけるあしびの あしからぬ きみをいつしか ゆきてはやみむ |
| 右一首依作者微不顕名字 |
| 巻第八 1432 春雑歌 作者不詳 |
〔語義〕
「おしてる」は、「難波」にかかる枕詞
「うちなびく」〔枕詞〕、ここでは「草香山」にかかる(草が風に靡く意から)
|
〔「左注」の意〕
右の一首は、作者の身分が低いので、その名を記さない |
〔歌意〕
難波を後にし、風にそよぐ草香山を
夕暮れに越えてくると
山も狭しと咲き覆うあしびの中を
心から離れることがないあなたのところへ
早く行って逢いたいものです |
「春」にかかる例は、『万葉集』中に十四例ある
意外なのは「冬こもり」という枕詞
これも「春」にかかる
そのかかり方は未詳とあるが、用例歌は、
| 冬こもり 春さり来れば 鳴かざりし 鳥も来鳴きぬ 咲かざりし 花も咲けれど 山を茂み 入りても取らず 草深み 取りても見ず 秋山の 木の葉を見ては
黄葉をば 取りてぞ偲ふ 青きをば 置きてぞ嘆く そこし恨めし 秋山吾は |
| 既出、〔書庫-7〕巻第一 16 雑歌 額田王 |
この歌、秋と春では、どちらが趣があり勝っているか、という天智天皇の問い掛けに
額田王が、この歌で「判定」した、とされる歌だ
しかし、そのことについては既出なので、ここでは触れない
問題は、枕詞「冬こもり」をみたい
早くから、「春」にかかる枕詞であることは、この詠歌によっても解る
だから、この「冬こもり」に取り換わって、「うちなびく」が新しく案出された、とも
掲題歌の原文「打靡」の「靡」は、
本来、雨や雪の降るさま、雪のとぶさま、煙の立つさま、などを形容する文字だという
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕では、
ここ数日扱ってきた「柿本人麻呂歌集」の「たなびく」に「霏□」(□は雨冠に微)があり
それに引かれて、「なびく」に「霏」を当てたものだろう、としている
|
| |
| [なきつ] |
「鳴きぬ」、「鳴きつ」それぞれの語句は、
同じ完了の助動詞「ぬ」、「つ」であり意味も同じだ
しかし、その使い分けには、研究がなされているようだ
上の動詞によって使い分けがあるようだが、その専門的なことは、まだ私には解らない
ただ、この「鳴きぬ」と「鳴きつ」の場合、「鳴く」という動詞は
例外的に両方の助動詞にも使われる、という
「鳴きぬ」が継続反復ないし恒時的事実をあらわすのに対して、「鳴きつ」は、即時的瞬間的であると言われる
(木下正俊「ツ・ヌの別とそれに関する訓釈」『万葉集語法の研究』所収) |
| |
|
|
| 【歌意1824】 |
梅の花が咲いている岡に家を構えていると
決して珍しいことではないですよ
うぐひすの鳴き渡る声が
こんなに聞こえるのは... |
歌そのものは、梅の花の咲く岡に家を構え
うぐいすの鳴き声を、のどかに聞く春の情緒を詠ったものだ
後の「歌の世界」になると、こうした「風流」もまた
一つのテーマとして扱われるのだろうが
『万葉集』の中で、このように接すると、
この「春の情緒」もまた、一つの生活観を見せてくれる
都で聞くうぐいすの鳴き声も、見事な庭園の「梅の花」もいい
しかし、都から離れた山村で目にする風景、そしてうぐいすの声...これもいい、と詠う
もっとも、この作者の生活圏が都周辺なのか、
あるいは実際に都から離れた山間なのか
それはわからない
しかし、そんな詮索をしなくても、山間に隠居する人の余生に憧れてしまう
「ともしくもあらず」とは、そのことを教えてくれないだろうか
ここでは、少なくないこと...珍しいことではないのですよ、と理を入れる
そのことこそが、都を離れて住むようになった人の、得意気な表情を知らせる
競い合うようにして詠う時代の「春の情景歌」ではなく
生活感に溢れた中で、ごく自然に「春を想う、知る、感じる」
何も特別なことではなく、これが「人の世の春だ」と言わんばかりに...
|


 |
掲載日:2013.12.02.
| 春雑歌 詠鳥 |
| 梅花 開有岳邊尓 家居者 乏毛不有 鴬之音 |
| 梅の花咲ける岡辺に家居れば乏しくもあらず鴬の声 |
| うめのはな さけるをかへに いへをれば ともしくもあらず うぐひすのこゑ |
| 巻第十 1824 春雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【注記】〔954・456〕〔2234〕
| 【1824】語義 |
意味・活用・接続 |
| うめのはな[梅花]〔万葉の植物〕 |
| うめ[梅] |
「むめ」とも表記、木の名・うめ、またその花や実 |
| 葉に先立って、白・紅・淡紅色などの香りのよい花が咲き、初春の花として愛好された |
| さけるをかへに[開有岳邊尓]咲いている岡の辺りに |
| いへをれば[家居者] |
| をれ[居り] |
[自ラ変・已然形]存在する・いる・ある |
| ば[接続助詞] |
[順接の確定条件]~ので |
已然形につく |
| ともしくもあらず[乏毛不有] |
| ともしく[ともし] |
[形シク・連用形][羨し]飽きない・心引かれる・うらやましい |
| |
[乏しい]不充分である・貧しい・少ない |
| うぐひすのこゑ[鴬之音]うぐひすの鳴き声 |
| 掲題歌トップへ |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [うめのはな] |
バラ科の落葉高木、中国原産だが、古く渡来
奈良遷都前後には貴族の観賞用として栽培された
『万葉集』には119首の歌に詠まれ、萩の141首に次ぐ
『万葉集』では、神亀四年(727年)正月に詠まれた歌が、もっとも早い例とされる
| 雑歌/(四年丁卯春正月勅諸王諸臣子等散禁於授刀寮時作歌一首[并短歌])反歌一首 |
| 梅柳 過良久惜 佐保乃内尓 遊事乎 宮動々尓 |
| 梅柳過ぐらく惜しみ佐保の内に遊びしことを宮もとどろに |
| うめやなぎ すぐらくをしみ さほのうちに あそびしことを みやもとどろに |
| 右神龜四年正月 數王子及諸臣子等 集於春日野而作打毬之樂 其日忽天陰 雨雷電 此 時宮中無侍従及侍衛 勅行刑罰皆散禁於授刀寮而妄不得出道路 于時悒憤即作斯歌作者 不詳 |
| 巻第六 954 雑歌 作者不詳 |
〔語義〕
「らく」は、接尾語で、「~すること・~することには」の意
「過ぐらく」で、「過ぎるのを」
「さほのうち」、現在の奈良市西北郊外の佐保一帯をさすという
「~のうち」というよな土地の呼び方は珍しく、
皇室の特別な設備が設けられていた場所ではないか、といわれている
「あそびしこと」
諸注は、その主語に、出仕する人々が、と解釈しているが
左注では、出仕する宮人たちが赴くのは、今の奈良市東方の春日野で、
この佐保とはかなり離れている
従って、この「あそびし」の主語は、他の宮人たちでは、と推測もされる
「とどろむ」は、賑やかに鳴り響く様子、興じる賑わい
|
〔歌意〕
梅や柳の見頃が過ぎるのを惜しみ、
この佐保の内に、大いに賑わい楽しく遊んだことを
ここに集まった者たちが、響かんばかりに語り合っている |
「梅」や「柳」...「梅」が愛好される「花」としては、いやにあっさり詠われたものだ
勿論、この歌の主題は、「梅」の観賞ではないので、当然かもしれない
次の「梅」の歌は、また痛切な挽歌だが、この歌で見逃せないのは、
「梅」の「植栽」が「あった」ことが詠われている、ということになる
| 挽歌/(還入故郷家即作歌三首) |
| 吾妹子之 殖之梅樹 毎見 情咽都追 涕之流 |
| 我妹子が植ゑし梅の木見るごとに心咽せつつ涙し流る |
| わぎもこが うゑしうめのき みるごとに こころむせつつ なみたしながる |
| 既出、〔万葉の植物〕 巻第三 456 挽歌 大伴宿禰旅人 |
〔語義〕
「むす」の原義は、飲食の喉に詰まるように胸が一杯になるの意
|
〔歌意〕
わが妻が植えた梅ノ木を
こうして見る度に胸が詰まって...
涙が流れてしまう |
この歌、大伴旅人の亡妻への、痛切な挽歌群(十一首)の内の最後の三首と言えるだろうが
その三首の歌は、旅人が大宰府から都に帰郷してからの歌
そこで、改めて妻が「植えた梅の木」を...眺めて涙する
大宰府で妻を亡くし、帰郷しても「形見」として庭に咲く梅の花...
この哀しみは、いつまで続くのだろう
|
| |
| [ともしく] |
「ともし」には、「少ない」という謂と、それから派生した「羨ましい」の意がある
この類型として、次の歌をみることができる
| 秋雑歌詠風 |
| 戀乍裳 稲葉掻別 家居者 乏不有 秋之暮風 |
| 恋ひつつも稲葉かき別け家居れば乏しくもあらず秋の夕風 |
| こひつつも いなばかきわけ いへをれば ともしくもあらず あきのゆふかぜ |
| 巻第十 2234 秋雑歌 作者不詳 |
〔語義〕
「稲葉かき別け」は、「家居」を修飾している語
周囲一面が稲田で、その稲葉に取り囲まれるようにして住む意を表している
|
〔歌意〕
家人を恋しく思いつつも
この一面の稲葉に囲まれた家に居ると
秋の夕風が、しきりに吹いてくる...
これも珍しいことではないことだが... |
初句の「恋ひつつも」には、
『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕が、「そよ吹く風を恋しく思うて」、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕が、「秋風を恋ひ待ちながら」とする
私は、『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕のいう、
家を離れて、田舎の田庄に来ている者が、家人を恋しく想う歌だと思う
私が感じるのは、ここに住んでいれば、秋の夕風が珍しいことではなく
その寂しさの余り、家人を恋しく思う歌のような気がする |
| |
|
|
| 【歌意1825】 |
はるがすみが、流れただようように移ろいゆくさま、
するとそのとき、うぐひすが青柳の枝をくわえ持って
鳴き声を小さく聞かせているではないか |
この歌が、たとえば理屈に合わない「くひもちて」鳴くとか
他に例のない「かすみがながれる」という表現など
特異は歌であることには違いないだろうが...
その割には、その扱いが、あまりにも淡白のような気がする
これまでの「うぐひす」の歌でも
それは、枝に止まって鳴くとか、
あるいは、鳴くながら飛び去るとか...
どこかで鳴き声が聞こえるとか...
言ってみれば、「遠景」としての「うぐひす」だと思う
しかし、この歌のうぐひすは、青柳をくちばしに挟み、鳴いている、という
作者の見える、すぐそばの青柳の細い枝に止まり
その枝をいたずらっぽく突きながら鳴いている、そんな描写なのかもしれない
すると、何も理屈がどうのこうのと論争しなくても
春かすみが、遠くに流れて行くさまを見ていた作者の前を
いきなり、うぐひすが飛んできて
その青柳に止まり、小枝を銜えたり突いたり、ときには鳴いたり...
そんな光景に魅入っている作者を浮かべることができる
あるいは、銜えたままでも、うぐひすは鳴けるものかもしれない
それは、私も見たことがないので、どうかな、とは思うが
しかし、先ほど述べたような光景なら、充分有り得ると思う
鳥の鳴き声は、その姿で知るのではなく
だいたい「鳴き声」だけで、満足させてしまう
ならば、この作者は...願ってもない、珍客を目の前に迎えたのかもしれない
もしそうであれば、私でもじっと魅入ってしまうだろう
お前が、あんなに「春の香り」とともに鳴いているのか...と
いや、春の香りそのものだ、と教えているのかもしれない
山間にこだまするうぐひすの鳴き声...
うぐひすがやってきたのは、まさに春を伴って、のことだ
おまけに、春かすみに紛れるようにして...
今日から、左頁の「語義」のところで
このサイトの「万葉集全歌集」の頁に併記して載せている「古語辞典」も利用することにした
まさに目標は、普通の「古語辞典」一冊そのものを解釈の補助として載せるものだが
基本的に、「全歌集」から「掲載した歌」に沿ってリンクできるようにしてあるが
このところ、随分と怠っていた
だから、また奮起を促す意味をこめて、こつこつ「語」を増やしていくことにする
左頁の「語義」からのリンクでは、「古語辞典」へ直接その「語」に繋がるが
見出し付きの「古語辞典」に辿り着くには、「万葉集全歌集」のトップ頁からとなる
そうか...「枕詞」も、まだまだ手間取っているし...
何でもかんでも詰め込んでしまう、そんな「夢」は、なかなか結果が残せないので
少々挫けることもある
しかし、どうせ素人のやることだ、自分が望む物を、どんどん欲張って作ろう
「枕詞」にしても、簡単な「原義」の説明から、詳細に出合った時には、
その都度更新もしよう
枕詞...やっと「カ行」まで終った...まだ先は長そうだ |
 |
掲載日:2013.12.03.
| 春雑歌 詠鳥 |
| 春霞 流共尓 青柳之 枝喙持而 鴬鳴毛 |
| 春霞流るるなへに青柳の枝くひ持ちて鴬鳴くも |
| はるかすみ ながるるなへに あをやぎの えだくひもちて うぐひすなくも |
| 巻第十 1825 春雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【注記】〔826・827〕
| 【1825】語義 |
意味・活用・接続 |
| はるかすみ[春霞] |
| ながるるなへに[流共尓] |
| ながるる[流る] |
[自ラ下二・連体形]漂いながら行く |
| なへに[接続助詞] |
(上代語)〔成立〕接続助詞「なへ」に格助詞「に」のついたもの |
| 一つの事柄と同時に他の事柄が存在・進行する意をあらわす |
| 「~するとともに・~するにつれて・~するちょうどそのときに」 |
| 〔接続〕活用語の連体形につく |
| あをやぎの[青柳之] |
| えだくひもちて[枝喙持而] |
| くひもち[食ふ持ち] |
[他タ四・連用形]口に咥え持つ・くわえる |
| て[接続助詞] |
|
| うぐひすなくも[鴬鳴毛] |
| も[終助詞] |
[感動・詠嘆]~よ・~なあ |
| 掲題歌トップへ |
〔はるかすみ・あをやぎの・て・も〕は、古語辞典の頁へリンク
「古語辞典」頁、まだ完成はしていないが、順次項目を追加
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [ながるる] |
この「流る」は、「春霞」が漂い移動している状態を言うのだろう
「かすみ」は、一般に「たなびく」といい、「立つ」、「居(う)」ともいうが
「かすみ」が「ながるる」というのは、この歌の一例だけだ
雪を「流れ来る」と詠った大伴旅人の歌がある
有名な「梅花歌三十二首」の中に、それがある
| 梅花宴/(梅花歌卅二首[并序] / 天平二年正月十三日 萃于帥老之宅 申宴會也 于時初春令月 氣淑風和梅披鏡前之粉 蘭薫珮後之香 加以 曙嶺移雲 松掛羅而傾盖
夕岫結霧鳥封q而迷林 庭舞新蝶 空歸故鴈 於是盖天坐地 促膝飛觴 忘言一室之裏 開衿煙霞之外 淡然自放 快然自足 若非翰苑何以□情 詩紀落梅之篇古今夫何異矣
宜賦園梅聊成短詠) |
| 和何則能尓 宇米能波奈知流 比佐可多能 阿米欲里由吉能 那何列久流加母[主人] |
| 我が園に梅の花散るひさかたの天より雪の流れ来るかも[主人] |
| わがそのに うめのはなちる ひさかたの あめよりゆきの ながれくるかも |
| 既出、〔万葉の植物〕巻第五 826 梅花宴 大伴宿禰旅人 |
〔語義〕
「かも」終助詞・詠嘆 |
〔歌意〕
わが庭に、梅の花が散る
ひさかたの空から、雪が流れ落ちてくるのかなあ |
この「春かすみ流るる」と、「雪の流れ来る」は、それぞれの原文が、
「春霞流」「由吉能那何列久流」、これは、漢籍の詩語「流霞」「流雪」の応用だという
(小島憲之『上代日本文学と中国文学』中)
『懐風藻』には、
兵部卿安倍朝臣首名の五言春日応詔に、「湛露仁智に重く 流霞松筠に軽し」、
大学頭箭集宿禰虫麻呂の五言侍讌に、「流霞酒処に泛かび 薫吹曲中に軽し」
(薫吹は、春風のこと)と見える
こうしてみると、「かすみながるる」という表現は、
その作者の漢籍への深さをもうかがうことが出来そうだ
大伴旅人は、『懐風藻』にも、「梅雪、残岸に乱ひ」と詩を残している
尚、この「梅花歌三十二首」では、この旅人の歌の次に、同族の大伴百代の歌があり
それは、この宴の参列者誰もが梅の花の風情を詠んでいる中で
| 梅花宴/(梅花歌卅二首[并序] / 天平二年正月十三日 萃于帥老之宅 申宴會也 于時初春令月 氣淑風和梅披鏡前之粉 蘭薫珮後之香 加以 曙嶺移雲 松掛羅而傾盖
夕岫結霧鳥封q而迷林 庭舞新蝶 空歸故鴈 於是盖天坐地 促膝飛觴 忘言一室之裏 開衿煙霞之外 淡然自放 快然自足 若非翰苑何以□情 詩紀落梅之篇古今夫何異矣
宜賦園梅聊成短詠) |
烏梅能波奈 知良久波伊豆久 志可須我尓
許能紀能夜麻尓 由企波布理都々[大監伴氏百代] |
| 梅の花散らくはいづくしかすがにこの城の山に雪は降りつつ[大監伴氏百代] |
| うめのはな ちらくはいづく しかすがに このきのやまに ゆきはふりつつ |
| 巻第五 827 梅花宴 大伴宿禰百代 |
〔語義〕
「しかすがに」は、「そうはいうものの」
「つつ」反復・継続の意で、和歌の文末に用いられた場合は、
後文を言い指して、余情をこめる・「~ことだ」 |
〔歌意〕
梅の花が散るとは、どこなんでしょう
それどころか、この城の山には、雪が降っているというのに... |
旅人の歌のすぐ後に配されているのが、また妙味といえる
|
| |
| [くひ] |
「くひ」は、『西本願寺本』に「啄」とあるのを、
『元暦校本』『類聚古集』により、「喙」と改めた
「啄」は、「ついばむ・くちばし」の意で、「喙」は「くちばし」、両者は同じとする
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕に、
「枝をくはへては鳴かれず、枝取持而の誤にて、枝ニトマリテの意ならむ」としている
しかし、『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕ではその点について、
「それは理屈である。さう考へては興味索然である」という
私には、「それは理屈だ」ということの方が、釈然としないが...
理屈では、どう駄目なのか、知りたいものだ
そこでその折衷案のような形での解釈が起こる
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕は、この描写を実景描写というより、
「春霞」と「青柳」と「うぐひす」の春の代表的景物を揃えて、と説明している
しかし、「歌意」になると...大方の注釈のように「枝を口に銜え持って」としている |
| |
|
|
| 【歌意1826】 |
わたしの愛しい人に、山を越えないでと...
その名を擁く莫越の山の呼子鳥よ
あの人を、呼び返してほしい
夜が更けないうちに... |
この歌、「莫越山」「呼子鳥」と
その名をまさに、歌の情感に盛り込み興じたものであり
女の切実な愛情を、藁にもすがるような思いで詠っている
自分では、もうどうにもならない
だから、山も鳥も、手を貸してくれ、と...
莫越山を越えて行こうとする男は、夫だろうか
それとも、恋人なのか
ここまで切実に形振り構わず想いを訴えるのは
この見送りの意味が、通常の別れとは違うものなのかもしれない
行ったきり、もう二度と戻ってこないのかもしれないと
女は直観して、不安を抱く
一旦生じた不安は、なかなか消せないものだ
次に逢ったときはじめて、その不安は「歓びの涙」になるのだろう
この歌は、そんな先の展開をも想像させてくれる
しかし、「よのふけぬとに」というのだから
やはりこの夜の別れたばかりの寂しさを詠ったものなのだろうなあ
夜の更けるまで、まだ時間があるというのに
あの人は行ってしまった...
そんな寂しさを詠ったものと思うのが自然なのだろう
一首の歌に触れるとき、ひとそれぞれに感じ方があるだろうが
私は、まず歌の情景を浮かべてしまう
この歌のように、あたかも今生の別れのような想いで泣きすがる情景
ただ一夜の別れのことであれば、あまりの激情と思える
いや、同居も叶わぬ環境であれば、それも切ない想いに繋がる
どんな情況下で、詠われたものかは解らないが
男を見送る姿に、追いかけることも出来ず、祈るように見詰める女の辛さを思う
今日は、思いがけずに一日中あることばに支配されていた
通勤の電車の中で、いつものように今夜の準備のため拾い読みをしていたら
「とに」の用例歌で持ち出した「かへりませ」の「ませ」に随分悩まされた
帰宅するまで、ずーっと頭から離れず
ひょっとすると、未解決のまま終るのでは、と
文庫本を読んでいたときは、すんなり読めたが
それは一つ一つの語義を拾い出さず、全体の歌意をまず浮かべようとするから
この「ませ」にしても、私の中では何も問題なく訳せた
ようは、現代でも使うような感覚の「行ってらっしゃいませ」の「ませ」のように
丁寧な言葉の「命令形」程度の感覚だった
しかし、「かへりませ」をいざ品詞で考えようとしたとき
私は、何の迷いもなく推量の助動詞「まし」だと思い込んでいた
すると、「ませ」は「未然形」だ...おかしい
しかも、接続する活用語は「未然形」...頭が混乱してきた
「かへり」は「ラ行四段」であり、「かへり」は「連用形」になる
これでは助動詞「まし」に接続するはずもない
そこで「かへり」に関係する、意として「帰る」になる周辺の語を探したが
何も手掛かりは得られない
結局仕事中も、そのことが頭から離れず、時折ノートを開いては
何とか見つけ出そうともがく
しかし、辞書もない状態での私の能力など、たかが知れている
助動詞「まし」の思い込みが離れなかったことが大きい
結局帰りに辞書を書店で立ち読みし、
上代で用いられた尊敬語の動詞「坐(ま)す・座(ま)す」を見つけ
その命令形が「ませ」、さらに活用語の「連用形」に接続...一気に解決した
これで今夜はスムーズに作業できると少々気も緩み、でも甘えて駅でビールを一杯
それがいけなかった
今度は、「まくらかむ」などという語に、またまたお手上げ状態になってしまって...
これも同じように歌意全体は、浮かべられる
いつものように、語句を一つ一つ確認しながら
その歌意が妥当か否かの作業になるのだが...
「まくらかむ」...どんな品詞の構成なのだろう、これも振り回された
幸い日中と違って、家には辞書もある
片っ端から引っ張りだすが...
名詞「枕」、動詞「枕(ま)く」くらいなもので
では「かむ」は何だ、と呟いてしまう
「まかむ」であれば、問題ない、動詞「まく」に助動詞「む」だ
原文「枕可牟」は、本当は「まかむ」ではないのか、
と、これまでの研究者たちを不遜にも疑った
動詞「枕(ま)く」が訓めるくらいだから、「枕可牟」を「まかむ」でもいいだろう、と
しかし、「枕(ま)く」しか載っていない...頼みの綱「岩波古語辞典」も...
こうなれば、古書店で非常に安く手に入れた我が「古語辞典軍団」を全部確認した
そして見つけたのが「まくらく」
この四段動詞「まくらく」の未然形「まくらか」に助動詞「む」で
漸く、これも決着...古語は、本当に辞書を引くのも大変だ
何しろ、元も言葉を知らなければ、かすりもしない
ちなみに手持ちの辞書の結果
「まくらく」の載っている辞書は、
『角川全訳古語辞典』『旺文社古語辞典(新訂版)』『旺文社古語辞典第九版』
載っていなかった辞書は、
『岩波古語辞典』『旺文社全訳古語辞典』『三省堂例解古語辞典』『学研全訳古語辞典』、
『大修館書店古語林』、つまり手持ちの辞書では載っていない方が多かった
それぞれ古語辞典にも個性があるのだろうが...何だか腑に落ちない
何とか、もっと楽な方法で読みこなせないものか、最近特にそう思う
でも、これもまた楽しい時間であることには違いないが
右頁の「狭野弟上娘子」の二首、夫・中臣朝臣宅守との応答歌全六十三首を
かつて全部載せようとしたが、つい他の歌群に想いがいってしまって...
久し振りに狭野弟上娘子の歌に接した
「はやかへりませ こひしなぬとに」の繰り返し詠う姿...泣けてくる
まだまだ深層には到っていないが、いつか本当に深く書きたいものだ
あの頃は...まだまだ未熟だった
〔悲話応答歌〕-引き裂かれた愛-
|



 |
掲載日:2013.12.04.
| 春雑歌 詠鳥 |
| 吾瀬子乎 莫越山能 喚子鳥 君喚變瀬 夜之不深刀尓 |
| 我が背子を莫越の山の呼子鳥君呼び返せ夜の更けぬとに |
| わがせこを なこしのやまの よぶこどり きみよびかへせ よのふけぬとに |
| 巻第十 1826 春雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【注記】〔1945〕〔3769・3770・4187・4419〕
| 【1826】語義 |
意味・活用・接続 |
| わがせこを[吾瀬子乎] |
| なこしのやまの[莫越山能] |
| よぶこどり[喚子鳥] |
| きみよびかへせ[君喚變瀬] |
| かへせ[返す] |
[他サ・命令形]もとのようにする・もとの状態にもどす |
| よのふけぬとに[夜之不深刀尓] |
| ふけ[更く] |
[自カ下二・未然形]時が経つ・(夜が)更ける |
| ぬ[助動詞・ず] |
[打消・連体形]~ない |
未然形につく |
| と(に)[外(に)] |
内、外の「と」が原義 〔ここでは打消し助動詞「ぬ」につく〕 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [わがせこを] |
「わがせこ」は、「わがせ」と同義で、
女性から夫・恋人などの親しい男性をいう語
和歌では、「わがせこを」とする語は多くあるが
古語辞典では、「枕詞」としての見出しはなく、しかし「枕詞」とする注釈書もある
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕などは、
地名「莫越(なこし)」にかかるとしている
そのかかり方の説明は、
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕によると、
「我が背子よ山を越えるな」の意で、山名にかけているとする
私が「我が背子を」で、まず最初に浮かべる歌は
弟、大津皇子を偲ぶ姉、大伯皇女の歌だ [既出『書庫-6』巻第二 105]
| 我が背子を大和へ遣るとさ夜更けて暁露に我れ立ち濡れし |
大切な人、愛する人のこという
|
| |
| [なこしのやまの] |
この山の比定は、明確ではなく、幾つかの説がある
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕に、
「今按、第三ニササレ浪イソ越道トヨメルは巨勢路ナレハ、今モ巨勢山ヲ云フトテカクハヨソヘタルニヤ」として以来、奈良県御所市古瀬の山をさす説が多い
それに倣うのが、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕、
『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕、
『万葉集総釈』〔楽浪書院、昭和10~11年成〕、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕などの諸注
ただし、この「越しの『コ(甲類)』」と、「巨勢の『コ(乙類)』」とは、
仮名違いであるので、「巨勢」とは解し難いとして、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕の補注は、次のように記している
「この歌の近くの地名を見ると、大和の国の香具山、巻向山、春日、佐保、三船山、東国の筑波山などであるから、東国の歌であると見てもよいかもしれない。そう見ると、延喜式神名帳、安房国、朝夷郡に、莫越山神社の名がある。この歌の莫越山と文字が一致するので、あげておく」とある
この「莫越山神社」は、
千葉県安房郡丸山町(現南房総市宮下町)に二社(宮下・沓見)あり、
宮下の莫越山神社では、この掲題歌の「莫越山」を当地と伝えて、
大晦日の夜にこの歌を歌い続ける神事がある、という
(今井福治郎『房総万葉地理の研究』に「村崎勇氏談」として記す)
このように『大系』では、安房の「莫越山神社」が、その文字の一致を含めて
極めて有力であるかのように書いてあるが
気になって、ネットで「莫越山神社」を調べてみた
すると、この神社の北側にある渡度山(とどやま)が、奈良県の巨勢山に似て
円錐形の秀麗な形(神奈備山)に見えることから、古代からこの山を神体として
その南麓に「遥拝所」として造営されたものと思われる、とあった
ここでは、「莫越山神社」の名の由来は解らなかったが
一つの想像として、古代この地に住む人たちにとって
実際に奈良の巨勢山を見たであろう人たちから
その神聖な「山」を神体とする神社が造られたのだとしたら
少なくとも、本来の「莫越山」は、奈良の「山」であったとも考えられる
そう思うと、確かに「文字表記」では、安房の神社名に拠る東国だとするよりも
本家本元の奈良の「莫越山」が、その名を失っても
遠くはなれた、この東国の巨勢山に似た「莫越山」が
その遠さゆえに、ごく自然にその名を残しているのではないだろうか
と、私自身が遠い遥かな古代に想いを馳せて、「莫越山」と...呟いている |
| |
| [よぶこどり] |
古語辞典によると、その鳴き声が人を呼ぶように聞こえる鳥、とあり
今の「かっこう」とするのが通説となっている
『万葉集』には、九首ほど詠われているが、春または晩春の景物とされている
ただし、一首だけ例外があり、「夏雑歌」に「季節外れ」の飛来を詠う歌がある
| 夏雑歌詠鳥 |
| 旦霞 八重山越而 喚孤鳥 吟八汝来 屋戸母不有九二 |
| 朝霞八重山越えて呼子鳥鳴きや汝が来る宿もあらなくに |
| あさかすみ やへやまこえて よぶこどり なきやながくる やどもあらなくに |
| 巻十 1945 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
〔語彙〕
「あさかすみ」は原文「旦霞」だが、現在の諸注はほとんど「霞」を「霧」とし、
「あさぎりの」としている
どちらも「やへやま」にかかる枕詞だが、「霞と霧」の感覚の違いは既出
そもそも、諸本には「霞」とあるが、『類聚古集』が「霞」を「霧」とし
『元暦校本』は「旦霞」としながらも、「霞」の右に赭で「霧」と記し、
その訓を「あさきりの」と訓んでいることや、〔10-1949〕に、
| 旦霧 八重山越而 霍公鳥 宇能花邊柄 鳴越来 |
| 朝霧の八重山越えて霍公鳥卯の花辺から鳴きて越え来ぬ |
との表現があることなどから、
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕が『類聚古集』の本文を採り、
「朝霧の」と訓んで以来、それに従うのが殆どの諸注といえる
しかし、「霧」とするのは、『類聚古集』の一書のみであり、『古今和歌六帖』に、
「朝がすみやへの山こえしよぶこ鳥鳴くやながくるやどはあらなくに」とあり
原文「旦霞」は、手の入れようがない
別の歌で、同じ表記〔旦霧 八重山越而〕があるからといって、
だから、これも本来はそうなのだろう、とするのは論理的ではないと思う
そもそも、「歌」は同じ語句になるのが珍しいくらいだ
この時代の表記法や、慣用句で、確かに多くの語句の類似性はあるが
それでも別歌として存在するのであれば、その表記があるから、というのはおかしい
出来るだけ原文は、いじらない方がいいと思う |
〔歌意〕
朝かすみが、八重に立つように幾重にも重なり合った山を越えて、呼子鳥よ
鳴きながら、お前はやってきたのだな
しかし、どうして今頃...ここには、お前の宿などないではないか |
人を呼ぶように鳴く、というのは
人恋しくて鳴く、そしてやって来た、とも解釈できる
そうした「人」が思う「呼子鳥」を、どうしてこの時期にやってきたのか、と
哀れに思って詠った歌のように感じる
そんなに人恋しかったのか...しかし、お前が休める樹木はないのだよ
この後の作者の行動が感じられる歌でもありそうなのだが...
「呼子鳥」が、一般には「かっこう」とは言われているが、
その他に、「ほととぎす」「つつどり」「じゅういち」を含め
この四種を「呼子鳥」とし、「呼子鳥はほととぎすの歌名」とするのもある
しかし、『万葉集』中での「呼子鳥が九首」に対して、「ほととぎすは百五十六首」
しかも、「ほととぎす」は、夏の典型的な景物とされているので
やはり、「呼子鳥」を「ほととぎす」とするのは無理があるだろう |
| |
| [よのふけぬとに] |
この語句で一番手間取ってしまった
そもそも「とに」という語は、古語辞典には載っていない
何とか辿り着いたのが、「と(外)」
これは、このサイトでの「古語辞典」頁ですでに収録していた
しかし、そのとき活用した辞書では、充分理解できなかった、ということか
まず、その「外」から語義を拾い出してみる『岩波古語辞典』
【「と(外)」】
「内」「奥」の対。自分を中心にして、ここまでが「うち」だとして区切った線の向こう。自分に疎遠な場所だという気持ちが強く働く所。時間に転用されて、多くは未だ時の至らない以前をさす。類義語「ほか」は、はずれの所。「よそ」は、無縁・無関係の所。
この元の意味があって、これからこの歌に関わるところを書き出す
時間的に(多くは打消しの助動詞「ぬ」を受けて「とに」の形で)
「~しない先に・~しないうちに」、とする
この用例は、『万葉集』中でも掲題歌を含め五例しかなく、以下その例歌を載せる
| (中臣朝臣宅守与狭野弟上娘子贈答歌) |
| 和我屋度能 麻都能葉見都々 安礼麻多無 波夜可反里麻世 古非之奈奴刀尓 |
| 我が宿の松の葉見つつ我れ待たむ早帰りませ恋ひ死なぬとに |
| わがやどの まつのはみつつ あれまたむ はやかへりませ こひしなぬとに |
| 巻第十五 3769 贈答歌 狭野弟上娘子 |
〔語義〕
「はや」は副詞で、早く・すみやかに
「かへりませ」の「ませ」は、補助動詞サ行四段「ます(座す・坐す)」の命令形
上代に用いられた尊敬語で、動詞の連用形について、尊敬の意を表す
「~ていらっしゃる・お~になる」
「こひしなぬ」は、自動詞ナ変「恋ひ死ぬ」の未然形「恋ひ死な」に、
打消しの助動詞「ず」の連体形「ぬ」がついたもので、
「恋焦がれて死なない」 |
〔歌意〕
家の庭の、松の葉を見ながら
わたしは、あなたを待つつもりです
ですから、どうか早く帰ってきてください
わたしが、恋死なないうちに... |
| |
| 比等久尓波 須美安之等曽伊布 須牟也氣久 波也可反里万世 古非之奈奴刀尓 |
| 他国は住み悪しとぞ言ふ速けく早帰りませ恋ひ死なぬとに |
| ひとくには すみあしとぞいふ すむやけく はやかへりませ こひしなぬとに |
| (右九首娘子) |
| 巻第十五 3770 贈答歌 狭野弟上娘子 |
〔語義〕
「あし」は、形容詞シク「悪し」で、「住みあし」とは、「住にくい環境」
「すむやけく」は、「すみやけし」と同根の形容詞シク「速やけし」の連用形で、
「速やかに」という意
下二句は同上
|
〔歌意〕
他国は、住にくいところだといいます
どうか、速やかに帰ってきてください
わたしが、恋死なないうちに... |
| |
| 豫作七夕歌一首 |
| 妹之袖 我礼枕可牟 河湍尓 霧多知和多礼 左欲布氣奴刀尓 |
| 妹が袖我れ枕かむ川の瀬に霧立ちわたれさ夜更けぬとに |
| いもがそで われまくらかむ かはのせに きりたちわたれ さよふけぬとに |
| 巻第十九 4187 七夕歌 大伴宿禰家持 |
〔語義〕
「いもがそで」は、枕詞もあるが、その場合は「袖を巻くこと」から、
地名「巻来(まきき)」にかかるので、この歌は、実際の意味をいうのだと思う
「まくらかむ」は、他カ四段動詞「枕(まくら)く」の未然形「まくらか」に、
意志の助動詞「む」の終止形、だと思う
この「まくらく」という動詞、なかなか辞書では見つからない
これも、幾つかの辞書を引き出しての発見だった
同じ漢字の見出しでは「枕(ま)く」はある...しかし、「枕(まくら)く」は...
どちらも、その語義は同じなのだが...
従って、「まくらかむ」の意味は、「枕として寝たい」
「さよ」は「夜、「さ」は接頭語
|
〔歌意〕
妻の袖を、わたしは枕にして寝たい
川の瀬に、霧よ立ち込めてくれ
妻が待っている、この夜が更けないうちに... |
| |
| 獨惜龍田山櫻花歌一首 |
| 多都多夜麻 見都々古要許之 佐久良波奈 知利加須疑奈牟 和我可敝流刀尓 |
| 龍田山見つつ越え来し桜花散りか過ぎなむ我が帰るとに |
| たつたやま みつつこえこし さくらばな ちりかすぎなむ わがかへるとに |
| (右三首二月十七日兵部少輔大伴家持作之) |
| 巻第二十 4419 獨惜歌 大伴宿禰家持 |
〔歌意〕
竜田山を、桜花を見ながら越えて来たが
その桜も、散っているのではないだろうか...
わたしが帰るときまでは、散らないでいてほしい |
〔注〕
ここでの「とに」の用法は、他の四首とは違って、その前に打消しの語がない
だから、「~しないうちに」とは訳せないとするが
この歌を自然に訳せば、「帰らない」ではなく「帰るまでに」として
疑問の係助詞「か」を伴う「散るのだろうか」と合わせ
「帰るまでに散るのだろうか」が、同じ意味の「帰らないうちに散るだろうか」
こうすると、まったく同じような意味になる
打消しの語はなくても、疑問の「か」があることによって
歌意全体の用法としては、問題ないだろう、と思う
|
|
| |
|
|
| 【歌意1827】 |
朝になると、堰にやってきて鳴く貌鳥よ
お前までも、あの人を恋しく思っているのか
こんなに、いつまでも鳴き続けるなんて... |
「かほ鳥」が、「かっこう」という説が有力で
そのことには、私には何も意見を言える知識もないが
仮に、「かっこう」であるなら、
その「かっこう」として今まで知っていた一面とは別の姿を「かほ鳥」は見せてくれる
右頁で触れた、「ひばりの歌名」とするように
この「かほ鳥」の用例は、まさに「歌語」であり、「歌名」ではないか
どこかもの悲しい「鳥」のイメージを受ける
「かほ鳥」と詠えば、それがあたかも「枕詞のように」、片恋などの調べになる
昨日の「呼子鳥」もそうだが、学術的な「鳥名」の解明だけに陥るのではなく
「歌名」としての「鳥」のあり方を、受け入れてもいいように思える
「かほ鳥」と詠えば、その歌の「調べ、香り」が、言葉に代わって心に響くように...
その意味で、やはり「鳥」に自分の心を重ねた歌を、ここに載せる
| 雑歌/帥大伴卿宿次田温泉聞鶴喧作歌一首 |
| 湯原尓 鳴蘆多頭者 如吾 妹尓戀哉 時不定鳴 |
| 湯の原に鳴く葦鶴は我がごとく妹に恋ふれや時わかず鳴く |
| ゆのはらに なくあしたづは あがごとく いもにこふれや ときわかずなく |
| 巻第六 966 雑歌 大伴宿禰旅人 |
〔語義〕
「あしだづ」は、葦の生えている水辺にいるところから、「鶴」の異名
このような意から「枕詞」としての「あしたづの」は、「音(ね)なく」にかかる
「いもにこふれや ときわかずなく」は、掲題歌と類想
「ときわかず」、季節の区別がない、時を選ばない、いつもである |
〔歌意〕
湯の原でなく葦鶴は、私のように妻を恋しく思っているからか、
時を選ばず、いつも鳴いているなあ |
|
ここでも、改めて思う
このように作者が解っていて読む場合は、自然とその情景が無理なく心に入り込む
大伴旅人が、妻を亡くしたその悲しみを、
この次田の温泉宿で、鶴の鳴き声を聞き、我が身に響かせ「葦鶴」を同化させた歌だ
掲題歌〔1827〕も、かほ鳥がしきりに鳴くのを、自分と同化させている
しかし、その作者は誰か解らないので、
どのような「恋慕」なのか、いろいろと想像して見ることができる
「かほ鳥」の「片恋」のイメージも拭えない
「なれだにも きみにこふれや」という表現は、
そんなにしきりに鳴くのは、「お前もきっと恋しがっているのだろうか」というのだと思う
ならば、私と同じではないか
私の気持ちも解るだろう、なあ「かほ鳥よ」
自分以外の他の者までも、「慕う」、「恋心をいだく」その姿を知ると
人は、何かホッとするような気分になるのではないだろうか
同じように想いを胸に抱き、仲間意識が芽生える
ひょっとすると、万葉の人たちにとって「かほ鳥」は、
せつない恋心を共鳴させる「仲間」なのかもしれない
大伴旅人は、決して「葦鶴」に共鳴などしていない
しているのは、その「ときわかずなく」姿だ
しかし、「かほ鳥」よ、お前もなのか、という作者の解らない歌では
その「かほ鳥」に共鳴しているように思う...「仲間なんだなあ」と
|

|
掲載日:2013.12.05.
| 春雑歌 詠鳥 |
| 朝井代尓 来鳴杲鳥 汝谷文 君丹戀八 時不終鳴 |
| 朝ゐでに来鳴く貌鳥汝れだにも君に恋ふれや時終へず鳴く |
| あさゐでに きなくかほどり なれだにも きみにこふれや ときをへずなく |
| 巻第十 1827 春雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【注記】〔375・376〕【左頁】〔966〕
| 【1827】語義 |
意味・活用・接続 |
| あさゐでに[朝井代尓] |
| ゐで[井手・堰] |
〔堰(ゐせき)ともいう〕杭や石で川の流れを塞き止めた所 |
| きなくかほどり[来鳴杲鳥] |
| きなく[来鳴く] |
[自カ四・連体形]来て鳴く |
| かほどり[貌鳥・容鳥] |
美しい鳥の意とも、今の「かっこう」とも言われている |
| なれだにも[汝谷文] |
| だにも |
〔成立〕副助詞「だに」+係助詞「も」 |
| |
①最小限の一事をあげて強調する意を表す「せめて~だけでも」 |
| |
②軽いものをあげて他の重いものを類想させる「~さえも」 |
| 〔接続〕体言・活用語・副詞・助詞につく |
| きみにこふれや[君丹戀八] |
| こふれ[恋ふ] |
[他ハ上二・已然形]思い慕う・恋しく思う |
| や[係助詞] |
[疑問]~か 係り結びの「係り」 |
| 〔接続〕活用語には連体形・連用形につくが上代では「已然形」にもつく |
| ときをへずなく[時不終鳴] |
| をへ[終ふ] |
[他ハ下二・未然形]終える・終らせる・終りまでやる |
| ず[助動詞・ず] |
[打消・連用形]~ない |
未然形につく |
| なく[鳴く] |
[自カ四・連体形](鳥・虫・獣が)声を出す 係り結びの「結び」 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [かほどり] |
『万葉集』中では、五例ある
その表記は、掲題歌「杲鳥(10-1827)」の他に、
「可保等利(17-3996)」「容鳥(3-375)・(10-1902)」「貌鳥(6-1051)」
昨日の「呼子鳥」同様、「未詳」とされているが、
季節不明の「巻第三 375」の一首を除いて、いずれも「春の鳥」として詠まれている
それは、「かっこう」の鳴き声からきた名称とする説が有力だとしている
江戸時代の初期、長崎で発行された日本語とポルトガル語の辞書「日葡辞書」がある
当時の日本語(ローマ字表記)のポルトガル翻訳を辞書にしたもので、
約三万二千語を収録しており、当時の日本語の実相を知る上で、第一級資料とされている
明日香の万葉図書館にいくと、あの万葉集だらけの図書館にも、
この「日葡辞書」や、その研究書が多くある
その「日葡辞書」に「Cancodori、Campodori」とあるのも、
「かっこう説」の有力な一証となってるようだ
「かお鳥」を「ひばり」の歌名とする説もある(川口爽郎『万葉集の鳥』)
|
| |
| [ときをへずなく] |
「ときをへず」は、「ときを終らせない」となり、「いつまでも」の意味になる
「かほどり」の、そのような鳴き方を詠った歌がある
| 雑歌/山部宿祢赤人登春日野作歌一首[并短歌] |
| 春日乎 春日山乃 高座之 御笠乃山尓 朝不離 雲居多奈引 容鳥能 間無數鳴 雲居奈須 心射左欲比 其鳥乃 片戀耳二 晝者毛 日之盡 夜者毛 夜之盡
立而居而 念曽吾為流 不相兒故荷 |
| 春日を 春日の山の 高座の 御笠の山に 朝さらず 雲居たなびき 貌鳥の 間なくしば鳴く 雲居なす 心いさよひ その鳥の 片恋のみに 昼はも 日のことごと 夜はも 夜のことごと 立ちて居て 思ひぞ我がする 逢はぬ子故に |
| はるひを かすがのやまの たかくらの みかさのやまに あささらず くもゐたなびき かほどりの まなくしばなく くもゐなす こころいさよひ そのとりの かたこひのみに ひるはも ひのことごと よるはも よのことごと たちてゐて おもひぞわがする あはぬこゆゑに |
| 巻三 375 雑歌 山部宿禰赤人 |
〔語彙〕
「はるひを」は、「かすが」にかかる枕詞
春の日が、「かすむ」という意でかかる
「たかくらの」も、「みかさ」にかかる枕詞
高座は、高い座席、天皇の玉座「高御座タカミクラ」には、天蓋があることから
「御笠」の意で「三笠」にかかる
「あささらず」の「さらず」は、場所とは違って「時間」につく場合で、
その時の意味は、「~ごとに・~にはいつも」となる
「くもゐ」は、ずっと居座る雲
「しばなく」の「しば」は、「しばしば・しきりに」の意
「いさよひ」は、ああしようか、こうしようか、と決めかねること「ためらう」
「ひるはも」の「も」は、詠嘆
「ことごと」は、「悉く」の意で、すっかり
「たちてゐて」は、立ったり座ったりの意だが、「立っても居ても始終」ではなく
「いてもたってもいられず」のそわそわして落ち着かない表現 |
〔歌意〕
春日の山の、高座の三笠の山に朝になるたびに雲がたなびき
貌鳥が絶え間なくしきりに鳴いている
そのたなびく雲のように、私の心はためらい、
その貌鳥の鳴き声のように、私は片恋ばかりしている
昼も...そして夜も夜通しずっと、立ったり座ったり落ち着かず
こんなに私が想い悩んでいるのは、
逢ってもくれない、あの娘が... |
| |
| 反歌 |
| 高按之 三笠乃山尓 鳴鳥之 止者継流 戀哭為鴨 |
| 高座の御笠の山に鳴く鳥の止めば継がるる恋もするかも |
| たかくらの みかさのやまに なくとりの やめばつがるる こひもするかも |
| 巻三 376 雑歌 山部宿禰赤人 |
〔語彙〕
「つがるる」の「るる」は、自発の助動詞「る」の連体形で、四段の未然形につく |
〔歌意〕
高座の三笠の山に鳴く鳥が、
鳴きやんだかと思うとまた鳴き出すように
私の恋心も「そのように」、想いしずめては、また想い続けてしまう
そんな恋をしているのだなあ |
貌鳥は、このように「しきりに鳴き続ける」ような鳥で
その鳴き方を、人の「恋心」のありように重ねて詠っている
春の鳥といわれるのに、どこか「秋の鳥」のような哀しさもある |
|
|
| 【歌意1829】 |
紫草の根が、こうして延び広がっている横野の、春の野では
わたしが、あなたを想っているからなのか
うぐいすが、唱和するように鳴いています |
春の、のどかな野原
そこで女は、愛しい人に想いを馳せているのだろう
「むらさきのねはふ」で、どんな情景を浮かべるのだろう
野原を覆うような、その紫草の根...
自分の「想い」の拡がりゆくさまを見ているのかもしれない
そして、もう一つ忘れてならないのが「紫」という色
何しろ、平安時代には「色」の代表といわれる高貴な色だ
「紫」と名は出さなくても「色」と詠っただけで、それが「紫」を知らせるものだったようだ
この万葉時代の「紫」が、どこまで「深み」のあるものか解らないが
万葉時代から平安時代へ、時代が隔世しているのではなく、
人々の意識も、突発的な意識変化ではない自然に流れ着くものだろう
「むらさきのねはふ」では、自分の想いと、相手への畏敬の念があるのだと思う
さらに、「うぐひす」の鳴く声
古今集巻第十九雑躰〔1011〕歌に、その鳴き声を主観的に聞く歌が
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕の補注にあった
| 俳諧歌 |
| 題しらず |
| むめのはまみにこそきつれ うぐひすのひとくひとくといとひしもをる |
| 古今集 巻第十九 1011 雑躰歌 読人しらず |
この「ひとくひとく」は、「人来(く)、人来(く)」で、
「厭ひしもる」は、その人の訪れを嫌がって鳴いている、と解する歌だが
「うぐひす」の鳴き声を、このように「主観的」に聞くことが出来るのなら
掲題歌〔1829〕の「うぐひすなくも」もまた、
作者である女にとっては、とても好意的に聞こえるのかもしれない
この古今集の歌を例に出し、『新全集』では「恋人来る」とも解せるかもしれない、と
人の心が満ち足りているときには、目にするもの、聞くものすべてが好意的に見え、聞こえる
同じものを「見・聞く」のでも、
少しでも、不安があれば、その「見よう」も「聞きようも」も違うものだ
ここでは、「きみをかけつつ うぐひすなくも」
あなたを想いながら...あっ、うぐひすまでも、といえるのではないだろうか |
|
掲載日:2013.12.06.
| 春雑歌 詠鳥 |
| 紫之 根延横野之 春野庭 君乎懸管 鴬名雲 |
| 紫草の根延ふ横野の春野には君を懸けつつ鴬鳴くも |
| むらさきの ねばふよこのの はるのには きみをかけつつ うぐひすなくも |
| 巻第十 1829 春雑歌 詠鳥 作者不詳 |
| 【1829】語義 |
意味・活用・接続 |
| むらさきの[紫之] |
| むらさき[紫・紫草] |
草の名・その草の根で染めた赤紫色 |
| もと、武蔵野に多く自生し、根は赤紫色の染料とした |
| ねばふよこのの[根延横野之] |
| ねばふ[根延ふ] |
[自ハ四・連体形]根が張る・根が長くのびる |
| よこの[横野] |
一説では、大阪市生野区巽大地町の式内社横野神社のある一帯 |
| はるのには[春野庭]春の野では |
| きみをかけつつ[君乎懸管] |
| かけ[掛く・懸く] |
[他カ四・已然形]心にとめる・心を託す・慕う |
| つつ[接続助詞] |
[反復]~(し)ながら |
連用形につく |
| うぐひすなくも[鴬名雲] |
| も[終助詞] |
[感動・詠嘆]~よ・~なあ |
文末につく |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [むらさき]「色の代表『紫』」〔古語辞典より〕 |
平安時代には、紫は色彩の中の代表であった。単に「濃き」「うすき」と言った場合でも、それは紫をさした。また「色ゆるさる」「ゆるし色」ということばがあったように、一般の人が着ることを許されない高貴な色であった。この紫を生かしたのが、「源氏物語」である。桐壺の更衣(桐の花は紫)、藤壺、さらにその「紫のゆかり」としての紫の上と、紫は理想の象徴として物語全体をおおっている。
|
| |
| [よこの] |
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕には、『日本書紀』の仁徳紀の河内横野、
その式内社の河内渋川郡横野神社を例示しつつ、
「野にの横手にながきをいふにて、地名にあらし」としている
社名の横野も、真淵式に考えると、「もと野の形状からきた地名を受けているもの」
になるのかもしれない |
| |
|
 |
| 【歌意1830】 |
春なんだなあ
妻を探し求めて、
うぐひすが木枝の先を、伝え移りながら、
また、しきりに鳴いているではないか... |
春の、のどかな情景というよりも
やたらとうるさい、うぐいすの鳴き声を、苦笑いしながら聞いているような歌だ
そこに、春になった実感をこめたのだろうか
いや、まだまだ想いは拡がる
このうぐいすに、自分を重ねれば
妻を求めて、こんなにも積極的に動ける「うぐいす」を
作者は羨ましく思ったのかもしれない
このうぐいすのように、奔放に妻探しが出来ない我が身を、嘆いている...
あるいは、老境に入った者が
俺も若い頃は、あんなに盛んだったのに、
今では、やけにうるさく感じてしまう
もう、老いてしまったのだなあ...と、これも嘆きの詠歌
昨日も書いたが、「作者不詳歌」というのは
単純に鑑賞したくても、その人柄が想像できないので
こんな風に、やけに妄想のような「心象風景」が浮んでしまう
これも、私だけの『万葉集』の楽しみ方にしておこう
そう思えば、「ある歌」を、自分の年代ごとに触れてみれば
それが、自分自身の「感性」の移り行く姿なのだ、と確認もできる
それも、いいことだ
|

 |
掲載日:2013.12.07.
| 春雑歌 詠鳥 |
| 春之在者 妻乎求等 鴬之 木末乎傳 鳴乍本名 |
| 春されば妻を求むと鴬の木末を伝ひ鳴きつつもとな |
| はるされば つまをもとむと うぐひすの こぬれをつたひ なきつつもとな |
| 巻第十 1830 春雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【注記】〔3961・3751・3760〕
| 【1830】語義 |
意味・活用・接続 |
| はるされば[春之在者]春になると |
| つまをもとむと[妻乎求等] |
| もとむ[求む] |
[他マ下二・終止形]手に入れようと探す・欲しいと願う |
| と[格助詞] |
[引用]~と 〔接続〕体言、体言に準ずる語につく |
| うぐひすの[鴬之] |
| の[格助詞] |
[主語]~が 〔接続〕体言、体言に準ずる語につく |
| こぬれをつたひ[木末乎傳] |
| こぬれ[木末] |
〔上代語〕「このうれ」の転、こずえ・木の枝の先 |
| つたひ[伝ふ] |
[自ハ四・連用形]ある所から他の所へ何かに沿って移動する |
| なきつつもとな[鳴乍本名] |
| つつ[接続助詞] |
[継続]~しつづけて |
連用形につく |
| 前の句の連用形「つたひ」と、この連用形「なき」を併せて受けている |
| もとな[副詞] |
根拠もなく・理由もなく・しきりに・やたらに |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [はるされば] |
原文「春之在者」は、一般的に「~されば」として表記されて場合とちがう
普通に「~されば」と表記されるのは、「去」や仮名書きの「佐礼・左礼・散礼」が多い
しかし、この歌を含めて、三例だけ「之者」の用字例がある
この表記の特徴は、強調の副助詞「し」を用いる「しあれば」を約したものという
ごく普通に読めば、「はるしあれば」とし、そう解することになると思う
|
| |
| [もとな] |
「もとな」の原義は、「本(元)・無」で、
「訳もなく・理由もなく」の意を表す副詞と言われている
次の用例歌では、その本来の「意」に用いられている
贈答歌/(平群氏女郎贈越中守大伴宿祢家持歌十二首)
|
| 佐刀知加久 伎美我奈里那婆 古非米也等 母登奈於毛比此 安連曽久夜思伎 |
| 里近く君がなりなば恋ひめやともとな思ひし我れぞ悔しき |
| さとちかく きみがなりなば こひめやと もとなおもひし あれぞくやしき |
| (右件十二首歌者時々寄便使来贈非在一度所送也) |
| 既出、〔書庫-6〕巻第十七 3961 贈答歌 平群女郎 |
〔歌意〕
やっとあなたが私の里の近くに戻って来られ
遠く離れていた、恋の苦しさも消えるかと
わけもなく思っておりましたが
そうではなかったのですね...私が浅はかでした |
しかし、次の用字例では、また別の「もとな」の「意」となる
悲別歌/(中臣朝臣宅守与狭野弟上娘子贈答歌)
|
| 宇流波之等 安我毛布伊毛乎 於毛比都追 由氣婆可母等奈 由伎安思可流良武 |
| 愛しと我が思ふ妹を思ひつつ行けばかもとな行き悪しかるらむ |
| うるはしと あがもふいもを おもひつつ ゆけばかもとな ゆきあしかるらむ |
| (右四首中臣朝臣宅守上道作歌) |
| 既出、〔悲話応答歌〕巻第十五 3751 悲別歌 中臣朝臣宅守 |
〔語義〕
「うるはし」については、【注記】
「ゆけばか」、四段「行く」の已然形「ゆけ」に接続助詞「ば」で、
「順接の確定条件」(~ので・~だから・~したところ)になり、
それに、疑問の係助詞「か」がついている
「あしかる」は、形容詞シク(ラ変)「悪し」の連体形、「~づらい・わるい」
「らむ」は、原因推量で「(~というので)~のだろう」
この接続は、活用語の終止形につくが、ラ変の語には連体形につく
|
〔歌意〕
美しく、そしてきちんとしているあなたを
しきりに想って、この道中を行くからなのか
こんなにも心もとなく、辛い道のりなのか... |
| |
悲別歌/(中臣朝臣宅守与狭野弟上娘子贈答歌)
|
| 於毛比都追 奴礼婆可毛等奈 奴婆多麻能 比等欲毛意知受 伊米尓之見由流 |
| 思ひつつ寝ればかもとなぬばたまの一夜もおちず夢にし見ゆる |
| おもひつつ ぬればかもとな ぬばたまの ひとよもおちず いめにしみゆる |
| (右十四首中臣朝臣宅守) |
| 巻第十五 3760 悲別歌 中臣朝臣宅守 |
〔語義〕
「ぬればか」は、同上の「ゆけばか」と同じ「疑問条件」
「ぬれ」は「寝(ね)」の已然形 |
〔歌意〕
あなたを、しきりに想いながら寝るので
一夜も欠かすことなく、夢に見ることができるだろうか |
この用例歌では、「むやみに」とか「しきりに」というような意味合いになる
「訳もなく・根拠もなく」ではなく、もっと積極的な「意志」がある
このように、原因の推定がされるものには「しきりに」のような訳仕方になる
掲題歌のように文末にあって「~つつもとな」となる場合は、
「しきりに~してしようがない」というような、
嘆きの気持ちをこめることが多いようだ |
| |
[うるはし]
|
|
「うるはし」と「うつくし」とは意味の上で重なるところが多く、
そのために正訓字「愛」の読み分けが困難とされる
ただ、仮名書例についてみれば、このように「と思ふ」に続く場合、
または「ミ語法+思ふ」ないし「ミ語法+す」という形においては、
「うるはし」が普通とされている |
| |
|
|
| 【歌意1831】 |
春日にある、羽易の山を越え、
「佐保の内」へ、鳴きながら飛んで行くのは、
誰を呼ぶ「呼湖鳥」なのだろう |
たった一文字の解釈の仕方で、歌の「調べ」が大きく変わる...
その一つの例が、この歌だと思う
上代の格助詞「ゆ」を、どんな風に解すればいいのだろう
ありきたりの注釈書では、特に「訳」に気を遣わず、
「起点」とするような訳し方が多い
「羽易の山から」とするのがそうだ
しかし、手持ちの「註釈書」で拾い出すと、「経由点」もそこそこある
まず、『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕がそうだ
「羽易の山を通って」とある
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕にしても、「羽易の山の上を通って」と...
「たれよぶこどり」の【注記】で採り上げた〔1717〕歌
これを訳していて、「経由点」の方がいい、いやその方が、歌の情景に奥行きがある
そう感じた
この〔1717〕では、「たきのうへの」という描写がそう訳させたのだと思う
その宮滝の辺りの上流にある三船山
そこから、というよりも、そこを越えて飛んできた「呼子鳥」と感じた方が
「呼子鳥」の「誰かを探す」姿が、より現実的だ
「三船山」に居た「呼子鳥」ではなく、すでにあちこちを探がしながら
鳴き渡ってきた「呼子鳥」
誰に呼び掛け、探がし求めているのか...
そんな彷徨う姿、いや「鳴き声」に反応して、作者は応える
「お前は、いったい誰を探しているんだ」と
これも春の風物詩かもしれない
しかし、それにしては、少しもの悲しくもある
冒頭で述べた、一字の解釈の仕方で、大きく歌意を違えて受けてしまう、と言ったのは
まさに、この点にある
仮に、大方の解のように「起点」であれば
「三船山の呼子鳥」が、佐保の内へ、誰かを呼びながら飛んでいったのだろう
それが自然の解釈になる...少なくとも、私にはそう思える
しかし、「経由点」なら、何処から来たのか、必死になって誰かに呼びかける呼子鳥
佐保の内の方へ、飛んで行くあの呼子鳥は、誰を呼んでいるのだろう
そんな「お節介」が、胸に宿る
「春」が、何でもかんでも...「春らしく」ある必要はない、と思う
|
 |
掲載日:2013.12.08.
| 春雑歌 詠鳥 |
| 春日有 羽買之山従 狭帆之内敝 鳴徃成者 孰喚子鳥 |
| 春日なる羽易の山ゆ佐保の内へ鳴き行くなるは誰れ呼子鳥 |
| かすがなる はがひのやまゆ さほのうちへ なきゆくなるは たれよぶこどり |
| 巻第十 1831 春雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【注記】〔1717〕
| 【1831】語義 |
意味・活用・接続 |
| かすがなる[春日有] |
| なる[助動詞・なり] |
[存在・連体形](場所などを表す語を受けて)~にある・~にいる |
| 〔接続〕体言、及び準ずる語、活用語の連体形につく(但し、活用語につく例は上代にない) |
| はがひのやまゆ[羽買之山従] |
| ゆ[格助詞](上代語) |
[起点・経由点]~から・~以来・~を通って |
| 〔接続〕体言、及び準ずる語、活用語の連体形などにつく |
| さほのうちへ[狭帆之内敝] |
| へ[格助詞] |
[方向]~に向って・~の方へ |
体言につく |
| なきゆくなるは[鳴徃成者] |
| なる[助動詞・なり] |
[推定伝聞・連体形]~のようだ・~の声が聞こえる |
| 〔接続〕終止形、ラ変には連体形につく |
| たれよぶこどり[孰喚子鳥] |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [かすが] |
奈良市東部の春日山地西麓一帯の地
平城京の東方郊外にあたる
「春日」と呼ばれる地域は、古くは奈良市北部の佐保川流域を北限とし、
南部は天理市櫟本町に至る広い地域であったが、
奈良遷都以後、若草山・御笠山の西麓に続く台地で、
佐保川から能登川に至る範囲が春日野と呼ばれ、官人の遊宴の場所となった、という
|
| |
| [はがひのやま] |
羽易の山が、春日の地にあったことは、この歌でも解るが、所在未詳
もう一つ、「羽易(はがひ)」には枕詞「大鳥の」にかかる「大鳥の羽易の山」もあり、
そもそも「「羽交」が固有名詞ではなく、
大鳥が羽を拡げたように見えることからの形容ではないか、とされている
固有名詞に拘る説の一つとして、次のようなものもある
江戸時代中期、初の幕府による「幕撰地誌」とされる『日本與地通志畿内部』、
通称『五畿内志』といわれる「地誌」の中に、「大和志」があり
その「添上郡春日山の条」に、
「有三峯、日本宮峯又名浮雲、曰水屋峯又名羽賀、曰高峯又名香山」とある
ここで「春日山」の最高峰「花山」の一名としている
そして、北島葭江著『大和地誌』も、、その花山説を支持して、
「やはり、春日山即ち花山であらうと思ふ。春日神社旧神職の住宅地であった高畑町の辺りから、此の春日山を仰ぐと、御蓋山が著しく前に突出して恰も大鳥の首の如く、而して其の後の春日山が羽を拡げたやうにみえるからであらう」
|
| |
[ゆ]
|
|
上代の格助詞「ゆ」には、四種の用法がある
①起点(動作の時間的・空間的な起点) 「~以来・~から」
②経由点(移動する動作の経由点) 「~から・~を通って」
③手段(動作の手段) 「~で・~によって」
④比較の基準 「~よりも」
この歌で、用いられたのは、①か②だと思うが、そのどちらかは...
①で解釈する註釈書もあるし、②で解釈する注釈書もる
〔参考〕
同義の助詞「ゆり」「よ」「より」があるが、用例が少なく、
意味の違いは不明だとされている
「ゆ」が最も古く、中古に入ると「より」だけが用いられた |
| |
| [さほのうち] |
犬養孝著『万葉の旅・上』によると、
[佐保は、東大寺転害門から法華寺に至る一条通り(平城京の一条南大路)を中心とする一帯。「内」はその区域内をさす語であるが、特に佐保川の右岸から北方佐保山にかけての一帯を当時「佐保の内」といった]とする
この「佐保」には大伴氏や貴族高官の邸宅があったことでも知られる
平城遷都後に、大伴旅人の父・大納言兼大将軍大伴安麻呂がこの佐保に新邸を営み
「佐保大納言」と呼ばれた
そして、長男の旅人、そのまた長男の家持の三代がここに邸を構え
「佐保大納言家」と呼ばれるようになった
|
| |
| [たれよぶこどり] |
「呼子鳥」の「呼ぶ」を活用して、「誰」を置く
同じような表現に、次の歌がある
| 雑歌/幸芳野離宮時歌二首 |
| 瀧上乃 三船山従 秋津邊 来鳴度者 誰喚兒鳥 |
| 滝の上の三船の山ゆ秋津辺に来鳴き渡るは誰れ呼子鳥 |
| たきのうへの みふねのやまゆ あきづへに きなきわたるは たれよぶこどり |
| (右二首作者未詳) |
| 巻第九 1717 雑歌 作者不詳 |
〔語義〕
「うへ」、この歌では「辺り・ほとり・付近」と解する
「ゆ」は、掲題歌の「ゆ」と同じだが、「経由点」の方がいい気がする
やはり掲題歌も同様に、「経由点」の方が、歌の情景に奥行きを感じることができる
「きなき」は、自動詞カ行四段「きなく」の連用形、「来て鳴く」
「わたる」は、動詞の連用形について、時間的には「ずっと~し続ける」で、
空間的には「あたり一面に」となる
|
〔歌意〕
吉野の宮滝の上流の方から、三船山を越え
この吉野の秋津の辺りで鳴き声を響かせているのは
いったい誰を呼ぶ呼子鳥だろう
|
その鳴き声が、誰かを探して呼び掛けている
この吉野の宮滝の辺り一帯に響かせて...
「呼子鳥」の鳴き声を知っているからこそ
こうして、誰かを呼ぶのだ、と想うのだろう
その名前からして、そのように聞こえるから、付けられたのかもしれないが...
|
| |
|
|
| 【歌意1832】 |
呼子鳥よ、お前がいくら鳴き、呼びかけても、誰も応えないのだから
もう鳴くのはやめなさい、呼子鳥よ
佐保の山辺を、その高みまでも翔け、また野に下り翔んではいるのになあ... |
前の歌〔1831〕の時を経て、未だに鳴き飛び続ける呼子鳥に
つい、愛おしくなって呼び掛けた感のする歌だ
呼子鳥の鳴きながら飛翔する姿を詠じたもので終るのなら、
確かに、これは「春雑歌詠鳥」として分類されるのは正しい
逆に言えば、この分類のおかげで、そのようにしか感受出来ないのかもしれない
私が感じた、「愛おしくなって」というのは、
誰も応えはしないのに、それでも鳴く呼子鳥の姿が
どうしても「春」を想起せず、「秋の深み」や「冬の木枯らし」を思うからだ
それは、人のかける「情け」にある
他人にかける「情け」は、私には「春」では感じない
まさに、自分の春めいた気分に浮かれ、何を見ても、何を聞いても、「善し」とするだろう
「呼子鳥」という名前が、「春の鳥」であることは、このさい置いておく
その名を担っている「鳥」の、もの悲しい姿を、感じてしまった
同じような感じ方をしている注釈書に出合った
勿論、私とはその深さにおいて、比べようもないのだが
その注釈書、『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕では、
佐保の山辺に懸想した人があり、そこへ往復している人が、
「我とその苦しい恋を止めよと諌めてゐる心を、呼子鳥に寄せて云ってゐる」と
私も、そのように具体性はないものの、同じような感じを持ったものだ
しかし、『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕で、この解釈を、
「そのように解することも不可能ではないが、春雑歌で詠鳥の中に位置することからすれば、そのまま呼子鳥を詠んだものとして、味わいたい」としている
これこそ、単純な理屈で済まそうとしている
「呼子」という「名前」を借りて、確かに「春」に分類されるだろうが
詠じる作者は、「秋の気分」では、有り得ないのだろうか
いや、「春」であるので、そのような「秋気分」では詠わないもの、と決まっているのだろうか
人の「心」は、いつの季節も、計り知れないほど深いものだ
この歌の分類が、「春雑歌」ではなく、単に「雑歌」であれば
「春の鳥である呼子鳥」を用いた、「愁歌」の歌だと感じても、不思議ではない、と思う
ついでに言えば、『万葉集』の「部立て」は、決して厳格なものではない
使われる「語」が季節を示めすことは理解できるが
その内容にまで、「枠」を何が何でも、と設けることもないと思う
さて、右頁の【注記】で、補足したいことがあったので、ここに改めて書くことにする
| 〔243〕 |
| 「瀧上之」 |
この歌の「滝」は、題詞にもあるように、「吉野の滝」だ
吉野町宮滝付近...私は、つい最近まで「宮滝」を「滝」かと思っていたが
それは間違いで、「宮滝」という地名だった
勿論、山に入れば、「滝」もあるが
そもそも、当時の「滝」の概念を知らないと、この歌に限らず、
違った情景を浮かべることになってしまう
中国の宋の時代に作られた、『集韻』(1039年)という、ある種の「異体字字典」がある
その中に、「滝、奔湍(タン・はやせ)」とある
当時の「滝」の字は、「激流」の意味だったことがわかる
そして、今で言う「滝」は、万葉の当時「たるみ(垂水)」といい、
「奔流・急流」の「タキ」と区別があった
従って、「滝」とあれば「激流」と訳すのが自然なことだ
昨日の【注記】で採り上げた〔1717〕も、「滝」だが、
正直、ここ吉野での「滝」の表記には迷うことがある
地名「宮滝」を、単に「滝」といっているかもしれない、
昨日は、そう訳した
しかし、その同じ語句でありながら、この歌は
「いのち」だろうか...
古代の吉野川は、もっと推量も多く、かなりの急流だったかもしれない
吉野の「激流」の上に聳える三船山
「つねにあらむと」というのは、三船山に腰を据えてかかる雲のように
自分の命を、ずっと、とは思わない、という語句通りに思えば「諦観」の想い
そこには、地名である「宮滝」の「滝」よりも
当時の本来の意味の「激流」の方が似合っている
自分の激しい恋心、あるいは政治的な野心
それが吉野の激流に与するような「三船山に居る雲」のように
いつまでも、想い続けていられるものだろうか...死んでも構わない |
| 「居雲乃」 |
今で言う「滝」もそうだが、「激流」でも、
その上方の山に、雲がかかることを詠んだ歌は多い
三船山の雲については、『懐風藻』の吉田宜の「従駕吉野宮詩」がある
「雲ハ巻ク三舟ノ渓」 |
〔参考〕
この歌を、諦観の歌のように感じたのは、もう一つ理由がある
それは、作者・弓削皇子のことだ
彼は、この詠歌の半年後に歿する
実権者太政大臣高市皇子が歿したとき、
皇嗣選考会儀で、近江朝の大友皇子の子である葛野王が、軽皇子(後の文武帝)を推した時、弓削皇子が反対し、即座に葛野王に叱責され、以来文武天皇即位後は、失意の境遇にあったその中での、この詠歌なのだと思う
すでに、自分の将来を悲観しており、「いつまでも生きられようか」と... |
| 〔393〕 |
| 「軽池之」 |
「軽」は奈良県橿原市大軽・見瀬・石川・五条野各町一帯の地
明日香村に隣接する
『日本書紀』「応神紀十一年十月の条」に、
「剣池・軽池・鹿垣池・厩坂池を作る」とある
『古事記』「祟神記」には、
「軽の酒折の池を作りき」とあり、
さらに「垂仁記」には、軽の池に舟を浮かべた話しも載っている |
| 「浦み」 |
原文の「うら」は、「氵」に「内」[以下ウラ]
この漢字の意味は、中国の明時代末期(17世紀中頃)に編纂された漢字字典『正字通』に、
「水ノ曲流スルヲ「ウラ」ト為ス」とあり、
孔子の編纂とされる歴史書『春秋』の、
代表的な注釈書である『春秋左伝「閔公二年春の条」』
「虢公、犬戒ヲ渭ノ「ウラ」ニ敗ル」の杜預注に、
「河水ノ隈曲ヲ「ウラ」ト曰フ」とある
つまり、「川の流れが湾曲しているところ」をいうものと解せる |
『万葉集』では、「借音」も「借訓」も入り乱れての表記なので
平安時代に「訓」をつける作業というのは、気の遠くなるような仕事だったことだろう
今でこそ、中国の文献もデータとして閲覧できるが、万葉の時代で
自分が使おうとする「文字」の正確な「知識」も、知り得る「人たち」...
確かに、庶民の歌も多いだろうが、それを聞いて書き留めたのは、
こうした「知識人」たちの作業だったのだろう
|
|
掲載日:2013.12.09.
| 春雑歌 詠鳥 |
| 不答尓 勿喚動曽 喚子鳥 佐保乃山邊乎 上下二 |
| 答へぬにな呼び響めそ呼子鳥佐保の山辺を上り下りに |
| こたへぬに なよびとよめそ よぶこどり さほのやまへを のぼりくだりに |
| 巻第十 1832 春雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【注記】〔243・393〕 【左頁補注】〔243・393〕
| 【1832】語義 |
意味・活用・接続 |
| こたへぬに[不答尓] |
| こたへ[答ふ・応ふ] |
[自ハ下二・未然形]人の問いに返事をする・反応する |
| ぬ[助動詞・ず] |
[打消・連体形]~ない |
未然形につく |
| に[接続助詞] |
[逆接]~のに・~けれども |
連体形につく |
| なよびとよめそ[勿喚動曽] |
| な~そ[副詞~終助詞] |
[禁止]~するな・~してくれるな [~]は動詞の連用形 |
| よび[呼ぶ] |
[他バ四・連用形]大声で何かを言う・呼び掛ける・招く |
| とよめ[響む・動む] |
[他マ下二・連用形]鳴き声を響かせる・鳴り響かせる |
| よぶこどり[喚子鳥]〔既出、2013年12月4日〕 |
| さほのやまへを[佐保乃山邊乎]〔既出、2013年12月8日参照〕 |
| のぼりくだりに[上下二] |
| のぼり[上り・登り] |
高い所へのぼること |
| くだり[下り] |
高い所から低い所へ移ること |
| に[間投助詞] |
[感動・詠嘆]~のであるよ・~になあ・~まあ~ことだ |
| 〔接続〕体言及び体言に準ずる語、副助詞「さへ」などにつく |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [な~そ] |
上代語の副詞「な」単独でも、動詞の連用形(カ変・サ変は未然形)の上について、
その動詞の表す動作を禁止する
「な~そ」は、単独の「な」による表現と比べて穏やかで、願望をこめた禁止表現
上代には、「な」単独が多く見られたが、中古末期以降には
「な」が省略され「~そ」のみの形で用いられることもあった
なお、「な~そ」についてはこの形で、一つの終助詞とする説もある
|
| |
| [のぼりくだりに] |
この句の「のぼりくだり」の「意味」は解る
ようは、のぼったり、くだったり...と言うことなのだが
結語の助詞「に」の扱い方で、また解釈が違ってくる
いや、解釈というよりも、「訳する言葉」が違ってくる
助詞「に」には、「格助詞・接続助詞」と、上代語の「終助詞・間投助詞」がある
歌の概訳が、佐保の山辺を「上へ下へ」、しかし「誰も応えないのに」との意味合いから
この結語の助詞「に」もまた逆接の接続助詞で、「~のに」だと思ったのだが
そうすると、接続が「連体形」となり、「のぼり」も「くだり」も
それぞれが動詞であれば、四段の「連用形」となり、接続はできない
そもそも「のぼり」や「くだり」を連用形とすることで、助詞「に」への接続はできない
ならば、「のぼり」、「くだり」は「名詞」、つまり「体言」と言える
それだと、格助詞「に」には接続する
ところが、格助詞として解そうとすると...どうも歌意に相応しくない
私には、「逆接」的な意味合いが相応しいと思えるからだ
そこで、残った手段が、上代語の「間投助詞」で、感嘆を表現することだ
「あんなに、翔け上ったり、降りたりしているのになあ」と訳せないだろうか
この「間投助詞」は、体言に付く
多くの注釈書が「のぼりくだりして」と訳している
それは、言外に「逆接」の意味を含んでいるのだろう
こんな私の解説など、まったくの見当違いかもしれないが、また数年後には
この歌、どんな風に読むのか、楽しみだ
尚、私に、この「感嘆」の手掛かりになった歌二首を載せるが
他の「語義」でも、触れたいことがあるので、左頁に、また書くことにする
ここでは、感嘆の間投助詞「に」を中心にした
| 雑歌/弓削皇子遊吉野時御歌一首 |
| 瀧上之 三船乃山尓 居雲乃 常将有等 和我不念久尓 |
| 滝の上の三船の山に居る雲の常にあらむと我が思はなくに |
| たきのうへの みふねのやまに ゐるくもの つねにあらむと わがおもはなくに |
| 巻第三 243 雑歌 弓削皇子 |
〔語義〕
「ゐるくも」は、「居る」が尻を落ち着けて座るという意のことで
雲が、山に腰を据えている、と解する
「おもはなくに」の「な」は、打消の助動詞「ず」の未然形
それに「く」がつくことで、体言化する[ク語法]
ここでの「に」は、格助詞とし、「逆接」の意としているが
「なくに」を文の終止形式として用いる場合は、「詠嘆」を表す、とある
私見だが、それが上代語の感嘆の「間投助詞」だと思う |
〔歌意〕
吉野川の激流の上に聳え立つ三船山
そこにいつもかかっている雲のように、
いつまでも生きていようとは、私は思わないのだがなあ |
| |
| 譬喩歌 / 紀皇女御歌一首 |
| 軽池之 ウラ廻徃轉留 鴨尚尓 玉藻乃於丹 獨宿名久二 |
| 軽の池の浦廻行き廻る鴨すらに玉藻の上にひとり寝なくに |
| かるのいけの うらみゆきみる かもすらに たまものうへに ひとりねなくに |
| 巻第三 393 譬喩歌 紀皇女 |
〔語義〕
「すらに」の用法では、『万葉集講義』〔山田孝雄、昭和3~12年成〕によると、
「すら」よりも一層その修飾的な意を確かめたものだという
軽いものを挙げて、重いものを類推させる意の副助詞「すら」に、
副詞語尾「に」の加わったもの 「~でさえも」
「なくに」、これが歌の末尾に来たときには、上の〔243〕と同様になる
その働きには、三種類あり、
①、「~ないことだ」のように、詠嘆のみの用法
②、「~ないのに」のように、逆接の用法
③、「~ないのになあ」のように、逆接で詠嘆の用法
掲題歌〔1832〕も、これに当ると思う
ただし、このように明確な使い分けは難しいようで、
やはり、歌全体の歌意に沿うものを理解しなければならない、と思う
|
〔歌意〕
軽の池の「浦」を泳ぎ廻る鴨でさえも
玉藻の上で、一人寝はしないのになあ |
|
| |
|
 |
| 【歌意1833】 |
梓弓を張る...その「はる」に響く春山の近くに
住んでいるのだから、今頃絶えず聞いていることでしょうね、
うぐいすの鳴き声を... |
作者自らは、山里ではなく、都だろうか
そんなに日常の情景としての「うぐひすの鳴き声」はないのだろう
山里、春の山の近くに住んでいる「愛しい人」なのか、あるいは友人なのか
そんな「親しさ」を感じさせる歌だ
これぞ「春の歌」だと思う
最近、「呼子鳥」の歌では、随分「春らしからぬ」人の想いを描いたものだが
この歌では、何よりもその中心は、「うぐひすの鳴き声」だ
都人(とすれば)が、山辺に住む親しい人に、「いいなあお前は」「いいですね、そちらは」と
「春山の近くに住む」人が、かつてこの環境を、自慢していたのかもしれない
そのことを「都人」が思い出し、こう詠ったとすれば、まさに「のどかな春」だ
右頁での【注記】〔きくらむ〕の続きになる
「をらば」が仮定条件であれば、現在推量の助動詞「らむ」はおかしい、とした
ならば、そう訓じている諸注はどんな解釈をしているのだろう
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕の解釈は、
「(梓弓) 春山近く お住まいなら 絶えず聞こえているでしょうね うぐいすの声が」
確かに、作者は相手が春山の近くに住む人だと思い
それなら、うぐいすの鳴き声が、絶えず聞こえているでしょう、と言っている
「お住まいなら」というのは、本当に「仮定条件」なのだろうか
日本語の曖昧さ、難しさがここにある
「そこに住んでいるあなたなら」とも「住んでいたとしたら」とも取れる
しかし、この文章では普通に読めば「春山近く、そこに住んでいるのですから」だと思う
あきらかに現在推量の助動詞「らむ」に重点を置いている
ならば、この『新全集』の「訓」は、「をらば」ではなく、「をれば」にすべきではないか
もう一つ、『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕の解釈では、
「梓の弓を張る-春山に近く家にいたなら、しきりに聞いているだろう鶯の声よ」
これなら、私には矛盾は感じない
うぐいすの鳴き声を「聞く」のは、作者自身だ
もっとも、春山の近くの家が、作者自身の「家」でなければならないが
今、そこから離れ、その故郷の「家」を想い、
「私が、そこにいたのなら、今頃うぐいすの鳴き声を聞いているだろう」
この時の「らむ」は、それこそ一般的ではなくとも、「単なる推量」として有り得るのだから
むしろ、「らむ」がその原文「良牟」を動かせないので、
それでも「をらば」と訓むなら、この「解釈」しかないだろう
私は、『新全集』よりも、理解できる
ただ、私が解するなら、「望郷」の歌とするより
春の山里への憧れを想い描く歌の方が、似合っていると思う
ここまで、あまり部立て「春雑歌」の「春」に拘る気もなかったが
この歌では、やっと素直に「春らしさ」を感じさせてくれたような気がする
「望郷の歌」とするには、「春」は似合わない
と、また偏屈な感じ方をしていることだろうが...
|

|
掲載日:2013.12.10.
| 春雑歌 詠鳥 |
| 梓弓 春山近 家居之 續而聞良牟 鴬之音 |
| 梓弓春山近く家居れば継ぎて聞くらむ鴬の声 |
| あづさゆみ はるやまちかく いへをれば つぎてきくらむ うぐひすのこゑ |
| 巻第十 1833 春雑歌 詠鳥 作者不詳 |
| 【1833】語義 |
意味・活用・接続 |
| あづさゆみ[梓弓] |
| はるやまちかく[春山近]春山に近くに |
| いへをれば[家居之] |
| をれ[居り] |
[自ラ変・已然形]いる・存在する |
| ば[接続助詞] |
[順接の確定条件]~ので・~だから |
已然形に付く |
| つぎてきくらむ[續而聞良牟] |
| つぎ[継ぐ・続ぐ] |
[他ガ四・連用形]継続する・継ぎたす・保つ |
| て[接続助詞] |
[原因・理由]~ので・~のために |
連用形に付く |
| らむ[助動詞・らむ] |
[現在推量・終止形]今頃~しているだろう |
終止形に付く |
| うぐひすのこゑ[鴬之音]うぐひすの鳴き声 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [梓弓] |
梓の木でできた弓
梓の木は、「きささげ説」「あかめがしは説」「をのをれ説」「よぐそみねばり説」など
諸説があるが、現在は「よぐそみねばり説」が定説とされている
(松田修『増訂万葉植物新考』)
そもそも、「よぐそみねばり」とは、どんな木なのだろう
ネットで調べてみた
[グリーンカレッジ岩泉]「安家の樹木図鑑」によると
| 和名:ミズメ(ヨグソミネバリ、アズサ)、カバノキ科、カバノキ属 |
| 広葉樹/落葉樹。 樹皮を傷つけると、水のような樹液が出ることからこの名が付いた。 高さは20~25mほどになる高木。 本州、四国、九州に分布する。
5月頃、若葉と共に雄花は7~9cmで尾状に垂れ下がり、雌花は円柱形で上向きに咲く。 樹皮は暗灰色で、横長の皮目が並び、サクラの樹皮に似ているが、剥がれやすい。
葉は新しい枝に互生し、翌年からは短い枝に2枚ずつ付く。葉の身は卵形で、葉縁は重鋸歯(ギザギザが重なり合った形)。 果穂は、雄花の形がそのまま太くなる。堅果は3mm程度で、10月ごろに熟し、風で散布される。
木材は重くて堅いが、割れにくく狂いが少ない。木目が美しく、フローリング等の建築材や家具やテーブル・カウンター、漆器木地としても使用される。細工がしやすいため、こけしの材料としても使用される。
古くは梓弓(あずさゆみ)という神事に用いる弓の材料として使用され、万葉集の中にも登場したり、正倉院にも残っている。枝を折るとサロメチールのような独特のにおいがする。 |
ネットで「よぐそみねばり」と検索すると、「夜糞峰榛」と漢字が当てられているが、
その独特の匂いのせいかもしれない
とは言っても、その命名の由縁を知りたいものだ
和名「ミズメ」だが、別名として、他に「アズサ」ともあり
万葉の時代には、「あずさ」と言っていたのだろうか
|
| |
| [家居之] |
この語句の「訓」には、ここで採り上げた「いへをれば」と「いへをらば」がある
訓み方としては、両者とも可能だが、その意味は大きく違う
「いへをれば」の「をれ」は、自動詞ラ変「居り」の已然形「居れ」
これが、接続助詞「ば」につくと、「順接の確定条件」になる
原因・理由の「~ので・~だから」
単純接続の「~すると・~したところ」
恒常条件の「~するときはいつも・~すると必ず」
というふうに...
「いへわらば」の「をら」は、同動詞の未然形「居ら」で、
それに、接続助詞「は」がついて、「順接の仮定条件」となる
その意味は、「~(する)なら・~だったら」と
この歌で、それぞれの訓で訳してみると
「家にいるのだから」、「家にいたなら」
確定条件の方は、「家にいることが確実」であり
仮定条件の方は、「もし家にいるのだったら」と、その確実性はない
これを、どう訳せば、他の語句と矛盾しないか...
それは、次の句の「助動詞・らむ」で補えると思う
ただし、この両者の「訓」も、諸注では様々であり、
比較の意味で、一例に過ぎないが、ここに載せておく
| 「をれば」 |
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕
『万葉集』〔伊藤博校注、角川ソフィア文庫、平成十年18版〕
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕など |
| 「をらば」 |
『萬葉集本文篇』〔塙書房・佐竹昭広、昭和38年成〕
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕など |
|
| |
| [きくらむ] |
終止形「聞く」に続く、現在推量の助動詞「らむ」
この助動詞「らむ」は、他の推量の助動詞「む」と違い、
目の前にない現在の事実について推量する意を表す
「む」であれば、単純に「~だろう」と推量するが、
「らむ」は「事実」についての推量となる
(もっとも「らむ」にも「む」と同様に単なる推量もあるが、一般的ではない)
となると、「きくらむ」の訳は、「今頃聞いているだろう」がその直訳だ
「む」であれば、「聞いているのだろう」と自分の思いが優先している
そこで、前の句「いへをれば(をらば)」に関わってくる
あくまで、私の充分とはいえない知識ではあるが、
「らむ」が事実の推量であれば、当然「家にいる」のは、事実となる
そうであれば、「家に居るので、今頃聞いているだろう」が普通に訳せる
当然、その場合の「家に居る」のは、作者ではないことになる
仮に「をらば」、「家にいるのなら」だとすれば、事実かどうかも解らず
ただ推量で言うので、「家に居るのなら、聞いているだろう」の意だが
その訓となると、「らむ」ではなく「いえをらば つぎてきかむ」、
七文字にこだわるなら、「つぎてしきかむ」ではないだろうか (「し」は強調の副助詞)
しかし、「をらば」と訓みながら、「らし」をどう解釈するのだろう
これについては、左頁に書き留めたい |
| |
|
|
| 【歌意1834】 |
草木がその枝葉を春風になびかせる春になったので、
篠竹のこずえに、尾羽を触れさせるかのように賑やかに
うぐいすが鳴いているなあ |
うぐいすが、篠の葉先にその尾羽を触れさせるように鳴いている
作者が見ているのは、うぐいすのその姿なのだろうか
あるいは、揺れ動く篠のこずえ、その辺りから盛んに聞こえるうぐいすの声
それを、ああ、あそこでうぐいすが鳴いているのだなあ、と心を動かされたものか...
具体的に、尾羽が篠のこずえに、触れながら鳴く
とする注釈書が殆どだろうが、私はそうは思わない
それは、和歌鑑賞の技術的な解釈の捉え方ではなく
作者が、どんな気持ちで詠じたのか、それをも歌に触れるならば、感じたいからだ
実際は、うぐいすの、その姿を見ているかもしれないし、おそらく...そうだろう
しかし、それをそのまま素直に描写するのではなく
「見えなかった」うぐいすを、その鳴き声を頼りに、こずえを騒がせている
そう思うことで、「目」ではなく「心」で春の香りを感じ取っているのではないだろうか
心に染みる余情を味わう時、目を閉じて耳を傾けることがある
草木の枝や葉をやさしく揺れる春風
篠のこずえが揺れることで、確かに見えない「風」、春風を感じることが出来る
しかし、それでも目を閉じて...揺れるこずえさえも、「耳」で感じる
そこに、うぐいすの鳴き声が...そうか、あの鳥たちが...
それが、春の実感を際立たせてくれる
私は、この歌をそんな風に感じたい
風に向かい、篠の「しずか」なざわめきに向い、うぐいすの「鳴き声」に...向う
|
 |
掲載日:2013.12.11.
| 春雑歌 詠鳥 |
| 打靡 春去来者 小竹之末丹 尾羽打觸而 鴬鳴毛 |
| うち靡く春さり来れば小竹の末に尾羽打ち触れて鴬鳴くも |
| うちなびく はるさりくれば しののうれに をはうちふれて うぐひすなくも |
| 巻第十 1834 春雑歌 詠鳥 作者不詳 |
| 【1834】語義 |
意味・活用・接続 |
| うちなびく[打靡]〔枕詞〕「はる」にかかる [詳細は既出、12月1日掲載歌] |
| はるさりくれば[春去来者] |
| さり[去る] |
[自ラ四・連用形](季節などの語について)近づく・来る |
| くれ[来(く)] |
[自カ変・已然形]来る |
| ば[接続助詞] |
[順接の確定条件]~ので・~だから |
已然形に付く |
| しののうれに[小竹之末丹] |
| しの[篠] |
篠は、篠竹・女竹と呼ばれる細い竹 |
| うれ[末] |
(「うら」の転) 木の枝や草の葉の先端、こずえ |
| をはうちふれて[尾羽打觸而] |
| をは[尾羽] |
鳥の尾と羽、あるいは尾の羽 |
| うち[打ち] |
[接頭語]動詞について、その意味を強めたりする |
| ふれ[触る] |
[自ラ下二・連用形]触れる |
| て[接続助詞] |
[補足・行われ方]~て・~ようにして |
連用形に付く |
| うぐひすなくも[鴬鳴毛] |
| も[終助詞] |
[感動・詠嘆]~よ・~なあ〔接続〕文末、文節末の種々の語につく |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [しののうれに] |
現在の諸本、諸注の殆どが、「小竹之末丹」とし「しののうれに」と訓じているが
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕の雅澄は、
原文は「小竹之米丹」であり、『元暦校本』が「米」を「末」としたため
それによって、「しののうれに」とするテキストが多い、という
雅澄の『古義』では「小竹之米丹」で、「しののめに」とする
それに、五字句となり、語調も確かにいいには違いない
雅澄が「しのの~」で採り上げた歌を載せる
| 寄物陳思 |
| 秋柏 潤和川邊 細竹目 人不顏面 公无勝 |
| 秋柏潤和川辺の小竹の芽の人には忍び君に堪へなくに |
| あきかしは うるわかはへの しののめの ひとにはしのび きみにあへなくに |
| (以前一百四十九首柿本朝臣人麻呂之歌集出) |
| 巻第十一 2482 寄物陳思 柿本人麻呂歌集 |
〔語義〕
「あきかしは」、「うるわかは」にかかる枕詞
「秋柏」が霧などに潤うことからの意
「しのび」は、堪える、耐える、隠れるなどの動詞「忍ぶ」の連用形
その連用形「しのび」で文が終るのは、「対偶中止法」だと思う
「あへなく」は、耐える、持ちこたえるの動詞「敢ふ」の未然形「あへ」に、
打消しの助動詞「ず」のク語法「なく」
|
〔歌意〕
秋の柏が潤う潤和川のほとりの「篠で編んだ目」のように
人目には、この想いを隠せても、
あなたに逢えば、堪えられそうもありません |
私の調べ方が足りないのかもしれないが、「しののうれ」も「しののめ」も
それぞれ一首しか『万葉集』では確認できなかった
しかし、雅澄の説を採ると、「しののうれ」はなくなり、
「しののめ」が二首になる
尚、この訓み方として例を挙げた〔2482〕の「め」も、掲題の〔1834〕歌の「め」も、
雅澄は、「群れ」の意である「群(め)」を当てている
殆どの語義解釈では、「しののめ」は、「小竹の芽、あるいはそれで編んだ目」とするが
彼は、「小竹・篠竹の芽や目」が、群生とか群れているように捉えたのかもしれない
|
| |
| [ふれ] |
鹿持雅澄は、この歌によほど思い入れがあるのだろうか、まさに孤軍奮闘の観がある
この句でも、ほとんどの諸本・諸注が「をはうちふれて」とするのを
雅澄は「をはうちふりて」としている
「触れて」と「触りて」の違いは、「下二段活用連用形・ふれ」とするか、
あるいは「四段活用連用形・ふり」を採るか、になると思う
どちらも意味は「さわる・触れる」のことだが、
古語辞典では「下二段」の方が、もっと幅広い解釈を載せている〔古語辞典「触る」〕
今の私には、どちらがいいのか判断のしようがない...今度は「動詞」の本を読もう
|
| |
|
|
| 【歌意1835】 |
朝の霧に、しっとりと濡れて、呼子鳥よ
三船の山の辺りから、鳴きながらおまえは飛んでゆく... |
この歌も、右頁の注記に載せた用例歌のように
「見える」すがたを描写することも可能だが
敢えて、「見える」を使わずに「訳」をしてみた
舟を漕ぎ出す、とか漕いでいる、というのは
それをいうことで「見える」ことを言っていると同じなのだが
この掲題歌...「鳴く」は決して「見える」行為とは限らない
見えなくても、鳴き声で、その存在を知ることができるのだから
本当に見えているのかどうか...
ただ、この歌の場合、鳴き声によって「見えた」としても、
朝霧に「しっとり」と濡れている様を言うのだから、二重の「見える」要素があるわけだ
もっとも、朝霧の中で鳴くのは、
濡れながら飛んでいる、という作者の想像かもしれないが...
それでも、「霧」の中を「翔」ぶことは、確かに見えなくても、「しっとり」濡れて、とは思う
「しっとり」...
「霧」に濡れる語として、「しっとり」観は妥当だろうとは思う
雨の「靄」と違い、そんなに濡れはしないだろう
だから、「しっとり」と「ことば」にするのも頷ける...
しかし、「しののに」には悩まされる
古語辞典には、「しっとり」も「ぐっしょり」もある
それに『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕では、「ぐっしょり」として
その歌意は「朝霧に ぐっしょり濡れて 呼子鳥が 三船の山を 鳴き渡っている」
この「ぐっしょり」と解せば、間違いなく作者は「呼子鳥」を「見える」と言える
鳴き声だけで、霧の中を飛んでいる呼子鳥を「感じる」のではなく
鳴き声のみならず、「ぐっしょり」と濡れそぼっている「呼子鳥」を見ている
「見えなく」ても「見ゆ」ではなく、「見えているからこそ」の「見ゆ」だ
動詞の終止形を受けて、「現在~しつつある」とする「見ゆ」の用法
それは、描写的に表現する作者の心の働きだ、という
「見ゆ」が「見える」意味を持つ以上、私などどうしても「視覚上」に限定してしまうが
万葉人は、そうではなかった
ある動作を理解、感知することで、自分の「心」をも描写している、ということか
呼子鳥が「ぐっしょり」でも「しっとり」でもいい
霧の中を濡れ、鳴き飛んでいる、という実際の光景の「描写」を
作者は、心の動きに投影させて「見ゆ」と表現した
その「心の描写」を、私は感じたいのだが...
「しっとり」濡れては、風情のある春の景色
「ぐっしょり」濡れて、は...「春の風情」とはいかない
ならば、どちらが作者の「心の描写」なのだろう
手掛かりを懸命に探した
すると、この同じ巻第十の「夏雑歌」の問答に、「しののにぬれて」があった
『万葉集』中、この語句は、掲題歌と二首しかなかった
| 夏雑歌問答歌 |
| 宇能花乃 咲落岳従 霍公鳥 鳴而沙度 公者聞津八 |
| 卯の花の咲き散る岡ゆ霍公鳥鳴きてさ渡る君は聞きつや |
| うのはなの さきちるをかゆ ほととぎす なきてさわたる きみはききつや |
| 巻十 1980 夏雑歌 問答歌 作者不詳 |
〔語義〕
「なきてさわたる」の「さ」は接頭語で、語調を整える |
〔歌意〕
卯の花が散った岡の上を、
ほととぎすが、鳴きながら飛んでゆく...
あなたは、それを聞いたのでしょうか |
| |
| 聞津八跡 君之問世流 霍公鳥 小竹野尓所沾而 従此鳴綿類 |
| 聞きつやと君が問はせる霍公鳥しののに濡れてこゆ鳴き渡る |
| ききつやと きみがとはせる ほととぎす しののにぬれて こゆなきわたる |
| 巻十 1981 夏雑歌 問答歌 作者不詳 |
〔語義〕
「こゆ」は、ここを通って、の意
「ゆ」が「をかゆ」の「ゆ」と同じで「通って」の意になる |
〔歌意〕
聞いたか、とあなたはお尋ねになりました
そのほととぎすが、しっとりと濡れて
今ここを鳴いて飛んで行きましたよ |
「問答歌」だから、取り敢えず、こんな風な意味合いの歌として解せばいいが
ここで「しののにぬれて」を解するには、
問歌の応答に相応しい「ことば」としてではないといけない
ただ、どちらの歌も「きみ」と呼んでいることから
お互いが男で、親友との問答歌だろう、とされているが
男女ともに、高貴な立場の人であれば、こうした呼び掛けも有り得るはずだ
中古以降は、男女相互間にも「きみ」は使われた、とある
ある日突然そうなったわけでもないだろう
その風潮は...すでにあった時代だと思いたい
卯の花が散ると、ほととぎすは、ここから去っていかなければならない
問歌の作者は、そんなほととぎすの鳴き声を「哀しみ」の声と感じている
女として、自分の元から去ってゆく男への、切ない想いなのかもしれない
そして男は応える
「聞きましたか」と、あなたが尋ねたそのほととぎす
何か憂いでもあるように、しっとりと濡れそぼって...鳴きながら飛んで行きました
女の直接的な訴えでもないのに、そこに男が見たものは
「しののにぬれて」飛び去っていったほととぎす
何故、「問い歌」で、雨とか霧などの濡れる要素がないのに
ここで「しののにぬれて」の語句が出るのだろう
「潤ふ」鳴き声を、女の化身である「ほととぎす」に見たのだろうか
濡れているのは、女の「涙」なのかもしれない
男が応える「しののにぬれて」と...それでも、飛んで行ってしまった
この問答歌から感じられる「しののに」は、決してぐっしょり濡れているものではない
「心」は、確かに濡れていても、それを率直に言ったり返したりしない仲の男女
それならば、やはり「しののにぬれて」は、しっとりと濡れていなければならない、と思う
|
|
掲載日:2013.12.12.
| 春雑歌 詠鳥 |
| 朝霧尓 之努々尓所沾而 喚子鳥 三船山従 喧渡所見 |
| 朝霧にしののに濡れて呼子鳥三船の山ゆ鳴き渡る見ゆ |
| あさぎりに しののにぬれて よぶこどり みふねのやまゆ なきわたるみゆ |
| 巻第十 1835 春雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【注記】〔932・1008・1037〕【左頁】〔1980・1981〕
〔青は「注記」へ、赤は「古語辞典」へリンク〕
| 【1835】語義 |
意味・活用・接続 |
| あさぎりに[朝霧尓] 朝、立ちこめる霧に |
| しののにぬれて[之努々尓所沾而] |
| しののに[副詞] |
(全身が濡れそぼつさまに用いて)しっとりと・びっしょりと |
| よぶこどり[喚子鳥] 既出〔2013年12月4日に詳細〕 |
| みふねのやまゆ[三船山従] |
| ゆ[格助詞] |
[経由点]~から・~を通って |
| 〔接続〕体言、体言に準ずる語、活用語の連体形などにつく |
| なきわたるみゆ[喧渡所見] |
| わたる[渡る] |
[自ラ四・終止形](動詞の連用形の下について)ずっと~続ける |
| みゆ[見ゆ] |
[自ヤ下二・終止形]見える・目に映る |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [あさぎりに] |
季語としては、春が「霞」、秋が「霧」とされているが、
上代では、その区別もなかった、とされている
|
| |
| [みふねのやま] |
三船山は、吉野川の南岸に位置し、象谷の東方の山
標高487メートル、今は御船山とも船岡山ともいう
宮滝から南東方角に見える山で、
『万葉集』では、「滝の上の三船の山」とも詠われている
|
| |
| [みゆ] |
「見ゆ」は、動詞・助動詞の終止形を受ける
この用法は、古今集以後には見られないようだ
この用法については、次の説がある
「古代の『見ゆ』は、上の文を完全に終結させた後で、それを受けているのであって」、
それは「存在を視覚によって把捉した古代的思考」、「存在を見えるすがたにおいて描写的に把捉しようとする古代の心性」があった
(佐竹昭広「見ゆの世界」『万葉集抜書』)
| 雑歌/(山部宿祢赤人作歌二首[并短歌])反歌一首 |
| 足引之 山毛野毛 御猟人 得物矢手挟 散動而有所見 |
| あしひきの山にも野にも御狩人さつ矢手挾み騒きてあり見ゆ |
| あしひきの やまにものにも みかりひと さつやたばさみ さわきてありみゆ |
| 右不審先後 但以便故載於此次 |
| 巻第六 932 雑歌 山部宿禰赤人 |
〔語義〕
「みかりひと」は、供奉の狩人なので「み」をつけている
「さつや」は、「さつ」を「さち」としているため
その例として、「月(つき)⇒月夜(つくよ)」「栗(くり)⇒栗栖(くるす)」など
そして「さち」は、『古事記』に「海佐知」、『日本書紀』に「海幸」のように、
獲物を得る呪能的なものをいう
「弓・矢・釣り針」など
この歌では、「矢」の讃称としていうようだ |
〔歌意〕
山にも野にも、この一面いたるところで、
狩りに供奉する人たちが、矢を手に手に挟んで
盛んに乱れ騒いでいるのが見える |
この〔932〕歌では、狩人たちの饗宴のさまを「見える」姿として「見ゆ」とするが
解釈の「訳」は、「ことば」としての描写の仕方であって、
次の用例歌のような「ことば」にも使い得るものだ
実際は、〔932〕にしても、「見える」としないで「騒いでいる」とするのもいい
何故なら、「見える」行為が「見ゆ」の語で明白だから、と思う
同じように次にも二首挙げておく
| 雑歌/筑後守外従五位下葛井連大成遥見海人釣船作歌一首 |
| 海□嬬 玉求良之 奥浪 恐海尓 船出為利所見 □=「女」偏に「感」 |
| 海女娘子玉求むらし沖つ波畏き海に舟出せり見ゆ |
| あまをとめ たまもとむらし おきつなみ かしこきうみに ふなでせりみゆ |
| 巻第六 1008 雑歌 葛井連大成 |
〔語義〕
「もとむ」は、他動詞マ行下二段「求む」の終止形
「手に入れようと探す・欲しいと願う」など
「らし」は、ある根拠・理由に基づき、確信をもって推定する意の、
助動詞「らし」の終止形、接続は、動詞の「終止形」につく
ただしラ変動詞には「連体形」につく
「~にちがいない・きっと~だろう」
「かしこき」は、形容詞ク活用「かしこし」の連体形
「畏し・恐し」と「賢し」の二つの用法があるが、この歌のように、
その原義は「畏れ」であり、中古以降に、「並外れた学識・才能など」の意もなる
「恐ろしい・畏れ多い・尊い」
「せり」は、サ変動詞「す」の未然形「せ」に、
完了の助動詞「り」の終止形「り」が付いたもの
「ふなでせり」で「終止形」となり、「見ゆ」が受ける |
〔歌意〕
海人の娘が、きっと玉を手に入れようとしているのだろう
沖の波が荒立つ恐ろしい海に、舟を漕ぎ出している |
| |
| 雑歌/〔(十二年庚辰冬十月依大宰少貳藤原朝臣廣嗣謀反發軍 幸于伊勢國之時)狭殘行宮大伴宿祢家持作歌二首〕 |
| 御食國 志麻乃海部有之 真熊野之 小船尓乗而 奥部榜所見 |
| 御食つ国志摩の海人ならしま熊野の小舟に乗りて沖へ漕ぐ見ゆ |
| みけつくに しまのあまならし まくまのの をぶねにのりて おきへこぐみゆ |
| 巻第六 1037 雑歌 大伴宿禰家持 |
〔語義〕
「みけつくに」、「みけ」は神や天皇の召し上がり物、
「つ」は、「の」の意の上代の格助詞
従って、「みけつくに」は、天皇の召し上がり物を献上する国
「ならし」は、断定の助動詞「なり」の連体形「なる」と、推定の助動詞「らし」で「なるらし」からの転
「~であるらしい・~であるにちがいない」
「まくまの」の「ま」は美称
名詞・形容詞などについて、真実・正確・純粋・称讃・強調などを表す
ここでは、熊野が対象 |
〔歌意〕
御食つ国の志摩の海人に違いない
熊野の小舟に乗って、沖へ漕ぎ出ているのは |
ここで、また前述の(佐竹昭広「見ゆの世界」『万葉集抜書』)から引用したい
「形状性用言”見ゆ”の意味は、見えて来る作用ではなく、見えるという状態である」
古代では「”見ゆ”を用いる必要のないような場合にも、好んで”見ゆ”を使う。これは語の選択に関する問題である。語の選択の問題は、...文体の問題に属する。”古今集”以後、急激におとずれた”見ゆ”の衰退は、換言すれば”見ゆ”を用いる文体が抱懐したことである。存在を視覚によって把握する古代的思考の後退こそ、その決定的要因であった」
幾つかの注釈書でも、「見える」と歌意に使用したり、
「見ゆ」を、その「見える」状態として、「~いる」というような訳仕方をしていたり
様々だが、概ねその「書」の中では、一貫しているようだ
それはそれぞれの「ルール」かもしれないし、偶然かもしれないが...
「歌意」に用いる「ことば」は、「揺れ動く」ものでもいいと思うのだが...
私も、時を経て同じ歌を読めば、たとえ同じ歌意として解釈しても
その「訳仕方」には、縛られるつもりもないし...
|
| |
|
|
| 【歌意1836】 |
草木がうちなびく、春がやってきたが
それなのに、天雲が霧のように一面立ち込めて
雪が降っているではないか |
この歌も、右頁の注記に載せた〔1445〕と逆の設定で、類想歌だと思う
〔1445〕歌は、
「雪が降っているのに、何ともう鶯が鳴いている...春なんだなあ」
と、早春を思わせるような歌だ
そして、掲題のこの歌は、
「春がやってきた、というのに、雪が降っている...春なのになあ」
と、早春には違いないだろうが、まだ雪が降るのか」と嘆いている
感覚的には、ほぼ同じ季節の頃の、その「境」で二首は交わるような気がする
どちらも、「霧が一面に掛かるように」雪が降る
その現象は同じだろう
しかし、掲題歌は、「春になっていると思っていたのに」との「降る雪」への意外性
〔1445〕は、「降る雪」もまた、早春の「景物」として受け入れている
掲題歌で、明確にその気持ちが解る語は、やはり「しかすがに」だと思う
事実を述べた後に、「そうはいっても」と言葉を残すのは
自分では、「まだ春じゃないのかな」という若干の懸念もあるのだろう
このように読めるのは、大方の注釈書でも同じようだが
「しかしがに」を添えた歌は、やはりこう感じるのが自然だと思う
「順接の確定条件」、「已然形+ば」を、
「順接の確定条件」にしながら、「しかすがに」で否定し、結果として「逆接」にするのは
私の乏しい知識では、「逆接の確定条件」それは「已然形+ども」とするよりも
歌の語句に「しかすがに」という語を添えるための「語調」を重視したからではないか
ふと、そんな風に思ってしまった
ただ、【注記】でも触れたように、
この掲題歌の「雪は降りつつ」も、また「春の景物」とする解釈する注釈書を一つ載せる
| 『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕 |
| [歌意] |
霞こめて春がやって来たので、さすがに天雲がやわらかく曇っている
雪が降り続けていても... |
【『紀州本』にのみ載る「詠雪」】
諸本の中で、「紀州本」だけに、この歌から十一首を「詠雪」としている
他の諸本には見当たらず、これまでの「詠鳥」のままだ
しかし、歌の内容を見れば、確かにこの歌から十一首は「雪」が主であり
これまでの「詠鳥」の題詞は、及ばない内容だとするのが通説になっている
ただし『紀州本』の目録にも、「詠鳥二十四首 十三或 詠残雪十一首或本」とある
このことは、原本では「詠鳥」で二十四首あったもの、と記されているが
或本では、その内の十一首が「詠雪」とあるため、
「紀州本」はそれに倣った、ということになる
本来、この記事は昨日[2013年12月13日]にアップするつもりだったが
なかなか時間通りにすすめられず、一日後れてのアップになった
ただし、「掲載日」の日付は、検索し易いように、予定通りの日付にしておく
今日は、先日以来、「佐保」の歌も幾つか採り上げていて
その中で、偶然知った奈良市佐保の「佐保山茶論」での「歴史講座」の日だったので
初めてだけど、参加させてもらった
講演者が、このHPでも随分役立たせていただいている『万葉集全注』巻第十二の執筆者
高岡市万葉歴史館名誉館長の小野寛博士で、やはり佐保出身ということの縁であった
大伴家持への思い入れもとてもよく
「郎女・女郎・娘子」などの表記の意味から、家持が関わる女性たちへの背景など
もっともっと、聞きたかったのだが
何度か、この講座には招かれているようなので、今度も是非参加したいものだ
「佐保山茶論」の入り口に、家持の歌碑があった
そして、その揮毫が、この小野寛博士
|



|
掲載日:2013.12.13.
| 春雑歌 詠鳥(詠雪) |
| 打靡 春去来者 然為蟹 天雲霧相 雪者零管 |
| うち靡く春さり来ればしかすがに天雲霧らひ雪は降りつつ |
| うちなびく はるさりくれば しかすがに あまくもきらひ ゆきはふりつつ |
| 巻第十 1836 春雑歌 詠鳥(詠雪) 作者不詳 |
【注記】〔1445・1646・1647・2344・2346・2349〕
〔青は「注記」へ、赤は「古語辞典」へリンク〕
| 【1836】語義 |
意味・活用・接続 |
| うちなびく はるさりくれば[打靡 春去来者] 既出〔2013年12月11日〕 |
| しかすがに[然為蟹] |
| しかすがに[然すがに] |
(上代語)そうはいうものの・しかしながら |
| あまくもきらひ[天雲霧相] |
| あまくも[天雲] |
(「あまぐも」、上代では「あまくも」ともいう) 空にある雲 |
| きらひ[霧らふ](上代語) |
霧や霞が立ちこめる・霧や霞で曇る |
| ゆきはふりつつ[雪者零管] |
| ゆ[格助詞] |
[経由点]~から・~を通って |
| 〔接続〕体言、体言に準ずる語、活用語の連体形などにつく |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [しかすがに] |
副詞「然(しか)」にサ変動「為(す)」の終止形「す」、接続助詞「がに」のついたもの
中古以降は「さすがに」が用いられた
接続助詞「がに」が、逆接の意味を持つので、当然そうなるのだが
この歌では、その前句に「春去り来れば」...これは「順接の確定条件」
古語辞典の語義だけを拾い出せば、
「春になったので、そうは言うものの」となり、結句の「雪が降る」に繋がる
そこに、現代的には矛盾は感じないのだが、
しかし、これに対しては、単純にそうは言えないようだ
現代的な感覚で、この歌に触れると
「春なのに、雪が降るとは...」
勿論、こうした注釈書も多い
「しかすがに」の語句が、しっかり利いている
そして、もう一方の説とは、「早春に雪が降る」こと自体もまた
珍しくはあっても、「春なんだなあ、雪は降っているけど」とする
勿論、そう思わせる根拠がある
「しかすがに」がかかる次の句「あまくもきらひ」
これについては、「注記」のその「項」で触れる
|
| |
| [あまくもきらひ] |
まず、「霧らひ」の理解からしなければならない
自動詞ラ行四段「霧(き)る」の未然形「きら」に、
上代の反復・継続の助動詞「ふ」がついた上代語だ (「きらひ」は連用形)
『万葉集』中で、この語を用いた歌の歌意を見てみる
| 春雑歌/大伴宿祢家持鴬歌一首 |
| 打霧之 雪者零乍 然為我二 吾宅乃苑尓 鴬鳴裳 |
| うち霧らし雪は降りつつしかすがに我家の苑に鴬鳴くも |
| うちきらし ゆきはふりつつ しかすがに わぎへのそのに うぐひすなくも |
| 巻第八 1445 春雑歌 大伴宿禰家持 |
〔語義〕
「うちきらし」は、他動詞サ行四段「打ち霧らす」の連用形
「空一面霧がかかったようにして曇らせる」の意
「うち」は接頭語で、動詞について意味を強めたりする
「わぎへ」は、「我が家(わがいへ)」の転、自分の家・我が家
「も」は、感嘆の終助詞 |
〔歌意〕
空が霞むほどに雪が降り続いている
しかしながら、我家の庭では、なんとうぐいすが鳴いているではないか... |
| |
| 冬雑歌/安倍朝臣奥道雪歌一首 |
| 棚霧合 雪毛零奴可 梅花 不開之代尓 曽倍而谷将見 |
| たな霧らひ雪も降らぬか梅の花咲かぬが代にそへてだに見む |
| たなぎらひ ゆきもふらぬか うめのはな さかぬがしろに そへてだにみむ |
| 巻第八 1646 冬雑歌 安倍朝臣奥道 |
〔語義〕
「たな」は一面に、の意の接頭語
「ふらぬか」は、「ぬ」が打消しの助動詞「ず」の連体形で、「か」は疑問の係助詞「代(しろ)」は、代わり、代用
「そへて」の「そへ」は、他動詞ハ行下二段「添ふ・副ふ」の連用形で、
「なぞらえる・たとえる」の意がある
「だに」は強調の副助詞で、「せめて~だけでも・~だけなりと」の意 |
〔歌意〕
空一面に霧が立ち込めるような雪が降らないだろうか
梅の花が咲かない代わりに、
その雪を梅の花に擬えて見たいものだ |
| |
| 冬雑歌/若櫻部朝臣君足雪歌一首 |
| 天霧之 雪毛零奴可 灼然 此五柴尓 零巻乎将見 |
| 天霧らし雪も降らぬかいちしろくこのいつ柴に降らまくを見む |
| あまぎらし ゆきもふらぬか いちしろく このいつしばに ふらまくをみむ |
| 巻第八 1647 冬雑歌 若桜部朝臣君足 |
〔語義〕
「あまぎらし」は、他動詞サ行四段「天霧らす」の連用形・「空を一面に曇らせる」
「いちしろく」は、「顕著に・いちじるしく」
「いつ」は、「いつかし(橿)」「いつも(藻)」などのように、
植物に冠して、その繁茂するさまをほめる接頭語、「柴」にかかる
「柴」は小さな「木」をいう
「まく」は、上代語で未来の推量を表す「~だろうこと・~であろうようなこと」
活用語の未然形につく |
〔歌意〕
空を曇らせて、この柴の野原一面雪が降り積もらないものか
その光景を、私は見たい |
| |
| 冬相聞 寄雪 |
| 一眼見之 人尓戀良久 天霧之 零来雪之 可消所念 |
| 一目見し人に恋ふらく天霧らし降りくる雪の消ぬべく思ほゆ |
| ひとめみし ひとにこふらく あまぎらし ふりくるゆきの けぬべくおもほゆ |
| 巻第十 2344 冬相聞 作者不詳 |
〔語義〕
「ひとめみし」は、一目逢っただけの人
「こふらく」は、動詞「恋ふ」に、名詞化する上代の接尾語「らく」
「恋すること」の意
|
〔歌意〕
ただ一目見ただけの人に、恋してしまっって
それは、この大空一面に空を曇らせ降っては消える雪のように
わたしの命も、今にも消え入りそうに思われる |
| |
| 冬相聞 寄雪 |
| 如夢 君乎相見而 天霧之 落来雪之 可消所念 |
| 夢のごと君を相見て天霧らし降りくる雪の消ぬべく思ほゆ |
| いめのごと きみをあひみて あまぎらし ふりくるゆきの けぬべくおもほゆ |
| 巻第十 2346 冬相聞 作者不詳 |
〔語義〕
「いめのごと」は、夢の中でのように
「あいみて」は、出逢って
第三・四・五句は、〔2344〕と同じ |
〔歌意〕
夢の中での出逢いのように
ほんの僅かな時間だけ、あなたとお逢いしたので、
空一面かき曇って降って来る雪のように
命も消えてしまいそうに思われます |
| |
| 冬相聞 寄雪 |
| 天霧相 零来雪之 消友 於君合常 流經度 |
| 天霧らひ降りくる雪の消なめども君に逢はむとながらへわたる |
| あまぎらひ ふりくるゆきの けなめども きみにあはむと ながらへわたる |
| 巻第十 2349 冬相聞 作者不詳 |
〔語義〕
「けなめども」は、原文「消友」を、旧訓は「きえぬとも・きゆれとも」だが
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕が、「きえめども」
そして、『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕が、「けなめども」とする
「消なめ」は、消える意の動詞「く」の連用形「け」に、
完了の助動詞「ぬ」の未然形「な」、
さらに推量の助動詞「む」の已然形「め」がついたもの
「ども」は、「逆接の確定条件」を表する接続助詞で、「已然形」につく
「~けれども・~のに・~だが」の意
「きみにあはむと」は、あなたにいつか逢いたい、とそれだけを支えに、という意
|
〔歌意〕
空一面かき曇って降ってくる雪のように、
はかなく消えそうな私の命なのですが
あなたに、お逢いしたいばかりに
ただそれだけを思って、こうして生きながらえているのです |
こうして見ると、「あまくもきらひ」もまた「雪」に自然に掛かる語句には違いない
しかし、部立てをそのままの「意味」で解釈するのなら
最初の〔1445〕が「春雑歌」も妥当でありで、
それ以外も、まさに「冬」の情景そのものだ
〔1445〕は、雪は降っているけど、うぐいすが鳴いている...春になったのだなあ
そんな家持の早春の感嘆の詠歌に思えてならない
だとすると、この掲題歌、確かに「春なのだが、それなのにまだ雪が降ると(冬)」
早春の「雪」も、「早春」とは名ばかりで、まだまだ「冬」なのかもしれない
そんな詠嘆なのかもしれない
|
| |
|
|
| 【歌意1837】 |
梅の花の上に、こんなに降り覆う雪を
両手で包み持って、あなたにお見せしようと
でも、手にすれば消え、また取れば消え、
私の想いのように、なかなかお見せすることができません |
春の梅の花に降り積もる雪
その「美しき」ものを、愛しい人に見せようと思う
しかし、取っても取っても、雪ははかなく掌で消えて行く
自分の秘かな想いもまた、あの人には伝わらないのだろうか...
雪のように、儚い自分の想いを、知る
「雪」を見せたい、というのは
何も、人が手にしなくても、その光景を見せることはできる
しかし、手にした途端消え行く雪に、この女は平常心ではいられなかったはずだ
こんなはずではない、どうして私の想いが届かないのだろう、と必死に繰り返し包み持つ
こんなに梅の花に積もる雪が綺麗なので、ついあなたに見せたくなりました
という程度なら、何度も何度も消える雪を...包もうとするだろうか
はかない「孤悲」の、それでも自分は精一杯想っていることを、
自分自身が確認したい...そんな歌だと思う
|
 |
掲載日:2013.12.14.
| 春雑歌 詠鳥(詠雪) |
| 梅花 零覆雪乎 褁持 君令見跡 取者消管 |
| 梅の花降り覆ふ雪を包み持ち君に見せむと取れば消につつ |
| うめのはな ふりおほふゆきを つつみもち きみにみせむと とればけにつつ |
| 巻第十 1837 春雑歌 詠鳥(詠雪) 作者不詳 |
【注記】〔4048〕
〔青は「注記」へ、赤は「古語辞典」へリンク〕
| 【1836】語義 |
意味・活用・接続 |
| うめのはな[梅花] |
| ふりおほふゆきを[零覆雪乎] 雪が降り一面を覆う、その雪を |
| つつみもち[褁持]両手で包み持つの意なのだろう |
| きみにみせむと[君令見跡]あなたに見せようと |
| とればけにつつ[取者消管] |
| ば[接続助詞] |
[順接・恒常条件]~するときはいつも |
已然形につく |
| け[消(く)] |
[自カ下二・連用形]消える・なくなる |
| 〔参考〕連体形・已然形・命令形の確かな用法は見当たらない |
| に[助動詞・ぬ] |
[完了・連用形]~てしまう |
連用形につく |
| つつ[接続助詞] |
[反復・継続]~ては・~つづけて |
連用形につく |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [つつみもち] |
現代的には、このように雪を「つつむ」場合には、まず両手で、と思うが
この時代、女性が同じような行為をする場合、
袖を使って雪を包み込むものかもしれない
他動詞「つつむ」には、普通に「中に入れる・おおい囲む」の意の他に、
「隠くす・秘める」の意味もある
この歌でも、この意を少しでも添えることが出来るのではないか、と思う
そう思いたくなるのは、『万葉集』中での「つつみ」の対象が
「白玉・鰒玉・燃える火・白波・玉津島」など、美しいもの、貴重なもの、特別なもの、
さらには、つつみがたいものを「つつむ」奇跡的な行為として用いられており
この歌のように、梅の花を覆うように降り積もる雪を
単に物としてだけで捉えるのではない気がする
|
| |
| [け] |
一般的に、「消える」ことを意味する動詞としては、
自動詞ヤ行下二段「消(き)ゆ」が馴染み深い
その意味も、「(形のあるもの、見えていたものが)形がなくなる・消える」とある
しかし、この歌の「け」は、自動詞カ行下二段「消(く)」だ
ただし、古語辞典によると、連体形・已然形・命令形の確かな用例がない、とされる
だから、この「消(く)」を使った他の歌でも、自動詞カ変「来(く)」と見做される歌もある
| 新川郡渡延槻河時作歌一首 |
| 多知夜麻乃 由吉之久良之毛 波比都奇能 可波能和多理瀬 安夫美都加須毛 |
| 立山の雪し消らしも延槻の川の渡り瀬鐙漬かすも |
| たちやまの ゆきしくらしも はひつきの かはのわたりせ あぶみつかすも |
| (右件歌詞者 依春出擧巡行諸郡 當時當所属目作之 大伴宿祢家持) |
| 巻第十七 4048 属目歌 大伴宿禰家持 |
〔語義〕
「ゆきし」の「し」は、強意の副助詞
「くらしも」は、「消(く)らしも」で、ここにカ行下二段「消(く)」がある「終止形」
「らし」は、推量の助動詞「らし」で動詞の終止形付く
そして、この「らし」連体形が、詠嘆の係助詞「も」に付く
「はひつき」は、延槻川(早月川)のこと
「わたりせ」は、徒渉が容易な浅瀬
「つかすも」は、「漬かす」は「漬かるに任せる」の意 |
〔歌意〕
立山のあの雪が、今は融けているようだ
延槻川の渡り瀬で、この鐙まで水に濡らしてしまった |
この歌の「く」は、カ行下二段「消(く)」が通説だが、
これをか行変格動詞「来(く)」とする説もある
しかし、その「来」で、どうやって訳すのだろう
|
| |
|
|
| 【歌意1838】 |
あんなに咲いていた梅の花が、今はすっかり散ってしまった
それなのに、白雪が
しきりに、とても尽きることもないように降りしきって... |
梅の花は、咲き散ってしまったのに
まだ、雪は降り続くのか
春ののどかさを愛でようと思っても
なかなか、望むようにはいかないものだ
いや、こうして「春の雪」を、訝しく思いながら鑑賞することも
「春の風情」として思えるのかもしれない
現代では、春に雪、と言えば
すぐに「異常気象」と言いかねないが
自然の現象は、何も決められた通りに事を運んでいるのではなく
いろんな要因が絡まって、その中でも確率的に、「予想」したり出来るものだが
何も、予想できたからといって、何でもかんでも「ありがたい」訳ではないだろう
私も、かつて山登りに夢中であった頃は、
少なくとも早朝のラジオから流れる情報で天気図に書き込んだものだ
何の為に...山登りを、より確実に登り切るために...
しかし、一旦山を降りてしまえば、もう天気のことなど気にもしなかった
雨が降ろうが、雪になろうが、それで一日の行動が変わることもなく
なるがままの天気の中で、しなければならないことをする
きっと、そのころの私が、この掲題歌のような万葉歌に触れても
少しも惹かれることはなかっただろう
当時の私は、もっと激情的な「想い」の歌ばかりに惹かれていたものだを
花や、雪などを、いくら人が詠じようが、自分とは重ねることができなかった
見えるものではなく、見えないものにこそ、歌の意義があるものだ、と
しかし...やはり人の想いの変化というのは面白いものだ
今まで「見えるもの」として見ていた「自然現象」
吹雪や嵐、雨...
何もそれらを「見なく」てもよいと思うようになった
確かに「目」には映る...だから、物理的には「見える」
目を閉じたら、当然「見えない」
しかし、詠歌の「見える」こととは、この目を閉じたら見えなくなる「見える」ではなかった
だから、目の前の「風物」を詠んだとされるものでも、
こうしてその場にいない、我々が感じるのは、
「見えない」ものを「見える」ように浮かべるからだ
とすれば、作者だって同じだろう
決して「見えて」いるから詠うのではなく、感じているから「詠える」のだと思う
極端に言えば、「見てはいけない」「見える必要もない」ものを、感じて目の前に投影している
だから、掲題歌のように、ただ見ているだけなら
雪が降ってきた、せっかく春めいてきたのに、おお寒い、
と、ちょっとした感想を詠ったものではないはずだ
そこで目を閉じれば、何が見える...
しきりに降り続く雪
梅の花が散っても尚、お前はやってくるのか、と会話が出来るではないか
肌で感じる「降る雪」の「想い」を、ことばを紡ぐことで、応えてやる
それが、「詠歌」のように思えてきた
仮に...おそらくかなりの飛躍だが、
この歌の作者が、先ほどのように目を閉じて、春の雪と会話してそれを詠ったものだとする
しかし、何百年も、千数百年も後の人には、そんな光景など思いもつかない
作者の目の前に、梅の花が散っているのに、雪が降り続け...その光景を詠じた
そう現象としては解するだろう
そして、多くの歌意にもみられるように、それは何を感じて詠ったものか、と続く
「見えたもの」が大前提で論じられる「歌意」ならば、まさに「自縛」そのものだ
作者本人が、我々に直に歌意を伝えられない古代の歌には
定説という「決め事」ではなく、その当時の「語彙」を知るしか方法がない
そして、作者以外で、誰も作者本人の「うたごころ」は解らない
そうした宿命を持っているのが、『万葉集』だ
だから...『万葉集』と会話をしたい、と不遜にも思う
そのために、自分には何が足りないか...もっともっと知らなければ、と思う
|
 |
掲載日:2013.12.15.
| 春雑歌 詠鳥(詠雪) |
| 梅花 咲落過奴 然為蟹 白雪庭尓 零重管 |
| 梅の花咲き散り過ぎぬしかすがに白雪庭に降りしきりつつ |
| うめのはな さきちりすぎぬ しかすがに しらゆきにはに ふりしきりつつ |
| 巻第十 1838 春雑歌 詠鳥(詠雪) 作者不詳 |
【注記】〔1493・4419・1603〕〔942〕
〔青は「注記」及び「古語辞典」関係へ、尚注記以外は新しいウィンドウで開く〕
| 【1838】語義 |
意味・活用・接続 |
| うめのはな[梅花] |
| さきちりすぎぬ[咲落過奴] |
| さきちり[咲き散る] |
「咲いて散る」の意の複合語[連用形] |
| すぎ[過ぐ] |
[自ガ上二・連用形]盛りが過ぎる・終りになる |
| ぬ[助動詞・ぬ] |
[完了・終止形]~てしまう・~てしまった |
連用形につく |
| しかすがに[然為蟹] |
| しかすがに[然すがに] |
(上代語)そうはいうものの・しかしながら |
副詞「然(しか)」にサ変動「為(す)」の終止形「す」、接続助詞「がに」のついたもの
中古以降は「さすがに」が用いられた |
| しらゆきにはに[白雪庭尓]白い雪が庭に |
| ふりしきりつつ[ふりしきりつつ]しきりに降り続く |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [さきちりすぎぬ] |
この「咲いて散る」というような語句は、訳して表現することは殆どない
この歌のように、「過ぎぬ」(ピークを過ぎてしまった)とする「内容」的なものだ
単独での「咲きて散る」という表現は、『万葉集』中でも、
「咲きて散る」(九例)、「咲きか散る」(一例)、「咲きかも散る」(二例)など、
それほど多くない
そして、この歌のように、「咲き散り過ぎぬ」と詠うのは、この歌一首しかない
ここで比較したかったのは、
「咲きて散る」と、「散り過ぎ」の心象的な詠い方を見たかったからだ
「散り過ぎ」の用例として、次の三首を挙げる
| 夏雑歌/大伴家持惜橘花歌一首 |
| 吾屋前之 花橘者 落過而 珠尓可貫 實尓成二家利 |
| 我が宿の花橘は散り過ぎて玉に貫くべく実になりにけり |
| わがやどの はなたちばなは ちりすぎて たまにぬくべく みになりにけり |
| 巻第八 1493 夏雑歌 大伴宿禰家持 |
〔語義〕
「たまにぬくべく」は、玉に通せるほどの
「べく」は推量の助動詞「べし」の連用形で、動詞の終止形につく |
〔歌意〕
我家の庭の橘の花は、すっかり散ってしまって
玉に貫けるくらいに、実がなってしまった |
| |
| 獨惜龍田山櫻花歌一首 |
| 多都多夜麻 見都々古要許之 佐久良波奈 知利加須疑奈牟 和我可敝流刀尓 |
| 龍田山見つつ越え来し桜花散りか過ぎなむ我が帰るとに |
| たつたやま みつつこえこし さくらばな ちりかすぎなむ わがかへるとに |
| 既出〔2013年12月4日、注記〕巻第二十 4419 獨惜桜花 大伴宿禰家持 |
| |
| 秋雑歌/(大伴宿祢家持秋歌三首) |
| 狭尾壮鹿乃 胸別尓可毛 秋芽子乃 散過鶏類 盛可毛行流 |
| さを鹿の胸別けにかも秋萩の散り過ぎにける盛りかも去ぬる |
| さをしかの むなわけにかも あきはぎの ちりすぎにける さかりかもいぬる |
| 右天平十五年癸未秋八月見物色作 |
| 巻第八 1603 秋雑歌 大伴宿禰家持 |
〔語義〕
「むなわけにかも」の、「むなわけ」が胸で繁みなどを押し分けること
この「わく」は、四段ではなく、他動詞カ行下二段「別く」の連用形だと思う
「にかも」は、格助詞「に」、確定条件の疑問の係助詞「かも」がついて、
「~のためにか」
「ける」は過去の助動詞「けり」の連体形
「さかり」は、活動力や勢いが盛んなさま、またその時期
「いぬる」は、自動詞ナ変「往ぬ」の連体形で、「過ぎ去る」の意
「過ぎにける」も、「去ぬる」もともに連体形というのは
私の拙い解釈では、詠嘆・余情の表現としての「連体形止め」だと思う
ここでの要点は、「むなわけにかも」と「さかりかも」であり、
秋萩がこんなに散っているのは、どちらなんだろうか、と詠じたもの
|
〔歌意〕
牡鹿が、その胸で押し別けたからなのだろうか
秋萩が、すっかり散ってしまっているなあ
それとも、秋萩の花の盛りが過ぎてしまったからなのだろうか... |
「散り過ぎ」と用いる歌の心情では、
「咲いている」という本来はもっとも愛でる時期のことより、
「散っている」姿そのものを、感情をこめて見詰めている
それが「散り過ぎ」の歌の重きを成しているところだと思う
「咲き散る」と「散り過ぎ」を併せて詠うこの歌...
「花は咲き、そして散る」という流れではなく
「ああ、あの美しく咲いていた花も...散ってしまったのか...」
私は、そう感じたい
「いつかは散る花」ではなく、散ってしまった後に、初めて気づく
「花は散るもの」だと
だから、あまり訳さないとされる「咲いて散る」(それが花そのものだから)ではなく
「美しく咲いていた花、なのに散ってしまった」と心情的な受け方をしてしまう
|
| |
| [ふりしきりつつ] |
原文の「零重管」は、旧訓「ふりかさねつつ」
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕、「ふりつもりつつ」
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕、
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕など、「ふりしきにつつ」
『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕、
『万葉集総釈』〔楽浪書院、昭和10~11年成〕以下の諸注に広く支持されているのが、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕の「ふりしきりつつ」
「しきる」の意味を知る手掛かりの一つに、「四寸流白波」の語句がある
雑歌/[(三年丙寅秋九月十五日幸於播磨國印南野時笠朝臣金村作歌一首[并短歌])
反歌二首]) |
| 徃廻 雖見将飽八 名寸隅乃 船瀬之濱尓 四寸流思良名美 |
| 行き廻り見とも飽かめや名寸隅の舟瀬の浜にしきる白波 |
| ゆきめぐり みともあかめや なきすみの ふなせのはまに しきるしらなみ |
| 巻第六 942 雑歌 笠朝臣金村 |
〔語義〕
「ゆきめぐり」は、浦の入りくんだ辺りを巡り歩くこと
「みともあかめや」は、見ても飽きることがあるだろうか
「や」は否定を伴う疑問
「なきすみ」とは、地名なのだろうか
「しきる」は、自動詞ラ行四段「頻る」の連体形で、度重なる、繰り返して起こる
原文の「重」の訓に、『名義抄』では「かさぬ・かさなる・しげる・しきる」とある
古語辞典でも「頻る」として、「しきる」は度重なる、重なることなどの意を持つ |
〔歌意〕
浦の入り江を気ままに歩き、見ていて飽きることがあるだろうか
名寸隅の舟瀬の浜に、しきりに重なり合いながら打ち寄せる波...その白波は |
このように「しきる」が、何度も繰り返し行われる様子をいうものだとする
すると、掲題歌の「ふりしきりつつ」というのは、
しきりに、止むこともなく降り続く雪、ということだろうし
旧訓や、その後の訓で、あたかも「積もる」ような訓を当てるのは
やはり違うような気がする
もっとも、止むことなく絶えず降る、ということは
結果として「積もること」には違いないが
この歌を読むには、「しきる」語から、積もる様子ではなく
降り続けている様子を詠じたものだと思う
|
| |
|
|
| 【歌意1840】 |
冷たい冬の名残の風にのって、雪は降るのだが
しかし、そうはいっても、山には霞がたなびいている
はやり春になっているのだなあ
|
まだ冬は終っていないと...
風も冷たく吹き、雪さえも降る
しかし、山辺を見遣ると、かすみがたなびいている
次第にこみ上げる春の「歓び」というような歌だと思う
右頁の掲題では、通説に拠った「訓」を当てたが
歌意として訳してみたら、「注記」に書いたような「たなびく」にしてしまった
陰暦で言う「春」とは、現代ではまだまだ「冬」のことだ
さらに、最近では随分遅くまで雪を見かけることもある
歌そのものに、季節感を必然とするのは、あまり拘りはしないが
その季節の「人が胸打つ」こころを詠ったものが、
結果として「季節感」を詠じた、というのだろう
特に、『万葉集』を始め「季節」を部立てとして詠む歌集は多い
後には、「季語」として特定の語句まで生まれている
その「季語」に拘る必要もないが、それほど歌を詠む人にとって
毎年巡ってくる「季節」は、「心待ち」にし、詠まずにはいられないものなのだろう
しかし、この歌のように、「春というのに、雪が...」
こんな季節の境を詠じた歌が多いことに、あらためて気づく
そもそも、「季節」は曖昧な「自然の姿」だ
決まっているようで、実は決まっていない
確かに、季節は巡ってくる
それは誰しも疑いは持たない
しかし、ではいつから「春」になる
いつから「秋」になる
そう、「立春」や「立秋」という言葉がある
それが目安であることは、誰もが知っている
だからと言って、杓子定規に、「今日から春です」などという人はいない
この歌で作者が感じるように
そろそろ、春だろうに...まだまだ雪が降るなあ
でも、山の方に、霞がたなびいているじゃないか
やっぱり、春は来ていたんだ...
歌は、こんな風に詠むのだろう
うぐひすの鳴き声を聞きながらも、訝しげに春の雪を見る
梅の花が散り始めているのに、また春の雪を見る
こころの中では、「春の雪」は一つの「春の景物」なのに
詠じることばでは、「雪は冬の景物」になっている
だから、「春に見る雪」が、こんなに多く詠われているのかもしれない
決して当たり前の概念ではなく、目の前の「当たり前」のことでも、「いや、違うなあ」と
そう詠ってみることが、詠じる者の「粋」なのかもしれない
|

 |
掲載日:2013.12.16.
| 春雑歌 詠鳥(詠雪) |
| 風交 雪者零乍 然為蟹 霞田菜引 春去尓来 |
| 風交り雪は降りつつしかすがに霞たなびき春さりにけり |
| かぜまじり ゆきはふりつつ しかすがに かすみたなびき はるさりにけり |
| 巻第十 1840 春雑歌 詠鳥(詠雪) 作者不詳 |
【注記】〔1449〕
〔青は「注記」及び「古語辞典」関係へ、尚注記以外は新しいウィンドウで開く〕
| 【1840】語義 |
意味・活用・接続 |
| かぜまじり[風交] |
| まじり[交じる] |
[自ラ四・連用形](あるものの中に他のものが)交じる・混じる |
| ゆきはふりつつ[雪者零乍] |
| つつ[接続助詞] |
[(打消の表現を導く時)逆接]~ながらも |
連用形につく |
| しかすがに[然為蟹] |
| しかすがに[然すがに] |
[副詞](上代語)そうはいうものの・しかしながら |
副詞「然(しか)」にサ変動「為(す)」の終止形「す」、接続助詞「がに」のついたもの
中古以降は「さすがに」が用いられた |
| かすみたなびき[霞田菜引] |
| たなびき[棚引く] |
[自カ四・連用形]雲や霞などが横に長く引く |
| はるさりにけり[春去尓来] |
| さり[去る] |
[自ラ四・連用形](季節や時には)近づく・来る |
| に[助動詞・ぬ] |
[完了・連用形]~てしまう・~てしまった |
連用形につく |
| けり[助動詞・けり] |
[過去詠嘆・終止形]~たことよ・~ことよ |
連用形につく |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [まじり] |
この初句の原文「風交」は、ほとんどの注釈書で「かぜまじり」と訓をつけている
しかし、手元の諸注を幾つか開いてみると
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕では、「かぜまじへ」とある
確かに原文「風交」を浅学の私が、どっちが正しいか、などと解りはしないが
それでも、素人が古語辞典などで調べ得る範囲で、考えてはみた
また、後で触れることになるが、この「かぜまじへ」とする注釈書では、
少なくとも前述の二書においては、
第四句「霞田菜引」を「かすみたなびく」と「終止形」にしている
「かぜまじり~かすみたなびき」と、「かぜまじへ~かすみたなびく」の構文のようだ
もっとも、第四句を終止形で終らせれば、結句の「春」が強調されるだろうが...
問題は、素人が単純に「風を交へて」と思ったとき
その古語の「交へる」語を、
無意識の内に「風に交じって・風とともに」くらいしか思わないことだろう
現代語であれば、それで充分だ
しかし、厄介なのは、古語にこの意味での「交じる」動詞は、幾つもある
| まじはる(交はる) |
自ラ行四段 |
ら・り・る・る・れ・れ |
①いりまじる・まぎれこむ
②交際する・付き合う
③男女が関係する・情を交わす |
| まじふ(交じふ・雑じふ) |
他ハ行下二段 |
へ・へ・ふ・ふる・ふれ・へよ |
| 混ぜ合わせる・混合させる |
| まじらふ(交じらふ) |
自ハ行四段 |
は・ひ・ふ・ふ・へ・へ |
①まじり合う・まざる
②仲間に入る・交際する・宮仕えする |
| まじる(交じる・混じる・雑じる) |
自ラ行四段 |
ら・り・る・る・れ・れ |
①あるものの中に他のものが入り込む・まざる
②人に立ちまじる・仲間に入る・宮仕えする
③山や野に分け入る |
| かはす(交はす) |
他サ行四段 |
さ・し・す・す・せ・せ |
①互いに遣り取りする・通じ合う
②まじえる
③(「変はす」とも書いて)変える・ずらす |
| かふ(交ふ) |
他ハ行下二段 |
へ・へ・ふ・ふる・ふれ・へよ |
| 交差させる・交わす |
他にも、補助動詞として動詞の連用形に付く用法もあるが
この歌では、名詞「風」に付くので、挙げなかった
『万葉集』中で、「風交」と原文で詠っているのは、三首ある
掲題歌〔1840〕の他に、〔1449〕と、〔4184〕
前者は、大伴坂上郎女、後者は大伴家持の詠歌
家持の方は長歌なので、ここでは扱わないで、坂上郎女の歌を載せる
| 春雑歌/大伴坂上郎女歌一首 |
| 風交 雪者雖零 實尓不成 吾宅之梅乎 花尓令落莫 |
| 風交り雪は降るとも実にならぬ我家の梅を花に散らすな |
| かぜまじり ゆきはふるとも みにならぬ わぎへのうめを はなにちらすな |
| 巻第八 1449 春雑歌 大伴坂上郎女 |
〔語義〕
「かぜまじり」は後述
「ゆきはふるとも」、「雪は降っているが」
「みにならぬ」、「実がなっていない」で「花だけで散らさないで」と続く |
〔歌意〕
風に交じって、雪は降っているけど
まだ実もつけない我家の梅を
それまで待つこともなく、花だけで散らさないでくれ
|
この歌、坂上郎女の娘・二嬢を梅の若木に譬えて詠ったもの、ともいうが
ならば、「風交雪」は、何を意味するのだろう...
と、それは今日のテーマではないので深入りはしない
この歌の原文「風交」もまた、「かぜまじり」がほとんどの中で、
『岩波』の大系は、やはり「かぜまじへ」とするが
『講談社文庫』は、これには「かぜまじり」としている
解釈上では、簡単に読み流してしまうものだが...
「かぜまじり」、「かぜまじへ」に、それぞれ助詞を添えるとどうなるだろう
「かぜにまじり」、「かぜをまじへ」、これではっきりする
「交」の幾つかの動詞での違いが大差のないものなので
この助詞を想定した場合で手掛かりになりそうだ
「かぜに」は、「風が主体」と言える
雪が降り続く、「風に交じって」...
「かぜを」が、「雪が主体」とすれば、「風を誘い込んで」のような感じだろう
前述の二書も、「かぜまじへ」では、「風を交へて」としている
歌意の解釈上では、その使い分けを意識することになるが
では、「交じり」と「交じへ」の、どちらの動詞も接続の問題など、成り立つのか
と、いうことになる
「交じり」は、「まじはる・まじる」の「連用形」しかなく
当然次の句の「降り」と併用で、「つつ」にかかると思う
同じく「つつ」に掛かるとすれば、やはり「連用形」なので
「交じへ」が連用形になるのは、「まじふ・かふ」だが「かふ」では語義も語調も違う
では、「まじふ」ということになるだろうか
後は、古語辞典の基本的な用例から、語意を想うしかない |
| |
| [たなびき] |
ここも、原文「霞田菜引」を、通説では「かすみたなびき」(連用形)とあるが
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕では、「たなびく」(連体形)とし
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕や、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕では、「たなびく」(終止形)とする
通説の様に「連用形」では、霞がたなびいて「春になる」にかかり
「連体形」だと、霞がたなびいている「春」に、
そして「終止形」では、「霞がたなびく」で止る
これは、「春になっている」ことを、強調させているみたいに感じられる
連用形、連体形はどちらも修飾する語に掛かるが、
終止形の語調もまた捨て難い
前の「注記」で書いたように
「かぜまじり~たなびき」、「かぜまじへ~たなびく」
歌意としての解釈上のルールではないだろうが、何となく符牒のようなものを感じる
「かぜまじり」と訓じて、「かすみたなびく」とは詠っていないからだ
勿論、その逆もそうだ
「かぜまじへ」と訓じて「かすみたなびき」もない
もっとも、私の調べ方も充分ではないかもしれないが...
通説を引用して「訓」じたが、今芽生えたのは、「終止形」で終るのもいいかな、と
|
| |
|
|
| 【歌意1841】 |
山あいに、うぐひすが鳴いている
そう、もう草木もなびくように、春にはなっているのだが...
この雪が、辺り一面に降っているのが、気も塞がれることだ
|
作者が、春の雪を好むのかどうかは、実際には解らないが
「ふりしきる」ということばが、一面に降る、ことを思えば
歓迎せざる光景だと思う
春なんだぞ、まだ降るのか、お前は...
単純に、「ゆきふりぬ」では、勿論結句の字数には合わないが
そんな意味合いであれば、客観的な「春の雪」をおおらかに観賞するだけの気持ちだろうが
「ふりしきる」というのは、「こんなにも降って」と、半ば呆れて嘆いている感じだ
このところ、こうした中途半端な時期の「雪」を採り上げているが
「冬の雪」は紛れもなく「冬の景物」だろうが
「春の雪」は、いったい万葉人にとって、どんな「心持」なのだろう
未練たらしく降る雪に、愛おしささえ感じているのではないだろうか
お前も、おかしな奴だ、ほどの軽い嫌味でもいえるような相手だと思って...
そう思えば、「春の雪」は、現実の「春の景物」にはなりえなくても
詠じる者にとっては、春には欠かせない「歌の心」なのかもしれない
少しでも季節感が狂うと騒ぐマスコミに影響されている現代
そもそも、気紛れな自然現象を、あるがままに受け入れる万葉人
それを歌に詠める人たちの感性...
現代は、あまりにも「理論性」が重きが、ごく自然に受け入れられている
だからこそ、万葉人の、「おおらさか」が際立つのかもしれない
さて、右頁の「穂積皇子」の歌に戻ろうと思う
この歌が詠われた背景は、〔書庫-6〕に書いたように
随分と生々しい恋愛関係の当事者であり、その通説には、私は従えなかった
それでも、自分が思う当事者たちの「想い」を「文章」にしたとき
もう私にとって、この穂積皇子は、好感の持てる皇子になっていた
それに、あの大伴坂上郎女が、皇子の最後の妻というのも
大伴家との繋がりを思うと、決して見逃せない存在だ
この〔203〕は、穂積皇子が愛した但馬皇女が亡くなり、その墓のある岡を眺めて、
雪が降るのを、皇女が寒がるから降るな、と
涙を流し詠んだ歌、「挽歌」だ
右頁に書いたように、原文「零雪」を
多くの諸注が訓じているように「ふるゆきは」として
もうげんぶんを離れ、「ふるゆき」という言葉の解釈に沿い、
「雪が降っている状態」のように歌意を書いていた
勿論、どの注釈書でもそうだ
「ふるゆき」に、なにも異訓もなければ、ことなる解釈もない
ただ、題詞には「雪落」とあり、「降る」ことを「落」で表記し
本文では、「零」としているのが気になった
「落つ」とは、古語でも、雪や雨が「降る」意味があり
雪が当たり前のように「空から落ちてくる」現象を、「雪が降る」、「雪が落つ」
そう思うのは自然であり、そこに深い意味など求めはしない
しかし「零之」となると、この「零」とは何だ、と思ってしまう
古語で「零」もまた「降る」意味だ、と言われるかもしれないが
何故「落」と使い分けるのか、その説明を見たことがない
おそらく、説明するほどのこともなく、「零」は「降る」ことだ、というのだろう
「零」の古語辞典で引くのは、私には困難だった
その読み方では、引けない
ましてげんだいの読み方では、当然載っていない
万葉人が「零」を使っている以上
古語辞典にも、載っていてもおかしくないはずだ
これは、明日香の図書館での宿題になってしまうが...
年のため、現代用語で、「零」の意味を調べていたら
その熟語として「零雨(レイウ)」「零露(レイロ)」があり、
その意味が、右に書いたように「こぬか雨、静かに降る雨、したたり落ちる露」など
何となくそのニュアンスを感じられる言葉だった
そこに「零雪」と置き換えたら、どうなるのだろう
しずかに降る雪...
詠じる作者、穂積皇子はそんな意識はないのかもしれない
何しろ、「零雪」も『万葉集』中には16例あり、どれも「降る雪」と訓まれている
だから、私が拘るほどの意味もないのだろう
「雪が落る」が一つの文をなすように、「零る雪」は、一つの修飾された「語」だ
ただそれだけの違いなのだとは思う
しかし、では何故穂積皇子は、「ふるゆきは(零雪)」と詠ったのだろう
「ゆきのふる(雪之落)」とか、「ゆきはふる(雪者落)」でもよいではないか
「ふるゆきは」と「零雪」を当てて訓む他の歌を今引っ張りだすのは時間がかかるので
近いうち...おそらくこのところの部立て「詠雪」の中でも、扱えると思う
「零雪」の意味を、何故「ふるゆきの」と詠いたかったのか、と考えてみる
「零」には、「こぼれる」という意味も現代ではある
「零(こぼ)れ桜」、「零れ梅」などのように、咲き満ちてこぼれ落ちる、ことを言う
雪が空から「零れ落ちる」と、現代では「零れ雪」を当ててしまいそうだ
のまだ冬は終っていないと...
いや、「こぼれゆき」でもいいのではないか
そう思って、たった今古語辞典を引いたら、「こぼる」で「零る・溢る」があった
驚いた、
私の無知さをさらけ出したことになるが、「零」を「こぼれる」と読むことを知らなかった
上の「零れ桜」や「零れ梅」は、完全に当て字かと思っていた
意外な出逢い方もあるものだ...確か以前にもこんな風に出逢った「語」があった
| こぼる(零る・溢る) |
自ラ下二段 |
れ・れ・る・るる・るれ・れよ |
①こぼれる・流れ出る・溢れ出る
②(表情として)外に現れる
③散る・落ちる |
| こぼれいづ(零れ出づ) |
自ダ下二段 |
で・で・づ・づる・づれ・でよ |
①涙や水などが溢れ出る
②はみ出す |
| こぼれかかる(零れ掛かる) |
自ラ四段 |
ら・り・る・る・れ・れ |
①(髪などが)落ちてかかる・垂れかかる
②涙や水などが零れ落ちて降りかかる
|
| こぼす(零す・溢す) |
他サ四段 |
さ・し・す・す・せ・せ |
①溢れさせる・こぼす
②すきまから、はみ出させる |
このことから、「こぼる」を用いれば、「こぼるるゆき」でもいいはずだ
「空から溢れ落ちる雪よ」、というような意味でもいいはずだ
私は、あっさり「ふるゆきは」と読むより、
「こぼるるゆき」と初句を訓めば、その方が穂積皇子の「悲傷涙涕歌」に
よりいっそうその心情が備わると思う
他の用例は、今後の課題だが、「零」を「落」と同じように訳すのは、やはり抵抗がある
単なる「降り落ちる」現象では、それを客観的に観ることになるが
「零れ落ちる」「溢れ落ちる」のであれば、そこに自分の訴えることの出来る感情を感じる
朝、まさかこんな展開になるとは思わず、今夜は早く終えられそうだ、と
この掲題歌を読んだとき、そう思った
しかし、偶然にしても、今夜は読み甲斐のある「語句」に出逢った
だから、『万葉集』は楽しい
たとえ、思い込みであっても、誰も万葉人と直に話せる人はいないのだから...
|
| |
|
掲載日:2013.12.17.
| 春雑歌 詠鳥(詠雪) |
| 山際尓 鴬喧而 打靡 春跡雖念 雪落布沼 |
| 山の際に鴬鳴きてうち靡く春と思へど雪降りしきぬ |
| やまのまに うぐひすなきて うちなびく はるとおもへど ゆきふりしきぬ |
| 巻第十 1841 春雑歌 詠鳥(詠雪) 作者不詳 |
【注記】〔203〕
〔青は「注記」及び「古語辞典」関係へ、尚注記以外は新しいウィンドウで開く〕
| 【1841】語義 |
意味・活用・接続 |
| やまのまに[山際尓] |
| やまのま[山の間] |
山あい・山と山の間 |
| に[格助詞] |
[位置]~に・~で |
体言につく |
| うぐひすなきて[鴬喧而] |
| て[接続助詞] |
[並立]~て |
連用形につく |
| うちなびく[打靡]〔枕詞〕「春」にかかる |
| はるとおもへど[春跡雖念] |
| おもへ[思ふ] |
[他ハ四・已然形]考える・思う・思案する |
| ど[接続助詞] |
[逆接の確定条件]~けれども・~のに・~だが |
已然形につく |
| ゆきふりしきぬ[雪落布沼] |
| ふりしき[降り敷く] |
[自カ四・連用形]一面に降る |
| ぬ[助動詞・ぬ] |
[完了・終止形]~てしまう・~てしまった |
連用形につく |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| [やまのま] |
原文「山際」を現代でも、「山の際」、空が山と接する境目、
あるいは、「山に近いところ」、「山のふもと」など、同じ感覚で使うが、
どうも、この歌では違うようだ
「山あい」や「山と山の間」と一応語義を収めたが
これは、多分に歌全体の歌意からもたらされた「解釈」だと思う
ただ、強引にそうしているのではなく、
「際」という意味をも、拾い出して説明してあった
「際」には、「あいだ・ほとり・境界」の意味があるようだ
ついでに、一般的な「やまぎは」と「やまのは」の違いの説明を載せておく
(古語辞典より)
「春はあけぼの。やうやうしろくなりゆく、山ぎはすこしあかりて、むらさくだちたる雲のほそくたなびきたる。・・・秋は夕暮れ。夕日のさして山の端いと近うなりたるに」(枕草子)のように、対照的に用いられた場合の「山ぎは」は「山の稜線に接するあたりの空の部分」、「山の端」は「山の、空に接するあたり」をいう。
|
| |
| [ゆきふりしきぬ] |
原文「雪落」の「落」は、自動詞タ行上二段「落つ」そのもので、
幾つかの意味合いを持つ動詞だが、その中に、確かに「(雨や雪などが)降る」とある
だから、これまでも、何首かの「雪落」を原文とする歌を載せ、
それが「ゆきふる(り)」などと訓じられていても、何も不思議には思わなかった
それに、私自身が万葉の人たちと会話する気持ちで始めた「擬想返歌」でも、
最近では「ゆきおちて」など、「雪落」を結構意識した用い方をしていた
このところ、連続で採り上げている「詠雪」で、
「春雑歌」の部立てなのに、と「春の雪」もまた「春の景物」なのだろうなあ
ひとり感心しながら続けていたが
今日、ふと「雪落」を調べてみたくなった
帰宅して、パソコンのデータから、「雪落」を拾い出すと、全部で15例
題詞に使われているのが三例、左注で一例
そして、本文で九例 (題詞一例で、三首載せているのもあるので実質的には13例)
「雪落」は、例外なく「雪が降る」さまを詠っていた
しかし、一首だけ気になる歌があった
今日はそれを本当はメインにしたいほど、気持ちが弾んでしまった
以前にも、穂積皇子と但馬皇女の悲恋には触れたことがあったので
ここでは詳しくは書かないが、私の好きな高市皇子絡みだったので
なかなか、この二人には触れたくなかったものだ
しかし、私なりにその誤解も解けて...あくまで私なりに...
| 挽歌/但馬皇女薨後穂積皇子冬日雪落遥望御墓悲傷流涕御作歌一首 |
| 零雪者 安播尓勿落 吉隠之 猪養乃岡之 寒有巻尓 |
| 降る雪はあはにな降りそ吉隠の猪養の岡の塞なさまくに |
| ふるゆきは あはになふりそ よなばりの ゐかひのをかの さむからなくに |
| 既出〔書庫-6〕巻第二 203 挽歌 穂積皇子 |
〔歌意〕「2013年5月16日時点の解釈」
降る雪よ、そんなに深く積もらないでくれ |
| 吉隠の猪養の岡が...あの人が眠る岡が、寒くなるのは辛いことだ |
|
ここで気になったというのは、題詞に「雪落」とあり、本文に「零雪」とあること
ちなみに「零雪」も拾い出してみたが、それは16例あった
しかし、「降る雪」という風に、どれも「雪落」と同じ訳で
その違いを述べた注釈書にも...今のところ出合っていない
古語辞典でも「零」を引こうにも、古語で「零」はどうやって引くのだろう
それこそ、「漢字の字典」が必要になる
現代での「零」は、単純に「ゼロ」の意の方が圧倒的に知られるが
この当時の「零」は、同じ「落ちる」の「降る」でも、何か違うのではないか、と思う
仕方なく、現代語の「零」で、その熟語「零雪」を探したが、それはなく
「零雨」、「零露」というのが見つかった
こぬか雨、静かに降る雨、したたり落ちる露など...
現代での意味はそうなのだろう
では、「零雪」を同じように解そうとすれば、どうなるだろう
しずかに降る雪...理屈ではそうなる
単純に「降る雪」というのではなく、「静かに降る雪」なのだろうか
「雪落」が、雪が降ることの現象を見せているのに、「零雪」は、見る者の主観も交じる
そんな気がしてきた
最も、「雪が降る」とした場合に「雪落」で、
「降る雪」と連体形で「雪」を修飾する場合の用法が「零雪」かもしれないが
それでも、漢字を使い分けるのは、何か意味があるのでは、とは思う
この〔203〕については、もう一度読み直したい
それを左頁に載せる
|
| |
|
 |
| 【歌意1842】 |
山の上になおも降り、そして積もる雪
山の風が、ここまで雪を散らせているらしい
春だというのになあ...
|
作者が、降り散る雪を見ているのは、作者の居る山麓に降る雪ではなく
山に降っている雪が、風に吹かれて、ここまでやって来た
しかし、それだけであれば、「春なのになあ」と嘆くこともない
山麓は、すでに春の訪れを知らせている
それでも詠嘆するのは、山に降り積もる雪の様を見て
もう春なんだから、こちらまで降らすなよ、と少々懇願する気分なのではないだろうか
私には、それが自然な解釈に思えた
しかし、この歌の解釈で、多くの注釈書では「ふりおけるゆきし」としている
詳しくは右頁に書いたが、それには矛盾があると思う
「降り置ける雪」というと、完了の助動詞の影響を受けなくてはならない
では、峯にある雪は、現在降り積もる雪ではなく
「冬の時期から降り積もった雪」ということになり、
それが山の春風に運ばれて山麓まで吹き散らすのであれば
作者は、何も「春なのになあ」と嘆かなくともいいはずだ
むしろ、「冬の雪を春の風が吹き飛ばしている」様を詠じた方がいい
その様を見るならば、「春なんだなあ」と...
勿論、私の歌の受け入れ方が絶対正しい、というつもりはない
現に、何年か前に載せた歌の解釈を、今改めて読み返せば
あの頃は、そんな風に感じていたのか、と思うこともしばしばある
ただ、その頃と確実に違うのは、今の私は歌の語義を自身で拾い出している点だ
だから、時には感覚的にこうだろう、と思う若い頃と違って
どうしても、こうならなければならない、と「自惚」てしまうこともある
ただ、それでも『万葉集』のような原文が、現在の日本語としては曖昧な「表記」である以上
その「表記」の解釈を、私が間違いなくできるか、といえば絶対にありえない
それは、直接万葉歌にアプローチしているので
本来その解釈の手助けになるはずの『万葉集』全体の「仕組み」や「ルール」を
私は殆ど備えていない
単に、古語辞典で語義を拾い出し、自身に納得させているだえだ
勿論、私のこれまで歩んできた道が、『万葉集』とはまったく無関係なものだったので
それは、やむをえないことだろう
だから、遅まきながら、今では少しでも関連書物に接しようとしているが
その中途の段階でも、毎晩のように「歌」に接していると
ついつい、独断的になってしまう
もっと検証が必要な事柄まで、疎かにしながら、書き進めてしまう
先日、専門家の講演を聞き、今後はそんな「生の講義」の機会をどんどん増したい
と、痛切に思った
歌そのものの、研究者の解釈を最終的に求めているのではなく
『万葉集』とは、こんな歌集なのだ、という側面的な手掛かりが欲しい
解釈自体は、そこから「自分」の感性で行うものだ
今夜は、断りきれない忘年会
帰宅して、何もせずに横になったら...もう気力も萎えてしまって...
それでも、何とか起き出して『万葉集』を開く...もう確実に、以前の私ではない
元来ずぼらな私は、一旦気を緩めると、ずるずると投げ出してしまう
それを直すためでもある「一日一首」へのこだわり...今夜も何とか持ち堪えた |
| |
 |
掲載日:2013.12.18.
| 春雑歌 詠鳥(詠雪) |
| 峯上尓 零置雪師 風之共 此聞散良思 春者雖有 |
| 峰の上に降り置く雪し風の共ここに散るらし春にはあれども |
| をのうへに ふりおくゆきし かぜのむた ここにちるらし はるにはあれども |
| 右一首筑波山作 |
| 巻第十 1842 春雑歌 詠鳥(詠雪) 作者不詳 |
【注記】〔323〕
〔青は「注記」及び「古語辞典」関係へ、尚注記以外は新しいウィンドウで開く〕
| 【1842】語義 |
意味・活用・接続 |
| をのうへに[峯上尓] |
| を[峯] |
山の尾根・山の小高いところ |
| に[格助詞] |
[位置]~に・~で |
体言につく |
| ふりおくゆきし[零置雪師] |
| ふり[降る] |
[自ラ四・連用形](雨・雪などが)降る 連用形につく |
| おく[置く] |
[補助動詞カ四・連体形]あらかじめ~する |
連用形につく |
| 動詞の連用形、または連用形に助詞「て」の接続したものにつく |
| し[副助詞] |
語調を整え、強意を表す |
| 〔接続〕体言、活用語の連体、連用形、副詞、助詞などにつく |
| かぜのむた[風之共]〔枕詞〕「春」にかかる |
| むた[共] |
(助詞「の」「が」の下について) ~とともに |
| ここにちるらし[此聞散良思] |
| らし[助動詞・らし] |
[推量・終止形]~に違いない・きっと~だろう |
終止形につく |
| はるにはあれども[春者雖有] |
| には |
〔格助詞「に」+係助詞「は」〕「に」の意味にり、種々の意になる「~には」 |
| あれ[補助動詞ラ変] |
[已然形](形容詞・形容動詞の連用形・副詞及び一部の助動詞の連用形の下について)状態・存在の表現を助ける |
| ども[接続助詞] |
[逆接の確定条件]~けれども・~のに |
已然形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、282語と、およそ言われている半分程度だしかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| [ふりおくゆきし] |
原文「零置雪」(「し」は強調の助詞)
今夜もまた、「ふるゆき」の新たな表現に出合ってしまった
「雪落」が十五例、「零雪」が十六例
そして、今夜の「零置雪」は、たったの二例
それにも関わらず、「訓」の不可思議さがここでもあった
一般的なテキストでは「ふりおけるゆき」がほとんどだ
私も、以前の記事では、「ふりおけるゆき」と無条件に書き、読んでいた
しかし、今は違う
とにかく、自分で語義を確認してから、歌を理解しよう、いや感じようと思っている
だから、つい原文にも目がいってしまう
そして、僅か二例の原文「零置雪」だから、ともう一つの歌〔323〕を引っ張りだした
| 雑歌/(詠不盡山歌一首[并短歌])反歌 |
| 不盡嶺尓 零置雪者 六月 十五日消者 其夜布里家利 |
| 富士の嶺に降り置く雪は六月の十五日に消ぬればその夜降りけり |
| ふじのねに ふりおくゆきは みなづきの もちにけぬれば そのよふりけり |
| (右一首高橋連蟲麻呂之歌中出焉 以類載此) |
| 巻第三 323 雑歌 高橋連虫麻呂 |
〔語義〕
「みなずき もちにけぬれば」は陰暦六月、現代では七月から八月初旬にかけての頃
「陰暦十五日」を「望(もち)の日」と称している
「けぬれば」の接続助詞「ば」は、已然形につく順接の確定恒常条件で、
「~するときはいつも・~すると必ず」
「けり」は、話し手の体験しないことがらに用いる |
〔歌意〕
富士の峯に降り積もった雪は、六月の十五日に消えると
その夜、また降るというらしい |
〔参考Ⅰ〕
『仙覚抄』に、
「富士ノ山ニハ、雪ノフリツモリテアルカ、六月十五日ニ、ソノ雪ノキエテ、子ノ時ヨリソモニハ、又フリカハルト、駿河国風土記ニミエタリト伝ヘリ」
子の時とは、十六日の午前零時頃をさす |
〔参考Ⅱ〕
「()」の意味は、その「()」内の記述が、及ぶことを意味とさせているが
この左注は、この次の歌〔324〕の左注として記されている
そのため、作者とされる「高橋連虫麻呂」の歌は、その〔324〕一首とする説
いや、この〔323・324〕は、長歌〔322〕の反歌であり、
その長歌の作者は記されていないのは、〔324〕の左注でいう「一首」が
その「長歌と反歌二首」をさしていう、との説がある
|
この原文「零置雪」には、現代では異訓もなく、「ふりおくゆき」とされている
とは言っても、旧訓では「ふりおけるゆき」と訓じていたようで
『類聚古集』『古葉略類聚鈔』がそれに当る
しかし、『紀州本』以後は「ふりおくゆき」とすることが定着し、今日にいたる
それを解説したのが、『万葉集講義』〔山田孝雄、昭和3~12年成〕で、
それによると、「リ」の訓み添えの例は巻第三にはほとんどなく、
必ず「ル(在)」「ル(有)」が表記されているので、今如く「零置雪」とのみある場合は、
「ふりおくゆき」と訓むのがよい...と言っている
確かに、「巻第三では」と断ってはいるが、
この表記論からすれば、掲題歌〔1842〕もまた、同じことがいえると思うのだが
それは、逆にほとんどの注釈書が「ふりおけるゆき」としている
〔323〕歌における「旧訓」と同じではないだろうか
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕などが「ふりおくゆき」だ
「おけるゆき」、「おくゆき」の違いは何だろう
「おける」は、四段動詞「置く」の已然形「おけ」に、完了の助動詞「り」の連体形「る」
その意味は、「降りつもった雪・降りつもっている雪」
「おくゆき」では、四段動詞「置く」の連体形「おく」で、「降りつもる雪」
この解釈の違いが、それぞれの歌意の違いになる
私の感じるままに書くのなら、「おくゆき」の方がいいと思う
少数派であるが、表記論的な前述の説明が根拠ではなく
この歌そのものが、「降りける雪」では、何かおかしい
それだと、降り積もっていた雪、もしくは継続中であっても以前からの継続なので
その「積もり始めは、冬」のことなのだから、結句の「はるにはあれども」とはならない
「冬の雪が風に吹かれて山麓まで運ばれてきた」...それが春でも矛盾はしない
そして、結句の「はるにはあれど」と嘆かせるのは
まさに、現在降り積もる雪が風に運ばれるからこそ、ではないだろうか
「降り積もる雪」は、「冬の雪」ではなく、「春に訪れた雪」だからこそ
作者は詠じている...私は、そう思う
|
| |
|
|
| 【歌意1843】 |
いとしいあの方のために、山の田の沢で
「ゑぐ」を摘んでいると、雪解け水のせいで
裳の裾が濡れてしまいました
|
この歌の情景にも、やはり幾つかの場面が浮ぶ
「君がため」と言う表現は、「あなたのため」、「いとしいあなたのため」
諸注にも、いろいろと訳されているが...
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕では、こんな例を載せている
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| 塊茎に添えて贈ったので、実際に自分の採んだエグではないのだろう |
| 『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕 |
| 妻が夫の許へ、恵具を贈ってやるのに添えたもので、挨拶の歌である |
この解釈をみると、贈った「エグに添えた歌」が前提になっている
であれば、初句の「きみがため」は、「あなたのために」で辻褄が合う
おそらく、大方の解釈のように、実際はその方が現実的かもしれない
あなたのために、裾を濡らしてまで摘みとった「えぐ」を贈りましたよ、と
しかし、もう一つの可能性を思い浮かべてしまった
それは、いかにも「雪解けの春」をこころ弾ませている女の姿だ
さあ、春になったので、「えぐ」をあの方に贈ろう
でも、雪解け水のせいで、裾が濡れてしまった
そう「濡れた」ことを嫌がる風でもなく、「春」になったこと、
そして「愛しいあの人」へ、贈るために自分は濡れてまでも...
それを悦んでいるように思えてならない
自分の夫、恋人へ
あなたのために、裾を濡らして「えぐ」を採ったのですよ
そう添えられた歌を...果たして、男はどう思うだろう
私は、この歌がよく言われる「歌謡として謡われた」ものだという評価はしたくない
この評価の言われる由縁は、類想歌が幾つかあるからだ
その中でも、「類歌」と私が思う歌がある
| 雑歌羈旅作 |
| 君為 浮沼池 菱採 我染袖 沾在哉 |
| 君がため浮沼の池の菱摘むと我が染めし袖濡れにけるかも |
| きみがため うきぬのいけの ひしつむと わがそめしそで ぬれにけるかも |
| (右四首柿本朝臣人麻呂之歌集出) |
| 巻第七 1253 羈旅歌 柿本人麻呂歌集 |
〔語義〕
「浮沼の池」は所在未詳だが、「浮き」は「泥」の意があり
普通名詞として「泥沼」と考える説もある
そして人麻呂の縁の石見には、三瓶山麓に「浮布(うきぬ)の池」があり
そこだとする、説もある
「ひし」は、池に生える「ひし科」の一年草
泥中から長い茎を水面に出して光沢のある菱形の葉を浮べ、白い花を開く
「実」はとげがあるが、中の種子は食用となる
「かも」は、感嘆の終助詞「~であることよ」
|
〔歌意〕
いとしいあの人のために、泥池に浮ぶ菱の実を採っていたら、
わたしの色染めした袖が、濡れてしまいました |
「想い」が同じ歌だとは思う
愛しい人のために、自分の衣服を濡らしてまで「ひしの実」を採ろうとする
この歌で私が掲題歌との共通点を感じるのは、ことに結句の「かも」からだ
この「かも」は、「疑問や反語」などの助詞であるとともに、「詠嘆・感動」の助詞でもある
あの人のために、「ひしの実」を採っていたら、袖が濡れてしまったわ、と満足げな笑顔
決して濡れてしまったことを悔やむのではない
むしろ、自分がここまでしていることに、悦びを感じて、だからこそ詠じることが出来た歌だ
ここまでしたのですよ、と相手にいう必要はなく
言わないからこそ、この悦びに満ちた歌が気持ちよく響いてくる
歌が詠者の素直な気持ちを表現する一つの手段であれば
類型化した表現だから、これは「歌謡の一種だ」と決め付けるのではなく
結果的に同じような表現になることは、いくらでもあるがずだ
この歌もまた、いい歌だと思う
|
| |
|
掲載日:2013.12.19.
| 春雑歌 詠鳥(詠雪) |
| 為君 山田之澤 恵具採跡 雪消之水尓 裳裾所沾 |
| 君がため山田の沢にゑぐ摘むと雪消の水に裳の裾濡れぬ |
| きみがため やまたのさはに ゑぐつむと ゆきげのみづに ものすそぬれぬ |
| 巻第十 1843 春雑歌 詠鳥(詠雪) 作者不詳 |
【左頁】〔1253〕
〔青は「注記」及び「古語辞典」関係へ、尚注記以外は新しいウィンドウで開く〕
| 【1843】語義 |
意味・活用・接続 |
| きみがため[為君] |
| ため[為] |
[利益・たすけ]~のために |
| やまたのさはに[山田之澤] |
| やまた[山田] |
山間の田 |
| さは[沢] |
草が茂り水も多い低湿地 |
| に[格助詞] |
[位置]~に・~で |
体言につく |
| ゑぐつむと[恵具採跡] |
| ゑぐ[植物名] |
「くろくわい」カヤツリグサ科の多年草 |
| つむ[抓む・摘む] |
[他マ四・連体形]指先で摘む・つねる・(植物などを)摘み採る |
| と[格助詞] |
[引用]あとに続く状態の理由・原因をいう ~と |
| 〔接続〕体言、および体言に準ずる語(連体形)につく |
| ゆきげのみづに[雪消之水尓] |
| ゆきげ[雪消・雪解] |
雪が消えること・雪解け水 |
| ものすそぬれぬ[裳裾所沾] |
| すそ[裾] |
裳(衣服)の下の端の部分 |
| ぬれ[濡る] |
[自ラ下二・連用形]水などがつく・ぬれる |
| ぬ[助動詞・ぬ] |
[完了・終止形]~てしまった・~しまう |
連用形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、282語と、およそ言われている半分程度だしかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| [ゑぐ] |
池や沢に群生する
高さ40~60センチ、塊茎は黒褐色、径6~10ミリ、食用となる
「おおくろぐわい」の塊茎は大形で径2~4センチになるらしい
澱粉を含み甘味がある
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕によると、
「わざわざ採集するほどのものではないが、春水田を鋤起こす時にあらわれるのを、少年少女が拾い集めることが、私の幼時にも経験した」と著書は書いている
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕の「注」では、
あくが強い意の形容詞「エグシ」の語幹に、その名が由来した、とする
|
| |
|
 |
| 【歌意1844】 |
梅の枝を、鳴きながら飛び、移ってゆくうぐいす
その羽に、白妙のような真っ白な沫雪が降り落ちている
|
「しろたへの」は枕詞で「雪」にかかるが、
この歌では、「しろたへに」であり「枕詞」としてではなく
「白栲」のその「白さ」をも詠っている
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕によると、
「梅・うぐいす・白雪の取り合わせは、六朝、初唐詩の影響」と評しているが
この組み合わせ自体は、「春を詠」う『万葉集』でも、それほど珍しくないはずだ
それでも、この歌の評価が高いのは、
きっとその「うぐひすのはね」に降る「沫雪」の情景だろう、と思う
私自身は、鳥が雪を纏いながら飛ぶ姿は見たこともないが
仮に、その光景に出合ったら、おそらく魅入ってしまうことだろう
確かに、惹き付けられる「美しさ」があると思う
うぐいすが、降り付く雪を、その飛翔で落としながらも、梅が枝に飛び渡る
「はるつげどり」とも言われるこの鳥の、「雪と戯れる優雅さ」に
一度は遭遇したい
そんな「望み」を抱かせてくれる歌だと思う
それほど、叶うことが難しい情景なのだろうと思うのだが、
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕が言う、
「作者は事象を云ってゐる如くであるが、実は美観を云はうとしてゐるもので、その為に相当な無理をしてゐるのである」の評は、まさに、逆説的にこの歌の「美しさ」を言うものだ
それに、作者には、この情景が「心」で見えているのかもしれず
だからこそ、詠じることも可能だと思う
「美観を言うのではなく」、「梅、うぐいす、そして沫雪」を目の前にしたとき
作者には、このような光景が自身の心に投影されたのかもしれない
明日香の村を歩くと、あちこちでうぐいすの鳴き声が聞こえる
ただ、残念ながら雪の明日香にはまだ出合っていないが
どこかの山間の人里で...きっとこの光景に出逢える、と思いたい
|
| |
|
掲載日:2013.12.20.
| 春雑歌 詠鳥(詠雪) |
| 梅枝尓 鳴而移徙 鴬之 翼白妙尓 沫雪曽落 |
| 梅が枝に鳴きて移ろふ鴬の羽白妙に沫雪ぞ降る |
| うめがえに なきてうつろふ うぐひすの はねしろたへに あわゆきぞふる |
| 巻第十 1844 春雑歌 詠鳥(詠雪) 作者不詳 |
〔青は「注記」及び「古語辞典」関係へ、尚注記以外は新しいウィンドウで開く〕
| 【1844】語義 |
意味・活用・接続 |
| うめがえに[梅枝尓] |
| なきてうつろふ[鳴而移徙] |
| て[接続助詞] |
[並立]~て・~ながら・~つつ |
連用形につく |
| うつろふ[移ろふ] |
[自ハ四・連体形]移動する・場所を変える |
| うぐひすの[鴬之] |
| はねしろたへに[翼白妙尓] |
| しろたへ[白栲・白妙] |
こうぞ(木の名)の繊維で作った白い布・白いこと・白い色 |
| に[格助詞] |
[状態・比況]~のように〔接続〕体言、活用語の連体形につく |
| あわゆきぞふる[沫雪曽落] |
| あわゆき[泡雪・沫雪] |
泡のように消えやすい雪 |
| ぞ[係助詞] |
[強調](文中の場合は、他の何物でもなく、まさに「そのもの」という意味の強調) 係り結びの「係り」、体言などにつく |
| ふる[降る](「結び」) |
[自ラ四・連体形]雨や雪などが降る・比喩的に涙が流れ落ちる |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、282語と、およそ言われている半分程度だしかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| [うつろふ] |
この語の原義は、「移り続ける・変わってゆく」だが、他に次の用い方がされている
| ①移動する・場所を変える |
| ②色が変わる・色づく・色や香りが染まる |
| ③色がさめ続ける・色が褪せる・衰える |
| ④(花などが)散る |
| ⑤時が過ぎ行く |
| ⑥心が他の方へ移る・心変わりする |
この語の原義は、①だが、②・③がよく使われる
自動詞ラ行四段「うつる」の未然形「うつら」に、
動作の反復・継続を表す上代の助動詞「ふ」のついた「うつらふ」が転じたもの
この歌では、「①」の用法になる
|
| |
| [あわゆき] |
この「あわゆき(泡雪・沫雪)」は、「あはゆき(淡雪)」とは違う
「泡雪・沫雪」は、その字義のように、泡のように消えやすい「雪」のことだが
「淡雪」は、春先などに降る、消えやすい雪、と古語辞典にあり
その違いを思い浮かべると、確かに違う
「泡雪・沫雪」は、「物質的な雪」であり、
「淡雪」は、「心象的な雪」だと思う
|
| |
|
|
| 【歌意1847】 |
旧年の暮れが、昨日だというのに
はるかすみが、もう春日の山に早くも立ってきたではないか...
|
この歌、『古今和歌集』の「春歌上・1」を思い起こさせる
| ふるとしに春たちける日よめる |
| 年の内に春はきにけり ひととせをこぞとやいはん ことしとやいはん |
| 古今和歌集 巻第一 1 春歌上 在原元方 |
同じ年のうちに、春はきてしまった
この一年を、去年と言えばいいのか、今年と言えばいいのか... |
この歌、もう十年も前に触れた歌だが、第一番歌ということもあって、よく覚えている
暮れも押迫った年内に「立春」が来ることなんて、知りもしなかった
しかし、今思うと、何だか理解できないところもある
そもそも「立春」というのは、新年になってからではないのだろうか
そう思うと、「暦」の歴史に疎い私には、また知りたい欲求が沸き起こってくる
「立春」という言葉ではなく、暦上では、まだ冬なのに...つまり年内なのに
霞が立つような日々になった、ということなのだろうか
そうであれば、実際の季節感とのズレも理解できるのだが...
掲題歌にしても、こうした暦上の季節と実際の季節感を詠うとというのは
それが、珍しいこと、ということなのだろうか
当たり前のことなら、何も感慨深く詠うこともない
何だか今年はおかしな「暦」の「いたずら」があるものだなあ、という感じの歌だ
明確に季節を切り割ることなどできはしないから、どうしても人はそれぞれの季節感に負う
だから、もう春になったよ、というものがいれば、いやまだ冬だ、と言い返すものもいる
ほら、暦を見てみろ、「春だろう」と言えば
ほら、あの山を見てみろ、まだ霞も立たず、雪もあんなに積もっているぞ、と
案外、そんな遣り取りをしながら、季節の移ろいを知っていくのもいいかもしれない
むしろ、今の私なら、その方が好きになりそうだ
「詠歌」も「詠霞」も、こうした季節の変わり目に
その「惑う」情感を詠っているものが多いような気もする
『万葉集』全体の季節を詠う歌がそうだと言わないが
歌として、作者以上に、それを読み受ける者の立場で感じるのは
まさに、そうした「うつろひ惑ふ」心の、感嘆なのだろう、と思う
「春は春」ではなく「春だというが、俺は冬だと思う」と、「季節の緩さ」を詠うのが好きだ |
| |
 |
掲載日:2013.12.21.
| 春雑歌 詠霞 |
| 昨日社 年者極之賀 春霞 春日山尓 速立尓来 |
| 昨日こそ年は果てしか春霞春日の山に早立ちにけり |
| きのふこそ としははてしか はるかすみ かすがのやまに はやたちにけり |
| 巻第十 1847 春雑歌 詠霞 作者不詳 |
【注記】〔410〕
〔青は「注記」及び「古語辞典」関係へ、尚注記以外は新しいウィンドウで開く〕
| 【1847】語義 |
意味・活用・接続 |
| きのふこそ[昨日社] |
| こそ[係助詞] |
[強調]~こそ 〔係り結びの「係り」で、「結び」は已然形〕 |
| 〔接続〕殆どの品詞につく |
| としははてしか[年者極之賀][「しか」は、助動詞「き」の已然形で係り結びの「結び] |
| はて[果つ] |
[補助動詞タ下二・連用形]「~終る・すっかり~きる」 |
| しか[助動詞・き] |
[過去・已然形]~た・~ていた |
連用形につく |
| はるかすみ[春霞] 春の霞 〔この場合、枕詞の「はるがすみ」とは違う〕 |
| かすがのやまに[春日山尓]奈良市東方、春日大社の奥の山 |
| はやたちにけり[速立尓来] |
| はや[早] |
[副詞]早くも・すでに |
| たち[立つ] |
[自タ四・連用形](風・波・雲・霧・霞・煙などが)生じる |
| に[助動詞・ぬ] |
[完了・連用形]~てしまう・~てしまった |
連用形につく |
| けり[助動詞・けり] |
[過去・終止形]~たのだ・~たなあ |
連用形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、282語と、およそ言われている半分程度だしかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| [はつ] |
自動詞タ行下二段「果(は)つ」[終りになる・終る・死ぬ]の意だが、
動詞の連用形に続く場合には「補助動詞」の働きになる
| 例 語 |
意 味 |
| 明かし果つ |
明け方まで寝ないでいる |
| 散(あ)れ果つ |
まったく離れてしまう |
| 否(いな)び果つ |
ことわりきる |
| 言ひ果つ |
終りまで言いつくす・言い切る |
| 移り果つ |
すっかり変化しきってしまう |
| 恨み果つ |
徹底的に恨む・恨み切る |
| 書き果つ |
書き終える |
| 枯れ果つ |
残らずすっかり枯れる |
| 離(か)れ果つ |
すっかり遠ざかる・縁が切れる |
| 消え果つ |
すっかり消えてなくなる・息が途絶える・関係がすっかり絶える |
| 聞き果つ |
最後まで聞く |
| 暮れ果つ |
日がすっかり暮れる・(季節・年が)押しつまる |
| 忍び果つ |
感情を抑えて秘密にしとおす・こらえきる |
| 住み果つ |
いつまでも住み続ける・夫婦が共に住み続ける・添い遂げる |
| 背(そむ)き果つ |
すっかり俗世間を離れる・出家してしまう |
| 絶え果つ |
すっかり絶えてしまう・息が絶えてしまう・死ぬ |
| 散り果つ |
すっかり散る・散り終わる |
| 成り果つ |
完了する・終る・済む・完全に~となる・変わり果てる |
| 乗り果つ |
車などに乗ってしまう |
| 隔(へだ)て果つ |
すっかり隔てる・すっかり遠ざかる |
| 侘び果つ |
すっかり思い悩む・ふさぎこむ |
|
| |
| [はるかすみ] |
枕詞「はるがすみ」もあるが、この歌の場合は、
結句に「はやたちにけり」とあり、その主語となるのが「はるがすみ」なので
枕詞ではなく、実景描写で解釈できるはずだ
もっとも、枕詞としてもかかる「春日」も、しっかりと使われている
このような例は、いくつかあるようで
| 譬喩歌/大伴宿祢駿河麻呂娉同坂上家之二嬢歌一首 |
| 春霞 春日里之 殖子水葱 苗有跡云師 柄者指尓家牟 |
| 春霞春日の里の植ゑ子水葱苗なりと言ひし枝はさしにけむ |
| はるかすみ かすがのさとの うゑこなぎ なへなりといひし えはさしにけむ |
| 巻第三 410 譬喩歌 大伴宿祢駿河麻呂 |
〔語義〕
「かすがのさと」、地名「春日の里」とも解せるが、単に「春の日」として、
枕詞「はるかすみ」に「かすが」をかけたと言われている
どちらとも解せるこうした語句は、そのまま訳す注釈書もあるし、無訳のものもある「こなぎ」は、食用に栽培してある「こなぎ」
なぎ、ともいい、「みずあおい科」の一年草
「みずなぎ」は、京中の溝や低湿地に芹、蓮などとともに植えられた野菜
羹や漬物にしたりして食された
「さし」は、自動詞サ行四段「指す」の連用形で、「草木が萌え出る・芽が出る」
「瑞枝(みづえ)さし繁(しじ)に生いたる栂の木」(瑞々しい枝が萌え出て、ぎっしりと生え伸びた栂の木)のように使われる
「けむ」は、過去の動作・状態を推量する助動詞「けむ」の終止形 |
〔歌意〕
春霞のたなびく、かすがの里の、植えてある水葱は、
まだ苗だと仰っていましたが
もうその枝も伸びたことでしょうね
〔大伴坂上郎女の二女、大嬢の妹に駿河麻呂が求婚し、かつてはまだ苗のように幼いといわれたものを、もう立派に成長したのでしょう、と母・坂上郎女に宛てた歌〕 |
この用例歌の「はるがすみ」は、それが働く語句もなく、
「春日の里」を導く枕詞には違いないが、私には「はるがすみ」そのもので
「はるがすみたつ」とか「はるがすみたなびく」のような意味合いもあると思うので
枕詞をやたらと訳さなくてもいい、ということではなく
歌意に言葉を補って、訳しても不自然でないものは、そうした方がいいと思う
|
| |
| [はや] |
副詞として、「早くも・すでに・早く・しみやかに」とともに
多く助動詞「けり」を文末に伴って、「実は・ほかでもない」の意もある |
| |
|
|
| 【歌意1848】 |
寒い冬が過ぎ去り、暖かな春がやっと来たようだ
朝日のさしている春日山に、かすみがたなびいているのだから... |
結句で「~だから」と読むことはないのだが
第二句までの推量の根拠が、結句にあるのなら
どうしてもそう読んでしまう
あまりにも、拙劣な訳し方になったが、
ことばにせず、自分で呟くとすれば、自身への説明めいた気持ちもあるはずだ、と思った
当時の「春」は、実際の季節感としては、まだまだ「寒い」環境だとおもうのに
こうして歌では、「暖かい春」として詠われる
現代の太陽暦でも、その季節感のズレは当たり前のようにあるのだが
この当時でも、幾つかの歌で感じるように、そのズレはあった
春なのに、まだ雪が降るのか、などと詠めば、
まさにそのズレに感じ入ったものだろうし
草木の茂る詠歌や、桜などの春が登場すれば、まさに「春の謳歌」だろう
しかし、「梅、鶯、雪」というのが、何とも言えずに、季節の「曖昧さ」を
逆に「心の温かさ」として響かせてくれる
冬が過ぎた、と断言してしまえば、もう春には違いないのだが
こうした季節感よりも、降る雪を羽に纏いながら、梅の枝を飛び渡る「うぐひす」
私には、そのような歌が、一層こころに残る
この歌のように、漢語を使って季節を詠めば...その想い描く情景は狭い
やはり、詠む歌といえども、視覚的に印象付けられるのは、『万葉集』に限らず
「歌の宿命」なのだろう
しかし、『万葉集』ほどではないはずだ
以降の歌集には、詠うことばが、そのまま表記されるのだから... |
| |


|
掲載日:2013.12.22.
| 春雑歌 詠霞 |
| 寒過 暖来良思 朝烏指 滓鹿能山尓 霞軽引 |
| 冬過ぎて春来るらし朝日さす春日の山に霞たなびく |
| ふゆすぎて はるきたるらし あさひさす かすがのやまに かすみたなびく |
| 巻第十 1848 春雑歌 詠霞 作者不詳 |
【注記】〔1888・2172〕
〔青は「注記」及び「古語辞典」関係へ、尚注記以外は新しいウィンドウで開く〕
| 【1848】語義 |
意味・活用・接続 |
| ふゆすぎて[寒過] |
| すぎ[過ぐ] |
[自ガ上二・連用形]時が過ぎる・経過する |
| て[接続助詞] |
[単純接続]~て・そして |
連用形につく |
| はるきたるらし[暖来良思] |
| き[来(く)] |
[自カ変・連用形]来る・行く・通う |
| たる[助動詞・たり] |
[完了・連体形]~た・~ている |
連用形につく |
| らし[助動詞・らし] |
[推量・終止形]~にちがいない・~らしい |
| 〔接続〕終止形に付くが、ラ変には「連体形」につく (「たり」はラ変活用型) |
| あさひさす[朝烏指] 朝日のさす |
| かすがのやまに[滓鹿能山尓]奈良市東方、春日大社の奥の山 |
| かすみたなびく[霞軽引]かすみが、たなびいている |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、282語と、およそ言われている半分程度だしかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| [ふゆすぎて はるきたる] |
原文「寒過暖来」の表記は、『万葉集』中でも珍しく、
この歌を含めて二首しかない
| 春雑歌歎舊 |
| 寒過 暖来者 年月者 雖新有 人者舊去 |
| 冬過ぎて春し来れば年月は新たなれども人は古りゆく |
| ふゆすぎて はるしきたれば としつきは あらたなれども ひとはふりゆく |
| 巻第十 1888 春雑歌 詠旧 作者不詳 |
〔語義〕
「はるし」の「し」は、強意の副助詞で、語調を整える
格助詞「の」として、主語を表す注釈書も多い
「きたれば」の「たれ」は、掲題歌の完了の助動詞「たり」と同じで已然形
それに接続助詞「ば」がついて、「順接の確定条件・恒常条件」になる
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕では、「きたる」とし
「来至(きいた)る」の「約音」とし、「来(く)」よりも、到着の意が強い、とする
|
〔歌意〕
冬が過ぎ、そして春がくると、やはりまた
年月は新しくなるのだが...人は老いてゆくばかりだ |
このように、「寒い=冬」、「暖かい=春」として、
漢字の意から表現する「義訓的用字」を使った背景には、
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕にも解説されており
「文選呉都賦の『露往霜来』に『呂延済曰。露秋也。霜冬也』と注がある」と記している
小島憲之『上代日本文学と中国文学』中も、
唐楊烱の「幽蘭賦」・駱賓王の「答員半于書」の例を加え示して、
「その表記者の頭の中には」「『露往霜来』の表現が思ひ浮べられたのではなかろうか」
と、する
なるほど、そこまで「教養」優れた人物であるのなら、
この二首は同じ作者である可能性が高いとは思うが、
「作者不詳歌」は、それ自体で、いわくのある歌なので、野暮な詮索はするな
ということなのかもしれない
しかし、当時の知識人の中でも、この唐の賦を意識して詠ったのが、
この二首しかないのであれば...自ずと「名乗って」いるようなものだ
同じ用法で、「秋」も一首ほどあった
| 秋雑歌詠露 |
| 冷芽子丹 置白霧 朝々 珠年曽見流 置白霧 |
| 秋萩に置ける白露朝な朝な玉としぞ見る置ける白露 |
| あきはぎに おけるしらつゆ あさなさな たまとしぞみる おけるしらつゆ |
| 巻第十 2172 秋雑歌 詠露 作者不詳 |
〔語義〕
「おける」は、自動詞カ行四段「置く」の已然形「おけ」に、
完了の助動詞「り」の連体形「る」がついたもの
「おく」の意味は、霜や露が降りることをいう
「あさなさな」は、朝ごとに、の意
「たまと」の「と」は、格助詞で、~と思っての意
「しぞ」は、強意の副助詞「し」と係助詞「ぞ」で、係り結びの「係り」
「みる」が他動詞マ行上一段「見る」の連体形で係り結びの「結び」
結句に、第二句を繰り返すのは、歌謡に多い形式
|
〔歌意〕
秋萩に降りかかる白露
朝ごとに、玉と思って私は見ている
この萩の枝にかかる白露を... |
「冷たい=秋」として、ここでも漢籍の影響が見られるが
冷たいことと、秋というのは、少し似合わないように思うが
これも、現代的な感覚から判断してはいけないのだろう
「露」という「秋」にもっぱら詠われる歌であれば、
それに「萩」も詠まれてる以上...やはり「秋」なのだろう
調子に乗って、「夏」はどうだろう、と調べてみたが
夏については、こうした「義訓的用字」は見られなかった |
| |
| [あさひさす] |
原文「朝烏」を、「朝日」と訓むのは、やはり気にはなっていたが
太陽の中に三本足の烏がいるとする中国の伝説からくるようだ
「准南子」精神訓に「日中有踆烏」が、
芸文類聚所引「五経通義」に、「日中有三足烏」ともあることが、言われている
文選蜀都賦には、「陽烏」の例があり、
『懐風藻』の大津皇子の臨終の詩にも「金烏」の語があり、
いずれも「太陽」を称している
|
| |
|
|
| 【歌意1849】 |
うぐひすのさえずりが聞こえてくる、春になったらしい
春日山に、ほら、かすみがたなびいている
夜だというのに、夜目にもはっきりと... |
朝や夕方にたなびく「かすみ」
万葉の初期の頃は、「かすみ」は春の「季語」として使われておらず
七夕歌にも、その例は見える
次第に、春の遠くにたなびくのを「かすみ」といい、
近くに立ちこめるのを「きり」というようになった、とある
この歌のように、「かすみ」で春を知るのは、そうした情感が定着した頃だと解る
この歌に触れるまで、「かすみ」が夜にたなびくとは思いもしなかった
いや、正確に言えば、考えたこともなかった
しかし、「夜目にも」と詠われたことで、ふと「夜にかすみ」が、と...
勿論、見通しの利かない「夜」
その「夜」でも、「かすみ」の気配が感じられる、ということで
「かすみ」の存在を際立たせている
夕方にたなびく「かすみ」...
実際に見えるのかもしれない
現代と違って、日が沈むと、街の灯かりに邪魔されることなく
夜空の透明感のある「闇」と、山という物体の「闇に浮ぶ影」は、
おそらく、考えられないほど、くっきりと見えるものだ、と思う
それに、月明かりや、星明りがあれば...万葉時代の「夜」は
決して「漆黒の闇」ではなかったはずだ
夜行性の動物が、暗がりでも見えるように
「夜目」は、人に於いても、絶望的な暗さではなかったものだと、思う
夜空のもとで、山のシルエットを見る
きっと、ところどころに「山の影」と、それが「かすむ」ところがあるのだろう
山の稜線が途切れたり、また現れたり...
それでも、「かすみがたなびいている」気配だと感じることができる
作者は、じっとそこに見入って、春になった、と確信し、
そばに誰もいないだろうに、思わず「ほら」と言ったような気もする
つい、そんな「ことば」を入れてしまいたくなるほど、嬉しかったのだろう
いきなり目の前に現れる季節ではなく
ぼーっと立ち湧き上がる「ほのぼの」とした、そして「逍遥感」が浮んでくる |
| |
 |
掲載日:2013.12.23.
| 春雑歌 詠霞 |
| 鴬之 春成良思 春日山 霞棚引 夜目見侶 |
| 鴬の春になるらし春日山霞たなびく夜目に見れども |
| うぐひすの はるになるらし かすがやま かすみたなびく よめにみれども |
| 巻第十 1849 春雑歌 詠霞 作者不詳 |
【注記】〔1051〕
〔青は「注記」及び「古語辞典」関係へ、尚注記以外は新しいウィンドウで開く〕
| 【1849】語義 |
意味・活用・接続 |
| うぐひすの[鴬之 ]〔「春」にかかる枕詞的用法〕 |
| はるになるらし[春成良思] |
| なる[成る] |
[自ラ四・終止形](それまでとは違ったもの・状態に)なる |
| らし[助動詞・らし] |
[推量・終止形]~にちがいない・~らしい |
終止形に付く |
| かすがやま[春日山]奈良市東方、春日大社の奥の山 |
| かすみたなびく[霞棚引]かすみが、たなびいている |
| よめにみれども[夜目見侶] |
| よめ[夜目] |
夜、暗い中で物を見ること、また夜、物を見る目 |
| ども[接続助詞] |
[逆接の確定条件]~けれども・~のに・~だが |
已然形に付く |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、282語と、およそ言われている半分程度だしかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| [うぐひすの] |
その季節の代表的な景物をとって、「枕詞」にした、という解説もあるが
「うぐひす」が、実際に「春の代表的な景物」であるにしても、
枕詞として「うぐひすの春」という用例は、この歌以外には見つからなかった
同じように僅か一例であっても、枕詞的用法(あるいは「枕詞」)と言われている歌がある
「陽炎(かげろふ)」の意である、
「春の晴れた日に地上から水蒸気などがゆらゆらと立ち昇る現象」から、
「かげろふ」の転で、「かぎろひ」が枕詞「かぎろひの」として、それに当る
| 雑歌/悲寧樂故郷作歌一首[并短歌] |
| 八隅知之 吾大王乃 高敷為 日本國者 皇祖乃 神之御代自 敷座流 國尓之有者 阿礼将座 御子之嗣継 天下 所知座跡 八百萬 千年矣兼而 定家牟
平城京師者 炎乃 春尓之成者 春日山 御笠之野邊尓 櫻花 木晩牢 皃鳥者 間無數鳴 露霜乃 秋去来者 射駒山 飛火賀タケ丹 芽乃枝乎 石辛見散之 狭男壮鹿者 妻呼令動
山見者 山裳見皃石 里見者 里裳住吉 物負之 八十伴緒乃 打經而 思煎敷者 天地乃 依會限 萬世丹 榮将徃迹 思煎石 大宮尚矣 恃有之 名良乃京矣
新世乃 事尓之有者 皇之 引乃真尓真荷 春花乃 遷日易 村鳥乃 旦立徃者 刺竹之 大宮人能 踏平之 通之道者 馬裳不行 人裳徃莫者 荒尓異類香聞 |
| やすみしし 我が大君の 高敷かす 大和の国は すめろきの 神の御代より 敷きませる 国にしあれば 生れまさむ 御子の継ぎ継ぎ 天の下 知らしまさむと
八百万 千年を兼ねて 定めけむ 奈良の都は かぎろひの 春にしなれば 春日山 御笠の野辺に 桜花 木の暗隠り 貌鳥は 間なくしば鳴く 露霜の 秋さり来れば 生駒山 飛火が岳に 萩の枝を しがらみ散らし
さを鹿は 妻呼び響む 山見れば 山も見が欲し 里見れば 里も住みよし もののふの 八十伴の男の うちはへて 思へりしくは 天地の 寄り合ひの極み
万代に 栄えゆかむと 思へりし 大宮すらを 頼めりし 奈良の都を 新代の ことにしあれば 大君の 引きのまにまに 春花の うつろひ変り 群鳥の
朝立ち行けば さす竹の 大宮人の 踏み平し 通ひし道は 馬も行かず 人も行かねば 荒れにけるかも |
| やすみしし わがおほきみの たかしかす やまとのくには すめろきの かみのみよより しきませる くににしあれば あれまさむ みこのつぎつぎ あめのした しらしまさむと やほよろづ ちとせをかねて さだめけむ ならのみやこは かぎろひの はるにしなれば かすがやま みかさののへに さくらばな このくれがくり かほどりは まなくしばなく つゆしもの あきさりくれば いこまやま とぶひがたけに はぎのえを しがらみちらし さをしかは つまよびとよむ やまみれば やまもみがほし さとみれば さともすみよし もののふの やそとものをの うちはへて おもへりしくは あめつちの よりあひのきはみ よろづよに さかえゆかむと おもへりし おほみやすらを たのめりし ならのみやこを あらたよの ことにしあれば おほきみの ひきのまにまに はるはなの うつろひかはり むらとりの あさだちゆけば さすたけの おほみやひとの ふみならし かよひしみちは うまもゆかず ひともゆかねば あれにけるかも |
(右廿一首田邊福麻呂之歌集中出也)
[この歌から巻第六末の1071まで、田辺史福麻呂歌集出] |
| 巻第六 1051 雑歌 田辺史福麻呂歌集 |
| 〔歌意〕[『新編日本古典文学全集万葉集』〔小学館、平成8年成〕より] |
| (やすみしし) わが大君の 君臨される 大和の国は 神武の 帝の御代以来 都してこられた 国であるので お生まれになる 日の御子が代々 ここで天下を お治めになるだろうと 限りない 未来まで見通して 都をお定めになったという 奈良の都は (かぎろひの) 春ともなると 春日山や 三笠の野辺に 桜花の 木陰に隠れて かお鳥は 絶え間なく鳴き (露霜の) 秋ともなれば 生駒山や 飛火が岡に 萩の枝を 踏みしだいて散らし 雄鹿は 妻を声高く呼び立てる 山を見ると 山も見飽きず 里を見ると 里も住みよい もろもろの官人たちが 末永く 思ったことは 天地の 寄り合う限り 永久に 栄えて行くだろうと 思っていた 宮殿なのに 頼りにしていた 奈良の都を 新しい時代の 事であるから 大君の 仰せに従い (春花の) 移り変わって (群鳥の) 朝出て行ったので (さす竹の) 大宮人が 踏みならし 通った道は 今は馬も行かず 人も通らないので 荒れてしまったことだ |
ここの「注記」枕詞とは関係ないが、この歌について補足すると
奈良時代には、一時期、都を寧楽から久邇に遷したことがあった
この歌は、その時の、寧楽京に対する「想い」を詠ったものだが
この歌の直後〔この長歌に併せた反歌二首の後の、長歌1054〕では、
その新京である、久邇京讃歌を詠ってる
歌の出典が「田辺福麻呂歌集」とあり、通説では本人の詠歌集だといわれているので
田辺福麻呂自身が、寧楽京への未練めいた歌を詠い、また新京への讃歌とは...
しかし、ある意味では、こうした想いもまた自由に詠えたということであれば
奈良時代の雰囲気も少しは感じられる
「春」にかかる枕詞で、代表的なものは「ふゆごもり(冬隠り)」とされ、九例ある |
| |
|
|
| 【歌意1850】 |
冬の間、霜に打たれ霜枯れしていた柳も
こうして見ている人たちが、鬘にできるほどに
盛んに芽吹き始めたことだ |
「しもがれ」...動詞の霜枯れは、おそらくよく使われるだろうが
『万葉集』中での「しもがれ」は、初めて目にした
語感もいい、それに、冬の間霜に草木が打ち枯れる、という「雪」を使わなくても
その荒涼とした「冬の厳しさ」が伝わってくる
むしろ、「雪」よりも、肌寒さを感じてしまう
「しもがれ」は、『万葉集』中に、この一首しかなかった
通常、「柳」を「萌え出る春の柳」のように詠うらしいが
「霜枯れの冬の柳」というのは、ちょっと意表を突くような詠い方だ、と思う
実際に、柳の「芽や花」が、冬に見られるのではなく
あくまでも、冬の間は「霜枯れ」していた「春芽の出る柳」
そこに、「柳」の堪え忍ぶ強靭な生命力さえも感じてしまう
私にとって、その「柳の力強さ」のよく理解できる歌がある
| 東歌相聞 |
| 楊奈疑許曽 伎礼波伴要須礼 余能比等乃 古非尓思奈武乎 伊可尓世余等曽 |
| 楊こそ伐れば生えすれ世の人の恋に死なむをいかにせよとぞ |
| やなぎこそ きればはえすれ よのひとの こひにしなむを いかにせよとぞ |
| 巻第十四 3511 東歌相聞 作者不詳 |
〔語義〕
「やなぎこそ」は、柳なら・柳こそは
「きればはえすれ」は、伐ればまた生えもするが・伐ればまた生えてもこよう
「はえすれ」は、下二段「生(は)ゆ」の連用名詞形に、サ変動詞「す」がつき、
それが複合動詞「はえす」になったもの
「はえすれ」はその已然形
「こいにしなむを」の「を」は、「逆接の接続助詞」で、~のに
「いかにせよとぞ」の次に「言ふ」が省かれている |
〔歌意〕
楊の木なら、伐ればまた生えもするでしょう
生身のこの私が、恋の苦しさに死のうとしているのに
いったいあなたはどうせよと、いうのでしょうか |
楊の木は、いくら伐ってもすぐまた生える
しかし、生身の人間である私は、死んだた二度と再び生き返ることはない
その「生身の人間」が、死ぬほどの恋をしているのに...
相手からは、何も報いのない片恋の「孤悲」なのだろう
この語調の激しさに、「やなぎ」が比喩的に出されるのは
単に再生する「木」、というだけではなく
「やなぎ」の強靭な生命力もまた表現されている
その強靭な生命力の「やなぎ」を「春の歌」に添えるのも
初句、第二句で「霜枯れの冬の柳」を思い浮かべたところから始まって
芽吹き、そしてそれを鬘にしようと、人が見ている情景...
単に、春がやって来た、という説明的な歌ではなく
時が流れる映像のような、感じがする歌だ
ちなみに、「やなぎ」の仲間には、挿木が容易で、
切り取った枝を、そのまま挿しただけで、発根し生長するという
確かに力強い木なのだと思う
|
| |
 |
掲載日:2013.12.24.
| 春雑歌 詠柳 |
| 霜干 冬柳者 見人之 蘰可為 目生来鴨 |
| 霜枯れの冬の柳は見る人のかづらにすべく萌えにけるかも |
| しもがれの ふゆのやなぎは みるひとの かづらにすべく もえにけるかも |
| 巻第十 1850 春雑歌 詠柳 作者不詳 |
【注記】〔1852〕〔4313・4160〕【左頁】〔3511〕
〔青は「注記」及び「古語辞典」関係へ、尚注記以外は新しいウィンドウで開く〕
| 【1850】語義 |
意味・活用・接続 |
| しもがれの[霜干 ] |
| しもがれ[霜枯る] |
[自ラ下二・連用形]霜に打たれて草木が枯れる |
| の[格助詞] |
[連体修飾語]~の 〔接続〕体言、及び準ずる語につく |
| ふゆのやなぎは[冬柳者] |
| やなぎ[柳] |
[木の名]枝垂れ柳 |
| みるひとの[見人之] 見ている人が |
| かづらにすべく[蘰可為] |
| かづら[鬘] |
①上代、つる草や草木の枝だ・花などを髪に巻きつけて飾りとしたものかづら ②(女性が)別の髪の毛を束ねて作り、髪が少ないときや短い時、自分の髪の毛に添えるもの・かもじ |
| す[為(す)] |
[他サ変・終止形]ある動作を行う・ある行為をする |
| べく[助動詞・べし] |
[可能推量・連用形]~ことができそうだ |
終止形に付く |
| もえにけるかも[目生来鴨] |
| もえ[萌ゆ] |
[自ヤ下二・連用形]草木などの芽が出る・芽ぐむ |
| に[助動詞・ぬ] |
[完了・連用形]~てしまう・~てしまった |
連用形に付く |
| ける[助動詞・けり] |
[過去・連体形]~たのだ・~たなあ |
連用形に付く |
| かも[終助詞] |
[詠嘆・感動]~であることよ |
連体形に付く |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、282語と、およそ言われている半分程度だしかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| [しもがれの ふゆのやなぎ] |
歌論書としては、現存最古の『歌経標式』〔藤原濱成(742~790)藤原京家、麻呂の子〕に「霜枯れのしだり柳の」とあり、この時代にも「柳」と「楊」の区別があった
「柳」の字を当てるのは、一般に「枝垂れ柳」のことで
「楊」を当てるのが、「猫柳、川柳」とされている
「枝垂れ」る「枝垂れ柳」とは違って、「猫柳、川柳」は枝が上に向って伸びる
この掲題歌の「柳」は、「枝垂れ柳」だが、
この「詠柳八首」でも「楊」は、「柳」と表記が使い分けて詠われている
その一首を載せる
| 春雑歌詠柳 |
| 山際尓 雪者零管 然為我二 此河楊波 毛延尓家留可聞 |
| 山の際に雪は降りつつしかすがにこの川楊は萌えにけるかも |
| やまのまに ゆきはふりつつ しかすがに このかはやぎは もえにけるかも |
| 既出〔万葉の植物Ⅱ〕巻第十 1852 春雑歌 詠柳 作者不詳 |
〔歌意〕
山間には、なおも雪が降り続いている
しかしそうは言っても、平地では、もう季節は春
この川柳も、芽吹いているではないか |
「早春の雪」と合わせての「楊」の歌
掲題歌〔1850〕のように、冬の間、霜にあたって枯れていた「やなぎ」が
春の訪れと共に、元気よく芽吹いてきた
「冬の間、よく頑張ったな」とでもいうように、
「山間の雪」を眺めながら、「やなぎ」の生命力を詠っているように思う |
| |
| [かづら] |
「柳の鬘」は、葉のついたままの柳の枝をたわめて、髪飾りにしたもの
三月の節句に用いた
この行為は、本来植物の生命力を身に付着させるための呪的行為だったが、
万葉の時代では、すでに髪飾りになり、風流な行為ともされた
それでも、なお「呪的行為」を認識していた歌として、
大伴家持の詠歌二首を載せる
| 二月十九日於左大臣橘家宴見攀折柳條歌一首 |
| 青柳乃 保都枝与治等理 可豆良久波 君之屋戸尓之 千年保久等曽 |
| 青柳の上枝攀ぢ取りかづらくは君が宿にし千年寿くとぞ |
| あをやぎの ほつえよぢとり かづらくは きみがやどにし ちとせほくとぞ |
| 巻第十九 4313 宴席歌 大伴宿禰家持 |
〔語義〕
「かづらく」は、他動詞カ行四段「かづらく」で、つる草や草木の枝・花を鬘(髪飾りとして)つける、その連体形で、攀ぢ取った「柳の枝」が省略されていると思う
「ほく(祝く・寿く)」は、祝福する、祝う、でその連体形
|
〔歌意〕
青柳の梢を折り取り、鬘にするのは、
わが君の家に、千代の寿を祝うためなのです
|
| |
| 天平勝寶二年正月二日於國廳給饗諸郡司等宴歌一首 |
| 安之比奇能 夜麻能許奴礼能 保与等理天 可射之都良久波 知等世保久等曽 |
| あしひきの山の木末のほよ取りてかざしつらくは千年寿くとぞ |
| あしひきの やまのこぬれの ほよとりて かざしつらくは ちとせほくとぞ |
| 右一首守大伴宿祢家持 |
| 巻第十八 4160 宴席歌 大伴宿禰家持 |
〔語義〕
「ほよ」は、樹木に寄生する植物、「寄生木(やどりぎ)」、常緑樹で尊重された
「かざしつらく」は、花や枝を装飾として冠にさす他動詞サ行四段「挿頭(かざ)す」、その連用形「かざし」に完了の助動詞「ぬ」の終止形「つ」
これらに、名詞化する働きのある接尾語「らく」(終止形につく)だと思う
「ちとせほくとぞ」は、上の〔4313〕歌と同じ
|
〔歌意〕
山の梢の「ほよ」を取って、髪に挿したのは
千年の寿を祈って、そうしたのですよ
|
これらの歌では、花や枝を髪飾りにすることが
はっきりと祝いや、願い事の行為であることを教えてくれる
また天平十九年(747年)五月五日の太上天皇(元正)詔に、
「昔、五月の節には常に菖蒲を用ゐて蘰せり。このごろすでに此の事を停めぬ。今より後、菖蒲の蘰に非ざる者を宮中に入るることなかれ」とある
この頃では、すでに「儀式」であっても、呪的要素は薄れていた、ということになる |
| |
| [もえ] |
この「萌え」は、草木が芽を出す意の、自動詞ヤ行下二段「萌ゆ」の連用形
原文「目生」は、芽(目)が生じる(出る)意の用字
「萌」の訓は、『名義抄』に「きざす・もゆ」とある |
| |
|
|
| 【歌意1851】 |
浅葱色に染め掛けたように思えるほどに、
あざやかな楊の花穂、
いままさに芽吹いているのだなあ |
これほど、懸命に「やなぎ」のことを知ろうとしたことは、かつてなかった
「やなぎ」と聞けば、間違いなく「枝垂れ柳」を思い浮かべ
それこそ、井戸の横に立っており、そこに...私の最も怖い「幽霊」の構図
そんな柳は、極端にしても
どこかで見かける「柳」もまた、風になびく「枝垂れ柳」くらいしか目には留まらない
しかし、ここで「やなぎ」を詠った万葉歌にいくつか触れ
同じ「やなぎ」という名が付く木なのに、その対象の違いによって
詠じた人の気持ちまで違って思えるのは、
確かに景観の違いでは感動も違ってくるものだ、と思う
正直、その作者が詠じた心に、忠実に歌意を探ろうとするのがすべてではなく
その作者が与えてくれた「ここのの景色」に、何を自分は感じることができるか...
それが、当初からの私の目標だった
だから、実際の詠じた作者の心の内までは理解できないのは、それが目標ではないから
しかし、その作者が提供してくれた「目の前の映像・心に響く心の映像」は
自分なりに全力で知りたいと思う
その上で、自分の響く感じ方を、素直に書き残したいものだ
ということは、私自身でさえ、時を変えればまた感じ方も違ってくる
それが、成長とか、より理解力が増した、というのではなく
「想い」というのが、往ったり来たり、揺れ動く心である以上
何年も同じ気持ちで、同じ歌を感じられることの方が、難しいものだ
十年以上も前に始めたこのサイトでの、私の「感じ方」には
まったく自力で解釈しようとする気概がなかった
通り一遍の、諸注の解釈を「これは助かる」と鵜呑みにし
その歌の中に、自分を放り込むだけの「想い」を綴っていた
だから、「柳」も「楊」も、何も戸惑うことなく、私には「やなぎ」だったものだ
過去の自分の「想い」は、それはそれで大事にしたい...だからそのまま残しているが
ときどき、どうしてこんな風に感じたのだろう、と思うこともある
しれが、そのときの私の「想い」だった、ということなのだが...照れ臭いこともある
浅葱色に萌え並ぶ「楊」を、作者と同じように眺めているとすれば
私は、どんな歌を詠むのだろう
「萌える春」を想うのか、あるいはその季節感ではなく
浅葱色に若葉の染まる「楊」に、もっと別の何かを想うのか...
そう言えば、ひさしくそんな風に「時に耽る」経験をしていない
目の前の景観から導かれるようにして...「何かを想う」、そんな経験を
本当に久しく味わっていない
それが、ふと寂しく思えてきた
「柳」の例歌として、「注記」で採り上げた〔1855〕歌
このような「しだれやなぎ」の繊細なその「形状」は、わりとすんなり心に沁み込む
風に揺れる様ひとつとっても、そこには詩情が芽生えるだろう
目に見えない「風」も、柳にはそれを揺らすことによって「目に映る」
そこから詩情も拡がる...果てしなく
しかし「川楊」の場合は、そこに独特な「尾状花穂」がある
それ自体が、すでに詩情の拡がりを妨げている...視覚が限定されてしまう
降り落ちる雪、とか
花穂をつつく鳥たち、とか...見えるもの同士の世界観だ
一度、川楊の水辺でも、散策したいものだ |
| |


|
掲載日:2013.12.25.
| 春雑歌 詠柳 |
| 淺緑 染懸有跡 見左右二 春楊者 目生来鴨 |
| 浅緑染め懸けたりと見るまでに春の楊は萌えにけるかも |
| あさみどり そめかけたりと みるまでに はるのやなぎは もえにけるかも |
| 巻第十 1851 春雑歌 詠柳 作者不詳 |
【注記】〔1855〕
〔青は「注記」及び「古語辞典」関係へ、尚注記以外は新しいウィンドウで開く〕
| 【1851】語義 |
意味・活用・接続 |
| あさみどり[淺緑 ] 薄い緑色・浅葱色 |
| みどり[緑・翠] |
新芽・若葉、またその色・緑色、青色などにも通じて用いられた |
| そめかけたりと[染懸有跡] |
| そめ[染む] |
[他マ下二・連用形]染める・思い込む・心を深く寄せる |
| かけ[掛く・懸く] |
[他カ下二・連用形]おおう・かぶせる |
| たり[助動詞・たり] |
[完了状態・終止形]~ている・~た |
連用形に付く |
| と[格助詞] |
[比喩]~のように・~と同じに 〔接続〕体言、準ずる語につく |
| みるまでに[見左右二] |
| までに |
〔程度・限度をはっきりと表す〕~くらいに・~ほどに・~までも |
| 〔接続〕体言、それに準ずる語、動詞・助動詞の連体形、副詞や助詞など種々の語に付く |
| 〔成立〕副助詞「までに、格助詞「に」 |
| はるのやなぎは[春楊者] |
| やなぎ[楊] |
この「楊」は、「かわやなぎ」(別名、ネコヤナギ)のこと |
| もえにけるかも[目生来鴨] |
| もえ[萌ゆ] |
[自ヤ下二・連用形]草木などの芽が出る・芽ぐむ |
| に[助動詞・ぬ] |
[完了・連用形]~てしまう・~てしまった |
連用形に付く |
| ける[助動詞・けり] |
[過去・連体形]~たのだ・~たなあ |
連用形に付く |
| かも[終助詞] |
[詠嘆・感動]~であることよ |
連体形に付く |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、282語と、およそ言われている半分程度だしかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| [あさみどり] |
枕詞「あさみどり」もあるが、この歌は、枕詞ではなく
実際の「色」を表現している
『万葉集』中では、「あさみどり」は、この一首しかなく
「枕詞」の用法としては、古今集あたりから出てくると思う |
| |
| [そめかけたりと] |
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕では、この語句の解釈を、
「色を掛けた」とし、その訓を「しみかけたりと」としている
比喩的な表現とされている語句が、実際に浅緑の色に染められたとした解釈になっている |
| |
| [までに] |
原文「左右」を「まで」と訓む用法は、
「戯書」(義訓より戯れの度合を強めて連想・類推に基づき、その漢字の意味・音・訓とは掛け離れた読みを与えるもの)と呼ばれるもので、
「両手」「諸手」を「真手(まで)」と称したことによる
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕の補注によると、
石山寺縁起絵巻に、平安初期、梨壺の五人の内の一人、源順が、
この表記を「まで」と解読するに至った逸話が描かれている、という
それは、その当時でも、『万葉集』の表記は、一種の符牒のようなものだったと伺える
この梨壺の五人によって点けられた『万葉集』の訓は、
「古点」(951年)と言われるものだが、『万葉集』の最終的な成立が8世紀末とするなら、それから150年~200年後の時代には、このように「解読作業」は大変なものだった
そして、そこを起点にして、今日に至るまでの「訓点」の作業は...まだ未完のままだ |
| |
| [やなぎ] |
原文の「楊」は、昨日も触れたが、川柳のことで
一般に、枝の枝垂れる「柳」とは区別されて使われている、
両者を比較の意味で調べてみた
「川楊」は、水辺に生え早春、葉よりも早く白絹毛の密生した尾状花穂を出す、とされ
落葉低木で高さ0.5~2メートル
「柳」は、「しだれやなぎ」とも言われ、落葉高木、高さ5~10メートル
枝は柔軟で糸のように下垂れし、早春、黄緑色の花を開く
前述の『全註釈』や、『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕もまた
この歌を「川楊」として解釈し、
「若葉した河楊を、やや遠くより眺めての感である」としているが
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕は、上三句の「形状表現」から
「しだれやなぎ」の方が相応しい、としている
松田修『増訂万葉植物親考』、小清水卓二『万葉植物 写真と解説』を引き合いに出し
これらの著書、いずれも「しだれやなぎ」としていることを挙げ、こう締め括る
「川楊で早春特に目を惹くのは、白絹毛の尾状花穂であるから、この歌の場合は、しだれ柳と解する方が穏やかであろう」と
私には解らないが、上三句で「しだれやなぎ」の「形状表現」というのは、何なのか...
どこに「形状表現」を見ることができるのだろう
この「しだれやなぎ」とする解釈の仕方は、だいたい次のような「歌意」になっている
「浅緑色に染めた糸を、枝に掛けたように見える」
なるほど、そう見れば、確かに「しだれやなぎ」こそ相応しい、と思う
勿論、枝だそのものが若葉の浅緑色に覆われ、緑の糸をつけたように、との歌意もある
いずれも、「しだれやなぎ」を思い描けば、不思議な眺めではないだろう
しかし、漢字を音として使うのではなく
その意味を考慮して使う場合の使い分けは、『万葉集』もまた優れていると思う
「しだれやなぎ」の「形状表現」というが、「糸を掛けたように」とは
この歌で、確実に言い得るものだろうか
浅緑の若葉をさして、それがまるで浅葱色に染めたように一面を覆う
そうも考えられる
もっとも、「染懸」の「そめかけ」の「懸け」が、
古語辞典でも、最初に「ぶらさげる・とりつける」の意を持つからだろうが
他にも、意味を載せている、「おおう・かぶせる」と
この当時の「掛く・懸く」には、どちらの意味合いが強いのだろう
私は、川楊がその浅葱色した若葉を一面に覆い見せている光景の方が、
結句の「もえにけるかも」にこそ、相応しいと思う
糸のように「しだれ」るさまよりも、「萌え」に似合うのは、
下から「いづる」花穂ではないかと思う
「しだれやなぎ」が、まさに「糸」のように詠われた歌がある
| 春雑歌詠柳 |
| 青柳之 絲乃細紗 春風尓 不乱伊間尓 令視子裳欲得 |
| 青柳の糸のくはしさ春風に乱れぬい間に見せむ子もがも |
| あをやぎの いとのくはしさ はるかぜに みだれぬいまに みせむこもがも |
| 巻第十 1855 春雑歌 詠柳 作者不詳 |
〔語義〕
「あをやぎの」は、枕詞で、「糸」にかかる
「くはし(細し・美し)さ」は、細やかで美しい・うるわしい、の意の形容詞「くはし」
それに接尾語「さ」がついたもの
接尾語「さ」は、形容詞の語幹(シク活用は終止形)について、程度・状態を表す名詞をつくる
そして、「いとのくはしさ」のように、「~の~さ」の用法で、感嘆の意をも表す
「いまに」の「い」は上代の「間投助詞」で、動詞・助動詞の連体形について、
連体修飾語を強調する
「もがも」は、願望を表す助詞「もが」に詠嘆の終助詞「も」がついた形 |
〔歌意〕
青柳の、まるで糸のような美しさよ
春風に吹かれ、乱れてしまわないうちに、
この美しさを見せてやりたい娘でもいれば、いいのだがなあ |
この歌は、まさに「しだれやなぎ」なればこその、若々しい躍動感がある
そして何より、「春風に乱れ」る表現は、「川楊」には似合わないものだ
「春風に乱れる枝垂れ柳」
「萌ゆる若葉の川楊」...そんな風に感じたいものだ |
| |
|
|
| 【歌意1853】 |
山間の雪は、まだ消えてもいないのに
それでも、こんなに水飛沫をあげて流れる川のほとりでは
やなぎが芽吹いているよ |
『全注』の「考」によれば、この前の歌〔1852〕(12月24日)との連作の説を紹介しているが
確かに、同一人、あるいは別人であっても、同じ場所で共に詠じたような気もする
しかし、その情景を思い浮かべてみると、やはり違うものだと思う
前歌では、「雪がなおも降り続いているのに、楊が芽生えた」といい、この歌では、
「雪はまだ残っているのに、雪解けのせいか川の水量がこんなに溢れ、ほとりでは楊も芽生えている」と詠う
明らかに、その「視点」が違う...時期が違うと思う
掲題歌の方が、よりいっそう春めいた気持ちを表現している
この歌、「やなぎ」という言葉は出ていない
しかし、部立てが「春雑歌詠柳」であり、川のほとりにある木と言えば
自然と「やなぎ」を思い浮かべる
そして「かはのそひ」には、「もえにける」のが「やなぎ」とも容易にわかる
文字に「やなぎ」がなくて、そこからも前歌との連作か、ということだろう
前歌で「川楊」と詠われているのが、この掲題歌までも支配しているのかもしれない
しかし、問答とか連作との題詞がない以上、どれも推測に過ぎない
この歌そのものを純粋に鑑賞するには、「詠柳」だけに頼るしかないだろう
観賞し、その情景を思い浮かべ、自分のなかに取り入れる
それが一連の作なのかどうか...今は深入りはしない
里で迎える「春」にもいろいろある
うぐひすの鳴き声、梅の花...
しかし、この歌のように「みなぎらふかは」もまた、そうではないかと思う
のどかな「静的な春」の訪れではなく
雪解け水の奔流を目の前にして、「春を知る」
そして、その周りに目をやると、楊が芽吹いている
「みなぎらふ」川の激流の音に、もううぐひすの鳴き声は、登場する余地もない
いや、耳を澄ませば、その鳴き声も聞こえるかもしれない
しかし、作者の心は...私もまた、その場に居合わせたら、
雪消の水に、こころ奪われ、春を実感しただろう
そこに、柳の芽吹きや、うぐひすの鳴き声があろうと...
私には、「みみなぎらふかは」そのものが、「春」の景物なのだから... |
| |


|
掲載日:2013.12.26.
| 春雑歌 詠柳 |
| 山際之 雪者不消有乎 水飯合 川之副者 目生来鴨 |
| 山の際の雪は消ずあるをみなぎらふ川の沿ひには萌えにけるかも |
| やまのまの ゆきはけざるを みなぎらふ かはのそひには もえにけるかも |
| 巻第十 1853 春雑歌 詠柳 作者不詳 |
〔青は「注記」及び「古語辞典」関係へ、尚注記以外は新しいウィンドウで開く〕
| 【1853】語義 |
意味・活用・接続 |
| やまのまの[山際之 ] |
| やまのま[山の間] |
山あい・山と山の間 〔12月17日参照〕 |
| ゆきはけざるを[雪者不消有乎] |
| け[消(く)] |
[自カ下二・未然形]消える・なくなる |
| 〔参考〕連体形・已然形・命令形の確かな用例は見当たらない |
| ざる[助動詞・ず] |
[打消・連体形]~ない |
未然形に付く |
| を[接続助詞] |
[逆接]~のに |
連体形に付く |
| みなぎらふ[水飯合] |
| みなきらふ[漲らふ] |
[上代語・自ハ四・連体形]水が満ち溢れている・水勢が盛んになる |
| 〔成立〕四段動詞「漲(みなぎ)る」の未然形「みなぎら」に反復・継続の助動詞「ふ」 |
| かはのそひには[川之副者] |
| そひ[傍(そひ)] |
傍ら・そば |
| 〔自ハ四動詞「添ふ・副ふ」の、そばに寄りついている、が原義だと思う〕 |
| には |
~では〔成立〕断定の助動詞「なり」の連用形「に」+係助詞「は」 |
| 〔接続〕助動詞「なり」の接続する、「体言・活用語の連体形」 |
| もえにけるかも[目生来鴨] |
| もえ[萌ゆ] |
[自ヤ下二・連用形]草木などの芽が出る・芽ぐむ |
| に[助動詞・ぬ] |
[完了・連用形]~てしまう・~てしまった |
連用形に付く |
| ける[助動詞・けり] |
[過去・連体形]~たのだ・~たなあ |
連用形に付く |
| かも[終助詞] |
[詠嘆・感動]~であることよ |
連体形に付く |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だしかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| [みなぎらふ] |
以前「きらふ(霧らふ)」を採り上げたことがあった
上代語である「霧らふ」は、霧や霞が立ちこめる・霧や霞で曇る、の意がある
それが、「みな(水)」に付くことで、何となくイメージが沸くが、少々違った
それに、この訓「みなぎらふ」にも、異訓が多く、定まってはいないようだ
まず、原文の「水飯合」は間違いないようだが、それでは「みなぎらふ」とは訓めない
旧訓では、これを「なかれあふ」としているが、私にはそれも思い浮かばなかった
「なかれあふ」とは「流れ合ふ」のことなのだろうか
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕は、
「飯」を「激」の誤りとして、「みなきらふ」とし、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕も、その誤字説を採るが
訓では、「たぎちあふ」としている
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕は、「殺」の誤りとし
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕もまた「殺」とするが、
その異体字(変換不可能)として、共に「みなぎらふ」とした
この「みなぎらふ」の意味は、水量が豊で、水飛沫をあげながら流れる様子のこと
今は、この「訓」が、多く用いられている
旧訓「なかれあふ」に戻って、その意味を考えると
どうしても「流れ合ふ」を浮かべてしまう
「合ふ」は、一つになること、などの意味があるので
本流に支流からの川の流れがあつまり、勢いや激しさを増すような感じもする
ただし、それでも「水飯合」の原文表記では、思いも付かない |
| |
| [かはのそひには] |
この原文「川之副者」もまた、異訓が多い
『西本願寺本』、
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕、
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕が、「かはのそへれば」
『紀州本』、「かはのそへしは」
『元暦校本』、「かはのそへは」
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕、
『日本古典文学全集』〔小学館、昭和50年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕など、「かはのそひには」
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕、「かはのたくへは」
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕、「かはぞひやなぎ」
また、「副」を「柳」の誤りとする、
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕の説に従って
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕は、「かはのやなぎは」
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕、「かはしたぐふは」
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕、「かはにしそへば」
以上のように、原文の誤字・誤写説をまじえて多くの「訓」がある
原文「副」には「そふ・たぐふ」などの用字例もあるので、判断は難しい
ただし、「川のほとりでは」の意で考えると「かはのそひには」が一般的だ、とされる
「そひ」には「傍」の用字もあることからだと思う
なお、『小学館古語大辞典』には、次のような説明があるという
名義抄の「浜」の字に、「キハ・キシ・ホトリ」などと共に「ソヒ」の訓がある、と
|
| |
| この歌の『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕[考]より |
| 『代匠記』は、前歌と同じ作者によるものとし、「二首ニテ意ヲ云ヒハタスナリ。蓋山ノ雪ハ消サルニ、サスカニ水ノヌルム川ノシヒタレは柳ノモエタルトナリ。副者ハ、タクヘハト読ヘシ」とし、『略解』は、二首を問答としたが、佐伯梅友『万葉語研究』は、「かはにししへば」と訓んで、『代匠記』と同じく同一人による連作とした。もしも同一人による自問自答、あるいは前歌に対する唱和の歌としてこれが詠まれたとすれば、「川のほとりなので」の意で、山の雪はまだ消えないのに川のほとりの柳が芽吹いた理由を述べたことになるが、歌としては、同じ問答の形でも、〔巻七・1292〕などとは異なり、あまりにも理に落ち如何かと思われる。 |
| |
|
|
| 【歌意1854】 |
毎朝...朝ごとにわたしが見る柳よ
うぐひすが、楽しみにしてやって来て、その枝に止り
必ず、鳴くような立派な木に
早くなってくれよ |
若い柳の木を、まるで我が子のように「愛しんで」いる歌だ
毎朝見ている...まだまだ幼い「柳の木」に、
やがて、うぐひすがやって来て、居心地もよくそこに止り
美しいさえずりを奏でる姿を、想像してみる
そんな「立派な木」に、早くなってくれよ、と
それは、単に樹木が大きくなる成長だけをいうのではなく
うぐひすが、「居心地よく」、お前を選んで飛んでくるような「魅力溢れる木」になってくれ
そんな「親心」のような心情なのだろう
こうして、毎朝見る柳、あるいはその群は
未だうぐひすの、やってこない木々なのだろう
他の所では、春の始まりを謳歌する、うぐひすの鳴き声が聞こえる
しかし、自分のところでは、まだそんな木々にはなっていない
寂しさ...いや、違う
今はこうであっても、やがて成長して、うぐひすの鳴き声とともに
「早春」の息吹を見せてくれる
その将来への「期待」「楽しみ」の方が、寂しさより勝る
厳しい冬を、降り積もる雪をも耐え抜いたお前だ
きっと、立派に成長してくれるだろう
「はやなれ」...「あせらなくてもいいぞ」、と呟く |
| |
 |
掲載日:2013.12.27.
| 春雑歌 詠柳 |
| 朝旦 吾見柳 鴬之 来居而應鳴 森尓早奈礼 |
| 朝な朝な我が見る柳鴬の来居て鳴くべき森に早なれ |
| あさなさな わがみるやなぎ うぐひすの きゐてなくべき もりにはやなれ |
| 巻第十 1854 春雑歌 詠柳 作者不詳 |
〔青は「注記」及び「古語辞典」関係へ、尚注記以外は新しいウィンドウで開く〕
| 【1854】語義 |
意味・活用・接続 |
| あさなさな[朝旦 ] (「あさなあさな」の約) |
| あさなさな[朝なさな] |
[副詞]朝ごとに・毎朝 |
| わがみるやなぎ[吾見柳] 私が見る柳よ (結句の命令形を受け、呼び掛けになる) |
| うぐひすの[鴬之] |
| の[格助詞] |
[主語]~が 〔接続〕体言、それに準ずる語に付く |
| きゐてなくべき[来居而應鳴] |
| きゐ[来居る] |
[自ワ上一・連用形]来てそこにじっとしている、とまっている |
| て[接続助詞] |
[並立]~て |
連用形に付く |
| べき[助動詞・べし] |
[可能推定・連体形]~ことができよう |
終止形に付く |
| もりにはやなれ[森尓早奈礼] |
| もり[森・杜] |
樹木がこんもりと茂った所・神社のある地で、高い木の茂った所 |
| に[格助詞] |
[動作の帰着点]~に |
体言に付く |
| はや[早] |
[副詞]早く・すみやかに・早くも・すでに |
| なれ[成る] |
[自ラ四・命令形]成長する・変化する |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だしかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [なくべき] |
ほとんどの注釈書では「なくべき」だが、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕では「なくべく」としている
連用形「べく」と、連体形「べき」の違い
当然修飾する語に、違いがある
「べく」だと、「うぐひすが来て鳴くことのできるような、立派な木になれ」だろうし
「べき」では、「うぐひすが来て鳴くことのできるような、立派な木になれ」となる
原文の「来居而應鳴」は、漢文であり、「應鳴」とはどんな意味になるのだろう
現代語の漢和辞典しか持っていないが、「応」の意味には「こたえる」の他に
再読文字として「まさに~べし」とある
訓で「べし」としているので、現代の漢和辞典でも、その「まさに~べし」は残っている
古来からの読み方として、変化もないのかもしれない
すると、「まさに鳴くべし」
では、「まさに」には、どんな意味があるのだろう
今度は古語辞典を持ち出すので、あまりよくない調べ方だが
それによると、幾つか用法のある中で、下に「べし」を伴って、という項目があった
実際に本歌で「まさに」と訓じてはいないが、「應」の用字が、それを意味する
そして「まさに~べし」は、「きっと・必ず・~するのが当然」という
そのような意味合いで「来居而應鳴」を解すると
うぐひすが、「来てそこに止って、必ず鳴く」となり
その先に続く言葉は、「木」だろう...「連体形べき」ではないだろうか
「来てそこに止って、必ず、きっと〔なれ〕」では、何だか無理がある
鹿持雅澄の「べく」の訓の理由、また明日香での宿題が増えた
角川ソフィア文庫の『万葉集』〔伊藤博校注〕も「べく」としている |
| |
| [もり] |
古語辞典に書かれている「森」は、一般的な解釈であり、
本来は、神霊の依りつく高い木のあるところ、という
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕の「注」によると
方言にも、一本の巨木を「もり」という例があり
なおかつ、『枕草子』には、
「森などといふべくもあらず、ただ一木あるを、なにごとにつけけむ」(森は)とある
方言の「もり」は、まさに「神の宿る巨木」を、それのみでも「もり」というに相応しい
そして、『枕草子』については、私は読んだこともないので、
その前後との脈絡は分からないが、
「べくもあらず」の意味が、「~できそうもない・~はずもない」などであり
「つけけむ」の「けむ」が、過去の推量であるので
「森などと言うはずもない、たった一本の木立に、何があってそう名付けたのだろう」
というような意味になるだろうか...全体を知らないので、何ともいえないが
語義を拾うと、この部分はそう解釈してしまう
そうなると、『枕草子』の一文でいう「一本の木なのに森とは」を裏返せば
その一本の木を「森」と古来から言っていた、ということになるだろう
もっとも、そのことと、この掲題歌の「森」がどんな関わりがあるのか...
「神が宿る」というのは、この際外しておいて、「森」と表記はするが
うぐひすが止って鳴くような、立派な「木」になれ、と意味なのかもしれない
「森」というより、やはり「木」の方が相応しい
ここでもまた、角川ソフィア文庫の『万葉集』〔伊藤博校注〕では
結句が「茂(しげ)にはやなれ」としている
前項の「べく」が『古義』に倣ったものとしても、
その『古義』は「森(もり)」であるのに
訓はともかくとして、柳の木の「立派に茂る」状態を描いた訓だとは思う |
| |
|
|
| 【歌意1857】 |
梅の花を手にとって見ていると
我が家の庭の、柳のような美しい眉をした妻のことが
思われてならない |
この歌の特徴は、二段階的な連想をさせられてしまうことにあると思う
まず、どこかで綺麗な「梅の花」を見かけ、その枝を、手に持って見る
すると、そこに我が家の前庭に立つ柳の「青柳の糸」のような美しさを見出してしまう
それは、美しいと評判の妻の「柳眉」をしのばせ
やがて、梅の花の美しい枝振りから妻への思慕へ、想いは占められてゆく...
「妻」を思わせる「柳眉」で、妻への想いを「美しい妻」と愛情豊かに詠う
いい歌だと思う |
| |
 |
掲載日:2013.12.28.
| 春雑歌 詠柳 |
| 梅花 取持見者 吾屋前之 柳乃眉師 所念可聞 |
| 梅の花取り持ち見れば我が宿の柳の眉し思ほゆるかも |
| うめのはな とりもちみれば わがやどの やなぎのまよし おもほゆるかも |
| 巻第十 1857 春雑歌 詠柳 作者不詳 |
〔青は「注記」及び「古語辞典」関係へ、尚注記以外は新しいウィンドウで開く〕
| 【1857】語義 |
意味・活用・接続 |
| うめのはな[梅花 ] |
| とりもちみれば[取持見者] |
| とりもち[取り持つ] |
[他タ四・連用形]手に持つ・奪い取る・一緒に連れていく |
| みれ[見る] |
[他マ上一・已然形]目に留める・眺める・理解する・ためす |
| ば[接続助詞] |
[順接確定条件・単純接続]~すると・~したところ |
| 〔接続〕已然形に付けば「順接確定条件」、未然形に付けば「順接仮定条件」 |
| わがやどの[吾屋前之] |
| やど[屋戸・宿] |
家の敷地・屋敷のうち・庭先・前庭・住む所・自宅・宿る所 |
| やなぎのまよし[柳乃眉師] |
| まよ[眉] |
[「まよ」は「まゆ」の古形]まゆ |
| し[副助詞] |
語調を整え、強意を表す |
| おもほゆるかも[所念可聞] |
| おもほゆる[思ほゆ] |
[自ヤ下二・連体形]自然に思われる・しのばれる |
| 〔成立〕四段「思ふ」の未然形「おもは」に、上代自発の助動詞「ゆ」で「おもはゆ」の転 |
| かも[終助詞] |
[詠嘆・感動]~であることよ |
連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だしかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [とりもちみれば(取持見者)] |
多くの諸注が底本にしている『 西本願寺本』が、「取持見者(とりもちみれば)」とするが『元暦校本』には、「取持而見者」とされており、それに従い訓む注釈書もある
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕などは、
「とりもちてみれば」としている
|
| |
| [わがやどの(吾屋前之)] |
古語辞典に載る、「やど」の意味は幅が広い
まさに「宿」、家そのものもあるが
家の敷地だとか、家の庭もある
だからと言うわけだろうか、この語句の訓に、「わがにはの」とする注釈書がある
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕が、その訓をとっている
この注釈書では、第二句でも、広く使われている底本『西本願寺本』ではなく、
『元暦校本』の「而」を載せている訓に基づいているが、
この第三句でも、「やど」を「には」として訓む
表記上も、「屋前」に「屋敷の前」とすれば、何となく「前庭」を思い抱かせており
「わがにはの」でも、不自然さはないと思う |
| |
| [やなぎのまよし] |
この表現は、柳の新葉を「眉」にたとえたものが、本となっている
「柳の葉」を「柳の眉」と置き換えるのは、
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕によると、
「柳ノ眉ニハ妻ヲ兼テ云なるへし」とあり、
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕もまた、
「柳の葉を『柳の眉し』と云ひかへてゐるのは、単に葉といふだけではなく、その葉の如き眉をした妻といふことを暗示しようがためである」としている
漢語には、「柳眉」という語を、美女の表現として、よく使われているようだ
|
| |
|
|
| 【歌意1859】 |
美しく咲き誇る桜花
まだその盛りの時が過ぎてもいないのに
人々に、もっとも愛され、惜しまれる時こそ今、と思って
散っているのだろう |
桜が誰もから愛されるのは
その散る潔さを、一つにあげることがある
確かに、見事に咲いて、あっという間に散ってゆく桜花は
その「いさぎよさ」を強烈に見せ付けてくれる
咲き誇る姿が素晴らしければ素晴らしいほど
その短い花開く姿は、「いさぎよさ」と同時に「はかなさ」をも見せる
そこに、「桜花」自身がどんな「想い」を持って、そうするのか、などとは
考えたこともなかったが
この歌に触れると、なるほど桜花とは、そんな「引き際の哲学」があるのか、と思う
勿論、現実の事象に対して、人が感じる想いを言う時は
間違いなく、それは自分自身の「想い」に重なっていなければならないはずだ
しかし、それが実践できているかどうか、
むしろ、実践できていない方が多いからこそ、よりいっそう「憧れ」てしまうものだろう
どうして、そんなに早く散ってしまうのだ
と、文句の一つや二つでも言いたくなるのが、右頁「注記」の〔1429〕だと思う
桜が、ずっと長く毎日でも咲いて、自分の前にあるのなら
こんなに激しく「想う」ことなどないだろうに、と嘆いてみせる
言い換えれば、そんな有り触れたお前なら、誰が恋したりするものか、ということだ
ならば、文句の一つや二つではなく
この〔1429〕歌でさえも、その「いさぎよさ」が故に、恋してしまうのだなあ、と
掲題歌は、きっと桜花は、人がどんな情況のもとで自分を愛でてくれるのか
それを知っているのだろう、と確信して思っている
季節を間違うことなく、咲く花
それを「人の心」と同じように擬えるのも、決して不思議なことではない、と思った
「擬人法」とか「擬人化」とか言うが、そうではない
万葉の人たちは、本心でそう感じていたのかもしれない
お前の「いさぎよさ」を、俺も時として見習おう
そう思いたくなる時だって、人にはある
なかなか、それが難しいことを知っているから... |
| |

 |
掲載日:2013.12.29.
| 春雑歌 詠花 |
| 櫻花 時者雖不過 見人之 戀盛常 今之将落 |
| 桜花時は過ぎねど見る人の恋の盛りと今し散るらむ |
| さくらばな ときはすぎねど みるひとの こひのさかりと いましちるらむ |
| 巻第十 1859 春雑歌 詠花 作者不詳 |
【注記】〔1429・2124〕
〔青は「注記」及び「古語辞典」関係へ、尚注記以外は新しいウィンドウで開く〕
| 【1859】語義 |
意味・活用・接続 |
| さくらばな[櫻花 ] |
| ときはすぎねど[時者雖不過] |
| すぎ[過ぐ] |
[自ガ上二・未然形]盛りが過ぎる・終りになる |
| ね[助動詞・ず] |
[打消・已然形]~ない |
未然形につく |
| ど[接続助詞] |
[逆接確定条件]~けれども・~だが・~のに |
已然形につく |
| みるひとの[見人之] |
| こひのさかりと[戀盛常] |
| こひ[恋] |
恋しく思うこと・心が惹かれること |
| さかり[盛り] |
活動力や勢いが盛んなさま・また、その時期・人が充実している時期 |
| と[接続助詞] |
[引用]~と言って・~と思って〔接続〕体言それに準ずる語につく |
| いましちるらむ[今之将落] |
| し[副助詞] |
語調を整え、強意を表す |
| らむ[助動詞・らむ] |
[目の前の原因・理由を推量・終止形]~のだろう |
終止形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だしかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [こひのさかりと] |
桜花に対する、人々の「恋する想い」で、その最も盛んな時期
それを、「引用」の接続助詞「と」で、桜花が自ら、そう思って、という意味になる
花に「恋」を当てる歌は多い
次の二首も、花に「恋こころ」を詠う
| 春雑歌/(山部宿祢赤人歌四首) |
| 足比奇乃 山櫻花 日並而 如是開有者 甚戀目夜裳 |
| あしひきの山桜花日並べてかく咲きたらばいたく恋ひめやも |
| あしひきの やまさくらばな ひならべて かくさきたらば いたくこひめやも |
| 巻第八 1429 春雑歌 山部宿禰赤人 |
〔語義〕
「ひならべて」は、自動詞バ行下二段「日並ぶ」の連用形に、接続助詞「て」で、
「日数を重ねて・何日も続いて」
「かく(斯く)」は、副詞で、「このように」の意味
「さきたらば」は、四段「咲く」の連用形「さき」に完了の助動詞「たり」の未然形それに接続助詞「ば」で、未然形+「ば」は「順接の仮定条件」で「~なら」
「いたく」は、形容詞ク活用「いたし(甚し)」の連用形、「程度が甚だしい・激しい」
「めやも」は、詠嘆の反語の意で、「~だろうか、いや~でないなあ」 |
〔歌意〕
美しく咲く山の桜花が、
いつもずっとこんな風に咲いていてくれるのなら
こんなに激しく(桜花に)恋することなど、あるだろうか... |
| |
| 秋雑歌詠花 |
| 秋芽子 戀不盡跡 雖念 思恵也安多良思 又将相八方 |
| 秋萩に恋尽さじと思へどもしゑやあたらしまたも逢はめやも |
| あきはぎに こひつくさじと おもへども しゑやあたらし またもあはめやも |
| 巻第十 2124 秋雑歌 詠花 作者不詳 |
〔語義〕
「こひつくさじ」は、「恋心を傾け尽さない」
「ども」は、「逆接確定条件」で、「~けれども・~のに・~だが」
「いゑや」は、感嘆詞で、断念や決意、または嘆息したりするときに発する語
「ええい・ええままよ」などと訳される
「あたらし」は、形容詞シク活用「惜(あたら)し」で、「惜しい・もったいない」、
更に「そのままにしておくのが惜しいほど立派だ」の意味を持つ
「またも」は、「ふたたび」
「あはめやも」は、反語で「逢うことができるだろうか、できやしない」 |
〔歌意〕
秋萩に、恋心を抱いたりはしないぞ、と
そう思うのだが
ええい、かまうものか...やはり見逃せはしない
このように美しい花に、二度と逢うことなどできるものか |
「桜花」も「秋萩」も、まさに「恋する花」として詠う
まるで、恋人への情熱的な「想い」を詠うようだ
人が、花に対して抱く「想い」をこの二首は教えてくれるが
掲題の歌については、今度は人が「花自身の想い」をおしはかって、慈しんでいる
秋萩の歌では、もう一つ感じられることがある
人の持つ「恋心」
秋萩に恋しても、会話はできず、人はただただ見遣ることしかできない
言ってみれば、片恋のようなものだ
だから、決して恋などしないぞ、と思うのだが
でも、その美しさに、恋心を押さえ込むことなどできず、想いを顕わにする
そんな歌のようにも思える
| 「あたらし」の類語 |
| 中古以降、「新しい」の意の「あらたし」と混同して、「新しいの意」にも用いるが、本来は別語。「惜(お)しいの意」の「あたらし」は、形容詞「惜(を)し」に押されてやがて用いられなくなるが、その語幹は「あたら青春を無為に過ごす」のように、「惜しいことに」の意の副詞、または「惜しむべき」の意の連体詞として現代語にも残っている。 |
| あたらし |
優れたものが、失われるのを惜しむさま |
| くちをし |
物事が期待外れでがっかりするさま |
| くやし |
自分のした行為を反省して後悔するさま |
| をし(惜し) |
強い愛着を感じているものが失われるのを惜しむさま |
|
| |
| [いましちるらむ(今之将落)] |
この訓は、多くの諸本が「いましちるらむ」と訓むが、
『萬葉集』〔桜楓社、昭和55年補訂版〕が、「いまはちるらむ」とする
「し」は、強意の「副助詞」で、「は」は係助詞だが
主語にあたる語句を「とりたてて提示する・題目を表す」用法から、強調となり
「係り結び」と同じ働きになると思うが
本によっては、文末の活用形を制約する(連体形・已然形)のが「係り結び」となり、
「は」(他に「も」)は、その制約がなく、無条件で「終止形」で終るので、
係助詞「は」を「係り結び」とは言わないようだ
しかし、「とりたて」で用いられる「は」は、間違いなく「係り結び」だと思う |
| |
|
|
| 【歌意1860】 |
わたしが庭に刺し添えた柳の、
糸のように細い小枝を吹き乱しているこの風に
いとしい娘の髪に、わたしが挿した梅の花も、
散っているのだろうか |
「刺」の字に、随分悩まされた
大方の諸注が説くように、男は青柳の小枝を髪にかざし
女が梅の花を髪にかざす...
岩波の『大系』では、女の方は、「家の梅の花」が散る、としている
(『新大系』では、髪に挿している梅の花、としている)
男が髪に青柳の小枝をさし、それが風に乱れるので、
この風は、きっといとしい女の家の梅の花を、散らしているだろう、と懸念していることになる
しかし、私にはその逆の方がいい
根拠はない
右頁の「注記」でも書いたように、様々な解釈ができ
尚且つ、他の歌の用法も考えると、
男が自分の庭に青柳を添え挿して植えた
しかし、その青柳の枝は、吹き乱れる春の風に花を散らしている
この風では、いとしいあの娘の髪に、自分が挿してやった梅の花も...散っているだろうか
柳の糸のような枝の、風に乱される様から、
いとしい娘のことを思い浮かべるのに、そこに「梅の髪飾り」が、「風」に乱されている
しかも、その「髪飾り」は自分が挿したものだ
あまり気持ちの良いものではないはずだ
「風」に対する恨めしさが、この歌の気持ちではないかと思う |
| |



 |
掲載日:2013.12.30.
| 春雑歌 詠花 |
| 我刺 柳絲乎 吹乱 風尓加妹之 梅乃散覧 |
| 我がさせる柳の糸を吹き乱る風にか妹が梅の散るらむ |
| わがさせる やなぎのいとを ふきみだる かぜにかいもが うめのちるらむ |
| 巻第十 1860 春雑歌 詠花 作者不詳 |
【注記】〔1687・3925・3927・825〕
〔青は「注記」及び「古語辞典」関係へ、尚注記以外は新しいウィンドウで開く〕
| 【1860】語義 |
意味・活用・接続 |
| わがさせる[我刺 ] |
| させ[挿す] |
[他サ四・已然形]さし入れる・さしはさむ・髪にさす |
| る[助動詞・り] |
[完了・連体形]~ている・~てある・~てしまった |
已然形につく |
| やなぎのいとを[柳絲乎] |
| いと[糸] |
糸・糸のように細長いもの・特に蜘蛛の糸や青柳の枝など |
| ふきみだる[吹乱] |
| みだる[乱る] |
[他ラ四・連体形]乱す・秩序を乱す |
| かぜにかいもが[風尓加妹之] |
| にか |
(連体形の結びを伴って)「にかあらむ・にかありけむ」の形で
~であろうか・~であっただろうか〔接続〕体言、連体形につく |
| 〔成立〕断定の助動詞「なり」の連用家「に」+係助詞「か」 |
| うめのちるらむ[梅乃散覧] |
| らむ[助動詞・らむ] |
[推量・連体形]~だろう〔係り結びの「結び」〕 |
終止形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だしかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [わがさせる] |
一般的に、この訓は「わがかざす」とする注釈書が多い
その原文「刺」を「かざす」と訓む例として、挙げられているのが次の歌だ
| 獻舎人皇子歌二首 |
| 妹手 取而引与治 フサ手折 吾刺可 花開鴨 |
| 妹が手を取りて引き攀ぢふさ手折り我がかざすべく花咲けるかも |
| いもがてを とりてひきよぢ ふさたをり わがかざすべく はなさけるかも |
| (右柿本朝臣人麻呂之歌集所出) |
| 巻第九 1687 雑歌 柿本人麻呂歌集 |
〔語義〕
「ひきよぢ」は、掴んで前に引っ張り寄せる
「ふさ」の原文は変換不能文字だが、その文字は「総(ふさ)」と同訓で
正倉院文書に、手首の部分を「手総(たぶさ)」と書いた文書があるという
「かざす」の原文「吾刺」が、掲題歌〔1860〕の例として引き合いに出されている
ここでは、手折った花枝を「刺」のだから、
「挿す」、つまり「かざす」との訓点があるのだと思う
|
〔歌意〕
むすめの手を引き寄せ
「房」を手折っては、わたしが挿してやる花が、咲いたなあ |
この歌で浮ぶ動作は、間違いなく「(かざす)挿頭」にちがいない
だから、「さす(挿す)」でも、「かざす」でも、いいようだが
「かざす」の意味は、より具体的に「髪に花枝を飾る」とすることなので
だから「かざす」が、異訓もなく訓まれているのだろう
しかし掲題歌に、その同じような情況が当てはまるのかどうか、解らない
手掛かりは「やなぎのいと」だろう、きっと
この「やなぎのいと」の「いと」は、「青柳の細い枝」をも指すらしい
「細長い枝」が「さす」と重なって連想させるのは、やはり「髪に挿す」なのかな
この「わがかざす」では、「髪に挿す」と意味が固定してしまうが
私が用いた「わがさせる」や、「わがさしし」とする訓では、
「刺」を「挿し木にした」とする説もある
文字通り「さす(刺)」だ
古語辞典での「刺す」の意味は、「突き刺す」を基本とした意味になっている
この「挿し木にした」と解釈しているのが、
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕、
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕、
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕、
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕など
そして、同じ「させる」と訓じても、その解釈は「かざす」の「髪に挿す」とするのが、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕など
(尚、『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕は「かざす」)
この歌では、「やなぎのいと」でしか、「髪に挿す」ことの手掛かりはないと思うが
梅と柳の二種の花を共に詠ったうたがあり、それはどんな情況なのか気になった
共に既出の歌だが、ここに載せる〔書庫-4、2013年3月13日〕
| (追和大宰之時梅花新歌六首) |
| 春雨尓 毛延之楊奈疑可 烏梅乃花 登母尓於久礼奴 常乃物能香聞 |
| 春雨に萌えし柳か梅の花ともに後れぬ常の物かも |
| はるさめに もえしやなぎか うめのはな ともにおくれぬ つねのものかも |
| 巻第十七 3925 梅花宴 大伴宿禰書持 |
〔語義〕
「し」は、語調を整え強調する、副助詞
「か」は、疑問の係助詞
「ぬ」は、打消の助動詞「ず」の連体形
「つね」は、「普通・当たり前・いつも」 |
〔歌意〕
春雨に急かされて、早く萌え出た柳なのだろうか
それとも、そんなことに関わらず
梅の花に遅れずに芽生える、ごく普通の柳なのだろうか |
| |
| 遊内乃 多努之吉庭尓 梅柳 乎理加謝思底婆 意毛比奈美可毛 |
| 遊ぶ内の楽しき庭に梅柳折りかざしてば思ひなみかも |
| あそぶうちの たのしきにはに うめやなぎ をりかざしてば おもひなみかも |
| (右十二年十二月九日大伴宿祢書持作) |
| 巻第十七 3927 梅花宴 大伴宿禰書持 |
〔語義〕
「あそぶうちの」は、種々の遊びの中で、とか今まさにその間、とか諸説が多い
「おもひなみかも」の意は、「おもひなみ」が「思いもない」のミ語法で
「心残りがない」
「かも」は、「ミ語法+かも」で、一般的には「疑問条件」
この「おもひなみかも」にもまた、諸説が多い |
〔歌意〕
遊んでいる楽しい園遊で、梅や柳を折り
それを飾ったり愛でながら飲み明かしてしまえば
(そのあと散っても)もう何の心残りもないからでしょうか
|
この大伴書持の歌は、題詞に「追和大宰之時梅花新歌六首」とあるように、
十年前の、父・大伴旅人たちが大宰府での梅花宴で詠んだ「梅花三十二首」に
その時の歌に唱和して詠ったものと解釈している
ということは、この歌(歌群)は、それに見合った歌と響き合わなければならない
そうでなければ、単独でこの歌を拾っても、歌意が掴みにくい
この歌に「唱和」したのでは、とされている歌が、次の歌だ
| (梅花歌卅二首[并序] / 天平二年正月十三日 萃于帥老之宅 申宴會也 于時初春令月 氣淑風和梅披鏡前之粉 蘭薫珮後之香 加以 曙嶺移雲 松掛羅而傾盖
夕岫結霧鳥封q而迷林 庭舞新蝶 空歸故鴈 於是盖天坐地 促膝飛觴 忘言一室之裏 開衿煙霞之外 淡然自放 快然自足 若非翰苑何以□情 詩紀落梅之篇古今夫何異矣
宜賦園梅聊成短詠) |
| 阿乎夜奈義 烏梅等能波奈乎 遠理可射之 能弥弖能々知波 知利奴得母與斯[笠沙弥] |
| 青柳梅との花を折りかざし飲みての後は散りぬともよし[笠沙弥] |
| あをやなぎ うめとのはなを をりかざし のみてののちは ちりぬともよし |
| 巻第五 825 梅花宴 沙弥満誓 |
〔語義〕
「をりかざし」は「をり」は「折る」だろうが、「かざし」は、髪に挿すではなく、
飾り付けるという意味なのだと思う |
〔歌意〕
青柳も梅も、この酒宴に飾って飲み明かせば
後は散ってしまっても、もういいではないか |
この〔825〕に唱和するとすれば、〔3927〕歌ほど「問答」めいた関係ではないかと思う
ところが、〔3927〕の解釈では、あまりこのことには触れられておらず、
〔3927〕単独で、歌意を収めてしまっている
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕などでは、
「遊びの内に、喜び溢れる宴席の庭で、梅や柳を折りかざしたら、こころ晴れやかになるものだろうよ」と解釈している
大伴書持自身が、十年前の梅花宴に参加したつもりになって、詠んだとしたものだろう
でも、歌の響き合う姿だからこそ「追和」と題するに相応しいと思うのだが...
話しが逸れたが、「かざす」とした場合、
「飾り付ける」意味をも考慮したい、ということだ
|
| |
|
|
| 【歌意1861】 |
としごとに、梅の花は必ず咲くものだが
こんなふうに現世に生きるわたしには、
もう「はる」という人生の季節は、めぐってこないだろうなあ |
こんな歌を詠う心境というのは、どんなものだろう
老境に入った者の、無常観か...
それとも、不遇にうちしがれる「人」の弱音か...
原文「君」と「我」
江戸時代の契沖が、誤字説を唱える前では、一様に「君」として誰もが目にしていた
すると、それ以前とそれ以後での、この歌の解釈もまた、違うものだ
契沖の『代匠記』に書かれている、「世人君トハ・・・」では、
「君」が「世間一般」の人を総じて言うのか、「我」と書き誤ったものか
あるいは、この前の歌〔1860〕歌と同じ作者であって、その歌に詠われる「妹」のことか、
などと可能性を述べた後、赤人歌集の歌を例に挙げ、「誤字説」としている
世の無常をこめた詠い振り、なのだろうか
「君」とすれば、「不遇な境遇の人」とする説に導かれるが
では、その「君」は作者とどんな関係を持つ者なのか...
それが示されなければ、「歌」の奥行きがなくなる
私には、「君」ではとても不充分な歌になってしまうと思う
「我」とし、その対象者が自分であるからこそ、歌は完結する
作者の境遇には、思うところも多くあるだろう
しかし、少なくとも「うたごころ」を深めてゆく対象が明確になる
老境に入り、もう以前のような「希望に満ちた春」には無縁になった
そんな歌ではないだろうか
この歌の類想歌として、つい先日採りあげた一首を思い出した
| 春雑歌歎旧 |
| 寒過 暖来者 年月者 雖新有 人者舊去 |
| 冬過ぎて春し来れば年月は新たなれども人は古りゆく |
| ふゆすぎて はるしきたれば としつきは あらたなれども ひとはふりゆく |
| 既出〔書庫-13、2013年12月22日〕巻第十 1888 春雑歌 歎旧 作者不詳 |
〔歌意転載〕
|
冬が過ぎ、そして春がくると、やはりまた
年月は新しくなるのだが...人は老いてゆくばかりだ |
このときは、「寒過暖来」の表記の「義訓的用字」の例として採りあげたが、
この歌の「想い」が、掲題歌〔1861〕に通じるものがある、と思う
老境に入っては、「季節感」によって「こころ」も左右されることない
年は進み行くものであっても、「季節」に翻弄されたり、惑わされるようなことはない
その意味では、嘆きとともに、「季節」を超えた「悠然さ」もまた自然と備わってくる
〔1888〕では、老いてゆくばかりだ、と私も嘆いたものだが
掲題歌とともに詠じてみると、一概にそうでもないように感じてきた
「時間は制御はできない」ものだが、「季節感」なら、もうそんなもの「どうでもいい」
と、「なるようになれ」「放っておけ」のような、
老境に入った者の「意気地」のようなものさえ感じてしまう
私自身が、そうだからなのだろう...きっと
|
| |

|
掲載日:2013.12.31.
| 春雑歌 詠花 |
| 毎年 梅者開友 空蝉之 世人我羊蹄 春無有来 |
| 年のはに梅は咲けどもうつせみの世の人我れし春なかりけり |
| としのはに うめはさけども うつせみの よのひとわれし はるなかりけり |
| 巻第十 1861 春雑歌 詠花 作者不詳 |
【注記】〔4192〕【左頁・類想歌】〔1888〕
〔青は「注記」及び「古語辞典」関係へ、尚注記以外は新しいウィンドウで開く〕
| 【1861】語義 |
意味・活用・接続 |
| としのはに[毎年 ] |
| としのは[年の端] |
毎年・年ごと |
| うめはさけども[梅者開友] |
| ども[接続助詞] |
[逆接の確定条件]~けれども・~のに・~だが |
已然形につく |
| うつせみの[空蝉之] |
| うつせみ |
[「うつそみ」の転]この世の人・この世・現世 |
| よのひとわれし[世人我羊蹄] |
| し[副助詞] |
語調を整え、強意を表す |
| 〔接続〕体言または活用語の連体形・連用形、副詞、助詞などにつく |
| はるなかりけり[春無有来] |
| なかり[無し] |
[形ク・連用形]無いも同然である・世間から見捨てられている |
| けり[助動詞・けり] |
[詠嘆・過去・終止形]~たことよ・~ことよ |
連用形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だしかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [としのはに(毎年)] |
原文「毎年」を「としのはに」とする諸注は多い
『万葉集』中で、「毎年」の表記は、この歌を含めて四例だが
そのいずれも「としのはに」と訓じている
よく言われるその根拠として、次の歌が挙げられる
| (詠霍公鳥并時花歌一首[并短歌](反歌二首)) |
| 毎年尓 来喧毛能由恵 霍公鳥 聞婆之努波久 不相日乎於保美 [毎年謂之等之乃波] |
| 毎年に来鳴くものゆゑ霍公鳥聞けば偲はく逢はぬ日を多み [毎年謂之等之乃波] |
| としのはに きなくものゆゑ ほととぎす きけばしのはく あはぬひをおほみ |
| 右廿日雖未及時依興預作也 |
| 巻第十九 4192 詠霍公鳥并時花歌 大伴宿禰家持 |
〔語義〕
「きなく」は、「来て鳴く」
「ものゆゑ」は、接続助詞で、「逆接の確定条件」〔~のに〕
「きけば」は、四段「きく」の已然形「きけ」に接続助詞「ば」で、順接の恒常条件「きくときはいつも」という解釈になる
「しのはく」は、なつかしむ・賞美する、の四段「偲ぶ」の名詞形で詠嘆
「あはぬひをおほみ」は、間投助詞「を」の「~を~み」用法で、「~が~ので」
|
〔歌意〕
年ごとに、やって来ては鳴くのに
ほととぎす、その鳴き声を聞くときはいつも、聴き入ってしまうものだなあ
逢わない日が多いものだから... |
この歌には、家持自身の「注記」が添えられている
「毎年謂之等之乃波」がそれで、「毎年、これを『としのは』と謂ふ」
僅か四例の「毎年」の表記で、「としのは」と訓ませる指示があるのだから、
その他の訓はないだろう、と思ったら、一つあった
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕は、「としごとに」と訓じている
もっとも、「としのはに」も「としごとに」も、その意味は同じなので
訓による歌意の違いは起こらないだろう
|
| |
| [よのひとわれし] |
この語句は、誤字説が有力とされ、それが通説になっている
原文は「世人君羊蹄」
諸本に異同はなく、「君」が誤写とは考えられない
しかし、通説は「君」ではなく「我」となっている
初めてこれを、「我」の誤字、とするのが、
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕で、
その中で、こう述べている
「世人君トハ、世間ノ人ヲ総テ指て云歟。又君ハ吾ヲ書誤マレル歟。又右ノ歌ト同シ人ノ読テ右ノ妹ヲ指テ云歟。赤人ノ集ニ、世ニワレシモソ春ナカリケルトアレハ、彼集取用ラルル事マレナルモノナレト、吾ヲ書誤マレリト義ヲ立ル證トハ成侍ルヘシ」とする
簡単に内容を理解すると、山部赤人歌集に、
「としごとに梅は散れどもうつせみのよにわれはしも春なかりける」とあり
そこから推定して、「我」を「君」と書誤った、としている
勿論、原文のまま「君」として、
その解釈を「不遇の人、あるいは死亡した人をさす」とする注釈書もある
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕、
『万葉集総釈』〔楽浪書院、昭和10~11年成〕、
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕などが、そうだ
「羊蹄」を「し」と訓じるのは、借訓文字
『日本書紀』斉明紀五年三月の条の、地名「後方羊蹄」の訓注に、
「斯梨蔽之(しりへし)」とあり、
『和名抄』にも、「羊蹄菜」について「和名之布久佐(しふくさ)一云之(し)」とある
「羊蹄(し)」の原義は、
タデ科の多年草、原野や道端に自生する「羊蹄(ぎしぎし)」の古名といわれている |
| |
|
|
 |
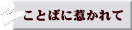  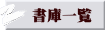  |











































