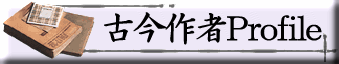
| 作 者 名 | 定家貞応年間書写本(一般的な古今和歌集) | 異本所載歌 | |
| あ | 在原元方 (ありはらのもとかた) | ||
| 業平の孫、棟梁の子。大納言藤原国経の猶子となる。猶子とは仮の親子関係だが、養子と異なり相続を目的としない。 |
1、130、195、206、261、339、473、 474、480、626、630、751、1062 (13) |
||
| 安倍仲麿 (あべのなかまろ) | |||
| 文武2年(698)生。霊亀2年(716)18歳で遣唐学生に選ばれ、吉備真備・玄昉らとともに翌年入唐。玄宗に仕え、李白・王維らと交わり文名が高かった。唐名朝衡。天平勝宝5年(753)、遣唐大使として入唐していた藤原清河とともに帰国しようとしたが、途中安南に漂着、同地の反乱に遭って一行のほとんどが殺害された。かろうじて唐に戻り、宝亀元年(770)その地で没した。在唐54年73歳。潞洲大都督の称号を贈られた。承和3年(836)贈正二位。 | 406 | ||
| お | 凡河内躬恒 (おほしかふちのみつね) | ||
| 選者の一人。寛平6年(894)2月、甲斐少目。延喜7年(907)丹波権大目。同11年、和泉権掾。淡路掾にもなっている。延喜7年宇多法皇の大堰川行幸に供奉して、貫之・是則・忠岑らとともに和歌を詠進、同16年の石山寺御幸、同21年の春日社御参詣等にも和歌を奉っている。生没年不明。 | 30、40、41、67、86、104、110、120、127、132、134、161、164、167、168、179、180、190、213、219、233、234、277、304、305、313、329、338、358、360、382、383、399、414、416、481、580、584、600、608、611、612、614、636、662、663、686、750、794、840、929、956、957、976、977、978、1005、1015、1035、1067 (60) | 1132、1137 | |
| き | 紀貫之 (きのつらゆき) | ||
|
選者の一人。貞観14年(872)生まれ?。紀茂行の子。延喜6年(906)年1月、平貞文・紀淑望とともに従五位下、2月越前権少 掾、これ以前に御書所預となっている。以後内膳典膳・少内記・大内記・加賀介・美濃介・大監物・右京亮などを経て、延長8年(930)正月土佐守、承平5年(935)2月帰京、天慶3年(940)3月玄蕃頭、5月旧のごとく朱雀院別当、同6年従五位上、同8年3月木工権頭。若くして「寛平御時后宮歌合」や「貞観親王家歌合」に歌をとられ、以後歌合では、昌泰元年(898)「亭子院女郎 花合」・延喜5年(905)「平貞文家歌合」・延喜13年「亭子院歌合」・「内裏菊合」等に歌を詠進している。また延喜7年には宇多法皇の大堰川行幸に供奉し、その折の宴に歌と序文を奉ったり、土佐守時代にはみずから歌合を催すほかに「新撰和歌集」を編み、後にその漢文序をつくっている。その他、数多くの屏風歌を作り当時の公的世界に仮名文字の文芸としての和歌の地歩を築くのに大きな役割を果たした。「土佐日記」は土佐国から帰任の途中の旅日記。天慶8年(945)8月から10月までの間に没?。 |
2、9、22、25、26、39、42、45、49、 58、59、78、79、82、83、87、89、94、115、116、117、118、124、128、156、160、162、170、232、240、256、260、262、276、280、297、299、311、312、323、331、336、342、352、363、371、380、381、384、390、397、404、415、427、428、436、439、460、461、471、475、479、482、572、573、574、579、583、587、588、589、597、598、599、604、605、606、633、679、697、729、734、804、834、838、842、849、851、852、880、881、915、916、918、919、931、980、1002、1010、1101、1103、1111 (102) |
1114、1115、1116 | |
| そ | 素性法師 (そせいほふし) | ||
| 遍照の子。俗名良峯玄利、良因朝臣ともいう。父が法師なので彼も出家させられ、雲林院に住み、寛平8年(896)雲林院に行幸の日に権律師となった。のちに石上の良因院に移った。昌泰元年(898)宇多上皇の大和の宮滝遊覧の折には、住居の名をとって良因朝臣と号して数日間前駆し、和歌を献じた。延喜年間にも諸所で屏風歌等を詠進している。延喜9年頃没?。 |
6、37、47、55、56、76、92、95、96、109、114、126、143、144、181、241、244、273、293、309、353、354、356、357、421、470、555、575、691、714、722、799、802、830、947、1012 (36) |
||
| に | 二条の后 (にでうのきさき) | ||
| 藤原長良の次女高子。承和9年(842)生。貞観元年(859)従五位下、五節舞姫となる。清和天皇の東宮時代にその妃となり、陽成天皇を産む。のち、女御、中宮となり、元慶元年(877)陽成天皇即位によって皇太夫人、同6年皇太后となったが、寛平8年(896)僧善祐と通じたかどによって后位を止められた。延喜10年(910)没、69歳。天慶6年(943)旧に復された。 | 4 | ||
| ふ | 文屋有季 (ふんやのありすゑ) | ||
| 「古今和歌集目録」には「有材」とある。底本・清輔本は「有季」。伝未詳。 | 997 | ||
| み | 壬生忠岑 (みぶのただみね) | ||
| 生没年未詳。壬生安綱の子。忠見の父。藤原定国の随身を勤めたことが「大和物語」に見え、右衛門府生、御厨子所預などを歴任、六位摂津権大目に至る。「寛平后宮歌合」の作者であり、早くから歌人として知られた。「古今和歌集」撰者の一人。三十六歌仙の一人。家集に「忠岑集」があり、「忠岑十体(和歌体十種ともいう)」という歌論書もある。「古今和歌集」に三十五首、「後撰集」以下に約四十七首ある。 | 835 | 1127 | |
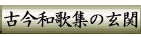 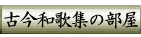 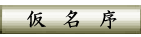 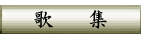 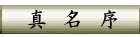 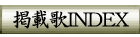
|
| BGM:四季「冬-第三楽章」/Vivaldi Yukiさん自作(ピアノ編曲)自演のBGMです |
|