この巻は東歌を集めた一巻である。短歌ばかり二百三十八首から成り、その中で国名を明らかにするものを前半に、不明の歌を後半に置き、後半を「未勘国歌」と称する。それは目録に「未勘国雑歌」などとすることによるが、本来は巻末に、「以前の歌詞は、未だ国土山川の名を勘へ知ること得ず」とあることから発したもので、その前半は「勘国歌」と呼ばれることがある。そのそれぞれを内容によって雑歌・相聞・譬喩歌などと細分する。
巻全体の構成は次のとおりである。
| 勘国歌 |
未勘国歌 |
| 雑 歌 3362~3366 |
5首 |
雑 歌 3457~3473 |
17首 |
| 相 聞 3367~3447 |
81首 |
相 聞 3474~3588 |
115首 |
| |
|
防人歌 3589~3593 |
5首 |
| 譬喩歌 3448~3456 |
9首 |
譬喩歌 3594~3598 |
5首 |
| |
|
挽 歌 3599 |
1首 |
この「勘国歌」は、三つの部立ごとに国名で分け、遠江以遠の東海道、信濃以遠の東山道、というふうに配列してある。表示すれば次のごとくなる。
| 雑 歌 |
上総(3362)、下総(3363)、常陸(3364・3365)、信濃(3366) |
| 相 聞 |
遠江(3367・3368)、駿河(3369~3375)、伊豆(3376)、相模(3377~3389)、武蔵(3390~3399)、
|
| |
上総(3400~3401)、下総(3402~3405)、常陸(3406~3415)、信濃(3416~3419)、上野(3420~3442)、 |
| |
下野(3443・3444)、陸奥(3445~3447) |
| 譬喩歌 |
遠江(3448)、駿河(3449)、相模(3450~3452)、上野(3453~3455)、陸奥(3456) |
この順序は『延喜式』や『「和名抄』などのそれと一致する。ただし、万葉当時、武蔵国は上野国と下野国との間に置かれていた。それが東海道に配属を改められたのは万葉集の最後の歌(4540)の作られた天平宝字三年(759)から十二年後の宝亀二年(771)冬十月のことである。この事実を拠に山田孝雄は万葉集の編纂成立の時期を宝亀二年よりも後とした。また、万葉集ではアヅマの範囲について、①足柄・碓氷両峠以東、②遠江・信濃以東、③鈴鹿・不破両関以東などと、いろいろに解釈できる用法を見るが、この巻のそれは②であることが知られ、また巻第二十の防人に徴発される東国兵士の地域的対象もまたこれと矛盾しない。これに比べれば歌数も合計十三首と少なく、正確な比較はできないが、『古今集』巻第二十にも東歌が並べられており、それは、みちのくのうた(1087~1093)、さがみのうた(1094)、ひたちのうた(1095・1096)、かひうた(1097・1098)、いせうた(1099)、という順序で、『延喜式』などとは逆の配列とも思われず、伊勢国を含めているのも万葉集とは異なっている。
|
 |
未勘国の歌については、雑歌は全く無秩序だが、相聞に関しては整然たる配列基準が認められる。即ち、まず「正述心緒」と「寄物陳思」とに分け、後者は、衣服(3500~3503)、器材(3504~3510)、植物(3511~3529)、気象(3530~3541)、動物(3542~3564)、地象(3565~3587)、神祇(3588)と並び、巻第十一・十二の順序とは多少異なっている。
この巻には、他巻にない訛音や東国語独特の語彙や語法の目立つ歌が多い。語法の点では「せろ」「ねろ」など非四段動詞の命令形にロが付いたものが見え、今日の関東方言の原型と見るべき傾向と説明されている。このロはまた、「児ろ」「背ろ」「嶺ろ」など、主に一音節名詞に付く接尾語(時には間投助詞的な働き)のそれと関係があろう。打消しの助動詞にナフという不規則変化の活用をする語があり、また「合はすがへ」など動詞の終止形について反語を表す終助詞ガへも中央語に見当たらない。音韻面では、中央語のチがシとなるのが目立つ。「いづち(何方)」「はなち(離)」がイヅシ・ハナシとなるなどがそれである。もっとも、当時、中央語ではチは「ti」、シはむしろ現在の「チ」と同じ「tʃi」であったか、と考えられるため、目くるめく思いがしなくもない。「降ろ雪」「引こ舟」など、動詞の連体形の活用語尾の母音がオ列甲類に開くとか、「かなしけ児ら」「なやましけ人妻」など、形容詞の連体形の活用語尾がエ列甲類の音のケになることがあるとかも注目される。
これらは言語面で観察される特色のほんの一端に過ぎないが、同じく東国方言で歌われた巻第二十の防人歌に比べれば方言色が少ないほうで、特殊仮名遣いの誤りについても、乱れ音節の枠がかなり狭い。東歌の言葉がこのように中央語に近い面があることについて、何者かによって京言葉に反転させられた「観念的俚言」ではなかろうか、という仮説も提出されている。一考の価値はあるが、それにしても「まつしだす」(3380)、「恋ふばそも」(3400)、「まゆかせらふも」(3563)などの難解な用語がままあり、そのために口語訳でやむを得ず原語のままにしたところが幾つかある。
|
右のことと恐らく関連することであろうが、一般に、格別に民謡的性格が濃いといわれる東歌のうち、特に巻首辺りに、京人の作ではないかと言う人もあるくらいに洗練された詠風の歌が散見する。
| |
夏麻引く海上潟の沖つ洲に船は留めむさ夜更けにけり |
3362 |
| |
葛飾の真間の浦廻を漕ぐ船の船人騒く波立つらしも |
3363 |
| |
信濃なる須我の荒野に霍公鳥鳴く声聞けば時過ぎにけり |
3368 |
などがそれである。第一首冒頭の歌は上三句が巻第七の1179と全同で、歌境は巻第三・276の高市黒人の羈旅歌や巻第七の1233に共通している。第二首も巻第七・1232の上二句「風早の三穂の浦廻を」を東国の地名にすげ替えたに過ぎない。
また、この巻の中には「人麻呂歌集に出でたり」という脚注や左注を有する歌が五首もある。
| |
ま遠くの雲居に見ゆる妹が家にいつか至らむ歩め我が駒 |
3460 |
は、巻第七の1275、「行路」の題詞を持つ『人麻呂歌集』の歌と小異はあるが、古代の歌集ではこの程度の異同は無視してよい。
| |
相見ては千年やいぬるいなをかも我れやしか思ふ君待ちがてに |
3489 |
は、巻第十一の2544と重出であるが、それは『人麻呂歌集』出でなく、出典不明の歌群の中に属するのは編纂者の見誤りであろう。
| |
あり衣のさゑさゑしづみ家の妹に物言はず来にて思ひ苦しも |
3500 |
も『人麻呂歌集』出というのだが、その相手方の「玉衣のさゐさゐしづみ」(506)は「柿本朝臣人麻呂が歌三首」という題詞の下に収められたものの一首でしかない。もっとも、巻第三・四の中の「人麻呂作歌」には、巻第一・二におけるそれほどに伝来の確かでないものがあると思われる(現にその三首のうちの一つ504の相手は巻第十一・2419で『人麻呂歌集』出歌群に属する)。あとの二首、
| |
上野伊奈良の沼の大藺草外に見しよは今こそまされ |
3436 |
| |
梓弓末は寄り寝むまさかこそ人目を多み汝をはしに置けれ |
3510 |
に至っては連れ合いを探すすべがない。万葉集に現存する以外に、かつて存在していた『人麻呂歌集』の中にこの原歌があったのであろうか。あるいは編纂者の思い違いということも考えられないでもない。
東歌にはまだ疑問の点が多く、今後の研究に待つところが量り難いばかりに残されている。 |
 |
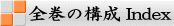 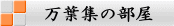 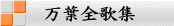 |
 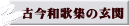 |
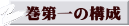 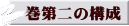 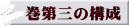 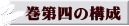 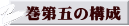 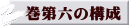 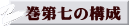 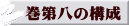 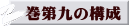 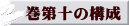 |
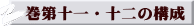 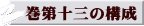 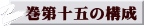 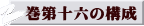 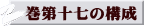 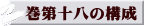 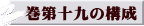 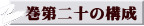 |