この巻は、作者名を記さないという一点を除けば、巻第八と構造を同じくする。即ち、縦に春・夏・秋・冬の四季の別を設け、横を雑歌・相聞の二部に切り分ける。ただし、歌の新古を判ずるすべがないため、詠み込まれている事物、言うなれば「季語」を頼りに「物」単位にまとめて、雑歌は「詠何」、相聞は「寄何」の題詞を置き、その建前で通せる限り通すことに努め、窮すれば臨機応変の題を立てることにする。これは巻第七の雑歌・譬喩歌における方針と同じである。この「詠何」「寄何」の題の置き方は、これら作者不明歌群の中にあって模範とした先行資料たる『人麻呂歌集』ならびに『古歌集』(『古歌』というも同じであろう)の分類・配列に倣ったものであるが、それら一代前に成った歌集から移したものと、それ以外の出典不明の歌とを混ぜないように、左注にいちいち「右何首柿本朝臣人麻呂歌集出」などと記してある。ただし、巻第七ではその原拠の示し方に一貫性がなく、整理不充分な点が認められたが、巻第十では、八項目中六項まで、最初にそれらの先行資料を内容によって細分せず、無題のままに据える。
例えば、巻首「春雑歌」の題目の次に題なしで『人麻呂歌集』出の歌七首が置かれている。それら七首は偶然にも共に霞を詠んだ歌であるが、出典不明の部で「詠霞」の題詞を立てた1847以下の三首の前などにそれを置くことをしない。「春相聞」でも同様に『人麻呂歌集』出の無題七首が並ぶが、その内容は、鳥(1894)・花(1895)の次にまた鳥(1896)・花(1897)が来ており、恐らく原資料の配列のままに記したのであろう。この形式に従わない「秋雑歌」は、『人麻呂歌集』出(計54首)が四箇所(「七夕」「詠花」「詠黄葉」「詠雨」)に分散している。その原因は、けだしその中の七夕歌(38首)の歌数が著大に多いことにあろう。「夏雑歌」でもその標目の次に題詞「詠鳥」があって、その初めに「右古歌集中出」の左注を有する長反二首の歌が置かれている。巻第十も、この点から言えば必ずしも厳密に体裁が整っていると言い切れない。
|
 |
右の不揃いとは直接の関係がないが、巻第十の現存本の転写過程の比較的古い段階に生じたとおぼしい脱漏を二点あげておこう。その一つは、「春雑歌」の中に「詠雪」の題詞があるべくして見当たらないことである。前に触れた『人麻呂歌集』の七首(1816〜1822)の次に「詠鳥」の題で二十四首の歌が並んでいるが、その題に正しく当てはまるのは1835までの十三首で、その次の「うちなびく春さり来ればしかすがに天雲霧らひ雪は降りつつ」(1836)を初めとする十一首は、春の雪を詠んだものでしかない。ただ注目すべき本として紀州本があり、それには1836の歌の前に「詠雪」の題詞がある。それが後世の書写者の書入でない証に同本の目録にも「詠鳥二十四首」の下に小字で「十三或詠残雪十一首或本」とあるのを示せばよかろう。紀州本だけが原本の姿を留めていると思われる。
今一つの脱漏は「春相聞」の末尾の「譬喩歌」の題詞および歌(一首?)である。これは紀州本だけでなく、元暦校本の赭(元赭)と広瀬本とも共通するが、この部分(1940の次)に「譬喩歌」の一行がある。巻第七には譬喩歌が108首もあるため、雑歌に比肩する部立の一つとしての扱いがなされていたが、巻第十では、歌数僅少のゆえをもってか、題詞並みに格下げされて、「春雑歌」「夏雑歌」「秋相聞」の各最後に一首ずつ置かれている。それを思えば、原本では、「春相聞」の末尾にも譬喩歌があったに違いない。目録に、元暦校本だけであるが、「問答十一首」の次に「譬喩歌不見」とあるのもそれを証明する。
|
巻第十に限らないが、作者不明の巻々の歌に類歌・小異歌が多いことは先に一部の例を引いて述べた。その中の幾つかは他人の空似というべき場合もあろうが、やはり歌が原作者の許から離れて漂い歩き、多数の人の共感・支持を得て広域社会の共有俗謡となり、あるいは無意識に、あるいは故意に、地名や人称語などの置き換えが行われるようになったケースが多かろう。この巻の中だけでも、
このころの暁露に我がやどの萩の下葉は色づきにけり (2186)
このころの暁露に我が宿の秋の萩原色づきにけり (2217)
我が門の浅茅色づく吉隠の浪柴の野の黄葉散るらし (2194)
我がやどの浅茅色づく吉隠の夏身の上にしぐれ降るらし (2211)
などが拾い上げられ、他巻の歌との類似例には次のようなものがあり、一部に作者名を明らかにするものも混じる。
片縒りに糸をぞ我が縒る我が背子が花橘を貫かむと思ひて (1991)
紫の糸をぞ我が搓るあしひきの山橘を貫かむと思ひて (巻第七・1344)
うち靡く春さり来らし山の際の遠き木末の咲きゆく見れば (1869)
うち靡く春来るらし山の際の遠き木末の咲きゆく見れば (巻第八・1426 尾張連)
春日なる羽がひの山ゆ佐保の内へ鳴き行くなるは誰れ呼子鳥 (1831)
滝の上の三船の山ゆ秋津辺に来鳴き渡るは誰れ呼子鳥 (巻第九・1717 作者未詳)
春霞山にたなびきおほほしく妹を相見て後恋ひむかも (1913)
香具山に雲居たなびきおほほしく相見し子らを後恋ひむかも (巻第十一2453)
恋ひつつも今日は暮らしつ霞立つ明日の春日をいかに暮らさむ (1918)
恋ひつつも今日はあらめど玉櫛笥明けなむ明日をいかに暮らさむ (2896)
煩を避けてこれ以上例示することは控えるが、この類の類歌・小異歌の多さは、次の巻第十一および巻第十二の両巻の間で一段と数を増す。便利な計器類のなかった当時のことゆえ、この程度の類同は欠陥として咎め立てるに当らぬとも言えようが、作者不明の巻々の没個性的一面を示す何よりの証でる。
|
 |
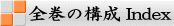 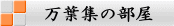 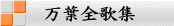 |
  |
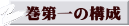 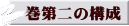 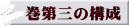 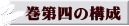 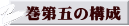 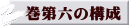 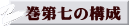 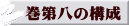  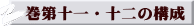 |
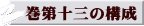  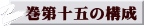 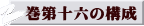 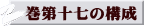 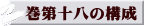 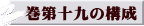 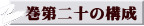 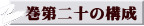 |