|
|
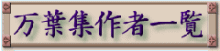
|
| 歌番号は、すべて「新編国歌大観」に依るもの。併用されている書籍もあるので、参考にして欲しい。ただし説明内容は、小学館「新編日本古典文学全集」巻末人名解説を中心にしている。 尚、歌番号の相違は、底本とする古写本で、「在る本では」とか「一つには」、あるいは題詞の中の「漢詩」などの歌数への取り扱い方が大きいと思う。 〔参考『万葉集全巻の構成及び歌数 -新国歌大観歌番号による』〕 |
| 県犬養橘美千代 (あがたいぬかひのたちばなのみちよ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はじめ美努王(敏達天皇の玄孫、708年卒)嫁して、葛城王(橘諸兄)らを生んだが、後に藤原不比等の室となり、光明子(701年生まれ、聖武天皇の皇后)を生み、天平五年(733)に薨じた。 従一位追贈、更に後、正一位を追贈、大夫人と追尊された。 19-4259 6-1014左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県犬養宿禰持男 (あがたいぬかひのすくねもちを) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝未詳。次項吉男の兄弟か。県犬養宿禰は、前項橘美千代の実家。 8-1590 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県犬養宿禰吉男 (あがたいぬかひのすくねよしを) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天平勝宝二年(750)正六位上で但馬掾となり、天平宝字二年(758)従五位下。その後、肥前守、上野介、伊予介などを歴任した。 8-1589 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県犬養宿禰人上 (あがたいぬかひのすくねひとかみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝未詳。内礼正であった時、詔によって大伴旅人の看護を命ぜられた。 3-462 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安貴王 (あきのおほきみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 志貴皇子の孫。春日王の子。天平元年(729)従五位下、同十七年従五位上。 神亀元年(724)頃因幡八上采女を娶って、愛情盛んであったが、不敬の罪に当てられ、本郷に退けられた後悲嘆して詠んだ歌が見える。妻は紀女郎。子の市原王は自分が一人子であることを嘆いている。 3-309 4-537,538 8-1559 4-646題、6-993題 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安積皇子 (あさかのみこ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖武天皇の皇子。母は夫人県犬養広刀自。天平十六年(744)閏正月十一日難波行幸があった時、脚病を発して、河内の桜井頓宮(東大阪市若草町付近)から恭仁京に帰り、翌々日没した。 年十七歳。藤原氏から出た光明皇后の生んだ子は安倍内親王(後の四十六代孝謙天皇)しかいないため、有力な皇位継承候補を除く目的で藤原仲麻呂が皇子を毒殺したとする説もある。 3-478題、6-1044題 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝倉益人 (あさくらのますひと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上野国の防人。伝未詳。「孝徳紀」に「朝倉君」(名不明)という東国の豪族が見え、「和名抄」の上野国那波郡朝倉郷(現前橋市朝倉)付近の出身と考えられる。 君姓を持たない朝倉氏もそれと関係があろう。 20-4429 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻田連陽春 (あさだのむらじやす) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渡来人系の人で初め答本陽春といったが、神亀元年(724)正八位上の時、麻田連を賜る。天平初年大宰府の大典として筑前に在り、大伴君熊凝の死を悼み、代わってその志を述べる歌を詠んでいる。 「大宰府牒案」にも天平三年(731)当時従六位上大宰大典であったことを記す。同十一年外従五位下。のち石見守となり、在任中に賦した詩一首を「懐風藻」に伝える。十七年以後の作であろうという。 4-572,573 5-888,889 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葦屋の処女 (あしのやのをとめ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摂津国菟原郡(今の兵庫県芦屋市から神戸市の東部にかけての地)の東部、葦屋の辺に住んでいたといわれる伝説上の美人。菟原処女と呼ぶこともある。千沼壮士と菟原壮士と、二人の男に求婚されて自殺したという説話は、後の「大和物語」の中にもあり(147段)、そこではいっそう説明的要素が付加されている。現在、神戸市東灘区御影塚町に処女塚と称する古墳があり、その東西に求女塚と呼ばれる古墳が、東灘区住吉宮町と灘区味泥町にある。妻争いの伝説はむしろこれらの古墳群を見て生まれたものか。 9-1805題詞、歌・1806、1813題詞、歌・1814、19-4235題詞、歌・4236 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安宿王 (あすかべのおほきみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長屋王の子。母は藤原不比等の娘。天平九年(737)従五位下。玄蕃頭・治部卿・中務大輔などを経て天平勝宝三年(751)正四位下、同五年四月播磨守となった。翌年九月内匠頭を兼ね、万葉集の記載によると、同八年頃讃岐守であったことが知られる。天平宝字元年(757)橘奈良麻呂の変に座し、佐渡に流されたが、のち許されたらしく、宝亀四年(773)には高階真人の姓を賜っている。 20-4325,4476 20-4496題詞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安宿奈杼麻呂 (あすかべのなどまろ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百済公奈登麻呂ともある。天平神護元年(765)正六位上から、外従五位下を授けられた。 20-4496 20-4497左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明日香皇女 (あすかのひめみこ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天智天皇の皇女。母は大臣安倍倉梯麻呂の娘、橘娘。文武四年(700)浄広肆の位で薨。 2-196題 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚見王 (あつみのおほきみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統未詳。天平勝宝元年(749)従五位下。同七年、少納言であった時に奉幣使として伊勢神社に派遣され、天平宝字元年(757)従五位上となった。 4-671 8-1439,1462 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安曇外命婦 (あづみのげみやうぶ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝未詳。安倍朝臣虫麻呂の母。 4-670左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安曇宿禰三国 (あづみのすくねみくに) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天平宝字八年(764)に従五位下に叙せられた。藤原仲麻呂討伐に功があったとの理由による。 20-4448左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安都宿禰年足 (あとのすくねとしたり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝未詳。宝亀年間(770~80)に経師として頻出する阿刀(阿都)年足との異同は明らかでない。 4-666 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安都扉娘子 (あとのとびらのをとめ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝未詳。安都は氏。扉は名か。家持をとりまく女性たちの一人。 4-713 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粟田朝臣人 (あはたのあそみひと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必登とも記す。和同四年(711)従五位下。同七年迎新羅使右副将軍となり、神亀元年(724)従五位上に進んだ。 (5-821) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粟田朝臣人上 (あはたのあそみひとかみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和銅七年(714)従五位下。天平元年(729)正五位上。同四年造薬師寺大夫となり、武蔵守従四位下で卒した。 (5-821) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粟田女王 (あはためのおほきみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統未詳。養老七年(723)従四位下。天平十一年(739)従四位上、同二十年三月正四位上。天平宝字八年(764)正三位で薨じた。 18-4084 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粟田女娘子 (あはためのをとめ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝未詳。家持に歌を贈っている。粟田は姓か。 4-710,711 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淡海真人三船 (あふみのまひとみふね) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大友皇子の曾孫。葛野王の孫。池辺王の子。はじめ御船王といったが、天平勝宝三年(751)淡海真人の姓を賜った。同八歳五月内豎であった時に、出雲守大伴古慈悲と共に朝廷を謗り、人臣として礼に欠けるところがあったというかどで、左右衛士府に禁ぜられたが、三日後に許された。天平宝字五年(761)従五位下、参河守となり、更に文部少卿、美作守、兵部大輔、大宰少弐、刑部大輔、大学頭兼文章博士などを歴任した。延暦四年(785)刑部卿従四位下兼因幡守で卒。六十四歳。聡明で群書を広く読み、文筆に秀で、「経国集」に五首の詩を載せ、また宝亀十年(779)「唐大和上東征伝」一巻を撰した。藤原仲麻呂の謀叛の際、当時、造池使として近江国の陂池の修理に携わっていた三船は、宇治から近江国の国衙に逃れようとする仲麻呂の使者を捕え、勢多の橋を焼き、瀬田川の渡河を不能にし、仲麻呂に打撃を与えた。その功によって正五位上勲三等を授けられ、更に近江介に任ぜられたという。 20-4491左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安倍朝臣息島 (あへのあそみおきしま) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天平勝宝四年(752)十月頃、上野介正六位上であったことが、正倉院宝物古裂の調黄絁墨書によって知られる。 5-828 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安倍朝臣奥道 (あへのあそみおきみち) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天平宝字六年(762)従五位下。若狭守、大和介、摂津大夫、左衛士督、中務大輔、左兵衛督、内蔵頭などを歴任。宝亀五年(774)但馬守従四位下をもって卒。一時息部姓を称していたことがある。藤原仲麻呂の乱に座して改姓させられたものか。 8-1646 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安倍朝臣沙美麻呂 (あへのあそみさみまろ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天平九年(737)従五位下。少納言、左中弁などを歴任。天平勝宝元年(749)従四位上となり、天平宝字二年(758)中務卿参議正四位下で卒。 20-4457左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安倍朝臣継麻呂 (あへのあそみつぐまろ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天平七年(735)従五位下。翌年二月遣新羅大使となって六月に出発したが、その帰途対馬において卒した。 15-3678,3690,3722,3728,3730 15-3671左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安倍朝臣豊継 (あへのあそみとよつぐ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天平九年(737)外従五位下から従五位下に進む。 6-1007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安倍朝臣広庭 (あへのあそみひろには) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 右大臣御主人の子。慶雲元年(704)頃従五位上。伊予守、宮内卿、左大弁、参議、知河内和泉事などを歴任。神亀元年(724)頃従三位となり、同四年中納言に進んだ。天平四年(732)七十四歳で薨。 「懐風藻」に詩二首がある。 3-305,373 6-980 8-1427 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安倍朝臣虫麻呂 (あへのあそみむしまろ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿部とも書く。安曇外命婦の子。天平九年(737)外従五位下。皇后宮亮、中宮少進、中務少輔などを歴任。同十二年藤原広嗣の謀叛の際、佐伯常人とともにこれを討ち、その功によって従五位上に進み、翌年播磨守となり、天平勝宝四年(752)中務大輔従四位下で卒した。 4-668,675 6-985 8-1581,1582 4-670左注、6-1045題、8-1654左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿倍女郎 (あへのいらつめ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉集には阿倍女郎・安倍女郎と記したものが少なくとも二人は見える。 a 〔271〕の作者。 b 〔508,509〕の作者。安倍と記す。 c 〔517,519〕の作者で、中臣朝臣東人がこれに答えている。4-518題。 d 〔1635〕の題詞に見え、家持が歌を贈っている。安倍と記す。 一般には d だけ切り離し、abc を同一人見るが、c は a よりやや時代が遅れ、異同が明らかでない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海犬養宿禰岡麻呂 (あまのいぬかひのすくねをかまろ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻第六-996(1001) 注『海犬養宿禰岡麻呂』」より引用】 犬を飼養して屯倉や宮廷の蔵の警備にあたった犬養部を掌握する氏族。後に軍事氏族となり、複姓の県犬養氏は茅淳県(ちぬのあがた)、若犬養氏は内蔵の警備にあたったのでこの名があり、海犬養氏や安曇犬養氏は、海部を管掌する安曇氏と関係をもつようになって、この名となったといわれる。藤原宮、平城宮および初期の平安宮の宮城門(十二門)には、それぞれこの門を警備した由来をもつ氏族の門号がついており、県犬養門(後の郁芳門)、若犬養門(皇嘉門)、海犬養門(安嘉門) もその例であり、これら十二氏を門号氏族という。三氏は天武十三年(684)十二月、連(むらじ)より宿禰の姓を賜う。天平十二年十二月の藤原広嗣の乱に、軍曹として従軍した海犬養宿禰五百依の名が見えるが(続紀)、天平宝字五年(761)の正六位上右京少進が、見得る最後の記述であり(正倉院文書、「摂津国安宿王家家地倉売買券」および「神祇大輔中臣毛人等百七人歴名」)、海犬養氏は、奈良時代に至っては、従五位下に昇進しえない階層となっていたかにみえる。ただこの五百依は天平勝宝三年(751)十一月、橘諸兄の家令であった(正倉院文書、左大臣家蝶)。家令としての職は天平年間にも遡りえよう。とすれば、岡麻呂が詔に応じえた事情や、岡麻呂の作が家持の手に渡りうる事情も、ある程度推定を可能にしうる。 6-1001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荒木稲布 (あらきだ/くわうじのいなしき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻第五-832(836) 注『荒氏稲布』」より引用】 大宰府の主神。正七位下相当。諸々の祭祠の事を掌る。荒氏は、「荒木・荒木田・荒田」 その他が考えられるが、神官としては荒木田氏がふさわしい。稲布は伝未詳。 5-836 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有間皇子 (ありまのみこ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三十六代孝徳天皇の皇子。母は安倍倉梯麻呂の娘小足媛。斉明三年(657)狂人をよそおい、紀伊の牟婁の湯に療養し、帰京後、伯母の斉明天皇にその効を説いた。翌四年冬、天皇・皇太子(天智)らが牟婁におもむいた間に、留守官の蘇我赤兄にそそのかされて、謀反を謀ったが、当の赤兄に捕らえられ、十一月九日牟婁に護送されて、皇太子自らの訊問を受けた。有間皇子は、天と赤兄とのみが知る、自分は知らぬと答えた。許されて帰京するかと思われたが、十一月藤白坂(和歌山県海南市藤白)で絞首刑に処せられた。時に年19歳。 (141、142)作歌。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雄略天皇 (いうりやくてんわう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十一代。諡は大泊瀬稚武天皇、泊瀬朝倉宮御宇天皇と呼ばれる。允恭天皇の第五子。「古事記」や「日本書紀」に直情径行に振舞った伝説やそれにまつわる歌謡が多く見られる。即ち、兄安康天皇を暗殺した従弟の眉輪王を討ったばかりでなく、この仇討ちに協力的でなかった兄皇子たちを殺し、また皇位継承のライバル磐坂市辺押磐皇子をも欺き殺した後、皇位についた。即位後も粗暴な振る舞いが多かったので、天下こぞって「甚だ悪しくいます天皇なり」と言ったという。女性関係でも無造作であったとする説話に富み、三輪川で洗濯する童女に結婚の約束をしたまま忘れて八十年間待たせたとか、春日の袁杼比売に求婚しにおもむいた際、袁杼比売が岡辺に隠れたので、「娘子のい隠る岡を金鉏も五百箇もがも鉏きばぬるもの」と歌を詠んだとか、逸話も多く、万葉集の巻頭「籠もよみ籠持ち」の作者として伝えられるのも不審でならない。埼玉県稲荷山古墳の鉄剣銘に「斯鬼宮」で天下を治めたと見える「獲加多支鹵大王」や、熊本県江田船山古墳の鉄剣に見える「治天下獲□□□鹵大王」はこの天皇と見られ、既にその統治が九州から関東に及ぶ全国的なものであったことが知られる。また477?~502年の間に南朝の諸王朝に使いを派遣し、その冊封を受けた倭国王武とはこの雄略天皇のことか、といわれる。この通交は低下しつつあった朝鮮半島での日本の影響力を挽回する意図から出たものと考えられる。「日本書紀」によると在位二十三年、六十二歳で崩じたとある。「古事記」の百二十四歳崩御の記事は信じられない。 1-1 9-1668 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軍王 (いくさのおほきみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝未詳。一説に「日本書紀」に見える軍君と同義で、百済の義慈王の子で日本に質となって滞在していた余豊璋かとする。 その場合コニキシオホキミと読み、コニは軍(君と同音)の百済音、キシは敬称とになされる。 1-5,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池田朝臣真枚 (いけだのあそみまひら) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天平宝字八年(764)従五位下を授けられ、軍監、上野介、少納言、長門守を経て、延暦六年(787)鎮守府将軍となったが、敗軍の責任を問われ、官を解かれた。 16-3862題詞・3863歌 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池辺王 (いけのへのおほきみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大友皇子の孫。葛野王(天智天皇の皇子大友皇子の子)の子。淡海三船の父。神亀四年(727)従五位下。天平九年(737)内匠寮の長官となる。淡海三船の卒伝によると従五位上まで上ったことが知られる。 4-626題 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川朝臣君子 (いしかわのあそみきみこ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉美侯とも。号を少郎子という。和銅六年(713)従五位下。播磨守、兵部大輔、侍従などを歴任。神亀元年(724)正五位下、同三年従四位下に進んだ。 この頃風流侍従の一人として知られている。万葉集には神亀年中(724~29)に大宰少弐になったとあるが、「続日本紀」にそのことはもれている。 3-281 3-248左注・281左注、9-1780題、11-2751左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川朝臣足人 (いしかはのあそみたるひと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和銅四年(711)従五位下。神亀元年(724)従五位上。その後、大宰少弐となって帥の大伴旅人の配下にあったが、同五年遷任し、大宰府を去った。 6-960 4-552題 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川朝臣年足 (いしかはのあそみとしたり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 左大弁従三位石足の長子。蘇我氏の末裔。少判事を振出しに官途につき、天平七年(735)従五位下。出雲守・陸奥守・左中部弁・春宮大夫・式部卿・治部卿・大宰帥・兵部卿・中納言などを歴任。 天平宝字六年(762)御史大夫(大納言)正三位兼文部卿(式部卿)神祇伯で薨じた。藤原仲麻呂と親しく、中臣氏以外から神祇伯に任ぜられたのは珍しい。 またしばしば写経業を行い、「大般若経」を浄土寺(飛鳥の山田寺)に施入するなどのこともあった。卒伝によれば政務に練達で、出雲守時代に善政を施したという。 大阪府高槻市真上からその墓誌と火葬墓が発見されている。年七十五歳。 (9-1732) 19-4298 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川朝臣広成 (いしかはのあそみひろなり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天平宝字二年(758)従五位下。同四年高円朝臣の姓を賜り文部少輔となった。 「新撰姓氏録」の記載などから、文武天皇の皇子(母は石川刀自娘)であったが、首皇子(後の聖武)を擁する藤原氏の策謀によって、和銅六年(713)十一月に母刀自娘が嬪の地位を退けられ、それとともに臣籍に下ったとする説がある。 4-699 8-1604,1605 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川朝臣宮麻呂 (いしかはあそみみやまろ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大臣大紫石川連子の子。慶雲二年(705)従四位下大宰大弐。和銅六年(713)右大弁従三位で薨。 3-248左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川郎女(いしかはのいらつめ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉集には石川郎女または石川女郎が詠んだとする歌が八首あり、かつその異同が明らかでないものが、多く見て六人ある。 1. 久米禅師に求婚され、これと唱和した天智天皇代のもの。(97,98) 2. 字は大名児、石川女郎ともいい、また同一歌でも古写本相互で、時に本条と目録とで相違することがある。草壁皇子の求愛を退けて、大津皇子と逢い、津守連通に占いで暴露されたもの。 (108)の作者で、(107,109,110)の題詞にも その名が見える。 3. 石川女郎とあり、計略によって大伴宿祢田主に近づいたが思いを果たさず、後で戯れの歌を贈ったもの。(126,128)の作者。 4. 大津皇子の宮の侍女、石川女郎とあり、字を山田郎女とも言うもの。大伴宿祢宿奈麻呂に歌を贈っている。(129)の作者。 5. 安曇外命婦(安倍朝臣虫麻呂の母)と姉妹で、石川内命婦・石川命婦・佐保大伴大家などと呼ばれ諱を邑婆と言うもの。大伴安麻呂に嫁し、坂上郎女を生んだ。 長命で天平九年(737)頃まで生きていたらしい。(521,4463)の作者。 6. 石川女郎とあり、藤原宿奈麻呂(宇合の第二子、716-77)の妻であったが、愛情が薄れ離別された。(4515)の作者。 上記のうち、「1」,「6」はともに年代的に離れすぎ明らかに別人。「2」、「3」、「4」については、「2」、「4」同一人、「2」、「3」、「4」とも同一人などの諸説があるが、ともに決定は困難。 「5」はそれらと年代的に矛盾はしないが、大伴氏内部の問題としてそれら「2」、「3」、「4」のいずれとも結びつく可能性は薄い。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川夫人 (いしかはのぶにん) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「天智紀」には夫人と呼ばれるものが見えず、嬪の一人、蘇我石川麻呂の娘、姪娘などをさすかというが疑わしい。 「天武紀」朱鳥元年(686)に見える石川夫人は、蘇我赤兄の娘で大蕤娘と呼ばれ、天武夫人となって穂積皇子や紀皇女を生み、神亀元年(724)に没した人だが、この人を遡らせて呼んだものか。 2-154 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川命婦 (いしかはのみやうぶ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川内命婦・佐保大伴大家などとも呼ばれ、諱を邑婆といった。石川年足らと同じく蘇我氏の出身か。大伴安麻呂の後妻となり、坂上郎女らを生んだ。 長命であったらしく、天平九年(737)頃まで存命していた。 4-522 20-4463 3-464左注、4-670左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石上朝臣乙麻呂 (いそのかみのあそみおとまろ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弟麻呂にも作る。左大臣石上麻呂の第三子。宅嗣の父。神亀元年(724)従五位下。 天平四年(732)従五位上丹波守となったが、同十一年従四位下左大弁の時、久米連若比売(藤原宇合の未亡人)と通じた罪で土佐国に流され、同十三年頃許された。 同十八年正月、その人物を買われて遣唐大使に任ぜられたが、計画は実行されずに終わった。常陸守・右大弁を経て、天平勝宝二年(750)従三位中納言兼中務卿で薨。 「懐風藻」に詩四首を載せるほか、詩集「銜悲藻」二巻(逸書)があった。 3-371,377 6-1024題 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石上朝臣堅魚 (いそのかみのあそみかつを) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 養老三年(719)従五位下。神亀三年(726)従五位上。天平三年(731)正五位下。同八年正五位上。 8-1476 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石上朝臣麻呂 (いそのかみのあそみまろ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もと物部連。壬申の乱では近江方についたが、乱後は天武天皇に仕えた。天武五年(676)遣新羅大使に任ぜられ、翌年帰国。 大宝元年(701)正三位大納言となり、大宰帥を兼ね、慶雲元年(704)右大臣、和銅元年(708)左大臣正二位に進んだ。養老元年(717)七十八歳で薨。従一位に追贈された。 1-44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石上朝臣宅嗣 (いそのかみのあそみやかつぐ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中納言乙麻呂の子。天平勝宝二年(751)従五位下となり、参河守、上総守、文部大輔、大宰少弐、常陸守、中衛中将などを歴任。天平神護二年(766)参議となった。 神護景雲二年(768)従三位。更に式部卿兼大宰帥、中納言兼中務卿を経、天応元年(781)大納言正三位兼式部卿をもって薨。五十三歳。正二位を追贈された。 文人としても知られ、書庫を建てて芸亭と名付け、その蔵書を一般に公開した。「経国集」「唐大和上東征伝」に詩を載せる。 19-4306 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 板茂連安麻呂 (いたもちのむらじやすまろ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神亀二年(725)三月、書学生の貢進に当り、安麻呂その他の筆跡を基準としたことが「令集解」学令の古記によって知られる。 当時、能書の聞え高かった人と思われる。天平七年(735)九月に右大史従六位下。 5-835 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市原王 (いちはらのおほきみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 志貴皇子の曾孫。安貴王の子。天平十五年(743)従五位下。備中守、玄蕃頭などを歴任。天平勝宝八年(756)に正五位下冶部大輔と見えている。天平宝字七年(763)造東大寺長官。 正倉院文書によると、天平十一年以降、皇后宮職およびその後身の金光明寺(東大寺)の写経司に出仕して長官にもなったことが知られる。 3-415 4-665 6-993,1012,1046 8-1550,1555 20-4524 8-1598左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出雲娘子 (いづものをとめ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝未詳。 3-432題詞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因幡八上采女 (いなばのやかみのうねめ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因幡国八上郡(現在の鳥取県八頭郡)から出た采女。一説に藤原麻呂の子、浜成(「歌経標式」の著者)の生母かとされる。 4-538左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石田王 (いはたのおほきみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統未詳。ただし「薬師寺縁起」には忍壁皇子の子で山前王の弟とある。イシダとも読まれる。仮にイハタと読む。 3-423題、425題、428左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磐姫皇后 (いはのひめわうごう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仁徳天皇の皇后。武内宿禰の孫。葛城襲津彦の娘。履中・反正・允恭三天皇を生む。仁徳天皇が女性遍歴を続けたことを怒り嫉妬し、相手の吉備の黒比売らをその郷里に退けたことが記紀に見える。 仁徳三十五年山背の筒城宮で崩じた。 2-85~89 2-90左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊保麻呂 (いほまろ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝未詳。「下総国養老五年戸籍」の孔王部五百麻呂をはじめ、同名の人は多い。 9-1739 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今城王 (いまきのおほきみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「東大寺奴婢籍帳」によると、天平二十年(748)頃正七位下兵部少部であったことが知られる。天平宝字元年(757)従五位下。冶部少輔、左少弁、上野守、駿河守などを歴任。同八年正月従五位上。 藤原仲麻呂(恵美押勝)の乱(764)に座して本位を奪われたが、宝亀二年(771)復位。母の大伴女郎について諸説があるが、岸本由豆流の「攷証」に、大伴坂上郎女ではないか、父親は穂積皇子であろう、とするのが最も当を得ていると思われる。それによれば坂上大嬢の異父兄、家持とはいとこ同士の関係に当り、巻第二十を中心とした両人の親密な関係が自然に理解できる。 →大原真人今城 8-1608 20-4466,4468,4483,4499,4500,4520,4529,4531 4-522題、540題、20-4463左注、4464題、4504左注、4505題、4506左注、4516題、4539題 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 忌部首黒麻呂 (いむべのおびとくろまろ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天平宝字二年(758)従五位下。翌年連姓を賜り、同六年内史局(図書寮)助となった。 6-1013 8-1560,1651 16-3870 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允恭天皇 (いんぎょうてんわう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十九代。諡は雄朝孋稚子宿禰天皇と呼ばれる。仁徳天皇の皇子。母は磐姫皇后。 姓氏の混乱を正すために盟神探湯(神に誓って熱湯に手を入れ、その結果によって真偽を判断すること)を行い、また新羅と親善したという。 「日本書紀」には、皇后の妹弟姫を愛し、これと唱和した短歌四首が見える。 2-90左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇治若郎子 (うぢのわきいらつこ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応神天皇の皇子。母は日触使主の娘、宮主宅媛。仁徳天皇の異母弟。山背国宇治の宮に住んだので菟道稚郎子と呼ばれた。百済の博士王仁に典籍を学び、大いに通達した、という。 応神天皇はその才を愛して皇太子とし、大鷦鷯皇子(仁徳)をその補佐役に任じたが、応神崩後、仁徳と皇位を譲り合い、ついに自殺したとある。 9-1799題詞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇遅部黒女 (うぢべのくろめ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武蔵国豊島郡の防人椋椅部荒虫の妻。伝未詳。宇遅部は応神天皇の皇子宇遅和紀郎子(宇治若郎子)の名代といわれる。 武蔵国の国分寺跡出土の瓦の銘に、同国豊島郡の人で宇遅部白岐太など、同じ姓を残す者が数名見える。 20-4441 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海上女王 (うなかみのおほきみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海上王とも記す。志貴皇子の娘。養老七年(723)従四位下。翌神亀元年従三位に進んだ。 4-534 4-533題 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇努首男人 (うぬのおびとをひと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百済系の出身。養老四年(720)正六位上豊前守で隼人の乱を鎮める将軍となる。〔964〕の歌が詠まれた神亀五年(728)当時も豊前守であった。 6-964 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 味稲 (うましね) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柘枝伝説に見える吉野川沿岸の漁夫の名。「懐風藻」には美稲と見え、ともにウマシネと読まれるが、「続日本後紀」の長歌には熊志禰となっている。 3-388左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬史国人 (うまのふびとくにひと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬毘登とも記す。河内国伎人郷の人。天平十年(738)頃少初位下であったことが正倉院文書で知られる。天平宝字八年(764)従六位上から外従五位下に叙せられた。 天平神護元年(765)武生連の姓を賜った。 20-4482 20-4481題詞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 占部虫麻呂 (うらべのむしまろ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下総国の防人。伝未詳。正倉院文書によると、下総国埴生郡阿佐郷に占部国麻呂という者があったことが知られる。 20-4412 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 榎井鉢麻呂 (えのゐのはちまろ)か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集巻第五-838(842) 頭注『大隅目榎氏鉢麻呂』より引用】 『延喜式』によれば大隅国は中国(国の等級の一つ。国には規模の大小によって「大・上・中・下」の四等級があった) で、掾を欠き、その目(さかん)は大初位下相当官。榎氏は「榎井」などの略か。 鉢麻呂は伝未詳。 6-1020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 榎井王 (えのゐのおほきみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 志貴皇子の子。光仁天皇の弟か。 6-1020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 縁達師 (えんだちし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝未詳。縁は百済系の姓、名が達師という渡来人かとする説もあるが、縁達が名で、それに法師の意の師を加えたとする説のほうが穏当であろう。 8-1540 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 置始東人 (おきそめのあづまと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝未詳。 1-66 2-204,205,206 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 置始連長谷 (おきそめのむらじはつせ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝未詳。天平勝宝六年(754)三月、家持の荘園に酒壺と花を携えて訪れ、歌を詠んだことが見える。 20-4326 8-1598左注、20-4327左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息長真人国島 (おきながのまひとくにしま) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天平宝字六年(762)従五位下を授けられた。 20-4396左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 忍坂王 (おさかのおほきみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天平宝字五年(761)無位から従五位下を授けられた忍坂王という人があるが、〔1598〕左注の忍坂王と同一人か否か不明。 後年、大原真人赤麻呂という姓を賜ったとあり、高安王・門部王・今城王などと同じく臣籍に降ったものであろう。 8-1598左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 忍坂部乙麻呂 (おさかべのおとまろ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝未詳。文武三年(699)一月、または慶雲三年(706)九月、大行(文武)天皇の難波従駕。 1-71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刑部垂麻呂 (おさかべのたりまろ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝未詳。刑部は忍坂部に同じ。 3-265,430 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 忍壁皇子 (おさかべのみこ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 忍坂部・刑部とも記す。天武天皇の第二皇子。母は宍人臣大麻呂の娘、カジ媛娘。泊瀬部皇女・多紀皇女らと同母。 天武十年(681)川島皇子らとともに、帝紀および上古の諸事を記定し、また文武四年(700)には藤原不比等らと律令の撰定にも力を尽くした。 大宝三年(703)知太政官事となり、慶雲二年(705)三品で薨。 2-194題、3-235左注、9-1686題 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小野朝臣老 (おののあそみおゆ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第五-820の作者記名は 「少弐小野大夫」。以下有斐閣「萬葉集全注巻第五-816 『小野大夫』」からの引用。 少弐は底本には「小弐」と書く。以下の小監、小典も同様で、これらの官職名の小・少通用は上代金石文にも「威奈真人大村(いなのまひとおおむら)墓誌」に、小納言、左小弁とあるなど、例は多い。 少弐は大弐に次ぎ従五位下相当。定員二名。掌るところは大弐に同じ。 大夫は、四位・五位の称。ここは小野朝臣老(おののあそみおゆ)。神亀五年(728)十一月作とみられる「6-九五八題詞」に、大弐とあるのは後の官を以て記したもの。 尾山篤二郎氏(「奈良朝の大宰府の歴史一般(二)」万葉集大成13月報) は、「何時大弐に陞進したかだが、彼が天平六年正月従四位下に叙せられた時と一緒だらう」というが、大弐は当時正五位上官であること先述の通りであるから、おそらく天平五年(733)三月正五位上昇叙の前後で、前出紀男人遷任上京の後を受けたものであろう。同六年一月従四位下、同九年六月疫瘡で卒した。同十年七月の周防国正税帳に、「大弐従四位下小野朝臣骨送使」のことが見える(尾山・前記論文)。短歌三首 3-331 5-820 6-963 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小野朝臣国堅 (おののあそみくにかた) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻第五-844(848) 注『小野氏国堅』」より引用】 天平九年ごろから十八年ごろまで、写経司の経師や史生としての名を多く正倉院文書に残す。 天平十一年に無位と大初位上と両様の文書が見えるので、その年叙とすると、梅花宴当時無位ということになる。小野老の私的な供人なのであろう。 5-848 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小野臣淑奈麻呂 (おののおみすくなまろ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻第五-833(837) 注『大令史野氏宿奈麻呂』」より引用】 大令史は、大判事の書記。「判文抄写すること」(職員令) を掌る。大初位上相当。天平六年出雲国計会帳(寧楽遺文上) その他に、出雲国目(さかん)正八位下の小野朝臣淑奈麻呂(おののあそんすくなまろ)と見える人(古典全集)。 5-837 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小野朝臣田守 (おののあそみたもり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻第五-846(850) 注『小野氏淡理』」より引用】 「小野氏淡理」は、「小野朝臣田守」(20-4538[旧4514]題詞)であろう(全註釈)。続日本紀天平十九年正月丙申条、正六位上より従五位下に昇り、以後大宰少弐、遣新羅大使、左少弁、刑部少輔、遣渤海大使などを歴任。先の少弐老の近親者であろう。息男かもしれない。 5-850 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生石村主真人 (おひしのすぐりまひと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天平十年(738)頃、美濃少目。天平勝宝二年(750)正六位上より外従五位下となる。「続日本紀」や「正倉院文書では大石に作る。 オヒシはオヒイシの約。オホイシ(大石)も約音でオヒシとなることがある。 3-358 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大石蓑麻呂 (おひしのみのまろ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝未詳。天平十八年(746)頃東大寺写経所に勤務していたことが正倉院文書によって知られている。 15-3639 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伯皇女 (おほくのひめみこ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大来皇女とも記す。天武天皇の皇女。母は天智天皇の皇女、大田皇女。大津皇子の同母姉。斉名七年(661)筑紫に軍を進める途中、備前国大伯の海で生まれたのでその名が付けられた。 天武二年(673)斎宮となり、翌年伊勢に赴いた。天武天皇が崩じ、大津皇子も没した後の朱鳥元年(686)十一月、十二年ぶりに還京。大宝元年(701)十二月薨。年41歳。 105,106,163,164,165,166作歌。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大蔵忌寸麻呂 (おほくらのいみきまろ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天平八年(736)正七位上で遣新羅少判官となり、翌年入京した。 正倉院文書には、天平勝宝年間(749~57)造東大寺司判官(後、次官)として自署した書類が多く存在するほか、「続日本紀」にも、天平宝字二年(758)丹波守当時従五位下に進み、同七年玄蕃頭に任ぜられ、更に宝亀三年(772)に正五位下になったことが見える。 15-3725 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邑知王 (おほちのおほきみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大市王とも記す。長親王の第七子。天平十一年(739)従五位下、同十五年刑部卿となった。十八年四月内匠頭、天平勝宝四年(752)文室真人の姓を賜る。 大蔵卿、弾正尹、節部卿、出雲守、民部卿などを歴任。天平神護元年(765)従三位となり、更に参議、中務卿、大納言にもなったが、宝亀五年(774)に退き、同十一年正二位をもって薨じた。七十七歳。 17-3948左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大津皇子 (おほつのみこ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天武天皇の第四皇子。母は天智天皇の皇女、大田皇女(持統天皇の同母姉)。天武天皇崩後二十五日目の、朱鳥元年(686)十月三日、謀反の罪によって処刑された。 年24歳。大田皇女の死後、天智天皇に愛されて育ったらしく、風貌たくましく音吐朗々として才学があり、とりわけ文筆を愛し、詩賦はこの皇子から興ったと「日本書紀」に見える。 「懐風藻」にはさらに、多力にして剣を撃つことにも秀で、性放逸、法度になじまず、人士と見れば身を低くして礼遇したため、諸人の支持が厚かったが、たまたま占星をよくする新羅僧行心というものに、臣下で終わる骨相ではないといって謀反をすすめられ、遂にその身を誤ったと記す。しかし、皇子に比べ凡庸の人であったらしい草壁皇子の地位の安全を願う持統天皇の挑発によってこの変は起こされたといわれている。「懐風藻」に四首の詩が見える。 2-107,109 3-419 8-1516作歌 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大舎人部千文 (おほとねりべのちふみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常陸国那賀郡の防人。伝未詳。正倉院戸籍の断簡に大舎人部佐美足という常陸国人の名が見える。 20-4393,4394 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴郎女 (おほとものいらつめ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉集には大伴郎女または大伴女郎と呼ばれるものが三人見える。 a 大伴坂上郎女(525及び528の題詞)。 b 大伴旅人の妻(1476の左注)。 c 大伴家持の妹(4208の左注)。女郎と記す。 この他に「522」の題詞に今城王の母として大伴女郎の名が見えるが、(a) と見る説が自然であろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴坂上郎女 (おほとものさかのうへのいらつめ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安麻呂の娘。旅人の異母妹。母は石川郎女(e)。初め穂積皇子に愛されたが、皇子の薨後藤原麻呂の妻となる。のち異母兄宿奈麻呂に嫁し、坂上大嬢(のち家持の妻)らを生んだ。 「960」の題詞や「1661」の左注によると、旅人の薨後、大伴一族の中心的存在として重んじられていたものかと思われる。その作品は才気に溢れ、家持の作歌生活に大きな影響を与えた。 残された歌で最も時代が下るものは天平勝宝二年(750)の作で、そのとき五十五歳前後であったかと推定されている。 3-382,383,404,413,463,464 4-528,529,530,531,532,566,567,588,589,622,623,650,652,654,655,659,660,661,662,663,664,669,670,676,677,686,687,688,689,690,691,692,724,726,727,728,729,763,764 6-968,969,984,986,987,988,997,998,1000,1022,1032 8-1436,1437,1449,1451,1454,1478,1479,1488,1502,1504,1506,1552,1564,1565,1596,1597,1624,1655,1658,1660 17-3949,3950,3951 18-4104,4105 19-4244,4245 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴坂上二嬢 (おほとものさかのうへのじぢゃう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次項大伴坂上大嬢の妹。駿河麻呂とはまたいとこの関係か。二嬢とは二番目の娘の意。 3-410題 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴坂上大嬢 (おほとものさかのうへのだいぢゃう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿奈麻呂の娘。母は坂上郎女。大伴田村大嬢の異母妹で、家持の従妹に当り、家持に嫁した。 4-584,585,586,587,732,733,734,738,740,741 8-1628 3-406題、411題 4-726題、727左注、730題、736題、742題、744題、759題、762左注、763題、768題、770題、773題 8-1452題、1449題、1468題、1510題、1511題、1626題、1631題、1633題、1636題、1666題 19-4193題、4222左注、4245左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴佐提比古 (おほとものさてひこ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狭手彦とも記す。大伴金村の三男。宣化天皇二年(537)任那を助けて新羅を討ち、また欽明天皇二十三年(562)百済を助けて高句麗を破った。 逸文「肥前国風土記」によれば松浦佐用媛との別離の説話はその前回の出動の際のものらしい。→松浦佐用姫。 5-875序 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴宿禰東人 (おほとものすくねあづまと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天平宝字二年(758)従五位下。式部少輔、少納言、周防守、弾正弼などを歴任した。 6-1038 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴宿禰池主 (おほとものすくねいけぬし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天平十年(738)春宮坊少属従七位下で珠玉を覔める使者として駿河国を通過したことが正倉院文書に見える。同十八年家持が越中守となった時、その国の掾で、家持と盛んに歌や詩文の贈答を行った。 後、同二十一年三月までに越前掾に転じており、天平勝宝三年(751)八月頃まではその職にあって、ときどき家持と贈答している。 同五年左京少進として大和にあり、同八歳には式部少丞(従六位上相当官)であった。天平宝字元年(757)橘奈良麻呂の叛に加担し投獄されたが、その終りは不明。 8-1594 17-3966,3967,3968,3971,3989,3990,3995,3996,3997,3998,4017,4018,4027,4028,4029,4032,4033,4034 18-4098,4099,4152,4153,4154,4155,4156,4157 20-4319,4324 17-3994後詩序 17-3983左注・3987題詞・4019題詞・4022左注・4031左注、18-4097題詞・4201題詞、19-4213題詞・4276題詞、20-4483左注・4499題詞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴宿禰稲公 (おほとものすくねいなぎみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安麻呂の子。旅人の異母弟。坂上郎女の同母弟か。稲君とも記す。衛門大尉を経て、天平十三年(741)従五位下で因幡守となり、兵部大輔、上総守などを歴任。 天平宝字二年(758)従四位下大和守の時奇瑞を奏したことが見える。 4-589 (左注によれば、姉坂上郎女作という) 8-1557 4-570左注、589題、8-1553題 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴宿禰牛養 (おほとものすくねうしかひ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咋子の孫。小吹負の子。安麻呂の従弟。和銅二年(709)従五位下。遠江守、左衛士督を歴任し、天平十年(738)従四位下摂津大夫、同十七年参議従三位となる。 天平勝宝元年(749)正三位中納言をもって薨。 17-3948左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴宿禰像見 (おほとものすくねかたみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形見とも記す。天平宝字八年(764)従五位下。神護景雲三年(769)左大舎人助、宝亀三年(772)従五位上。天平勝宝二年(750)摂津少進正六位上であったことが正倉院文書に見える。 4-667,700,701,702 8-1599 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴宿禰古慈悲 (おほとものすくねこじひ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吹負の孫。祖父麻呂の子。古慈斐とも、祜信備・祜志備などとも記し、コジヒ・コシビと二通りの呼び方があった。万葉集では前者をとる。 天平十一年(739)従五位下、天平勝宝元年(749)従四位上。同八年出雲守であった時、朝廷を誹謗したとの讒言によって禁固され、その時に家持は「族を喩す歌」を作った。 天平宝字元年(757)土佐守在任中に橘奈良麻呂の変に座して任国流罪となったが、後、許されて復位し、宝亀元年(770)大和守となり、同六年従三位に進み、同八年に八十三歳で薨じた。 19-4286題詞、20-4491左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴宿禰胡麻呂 (おほとものすくねこまろ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅人の甥。宿奈麻呂の子か。古麻呂、古満などとも記す。天平五年(733)大学寮の官人として遣唐使に加わり入唐、同十七年従五位下。 左少弁を経て天平勝宝二年(750)遣唐副使となり、同四年に再び渡唐し、鑑真を伴い帰ることに力を尽くした。のち正四位下左大弁兼陸奥鎮守府将軍となったが、天平宝字元年(757)橘奈良麻呂の変に加担し、捕らえられて杖下に死んだ。二度目の在唐の折、朝貢の席次について唐側の扱いに憤り、日本の新羅に対する優位を主張し貫いたことが「続日本紀」に見える。 4-570左注、19-4286題詞、左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴宿禰宿奈麻呂 (おほとものすくねすくなまろ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安麻呂の子。旅人、田主らの弟。和銅元年(708)従五位下。左衛士督を経て、備後守として在任中按察使となり、安芸・周防の両国を管した。神亀元年(724)従四位下。 万葉集には右大弁であったことが見える。田村の里に住み、娘に田村大嬢がいた。異母妹坂上郎女と結婚し、坂上大嬢らを生ませた。 4-535,536 2-129題詞、4-589題詞、762左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴宿禰駿河麻呂 (おほとものすくねするがまろ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴御行の孫か。天平十五年(743)従五位下。同十八年越前守。 天平宝字元年(757)橘奈良麻呂の変に連座して処罰されたが、後に許され、宝亀元年(770)出雲守となった後、肥後守、陸奥按察使兼鎮守府将軍などを歴任。同七年正四位上参議で卒。 従三位を追贈。坂上大嬢の妹二嬢に求婚している。 3-403,405,410,412,(414) 4-649,651,656,657,658 8-1442,1664 4-652左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴宿禰田主 (おほとものすくねたぬし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安麻呂の二男。旅人の弟。母は巨勢郎女。字は仲郎、容姿優艶の聞え高く、石川女郎(c)が計略によって近づこうとしたことが見える。 2-127 2-126題詞・左注、128題詞・左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴宿禰旅人 (おほとものすくねたびと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安麻呂の長男。万葉集では大伴卿として見え、また淡等(810前書)と自署する(東大寺献物帳にも「大伴淡等」とある)。和銅三年(710)左将軍。翌年従四位下。 中務卿、中納言を経て養老四年(720)征隼人持節大将軍。翌年従三位。神亀元年(724)正三位。同四年頃大宰帥として筑紫に下る。天平二年(730)冬大納言となって帰京。 翌年秋、従二位で薨。年67歳。筑紫に赴任早々妻の大伴郎女を失い、自らも脚瘡のために死に瀕したことがある。酒を讃え、また望郷の念をしばしば素直に歌に託して特異な作風で注目される。 3-318,319,334,335,336,337,338,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,441,442,443, 449,450,451,452,453,454,455,456 4-558,577,578,580 5-796(序),810(前書),811,814(前書),815(後書),826,865,866,867 6-961,962,965,966,972,973,974,975 8-1477,1545,1546,1643,1644 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴宿禰千室 (おほとものすくねちむろ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝未詳。「4322」にも「古今未詳」の脚注がある。 4-696 20-4322 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴宿禰書持 (おほとものすくねふみもち) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴家持の弟。天平十八年(746)九月没。その死を悲しんだ家持の長歌「3979」の自注に、生来花草花樹を愛し、寝院の庭に多く植えてあったと見える。 3-466 8-1484,1485,1591 17-3923,3924,3925,3926,3927,3928,3931,3932 17-3935左注、3979題、3981左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴宿禰三中 (おほとものすくねみなか) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統未詳。御中とも記す。天平八年(736)従六位下であった時に遣新羅副使となり、翌年帰朝した。十二年外従五位下。兵部少輔、山陽道巡察使、大宰少弐、長門守などを歴任。 同十八年従五位下。翌年刑部大判事となった。天平元年摂津班田使であった時に、配下の丈部竜麻呂が自殺したのを悼んで歌を詠んでいる。 3-446,447,448 15-3723,3729 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴宿禰道足 (おほとものすくねみちたり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安麻呂の従弟。慶雲元年(704)従五位下、天平元年(729)正四位下右大弁となる。同三年参議を兼ね、十三年頃卒したらしい。「大伴系図」や「公卿補任」などでは安麻呂の子になっている。 6-967題詞・左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴宿禰三依 (おほとものすくねみより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天平二十年(748)従五位下。「大伴氏系図」には御行の子とあるが、確かではない。主税頭、三河守、仁部(民部)少輔、遠江守、義部大輔、出雲守などを歴任。宝亀五年(774)散位従四位下で卒。 神亀末から天平初年にかけて旅人の配下として筑紫にあった。梅花宴三十二首中に見える豊後守大伴夫人(823の作者)も三依かとする説があるが、疑わしい。 4-555,581,653,693 4-559題詞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴宿禰村上 (おほとものすくねむらかみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝亀二年(771)従五位下で肥後介、翌年阿波守となった。天平勝宝六年(754)家持の家で歌を詠んだ時は民部少丞(従六位下相当官)であった。 8-1440,1441,1497,(1577) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴宿禰百代 (おほとものすくねももよ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅人が大宰帥であった天平二年(730)頃、大宰大監としてその配下にあった。同十年外従五位下兵部少輔となり、美作守、鎮西副将軍、豊前守などを歴任。同十八年従五位下、翌年正五位下に進んだ。 3-395 4-562,563,564,565,569 5-827 4-570左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴宿禰家持 (おほとものすくねやかもち) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅人の長男。天平十年(738)頃内舎人、同十七年従五位下。十八年越中守として赴任し、天平勝宝三年(751)少納言となって帰京。同六年兵部少輔となり、さらに兵部大輔、右中弁を歴任。 天平宝宇二年(758)因幡守となる。その後信部(中務)大輔、薩摩守、大宰少弐、中務大輔、左京大夫、衛門督、参議、左大弁兼東宮大夫などを歴任。 藤原仲麻呂にうとまれ一時左遷されたが間もなく復帰し、陸奥按察使鎮守府将軍を兼ね、延暦四年(785)中納言従三位で薨じた。 68歳。しかし、死後一ヶ月足らずのうちに、藤原種継暗殺事件に連座した罪で除名(延暦二十五年復位)。 万葉集中に作品多く、その数は長歌46首、短歌432首、旋頭歌1首、量において群を抜いている。 内容は多方面にわたり、一部凡作も混じるが、越中にあって特殊な素材を詠んだ歌、大伴氏の族長としての自覚から生まれた勇壮な長歌、繊細優美な感興を飾り気なく述べた小品などには、非凡な才能がうかがわれる。また万葉集の編纂の中心的存在と見なされ、特に兵部少輔時代に筑紫に下る防人らを閲し、防人歌を撰録したことは注目に値する。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴宿禰安麻呂 (おほとものすくねやすまろ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐保大納言卿とも〔652左注〕。長徳の子。 壬申の乱の際、兄の御行(高市大卿)、叔父の馬来田・吹負とともに天武側について功があり、累進して大宝元年(701)従三位となり、式部卿、兵部卿、参議などを経て慶雲二年(705)大納言兼大宰帥、和銅七年(714)五月、大納言兼大将軍正三位で薨じた。従二位を贈られる。 2-101 (3-302) 4-520 2-126題詞、3-464左注、4-531左注、535題、651左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴宿禰四綱 (おほとものすくねよつな) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四縄とも記す。旅人が大宰帥であった天平二年(730)前後、防人司佑としてその配下にあった。正倉院文書によると天平十年(738)頃大和少掾、同十七年頃雅楽助正六位上であったことが知られる。 3-332,333 4-574,632 8-1503 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴田村大嬢 (おほとものたむらのだいぢゃう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿奈麻呂の娘。坂上大嬢らの異母姉。 4-759,760,761,762 8-1453,1510,1626,1627,1666 4-589題詞、762左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴連御行 (おほとものむらじみゆき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 右大臣大紫冠長徳の子。安麻呂(旅人の父)の兄で、壬申の乱に功があり、その後、兵部大輔を経て、大宝元年(701)大納言正広参で薨。正広弐右大臣を追贈された。 19-4284 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大伴連長徳 (おほとものむらじながとこ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咋子の子。御行、安麻呂の父。舒明・皇極・孝徳三大に仕え、右大臣大紫位にまで昇り、白雉二年(651)没。 2-101題詞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大汝・大穴道 (おほなむぢ・おほあなみち) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大国主命の異名。これらの他に、大己貴・大穴牟遅・大穴持などとも記し、ア音の有無、ミ・ム・モの動揺、チの清濁など、形に多少の変化がみられるが、それぞれ表記に即した読み方をし、統一していない。更に、八十桙・葦原色許男・宇都志国玉など、数多くの名があり、記紀や「出雲国風土記」「播磨国風土記」などに見える出雲神話の中心的神格。少彦名命と協同して国土を経営したと言い伝えられ、万葉集ではしばしば物事の由来の古いことをいう例に引かれる。大神神社に祭る大物主神はその幸魂・奇魂といわれる。 3-358歌、6-968歌、7-1251歌、18-4130歌 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太朝臣徳太理 (おほのあそみとこたり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徳足とも記す。天平十七年(745)外従五位下。 17-3948左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大原真人今城 (おほはらのまひといまき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もと今城王といった。大伴女郎の子(522題詞)。高安王およびその弟の門部王・桜井王より若いが、同じく大原真人の姓を賜っていることから考えて、その三兄弟の内の誰かの子かとする説がある。 「東大寺奴婢籍帳」には、天平二十年(748)正七位下兵部少丞であったことが見える。 その後、上総大掾、兵部大丞、治部少輔、左少弁、上野守などを歴任。天平宝字元年(757)従五位下に叙せられ、同八年従五位上まで進んだが、宝亀二年(771)復位するまで無位に落とされた。 藤原仲麻呂の乱に連座したためか、という。後、更に兵部少輔、駿河守に任ぜられた。→今城王。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大原真人桜井 (おほはらのまひとさくらゐ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もと桜井王といった。高安王の弟。和銅七年(714)従五位下。天平十一年(739)高安王と共に臣籍に下り、大原真人桜井と名のった。 同十六年大蔵卿従四位下の時、鈴鹿王らと共に久邇(恭仁)京の留守を預かったことがある。 8-1618 20-4502 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大原真人高安 (おほはらのまひとたかやす) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もと高安王といった。長皇子の孫か。和銅六年(713)従五位下。養老初年、紀皇女と通じたことによって、伊予国守に左遷されたという所伝がある(3112左注)。その後、摂津大夫、衛門督などを歴任。 天平十一年(739)臣籍に入り、大原真人の姓を賜った。同十四年正四位下で卒。 4-628 8-1508 17-3974 4-580題詞、8-1448題詞、12-3112左注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大神女郎 (おほみわのいらつめ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝未詳。その作品はいずれも家持に贈った歌である。 4-621 8-1509 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大神朝臣奥守 (おほみわのあそみおきもり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天平宝字八年(764)従五位下を授けられた。 16-3863 16-3862題詞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大宅女 (おほやけめ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝未詳。豊前国の娘子。遊女の類か。 4-712 6-989 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大網公人主 (おほよさみのきみひとぬし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝未詳。公は君に同じく姓の一種。主として地方の皇別氏族に用いる。 3-416 |
| 孝謙天皇 (かうけんてんわう) |
| 四十六代の女帝。重祚して四十八代称徳天皇となる。諱は阿倍、諡を高野姫天皇という。聖武天皇の皇女で、母は光明皇后。養老二年(718)に生まれ、神亀五年(728)に皇太子となった。 天平勝宝元年(749)皇位についたが、藤原仲麻呂を長官とする紫微中台に拠った皇太后(光明)が政治の実権を掌握した。 天平宝字二年(758)淳仁天皇に譲位したが、寵臣道鏡のことで天皇と間隙を生じ、ついにこれを廃して同八年再び即位し、神護景雲四年(770)五十三歳で崩じた。 孝謙時代は仲麻呂を、称徳時代は道鏡をそれぞれ偏重し、それによって奈良時代後半の政治が乱れる因となった。 19-4288,4289,4292 |
| 高氏義通 (かうしよしみち) |
| 【有斐閣「萬葉集全注巻第五-835(839) 注『高氏義通』」より引用】 高氏は、高丘、高田、高橋、高向、高屋、高安、高(こう)などの氏がある。医術者としては「高」氏か。義通、伝不明。 5-839 |
| 鏡王女 (かがみのおほきみ) |
| 鏡姫王・鏡女王とも記される。従来額田王の姉かとされたが、その墓が舒明天皇陵の域内にあることから推して、舒明天皇の皇女ではないかといわれる。 初め天智天皇に愛されたが、のち藤原鎌足の正室となり、天武十二年(683)七月薨。今日の興福寺(奈良市登大路町)の前身山階寺は鎌足が病気の際、女王の発願によって開基されたものという。 2-92,93 4-492 8-1423,1611 2-91題詞・94題詞 |
| 柿本朝臣人麻呂 (かきのもとのあそみひとまろ) |
| 生没年未詳。万葉集以外に所伝はなく、低い官位で終わったものか。ただし、「古今集・序文」に「正三位(おほきみつのくらい)」と見え、それも含めて、数多くの「人麻呂研究」がある。 実際、紀貫之らによって、「歌聖」とまで言われた歌人が、一体「万葉集」以外の書物、それは正史をも含め、名を漏らすことがあるだろうか。謎の多い歌人であるが、もっとも魅力ある歌人と言える。 挽歌にその人柄を偲ばせる。もう一つの謎「柿本朝臣人麻呂歌集」の存在。万葉集には「人麻呂作歌」84首の他に、この「人麻呂歌集中出」が370首もある。 この「人麻呂歌集」が果たして人麻呂自身の作歌か、あるいは違うのか、これも論争の最中にある。しかし、何といっても最大の謎は、彼の死をめぐる謎。いつか、そのコ-ナ-を設けたい。 1-29,30,31,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49 2-131,132,133,134,135,136,137,138,139,167,169,194,195,196,197,198,199,200,201,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223 3-235,240,241,242,250,251,252,253,254,255,256,257,263,264,266,268,306,307,429,431,432,433 4-499,500,501,502,504,505,506 15-3633 「柿本朝臣人麻呂歌集」は、その都度以下追記する。 2-146 ,10-2337,2338,11-2394 |
| 笠朝臣金村 (かさのあそみかなむら) |
| 伝未詳。作歌年代の明らかなものは霊亀元年(715)から天平五年(733)までで、行幸従駕の作が多く、車持千年や山部赤人と並ぶ時、必ず最初に置かれるところからみて、当時の評価は赤人よりも上だったものか。しかし、作風はおおむね類型的で、器用ともいえるが、新鮮さに欠けるうらみがある。金村歌集、金村歌中とあるものも彼の作であろう。 その作品の一部に、題詞の書式に特色が見られ、おそらく本人自記の資料から採ったものと考えられる。 3-367,368,369,370 4-546,547,548,549,550,551 6-912,913,914,915,916,917,925,926,927,933,934,935,940,941,942 8-1457,1458,1459,1536,1537 金村歌集、金村歌中とあるもの 2-230,231,232 3-372 6-955,956,957,958 9-1789,1790,1791,1792,1793 |
| 笠女郎 (かさのいらつめ) |
| 伝未詳。家持と関係のあった女性の一人。 3-398,399,400 4-590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613 8-1455,1620 |
| 膳部王 (かしはでのおほきみ) |
| 膳夫王・膳王とも記す(続日本紀)。長屋王の子。長男か。母は草壁皇子の娘、吉備内親王。 神亀元年(724)無位より従四位下を授けられ、同六年二月、長屋王が讒言にあって自決した際、母や弟たちとともに自縊して死んだ。 6-959 3-445題詞 |
| 春日王 (かすがのおほきみ) |
| 万葉集に春日王と呼ばれるものが二人見えるが、明らかに別人で紛れることがない。 a 〔244〕の作者。文武三年(699)浄大肆(従四位上に相当)で卒か。 b 〔672〕の作者。志貴皇子の子。養老七年(723)従四位下。天平十七年(745)散位正四位下をもって卒。 |
| 春日蔵首老 (かすがのくらのおびとおゆ) |
| 蔵首は姓。もと僧で、法名を弁基といったが、大宝元年(701)勅によって還俗した。和銅七年(714)従五位下。「懐風藻」に詩一首を載せ、従五位下常陸介春日蔵首老、年五十二、と見える。 1-56,62 3-285,287,289,302 9-1723 3-301左注 |
| 門部王 (かどべのおほきみ) |
| 河内王の子。高安王の弟。和銅三年(710)従五位下。伊勢守、出雲守・弾正尹、右京大夫などを歴任。天平十一年(739)兄の高安王らと臣籍に下り、大原真人の姓を賜った。 同十七年従四位上大蔵卿で卒。風流侍従と称せられ、同六年二月朱雀門で天皇臨席のもとに歌垣が行われた際、五品以上の風流者の随一として長田王らと参加したことが見える。 更に「続日本紀」にはもう一人同名異人の門部王が見える。それは高市皇子の子、長屋王の弟。 3-313,329,374 4-539 6-1018 |
| 門部連石足 (かどべのむらじいそたり) |
| 伝未詳。天平初年、筑前掾として筑紫にあり、梅花宴で歌を詠んでいる。 4-571 5-849 |
| 川島皇子 (かはしまのみこ) |
| 河島皇子とも。天智天皇の第二皇子。天武十年(681)、忍壁皇子らとともに帝紀と上古の諸事の記録に当たった。同十四年浄大参。持統五年(691)35歳で薨。 「懐風藻」に詩一首を載せる。大津皇子と親しかったが、その謀反を朝廷に密告したことが「日本書紀」に見える。妃は泊瀬部皇女。 1-34 |
| 河辺朝臣東人 (かはへのあそみあづまと) |
| 神護景雲元年(767)従五位下。宝亀元年(770)石見守となった。 8-1444 6-983左注、8-1598左注、19-4248左注 |
| 河村王 (かはむらのおほきみ) |
| 系統未詳。「続日本紀」に宝亀八年(777)に無位の川村王に従五位下を授ける由が見えるが、それとの異同は不明。 16-3839,3840 |
| 河内王 (かふちのおほきみ) |
| 川内王とも記す。門部王の父。朱鳥元年(686)新羅客の金智祥の饗応接待役として筑紫に下る。持統三年(689)大宰帥となり、同八年四月浄大肆(従四位上に相当)の位と賻物(香典の品)とを賜った。 その直前に卒したものと思われる。豊前国鏡山に葬る時に手持女王が挽歌を詠んでいる。「続日本紀」には最小限もう一人の河内王が見えるが、それは長皇子の子か。 3-420題詞 |
| 河内女王 (かふちのおほきみ) |
| 高市皇子の娘。天平十一年(739)従四位上、同二十年正四位下、天平宝字二年(758)従三位に昇ったが、その後無位にに落とされた。不破内親王の事件に座したためかという。 宝亀四年(773)正三位に復し、同十年に薨じた。 18-4083 |
| 神社忌寸老麻呂 (かみこそのいみきおゆまろ) |
| 【有斐閣「萬葉集全注巻第六-976(981) 注『神社忌寸老麻呂』」より引用】 伝未詳。代匠記は「孝徳紀」 二年三月十九日粂の東国国司の「神社福草」、続紀和銅三年正月、従六位上より従五位下を授けられた神社忌寸河内をあげる。 なお、天平勝宝二年三月の勘籍断簡に某郷戸主の神社忌寸石島とその戸口・神社忌寸祖父麻呂がある。全釈は、「式神名帳」の近江国浅井郡上許曾神社と関係する氏かという。 天平神護三年八月、従三位で薨じた前の内命婦・神社女王があり、この女王も神社忌寸氏と何らかのかかわりをもつ者かもしれない。 6-981,982 |
| 上毛野君駿河 (かみつけのきみするが) |
| 伝未詳。天平勝宝七年(755)二月に上野国の大目として防人の部領使となった。上毛野君は上野国の代表的豪族。 ただし、上野国以外の国でも同じ姓を名のる者があり、また天平勝宝二年に渡来人系の田辺史に同じ姓を賜ったことがあるので、決定はできない。 20-4431左注 |
| 上道王 (かみつみちのおほきみ) |
| 穂積皇子の子。和銅五年(712)従四位下。神亀四年(727)四月に卒。 4-697題詞 |
| 上宮聖徳皇子 (かみつみやしやうとこのみこ) |
| 三十一代用明天皇の皇子。母は用明天皇の異母妹穴穂部間人皇女。推古天皇の甥。厩戸皇子・豊聡耳皇子などとも呼ばれる。 推古天皇の皇太子となり万機を摂政し、十七条の憲法を定め、位階制度を整え、また隋と国交を結び、仏教の興隆に努め、法隆寺を創建した。推古三十年(622)四十九歳で薨じた。 3-418 |
| 上古麻呂 (かみのこまろ/かみのふるまろ) |
| 「中央公論社『澤瀉久孝萬葉集注釈』」 の解説。 「上(カミ)」 の氏は新撰姓氏録左京、右京、摂津、和泉、の諸藩に「上村主(カミノスクリ)」 があり、いづれも廣階(ヒロハシ)連と同祖とあり、「廣階連、魏武皇帝男陳思王植之後也」 とある。 右京諸藩に上勝(マサ)あり、「百済国人多利須須之後也」とあり、又河内国諸藩に上曰佐(ヲサ)があり、「百済国人久尓能古使主之後也」とある。これらのいづれか不明であるが、帰化人の子孫と思はれる。 古麻呂は童蒙抄にフルマロ、万葉考にコマロとある。 古慈悲(コジヒ、20・四四六七) の例はあるが、人麻呂、垂麻呂(二六三)、安麻呂(2・一〇一) などの例により、古人の場合と同じく、「古」を訓読して「フルマロ」と訓むべきであらう。伝未詳。 「有斐閣『萬葉集全注巻三-356(旧歌番号) 考』」 の解説。 上古麻呂は、伝未詳。また「古麻呂」はフルマロかコマロか不明。一応コマロと訓んでおく。奈良遷都後、飛鳥の故郷を偲んで作った歌であろう。 次に赤人の歌がくるので、この古麻呂で一区切りをしておけばよかろう。前歌は神代を思いやり、今の歌は飛鳥の故郷を思いやるという点で共通しており、この二首は一組にできると考えられる。 大きくは三五二番歌から一括できる。この三五二~三五六番歌は、羇旅の回想歌・国偲び歌といったテーマで一括されたものとみられる。 そして時代的に推定できるのは、前の生石真人の、天平十年(738)と天平勝宝二年(750)の史料しかなく、はっきりは分からない。 3-359(新歌番号) |
| 巫部麻蘇娘子(かむなぎべのまそをとめ) |
| 伝未詳。 4-706,707 8-1566,1625 |
| 甘南備真人伊香 (かむなびのまひといかご) |
| もと伊香王といった。系統未詳。天平十八年(746)従五位下雅楽頭。 天平勝宝元年(749)従五位上、同三年甘南備真人の姓を賜る。美作介・備前守・主税頭・越中守などを歴任し、宝亀三年(772)正五位下、同八年正五位上に叙せられた。 20-4513,4526,4537 |
| 賀茂女王(かものおほきみ) |
| 長屋王の娘。母は阿倍朝臣という。 4-559,568 8-1617 |
| 鴨君足人(かものきみたるひと) |
| 伝未詳。君は姓。 3-259,260,261,262 |
| 軽太郎女(かるのおほいらつめ) |
| 允恭天皇の皇女。木梨軽皇子の同母妹。一名を衣通郎女という。 兄軽皇子と通じ、伊予に流された兄を追って同地で兄妹心中した、と「古事記」にあるが、「日本書紀」では、太郎女だけ伊予に流されたとある。 (2-90)2-90左注 |
| 私部石島(きさきべのいそしま) |
| 下総国葛飾郡の防人。伝未詳。正倉院文書の写経生の名に「私石島」という者があり、天平七年(735)から同十四年頃まで勤務していたことが知られる。 この「私石島」はまた「私部石島」とも書き、「私部」と「私」とは通用するが、この二人は別人であろう。 私部姓は各地に多く分布するが、養老戸籍には、この下総国葛飾郡大島郷に私部真呰を戸主とする戸がみられる。 20-4409 |
| 磯部法麻呂(きそべののりまろ)か |
| 【有斐閣「萬葉集全注巻第五-836(840) 注『磯氏法麻呂』」より引用】 陰陽師は、「占筮(せんぜい)し地を相ること」(職員令)を掌る。正八位上相当。磯氏は、磯部氏か。法麻呂は伝不明。 【小学館「新編日本古典文学全集萬葉集 巻第五-836(840) 頭注『陰陽師は・・・』」より引用】 陰陽師は天文・気象・暦・時刻・卜占などを掌る官。大宰府のそれは正八位上相当官で、単に占筮(せんぜい)相地のみならず、一朝有事の際は軍幕の中に加えられ、敵軍の動静を予兆予見し、作戦計画に関して意見具申する任務をも帯びていた。磯氏は「磯部(いそべ)」などの略であろう。法麻呂は伝未詳。 5-840 |
| 木梨軽皇子(きなしのかるのみこ) |
| 軽太子ともいう。允恭天皇の皇太子。母は忍坂大中姫命。「古事記」では、允恭天皇崩後、同母妹の軽太郎郎女と通じて捕えられ伊予の湯に流され、後を追った太郎女と同地で心中したとあるが、「日本書紀」では密通事件は天皇在世時のことで軽太郎女だけが伊予に流され、軽皇子は皇位継承の争いで弟安康天皇に敗れ自殺したことになっている。 13-3277,3278 2-90題詞 |
| 紀朝臣飯麻呂(きのあそみいひまろ) |
| 式部大輔正五位下古麻呂の長子。天平元年(729)従五位下。同十二年藤原広嗣の乱に征討副将軍に任じられ、右大弁、常陸守を経て、天平勝宝元年(749)大倭守となり、従四位上に叙せられた。 更に大宰大弐、大蔵卿、右京大夫などを歴任、天平宝字二年(758)に参議紫微大弼正四位下兼左大弁として見える。同六年従三位で薨じた。 19-4281題詞 |
| 紀朝臣鹿人(きのあそみかひと) |
| 鹿人大夫ともいう。紀女郎の父。天平九年(737)外従五位下主殿頭、同十二年外従五位上。翌年大炊頭となる。天平初年典鋳正であったことが見える(1553題詞)。 6-995,996 8-1553 4-646題詞 |
| 紀朝臣清人(きのあそみきよひと) |
| 文章家。和銅七年(714)勅命によって国史の撰述に当たる。 翌年従五位下を授けられ、養老五年(721)東宮侍講となり、天平十三年(741)治部大輔兼文章博士、同十六年従四位下、同十八年五月武蔵守となり、天平勝宝五年(753)卒。 17-3945 |
| 紀朝臣豊河(きのあそみとよかは) |
| 天平十一年(739)正六位上から外従五位下に進む。 8-1507 |
| 紀朝臣男梶(きのあそみをかぢ) |
| 尾楫・小楫とも記す。天平十五年(743)外従五位下弾正弼、同十七年従五位下、十八年四月大宰少弐となった。その後、兵部少輔、山背守などを歴任、天平宝字四年(760)和泉守となった。 17-3946 |
| 紀朝臣男人(きのあそみをひと) |
| 慶雲二年(705)従五位下、養老七年(723)従四位下。神亀五年(728)丹比県守のあとを受けて大宰大弐となったと思われ、天平二年(730)正月の梅花三十二首の中にその作がある。 翌三年正月従四位上、同年三月三十日付の「大宰府牒案」に大弐として署名している。八年正四位下に進み、九年頃右大弁であったことが知られる。翌十年五十七歳で卒したが、その時も大宰大弐であった。 小野老の病没による臨時の人事配置だったのであろう。「懐風藻」に詩三首を載せる。天平十一年(739)正六位上から外従五位下に進む。 5-819 |
| 紀女郎(きのいらつめ) |
| 紀朝臣鹿人の娘で、名を小鹿といい、安貴王の妻となったが、王が失脚した後、大伴家持に接近したらしく、家持との贈答歌が万葉集に二箇所に分かれて見える。 〔646〕の怨恨の対象は不明。 4-646,647,648,765,766,779,785 8-1456,1464,1465,1652,1665 4-772題詞・778題詞・780題詞、8-1514題詞 |
| 紀皇女(きのひめみこ) |
| 天武天皇の皇女。母は蘇我赤兄の娘、大蕤娘。穂積皇子の同母妹。生没年は未詳だが、「続日本紀」は皇子・皇女の没年をもらさない慣わしだから持統十年(696)以前に薨じだのではないかとする説がある。〔3112〕の左注には高安王に嫁して叱責された旨の記述があり、年代の上で疑問の点があるが、一応伝誦のままとする。なお〔428〕の左注の「或伝」によれば石田王の妻だったとも考えられる。 3-393 12-3112 2-119題詞、3-428題詞 |
| 吉備津采女(きのつのうねめ) |
| 吉備国の津郡出身の采女の意。津郡は「和名抄」の備中国都宇郡、現在の岡山県都窪郡に当たる。 〔218〕の歌の中で「志賀津の児ら」とある、その志賀は滋賀県大津市の北部をいい、その相違は不審だが吉備は生国、志賀は生前の居住地かとする説がある。 2-217題詞 |
| 草壁皇子(くさかべのみこ) |
| 天武天皇の第三皇子。母は持統天皇。日並皇子ともいうのは天皇と並んで天下に臨む意で、草壁皇子に限って用いる称号。 天武十年(681)皇太子として万機を委ねられたが、持統三年(689)二十八歳で薨去。天平宝字二年(758)岡宮御宇天皇と追尊された。 2-110 1-49歌、2-167題詞・171題詞 |
| 草嬢(くさのをとめ) |
| 伝未詳。またカヤノヲトメと読む説もある。 4-515 |
| 久米朝臣広縄 (くめのあそみひろつな) |
| 天平二十年(748)頃、大伴池主が越前掾となって転任した後、越中掾に着任し、大伴家持の下僚として公私両面で家持と近かった。 正倉院文書によると、天平十七年頃左馬少允従七位上であったことが知られる。 「広縄」はヒロナハと読む可能性もあるが、大伴四縄を「四綱」と記すことがあり、正倉院文書に見える校生の名「刑部金綱」を「金縄」と書くこともあるため、ヒロツナと読んでおく。 18-4074,4077 19-4225,4227,4233,4234,4246,4255,4276 18-4090題詞・4140題詞・4161題詞、19-4259左注・4262左注・4272題詞 |
| 久米禅師 (くめのぜんじ) |
| 伝未詳。禅師は僧の意か。 2-96,99,100 |
| 久米の若子 (くめのわくご) |
| 久米氏のある青年の通称か。柿本人麻呂も柿本若子といわれる(歌経標式)。伝説上の人物かとも思われ、一説に弘計王(顕宗天皇)の別名を来目稚子といったのでこれに擬する向きもあるが、不明。 3-310歌、4-438歌 |
| 久米女王 (くめのおほきみ) |
| 系統未詳。天平十七年(745)従五位下を授けられたことが見える。 8-1587 |
| 按作主人益人 (くらつくりのすぐりますびと) |
| 伝未詳。〔1009〕の左注に、天平六、七年頃内匠寮大属として、その長官佐為王を饗応したことが見える。 3-314 6-1009 |
| 内蔵忌寸縄麻呂 (くらのいみきなはまろ) |
| 縄万呂・縄丸とも記し、姓も伊美吉と書くことがある。天平十八年(746)七月から天平勝宝三年(751)七月までの五年間、大伴家持が越中守であった当時、同国の介であった。 「越中国官倉納穀交替帳」(平安遺文・一)にも、天平勝宝三年六月頃、縄麻呂が正六位上で同国の介であったことを記す。 正倉院文書によると、天平十七年にも正六位上で、大蔵少丞であったこと、天平勝宝五年には造東大寺司判官であったことが知られる。 「色葉字類抄」には、ウの部の姓氏の項に収められていて、ウチノクラと訓が付せられており、「和名抄」には、官職名の内蔵寮に「宇知久良乃豆加佐」の訓があり(「色葉字類抄」も同じ)、それらによって「内蔵」はウチノクラと読むべきかとも思われる。 17-4020 18-4111 19-4224,4257 19-4254左注・4274題詞 |
| 倉橋部女王 (くらはしべのおほきみ) |
| 伝未詳。〔1617〕の作者とする伝えがある。 3-444 6-1617左注 |
| 車持朝臣千年 (くるまもちのあそみちとせ) |
| 伝未詳。笠朝臣金村や山部宿禰赤人と同時代の歌人で、行幸に供奉して歌を詠んだ。 6-918,919,920,921,936,937・(955,956,957,958) |
| 光明皇后 (くわうみょうわうごう) |
| 藤原不比等の娘。本名は安宿媛。母は県犬養宿禰三千代。聖武天皇の皇后。孝謙天皇の生母。天平宝字四年(760)六十歳で崩じた。 臣籍から皇后が出ることは異例で、異母兄藤原武智麻呂らの強い擁立運動が功を奏したものである。 聖武天皇譲位後も孝謙天皇の後見的存在として重きをなし、武智麻呂の第二子仲麻呂は叔母光明皇后の家政機関紫微中台を中心に権勢を振った。 8-1662 19-4248,4264 6-1014左注、8-1598左注、19-4292題詞、20-4325題詞・4481題詞 |
| 元仁 (ぐわんにん) |
| 未詳。渡来人、僧侶、学者の漢風の名など、諸説がある。 9-1724,1725,1726 |
| 元正天皇 (げんしゃうてんわう) |
| 四十四代。本名は氷高皇女。諡は日本根子高瑞浄足姫天皇と呼ばれる。草壁皇子と元明女帝との間に生まれ、文武天皇の姉に当たる。 元明天皇から譲位された後、甥の聖武天皇の成人を待つ間、中継ぎの天皇として九年在位し、独身のまま天平二十年(748)六十九歳で崩じた。 8-1641 18-4081,4082 20-4317,4461 (6-973,974,1014)、17-3944題詞、18-4080題詞 |
| 元明天皇 (げんめいてんわう) |
| 四十三代。本名は阿閇皇女。諡は日本根子天津御代豊国成姫天皇と呼ばれる。天智天皇の第四皇女。母は蘇我石川麻呂の娘、姪娘(持統天皇らの母、遠智娘の妹)。 草壁皇子の妃となり文武・元正両天皇を生む。二十九歳の時、草壁皇子が薨じ、さらに文武天皇が崩ずると即位した。その時四十七歳、慶雲四年(707)であった。 その後八年間在位したが、その間に、和同開珎の鋳造流通、和銅三年(710)の奈良遷都、「古事記」の撰進などのことがあった。元正天皇に譲位後六年、養老五年(721)六十一歳で崩じた。 その即位詔に、前年先帝(文武)不豫の際、自分(元明)に譲位しようとされたが固辞した。 今やむなく即位するが、これは持統から文武への譲位が近江大津宮御宇天皇(天智)の「不改常典」によるものであった。それの延長である、と見える。 その「不改常典」の内容について諸説あるが、一般に皇位の直系相続の正当性を意味するものと解釈されている。 1-35,76,(78) 1-22左注・78題詞 |
| 児島 (こしま) |
| 筑紫の遊女で、筑紫娘子とも。姓名は不明。「児島」は字。巻第三の〔384〕の歌も同じく天平二年(730)十二月大伴旅人が帰京する際に詠んだ歌であろう。 3-684 6-970,971 |
| 巨勢朝臣宿奈麻呂 (こせのあそみすくなまろ) |
| 神亀五年(728)外従五位下、翌天平元年少納言従五位下、同五年従五位上。 天平元年、長屋王が謀叛の罪で捕えられたとき、舎人皇子、新田部皇子、藤原武智麻呂らと供にその罪を窮問する役に充てられた。 8-1649 6-1021題詞 |
| 巨勢朝臣奈弖麻呂 (こせのあそみなてまろ) |
| 巨勢人の子。天平三年(731)従五位下。民部卿、参議、左大弁を経て、同二十年正三位。天平勝宝元年(749)従二位大納言となり、同五年に八十四歳で薨じた。 19-4297 17-3948左注 |
| 巨勢斐太朝臣島村 (こせひだのあそみしまむら) |
| 天平九年(737)外従五位下。同十六年平城京留守司、南海道巡察使となり、更に同十八年従五位下刑部少輔となった。 16-3867左注 |
| 巨曾部朝臣対馬・巨曾倍朝臣津島 (こそべのあそみつしま) |
| 天平四年(732)八月山陰道の節度使の判官となり、外従五位下を授けられた。正倉院文書によると、同二年頃倭介正六位上であったことが知られる。 6-1028 8-1580 |
| 巨勢郎女 (こせのいらつめ) |
| 巨勢臣人の娘。大伴安麻呂の妻となり、田主を生んだ。旅人、宿奈麻呂もその所世か。 2-102 2-101題詞・126題詞 |
| 巨勢臣人 (こせのおみひと) |
| 比等・比登などとも記す。天智十年(671)、大錦下(従四位上ないし下に相当)であった時に御史大夫(大納言に相当)となる。 天智天皇崩御の前、蘇我赤兄らとともに大友皇子を奉じ、天皇の詔に背かないことを誓った。翌年の壬申の乱では近江軍の将として戦ったが敗れ、乱後子孫とともに配流された。 〔4297〕の作者で従二位大納言に昇った巨勢奈弖麻呂および大伴安麻呂の妻となった巨勢娘子は、その子。 2-102題詞 |
| 小鯛王 (こだひのおほきみ) |
| 系統未詳。別名を置始多久美といった。「藤氏家伝」に、神亀年間(724~729)の人物を述べて、六人部王〔1615〕・長田王〔81〕・門部王〔313〕・桜井王〔1618〕・石川朝臣君子らとともに風流侍従と呼ばれた人々の中に見える置始工とはこの人かという。 16-3841,3842 |
| 碁檀越 (ごのだんをち) |
| 伝未詳。碁は氏で、檀越は仏のために財物を布施するもの、即ち施主を意味する普通名詞としての用法か。正倉院文書に「碁女」という名の婢があったことが知られる。 4-503題詞 (作、碁檀越妻) |
| 子部王 (こべのおほきみ) |
| 伝未詳。一説に、〔3843〕の作者児部女王と同一人かという。あるいは、但馬皇女の身辺の人か。 (8-1519、16-3843) |
| 高麗朝臣福信 (こまのあそみふくしん) |
| はじめ消奈公(肖奈公)といったが、後、消奈王・高麗朝臣・高倉朝臣とつぎつぎに改姓させられた。 渡来人で父祖の代から武蔵国高麗郡(現埼玉県川越市付近)に住んだが、伯父消奈行文に連れられて上京。天平十一年(739)従五位下。 天平勝宝元年(749)紫微少弼兼中衛少将従四位上となり、翌年高麗朝臣の姓を賜った。信部大輔、内匠頭、但馬守などを歴任し、天平神護元年(765)従三位。 更に造宮卿、弾正尹などになったが、延暦四年(785)致仕して、同八年八十一歳で薨した。 19-4288題詞 |
| 斉明天皇 (さいめいてんわう) |
| 初め三十五代皇極天皇。重祚して三十七代斉明天皇となる。本名は宝皇女。諡は天豊財重日足姫天皇。明日香川原宮御宇天皇、後岡本宮御宇天皇などと呼ばれる。 舒明天皇の弟、茅淳王の娘。最初、用明天皇の孫、高向王に嫁し、漢皇子を生んだが、のち舒明天皇の皇后となり、天智・天武両天皇と間人皇女を生んだ。舒明崩御後即位し、皇極天皇となった。 蘇我氏滅亡の後、弟軽皇子(孝徳)に譲位し、孝徳天皇崩御の後、再び即位し、斉明天皇となった。 板蓋宮炎上後、川原宮に移り、さらに岡本宮を復興したほか大規模な土木工事を行い、また旅行を好み紀温湯・吉野・近江比良に行幸するなど民心を無視するような挙をあえてした。 斉明七年(661)正月百済救援のため筑紫におもむき、七月、筑紫朝倉宮で崩じた。六十八歳であったと伝える。 (4-488,489) 1-8左注・12左注・15左注、4-490左注、9-1669題詞 |
| 佐為王 (さゐのおほきみ) |
| 美努王の子。葛城王(橘諸兄)の弟。和銅七年(714)従四位下となり、山上憶良らと共に東宮(後の聖武天皇)に侍したこともある。 天平八年(736)、兄葛城王と臣籍に降り、橘宿禰佐為と名のったが、翌年八月、天然痘に冒され、中宮大夫兼右兵衛率正四位上をもって卒した。 6-1009左注・1014左注・1018題詞・1019左注、16-3879左注 |
| 坂門人足 (さかとのひとたり) |
| 大宝元年(701)九月太上天皇(持統天皇)の紀伊行幸に従駕(万)。 1-54 |
| 境部王 (さかひべのおほきみ) |
| 坂合部王とも記す。穂積皇子の子。養老元年(717)無位から従四位下を授けられ、同五年治部卿に任ぜられた。 「懐風藻」に長屋王の宅において宴する詩ほか一首を載せ、年二十五とある。ただし、「皇胤紹運録」には、長皇子の子となっている。 16-3855 |
| 坂門ら |
| 尺度とも書く。〔54〕の作者坂門人足と同族であろうが、伝未詳。 16-3843歌 |
| 坂本朝臣人上 (さかもとのあそみひとかみ) |
| 天平勝宝(749~57)の末年頃から宝字(757~65)にかけて、無位で造東大寺司に勤務していたことが、正倉院文書によって知られる。 20-4351左注 |
| 桜井王 (さくらゐのおほきみ) |
| 長皇子の孫。高安王の弟。和銅七年(714)従五位下。天平十一年(739)兄高安王と共に臣籍に下り、大原真人の姓を賜った。遠江守であったことは「続日本紀」にはみえない。風流侍従と呼ばれた一人。 →大原真人桜井 |
| 薩妙観 (さつのめうくわん) |
| 内命婦。養老七年(723)従五位上。神亀元年(724)河上忌寸の姓を賜り、天平九年(737)正五位下に叙せられた。「薩」は渡来人の姓。 20-4462,4480 20-4479題詞 |
| 狭野弟上娘 (さののおとがみをとめ) |
| 伝未詳。蔵部の女嬬は斎宮寮の下級の女官であり、それならば伊勢に住むはず。そのため「後宮職員令」の蔵司の女嬬ではないかとする説がある。 15-3745,3746,3747,3748,3767,3768,3769,3770,3771,3772,3773,3774,3775,3789,3790,3791,3792,3793,3794,3795,3796,3799,3800 |
| 佐伯直子音 (さへきのあたひこおびと) |
| 天平三年(731)四月の「筑前国司牒案」に、筑前介正三位上勲五等として署名している。この「正三位」は「正六位」などの誤りかといわれる。 (5-834) |
| 佐伯宿禰赤麻呂 (さへきのすくねあかまろ) |
| 伝未詳。佐伯氏は大伴氏の一族で互いに結び付きが深い。 3-408 4-631,633 3-407題詞、4-630題詞 |
| 佐伯宿禰東人 (さへきのすくねあづまと) |
| 天平四年(732)西海道節度使の判官となり、外従五位下を授けられた。 4-625 4-624題詞 |
| 佐用姫 (さよひめ) |
| 逸文「肥前国風土記」の帔揺岑の条にもその伝説が見える。 それによると、宣化天皇の代、任那に派遣された大伴狭手彦(佐提比古)がこの地の篠原村の弟媛という容姿端正な美女に求婚し、弟媛が別れに際してこの峰で領巾を振り招いたとある。 さらに現行「肥前国風土記」にはこれに続けて、狭手彦に似た男が夜毎に訪れ、これを怪しんだ女は績麻をを男の裾につけその正体を蛇と見破ったが、蛇も女も死んでいた、という三輪山伝説を載せている。 5-872歌・875題詞・875序/歌・876・877・878・879歌・887題/歌 |
| 志賀津の児ら (しがつのこら) |
| 吉備津采女をさすか。吉備は生国、志賀(滋賀県大津市北部)は生前の居住地とみる説による。→吉備津采女 2-218歌 |
| 志貴皇子 (しきのみこ) |
| 天智天皇の第七皇子。白壁王(四十九代光仁天皇)、湯原王らの父。施基・芝基・志紀などとも記す。天武天皇の皇子磯城皇子とは同名別人。 霊亀元年(715)二品を授けられ、翌二年八月薨。万葉集では元年九月薨とある。光仁天皇が即位すると春日宮御宇天皇と追尊され、また墓の所在地により田原天皇とも呼ばれた。 1-51,64 3-269 4-516 8-1422,1470 1-84題詞、2-230題詞、4-534題詞・634題詞・672題詞、6-1020題詞 |
| 志紀連大道 (しきのむらじおほみち) |
| 【小学館「新編日本古典文学全集巻第五-837(841) 頭注『算師は物数の・・・』より引用】 算師は物数の計算を掌る官。大宰府のそれは正八位上相当官。原文「笇」は「算」に同じ。志氏大道は、志紀連大道か。 暦算家。『家伝』下「武智麻呂伝」にもその名が見える。 5-841 |
| 史氏大原 (じのおほはら) |
| 【有斐閣「萬葉集全注巻第五-826(830) 注『史氏大原』」より引用】 大典は少監に次ぐ大宰府四等官の上席。定員二名。正七位上相当。「事を受けて上抄し、文案を勘署し、稽失を検へ出し、公文読み申すこと」(職員令)。史氏は、史部か(万葉考)。大原は伝未詳。歌は日頃部下の勤務評定をしている役人らしい歌。 5-830 |
| 志斐嫗 (しひのおみな) |
| 伝未詳。「新撰姓氏録」左京皇別上に、安倍志斐連名代という者があり、天武天皇に、楊の花を差し上げ、こぶしの花だと称し、群臣が楊の花だと言うのを聞き入れなかったという逸話を載せ、そこからシヒ(強引の意)の名をもらったと説明している。その一族か。あるいは志斐連の一族か。志斐を名と解する説もある。 (238)作歌 |
| 島足 (しまたり) |
| 伝未詳。上代の文献には、安勅島足・竹志島足・菅生島足など、十数名の同名人がある。 9-1728 |
| 椎野連長年 (しひのむらじながとし) |
| 伝未詳。「続日本紀」神亀元年(724)の条に、正七位上四比忠男という者があり、椎野連の姓を賜ったことが見える。その一族であろう。四比は渡来人の姓。 (16-3844) |
| 聖武天皇 (しやうむてんわう) |
| 四十五代。文武天皇の皇子。母は藤原不比等の娘、宮子。本名は、首皇子。諡は天璽国押開豊桜彦命、平城宮御宇天皇と呼ばれる。 大宝元年(701)に生まれ、和銅七年(714)立太子、神亀元年(724)即位。 皇后は不比等の娘、光明子。仏教文化に彩られた、華やかな天平時代を象徴する存在であったと同時に、皇親と藤原・橘両氏とが醜い勢力争いを続ける中に、転々と遷都し、かつ、凶作・疫病などの天災に見舞われ、不安な政情に明け暮れした。天平感宝元年(749)譲位し、天平勝宝八年(756)五十六歳で崩じた。 4-533,627 6-978,979,1014,1034 8-1543,1544,1619,1642 19-4293 4-629題詞・724題詞・726題詞、6-1031題詞、8-1618題詞・1662題詞、19-4259題詞・4293左注、20-4325題詞・4481題詞 |
| 淳仁天皇 (じゅんにんてんわう) |
| 四十七代。天武天皇の孫。舎人親王の第七皇子。本名は大炊王。 天平勝宝九年(757)四月、聖武太上天皇の遺詔によって立てられた皇太子道祖王が不品行を理由に廃された後、孝謙天皇と藤原仲麻呂に推されて皇太子となった。 仲麻呂の子真従の未亡人を妻としていた縁で、仲麻呂の田村第に住み、翌天平宝字二年(758)即位した。 同六年頃、孝謙上皇が道鏡を近づけたことから、天皇は上皇と不和になり、天皇と仲麻呂、上皇と道鏡という対立関係が生じ、その結果、上皇は国家の大事と賞罰を行使する権利を天皇から奪うことを宣言した。同八年、仲麻呂が謀叛するに及んで、天皇は廃され、淡路に護送され、天平神護元年(765)幽憤のうちに崩じた。三十三歳。 20-4510 |
| 舒明天皇 (じょめいてんわう) |
| 三十四代。本名は田村皇子。諡は息長足日広額天皇、高市岡本宮御宇天皇と呼ばれる。三十代敏達天皇の孫で押坂彦人大兄皇子の子。推古天皇の崩御後、蘇我蝦夷に推されて皇位についた。 飛鳥岡本宮に都し、姪の宝皇女(後の皇極・斉明天皇)を立てて皇后とし、その間に天智・天武両天皇と間人皇女が生まれた。 在位十三年で641年四十九歳で崩じた。遣唐使の派遣、高麗・百済との修交、蝦夷の鎮圧などに力を用いた。 舒明十一年(639)十二月から翌年四月にかけて伊予の温湯宮におもむいたことは万葉集にも見え、のち斉明天皇が筑紫に行く途中ここに寄る縁となった。 1-2 8-1515 (9-1668) 1-3題詞・6左注・8左注、4-490左注、9-1668左注 |
| 神功皇后 (じんぐうわうごう) |
| 十四代仲哀天皇の皇后。息長足日女命、足日女命などとも呼ばれる。 「日本書紀」によれば、熊襲を討つため天皇と筑紫におもむき、香椎宮(橿日宮)にあった時、皇后に神がかりして新羅を討つことを勧めたが、天皇は信じないで崩じたので、皇后は喪を秘めて海を渡り、戦わずして新羅、更に百済・高句麗をも従えた。帰還後、応神天皇を生み、摂政皇太后として百歳まで在世したとある。 5-817歌・873歌、15-3707歌 |
| 推古天皇 (すいこてんわう) |
| 三十三代。諡は豊御食炊屋姫天皇と呼ばれる。日本最初の女帝。二十九代欽明天皇の皇女。母は蘇我稲目の娘、堅塩媛。異母兄敏達天皇の皇后となり、三十二代祟峻天皇崩御後即位。 聖徳太子に万機を摂政させ、推古三十六年(628)に七十五歳で崩じた。 3-418題詞 |
| 少彦名・少御神 (すくなびこな・すくなみかみ) |
| 大国主命と協力して国造りに力があったと伝えられる神。小さな子神で知恵があり、最後は粟の茎の弾力によって常世の国に飛び去ったと伝えられる。 3-358歌、6-968歌、7-1251歌、18-4130歌 |
| 清江娘子 (すみのえをとめ) |
| 伝未詳。〔65〕に見える「住吉の弟日娘」と同一人かともいう。遊女の類であろう。 1-96 |
| 駿河婇女 (するがのうねめ) |
| 駿河国駿河郡から貢進された采女。駿河郡は今日の駿東(すんとう)郡(沼津市・御殿場市を含む) に当たる。巻八-1424 の作者駿河采女との異同は不明。 4-510 (8-1424 |
| 小弁 (せうべん) |
| 伝未詳。左少弁または右少弁だった官人か。 9-1738 3-308左注、9-1723左注 |
| 消奈行文 (せなのぎやうもん) |
| 武蔵国高麗郡出身。養老五年(721)当時、明経第二博士として賞されたことがある。神亀四年(727)従五位下を授けられた。 「懐風藻」に詩二首を載せ、大学助、年六十二と記す。高麗福信の伯父。「消奈」は「背奈」と誤記されることが多いが、本来高句麗の五部の一つ消奴部に由来する姓。 「続日本紀」には「肖奈」とあるが、今は万葉集の表記「消奈」に従っておく。 16-3858 |
| 衣通王 (そとほりのおほきみ) |
| 軽太郎女の異名。その体の光が衣を通して照り輝いたところからその名がある。 「日本書紀」では、允恭天皇の皇后(木梨軽皇子・軽太郎女の母、忍坂大中姫命)の妹で、允恭に愛された弟姫の異名として、その名が用いられている。→軽太郎女 |
| 園臣生羽 (そののおみいくは) |
| 伝未詳。園は氏、臣は姓、生羽は名。 2-123題詞 |
| 村氏彼方 (そんしをちかた) |
| 【有斐閣「萬葉集全注巻第五-840(844) 注『村氏彼方』」より引用】 下国の目(さかん)で、少初位上相当。村氏は、村国、村君、村山その他の氏あり。彼方は伝不明。 5-844 |
| 高田女王 (たかたのおほきみ) |
| 長皇子の曾孫か。父は高安王。 4-540,541,542,543,544,545 8-1448 |
| 田形皇女 (たがたのひめみこ) |
| 天武天皇の皇女。母は蘇我赤兄の娘、大蕤娘。穂積皇子、紀皇女の同母妹。慶雲三年(706)伊勢神宮に仕え、神亀元年(724)二品を授けられ、同五年に薨じた。 8-1615題詞 |
| 高橋朝臣 (たかはしのあそみ) |
| 名不明。高橋国足(天平十年遠江国少掾正六位下、同十八年従五位下越後守)、子老(天平勝宝七年越前国介、天平宝字元年従五位下)、老麻呂(天平宝字二年従五位下遣渤海副使)など、諸説がある。 高橋朝臣は天皇の膳部のことをつかさどる家柄。 『高橋氏文』や『新撰姓氏録』に、景行天皇の東国巡幸の際、大蛤を奉った功により、膳臣の姓を賜り、さらに天武十二年(683)高橋朝臣を賜ったことが見える。 3-484,485,486 3-486左注 |
| 高橋朝臣安麻呂 (たかはしのあそみやすまろ) |
| 養老二年(718)従五位下。宮内大輔、征夷副将軍、右中弁などを歴任。天平十年(738)正月従四位下となり、同年十二月大宰大弐に任ぜられた。 6-1031左注 |
| 高橋連虫麻呂 (たかはしのむらじむしまろ) |
| 伝未詳。天平四年(732)藤原宇合が西海道の節度使となったときに作った歌があり、養老年間(717-24)宇合が常陸守であった頃から仕えていたものか。 高橋虫麻呂歌集出とか高橋虫麻呂歌中出とかあるのもほとんど彼の作品と考えられ、そのうち特に伝説に取材した叙事的内容のものに特色がある。 (976,977)作歌。 6-976,977 【虫麻呂歌集中】 3-322,323,324 8-1501 9-1742,1743,1744,1745,1746,1747,1748,1749,1750,1751,1752,1753,1754,1755,1756,1757,1758,1759,1760,1761,1762,1763,1764,1784,1785,1811,1812,1813,1814,1815 |
| 高向村主老 (たかむこのすぐりおゆ) |
| 天平十七年(745)頃雅楽少允正六位上であったことが正倉院文書で知られ、また「続日本紀」にも天平勝宝二年(750)に正六位上から外従五位下になったことが見える。 (5-845) |
| 高安王 (たかやすのおほきみ) |
| 大原真人高安。長皇子の孫か。和銅六年(713)従五位下。養老初年、紀皇女と通じたことによって、伊予国守に左遷されたという所伝がある〔3112左注〕。 その後、摂津大夫、衛門督などを歴任。天平十一年(939)臣籍に入り、大原真人の姓を賜った。同十四年正四位下で卒。 4-628 8-1508 17-3974 4-580題詞、8-1448題詞、12-3112左注 |
| 高安大島 (たかやすのおほしま) |
| 伝未詳。〔67〕の歌は目録には「作主未詳歌」として、下に小字で「高安大島」と記す。 1-67 |
| 高丘連河内 (たかをかのむらじかふち) |
| もと楽浪河内といい、養老五年(721)佐為王や山上憶良らと東宮(後の聖武天皇)に侍した。神亀元年(724)高丘連の姓を賜り、天平三年(731)外従五位下。 同十四年には紫香楽の離宮の造宮輔に任ぜられ、十八年五月中五位下、天平勝宝六年(754)正五位下に進んだ。伯耆守、大学頭にもなったことがある。 6-1042,1043 17-3948左注 |
| 多紀皇女 (たきのひめみこ) |
| 天武天皇の皇女。母は宍人臣大麻呂の娘、カジ媛娘。忍壁皇子、泊瀬部皇女らと同母。朱鳥元年(686)、文武二年(698)、慶雲三年(706)にたびたび伊勢に遣わされたことが見える。 志貴皇子の妃。春日王の母。天平勝宝三年(751)一品で薨。 4-672題詞 |
| 当麻真人麻呂 (たぎまのまひとまろ) |
| 伝未詳。真人は姓。当麻氏は用明天皇の皇子麻呂古王の子孫。 1-43題詞、4-514題詞 |
| 高市大卿 (たけちのだいきゃう) |
| 大伴御行のことか。高市はその住んだ地の名によって呼んだものであろう。 御行は長徳の子。安麻呂の兄。壬申の乱で功があり、兵部大輔を経て大納言となり、大宝元年(701)に正広参(養老令の正三位に相当)で薨じ、右大臣を追贈された。 4-652左注 |
| 高市古人 (たけちのふるひと) |
| 未詳。高市黒人の「黒人」を〔32〕の歌の原文の初め二字の「古人」と誤ったものとも考えられる。 1-32,33 |
| 高市皇子 (たけちのみこ) |
| 天武天皇の数多い皇子のうち最年長であったが、母が身分の低い胸形君徳善の娘、尼子娘というものであったために、その位は草壁・大津の二皇子に次いだ。 壬申の乱の際、19歳で指揮官として軍事を委ねられ、味方を勝利に導いた。持統三年(689)草壁皇子が薨じ、翌年太政大臣となったが、同十年43歳で薨じた。 [169]の脚注で「後皇子尊」と記し、また、[156,199] の題詞に「高市皇子尊」と尊号を付けてあることは、草壁亡き後、皇太子なみに遇せられていたことの証であろう。 2-156、157、158作歌。 |
| 高市連黒人 (たけちのむらじくろひと) |
| 伝未詳。持統・文武両天皇の頃の歌人。行幸に供奉したほか各地に旅行し、旅の歌を多く詠んだ。残っている歌は十八首、短歌ばかりだが、印象鮮明で自然観照的なものが多い。 1-32,33,58,70 3-272,273,274,275,276,277,278,279,280,282,283,286,308 9-1722 17-4040 1-32題詞 |
| 橘朝臣奈良麻呂 (たちばなのあそみならまろ) |
| 諸兄の子。初め宿禰姓。天平十二年(740)従五位下、同年更に従五位上に昇叙。大学頭、摂津大夫、民部大輔、侍従、右大弁などを歴任。 天平勝宝二年(750)に朝臣姓となり、天平宝字元年(757)六月右大弁に任ぜられたが、同月二十八日山背王が、奈良麻呂に叛意があり、兵器を集めて藤原仲麻呂の田村宮(前月初めに孝謙天皇が移り住む)を包囲しようと計画中だ、と密告した。 このいわゆる橘奈良麻呂の変は、皇族および橘・大伴・佐伯その他の諸氏のうち、仲麻呂を除き人心を刷新しようとする人々の計画を仲麻呂側が未然に察知して失敗させ、結果的には仲麻呂独裁体制を築くに至った政治事件である。 これに関係して処罰されたものは四百四十三人にのぼり、その中には黄文王・道祖王・安宿王・塩焼王・大伴胡麻呂・大伴古慈悲・大伴池主・佐伯大成・佐伯全成・多治比犢養・丹比国人らも含まれ、それらはあるいは獄死し、あるいは流された。奈良麻呂、「尊卑分脈」によれば享年三十七歳。相当な蔵書家であったらしく、乱後480余巻の家書が没官されたという。 6-1015 8-1585,1586 19-4303題詞、20-4478題詞 |
| 橘朝臣諸兄 (たちばなのあそみもろえ) |
| 初め葛城王といい、美努王(敏達天皇の玄孫、708年卒)の子。母は県犬養宿禰三千代。和銅三年(710)従五位下となり、天平元年(729)左代弁、同四年従三位と進んだ。 同八年臣籍に降り、母方の姓を請い許されて橘宿禰諸兄を名乗った。 この後、大納言を経て、右大臣、左大臣となり、位も天平勝宝元年(749)には正一位と最高位を極め、翌年朝臣の姓を賜ったが、同八年二月に致仕し、翌年正月に薨じた。 七十四歳。天平十八年頃を頂点として、次第に実力をつけてきた藤原氏にその差を縮められ、晩年には仲麻呂らにその実権を握られていたものと思われる。 勝宝八年に致仕したのも、その二ヶ月前に酒席で朝廷を誹謗するような言辞があったという密告によるものである。 6-1029、17-3944、18-4080、19-4294、20-4471、4472、4478、4479 |
| 橘宿禰文成 (たちばなのすくねあやなり) |
| 佐為王の子。伝未詳。目録には、「橘文明」とある。『名義抄』に「明、ナル」とあり、「文明」も文成と同じと見てよい。 6-1019 |
| 橘宿禰佐為 (たちばなのすくねさい)→佐為王 |
| 橘宿禰奈良麻呂 (たちばなのすくねならまろ) →橘朝臣奈良麻呂 (たちばなのあそみならまろ) |
| 橘宿禰諸兄 (たちばなのすくねもろえ) →橘朝臣諸兄 (たちばなのあそみもろえ) |
| 丹比真人 (たぢひのまひと) |
| 丹比は氏、真人は姓。いずれも名を欠く。 2-226 9-1730 |
| 丹比真人県守 (たぢひのまひとあがたもり) |
| 多治比にも作る。左大臣島の子。慶雲二年(705)従五位下、霊亀元年(715)従四位下、翌二年第八次遣唐使押使に任ぜられ、養老二年(718)帰朝。 同五年正四位上中務卿、天平元年(729)大宰大弐で権参議となり、従三位に叙せられ、民部卿に遷任。同三年参議、六年正三位に進み、九年六月中納言で薨じた。 4-558題詞 |
| 丹比真人乙麻呂 (たぢひのまひとおとまろ) |
| 屋主の第二子。天平神護元年(765)従五位下となり、同年十月紀伊行幸の時、御前次第司次官を務めた。 8-1447 |
| 丹比真人笠麻呂 (たぢひのまひとかさまろ) |
| 伝未詳。 3-288、4-512,513 |
| 丹比真人国人 (たぢひのまひとくにひと) |
| 天平八年(736)従五位下。民部少輔、大宰少弐、右大弁、摂津大夫、遠江守などを歴任し、従四位下まで昇ったが、天平宝字元年(757)七月、橘奈良麻呂の変に連座し、伊豆に流された。 3-385,386 8-1561 20-4470 |
| 多治比真人鷹主 (たぢひのまひとたかぬし) |
| 天平宝字元年(757)六月、橘奈良麻呂の陰謀に加わり、安宿王・黄文王・大伴胡麻呂・大伴池主らとしばしば密議を凝らした。獄死。配流いずれに終わったか不明。 19-4286 |
| 多治比真人土作 (たぢひのまひとはにし) |
| 左大臣島の孫。天平十一年(740)従五位下、同十五年検校新羅客使となり、新羅使の無礼を指摘したことがある。摂津介、民部少輔などを歴任し、天平勝宝元年(749)に紫微大忠を兼ねた。 その後、尾張守、文部大輔、左京大夫などを歴任し宝亀二年(771)参議治部卿従四位上をもって卒した。 19-4267 |
| 多治比真人広成 (たぢひのまひとひろなり) |
| 文武朝の左大臣正二位島の第五子。和銅元年(708)従五位下。下野守、越前守などを歴任し、天平三年(731)従四位上となり、四年八月遣唐大使に任ぜられ、翌年四月難波より出航し、六年十一月種子島に帰着。同船者に玄昉、下道(吉備)真備らがいた。その後、同九年に参議中納言に任ぜられ従三位に進み、更に式部卿を兼ね、十一年に薨じた。「懐風藻」に詩三首を載せる。 5-900左注 |
| 丹比真人屋主 (たぢひのまひとやぬし) |
| 神亀元年(724)従五位下。天平十七年(745)従五位上。同二十年正五位下。その間、備前守・左大舎人頭を歴任。 6-1035 8-1446 8-1447題詞 |
| 多治比部北里 (たぢひべのきたさと) |
| 天平勝宝二年(750)頃、越中国砺波郡主帳であった。 「越中国官倉納穀交替帳」(平安遺文・一)に、同三年同国某郡の主帳であった外大初位蝮部北里、天平宝字元年(757)主政外初位上となった蝮部北里はこれと同一人物であろう。 18-4162題詞 |
| 但馬皇女 (たぢまのひめみこ) |
| 天武天皇の皇女。母は藤原鎌足の娘、氷上娘。高市皇子、穂積皇子らの異母妹。三品に進む。和銅元年(708)六月に薨。 2-114,115,116 8-1519 2-203題詞 |
| 田道間守 (たぢまもり) |
| 「日本書紀」 の記載によると、天日槍の子孫で、垂仁天皇の命を受け、非時香果を取りに常世の国へ行ったが、九年を経て持ち帰った時は、天皇の崩御後であったために嘆き悲しみ、陵の前に叫哭して死んだ、とある。「古事記」にもそれとほとんど同じような記事が見える。 18-4135歌 |
| 竜田彦 (たつたひこ) |
| 奈良県生駒郡三郷町立野の竜田神社の祭神。『延喜式』神名帳に「竜田比古・竜田比女二座」とあり、祝詞「竜田風神祭」には、祟神天皇の夢に現れた二神が、幣帛を奉れば五穀を悪しき風荒き水にあわせず保護しようと告げ、それから竜田の地に祭られるようになったことが記されている。なお、どう郡斑鳩町竜田にも竜田神社があり、両社の関係や祭神のことなど、不明な点がある。 9-1752歌 |
| 丹波大女娘子 (たにはのおほめのをとめ) |
| 伝未詳。丹波は姓。大女は名か。 4-714,715,716 |
| 田口朝臣広麻呂 (たくちのあそみひろまろ) |
| 伝未詳。慶雲二年(705)従六位下より従五位下に進む。 3-430 |
| 田口朝臣益人 (たくちのあそみますひと) |
| 慶雲元年(704)従五位下。和銅元年(708)三月十三日の条に、従五位上で上野守となる旨を記す。翌年右兵衛率。霊亀元年(715)正五位上に進む。 3-299,300 |
| 田部忌寸櫟子 (たのべのいみきいちひ) |
| 伝未詳。天智天皇の大殯の時に歌を詠んだ舎人吉年と贈答しているところからみて、天智・天武の頃の人と推定される。 4-495,496,497,498 |
| 田辺史福麻呂 (たのべのふびとさきまろ) |
| 天平二十年(748)三月、造酒司令史であった時、橘諸兄の使者として越中国におもむき、国守であった家持と飲宴遊覧、作歌したことが、巻十八の初めに見える。 「田辺福麻呂歌集」は彼の作品を集めたものであろう。 18-4056,4057,4058,4059,4060,4062,4063,4064,4065,4066,4070,4073,4076 18-4086左注 【田辺福麻呂歌集中出とあるもの】 6-1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1063,1064,1065,1066,1067,1068,1069,1070,1071 9-1796,1797,1798,1804,1805,1806,1807,1808,1809,1810 |
| 田辺史真上 (たのべのふびとまかみ) |
| 天平十七年(745)頃、諸陵大允従六位上であったことが正倉院文書によって知られる。 (5-843) |
| 足日女 (たらしひめ) →神功皇后・息長足日女命に同じ |
| 手持女王 (たもちのおほきみ) |
| 伝未詳。 3-420,421,422 |
| 丹氏麻呂 (たんしまろ) |
| 【有斐閣「萬葉集全注巻第五-827(832) 注『丹氏麻呂』」より引用】 大判事は司法官。大宰府の大判事は従六位下相当。掌るところは、「犯状を安覆し、刑名を断り定め、諸の争訟を判ること」(職員令)。 丹氏は、丹治比(たじひ)、丹波(たにわ)、また丹生(にう)氏とも考えられる。麻呂は伝不明。 5-832 |
| 持統天皇 (ぢとうてんわう) |
| 四十一代。本名は鸕野讃良皇女。諡は高天原広野姫天皇、藤原宮御宇天皇と呼ばれる。天智天皇の第二皇女。母は蘇我石川麻呂の娘、遠智娘。大伯皇女・大津皇子姉弟の母である大田皇女の同母妹。 大田皇女とともに大海人皇子(天武)に嫁し、草壁皇子を生んだ。 天智十年(671)天武とともに吉野に入り、壬申の乱が終わった翌天武二年(673)、天武天皇即位とともに皇后となり、政治家として優れた才幹を発揮して天皇を助けた。 天武天皇の崩御後、称制(即位しないで天皇の職権を代行すること)し皇太子としての草壁皇子の地位を確保することに努めたが、持統三年(689)草壁皇子が薨ずると翌年自ら皇位につき、夫天武天皇の偉業を継いで、飛鳥浄御原令の完成、庚午年籍の作成、兵制の整備、藤原宮の造営など意欲的な政治を行った。 十一年文武天皇に譲位し、大宝二年(702)五十八歳で崩じた。旅行を好み、ことに吉野へは三十回以上も行幸し、これに供奉した柿本人麻呂らの秀歌を生む機縁を作ったことも注目される。 1-28 2-159,160,161,162 (3-237) 1-34左注・39左注・44左注・54題詞・57題詞・66題詞・70題詞、3-235題詞、9-1671題詞 |
| 智奴王 (ちぬのおほきみ) |
| 智努・知努などとも記す。長親王の子。養老元年(717)従四位下、木工頭、造宮卿(恭仁京)などを経て、天平十八年(746)四月正四位上、翌年従三位となった。 天平勝宝四年(752)文室真人の姓を賜り、更に摂津大夫、治部卿、出雲守、参議、中納言などを歴任。 天平宝字五年(761)正三位となり、文室真人浄三と改名し、同八年従二位御史大夫(大納言)で退き、宝亀元年(770)薨。七十八歳。 また敬虔な仏教信者としても知られ、薬師寺の仏足石は、智奴王が亡夫人茨田郡王の追善のために造立したものである。 19-4299 17-3948左注 |
| 智奴女王 (ちぬのおほきみ) |
| 系統未詳。養老七年(723)従四位下、神亀元年(724)従三位。 ただし、〔4501〕の題詞に「智努女王卒後」とあり、三位以上の者の死には「薨」の字を用いる例に適わないため、同名の別人がいたかとする説もある。 20-4501題詞 |
| 張福子 (ちゃうふくし) |
| 奈良朝初期の医師。『家伝』下「武智麻呂伝」にも方士(ほうし)としてその名が見える。渡来人であろう。 大宰府の医師は正八位上相当。 5-833 |
| 通観 (つうくわん) |
| 僧。娘子らが乾した鮑を贈り、戯れに呪願を請うたのに答えた歌が見え、他に吉野の詠一首もある。 3-330,356 |
| 調首淡海 (つきのおびとあふみ) |
| 壬申の乱に功があり、和銅二年(709)従五位下、養老七年(723)正五位上に進んだ。神亀四年(727)高齢であることによって多くの賜物を授けられた。「続日本紀」には調連とある。 1-55 |
| 筑紫娘子 (つくしのをとめ) |
| 遊女で字を児嶋といい、天平二年(730)十二月大伴旅人が帰京する際にも歌を贈っている。 3-384 6-970,971 |
| 角朝臣広弁 (つのあそみひろべ) |
| 伝未詳。広弁の読み方も不明だが、仮に本居宣長のヒロベと読む説による。 8-1645 |
| 角麻呂 (つのまろ) |
| 伝未詳。角は氏、麻呂は名か。 3-295,296,297,298 |
| 津守連通 (つもりのむらじとおる) |
| 和銅七年(714)従五位下を授けられ、美作守となった。養老七年(723)従五位上に進む。養老五年正月、陰陽道の達人として朝廷から褒賞を受けた。 2-109題詞 |
| 田氏肥人 (でんじのこまひと) |
| 【有斐閣「萬葉集全注巻第五-833(837) 注『田氏肥人』」より引用】 少令史は大令史の下席。大初位下相当。田氏は、「田口、田中、田辺、田部等」 の氏があるが、「肥人」 は伝不明。 5-837 |
| 天智天皇 (てんぢてんわう) |
| 三十八代。本名は葛城皇子。中大兄皇子ともいう。諡は天命開別天皇、近江大津宮御宇天皇と呼ばれる。三十四代舒明天皇の第一皇子。母は皇極(重祚して斉明)天皇。間人皇女・天武天皇の同母兄。 父舒明天皇が崩じた時十六歳であったとする記事によれば、推古三十四年(626)に生まれ、四十六歳で崩じたことになるが、五十八歳説もある。 皇極四年(645)蘇我石川麻呂や藤原鎌足と謀って蘇我蝦夷・入鹿の父子を討ち、次いで大化の改新の治績をあげた。孝徳天皇即位後、異母兄古人大兄を滅ぼし、功臣の蘇我石川麻呂を讒によって失い、ついには孝徳天皇とも反目し孤立させるなど、専制的傾向を強め、皇極天皇が重祚して斉明天皇となっても改まることはなかった。 斉明七年(661)百済救援のため天皇を奉じて筑紫におもむいたが、白村江の決戦で敗れ、長い間の朝鮮半島への影響力を失った。 天皇崩後、飛鳥に帰ったが皇太子として称制し、近江遷都後の天智七年(668)正月に初めて即位、倭姫王(倭皇后)を皇后しに、弟大海人皇子を皇太子とした。十年十二月崩じた。 1-13,14,15 2-91 1-16題詞・18左注・20題詞・21左注、2-147,148,149,150,151題詞、4-491題詞、8-1610 |
| 天武天皇 (てんむてんわう) |
| 四十代。本名は大海人皇子。諡は天淳中原瀛真人天皇、清御原宮御宇天皇と呼ばれる。舒明天皇の皇子。母は斉明天皇。天智天皇・間人皇女の同母弟。 天智天皇の皇女、大田・鸕野讃良(持統)両皇女を妃とし、鸕野讃良は皇后となった。 天智七年(668)天智天皇が即位するとともに皇太子となったが、政治的利害や、皇位継承の問題などで、しだいに天智天皇との間に疎隔を生じた。 同十年秋天智天皇が病に倒れると、大海人皇子を呼び、後事を託そうとしたが、皇子は天智の皇后の倭大后に皇位を譲り、天智天皇の皇子、大友皇子に政治を委ねるよう進言し、自分は天皇のために出家したいと願って、妃鸕野讃良と吉野に入った。 天智天皇の崩じた後、大友皇子が近江京の主となったが、世間の同情は天武に集まり、やがて翌年の壬申の乱が起こった。 天武は吉野を出て東国に向かい兵力を結集し、十九歳の長子高市皇子を指揮官に任じた。天武方の機動力と攻撃力は近江方を圧倒し、大友皇子の自縊によって戦いは終わった。 天武は飛鳥清御原宮に即位し天智天皇の偉業の発展に努め、兵制を整え、皇権を確立し、政治機構を整備し、新しい位階制を設けるなど律令国家の基礎を置いた。 律令や国史の編纂にも着手している。朱鳥元年(686)九月崩じた。五十六歳というが、六十五歳説もある。 1-21,25,27 2-103 1-21左注・22左注・24左注、2-159題詞・160題詞・162題詞、20-4503題詞 |
| 豊島采女 (としまのうねめ) |
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻第六-1026(1030)」頭注】 采女は、諸国から奉られ、天皇の私物として遇された女性。郡司の少領以上の者の姉妹または娘で美貌の者を採用した。 作者は豊島郡から奉られた采女であろうが、氏名・伝未詳。「和名抄」の郡名に豊島が二つあり、一つは摂津国の「豊島、手島(てしま)」(大阪府豊中・箕面・池田の三市の一帯)、他は武蔵国の「豊島、止志末(としま)」(東京都豊島区) である。ただし、 大化以後に畿内から采女を奉った確例がなく武蔵からはある。よってしばらく武蔵国豊島郡から出た采女と解し、「トシマ」と読む。 6-1030、1031 |
| 舎人皇子 (とねりのみこ) |
| 天武天皇の第九皇子。母は天智の皇女新田部皇女。養老二年(718)一品を授けられ、翌年新田部皇子とともに皇太子(聖武)の補佐役に任ぜられ、同四年藤原不比等が薨ずると知太政官事となった。 天平七年(735)薨。「日本書紀」撰修の総裁をも勤め、朝廷の中で重きをなした。四十七代淳仁天皇はその皇子。 2-117 9-1710 20-4318 8-1687題詞、9-1708題詞・1778題詞、16-3861左注 |
| 舎人吉年 (とねりのよしとし) |
| 舎人という氏の女官か。〔152〕では天智天皇の崩後、大殯の時に挽歌を詠み、また〔495・498〕では大宰府に派遣される田部忌寸櫟子と贈答している。 吉年の読み方は、キネかヨトシまたはエトシか不明だが、正倉院文書には「六人部吉年」という男性名が見え、疑いを残す。 2-152 4-495 |
| 舎人娘子 (とねりのをとめ) |
| 大宝二年(702)十月、太上天皇の参河行幸に従駕。 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻第二-117」頭注】 伝未詳。「61」などの作者。舎人皇子は舎人氏に養育され、あるいは舎人娘子とは乳兄妹の関係であったか。 『文徳実録』嘉祥三年 (850) 五月の条に、先朝の制に、乳母の姓をもって皇子の名とす、とあり、大海人皇子をはじめ実例が多い。万葉集で、~娘子とあるものはおおむね卑姓の出身。 1-61 2-118 8-1640 |
| 豊前国娘子 (とよくにのみちのくちのをとめ) |
| 【有斐閣「萬葉集全注巻第六-984(989) 注『鑑賞』」より抜粋引用】 -豊前国の娘子について、古典集成は「遊行女婦か」とするが、歌をよみ、貴人を接待しうる教養をもつ女性が、何故豊前国を離れて京に移ったのか、その辺の事情は不明とするほかはない。 6-989 |
| 土理宣令 (とりのせんりゃう) |
| 刀理宣令とも記す。渡来人系の文人官僚。養老五年(721)従七位下の時、佐為王や山上憶良らとともに退朝後、東宮(聖武)に侍した。 「懐風藻」には、正六位上、年五十九と見え、詩二首を載せ、また「経国集」にも対策文(官吏の採用試験の答案)二篇を残す。〔316〕の他に〔1474〕の歌をも作る。 ノブヨシかセンリャウか、名の読み方不明。仮にセンリャウと音読する。 3-316 8-1474 |
| 十市皇女 (とをちのひめみこ) |
| 天武天皇の皇女。母は額田王。天智天皇の皇子大友皇子の妃となり、葛野王を生んだ。壬申の乱で父天武天皇と夫の大友皇子とが戦い、その結果夫の死に終わるという悲劇の中心に身を置いた。 乱後大和に移ったが、天武七年(678)四月七日、急病で宮中に薨じた。 1-22題詞、左注、2-156題詞・158左注 |
| 長田王 (ながたのおほきみ) | ||
| 系統未詳。和同四年(711)正五位下。近江守、衛門督、摂津大夫などを歴任。天平九年(737)散位正四位下で卒。 風流侍従と称せられ、天平六年二月、天皇臨席のもとに行われた朱雀門の歌垣において、五品以上の風流者の随一として門部王らと参加したことが見える。 1-81,82,83 3-246,247,249 |
||
| 中皇命 (なかつすめらみこと) | ||
| 間人皇女か。間人皇女は舒明天皇の皇女。母は皇極天皇で、中大兄皇子の妹、天武天皇の姉に当たる。 三十六代孝徳天皇の皇后となり難波宮に在ったが、孝徳天皇と反目した中大兄皇子に連れられ、母の皇極上皇らと飛鳥に帰った。 孤立した孝徳天皇は恨んで、「かなきつけ我が飼ふ駒を引き出せず我が飼ふ駒を人見つらむか」と歌を詠んで崩じた。斉明天皇崩御後も天智は称制し、天智四年(665)二月皇女が薨じた後、同七年にようやく即位した。あるいはその間、間人皇女を名義上の天皇とし、そのために中皇命と呼んだものか。斉明天皇と見る説もある。 1-3,4,10,11,12 |
||
| 中臣朝臣東人 (なかとみのあそみあづまと) | ||
| 意美麻呂の子。清麻呂の兄。宅守の父。和同四年(711)正七位上より従五位下。式部少輔。右中弁を経て天平四年(732)兵部大輔。翌年従四位下。のち刑部卿にまで進んだ。 4-518 |
||
| 中臣朝臣清麻呂 (なかとみのあそみきよまろ) | ||
| 中納言正四位上意美麻呂の子。天平十五年(743)従四位下。神祇大副、尾張守などを歴任、天平勝宝三年(751)従五位上となった。 同六年左中弁。その後、文部大輔参議、左大弁兼摂津大夫、神祇伯兼中納言などを歴任し、位も天平神護元年(765)に従三位となり、天応元年(781)に致仕した時は右大臣正二位であった。 延暦七年(788)薨。八十七歳。光仁天皇の信頼絶大なものがあり、長岡遷都後も平城旧京の右京二条二坊にとどまって余生をを送った。 20-4320,4523,4528,4532 19-4282左注、20-4520題詞 |
||
| 中臣朝臣武良自 (なかとみのあそみむらじ) | ||
| 『中臣系図』に正六位上尾張掾武良自士とあるものがあり、中臣〔3745〕の従兄弟に当たる者可かという。 8-1443 |
||
| 中臣朝臣宅守 (なかとみのあそみやかもり) | ||
| 東人の第七男。天平十年(738)頃、蔵部女嬬狭野弟上娘子を娶ったときに勅断されて、越前国に配流された。 同十二年六月の大赦の際、穂積老らは許されて入京したが、宅守は石上乙麻呂らと共にその限りでないとされた。後、許されたらしく、天平宝宇七年(763)に従六位上から従五位下を授けられた。 しかし、その翌年恵美押勝(藤原仲麻呂)の乱によって除名された。「中臣系図」には神祇大副であったことが記されている。 彼の越前配流の原因について、狭野弟上娘子との関係かとする説もあるが、娘子を娶るとはあっても、奸すと書いていない事を根拠に、それ以外に理由を求める者もある。 15-3749,3750,3751,3752 3753,3754,3755,3756,3757,3758,3759,3760,3761,3762,3763,3764,3765,3766,3776,3777,3778,3779,3780,3781,3782,3783,3784,3785,3786,3787,3788,3797,3798,3801,3802,3803, 3804,3805,3806,3807 |
||
| 中臣女郎 (なかとみのいらつめ) | ||
| 伝未詳。大伴家持に歌を贈っている。 4-678,679,680,681,682 |
||
| 長忌寸奥麻呂 (ながのいみきおきまろ) | ||
|
||
| 長皇子 (ながのみこ) | ||
| 那我親王とも記す。天武天皇の第六皇子。母は天智天皇の皇女、大江皇女。弓削皇子の同母兄。両人双生とする説もある。持統七年(693)浄広弐。慶雲元年(704)二品、霊亀元年(715)一品で薨じた。 1-60,65,73,84 2-130 1-69左注、3-240題詞 |
||
| 長屋王 (ながやのおほきみ) | ||
| 高市皇子の子。母は御名部皇女。慶雲元年(704)正四位上。 宮内卿、式部卿、大納言、右大臣を経て、神亀元年(724)正二位左大臣となったが、同六年二月藤原氏の讒言にあって、妃吉備内親王(草壁皇の皇女)や膳部王らの諸王子とともに自決した。 年五十四歳。「尊卑分脈」には四十六歳と見える。漢詩文を好み、佐保の私邸(作宝楼)にしばしば多くの文人を招き、宴遊を催した。 「懐風藻」には詩三首を載せる。その邸宅が平城左京三条二坊にあったことが発掘調査によって判明したが、それと作宝楼との関係は明らかでない。 1-75 3-270,303,304 8-1521 3-444題詞、4-1642左注 |
||
| 楢原造東人 (ならはらのみやつこあづまと) | ||
| 儒家。天平十年(738)近江大掾から大宰大監となり、同十七年外従五位下、十八年五月従五位下、十九年駿河守。天平勝宝二年(750)勤臣の姓を賜り、天平宝字元年(757)正五位下となった。 17-3948左注 |
||
| 新田部皇子 (にひたべのみこ) | ||
| 天武天皇の第十子。母は鎌足の娘、五日重娘。養老四年(720)知五衛および授刀舎人事となり、神亀元年(724)一品。天平三年(731)畿内大惣管。同七年薨。唐招提寺はその旧宅跡に建てられたもの。 3-263題詞、8-1469題詞、16-3857題詞・左注 |
||
| 丹生王 (にふのおほきみ) | ||
| 伝未詳。丹生女王と同とする説がある。 (3-420,421,422) |
||
| 丹生女王 (にふのおほきみ) | ||
| 系統未詳。天平十一年(739)従四位上。天平勝宝二年(750)正四位上。神亀五年(728)頃旅人が大宰帥になって赴任した時、これに歌を贈っている。 〔812,813〕の作者も丹生女王かとする説がある。石田王が卒した時に挽歌〔423〕を詠んだ丹生王も同一人かという。 4-556,557 8-1614 |
||
| 仁徳天皇 (にんとくてんわう) | ||
| 十六代。諡は大鷦鷯天皇。難波高津宮御宇天皇とも呼ばれる。応神天皇の皇子。弟宇治若郎子(菟道稚郎子)と皇位を譲り合ったが、若郎子が自害したため即位したと見える。 難波に都し、仁政を行い、また治水・勧農などに力を注いだと伝えられる。 一方、女性関係にも艶聞が絶えず、磐姫皇后の嫉妬に悩みながら、左注の八田皇女の他に桑田玖賀媛、吉備の黒比売などと恋愛遍歴を続ける説話が記紀に見える。 2-85題詞・90左注、4-487題詞 |
||
| 額田王 (ぬかたのおほきみ) | ||
| 鏡王(宣化天皇の三世の孫か)の娘。初め大海人皇子(天武)の寵を受け、十市皇女を生んだが、のち天智天皇のもとに移った。 生没年未詳だが、十市皇女の子で慶雲二年(705)に三十七歳で没した葛野王の年齢を基準にして舒明十年(638)頃の生まれか、とする説がある。 持統天皇の御代に弓削皇子と唱和した歌〔112〕が見えるが、その頃五十五~六十歳であったと思われる。 題詞に額田王の歌とあっても、左注に斉明天皇または天智天皇の作とする異伝があることは、既に歌人として才能が認められ、求められて代作することがあった証であろう。 ただし、「秋の野のみ草刈り葺き」〔7〕の歌だけは、舒明十年生まれとする説によると十一歳となり、幾分生年をさかのぼらせるべきかとも考えられるが、その標題や左注も曖昧で、疑問とするほかない。 1-7,8,916,17,18,20 2-112,113,151,155 4-491 (8-1610) 1-8左注、2-111題詞 |
||
| 抜気大首 (ぬきけのおほびと) | ||
| 伝未詳。抜気を氏、大首を姓とみる説や、抜を氏、気大を名、首を姓とみる説などがある。とりあえず、ヌキケノオホビトと読んでおく。 9-1771,1772,1773 |
||
| 能登臣乙美 (のとのおみおとみ) | ||
| 天平二十年(748)四越中掾久米朝臣広縄の館での宴に参加。時に羽咋郡擬主帳。 18-4093 |
| 羽栗 (はくり) |
| 翼・翔兄弟のうちのいずれかをさすか。二人は、山背国乙訓郡の人羽栗吉麻呂の子。 霊亀二年(716)吉麻呂が阿倍仲麻呂の従者として入唐した時、唐女を娶って生ませた子供で、天平六年(734)父に従って来日した。その時、翼は十六歳、翔は十四歳。 翼は聡明の聞こえ高く、特に医薬の業に秀で、内薬正侍医として重んぜられ、正五位下に進んだ。遣唐准判官として入唐したこともある。 延暦十七年(798)卒。弟翔は天平宝字五年(761)藤原河清(清河)の帰国を要請すべく遣わされて入唐したが、そのまま帰らなかった。あるいは父の吉麻呂と考えられなくもない。 15-3662 |
| 間人宿禰大浦 (はしひとのすくねおほうら) |
| 伝未詳。 3-292,293 (9-1689,1690) 9-1767左注 |
| 間人連老 (はしひとのむらじおゆ) |
| 伝未詳。「孝徳紀」白雉五年(654)二月の冬の遣唐使判官の中に見える小乙下中臣間人連老と同じ人か。この連は姓の一つで、天武天皇の代になって宿禰に改められた。 〔3〕の題詞の中の中皇命が間人皇女だとすると、皇女の名は、その乳母などがこの老の近親者であったところから付けられたものかと想像される。 実際は、その当時十歳前後であった皇女に代わって老がこの歌を詠んだものであろう。 1-3題詞 |
| 丈部直大麻呂 (はせつかべのあたひおほまろ) |
| 下総国印波郡の防人。伝未詳。下総国印波郡の采女に丈部直広成という者があり、また、天応年間(781~782)に同郡の大領であった丈部直牛養という者があった。 20-4413 |
| 丈部黒当 (はせつかべのくろまさ) |
| 遠江国佐野郡の防人。伝未詳。正倉院文書に、同郡の散事に丈部塩麻呂という者があったことを記す。 20-4349 |
| 丈部竜麻呂 (はせつかべのたつまろ) |
| 天平元年(729)摂津国の班田史生として在任中自縊して死んだ。 丈部はハセツカヒベの約で、正倉院文書の経師たちに丈部・杖部の両様に記すものがあり、元来、杖を持って走り使いをする者の意であったと思われる。 丈部の氏は出雲・美濃・常陸・陸奥などに若干かたよって見え、万葉集では遠江・駿河・上総などの出身者に多い。「続日本紀」宝亀元年(770)七月十八日の条に常陸国那賀郡出身の同名異人が見える。 3-446題詞 |
| 丈部造人麻呂 (はせつかべのみやつこひとまろ) |
| 相模国の防人。伝未詳。霊亀元年(715)同国足下郡の丈部造智積という者が孝行の故で表彰されている。それと関係があるか。 20-4352 |
| 波多朝臣小足 (はたのあそみをたり) |
| 伝未詳。「続日本紀」には波太朝臣広足・百足などの名前が見え、それらと同族かと思われる。本条は類聚古集などの非仙覚本に「小足」とあるが、目録には全古写本に「少足」に作っている。 3-317 |
| 秦伊美吉石竹 (はだのいみきいはたけ) |
| 伊波多気とも記す。天平勝宝元年(749)頃、越中少目として家持の配下にあった。天平宝字八年(764)藤原仲麻呂討伐の功により正六位上から外従五位下を授けられ、更に飛騨守、播磨介に進んだ。 18-4110題詞・4159左注、19-4249左注 |
| 秦忌寸朝元 (はだのいみきてうぐわん) |
| 医術家。弁正法師の子。大宝年間(701~704)、父が学生として入唐中、唐土で生まれ来日した。養老三年(719)忌寸姓を授けられ、同五年従六位下の時、医術の師範として賞せられた。 天平二年(730)弟子をとって漢語を教授することを許可され、同九年外従五位上で図書頭となり、同十八年三月主計頭となった。 「懐風藻」には、天平五年入唐判官となって渡唐した折、玄宗皇帝がその父弁正の縁故によって優詔し、厚く賞揚した、と書いてある。 17-3948左注 |
| 秦忌寸八千島 (はだのいみきやちしま) |
| 伝未詳。天平十八年(746)頃、越中大目として家持の配下にあった。 17-3973,3978 17-4013題詞 |
| 秦間満 (はだのはしまろ) |
| 伝未詳。ママロと読む説もある。一説に、〔3703〕の作者秦田麻呂と同一人かとする。上代の秦氏の大部分は、忌寸姓を持つ者と無姓の渡来人の子孫との二つに分かれる。この間満や田麻呂は後者か。 15-3611 |
| 泊瀬部皇女 (はつせべのひめみこ) |
| 長谷部内親王とも記す。天武天皇の皇女。母は宍人臣大麻呂の娘、カジ媛娘。忍壁皇子・多紀皇女らと同母。川島皇子の妃。天平九年(737)三品となり、十三年薨。 2-194題詞・195左注 |
| 土師宿禰水道 (はにしのすくねみみち) |
| 伝未詳。御道・水通とも記し、字を志婢麻呂といった。天平二年(730)の梅花宴で歌を詠み〔847〕、また色の黒い同僚を失う戯笑歌を作ったことがある。ハニシは約めてハジともいう。 4-560,561 5-847 16-3866 16-3867左注 |
| 土師宿禰百村 (はにしのすくももむら) |
| 養老五年(721)正七位上であった時、山上憶良らと共に東宮(後の聖武天皇)に侍した。 (5-829) |
| 林王 (はやしのおほきみ) |
| 天平十五年(743)従五位下、図書頭になり、天平宝字五年(761)従五位上に進んだ。宝字三年に無位から従四位下に叙せられ、木工頭となった林王は別人であろう。 別に三島王の子で、後の山部真人の姓を賜った林王もあるが、これと第二の林王との異同は不明。 17-3948左注、19-4303題詞 |
| 常陸娘子 (ひたちのをとめ) |
| 藤原宇合が常陸国守として在任中に娶った女か。〔131〕題詞参照。 4-524 |
| 土形娘子 (ひぢかたのをとめ) |
| 伝未詳。土形氏は大山守命(仁徳天皇の異母弟で、謀叛を起し仁徳天皇に滅ぼされた)の子孫。 3-431題詞 |
| 檜隈女王 (ひのくまのおほきみ) |
| 天平七年(735)閏十一月十日の相模国封戸祖交易帳に従四位下檜隈女王食封のことが見える。同九年従四位上に進んだ。高市皇子の娘かという。 2-202左注 |
| 檜前舎人石前 (ひのくまのとねりいはさき) |
| 武蔵国那珂郡の防人。伝未詳。檜前舎人は檜前廬入宮に都した二十八代宣化天皇の代に朝廷に舎人を出すために設けられた名代・子代。 20-4437左注 |
| 兵部川原 (ひやうぶのかはら) |
| 兵部省の役人で川原氏のものか。ただし、川原(または河原)氏で該当しそうな人は見えない。 9-1741 |
| 広河女王 (ひろかはのおほきみ) |
| 穂積皇子の孫。上道王の娘。天平宝字七年(763)従五位下を授けられる。 4-697,698 |
| 広瀬王 (ひろせのおほきみ) |
| 系統未詳。小治田広瀬王ともいう。「続日本紀」に和銅元年(708)従四位上大蔵卿。 養老二年(718)正四位下、同六年卒と見え、「書紀」には天武十年(681)川島皇子らと帝紀および上古の諸事の記録に当たった、とある。 ただし万葉集の広瀬王はこれと別人で、「薬師寺縁起」に磯城皇子の子としてあげられた人物とし、叙位以前に夭折したとみる説もある。 8-1472 1-44左注 |
| 布勢朝臣人主 (ふせのあそみひとぬし) |
| 天平勝宝四年(752)に正六位上判官として入唐、同六年四月に帰朝して、七月従五位下駿河守となる。翌年、防人部領使となって防人歌を提出している。 天平宝字三年(759)右少弁となり、上総守、式部大輔などを歴任し、神護景雲三年(769)出雲守となった。 20-4370左注 |
| 藤原朝臣宇合 (ふぢはらのあそみうまかひ) |
| 不比等の第三子。式家の祖。霊亀二年(716)遣唐副使となり、養老二年(718)帰朝。 翌三年正五位上常陸守として、安房・上総・下総の按察使となり、神亀元年(724)式部卿持節大将軍として蝦夷を討った。同三年式部卿従三位として知造難波宮事となり、さらに参議、西海道節度使などを経て、天平六年(734)正三位兼大宰帥となり、同九年八月四十四歳で薨じた。 「懐風藻」に詩六首、「経国集」に賦一篇を載せる。 「72」の歌を詠んだ慶雲三年(706)当時彼は十三歳で、歌の内容から不自然なものがあるが、元暦校本などの目録には「作主未詳歌」とし、赭で「式部卿藤原宇合」とある。 1-72 3-315 8-1539 9-1733,1734,1735 4-524題詞、6-976題詞 |
| 藤原朝臣鎌足 (ふぢはらのあそみかまたり) |
| 旧姓中臣連。中臣御食子の長子。初め軽皇子(孝徳)と親交を結んだが、のち中大兄皇子(天智)に接近し、これを助けて、皇極四年(645)蘇我入鹿を誅し、大化の改新の中心的役割を果たした。 天智天皇の信任は極めて厚く、天智八年(669)十月薨ずる前日、天皇自ら見舞い大織冠と藤原朝臣の姓を授けた。 年五十六歳。深謀遠慮、包容力に富み、大海人皇子(天武)にもよしみを通じ、家伝によれば、天智七年浜楼に酒宴した際、大海人皇子が長槍で敷板を貫き、怒った天智天皇が殺そうとしたとき、鎌足が止め、以後大海人皇子は徳として鎌足を重んじたとある。 奈良時代に成立した藤原氏の氏神春日大社が鹿島・香取の神を祭神としていることや、「大鏡」の裏書などにその生誕地を常陸国鹿島とする所伝を記してあることかた常陸出身とする説もある。 2-94,95 1-16題詞・21左注、2-93題詞 |
| 藤原朝臣清河 (ふぢはらのあそみきよかわ) |
| 北家房前の第四子。天平十二年(740)従五位下。中務少輔、大養徳守を歴任し、同十八年従四位下。天平勝宝元年(749)参議となった。 翌年九月遣唐大使に任ぜられ、同四年閏三月正四位下に進められた後、副使の胡麻呂や吉備真備らと共に出発したらしい。唐では河清と名乗り玄宗皇帝に謁し、その礼儀正しさを褒められたこともある。 帰国の途中、逆風に遭い、安南(ベトナム)の驩酬に漂着し、迫害されながらわずかに難を逃れて長安に帰り、唐朝に仕えて次第に重用され高官に任ぜられた。 日本から迎えの大使を派遣したこともあり、在唐大使のまま官位を進め、従三位に至ったが、宝亀末年頃、彼土で薨じた。朝廷では従二位を追贈した。 (4265,4268)作歌。 |
| 藤原朝臣久須麻呂 (ふぢはらのあそみくすまろ) |
| 藤原仲麻呂(恵美押勝)の二男。天平宝字二年(758)従五位下。美濃守、大和守、左右京尹などを経て同六年参議兼丹波守となったが、同八年、父仲麻呂の謀叛に際して殺された。 巻第四の末尾に家持と贈答した歌が収められており、これだけで詳しい事情は分からないが、あるいは天平十一年(739)に死んだ家持の亡妾の遺子が娘で、それを家持が引き取って養っていたのを、同十八年頃久須麻呂が、将来妻に申し受けたいと言ってきたものと解するのが自然だろう。 4-794,795 4-789、792題詞 |
| 藤原朝臣宿奈麻呂 (ふぢはらのあそみすくなまろ) |
| 式家宇合の第二子。天平十二年(740)兄広嗣の謀叛に座し、伊豆に流されたが、同十四年に許され、大宰少判事となる。同十八年従五位下上総守。 天平勝宝四年(752)十一月相模守となり、防人部領使として防人歌を提出している。その後、民部少輔、右中弁、上野守、大宰帥などを歴任。天平神護二年(766)従三位。 宝亀元年(770)参議となり、良継と改名した。同八年内大臣従二位をもって薨。 六十二歳。従一位を追贈された。仲麻呂の無道を深く憎み、佐伯今毛人・石上宅嗣・大伴家持らと謀って仲麻呂を殺そうとしたが、密告され、検問された。 しかし、他の三人をかばい、独り罪を着て位を奪われ、二年後に仲麻呂が謀叛を起こすや、これを討って恨みを晴らした、とその薨伝にある。 20-4354左注・4515左注 |
| 藤原朝臣継縄 (ふぢはらのあそみつぐなは) |
| 南家武智麻呂の長男豊成の二男。母は従五位上路真人虫麻呂という者の娘。 天平宝字七年(763)従五位下に叙せられた後、官位共に昇叙され、最後は右大臣正二位兼皇太子傳中衛大将に至り、延暦十五年(796)七十歳で薨じた。 薨伝には、格別の功績なく、才能も乏しかったが、謙恭な人柄で世のそしりを免れた、とある。 19-4240左注 |
| 藤原朝臣豊成 (ふぢはらのあそみとよなり) |
| 南家武智麻呂の長男。仲麻呂の兄。神亀元年(724)従五位下。 兵部卿、参議を経て、天平十三年(741)従三位、同十五年中納言、二十年に従二位大納言となり、天平勝宝元年(749)右大臣に上ったが、弟仲麻呂の中傷によって大宰府員外帥に左遷された。 仲麻呂が誅滅された後、復帰して従一位に至り、天平神護元年(765)薨じた。六十二歳。 17-3944前序・3948左注 |
| 藤原朝臣執弓 (ふぢはらのあそみとりゆみ) |
| 系統未詳。天平宝字元年(757)従五位下。正倉院文書の天平宝字二年八月一日付詔書に仲麻呂の二男、従五位上藤原真先の記した下に「弓取」の注があるのによって、真先と同一人かとする説がある。 20-4506 |
| 藤原朝臣永手 (ふぢはらのあそみながて) |
| 房前の第二子。八束(真楯)の兄。天平九年(737)従五位下。 天平勝宝二年(750)従四位上、同四年大倭守、同六年従三位となり、中納言、式部卿、大納言、右大臣を歴任し、天平神護二年(766)左大臣、宝亀元年(770)には正一位を極め、翌年薨じた。 五十八歳。太政大臣を追贈された。光仁天皇の即位に際しては、藤原百川と共に、その推進力となった。 19-4301 |
| 藤原朝臣広嗣 (ふぢはらのあそみひろつぐ) |
| 宇合の長子。天平九年(737)従五位下。宇合らの兄弟が相次いで薨じた後、藤原氏は橘諸兄政権下に無力化し、広嗣自身も大養徳守まで上っていたが、ほどなく大宰少弐に左遷された。 十二年八月上表して失政を指摘し、諸兄のブレーンであった僧玄昉と吉備真備を除くのを目的とし筑前で兵を挙げた。朝廷は兵一万七千を派遣して討ち、ついに十一月一日広嗣は逮捕、処刑された。 8-1460 |
| 藤原朝臣仲麻呂 (ふぢはらのあそみなかまろ) |
| 武智麻呂の第二子。豊成の弟。天平六年(734)従五位下。民部卿、参議兼左京大夫を経て、同十七年正四位上で近江守を兼ねた。同十八年三月式部卿従三位、同二十年正三位に進む。 天平勝宝元年(749)大納言兼紫微令となり、翌年従二位。 しだいに孝謙天皇の寵を得、兄豊成を左遷し、姻戚関係にある大炊王を立てて皇太子とし、聖武天皇の指名した道祖王と代え、天平宝字元年(757)紫微内相となり、翌年大炊王を推して皇位につけ、淳仁天皇とし、自らは大保(右大臣)となり、恵美押勝と改名して、功封三千戸、功田一百町を受けて権勢をほしいままにした。 更に同四年従一位太師(太政大臣)、同六年正一位を極めた。 しかし、新たに孝謙天皇の寵を得て台頭した道鏡の勢力に押されて謀叛を計り、同八年九月宇治を経て近江に走り、同国高島郡勝野において妻子・従類と共に、滅ぼされた。五十九歳。 19-4266 20-4511 17-3948左注、20-4517題詞 |
| 藤原朝臣房前 (ふぢはらのあそみふさざき) |
| 不比等の第二子。北家の祖。兄は南家の祖、武智麻呂。慶雲二年(705)従五位下。元明天皇の信任厚く、養老元年(717)兄武智麻呂より先に参議となり、その崩御直前に内臣に任ぜられ、後事を託された。 その後中衛大将、中務卿、東海東山二道節度使などを歴任。天平九年(737)四月、全国的に流行した天然痘のために兄の武智麻呂、弟の宇合・麻呂らと相前後して薨じた。 民部卿正三位、五十七歳。正一位左大臣(のち太政大臣も)を追贈された。「懐風藻」に詩三首を載せる。 5-816 3-401題詞、5-815左注、9-1769左注、19-4252左注 |
| 藤原朝臣不比等 (ふぢはらのあそみふびと) |
| 史とも記す。鎌足の第二子。大宝律令の撰定に力を尽くし、大宝元年(701)正三位大納言、和銅元年(708)正二位右大臣と進み、養老四年(720)六十三歳で薨。太政大臣を追贈された。 武智麻呂ら男の子四人はいずれも高官として天平初年の政界に活躍し、娘の宮子と光明子とはそれぞれ文武・聖武両天皇の夫人および皇后となり、外戚としての地位を固めた。 普通名詞としてのフビトはフミヒト(文人)の約で、ヒを濁って読む。 3-381題詞、19-4259題詞 |
| 藤原朝臣麻呂 (ふぢはらのあそみまろ) |
| 不比等の第四子。母はその異母妹五百重娘(藤原夫人)。京家の祖。養老元年(717)従五位下。同五年、従四位上左右京大夫。天平三年(731)参議兵部卿。同九年七月従三位をもって薨。 「懐風藻」に詩五首を載せる。平城京二条大路跡(奈良市法華寺町)から天平八年八月二日付けの木簡が出土し、それに「中宮職移兵部省卿宅政府」云々とあるところから、その邸宅が左京二条二坊五坪にあった可能性が高いとされている。 「歌経標式」の著者浜成は麻呂と因幡八上采女との間に生まれた子であろうという。大伴坂上郎女を娶ったことがある。 4-525,526,527 4-531左注 |
| 藤原朝臣武智麻呂 (ふぢはらのあそみむちまろ) |
| 不比等の長子。南家の祖。大宝四年(704)大学助。慶雲二年(705)従五位下。大学頭、近江守、図書頭、侍従、式部卿を経て、養老五年(721)従三位中納言。神亀元年(724)正三位。 天平元年(729)大納言。同三年大宰帥を兼ねる。同九年七月疾病に倒れ、死の直前、左大臣正一位を贈られて薨。年五十八歳。後、太政大臣を追贈される。 その子仲麻呂が編纂させた『家伝』下「武智麻呂伝」には、その学問、詩文に対する造詣のことが記されている。 (7-1214) |
| 藤原朝臣八束 (ふぢはらのあそみやつか) |
| 房前の第三子。母は県犬養橘三千代と美努王との間に生まれた牟漏女王。のち真楯と改名。 天平十二年(740)に従五位下となり、治部卿、参議、中務卿、摂津大夫、大宰帥などを歴任し、天平神護二年((766)正三位大納言兼式部卿をもって薨。 年五十二歳。度量弘深で私利を求めず、廉直明敏で、上下の信望が厚かった。冬嗣はその孫で、中古の摂関家は彼から出た。 3-401,402 6-992 8-1551,1574,1575 19-4295,4300 6-983左注・1044題詞 |
| 藤原夫人 (ふぢはらのぶにん) |
| 藤原鎌足の娘。五百重娘。大原大刀自ともいい、姉氷上娘とともに天武天皇の夫人となり、新田部皇子を生んだ。のち異母兄不比等のの妻となり、麻呂を生んだ。 2-104 8-1469 2-103題詞 |
| 葛井連大成 (ふじゐのむらじおほなり) |
| 旧姓白猪史。百済系渡来人の子孫。神亀五年(728)正六位より外従五位下。天平二年(730)正月筑後守として梅花宴にあって歌を詠んでいる。 4-579 5-824 6-1008 2-103題詞 |
| 葛井連広成 (ふじゐのむらじひろなり) |
| 養老三年(719)従六位下で遣新羅使となり、天平三年(731)外従五位下。同二十年散位従五位上の時、聖武天皇はその私宅に行幸、一泊し、広成夫婦は正五位上を授けられた。 広成の妻は命婦県犬養宿禰八重で、光明皇后の生母県犬養橘三千代の親族。漢文学に造詣深く、「懐風藻」に詩二首、「経国集」に文二篇を載せる。 6-967 6-1016題詞 |
| 葛井連諸会 (ふじゐのむらじもろあひ) |
| 天平十七年(745)外従五位下、同十九年相模守。天平宝字元年(757)従五位下。「経国集」に和同四年(711)の対策文を載せる。 17-3947 |
| 道祖王 (ふなどのおほきみ) |
| 新田部皇子の子。天平九年(737)従四位下。同十二年従四位上。天平勝宝八歳(756)聖武天皇の遺詔によって孝謙天皇の皇太子になったが、翌年三月に廃されて諸王に降ろされた。 同年七月橘奈良麻呂の変に座してマドヒと名を改められ、杖で打たれて死んだ。 19-4308 |
| 船王 (ふなのおほきみ) |
| 舎人皇子の子。淳仁天皇の兄。神亀四年(727)従四位下。天平十五年(743)従四位上。同十八年弾正尹。 淳仁即位後、天平宝字二年(758)に従三位に叙せられ、翌年親王となり、大宰帥、信部卿(中務卿)、二品と累進した。 しかし、淳仁天皇が廃されると、親王から王に降ろされ、藤原仲麻呂の謀に加担した罪で同八年隠岐に流された。 6-1003 (19-4303) 19-4281左注 |
| 吹芡刀自 (ふふきのとじ) |
| 伝未詳。刀自は女性の尊称。十市皇女の伊勢参宮に供奉した。 「芡」は音ゲム、ミヅフフキと読まれ、すいれん科のおにばすのことをいうが、吹芡の訓は不明で、仮にフフキと読む説に従うが、疑いを残す。元暦校本や冷泉本の目録には「吹黄」に作る。 1-22 4-493,494 |
| 文忌寸馬養 (ふみのいみきうまかひ) |
| 霊亀二年(716)正七位下の時、壬申の乱における父禰麻呂の功によって田を賜った。 天平九年(737)外従五位下。翌年主税頭となり、その後、筑後守、鋳銭長官などを歴任。天平宝字二年(758)従五位下となった。 8-1583,1584 |
| 平栄 (へいえい) |
| 東大寺の僧。天平勝宝元年(749)五月頃、越前・越中方面に占墾地使となって下ったことは、万葉集のみならず、正倉院文書にもしばしば記され、荘園の図籍に自署してもいる。 やがて東大寺主(三綱の次席)となり、更に勝宝の末年から宝字(757~65)初年にかけて上座(三綱の首席)となったことも、正倉院文書や東南院文書などに残る数多くの帳簿類から知られる。 18-4109題詞 |
| 日置少老 (へきのをおゆ) |
| 伝未詳。ヘキはヒオキの約。少老をヲオユと読むことは確実でない。 3-357 |
| 平群朝臣広成 (へぐりのあそみひろなり) |
| 天平五年(733)遣唐大使多治比真人広成に従って判官として入唐したが、翌年蘇州から帰国の途についた時に、悪風に遭い、彼の乗った船は漂流して崑崙国(インドシナ)に着き、乗員百十五名の内、広成を含めてわずか四人がかろうじて唐に帰り着いた。 その後、阿倍仲麻呂らの口利きによって渤海に渡り、またもや危機にさらされながら同十一年十月出羽国(山形・秋田両県)にたどりついた、という体験の持ち主。 その後に正五位上となり、刑部大輔、式部大輔、摂津大夫などを歴任。天平勝宝五年(753)従四位上武蔵守をもって卒した。 (16-3864) 16-3865歌 |
| 穂積朝臣老人 (ほづみのあそみおきな) |
| 天平九年(737)外従五位下、左京亮。同十八年従五位下内蔵頭となった。 (16-3865) 16-3864歌 |
| 穂積朝臣老 (ほづみのあそみおゆ) |
| 和銅二年(709)従五位下。養老二年(718)正五位上。左副将軍、式部大輔などを歴任。 同六年(元正天皇)を批判した罪で斬刑を宣告されたが、皇太子(聖武)のとりなしで佐渡配流に減刑され、天平十二年(740)許された。同十六年大蔵大輔として恭仁(久邇)京留守官となる。 天平勝宝元年(749)卒。 3-291 13-3255左注、17-3948左注 |
| 穂積皇子 (ほづみのみこ) |
| 天武天皇の第七皇子。母は蘇我赤兄の娘、大蕤娘。文武天皇の慶雲二年(705)、忍壁皇子のあとを受け、二品で知太政官事となり、和銅八年(715)正月一品を授けられ、同年七月薨。 異母妹但馬皇女と結ばれ、皇女の薨後、大伴坂上郎女を娶ったことが見える。 2-203 8-1517,1518 16-3838 2-114題詞・115題詞・116題詞、4-531左注・627題詞・697題詞、16-3855題詞 |
| 円方女王 (まとかたのおほきみ) |
| 長屋王の娘。天平九年(737)従五位下から従四位下に進み、天平宝字七年(763)正四位上、同八年従三位、神護景雲二年(768)正三位。宝亀元年(774)薨。 20-4501 |
| 真間娘子 (ままのをとめ) |
| 真間の辺りにいたという伝説上の女性。テゴ(ナ)と通称した。真間はもと崖を意味する普通名詞で、千葉県市川市真間町付近の国府台高地の南側の崖下をいう、とされる。 3-434題詞/歌・435・436歌、9-1811題詞/歌、14-3402・3403歌 |
| 満誓沙弥 (まんぜいさみ) |
| 沙弥満誓とも。俗名笠朝臣麻呂。慶雲元年(704)従五位下。同三年美濃守となり、和銅元年(708)再任。 木曽路の開通などのすぐてた治績をあげたのでしばしば賞され、また養老元年(717)の多度山行幸の際、国守として従四位上を授けられ、さらに尾張・三河・信濃の管理をも委任された。 同四年右大弁となったが、翌年元明上皇の病気平癒祈願のため出家し、満誓と名のった。 同七年筑紫観世音寺の別当となり大宰府におもむき、神亀四年(727)頃帥として下った大伴旅人と知り合って交遊した。 3-339,354,394,396 4-575,576 5-825 |
| 茨田王 (まんだのおほきみ) |
| 系統未詳。天平十一年(739)従五位下。翌年従五位上。同十六年二月聖武天皇が難波に行幸していた当時、少納言として久邇京に駅鈴と内外の印とを取りに遣わされたことがある。 宮内大輔、越前守を歴任。中務大輔になったことは「続日本紀」に見えない。 19-4307 |
| 三形王 (みかたのおほきみ) |
| 御方王とも記す。系統未詳。天平勝宝元年(749)従五位下、天平宝宇三年(759)従四位下木工頭。大監物になったことは「続日本紀」に見えない。 20-4512,4535 |
| 三方沙弥 (みかたのさみ) |
| 伝未詳。沙弥は入門したばかりの僧をいうが、転じて名として用いたのかもしれない。 沙弥は半俗半僧の生活をしていたかと思われる〔576〕参照。『古今著聞集』巻第五や『十訓抄』などに歌を詠む物乞いがあり、ある人はこれを三方沙弥だといった、という伝説を載せる。 中古では歌詠む乞食僧として説話の世界に生きていたものと思われる。 2-123,125 4-511 6-1031左注、10-2319左注、19-4252左注 |
| 三国真人人足 (みくにのまひとひとたり) |
| 慶雲二年(705)従五位下。和銅八年(715)従五位上。養老四年(720)正五位下。 8-1659 |
| 三島王 (みしまのおほきみ) |
| 舎人親王の第四子。淳仁天皇の兄。養老七年(723)正月従四位下になった。 5-887 |
| 水江の浦島子 (みづのえのうらのしまこ) |
| 『雄略紀』二十二年の冬には、「丹波国余社郡菅川の人、瑞江浦嶋子」とあり逸文『丹後風土記』には、「水江浦嶋子」の他に、「筒川嶼子」とも、単に「嶼子」ともある。 風土記に見える歌に、「宇良志麻能古」とあるところから、一般には「浦島の子」と呼ばれているが、歌は後に生まれたものとみて、「浦の島子」とと呼ぶことにする。 9-1744 |
| 御名部皇女 (みなべのひめみこ) |
| 天智天皇の皇女。母は蘇我石川麻呂の娘、宗我嬪。元明天皇の同母姉。高市皇子の室となり、長屋王を生む。慶雲元年(704)一百戸増封されたことが「続日本紀」に見える。 1-77 |
| 水主内親王 (みぬしのひめみこ) |
| 天智天皇の皇女。母は栗隈首徳万の娘、黒媛娘。霊亀元年(715)四品であった。天平九年(737)二月三品に進み、同八年に薨じた。 内親王の所蔵する経巻は薨後東大寺に施入されたが、写経のためりようされることが多く、その目録も作られていたことが、正倉院文書によって知られる。 20-4463左注 |
| 三野連石守 (みののむらじいそもり) |
| 伝未詳。天平二年(730)大伴旅人が筑紫から帰京する際の従者の一人だった。石守の「石」の字はイシ・イソ・イハなどいずれにも読める。仮にイソモリと読んでおく。 8-1648 17-3912 |
| 三野連岡麻呂 (みののむらじをかまろ) |
| 明治五年(1872)、大和国平群郡萩原村(現在の奈良県生駒市竜王台)で銅版の墓誌が発掘された。 それによると、大宝元年(701)五月遣唐使に従って渡唐し(ただし、筑紫より入海直後風浪に遭い、出発は翌年に延期された)。このときの、遣使には山上憶良がいる。帰朝は慶雲元年(704)七月。 『続日本紀』にその報告の内容が載っている。 西本願寺本など行間に朱で「国史云々」として、一行は百六十人、五隻に分乗し、三野連岡麻呂は当時「小商監従七位下中宮小進」であった、と記されている。 霊亀二年(716)従五位下主殿寮頭となり、神亀五年(728)六十七歳で卒したことが知られる。墓誌には「美努岡万」、『続日本紀』」には「美努連岡麻呂」とある。 1-62題詞 |
| 三原王 (みはらのおほきみ) |
| 御原王とも。舎人皇子の子。淳仁天皇の兄。養老元年(717)従四位下。天平九年(737)弾正尹となった後、治部卿、大蔵卿、中務卿を歴任。天平勝宝四年(752)正三位で薨じた。 8-1547 |
| 壬生使主宇太麻呂 (みぶのおみうだまろ) |
| 宇陀麻呂・宇太万侶とも記す。天平十六年(734)正七位上少外記勲十二等で造公文使録事として出雲に遣わされたことが正倉院文書で知られる。 同八年従六位上で遣新羅使の大判官となり、翌年正月に入京した。同十八年には正六位上から外従五位下に叙せられ、右京亮となり、天平勝宝二年(750)五月但馬守に任ぜられた。 同年六月の但馬国司牒に守外従五位下勲十二等と自署しており、同六年玄蕃頭となった。天平十年の上階官人歴名に「上野介使主于太麻呂」とあるのも同一人かという。 15-3634,3691,3696,3697,3724 15-3600題詞・3634左注 |
| 三輪朝臣高市麻呂 (みわのあそみたけちまろ) |
| 旧姓三輪君。天武十三年(684)に賜姓。大神朝臣・大三輪朝臣ともいう。壬申の乱に功があり、中納言、長門守、左京大夫を歴任。慶雲三年(706)従四位上をもって五十歳で卒。 贈従三位。万葉集中に確かな作品はないが、〔1774〕は彼の作かともいう。「懐風藻」に詩一首を載せる。 持統天皇の伊勢行幸を冠位を捨てて諫止しようとしたことは『霊異記』上二十五話にも見え、忠臣として賞揚されている。 1-44左注、9-1774題詞・1776題詞 |
| 六人部王 (むとべのおほきみ) |
| 系統未詳。和銅三年(710)従四位下となり、天平元年(729)正四位上で卒した。『家伝』下「武智麻呂伝」に、十余人もの風流侍従の名があげられているうち、第一にその名を記してある。 〔68〕の作者身人部王と同一人であろう。 1-68 8-1615題詞 |
| 身人部王 (むとべのおほきみ) |
| 系統未詳。「続日本紀」および〔1615〕の題詞の下に見える「六人部王」とあるのと同一人か。和銅三年(710)従四位下。天平元年(729)正四位上をもって卒。 1-68 |
| 六人部連鯖麻呂 (むとべのむらじさばまろ) |
| 佐婆麻呂と自署することがある。天平勝宝三年(751)に舎人佑、従六位上であったこと、天平宝字二年(758)頃正六位上伊賀守であったことが正倉院文書などで知られる。 宝字八年外従五位下に叙せられた。 15-3716,3717,3718 |
| 守部王 (もりべのおほきみ) |
| 舎人皇子の子。船王の弟。淳仁天皇の兄。天平十二年(740)従四位下、従四位上になった。淳仁天皇即位以前に卒したか。 6-1004,1005 |
| 文武天皇 (もんむてんわう) |
| 四十二代。本名は軽皇子。諡は天之真宗豊祖父天皇と呼ばれる。草壁皇子の皇子。母は元明天皇。四十四代元正天皇の弟。持統十一年(697)皇太子となり、次いで即位した。 在位十一年で慶雲四年(707)と二十五歳で崩御。律令の撰定、遣唐使の復活などのことがあった。「懐風藻」に詩三首を載せる。 1-45題詞・71題詞・74題詞/左注、9-1671題詞 |
| 八代女王 (やしろのおほきみ) |
| 矢代女王とも。天平九年(737)正五位下。聖武天皇崩御後の天平宝字二年(758)の条に、従四位下矢代女王は先帝に愛されていたのにその志を改めたとの理由で、その位記を削られたことが「続日本紀」に見える。 4-629 |
| 安見児 (やすみこ) |
| 伝未詳。天智天皇の皇子大友皇子がその母宅子娘が伊賀市出身の采女で后妃の列に入れられない卑しい出身であるために、皇太子として不利と考えられていたのに対し、采女が必ずしも卑しくないことを示そうとして、人臣第一の鎌足も安見児を娶り、大友皇子の立場を補強したとする説がある。 2-95題詞/歌 |
| 八田皇女 (やたのひめみこ) |
| 十五代応神天皇の皇女。宇治若郎子(菟道稚郎子)の同母妹。仁徳天皇は若郎子の遺言もあって、皇女を妃として後宮に納れようとし、磐姫皇后に承諾を求めるが、皇后は許さなかった。 数年後たまたま皇后が不在の間に天皇は皇女を宮中に召し、そのため皇后は山背の筒城宮に籠居する。磐姫皇后の崩御後、三十八年五月に皇后となった。 2-90左注 |
| 八千桙 (やちほこ) |
| 八千矛とも。大国主命の別名の一つ。この神は、大穴牟遅とこの八千桙の他に、また葦原色許男・宇都志国玉の名もあった、と「古事記」に伝える。 6-1069歌、10-2006歌 |
| 矢作部真長 (やはぎべのまなが) |
| 天平勝宝七年(755)二月下総国結城郡より防人として筑紫に派遣された。 20-4410 |
| 山口忌寸若麻呂 (やまぐちのいみきわかまろ) |
| 伝未詳。天平初年大宰府の少典として旅人の配下にあった。 4-570 5-831 |
| 山口女王 (やまぐちのおほきみ) |
| 伝未詳。〔616〕以下の歌も家持に贈った歌である。 4-616,617,618,619,620 8-1621 |
| 山前王 (やまさきのおほきみ) |
| 忍壁皇子の子。慶雲二年(705)無位より従四位下。養老七年(723)十二月卒。 「懐風藻」に詩一首載せる。仮にヤマサキとしてあげるが、ヤマクマと読むこともできる。 3-426,427,428 |
| 山背王 (やましろのおほきみ) |
| 長屋王の子。母は不比等の娘。後に藤原弟貞。天平元年(729)二月長屋王の変に王子は多く自経したが、王は不比等の娘の所生の故に安宿王とともに死を免れた。 同十二年十一月無位より従四位下。同十八年九月右大舎人頭、天平勝宝八年(756)五月聖武太上天皇の崩御に山作司。同十二月勅により大安寺に遣わされ、梵網経講ぜしめ、時に出雲守。 天平宝字元年(757)五月従四位上、同六月但馬守。橘奈良麻呂の反乱を告げた功により、同七月従三位、同四年正月までに藤原弟貞の名を賜った。 同月坤宮大弼、同六年十二月参議、同七年十月に薨じた。時に参議、礼部卿。 20-4497 20-4498左注 |
| 山田史君麻呂 (やまだのふひときみまろ) |
| 天平十九年(747)九月越中守大伴宿禰家持の飼っていた鷹の養吏。 17-4038・4039左注 |
| 山田史土麻呂 (やまだのふひとひじまろ) |
| 天平勝宝五年(753)五月少主鈴。 20-4318左注 |
| 山田御母 (やまだのみおも) |
| 山田史女島。命婦。比売島(女)にもつくる。孝謙天皇の乳母。天平十九年(747)より天平勝宝七年(755)まで東大寺写経所に写経を命じている。天平勝宝元年七月正六位上より従五位下。 同七年正月乳母の故に同族七人と共に姓山田御井宿禰を賜った。天平宝字元年(757)八月既に故人であったが、橘奈良麻呂の謀叛を聞きながら奏しなかった故に、御母の名を除き宿禰の姓を奪い、旧姓山田史に復せしめられた。 20-4328題詞 |
| 大倭宿禰小東人 (やまとのすくねをあづまと) |
| 法律家。大和国造家の出身。元明朝の刑部少輔五百足の子。はじめ忌寸であったが、天平九年(737)宿禰姓を賜り、天平宝字元年(757)の後半に長岡と改名した。 霊亀二年(716)二十八歳で律令研究の遣唐請益生に選ばれて、翌年渡唐、養老二年(718)に帰国したらしく、その後、「養老律令」の編纂に従事した。 天平十二年(740)の藤原広嗣の乱に連座して流罪となったが、後に許されて、同十九年従五位下。刑部少輔、摂津亮、参河守、紫微大忠、左京大夫などを歴任、神護景雲三年(769)正四位下、八十歳で卒した。地方官としては仁恵を欠くとも評されたが、晩年まで壮健に勤務し、衰えを知らなかった。 〔1740〕の作者の式部大倭は、この小東人をさしたのではないかといわれる。彼が式部省にあったという記録はないが、彼と共に渡唐し、親交があった藤原宇合が神亀三年(726)に式部卿になった時、丞官としてその職にあったのではないか、と推定するのである。宇合が国守となって常陸に在任中、倭判官に詩を贈ったことが「懐風藻」から、知られるが、その倭判官も小東人と考えられている。 (9-1740) |
| 倭大后 (やまとのだいごう) |
| 天智天皇の皇后。天智の異母兄で天智に滅ぼされた古人大兄皇子の娘。天智十年(671)十月十七日、天智が皇太子(天武)に後事を託そうとした時、天武は辞退し、代わりにこの大后に皇位を譲るように進言したことがある。 2-147,148,149,153 |
| 山上臣憶良 (やまのうへのおみおくら) |
| 大宝元年(701)42歳のとき、遣唐少録となり、粟田朝臣真人に従って翌二年渡唐。慶雲四年(707)頃帰朝したらしい。 和銅七年(714)従五位下、霊亀二年(716)伯耆守となり、養老五年(721)佐為王らとともに退朝後、東宮に侍した。 神亀末年に筑前守に任ぜられ、同じ頃大宰帥として下った大伴旅人と交遊し、漢文的色彩の濃い、特色ある巻五の成立の原動力となった。大陸的教養と謹直な性格とが融け合って、 人間性に富んだ道徳的・思想的内容を詠んだ長歌や漢文に特色があり、注目すべき作風がうかがわれる。「類従歌林」七巻は彼の編で、万葉集編纂の際に参考されたが、今日伝わらない。 1-63 2-145 3-340 5-798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,817,818,822,(851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864),872,873,874, (875,876,877,878,879),880,881,882,883,884,885,886,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907, 908,909,910,(911) 6-983 8-1522,1523,1524,1525,1526,1527,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1541,1542 9-1720,(1768,1769), 16-(3882,3883,3884,3885,3886,3887,3888,3889,3890,3891) 1-6・7・8・12・18左注・34題詞・85左注、9-1677左注、18-4089左注、19-4189左注 |
| 仙柘枝 (やまびめつみのえ) |
| 「柘枝伝(しゃくしでん)」。「柘枝仙媛」 に関する伝記的小説。漢文的潤色を受けた文体で書かれた某官人の述作か。柘枝伝説はその具体的内容を明らかにしないが、柘の枝が吉野川の漁夫味稲(うましね)と梁に掛かって美女と化し、やがて味稲と同棲したが、遂に昇天したしたという筋かと思われる。『懐風藻』や『続日本後紀』所載の長歌などに見え、その間内容に多少の差があるが、もとは白鳥処女伝説の一種で、これに中国渡来の神仙思想をからませたものといわれる。 3-388,389 |
| 山部宿禰赤人 (やまべのすくねあかひと) |
| 生没年未詳。宮廷家人として聖武天皇の行幸に供奉し、また、旅にあって優れた叙景歌を残した。 3-320,321,325,326,327,328,360,361,362,363,364,365,375,376,381,387,434,435,436 6-922,923,924,928,929,930,931,932,938,939,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,1006,1010,1011 8-1428,1429,1430,1431,1435,1475 17-3937 |
| 弓削皇子 (ゆげのみこ) |
| 天武天皇の第八皇子。母は天智天皇の皇女大江皇女。長皇子の同母弟。持統七年(693)浄広弐の位を授けられ、文武三年(699)薨。 高市皇子が薨じた後、皇嗣の選考会議の時、草壁皇子の遺子軽皇子(文武)を立てようとした葛野王(大友皇子の子)に反対しようとして葛野王から叱責されたことが「懐風藻」に見える。 2-111,119,120,121,122 3-243(245) 8-1471,1612 2-130題詞・204題詞、9-1705題詞・1713題詞・1777題詞 |
| 湯原王 (ゆはらのおほきみ) |
| 志貴皇子の子。万葉後期を代表する作者の一人。 3-378,379,380 4-634,635,638,639,641,643,645,673 6-990,991,994 8-1548,1549,1554,1556,1622 |
| 誉謝女王 (よざのおほきみ) |
| 伝未詳。慶雲三年(706)従四位下で卒。 1-59 |
| 依羅娘子 (よさみのをとめ) |
| 人麻呂の妻の一人。〔131〕の題詞に見える妻と同一人で石見国で娶った女かと思われるが、河内国に依網の郷名が見えることから、その地の女かとする説もある。 2-140,224,225 |
| 吉田連老 (よしだのむらじおゆ) |
| 伝未詳。字は石麻呂。 16-3875,3876 16-3876左注 |
| 吉田連宜 (よしだのむらじよろし) |
| キチダとも読む。百済の渡来僧、恵俊。文武四年(700)八月その医術を用いるために還俗させられ、姓を吉、名を宜と賜り、務広肆を授けられた。 和銅七年(714)正月正六位下より従五位下。養老五年(721)正月医術の道の師範たつに堪えるの故に絁・糸・布・鍬などを賜った。時に従五位上。 神亀元年(724)五月吉田の姓を賜り、天平二年(730)三月その衰老によりその道を伝習せしめられた。同五年十二月図書頭、同九年九月正五位下、同十年閏七月典薬頭。 神亀の頃方士として名がある。「懐風藻」に詩二首があり、歳七十とある。 5-868の前の書簡、868,869,870,871 |
| 余軍 (余明軍) (よのみやうぐん) |
| 百済の王族系の人で、大伴旅人の資人となった。底本など「金明軍」とあるが、桂本や元暦校本などに「余」に作るのに拠る。 3-397,457,458,459,460,461 4-582,583 |
| 理願 (りがん) |
| 新羅国の尼。大伴安麻呂の家に寄住し、天平七年(735)に病死した。 3-463題詞・464左注 |
| 若麻続部羊 (わかおみべのひつじ) |
| 天平勝宝七年(755)二月上総国長柄郡より防人として筑紫に派遣された。 20-4383 |
| 若麻続部諸人 (わかおみべのもろひと) |
| 天平勝宝七年(755)二月上総国長柄郡より防人として筑紫に派遣された。 20-4374 |
| 若桜部朝臣君足 (わかさくらべのあそみきみたり) |
| 伝未詳。 8-1647 |
| 若舎人部広足 (わかとねりべのひろたり) |
| 天平勝宝七年(755)二月常陸国茨城郡より防人として筑紫に派遣された。 20-4387,4388 |
| 若宮年魚麻呂 (わかみやのあゆまろ) |
| 伝未詳。 3-390 3-392左注、8-1434左注 |
| 若倭部身麻呂 (わかやまとべのみまろ) |
| 天平勝宝七年(755)二月遠江国麁玉郡より防人として筑紫に派遣された。 20-4346 |
| 若湯座王 (わかゆえのおほきみ) |
| 伝未詳。 3-355 |
| 小田事 (をだのつかふ) |
| 伝未詳。 事を京大本など「ツカフ」と読む。『古今六帖』に〔二九一〕の歌を載せ、作者を「をたのことぬし」と記するところから、「主」の字がおちたものかと『万葉代匠記』はいう。 3-294 |
| 小野老朝臣 (をののおゆのあそみ) |
| 養老三年(719)従五位下。天平元年(729)従五位上。この前後大宰少弐として帥大伴旅人の配下にあった。同九年大宰大弐従四位下で卒した。 3-331 5-820 6-963 |
| 麻績王 (をみのおほきみ)[白水郎] |
| 天武四年(675)四罪を犯し因幡へ配流(紀)。伊勢国の伊良虞に配流(万)。あるいは常陸国行方郡板来へ配流(風土記)とも。 1-23(題詞、本歌中) 1-24 |