| 【歌意2961】 |
嘆かわしいのですが、いつもと違って気掛かりなのです
あなたの想いが、とても不安で...心変わりしたのでは、と
せめて逢っているこのときだけでも
そんなわたしの不安など払拭する配慮をしてください |
随分、強引な解釈になってしまったと思う
強引と言うのは、「いぶせし」の原因が、「男の気持ち」だと思ったからだ
そんな解釈は、どの注釈書でも載っていない
何故だか、気の晴れない「自分」を、
何とか癒して欲しい、というような歌意がほとんどだ
だから、そう感じられる人にとっては、
この歌の前後にも、何かこの女性が「気掛かり」にしている「見えない歌」が見えるのだろう
しかし私には、この巻第十二の「正述心緒」歌群の中で、
どうしても男女間の一筋縄ではいかない「悲痛」な響きを感じてしまう
だから、その流れで、こんな解釈になってしまったのだろう
女が自分の訳の解らない「憂鬱」を、男に訴えた、という歌であるより
心変わりを心配する女の「いじらしさ」が、詠う動機にはなるだろう
古語の文法のみならず、その時代の生活習慣など
私には、解らないことがまだまだ多い
その中で、断定的に「これが本当の歌意だ」などとは、私にはその能力もない
しかし、それでいいと思う
今の私が、それぞれの歌を、「どう感じたか」であり
おそらく、また数年後に、この歌を読み返したとき、別の解釈をするかもしれない
それは、紛れもなく、その時の私が感じたことなのだろうから...それも、いいはずだ
もっとも、こうした「古典」を教える立場の人では、そうはいかないだろう
その点で、素人の「うたごころ」は、こうした受け入れ方もあるのだ、と思いたい
詠まれた歌は「不変」であっても
読む人は、その成長に合わせるかのように、自分の中に昇華していけるものだ
そして、それが出来るのも
こうした『万葉歌』のような古歌の作者が、存命しており
詠歌の歌意を、当事者として解説できない「現代」だから、のことだ
作者の本当に「意思」は解らない
現在では、残された「文字」によって、それでも様々な解釈が生じている
ならば、そのときの自分が一番すっきり受け入れられる感じ方でもいいはずだ
もっと古語の読解力が身に付けば...また新たな『万葉の世界』が、
私の前に現れると思っている
おそらく、明日から10日間ばかり、この更新も休止になると思う
再開は、12日頃の予定...計画通りに事がすすめば...
|
 |
掲載日:2013.11.01.
| 正述心緒 |
| 得田價異 心欝悒 事計 吉為吾兄子 相有時谷 |
| うたて異に心いぶせし事計りよくせ我が背子逢へる時だに |
| うたてけに こころいぶせし ことはかり よくせわがせこ あへるときだに |
| 巻第十二 2961 正述心緒 作者不詳 |
【注記】に〔4331〕歌
| 【2961】語義 |
意味・活用・接続 |
| うたてけに[得田價異] |
| うたて[副詞] |
ますます・ひどく・異様に・不快に・嘆かわしく・普通でないさま |
| けに[異に] |
[副詞]普通と違う・際立っている |
| こころいぶせし[心欝悒] |
| いぶせし |
[形ク・終止形]気持ちが晴れない・気掛かりだ |
| ことはかり[事計] |
ことはかり[事計り]
|
事のはからい・処置・配慮 |
| よくせわがせこ[吉為吾兄子] |
| よく[善くす] |
[他サ変・語幹]上手にする・巧みにする・念入りにする |
| せ[助動詞・す] |
[上代の軽い尊敬、親愛の意・命令形]~なさる |
| あへるときだに[相有時谷] |
| る[助動詞・り] |
[継続・連体形]~ている |
已然形につく |
| だに[副助詞] |
[強調]せめて~だけでも・~だけなりと |
体言につく |
| 掲題歌トップへ |
【注記】〔諸本、諸註釈書の解説は、『万葉集全注』〔伊藤博、昭和58年~〕による〕
| [うたてけに] |
『元暦校本』『広瀬本』『西本願寺本』以下の諸本で、「うたかへる(疑へる)」と訓み、
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕も、「異は累を誤れるか」といい、
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕は、「異」を「婁(る)」に改めている
それを『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕が「うたてけに」と訓じた
その根拠としているものとして、鹿持雅澄は次の一首を挙げる
| (七夕歌八首) |
| 秋等伊閇婆 許己呂曽伊多伎 宇多弖家尓 花仁奈蘇倍弖 見麻久保里香聞 |
| 秋と言へば心ぞ痛きうたて異に花になそへて見まく欲りかも |
| あきといへば こころぞいたき うたてけに はなになそへて みまくほりかも |
| (右大伴宿祢家持獨仰天海作之) |
| 巻第二十 4331 七夕歌 大伴家持 |
ここで、「うたてけに」は「うたて殊更に」の意だと説く
『全注』によれば、これは雅澄の「大発見」だということになる
以来、『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕は「うたてある」と意改したが、
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕、『岩波文庫新訓』から現在に至るまで
この「訓」は動かない
「うたて」は「うたた」を原形とし、自分の意志とは関係なしに
事態や心情が、どんどん進んで行く状態を表している |
| |
| [うたて] |
「うたて」には、副詞、形容詞「うたてし」の語幹、形容動詞があるが
古語辞典に拠ると、中古では語幹「うたて」だけが用いられることが多く、
中古末期から、形容詞の用法が一般化する、とある
また、副詞「うたた」の転じたもので、
程度が進み過ぎる異常なさまに対する不快感から、
「異様に・怪しく・気味悪く」、「いやに・不快に・情けなく」の意が生じたもの |
| |
| [ことはかり] |
「ことはかり」と言う場合、「懸けず忘れむ事計り」(書庫-10・2910)や、
「しましくも心休めむ事計り」(書庫-11・2920)などというように、
何の「事計り」なのかがわかるが、今日の歌には、それがない
従って、様々な解釈がなされている
『万葉集総釈』〔各巻分担、楽浪書院、昭和10~11年成〕、
「ここは寧ろ恋の仕草で、打解けてよろしく取計らふ意だろう」
『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕、
「ここは取り成し、愛情を意味する」
『大成本文篇』、「いいぐあひにやってくださいよ」
などと訳している
こうしてみると、この「ことはかり」の解釈は、
初句の「うたてけに」の影響が大きいのではないか、と思える
大方の解釈のように「いつもと違って、気分が晴れない」とすれば、
「何とか、この鬱陶しさを晴らしてください」というような意味にはなるだろうが
「うたてけに」を、もう少し違った意味で捉えたら、どうなるのだろう
たとえば、「いつもと違うあなた」なので、「私は不安だ」とでもいうような情況なら、
「そんな私の気掛かりなど、何でもないように配慮してください」とか...
そうなると、『大成本文篇』の解釈の方が、私が感じた「意」に近いような気もする
『万葉集全注』〔伊藤博、昭和58年~〕も、そのような解釈なのだと思う
|
| |
| [よくせ] |
どうしても解らなかった
副詞「よく」に、サ変動詞「為(す)」かと思えば、その活用「せ」は未然形になるし
サ変動詞「善くす」だと、やはり「せ」では活用は未然形だ
未然形は単独で用いられることはなく、中止法もない...はず
苦し紛れに、「善くす」の語幹「よく」に、軽い尊敬の助動詞「す」の命令形「せ」で、
何とか語句は繋がるが、動詞の語幹なんて...
でも、歌意としては、それで当てはまると思うのだが...
勿論、そのような「歌意」であるならば、だけど...
大きな宿題だ
|
| |
|
|
| 【歌意2962】 |
夜になって、愛しい娘の家の前に近づくと
あの娘が家から出てくる姿を見つけ
この足は、しっかり地を踏みしめているはずなのに
何故か気持ちもうわのそらで、落ち着かない
わたしが来たのを察して出てきたのだろうか... |
最後の部分の訳は、完全な意訳になってしまったが
この気持ちは、どうしても欠かせないと思う
右頁の注記で書いたように、男歌か、女歌かとは違う作者の「想い」が
この歌でも、読者に委ねられている
勿論、実作者はそんな意図はないだろうが、作者の本意を知ることもできない今では
読者の「気の向く」解釈もまた、許されるのではないだろうか
どんなに偉い学者が言葉を尽しても、
それとて、推測に過ぎないのだから...
更に、語義を吟味した上での「人の想い」であれば、
尚更、読者様々に感じ方もあるものだ
おそらく一般的な解釈では、自分の来訪を感じ取った娘が
待ち切れずに、家から出てきて、自分を迎えてくれる、というのだろう
しかし、そう解してしまうと、
作者が、地に足も着かないような落ち着きのなさを詠うのとスムーズに重ならない
むしろ、娘が男の訪れの気配を感じて外へ出てみると
そこに、恋人がやって来て、その姿を見せる
そのために、娘は戸口で嬉しさの余り我を忘れるような高揚感に包まれる
男が、次第に近づいてくるほどに、ますます気持ちは高まる...
まるで、地に足が着いていないかのように...
しかし、この「女歌」とするには、歌意としては私には自然だとしても
「歌」の語句からすれば、かなり難しい解釈になる
だから、そのことはこの際問わず、
「人の気持ち」で解釈してみた
すると、戸口で自分を待つ娘の姿を見て、男が「ときめく」よりも
娘は、他の用があって、家から出てきた
家のちょっとした仕事なのだろう
その様子を女の家に近づきつつ見ることになった男の、「ときめき」ではないだろうか
娘は、自分に気がついてはいない
しかし、その娘の仕草を見ながら近づくことが、男を更に「ときめかせる」
もうすぐ、あの娘に声を掛けられる...もうすぐ、だ
久し振りに逢う娘なのだろうか...初々しさを感じてしまう
老いてくると、その「ときめき」も...枯れてしまって...寂しいものだ
|
 |
掲載日:2013.11.13.
| 正述心緒 |
| 吾妹子之 夜戸出乃光儀 見而之従 情空有 地者雖踐 |
| 我妹子が夜戸出の姿見てしより心空なり地は踏めども |
| わぎもこが よとでのすがた みてしより こころそらなり つちはふめども |
| 巻第十二 2962 正述心緒 作者不詳 |
【注記】に〔2546〕歌
| 【2962】語義 |
意味・活用・接続 |
| わぎもこが[吾妹子之] |
| よとでのすがた[夜戸出乃光儀] |
| よとで[夜戸出] |
「朝戸出」の対義語のようだ |
| みてしより[見而之従] |
て[接続助詞]
|
[単純接続]~て・そして |
連用形につく |
| し[副助詞] |
語調を整え強意を表す |
| 〔接続〕体言、活用語の連体形・連用形、副詞、助詞などにつく |
| より[格助詞] |
[動作・作用の時間的・空間的な起点]~から |
〔接続〕体言、活用語の連体形につく、
ただし体言に準じて形容詞の連用形や副詞、一部の助 詞につく例もある |
| こころそらなり[情空有] |
| そらなり[空なり] |
[形容動詞ナリ・終止形]うわのそらだ・気持ちもそぞろである |
| つちはふめども[地者雖踐] |
| つち[土・地] |
大地・地上・土の上 |
| ども[接続助詞] |
[逆接の確定条件]~けれども・~のに・~だが |
已然形につく |
| 掲題歌トップへ |
【注記】〔諸本、諸註釈書の解説は、『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕による〕
| [よとで〔夜戸出〕] |
この語は、『万葉集』中でも、この一例しか見られない
古語辞典には、「夜戸」も「夜戸出」も載っていない
しかし、対義語として考えられる「朝戸」「朝戸出」は載っている
〔朝戸〕
朝、起きて開ける戸
〔朝戸出〕
朝、戸を開けて家を出ること
これから類想するのは、
「夜、戸を開けること」「夜、戸を開けて家を出ること」となるだろう
『万葉集』中には、「朝戸」は五例、「朝戸出」は三例
この歌では、「夜戸出」の他の用例がないので、どの註釈も迷っているようだ
勿論、表記通りに「吾妹子」を解せば、「男歌」になるだろうが
その場合は、女の家を訪れると、そこで戸を開けて出てきた女の姿を見て、
という歌意になるだろう
何故、女が外に出ていたか、には様々な解釈があるようだ
しかし、諸注の中にも、
『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕のように、
「むしろ初句を改めて、女の歌とした方が、自然的と思われる歌である」とするが、
この諸論を掲載している『全注』では、「これはやはり男の歌である」として
『新潮日本古典集成万葉集』〔新潮社、昭和51~59年成〕の所論を載せる
「闇の中で自分を待つ女の姿に心奪われた男の歌」と...
しかし、私には、何度も「軽々に誤記とか誤写説は採りたくない」と思いながらも
この歌のような心情では、「女歌」である方が、その余情を多く感じられると思う
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕でも、
「あるいは『我妹子』は『我が背子』とあったのが歌い換えられたものか」ともある
ただし、そうなると「夜戸出の姿」、というのがやはり気にかかる
夜、家から外へ出る姿なので、それは男では有り得ない
あるいは、強引にも解せば、格助詞「の」の「時」の用法で、
夜、家を出たとき見えた「我背子」の姿...のようにも訳せればいいのだが...強引過ぎる
もっとも、この歌を「男歌」とする根拠の一つに、
表記以外では類句がある
それは下二句「こころそらなり つちはふめども」の類句について
そのいずれも「男歌」だから、というのもあるだろう
このことは、その「下二句」も【注記】で採り上げる |
| |
| [こころそらなり つちはふめども] |
類句に、〔2899〕[書庫-10]がある
| 立居 田時毛不知 吾意 天津空有 土者踐鞆 |
| たちてゐて たどきもしらず あがこころ あまつそらなり つちはふめども |
| 巻第十二 2899 正述心緒 作者不詳 |
さらに、下二句が同じ一首は、
| 徊俳 徃箕之里尓 妹乎置而 心空在 土者踏鞆 |
| た廻り行箕の里に妹を置きて心空なり地は踏めども |
| たもとほり ゆきみのさとに いもをおきて こころそらなり つちはふめども |
| 巻第十一 2546 正述心緒 作者不詳 |
〔語釈〕
「たもとほり」は、自動詞ラ行変格「徘徊(たもとほ)る」の連用形で、
『同じところを行ったり来たりする・さまよう・遠回りをする・迂回する』の意
また「行き」の枕詞でもあるが、古語辞典では「枕詞・たもとほり」はなかった
「行箕(ゆきみ)」が「地名か」として、所在地未詳とされている
となると、動詞の連用形ならば、「行箕」が地名であるのはおかしい
では、「枕詞」だろうが、その由来は「動詞・徘徊る」なのだろう
あるいは、「行箕」が、「地名」ではないのかもしれないし... |
〔歌意〕
あちこちとさまよい、
その「ゆきみ」の里に、愛しいあの娘を残してきたので
心は、うわのそらだ...気持ちが少しも落ち着かない
足は地を踏んでいると言うのに...
|
前項で書いたように、この語句が「男歌」として用いられているので
〔2962〕歌もまた、「男歌」では、という推測になっているのではないだろうか
もっとも、〔2899〕歌の方は、「男歌」「女歌」は曖昧だが... |
| |
| |
|
|
| 【歌意2963】 |
海石榴市の八十の衢であった歌垣のとき
あの人が結んでくれた、この紐を
いくら他の人がわたしに言い寄ってきても、
いま解くのはしのびない...できないことです |
昔、あの人がこの海石榴市の歌垣で、私に結んでくれた「紐」
その「紐」は、二人の仲を約束するものだった
しかし、それを大事にし、尚且つ「解くことになるのは、残念だ」などという
あれから、どんなに他の男から求婚されても
決して紐を解こうとはしなかった
でも、やはりあの約束は...偽りだったのか、と女は不安に押し潰される
今は「解かない」と思っている、この「愛の紐」
しかし、いつか...「解くことになるだろう」と、無念さがこみ上げてくる
心地よい追懐と、今後への切なさ...
その心情を、下二句で十分感じることができる
人の想いはうつろうもの
いくら否定しても、それが「人のこころ」だと思う
それに、それは決して愚かなことではない
そうやって、お互いが傷つき、傷つけられながらも、成長してゆく
この女性は、後にまた切ない「恋歌」を詠えるはずだ...
その切なさを、人の「年輪」に出来ることは、素晴らしいことだと思う
「海石榴市」が歌垣で古来から有名な場であった、というのはよく聞くことだが
それでも、その「海石榴市」の語句を用いながら、次の二首のような微妙な歌もある
「問答歌」については、以前書いたことがある 〔書庫-6 2013年5月31日問答歌と贈答歌〕
| 問答歌 |
| 紫者 灰指物曽 海石榴市之 八十街尓 相兒哉誰 |
| 紫は灰さすものぞ海石榴市の八十の街に逢へる子や誰れ |
| むらさきは はひさすものぞ つばきちの やそのちまたに あへるこやたれ |
| 巻第十二 3115 問答歌 作者不詳 |
〔語釈〕
「紫は灰さすものぞ」は、「つばき」を起こす「序」
染色には染料に触染剤を加えて発色させるもので、紫染めには椿の木灰が最適とされた
「逢へる児や誰」
原文「相児」で「あひしこ」とも旧訓では訓む
『元暦校本』『広瀬本』『紀州本』などの諸本、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕、
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕などの註釈書
しかし、『西本願寺本』以降は「(あへるこ)逢へる児」が定訓となっている
まさに「今逢っている児」という意からすると、この定訓も頷ける
「逢ひし児」であれば、「今はここにいない」過去のことになる |
〔歌意〕
紫染めには、灰を加えるものです
そしてそれには「椿」の灰がいいと言います
その「椿」の「海石榴市」の「衢」で、こうして出逢ったあなたは、
名は何と言うのですか |
| |
| 足千根乃 母之召名乎 雖白 路行人乎 孰跡知而可 |
| たらちねの母が呼ぶ名を申さめど道行く人を誰れと知りてか |
| たらちねの ははがよぶなを まをさめど みちゆくひとを たれとしりてか |
| 右二首 |
| 巻第十二 3116 問答歌 作者不詳 |
〔語釈〕
「母が呼ぶ名を」の原文「母之召名乎」の訓にも、幾つかの訓があった
「お(を)やのめすなを」とするのが、 『元暦校本』『広瀬本』『西本願寺本』で、
『西本願寺本』ではさらに、「母」の左に「はは」とある
従って、『神宮文庫本』以下諸本はすべて「ははのめすなを」と訓む
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕に「ハハカヨフナヲとも読へし」
としたことから、『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕以下の諸注はこれに倣う
ただし、『岩波文庫新訓』のみ旧訓により、その改訂版の脚注に、
「『召す』或『よぶ』と記している
「申さめど」の原文「雖白」は、「白」が上の人に真実を申し述べること、申しあげる
「申さめ」は「申さむ」の已然形で「申し上げたいけれど・申しましょうが」
「道行く人を」の原文「路行人乎」は、旧訓「みちゆきひとを」で、
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕、
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕、
『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕、
『万葉集総釈』〔各巻分担、楽浪書院、昭和10~11年成〕、
『日本古典文学全集』〔小学館、昭和50年成〕、
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕が同訓
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕が、
「みちゆくひとを」と訓み、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕、
『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕、
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕以下、
『万葉集釈注』〔伊藤博、平成7年~11年成〕までの諸注の多くがこれに拠る
「道を行く人」とは、「行きずりの人」の意で、
この歌の場合、行きずりの人であるあなたを、
「誰と知りてか」、どなたと知って名を申しましょうか、となる
問い掛けの歌〔3115〕が、「名を尋ねる」ことに対する応答歌だが
歌垣の場で、名を尋ねる人に「誰と知りてか」と応答することは有り得ないという
だから、歌垣で詠ったのではないという説もあり、
海石榴市で詠われる歌が何でも「歌垣」の歌というわけではないようだ
海石榴市が「歌垣」で有名になり、
どうしてもその背景に「歌垣」を浮かべてしまうのかもしれない
|
| 〔歌意〕 |
母が呼ぶ私の名を申し上げたいと思いますが、
行きずりの人であるあなたを、
どなたと知って申し上げればいいのでしょうか |
「問答歌」が、必ずしも当事者の掛け合いではないことは、先日知ったばかりだ
だから、この二首が「問答歌」には相応しくない、という説もあるし
「問答歌」を編集過程でセットする時、選び出された「二首」に
何となく「すれ違い」を感じることもあるが
この歌の場合は、「名を尋ね」、「行きずりの人に、名は申し上げられない」という二点で、
少なくとも、「問答歌」にはなっていると思う
ただし、それが「歌垣」の場であるかどうかは、私には推測する知識もないが、
応答するある種のマナーのような感じで「誰と知りてか」とは言わない、
そういうものであるのなら、これは「歌垣」での「問答歌」ではないのだろう
またある説では、歌垣であれば、「道行く人」つまり「行きずりの人」はおかしい、と
しかし、歌垣に集まる人たちは、すべてが知り合いではないだろう、と思う
当然、初めて見かける人も多くいるはずだ
「歌垣」がどのようにして行われているのか、さっぱり分からないが
広場で、ざわめくほどに人が集まり、それぞれの「恋」を求める
そうした場であるのなら、表現は「道を行く人」であっても
実際は、「行きずり」であることと同じではないか、とも思える
「歌垣」の実態とは、いったいどんなものなのだろう
また、宿題に追加しなければならないようだ
|
|
掲載日:2013.11.14.
| 正述心緒 |
| 海石榴市之 八十衢尓 立平之 結紐乎 解巻惜毛 |
| 海石榴市の八十の街に立ち平し結びし紐を解かまく惜しも |
| つばきちの やそのちまたに たちならし むすびしひもを とかまくをしも |
| 巻第十二 2963 正述心緒 作者不詳 |
【注記】に〔1812〕歌、【左頁】に〔3115〕、〔3116〕歌
| 【2963】語義 |
意味・活用・接続 |
| つばきちの[海石榴市之] |
| つばきち[海石榴市] |
奈良県桜井市金屋付近と比定されているが、諸説あり |
| の[格助詞] |
[所在]~の・~にある〔接続〕体言、体言に準ずるものにつく |
| やそのちまたに[八十衢尓] |
| やそ[八十] |
(「そ」は十の意) 八十、また、数の多いことにいう |
| ちまた[巷・岐] |
道の分かれる所・辻・追分・街路・ある物事の行われている場所 |
| たちならし[立平之] |
たちならし[立ち均す]
|
[他サ四・連用形](立って地面を踏みつけ平にするほど) |
| |
しばしば行き来する |
| むすびしひもを[結紐乎] |
| し[助動詞・き] |
[過去・連体形]~た・~ていた |
連用形につく |
| 過去に直接経験した事実、または過去にあったと信じられる事実を回想していう意 |
| とかまくをしも[解巻惜毛] |
| とか[解く] |
[他カ四・未然形]結び目をほどく |
| まく |
[未来の推量]~だろうこと・~であろうようなこと |
| 〔成立・接続〕推量の助動詞「む」のク語法・未然形につく |
| をし[惜し・愛し] |
[形シク・終止形]失うにしのびない・惜しい・愛しい |
| も[終助詞] |
[詠嘆・感動]~よ・~なあ |
| 〔接続〕文末・文節末の種々の語につく |
| 掲題歌トップへ |
【注記】〔諸本、諸註釈書の解説は、『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕による〕
| [海石榴市] |
「つばきち」、その音便で「つばいち」として訓はあるが、大方の古語辞典には、
「つばいち」のみの採録があり、「つばきち」は、私の手持ちの辞書では、
岩波書店の古語辞典に、載っているのみ
ということは、一般的には「つばいち」と読むのが普通なのだろう
しかし、この『万葉集』中に多くある「海石榴市」を、
私はこれまで、何も考えずに「つばいち」と読んでいたが、
この歌を解釈しようと、注釈書などを開いていると、
どうしても「つばきち」とした方がいいのでは、と思えてきた
結論から先に言えば、表記は「つばきち」で、しかし詠じるときは「つばいち」、
それもあっていいのではないか、と...
現代でも、表記上の「文字」と、それを発する時の「音」に違いがあるものも多い
確かに、「つばきち」と声に出して言う場合より、「つばいち」と言った方が容易い
「海石榴」は『出雲国風土記』の「意宇郡の山野にある草木」の項に、
「海榴、字を或は椿に作る」とあり、『倭名抄』に「椿」は和名「豆波岐」とし、
「楊氏漢語抄に云ふ、海石榴」とある
これは「つばき」と言っている
「海石榴市」は椿を街路樹に植えた市の意で、
大和の三輪山南西麓の奈良県桜井市金屋にその地名が残っている
『枕草子』にも「市はつば市・・・」とあるほどに、
平安時代から明治の初めまで初瀬詣でや伊勢参りの旅人で賑わっていた
『日本書紀』「武烈天皇即位前紀」に、ここ「海石榴市」で歌垣があったことが記され
古来歌垣で知られた地となる |
| |
| [ちまた (衢)] |
「衢」は四方からの大通りが集まっている所で、「ちまた」というらしい
「街」と同義語
「八十の衢」とは、その集まってくる道、分かれて行く道の多いことを表している
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕では、その解説に、
「東は泊瀬、南は忍坂・山田・磐余、西は当麻に至る横大路に近く、北は上ツ道・山辺道に通じる四通八達の交通の要地であるのみならず、泊瀬川による水路の便もあった」とある |
| |
| [たちならし] |
この古語辞典そのままの解釈として、次の一首を載せる
| 挽歌(詠勝鹿真間娘子歌一首[并短歌])反歌 |
| 勝壮鹿之 真間之井見者 立平之 水挹家武 手兒名之所念 |
| 勝鹿の真間の井見れば立ち平し水汲ましけむ手児名し思ほゆこの |
| かつしかの ままのゐみれば たちならし みづくましけむ てごなしおもほゆ |
| (右五首高橋連蟲麻呂之歌集中出) |
| 既出 書庫3 巻第九 1812 挽歌 高橋虫麻呂歌集 |
古語辞典の用例での解釈では「たちならし」の部分を、「しばしば行き来して」とある
歌意としては、
「葛飾の真間の井戸を見ると、
昔ここにしばしば通って水を汲んだであろう手兒名のことが偲ばれてくる」
「手兒名」の伝承は、ここでは省くが、この歌の作者は、
この真間の井戸に何度も何度も通い水を汲む「娘」を偲んでいる
この用例に倣って〔2963〕を解釈している諸注は、
『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕、
『万葉集総釈』〔各巻分担、楽浪書院、昭和10~11年成〕、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕、
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37成〕、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕などがある
この「たちならし」を別の解釈として説いたのが、鹿持雅澄だ
その『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕で、
「この葛飾の真間の井を来て見れば、井の辺りに立平して、水汲み賜ひけむ娘子が形貌のまのあたりみゆるやうにて、一すじに恋しくおもはるる、となり」
つまり、「男女集まりて歌垣に立る間」と解している
そして、それに倣った諸注は、
『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕、
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕、
『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
『日本古典文学全集』〔小学館、昭和50年成〕、
『新潮日本古典集成万葉集』〔新潮社、昭和51~59年成〕、
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕、
『万葉集釈注』〔伊藤博、平成7年~11年成〕などがある
ここでも、また岩波の「旧・新大系」は、違う解釈を採っている
『万葉集全注』〔伊藤博、昭和58年~〕では、
「海石榴市」が『日本書紀』に「歌垣」であったと記されており
古くから「歌垣」で知られた場所であったことから、
この歌も、「歌垣」を背景に解釈していいだろう、としている
『全釈』に「上代の歌垣の風がしのばれる歌である。歌垣の場で、ある男(それは多分名をだに知らぬ男であらう)と契った時、その男が結んでくれた紐を、今他の男の為に解くのは惜しいといふので、夢のやうな会合への追懐が、新たな求婚者によって蘇えって、名残惜しく思はれるのである」の評を紹介し、
「甘い哀愁をただよわせ、情緒纏綿、謡いものとして永く伝わった歌だろう」と結ぶ |
| |
|
 |

「いのちおとろへぬれば」...きみをしぞおもふ... |
|
|
|
| 【歌意2964】 |
わたしの年も、こんなになってしまいました
すっかり衰えてしまったこの命です
古びた白栲の袖が、馴染んで着れるように
あなたと馴れ親しんだあの頃が
今しきりに思われてなりません |
命が「衰える」とは、死期の予感を言うのだろうか
老いて単に若い頃愛し合った「君」を想い懐かしむ
多くの注釈書は、そんな風に解釈している
そこに、老いることから自然と懐かしむ愛しい人とは、
当然、相手も老いている「姿」ではない
死別かもしれない、という注釈書もあった
私も、その方が、詠うには自然な想いなのだと思う
しかし、私が更に感じたのは
この作者の女性自身もまた、「死期」を感じているのではないか、と
老いたことを、敢えて表現するのは
「あの頃」が随分遠い昔のことであり
図らずも、自分はこれほどまでに長く生きてきた
そう思った瞬間から、まさに「あの頃」が輝きを持って浮かび上がってきたような...
そんな情景を感じさせる歌のように思える
右頁の【注記】に読み難いほどの羅列をしたが
このところ、よく思うことがある
いったい、私たちが「読む」万葉集の正体は何なのだろう、と
平安時代から、現代に至るまでにも、数多くの異訓のオンパレード
その訓を、疑いもせずまさに作者自身の「声」だと信じていた頃が、
今思い返せば、とても無邪気だったと思えてならない
前にも触れたが、定訓のない「歌」を多くの学者が研究し、
それぞれが、自信を持って世に出している
しかし、その中で今日まで残るものといえば、
やはりその時代の「権威者」による、「お墨付き」なのだろう
とすれば、より実作者の声に近いものであっても、
失われてしまうこともあり得る、ということではないだろうか
素人考えでは、平安期に点けられた「訓」は、少なくとも江戸時代の学者より
万葉の当時の「言葉」を理解している、と思うのだが
こうも鎌倉時代を経て、江戸時代、あるいは現代に至るまでの「改訓」を知ってみると
「訓点」の作業そのものへの本質的な研究だけではなく
「註釈書」の研究、つまり仕上げられた「定訓」に異論を掲げ
そこに自分の新訓を提起し、それが多くに支持されれば、決まって新たな「定訓」になる
勿論、血の滲むような研究の土台があってのことだが
その研究と言っても、「校本」は限られている
しかも、例外なく「古写本」には「誤記・誤写」が付き物で
そこに、幾つかの系統の「校本」が存在し、
研究者は、その選択からスターとしなければならない
異なる表記を並べて、どちらかを選ぶということは
またどちらかを「捨てる」ということだ
そこにも、完全という確証は存在はしない
その積み重ねを、師弟関係にある研究者たちが継続して引き継げば
もう原点に立ち返るなど出来ようもない
仮に原点復帰を望めば、それまでの研究に携わった諸々の資料が「無」になってしまう
だから、尚更過去に「師」が選んだ「道」を信じて進むしかない
しかし、『万葉集』に限っていえば
誤記とか誤写を許容するなら、どんな解釈だって可能になってくる
少しの不都合も、そうした「誤記・誤写」を活用すれば、自身の仮説は成り立つ
そんなケースも、少なからずあったと思う
最近になって、つくづく思う
『万葉集』には、こんなに異訓だけではなく「改訓」もあったのか、と
そうなると、『万葉集』の研究と言うのは
一つの歌集論ではなく、当時の言語を研究するのが、大前提になるのではないか
しかも、その表記法まで理解しなければ、とても辿り着けないものだ
だから、私のような単なる『万葉集』ファンには、
現在、どんなにか多くの親切な解説書があり、それぞれの解釈が違ってはいても
それに頼るしかないのかもしれない
そうなると...『万葉集』を読んで、万葉人の魂に触れるという願いも
結局は、「ある時代」の「偉い学者」の「成果」に拠ることになる
何だか寂しいものだが...しかし、少しでも「こんな訓もある、あんな訓もある」と知れば
その中から、自分が素直に感じられる「うたごころ」も現れてきそうだ
たとえ、それが実作者の「うたごころ」ではなかったにしても...
でも、「あなたの歌を、私はこう感じましたよ、ありがとう」とは言える
私には、この方法でしか、『万葉集』に触れることはできない |

 |
掲載日:2013.11.15.
| 正述心緒 |
| 吾齡之 衰去者 白細布之 袖乃狎尓思 君乎母准其念 |
| 我が命の衰へぬれば白栲の袖のなれにし君をしぞ思ふ |
| わがいのちの おとろへぬれば しろたへの そでのなれにし きみをしぞおもふ |
| 巻第十二 2964 正述心緒 作者不詳 |
【注記】に〔10〕歌
| 【2964】語義 |
意味・活用・接続 |
| わがいのちの[吾齡之] 私のいのちが |
| おとろへぬれば[衰去者] |
| おとろへ[衰ふ] |
[自ハ下二・連用形]弱くなる・みにくくなる |
| ぬれ[助動詞・ぬ] |
[完了・已然形]~てしまった・~てしまう |
連用形につく |
| ば[接続助詞] |
[順接の確定条件]~ので・~だから |
已然形につく |
| しろたへの[白細布之] |
〔枕詞〕「衣・袂・袖・紐・帯」(白栲で衣服を作ることから) |
| |
また、その白いことから「雲・雪・波」などにかかる |
| そでのなれにし[袖乃狎尓思] |
| なれ[馴る・慣る] |
[自ラ下二・連用形]習慣になる・親しむ・うちとける |
| にし |
~た・~てしまった |
連用形につく |
| 〔成立〕完了の助動詞「ぬ」の連用形「に」に過去の助動詞「き」の連体形「し」 |
| きみをしぞおもふ[君乎母准其念] |
| し[副助詞] |
語調を整え、強意を表す |
| ぞ[係助詞] |
[強調]~を |
| 掲題歌トップへ |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [吾齢之] |
この原文「吾齢之」は、『尼崎本』、『西本願寺本』には、「歯」とあるが、
共に、その異本として「齢」がある、と添記している
『広瀬本』が「齢」であり、『神宮文庫本』『紀州本』以下諸本は「齢」とする
「歯」の『万葉集』中の用例は一首だが、その歌では、
| 雑歌/中皇命徃于紀温泉之時御歌 |
| 君之齒母 吾代毛所知哉 磐代乃 岡之草根乎 去来結手名 |
| 君が代も我が代も知るや岩代の岡の草根をいざ結びてな |
| きみがよも わがよもしるや いはしろの をかのくさねを いざむすびてな |
| (右檢山上憶良大夫類聚歌林曰 天皇御製歌[云々]) |
| 巻第一 10 中皇命 |
ここでの「歯」は、「齢」と同じように「寿命」「よわい」のように扱われている
この〔2964〕で『尼崎本』は、本文のみで「訓」はなく、
『紀州本』が「わかよはひ」と五音に訓んでいる
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕に、
「ワカヨハヒノ或はワカヨハヒシと読へし」と言い、
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕が、
「わかとしの」と訓じている
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕は、「わがよはひの」と訓み、
田中道麿『万葉問聞抄』には「ワガヨハヒシとよまんか」と本居宣長に質問しているが、
宣長は答えていないようだ
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕は、「わがよはひし」で、
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕は、
「之」を「衍字」(余りの字、語句の中に間違って入った字)として、
「わがよはひ」と訓み、
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕、『岩波文庫新訓』は、
「わがよはひし」と訓んで、それが長い間定訓になっていた
しかし、その「訓」では「字余り例の例外」として、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕が、「おのがよの」と五音に訓む
この「吾」を「おのが」と訓んだ例は、『万葉集』中にはないものの、
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37成〕は、迷いながらもこの訓を採る
そして、『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕もそれに拠る
『日本古典文学全集』〔小学館、昭和50年成〕、
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕が、「わがいのちし」と訓み
『万葉集釈注』〔伊藤博、平成7年~11年成〕は、「わがいのちの」と訓む
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕は、
古く『童蒙抄』が試みた、「わがとしの」と訓んでいる
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37成〕が、
「ワガトシノと訓む事も考へられるが」といい、「齢」を『万葉集』では、
「年齢」の意に「とし」と訓んだ例がないので採用しなかったとする |
| |
| [おとろへぬれば] |
「衰去者」は旧訓では「おとろへゆけば」だったが、
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕が、「おとろへぬれば」と訓じて以来、
それが定訓になっている
この訓だと、語意は「衰えてしまったので」となる
他に、『万葉集釈注』〔伊藤博、平成7年~11年成〕が、「おとろへゆけば」を復活させ、
「次第に衰えてゆくにつけて」と解釈している
面白いと思ったのは、『新古今和歌集』にこの歌が採録されており
まさに、旧訓のままの「歌の姿」を教えてくれることだ
| わがよはひ おとろへゆけば しろたへの そでのなれにし きみをしぞおもふ |
| 新古今和歌集巻第十五 恋歌五 1426 よみ人知らず |
少なくともこの時代、鎌倉時代の初期、
後世の学者たちが騒いで「訓」を論じる以前には
この時代の人たちには、『万葉集』のこの歌は、こう訓まれていたということだ
もっとも、だからと言って、当時でもすでに『万葉集』は難解な歌集だった
その推定される成立から、約二百五十年も経っているのだから...
純粋な日本語表記ではない『万葉集』は、鎌倉時代の初期でも
確実な「訓」は少なかった、だから「梨壺」が設立されたという背景もある |
| |
| [なれ] |
「馴る・慣る」の他に「萎る・褻る」とも表記し、
衣服の糊けがなくなり、よれよれになる、古びる、という意味もある
この歌では、この意味合いが強いと思う
また、原文「狎」は、動物をならす、動物がなれるという意味があり、「馴」と同じ意
これらのことから、二人の仲が、古くからのものだったと思われ
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕では、
この「馴れにし君」を、「かつて婚姻を通じてゐた」と意と解し、
「老境に入って、かつて馴れた人を想起してゐる。生別か、死別か。死別したとすれば、一層あはれである。寂しい境地が、よく描かれて、情味の豊かな作となっている。わが白栲の袖の馴れた君といふ表現も、情趣を感じさせる」とある
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕他、
『新潮日本古典集成万葉集』〔新潮社、昭和51~59年成〕や、
『万葉集釈注』〔伊藤博、平成7年~11年成〕も、
「昔馴れ親しんだ男、馴染んだ男」として、
「今まで親しく馴れ親しんでいるとか、長い間馴れ親しんで来たと」とは解さない |
| |
| [君乎母准其念] |
この結句は、難訓とされている
「きみを・・・おもふ」には、異訓はないが、「母准其」の訓に、
定訓といわれるものがない
流れ的には「あなたを想う」という解釈だから、そこが強調の語だとは解る
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕は、
「其」を「衍字」として「きみをもそおもふ」と訓む
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕は、
「母准」を「羅」一字を誤ったとして「きみをらぞおもふ」と訓む
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕は、
「准」を「衍字」として、「きみをもぞおもふ」と訓む
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕は、
「母」を「衍字」とし、さらに「准」を「進」の誤りとみて「きみをしそおもふ」と訓む
『字音弁証』に「准」に「し」の音ありと論じるのによって、
「母」を「衍字」として「きみをしぞおもふ」と訓じるのが、
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕、
『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕、
『万葉集総釈』〔各巻分担、楽浪書院、昭和10~11年成〕、
『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕、
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37成〕の諸注
「母准」に「衍」があるだろうといい、いずれが「衍字」なのか言わないのが、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕も、
「母准」のいずれが「衍」か決められないが、歌意から「きみをしぞおもふ」と訓むが、
その同増訂版に「母准」を「母に准ずる人の意」として「も」と訓み、
「きみをもぞおもふ」とする
しかし、「もぞ」という文型は例がない
「母准」を「し」と訓んでその理由は不明とするのが、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕、
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕、
『万葉集釈注』〔伊藤博、平成7年~11年成〕の諸注となる |
| |
|
|
| 【歌意2966】 |
あなたは、もうこれからは、
逢わないと思っているわけでもないでしょうに
わたしの白栲の袖は、
涙が止らず、乾く間もありません |
男に対する、女の不信感が芽生えたものだろうか
男が、じかに「もう逢わない」というような素振りは見せなくても
女は、敏感にそれを感じて
そんなことはないだろう、と思いつつも
涙が途絶えることもない...
恋人同士の、このような言葉に表れない「気持ち」や「気配」というのは
恋人同士だからこそ、敏感になってしまうものだ
しかも、それは決して望むような予感ではなく
そうなって欲しくない、祈るような憔悴の日々をもたらす
一度芽生えたこの「不安」あるいは「不信」というものは
男には、なかなか感じてもらえないものだと思う
だからこそ、女のその感情や仕草が、目に見えて男に伝わるまで
男からは、希望の言葉はもらえないのだろう
不安の中に日々を過ごし、涙がこうも止むことなく流れる...
そこまでの姿を見れば...男の優しい言葉も、あるいはその態度も...表れる
しかし、それまでの「せつなさ」は...いや、それが「恋」というものだ、と思う
やはり「恋」は「孤悲」という文字が似合う
『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕での、この歌の解説に
グッとくるものがあった
「吾が涙のかく落つるは、君が逢はじとする前兆かと疑ったもの」といい、
その己の涙に「不吉な予感」を感じたものと想像する
相手に抱いたひそかな不安を訴えている
この説明は、不安を先に予感して「泣いた」のではなく
何故か「涙」する
その自分の姿に、「ああ、あの人は...」と思い当たる節を確認し始めた、ということだろう
どうして「涙」が落ちてくるのか...
女は、ハッとしたのかもしれない
そんな戸惑い、苦悩...私にも想像できる
やはり、言葉でじかに確認したくなるものなのだろう
それが出来ないからこそ、こうした歌が詠えるのかもしれないが... |
 |
掲載日:2013.11.16.
| 正述心緒 |
| 従今者 不相跡為也 白妙之 我衣袖之 干時毛奈吉 |
| 今よりは逢はじとすれや白栲の我が衣手の干る時もなき |
| いまよりは あはじとすれや しろたへの わがころもでの ふるときもなき |
| 巻第十二 2966 正述心緒 作者不詳 |
【注記】に〔802〕〔3732〕〔4058〕歌
| 【2966】語義 |
意味・活用・接続 |
| いまよりは[従今者] |
| より[格助詞] |
[起点]~から 〔接続〕体言、活用語の連体形につく |
| は[係助詞] |
[否定の内容]~は (下の否定の語に呼応して内容を明確にする) |
| あはじとすれや[不相跡為也] |
| じ[助動詞・じ] |
[打消の推量・]~ないだろう・~まい |
未然形につく |
| すれ[為(す)] |
[他サ変・已然形]ある行為をする・ある動作をする |
| や[係助詞] |
[反語的疑問]~(だろう)か(いや、~ない) |
種々の語につく |
| しろたへの[白妙之] |
〔枕詞〕「衣・袂・袖・紐・帯」(白栲で衣服を作ることから)
また、その白いことから「雲・雪・波」などにかかる |
| わがころもでの[我衣袖之] |
| ころもで[衣手] |
衣の手の部分・袖 |
| の[格助詞] |
[主語]~が 〔接続〕体言および体言に準ずる語につく |
| ふるときもなき[干時毛奈吉] |
| ふる[干(ふ)・乾(ふ)] |
[(上代語)自ハ上二・連体形]〔「ひる(干る)・(乾る)」に同じ〕
かわく・潮が引く・水が少なくなる |
| なき[無し] |
[形ク・連体形]ない |
| 第二句の係助詞「や」を受けて、連体形で結ぶ、疑問・反語表現の「係り結び」 |
| 掲題歌トップへ |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [あはじとすれや] |
この訓は『類聚古集』、『広瀬本』からのもので、
『陽明本』が「あはじとするや」としているが、これを採った注釈書は、
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕のみとなっている
「あはじとすれや」は、「あはじとすればや」の意であり、
「もう逢うまいと思っているからなのか、そんなことはないはずなのに」とする |
| |
| [ふるとき] |
原文「干時」は、旧訓「ひるとき」で、
『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕以下、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕までの諸注では「ひるとき」と訓む
「ふる」は上代語の上二段活用連体形で、「ひる」は中古以降の上一段連体形
『私注』までの「ひるとき」の訓の時代にあって、
『定本万葉集』〔佐佐木信綱・武田祐吉、昭和15~23年成〕だけは「ふるとき」とし、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕から「「ふるとき」と改訓されている
私は、単純に上代では「乾く」などの意を「上二段活用」だから、
上代語「干(ふ)・乾(ふ)」の連体形「ふる」だと思ったが、そもそも万葉時代が
上代、中古時代曖昧な時代なのでは、と思うと
その使用語が、「これだ」とは、確かに言い切れないのだろう
この語句の場合、何故「ふるとき」が正しいと説明するのに
次の三首を引き合いに出して、確定している
| 日本挽歌一首 |
| 伊毛何美斯 阿布知乃波那波 知利奴倍斯 和何那久那美多 伊摩陀飛那久尓 |
| 妹が見し楝の花は散りぬべし我が泣く涙いまだ干なくに |
| いもがみし あふちのはなは ちりぬべし わがなくなみた いまだひなくに |
| (神龜五年七月廿一日 筑前國守山上憶良上) |
| 既出、〔万葉の植物Ⅱ〕巻第五 802 山上憶良 |
妻が見た、せんだんの花が散ってしまいそうだ
わたしの泣く涙は、まだ乾かないのに... |
| |
| (竹敷浦舶泊之時各陳心緒作歌十八首) |
| 之保非奈婆 麻多母和礼許牟 伊射遊賀武 於伎都志保佐為 多可久多知伎奴 |
| 潮干なばまたも我れ来むいざ行かむ沖つ潮騒高く立ち来ぬ |
| しほひなば またもわれこむ いざゆかむ おきつしほさゐ たかくたちきぬ |
| 巻第十五 3732 羈旅 遣新羅使 |
潮が引いたなら、またも出航だ
さあ、行こう
沖の潮騒も、音高くなってきた |
| |
| (天平廿年春三月廾三日左大臣橘家之使者造酒司令史田邊福麻呂饗于守大伴宿祢家持舘爰作新歌并便誦古詠各述心緒) |
| 奈呉能宇美尓 之保能波夜非波 安佐里之尓 伊泥牟等多豆波 伊麻曽奈久奈流 |
| 奈呉の海に潮の早干ばあさりしに出でむと鶴は今ぞ鳴くなる |
| なごのうみに しほのはやひば あさりしに いでむとたづは いまぞなくなる |
| (右四首田邊史福麻呂) |
| 巻第十八 4058 宴席 田辺福麻呂 |
奈呉の海に、潮が引いたらすぐにでも餌を得ようと
鶴はその構えを見せるように、鳴いているようだ |
これらの「ひ」の原文「飛・非」は「乙類のヒ」で、
動詞の未然形(ひなくに・ひば)と連用形(ひなば)が「乙類」であるのは、
「上二段活用」であることを示し、
その連体形は「ふる」だとするのが、根拠となっている
| 自動詞ハ行上二段活用 (干・乾) |
| 未然形 |
連用形 |
終止形 |
連体形 |
已然形 |
命令形 |
| ひ |
ひ |
ふ |
ふる |
ふれ |
ひよ |
確かに、これは素人の私にも明快な説明だとは思う
ならば、どうして旧訓では「ひるとき」と訓んだのだろう
訓点当時に、表記の「乙類・甲類」の区別が、厳格ではなかったのだろうか
また、調べてみよう |
| |
|
|
| 【歌意2967】 |
夢ではないかと、心も乱れてしまいました
幾月もの長い間、音沙汰もなかったあなたから
使者の方がこうやって何度も便りをしてくれますので... |
この歌で、まずどんな情況を思い浮かべるのだろう...直感的に...
「通う」という語には、同じところを往来するような意味があり
長い間、音信もなかった男から、このように「便り」も届き出した、とするのか
夢かと思って気持ちもうろたえたかのような表現から、
まさに、いま愛しい男からの「便り」を受け取った「歓び」の詠歌...
私には、当初の驚きを回想して詠う女性の姿が浮ぶ
思いもしなかった「便り」に心を躍らせ、しばらくその余韻に浸っていたのだろう
そして、やがて気持ちも落ち着いてきて、やっと当初の「驚嘆」を歌にする
こうした内容の歌は、客観的に想いを起こすのに時が必要なものだ
勿論、そうではないケースもあるだろうが
悲しみに打ち沈む中での思わず発する声ではなく
予想外の歓びならば、後に何度も何度もかみ締めることが出来るだろし
その心情を、詠じることもまたいっそう、歓びを深めるものなのだろう
今夜も、改めて「訓」のことで思いを廻らせてしまった
右頁にこのところ何度も、その「訓」の経緯を書いているが
これほどまでに、定訓への道程が「遠い」ものなら
そのうち...何十年後か何百年後か、あるいはもっと近い将来かもしれないが
それこそ、『万葉集』って、どうやって読むのだろう、となるのではないだろうか
確かに、多くの解説書や註釈書がある以上、読むのには困らない
しかし、そうやって『万葉集』に馴染んできた『万葉集ファン』たちに
突然、これが本当の『万葉集の姿』だといって、「原文」を見せれば
みんなきっと困惑するだろう
でも、その原文以外に、本当の『万葉集』は存在していないのも事実だ
夢のまた夢、と思うにしても
いつか...「万葉時代の註釈書」でも発掘されればなあ、と
同時代的資料がないことが、すべての研究に「仮説」しか残せなくなっているのだから...
|


 |
掲載日:2013.11.17.
| 正述心緒 |
| 夢可登 情班 月數多 干西君之 事之通者 |
| 夢かと心惑ひぬ月まねく離れにし君が言の通へば |
| いめかと こころまどひぬ つきまねく かれにしきみが ことのかよへば |
| 巻第十二 2967 正述心緒 作者不詳 |
【注記】に〔790〕〔4036〕歌
| 【2967】語義 |
意味・活用・接続 |
| いめかと[夢可登] |
| か[係助詞] |
[疑問]~か・~だろうか |
| 〔接続〕体言・活用語・副詞・接続助詞などが主語・目的語・連用修飾語になっているもの |
| と[格助詞] |
[引用]~と |
「~と言って・~と思って・~として」などの意で、あとに続く動作・状態の目的・
状況・原 因・理由などを示す
〔接続〕体言、体言に準ずる語につく |
| こころまどひぬ[情班] |
| まどひ[惑ふ] |
[自ハ四・連用形]心が乱れる・慌てる・うろたえる |
| ぬ[助動詞・ぬ] |
[完了・終止形]~てしまう・~てしまった |
連用形につく |
| つきまねく[月數多] |
| つき[月] |
時間の単位・陰暦で月がまったく見えない夜から、次の見えない夜までの期間をいう・二十九日または三十日で一ヶ月となり、十二ヶ月または十三ヶ月で一年となる |
| まねく[まねし] |
[形ク・連用形](上代語)度重なる・数が多い |
| かれにしきみが[干西君之] |
| かれ[離る] |
[自ラ下二・連用形](時間的に)間をおく・足が遠くなる |
| |
(空間的に)離れる・遠ざかる |
| |
(精神的に)うとくなる・よそよそしくなる |
| にし |
~た・~てしまった |
連用形につく |
| 〔成立〕完了の助動詞「ぬ」の連用形「に」+過去の助動詞「き」の連体形「し」 |
| ことのかよへば[事之通者] |
| こと[言] |
口に出していう・ことば・うわさ・評判 |
| かよへ[通ふ] |
[自ハ四・已然形]通じる・よく知っている・行きとどく |
| ば[接続助詞] |
[順接の確定条件]~ので・~だから |
已然形につく |
| 掲題歌トップへ |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [いめかと] |
原文「夢可登」を『元暦校本』『類聚古集』『広瀬本』『西本願寺本』『紀州本』、
『活字附訓本』『寛永版本』の諸本では「ゆめかとも」と訓み、
『神宮文庫本』『細井本』は「ゆめかとよ」、
『大矢本』『京都大学本』は、「ゆめかとし」と訓む
『京都大学本』は漢字の左に、赭で「ゆめかとよ」ともある
諸注では、
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕が、「登」の下に「毛・母」などの
脱字があったのではないか、として「ゆめかとも」と訓じたが、
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕は「夢」は「いめ」と正し、
さらに、この初句を「四音句」だとした
それが「いめかと」で、以来定訓となる
それでも、異訓もあり
『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕は「いめとかも」、
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕は「いめにかと」、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕と、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕が旧訓による「いめかとも」
この諸注のみが、定訓を採っていない |
| |
| [情班] |
これが「難訓」だったようで、『元暦校本』『類聚古集』『広瀬本』『西本願寺本』は、「おもほゆるかも」と「義訓」している
『西本願寺本』は漢字の左に別字の青で「おもひつかめや」とあり、
「つ」を墨で消して「わ」と直し、「おもひわかめや」とする
『紀州本』以下『寛永版本』までこの訓だが、
『神宮文庫本』『細井本』は「こころはかりて」とする
その根拠と推測されるのが、〔巻第二・167〕の、「日並皇子殯宮挽歌」に、
「神分 分之時」とある「分」を「はからふ」の意があるので「はかる」としたように
「班」を「はかる」と訓むのだろうか、
と、『万葉集全注』〔伊藤博、昭和58年~〕では言うが
この説明では、私にはよけいに難しく感じられる
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕は、「班」を「恠」の誤りとして、
「こころあやしも」と訓む
しかし、『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕の鹿持雅澄は、
「それならば、アヤシマレヌ、と言わねば上のイメカトに呼応しない」と反論して、
「班」は「斑」で、「こころまどひぬ」と訓ませたのではないか、という
これが後の賛同を得て、
『新潮日本古典集成万葉集』〔新潮社、昭和51~59年成〕、
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕、
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕が、これに拠った
しかし、『定本万葉集』〔佐佐木信綱・武田祐吉、昭和15~23年成〕が、
「こころはまどふ」の新訓を出して、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕、
『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕などが、これに拠る
原文のありかたに最も忠実な訓みは、これではないか、と『全注』はいう |
| |
| [つきまねく] |
原文は、「月数多」とするのが、『元暦校本』 『大矢本』『京都大学本』で、
『西本願寺本』 『神宮文庫本』 『紀州本』『細井本』は、「月数多二」と「二」がつく
『寛永版本』は、これに拠っている
そして、それらの諸本の訓は「つきひさに」で異訓はない
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕は、これを「つきさはに」と改め、
「数多」の左に「あまた」とある
原文が「月数多」なら「つきあまた」と訓むことを考えたのでは、といわれている
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕は、「二」のない原文に従い、
「つきまねく」と訓み、
『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕、
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕、
『岩波文庫新訓』、
『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕、
『万葉集総釈』〔各巻分担、楽浪書院、昭和10~11年成〕、
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕がこれに拠る
『定本万葉集』〔佐佐木信綱・武田祐吉、昭和15~23年成〕が「つきあまた」と訓み、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕がこれに拠る
しかし、『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕以後、
『万葉集釈注』〔伊藤博、平成7年~11年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕まですべて「つきまねく」とする
次の用例からも、「まねし」が適当だとは思われる
| 相聞/(大伴宿祢家持報贈藤原朝臣久須麻呂歌三首) |
| 如夢 所念鴨 愛八師 君之使乃 麻祢久通者 |
| 夢のごと思ほゆるかもはしきやし君が使の数多く通へば |
| いめのごと おもほゆるかも はしきやし きみがつかひの まねくかよへば |
| 既出、〔書庫-4〕巻第四 790 相聞 大伴家持 |
夢のように思えてなりません
お慕いするあなたからの使者が、
このように何度も何度も通ってこられますので |
| |
| (思放逸鷹夢見感悦作歌一首[并短歌]) |
| 矢形尾能 多加乎手尓須恵 美之麻野尓 可良奴日麻祢久 都奇曽倍尓家流 |
| 矢形尾の鷹を手に据ゑ三島野に猟らぬ日まねく月ぞ経にける |
| やかたをの たかをてにすゑ みしまのに からぬひまねく つきぞへにける |
| (右射水郡古江村取獲蒼鷹 形容美麗鷙雉秀群也 於時養吏山田史君麻呂調試失節野猟乖候 摶風之翅高翔匿雲 腐鼠之餌呼留靡驗 於是張設羅網窺乎非常奉幣神祇恃乎不虞也
粤以夢裏有娘子喩曰 使君勿作苦念空費精神 放逸彼鷹獲得未幾矣哉 須叟覺寤有悦於懐 因作却恨之歌式旌感信 守大伴宿祢家持 [九月廾六日作也]) |
| 巻第十七 4036 狩猟 大伴家持 |
矢形尾の鷹を手に、三島野で狩りをしない日が、何日も続き
もうひと月も経ってしまった |
これらの歌の「まねく」は「使」の来る回数が多いこと、
日が度重なることを「まねし」と言っている
古語辞典にも、数が多い、の他に「度重なること」と載っている
|
| |
|
|
| 【歌意2968】 |
長い年月にわたり
夜になると、あなたの夢ばかり見たものでした |
激情的な言葉もなく、非常に静かな「想い」の歌だ
「愛しい男」は、このあと戻ってくるのか、あるいは別れた後の歌なのか...
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕は、「夫が旅にいるものとみえる」とする
この当時の「夢に見える」のは、「俗信」とも言われるもので
相手が自分を思ってくれているしるし、とされている
だから、夫婦間や恋人同士の「夢」は、一種の「安心感」を与えるものなのだろう
さらに、感じられるのは
この「俗信」を信じている、揺るぎない女の「想い」が伝わる
だから、安心して待っている、という姿が...
しかし、逆の見方も出来ると思う
「俗信」に頼ったのではなく、ずっと「愛しい人」の夢を見続けるのは
それが、どんな「意味」があろうと、少なくとも自分が「想う」からだ、と
「俗信」に頼れば、仮に「夢」に現れなければ、こんなにも落ち着くことはできない
しかし、「俗信」を当てにしなければ、
仮に「夢」を見ることがなくても
それは、自分の想いが足りなかったからだ、と思い直すこともできる
この歌は、そんな「女の落ち着いた心の強さ」も感じることが出来る
|
|
掲載日:2013.11.18.
| 正述心緒 |
| 未玉之 年月兼而 烏玉乃 夢尓所見 君之容儀者 |
| あらたまの年月かねてぬばたまの夢に見えけり君が姿は |
| あらたまの としつきかねて ぬばたまの いめにみえけり きみがすがたは |
| 巻第十二 2968 正述心緒 作者不詳 |
| 【2968】語義 |
意味・活用・接続 |
| あらたまの[未玉之]〔枕詞〕「年」にかかる |
| としつきかねて[年月兼而] |
| かね[重(かさ)ぬ] |
[他ナ下二・連用形]積み重ねる・度重ねる |
| て[接続助詞] |
[補足]~て・~ようにして |
連用形につく |
| ぬばたまの[烏玉乃]〔枕詞〕「夢」にかかる |
| いめにみえけり[夢尓所見] |
| けり[助動詞・けり] |
[過去・終止形]~た・~たのであった |
連用形につく |
| 以前から現在まで続いている事柄や伝承を回想する意 |
| きみがすがたは[君之容儀者]あなたの姿は |
| 掲題歌トップへ |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [未玉之] |
原文「未玉」はこの歌のみに見られる
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕が、『倭名抄』で「璞」について、
和名「阿良太万」とあり「玉、未理也」とあるのを引いて、
「未玉は、義を以って書るにて、未理玉の謂なり」とある
まだ研磨しない玉の意と解していたことを示す表記という |
| |
| [夢尓所見(いめにみえけり)] |
旧訓は「ゆめにそみゆる」
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕は、「所見」に「みえつる」と訓むが、
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕は「いめにぞみゆる」と訓んでいる
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕が、「いめにそみゆる」と訓むなら、
「尓」の下に「曽」の字など脱かといい、あるいは「尓」は「西」の誤りで、
「いめにしみえつ」か、という
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕が「いめにぞみえし」と過去形に訓み、
『岩波文庫新訓』も、『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕もこれに拠る
他は「そ」を訓み添えて「いめにそみゆる」としてきたが、
『萬葉集本文篇』〔塙書房・佐竹昭広、昭和38年成〕に、「いめにみえけり」と改訓し、
それが多く採られている
この『塙本』、ようやく古書店で手に入れた
本文のみだが、非常に見易く、これから大いに役立てよう |
| |
|
|
| 【歌意2969】 |
これからは、いくらあの人を恋しく想っても、
逢うことは叶うのだろうか...いや、出来ないだろうなあ、きっと
だから、せめて私の床から去らず
ずっと夢に現れてほしい
|
どんなに想っても、逢うことは叶わない、というのは
どんな状況なのだろう
しかも、「いまよりは」といい、それまでは「逢えていた」ということだ
男は、いつ帰れるか分からない旅にでもでたのだろうか
公務で、非常に厳しい何かの「紛争地域」だったのかもしれない
あるいは、その紛争の当事者とも...
まだまだ考えられる
愛しい女性が、他の男と結婚するため、近づくことが出来なくなった
そうとも考えられるが
こうして「歌」にすると、どのような心情が「うたごころ」に合うのだろう
私は、「逢はめやも」を詠嘆の反語のように思う
決して「逢えない」わけではないのに、「逢うことが」できない
いや、すべきではない、という気持ちが滲み出ている
「詠嘆」では、「逢うべきではない」という気持ちと相反するようだが
それは違うと思う
「逢う」、「逢いたい」、「逢えるだろうか」、「逢ってはいけないのだろうか」など
様々な逡巡を男は巡らせている
極端に言えば、詠いながらもまだ、その気持ちの整理はつかず
溜息混じりに、「逢はめやも」と言ったのかもしれない
そんな自分の未練を「嘆く」歌だと思う
そして、決して「男らしく」ない「未練」を懇願するようにして、やはり「嘆く」
これまでの多くの諸注では、
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕のいう、
「旅立つ時の歌なり」として、ほとんどそれに拠っている
ただし、『万葉集釈注』〔伊藤博、平成7年~11年成〕で、これについて、
「旅立つ時の歌」とするには、「第三句の反語形〔逢はめやも〕の詠嘆がきにかかる」とし、
逆に「女が遠くへ転居する場合とも考えられる」という
この説明に、私も同じような気持ちをいだいた
やはり「逢はめやも」の詠嘆を籠めた「反語」とすると、「旅立ち」ではないと思う
ということは、『井上新考』に基づくその系統の解釈では、「詠嘆」の気持ちを抑えている
そうなるのだろうか...確かに、幾つかの諸注をみても、詠嘆を全面にしたものはない
私も詠嘆が気にかかる
だから、男の旅立ちではなく、男の「未練を残した別れ」に思う
揺れ動く気持ちを、何とかしよう、ではなく
そのままに任せて「嘆く姿」が、この歌の「姿」ではないかと思う
他の注釈書で、この歌のテーマを述べたものを二つ挙げておく
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕は、
「子細ありて別れし歌と聞こえたり」
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕は、
「故ありて、女に長く別るる事ありし時よめる」という
結局は、この「故ありて」の「故」が解らない以上、
この歌の本当に歌意は、誰にも解らない、ということになる
そこに、推論を求めれば、以下はすべて「推論」になるのだから...
これが、ある意味での『万葉集』への触れ合い方なのだろう
そうやって、万葉歌を、自分の世界観で感じることになるのも、またいいものだ
|


|
掲載日:2013.11.19.
| 正述心緒 |
| 従今者 雖戀妹尓 将相哉母 床邊不離 夢尓所見乞 |
| 今よりは恋ふとも妹に逢はめやも床の辺去らず夢に見えこそ |
| いまよりは こふともいもに あはめやも とこのへさらず いめにみえこそ |
| 巻第十二 2969 正述心緒 作者不詳 |
【注記】に〔2506〕〔2642〕歌
| 【2969】語義 |
意味・活用・接続 |
| いまよりは[従今者] |
| より[格助詞] |
[起点]~から 〔接続〕体言、活用語の連体形につく |
| は[係助詞] |
[否定の内容]~は (下の否定の語に呼応して内容を明確にする) |
| 〔接続〕名詞、助詞、活用語の連体形・連用形などの種々の語につく |
| こふともいもに[雖戀妹尓] |
| とも[接続助詞] |
[逆接の仮定条件]たとえ~しても |
終止形につく |
| あはめやも[将相哉母] |
| めやも |
[反語]~だろうか(いや、~でないなあ) |
未然形につく |
| 〔成立〕推量の助動詞「む」の已然形「め」+反語の終助詞「やも」 |
| とこのへさらず[床邊不離] |
| とこ[床] |
寝床 〔「とこのへ」寝床のあたり〕 |
| さら[去る] |
[自ラ四・未然形]離れて行く・遠ざかる |
| ず[助動詞・ず] |
[打消・連用形]~ない |
未然形につく |
| いめにみえこそ[夢尓所見乞] |
| こそ[助動詞・こす] |
[希求願望・命令形](上代語)~て欲しい・~てくれ |
〔成立〕「おこす」の頭母音の脱落した形とも、「来(こ)為(す)」からとも、助詞「こそ」が
活用したものとも、諸説がある 〔接続〕動詞の連用形につく |
| 掲題歌トップへ |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [めやも] |
この「めやも」は、その構成する品詞に、結構苦しむ
しかし、基本的には「反語」なので、だいたいの語意で済ませてしまうが
敢えて、その構成を見詰めると...本当に、ややこしく思えてしまう
上表の語義で採り上げたのは、古語辞典にそのまま「めやも」があり
それを挙げたものだが、その〔成立ち〕には、次のような解説があった
推量の助動詞「む」の已然形「め」に、反語の終助詞「やも」がついたもの、と
『万葉集全注』〔伊藤博、昭和58年~〕によれば、
「や」は、疑問の助詞であるが、動詞の已然形に接続して「反語」を表す、とあり
その「や」の前に推量の助動詞「む」の已然形「め」があるので、
「めや」で反語となるのは解る
実際、古語辞典でも「めや」の項目があり、その〔成立ち〕には、
推量の助動詞「む」の已然形「め」に、反語の終助詞「や」がついたもの、とある
さらに、『全注』では、
「も」は詠嘆の助詞で、「やも」と続けた場合は「反語」と解してよい、とあるが
それは、「詠嘆」の解釈が消えて「反語」になるということなのだろうか
たしかに「やも」には、係助詞、終助詞ともに「反語・疑問」の意しかない
「詠嘆」の意を残して歌意が通るかどうか、と言うことになるだろうが
その場合でも、反語「めや」に、詠嘆の終助詞「も」で構文は成り立つと思う
問題は、この歌の感じに沿えるかどうか、だ |
| |
| [とこのへさらず] |
この「とこのへさらず」は、『万葉集』中に、三例しかなく
一つは、山上憶良の長歌〔巻五-909〕で、もう一つの用例が、
次の柿本人麻呂歌集出にある
| 寄物陳思 |
| 里遠 眷浦經 真鏡 床重不去 夢所見与 |
| 里遠み恋ひうらぶれぬまそ鏡床の辺去らず夢に見えこそ |
| さとどほみ こひうらぶれぬ まそかがみ とこのへさらず いめにみえこそ |
| (以前一百四十九首柿本朝臣人麻呂之歌集出) |
| 巻第十一 2506 寄物陳思 柿本朝臣人麻呂歌集 |
| |
〔語義〕
「遠み」の「み」は、形容詞「遠し」の語幹「遠(とほ)」につき、
多くは「~(名詞)を~み」の形になるが、「~ので・~から」の意になる
「うらぶれ」は、自動詞ラ行下二段「うらぶる」で、「侘しく思う・悲しみに沈む」
この「うら」は、「こころ」の意
「まそかがみ」は、鏡の性質・使い方などから、「見る・照る・磨く」などにかかる
この歌では「床」にかかる
「とこのへさらず いめにみえこそ」の語義は上表
|
〔歌意〕
こんなにもあなたの里が遠いので
私は恋焦がれて、悲しみに沈んでいます
ですから、どうか私の寝床から離れずに
夢に見えてください |
この〔2506〕歌では、結句も同じで、「とこのへさらず いめにみえこそ」となれば
この二首には、片や「柿本人麻呂歌集」という出典があったものと推測されるし
歌人・斉藤茂吉『評釈篇』は、「床のへ去らず」の句に面白味があり、といい
巻第十二の歌は、おそらく「柿本人麻呂歌集」のこの歌が、
流伝の際に変化したものだろう、という
しかし、「柿本人麻呂歌集」を元にしたと思われる歌は多く、
仮に茂吉が「面白い」というほどの「語句」であれば、
もっと多くあってもいいような気もするが、僅かこの二首...
私には、「床のへ去らず」と「いめにみえこそ」は、
一種の慣用句であってもいいように思える
言葉の流れとして、「私の寝床を離れず、夢に現れて」というのも、自然なことだから
そして、この類歌とされている歌〔2642〕こそ、「柿本人麻呂歌集出」であり
それは、単に語句が同じと言うだけではなく、「歌意」も「同じ」だと思う
| 寄物陳思 |
| 里遠 戀和備尓家里 真十鏡 面影不去 夢所見社 |
| 里遠み恋わびにけりまそ鏡面影去らず夢に見えこそ |
| さとどほみ こひわびにけり まそかがみ おもかげさらず いめにみえこそ |
| 右一首上見柿本朝臣人麻呂之歌中也 但以句々相換 故載於茲 |
| 巻第十一 2642 寄物陳思 柿本朝臣人麻呂 |
その左注に、「この歌は、既に柿本人麻呂の歌の中に見える」とあるも、
「少しずつ句が相違しているので、ここに載せる」とする
柿本人麻呂の詠歌として、ここに載せるが、
この歌は以前「人麻呂歌集出」の歌としても載せている、
しかし、語句が少しずつ違えているので、ここに載せる、ということだ
では、これは「類歌」というよりも、「同じ歌」だと言うべきだと思う |
| |
| [いめにみえこそ] |
この訓は、古くから「いめにみえこそ」と諸本で訓まれていたという
この歌には、昨日のような「そ」を挿入する異訓はないらしい
原文に「乞」の字があるからだろうか
「こそ」と読んだとき、すぐに浮ぶのが係助詞、終助詞の「こそ」だった
しかし、「強調」の意のある係助詞では...「夢に見えてこそ」というのも合わない
終助詞の「こそ」であれば、「希望」の意で「~てほしい」となり
その場合の接続も、動詞の連用形につくので、これは「合う」
しかし、ほとんどの注釈書は、上代の助動詞「こす」の命令形「こそ」とする
上代の歌だから、「上代語」の助動詞を使ったものと解釈したのだろうか
古語辞典でも、「希望」の終助詞「こそ」は、希望の助動詞「こす」の命令形「こそ」が
もとになるのでは、とするが、はっきりとしていないようだ
ついでに記せば、異訓はないといっても、次の二書のみは異訓を載せている
『広瀬本』には「ゆめにみえこち」、
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕は「ゆめにみえこせ」 |
| |
|
|

| 「こととがめせぬゆめ」...それが本当の望み... |
|
|
|
| 【歌意2970】 |
他人に見られ、あれやこれやと
責め立てられることのない夢にだけでも
絶えることなく、いつも私の前に現れてください
そうすれば、この苦しい恋も、
少しはおさまるでしょう
[人目が多くて、直に逢えないのです]
|
二人の仲は、まだ親に認められてはいないのだろうか
だから、どんなに逢いたくても、我慢はしよう
ただ、人目も気にせず、誰も何も言えない「夢」の中であれば...
私は、どんな我慢でもできます
ですから、せめて夢にだけでも、その姿を見せてください...
お互いの「恋心」を、親が承認するまでも待てない、「若さ」
でも、「或本」の頭の二句に触れると
少し意味合いが違ってくるのではないだろうか
確かに、「人目が多い」ことは、上述の場合でも二人にとっては大きな問題になる
しかし、敢えて「ただにはあはず」と言えば...
決められた約束事であれば、普段でも「逢える」はずだ
しかし、「直接逢うことはできない」
何故だろう
これは、私が最初に感じた状況とは違うのかもしれない
こうした作者不詳の歌というのは
その作者の環境がさっぱり分からず、とんでもない解釈までしてしまいそうだ
しかし、この歌からは、何も二人の置かれている環境など知りようがない
この歌に限らず、巻第十一やこの十二には、そんな歌だらけだ
既出の〔2924〕歌を、右頁に載せたが、そう言えばこの歌
『遊仙窟』の物語の影響もあったことを、思い出した
「やどさすなゆめ」が、確かそうだった
男が、夢の中で逢いに行くので、「鍵」を掛けないでおくれ、と言い聞かせている
男の方から、夢で逢おう、という
では、この〔2970〕歌は...
女の方から、夢にでも逢いに来てくれ、というものだ
人目を気にしないですむ、「夢」でこそ、二人は「逢瀬」を重ねることが出来る
この時代、いやこの時代に限らず
逢うことの叶わない二人にとって、「夢」と言うのは、あるいは「現実」なのかもしれない
「夢で逢う」という概念は、いつ頃からあるのだろう
勿論、夢そのものは、誰でも見るはずだ
しかし、日常の生活では、逢うことの難しい二人が
「夢」を、その現実的な「逢瀬」の手段として、お互いに望みを伝えるのは
これも、『遊仙窟』などのように、大陸からの影響なのだろうか
『万葉集』にも、「夢」を背景とした「恋歌」は多い
そして、相手を想ってくれているからこそ、自分の「夢」に現れる、という「俗信」まで...
その「俗信」の源流を知りたいと思うのだが...
素人では、その「俗信」がすでに前提として、諸々の歌が解釈されている現状では
その源流に辿り着くには、長い長い航海が必要だということだ
この歌のように、逢えないのなら、せめて夢にずっと現れてくれ、と願うのは
「俗信」を持ち出せば、「ずっと私のことを想っていてくれ」ということになる
それを、直接的な「ことば」ではなく、「夢」というもう一つの「現実の世界」を作った
そうも思えてしまう
「夢で逢う」ことは、実際に逢うことと同じようなものなのかもしれない
だから、「夢にでも現れて欲しい」と...
勿論、それが続けば、やがて「夢」が「現実」ではないことを知る
そして、また「恋歌」が...詠われる...
|
 |
掲載日:2013.11.20.
| 正述心緒 |
| 人見而 言害目不為 夢谷 不止見与 我戀将息 或本歌頭云 人目多 直者不相 |
| 人の見て言とがめせぬ夢にだにやまず見えこそ我が恋やまむ[人目多み直には逢はず] |
| ひとのみて こととがめせぬ いめにだに やまずみえこそ あがこひやまむ |
| [ひとめおほみ ただにはあはず] |
| 巻第十二 2970 正述心緒 作者不詳 |
【注記】に〔2924〕〔1000〕〔2861〕歌
| 【2970】語義 |
意味・活用・接続 |
| ひとのみて[人見而]人が見て |
| こととがめせぬ[言害目不為] |
| こととがめ[言咎め] |
詰問・言葉で咎めること |
| せ[為(す)] |
[他サ変・未然形]ある動作を行う・ある行為をする |
| ぬ[助動詞・ず] |
[打消・連体形]~ない |
未然形につく |
| いめにだに[夢谷] |
| だに[副助詞] |
[強調]せめて~だけでも・~だけなりと |
| 〔接続〕体言・活用語・副詞・助詞につく、複合語に用いられることもある |
| やまずみえこそ[不止見与] |
| やま[止む] |
[自マ四・未然形]続いていたものが終りになる・絶える |
| ず[助動詞・ず] |
[打消・連用形]~ない |
未然形につく |
| こそ[助動詞・こす] |
[希求願望・命令形](上代語)~て欲しい・~てくれ |
〔成立〕「おこす」の頭母音の脱落した形とも、「来(こ)為(す)」からとも、
助詞「こそ」が 活用したものとも、諸説がある
〔接続〕動詞の連用形につく |
| あがこひやまむ[我戀将息] |
| やま[止む] |
[自マ四・未然形]続いていたものが終りになる・絶える |
| む[助動詞・む] |
[推量・終止形]~だろう |
未然形につく |
| 或本の歌の頭(かみ)に云はく [或本歌頭云] |
| ひとめおほみ ただにはあはず [人目多 直者不相] |
| ある本の歌には、上の二句が「人目が多いので、直には逢えないが」とある |
| 掲題歌トップへ |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [ひとのみて こととがめせぬ いめにだに] |
この三句とほとんど同じ句の歌がある
| 正述心緒 |
| 人見而 事害目不為 夢尓吾 今夜将至 屋戸閇勿勤 |
| 人の見て言とがめせぬ夢に我れ今夜至らむ宿閉すなゆめ |
| ひとのみて こととがめせぬ いめにわれ こよひいたらむ やどさすなゆめ |
| 既出、〔書庫-8〕 巻第十二 2924 正述心緒 作者不詳 |
| |
人が見ても、咎め立てなどしない夢の中で
今夜私は、あなたに逢いに行くのだから
家の戸の「鍵」はしないでおくれよ |
「夢」は誰も介入できず、とがめ立てすることのないもの
副詞「だに」については、この歌では、まだ起こっていない未来の事柄とともに
最小限の一事をあげる「強調」の意で用いたが
古語辞典には、他の用法で、
「類想」 ~だって・~のようなものでさえ
「添加」 ~までも
がある
そして、辞書での解説では、奈良時代は「強調」の用法だけで、
「類想」は平安時代以降の用法であり、「すら」とほぼ同じ意味に使われているという
「添加」については、「さへ」が広く使われるようになったために、
逆に「だに」が「さへ」の意味で使われたもの、とある
「だに」を受ける語句は、「打消・反語・命令・意志・願望・仮定」の表現とする |
| |
| [やまずみえこそ] |
原文「不止見与」で、旧訓は「やますをみえよ」だが、
『神宮文庫本』『細井本』のみ、「やますもみえよ」としている
これを『万葉代匠記(初稿本)』〔契沖(1640~1701)、貞亨四年(1687)成〕に、
「ヤマスミエコソともよむへし」といい、同じく契沖の、
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕には、
| 雑歌/大伴坂上郎女宴親族歌一首 |
| 如是為乍 遊飲與 草木尚 春者生管 秋者落去 |
| かくしつつ遊び飲みこそ草木すら春は咲きつつ秋は散りゆく |
| かくしつつ あそびのみこそ くさきすら はるはさきつつ あきはちりゆく |
| 巻第六 1000 雑歌 大伴坂上郎女 |
| |
さあ、こうしてみなさん、遊び飲んでください
草木でさえ、春は大いに茂り、秋に散って行くのです |
この歌の解釈も複雑なものがあるだろう
しかし、ここでは「こそ」に契沖の考察を見る
「此与(與)ノ字、乞ノ字ト同シク願フ詞ノコソト読ヌヘキ所多シ」と説く
「与」を「こそ」と訓むのは、昨日の〔2506〕歌でも使われ、
同じく昨日の〔2969〕歌の「乞」も、同じだ、ということだ
さらに、「与」の用例として、これも既出だが、
| 正述心緒 |
| 現 直不相 夢谷 相見与 我戀國 |
| うつつには直には逢はず夢にだに逢ふと見えこそ我が恋ふらくに |
| うつつには ただにはあはず いめにだに あふとみえこそ あがこふらくに |
| (右廿三首柿本朝臣人麻呂之歌集出) |
| 既出、〔書庫-10〕巻第十五 2861 正述心緒 柿本朝臣人麻呂歌集 |
| |
目覚めているときには、じかに逢うこともできません
せめて夢の中だけでも「逢うこと」が叶ってほしい
わたしが、こんなにも「恋」しているのですから... |
この〔2861〕歌では、「こそ」を、私は希望の終助詞「こそ」としている
そのときは、上代の助動詞「こす」など思いも及ばなかった
しかし、「希望・願望」という語意も、構文的にも、どちらも成り立つものだ
昨日も書いたが、この二つは区別が難しいというが、
そもそも、上代の助動詞「こす」の命令形「こそ」が、終助詞「こそ」の基であるのなら
結局は、その口語訳においても厳密な使い分けはできないと思う |
| |
| [頭(かみ)] |
これは「頭句」ともいい、この歌のように第一・二句をさすが
上三句をさすものや、長歌の上六句、あるいは第一句のみをさすものがある
『歌経標式』でも、第一句を「頭」と称しているが、その一貫性はない
(本サイトに『歌経標式』解題)を載せている) |
| |
|
|
| 【歌意2971】 |
実のところ、便りまでも途絶えています
ならば、せめて夢にだけでも、
ずっとずっと、途切れることなく見えて欲しい
いつか、じかにお逢いするまでは...
|
第二句の「訓」で「ことはたえたり」とする感覚と、
「こともたえたり」とするそれでは、かなりの違いがある
「は」であれば、「便り」それ自体の「絶えている」ことの強調になると思うが
「も」であれば、他の手段...逢うこともなくなり、「便りさえも」といい
愛しい人への継続的な関係の手掛かりすべてが、この「も」に凝縮されている
逢わなくなったうえに、便りさえもなくなり...
残る希望は、「せめて夢の中にでも」と切に願う
私の思う「夢」の背景には、「想い続けてください」という言外の気持があり
現実には逢えなくても、想いさえ確認できれば、それにすがって生きていける
そんな「愛おしさ」が、この歌の「香」だと思う
結句の、「ただにあふまでに」は、小声で、ぼそぼそ、としおらしく呟く
実際に、逢えるなどとは思っていない
しかし、その「希望」がなければ、「夢」に現れて欲しい、という願いだけでは
気の遠くなるほどの「むなしさ」がある
逢えないことは解っています、
便りだって途切れました、
でもいつかまた逢える日まで
せめて夢の中ででも、逢ってください
|
 |
掲載日:2013.11.21.
| 正述心緒 |
| 現者 言絶有 夢谷 嗣而所見与 直相左右二 |
| うつつには言も絶えたり夢にだに継ぎて見えこそ直に逢ふまでに |
| うつつには こともたえたり いめにだに つぎてみえこそ ただにあふまでに |
| 巻第十二 2971 正述心緒 作者不詳 |
| 【2971】語義 |
意味・活用・接続 |
| うつつには[現者] |
| うつつ[現] |
現実・正気・夢心地 |
| には |
~には 〔成立〕格助詞「に」+係助詞「は」 |
体言につく |
| 〔格助詞「に」の意味によって、種々の意味を表す〕 |
| こともたえたり[言絶有] |
| も[係助詞] |
[添加]~もまた |
| 〔接続〕名詞、助詞、用言や助動詞の連体形・連用形など、種々の語につく |
| たえ[絶ゆ] |
[自ヤ下二・連用形]途絶える・縁が切れる |
| たり[助動詞・たり] |
[完了・終止形]~ている |
連用形につく |
| いめにだに[夢谷] |
| だに[副助詞] |
[強調]せめて~だけでも・~だけなりと |
| 〔接続〕体言・活用語・副詞・助詞につく、複合語に用いられることもある |
| つぎてみえこそ[嗣而所見与] |
| つぎ[継ぐ・続ぐ] |
[他ガ四・連用形]続ける・保つ・持ち続ける |
| て[接続助詞] |
[継続]~て |
連用形につく |
| こそ[助動詞・こす] |
[希求願望・命令形](上代語)~て欲しい・~てくれ |
〔成立〕「おこす」の頭母音の脱落した形とも、「来(こ)為(す)」からとも、
助詞「こそ」が 活用したものとも、諸説がある
〔接続〕動詞の連用形につく |
| ただにあふまでに[直相左右二] |
| ただに[直(ただ)] |
[形動ナリ・連用形]直接であるさま・じか |
| までに |
[程度・限度を明確にする]~ほどに・~までも |
| 〔接続〕体言および体言に準ずる語、動詞・助動詞の連体形、副詞や助詞など種々の語につく |
| 〔成立〕副助詞「まで」+格助詞「に」 |
| 掲題歌トップへ |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [うつつ]古語辞典より |
現実に存在するさまをいう形容詞「現(うつ)し」の語幹を重ねた「うつうつ」の略と見られる語で、原義は現実に存在すること
①(死に対して)生きている状態
②(夢に対して)目が覚めているさま・現実
③(意識の確かでない状態に対して)気の確かな状態・正気
④(誤って)夢心地・夢か現実かわからないような状態 |
| |
| [こともたえたり] |
原文「言絶有」は、旧訓「ことたえたれや」で、
その異訓は、『広瀬本』の「ことたえれや」、『大矢本』の「ことたえたれか」だが、
「や・か」に当る本文はないので、
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕(初稿本も含め)が、
「ことたえたるを」と訓み、
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕、
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕が、「ことたえにたり」と訓んだ
『岩波文庫新訓』『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕、
『万葉集総釈』〔各巻分担、楽浪書院、昭和10~11年成〕、
『定本万葉集』〔佐佐木信綱・武田祐吉、昭和15~23年成〕、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕、
『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕、
『萬葉集本文篇』〔塙書房・佐竹昭広、昭和38年成〕がこれに拠る
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕は、
歌の意味から「ことたえにけり」とし
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕がこれに拠る
『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕は、「ことはたえたり」と訓み、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕がこれに拠る
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕が、「こともたえたり」と訓み、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕、
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37成〕、
『日本古典文学全集』〔小学館、昭和50年成〕、
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕、
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕、
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕、
『万葉集釈注』〔伊藤博、平成7年~11年成〕などが、これに拠る
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕は、「ことたえてあり」とする
|
| |
|
|
| 【歌意2974】 |
妻と離れて、袖も交わさないで寝るのは
寂しいものだ
今夜は、さっさと明けるなら明けてほしい
|
一人寝の寂しい夜
男の嘆き悲しむ歌のようだ
早く夜も明けてくれ、そうしれば一人寝の寂しさなんか、と...
「早も」という語に、男の「寂しさ」が沁み込む
寝付けないほどの「寂しさ」
それが「あけばあけなむ」という言葉に発せられるものだろう
男は、長い旅にでも出ているのだろうか
もっとも、この時代の「旅」といえば公務なのだろうが
幾夜も同じ気持ちで過ごすのは、今も昔も同じことだ
似たような歌がある
| 正述心緒 |
| 敷細 枕動而 宿不所寝 物念此夕 急明鴨 |
| 敷栲の枕動きて寐ねらえず物思ふ今夜早も明けぬかも |
| しきたへの まくらうごきて いねらえず ものもふこよひ はやもあけぬかも |
| 巻第十一 2598 正述心緒 作者不詳 |
〔語釈〕
「まくらうごきて」、眠れなくて輾転反側し、そのために枕の位置が定まらないことをいう |
〔歌意〕
あの人のことを想うと、枕の定まることがないほど
寝付くことが出来ず、悶々としてしまう
こんなに物思いする夜など、さっさと明けてくれ |
この歌も、確かに「類想歌」といえばそうなのだろう
しかし、私には本質的な違いがあると思う
〔2974〕歌は、間違いなく「一人寝」の寂しさを詠ったものだが
〔2598〕歌は、「ものおもふ」と詠っており、この「ものおもふ」は、
思い悩む、思いに耽る、と言う意味だ
勿論、〔歌意〕にしたように、ごく自然に思われるのは、「恋心」だとは思う
しかし、「そでかれてぬる」と「まくらうごきていねらえず」の違いは明白ではないか
片や、共に寝た女への郷愁に苛まれ、片やただ単に「おもふ」ことだけで眠れない
〔2974〕歌が、夫婦の仲でのしばしの「別れ」であり
〔2598〕歌は、まだ若者の「恋やつれ」のような歌だ
それでも、夜は一層寂しく思ったり、余計なことをしきりに思ったりで
疎ましく感じるものなのだろう
早く明けてくれ、夜なんて
この一点においては、「類歌」とは言えるが、「類想歌」とするのはちょっと違うと思う
そもそも、「類想歌」とか「類歌」とやたらに注釈書には出てくるが
それには、はっきりとした区別がないのではないかと思う
私自身も、ついさっきまでは、同じように捉えていた
しかし、この「類想歌」と言われている二首を並べたとき
いや、これは「想い」の根本が違うぞ、と感じた
ならば、「類想歌」ではないことになる
似たような歌、と言う意味で「類歌」であれば、まだ納得も出来る
先日も書いたことがあるが、同じ歌を少々の語句が違うからと言って
「別歌」とし、その本歌は、何々歌集から採り上げたもの、というようなことがあった
その編者の姿勢に、『万葉集』編纂に関わった人たちの苦悩が感じられた
同じ歌であっても、少々の語駒の違いで、別歌、つまり「類想歌」になってしまう
しかし、その「想い」は、語句は違っても「同じ」だと解っているなら
それは、決して「類想歌」ではなく「同歌」なのではないか
「類想歌」あるいは「類歌」と言うのは
全く違う時と場所で、別々の作者が詠ったものが、その「想い」に重なる「歌」だと思う
「本歌」の存在が解っておりながら、少しの語句の違いで別歌とし、更には「類想歌」とは、
私には、ちょっと理解し難いことだ
もっとも、『万葉集』の編者よりも、大方は後の時代の註釈書を著わす学者がそうする
研究の結果、この歌とあの歌は「類想歌」だ、というように...
「類想」の視点だけで『万葉集』を読めば、どれもが「類想歌」になってしまいそうだ
同じような「想い」の歌は、とても多い
だからこそ「類歌」と「類想歌」とは、もっと明確に仕分ける必要があるのでは、と思う
それに、『万葉集』の編者たちの時代...現代的な感覚でのデータの活用はできなかった
すべてが、膨大な原資料の山の中から、「編者」たる人による作業だ
「同じ歌」の「異訓」...写本の過程で、充分起こり得る
それを「異訓」とすれば問題ないが、「別歌」とすれば...
そこからまた後世の悩ましい研究に...中世あるいは江戸時代の「訓」の定着の仕方をみても
垣間見るだけでは、非常にラフな感じで「訓」が定められてしまうかのように見えるが、
どれほどの「想い」で、「訓」を作者の「声」としようともがいているか...
その未だに混沌とした状況である『万葉集』の...それもまた「魅力」の一つなんだろうなあ
|
 |
掲載日:2013.11.22.
| 正述心緒 |
| 白細之 袖不數而宿 烏玉之 今夜者早毛 明者将開 |
| 白栲の袖離れて寝るぬばたまの今夜は早も明けば明けなむ |
| しろたへの そでかれてぬる ぬばたまの こよひははやも あけばあけなむ |
| 巻第十二 2974 正述心緒 作者不詳 |
【注記】〔4〕〔947〕〔2676〕〔2939〕歌、【類歌】左頁〔2598〕歌
| 【2974】語義 |
意味・活用・接続 |
| しろたへの[白細之]〔枕詞〕「袖」にかかる |
| そでかれてぬる[袖不數而宿] |
| かれ[離(か)] |
[自ラ下二・連用形](空間的に)離れる・遠ざかる |
| て[接続助詞] |
[補足]~て・~ようにして |
連用形につく |
| ぬる[寝(ぬ)] |
[自ナ下二・連体形]眠る・横になる・男女が共寝する |
| ぬばたまの[烏玉之]〔枕詞〕「今夜」にかかる |
| こよひははやも[今夜者早毛] |
| はや[副詞] |
早く・すみやかに・早くも・すでに |
| も[係助詞] |
[並列]~も |
| 〔接続〕名詞、助詞、用言や助動詞の連体形・連用形など、種々の語につく |
| あけばあけなむ[明者将開] |
| あけ[明(あ)く] |
[自カ下二・未然形]夜が明ける・明るくなる |
| ば[接続助詞] |
[順接の仮定条件]~(する)なら・~だったら |
未然形につく |
| なむ[終助詞] |
〔「なん」とも表記〕他に対する願望の意を表す |
未然形につく |
| |
~てほしい・~てもらいたい |
〔参考〕上代には「なむ」と同じ意味で、「なも」も用いた
相手に向って直接言うのではなく、話し手が独り言のように言う場合に用いる |
| 掲題歌トップへ |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [袖不數而宿] |
『元暦校本』は本文「袖不数而当」とあり、「そてかすへすて」と訓んでいる
『古葉略類聚鈔』は、本文はなく「訓」は同じで、「袖数へずて」だろう、とする
『広瀬本』『西本願寺本』『紀州本』『大矢本』『京都大学本は、
本文「袖不数而』で「宿」に当る字は無く、「そてかへすして」と訓む
『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕が同訓で、
「袖かへすとはかたしきたる袖を左右かへぬ心なり」とあり、
これは、一人寝のわびしさをいうのだ、という
『神宮文庫本』『細井本』は、本文「袖不数而宿」とあり、「そてかへてぬる」との訓
これは『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕では「袖更へで寝る」だろう、とする
「袖を交わさずして寝る」のだという
江戸時代の版本はこの本文に拠っているが、「そてかへすしてぬる」と訓付けしている
『万葉代匠記(初稿本)』〔契沖(1640~1701)、貞亨四年(1687)成〕は、「数」を
| 雑歌/(天皇遊猟内野之時中皇命使間人連老獻歌)反歌 |
| 玉尅春 内乃大野尓 馬數而 朝布麻須等六 其草深野 |
| たまきはる宇智の大野に馬並めて朝踏ますらむその草深野 |
| たまきはる うちのおほのに うまなめて あさふますらむ そのくさふかの |
| 巻第一 4 雑歌 中皇命 |
〔語釈〕
枕詞「たまきはる」は、「内」やその同音の地名「宇智」にかかるが、
その理由は不明とされている
「うまなめて」、馬をつなれて
副詞「並(な)べて」と同じで、他動詞バ行下二段「並(な)ぶ」の連用形「なべ」に、
接続助詞「て」がつき、一般化した語
基本的には、同列に並べての意味、そこから、「総じて・一般に・普通」の意になる
|
〔歌意〕
霊気の漲る宇智の大野に、馬を一面に並べ
朝、踏んでいらっしゃることでしょう、その深く茂った草々を |
この歌の訓みにより、「袖をならべぬ」の意として「そてなめすて(袖並めずて)」と訓む
従って、『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕「そてなめすてぬる」
この訓を、『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕、
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕、
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕が採る
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕は、
「数」は「索」に通じるとして、「巻く」の意にとり「そでまかでぬる」と訓んだ
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕は、その訓みをとり、
「不数」を「不巻」の誤りとした
『万葉集問目』に、本居宣長が「不巻而ノ誤ニハアラズヤ」と賀茂真淵に問い、
真淵が「巻」の草体を示して「数」の草体に誤ったのだろう、と答えている
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕はそれを受け継いで、更に「而」の字が
「官本」に「なきをよしとす」とあるが、現存諸本で「而」の無いのは『陽明本』他一書
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕は、その歌意をもって、
「そてかれてぬる」と訓む
『万葉集総釈』〔各巻分担、楽浪書院、昭和10~11年成〕が、その補強として
| 雑歌/過辛荷嶋時山部宿祢赤人作歌一首[并短歌] |
| 味澤相 妹目不數見而 敷細乃 枕毛不巻 櫻皮纒 作流舟二 真梶貫 吾榜来者 淡路乃 野嶋毛過 伊奈美嬬 辛荷乃嶋之 嶋際従 吾宅乎見者 青山乃 曽許十方不見 白雲毛
千重尓成来沼 許伎多武流 浦乃盡 徃隠 嶋乃埼々 隈毛不置 憶曽吾来 客乃氣長弥 |
| あぢさはふ 妹が目離れて 敷栲の 枕もまかず 桜皮巻き 作れる船に 真楫貫き 我が漕ぎ来れば 淡路の 野島も過ぎ 印南嬬 辛荷の島の 島の際ゆ 我家を見れば 青山の
そことも見えず 白雲も 千重になり来ぬ 漕ぎ廻むる 浦のことごと 行き隠る 島の崎々 隈も置かず 思ひぞ我が来る 旅の日長み |
| あぢさはふ いもがめかれて しきたへの まくらもまかず かにはまき つくれるふねに まかぢぬき わがこぎくれば あはぢの のしまもすぎ いなみつま からにのしまの しまのまゆ わぎへをみれば あをやまの そこともみえず しらくもも ちへになりきぬ こぎたむる うらのことごと ゆきかくる しまのさきざき くまもおかず おもひぞわがくる たびのけながみ |
| 巻第六 947 雑歌 山部赤人 |
〔語釈〕
「めかれて」、目に触れず・目が離れて・別れて |
〔歌意〕
妻と別れて随分とその手枕もしていない
桜皮を巻いて造った船に梶をとって漕いでいると
淡路の野島も通り過ぎ、印南つまも過ぎ
辛荷の島々の間から、故郷の方を見る
青山のどの辺りがそれとも分からず
白雲も幾重にも重なってきて、漕ぎ廻る
あちこちの浦に行き隠れる岬の数々
どこに泊っても、恋しく想い続けてしまうことだ
こんなに旅が長くなると... |
| |
| 寄物陳思 |
| 二上尓 隠經月之 雖惜 妹之田本乎 加流類比来 |
| 二上に隠らふ月の惜しけども妹が手本を離るるこのころ |
| 二上に隠らふ月の惜しけども妹が手本を離るるこのころ |
| 既出、〔書庫-8〕巻第十一 2676 寄物陳思 作者不詳 |
| |
| 正述心緒 |
| 浦觸而 可例西袖ヲ 又巻者 過西戀以 乱今可聞 |
| うらぶれて離れにし袖をまたまかば過ぎにし恋い乱れ来むかも |
| うらぶれて かれにしそでを またまかば すぎにしこひい みだれこむかも |
| 巻第十二 2939 正述心緒 作者不詳 |
〔語釈〕
「うらぶれて」、侘しく思う・悲しみに沈む
「かれにしそでを」、離れてしまった袖を
「こひい」、「い」は強調の助詞
「みだれ」、あれこれと思い悩む・平静さを失う |
〔歌意〕
侘しく思って、もう離れてしまった袖を
あの頃のように巻けば
過ぎ去った恋だというのに、
また思い悩んでしまうことだろうなあ |
など、これらのように「袖をかれる」ということが、決して不当ではないとして
この訓みを採ったが、「そでなめず」がこの時代の定訓だった
『岩波文庫新訓』は、「袖不敷而」と意改して「そでしかずて」と訓み、
その改訂版に「そでなめずてぬる」に改めた
『大成本文篇』に至って「そでかれてぬる」が復活する
そして、現在では、これが定訓だといえるものになっている
「恋人の袖を離れて一人で寝ること」の意として... |
| |
|
|
| 【歌意2975】 |
白栲の妻の手枕をして、心地よく眠るなど
そんなように人並みに眠ることはできず
わたしは、ずっと妻を想いつづけていくことだろうか
|
旅先なのかどうか、分からないが
妻と離れて、一人寝の夜の寂しさを、前の歌〔2974〕と同じように嘆き詠う
あるいは、同じ作者かもしれない
この夜、作者がどうしようもなく寂しさを綴った歌が、ここに並ぶ...
前歌で、捨て鉢気味に、「さっさと夜も明けてくれ」と言い放った
しかし、この歌では、ふと我に返ったように、行く末を見据えている
「こひわたりなむ」
この「わたり」は、一般的な川を渡る、というような「わたり」ではなく
動詞の連用形の下につき、「~しつづける」という意味の補助動詞みたいな働きをしている
ずっと恋し続けて...それは、帰る見込みもない「旅」だったのだろうか
そんなことはないだろうが
おそらく、一般的な職務だと言われ旅立ったものの
いざ赴任してみると...その現実は、想像以上に厳しく
ひょっとしたら、もう帰れないのでは、と不安も掠め始め...
今でこそ、電話も交通も比較にならないほどの世の中になっているが
それが一切ない当時の「旅」というのは、
おそらく私たちの想像以上の「不安」に、支配されてしまうのだろう
一人寝の寂しい夜だからこそ、どんなに振り払っても消えない「たもとゆたけく」が
他の人たちにはなせても、自分にはできない
その「想い」に打ち沈む男の、再起の歌があるのかもしれない
前の歌と同じ作者だとすれば、まるで物語のような構成になっている
愛しい人がいない、こんなところに自分はいる
一人寝なんて、とても耐えられない
夜なんか、とっとと去ってしまえ
こんなことを想いながら、私はずっとここで過ごさなければならないのだろうか...
と、そこでこの男の「嘆き」は途切れている
しかし、これに続くような歌があってもいいような気もする
今挙げた二首の歌が、それぞれ別の振り分けで配列されていたら
その一首ごとに、同じような気持ちなんだなあ、と感じるだけだろうが
こうして二首が並ぶと、「同じ作者」の嘆きの詠歌であり
『万葉集』編者にも、その意識はあったのでは、と思えてしまう
ただ、おそらく膨大に積まれた資料の中から、
仮に作者が一連の歌を残したとしても、それを見つけ出すことは、
やはり、困難だったことと思う
私が、この詠者であれば
まさに「寂しさに打ちしがれて」いる最中では、決して詠うことは出来ず
少なくとも、その「不安」が解消された後に、回想しながらでも詠いたい、と思うだろう
あんな時代があった、と
問答歌が、それに釣り合うような「歌」を引っ張りだすように
『万葉集』編者も、少しは試みたかもしれない
しかし、あまりにも資料が多くて...と想像してしまう
そう思ったのは、この二首を並べたのが、その「意思」ではないかと、思うからだ |

 |
掲載日:2013.11.23.
| 正述心緒 |
| 白細之 手本寛久 人之宿 味宿者不寐哉 戀将渡 |
| 白栲の手本ゆたけく人の寝る味寐は寝ずや恋ひわたりなむ |
| しろたへの たもとゆたけく ひとのぬる うまいはねずや こひわたりなむ |
| 巻第十二 2975 正述心緒 作者不詳 |
【注記】〔442〕〔787〕〔1033〕〔2373〕歌
| 【2975】語義 |
意味・活用・接続 |
| しろたへの[白細之]〔枕詞〕「手本」にかかる |
| たもとゆたけく[手本寛久] |
| たもと[袂] |
[手(た)本(もと)の意]肘から肩までの部分・二の腕 |
| |
また、衣服の袖のたれた袋状の部分 |
| ゆたけく[豊けし] |
[形ク・連用形]余裕がある・ゆったりしている |
| ひとのぬる[人之宿] |
| ぬる[寝(ぬ)] |
[自ナ下二・連体形]眠る・横になる・男女が共寝する |
| うまいはねずや[味宿者不寐哉] |
| うまい[熟寝・味寝] |
気持ちよく寝入ること・熟睡 |
| ね[寝(ぬ)] |
[自ナ下二・未然形]眠る・横になる・男女が共寝する |
| ず[助動詞・ず] |
[打消・連用形]~ない |
未然形につく |
| や[係助詞] |
[疑問]~か (係り結びの「係り」) |
連用形につく |
| こひわたりなむ[戀将渡] |
| わたり[渡る] |
[自ラ四・連用形](動詞の連用形の下について) |
| |
(時間的に)ずっと続ける、の意を表する |
| な[助動詞・ぬ] |
[完了・未然形]~てしまう・~てしまった |
連用形につく |
| む[助動詞・む] |
[推量・連体形]~だろう (「係り結び」) |
未然形につく |
| 掲題歌トップへ |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [たもとゆたけく] |
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕では、「手本」の意味は、
手の元で、手首あるいは袖口のあたりをいう、と解しているが
古語辞典でも、「手首」の辺りとしたり、「肘から肩」にかけてとしたり
「手の元」の解釈がまちまちだ
肩口から伸びるからそこが「手」の始まりか
あるいは、手先からとすれば、それが「手元」なのか...
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕は、「腕全体」としている
こうしたそれぞれの解釈も、歌意全体の合うのかどうか、で決められると思うが、
その歌意も、また難しそうだ
次の歌から、何か探れはしないだろうか
| 挽歌/(神龜五年戊辰大宰帥大伴卿思戀故人歌三首) |
| 應還 時者成来 京師尓而 誰手本乎可 吾将枕 |
| 帰るべく時はなりけり都にて誰が手本をか我が枕かむ |
| かへるべく ときはなりけり みやこにて たがたもとをか わがまくらかむ |
| (右二首臨近向京之時作歌) |
| 既出、〔書庫-3〕巻第三 442 挽歌 大伴宿禰旅人 |
〔歌意〕
都に帰るときがきた
そこでは、いったい誰が私の「腕」を「枕」として眠るのだろう |
| |
| 相聞/(大伴宿祢家持贈娘子歌三首) |
| 打乍二波 更毛不得言 夢谷 妹之手本乎 纒宿常思見者 |
| うつつにはさらにもえ言はず夢にだに妹が手本を卷き寝とし見ば |
| うつつには さらにもえいはず いめにだに いもがたもとを まきぬとしみば |
| 巻第四 787 相聞 大伴宿禰家持 |
〔歌意〕
現実では、勿論言えることではなく
せめて、あの娘が手枕をしてくれる夢でも、
見ることができたら... |
| |
| 雑歌/十二年庚辰冬十月依大宰少貳藤原朝臣廣嗣謀反發軍 幸于伊勢國之時河口行宮内舎人大伴宿祢家持作歌一首 |
| 河口之 野邊尓廬而 夜乃歴者 妹之手本師 所念鴨 |
| 河口の野辺に廬りて夜の経れば妹が手本し思ほゆるかも |
| かはぐちの のへにいほりて よのふれば いもがたもとし おもほゆるかも |
| 巻第六 1033 雑歌 大伴宿禰家持 |
〔歌意〕
河口のほとりに、仮の宿をとると
夜も更けるにつれて、妻の手枕で共寝したことが
思われてならない |
「たもとゆたけく」だけでは、なかなかイメージが沸かなかったが
この三首に共通する「手本」とは、まさに「手枕」だと思う
とすれば、それが出来るのは、「腕」ではないだろうか
手首の辺り、とか、袖口とかと訳してイメージすることは難しい
だから肘から肩までの二の腕、もしくは腕全体とした方がいいと思う
「ゆたけく」に、「ゆったりとしている」など「寛ぐ」意味からして
袖口あたりだけを「手枕」にして、「ゆったり」とは出来ないはずだ
やはり腕全体で、広く寛がせる方が、自然にイメージを浮かべることができる |
| |
| [ひとのぬる] |
ここでの「人」は、勿論「妹」ではないはずだ
世間の他の人たちのことを言っていると思う
しかし、『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕は、この「人」を、
「妹をさす」としている
すると、自分がいないのに、「妹」は寛いでゆったりと寝ている、となってしまう
それはおかしい
世間ではみんな共寝で「寛いで」寝ているのに、自分は...となる方が自然な感じ方だ
この「ひとのぬる うまいはねずや」と同じような用例がある
| 正述心緒 |
| 人所寐 味宿不寐 早敷八四 公目尚 欲嘆 [或本歌云 公矣思尓 暁来鴨] |
人の寝る味寐は寝ずてはしきやし君が目すらを欲りし嘆くも
[或本歌云 君を思ふに明けにけるかも] |
ひとのぬる うまいはねずて はしきやし きみがめすらを ほりしなげくも
[きみをおもふに あけにけるかも] |
| (以前一百四十九首柿本朝臣人麻呂之歌集出) |
| 巻第十一 2373 正述心緒 柿本人麻呂歌集 |
〔歌意〕
人並に共寝もせず、
愛しいあなたを、一目だけでも見たい、と
願い嘆き続けることでしょうね
〔あなたを想っているうちに、夜が明けてしまいました〕 |
この歌でも、世間の他の人たちは、としなければ意味が通らない
|
| |
|
|
| 【歌意1816】 |
気高い香具山に、
今夕になって、霞がたなびいている
おそらく、もう春になるのだろうなあ
|
大阪から奈良の葛城に入ると、その真正面に見える山が、「天の香具山」だ
いつもその山に向って、明日香に行くことになるが
その香具山の後方にも、それこそ「かすみたなびく」がごとく、山々が連なる
古代に、どうしてこの「天の香具山」が特別な山だとされたのだろう
いつもそう思って眺めてしまう
格別高い山でもない
寧ろ、畝傍山や耳成山は、平地にもっこりと居座っているので
その方が、特別な意味を感じてしまうのだが...
しかし、そんな現代人の「目」で、この山を思うのはやめよう
その本当の理由は知らずとも、
万葉の時代の人々にとっては、かけがいのない山には違いない
そして、その時代の人々の心に触れようとしている私にとって
その気持ちは、理解できるとか、出来ないの問題ではなく
そうあることに対して、敬意を持たなければならない
山が靄ると、明日香の町は、とても幽玄な世界に変貌する
山間から立ちこめる靄は、そのまま万葉時代を思わせる雰囲気を醸し出してくれる
春先...まだ冷たい風に当たりながら、明日香を歩くと...
いや、私はまだそうやって「春の気配」を感じたことがなかった
このような歌が詠めるのは、そこに住む人の必然的な「季節感」なのだろう
確か、大陸から暦が導入されたのは、それほど古いことではなかったはずだ
四季を愛でる歌の数々...それは、「暦」という馴染みが無くても
人が、その気配で感じ取るからこそ、自然豊かな事象に事寄せて詠えるものだ
現代のように、「暦の上では」という言葉など必要もない
今、肌で感じる気配こそが、「暦」なのだから...
|



|
掲載日:2013.11.24.
| 春雑歌 |
| 久方之 天芳山 此夕 霞霏□ 春立下 (□=雨冠に微) |
| ひさかたの天の香具山この夕霞たなびく春立つらしも |
| ひさかたの あめのかぐやま このゆふへ かすみたなびく はるたつらしも |
| 巻第十 1816 春雑歌 柿本人麻呂歌集 |
【注記】〔1532〕〔432〕〔1710〕〔2033〕〔2065〕歌
| 【1816】語義 |
意味・活用・接続 |
| ひさかたの[久方之]〔枕詞〕「天」にかかる |
| あめのかぐやま[天芳山] 現在の奈良県橿原市から桜井市にかかる |
| 多武峰の端山にあたり独立峰ではない、畝傍山・耳成山と共に「大和三山」の一つ |
| このゆふへ[此夕] |
| この |
自分に最も近いものを指示する・この・ここの・このような |
| かすみたなびく[霞霏□](□=雨冠に微) |
| かすみ[霞] |
微細な水滴が空中に浮遊して、空や遠方がはっきり見えない |
| たなびく[棚引く] |
[自カ四・終止形]雲や霞などが横に長く引く |
| はるたつらしも[春立下] |
| たつ[立つ] |
[自タ四・終止形](年月や季節などが)始まる |
| |
(時間的に)ずっと続ける、の意を表する |
| らし[助動詞・らし] |
[推量・連体形]きっと~だろう |
終止形につく |
| も[終助詞] |
[感動詠嘆]~よ・~なあ |
種々の語につく |
| 掲題歌トップへ |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [ひさかたの] |
「雨」や「月」などにもかかる
用字例として「久堅(の)」「久方(の)」とあるように、
その広大無窮さをいう詞らしいが、その語義は未詳とされている |
| |
| [あめのかぐやま] |
現代での一般的な表記は「天の香具山」だろう
『伊予国風土記逸文』には、「天から降ったという伝説」もある
『記紀神話(岩屋戸の条)』では、「高天原の神聖な山」として登場する
この山の表記例は「香具山・香来山・芳来山・芳山・香山・高山」などがあり
「芳山」について、『万葉集総釈』〔各巻分担、楽浪書院、昭和10~11年成〕に、
「かぐに『芳』字を宛てたのは、この字の訓がカグハシであるから、借用したもの」とする「芳」は「香」とも通用したので「香山」の用例〔261・262・2453〕もあり、
それで「芳山・芳来山(259)」とも使ったものか
|
| |
| [かすみ]古語辞典「霞と霧の違い」 |
霞は霧とは同じ現象であるが、平安時代ごろから春のものを「霞」、
秋のものを「霧」と区別した
また、遠くにたなびくのを「霞」、近くに立ちこめるのを「霧」と考えた
上代では季節による区別はなく、『万葉集』(8-1532)にみえる「霞立つ天の河原に..」は、秋、陰暦七月の七夕の歌である
| 秋雑歌七夕/(山上臣憶良七夕歌十二首) |
| 霞立 天河原尓 待君登 伊徃還尓 裳襴所沾 |
| 霞立つ天の川原に君待つとい行き帰るに裳の裾濡れぬ |
| かすみたつ あまのかはらに きみまつと いゆきかへるに ものすそぬれぬ |
| 巻第八 1532 秋雑歌七夕 山上臣憶良 |
|
| |
| [たなびく] |
原文の「霏□」(□は、雨冠の下に「微」)は、人麻呂の造語と言われている
「たなびく」のこの表記の用例は、人麻呂作歌と、人麻呂歌集非略体歌にのみに見える
漢籍に六朝頃より少しずつ見出され、初唐までは例の少ない「霏微」があり、
それは一般に「雨・雪・露・霜」などの天然現象の「降る」姿を形容している
小島憲之『上代日本文学と中国文学』「中」において、
その「微」に「雨冠」を付けたのは、人麻呂の発明だという
この用例が集中しているのも、この巻第十が多いが、その巻第十の歌は、
おそらく近々ここでも採り上げることになるので、
その他の用例を見る (なお、第十用例五首は、一首のみ例外とすして、歌だけ載せる)
| 挽歌/溺死出雲娘子火葬吉野時柿本朝臣人麻呂作歌二首 |
| 山際従 出雲兒等者 霧有哉 吉野山 嶺霏□ (□=雨冠に微) |
| 山の際ゆ出雲の子らは霧なれや吉野の山の嶺にたなびく |
| やまのまゆ いづものこらは きりなれや よしののやまの みねにたなびく |
| 巻第三 432 挽歌 柿本人麻呂歌集 |
〔歌意〕
山の際のあたりに立ち込める出雲娘子は、
霧なのだろうか
この吉野の山の嶺に、たなびいているではないか |
| |
| 雑歌/舎人皇子御歌一首 |
| 黒玉 夜霧立 衣手 高屋於 霏□麻天尓 (□=雨冠に微) |
| ぬばたまの夜霧は立ちぬ衣手を高屋の上にたなびくまでに |
| ぬばたまの よぎりはたちぬ ころもでを たかやのうへに たなびくまでに |
| 巻第九 1710 雑歌 柿本人麻呂歌集 |
〔歌意〕
これほど深い暗闇に立ち込める「夜霧」
衣手の高屋の上にたなびくほどに... |
| |
| 1818 いにしへの人の植ゑけむ杉が枝に霞たなびく春は来ぬらし |
| 1819 子らが手を巻向山に春されば木の葉しのぎて霞たなびく |
| 1820 玉かぎる夕さり来ればさつ人の弓月が岳に霞たなびく |
| 1821 今朝行きて明日には来なむと云子鹿丹朝妻山に霞たなびく |
| 1822(例外) 子等名丹 關之宜 朝妻之 片山木之尓 霞多奈引 |
| 子らが名に懸けのよろしき朝妻の片山崖に霞たなびく |
| 以上五首、柿本人麻呂歌集で、この巻第十は次からは「春雑歌詠鳥」になる |
|
| |
| [らしも] |
「下」を「らしも」と訓むのは「ら」の訓み添え、という
「ら」の「訓み添え」例を挙げる
| 秋雑歌七夕 |
| 天漢 梶音聞 孫星 与織女 今夕相霜 |
| 天の川楫の音聞こゆ彦星と織女と今夜逢ふらしも |
| あまのがは かぢのおときこゆ ひこほしと たなばたつめと こよひあふらしも |
| (右柿本朝臣人麻呂歌集出) |
| 巻第十 2033 秋雑歌 柿本人麻呂歌集 |
〔歌意〕
天の川に、梶の音が聞こえる
彦星と織姫が、きっと逢うのだろう |
| |
| 秋雑歌七夕 |
| 天河 白浪高 吾戀 公之舟出者 今為下 |
| 天の川白波高し我が恋ふる君が舟出は今しすらしも |
| あまのがは しらなみたかし あがこふる きみがふなでは いましすらしも |
| 巻第十 2065 秋雑歌 作者不詳 |
〔歌意〕
天の川の白波が高いのですが、
わたしの恋しいあなたは、
まさに今、舟を漕いでいるのですね...それで波が立って... |
助動詞「らし」は、ある根拠・理由に基づき、
確信を持って推定する意をあらわすものだ
だから、この用例の二首もそうだが、「らし」と解するのは問題ないと思うが
表記上に「ら」を「訓み添え」る、というのは
この歌の解釈から、それが妥当だ、ということなのだろうか
確かに、日本語を外国文字の表記で完全に表現できるとは思わないが
そうなると、まず歌意からのアプローチというのも
決して軽んじてはならない、ということなのだろう
そう言えば、あまり多くは知らないが、『古義』の鹿持雅澄なども、
その歌意に沿えば、こうなる、というようなことをあったような気がする
我々素人には、歌意から推測する訓も、決してルール違反ではないのだが
正規の研究でも、あることなのだ、と改めて思う |
| |
|
|
| 【歌意1817】 |
巻向の檜原に立ちこめる春がすみ
その春かすみのように、おぼろげで曖昧な気持ちなら
こんなに苦労して、ここまで来たりするでしょうか
|
なるほど、「序詞」をしっかり訳せば、歌意もしっかりするものだ
この歌は、雑歌と仕分けられているが、多くの注釈書では、「相聞的発想の歌」だ、としている
私もそう思う
しかし、何故「雑歌」として、この巻第十の冒頭七首に配されたのだろう
以降の歌は、「詠~」として、鳥や霞、花、柳などと仕分けられているのに...
まあ、それは研究者の仕事だろうから、私は歌だけを見よう
「巻向」という地名は、奈良に行くと結構有名なところで
纏向遺跡など、多くの考古学ファンや古代史ファンも行くところだが
こと『万葉集』に限っては、それほどでもないらしい
この『万葉集』中での、「巻向」の地を詠んだ歌は十二首あるが、
そのうち十一首は「柿本人麻呂歌集非略体歌であり、
残りの一首も、作者不詳の「問答歌」の「答歌」の方で詠まれているだけだ
そこから思うのが、「巻向」という地と柿本人麻呂の関係だろう
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕の解説の中で、次の説を紹介している
武田祐吉氏は、
「弓月が岳を詠んだ歌二首を含めて巻向弓月方面が人麻呂歌集に特有の方面である」と指摘し、「その表現内容から巻向山が亡き妻に関係ある山である」〔『国文学研究 柿本人麻呂歿』〕
と述べ、
さらに、これを受けて稲岡耕二氏は、
「巻向の妻の死の体験を経て、人麻呂の歌の動乱調が形成されたことを説いた」
〔「人麻呂における『動乱調』の形成」『万葉集研究』第五集所収〕
言うまでもなく、『全注』はこれらを肯定している
確かに、人麻呂がこの「巻向の地」に格別の想いがあったことは間違いないと思う
ただし、この歌はあくまで「人麻呂歌集歌」の歌であり
そもそも学界が、それらがすべて人麻呂の歌ではないだろう、としているのに
やや人麻呂歌よりの考察ではないかと思う
勿論、他の者が詠おうが、それを自らの歌集に採録したのは人麻呂だろうから
その意味では、「巻向」と「柿本人麻呂」との深い縁というのも頷ける
さて、そうした時代の研究や人麻呂歌集歌の実証的な「考察」はともかく
この歌そのものを、じっくりと鑑賞してみよう
「序詞」でいう、春かすみのように、あなたへの「想い」がおぼろげであるのなら
「なづみこめや」...どうして、こんなに苦労してまで、やって来よう
それは、私の気持ちが、決していい加減なものじゃない、と解ってもらえますね
その「苦労」の程度が、「なづみ」を古語辞典で引いてみるとよく解る
早瀬の川、荒れた原野、豪雪などの歩行に妨げになるような状態で、「行き悩む」こと
「苦労」することの具体的な情況が、この語には詰まっている
勿論、比喩的な言葉だろうが、それほど大変だったのだぞ、と言いたいのだろう
では、そこまで言わせたのは、どうしてなのか、と
何か誤解や不信感を持たれたからではないか
何でもない状況であれば、こんなに苦労してやってきたよ、ですむ
何も「反語表現」で訴えなくてもいい
相手の「歌」が知りたい...
これは、単に叙景を詠む歌ではないはずだ
前の歌〔1816〕(昨日掲載)のような、本物の「春雑歌」というものではない、と思う
「春のかすみ」を単に用いただけの、「相聞歌」なのだから...と、思う
ここで、人麻呂以外で「巻向」を詠んだ歌を載せる
ただし、「問答歌」なので、一組として掲載する
| 問答歌 |
| 久堅乃 雨零日乎 我門尓 蓑笠不蒙而 来有人哉誰 |
| ひさかたの雨の降る日を我が門に蓑笠着ずて来る人や誰れ |
| ひさかたの あめのふるひを わがかどに みのかさきずて けるひとやたれ |
| 巻第十二 3139 問答歌 作者不詳 |
〔歌意〕
こんな雨の降る日なのに、
我家の門に、蓑笠も着けずにやって来るなんて
いったい誰なのでしょう |
| |
| 纒向之 病足乃山尓 雲居乍 雨者雖零 所沾乍焉来 |
| 巻向の穴師の山に雲居つつ雨は降れども濡れつつぞ来し |
| まきむくの あなしのやまに くもゐつつ あめはふれども ぬれつつぞこし |
| 右二首 |
| 巻第十二 3140 問答歌 作者不詳 |
〔歌意〕
巻向の穴師の山には、雨雲がかかっています
その雨に濡れながらも、あなたに逢いにやって来たのです |
こんなに雨降りなのに、傘も持たないでやって来る人は、どんな人なんですか、と問い
巻向の山には雲がかかり雨も降っていますが、それでもやって来ました
早く逢いたい、という気持ちが急くので、笠も持たずに、来たのです、と答える
これが、「問答歌」というものなのだろう
相聞のようで、そのことよりも、一組の歌の掛け合いを目論んでいる
しかし、この歌もまた、実際に当事者同士が同じ場で交したものかどうか...
だから、厳密に言うと、問いに対する「答え」にはなっていない
「誰か」と問いているのに、「雨でも、濡れながら来た私の気持ち」を伝えようとしている
一見、辻褄が合いそうで、やはりちぐはぐだ
もっとも、「問い」が、相手を知っていての「戯れ」の歌であれば
また意味も違ってくるだろうから、むしろそう解釈しなければならない、と思う
まあ、なんて、あなたって人は、こんな雨の中を、蓑も着けないで...
そうなると、今日採り上げた歌〔1817〕歌になるではないか
まさに「なづみこめやも」だ
この作者不詳の「問答歌」、これも人麻呂歌集歌との類想歌とすれば
確かに、その記載はないものの、結局「巻向」十二首は全部「人麻呂歌集歌」になる
私には、そんな気がしてならない
『万葉集』の編者が、「問歌」に見合う「答歌」を探したとき
それにちょうどいい歌が「柿本人麻呂歌集中」にあった
しかし、「答歌」だけを『人麻呂歌集歌出』とは出来ないので、記載しなかった
その可能性もあるのではないだろうか
それほど、人麻呂と深い関わりがある「巻向」といい、「なづむ」的な行動が
どうしても私をそんな風に思わせてしまう
|
|
掲載日:2013.11.25.
| 春雑歌 |
| 巻向之 桧原丹立流 春霞 欝之思者 名積米八方 |
| 巻向の桧原に立てる春霞おほにし思はばなづみ来めやも |
| まきむくの ひはらにたてる はるかすみ おほにしおもはば なづみこめやも |
| 巻第十 1817 春雑歌 柿本人麻呂歌集 |
【注記】〔924〕【左頁】問答歌〔3139・3140〕
| 【1817】語義 |
意味・活用・接続 |
| まきむくの[巻向之] |
| 巻向は奈良県桜井市三輪の東北、車谷から穴師にかけての地 |
| ひはらにたてる[桧原丹立流] |
| ひはら[檜原] |
檜の生い茂っている原 |
| |
奈良時代では初瀬・巻向・三輪の辺りの檜原が有名だった |
| たて[立つ] |
[自タ四・已然形](風や波などが)起こる・立つ・立ち昇る |
| る[助動詞・り] |
[完了・連体形]~ている |
已然形につく |
| はるかすみ[春霞]ここまでが「おほ」を導く序詞 |
| はるかすみ[春霞] |
春の霞・(霞は、微細な水滴が空中に浮遊してかすむ状態) |
| おほにしおもはば[欝之思者] |
| おほに[凡] |
[形動ナリ・連用形]普通だ・おぼろに・通り一遍だ |
| し[副助詞] |
語調を整え、強意を表す |
| 〔接続〕体言または活用語の連体形・連用形、副詞、助詞などにつく |
| おもは[思ふ] |
[他ハ四・未然形]考える・思案する・願う・望む |
| ば[接続助詞] |
[順接の仮定条件]~なら・~だったら |
未然形につく |
| なづみこめやも[名積米八方] |
| なづみ[泥(なづ)む] |
[自マ四・連用形]行き悩む・難渋する・悩み煩う |
| こ[来(く)] |
[自カ変・未然形]来る・行く・通う |
| めや |
[反語の意]~だろうか(いや、~ない) |
未然形につく |
| 〔成立〕推量の助動詞「む」の已然形「め」+反語の終助詞「や」 |
| も[終助詞] |
[感動詠嘆]~よ・~なあ |
種々の語につく |
| 掲題歌トップへ |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [まきむく(巻向)] |
檜の多いところとして知られ、垂仁・景行両天皇の宮殿があったとされる地でもある
古語辞典では、「巻向」は「歌枕」としてあり
そもそも、『万葉集』での「歌枕」という解説書はみたことがなかったので
ついでに、調べてみた
「歌枕」は後の時代の修辞かと思っていたが、そうでもないようだ
簡単に書くと、
「古来繰り返し和歌に詠み込まれ、特定のイメージが固定した諸国の名所」とある
なるほど、「繰り返し」といわれるほどだから、確かに「万葉時代」だけでは
まだその期間や、名所としての認識が薄い時代、ということなのかな
古語辞典での「歌枕」という表現は、後世に「名所」となったことからなのかもしれない
しかし、その「歌枕」の用例をみると、数は少ないが、『万葉集』もあった
「和歌の浦」がそうだ
| 雑歌/〔(神龜元年甲子冬十月五日幸于紀伊國時山部宿祢赤人作歌一首[并短歌])反歌二首〕/右年月不記 但称従駕玉津嶋也 因今檢注行幸年月以載之焉 |
| 若浦尓 塩満来者 滷乎無美 葦邊乎指天 多頭鳴渡 |
| 若の浦に潮満ち来れば潟をなみ葦辺をさして鶴鳴き渡る |
| わかのうらに しほみちくれば かたをなみ あしへをさして たづなきわたる |
| 右年月不記 但称従駕玉津嶋也 因今檢注行幸年月以載之焉 |
| 巻第六 924 雑歌 山部赤人 |
〔歌意〕
和歌の浦に、潮が満ちてくると
干潟がなくなるので、
葦辺を目指して、鶴が鳴き続けている |
この時代の「和歌の浦」が、天皇が行幸するほどだから、景勝地だとは思う
こうして詠われ続け、「歌枕」といわれるようになったのかな
せっかくだから、「枕詞」と「序詞」についても、簡単な説明を載せておく
「古語辞典より」
〔枕詞〕
①ある特定の語句を言い起こしたり、語調を整えたりするために、
その語句の前に用いられる決まった言葉
②古くは実質的な意味を持った修飾語であったものが、形式化し、
意味を失ったもの
③大部分は五音
この「枕詞」については、現在その一覧表を作っている最中で、
中心は、古語辞典の原義の解説だが、もっと詳しい説明に触れれば、随時更新する
〔序詞〕
①ある語句を導き出すために前置きとして用いられる表現で、七音以上からなる
②枕詞と異なり、固定的でなく、作者によって自由に創作される
下の語句の導き方には、大別して三種ある
1、意味の関連で導くもの
2、掛詞で導くもの
3、同音の反復で導くもの
[訳すときの注意点]
序詞は原則として訳すが、その場合「~のように・その~ではないが」などと
語を補って訳すといい
となると、この「序詞」は、研究者によっても解釈は様々だろう、と思う |
| |
| [かすみ]古語辞典「霞と霧の違い」 |
霞は霧とは同じ現象であるが、平安時代ごろから春のものを「霞」、
秋のものを「霧」と区別した
また、遠くにたなびくのを「霞」、近くに立ちこめるのを「霧」と考えた
上代では季節による区別はなく、『万葉集』(8-1532)にみえる「霞立つ天の河原に..」は、秋、陰暦七月の七夕の歌である
|
| |
| [なづみ] |
「なづむ」は、何かに妨げられて思うように進まない状態をいう
水・雪・草などに歩行を妨げられて苦労するのに多く用いられる |
| |
|

|
| 【歌意1818】 |
いにしえの人が植えたであろう、あの杉の木枝に
かすみが、たなびいている
もう春が来たということだろう
|
この歌が、表面的な叙景歌であるはずがない
あまりにも、端的過ぎる
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕に、面白い解釈があった
「古への人の植ゑけんとは、唯だ年経りたるを言ふのみ」と
しかし、何のための「長き年月」の比喩なのだろう
その「老木」に「かすみがたなびい」て、春がきたと予感するものだが
「老木」である必然性もない
さすがに、『略解』の解釈は一般的ではないらしく
『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕の、
「この山に杉を植ゑることが、古来行われたものであらう」や、
『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕の、
「文字通りに古人の植ゑたと解すべきである」とする説が通っている
『全釈』は理解できても、『評釈』には説明が充分ではない
要は、言葉通りの叙景歌として鑑賞すべきか、ということなのだろうか
しかし、「歌」が「歌」であるためには
詠じた作者が、確かに感動したもの、心を揺さぶられたものがあるはずだ
単に、目の前の事実を「言葉」にしただけでは、「歌」ではなくなる
それは、「記録」ではないか
私も、考えてみた
この歌は、作者が何に感じ入ったものなのか、と
「老木にかすみがたなびく」ことが、そうなのか
あるいは、「春がきたのだなあ」という感慨なのか
「老木」...この杉の木は、古人が植えたものだろう、とする「老木」
その「よわい」を、作者自身に重ねることができるのではないか
こんな「老木」にも「春の兆し」が舞い降りている
もう自分の人生は、このまま死期を待つだけの身になっているのに
何としたことか、また「春を迎えること」が出来るではないか
「まるで私のような老木にも、まだまだ生きながらえさせてくれるのだなあ」
そう感じることが出来れば、単に叙景的な歌だと思うのではなく
その中に、「春の芽吹き」までも作者は感じたはずだ
そして、これなら「老木」である必然性が生かされる
いや、作者にまったくそんな気持ちはなくても、
この歌に接した私は、そう感じることができる
自身に重ね置いて...
歌の「技巧的」な点からすれば、
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕で、このように述べている
「事実として老杉であるのを、『古の人が植ゑけむ』と、人事的に、しかも遠い古にまでも溯り得る物に云ひかへ、それと今年の春のしるしとして新たに現れてきた霞とを結び合わせてゐるのは、これまた対照法を用ゐて悠久な時の気分を絡ませようとしたのである」としている
一見、私の感じたことと同じだ、と思ったが
そうでもなかった
この解釈は、あくまで「いにしへと現代」を絡ませ、
作者が「悠久」の姿を表現させようとしたもの、という意味ではないか
その意味では、これも単に叙景的なこの歌の「文字面」で理解できる
ただ、何故「老木」なのか、の点に於いては、私も同じだ
そして、作者は「感じ入った」ことを「詠んだ」のであって
「歌」として、「名歌」でも残そうとして「詠んだ」のではない、と思う
この時代の歌で、後世に論じられるような「技巧」は、
それほど特出したものはないと思う
今日、長谷寺、室生寺と秋を楽しんできた
一人静かに歩きたかったが、どちらも大勢の人が訪れていて
平日であっても、秋を名残惜しむ人は多いものだ、と感心した
往路は、南阪奈道で橿原、桜井と通じて長谷寺に行ったが
復路では、室生寺からは西阪奈道を通ることになる
しかし、数日前から高速の集中工事が行われており
天理インターからずっと先まで、十数キロの渋滞情報
已む無く、天理から南下して南阪奈で帰ることを選択した
そのおかげで、「巻向」を走りながらではあるが通ることも出来
その国道沿いの「箸墓古墳」も、信号待ちでゆっくり見ることができた
もっとも、「箸墓古墳」には、あまり魅力は感じないが...あんな環境では...これはおかしい
|
|
掲載日:2013.11.26.
| 春雑歌 |
| 古 人之殖兼 杉枝 霞霏□ 春者来良之 □=雨冠の下に微 既出「たなびく」 |
| いにしへの人の植ゑけむ杉が枝に霞たなびく春は来ぬらし |
| いにしへの ひとのうゑけむ すぎがえに かすみたなびく はるはきぬらし |
| 巻第十 1818 春雑歌 柿本人麻呂歌集 |
| 【1818】語義 |
意味・活用・接続 |
| いにしへの[古] |
| いにしへ[古] |
遠く過ぎ去った世・ずっと昔・過去・昔 |
| の[格助詞] |
[連体修飾語]~の・~である〔接続〕体言、体言に準ずる語 |
| ひとのうゑけむ[人之殖兼] |
| うゑ[植(う)う] |
[他ワ下ニ・連用形]植物の種子や根を土に埋める・植える |
| けむ[助動詞・けむ] |
[過去の推量・連体形]~ただろう |
連用形につく |
| すぎがえに[杉枝] |
| すぎがえ[杉枝] |
杉の枝 |
| に[格助詞] |
[相手・動作の対象]~に |
体言につく |
| かすみたなびく[霞霏□]□=雨冠の下に微 既出「たなびく」 |
| はるはきぬらし[春者来良之] |
| き[来(く)] |
[自カ変・連用形]来る・行く・通う |
| ぬ[助動詞・ぬ] |
[完了・終止形]~てしまう・~てしまった |
連用形につく |
| らし[助動詞・らし] |
[確信の推定・終止形]~にちがいない |
終止形につく |
| 掲題歌トップへ |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [いにしへ] |
ナ変動詞「往(い)ぬ」の連用形「いに」に、過去回想の助動詞「き」の連体形「し」、
それに名詞「方(へ)」が修飾されて「体言」を構成する
「遠く過ぎ去った時代」をいう
自分の過去の経験をいう「むかし」に対して、
遥かに遠い過去をいうことが多いが、自分と係わった過去の人や事をいうこともある |
| |
| [うゑ] |
この動詞「植(う)う」は、初めて知った
助動詞「けむ」が連用形に接続することから
「うゑ」は、連用形だとは予測はできたが、その「うゑ」が、古語辞典で引けなかった
「うゑる」と、引いてみたり、「う」と引いてみたり...
しかし、「う」と引いたとき、「うう」とあった
「ワ行の下二段動詞」に初めて出合った
まだまだこうした出合いが楽しめるのも、古語辞典ならではのことだ
というか、私自身が、まだまだ追いついていない、ということだ
古語を古語辞典で引くとき、結構こうした例はある
語句は解っていても、その元の「語」を知らなければ、探せない
以前、「~へて」の連用形「経」を古語辞典で探したとき
「へる」だと思ってしまった
よく考えればわかることだが、「へる」が「終止形」だと思い込んでいた
やっと「下二段活用」を思い出し、「経(ふ)」に辿り着いたものだが
こんなことでも、随分手間をかけてしまうので
もっと意義ある手間の掛け方を心掛けなければ、と肝に銘じておく
今回は、たまたま「う」と同頁に「うう」があったので、運が良かった
私の知識、能力なんて、まだまだこんなものだ
ただし、少しずつでも「ため」にはなっている...とは思う
|
| |
| [すぎがえ] |
杉は、人間の生活の場である低地に多いことと通直で木目が通っていて、
軟らかく加工し易いのと、湿地に対する耐久力が大きいので、
縄文・弥生時代を通じて建築・構築材として多く用いられた、とする
(苅住昇「古代のスギの文化」林業技術488号) |
| |
|

|
| 【歌意1819】 |
愛しいあの子が手枕する、その名を抱くような巻向山に
春がきたので
木の葉を押し分けて、霞がたゆたっている
|
早春のおおらかな歌、とされている
しかし、なかなか...じっくり眺めないと、そのおおらかさは解らない
私は、かなり意訳したつもりだが
それでも、まだ「歌意」を充分なぞることは出来ないと思っている
「巻向山に春霞がかかる」風景描写と、歌の字面では捉えるだろうが
仮に、その「春のおおらかな叙景歌」であれば、まさに「歌の言葉通り」だろう
しかし、右頁の「注記」を書いているうちに、
「しのぐ」という言葉が、もっと意味を持つのではないか、と思うようになってきた
つまり、「このはしのぎて」のことだ
「木の葉を押し分けて」というのは、春霞が木の葉の上一面に覆い、たなびく描写だが
もう一つの「想い」は、重ならないだろうか
日本語の「しのぐ」ではなく、原文の「凌」には、「侵犯する、押し退ける」との意味もある
春霞が、木の葉の領域を侵犯して、覆い被さる様...
どうも「春かすみ」という語感と、「凌」の語感とが私にはマッチしない
本来であれば、「春かすみ」と協調するはずの「おおらかな」春の情景が
「凌」という「文字」を使うことで、何か挑むような「気持ち」を持たされてしまう
極端な言い方をすれば、
「とうとう春がきたのか」「きてしまったのか」とでもいうような...
こんな風に感じれば、捻くれ者になるだろうが、
しかし、普通に...私なりに普通にこの歌を読むとき、いや目にするとき
やはり「凌」、「そのぐ」は言葉が「乱暴」に思えてしまう
仮に、その感じ方を進めるとすれば
いったい、どんな「詠歌」になるだろう
そもそも、この「巻向」も、あるいは「こらがてを巻向山」という語は
人麻呂特有のものだと知ったばかりだ
そして、彼のこだわり続けた「巻向」は...
「かすみ」が、「たなびく」のは、何か不吉な予兆のようなものを感じたのかもしれない
ふと、そんな想いに捉われた
人麻呂の時代とは、決して穏やかな時代ではなかったはずだ
勿論、「人麻呂歌集」の歌が即人麻呂作とはまだ限らないが
少なくともこの時代を時に客観的に、時に当事者の一人として歌を詠む歌人人麻呂
ある拘りをこめて詠じる歌に、何かの深い「想い」が籠められていやしないか
そんなことを想いながら...春の「かすみたなびく」ではなく
その前の句、「このはしのぎて」と一緒に「想い」を馳せてみたい
まだまだ、そこの「深い想い」にまでは到達できないが
しばらく続く、人麻呂歌集の鑑賞の中で、少しでも知ることができれば、と思う
|





|
掲載日:2013.11.27.
| 春雑歌 |
| 子等我手乎 巻向山丹 春去者 木葉凌而 霞霏□ □=雨冠の下に微 既出「たなびく」 |
| 子らが手を巻向山に春されば木の葉しのぎて霞たなびく |
| こらがてを まきむくやまに はるされば このはしのぎて かすみたなびく |
| 巻第十 1819 春雑歌 柿本人麻呂歌集 |
【注記】〔904・3340〕〔1097・1272〕〔2170〕〔1659・1613〕
| 【1819】語義 |
意味・活用・接続 |
| こらがてを[こらがてを]〔枕詞〕「巻向山」にかかる |
| 愛しい女性の腕を巻く(枕にする)意から、その同音を含む「巻向山」にかかる |
| まきむくやまに[巻向山丹] |
| 三輪山の東方やや北寄りに位置する山・その最高峰を「弓月が岳」という |
| 「こらがてを まきむくやま」の表現例 |
| はるされば[春去者] |
| され[去る] |
[自ラ四・已然形](季節や時を表す語について)近づく・来る |
| ば[接続助詞] |
[順接の確定条件]~ので・~だから |
已然形につく |
| このはしのぎて[木葉凌而] |
| しのぎ[凌ぐ] |
[他ガ四・連用形]押さえつける・押しふせる・踏みしだく |
| て[接続助詞] |
[単純接続]~て・そして |
連用形につく |
| かすみたなびく[霞霏□ □=雨冠の下に微 既出「たなびく」] |
| 掲題歌トップへ |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [こら] |
「子ら」には、「子ども」をいう場合や、年少の者、目下の者に呼びかける場合もあるが、男が女を親しんでいう場合が多い
その場合の「ら」は、親愛の情けを籠めた接尾語
| 〔(老身重病經年辛苦及思兒等歌七首 [長一首短六首]〕反歌 |
| 周弊母奈久 苦志久阿礼婆 出波之利 伊奈々等思騰 許良尓佐夜利奴 |
| すべもなく苦しくあれば出で走り去ななと思へどこらに障りぬ |
| すべもなく くるしくあれば いではしり いななとおもへど こらにさやりぬ |
| (天平五年六月丙申朔三日戊戌作) |
| 巻第五 904 山上臣憶良 |
〔歌意〕
どうしようもないほど苦しくて仕方ないので
この状況から逃げ出してしまいたいと思うのだが、
この子らに邪魔されてしまって... |
【こら(許良)】小学館新編日本古典文学全集万葉集による
原文「許良」の「許(こ)」は、乙類の「こ」に当る
「子等」と解するには、「子」の「こ」が甲類であるべき点に疑問があり、
「こ」の甲乙の発音の別は平安初期まで守られていた
「これ・ここ・この」などの「此」は乙類で、
作者は傍らの「子等」をさして、「こいつら」といった説
|
| |
| 挽歌 |
| 礒城嶋之 日本國尓 何方 御念食可 津礼毛無 城上宮尓 大殿乎 都可倍奉而 殿隠 々座者 朝者 召而使 夕者 召而使 遣之 舎人之子等者 行鳥之 群而待 有雖待 不召賜者 劔刀 磨之心乎 天雲尓 念散之 展轉 土打哭杼母 飽不足可聞 |
| 礒城島の 大和の国に いかさまに 思ほしめせか つれもなき 城上の宮に 大殿を 仕へまつりて 殿隠り 隠りいませば 朝には 召して使ひ 夕には
召して使ひ 使はしし 舎人の子らは 行く鳥の 群がりて待ち あり待てど 召したまはねば 剣大刀 磨ぎし心を 天雲に 思ひはぶらし 臥いまろび ひづち哭けども 飽き足らぬかも |
| しきしまの やまとのくにに いかさまに おもほしめせか つれもなき きのへのみやに おほとのを つかへまつりて とのごもり こもりいませば あしたには めしてつかひ ゆふへには めしてつかひ つかはしし とねりのこらは ゆくとりの むらがりてまち ありまてど めしたまはねば つるぎたち とぎしこころを あまくもに おもひはぶらし こいまろび ひづちなけども あきだらぬかも |
| 右一首 |
| 巻第十三 3340 挽歌 作者不詳 |
〔歌意〕
大和の国でも、どうしてこのようなところへお隠れになってしまわれたのか
朝には君に召し使え、夕べには召してお使いになった舎人たちは
そろってみなが、ずっとお待ちしているが、
いっこうにお呼びがかからないので
いつも献身的で、忠実であった気持ちを、今は天雲のかなたにかなぐり捨て、
身を震わせ、のたうちまわって泣くのですが
それでも、少しも気はやすまらないのです |
この例歌での「こら」は、子ども、もしくは年少の者たちや、目下の者たちの用例 |
| |
| [こらがてを まきむくやま] |
この表現も、「柿本人麻呂歌集非略体歌」にのみ見える
「巻向」が人麻呂の「ことば」であるから、当然と言えばそうだが...
| 雑歌/詠山 |
| 三毛侶之 其山奈美尓 兒等手乎 巻向山者 継之宜霜 |
| 三諸のその山なみに子らが手を巻向山は継ぎしよろしも |
| みもろの そのやまなみに こらがてを まきむくやまは つぎしよろしも |
| (右三首柿本朝臣人麻呂之歌集出) |
| 巻第七 1097 雑歌 柿本人麻呂歌集 |
〔歌意〕
三輪山のその山並みに、
まるで愛しい子の手枕をしているかのような姿の巻向山は
その連なり具合が、何ともいえずいいものだ |
| |
| 雑歌/就所發思 |
| 兒等手乎 巻向山者 常在常 過徃人尓 徃巻目八方 |
| 子らが手を巻向山は常にあれど過ぎにし人に行きまかめやも |
| こらがてを まきむくやまは つねにあれど すぎにしひとに ゆきまかめやも |
| (右二首柿本朝臣人麻呂之歌集出) |
| 巻第七 1272 雑歌 柿本人麻呂歌集 |
〔歌意〕
愛しい子の手枕のような姿の巻向山は、
このようにずっと変わらずにあるが
亡くなった人に逢いに行って、手枕をすることが出来るだろうか... |
この「こら」は、前項の用例の「こら」とは違って
多くの歌に見られ男が女を親しんでいう場合にあたる
何故なら、「巻向山」を引きだすのに、
「子らが手を」という枕詞の「原義」そのままに説明できるからだ
さらに言えば、同じ語感での「歌」が浮ぶ
ただし、この用例歌は、「枕詞の原義」ではなく、
「枕詞の同音」から引き出せるもの
| 秋雑歌詠鳥 |
| 妹手呼 取石池之 浪間従 鳥音異鳴 秋過良之 |
| 妹が手を取石の池の波の間ゆ鳥が音異に鳴く秋過ぎぬらし |
| いもがてを とろしのいけの なみのまゆ とりがねけになく あきすぎぬらし |
| 巻第十 2170 秋雑歌 作者不詳 |
〔語義〕
「いもがてを」は、『万葉集』中に二首しかない「枕詞」であり、
その原義は、「妹の手を取る」の意からで、
その同音が含まれる地名〔現大阪府高石市取石(とりいし)〕の、
「取石(とろし)」にかかる
「こらがてを」と較べて、その意味合いには同じところがあると思う
|
〔歌意〕
あの娘の手を取った「取石の池」の波間から聞こえる
鳥の鳴き声がいつもとは違っているようだ
もう秋は過ぎ去ったということなのだろう |
|
| |
| [凌] |
「しのぎ」の仮名表記例として、
| 冬相聞 / 三國真人人足歌一首 |
| 高山之 菅葉之努藝 零雪之 消跡可曰毛 戀乃繁鶏鳩 |
| 高山の菅の葉しのぎ降る雪の消ぬと言ふべくも恋の繁けく |
| たかやまの すがのはしのぎ ふるゆきの けぬといふべくも こひのしげけく |
| 巻第八 1659 冬相聞 三国真人人足 |
〔歌意〕
高山の菅の葉を押さえつけるように降る雪でさえも
やがて消えてしまうのに
わたしもいっそのこと死んでしまいたいと...
この恋のしげき苦しさには... |
| |
| 秋相聞/丹比真人歌一首 [名闕] |
| 宇陀乃野之 秋芽子師弩藝 鳴鹿毛 妻尓戀樂苦 我者不益 |
| 宇陀の野の秋萩しのぎ鳴く鹿も妻に恋ふらく我れにはまさじ |
| うだののの あきはぎしのぎ なくしかも つまにこふらく われにはまさじ |
| 巻第八 1613 冬相聞 丹比真人[名闕] |
〔歌意〕
宇陀の野の秋萩を踏みしだいて鳴く鹿も
妻に恋するわたしの激しい気持ちには、及ばないだろう |
この二首では「凌ぐ」の仮名表記例として載せたものだが
〔1659〕は、上三句が「消」を導く序詞として、訳すことができ
菅の葉を「押さえつけるようにして降る雪」でさえも、やがて儚く「消える」となる
〔1613〕は、「秋萩を踏みしだいて鳴く鹿の激しい想いも」、
「私の妻への想いには及ばない」と...
つまり、自分の「気持ち」の「むなしさ」や「激しさ」を
「しのぐ」という言葉を用いてより一層の「強調」表現のように思える
勿論、普通に「しのぐ」という意味を使う歌もあるだろうが
たまたま、この表記例を並べたら...こうなってしまった |
| |
|
|
| 【歌意1820】 |
薄明かりのさす夕暮れなったので、
猟人の持つ弓、その名の「弓月ヶ岳」に
かすみが、かかっている
|
「かすみ」、朝や夕方に、空気中の細かい水滴のため、遠方が「かすんで」見える現象
「かすんで、見える」、それで「かすみ」というのかな
以前、本来は季節的な区別のなかった「霞と霧の違い」を載せたが
季語として成り立ったように、「春は霞」、「秋は霧」という
しかし、また別の区別もあったようだ
遠く広範囲にたなびくものが「霞」
近くに立ちこめるものが「霧」...私には、季節で区別するよりも、この方がいい
夕暮れになったので、「弓月ヶ岳」に「かすみ」がたなびく
まさに、そのままの風景の描写だといえる
もっと読んで味わってみたい
短歌の文字数は「三十一文字」だ
とても少ない文字数だといえる
もっとも、俳句は「十七文字」で、もっと少ないが...
確かに、人が感じた「想い」を、言葉が少ないからと言って「尽していない」とは言えない
どんなに少ない文字数からなる「言葉」でも、人の感動や感情は表現できる
感嘆詞などそのいい例だ
ただ、その後から説明がついてくるので
感嘆詞だけで、「文章」とはならないだろうが、
私は、それでも「成り立つ」と思っている
本来、何かに感じ入って、それを表現するには
感じた瞬間、感動したその時というのは、声など出ないし
まして筆を持つことも出来ないだろう
ただただ、「立ち尽くす」しかないのではないだろうか
穏やかな光景を目にして、ゆったりと「想い」を廻らせる
それが出来るのは、「感じ入る自分」と、それを客観的に「見詰める自分」がいるからだ
嗚咽しながら、動揺もなく理路整然と言葉をつなぐ...そんなこと出来るだろうか
この歌のように、確かに目の前の「春の夕暮れ」に見惚れてはいようが
実際は、そんな自分の姿を見て、もう一人の「自分」が詠わせているのではないか
先ほど書いた、限られた少ない文字数で「感動」を表現するのに
私なら、感嘆詞だけでも一言発して終るだろうが、
それでは「歌詠み」の名がすたる、とでもいうように、言葉を紡ぐ
本来は、そんなに必要のない「言葉」なのかもしれない
だから、「枕詞」が「二つ」も組み入れられているのが、
まさに、私が感じたような「実情」ではないか、と思った
「枕詞」では、その語義を解するものもあれば、
語調を整えるだけのものもある
それにしても、「三十一文字」の中に、「十文字」を差し込むのは
普通に考えれば、もったいないことだと思う
しかし...「言葉が出なかった」のだと思えば、それも理解できる
「玉かぎる」、この枕詞が気に掛かっている
そもそも、「玉かぎる」を枕詞としたとき「かぎる」は「微かな光を発する」とされる
しかし「かぎる」を単独で調べても、どこにもその「意」には出合わない
現代でも通じるように「限定」の意味が載せられている
ではなぜ「玉かぎる」が、「玉のほのかに光る」意から、
「夕・日・ほのか」などに掛かるのだろう
原文の「玉蜻」...この「蜻」は、なぜ「かぎる」なのか、と不思議に思う
古語辞典でも、「かぎる」を引いたら、その直後に「陽炎(かぎろひ)」と続いていた
その項目の意味合いは、「明け方にさし始める光・曙光」とある
これではないのか、と思わず「かげろう」を変換してみる
すると、「陽炎」の他に「蜻蛉」とも候補が出る
そこから来たのだろうか...「蜻」、今度明日香で調べてみよう
|
|
掲載日:2013.11.28.
| 春雑歌 |
| 玉蜻 夕去来者 佐豆人之 弓月我高荷 霞霏□ □=雨冠の下に微 既出「たなびく」 |
| 玉かぎる夕さり来ればさつ人の弓月が岳に霞たなびく |
| たまかぎる ゆふさりくれば さつひとの ゆつきがたけに かすみたなびく |
| 巻第十 1820 春雑歌 柿本人麻呂歌集 |
【注記】〔4364〕〔1091〕
| 【1820】語義 |
意味・活用・接続 |
| たまかぎる[玉蜻]〔枕詞〕「夕・日・ほのか・はろか・磐垣淵(いわかきふち)」にかかる |
| 「かぎる」は、「微光を発する」の意で、「玉」のほのかに光る状態から |
| ゆふさりくれば[夕去来者] |
| さり[去る] |
[自ラ四・連用形](季節や時を表す語について)近づく・来る |
| くれ[来(く)] |
[自カ変・已然形]来る・行く・通う |
| ば[接続助詞] |
[順接の確定条件]~ので・~だから |
已然形につく |
| さつひとの[佐豆人之]〔枕詞〕「弓」にかかる |
| 「さつ人」は猟師のことで、弓を使うことから「弓」にかかる |
| ゆつきがたけに[弓月我高荷] |
| ゆつきがたけ[弓月ヶ岳] |
巻向山の主峰 |
| かすみたなびく[霞霏□ □=雨冠の下に微 既出「たなびく」] |
| 掲題歌トップへ |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [さつひと] |
原文「佐豆人」の「豆(つ)」は一般に濁音「づ」に用いるが、
清音の用例もある
| 防人歌/(天平勝寳七歳乙未二月相替遣筑紫諸國防人等歌) |
| 等知波々江 已波比弖麻多祢 豆久志奈流 美豆久白玉 等里弖久麻弖尓 |
| 父母え斎ひて待たね筑紫なる水漬く白玉取りて来までに |
| とちははえ いはひてまたね つくしなる みづくしらたま とりてくまでに |
| 右一首川原虫麻呂 ( / 二月七日駿河國防人部領使守従五位下布勢朝臣人主實進九日歌數廿首 但拙劣歌者不取載之) |
| 巻第二十 4364 防人歌 川原虫麻呂 |
〔語義〕
「とち」は「父」の訛り
「え」は、呼び掛けを示す助詞「よ」の訛り
「いはひて」は、身の穢れを払って
「みづくしらたま」は、水に浸っている真珠の玉
「とりてくまでに」は、取ってくるまでに |
〔歌意〕
父よ、母よ
斎戒して無事を願っていておくれ
筑紫の水底にある「真珠」を
土産として持って帰るまでは... |
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕は、これを「漢音」によったものか、
としている
|
| |
| [ゆつきがたけ] |
この「弓月ヶ岳」も他の表記例は、
| 雑歌/詠雲 |
| 痛足河 々浪立奴 巻目之 由槻我高仁 雲居立有良志 |
| 穴師川川波立ちぬ巻向の弓月が岳に雲居立てるらし |
| あなしがは かはなみたちぬ まきむくの ゆつきがたけに くもゐたてるらし |
| (右二首柿本朝臣人麻呂之歌集出) |
| 巻第七 1091 雑歌 柿本人麻呂歌集 |
〔語義〕
「痛足川(あなしがは)」は、
奈良県東北部、穴師山(あなしやま)と三輪山との間を西に流れ
「かはなみたちぬ」、川波が立ってきた
「くもゐたてるらし」〔注〕
初瀬川に入る巻向川の穴師辺りでの称 |
〔歌意〕
穴師川に、川波が立ってきた
巻向山の弓月ヶ岳に、雲が湧き立っているに違いない |
〔注〕「くもゐたてるらし」
原文はほとんどの古写本に「雲居立有良志」とあり
『神宮文庫本』『仙覚寛元本』系の諸本にのみ「有」がない
その場合の訓は、「くもゐたつらし」と当時訓じていた「抄出本」に合わせた
二次的本文と思われている
同一行の音節が連続すると約音化する例は、類例も少なくない |
| |
|

|
| 【歌意1821】 |
あの娘が、帰り際の私の言葉を、そのまま言って
「今朝は帰って行くが、また明日来よう」と...
そのように愛らしく言うあの娘の「朝妻」山に、かすみがたなびいている
|
この歌の訓が、定訓とするものがないようで
そのため、第二句、三句の訓じ方で、歌の解釈が大きく変わってしまう
訓の違いで、歌そのものの「誰の気持ち」なのかまで変わるのは、
珍しいのではないかと思う
私は、この訓をまず「語感」から自然に感じられたが
それで窮してしまった
「きなむ」としたため、「また来よう」という意思表示をしたのは「誰?」と
家を出て、帰っていく「人」が、「言い残した言葉」とするのが普通だが
そうなると、帰って行くのは「女」になる
この訓で、何気なく読んでいると、確かにそうだ
霞のたなびく、あの山の彼方へ帰って行く女...そんな光景も、確かに悪くはない
男は、未練たらしく、その女を見送り...霞のたなびく「朝妻山」に目を遣る...
その方向へ、女は帰って行く...
しかし、当時の「通い婚」の背景で読むと
この訓に従えば、この「言い残した言葉」を、
見送りがけに門のところで、女が男の真似をして呟き
「忘れないでね、約束ですよ」と微笑んでいるように感じることも出来る
相手の意に擬えて詠む歌は、結構ある
これも、その一首なのかもしれない
そして、そのようにこの歌を読み返してみると...
この女性が、とても魅力的で茶目っ気のある女性に思えてしまう
だから、男は...「朝妻山」の春霞を見るように、ほのぼのとした心地で歩きだす
多くの諸注にあるように、「こね」とすれば
それはそれで、朝帰って行く男を見送り、「明日も来てね」ということだ
こうした歌の方が、すんなり胸に染み込むが...
女性の「魅力」を引き出しているのは、間違いなく「きなむ」と訓じた方だ
こんな風に『万葉歌』を、当時の詠者は、
後世のさまざまな人たちが、あれやこれや、と
いやこうだ、こうに違いない、とか騒ぎながら鑑賞しているなど
決して思ってはいなかったことだろう
でも、それは仕方ないことだ
発する言葉が、そのまま自国の文字で...自分たちの文字で残せなかった時代のこと
だから、勘弁してもらうしかないだろう
このように、長い間、しかも現代においてさえも、その歌の「本当のこころ」には及ばない
それを承知の上で鑑賞するしかないのが、『万葉集』だということなのだから...
この歌は、随分と手間取ってしまった
解釈そのものよりも、その解釈の基になる「訓」に、確認すべきことが多くあった
この歌を、仮に翌日が休日ではなかったら...
そう思うと、またまた運の良さを感じる
少し前までは、任意に『万葉歌』を選んでいた
朝の通勤電車が、その作業の場となっていたが
今は、巻別にある程度の歌順を意識している
少なくとも、毎朝歌を選ぶ手間が省け、いきなり、準備の段取りに入れる
毎晩の限られた時間の中で、毎日続けようと思えば...少しでも、効率をよくしないと...
しかし、この歌のように一見何気ない歌でも、
非常に手ごわい「歌」もあり得る
今後、平日でこんな場合には、どうしよう...
また新たな悩みを抱えてしまった
|







 |
掲載日:2013.11.29.
| 春雑歌 |
| 今朝去而 明日者来牟等 云子鹿丹 旦妻山丹 霞霏□ □=雨冠の下に微 「たなびく」 |
| 今朝行きて明日は来なむと云子鹿丹朝妻山に霞たなびく |
| けさゆきて あすはきなむと いひしこが あさづまやまに かすみたなびく |
| 巻第十 1821 春雑歌 柿本人麻呂歌集 |
【注記】〔62・182・2129・2524・130・2368・4101〕〔874・2360〕
| 【1821】語義 |
意味・活用・接続 |
| けさゆきて[今朝去而] |
| けさ[今朝] |
今日の朝・今暁 |
| ゆき[行く] |
[自カ四・連用形]進み行く・去る・時が移り行く |
| て[接続助詞] |
[単純接続]~て・そして |
連用形につく |
| あすはきなむと[明日者来牟等] |
| あす[明日] |
今夜が明けて迎える日・あすの日・ごく近い将来 |
| き[来(く)] |
[自カ変・連用形]来る・行く・通う |
| なむ |
[強い意志]~てしまおう・~しよう |
連用形につく |
| 〔成立〕助動詞「ぬ」の未然形「な」+助動詞「む」 |
| と[格助詞] |
[引用]~と |
| 「~と言って・~として」などの意で、後に続く動作などの状況、理由を示す |
| いひしこが[云子鹿丹] ここまで〔序詞〕 |
| し[副助詞] |
語調を整え、強意を表す |
| 〔接続〕体言または活用語の連体形・連用形、副詞、助詞などにつく |
| あさづまやまに[旦妻山丹] |
| あさづまやま[朝妻山] |
奈良県御所市朝妻の地、金剛山の東麓にあたる |
| かすみたなびく[霞霏□ □=雨冠の下に微 既出「たなびく」] |
| 掲題歌トップへ |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [けさ・あす] |
此(コ)の転の「き」と、アサ(朝)との複合語の約か、とされている
『万葉集』中の「今朝(けさ)」の用例は、十首ほどあるが、
「けさ」という古語が、どうしても馴染めない
実際、手持ちの古語辞典を引いても、幾つかの辞書にはあるが、載っていない辞書もある
さらに、簡単に「今日の朝」とだけ説明している
取り立てて「古語辞典」に載せるほどの言葉でもない、ということなのか
岩波の古語辞典では、結構詳しく解説されているのが〔あす〕
「あす」は、中世以後次第に「あした」と併用されるようになった
asa(朝)、asita(朝)、asu(明日)、asate(明後日)に共通する「as」は、
「夜明け」を意味した語根であろう、としている
|
| |
| [あすはきなむと いひしこが] |
この第二句と三句には定訓がなく、難訓とされている
底本には、掲題のように「明日者来牟等云子鹿丹」とあるが、
『元暦校本』に「明日者来牟等云子鹿」とあり、「丹」が除かれている
ここでは、それに拠る
『元暦校本』は、「あすはこむといふしかすかに」
『西本願寺本』は、「あすはきなむといふこかに」
『元暦校本』の「鹿」は「庶」に紛らわしいが、同書の他の「鹿」の用字例に照らして
「鹿」と見做されている
この二句の「訓」も定訓がないだけあって、いろいろとある
『万葉代匠記(初稿本)』〔契沖、貞亨四年(1687)成〕「あすはこむと いふこかに」
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕、
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕、
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕「あすはきなむと いふこかに」
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕「あすはきなむと いひしこが」
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕「あすはこむちふはしけやし」
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕、
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕「あしたはこねと いひしがに」
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕「あすにはこねと いひしこを」
『万葉集校注』〔伊藤博・角川文庫、平成10年第18版〕「あすにはこねと いひしこが」
『難語難訓攷』「あすにはこねといふ こらがなの」
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37成〕「あすはこねと」第三句無訓
『塙書房』・『日本古典文学全集』〔小学館、昭和50年成〕「あすはこむと」第三句無訓
『桜楓・旺文社文庫』「あすはきなむと」第三句無訓
これほどの「訓」があり、更に第三句「云子鹿丹」を訓じ難いとする諸注もある
『難語難訓攷』は、「明日者来牟等云 子鹿丹」と特徴的な訓ををつけている
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕は、
「いふこかに」「いふしがに」は原文に沿った訓とするが、
下句との意味の繋がりが曖昧とする
そして、充分な根拠はないものの「丹」の字のない『元暦校本』に従って、
「いひしこが」と訓む
私も、この訓の方がこの歌全体のバランスを取るものだと思う
「いふこかに」では、確かに続く「朝妻山に霞たなびく」では意味を採るのは難しい
これらの用法での解釈の比較をしてみる
| 雑歌/三野連[名闕]入唐時春日蔵首老作歌 |
| 在根良 對馬乃渡 々中尓 幣取向而 早還許年 |
| 在り嶺よし対馬の渡り海中に幣取り向けて早帰り来ね |
| ありねよし つしまのわたり わたなかに ぬさとりむけて はやかへりこね |
| 巻第一 62 雑歌 春日老 |
〔語義〕
「ありねよし」は、「対馬」の枕詞
「ありね」は、高く現れている嶺の意か、という
「ぬさ」は、神に祈願する時、特に旅の平安を祈る時に捧げる品
「取り向く」は、「手向け」として奉ること |
〔歌意〕
嶺の連なる対馬の海路
その海原の海神に幣を捧げ祈るので
一日でも早く、帰ってきてください |
| |
| 挽歌/(皇子尊宮舎人等慟傷作歌廿三首) |
| 鳥グラ立 飼之鴈乃兒 栖立去者 檀岡尓 飛反来年 |
| 鳥座立て飼ひし雁の子巣立ちなば真弓の岡に飛び帰り来ね |
| とぐらたて かひしかりのこ すだちなば まゆみのをかに とびかへりこね |
| 巻第二 182 挽歌 舎人 |
〔語義〕
「とぐら」は、鳥の止まり木、鳥小屋 |
〔歌意〕
鳥屋も造って、飼った雁の雛よ
成長して巣立ったのなら、
この真弓の岡に飛び帰って来いよ |
| |
| 秋雑歌詠花 |
| 春日野之 芽子落者 朝東 風尓副而 此間尓落来根 |
| 春日野の萩し散りなば朝東風の風にたぐひてここに散り来ね |
| かすがのの はぎしちりなば あさごちの かぜにたぐひて ここにちりこね |
| 巻第十 2129 秋雑歌 作者不詳 |
〔語義〕
「あさごち」は、「東風(こち)」で東方から吹いてくる風
東は春に当るとする五行説の影響を受けて、中古以降は春に限って用いられた
「たぐひて」、「たぐふ」は、連れ添う・伴われる、の意 |
〔歌意〕
春日野の、萩が散ったなら、
朝東風の風に添って、ここまで散って来てくれ |
| |
| 正述心緒 |
| 奥山之 真木乃板戸乎 押開 思恵也出来根 後者何将為 |
| 奥山の真木の板戸を押し開きしゑや出で来ね後は何せむ |
| おくやまの まきのいたとを おしひらき しゑやいでこね のちはなにせむ |
| 巻第十一 2524 正述心緒 作者不詳 |
〔語義〕
「奥山の」は、「真木」の枕詞
「まき」は杉・檜の類で、「まきのと」ともいい
男が女に逢いに行く通い路にあるものとして詠まれ
恋の障壁の象徴として、よく使われている
「奥山」は、その「真木」の産地として、枕詞になったのだろう
「しゑや」は、捨て鉢な気分から発する感動詞で、「ええい、くそっ」のように |
〔歌意〕
奥山の真木の戸を押し開けて
ええい、もう出て来ておくれ、
後のことなど、知ったことか |
| |
| 相聞/長皇子与皇弟御歌一首 |
| 丹生乃河 瀬者不渡而 由久遊久登 戀痛吾弟 乞通来祢 |
| 丹生の川瀬は渡らずてゆくゆくと恋痛し我が背いで通ひ来ね |
| にふのかは せはわたらずて ゆくゆくと こひたしわがせ いでかよひこね |
| 巻第二 130 相聞 長皇子 |
〔語義〕
「丹生川」は他にも詠まれるが、その趣は急流だったとされる
「ゆくゆくと」は、どんどん行くことを表す副詞
川の深浅を顧慮せずに直進するさま
「こひたしわがせ」は、弟皇子への親しみをこめた呼称
「わがせ」は、年齢の上下に関わらず親しい間柄の男子への呼称
「いで」は、「いざ」に近いが、それよりも強制する力が強い |
〔歌意〕
丹生の川の瀬など渡らず
さあ、親愛なる弟よ
真っ直ぐに、こちらへ通って来ておくれ |
| |
| 旋頭歌 |
| 玉垂 小簾之寸鶏吉仁 入通来根 足乳根之 母我問者 風跡将申 |
| 玉垂の小簾のすけきに入り通ひ来ねたらちねの母が問はさば風と申さむ |
たまだれの をすのすけきに いりかよひこね
たらちねの ははがとはさば かぜとまをさむ |
| (右五首古歌集中出) |
| 巻第十一 2368 旋頭歌 古歌集 |
〔語義〕
「たまだれ」は、穴を穿った数多くの玉を緒に通して垂したすだれ
「小簾(をす)」は、篠や葦の類を編んで作ったすだれ
「すけき」は、隙間のこと |
〔歌意〕
玉垂れの簾の隙間を通って、入って通って来て下さいね
母に訊かれたら、風でしょう、と応えておきましょう |
| |
| (越中國守大伴家持報贈歌四首)一 答属目發思兼詠云遷任舊宅西北隅櫻樹 |
| 和我勢故我 布流伎可吉都能 佐久良婆奈 伊麻太敷布賣利 比等目見尓許祢 |
| 我が背子が古き垣内の桜花いまだ含めり一目見に来ね |
| わがせこが ふるきかきつの さくらばな いまだふふめり ひとめみにこね |
| (三月十六日) |
| 巻第十八 4101 属目發思 大伴宿禰家持 |
〔語義〕
「ふるきかきつ」は、垣で仕切られた地域
後世「かいと」と呼ばれて共同生活を営む農業中心の村落をさすように変化するが、
古くは個人の住宅地の、かなり広域を占めるものをさした
「ふるき」というのは、かつて「池主」が住んでいたので、そう呼ぶ
「ふふむ」は、花がまだ開かないで蕾のままの状態を保つことをいう |
〔歌意〕
あなたが以前住んでいた館の桜花
いまだに蕾のままですが、一度見においでください |
これらの「来ね」の用例から、
「来牟」と「来年」が、その「牟・年」字の似ているので、
「来牟」を「来年」と見做して訓じてでもいるかのような気もする
実際に、以上の用例歌は「こね」と訓じ、異訓もないことから
「こね」とする語釈も通じるのだろう
しかし、「こね」とすると、
その意味は、用例でも解るように、「ね」を希求の終助詞としており
相手に、求める気持ちで詠われている
だから、この掲題歌を「こね」と訓じるならば、当然「希求」の気持ちとなる
しかし、「きなむ」とすると、また意味が違う
「きなむ」は、「来よう」という「意志」が表れている
その用例を載せてみる
| (憶良誠惶頓首謹啓 / 憶良聞 方岳諸侯 都督刺使 並依典法 巡行部下 察其風俗 意内多端口外難出 謹以三首之鄙歌 欲寫五蔵之欝結 其歌曰) |
| 毛々可斯母 由加奴麻都良遅 家布由伎弖 阿須波吉奈武遠 奈尓可佐夜礼留 |
| 百日しも行かぬ松浦道今日行きて明日は来なむを何か障れる |
| ももがしも ゆかぬまつらぢ けふゆきて あすはきなむを なにかさやれる |
| 天平二年七月十一日 筑前國司山上憶良謹上 |
| 巻第五 874 雑歌 山上臣憶良 |
〔語義〕
「ゆかぬ」、この第二句の「行く」は、時間が経過する意
大宰府のあった二日市から玉島川河口の浜崎まで、約六十キロ、
その頃の行程で、一日半の道のりだとされてる
「さやれる」の、「さやる」の意は、妨げること |
〔歌意〕
「百日」も、そんなにかからない松浦路は、
今日行って、明日には帰って来られるというのに
何が邪魔して、行けないのでしょう |
| |
| 旋頭歌 |
| 狛錦 紐片叙 床落邇祁留 明夜志 将来得云者 取置待 |
| 高麗錦紐の片方ぞ床に落ちにける明日の夜し来なむと言はば取り置きて待たむ |
こまにしき ひものかたへぞ とこにおちにける
あすのよし きなむといはば とりおきてまたむ |
| (右十二首柿本朝臣人麻呂之歌集出) |
| 巻第十一 2360 旋頭歌 柿本人麻呂歌集 |
〔語義〕
「高麗錦」は、赤地錦の類か、という
「高麗」は高句麗ともいい、現在の中国の東北地方南部から、朝鮮半島北部にかけ、
その地域にかつて存在した国の名
668年に滅亡したが、その文化は日本古代文化に大きく影響を与え、
「高麗」の名は、その様式を受け継いだ高級工芸品に冠して用いられた
この歌での用字は、七夕伝説の異国情緒を醸し出すものか、と言われている
「かたへ」は、一対あるものの、片一方をいう
「あすのよし」は、この場合「日没時」が一日の始まりとするので、「今夜」 |
〔歌意〕
高麗錦の紐が片一方、床に落ちていました
今夜にも、来ると仰るのなら、
大事に取り置き、お待ちしています |
このように「きなむ」という用例は、「意志」がこめられる
この掲題歌で、来る、という「意志」を持つのは... |
| |
|
|
| 【歌意1822】 |
いとしいあの娘の名に結びつけたら、まさにふさわしい「朝妻」
その「朝妻」の名を引く「朝妻山」の切り立った斜面に
かすみが、たなびいている
|
柿本人麻呂歌集で、続く「朝妻山」の歌
連作かもしれない...
前歌では、漠然と見渡す「朝妻山」の霞
この歌では、その切り立つ崖にたなびく霞を詠う
女の家からの帰り道なのだろうか
たった今、別れてきたばかりなのに、女への想いが、いっそう増して
まるで眼前の朝妻山を、その愛しい女に見据えている
満ち足りた想いと、たとえいっときでも離れ離れになる寂しさを
その「名」で結びつけるようにして、「こころ」を埋めてゆく
いい歌だ
さてこの歌で、巻第十の冒頭歌である「柿本人麻呂歌集」七首
一応、「人麻呂歌集」の一群は、「春相聞」の冒頭の七首までない
「人麻呂歌集」歌が、「夏」を除き、「春・秋・冬」三季の雑歌・相聞の冒頭に置かれている
『柿本人麻呂歌集』には、様々な説があるが
この巻第十を追いかけていくうちに、何か新しいものでも感じられたら、と思う
|

|
掲載日:2013.11.30.
| 春雑歌 |
| 子等名丹 關之宜 朝妻之 片山木之尓 霞多奈引 |
| 子らが名に懸けのよろしき朝妻の片山崖に霞たなびく |
| こらがなに かけのよろしき あさづまの かたやまきしに かすみたなびく |
| 巻第十 1822 春雑歌 柿本人麻呂歌集 |
【注記】〔3809〕
| 【1822】語義 |
意味・活用・接続 |
| こらがなに[子等名丹] |
| ら[接尾語] |
親愛の情を示す 〔接続〕名詞、代名詞につく |
| が[格助詞] |
[連体修飾語・所有]~の〔接続〕体言または連体形につく |
| に[格助詞] |
[相手]~に 〔接続〕体言または連体形につく |
| かけのよろしき[關之宜 朝妻之] |
| かけ[掛け・懸け] |
ことばにかけていうこと |
| の[格助詞)] |
[連体修飾語・資格]~という・~である |
体言につく |
| よろしき[宜し)] |
[形シク・連体形]ふさわしい・すぐれている・好ましい |
| あさづまの[朝妻之] |
| あさづま[朝妻] |
朝妻山・奈良県御所市朝妻の地、金剛山の東麓にあたる |
| かたやまきしに[片山木之尓] |
| かたやまきし[片山崖] |
一つだけ孤立している山の崖・片方だけが切り立つ山の崖 |
| かすみたなびく[霞多奈引「たなびく」] |
| 掲題歌トップへ |
【注記】(諸本諸註釈書の解説は『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~〕拠)
| [なにかけ] |
さすがに岩波の古語辞典、と唸ってしまった
この「名に掛ける」と言う意味の「かけ」を辞書で探したが
ほとんどの辞書は、下二段動詞「かく」しか載っておらず
この歌のように「かけ」とすれば、それは「未然形か連用形」の活用になる
しかし、それでは次の格助詞「の」に接続はできない
格助詞「の」は、体言かそれに準ずる語、つまり活用語の終止形・連体形に接続する
ならば、「かけのよろしき」ではなく、
「かくのよろしき」か「かくるのよろしき」でなければ...
手当たり次第古語辞典を引いたが、どれも「下二段」動詞「かく」しか載っていない
上代では「四段」もあるが、それでも「かけ」活用は合わない
この時点では「名詞」の「かけ」は、「売り掛け」とかの意味でしか目に入らなかった
そこで、いつも困った時の「岩波古語辞典」を持ち出す
この辞典、何しろ大きいので、あまり机上で開きたくないのだが
ここから先に進めないのでは困るから、止むを得ず...
すると、「あった」
動詞「かく」ではなく、下二段動詞「かけ」として...
それもおかしなことだが、確かに動詞「かけ」になっている
そして、同じ見出しで、名詞「かけ」があった
この名詞「かけ」が欲しかったので、やっとこれで進めると...
念のために、あらためて他の辞典で名詞「かけ」をみると...
しっかり「ことばにかけていうこと」とあった
「掛売り」とか「売り掛け」とは別に...
またとんでもない手間をかけてしまった...まだまだ辞書を充分使いこなしていない
「名に掛け」というのは、同じ用例がある
| 雑歌/(昔物有娘子 字曰櫻兒也 于時有二壮子 共誂此娘而捐生挌競貪死相敵 於是娘子戯欷曰 従古来今未聞未見一女之見徃適二門矣 方今壮子之意有難和平
不如妾死相害永息 尓乃尋入林中懸樹經死 其兩壮子不敢哀慟血泣漣襟 各陳心緒作歌二首) |
| 妹之名尓 繋有櫻 花開者 常哉将戀 弥年之羽尓 [其二] |
| 妹が名に懸けたる桜花咲かば常にや恋ひむいや年のはに [其二] |
| いもがなに かけたるさくら はなさかば つねにやこひむ いやとしのはに |
| 既出、〔書庫-1〕 巻第十六 3809 有由縁雑歌 作者不詳 |
〔歌意〕
あの娘の名、桜児と同じ名の桜の花が咲いたなら
わたしは、いつも恋い慕うことだろうか
幾年を重ねても、毎年同じように... |
ただし、掲題歌の「朝妻」は、用例歌の「桜」のように
明確な「名」ではなく、「朝に帰る夫」や「朝に見送る妻」と「朝妻山」を掛けてもいる
|
| |
|
|
 |
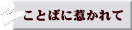  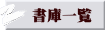  |



































