巻第一から巻第六まで、中に一部、作者未詳の歌も混じっていたが、原則的には作者名の明らかな作品を、雑歌・相聞・挽歌という三大部立の建前を守りつつ、それぞれの部の中で、出来る限り作られた年代という時間の先後に忠実に配列しようとしてきた。この方針は巻第九にも受け継がれており、巻第八も春・夏・秋・冬の四季別という第二の時間基準を組み入れているというだけで、これも作者の名が明らかな巻である。
ところが、おびただしい量の原資料をこのように整然と分類・配列できるものはよいが、作者も(時には男女別も)年代の新古も詠まれた時の背後事情も分からないものについてはなすすべがない。卑近なたとえで言えば、個人の家で何代か前から伝わった和漢洋、種々雑多の蔵書を書架に分類して並べようとしたらまず途方に暮れることであろう。更に砕けた例で言えば、整理されないままに数十年間、放置・山積みされていた家族の大小さまざまな写真をアルバムに貼ろうとしているようなものである。作業半ばで困惑し茫然と立ち尽くすに違いない。万葉集の歌の場合に立ち返って言えば、この巻第七および、巻第十・十一・十二・十三、そして十四のいわゆる作者不明の巻々、六巻は、相似た巻、特色ある巻と仕分けて、今日から見れば、それなりによく分類・配列したもの、と編纂者の労を讃えるべきであろう。
その手始めが巻第七である。内容の上から雑歌・譬喩歌・挽歌に分けられているのは巻第三と似ている。しかし、他巻にも多かれ少なかれその傾向はあるが、その分類が必ずしも正確に守られていず、雑歌の部にも相聞らしい歌があったり、譬喩歌とあるからにはすべて隠喩表現であるべきなのに、実際には「寄物陳思」ともいうべき直喩の歌が混じっていたりして、厳密な意味から言えば分類の不徹底さが目立つ巻である。 |
 |
また、その雑歌は「何を詠む(詠何)」、譬喩歌は「何に寄する(寄何)」というふうに、題材や媒材による類聚方式をとっており、題詞を設けている。譬喩歌はおおむねその原則に従っているが、雑歌では「何を詠む」とはるのは初めの部分の約四分の一で、あとは「吉野にして作る」「山背にして作る」「摂津にして作る」「羈旅にして作る」「問答」「臨時」「所に就きて思ひを発す」「物に寄せて思ひを発す」「行路」「旋頭歌」などと原則を逸脱した配列がなされ、あたかも後続の作者不明の諸巻の分類が円滑になるようにしわ寄せを先取りしたかのごとき形になっている。この雑簒の原因はいろいろ考えられようが、主として原資料における分類の不適切、歌数の偏りによるものではなかろうか。その原資料でも、幾つかあるうち、比較的に年代の古い『柿本朝臣人麻呂歌集』や『古歌集』(『古歌』というのも同じか)の方式になるべく従おうと編纂者は考えたもののように思われる。
その「『柿本朝臣人麻呂歌集』、略していわゆる『人麻呂歌集』は、既に巻第二・三に一首ずつ、これから出たと注記されているが、それら146・245は、それぞれその直前の有間皇子の自傷歌、弓削皇子の早逝予告歌に関連併記したという形で挟み込まれたもので、その前後の時代順に配列された諸歌から浮き上がっている。その点、巻第十三・十四にも人麻呂歌集が三首ずつあるが、3267(3268はそれの反歌)は3264の異伝、3323は3319の異伝で、言わば参考までにあげたに過ぎず、3460・3500の左注に見えるものも、ちなみに示せば『人麻呂集』にはこうなっている、とそれぞれおもて歌との題句の異同を書き入れただけと言ってよく、その意味では、巻第一・二などに、山上憶良の「『類聚歌林』にはこう記されている、と別伝を注してあったのと大差ない扱いである。
しかも巻第七・九・十・十一・十二の五巻に数十首、時に百数十首収められている人麻呂歌集歌は、大部分が原資料からまとめて切り分けられ、貼り継がれたのではないかと思われるばかりである。その原資料の成立過程や人麻呂その人との関係など、今日もなお明らかでない面はあるが、万葉集に収められている状態から推して、これが編纂の際に幾つかあった先行資料の代表として重んぜられ、その分類法が万葉集の典拠とされたらしいことは諸家の一致して認めるところである。この題材・媒材によって類聚するということはもともと中国の一大類書『芸文類聚』などに学んだものであろうが、万葉集のこの巻第七の雑歌や譬喩歌、巻第十一・十二の寄物陳思歌などに見られる物による配列は、中国の類聚方式を受け継いだ『人麻呂集』のそれを踏襲したものと考えられる。
|
この『人麻呂集』に比べると、『古歌集』は歌の数も少なく類聚形式によらなかったと思われるが、この巻第七に関する限り、むしろ『人麻呂集』以上に古い資料だったのではないかと思われる節がある。例えば、次のような事実がそれである。
志賀の海人の塩焼く煙風を疾み立ちは上らず山にたなびく (1250)
右の件の歌は、古集の中に出でたり。
とある。その「右」のさす範囲は諸説があって明らかではないが、その後に、
大穴道少御神の作らしし妹背の山を見らくし良しも (1251)
我妹子と見つつ偲はむ沖つ藻の花咲きたらば我に告げこそ (1252)
君がため浮沼の池の菱摘むと我が染めし袖濡れにけるかも (1253)
妹がため菅の実摘みに行きし我山道に迷ひこの日暮らしつ (1254)
右の四首、柿本朝臣人麻呂が歌集に出でたり。
とある。『人麻呂集』のほうが後に置かれている。その次に「問答」の四首(1255〜1258)と「臨時」の十二首(1259〜1270)を並べたあと、
所に就きて思ひを発す 旋頭歌
ももしきの大宮人の踏みし跡所 沖つ波来寄せざらましを (1271)
右の十七首、古歌集に出でたり。
とあって、その十七首は「問答」から始まっていることが知られる。ところが、そのすぐ後に、
児らが手を巻向山は常にあれど過ぎにし人に行き巻かめやも (1272)
巻向の山辺とよみて行く水の水沫のごとし世人我等は (1273)
右の二首は、柿本朝臣人麻呂が歌集に出でたり。
とあり、その二首は『古歌集』の「ももしきの」(1271)と無常観を詠んだ歌という点で互いに響き合っていると思われる。これも『人麻呂集』が後置されている証である。 |
 |
これら『古歌集』および『人麻呂集』から巻第七に採り入れら歌には、確実に平城遷都以後の作とみるべきものがない。しかし、それらを除いた出所不明の歌には、
春日山おして照らせるこの月は妹が庭にもさやけかりけり (1078)
春日なる三笠の山に月の舟出づ みやびをの飲む酒坏に影に見えつつ (1299)
のように、平城遷都後の作かと思われるものが幾つかあり、全体としては霊亀・養老の頃の作とみてよい歌が、かなりの数にのぼるのではなかろうか。
なお、この『人麻呂集』の「何を詠む」「何に寄する」という分類形式を模しながら、万葉集の中では前後矛盾していることがある。それについては巻第十の解説の中で一括して述べよう。
巻末に挽歌が置かれていることは先に述べた。その直前に「挽歌」の標目があるのは当然であるが、次の歌との間に、あたかも題詞のように一字下げて、底本(西本願寺本)では「雑歌」、神宮文庫本などでは「雑挽」の一行があるのは無視できない。これは巻末の「羈旅歌」の題詞を有する一首(1421)だけが雑歌的内容であるかあrである。本書(日本古典文学全集)は元暦校本などの、「雑歌」とも「雑挽」ともない形に従ったが、目録(元暦校本は目録を欠く)には「挽歌」の次に「雑挽十二首」「或本歌一首」「羈旅歌一首」と続いている。この最後の一首がここに書き込まれたのは、あるいは巻第十六までの編纂が終わったあとではないだろうか。 |
 |
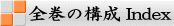 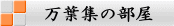 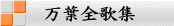 |
  |
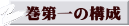 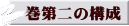 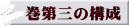 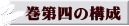 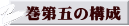 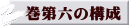 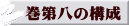  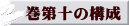 |
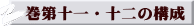 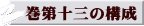  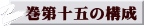 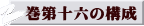 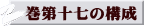 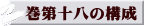 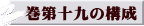 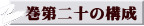 |