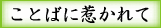| あ | 意 味 | 用 例(万葉集・記紀・古今・新古今集を主にして) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あ | 〔感嘆詞〕感動や驚嘆を表わす声。重ねて「ああ」ともなる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あ [畔] | 田と田のさかい。あぜ。くろ。 | くさぐさの罪事は、天つ罪と、あ放ち(アゼヲコワスコト)― (祝詞) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あ [吾・我・僕] | 自称の人代名詞。わたし。われ。 | うつそみの人なる我れや明日よりは二上山を弟背と我が見む(万2-165) 出でて行きし日を数へつつ今日今日と我を待たすらむ父母らはも(万5-894) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あ [彼] | 遠称の指示代名詞。事物をさす。あれ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あい [愛] | 〔名詞〕 ①《仏教語》ものに対する激しい欲望。執着。 ② 親子・兄弟などが互いにいつくしみ合う心。 ③ 秘蔵すること。愛玩すること。 ④ 愛想。男女間の「愛」は英語loveの翻訳で、古典では「愛」が男女間の愛情の意味に使われることは少なかった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あいしょう [哀傷] | 〔名詞・自動詞サ変〕 ① 人の死を悲しみ悼むこと。 |
①-所以因製歌詠為之哀傷也それゆえに歌詠をつくりてあいし給ふと言へり- (万1-8左注) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② 歌集の中の編の名。哀傷の心を詠んだ歌を集めた編。 |
古今和歌集以後、勅撰集の部立ての名となった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あいす [愛す] | 〔他動詞サ変〕 ① いとおしく思う。かわいがる。 ② 大切にする。大事に思う。好む。 ③ 機嫌をとる。適当にあしらう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あいたんどころ [朝所] | 「あしたどころ」の転。「あいたどころ」とも。参議(大・中納言に次ぐ要職)以上の人々が食事をしたり政務をとったりしたところ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あうら [足占・足卜] | 「あしうら」とも。 |
月夜よみ門に出で立ち足占して行く時さへや妹に逢はずあらむ(万12-3020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歩数で物事の吉凶を占う古代占法の一種。 目標まで吉または凶のことばをとなえて歩み、達したときのことばによって定めるともいう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あか [垢] | 〔名詞〕皮膚にたまる汚れ。 | 我が旅は久しくあらしこの我が着る妹が衣の垢つく見れば(万15-3689) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あが [吾が・我が] | 〔上代語〕 ① (「が」が主格を示す場合) 私が。私は。 ② (「が」が連体核を示す場合) 私の。 |
① 粟島の逢はじと思ふ妹にあれや安寐も寝ずて我が恋ひわたる(万16-3655) ② -音のみを 聞きてあり得ねば 我が恋ふる 千重の一重も-(万2-207) ② 標結ひて我が定めてし住吉の浜の小松は後も我が松(万3-397) ② -天地は 広しといへど 我がためは 狭くやなりぬる 日月は-(万5-896) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あがおもの [我が面の] | 【和歌】私の顔。 | 我が面の忘れむしだは国溢り嶺に立つ雲を見つつ偲はせ(万14-3536) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あかかがち [赤酸槳] | 〔上代語・名詞〕熟して赤くなった、たんぱほおずき(植物名)。 | その目はあかかがちの如くして、身一つに八頭八尾あり (記・上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あがかに | 〔上代語・副詞〕苛立って足をばたばたさせるほど。 | 言立てば足もあがかに嫉みたまひき(記・下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あがき [足掻き] | 〔名詞〕 ① (牛馬などが)足で地面をかくこと。転じて馬などの歩み。 ② 生活が苦しくて、もがくこと。あくせくすること。 |
① 青駒が足掻きを速み雲居にぞ妹があたりを過ぎて来にける (万2-136) ① 赤駒が足掻き速けば雲居にも隠り行かむぞ袖まけ我妹(万11-2515) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足掻きの水。馬などが、けたてたときにはねる水。 | 鸕坂川渡る瀬多みこの我が馬の足掻きの水に衣濡れにけり(万17-4046) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あかきこころ [赤き心・明かき心] | 清い心、偽りのない心。特に朝廷に対する忠誠心。 ⇔黒き心 | 然らば何を以ちてか、いましがあかきこころは明かさむ(神代紀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あかぎぬの [赤衣の・赤絹] | 【枕詞】純裏(ひたうら)にかかる。 | 赤絹の純裏の衣長く欲り我が思ふ君が見えぬころかも(万12-2984) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あがきみ [吾が君] | 〔人称代名詞〕 相手(友人や恋人など) を親しみ敬って呼びかける語。あなた。いとしい人。 |
我が君はわけをば死ねと思へかも逢ふ夜逢はぬ夜二走るらむ(万4-555) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻第四-552 注『我が君』」】 「君」には「アガ」を冠するのが常で、「ワガ君」ということはない。「尊安我吉美(たふときあがきみ)」(19・四一六九) の仮名書の他、「乞吾君(いであがきみ)」(六六〇) のように字あまり例外法則の上からも「アガ」でなければならない例が幾つかある。代名詞の「キミ」は普通女から男に対して用いるが、まれには男から女にいうこともある。殊にこの歌のように「ワケ」と相対して用いてある場合、敬意も少なく戯れの気持ちが強い。このあとの「五五六」の歌は賀茂女王から大伴三依に贈ったものであり、この「我が君」も賀茂女王をさすと考えてよい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あがく [足掻く] | 〔自動詞カ行四段〕 ① (牛馬などが)足で地面をかく。またはそのようにして歩む。 ② 手足を動かしてもがく。 ③ 気をもんで働く。あくせくする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あがこころ [吾が心] | 【枕詞】「清隅(きよずみ)」「明石」「筑紫」に懸かる。我が心。 | -我が心明石の浦に船泊めて-(万15-3649) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あかごま [赤駒] | 〔名詞〕 赤毛の馬。 |
赤駒の越ゆる馬柵の標結ひし妹が心は疑ひもなし(万4-533) 赤駒が足掻速けば雲居にも隠り行かむぞ袖まけ我妹(万11-2515) 大君は神にしませば赤駒の腹這ふ田居を都と成しつ(万19-4284) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あかしおほと [明石大門・明石の門] | 燈火の明石大門に入らむ日や漕ぎ別れなむ家のあたり見ず(万3-255) 天離る鄙の長道ゆ恋ひ来れば明石の門より大和島見ゆ [一本云 家のあたり見ゆ](万3-256) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 『付録 地名一覧』」】 -明石大門・明石の門 明石海峡。兵庫県明石市付近の明石海岸と淡路島の北端との間にある海峡。大阪湾と播磨湾とをつなぐ。幅約四キロメートル。 これを出入りする船は、最大時速九キロメートルに達する潮流を利用した。 【有斐閣「萬葉集全注巻三-254 注『明石大門』」】 明石海峡で、明石市と淡路の北端との海峡。明石の櫛淵 (くしふち) から西は畿外であった。 (大化二年〔六四六年〕正月一日の大化改新の詔による) から、海路では明石海峡が畿外と畿内とを分ける海坂(うなさか 海の境界) であった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あかしのうら [明石の浦] | 〔地名〕白砂青松の美景で名高い。「源氏物語」の舞台ともなった。 | 見渡せば明石の浦に燭す火のほにそ出でぬる妹に恋ふらく(万3-329) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明石市にある海岸。明石大門(あかしおおど=明石海峡)を隔てて淡路島に対している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あかす [明かす] | 〔他動詞サ行四段〕 ① 明るくする。② 夜が明けるまで事をし続ける。 ③ 夜が明けるのを待つ。④ 生活する。明かし暮らす。暮らす。 |
① 海原の沖辺に燈し漁る火は明かして燈せ大和島見ゆ(万15-3670) ② -思ひつつ 眠も寝かてにと 明かしつらくも 長きこの夜を(万4-485) ② 志賀の浦に漁りする海人家人の待ち恋ふらむに明かし釣る魚 (万15-3675) ③ 蠣貝に足蹈ますな明かしてとほれ (紀・下) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あかず [飽かず] | 〔四段動詞「飽く」の未然形に打ち消し助動詞「ず」の付いたもの] ① 満足しない。物足りない。② 飽きない。嫌になることがない。 |
② 河上のつらつら椿つらつらに見れども飽かず巨勢の春野は(万1-56) ② -見れども飽かず 望月の いやめづらしみ 思ほしし 君と時どき-(万2-196) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あがたみ [県見] | 田舎見物。地方巡視。 | 文屋康秀が三河の尉になりて、あがたみにはえいでたたじやと (古今雑下詞書) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あかだま [赤玉・赤珠] | 〔名詞〕赤い玉。明るく光る玉。 | -赤玉は緒さへ光れど-(記・上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あかつ [頒つ] | 〔他動詞タ行四段〕分ける。割り当てる。(わかつ、あがつ) | いくさびとにあかち賜ふ (神武紀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あかつき [暁] | 〔名詞〕 「明時」の転。上代は「あかとき」、中古以後は「あかつき」夜中過ぎから夜明けまで。未明。 後世は明け方に近い時間をさすようになったが、「あかつき」「しののめ」は「あけぼの」よりやや早く、まだ明けやらない時をいう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -おき [暁起き] | 〔名詞〕夜中過ぎに早起きすること。 | 山路にてそぼちにけりな白露の暁起きの菊のしづくに(新古羈旅-924) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あかで [飽かで] | [「飽く」の未然形に打ち消しの接続助詞「で」のついたもの。] 物足りなく。満足しないで。 |
むすぶ手のしづくににごる山の井のあかでも人に別れぬるかな (古離別-404) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あかとき [暁] | 〔名詞〕《上代語》「明時(あかとき)」の意。 平安以後は「あかつき」。 |
我が背子を大和へ遣るとさ夜更けて暁露に我が立ち濡れし(万2-105) あかときの夢に見えつつ楫島の磯越す波のしきてし思ほゆ(万9-1733) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -くたち [暁くたち] | 〔名詞〕「暁くだち」とも。夜が明けて暁近くになるころ。 | こよひのあかときくだち鳴く鶴の思ひは過ぎず恋こそ増され(万10-2273) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -づき [暁月] | 〔名詞〕「あかつきづき」の古形。夜中過ぎの空に照る月。 | さ夜更けて暁月に影見えて鳴くほととぎす聞けばなつかし(万19-4205) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -づくよ [暁月夜] | 〔名詞〕「あかつきづくよ」とも。夜中過ぎの月の残っているころ。 | しぐれ降る暁月夜紐解かず恋ふらむ君と居らましものを(万10-2310) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -つゆ [暁露] | 〔名詞〕[後「あかつきつゆ」] 夜中過ぎにおく露。明け方の露。 | 我が背子を大和へ遣るとさ夜更けて暁露に我が立ち濡れし(万2-105) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -やみ [暁闇] | 〔名詞〕「あかつきやみ」 | 夕月夜暁闇のおほほしく見し人ゆゑに恋ひわたるかも(万12-3017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あかなくに [飽かなくに] | 〔なりたち〕「飽く」の未然形に打消助動詞「ず」の古い未然形「な」、接尾語「く」、助詞「に」のついたもの。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春雨に匂へる色もあかなくに香さへなつかし山吹の花(古春下-122) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あかぬわかれ [飽かぬ別れ] | 「諦めきれない別れ」の意から、名残尽きない別れ。 | ちぎりきやあかぬわかれに露おきし暁ばかりかたみなれとは (新古恋四-1301) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あかね [茜] | 〔名詞〕 つる草の名。初秋に白色の花が咲く。根から茜色の染料を取る。 また、それで染めた、ややくすんだ赤色。〔秋〕あかね |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -さし [茜さし] | 【枕詞】「照る」に懸かる。 | 泊瀬の斎槻が下に我が隠せる妻あさねさし照れる月夜に人見てむかも((万11-2357) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -さす [茜さす] | 【枕詞】茜色に美しく輝く意から、 「日」「昼」「紫」「照る」「月」「君が心」などに懸かる。 |
あかねさす紫野行き標野行き野守は見ずや君が袖振る(万1-20) あかねさす日は照らせれどぬばたまの夜渡る月の隠らく惜しも(万2-169) 飯食めどうまくもあらず行き行けど安くもあらず茜さす君が心し忘れかねつも (万16-3879) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あがふ [贖ふ] | 「あがなふ」の古形。金品を出して罪を償う。代わりの物を出して埋め合わせる。 | 中臣の太祝詞言言ひ祓へ贖ふ命も誰がために汝れ(万17-4055) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あかぼしの [明星の] | 【枕詞】「明く」「飽く」などに懸かる。明星は金星。 | -明星の明くる朝は敷栲の-(万5-909) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あかも [赤裳] | 〔名詞〕紅色の腰裳。 | -さ丹塗りの大橋の上ゆ紅の赤裳裾引き山藍もち-(万9-1746) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あから [赤ら] | 赤みをおびて美しいさまにいう語。 | 月待ちて家には行かむ我が挿せる赤ら橘影尓に見えつつ(万18-4084) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -がしは [赤ら柏] | 〔名詞〕 柏の一種。若葉が赤味を帯びたもの。 上代その葉が供物を盛る具として用いられた。 今の「赤目柏」のことという。 |
印南野の赤ら柏は時はあれど君を我が思ふ時はさねなし(万20-4325) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -けし [赤らけし] | 〔形容詞ク活用名詞〕 赤みを帯びている。 | 初土は膚赤らけし(記・中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ひく [赤らひく] | 【枕詞】赤みを帯びるという意から「日」「朝」「肌」「子」「敷妙」などに懸かる。 | ぬばたまのこの夜な明けそ赤らひく朝行く君を待たば苦しも(万11-2393) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -をとめ [赤ら乙女] | 血色のいい美しい少女。 | -赤ら乙女をいざささば良らしな-(記・中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -をぶね [赤ら小舟] | 赤く塗った小さな舟。 | 沖行くや赤ら小舟につと遣らばけだし人見て開き見むかも(万16-3890) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -さま | 〔形容動詞ナリ活用〕にわかに。たちまち。急に。 | 逐はれたる嗔猪、草中よりあからさまに出でて人を遂ふ (雄略紀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この意味は、主として上代に用いられている。以後は、ちょっとかりに、かりにも、あきらか、明白に。などの意が主流となる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あからしまかぜ [暴風] | 〔名詞〕暴風。はやて。 | 海の中にしてにはかにあからしまかぜに遭ひぬ (神武紀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あからぶ [明からぶ] | 心を晴らす。 | 山川の浄き所をばたれとともにか見そなはし明からべたまむ(続紀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あがり [殯] | 〔名詞〕死体を葬るまでの間、しばらく安置しておくこと。もがり。 | 豊浦宮にもがりして无火あがりをす(仲哀紀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あかる [赤る] | 〔形容詞〕「赤し」の語幹「あか」に接尾語「る」が付いて動詞に。 ① 赤くなる。② 熟して赤くなる。 |
① 赤れるをとめ(応神紀) ②-島山に赤る橘うずに刺し紐解き放けて-(万19-4290) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あかる [明かる] | 〔自動詞ラ行四段〕明るくなる。 【参考】 「明かる」 と「赤る」 は同じ語源の語。「明かる」 は光についていうのに対して、「赤る」 は色についていう。 枕草子「春はあけぼの。やうやうしろくなりゆく、山ぎは少し明かりて-」 春は夜明け方(が趣がある)。この用例も、「赤りて(赤みを帯びて) とも解釈できる。」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あかる [別る・散る] | 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 (その場を) 離れる。退出する。別れる。別々になる。 【「あかる」 と「わかる」 】 「あかる」 は「つどふ」 に対する語で、一つに集まった場所から別々に離れて行く意が原義。「わかる」 は「あふ」 に対する語で、一つのものが別々になる意が原義。 なお「たらちねの母を別れて-」 (万20-4372) のように、「-を別る」 ともいう点が現代語と異なる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あがる [上がる・揚がる・騰がる] | 1〔自動詞ラ行四段〕 ① 上に移る。高くなる。② 官位が進む。 ③ 学問・技芸技芸などが上達する。腕が上がる。 ④ 時代がさかのぼる。昔になる。⑤ (馬が) はねる。あばれる。 ⑥ のぼせる。⑦ 宮中・殿中などに参上する。まいる。 ⑧ 完成する。終わる。止む。 2〔他動詞ラ行四段〕飲む・食うの尊敬語。 |
1-① うらうらに照れる春日にひばり上がり心悲しも独し思へば(万19-4316) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あき(あきのた) [秋] | 〔名詞〕四季の一つ。陰暦七月から九月までの称。立秋から立冬の前まで。 |
秋の田の穂の上に霧らふ朝霞いつへの方に我が恋やまむ(万2-88) -自妻と 頼める今夜 秋の夜の 百夜の長さ ありこせぬかも(万4-549) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻一-7 注『秋』」】 原文「金野乃」の「金」は、中国の五行説に基づいて「秋」を表わしたもの。 木・火・土・金・水の五行を四季に配すると、木は春、火は夏、金は秋、水は冬にあたる。 【参考】 木の葉も落ち、草も枯れ、衰えが意識されてさびしく悲しい風情の季節とされた。夜長も秋の特徴であり、中古以後、和歌では同音から多く「飽き」にかけて用いられた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -かけて [秋かけて] | 秋になると。 | 降りにけり時雨は袖に秋かけていひしばかりを待つとせしまに (新古恋四-1334) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -かたまく [秋かたまく] | 秋に向かう。秋のころを待つ。 | 磯の間ゆ激つ山川絶えずあらばまたもあひ見む秋かたまけて(万15-3641) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -さらば [秋さらば] | 秋になったならば。 | 秋さらば見つつしのへと妹が植ゑし屋前のなでしこ咲きにけるかも (万3-467) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -さりくれば [秋さり来れば] | 秋がやってきたら。 | -霜露の秋さり来れば生駒山飛火が岳に-(万6-1051) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -されば [秋されば] | 秋になると。 | 秋されば春日の山の黄葉見る奈良の都の荒るらく惜しも(万8-1608) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -たつ [秋立つ] | 秋になる。立秋になる。参照「立つ」 |
-春へは花かざし持ち秋立てば黄葉かざせり-(万1-38) -つそみと 思ひし時に 春へは 花折かざし 秋立てば-(万2-196) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -つば [秋つ葉] | 秋の紅葉。 | 秋つ葉ににほへる衣我れは着じ君に奉らば夜も着るがね(万10-2308) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のか [秋の香] | 秋草の香(一説には松茸の香)。 | 高松のこの嶺も狭に笠立てて満ち盛りたる秋の香のよさ(万10-2237) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のこゑ [秋の声] | 秋の気配。草木吹き渡る風の音や砧の響きなどに感じる秋のもの寂しさ | 五十鈴川空やまだきに秋の声したつ岩ねの松のゆふかぜ(新古神祇-1885) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のそで [秋の袖] | 秋着る衣服の袖。 | 松島やしほ汲む海士の秋の袖月はもの思ふならひのみかは(新古秋上-401) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のそら [秋の空] | 秋の天候の定まらないところから。また「飽き」にかけて心の移り易さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のたもと [秋の袂] | 涙で濡れている衣の袂。涙で濡れ易いことのたとえ。 | 物思はでただおほかたの露にだに濡るれば濡るる秋の袂を(新古恋四-1314) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のは [秋の葉] | 秋の葉。紅葉した葉。もみじ。 | -秋の葉のにほひに照れるあたらしき身のさかりすらー(万19-4235) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のほ [秋の穂] | 秋のよく実った稲穂。 | 秋の穂をしのに押しなべ置く露の消かもしなまし恋ひつつあらずは (万10-2260) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のももよ [秋の百夜] | ただでさえ長い秋の夜を百も続けたほどの非常に長い夜。 | 今夜の早く明けなばすべをなみ秋の百夜を願いつるかも(万4-551) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ゆく [秋行く] | 秋になる。秋が来る。秋が過ぎて行く。 |
-春されば 春霞立つ 秋行けば 紅にほふ 神なびの-(万13-3241) 神なびのみむろの山を秋ゆけば錦たちきる心地こそすれ(古秋下-296) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -よりのちのあき [秋よりのちの秋] | 〔名詞〕陰暦の閏の九月。 | なべて世の惜しさにそへて惜しむかな秋より後の秋の限を(新古秋下-550) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -かしは [秋柏] | 【枕詞】「うるわ川」に懸かる。「秋柏」が霧などに潤うことから。 | 秋柏潤和(うるわ)川辺の小竹の芽の人には忍び君に堪へなくに(万11-2482) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -かぜ [秋風] | 〔名詞〕 ① 秋吹く風。 ②「厭き」にかけて、愛情の醒めるのにたとえる。 |
① 秋風の寒き朝明を佐農の岡越ゆらむ君に衣貸さましを(万3-364) ② 秋風は身をわけてしも吹かなくに人の心のそらになるらむ(古恋五-787) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -かぜの [秋風の] | 【枕詞】「吹く」「千江(ちえ)」に懸かる。 | 秋風のふきあげにたてるしらぎくは花かあらぬか浪のよするか(古秋下-272) 秋風の千江の浦廻の木屑なす心は寄りぬ後は知らねど(万11-2733) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -かぜに [秋風に] | 【序詞】古今以降、枕詞が長い文節となり「序詞」となる | 秋風にあへずちりぬるもみぢばのゆくへさだめぬ我ぞかなしき(古秋下-286) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -きぬと [秋来ぬと] | 秋きぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる(古秋上-169) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -きの [秋葱の] | 【枕詞】「ふたごもり」に懸かる。 | あききのいやふたごもり思へかし(仁賢紀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -くさの [秋草の] | 【枕詞】「結ぶ」に懸かる。 | 神さぶといなにはあらず秋草の結びし紐を解くは悲しも(万8-1616) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -さ [秋沙] | 〔名詞〕「あきさがも」の略。鴨の一種。あいさ・あいさがも。 | 山の際に渡るあきさの行きて居むその川の瀬に波立つなゆめ(万7-1126) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -さりごろも [秋さり衣] | 〔名詞〕秋になって着る服。 | 織女の五百機立てて織る布の秋さり衣誰れか取り見む(万10-2038) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -さる [秋さる] | 〔自動詞サ行四段〕秋になる。 | 秋されば置くしら露にわがやどの浅茅が上葉色づきにけり(新古秋下-464) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あぎ [吾君] | 〔代名詞〕相手を親しみ敬っていう語。 | さざき(大雀命)あぎの言ぞわが思ほすがごとくなる(記・中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきじこり [商じこり] | 〔名詞〕買い損ない。商売上のしくじり。 | 西の市にただひとり出でて目並べず買ひてし絹の商じこりかも(万7-1268) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきしの [秋篠] | 奈良県奈良市秋篠町。市の西郊、西部生駒山の東方の地。 奈良時代の光仁・桓武天皇の勅願寺秋篠寺があり、天平時代の伎芸天像は名高い。また、砧の音、霧の風情で知られる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきしのや [秋篠や] | あきしのやと山の里や時雨(しぐ)るらむいこまのたけに雲のかかれる (新古冬-585) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきた [秋田] | 〔名詞〕稲の実った田。 | 雲隠り鳴くなる雁の行きて居む秋田の穂立繁くし思ほゆ(万8-1571) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきだる [飽き足る] | 〔自動詞ラ行四段〕満足する。飽きるほど十分だと思う。 〔語法〕 普通、下に打ち消しの語をともない「あきだらぬ」「あきだらず」 の形か、 または反語の形で用いられる。 |
-夜はも 夜のことごと 伏し居嘆けど 飽き足らぬかも(万2-204) 梅の花手折りかざして遊べども飽き足らぬ日は今日にしありけり(万5-840) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきちかう・・・ | 〔名詞〕きちかうの花 (きちかうの花は、桔梗の花) |
秋ちかう野はなりにけり白露のおける草葉も色かはりゆく(古物名-440) 「秋近うのはなりにけり」に「きちかうの花」が隠してある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきづ [秋津・蜻蛉] | 〔名詞〕中古以後は「あきつ」「とんぼ」の古名 | あきづ来てそのあむをくひて飛ぎき(記・下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -しま [秋津島・秋津洲・蜻蛉洲] | 「日本国」の略称。また大和国をさしていう。あきつくに、あきつしまね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】「やまと」に懸かる。 | -海原は鷗立ち立つうまし国ぞ蜻蛉島大和の国は(万1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ひれ [蜻蛉領布] | 〔名詞〕とんぼの羽根のように美しい布。上代、婦人が飾りに用いた。 | -まそみ鏡に蜻蛉領布負ひ並め持ちて馬買へ我が背(万13-3328) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきつかみ [秋津神・現神] | 〔名詞〕現世に姿を現している神の意から、天皇を尊んでいった語。 | 現つ神我が大君の天の下八島の内に国はしもさはにあれども-(万6-1054) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきづく [秋付く] | 〔自動詞カ行四段〕秋らしくなる。秋めいてくる。 | -秋づけば時雨の雨ふり-(万18-4135) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきづののへ [秋津の野辺] | 今、秋津の名は残ってないが、吉野川を挟んで、宮滝とその対岸へかけて、秋津野と言ったものと思われる。 宮滝の対岸御園の字に「アキト」という地名があり、それが秋津の名残と言われている。 上流の川上村に今蜻蛉滝というところがあり、その地という説もあるが、「野」に相応しくないとされる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきづはの [蜻蛉羽の] | 【枕詞】「そで」に懸かる。 | あきづ羽の袖振る妹を玉櫛笥奥に思ふを見たまへ我が君(万3-379) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あぎとふ | ①小児らが片言でものを言う。 ②魚が水面に浮いて口を開閉する。 |
① 皇子の鵠(白鳥)の音を聞きて始めてあぎとひしたまひき(垂仁紀) ② 魚みな浮び出でて水のままにあぎとふ(神武紀) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきの [阿騎野] (あきのおほの) [阿騎の大野] |
〔地名〕[「安騎野」「吾城野」「阿紀野」とも書く] 今の奈良県宇陀郡大宇陀町付近の野。上代の狩猟地。 |
-夕去り来れば み雪降る 安騎の大野に 旗すすき 小竹を押しなべ- (万1-45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきのはの [秋の葉の] | 【枕詞】「にほふ」に懸かる。 | -二上山は春花の咲ける盛りに秋の葉のにほへる時に-(万17-4009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきはぎ [秋萩] | 〔名詞〕花が咲いている秋の萩。 |
我妹子に恋ひつつあらずは秋萩の咲きて散りぬる花にあらましを(万2-120) -人の嘆きは相思はぬ君にあれやも秋萩の散らへる野辺の-(万15-3713) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきはぎの [秋萩の] | 【枕詞】「うつる」「しなふ」「花野」に懸かる。 | 吹きまよふ野風をさむみ秋萩のうつりもゆくか人の心の(古恋五-781) 秋萩の花野のすすき穂には出でず我がひわたる隠り妻はも(万10-2289) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきやま [秋山] | 〔名詞〕美しく照り映える秋の山。 | -取りても見ず 秋山の 木の葉を見ては 黄葉をば 取りてぞ偲ふ-(万1-16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきやまの [秋山の] | 【枕詞】「したふ(紅葉する)」「いろなつかし」などに懸かる。 | 秋山の したへる妹 なよ竹の とをよる子らは いかさまに-(万2-217) 秋山のしたひが下に鳴く鳥の声だに聞かば何か嘆かむ(万10-2243) -うらぐはしも春山のしなひ栄えて秋山の色なつかしき-(万13-3248) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきらけし [明らけし] | ① 明らかである。はっきりしている。 ② 曇りなく潔白である。清浄である。 |
-我を召すらめや明けく我が知ることを歌人と-(万16-3908) 磯城島の大和の国に明らけき名に負ふ伴の男心つとめよ(万20-4490) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あきらむ [明らむ] | 〔他動詞マ行下二段〕【メ・メ・ム・ムル・ムレ・メヨ】〔なりたち〕形容動詞「あきらかなり」の語幹の一部「あきら」に接尾語「む」をつけて動詞としたもの。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① (事情・道理・理由・原因などを) 見極め、明らかにする。明白に判別する。 ② 事実をはっきりさせる。釈明する。 ③ 心を明るく楽しくする。心を晴らす。 |
① 秋の花種にあれど色ごとに見し明らむる今日の貴さ(万19-4279) ③ -見し明らめし 活道山 木立の茂に 咲く花も うつろひにけり-(万3-481) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あく [明く] | 〔自動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 夜が明ける。明るくなる。また、年・月・日などが改まる。 |
玉櫛笥覆ふをやすみ明けていなば君が名はあれど吾が名し惜しも(万2-93) 今夜の早く明けなばすべをなみ秋の百夜を願ひつるかも(万4-551) 秋の夜の明くるも知らず鳴く虫はわがごとものやかなしかるらん(古今秋上-197) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あく [開く・空く] | 〔自動詞カ行四段〕 ① 閉じてあるものなどが開く。あく。隙間・切れ目などができる。 ② (差し止められていたことなどが) 解除される。終りになる。 ③ 官職や地位に欠員ができる。 |
① 玉櫛笥覆ふを安み明けていなば君が名はあれど吾が名し惜しも(万2-93) ① 我が思ひを人に知るれや玉櫛笥開き明けつと夢にし見ゆる(万4-594) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 閉じられているものなどを開ける。隙間・切れ目などをつくる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あく [飽く・厭く] | 〔自動詞カ行四段〕 ① 十分満足する。心ゆく。 ② あきあきする。いやになる。いとわしくなる。 |
① 沖つ風いたく吹きせば我妹子が嘆きの霧に飽かましものを(万15-3638) ② 玉藻よし 讃岐の国は 国からか 見れども飽かぬ 神からか -(万2-220) ② まそ鏡見飽かぬ君に後れてや朝夕にさびつつ居らむ(万4-575) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔語法〕 中古以後は、「あく」が単独で用いられることが少なく、ほとんどが「あかず」の形で用いられる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あくた [芥] | 〔名詞〕 さざきごみ、ちり、くず。 | 天にある日売菅原の草な刈りそね蜷の腸か黒き髪にあくたし付くも (万7-1281) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あくまで [飽くまで] | 〔副詞〕 思う存分。心ゆくまで。十分に。 |
難波潟潮干のなごり飽くまでに人の見む子を我しともしも(万4-536) 都辺に立つ日近づく飽くまでに相見て行かな恋ふる日多けむ(万17-4023) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あぐむ [足組む・趺む] | 〔自動詞マ行四段〕両足を組む。あぐらを組む。 | その剣の前にあぐみ坐して-(記・上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あぐら [胡床・呉床] | 「足座(あしぐら)」の略。上代、貴人があぐらをして座る席。 | しし待つとあぐらにいまし」(記・下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あぐらゐ [胡床居] | 〔名詞〕あぐらして座っていること。 | あぐらゐの神の御手もちひく琴に(記・下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あくるあした [明くる朝] | 〔名詞〕次の日の朝。翌朝。明るくつとめて。 | -明星の明くる朝は敷栲の床の辺去らず-(万5-909) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あけ [朱・緋・赤] | 「赤」の転。 ① 赤。赤い色。朱色、緋色などもいう。 ② 「緋衣(あけごろも)」の略。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あけ [明け] | 〔名詞〕夜が明けること。夜明け。 | 旅にしてもの恋しきに山下の赤のそほ船沖を漕ぐ見ゆ(万3-272) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あけくれ [明け暮れ] | 〔名詞〕夜明けと夕暮れ。朝晩。転じて、日常。毎日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あけくれ [明け暮れ] | 〔副詞〕明けても暮れても。いつでも。常に。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あけぐれ [明け暗れ] | 〔名詞〕夜明け前のまだ薄暗いとき。未明。 | -恋ひつつ居れば 明け闇の 朝霧ごもり 鳴く鶴の 音のみし泣かゆ-(万4-512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あけ(のそほぶね) [朱(の曽保船)] |
〔名詞〕「そほ」は塗料にした赤い土。赤く塗った奈良時代の船。 | 旅にしてもの恋しきに山下の赤のそほ船沖に漕ぐ見ゆ(万3-272) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あげ [上げ] | 〔名詞〕上へあげること。「上げ田」の略。 | 水を多み上田に種蒔き稗を多み選らえし業ぞ我がひとり寝る(万12-3013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あけく [明け来] | 〔自動詞カ行変格〕【コ・キ・ク・クル・クレ・コ(コヨ)】次第に夜が明けてくる。 | -荒礒の上に か青なる 玉藻沖つ藻 明け来れば 波こそ来寄れ-(万2-138) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あけさる [明けさる] | 「明く」と「去る」の複合。夜が明けて朝になる。 | -明け去れば榛のさ枝に夕されば藤の茂みに-(万19-4231) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あげた [上げ田] | 〔名詞〕高いところの作った水田。よく乾くという。 | 兄あげたをつくらば(神代紀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あげちらす [上げ散らす] | 〔他動詞サ行四段〕格子などを開け放す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あげつらふ [論ふ] | 〔他動詞カ行四段〕「挙げ連る」の意。 (一説に「あげ」は言挙げ、「つらふ」は争うの意)。 道筋を立てて論じる。よしあしを言い立てる。 |
貴賎をあげつらふことなかれ。ただその心をのみ重みすべし(継体紀) まづつばらかに黄泉神とあげつらはむ(記・上) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あけぬ [明けぬ] | 「ぬ」は打ち消しの助動詞「ず」の連体形。夜明け前。 | 明けぬとて野辺より山に入る鹿のあと吹きおくる萩の下風(新古秋上-351) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あけぼの [曙] | 「ほのぼの明け」の転という。夜がほのぼのと明けようとしている。 〔参考〕 枕草子冒頭の「春はあけぼの」が有名だが、「あけぼの」の用例は枕草子中のもこれだけで他になく、またこれ以前の歌・物語・日記にも「あかつき」が多用され「あけぼの」はほとんど出て来ない。一方「春のあけぼの」を美とする用例は、この枕草子以後急速に増し、多くの歌などによまれ、新古今集では代表的な季節の美となった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あげまき [揚げ巻き] | 〔名詞〕 ① 昔の子どもの髪の結い方の一つ。 振り分け髪を中央から左右に巻き上げ両方の耳のところで結い上げたもの。 ② 髪をあげまきに結う年頃。 |
① いまだあげまきにもあらぬ(景行紀) ② 天皇かぶろにましますよりあげまきにいたるまでに(允恭紀) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あこ [吾子・我子] | 「あご」とも。子またはそれに準じる者を親しんで呼ぶ語。 | 今だにもあこよ(神武紀)大船に真楫しじ貫きこの我子を唐国へ遣る斎へ神たち (万19-4264) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あご [顎・腭] | 〔名詞〕口の上下にある器官。あぎ・あぎと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あご [網子] | 「あみこ」の略。地引網を引く人。網引きする人。 | 大宮の内まで聞こゆ網引すと網子ととのふる海人の呼び声(万3-239) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あごねのうら [阿胡根の浦] | 〔地名〕所在未詳 | 我が欲りし野島は見せつ底深き阿胡根の浦の玉ぞ拾はぬ [或頭云 我が欲りし子島は見しを](万1-12) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさ [朝] | 〔名詞〕夜が明けてから、しばらくの間。 ⇒「あした」 | -坂鳥の 朝越えまして 玉限る 夕去り来れば み雪降る -(万1-45) 春日山朝立つ雲の居ぬ日なく見まくの欲しき君にもあるかも(万4-587) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさ [浅] | 「浅し」の語幹から、浅い・薄い・軽い、の意。 | 浅瀬・浅緑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさ [麻] | 〔名詞〕あさを。たいま。 くわ科の一年生栽培草木。夏から秋にかけて刈り、皮から繊維をとる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさあけ [朝明け] | 夜明け方。あさけ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あざあざと [鮮鮮と] | 〔副詞〕あざやかに。はっきりと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさあらし [朝嵐] | 〔名詞〕朝、強く吹く冷たい風。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさい [朝寝] | 「い」は睡眠の意味の名詞。あさね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさか [浅香] | 〔地名〕 | 夕さらば潮満ち来なむ住吉の浅香の浦に玉藻刈りてな(万2-121) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪市住吉区浅香町から堺市にかけての地域。古くは海で、「浅香の浦」、「浅香潟 (がた)」などと和歌に詠まれた。〔歌枕〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさかげ [朝影] | ① 朝、鏡や水に映る姿。 ② 朝日に照らされて映る細長い影の意から、身の痩せ細った姿の譬。 |
①-朝影見つつ娘子らが手に取り持てるまそ鏡-(万19-4216) ② 朝影に我が身はなりぬ韓衣裾のあはずて久しくなれば(万11-2626) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさがすみ [朝霞] [諸注参照] | 朝立つ霞。[一般的には「春」] |
① 秋の田の穂の上に霧らふ朝霞いつへの方に我が恋やまむ(万2-88) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】 煙のたなびくさまが似ていることから「鹿火(かひ)」に、 幾重にもかかることから「八重(やへ)」に、 かすんで見えることから「ほのか」に、 その時季に立つことから「春日(かすが)」などにかかる。 |
朝霞鹿火屋(かひや)が下に鳴くかはづ声だに聞かば我れ恋ひめやも (万10-2269) 朝霞八重山越えて呼子鳥鳴きや汝が来る宿もあらなくに(万10-1945) 殺目山行き返り道の朝霞ほのかにだにや妹に逢はざらむ(万12-3051) 朝霞春日の暮は木の間より移ろふ月をいつとか待たむ(万10-1880) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさかは [浅川] | 〔名詞〕水の浅い川。浅川わたる 男女の縁の薄いたとえ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさがは [朝川] | 朝渡る川。朝の川。 ⇔ 夕川。 | -大宮人は 舟並めて 朝川渡る 舟競ひ 夕川渡る この川の-(万1-36) 人言を繁み言痛みおのが世にいまだ渡らぬ朝川渡る(万2-116) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あざがへす [糾返す] | 「糾ふ(交える、組む)」と「返す」の複合。 繰り返す。引っ繰り返す。何度も何度もする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさがほ [朝顔・朝貌] | ① 朝起きたばかりの顔。あさがたち。 ② 草木の名。今のあさがお。しののめぐさ。秋 ③ 草木の名。今の桔梗、むくげ、ひるがお、と諸説がある。 |
③ 朝顔は朝露負ひて咲くといへど夕影にこそ咲きまさりけれ(万10-2108) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさがほの [朝顔の] | 【枕詞】「ほ」に懸かる。 | 言に出でて言はばゆゆしみ朝顔の穂には咲き出ぬ恋もするかも(万10-2279) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさがみ [朝髪] | 朝起きたばかりで整えていない髪。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさがみの [朝髪の] | 【枕詞】「乱る」に懸かる。 | 朝髪の思ひ乱れてかくばかり汝姉がふれぞ夢に見えける(万4-727) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさかやま [朝香山・安積山・浅香山] | 三重県一志郡にある山。紅葉、蛍の名所。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島県郡山市にある小高い山。安積の沼とともに有名。万葉集には風流な前采女(さきのうねめ)に関する伝説がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】「浅し」に懸かる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさがら [麻幹] | 〔名詞〕 麻の茎の皮を剥ぎ取ったもの。をがら。 盂蘭盆の聖霊会の箸に用い、また焼いて火口(ほぐち)の炭、画工の焼筆などにする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさがり [朝狩り] | 〔名詞〕早朝行う狩り。 | -み執らしの 梓の弓の 中弭の 音すなり 朝猟に 今立たすらし 夕猟に-(万1-3) 後れ居て恋ひば苦しも朝猟の君が弓にもならましものを(万14-3590) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさぎぬ [麻衣] | 〔名詞〕 ① 麻の布で仕立てた衣服。② 喪のときに着る麻の衣服。 |
-真間の手児名が麻衣に青衿着け-(万9-1811) -宮の舎人もたへの穂のあさぎぬければ-(万13-3338) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさぎり [朝霧] | 〔名詞〕朝、立ちこめる霧。秋 ⇔夕霧 | 朝霧のたなびく田居に鳴く雁を留め得むかも我がやどの萩(万19-4248) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -がくり [朝霧隠り] | 立ち込める朝霧の中に隠れて。 | 明け暮れの朝霧隠り鳴きて行く雁は我が恋妹に告げこそ(万10-2133) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさぎりごもり [朝霧籠り] | 立ち込めた朝霧の中に籠って。 | -恋ひつつ居れば 明け闇の 朝霧ごもり 鳴く鶴の 音のみし泣かゆ-(万4-512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさぎりの [朝霧の] | 【枕詞】「思ひまどふ」「乱る」「八重山」「立つ」「おほに」に懸かる。 | -あさぎりの思ひまどひて杖足らず八尺のなげき嘆けども-(万13-3358) 朝霧のおほに相見し人故に命死ぬべく恋ひわたるかも(万4-602) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさぐもり [朝曇り] | 〔名詞〕朝、空の曇っていること。 | 朝ぐもり日の入り行けばみ立たしの島に下り居て嘆きつるかも(万2-188) さびしさはみやまのあきのあさぐもり霧にしをるるまきのした露 (新古秋下-492) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさけ [朝明] | 「あさあけ」の略。夜明け方。 | 今朝の朝明雁が音聞きつ春日山もみちにけらし我が心痛し(万8-1517) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のすがた [朝明の姿] | 明け方起きて出で立つ姿。特に夜明けに女の家を出て行く男の姿。 | 我が背子が朝明の姿よく見ずて今日の間を恋ひ暮らすかも(万12-2852) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のなごり [朝明の余波] | 明け方、潮の引いたあとになぎさに残る海水。 | 名児の海の朝明のなごり今日もかも磯の浦廻に乱れてあらむ(万7-1159) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさげ [朝食] | 〔名詞〕古くは「あさけ」、「朝のけ(食事)の」意。朝の食事。⇔ゆうげ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あざけり [嘲り] | 嘲笑、馬鹿にして笑うこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あざける [嘲る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 声を上げて詩歌を吟じる。風月に興じて吟じる。また、あたり構わず大声をあげる。 〔他動詞ラ行四段〕 ② そしり笑う。嘲笑する。わるくいう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさこぎ [朝漕ぎ] | 〔名詞〕朝、舟を漕ぎ出すこと。 | 朝床に聞けば遥けし射水川朝漕ぎしつつ唱ふ舟人(万19-4174) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさこち [朝東風] | 〔名詞〕朝、吹く東の風。春 | 春日野の萩散りなば朝東風の風にたぐひてここに散り来ね(万10-2129) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさごと [浅事] | 〔名詞〕あさはかなこと。つまらないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさごほり [朝氷・浅氷] | 〔名詞〕初冬や初春の朝はる薄い氷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】氷が融ける意から、「とく」に懸かる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさごろも [麻衣] | 〔名詞〕あさぎぬ。 | 麻衣着ればなつかし紀伊の国の妹背の山に麻蒔く我妹(万7-1214) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あささらず [朝去らず] | [「さる」は離れて行くの意。朝を離れて行かないの意から] 朝ごとに。毎朝。 | -御笠の山に朝さらず雲居たなびき-(万3-375) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あささる [朝さる] | 〔自動詞ラ行四段〕[「さる」は時が来るの意] 朝になる。明けはなれる。明けさる。⇔夕さる |
-朝されば妹が手にまく鏡なす-(万15-3649) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさじのはら [浅小竹原] | 〔名詞〕丈の低いしの竹のはえている原。 | あさじのはら腰なづむ空は行かず足よ行くな(記・中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさしほ [朝潮] | 〔名詞〕朝、さしてくる潮。⇔夕潮 | 堀江より朝潮満ちに寄る木屑貝にありせばつとにせましを(万20-4420) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさじみ [朝凍み] | 〔名詞〕朝、道路などが凍っていること。冬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさじめり [朝湿り] | 〔名詞〕朝、霧や露で、しっとりとしめっていること。 | 薄霧のまがきの花の朝じめり秋は夕べとたれかいひけむ(新古秋上-340) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさしもの [朝霜の] | 【枕詞】 朝の霜は消えやすいことから「消(け)」に、また同音の「御木(みけ)」に懸かる。 |
朝霜の消ぬべくのみや時なしに思ひわたらむ息の緒にして(万12-3059) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさすずみ [朝涼み] | 〔名詞〕夏の朝の涼しい頃。朝すず。夏の朝、涼しい風に吹かれること。夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさせ [浅瀬] | 〔名詞〕水が浅く、波の立つところ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -にあだなみ [浅瀬にあだ波] | 思慮の浅いものは、事に当たって落ち着きがないこと。 古今集の恋四 「そこひなき淵やはさわぐ山川の浅き瀬にこそあだ波はたて」によるという。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさぜち [朝節] | 〔名詞〕節句の朝、節句舞をすること。⇔ゆふぜち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさだち [朝立ち] | 〔名詞〕朝早く、旅に出ること。朝の旅立ち。 | -天離る 鄙治めにと 朝鳥の 朝立ちしつつ 群鳥の 群立ち行かば -(万9-1789) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさだつ [朝立つ] | 〔自動詞タ行四段〕 朝早く旅立つ。 |
-白たへの 天領巾隠り 鳥じもの 朝立ちいまして 入日なす-(万2-210) -群鳥のあさだちいなばおくれたる吾や悲しき-(万17-4032) 群鳥の朝立ち去にし君が上はさやかに聞きつ思ひしごとく [一云 思ひしものを](万20-4498) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさぢがはな [浅茅が花] | 〔名詞〕あちがやの花。茅花の伸びて短い穂になったもの。春 | 秋萩は咲くべくあらし我がやどの浅茅が花の散りゆく見れば(万8-1518) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさぢはら [浅茅原] (あさぢがはら) |
〔名詞〕 「浅茅」が一面に生えている野原。 荒れ果てた家や庭の形容としても多く用いられる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】「ちはら」と「つはら」の類似音から「つばらつばら」にかかる。 | 浅茅原つばらつばらにもの思へば古りにし里し思ほゆるかも(万3-336) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさぢふ [浅茅生] | 〔名詞〕浅茅の生えているところ。「あさぢがはら」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「生」は草などのはえているところをいい、他に「蓬生(よもぎふ)」「麻生(をふ)」などがある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさぢふの [浅茅生の] | 【枕詞】「小野」に懸かる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさづくひ [朝づく日] | 〔名詞〕朝日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】「向かふ」「日向」に懸かる。 | 朝月の日向黄楊櫛古りぬれど何しか君が見れど飽かざらむ(万11-2505) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさづくよ [朝月夜] | 〔名詞〕 ①「つくよ」は「月」の意。明け方の月。 ② 月の残っている夜明け。秋 ⇔夕月夜 |
①-朝月夜さやかに見れば栲の穂に夜の霜降り-(万1-79) ②-あさづくよ明けまく惜しみ-(万9-1765) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさつゆ [朝露] | 〔名詞〕朝、草木においた露。はかないものの譬えにいう。秋 | -思ひ恋ふらむ 時ならず 過ぎにし子らが 朝露のごと 夕霧のごと(万2-217) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさつゆの [朝露の] | 【枕詞】朝露の状態から「消(け)」「置(お)く」に懸かる。 | -あさつゆの消なば消ぬべく恋ふらくも-(万13-3280) 後つひに妹は逢はむと朝露の命は生けり恋は繁けど(万12-3054) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさて [麻布・麻手] | 〔名詞〕「あさで」とも。「麻栲(あさたへ)」の略。また「で」は接尾語とも、「麻の葉」が手を広げた形に似ているところから、ともいう。 【有斐閣「萬葉集全注巻四-521 注『麻手刈り干し』」】 「アサデ」は、加工品としての麻糸・麻布に対する、原料としての刈り取って来たばかりの麻をいうか。「テ」は素材を表わす語のそれであろう。代匠記は「手といふは、麻の葉は人の手をひろげたるに似たれば麻手といへり」 と言うが、攷證はこれを否定し、東国方言とする。麻は、「小垣内(をかきつ)の 麻を引き干し」(9・一八〇〇) とあるように、一般に刈り取らずに引き抜くが、またこのように刈り取ることもあったのであろうか。あるいは作者は実際にはこのような作業に携わらないで詠んだとも考えられる。麻は播種から収穫・製布に至るまですべての工程が女の仕事であった(渡部和雄「東国の麻」国語と国文学四〇年三月)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさと [朝戸] | 〔名詞〕朝方開ける戸。朝起きてあける戸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさどこ [朝床] | 〔名詞〕朝、まだ寝床にいること。朝の寝床。 | 天若日子があさどこに寝し高胸坂に中りて死にき(紀・上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさとりの [朝鳥の] | 【枕詞】「あさどりの」とも。「通ふ」「ねなく」「朝立つ」にかかる。 | -あさとりの通はす君が-(万1-196) 朝鳥の哭のみし泣かむ我妹子に今またさらに逢ふよしをなみ(万3-486) -あさとりの朝立ちしつつ-(万9-1789) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさな [朝菜] | 〔名詞〕朝飯の副食物。海草、野菜など。⇔夕菜 | いざ子ども香椎の潟に白栲の袖さへ濡れて朝菜摘みてむ(万6-962) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさなあさな [朝な朝な] | 〔副詞〕毎朝。朝ごとに。あさなさな。⇔夜な夜な | 朝な朝な立つ川霧のそらにのみうきて思ひのある世なりけり(古恋一-513) あさなさな上がるひばりになりてしか都に行きて早帰り来む(万20-4457) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさなぎ [朝凪] | 〔名詞〕朝がた、海上の風が穏やかになり、波も静まること。夏 ⇔夕なぎ | -あさなぎにかこの声呼び-(万4-512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさにけに [朝に日に] | 〔副詞〕朝ごとに。朝に昼に。いつも。 | いかならむ日の時にかも我妹子が裳引きの姿朝に日に見む(万12-2909) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさの [浅野] | 〔地名〕 淡路島の北淡町浅野。その浅野を少し山手へ登ったところに、「紅葉の滝」がある。 |
-滝の上の 浅野の雉 明けぬとし 立ち騒くらし いざ子ども-(万3-391) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさはふる[朝羽振る] | 朝がた鳥が羽ばたく。風や波が立つことのたとえ。⇔ 「夕羽振る」 | -青なる玉藻沖つ藻あさはふる風こそ寄らめ夕羽振る波こそ来寄れ- (万2-131) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あざはる [糾はる] | 〔自動詞ラ行四段〕絡み合う。捩れ合う。纏わり付く。あざなはる。 | わが手をば妹にまかしめ、まさきづら手抱きあざはり(継体紀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさひ [朝日] | 〔名詞〕朝のぼる太陽。対語→夕日(ゆふひ) | 朝日照る佐田の岡辺に群れ居つつ我が泣く涙やむ時もなし(万2-177) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさひかげ [朝日影] | 〔名詞〕「かげ」は光の意。朝日の光(=朝影)。 | 朝日影にほへる山に照る月の飽かざる君を山越しに置きて(万4-498) 朝日かげにほへる山のさくら花つれなく消えぬ雪かとぞ見る(新古春上-98) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -さし [朝日さし] | 【枕詞】「そがひに見ゆ」「まぎらはし」にかかる。 | 朝日さしそがひに見ゆる-(万17-4027) 上つ毛野まぐはしまとに朝日さしまきらはしもなありつつ見れば (万14-3426) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -さす [朝日さす] | 【枕詞】朝日が「かすか」にさし始めるところから、地名の「春日」にかかる。 | 冬過ぎて春来るらし朝日さす春日の山に霞たなびく(万10-1848) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -なす [朝日なす] | 【枕詞】「なす」は「・・・のように」の意。 朝日のまばゆく美しい情景から「まぐはし」にかかる。 |
-あさひなすまぐはしも夕日なすうらぐはしも-(万13-3248) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -の [朝日の] | 【枕詞】「ゑみさかゆ」にかかる。 | あさひのゑみさかえきて(記・上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさびらき [朝開き] | 〔名詞〕泊まっていた船が、朝早く出発すること。 | あさびらき漕ぎ出てくれば武庫の浦のしほひの潟に鶴が声すも (万15-3617) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさぶすま [麻衾] | 〔名詞〕「ふすま」は掛け布団の意。麻布で作った、粗末な夜具。 | -寒くしあればあさぶすまひきかがふり-(万5-896) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさぼらけ [朝朗け] | 〔名詞〕朝の、ほのぼのと明るくなった頃。夜明け方。 | 朝ぼらけ有り明けの月と見るまでに吉野の里に降れる白雪(古冬-332) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさみ [浅み] | 〔名詞〕「み」は名詞を作る接尾語。川などの浅い所。⇔深み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさみや [朝宮] | 〔名詞〕朝の宮殿。また、朝の宮仕え。[対義語:夕宮(ゆふみや)] | -川藻のごとく なびかひの 宜しき君が 朝宮を 忘れたまふや-(万2-196) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさむ [浅む] | 〔他動詞マ行四段〕あなどる。ばかにする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あざむく [欺く] | 〔他動詞カ行四段〕① だます。悪い方へと誘う。② あなどる。ばかにする。 | 布施置きて我れは祈ひ祷むあざむかず直に率行きて天道知らしめ(万5-911) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさもよし [朝(麻)裳よし] | 【枕詞】「よし」は詠嘆の助詞。 「紀」(紀国、紀人、城上)に懸かる。 |
-畝傍を見つつ あさもよし 紀伊路に入り立ち 真土山 越ゆらむ君は-(万4-546) あさもよし紀伊へ行く君が真土山越ゆらむ今日ぞ雨な降りそね (万9-1684) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさもよひ [朝催ひ] | 〔名詞〕① 朝食の支度、また食事をすること。② 朝食の頃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】「あさもよし」の転じたもの。「き」に懸かる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あざやか [鮮やか] | 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 ① 明らかに麗しいさま。はなやか。② 際立っているさま。はっきり。 ③ すっきりとしたさま。 ④ 性質・言動などが、きっぱりとしているさま。 ⑤ 新鮮だ。生きがいい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あざやぐ [鮮やぐ] | 〔自動詞ガ行四段〕(普通「たり」「て」を伴って) ① 際立っている。極めて新鮮な趣を見せる。 ② てきぱきしている。快活だ。はっきりしている。 ③ しなやかでない。ごわごわしている。どぎつい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞ガ行下二段〕【ゲ・ゲ・グ・グル・ぐれ・ゲヨ】 あざやかにする。はでにする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさゆふ [朝夕] |
〔名詞〕 ① 朝と夕。朝と晩。転じて、日常。副詞的にも用いる。 ② 朝夕の炊煙。生活。生計。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔副詞〕毎日。いつも。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさよひ [朝宵] | 〔名詞〕朝と夕。朝も晩も。 | 畏きや天の御門を懸けつれば音のみし泣かゆあさよひにして(万20-4504) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさらか [浅らか] | 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 薄いさま。浅いさま。あっさりしたさま。 |
くれなゐの薄染め衣浅らかに相見し人に恋ふるころかも(万12-2978) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あざらか [鮮らか] | 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 「らか」は接尾語。「らか」は接尾語。 新鮮なさま。いきいきとしているさま。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あざらけし [鮮らけし] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 「あさらけし」とも。 鮮やかである。新鮮である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさらのころも [浅らの衣] | 〔名詞〕薄い色で染めた衣服。 | 桃花染めの浅らの衣浅らかに思ひて妹に逢はむものかも(万12-2982) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさり [浅り] | 〔名詞〕海や川などの水の浅いところ。浅瀬。あさみ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさり [漁り] | 〔名詞・他動詞サ行変格〕 ① 魚を獲ること。食物を探し求めること。 ② えさを求めること。 |
① あさりすと磯に我が見しなのりそをいづれの島の海人か刈りけむ (万7-1171) ② 夕なぎにあさりする鶴潮満てば沖波高み己妻呼ばふ(万7-1169) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさる [漁る] | 〔他動詞ラ行四段〕 ① えさや食物を求める。② 魚貝や海藻をなどを採る。 ③ 物を探し求める。探し出す。 |
① 草香江の入江にあさる葦鶴のあなたづたづし友なしにして(万4-578) ① 春の野にあさる雉の妻恋ひにおのがあたりを人に知れつつ(万8-1450) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あざる [狂う・戯る] | 〔自動詞ラ行四段〕(語感)正常な心を失う。異常な心理になる。 ① 取り乱して騒ぐ。うろたえる。② 荒れすさぶ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 ① ふざける。② つろぐ。儀式ばらないでくだける。③ 風雅だ。しゃれる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あざる [鯘る] | 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 魚肉などが腐る。 |
海人の苞苴 (オホニヘ、網籠に入れた魚の贈り物)、かよふあひだにあざれぬ (仁徳紀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あざれがまし | 〔形容詞シク活用〕【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 ふざけてみえる。まじめでないように見える。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あざればむ | 〔自動詞マ行四段〕まじめでないように見える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あざわらふ [あざ笑ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 ① 周囲に対する気兼ねや遠慮なしに大声で笑う。 ② 人を軽蔑して笑う。嘲笑する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あし [足・脚] | 〔名詞〕人間や動物の、からだを支えたり移動したりするための器官。あし。 ① 歩くこと。歩み。② 物の下で上をささえているもの。 ③ 太刀の名所で帯取りをつける金具。足がね。④ 餅などのねばり。 ⑤「銭」の異名。⑥ 船の水につかっている部分。 |
我が聞きし耳によく似る葦の末の足ひく我が背つとめ給ぶべし(万2-128) ① 夢路には足もやすめず通へどもうつつに一目見しごとはあらず (古今恋三-658) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -があがる [足が上がる] | 頼るところがなくなる。職を失う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -たゆく [足たゆく] | 足がだるくなるほど、たびたび。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のけ [足の気] | 脚気。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ふみぬく [あし踏みぬく] | 勢いよく足を踏む。踏みつける。 | 三宅の原ゆ 直土に 足踏み貫き 夏草を-(万13-3309) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -をかぎりに [足を限りに] | 足の力の続く限り。足をはかりに。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -をくはる [足を食はる] | わらじで足を痛める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -をそら [足を空] | 慌てて心の落ち着かないさま。急いでいくさま。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あし [葦・蘆] | 〔名詞〕植物の名。=よし。 水辺にはえ春芽を出す。秋、細かい紫色の小花からなる大きな穂を出す。 水辺の、特に「難波 (なには)」の景物として歌に詠まれることが多い。 秋 葦の芽・春 葦茂る・夏 葦の花・秋 葦の穂 |
我が聞きし耳によく似る葦の末の足ひく我が背つとめ給ぶべし(万2-128) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のかりね [葦の仮寝] | 葦を序とし「刈り根」を「仮寝」に言いかけたもの。ちょっと寝ること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のかりほ [葦の仮庵] | 葦を序とし「刈り穂」を「仮庵」に言いかけたもの。仮の宿。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のしのや [葦の篠屋] | 葦または篠で屋根を葺いた家。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のふしのま [葦の節の間] | 短いことの形容。 | 難波潟みじかき葦のふしのまもあはでこの世を過ぐしてよとや (新古恋一-1049) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のまよひ [葦の迷ひ] | 葦が風に乱れるように、歩み行く足の乱れること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のまろや [葦の丸屋] | 葦で葺いた粗末な仮の小屋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のや [葦の矢] | 葦の茎で作った矢。宮廷で十二月晦日の追儺の儀式の時、鬼を射るのに桃の木の弓とともに用いたもの。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あし [悪し] | 〔形容詞シク活用〕【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 ① 悪い。みにくい。卑しい。不快である。憎い。粗末だ。まずい。 ② へただ。不都合だ。失礼だ。具合が悪い。 ③(性格や行動の)たけだけしく恐ろしい。険しい。険悪である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔語法〕この語の連体形は「あしき」が普通だが、「あしかる」の例がまれに見える。終止形に「あしし」を用いた例もまれにある。 〔参考〕「あし」と「わろし」との違い。 ともに形容詞で、「悪い」の意が本義だが、用例を見ると、自然使い分けがある。 「あし」は、用い方によっていろいろ内容は変るが、だいたいは本質的に悪いと積極的に否定する意識の上に立って言う。 これに対して「わろし」は、「よくなくて、従って悪い」というような、相対的・消極的な否定の意識、しかも外面的な意味で用いる。 この関係は「よし」に対する「よろし」の関係と同じである。なお「あし」は上代から使われるが、「わろし」は中古に入ってから、見られる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -かんなる [悪しかんなる] | 悪い。よくない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -きもの [悪しきもの] | 人に祟って害を加える怪物。=もののけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -けひと [悪しけ人] | 「悪しき人」の東国なまりという。悪い人。悪者。 | ふたほがみ悪しけ人なりあたゆまひ我がする時に防人にさす(万20-4406) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしあらひ [足洗ひ] | 〔名詞〕 ① 足を洗うたらい。② 足で踏んで物を洗うこと。 ③ 人の足を洗うような卑しい職業の者。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしうら [足占] | →あうら。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あじか [簣] | ざるのような形をした、土などを入れて運ぶ道具。竹、葦、藁等で編む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしかき [葦垣] | 葦でつくった垣。 | 葦垣の中のにこ草にこやかに我れと笑まして人に知らゆな(万11-2772) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしかきの [葦垣の] | 【枕詞】 葦の垣は古びやすく壊れやすいことから、「ふる」「思ひ乱る」に また間をつめてつくることから、「間ぢか」 に 垣の隔てる性質から、「外(ほか)」 に 葦の一名「よし」から、「吉野」 にかかる。 |
-難波の国は 葦垣の 古りにし里と 人皆の-(万6-933) -天雲の ゆくらゆくらに 葦垣の 思ひ乱れて 乱れ麻の-(万13-3286) 我が背子に恋ひすべながり葦垣の外に嘆かふ我れし悲しも(万17-3998) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしかけ [足掛け] | 〔名詞〕 ① 足を踏みかけるもの。足場。 ② 年月を年や月にまたがって、おおまかに数えること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしかせ [足枷] | 〔名詞〕「あしがせ」とも。罪人の足にはめて自由のきかないようにした刑具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしがちる [葦が散る] | 【枕詞】葦の群生地「難波(なには)」にかかる。 | 海原のゆたけき見つつ葦が散る難波に年は経ぬべく思ほゆ(万20-4386) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしがなへ [足鼎] | 〔名詞〕底に三本の足がある釜で、食物を煮るのに用いる。今の香炉がこの形。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしがに [葦蟹] | 〔名詞〕葦の生えている水辺にいる蟹。 | -難波の小江に 廬作り 隠りて居る 葦蟹を 大君召すと-(万16-3908) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしかび [葦牙] | 〔名詞〕葦の若芽。 | 形葦牙の抜け出たるがごとし (神代紀・上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしがも [葦鴨] | 〔名詞〕(葦の生えてる水辺にいるところから)「鴨」の異名。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしがもの [葦鴨の] | 【枕詞】「うち群れ」にかかる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしがらやま [足柄山] | 〔地名〕 | とぶさ立て足柄山に船木伐り木に伐り行きつあたら船木を(万3-394) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
神奈川県南足柄市・足柄上郡と静岡県との境をなす足柄・箱根山の群の総称。 中央と関東とを結ぶ要路として知られ、静岡県駿東郡小山町から矢倉沢を経て南足柄市関本へ越える道がいわゆる足柄越えであるが、延暦二十一年(802)の富士山の噴火によってふさがり、以後箱根路が開かれることになる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしがらをぶね [足柄小舟] | 〔名詞〕足柄山の木材で造った船。足柄山は良い舟材を産出して知られた。 | 百づ島足柄小舟歩き多み目こそ離るらめ心は思へど(万14-3384) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしかり [葦刈り] | 〔名詞〕葦を刈ること。また、その人。秋 | 葦刈りに堀江漕ぐなる楫の音は大宮人の皆聞くまでに(万20-4483) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -をぶね [葦刈り小舟] | 〔名詞〕葦を刈って積む船。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしきた [芦北] | 〔地名〕 | 芦北の野坂の浦ゆ船出して水島に行かむ波立つなゆめ(万3-247) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1『付録地名一覧』」】 熊本県芦北郡および水俣市の地。熊本県の海岸寄りの南端にあり、鹿児島県に隣接する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしぎぬ [絁] | 〔名詞〕「悪し絹」の意から、糸が粗く、粗悪な絹織物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしく [悪しく] | 〔副詞〕形容詞「あし」の連用形から、悪く、間違えて、へたに。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしげ [悪し気] | 形容詞「あし」に、様子を表す接尾語「げ」がついたもの。 悪い様子。 いかにもへたな様子。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしこ [彼処] | 〔遠称の指示代名詞〕場所をさす。あそこ。=かしこ、かのところ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしざま [悪し様] | 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 薄いさま。浅いさま。あっさりしたさま。 (多く、悪意を含む)悪い様子。⇔善様(よざま)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あししろ [足代] | 〔名詞〕① 材木を組んで、高いところに登る足掛かり。足場。②基礎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしじろのたち [足白の太刀] | 〔名詞〕二つの足金を銀で作った太刀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしすだれ [葦簾] | 〔名詞〕 ① 葦の茎を、糸で編んで作ったすだれ。よしず。 ② 諒闇の時、天皇のこもる御座にかける鈍色の布で淵を取ったよしず。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしずり [足摺り] | 〔名詞〕(怒りや悲しみなどで) 足を地面に摺り、身もだえして怒り嘆くこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしずる [足摺る・足摩る] | 〔自動詞ラ行四段〕「あしする」とも。 (怒りや悲しみなどで) 足摺りをする。地団駄を踏む。 |
-立ち踊り 足摺り叫び 伏し仰ぎ-(万5-909) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしぞろへ [足揃へ] | 〔名詞〕陰暦五月五日の賀茂祭りの競馬に先立ち、五月一日に試乗すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あした [朝] | 〔名詞〕 ① あさ。⇔ゆふべ。宵。 ②(何か事が起こったあとの朝の意から)翌朝。 〔古文では、明日の意味での用例は少ない〕 |
① 矢釣山木立も見えず降りまがふ [雪につどへる朝楽しも] (万3-264)下二句定訓なし ② -思ひ居れか 栲縄の 長き命を 露こそば 朝に置きて 夕には-(万2-217) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【あした】は夜の時間の終り 「あさ」の意に近いが、「あさ」が一日を昼と夜に分けた、昼の時間の始まりを表すのに対して、 「あした」は「ゆふべ→よひ→よなか→あかつき→あけぼの→あした」と続く、夜の時間の終りを表す。 「あさ」は「あさかげ」「あさつゆ」など複合語となることが多く、単独では多く「あした」が使われた。⇒「あかつき」「あさ」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のつゆ [朝の露] | ① 朝の間、草葉などにおく露。あさつゆ。 ② 人生など、はかなく消えやすいたとえ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ゆふべ [朝夕べ] | 朝夕。いつも。常々。 | まそ鏡見飽かぬ君に後れてや朝夕にさびつつ居らむ(万4-575) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -どころ [朝所] | 〔名詞〕 → あいたんどころ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしだか [足高] | 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 ① 足の丈の高いさま。すねの長く見えるさま。 ② 道具の、高い足の付いたもの。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしだち [足立ち] | 〔名詞〕足を立てる所。足場。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしたづ [葦田鶴] | 〔名詞〕「鶴」の異名。葦の生えている水辺にいるところからいう。 | 潮干れば葦辺の騒くあしたづの妻呼ぶ声は宮もとどろに(万6-1068) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしたづの [葦田鶴の] | 【枕詞】「音になく」「たづたづし」「乱る」に懸かる。 | 住江のまつほど久になりければあしたづのねになかぬ日はなし(古恋五-779) 君に恋ひいたもすべなみ葦鶴の哭のみし泣かゆ朝夕にして(万3-459) 草香江の入江にあさる葦鶴のあなたづたづし友なしにして(万4-578) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしだま [足玉] | 〔名詞〕上代、足首につけた飾りの玉。 | 皇女がもたる足玉手玉をな取りそ(仁徳紀) 足玉も手玉もゆらに織る服を君が御衣に縫ひもあへむかも(万10-2069) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしだまり [足溜まり] | 〔名詞〕① ちょっと止まる所。② 足をかける所。足がかり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしつき [足付き] | 〔名詞〕① 歩き方。②「足付き折敷」の略、足の付いた折敷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしつき [葦付き] | 〔名詞〕淡水に生える藻の一種。葦の茎や石などに付く。あしつきのり。 | 雄神川紅にほふ娘子らし葦付き取ると瀬に立たすらし(万17-4045) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしつぎ [足継ぎ] | 〔名詞〕踏み台。踏継ぎ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしづつ [葦筒] | 〔名詞〕葦の茎の内側についている薄い紙のような皮。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしづつの [葦筒の] | 【枕詞】「一重」「薄き」にかかる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしづの [葦角] | 〔名詞〕角のようにとがっているところから、葦の新芽。葦牙(あしかひ)。春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしつを [足津緒] | 〔名詞〕 ① 琴の弦の端に、白、黄色、浅黄、薄萌黄の四色の糸をよった組み糸で結びかがったもの。 ② 乗馬の口につけて引く、太く長いさしなわ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしで [葦手] | 〔名詞〕「手」は筆跡で、葦のように書いた筆跡の意。 ① →あしでがき。② 紅などで、葦の形を下絵にした紙。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしでがき [葦手書き] | 〔名詞〕 平安時代に始められた美術的な仮名書き書体の一つ。水の流れを絵に書いて、そばに歌を墨書書きの草仮名で、葦の生い茂っているように細く書いたもの。 のちには石・家・島などの形にもかたどって書いた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしてかげ [足手影] | 〔名詞〕「かげ」は、姿・形の意。 ① 手足の影。面影。② (「人の足手影」の形で) 人影が多くあること。人の賑わい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしどり [足取り] | 〔名詞〕あるきつき。足の運び。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしなふ [蹇ふ] | 〔自動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 足が自由にならないで思うように歩けない。=あしなへぐ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしなへ [蹇へ・跛へ] | 〔名詞〕足の不自由なこと。 | 那良戸よりはあしなへ盲会はむ(記・中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしなみ [足並み] | 〔名詞〕① 隊を組んでいくときの足の揃い方。歩調。②足ごと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -あしなみに [足並み] | 〔副詞〕一歩進むごとに。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしに [葦荷] | 〔名詞〕刈り取った葦の積み荷。 | 大船に葦荷刈り積みしみみにも妹は心に乗りにけるかも(万11-2758) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしねはふ [葦根はふ] | 【枕詞】「した」「憂き」にかかる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしのねの [葦の根の] | 【枕詞】「ねもころ」「分く」「短き」「憂き」「夜」「世」にかかる | 葦の根のねもころ思ひて結びてし玉の緒といはば人解かめ(万7-1328) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしばや [足速] | 〔名詞・形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 「あし」は船の水に浸かっている部分の意。あはや。 歩くことの速いこと。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -をぶね [足速小舟] | 〔名詞〕船足の速い小舟。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしはら [葦原] | 〔名詞〕葦の生い茂った広い原。 | 葦原にしけしき小屋に(記・中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のなかつくに [葦原の中国] | (葦原の生い茂った、高天原と黄泉の中間にある国の意で)日本国の称。 | 今葦原の中国をことむけをへぬとまをす(記・上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のみずほのくに [葦原の瑞穂の国] | (葦原の中にあって、瑞々しい稲の実っている国の意で) 日本の美称。 | -葦原の 瑞穂の国を 天地の 寄り合ひの極み 知らしめす-(万2-167) 葦原の 瑞穂の国を 天下り 知らしめしける すめろきの(万18-4118) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしひ [葦火] | 〔名詞〕「あしび」 とも。葦を乾かして、焚き木としてもやす火。 |
難波人葦火焚く屋の煤してあれどおのが妻こそ常めづらしき(万11-2659) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【葦火を焚く家の妻】 古代では、「照る・かかやく・かがよふ(=きらめく)・光る・にほふ(=照り輝く) 」などの語で美しさが語られる。 古代人にとっては、あたりを明るくするような、はなやかな美しさこそが理想のものだったのだろう。 だから、こそ、前項の用例に引いた「万葉集」 の「難波人(なにはひと)・・・」 の歌が強烈に胸を打つ。 難波の葦を、燃料に煮炊きをするから、家の中は煤だらけになる。その家にあってすすけているけれども、すすけくすんだ妻だからこそいっそういとしいのである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしび [馬酔木] | 〔名詞〕木の名。 春、つぼ形の白い小花をふき状につける低木。 葉に毒があって、牛馬が食うと中毒する。 奈良地方の馬酔木は、特に有名。あせみ、あせび、とも言う。 |
磯の上に生ふる馬酔木を手折らめど見すべき君が在りと言はなくに (万2-166) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ーなす [馬酔木なす] | 【枕詞】馬酔木の花が、一斉に咲くことから、「栄ゆ」 にかかる。 | 酔木なす栄えし君が掘りし井の石井の水は飲めど飽かぬかも(万7-1132) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしひきの [足引きの] | 【枕詞】上代は「あしひきの」の後、「あしびきの」と濁る。 「山・峰・尾の上・やつを・岩根・岩・木・あらし・野・遠面・葛城山・笛吹山・岩倉山」などにかかる。 〔転、形容詞〕 「あしひきの」は「山」にかかる枕詞であったが、慣用のうちに「山の」の意にも用いられるようになった。 |
あしひきの山のしづくに妹待つと我れ立ち濡れぬ山のしづくに(万2-107) むささびは木末求むとあしひきの山の猟夫にあひにけるかも(万3-269) あしひきの山川の瀬の鳴るなへに弓月が岳に雲立ちわたる(万7-1092) 〔転〕 あしひきの岩根こごしみ菅の根を引かば難みと標のみそ結ふ(万3-417) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 語義には「青繁木(あをしみき)」の意。「足を曳きあえぎつつ登る」の意、「山すそを長く引く」の意など多くの説がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしふ [葦生] | 〔名詞〕葦の生い茂ったところ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしぶ [葦火] | 〔名詞〕上代東国方言。「ぶ」は 「火」 の意。→あしび | 家ろには葦火焚けども住みよけを筑紫に至りて恋しけ思はも(万20-4443) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしふいご [足鞴] | 〔名詞〕足指で柄をはさみ押したり引いたりして風を起こすふいご。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしぶみ [足踏み] | 〔名詞〕舞などの足拍子。あしどり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしべ [葦辺] | 〔名詞〕葦の生えている水辺。 | 若の浦に潮満ち来れば潟をなみ葦辺をさして鶴鳴き渡る(万6-924) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしほやま [葦穂山] | 【枕詞】「悪しかる」にかかる。 | 筑波嶺にそがひに見ゆる葦穂山悪しかるとがもさね見えなくに(万14-3409) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしま [葦間] | 〔名詞〕葦のしげみの間。 | すむひともあるかなきかのやどならしあしまのつきのもるにまかせて (新古雑上-1528) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしまくら [葦枕] | 〔名詞〕葦の生えている水辺で宿ること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしまゐり [足参り] | 〔名詞〕貴人の足をもみさすること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あしもと [足元・足下] | 〔名詞〕① あしのあたり。② 身のまわり。③ 足の運び具合。 | -遠きところも出でたつあしもとよりはじまりて-(古今・仮名序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -からとりがたつ [足元から鳥が立つ] | 突然身辺に意外なことが起こる。または、急に思い立って物事を始める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のあかるいうちに [足元の明るい内に] |
日が暮れぬうち。転じて自分の運が、まだ傾ききらないうちに。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -をみる [足元を見る] | 弱点に乗じる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あじろぎ [網代木] | 〔名詞〕[「あじろき」とも] 「あじろ」を支えるために打つ杭。〔冬〕 | もののふの八十宇治川の網代木にいさよふ波の行くへ知らずも(万3-266) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あす [浅す] | 〔自動詞サ行下二段〕【セ・セ・ス・スル・スレ・セヨ】 海や川などが浅くなる。水がかれる。 |
ひさかたの天の探女が石船の泊てし高津はあせにけるかも(万3-295) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あす [褪す] | 〔自動詞サ行下二段〕【セ・セ・ス・スル・スレ・セヨ】 色などが淡く、さめてくる。影などが薄くなる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あす [明日] | 〔名詞〕あした。翌日。 | うつそみの人なる我れや明日よりは二上山を弟背と我が見む(万2-165) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あすか [明日香] | 〔地名〕[歌枕]「飛鳥」とも書く。 | 飛ぶ鳥の明日香の里を置きて去なば君があたりは見えずかもあらむ [一云 君があたりを見ずてかもあらむ](万1-78) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今の奈良県高市郡明日香村および橿原市東部。北は大和三山で限られ、飛鳥川がその中央部を流れる。推古天皇以後約百年間、皇居のあった地。 明日香の枕詞「飛ぶ鳥の」から「飛鳥」の字をあてる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あすかかぜ [明日香風] | 〔名詞〕飛鳥の地を吹く風。 | 采女の袖吹きかへす明日香風都を遠みいたづらに吹く(万1-51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あすかがは [飛鳥川] | 〔地名〕[歌枕] |
-偲ひ行かむ 御名にかかせる 明日香川 万代までに はしきやし-(万2-196) 明日香川しがらみ渡し塞かませば流るる水ものどにかあらまし [一云 水の淀にかあらまし](万2-197) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今の奈良県高市郡南部の高取山に源を発し、明日香地方を貫流し、磯城郡で大和川に注ぐ川。古来、淵瀬の定まらないことで知られ、世の無常にたとえて歌に詠まれた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あそそに | 〔副詞〕《上代語》うすうす。ほのかに。 | -君はあるらむと あそそには かつは知れども しかすがに-(万4-546) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あそび [遊び] | 〔名詞〕 ① 慰み。行楽。② 詩歌。音楽。遊芸など。 ③ 特に管弦のあそび。音楽を奏でること。④ 狩り。⑤ 神楽。歌舞。 ⑥ 子供の遊戯。⑦ 賭け事や酒色にふけること。遊興。 ⑧ 「遊び女 (め)」の略。明 |
① 白露を取らば消ぬべしいざ子ども露に競ひて萩の遊びせむ(万10-2177) ④ 鳥の遊び、すなどり(=漁) しに(記上) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あそびを [遊び男] | 〔名詞〕雅楽を奏する人。楽人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あそぶ [遊ぶ] | 〔自動詞バ行四段〕 ① 好きなことをして、心を慰める。管弦を奏し、狩り・行楽・遊園などを楽しむ。 ② 詩歌・管弦などを楽しむ。音楽を奏する。 ③ 遊戯・娯楽を楽しむ。また、働かずに過ごす。 ④ 鳥獣や魚などが、動き回る。 |
① -思ほしし 君と時どき 出でまして 遊びたまひし-(万2-196) ① 月夜よし川の音清しいざここに行くも行かぬも遊びて行かむ(万4-574) ① ももしきの大宮人の罷り出て遊ぶ今夜の月のさやけさ(万7-1080) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞バ行四段〕音楽を演奏する。舞楽をする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あた [仇・敵・賊] | 〔名詞〕《近世の中ごろから「あだ」》 ① 害をなすもの。自分に向かって攻めてくるもの。敵。かたき。 ② 害。危害。③ 恨みの種。 |
① 大君の 遠の朝廷と しらぬひ 筑紫の国は 敵守る お-(万20-4355) ③ 形見こそ今はあたなれこれなくは 忘るるときもあらましものを (古今恋四-746) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あたたけし [暖けし] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 暖かい。 | しらぬひ筑紫の綿は身に付けていまだは着ねど暖けく見ゆ(万3-339) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あたひ [価・値] | 〔名詞〕 ① そのものの値打ちに相当する代わりの物。値段。 ② 風流を解する人。粋人。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -なきたから [無き宝] | 〔名詞〕値のつけられないほど尊い宝。 | 価なき宝といふとも一坏の濁れる酒にあにまさめやも(万3-348) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あたふ [与ふ] | 〔他動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 (事物や影響などを)与える。 |
-みどり子の 乞ひ泣くごとに 取り与ふる 物しなければ-(万2-210) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あたむ [仇む] | 〔他動詞マ行四段〕うらむ。かたきとする。敵視する。 | ① -敵見たる 虎か吼ゆると 諸人の おびゆるまでに [一云 聞き惑ふまで] -(万2-199) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あたら [惜] | 〔形容詞「惜(あたら)し」 の語幹〕 ① (連体) 惜しむべき。もったいない。せっかくの。 ② (副詞) 「あったら」とも。もったいないことに。おしくも。 む |
① とぶさ立て足柄山に船木伐り木に伐り行きつあたら船木を(万3-394) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あたり [辺り] | 〔名詞〕 ① あるものの周辺。付近。近いところ。 ② 婉曲に家・人などをさす語。 |
① 埴生坂我が立ち見ればかぎろひの燃ゆる家群妻が家の辺り-(記下) ① 燈火の明石大門に入らむ日や漕ぎ別れなむ家のあたり見ず(万3-255) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あぢ | 〔名詞〕 水鳥の名。鴨の一種。味鴨または巴鴨といわれる小形の水鳥で、雄の顔には淡黄褐色と緑色からなる巴形の斑紋がある。秋飛来し春帰る。 |
-鴨つま呼ばひ 辺つへに あぢ群騒き ももしきの 大宮人の-(万3-259) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あぢさはふ | 【枕詞】 「目・夜昼知らず」 にかかる。 |
-常宮と 定めたまひて あぢさはふ 目言も絶えぬ 然れかも-(万2-196) 朝戸を早くな開けそあぢさはふ目が欲る君が今夜来ませる(万11-2560) -春鳥の 哭のみ泣きつつ あぢさはふ 夜昼知らず かぎろひの-(万9-1808) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あぢむら [あじ群] | 〔名詞〕あじ鴨の群れ。この鳥は群棲するため群れとなる。〔季語:冬〕 | -人さはに 国には満ちて あぢ群の 通ひは行けど 我が恋ふる-(万4-488) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -の [あぢ群の] | 【枕詞】 あじ鴨の群れが騒ぎ、往来することから、「騒(さわ)く」「通ふ」「撓(とを)よる」にかかる。 |
-人さはに 国には満ちて あぢ群の 通ひは行けど 我が恋ふる-(万4-488) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あづさゆみ [梓弓] | 〔名詞〕梓の木で作った弓。梓。 | -い寄り立たしし み執らしの 梓の弓の 中弭の 音すなり 朝猟に-(万1-3) -心振り起し 剣大刀 腰に取り佩き 梓弓 靫取り負ひて 天地と-(万3-481) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】 弓の縁。「い・いる・ひく・はる・本・末・弦・おす・寄る・かへる・ふす・たつ・や・音」にかかる。 |
梓弓引きみ緩へみ来ずは来ず来ば来そをなぞ来ずは来ばそを(万11-2648) 梓弓春山近く家居れば継ぎて聞くらむ鴬の声(万10-1833) -玉梓の 使ひの言へば 梓弓 音に聞きて [一云 音のみ聞きて] -(万2-207) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あづま [東] | 〔名詞〕 ① 京都から見て本州東方諸国の総称。東国。 ② 鎌倉幕府の称。または、京都から鎌倉を称した語。 ③ 東琴(あづまごと) の略。 |
① -定めたまふと 鶏が鳴く 東の国の 御いくさを 召したまひて-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 「①」の範囲は文献や時代によって、逢坂の関以東、箱根山以東など、異なる。「源氏物語(常夏)」 に「あづまとぞ、名も立ち下りたるやうなれど」 と東琴について述べている件(くだり) から察して、都人は文化の遅れた辺鄙な土地という感覚で「あづま」 を理解していたらしい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あづまひと [東人] | 〔名詞〕 東国 (三河・信濃以東をいうか) の人。(あづまうど) | 東人の荷前の箱の荷の緒にも妹は心に乗りにけるかも [禅師](万2-100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あづまをみな [東女] | 〔名詞〕東国の女。(都の人から低く見られていたところから) 卑しい女。田舎娘。 | 庭に立つ麻手刈り干し布さらす東女を忘れたまふな(万4-524) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あと [跡] | 〔名詞〕[「足(あ)処(と)」の意] ① 足跡。② 出入り。往来。③ 足。足もと。足の方。④ 歩いた道。行方。 ⑤ 形見。遺跡。痕跡。⑥ 根拠。⑦ 筆の跡。文字。書いたもの。筆跡。 ⑧ 手本。前例。しきたり。⑨ 家督。後継者。 |
③ -父母は 枕の方に 妻子どもは 足の方に 囲み居て 憂へさまよひ-(万5-896) ⑤ 我が背子が跡踏み求め追ひ行かば紀伊の関守い留めてむかも(万4-548) ⑤ 吹く風の 見えぬがごとく 跡もなき 世の人にして 別れにし(万15-3647) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あとなし [跡無し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① 人の訪れがない。② 跡形がない。③ 根拠がない。事実でない。 ④ 前例がない。比類がない。 |
② 世の中を何に喩へむ朝開き漕ぎ去にし船の跡なきごとし(万3-354) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あどもふ [率ふ] | 〔他動詞バ行四段〕《上代語》 引き連れる。一説に、声をかけて隊列などを整える意とも。 |
-大御手に 弓取り持たし 御軍士を 率ひたまひ 整ふる-(万2-199) -召し集へ 率ひたまひ 朝狩に 鹿猪踏み起し 夕狩に 鶉雉踏み立て-(万3-481) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あな | 〔感動詞〕[喜怒哀楽の感動から自然に発せられる声から生じた語] ああ。あら。 |
あな醜賢しらをすと酒飲まぬ人をよく見ば猿にかも似る(万3-347) 草香江の入江にあさる葦鶴のあなたづたづし友なしにして(万4-578) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔語法〕 「あな」のあとには多く形容詞(ク活用はその語幹、シク活用は終止形)がくるが、ときには形容動詞(語幹)がくる。また、間投助詞「や」を伴うものもある。 【有斐閣「萬葉集全注巻三-344」 注『あな醜』】 アナは感動詞。ミニクは「見苦(みにく)し」の語幹。原文の「痛」は「痛(つう)なること切(せつ)なること」の意で、アナと訓む。 『古語拾遺』に「阿那於茂志呂(アナオモシロ)」に注して「古語ニ事ノ甚ダ切ナル皆阿那ト称(い)フ」とあるのが参考になり、なお神武紀訓注に「大醜、此云/鞅奈瀰尓勾(アナミニク)」とある。 アナ+形容詞語幹の例は多い。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あに [豈] | 〔副詞〕 ①(下に打消しの語を伴って) 決して。何も。 ②(下に反語の語を伴って) どうして。なんで。 |
① なつむしのひむしの衣二重着て囲み宿りはあによくもあらず(仁徳紀) ② 価なき宝といふとも一坏の濁れる酒にあにまさめやも(万3-348) ② 夜光る玉といふとも酒飲みて心を遣るにあにしかめやも(万3-349) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あは [粟] | 〔名詞〕イネ科の作物。「五穀」の一つ。あわ。 | ちはやぶる神の社しなかりせば春日の野辺に粟蒔かましを(万3-407) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あはしま [粟島] | 淡路の野島の崎の浜風に妹が結びし紐吹き返す(万3-252) 武庫の浦を漕ぎ廻る小舟粟島をそがひに見つつともしき小舟(万3-361) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 巻三-358 『付録 地名一覧』】 所在未詳。四国の阿波方面とか、屋島の北にある島、淡路島の属島など諸説がある。 万葉集には他に周防(すおう 山口県の東南部)の屋代島をさしたかと思われる例(旧三六三一) もある。 【有斐閣「萬葉集全注巻三-358 注『粟島』」】 「淡島」ではなく、「粟島」と表記しているので、四国をさすと考えてよい。ここでは武庫の浦から背向(そがい)に見える島だから四国をさすのである。 それは「淡路を過ぎ 粟島を そがひに見つつ」(4・五〇九) とある「粟島」も淡路(この名が「アハ/四国への道」 という意に基づいている) との関係において、四国だと認定できる。一方、巻十五の三六三一番歌の「安波之麻(アハシマ)」は同じ発音でも、「周防国玖河郡麻里布浦」を行く時の歌だから、山口県東南部の屋代島に比定できるわけで、常にアハシマは「四国」だとは限らない。 さて、古典集成に注意するように、「粟島」に「逢ふ」をかけていると見なければ、この歌の面白さは分からない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あはぢ [淡路] | 〔地名〕淡路島。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あはに | 〔副詞〕多く。たくさん。 | 降る雪はあはにな降りそ吉隠の猪養の岡の寒からまくに(万2-203) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻二-203 注『あはに』」】 「アハニ」の解釈には諸説あって、「淡に」の意とするもの(拾穂抄)、「アハ」を地名とするもの(攷證)、「多に」の意で「サハ」と「アハ」とが通ずるとするもの(新考など)が見られる。 「淡に」では一首の歌意にあらず、地名説も、下句の「吉隠の猪養の岡」との関連を考えると成り立ち難いように思われる。 私注には「安幡尓」の字面によって「アバニ」と訓み、「小地名の今に伝へられぬもののあることはこの歌の猪養の如くであるから、藤原京から吉隠への途上に安幡といふ地が存在したといふ推定も、全然否定は出来ないことであらう」といい、巻七・一四〇一の「かがみなす吾が見し君を阿婆の野の花立花の玉に拾ひつ」の「阿婆」と、二〇三歌の「安幡」とが同一の地ではなかろうかとする。 地名説としてよく考えられたものであるが、結句を「寒からまくに」と訓むか「塞(関)にならまくに」と訓むかによって、その可否は左右されるように思われる。 澤瀉注釈にこれらの説を批判した上で、略解に「宣長云、近江の浅井郡の人の云く、其あたりにては、浅き雪をばゆきといひ、深く一丈もつもる雪をばあはといふと也。 ここによくかなへり」とするも、確かに北越雪譜や、伴蒿蹊の閑田耕筆(一)などに見られるものの、多くは雪崩の意に用いられていて今の場合に適切とはし難いと否定している。 ちなみに、閑田耕筆には、「近江彦根の陪臣大菅中養父、其主の領地を検する時、或山家にて不納を責るにつきて其家の後山に林繁茂せるを見付、是を伐剪て、代(シロ)なさば、かく未納にも及ぶまじきをと咎む。 農夫いな、これなくてはあわのふせぎ、いかにともすべからずといふ。それは何の事ぞと問しに、雪はつもる物なり。 あわはつみて崩るるものなれば、林をもて防がざれば、家をうちたふすなりと答へけるに、中養父は古義を好む人なれば、はじめてとさとりぬ。 万葉集に『ふる雪はあわになふりそ吉隠のゐかひの岡の塞ならまくに』とあるも正しく是にてあわは降りて崩るる故に塞そなりがたければ、あわにはふることなかれといふなりけりとなり」とあって、蒿蹊もアワを崩れるものとして理解していたことが知られる。 それでは、二〇三歌にはふさわしくないであろう。サハとアハとの通用を最初に考えたのは井上新考で、「案ずるにアハはサハの誤にあらでアハ即サハにてサハは元来サアハの約即アハにサの添へるなるべし」と推定したのであるが、澤瀉注釈にこれを補強し、佐竹昭広説として上代国語におけるア行音のサ行音に転じて用いられた例をあげている。 播磨風土記賀古郡の鴨波(アハハ)里に「昔大部造等始祖、古理賣(コリメ)耕此之野多種粟。故曰粟々(アハハ)里」とある。 アハハは、アハアハの略で、その一つのアハは多(サハ)の意であって、これはアハ、サハ通用の例と見られると言い、そのほか、アクとサク、アカルとサカルなどの動詞も例にあげられている。この説に従うべきか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あはに [淡に] | 〔副詞〕はかなく。たよりなく。淡く。ゆるく。 【参考】和歌では多く「泡(あわ)」にかけて詠む。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あはれ | 〔名詞〕 ① しみじみとした感慨。身にしみた感動。 ② しみじみと感じる情趣。ふぜい。 ③ 悲哀。寂しさ。④ 愛情。同情。⑤ 人情。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 ① しみじみと感動する。感に堪えない。 ② しみじみと情趣が深い。 ③ こころがひきつけられ、面白い。美しい。 ④ やさしく、優美だ。⑤ かわいい。いとしい。なつかしい。 ⑥ 気の毒だ。不憫だ。かわいそうだ。⑦ 尊い。ありがたい。 ⑧ 愛情が深い。やさしい。⑨ 立派だ。嘆賞すべきだ。感心だ。 |
④ あはれなるやうにて強からず(古今仮名序) ⑥ 家ならば妹が手まかむ草枕旅に臥やせるこの旅人あはれ(万3-418) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔感動詞〕感嘆・嘆美・悲哀・哀憐・同情・愛着・驚嘆などの感動を表す。 ああ。ほんとうに。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【語史】 「あはれ」 は元来「ああ、はれ」 という感動のことばのつまったものといわれ(宣長説)、感動詞で、奈良時代までは、まだ形容動詞も名詞もなかったが、中古になって「あはれなり」 という形容動詞ができ、「しみじみとした感動」 の状態を表すようになり、さらに転じて、その語幹「あはれ」 が名詞として用いられるようになった。 【文学理念「あはれ」】 平安時代、「をかし」 とともに重要な美的理念となった語。人間の運命や自然・世態に接して深い感動の境地に没入して、それに同感してしみじみとした思いに浸る状態を表す。すばらしい、愛らしい、かわいそうである、悲しいなど、さまざまな感情で心動かされた状態である。本来、人間として事に触れて感動しない者は無風流な者であって、人の心の分からない人間ということになる。→「をかし」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -がる | 〔他動詞ラ行四段〕[「がる」は接尾語] ① ひどく悲しく思う。② 感嘆する。ほめたたえる ③ いたましく思う。同情する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ぶ | 〔他動詞バ行四段〕→「あはれむ」 | 花をめで、鳥をうらやみ、霞みをあはれび(古今仮名序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -まし [憐れまし] | 〔形容詞シク活用〕【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 [動詞「あはれむ」に対応する形容詞] あわれをそそるさま。あわれっぽい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -み [憐れみ] | 〔名詞〕いとしい。または、かわいそうだと思うこと。また、その気持ち。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -む | 〔他動詞マ行四段〕 ① 情趣を感じる。。めでる。② 気の毒に思う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あひ [相] | 〔接頭語〕動詞に付いて、 ① いっしょに。二人で。② 互いに。③ 語調を整え、重みを加える。 |
③ 佐保過ぎて奈良の手向けに置く幣は妹を目離れず相見しめとそ(万3-303) ③ たらちねの親の守りとあひ添ふる心ばかりは関なとどめそ(古今離別-368) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あびき [網引き] | 〔名詞〕「あ」は「網」の意。 魚を捕るために、網を引くこと。 |
大宮の内まで聞こゆ網引すと網子ととのふる海人の呼び声(万3-239) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あひだ [間] | 〔名詞〕 ① 物と物との隔たり。すきま。 ② ある事の起きているひと続きのとき。とき。 ③ 一つのことがやんで次が始まるまでの時の隔たり。絶え間。ひま。 ④ 二つのこと、または、ものの範囲。~のうち。 ⑤ (人と人との) 間柄。 ⑥ 形式名詞として接続助詞のように用いて原因・理由を示す。~ので。~だから。 |
② -草枕 旅なる間に 佐保川を 朝川渡り 春日野を そがひに見つつ-(万3-463) ② 真袖持ち床うち掃ひ君待つと居りし間に月かたぶきぬ(万11-2675) ③ しきたへの手枕まかず間置きて年そ経にける逢はなく思へば(万4-538) ③ 霍公鳥間しまし置け汝が鳴けば我が思ふ心いたもすべなし(万15-3807) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -なし | 絶え間がない。 | 大伴の御津の白波間なく我が恋ふらくを人の知らなく(万11-2746) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -よ [間夜] | 〔名詞〕会った次に会うまでの間の夜。会わないでへだたっている夜。 | 小筑波の嶺ろに月立し間夜はさはだなりぬをまた寝てむかも(万14-3413) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あひみる [相見る・逢ひ見る] | 〔他動詞マ行上一段〕【ミ・ミ・ミル・ミル・ミレ・ミヨ】 ① 対面する。会見する。② 男女が関係を結ぶ。 |
① 山辺の御井を見がてり神風の伊勢娘子どもあひ見つるかも(万1-81) ① 岩屋戸に立てる松の木汝を見れば昔の人を相見るごとし(万3-312) ② 相見ずは恋ひざらましを妹を見てもとなかくのみ恋ひばいかにせむ(万4-589) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あふ [合ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 ① 一つになる。一緒になる。一致する。 ② 調和する。似合う。つり合う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔補助動詞ハ行四段〕[動詞の連用形の下に付いて] 複数のものが同じ動作をする意。「みんな~する・~しあう」 |
うらさぶる心さまねしひさかたの天のしぐれの流れあふ見れば(万1-82) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あふ [会ふ・逢ふ・合ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 ① 出会う。対面する。来あわせる。 ②(時間・機会に)出くわす。あたる。適合する。 ③ 男女が契る。結婚する。④ 立ち向かう。対抗して争う。 |
① 楽浪の志賀の [一云 比良の] 大わだ淀むとも昔の人にまたも逢はめやも [一云 逢はむと思へや](万1-31) ① 直に逢はば逢ひかつましじ石川に雲立ち渡れ見つつ偲はむ(万2-225) ② 大君の和魂あへや豊国の鏡の山を宮と定むる(万3-420) ④ 香具山と耳成山とあひし時立ちて見に来し印南国原(万1-14) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あふ [敢ふ] | 〔自動詞ハ行下二段活用〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 ① たえる。もちこたえる。こらえる。 ② まあ、よしとする。さしつかえない。 |
① -見えつつ かく恋ひば 老いづく我が身 けだしあへむかも (万19-4244) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔補助動詞ハ行下二段活用〕(動詞の連用形の下について) 終わりまで~しおおせる。完全に~しきる。また、しいて~する。 【語法】 「あへず」「あへなむ」と、助動詞をともなって用いられることが多い。 |
天雲に雁ぞ鳴くなる高円の萩の下葉はもみちあへむかも(万20-4320) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あふ [(接ふ)] | 【有斐閣「万葉集全注巻第二-116 題詞「接」」注】但馬皇女在高市皇子宮時竊接穂積皇子事既形而御作歌一首 「万象名義」に「子反會・□□持・合」とあり、「新撰字鏡」に「子□反支也持也引也跡也交也會也対也」と注されている。 「交」は「人妻に吾も交らむ」(9・1759) の例のように「マジハル」とも訓まれるが、男女関係を広くあらわす「アフ」とも訓まれるので、ここは「交・会・接」に通ずる訓としてそれによっておく。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あふぐ [仰ぐ] | 〔他動詞ガ行四段〕① 顔を上に向ける。見上げる。② 尊敬する。敬う。 | -大船の 思ひ頼みて 天つ水 仰ぎて待つに いかさまに-(万2-167) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あふみ [近江] (近江の海・近江の湖) | 〔地名〕旧国名。東山道八カ国の一つ。今の滋賀県。 | 近江の海夕波千鳥汝が鳴けば心もしのにいにしへ思ほゆ(万3-268) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琵琶湖は淡水なので、古くは「淡海」と書いた。 「近江」は、「遠江(とほたふみ)」に対して「近つ淡海(=都に近い淡海、すなわち琵琶湖)」の意。近江の海。近江の湖。 [淡海] 淡海(=淡水の海)のある国、近江の国(滋賀県)。[近江の海] 歌枕。「近江の湖(うみ)」とも書く。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 『付録 地名一覧』」】 今日の滋賀県に当たる。元来、淡水湖を意味する普通名詞「アハウミ(淡海)」 の約。 「近江」と記すのは、遠ツアフミ即ち浜名湖のある東海道の国名「遠江(とおとうみ)」に対する書き方。『和名抄』には「知加津阿不三(ちかつあふみ)」の訓が見られる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あへく [喘く] | 〔自動詞カ行四段〕〔中世以降「あへぐ」〕息をきらす。せわしく呼吸する。 | -海路に出でて あへきつつ 我が漕ぎ行けば ますらをの-(万3-369) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あへのいちぢ [阿倍の市道] | 〔名詞〕 阿倍の市へ行く道。「アヘ」は駿河の国府のあった現在の静岡市の古名。 駿河の国府は大宝年間(701~704) に廬原から阿倍に移ったといわれる。 |
焼津辺に我が行きしかば駿河なる阿倍の市道に逢ひし児らはも(万3-287) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あへのしま [阿倍の島] | 〔地名〕 | 阿倍の島鵜の住む磯に寄する波間なくこのころ大和し思ほゆ(万3-362) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全集万葉集巻三-359 注『阿倍の島』」】 未詳。摂津(『八雲御抄』、仙覚抄)、大阪市阿倍野区(『地名辞書』)、紀州海部郡(海草郡) の阿部島(檜嬬手)、播磨国風土記にいう加古郡阿閇津あたり(私注) などの説があるが確証はない。「阿倍」には「饗(あへ)」に基づいた命名で、島の名となっているのであるから、航行上の安全を祈願して神に饗応する場所をもった島の意であろうと考えられる。ただし、どの島であるかは未詳。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あま [天] | 〔名詞〕天。空。 【参考】「あめ」の古形という。 多く「天の」「天つ」「天飛ぶ」など、他の語に付いた形で用いられる。 |
ひさかたの天行く月を網に刺し我が大君は蓋にせり(万3-241) あをによし奈良の都にたなびける天の白雲見れど飽かぬかも(万15-3624) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あま [尼] | 〔名詞〕 ① 出家して仏門に帰依した女性。 ②《近世語》童女・女性をいやしめていう語。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あま [海人・海士・白水郎] | 〔名詞〕[「海女あまめ」とも] ① 漁業や製塩に従事する人。漁師。漁夫。あまびと。 ②〔「海女」とも書く〕海に潜って貝・海藻などをとる女性。 |
① 打ち麻を麻続の王海人なれや伊良虞の島の玉藻刈ります(万1-23) ① 大宮の内まで聞こゆ網引すと網子ととのふる海人の呼び声(万3-239) ① 荒たへの藤江の浦にすずき釣る海人とか見らむ旅行く我れを(万3-253) ② -たづきを知らに 網の浦の 海人娘子らが 焼く塩の 思ひぞ焼くる(万1-5) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまぐも [天雲] | 〔名詞〕《上代は「あまくも」》空にある雲。雲。 | -斎きの宮ゆ 神風に い吹き惑はし 天雲を 日の目も見せず-(万2-199) 天雲のそくへの極み遠けども心し行けば恋ふるものかも(万4-556) 思はぬにしぐれの雨は降りたれど天雲晴れて月夜さやけし(万10-2231) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまぐもの [天雲の] | -天雲の 八重かき別けて [一云 天雲の八重雲別けて] -(万2-167) -道の行き逢ひに 天雲の 外のみ見つつ 言問はむ よしのなければ-(万4-549) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】〔上代は「あまくもの」〕 「はるか・たゆたふ・ゆくらゆくら・行く・別る・奥・よそ・たどきも知らず」 などにかかる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまざかる [天離る] | 【枕詞】[「あまさかる」とも] 天空のはるか彼方に離れていることから、 「ひな(田舎)」「向かふ」にかかる。 |
天離る鄙の荒野に君を置きて思ひつつあれば生けるともなし(万2-227) 天離る鄙の長道ゆ恋ひ来れば明石の門より大和島見ゆ [一本云 家のあたり見ゆ](万3-256) 天離る鄙に五年住まひつつ都のてぶり忘らえにけり(万5-884) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまたらす [天足らす] | 〔四段動詞「あまたる」の未然形「あまたら」+上代尊敬の助動詞「す」〕 天に満ちていらっしゃる。 |
天の原振り放け見れば大君の御寿は長く天足らしたり(万2-147) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまつ [天つ] | 《連体》〔名詞「天(あま)」に「の」の意の上代の格助詞「つ」の付いたもの〕 天の。天にある。 「あまつ風・あまつ神・あまつ空・あまつ少女(をとめ)」 |
-食す国 四方の人の 大船の 思ひ頼みて 天つ水 仰ぎて待つに-(万2-167) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまづたふ [天伝ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕大空を伝わる。 | -大殿の上に ひさかたの 天伝ひ来る 雪じもの 行き通ひつつ-(万3-263) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】「入日」「日」にかかる。 | -隠らひ来れば 天伝ふ 入日さしぬれ 大夫と-(万2-135) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまつつみ [雨障み] | 〔名詞〕雨に降られて、家にとじこもっていること。=雨障(あまざは)り。 | 雨つつみ常する君はひさかたの昨夜の夜の雨に懲りにけむかも(万4-522) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまつみや [天つ宮] | 〔名詞〕 | -日の皇子 ひさかたの 天つ宮に 神ながら 神といませば-(万2-204) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1巻二-204 頭注「天つ宮」】 殯宮。天ツは日ノ皇子であり、しかもその霊が今や空の上に上って行かれたのでいう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまてらす [天照らす] | 《動詞「あまてる」 の未然形+上代の尊敬の助動詞「す」。あまでらす、とも》 ① 《上代語》天に輝いておられる。天空でお照らしになる。 ② 天下をお治めになる。君臨なさる。 |
① -神集ひ 集ひいまして 神分り 分りし時に 天照らす 日女の命-(万2-167) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【全注巻二注】 [天照らす日女の尊] 天照大神のこと。書紀に「大日孁貴」(本文) とも「大日孁尊」(一書) ともあり、「大日孁貴、此云於保比屡咩能武智。-一書云、天照大神。 一書云、天照大日孁尊」 の注がある。アマテラスは、アマ(天)・テラ(照)・ス(尊敬) で、「天に坐々て照り賜ふ意」(記紀) を表す。 ヒルメは、元来日に仕える巫女を意味したが、それが神格化され、日の女神の成立を見たものと推測される。(松村武雄『日本神話の研究』第二巻)。 記紀神話の中心となる神であり、その性格も複雑であるが、皇祖神的性格、太陽神的性格、司霊者的性格の三要素を、主要な特徴としてあげることができる。 アマテラスオオミカミという呼称以前に、アマテラスヒルメあるいはヒルメノミコトなどと呼ばれていたと思われる。ヒルは日の古語で、ヒルメは日の妻。 アマテラスは、そのヒルメにかかる枕詞的修飾語である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまてる [天照る] | 〔自動詞ラ行四段〕大空にあって照る。 | ひさかたの天照る月は見つれども我が思ふ妹に逢はぬころかも(万15-3650) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまとぶや [天飛ぶや] | 【枕詞】 空を飛ぶの意から「鳥」「雁」に、 また、「雁」に似た音の地名「軽(かる)」にかかる。 |
天飛ぶや 軽の道は 我妹子が 里にしあれば ねもころに -(万2-207) 天飛ぶや雁を使に得てしかも奈良の都に言告げ遣らむ(15-3698) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまねし [遍し・普し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 すみずみまで行き渡っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまの [天の] | 〔連体詞〕[名詞「天(あま)」に格助詞「の」が付いたもの] 「あめの」とも。天空、または宮廷に関係ある事物に冠する語。 「天(てん)の」「天にある」 〔例語〕 「天の岩戸」「天の河原」「天の原」 【参考】 「天(あめ)の」の古い語形とする説がある。 |
大和には 群山あれど とりよろふ 天の香具山 登り立ち 国見をすれば-(万1-2) うらさぶる心さまねしひさかたの天のしぐれの流れあふ見れば(万1-82) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまのかはら [天の河原] | 〔名詞〕 ① 天上にあるという安の河の河原。② 天の川の河原。 |
① 天地の 初めの時 ひさかたの 天の河原に 八百万 千万神の-(万2-167) ② 狩り暮らしたなばたつめに宿からむ天の河原に我は来にけり (古今羇旅-418) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまのかぐやま [天の香久山] | 〔地名〕《上代の仮名書き例では「あめのかぐやま」》 今の奈良県橿原市の東部にある山。大和三山の一つ。 天(=高天原)から降った山だという言い伝えからこの名がある。 |
天降りつく 天の香具山 霞立つ 春に至れば 松風に 池波立ちて-(万3-259) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまのつりぶね [海人の釣舟] | 〔名詞〕漁夫が釣りをする船。 | 風をいたみ沖つ白波高からし海人の釣船浜に帰りぬ(万3-297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまのはら [天の原] | 〔名詞〕 ① 広々とした大空。 ② 「天つ神」のいると想像された天上界。高天原 (たかまのはら)。 |
① あまの原ふりさけみればおおきみのみ命はながくあまたらしたり (万2-147) ① あまの原ふりさけみれば春日なるみかさの山にいでし月かも (古今羇旅-406) ② ひさかたの 天の原より 生れ来る 神の命 奥山の-(万3-382) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】「富士」にかかる。 | 天の原富士の柴山この暗の時ゆつりなば逢はずかもあらむ(万14-3369) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまひれ [天領巾] | 〔名詞〕「あまつひれ」とも。 天女が肩にかける装飾用の布。天女の羽衣。 |
-かぎろひの 燃ゆる荒野に 白たへの 天領巾隠り 鳥じもの-(万2-210) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまをとめ [海人少女] | 〔名詞〕年若い少女。漁師の未婚の女。 | - 網の浦の 海人娘子らが 焼く塩の 思ひぞ焼くる 我が下心(万1-5) -ますらをの 手結が浦に 海人娘子 塩焼く煙 草枕 旅にしあれば-(万3-369) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あみさす [網さす] | 〔他動詞サ行四段〕飛ぶ鳥を捕らえるために網を張る。 | 二上のをてもこのもに網さして我が待つ鷹を夢に告げつも(万17-4037) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あみにさす [網にさす] | 〔他動詞サ行四段〕網でとらえる。 | ひさかたの天行く月を網に刺し我が大君は蓋にせり(万3-241) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あみのうら [あみの浦] | 〔地名〕鳥羽湾の西に突出する小浜地区の入海で、今に「アミノ浜」というか。 | 嗚呼見の浦に舟乗りすらむをとめらが玉裳の裾に潮満つらむか(万1-40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あめ [天] | 〔名詞〕① 空。天空。②「天つ神」のいる天上の世界。高天原。 | ①「ひばりは天に翔(かけ)る」(記下) ① -万代に 過ぎむと思へや 天のごと 振り放け見つつ-(万2-199) ② -日女の命 [一云 さしあがる 日女の命] 天をば 知らしめすと-(万2-167) ② あめにしては下照姫に始まり、粗金の(あらがねの)地にしては (古今仮名序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あめ [雨] | 〔名詞〕 雨。また、涙のたとえ。 |
-耳我の嶺に 時なくぞ 雪は降りける 間無くぞ 雨は振りける-(万1-25) 雨つつみ常する君はひさかたの昨夜の夜の雨に懲りにけむかも(万4-522) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あめつち [天地] | 〔名詞〕 ① 天と地。 ② 天の神と地の神。 |
① -ここだ貴き 天地 日月と共に 足り行かむ 神の御面と-(万2-220) ① -この歌、天地のひらけはじまりける時よりいでにけり-(古今仮名序) ② 天地の神も助けよ草枕旅行く君が家に至るまで(万4-552) ② いざ子どもたはわざなせそ天地の堅めし国ぞ大和島根は(万20-4511) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-317 注「天地剖判神話(てんちほうはんしんわ)」】 天と地が分かれた神代の時代から。もと天と地は一つであって、それが天と地との二つに分かれたという神話がある。 これを「天地剖判神話」というが、この神話は中国他諸外国に普通に見られるもので、日本の上代文献では、記序・紀・『古語拾遺』と、この万葉集に見える。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あめの [天の] | 〔連体詞〕「あまの」に同じ。 | -天の香具山 登り立ち 国見をすれば 国原は 煙立ち-(万1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あめのした [天の下] | 〔名詞〕[「あめがした」とも] ①(地理的・社会的な意味で)この世の中。天下。 ② 日本の国土。 |
② やすみしし 我が大君の きこしめす 天の下に国はしも- (万1-36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あめのみかげ [天の御蔭] | 〔名詞〕天子の立派な宮殿。日の御蔭。 | 「皇御孫(すめみま)の命の天の御蔭、日の御蔭と造り仕へまつれる」(祝詞) 高知るや 天の御蔭 天知るや 日の御蔭の 水こそば つねにあらめ(万1-52) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あもりつく [天降り付く・天降り著く] | 【枕詞】香久山は天から降ったという伝説から、 「天(あま)の香久山」「神の香久山」」にかかる。 |
天降りつく 天の香具山 霞立つ 春に至れば 松風に 池波立ちて-(万3-259) 天降りつく 神の香具山 うち靡く 春さり来れば 桜花 木の暗茂-(万3-262) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あもる [天降る] | 〔自動詞ラ行上二段〕【リ・リ・ル・ルル・ルレ・リヨ】 [天降(あまおる)の転か] ① 天上からおりる。天下る。 ② 行幸する。 |
① 久方の 天の門開き 高千穂の 岳に天降りし 皇祖の-(万20-4489) ② -高麗剣 和射見が原の 仮宮に 天降りいまして 天の下-(万2-199) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あや [文・彩] | 〔名詞〕 ① 物の表面に現れるいろいろの型や模様。 木目・水の波紋・織物の模様など。 ② 条理。わけ。筋道。③ 音楽の節回し。 ④ 文章の飾り。修辞。おもしろみ。 |
① -寄し巨勢道より 我が国は 常世にならむ 図負へる くすしき亀も- (万1-50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あや [綾] | 〔名詞〕 ① いろいろな模様を織り出した絹織物。綾織り。綾織物。 ② 綾織りにした織物の地合。 特に斜めに線の交差した綾織りの模様。綾地。 ③ 美しさ。彩り。④ 物事の筋道。理由。⑤「綾竹(あやだけ)」の略。 |
② 水の面に綾織り乱る春雨や山の緑をなべて染むらむ(新古今春上-65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あやに | 〔副詞〕言いようもなく。わけもなく。むしょうに。 | くへ越しに麦食む小馬のはつはつに相見し子らしあやに愛しも(万14-3558) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あやめ [菖蒲] | 〔名詞〕 ① しょうぶ(=草ノ名)の古名。水辺に生え、初夏に淡黄色の花をつける。葉が剣の形をし、香気が強いので、昔から邪気を払うものとされる。 「端午」の節句に、軒にさしたり、湯に入れたりする。=菖蒲草(あやめぐさ)。 ② 草の名。あやめ。葉は剣状で、初夏に紫または白の花をつける。花あやめ。 ③ 誤って「はなしょうぶ」「かきつばた」の類をいう。 ④ 「襲(かさね)の色目」の名。表は青、裏は紅梅または白色。(一説には表は白、裏は萌黄色とも)。 ⑤ 香の名。⑥ 陰暦五月の異称。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あやめぐさ [菖蒲草] | 上項「あやめ」の「①」。 | -ほととぎす 鳴く五月には あやめぐさ 花橘を 玉に貫き-(万3-426) ほととぎす鳴くや五月のあやめ草 あやめも知らぬ恋もするかな(古今恋一-469) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】同音の「あや」に、また、根を賞することから「ね」にかかる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あゆ [鮎・香魚・年魚] | 〔名詞〕 淡水魚の一種。肉に香があり、食して美味。寿命は一年のものが多い。「氷魚(ひを)」はその稚魚。 |
-川瀬には 鮎子さ走り いや日異に 栄ゆる時に 逆言の-(万3-478) 松浦なる玉島川に鮎釣ると立たせる子らが家道知らずも(万5-859) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あゆちがた [年魚市潟] | 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 『付録 地名一覧』」】 尾張国愛智郡(和名抄)の海岸の潟をなしていた地域。名古屋市熱田区および南区の西方一帯に当たる。ただし名古屋港埋め立てのため、当時の海岸線の実態は不明。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あら- [荒・粗] | 〔接頭語〕 ① こまやかでない。目が粗い、の意を表す。 「荒垣・荒籠(こ)・荒栲(たへ)」 ② 荒廃した、人気のない、の意を表す。「荒野・荒山」 ③ 勢いが激しい、の意を表す。「荒磯・荒波」 【有斐閣「萬葉集全注巻三-241 注『荒山中に』」】 「荒」は人気のまれな荒涼たるさまに用いる。御猟場の山中をさす。 |
② 大君は神にしませば真木の立つ荒山中に海を成すかも(万3-242) ③ 荒波に寄り来る玉を枕に置き我ここにありと誰か告げけむ(万2-226) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あらかじめ [予め] | 〔副詞〕 前々から。それに先だって。かねて。 |
出でて行く道知らませばあらかじめ妹を留めむ関も置かましを(万3-471) -ゆゆしくあらむと あらかじめ かねて知りせば 千鳥鳴く-(万6-953) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あらき [殯・荒城] | 〔名詞〕 貴人の死後、正式に埋葬の行われるまで、死体を棺に収めて安置しておくこと。 また、その場所。「殯(もがり・あがり)」 |
大君の命恐み大殯の時にはあらねど雲隠ります(万3-444) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あらし [嵐] | 〔名詞〕山から吹きおろす強い風。激しい風。 | み吉野の山のあらしの寒けくにはたや今夜も我が独り寝む(万1-74) 霞立つ春日の里の梅の花山のあらしに散りこすなゆめ(万8-1441) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あらし [荒らし] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① (風や波、また物音などが)強く激しい。猛烈だ。 ② (性質・態度・言葉などが)乱暴だ。荒々しい。 ③ 荒れ果てている。荒涼としている。 ④ (山などが)けわしい。 |
① 潮騒に伊良虞の島辺漕ぐ舟に妹乗るらむか荒き島廻を(万1-42) ③ 神風の伊勢の浜荻折り伏せて旅寝やすらむ荒き浜辺に(万4-503) ④ 周防なる磐国山を越えむ日は手向けよくせよ荒しその道(万4-570) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あらし [粗し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 こまかでない。まばらである。粗雑だ。 |
須磨のあまの塩焼き衣筬(をさ)をあらみまどほにあれや君がきまさぬ (古今恋五-758) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あ-らし | 〔なりたち〕[ラ変動詞「有り」の連体形「ある」+推量の助動詞「らし」] 「あるらし」の転 ⇒「らし」 あるようだ。あるにちがいない。 |
武庫の海の庭よくあらし漁りする海人の釣舟波の上ゆ見ゆ(万15-3631) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あらしを [荒らし男] | 〔名詞〕強く勇敢な男。荒ち男。 | 荒し男のいをさ手挟み向ひ立ちかなるましづみ出でてと我が来る (万20-4454) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あらす [荒す] | 〔他動詞サ行四段〕 ① 荒れるにまかせる。損なわれるまで放っておく。 ② 損なう。傷つける。 |
① 夕霧に千鳥の鳴きし佐保路をば荒しやしてむ見るよしをなみ (万20-4501) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あらず | 〔ラ変動詞「有り」の未然形「あら」+打消しの助動詞「ず」〕 ① ない。いない。存在しない。 ② ~ない。 |
① なかなかに人とあらずは酒壷になりにてしかも酒に染みなむ(万3-346) ② 我が祭る神にはあらずますらをにつきたる神そよく祭るべし(万3-409) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あらそふ [争ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 ① 抵抗する。さからう。 ② 張り合う。競争する。 |
① 春雨に争ひかねて我が宿の桜の花は咲きそめにけり(万10-1873) ② 香具山は 畝傍を愛しと 耳成と 相争ひき 神代より-(万1-13) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あらたへ [荒妙・荒栲] | 〔名詞〕 ① 藤などの繊維で織った目の粗い織物。粗末な布。 ② 中古以降、絹織物に対しての麻織物。 |
① 荒栲の布衣をだに着せかてにかくや嘆かむ為むすべをなみ(万5-906) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中央公論社「萬葉集注釈巻第一-28・50 しろたへ・あらたへ」注】 [28]「たへ」は楮 (かぢ) の木の繊維で織った布。-「妙」は借字である。 しかし「白たへの麻衣」(2・199)ともいひ、白い色の布をすべて白たへといひ、単に白い色をもいふ。今 (私注:28番歌) もその意である。 [50]「たへ」は既に述べた(28)。布の総稱で、「荒」は「和( にき)」に対して用ゐ、粗雑の意。 延喜式踐祚大嘗祭に「麁妙服」に「神語所謂阿良多倍是也」と注し、古語拾遺には「織布」に「古語、阿良多倍 (アラタヘ)」と注してゐる。 藤葛の繊維で織つた布は荒いので、「藤」の枕詞 (あらたへの)として用ゐた。 「藤」は必ずしも今の美しく花房を垂れる藤ばかりでなくそれに類した、葛の繊維の織物になるやうなものを総稱したので、今も大和の田舎では「くず」をフヂと云つている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あらたへの [荒妙の・荒栲の] | 【枕詞】 「あらたへ」は藤の繊維で織ったことから「藤」にかかる。 |
やすみしし 我が大君 高照らす 日の皇子 荒栲の 藤原が上に-(万1-50) 荒栲の藤江の浦に鱸釣る海人とか見らむ旅行く我れを(万3-253) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あらたま [粗玉・璞] | 〔名詞〕掘り出したままで、まだ磨いていない玉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あらたまの [新玉の・荒玉の] | 【枕詞】「年・月・日・来経(きふ)・春」 にかかる。 | -おしてる 難波の国に あらたまの 年経るまでに-(万3-446) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あらたよ [新た世(代)] | 〔名詞〕新しい天皇の治世。新時代。 | -奈良の都を 新代の ことにしあれば 大君の 引きのまにまに-(万6-1051) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あらどこ [荒床] | 〔名詞〕荒れた寝床。寂しい寝床。荒涼として人気のない寝床。 | -枕になして 荒床に ころ臥す君が 家知らば 行きても告げむ-(万2-220) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あらなくに | 「アラズ」の「ク語法」 |
宇治間山朝風寒し旅にして衣貸すべき妹もあらなくに(万1-75) 三笠山野辺行く道はこきだくも繁く荒れたるか久にあらなくに(万2-232) 馬ないたく打ちてな行きそ日並べて見ても我が行く志賀にあらなくに(万3-265) 明日香川川淀去らず立つ霧の思ひ過ぐべき恋にあらなくに(万3-328) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集第一-75 あらなくに」頭注】 アラナクは、アラズのク語法。ク語法+「ニ」、特に「ナクニ」が歌末にある場合、~であることよ、のような詠嘆的な意味を表することが多い。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あらの [荒野] | 〔名詞〕 人けのない寂しい野。荒れるにまかせてある野。 |
天離る鄙の荒野に君を置きて思ひつつあれば生けるともなし(万2-227) 信濃なる須我の荒野に霍公鳥鳴く声聞けば時過ぎにけり(万14-3366) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (あらはる) [形はる] | 【有斐閣「万葉集全注巻第二-116 題詞原文】但馬皇女在高市皇子宮時竊接穂積皇子事既形而御作歌一首 「万象名義 」(巻ニ之一) に「胡□反見・掌容・常・象」、「名義抄」に「見」・「示」などとともに「アラハル」の訓がある。 穂積皇子との関係の露顕した時に皇女の作られたのが「116歌」であるという。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あらぶ [荒ぶ] | 〔自動詞バ行上ニ段〕【ビ・ビ・ブ・ブル・ブレ・ビヨ】 ① 暴れる・乱暴する。② 未開である。荒れている。 ③ 気持ちが荒れすさぶ。また、親しみが薄れる。うとくなる。 |
① 「荒ぶる神どもを言向(ことむ) け平和(やは) し」 (記中) ② 「葦原の中つ国はもとより荒びたり」(紀・神代) ③ 嶋の宮上の池なる放ち鳥荒びな行きそ君いまさずとも(万2-172) ③ 筑紫船いまだも来ねばあらかじめ荒ぶる君を見るが悲しさ(万4-559) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あらまし | 〔名詞〕 ① あらかじめあれこれと思い計ること。願い。また予期。予定。 ② 概略。だいたいの内容。 |
① 我妹子に恋ひつつあらずは秋萩の咲きて散りぬる花にあらましを (万2-120) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 ラ変動詞「有り」の未然形「あら」に反実仮想の助動詞「まし」の付いた形から生じたかと推定され、本来は「①」の意。 動詞「あらます」(サ四)は、中世以降、「あらまし」を活用させたもの。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔副詞〕「あらましに」とも。おおよそ。ひととおり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あらまし [荒まし] | 〔形容詞シク活用〕 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 荒々しい。激しい。けわしい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あらまし [有らまし] | 〔なりたち〕ラ変動詞「有り」の未然形「有る」+反実仮想の助動詞「まし」。 事実に反することを仮に想像して、 「こうなったらなあ」と希望する気持ちを表す。 (~で)あったらよかったのに。 |
神風の伊勢の国にもあらましを何しか来けむ君もあらなくに(万2-163) かく恋ひむものと知りせば夕べ置きて朝は消ぬる露にあらましを(万12-3052) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あられ [霰] | 〔名詞〕 ① 水蒸気が空中で凍って降る小さい氷の塊。 ②「霰地(あられぢ)」の略。 |
① 霰打つ安良礼松原住吉の弟日娘女と見れど飽かぬかも(万1-65) (「あられうつ」、同音で「あられ松原」にじかかる枕詞とする説がある) ① 霰降り吉志美が岳を険しみと草取りかなわ妹が手を取る(万3-388) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あられぢ [霰地霰] | 〔名詞〕織物などの模様の名。あられをかたどった小紋を織り出したもの。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あられまつばら [安良礼松原] | 〔地名〕所在未詳。大阪市住之江区安立(あんりゅう)付近か。 安立二丁目の安立南公園内に「霰松原」の碑がある。 [同区帝塚山方面説、非地名説がある] |
霰打つ安良礼松原住吉の弟日娘女と見れど飽かぬかも(万1-65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻第一-65 安良礼松原」注】 -摂津志二に「霰松原、在住吉安立((ありふ) 町、林中有豊浦神社。」とある。大日本地名辞書もまたこの地としている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あり [有り・在り] | 〔自動詞ラ変〕【ラ・リ・リ・ル・レ・レ】 ① 存在する。(人が)いる。(ものが)ある。 ② 生きている。生存する。③ 生活する。住む。④ そこにいる、ある。 ⑤ 仕える、侍る。 ⑥ 過ごす、経る。⑧ 立派である。⑨ 評判のある。 |
① 真木柱太き心はありしかどこの我が心鎮めかねつも(万2-190) ① 常磐なす岩屋は今もありけれど住みける人そ常なかりける(万3-311) ① 寂しさに堪へたる人のまたもあれな庵ならべむ冬の山里(新古冬-627) ② 妻もあらば摘みて食げまし沙弥の山野の上のうはぎ過ぎにけらずや(万2-221) ③ -天離る 鄙に一日も あるべくもあれや(万18-4137) ⑤ 我が行きは久にはあらじ夢のわだ瀬にはならずて淵にもありこそ(万3-338) ⑥ 鴨山の岩根しまける我をかも知らにと妹が待ちつつあるらむ(万2-223) ⑧ 飼飯の海の庭良くあらし刈り薦の乱れて出づ見ゆ海人の釣船(万3-257) ⑨ 秋の田の穂向きの寄れる片寄りに君に寄りなな言痛くありとも (万2-114) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あり | 〔補助動詞ラ変〕【ラ・リ・リ・ル・レ・レ】 ①(形容詞・形容動詞の連用形、副詞、打消しの助動詞「ず」の連用形、 推量の助動詞「べし」の連用形「べく」などに続いて) 「状態・存在の表現を助ける。」 ② 助詞「て」「つつ」のついた語について、 その動作・作用の存続の状態を表わす。「~ている。~てある。」 ③ 断定助動詞「なり・たり」の連用形「に・と」について指定の意を表わす。 「~である。」 ④ 中世以降「にて」から転じた助詞「で」について指定の意を表わす。 「~である。~だ。」 ⑤ 尊敬の意を表わす接頭語「御」を冠した敬語名詞について、 尊敬の複合動詞として用いる。 【語法】 〔接続〕 接続する際に係助詞「ぞ」「こそ」「は」「も」などの語を間に介することが多い。 |
① 栲領巾のかけまく欲しき妹の名をこの勢能山にかけばいかにあらむ [一に云ふ 替へばいかにあらむ](万3-288) ① -山からし 貴くあらし 川からし さやけくあらし 天地と-(万3-318) ② かくばかり恋ひつつあらずは高山の磐根しまきて死なましものを (万2-86) ② ありつつも君をば待たむうち靡く我が黒髪に霜の置くまでに(万2-87) ② 後れ居て恋ひつつあらずは追ひ及かむ道の隈廻に標結へ我が背 (万2-115) ② 人皆は今は長しとたけと言へど君が見し髪乱れたり(てあり)とも[娘子] (万2-124) ② 我が御門千代とことばに栄えむと思ひてありし我れし悲しも(万2-183) ② -野ごとに つきてある火の [一云 冬こもり 春野焼く火の] 風の共-(万2-199) ② 天離る鄙の荒野に君を置きて思ひつつあれば生けるともなし(万2-227) ② -むせつつあるに 天地の 神言寄せて しきたへの 衣手交へて-(万4-549) ② 妹が目を見まく堀江のさざれ波しきて恋ひつつありと告げこそ (万12-3038) ③ 玉葛花のみ咲きてならざるは誰が恋ならめ我は恋ひ思ふを(万2-102) 「ならめ」⇒「~にあらめ」 ③ 風流士に我れはありけりやど貸さず帰しし我れぞ風流士にはある (万2-127) ③ いつはなも恋ひずありとはあらねどもうたてこのころ恋し繁しも(万12-2889) ⑤「御覧あり」、「御嘆きあり」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ありかぬ [有りかぬ] | 〔自動詞ナ行下二段〕【ネ・ネ・ヌ・ヌル・ヌレ・ネヨ】 そうしていることが出来ない。そのままでいられない。 |
筑波嶺を外のみ見つつありかねて雪消の道をなづみ来るかも(万3-386) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ありがよふ [あり通ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 [「あり」は継続の意] 通い続ける。 |
翼なす あり通ひつつ 見らめども 人こそ知らね 松は知るらむ(万2-145) 片貝の川の瀬清く行く水の絶ゆることなくあり通ひ見む(万17-4026) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ありく [歩く] | 〔自動詞カ行四段〕 ① 歩き回る。出歩く。外出する。 ② (動物や舟などが) 動き回る。あちこち動く。 ③ (乗り物などで) 動き回る。 ④ (他の動詞の連用形について) -ア その動作をして回る意を表す。~して歩く。あちこちで~する。 -イ その動作をし続ける意を表す。~して過ごす。~して月日を送る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ありこす [有りこす] | 〔ラ変動詞[有り]の連用形[あり]+上代の他に対する希望の助動詞[こす]〕 「こす」は下二段に活用する 「そうあって欲しいと思う」 |
吉野川行く瀬の早みしましくも淀むことなくありこせぬかも(万2-119) -自妻と 頼める今夜 秋の夜の 百夜の長さ ありこせぬかも(万4-549) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ありそ [荒磯] | 〔「あらいそ」の転〕岩の多い、荒波の寄せる海岸。 |
-海辺を指して にきたづの 荒礒の上に か青なる 玉藻沖つ藻-(万2-131) み立たしの島の荒礒を今見れば生ひざりし草生ひにけるかも(万2-181) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1 巻二 181 頭注「島の荒磯」】 庭園内の池溝の水際に石組みした所。 昭和六十二年(1987) に出土した明日香の島庄遺跡には長さ約二五メートルの水路が斜めに横切っており、その岸の石組みは荒々しく、吉野宮瀧の景を模したようにも見える。 これをいうのであろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ありそも [荒磯面] | 〔名詞〕[「ありそおも」の転] 荒磯(あらいそ)の上。 | -島は多けど 名ぐはし 狭岑の島の 荒磯面に 廬りて見れば-(万2-220) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ありたつ [あり立つ] | 〔自動詞タ行四段〕 ① ずっと続いて立つ。変らず立つ。 ② いつも出掛ける。 |
①-始めたまひて 埴安の 堤の上に あり立たし 見したまへば-(万1-52) ①-さ婚(よば)ひ(=求婚)にありたたし-(記・上) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ありつつも | 引き続きこの状態で。命をこのまま永らえて。 | -絶ゆることなく ありつつも やまず通はむ 明日香の 古き都は-(万3-327) (万4-532) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ありつる [有りつる・在りつる] | 〔連体詞〕[ラ変動詞「有り」の連用形「あり」+完了助動詞「つ」の連体形「つる」] さっきの。先刻の。 【参考】 「ありつる」は比較的近い過去にあったことをいい、「ありし」は、それより遠い過去にあったことをいう。 |
-朝夕に ありつる君は いかさまに 思ひいませか うつせみの-(万3-446) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ありねよし [在根良し] | 【枕詞】 対馬には舟の航行中に目標になる、目立つ「ね(峰)」がある意から、 「対馬」にかかる。 |
在り嶺よし対馬の渡り海中に幣取り向けて早帰り来ね(万1-62) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ありまやま [有間山] | 【小学館「新編日本古典文学全集萬葉集 付録『有間山』」】 神戸市北区有馬町の有馬温泉の近くにある山。六甲山(931メートル) の北、有馬温泉の南側に射場山(いばやま、620メートル) その他の山がある。また六甲山そのものをさしたと思われる例(一一四〇) もある。. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ありわたる [在り渡る] | 〔自動詞ラ行四段〕生きながらえて年月を送る。ずっとそのままの状態で過ごす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ある [生る] | 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】《上代語》 (神々や天皇など神聖なものが) 生まれる。出現する。 |
ひさかたの 天の原より 生れ来る 神の命 奥山の 賢木の枝に-(万3-382) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ある [荒る] | 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 ①(天気や波風が)荒れさわぐ。あばれる。 ②(建物や人の心が)荒廃する。すたれる。 ③ 興ざめがする。しらける。 |
① 楽浪の国つ御神のうらさびて荒れたる都見れば悲しも(万1-33) ① 風吹きて海は荒るとも明日と言はば久しくあるべし君がまにまに (万7-1313) ② ひさかたの天見るごとく仰ぎ見し皇子の御門の荒れまく惜しも(万2-168) ② -剣太刀 身に添へ寝ねば ぬばたまの 夜床も荒るらむ-(万2-194) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻二-168 注『荒れまく』】 「アレマク」は、荒れむことの意。 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1 巻二168」頭注】 -アレマクヲシモ「荒レマク」 は荒レムのク語法。まだ荒れていないが、今後荒れ行くことが予想され、それが惜しまれるの意。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あるく [歩く] | 〔自動詞カ行四段〕→ 「ありく」 | 川風の寒き長谷を嘆きつつ君があるくに似る人も逢へや(万3-428) -赤駒に 倭文鞍うち置き 這ひ乗りて 遊び歩きし 世間や-(万5-808) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あれ [吾・我] | 〔代名詞〕 自称の人代名詞。私。 |
笹の葉はみ山もさやにさやげども我れは妹思ふ別れ来ぬれば (万2-133) 鴨山の岩根しまける我をかも知らにと妹が待ちつつあるらむ(万2-223) -我れをおきて 人はあらじと 誇ろへど 寒くしあれば 麻衾 - (万5-896) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あれ [彼] | 〔代名詞〕 ①(遠称の代名詞。遠い位置の人・事物・場所・時をさす。) あの人。あれ。あそこ。あの時。また少し離れた場所をさす。 ② 対称の人代名詞。あなた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あれつぐ [生れ継ぐ] | 〔自動詞ガ行四段〕次から次へと生まれる。 | 神代より 生れ継ぎ来れば 人さはに 国には満ちて あぢ群の-(万4-488) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あれてしか | あってほしいなぁ。~であったらなぁ。 | ひさかたの天飛ぶ雲にありてしか君をば相見むおつる日なしに (万11-2684) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あれど | 〔なりたち〕ラ変動詞「有り」の已然形「あれ」+接続助詞「ど」 (「~はあれど」の形で)~はともかく。~はさておき。 |
玉櫛笥覆ふを安み明けていなば君が名はあれど吾が名し惜しも(万2-93) -思へりし 妹にはあれど 頼めりし 児らにはあれど 世の中を-(万2-210) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あれども | 〔なりたち〕ラ変動詞「有り」の已然形「あれ」+接続助詞「ども」 (それは)さておいて。(それは)ともかくとして。 |
-神の命の 敷きいます 国のことごと 湯はしも さはにあれども -(万3-325) 妹とありし時はあれども別れては衣手寒きものにぞありける(万16-3613) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あれのことごと | あるものすべて、残らず。 | -麻衾引き被り布肩衣ありのことごと着襲へども寒き夜すらを- (万5-896) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あれのさき [安礼の崎] | 〔地名〕所在未詳。以下候補地。 ① 愛知県宝飯郡御津(みと)町大字御馬字梅田の地、音羽川の旧河口の崎。 ② 静岡県浜名郡新居(あらい)町の浜名湖西岸の出崎。 ③ 愛知県蒲郡市西浦町。 |
いづくにか船泊てすらむ安礼の崎漕ぎ廻み行きし棚無し小舟(万1-58) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あを [青] | 〔名詞〕 ① 晴れた空のようないろ。 ② 萌葱(もえぎ)色。黄色がかった緑や青味がかった緑をいうこともある。 ③ 馬の毛色の名。青味がかった黒。また、その馬。=青毛(あをげ)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [参考] 「あを」は、本来、黒と白の中間の不鮮明な色で、青・緑・藍などを含んだ広範囲の色彩をさした。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あを- [青-] | 〔接頭語〕(名詞に付いて) | -見したまへば 大和の青香久山は 日の経の 大御門に-(万1-52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若く未成熟である、人柄や技能が未熟である、などの意を表す。 そこから例歌のように、青く繁ったようすを詠い讃美する語を作ることにもなる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あをうま [青馬・白馬] | 〔名詞〕 ① 上代、「青毛馬。=青駒(あおこま)」。 ② 白馬、または「葦毛(あしげ)」の馬。 ③ 「白馬(あをうま)の節会(せちゑ)」の略。 |
① 水鳥の鴨の羽の色の青馬を今日見る人は限りなしといふ (万20-4518) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [語史] 表記が青馬から白馬(あおうま)に変わった時期の明確な記録は無いが、「延喜式(927 奏覧)」には「青馬」とある。 しかしこれより少し後には「白馬」に変わっていた推定される資料があり、醍醐天皇のころから白馬になったものと思われる。 [参考] 上代では、「あを」は「青・緑・藍(あい)」から灰色までを含んだ広い範囲の色を言った。 → [あを(青)]参照。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あをかきやま [青垣山] | 〔名詞〕垣根のように周りを囲んでいる青々とした山々。 | たたなづく青垣山の隔なりなばしばしば君を言問はじかも(万12-3201) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あをくも [青雲] | 〔名詞〕青みをおびた雲。 | 北山にたなびく雲の青雲の星離り行き月を離れて(万2-161) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あをくもの [青雲の] | 【枕詞】「出(い)づ」「白」 にかかる。 | 汝が母に嘖られ我は行く青雲の出で来我妹子相見て行かむ(万14-3540) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あをこま [青駒] | 〔名詞〕→ 「あをうま ①」 | 青駒が足掻きを速み雲居にそ妹があたりを過ぎて来にける(万2-136) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あをし [青し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】青い。 | - 取りてぞ偲ふ 青きをば 置きてぞ嘆く そこし恨めし 秋山吾は(万1-16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あをすがやま [青菅山] | 〔名詞〕 | -山さびいます 耳成の青菅山は 背面の 大御門に よろしなへ-(万1-52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青いすげ(=草の名)の生えている山、また、(「菅」は「清(すが)」の当て字として)草木の青く茂った清々しい山の意ともいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あをに [青丹] | 〔名詞〕[「に」は土の意] ① 青黒い土。② 岩緑青(いわろくしょう)の古名。染料や絵の具に用いた。 ③ 染め色の名。濃い青色に黄をかけた色。 ④ 襲'(かさね)の色目の名。表裏ともに黄色味を帯びた濃い青色。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あをによし [青丹よし] | 【枕詞】 「奈良」「国内(くぬち)」にかかる。 上代、奈良から青丹(=青土)が出たことによるという。 「よし」は詠嘆の助詞。 |
-あをによし 奈良の都の 佐保川に い行き至りて 我が寝たる-(万1-79) あをによし奈良の都は咲く花のにほふがごとく今盛りなり(万3-331) 悔しかもかく知らませばあをによし国内ことごと見せましものを(万5-801) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あをはたの [青旗の] | 【枕詞】 「木幡(こはた)」、「忍坂(おさか)の山」、「葛城の山」にかかる。 |
青旗の木幡の上を通ふとは目には見れども直に逢はぬかも(万2-148) -泊瀬の山 青旗の 忍坂の山は 走出の よろしき山の 出立の- (万13-3345) -我が立ち見れば 青旗の 葛城山に たなびける 白雲隠る-(万4-512) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あをやぎ [青柳] | 〔名詞〕青い芽をふいた柳。 [春] | 青柳梅との花を折りかざし飲みての後は散りぬともよし(万10-1855) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あをやぎの [青柳の] | 【枕詞】 青柳の枝や葉が細いところから「細き眉(まよね)」「いと」に、 鬘(かずら)「にすることから「葛城山」にかかる。 |
青柳の糸のくはしさ春風に乱れぬい間に見せむ子もがも(万14-3409) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あをやま [青山] | 〔名詞〕青々と草木の茂った山。 | 青山の嶺の白雲朝に日に常に見れどもめづらし我が君(万3-380) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あん [案] | 〔名詞〕考え。工夫。計画。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| い- | 〔接頭語〕《上代語》動詞に付いて、語調を整えたり意を強調する。 |
-つむじかも い巻き渡ると 思ふまで 聞きの畏く-(万2-199) -光も見えず 白雲も い行きはばかり 時じくぞ 雪は降りける-(万3-320) 富士の嶺を高み畏み天雲もい行きはばかりたなびくものを(万3-324) 岩の上にいかかる雲のかのまづく人ぞおたはふいざ寝しめとら(万14-3539) 奈良の山の 山の際に い隠るまで 道の隈 い積もるまでに(万1-17) -四方の道には 馬の爪 い尽くす極み 舟舳の い果つるまでに-(万18-4146) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【例語】 い懸かる・い隠る・い通ふ・い刈る・い組む・い漕ぐ・い堀(こ)ず・い副(そ)ふ・い立つ・い辿る・い回(た)む・い繁(つが)る・い継ぐ・い積もる・ い泊(は)つ [停泊する]・い這ふ・い拾ふ・い触る・い行き会ふ・い行き憚る・い行き回(もとほ)る・い行き渡る・い行く・い寄る・い別る・い渡る |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| い [寝・睡] | 〔名詞〕寝ること。睡眠。 |
安騎の野に宿る旅人うち靡き寐も寝らめやもいにしへ思ふに(万1-46) 大和恋ひ寐の寝らえぬに心なくこの洲崎廻に鶴鳴くべしや(万1-71) 妹を思ひ寐の寝らえぬに暁の朝霧隠り雁がねぞ鳴く(万15-3687) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 単独では用いられず、助詞を介して動詞「ぬ(寝)」とともに、「いの寝らえぬに」「いも寝ずに」などの句として用いられる。 また「熟寝(うまい)」「安寝(やすい)」などの語を作る。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| い | 〔格助詞〕 《上代語》主語を強調する。(接続:体言につく) |
否と言へど語れ語れと詔らせこそ志斐いは奏せ強ひ語りと言ふ(万3-238) 言清くいたくもな言ひそ一日だに君いしなくは堪へ難きかも(万4-540) 我が背子が跡踏み求め追ひ行かば紀伊の関守い留めてむかも(万4-548) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔間投助詞〕《上代語》連体修飾語を強調する。 (接続:動詞・助動詞の連体形につく) |
青柳の糸のくはしさ春風に乱れぬい間に見せむ子もがも(万10-1855) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いかさま [如何様] | 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 どのようだ。どんなふうだ。 |
-いかさまに 思ほしめせか [或云 思ほしけめか] 天離る 鄙にはあれど- (万1-29) 秋山の したへる妹 なよ竹の とをよる子らは いかさまに 思ひ居れか-(万2-217) -ありつる君は いかさまに 思ひいませか うつせみの 惜しきこの世を-(万3-446) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いかさま | 〔副詞〕[「いかさまにも」の略] ① どうみても。きっと。② ぜひとも。なんとかして。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔感動詞〕まったくその通り。なるほど。いかにも。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いかだ [筏] | 〔名詞〕材木や竹を並べて結びつけ、水に浮べ流すもの。 | -真木のつまでを 百足らず 筏に作り 泝すらむ いそはく見れば-(万1-50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いかづち | 〔名詞〕かみなり。雷神。「鳴る神」 とも。〔夏〕 | -御軍士を 率ひたまひ 整ふる 鼓の音は 雷の 声と聞くまで-(万2-199) 大君は神にしませば天雲の雷の上に廬りせるかも(万3-235) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いかづちのおか・いかづちやま [雷の丘・雷山] |
〔地名〕 | 大君は神にしませば雲隠る雷山に宮敷きいます(万3-236) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奈良県高市郡明日香村の雷丘。飛鳥川を挟んで南の甘樫丘に対し、高さ約十メートルばかりの小丘。 ただし、現在のそれは中央が切道となって北側を城山、南側を「上の山」と称するが、以前はもっと高かったかと思われる。 雄略天皇の命を受けた小子部栖軽が雷を捕らえた丘だという(霊異記上一)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いかに [如何に] | 〔副詞〕状態や程度また理由などを疑い、推測するときに用いる。 ① どのように。どう。 ② どんなに(~だろう)。さぞ(~だろう)。 ③ なぜ。なにゆえ。④ どんなに。どれほど。⑤ 感動を表す。なんとまあ。 |
① 朝に日に見まく欲りするその玉をいかにせばかも手ゆ離れずあらむ(万3-406) ② 栲領巾のかけまく欲しき妹の名をこの勢能山にかけばいかにあらむ [一に云ふ 替へばいかにあらむ](万3-288) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔感動詞〕相手に呼びかける語。おい。なんと。さて。もし。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いかにか [如何にか] | 〔副詞「いかに」+疑問の係助詞「か」〕 ① どのように。どういうふうに。 ② なぜか。どうしてか。 ③ (反語) どうして~か (そんなはうはない)。 |
① ふたり行けど行き過ぎがたき秋山をいかにか君がひとり越ゆらむ (万2-106) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いきづきあかす [息づき明かす] | 〔他動詞サ行四段〕ため息をつきながら夜を明かす。 | -うらさび暮らし夜はも息づき明かし嘆けどもせむすべ知らに-(万2-210) -昼はも嘆かひ暮らし夜はも 息づき明かし年長く病みしわたれば-(万5-902) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いく [生く] | 〔自動詞カ行四段・上二段〕【キ・キ・ク・クル・クレ・キヨ】 生きる。命を保つ。また、生き返る。助かる。 |
〔四段活用〕 衾道を引手の山に妹を置きて山道を行けば生けりともなし(万2-212) 衾道を引手の山に妹を置きて山道思ふに生けるともなし(万2-215) 事もなく生き来しものを老いなみにかかる恋にも我はあへるかも(万4-562) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 生かす。生存させる。命を助ける。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】自動詞の四段活用はおもに中古までで、上二段活用は中世以降の用法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いく [行く・往く] | 〔自動詞カ行四段〕[「ゆく」とも] (ある方向や場所に) 出かける。進み動く。 |
-ねもころに 見まく欲しけど やまず行かば 人目を多み-(万2-207) -八十伴の男と 出でて行きし 愛し夫は 天飛ぶや 軽の道より-(万4-546) 大伴の御津の泊りに船泊てて龍田の山をいつか越え行かむ(万15-3744) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】「いく」と「ゆく」は、ともに上代から用いられたが、「ゆく」の方が多く使われた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いくだ [幾許] | 〔副詞〕(多く、下に助詞「も」を付け、打消しの語を伴って) いくら。どれほど。 |
-深めて思へど さ寝し夜は 幾だもあらず - (万2-135) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いくだも [幾許も] | 〔副詞「いくだ」+係助詞「も」〕どれほども。いくらも。 | -深めて思へど さ寝し夜は 幾だもあらず - (万2-135) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いくぢやま [活道山] | 【有斐閣「萬葉集全注巻三-478 注『活道山』」】 旧訓「イクメチヤマ」 とあるが、玉の小琴に「イクヂヤマ」 と訓んだ。次の反歌に「活道(いくぢ)の道(みち)」 とあり、また「(天平十六年甲申春正月) 十一日に、活道の岡に登り、一株(ひともと)の松の下に集ひて飲む歌二首」(6・一〇四二の題詞、この歌の作者は市原王で、もう一首が家持作である) とある。所在不明であるが、久邇京付近の山で、眺望もよかった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いくよ [幾世・幾代] | 〔名詞〕どれほど多くの年代。何代。何年。 | 白波の浜松が枝の手向けぐさ幾代までにか年の経ぬらむ [一云 年は経にけむ] (万1-34) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いくり [海石] | 〔名詞〕海の中にある岩。暗礁。 | 「-由良(ゆら)の門(と)の門中(となか)のいくりに-」(記下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いけ [池] | 〔名詞〕水がたまった窪地。 | 嶋の宮まがりの池の放ち鳥人目に恋ひて池に潜かず(万2-170) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いさ | 〔感動詞〕 | 犬上の鳥籠の山なる不知哉川いさとを聞こせ我が名告らすな(万11-2719) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答えにくいことをぼかしたり、相手のことばを否定的に軽く受け流したりするときに使う。さあねえ。いや知らない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔副詞〕 (多く下に「知らず」を伴って)さあ、どうであろうか。 |
ひとはいさ心も知らずふるさとは花ぞ昔の香ににほひける(古今春上-42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いざ [(去来)] | 〔感動詞〕 ① 人を誘うときに発する語。さあ。 ② 自分から何かを始めようとするときに発する語。さあ。さて。どれ。 |
① 君が代も我が代も知るや岩代の岡の草根をいざ結びてな(万1-10) ① いざ子ども早く日本へ大伴の御津の浜松待ち恋ひぬらむ(万1-63) ① 月夜よし川の音清しいざここに行くも行かぬも遊びて行かむ(万4-574) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考「いさ」と「いざ」】 現代語では「小学生ならいざ知らず、高校生にもなって」などというので混同しがちであるが、元来「さあ(どうだか。わからない)」の意の「いさ」と、 「さあ(~しよう)」の意の「いざ」とは別語で、、明確に使い分けられていた。中世以降、「いさ知らず」という表現に限って、混同が始まった。 【参考】 表記「去来」は、日本語の「いざ」に相当する言葉として用いられた中国の俗語。例:「帰去来」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いさな [鯨・勇魚] | 〔名詞〕[「な」は魚の意] くじら。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -とり [鯨取り] | 【枕詞】「海・浜・灘」にかかる。 | -潟は [一云 礒は] なくとも 鯨魚取り 海辺を指して-(万2-131) -沖見れば とゐ波立ち 辺を見れば 白波騒く いさなとり 海を恐み-(万2-220) -真楫貫き下ろし いさなとり 海路に出でて あへきつつ-(万3-369) 鯨魚取り 浜辺を清み うち靡き 生ふる玉藻に-(万6-936) 昨日こそ船出はせしか鯨魚取り比治奇の灘を今日見つるかも(万17-3915) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いざみのやま [いざみの山] | 〔地名〕伊勢と大和の国境にある高見山 (海抜1249m) か。 | 我妹子をいざ見の山を高みかも大和の見えぬ国遠みかも(万1-44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いさやがは [不知哉川] | 【有斐閣「萬葉集全注巻四-487 注『不知哉川』」】 滋賀県犬上郡の霊仙山に発し、彦根市で琵琶湖に注ぐ大堀川のこと。芹川ともいう。イサ は、さあどうだか知らない、の意の感動詞。ヤ は間投助詞。以上三句序。類歟に、 犬上の鳥籠の山なる不知也川いさとを聞こせ我が名告らすな (11・二七一〇) というのがある。これにはイサヤ川―イサと同音反復の技巧があるが、今の歌にはあとのイサが表面化していない。おそらく、こんなに苦しい恋がずっと続いたらはたして命がもつかどううかわからない。とか、相手がどう思っているのか推し量りかねる、とかの不安な気持ちがこめられているのであろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いさよふ | 〔自動詞ハ行四段〕[中世以降は「いざよふ」] ぐずぐずして進むかねる。ためらう。 |
もののふの八十宇治川の網代木にいさよふ波の行くへ知らずも(万3-266) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いさよふつき [いさよふ月] | 出ようとして、または没しようとしてためらっている月。 また陰暦十六日の夜の月。 |
見えずとも誰恋ひざらめ山の端にいさよふ月を外に見てしか(万3-396) 山の端にいさよふ月を出でむかと待ちつつ居るに夜ぞ更けにける(万7-1075) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いざる [漁る] | 〔他動詞ラ行四段〕[後世は「いさる」] 魚や貝を採る。漁をする。 | 武庫の海船庭ならしいざりする海人の釣船波の上ゆ見ゆ(万3-258) 海原の沖辺に灯し漁る火は明かして灯せ大和島見む(万15-3670) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いし [石] | 〔名詞〕 ① 鉱石・岩石。「いは」が大きい石を言うのに対し、小さい石をさしていう。 ② 宝石。③ 碁石。④ 墓石。 |
① 佐保川の小石踏み渡りぬばたまの黒馬の来夜は年にもあらぬか(万4-528) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いしうら [石占] | 〔名詞〕上代の占いの一種。手に持った石の数や軽重、または蹴った石の状況で吉凶を占ったという。 | -夕占問ひ 石占もちて 我がやどに みもろを立てて 枕辺に-(万3-423) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いしかは [石川] | 〔名詞・河川名〕 【有斐閣「萬葉集全注巻二-224 注『石川の』」】 原文「石水之」。水をカハと訓む例は、「水可良思 清けくあらし」(3・三一五、旅人)などにも見られる。石川は、茂吉の「鴨山考」では、江川の上流と推定されている。 これを河内の石川と考える説のあることも既述。鴨山が葛城連山の中に求められるとすれば、石川はその麓を流れる川で、郡名にもなっているほど著名でもある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いしなみ [石なみ] | -上つ瀬に 石橋渡し 一に云ふ「石なみ」下つ瀬に 打橋渡す- (万2-196) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1巻二-196」頭注】 「石橋」に同じか。「ナミ」 は幾つかの物が列を成して並ぶ意の、四段動詞「なむ」 の名詞形。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いしばし [石橋] | 〔名詞〕【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1巻二-196」頭注】 川の浅瀬に置き並べた飛び石。 |
飛ぶ鳥の 明日香の川の 上つ瀬に 石橋渡し-(万2-196) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いしばし [石階] | 〔名詞〕石の階段。石段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いせ [伊勢] | 〔地名〕旧国名。 東海道十五ヶ国の一つ。今の三重県の大部分。勢州(せいしゅう)。 |
神風の伊勢の浜荻折り伏せて旅寝やすらむ荒き浜辺に(万4-503) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いせのうみ [伊勢の海] | 〔地名〕《歌枕》 今の三重県の志摩半島と愛知県の伊良湖埼に囲まれた内海。伊勢湾。 |
伊勢の海の沖つ白波花にもが包みて妹が家づとにせむ(万3-309) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いせをとめ [伊勢娘子] | 〔諸注引用〕巻第一-81 「伊勢娘子」 | 山辺の御井を見がてり神風の伊勢娘子どもあひ見つるかも(万1-81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いそ [礒] | 〔名詞〕海・湖などの波打ち際の岩石の多い所。 |
磯の上に おふる馬酔木を 手折らめど 見すべき君が ありと言はなくに(万2-166) 水伝ふ礒の浦廻の岩つつじ茂く咲く道をまたも見むかも(万2-185) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【「いそ」 と「はま」】 荒磯(ありそ) の語もあるように、波打ちぎわの岩石の多い所が「いそ」 であり、砂浜の語のあるように、海や湖に沿った陸の平地が「はま」 である。 「浜の真砂(まさご)」 は浜にある砂で、数の多いものの比喩として用いられた。 「浜の真砂の数多く積りぬれば」(古今仮名序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いそがくる [礒隠る] | 〔自動詞ラ変四段・下二段〕四段活用は上代に用いられた。 下二段【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 海辺の岩や石のかげに隠れる。 |
-淡路島 礒隠り居て いつしかも この夜の明けむと さもらふに-(万3-391) 見わたせば近きものから岩隠りかがよふ玉を取らずはやまじ(万6-956) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いそかげ [石影] | 〔名詞〕《上代語》〔「いそ」 は石・岩の意〕水面に映る岩の姿。 | 礒影の見ゆる池水照るまでに咲ける馬酔木の散らまく惜しも(万20-4537) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いそのかみきやう [石上卿] | 〔人名〕幸志賀時石上卿作歌一首 [名闕] 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻三-287 頭注」】 卿は三位以上の高官に対する尊称。三位以上の者は敬してその名を記さないことが多い。 石上氏で三位以上に昇り、奈良朝初期に在世してこの歌を作る条件に適う者としては、麻呂か、その第三子乙麻呂しかいない。 しかし麻呂はこの志賀行幸のあった養老元年の三月に七十八歳で薨じており、乙麻呂はこの当時正六位上かそれ以下で、従三位に叙せられるのはこれより三十一年後の天平二十年(748)である。遡って卿と称したとしてもこの後三六八の題詞において石上大夫(大夫は四・五位の称)とある。 一説に当時従四位上であった系統未詳の石上朝臣豊庭を右将軍の職にあったによって卿と称したとする。後考を待つ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いそのかみふる [石上布留] | 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 巻3『地名一覧』」】 石上は奈良県天理市の石上神宮付近から西方一帯の地の総称。布留はそのうち同神宮周辺の一部をさし、今も天理市布留町の名がある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いそのさき [礒の埼] | 〔名詞〕 | 磯の崎漕ぎ廻み行けば近江の海八十の港に鶴さはに鳴く(万3-275) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 巻3-273 頭注『磯の埼』」】 「磯」は「浜」の対。 琵琶湖で磯と呼べるのは湖北の葛籠尾崎(つづらおざき)を除けば滋賀県高島郡高島町勝野の明神岬ぐらいか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いそにふる [磯に触る] | 海岸の岩にぶつかる。 | 大君の命畏み磯に触り海原渡る父母を置きて(万20-4352) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いそはく [争はく] | 〔動詞「争(いそ)ふ」のク語法〕 競争すること。あらそい励むこと。 |
-百足らず 筏に作り 泝すらむ いそはく見れば 神からならし-(万1-50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いそみ [磯回] | 〔名詞〕〔「み」は湾曲した所の意〕 ① 湾曲した海岸。入り江。磯回(いそわ)。 ② 磯の周りを巡ること。 |
① 白波の寄する礒廻を漕ぐ舟の楫取る間なく思ほえし君(万17-3983) ② 大船に真梶しじ貫き大君の命恐み磯廻するかも(万3-371) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いた [甚] | 〔副詞〕《上代語》[形容詞「甚(いた)し」の語幹] 甚だしく。激しく。 |
いた泣かば人知りぬべし(記・下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いたし [甚し・痛し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 [「程度がはなはだしい」が基本の意] [甚し] ① (おもに連用形を用いて) 程度がはなはだしい。ひどい。すごい。 ② 非常によい。感にたえない。すばらしい。 [痛し] ① (肉体的に) 痛みを感じる。② (精神的に) 苦しい。苦痛である。 ③ いたわしい。かわいそうだ。④ いとしい。 |
[痛し] ① 風をいたみ沖つ白波高からし海人の釣船浜に帰りぬ(万3-297) [「~を~み」] ミ語法 ② 丹生の川瀬は渡らずてゆくゆくと恋痛し我が背いで通ひ来ね(万2-130) ② -聞けば 音のみし泣かゆ 語れば 心そ痛き 天皇の 神の皇子の-(万2-230) ② 霞立つ 長き春日の 暮れにける わづきも知らず むらきもの 心を痛み-(万1-5) [「~を~み」] ミ語法 ② 秋と言へば心ぞ痛きうたて異に花になそへて見まく欲りかも(万20-4331) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いたづら [徒ら] | 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 ① 物事が無益である、役に立たない、むだだ。 ② むなしい、はかない、あいている。 |
② 暇なく人の眉根をいたづらに掻かしめつつも逢はぬ妹かも(万4-565) ② 花の色は移りにけりないたづらに我が身世にふる眺めせしまに (古春下-113) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いたも [甚も] | 〔副詞「いた」+助詞「も」〕 非常に。はなはだしくも。 |
君に恋ひいたもすべなみ葦鶴の音のみし泣かゆ朝夕にして(万3-459) 言清くいたもな言ひそ一日だに君いしなくはあへかたきかも(万4-540) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いたる [至る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 行く着く。到達する。 ② (あるときが) やってくる。③ いきとどく。思い及ぶ。 ④ きわまる。極致に達する。 |
① -あをによし 奈良の都の 佐保川に い行き至りて 我が寝たる-(万1-79) ② -夕にいたれば 大殿を 振り放け見つつ 鶉なす い匍ひ廻り-(万2-199) ② 天降りつく 天の香具山 霞立つ 春に至れば 松風に 池波立ちて-(万3-259) ④ -天雲の そくへの極み 天地の 至れるまでに-(万3-423) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いち [市] | 〔名詞〕 人が集まって、物品を売買するところ。また、人が多く集まるにぎやかな所。 |
東の市の植木の木垂るまで逢はず久しみうべ恋ひにけり(万3-313) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻三-310 頭注『市』」】 市は各地の産物を場所や日時を定めて交易する仕組み。 私設もあったが、藤原宮の頃から国営の市(官市)が開かれ、平城京では左・右京にそれぞれ東市・西市が設けられるようになった。 東市(西市も同様)は総面積が四町(二六五メートル平方)で、四方築地堀で囲まれていたとみられる。 関市令によると市司(いちのつかさ)の管理統制のもとに、毎日正午門が開かれ、日没には鼓を合図に解散した。 その中には店舗が軒を連ね、商品が並び、大勢の人が集まり賑わった。また街路樹が植えてあり、その緑陰は市民の憩いの場ともなった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いちしば | 【小学館「新編日本古典文学全集萬葉集巻第四-513 頭注『イツシバ』」】 -この市柴原の- 「イチシバ」は「イツシバ」の転。「イツシバ(一六四三)」の「イツ」は「イツカシ(九)」のそれに同じ。原文は底本や元暦校本などには「此市柴乃」とあるが、桂本や金沢本には「此市柴原乃」となっているのによる。「バハ類音が連続する。「五柴原能(二七七〇)」の例もある。以上類音にして「イツシカ」を起こす序。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いつ [厳・稜威] | 〔名詞〕《上代語》 ① 激しい勢い。尊厳な威光。 ② 神聖なこと。清浄なこと。 |
① いつのをたけび踏みたけびて(記上) ② あら草をいつの席(むしろ)と刈り敷きて(祝詞) ② 莫囂円隣之大相七兄爪謁気我が背子がい立たせりけむ厳橿が本(万1-9) (青:難訓) ② 天霧らし雪も降らぬかいちしろくこのいつ柴に降らまくを見む (万8-1647) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いつ [何時] | 〔代名詞〕 ① 不定称の指示代名詞。はっきり定まらない時を示す。いつ。いつか。 ② (多く、格助詞「より」を伴って) いつも。ふだん。 |
① よく渡る人は年にもありといふをいつの間にそも我が恋ひにける(万4-526) ① -過ぐしやりつれ 蜷の腸 か黒き髪に いつの間か 霜の降りけむ- (万5-808) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -いつ [いつ何時] | ① いつもの時。平生。②しかじか(の日)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ぞ | (過去、未来の)ある時。いつだったか。そのうちいつか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ぞは | 将来いつかは。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -となく | ① いつと限ることなく。いつも。② いつのまにか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ともなし | いつと日を限ることない。いつも。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ともわかず | いつとも決まっていない。いつでも。 | 夕月夜さすやをかべの松の葉のいつともわかぬ恋もするかな (古今恋一-490) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のまさかも | いつの瞬間も。いつも。 | しらかつく木綿は花もの言こそばいつのまさかも常忘らえね(万12-3009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -はあれど | いつでもそうだがとりわけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ばかり | いつのころ。 | 貞観の御時、「万葉集はいつばかりつくれるぞ」と問はせたまひければ、 よみてたてまつりける (古今雑歌下詞書-997) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -をいつとて [いつを何時とて] | いつを限りの時として。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いつ [凍つ・冱つ] | 〔自動詞タ行下二段〕【テ・テ・ツ・ツル・ツレ・テヨ】 こおる。いてつく。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いづ [出づ] | 〔自動詞ダ行下二段〕【デ・デ・ヅ・ヅル・ヅレ・デヨ】 ① (中から外へ)出る。(表面に)現れる。 ② 出発する。③ 離れる。逃れる。 |
① 飼飯の海の庭良くあらし刈り薦の乱れて出づ見ゆ海人の釣船(万3-257) ① 我が背子し遂げむと言はば人言は繁くありとも出でて逢はましを(万4-542) ② -大船に 真楫貫き下ろし いさなとり 海路に出でて あへきつつ-(万3-369) ② 出でて去なむ時しはあらむをことさらに妻恋しつつ立ちて去ぬべしや(万4-588) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞ダ行下二段〕【デ・デ・ヅ・ヅル・ヅレ・デヨ】 ① 外に出す。表す。 ② (「うち出づ」「言(こと)に出づ」などの形で)口に出して言う。打ち明ける。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔補助動詞ダ行下二段〕【デ・デ・ヅ・ヅル・ヅレ・デヨ】 (動詞の連用形の下に付く場合)⇒次項「=いづ・= 出づ」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =いづ [=出づ] | 〔補助動詞ダ行下二段〕【デ・デ・ヅ・ヅル・ヅレ・デヨ】 ① (動詞の連用形の下に付いて) [ア] 「~はじめる」「~だす」の意を表す。 〔例語〕生き出づ・輝き出づ・香り出づ・匂ひ出づ・開け出づ(=咲き始める)・吹き出づ・降り出づ・萌え出づ [イ]「~て(外に)出る」の意を表す。 〔例語〕歩み出づ・走り出づ・はひ出づ・舞ひ出づ・ゐざり出づ ② (動詞の連用形の下に付いて)外に向かって行う、または外に表し出す意を表す。「~出す」 〔例語〕誘(いざな)ひ出づ・抱き出づ・思ひ出づ・漕ぎ出づ・捜し出づ・たづね出づ・調(てう)じ出づ(=食事をととのえて出す)・問ひ出づ・眺め出づ・引き出づ・待ち出づ・見出づ・迎へ出づ・呼び出づ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いつか [何時か] | 〔副詞〕〔なりたち〕[代名詞「何時 (いつ) 」+係助詞「か」] ① 未来のある時点についての疑問を表す。「いつになったら~か」 ② 過去のある時点についての疑問を表す。「いつの間に~か」 ③ 反語を表す。「いったいいつ~か (いや、そんなことはない)」 |
① 海の底沖つ白波龍田山いつか越えなむ妹があたり見む(万1-83) ① 我妹子に猪名野は見せつ名次山角の松原いつか示さむ(万3-282) ① つのさはふ磐余も過ぎず泊瀬山いつかも越えむ夜は更けにつつ(万3-285) ② ぬれてほす山路の菊の露のまにいつか千歳を我は経にけむ (古今秋下-273) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いつき [斎] | 〔名詞〕 ① 潔斎して神に仕えること。また、その人。 ② 神を祭る所。③ 斎女(いつきめ)の略。④ 斎の皇女(みこ)の略。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いつきのみや [斎の宮] | 〔名詞〕 ① 大嘗会のときの斎忌(ゆき)・主基(すき)の両神殿。 ② 伊勢・賀茂の斎きの皇女(みこ)の居所。③ 「いつきのみこ」 に同じ。 |
-渡会の斎きの宮ゆ 神風に い吹き惑はし 天雲を 日の目も見せず-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻二-199 注『渡会の斎の宮ゆ』】 「渡会」は和名抄の郡名に「渡会 和多良比」 とある。皇太神宮の鎮座する地。斎宮は、天照大神を斎き奉る宮すなわち神宮をさす。 垂仁二十五年紀に「故隧大神教其祠立於伊勢国因興斎宮于五十鈴川上」 とある。「斎宮」 をイツキノミヤと訓むか、イハヒノミヤと訓むか、説が分かれる。 旧訓はイツキノミヤであったが、万葉考にイハイノミヤと改め、古義などこれに従っている。 講義は「未だいづれをよしともいふべからず」 として旧訓により、以後の諸注もイツキノミヤと訓むものが多い。 澤瀉注釈に万葉集の本文では斎をイムまたはイハフと訓む例のみで、とくに「祝部らが斎(いは)ふ社」(10・二三〇九) のような例もあり、イツキノミヤと定めてしまうのが躊躇されるという。問題は残されているが、斎宮をイツキノミヤと訓む例のあることは確かであり、一応旧訓に従っておきたい。伊勢の渡会の皇大神宮から。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いつく [斎く] | 〔自動詞カ行四段〕汚れを除き、心身を清めて神に仕える。 | -こもりくの 泊瀬の山に 神さびに 斎きいますと 玉梓の-(万3-423) 左夫流児が斎きし殿に鈴掛けぬ駅馬下れり里もとどろに(万18-4134) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いづく [何処] | 〔代名詞〕[「く」は場所を表す接尾語] 場所ついての不定称の指示代名詞。「どこ」。 |
我が背子はいづく行くらむ沖つ藻の名張の山を今日か越ゆらむ(万4-514) -栗食めば まして偲はゆ いづくより 来りしものぞ まなかひに- (万5-806) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いつしか [何時しか] | 〔副詞〕[代名詞「いつ」+副助詞「し」+係助詞「か」] ① それと気づかぬうちに、事の進んでいたさま。知らぬ間に。いつの間にか。早くも。 ② (その時が来るように待ち望む気持ちをこめて) 早く。出来るだけ早い時期に。 ③ 事の起こった、あるいは起こるときがどの時かと考える語。いつか。 |
② いつしかと待つらむ妹に玉梓の言だに告げず去にし君かも(万3-448) ② 大原のこの市柴原のいつしかと我が思ふ妹に今夜逢へるかも(万4-516) ③ -淡路島 礒隠り居て いつしかも この夜の明けむと さもらふに-(万3-391) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ―と [何時しかと] | 〔副詞〕[副詞「いつしか」+格助詞「と」] ① いつの間にやら。いつの間にか早くも。 ② さっそく。すぐさま。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いつしば [厳柴] | 〔名詞〕[「いつ」は勢い盛んなの意] 生い茂った雑木。 | 天霧らし雪も降らぬかいちしろくこのいつ柴に降らまくを見む(万8-1647) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -はら [厳柴原] | 〔名詞〕雑木がたくさん茂っている原。 | 大原のこの市柴原のいつしかと我が思ふ妹に今夜逢へるかも(万4-516) 道の辺のいつ柴原のいつもいつも人の許さむ言をし待たむ(万11-2780) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いづち [何方・何処] | 〔代名詞〕[「ち」は場所を表す接尾語] 方向についての不定称。どの方角。どちら。どこ。 |
ここにして家やもいづち白雲のたなびく山を越えて来にけり(万3-290) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いづへ [何処辺] | 〔代名詞〕[「へ」は、辺りの意の接尾語] どちらの方向。どちら。 |
秋の田の穂の上に霧らふ朝霞いつへの方に我が恋やまむ(万2-88) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いづみがは [泉川] | 〔地名〕京都府相楽郡を流れる川。今の木津川。北流して淀川に合流する。 | -くすしき亀も 新代と 泉の川に 持ち越せる 真木のつまでを- (万1-50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻第一-50 泉の川」注】 今の木津川。当時、宇治川と泉川の流れ込むところに広大な巨椋の池があった (9・1699)。 先にも記したように、ここに流し落とした木材を、今度は泉川の逆流に沿って上げ、その上流からしばらく陸地を経て佐保川に流して下ろし、佐保川と泊瀬川の合流点から泊瀬川を逆流させて藤原へと運んだ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いつも [厳藻] | 〔名詞〕語義未詳。 一説に、生い茂った藻。「いつもいつも」にかかる序詞を構成する。 |
川の上のいつ藻の花のいつもいつも来ませ我が背子時じけめやも(万4-494) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いつも [何時も] | 〔副詞〕いつであっても。つねに。 | 妹が家に咲きたる梅のいつもいつも成りなむ時に事は定めむ(万3-401) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いづものをとめ [出雲娘子] | 【有斐閣「萬葉集全注巻三-429 注『出雲の子ら』」】 題詞の「出雲娘子」のこと。この名も前の「土形娘子」と同じ境遇が考えられるので、出雲出身の采女であろう。しかし、この「出雲」には「湧き出る雲」として、生命力・生産力の象徴としての意味を暗示させる。次の、はかない「霧」と対比。なお〔考〕参照。「子ら」は複数ではなくて親称。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いづら [何ら] | 〔代名詞〕[「ら」はおおよそを示す接尾語] 不定称の指示代名詞。 場所や方角・事態などを漠然とさして言う語。どこ。どのあたり。どのよう。 〔感動詞〕 相手をうながしたり、相手に問いかけたりするときに、用いる語。どうした。さあさあ。 |
〔代名詞〕 礒の上に根延ふむろの木見し人をいづらと問はば語り告げむか(万3-451) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いで | 〔感動詞〕 ① 人を行動に誘うのに用いる語。「さあ」「いざ」 ② 感動や驚き嘆く気持ちなどを表す語。「いやもう」「いやまあ」 ③ 決意や決心を表す語。「さあ」「どれ」 ④ 否定し反発する気持ちを表す語。「いや」「いいえ」 ⑤ ことばを改めて語り出すときなどに用いる語。「さて」 |
① 丹生の川瀬は渡らずてゆくゆくと恋痛し我が背いで通ひ来ね(万2-130) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いでく [出で来] | 〔自動詞カ行変格活用〕【コ・キ・ク・クル・クレ・コ(コヨ)】 ① 出てくる。現れる。 ② (事態や出来事が)発生する。起こる。(子供が)生まれる。 ③ できる。仕上がる。④ (時や機会が)めぐってくる。 |
① 倉橋の山を高みか夜隠りに出で来る月の光乏しき(万3-293) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いでたち [出で立ち] | 〔名詞〕 ① 旅に出ること。出立。 ② 世の中に出て身を立てること。立身出世。③ 装い。みごしらえ。扮装。 ④ 樹木や山がそびえ立っている姿。物の姿。たたずまい。 |
④ -たづさはり 我が二人見し 出で立ちの 百足る槻の木-(万2-213) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いでたつ [出で立つ] | 〔自動詞タ行四段〕 ① 出て立ち止まる。② 樹木・山などが聳え立つ。③ 旅立つ。出発する。 ④ 装う。身支度する。⑤ 宮仕えに出る。出仕する。 ⑥ 出世する。栄達する。⑦ 出る。 |
② -駿河の国と こちごちの 国のみ中ゆ 出で立てる 富士の高嶺は-(万3-322) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いでまし [行幸] | 〔名詞〕 (天皇・皇子・皇女などが)お出かけになること。 特に「行幸(ぎょうこう)。みゆき。 |
-我が大君の 行幸の 山越す風の ひとり居る-(万1-5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いでましどころ [行幸処] | 〔名詞〕行幸される場所。 | -鳴く鳥の 声も変はらず 遠き代に 神さび行かむ 行幸処(万3-325) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いでます [出で座す] | 〔自動詞サ行四段〕《「ます」 は尊敬の意を表す補助動詞》 ① 「出(い) づ」 の尊敬語。お出になる。お出かけになる。いらっしゃる。 ② 「来(く)」 の尊敬語。(こちらへ)来られる。 おいでになる。いらっしゃる。 ③ 「あり」 の尊敬語。おいでになる。いらっしゃる。 |
① けころもを時かたまけて出でましし宇陀の大野は思ほえむかも(万2-191) ① -望月の いやめづらしみ 思ほしし 君と時どき 出でまして-(万2-196) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いでみる [出で見る] | 〔他動詞マ行上一段〕【ミ・ミ・ミル・ミル・ミレ・ミヨ】 (その場所に)出て行って見る。 |
-心もありやと 我妹子が 止まず出で見し 軽の市に 我が立ち聞けば-(万2-207) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いと [糸] | 〔名詞〕 ① 糸。また、糸のように細い物。② 弦楽器の弦。転じて、弦楽器。 ③ 《女房詞》納豆。 |
① 我が持てる三つ合ひに搓れる糸もちて付けてましもの今そ悔しき(万4-519) ① 青柳の糸のくはしさ春風に乱れぬい間に見せむ子もがも(万10-1855) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いと | 〔副詞〕 ① (下に形容詞」・形容動詞・状態を表す動詞を伴って)たいそう。非常に。 ② まったく。ほんとうに。 ③ (下に打消の語を伴って) たいして。そんなに。それほど。 |
① 我妹子がやどの橘いと近く植ゑてし故に成らずは止まじ(万3-414) ② 国々の防人集ひ船乗りて別るを見ればいともすべなし(万20-4405) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いとま [暇] | 〔名詞〕 ① 仕事などのない時間。ひま。余裕。② 休み。休暇。 ③ 喪に服すこと。忌引き。④ 勤めをやめること。 ⑤ 別れ去ること。離別。死別。また、その際のあいさつ。いとまごい。 ⑥ 夫婦の関係を絶つこと。離縁。離婚。 ⑦ 絶え間。すきま。 |
① 志賀の海女は軍布刈り塩焼き暇なみくしげの小櫛取りも見なくに(万3-281) ① ももしきの大宮人は暇あれや梅をかざしてここに集へる(万10-1887) ⑦ 暇なく人の眉根をいたづらに掻かしめつつも逢はぬ妹かも(万4-565) ⑦ ひさかたの月は照りたり暇なく海人の漁りは灯し合へり見ゆ(万15-3694) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いな [否] | 〔感嘆詞〕 ① 人の申し出や行為に不同意を表わす語。いや、いいえ。 ② 相手の問いに対する否定の語。いえ、いいえ。 |
① み薦刈る信濃の真弓我が引かば貴人さびていなと言はむかも [禅師] (万2-96) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -いな [否々] | いやいや、いえいえ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -もうも [否も諾も] | いやもおうも。 | 何すと違ひは居らむ否も諾も友のなみなみ我れも寄りなむ(万16-3820) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -をかも [否も諾も] | 「を」は感動の助詞、そうではないだろうか。違うのだろうか。 | 筑波嶺に雪かも降らるいなをかも愛しき子ろが布乾さるかも(万14-3365) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いな | 〔終助詞〕 終助詞「い」と「な」の熟合したもの。確かめと感動を表わす。 〔接続〕文の終わりに付く。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いなだき [頂] | 〔名詞〕頭のてっぺん。いただき。 | いなだきにきすめる玉は二つなしかにもかくにも君がまにまに(万3-415) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-412 注『いなだき』」】 頭上に髪を集めて束ねたところ。イタダキ(頂上) と同源。「タ」と「ナ」との交替は、同地名を「五十田狭(イタサ)の小汀(をばま)」(神代紀下) とも「伊那佐(イナサ)の小浜」(記・上) ともいうこと、また「都多(ツタ)」(2・一三五) を「綱(ツナ)」(6・一〇四六) ともいうことなどに例がある。「髻鬘」(神代紀上) の古訓に「イナダキ」 とあり、『新撰字鏡』に「髻、伊太々支(イタゝキ)」 とあるように、単に頭上をさすのではなく、髻(もとどり・たきふさ・たぶさ) をさす。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いなびつま [稲日つま] | 【小学館「新編日本古典文学全集萬葉集 付録『地名一覧』」】 兵庫県加古川河口の高砂市付近をいうか。「イナビ」は「イナミ」に同じ。 『播磨国風土記』には「ナビツマ」という形も見え、陰妻(なびつま) の伝説から生まれた地名という。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いなみくにはら (いなびの) [印南国原(稲日野)] |
〔地名〕 |
香具山と耳成山とあひし時立ちて見に来し印南国原(万1-14) →「立ちて見に来し」 稲日野も行き過ぎかてに思へれば心恋しき加古の島見ゆ [一云 水門見ゆ](万3-254) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 『付録 地名一覧』」】 現在の兵庫県東部、加古郡および加古川・明石二市の一帯と言われる。『播磨国風土記』(揖保郡)上岡の里の条に「出雲国の阿菩(あぼの)大神、大倭国の畝傍・香久山・耳梨(みみなし)の三山相闘ふを聞かして、これを諫め止めむと欲して上り来ましし時、ここに到りて即ち闘ひ止みぬと聞き、その乗らせる船を覆して坐しき。 故に神阜(かみをか)と号(なづ)く」とある。万葉集では「印南国原」とあり、東西約三〇キロメートルも離れる点に疑問があるが、説話の伝搬は例が多く、ここもその一例と考えてよかろう。 【有斐閣「萬葉集全注巻三-253 注『稲日野』」】 兵庫県加古郡、加古川市、明石市一帯の平原 (荒木良雄「稲日都麻・印南野考」国語・国文昭和七年四月)。 播磨国風土記賀古郡・印南郡の条に「南ビ都麻(ナビツマ)」(妻が隠れる)の説話があり、また景勝の地でもある。 --- 明石から加古川あたりにかけての平野。明石には港があって、難波津から出港して二泊目、筑紫方面から帰ってくると、大和島が視野に入る最終段階の停泊地とされた。 [有斐閣「万葉集全注」] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いなみ(のうみ) [印南(の海)] | 〔地名〕 | 名ぐはしき印南の海の沖つ波千重に隠りぬ大和島根は(万3-306) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-303 注『印南』」】 二五三歌に「稲日野」とあった「稲日」と同地で、兵庫県明石市から加古川にかけての景勝地。そこの海が「印南の海」で「播磨灘」。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いにしへ [古] | 〔名詞〕[ナ変動詞「往(い)ぬ」の連用形「いに」に過去の助動詞「き」の連体形「し」、名詞「方(へ)」の付いたもの。] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① 遠く過ぎ去った世。ずっと昔。 ② 過ぎ去った時。過去。昔。いやもおうも。 |
① いにしへに恋ふる鳥かも弓絃葉の御井の上より鳴き渡り行く(万2-111) ① み吉野の滝の白波知らねども語りし継げば古思ほゆ(万3-316) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -びと [古人] | 〔名詞〕昔なじみの人。昔の恋人。以前の夫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ぶみ [古典] | 〔名詞〕昔の書物。古典。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いぬ [寝ぬ] | 〔自動詞ナ行下二段【ネ・ネ・ヌ・ヌル・ヌレ・ネヨ】 (名詞「寝(い)」と下二段動詞「寝(ぬ)とが複合したもの」)寝る。眠る。 |
真土山夕越え行きて廬前の角太川原にひとりかも寝む(万3-301) 古にありけむ人も我がごとか妹に恋ひつつ寐ねかてずけむ(万4-500) 夕されば小倉の山に鳴く鹿は今夜は鳴かず寐ねにけらしも (万8-1515) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いぬ [往ぬ・去ぬ] | 〔自動詞サ変〕【ナ・ニ・ヌ・ヌル・ヌレ・ネ】 ① 行ってしまう。去る。②過ぎ去る。時が移る。③世を去る。死ぬ。 |
① 飛ぶ鳥の明日香の里を置きて去なば君があたりは見えずかもあらむ [一云 君があたりを見ずてかもあらむ](万1-78) ③ - もみち葉の 過ぎて去にきと 玉梓の 使ひの言へば 梓弓-(万2-207) ③ -うち嘆き 妹が去ぬれば 茅渟壮士 その夜夢に見-(万9-1813 ③ いつしかと待つらむ妹に玉梓の言だに告げず去にし君かも(万3-448) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いのち [命] | 〔名詞〕 ① 生命・寿命。② 一生・生涯。③ 生命を支えるもの。唯一のよりどころ。 |
① 天の原振り放け見れば大君の御いのちは長く天足らしたり(万2-147) ① 我が命も常にあらぬか昔見し象の小川を行きて見むため(万3-335) ① わすれじの行く末までは難ければ今日を限りのいのちともがな (新古恋三-1149) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いのる [祈る] | 〔他動詞ラ行四段〕 [神聖の意を表す接頭語「い」に動詞「宣(の)る」が付いたもの神仏の名やまじないのことばを口に出し、幸いを求める意] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (神仏に)願をかける。 【参考】古くは「神仏を祈る」の形で用いられた。 |
哭沢の神社に三輪据ゑ祈れども我が大君は高日知らしぬ(万2-202) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いは [岩・石・磐・巌] | 〔名詞〕① 巨大な石。岩石。② 漁網のすそにつけるおもり。錨。 | -波の上を い行きさぐくみ 岩の間を い行きもとほり 稲日つま-(万4-512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いはかきふち [磐垣淵] | 〔名詞〕岩がその周りを垣のように取り囲んでいる淵。 | -大船の 思ひ頼みて 玉かぎる 磐垣淵の 隠りのみ 恋ひつつあるに-(万2-207) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いはがね [岩が根] | 〔名詞〕土の中に、しっかり根をおろしたような岩。岩根。 | 岩が根のこごしき山を越えかねて音には泣くとも色に出でめやも(万3-304) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いはくにやま [磐国山] | 【小学館「新編日本古典文学全集萬葉集 付録『磐国山』」】 山口県岩国市から西南の玖珂町に至る間の山か。 山陽道中最大の難所といわれ、JR岩徳線の柱野駅から西隣の欽明路駅までの間の欽明路トンネルの上に当る欽明路峠の山道が特に険しい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いはしろ [磐代] | 〔地名〕現在の和歌山県日高郡南部町岩代。 | 磐白の浜松が枝を引き結びま幸くあらばまた帰り見む(万2-141) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いはつつじ [岩躑躅] | 〔名詞〕石や岩の間に生えるつつじ。 | 水伝ふ礒の浦廻の岩つつじ茂く咲く道をまたも見むかも(万2-185) 思ひ出づる常盤の山の岩躑躅いはねばこそあれ恋しきものを(古今恋一-495) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いはと [岩戸] | 〔名詞〕 岩屋の入口の戸。堅固な岩の戸。 また、古墳の棺を安置した石室の戸。「岩屋戸」とも。 |
-天の原 岩戸を開き 神上り 上りいましぬ [一云 神登り いましにしかば] -(万2-167) 豊国の鏡の山の岩戸立て隠りにけらし待てど来まさず(万3-421) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いはとこ [岩床] | 〔名詞〕表面が平らな岩。 | -栲の穂に 夜の霜降り 岩床と 川の氷凝り 寒き夜を-(万1-79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いはね [岩根] | 〔名詞〕岩の根もと。大きい岩。いわお。 | かくばかり恋ひつつあらずは高山の磐根しまきて死なましものを(万2-86) 妹に逢はずあらばすべなみ岩根踏む生駒の山を越えてぞ我が来る (万15-3612) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いはばしる [石走る] | 〔自動詞ラ行四段〕水が岩の上を激しく走り流れる。 | 石走りたぎち流るる泊瀬川絶ゆることなくまたも来て見む(万6-996) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】「滝」「垂水(たるみ)」、地名「近江(淡海あふみ」にかかる。 | 石走る瀧もとどろに鳴く蝉の声をし聞けば都し思ほゆ(万15-3639) 命をし幸くよけむと石走る垂水の水をむすびて飲みつ(万7-1146) -天離る 鄙にはあれど 石走る 近江の国の 楽浪の-(万1-29) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いはひべ [斎ひ瓮] | 〔名詞〕 神に供える酒を入れる神聖な瓶。 多くは陶製で底が丸く、地面を掘って据えたらしい。 |
-さかきの枝に しらか付け 木綿取り付けて 斎瓮を 斎ひ掘り据ゑ-(万3-382) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いはふ [斎ふ] | 〔他動詞ハ行四段〕 ① 忌謹んで吉事を祈る。斎戒して無事を願う。 ② 神としてあがめ祭る。 |
① 櫛も見じ屋内も掃かじ草枕旅行く君を斎ふと思ひて(万19-4287) ② -木綿取り付けて 斎瓮を 斎ひ掘り据ゑ 竹玉を しじに貫き垂れ-(万3-382) ② 祝らが斎ふ社の黄葉も標縄越えて散るといふものを(万10-2313) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いはふね [岩船・磐船] | 〔名詞〕神を乗せて天空を航行するという、岩で作られた船。 また、堅固で神聖な船。「天(あま)の岩船」とも。 |
ひさかたの天の探女が石船の泊てし高津はあせにけるかも(万3-295) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いはほ [巖] | 〔名詞〕[「岩秀(いはほ)」の意。「ほ(秀)は突き出て目立つ物の意。] ひときわ聳え立った大岩。巨岩。 |
-出で立ちて みそぎてましを 高山の 巌の上に いませつるかも(万3-423) 巌すら行き通るべきますらをも恋といふことは後悔いにけり(万11-2390) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いはみ [石見] | 〔地名〕 旧国名。山陰道八カ国の一つ。今の島根県西部。石州 (せきしゆう)。 |
石見の海 角の浦廻を 浦なしと 人こそ見らめ 潟なしと-(万2-131) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いはむら [岩群] | 〔名詞〕岩の多く集まったところ。岩の群。 | 川の上のゆつ岩群に草生さず常にもがもな常処女にて(万1-22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いはむすべ [言はむ術] | 〔なりたち〕 [四段動詞「言ふ」の未然形「いは」+推量助動詞「む」の連体形「む」+名詞「術(すべ)」] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言おうとする方法・手段。言いよう。 | 言はむすべせむすべ知らず極まりて貴きものは酒にしあるらし(万3-345) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いはもと [岩本] | 〔名詞〕岩の根本。 | 奥山の岩本菅を根深めて結びし心忘れかねつも(万3-400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いはや [岩屋・窟] | 〔名詞〕 岩に横穴を掘って作った住居。また、岩の間に自然に出来た洞穴。岩室。 |
常磐なす岩屋は今もありけれど住みける人そ常なかりける(万3-311) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いはやと [岩屋戸] | 〔名詞〕岩屋の戸、また、戸口。 | 岩屋戸に立てる松の木汝を見れば昔の人を相見るごとし(万3-312) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いはれ [磐余] | 〔地名〕 | つのさはふ磐余も過ぎず泊瀬山いつかも越えむ夜は更けにつつ(万3-285) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 『付録 地名一覧』」】 奈良県桜井市南西部から橿原市香久山の東北麓にかけての一帯。この地に神功皇后の磐余稚桜宮をはじめとして都が営まれたことがある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いはれのいけ [磐余の池] | 〔地名〕 | 百伝ふ磐余の池に鳴く鴨を今日のみ見てや雲隠りなむ(万3-419) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 『付録 地名一覧』」】 奈良県桜井市の西南部、香久山の東北にあった池。 「履中紀」二年に磐余の池を作ったとあるが、現在その遺址なく、範囲を明らかにしない。一説にJR桜井線香久山駅の南、東尻池町御厨子周辺の低地に擬する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いひ [飯] | 〔名詞〕米などを蒸したもの。のちには炊いたものにもいう。飯。ご飯。 | 家にあれば笥に盛る飯を草枕旅にしあれば椎の葉に盛る(万2-142) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いひつぐ [言ひ継ぐ] | 〔他動詞ガ行四段〕言い伝える。語り伝える。 | -雪は降りける 語り継ぎ 言ひ継ぎ行かむ 富士の高嶺は(万3-320) -神代より 人の言ひ継ぎ 国見する 筑波の山を 冬ごもり -(万3-385) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いふ [言ふ] | 〔他ハ行四段〕 ① 心に思っていることを言葉で相手に伝える。話す。 ② 言葉で形容する。③ 名付ける。呼ぶ。 ④ 世の中でそういう。伝聞する。⑤ 名を付けて区分する。わきまえる。 ⑥ 詩歌を詠む。吟ずる。 |
① - 玉梓の 使ひの言へば 梓弓 音に聞きて [一云 音のみ聞きて] -(万2-207) ① 来むと言ふも来ぬ時あるを来じと言ふを来むとは待たじ来じと言ふものを (万4-530) ② -胸こそ痛き 言ひもえず 名づけも知らず -(万3-469) ③ 妹と言はばなめし畏ししかすがに懸けまく欲しき言にあるかも (万12-2927) ④ -露こそば 朝に置きて 夕には 消ゆといへ 霧こそば 夕に立ちて-(万2-217) ④ 天雲の 向伏す国の もののふと 言はるる人は 天皇の 神の御門に-(万3-446) ⑤ 畑子らが夜昼といはず行く道を我れはことごと宮道にぞする(万2-193) ⑤ -ぬばたまの 夜昼といはず 思ふにし-(万4-726) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔自動詞ハ行四段〕 ① 言い寄る。求婚する。② (動物が)鳴く。 ③ 区別する。わきまえる。(多く「~といはず」の否定の形で用いられる) |
③ -ぬばたまの 夜昼といはず 思ふにし 我が身は痩せぬ 嘆くにし-(万4-726) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いふる [い触る] | 〔自動詞ラ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】《上代語》 [「い」は強意の接頭語] 触れる。触る。 |
みつみつし久米の若子がい触れけむ礒の草根の枯れまく惜しも(万3-438) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いへ [家] | 〔名詞〕 ① 人の住む建物。住まい。② 自分の家。我が家。③ 妻。 ④ 血の繋がりのある者。血筋。家族。⑤ 家の名跡。家名。⑥ 家柄。 ⑦ 家柄のよいこと。名門。 |
② 妹が家も継ぎて見ましを大和なる大島の嶺に家もあらましを [一云 妹があたり継ぎても見むに] [一云 家居らましを](万2-91) ② 苦しくも降り来る雨か三輪の崎狭野の渡りに家もあらなくに(万3-267) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いへぢ [家路・家道] | 〔名詞〕 ① 家の方へ向かう道。② 我が家へ帰る道。帰路。 |
① 児らが家道やや間遠きをぬばたまの夜渡る月に競ひあへむかも(万3-305) ① 松浦なる玉島川に鮎釣ると立たせる子らが家道知らずも(万5-860) ② 草枕この旅の日に妻離り家道思ふに生けるすべなし(万13-3361) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いへづと [家苞] | 〔名詞〕家への土産。 | 伊勢の海の沖つ白波花にもが包みて妹が家づとにせむ(万3-309) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いへのしま [家の島] | 〔地名〕 | -なづさひ行けば 家の島 荒磯の上に うち靡き 繁に生ひたる-(万4-512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 『付録 地名一覧』」】 家島とも。兵庫県飾磨郡家島町。家島本島・男鹿島・西島・坊勢島などからなり、姫路市の飾磨港の西南一八キロメートルの沖にある。 瀬戸内海を航行する旅人は家族を意味する「家」の語を持つこの島に親愛の情を抱きつつ過ぎて行った。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いほ [五百] | 〔名詞〕(多く接頭語的に用いて)五百(ごひゃく)。また、数の多いこと。 【例語】 「五百枝(え)」「五百日(か)」「五百年(とせ)」「五百機(はた)」「百夜(よ)」など。 |
大君は神にしませば天雲の五百重が下に隠りたまひぬ(万2-205) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いほえ [五百枝] | 〔名詞〕たくさんの枝。 | みもろの 神名備山に 五百枝さし しじに生ひたる つがの木の-(万3-327) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いほえなみ [五百重波] | 〔名詞〕幾重にも重なって立つ波。いほえ | -夕なぎに 五百重波寄す 辺つ波の いやしくしくに 月に異に-(万6-936) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】名詞「五百重波」の意から、「立つ」にかかる。 | み崎廻の荒磯に寄する五百重波立ちても居ても我が思へる君(万4-571) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いほさきのすみだがはら [廬前の角太河原] |
真土山夕越え行きて廬前の角太川原にひとりかも寝む(万3-301) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔地名〕 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 『付録 地名一覧』」】 角太河原は和歌山県橋本市隅田町を流れる紀ノ川の河原。真土山を西に越えて南下した地点に当たる。廬前はこの隅田町辺りの総名か。 いま隅田八幡の鳥居の辺りにイオサキの地名が残る。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いほはら [廬原] | 〔地名〕静岡県庵原郡。近年郡内町村の多くが清水市に編入された。 |
廬原の清見の崎の三保の浦のゆたけき見つつ物思ひもなし(万3-299) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いほへ [五百重] | 〔名詞〕幾重にも重なっていること。 | 大君は神にしませば天雲の五百重が下に隠りたまひぬ(万2-205) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いほり [廬・庵] | 〔名詞〕 ① 旅先などで、仮小屋に泊ること。 ② 粗末な仮りの家。僧侶や世捨て人の住居。(=庵 あん・いほ) |
① 宵に逢ひて朝面無み名張にか日長き妹が廬りせりけむ(万1-60) ② さびしさに堪へたる人のまたもあれないほりならべむ冬の里 (新古冬-627) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いほる [廬る・庵る] | 〔自動詞ラ行四段〕仮の住まいをつくって宿る。 | -狭岑の島の 荒磯面に 廬りて見れば 波の音の 繁き浜辺を-(万2-220) 大君は神にしませば天雲の雷の上に廬りせるかも(万3-235) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いま [今] | 〔名詞〕 ① (過去・未来に対して) 現在、自分が直面しているとき。現在。現代。 ② (古いものに対して) 新しいこと。新しいもの。 |
① 秋さらば今も見るごと妻恋ひに鹿鳴かむ山ぞ高野原の上(万1-84) ① 常磐なす岩屋は今もありけれど住みける人そ常なかりける(万3-311) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いま [今] | 〔副詞〕 ① ただいま。目下。② すぐに。ただちに。③ まもなく。近いうちに。 ④ その上。さらに。もう。⑤ 新しく。今度。 |
① み立たしの島の荒礒を今見れば生ひざりし草生ひにけるかも(万2-181) ① 梅の花今盛りなり百鳥の声の恋しき春来るらし [小令史田氏肥人](万5-838) ② 憶良らは今は罷らむ子泣くらむそれその母も我を待つらむそ(万3-340) ② 今来むと言ひしばかりに長月の有明の月を待ち出でつるかな (古今恋四-691) ④ 我が宿の萩花咲けり見に来ませいま二日だみあらば散りなむ(万8-1625) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いまさら [今更] | 〔副詞〕 ① 今あらためて。今あらたに。 ② 今はじめて。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いまさらなり [今更なり] | 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 ① 今となっては、どうにもならない。今となってはしかたがない。 ② まったく初めてである。事新しい。 |
今更に何をか思はむうちなびく心は君に寄りにしものを(万4-508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いまし [今し] | 〔名詞「いま」+ 強意の副助詞「し」 〕 たった今。今ちょうど。 |
霍公鳥今し来鳴かば万代に語り継ぐべく思ほゆるかも(万17-3936) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いましは [今しは] | 今は。今こそは。 | あらたまの年の経ぬれば今しはとゆめよ我が背子我が名告らすな(万4-593) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻第四-590 注『今しはと』」】 「今シ」 は「今」 に強意の「シ」 が付いた形であるが、熟合して一語のように用いられることが多い。遊仙窟の古訓に「向来」の二字を「イマシ」 と読ませた例は多く、「今しはし名の惜しけも我はなし」(七三二) のように、「今シハシ」 という語形さえもある。古今和歌集巻第十五の「今しはとわびにしものを」(七七三) の歌において、梅沢本はその第一句の右に「今はと同事也」 と注している。冒頭から「今しは」 までは相手の心中を忖度した言葉。この下に、もう公表してもよかろう、というような内容が省かれている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| います [坐す・在す] | [上代の尊敬の動詞「坐(ま)す」に接頭語「い」の付いたもの] ①〔自動詞サ行四段・サ変〕【セ・シ・ス・スル・スレ・セヨ】 ア:「あり」の尊敬語。「いらっしゃる」「おいでになる」 イ:「行く・来(く)」の尊敬語。「おでかけになる」「おいでになる」 ②〔他動詞サ行下二段〕サ変【セ・セ・ス・スル・スレ・セヨ】 「あらしむ」「行かしむ」の対象になる者を尊敬していう。 「いらっしゃるようにさせる」「おいでにならせる」「いらっしゃらせる」 |
①「ア」-千代までに いませ大君よ 我れも通はむ(万1-79) ①「ア」嶋の宮上の池なる放ち鳥荒びな行きそ君いまさずとも(万2-172) ①「ア」-よけくもぞなき うつそみと 思ひし妹が 灰にていませば(万2-213) ①「ア」-平けく 親はいまさね つつみなく 妻は待たせと-(万20-4432) ①「イ」-白たへの 天領巾隠り 鳥じもの 朝立ちいまして 入日なす-(万2-210) ①「イ」家思ふと心進むな風まもりよくしていませ荒しその道(万3-384) ①「イ」他国に君をいませていつまでか我が恋ひ居らむ時の知らなく(万15-3771) ② -神下し いませまつりし 高照らす 日の御子は 飛ぶ鳥の-(万2-167) ② -出で立ちて みそぎてましを 高山の 巌の上に いませつるかも(万3-423) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 「①」の自動詞は上代では四段、中古から「おはす(サ変)」に類推してサ変に転じていく。 「②」の他動詞の用法は、自動詞を下二段に活用させ、使役の意を持たせたもの。用例は少ない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔補助動詞サ行四段・サ変〕サ変【セ・シ・ス・スル・スレ・セヨ】 (用言の連用形に付いて)尊敬の意を表す。 「~て(で)いらっしゃる」「~て(で)おいでになる」 |
大君は神にしませば雲隠る雷山に宮敷きいます(万3-236) -見む時までは 松柏の 栄えいまさね 貴き我が君[御面謂之美於毛和] (万19-4193) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いまだ [未だ] | 〔副詞〕 ① (下に打消の表現を伴って) まだ。今でもまだ。 ② (下に肯定表現を伴って) まだ。今もなお。 |
① 人言を繁み言痛みおのが世にいまだ渡らぬ朝川渡る(万2-116) ① しらぬひ筑紫の綿は身に付けていまだは着ねど暖けく見ゆ(万3-339) ① 筑紫船いまだも来ねばあらかじめ荒ぶる君を見るが悲しさ(万4-559) ① 見まつりていまだ時だに変はらねば年月のごと思ほゆる君(万4-582) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いまちづき [居待ち月] | 〔名詞〕 (座って、月の出るのを待つ意から) 陰暦十八日の夜の月。 特に、八月十八日の夜の月をいう。居待ちの月。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】「明石(あかし)」 にかかる。 | -伊予に廻ほし 居待月 明石の門ゆは 夕されば 潮を満たしめ-(万3-391) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いまは [今は] | 〔名詞〕[名詞「今」+係助詞「は」] 臨終。死に際。死期。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いまは [今は] | 〔なりたち〕名詞「いま」+係助詞「は」 (「今はもうかぎりだ」の意から) 今となっては。もうこれまで。 |
昔こそ難波田舎と言はれけめ今は都引き都びにけり(万3-315) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いままた [今また] | 今ふたたび。 | 朝鳥の音のみや泣かむ我妹子に今また更に逢ふよしをなみ(万3-486) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いめ [夢] | 〔名詞〕《上代語》 [「寝(い)目」の意か。夢。 |
真野の浦の淀の継橋心ゆも思へや妹が夢にし見ゆる(万4-493) 秋されば恋しみ妹を夢にだに久しく見むを明けにけるかも(万15-3736) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いめのわだ [夢のわだ] | 〔地名〕奈良県吉野郡吉野町宮瀧付近の淵の名。 | 我が行きは久にはあらじ夢のわだ瀬にはならずて淵にもありこそ(万3-338) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 『付録 地名一覧』」】 喜佐谷を北流してきた象(きさ)の小川が小瀑をなして吉野川に落ち込むあたり。 『懐風藻』の「従駕吉野宮」(八〇、吉田宣の作)に、「今日夢の淵の上に、遺響千年に流らふ」と見える。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いも [妹] | 〔名詞〕 男性から、年齢の上下にかかわりなく、妻・恋人・姉妹など女性を親しんで呼ぶ語。⇔兄(せ) 【参考】 普通は男性から女性に対していうが、時には女性同士が親しんで用いたこともある。 |
紫のにほへる妹を憎くあらば人妻故に我れ恋ひめやも(万1-21) 妹が家も継ぎて見ましを大和なる大島の嶺に家もあらましを [一云 妹があたり継ぎても見むに] [一云 家居らましを](万2-91) しひきの山のしづくに妹待つと我れ立ち濡れぬ山のしづくに(万2-107) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いもせ [妹背] | 〔名詞〕 ① 「いも」 と呼び「せ」 と呼ぶ間柄。親しい男女の関係。夫婦。 ② 兄と妹。姉と弟。 |
① 後れ居て恋ひつつあらずは紀伊の国の妹背の山にあらましものを(万4-547) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いもせやま [妹背山] | 【小学館「新編日本古典文学全集萬葉集 付録『地名一覧』」】 「妹背の山・妹背山」(勢能山) 和歌山県伊都郡かつらぎ町の背ノ山(168m) と紀ノ川を挟んで対岸の妹山(124m) とを合わせて呼んだもの。北の和泉山脈と南の竜門山脈が最も接近する地点。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いももあれも [妹も我れも] | 【枕詞】 妻も私も潔白である、ということから「清(きよみ)」にかかる。 |
妹も我れも清みの川の川岸の妹が悔ゆべき心は持たじ(万3-440) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いや [弥] | 〔接頭語〕[「いよ」の転] ① いよいよ、ますますの意を表す。 ② いちだんと、非常に、まったくの意を表す。 ③ 最も、いちばんの意を表す。 【参考】 「副詞」とみる説もある。 |
① 去年見てし秋の月夜は照らせども相見し妹はいや年離る(万2-211) ① -ひさかたの 天伝ひ来る 雪じもの 行き通ひつつ いや常世まで(万3-263) ① 新しき年の初めの初春の今日降る雪のいやしけ吉事(万20-4540) ② いや愚(をこ)にして(=愚かで)(記中) ③ いや先立てる兄(え)をし枕(ま)かむ(記中) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -つぎつぎに [弥次次に] | 〔副詞〕いよいよ次々に。しだいしだいに。 | -栂の木の いや継ぎ継ぎに 天の下-(万1-29) -つがの木の いや継ぎ継ぎに 玉葛 絶ゆることなく-(万3-327) -三船の山に 瑞枝さし 繁に生ひたる 栂の木の いや継ぎ継ぎに-(万6-912) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -とほながし [弥遠長し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① (距離が) 一段と遠く長い。 ② (時間的に) 遠く隔たっている。永久だ。 |
① 富士の嶺のいや遠長き山道をも妹がりとへばけによばず来ぬ(万14-3370) ② -天地の いや遠長く 偲ひ行かむ 御名にかかせる 明日香川-(万2-196) ② -玉葛 いや遠長く 祖の名も 継ぎ行くものと 母父に 妻に子どもに-(万3-446) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いゆく [い行く] | 〔自動詞カ行四段〕[「い」は接頭語] 行く。 | -あをによし 奈良の都の 佐保川に い行き至りて 我が寝たる-(万1-79) -い行きはばかり 時じくそ 雪は降りける 語り継ぎ 言ひ継ぎ行かむ-(万3-320) 今さらに君はい行かじ春雨の心を人の知らざらなくに(万10-1920) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いよいよ [愈愈] | 〔副詞〕[「いよいよ」の転か] ① なおその上に。いっそう。ますます。 ② とうとう。ついに。確かに。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いよ [伊予] | 〔国名〕 | -奇しきものか 淡路島 中に立て置きて 白波を 伊予に廻ほし-(万3-391) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛媛県に当たる。古くは四国全部をいう。「持統紀」三年の條に「伊予総領」の職名が見え、当時四国全体を統轄する総領が伊予に置かれていた可能性がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いよのたかね [伊予の高嶺] | -宣しき国と こごしかも 伊予の高嶺の 射狭庭の 岡に立たして-(万3-325) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-322 注『伊予の高嶺の射狭庭の岡』」】 「伊予の高嶺」については諸説があったが、武智雅一の、石鎚山脈、特に道後の東北に近い高縄山・福見山また射狭庭の背景として聳える山々をいうとする説(「『伊予の高嶺』私考」万葉昭和三十年七月) が認められるようになった。 そこで、「高嶺の」のノは、その山々に続いて存在する、の意として、次の「射狭庭の岡」(愛媛県松山市道後温泉の裏にある伊佐尓波(いさにわ)の岡と湯月城址の岡。 海抜七十メートルほどの小丘) との地理的関係が理解できるわけである。 ところが近年奥村恒哉は、「こごしかも伊予の高嶺」といえば、「石鎚山」をさすより外はないこと、そして「高嶺の射狭庭の岡」という表現からは石鎚山の中に射狭庭の岡があるとしなければならないが、現に道後温泉から石鎚山は遠きに過ぎて視野に入らないので右の説は無理だとし、「伊予の高嶺」という表現に歌枕的性格を認め、「石鎚山」の名に「石土毘古(イハツチビコ)命」(記上巻) の巨石信仰があり、神代以来の聖域として、石鎚山及び比較的近距離にある道後周辺の山々が考えられたので、赤人の「こごしかも 伊予の高嶺の 射狭庭の 岡」の表現があるのだと考え、「赤人は道後温泉の一部分となるのである。」と述べている(「こごしかも伊予の高嶺」国語国文昭和五十五年二月)。 首肯できる説と思われる。すなわち石鎚山の一峰として赤人が認めたのだ、ということを理解させてくれる論文である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いよよ [愈] | 〔副詞〕[「いよいよ」の転か] ますます。その上に。いっそう。 |
昔見し象の小川を今見ればいよよさやけくなりにけるかも(万3-319) 世間は空しきものと知る時しいよよますます悲しかりけり(万5-796) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いよる [い寄る] | 〔自動詞ラ行四段〕《上代語》「い」は「接頭語」 寄る・近寄る。 | -夕には い寄り立たしし み執らしの-(万1-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いらごがしま [伊良湖が島] | 【地名・歌枕】 今の愛知県渥美半島の突端、伊良湖岬。 島ではないが、「万葉集」では「いらごのしま」と歌われた。 |
打ち麻を麻続の王海人なれや伊良虞の島の玉藻刈ります(万1-23) 潮騒に伊良虞の島辺漕ぐ舟に妹乗るらむか荒き島廻を(万1-42) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いりえ [入り江] | 〔名詞〕海や湖が陸に入り込んだところ。入り海。 | 草香江の入江にあさる葦鶴のあなたづたづし友なしにして(万4-578) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いりたつ [入り立つ] | 〔自動詞タ行四段〕 ① 深く入る。はいりこむ。 ② 親しく出入りする。親しくする。 ③ 物事に深く通じている。 |
① -見つつ あさもよし 紀伊路に入り立ち 真土山 越ゆらむ君は-(万4-546) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いりひ [入り日] | 〔名詞〕夕日。落日。 | -天伝ふ 入日さしぬれ 大夫と 思へる我れも 敷栲の-(万2-135) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いりひなす [入り日なす] | 【枕詞】入り日のごとくの意から「隠る」(亡くなる)にかかる。 | -朝立ちいまして 入日なす 隠りにしかば 我妹子が 形見に置ける- (万2-210) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いる [入る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 中に入る。はいっていく。 ② (日や月が) すっかり沈む。隠れる。没する。 ③ (宮中・仏門などに) はいる。④ 入り用とする。必要とする。 ⑤ ある状態・境地にする。⑥ 時間・時期になる。 ⑦ (心・力が) こもる。はいりこむ。 ⑧ (「来(ク)」「行く」「あり」の代用語。「せ給ふ」などの尊敬語を伴って) 「いらっしゃる。おいでになる。」 〔補助動詞ラ行四段〕(動詞の連用形の下に付いて) 「すっかり~する。まったく~になる。」 〔他動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 ⑨ 中に入れる。加える。⑩ (心・力を) こめる。加える。 〔補助動詞ラ行下二段〕(動詞の連用形の下に付いて) 中に入れる。受け入れるの意を表す。 |
①-山を茂み 入りても取らず 草深み -(万1-16) ② 朝ぐもり日の入り行けばみ立たしの島に下り居て嘆きつるかも(万2-188) ⑦ 何ゆゑか思はずあらむ紐の緒の心に入りて恋しきものを(万12-2989) ⑩-力をも入れずして天地を動かし-(古今・仮名序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いる [射る] | 〔他動詞ヤ行上一段〕【イ・イ・イル・イル・イレ・イヨ】 矢などを放つ。矢などを射当てる。 【参考】 「ヤ行上一段活用」の動詞は「射る・沃(い)る」「鋳(い)る」の三語だけ。 |
大丈夫のさつ矢手挟み立ち向ひ射る圓方は見るにさやけし(万1-61) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いろ [色] | 〔名詞〕 ① 色合い。色彩。② 位階によって定められている色。当色(とうじき)。 ③ 天皇・皇族以外は、原則として身に着けることを禁じられた色。禁色(きんじき) ④ 喪服の色。鈍色(にびいろ=濃いねずみ色)。また、喪服。 ⑤ 顔色。表情。様子。そぶり。⑥ 情趣。風情。けはい。 ⑦ (心の) 優しさ。情味。⑧ 表面的なはなやかさ。派手。華美。 ⑨ 恋愛。色ごと。情事。⑩ 女性。恋人。⑪ 種類。品(しな)。 |
① 託馬野に生ふる紫草衣に染めいまだ着ずして色に出でにけり(万3-398) [⑤ 託馬野に生ふる紫草衣に染めいまだ着ずして色に出でにけり(万3-398)] ⑥ 春の色の至りいたらぬ里はあらじ さけるさかざる花の見ゆらん(古今春下-93) ⑧ 今の世の中、色につき、人の心、花になりにけるより(古今仮名序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 ① 美しい。つややかだ。 ② 好色である。浮気である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【色の分化】 虹(にじ)の色は「赤・橙・黄・緑・青・藍・紫」 の七色だが、古い時代には「あか・あを」 の二色だった。「紫・赤・橙・黄」 は「あか」、「緑・青・藍」 は「あを」 の領域に入る。 「橙」 は柑橘類の一種の名、「緑」 は草木の若芽、「藍・紫」 は草の名。これらの語を「~のような色」 と用いて、領域が分化されたのである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いろせ | 〔名詞〕《上代語》「いろ」 は同母を表す接頭語。 同じ母から生まれた兄、または弟。 |
うつそみの人なる我れや明日よりは二上山を弟背と我が見む(万2-165) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いろにいづ [色に出づ] | (心の中の思いが) 顔色や素振りに表れる。 下二段動詞「出づ」の活用。 |
岩が根のこごしき山を越えかねて音には泣くとも色に出でめやも(万3-304) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| う | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| う [得] | 〔他動詞ア行下二段〕【エ・エ・ウ・ウル・ウレ・エヨ】 ① 手に入れる。自分のものにする。 ② 身に受ける。身につける。会得する。 ③ (多く「心を得」「意を得」の形で) さとる。理解する。 ④ (用言の連体形に「を」「こと」の付いた形を受けて) することができる。 |
① 我れはもや安見児得たり皆人の得かてにすといふ安見児得たり (万2-95) ② -しかあれど、これかれえたる所、えぬ所互ひになむある- (古今仮名序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔補助動詞ア行下二段〕動詞の連用形の下に付いて 「~することができる」 |
留め得ぬ命にしあればしきたへの家ゆは出でて雲隠りにき(万3-464) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| う [鵜] | 〔名詞〕 水鳥の名。全身黒色で、くちばしが長い。 鵜飼に用いられるのは海鵜(うみう)の飼育されたもの。 |
阿倍の島鵜の住む磯に寄する波間なくこのころ大和し思ほゆ(万3-362) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のまねするからす [(-の真似する烏)] |
自分の能力をかえりみず人の真似をして失敗するもののたとえ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のめたかのめ [(-の目鷹の目)] |
鵜が魚を、鷹が小鳥をねらうときのように目を鋭くして物を探すさま。また、その目つき。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うう [飢う・餓う] | 〔自動詞ワ行下二段〕【ヱ・ヱ・ウ・ウル・ウレ・ヱヨ】 空腹に苦しむ。飢える。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うう [植う] | 〔他動詞ワ行下二段〕【ヱ・ヱ・ウ・ウル・ウレ・ヱヨ】 植物の種子や根を土にうめる。植える。種をまく。 |
橘をやどに植ゑ生ほし立ちて居て後に悔ゆとも験あらめやも(万3-413) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うかは [鵜川] | 〔名詞〕川で鵜を使って鮎などの川魚をとること。また、それを業とする人。 |
-上つ瀬に 鵜川を立ち 下つ瀬に 小網さし渡す-(万1-38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻第一-38」頭注】 鵜川は川漁の一種。昼間、鵜を首縄をかけずに放ち、上流から下流に向けて魚を追わせ、事前に設けた敷網に魚が集まったところで、その網を上げる漁法。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うかぶ [浮かぶ] | 〔自動詞バ行四段〕 ① 物の表面に浮いている。特に水面に浮いている。⇔「沈む」 ② (水面に浮いているように)揺れ動いて定まらない。不安定である。 ③ (気持ちや態度が)浮ついている。落ち着かない。 ④ 物事が表面に現れる。出てくる。 ⑤ 思い起こされる。自然と思い出す。 ⑥ 苦しい境遇から抜け出る。救われる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞バ行下二段〕【ベ・ベ・ブ・ブル・ブレ・ベヨ】 ① 水面に浮かべる。 ② 苦しい境遇から救い出す。世に出す。 ③ 暗記する。暗唱する。 |
①-もののふの 八十宇治川に 玉藻なす 浮かべ流せれ 其を取ると- (万1-50) ① -継ぎきたる 那珂の港ゆ 船浮けて 我が漕ぎ来れば 時つ風-(万2-220) ① 春柳かづらに折りし梅の花誰れか浮かべし酒坏の上に [壹岐目村氏彼方] (万5-844) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うから [親族] | 〔名詞〕[上代は「うがら」] 血縁の人。身内の人。親族。一族。=族(やから) | -良しと聞かして 問ひ放くる 親族兄弟 なき国に 渡り来まして-(万3-463) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うきね [浮き寝] | 〔名詞・自動詞サ変〕【セ・シ・ス・スル・スレ・セヨ】 ① 水鳥が水に浮かんだまま寝ること。 また、そのように水上に船をとどめて寝ること。 ② 流す涙に浮き上がるほどの悲しみを抱いて寝ること。 ③ 男女がはかない契りを結ぶこと。 |
① 海原に浮寝せむ夜は沖つ風いたくな吹きそ妹もあらなくに(万15-3614) ② しきたへの枕ゆくくる涙にそ浮き寝をしける恋の繁きに(万4-510) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うく [浮く] | 〔自動詞カ行四段〕 ① 浮ぶ。漂う。⇔「沈む」② 落ち着かない。安定しない。浮つく。 ③ いいかげんである。あてにならない。 ④ 陽気になる。うきうきする。⑤ 表面にあらわれる。出る。 |
①-身もたな知らず 鴨じもの 水に浮き居て 我が作る 日の御門に- (万1-50) ① 家にてもたゆたふ命波の上に思ひし居れば奥か知らずも [一云 浮きてし居れば](万17-3920) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うく [浮く] | 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 浮かべる。浮くようにする。 |
久方の天の川に舟浮けて今夜か君が我がり来まさむ(万8-1523) 柔びにし 家を置き こもりくの 泊瀬の川に 舟浮けて 我が行く川の (万1-79) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うごかす [動かす] | 〔他動詞サ行四段〕 ① 物を動くようにする。② 感動させる。 |
① 君待つと我が恋ひ居れば我が屋戸の簾動かし秋の風吹く(万4-491) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うす [失す] | 〔自動詞サ行下二段〕【セ・セ・ス・スル・スレ・セヨ】 ① なくなる。消え去る。② 死ぬ。 |
① -夕に立ちて 朝には 失すといへ 梓弓 音聞く我れも 凡に見し-(万2-217) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うた [歌・唄] | 〔名詞〕 ① 声を長く引き、節をつけて歌う詞の総称。多く音楽を伴う。 ② 和歌や歌謡・漢詩などの総称。詩歌。 ③ 和歌のうち、特に三十一音の短歌形式のもの。 |
- 岡に立たして 歌思ひ 辞思ほしし み湯の上の 木群を見れば-(万3-325) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うだ (うだのおほの) [宇陀 (宇陀の大野)] |
〔地名〕 大和の国の地名。現在の奈良県大宇陀町を中心に、榛原町に」かけての一帯は「宇陀の大野」 と呼ばれた。 神武東征伝説では、天皇の軍は吉野からここを通って大和に入ったという。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うたがふ [疑ふ] | 〔他動詞ハ行四段〕疑う。不審に思う。 | 赤駒の越ゆる馬柵の標結ひし妹が心は疑ひもなし(万4-533) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うち- [打ち] | 〔接頭語〕 (動詞について)動詞の意味を強めたり、 「ちょっと・すばやく・すっかり」など種々の意を添えたりする。 また単に語調を整えるためにも用いられる 〔語例〕 「打ち出づ・打ち驚く・打ちまもる・打ち語らふ・打ち絶ゆ」 |
塩津山うち越え行けば我が乗れる馬そつまづく家恋ふらしも(万3-368) うち靡く春さり来れば小竹の末に尾羽打ち触れて鴬鳴くも(万10-1834) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うち [内] | 〔名詞〕 ① (部屋などの)奥の方。中の方。内部。② 家。家の中。③ 心の中。 ④ (空間的・地域的に)国内。区域内。 ⑤ (数量的に)一部分。その中。以内。 ⑥ (時間的に)期間中。あいだ。⑦ 〔「内裏」とも書く〕宮中。内裏。 ⑧ 天皇。主上。⑨ (儒教を「外(ほか・そと)」というのに対して)仏教。 ⑩ 私事。⑪ (妻が自分自身または夫をさして)妻。夫。 |
① 大宮の内まで聞こゆ網引すと網子ととのふる海人の呼び声(万3-239) ④ やすみしし我が大君の敷きませる国の中には都し思ほゆ(万3-332) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うちいづ [打ち出づ] | 〔自動詞ダ行下二段〕【デ・デ・ヅ・ヅル・ヅレ・デヨ】「うち」は接頭語 ① 出る。現れる。② でしゃばる。③ 出発する。 〔他動詞ダ行下二段〕【デ・デ・ヅ・ヅル・ヅレ・デヨ】 ① (音や火を)打って出す。 ② ちょっと出す。 特に室内の御簾や牛車の下簾から、女房たちの袖口や裾などを少し出す。 ③ 口に出す。言い出す。 |
〔自動詞ダ行下二段〕 ① 田子の浦ゆうち出でて見ればま白にそ富士の高嶺に雪は降りける(万3-321) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うちこゆ [打ち越ゆ] | 〔他動詞ヤ行下二段〕【エ・エ・ユ・ユル・ユレ・エヨ】 (山・関を) 超える。 |
四極山うち越え見れば笠縫の島漕ぎ隠る棚なし小舟(万3-274) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うちそ [打ち麻] | 〔名詞〕「そ」は「麻」の古名。打って柔らかくした麻。打ち麻(そ)。 | 娘子らが績み麻のたたり打ち麻懸けうむ時なしに恋ひわたるかも (万12-3003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うちそを [打ち麻を] | 【枕詞】麻績(をみ)にかかる。「打つ麻を」「を」は間投助詞。→「を」 同義の「枕詞」で、「打ち麻やし」もある。 |
打ち麻を麻続の王海人なれや伊良虞の島の玉藻刈ります(万1-23) -刺部重部 なみ重ね着て 打麻やし 麻続の子ら あり衣の-(万16-3813) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うちなびく [打ち靡く] | 〔自動詞カ行変動詞〕[「打ち」は接頭語] ① 横に倒れ伏す。② ある方に引き寄せられる。③ 従う、同意する。 |
② 安騎の野に宿る旅人うち靡き寐も寝らめやもいにしへ思ふに(万1-46) ②-鳴きし響めば うち靡く 心もしのに そこをしも-(万17-4017) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】 草が靡く様子から、「草木」「黒髪」に、 また、草木が伸びてなびくことから「春」にかかる。 |
おしてる 難波を過ぎて うち靡く 草香の山を 夕暮れに-(万8-1432) ありつつも君をば待たむうち靡く我が黒髪に霜の置くまでに(万2-87) うち靡く春立ちぬらし我が門の柳の末に鴬鳴きつ(万10-1823) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うちのへ [内の重] | 〔名詞〕[「へ」は接尾語] 宮殿の最も内側のの門や垣。また、その内部。 | -神の御門に 外の重に 立ち候ひ 内の重に 仕へ奉りて-(万3-446) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うぢのみやこ [宇治の都] | 〔地名・名詞〕 ミヤコは宮のあるところの意。ここは近江行幸の途中途中仮泊した行宮。 その跡は宇治市下居の下居神社付近かと伝える。 |
秋の野のみ草刈り葺き宿れりし宇治の宮処の仮廬し思ほゆ(万1-7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 『付録 地名一覧』」】 京都府宇治市。大和と近江とを結ぶ道筋に当たる。京阪電車三室戸駅の南西に菟道稚郎子の墓と伝える陵墓がある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うちはし [打ち橋] | 〔名詞〕 ① 板を架け渡しただけの仮の橋。 ② 廊下のある部分を切り、板を渡して橋としたもの。 中庭への出入りなどのとき取り外しが出来る。 |
① -下つ瀬に 打橋渡す 石橋に 一に云ふ「石なみに」生ひなびける-(万2-196) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うちひさす | 【枕詞】太陽のように輝き照らす意から、「都」「宮」「宮路」 にかかる。 | -敷きます国に うちひさす 都しみみに 里家は さはにあれども-(万3-463) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うぢまやま [宇治間山] | 宇治間山朝風寒し旅にして衣貸すべき妹もあらなくに(万1-75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「大和志」によれば、「在池田荘千股村」(吉野郡)とあり、奈良県吉野郡吉野町千股(ちまた)と言われる。 飛鳥から上市への道は、明日香村岡から稲淵・栢森(かやのもり)を経て芋峠を越え、千股を通る道が最も近い。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うちみのさと [打廻の里] | 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 『付録 地名一覧』」】 奈良県高市郡明日香村の近くであろうが、所在不明。雷丘の付近とする説もある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うちよす [打ち寄す] | 〔「うち」は接頭語〕 〔自動詞サ行下二段〕【セ・セ・ス・スル・スレ・セヨ】 ① 波が岸に寄せる。② 馬に乗って近寄る。 〔他動詞サ行下二段〕【セ・セ・ス・スル・スレ・セヨ】 (波が物を) 岸のほうに運ぶ。 |
① 川風のすずしくもあるか うちよする波とともにや秋はたつらん(古今秋上-170) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うちよする [打ち寄する] | 【枕詞】「駿河(するが)」にかかる。 | なまよみの 甲斐の国 うち寄する 駿河の国と こちごちの 国のみ中ゆ-(万3-322) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うつ [打つ・討つ・撃つ] | 〔他動詞タ行四段〕 ① 物を何か他の物に強く当てる。 ア:強くたたく。ぶつ。殴る。 イ:攻める。討伐する。やっつける。 ウ:撃ち殺す。撃ち滅ぼす。 エ:(武器で)斬る。断ち切る。 オ:(石などを)強くたたいて火を出す。 カ:(楽器・鐘など音の出るものを)打ち鳴らす。 キ:生地を砧で打ってつやを出す。 ク:綿弓(わたゆみ)で弾く。 ケ:鉄を鍛えて刀剣などをつくる。 コ:鍬で土を掘り起こす。 サ:馬を進めるために鞭で打つ。馬を走らせる。馬に乗って行く。 シ:(碁・双六・賭博などの)勝負をする。 ス:(点や印などを)書き付ける。 ② 強くたたいて食い込ませる。また、ある状態に作り上げる。 ア:杭などを強くたたいて、深くくいこませる。たたきこむ。打ち込む。 イ:額や立札などを掲げる。打ち付ける。 ウ:設営する。仮に設ける。 エ:(幕などを)張る。 オ:(紙・革などの)裏打ちをする。 カ:(閂を槌で叩いて)門の戸締りをする。 ③ 物を投げて命中させる。 ④(水などを)まく。ばらまく。 ⑤ 計画的に物事をする。 ア:芝居などを興行する。 イ:行う。わざとする。 |
①「ア」面忘れだにもえすやと手握りて打てども懲りず恋といふ奴 (万11-2579) ①「ウ」西の方の悪しき人どもを打ちにつかはして(記中) ①「オ」その火打ちもちて火を打ち出で (記中) ①「コ」打つ田には稗はしあまたありといへど選えし我れぞ夜をひとり寝る (万11-2480) ①「ス」かにかくに物は思はじ飛騨人の打つ墨縄のただ一道に (万11-2656) ②「ア」下つ瀬に真杙(まくひ)をうち(記下) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔自動詞タ行四段〕(雨や波などが)強く叩きつける。 | 霰打つ安良礼松原住吉の弟日娘女と見れど飽かぬかも(万1-65) 風吹けば波打つ岸の松なれやねにあらはれて泣きぬべらなり(古今-671) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔自動詞タ行下二段〕【テ・テ・ツ・ツル・ツレ・テヨ】 [他動詞四段の受身形] ① 押し潰される。②負ける。ひけをとる。③神仏の罰を受ける。 ④ 圧倒される。気おくれする。気をのまれる。⑤合点がいく。納得する。 ⑥(魚などが)腐る。すえる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うつくし [美し・愛し] | 〔形容詞シク活用〕 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 ① かわいい。いとしい。② (小さくて)かわいらしい。愛らしい。 ③ きれいだ。うるわしい。④ 立派だ。見事だ。優れている。 |
① 愛しき人のまきてししきたへの我が手枕をまく人あらめや(万3-441) ① 父母を 見れば貴し 妻子見れば めぐし愛し 世間は -(万5-804) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うつせみ [空蝉・現人・(空蝉)] | 〔名詞〕① この世の人、現実に肉体を持ったもの。②現世、この世。 |
① うつせみは数なき身なり山川のさやけき見つつ道を尋ねな (万20-4492) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (空蝉)蝉の抜け殻、蝉 夏 | 空蝉の鳴く音やよそにもりの露ほしあへぬ袖を人のとふまで (新古恋一-1031) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔語史〕 「うつしおみ」から転じた語で「空蝉」「虚蝉」などの字があてられたが、初めは無常観を含まず、枕詞として単に「この世」という意味で「世」などにかかった。 それが上代末期から、仏教的無常観と「空蝉」の文字の連想から「はかないこの世」の意を含むようになり、また中古以降は、虫の「せみ」や「せみのぬけがら」の意味も生じた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うつせみの [空蝉の・虚蝉の] | 【枕詞】「世」「命」「人」「借れる身」「うつし心」にかかる。 | 玉ならば手にも巻かむをうつせみの世の人なれば手に巻きかたし (万4-732) うつせみの命を惜しみ波に濡れいらごの島の玉藻刈り食む(万1-24) うつせみの人目を繁み石橋の間近き君に恋ひわたるかも(万4-600) -うつせみの 借れる身なれば 露霜の 消ぬるがごとく あしひきの-(万3-469) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うつそみ [現そみ] | 〔名詞〕【「うつせみ」の古形】この世の人。この世。現世。 | うつそみの人なる我れや明日よりは二上山を弟背と我が見む(万2-165) -うつそみと思ひし時に春へは花折かざし秋立てば黄葉かざし- (万2-196) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うつたへ [打つ栲] | 〔名詞〕[「うちたへ」とも] 打って、つやを出した「栲(たへ)」。 |
-あり衣の 財の子らが 打つ栲は 延へて織る布 日さらしの-(万16-3813) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うつたへに [打つ栲に] | 〔副詞〕(下に打消しや反語を伴って) 決して。まったく。ことさら。 |
神木にも手は触るといふをうつたへに人妻といへば触れぬものかも(万4-520) うつたへに籬の姿見まく欲り行かむと言へや君を見にこそ(万4-781) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うづら [鶉] | 〔名詞〕鳥の名。鶉。草深い野に住むとされ、秋の景物として歌に詠まれる。 | - 夕にいたれば 大殿を 振り放け見つつ 鶉なす い匍ひ廻り 侍へど-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うつる [移る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 移り変わる。 ア-場所・位置を変わる。移動・移転。 イ-時が過ぎる。時代が変わる。変移。 ウ-心が変わる。興味が他に転じる。 エ-官位が変わる。転任する。 ② 色あせる。衰える。③ 花が散る。④ 色・香がしみつく。染まる。 ⑤ (物の怪などが) のり移る。⑥ 死ぬ。あの世へ行く。 |
② 花の色はうつりにけりないたづらに 我が身世にふる長雨せしまに(古今春下-113) ③ 今日だにも庭を盛とうつる花消えずはありとも雪かとも見よ(新古今春下-135) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うつろふ [移ろふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 [四段動詞「移る」の未然形+上代の反復・継続の助動詞「ふ」=うつらうの転] ① 場所が変わる。移転する。② 色が変わる。色づく。色や香に染まる。 ③ 色が褪せる。衰える。④ 花や葉が散る。 ⑤ 時が過ぎる。盛りが過ぎて衰えていく。⑥ 心変わりする。 |
① 梅が枝に鳴きて移ろふ鴬の羽白妙に沫雪ぞ降る(万10-1844) ④ 見れど飽かずいましし君がもみち葉の移ろひ行けば悲しくもあるか(万3-462) ⑥ 月草のうつろひ易く思へかも我が思ふ人の言も告げ来ぬ(万4-586) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うなはら [海原] | 〔名詞〕広々とした海。また、広々とした湖・池。 | -国見をすれば 国原は 煙り立ち立つ 海原は 鴎立ち立つ うまし国ぞ-(万1-2) 海原の沖行く船を帰れとか領巾振らしけむ松浦佐用姫(万5-878) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うねびやま [畝傍山] | 〔地名〕今の奈良県橿原市にある山。 【歌枕】香具山・耳成山とともに大和三山といわれる。 |
→ 大和三山(香具山) -軽の市に 我が立ち聞けば 玉たすき 畝傍の山に 鳴く鳥の-(万2-207) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うねめ [采女] | 〔名詞〕[「うねべ」とも] 古代天皇の食事に奉仕した後官の女官。 郡の次官以上の娘で、容姿の美しい、才能のある者から選ばれた。 大化改新後、制度化された。 |
采女の袖吹きかへす明日香風都を遠みいたづらに吹く(万1-51) 我れはもや安見児得たり皆人の得かてにすといふ安見児得たり(万2-95) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うのはな [卯の花] | 〔名詞〕 ① うつぎの花。五月頃、房になって吊鐘状の白い五弁の花が咲く。古くから歌人に愛された。夏 ② 襲(かさね)の色目の名。表は白、裏は萌黄(もえぎ)。夏に用いる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うのはなくたし [卯の花腐し] | 〔名詞〕長く降り続いて卯の花を散らす意から、[五月雨]の異称 夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うはぎ | 〔名詞〕よめな(=植物ノ名)の古名。 山野に自生。若葉を食用にする。花は淡紫色で初秋に咲く。おはぎ。春 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うへ [上] | 〔名詞〕 ① 上位。上部。高方。② 物の表面。うわべ。おもて。 ③ あたり。ほとり。付近。④ 天皇。主上。また、上皇。 ⑤ 天皇、その他の皇族の座のあたり。 ⑥ 清涼殿の殿上の間(ま)。⑦ 貴婦人。奥方。⑧ 将軍。殿様。主君。 ⑨ 貴婦人の称号の下に付けて尊敬の意を表す。 ⑩ その人やその物事に関する事柄。 ⑪ あることにさらに物事が加わる意。そのうえ。 ⑫ (下に「は」を伴って) ~からには。~以上は。 |
② -奈良の都の 佐保川に い行き至りて 我が寝たる 衣の上ゆ-(万1-79) ③ -我が大君 高照らす 日の皇子 荒栲の 藤原が上に 食す国を-(万1-50) ③ -海辺を指して 柔田津の 荒礒の上に か青なる 玉藻沖つ藻-(万2-131) ③ -歌思ひ 辞思ほしし み湯の上の 木群を見れば 臣の木も-(万3-325) ③ 石走る垂水の上のさわらびの萌え出づる春になりにけるかも (万8-1422) ⑥ 寛平の御時、なぬかのよ、「うへにさぶらふをのこども歌たてまつれ」 と仰せられける時に、人にかはりてよめる(古今秋上-177詞書) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うべ [宜・諾] | 〔副詞〕平安中期以降、「むべ」とも表記。肯定の意を表す。 もっともなことに。なるほど。いかにも。 |
夢にだに見えむと我れはほどけども相し思はねばうべ見えざらむ (万4-775) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うま [午] | 〔名詞〕 ① 十二支の七番目。② 方角の名。南。 ③ 時刻の名。今の正午頃およびその前後約二時間(午前十一時~午後一時頃) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うま [馬] | 〔名詞〕「むま」とも表記 ① 動物の名。うま。 乗馬・農耕・運搬・競技・合戦などのために広く飼育された。 ② 双六の駒。③ 将棋の駒の名。 |
① たまきはる宇智の大野に馬並めて朝踏ますらむその草深野(万1-4) ① 見まく欲り我がする君もあらなくに何しか来けむ馬疲るるに(万2-164) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【高価だった馬】 大陸から渡来してきた馬は、便利な乗り物として重要な役割を果たしていた。「伊勢物語」 「源氏物語」 などには、馬を使って移動した場面が見える。 しかし、だれでも持てたわけではなかった。「万葉集」 には、よその夫が馬で行くのに、自分の夫は徒歩で行くので母の形見である真澄み鏡と蜻蛉領布(あきづひれ) で馬を買わせようとする、愛情あふれる妻の長歌がある。馬は高価だったのである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うまこり | 【枕詞】 うまこりは煮こごりのことで、その風味に心ひかれるところから、 「ともし (=心ひかれるの意) 」にかかる。 |
-香れる国に 味凝り あやにともしき 高照らす 日の御子(万2-162) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うまさけ [旨酒・味酒] | 【枕詞】 「うまさけ」である「神酒(みわ・神に供える酒)」から同音の「三輪」、三輪山の別名「三諸(みもろ)」「三室(みむろ)」にかかる。 また、酒は醸(か=噛む)んでつくったところから「神(かむ)」にもかかる。 |
味酒 三輪の山-(万1-17) 我が衣色取り染めむ味酒三室の山は黄葉しにけり(万7-1098) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うまし [甘し・美し・旨し] | 〔形容詞シク活用〕【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 ① 立派だ。素晴らしい。 ② 満ち足りて快い。美しい。 |
①-うまし国ぞ 蜻蛉島 大和の国は(万1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① 味が良い。美味しい。 ② 都合がよい。また、お人よしだ。 |
① 飯食めど うまくもあらず 行き行けど 安くもあらず-(万16-3879) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うませ [馬柵・馬塞] | 〔名詞〕馬を出さないように囲った柵。 | 赤駒の越ゆる馬柵の標結ひし妹が心は疑ひもなし(万4-533) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うまひと [貴人] | 〔名詞〕 「うま」は「良い」「尊い」の意の接頭語。位の高い人。徳の高い人。 |
この夜の夢に、ひとりのうまひとあり(祟神紀) み薦刈る信濃の真弓我が引かば貴人さびていなと言はむかも [禅師] (万2-96) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うみ [海] | 〔名詞〕広く水をたたえている所。海洋・沼・湖など。 | 近江の海夕波千鳥汝が鳴けば心もしのにいにしへ思ほゆ(万3-268) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うみぢ [海路] | 〔名詞〕海上の、船の航路。かいろ。「海つ路(ぢ)」とも。 | -いさなとり 海路に出でて あへきつつ 我が漕ぎ行けば-(万3-369) あしひきの山道は行かむ風吹けば波の塞ふる海道は行かじ(万13-3352) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うみつぢ [海つ路] | 〔名詞〕〔「つ」は「の」の意の上代の格助詞〕「うみぢ」 に同じ。 | 海つ道のなぎなむ時も渡らなむかく立つ波に船出すべしや(万9-1785) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うめ [梅] | 〔名詞〕〔「むめ」とも表記〕 ① 木の名。うめ。また、その花や実。 葉に先立って、白・紅・淡紅色などの香りのよい花が咲き、 初春の花として愛好された。上代、中国から渡来したという。 ② 「梅襲(うめがさね)」の略。襲(かさね)の色目の名。 表は濃い紅梅、裏は紅梅。陰暦十一月から二月ころまで着用。 |
ぬばたまのその夜の梅をた忘れて折らず来にけり思ひしものを(万3-395) 妹が家に咲きたる梅のいつもいつも成りなむ時に事は定めむ(万3-401) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うら- | 〔接頭語〕何となく~の心持ちがする。「うら悲し」「うら寂し」 【うらなく】 ひとりでに泣けてくる |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【「うら-」という構成の語】 「うら」は「裏で見えない」という意味から、「心」の意を表し、多く「うらも無し」の形で使われる。形容詞には「うら-」という構成を持つ語がある。 例えば、「うらがなし」は、「こころ悲しい」、「うらさびし」は 「こころ寂しい」「うらなし」は「無心だ」という意となる。 「うら-」という構成の語には、「うら」の意味が生きていることが多い。「うらやまし」も心が病む感じをいったのが原義。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うら | 〔名詞〕心。内心の思い。 | うらもなく我が行く道に青柳の張りて立てれば物思ひ出つも (万14-3462) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うら [末] | 〔名詞〕「うれ(末)の古形。草木の枝や葉の先。こずえ。 | うら若み花咲きかたき梅を植ゑて人の言繁み思ひぞ我がする(万4-791) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うら [占・卜] | 〔名詞〕 吉凶を判定するため、物の形や兆候で神意を問うこと。うらない。 |
大船の津守が占に告らむとはまさしに知りて我がふたり寝し(万2-109) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【占いの伝統】 占いのは古く、鹿の肩の骨を焼いて割れ目を見る「太古(ふとまに)」、亀の甲を焼いて割れ目を見る「亀の卜(うら)」があった。 そのほかにも、夢を判断する「夢占(ゆめうら)」、十字路に立って、通行人の言葉を聞く「辻占(つじうら)」、夕方、道や門に立って、通行人の言葉を聞く「夕占(ゆふうら)」、歌から判断する「歌占(うたうら)」などがある。将来の吉凶を知りたいと思う気持ちには、長い伝統があったことになる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うら [浦] | 〔名詞〕 ① 海や湖などが湾曲して陸地に入り込んだ所。入り江。 ② 海辺。海岸。 |
① 石見の海 角の浦廻を 浦なしと 人こそ見らめ 潟なしと [一云 礒なしと] 人こそ見らめ (万2-131) ② 見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮れ (新古今秋上-363) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うら [裏] | 〔名詞〕 ① 裏面。内部。奥。 ② 着物などの内側につける布。裏地。 ③ 連歌・俳諧で、懐紙を二つ折りにした場合の裏の面。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うらなく [うら泣く] | 〔自動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 [「うら」は心の意] ① 心の中で、自然と泣けてくる。② しのびなく。 |
-心を痛み ぬえこ鳥 うら泣け居れば 玉たすき 懸けのよろしく-(万1-5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うらがなし [うら悲し] | 〔形容詞シク活用〕 【シカラ・シク・(シカリ)・シ・シキ・(シカル)・シケレ・シカレ】 《「うら」 は心の意》なんとなく悲しい。もの悲しい。 |
朝日照る嶋の御門におほほしく人音もせねばまうら悲しも(万2-189) 春の野に霞たなびきうら悲しこの夕影に鴬鳴くも(万19-4314) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うらさぶ [うら荒ぶ] | 〔自動詞バ行上二段〕【ビ・ビ・ブ・ブル・ブレ・ビヨ】 [「うら」は心の意] 心がすさむ、心が寂しく感じる。 |
楽浪の国つ御神のうらさびて荒れたる都見れば悲しも(万1-33) うらさぶる心さまねしひさかたの天のしぐれの流れ逢ふ見れば(万1-82) -我が寝し 枕づく つま屋の内に 昼はも うらさび暮らし 夜はも-(万2-210) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うらみ [浦廻・浦回] | 〔名詞〕 海岸の曲がりくねったところ。湾。浦回(うらわ)。 |
石見の海角の浦廻を浦なしと人こそ見らめ-(万2-131) 水伝ふ礒の浦廻の岩つつじ茂く咲く道をまたも見むかも(万2-185) 風早の美穂の浦廻の白つつじ見れどもさぶしなき人思へば [或云 見れば悲しもなき人思ふに](万3-437) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うらむ [恨む・怨む] | 〔他動詞マ行上二段〕【ミ・ミ・ム・ムル・ムレ・ミヨ】 ① 恨みに思う。不満に思う。憎く思う。 ② 恨みごとを言う。不平を言う。 ③ 恨みを晴らす。しかえしをする。 ④ 悲しむ。嘆く。 ⑤ (自動詞的な用法で虫や風などが)悲しげに音をたてる。 |
① 逢はずとも我れは恨みじこの枕我れと思ひてまきてさ寝ませ (万11-2637) ② 花散らす風のやどりはたれかしる我に教へよ行きてうらみむ (古今春下-76) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 語源は「心(うら)見る」と考えられ、上代は上一段活用か。中古には上二段、近世には四段に活用し、現代に至っている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うらめし [恨めし・怨めし] | 〔形容詞シク活用〕 【シカラ・シク・(シカリ)・シ・シキ・(シカル)・シケレ・シカレ】 動詞「うらむ」に対応する形容詞。 恨みに思われる。残念である。 |
恨めしく君はもあるか宿の梅の散り過ぐるまで見しめずありける (万20-4520) 春日野に粟蒔けりせば鹿待ちに継ぎて行かましを社し恨めし(万3-408) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うるはし [麗し・美し・愛し] | 〔形容詞シク活用〕 【シカラ・シク・(シカリ)・シ・シキ・(シカル)・シケレ・シカレ】 ① (風景などが) 壮麗だ。立派だ。見事だ。 ② 端正で美しい。きちんと整っている。 ③ 格式通りで、きちんとしている。 ④ 人との交わり方が誠実である。親密である。⑤ 礼儀正しい。 ⑥ 正真正銘である。いい加減なまやかしでない。 |
① 倭の国のまほろばたたなづく青垣山ごもれる倭し麗し(記・中) ② -出でて行きし 愛し夫は 天飛ぶや 軽の道より 玉だすき-(万4-546) ② 愛しと我が思ふ妹を思ひつつ行けばかもとな行き悪しかるらむ(万15-3751) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うれ [末] | 〔名詞〕「うら」の転。 木の枝や草の葉の先端。こずえ。 |
我が聞きし耳によく似る葦の末の足ひく我が背つとめ給ぶべし(万2-128) 後見むと君が結べる磐代の小松がうれをまたも見むかも(万2-146) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うれむそ [うれむそ] | 〔副詞〕「うれむぞ」とも。どうして。 | わたつみの沖に持ち行きて放つともうれむそこれのよみがへりなむ(万3-330) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-327 注『うれむそ』」】 「有廉叙(ウレムゾ)」(11・二四八七) と合わせて二例しかない。代匠記に「語勢ヲ以テ推スルニ、ナンソ、イカンソナト云ニ同シク聞ユ」とある程度しか分かっていないが、「どうして~であろうか。いやそうではない」 と反語を導く副詞に係助詞ソのついたものであろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うゑき [植木] | 〔名詞〕 ① 山野などに生えている木。 ② 庭や鉢などに植えた木。また、植える木。 |
② 東の市の植木の木垂るまで逢はず久しみうべ恋ひにけり(万3-313) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うゑこなぎ [植ゑ小水葱] | 〔名詞〕植え付けた若い水葱(なぎ=水草の一種)。自生するものにもいう。 | 春霞春日の里の植ゑ子水葱苗なりと言ひし枝はさしにけむ(万3-410) 上つ毛野伊香保の沼に植ゑ小水葱かく恋ひむとや種求めけむ(万14-3434) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| え | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| え [枝・肢] | 〔名詞〕 ① 草木のえだ。② (人間や獣などの)手足。四肢。③ 一族。子孫。 |
① 磐白の浜松が枝を引き結びま幸くあらばまた帰り見む(万2-141) ① -堤に立てる 槻の木の こちごちの枝の 春の葉の 繁きがごとく-(万2-210) ① -百足る槻の木 こちごちに 枝させるごと 春の葉の-(万2-213) ① 春霞春日の里の植ゑ子水葱苗なりと言ひし枝はさしにけむ(万3-410) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| え [柄] | 〔名詞〕手に持つための、器物についている棒の部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| え [得] | 〔下二段動詞「う(得)」の連用形の副詞化〕 ①(下に肯定の言い方を伴って)可能の意。~することができる ②(下に打消し又は反語の言い方を伴って)不可能の意。 ~することができない、~できようか(できない) |
①-ここにその荒き波おのづからなぎて、御船え進みき-(記・中) ② 玉かつま安倍島山の夕露に旅寝えせめや長きこの夜を(万12-3166) ② - 侍ひえねば 春鳥の さまよひぬれば 嘆きも いまだ過ぎぬに-(万2-199) ② -頼めりし 児らにはあれど 世の中を 背きしえねば かぎろひの-(万2-210) ② - 降る雪を 火もて消ちつつ 言ひも得ず 名付けも知らず -(万3-322) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔参考〕 現在、関西方言に「よう~ん」の語法があるが、これは「②」の「え~ず(打消し)」の変化したもの。 〔語法〕 「①」は主に上代に見られる。 また後世、叙述語を省略して、「え」だけで否定を表わす用法が見られる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| え | 〔感嘆詞〕(上代語)感動を表わす、ああ。 | -鮎こそは島辺も良き。え苦しゑ-(天智紀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終助詞「よ」のなまったもの、呼び掛けの意、~よ〔上代東国方言〕 | 父母え斎ひて待たね筑紫なる水漬く白玉取りて来までに(万20-4364) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上代の助動詞「ゆ」の未然形または連用形 〔接続;未然形につく〕 | ひな曇り碓氷の坂を越えしだに妹が恋しく忘らえぬかも(万20-4431) 人はよし思ひやむとも玉葛影に見えつつ忘らえぬかも (万2-149) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| えだ [枝・肢] | 〔名詞〕① 草木の枝。② (人間や獣などの) 手足。四肢。③ 一族。子孫。 | ① -神の命 奥山の さかきの枝に しらか付け 木綿取り付けて-(万3-382) ② 夫婦の四つのえだを木に張りて(雄略紀) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| えなつ [得名津] | 〔地名〕 | 住吉の得名津に立ちて見渡せば武庫の泊まりゆ出づる船人(万3-286) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 『付録 地名一覧』」】 大阪市住之江区住之江町・安立町、住吉区南部の墨江辺りから堺市浅香山町・遠里小野町にかけての一帯かという。 後の堺港の前身に発展する開港場とみる説もある。 『住吉大社神代記』に「朴津(えなつ)」として見え、また開口神社文書に文治三年(1187)の田地寄進状があり、それに「摂津国住吉郡朴津郷」の地名が見える。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おいなみに [老い次に] | 〔副詞〕年老いたころに。老境に入って。 | 事もなく生き来しものを老いなみにかかる恋にも我はあへるかも(万4-562) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おう [応 (漢和辞典)] | 【三省堂「全訳 漢辞海」】 [オウ・こた-える] 〔動詞〕 ① こたえる。こたふ。 ア:返事をする。回答する。 イ:承知する。聞き入れる。 ② 相応しい。ちょうど合う。 ③ 共鳴する。調和する。 ④ 受ける。引き受ける。 ⑤ 対処する。処理する。 ⑥ 呼応する。⑦ 兵役につく。徴用に従う。⑧ 加勢する。 ⑨ 予言が適応する。効き目が表われる。 |
〔助動詞〕まさに~べし。 〔副詞〕まさに~べし。すぐさま。~と同時に。すぐ。ただちに。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【句法 Ⅰ】 助動詞として、その目的語である述語構造の前に置き、道理や客観的状況から当然のこととして、ある行為をしたり、またある状態であるべきことを表す。 「まさに~べし」と再読し、「応レ[動詞]二・・・一(まさニ・・・を[動詞]すベシ)という形で用いる。「~すべきである」「~であるべきである」「~しなければならない」などと訳す。 [この句法を用いたと思われる歌] 宇治間山朝風寒し旅にして衣貸すべき妹もあらなくに(万1-75) 原文「衣応借」の通訓は「ころも貸すべき(連体形)」であり、原文「借」が「応」に掛かっているために、助動詞「べし」で、相手の立場からみて、「応借」は「貸」という意味に解釈するのだと思う。 【句法 Ⅱ】 状況に対する推量を表す。助動詞の場合と同様に「まさニ・・・ベシ」と再読する。「おそらく~であろう」「たいてい~のはずである」「たぶん~であろう」などと訳す。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おうのうみ [飫宇の海] | 〔名詞〕 島根県沖の中(なか)の海。 |
飫宇の海の河原の千鳥汝が鳴けば我が佐保川の思ほゆらくに(万3-374) 意宇の海の潮干の潟の片思に思ひや行かむ道の長手を(万4-539) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 島根県の中海を指す。『出雲風土記』に見える意宇(おう)郡は、中海と宍道湖の南岸に当たり、今の能義郡及び八束郡と安来市、松江市の一部に当たる。これを貫いて意宇(いう)川が西北流し中海に注いでいる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おかみ [龗] | 〔名詞〕雨や雪などをつかさどる神。竜神。水の神。 | 我が岡のおかみに言ひて降らしめし雪のくだけしそこに散りけむ (万1-104) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おかみ [御上] | 〔名詞〕① 天皇。朝廷。② 政府。官庁。③ 武家で主君の敬称。④ 貴人の敬称。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おき [沖] | 〔名詞〕 ① 海や湖または川の、岸から遠く離れた水面。 ② (「沖を深めて」の形で比喩的に)心の中。心の奥。 |
① -我が漕ぎ来れば 時つ風 雲居に吹くに 沖見れば とゐ波立ち-(万2-220) ② 海の底おきを深めて我が思へる君には逢はむ年は経ぬとも(万4-679) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おきさく [沖放く] | 〔自動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 「〔さく〕は離れる意」 沖の方に遠ざかる。岸から離れる。 |
鯨魚取り 近江の海を 沖放けて 漕ぎ来る船 辺に付きて―(万2-153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おきつかい [沖つ櫂] | 〔名詞〕沖を漕ぐ船のかい。⇔ 辺(へ)つ櫂 | ―漕ぎ来る船 辺付きて 漕ぎ来る船 沖つ櫂 いたくな撥ねそ―(万2-153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おきつ [沖つ] | 〔連体詞〕[「つ」は「の」の意の上代の格助詞] 沖の。沖にある。 | 〔名詞〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おきつしま [沖つ島] | 縄の浦ゆそがひに見ゆる沖つ島漕ぎ廻る船は釣りしすらしも(万3-360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-360 注『そがひに見ゆる沖つ島』」】 ソガヒは背後。ソ(背)ムカヒ(向) が縮まってソガヒとなった。萬葉集注釈に、このソガヒの表現の生じた背景を説明して、「たとへば作者は沖の島を後にして縄の浦へ航行してゐたので、縄の浦でふりかへつてみると沖の島が見えたので『そがひに見ゆる』と云つた」とある。「沖つ島」は沖合に見える島をいう。 通説では兵庫県の相生湾口の鬘島(かつらじま) をさす。もしそうだとすると、那波から鬘島まで約六キロメートルある。それに対し、吉井巌は、漢籍(『淮南子』兵略訓など) の「背向」 の翻訳語かとし、「前後」あるいは「向かったり背にしたりする意」と述べた。これによれば「鬘島、君島や遥かの家島群島を含むもの」となる。 しかし、ソガヒの語を「背向かひ」と解する限り、「前後」とみるのは無理のように思われる。そこでしばらく註釈の説に従っておく。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おきつしらなみ [沖つ白波] | 〔名詞〕沖に立つ白い波。 |
海の底沖つ白波龍田山いつか越えなむ妹があたり見む(万1-83) 伊勢の海の沖つ白波花にもが包みて妹が家づとにせむ(万3-309) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 「白波が立つ」という連想から、「立田山」の序詞、「しら」と同音であることから「知らず」の序詞となる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おきつなみ [沖つ波] | 〔名詞〕沖の波。 | 沖つ波来寄する荒礒をしきたへの枕とまきて寝せる君かも(万2-222) 沖つ波辺波立つとも我が背子がみ船の泊り波立ためやも(万3-248) ま幸くて妹が斎はば沖つ波千重に立つとも障りあらめやも(万15-3605) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】 沖の波が動くさまから、「頻(し)く・競(きほ)ふ・撓(とを)む・たかし」などにかかる。 |
-月に日に異に [或本歌曰 沖つ波しきてのみやも恋ひわたりなむ](万11-2601) -別れにしより 沖つ波 とをむ眉引き 大船の ゆくらゆくらに-(万19-4244) 沖つ波たかしの浜の浜松の 名にこそ君を待ちわたりつれ(古今雑上-915) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おきつも [沖つ藻] | 〔名詞〕沖の海底に生えている藻。⇔ 辺(へ)つ藻。 | -か青なる 玉藻沖つ藻 朝羽振る 風こそ寄せめ -(万2-131) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おきつもの [沖つ藻の] | 【枕詞】 沖の藻が波に隠れ、なびくところから、「なばる」「なびく」にかかる。 |
我が背子はいづく行くらむ沖つ藻の名張の山を今日か越ゆらむ(万1-43) -照る月の 雲隠るごと 沖つ藻の 靡きし妹は 黄葉の-(万2-207) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おきな [翁] | 〔名詞〕 ① 年取った男。老人。⇔「老女 (おみな)」「嫗 (おみな・おうな)」 ② 老人が自分をへりくだっていう語。わし。じじ。 ③ 老人を親しみ敬って呼ぶ語。おじいさん。 ④ 能楽に用いられる老人の面。おきな面。 ⑤ 能の曲名。「④」をつけ、能楽の最初に式典として行う演目。種々の点で能以前の古い演劇の形を残している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おきへ [沖辺・沖方] | 〔名詞〕沖の方。沖のあたり。 | 玉藻刈る沖へは漕がじ敷栲の枕のあたり忘れかねつも(万1-72) 海原の沖辺に灯し漁る火は明かして灯せ大和島見む(万15-3670) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おく [奥] | 〔名詞〕 ① 内部へ深く入った所、。② 奥の間。家人の常にいる室。 ③ 将来。行く末。 ④ 江戸時代、将軍や大名などが公務をみる「表(おもて)」に対し、 くつろぐ場所、夫人たちのいる所。⇔ 表 ⑤ 貴人の妻の住む所。また、その妻に対する敬称。 ⑥ 物事の終わり。季節の終わり。最後。⑦ 書物や手紙の終わり。末尾。 ⑧ 心の奥。心に深く秘めていること。 ⑨ 〔陸奥(みちのく)の略〕奥州。 |
③ あらかじめ人言繁しかくしあらばしゑや我が背子奥もいかにあらめ(万4-662) ⑧ あきづ羽の袖振る妹を玉くしげ奥に思ふを見たまへ我が君(万3-379) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -まけて [おく設けて] | 将来のことをあらかじめ考えて。行く末長く。 | 近江の海沖つ島山奥まけて我が思ふ妹が言の繁けく(万11-2443) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -まへて | 「おくまけて」の転。将 | 奥まへて我れを思へる我が背子は千年五百年ありこせぬかも(万6-1029) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おく [置く] | 〔自カ行四動詞〕霜や露が降りる | ありつつも君をば待たむうち靡く我が黒髪に霜の置くまでに(万2-87) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他カ行四動詞〕 ① 物をその位置に置く。据える。 ② そのままにする。捨て置く。③ 後に残す。見捨てる。 ④ のぞく。さしおく。⑤ へだてる。⑥ 設ける。設置する。 ⑦ 模様をつける。⑧ 計算する。数える。 |
-をとめの床のべにわがおきし剣の太刀-(記・中) ① -思ひ居れか 栲縄の 長き命を 露こそば 朝に置きて 夕には-(万2-217) ① 佐保過ぎて奈良の手向けに置く幣は妹を目離れず相見しめとそ(万3-303) ① -奇しきものか 淡路島 中に立て置きて 白波を 伊予に廻ほし-(万3-391) ② -黄葉をば 取りてぞ偲ふ 青きをば 置きてぞ嘆く-(万1-16) ③ -神さびせすと 太敷かす 都を置きて 隠口の 初瀬の山は-(万1-45) ③ 飛ぶ鳥の明日香の里を置きて去なば君が辺りは見えずかもあらむ (万1-78) ③ -形見に置ける みどり子の 乞ひ泣くごとに 取り与ふる-(万2-210) ③ 衾道を引手の山に妹を置きて山道を行けば生けりともなし(万2-212) ④ -ひげ掻き撫でて 我れをおきて 人はあらじと-(万5-896) ⑥ 荒波に寄り来る玉を枕に置き我ここにありと誰か告げけむ(万2-226) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔補助カ行四〕 ①(動詞の連用形について) ア:~のこす、~のこしておく イ:あらかじめ~する、かねて~する ②(助詞「て」を伴う動詞につき)あらかじめ~する ③「~(せねば)置かぬ」「~ (しないで) 置こうか」の形で、遣り通すの意。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おくつき [奥つ城] | 〔名詞〕《上代語]》[「つ」は「の」の意の上代の格助詞] =奥(おき)つ城 奥まった場所に構えて作ったあるものの意。墓。神や霊の鎮座している所。 |
-葛飾の 真間の手児名が 奥つきを こことは聞けど 真木の葉や-(万3-434) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おくやま [奥山] | 〔名詞〕人里離れた奥深い山。 | 奥山の菅の葉しのぎ降る雪の消なば惜しけむ雨な降りそね(万3-302) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おくやまの [奥山の] | 【枕詞】 「深き」「真木(まき)」「立つ木」にかかる。 |
奥山の真木の板戸を音早み妹があたりの霜の上に寝ぬ(万11-2623) とぶ鳥のこゑもきこえぬ奥山の ふかき心を人は知らなん(古今恋一-535) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おくれゐる [後れ居る] | 〔自動詞ワ行上一段〕【イ・イ・イル・イル・イレ・イヨ】 取り残されている。 |
後れ居て恋ひつつあらずは追ひ及かむ道の隈廻に標結へ我が背(万2-115) 後れ居て我れはや恋ひむ印南野の秋萩見つつ去なむ子故に(万9-1776) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おくる [後る・遅る] | 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 ① あとになる。遅れる。② とどまる。あとに残る。 ③ 先立たれる。生き残る。④ (才能などが) 劣る。足りない。 ⑤ 髪の毛の生え方が遅くて短い。⑥ 気おくれがする。臆病になる。 |
① のち蒔きのおくれて生ふる苗なれど あだにはならぬたのみとぞ聞く(古今物名-467) ② まそ鏡見飽かぬ君に後れてや朝夕にさびつつ居らむ(万4-575) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おさ(そ)ふ [抑ふ・抑ふ] | 〔他動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 ① 手などを当てて力を加える。押さえる。 ② (痛むところを手で押さえる意から) 我慢する。こらえる。 ③ 押しとどめる。制止する。 ④ 《近世語》相手が差そうとする杯を押し返してもう一度相手に飲ませる。 |
③ -大御馬の 口抑へ止め 御心を 見し明らめし 活道山-(万3-481) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おしてる [押し輝る] | 〔自動詞ラ行四段〕くまなく輝る。 | 窓越しに月おし照りてあしひきのあらし吹く夜は君をしぞ思ふ(万11-2687) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おしてる [押し輝る] | 【枕詞】「難波(なには)」 にかかる。 | -大君の 命恐み おしてる 難波の国に あらたまの-(万3-446) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おしなぶ [押し靡ぶ] | 〔他動詞バ行下二段〕【ベ・ベ・ブ・ブル・ブレ・ベヨ】 〔おしなむ〕とも。押しなびかせる。押しふせる。 |
-真木立つ 荒き山道を 岩が根 禁樹押しなべ 坂鳥の-(万1-45) -安騎の大野に 旗すすき 小竹を押しなべ 草枕 旅宿りせす-(万1-45) 印南野の浅茅押しなべさ寝る夜の日長くしあれば家し偲はゆ(万6-945) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おしなぶ [押し並ぶ] | ① 押しならす。すべて同じようにする。 ② (多く下に助動詞「たり」を伴って)優劣なく一様である。普通だ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おすひ [襲] | 〔名詞〕 上代の衣服の一種。頭からかぶって衣服の上から全身を包むように垂らした長いきれ。男女ともに着たが、おもに、女性が神事の時などに着た。 |
-膝折り伏して たわやめの おすひ取りかけ かくだにも-(万3-382) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おそ [鈍] | [形容詞「鈍 (おそ) し」の語幹。にぶいこと。愚か。 | 風流士と我れは聞けるをやど貸さず我れを帰せりおその風流士(万2-126) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おそり [恐り・畏り] | 〔名詞〕おそれ。不安。心配。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おそる [恐る・畏る・懼る] | 〔自動詞ラ行上二段・四段〕【リ・リ・ル・ルル・ルレ・リヨ】 ① こわがる。② はばかる。 |
① 春日野の山辺の道をおそりなく通ひし君が見えぬころかも(万4-521) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ。ル・ルル・ルレ・レヨ】 ① 心がひるむ。こわがる。② 気づかう。心配する。③ 畏敬する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【語法】 上代には、上二段・四段に活用したが、平安時代中期から下二段活用が使われ始め、次第に下二段活用に統一されたいった。中古の和文にには用例が用例は少ない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おつ [落つ] | 〔自動詞タ行上二段〕【チ・チ・ツ・ツル・ツレ・チヨ】 ① 落ちる。落下する。 ② (雨や雪などが)降る。(木の葉や花が)散る。 ③ 光がさす。照らす。 ④ (日や月が)沈む。没する。 ⑤ 抜け落ちる。欠け落ちる。 ⑥ 落ちぶれる。身をもちくずす。堕落する。 ⑦ つき物が去る。病気が治る。 また、生ものを断つ食事を止め、普通の食事に戻る。精進落ちをする。 ⑧ 戦いに敗れて逃げる。逃げ落ちる。 ⑨ (城などが)敵の手にわたる。陥落する。 ⑩ 白状する。自供する。 |
② 風吹けば落つるもみぢば水きよみちらぬ影さへ底に見えつつ (古今秋下-304) ③ 冬枯れの森の朽ち葉の霜の上に落ちたる月の影の寒けさ (新古今冬-607) ③ 山越しの風を時じみ寝る夜おちず家なる妹を懸けて偲ひつ(万1-6) ③ -その雨の 間なきがごと 隈もおちず 思ひつつぞ来し その山道を (万1-25) ⑤ -我が行く川の 川隈の 八十隈おちず 万たび かへり見しつつ- (万1-79) ⑤ 我が背子が着せる衣の針目落ちずこもりにけらし我が心さへ(万4-517) ⑥ 名にめでて折れるばかりぞ女郎花我落ちにきと人にかたるな (古今秋上-226) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おと [音] | 〔名詞〕 ① 空気の波動で生じる聴覚の刺激。声。響き。 ② うわさ。評判。③ おとづれ。たより。④ 答え。返事。 |
① -梓の弓の 中弭の 音すなり 朝猟に 今立たすらし 夕猟に-(万1-3) ① ますらをの鞆の音すなり物部の大臣盾立つらしも(万1-76) ① ぬばたまの月に向ひて霍公鳥鳴く音遥けし里遠みかも(万17-4012) ② -そこ故に せむすべ知れや 音のみも 名のみも絶えず-(万2-196) ② - 玉梓の 使ひの言へば 梓弓 音に聞きて [一云 音のみ聞きて] -(万2-207) ② -夕に立ちて 朝には 失すといへ 梓弓 音聞く我れも 凡に見し-(万2-217) ② 音のみに聞きて目に見ぬ布勢の浦を見ずは上らじ年は経ぬとも (万18-4063) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おとひをとめ [弟日娘子] | 現代の諸書では、当時の「遊行女婦 (うかれめ)」のことだろう、とするが、鹿持雅澄の「万葉集古義」から、その注釈を載せる。 |
霰打つ安良礼松原住吉の弟日娘女と見れど飽かぬかも(万1-65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おのが [己が] | 〔代名詞「己 (おの)」+格助詞「が」〕① 自分自身が。② 自分自身の。③ 私が。 | ② 人言を繁み言痛みおのが世にいまだ渡らぬ朝川渡る(万2-116) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おのづま [己夫・己妻] | 〔名詞〕 ① 自分の夫 [己夫]。② 自分の妻 [己妻]。 |
① つぎねふ 山背道を 人夫の 馬より行くに 己夫し-(万13-3328) ② -衣手交へて 自妻と 頼める今夜 秋の夜の 百夜の長さ-(万4-549) ② 己妻を人の里に置きおほほしく見つつぞ来ぬるこの道の間(万14-3593) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おび [帯] | 〔名詞〕 ① 着物を着るとき、腰にまとい結ぶための細長い布。 また、束帯の装束のとき、袍の腰を締めるのに用いる細長い牛革。 ② 自社参拝のさいなどに肩にかける紐。掛け帯。 ③ 妊婦が五か月目から腹にまく布。岩田帯。斎肌帯(ゆわだおび)。 ④ 腰に帯びる刀。佩刀(はいとう)。 |
① 古に ありけむ人の 倭文幡の 帯解き交へて 廬屋立て-(万3-434) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おひしく [追ひ及く] | 〔自動詞カ行四段〕追いつく。 | 後れ居て恋ひつつあらずは追ひ及かむ道の隈廻に標結へ我が背(万2-115) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おひつぐ [生ひ継ぐ] | 〔自動詞ガ行四段〕次々に生えて出てくる。生え代わって後を継ぐ。 | - 生ひ継ぎにけり 鳴く鳥の 声も変はらず 遠き代に 神さび行かむ(万3-325) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おびゆ [怯ゆ] | 〔自動詞ヤ行下二段〕【エ・エ・ユ・ユル・ユレ・エヨ】こわがる。おびえる。 | -虎か吼ゆると 諸人の おびゆるまでに [一云 聞き惑ふまで] -(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おふ [生ふ] | 〔自動詞ハ行上二段〕【ヒ・ヒ・フ・フル・フレ・ヒヨ】 生ずる。はえる。生長する。 |
み立たしの島の荒礒を今見れば生ひざりし草生ひにけるかも(万2-181) 飛ぶ鳥の 明日香の川の 上つ瀬に 生ふる玉藻は 下つ瀬に (万2-194) ぬばたまの夜の更けゆけば久木生ふる清き川原に千鳥しば鳴く(万6-930) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おふ [負ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 相応しい。相応する。 |
宜しなへ我が背の君が負ひ来にしこの背の山を妹とは呼ばじ(万3-289) 文屋康秀〔の歌〕は、言葉はたくみにて、そのさま身に負はず(古今仮名序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞ハ行四段〕 ① 背に乗せる。背負う。 ② (「名に負ふ」の形で)身に持つ。名前などをそなえる。 ③ (苦痛・災難・恨みなどを)身に引き受ける。こうむる。 ④ 借金する。物を借りる。 |
①-我が国は 常世にならむ 図負へる くすしき亀も 新代と-(万1-50) ① - 梓弓 靫取り負ひて 天地と いや遠長に 万代に かくしもがもと-(万3-481) ② 名にしおはばいざことはむ都鳥わが思ふ人は有りやなしやと (古今羈旅-411) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おふ [追ふ] | 〔他動詞ハ行四段〕 ① 追いかける。あとを追う。 ②(目的地に)向って行く。 ③ 追い出す。追い払う。 ④(多く「先を追ふ」の形で) 貴人が通るとき、通り道にいる人を追い払う。 先払いをする。 |
① -行きのまにまに 追はむとは 千度思へど たわやめの-(万4-546) ③ 霍公鳥鳴きしすなはち君が家に行けと追ひしは至りけむかも (万8-1509) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おぶ [帯] | 〔他動詞バ行四段・上二段〕【ビ・ビ・ブ・ブル・ブレ・ビヨ】 ① 身に着ける。腰に下げる。② ふくむ。 【語法】 上代では四段に、中古からは上二段に活用した。 |
① 大伴の名に負ふ靫帯びて万代に頼みし心いづくか寄せむ(万3-483) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほ [大-] | 〔接頭語〕 ① 大きい、広い、などの意を表す。 ② 量の多い、の意を表す。 ③ 程度の甚だしい、の意を表す。④ 尊敬・賞賛の意を表す。 |
② 我が里に大雪降れり大原の古りにし里に降らまくは後(万2-103) ③ 烏とふ大をそ鳥のまさでにも来まさぬ君をころくとぞ鳴く(万14-3542) ④ 大殿の この廻りの 雪な踏みそね しばしばも 降らぬ雪ぞ-(万19-4251) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほ- [大-] | 〔接頭語〕(名詞に付いて) ① 大きいこと、広いこと、量の多いこと、程度の甚だしいことを表す。 「大袿(うちき)・大海・大雪」 ② 尊敬・賞賛の意を表す。 「大内(うち)・大君・大宮人」 |
-引き放つ 矢の繁けく 大雪の 乱れて来れ [一云 霰なす そちより来れば]- (万2-199) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほ [凡] | 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 普通だ。一通りだ。通り一遍だ。 |
-朝には 失すといへ 梓弓 音聞く我れも 凡に見し こと悔しきを-(万2-217) そら数ふ大津の児が逢ひし日に凡に見しくは今ぞ悔しき(万2-219) おほならばかもかもせむを畏みと振りたき袖を忍びてあるかも(万6-970) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほかり [多かり] | 〔ク活用形容詞「多し」の補助活用の連用形・終止形〕多い。多くある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 ふつう補助活用(カリ活用)には終止形はなく「かり」は連用形語尾であるが、中古の和文では「多かり」が本活用の終止形「多し」に代わって用いられた。 なお、漢文訓読では「多し」が使われている。 → 「多(おほ)し」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほき [大き-] | 〔接頭語〕 ① (名詞に付いて) 偉大である、また大きいの意を添える。 「~海・~聖」など。 ② 同じ位階・官職のうちの上位をいう。「~ひとつのくらゐ(正一位)」など。 |
① -青香具山は 日の経の 大御門に 春山と 茂みさび立てり-(万1-52) ① 酒の名を聖と負せし古の大き聖の言の宣しさ(万3-342) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほき [大き] | 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 ① 大きい。② (程度が) はなはだしい。たいへんだ。 |
① 一日には千たび参りし東の大き御門を入りかてぬかも(万2-186) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほきみ [大君・大王] | 〔名詞〕 ① 天皇・皇族の尊称。 ② 親王・諸王の尊称。後に「親王(みこ)」に対して、諸王の称。 |
① 天の原振り放け見れば大君の御寿は長く天足らしたり(万2-147) ① 大君は神にしませば天雲の五百重が下に隠りたまひぬ(万2-205) ① 大君は神にしませば雲隠る雷山に宮敷きいます(万3-235) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おおきみの [大君の] | 【枕詞】地名「三笠(みかさ)」にかかる。 | 大君の御笠の山の黄葉は今日の時雨に散りか過ぎなむ(万8-1558) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほきみの みことかしこみ [大君の命恐み] |
大君の 命畏み 柔びにし 家を置き こもりくの 泊瀬の川に 舟浮けて-(万1-79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔慣用句〕【有斐閣「万葉集全注巻第一-79 大君の命畏み」注】 天皇の命令を恐れ畏む慣用句。公の場でうたわれる歌に現れることが多く、長歌の冒頭や、短歌でも一座の最初の歌の冒頭に用いられるのが普通。 奈良朝の慣用句と言ってよく、これはその最も早い例。 「王之御命恐 (オホキミノミコトカシコミ) 」(13・3333) 、 「於保吉美能美許等可之古美 (オホキミノミコトカシコミ) 」(20・4328))など。「畏み」は「畏し」の「ミ語法」。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほし [多し] | 〔形容動詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 多い。 |
みもろの神の神杉已具耳矣自得見監乍共寝ねぬ夜ぞ多き(万2-156) -やまず行かば 人目を多み まねく行かば 人知りぬべみ-(万2-207) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【上代語「おほし」と「多し」「多かり」】 上代では「おほし」は「大し」とも書かれ、「数量が多い」「容量が大きい」「りっぱだ」「正式だ」などの意味があった。 中古以降、数量的な多さは、形容詞「多し・多かり」を使い。容積の大きさには形容動詞「大きなり」を使うようになった。 これが中世末期になると、さらに「多い」「大きい」と区別が明確になる。 なお、中古までの和文では、終止形は「多かり」が一般的で、「多し」は漢文訓読語として使われた。→ 参考「多かり」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほしまのね [大島の嶺] | 〔地名〕所在未詳。 |
妹が家も継ぎて見ましを大和なる大島の嶺に家もあらましを [一云 妹があたり継ぎても見むに] [一云 家居らましを] (万2-91) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻第二-91 大島の嶺」注】 所在未詳。「ネ」は山の高い所。「ミネ」はそれに接頭語「ミ」の添えられた形で、本来は山の頂が神の降臨する神聖な場所であるのを讃えることばだったらしい。 「大島の嶺」は所在未詳であるが、日本後紀大同三年九月十九日の条に平群朝臣賀是麻呂の「伊賀爾布久賀是爾阿礼婆可於保志萬乃乎婆奈能須恵乎布岐牟須悲太留 (いかにふく かぜにあればか おほしまの をばなのすゑを ふきむすびたる) 」という歌があり、平群氏の本居が大和の平群郡だから、この歌の「於保志萬」(大島) も平群郡かと言われる (攷証) 。 澤瀉久孝は、その攷証説を踏まえ、「大島の嶺」を現在の信貴山もしくはその近くの一峯と推定している (『万葉小径』)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほす [生ほす] | 〔他動詞サ行四段〕① 生えさせる。成長させる。② 養育する。育て上げる。 | 我が宿に韓藍蒔き生ほし枯れぬとも懲りずてまたも蒔かむとそ思ふ(万3-387) 橘をやどに植ゑ生ほし立ちて居て後に悔ゆとも験あらめやも(万3-413) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほす [負ほす・課す] | 〔他動詞サ行下二段〕【セ・セ・ス・スル・スレ・セヨ】 [動詞「負ふ」の使役形「負はす」の転] ① 背に乗せる。背負わせる。② 責任を負わせる。罪をきせる。 ③ 名づける。④ (債務・傷などを)負わせる。 ⑤ 与える。当てはめる。付ける。 |
② こづたへばおのが羽風にちる花を たれにおほせてここらなくらん (古今春下-109) ③ 酒の名を聖と負せし古の大き聖の言の宣しさ(万3-342) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほつのみや (地名・おほ) [大津の宮 (地名・大津)] |
〔名詞〕近江(滋賀県)にあった天智天皇の皇居。 天智天皇の六年 (667)、宮を大和の飛鳥から移したが、壬申の乱を経て僅かの間に荒廃した。 |
-石走る 近江の国の 楽浪の 大津の宮に 天の下 知らしめしけむ- (万1-29) 我が命しま幸くあらばまたも見む志賀の大津に寄する白波(万3-291) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほとの [大殿] | 〔名詞〕 ① 宮殿・邸宅の敬称。特に、寝殿・正殿をいう。 ② 大臣の敬称。おとど。 ③ 貴人である当主の敬称。または、その父に対する敬称。 |
①-ここと聞けども 大殿は ここと言へども 春草の-(万1-29) ① -日の皇子 敷きいます 大殿の上に ひさかたの 天伝ひ来る-(万3-263) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほとも [大伴] | 〔氏名〕 大伴氏は天孫降臨の時、その祖が天靫負部(あめのゆげいベ) と呼ばれたと伝える(姓氏録)。 |
大伴の名に負ふ靫帯びて万代に頼みし心いづくか寄せむ(万3-483) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほともの [大伴の] | 【枕詞】「御津(みつ)」「見つ」「高師(たかし)」にかかる。 | いざ子ども早く日本へ大伴の御津の浜松待ち恋ひぬらむ(万1-63) 大伴の見つとは言はじあかねさし照れる月夜に直に逢へりとも (万4-568) 大伴の高師の浜の松が根を枕き寝れど家し偲はゆ(万1-66) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほとりの [大鳥の] | 【枕詞】大鳥の「羽交(はが)ひ」の意から、「羽易(はがひ)の山」にかかる。 | -逢ふよしをなみ 大鳥の 羽易の山に 我が恋ふる 妹はいますと-(万2-210) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほなむぢ [大汝] | 大汝少彦名のいましけむ志都の石屋は幾代経ぬらむ(万3-358) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻3-355 注『大汝』」】 大国主神の異名。記では「亦ノ謂大穴牟遅(おほあなむぢ)神」とあり、偉大な、金穴に坐す貴(むち)神とも、偉大な洞窟に坐す貴神とも、偉大な、汝(なむち)と呼びかけたのが名となったとも諸説がある。「大地持(おおなも)ち」とする説もあるが、これは「地(な)」の確証がないこと、またそう解釈しては「大国主」とイメージが重なり過ぎて、「亦の名」で結ばれる必然性がなくなるので支持できない。 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻三-355 頭注『大汝』」】 大国主命。記紀や風土記などに見える出雲神話の中心的神格。天孫降臨に際して国土を譲ったが、その奇魂(くしみたま)としての大物主神は三輪山に招請され、大神神社の祭神とされた。この神明は異文が多く、どれが原形か判定困難。「大己貴= (訓注、於褒婀娜武智/オホアナムチ)」(「神代紀」上)、「大穴持」(出雲国造神賀詞/イヅモノクニノミヤツコカムヨゴト) では「チ」が清音だが、「大穴牟遅」(古事記) によれば濁音。万葉集ではここを含めて「大汝」二例(播磨国風土記も)、「大穴道」一例、「於保奈牟知」一例。最後の仮名書きだが、後世の補修本文かとも思われる。「汝」がナムチかナムヂかにも問題があるが、一応ナムヂとし、個々の表記に沿った読み方をし、統一しないことにした。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほのなるみかさのもり [大野なる三笠の杜] |
【小学館「新編日本古典文学全集萬葉集 付録『地名一覧』」】 -大野なる三笠の杜- 福岡県大野城市山田。現在もその跡という小さな森があり、石造りの祠もある。「神功前紀」に皇后が羽白熊鷲(はじろくまわし)という翼のある賊を討とうとして、橿日宮から松峡宮に遷った時、旋風に御笠を吹き落されたので、そこを御笠という、と見える。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほはら [大原] | 〔地名〕 ① 京都市左京区大原。 八瀬 (やせ) の北の山あいの地で、寂光院・三千院・惟喬親王の御墓などがある。炭・薪の産地。ここから京都へ物売りに出る女を大原女 (おはらめ) という。古くは小原 (おはら)。 ② 奈良県高市郡明日香村小原。藤原鎌足の生地という。 |
② 我が里に大雪降れり大原の古りにし里に降らまくは後(万2-103) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほふ [被ふ・覆ふ] | 〔他動詞ハ行四段〕 ①(全体を隠すように)上からかぶせる。 ② 包み隠す。かぶせて見えなくする。 ③(威光・徳などを)広く行き渡らせる。 |
① 天の下すでに覆ひて降る雪の光りを見れば貴くもあるか(万17-3945) ② 玉櫛笥覆ふを安み明けていなば君が名はあれど吾が名し惜しも (万2-93) ② - 日の目も見せず 常闇に 覆ひ賜ひて 定めてし 瑞穂の国を-(万2-199) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほぶね [大船] | 〔名詞〕大型の船。 | 大船を漕ぎのまにまに岩に触れ覆らば覆れ妹によりては(万4-560) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほぶねの [大船の] | 【枕詞】[枕詞一覧] 大船が頼りになる意から「たのむ」、 船の進むさま、泊るところから「たゆたふ」「ゆた」「ゆくらゆくら」「渡り」「津」、 船の「かぢとり」の類似から「香取 (かとり)」にかかる。 |
大船の思ひ頼める君ゆゑに尽す心は惜しけくもなし(万13-3265) 大船の泊つる泊りのたゆたひに物思ひ痩せぬ人の子故に(万2-122) -か行きかく行き 大船の たゆたふ見れば 慰もる 心もあらず-(万2-196) -味寐は寝ずて 大船の ゆくらゆくらに 思ひつつ -(万13-3288) -かへり見すれど 大船の 渡の山の 黄葉の 散りの乱ひに-(万2-135) 大船の津守が占に告らむとはまさしに知りて我がふたり寝し(万2-109) 大船の香取の海にいかり下ろしいかなる人か物思はずあらむ(万11-2440) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おぼぼし | 〔形容詞シク活用〕《「おほほし」 とも》 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 ① ぼんやりしている。はっきりしない。 ② 心が晴れない。ゆううつである。 |
① ぬばたまの夜霧の立ちておほほしく照れる月夜の見れば悲しさ(万6-987) ② 夢にだに見ざりしものをおほほしく宮出もするかさ桧の隈廻を(万2-175) ② -玉桙の 道だに知らず おほほしく 待ちか恋ふらむ 愛しき妻らは(万2-220) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほまへつきみ [大臣] | 〔名詞〕天皇の前に伺候する者の長の意。⇒「大臣(だいじん)」 | ますらをの鞆の音すなり物部の大臣盾立つらしも(万1-76) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほみ― [大御―] | 〔接頭語〕 (名詞に付いて) 強い尊敬を表す。多く、神や天皇に関して用いる。 |
かからむとかねて知りせば大御船泊てし泊りに標結はましを (万2-151) -皇子ながら 任けたまへば 大御身に 大刀取り佩かし 大御手に-(万2-199) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -うま [大御馬] | 〔名詞〕天皇や皇族がお乗りになる馬。 | -夕狩に 鶉雉踏み立て 大御馬の 口抑へ止め 御心を-(万3-481) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほみかど [大御門] | 〔名詞〕[「おほみ」は接頭語] ① 皇居や貴人の家の門。ご門。② 宮殿。皇居。 | ② - 藤井が原に 大御門 始めたまひて 埴安の 堤の上に あり立たし-(万1-52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほみけ [大御食] | 〔名詞〕[「大御(おほみ)」は接頭語] 神や天皇の召し上がる食物。 | -行き沿ふ 川の神も 大御食に 仕へ奉ると 上つ瀬に 鵜川を立ち- (万1-38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほみや [大宮] | 〔名詞〕 ① 皇居・神宮の敬称。 ② 太皇太后・皇太后の敬称。中宮を「宮」というのに対して用いる。 ③ 母に当る宮(=内親王)の敬称。 |
① -天皇の 神の命の 大宮は ここと聞けども 大殿は ここと言へども- (万1-29) ① 大宮の内まで聞こゆ網引すと網子ととのふる海人の呼び声(万3-239) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほみやつかへ [大宮仕へ] | 大宮に仕える者、という名詞形 | 藤原の大宮仕へ生れつくや娘子がともは羨しきろかも(万1-53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほみやどころ [大宮処] | 〔名詞〕[古くは「おほみやところ」と清音] 皇居のある地。また、皇居。 | 三香の原布当の野辺を清みこそ大宮所 [一云 ここと標刺し] 定めけらしも (万6-1055) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほみやびと [大宮人] | 〔名詞〕[古くは「おほみやひと」と清音] 宮中に仕える人。 |
-鴨つま呼ばひ 辺つへに あぢ群騒き ももしきの 大宮人の 罷り出て-(万3-259) 三香の原久迩の都は荒れにけり大宮人のうつろひぬれば(万6-1064) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほやまと [大倭・大日本] | 〔名詞〕日本の美称。 | -皇子の尊 万代に 食したまはまし 大日本 久迩の都は-(万3-478) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほゆきの [大雪の] | 【比喩的枕詞】「乱れ」にかかる。 | -矢の繁けく 大雪の 乱れて来れ [一云 霰なす そちより来れば]-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おほわだ [大曲] | 〔名詞〕 湖や川などが陸地に大きく入り込んでいるところ。 |
楽浪の志賀の [一云 比良の] 大わだ淀むとも昔の人にまたも逢はめやも [一云 逢はむと思へや](万1-31) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おみ [臣] | 〔名詞〕 ① 家来。臣下。 ② 上代の姓(かばね)の一つ。その中心となる者は朝廷から大臣(おおおみ)の称を賜り、大連(おおむらじ)とともに後の大臣(だいじん)の地位にあった。 のちには、天武天皇の時に定められた「八色の姓」の第六位。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のをとこ [臣の壮士] | 臣下として天皇に仕える若い男子。 | もののふの臣の壮士は大君の任けのまにまに聞くといふものそ(万3-372) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おみな [嫗] | 〔名詞〕老女。おうな。⇔「翁 (おきな)」 【参考】のちに「おむな」となる。「をみな」 (女) とは別。 |
汝 (な) は誰 (たれ) しの嫗ぞ(記下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おみのき [臣の木] | 〔名詞〕樅の木の古名か。 | -み湯の上の 木群を見れば 臣の木も 生ひ継ぎにけり 鳴く鳥の-(万3-325) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おむな [嫗] | 〔名詞〕[「おみな」 の転] 老女。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもかげ [面影] | 〔名詞〕 ① 顔つき。姿。ようす。② 目先に浮かぶ人の顔かたち。幻影。まぼろし。 ③ (歌学用語) 余情として浮かんでくる情景・情趣。 ④ (連歌・俳諧用語) 「面影付け」の略。 |
陸奥の真野の草原遠けども面影にして見ゆといふものを(万3-399) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもちち [母父] | 〔名詞〕母と父。 | -継ぎ行くものと 母父に 妻に子どもに 語らひて 立ちにし日より-(万3-446) -こやせる君は 母父が 愛子にもあらむ 若草の 妻もあらむと-(万13-3353) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもなし [面無し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 恥知らずである。あつかましい。 【語感】 恥ずかしさも忘れたように、平気で振舞っており、そばで見ていられない感じ。 |
宵に逢ひて朝面無み名張にか日長き妹が廬りせりけむ(万1-60) [「面無み」⇒「面無し」の「ミ語法」] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもはゆ [思はゆ] | [四段動詞「思ふ」の未然形「おもは」+上代の受身・自発の助動詞「ゆ」] 思われる。自然とその思いになる。 |
かへらひ見つつ 誰が子ぞとや 思はえてある かくのごと(万16-3813) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもひ [思ひ] | 〔名詞〕 ① 思うこと。考え。思慮。② 願い。希望。③ いつくしみ。いとおしみ。 ④ もの思い。憂い。心配。⑤ 恨み。執念。⑥ 推察。想像。 ⑦ 喪に服すこと。喪中。 【参考】 和歌では恋い慕う気持ちの意の「おもひ」の「ひ」を、「火」に掛けていうことが多い。 |
③ 我が思ひを人に知るれや玉櫛笥開き明けつと夢にし見ゆる(万4-594) ⑦ 思ひに侍りける年の秋、山寺へまかりける道にて(古今哀傷詞書-842) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもふ [思ふ] | 〔他動詞ハ行四段〕 ① 考える。思案する。思い起こす。 ② 思い知る。思いわきまえる。③ 希望する。願う。 ④ 懐かしむ。しのぶ。追想する。⑤ 愛する。慕う。恋う。 ⑥ 心配する。悲しむ。⑦ 推量する。想像する。予想する。 |
③ 我が御門千代とことばに栄えむと思ひてありし我れし悲しも(万2-183) ③ -けだしくも 逢ふやと思ひて [一云 君も逢ふやと] -(万2-194) ④ -旗すすき 小竹を押しなべ 草枕 旅宿りせす いにしへ思ひて(万1-45) ④ 葦辺行く鴨の羽交ひに霜降りて寒き夕は大和し思ほ(は)ゆ(万1-64) ④ いにしへに恋ふらむ鳥は霍公鳥けだしや鳴きし我が念 (も) へるごと (万2-112) ⑤ 飫宇の海の潮干の潟の片思に思ひや行かむ道の長手を(万4-539) ⑥ あをによし奈良の家には万代に我れも通はむ忘ると思ふな(万1-80) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ゑに [思ふゑに] | 「思ふ故に(おもふゆゑに)」の音韻変化したもの。 恋い慕っているので。かわいいと思うから。 |
思ふゑに逢ふものならばしましくも妹が目離れて我れ居らめやも (万15-3753) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -こ [思ふ子] | かわいく思う子。まなご。恋人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -さま [思ふ様] | 〔名詞〕思うよう。考え方。 〔形容動詞〕思うまま。思うとおり。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -そら [思ふ空] | 〔名詞〕思う気持ち。 | -我れは立ちて 思ふそら 安けなくに 嘆くそら- (万13-3313) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -どち [思ふどち] | 〔名詞〕「思ひどち」とも。気の合った友達同士。 | 春日野の浅茅が上に思ふどち遊ぶ今日の日忘らえめやも (万10-1884) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ひ [思ふ日] | 〔名詞〕この世を去った人を思う日。命日。忌日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ひと [思ふ人] | 〔名詞〕 ① 恋人。深く思う相手。 ② 親しい人。仲のいい人。(恋人に限らず父母など)心に思う人。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもひいづ [思ひ出づ] | 〔他動詞ダ行下二段〕【デ・デ・ヅ・ヅル・ヅレ・デヨ】 思い出す。 |
佐保山にたなびく霞見るごとに妹を思ひ出で泣かぬ日はなし(万3-476) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもひすぐ [思ひ過ぐ] | 〔自動詞ガ行上二段〕【ギ・ギ・グ・グル・グレ・ギヨ】 思ひ慕う心が消える。忘れる。 |
明日香川川淀去らず立つ霧の思ひ過ぐべき恋にあらなくに(万3-328) 神なびの三諸の山に斎ふ杉思ひ過ぎめや苔生すまでに(万13-3242) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもひたのむ [思ひ頼む] | 〔他動詞マ行四段〕 頼みに思う。 |
-後も逢はむと 大船の 思ひ頼みて 玉かぎる 磐垣淵の-(万2-207) -万代に 絶えじと思ひて [一云 大船の 思ひたのみて] 通ひけむ-(万3-426) 大船の思ひ頼みし君が去なば我は恋ひむな直に逢ふまでに(万4-553) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもひやむ [思ひ止む] | 〔他動詞マ行四段〕思うことをやめる。思わなくなる。 | 人はよし思ひやむとも玉葛影に見えつつ忘らえぬかも(万2-149) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもひやる [思ひ遣る] | 〔他動詞ラ行四段〕 ① 遠くに思いをはせる。また、想像する。 ② 人の身の上・心情などに思いをめぐらす。気遣う。 ③ 憂いの気持ちなどを払う。気を晴らす。 |
思ひ遣るすべのたづきも今はなし君に逢はずて年の経ぬれば(万13-3275) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもほす [思ほす] | 〔他動詞サ行四段〕 [四段動詞「思ふ」の未然形「おもは」に上代の尊敬の助動詞「す」が付いた「おもはす」の転] 【参考】 主として上代に使われ、平安時代になっても使われたが、「おぼす」の方が圧倒的に多くなっていく。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「思ふ」の尊敬語。お思いになる。 | - いかさまに思ほしめせか [或云 思ほしけめか] 天離る- (万1-29) 秋山の木の下隠り行く水の我れこそ益さめ思ほすよりは(万2-92) 藤波の花は盛りになりにけり奈良の都を思ほすや君(万3-333) 【「いかさまに 思ほしめせか」】→「いかさま」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもほゆ [思ほゆ] | 〔自動詞ヤ行下二段〕【エ・エ・ユ・ユル・ユレ・エヨ】 〔構成〕 四段動詞「思ふ」の未然形に、上代の自発の助動詞「ゆ」のついた「思はゆ」の転。 |
葦辺行く鴨の羽交ひに霜降りて寒き夕は大和し思ほゆ(万1-64) けころもを時かたまけて出でましし宇陀の大野は思ほえむかも(万2-191) 黄葉の散りゆくなへに玉梓の使を見れば逢ひし日思ほゆ(万2-209) 近江の海夕波千鳥汝が鳴けば心もしのにいにしへ思ほゆ(万3-268) 瓜食めば 子ども思ほゆ 栗食めば まして偲はゆ(万5-806) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おや [親・祖] | 〔名詞〕 ① 父母または、養父母。古くは、特に母をいうことが多い。 |
① みさご居る磯廻に生ふるなのりその名は告らしてよ親は知るとも(万3-365) ① -花橘のかぐはしき親の御言朝夕に聞かぬ日まねく-(万19-4193) ② -玉葛 や遠長く祖の名も継ぎゆくものと母父に 妻に子どもに-(万3-446) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おゆ [老ゆ] | 〔自動詞ヤ行上二段〕【イ・イ・ユ・ユル・ユレ・イヨ】 ① 年をとる。② 弱る。衰える。また、季節などの盛りが過ぎる。 |
① 黒髪に白髪交り老ゆるまでかかる恋にはいまだあはなくに(万4-566) ① 年経れば齢はおいぬいかはあれど花をし見れば物思ひもなし(古今春上-52) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| およづれ [妖] | 〔名詞〕[「およづれごと」の略] | -玉梓の 人そ言ひつる 逆言か 我が聞きつる たはことか-(万3-423) -たはことか 人の言ひつる およづれか 人の告げつる-(万19-4238) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ごと [妖言] | 〔名詞〕人を迷わすことば。 | たはことかおよづれことかこもりくの泊瀬の山に廬りせりといふ(万7-1412) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| およぶ [及ぶ] | 〔自バ行四段〕 ① 届く。達する。至る。 ② 届くように前屈みになる。及び腰になる。 ③ 追いつく。 ④(多く打消しの表現を伴って)匹敵する。肩を並べる。 ⑤(「~におよぶ」の形で)ついに~になる。 ⑥(下に打消しの語を伴い、多く「^におよばず」の形で ア:~ができる。イ:~が必要である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おりゐる [下り居る] | 〔自動詞ワ行上一段〕【ゐ・ゐ・ゐる・ゐる・ゐれ・ゐよ】 ① 降りてそこにじっとしている。馬などから降りてすわる。腰をおろす。 ② (天皇や斎院などが) その地位を退く。退位する。 |
① 朝ぐもり日の入り行けばみ立たしの島に下り居て嘆きつるかも(万2-188) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おろす [下す] | 〔他動詞サ行四段〕 ① 低い方へ移す。② 下に垂れ下げる。③ 乗物から他の場所へ移す。 ④ 水に投げ入れる。沈ませる。⑤ 陸から水面に移す。⑥ 切り落とす。 ⑦ 剃髪する。頭を剃って出家する。⑧ 山など高い所から風が吹き下ろす。 ⑨ (「手をおろす」の形で) 事にあたる。処理する。 ⑩ (貴人の前から) 退出させる。⑪ 位をさげる。位を退かせる。 ⑫ 神仏の供物、貴人の飲食物の残りや使用後の品などをいただく。おさがりをいただく。 ⑬ 神霊をよりましに乗り移らせる。⑭ 悪く言う。けなす。ののしる。 ⑮ 新しい品を使い始める。取り出して使う。⑯ すりくだく。すりへらす。 ⑰ 堕胎する。⑱ 魚や鳥・獣などを調理する。切り分ける。 |
④ -大船に 真楫貫き下ろし いさなとり 海路に出でて あへきつつ-(万3-369) ④ 大船の香取の海にいかり下ろしいかなる人か物思はずあらむ(万11-2440) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| か | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| か [鹿] | 〔名詞〕鹿の古名。 【参考】 「ゐ(猪)」→「ゐのしし」と同様、「か(鹿)」についても、「かのしし」という呼び方がある。 |
秋さらば今も見るごと妻恋ひに鹿鳴かむ山ぞ高野原の上(万1-84) 妻恋ひに鹿鳴く山辺の秋萩は露霜寒み盛り過ぎゆく(万8-1604) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| か [可] | 〔名詞〕よいこと。善。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| か [香] | 〔名詞〕かおり。におい。 | 五月待つ花たちばなのかをかげば昔の人の袖のかぞする(古今夏-139) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| か [彼] | 〔代名詞〕遠称の指示代名詞。人や事物をさす語。あの。あれ。あちら。 【参考】 独立して用いた例は少なく格助詞「の」とともに用い、「かの」となるのが」ふつうである。 →「彼(か)の」。 |
思へども人目つつみの高ければかはとみながらえこそ渡らね(古今恋三-659) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| か | 〔副詞〕(多く「か・・かく・・」の形で) あのように。ああ。 | -波のむた か寄りかく寄り 玉藻なす 寄り寝し妹を-(万2-131) -玉藻なす か寄りかく寄り 靡かひし 嬬の命の たたなづく-(万2-194) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻二-131 注 「-か寄りかく寄り」】 旧訓「カヨリカクヨリ」であったのを、古義に「カヨリカクヨル」と訂した。以下の諸注も二説に分かれる。 「カクヨル」 と訓めば、次の玉藻の修飾語となり、「カクヨリ」 ならば「寄り寝し」 にかかることになる。 茂吉評釈・佐佐木評釈・全註釈など後説によっているが、最近の注釈書の多くは前説を採る(注釈・窪田評釈・私注・古典大系・古典全集・古典集成など)。 茂吉は「此句は下の妹の行為を表はさむための誘導表現である」 と言い、全註釈には「調子の上からは、カヨリカクヨリがすぐれている。」 と記すが、いずれも理由は明確でない。 それに対し前説(カクヨル)を採用するものは、「玉藻」に直接かかることを当然とし、「カクヨリ」では「より寝し」を修飾することになり、「作者が浪と共にねることになつて」不適当だと言う。 旧訓以来の伝統的な訓ではあるが、「カクヨリ」 は文脈上ふさわしくないであろう。 古義に「こをカヨリカクヨリと訓て、妹がよることとするはひがことなり。こは玉藻のよる事を云るなれば必かよりかくよるとよむべきことなり」 と評したのが正しい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| か- |
〔接頭語〕(主に形容詞、または動詞について) 語調を整え、または語意を強める。 「-青」、「-弱し」、「-寄る」。 |
-海辺を指して にきたづの 荒礒の上に か青なる 玉藻沖つ藻-(万2-131) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ーか |
〔接尾語〕 (物の状態・性質を表す語などについて) それが目に見える状態であることを示す形容詞の語幹をつくる。 「さや-」、「のど-」、「ゆた-」。 |
明日香川しがらみ渡し塞かませば流るる水ものどにかあらまし [一云 水の淀にかあらまし](万2-197) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (日) 日数を表す。「十-(とをか)」、「百-(ももか)」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (処) 場所の意を表す。「あり-(ありか)」、「すみ-(すみか)」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (荷) 天秤棒などでになう荷物を数える語。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (箇・個) (漢語の数詞について) ものを数えるのに用いる語。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| か [係助詞・終助詞・副助詞] | 〔係助詞〕 ① 文中に用いられる場合、文末を活用語の連体形で結ぶ、係助詞の形式。 ア:疑問の意を表す。「~か」「~だろうか」 イ:反語の意を表す。「・・であろうか、いや・・ではない)」 ② 文末に用いられる場合。 ア:疑問の意を表す。「~か」「~だろうか」 イ:(多く「かは」「かも」「ものか」の形になって)反語の意を表す。 「・・・(だろう)か、(いや、・・・ではない)」 ウ:(打消しの助動詞「ず」の連体形「ぬ」に付いて、 「ぬか」「ぬかも」の形で) 願望を表す。「~ないかなあ」 ③(推量の助動詞「む」の已然形「め」に付いて)多く詠嘆の終助詞「も」を伴って反語の意を表す。「~だろうか、いや~ではない」 ④ 上代では動詞の已然形に接続助詞「ば」を介さずに原因・理由を表す用法があり、それに直接「か」が付いた。 ⑤ 問いの意を表す。「~か」 〔接続〕 体言・活用語・副詞・接続助詞などが主語・目的語・連用修飾語などとなっているものに付く。 |
①「ア」大和には鳴きてか来らむ呼子鳥象の中山呼びぞ越ゆなる(万1-70) ①「ア」我が盛りまたをちめやもほとほとに奈良の都を見ずかなりなむ(万3-334) ①「ア」松浦川川の瀬早み紅の裳の裾濡れて鮎か釣るらむ(万5-865) ①「ア」まそ鏡照るべき月を白栲の雲か隠せる天つ霧かも(万7-1083) ①「イ」つれもなき佐田の岡辺に帰り居ば島の御階に誰れか住まはむ(万2-187) ①「イ」-生きとし生けるもの、いづれか歌をよまざりける-(古今・仮名序) ②「ア」たけばぬれたかねば長き妹が髪このころ見ぬに掻き入れつらむか [三方沙弥](万2-123) ②「ア」-なよ竹の とをよる子らは いかさまに 思ひ居れか-(万2-217) ②「ア」三笠山野辺行く道はこきだくも繁く荒れたるか久にあらなくに(万2-232) ②「ア」倉橋の山を高みか夜隠りに出で来る月の光乏しき(万3-293) ②「ウ」我が命も常にあらぬか昔見し象の小川を行きて見むため(万3-335) ②「ウ」二上の山に隠れる霍公鳥今も鳴かぬか君に聞かせむ(万18-4091) ④ 葦邊より満ち来る潮のいや増しに思へか君が忘れかねつる(万4-620) ④ 我妹子がいかに思へかぬばたまの一夜もおちず夢にし見ゆる(万15-3669) ⑤ 君が行き日長くなりぬ山尋ね迎へか行かむ待ちにか待たむ(万2-85) ⑤ -讃岐の国は 国からか 見れども飽かぬ 神からか ここだ貴き-(万2-220) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔終助詞〕 ① 詠嘆、感動を表わす。「・・だなあ」 ②「しか」「てしか」「ぬか」「ぬかも」の形で用いられ、詠嘆を含む願望を表わす。(・・たいしたものだなあ) ③ 呼びかけを表わす。(・・よ) ④ 疑問(不確かな事柄についての疑念を表明したり、聞き手に答えを求めたりする) 〔接続〕 体言、活用語の連体形に付く。 |
① 夢にだに見ざりしものをおほほしく宮出もするかさ桧の隈廻を(万2-175) ① 御笠山野辺行く道はこきだくも繁く荒れたるか久にあらなくに(万3-232) ① 苦しくも降り来る雨か三輪の崎狭野の渡りに家もあらなくに(万3-267) ① 静けくも岸には波は寄せけるかこれの屋通し聞きつつ居れば(万7-1241) ④ 何時の間も神さびけるか香具山の桙杉が本に苔生すまでに(万3-261) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔副詞〕[多く「か~かく~」 の形で] あのように。ああ。 |
波こそ来寄れ 波のむた か寄りかく寄り 玉藻なす 寄り寝し妹を(万2-131) -思ひしなえて 夕星の か行きかく行き 大船の たゆたふ見れば-(万2-196) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| が [主要助詞一覧] |
〔格助詞〕 ① [連体修飾語] ア:所有を表す。「~の」 イ:所属を表す。「~の」 ウ:類似を表す。「~のような」 エ:(下にくるはずの名詞を略した形で)「~のもの」 オ:体言・連体形の下に付き、 「ごとし」「「まにまに」「「からに」などに続ける。「~の」 ② [感動文の主語] 「が」+形容詞語幹(シク活用は終止形)+接尾語「さ」の形の感動文の主語を表す。 「~が」 ③ [主語] ア:体言を受けるもの。「~が」「~の」 イ:体言に準じて用いられている連体形をうけるもの。「~が」 ウ:「イ」と同じ形であるが、「が」の下の部分がさらに連体形で体言に準じて用いられているもの。下の部分に対して主語を表すが、訳すときには、いわゆる同格に解釈する。「~で」「~であって」 ④ [対象] 希望や能力や感情の対象を表す。「~が」 〔接続〕体言または活用語の連体形に付く。 |
① [ア] 家に来て我が屋を見れば玉床の外に向きけり妹が木枕(万2-216) ① [ア] 妹が名は千代に流れむ姫島の小松がうれに蘿生すまでに(万2-228) ① [ア] 高円の野辺の秋萩な散りそね君が形見に見つつ偲はむ(万2-233) ① [ア] 我が庵は都のたつみ鹿ぞ住む世をうぢ山と人はいふなり (古今雑下-983) ① [イ] なでしこが花取り持ちてうつらうつら見まくの欲しき君にもあるかも (万20-4473) ① [イ] 白波の浜松が枝の手向けぐさ幾代までにか年の経ぬらむ [一云 年は経にけむ] (万1-34) ① [オ] -槻の木の こちごちの枝の 春の葉の 繁きがごとく-(万2-210) ① [オ] あをによし奈良の都は咲く花のにほふがごとく今盛りなり (万3-331) ② 筑紫船いまだも来ねばあらかじめ荒ぶる君を見るが悲しさ(万4-559) ③ [ア] 大船の津守が占に告らむとはまさしに知りて我がふたり寝し (万2-109) ③ [ア] うつそみの人なる我れや明日よりは二上山を弟背と我が見む(万2-165) ③ [ア] -妹が名呼びて 袖そ振りつる [一云 名のみを聞きてありえねば]-(万2-207) ③ [ア] -羽易の山に 汝が恋ふる 妹はいますと 人の言へば -(万2-213) ③ [ア] -思ひ恋ふらむ 時ならず 過ぎにし子らが 朝露のごと- (万2-217) ③ [ア] 鴨山の岩根しまける我をかも知らにと妹が待ちつつあるらむ(万2-223) ④ -山高み 川とほしろし 春の日は 山し見が欲し 秋の夜は-(万3-327) ④ 忘れ草我が紐に付く香具山の古りにし里を忘れむがため(万3-337) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔接続助詞〕 ① [単純接続] 前後の事柄を単純につなぐ。「~が」 ② [逆接] 逆接の意を表す。「~けれど」「~が」「~のに」 〔接続〕活用語の連体形に付く。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かがみなす [鏡なす] | 【枕詞】 鏡のように見るの意から、「見る・み」 に、また「思ふ」 にかかる。 |
-もみち葉かざし 敷栲の 袖携さはり 鏡なす 見れども飽かず-(万2-196) 櫛笥に乗れる 鏡なす 御津の浜辺に さ丹つらふ 紐解き放けず-(万4-512) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かがみやま [鏡山] | 梓弓引き豊国の鏡山見ず久ならば恋しけむかも(万3-314) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻 『付録 地名一覧』」】 福岡県田川郡香春町鏡山にある小山。大宰府から豊前国府を経て北九州方面へ出る官道田河道に沿って聳え、人の目を引く。 山の西南に鏡山神社、河内王陵があり、前者については逸文『豊前国風土記』に、神功皇后が鏡を置いた、とする由縁を載せ、後者は宮内庁の陵墓参考地と指定され、高さ三~四メートルの盛土の円墳が残っている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かからむ [斯からむ] | 〔成立ち〕ラ変動詞「斯かり」の未然形「かから」+推量の助動詞「む」 こうなるだろう。 |
かからむとかねて知りせば大御船泊てし泊りに標結はましを(万2-151) かからむとかねて知りせば越の海の荒礒の波も見せましものを(万17-3981) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かかり [掛かり・懸かり] | 〔名詞〕 ① 女性の髪の肩に垂れ下がったようす。また、その下がり具合。 ② 蹴鞠(けまり)を行う場所。また、蹴鞠を行う場所の垣に植えた木。 四本かかりが普通で、艮(うしとら、北東)に桜、巽(たつみ、南東)に柳、 坤(ひつじさる、南西)に楓、乾(いぬい、北西)に松を植える。 ③ 寄りかかるところ。④ 風情。趣。⑤ 構え。結構。つくり方。 ⑥ 関係すること。また、その人。⑦ 経費。出費。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かかり [斯かり] | 〔自動詞ラ行変格〕【ラ・リ・リ・ル・レ・レ】 〔副詞「斯く」にラ変動詞「有り」の付いた「かくあり」の転〕 こうだ。こんなだ。かようである。 |
事もなく生き来しものを老いなみにかかる恋にも我はあへるかも(万4-562) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かがり [篝] | 〔名詞〕① かがり火をたく鉄製の籠。② 「篝火(かがりび)」の略。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かかりしかども [斯かりしかども] | 〔成立ち〕ラ変動詞「斯かり」の連用形「かかり」+過去の助動詞「き」の已然形「しか」+接続助詞「ども」 こうであったが。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かかりどころ [斯かり所・懸かり所] | 〔名詞〕 たよりとするところ。また、たよりとするもの。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かかりば [掛かり端・懸かり端] | 〔名詞〕 女性の、頬の両側から肩に垂れかかっている髪の先。また、そのようす。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かがりび [篝火] | 〔名詞〕 鉄製の籠にたく火。夜の警護や屋外照明、また漁の際に用いた。 おもに松材を燃やす。かがり。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かかる [皸る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ひびやあかぎれが切れる。 |
稲つけばかかる我が手を今夜もか殿の若子が取りて嘆かむ(万14-3478) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かかる [懸かる・掛かる] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 垂れ下がる。② 寄りかかる。もたれかかる。すがる。 ③ たよる。たよりどころとする。④ (目や心に) とまる。つく。 ⑤ 泊まる。停泊する。⑥ (雨、雪などが) 降りかかる。 ⑦ 関わる。関係する。⑧ かかわりあう。巻き添えにあう。連座する。 ⑨ 関心が向く。⑩ 通りかかる。さしかかる。 ⑪ (霊などが) のりうつる。つく。⑫ 襲いかかる。攻めて行く。 |
⑥ 山ふかみ春とも知らぬ松の戸に たえだえかかる雪の玉水(新古春上-3) ⑪ ―月の神、人にかかりて謂(かた)りてのたまはく(顕宗紀) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かかる [斯かる] | 〔ラ変動詞「斯かり」の連体形から〕このような。こういう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かかるに [斯かるに] | 〔接続詞〕こうしているうちに。こうしていると。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かかるほどに [斯かる程に] | 〔成立ち〕連体詞「斯かる」+名詞「程」+格助詞「に」 こうしているうちに。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かかるままに [斯かる儘に] | 〔成立ち〕連体詞「斯かる」+名詞「儘」+格助詞「に」 こんなふうであるのに従って。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かかれど [斯かれど] | 〔接続詞〕こうではあるけど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かかれば [斯かれば] | 〔接続詞〕このようであるから。だから。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かき- [掻き] | 〔接頭語〕[動詞に付いて] 語勢を強めたり語調を整えたりする。 一面に、手にとって、軽く、ちょっと、などの意を表す。 「-暗 (く) る」「-暮らす」「-曇る」「-結ぶ」 |
[語法] 音便で「かい」「かっ」ともなる。 「掻く」の原義のこめられている「掻き上ぐ」「掻き弾く」などの「掻き」は動詞の連用形で、接頭語としない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かき [垣・墻・牆] | 〔名詞〕家屋敷などの周囲に巡らす囲い。垣根。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かきいる [掻きいる] | たけばぬれたかねば長き妹が髪このころ見ぬに掻き入れつらむか [三方沙弥](万2-123) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻第二-123 掻入」頭注】 「掻き入れつらむか」-掻キ入ルは筋立 (櫛) のとがった方などを用いて後れ毛を詰め込み、髪型を整えることをいうか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かぎろひ [陽炎] | 〔名詞〕 ① 明け方日が出る頃に地平線上に赤みを帯びて見える。曙光。 ② →「かげろふ」春 |
東の野にかぎろひの立つ見えてかへり見すれば月傾きぬ(万1-48) いまさらに雪降らめやもかぎろひの燃ゆる春べとなりにしものを (万10-1839) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かぎろひの [陽炎の] | 【枕詞】 「かぎろひ」の「②」は、春立つことから「春」に、 またその様子から「心燃ゆ」にかかる。 |
-奈良の都は かぎろひの 春にしなれば 春日山 御笠の野辺に-(万6-1051) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かく [格] | 〔名詞〕 ① 法則・きまり。しきたり。② 位。身分。③ 流儀。手段。 ④ 品格。風格。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かく [駆く・駈く] | 〔自動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 ① 馬でかける。疾走する。② 馬で攻め入る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かく [欠く] | 〔他動詞カ行四段〕 ① こわす。損じる。② もらす。ぬかす。怠る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔自動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 ① 損なわれる。② 不足する。欠ける。 |
② 世の中は空しきものとあらむとそこの照る月は満ち欠けしける(万3-445) ②-阿後尼の原を 千年に 欠くることなく 万代に-(万13-3250) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かく [舁く] | 〔他動詞カ行四段〕肩に乗せて運ぶ。かつぐ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かく [掛く・懸く] | 〔他動詞カ行四段〕《上代語》かける。関係する。 | -かまどには 火気吹き立てず 甑には 蜘蛛の巣かきて-(万5-896) -いや遠長く 偲ひ行かむ 御名に懸かせる 明日香川-(万2-196) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 ① ぶらさげる。取り付ける。固定する。② 心にとめる。心を託す。 ③ 兼ねる。かけもつ。兼任する。④ はかりくらべる。⑤ だます。 ⑥ おおう。かぶせる。⑦ 口に出して言う。話しかける。 ⑧ 火をつける。放つ。⑨ 賭け事をする。賭けとして出す。 ⑩ 目標にする。目ざす。⑪ ある期間にわたる。 ⑫ (動詞の連用形の下について) 「こちらから~する・途中まで~する・~かける」 |
① 左夫流児が斎きし殿に鈴掛けぬ駅馬下れり里もとどろに(万18-4134) ① -木綿だすき かひなに掛けて 天なる ささらの小野の-(万3-423) ② 山越しの風を時じみ寝る夜おちず家にある妹を懸けて偲ひつ(万1-6) ② -天のごと 振り放け見つつ 玉たすき 懸けて偲はむ 恐くありとも-(万2-199) ② ちはやぶる賀茂の社のゆふだすき一日も君をかけぬ日はなし (古今恋一-487) ⑦ 栲領巾のかけまく欲しき妹の名をこの勢能山にかけばいかにあらむ [一に云ふ 替へばいかにあらむ](万3-288) ⑩ わたの原八十島かけてこぎいでぬと人にはつげよあまの釣舟 (古今羈旅-407) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かく [掻く] | 〔他動詞カ行四段〕 ① 引っ掻く。② (弦楽器を) 弾く。つまびく。③ 払いのける。おしやる。 ④ 切り取る。⑤ くしけずる。とかす。⑥ (食物を) 掻きこむ。 ⑦ (畑などを) 耕す。すきかえす。 |
① 暇なく人の眉根をいたづらに掻かしめつつも逢はぬ妹かも(万4-565) ① 眉根掻き鼻ひ紐解け待つらむかいつかも見むと思へる我れを (万11-2412) ③-知らしめす 神の命と 天雲の 八重かけ別きて-(万2-167) ⑤-裳には織り着て 髪だにも 掻きは梳らず 沓をだに-(万9-1811) ⑦ 金門田を荒垣ま斎み日が照れば雨を待とのす君をと待とも (万14-3583) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かく [斯く] | 〔副詞〕 このように。こんなに。こう。 |
-相争ひき 神代より かくにあるらし 古も しかにあれこそ-(万1-13) -しかしもあらむと [一云 かくしもあらむと] 木綿花の 栄ゆる時に-(万2-199) かく故に見じと言ふものを楽浪の旧き都を見せつつもとな(万3-308) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -し [斯くし] | 〔副詞「斯(かく)」+強めの副助詞「し」〕「かく」の強調。 このようにも。こんなふうに。 |
- 梓弓 靫取り負ひて 天地と いや遠長に 万代に かくしもがもと-(万3-481) 一日こそ人も待ち良き長き日をかくし待たえばありかつましじ(万4-487) あらかじめ人言繁しかくしあらばしゑや我が背子奥もいかにあらめ(万4-662) 世の中は恋繁しゑやかくしあらば梅の花にもならましものを [豊後守大伴大夫](万5-823) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かくさふ [隠さふ] | 《上代語》隠し続ける。繰り返し隠す。 〔成り立ち〕四段動詞「隠す」の未然形「かくさ」に、上代の反復・継続の助動詞「ふ」 。 |
三輪山をしかも隠すか雲だにも心あらなも隠さふべしや(万1-18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かくす [隠す] | 〔他動詞サ行四段〕 見えないようにする。 |
三輪山をしかも隠すか雲だにも心あらなも隠さふべしや(万1-18) 家離りいます我妹を留めかね山隠しつれ心どもなし(万3-474) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かくばかり [斯くばかり] | 〔副詞〕〔なりたち〕[副詞「斯く」+副助詞「ばかり」] これほどまでに。こんなにも。 |
かくばかり恋ひつつあらずは高山の磐根しまきて死なましものを(万2-86) -かくばかりすべなきものか世間の道(万5-896) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かぐやま [香具山] | 〔地名〕今の奈良県橿原市東部にある山。 |
香具山は 畝傍を愛しと 耳成と 相争ひき 神代より かくにあるらし 古も しかにあれこそ うつせみも 妻を争ふらしき(万1-13) 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集」頭注】 この三山歌は、歌詞の解釈によって三山の性別が異なり、おおむね、 A 香具山(女)が畝傍(男)を雄々しと思ってそれまで親しかった耳梨(男)ともめるに至った。 B 香具山(男)が畝傍(女)を愛々しと思って耳梨(男)と妻争いをした。 C 香具山(女)が畝傍(男)を雄々しと思って耳梨(女)と男を取り合った。 以上の三説があり、それぞれ一長一短がある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【歌枕】 高天原にあった山が地上に降ったものだといわれ、古来、神聖視された。「古事記」に「あめのかぐやま」とあるが、一般に「天(あま)の香具山」と呼ばれている。 耳成(みみなし)山・畝傍(うねび)山とともに大和三山といわれる。 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 『付録 地名一覧』天の香久山」】 香久山に同じ。大和三山の一つ。天から降り来たった山と言い伝えられ、天ノをつけることがあり、また「天降りつく天の香久山」(二五七)などともいう。 後世になると、アマノカグヤマと呼ばれるが、『古事記』中の歌謡に「阿米能迦具夜麻」とあるのによって、アメノカグヤマと読む。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かぐやまのみや [香具山の宮] | 〔名詞〕 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1巻二-199 頭注 香具山の宮」】 高市皇子の宮殿。藤原京左京三坊辺りかと言われる。 |
-我が大君の 万代と 思ほしめして 作らしし 香具山の宮 万代に- (万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かくらく [隠らく] | 隠れること。〔なりたち:四段動詞「隠る」 のク語法〕 | あかねさす日は照らせれどぬばたまの夜渡る月の隠らく惜しも(万2-169) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かくらふ [隠らふ] | 〔四段動詞「隠る」の未然形「かくら」+上代の反復・継続の助動詞「ふ」〕 [上代語] ずっと隠れている。また、見え隠れする。 |
-振り放け見れば 渡る日の 影も隠らひ 照る月の-(万3-320) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かくる [隠る] | 〔自ラ行四段動詞〕(上代語) ① 隠れる。② 「死ぬ」の語を避けていう語。亡くなる。隠れる。 |
① 名ぐはしき印南の海の沖つ波千重に隠りぬ大和島根は(万3-306) ② 大君は神にしませば天雲の五百重が下に隠りたまひぬ(万2-205) ② -燃ゆる荒野に 白たへの 天領巾隠り 鳥じもの 朝立ちいまして-(万2-210) ② 豊国の鏡の山の岩戸立て隠りにけらし待てど来まさず(万3-421) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔自ラ行下二段動詞〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 ① 隠れる。②「死ぬ」の語をさけていう語。 |
① 春の夜のやみはあやなし梅の花色こそ見えね香やは隠るゝ(古春上-41) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かくれ [隠れ] | 〔名詞〕① 隠れること。② 隠れたところ。物陰。③ 隠れ場所。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ぬ [隠れ沼] | 〔名詞〕草などに覆い隠された沼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ぬの [隠れ沼の] | 【枕詞】「下に通ひて」「底」に懸かる。 | 紅の色にはいでじ隠れ沼のしたに通ひて恋ひは死ぬとも(古恋三-661) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かげ [影・景] | 〔名詞〕 ①(日・月・灯などの)光。 ②(光に照らし出された物の)姿・形。 ③ 鏡や水などに映った姿・形。映像。 ④ 目の前にいない人の、想像される姿。おもかげ。 ⑤ 光の反対側に出る暗い像。影。影法師。 ⑥ 影法師のように、いつもつきまとって離れないもの。 ⑦ 影法師のように、形だけで中身のないもの。魂の抜け殻。 ⑧ 本物に似せたもの。模造品。 |
①-振り放け見れば渡る日の影も隠らひ照る月の光も見えず-(万3-320) ④ 人はよし思ひやむとも玉葛影に見えつつ忘らえぬかも(万23-149) ⑤ 橘の蔭踏む道の八衢に物をぞ思ふ妹に逢はずして [三方沙弥](万2-125) ⑥ よるべなみ身をこそ遠くへだてつれ心は君が影となりにき(古今恋三-619) ⑦ 恋すれば我が身は影となりにけりさりとて人に添うはぬものゆゑ (古今恋一-528) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考 古語の「影」】 光が射したことで、そこにあるように目に映ったものが、「影」の意味である。 その意味から「①」の「日の影」「御灯火(みあかし)の影」のような「光」の意味になり、「②」の「人の影」も月が光を投げ掛けた結果現れた姿である。 「③」以下の意味も実体をいうのではなく、実体から離れた所に現れる姿である。 現代語の「撮影」が姿を写すことであるとして、「姿」と捉えることがあるが、これも光の射すこと、実体とは離れた所に現れるということが意識の中にある。 「人影もなし」などの「影」も同じである。言葉を理解する時、しばしば、この語は他のどういう語が当てはまるかという見地から意味の考えられることがあり、それも便利な方法といえるが、どういう意味でこの語ができたかを考えることも大事である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かげとも [影面] | 〔名詞〕《上代語》[「かげつおも」の転。「かげ」は光の意。] 日の当る方。南側。⇔「背面(そとも)」 |
-名ぐはしき 吉野の山は かげともの 大御門ゆ 雲居にぞ-(万1-52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かけのよろしく [懸けの宜しく] | 〔万葉集全注〕 かかわらせるのにうってつけに、の意 | -ぬえこ鳥 うら泣け居れば 玉たすき 懸けのよろしく 遠つ神-(万1-5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かげろふ [陽炎] | 〔名詞〕(「かぎろひ」の転) 春の晴れた日に、地上から水蒸気などがゆらゆらと立ちのぼる現象。 転じて、はかなく消えやすいもののたとえ。〔春〕 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かこ [水手・水夫] | 〔名詞〕船頭。船乗り。= 船子(ふなこ) | -朝なぎに 水手の声呼び 夕なぎに 楫の音しつつ 波の上を-(万4-512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かこのしま [加古の島] | 稲日野も行き過ぎかてに思へれば心恋しき加古の島見ゆ [一云 水門見ゆ](万3-254) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集『付録地名一覧』」】 兵庫県加古川河口にあった三角州上の島か。 現在この付近に島はないが、『播磨国風土記』(印南郡)に見える海中の小島、南ビ都麻がそれあともいう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かさ [笠・傘] | 〔名詞〕 ① 雨や雪を防いだり、日光を遮ったりするために、頭にかぶるもの。 奈良時代以前は多く菅笠、平安時代以後は檜笠・塗り笠・綾藺(あやい)笠・ 市女(いちめ)笠・竹笠、江戸時代は編み笠。 ② 柄のついたさし傘。から傘。③ きのこの上部の平たい部分。 ④ 筆のさやなど、上において物をおおうもの。 |
③ 高松のこの峰も狭に笠立てて満ち盛りたる秋の香のよさ(万10-2237) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かざす [挿頭す] | 〔他動詞サ行四段〕 ① 草木の花や枝、造花などを髪や冠に装飾としてさす。 ② 飾り付ける。 |
① -へは 花折かざし 秋立てば もみち葉かざし 敷栲の-(万2-196) ① ももしきの大宮人は暇あれや梅をかざしてここに集へる(万10-1887) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かさぬい [笠縫] | 逆風が吹いて出航が出来ないときなど、風が静まるまで様子をうかがうこと。 | 四極山うち越え見れば笠縫の島漕ぎ隠る棚なし小舟(万3-274) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-272 注」】 笠縫-未詳。 前の「四極山」について、大阪説をとる者は、大阪市東成区深江・片江町、生野区片江町、東大阪市足代の一帯とし、一方の愛知説をとる者は、渥美湾中の島に求めている。 これについても〔考〕参照。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かさ(の)やま | 〔山名〕未詳。 | 雨降らば着むと思へる笠の山人にな着せそ濡れは漬つとも(万3-377) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻三-374 頭注『笠の山』」】 未詳。諸注の多くは奈良市東方の三笠山と解するが、桜井市笠の地の山かとする説もある。 【有斐閣「萬葉集全注巻三-374 注『笠の山』」】 未詳。ただし諸注多く奈良市の三笠山のこととする。前の赤人の歌(三七二、三七三) に「御笠の山」 を詠じ、その縁でここに「笠の山」 の歌が排列されたと見るべき公算が大きいとすると、通説の「三笠山」 とするのが認められよう。しかるに、石上乙麻呂の宅地が山辺郡石上(奈良県天理市石上) であるから、磯城郡上之郷村笠(奈良県桜井市笠) の笠山をさすとする説(代匠記精撰本・講義) があるが、これは笠を着た観音像を安置するところから出た名であるから取るべきではない(私注)。さて、「笠の山よ」 と呼び掛けたもの。以下「笠」 と「濡る」 が主題の題材になっているので、「雨降らば着むと思へる」 は「笠の山」 を導くための、単なる序詞ではないことが分かる。すなわち、「笠の山」 という山の名と形から「雨・笠・濡」 の題材における自分と他人と恋人との心理を主題としているのであるから、単なる序詞ではないのである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かざはや [風速・風早] | 〔名詞〕強い風の吹くこと。 | 風早の美穂の浦廻の白つつじ見れどもさぶしなき人思へば [或云 見れば悲しもなき人思ふに](万3-437) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かざまもり [風まもり] | 家思ふと心進むな風まもりよくしていませ荒しその道(万3-384) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-381 注 『風まつり』」】 原文「風候」 とある。類聚古集や流布本には「候」 の字が「侯」 と写され、旧訓マチテとなった。しかし、校本万葉集所引代匠記初稿本書入には「侯」 は「候」 の誤りかとし、カセマモリとした。まさに「候」 の字であって、紀州本以下の古写本のほとんどが「候」 字に写しており、また「風守(カゼマモリ)」(7・一三九〇) と動詞の例もあるように、今は体言として、塙本にカザマモリと訓むのがよく、航海の時、よく風向きを観察して、出発の頃合いを待つこと。マモリは「目守(まも)り」 が語源。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かし [橿] | 〔名詞〕「あかがし・あらかし」 など、ぶな科の常緑高木の総称。 | 莫囂円隣之大相七兄爪謁気我が背子がい立たせりけむ厳橿が本(万1-9)(青:難訓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かしこし [畏し・恐し・賢し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 人間業とは思えない霊力に対し、恐れ敬う感じを表す。 「①」が原義。転じて、中古以降、「②」の、並外れた学識・才能などのあるさまにいう。 ① [畏し。恐し。] ア:恐ろしい。こわい。 イ:恐れ多い。尊い。もったいない。 ② [賢し] ア:才知に富む。利口である。 イ:すぐれている。りっぱだ。 ウ:好都合だ。運がいい。 エ:(連用形を副詞的に用いて) 程度が甚だしく。非常に。挿 |
① -思ふまで 聞きの恐く [一云 諸人の 見惑ふまでに] -(万2-199) ①「ア」-辺を見れば 白波騒く いさなとり 海を恐み 行く船の-(万2-220) ①「ア」大海の波は畏ししかれども神を斎ひて舟出せばいかに(万7-1236) ①「イ」大君の 命畏み 柔びにし 家を置き こもりくの 泊瀬の川に-(万1-79) ①「イ」-い這ひ拝み 鶉なす い這ひもとほり 恐みと 仕へ奉りて-(万3-240) [「かしこみ」を「かしこし」の「ミ語法」とする説] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かしこむ [畏む] | 〔自動詞マ行四段〕 ① 恐れ憚る。恐れ多いと思う。 ② 慎んでうけたまわる。 |
① 大后の妬みをかしこみて、もとつ国に逃げ下りき(記下) ② 大君の 命畏み 柔びにし 家を置き こもりくの 泊瀬の川に-(万1-79) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かしはら [橿原] | 〔地名〕 今の奈良県橿原市。 記紀に神武天皇の皇居(=橿原の宮)のあったところと伝えられる。 |
玉たすき 畝傍の山の 橿原の ひじりの御代ゆ-(万1-29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のみや [橿原の宮橿] | 〔名詞〕 記紀に神武天皇即位の宮と伝えられるところ。 その跡地と伝えられた所に今の橿原神宮がある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かす [貸す・借す] | 〔サ行四段動詞〕貸す。 | 秋風の寒き朝明を佐農の岡越ゆらむ君に衣貸さましを(万3-364) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かすがの [春日野] | 〔地名〕《歌枕》 今の奈良市の、春日山の裾野の台地一帯。奈良公園付近。 |
ちはやぶる神の社しなかりせば春日の野辺に粟蒔かましを(万3-407) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かすがのさと [春日の里] | 〔地名〕奈良市街地の東南方百毫寺町付近に当たり、春日(三笠)山よりも南、能登川を隔てて高円山の西麓に位置する一帯の称。京北班田図(西大寺蔵)に上春日里、春日里が見えるが、万葉集の「春日里」は条里称呼と限定はできない。 平城京からは郊外になるので「里(さと)」。 |
春霞春日の里の植ゑ子水葱苗なりと言ひし枝はさしにけむ(万3-410) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かすがのやま [春日の山] | 〔地名〕 奈良市の東方、春日神社を中心とする一帯を「春日(かすが)」。 その丘陵地帯が「春日野(かすがの)」。 それを含んだ山並みを「春日山」と総称した。 春日・御蓋(みかさ)・若草などの山地一帯の総称。最高は花山の497m。 |
春日を 春日の山の 高座の 三笠の山に 朝去らず 雲居たなびき-(万375) 春日山朝立つ雲の居ぬ日なく見まくの欲しき君にもあるかも(万4-587) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かすみ [霞] | 〔名詞〕微細な水滴が空中に浮遊して、空や遠方などがはっきり見えない現象。 | 霞立つ天の川原に君待つとい行き帰るに裳の裾濡れぬ(万8-1532) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考「霧」と「霞」の違い】 霞と霧とは同じ現象であるが、平安時代ごろから春のものを霞、秋のものを霧と区別した。また、遠くにたなびくのを霞、近くに立ち籠めるのを霧と考えた。 上代では季節による区別はなく、「万葉集」<8-1532>に見える「霞立つ天の河原に・・・」は秋、陰暦七月の七夕の歌である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かすみたつ [霞立つ] | 【枕詞】「春日(かすが)」にかかる。 | -春草の 茂く生ひたる 霞立つ 春日の霧れる-(万1-29) 天降りつく 天の香具山 霞立つ 春に至れば 松風に 池波立ちて 桜花-(万3-259) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かぜ [風] | 〔名詞〕 ① 空気の流動。かぜ。 ② 風習。ならわし。伝統。 ③ 風邪。感冒。古くは腹の病気まで含んでいたと言う。 |
① -玉藻沖つ藻 朝羽振る 風こそ寄せめ 夕羽振る 波こそ来寄れ-(万2-131) ① 風をだに恋ふるはともし風をだに来むとし待たば何か嘆かむ(万4-491) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かた [方] | 〔名詞〕 ① 方向。方角。向き。② 場所。位置。地点。③ 方面。それに関する点。 ④ 手段。方法。⑤ ころ。時節。⑥ さま。ようす。おもむき。⑦ 組。仲間。 ⑧ くみすること。味方すること。⑨ 人に対する敬称。お方。 |
① はしけやし我家 (わぎへ) のかたよ雲居たちくも(記中) ① ここにありて筑紫やいづち白雲のたなびく山の方にしあるらし(万4-577) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かた [形・型] | 〔名詞〕 ① 物のかたち。形状。 ② 肖像画。物の形を描いた絵。③ 模様。 ④ (物事のあったことを示す) しるし。 ⑤ 占いをして出た形。 ⑥ しきたり。慣例。型式。⑦ 抵当。担保。 |
① ふきあげの浜のかた に菊植ゑたりけるを詠める (古今秋下詞書-272) ⑤ 生ふしもとこの本山のましばにも告らぬ妹が名かたに出でむかも (万14-3508) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かた [肩] | 〔名詞〕 ① かた。 ② 衣服の肩にあたる部分。 |
① - かかふのみ 肩にうち掛け 伏廬の- (万5-896) ② 今年行く新防人が麻衣肩のまよひは誰れか取り見む (万7-1269) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -やく [肩焼く] | 鹿の肩骨を火にあぶり、そのひびの入り方で吉凶を占う。 | 武蔵野に占部肩焼きまさでにも告らぬ君が名占に出にけり(万14・3391) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かた [潟] | 〔名詞〕 ① 遠浅の海岸で、潮の干満によって見え隠れするところ。ひがた。 ② 浦。入り江。 ③ 海岸に続いている湖沼。 |
① 飫宇の海の潮干の潟の片思に思ひや行かむ道の長手を(万4-539) ① 若の浦に潮満ち来れば潟をなみ葦辺をさして鶴鳴き渡る (万6-924) ② 松浦がた佐用姫の子が領巾振りし山の名のみや聞きつつ居らむ (万5-872) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かたこひ [片恋ひ] | 〔名詞〕片想い。⇔「諸 (もろ) 恋ひ」 | ますらをや片恋せむと嘆けども醜のますらをなほ恋ひにけり (万2-117) 旅に去にし君しも継ぎて夢に見ゆ我が片恋の繁ければかも (万17-3951) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (かたこひづま) [片恋ひづま] | 【澤瀉久孝 中央公論社「萬葉集全注巻二-196」 訓釋「かたこひづま」】 皇女が亡くなつて、ひとり思ひに堪へぬ夫の君であるから「片恋ひ夫」と云つたのである。一云によると「片恋ひしつつ」 といふ事になる。 万葉考にはそれを本文に改めた。一見その方が穏やかにも見えるが、「片恋ひしつつ」 は下の「かよはす君」 と同格の主語となつてゐるのだからそれはそれで認められる。 むしろ「片恋ひしつつ」 の方が原案であつて、それに推敲を加へて対句としたものと見るべきであらう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かたし [難し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① 容易でない。難しい。 ② 滅多にない。まれである。 |
① ふたり行けど行き過ぎがたき秋山をいかにか君がひとり越ゆらむ(万2-106) ① 一日には千重波しきに思へどもなぞその玉の手に巻き難き(万3-412) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔接尾ク型〕 (動詞の連用形に付いて)そうすることの困難な様を表す形容詞を作る。 |
ふたり行けど行き過ぎかたき秋山をいかにか君がひとり越ゆらむ (万2-106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かたて [片手] | 〔名詞〕 ① 片方の手。② (二人一組で) 一方の人。相手。③ 片手間。かたわら。かた |
① -斎瓮を 前に据ゑ置きて 片手には 木綿取り持ち 片手には-(万3-446) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かたぶく [傾く] | 〔自動詞カ行四段〕「かたむく」の古形。 ① かたむく。斜めになる。 ② (日や月が)西に沈もうとする。 ③ 終りに近くなる。滅びる。衰える。 ④ 首をかしげて考える。 |
② 東の野にかぎろひの立つ見えてかへり見すれば月傾きぬ(万1-48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・クル・クレ・ケヨ】 ① かたむける。横に倒す。 ② 衰えさせる。滅ぼす。 ③ 非難する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かたまく [片設く] | 〔自動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・クル・クレ・ケヨ】 時が移って、ある時期になる。時節がめぐってくる。 その時になるのを待ち受ける。 |
けころもを時かたまけて出でましし宇陀の大野は思ほえむかも(万2-191) 梅の花散り乱ひたる岡びには鴬鳴くも春かたまけて [大隅目榎氏鉢麻呂](万5-842) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かたみ [形見] | 〔名詞〕 ① 昔の思い出となるもの。 ② 死んだ人や別れた人などの思い出となるもの。 |
① 梅(むめ)が香を袖にうつしてとどめてば春は過ぐともかたみならまし (古今春上-46) ② ま草刈る荒野にはあれど黄葉の過ぎにし君の形見とぞ来し (万1-47) ② -我妹子が 形見に置ける みどり子の 乞ひ泣くごとに 取り与ふる-(万2-210) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かたもひ [片思ひ] | 〔名詞〕[「かたおもひ」の転] 男女の一方だけが相手を慕うこと。片思い。 |
飫宇の海の潮干の潟の片思に思ひや行かむ道の長手を(万4-539) つれもなくあるらむ人を片思に我れは思へばわびしくもあるか(万4-720) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かたより [片縒り・片撚り] | 〔名詞〕一方の糸だけによりをかけること。 | 片縒りに糸をぞ我が縒る我が背子が花橘を貫かむと思ひて (万10-1991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かたよる [片寄る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 中央・中心から一方に寄る。 ② 一方に力を貸して、味方する。 |
① 秋の田の穂向きの寄れる片寄りに君に寄りなな言痛くありとも (万2-114) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かたらく [語らく] | 〔なりたち〕[四段動詞「語る」のク語法。 語ることには。語るところでは。 |
-衣ひづちて 立ち留まり 我れに語らく なにしかも もとなとぶらふ-(万2-230) -道来る人の 伝て言に 我れに語らく はしきよし 君はこのころ-(万19-4238) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かたらふ [語らふ] | 〔上代語〕[四段動詞「語る」の未然形+上代の反復・継続の助動詞「ふ」] 繰り返し語る。語り続ける。 〔他動詞ハ行四段〕 ① あれこれ話す。話し続ける。② 話し合う。相談する。 ③ 親しく交わる。交際する。④ 男女が互いに言い交わす。夫婦の約束をする。 ⑤ (人を説得して) 仲間に引き入れる。⑥ かけあって頼む。説いて頼み込む。 |
〔上代語〕 -継ぎ行くものと 母父に 妻に子どもに 語らひて 立ちにし日より-(万3-446) 〔他動詞ハ行四段〕 ① -さきくさの 中にを寝むと 愛しく しが語らへば いつしかも-(万5-909) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かたりつぐ [語り継ぐ] | 〔他動詞ガ行四段〕つぎつぎと語り伝える。 | ますらをの弓末振り起し射つる矢を後見む人は語り継ぐがね(万3-367) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かたる [語る] | 〔他動詞ラ行四段〕 ① 話して聞かせる。言う。② (物語などを)節をつけて読む。 |
① -聞けば 音のみし泣かゆ 語れば 心そ痛き 天皇の 神の皇子の-(万2-230) ① 否と言へど語れ語れと詔らせこそ志斐いは奏せ強ひ語りと言ふ(万3-238) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かぢ [梶・楫] | 〔名詞〕 船を漕ぐ道具。櫓や櫂の総称。 |
-白波騒く いさなとり 海を恐み 行く船の 梶引き折りて-(万2-220) ゆらのとをわたるふなびとかぢをたえ 行方も知らぬ恋のみちかな (新古今恋一-1071) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かつ | 〔補助動詞タ行下二段〕【テ・テ・ツ・ツル・ツレ・テヨ】《上代語》 「~できる。~に耐える。」 |
皆人を寝よとの鐘は打つなれど君をし思へば寐ねかてぬかも(万4-610) 梓弓引かばまにまに寄らめども後の心を知りかてぬかも(万2-98) 直に逢はば逢ひかつましじ石川に雲立ち渡れ見つつ偲はむ(万2-225) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔語法〕 動詞の連用形の下に付いて、下に助動詞「ず」の連体形「ぬ」および古い形の連用形「に」、また「まじ」の古い形「ましじ」など打消の語を伴って「かてぬ」「かてに」「かつましじ」の形で用いられることが多い。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かつ [且つ] | 〔副詞〕 ① 一方では。片一方では。 ② (「かつ~かつ~」と用いられる場合) 一方では~し、他方では~する。 ③ すぐに。そばから。たちまち。 ④ わずかに。ちょっと。 ⑤ (「見る・知る・聞く」などの動詞の上に付いて) すでに。もう。 |
① 世の中し常かくのみとかつ知れど痛き心は忍びかねつも(万3-475) ③ -さ夜は明け この夜は明けぬ 入りてかつ寝む この戸開かせ(万13-3324) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かつ [且つ] | 〔接続詞〕[副詞「かつ」からの転] そのうえ。また。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かづく [潜く] | 〔自動詞カ行四段〕 水中にもぐる。水中にもぐって魚や貝などをとる。 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・クル・クレ・ケヨ】 水中にもぐらせる。 |
〔自動詞カ行四段〕 嶋の宮まがりの池の放ち鳥人目に恋ひて池に潜かず(万2-170) 人漕がずあらくもしるし潜きする鴛鴦とたかべと船の上に住む(万2-260) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かつしか [葛飾] | 〔地名〕[上代「かづしか」とも] 下総の国の郡名。今の東京都葛飾区、千葉県市川市あたりの江戸川流域。 真間(まま)の手児名(てこな)の伝説で知られる。〔歌枕〕 |
-廬屋立て 妻問ひしけむ 葛飾の 真間の手児名が 奥つきを-(万3-434) 勝鹿の真間の井見れば立ち平し水汲ましけむ手児名し思ほゆ(万9-1812) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かづら [葛・蔓] | 〔名詞〕つる草の総称。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かづら [鬘] | 〔名詞〕 ① 上代、つる草や草木の枝・花などを巻きつけて髪飾りとしたもの。 ② 別の髪の毛を束ねて自分の髪の毛に添えるもの。添え髪。かもじ。 ③ 能の仮面と一緒に用いるつけ髪。髪形・毛色・結い方で数種ある。 ④ 毛髪で種々の髷形をつくり、俳優が頭にかぶるもの。 |
① -あやめぐさ 花橘を 玉に貫き [一云 貫き交へ] 縵にせむと-(万3-426) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かつらきやま [葛城山] | 【有斐閣「萬葉集全注巻四-509」 注『葛城山』】 大和と南河内との境を成し、水越峠を間にして南北に連なる二つの山、北は今日いうところの葛城山(958m)、南は金剛山(1125m)、これらを合わせていう。難波の地から東南に当たり、この前に「家の辺り 我が立ち見れば」とあることから考えて、作者丹比笠麻呂の家は藤原京を中心とした奈良盆地南部の地に在ったと思われる。葛城は今日一般に「カツラギ」と呼ばれているが、古くは「迦豆良紀」(記・五八) であった。総釋巻第四の著者石井庄司氏は奈良県出身(生駒郡三郷町) である。氏の証言によれば、今も大和・河内の古老は「カヅラキ」とはっきり「ツ」を濁り、「キ」を清音に唱えているという。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かてに | 〔なりたち〕 上代の補助動詞「かつ」の未然形+打消の助動詞「ず」の上代の連用形「に」 「~できなくて」「~しかねて」「堪え切れないで」 |
稲日野も行き過ぎかてに思へれば心恋しき加古の島見ゆ [一云 水門見ゆ] (万3-254) 淡雪のたまればかてにくだけつつわが物思ひのしげきころかな (古今恋一-550) 我れはもや安見児得たり皆人の得かてにすといふ安見児得たり(万2-95) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| がてに [諸注参照] | [「かてに」の濁音化したもの] 「~しにくいように」「~しかねるように」「~できないで」 |
春されば我家の里の川門には鮎子さ走る君待ちがてに(万5-863) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| がてり | 〔接続助詞〕《上代語》[他の動作をも兼ねて行う意を表す] 「~(の) ついで(に)。~(し) ながら」 〔接続〕動詞の連用形に付く。 |
山辺の御井を見がてり神風の伊勢娘子どもあひ見つるかも(万1-81) 雨降らずとの曇る夜のぬるぬると恋ひつつ居りき君待ちがてり (万3-373) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かど [門] | 〔名詞〕 ① 門。また、門のあたり。門前。 ② 家。家柄。 |
① -夏草の 思ひ萎へて 偲ふらむ 妹が門見む 靡けこの山(万2-131) ① うち靡く春立ちぬらし我が門の柳の末に鴬鳴きつ(万10-1823) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かなし [愛し・悲し・哀し] | 〔形容詞シク活用〕 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 ① [愛し] ア:かわいい。いとおしい。 イ:身にしみて面白い。強く心が引かれる。素晴らしい。 ② [悲し・哀し] ア:かわいそうだ。心がいたむ。 イ:ひどい。口惜しい。しゃくだ。 |
① [ア] 筑波嶺に雪かも降らるいなをかも愛しき子ろが布乾さるかも (万14-3365) ① [イ] みちのくはいづくはあれどしほがまの浦こぐ舟の綱手かなしも (古今東歌-1088) ② [ア] 我が御門千代とことばに栄えむと思ひてありし我れし悲しも(万2-183) ② [ア] 行くさには二人我が見しこの崎をひとり過ぐれば心悲しも [一に云ふ 見もさかず来ぬ](万3-453) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【語義】 人事に対しては情愛が痛切で胸が詰まる感じ、自然に対しては深く心を打たれる感じを表す。 可愛がる意の動詞「かなしうす」(サ変)、「かなしくす」(サ変)、可愛いと思う、悲しく思う意の動詞「かなしがる」(ラ行四段)、「かなしぶ」(バ行上二段→四段)、「かなしむ」(マ行四段)は派生語。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かなふ [適ふ・叶ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 ① 適合する。ちょうどよい。条件に合う。 ② 思い通りになる。願いが成就する。 ③ (多く下に否定表現を伴って) ア・匹敵する。つりあう。 イ・できる。許可される。 〔他動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 望みどおりにさせる。 |
① 熟田津に船乗りせむと月待てば潮もかなひぬ今は漕ぎ出でな (万1-8) ① 世の中の遊びの道にかなへるは酔ひ泣きするにあるべくあるらし(万3-350) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻三-347 頭注『かなへるは』」】 原文は諸本共「冷者」とあり、このままで「スズシキハ」と読み、心が清く爽やかであるのは、などと解するのが一般的だが、「怜」の誤りとして「タノシキハ」などとする説もある。『拾穂抄』には「洽者」とあり、しばらくこれによる。『名義抄』に「洽、カナフ」とあり、古本『玉篇』にも「洽、合也」とある。 【有斐閣「萬葉集全注巻三-347 注『楽しきは』」】 原文「怜」は「玉の小琴」の説によった。流布本「冷者」とあり、「マシラハハ」とあるが、代匠記「オカシキハ」、万葉考「サブシクハ」、古義「洽者(アマネキハ)」、生田耕一『万葉集難語難訓攷』「冷者(スズシキハ)」、古典全集「スズシキハ」と訓み、『琱玉集』嗜酒篇、管輅(かんろ)の故事――彼が酒を飲むと「清冷」(弁舌さわやかな状態) になったという――に関連するかと述べる等の諸説がある。しかし、注釈に詳しく例を挙げるように、「遊ぶ内のたのしき庭に」(17・三九〇五)、「今日の日はたのしく遊べ」(18・四〇四七)、「楽しきをへは・・・遊ぶにあるべし」(19・四一七四) などの「遊び」と「楽し」が連続すること、また「スズシ」が精神的に用いられるのは平安朝以後の例しかないこと、さらに「酔ひ泣き」が「スズシ」ということは合点がゆかないので、玉の小琴の「怜者(タノシキハ)」(もっともタヌシキハとしているが) に従うことにする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かにもかくにも | ともかくも。いずれにしても。 | いなだきにきすめる玉は二つなしかにもかくにも君がまにまに(万3-415) 白髪生ふることは思はず変若水はかにもかくにも求めて行かむ(万4-631) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ーかぬ | 〔接尾ナ変下二型] 【ネ・ネ・ヌ・ヌル・ヌレ・ネヨ】 (動詞の連用形に付いて) 「~のが難しい」「~ことができない」の意の動詞を作る。 |
楽浪の志賀の辛崎幸くあれど大宮人の舟待ちかねつ (万1-30) 古りにし嫗にしてやかくばかり恋に沈まむ手童のごと [恋をだに忍びかねてむ手童のごと](万2-129) 真木柱太き心はありしかどこの我が心鎮めかねつも(万2-190) -夜床も荒るらむ [一云 荒れなむ] そこ故に 慰めかねて けだしくも-(万2-194) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【例語】 言ひかぬ・思ひかぬ・こしらへかぬ(=なだめることができない)・忍びかぬ・堪へかぬ(=がまんできない)・とどめかぬ・飛び立ちかぬ・慰めかぬ・待ちかぬ・見かぬ・忘れかぬ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かぬ [予ぬ] | 〔他動詞ナ行下二段〕【ネ・ネ・ヌ・ヌル・ヌレ・ネヨ】 ① 将来のことを心配する。 ② 予想する。 |
① 玉藻刈る沖へは漕がじ敷栲の枕のあたり忘れかねつも(万1-72) ① 真木柱太き心はありしかどこの我が心鎮めかねつも(万2-190) ① 伊香保ろの沿ひの榛原ねもころに奥をなかねそまさかしよかば (万14-3429) ② -八百万 千年を兼ねて 定めけむ 奈良の都は かぎろひの-(万6-1051) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| がね | 〔接続助詞〕 願望・禁止・命令・意志などの理由・目的を表す。 「~となるように」「~であろうから」 〔接続〕活用語の連体形につく。 |
ますらをの弓末振り起し射つる矢を後見む人は語り継ぐがね(万3-367) 佐保川の岸のつかさの柴な刈りそねありつつも春し来たらば立ち隠るがね (万4-532) 梅の花我れは散らさじあをによし奈良なる人も来つつ見るがね(万10-1910) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【語法】 上代に用いられたもの。禁止・命令・意志などの表現に続く和歌の第五句に用いられ、意味的に倒置と判断されるので接続助詞と分類される。 終助詞とする説、 「雪寒み咲きには咲かぬ梅の花よりこの頃はしかにもあるがね(=ママヨ、ココシバラクハソウシテイルガヨイ)」(万10-2333) などの場合、他にあつらえ望む意の終助詞とし、二種類の助詞を認める説もある。 【参考】 語源には諸説がある。「が」 によって指定し、「ね」 によって希望を表すという説、 「予(か)ねて」「予(か)ねる」 にさかのぼる「婿がね」「后(きさき)がね」 の「料(かね)」 の助詞化したものという説、 また、「が種(ね)」 の意だとする説などがある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かねて [予ねて] | 〔成立ち〕下二段動詞「予(か)ぬ」の連用形「かね」+接続助詞「て」 ① 〔副詞〕前もって。あらかじめ。前々から。 ②(日数などを表わす語の前や後に用いて)…以前に。 |
① かからむとかねて知りせば大御船泊てし泊りに標結はましを (万2-151) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かは [川・河] | 〔名詞〕集まった水が地表の細長いくぼみに沿って流れるもの。 | 飛ぶ鳥の 明日香の川の 上つ瀬に 石橋渡し [一云 石なみ] -(万2-194) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かはかぜ [川風] | 〔名詞〕 川を吹き渡る風。また、川から吹いてくる風。 |
川風の寒き長谷を嘆きつつ君があるくに似る人も逢へや(万3-428) 川風の涼しくもあるか打ちよする波とともにや秋は立つらむ(古今秋上-170) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かはぎし [川岸] | 〔名詞〕川の岸辺。川のほとり。 | 妹も我れも清みの川の川岸の妹が悔ゆべき心は持たじ(万3-440) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かはくま [川隈] | 〔名詞〕川の流れの折れ曲がっているところ。 | -泊瀬の川に 舟浮けて 我が行く川の 川隈の 八十隈おちず-(万1-79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かはせ [川瀬] | 〔名詞〕川の中の浅瀬。川の流れが速く、浅いところ。 | 楽浪の志賀津の児らが [一云 志賀の津の児が] 罷り道の川瀬の道を見ればさぶしも (万2-218) 山川の清き川瀬に遊べども奈良の都は忘れかねつも(万15-3640) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かはづ [蛙] | 〔名詞〕 ① かじかがえるの異称。 形の小さいかえるで、谷川の岩場にすみ、夏から秋にかけて澄んだ美しい声で鳴く。 ② かえるの異称。〔春〕 |
① -鶴は乱れ 夕霧に かはづは騒く 見るごとに 音のみし泣かゆ -(万3-327) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かはと [川門] | 〔名詞〕川幅の狭くなったところ。また、川の渡り場。 | 千鳥鳴く佐保の川門の瀬を広み打橋渡す汝が来と思へば(万4-531) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かはも [川藻] | 〔名詞〕淡水に産する藻の総称。 | -絶ゆれば生ふる 打橋に 生ひををれる 川藻もぞ 枯るれば生ゆる-(万2-196) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かはよど [川淀] | 〔名詞〕川の水の淀んでいるところ。 | 明日香川川淀去らず立つ霧の思ひ過ぐべき恋にあらなくに(万3-328) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かはら [河原・川原] | 〔名詞〕〔「かははら」の転〕 ① 川辺の水がなくて、砂や石の多い所。 ② 京都の賀茂川の河原。 近世では、特に歌舞伎芝居や夕涼みの行われた賀茂川の四条河原をさす。 |
飫宇の海の河原の千鳥汝が鳴けば我が佐保川の思ほゆらくに(万3-374) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かはらふ [変はらふ] | 〔四段動詞「変はる」の未然形+上代の反復・継続の助動詞「ふ」〕 変わってゆく。 |
-常なりし 笑まひ振舞 いや日異に 変らふ見れば 悲しきろかも(万3-481) - 朝の笑み 夕変らひ 吹く風の 見えぬがごとく 行く水の -(万19-4184) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かはる [変わる] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 前と変化する。変わる。 ② 年月などが改まる。 |
① 我が背子が宿のなでしこ日並べて雨は降れども色も変らず(万20-4466) ② み立たしの島をも家と棲む鳥も荒びな行きそ年かはるまで(万2-180) ② -いたもすべなみ あらたまの 月の変れば 為むすべの-(万13-3343) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かはる [代わる・替はる] | 代理する。交代する。 | 今替る新防人が船出する海原の上に波なさきそね(万20-4359) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かひ [貝] | 〔名詞〕 ① 貝または貝殻。上代は装身具としての玉の材料にし、のちには貝合わせ・貝覆いなどの遊びに用いた。 ② ほら貝。時報・号令などの合図に用いた。 |
今日今日と我が待つ君は石川の貝に [一云 谷に] 交じてありといはずやも (万2-224) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かひ(のくに) [甲斐(国)] | 〔国名〕 | なまよみの 甲斐の国 うち寄する 駿河の国と こちごちの 国のみ中ゆ-(万3-322) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻三-319 頭注『甲斐の国』」】 山梨県。一般に「峡」が語源と言われるが、峡は「山の可比」(三九二四) などとあり、ヒの仮名が合わない。この下に並立助詞の「ト」が省略されている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かひな [肱・腕] | 〔名詞〕 ① 肩からひじまでの部分。二のうで。 ② (のちに) 肩から手首までの部分。うで全体。 |
① -木綿だすき かひなに掛けて 天なる ささらの小野の-(万3-423) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かふ [交ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕[動詞の連用形の下に付いて] 互いに~しあう。入れ違いに~する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 交差させる。交わす。 |
敷栲の袖交へし君玉垂の越智野過ぎ行くまたも逢はめやも [一云 越智野に過ぎぬ](万2-195) -天地の 神言寄せて 敷栲の 衣手交へて 己妻と 頼める今夜-(万4-549) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かふ [換ふ・代ふ] | 〔他動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 交換する。引き換えにする。 |
栲領巾のかけまく欲しき妹の名をこの勢能山にかけばいかにあらむ [一に云ふ かへばいかにあらむ](万3-288) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かふ [飼ふ] | 〔他動詞ハ行四段〕 動物に飲食物を与える。また、動物を養う。飼育する。 |
鳥座立て飼ひし雁の子巣立ちなば真弓の岡に飛び帰り来ね(万2-182) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かふち [河内] | 〔名詞〕[「かはうち」の転] 川が曲折して流れているところ。特に谷あいの川の流域。 |
-山川の 清き河内と 御心を 吉野の国の 花散らふ-(万1-36) -たたなづく 青垣隠り 川なみの 清き河内ぞ 春へは-(万6-928) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かへす [反す・返す・帰す・覆す] | 〔他動詞サ行四段〕 ① 元の状態に戻す。② 持ち主に返す ③ 元の場所へ戻す。返してやる。 ④ 無理やり帰す。追い返す。 ⑤ 報復する。むくいる。 ⑥ 官職を辞める。辞任する。 |
③ -病あらせず 速けく かへしたまはね もとの国辺に-(万6-1025) ④ 風流士に我れはありけりやどかへさず帰しし我れぞ風流士にはある (万2-127) ④ 我妹子がやどの籬を見に行かばけだし門より帰してむかも(万4-780) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かへす [反す] | 〔他動詞サ行四段〕 ひるがえす。うらがえす |
采女の袖吹きかへす明日香風都を遠みいたづらに吹く(万1-51) いとせめて恋しき時はむばたまの 夜の衣を反してぞ着る(古今恋二-554) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かへらふ [反らふ・返らふ・覆らふ] | 〔自動詞ラ行四段「かへる〕の継続態。 | -朝夕に 返らひぬれば 大夫と 思へる我れも-(万1-5) 朝日照る佐田の岡辺に泣く鳥の夜哭きかへらふこの年ころを(万2-192) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かへりみる [顧みる] | 〔他動詞マ行上一段〕【ミ・ミ・ミル・ミル・ミレ・ミヨ】 [現代語では「①・②」の意で用いるが、「人を顧みる」の形の「④」に留意] ① 後を振り返って見る。② 自分を反省する。③ 心にかける。懸念する。 ④ 世話する。 |
① -八十隈おちず 万たび かへり見しつつ 玉桙の 道行き暮らし- (万1-79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かへる [反る・返る・覆る・帰る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① ア-裏返る・ひるがえる イ-ひっくり返る。くつがえる。 ② ア-もとの位置や状態に戻る。 ② イ-年が改まる。 ② ウ-色が褪せる。 |
① ア 天の川霧立ち上る織女の雲の衣のかへる袖かも(万10-2067) ① イ 大船を漕ぎの進みに岩に触れ覆らば覆れ妹によりては(万4-560) ② ア 見れど飽かぬ吉野の川の常滑の絶ゆることなくまたかへり見む(万1-37) ② ア 在り嶺よし対馬の渡り海中に幣取り向けて早帰り来ね(万1-62) ② ア 鳥座立て飼ひし雁の子巣立ちなば真弓の岡に飛び帰り来ね(万2-182) ② ウ 思ひおく人の心にしたはれて露分くる袖のかへりぬるかな (新古今羈旅-988) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かへる [孵る] | 卵が孵る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かへる | 〔補助動詞ラ行四段〕(動詞の連用形の下について) 動作・状態のはなはだしい意を表す。 「すっかり~する。ほとんど~するほどになる。」 |
思ふにし死にするものにあらませば千たびぞ我れは死にかへらまし (万4-606) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かへるさ [帰るさ] | 〔名詞〕[「さ」は接尾語] 帰るとき。帰りがけ。→来(く)さ・行くさ |
妹と来し敏馬の崎を帰るさにひとりし見れば涙ぐましも(万3-452) 帰るさに妹に見せむにわたつみの沖つ白玉拾ひて行かな(万15-3636) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かほどり [貌鳥・容鳥] | 〔名詞〕「かほとり」とも。 美しい鳥の意とも、また特に、かっこうともいわれる。 |
-雲居たなびき 容鳥の 間なくしば鳴く 雲居なす 心いさよひ-(万3-375) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かまめ [鷗] | 〔名詞〕《上代語》海鳥の名。かもめ。 | -海原は 鴎立ち立つ うまし国ぞ 蜻蛉島 大和の国は(万1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かみ [上] | 〔名詞〕 ① 位置の高いところ。上の方。② 川の上流。川上。 ③ 身分や官位が高位の人。また、政府・官庁などの敬称。また天皇の尊称。④ 年上の人。年長者。⑤ すでに書いている前の部分。⑥ 以前。昔。 ⑦ 和歌の上の句。また、各句の初めの文字。 ⑧ 月の上旬。<⇔「下(しも)> |
②-上つ瀬に 鵜川を立ち 下つ瀬に 小網さし渡す-(万1-38) ② 嶋の宮上の池なる放ち鳥荒びな行きそ君座さずとも(万2-172) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かみ [神] | 〔名詞〕 ① 人間を超えた能力を持つ存在。 「恐れかしこむべきもの」「神」⇒ 「かむながら」 ② 雷。 ③ 神話で、国土創造・支配したとされる神。 ④ 天皇の尊称。 |
① この沼の中に住める神、いとちはやぶる神なり(記中) ① 玉藻よし 讃岐の国は 国からか 見れども飽かぬ 神からか-(万2-220) ① 思はぬを思ふと言はば大野なる三笠の杜の神し知らさむ(万4-564) ③ 高天の原になれる神の名は天之御中主の神(記上) ④ -ひじりの御代ゆ [或云 宮ゆ] 生れましし 神のことごと-(万1-29) ④ -ひさかたの 天つ宮に 神ながら 神といませば そこをしも-(万2-204) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考「神仏習合の世界」】 「徒然草」第五十二段は、仁和寺の老法師が石清水八幡宮を訪ねたつもりで、末寺の極楽寺や末社の高良社を拝んで帰った話しである。 神社に末寺があるというのは、不自然な感じがするかもしれないが、明治の神仏分離令以前には、こうした現象がどこでも見られた。 仏教が日本に定着する際、土着の神道を取り込んでいったのである。それを神仏習合または神仏混交と呼んでいる。 【有斐閣「万葉集全注巻第一-29 神」注】 「神」は歴代の天皇を、神代の直系に属する現人神(あらひとかみ)としてとらえた語。この「現人神」思想は、壬申の乱を契機にして盛んになった。 人麻呂も、別に「大君は神にしませば」と詠っている。これは、人間は常住不変ではありえないという認識の反措定であって、近江荒都を素材に取り込んで人生の無常を述べる人麻呂の意識と深くかかわる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のみかど [神の御門] | ① 神の居られるところ。神殿。② 皇居。朝廷。 | -もののふと 言はるる人は 天皇の 神の御門に 外の重に 立ち候ひ-(万3-446) すめろぎの神の御門を畏みとさもらふ時に逢へる君かも(万11-2513) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かみ [髪] | 〔名詞〕髪の毛。毛髪。 | 嘆きつつますらをのこの恋ふれこそ我が結ふ髪の漬ちてぬれけれ (万2-118) 人皆は今は長しとたけと言へど君が見し髪乱れたりとも [娘子](万2-124) -蜷の腸 か黒き髪に いつの間か 霜の降りけむ 紅の-(万5-808) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かみがくる [神隠る] | 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 お亡くなりになる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かみかぜ [神風] | 〔名詞〕[「かむかぜ」の転] 神の威力によって起こるという激しい風。 | -渡会の 斎きの宮ゆ 神風に い吹き惑はし 天雲を 日の目も見せず-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かみかぜの [神風の] | 【枕詞】[「かみかぜ」は「かむかぜ」の転] 「伊勢」にかかる。 |
神風の伊勢の浜荻をりふせて旅寝やすらむあらき浜辺に (新古今羈旅-911) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かみさぶ [神さぶ] | 〔自動詞バ行上二段〕【ビ・ビ・ブ・ブル・ブレ・ビヨ】 [「さぶ」は接尾語、「かむさぶ」「かうさぶ」「かんさぶ」ともいう] ① 神々しい様子になる。おごそかになるさま。 ② 古めかしくなる。古びているようすになる。 ③ 年功を積んでいる。老練で円熟している。 |
① 難波津を漕ぎ出て見れば神さぶる生駒高嶺に雲ぞたなびく (万20-4404) ② 娘子らが玉櫛笥なる玉櫛の神さびけむも妹に逢はずあれば(万4-525) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かみつせ [上つ瀬] | 〔名詞〕川の上流にある水の浅いところ。《対義語:下つ瀬》 | 飛ぶ鳥の 明日香の川の 上つ瀬に 生ふる玉藻は 下つ瀬に -(万2-194) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かみのみおも [神の御面] | -天地 日月と共に 足り行かむ 神の御面と 継ぎ来る 那珂の港ゆ-(万2-220) 〔神の御顔〕と解釈される |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1巻二-220 頭注『神の御面』」】 『古事記・上』の国生み神話の中に、伊予之二名(いよのふたなの)島つまり四国は、身一つにして面(おも)四つあり、面ごとに名あり、と見え、そのうち讃岐は飯依比古(いいよりひこ)という、とある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かみのみこと [神の命] | ① 神の尊称。神様。②天皇の尊称。 ③ (「神の御言」の意で) 神のおつげ。 |
①-寄り合ひの極み 知らしめす 神の命と 天雲の-(万2-167) ② 高御倉 天の日継と すめろきの 神の命の 聞こしをす(万18-4113) ③ 天皇御琴を控かして建内宿禰の大臣沙庭にてかみのみことを請ひき (記中) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かみのやしろ [神の社] | 〔名詞〕 | ちはやぶる神の社しなかりせば春日の野辺に粟蒔かましを(万3-407) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-404 注『神の社』」】 今日の「神社」の概念とほぼ同じと考えられる。もちろん「神社」 と書いて「モリ」と訓む場合(2・二〇二) もあり、それは具体的には「森」であったり「神社」であったりするが、「神社」や「社」を「ヤシロ」 と訓めば、それは社殿を設けたお宮をいうのである。「ヤシロ」は「屋代」で、屋を設けた一区画をいうから、社殿があるのである。その意味で武田裕吉が「建造物の意よりも、神のまします土地の意に多く使用」(「やしろ考」神道学昭和三十年五月) と述べているのにはそのまま同意できない。春日神社は社地の研究(福山敏男『日本建築史の研究』) からすると、社殿があったと考えてよいと私には思われる。赤麻呂の妻を譬ている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かみをか [神岳] | 〔地名〕 | -明け来れば 問ひたまふらし 神岳の 山の黄葉を 今日もかも-(万2-159) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【「小学館・新編日本古典文学全集萬葉集巻二-159頭注より】 明日香の神奈備の地。 → 94 (みもろの山)。甘橿丘の北の雷丘か。橘寺の南にある通称ふぐり山という小丘に接する説その他もあって確定的でない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かむ [神] | 〔名詞〕《「かみ(神) の古形》他の動詞について複合語を形成する。 「かむあがる」「かむさぶる」 など。 |
-八百万 千万神の 神集ひ 集ひいまして 神分り 分りし時に -(万2-167) -置かしたまひて 神ながら 神さびいます 奇し御魂-(万5-817) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かむ [醸む] | 〔他動詞マ行四段〕《上代語》(古くは米を噛んで酒を造ったことから) 酒を醸造する。 |
君がため醸みし待酒安の野にひとりや飲まむ友なしにして(万4-558) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かむかぜの [神風の] | 【枕詞】[「かみかぜの」の古形] ⇒「かみかぜの」 | 山辺の御井を見がてり神風の伊勢娘子どもあひ見つるかも(万1-81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かむから [神柄] | 〔名詞〕神の性格・性質。神格。 | - 秋津の宮は 神からか 貴くあるらむ 国からか 見が欲しからむ- (万6-912) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かむき [神木] | 〔名詞〕神の宿る神聖な木。手が触れると罰が当たるとされた。しんぼく。 | 神木にも手は触るといふをうつたへに人妻といへば触れぬものかも(万4-520) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かむさび [神さび] | 〔名詞〕神らしい振る舞い。神々しく振舞うこと。 | -こもりくの 泊瀬の山に 神さびに 斎きいますと 玉梓の-(万3-423) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かむさぶ [神さぶ] | 〔自動詞バ行上二段〕【ビ・ビ・ブ・ブル・ブレ・ビヨ】 神がとどまる。鎮座する。⇒「かみさぶ」、⇒接尾語「さぶ」 |
-神ながら 神さびせすと 吉野川 たぎつ河内に-(万1-38) 聞きしごとまこと尊くくすしくも神さびをるかこれの水島(万3-246) 何時の間も神さびけるか香具山の桙杉が本に苔生すまでに(万3-261) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かむすぎ [神杉] | 〔名詞〕(「かみすぎ」とも)神が天から降りる神聖な杉 | みもろの神の神杉已具耳矣自得見監乍共寝ねぬ夜ぞ多き(万2-156) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かむながら [神随・随神・惟神] | 〔副詞〕[「かんながら」とも] ① 神でおありになるままに。神の本性のままに。 ② 神のみ心のままに。神の意志のままに。 |
①-食す国は 栄えむものと 神ながら 思ほしめして-(万18-4118) ② 葦原の 瑞穂の国は 神ながら 言挙げせぬ国 しかれども- (万13-3267) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かむなびやま [神奈備山] | 〔名詞〕 | みもろの 神名備山に 五百枝さし しじに生ひたる つがの木の-(万3-327) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神の鎮座する山の称。特に、、今の奈良県明日香村にある三諸(みもろやま)、および奈良県斑鳩町にある三室山(みむろやま)の異称。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かむはぶる [神葬る] | 〔他動詞ラ行四段〕神として葬る。 | -いまだ尽きねば 言さへく 百済の原ゆ 神葬り 葬りいまして-(万2-199) -磐余を見つつ 神葬り 葬りまつれば 行く道の たづきを知らに-(万13-3338) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かむみや [神宮] | 〔名詞〕神まつられている宮殿。 | -神宮に 装ひまつりて 使はしし 御門の人も 白栲の 麻衣着て-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かむよ(かみよ) [神代] | 〔名詞〕「かむ(神)」は「かみ」の古形。 神々が国を治めたという神話時代。 記紀神話の天地開闢から神武天皇治世の前までをいう。 |
大君の遠の朝廷とあり通ふ島門を見ればかみよし思ほゆ(万3-307) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かめ [亀] | 〔名詞〕 ① 爬虫類の動物。かめ。[亀鳴く(春)、亀の子(夏)] ② 亀の甲。甲を焼いて生じたひび割れで吉凶を占った。 |
②-占部据ゑ 亀もな焼きそ 恋ひしくに 痛き我が身ぞ -(万16-3833) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かも [鴨] | 〔名詞〕 水鳥の一種。かも。 雁が秋の訪れにかかわりをもつのに対し、鴨は冬のものとされる。 [冬] |
葦辺行く鴨の羽交ひに霜降りて寒き夕は大和し思ほゆ(万1-64) -桜花 木の暗茂に 沖辺には 鴨つま呼ばひ 辺つへに あぢ群騒-(万3-259) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かも | 〔終助詞〕[終助詞「か」に終助詞「も」がついたもの] ① 詠嘆・感動の意。「~であることよ」 ② 完了の助動詞「ぬ」に付いて「ぬかも」」の形で希望の意。 「~して欲しいなぁ、~してくれないかなぁ」 |
① -この山の いや高知らす 水激る 瀧の宮処は 見れど飽かぬかも (万1-36) ① 山辺の御井を見がてり神風の伊勢娘子どもあひ見つるかも(万1-81) ① み立たしの島の荒礒を今見れば生ひざりし草生ひにけるかも(万2-181) ① 朝ぐもり日の入り行けばみ立たしの島に下り居て嘆きつるかも(万2-188) ① けころもを時かたまけて出でましし宇陀の大野は思ほえむかも(万2-191) ① ひさかたの天知らしぬる君故に日月も知らず恋ひわたるかも(万2-200) ① 隼人の薩摩の瀬戸を雲居なす遠くも我は今日見つるかも(万3-249) ① 浅茅原つばらつばらに物思へば古りにし里し思ほゆるかも(万3-336) ① 人ごとに折りかざしつつ遊べどもいやめづらしき梅の花かも (万5-832) ② 春日なる御笠の山に月も出でぬかも佐紀山に咲ける桜の花の見ゆべく (万10-1891) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かも | 〔終助詞〕[係助詞「か」に終助詞「も」の付いたもの] ① 疑いの意を表わす。「~か、~だろうか」 ② 反語の意を表わす。「~だろうか、いや~ではない」 |
① み薦刈る信濃の真弓我が引かば貴人さびていなと言はむかも [禅師] (万2-96) ① 暁の家恋しきに浦廻より楫の音するは海人娘子かも(万15-3663) ② 水伝ふ礒の浦廻の岩つつじ茂く咲く道をまたも見むかも(万2-185) ② -つむじかも い巻き渡ると 思ふまで 聞きの畏く-(万2-199) ② うらぶれて離れにし袖をまたまかば過ぎにし恋い乱れ来むかも (万12-2939) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かも | 〔係助詞〕[係助詞「か」に終助詞「も」の付いたもの] 疑いの意を表わす。「~だろうか」 |
飛ぶ鳥の明日香の里を置きて去なば君があたりは見えずかもあらむ [一云 君があたりを見ずてかもあらむ](万1-78) 橘の嶋の宮には飽かねかも佐田の岡辺に侍宿しに行く(万2-179) 今日もかも明日香の川の夕去らずかはづ鳴く瀬のさやけくあるらむ [或本の歌發句に云はく 明日香川今もかもとな](万3-359) 妹が家に雪かも降ると見るまでにここだもまがふ梅の花かも(万5-848) 妹も我れも一つなれかも三河なる二見の道ゆ別れかねつる(万3-278) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔接続〕体言または活用語の連体形につく。ただし係助詞は已然形につく場合もある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔語法〕 上代、特に「万葉集」に用いられ、中古以降は擬古的なもの、たとえば万葉調の歌などに見られる。 推量の助動詞「む」の已然形「め」について反語表現を表すのは、「やも」 と同じく上代の用法である。 「係助詞」の用法は「か」と同じく係り結びの法則に従って、結びは連体形となる。また上代の用法に、活用語の已然形に直接ついて疑いを表わすものがある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かもかくも | どのようにも。とにもかくにも。=かもかも。 | 妹が家に咲きたる花の梅の花実にし成りなばかもかくもせむ(万3-402) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かもかも | =かもかくも。 | 言痛くはかもかもせむを岩代の野辺の下草我れし刈りてば [一云 紅の現し心や妹に逢はずあらむ](万7-1347) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かもじもの [鴨じもの] | 〔副詞〕[「じもの」は、「~のようなもの」の意の接尾語] 鴨のように。 |
騒く御民も 家忘れ 身もたな知らず 鴨じもの 水に浮き居て(万1-50) 鴨じもの浮寝をすれば蜷の腸か黒き髪に露ぞ置きにける(万15-3671) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻第一-50 鴨じもの」頭注】 「水に浮く」の枕詞。ジモノは、「~でもないのに、~であるかのように」の意。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かもやま [鴨山] | 〔地名〕柿本人麻呂が石見国(島根県)で死をむかえた際の歌から、今の島根県の地名かと言われるが、未詳。 |
鴨山の岩根しまける我をかも知らにと妹が待ちつつあるらむ(万2-223) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻二-223」 注『鴨山』】 鴨山の所在地については諸説がある。 (1) 国府または国府に近い山とする説。 (2) 高津鴨嶋説。 (3) 浜田城山説。 (4) 那賀郡神村説。 (5) 那賀郡二宮村恵良説。 (6) 斎藤茂吉『柿本人麿雑纂篇』の説。 これに対し、神田秀夫『人麻呂歌集と人麻呂伝』、土屋文明私注には、 (7) 大和の葛城連山中の鴨山とする説を提示している。 あとの依羅娘子作歌中の「石川」などと合わせて考えると(7)説の可能性があり、人麻呂が石見国で没したというのは、没後の伝承の公算が大きい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かや [茅・葺] | 〔名詞〕すすき・ちがや・すげなど、屋根を葺くのに用いる草の総称。 |
我が背子は仮廬作らす草なくは小松が下の草を刈らさね(万1-11) 大名児を彼方野辺に刈る草の束の間も我れ忘れめや(万2-110) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「草」を「かや」と訓む例 【有斐閣「万葉集全注巻第二-110 かるかやの」注】(文中、旧歌番号) -なお「草」を「カヤ」と訓むことは、「可流加夜能 (カルカヤノ)」(14・3499) という仮名書き例や、巻三の「真野乃草原」(3・396) を古今六帖などに「カヤハラ」と伝えている例などによって確かめられる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -はら [茅原・萱原] | 〔名詞〕茅の茂った野原。 「真野の草原(かやはら)」参照。 | 陸奥の真野の草原遠けども面影にして見ゆといふものを(万3-399) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かや | 〔終助詞〕 ① [詠嘆の終助詞「か」に間投助詞「や」の付いたもの] 詠嘆・感動の意を表す。~だなあ。]かも ② [疑問の係助詞「か」に間投助詞「や」の付いたもの] ア:疑問・不定の意を表す。~であるか。 イ:反語・反問の意を表す。~(である)か(いや、とんでもない)。 ~(である)かい。 [接続] 体言または活用語の連体形に付く。 |
① うれたきかや(紀神武) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 「①」と「②」とは成り立ちを異にしており、「①」から「②」の用法が生じたものではない。「①」は特に上代、「②」は中世以降の用法となる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かよふ [通ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 ① 人が行き来する。往来する。通う。② 鳥・雲・風などが通る。 ③ 男が女のもとへ行き夫婦生活をする。結婚する。 ④ 物事に通じる。⑤ 手紙などが行き来する。 ⑥ (気持ちや言葉などが) 通じる。⑦ 流れなどが続く。 ⑧ 互いによく似る。共通する。⑨ 交差する。入り交じる。 |
① -寒き夜を 息むことなく 通ひつつ 作れる家に 千代までに-(万1-79) ① -朝鳥の 一に云ふ [朝霧の] 通はす君が 夏草の 思ひしなえて-(万2-196) ② 風かよふ寝ざめの袖の花の香にかをるまくらの春の夜の夢 (新古今春下-112) ③ 春日野の山辺の道をおそりなく通ひし君が見えぬころかも(万4-521) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ーから [-柄] | 〔名詞〕(接尾語) [連濁で「がら」とも] (名詞に付いて) その物に備わっている本来の品格・性質・身分・状態などの意を表す。 |
玉藻よし 讃岐の国は 国からか 見れども飽かぬ 神からか ここだ貴き-(万2-220) -吉野の宮は 山からし 貴くあらし 川からし さやけくあらし 天地と-(万3-318) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かよりあふ [か寄り合ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕《上代語》[「か」は接頭語] 寄り合う。互いに近づく。 (一説に、「か」は「斯・此」で、このようにの意とも) |
秋の田の穂田の刈りばかか寄りあはばそこもか人の我を言なさむ(万4-515) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| から [故・柄] | 〔名詞〕[語源的には「族(やから)・同胞(はらから)」などの「から」と同じで、血のつながりを意味した語かという] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原因・理由を示す語。ゆえ。ため。 | 我が母の袖もち撫でて我がからに泣きし心を忘らえのかも(万20-4380) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| からあゐ [韓藍] | 〔名詞〕① 鶏頭(=けいとう、植物の名)の異名。② 美しい藍色。 | ① 我がやどに韓藍蒔き生ほし枯れぬとも懲りずてまたも蒔かむとそ思ふ(万3-387) ① 秋さらば移しもせむと我が蒔きし韓藍の花を誰れか摘みけむ(万7-1366) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| からさき [唐崎・辛崎] | 〔地名〕[歌枕] 今の滋賀県大津市下阪本町。琵琶湖の西岸にあり、「唐崎の夜雨」は近江八景の一つ。一つ松・唐崎神社で有名。→「志賀」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| からに | 〔接続助詞〕格助詞「から」に格助詞「に」の付いたもの。 ① 軽い原因が重い結果を生じる意を表す。~だけで。ただ~だけで。 ② 二つの動作・状態が続いて生じる意を表す。~と同時に。~とすぐ。 ~やいなや。 ③ (おもに「むからに」の形で、逆接の仮定条件を表し) たとえ~だとしても。 ~だからといって。~たところで。 |
① ただ一夜隔てしからにあらたまの月か経ぬると心惑ひぬ(万4-641) ② すみのえの松を秋風吹くからに声うちそふる沖つ白波(古今7賀-360) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【接続】活用語の連体形に付く。 【参考】 「から」は本来名詞だったと考えられており、上代では「手に取るがからに(=手に取るだけで) 忘ると海人言ひし恋忘れ貝、言にしありけり」(万7-1216) の例のように、格助詞「が」「の」に続く、体言としての働きを残した例もある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| からびと [唐人・韓人] | 〔名詞〕中国や朝鮮半島の人。 | 韓人の衣染むといふ紫の心に染みて思ほゆるかも(万4-572) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かり [仮] | 〔名詞・形容動詞ナリ活用〕一時的。間に合わせ。かりそめ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かりいほ [仮庵・仮廬] | 〔名詞〕 仮に作ったいおり。仮に泊る小屋。かりほ。 |
秋の野のみ草刈り葺き宿れりし宇治の宮処の仮廬し思ほゆ(万1-7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かりこもの [刈り薦の・刈り菰] | 【枕詞】 刈り菰は乱れやすいことから、「乱(みだ)る」にかかる。 |
飼飯の海の庭良くあらし刈り薦の乱れて出づ見ゆ海人の釣船(万3-257) 都辺に行かむ船もが刈り薦の乱れて思ふ言告げやらむ(万15-3662) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かりぢのをの [猟路の小野] | 【有斐閣「萬葉集全注巻三-239 注『猟路の小野』」】 諸説があるが、鳴上善治は狩猟に関係のある小字名を調査し、奈良県宇陀郡榛原町上萩原(玉立、小鹿野、西峠)地域を主に、長峰、山辺三、戒場地域、下萩原地域、下井足地域、篠楽、雨師地域にかけての原野、丘陵であった(「『猟路の池』榛原の説」万葉昭和四十九年九月)と説く。これによる。 「小野」の「小」は愛称の接頭語で、鹿や猪のよくとれる野を言い、必ずしも小さいわけではない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かりのこ [雁の子] | 〔名詞〕① がんやかもなどの卵。② がんやかもなどの水鳥。 | ② 鳥座立て飼ひし雁の子巣立ちなば真弓の岡に飛び帰り来ね(万2-182) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かりばか [刈りばか] | 〔名詞〕 刈り取る土地の範囲、また刈り取る仕事の量。 |
秋の田の穂田の刈りばかか寄りあはばそこもか人の我を言なさむ(万4-515) 天にあるやささらの小野に茅草刈り草刈りばかに鶉を立つも(万16-3909) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かりみや [仮宮] | 〔名詞〕かりに設けた宮。行宮。 | -高麗剣 和射見が原の 仮宮に 天降りいまして 天の下-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かる [軽] | 〔地名〕 今の奈良県橿原市の地名。 付近の山野は、軽大野(かるのおおの)と呼ばれた狩猟場。 |
天飛ぶや 軽の道は 我妹子が 里にしあれば ねもころに 見まく欲しけど-(万2-207) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かる [枯る・乾る・涸る・嗄る] | 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 ① [枯る・乾る・涸る] ア 植物が枯れる。水気を失う。また、虫・魚などが死んで干からびる。 イ 芸などで、未熟さがなくなり、老練の境に達する。枯れる。 ② [乾る・涸る] 水が干上がる。 ③ [嗄る] 声がしわがれる。 【参考】 「①」 は和歌では「離(か) る」 と掛詞になることが多い。 |
① ア -絶ゆれば生ふる 打橋に 生ひををれる 川藻もぞ 枯るれば生ゆる-(万2-196) ① ア みつみつし久米の若子がい触れけむ礒の草根の枯れまく惜しも(万3-438) ② -潮を満たしめ 明けされば 潮を干れしむ 潮さゐの 波を恐み-(万3-391) ② 耳成の池し恨めし我妹子が来つつ潜かば水は涸れなむ(万16-3810) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かる [離る] | 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 ① (空間的に) 離れる。遠ざかる。 ② (時間的に) 間をおく。足が遠くなる。 ③ (精神的に) うとくなる。よそよそしくなる。 【参考】 和歌では「枯る」 と掛詞になることが多い。 |
② 山里は冬ぞさびしさまさりける 人目も草もかれぬと思へば(古今冬-315) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かる [刈る] | 〔他動詞ラ行四段〕 茂っている植物などを切り取る。 |
玉藻刈る沖へは漕がじ敷栲の枕のあたり忘れかねつも(万1-72) 岡に寄せ我が刈る萱のさね萱のまことなごやは寝ろとへなかも(万14-3520) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かる [狩る・猟る] | 〔他動詞ラ行四段〕 ① 鳥獣を追い立てて捕える。 ②(花・紅葉などを)たずねもとめる。 |
① 日並の皇子の命の馬並めてみ狩り立たしし時は来向ふ (万1-49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かる [借る] | 〔他動詞ラ行四段〕 ① 借りる。借用する。② 真実ではなく、仮の形を現している。 |
① 人妻とあぜかそを言はむしからばか隣の衣を借りて着なはも (万14-3491) ② - うつせみの 借れる身なれば 露霜の 消ぬるがごとく あしひきの- (万3-469) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かるかや [刈萱] | 〔名詞〕 ① 屋根を葺く材料とする、刈り取ったかや。 ② イネ科の多年草。かるかや。[秋] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かるかやの [刈萱の] | 【枕詞】 |
大名児を彼方野辺に刈る草の束の間も我れ忘れめや (万2-110) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刈り取ったかやの縁で「乱る」「束 (つか)」「穂」にかかる。また、「刈る草」は「束の間」にかかる比喩的序詞として好んで用いられた。 「束 (つか)」はこぶし一握りの長さで、「かや」の一掴みから短い時間を表す「つかのま」に転じている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かるのいけ [軽の池] | 軽の地にあった池。 | 軽の池の浦廻行き廻る鴨すらに玉藻の上にひとり寝なくに(万3-393) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻三『付録 地名一覧』」】 軽は奈良県橿原市大軽・見瀬・石川・五条野の諸町一帯の地。「応神紀」十一年十月の条に軽の池を作ったことが見える。最近まで大軽町に同名の池があったが、現在は埋め立てられ、宅地に造成され消滅した。 【有斐閣「萬葉集全注巻三-390 注『軽の池』」】 「軽」 は奈良県橿原市大軽・見瀬・石川・五条野各町一帯の地。明日香村に隣接する。応神紀十一年十月の条に「剣池・軽池・鹿垣池・厩坂池を作る」 とあり、垂仁記には軽の池に舟を浮かべた話も載っている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かるのいち [軽の市] | 〔名詞〕 |
-心もありやと 我妹子が 止まず出で見し 軽の市に 我が立ち聞けば-(万2-207) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中央公論社「澤瀉久孝『萬葉集注釈巻二-207 訓釋 軽の市に』」】 「軽の市」は訓釋のはじめに天武紀を引用しておいたやうに、奈良に於ける東の市(三・三一〇)、西の市(七・一二六四)の如く、藤原京の市の立つところとなつてゐたので、人麻呂の妻も不断にそこへ出入りしてゐて、そのなつかしい市に人麻呂も今立つて耳を傾けようとするのである。 【有斐閣「萬葉集全注巻二-207 注『軽の市』」】 当時の市は「凡市恒以午時集、日入前撃鼓三度散」(関市令)と見えるように、午の時(正午前後の二時間)に集まり、日没前に終わったらしい。 その実態や当時の商業発達の程度など必ずしも明らかでないが、市の広場では一定の政治的行事や雨乞い、死刑の執行なども行われていたふしがあるから、中央では市がある程度恒常化し制度化していたことが推測されるという(岩波思想体系本『律令』補注)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かをる [薫る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① (霧・煙・火の気、潮の毛気などが) 立ち込める。 ② よい匂いがする。③ つややかに美しく見える。 |
①-靡みたる波に 潮気のみ 香れる国に 味凝り あやにともしき-(万2-162) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| き ⇒ 「主要助動詞活用表」 | 過去の助動詞「き」 ① 過去に直接経験した事実、また過去にあったと信じられる事実を回想して言う意を表す。 ~た。~ていた。 ② (平安末期以降の用法) 動作が完了して、その結果が存続している意を表す。 ~ている。~である。 〔接続〕 普通、活用語の連用形に付く。カ変・サ変の動詞には、特別な付き方をする。 |
① 三輪山の山辺真麻木綿短か木綿かくのみからに長くと思ひき(万2-157) ① 真木柱太き心はありしかどこの我が心鎮めかねつも(万2-190) ① -神宮に 装ひまつりて 使はしし 御門の人も 白栲の 麻衣着て-(万2-199) ① 黄葉の散りゆくなへに玉梓の使を見れば逢ひし日思ほゆ(万2-209) ① そら数ふ大津の児が逢ひし日に凡に見しくは今ぞ悔しき(万2-218) ① 淡路の野島の崎の浜風に妹が結びし紐吹き返す(万3-252) ① いつしかと待つらむ妹に玉梓の言だに告げず去にし君かも(万3-448) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| き [木・樹] | 〔名詞〕 ① (「け(木)」とも) 樹木。古くは、海藻なども含めた植物全般を指した。また、材木。 ② (「柝」とも書く) 歌舞伎で、幕の開閉などの合図のために打つ拍子木。 |
① -堤に立てる 槻の木の こちごちの枝の 春の葉の 繁きがごとく-(万2-210) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| き [紀] | 〔名詞〕 ①「日本書紀」の略称。②紀の国。紀伊。紀州。 |
①「紀に曰はく」(万1-27左注) ② あさもよし紀人羨しも真土山行き来と見らむ紀人羨しも(万1-55) ② 後れ居て恋ひつつあらずは紀伊の国の妹背の山にあらましものを(万4-547) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| き [酒] | 〔名詞〕酒。 | 験なき物を思はずは一坏の濁れる酒を飲むべくあるらし(万3-341) - うち撫でぞ ねぎたまふ 帰り来む日 相飲まむ酒ぞ この豊御酒は(万6-978) 皇祖の遠御代御代はい重き折り酒飲みきといふぞこのほほがしは(万19-4229) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| き [着] | 〔名詞〕着ること。また、着るもの。 | 須磨の海人の塩焼き衣の藤衣間遠にしあればいまだ着馴れず(万3-416) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きかく [聞かく] | 〔「聞く」のク語法〕 聞くこと。 |
梓弓爪引く夜音の遠音にも君の御幸を聞かくし良しも(万4-534) それをだに思ふ事とて 我が宿を見きとないひそ人の聞かくに(古今恋五-811) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きき [聞き] | 〔名詞〕① 聞くこと。見聞。② 他人に聞こえること。風聞。評判。 | ① -い巻き渡ると 思ふまで 聞きの畏く [一云 諸人の 見惑ふまでに] -(万2-199) ① -百鳥の 来居て鳴く声 春されば 聞きのかなしも いづれをか -(万18-4113) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きぎし [雉子] | 〔名詞〕雉(きじ) の古名。雉子(きぎす)。 | -滝の上の 浅野の雉 明けぬとし 立ち騒くらし いざ子ども-(万3-391) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ききまどふ [聞き惑ふ] | 〔他動詞ハ行四段〕 聞いて心が乱れる。耳にした音や声の正体がわからず困惑する。 |
-虎か吼ゆると 諸人の おびゆるまでに [一云 聞き惑ふまで] -(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きく [聞く・聴く] | 〔他動詞カ行四段〕 ① 聞いて心に思う。聞き知る。 ② 人のことばに従う。聞き入れる。③問う。たずねる。 ④ (味を)ためす。(匂いを) かぐ。 |
① -天皇の 神の命の 大宮は ここと聞けども 大殿は -(万1-29) ① 我が聞きし耳によく似る葦の末の足ひく我が背つとめ給ぶべし(万2-128) ① - 玉梓の 使ひの言へば 梓弓 音に聞きて [一云 音のみ聞きて] -(万2-207) ② もののふの臣の壮士は大君の任けのまにまに聞くといふものそ(万3-372) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きこしめし [聞こし召し] | 〔他動詞サ行四段連用形〕 [動詞の上に付いて「聞き」の尊敬の意を表す。] 「お聞き~になる」「聞き~なさる」 |
【例語】 「聞こし召し明らむ(=お聞きになって、はっきりさせる)」 「聞こし召し合はす」・「聞こし召し入る」・ 「聞こし召し驚く」 「聞こし召し出(い)づ(=聞き出しなさる)」 「聞こし召し疎(うと)む(=お聞きになって嫌がる)」 「聞こし召し置く(=お聞きになって、心に留めておられる)」 「聞こし召し知る」・「聞こし召し付く」 「聞こし召し過(す)ぐ(=お聞き過ごしになる)」 「聞こし召し伝ふ(=聞き伝えなさる)」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きこしめす [聞こし召す] | 〔他動詞サ行四段〕 [尊敬の四段動詞「聞こす」の連用形「きこし」に尊敬の四段補助動詞「めす」が付いたもの] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①「聞く」の尊敬語。「お聞きになる」 ②「聞き入る」の尊敬語。「お聞き入れになる」「ご承知なさる」 ③「食ふ・飲む」の尊敬語。「召し上がる」「お飲みになる」 ④「治む」「行ふ」の尊敬語。「お治めになる」「なさる」 |
④ やすみしし 我が大君の きこしめす 天の下に 国はしも- (万1-36) 原文「所聞食」は、「食」を「をす」とも訓まれ、 「きこしをす」とも解される。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 高い敬意を表し、多く天皇・皇后などの動作に用いられている。 なお、この語は、「聞き合はす⇒聞こし召し合はす」「聞き入る⇒聞こし召し付く」のような複合語を作る。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きこしをす [聞こし食す] | 〔他動詞サ行四段〕《上代語》 [尊敬の四段動詞「聞こす」の連用形「きこし」に尊敬の四段動詞「食(を)す」の付いたもの] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「治む」の尊敬語、お治めになる。聞こし召す。 | やすみしし 我が大君の きこしをす 天の下に 国はしも- (万1-36) 天雲の向伏す極みたにぐくのさ渡る極み聞こし食す国のまほらぞ (万5-804) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きこゆ [聞こゆ] | 〔自動詞ヤ行下二段〕【エ・エ・ユ・ユル・ユレ・エヨ】 [四段動詞「聞く」の未然形「きか」+上代の受身・自発・可能の助動詞「ゆ」の付いた「きかゆ」の転] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① 音や声が耳に入る。聞こえる。 ② うわさされる。世に知られる。 ③ 理解される。わけが分かる。判明する。 |
① 旅にしてもの恋ほしきに鶴が音も聞こえざりせば恋ひて死なまし (万1-67) ① -玉たすき 畝傍の山に 鳴く鳥の 声も聞こえず 玉桙の 道行き人も-(万2-207) ① 大宮の内まで聞こゆ網引すと網子ととのふる海人の呼び声(万3-239) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きさ [象] | 〔地名〕奈良県吉野郡吉野町宮滝の対岸の樋口・中荘・園の喜佐谷および谷を囲む山のあたり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きさやま [象山] | 喜佐谷入口西側の山。宮滝から吉野川を隔てて南正面の山。 [象の中山] | 大和には鳴きてか来らむ呼子鳥象の中山呼びぞ越ゆなる(万1-70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きさのをがは [象の小川] | 喜佐谷を流れる川。吉野の金峰山と水分山とに発して山裾で合流し、喜佐谷を北流して宮滝の柴橋の下で吉野川に注ぐ。 |
昔見し象の小川を今見ればいよよさやけくなりにけるかも(万3-319) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-319 注『象の小川』」】 「象」をキサと訓むのは、象の牙が年齢を刻んでおり、「象」と言えば、上代人は動物そのものではなく象牙(ぞうげ)として接していたので、象のことをキサと言うようになった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きし [岸] | 〔名詞〕 ① 陸地が川・湖・海などの水に接する所。岸。 ② 岩や地面の切り立った所。崖。 |
① 草枕旅行く君と知らませば岸の埴生ににほはさましを(万1-69) ① 静けくも岸には波は寄せけるかこれの屋通し聞きつつ居れば (万7-1241) ② 磐代の崖の松が枝結びけむ人は帰りてまた見けむかも(万2-143) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きしく [来及く] | 〔自動詞カ行四段〕続いて来る。度重ねて来る。 | 百重にも来しかぬかもと思へかも君が使ひの見れど飽かざらむ(万4-502) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きしみがたけ [吉志美が岳] | 〔山名〕 | 霰降り吉志美が岳を険しみと草取りかなわ妹が手を取る(万3-388) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-385 注『吉志美が岳』」】 底本など「志」の文字を欠くが、古葉略類聚鈔・紀州本によって補い「吉志美」とする。所在未詳。肥前国風土記によると、肥前国の杵島郡にある孤立丘陵の名であるが、この歌の左注によると、吉野にあることになる。実際にそのような名の山が無くとも、「杵島曲」と言われるような民謡が流伝するか借用されるかして、「仙女柘枝(つみのえ)の伝説」ができていったのであるから、その伝説の享受者は吉野にある山の名ということにしておけばよかったのである。「岳(たけ)」は「高いもの」の意。集中、題詞に「岳(たけ)」を用いた例は既出(三八二) の通りであるが、歌詞に「岳(たけ)」を用いた例はなく、「高(タケ)」(7・一〇八七) や、このように「高嶺(タケ)」と書かれるのである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きす [着す・著す] | 〔他動詞サ行下二段〕【セ・セ・ス・スル・スレ・セヨ】 着せる。身に着けさせる。 |
雨降らば着むと思へる笠の山人にな着せそ濡れは漬つとも(万3-377) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きすむ [蔵む] | 〔他動詞マ行四段〕 大切にしまう。隠しもつ。 |
いなだきにきすめる玉は二つなしかにもかくにも君がまにまに(万3-415) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-412 注『きすめる玉』」】 「キスム」は「蔵(おさ)める」の意。播磨国風土記、賀毛郡の条に「伎須美野(キスミノ)」の地名説話があって、そこの地形が「縫(ぬ)へる衣を樻(ひつ)の底に蔵(きす)めるが如し」 ということに基づくとある。さて「髻」に蔵めた玉とは、法華経安楽行品(第十四) に、仏法の至上なることを、転輪王の「髻中の明珠」 に譬、「独リ王ノ頂上ニノミ此ノ一珠有リ」 とある。この玉を愛する女に譬える。ただ一つだから「二つなし」 と言った。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きぞ [昨・昨夜] | 〔名詞〕 「きそ」とも。昨夜。ゆうべ。 |
-衣ならば 脱く時もなく 我が恋ふる 君ぞ昨夜の夜 夢に見えつる(万2-150) 比多潟の礒のわかめの立ち乱え我をか待つなも昨夜も今夜も(万14-3585) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きたやま [北山] | 〔地名〕 今の京都市北方にある山々の総称。船岡山・衣笠山などの一帯をいう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きたる [来る] | 〔自動詞ラ行四段〕[「来(き)至(いた)る」の転] 来る。やって来る。 |
春過ぎて夏来るらし白栲の衣干したり天の香具山(万1-28) -矢の繁けく 大雪の 乱れて来れ [一云 霰なす そちより来れば]-(万2-199) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -きみ [来る君] | 〔接尾語〕(人を表す名詞に付いて)尊敬の意を表す。 【例】尼君・姫君 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きぢ [紀路] | 紀伊への道。「~道(ち)」は、~を通っている道、~へ行く道、の意。 | これやこの大和にしては我が恋ふる紀路にありといふ名に負ふ背の山 (万1-35) -畝傍を見つつ あさもよし 紀伊路に入り立ち 真土山 越ゆらむ君は-(万4-546) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きなく [来鳴く] | 〔自動詞カ行四段〕来て鳴く。 | 冬こもり 春さり来れば 鳴かずありし 鳥も来鳴きぬ 咲かずありし-(万1-16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きぬ [衣] | 〔名詞〕 ① 着物。衣服。ころも。② 皮膚。地肌。一説に「おしろい」の意とも。 |
① 綜麻形の林のさきのさ野榛の衣に付くなす目につく吾が背(万1-19) 【有斐閣「万葉集全注巻第一」第十九番注】 「衣(きぬ)」は目に見える衣服。上衣。目に見えない肌着をいう「ころも」の対。 →「ころも」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きのがさ [衣笠・蓋] | 〔名詞〕 ① 絹を張った長い柄の傘。貴人の行列の時、従者が後ろからさしかけた。 ② 仏像などにかざす絹張の笠。天蓋。 |
ひさかたの天行く月を網に刺し我が大君は蓋にせり(万3-241) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きのふ [昨日] | 〔名詞〕① 前の日。きのう。② ごく近い過去。 | ① 東のたぎの御門に侍へど昨日も今日も召す言もなし(万2-184) ② きのふこそ早苗とりしかいつのまに稲葉そよぎて秋風の吹く(古今・秋上-172) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -けふ [昨日今日] | 〔名詞〕昨今。近頃。つい最近。 | つひにゆく道とはかねてききしかど 昨日今日とは思はざりしを(古今哀傷-861) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きのへのみや [城上の宮] | -御食向かふ 城上の宮を 常宮と 定めたまひて あぢさはふ 目言も絶えぬ-(万2-196) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【澤瀉久孝「萬葉集注釈巻二-196 題詞の條」】[中央公論社 昭和33年初版] 明日香皇女木※(瓦+缶)殯宮之時柿本朝臣人麻呂作歌一首[并短歌] 「木※(瓦+缶)」の「※」の字、-西本願寺本により改め、「缶」に同じく「厳瓫(イツヘ)」(神武紀)、「齋戸(イハヒヘ)」(三・三七九) などの「へ」にあたり、河邉臣瓊缶(ニヘ)」(欽明紀廿三年) とも用ゐられ、「へ」の仮名に用ゐた。 「木※」の二字をもと「コカメ」と訓でゐたのを万葉考に「キノベ」と改め、和名称(六) 広瀬郡城戸の地としたのに従ふべきであるが、次には「城上」、「木上」(一九九) とも書かれ、「へ」は清音とする。今北葛城郡広陵町大塚のあたりと云はれてゐる。墓地は今明らかでない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きはまりて [極まりて] | 〔副詞〕〔なりたち〕四段動詞「極まる」の連用形+接続助詞「て」 きわめて。このうえなく。 |
言はむすべせむすべ知らず極まりて貴きものは酒にしあるらし(万3-345) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きはまる [極まる・窮まる] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 限度に達する。② 尽きる。終わる。③ 決まる。④ 行詰って苦しむ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きはみ [極み] | 〔名詞〕 終わるところ。果て。限り。 |
-葦原の 瑞穂の国を 天地の 寄り合ひの極み 知らしめす-(万2-167) 天地を照らす日月の極みなくあるべきものを何をか思はむ(万20-4510) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きび [吉備] | 〔地名〕備前・備中・備後・美作(みまさか) の四か国。(岡山県・広島県の呼称) | 古人の飲へしめたる吉備の酒病まばすべなし貫簀賜らむ(万4-557) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きほひ [競ひ] | 〔名詞〕 ① 競うこと。張り合うこと。 ② 激しい勢い。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きほふ [競ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 ① 張り合って勇み立つ。先を争う。 ②(木の葉が)散り乱れる。争って散る。 |
①-大宮人は 舟並めて 朝川渡る 舟競ひ 夕川渡る この川の-(万1-36) ① 児らが家道やや間遠きをぬばたまの夜渡る月に競ひあへむかも(万3-305) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きます [来座す] | 〔カ変動詞「来(く)」の連用形+尊敬の補助動詞「ます」〕 おいでになる。 |
豊国の鏡の山の岩戸立て隠りにけらし待てど来まさず(万3-421) 一年にひとたびきます君まてば やどかす人もあらじとぞ思ふ(古今羇旅-419) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きみ [君] | 〔名詞〕 ① 天皇。天子。② 主君。主人。③ 貴人をさして言う語。お方。 ④ (人名・官名の下に付けて) 敬意を表す。⑤ 遊女。 |
① 君が代も我が代も知るや岩代の岡の草根をいざ結びてな(万1-10) ② 藤波の花は盛りになりにけり奈良の都を思ほすや君(万3-333) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔代名詞〕対称の人名代名詞。あなた。 【参考】 上代では、主として女性から男性を呼ぶのに用いたが、中古以降は男女相互間に用いられた。 |
今日今日と我が待つ君は石川の貝に [一云 谷に] 交じてありといはずやも(万2-225) 白菅の真野の榛原行くさ来さ君こそ見らめ真野の榛原(万3-284) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きみ [気味] | 〔名詞〕① 香りと味。② 趣。味わい。③ 気持ち。気分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きみがきる [君が着る] | 【枕詞】「君が着る御笠(みかさ)の意で、地名「三笠」にかかる。 | 君が着る御笠の山に居る雲の立てば継がるる恋もするかも(万11-2683) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きみがさす [君がさす] | 【枕詞】「きみがさす御笠」の意で、地名「三笠」にかかる。 | きみがさす三笠の山のもみぢ葉のかみな月雨のそめ(古今雑体-1010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きむかふ [来向かふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 やって来る。近づいてくる。 |
日並の皇子の命の馬並めてみ狩り立たしし時は来向ふ(万1-49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きもむかふ [肝向かふ] | 【枕詞】 「きも(=肝臓)」は心臓に向かい合っている、という意で「心」にかかる。 | -延ふ蔦の 別れし来れば 肝向ふ 心を痛み 思ひつつ-(万2-135) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きやまのみち [城山の道] | 【小学館「新編日本古典文学全集萬葉集 付録『地名一覧』」】 城山は佐賀県三養基郡基山町にある標高501mの山。坊主山とも。白村江敗戦の後、この山に百済式の城が築かれたのでその名がある。城山の道は、その基山町から約4km北の福岡県筑紫野市原田に出るいわゆる両国峠をいう。古代の駅路に当たり、城山の東南麓を通っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きゆ [消ゆ] | 〔自動詞ヤ行下二段〕【エ・エ・ユ・ユル・ユレ・エヨ】 ① (形のあるもの、見えていたもの)形がなくなる。 (雪・露・霜などが)消えてなくなる。見えなくなる。 ② 火の気がなくなる。③ 無くなる。滅ぶ。 ④ (意識していたこと、または意識が)なくなる。正気を失う。失神する。 ③ 死ぬ。 |
① -露こそば 朝に置きて 夕には 消ゆといへ 霧こそば 夕に立ちて-(万2-217) けふこずはあすは雪とぞふりなまし 消えずは有りとも花と見ましや(古今春上-63) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きよし [清し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 [少しの穢れもなく美しいさま] ①(風景が)綺麗である。清らかである。澄んでいる。 ②(容姿が)すっきりとして美しい。 ③(心が)潔い。邪念がない。潔白である。 ④(連用形を用い連用修飾語として) 残るところなく。すっかり。 |
① -山川の 清き河内と 御心を 吉野の国の 花散らふ-(万1-36) ① 月夜よし川の音清しいざここに行くも行かぬも遊びて行かむ(万4-574) ③ 言清くいたくもな言ひそ一日だに君いしなくは堪へ難きかも(万4-540) ③ -大夫の 清きその名を いにしへよ 今のをつづに 流さへる- (万18-4118) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きよみのかは [清みの川] | 【有斐閣「萬葉集全注巻三-437 注 『清の川の川岸』」】 「清の川」は原文「清之河」 とあり、その「清之」 をサヤケキ(類聚古集)、サヤケノ(紀州本)、キヨメシ(仙覚抄) などと訓んでいたのを、代匠記に「キヨミノ」と改め、飛鳥川を浄御原の辺では「キヨミノ川」と言ったものと説いた。これに従っておく。 |
妹も我れも清みの川の川岸の妹が悔ゆべき心は持たじ(万3-440) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きよみのさき [清見の埼] | 〔地名〕清水市興津清見寺町の磯崎。 | 廬原の清見の崎の三保の浦のゆたけき見つつ物思ひもなし(万3-299) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きよみはらのみや [浄御原宮] | 天武天皇の皇居。 【澤瀉注釈巻一第二二より】 天武紀元年九月の條に 「庚子(十二日) 詣于倭京而御嶋宮。癸卯(十五日)自嶋宮移崗本宮。是歳、營宮室於岡本宮南。即冬遷以居焉。是謂飛鳥浄御原宮。」 とあつて、壬申の乱平ぎて大和へ帰られ、間もなく造営せられたところであり、前に述べた岡本宮の南にあたり、喜田貞吉博士が明日香村の飛鳥小学校の附近とせられたのに従ふべきものと思はれる。即ち雷岡の東である。高市村上居(ジヤウゴ) の地とする説はあたらない (『帝都』七六頁-七九頁参照)。 古事記の序文には 「飛鳥清原大宮」 とある。元暦本には 「御」 の字がないが、右に朱筆で加へられてをり、元暦本書写の際に脱し、校合にあたり加へたものと思はれる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きよる [来寄る] | 〔自動詞ラ行四段〕 寄って来る。寄せて来る。 |
-朝羽振る 風こそ寄せめ 夕羽振る 波こそ来寄れ-(万2-131) -我妹子に 近江の海の 沖つ波 来寄る浜辺を くれくれと-(万13-3251) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きり [霧] | 〔名詞〕〔動詞「霧る」の連用形から〕 細かい水滴が地面や水面近くに立ち込めて煙のように見えるもの。〔秋〕 |
-露こそば 朝に置きて 夕には 消ゆといへ 霧こそば 夕に立ちて-(万2-217) 山の際ゆ出雲の児らは霧なれや吉野の山の嶺にたなびく(万3-432) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 古くは、春秋ともに霞とも霧ともいったが、中古以降、春立つのを霞、秋立つのを霧といった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きる [霧る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 霧や霞がかかる。かすむ。② 涙で目がかすむ。 |
① -ここと言へども 春草の 茂く生ひたる 霞立つ 春日の霧れる- (万1-29) ① 秋の田の穂の上に霧らふ朝霞いつへの方に我が恋やまむ(万2-88) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きる [着る] | 〔他動詞カ行上一段〕【キ・キ・キル・キル・キレ・キヨ】 ① (衣類を)身に着ける。着る。また、はく。頭にかぶる。 ② (恩や罪などを)身に受ける。身に負う。 |
① -装ひまつりて 使はしし 御門の人も 白栲の 麻衣着て 埴安の-(万2-199) ① 人見ずは我が袖もちて隠さむを焼けつつかあるらむ着ずて来にけり(万3-271) ① しらぬひ筑紫の綿は身に付けていまだは着ねど暖けく見ゆ(万3-339) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 現在の「着る」より用法は広く、「はく・かぶる」の意でも使われた。「②」は「着る」を比喩的に用いたもの。「カ行上一段活用動詞」は「着る」の一語だけ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| く | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| く [来] | 〔自動詞カ行変格活用〕【コ・キ・ク・クル・クレ・コヨ】 ① 来る。 ② 行く。通う。 ③ (動詞の連用形に付いて)~てくる。~てきている。 |
① はしけやし我家のかたよ雲居たちくも-(記中) ① 在り嶺よし対馬の渡り海中に幣取り向けて早帰り来ね(万1-62) ① 鳥座立て飼ひし雁の子巣立ちなば真弓の岡に飛び帰り来ね(万2-182) ① -矢の繁けく 大雪の 乱れて来れ [一云 霰なす そちより来れば]-(万2-199) ② 限りなくき思ひのままに夜もこむ夢路をさへに人はとがめじ (古今恋三-657) ③ 夕さらば潮満ち来なむ住吉の浅香の浦に玉藻刈りてな(万2-121) ③ -天地 日月と共に 足り行かむ 神の御面と 継ぎきたる 那珂の港ゆ-(万2-220) ③ 宜しなへ我が背の君が負ひ来にしこの背の山を妹とは呼ばじ(万3-289) ③ ぬばたまの夜さり来れば巻向の川音高しもあらしかも疾き(万7-1105) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| く [消] | 〔自動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 消える。なくなる。 【参考】 連体形・已然形・命令形の確かな用例は見当たらない。 |
-まつろはず 立ち向ひしも 露霜の 消なば消ぬべく 行く鳥の -(万2-199) 奥山の菅の葉しのぎ降る雪の消なば惜しけむ雨な降りそね(万3-302) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くく [漏く・潜く] | 〔自動詞カ行四段〕もれる。くぐりぬける。すき間を通り抜ける。 | あしひきの山辺に居れば霍公鳥木の間立ち潜き鳴かぬ日はなし(万17-3933) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くぐつ [裏] | 〔名詞〕 ① 海辺に生える莎草(くぐ)という植物で編んだ袋。 海藻などを入れるのに使う。 ② 糸や藁で編んだ網の袋。 |
潮干の三津の海女のくぐつ持ち玉藻刈るらむいざ行きて見む(万3-296) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くくる [潜る] | 〔自動詞ラ行四段〕[平安末期頃から「くぐる」] ① 物のすき間を通り抜ける。② (水に) もぐる。 |
① しきたへの枕ゆくくる涙にそ浮き寝をしける恋の繁きに(万4-510) ② 水くくる玉に交じれる磯貝の片恋ひのみに年は経につつ(万11-2806) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くごほう [ク語法] | 「言はく」「恋ふらく」「恋しけく」 のように語尾が「く」になって体言のように用いられる活用語の一用法。 たとえば 「語らく」「「老ゆらく」「為 (す) らく」「来 (く) らく」などのように動詞につき、「寒けく」「悲しけく」などのように形容詞につき、「(有ら)なく」「(有り)けらく」などのように助動詞につく。 これらの用法について、従来から諸説があったが、接続がまちまちのために説明しにくかった。 そこで、これを統一的に説明するために、「-aku」という語を考え、この語がそれぞれの連体形についてできたものであるとする、古くからの説が近年有力になった。 たとえば、「語らく kataru(連体形)+aku→katar aku→kataraku」 ただ、この考えには、「-aku」という語が単独で用いられた例がない点、過去の助動詞「き」 の連体形「し」 に接続した場合、たとえば「言ひしく」 などの「―しく」 について例外として考えなければならない点など、問題がある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くさ [草] | 〔名詞〕① 草本植物の俗称。草。② 屋根葺きや壁の材料とするわら・かやの類。 | ① み立たしの島の荒礒を今見れば生ひざりし草生ひにけるかも(万2-181) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くさ [来さ] | 〔名詞〕《「さ」 は時の意の接尾語》来るとき。→ 行くさ ・帰へるさ | 白菅の真野の榛原行くさ来さ君こそ見らめ真野の榛原(万3-284) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くさかえ [草香江] | 【小学館「新編日本古典文学全集萬葉集 付録『地名一覧』」】 難波江(なにわえ) とも。草香は東大阪市日下町の辺り。古くは今日の大阪市住吉区帝塚山付近から北は東淀川区崇禅寺辺りまで長く延びた上町台地を残して、生駒山西麓を東岸に、寝屋川、摂津、守口、門真、大東、東大阪の各市と大阪市の東半分を占める広大な入江があり、これに山城川(現・淀川) と旧大和川(宝水の新大和川開削以後、大阪市と堺市との間を流れるようになった) とが流れ込んで江湾をなしていた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くさね [草根] | 〔名詞〕《「ね」 は接尾語。大地にしっかりくい込んだものをいう》 草。 | 君が代も我が代も知るや岩代の岡の草根をいざ結びてな(万1-10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くさふかの [草深野] | 〔名詞〕草の深い野。 | たまきはる宇智の大野に馬並めて朝踏ますらむその草深野(万1-4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くさまくら [草枕] | 【枕詞】 「旅・結ぶ・ゆふ・かり・露」、地名「多胡」などにかかる。 草を枕に寝る不自由な旅の体験から生まれた。 |
人もなき空しき家は草枕旅にまさりて苦しかりけり(万3-454) 草枕結びさだめむかた知らずならはぬ野辺の夢のかよひ路 (新古今恋四-1315) 草枕ゆふべの空を人とはばなきても告げよ初かりの声(新古今羈旅-960) 我が恋はまさかも愛し草枕多胡の入野の奥も愛しも(万14-3421) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くしげ [櫛笥・匣] | 〔名詞〕櫛などの化粧道具を入れる箱。櫛箱。 | 志賀の海女は軍布刈り塩焼き暇なみくしげの小櫛取りも見なくに(万3-281) 君なくはなぞ身装はむ櫛笥なる黄楊の小櫛も取らむとも思はず(万9-1781) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くしろ [釧] | 〔名詞〕上代の装身具の一つ。 貝・石・玉・金属などで作り、手首や腕にはめる輪。 腕輪。 |
我妹子は釧にあらなむ左手の我が奥の手に巻きて去なましを(万9-1770) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くしろつく [釧着く] | 【枕詞】釧をつける「手(た)」から同音を含む地名「手節(たふし)」にかかる。 | 釧着く答志の崎に今日もかも大宮人の玉藻刈るらむ(万1-41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻第一-41」頭注】 地名「たふし」を手の関節と解し、釧が巻き付けられた手首の意。原文「手節」の表記は平城宮木簡にもある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くず [葛] | 〔名詞〕 秋の七草の一つ。つる草で、秋に赤紫色の蝶形の小花をつける。 つるからは葛布(くずふ)を製し、根からはでんぷんをとる。 |
-延ふ葛の いや遠長く [一云 葛の根の いや遠長に] -(万3-426) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くすし [奇し] | 〔形容詞シク活用〕 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 ① 不思議だ。神秘的だ。霊妙だ。「奇(く)し」とも。 ② 親しみ憎く窮屈だ。とっつき難い。 |
①-我が国は 常世にならむ 図負へる くすしき亀も 新代と-(万1-50) ① 聞きしごとまこと尊くくすしくも神さびをるかこれの水島(万3-246) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くだく [砕く] | 〔他動詞カ行四段〕 ① こなごなにする。うちこわす。 ② 思い苦しむ。心を痛める。③ 打ち破る。勢いをくじく。 ④ 力を尽す。労する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔自動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 ① こなごなになる。こわれる。くずれる。 ② 思い乱れる。悩む。③ 整わない。まとまりがない。 |
① 我が岡のおかみに言ひて降らしめし雪のくだけしそこに散りけむ(万2-104) ② 聞きしより物を思へば我が胸は破れて砕けて利心もなし (万12-2906) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くだす [下す・降す] | 〔他動詞サ行四段〕 ① 高い所から低い所へ移す。おろす。また、(雨などを) 降らせる。 ② 都から地方へつかわす。 ③ (命令・判決などを) 申し渡す。(者などを) 与える。下賜する。 ④ 筆を紙などにおろす。 ⑤ 調子を下げる。音を低める。 |
③ -神下し いませまつりし 高照らす 日の御子は 飛ぶ鳥の-(万2-167) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くだのふえ [小角・管の笛] | -整ふる 鼓の音は 雷の 声と聞くまで 吹き鳴せる 小角の音も-(万2-199) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔名詞〕楽器の一つ。管の形をした軍用の小さな笛。 【有斐閣「萬葉集二-199 注「小角」」】 「小角」 は、和妙抄に「小角、久太乃布江」 とあり、「大角、波良乃布江」 に対して、軍陣に用いる角制の小笛をあらわす。 軍防令によると、各軍団(兵士一千人) にはそれぞれ鼓二面と大角二口、小角四口が置かれた。 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1巻二-199 頭注 小角」】 軍隊で吹き鳴らす笛の一種。軍防令に「各軍団は鼓二、大角(はらのふえ)二、小角(くだのふえ)四を置け」 とある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くだらのはら [百済の原国] | 〔地名〕 | -いまだ尽きねば 言さへく 百済の原ゆ 神葬り 葬りいまして-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻二-199 注「百済の原」」】 クダラノハラは、奈良県北葛城郡広陵町百済の付近の原をいう。今の近鉄田原本駅の西である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くだる [下る・降る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 高い所から低い所へ移る。上から下へ行く。降りる。下がる。 ② (雨や雪などが) 降る。③ 川の下流へ移動する。 ④ 都から地方へ行く。下向する。 ⑤ (内裏が北にあったところから) 都の中を北から南へ行く。 ⑥ (命令などが) 言い渡される。通達される。 ⑦ 上位の者から下位の者に与えられる。下賜される。 ⑧ 時が過ぎる。時代が移る。末世となる。⑨ 地位が下がる。落ちぶれる。 ⑩ 地位・品性などが劣る。⑪ 降参する。⑫ へりくだる。 |
③ -楫引き上り 夕潮に 棹さし下り あぢ群の 騒き競ひて-(万20-4384) ④ 左夫流児が斎きし殿に鈴掛けぬ駅馬下れり里もとどろに(万18-4134) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くち [口] | 〔名詞〕 ① 人や動物の、飲食・発声をする器官。くち。鳥ではくちばし。 ② 言語。ことば。物の言い方。③ うわさ。評判。④ 出入口。出し入れ口。 ⑤ 物事のはじめ。起こり。⑥ 種類。類。 ⑦ (就職や嫁入りなどの) 先。入りうる場所。⑧ 馬の口縄。手綱。 ⑨ へり。先端。かど。 ⑩ (円筒などの) 切り口。また、その直径。 |
⑧ -夕狩に 鶉雉踏み立て 大御馬の 口抑へ止め 御心を-(万3-481) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くに [国] | 〔名詞〕 ①「天」に対する「地」。大地。② 国土。国家。 ③ 行政上の一単位としての地域。。国。または郡。 ④ 国ごとに置かれた地方政府。国府。⑤ 地方。田舎。 ⑥ 故郷。ふるさと。⑦ 国政。帝位。 |
② 神代より 生れ継ぎ来れば 人さはに 国には満ちて あぢ群の-(万4-485) ③ やすみしし我が大君の敷きませる国の中には都し思ほゆ(万3-332) ④ -天の下に 国はしも さはにあれども 山川の 清き河内と 御心を-(万1-36) ⑥ 燕来る時になりぬと雁がねは国偲ひつつ雲隠り鳴く(万19-4168) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くにつ(み)かみ [国つ(御)神・地祇] |
〔名詞〕[「つ」は「の」の意の上代の格助詞] ① 国土を支配し守護する神。地神。 ② 天孫降臨以前、この国土に土着して一地方を治めていた神。 土着の豪族を神格化していったもの。 |
①-天つ神 仰ぎ祈ひ祷み 国つ神 伏して額つき かからずも-(万5-909) ② この国にちはやぶる荒ぶるくにつかみどもの多(さは)なりと思ほす (記上) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くにのみやこ [恭仁京・久邇京] | 【有斐閣「萬葉集全注巻三-475 注『大日本久邇の都』」】 「大日本」 の用字の初出。久邇京の正式名であって、続紀、天平十三年十一月の条に、右大臣橘諸兄が、この朝廷の万代に伝えるべき名称をどうしますかと伺ったところ、「大養徳恭仁大宮(おほやまとくにのおほみや)」 と答えたとある。その「万代」 を頭に浮かべているはずである。橘諸兄は大伴氏の庇護者であり、家持は内舎人として、聖武天皇に従い久邇京に駐在したことがあった。「日本」を「ヤマト」 と訓むのは「日本(ひのもと)の 大和(やまと)の国」(3・三一九) という枕詞の用字がそのまま「ヤマト」と訓まれるようになり「磯城島(シキシマ)の 日本(ヤマト)の国」(13・三三二六)、また、「いざ子ども早く日本(やまと)へ」(1・六三、憶良) の如き使用例が見られる。――「飛鳥(とぶとり)の明日香(あすか)」 →「飛鳥(あすか)」・「長谷(ながたに)の泊瀬(はつせ)」 →「長谷(はつせ)」等の類――。ヤマトの命名は元来「山のある所」の意で、四周山に囲まれた盆地の地形をヤマト(甲類) と言ったものと私は考えるが、国名として特立させてヤマト(乙類)の発音に変えたものであろうと思う。「大日本」の「大」は美称。単に山城(京都府)の久邇京なのではなく、「大日本の久邇京」との自覚(もちろん天皇を始めとする為政者の国家統治上の) に基づく。久邇京は、京都府相楽郡加茂・山城・木津町にわたる範囲の天平十二年~十六年(740~744年) の都。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くにはら [国原] | 〔名詞〕国土の、広く平な土地。平野。 | -国見をすれば 国原は-(万1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くにへ [国辺] | 〔名詞〕国のあたり。故郷のあたり。 | -天さがる 鄙の国辺に 直向かふ 淡路を過ぎ 粟島を そがひに見つつ-(万4-512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くにみ [国見] | 〔名詞〕 天皇が高い所に登って国土を望み見ること。豊穣を祈る儀礼であった。 |
大和には 群山あれど とりよろふ 天の香具山 登り立ち 国見をすれば-(万1-2) -たぎつ河内に 高殿を 高知りまして 登り立ち 国見をせせば-(万1-38) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くま [隈] | ① 川や道などの曲がり角。② 中心地から離れた所。 ③ 奥まって目に付きにくい場所。 ④ 心中に隠しておくこと。秘密。隠し立て。 ⑤ 曇り。かげり。⑥ 欠点。短所。映えないところ。 ⑦ 歌舞伎で、荒事をする役者が、顔にほどこす彩色。くまどり。 |
①-い隠るまで 道の隈 い積もるまでに つばらにも- (万1-17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くまの [熊野] | 〔名詞〕[み熊野] 「み」は接頭語。固有名詞では「吉野」「熊野」とのみ付く。 熊野は旧紀伊國牟婁郡をさす。ただし旧牟婁郡は現在東・西(和歌山県)、南・北(三重県) に分かれ、旧歌番号496の「三熊野之」は、どのあたりか未詳。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -み [隈回・隈廻] |
〔名詞〕《上代語》[「み」は接尾語] 道の曲がり角。 |
後れ居て恋ひつつあらずは追ひ及かむ道の隈廻に標結へ我が背 (万2-115) -玉桙の 道の隈廻に 草手折り 柴取り敷きて 床じもの-(万5-890) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くむ [汲む・酌む] | 〔他動詞マ行四段〕 ① 水などを器にすくいとる。くむ。 ② 酒や茶を器につぐ。また、それを飲む。 ③ 思いやる。推量する。 |
① 山吹の立ちよそひたる山清水汲みに行かめど道の知らなく (万2-158) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くめのわくご [久米の若子] | 〔名詞〕若者。 | はだすすき久米の若子がいましける [一云 けむ] 三穂の岩屋は見れど飽かぬかも [一云 荒れにけるかも](万3-310) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻三-307 『付録 人名一覧』」】 久米氏のある青年の通称か。柿本人麻呂も柿本若子」といわれる(歌経標式)。 伝説上の人物かとも思われ、一般に弘計(おけ)王(顕宗天皇)の別名を来目稚子(くめのわくご)といったのでこれに擬する向きもあるが、不明。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くも [雲] | 〔名詞〕 ① (空の)雲。② 雲のように見えるもの。 ③ 心が晴れないことにたとえていう語。 ④ 火葬の煙を雲に見立て、死ぬことにたとえていう語。 |
① 直に逢はば逢ひかつましじ石川に雲立ち渡れ見つつ偲はむ(万2-225) ① 滝の上の三船の山に居る雲の常にあらむと我が思はなくに(万3-243) ① 春日山朝立つ雲の居ぬ日なく見まくの欲しき君にもあるかも(万4-587) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くもがくる [雲隠る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 雲に隠れる。② 貴人が死ぬ意の婉曲表現。 |
① -照る月の 雲隠るごと 沖つ藻の なびきし妹は もみち葉の-(万2-207) ① 慰むる心はなしに雲隠り鳴き行く鳥の音のみし泣かゆ(万5-903) ② 百伝ふ磐余の池に鳴く鴨を今日のみ見てや雲隠りなむ(万3-419) ② 大君は神にしませば雲隠る雷山に宮敷きいます(万3-236) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 ① 雲に隠れる。② 貴人が死ぬ意の婉曲表現。 ③ 心に愁いやくもりがある。 【参考】上代は四段活用、中古以降は下二段活用。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くものなみ [雲の波] | ① 波のように幾重にも重なったくも。 ② 雲のように高くたった波がしら。 |
① 天の海に雲の波立ち月の舟星の林に漕ぎ隠る見ゆ(万7-1072) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くもま [雲間] | 〔名詞〕 ① 雲の絶え間。 ② 雨の上がった時。晴れ間。 |
① 雲間よりさ渡る月のおほほしく相見し子らを見むよしもがも(万11-2454) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くもゐ [雲居・雲井] | 〔名詞〕[「ゐ」は上一段動詞「居(ゐ)の連用形] ① 雲のある所。空。天空。② 雲。③ はるか離れた所。 ④(庶民から遠く離れた所の意から)皇居・宮中。 ⑤ 皇居のある所。都。隈。 |
① -我が漕ぎ来れば 時つ風 雲居に吹くに 沖見れば とゐ波立ち-(万2-220) ① -朝さらず 霧立ちわたり 夕されば雲居たなびき雲居なす- (万17-4027) ② -朝さらず 霧立ちわたり 夕されば 雲居たなびき雲居なす- (万17-4027) ③ 隼人の薩摩の瀬戸を雲居なす遠くも我は今日見つるかも(万3-249) ③ ま遠くの雲居に見ゆる妹が家にいつか至らむ歩め我が駒(万14-3460) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くやし [悔し] | 〔形容詞シク活用〕【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 後悔される。残念だ。無念だ。 |
-梓弓 音聞く我れも 凡に見し こと悔しきを 敷栲の 手枕まきて-(万2-217) そら数ふ大津の児が逢ひし日に凡に見しくは今ぞ悔しき(万2-219) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くゆ [悔ゆ] | 〔自動詞ヤ行上二段〕【イ・イ・ユ・ユル・ユレ・イヨ】 悔やむ。後悔する。 |
橘をやどに植ゑ生ほし立ちて居て後に悔ゆとも験あらめやも(万3-413) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くゆ [崩ゆ] | 〔自動詞ヤ行下二段〕【エ・エ・ユ・ユル・ユレ・エヨ】 くずれる。 |
うるはしと我が思ふ心速川の塞きに塞くともなほや崩えなむ(万4-690) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くゆ [蹴ゆ] | 〔他動詞ヤ行下二段〕【エ・エ・ユ・ユル・ユレ・エヨ】 《上代語》蹴(け)る。 |
毬(まり)を蹴ゆる侶(ともがら)(皇極紀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くらす [暮らす] | 〔他動詞サ行四段〕 ① (日を暮れさせることから) 日の暮れるまで時間を過ごす。 ② 毎日を送る。歳月を送る。 ③ (動詞の連用形の下に付いて用いられる場合) 「日が暮れるまで・・・」「・・・続けて一日を過ごす」などの意になる。 |
① -玉桙の 道行き暮らし あをによし 奈良の都の 佐保川に-(万1-79) ① 春さればまづ咲くやどの梅の花独り見つつや春日暮らさむ [筑前守山上大夫](万5-822) ③ -我が寝し 枕づく つま屋の内に 昼はも うらさび暮らし 夜はも-(万2-210) ③ 梅の花咲きたる園の青柳を蘰にしつつ遊び暮らさな [小監土氏百村] (万5-829) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【例語】 思ひ暮らす・語らひ暮らす・恋ひ暮らす (=一日中恋しく思う) ・眺め暮らす・嘆き暮らす・臥し暮らす (=日暮れまで横になっている) ・降り暮らす |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くらはしのやま [倉橋の山] | 〔地名〕 | 倉橋の山を高みか夜隠りに出で来る月の光乏しき(万3-293) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-290 注『倉橋の山』」】 奈良県桜井市倉橋の東南にある音羽山(八五一メートル) かとも、南にある多武峰(六一九メートル) かともいうが、後説が正しかろう(〔考〕参照)。 しかるに、従来前説の「音羽山」と解されてきたのは、仁徳記に、速総別(はやぶさわけ)王と女鳥(めとり)王との逃避行において「倉椅山(くらはしやま)に騰(のぼ)りて」とあり、これは倉橋山を越えて宇陀の蘇迩(そに)に到るとあるように、大和から伊賀・伊勢の方に脱出する経路に当たるわけなので、東の宇陀の蘇迩(奈良県宇陀郡曽爾村)から逆に西の山を探れば、音羽山となるからである。 さて、原文「椋(くら)」の字は、狩谷棭斎の『日本霊異記攷證』(上、第十話)に、「京」は「倉」の意であったが、京都の意に用いられていたので混同を避けて「木」扁を加えたものとあり、講義は日本上代の「あざくら」は木造方形のクラであったので、「京」に木扁を加えて「椋」としたものと説いた。クラの語に「暗(くら)」がかけてある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くる [暗る・眩る] | 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 ① 目の前が真っ暗になる。目が眩む。 ② (涙で)目が曇り見えなくなる。③ 心が乱れ惑う。理性がなくなる。 |
① -春に至れば 松風に 池波立ちて 桜花 木の暗茂に 沖辺には-(万3-259) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くる [暮る・昏る] | 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 ① 日が暮れる。② 季節が過ぎる。年月が終わる。 |
① 霞立つ 長き春日の暮れにける わづきも知らず むらきもの 心を痛み-(万1-5) ② 暮れてゆく春のみなとは知らねども霞に落つる宇治の柴舟(新古今春下-169) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くるし [苦し] | 〔形容詞シク活用〕【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 ① 痛みや悩みでつらい。苦しい。 ② いとわしい。見苦しい。不快だ。 ③ 差しさわりがある。不都合だ。 |
① 難波潟潮干なありそね沈みにし妹が姿を見まく苦しも(万2-229) ① 苦しくも降り来る雨か三輪の崎狭野の渡りに家もあらなくに(万3-267) ① 都なる荒れたる家にひとり寝ば旅にまさりて苦しかるべし(万3-443) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くれ [暮れ] | 〔名詞〕 ① 日が没して、あたりが暗くなるころ。日暮れ。夕暮れ。 ② 年や月や季節などの終わりのころ。末。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くろかみ [黒髪] | 〔名詞〕 つやのある真っ黒な頭髪。 |
居明かして君をば待たむぬばたまの我が黒髪に霜は降るとも(万2-89) ぬばたまの黒髪濡れて沫雪の降るにや来ますここだ恋ふれば (万16-3827) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くろかみの [黒髪の] | 【枕詞】「乱れ」「解け」にかかる。「枕詞一覧」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くろま [黒馬] | 〔名詞〕黒い馬。 | 佐保川の小石踏み渡りぬばたまの黒馬の来夜は年にもあらぬか(万4-528) -ぬばたまの 黒馬に乗りて 川の瀬を 七瀬渡りて うらぶれて-(万13-3317) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| け- [気-] | 〔接頭語〕(動詞・形容詞・形容動詞に付いて) 「~のようすである・~の感じだ・なんとなく~だ」 の意を表す。 【例】「気恐ろし・気劣る・気すさまじ・気高し」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| け [日] | 〔名詞〕上代語 「日(ひ)」の複数。二日以上の期間をいう。日々。日数。 【参考】「二日(ふつか)」 「三日(みか)」 の 「か」 と同義語と言われる。 |
馬ないたく打ちてな行きそ日ならべて見ても我が行く志賀にあらなくに(万3-265) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| け [気] | 〔名詞〕 ① 気持ち。気分。② ようす。気配。 |
② -沖つ藻も 靡みたる波に 潮気のみ 香れる国に-(万2-162) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| け [筍] | 〔名詞〕容器。特に、飯を盛るのに用いる器。 | 家にあれば笥に盛る飯を草枕旅にしあれば椎の葉に盛る(万2-142) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| け [消] | 〔下二段動詞「消ゆ」の未然形・連用形「きえ」の転〕消える。→「消ゆ」 | 富士の嶺に降り置く雪は六月の十五日に消ぬればその夜降りけり(万3-323) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| けころも [毛衣] | 〔名詞〕《「けごろも」 とも》鳥の羽毛。毛皮で作った衣服。かわごろも。 |
けころもを時かたまけて出でましし宇陀の大野は思ほえむかも(万2-191) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻二-191 注「けころもを」」】 春にかかる「枕詞」とする説も多く見られるが(講義・評釈篇・全註釈・私注・窪田評釈・注釈・古典全集・古典集成)、精考・古典大系では毛の衣とし、枕詞と見ない説をとる。 実質的な表現として理解されうるならば、その方が良いが、その可能性は乏しいようだ。 ケゴロモは代匠記(初稿本) に「鳥けた物の毛をもてをれる衣なり」 とし、考には皮衣とする。 また全註釈には「褻衣で、著古した衣服をいう」 ものと見て、それを解く意で次の「トキ」 に冠する枕詞と見る。注釈・古典全集などもこれによっている。 神楽歌に「すべ神は よき日祭れば 明日よりは朱の衣を褻衣にせむ」 とあるのも、普段着のこと。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| けさ [今朝] | 〔名詞〕今日の朝。 | 我が背子にまたは逢はじかと思へばか今朝の別れのすべなかりつる(万4-543) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| けす [着す・著す] | 〔他動詞サ行四段〕《上代語》「着る」の尊敬語。お召しになる。 | 我が背子が着せる衣の針目落ちずこもりにけらし我が心さへ(万4-517) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻四-514 注「着せる」」】 「ケス」は動詞「キル」の敬語。上一段活用の動詞に敬語の「ス」が付くと、見ル → (召) のように [-iru → -esu] となる。 「着セリ」は現在相手が着用しているのを見て言っている。「汝が着せる 襲(おすひ)の裾に 月立ちにけり」(記・二七) もその点において同じである。 原文「盖世流」の「盖」は俗字。攷證の一案はこれを字音表記と見るが、「蓋」は泰韻字で、泰韻(-âi) には「太・大・奈・帯」などの字が属するが、エ甲類を写すには適わない。 「雨降らば将盖と思へる笠の山」(3・三七四) など、被る意に用いた例はあり、ここはそれで用いた表意文字である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| けだし [蓋し] | 〔副詞〕 ① [下に疑問の語を伴って] 疑いの気持ちをこめて推量する意を表す。 「もしかすると」 「ひょっとしたら」 「あるいは」 ② [下に仮定の表現を伴って] 万一の場合を仮定する意を表す。「もしかして」「万一」 ③ おおよその意を表す。 「おおかた」「大体」「ざっと」 【参考】 中古以後の「けだし」は漢文訓読語で、主に漢文脈の中で使用される。 |
① いにしへに恋ふらむ鳥は霍公鳥けだしや鳴きし我が念へるごと (万2-112) ① 馬の音のとどともすれば松蔭に出でてぞ見つるけだし君かと (万11-2661) ② 山守はけだしありとも我妹子が結ひけむ標を人解かめやも(万3-405) ② 我が背子しけだし罷らば白栲の袖を振らさね見つつ偲はむ (万15-3747) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| けだしく [蓋しく] | 〔副詞〕きっと。 | 我妹子が形見の合歓木は花のみに咲きてけだしく実にならじかも (万8-1467) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| けだしくも [蓋しくも] | 〔副詞〕 ① もし。ひょっとしたら。② おそらく。たぶん。 |
① 琴取れば嘆き先立つけだしくも琴の下樋に妻や隠れる(万7-1133) ② など鹿のわび鳴きすなるけだしくも秋野の萩や繁く散るらむ (万10-2158) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| けつ [消つ] | 〔他動詞タ行四段〕 ① 消す。消滅させる。無くする。② けなす。非難する。傷つける。 ③ おさえつける。圧倒する。制する。 |
① - 燃ゆる火を 雪もて消ち 降る雪を 火もて消ちつつ 言ひも得ず-(万3-322) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| けながし [日長し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 「け」は二日(ふつか)、三日(みっか)の「か」と同意。「日 (か)の転。 日数がかかる。時日が長く経過する。 |
君が行き日長くなりぬ山尋ね迎へか行かむ待ちにか待たむ(万2-85) 君が行き日長くなりぬ山たづの迎へを行かむ待つには待たじ(万2-90) 相見ずて日長くなりぬこの頃はいかに幸くやいふかし我妹(万4-651) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| けに [異に] | 〔副詞〕[形容動詞「異(け)なり」の連用形の副詞化] 特に。いっそうまさって。いよいよ。 |
-鮎子さ走り いや日異に 栄ゆる時に 逆言の 狂言とかも 白たへに-(万3-478) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| けひのうみ [飼飯の海] | 〔地名〕 淡路島西海岸。兵庫県三原郡西淡町松帆の慶野松原の海岸。 |
飼飯の海の庭良くあらし刈り薦の乱れて出づ見ゆ海人の釣船(万3-257) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| けふ [今日] | 〔名詞〕この日。本日。きょう。 |
東のたぎの御門に侍へど昨日も今日も召す言もなし(万2-184) 今日今日と我が待つ君は石川の貝に [一云 谷に] 交じてありといはずやも (万2-224) 三島野に霞たなびきしかすがに昨日も今日も雪は降りつつ(万18-4103) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1巻二-224 頭注『今日今日と』」】 今日こそ来るだろう、今日こそ来るだろうと。原文「且~且~」は事物を列挙する漢籍の用法。 【有斐閣「萬葉集全注巻二-224 注『今日今日と』】 原文「且今日々々々」。且を西本願寺本など旦とするが、紀州本・細井本・温故堂本による。且は、古義に「且は不定辞也と注せり。 たしかに其日と定めず今日か今日かとおもふよしにて書る字なるべし」と言う。 講義に「且今」(10・二三二三)の例をあげ、「『且』字は漢文の助字として、種々の用法ある字なるが、そのうちに戦国策に〔且天下之半〕といへるに注して〔猶幾也〕といへるが如く、類聚名義抄に『ナム~トス』といふ訓あるその意にて、『且今』の二字を『イマカ』と訓すべく用ゐたるなるべし。 然りとして考ふれば『且今日』は『ケフカ』にて、『且今日且今日』は『ケフカケフカ』といふ意をあらはせる字面といはざるべからず」と注するが、古典全集には 「且~且」の表記は事物を列挙する漢籍の用字法によると説いている。 巻九の「且今日且今日吾が待つ君が船出すらしも」 (一七六五) も巻十二の 「且今日々々々云ふに年を経にける」 (二二六六)も、いずれもケフケフトと訓むことは間違いないが、「且」字の用法について、なお不明確な点を残す。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| けぶり [煙・烟] | 〔名詞〕〔「けむり」の古形〕 ① けむり。 ② かすみ・塵・しぶき・水蒸気など、けむりのように立ちのぼるもの。 また、たなびき、かすむもの。 ③ 立木などの萌え出たばかりの芽が、煙のように霞んで見えるもの。 ④ 火葬のけむり。また、火葬。死のたとえにいう。 ⑤ 飯をたくけむり、転じて、生計。 ⑥ 地獄で罪人を責める火のけむり。⑦ たばこの煙。 |
① -手結が浦に 海人娘子 塩焼く煙 草枕 旅にしあれば ひとりして-(万3-369) ① 志賀の海人の塩焼く煙風をいたみ立ちは上らず山にたなびく(万7-1250) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のなみ [けぶりの波] | はるかかなたに、けむりのように霞んで見える波。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -くらべ [煙比べ] | 〔名詞〕〔「煙」は、恋の炎のけむりの意〕 思いの深さを比べること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| けぶる [煙る・烟る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 煙が立ち上がる。けむったりかすんだりしているように見える。 ② ほんのりと美しく見える。 ③ 火葬にされて煙となる。 |
-天の香具山 登り立ち 国見をすれば 国原は 煙り立ち立つ 海原は-(万1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| けまく | 〔助動詞「けむ」のク語法〕~たということ。~たであろうこと。 | つのさはふ 磐余の道を 朝去らず 行きけむ人の 思ひつつ-(万3-426) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| けむ [主要助動詞活用表] | 〔諸説あるが、過去の助動詞「き」の古い未然形と言われる「け」に推量の助動詞「む」が付いたものか。「けん」とも表記される〕 ① 過去のある動作・状態を推量する意を表す。 「~ただろう。~ていただろう。」 ②(疑問語とともに用いて)過去の事実について、 時・所・原因・理由などを推量する意を表す。 「(どうして) ~たのだろう (か)。」 ③ 過去の事実を人づてに聞き知ったように婉曲に表す。 「~たという。~たとかいう。」 |
① -望月の 満しけむと 天の下 食す国 四方の人の 大船の-(万2-167) ① -敷栲の 手枕まきて 剣太刀 身に添へ寝けむ 若草の その嬬の子は-(万2-217) ① 真木の葉のしなふ勢能山しのはずて我が越え行けば木の葉知りけむ(万3-294) ① 昔こそ難波田舎と言はれけめ今は都引き都びにけり(万3-315) ② 荒波に寄り来る玉を枕に置き我ここにありと誰か告げけむ(万2-226) ③ -楽浪の 大津の宮に 天の下 知らしめしけむ 天皇の-(万1-29) ③ 我を待つと君が濡れけむあしひきの山のしづくにならましものを (万2-108) ③ ももしきの大宮人の熟田津に船乗りしけむ年の知らなく(万3-326) ③ 山守はけだしありとも我妹子が結ひけむ標を人解かめやも(万3-405) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔接続〕 活用語の連用形に付く。ただし、時に関係している助動詞や推量を表す助動詞には付かない。また上代には形容詞に付いた例がない。 さらに、上代・中古には、形容動詞に付いた例がない。 また助動詞「ず」に付く場合、中古からは「ざり」に付いて「ざりけむ」と用いられるが、上代では「ず」に付いて、【接続例】のように、「ずけむ」の形が用いられた。 【接続例】 松反りしひにてあれかもさ山田の翁がその日に求めあはずけむ (万17-4038) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| けらし | 〔助動詞特殊型〕【〇・〇・ケラシ・ケラシ(ケラシキ)・ケラシ・〇】 [過去の助動詞「けり」の連体形「ける」に推定の助動詞「らし」で「けるらし」の転] 〔接続〕活用語の連用形につく。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① 過去の動作・状態について、ある根拠によって推定する意を表す。 「~たらしい」 ② 「けり」というところを婉曲に表す。「~たことよ」 |
① 桜田へ鶴鳴き渡る年魚市潟潮干にけらし鶴鳴き渡る(万3-273) ① 豊国の鏡の山の岩戸立て隠りにけらし待てど来まさず(万3-421) ① 我が背子が着せる衣の針目落ちずこもりにけらし我が心さへ(万4-517) ① 年魚市潟潮干にけらし知多の浦に朝漕ぐ舟も沖に寄る見ゆ(万7-1167) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| けり [来り] | 〔自動詞ラ行変格〕【ラ・リ・リ・ル・レ・レ】 〔「カ変動詞「来(く)」の連用形「き」にラ変動詞「あり」のついた「きあり」の転」〕 来ている。来た。 |
-まして恋しみ 雪消する 山道すらを なづみぞ我が来る(万3-385) - 玉梓の 使の来れば 嬉しみと 我が待ち問ふに およづれの-(万17-3979) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| けり [主要助動詞活用表] | 〔助動詞ラ変型〕 [過去の助動詞「き」+「あり」=「きあり」の転とも、「来 (き)」に「あり」の付いた「きあり」の転とも] [基本義] 現状から過去の記憶を思い起こす語。現状を述べる語に付けたり、現状から思い起こす過去の出来事を表す語に付けたりする。 「今は・・・となっているが、昔は・・・だった」。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去の伝聞とする説もある。 ① 現状を述べ、過去の体験を思い起こす意を表す。「~たのだ」 ② 人づてに聞いた過去の出来事であることを表す。 「~たとさ・~たそうだ」 ③ 過去にあった事柄や以前から現在まで続いている事柄を回想していう。 「~た・~たのであった」 ④ 詠嘆の意をこめて、これまでにあったことに今気付いた意を表す。 「~たことよ」 〔接続〕活用形の連用形に付く |
① 家に来て我が屋を見れば玉床の外に向きけり妹が木枕(万2-216) ③ 常磐なす岩屋は今もありけれど住みける人そ常なかりける(万3-311) ④ ますらをや片恋せむと嘆けども醜のますらをなほ恋ひにけり (万2-117) ④ 風流士に我れはありけりやど貸さず帰しし我れぞ風流士にはある (万2-127) ④ み立たしの島の荒礒を今見れば生ひざりし草生ひにけるかも(万2-181) ④ 三笠山野辺ゆ行く道こきだくも荒れにけるかも久にあらなくに(万2-234) ④ 否と言へど強ふる志斐のが強ひ語りこのころ聞かずて朕恋ひにけり(万3-237) ④ 何時の間も神さびけるか香具山の桙杉が本に苔生すまでに(万3-261) ④ 人見ずは我が袖もちて隠さむを焼けつつかあるらむ着ずて来にけり(万3-271) ④ 早来ても見てましものを山背の高の槻群散りにけるかも(万3-280) ④ ひさかたの天の探女が石船の泊てし高津はあせにけるかも(万3-295) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こ- [小] | 〔接頭語〕 ① (名詞について) 小さい、愛らしい、若い、少ないなどの意を表す。 「小家・小萩・小姫君・小雨」など。 ② (数量を表す名詞について) 少し足りないがほぼ近い、およその意を表す。 「小一里・小半時」など。 ③ (多く、体の部分を表す名詞について、その名詞を受ける動詞を修飾して) 僅か、少しの意を表す。「小首をかたぶく・小耳にはさむ」など。 ④ (副詞・用言について) ちょっと、なんとなく、の意を表す。 「小暗し・小粋(こいき)」など。 ⑤ (名詞・用言について) 軽んじる気持ちを表す。「小わっぱ・小ざかし」など。 ⑥ (名詞・用言について) 語調を整えたり、意味を強めたりする。 「小鬢(こびん)・小しゃく」など。 |
① 佐保川の小石踏み渡りぬばたまの黒馬の来夜は年にもあらぬか(万4-528) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こ [木] | 〔名詞〕多く複合語を作る。木 (き) 。 [例語] 「木隠れ」「木の葉」「木の間」 |
秋山の木の下隠り行く水の我れこそ益さめ思ほすよりは(万2-92) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こ [子・児] | 〔名詞〕 ① 幼いもの。子ども。② 人を親しんで呼ぶ語。男女共に用いる。 |
① 銀も金も玉も何せむにまされる宝子にしかめやも(万5-807) ② -この岡に 菜摘ます子家聞かな 告らさね そらみつ 大和の国は-(万1-1) ② 大船の泊つる泊りのたゆたひに物思ひ痩せぬ人の子故に(万2-122) ② -思へりし 妹にはあれど 頼めりし 児らにはあれど 世の中を-(万2-210) ② -敷栲の 手枕まきて 剣太刀 身に添へ寝けむ 若草の その嬬の子は-(万2-217) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-475 注『鮎子さ走り』」】 原文「年魚小狭走」とある。「年魚」は「春ニ生レ夏ニ長ジ秋ニ衰ヘ、冬ニ死ヌ。故(かれ)、年魚ト名(なづ)ク」(倭名抄) とある通りである。その下の「小(こ)」の字は、愛称の接尾語とする説もあるが、形の小さいという意味で、子鮎(若鮎) を表そうとしたものであろう。それならば「川の瀬に 年魚兒狭走」(19・四一五六、家持) と書いてもよかったはず。しかし「小」の字を用いている以上は、形が小さい、漁獲の対象ではない、の意識で用いたものであろう。サ走ルのサは接頭語。走ルはぴちぴち跳ねながら泳ぐさま。松浦川に遊ぶ歌の「娘等(をとめら)の更に報(こた)ふる歌」(5・八五九) の中に「阿由故佐婆斯留(アユコサバシル)」とある。そして同じ作者が「和可由(ワカユ)」(5・八五八) と「若鮎」とも表現しているから、「鮎子」は「若鮎」でもある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こえく [越え来] | 〔自動詞カ行変格〕【コ・キ・ク・クル・クレ・コ(コヨ)】 越えて来る。 |
-かへり見すれど いや遠に 里は離りぬ いや高に 山も越え来ぬ-(万2-131) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こぎかくる [漕ぎ隠る] | 〔自動詞ラ行四段〕漕いでいった舟が物陰に隠れる。 | 四極山うち越え見れば笠縫の島漕ぎ隠る棚なし小舟(万3-274) あゆの風 [越俗語東風謂之あゆの風是也] いたく吹くらし 奈呉の海人の釣する小船漕ぎ隠る見ゆ(万17-4041) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こぎいづ [漕ぎ出づ] | 〔自動詞ダ行下二段〕【デ・デ・ヅ・ヅル・ヅレ・デヨ】 舟を漕いで出るこ。 |
わたの原八十島かけてこぎいでぬとひとにはつげよあまの釣舟 (古今羈旅-407) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こぎく [漕ぎ来] | 〔自動詞カ行変格〕【コ・キ・ク・クル・クレ・コ(コヨ)】 (舟を)漕いで来る。 |
-放けて 漕ぎ来る船 辺付きて 漕ぎ来る船 沖つ櫂―(万2-153) -那珂の港ゆ 船浮けて 我が漕ぎ来れば 時つ風 雲居に吹くに-(万2-220) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こぎたみゆく [漕ぎ回み行く] | 〔自動詞カ行四段〕漕ぎ回って行く。 | いづくにか船泊てすらむ安礼の崎漕ぎ廻み行きし棚無し小舟(万1-58) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こぎたむ [漕ぎ回む] | 〔自動詞マ行上二段〕【ミ・ミ・ム・ムル・ムレ・ミヨ】 (舟で)漕ぎめぐる。 |
磯の崎漕ぎ廻み行けば近江の海八十の港に鶴さはに鳴く [未詳](万3-275) -白雲も 千重になり来ぬ 漕ぎ廻むる 浦のことごと 行き隠る- (万6-947) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こぎみる [漕ぎ回る] | 〔他動詞マ行上一段〕【ミ・ミ・ミル・ミル・ミレ・ミヨ】漕ぎまわる。 | 縄の浦ゆそがひに見ゆる沖つ島漕ぎ廻る船は釣りしすらしも(万3-360) 島伝ひ敏馬の崎を漕ぎ廻れば大和恋しく鶴さはに鳴く(万3-392) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こぐ [漕ぐ] | 〔他動詞ガ行四段〕 ① 櫓や櫂を使って船を進める。 ② 深い雪や泥の中を歩く。進みにくい所をかき分けるようにして進む。 |
① 潮騒に伊良虞の島辺漕ぐ舟に妹乗るらむか荒き島廻を(万1-42) ① 玉藻刈る沖へは漕がじ敷栲の枕のあたり忘れかねつも(万1-72) ① 燈火の明石大門に入らむ日や漕ぎ別れなむ家のあたり見ず(万3-255) ① -いさなとり 海路に出でて あへきつつ 我が漕ぎ行けば-(万3-369) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こけ [苔・蘿] | 〔名詞〕 土や木・岩などに生る蘚苔 (せんたい) 類・地衣類や一部の藻類などの称。 |
従吉野折取蘿生松柯遣時額田王奉入歌一首(万2-113題詞「蘿」) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こけむす [苔産す・苔生す] | 〔自動詞サ行四段〕 苔が生える。転じて、古めかしくなる。漕ぎ回って行く。 |
妹が名は千代に流れむ姫島の小松がうれに蘿生すまでに(万2-228) 何時の間も神さびけるか香具山の桙杉が本に苔生すまでに(万3-261) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここ [此処] | 〔代名詞〕 ① [近称の指示代名詞] 事物・場所をさす。 ここ。この場所。こちら。この点。このこと。 ② [自称の人代名詞] この身。私。 ③ [対称の人代名詞] あなた。 ④ [他称の人代名詞] こちらの方。 |
① ここにして家やもいづち白雲のたなびく山を越えて来にけり(万3-290) ① -葛飾の 真間の手児名が 奥つきを こことは聞けど 真木の葉や-(万3-434) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 「②、③、④」 の人代名詞と考えられる用法は、「①」の場所をさし示す用法から派生したもので、多く「ここに」の形で現れる。 同様の語に「そこ」(対称・あなた)、「かしこ」(他称・あちらの人) がある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こごし | 〔形容詞シク活用〕《上代語》 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 岩がごつごつして重なり、険しい。 |
岩が根のこごしき山を越えかねて音には泣くとも色に出でめやも(万3-304) 神さぶる岩根こごしきみ吉野の水分山を見れば悲しも(万7-1134) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全集万葉集巻三-322 注『こごしかも』」】 | -島山の 宣しき国と こごしかも 伊予の高嶺の 射狭庭の 岡に立たして-(万3-325) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「極此疑」(ただし「疑」は「凝」とあるのを、細井本等により改められた) とある。「コゴシ」は三〇一番歌にもあった。凝り固まってごつごつしたさま。 「カモ」は詠嘆の間投助詞、「コゴシ」は語幹のままで連体修飾となっている。 さて、「極」字がもし字音に基づく用字だとすると、やはり「極此」は「ココシ」としか読めまい(拙稿「表意・表意をめぐって-『極此鴨』『今時者四』の場合」『澤瀉博士喜寿記念・万葉学論叢』)。しかし、国語としては明らかに「コゴシ」であって「ココシ」ではない。したがって、「ココシ」と「コゴシ」の二重形を認めるのは少し無理かも知れない。その点、古典全集が『広韻』に「極、窮也、高也、渠力切」とあり、意味と音(呉音ゴク)との両面から「コゴシ」と訓もうとしているのは認められよう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここだ [幾許] | 〔副詞〕《上代語》 ① (数や量について)たくさんに。 ② (程度について)たいそう。 |
① み吉野の象山の際の木末にはここだも騒く鳥の声かも(万6-929) ② - 国からか 見れども飽かぬ 神からか ここだ貴き 天地 日月と共に-(万2-220) ② 多摩川にさらす手作りさらさらになにぞこの子のここだ愛しき(万14-3390) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここだく [幾許] | 〔副詞〕《上代語》(こんなにも)多く。(こんなにも)ひどく。 | 相見ぬは幾久さにもあらなくにここだく我れは恋ひつつもあるか(万4-669) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここに [此に・茲に] | 〔副詞〕この時に。この場合に。 | いにしへに梁打つ人のなかりせばここにもあらまし柘の枝はも(万3-390) 月夜よし川の音清しいざここに行くも行かぬも遊びて行かむ(万4-574) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔接続詞〕前文を受けて、次のことを言い起す語。 さてそこで。それで。それゆえ。 |
荒波に寄り来る玉を枕に置き我ここにありと誰か告げけむ(万2-226) 遠妻の ここにしあらねば 玉桙の 道をた遠み 思ふそら 安けなくに-(万4-537) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こころ [心] | 〔名詞〕 ① 知識・感情・意志の総称。(肉体に対する) 精神。 ② 思い遣り。情愛。③ 道理をわきまえる心。思慮。考え。 ④ あだし心。二心。⑤ 気持ち。ここち。⑥ わけ。意味。意義。 ⑦ おもむき。風情。情趣。⑧ (物の) 中心。⑨ 趣向。くふう。 ⑩ 心ばせ。意向。望み。⑪ 情趣を感じる気持ち。 ⑫ 無心のものを有心のようにみなしていう語。⑬ 胸。むなさき。 ⑭ 心構え。用意。⑮ 意趣。うらみ。 |
① 心には千重に百重に思へれど人目を多み妹に逢はぬかも (万12-2922) ② 梓弓引かばまにまに依らめども後の心を知りかてぬかも [郎女] (万2-98) ② 堀江越え遠き里まで送り来る君が心は忘らゆましじ(万20-4506) ④ 人言を繁み言痛み逢はざりき心あるごとな思ひ我が背子(万4-541) ④ たえず行く飛鳥の川の淀みなば心あるとや人の思はむ (古今恋四-720) ⑤ 真木柱太き心はありしかどこの我が心鎮めかねつも(万2-190) ⑤ -聞けば 音のみし泣かゆ 語れば 心そ痛き 天皇の 神の皇子の-(万2-230) ⑤ もろ人の願ひをみつの浜風にこころすずしき四手(シデ)の音かな(新古今神祇-1904) ⑩ 天地とともに終へむと思ひつつ仕へまつりし心違ひぬ(万2-176) ⑪ こころなき身にもあはれは鴫立つ沢の秋の夕暮れしられけり (新古今秋上-362) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こころあり [心有り] | 〔心+ラ変動詞「あり」〕【ラ・リ・リ・ル・レ・レ】 ① 思い遣りがある。人情がある。 ② 物の道理がわかる。思慮分別がある。 ③ 情趣を解する。⇔「心無し」 ④ 思うところがある。下心がある。ニ心がある。 |
① 三輪山をしかも隠すか雲だにも心あらなも隠さふべしや(万1-18) ④ 人言を繁み言痛み逢はざりき心あるごとな思ひ我が背子(万4-541) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こころすすむ [心進む] | 〔自動詞マ行四段〕心がはやる。 | 家思ふと心進むな風まもりよくしていませ荒しその道(万3-384) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こころど [心ど] | 〔名詞〕 しっかりした心。気力。 |
遠長く仕へむものと思へりし君しまさねば心どもなし(万3-460) 家離りいます我妹を留めかね山隠しつれ心どもなし(万3-474) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こころなし [心無し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① 道理を解さない。思慮や分別がない。 ② 人情を解さない。思い遣りがない。つれない。 ③ 情趣を解さない。風流心がない。 |
②-しばしばも 見放けむ山を 心なく 雲の 隠さふべしや-(万1-17) ② 大和恋ひ寐の寝らえぬに心なくこの洲崎廻に鶴鳴くべしや(万1-71) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こさめ [小雨] | 〔名詞〕細かく降る雨。 用例は万葉集に集中して見られ、「小雨」のほかに「霂」「霂霂」の表記が用いられている。 |
-何かと問へば 玉鉾の 道来る人の 泣く涙 小雨に降れば 白たへの -(万2-230) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こし [越] | 〔地名〕越前・越中・越後の総称。現在の石川県に当たる加賀・能登は、当時は一郡名であったり、分置・合併を繰り返していたりして固定していなかった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こし [腰] | 〔名詞〕 ① 腰。② 衣服または袴の腰にあたるところ。また、そのあたりに結ぶひも。 ③ 障子・乗り物などの中ほどより少し下の部分の称。 ④ 山の中腹から少し下のところ。山裾。 ⑤ 和歌の第三句の五文字。(第一句を頭、第二句を胸、第四、五句を尾という) |
② -心振り起し 剣大刀 腰に取り佩き 梓弓 靫取り負ひて 天地と-(万3-481) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こしぢ [越路] | 〔名詞〕 北陸地方へ行く道。また、北陸道(=今の北陸地方のほぼ全域)の古称。 |
さざれ波礒越道なる能登瀬川音のさやけさ激つ瀬ごとに(万3-317) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こしま [子島] | 〔地名〕所在未詳 | 我が欲りし野島は見せつ底深き阿胡根の浦の玉ぞ拾はぬ (万1-12) [或頭云 我が欲りし子島は見しを] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こす [越す] | 〔自動詞サ行四段〕 ① 物の上を越えて通る。越える。 ② 前のものを抜いてその先を行く。追い越す。 ③ (間を隔てるものなどを越えて)行く。また、来る。 ④ 基準を上回る。超過する。 ⑤ 時間や時節を過ぎる。年などを越す。 |
① -行幸の 山越す風の ひとり居る 我が衣手に 朝夕に 返らひぬれば-(万1-5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞サ行四段〕越えさせる。運ぶ。 | 大坂に継ぎ登れる石群を手越しに越さば越しかてむかも(崇神紀) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こす | 〔助動詞サ行下二型〕【コセ・〇・コス・〇・〇・コセ】《上代語》 [動詞「遣(おこ)す」の語頭の略とも] 他に対してあつらえ望む意を表す。~て欲しい。 〔接続〕動詞の連用形につく。 【参考】 他に対してあつらえ望む意を表す助詞「こそ」があるが、これを「こす」の命令形に加える説もある。 |
-自妻と 頼める今夜 秋の夜の 百夜の長さ ありこせぬかも(万4-549) 梅の花今咲けるごと散り過ぎず我が家の園にありこせぬかも[少貳小野大夫](万5-820) 霞立つ春日の里の梅の花山のあらしに散りこすなゆめ(万8-1441) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こせ [巨勢] | 〔地名〕奈良県御所市古瀬。紀伊や吉野への通路にあたる。 | 川の上のつらつら椿つらつらに見れども飽かず巨勢の春野は(万1-56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こせぢ [巨勢路] | 〔名詞〕 奈良県高市郡の西の地。飛鳥から巨勢を通って今の五條市に向かう道。 |
- 知らぬ国 寄し巨勢道より 我が国は 常世にならむ 図負へる- (万1-50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こせやま [巨勢山] | 〔地名〕奈良県高市郡の西部、巨勢の峡谷の東西の山地。 | 巨勢山のつらつら椿つらつらに見つつ偲はな巨勢の春野を(万1-54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻第一-54 こせやま」注】 「巨勢」は前に「巨勢道」(1・50)とあった地。巨勢氏の本貫。今、国鉄和歌山線と近鉄吉野線との交叉する吉野口駅のあるところ。 その地の山。交通の要衝で、紀伊への旅路には飛鳥を出て必ず通る地。 ここから今木峠を越えれば吉野、西南に重阪峠を越えれば宇智(ウチ) (1・3) に出て紀伊路に入る。ここで休憩があったのであろうか。 (「国鉄」⇒「JR」) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こそ | 〔係助詞〕他を否定して、一つの事物を強く指示する意を表わす。 ① 係り結び形式。文末に已然形の結びをとる。「~こそ」 ② 強調逆接表現。「こそ~已然形」の形が一文中に挿入されている場合は、已然形の部分で文が終止せず、逆接の条件句となってその事態を強調し、以下に続いていく。 「確かに~は~だが。~は~だけれども」 ③「未然形+ば+こそ~已然形」の形で、仮定条件を強め、逆接の条件句となって、その事態を強く否定して、以下に続いていく。 「ほんとうに~ならば~だが、~ではないのだから」 ④ 結びの流れ・消滅。 已然形で結ばれるはずの語に、「に・を・とも・ども・ば」などの接続助詞が付くと、逆接助詞の支配をうけて結びが流れ、条件句となって以下に続いていく。 また、已然形で結ばれるはずの語が、下の体言に引かれて連体形となり結びが消滅する場合もある。 ⑤ 結びの省略。 多く「にこそ」の形で、「こそ」が文末にある場合は、已然形の結びが省略されたもので、「あれ」「あらめ」などの語を補う。 ⑥「もこそ~已然形」の形で、懸念や不安を表す。 〔接続〕いろいろな語に付く。また複合動詞の間にも入る。 終助詞・間投助詞を除き、ほとんどの品詞に付く。 また主語、目的語、連用修飾語、接続表現などのほか、平安時代以降は、 「思ひこそ寄らざりつれ」(枕草子) のように、複合動詞の中間にも入る。 ただし、連体修飾語には付かない。 |
① -そらみつ 大和の国は おしなべて 我れこそ居れ しきなべて-(万1-1) ② -思ひ居れか 栲縄の 長き命を 露こそば 朝に置きて 夕には-(万2-217) ② 白菅の真野の榛原行くさ来さ君こそ見らめ真野の榛原(万3-284) ② 春の夜のやみはあやなし梅の花色こそ見えね香やはかくるる (古今春上-41) 〔語法〕例 ア:難波人葦火焚く屋の煤してあれどおのが妻こそ常めづらしき (万11-2659) -山高み 川とほしろし 野を広み 草こそ茂き 鮎走る- (万17-4035) イ:竜田姫たむくる神のあればこそ秋のこのはのぬさとちるらめ (古秋下-298) :はつかりのなきこそわたれ世の中の人のこころの秋しうければ (古恋五-804) ウ:昔こそ外にも見しか我妹子が奥つ城と思へばはしき佐保山(万3-477) :きのふこそさなへとりしかいつのまに稲葉そよぎて秋風のふく (古秋上-172) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔語法〕 この「こそ」を受けて終止する活用語は已然形で結ぶのが普通であるが、上代には、(ア)例のように形容詞の連体形で結んだものもある。 これは形容詞および形容詞型助動詞の活用が未発達で已然形がなかったためと考えられる。 また、(イ)のように、結びの語がさらに逆接の意味で下に続くものもあり、(ウ)は接続助詞を伴わない場合で、和歌など韻文では中世にまで見られる用法。 〔参考〕 「こそ」は「ぞ」よりも一段と強い意を表わすとされ、語源は指示語の「此其」であるといわれている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔終助詞〕他にあつらえ望む意を表わす。~て欲しい。~てくれ。 〔接続〕動詞の連用形に付く。 〔語法〕上代に限っての用法である。本来は係助詞の「こそ」であろうが、接続が動詞の連用形に限られるなど用法が狭く、終助詞と考えられる。 |
我が行きは久にはあらじ夢のわだ瀬にはならずて淵にもありこそ(万3-338) うつつには逢ふよしもなしぬばたまの夜の夢にを継ぎて見えこそ (万5-811) 鴬の待ちかてにせし梅が花散らずありこそ思ふ子がため[筑前拯門氏石足] (万5-849) 梅の花夢に語らくみやびたる花と我れ思ふ酒に浮かべこそ(万5-856) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔接尾語・間投助詞〕親愛の情をもって呼び掛ける意を表わす。~さんよ。 〔接続〕人名を表わす語に付く。 |
〔語法〕中古の用法。 一説に、間投助詞ともいう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -あらめ | 係助詞「こそ」にラ変動詞「あり」の未然形と推量の助動詞「む」の已然形の付いたもの。 逆接の意の条件を表わす。~よいだろうけども。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ありけれ | 係助詞「こそ」にラ変動詞「あり」の連用形と過去の助動詞「けり」の已然形の付いたもの。 ~するやいなや。 |
〔語法〕中古の末頃からの用法で、特に軍記物に多い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -あれ | 係助詞「こそ」にラ変動詞「あり」の已然形の付いたもの。 ①「こそかくあれ」「こそ多くあれ」の意をもって逆接の意の条件を表わす。 連用形と過去の助動詞「けり」の已然形の付いたもの。 「~するやいなや。」 ② 単なる逆接の意の条件を表わす。 ③ 単に強意を表わす。 |
① いまこそあれ我もむかしは男山さかゆく時もありしものなり (古雑上-889) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -なからめ | 係助詞「こそ」に、形容詞「なし」の未然形と、推量の助動詞「む」の已然形の付いたもの。 「~ではないあろうが」の意から、~ではないだろうが、それはそれとして、の意。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こぞ [去年・昨夜] | 〔名詞〕 ① (去年) 昨年。② (昨夜) ゆうべ。 |
① 去年見てし秋の月夜は照らせども相見し妹はいや年離る(万2-211) ② 下泣きに我が泣く妻を昨夜こそは安く肌触れ(記下) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こだかし [木高し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 こずえが高い。木の丈が高い。 |
妹として二人作りし我が山斎は木高く茂くなりにけるかも(万3-455) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こだち [木立] | 〔名詞〕木々が群がり立っているようす。 | 矢釣山木立も見えず降りまがふ[雪に騒ける朝楽しも](万3-264)下二句定訓なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こたふ [答ふ・応ふ] | 〔自動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 ① 返事をする。答える。② こだまする。反響する。 ③ 応じる。報いる。また、神などが感応する。④ 心に沁み通る。感じる。 ⑤ あいさつする。知らせる。 |
① -我が身にしあれば 道守が 問はむ答へを 言ひ遣らむ-(万4-546) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こだる [木垂る] | 〔自動詞ラ行四段〕 樹木が茂って枝が垂れる。 |
東の市の植木の木垂るまで逢はず久しみうべ恋ひにけり(万3-313) 薪伐る鎌倉山の木垂る木を松と汝が言はば恋ひつつやあらむ(万14-3452) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こちごち [此方此方] | 〔代名詞〕《上代語。指示代名詞》あちこち。あちらこちら。 | -堤に立てる 槻の木の こちごちの枝の 春の葉の 繁きがごとく-(万2-210) なまよみの 甲斐の国 うち寄する 駿河の国と こちごちの 国のみ中ゆ-(万3-322) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こちたし [言痛し・事痛し] | 〔形容詞ク活用〕(「こといたし」の転) 【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ①(人の口が) うるさい。わずらわしい。 ② 大袈裟である。仰々しい。ことごとしい。 ③ 甚だ多い。おびただしい。 |
① 秋の田の穂向きの寄れる片寄りに君に寄りなな言痛くありとも (万2-114) ① 人言を繁み言痛みおのが世にいまだ渡らぬ朝川渡る(万2-116) ① 人言はまこと言痛くなりぬともそこに障らむ我れにあらなくに (万12-2898) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こと [言] | 〔名詞〕 ① ことば。言語表現。② 人のうわさ。評判。③ 和歌 |
① -岡に立たして 歌思ひ 辞思ほしし み湯の上の 木群を見れば-(万3-325) ① 月草のうつろひ易く思へかも我が思ふ人の言も告げ来ぬ(万4-586) ② 秋の田の穂田の刈りばかか寄りあはばそこもか人の我を言なさむ(万4-515) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こと [事] | 〔名詞〕 ① 世の中に起こる事柄。現象。 ② 重大なできごと。大事。事件。 ③ 人のするいろいろな事柄。行為。動作。 ④ 仕事。任務。政務。⑤ 行事。儀式。⑥ 事情。わけ。意味。 ⑦ (用言及び助動詞の連体形の下に付いて) 動作・作用・状態を表わす名詞を作る。「~すること」「~であること」 ⑧ (文を止めて) 感動の意を表す。「~であることよ」「~だなあ」 |
① -天地に 悔しきことの 世間の 悔しきことは 天雲の-(万3-423) ③ -岩床と 川の氷凝り 寒き夜を 息むことなく 通ひつつ -(万1-79) ③ -我が待つ君が 事終り 帰り罷りて 夏の野の さ百合の花の- (万18-4140) ⑦ 東のたぎの御門に侍へど昨日も今日も召すこともなし(万2-184) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ごと [毎] | 〔接尾語〕~のたびに。毎~。どの~も。 |
玉葛実ならぬ木にはちはやぶる神ぞつくといふならぬ木ごとに (万2-101) -露霜の 置きてし来れば この道の 八十隈ごとに 万たび- (万2-131) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ごと [如] | (比況の助動詞「ごとし」の語幹 ①(連用修飾語となって)~のように。 ②(述語となって)~のようだ。 〔接続〕体言および副詞「かく・さ」に助詞「の」が付いたものや、活用語の連体形のおよび代名詞「我(わ)・吾(あ)」に助詞「が」が付いたものに付く。 |
① 秋さらば今も見るごと妻恋ひに鹿鳴かむ山ぞ高野原の上(万1-84) ① いにしへに恋ふらむ鳥は霍公鳥けだしや鳴きし我が念へるごと (万2-112) ① 古りにし嫗にしてやかくばかり恋に沈まむ手童のごと [恋をだに忍びかねてむ手童のごと](万2-129) ① -隠りのみ 恋ひつつあるに 渡る日の 暮れぬるがごと 照る月の-(万2-207) ① 聞きしごとまこと尊くくすしくも神さびをるかこれの水島(万3-246) ① 人言を繁み言痛み逢はざりき心あるごとな思ひ我が背子(万4-541) ② さ寝らくは玉の緒ばかり恋ふらくは富士の高嶺の鳴沢のごと (万14-3372) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 ①は「ごとし」の連用形「ごとく」と同じく連用修飾語を作るが、中古の和文調の文章では「ごとく」はあまり用いられず、語幹だけの「ごと」が多く用いられた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ーごと [-毎] | 〔接尾語〕[多く「に」を伴って] ① (名詞、動詞の連体形に付いて) ~たびに、いつも、の意を表す。 ② (名詞に付いて) それぞれ、みな、の意を表す。 |
① -太敷きいまし みあらかを 高知りまして 朝言に 御言問はさず-(万2-167) ① -みどり子の 乞ひ泣くごとに 取り与ふる 物しなければ-(万2-210) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ことごと [尽・悉] | 〔名詞〕 全部。すべて。 |
ひじりの御代ゆ [或云 宮ゆ] 生れましし 神のことごと 栂の木の(万1-29) 畑子らが夜昼といはず行く道を我れはことごと宮道にぞする(万2-193) -昼はも 日のことごと 夜はも 夜のことごと-(万2-204) -あかねさす 日のことごと 獣じもの い匍ひ伏しつつ ぬばたまの-(万2-199) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔副詞〕 ① ある限りすべて。残らず。 ② 完全に。まったく。 |
① 悔しかもかく知らませばあをによし国内ことごと見せましものを (万5-801) 【参考「あをによし」】 「万葉集」中、枕詞「あをによし」が「なら」ではなく「国内 (くぬち)」にかかる唯一の例。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ことさへく [言さへく] | 【枕詞】〔「さへく」はさえずるの意〕 外国のことばがわかりにくいことから、「百済(くだら)」「韓(から)」にかかる。 |
つのさはふ 石見の海の 言さへく 唐の崎なる 海石にぞ-(万2-135) -思ひも いまだ尽きねば 言さへく 百済の原ゆ-(万2-199) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ことさら [殊更] | 〔副詞〕 ① わざと。故意に。② とりわけ。ことに。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 ① 事改めてするさま。わざわざ。 ② とりわけ甚だしいさま。格別。特別。 |
① 出でて去なむ時しはあらむをことさらに妻恋しつつ立ちて去ぬべしや(万4-588) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ごとし [如し] | 〔助動詞ク型〕【○・ごとく・ごとし・ごとき・○・○】 ① ある事柄が他のある事柄と同じである意。~(と)同じだ。 ② ある事柄を他の似ている事柄に比べたとえる意を表わす。 「~(の)ようだ」「~に似ている」 ③(平安末期以降)多くの中からあるものを例示する意を表わす。 「たとえば~(の)ようだ」 |
① 岩屋戸に立てる松の木汝を見れば昔の人を相見るごとし(万3-312) ② -風の共 靡かふごとく 取り持てる 弓弭の騒き み雪降る-(万2-199) ② -槻の木の こちごちの枝の 春の葉の 繁きがごとく 思へりし-(万2-210) ② 世の中を何に喩へむ朝開き漕ぎ去にし船の跡なきごとし(万3-354) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔接続〕 活用語の連体形に直接、またはそれに助詞「が」の付いたものや、体言に助詞「の」「が」が付いたものに付く。 中世以降、体言にも直接付くようになった。 【参考】 平安時代には、「ごとし」と同じ意味を表わす語に、「やうなり」があり、「ごとし」は漢文調の文章で用いられ、「やうなり」は仮名で書かれた和文調の文章で用いられた。 「ごとくなり」も「ごとし」と同様に漢文調の文章で用いられたが、語幹にあたる「ごと」だけは別で、逆に、もっぱら和文調の文章に用いられた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こととふ [言問ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 ① ものを言う。話す。 ② (男女が求愛の言葉や歌を) 言いかける。 (親しい者どうしが) 声をかけて語り合う。 ③ 尋ねる。質問する。 ④ 訪問する。または、便りをする。 |
① - 験をなみと 言問はぬ ものにはあれど 我妹子が 入りにし山を-(万3-484) ① 言とはぬ木にもありとも我が背子が手馴れの御琴地に置かめやも(万5-816) ② -天雲の 外のみ見つつ 言問はむ よしのなければ 心のみ-(万4-549) ② 天地のいづれの神を祈らばか愛し母にまた言とはむ(万20-4416) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ことなし [事無し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① 何事もない。平穏無事である。 ② 面倒なことがない。容易である。 ③ 悪いところが無い。非難すべき点がない。 |
① 吉野川行く瀬の早みしましくも淀むことなくありこせぬかも (万2-119) ① - 妹がため 我も事なく 今も見るごと たぐひてもがも(万4-537) ③ 大君の御笠に縫へる有間菅ありつつ見れど事なき我妹(万11-2767) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻四-534 注『事なく』」】 「事ナシ」は、無事平穏、幸福である、の意。遊仙窟の古訓に「好去(コトムナシイネ)」(醍醐寺本) とあるのは、「コトモナシ」の転であろう。名義抄に「好、コトムナシ」とあるのも、右の遊仙窟からの採択かもしれない。名義抄にはその他にも「美、コトモナシ」 の例がある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ことなす [言成す] | 〔他動詞サ行四段〕 あれこれ噂をする。 |
秋の田の穂田の刈りばかか寄りあはばそこもか人の我を言なさむ(万4-515) 大和の宇陀の真埴のさ丹付かばそこもか人の我を言なさむ(万7-1380) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こども [子供・子等・児等] | 〔名詞〕[「ども」は複数を表す接尾語] ① 若い人々や、年下の人々を親しんで呼ぶ語。 ②(親に対して)子供。子供たち。 ③ 幼い子供。 【参考】 一人でも「こども」という場合もある。 |
① いざ子ども早く日本へ大伴の御津の浜松待ち恋ひぬらむ(万1-63) ② 瓜食めば 子ども思ほゆ 栗食めば まして偲はゆ いづくより- (万5-806) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ことよす [言寄す・事寄す] | 〔自動詞サ行下二段〕【セ・セ・ス・スル・スレ・セヨ】 ① ことばを添えて助ける。はからう。 ② かこつける。いいわけにする。 |
① -むせつつあるに 天地の 神言寄せて しきたへの 衣手交へて-(万4-549) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こぬれ [木末] | 〔名詞〕《上代語》[「このうれ」の転] こずえ。木の枝の先。 | むささびは木末求むとあしひきの山の猟夫にあひにけるかも(万3-269) み吉野の象山の際の木末にはここだも騒く鳥の声かも(万6-929) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この [此の] | 〔なりたち〕[代名詞「こ」+助詞「の」] ① [自分に最も近いものを指示する語] 「この」「ここの」 ② [話題となっているものを指示する語] 「この」 ③ [今に繋がる、ある期間を指示する語] 「それ以来、今日までの」 ④ [相手をしかりつける感じでいう語] 【参考】 文語では「こ」は代名詞で、「の」は格助詞。口語では「この」で、連体詞。 |
①-み篭持ち 堀串もよ み堀串持ち この岡に 菜摘ます子 家聞かな- (万1-1) ① 大和恋ひ寐の寝らえぬに心なくこの洲崎廻に鶴鳴くべしや(万1-71) ① 真木柱太き心はありしかどこの我が心鎮めかねつも(万2-190) ③ 朝日照る佐田の岡辺に泣く鳥の夜哭きかへらふこの年ころを(万2-192) ③ 秋立ちて幾日もあらねばこの寝ぬる朝明の風は手本寒しも(万8-1559) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このかた [此の方] | 〔名詞〕 ① こちらの方。こちら側。⇔「彼方 (をちかた)」 ② それ以後。それ以来。 |
① 見わたしに 妹らは立たし この方に 我れは立ちて-(万13-3313) ② かの御時よりこのかた、年は百年あまり、代は十継になむなりにける (古今仮名序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このごろ [此の頃] | 〔名詞〕[上代は「このころ」] ① この数日もの間。最近。近ごろ。② 近いうち。近日中。 ③ 今頃。今時分。 |
① たけばぬれたかねば長き妹が髪このころ見ぬに掻き入れつらむか [三方沙弥](万2-123) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このは [木の葉] | 〔名詞〕樹木の葉。特に紅葉や落葉。〔冬〕 | -草深み 取りても見ず 秋山の 木の葉を見ては 黄葉をば 取りてぞ偲ふ -(万1-16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このよ [此の世] | 〔名詞〕 ① 人の生きている世。現世。② 今の世の中。当代。現代。③ 世間。世の中。 |
① この世にし楽しくあらば来む世には虫に鳥にも我はなりなむ(万3-351) ① この世には人言繁し来む世にも逢はむ我が背子今ならずとも(万4-544) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こひ [恋(孤悲)] | 〔名詞〕 目の前にいない、人や事物を慕わしく思うこと。恋慕。 恋しく思うこと。心が惹かれること。恋愛。 |
玉葛花のみ咲きてならざるは誰が恋ならめ我は恋ひ思ふを(万2-102) 古りにし嫗にしてやかくばかり恋に沈まむ手童のごと [恋をだに忍びかねてむ手童のごと](万2-129) 丹生の川瀬は渡らずてゆくゆくと恋痛し我が背いで通ひ来ね(万2-130) 明日香川川淀去らず立つ霧の思ひ過ぐべき恋にあらなくに(万3-328) 事もなく生き来しものを老いなみにかかる恋にも我はあへるかも(万4-562) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考 古語の「恋」】 「恋」は現代語では異性間の感情に使われるのが普通であるが、古語では、広く、人や事物に対して慕わしく思う気持ちを表す。 そして自分の求める人や事物が自分の手中にある時は「恋」の思いとならず、手中にしたいという思いが叶えられず、強くそれを願う切ない気持ちが恋なのである。 そのため古語の「恋」は、現代語の「恋慕」に近い意味を表している。 その意味からいって、古語の「恋」は喜びにはならず、悲しさ、苦しさ、涙などと結びつく思いであった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こひく [恋ひ来] | 〔自動詞カ行変格活用〕【コ・キ・ク・クル・クレ・コヨ】 恋しい思いを抱きながら来る。 |
天離る鄙の長道ゆ恋ひ来れば明石の門より大和島見ゆ [一本云 家のあたり見ゆ](万3-256) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こひし [恋し] | 〔形容詞シク活用〕【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 〔古くは「こほし」とも〕恋しい。慕わしい。なつかしい。 |
稲日野も行き過ぎかてに思へれば心恋しき加古の島見ゆ [一云 水門見ゆ](万3-254) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こひのむ [乞ひ祈む・請ひ祈む] | 〔他動詞マ行四段〕 神仏に願い祈る。祈願する。 |
-平けく ま幸くませと 天地の 神を乞ひ祷み いかにあらむ-(万3-446) 我が背子しかくし聞こさば天地の神を乞ひ祷み長くとぞ思ふ(万20-4523) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こひわたる [恋ひ渡る] | 〔自動詞ラ行四段〕恋い慕いつづける。 | ひさかたの天知らしぬる君故に日月も知らず恋ひわたるかも(万2-200) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こふ [乞ふ・請ふ] | 〔他動詞ハ行四段〕 ① 求める。ねだる。望む。② 神仏に祈願する。 |
① -みどり子の 乞ひ泣くごとに 取り与ふる 物しなければ 男じもの-(万2-210) ② 天地の神を祈ひつつ我れ待たむ早来ませ君待たば苦しも(万15-3704) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こふ [恋ふ] | 〔他ハ行上二段〕【ヒ・ヒ・フ・フル・フレ・ヒヨ】 ① 思い慕う。懐かしく思う。 ②(異性を)恋しく思う。恋慕する。 |
① 旅にしてもの恋ほしきに鶴が音も聞こえざりせば恋ひて死なまし (万1-67) ① 大和恋ひ寐の寝らえぬに心なくこの洲崎廻に鶴鳴くべしや(万1-71) ① 否と言へど強ふる志斐のが強ひ語りこのころ聞かずて朕恋ひにけり(万3-237) ① 人言を繁みと妹に逢はずして心のうちに恋ふるこのころ(万12-2956) ② かくばかり恋ひつつあらずは高山の磐根しまきて死なましものを (万2-86) ② ますらをや片恋せむと嘆けども醜のますらをなほ恋ひにけり(万2-117) ② 嘆きつつますらをのこの恋ふれこそ我が結ふ髪の漬ちてぬれけれ (万2-118) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こまくら [木枕] | 〔名詞〕木製の枕。 | 家に来て我が屋を見れば玉床の外に向きけり妹が木枕(万2-216) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こまつ [小松] | 〔名詞〕小さな松。 |
後見むと君が結べる磐代の小松がうれをまたも見むかも(万2-146) 妹が名は千代に流れむ姫島の小松がうれに蘿生すまでに(万2-228) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【参考】 平安時代、正月の最初の子(ね)の日に、野で若菜を摘み小松を引き抜いて長寿を祈る行事が行われた。これを「小松引き」または「子の日の遊び」という。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こまつるぎ [高麗剣] | 【枕詞】柄に環(わ)があることから「わ」にかかる。 | -高麗剣 和射見が原の 仮宮に 天降りいまして 天の下-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こむよ [来む世] | 〔名詞〕来世。死後の世界。後世(ごせ)。 | この世にし楽しくあらば来む世には虫に鳥にも我はなりなむ(万3-351) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こむら [木叢・木群] | 〔名詞〕木の群がり生えているところ。 | -岡に立たして 歌思ひ 辞思ほしし み湯の上の 木群を見れば -(万3-325) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こも [菰・薦] | 〔名詞〕 ① 植物の名。まこも。イネ科で、水辺に群生する。 ② 粗く織ったむしろ。もと、まこもで作ったことから。こもむしろ。 |
① 三島江の玉江の薦を標めしより己がとぞ思ふいまだ刈らねど (万7-1352) ②-小屋の醜屋に かき棄てむ 破れ薦を敷きて 打ち折らむ- (万13-3284) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こもり [隠り・籠り] | 〔名詞〕 ① 隠れること。こもること。 ② 社寺に泊まり込んで祈ること。おこもり。参籠(さんろう)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こもりえり [隠り江] | 〔名詞〕島や岬の陰に隠れたりして見えない入り江。 | 三津の崎波を恐み隠り江の舟公宣奴嶋尓(万3-250) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こもりくの [隠りくの] | 【枕詞】[「隠りく」は山に囲まれた所の意] 地名「泊瀬 (はつせ)」にかかる。 | -さ丹つらふ 我が大君は こもりくの 初瀬の山に 神さびに-(万3-423) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こもりぬ [隠り沼] | 〔名詞〕 草などが茂って、隠れて見えない沼。また、水が流れ出る口のない沼。 和歌でやり場のない鬱々とした心情にたとえる。 |
あぢの棲む須沙の入江の隠り沼のあな息づかし見ず久にして(万14-3569) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こもりぬの [隠り沼の] | 【枕詞】「隠り沼」が草などの下にあって見えないことから、「下」にかかる。 | 隠り沼の下に恋ふれば飽き足らず人に語りつ忌むべきものを(万11-2728) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こもる [籠る・隠る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 囲まれている。中にはいっている。② 隠れる。ひそむ。③ 閉じこもる。 ④ 神社や寺に泊まって祈る。参籠する。 |
① 「倭は国のまほろばたたなづく青垣山こもれる倭しうるはし」(記中) ① 我が背子が着せる衣の針目落ちずこもりにけらし我が心さへ(万4-517) ② 春日野は今日はな焼きそ若草のつまもこもれり我もこもれり(古今春上-17) ③ 二上の峰の上の茂に隠りにしその霍公鳥待てど来鳴かず(万19-4263) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こやがけ [小屋掛け] | 〔名詞〕芝居などの仮小屋をつくること。また、その仮小屋。 | 処女を過ぎて夏草の茂る野島の埼で小屋がけして泊っているよ我々は(万3-251左注) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こやす [臥やす] | 〔自動詞サ行四段〕《上代語》「臥(こ)ゆ」 の尊敬語。 おやすみになる。横におなりになる。 |
-立たせば 玉藻のもころ 臥やせば 川藻のごとく なびかひの-(万2-196) -波の音の 騒く港の 奥城に 妹が臥やせる 遠き代に-(万9-1811) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こゆ [臥ゆ] | 〔自動詞ヤ行上二段〕【イ・イ・ユ・ユル・ユレ・イヨ】《上代語》 伏す。横になる。 【参考】 「こいふす・こいまろぶ」 などの複合動詞として使われる。 四段活用と考える立場もある。 |
-うち靡き 床に臥い伏し 痛けくの 日に異に増せば 悲しけく-(万17-3984) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こゆ [越ゆ・超ゆ] | 〔自動詞ヤ行下二段〕【エ・エ・ユ・ユル・ユレ・エヨ】 ① (ある場所・境界・障害物・時点などを) 越える。通り過ぎる。 ② (水準・程度・限度などを) 越える。上回る。まさる。 ③ (官位などが) 上になる。 |
①-そらにみつ 大和を置きて あをによし 奈良山を越え-(万1-29) ① ふたり行けど行き過ぎがたき秋山をいかにか君がひとり越ゆらむ (万2-106) ①-坂鳥の 朝越えまして 玉限る 夕去り来れば み雪降る -(万1-45) ① 大和には鳴きてか来らむ呼子鳥象の中山呼びぞ越ゆなる(万1-70) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こよひ [今宵] | 〔名詞〕 ① 今夜。今晩。② (夜が明けてから) 前日の夜のこという。昨夜。昨晩。 |
① 海神の豊旗雲に入日みし今夜の月夜さやけくありこそこ(万1-15) ① 衣手の別る今夜ゆ妹も我もいたく恋ひむな逢ふよしをなみ(万4-511) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 古くは日没から一日が始まると考えられていたので、②のように、夜が明けた後、昨夜のことをいった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こら [子等・児等] | 〔名詞〕[「ら」は接尾語] ① 子供たち。② 人、特に女性を親しみ呼ぶ語。 |
① すべもなく苦しくあれば出で走り去ななと思へどこらに障りぬ(万5-904) ② -思ひ恋ふらむ 時ならず 過ぎにし子らが 朝露のごと 夕霧のごと(万2-217) ② 楽浪の志賀津の児らが [一云 志賀の津の児が] 罷り道の川瀬の道を見ればさぶしも (万2-218) ② 焼津辺に我が行きしかば駿河なる阿倍の市道に逢ひし子らはも(万3-287) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こる (ここる) [凝る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 寄り集まる。密集する。固まる。② 凍る。③ 深く思い込む。熱中する。 |
②-夜の霜降り 岩床と 川の氷凝り 寒き夜を-(万1-79) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こる [懲る] | 〔自動詞ラ行上二段〕【リ・リ・ル・ルル・ルレ・リヨ】 こりる。 |
我が宿に韓藍蒔き生ほし枯れぬとも懲りずてまたも蒔かむとそ思ふ(万3-387) 頼めつつあはで年ふるいつはりにこりぬ心を人は知らなむ(古今恋二-614) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こる [伐る・樵る](きる) | 〔他動詞ラ行四段〕木を切る。伐採する。 | とぶさ立て足柄山に船木伐り木に伐り行きつあたら船木を(万3-394) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これ [此・是・之] | 〔代名詞〕 ① 近称の指示代名詞。話し手に近い事物・場所などをさす。 ア:事物をさす。このもの。このこと。 イ:場所をさす。ここ。 ウ:時をさす。今。この時。 エ:すぐ前に話題となったものをさす。 ② 人代名詞。 ア:自称。私。 イ:対称。(「こちらの方」の意から転じて)あなた。 ウ:近称。この人。 ③ (漢文の助字「之」「是」などを「これ」と訓読したことから) 漢文訓読体の文章で、語調を整え、または強める語。 〔感動詞〕 人に呼び掛けて注意を促すときの語。おい。もし。これこれ。 |
① ア:あしひきの山行きしかば山人の我れに得しめし山づとぞこれ(万20-4317) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これの [此の] | 〔代名詞〕[「此の人」の略。] 自分の配偶者を指していう。わが夫。わが妻。【類語 此方(こち)の人】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔指示代名詞「これ」+格助詞「の」〕この。 | 聞きしごとまこと尊くくすしくも神さびをるかこれの水島(万3-246) 草枕旅の丸寝の紐絶えば我が手と付けろこれの針持し(万20-4444) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これやこの [此や此の] | 〔慣用句〕 これがまあ(あの~か)。 【想い抱いているまだ見ていないものを眼前にしたときの感動の表現】 [「新編日本古典文学全集万葉集」35番頭注] 「あのかねて聞いていた~だったのか」 [「全注」] 「や」は疑問的詠嘆。 |
これやこの大和にしては我が恋ふる紀路にありといふ名に負ふ背の山 (万1-35) これやこの名に負ふ鳴門のうづ潮に玉藻刈るとふ海人娘子ども (万15-3660) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ころ [頃] | 〔名詞〕 ① おおよその時をいう語。その前後。時分。② 時節。季節。 ③ 適当な大きさや程度。 ④ 年、月、日などの下に付いて、数~間も、何~もの間の意を表す。 |
① 春日野の山辺の道をおそりなく通ひし君が見えぬころかも(万4-521) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ころふすきみが [ころ臥すきみが] | -枕になして 荒床に ころ臥す君が 家知らば 行きても告げむ -(万2-220) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集注釈巻二-220」 注『ころ伏す君が』】 「自伏君之」は旧訓コロフスキミカ。山田孝雄『万葉集考叢』に、コロブスという語は古今を通じ例の見られない語であり、一九六歌の「立者 玉藻之如許呂 臥者・・・」の誤読から「許呂臥」をコロブスと訓む訓は生まれたのであろうとし、ヨリフスの訓を提示した。新考にはこの山田説を承け、コロブスを否定した上で、「自」を「臥」の誤字としてコイフスと読んでいる。 この山田説には二つの問題がある。すなわち、一九六歌の本文を「玉藻之如許呂」としている点(金澤本によれば玉藻之母許呂)と、ヨリフスのヨの甲乙の別とである。 大野晋「奈良朝語訓釈断片」(国文学昭和二十六年九月)に、出自を示すヨリのヨは甲類、「寄り」のヨは乙類であって、仮名違いなので、山田説は成り立たないという。 そして倭訓栞、大言海に独立することをコロタツ、孤立の旗をコロタツなどという例のあること、成実論天長点に、「如黒白牛自不相繋倶以縄繋」とあり、自をコロトと訓んでいることをあげ、自分自身、あるいは独りを意味するコロという語があるので、「自伏」はコロフスと訓むのが正しく、「みずから一人で伏す」意に解されると説いている。緻密な考察で肯定されると思う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ころも [衣] | 〔名詞〕 ① 衣服。着物。② 僧の着る法衣。僧服。 【参考】 平安時代の仮名文では、衣服のことを言うときは普通「きぬ」を使い、「ころも」は①の意味の歌語や②の意味で用いられた。 |
① 春過ぎて夏来るらし白栲の衣干したり天の香具山(万1-28) ① -玉鉾の 道来る人の 泣く涙 小雨に降れば 白たへの 衣ひづちて-(万2-230) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ころもで [衣手] | 〔名詞〕 「袖」の歌語。転じて上衣そのものを指すことも多い。 当時男女とも、筒袖の服を着用し、袖丈が手よりも長いことがあった。 |
-ひとり居る 我が衣手に 朝夕に 返らひぬれば-(万1-5) -ただひとりして 白たへの 衣手干さず 嘆きつつ 我が泣く涙-(万3-463) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ころもでの [衣手の] | 【枕詞】 袖が風にひるがえる意から「かへる」、神の縁の手(た)から「田上 (たなかみ)に、 その他「別る」「別 (わ)く」「真若 (まわか)」「名木 (なき)」などにかかる。 |
-早川の 行きも知らず 衣手の 帰りも知らず 馬じもの -(万13-3290) -石走る 近江の国の 衣手の 田上山の 真木さく-(万1-50) 衣手の別かる今夜ゆ妹も我れもいたく恋ひむな逢ふよしをなみ(万4-511) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ころもでを [衣手を] | 【枕詞】 布を織ることから「をり」、砧で打つことから「うつ」、衣を敷くことから「敷津」 手から「た」音のある「たか」にかかる。 |
-門に寄り立ち 衣手を 折り返しつつ 夕されば 床打ち払ひ-(万17-3984) 衣手を打廻の里にある我を知らにそ人は待てど来ずける(万4-592) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こゑ [声] | 〔名詞〕 ① 人の声や動物の鳴き声。② 物の立てる音。③ 鐘や楽器の音色。 ④ 発音。アクセント。 ⑤ (「訓」 に対して) 漢字の音(おん)。字音。 |
① -玉たすき 畝傍の山に 鳴く鳥の 声も聞こえず 玉桙の 道行き人も-(万2-207) ① -朝なぎに 水手の声呼び 夕なぎに 楫の音しつつ 波の上を-(万4-512) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さ | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さ- | 〔接頭語〕 ① (名詞・動詞・形容詞に付いて)語調を整えたり意味を強める。 ②(名詞に付いて)「若々しい」に意を添える。上代の地方行政の区。 参考 ①には「小」、②には「早」を当てることがある |
① 佐保川にさわける千鳥さ夜更けて汝が声聞けば寐ねかてなくに (万7-1128) ① 我が背子を大和へ遣るとさ夜更けて暁露に我が立ち濡れし(万2-105) ② 石走る垂水の上のさわらびの萌え出づる春になりにけるかも(万8-1422) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -さ | 〔接尾語〕 ①(形容詞の語幹〔シク活用は終止形〕、形容動詞の語幹付いて) 程度・状態の意を表す名詞を作る。 ②(「~の~さ」・「~が~さ」の形で文末に付いて) 感動の意を表す。~ことよ ③(移動性の意を持つ動詞の終止形に付いて)「~とき」「~場合」の意の名詞を作る。 ④(名詞に付いて)「~の方向」の意の名詞を作る。 参考 ④には「様」を当てることがある。 |
①【例語】いみじさ・かなしさ・口惜しさ・心もとなさ・尊さ・つれなさ ① 筑紫船いまだも来ねばあらかじめ荒ぶる君を見るが悲しさ(万4-559) ② 酒の名を聖と負せし古の大き聖の言の宣しさ(万3-342) ② 大君の御笠の山の帯にせる細谷川の音のさやけさ(万7-1106) 畳薦牟良自が礒の離磯の母を離れて行くが悲しさ(万20-4362) ③ 帰 るさに妹に見せむにわたつみの沖つ白玉拾ひて行かな(万15-3636) 【例語】あふさきるさ・来(く)さ・行くさ・・・ ④ 縦さにもかにも横さも奴とぞ我れはありける主の殿戸に(万18-4156) 【例語】逆さ・・・ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さ | 〔代名詞〕他称の人名代名詞。そいつ。 | 参考 格助詞「が」を伴って「さが」の形で用いられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さ [然] | 〔副詞〕(前述されたことをさして)そう。その通りに。そのように。 | 参考 上代では、一般に「然(しか)」が用いられた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さえだ [小枝] | 〔名詞〕[「さ」は接頭語] 木の枝。また、小枝。 | この夕柘の小枝の流れ来ば梁は打たずて取らずかもあらむ(万3-389) 八千種の花は移ろふ常盤なる松のさ枝を我れは結ばな(万20-4525) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さか [坂] | 〔名詞〕 傾斜している道。さか。 |
百足らず八十隈坂に手向せば過ぎにし人にけだし逢はむかも(万3-430) 坂越えて安倍の田の面に居る鶴のともしき君は明日さへもがも(万14-3544) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さかえ [栄え] | 〔名詞〕繁栄。栄華。 | はしきやし栄えし君のいましせば昨日も今日も我を召さましを(万3-457) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さかき [榊・賢木] | 〔名詞〕 ① 常緑樹の総称。ときわ木。特に神事に用いる木。 ② ツバキ科の常緑樹の名。枝葉を神事に用いる。 |
② -神の命 奥山の さかきの枝に しらか付け 木綿取り付けて -(万3-382) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-379 注『賢木』」】 サカキと言えば今日つばき科の常緑樹をさして言う。私は昔もそうだったと考える。しかし、昔、内宮神官、荒木田久老の槻落葉別記に西村重波が神楽歌の榊に「榊葉の香をかぐはしみ」 とあり、新古今第十九に「榊葉の香」 とあることなどを挙げて、今の榊には葉に香気なき事を疑い、昔のサカキは樒(しきみ)であろうと述べ、樒は倭名抄(巻十) に「香木也」 とあり、外宮の神事に用いられた花賢木(はなさかき)は樒であった、と述べたことから、現代では、昔は今の榊であったとは言えない、だからそのサカキの名の如く、「栄木(さかき)」 すなわち常緑樹でありさえすれば何の木でもよかった、というように思考がエスカレートしている場合も多い。その根本はやはり、「榊葉の 香(か)をかぐはしみ 求めくれば 八十氏人ぞ 円居せりける 円居せりける」(神楽歌、採物、榊、二) 及び「おく霜に色も変わらぬ榊葉の香(か)をやは人のとめてきつらむ」(新古今集19・一八六九、神楽をよみ侍りける、紀貫之) の二例に見える、榊葉の香りに対する疑問にある。確かに今日、玉串奉奠(たまぐしほうてん) において経験する限り、榊葉の香りはない。しかし、五月の開花期の榊はまことに微妙なそしてよい香りがするのである。それならば、上掲の二首は初夏の榊葉の歌で、臭覚的な「香」りを指して言ったものかというと、そうとは思えない。それならばいかなる「香」 であり、また、「かぐはし」 であるのか。ここで注意されるのは、いずれも神楽歌の採物としての榊葉であるということである。そのことは、榊葉が、紀貫之の歌にもあるように、「おく霜に色も変わらぬ榊葉」 で、霜枯れせぬ常緑の葉であることが必要である。だから神の依りましとなる。それならば椿の葉でもよいではないかとの疑問が生じる。しかし、椿は花が大きく、花の咲く時と花の無い時との差があり過ぎて、神楽の採物としては四季を通じての安定性に欠けると思われる。その点榊は花が咲くことさえ知らぬ人が多いように、花は小さく、したがって四季を通じて常緑の葉のみという印象で用いることができる。この点を私をして、サカキは榊だと決定させるのである。そこで「香」 「かぐはし」 の問題に移ると、神が依りましたところの榊葉に対して、神の気(け) を「香(か)」 と認識し、それが揺曳(ようえい) することを「かぐはし」 と表現したもの(次の「しらか付く」参照) と考える。さて、前者の歌は、その香りを求めてくると、神楽の席にたくさんの氏子たちがいた、というのである。榊につられて深山に来ると山人がいたという歌ではなかったのである。斎宮の忌詞(いみことば) を始めとして、日本では神事と仏事とを厳に区別しており、まして神の宿る木として用いる種類が「梻(しきみ)」 だとか、いや常緑樹でありさえすればよい――「常緑」 でなければならぬことは、上掲の「おく霜に色もかわらぬ」(新古今集) がよく示している――とか言うものではなかったのである。伊勢神宮の式年遷宮の記録によると、「前山(まえやま)」 という山が「榊の山」 で、榊が栽培されていて、厳重に監視されたことが分かる。神事というものはかくの如くして守られるのである。ただし榊が産出する地域であるのに、それを用いない神社がある理由は不明。さて、、『新撰字鏡』に榊・〇[木偏+祀]・椗・杜・龍眼をサカキと訓む。上二字は国字。第三字は「碇」 の俗字で、香木の名。これによると、「榊」 が香りをもつ木であるとも言える。第四字は神の宿る「森」 の意(義訓である) を、さらにサカキ(神の宿る木であるから) と義訓したものである。第五の龍眼は茘枝(れいし) とともに霊木の一つであったので、日本でサカキと訓まれたものか。いずれにしても、サカキは国産の椿科の植物で神事にのみ用いられた木であったので、国字が作られ、また「賢木・坂木」 などの発音に基づく表記が用いられたものと考えてよい。「奥山の賢木」 というのは人里離れて俗塵に染まぬ清浄性を表している。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さかし [賢し] | 〔形容詞シク活用〕 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 ① かしこい。才知がある。② 上手だ。優れている。 ③ 気丈である。しっかりしている。分別がある。判断力がある。 ④ こざかしい。りこうぶっている。なまいきである。⑤ 知識がある。 ⑥ さかんである。めでたい。 |
① 古の七の賢しき人たちも欲りせしものは酒にしあるらし(万3-343) ④ 賢しみと物言ふよりは酒飲みて酔ひ泣きするし優りたるらし(万3-344) 「さかしみ」の「み」はミ語法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】「さかし」と「かしこし」との違い ともに、知能の働きのすぐれている意を表すが、「かしこし」は、多くすばらしいという畏敬の念をもって使われ、「さかし」は、知能の働きが顕著にあらわれていることへの畏怖の念をもっていう場合に使われ、反発する感じを伴って用いることがある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さがし [険し・嶮し] | 〔形容詞シク活用〕 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 ① (山などが) 険しい。② あぶない。危険である。 |
霰降り吉志美が岳を険しみと草取りかなわ妹が手を取る(万3-388) 「さがしみ」の「み」はミ語法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さかしら [賢しら] | 〔名詞・形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 [「ら」は接尾語]さかし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① りこうぶること。 ② 差し出がましいことをするさま。出しゃばるさま。おせっかい。 ③ 人をおとしいれるための告げ口。讒言。 |
① あな醜賢しらをすと酒飲まぬ人をよく見ば猿にかも似る(万3-347) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さかつぼになりにてしかも [酒壺になりにてしかも] |
なかなかに人とあらずは酒壷に成りにてしかも酒に染みなむ(万3-346) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-343 注『酒壺になりにてしかも』」】 「壺」は「都保須美礼(ツホスミレ)」(8・一四四四) や「壺、都符(ツフ)」(敏達紀十三年訓注) の例から「ツホ」と清音であった。「にてしかも」 の「に」 は完了の助動詞「ヌ」 の連用形。 「テシカ」 の「テ」 は完了の助動詞「ツ」 の連用形「テ」 に、回想の助動詞「キ」 の已然形「シカ」 の付いた形。 浜田敦は「この『しか』、『てしか』の『しか』を以て、『まし』の已然形『ましか』に対して同形の未然形『ましか』の存在すると同様、已然形『しか』と同形の未然形を考へる事によつて、これが『さうなつてゐたら』の如き意となり云々」 として願望表現になったと説明している(「上代に於ける願望表現について」国語と国文学昭和二十三年二月)。 この「テシカ」 が平安時代以後「テシガ」 と濁音になり、「シ」は回想の助動詞「キ」 の連体形、「ガ」 は願望の助詞とみられるようになった。 ともかく奈良時代には「テシカ」 の語形で、全体で願望の意の終助詞に用いられた。 「モ」 は詠嘆の助詞。さて、この「酒壺になりにてしかも酒に染みなむ」 は、山田孝雄の「琱玉集(ちょうぎょくしゅう)と本邦文学」(芸文大正十三年十一月) により、漢籍に見えた逸話に由来することが明らかになった。すなわち『琱玉集』(巻十四) 嗜酒篇第五に、鄭泉(ていせん) という酒好きの男がその遺言として「我死ナバ竈(かまど)ノ側ニ埋ムベシ。数百年ノ後ニ、化シテ土ト成リ、願ハクハ酒瓶ニ為(つく)ラレ、心願を獲ム」 と言ったという。そして、この文の末尾に「呉書ニ出ヅ」 とある。 また、『呉志』を検するに、巻二、黄武元年十二月の条に鄭泉の記事があり、その割注に「呉書ニ曰ク」 として、その博学嗜酒のさまを叙し、その後半に「泉卒スルニ臨ミテ同類ニ謂テ曰ク『必ズ我ヲ陶家ノ側ニ葬レ。庶(ねが)ハクハ百歳ノ後ニ化シテ土ト成リ、幸ニ取ラレテ酒壺ト為(な)ラバ、実ニ我ガ心ヲ獲ム』トイフ」 とある。 さらにもう一つの文献にも鄭泉の話が載せられている。 それは、『芸文類聚』巻二十六、人部、言志に『呉書』として掲載するが、しかし博学嗜酒のさまを叙しながら、肝腎の遺言の箇条が無いのである。 これ以外にも鄭泉の話を載せる文献があったかも知れないが、もし上述の三文献が存在した場合、旅人はどの文献の教養によるものであろうか。 山田孝雄は『呉志』は神護景雲三年(769) に大宰府の学府に賜ったのだから、旅人が帥であったのはこれより三、四十年も前のことであり、旅人が『呉志』を見たということは疑わしいとして、『琱玉集』に依ったものとした。しかし、『呉志』は養老四年(720) 成立の日本書紀の潤色に用いられている(小島憲之『上代日本文学と中国文学』上)。 したがって、旅人は帥着任以前に『呉志』を読むことができたはずである。その上で、旅人が「酒壺」 という語を用いている点に着目すると、『琱玉集』には「呉書ニ出ヅ」とありながら、「酒瓶」 とあるのに対して、『呉志』引用の『呉書』には「酒壺」とあるから、やはり旅人の直接の出典は『呉志』とみるべきではなかろうか。 かつまた『芸文類聚』ではないことは、「酒瓶」も「酒壺」 も引用されていないことによって、分かる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さかどりの [坂鳥の] | 【枕詞】「坂鳥」は早朝、山を越えて飛ぶ鳥。そこから「朝越ゆ」にかかる。 | -岩が根 禁樹押しなべ 坂鳥の 朝越えまして 玉限る-(万1-45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さかゆ [栄ゆ] | 〔自動詞ヤ行下二段〕【エ・エ・ユ・ユル・ユレ・エヨ】 繁栄する。また、繁茂する。 |
我が御門千代とことばに栄えむと思ひてありし我れし悲しも(万2-183) -木綿花の 栄ゆる時に 我が大君 皇子の御門を-(万2-199) -鮎子さ走り いや日異に 栄ゆる時に 逆言の 狂言とかも 白たへに-(万3-478) 御民我れ生ける験あり天地の栄ゆる時にあへらく思へば(万6-1001) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さがらかやま [相楽山] | 〔山名〕京都府相楽(そうらく)郡の山々の総称か、あるいは同郡木津町相楽(さがらか) の地の山か。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さかり [盛り] | 〔名詞・形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 ① 活動力や勢いが盛んなさま。栄えているさま。また、その時期。 ② 人間として充実している時期。若い盛り。男盛り。女盛り。 |
① あをによし奈良の都は咲く花の薫ふがごとく今盛りなり(万3-331) ① -夏の盛りと 島つ鳥 鵜養が伴は 行く川の 清き瀬ごとに-(万17-4035) ② 我が盛りまたをちめやもほとほとに奈良の都を見ずかなりなむ(万3-334) ② 我が盛りいたくくたちぬ雲に飛ぶ薬食むともまた変若めやも(万5-851) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さかる [離る] | 〔自動詞ラ行四段〕(対象から自然に) 遠く離れる。遠ざかる。 | -万たび かへり見すれど いや遠に 里は離りぬ-(万2-131) 北山にたなびく雲の青雲の星離り行き月を離れて(万2-161) 去年見てし秋の月夜は照らせども相見し妹はいや年離る(万2-211) 我が船は比良の湊に漕ぎ泊てむ沖辺な離りさ夜ふけにけり(万3-276) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さき [先・前] | 〔名詞〕 ① 先端。端。末端。② 先頭。前。先陣。③ 第一。上位。 ④ 前途。将来。⑤ 以前。過去。 ⑥「先追ひ」「先払ひ」の略。 貴人の外出のとき、道の前方にいる人々を追い払うこと。また、それをする人。 |
① 綜麻形の林のさきのさ野榛の衣に付くなす目につく吾が背(万1-19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さき [幸] | 〔名詞〕栄えていること。さいわい。幸福。 | 大夫の心思ほゆ大君の御言の幸を[一云 の]聞けば貴み [一云 貴くしあれば] (万18-4119) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さき [崎] | 〔名詞〕 ① 山・丘が平地に突き出た部分。 ② 山・丘などの海や湖に突き出た部分。岬。 |
① 玉釧まき寝し妹を月も経ず置きてや越えむこの山の崎(万12-3162) ② 磯の崎漕ぎ廻み行けば近江の海八十の港に鶴さはに鳴く(万3-275) ② 島伝ひ敏馬の崎を漕ぎ廻れば大和恋しく鶴さはに鳴く(万3-392) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さきく [幸く] | 〔副詞〕無事に。しあわせに。変わりなく。 | 我が背子は幸くいますと帰り来と我れに告げ来む人も来ぬかも (万11-2388) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さく [咲く] | 〔自動詞カ行四段〕 ① 花が開く。 ② (波頭の白いのを花にたとえて) 波が立つ。 |
① -鳥も来鳴きぬ 咲かざりし 花も咲けれど 山を茂み -(万1-16) ① 我妹子に恋ひつつあらずは秋萩の咲きて散りぬる花にあらましを(万2-120) ② 今替る新防人が船出する海原の上に波なさきそね(万20-4359) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さく [放く・離く] | 〔他動詞カ行四段〕放つ。遠くへやる。 | 行くさには二人我が見しこの崎をひとり過ぐれば心悲しも [一に云ふ 見もさかず来ぬ](万3-453) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さく [放く・離く] | 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 ① 離す。放つ。② 仲をへだてる。引き離す。 ③ (動詞の連用形に付いて) ~して思いを晴らす。 ④ (「見さく」の形で) 遠く見やる。 |
③ -語り放け 見放くる人目 乏しみと 思ひし繁し そこゆゑに-(万19-4178) ④ -しばしばも 見放けむ山を 心なく 雲の 隠さふべしや(万1-17) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さぐくむ | 【有斐閣「萬葉集全注巻第四-509 注『さぐくむ』」】 -「サグクム」は波を押し分けて進む意か。「岩根さくみて なづみ来し」(2・二一〇) などと見える。山・岩根を越えて行く行く意の「サクム」と同源かという。 【中央公論社「萬葉集注釈巻第四-509 訓釋『さぐくみ』」】 「さぐくみ」は 「岩根さくみて」(2・二一〇) の「さくみ」と同意の語と云はれてゐる。全註釈には「さくみ」 は山、岩根に就いて云ひ、「さぐくみ」 は「奈美乃間乎(ナミノマヲ) 伊由伎佐具久美(イユキサグクミ)」(20・四三三一) と、波に就いていふから、「一往別語として取り扱ふべきである」 と云はれてゐる。巻廿のは家持が今の作を踏襲したと見るべきもので、必ずしも石と水とによつて区別さるべきものとまで考へるに及ばないであらう。「さくみ」 と「さぐくみ」 とは、「ひぢ」(2・一一八) と「ひづち」(2・一九四) との関係にも似た類似語と見るべきであらう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さぐめ [探女] | 〔名詞〕 | ひさかたの天の探女が石船の泊てし高津はあせにけるかも(万3-295) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-292 注『天の探女が』」】 原文「天之探女之」とある。「天之」はアメノともアマノとも訓めるが、神代紀下の「天探女、此云/阿麻能左愚謎(アマノサグメ)」によってアマノと訓む。 ただし記ではその表記の原則によってアメノと訓むので、今の訓みの参考にはならない。天の探女は記紀にその物語を載せるが、『続歌林良材集』上には「津國風土記に云、難波高津は天稚彦天下りし時天稚彦に属て下れる神天の探女磐舟に乗して爰に至る。天磐舟の泊まる故を以て高津と号すと云々」とあり、今の歌はこの伝説の系統によったものである。 後世アマノジャクとて、天上界にいる、物事を探り出す魔女と思われていた。「探女之」の「之」をノと訓む説やガと訓む説があるが、これは魔女・邪鬼の類であるので、ガ助詞(軽んじあなどる気持ち)で訓む。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さくむ | 〔他動詞マ行四段〕踏み分けて行く。 |
-我が恋ふる 妹はいますと 人の言へば 岩根さくみて なづみ来し-(万2-210) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ささ [笹・小竹] | 〔名詞〕丈が低く、茎の細い竹の総称。 | 笹の葉はみ山もさやにさやげども我れは妹思ふ別れ来ぬれば (万2-133) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さくら [桜] | 〔名詞〕 ① 木の名。花の名。[さくらばな=桜の花] ② 桜襲(さくらがさね)の略。 |
-松風に 池波立ちて 桜花 木の暗茂に 沖辺には 鴨つま呼ばひ-(万3-259) 桜花散りかひくもれ老いらくの 来むといふなる道まがふふがに(古今賀-349) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さくらだ [桜田] | 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 『付録 地名一覧』」】 『和名抄』に尾張国「愛智郡作良」と見える地名サクラの付近の田の意であるが、そのまま地名として用いたものであろう。 現在、名古屋市南区に元桜田町、桜本町、西桜町などの名が残っており、名鉄名古屋本線桜駅の西に小円墳があり、その頂きに桜神明社という社もある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さけ [酒] | 〔名詞〕 米で醸した飲料。酒。 |
験なき物を思はずは一坏の濁れる酒を飲むべくあるらし(万3-341) 古人の飲へしめたる吉備の酒病まばすべなし貫簀賜らむ(万4-557) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ささぐ [捧ぐ] | 〔他動詞ガ行下二段〕【ゲ・ゲ・グ・グル・グレ・ゲヨ】[さしあぐ]の転。 ① 手で上へ高く持ち上げる。② 高く上げる。③ 奉る。献上する。 ④ 声を高くする。 |
② -ささげたる 幡の靡きは 冬こもり 春さり来れば 野ごとに-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ささなみ [細波・小波] | 〔名詞〕[後世は「さざなみ」] 風のために水面に立つ細かな波。また、小さな波。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ささなみ | 〔古地名〕 | かく故に見じと言ふものを楽浪の旧き都を見せつつもとな(万3-308) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琵琶湖の西南部で大津京の一帯を指す古地名。 書紀に「北は近江の狭狭波の合坂山より以来を畿内(うちつくに)とす」(大化二年正月)とあり、また「難波津より発ちて、船を狭狭波山に控(ひ)き引(こ)して、飾り船を装ひて乃ち往きて近江の北の山に迎へしむ」(欽明三十一年七月紀) ともある。原文「神楽浪」の「神楽」は戯書。神楽のはやしにササと掛声するので神楽をササと訓む。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ささなみの [細波の・小波の] | 【枕詞】「さざなみの」とも。 琵琶湖周辺の地名や湖水に関連させて、「大津」「比良山」「志賀」「連庫(なみくら)山」「長等(ながら)山」「なみ」「寄る」「夜」「あやし」「古き都」などにかかる。 |
-石走る 近江の国の 楽浪の 大津の宮に-(万1-29) 楽浪の比良山風の海吹けば釣りする海人の袖返る見ゆ(万9-1719) 楽浪の志賀の [一云 比良の] 大わだ淀むとも昔の人にまたも逢はめやも [一云 逢はむと思へや]-(万1-31) 楽浪の志賀さざれ波しくしくに常にと君が思ほえたりける(万2-206) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ささらのをの [ささらの小野] | 【有斐閣「萬葉集全注巻三-420 注『ささらの小野』」】 天上界にあるささらといふ名の小野で、そう信じられていた野である。「天にあるや神楽良能小野(ササラノヲノ)」(16-三八八七) とも見える。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さざれなみ [細れ波] | 〔名詞〕[「さざれ」は接頭語] さざなみ。 | 楽浪の志賀さざれ波しくしくに常にと君が思ほえたりける(万2-206) さざれ波礒越道なる能登瀬川音のさやけさ激つ瀬ごとに(万3-317) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さしあがる [差し上がる] | 〔自動詞ラ行四段〕《「さし」 は接頭語》(太陽や月が) 昇る。 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1」 167頭注】 「さしあがる」-十一世紀くらいまでは日についてサシアガルというのが例。 |
-日女の命 [一云 さしあがる 日女の命] 天をば 知らしめすと-(万2-167) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さしかふ [差し交ふ] | 〔他動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 互いに交差させる。交わしあう。 |
白たへの 袖さし交へて なびき寝し 我が黒髪の ま白髪に-(万3-484) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さしわたす [差し渡す] | 〔自動詞サ行四段〕 ① 直接向かい合う。面と向かう。② 直接自分でする。 ③ 血が直接つながる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞サ行四段〕 ① 一方から他方へかけ渡す。② 棹をさして舟を対岸へ行かせる。 |
①-上つ瀬に 鵜川を立ち 下つ瀬に 小網さし渡す-(万1-38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さしわたる [差し渡る] | 〔自動詞ラ行四段〕流れに棹を差して渡る。差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さす [射す・差す・指す] | 〔自動詞サ行四段〕 ① 光が照り入る。さす。 ② 草木がもえ出る。芽が出る。 ③ 潮が満ちてくる。 ④ (雲が) わく。立ちのぼる。 |
② -百足る槻の木 こちごちに 枝させるごと 春の葉の 繁きがごとく-(万2-213) ② 春霞春日の里の植ゑ子水葱苗なりと言ひし枝はさしにけむ(万3-410) ② 瀧の上の 三船の山に 瑞枝さし 繁に生ひたる 栂の木の- (万6-912) ③ わかの浦に月の出で潮のさすままに夜鳴く鶴の声ぞかなしき (新古雑上-1554) ④ 八雲さす出雲の子らが黒髪は吉野の川の沖になづさふ(万3-433) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞サ行四段〕 ① 事物を指し示す。 ア:指さす。 イ:目指す。 ウ:それと確かめ定める。指定する。 エ:指名する。任命する。 ② かざす。さしかける。 ③ 物を設ける。 ④ 物を前方へさし出す。 |
①-ウ -あしひきの 山辺をさして 夕闇と 隠りましぬれ 言はむすべ-(万3-463) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さすたけの [刺す竹の] | 【枕詞】 「さすだけの」 とも。「さす」 は生えて伸びる意で、竹は勢いよく生長するので、繁栄を祝って「君・大宮・舎人・皇子」 などにかかる。 |
「さすたけの君はや無き」(紀・推古) -一云 さす竹の 皇子の宮人 ゆくへ知らにす-(万2-167) -道を来れば うちひさす 宮女 さす竹の 舎人壮士も 忍ぶらひ-(万16-3813) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さだのをか(へ) [佐太の岡(辺)] | 〔地名〕 | 朝日照る佐田の岡辺に群れ居つつ我が泣く涙やむ時もなし(万2-177) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻二 177 注」】 佐太の岡は、現在の高鳥町佐田で、岡宮天皇陵(日並皇子の陵) のある丘陵を指す。なお、佐田の岡の歌われる時は常に、「佐田の岡辺」 とあることに注目し、渡瀬昌忠、真弓の岡が殯宮のある丘陵本体で、舎人たちの奉仕する場所が丘陵南端で「佐田の岡辺」 と称されたのではないかという(『柿本人麻呂研究 島の宮の文学』)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さだむ [定む] | 〔他動詞マ行下二段〕【メ・メ・ム・ムル・ムレ・メヨ】 ① 決める。決定する。② 評議する。議論する。また、判定する。 ③ 治める。平定する。 |
① 妹が家に咲きたる梅のいつもいつも成りなむ時に事は定めむ(万3-401) ③ -日の目も見せず 常闇に 覆ひ賜ひて 定めてし 瑞穂の国を-(万2-199) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さだめ [定め] | 〔名詞〕 ① 決めること。決定。② 論議。評議。判定。 ③ おきて。きまり。規則。基準。④ 安定。 |
① -城上の宮を 常宮と 定めたまひて あぢさはふ 目言も絶えぬ-(万2-196) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さつき [皐月・五月・早月] | 〔名詞〕陰暦五月の異称。早苗月(さなえづき)。 | -ほととぎす 鳴く五月には あやめぐさ 花橘を 玉に貫き-(万3-426) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さつまのせと [薩摩の瀬戸] | 〔地名〕 | 隼人の薩摩の瀬戸を雲居なす遠くも我は今日見つるかも(万3-249) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1 『付録地名一覧 薩摩の瀬戸』」】 鹿児島県阿久根市黒之浜と天草諸島の南端長島(同県出水郡東町)との間の、長さ約四キロメートル・幅三〇〇~七〇〇メートルの海峡。 今は黒之瀬戸と呼ばれ、阿久根市梶折鼻と長島との間に黒之瀬戸大橋が架けられ、国道三八九号が通じている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さつや [猟矢] | 〔名詞〕狩猟に使う矢。(=猟矢 ししや) | 大丈夫のさつ矢手挟み立ち向ひ射る圓方は見るにさやけし(万1-61) -梓弓 手に取り持ちて ますらをの さつ矢手挟み 立ち向かふ-(万2-230) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さつゆみ [猟弓] | 〔名詞〕狩猟に使う弓。 | - 剣太刀 腰に取り佩き さつ弓を 手握り持ちて-(万5-808) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さつを [猟夫] | 〔名詞〕猟師。(=猟人 さつひと) | むささびは木末求むとあしひきの山のさつ男にあひにけるかも(万3-269) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さで [叉手・小網] | 〔名詞〕漁具の一つ。柄のあるすくい網。さで網。 | 三川の淵瀬もおちず小網さすに衣手濡れぬ干す子はなしに(万9-1721) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さと [里] | ① 人家が集まっているところ、人里。 ② 上代の地方行政の区画の一つ、人家五十戸の地。 ③ 宮中に仕える人が、宮中に対して自分の住む家を言う語。 ④ 田舎、在所。⑤ 妻・養子・奉公人などの実家。 ⑥ 養育費を出して子どもを他人にあずけること。⑦ 遊里。 ⑧ 素性、育ち。⑨(寺に対して)俗世間。 |
① -かへり見すれど いや遠に 里は離りぬ-(万2-131) ① 我が背子が古家の里の明日香には千鳥鳴くなり夫待ちかねて(万3-270) ② 橘を守部の里の門田早稲刈る時過ぎぬ来じとすらしも(万10-2255) ③ 浅茅原つばらつばらに物思へば古りにし里し思ほゆるかも(万3-336) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さぬき(のくに) [讃岐(の国)] | 〔地名〕旧国名。南海道六か国の一つ。今の香川県。讃州。 |
玉藻よし 讃岐の国は 国からか 見れども飽かぬ 神からか ここだ貴き-(万2-220) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さなかづら (さねかづら) [さな葛(さね葛)] |
〔名詞〕「さね葛」の古名。 | さなかづらの根をうすにつき(記中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山野に自生する常緑つる性低木の名。今の「びなんかずら」。その茎の粘液は、製紙用の糊、または髪油として用いた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】 類似音の「さね」に、「さねかづら」のつるの状態から「のちもあふ」「絶えず」「いや遠長く」にかかる。 |
玉櫛笥三諸の山のさな葛さ寝ずはつひに有りかつましじ [玉くしげ三室戸山の] (万2-94) -今さらに 君来まさめや さな葛 後も逢はむと 慰むる-(万13-3294) 大船の 思ひ頼みて さな葛 いや遠長く 我が思へる -(万13-3302) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さにつらふ [さ丹つらふ] | 【枕詞】 [接頭語「さ」+名詞「丹(に)」+名詞「頬(つら)」+接尾語「ふ」 紅顔の意を表す] 赤いもの、美しいものを修飾し、「妹(いも)」「君」「色」「ひも」「もみち」「わご大王」にかかる。 |
さ丹つらふ妹を思ふと霞立つ春日もくれに恋ひわたるかも(万10-1915) -答へ遣る たづきを知らに さ丹つらふ 君が名言はば-(万13-3290) さ丹つらふ色には出でず少なくも心のうちに我が思はなくに(万11-2528) -御津の浜辺に さ丹つらふ 紐解き放けず 我妹子に -(万4-512) -しぐれをいたみ さ丹つらふ 黄葉散りつつ 八千年に -(万6-1057) なゆ竹の とをよる御子 さにつらふ 我が大君は こもりくの-(万3-423) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さね [さ寝] | 〔名詞〕「さ」は接頭語。 男女が共寝をすること。 |
玉櫛笥三諸の山のさな葛さ寝ずはつひに有りかつましじ [玉くしげ三室戸山の] (万2-94) ま愛しみさ寝に我は行く鎌倉の水無瀬川に潮満つなむか(万14-3383) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さね [実] | 〔副詞〕 ① ほんとうに。必ず。 ② (下に打消しの語を伴って) 決して。少しも。 |
たち変り月重なりて逢はねどもさね忘らえず面影にして(万9-1798) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さね | 〔上代語〕お~てください。~なさってください。 【なりたち】 上代の尊敬の助動詞「す」の未然形「さ」+他に対する願望の終助詞「ね」 |
-この岡に 菜摘ます子 家聞かな 告らさね-(万1-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さぬのをか [佐農の岡] | 〔地名〕 | 秋風の寒き朝明を佐農の岡越ゆらむ君に衣貸さましを(万3-364) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-361 注『佐農の岡』」】 未詳。紀州の「狭野(さの)」(二六五〔注〕参照) 説があるが、六首が構成された羇旅の歌としてみた時、遠過ぎる嫌いがある。 また和名抄の但馬国気多郡の「狭沼、左乃(サノ)」(今の豊岡の南にある佐野) かとする説(澤瀉注釈) もある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さは(に) [多(に)] | 〔副詞〕数多く。たくさん。 【参考】 類義語の「ここだ」は数量の多いさまだけでなく、程度のはなはだしい様子にも用いられる。 |
磯の崎漕ぎ廻み行けば近江の海八十の港に鶴さはに鳴く [未詳](万3-275) 神代より 生れ継ぎ来れば 人さはに 国には満ちて-(万4-488) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -さぶ | 〔接尾語上二型〕 名詞についてそのものらしい態度・状態であることを表わす語。 「らしい」「らしくなる」の意を添える。 |
- 娘子らが 娘子さびすと 唐玉を-(万5-808) み薦刈る信濃の真弓我が引かば貴人さびていなと言はむかも [禅師](万2-96) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さばへ [五月蠅] | 〔名詞〕 ① 陰暦五月の真夏にむらがりさわぐはえ。② うるさいこと。群がり騒ぐこと。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -なす [五月蠅なす] | 【枕詞】「さわぐ」「荒ぶ」 などにかかるさ | -皇子の御門の 五月蝿なす 騒く舎人は 白たへに 衣取り着て-(万3-481) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さぶ [荒ぶ] | 〔自バ行上二段〕【ビ・ビ・ブ・ブル・ブレ・ビヨ】 ① 荒れる。② 古くなる。③ うすれる。④ 衰える。 |
① まそ鏡見飽かぬ君に後れてや朝夕にさびつつ居らむ(万4-575) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さぶ [寂ぶ] | 〔自バ行上二段〕【ビ・ビ・ブ・ブル・ブレ・ビヨ】 ① 心に寂しく思う。わびしがる。② 寂しくなる。③ 古びて雅趣を帯びる。 |
① まそ鏡見飽かぬ君に後れてや朝夕にさびつつ居らむ(万4-575) ② 長月もいくありあけになりぬらむ浅茅の月のいとどさびゆく (新古秋下-521) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さぶし [寂し・淋し] | 〔形容詞シク活用〕《上代語》[「さびし」の古形] 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 気持ちが塞いで楽しめない。さびしい。ものたりない。 |
楽浪の志賀津の児らが [一云 志賀の津の児が] 罷り道の川瀬の道を見ればさぶしも (万2-218) 桜花今ぞ盛りと人は言へど我れは寂しも君としあらねば(万18-4098) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さぶるこ [さぶる児] | 〔名詞〕遊女。浮かれ女。 | 左夫流児が斎きし殿に鈴掛けぬ駅馬下れり里もとどろに(万18-4134) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さへ | 〔副助詞〕 ① 添加の意を表す。~までも。 ② 程度の軽いものをあげ、重いものはなおさらだと類推させる意を表す。~さえ。 [接続] 体言・活用語の連体形・助詞などに付く。主語・目的語などを含め、連用修飾語に付く。 |
明日香川明日だに [さへ] 見むと思へやも [思へかも] 我が大君の御名忘れせぬ [御名忘らえぬ](万2-198) ① 我が背子が着せる衣の針目落ちずこもりにけらし我が心さへ(万4-517) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【文法】 本来は①「~だけでなく、さらに~まで」 のような添加の意を表したが、「だに」 と混同して、 「からすの寝どころへ行くとて、三つ四つ、二つ三つなど飛び急ぐさへ(=までも) あはれなり」(枕草子・一) のように添加でない単なる強調を表す用法が生じた。②は、中世の頃から生まれた用法であり、中古までは「だに」 で表されたものである。→だに |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さへき [禁樹] | 〔名詞〕通行の邪魔をする木。 | -真木立つ 荒き山道を 岩が根 禁樹押しなべ 坂鳥の 朝越えまして-(万1-45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さへなふ | 〔他動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 [障(さ)へに敢(あ)ふ」の転] 防ぎきる。拒みとおす。断る。 |
障へなへぬ命にあれば愛し妹が手枕離れあやに悲しも(万20-4456) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さへに | 〔副助詞〕[副助詞「さへ」に助詞「に」の付いたもの] ~までもまあ~ことだ。 |
咲きそめし宿しかはれば菊の花 色さへにこそうつろひにけれ(古今秋下-280) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 「に」 を格助詞とみることもできるが、「夢路をさへに人はとがめじ」(古今・恋三) などと「を」 にも付くので、同類の格助詞は重ね用いられることがないという点から間投助詞と見るのがよいと考えられている。また、終助詞、接続助詞、接尾語と見る説もある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さほ [佐保] | 〔名詞〕奈良市北部佐保川の北岸。法蓮町・法華寺町の一帯をいう。 貴族の住宅地として知られ、長屋王の別邸「作宝桜(さほろう)」(作宝宮)もここにあった。 |
佐保過ぎて奈良の手向けに置く幣は妹を目離れず相見しめとそ(万3-303) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻三-300 頭注『佐保過ぎて』」】 長屋王の邸宅は左京三条二坊、今日の奈良市二条大路南一丁目にあった。「佐保宅」(一六三八)もあったことが知られるが、ここはそれに立ち寄らなかったことを言うのであろう。 佐保宅(作宝宮)の造営は神亀年間(724~729)以降に下るとする説もあるが、両宅並存の可能性もある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さほのやま・さほやま [佐保の山・佐保山] |
【小学館「新編日本古典文学全集萬葉集 付録『地名一覧』」】 平城京左京の東北張出し部である外京の北に起伏している低山。今日では開発が進められ、その中心部は遊園地と化してしまった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さほがは [佐保川] | 〔名詞〕[歌枕] 今の奈良県奈良市の春日山に源を発し、大和川に注ぐ川。 よく千鳥・川霧が詠み込まれる。 |
-あをによし 奈良の都の 佐保川に い行き至りて 我が寝たる-(万1-79) 飫宇の海の河原の千鳥汝が鳴けば我が佐保川の思ほゆらくに(万3-374) 佐保川の小石踏み渡りぬばたまの黒馬の来夜は年にもあらぬか(万4-528) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さまねし | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 「さ」は接頭語。「数が多い。度重なる。」 接頭語「さ」+形容詞「あまねし」 |
うらさぶる心さまねしひさかたの天のしぐれの流らふ見れば(万1-82) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さまよふ [吟ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 嘆いてうめき声をだす。嘆き悲しむ。 |
-春鳥の さまよひぬれば 嘆きも いまだ過ぎぬに 思ひも-(万2-199) -足の方に 囲み居て 憂へさまよひ かまどには 火気吹き立てず-(万5-896) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さまよふ [彷徨ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 ① うろうろする。また、流浪する。 ② 心が定まらない。うつろいやすく浮気である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さみねのしま [狭岑の島] | 〔地名〕 | -をちこちの 島は多けど 名ぐはし 狭岑の島の 荒磯面に-(万2-220) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中央公論社「萬葉集注釈巻二-220 題詞注『狭岑島』」澤瀉久孝】 狭岑島は仲多度郡塩飽(シアク)諸島の中の砂彌(サミ)島である。坂出市の西北の海上にある。 サミネの語については講義にネはシマネのネであるとし「瀬戸内海のこの辺の島又は岩礁にていはば、平根(ヒラネ・讃岐) 赤穂根島(アカホネシマ・伊予) 高根島(タカネ・安芸) 宿根島(スクネ・安芸) 平根島(周防) などあり。」としてサミの島をサミネと云ひ、更にサミネの島とも云つたとある。 全註釈には反歌に「佐美の山」とあるによつて「佐美の嶺」の義であらうとある。語原としては講義の説の如くであつたかも知れないが、歌の中にも「岑」の字が書かれてをり、少なくも人麻呂は砂彌の嶺の島の意と考へてゐたものと思はれる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さみのやま [作美の山] | 〔地名〕 | 妻もあらば摘みて食げまし沙弥の山野の上のうはぎ過ぎにけらずや(万2-221) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻二-221 注『作美の山』」】 原文「作美乃山」。西本願寺本に「作」を「佐」とするが、金澤本・類聚古集・古葉略類聚鈔による。注釈には、金澤本の「作」の方を誤りとしている。 犬養孝「人麻呂と風土」によると、沙弥島には三つの小丘があり、「作美の山」はそのいずれかであろうという。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さむし [寒し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① 寒い。冷たい。 ② 寒々としている。 ③ 貧しい。貧弱である。 |
① 流らふる妻吹く風の寒き夜に我が背の君はひとりか寝らむ(万1-59) ① 宇治間山朝風寒し旅にして衣貸すべき妹もあらなくに(万1-75) ① 秋の夜は暁寒し白栲の妹が衣手着むよしもがも(万17-3967) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さもらふ [候ふ・侍ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕〔四段動詞「守(も)る」の未然形「もら」 に上代の反復・継続の助動詞「ふ」 の付いた「もらふ」 に接頭語「さ」 の付いたもの。〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① 様子を見ながら好機の到来を待つ。時機をうかがう。 ② 貴人のそばに控えて命令を待つ。伺候する。 |
① - 朝なぎに 舳向け漕がむと さもらふと 我が居る時に-(万20-4422) ② 東のたぎの御門に侍へど昨日も今日も召す言もなし(万2-184) ② -侍ひえねば 春鳥の さまよひぬれば 嘆きも いまだ過ぎぬに-(万2-199) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さやか [清か・明か・分明] | 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 ① (視覚的に) はっきりしている。明瞭である。 ② (聴覚的に) 音声が高く澄んでいる。③ 明るい。 |
①-我が寝たる 衣の上ゆ 朝月夜 さやかに見れば 栲の穂に-(万1-79) ① 秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる (古今秋上-169) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さやぐ | 〔自動詞ガ行四段〕 さやさやと音をたてる。そよぐ。 |
笹の葉はみ山もさやにさやげども我れは妹思ふ別れ来ぬれば(万2-133) 笹が葉のさやぐ霜夜に七重着る衣に増せる子ろが肌はも(万20-4455) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さやけさ [清明さ] | 〔名詞〕[「さ」は接尾語] 澄んではっきりしていること。澄み切っていること。すがすがしいこと。 |
さざれ波礒越道なる能登瀬川音のさやけさ激つ瀬ごとに(万3-317) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さやけし [清けし・明けし] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① 澄み切っている。清くすがすがしい。 ② はっきりしている。明るい。冴えている。 |
① うつせみは数なき身なり山川のさやけき見つつ道を尋ねな(万20-4492) ① 昔見し象の小川を今見ればいよよさやけくなりにけるかも(万3-319) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 意味用法において「清し」に近い語でるが、「清し」が対象そのものの汚れないようすを表すのに対して、「さやけし」は対象に接して呼び覚まされるさわやかな感覚を表すという違いがある。 具体的に言えば、「さやけし」は汚れない清らかな自然に触れて感じる清々しさ、人間の矜持などの澄み切った心境などを表す。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さやに [清に] | 〔副詞〕はっきりと。明らかに。 | 笹の葉はみ山もさやにさやげども我れは妹思ふ別れ来ぬれば(万2-133) 日の暮れに碓氷の山を越ゆる日は背なのが袖もさやに振らしつ(万14-3420) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよ [小夜] | 〔名詞〕[「さ」は接頭語] 夜。 | 我が船は比良の湊に漕ぎ泊てむ沖辺な離りさ夜ふけにけり(万3-276) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さらす [晒す・曝す] | 〔他動詞サ行四段〕 ① 布などを白くするため、何度も水洗いして、日に当てる。 ② 日光や雨風のあたるままにしておく。 ③ 多くの人の目に触れるようにする。 |
① 庭に立つ麻手刈り干し布さらす東女を忘れたまふな(万4-524) ① 多摩川にさらす手作りさらさらになにぞこの子のここだ愛しき(万14-3390) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さらに [更に] | 〔副詞〕 ① 重ねて。そのうえ。ますます。 ② 新たに。もう一度。改めて。 ③ (下に打消しの語を伴って) 全然(~ない)。決して(~ない)。さ |
① ぬばたまの夜渡る月のゆつりなばさらにや妹に我が恋ひ居らむ(万11-2681) ③ 朝鳥の音のみや泣かむ我妹子に今また更に逢ふよしをなみ(万3-486) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ざらまし | [打消助動詞「ず」の未然形「ざら」+反実仮想助動詞「まし」] (もし~だったら)~ないであろうに。 (もし~だったら)~なかったであろうに。 |
人言の繁きこのころ玉ならば手に巻き持ちて恋ひざらましを(万3-439) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さり [然り] | 〔自動詞ラ行変格〕【ラ・リ・リ・ル・レ・レ】 [副使「然 (さ) 」にラ変動詞「有り」の付いた「さあり」の転] 「そうである」「そのようである」 【文法】 各活用形が接続助詞を伴って、その全体で接続詞となる場合が多い。 「さらば」「さりとて」「さるに」「されば」など。 また、連体形の「さる」が体言を修飾して連体詞として扱われる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さる [然る] | 〔連体詞〕[ラ変動詞「然(さ)り」の連体形から] ① (前の語や内容を受けて) そのような。あのような。これこれの。 ② しかるべき。相応の。れっきとした。 ③ ある [或る] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さる [猿] | 〔名詞〕 ① 動物の名。さる。 ② ずるがしこい者、すばしっこい者などをののしって言う語。 |
あな醜賢しらをすと酒飲まぬ人をよく見ば猿にかも似る(万-347) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さる [去る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 離れていく。遠ざかる。 ② (季節や時を表す語に付いて) 近づく。来る。 ③ 変化する。移り変わる。(色が) あせる。 ④ 退位する。退く。 〔他動詞ラ行四段〕 ⑤ 遠ざける。離す。⑥ 離縁する。 |
① 明日香川川淀去らず立つ霧の思ひ過ぐべき恋にあらなくに(万3-328) ② -ささげたる 幡の靡きは 冬こもり 春さり来れば 野ごとに-(万2-199) ② 天降りつく 神の香具山 うちなびく 春さり来れば 桜花 木の暗繁に-(万3-262) ② 秋さらば見つつ偲へと妹が植ゑしやどのなでしこ咲きにけるかも (万3-467) ② ぬばたまの夜さり来れば巻向の川音高しもあらしかも疾き (万7-1105) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進行する、移動する意が原義。現代語ではもっぱらこの場を基点として移動する意で用いるが、上代以降は「自動詞②」の、それまで存在していた場を基点として移動する(この場から見ると「近づく」意でも用いる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さわぎ [騒ぎ] | 〔名詞〕《上代は「さわき」》 ① やかましいこと。騒ぐこと。 ② あわただしく落ち着かないこと。混雑。とりこみ。 ③ 戦乱。騒動。異変。④ 遊興。遊芸。 |
③ -風の共 靡かふごとく 取り持てる 弓弭の騒き み雪降る-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さわぐ [騒ぐ] | 〔自動詞ガ行四段〕[上代は「さわく」] ① やかましく声や音をたてる。騒がしくする。 ② 忙しく動き回る。忙しく立ち働く。 ③ 不穏な動きを見せる。騒動が起きる。 ④ 心が落ち着かなくなる。動揺する。 ⑤ あれこれと噂する。評判する。 |
① -沖見れば とゐ波立ち 辺を見れば 白波騒く いさなとり 海を恐み-(万2-220) ① み吉野の象山の際の木末にはここだも騒く鳥の声かも(万6-929) ② -玉藻なす 浮かべ流せれ 其を取ると 騒く御民も 家忘れ-(万1-50) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さゐさゐし [騒々し] | 〔形容詞シク活用〕 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 騒ぐさま。また、うるさい音のするさま。さらさらと鳴るさま。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さゐさゐしづみ [騒々沈み] | 「さゑさゑしづみ」とも。語義未詳。 さらさらと音を立てていたものがしずまる、心が沈んでなどの意か。 |
玉衣のさゐさゐしづみ家の妹に物言はず来にて思ひかねつも(万4-506) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さを [棹・竿] | 〔名詞〕 ① 水底や岸をついて舟を進めるための長い棒。木や竹でつくる。 ② 衣を掛ける細長い棒。衣紋棹(えもんざお)。 |
-大宮人の 罷り出て 遊ぶ船には 楫棹も なくてさぶしも 漕ぐ人なしに(万3-259) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| し [死] | 〔名詞〕生命を失うこと。死ぬこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| し →「主要助詞」 →「主要助動詞」 |
〔副助詞〕語調を整え強意を表わす。 〔接続〕体言、活用語の連体形、連用形、副詞、助詞などにつく |
秋の野のみ草刈り葺き宿れりし宇治の京の仮廬し思ほゆ(万1-7) 大伴の高師の浜の松が根を枕き寝れど家し偲はゆ(万1-66) -八十隈おちず 万たび かへり見しつつ 玉桙の 道行き暮らし- (万1-79) かくばかり恋ひつつあらずは高山の磐根しまきて死なましものを (万2-86) 我が御門千代とことばに栄えむと思ひてありし我れし悲しも(万2-183) -みどり子の 乞ひ泣くごとに 取り与ふる 物しなければ-(万2-210) 賢みとものいふよりは酒飲みて酔ひ泣きするしまさりたるらし(万3-344) 風まじへ雨降る夜の雨まじへ雪降る夜はすべもなく寒くしあれば- (万5-896) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去の助動詞「き」の連体形。(~ていた) 〔接続〕連用形(カ変・サ変には特殊な接続をする) 連体形「し」で文を終止し、詠嘆・感動の意。 |
-夕には い寄り立たしし み執らしの 梓の弓の 中弭の 音すなり 朝猟に-(万1-3) その雨の 間なきがごと 隈もおちず 思ひつつぞ来し その山道を(万1-25) わが背子を大和へ遣るとさ夜更けて暁露にわが立ち濡れし(万2-105) 船の津守が占に告らむとはまさしに知りて我がふたり寝し(万2-109) 人皆は今は長しとたけと言へど君が見し髪乱れたりとも [娘子](万2-124) 我が御門千代とことばに栄えむと思ひてありし我れし悲しも(万2-183) 一日には千たび参りし東の大き御門を入りかてぬかも(万2-186) けころもを時かたまけて出でましし宇陀の大野は思ほえむかも(万2-191) 今のみのわざにはあらず古の人そまさりて哭にさへ泣きし(万4-501) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尊敬の助動詞「す」の連用形。軽い尊敬、親愛の意を表す。 お~になる。~なさる。 〔接続〕四段・サ変の未然形。 |
香具山と耳成山とあひし時立ちて見に来し印南国原(万1-14) ひさかたの天知らしぬる君故に日月も知らず恋ひわたるかも(万2-200) -海神の 手に巻かしたる 玉だすき かけて偲ひつ 大和島根を-(万3-369) たくづのの 新羅の国ゆ 人言を 良しと聞かして 問ひ放くる-(万3-463) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| じ | 〔助動詞特殊型〕【○・○・ジ・ジ・ジ・○】 ① 打消しの推量の意を表わす。~ないだろう ② 主語が自称の場合、打消しの意を表わす。~しないつもりだ 〔接続〕活用語の未然形に付く。 |
① 我が行きは久にはあらじ夢のわだ瀬にはならずて淵にもありこそ(万3-338) ① 我が背子にまたは逢はじかと思へばか今朝の別れのすべなかりつる(万4-543) ① 幾世しもあらじ我が身をなぞもかくあまの刈る藻に思ひ乱るる (古雑下-934) ② 玉藻刈る沖へは漕がじ敷栲の枕のあたり忘れかねつも(万1-72) ② 宜しなへ我が背の君が負ひ来にしこの背の山を妹とは呼ばじ(万3-289) ② 櫛も見じ屋内も掃かじ草枕旅行く君を斎ふと思ひて(万19-4287) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔語法〕話し相手の動作であるかどうかによって、①か②が決まる。なお已然形の用例としては、係助詞「こそ」の結びだけで、代表的なものとして、「人はなど訪はで過ぐらむ風にこそ知られじと思う宿の桜を」(新続古今・春下)がある。わずか一、二例なので、活用形としてはっきり認められてはいない。 | 〔参考〕「じ」は「む」の打消し。「ず」に比べて多少遅疑する意を含み、「まじ」に比べて打ち消しの意が強く、推量の意が軽い。これらから、「じ」は「ず」と「まじ」との中間に位すると考える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しか [鹿] | 〔名詞〕 ① しか(=動物ノ名)。 めすは「めか」というのに対し、「しか」は雄鹿をさす場合が多い。 ② 「囲ひ女郎」の異称。 |
① 大和辺に君が立つ日の近づけば野に立つ鹿もとよめてそ鳴く(万4-573) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しか [然] | 〔副詞〕(前述されたことをさして)そのように。そのとおりに。 | -古も しかにあれこそ うつせみも 妻を争ふらしき(万1-13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しが [志賀] | 〔地名〕[歌枕] 今の滋賀県大津市および滋賀郡一帯。七世紀後半、天智天皇の大津の宮が置かれたが、都であることわずかで、壬申の乱ののちに廃都となった。「ささなみの志賀」「志賀の都」として、懐古の情をもって和歌に詠まれた。 |
楽浪の志賀の辛崎幸くあれど大宮人の舟待ちかねつ(万1-30) 馬ないたく打ちてな行きそ日並べて見ても我が行く志賀にあらなくに(万3-265) 【志賀の辛崎(唐崎)】大津市下阪本町。 琵琶湖の西岸にあり「唐崎の夜雨」は近江八景の一つ。一つ松・唐崎神社で有名。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔地名〕福岡市東区に属する志賀島。西の玄海島とともに博多湾の出入口をなしている。 | 志賀の海女は軍布刈り塩焼き暇なみくしげの小櫛取りも見なくに(万3-281) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかすがに [然すがに] | 〔副詞〕[副詞「しか」+サ変動詞「す」+接続助詞「がに」] しかしながら。そうはいうものの。 |
-かつは知れども しかすがに 黙もえあらねば 我が背子が-(万4-546) うち霧らひ雪は降りつつしかすがに我家の苑に鴬鳴くも(万8-1445) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しがつ [志賀津] | 〔地名〕 【有斐閣「萬葉集全注巻二-218 注『志賀津の子ら』」】 志賀津は志賀の大津をさす。題詞には「吉備津采女」とあるのに、ここに「志賀津の子ら」と言われているのはなぜか。 一説では、吉備津の采女と志賀津の子らとは同人で、近江朝の采女であったから「志賀津の子ら」「大津の子」などと呼ばれたのであろうと考えるのであるが(澤瀉久孝「万葉の虚実」『万葉歌人の誕生』)、そのほか、現職の采女が夫を持つはずはないと考え、吉備津は生国を、志賀津は夫たる人の住所もしくは結婚後の住所をあらわすのではないかとする説(講義・全註釈)や、采女の夫が大津連・大津造であったのを「志賀津の子ら」と表現したものと考える説(神堀忍「『吉備津采女』と『天数ふ大津の子』」万葉八十三号)がある。 しかし、結婚後の采女ならば「前采女」(16・三八〇七左注)とあるべきだし、澤瀉論文に指摘されているように「采女死時」という題詞は現任の采女の死を表したものとうけとるべきであろう。 また、神堀説では、夫たる大津連の男性の、配流されてゆく、その川瀬の道を見ると悲しいということになるが、「罷り道の川瀬の道」は、配流のための川沿いの道を意味するものとは考え難いと思われる。そのことは、次の詩句の〔注〕に述べる。なお、「楽浪の志我」および「天数ふ凡」を、次の「津」を言うための序詞として、措辞上の技巧と見る説(私注)もあるが、巻七に「ささなみの志賀津の浦」(一三九八) の例も見られ、「志我」までを序というのは無理だと思われる。楽浪の志我の大津の宮に仕えた采女の、の意。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかのはまへ [志賀の浜辺] | 【有斐閣「萬葉集全注巻第四-566 注『志賀の浜辺』」】 志賀は福岡市東区志賀町の志賀島、博多湾の入口を扼し、福岡市中心部の北西に当たる。「カ」は清音。ただしこの場合、大宰府から陸路を取って東に帰るのに志賀島を通るはずがないため、福岡市東部の博多湾沿岸、箱崎、名島、香椎などの海岸地帯をさす、とする説がある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかも [然も] | 〔副詞〕①そのように。そんなにまで。②まったく。ほんとうに。 | 三輪山をしかも隠すか雲だにも-(万1-18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔接続詞〕①なおその上に。それでいて。②けれども。しかるに。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかも | 副助詞「し」に係助詞「か」、終助詞「も」のついたもの。 疑問を表わす語について疑問・不安・反語の意を強める。 |
佐保川に鳴くなる千鳥何しかも川原をしのひいや川のぼる(万7-1255) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しがらみ [柵] | 〔名詞〕 ① 川の中に杭を打ち並べて、それに柴や竹などを横にして渡して、水流を堰き止めるもの。 ② 物事をせきとめるもの。 |
① 明日香川しがらみ渡し塞かませば流るる水ものどにかあらまし [一云 水の淀にかあらまし](万2-197) ① 山川に風のかけたるしがらみは 流れもあへぬ紅葉なりけり(古今秋下-303) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかり [然り] | 〔自動詞ラ変〕【ラ・リ・リ・ル・レ・レ】 [副詞「然(しか)」 にラ変補助動詞「あり」 の付いた「しかあり」 の転] そのとおりである。そのようだ。 |
照りやたまはぬ 人皆か 我のみやしかる わくらばに 人とはあるを 人並に(万5-896) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかれども [然れども] | 〔接続詞〕 [ラ変動詞「然(しか)り」の已然形「しかれ」に接続助詞「ども」の付いたもの] そうではあるが。しかしながら。 【参考】 平安時代以降、漢文訓読体の文章に用いられた語。 和文では「されども」を用いるのが一般的である。 |
-高くしたてて 神ながら 鎮まりましぬ しかれども 我が大君の-(万2-199) 恋と言へば薄きことなりしかれども我れは忘れじ恋ひは死ぬとも(万12-2951) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかれば [然れば] | 〔接続詞〕 [ラ変動詞「然り」 の已然形「しかれ」 に接続助詞「ば」 の付いたもの] ① そうであるから。だから。② さて。ところで。 【参考】漢文訓読体から生じた語 |
(-目言も絶えぬ 然れかも あやに哀しみ ぬえ鳥の 片恋づま-万2-196 ) 【巻二-196「しかれかも」 有斐閣「萬葉集全注巻二-196 注」】 「然ればかも」で、そうであるからか、の意。この句がどこまで掛かるか説が分かれるが、講義に、下の「たゆたふ」にまで及ぶと考えられているのが妥当と思われる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しきたへ [敷妙・敷栲] | 〔名詞〕 ①寝床に敷く布。一説に織り目の細かい織物とも。 ②《女房詞》枕のこと。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しきたへの [敷妙の・敷栲の] | 【枕詞】 「敷き栲」が寝具として用いられることから、「枕」「床」「衣」「たもと」「袖」などに、 転じて「家」「黒髪」などにかかる。 |
玉藻刈る沖へは漕がじ敷栲の枕のあたり忘れかねつも(万1-72) -明星の 明くる朝は 敷栲の 床の辺去らず 立てれども 居れども-(万5-909) -大夫と 思へる我れも 敷栲の 衣の袖は 通りて濡れぬ(万2-135) -玉藻なす 靡き我が寝し 敷栲の 妹が手本を 露霜の-(万2-138) 敷栲の袖交へし君玉垂の越智野過ぎ行くまたも逢はめやも [一云 越智野に過ぎぬ] (万2-195) 置きていなば妹恋ひむかも敷栲の黒髪敷きて長きこの夜を[田部忌寸櫟子] (万4-496) -慕ひ来まして 敷栲の 家をも作り あらたまの 年の緒長く-(万3-463) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しきなぶ [敷き靡ぶ] | 〔他動詞バ行下二段〕【ベ・ベ・ブ・ブル・ブレ・ベヨ】 その地方や国土を統治する。くまなく支配する。 |
-我れこそ居れ しきなべて 我れこそ座せ-(万1-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しきに [頻に] | 〔副詞〕しきりに。たびたび。 | 一日には千重波しきに思へどもなぞその玉の手に巻き難き(万3-412) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しきます [敷きます] | 《上代語》[四段動詞「敷(し)く」の連用形+尊敬の補助動詞「ます」] お治めになる。 |
-大君の 敷きます国に うちひさす 都しみみに 里家は-(万3-463) -風流士の かづらのためと 敷きませる 国のはたてに 咲きにける-(万8-1433) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しく [及く・若く・如く] | 〔自動詞カ行四段〕 ① 追いつく。至りつく。 ② 肩を並べる。匹敵する。及ぶ。 |
① 後れ居て恋ひつつあらずは追ひ及かむ道の隈廻に標結へ我が背(万2-115) ② 夜光る玉といふとも酒飲みて心を遣るにあに及かめやも(万3-349) ② 銀も金も玉も何せむにまされる宝子にしかめやも(万5-807) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しく [敷く・頷く] | 〔自動詞カ行四段〕一面に広がる。一面に散らばる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞カ行四段〕 ① 物を平らに広げる。一面に置く。 ② 治める。領する。 ③ 広く及ぼす。広める。 |
① あらかじめ君来まさむと知らませば門に宿にも玉敷かましを(万6-1018) ② -神ながら 太敷きまして すめろきの 敷きます国と-(万2-167) ② 大君は神にしませば雲隠る雷山に宮敷きいます(万3-236) ② 天皇の 敷きます国の 天の下 四方の道には 馬の爪 -(万18-4146) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しくしく(と・に) [頗く頗く(と・に)] |
〔副詞〕うち続いて。しきりに。 | 楽浪の志賀さざれ波しくしくに常にと君が思ほえたりける(万2-206) 春雨のしくしく降るに高円の山の桜はいかにかあるらむ(万8-1444) 山吹は日に日に咲きぬうるはしと我が思ふ君はしくしく思ほゆ(万17-3997) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しぐれ [時雨] | 〔名詞〕 ① 秋の末から冬の初めにかけて、降ったり止んだり定めなく降る雨。[冬] ② 涙をこぼして泣くこと。 |
① うらさぶる心さまねしひさかたの天のしぐれの流れあふ見れば(万1-82) ① 神無月しぐれにぬるるもみぢばは ただわび人の袂なりけり(古今哀傷-840) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しげ [繁] | 〔名詞〕[形容詞「繁し」の語幹] 茂み。木が茂っているところ。 | - 御心を 見し明らめし 活道山 木立の茂に 咲く花も うつろひにけり-(万3-481) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しげし [茂し・繁し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① 草木が生い茂っている。 ② 量が多い。たくさんある。 ③ 絶え間ない。しきりである。 ④(数量・度数が多くて)煩わしい。うるさい。 |
①-大殿は ここと言へども 春草の 茂く生ひたる 霞立つ-(万1-29) ② 三笠山野辺行く道はこきだくも繁く荒れたるか久にあらなくに(万2-232) ③ -聞きの恐く [一云 諸人の 見惑ふまでに] 引き放つ 矢の繁けく-(万2-199) ④ 人言を繁み言痛みおのが世にいまだ渡らぬ朝川渡る(万2-116) ④ この世には人言繁し来む世にも逢はむ我が背子今ならずとも(万4-544) 【例歌③の「しげしく」】 「しげけく」は形容詞「しげし」のク語法。 【例歌④の「しげみ」】 「しげみ」は形容詞「しげし」のミ語法。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しげる [茂る・繁る] | 〔自動詞ラ行四段〕草木が伸びて、枝葉が重なり合う。 | ④ この世には人言繁し来む世にも逢はむ我が背子今ならずとも(万4-544) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しこ [醜] | 〔名詞〕醜いもの、ごつごつと頑強なものをさしていう語。 ののしりや、卑下の意がこめられる。 [語法] 直接体言に付いたり、多く格助詞「つ」「の」を伴って用いられる。 |
ますらをや片恋せむと嘆けども醜のますらをなほ恋ひにけり(万2-117) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しし [肉・穴] | 〔名詞〕肉。 | -み箱の皮に 我が肉は み膾はやし 我が肝も み膾はやし-(万16-3907) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しし [獣] | 〔名詞〕 ① 野獣。食用となる獣。特に、猪や鹿をさすことが多い。 両者を区別するときは「ゐのしし」「かのしし」と言った。 ② 「獣狩(ししが)り」の略。山野で獣をとること。 |
① -八十伴の男を 召し集へ 率ひたまひ 朝狩に 鹿猪踏み起し-(万3-481) ② 春日野に粟蒔けりせば鹿待ちに継ぎて行かましを社し恨めし(万3-408) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ししじもの [鹿じもの・猪じもの] | 【枕詞】 しし(=鹿・猪)のようにの意で、 「い這(は)ひ」「膝折(ひざをり)」「弓矢囲(かく)み」「水漬(みづ)く」などにかかる。 |
-あかねさす 日のことごと ししじものいはひ伏しつつ ぬばたまの- (万-199) -竹玉を 繁に貫き垂れ ししじもの 膝折り伏して たわや女の - (万3-382) -惑ひによりて 馬じもの 縄取り付け ししじもの 弓矢囲みて- (万6-1024) -ししじもの水漬くへごもり-(武烈紀) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しじに [繁に] | 〔副詞〕いっぱいに。数多く。ぎっしりの。 | みもろの 神名備山に 五百枝さし しじに生ひたる つがの木の-(万3-327) -繁に貫き垂れ 獣じもの 膝折り伏して たわや女の 襲取り懸け-(万3-382) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しじぬく [繁貫く] | 〔他動詞カ行四段〕(船ばたに櫂などを) たくさんとりつける。 | 大船に真梶しじ貫き大君の命恐み磯廻するかも(万3-371) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| した [下] | 〔名詞〕 ① 下方、底。② 目上の恩顧を蒙ること。おかげ。 ③ 地位・格式などの低いこと。またその人・地位。 ④ 年齢の若いこと。⑤ 力の足りないこと。負けそうなようす。 ⑥ 内、内部、裏。⑦ 内々。ひそか。表だたないこと。 ⑧ 心の中。心の奥。心底。⑨ 直後。⑩ 後部。 ⑪ 使い古しの品物を売り払うこと。下取り。 |
① 我が背子は仮廬作らす草なくは小松が下の草を刈らさね(万1-11) ① あすか川下濁れるを知らずして背ななと二人さ寝て悔しも(万14-3566) ⑥ 蒸し衾なごやが下に臥せれども妹とし寝ねば肌し寒しも(万4-527) ⑥ 我妹子が形見の衣下に着て直に逢ふまでは我れ脱かめやも(万4-750) ⑦ 秋山の木の下隠り行く水の我れこそ益さめ思ほすよりは(万2-92) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ゆ [下ゆ] | 心を表わす「下」に、上代の格助詞「ゆ」が付き、こっそり。 心の中で、人知れず。 |
隠り沼の下ゆは恋ひむいちしろく人の知るべく嘆きせめやも(万12-3035) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ゆくみづ [した行く水] | 物陰を流れる水。 | -したひ山 下行く水の 上に出でず 我が思ふ心 安きそらかも(万9-1796) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しだ | 〔名詞〕上代語。行きしな、帰りしななどの「しな」の古語。 「さだ」とも。とき。ころ。 |
我が面の忘れむしだは国はふり嶺に立つ雲を見つつ偲はせ(万14-3536) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しだごころ [下心] | 〔名詞〕 ① 内心・心底。表面に表さない気持ち。 ② あらかじめ心に期すること。かねてのたくらみ。 |
天雲のたなびく山の隠りたる我が下心木の葉知るらむ(万7-1308) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| したふ | 〔自動詞ハ行四段〕木の葉が赤く色づく。紅葉する。 | 秋山の したへる妹 なよ竹の とをよる子らは いかさまに-(万2-217) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| したふ [慕ふ] | 〔他動詞ハ行四段〕 ① 心がひかれてあとを追う。ついてゆく。 ② 恋しく思う。懐かしく思う。愛惜する。 ③ 手本とすべき人物について学ぶ。師事する。 |
-佐保の山辺に 泣く子なす 慕ひ来まして しきたへの-① (万3-463) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しづ [倭文] | 〔名詞〕[上代は「しつ」] 日本固有の織物の名。 栲(たえ)・麻・苧(お)などの横糸を青・赤などに染めて、乱れ縞模様に交ぜ織にしたもの。後には、旧式であることの象徴ともなった。 =倭文機(しづはた)・倭文織(いづおり)・倭文布(しどり)。 |
-ちはやぶる 神の社に 照る鏡 倭文に取り添へ 祈ひ祷みて-(万17-4035) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しづか [静か・閑か] | 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 ① 心が落ち着いているさま。やすらかなさま。 ② 物音のないさま。静かだ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しづく [沈く] | 〔自動詞カ行四段〕 ① 水底に沈んでいる。② 水面に映って見える。 |
① 水底に沈く白玉誰が故に心尽して我が思はなくに(万7-1324) ② 水の面にしづく花の色さやかにも君がみかげの思ほゆるかな(古哀-845) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しづく [雫・滴] | 水のしたたり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しづくも [雫も] | 〔副詞〕いささかも。つゆほども。すこしも。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しづけし [静けし] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 静かである。穏やかだ。落ち着いている。 |
-立ち騒くらし いざ子ども あへて漕ぎ出む にはも静けし(万3-391) 暁と夜烏鳴けどこの岡の木末の上はいまだ静けし(万7-1266) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しつのいはや [志都の岩屋] | 〔名詞〕 | 大汝少彦名のいましけむ志都の石屋は幾代経ぬらむ(万3-358) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 島根県大田市の真南約四四キロメートル、広島県との県境に近い邑智郡瑞穂町岩屋にある弥山(610メートル)の麓の大岩窟か。志都岩屋神社という社もある。 一説に大田市静間町海岸の岩窟かとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しづはた [倭文機] | 〔名詞〕[上代は「しつはた」] 「倭文(しづ)」 を織る織機。また、その機で織った布。=倭文 |
古に ありけむ人の 倭文幡の 帯解き交へて 廬屋立て-(万3-434) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しづまる [鎮まる・静まる] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 神が鎮座する。② 騒ぎや戦乱がおさまる。静かになる。 ③ 気性や態度が落ち着く。④ 寝静まる。⑤ 勢力が衰える。しおれる。 |
① -高くしたてて 神ながら 鎮まりましぬ しかれども-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しづむ [沈む] | 〔自動詞マ行四段〕 ① 水中に没する。水中を下方に移動する。沈む。⇔「浮かぶ・浮く」 ② 没落する。落ちぶれる。 ③ 罪・苦界などにおちこむ。死者の霊が成仏できない。 ④ ふさぎ込む。うちしおれる。⑤ なやみわずらう。病気になる。 ⑥ 勢いが弱くなる。⑦ 泣き伏す。 |
① 難波潟潮干なありそね沈みにし妹が姿を見まく苦しも(万2-229) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞マ行下二段四段〕【メ・メ・ム・ムル・ムレ・メヨ】 ① 水中に沈める。⇔「浮かぶ」② 没落させる。失意の状態にする。 ③ (評判などを) おとす。④ 質に入れる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しづむ [鎮む] | 〔他動詞マ行下二段〕【メ・メ・ム・ムル・ムレ・メヨ】 ① 神を鎮座させる。② 乱をおさえる。鎮定する。 ③ 気持ちを落ち着かせる。感情の高ぶりを抑える。 ④ 静かにさせる。寝静ませる。 |
② -水の激ぎちそ 日本の 大和の国の 鎮めとも います神かも-(万3-322) ③ 真木柱太き心はありしかどこの我が心鎮めかねつも(万2-190) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| して | [サ変動詞「為(す)」の連用形「し」に接続助詞「て」] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔格助詞〕 ① [使役の対象] ~に命じて。~に。~をして。 ② [手段・方法] ~で。~でもって。 ③ [人数・範囲] ~で。~とともに。 〔接続〕 体言及び活用語の連体形など体言に準じたものや格助詞「を」に付く。 |
③ -たもとほり ただひとりして 白たへの 衣手干さず 嘆きつつ-(万3-463) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| して | 〔接続助詞〕 「状態が~であって」の意で、下文に続ける。 ① [形容詞及び形容詞型活用の助動詞の連用形に付く場合] ~て。~で。 ② [形容動詞、断定の助動詞「なり・たり」などの連用形に付く場合] ~であって。~で。 ③ [「ずし」の形になる場合] ~(ない)で。~(なく)て。 |
① み薦刈る信濃の真弓引かずして弦はくるわざを知ると言はなくに [郎女] (万2-97) ⇒「ずして」 ① 秋山の黄葉を茂み惑ひぬる妹を求めむ山道知らずも [一云 路知らずして](万2-208) ① 玉櫛笥みもろと山を行きしかばおもしろくしてにしへ思ほゆ(万7-1244) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| して | 〔副助詞〕 副詞及び格助詞「を」「に」「より」「から」に付いて意味を強めたり、はっきりさせたりする。 |
これやこの大和にしては我が恋ふる紀路にありといふ名に負ふ背の山(万1-35) 陸奥の真野の草原遠けども面影にして見ゆといふものを(万3-399) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しでのたをさ [賎の田長] | 〔名詞〕ホトトギスの異名。 語源は「賎(しづ)の田長」で、田植えの時期を告げる鳥の意であったが、音の類似から「死出」に結び付けて、「死出の山」を越えて来る鳥と解されるようになった、という説がある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しなふ [撓ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 ① しなやかにたわむ。たおやかに美しい曲線をなす。 ② 逆らわずに従う。 |
① 真木の葉のしなふ勢能山しのはずて我が越え行けば木の葉知りけむ(万3-294) ① 立ちしなふ君が姿を忘れずは世の限りにや恋ひわたりなむ(万20-4465) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しなゆ [撓ゆ・萎ゆ] | 〔自動詞ヤ行下二段〕【エ・エ・ユ・ユル・ユレ・エヨ】 しおれる。しぼむ。 |
-いや高に 山も越え来ぬ 夏草の 思ひ萎えて 偲ふらむ-(万2-131) 君に恋ひ萎えうらぶれ我が居れば秋風吹きて月かたぶきぬ(万10-2302) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しぬ [死ぬ] | 〔自動詞ナ変〕【ナ(ズ)・ニ(タリ)・ヌ・ヌル(コト)・ヌレ(ドモ)・ネ】 命を失う。息が途絶える。死ぬ。 【参考】 死の忌まわしさを軽減するため、「絶(た)ゆ」「失(う)す」「はかなくなる」「隠る」など、婉曲に表現する数多くの別語がある。 |
旅にしてもの恋ほしきに鶴が音も聞こえざりせば恋ひて死なまし(万1-67) かくばかり恋ひつつあらずは高山の磐根しまきて死なましものを(万2-86) 君が家に我が住坂の家道をも我は忘れじ命死なずは(万4-507) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しの [篠] | 〔名詞〕群生する細い竹の総称。やだけ・めだけの類・しのだけ | うち靡く春さり来れば小竹の末に尾羽打ち触れて鴬鳴くも(万10-1834) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しのぐ [凌ぐ] |
〔他動詞ガ行四段〕 ① 押さえつける・押しふせる・踏み分けて進む ② 障害・困難を耐えしのぶ、またそれを乗り越える ③(相手を)凌駕する・押しのけて上に立つ ④あなどる・いやしめる |
① 奥山の菅の葉しのぎ降る雪の消なば惜しけむ雨な降りそね(万3-302) ① 宇陀の野の秋萩しのぎ鳴く鹿も妻に恋ふらく我れにはまさじ(万8-1613) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しのに | 〔副詞〕 ① なよなよとなびいて・しおれて、また心がしんみりとするさま ② しきりに・しげく |
① 近江の海夕波千鳥汝が鳴けば心もしのにいにしへ思ほゆ(万3-268) ② 逢ふことはかたのの里のささの庵しのに露散る夜半の床かな (新古恋二-1110) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しののに [しののに] | 〔副詞〕 (全身が濡れそぼつさまに用いて)しっとりと・びっしょりと |
朝霧にしののに濡れて呼子鳥三船の山ゆ鳴き渡る見ゆ(万10-1835) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しのはゆ [偲はゆ] | 《上代語》 〔なりたち〕「しのばゆ」とも。 [上代の四段動詞「偲ふ」の未然形「しのは」+上代の自発の助動詞「ゆ」] しのばれる。自然に思い出される。 |
大伴の高師の浜の松が根を枕き寝れど家し偲はゆ(万1-66) 印南野の浅茅押しなべさ寝る夜の日長くしあれば家し偲はゆ(万6-945) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しのぶ [忍] | 〔名詞〕①「忍ぶ草」の略。「忍摺(しのぶず)り」の略。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しのぶ [忍ぶ] | 〔他動詞バ行上二段〕【ビ・ビ・ブ・ブル・ブレ・ビヨ】 〔他動詞バ行四段〕 ① 堪える。堪える。② つつみ隠す。秘密にする。 |
① 世の中し常かくのみとかつ知れど痛き心は忍びかねつも(万3-475) ① 万代に心は解けて我が背子が捻みし手見つつ忍びかねつも(万17-3962) ① 古りにし嫗にしてやかくばかり恋に沈まむ手童のごと [恋をだに忍びかねてむ手童のごと](万2-129) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔自動詞バ行上二段〕【ビ・ビ・ブ・ブル・ブレ・ビヨ】 〔自動詞バ行四段〕 ① 隠れる。人目を避ける。 ② 感情をおさえる。こらえる。我慢する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しのぶ [偲ぶ] | 〔他動詞バ行四段・上二段〕【ビ・ビ・ブ・ブル・ブレ・ビヨ】 《上代は「しのふ」》 ① 思い慕う。恋う。懐かしむ。 ② 賞美する。 |
① 山越しの風を時じみ寝る夜おちず家なる妹を懸けて偲ひつ(万1-6) ① -山も越え来ぬ 夏草の 思ひ萎へて 偲ふらむ 妹が門見む-(万2-131) ① -振り放け見つつ 玉たすき 懸けて偲はむ 恐くありとも-(万2-199) ① 直に逢はば逢ひかつましじ石川に雲立ち渡れ見つつ偲はむ(万2-225) ① 高円の野辺の秋萩な散りそね君が形見に見つつ偲はむ(万2-233) ② -秋山の 木の葉を見ては 黄葉をば 取りてぞ偲ふ 青きをば-(万1-16) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 上代には「忍ぶ」はバ行上二段活用、「偲ぶ」は「しのふ」でハ行四段活用。二語は別語であったが、「人知れず思い慕う」のと、「人目にとまらぬようにする」のとは、意味の上で似ているので混同されるようになり、中古以降、「忍ぶ」は四段活用でも、「偲ぶ」は上二段活用でも用いられるようになった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しば [芝] | 〔名詞〕 野原や道端に生える雑草。今のシバのように背の低いものとは限らない。 一面に生えているところを芝生(しばふ)という。=芝草(しばくさ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しば [柴] | 〔名詞〕 山野の小さな雑木。また、薪や垣にするために折った、その枝。 柴木。柴(ふし)。 |
佐保川の岸のつかさの柴な刈りそねありつつも春し来らば立ち隠るがね(万4-532) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しば(しば) [屡] | 〔副詞〕しばしば。たびたび。しきりに。 |
【参考】 「しば鳴く」「しば立つ」「しば見る」 などのように、動詞に冠して用いられることが多い。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しばなく [屡鳴く] | 〔自動詞カ行四段〕繰り返し鳴く。 | -雲居たなびき 容鳥の 間なくしば鳴く 雲居なす 心いさよひ-(万3-375) ぬばたまの夜の更けゆけば久木生ふる清き川原に千鳥しば鳴く(万6-930) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しはつやま [四極山] | 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 『付録 地名一覧』」】 所在未詳。大阪市住吉区から東住吉区の東南部にかけての地の丘か。 巻六に「四極の海人」(九九九) とあり、「雄略紀」十四年の条にも見える「磯歯津路(しはつぢ)」と関係があろう。 一説に『和名抄』に参河国「幡豆郡磯泊 之波止」とあるのによって、愛知県幡豆郡幡豆町、吉良町ふきんとするものもある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しひ [椎] | 〔名詞〕ブナ科の常緑高木。実は食用となる。 | 家にあれば笥に盛る飯を草枕旅にしあれば椎の葉に盛る(万2-142) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しひ [志斐] | 〔氏名〕 | 否と言へど強ふる志斐のが強ひ語りこのころ聞かずて朕恋ひにけり(万3-237) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-236 注『志斐のが』」】「「志斐」は氏名。 新撰姓氏録に、楊の花を辛夷(こぶし)の花だと強弁した阿倍志斐連名代(あえのしいのむらじなしろ)の話を天武朝のこととして載せる。 この一族か。老婆であったことが題詞の「嫗(おみな)」から分かる。名は不明。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しひがたり [強ひ語り] | 〔名詞〕無理に話を聞かせること。また、その話。 | 否と言へど強ふる志斐のが強ひ語りこのころ聞かずて朕恋ひにけり(万3-237) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しふ [強ふ] | 〔他動詞ハ行上二段〕【ヒ・ヒ・フ・フル・フレ・ヒヨ】 無理強いをする。強いる。嫌がる相手に強く実行を迫る。 |
否と言へど強ふる志斐のが強ひ語りこのころ聞かずて朕恋ひにけり(万3-237) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しほ [塩] | 〔名詞〕① 食塩。塩加減。塩味。 | -網の浦の 海人娘子らが 焼く塩の 思ひぞ焼くる 我が下心(万1-5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しほ [潮・汐] | 〔名詞〕 ① 海水。海水の干満。 ② よい機会。よい頃合い。しおどき。 ③ 愛嬌。愛らしさ。 |
① 夕さらば潮満ち来なむ住吉の浅香の浦に玉藻刈りてな(万2-121) ① -夕されば 潮を満たしめ 明けされば 潮を干れしむ 潮さゐの-(万3-391) ① 若の浦に潮満ち来れば潟をなみ葦辺をさして鶴鳴き渡る(万6-924) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しほさゐ [潮騒] | 〔名詞〕潮の満ちてくるとき、波が立ち騒ぐこと。 | 潮騒に伊良虞の島辺漕ぐ舟に妹乗るらむか荒き島廻を(万1-42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しほつやま [塩津山] | 〔山名〕 | 塩津山うち越え行けば我が乗れる馬そつまづく家恋ふらしも(万3-368) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滋賀県伊香郡西浅井町の塩津浜から沓掛を経て福井県の敦賀に越えるいわゆる塩津越えの山。 塩津の地名は、越前産の塩を塩津越えで運び、ここから大津まで湖上輸送したところから出た。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しほひ [潮干] | 〔名詞〕潮の引くこと。また、潮の引いた海岸。 |
難波潟潮干なありそね沈みにし妹が姿を見まく苦しも(万2-229) 桜田へ鶴鳴き渡る年魚市潟潮干にけらし鶴鳴き渡る(万3-273) 潮干の三津の海女のくぐつ持ち玉藻刈るらむいざ行きて見む(万3-296) 荒津の海潮干潮満ち時はあれどいづれの時か我が恋ひざらむ(万17-3913) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-293 注 『塩干乃』」】 原文「塩干乃」とある。旧訓にシホカレノとあるが、万葉考にシホヒノと訓んだ。 そこで、カレとヒの語はいかなる語に用いられるかについて検すると「海は潮干(しほひ)て山は枯(かれ)すれ」(16・三八五二) を始めとして、集中、潮と涙と袖(衣袖コロモデを含む) についてはヒル、霜と水と山と植物についてはカルというように明瞭に区別がある。したがって、ここはシホヒノと四音で字足らずに訓む(大島信生説)。初句に字足らずの例は多い。 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 巻三-293 頭注『潮干(シホカレ)』」】 引潮。『高橋氏文』に、「船潮涸(しほかれ)ニ遇ヒテ」とある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しほやき [塩焼き] | 〔名詞〕海水を煮詰めて塩を作ること。また、その人。 | 志賀の海女は軍布刈り塩焼き暇なみくしげの小櫛取りも見なくに(万3-281) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『製塩法について』 奈良時代や平安時代には、どのような方法で製塩したのかあまり明らかではない。 たぶん、海藻を焼いて作る方法や、海辺に建てた塩屋の中で、塩尻(しおじり)や塩浜(=ともに塩田)の塩砂を塩釜に入れて煮る方法が行われたのであろう。 塩浜を作り、天日を利用した製塩法も早くから行われていたかもしれないが、こうした製塩法が進歩したのは室町時代からで、土手を築く方法も瀬戸内海その他ではじめられ、江戸時代に発達した。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しま [島] | 〔名詞〕 ① 周囲を水に囲まれた陸地。 ② (「山斎」 とも書く) 庭の泉水の中の築山(つきやま)。 また、築山・泉水のある庭園。 ③ (近世語) 特定の地域。特に、遊郭・色町。 |
① -行く船の 梶引き折りて をちこちの 島は多けど 名ぐはし-(万2-220) ① 大大和道の島の浦廻に寄する波間もなけむ我が恋ひまくは(万4-554) ② 妹としてふたり作りし我が山斎は木高く茂くなりにけるかも(万3-455) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しまし [暫し] | 〔副詞〕《上代語》「しばし」の古形。= 暫 (しま) しく。少しの間。 | 霍公鳥間しまし置け汝が鳴けば我が思ふ心いたもすべなし(万15-3807) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しましく [暫しく] | 〔副詞〕《上代語》⇒ しまし。しばらくの間。 | 秋山に落つる黄葉しましくはな散り乱ひそ妹があたり見む [一云 散りな乱ひそ] (万2-137) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しまづたふ [島伝ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕(船が) 島から島へと伝っていく。 | 島伝ひ敏馬の崎を漕ぎ廻れば大和恋しく鶴さはに鳴く(万3-392) -真楫貫き 礒漕ぎ廻つつ 島伝ひ 見れども飽かず み吉野の-(万13-3246) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しまと [島門] | 〔名詞〕島と島、または島と陸地との間の狭い水路。島の瀬戸。 | 大君の遠の朝廷とあり通ふ島門を見れば神代し思ほゆ(万3-307) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しまみ [島回・島曲・島廻] | 〔名詞〕島のまわり。島の周囲。 | 潮騒に伊良虞の島辺漕ぐ舟に妹乗るらむか荒き島廻を(万1-42) 百伝ふ八十の島廻を漕ぐ舟に乗りにし心忘れかねつも(万7-1403) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔名詞・自動詞サ変〕島を廻ること。島めぐり。 | 島廻すと磯に見し花風吹きて波は寄すとも採らずはやまじ(万7-1121) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しまのみや(しまのみかど) [島の宮(御門)] |
嶋の宮まがりの池の放ち鳥人目に恋ひて池に潜かず(万2-170) 光る我が日の御子のいましせば島の御門は荒れざらましを(万2-173) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻二 170」 注】 草壁皇子の宮殿を島の宮という。現在の明日香の島の庄すなわち石舞台古墳附近にあったことは確実と言われる(岸俊男「万葉集と遺跡」 国文学昭和五十三燃四月)。 天武元年紀に「倭京に詣りて嶋宮に御す」 とあるのも、同五年正月紀に「天皇、嶋宮に御して宴しき」 とあるのも同じ宮を指す。 庭に池を作り、池の中に小嶋を築く造園法が当時として珍しかったところからの呼称である。 なお、「嶋の大臣」 と呼ばれた蘇我馬子の家と直結して考えられるものかどうかは、まだ不明という(岸前掲稿)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しまやま [島山] | 〔名詞〕 ① 島と山。島の中の山。また、川や水に面した島のような地勢。 ② 庭園の池の中に作った山。 |
① -さはにあれども 島山の 宣しき国と こごしかも 伊予の高嶺の-(万3-325) ① 島山を い行き廻れる 川沿ひの 岡辺の道ゆ 昨日こそ-(万9-1755) ② -八十伴の男の 島山に 赤る橘 うずに刺し 紐解き放けて-(万19-4290) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しみさぶ [茂みさぶ・ 繁みさぶ] | 〔自動詞バ行上二段〕【ビ・ビ・ブ・ブル・ブレ・ビヨ】 [「さぶ」は接尾語] こんもりと繁っている。木や草が深く茂っている。 |
-日の経の 大御門に 春山と 茂みさび立てり 畝傍の この瑞山は-(万1-52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しみづ [清水] | 〔名詞〕清らかな湧き水。 | 山吹の立ちよそひたる山清水汲みに行かめど道の知らなく (万2-158) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しみみに [茂みみに] | 〔副詞〕[「しみしみに」の転] よく茂って。茂り満ちて。すきまなく。=茂(し)みに |
-敷きます国に うちひさす 都しみみに 里家は さはにあれども-(万3-463) 忘れ草垣もしみみに植ゑたれど醜の醜草なほ恋ひにけり(万12-3076) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しむ [染む・浸む] | 〔自動詞マ行四段〕 ① (色に)染まる。色・香りが染みつく。 ② ひたる。うるおう。しみ込む。 ③ 深く感じる。心にしみる。 ④ 熱心になる。関心をもつ。執着する。 |
① 蓮葉(はちすば)の濁りにしまぬ心もてなにかは露をたまとあざむく(古今夏-165) ② なかなかに人とあらずは酒壷に成りにてしかも酒に染みなむ(万3-346) ③ 韓人の衣染むといふ紫の心に染みて思ほゆるかも(万4-572) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞マ行下二段〕【メ・メ・ム・ムル・ムレ・メヨ】 ① 染まるようにする。染める。色・香りをしみ込ませる。 ② 深く心にとめる。深く思いつめる。 |
① 託馬野に生ふる紫草衣に染めいまだ着ずして色に出でにけり(万3-398) ① 我が衣色取り染めむ味酒三室の山は黄葉しにけり(万7-1098) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しむ [凍む] | 〔自動詞マ行上二段〕【ミ・ミ・ム・ムル・ムレ・ミヨ】 冷気がしみる。こおる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しむ | 〔使役の助動詞〕 [だれかにそうさせるように仕向けて起こった事態であることを示す語] 「~せる」「~させる」ぶ ① 使役の意を表す。「~させる」 ② (多く「しめ給ふ」の形で) 程度の高い尊敬の意を表す。「お~なさる」 ③ 謙譲の語に付いて、程度の高い謙譲の意を表す。 〔接続〕活用語の未然形に付く。 |
① 我が岡のおかみに言ひて降らしめし雪のくだけしそこに散りけむ (万2-104) ① 暇なく人の眉根をいたづらに掻かしめつつも逢はぬ妹かも(万4-565) ① 恨めしく君はもあるか宿の梅の散り過ぐるまで見しめずありける (万20-4520) ③ 古人の飲へしめたる吉備の酒病まばすべなし貫簀賜らむ(万4-557) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【語法】 上代では使役の意味として用いられた。中古では、使役の「す・さす」が一般に用いられ、使役の「しむ」は、漢文訓読などの特殊な領域だけに用いられるようになる。 また、尊敬の意味として用いられるようになるのは中古からである。中古以後は使役・尊敬、さらに末期になって現れた謙譲の三用法がある。 物語における用例は男性のことばの場合がほとんどになる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しめ [標] | 〔名詞〕 ①(「占め」の意) 土地の領有や場所の区画を示し、人の立ち入りを禁じるための標識。 木を立てたり縄を張ったりする。また山道などの道しるべの標識。 ②「標縄」の略。 |
① 山守はけだしありとも我妹子が結ひけむ標を人解かめやも(万3-405) ① 大伴の遠つ神祖の奥城はしるく標立て人の知るべく(万18-4120) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【発展 「しめ」と「しめなは」】 「しめ」は下二段動詞「しむ(占む・標む)」の名詞形である。 「しめ」を設置する方法としては、草や枝をひき結んだり、わら・萱・などでいわゆる「しめなは」を張ったり、くいを立てたりする。 そこで「しめゆふ」「しめたつ」「しめさす」などの言い方が生れる。 中古以降は「しめなは」は神域などの聖なる場所を示すものとして用いられ、それ自体に呪術的な威力を認める考え方も生れた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しめす [示す] | 〔他動詞サ行四段〕 ① 表して見せる。示す。 ② (神仏などが) 告げ知らせる。(夢などで) 教え告げる。 |
① 潮干なば玉藻刈りつめ家の妹が浜づと乞はば何を示さむ(万3-363) ① にほ鳥の潜く池水心あらば君に我が恋ふる心示さね(万4-728) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しめの [標野] | 〔名詞〕 上代、皇室などの所有する原野で、一般の人の立ち入りを禁じた所。 狩場などにされた。禁野 (きんや)。 |
あかねさす紫野行き標野行き野守は見ずや君が袖振る(万1-20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しめゆふ [標結ふ] | 〔他ハ行四段〕 ① 草をひき結んで道しるべとする。 ② 領有や立ち入り禁止を表すためにしめなわを張る。 ③ 夫婦仲を契る。 |
① 後れ居て恋ひつつあらずは追ひ及かむ道の隈廻に標結へ我が背(万2-115) ② 楽浪の大山守は誰がためか山に標結ふ君もあらなくに(万2-154) ② 赤駒の越ゆる馬柵の標結ひし妹が心は疑ひもなし(万4-533) ③ 標結ひて我が定めてし住吉の浜の小松は後も我が松(万3-397) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しめの [示す] | 〔他サ行四段〕 ① 表してみせる。示す。 ②(神仏などが) 告げ知らせる。(夢などで) 教え告げる。 |
① にほ鳥の潜く池水心あらば君に我が恋ふる心示さね(万4-728) ② 我妹子に猪名野は見せつ名次山角の松原いつか示さむ(万3-282) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しも [霜] | 〔名詞〕霜。また、白髪をたとえていう。 | ありつつも君をば待たむうち靡く我が黒髪に霜の置くまでに(万2-87) -さやかに見れば 栲の穂に 夜の霜降り 岩床と-(万1-79) -蜷の腸 か黒き髪に いつの間か 霜の降りけむ-(万5-808) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しも [下] | 〔名詞〕 ① 位置の低いところ。下の方。②川の下流。川下。 ③ 官位や身分の低い者。また、(君主・朝廷に対して)臣下。人民。 ④ 和歌の下の句。七・七の二句。⇔上(かみ) ⑤ 年下の人。年少者。⑥後の部分。終りの方。⑦後の時代。後世。 ⑧ 宮中や貴人の家で、女房の詰め所。局。 ⑨ 裏手。裏側。⑩月の下旬。⇔「上(かみ)」 |
② -上つ瀬に 鵜川を立ち 下つ瀬に 小網さし渡す-(万1-38) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しも →「主要助詞」 | 〔副助詞〕[副助詞「し」に係助詞「も」の付いたもの] ① 強意を表す。 ~それそのもの。 ② とりたて。特にその事柄を取り立てて示す意を表す。 よりによって。~にかぎって。 ③(活用語の連体形に付いて)(~にもかかわらず)かえって、の意。 ④(打消の語と呼応して)かならずしも(~ではない)、の意を表す。 〔接続〕 体言・格助詞など様々の語に付く。 用法状は主語・連用修飾語、接続助詞に付く。 「係助詞」とする説もある。 |
① -万代に しかしもあらむと [一云 かくしもあらむと] 木綿花の-(万2-199) ① 旅に去にし君しも継ぎて夢に見ゆ我が片恋の繁ければかも(万17-3951) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しもつせ [下つ瀬] | 〔名詞〕川の下流の瀬。 | - 明日香の川の 上つ瀬に 生ふる玉藻は 下つ瀬に 流れ触らばふ-(万2-194) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しらか [白香] | 〔名詞〕 麻・楮などの樹皮の繊維を白くさらし、細かく裂いて白髪のようにし、束ねたもの。神事に用いる。 |
-神の命 奥山の さかきの枝に しらか付け 木綿取り付けて-(万3-382) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -つく [白香つく] | 【枕詞】「ゆふ(木綿)」 にかかる。 | しらかつく木綿は花もの言こそばいつのまえだも常忘らえね(万12-3009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しらきのくに [新羅の国] | 【小学館「新編日本古典文学全集萬葉集 付録『地名一覧』」】 朝鮮半島の東南部にあって平安時代初めまでわが国と外交関係があった。万葉集巻第十五には、天平八年(736年) に遣わされた遣新羅使人の歌が収められており、『懐風藻』には新羅使とわが官人との文学交流の詩も残る。「キ」 は清音。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しらく [白く] | 〔自動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 ① 白くなる。② きまりが悪くなる。③ 興ざめる。 |
① ぬばたまの黒髪変はり白けても痛き恋にはあふ時ありけり(万4-575) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 打ち明ける。白状する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しらくも [白雲] | 〔名詞〕 白い雲。はくうん。 |
大君は千歳にまさむ白雲も三船の山に絶ゆる日あらめや(万3-244) ここにして家やもいづち白雲のたなびく山を越えて来にけり(万3-290) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しらくもの [白雲の] | 【枕詞】 ① 雲が湧きあがったり、消えたり、山にかかったりすることから、 同音を含む「立つ・竜田の山」にかかる。 ② 白雲が途切れる意から、「絶(た)ゆ」にかかる。 |
① 惜しむから恋しきものを 白雲のたちなむのちは なに心地せむ(古今離別-371) ① 白雲の 龍田の山の 露霜に 色づく時に うち越えて 旅行く君は-(万6-976) ② 白雲の絶えにし妹をあぜせろと心に乗りてここば愛しけ(万14-3538) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しらしめす [知らし召す・ 領らし召す] |
〔他動詞サ行四段〕 [四段動詞「知る」の未然形「しら」に上代の尊敬の助動詞「す」の付いた「しらす」の連用形「しらし」に尊敬の補助動詞「召す」が付いて一語になったもの] 「知るの尊敬語」。 お治めになる。統治なさる。 |
-楽浪の 大津の宮に 天の下 知らしめしけむ 天皇の-(万1-29) - 日女の命 [一云 さしあがる 日女の命] 天をば 知らしめすと-(万2-167) 高御座 天の日継と 天の下 知らしめしける 天皇の 神の命の-(万18-4122) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しらす [知らす・領らす] | 〔なりたち〕「知る」の尊敬語。 [四段動詞「知る」の未然形「しら」+上代の尊敬の助動詞「す」] お治めになる。統治なさる。 |
-絶ゆることなく この山の いや高知らす 水激る 瀧の宮処は-(万1-36) 思はぬを思ふと言はば大野なる三笠の杜の神し知らさむ(万4-564) -あをによし 奈良の都に 万代に 国知らさむと やすみし-(万19-4290) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しらず [知らず] | 〔動詞「知る」 の未然形+打消の助動詞「ず」〕 ① わからない。見当がつかない。 ② (断定を差し控え、下に疑問の終助詞「か」 を伴って) さあ、~だろうか。~かしら。 ③ (話題に取り上げるのを差し控え、~は知らず」の形で) ~はさておいて。~はともかく。 |
① -数多くなりぬれ そこ故に 皇子の宮人 ゆくへ知らずも-(万2-167) ① ひさかたの天知らしぬる君故に日月も知らず恋ひわたるかも(万2-200) ① -言ひも得ず名付けも知らず奇しくもいます神かも 石花の海と-(万3-322) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しらすげの [白菅の] | 【枕詞】白菅(=草の名)の名所である「真野(まの)」にかかる。 | いざ子ども大和へ早く白菅の真野の榛原手折りて行かむ(万3-283) 白菅の真野の榛原行くさ来さ君こそ見らめ真野の榛原(万3-284) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しらとり [白鳥] | 〔名詞〕羽毛の白い鳥。白鳥や鷺など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しらとりの [白鳥の] | 【枕詞】白い鳥である「鷺(さぎ)」、鳥が「飛ぶ」の音から「鳥羽(とば)」にかかる。 | 白鳥の鷺坂山の松蔭に宿りて行かな夜も更けゆくを(万9-1691) 白鳥の飛羽山松の待ちつつそ我が恋ひ渡るこの月ごろを(万4-591) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しらなみ [白波・白浪] | 〔名詞〕 ① 白く立つ波。 ②(後漢書に見える賊の名「白波族(はくはぞく)」から) 盗賊の異称。 |
① -沖見れば とゐ波立ち 辺を見れば 白波騒く いさなとり-(万2-220) ① 我が命しま幸くあらばまたも見む志賀の大津に寄する白波(万3-291) ① 白波の浜松が枝の手向け草幾代までにか年の経ぬらむ [一云 年は経にけむ] (万1-34) 【「万1-34」】 この歌の「しらなみの」は「枕詞」でなく実景を伴うが、「白波の(寄す)浜」の述語にあたる「よす」を省いた形で、「枕詞的用法」とされる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しらなみの [白波の・白浪の] | 【枕詞】波の連想から、「よる」「かへる」「「うち」などにかかる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しらに [知らに] | 〔なりたち〕 [四段動詞「知る」の未然形「しら」+打消の助動詞「ず」の上代の連用形「に」] 知らないで。知らないので。 |
埴安の池の堤の隠り沼のゆくへを知らに舎人は惑ふ(万2-201) 鴨山の岩根しまける我をかも知らにと妹が待ちつつあるらむ(万2-223) 山守がありける知らにその山に標結ひ立てて結ひの恥しつ(万3-404) -旅にしあれば 思ひ遣る たづきを知らに 網の浦の 海人娘子らが-(万1-5) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻二-201 考『「不知」の訓について」』】 前歌の〔注〕にも記したとおり、「不知」はシラニと読む場合と、シラズと読む場合と二通りある。佐伯梅友『万葉語研究』に、確実にシラニの例とされるもの (万葉二一例、記紀四例) と、シラズの例(六例) とを比較し、前者は「思ひやる たづき白土(シラニ) 網の浦の あま乙女らが 焼く塩の 思ひそ焼くる」(1・五) のように、次に来る事柄、すなわちこの歌なら「思ひそ焼くる」の理由を表す時に用い、後者は「かくのみや息づき居らむあらたまのきへゆく年の限り斯良受堤」(5・八八一) のように単に状態を表す時に用いているという。万葉集燈に「白土は里言にシラヌノデといふ心也」とし、美夫君志に「にはぬの活きたる也。白土(しらに)は俗にシラヌノデといふ意なり。しらずといふとは少し異なり。」と記すことも、単なるあて推量ではなかったと言うことができる。『万葉語研究』に、「シラニ」の「ニ」について、「『ニ』は誰もいふ如く打消しの『ぬ』の活用で、連用形であるが、万葉時代には既に『知ラニ』と『カテニ』とだけであると言ってもよい位に用途が限られ、同時にその意味も限られてしまってゐる。而してその用法意味は『高ミ』『遠ミ』等に頗る相似たるものがある」と説いているのも注目される。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しらぬひ [不知火] | 〔名詞〕 陰暦七月晦日ごろの深夜に、九州の有明海や八代海で見えるという無数の火影。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しらぬひ [不知火] | 【枕詞】「筑紫(つくし)」にかかる。 | しらぬひ筑紫の綿は身に付けていまだは着ねど暖けく見ゆ(万3-339) 大君の 遠の朝廷と しらぬひ 筑紫の国に 泣く子なす 慕ひ来まして-(万5-798) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しらまゆみ [白真弓・白檀弓] | 【枕詞】 弓は弦(つる)を張り、それを引いて射る、の意から、「はる」「ひく」「い」などにかかる。 |
天の原振り放け見れば白真弓張りてかけたり夜道は良けむ(万3-292) 白真弓いま春山に行く雲の行きや別れむ恋しきものを(万10-1927) 天の原行きて射てむと白真弓引きて隠れる月人壮士(万10-2055) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しる [知る] | 〔他動詞ラ行四段〕 ① (「領る」「治る」ともかく) ア:治める。統治する。 イ:領有する。占める。 ② 理解する。認識する。③ 経験する。体験する。 ④ 世話する。面倒をみる。⑤ 付き合う。交際する。 |
① ア- ひさかたの天知らしぬる君故に日月も知らず恋ひわたるかも(万2-200) ② -我が作る 日の御門に 知らぬ国 寄し巨勢道より 我が国は- (万1-50) ② -人目を多み まねく行かば 人知りぬべみ さね葛 後も逢はむと-(万2-207) ② かくばかり恋ひむものぞと知らませば遠くも見べくあらましものを (万11-2376) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔自動詞ラ行四段〕 わかる。 |
み吉野の滝の白波知らねども語りし継げば古思ほゆ(万3-316) ももしきの大宮人の熟田津に船乗りしけむ年の知らなく(万3-326) 岩戸破る手力もがも手弱き女にしあればすべの知らなく(万3-422) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 知らせる。 |
我が思ひを人に知るれか玉櫛笥開きあけつと夢にし見ゆる(万4-594) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しるし [標・印・証] | 〔名詞〕 ① 他と区別のつく目印。② 証拠。③ 合図。 |
① 人漕がずあらくもしるし潜きする鴛鴦とたかべと船の上に住む(万3-260) ② 引間野ににほふ榛原入り乱れ衣にほはせ旅のしるしに(万1-57) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しるし [験・徴] | 〔名詞〕① 前兆。② 霊験。効き目。 | ② 験なき物を思はずは一坏の濁れる酒を飲むべくあるらし(万3-341) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しるし [璽] | 〔名詞〕三種の神器の一つ。神璽。八坂瓊(やさかに)の曲玉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しろ [白] | 〔名詞〕色の名。雪や塩のような色。多く複合語の中に用いられる。 | 田子の浦ゆうち出でて見ればま白にそ富士の高嶺に雪は降りける(万3-321) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しろかみ [白髪] | 〔名詞〕 [「しらかみ」とも] 白くなった頭髪。=白髪(しらが・はくはつ) |
-我が黒髪の ま白髪に 成りなむ極み 新た代に 共にあらむと-(万3-484) 黒髪に白髪交り老ゆるまでかかる恋にはいまだあはなくに(万4-566) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しろし [白し] | 〔形容詞ク活用名詞〕【カラ・ク(カリ)シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① 色が白い。② 生地のままで、色がついていない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しろたへ [白栲・白妙] | 〔名詞〕 ① こうぞ(=木の名)の繊維で織った白い布。 ② 白い色。白いこと。 |
① 春過ぎて夏来るらし白栲の衣干したり天の香具山(万1-28) ① -神宮に 装ひまつりて 使はしし 御門の人も 白栲の 麻衣着て-(万2-199) ② 梅が枝に鳴きて移ろふ鴬の羽白妙に沫雪ぞ降る(万10-1844) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しろたへの [白栲の] | 【枕詞】 白栲で衣服を作ることから「衣」「袂」「袖」「帯」「紐」などに、 また、その白いことから「雲」「雪」「波」などにかかる。 |
白栲の手本ゆたけく人の寝る味寐は寝ずや恋ひわたりなむ(万12-2975) 夜も寝ず安くもあらず白栲の衣は脱かじ直に逢ふまでに(万12-2857) 白栲の袖別るべき日を近み心にむせひ音のみし泣かゆ(万4-648) まそ鏡照るべき月を白栲の雲か隠せる天つ霧かも(万7-1083) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| す | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| す [為] | 〔自動詞サ行変格〕【セ・シ・ス・スル・スレ・セヨ】 ① ある動作が起こる。ある行為がなされる。 ② さまざまの他の自動詞の代用とする。 〔他動詞サ変〕 ③ ある動作を行う。ある行為をする。 ④ さまざまの他の他動詞の代用とする。 【参考】 サ行変格活用の動詞には「す・おはす」がある。「す」は体言に付いてさまざまな複合動詞を作る。 |
我れはもや安見児得たり皆人の得かてにすといふ安見児得たり(万2-95) ますらをや片恋せむと嘆けども醜のますらをなほ恋ひにけり(万2-117) 見まく欲り我がする君もあらなくに何しか来けむ馬疲るるに(万2-164) さつき待つ花たちばなの香をかげば昔の人の袖の香ぞする (古今夏-139) ① 朝日照る嶋の御門におほほしく人音もせねばまうら悲しも(万2-189) ① 武庫の海船庭ならしいざりする海人の釣船波の上ゆ見ゆ(万3-258) ① 人漕がずあらくもしるし潜きする鴛鴦とたかべと船の上に住む(万3-260) ③ 畑子らが夜昼といはず行く道を我れはことごと宮道にぞする(万2-193) ③ -せむすべ知らに 音のみを 聞きてあり得ねば 我が恋ふる-(万2-207) ③ 芦北の野坂の浦ゆ船出して水島に行かむ波立つなゆめ(万3-247) ④ -太敷きいまし みあらかを 高知りまして 朝言に 御言問はさぬ-(万2-167) ④ あかねさす日は照らせれどぬばたまの夜渡る月の隠らく惜しも(万2-169) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| す →「主要助動詞活用表」 | 〔助動詞〕 | み立たしの島を見る時にはたづみ流るる涙止めそかねつる(万2-178) -任けたまへば 大御身に 大刀取り佩かし 大御手に 弓取り持たし-(万2-199) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| す | 〔助動詞四型〕《上代語》軽い尊敬、親愛の意を表す。 ⑤ お~になる。~なさる。 〔接続〕四段・サ変の動詞の未然形に付く |
⑤ -任けたまへば 大御身に 大刀取り佩かし 大御手に 弓取り持たし-(万2-199) ⑤ この岡に 菜摘ます子 家聞かな 告らさね そらみつ 大和の国は-(万1-1) ⑤ -天地の いや遠長く 偲ひ行かむ 御名にかかせる 明日香川-(万2-196) ⑤ -我が大君の 万代と 思ほしめして 作らしし 香具山の宮 万代に-(万2-199) ⑤ 我が背子が宿なる萩の花咲かむ秋の夕は我れを偲はせ(万20-4468) ⑤ 莫囂円隣之大相七兄爪謁気我が背子がい立たせりけむ厳橿が本 (万1-9) (青:難訓) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| す | 〔助動詞下二段型〕【セ・セ・ス・スル・スレ・セヨ】 ① 使役の意を表す。~せる。 ② 尊敬の動詞「賜ふ」「宣(のたま)ふ」などに付いて、 最高の尊敬の意を表す。 ③ 謙譲の動詞「参る」「奉る」「申す」などに付いて、謙譲の意を強める。 ④ 尊敬の補助動詞「給ふ」「おはします」「まします」、 尊敬助動詞「らる」などとともに用いて、尊敬の意を更に強める。 [最高敬語。] お~になられる。~なされる。 ⑤ 受け身の「る」に代えて用いる。~れる。 [接続] 四段・ナ変・ラ変・の動詞の未然形に付く。 上一段・上二段・下一段・下二段・カ変・サ変に接続する「さす」と、 対応する。→さす(助動詞下二段型) |
① 我妹子に猪名野は見せつ名次山角の松原いつか示さむ(万3-282) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ず | 〔助動特殊型〕
② 連体形「ぬ」が終助詞「か」に続いて願望の意。~してほしい。 ③ 已然形「ね」が接続助詞「ば」に続き、逆接仮定条件。~ないのに。 〔接続〕用言および助動詞の未然形に付く |
① -草枕 旅にしあれば 思ひ遣る たづきを知らに 網の浦の-(万1-5) 神風の伊勢の国にもあらましを何しか来けむ君もあらなくに(万2-163) 嶋の宮まがりの池の放ち鳥人目に恋ひて池に潜かず(万2-170) み立たしの島の荒礒を今見れば生ひざりし草生ひにけるかも(万2-181) 畑子らが夜昼といはず行く道を我れはことごと宮道にぞする(万2-193) 人言を繁み言痛み逢はざりき心あるごとな思ひ我が背子(万4-541) おろかにぞ我れは思ひし乎布の浦の荒礒の廻り見れど飽かずけり (万18-4073) ② 我が命も常にあらぬか昔見し象の小川を行きて見むため(万3-335) ③ 我が宿の萩の下葉は秋風もいまだ吹かねばかくぞもみてる(万8-1632) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【語法】 この打消しの助動詞は「ず」の系列と「ぬ」の系列から成り、さらにその不備な用法、すなわち他の助動詞との接続関係を補う意味で、連用形「ず」に動詞「あり」がついた「ざり」の系列が生じた。未然形「な」・連用形「に」は上代に限って用いられたが、以後も和歌などには擬古的に用いられた。また多くはないが、上代には助動詞「けり」「けむ」「き」などが「ざり」にではなく、直接「ず」に接続した。 なお、連体形「ざる」が助動詞「なり (伝聞・推定)」「めり (推量)」につづく場合、撥音便になる、その撥音「ん」を表記しなかったので「ざなり」「ざめり」となっていった。 【参考】 連用形「ず」に係助詞「は」のついた「ずは」を、未然形「ず」に接続助詞「ば」のついたものと考えて、未然形「ず」を認める説があるが、今日では接続助詞「ば」の類推からで、正しくは係助詞であるとして、未然形「ず」を認めない説が有力である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔助動サ変型〕【○・○・ズ・ズル・ズレ・○】 「むとす」が詰って「むず」「んず」「うず」となり、さらに「ず」となったもの。 意志の意を表わす。~よう。 〔接続〕未然形につく |
【参考】打消しの助動詞「ず」も未然形につくので誤りやすい。「むとす」になおして意味が通じればこの意志を表わす「ず」だと判別するより他はない。現在も中部地方の方言として残っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ずあり [不~有] | 一般的に「不~有」表記は、「ずあり」と訓まれるのが多いと思うが、諸注さまざま。 「古義」においても、 不喧有之(ナカザリシ)は、冬は鳴ず有しなり。 不開有之(サカザリシ)は、冬は開ず有しなり。 のように、たんなる「約」のように述べている。 そうなると、語調によるところも、大きくなるだろう。 |
-鳴かざり(ずあり)し 鳥も来鳴きぬ 咲かざり(ずあり)し-(万1-16) 娘子らが玉櫛笥なる玉櫛の神さびけむも妹に逢はずあれば(万4-525) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すう [据う] | 〔他動詞ワ行下二段〕【エ・エ・ウ・ウル・ウレ・エヨ】 ① きちんと置く。一定の位置に置く ② とどめおく。人を置く。見張りをさせる。③ (種などを) まく。植え付ける。 ④ (鳥などを) とまらせる。⑤ (人を) すわらせる。 ⑥ 地位につける。妻として迎える。⑦ 設ける。設置する。 ⑧ おちつかせる。しずめる。⑨ 判を押す。印を押す。⑩ 灸をすえる。 |
① -斎ひ掘り据ゑ 竹玉を しじに貫き垂れ 鹿じもの 膝折り伏して-(万3-382) ⑦ -枕辺に 斎瓮を据ゑ 竹玉を 間なく貫き垂れ 木綿だすき-(万3-423) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すが [菅] | 〔名詞〕 すげ(=草の名)。多く、複合語で用いられる。 |
奥山の菅の葉しのぎ降る雪の消なば惜しけむ雨な降りそね(万3-302) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すがた [姿] | 〔名詞〕 ① 衣服を身に着けたようす。身なり。容姿。服装。 ② 物の形。ありさま。また、趣のあるようす。 ③ 歌論や俳論で、ことば(=表現)と意味(=内容)とにわたる全体的な表現様態。歌体。句体。歌・句の格調。 【類語】 「ありさま」 事物のようすや状態。人については容姿・態度。 「かたち」 物の形状。人については容貌・顔立ち。 「すがた」 服装を含む人の外見的印象・身なり。また、事物の風情や趣。 |
難波潟潮干なありそね沈みにし妹が姿を見まく苦しも(万2-229) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すがのねの [管の根の] | 【枕詞】 すげの根の状態から、「長し・乱る」に、 また「ね」の音から「ねもころ」にかかる。 |
あしひきの山に生ひたる菅の根のねもころ見まく欲しき君かも(万4-583) いなと言はば強ひめや我が背菅の根の思ひ乱れて恋ひつつもあらむ(万4-682) 菅の根のねもころごろに照る日にも干めや我が袖妹に逢はずして(万12-2868) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すぎむら [杉叢] | 〔名詞〕 杉が群がって生えている所。 |
石上布留の山なる杉群の思ひ過ぐべき君ならなくに(万3-425) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すぐ [過ぐ] | 〔自動詞ガ行上二段〕【ギ・ギ・グ・グル・グレ・ギヨ】 ① 通り過ぎる。通過する。 ② 時が過ぎる。経過する。 ③ 世を渡る。生活する。 ④ 度を越える。優る。 ⑤ 盛りが過ぎる。終りになる。 |
① 新治筑波を過ぎて幾夜か寝つる日日なべて夜には九夜日には十日を (記・中) ① ふたり行けど行き過ぎがたき秋山をいかにか君がひとり越ゆらむ(万2-106) ① 敷栲の袖交へし君玉垂の越智野過ぎ行くまたも逢はめやも [一云 越智野に過ぎぬ] (万2-195) ② 春過ぎて夏来るらし白栲の衣干したり天の香具山(万1-28) ⑤ 梅の花咲き散り過ぎぬしかすがに白雪庭に降りしきりつつ(万10-1838) ⑤ -思ひ恋ふらむ 時ならず 過ぎにし子らが 朝露のごと 夕霧のごと(万2-217) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すくなびこな [小彦名] | 大汝少彦名のいましけむ志都の石屋は幾代経ぬらむ(万3-358) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-355 注『少彦名』」】 「少(すくな)」は「大(おほ)」に対して、次位にあるものをいう。「彦名」は男性の「彦」に愛称の「ナ」が接尾語としてついた名。 この「少(すくな)」を「小人(こびと)」の「小(こ)」と同義とするのは説話に引かれ過ぎた解釈で、「小(こ)」を「少(すくな)」という国語で表すことはない。 また「少地彦名(すくななひこな)」の「地(な)」の省略だとする説も「大汝」を「大地持(おほなも)ち」と解したことに対応させようとしたものに過ぎない。 この「大汝・少名彦」の二つの名は、記紀ともに出雲系神話の神として、かつ二神協力して葦原の中国の国土経営に活躍する神話に見える。 したがって、土地神としての名を持つものとして「大地持(おほなも)ち」「少地彦名(すくななひこな)」という解釈が容易に受容されたのであろうが、国造りにおける土地性は「大国主神」という神名に表れているのであるから、「大穴牟遅(持)」に引き当てるのは誤りである。 それよりも、ここの歌にあるように、二神とも「石室(いはや)」にましましたという点からは、洞窟の神とする解する(西郷信綱『古事記注釈』二) 方がはるかに妥当性がある。 この洞窟は、現し国と他界(「黄泉の国」ばかりではなく「常世の国」をもさす) との堺にある洞窟と考えてよい。 果たして、少彦名神は常世から渡来して大穴牟遅神に智恵を与え協力して――こういう神は常に異形をもって想念されている。この場合は小人である。常世は復活の国だから憧形で考えられたのは当然である。――、再び常世の国へ戻ってゆく。その洞窟の現し国側に大穴牟遅神、常世の国側に少彦名神が坐すのを、両神揃って洞窟の中に坐す、と考えることはごく自然な思惟である。 二神連名の表現(6・九六三、7・一二四七、18・四一〇六) は、物事の由緒の古さを言う場合に用いられている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すげ [菅] | 〔名詞〕 草の名。種類が多く、山野に自生する。葉で笠や蓑などを作る。すが。 |
奥山の岩本菅を根深めて結びし心忘れかねつも(万3-400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すさき [州崎・洲崎] | 〔名詞〕川や海の土砂が盛り上がって、岬のように川や海に突き出た所。 | 大和恋ひ寐の寝らえぬに心なくこの洲崎廻に鶴鳴くべしや(万1-71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ずして | [打消の助動詞「ず」の連用形+接続助詞「して」] 前の事柄を打ち消して、後の事柄に続ける。 ① 順接の関係で続く。「~(し)ないで、~。」「~(で)なくて、~。」 ② 逆接の関係で続く。「~(し・で)ないけれども、~。」 |
① み薦刈る信濃の真弓引かずして弦はくるわざを知ると言はなくに [郎女] (万2-97) ① 橘の蔭踏む道の八衢に物をぞ思ふ妹に逢はずして [三方沙弥](万2-125) ① 託馬野に生ふる紫草衣に染めいまだ着ずして色に出でにけり(万3-398) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すず [鈴] | 〔名詞〕 ① 鳴り物の一つ。上代から装飾・駅鈴・神楽など多方面に用いられた。 多く、金属製。 ② 紋所の名。「①」の形を図案化したもの。 |
① 左夫流児が斎きし殿に鈴掛けぬ駅馬下れり里もとどろに(万18-4134) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すずき [鱸] | 【有斐閣「萬葉集全注巻三-252 注『鱸』」】 本州沿岸浅海に分布する大きな魚。 原文「鈴寸」は借訓。晩春から初秋にかけてよく釣れる。 |
荒たへの藤江の浦にすずき釣る海人とか見らむ旅行く我れを(万3-253) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すそ [裾] | 〔名詞〕 ① 衣服の下の端の部分。② 髪の毛の先。③ 山の麓。④ 馬の脚。 ⑤ 物の端。末端。 |
① 嗚呼見の浦に舟乗りすらむをとめらが玉裳の裾に潮満つらむか(万1-40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 古代の衣服の下の端の部分をいうのが原義。転じて、形の似ている山のふもと、髪の毛の先の部分をいい、さらに末端の意で川の下、物の端をいう。また、原義の「裾(すそ)」が、衣服の膝から下の足の部分にあたることから、人の足の膝から下や人が乗っている馬の脚の意にも用いられる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すだつ [巣立つ] | 〔自動詞タ行四段〕 雛が成長して、巣から飛び立つ。 |
鳥座立て飼ひし雁の子巣立ちなば真弓の岡に飛び帰り来ね(万2-182) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞下二段〕【テ・テ・テ・ツル・ツレ・テヨ】 親鳥が雛を育てて、巣から飛び立たせる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すだれ [簾] | 〔名詞〕[「簀(す)垂れ」の意] ① 細く削った竹や葦などを糸で編んだもの。 上から垂らして日よけや部屋の仕切りに用いる。〔季語:夏〕 ② 輿・牛車などの人の乗るところの前後に垂らした簾。 緋色の糸で編んだ。「赤色簾」は高級の車に用い、青糸で編んだ「青簾」は中級以下の車に用いる。 |
① 君待つと我が恋ひ居れば我が屋戸の簾動かし秋の風吹く(万4-491) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ずて | 〔打消しの助動詞「ず」の連用形「ず」+接続助詞「て」〕 「~ないで」「~ではなくて」 【参考】 上代に使われた語。中古以後は主として和歌の中で使われた。 接続助詞「で」は、この語の転とする説もある。 |
丹生の川瀬は渡らずてゆくゆくと恋痛し我が背いで通ひ来ね(万2-130) 否と言へど強ふる志斐のが強ひ語りこのころ聞かずて朕恋ひにけり(万3-237) - 時じき時と 見ずて行かば まして恋しみ 雪消する 山道すらを-(万3-385) 松が枝の土に着くまで降る雪を見ずてや妹が隠り居るらむ(万20-4463) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ずは | 〔なりたち〕[打消の助動詞「ず」の連用形+係助詞「は」] ① 「~ないで」 ② 順接の仮定条件の打消を表す。「~ないならば。~なかったら。」 〔語法〕 中世に生じた「ずんば」という形や、「未然形」に接続する接続助詞「ば」の類推から、近世には「ずば」という形がみられる。 |
① かくばかり恋ひつつあらずは高山の磐根しまきて死なましものを (万2-86) ① 験なき物を思はずは一坏の濁れる酒を飲むべくあるらし(万3-341) ① 我が思ひかくてあらずは玉にもがまことも妹が手に巻かれなむ (万4-737) ② 玉櫛笥三諸の山のさな葛さ寝ずはつひに有りかつましじ [玉櫛笥三室戸山の] (万2-94) ② 後れ居て恋ひつつあらずは追ひ及かむ道の隈廻に標結へ我が背 (万2-115) ② 人見ずは我が袖もちて隠さむを焼けつつかあるらむ着ずて来にけり(万3-269) ② 我妹子がやどの橘いと近く植ゑてし故に成らずは止まじ(万3-414) ② けふ来ずはあすは雪とぞ降りなまし消えずは(①)ありとも花と見ましや (古今春上-63) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【諸注参照】 上記のように解釈するほか、「ずば」として「ず」の未然形に接続助詞「ば」が付いたという解釈もある。「ば」と濁らず使われたので、現在では前者の解釈が一般的である。 最初「~ないで」の意味で使われていたものが、「~ないならば」の意味に転じていったのである。 「竹取物語」に「焼けずはこそ」とある例 (係助詞なら「こそは」 となるのが普通)や、「古今集」で「花し散らずは」などと用いられている例 (副助詞「し」は「~ば」と条件句で受ける) などから、接続助詞と解されるように、「ず」の未然形に接続助詞「ば」の付いた意の例が、時代がくだるにつれて増加している。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すはう [周防] | 【有斐閣「萬葉集全注巻第四-567 注『周防』」】 山口県東南部。和名抄に、「周防、須波宇」 とあり、旧訓も「スハウナル」 であった。記紀には、「周芳」 という表記が見え、その「芳」 は書紀・万葉で「ハ」 の仮名に使われているから「スハ」 と読むことにする。和歌童蒙抄にも「すはにある・・・」 としてこの歌を引く。しかし、「芳」 は敷方切、呉音としては小差があるが漢音では共に「ハウ」 の音で、「周芳」 も「周防」 と同じく「スハウ」 と読まれた可能性もなくはない。日本語は二重母音を避ける傾向の言語であるが、地名は必ずしもその例に従わないことがあったのではないか。さきの「飫宇」(五三六) などもその例外の一例である。今は疑問を提出することにとどめておく。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すべ | 〔名詞〕手段。方法。仕方。 | -言はむすべ せむすべ知らに 音のみを 聞きてあり得ねば-(万2-207) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すべなし [術無し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 方法がない。どうしようもない。また、苦しい。 |
うちひさす宮に行く子をまかなしみ留むれば苦し遣ればすべなし(万4-535) -来立ち呼ばひぬ かくばかり すべなきものか 世間の道(万5-896) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すま [須磨] | 〔地名〕須磨は神戸市須磨区一帯。 | 須磨の海人の塩焼き衣の藤衣間遠にしあればいまだ着馴れず(万3-416) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すまふ [住まふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 《動詞「住む」 の未然形「すま」 に上代の反復・継続の助動詞「ふ」が付いて一語化したもの》 住み続ける。暮らしていく。 |
つれもなき佐田の岡辺に帰り居ば島の御階に誰れか住まはむ(万2-187) -あらたまの 年の緒長く 住まひつつ いまししものを 生ける者-(万3-463) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すみさか [住坂] | 【小学館「新編日本古典文学全集萬葉集 付録『地名一覧』」】 奈良県宇陀郡榛原町萩原の西方、西峠の旧道の坂か。近鉄大阪線榛原駅の西北に当たり、大和と伊勢とえお結ぶ交通上の要衝として西の門戸の「大坂」(二一八五)と共に重要視された。「神武前紀」には、この坂に「焃炭(おこしずみ)」を置いたのによってこの名がある、という地名伝説を載せる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すみのえ(すみよし) [住江・住吉] | 〔地名〕[「住吉(すみよし)」の古称] ① 現在の大阪市住吉区の辺り。海に面した松原の続く景勝の地。 住吉大社があり、古くは松の名所で知られた。 平安時代以降「すみよし」と称した。[歌枕] ②「住吉大社」の略。摂津の国一の宮である住吉大社。 海の守護神・和歌の神として信仰を集める。住吉神社。 (住吉の御田植え[夏]) |
① 霰打つ安良礼松原住吉の弟日娘女と見れど飽かぬかも(万1-65) ① 住吉の得名津に立ちて見渡せば武庫の泊まりゆ出づる船人(万3-286) ① 夕さらば潮満ち来なむ住吉の浅香の浦に玉藻刈りてな(万2-121) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すむ [住む] | 〔自動詞マ行四段〕 ① 居所と定めて居つく。居住する。 ② 夫として女のもとに通う。結婚生活をいとなむ。 |
① み立たしの島をも家と棲む鳥も荒びな行きそ年かはるまで(万2-180) ① 人漕がずあらくもしるし潜きする鴛鴦とたかべと船の上に住む(万3-260) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すめかみ [皇神] | 〔名詞〕[「すべがみ」とも] ① 皇室の先祖にあたる神。天照大神をいう。 ② 一定の区域を支配する神。 |
① 吾が大君ものな思ほしそ皇神の副へて賜へる我なけなくに(万1-77) ①-大和の国は 皇神の 厳しき国 言霊の 幸はふ国と 語り継ぎ-(万5-898) ②「山口に坐す皇神等の前にも」(祝詞) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すめろき [天皇] | 〔名詞〕「すべらき」「すめらき」「すめろぎ」とも。 天皇。また、皇統を指すこともある。 |
-天の下 知らしめしけむ 天皇の 神の命の 大宮は-(万1-29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ずや | 〔成り立ち〕 打消し助動詞「ず」の終止形+係助詞「や」 ① 下に推量の表現を伴って、打消しの疑問の意を表す。 「~でないで~だろうか」「~ないで~か」 ② 文末に用いて、打消しの反語・疑問を表す。「~ではないか」 |
② あかねさす紫野行き標野行き野守は見ずや君が袖振る(万1-20) ② 妻もあらば摘みて食げまし沙弥の山野の上のうはぎ過ぎにけらずや(万2-221) ② 今日今日と我が待つ君は石川の貝に [一云 谷に] 交じてありといはずやも(万2-224) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すら | 〔副助詞〕 1〔類推〕 ~でさえ。~だって。 ある事を特に強調して、他のものを類推させる意を表す。 2〔強調〕 ~までも。~でさえも。 ある一事を特に強調する意を表す。 〔接続〕体言、活用語の連体形、副詞、助詞などに付く。 |
2-嬬の命の たたなづく 柔肌すらを 剣太刀 身に添へ寝ねば-(万2-194) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 上代に多く用いられたが、中古に「だに」 にとって代わられ、「すら」 は和歌や漢文訓読文に残る程度になった。 現代語の「すら」 はこの系統のものである。 中古以降、音韻変化した「そら」 という形も見られる。 なお、上代には「すらに・すらを」 の形でも用いられる。 この「に・を」 は本書(旺文社全訳古語辞典第三版) では間投助詞としたが、 「に」 を副詞をつくる語尾、「を」を格助詞または係助詞とする説もある。 →さへ・だに |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すらく [為らく] | 〔なりたち〕サ変動詞「為(す)」 のク語法。 する事。為す事。 |
この岡に小鹿踏み起しうかねらひかもかもすらく君故にこそ(万8-1580) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すらに | 〔なりたち〕副助詞「すら」+間投助詞「に」 ~でさえ。~でさえも。~だって。 |
軽の池の浦廻行き廻る鴨すらに玉藻の上にひとり寝なくに(万3-393) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すらを | 〔なりたち〕副助詞「すら」+間投助詞「を」 一つのことを特に取り立てて、逆接的に下に続けていう。 ~であっても。~であるのに。 |
-靡かひし 嬬の命の たたなづく 柔肌すらを 剣太刀 身に添へ寝ねば-(万2-194) -まして恋しみ 雪消する 山道すらを なづみぞ我が来る(万3-385) -布肩衣 ありのことごと 着襲へども 寒き夜すらを 我れよりも-(万5-896) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| するが [駿河] | 〔地名〕静岡県の中央部。 | 焼津辺に我が行きしかば駿河なる阿倍の市道に逢ひし児らはも(万3-287) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中央公論社「萬葉集全注巻三-264 訓釋『駿河なる』」】 駿河は「須流河(スルガ)」(廿・四三四五) の仮名書例によりスルガと訓む。駿をスルと訓むは平群(ヘグリ)、播磨(ハリマ) など、n音尾をラ行に転ずる類である。 「駿河なる」は、駿河の国にある、の意。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すゑ [末] | 【語誌語感】 「本(もと)」の対義語。ひとつなぎになってまとまったものの、先端部をいう。そのものは空間的にまとまった「物」や「場所」であったり、時間的にまとまった「時代」「一生」などや、血縁関係や、経緯や因果などの事柄としてのまとまりなどと、大きく広がる。ときに現代語の「場末」「世も末」などの表現に残るように、中心から外れた衰えたところというニュアンスをもつことがあり、前後の文脈からの読みとりに注意したい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔名詞〕 ① 物の先端。場所の奥。端。はて。すそ。 ② 木のこずえ。枝先。 ③ 時間的な終わり。あと。将来。先々。行く末。 ④ 一生の終わり。晩年。年をとってから。 ⑤ 衰退期。末期。衰え尽きる時期。おしまい。 ⑥ 血筋の末。子孫。あとつぎ。 ⑦ ひと並びの順位のおしまいのほう。下位。末席。下々。 ⑧ 一連の経緯の終わり。結果。あげく。はて。 ⑨ 和歌の下の句。 【有斐閣「萬葉集全注巻二-202 注『すゑ』」】 「スヱ」は安定な状態におくことをあらわす。講義に「古の甕の類の今土中より発掘せらるるものを見るに、多くは底部丸くしてすわりのわるきものなれば、これを特に安定におくに心を用いゐたること想像せらる」という。万象名義に、「祈」に「渠依反禱也」とある。折も禱も「イノル」意。哭沢神社に神酒を供えて祈るけれども。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せ [兄・夫・背] | 〔名詞〕 女性から、夫・愛人・兄・弟などを呼ぶ語。また親しい男性を呼ぶ語。 |
綜麻形の林のさきのさ野榛の衣に付くなす目につく吾が背(万1-19) 防人に行くは誰が背と問ふ人を見るが羨しさ物思ひもせず(万20-4449) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せ [狭] | 〔形容詞「狭(せ) し」 の語幹。〕「~も狭に」 の形で用いられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せ [瀬] | 〔名詞〕 ① 川の水が浅い所。浅瀬。 ② 川の流れの速い所。早瀬。 ③ 物事に出あう時節。機会。 ④ 場所。⑤ その節(ふし)。その点。 【「せ」と「ふち」】 「せ」は多義語であるが、「世の中は何か常なるあすか川きのふの淵(ふち)ぞ今日は瀬になる」のように、「淵」に対して用いる場合は、川の、浅くて人が徒歩で渡ることができるところをいう。水が澱んで深いところが、「ふち」である。 |
① 丹生の川瀬は渡らずてゆくゆくと恋痛し我が背いで通ひ来ね(万2-130) ① 川上に洗ふ若菜の流れ来て妹があたりの瀬にこそ寄らめ(万11-2849) ② 吉野川行く瀬の早みしましくも淀むことなくありこせぬかも(万2-119) ② あしひきの山川の瀬の鳴るなへに弓月が岳に雲立ちわたる(万7-1092) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せ [過去助動詞] | 〔過去助動詞「き」 の未然形〕 つねに接続助詞「ば」 を伴って「せば」 の形で用いられる。 | 高光る我が日の御子のいましせば島の御門は荒れざらましを(万2-173) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せき [関] | 〔名詞〕[四段動詞「塞(せ)く」の連用形から] ① 物事をせき止めること。また、そのもの。へだて。 ② 国境などに門を設けて、通行人や通行物を検査したところ。=関所 ③ 水をせきとめるところ。堰(せき)。いせき。 |
② 出でて行く道知らませばあらかじめ妹を留めむ関も置かましを(万3-471) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せきもり [関守] | 〔名詞〕 関所の番人。恋路を邪魔する者のたとえにも言う。 |
我が背子が跡踏み求め追ひ行かば紀伊の関守い留めてむかも(万4-548) 人知れぬわが通ひ路の関守はよひよひごとにうちも寝なむ(古今恋三-632) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せく [塞く・堰く] | 〔他動詞カ行四段〕 ① せき止める。さえぎり隔てる。 ② さえぎって人に会わせない。妨害する。 ③ 抑える。制止する。 |
① 明日香川しがらみ渡し塞かませば流るる水ものどにかあらまし [一云 水の淀にかあらまし](万2-197) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せこ [兄子・夫子・背子] | 「せ」はもと女性が兄・弟・夫などを親しんで呼んだ語。 「こ」は親愛の情を表わす接尾語。 ① 女性が兄弟を呼ぶ語。 ② 夫が妻を、また女性が恋人を呼ぶ語。 ③ 男性同士が親しんで呼ぶ語。 |
① 我が背子を大和へ遣るとさ夜更けて暁露に我れ立ち濡れし(万2-105) ② 我が背子はいづく行くらむ沖つ藻の名張の山を今日か越ゆらむ(万1-43) ③ 沖つ波辺波立つとも我が背子が御船の泊り波立ためやも(万3-248) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せこ [勢子・列卒] | 〔名詞〕狩りの時、鳥獣をかりたてたり、逃げるのを防いだリする人夫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せす [為す] | 〔上代語〕 [なりたち(サ変動詞「す」の未然形「せ」+上代の尊敬の助動詞「す」)] 「なさる」「あそばす」 |
-磐舟浮べ 艫に舳に 真櫂しじ貫き い漕ぎつつ 国見しせして- (万19-4278) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せのうみ [石花の海] | -名付けも知らず 奇しくも います神かも石花の海と名付けて-(万3-322) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 『付録 地名一覧』」】 富士山の北西御坂山地の南側にあった湖の名。「剗(せ)の海」とも記す。 貞観六年(864)の大爆発の際、青木ヶ原溶岩流によって二分され、西湖、精進湖となり、その西の本栖湖も面積が半分となったといわれている。 【有斐閣「萬葉集全注巻三-319 注『せの海』」】 富士山の北側の西湖と精進湖。当時はひと続きであった。 原文「石花」とあるのは、俗称カメノテという甲殻類で、海浜の石に咲く花の如く付着している貝(セガイという)なので、「石花」と書く。ここはセの仮名に借りたもの。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せのやま [背の山・勢能山] | 〔名詞〕 【有斐閣「万葉集全注 35番背の山」注】 和歌山県伊都郡かつらぎ町の山。紀ノ川の北岸にある。 明日香から二泊目の地、南岸の妹山とともに、旅人の望郷を誘った。 |
これやこの大和にしては我が恋ふる紀路にありといふ名に負ふ背の山(万1-35) 栲領巾のかけまく欲しき妹の名をこの勢能山にかけばいかにあらむ [一に云ふ 替へばいかにあらむ](万3-288) 背の山に直に向へる妹の山事許せやも打橋渡す(万7-1197) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せば | 〔成立ち〕[過去の助動詞「き」の未然形「せ」+接続助詞「ば」] 事実に反する仮想の条件を表す。 「もし~たならば」 |
旅にしてもの恋ほしきに鶴が音も聞こえざりせば恋ひて死なまし(万1-67) いにしへに梁打つ人のなかりせばここにもあらまし柘の枝はも(万3-390) 春日野に粟蒔けりせば鹿待ちに継ぎて行かましを社し恨めし(万3-408) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せば-まし | 〔成立ち〕[過去の助動詞「き」の未然形「せ」(一説にサ変動詞「為(す)の未然形「せ」)+接続助詞「ば」+…+反実仮想の助動詞「まし」] 反実仮想。事実に反することや、実現しそうにないことを仮に想定し、その仮定の上に立って推量、想像する意を表す。 もし~(だっ)たら、~だろう(に)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はしきやし栄えし君のいましせば昨日も今日も我を召さましを(万3-457) 世の中にたえてさくらのなかりせば 春の心はのどけからまし(恋春上-53) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せむすべ [為む術] | 〔名詞〕 [サ変動詞「為(す)」の未然形「せ」 に、 推量の助動詞「む」 の連体形「む」 と名詞「術(すべ)」のついたもの] なすべきてだて。対処のしかた。 |
-そこ故に せむすべ知れや 音のみも 名のみも絶えず 天地の-(万2-196) 言はむすべせむすべ知らず極まりて貴きものは酒にしあるらし(万3-345) -天知らしぬれ 臥いまろび ひづち泣けども 為むすべもなし(万3-478) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そ [衣] | 〔名詞〕着物。ころも。多くは「御衣(みそ・おんぞ)」の形で用いる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そ [夫・其] | 〔代名詞〕[中称の指示代名詞] それ。そこ。また、なにがし。某。 |
-もののふの 八十宇治川に 玉藻なす 浮かべ流せれ 其を取ると-(万1-50) 我がやどに 花ぞ咲きたる そを見れど 心もゆかず はしきやし-(万3-469) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そ | 〔終助詞〕 ① 副詞「な」と呼応し、おもに動詞の連用形(カ変、サ変は未然形)の下に、 付いて、「な+連用形(未然形)+そ」の形で禁止の意を表わす。 ②「な~そ」の「な」がなく、「そ」だけで禁止の意を表わす。 〔接続〕 動詞および助動詞「す・さす・しむ・る・らる」の連用形に付く。 ただし、カ変・サ変の動詞には未然形に付く。 |
① おもしろき野をばな焼きそ古草に新草交り生ひは生ふるがに(万14-3471) 〔参考〕 禁止の意を表わす終助詞「な」を用いた「動詞の終止形+な」の形に比べて、やわらかくおだやかに禁止する言い方であるという。中古では、女性は、禁止を言うのに「な~そ」の形を用いるのが普通だった。②のように、「な」を用いない言い方は、誤写かと疑われる用例に現れ、確かな用例は、中古の末から見られるようになる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぞ | 〔係助詞〕(上代には「そ」とも) ① 文中にある場合、他の何物でもなく、 まさにそのものであるという意味での強調を表わす。 係り結びによって、「ぞ」を受ける文末の活用語は、連体形となる。 ア:主語を強調する場合。~が。 イ:目的語を強調する場合。~を。 ウ:種々の連用修飾語などを強調する場合。 ②「ぞ」を受けて、連体形で結ばれるはずの語に、 「に・を・と・ども・ど・ば」などの接続助詞が付くと、 接続助詞の支配を受けて結びが消滅し、 条件句となって下文に続いていく。 ③(多く「とぞ」の形で)形の上では文末にあるが、 ①の係り結び形式で、「ぞ」を受ける連体形の結びが省略される場合。 多くは「言うふ」または「聞く」などを補う。 ④ 文末にある場合。 ア:断定する意を表わす。 イ:告知する意を表わす。 ウ:疑問後とともに用いて問い質す意を表わす。~か ⑤「もぞ~連体形」の形で、悪い事態を予測し、 そうなっては困るという、不安や懸念の気持ちを表わす。 〔接続〕体言、活用語の連体形、種々の助詞などに付く。 |
①「ア」-音のみし泣かゆ 語れば 心そ痛き 天皇の 神の皇子の-(万2-230) ①「ア」-大空の月のひかりしきよければ影みし水ぞまづこほりける (古冬-316) ①「イ」み立たしの島を見る時にはたづみ流るる涙止めそかねつる(万2-178) ①「イ」-袖そ振りつる [一云 名のみを聞きてありえねば]-(万2-207) ①「ウ」大和には鳴きてか来らむ呼子鳥象の中山呼びぞ越ゆなる(万1-70) ①「ウ」橘の蔭踏む道の八衢に物をぞ思ふ妹に逢はずして [三方沙弥] (万2-125) ④「ア」-うまし国ぞ 蜻蛉島 大和の国は(万1-2) 憶良らは今は罷らむ子泣くらむそれその母も我を待つらむそ(万3-340) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そがひ [背向] | 〔名詞〕《上代語》後のほう。背中合わせ。 | 縄の浦ゆそがひに見ゆる沖つ島漕ぎ廻る船は釣りしすらしも(万3-360) -雑賀野ゆ そがひに見ゆる 沖つ島 清き渚に 風吹けば 白波騒き-(万6-922) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そくへ [退く方] | 〔名詞〕 遠く離れた方。遠方。 |
-世間の 悔しきことは 天雲の そくへの極み 天地の-(万3-423) - 天雲の そくへの極み この道を 行く人ごとに 行き寄りて-(万9-1805) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そこ [底] | 〔名詞〕 ① くぼんだもののいちばん下の部分。また、極まるところ。果て。 ② 奥深いところ。心の奥底。③ そのものの持つ真の力量。底力。 |
① 我が欲りし野島は見せつ底深き阿胡根の浦の玉ぞ拾はぬ [或頭云 我が欲りし子島は見しを](万1-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そこ (そこをしも) [其処・其所] | 〔代名詞〕 ① 中称の指示代名詞。場所を示す。そのところ。その場所。そこ。 ② 中称の指示代名詞。事物をさす。それ。そのこと。 ③ 対称の人名代名詞。親しい目下の者や友人に対して用いる。あなた。きみ。そこもと。 |
① 我が岡のおかみに言ひて降らしめし雪のくだけしそこに散りけむ(万2-104) ②-青きをば 置きてぞ嘆く そこし恨めし-(万1-16) ②-山道をさして 入日なす 隠りにしかば そこ思ふに-(万3-469) ② 秋の田の穂田の刈りばかか寄りあはばそこもか人の我を言なさむ(万4-515) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (そこをしも) | 【澤瀉久孝 中央公論社「萬葉集注釈」巻二-196 訓釋「そこをしも」】 「そこ」は、それ、その事。「し」 は強意。「も」は詠歎。その事をマア。万葉考にはこの句を本文とし、「今本然有鴨と有はかなはず」 と云ひ、略解、檜嬬手その他その説に従つてゐるものが多い。これは「然れかも」 では弱く「そこをしも」 の一筋の心が示されない為と「か」 の係詞を下で結ぶ語がない為とによるものであらうが、その「かも」 は「けるかも」 の「かも」 などに近いもので、疑問の意よりも詠歎の意が強くなつたものであり、「然ればよ」 といふに近く、「そこをしも」 よりも弱いとは云へず、「か」 の結びについては、前にも「何しかも」 の自然消滅の例を述べたが、ここはまた次に述べるやうな意味で自然消滅と見るべきものと思はれる。従つて「然れかも」 を本文とする事を妨げない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そこば [幾許・若干] | 〔副詞〕(程度について)たいそう。はなはだしく。 | -天皇の 神の皇子の 出でましの 手火の光りそ そこば照りたる(万2-230) -振り放け見れば 神からや そこば貴き 山からや 見が欲しからむ-(万17-4009) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そこゆゑ(に)[其処故(に)] | 〔接続詞〕それだから。そのため。 | -日月の 数多くなりぬれ そこ故に 皇子の宮人 ゆくへ知らずも-(万2-167) -夜床も荒るらむ [一云 荒れなむ] そこ故に 慰めかねて-(万2-194) -胸こそ痛き そこ故に 心なぐやと 高円の 山にも野にも-(万8-1633) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そち [其方] | 〔代名詞〕 ① 中称の指示代名詞。方角を指す。そこ。そちら。そっち。 ② 対称の人名代名詞。目下の者に対して用いる。おまえ。なんじ。 |
① -矢の繁けく 大雪の 乱れて来れ [一云 霰なす そちより来れば]-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そで [袖] | 〔名詞〕 ① 衣服の両腕を通す部分。② たもと。 ③ 牛車。輿などの、前後の出入り口の左右の部分。前方のを前袖、後方のを後袖、また袖の内面を裏・内といい、外面を袖表という。 ④ 鎧の肩からひじをおおい、矢・刀などを防ぐ部分。 ⑤ 文書・書物などの初めの右端の、余白の部分。 |
① 白たへの袖解き交へて帰り来む月日を数みて行きて来ましを(万4-513) ② -家づとに 妹に遣らむと 拾ひ取り 袖には入れて 帰し遣る-(万15-3649) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そでふる [袖振る] | 〔他動詞ラ行四段〕 ① 合図として、または別れを惜しんで、袖を振る。→「振る」 ② 袖を振って舞う。 |
① あかねさす紫野行き標野行き野守は見ずや君が袖振る(万1-20) ② あきづ羽の袖振る妹を玉くしげ奥に思ふを見たまへ我が君(万3-379) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そとも [背面] | 〔名詞〕[名詞「背(そ)+格助詞「つ」+名詞「面(おも)、「そつおも」の転] ① 山の斜面の日の当る側から見て、背後の方向。山の北側。北の方角。 ⇔「影面(かげとも)」 ② 背面。後ろの方向。 |
① -きこしめす 背面の国の 真木立つ 不破山超えて 高麗剣-(万2-199) -山の陽(みなみ)をかげともいひ、山の陰(きた)をそともといひき-(成務紀) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そね | 〔終助詞〕《上代語》 〔禁止の終助詞「そ」に、他に対する願望の終助詞「ね」の付いたもの。〕 「な~そね」の形で、懇願する気持ちをこめた禁止を表す。 「~してほしくない」「~しないでほしい」 |
難波潟潮干なありそね沈みにし妹が姿を見まく苦しも(万2-229) 高円の野辺の秋萩な散りそね君が形見に見つつ偲はむ(万2-233) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その [其の] | 〔成り立ち〕代名詞「其(そ)」+格助詞「の」 ① 話し手から少し離れた事物・人をさしていう語。 ② すでに話題にのぼった事物・人をさしていう語。 ③(多く下に打消しの表現を伴って)不定の事物・人をさし示す語。 「なんの」「どの」 ④ わざとはっきりその名を言わずに事物・人をさし示す語。 「なになにの」 |
① 八雲立つ出雲八重垣妻ごみに八重垣つくるその八重垣を(記上) ② -その雨の 間なきがごと 隈もおちず 思ひつつぞ来し その山道を(万1-25) ② 憶良らは今は罷らむ子泣くらむそれその母も我を待つらむそ(万3-340) ② 周防なる磐国山を越えむ日は手向けよくせよ荒しその道(万4-570) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】[小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻第一-25頭注] 上代語では一般に「カ・カレ・カノ」など後世の「あれ・あの」に当る遠称の使用例が少ないといわれ、「ソ・ソレ・ソノ」などの所謂中称の指示語が遠称にも用いられた。 この「ソノ」も遠称としての用法で、恐らく飛鳥から芋峠・上市を経て吉野まで山越えし川隈沿いに徒歩で来た道を指していったのだろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そふ [添ふ・副ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 ① つけ加わる。さらに備わる。 ② そばに寄り付いている。つき従う。つき添う。 ③ 夫婦として連れ添う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔自動詞ハ行下二段〕 [「年(月・日)にそへて」の形で] 伴う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 ① 付け加える。さらに備える。 ② つき従わせる。 ③ なぞらえる。たとえる。 |
② 吾が大君ものな思ほしそ皇神の副へて賜へる我なけなくに(万1-77) ③ たな霧らひ雪も降らぬか梅の花咲かぬが代にそへてだに見む(万8-1646) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そまやま [杣山] | 〔名詞〕材木を切り出すための山。=杣 | 我が大君天知らさむと思はねば凡にそ見ける和束杣山(万3-479) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -そむ | 〔接尾マ行下二段型〕 (動詞の連用形に付いて) ~しはじめる、はじめて~する。 |
さきそめしやどしかはれば菊の花 色さへにこそ移ろひにけれ(古今秋下-280) 東路のさやのなか山なかなかに なにしか人を思ひそめけむ(古今恋三-594) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そむ [染む] | 〔自動詞マ行四段〕 ① それまでと違う色になる。染まる。色づく。 ② 深く心に感じる。しみる。 |
① 君がさす三笠の山のもみぢ葉の色 神無月しぐれの雨の染めるなりけり (古今雑体-1010) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞マ行下二段〕【メ・メ・ム・ムル・ムレ・メヨ】 ① 液に浸して色を付ける。染み込ませる。染める。 ② 思い込む。心を深く寄せる。 |
① 韓人の衣染むといふ紫の心に染みて思ほゆるかも(万4-572) ② 心ざし深く染めてしをりければ 消えあへぬ雪の花と見ゆらむ(古今春上-7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そむく [背く] | 〔自動詞カ行四段〕 ① 後ろ向きになる。背中を向ける。② 従わない。反対する。さからう。 ③ 別れる。離れる。④ 世を捨てる。出家する。 |
④ -宜しき君が 朝宮を 忘れたまふや 夕宮を 背きたまふや-(万2-196) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 ① 後ろを向かせる。横の方を向かせる。② 離反する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぞも | 〔係助詞「ぞ(そ)」+係助詞「も」〕 ① 強く指示する語。~ぞ。~こそはまあ。 ② (疑問を表す語とともに用いられて) いったい~なのだろう。 |
① よく渡る人は年にもありといふをいつの間にそも我が恋ひにける(万4-526) ① 年渡るまでにも人はありといふをいつの間にぞも我が恋ひにける(万13-3278) ① 人よりは妹ぞも悪しき恋もなくあらましものを思はしめつつ(万15-3759) ② 沫雪かはだれに降ると見るまでに流らへ散るは何の花ぞも(万8-1424) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そら [空] | 〔名詞〕 ① 天。天空。② 空模様。天候。時節。転じて、あたり一帯の情景や雰囲気。 ③ 方向。目当て。場所。また、境遇。④ 気持ち。心境。 ⑤ 上のほう。上手。⑥ 天井裏。 |
① 久方の天つみ空に照る月の失せなむ日こそ我が恋止まめ(万12-3018) ④ -玉桙の 道をた遠み 思ふそら 安けなくに 嘆くそら 苦しきものを-(万4-537) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 ① 心がうつろで落ち着かないさま。気もそぞろなさま。うわのそら。 ② 根拠のないさま。あて推量。いいかげん。 ③ はかないさま。かいのないさま。 ④ (連用形「そらに」の形で) そらじて言う。暗唱する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そらかぞふ [空数ふ] | 【枕詞】「大津」など、「おほ」を語頭に持つ地名にかかる。 | そら数ふ大津の児が逢ひし日に凡に見しくは今ぞ悔しき(万2-219) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そらにみつ | 【枕詞】「そらみつ」に同じ。 |
-そらにみつ 大和を置きて あをによし 奈良山を越え-(万1-29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そらみつ | 【枕詞】[「そらにみつ」とも]「やまと(大和・倭)」にかかる。 | -そらみつ 大和の国は おしなべて 我れこそ居れ-(万1-29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| それ [其] | 〔代名詞〕 ① 中称の指示代名詞。やや離れた事物や場所をさしていう語。 それ。そこ。 ② 近い前に述べられた事物や人・場所をさしていう語。 そのこと。そのもの。そこ。その人。 ③ 不定称の指示代名詞。不明の事物、明示したくない事物をさす語。 なに。なにがし。しかじか。 ④ 対称の人代名詞。あなた。 |
② 憶良らは今は罷らむ子泣くらむそれその母も我を待つらむそ(万3-340) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| た | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| た- | 〔接頭語〕(動詞・形容詞について) 意味を強めたり語調を語調を整えたりする。 「-ばかる」「-ばしる」「-やすし」など。 |
ぬばたまのその夜の梅をた忘れて折らず来にけり思ひしものを(万3-395) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| だいじん [大臣] | 〔名詞〕「太政官(だいじやうくわん)の上官。 太政大臣・大臣・左大臣・右大臣・内大臣などをいう。 「大臣」=「おとど・おほいとの・おほいまうちのきみ・おほまうちきみ・おほまへつきみ」 |
ますらをの鞆の音すなり物部の大臣盾立つらしも(万1-76) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たか [高・多賀] | 〔名詞〕 京都府綴喜郡井手町多賀(たが)。神名帳に「高神社」の名が見える。 JR奈良線山城多賀駅の東約五00メートルの地に、今も同名の神社がある。 |
早来ても見てましものを山背の高の槻群散りにけるかも(万3-280) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-277 注『山背の多賀の槻群』」】 原文「山背高槻村」 とあり、古来難訓視されていたが、生田耕一は「山城の多賀(京都府綴喜郡井手町多賀)の槻の古群(こむら)」(『万葉集難語難訓攷』) と解き、タカノツキムラと訓み漸く定訓を得た。土地が高いから「高」と命名されたかという。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たが [誰が] | 〔代名詞「誰 (た)+格助詞「が」〕 ① (連体修飾語として) だれの。 ② (主語として) だれが。 |
① 玉葛花のみ咲きてならざるは誰が恋ならめ我は恋ひ思ふを(万2-102) ① 防人に行くは誰が背と問ふ人を見るが羨しさ物思ひもせず(万20-4449) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たかきのやま [高城の山] | 〔山名〕所在未詳。一説に吉野の金峯山の北北西一キロメートルに、城山と呼ばれる高城山(702メートル)があり、それかという。(『大和志』また『大和志料』下)。 | み吉野の高城の山に白雲は行きはばかりてたなびけり見ゆ(万3-356) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たかくらの [高座の] | 【枕詞】 「高座」 に御蓋(みかさ=天皇) があることから、地名「三笠(みかさ)」 にかかる。 |
春日を 春日の山の 高座の 三笠の山に 朝去らず 雲居たなびき-(万3-375) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たかし [高し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① ずっと上の方にある。高い。② 空の上方にある。高い。 ③ 身分・地位・家柄が上である。高貴である。 ④ 優れている。高尚である。自尊心がある。 ⑤(音や声が)大きい。⑥ 広く世に知られている。評判である。 ⑦(時間的に)遠い。老いている。 |
① 我妹子をいざ見の山を高みかも大和の見えぬ国遠みかも(万1-44) ① -城上の宮を 常宮と 高くしたてて 神ながら 鎮まりましぬ -(万2-199) ① 天地の 別れし時ゆ 神さびて 高く貴き 駿河なる 富士の高嶺を-(万3-320) ⑤ -葦刈ると 海人の小舟は 入江漕ぐ 楫の音高し そこをしも-(万17-4030) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たかしく [高敷く] | 〔他動詞カ行四段〕 ① 立派に造る。② 立派に治める。 |
① -続麻なす 長柄の宮に 真木柱 太高敷きて 食す国を -(万6-933) ② やすみしし 我が大君の 高敷かす 大和の国は すめろきの-(万6-1051) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たかしのはま [高師の浜] | 〔地名〕 ① 大阪府堺市浜寺から高石市高師浜におよぶ海浜。 白砂青松の景勝で知られた。[歌枕] ② 愛知県豊橋市の南、渥美半島の基部の海浜。 「更級日記」「十六夜日記」などに描かれた。[歌枕] |
大伴の高師の浜の松が根を枕き寝れど家し偲はゆ(万1-66) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たかしまのかつののはら [高島の勝野の原] |
いづくにか我が宿りせむ高島の勝野の原にこの日暮れなば(万3-277) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 『付録 地名一覧』」】 琵琶湖の西岸、滋賀県高島郡高島町勝野の付近の原というが、北の安曇川(あどがわ)町にかけての平野を広くいったものであろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たかしらす [高知らす] | 〔なりたち〕四段動詞「高知る」の未然形「たかしら」+上代の尊敬の助動詞「す」。 ① りっぱにお造りになる。 ② りっぱにお治めになる。 |
① -食す国を 見したまはむと みあらかは 高知らさむと 神ながら -(万1-50) ② 神代より吉野の宮にあり通ひ高知らせるは山川をよみ(万6-1011) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たかしる [高知る] | 〔他動詞ラ行四段〕 ① 立派に建てる。立派に造る。 ②(国などを)立派に治める。 |
① -たぎつ河内に 高殿を 高知りまして 登り立ち 国見をせせば-(万1-38) ② やすみしし 我が大君の 神ながら 高知らします 印南野の 大海の(万6-943) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たかだま [竹玉・竹珠] | 〔名詞〕細い竹を管玉のように輪切りにして、紐に通したもの。神事に用いた。 | -斎ひ掘り据ゑ 竹玉を しじに貫き垂れ 鹿じもの 膝折り伏して-(万3-382) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たかつ [高津] | 〔地名〕 【有斐閣「萬葉集全注巻三-292 注『高津』」】 大阪市東区法円坂のあたり。 天から降りてきたので、その津に「高」の修飾語がついた。 |
ひさかたの天の探女が石船の泊てし高津はあせにけるかも(万3-295) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たかてらす [高照らす] | 【枕詞】天高く照らす意から、「日」にかかる。 | やすみしし 我が大君 高照らす 日の皇子 神ながら 神さびせすと-(万1-45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たかどの [高殿] | 〔名詞〕高く造った建物。また、二階以上重ねて造った家。高楼。 | -たぎつ河内に 高殿を 高知りまして 登り立ち 国見をせせば-(万1-38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たかとぶ [高飛ぶ] | 〔自動詞バ行四段〕 地上から見上げる遥かな場所を移動する。空高く飛ぶ。 |
- 雲にもがも 高飛ぶ 鳥にもがも 明日行きて 妹に言問ひ-(万4-537) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たかのはら [高野原] | 〔地名〕 奈良県奈良市佐紀町の佐紀丘陵の西南一帯。 佐紀西町の西北山陵に高野山陵 (孝謙天皇陵) があり、西大寺 (高野寺とも) がある。 |
秋さらば今も見るごと妻恋ひに鹿鳴かむ山ぞ高野原の上(万1-84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たかべ [沈鳧] | 〔名詞〕こがも(=水鳥の名)の古名。 | 人漕がずあらくもしるし潜きする鴛鴦とたかべと船の上に住む(万3-260) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たかひかる [高光る] | 【枕詞】天に高く輝く意から「日」 にかかる。 | 高光る我が日の御子の万代に国知らさまし嶋の宮はも(万2-170) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たかひしる [高日知る] | (天上の世界を治める意で)天皇などの死を婉曲にいう表現。亡くなる。 | 哭沢の神社に三輪据ゑ祈れども我が大君は高日知らしぬ(万2-202) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たが(ご)ふ [違ふ] | 1〔自動詞ハ行四段〕 ① 食い違う。合わない。予期に反する。 ② そむく。さからう。従わない。③ 変わる。普通でなくなる。 ④ 行き違いになる。入れ違う。 2〔他動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 ① 違うようにさせる。そむく。② 間違える。取り違える。 ③ 「方違(かたたが)へ」 をする。 |
1〔自動詞ハ行四段〕 ① 天地とともに終へむと思ひつつ仕へまつりし心違ひぬ(万2-176) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たかまと [高円] | 〔地名〕 | 高円の野辺の秋萩いたづらに咲きか散るらむ見る人なしに(万2-231) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻二-231 注『高円の野辺の秋萩』」】 高円の野は、高円山の西麓、百毫寺付近から鹿野園方面にかけての傾斜地である。その野の秋萩はとくに美しかったのであろう。 芽子をハギと訓むこと既出(一二〇歌)参照。 注釈に、「集中萩の詠まれてゐる地名は廿一ヶ処に及んでゐるが、そのうち高円のものが最も多く、その辺りの萩が特に人目を惹いたものと思はれる」と言う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たかまとやま [高円山] | 〔地名〕「歌枕」 今の奈良市の東部、春日山の東南に続く山。 | -さつ矢手挟み 立ち向かふ 高円山に 春野焼く 野火と見るまで-(万2-230) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1巻二-230 頭注『高円山』」】 志貴皇子の宮殿はこの山の西北麓百毫寺町の辺りにあったといわれ、その墓(春日宮天皇陵)はその山の東南麓、須山町東金坊にある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たから [宝・財] | 〔名詞〕① 貴重なもの。財宝。② 金銭。財産。 | ① -大和の国の 鎮めとも います神かも 宝とも なれる山かも-(万3-322) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たき [滝] | 〔名詞〕[上代は「たぎ」] ① 急流。早瀬。〔夏〕 ② 崖から流れ落ちる水。垂水(たるみ)。 |
① 滝の上の三船の山に居る雲の常にあらむと我が思はなくに(万3-243) 【「たき」と「たるみ」】 石走る垂水の上のさわらびの萌え出づる春になりにけるかも(万8-1422) 【多芸の御門】 東のたぎの御門に侍へど昨日も今日も召す言もなし(万2-184) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【「たき」と「たるみ」】 「たき」は上代「たぎ」で、水が激しい勢いで流れる意の動詞「たぎつ」と関連があり、急流を言う。現代語の「滝」にあたるのは、「たるみ」である。 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1「巻二-184」頭注「多芸の御門」】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-242 注『滝の上の』」】 奈良県吉野郡吉野町宮瀧付近。「滝」は流れが岩に激してたぎるところをいう。『集韻』に「滝、奔淵」とある。ところが、今日の滝は上代「タルミ(垂水)」と言って、この奔流・急流の「タキ」と区別があった。したがって「滝」とあれば「激流」といっ訳語をあてるのが適当。たとえ、今日の宮瀧付近にある滝がそれだと言われていても、それによってか「滝」と口訳しているのは不正確であり、上代の吉野川はもっと水量が多かったことを考えなければならず、その意味ででも「滝」と訳すべきではない。「タキ」は名義抄や嘉歴元年(1326年)書写の梅沢本古今集にタキと清音であるから、講義のようにタギとは訓まない。 動詞としては「多藝津(タギツ)」(1・三九)と「タギツ」の語形となる。ただし「瀧都(ツ)」(10・二三〇八)や「瀧千(チ)」(11・二七一八)の表記から「タキツ」の語形をも二重形として認める説(拙著『日本上代の文章と表記』)がある。これは「瀧」を借訓表記とみた限り成り立つ説である。今、改めて考えるに、もし、「多藝津(タギツ)」の語形を正当なものとして認めるならば、一方の「瀧(タキ)」は動詞「激して流れる」の正訓字であり、「千(チ)」や「都(ツ)」は語尾表記となるから、「タキツ」ではなく「タギツ」と訓んでよいことになる。 したがってその場合は二重形ではなく、「タギツ」一つの語形となる。タギツの意味は「タギタギシ」に見られる「タギ(曲がりくねって凹凸がある。 上下・左右ともに用いる)」を語基(ごき)とする派生動詞で、なだらかでなく凹凸のある流れ方を「タギツ」と言ったものと考えられる。それに対する名詞の「タキ」の語源は未詳。 あるいはタギの語基(曲折・凹凸)から、特に「激流」の体言として卓立させるために「タキ」と清音化したものでもあろうか。次の「上(うへ)」は、地形的に「上方」の意。 宮瀧にかかる橋の上流右手に聳える山が三船山。舟岡山ともいう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たぎつ [激つ・滾つ] | 〔自動詞タ行四段〕 水が激しい勢いで流れる。水が湧き上がる。 また、そのように心がいらだつ。 |
高山の岩もとたぎち行く水の音には立てじ恋ひて死ぬとも(万11-2727) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たぎつせ [激つ瀬・滾つ瀬] | 〔名詞〕水が激しく流れる瀬。急流。 | さざれ波礒越道なる能登瀬川音のさやけさ激つ瀬ごとに(万3-317) たぎつ瀬に根ざしとどめぬうき草の うきたる恋も我はするかな(古今恋二-592) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たく [綰く] | 〔他動詞カ行四段〕 ① (髪を) かき上げる。たばね上げる。 ② 綱や手綱などをあやつる。たぐる。 ③ 舟を漕ぐ。 |
① たけばぬれたかねば長き妹が髪このころ見ぬに掻き入れつらむか [三方沙弥] (万2-123) ② -石瀬野に 馬だき行きて をちこちに 鳥踏み立て 白塗りの -(万19-4178) ③ 大船を荒海に漕ぎ出でや船たけ我が見し子らがまみはしるしも(万7-1270) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たぐ [食ぐ] | 〔他動詞ガ行下二段〕【ゲ・ゲ・グ・グル・グレ・ゲヨ】《上代語》 食べる。飲食する。 |
妻もあらば摘みて食げまし沙弥の山野の上のうはぎ過ぎにけらずや(万2-221) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たぐつの [栲綱] | 〔名詞〕楮の繊維で作った白い綱。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たぐつのの [栲綱の] | 【枕詞】 「栲綱」 の色から「白」「しら」 にかかる。 |
たぐつのの白き腕(ただむき)(記・上) たくづのの 新羅の国ゆ 人言を 良しと聞かして 問ひ放くる-(万3-463) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たくなは [栲縄] | 〔名詞〕楮(こうぞ)の繊維で作った白色の縄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たくなはの [栲縄の] | 【枕詞】 栲縄の長いところから「長し・千尋」にかかる。 |
-なよ竹の とをよる子らは いかさまに 思ひ居れか 栲縄の 長き命を-(万2-217) 栲縄の長き命を欲りしくは絶えずて人を見まく欲りこそ(万4-707) 水沫なすもろき命も栲縄の千尋にもがと願ひ暮らしつ(万5-907) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たくひれの [栲領布の] | 【枕詞】 栲領布は色が白く、また、肩に掛けるところから「白」「鷺(さぎ)」「かけ」にかかる。 |
かへらまに君こそ我れに栲領巾の白浜波の寄る時もなき(万11-2833) 栲領巾の鷺坂山の白つつじ我れににほはに妹に示さむ(万9-1698) 栲領巾のかけまく欲しき妹の名をこの勢能山にかけばいかにあらむ [一に云ふ 替へばいかにあらむ](万3-288) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たぐふ [比ふ・類ふ・副ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 ① 並ぶ。添う。いっしょにいる。 ② いっしょに行く。伴う。連れ立つ。③ 似合う。つり合う。 ④ 匹敵する。肩を並べる。はりあう。 |
① ひさかたの雨も降らぬか雨つつみ君にたぐひてこの日暮らさむ(万4-523) ① -妹がため 我も事なく 今も見るごと たぐひてもがも(万4-537) ② -この国より又つかひまかりいたりけるにたぐひて-(古今羇旅左注) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 ① 並ばせる。添わせる。いっしょにさせる。 |
① 花の香を風のたよりにたぐへてぞ鶯さそふしるべには遣る(古今春上-13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たごのうら [田子の浦] | 昼見れど飽かぬ昼見れど飽かぬ田子の浦大君の命恐み夜見つるかも(万3-300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻三-297 『付録 地名一覧』」】 富士川西岸の、静岡県庵原郡の蒲原・由比・倉沢の海浜。現在の田子の浦は富士川の東岸の富士市に属し、別の地である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たすく [助く・輔く・扶く] | 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 ① 事をしている人に力を添える。助ける。補佐する。助力する。 ② (力を添えて苦難や病苦などから) 救う。 ③ 倒れるのをささえる。力を添える。 |
① 天地の神も助けよ草枕旅行く君が家に至るまで(万4-552) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ただ [只・唯] | 〔副詞〕 ① それ一つに限っているさま。こればかり。それだけ。ただ、他になく。 ② わずかに。たった。③ 事情が単純であるさま。単に。 |
② -ただひとりして 白たへの 衣手干さず 嘆きつつ 我が泣く涙-(万3-463) ② 山峽に咲ける桜をただ一目君に見せてば何をか思はむ(万17-3989) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たたす [立たす] | 〔上代語〕 〔なりたち〕 四段動詞「立つ」の未然形「たた」+上代の尊敬の助動詞「す」 「お立ちになる」 |
-故(かれ)、二柱(ふたはしら)の神、天(あめ)の浮き橋にたたして-畳(記上) -夕には い寄り立たしし み執らしの 梓の弓の 中弭の 音すなり-(万1-3) 日並の皇子の命の馬並めてみ狩り立たしし時は来向ふ(万1-49) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たたなづく [畳なづく] | 〔自動詞カ行四段〕《上代語》 重なり合う。幾重にもうねり重なる。 |
倭は国のまほろばたたなづく青垣山ごもれる倭しうるはし(記・中) -か寄りかく寄り 靡かひし 嬬の命の たたなづく 柔肌すらを-(万2-194) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たたなはる [畳なはる] | 〔自動詞ラ行四段〕幾重にも重なる。重なり合う。うねり重なる。 |
-高殿を 高知りまして 登り立ち 国見をせせば たたなはる 青垣山 -(万1-38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集第一-38番頭注」】 たたなはる-幾重にも重なる。積む、重なる、の意の「委」について「委、タタナハル」(名義抄)とある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ただに | 〔副詞〕[形容動詞「ただなり」の連用形から ① 【直に】 ア:まっすぐに。イ:直接に。ずばりと。 ② 【徒に】 むなしく。なにもしないで。 ③ 【唯に・啻に】(下に打消・反語を表す語を伴って)ただ単に。 |
①ア -尾張にただに向かへる尾津の崎なる一つ松吾(あせ)を-(記中) ①イ 直に逢はば逢ひかつましじ石川に雲立ち渡れ見つつ偲はむ(万2-225) ①イ 大船の思ひ頼みし君が去なば我は恋ひむな直に逢ふまでに(万4-553) ①イ 赤駒のい行きはばかる真葛原何の伝て言直にしよけむ(万12-3083) ③ -大保をばただに卿とのみは思ほさず-(続日本紀) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たたぬ [畳ぬ] | 〔他動詞ナ行下二段〕【ネ・ネ・ヌ・ヌル・ヌレ・ネヨ】たたむ。 | 君が行く道の長手を繰り畳ね焼き滅ぼさむ天の火もがも(万15-3746) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たたはし | 〔形容詞シク活用〕 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 ① 満ち足りている。完全無欠だ。 ② いかめしくおごそかである。堂々としている。 |
① - 望月の 満しけむと 我が思へる 皇子の命は 春されば-(万13-3338) 【「たたはしけ」は上代の未然形】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ただむかふ [直向かふ] | 〔自動詞ハ行四段〕[「ただむこふ」とも] まっすぐに向き合う。 |
-天さがる 鄙の国辺に 直向かふ 淡路を過ぎ 粟島を そがひに見つつ-(万4-512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たち- | 〔接頭語〕動詞に付いて意味を強める。 「たち後(おく)る・たち隠る・たち騒ぐ・たち添ふ・たち別るetc」 【参考】動詞「立つ」の意味が残る時は接頭語としない。 |
山吹の立ちよそひたる山清水汲みに行かめど道の知らなく (万2-158) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -たち [-達] | 〔接尾語〕[「だち」とも](神・人を表す名詞・代名詞に付いて) ① 敬意をこめた、複数の意を表す。 ② 単数の人を表す語に付いて、漠然と敬意を示す。 「公達(きんだち)」「友達」 |
古の七の賢しき人たちも欲りせしものは酒にしあるらし(万3-343) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たち [太刀・大刀] | 〔名詞〕 ① 上代、刀剣の総称。 ② 平安時代以降、儀礼用または戦闘用の、そりのある大きな刀。 |
① -皇子ながら 任けたまへば 大御身に 大刀取り佩かし 大御手に-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たちかくる [立ち隠る] | 〔自動詞ラ行四段・下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 [「たち」は接頭語] 隠れる。 |
佐保川の岸のつかさの柴な刈りそねありつつも春し来らば立ち隠るがね(万4-532) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たぢから [手力] | 〔名詞〕手の力。腕の力。 | 岩戸割る手力もがも手弱き女にしあればすべの知らなく(万3-422) 君がため手力疲れ織れる衣ぞ春さらばいかなる色に摺りてばよけむ(万7-1285) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たちきく [立ち聞く] | 〔他動詞カ行四段〕 ① 立ったままで聞く。通りがかりなどに小耳にはさむ。 ② 物陰に立っていてそっと聞き耳を立てる。立ち聞きをする。 |
② -止まず出で見し 軽の市に 我が立ち聞けば 玉たすき 畝傍の山に-(万2-207) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たちさもらふ [立ち候ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕[「たち」は接頭語] 警護する。伺候する。奉仕する。 | -神の御門に 外の重に 立ち候ひ 内の重に 仕へ奉りて-(万3-446) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たちさわぐ [立ち騒ぐ] | 〔自動詞ガ行四段〕[「たち」は接頭語] 騒ぎ立てる。大騒ぎをする。 |
-滝の上の 浅野の雉 明けぬとし 立ち騒くらし いざ子ども-(万3-391) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たちばな [橘] | 〔名詞〕万葉集中六十八首の歌に詠まれている。 ① 果樹の名。こうじみかん。初夏に香りの高い白い花をつける。 果実はみかんに似ている。[秋・橘飾る、春・橘の花] ② 「襲 (かさね) の色目」の名。表は朽ち葉、裏は黄。 〔一説に、表は白、裏は青とも〕 ③ 紋所の名。「①」の葉と果実とを図案化したもの。 |
① 橘の蔭踏む道の八衢に物をぞ思ふ妹に逢はずして [三方沙弥](万2-125) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【参考】 「さつき待つ花たちばなの香をかげば昔の人の袖の香ぞする (古今夏)」の歌から、昔を思い出させるものとされ、象徴的に使われることがある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たちばな [橘] | 〔地名〕 | 橘の嶋の宮には飽かねかも佐田の岡辺に侍宿しに行く(万2-179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻二 179 注『橘の島の宮』」】 橘は地名。講義に「この橘の島の宮といふ語によりて、橘がその本来の地名なりしことを想像すべく、かくて、古橘といひし地は今の島荘までも包含せしものなるべく思はる」 と言う。 この点について、最近の調査報告として秋山日出雄「付・嶋宮伝承地発掘調査概要」(『明日香村史』上) には 「現在の島庄は応永二十七年以来の文書にその名が現れ、飛鳥川の右岸に位置し、左岸の橘とは別のようにも見られるが、島庄村は実は、明暦二年(一六五六) に橘村より村切りによって分村したのであった。現に口碑では、当時五戸の家々が橘より分かれて住んだと伝えている。 故に島庄の古い墓地は橘に存し、また島庄の氏神社は戦時中に一時は橘の氏神社に合祀したこともあるという。 このようにして島庄は、今でも橘とは密接な関係があることは、万葉集に『橘の嶋の宮』と歌われたことを理解するのに、はなはだ役立つところである」 と記す。 なお、古くは島の庄を含む広い範囲が橘と呼ばれていたことは間違いないとして、その名の起源に橘の樹の繁殖を考える説のあることも付記しておくべきだろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たちみる [立ち見る] | 〔他動詞マ行上一段〕【ミ・ミ・ミル・ミル・ミレ・ミヨ】 立ってものを見る。たたずんで見る。 |
-家のあたり 我が立ち見れば 青旗の 葛城山に たなびける 白雲隠る-(万4-512) -我が立ち見れば 長き世の 語りにしつつ 後人の 偲ひにせむと-(万9-1805) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たちむかふ [立ち向かふ] | 〔自動詞ハ行四段〕① 立って向かう。② 手向かう。 | ① 大丈夫のさつ矢手挟み立ち向ひ射る圓方は見るにさやけし(万1-61) ① -手に取り持ちて ますらをの さつ矢手挟み 立ち向かふ 高円山に-(万2-230) ② -まつろはず 立ち向ひしも 露霜の 消なば消ぬべく 行く鳥の-(万2-199) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たちよそふ [立ち装ふ] | 〔他動詞ハ行四段〕[たち]は接頭語。 飾る。装う。 | 山吹の立ちよそひたる山清水汲みに行かめど道の知らなく (万2-158) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たちわたる [立ち渡る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① (雲や霧などが)一面におおう。 ② (車などが)ずらりと並ぶ。 |
① 直に逢はば逢ひかつましじ石川に雲立ち渡れ見つつ偲はむ(万2-225) ① 春の野に霧立ちわたり降る雪と人の見るまで梅の花散る[筑前目田氏真上](万5-843) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たつ [立つ] | 〔自動詞タ行四段〕(縦になる、縦の状態である、という意味から) ① (人や動物が) 起立する。立ち止まっている。起き上がる。 ② たてに真っ直ぐになる。起立する。 ③ 高くのぼる。(鳥などが)飛び立つ。飛び去る。 ④ 雲・霧・霞・煙などが立ちこめる。 ⑤ 出発する。旅に出る。 ⑥ 風や波が起こる。⑦ 音などが高く響く。 ⑧ 位置を占める。位する。⑨ 退席する。その場をはなれる。 ⑩ (年月や季節などが)始まる。 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻第一-38 鵜川立つ」頭注】 「立つ」-四段「たつ」は「催す」の意。⇒「鵜川(うかは)」 |
① あしひきの山のしづくに妹待つと我れ立ち濡れぬ山のしづくに(万2-107) ① 莫囂円隣之大相七兄爪謁気我が背子がい立たせりけむ厳橿が本(万1-9)(青:難訓) ② -隠口の 初瀬の山は 真木立つ 荒き山道を 岩が根 禁樹押しなべ-(万1-45) ③ 味酒のみもろの山に立つ月の見が欲し君が馬の音ぞする(万11-2517) ④ -朝に置きて 夕には 消ゆといへ 霧こそば 夕に立ちて 朝には-(万2-217) ④ み吉野の三船の山に立つ雲の常にあらむと我が思はなくに(万3-245) ④ 明日香川川淀去らず立つ霧の思ひ過ぐべき恋にあらなくに(万3-328) ④ 霞立つすゑのまつやまほのぼのと波にはなるるよこぐもの空(新古春上-37) ⑤ 香具山と耳成山と闘ひし時立ちて見に来し印南国原(万1-14) ⑤ 大和辺に君が立つ日の近づけば野に立つ鹿もとよめてそ鳴く(万4-573) ⑥ -雲居に吹くに 沖見れば とゐ波立ち 辺を見れば 白波騒く - (万2-220) ⑥ 芦北の野坂の浦ゆ船出して水島に行かむ波立つなゆめ(万3-247) ⑥ -霞立つ 春に至れば 松風に 池波立ちて 桜花 木の暗茂に 沖辺には-(万3-259) ⑦ 堀江漕ぐ伊豆手の舟の楫つくめ音しば立ちぬ水脈早みかも(万20-4484) ⑧ -人丸は赤人が上に立たむことかたく-(古今・仮名序) ⑨ 今日のみと春を思はぬ時だにも立つことやすき花のかげかは (古今春下-134) ⑩ ひさかたの天の香具山この夕霞たなびく春立つらしも(万10-1816) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞タ行下二段〕【テ・テ・ツ・ツル・ツレ・テヨ】 ① 立てる。こしらえる。② 鳥などを追い立てる。 ③ 出発させる。④ 戸などを閉める。閉ざす。 |
① 鳥座立て飼ひし雁の子巣立ちなば真弓の岡に飛び帰り来ね(万2-182) ① 山守のありける知らにその山に標結ひ立てて結ひの恥しつ(万3-404) ① 橘の本に我を立て下枝取りならむや君と問ひし子らはも(万11-2494) ② -朝猟に 五百つ鳥立て 夕猟に 千鳥踏み立て 追ふ毎に-(万17-4035) ③ 赤駒が門出をしつつ出でかてにせしを見立てし家の子らは(万14-3555) ④ 豊国の鏡の山の岩戸立て隠りにけらし待てど来まさず(万3-421) ④ 門立てて戸も閉したるをいづくゆか妹が入り来て夢に見えつる(万12-3131) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [(たち)たつ] | あちらこちら盛んに立つ意。 炊煙の多さによって庶民の生活の賑わいを示す。 |
-国見をすれば 国原は 煙立ち立つ 海原は 鴎立ち立つ-(万1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たづ [鶴・田鶴] | 〔名詞〕鶴の異名。 上代にも「つる」という語はあったが、和歌には普通「たづ」を用いた。 |
大和恋ひ寐の寝らえぬに心なくこの洲崎廻に鶴鳴くべしや(万1-71) 桜田へ鶴鳴き渡る年魚市潟(あゆちがた)潮干にけらし鶴鳴き渡る(万3-273) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻第一-71 たづ」頭注】 鶴の「歌語」。丹頂ばかりでなく、なべづる・まなづるなど鶴類を広くさし、時に白鳥などの大型の鳥にも広く称した。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たづがね [鶴が音・田鶴が音] | 〔なりたち〕[「が」は「の」の意の格助詞] ① 鶴の鳴く声。② 鶴の異名。 |
たづがねの聞こえむときはわが名問はさね(記下) 旅にしてもの恋ほしきに鶴が音も聞こえざりせば恋ひて死なまし(万1-67) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たづき | 〔名詞〕《方便》上代は「たどき」とも。後「たつき・たつぎ」とも。 ① 手段・方法・手掛かり。 ② ようす。ありさま。見当。 |
をちこちのたづきも知らぬ山中におぼつかなくも喚子鳥かな(古今春上-29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たづさはる [携はる] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 互いに手を取る。連れ立つ。② 関係する。かかわる。 |
-秋立てば もみち葉かざし 敷栲の 袖携さはり 鏡なす-(万2-196) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たづたづし | 〔形容詞シク活用〕[「たどたどし」の古形] 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 心もとない。心細い。おぼつかない。 |
草香江の入江にあさる葦鶴のあなたづたづし友なしにして(万4-575) 夕闇は道たづたづし月待ちて行ませ我が背子その間にも見む(万4-712) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たつたやま [立田山・竜田山] | 〔地名〕[歌枕] 今の奈良県生駒郡三郷町の西方、信貴山の南にある山。紅葉の名所。 和歌では多く「たつ」「たち」を導き出す序詞となる。 |
海の底沖つ白波龍田山いつか越えなむ妹があたり見む(万1-83) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たづぬ [尋づぬ・訪づぬ] | 〔他動詞ナ行下二段〕【ネ・ネ・ヌ・ヌル・ヌレ・ネヨ】 ① 物事のあとをつけて行ってさがす。追いかける。 ② 事のわけを究明する。詮索する。 ③ 問いただす。質問する。聞きただす。④ 訪問する。訪れる。⑤ 告げる。 |
① 君が行き日長くなりぬ山尋ね迎へか行かむ待ちにか待たむ(万2-85) ① うつせみは数なき身なり山川のさやけき見つつ道を尋ねな(万20-4492) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たて [楯] | 〔名詞〕 ① 戦場で身を隠し、敵の矢・剣・弾丸などを防ぐ武具。儀式の装飾としても用いる。 ② 防ぎ守ること。また、そのもの。 |
① ますらをの鞆の音すなり物部の大臣盾立つらしも(万1-76) ② 今日よりは返り見なくて大君の醜の御楯と出で立つ我れは(万20-4397) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たとふ [喩ふ・譬ふ] | 〔他動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 たとえる。他の物事になぞらえていう。 |
世の中を何に喩へむ朝開き漕ぎ去にし船の跡なきごとし(万3-354) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たとへ [喩へ・譬へ] | 〔名詞〕「たとひ」とも。 たとえること。たとえとして引かれる話や事柄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たどほし [た遠し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】[「た」は接頭語] 遠い。 |
遠妻の ここにしあらねば 玉桙の 道をた遠み 思ふそら 安けなくに-(万4-537) -道をた遠み 間使も 遺るよしもなし 思ほしき 言伝て遣らず-(万17-3984) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たな | 〔語意不詳〕 例:「-其を取ると 騒く御民も 家忘れ 身もたな知らず 鴨じもの 水に浮き居て-(万1-50)」 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻第一50 たな」頭注】 「たな」は十分にの意。打消しと応じて、全然、の意となる。献身的に奉仕することを示す。 【有斐閣「万葉集全注巻第一-50 たな」注】(私注:文中歌番号は、旧歌番号) 「たな」はすっかり、一様にの意の形状言。「身をたな知りて」(9・1807)のように肯定形にも用いる。 【中央公論社「萬葉集注釈巻第一-50 身もたな知らず」注】(私注:文中歌番号は、旧歌番号) 「たな」の語原は不明であるが、 「身者田菜不知(ミハタナシラズ)」(9・1739)、 「身乎田名知而(ミヲタナシリテ)」(9・1807)、 「事者棚知(コトハタナシシ)」(13・3279) などの例と照合すると、すつかり、全く、などの意の接頭語で、上の「家も忘れ」と対して「身も顧みず」といふ程度の意と思はれる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たなかみやま [田上山] | 〔名詞〕 滋賀県大津市南部、大戸川(瀬田川支流)の上流にある山。 建築の良材である檜の名産地。 |
-石走る 近江の国の 衣手の 田上山の 真木さく 桧のつまでを-(万1-50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たななしをぶね [棚無し小舟] | 〔名詞〕左右の船端の内側に踏み板のない小さな舟。貧弱で安定性を欠く。 | いづくにか船泊てすらむ安礼の崎漕ぎ廻み行きし棚無し小舟(万1-58) 四極山うち越え見れば笠縫の島漕ぎ隠る棚なし小舟(万3-274) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たなばた [七夕・棚機] | 〔名詞〕 ① 機織。はた。② 「棚機つ女」の略。 ③ 五節句の一つ。牽牛・織女の二星が年に一度だけ逢うという陰暦七月七日の夕べ。 たなばた祭り。 |
② たなばたの今夜逢ひなば常のごと明日を隔てて年は長けむく(万10-2084) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【「棚機」の起源】 「棚機」と書くのは、この日、川辺に棚を設け、機(はた)で織った布を身に着けて川に入る禊を女性が行っていたことによるという。盆を前にした儀礼とする説もある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たなばたつめ [棚機つ女・織女] | 〔名詞〕〔「つ」は、「の」の意の上代の格助詞〕 ① 機(はた) を織る女。② 織女星を人にみたてたもの。 |
① 我がためと織女のそのやどに織る白栲は織りてけむかも(万10-2031) ② かりくらし織女にやどからん あまのかはらに我はきにけり(古今羇旅-418) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たなびく [棚引く] | 〔自動詞カ行四段〕 ① 雲や霞などが、横に長く引く。 〔他動詞カ行四段〕 ② たなびかせる。長く集め連ねる。 |
① 北山にたなびく雲の青雲の星離り行き月を離れて(万2-161) ① み吉野の高城の山に白雲は行きはばかりてたなびけり見ゆ(万3-356) ① 山の際ゆ出雲の児らは霧なれや吉野の山の嶺にたなびく(万3-432) ① ひさかたの天の香具山この夕霞たなびく春立つらしも(万10-1816) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-429 注『たなびく』」】 原文「霏□[雨の下に微] 」とある。この文字は元来中国六朝頃から少しずつ見出される「甘雨霏微トシテナホ宿霧ヲ蔵(をさ)ムルゴトシ」(梁元帝、謝勅送斉王瑞像還啓) の如き「霏微」(雨雪露霜などの天然現象のちらちらとふる姿を形容する語) に基づいて、「霏□[雨の下に微」 と、雨冠をつけて文字上の視覚的効果を狙ったもので、人麻呂の発明である(小島憲之『上代日本文学と中国文学』中)。タナビクは上の係助詞「ヤ」を受けて結んだ連体形である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たなれ [手慣れ・手馴れ] | 〔名詞〕 ① 手に扱いなれていること。愛用。 ② 動物を飼いならしてあること。手飼い。 |
① 言とはぬ木にもありとも我が背子が手馴れの御琴地に置かめやも(万5-816) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たに [谷] | 〔名詞〕山あいの細長くくぼんだところ。 |
今日今日と我が待つ君は石川の貝に [一云 谷に] 交じてありといはずやも(万2-224) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| だに | 〔副助詞〕 ① (まだ起こっていない未来の事柄とともに) 最小限の一例をあげて強調する。 「だに」を受ける語句は打消・反語・命令・意志・願望・仮定の表現。 「せめて~だけでも。~だけなりとも。」 ② (多く既定の事柄とともに) 軽いものをあげて、他にもっと重いものがあることを類推させる。 「だに」を受ける語句は、打消・反語の表現が多い。 「~だって。~のようなものでさえ。」 ③ 添加を表す。「~までも。」 〔接続〕 体言・活用語・副詞・助詞に付く。 複合語の間に用いられることもある。 【文法】 奈良時代は①も用法だけで、まだ起こっていない未来の事柄に関して用いられた。②は平安時代以降の用法で、、「すら」とほぼ同じ意味に使われている。③は「さへ」が広く使われるようになったために、逆に「だに」が「さへ」の意味で使われたもの。 |
① 明日香川明日だに [さへ] 見むと思へやも [思へかも] 我が大君の御名忘れせぬ [御名忘らえぬ](万2-198) ① いつしかと待つらむ妹に玉梓の言だに告げず去にし君かも(万3-448) ① 言清くいたくもな言ひそ一日だに君いしなくは堪へ難きかも(万4-540) ② 古りにし嫗にしてやかくばかり恋に沈まむ手童のごと [恋をだに忍びかねてむ手童のごと](万2-129) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -も [だにも] | 〔成り立ち〕副助詞「だに」+係助詞「も」 ① 最小限の一例をあげて強調する意を表す。 せめて~だけでも。 ② 軽いものをあげて、他の重いものを類推させる。 ~さえも。 |
① 三輪山をしかも隠すか雲だにも心あらなも隠さふべしや(万1-18) ② -うつせみと 思ひし妹が 玉かぎる ほのかにだにも 見えなく思へば(万2-210) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たのし [楽し] | 〔形容詞シク活用〕【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 ① 楽しい。愉快だ。② (物質面で)豊かである。富裕だ。 |
矢釣山木立も見えず降りまがふ「雪につどへる朝楽しも」(万3-264)下二句定訓なし 正月立ち春の来らばかくしこそ梅を招きつつ楽しき終へめ [大貳紀卿](万5-819) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たのむ [頼む] | 1〔他動詞マ行四段〕 ① 頼みにする。あてにする。② 信用する。信頼する。 2〔他動詞マ行下二段〕【メ・メ・ム・ムル・ムレ・メヨ】 ① 頼みに思わせる。あてにさせる。 |
1 -天の下食す国四方の人の 大船の思ひ頼みて天つ水 仰ぎて待つに- (万2-167) 1 -かくしもがもと 頼めりし 皇子の御門の 五月蝿なす 騒く舎人は-(万3-481) 1 -自妻と 頼める今夜 秋の夜の 百夜の長さ ありこせぬかも(万4-549) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たはこと [戯言] | 〔名詞〕 ① でたらめ。意味のないことば。たわけたことば。妄語。 ② うわごと。 |
① -逆言か 我が聞きつる たはことか 我が聞きつるも 天地に-(万3-423) ① あづきなく何のたはこと今さらに童言する老人にして(万11-2587) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たばさむ [手挟む旅] | 〔他動詞マ行四段〕 手に挟み持つ。脇に抱え持つ。 |
大丈夫のさつ矢手挟み立ち向ひ射る圓方は見るにさやけし(万1-61) -手に取り持ちて ますらをの さつ矢手挟み 立ち向かふ 高円山に-(万2-230) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たはる [戯る・狂る] | 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 ① 戯れる。ふざける。② みだらな行為をする。恋におぼれる。 |
人皆の かく惑へれば たちしなひ 寄りてぞ妹は たはれてありける- (万9-1742) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たばる [賜ばる・給ばる] | 〔他動詞ラ行四段〕[尊敬語の四段動詞「賜(た)ぶ」の謙譲語形] 「受く・もらふ」 の謙譲語。いただく。 |
古人の飲へしめたる吉備の酒病まばすべなし貫簀賜らむ(万4-557) 我が君に戯奴は恋ふらし賜りたる茅花を食めどいや痩せに痩す(万8-1466) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たはれを [戯れ男] | 〔名詞〕好色な男。放蕩をする男。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たひ [手火] | 〔名詞〕(「たび」とも) 手に持ち、道などを照らす火。たいまつなど。 |
-天皇の 神の皇子の 出でましの 手火の光りそ そこば照りたる(万2-230) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たび [旅] | 〔名詞〕 家を離れて、一時他の場所へ行くこと。また、その途中。旅行。 |
草枕旅行く君と知らませば岸の埴生ににほはさましを(万1-69) 旅にしてもの恋しきに山下の赤のそほ船沖を漕ぐ見ゆ(万3-272) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たびと [旅人] | 〔名詞〕[「たびびと」の転] 旅行者。旅にある人。 | 家にあらば妹が手まかむ草枕旅に臥やせるこの旅人あはれ(万3-418) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たびね [旅寝] | 〔名詞・自動詞サ変〕 旅先で寝ること。旅宿。また、自宅以外のところで寝ること。外泊。 =「旅枕(たびまくら)」 |
-玉裳はひづち 夕霧に 衣は濡れて 草枕 旅寝かもする 逢はぬ君故-(万2-194) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たびやどり [旅宿り] | 〔名詞〕旅先の宿泊。旅宿。⇒「旅寝(たびね)」 | み雪降る 安騎の大野に 旗すすき 小竹を押しなべ 草枕 旅宿りせす(万1-45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たひらけし [平らけし] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 穏やかである。無事である。 |
-片手には 和たへ奉り 平けく ま幸くませと 天地の 神を乞ひ祷み-(万3-446) -我が来るまでに 平けく 親はいまさね つつみなく 妻は待たせと-(万20-4432) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たぶ [賜ぶ・給ぶ] | 〔他動詞バ行四段〕「与ふ・やる・くる」などの尊敬語。 「お与えになる」「くださる」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔補助動詞バ行四段〕 ① 動詞の連用形に付いて、尊敬の意を表す。 「お~になる」「お~くださる」 ② 接続助詞「て」に付いて、恩恵を及ぼす動作として尊敬する意を表す。 「~てくださる」 |
① 我が聞きし耳によく似る葦の末の足ひく我が背つとめ給ぶべし(万2-128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【語史】 「たぶ」は「たまふ」がもとで「たまふ→たんぶ→たうぶ→たぶ」と変化したものとみる説と、逆に「たぶ」がもとで「たぶ→たばふ→たまふ」と変化したとみる説がある。 「たぶ」は「たまふ」に比べて敬意は低いが、上代以後ずっと用いられ、「補助動詞」は近世にまで用例が見える。 「補助動詞 ②」の用法は、中世から見あっれ、その命令表現は、下にさらに「給ふ」「せ給ふ」を付けて、「てたび給へ」「てたばせ給へ」の形をとることもある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たぶしのさき [手節の崎] | 〔地名〕[「たふしのさき」とも] 三重県鳥羽市答志(とうし)島の東端の岬。今の黒崎。〔歌枕〕 |
釧着く答志の崎に今日もかも大宮人の玉藻刈るらむ(万1-41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たふとし [尊し・貴し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① 敬うべきである。尊い。 ② 品位が高く、優れている。尊い。 ③ すぐれて価値がある。りっぱである。 |
① 父母を 見れば貴し 妻子見れば めぐし愛し 世間は かくぞことわり(万5-804) -赤玉は緒さへ光れど白玉の君が装ひしたふとくありけり-(記・上) ② -神からか ここだ貴き 天地 日月と共に 足り行かむ 神の御面と-(万2-220) ② 言はむすべせむすべ知らず極まりて貴きものは酒にしあるらし(万3-345) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たへ [栲] | 〔名詞〕こうぞの樹皮の繊維で織った布。また、布類の総称。 |
栲の袴を七重着(を)し(雄略紀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たへ [妙] | 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 ① 神々しいほどにすぐれている。何ともいえず素晴らしい。霊妙だ。 ② 上手だ。巧妙だ。 【語感】 自然や芸道などが際立ってすぐれ、神秘的にさえ思われる感じ。 |
①-海神の 神の宮の 内のへの 妙なる殿に たづさはり -(万9-1744) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たへがたし [堪へ難し] (あへがたし) |
〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 がまんしにくい。こらえられそうもない。つらい。苦しい。 |
言清くいたくもな言ひそ一日だに君いしなくは堪へ難きかも(万4-540) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たへのほ [栲の穂] | 〔名詞〕 純白。真っ白。 |
-朝月夜 さやかに見れば 栲の穂に 夜の霜降り 岩床と-(万1-79) 栲のほの 麻衣着れば 夢かも うつつかもと 曇り夜の(万13-3338) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たま [玉・珠] | 〔名詞〕 ①美しい石。宝石。②真珠。③美しいものの形容。 ④ (涙・露など)丸い形をしたものの総称。 |
① 銀も金も玉も何せむにまされる宝子にしかめやも(万5-807) ② 我が欲りし野島は見せつ底深き阿胡根の浦の玉ぞ拾はぬ [或頭云 我が欲りし子島は見しを](万1-12) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-346 注『夜光る玉』」】 夜光る名玉。『文選』西都賦などに見える「夜光」は「夜光珠・夜光璧」の略で宝玉の名である。 『芸文類聚』宝玉部の璧の条に『戦国策』や『続漢書』の出典例、珠の条に『広志』・『魏略』・『捜神記』の出典例を挙げているように、諸書に見える著名な名で、世俗的な有価の貴重なものとされた。それを旅人は訓読したもの。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -(に)ぬく [玉(に)貫く] | 〔他動詞カ行四段〕 玉の穴に緒を通す。多く、花・実・露などを玉に見立てていう。 |
-ほととぎす 鳴く五月には あやめぐさ 花橘を 玉に貫き-(万3-426) 霍公鳥何の心ぞ橘の玉貫く月し来鳴き響むる(万17-3934) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまかぎる [玉かぎる] | 【枕詞】[「かぎる」は「輝く」の意] 玉のほのかに光る状態から、「夕」「日」「ほのか」「はろか」 また、「磐垣淵(いはかきふち)」などにかかる。 |
玉かぎる夕さり来ればさつ人の弓月が岳に霞たなびく(万10-1820) -思ひ頼みて 玉かぎる 岩垣淵の 隠りのみ 恋ひつつあるに-(万2-207) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまかづら [玉葛・玉縵] | 〔名詞〕「たま」は接頭語で美称。葛の美称。つる草の総称。 | たまかづらはふ木あまたになりぬれば絶えぬ心のうれしげもなし(古恋四-709) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】 葛の蔓が延び広がる意から「長し・延ふ・筋・いや遠長く・絶ゆ」に、 また葛の花・実の意で、「花・実」に懸かる。 |
玉葛実ならぬ木にはちはやぶる神ぞつくといふならぬ木ごとに(万2-101) -つがの木の いや継ぎ継ぎに 玉葛 絶ゆることなく ありつつも-(万3-327) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまかづら [玉鬘] | 上代、多くの玉に緒を通し、髪にかけ垂らして飾りとしたもの。 | 「礼物として、押木の玉鬘を持たしめて奉りき」(記・下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】 玉鬘は髪飾りとして頭にかけるので「かく」、「かげ」に懸かる。 |
玉葛懸けぬ時なく恋ふれども何しか妹に逢ふ時もなき(万12-3007) 人はよし思ひやむとも玉葛影に見えつつ忘らえぬかも(万2-149) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまぎぬ [玉衣] | 〔名詞〕[「たま」は接頭語] 「たまきぬ」とも。美しい衣服。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまぎぬの [玉衣の] | 【枕詞】 衣ずれの音から「さゐさゐ」にかかる。 |
玉衣のさゐさゐしづみ家の妹に物言はず来にて思ひかねつも(万4-506) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまきはる | 【枕詞】「うち」「世」「命」「吾(わ)」などにかかる。 | たまきはる宇智の大野に馬並めて朝踏ますらむその草深野(万1-4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまくし [玉櫛] | 〔名詞〕[「たま」は接頭語] 髪の毛を梳いたり、」また、髪飾りにしたりする道具。 奈良時代以降、「黄楊(つげ)」で作ることが多く、竹・鼈甲製のものもある。 |
娘子らが玉櫛笥なる玉櫛の神さびけむも妹に逢はずあれば(万4-525) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまくしげ [玉櫛笥・玉匣] | 〔名詞〕[「たま」は接頭語] 櫛を入れる箱の美称。 | -家はあらむと 玉櫛笥 少し開くに 白雲の 箱より出でて-(万9-1744) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】 「玉櫛笥」に関連した語の「ふた・箱・開く・覆ふ・あく・奥・身」などにかかる。 |
玉櫛笥覆ふを安み明けていなば君が名はあれど吾が名し惜しも(万2-93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまくら [手枕] | 〔名詞〕 腕を枕にすること。てまくら。 |
-凡に見し こと悔しきを 敷栲の 手枕まきて 剣太刀 身に添へ寝けむ-(万2-217) しきたへの手枕まかず間置きて年そ経にける逢はなく思へば(万4-538) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまだすき [玉襷] | 〔名詞〕「たま」は接頭語で美称。「たすき」の美称。玉を飾った「たすき」。 「たすき」は神事の際、神主・巫女などの奉仕者が肩から斜めに掛けた紐や木綿(ゆう)または葛(かずら)の類。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】たすきを項にかけるところから「かく」、また「うなじ」と類音の「うね」にかかる。 | -止まず出で見し 軽の市に 我が立ち聞けば 玉たすき 畝傍の山に-(万2-207) 玉たすき懸けねば苦し懸けたれば継ぎて見まくの欲しき君かも(万12-3005) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまだれ(の) [玉垂れ(の)] | 【枕詞】玉を緒に通して垂らしたものの意から、緒と同音の「を」 にかかる。 | -玉垂の 越智の大野の 朝露に 玉藻はひづち 夕霧に-(万2-194) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまづさの [玉梓の・玉章の] | 【枕詞】 便りの使者が梓(あずさ)の杖を持ったことから、 「使ひ・人・妹(いも)などにかかる。 |
-もみち葉の 過ぎて去にきと 玉梓の 使ひの言へば 梓弓-(万2-207) -神さびに 斎きいますと 玉梓の 人ぞ言ひつる およづれか-(万3-423) 玉梓の妹は花かもあしひきのこの山蔭に撒けば失せぬる(万7-1420) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまどこ [玉床] | 〔名詞〕[「たま」は接頭語] 「床」の美称。 | 家に来て我が屋を見れば玉床の外に向きけり妹が木枕(万2-216) 明日よりは我が玉床をうち掃ひ君と寐ねずてひとりかも寝む(万10-2054) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまのを [玉の緒] | 〔名詞〕 ① 玉をつなぐ紐。また、その玉かざり。 ② (①がすぐ切れることから) 時間の短さをたとえていう。多く恋の歌に用いる。 ③ (「たま(魂)」を体内に封じ込めるひもの意から) 命。命の糸。 |
① 初春の初子の今日の玉箒手に取るからに揺らく玉の緒(万20-4517) ③ 玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることの弱りもぞする(新古今恋一-1034) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまのをの [玉の緒の] | 【枕詞】 玉を貫く緒の形状から「長き」「短き」「絶え」「乱れ」「継ぐ」に、 玉を隙間なく連ねることから「間も置かず」に、 生命の意から「現(うつ)し心」に、「を」の同音から「惜し」にかかる。 |
-新た代に 共にあらむと 玉の緒の 絶えじい妹と 結びてし-(万3-484) 相思はずあるらむ子ゆゑ玉の緒の長き春日を思ひ暮らさく(万10-1940) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまはる [賜る・給はる] | 〔他動詞ラ行四段〕 ①「受く」「もらふ」の謙譲語。「いただく」「頂戴する」。 ②「与ふ」「授く」の尊敬語。「お与えになる」「くださる」。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔補助動詞ラ行四段〕 [動詞の連用形、それに助詞「て」の付いたものに付いて] ① 謙譲の気持ちを表す。「~て(で)いただく」。 ② 尊敬の気持ちを表す。「~て(で)くださる」。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまふ [賜ふ・給ふ] | 〔他動詞ハ行四段〕 ①「与ふ」「授く」の尊敬語。「お与えになる」「くださる」。 ② (命令形「たまへ」が他の動詞の代りに用いられて)尊敬の気持ちを含んだ命令の意を表す。「~てください」「~なさい」。 |
② あきづ羽の袖振る妹を玉くしげ奥に思ふを見たまへ我が君(万3-379) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔補助動詞ハ行四段〕 ① [動詞の連用形の下に付いて] 尊敬の気持ちを表す。 「お~になる」「~なさる」「~て(で)くださる」。 ② [尊敬の助動詞「す・さす・しむ」の連用形に付いた「せたまふ・させたまふ・しめたまふ」の形で] 最も強い尊敬の気持ちを表す。 「お~になられる」「~なされる」「お~あそばす」 |
① 我が大君の 朝には 取り撫でたまひ 夕には い寄り立たしし-(万1-3) ① -荒栲の 藤原が上に 食す国を 見したまはむと みあらかは-(万1-50) ① -荒栲の 藤井が原に 大御門 始めたまひて 埴安の 堤の上に-(万1-52) ① -宜しき君が 朝宮を 忘れたまふや 夕宮を 背きたまふや-(万2-196) ① -出でまして 遊びたまひし 御食向かふ 城上の宮を 常宮と-(万2-196) ② -和射見が原の 仮宮に 天降りいまして 天の下 治めたまひ-(万2-199) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 上代では「お与えになる」「くださる」という動詞の意味が残っていて、「~て(で)くださる」の訳語があてはまる場合もあるが、中古以降は動詞としての意はうすれてしまっている。「②」のうち「しめたまふ」の形をとるのは男性のことばにおいてである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 ① 「受く」「もらふ」 の謙譲語。いただく。 ② 「飲む」「食う」 の謙譲語。いただいたものを飲む、食べる意。 |
① 古人の飲へしめたる吉備の酒病まばすべなし貫簀賜らむ(万4-557) ① 鈴が音の早馬駅家の堤井の水を給へな妹が直手よ(万14-3458) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔補助動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 「思ふ・見る・聞く」 などの連用形について、話し手が、自己や自己側の者の動作をへりくだって言う意を表す。 存じます。目に(耳に) いたします。見て(聞いて) ・・・と存じます。 ・・・させていただきます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまほこ [玉桙・玉矛・玉鉾] | 〔名詞〕[「たまぼこ」とも] ① 玉で飾った美しいほこ。 ②「たまほこの」が「道」にかかる枕詞であることから、転じて、道。 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集第一-79 玉桙」頭注】 「たまほこ」は、悪霊の侵入を防ぐために境界点に立てられた桙状の石柱。 |
② この程は知るも知らぬも玉鉾の行き交ふ袖は花の香ぞする(新古今春下-113) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまほこの [玉桙の・玉矛の] | 【枕詞】 [「たまぼこの」とも]「道」「里」にかかる。 |
-八十隈おちず 万たび かへり見しつつ 玉桙の 道行き暮らし-(万1-79) 三香の原 旅の宿りに 玉桙の 道の行き逢ひに 天雲の-(万4-549) 遠くあれど君にぞ恋ふる玉桙の里人皆に我れ恋ひめやも(万11-2603) 玉桙の道はつねにもまどはなん 人をとふとも我かとおもはむ(古今恋四-738) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たままつ [玉松] | 〔名詞〕[「たま」は接頭語で美称] 松の美称。 |
み吉野の玉松が枝ははしきかも君が御言を持ちて通はく(万2-113) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻第二-113 玉松」注】 玉は接頭語。玉藻、玉床などの例を見る。古事記にも玉垣・玉盞 (たまうき) などがある。「タマ」はもと霊力・霊魂を意味する語であったが、それが接頭語として用いられ、美称化した。 ここでは「玉梓」と同じく、相手の言葉 (歌) を運んできたものとして、とくに親しみをこめて呼んだのであろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまも [玉裳] | 〔名詞〕[「たま」は接頭語で美称] 美しい裳(=女性が腰から下にまとった衣服)。 |
-玉垂の 越智の大野の 朝露に 玉裳はひづち 夕霧に-(万2-194) 娘子らが玉裳裾引くこの庭に秋風吹きて花は散りつつ(万20-4476) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまも [玉藻] | 〔名詞〕[「たま」は接頭語で美称] 美しい藻。 |
玉藻刈る沖へは漕がじ敷栲の枕のあたり忘れかねつも(万1-72) -か青なる 玉藻沖つ藻 朝羽振る 風こそ寄せめ -(万2-131) 沖辺にも寄らぬ玉藻の浪のうへに乱れてのみや恋ひわたりなむ(古今恋一-532) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまもかる [玉藻刈る] | 【枕詞】 玉藻は沖にあるところから「沖」に、 また地名「敏馬(みぬめ)」「をとめ」などにかかる。 |
玉藻刈る沖へは漕がじ敷栲の枕のあたり忘れかねつも(万1-72) 玉藻刈る敏馬を過ぎて夏草の野島が崎に船近づきぬ(万3-251) 玉藻刈る処女を過ぎて夏草の野島が崎に廬りす我れは(万15-3628) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまもなす [玉藻なす] | 【枕詞】 「なす」は「のようになる」の意で、「浮かぶ」「寄る」「なびく」などにかかる。 |
-もののふの 八十宇治川に 玉藻なす 浮かべ流せれ 其を取ると-(万1-50) -波こそ来寄れ 波のむた か寄りかく寄り 玉藻なす 寄り寝し妹を-(万2-131) -玉藻は生ふる 玉藻なす 靡き寝し子を 深海松の-(万2-135) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまもよし [玉藻よし] | 【枕詞】美しい海藻を産することから地名「讃岐(香川県)」にかかる。 | 玉藻よし 讃岐の国は 国からか 見れども飽かぬ 神からか ここだ貴き-(万2-220) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たむく [手向く] | 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 ① 神仏に、幣帛・花・香などを供える。 ② 旅をしようとする人に、餞別を贈る。はなむけとして贈る。 |
① 百足らず八十隈坂に手向けせば過ぎにし人にけだし逢はむかも(万3-430) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たむけ [手向け] | 〔名詞〕 ① 武力によって鎮定すること。 ② 神や仏に幣帛・花・香などを供える。③旅の餞別。はなむけ。 ④「峠」(そこで道祖神に「たむけ」をするところから) から由来して、とうげ。 |
② 周防なる磐国山を越えむ日は手向けよくせよ荒しその道(万4-570) ② -瑞穂の国に手向けすと天降りましけむ-(万13-3241) ④ 佐保過ぎて奈良の手向けに置く幣は妹を目離れず相見しめとそ(万3-303) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ぐさ [手向け草] | 〔名詞〕たむけにする品 | -少女らにあふさか山に手向け草糸とりおきて-(万13-3251) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ため [為] | 〔名詞〕 ① 目的を果たそうとしてすること。…のため。 ② 原因・理由・…のせい。 ③ 利益。たすけ。たより。…のため。 |
① 我が命も常にあらぬか昔見し象の小川を行きて見むため(万3-335) ② 君がため醸みし待酒安の野にひとりや飲まむ友なしにして(万4-558) ③ 楽浪の大山守は誰がためか山に標結ふ君もあらなくに(万2-154) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たもと [袂] |
〔名詞〕 ① [手本(たもと)の意] ひじから肩までの部分。二の腕。 ② 袖。衣服の袖のたれた袋状の部分。 |
① 帰るべく時はなりけり都にて誰が手本をか我が枕かむ(万3-442) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たもとほる [徘徊る] | 〔自動詞ラ行四段〕[「た」は接頭語] 行ったり来たりする。さまよう。うろつく。 |
-言はむすべ せむすべ知らに たもとほり ただひとりして 白たへの-(万3-463) 乎布の崎漕ぎた廻りひねもすに見とも飽くべき浦にあらなくに [一云 君が問はすも](万18-4061) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たゆ [絶ゆ] | 〔自動詞ヤ行下二段〕【エ・エ・ユ・ユル・ユレ・エヨ】 ① 絶える。途絶える。切れる。 ② 息が絶える。死ぬ。 ③ 縁が切れる。 ④ 人の往来がとだえる。人里はなれる。 |
① 見れど飽かぬ吉野の川の常滑の絶ゆることなくまたかへり見む(万1-37) ① -生ひなびける 玉藻もぞ 絶ゆれば生ふる 打橋に-(万2-196) ① 大君は千歳にまさむ白雲も三船の山に絶ゆる日あらめや(万3-244) ③ -万代に 絶えじと思ひて [一云 大船の 思ひたのみて] 通ひけむ-(万3-426) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たゆたふ [揺蕩ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 ① あちこち揺れ動く。漂う。② 思い迷う。ためらう。 |
① 大船の泊つる泊りのたゆたひに物思ひ痩せぬ人の子故に(万2-122) ① 常止まず通ひし君が使来ず今は逢はじとたゆたひぬらし(万4-545) ① 大船のたゆたふ海にいかり下ろしいかにせばかも我が恋やまむ(万11-2747) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たゆひがうら [手結が浦] | 〔地名〕福井県敦賀市田結(たい)の海岸。敦賀湾の東岸にあたる。 | -我が漕ぎ行けば ますらをの 手結が浦に 海人娘子-(万3-369) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たよわし [手弱し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】[「た」は接頭語] か弱い。弱々しい。 |
岩戸割る手力もがも手弱き女にしあればすべの知らなく(万3-422) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たらちねの [垂乳根の] | 【枕詞】 「母」また、中古以降「親」にかかる。 |
-立ちにし日より たらちねの 母の命は 斎瓮を 前に据ゑ置きて-(万3-446) たらちねの母が手離れかくばかりすべなきことはいまだせなくに(万11-2372) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たり [完了の助動詞] 「主要助動詞活用表」 |
〔助動詞〕 ① 動作・作用が完了した意を表す。「~た」 ② 動作・作用の結果が存続している意を表す。「~ている」 ③ 動作・作用が継続している意を表す。「~ている」 ④ その状態であること、またはその性状をそなえていることを表す。 「~ている」「~た」 ⑤ (中世以降の用法) 終止形を重ね用いた「~たり~たり」で、 二つの動作・作用が並行している意を表す。 〔接続〕 ラ変を除く動詞の連用形、および「つ」を除く動詞型活用の助動詞の連用形につく。 |
① 山吹は撫でつつ生ほさむありつつも君来ましつつかざしたりけり (万20-4326) ② 我れはもや安見児得たり皆人の得かてにすといふ安見児得たり(万2-95) ② -神の御面と 継ぎきたる 那珂の港ゆ 船浮けて 我が漕ぎ来れば-(万2-220) ③ 山吹の立ちよそひたる山清水汲みに行かめど道の知らなく (万2-158) ③ あしひきの山に生ひたる菅の根のねもころ見まく欲しき君かも(万4-583) ④ -天皇の 神の皇子の 出でましの 手火の光りそ そこば照りたる(万2-230) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たる [足る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 十分である。不足がない。満ち整っている。 ② 相応している。ふさわしい。また、価値がある。 ③ 満足する。 |
① -我が二人見し 出で立ちの 百足る槻の木 こちごちに 枝させるごと-(万2-213) ① -斎ひ子も 妹にしかめや 望月の 足れる面わに 花のごと-(万9-1811) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たれ [誰] | 〔代名詞〕《近世以降は「だれ」 とも》 不定称の人代名詞。だれ。 |
つれもなき佐田の岡辺に帰り居ば島の御階に誰れか住まはむ(万2-187) 荒波に寄り来る玉を枕に置き我ここにありと誰か告げけむ(万2-226) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たわらは [手童] | 〔名詞〕[「た」は接頭語] 幼い子ども。 | 古りにし嫗にしてやかくばかり恋に沈まむ手童のごと [恋をだに忍びかねてむ手童のごと](万2-129) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たをやめ(たわやめ) [手弱女] | 〔名詞〕かよわい女。しとやかでやさしい女性。⇔「ますらを」 | 膝折り伏して たわやめの おすひ取りかけ かくだにも(万3-382) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たをる [手折る] | 〔他動詞ラ変四段〕手で折る。 | いざ子ども大和へ早く白菅の真野の榛原手折りて行かむ(万3-283) -労はしければ 玉桙の 道の隈廻に 草手折り 柴取り敷きて-(万5-890) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちかし [近し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① (時間的・空間的・数量的・心理的に) 隔たりが少ない。近い。 ② 血縁関係が近い。近親である。 ③ 物事の内容・性質の似ているさま。近い。 |
① 我妹子がやどの橘いと近く植ゑてし故に成らずは止まじ(万3-414) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちかづく [近づく] | 〔自動詞カ行四段〕 ① 近寄る。接近する。② 親密になる。むつまじくなる。 ③ 時日がさしせまる。時期が近くなる。 |
① 玉藻刈る敏馬を過ぎて夏草の野島の崎に船近づきぬ(万3-251) ③ 大和辺に君が立つ日の近づけば野に立つ鹿もとよめてそ鳴く(万4-573) ③ 都辺に立つ日近づく飽くまでに相見て行かな恋ふる日多けむ(万17-4023) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 近づける。近く寄せる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちたび [千度・千遍] | 〔名詞〕千回。また、度数の多いこと。 | 一日には千たび参りし東の大き御門を入りかてぬかも(万2-186) -追はむとは 千度思へど たわやめの 我が身にしあれば 道守が-(万4-546) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちとせ [千歳・千年] | 〔名詞〕千年。長い年月。限りない年数。 | 大君は千歳にまさむ白雲も三船の山に絶ゆる日あらめや(万3-244) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちどり [千鳥] | 〔名詞〕 ① 多くの鳥。 ② チドリ科の鳥の総称。小形で、海辺や川瀬などに群れすむ。 |
我が背子が古家の里の明日香には千鳥鳴くなり夫待ちかねて(万3-270) ② ぬばたまの夜の更けゆけば久木生ふる清き川原に千鳥しば鳴く(万6-930) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちはやぶる [千早振る] | 勢いの強い。荒々しい。 〔参考〕 神の意を表わす「ち」に形容詞「疾(はや)し」の語幹「はや」の付いたものに、 接尾語「ぶ」が付いた上二段動詞「ちはやぶ」の連体形と考えられている。 |
「この沼の中に住める神いと千早振る神なり」(記・中) -東の国の 御いくさを 召したまひて ちはやぶる 人を和せと-(万2-199) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】強力な力を持つ意から「神」「うぢ」に懸かる。 | 玉葛実ならぬ木にはちはやぶる神ぞつくといふならぬ木ごとに(万2-101) ちはやぶる神の社しなかりせば春日の野辺に粟蒔かましを(万3-407) ちはやぶる神の社に我が掛けし幣は賜らむ妹に逢はなくに(万4-561) 「ちはやぶるうぢの渡りに」(記・中) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちへ [千重] | 〔名詞〕幾重にも重なっていること。 【有斐閣「萬葉集全注巻二-207 注『チヘノヒトヘ』」】 幾重もの中の一重で、千に一つを言う。 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1巻二-207 頭注『千重の一重』」】 千分の一。ほんの一部分。 |
名ぐはしき印南の海の沖つ波千重に隠りぬ大和島根は(万3-306) はろはろに思ほゆるかも白雲の千重に隔てる筑紫の国は(万5-870) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちへなみ [千重波] | 〔名詞〕幾重にもつぎつぎと寄せてくる波。 | 一日には千重波しきに思へどもなぞその玉の手に巻き難き(万3-412) -朝なぎに 千重波寄せ 夕なぎに 五百重波寄す 辺つ波の-(万6-936) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちよ [千代・千世] | 〔名詞〕千年。長い年月。永久。 | -作れる家に 千代までに いませ大君よ 我れも通はむ(万1-79) 我が御門千代とことばに栄えむと思ひてありし我れし悲しも(万2-183) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちよろづ [千万] | 〔名詞〕限りなく多いこと。無数。 | 千万の軍なりとも言挙げせず取りて来ぬべき男とぞ思ふ(万6-977) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちる [散る] | 〔自ラ行四段〕 ①(花や葉などが)散る。 ② 散らばる。離れ離れになる。 ③ 世間に広まる。外へもれ聞こえる。 ④ 心がまとまらない。落ち着かない。 |
① やどりして春の山辺に寝たる夜は夢の内にも花ぞちりける(古春下-117) ① 黄葉の散りゆくなへに玉梓の使を見れば逢ひし日思ほゆ(万2-209) ① 我が岡のおかみに言ひて降らしめし雪のくだけしそこに散りけむ(万2-104) ① 高円の野辺の秋萩な散りそね君が形見に見つつ偲はむ(万2-233) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つ [津] | 〔名詞〕船の停泊所。船着き場。渡し場。港。 | 楽浪の志賀津の児らが [一云 志賀の津の児が] 罷り道の川瀬の道を見ればさぶしも (万2-218) -海上の その津を指して 君が漕ぎ行かば(万9-1784) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つ →「主要助動詞活用」 | 〔助動詞〕 ① 動作・作用が完了してしまった意を表す。 ~た。~てしまう。~てしまった。 ② 動作・作用の実現を確信したり確認したりする意を表す。 確実(強意)の用法。 ア:(単独で用いる場合)、必ず~。確かに~。~てしまう。 イ:(推量の助動詞とともに用いて、「てむ」「てまし」「つべし」などの形になる場合)、推量・意志・可能などの意を、「確かに」「きっと」「必ず」の気持ちで述べる。 〔接続〕連用形につく。 〔上代の格助詞〕「の」の意。 |
① 夕さらば潮満ち来なむ住吉の浅香の浦に玉藻刈りてな(万2-121) ① 我妹子に猪名野は見せつ名次山角の松原いつか示さむ(万3-282) ① こもりくの泊瀬娘子が手に巻ける玉は乱れてありと言はずやも(万3-427) ① うつせみの世は常なしと知るものを秋風寒み偲びつるかも(万3-468) ① 家離りいます我妹を留めかね山隠しつれ心どもなし(万3-474) ① 大海の底を深めて結びてし妹が心はうたがひもなし(万12-3042) ② みさご居る磯廻に生ふるなのりその名は告らしてよ親は知るとも(万3-365) ② 春日野の飛ぶ火の野守出でて見よ今幾日ありて若菜摘みてむ (古今春上-19) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つが [栂] | 〔名詞〕まつ科の常緑高木。 | -しじに生ひたる つがの木の いや継ぎ継ぎに 玉葛 絶ゆることなく-(万3-327) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-324」 注『栂の木の』】 ここまで(第九句)が「継ぎ継ぎに」を類音によって起こす序となる。しかし、明日香の実景に基づいた序である。 「栂の木」は「刀我乃樹(トガノキ)」(6・九〇七)とも言い、まつ科の常緑高木。 柿本人麻呂に「栂木乃(ツガノキノ) 弥継嗣尓(イヤツギツギニ)」(1・二九)の表現の先蹝がある。 その表現が『毛詩』周南(栂木)や『文選』(遊天台山賦)などの、蔓草などがからみつく木で、あたかも蔓草が長く続いてまつわり茂る如く、次々に天下を幸福に治めることを頭に浮かべた表現との小島憲之説(『上代日本文学と中国文学』中)がある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つかさ [阜] | 〔名詞〕土地の小高い所。 | 佐保川の岸のつかさの柴な刈りそねありつつも春し来らば立ち隠るがね(万4-532) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つかのま (つかのあひだ) [束の間] | ほんのちょっとの間。「束 (つか)」は、こぶしの一握りの長さ。 | 大名児を彼方野辺に刈る草の束の間 (あひだ) も我れ忘れめや(万2-110) 夏野行く小鹿の角の束の間も妹が心を忘れて思へや(万4-505) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つがのきの [栂の木の] | 【枕詞】類似音を重ねて「つぎつぎ」にかかる。 | -神のことごと 栂の木の いや継ぎ継ぎに 天の下-(万1-29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つかはす [使はす] | 〔なりたち〕四段動詞「使ふ」の未然形「つかは」+上代の尊敬の助動詞「す」 お使いになる。 |
-朝には 召して使ひ 夕には 召して使ひ 使はしし 舎人の子らは-(万13-3340) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つかひ [使ひ・遣ひ] | 〔名詞〕① 使いの者。使者。② 召使。そばめ。 | ① -玉梓の 使ひの言へば 梓弓 音に聞きて [一云 音のみ聞きて] -(万2-207) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つかふ [仕ふ] | 〔自動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 ① 貴人などのそばにいて用をする。仕える。 ② 役人として勤める。 |
① -下つ瀬に 小網さし渡す 山川も 依りて仕ふる 神の御代かも- (万1-38) ① 黒木取り草も刈りつつ仕へめどいそしきわけとほめむともあらず [一云仕ふとも] (万4-783) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つかふ [着かふ] | 〔四段動詞「着く」の未然形+上代の反復・継続の助動詞「ふ」〕 《上代語》たびたび着く。 |
こと放けば沖ゆ放けなむ港より辺著かふ時に放くべきものか(万7-1406) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つかふ [使ふ・遣ふ] | 〔他動詞ハ行四段〕 ① 使用する。はたらかす。身辺の用をさせる。② 役立てる。用いる。 ③ 持つ。所有する。④ 行う。なす。⑤ 消費する。 ⑥ あやつる。意のままに動かす。支配する。 |
① 常止まず通ひし君が使来ず今は逢はじとたゆたひぬらし(万4-545) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つかへまつる [仕へ奉る] |
〔複合動詞〕 [下二段「つかふ」の連用形「つかへ」に謙譲の補助動詞「奉る」の付いたもの] |
天地とともに終へむと思ひつつ仕へまつりし心違ひぬ(万2-176) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔自動詞ラ行四段〕[「仕ふ」の謙譲語] 「お仕へ申し上げる」 |
降る雪の白髪までに大君に仕へまつれば貴くもあるか(万17-3944) -鶉なす い這ひもとほり 恐みと 仕へ奉りて ひさかたの-(万3-240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞ラ行四段〕 [「す」「なす」「作る」「行ふ」などの動詞の代りに用いられて謙譲の意を表す] 「お~申し上げる」「お~する」 |
-つれもなき 城上の宮に 大殿を 仕へまつりて 殿隠り-(万13-3340) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 上代にのみ用いられ、中古以降にはその音便形「つかうまつる」、その省略形「つかまつる」が用いられた。 「他動詞」は、他の動詞の代りに用いられる用法なので、、その場に応じた訳語をあてる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つかる [疲る] | 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 ぐったりする。疲労する。 |
見まく欲り我がする君もあらなくに何しか来けむ馬疲るるに(万2-164) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つき [月] | 〔名詞〕 ① 月。特に、秋の澄んだ月。 ② 時間の単位。陰暦で、月がまったく見えない夜から、次の見えない夜までの期間を言う。二十九日または三十日で一か月となり、十二か月または十三か月で一年となる。 |
① 北山にたなびく雲の青雲の星離り行き月を離れて(万2-161) ① ひさかたの天行く月を網に刺し我が大君は蓋にせり(万3-241) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つき [槻] | 〔名詞〕けやき(=木の名)の古名。 | -走出の 堤に立てる 槻の木の こちごちの枝の 春の葉の -(万2-210) 早来ても見てましものを山背の高の槻群散りにけるかも(万3-280) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -つき [-坏・杯] | 〔接尾語〕器に盛った飲食物の数量を数える。杯。 | 験なき物を思はずは一坏の濁れる酒を飲むべくあるらし(万3-341) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つきくさ [月草・鴨跖草] | 〔名詞〕 ① 「つゆくさ」の古名。花の色が青色で、衣を摺るときの染料とした。 ② 「襲(かさね)の色目」の名。表ははなだ色、裏は薄はなだ色。 |
月草に衣色どり摺らめどもうつろふ色と言ふが苦しさ(万7-1343) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つきくさの [月草の] | 【枕詞】 「うつる・消(け)ぬ・かる」 などにかかる。 |
月草のうつろひ易く思へかも我が思ふ人の言も告げ来ぬ(万4-586) 朝咲き夕は消ぬる月草の消ぬべき恋も我れはするかも(万10-2295) 月草の借れる命にある人をいかに知りてか後も逢はむと言ふ(万11-2766) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つきごろ [月頃] | 〔名詞〕[「ごろ」は接尾語] ここ数か月もの間。数か月来。かなり長い間の意味で使うこともある。 |
白鳥の飛羽山松の待ちつつそ我が恋ひ渡るこの月ごろを(万4-591) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つぎはし [継ぎ橋] | 〔名詞〕川の中に柱を立て、橋げたの板を継いで渡した橋。 | 真野の浦の淀の継橋心ゆも思へや妹が夢にし見ゆる(万4-493) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つきひ [月日] | 〔名詞〕 ① 月と太陽と。 ② 月日。時日。歳月。 |
① 天なるや月日のごとく我が思へる君が日に異に老ゆらく惜しも(万13-3260) ② 白たへの袖解き交へて帰り来む月日を数みて行きて来ましを(万4-513) ② 草枕旅去にし君が帰り来む月日を知らむすべの知らなく(万17-3959) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つく [付く・着く・ 就く・即く] | 〔自動詞カ行四段〕 ① 接する。付着する。 ②(心につく、の形で)気に入る。ぴったり合う。 ③ つき従う。寄り添う。また、妻になる。 ④ 起こる。あらわれる。 ⑤ 味方する。くみする。 ⑥ 身を置く。安定する。着座する。とどまる。 ⑦(態度が)決まる。はっきりする。 ⑧ 加わる。添う。生じる。 ⑨(多く「憑く」と書く)神や物の怪などがとりつく。のりうつる。 ⑩ 身につく。そなわる。⑪ 火がつく。燃え移る。 ⑪ 届く。到着する。⑫ 即位する。ある身分になる。⑬ 色が移る。染まる。 |
① 藤原の大宮仕へ生れつくや娘子がともは羨しきろかも(万1-53) ① 旅とへど真旅になりぬ家の妹が着せし衣に垢付きにかり(万20-4412) ⑨ 玉葛実ならぬ木にはちはやぶる神ぞつくといふならぬ木ごとに(万2-101) ⑨ 我が祭る神にはあらずますらをにつきたる神そよく祭るべし(万3-409) ⑪ -冬こもり 春さり来れば 野ごとに つきてある火の -(万2-199) ⑫ -東宮をたがひにゆづりて、位につき給はで-(古今・仮名序) ⑬ 綜麻形の林のさきのさ野榛の衣に付くなす目につく吾が背(万1-19) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つく [付く・着く・ 就く・即く] | 〔他動詞カ行四段〕 ①(知識・能力などを)身に付ける。自分のものとする。 ② 名前をつける。命名する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つく [付く・着く・ 就く・即く] | 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 ① 接触させる。付着させる。つける。 ② 従わせる。つき添わせる。尾行させる。 ③ 身につける。着る。④ 託す。ことづける。⑤ 加える。添える。 ⑥ 名前をつける。命名する。⑦ 点火する。燃えつかせる。 ⑧ 心や目を向ける。関心を払う。⑨ 形を残す。記す。書きつける。 ⑩ 和歌、俳諧などで、上の句または下の句を詠み添える。 ⑪ 別な事柄と結びつける。関連させる。応ずる。 ⑫(他の動詞の連用形の下に付いて)習慣になっている状態をいう。 「いつも~する。~しなれる。~しつける。」 |
① -奥山の 賢木の枝に しらか付け 木綿取り付けて 斎瓮を-(万3-382) ③ 忘れ草我が紐に付く香具山の古りにし里を忘れむがため(万3-337) ③ しらぬひ筑紫の綿は身に付けていまだは着ねど暖けく見ゆ(万3-339) ③ 夏草の露別け衣着けなくに我が衣手の干る時もなき(万10-1998) ④ 常陸指し行かむ雁もが我が恋を記して付けて妹に知らせむ(万20-4390) ⑪ 心に思ふことを、見るもの聞くものにつけて言ひ出だせるなり(古今仮名序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つく [漬く] | 〔自動詞カ行四段〕水に浸る。水につかる。 | 広瀬川袖漬くばかり浅きをや心深めて我が思へるらむ(万7-1385) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つく [尽く] | 〔他動詞カ上二段〕【キ・キ・ク・クル・クレ・キヨ】 ① 終わる。終わりになる。果てる。 ② 消え失せる。なくなる。 |
① -さまよひぬれば 嘆きも いまだ過ぎぬに 思ひも いまだ尽きねば-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つく [突く・衝く・撞く] | 〔他動詞カ行四段〕 ① 刀や棒など長い物で刺す。② 打つ鳴らす。③ 細長いものを立てて支えとする。④ 頭・額などを地面や床に押し当てる。ぬかずく。 |
③ -天地の 至れるまでに 杖つきも つかずも行きて 夕占問ひ-(万3-423) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つぐ [次ぐ・継ぐ・接ぐ] | 〔自動詞ガ行四段〕 ① 連続する。続く。② 次に位置する。 |
① うつつには逢ふよしもなしぬばたまの夜の夢にを継ぎて見えこそ(万5-811) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞ガ行四段〕 ① 継続する。続ける。② つなぐ。③ 相談する。あとを継ぐ。 ④ 維持する。保つ。⑤ 繋ぎ合わせる。⑥ 注ぎ入れる。 ⑦ 「切る」の忌み詞。 |
① 妹が家も継ぎて見ましを大和なる大島の嶺に家もあらましを [一云 妹があたり継ぎても見むに] [一云 家居らましを](万2-91) ① -雪は降りける 語り継ぎ 言ひ継ぎ行かむ 富士の高嶺は(万3-320) ④ -天地 日月と共に 足り行かむ 神の御面と 継ぎ来る 那珂の港ゆ-(万2-220) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つぐ [告ぐ] | 〔他動詞ガ行下二段〕【ゲ・ゲ・グ・グル・グレ・ゲヨ】 告ぐ。伝える。 |
-ころ臥す君が 家知らば 行きても告げむ 妻知らば 来も問はましを-(万2-220) 荒波に寄り来る玉を枕に置き我ここにありと誰か告げけむ(万2-226) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つくし [筑紫] | 〔地名〕 「筑前(ちくぜん)」「筑後(ちくご)」の称。 古くは九州地方全体をさす。 「筑紫の島」九州。 |
しらぬひ筑紫の綿は身に付けていまだは着ねど暖けく見ゆ(万3-339) ここにありて筑紫やいづち白雲のたなびく山の方にしあるらし(万4-577) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つくしぶね [筑紫船] | 〔名詞〕筑紫と難波との間を往復する船。 | 筑紫船いまだも来ねばあらかじめ荒ぶる君を見るが悲しさ(万4-559) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つくば [筑波] | 〔地名〕[上代は「つくは」] 茨城県筑波山を中心とする地域。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つくばね [筑波嶺] | 〔地名〕[上代は「つくはね」] 茨城県の筑波・新治(にいばり)・真壁三郡にまたがる山。 山頂は女体・男体の二峰にわかれている。筑波の山。筑波山〔歌枕〕 |
-人の言ひ継ぎ 国見する 筑波の山を 冬ごもり 時じき時と-(万3-385) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つくまの [託間野] | 〔地名〕未詳。通説は、滋賀県坂田郡米原町筑摩かとする。 | 託馬野に生ふる紫草衣に染めいまだ着ずして色に出でにけり(万3-398) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-395 注『託間野』」】 未詳。「託」 は、ものに寄り付くの意で、名義抄にもツクの訓があり、地名ツクマノのツクに当てたものとして、人に寄り付くの意を連想させる表記とも言える。これに対し、「託」 を音読してタクマノと訓む説(講義) がある。これによると、タカマ・タクマの地名は和名抄を検すると、肥後の郡名の詫麻(たくま)、讃岐三野郡詫間(たくま)、伊予濃満郡宅万(たくま)、薩摩高城郡託万(たかま)、駿河有度郡の託美(たくみ)、阿波勝浦郡の託羅(たから) とあり、一方紫草の産地として、民部式(下) の交易雑物に見える国名に、相模・武蔵・常陸・信濃・大宰府などがあることから、通説の近江(滋賀県) はこの点で失格となり、肥後の託摩郡が有力だとしている。それだと、今の熊本市の東南部からその郊外にわたる地に当たる。注釈も、紫草の産地という面から見て肥後の託摩説に賛成し、「託馬(タクマ)」 と訓んでいる。私も大宰府より貢した紫草の産地として、肥後の詫摩郡が知られていたと考え、講義の説に従いたい。通説は、多分巻一-20歌の「茜さす紫野ゆき標野ゆき」 の「紫野」 は近江だと考えたからであろうが、これは滋賀県蒲生郡であって、滋賀県坂田郡米原町筑摩とは違うので、その点でも近江説は失格となる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つくよ [月夜] | 〔名詞〕[「つく」は「つき」の古形。 ① 月。月の光。② 月夜。月の明るい夜。 |
① 海神の豊旗雲に入日さし今夜の月夜さやけくありこそ(万1-15) ① 月夜よし川の音清しいざここに行くも行かぬも遊びて行かむ(万4-574) ② 去年見てし秋の月夜は照らせども相見し妹はいや年離る(万2-211) ② 春日山霞たなびき心ぐく照れる月夜にひとりかも寝む(万4-739) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つくる [作る・造る] | 〔他動詞ラ行四段〕 ①(建物・器物などを)こしらえる。建造する。 ② する。行う。③ 田畑を耕す。耕作する。④ 育てる。栽培する。 ⑤ 料理する。⑥(文章や詩歌などを)書く。創作する。 ⑦ 似せる。よそおう。とりつくろう。 |
① 八雲立つ出雲八重垣妻籠みに八重垣つくるその八重垣を(記上) ① -真木のつまでを 百足らず 筏に作り 泝すらむ いそはく見れば-(万1-50) ① - 通ひつつ 作れる家に 千代までに いませ大君よ 我れも通はむ(万1-79) ③ 足引きの山田作る子秀でずとも縄だに延へよ守ると知るがね(万10-2223) ⑦ -庭を秋の野につくりて-(古今秋上詞書-248) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つしま [対馬] | 〔地名〕旧国名。「西海道」十二ヶ国のひとつ。大陸渡航の要衝の島。 今の長崎県に属する。対州(たいしゆう)。 |
在り嶺よし対馬の渡り海中に幣取り向けて早帰り来ね(万1-62) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つたふ [伝ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 ある所から、他の所へ何かに沿って移動する。伝わる。 |
水伝ふ礒の浦廻の岩つつじ茂く咲く道をまたも見むかも(万2-185) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞ハ行下二段〕〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 ① さずける。教える。伝授する。② 受け継ぐ。譲り受ける。 ③ ことづける。言い知らせる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つつ | 〔接続助詞〕 ① 同じ動作・作用が繰り返し行われる意(反復)を表す。 「~し、また~して。~ては、~して。」 ② 動作・作用が引き続いて行われる意(継続)を表す。 「~し続けて。」 ③ 二つの動作・作用が同時に行われる意(並行)を表す。 「~とともに。~ながら。」 ④ 複数のものが同時にその動作を反復する意を表す。 「それぞれ~(し)て。みんなが~(し))ながら。」 ⑤ 前文と後文を単純に接続する。接続助詞「て」と同じ用法。 「~て。」 ⑥「①」の反復の用法であるが、「つつ」が打消しの表現を導くときは、逆接のようになる。「~ながらも」 ⑦ 反復・継続の意で、和歌の文末に用いられた場合は、後文を言い指して余情をこめる。「~ことだ」 〔接続〕動詞・助動詞の連用形に付く。 |
① -八十隈おちず 万たび かへり見しつつ 玉桙の 道行き暮らし- (万1-79) ① 高円の野辺の秋萩な散りそね君が形見に見つつ偲はむ(万2-233) ② 後れ居て恋ひつつあらずは追ひ及かむ道の隈廻に標結へ我が背 (万2-115) ② 天地とともに終へむと思ひつつ仕へまつりし心違ひぬ(万2-176) ② 鴨山の岩根しまける我をかも知らにと妹が待ちつつあるらむ(万2-223) ② つのさはふ磐余も過ぎず泊瀬山いつかも越えむ夜は更けにつつ(万3-285) ③ 我妹子が植ゑし梅の木見るごとに心咽せつつ涙し流る(万3-456) ③ 暇なく人の眉根をいたづらに掻かしめつつも逢はぬ妹かも(万4-565) ⑥ 我がここだ待てど来鳴かぬ霍公鳥ひとり聞きつつ告げぬ君かも (万19-4232) ⑦ きみがため春の野にいでてわかなつむ我が衣手に雪はふりつつ (古春上-21) 〔文法〕上代に多く用いられたが、中古以降は、次第に「ながら」にとって代わられた。①②の意味が基本的であり、他はそれから派生したものと考えられる。①と②の違いは、上にくる語による。「取る」のように瞬間的な動作を表す語の場合は①に、「思ふ」のように状態を表す語の場合は②になる。なお、【文法例歌】の例は、「住まひ」が状態を表す語である「住む」の未然形「住ま」に上代の反復・継続を表す助動詞「ふ」の連用形「ひ」が付いたものであるから、当然②の用法と考えられるが、現代語訳で「地方に五年間住み続けていて」とするのは、反復・継続の「ひ」と「つつ」とを重ねて「つづけつづけて」と訳す不自然さを避けたものである。 【文法・例】天離る鄙に五年住まひつつ都のてぶり忘らえにけり(万5-884) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つつじ [躑躅] | 〔名詞〕 ① 植物の名。春から初夏にかけて紅・白などの花を開く。 ② 襲(かさね)の色目の名。表は蘇芳色(すおういろ=紫赤色)、裏は濃い蘇芳色。 男子の下襲(したがさね)として用いるときは、表は白、裏は蘇芳色で、春から初夏にかけて着用する。 |
風早の美穂の浦廻の白つつじ見れどもさぶしなき人思へば [或云 見れば悲しもなき人思ふに](万3-437) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つつじばな [躑躅花] | 【枕詞】 「にほふ」にかかる。 |
-年月日にか つつじ花 にほへる君が にほ鳥の なづさひ来むと-(万3-446) -つつじ花 にほえ娘子 桜花 栄え娘子 汝れをぞも-(万13-3319) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つつみ [堤] | 〔名詞〕① 土手。堤防。② 土俵。 | -藤井が原に 大御門 始めたまひて 埴安の 堤の上に あり立たし-(万1-52) -取り持ちて 我がふたり見し 走出の 堤に立てる 槻の木の-(万2-210) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つつみ [慎み] | 〔名詞〕はばかりつつしむこと。遠慮。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つづみ [鼓] | 〔名詞〕 ① 胴に革を張って打ち鳴らす楽器の総称。太鼓の類。 ② 中世以降、特に胴の中央が細くなっている鼓をいう。 |
① -御軍士を 率ひたまひ 整ふる 鼓の音は 雷の 声と聞くまで-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つつむ [慎む] | 〔自動詞マ行四段〕気が引ける。気おくれする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞マ行四段〕気兼ねする。憚る。遠慮する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つつむ [障む・恙む] | 〔自動詞マ行四段〕 障害にあう。妨げられる。病気・けがなどがあって慎んでいる。 |
青海原風波靡き行くさ来さつつむことなく船は速けむ(万20-4538) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つつむ [包む・裏む] | 〔他動詞マ行四段〕 ① 中に入れる。覆い囲む。 ② 隠す。秘める。 |
① -石花の海と 名付けてあるも その山の つつめる海そ 富士川と-(万3-322) ② 伊勢の海の沖つ白波花にもが包みて妹が家づとにせむ(万3-309) ② 玉津島見れども飽かずいかにして包み持ち行かむ見ぬ人のため(万7-1212) ② たらちねの母にも言はずつつめりし心はよしゑ君がまにまに(万13-3299) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻三-306 頭注『包みて』」】 ツツムはなかの物が外から見えないように囲うことを広くいう。 その材料が藁・菰・すすき・竹の皮など多様なことは勿論、その対象も水や玉津島(一二二二)などの景さえも比喩でツツムことがあった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つと [苞・苴] | 〔名詞〕 ① 食品などをわらに包んだもの。わらづと。 ② その土地の産物。みやげ。 |
② 潮干なば玉藻刈りつめ家の妹が浜づと乞はば何を示さむ(万3-363) ② 堀江より朝潮満ちに寄る木屑貝にありせばつとにせましを(万20-4420) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つと | 〔副詞〕① じっと。そのままずっと。② 急に。さっと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つとに [夙に] | 〔副詞〕朝早く。早朝から。 | 天皇、夙に興き、夜(おそ)く寝(い)ねまして(仁徳紀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つどふ [集ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕集まる。寄り合う。 〔他動詞ハ行下二段〕集める。寄せ集める。【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 |
〔自動詞〕 -千万神の 神集ひ 集ひいまして 神分り 分りし時に 天照らす 日女の命-(万2-167) 〔他動詞〕 -もののふの 八十伴の男を 召し集へ 率ひたまひ 朝狩に-(万3-481) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【「つどふ」と「あふ」】 多くのものが一か所に集まる意を原義とするのが「つどふ」であり、二つのものが一つになる意を意を原義とするのが 「あふ」である。 軍団のように、あるまとまりが単位となって 「つどふ」あるいは「あふ」こともある。「つどふ」の対義語は「あかる」、「あふ」の対義語は「わかる」 である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つとむ [勤む・務む] | 〔他動詞マ行下二段〕【メ・メ・ム・ムル・ムレ・メヨ】 ① 努力して行う。② 自愛する。大事にする。③ 勤務する。奉公する。 ④ 仏教修行にはげむ。勤行する。 |
① 磯城島の大和の国に明らけき名に負ふ伴の男心つとめよ(万20-4490) ② 我が聞きし耳によく似る葦の末の足ひく我が背つとめ給ぶべし(万2-128) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つね [常] | 〔名詞〕 ① 普段。通例。② 普通。当り前。並。いつも。 |
② 雨つつみ常する君はひさかたの昨夜の夜の雨に懲りにけむかも(万4-522) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔名詞・形容動詞ナリ活用〕同じ状態にあること。変わらないこと。 | ② 川の上のゆつ岩群に草生さず常にもがもな常処女にて(万1-22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つねなし [常無し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 変わりやすい。無常だ。一定していない。 |
常磐なす岩屋は今もありけれど住みける人そ常なかりける(万3-311) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つねに [常に] | 〔副詞〕 ① いつも。始終。② いつまでも変らず。永久に。 |
① あしひきの山霍公鳥汝が鳴けば家なる妹し常に偲はゆ(万8-1473) ② -日の御蔭の 水こそば つねにあらめ 御井のま清水(万1-52) ② 滝の上の三船の山に居る雲の常にあらむと我が思はなくに(万3-243) ② 我が命も常にあらぬか昔見し象の小川を行きて見むため(万3-335) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つねにもがもな [常にもがもな] | 「永久不変であったらいいなあ」 |
川の上のゆつ岩群に草生さず常にもがもな常処女にて(万1-22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔成り立ち〕形容動詞「常なり」の連用形「常に」+願望の終助詞「もがも」+詠嘆の終助詞「な」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つの(つぬ) [角] | 〔名詞〕 ① 動物などの頭上にある骨状の突起物。 ② 「①」でつくった笛。角笛。③ 嫉妬。怒り。やきもち。 ④ 紋所の名。「①」を図案化したもの。 【角の浦廻】 |
① 夏野行く小鹿の角の束の間も妹が心を忘れて思へや(万4-505) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つの [綱] | 〔名詞〕綱 (つな) の古名。 | 栲 (たく) つのの白き腕 (ただむき) (記・上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つのが [角鹿] | 〔地名〕 「越」 は「越前・越中・越後」 の三国をさし、「角鹿」 はその中の越前の「敦賀」。 |
越の海の 角鹿の浜ゆ 大船に 真楫貫き下ろし いさなとり-(万3-369) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仲哀記に「都奴賀(ツルガ)」 とあり、また「角鹿(つのが)」 (垂仁紀二年) の表記もある。こんにちと同じ敦賀の形は、和名抄の「敦賀、都留我(ツルガ)」 に見える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のつ [角鹿の津] | 〔名詞〕福井県敦賀市の敦賀港。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つのさはふ [つのさはふ] | 【枕詞】地名「磐余」の「いは」にかかる。 | つのさはふ磐余も過ぎず泊瀬山いつかも越えむ夜は更けにつつ(万3-285) つのさはふ 磐余の道を 朝さらず 行きけむ人の 思ひつつ-(万3-426) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つののまつばら [角の松原] | 〔地名〕 | 我妹子に猪名野は見せつ名次山角の松原いつか示さむ(万3-335) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-279 注『角の松原』」】 兵庫県西宮市松原町津門。松原があったことは、「海人娘子漁り焚く火のおぼほしく角の松原思ほゆるかも」(17・三八九九) にも見える。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つばき [椿] | 〔名詞〕 ① 樹木の名。早春に開花。種子から椿油をとる。 [春] ②「襲(かさね)の色目」の名。表が蘇芳(すおう)で裏は赤。 (一説に、裏は紅とも)。冬期に用いた。 |
① 巨勢山のつらつら椿つらつらに見つつ偲はな巨勢の春野を(万1-54) ① 我妹子を早見浜風大和なる我れ松椿吹かざるなゆめ(万1-73) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つばら [委曲] | 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 「つばらか」に同じ。 |
-道の隈 い積もるまでに つばらにも 見つつ行かむを -(万1-17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -つばら [つばら委曲] | 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 こまごま。つくづく。しみじみ。 |
浅茅原つばらつばらに物思へば古りにし里し思ほゆるかも(万3-336) 朝開き入江漕ぐなる楫の音のつばらつばらに我家し思ほゆ(万18-4089) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つばらか [委曲か] | 〔形容動詞ナリ〕「つばら」とも。 ① 詳しいさま。細かいさま。 ② 思い残すことのないさま。十分なさま。 |
① -さやに照らして いふかりし 国のまほらを つばらかに-(万9-1757) ② 奥山の八つ峰の椿つばらかに今日は暮らさね大夫の伴(万19-4176) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つひに [終に・遂に] | 〔副詞〕[名詞「終 (つひ) +格助詞「に」] ① 結局。終りに。最後に。とうとう。 ② (多く下に打消し語を伴って) 最後の最後まで。 ③ (打消しの語を伴って) いまもって。まだ一度も。ついぞ。 |
① 生ける者遂にも死ぬるものにあればこの世にある間は楽しくをあらな(万3-352) ① 息さへ絶えて 後つひに 命死にける 水江の 浦島の子が(万9-1744) ② 我がゆゑにいたくなわびそ後つひに逢はじと言ひしこともあらなくに (万12-3130) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つま [嬬・妻・夫] | ①[夫]妻から夫を呼ぶ称 =せ ②[妻]夫から妻を呼ぶ称 =いも |
① -か寄りかく寄り 靡かひし 嬬の命の たたなづく 柔肌すらを-(万2-194) ① -出でて行きし 愛し夫は 天飛ぶや 軽の道より 玉だすき-(万4-546) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つま [褄] | 「(つま)端」の意から着物の襟先から下の縁。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つま [端] | ① はし、縁、きわ。② 軒のはし、軒ば。③ 端緒、手掛かり、きっかけ。 | ② 流らふるつま吹く風の寒き夜に我が背の君はひとりか寝らむ(万1-59) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つまごひ [妻恋ひ・夫恋ひ] | 〔名詞・自動詞サ行変格活用〕【セ・シ・ス・スル・スレ・セヨ】 夫が妻を、または妻が夫を恋しく思うこと。 また雌雄が相手を恋い慕うこと。 |
秋さらば今も見るごと妻恋ひに鹿鳴かむ山ぞ高野原の上(万1-84) 春の野にあさる雉の妻恋ひにおのがあたりを人に知れつつ(万8-1450) 出でて去なむ時しはあらむをことさらに妻恋しつつ立ちて去ぬべしや(万4-588) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つまごもる [妻隠る] | 〔自動詞ラ行四段〕(夫婦または雌雄が) いっしょにこもり住む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】 夫婦でこもる「屋」から「や」と同音を持つ地名「矢野」「屋上(やかみ)」にかかる。 地名「小佐保(をさほ)」にもかかるが、掛かり方は未詳。 |
-妹が袖 さやにも見えず 妻ごもる 屋上の-(万2-135) 妻ごもる矢野の神山露霜ににほひそめたり散らまく惜しも(万10-2182) 「つまごもる小佐保を過ぎ」(武烈紀) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つまづく | 〔自動詞カ行四段〕 ① 歩行中、つま先を物に突き当てる。けつまづく。 ② 途中で失敗する。しくじる。 |
① 塩津山うち越え行けば我が乗れる馬そつまづく家恋ふらしも(万3-368) ② -問はむ答へを 言ひ遣らむ すべを知らにと 立ちてつまづく(万4-546) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つまで [嬬手] | 〔名詞〕[「つま」は稜角(りょうかく)、「で」は材料の意] 角のある荒削りの材木。角材。 |
-田上山の 真木さく 桧のつまでを もののふの 八十宇治川に-(万1-50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つまとひ [妻問ひ] | 〔名詞〕 異性を恋い慕って言い寄ること。求婚。また、妻または恋人のもとへ通うこと。 |
秋萩の咲きたる野辺はさを鹿ぞ露を別けつつ妻どひしける(万10-2157) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つまどふ [妻問ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 異性を恋い慕って言い寄る。求婚する。また、妻または恋人のもとへ通う。 |
-廬屋立て 妻問ひしけむ 葛飾の 真間の手児名が 奥つきを-(万3-434) 夜もすがら妻どふ鹿の鳴くなべに 小萩が原の露ぞこぼるる(新古今秋下-446) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つまびく [爪弾く・爪引く] | 〔他動詞カ行四段〕 弓の弦を爪先ではじく。また、琴・三味線などの弦楽器を指の爪で引き鳴らす。 |
梓弓爪引く夜音の遠音にも君の御幸を聞かくし良しも(万4-534) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つまや [妻屋] | 〔名詞〕 夫婦の寝室。閨房(けいぼう)。ねや。 |
-二人我が寝し 枕づく つま屋の内に 昼はも うらさび暮らし 夜はも-(万2-210) 〔家に来て我が屋を見れば玉床の外に向きけり妹が木枕(万2-216)〕 家に行きていかにか我がせむ枕付く妻屋寂しく思ほゆべしも(万5-799) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻二-216 注『家来而 吾屋乎見者』」】 原文「家来而 吾屋乎見者」で諸本に異同なく、旧訓「イヘニキテワカヤヲミレハ」であったが、万葉考に「吾はもし妻の字にや」と言い、古義に「吾」を「妻」の誤字と断定して「ツマヤヲミレバ」と改訓した。しかしこの誤字説は必然性がない。注釈に「これは初句に『家』とあるのと重複する為の案と思はれる」と言うように、家と屋とが意味的に重複すると考えられたためであろうが、イヘとヤとは区別して用いられている。イヘが妻や家族のいるべき本拠を指す呼称であるのに対して、ヤは多く具体的建造物としての家をさす。この場合は夫婦の住んだ嬬屋を指してyと言ったと考えられ(尾崎暢殃『柿本人麻呂の研究』)、意味的重複は見られない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つみ [柘] | 〔名詞〕山桑(やまくわ=木の名) の異名。 | この夕柘の小枝の流れ来ば梁は打たずて取らずかもあらむ(万3-389) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つむ [積む] | 〔自動詞マ行四段〕 積もる。たまる。積もる。 〔他動詞マ行四段〕 ① 積み重なる。重ねる。② (船や車などに荷を) 載せる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つむ [摘む・抓む] | 〔他動詞マ行四段〕① 指先でつまむ。② つねる。③ (植物などを)摘みとる。 | ① -み裳の裾 摘み上げ掻き撫で ちちの実の 父の命は 栲づのの-(万20-4432) ③ あかねさす昼は田賜びてぬばたまの夜のいとまに摘める芹これ(万20-4479) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つむ [集む] | 〔他動詞マ行下二段〕【メ・メ・ム・ムル・ムレ・メヨ】集める。 | 潮干なば玉藻刈りつめ家の妹が浜づと乞はば何を示さむ(万3-363) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つむじ [旋風] | 〔名詞〕渦を巻いて吹く風。つむじ風。 | -つむじかも い巻き渡ると 思ふまで 聞きの畏く-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つもる [積もる] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 積み重なる。かさむ。② 量が増える。たまる。 〔他動詞ラ行四段〕 ① あらかじめ計算する。見積もる。推測する。 ② 見透かしてだます。一杯くわせる。見くびる。 |
① -山の際に い隠るまで 道の隈 い積もるまでに-(万1-17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つゆ [露] | 〔名詞〕 ① 大気中の水蒸気が水滴になり、草木の葉などについたもの。つゆ。 ② (露の量のわずかなことから) わずか。ほんの少し。 ③ (露が消えやすいことから) はかなく消えやすいこと。もろいこと。 ④ 涙をたとえていう語。 ⑤ 狩衣・水干・直垂 (ひたたれ) などの袖括りの紐の垂れ下がった部分。 |
① 我が背子を大和へ遣るとさ夜更けて暁露に我が立ち濡れし(万2-105) ③「つゆの命 (露のようにはかなく消えやすい命。露命<ろめい>)」 ③「つゆの世 (露のようにはかない世。無常の世)」など ④「つゆの宿り (露の置く所。涙で濡れる所)」など |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つゆ | 〔副詞〕 ① ほんの少し。ごくわずか。程度の甚だ少ないさまを表す。 ② (下に打消の語を伴って) 少しも。まったく。全然。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つゆじも [露霜] | 〔名詞〕「つゆしも」とも。 ① 露と霜。あるいは、単に露。 また、露が凍って薄い霜のようになったもの。〔秋〕 ② 年月。 |
① 妻恋ひに鹿鳴く山辺の秋萩は露霜寒み盛り過ぎゆく(万8-1604) ② -露霜は改まるとも、松吹く風の散り失せず-(古今仮名序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つゆしもの [露霜の] | 【枕詞】「消(け)」「置く」「秋」などにかかる。 | -露霜の 置きてし来れば この道の 八十隈ごとに 万たび-(万2-131) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つらつら | 〔副詞〕念を入れて思案するさま。よくよく。つくづく。 | 巨勢山のつらつら椿つらつらに見つつ偲はな巨勢の春野を(万1-54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つらつらつばき [列列椿] | 〔名詞〕たくさん並んで枝葉の茂った椿。「つらつら」を引き出す序詞。 | 川上のつらつら椿つらつらに見れども飽かず巨勢の春野は(万1-56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つらを [弦緒] | 弓に弦を取り付けること。弓のつる。弓弦 (ゆづる)。 | 梓弓弦緒取りはけ引く人は後の心を知る人ぞ引く(万2-99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つりぶね [釣舟] | 〔名詞〕漁師の舟のこと。 | 飼飯の海の庭良くあらし刈り薦の乱れて出づ見ゆ海人の釣船(万3-257) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つる [釣る・吊る] | 〔他動詞ラ行四段〕 ① 上から下げる。つるす。 ② 魚などを針にひっかけてとる。釣り上げる。 |
荒たへの藤江の浦にすずき釣る海人とか見らむ旅行く我れを(万3-253) 松浦川川の瀬光り鮎釣ると立たせる妹が裳の裾濡れぬ(万5-859) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つるぎ [剣] | 〔名詞〕《上代は「つるき」 とも》 刀剣。特に両刃の刀。剣太刀。 |
その御佩かせる十拳(とつか)剣抜きてその蛇(をろち)を切り散(はふ)りたまひしかば(記上) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -たち [剣太刀] | 〔名詞〕→ つるぎ。 | -ますらをの 心振り起し 剣大刀 腰に取り佩き 梓弓 靫取り負ひて-(万3-481) 剣大刀諸刃の利きに足踏みて死なば死なむよ君によりては(万11-2503) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つるぎたち [剣太刀] | 【枕詞】「身・磨ぐ・名・己(な)が心」にかかる。 | -柔肌すらを 剣太刀 身に添へ寝ねば ぬばたまの 夜床も荒るらむ-(万2-194) うち鼻ひ鼻をぞひつる剣大刀身に添ふ妹し思ひけらしも(万11-2645) -あり待てど 召したまはねば 剣大刀 磨ぎし心を 天雲に-(万13-3340) 常世辺に住むべきものを剣大刀汝が心からおそやこの君(万9-1745) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つれもなし | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① 何の関係もない。縁もない。② 冷淡である。よそよそしい。 |
① -いかさまに 思ほしめせか つれもなき 真弓の岡に 宮柱-(万2-167) ①つれもなき佐田の岡辺に帰り居ば島の御階に誰れか住まはむ(万2-187) ② 秋風の身にさむければ つれもなき人をぞ頼む 暮るゝ夜ごとに(古今巻12-555) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つゑ [杖] | 〔名詞〕 ① つえ。② 罪人を打つ刑具。 ③ 奈良時代の尺度の単位。ほぼ一丈(=約3メートル)。 ④ 弓一張りの長さをいう語。七尺五寸(=約2.3メートル)。 |
① -天地の 至れるまでに 杖つきも つかずも行きて 夕占問ひ-(万3-423) ③ 「河のほとりに虹(ぬじ)の見ゆること蛇(をろち)の如くして、四五杖(つゑよつゑ、つゑいつつゑ)ばかりなり」(雄略紀) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つをのさき {津乎の埼] | 葦辺には鶴がね鳴きて湊風寒く吹くらむ津乎の崎はも(万3-355) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻三-352 頭注」】 所在未詳。『仙覚抄』は伊代国野間郡(愛媛県今治市) にあるといい、『万葉代匠記』は、『和名抄』の「近江国浅井郡都宇」(滋賀県東浅井郡湖北町) かという。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| て [手] | 〔名詞〕 ① 手。腕。手首。② 手の指。③ 器具の取っ手。柄。④ 部下。手下。 ⑤ 文字。筆跡。⑥ 芸能の型。手振り。所作。⑦ 腕前。技量。 ⑧ 手立て。方法。手段。⑨ 奏法。調子。また、演奏される曲。 ⑩ 手しおにかけること。世話。手数。⑪ 方角。方面。⑫ 手傷。負傷。 |
① -我が恋ふる君 玉ならば 手に巻き持ちて 衣ならば 脱く時もなく-(万2-150) ① -任けたまへば 大御身に 大刀取り佩かし 大御手に 弓取り持たし-(万2-199) ① 神木にも手は触るといふをうつたへに人妻といへば触れぬものかも(万4-520) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【「男手」と「女手」】 「手」には、「文字」や「筆跡」の意味がある。「手習ひ」は、文字を書くことの練習を意味している。 「男手」、「女手」というのは、男の書く文字、女の書く文字の意であるが、要するに漢字と平仮名のことである。 「草(さう)の手」と呼ばれるものもあった。いわゆる草書(そうしょ)のことで、「男手」「女手」のちょうど中間に位置するものである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| て [主要助詞一覧] | 〔格助詞〕(上代東国方言)格助詞「と」の転。同義。 〔接続〕文の終止形に付く。特に引用を受ける。 |
妻もあらば摘みて食げまし沙弥の山野の上のうはぎ過ぎにけらずや(万2-221) 父母が頭掻き撫で幸くあれて言ひし言葉ぜ忘れかねつる(万20-4370) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔接続助詞〕完了の助動詞「つ」の連用形「て」の転。 ① 物事の起こる順序を表わす。~て、それから。そうして。 ② 原因・理由を表わす。~のために。~ので。 ③ 逆接の条件を表わす。~のに。~けれども。~ても。 ④ 仮定条件を表わす。もし~したら。 ⑤ 上下の語句を結ぶ。並列。⑥ ~のさまで。~のまま。状態。 ⑦「思ふ」「覚ゆ」「見ゆ」などの知覚する内容を表わす。~かのように。 ⑧ 補助用言に続く。 本来は叙述を確実にするためであったが、その意を失って単に添えて用いる。 〔接続〕 用言・助動詞 (「なり」「たり」の形のものを除く) の連用形に付く。 |
① 春過ぎて夏来るらし白栲の衣干したり天の香具山(万1-28) ① -神の命と 天雲の 八重かき別けて [一云 天雲の八重雲別けて] -(万2-167) ① 我が背子を大和へ遣るとさ夜更けて暁露に我が立ち濡れし(万2-105) ① 朝ぐもり日の入り行けばみ立たしの島に下り居て嘆きつるかも(万2-188) ① -高光る 我が日の皇子の 馬並めて み狩り立たせる 若薦を-(万3-240) ② 我が妻はいたく恋ひらし飲む水に影さへ見えてよに忘られず (万20-4346) ⑤ - 天のごと 振り放け見つつ 玉たすき 懸けて偲はむ 畏かれども-(万2-199) ⑥ 大船の津守が占に告らむとはまさしに知りて我がふたり寝し(万2-109) ⑥ -玉桙の 道行き人も ひとりだに 似てし行かねば すべをなみ-(万2-207) ⑥ 飼飯の海の庭良くあらし刈り薦の乱れて出づ見ゆ海人の釣船(万3-257) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔語法〕 本来完了の助動詞「つ」から転じたものであるから、中古には完了の意味の名残もあるが、まず接続の上で形容詞にそのまま付き、意味も原因・理由をはじめとし、逆接の意を表わすなど、助動詞とはっきりと区別される。⑤は対句表現のものが多く、⑥は形容詞の連用形に多い用法。⑧は「あり」「はべり」を下に伴うことが多い。 【参考】 形の上から助動詞「て」と助詞「て」を区別する場合、 「(て) む」・(て) けり・(て) き・(て) まし・(て) けむ」のように助動詞に、また「(て) ば・(て) ふ・(て) よ」のように助詞に続く「て」を助動詞、「に (て)」と「と (て)」のように助詞の下につく「て」を助詞とする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完了の助動詞「つ」の連用形。未然形。 〔接続〕連用形につく。 |
うつせみと 思ひし時に [一云 うつそみと 思ひし] 取り持ちて-(万2-210) 我妹子がやどの橘いと近く植ゑてし故に成らずは止まじ(万3-414) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| てこな [手児名] | 〔名詞〕《上代東国方言》[「な」は愛称を表す接尾語。「てごな」とも] かわいいおとめ。 |
葛飾の真間の入江にうちなびく玉藻刈りけむ手児名し思ほゆ(万3-436) -勝鹿の 真間の手児名が 麻衣に 青衿着け ひたさ麻を-(万9-1811) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| てしか | 〔終助詞〕《上代語》[完了助動詞「つ」の連用形「て」に願望終助詞「しか」 平安時代以降は「てしが」] 自己の願望を表す。「~たいものだなあ」。 〔接続〕活用語の連用形につく。 |
見えずとも誰恋ひざらめ山の端にいさよふ月を外に見てしか(万3-396) 朝な朝な上がるひばりになりてしか都に行きて早帰り来む(万20-4457) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -な | 〔終助詞〕[願望の終助詞「てしか」に詠嘆の終助詞「な」のついたもの] 平安時代以降は「てしがな」 〔接続〕活用語の連用形につく。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -も | 〔終助詞〕《上代語》[願望の終助詞「てしか」に詠嘆の終助詞「も」のついたもの] 自己の願望を表す。「~たいものだなあ」。 〔接続〕活用語の連用形につく。 |
なかなかに人とあらずは酒壷に成りにてしかも酒に染みなむ(万3-346) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ては | 〔接続詞「て」+係助詞「は」〕 ① 仮定の意を表す。 ~たらば。~たら。 ② ある事実のもとで、必然的に別の事態が導かれることを表す。 ~たからには。~た以上は。 ③ ある事実のもとでは、常に同じ結果の起こることを表す。 ~ときはいつも。~と。 ④ 動作・作用の反復を表す。 ~たかと思うと。~と。 ⑤ 特に取り立てて言う。口語の「ては」に同じ。 〔接続〕活用語の連用形に付く。 〔参考〕「ては」を一語とみる考え方もある。 |
① 大船を漕ぎのまにまに岩に触れ覆らば覆れ妹によりては(万4-560) ② -取りても見ず 秋山の 木の葉を見ては 黄葉をば 取りてぞ偲ふ- (万1-16) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| てむ | 〔完了の助動詞「つ」の未然形+推量の助動詞「む」〕 ① その事態の実現への強い意志を表す。~でしまおう。 ② その事態の実現を強く推量する意を表す。きっと~するだろう。 ③ 可能性に対する推量を表す。~することが出来るだろう。 ④ (助詞「や」を伴って) 相手に同意を求め、または勧誘する意を表す。→「てむや」 ⑤ 当然・適当の意を表す。~するのがよい。~のが当然だ。 |
① いざ子ども香椎の潟に白栲の袖さへ濡れて朝菜摘みてむ(万6-962) ② 我が背子が跡踏み求め追ひ行かば紀伊の関守い留めてむかも(万4-548) ③ 春日野の飛ぶ火の野守出でて見よ今いくかありて若菜摘みてむ(古今春上-19) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ても | 〔接続詞「て」+係助詞「も」〕 ①「て」で受けた語句の意味を「も」で強めながら下に続ける。 ~ても。~て。~てまあ。 ②「も」の働きで、上の語句を逆接的に下に続ける。 ~ても。~のに。~にもかかわらず。 ③ 逆接の仮定条件を表す。 たとえ~しても。~たとしても。 〔接続〕活用語の連用形に付く。 |
① 馬ないたく打ちてな行きそ日並べて見ても我が行く志賀にあらなくに(万3-265) ① み崎廻の荒磯に寄する五百重波立ちても居ても我が思へる君(万4-571) ② -山を茂み 入りても取らず 草深み 取りても見ず -(万1-16) ③ ぬばたまの黒髪変はり白けても痛き恋にはあふ時ありけり(万4-576) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| てや | 〔接続助詞「て」+係助詞「や」〕~て~か。 | 百伝ふ磐余の池に鳴く鴨を今日のみ見てや雲隠りなむ(万3-419) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔終助詞〕《近世語》 ① [終助詞「て」+間投助詞「や」] ア 感動の意を表し、自分と相手と両方に言い聞かせる気持ちで用いる。 ~わ。~よ。 イ 軽く相手をたしなめる気持ちで用いる。 ② [接続助詞「て」+間投助詞「や」] 希望の意や、遠回しに命令する意を表す。~てください。 〔接続〕 「①」は言い切った形に、「②」は動詞の連用形につく |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| てらす [照らす] | 〔他動詞サ行四段〕光を当てて明るくする。また、明らかにする。 | 去年見てし秋の月夜は照らせども相見し妹はいや年離る(万2-211) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| てる [照る] | 〔自動詞ラ行四段〕① 光を放つ。輝く。② (容貌や姿が) 美しく輝く。 【「照る」 という美しさ】 「万葉集」 には、「春の苑紅にほふ桃の花下照る道に出で立つをとめ」(二〇・四四二一) という歌があり、「下照る・照る」 が美しく輝く意であるのがわかる。「古事記」「日本書紀」 に登場する天稚彦(あめわかひこ) の妃は下照(したでる)姫という。 |
① あかねさす日は照らせれどぬばたまの夜渡る月の隠らく惜しも(万2-169) ① 去年見てし秋の月夜は照らせども相見し妹はいや年離る(万2-211) ① -天皇の 神の皇子の 出でましの 手火の光りそ そこば照りたる(万2-230) ② 新室を踏み鎮む子が手玉鳴らすも玉のごと照らせる君を内にと申せ(万11-2356) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| と | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| と | (連体修飾語を受け、多く「とに」の形で用いる) ① ~するときに。~するところに。 ②(否定表現を受けて)~うちに。 |
① 龍田山見つつ越え来し桜花散りか過ぎなむ我が帰るとに(万20-4419) ② 他国は住み悪しとぞ言ふ速けく早帰りませ恋ひ死なぬとに(万15-3770) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| と | 〔副詞〕[副詞「かく(かう)」と対で用いられることが多い] そのように。あのように。 |
三輪山の山辺真麻木綿短か木綿かくのみからに長くと思ひき(万2-157) 世の中し常かくのみとかつ知れど痛き心は忍びかねつも(万3-475) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| と | 〔格助詞〕 ① 動作を共同して行う者を表わす。「~と。~とともに。~と一緒に。」 ② 動作の相手を表わす。「~と。~を相手にして。」 ③ 比較の基準を表わす。「~と。~と比べて。~に対して。」 ④ 人の言葉や思うことなどを直接受けて、引用を表わす。 「言ふ・聞く・思ふ・見ゆ・知る」などの動詞へ続けて、その内容を示す ⑤「~と言って」「~と思って」「~として」などの意で、 あとに続く動作・状態の目的・状況・原因・理由などを示す。 ⑥ 擬声語・擬態語を受ける。 ⑦(多く「~となる」の形で)変化した結果、ある状態になる意を表わす。 「~に」。 ⑧ 比喩を表わす。~のように。~と同じに。「~として。」 ⑨ 直接、断定の助動詞「なり」に続いて、 「~というの(である)・~と思うの(である)」などの意を表わす。 「~とならば・~とにあり・~となり」などの形をとり、 「と」と「なり」の間に「思ふ・言ふ・する」などが省略されたもの。 ⑩ 体言またはそれに準ずるものを並列する。 ⑪ 同じ動詞の間において、意味を強める。上に来る動詞は連用形。 〔接続〕体言、体言に準ずる語、 ⑪の場合は動詞の連用形、④の引用の場合には文の言い切りの形に付く。 |
① 妹としてふたり作りし我が山斎は木高く茂くなりにけるかも(万3-452) ④ 我れはもや安見児得たり皆人の得かてにすといふ安見児得たり (万2-95) ④ 大船の津守が占に告らむとはまさしに知りて我がふたり寝し(万2-109) ④ ―石見の海 角の浦廻を 浦なしと 人こそ見らめ― (万2-131) ④ 外に見し真弓の岡も君座せば常つ御門と侍宿するかも(万2-174) ④ 佐保過ぎて奈良の手向けに置く幣は妹を目離れず相見しめとそ(万3-303) ⑤ あをによし奈良の家には万代に我れも通はむ忘ると思ふな(万1-80) ⑤ ますらをや片恋せむと嘆けども醜のますらをなほ恋ひにけり(万2-117) ⑤ 風流士と我れは聞けるをやど貸さず我れを帰せりおその風流士(万2-126) ⑤ うつそみの人なる我れや明日よりは二上山を弟背と我が見む(万2-165) ⑤ -天地の 寄り合ひの極み 知らしめす 神の命と 天雲の-(万2-167) ⑤ み立たしの島をも家と棲む鳥も荒びな行きそ年かはるまで(万2-180) ⑤ 我が御門千代とことばに栄えむと思ひてありし我れし悲しも(万2-183) ⑤ -けだしくも 逢ふやと思ひて [一云 君も逢ふやと] -(万2-194) ⑤ -神葬り 葬りいまして あさもよし 城上の宮を 常宮と 高く奉りて-(万2-199) ⑤ - もみち葉の 過ぎて去にきと 玉梓の 使ひの言へば 梓弓-(万2-207) ⑤ -露こそば 朝に置きて 夕には 消ゆといへ 霧こそば 夕に立ちて-(万2-217) ⑤ 沖つ波来寄する荒礒をしきたへの枕とまきて寝せる君かも(万2-222) ⑤ 否と言へど強ふる志斐のが強ひ語りこのころ聞かずて朕恋ひにけり(万3-237) ⑤ あな醜賢しらをすと酒飲まぬ人をよく見ば猿にかも似る(万3-347) ⑥ -夜はすがらに この床の ひしと鳴るまで 嘆きつるかも(万13-3284) ⑦ 我が背子を大和へ遣るとさ夜更けて暁露に我が立ち濡れし(万2-105) ⑧ 熟田津に船乗りせむと月待てば潮もかなひぬ今は漕ぎ出でな(万1-8) ⑧ -天地 日月と共に 足り行かむ 神の御面と 継ぎ来る 那珂の港ゆ-(万2-220) ⑧ -さつ矢手挟み 立ち向かふ 高円山に 春野焼く 野火と見るまで-(万2-230) ⑨ -常世辺に また帰り来て 今のごと 逢はむとならば この櫛笥- (万9-1744) ⑩ 畑子らが夜昼といはず行く道を我れはことごと宮道にぞする(万2-193) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| と | 〔接続助詞〕逆接の仮定条件を表わす。~ても。たとえ~ても。 〔接続〕 動詞・形容動詞・助動詞(形容詞型活用)の終止形、形容詞・助動詞(形容詞型活用・打消の「ず」)の連用形に付く。 |
-思ひつつ 眠も寝かてにと 明かしつらくも 長きこの夜を(万4-485) 風をだに恋ふるはともし風をだに来むとし待たば何か嘆かむ(万4-492) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ど | 〔接続助詞〕 ① 逆接の確定条件を表す。現にその事実がありながら、 予想に反した結果が現れることを示す。 「~けれども。~のに。~だが。」 ② 逆接の恒常条件を表す。 現にその事実があるわけではないが、その事実が現れた場合でも、 必ずその事実から予想される事態に反する結果になることを示す。 「~ても(やはり)。~ときでも。」 〔接続〕活用語の已然形に付く。 |
① 人皆は今は長しとたけと言へど君が見し髪乱れたりとも [娘子](万2-124) ① 山吹の立ちよそひたる山清水汲みに行かめど道の知らなく (万2-158) ① あかねさす日は照らせれどぬばたまの夜渡る月の隠らく惜しも(万2-169) ① 東のたぎの御門に侍へど昨日も今日も召す言もなし(万2-184) ① 真木柱太き心はありしかどこの我が心鎮めかねつも(万2-190) ① 否と言へど強ふる志斐のが強ひ語りこのころ聞かずて朕恋ひにけり(万3-237) ① しらぬひ筑紫の綿は身に付けていまだは着ねど暖けく見ゆ(万3-339) ② 大伴の高師の浜の松が根を枕き寝れど家し偲はゆ(万1-66) ② ふたり行けど行き過ぎがたき秋山をいかにか君がひとり越ゆらむ(万2-106) ② 昼見れど飽かぬ田子の浦大君の命恐み夜見つるかも(万3-300) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔参考〕 「ど・ども」は、ほぼ同じ意味に用いられる。ただし、平安時代では女性の書いた文章に、「ども」に比して「ど」が圧倒的に多く使われる。 ところが鎌倉時代に入ると、「むしろ」「ども」が一般的に使われるようになり、「ど」が減少する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| といふ | 〔なりたち〕 格助詞「と」+四段動詞「言ふ」の連体形。 ① ~である。~なる。 ② (下に「こと」「もの」など形式名詞を伴って) 「と」の受ける物事を取立てて示す。 |
① もののふの臣の壮士は大君の任けのまにまに聞くといふものそ(万3-372) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とか | 〔なりたち〕格助詞「と」+係助詞「か」 ① (文中にあって)不確実な推量を表す。 ~ということで~だろうか。 ② (文末にあって)伝聞を表す。 ~とかいうことだ。 【参考】 「①」は係り結びの法則によって、活用語の結びは連体形になる。 「②」は、下に「いふ」などの結びが省略された形。 |
① 荒たへの藤江の浦にすずき釣る海人とか見らむ旅行く我れを(万3-253) ① 海原の沖行く船を帰れとか領巾振らしけむ松浦佐用姫(万5-878) ② 逆言の狂言とかも高山の巌の上に君が臥やせる(万3-424) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とき [時] | 〔名詞〕 ① 月日の移り行く間。時間。 ② 一昼夜を区分した時間の単位。 一昼夜を二時間ずつに十二等分して一時(いっとき)とし、 そのそれぞれに十二支を配した。 また江戸時代、民間では日の出・日の入りを基準として昼夜に分け、 それぞれを六等分する実用的な時法も行われた。 ③ 時代。治世。④ 季節。時候。時節。⑤ 場合。おり。 ⑥ 時勢。世の成り行き。⑦ よい機会。好機。⑧ その頃。当時。 ⑨ その場。一時。当座。 ⑩ 勢いがあり、盛んな時期。羽振りのよいおり。 |
① 妹が見しやどに花咲き時は経ぬ我が泣く涙いまだ干なくに(万3-472) ① 見まつりていまだ時だに変はらねば年月のごと思ほゆる君(万4-582) ④ 日並の皇子の命の馬並めてみ狩り立たしし時は来向ふ(万1-49) ⑤ み立たしの島を見る時にはたづみ流るる涙止めそかねつる(万2-178) ⑤ -木綿花の 栄ゆる時に 我が大君 皇子の御門を-(万2-199) ⑦ 天の川八十瀬霧らへり彦星の時待つ舟は今し漕ぐらし(万10-2057) ⑧ -背きたまふや うつそみと 思ひし時に 春へは 花折かざし-(万2-196) ⑨ 恋ひ死なむ時は何せむ生ける日のためこそ妹を見まく欲りすれ(万4-563) ⑩時なりくる人の、にはかに時なくなりて嘆くを見て、 みずからの、嘆きもなく、喜びもなきことを思ひてよめる (古今雑下-967詞書) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻二-191 注 「春冬片設而(ときかたまけて」】 「春冬」 二字でハルフユと訓むのが旧訓であり、代匠記・考など江戸時代の注もそれに従ったが、そうするとハルフユカタマケテと九音になる。 第二句の、しかも母音音節を含まない字余りは不適当と思われるので、全註釈に「二字を合わせてトキと読む。時節の意である。 春冬の二字を書いたのは、生前の御事蹟について述べているのであるから、実際、春季および冬季に宇陀の野に出遊せられたことがあって、それを想起しているのであろう」 と言う。 狩猟の行われた時期が春と冬であったから春冬と書いてトキと訓ませるつもりであったという推定は正しいと思われる。-以下略- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ときかはす [解き交はす] | 〔他動詞サ行四段〕 互いに相手の帯・紐などを解きあう。解きあって共寝する。=解き交ふ |
高麗錦紐解きかはし天人の妻問ふ宵ぞ我れも偲はむ(万10-2094) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ときかふ [解き交ふ] | 〔他動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 ① → とくかはす。 ② 互いに相手の帯・紐などを解いて交換する。 |
① 古に ありけむ人の 倭文幡の 帯解き交へて 廬屋立て-(万3-434) ② 白栲の袖解き交へて帰り来む月日を数みて行きて来ましを(万4-513) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ときさく [解き放く] | 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 解き放つ。解きほどく。 |
-さにつらふ 紐解き放けず 我妹子に 恋ひつつ居れば 明け闇の-(万4-512) かくのみや我が恋ひ居らむぬばたまの夜の紐だに解き放けずして(万17-3960) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ときじ [時じ] | 〔形容詞シク活用〕 【ジカラ・ジク(ジカリ)・ジ・ジキ(ジカル)・ジケレ・ジカレ】 《上代語》「じ」は形容詞をつくる接尾語で、打消しの意を含む。 ① その時節にはずれている。その時期でない。 ② 時節に関係がない。いつもある。 |
① 川の上のいつ藻の花のいつもいつも来ませ我が背子時じけめやも(万4-494) ① 我が宿の時じき藤のめづらしく今も見てしか妹が笑まひを(万8-1631) ② -白雲も い行きはばかり 時じくそ 雪は降りける-(万3-320) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ときじく [時じく] | 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・】 (形容詞「時じ」の連用形から) 時期に関係ないさま。いつまでも。 |
-い行きはばかり 時じくそ 雪は降りける 語り継ぎ 言ひ継ぎ行かむ-(万3-320) 橘は花にも実にも見つれどもいや時じくになほし見が欲し(万18-4136) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ときつかぜ [時つ風・時津風] | 〔名詞〕[「つ」は「の」の意の上代の格助詞] ① 潮が満ちてくるときに吹く風。 ② その時に、うまい具合に吹く風。 |
① -我が漕ぎ来れば 時つ風 雲居に吹くに 沖見れば とゐ波立ち-(万2-220) ① 時つ風吹くべくなりぬ香椎潟潮干の浦に玉藻刈りてな(万6-963) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】「吹く」と同音を含む地名「吹飯(ふけひ)」にかかる。 | 時つ風吹飯の浜に出で居つつ贖ふ命は妹がためこそ(万12-3215) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ときどき [時時] | 〔副詞〕 ① おりにふれて。ときに応じて。② たまに。ときおり。 |
① -望月の いやめづらしみ 思ほしし 君と時どき 出でまして-(万2-196) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ときなし [時無し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 いつと決まったときがない。いつもである。絶え間がない。 |
み吉野の 耳我の嶺に 時なくぞ 雪は降りける 間無くぞ 雨は振りける(万1-25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ときならず [時ならず] | 時季外れである。その時期でない。思いがけなく。 | -思ひ恋ふらむ 時ならず 過ぎにし子らが 朝露のごと 夕霧のごと(万2-217) 時ならず玉をぞ貫ける卯の花の五月を待たば久しくあるべみ(万10-1979) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ときは [常盤・常磐] | 〔名詞・形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・】 〔「常盤(とこいは=永遠に変わらない大岩)」の転〕 ① 常に変わらないこと。永久不変。 ② 樹木の葉が一年じゅう緑であること。常緑。 |
① 常磐なす岩屋は今もありけれど住みける人そ常なかりける(万3-311) ② 八千種の花は移ろふ常盤なる松のさ枝を我れは結ばな(万20-4525) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とく [解く] | 〔他動詞カ行四段〕 ① 結び目をほどく。② (髪など)乱れもつれたものを整える。とかす。 ③ 知る。さとる。答を出す。 ④ [「溶く」とも書く] 固形のものを液状にする。とかす。 |
① -大刀(たち)が緒(を)もいまだ解かずて-(記上) ① 山守はけだしありとも我妹子が結ひけむ標を人解かめやも(万3-405) ④ 袖ひちてむすびし水のこほれるを春立つけふの風やとくらむ(古今春上-2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔自動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 ① 結び目がほどける。② 職をはなれる。解任になる。 ③ 心の隔てがなくなる。打ち解ける。安心する。 ④ [「溶く」とも書く] 固形のものを液状になる。とける。 |
① 我妹子し我を偲ふらし草枕旅のまろ寝に下紐解けぬ(万12-3159) ② 左近の将監(しやうげん)解けて侍りける時に(古今雑下・詞書) ③ 磐代の野中に立てる結び松心も解けずいにしへ思ほゆ(万2-144) ④ 谷風にとくる氷のひまごとに打ち出づる波や春のはつ花(古今春上-12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とく [説く] | 〔他動詞カ行四段〕説明する。解説する。言い聞かせる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とく [疾く] | 〔副詞〕[形容詞「疾(と)し」の連用形から] ① 早く。すみやかに。さっそく。 ② すでに。とっくに。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とぐ [遂ぐ] | 〔他動詞ガ行下二段〕【ゲ・ゲ・グ・グル・グレ・ゲヨ】 (目的などを) 果たす。なしとげる。 |
-結びてし ことは果たさず 思へりし 心は遂げず 白たへの-(万3-484) 我が背子し遂げむと言はば人言は繁くありとも出でて逢はましを(万4-542) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とこ [常-] | 〔接頭語〕《名詞・形容詞について 》「不変・永遠」 の意を表す。 「常世・とこ少女(をとめ)・とこなつかし」など。 |
我が御門千代とことばに栄えむと思ひてありし我れし悲しも(万2-183) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とこつみかど [常つ御門] | 〔名詞〕《「つ」 は「の」 の意の上代の格助詞。》 永久に変わらない御所。常宮(とこみや)。 |
外に見し真弓の岡も君座せば常つ御門と侍宿するかも(万2-174) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とこなめ [常滑] | あ川岸や川底の、苔など生えてつるつるした所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とこのやま [鳥籠の山] | 【有斐閣「萬葉集全注巻四-487 注『鳥籠の山なる』」】 「鳥籠の山」 は滋賀県彦根市正法寺町にある正法寺山。天武紀元年の条に「近江ノ将秦友足(はだのともたり)ヲ討チ鳥籠ノ山ニ斬ル」 とある。ナルはニ在ルの約。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とこみや [常宮] | 〔名詞〕永久に変わらず栄えている宮殿。常つ御門。 | -城上の宮を 常宮と 定めたまひて あぢさはふ 目言も絶えぬ-(万2-196) -神葬り 葬りいまして あさもよし 城上の宮を 常宮と 高く奉りて-(万2-199) やすみしし 我ご大君の 常宮と 仕へ奉れる 雑賀野ゆ そがひに見ゆる-(万6-922) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とぐら [鳥座・鳥塒] | 〔名詞〕鳥の巣。鳥小屋。 | 鳥座立て飼ひし雁の子巣立ちなば真弓の岡に飛び帰り来ね(万2-182) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ところ [処・所] | 〔名詞〕 ① 場所。地点。また、土地。区域。② その土地。その地方。 ③ その家。その邸。④ 点。箇所。こと。⑤ 地位。位置。 ⑥ 場合。時。際。⑦ (特に蔵人所、武者所など)役所をさしていう。 ⑧ (下に「の」を伴って)連体修飾であることを示す。 漢文の訓読から発生した言い方。 |
① 住吉の野木の松原遠つ神我が大君の幸行処(万3-298) ① 我れも見つ人にも告げむ葛飾の真間の手児名が奥つきどころ(万3-435) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とこやみ [常闇] | 〔名詞〕永遠の暗闇。常夜(とこよ)。 | -天雲を 日の目も見せず 常闇に 覆ひ賜ひて 定めてし 瑞穂の国を-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とこよ [常世] | 〔名詞〕 ① [多く(とこよ)の形で、副詞的に用いて] 永久に変わらないこと。不変。 ②「常世の国」の略。 |
① -ひさかたの 天伝ひ来る 雪じもの 行き通ひつつ いや常世まで(万3-263) ① 我妹子が見し鞆の浦のむろの木は常世にあれど見し人ぞなき(万3-449) ②-神の大御代に 田道間守 常世に渡り 八桙持ち 参ゐ出来し時- (万18-4135) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とこをとめ [常少女] | 「とこ」は永久不変の意。いつまでも年を取らない美しい少女。 | 川の上のゆつ岩群に草生さず常にもがもな常少女にて(万1-22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とし [年・歳] | 〔名詞〕 ① 一年。十二ヶ月。② 多くの歳月。世。③ 季節・時候。 ④ 年齢。よわい。⑤ 穀物。特に、稲。また穀物の実り。 |
① 新しき年の初めの初春の今日降る雪のいやしけ吉事(万20-4540) ② 白波の浜松が枝の手向けぐさ幾代までにか年の経ぬらむ [一云 年は経にけむ](万1-34) ② 去年見てし秋の月夜は照らせども相見し妹はいや年離る(万2-211) ② ももしきの大宮人の熟田津に船乗りしけむ年の知らなく(万3-326) ⑤ 我が欲りし雨は降り来ぬかくしあらば言挙げせずとも年は栄えむ (万18-4148) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のを [年の緒] | 年の長く続く続くのを緒にたとえていう語。 | -あらたまの 年の緒長く 住まひつつ いまししものを 生ける者-(万3-463) あらたまの年の緒長く逢はざれど異しき心を我が思はなくに(万15-3797) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ふ [年経] | 〔自動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 何年も経つ。 |
-あらたまの 年経るまでに 白たへの 衣も干さず 朝夕に-(万3-446) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| としごろ [年頃] | 〔名詞〕《古くは「としころ」 とも》 長年。長年の間。この何年もの間。数年来。 |
朝日照る佐田の岡辺に泣く鳥の夜哭きかへらふこの年ころを(万2-192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| としつき [年月] | 〔名詞〕 ① 年と月。月日。時間。② 長い歳月。また、年来。 |
-いかにあらむ 年月日にか つつじ花 にほへる君が にほ鳥の-(万3-446) 冬過ぎて春し来れば年月は新たなれども人は古りゆく(万10-1888) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とぞ(とそ) | 〔なりたち〕格助詞「と」+係助詞「ぞ」 ① [文中に用い] 「と」の受ける内容を強める。 ② [文末に用い、「言へる」などの結びが失われて] ~ということだ。 |
① ま草刈る荒野にはあれど黄葉の過ぎにし君の形見とぞ来し(万1-47) ① 我が宿に韓藍蒔き生ほし枯れぬとも懲りずてまたも蒔かむとそ思ふ(万3-387) ② 世の中は空しきものとあらむとそこの照る月は満ち欠けしける(万3-445) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ととのふ [調ふ・整ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 ① 不足なくそろう。完備する。② まとまる。調和している。 ③ 出来上がる。成就する。④ (楽器などの) 調子が合う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 ① そろえる。整頓する。② 用意する。工面する。 ③ (楽器などの) 調子を合わせる。④ 縁組をまとめる。縁づける。 |
① -御軍士を 率ひたまひ 整ふる 鼓の音は 雷の 声と聞くまで-(万2-199) ① 大宮の内まで聞こゆ網引すと網子ととのふる海人の呼び声(万3-239) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とどむ [止む・留む・停む] | 〔他動詞マ行上二段〕【ミ・ミ・ム・ムル・ムレ・ミヨ】 とどめる。 |
常磐なすかくしもがもと思へども世の事なれば留みかねつも(万5-809) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とどむ [止む・留む・停む] | 〔他動詞マ行下二段〕【メ・メ・ム・ムル・ムレ・メヨ】 ① とどめる。ひきとめる。② 制止する。おさえる。③ やめる。中止する。 ④ 注意をむける。心を」とめる。⑤ あとに残す。⑥ しとめる。 |
① 留め得ぬ命にしあればしきたへの家ゆは出でて雲隠りにき(万3-464) ① 夏麻引く海上潟の沖つ洲に船は留めむさ夜更けにけり(万14-3362) ② 我が背子が跡踏み求め追ひ行かば紀伊の関守い留めてむかも(万4-548) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とどろに | 〔副詞〕大きな音の鳴り響くさま。どうどう。ごうごう。 | 左夫流児が斎きし殿に鈴掛けぬ駅馬下れり里もとどろに(万18-4134) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とねり [舎人] | 〔名詞〕 ① 天皇・皇族などのそばに仕え、雑務や警護をした近衛府に属する下級官人。 貴族もかかえることを許された。大舎人・内舎人・小舎人の別がある。 「舎人男(とねりをとこ)」とも。 ② 貴人に従う身分の低い者。牛車の牛飼いや馬の口取りなど。 |
① 埴安の池の堤の隠り沼のゆくへを知らに舎人は惑ふ(万2-201) ① -白たへに 舎人よそひて 和束山 御輿立たして-(万3-478) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| との [殿] | 〔名詞〕 ① 身分の高い人の住む邸宅。御殿。 ② 身分の高い人を尊敬していうことば。特に、摂政・関白をいう。 ③ 主君。④ 妻から夫をさして呼ぶことば。 |
① 左夫流児が斎きし殿に鈴掛けぬ駅馬下れり里もとどろに(万18-4134) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とのぐもる [との曇る] | 〔自動詞ラ行四段〕〔「との」は一面に、ずっとの意〕 空が一面にくもる。すっかりくもる。 |
雨降らずとの曇る夜のぬれ漬てど恋ひつつ居りき君待ちがてり(万3-373) この見ゆる雲ほびこりてとの曇り雨も降らぬか心足らひに(万18-4147) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とのへ [外の重] | 〔名詞〕[「九重(ここのへ)の外の意」] 宮城の外郭。また、そこを守、左・右衛門の陣。 |
-神の御門に 外の重に 立ち候ひ 内の重に 仕へ奉りて-(万3-446) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とのゐ [宿直] | 〔名詞〕《「殿居(とのゐ)」の意 》 ① 夜間、宮中・役所などに宿泊して事務や警備をすること。宿直。 ② 夜間、天皇や身分の高い人のそばに仕えて、話などの相手をすること。 |
① 橘の嶋の宮には飽かぬかも佐田の岡辺に侍宿しに行く(万2-179) ② 外に見し真弓の岡も君座せば常つ御門と侍宿するかも(万2-174) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とは(ば) [永久] | 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 長く変わらないさま。とこしえ。 |
我が御門千代とことばに栄えむと思ひてありし我れし悲しも(万2-183) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とばやままつ [飛羽山松] | 【有斐閣「万葉集全注巻四-588 注『飛羽山松の』】 「トバ山」 は従来正確な所在地が不明であったが、最近大井重二郎氏は「東大寺四至図」「大仏燈油料田記録」 などの資料によって、東大寺の東北、現在三笠霊園の造営されている辺り、高さ217mの小峰の当たることを明らかにされた(「大伴寺の所在と佐保の奥津城附・鳥羽山」園田国文三号)。以上、松と同音の「待ツ」を起こす序であるが、「トバ」にも「永久」の意を含めたか。「常登婆尓(とことばに)」(2・一八三) とあり仏足歌にも「止己止婆尓」 とある。古今和歌集巻第十四の 津の国のなには思はず山城のとばにあひ見むことをのみこそ(六九六) の「トバ」は京都市伏見区の地名鳥羽をかけたものであるが、高松宮家貞応本・寂恵本・毘沙門堂本・古今訓点抄など、声点本のほとんどがその「ハ」に濁点を付している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とひさく [問ひ放く] | 〔自動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 問いを発する。遠くからことばをかける。 |
-良しと聞かして 問ひ放くる 親族兄弟 なき国に 渡り来まして-(万3-463) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とふ [問ふ・訪ふ] | 〔他動詞ハ行四段〕 ① 尋ねる。聞く。② 安否を問う。気づかう。 ③ 取り調べる。問いただす。④ 訪問する。見舞う。 ⑤ とむらう。死者の霊を慰める。 |
① -ころ臥す君が 家知らば 行きても告げむ 妻知らば 来も問はましを-(万2-220) ① -春野焼く 野火と見るまで 燃ゆる火を 何かと問へば 玉鉾の-(万2-230) ② 「さねさし相模(さがむ)の小野に燃ゆる火の火中(ほなか)に立ちて問ひし君はも」(記中) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とぶ [飛ぶ] | 〔自動詞バ行四段〕 ① 空をかける。空中に舞い上がる。② 走る。かける。はねる。 |
① 鳥座立て飼ひし雁の子巣立ちなば真弓の岡に飛び帰り来ね(万2-182) ① 白雲に羽うちかはし飛ぶ雁の数さへ見ゆる秋の夜の月(古今・秋上-191) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とぶさ [鳥総] | 〔名詞〕 梢や枝葉の茂った先。きこりが木を切ったあとに、これを切り株や地上に立てて山神を祭る風習があった。 |
とぶさ立て足柄山に船木伐り木に伐り行きつあたら船木を(万3-394) 鳥総立て船木伐るといふ能登の島山今日見れば木立繁しも幾代神びぞ(万17-4050) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻三-391 注『鳥総立て』】 仮名書きに「登夫佐多氐船木伎流等伊布能登乃嶋山 (トブサタテフナギキルトイフノトノシマヤマ)」(17・四〇二六) がある。「鳥総」 は枝葉のついた梢。樹木を伐る時、切株の上に同じ木の「鳥総」を立てて山の神を祭る木樵(きこり) の習慣があった。『八雲御抄』(巻四) に「杣にいりて木を切ては必木のすゑをきりて、切たる木の跡に立也。たとへばかはり也」 とあるのが「とぶさたて」 である。この習慣は古くからあったもので、大殿祭の祝詞に「皇御孫(すめみま)の命の御殿(みあらか)を、今奥山の大峡小峡(おほかひをかひ)に立てる木を、斎部の斎斧を持ちて伐り採りて、本末(もとすゑ)をば山の神に祭りて、中間らを持出で来て」 とある「本末」 が「鳥総」 に当たる(『冠辭考』)。講義は、『色葉字類抄』に「朶、トブサ」 とあり、『説文』に「樹木垂□[几の下に木]也」(枝葉のふさふさと多くついた梢) とあり、「堀川百首」 の俊頼の歌や、『後拾遺集』(十三) の祭主輔親の歌にも「とぶさ」 を詠んだものがあることを紹介し、「『トブサ』もその朶の義にて立木の末の枝葉のつきたる部分をいふと思はれたり。」 と述べた。以上の諸説に従うべきである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とぶとりの [飛ぶ鳥の] | 【枕詞】「明日香」にかかる。 |
飛ぶ鳥の明日香の里を置きて去なば君があたりは見えずかもあらむ(万1-78) -神下し いませまつりし 高照らす 日の御子は 飛ぶ鳥の 清御原の宮に-(万2-167) 飛ぶ鳥の 明日香の川の 上つ瀬に 石橋渡し [一云 石なみ] -(万2-194) [四音]にもとづく「訓」 とぶとり あすかのさとを おきていなば きみがあたりは みえずかもあらむ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻二167 注『飛鳥の浄の宮に』】 原文「飛鳥之」 をアスカノと訓むかトブトリノと訓むか、説が分かれる。地名アスカに「飛鳥」 の二字を宛てることは、枕詞から転じたものとする記伝(三十八) の説に従えば、人麻呂作歌の「飛鳥(トブトリノ) 明日香乃河」(194・196) などの例から「飛鳥」 をアスカと訓むようになったと考えられる。ただし、小野朝臣毛人墓誌(丁丑年) に「飛鳥浄御原宮」 とあるのを朱鳥元年以前の「飛鳥(アスカ)」 の例とすれば、ここもアスカノキヨミノミヤと訓まれる。このことは194歌の〔注〕に詳述する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とぶらふ [訪ふ] | 〔他動詞ハ行四段〕 ① 訪れる。見舞う。② 尋ね求める。さがす。 |
-なにしかも もとなとぶらふ 聞けば 音のみし泣かゆ-(万2-230) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とぶらふ [弔う] | 〔他動詞ハ行四段〕 ① 人の死をいたんで、その喪にある人を慰める。悔みをいう。弔問する。 ② 死者の霊を慰め供養する。追善を営む。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とほ [遠] | 〔形容詞「とほし」の語幹〕時間的、空間的」に遠く離れていること。 「遠長(なが)し・遠音(と)」。 |
梓弓爪引く夜音の遠音にも君の御幸を聞かくし良しも(万4-534) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とほし [遠し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① 距離や時間が非常に離れている。遠い。② 疎遠だ。親しくない。 ③ 関心がない。気が進まない。④ 関係がない。縁が薄い。 已然形「ケレ」が古形の「ケ」の場合もあった。 |
① 我妹子をいざ見の山を高みかも大和の見えぬ国遠みかも(万1-44) ① 采女の袖吹きかへす明日香風都を遠みいたづらに吹く(万1-51) [「遠み」ミ語法] ① 陸奥の真野の草原遠けども面影にして見ゆといふものを(万3-399) ① 天地の 遠き初めよ 世間は 常なきものと 語り継ぎ -(万19-4184) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【「とほし」と「はるけし」の違い】⇒「はるけし」 「とほし」は、ある地点からの距離、時間の隔たりの大きいことをいう。「はるけし」もまた、隔たりの大きさという意味においては同じだが、「とほし」が客観的な意味合いが濃いのに対して、「はるけし」は、その地点にまでなかなか行き着くことができなという、主観的な意味合いの濃い語として使われる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とほしろし | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① 雄大である。偉大である。 ② 《歌学用語》気品があって奥深い。 |
① -明日香の 古き都は 山高み 川とほしろし 春の日は-(万3-327) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とほす [通す・徹す] | 〔他動詞サ行四段〕 ① 端から端までとどかせる。通じさせる。また、通り抜けさせる。貫く。 ② (ある期間を) 継続させる。越す。 ③ 透き通す。すかす。 ④ 通行させる。往来させる。 ⑤ (動詞の連用形の下について) しとげる。やりとおす。 |
③ 玉垂の小簾の間通しひとり居て見る験なき夕月夜かも (万7-1077) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どほつかみ [遠つ神] | 【枕詞】「おほきみ」にかかる。 遠い昔の天つ神のようなの意。天つ神の血筋を受ける天皇を尊んで言う |
住吉の野木の松原遠つ神我が大君の幸しところ(万3-298) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とほづま [遠夫・遠妻] | 〔名詞〕 ① 「遠夫」 遠く離れて会うことのまれな夫。特に、「牽牛星をいう」。 ② 「遠妻」 遠く離れて会うことのまれな妻。特に、「織女星」をいう。 |
② 遠妻の ここにしあらねば 玉桙の 道をた遠み 思ふそら 安けなくに-(万4-537) ② 朝月の日向の山に月立てり見ゆ遠妻を待ちたる人し見つつ偲はむ(万7-1298) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とほながし [遠長し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① 遠く遥かである。② 永久である。 |
① 富士の嶺のいや遠長き山道をも妹がりとへばけによばず来ぬ(万14-3370) ② -名のみも絶えず 天地の いや遠長く 偲ひ行かむ -(万2-196) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とほのみかど [遠の朝廷] | ① 都から遠く離れた役所。諸国の国府や九州大宰府などをさす。 ② 朝鮮半島の新羅におかれた日本の政庁。転じて、新羅。遠 |
① 大君の遠の朝廷とあり通ふ島門を見れば神代し思ほゆ(万3-307) ① 大君の遠の朝廷と思へれど日長くしあれば恋ひにけるかも(万15-3690) ② -天皇の 遠の朝廷と 韓国に 渡る我が背は 家人の-(万15-3710) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とほる [通る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 通行する。往来する。 ② [「徹る」とも書く] つきぬける。通じる。 ③ 達せられる。やり遂げられる。 ④ [「透る」とも書く] 透き通る。 ⑤ 察知する。理解する。 |
① 若ければ道行き知らじ賄はせむ黄泉の使負ひて通らせ (万5-910) ②「すなはち矢、きじの胸よりとほりて、遂に天つ神のみもとに至る」(紀神代) ④「そのうるはしき色、衣(そ)よりとほりて晃(て)れり」 (紀允恭) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とまり [止まり・留まり] | 〔名詞〕 ① とまること。② 終り。果て。 ③ 最後まで連れ添うこと。また、その人。本妻。 |
② 年毎にもみぢ葉流す竜田川みなとや秋のとまりならむ(古今秋下-311) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とまり [泊り] | 〔名詞〕 ① 泊ること。宿泊。② 船着き場。港。③ 宿る場所。宿屋。 |
② 大船の泊つる泊りのたゆたひに物思ひ痩せぬ人の子故に(万2-122) ② かからむとかねて知りせば大御船泊てし泊りに標結はましを (万2-151) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とまる [止まる・留まる・泊まる] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 〔止まる・留まる〕 ア 動かなくなる。立ち止まる。 イ 取り止めになる。中止になる。 ウ あとに残る。生き残る。 エ (目や耳に)つく。印象付けられる。心が強くひかれる。 ② 〔泊まる〕 ア 船が停泊する。 イ 宿泊する。宿直する。 |
①-ア -小雨に降れば 白たへの 衣ひづちて 立ち留まり 我れに語らく-(万2-230) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とむ [止む・留む] | 〔他動詞マ行下二段〕【メ・メ・ム・ムル・ムレ・メヨ】 1-ア 進ませない。止める。 -イ 行かせないようにする。引き留める。禁じる。 -ウ あとに残す。とどめる。 -エ (「心をとむ」「目をとむ」 の形で) 心や目にとめる。関心を持つ。 2 宿泊させる。また、船を停泊させる。 |
1-ア み立たしの島を見る時にはたづみ流るる涙止めそかねつる(万2-178) 1-ア -大御馬の 口抑へ止め 御心を 見し明らめし 活道山-(万3-481) 1-イ うちひさす宮に行く子をまかなしみ留むれば苦し遣ればすべなし(万4-535) 2-明石の浦に 船泊めて 浮寝をしつつ わたつみの 沖辺を見れば-(万15-3649) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とむ [泊む] | 〔他動詞マ行下二段〕【メ・メ・ム・ムル・ムレ・メヨ】 船を停泊させる。また、宿泊させる。 |
-ゆくへを知らに 我が心 明石の浦に 船泊めて 浮寝をしつつ-(万15-3649) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とも [友・伴] | 〔名詞〕 ① 親しい仲間。友人。連れ。 ② 同一集団の人々。連中。 |
藤原の大宮仕へ生れ付くや娘子がともは羨しきろかも(万1-53) ① さ夜中に友呼ぶ千鳥物思ふとわびをる時に鳴きつつもとな(万4-621) ② -空言も 祖の名絶つな 大伴の 氏と名に負へる 大夫の伴(万20-4489) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とも [鞆] | 〔名詞〕 弓を射るとき、左の手首に結びつける革製の道具。 手首の保護や手首につけた「釧(くしろ)」の保護の為に用いる。 |
ますらをの鞆の音すなり物部の大臣盾立つらしも(万1-76) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とも | 〔接続助詞〕 ① 逆接の仮定条件を表す。たとえ~にしても。 ② 事実そうであったり、そうなるのが確実な事柄について、仮に仮定条件で表して意味を強める。「(~ではあるが)たとえ~でも。」 〔接続〕動詞・形容動詞・助動詞(動詞・形容動詞型活用)の終止形、形容詞・助動詞(形容詞型活用・打消「ず」)の連用形に付く。鎌倉時代以降は、動詞・形容動詞・助動詞(動詞・形容動詞型活用)の連体形に付く場合もある。 |
① 秋の田の穂向きの寄れる片寄りに君に寄りなな言痛くありとも (万2-114) ① 衾道を引手の山に妹を置きて山道を行けば生けりともなし(万2-212) ① 衾道を引手の山に妹を置きて山道思ふに生けるともなし(万2-215) ① 沖つ波辺波立つとも我が背子がみ船の泊り波立ためやも(万3-248) ② 居明かして君をば待たむぬばたまの我が黒髪に霜は降るとも(万2-89) ② -天のごと 振り放け見つつ 玉たすき 懸けて偲はむ 恐くありとも-(万2-199) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔終助詞〕(格助詞「と」に係助詞「も」の付いたもの。 相手の言葉に応じて同意する意を表す。もちろん~さ。~だとも。 〔接続〕活用語の終止形に付く。 |
〔参考〕 室町時代以降に用いられた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①「と」の受ける部分の意味をやわらげたり、含みを持たせたりする。 「~とも」 ② 同じ動詞・形容詞を重ねてその間に置いて、意味を強める。 〔接続〕 格助詞「と」と同じ。 ただし②の用法は、「と」では動詞の連用形+「と」に限られるが、「とも」ではシク活用形容詞の終止形も受ける。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ども | 〔接尾語〕 ①(体言に付いて)同類のものの複数を表わす。 「~ら。~いくつか。~の多く。」 ②(自然の語に付いて)謙譲の意を表わす。 ③(人物を表わす単数の体言に付いて)低く待遇し、 いやしめたり親しさを示したりする意を表わす。 |
① 山辺の御井を見がてり神風の伊勢娘子どもあひ見つるかも(万1-81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 同類の接尾語「たち・ばら」は人間だけに用いるのに対して、「ども」は人間以外の事物にも広く用いる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ども | 〔接続助詞〕接続助詞「ど」に係助詞「も」の付いたもの。 ① 逆接の確定条件。~けれども。~のに。~だが。 ② 逆接の恒常条件。たとえ~ても(やはり)。~ときでも。 〔接続〕活用語の已然形に付く。 |
① -天皇の 神の命の 大宮は ここと聞けども 大殿は -(万1-29) ① 梓弓引かばまにまに依らめども後の心を知りかてぬかも [郎女](万2-98) ① ますらをや片恋せむと嘆けども醜のますらをなほ恋ひにけり(万2-117) ① 哭沢の神社に三輪据ゑ祈れども我が大君は高日知らしぬ(万2-202) ① 去年見てし秋の月夜は照らせども相見し妹はいや年離る(万2-211) ② 梓弓引かばまにまに寄らめども後の心を知りかてぬかも(万2-98) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ともし [乏し] | 〔形容詞シク活用〕 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 ① 不十分である。少ない。② 貧しい。貧乏である。 |
① 海 山も隔たらなくに何しかも目言をだにもここだ乏しき(万4-692) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ともし [羨し] | 〔形容詞シク活用〕 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 ① その欲望がなくならない。そうしたい。② うらやましい。 ③ 珍しい。飽きることがない。 |
① 難波潟潮干のなごり飽くまでに人の見む子を我しともしも(万4-536) ① 見まく欲り来しくもしるく吉野川音のさやけさ見るにともしく (万9-1728) ②「日下江(くさかえ)の入り江の蓮(はちす)花渾身の盛り人ともしきろかも」(記下) ② 藤原の大宮仕へ生れ付くや娘子がともは羨しきろかも(万1-53) ③ 坂越えて安倍の田の面に居る鶴のともしき君は明日さへもがも (万14-3544) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 動詞「求(と)む」と関係のある語か。求めていたいさまの意から不足しているの意にも、またそれを欲している意にもなったものか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ともしびの [灯火の] | 【枕詞】灯火の明るいことから「あかし(明石)」にかかる。 | 燈火の明石大門に入らむ日や漕ぎ別れなむ家のあたり見ず(万3-255) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ともす [点す・灯す] | 〔他動詞サ行四段〕火を灯す。灯火をつける。 | 見渡せば明石の浦に燭す火のほにそ出でぬる妹に恋ふらく(万3-329) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とものうら [鞆の浦] | 【小学館「新編日本古典文学全集萬葉集 付録『地名一覧』」】 広島県福山市鞆町の海岸。停泊するには鞆港は良いが、景観を眺めるには東側の仙酔島・弁天島などの絶景が歌意に適していよう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ともに [共に] | 〔なりたち〕名詞「共(とも)」+格助詞「に」 (「と」「の」 のまたは名詞の下について)~と一緒に |
天地とともに終へむと思ひつつ仕へまつりし心違ひぬ(万2-176) -神からか ここだ貴き 天地 日月と共に 足り行かむ 神の御面と-(万2-220) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とよくに [豊国] | 〔地名〕豊前(福岡県東部)、豊後(大分県北部)の総称。 | 梓弓引き豊国の鏡山見ず久ならば恋しけむかも(万3-314) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とよはたくも [豊旗雲] | 〔名詞〕旗が靡いているような美しく大きな雲。 | 海神の豊旗雲に入日さし今夜の月夜さやけくありこそ(万1-15)→「わたつみ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注」】 「豊旗雲」は旗(吹き流し)のように横にたなびくめでたい雲。「豊」は呪的なほめ詞。「豊」の付く語はすべて呪的な讃美が籠められており、日常性と強い線を画する。 「豊葦原」「豊栄登」「豊御酒」など。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とよむ [響む・動む] | 〔中古末期ごろから「どよむ」〕 〔自動詞マ行四段〕 ① 鳴り響く。響き渡る。② 大声をあげて騒ぐ。騒ぎ立てる。 〔他動詞マ行下二段〕【メ・メ・ム・ムル・ムレ・メヨ】 鳴り響かせる。 |
〔他動詞マ行下二段〕 大和辺に君が立つ日の近づけば野に立つ鹿もとよめてそ鳴く(万4-573) 夜を長み寐の寝らえぬにあしひきの山彦響めさを鹿鳴くも(万15-3702) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とよもす [響もす] | 〔他動詞サ行四段〕 大きな声や音を立てる。鳴り響かす。 | 雨隠り物思ふ時に霍公鳥我が住む里に来鳴き響もす(万15-3804) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とら [虎] | 〔名詞〕動物の名。とら。 | -敵見たる 虎か吼ゆると 諸人の おびゆるまでに [一云 聞き惑ふまで] -(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とり- [取り-] | 〔接頭語〕(動詞に付いて)語調をととのえ、語の勢いを強める。 【例】「取り認(したた)む・取り繕(つくろ)ふ・取り賄(まかな)ふ」など」 |
-形見に置ける みどり子の 乞ひ泣くごとに 取り与ふる 物しなければ-(万2-210) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とり [鳥] | 〔名詞〕 ① 鳥類の総称。② 特に鶏。③ 特に雉。 |
① 朝日照る佐田の岡辺に泣く鳥の夜哭きかへらふこの年ころを(万2-192) ① 世間を憂しとやさしと思へども飛び立ちかねつ鳥にしあらねば (万5-897) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1 巻二 180」 頭注「住む鳥」】 記紀に、「鳥取部 (ととりべ)」「鳥甘部 (ととりかひべ)」「養鳥人 (とりかひひと)」などが宮廷に置かれていたと思われる記事がある。 律令制下ではこれが園池司の所轄になったらしく、天平十七年(745) 四月十六日付の園池司解に孔雀用の米一ヵ月分の支給を申請したものがある。 長屋王家木簡によれば、邸内で鶴が飼われていたことが知られる。ここも白鳥や鵞鳥・鶴などが放し飼いされていたのであろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とりおく [取り置く] | 〔他動詞カ行四段〕 ① しまっておく。預かっておく。 ② とりやめる。かたづける。また、葬る。 |
① 高麗錦紐の片方ぞ床に落ちにける明日の夜し来なむと言はば取り置きて待たむ (万11-2360) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とりかく [取り掛く] | 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 ① 手に取って掛ける。② 代価として支払う。③ 攻め始める。襲いかかる。 |
① -たわやめの おすひ取りかけ かくだにも 我は祈ひなむ-(万3-382) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とりがなく [鳥が鳴く・鶏が鳴く] | 【枕詞】「東(あづま)」にかかる。 | -定めたまふと 鶏が鳴く 東の国の 御いくさを 召したまひて-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻二-199 注「鶏が鳴く東の国の」】 「トリガナク」は枕詞。「東」 に冠する。掛かり方について、万葉集古義には「今按フに、こはさは鶏が鳴ぞ、やよ起キよ吾夫(アヅマ) と云意につづくなるべし」 と言うが、古典大系補注には「東国の言葉は、新村の民の言語として低く見られていた。殊に、母音の体系が大和地方と異なっていたので、その言葉は大和地方の人々には、曲がった言葉のように聞こえたのであろう。そこで、トリガナクという枕詞が東にかかることとなったのである。」 とし、「東国の言葉が解し難く鶏の鳴くように聞こえたによる」 と説いている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とりじもの [鳥じもの] | 【枕詞】 鳥のようなものの意から、「浮き」「朝立ち」「なづさひ」にかかる。 |
鳥じもの海に浮き居て沖つ波騒くを聞けばあまた悲しも(万7-1188) -白栲の 天領巾隠り 鳥じもの 朝立ちいまして-(万2-210) -稲日都麻 浦廻を過ぎて 鳥じもの なづさひ行けば-(万4-512) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とりつく [取り付く] | 〔自動詞カ行四段〕 ① すがりつく。② (霊魂などが) 乗り移る。③ 着手する。とりかかる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とりつく [取り付く] | 〔他動詞カ行下二段〕 ① 取り付ける。そこにつける。② (霊魂などを) 乗り移らせる。 |
① -さかきの枝に しらか付け 木綿取り付けて 斎瓮を-(万3-382) ② 己(おのれ)命(みこと)の和魂(にぎみたま)を八咫の鏡に取り付けて(祝詞) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とりとどこほる [取り滞る] | 〔自動詞ラ行四段〕すがって離れない。 | 衣手に取りとどこほり泣く子にもまされる我を置きていかにせむ [舎人吉年](万4-495) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とりなづ [取り撫づ] | 〔他動詞ダ行下二段〕【デ・デ・ヅ・ヅル・ヅレ・デヨ】 手に取ってなでる。大事にする。 |
やすみしし 我が大君の 朝には 取り撫でたまひ 夕には(万1-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とりむく [取り向く] | 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 手に取り、その方へ向けてさし出す。手向ける。 |
在り嶺よし対馬の渡り海中に幣取り向けて早帰り来ね(万1-62) -石田の杜の すめ神に 幣取り向けて 我れは越え行く 逢坂山を (万13-3250) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とりはく [取り矧く] | 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 弓に弦を取り付ける。 |
梓弓弦緒取りはけ引く人は後の心を知る人ぞ引く [禅師](万2-99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とりはく [取り佩く] | 〔他動詞カ行四段〕 取って腰につける。帯びる。 |
-大御身に 大刀取り佩かし 大御手に 弓取り持たし 御軍士を-(万2-199) -男さびすと 剣太刀 腰に取り佩き さつ弓を 手握り持ちて-(万5-808) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とりもつ [取り持つ・採り持つ] | 〔他動詞タ行四段〕 ① 手に持つ。 ② (「とりもちて」の転「とりもて」 の形で) 奪い取る。一緒に連れて行く。 さらって行く。 ③ 世話する。責任をもって行う。引き受けて行う。媒介する。 |
① -靡かふごとく 取り持てる 弓弭の騒き み雪降る 冬の林に-(万2-199) ① うつせみと 思ひし時に [一云 うつそみと 思ひし] 取り持ちて-(万2-210) ① 撫子が花取り持ちてうつらうつら見まくの欲しき君にもあるかも(万20-4473) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とりよろふ | 〔自動詞ハ行四段〕《上代語》語義未詳。整い備わる意か。 | 大和には 群山あれど とりよろふ 天の香具山-(万1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とる [取る・執る・採る・捕る] | 〔他動詞ラ行四段〕 ① 持つ。掴む。手にする。②捕まえる。捕える。③手に持って扱う。 ④ 収穫する。採集する。⑤自分のものにする。支配する。領有する。 ⑥ 奪う。取り上げる。没収する。⑦選び出す。採用する。⑧推量する。 ⑨(多く、「~にとりて」「~にとって」の形で)関連させる。 |
志賀の海女は軍布刈り塩焼き暇なみくしげの小櫛取りも見なくに(万3-281) ① 稲つけばかかる我が手を今夜もか殿の若子が取りて嘆かむ (万14-3478) ③ 白波の寄する礒廻を漕ぐ舟の楫取る間なく思ほえし君(万17-3983) ④ 妹がため菅の実とりに行くわれは山道に惑ひこの日暮らしつ (万7-1254) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とゑらふ | 〔自動詞ハ行四段〕《上代東国方言》[「とをらふ」の転] (波が)うねり立つ。揺れ動く。 |
行こ先に波なとゑらひ後方には子をと妻をと置きてとも来ぬ(万20-4409) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とをよる [撓よる] | 〔自動詞ラ行四段〕(若竹や弓のように) しなやかに撓(たわ)む。 | 秋山の したへる妹 なよ竹の とをよる子らは いかさまに 思ひ居れか-(万2-217) なゆ竹の とをよる御子 さ丹つらふ 我が大君は こもりくの-(万3-423) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とをらふ | 〔自動詞ハ行四段〕揺れ動く。 | -霞める時に 住吉の 岸に出で居て 釣舟の とをらふ見れば -(万9-1744) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| な | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| な | 〔副詞〕動詞の連用形の上について、動作を禁止する。 上代には下に「そ」の欠ける場合も見られる。 |
な思ひと君は言へども逢はむ時いつと知りてか我が恋ひずあらむ(万2-140) 嶋の宮上の池なる放ち鳥荒びな行きそ君いまさずとも(万2-172) 我が船は比良の湊に漕ぎ泊てむ沖辺な離りさ夜ふけにけり(万3-276) 我が背子が振り放け見つつ嘆くらむ清き月夜に雲なたなびき(万11-2677) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| な | 〔格助詞〕上代格助詞「の」の連体修飾語の用法に同じ。 | 「水門みなと」「水源みなもと」 -まなかひにもとな懸かりて安眠し寝さぬ (万5-806) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| な | 〔格助詞〕上代東国方言の「に」の転。 | 草かげの安努な行かむと墾りし道案努は行かず荒草立ちぬ(万14-3466) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| な | 〔係助詞〕「は」の転。(・・・は) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| な | 〔終助詞〕(上代) ① 自己の意志・希望を表わす。「・・しよう」 ② 他への勧誘・あつらえを示す。「(さあ・・・(し) ようよ)」 ③ 他に対する願望・期待を表す。「・・・(し) てほしい」 〔接続〕 動詞および動詞型活用の助動詞の未然形に付く。 |
① 熟田津の船乗りせむと月待てば潮もかなひぬ今は漕ぎいでな(万1-8) ① 巨勢山のつらつら椿つらつらに見つつ偲はな巨勢の春野を(万1-54) ① 秋の田の穂向きの寄れる片寄りに君に寄りなな言痛くありとも (万2-114) ① 夕さらば潮満ち来なむ住吉の浅香の浦に玉藻刈りてな(万2-121) ① 生ける者遂にも死ぬるものにあればこの世にある間は楽しくあらな (万3-352) ① 今知らす久迩の都に妹に逢はず久しくなりぬ行きて早見な(万4-771) ② 君が代も我が代も知るや岩代の岡の草根をいざ結びてな(万1-10) ③ 道の中国つみ神は旅行きもし知らぬ君を恵みたまはな(万17-3952) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| な | 〔終助詞〕 ① 感動や詠嘆の意を表わす。「なあ。・・たことだなあ。」 ② 念を押す意を表す。「・・・(だ) ね。・・・ぞ。」 |
① 大船の思ひ頼みし君が去なば我は恋ひむな直に逢ふまでに(万4-553) ① 花の色はうつりにけりないたづらに我が身世にふるながめせしまに (古春下-113) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| な | 打ち消しの助動詞「ず」の未然形の古形。 準体助詞「く」や終助詞「な」に連なる。 |
妹が見し棟の花も散りぬべしわが泣く涙いまだなくに(万5-802) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| な | 完了の助動詞「ぬ」の未然系。 | いざ桜我も散りなむひとさかり有りなば人にうきめ見えなん(古春下-77) 秋の田の穂向きの寄れる片寄りに君に寄りなな言痛くありとも(万2-114) 鳥座立て飼ひし雁の子巣立ちなば真弓の岡に飛び帰り来ね(万2-182) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| な | 〔終助詞〕強い禁止の意を表す。「・・・(する)な」 〔接続〕 動詞・助動詞の終止形に付く。 ただし「ラ変型活用」の語には連体形に付く。 |
我妹子を早見浜風大和なる我れ松椿吹かざるなゆめ(万1-73) あをによし奈良の家には万代に我れも通はむ忘ると思ふな(万1-80) 芦北の野坂の浦ゆ船出して水島に行かむ波立つなゆめ(万3-247) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 同類の禁止の表現には副詞「な」と終助詞「そ」が呼応した「な・・・そ」があるが、その方が穏やかで柔らかい言い方である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| な [菜] | 〔名詞〕葉・茎などを食用とする草の総称。 | -この岡に 菜摘ます子-(万1-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| な [名] | 〔名詞〕 ① 名前・呼び名。 ②うわさ・評判・名声。 ③ 名ばかりで実質が伴わないこと。名目。虚名。 |
① -妹が名呼びて 袖そ振りつる [一云 名のみを聞きてありえねば]-(万2-207) ① 酒の名を聖と負せし古の大き聖の言の宣しさ(万3-342) ② 玉櫛笥覆ふを安み明けていなば君が名はあれど吾が名し惜しも(万2-93) ② -妹が名呼びて 袖そ振りつる [一云 名のみを聞きてありえねば]-(万2-207) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| な [肴] | 〔名詞〕魚・鳥獣の肉・野菜など、酒・飯に添えて食べるもの。副食。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| な [魚] | 〔名詞〕食用とする魚。 | 足姫神の命の魚釣らすとみ立たしせりし石を誰れ見き [一云 鮎釣ると] (万5-873) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| な [儺] | 〔名詞〕「ついな」に同じ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| な [汝] | 〔代名詞〕対称の人名代名詞。 自分より目下の者や親しい人に対して用いる。おまえ。あなた。 |
近江の海夕波千鳥汝が鳴けば心もしのにいにしへ思ほゆ(万3-268) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なか [中・仲] | 〔名詞〕 ① 内部。うち。② 中央。真ん中。③ 中位。中等。中流。 ④ 多くのもののうちの一つ。⑤ 兄弟・姉妹のうちの二番目。⑥ 中旬。 ⑦ 男女の間柄。関係。 |
② -奇しきものか 淡路島 中に立て置きて 白波を 伊予に廻ほし-(万3-391) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ながし [長し・永し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① (距離的に) 隔たりが大きい。 ② (時間的に) 隔たりが大きい。 ③ 心がのんびりしたさま。心変わりしないさま。 |
① 人皆は今は長しとたけと言へど君が見し髪乱れたりとも [娘子](万2-124) ② -思ひ居れか 栲縄の 長き命を 露こそば 朝に置きて 夕には-(万2-217) ② 栲縄の長き命を欲りしくは絶えずて人を見まく欲りこそ(万4-707) ③ 咲く花もをそろはいとはしおくてなる長き心になほしかずけり(万8-1552) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ながす [流す] | 〔他動詞サ行四段〕 ① 流れるようにする。浮べ漂わす。 ② (涙や汗などを)こぼす。 ③ 流罪にする。左遷する。 ④ 世間に噂を広める。流布させる。 |
①-もののふの 八十宇治川に 玉藻なす 浮かべ流せれ 其を取ると-(万1-50) ① としごとにもみぢば流す竜田川水門や秋のとまりなるらむ(古今秋下-311) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ながち [長道] | 〔名詞〕「ながぢ」とも。長い道のり。遠路。 | 天離る鄙の長道ゆ恋ひ来れば明石の門より大和島見ゆ [一本云 家のあたり見ゆ](万3-256) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ながつき [長月] | 〔名詞〕「ながづき」とも。陰暦九月の異称。 | -縵にせむと 九月の しぐれの時は もみち葉を 折りかざさむと-(万3-426) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ながて [長手] | 〔名詞〕 長い道のり。=長道(ながち) |
飫宇の海の潮干の潟の片思に思ひや行かむ道の長手を(万4-539) 君が行く道の長手を繰り畳ね焼き滅ぼさむ天の火もがも(万15-3746) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なかなか [中中] | 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 ① 中途半端なさま。どっちつかずだ。 ② なまじっかだ。なまはんかだ。かえって~しないほうがよい。 |
② なかなかに人とあらずは酒壷に成りにてしかも酒に染みなむ(万3-346) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔副詞〕 ① なまじっか。② かえって。むしろ。 ③ (下に打消しの語を伴って) 容易には。とうてい。とても。 ④ 《近世語》ずいぶん。かなり。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔感動詞〕 謡曲・狂言などで、相手の言葉を受けて肯定する語。いかにも。はい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なかのみなと [中の湊] | 〔地名〕 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1巻二-220 頭注『中の湊』」】 中は讃岐国那珂郡。現在の丸亀市から琴平町にかけての一帯。 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1巻二-220 付録地名一覧」】 讃岐国那珂郡の湊。香川県丸亀市金倉町・中津町の辺り。金倉川河口に位置する。 【有斐閣「萬葉集全注巻二-220 注『中の水門』」】 中の水門は、代匠記(初稿本)に「彼国に那珂郡あり。中のみなとはそこなるへし」と言い、以後の諸注にそれがあげられている。全讃史、西讃府誌はじめ明治以降の郷土史に中津説が採用されたのである。犬養孝『万葉の風土 続』所収の「人麻呂と風土 さみねのしま」にも、中の水門は丸亀市西方、下金倉町(丸亀市内)の金倉川河口、すなわち今中津の名の残っている付近をいうとある。現在は河口東岸に工場や塩田が築堤に囲まれており、西岸には松原の公園もある。付近は、ごく遠浅で、一浬沖合の下真島まで、その三分の一は深さ一メートルを越えず、その先も四メートルを越えない浅海になっているらしい。なお、郷土史家宮武進の「万葉の中乃水門考」には、旧四条川河口の丸亀市中府町清門付近とする説が提示されている。現段階で中津説・清門説のいずれが正しいかを決定することは困難なようだ(丸亀市立図書館レファレンス係りの教示による)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ながら | 〔接続助詞〕 ① [体言、動詞の連用形などの下に付いて、そのありさまや、状態を変えないで、ある動作が行われることを表す] 「~のままで」「~のままの状態で」 ② [動詞の連用形の下に付いて、二つの動作が同時に並行して行われることを表す] 「~ながら」「~つつ」 ③ [動詞の連用形、体言、形容詞・形容動詞の語幹 (シク活用形容詞は終止形) などの下に付いて、逆接的に前後をつなぐ意を表す] 「~ても」「~のに」「~けれども」「~ものの」 ④ [体言の下に付いて、そのものの本性のままの状態である意を表す] 「~のままに」「~のままで」 ⑤ [おもに体言の下に付いて、その条件を変えず、すっかりそのままである意を表す] 「~のままで」「すっかりそのままで」 〔接続〕 体言、形容詞と形容動詞の語幹、動詞と動詞型の活用をする助動詞の連用形、助動詞「ず」の連用形、副詞に付く。活用語の連体形に付くこともある。 このうち、体言、動詞と動詞型の活用をする助動詞の連用形に付くものは上代からあるが、その他は中古になってからのものである。 |
① 夏の夜はまだ宵ながら明けぬるを雲のいづこに月やどるらむ(古今夏-166) ②-思ひ延べ 嬉しびながら 枕付く 妻屋のうちに 鳥座結ひ-(万19-4178) ④-皇子ながら 任したまへば 大御身に 大刀取り佩かし 大御手に -(万2-199) ④-天の日継と 神ながら 我が大君の 天の下-(万19-4278) ⑤ 萩の露玉にぬかむと取れば消(け)ぬよし見む人は枝ながら見よ (古今秋上-222) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【文法】 (1)上代では、「④」の意味で一般に使われた。語源は、連体修飾語をつくる上代の格助詞「な」(「海(う)な原」「目(ま)な子」などの複合名詞の中に残っている)に、そのままの状態であることを表す形容名詞「から」が付いたものと考えられている。「④」の意味が中古には「⑤」になる。なお「④・⑤」を接尾語とする説もある。 (2) 中古になると、各種の語に付くようになったが、用法の上でも二つの変化が起こった。 [ア:逆接の発生] 上代は「④」の意味が普通だったが、末期に「①」「②」の意味が発生した。⇒ (例歌右項) 中古になるとこの用法が多くなり、「③」の逆接へと発展した。つまり、「~のままで」の意味に「一方では」の意味が加わり「~のままであるが、一方では」となったと考えられる。 ⇒ (例歌右項) この逆接が「ながら」の中心的な用い方となって現代語に至っている。 [イ:「つつ」と似た意味の発生] 「~のままで」の意味からは、感情を表す用言(嘆く・うれし、など)に続ける用法が生まれた。もっとも古い例は、「②」の「万葉歌」である。 【文法例歌】 (2)「ア」 弥彦神の麓に今日らもか鹿の伏すらむ皮衣着て角つきながら(万16-3906) 日は照りながら(=照っているのに)雪のかしらにふりかかりけるを詠ませ給ひける (古今春上・詞書-8) (2)「イ」 -思ひ延べ 嬉しびながら 枕付く 妻屋のうちに 鳥座結ひ-(万19-4178) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ながらふ [永らふ・存ふ] | 〔自動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 ① 生きながらえる、長生きする。② 長続きする |
① ながらへばまたこの頃や忍ばれむ憂しと見し世ぞ今は恋しき (新古雑歌下-1843) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ながらふ [流らふ] | 〔自動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 ① 絶えずのどかに降る。② 経て行く、伝わる。 |
① うらさぶる心さまねしひさかたの天のしぐれの流らふ見れば(万1-82) ① 流らふる妻吹く風の寒き夜に我が背の君はひとりか寝らむ(万1-59) ② -世間は 常なきものと 語り継ぎ 流らへ来たれ -(万19-4184) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なかりせば | 〔なりたち〕 形容詞「無し」の連用形「なかり」+過去助動詞「き」の未然形「せ」+接続助詞「ば」 なかったならば。 |
ちはやぶる神の社しなかりせば春日の野辺に粟蒔かましを(万3-407) 世の中にたえて桜のなかりせば 春の心はのどけからまし(古今春上-53) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ながる [流る] | 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 ① 水などが低い方へ移り動く。流れる。 ② (涙・汗・血などが) 流れ落ちる。したたる。 ③ 水などに運ばれて行く。漂いながら行く。 ④ (月日などが) しだいに移って行く。(時が) 過ぎる。 ⑤ 次第に広まる。流布する。⑥ 順に次へ及ぶ。次々にめぐる。 ⑦ 生きながらえる。⑧ 流罪に処せられる。さすらう。 |
① 明日香川しがらみ渡し塞かませば流るる水ものどにかあらまし [一云 水の淀にかあらまし](万2-197) ① 逢坂の関に流るる岩清水 いはで心におもひこそすれ(古今恋一-537) ④ きのふといひけふとくらしてあすか川 流れて速き月日なりけり (古今冬-341) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なぎさ [渚・汀] | 〔名詞〕(海・湖・川などの) 水際。波打ち際。 | 古への古き堤は年深み池のなぎさに水草生ひにけり(万3-381) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なきさわのもり [哭沢の神社] | 〔名詞〕 | 哭沢の神社に三輪据ゑ祈れども我が大君は高日知らしぬ(万2-202) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻二-202」 注「哭沢の神社」】 「哭」の字既出(一五五歌)-「哭」は、犬がなき叫ぶ意を本義とする文字。転じて人の哀しんで泣き叫ぶ意を表す。-声をあげて泣くことをあらわす文字。 哭沢の神社は、香久山と埴安池をへだてた対岸にあった。いま橿原市木之本町に属し、畝尾都多木神社という。 祭神は泣沢女神で、古事記によれば、イザナキノミコトがイザナミノミコトの死を悲しんで泣いた時の涙になりませる神である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なきわたる [鳴き渡る] | 〔自動詞ラ行四段〕鳴きながら飛んでゆく。 | いにしへに恋ふる鳥かも弓絃葉の御井の上より鳴き渡り行く(万2-111) 桜田へ鶴鳴き渡る年魚市潟潮干にけらし鶴鳴き渡る(万3-273) 霍公鳥こよ鳴き渡れ燈火を月夜になそへその影も見む(万18-4078) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なく [泣く・哭く] | 〔自動詞カ行四段〕(人が) 涙を流し、声をあげる。 | 朝日照る佐田の岡辺に群れ居つつ我が泣く涙やむ時もなし(万2-177) 我妹子が我れを送ると白栲の袖漬つまでに泣きし思ほゆ(万11-2523) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なく [鳴く] | 〔自動詞カ行四段〕(鳥・虫・獣が) 声を出す。 | 大和には鳴きてか来らむ呼子鳥象の中山呼びぞ越ゆなる(万1-70) 朝日照る佐田の岡辺に鳴く鳥の夜哭きかへらふこの年ころを(万2-192) -玉たすき 畝傍の山に 鳴く鳥の 声も聞こえず 玉桙の 道行き人も-(万2-207) かはづ鳴く清き川原を今日見てはいつか越え来て見つつ偲はむ(万7-1110) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なく [泣く・哭く] | 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・コヨ】 [上代東国方言] 泣かせる。 |
しまらくは寝つつもあらむを夢のみにもとな見えつつ我を音し泣くる (万14-3490) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なく | 〔打消しの助動詞「ず」のク語法〕 「~ないこと」 |
-岩床と 川の氷凝り 寒き夜を 息むことなく通ひつつ 作れる家に -(万1-79) 山吹の立ちよそひたる山清水汲みに行かめど道の知らなく(万2-158) ももしきの大宮人の熟田津に船乗りしけむ年の知らなく(万3-326) 天の川去年の渡り瀬荒れにけり君が来まさむ道の知らなく(万10-2088) 白真砂御津の埴生の色に出でて言はなくのみぞ我が恋ふらくは(万11-2734) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なくこなす [泣く子なす] | 【枕詞】「慕ひ」「言(こと)だに問はず」「音(ね)のみし泣かゆ」などにかかる。 | -佐保の山辺に 泣く子なす 慕ひ来まして しきたへの 家をも作り-(万3-463) -筑紫の国に 泣く子なす 慕ひ来まして 息だにも いまだ休めず-(万5-798) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なぐさむ [慰む] | 〔自動詞マ行四段〕 気持ちがおさまる。心が安まる。気が紛れる。 〔他動詞マ行四段〕 ① 心を楽しませる。気分を晴らす。 ② からかう。 〔他動詞マ行下二段〕【メ・メ・ム・ムル・ムレ・メヨ】 ③ 気持ちをなごませる。心を楽しませる。 ④ なだめる。また、ねぎらう。 |
③ -夜床も荒るらむ [一云 荒れなむ] そこ故に 慰めかねて-(万2-194) ③ 「猛き武士の心をもなぐさむるは歌なり」(古今仮名序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なぐさもる [慰もる] | 〔下二段動詞「慰む」 の連体形「なぐさむる」 の転〕慰める。 | -か行きかく行き 大船の たゆたふ見れば 慰もる 心もあらず-(万2-196) -我が恋ふる 千重の一重も 慰もる 心もありやと 我妹子が-(万2-207) 草枕 旅の憂へを 慰もる こともありやと 筑波嶺に 登りて見れば-(万9-1761) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なくに | [打消の助動詞「ず」の「ク語法 なく」+助詞「に」] 「に」には、格助詞、断定の助動詞「なり」の連用形、接続助詞などの諸説がある。 ① ~ (し) ないことだなあ。 ② ~ (し) ないことだのに。~ (しないのに) 。 ③ ~ (し) ないことだから。~ (し) ない以上は。(逆接の詠嘆の用法) |
① 滝の上の三船の山に居る雲の常にあらむと我が思はなくに(万3-243) ① いかにして忘れむものぞ我妹子に恋はまされど忘らえなくに (万11-2602) ② 吾が大君ものな思ほし皇神の継ぎて賜へる我なけなくに(万1-77) ② -思ふそら 安けなくに 嘆くそら 苦しきものを み空行く-(万4-537) ② み山には松の雪だに消えなくに都は野辺の若菜つみけり(古今春上-18) ③ 軽の池の浦廻行き廻る鴨すらに玉藻の上にひとり寝なくに(万3-393) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なくはし [名細し・名美し] | 〔形容詞シク活用〕[「なぐはし」とも] 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 〔なりたち〕 [「名」+形容詞「くはし」。「くはし」はすぐれてよい、も意味する] 「名が美しい」「名高い」 |
-よろしなへ 神さび立てり 名ぐはしき 吉野の山は かげともの-(万1-52) -島は多けど 名ぐはし 狭岑の島の 荒磯面に 廬りて見れば-(万2-220) 名ぐはしき印南の海の沖つ波千重に隠りぬ大和島根は(万3-306) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なげかふ [嘆かふ・歎かふ] | 〔上代語。動詞「嘆く」の未然形+反復・継続の助動詞「ふ」〕 嘆き続ける。嘆きに嘆く。 |
-夕には 入り居嘆かひ わき挟む 子の泣くごとに 男じもの-(万3-484) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なげき [嘆き・歎き] | 〔名詞〕[「ながいき (長息)」の転 ] ① ためいき。嘆息。② 悲しみ。悲嘆。③ 嘆願。哀願。愁訴。 |
① 火遠理命 (ほをりのみこと) ・・・大きなるなげきし給ひき(記・上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なげきのきり [なげきの霧 (きり)] | 嘆いてため息をつくときに出る息を、霧にたとえた語。 | 沖つ風いたく吹きせば我妹子が嘆きの霧に飽かましものを(万15-3638) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なげく [嘆く・歎く] | 〔自動詞カ行四段〕 ① 嘆息する。溜息をつく。② 悲しむ。悲しんで泣く。 ③ 嘆願する。強く望む。祈る。 |
① ますらをや片恋せむと嘆けども醜のますらをなほ恋ひにけり(万2-117) ① 朝ぐもり日の入り行けばみ立たしの島に下り居て嘆きつるかも(万2-188) ① 君が行く海辺の宿に霧立たば我が立ち嘆く息と知りませ(万15-3602) ③ 天地を嘆き祈ひ祷み幸くあらばまたかへり見む志賀の唐崎(万13-3255) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なけなくに [無けなくに] | 〔なりたち〕 形容詞「無し」の上代の未然形「なけ」+打消の助動詞「ず」のク語法「なく」+助詞「に」。 「ないわけではないのに」「あるのに」 【参考】 「に」は、格助詞、断定の助動詞「なり」の連用形、接続助詞などの諸説がある。 |
吾が大君ものな思ほしそ皇神の副へて賜へる我がなけなくに(万1-77) 我が背子は物な思ひそ事しあらば火にも水にも我れなけなくに(万4-509) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なごし [和し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① なごやかである。穏やかである。 ② やわらかである。 |
② 蒸し衾なごやが下に臥せれども妹とし寝ねば肌し寒しも(万4-527) [「なご」は「なごし」の語幹] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なごり [名残] | 〔名詞〕[「波残り」の転か] ① 物事の過ぎ去ったあと、なおその気配・様子などの残ること。余情。余韻。 ② 別れたあとで、面影などが心に残って忘れられないこと。また、その面影。 ③ 残ること。残り。残余。遺産。 ④ 忘れ形見。遺児。子孫。⑤ 別れ。⑥ 最後。おわり。 ⑦ (連歌・俳諧用語) 連歌・連句一巻は四枚または二枚の懐紙の裏表に書くが、その最後の懐紙一折りの称。名残の折り。 |
① 難波潟潮干のなごり飽くまでに人の見む子を我しともしも(万4-536) ① 夕されば君来まさむと待ちし夜のなごりぞ今も寐ねかてにする(万11-2593) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なし [無し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① 存在しない。ない。いない。② 生きていない。この世にない。 ③ 不在である。留守だ。④ またとない。比類が無い。 ⑤ ないも同然である。世間から見捨てられている。 |
① ―石見の海 角の浦廻を 浦なしと 人こそ見らめ― (万2-131) ① 東のたぎの御門に侍へど昨日も今日も召す言もなし(万2-184) ① -みどり子の 乞ひ泣くごとに 取り与ふる 物しなければ-(万2-210) ② 風早の美穂の浦廻の白つつじ見れどもさぶしなき人思へば [或云 見れば悲しもなき人思ふに](万3-437) ③ 言清くいたくもな言ひそ一日だに君いしなくは堪へ難きかも(万4-540) ③ 老いらくの来むと知りせば門鎖してなしとこたへて逢はざらましを (古今雑上-895) ⑤ 衾道を引手の山に妹を置きて山道を行けば生けりともなし(万2-212) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔補助形容詞ク活用〕 形容詞型・形容動詞型活用の語の連用形、および体言に続く断定の助動詞「なり」の連用形「に」、またこれらに係助詞の付いた形に付いて、否定の意を表す。 ~ (で)ない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -なし | 〔接尾ク型〕 (名詞、形容詞の語幹などに付いて)意味を強め、「~の状態である」の意の形容詞をつくる。 |
【例語】 いときなし・いとけなし・いらなし・後ろめたなし・おぼつかなし・しどけなし・むくつけなし。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なす [寝す] | 〔自動詞サ行四段〕 [下二段動詞「寝(ぬ)」に上代の尊敬の助動詞「す」が付いたものの転] 「寝(ぬ)」の尊敬語。おやすみになる。 |
沖つ波来寄する荒礒をしきたへの枕とまきて寝せる君かも(万2-222) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞サ行四段〕[「寝(ぬ)」の他動詞形] 寝かせる。眠らせる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なす [鳴す] | 〔他動詞サ行四段〕鳴らす。 | -整ふる 鼓の音は 雷の 声と聞くまで 吹き鳴せる 小角の音も-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -なす | 〔接尾語〕《上代語》「名詞」まれに「動詞の連体形」について、 「~のように」「~のような」の意を表す。 |
綜麻形の林のさきのさ野榛の衣に付くなす目につく吾が背(万1-19) -矢の繁けく 大雪の 乱れて来れ [一云 霰なす そちより来れば]-(万2-199) -鹿じもの い這ひ拝み 鶉なす い這ひもとほり 恐みと 仕へ奉りて-(万3-240) 常磐なす岩屋は今もありけれど住みける人そ常なかりける(万3-311) 相模道の余綾の浜の真砂なす子らは愛しく思はるるかも(万14-3389) 鳴る瀬ろにこつの寄すなすいとのきて愛しけ背ろに人さへ寄すも(万14-3570) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なす [為す・成す] | 〔他動詞サ行四段〕 ① つくる。こしらえる。② 行う。する。 ③ (あるものを他のものの代わりに)用いる。 ④ あるものを変えて他のものにする。 ⑤ (役・位などに)任ずる。 ⑥ (動詞の連用形に付く場合) → 【為す】〔他動詞サ行四段〕(動詞の連用形の下に付いて) 「ことさら~・特に~・いかにも~であるように~」の意を表す。 |
③ -廬りて見れば 波の音の 繁き浜辺を しきたへの 枕になして-(万2-220) ③ -高山を 隔てになして 沖つ藻を 枕になし ひむし羽の-(万13-3350) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なすきやま [名次山] | 〔地名〕 | 我妹子に猪名野は見せつ名次山角の松原いつか示さむ(万3-282) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-279 注『名次山』」】 兵庫県西宮市名次(なつぎ)町の丘陵地帯。 「次」の字は「珠手次(タマダスキ)」(1・五) などに見え、スキと訓まれ、天武紀五年の訓注に「次、此云須岐(スキ)也」とある。 スクは四段動詞で、次に続く、次から次へ送る、の意で、「次」の字自体の意味である。スギとかツギとかの発音の変化によってできた語ではない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なぞ [何ぞ] | 〔代名詞「何」+係助詞「ぞ」=「なにぞ」の転「なんぞ」の撥音「ん」の表記されない形〕① (文末に用いて) なぜか。どうしてか。 ② 〔副詞〕 (語感:ある事態の生じたことに関して納得できない気持ちからその理由を問うという感じ) ア 疑問の意を表す。なぜか。どうして。 イ 反語の意を表す。どうして~か(いや、そうではない)。 〔語法〕 文中にある場合、これを受ける活用語は係り結びで連体形になる。 |
②-ア 一日には千重波しきに思へどもなぞその玉の手に巻き難き(万3-412) ②-ア 秋の夜を長みにかあらむなぞここば寐の寝らえぬもひとり寝ればか(万15-3706) ②-イ 君なくはなぞ身装はむ櫛笥なる黄楊の小櫛も取らむとも思はず(万9-1781) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なづく [名付く] | 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】名をつける。命名する。 | -名付けも知らず 奇しくも います神かも 石花の海と 名付けて-(万3-322) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なつくさ [夏草] | 〔名詞〕夏に生い茂る草。 | このころの恋の繁けく夏草の刈り掃へども生ひしくごとし(万10-1988) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なつくさの [夏草の] | 【枕詞】 夏草の状態や、それを刈る、また茂る場所などから、 「思ひ萎(しな)ゆ」「繁し」「深し」「かりそめ」、 また地名「野島」「あひね」などにかかる。 |
-いや高に 山も越え来ぬ 夏草の 思ひ萎へて 偲ふらむ-(万2-131) -夏草の 思ひしなえて 夕星の か行きかく行き 大船の-(万2-196) かれはてん後をば知らでなつくさの深くも人の思ほゆるかな-(古今恋四-686) -なつくさのあひねの浜の-(紀下) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なづさふ | 〔自動詞ハ行四段〕 ① 水に浮かぶ。浮き漂う。水に浸る。② なつく。馴れ親しむ。 |
① やくもさす出雲の児らが黒髪は吉野の川の沖になづさふ(万3-433) ① 山の端に月傾けば漁りする海人の燈火沖になづさふ(万15-3645) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なつの [夏野] | 〔名詞〕夏草が生い茂っている野。夏の季節の野。〔季語:夏〕 | 夏野行く小鹿の角の束の間も妹が心を忘れて思へや(万4-505) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なつみ(のかは) [夏美(の川)] | 〔地名〕 | 吉野なる夏実の川の川淀に鴨そ鳴くなる山影にして(万3-378) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻三-375」 頭注『夏実』】 奈良県吉野郡吉野町菜摘(なつみ)の地。宮滝から約一キロ東の上流。 なお原文は「夏実」「夏身」「夏箕」 と書かれ、それら「実」「身」「箕」 は乙類「ミ」を表す訓仮名で、現行の「菜摘」の表記は上代語の例に合わない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なづむ [泥む] | 〔自動詞マ行四段〕 ① 行悩む。難渋する。② 悩みわずらう。③ こだわる。執着する。 ④ ひたすら思い焦がれる。ひたすら打ち込む。 |
① -人の言へば 岩根さくみて なづみ来し よけくもそなき-(万2-210) ① -まして恋しみ 雪消する 山道すらを なづみぞ我が来る(万3-385) ① -大空ゆ通ふ我れすら汝がゆゑに天の川道をなづみてぞ来し(万10-2005) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なでしこ [撫子・瞿麦] | 〔名詞〕 ① 「秋の七草」 の一つ。初秋に淡紅色の花を開く。唐撫子(からなでしこ=石竹) を含めて言うこともあるが、普通は河原撫子(=大和撫子) をいう。 ② 「襲(かさね)の色目」 の名。表は紅梅、裏は青、または薄紫色。夏に用いる。 ③ いとし子。愛児。多く「①」に掛けていう。 ④ 紋所の名。「①」の花を図案化したもの。 |
① なでしこがその花にもが朝な朝な手に取り持ちて恋ひぬ日なけむ(万3-411) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| など | 〔副詞〕 ① [疑問の意] どうして。なぜ。原因や理由を問う。 ② [反語の意] どうして~か、(いや、~ない)。 |
-しじに生ひたる なのりそが などかも妹に 告らず来にけむ(万4-512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ななのさかしきひと [七人の賢しき人] |
竹林の七賢人。 中国晋の時代に、世俗をさけて竹林に集まり、清談したという七人の賢者。 |
古の七の賢しき人たちも欲りせしものは酒にしあるらし(万3-343) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【「萬葉集全注巻三-340 注『七の賢しき人たち』」】 竹林の七賢人。『世説新語(せせつしんご)』に、晋の阮籍(げんせき)・□(秫の下に山)康(けいこう)・山濤(さんとう)・劉伶(りゅうれい)・阮咸(げんかん)・向秀(こうしゅう)・王戎(おうじゅう) の七人の隠士が竹林で、酒を交わし、琴を弾じ、清談にふけった逸話(任誕篇) をさす。「タチ」は敬称の接尾語。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ななふすげ [七ふ菅] | 【「萬葉集全注巻三-420 注『七ふ菅』」】 「ふ」 は「節・編み目」 の意(14・三五二四)。七節もある長い菅の意という。菅は「天つ菅曽(すがそ)を本刈り断ち末刈り切りて云々」 と大祓詞(おおはらえのことば) にあるように、「祓へ」 の具として用いられた。祓えは元来、罪(過失と犯罪をすべていう) を犯した時、祓物(はらえつもの) を出して贖うことであった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なに [何] | 〔代名詞〕 不定称の指示代名詞。名前や実体の分からない物事をさす。なにもの。何事。 |
潮干なば玉藻刈りつめ家の妹が浜づと乞はば何を示さむ(万3-363) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔副詞〕疑問・反語を表す。なぜ(~か)。なにゆえ(~か)。 | 今更に何をか思はむうちなびく心は君に寄りにしものを(万4-508) 春霞みなにかくすらん さくら花ちるまをだにもみるべきものを(古今春下-79) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔感動詞〕念をおすために問い返す語。なんだって。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なにおふ [名に負ふ] | 〔なりたち〕[名詞「な」+格助詞「に」+四段動詞「負ふ」] ① 名として持つ。 ② 有名である。評判である。 |
貞観の御時、「万葉集はいつばかりつくれるぞ」と 問はせたまひければ、よみてたてまつりける 文屋ありすゑ ① 神無月時雨ふりおける楢の葉の名におふ宮のふるごとぞこれ (古今雑下-997) ②これやこの大和にしては我が恋ふる紀路にありといふ名に負ふ背の山 (万1-35) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なにか [何か] | 〔なりたち〕[代名詞「何」+係助詞「か」] 文末は連体形で結ぶ。 疑問にも反語にも用いる。「なにが~か・なにを~か」 |
よの中はなにか常なるあすか川 昨日の淵ぞ今日は瀬になる(古今雑下-933) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔なりたち〕[副詞「何」+係助詞「か」] 文末は連体形で結ぶ。 ① 疑問を表す。「なぜ~か・どうして~か」 ② 反語を表す。「どうして~か(いや、~ない)」 |
① -春野焼く 野火と見るまで 燃ゆる火を 何かと問へば 玉鉾の -(万2-230) ① あしひきの山も近きを霍公鳥月立つまでに何か来鳴かぬ(万17-4007) ② いのちだに心にかなふものならば なにか別れのかなしからまし(古今離別-387) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なにしか [何しか] | (原因・理由に関する疑問に用いて) どうして~か。なぜ~か。 〔成り立ち〕副詞「何」+副助詞「し」+係助詞「か」。 |
神風の伊勢の国にもあらましを何しか来けむ君もあらなくに(万2-163) 朝月の日向黄楊櫛古りぬれど何しか君が見れど飽かざらむ(万11-2505) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なには(のくに) | 〔地名〕現在の大阪市およびその周辺の地域。 | -おしてる 難波の国に あらたまの 年経るまでに-(万3-446) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なにはえ [難波江] | 〔地名〕「歌枕」 今の大阪市付近の海の古称。「難波潟(なにはがた)」とも。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なにはがた [難波潟] | 〔地名〕歌枕「なにはえ」に同じ。 | 難波潟潮干なありそね沈みにし妹が姿を見まく苦しも(万2-229) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なにはゐなか [難波田舎] | 昔こそ難波田舎と言はれけめ今は都引き都びにけり(万3-315) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-312 注『難波田舎』」】 平城京の都人が難波を軽蔑して「田舎」と言ったもので、都以外は皆「田舎」である。したがって、難波という田舎、長岡という田舎(これは伊勢物語での用例)の意である。柳田国男によれば、「ゐなか」とは、田があって人が生活するところの意(「地名の研究」『定本柳田国男集』20) という。対馬島の久根村には、久根浜と久根田舎との二つの大字があって、久根浜は海岸に面した場所、久根田舎は田があり人が耕作している箇所をいう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なにはをとこ | 【小学館「新編日本古典文学全集萬葉集 577頭注『難波をとこ』」】 使いに来た摂津職の若い官人を難波田舎の漁師並みの鄙人と見なしていう。戯笑的な口ぶりが感じられる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なのりそ [莫告藻・神馬藻] | 〔名詞〕「莫告藻(なのりそも)」 「ほんだわら(=海藻ノ名)」の古名。正月の飾りや食用とした。 歌では多く「な告(の)りそ(=人ニ告ゲルナ)」 に掛ける。 |
浜藻をなづけてなのりそもと謂ふ(弁恭紀) みさご居る磯廻に生ふるなのりその名は告らしてよ親は知るとも(万3-365) 沖つ波寄する荒礒のなのりそは心のうちに障みとなれり(万7-1399) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なのりその [莫告藻の] | 【枕詞】「名」 にかかる。 | -深海松の 見まく欲しけど なのりその おのが名惜しみ 間使も-(万6-951) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なば | 〔なりたち〕[完了助動詞「ぬ」の未然形+接続助詞「ば」] ~してしまったら。~たならば。 |
-立ち向ひしも 露霜の 消なば消ぬべく 行く鳥の 争ふはしに-(万2-199) 妹が家に咲きたる花の梅の花実にし成りなばかもかくもせむ(万3-402) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なはのうら [縄の浦] | 〔地名〕 | 縄の浦に塩焼く火のけ夕されば行き過ぎかねて山にたなびく(万3-357) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兵庫県相生市那波(なば)の海岸。講義に「如何にも海と山との相迫れる地にして、この歌にいへるに通へれば、或はこの地ならんか。 この地方製塩に名高き地なれば由ありと思はる」と述べている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なばり [隠り] | 〔名詞〕隠れること。多く、伊賀(三重県)の地名・名張にかける。 | 我が背子はいづく行くらむ沖つ藻の名張の山を今日か越ゆらむ(万1-43) 宵に逢ひて朝面無み名張にか日長き妹が廬りせりけむ(万1-60) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なばりのやま [名張の山] | 三重県名張市山。「孝徳紀」に、畿内・畿外の境とある。 | 我が背子はいづく行くらむ沖つ藻の名張の山を今日か越ゆらむ(万1-43) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻第一-43 名張の山 今日か越ゆらむ」注】 名張の山を越えたことを気遣うのは、名張が大和の東限で、この地の山を越えると異郷伊賀の国だったからである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なびかふ [靡かふ] | 〔「なびく」 の継続態〕 自動詞「なびく」 の未然形「なびか」 に反復・継続の助動詞「ふ」 反復・継続の助動詞「ふ」(四段型) は、 ① 動作の反復の意を表す。何度も~する。しきりに~する。 ② 動作の継続の意を表す。~しつづける。 |
② -靡かひし 嬬の命の たたなづく 柔肌すらを 剣太刀 -(万2-194) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1 万葉集巻二」 頭注「なびかひし」】 「ナビカフ」 は「ナビク」 の継続態だが、「語ラフ・戦フ」 が「語リアフ・叩キアフ」 の約であるように「ナビキ合フ」 の原義が生きている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なびきぬ [靡き寝] | 〔自動詞ナ行下二段〕【ネ・ネ・ヌ・ヌル・ヌレ・ネヨ】 寄り添って寝る。そば近く寄って寝る。 |
白たへの 袖さし交へて なびき寝し 我が黒髪の ま白髪に-(万3-484) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なびく [靡く] | 〔自動詞カ行四段〕 ① (風・波などの力におされて) 横に倒れ伏したように揺れる。 (煙などが) 横に流れる。 ② 心を寄せる。服従する。 |
① -夏草の 思ひ萎へて 偲ふらむ 妹が門見む 靡けこの山(万2-131) ① -下つ瀬に 打橋渡す 石橋に 一に云ふ「石なみに」生ひなびける-(万2-196) ② -靡かひし 嬬の命の たたなづく 柔肌すらを 剣太刀 -(万2-194) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 ① 横に倒れさせる。横になびかせる。 ② 自分の意に従わせる。 |
① おほならば誰が見むとかもぬばたまの我が黒髪を靡けて居らむ(万11-2537) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なふ | 〔助詞特殊型〕上代東国方言 【ナハ(ナバ)・〇・ナフ・ナヘ・ナヘ・〇】 打消しの意を表す。~ない。 〔接続〕動詞の未然形に付く。なへ 【参考】 口語の打消しの助動詞「ない」の原形かといわれる。 【文法】 連体形の「なへ」は次のように用いられ、まれに「のへ」の形も現れる。 |
会津嶺の国をさ遠み逢はなはば偲ひにせもと紐結ばさね(万14-3445) 武蔵野のをぐきが雉立ち別れ去にし宵より背ろに逢はなふよ(万14-3392) まを薦の節の間近くて逢はなへば沖つま鴨の嘆きぞ我がする(万14-3545) 〔例〕 「麻久良我(=地名か)の古河の渡りの韓楫(カラカヂ)の音高しもな(=噂が高いことだな)寝なへ児ゆゑに(=共寝しない子のせいで)」 「遠しとふ(=という)故奈(こな)の白嶺に逢ほ時(しだ) (=逢う時) も逢はのへ時 (=逢わない時) も汝(な)にこそ寄され (=関係があるといわれるのに)」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なぶ [靡ぶ] | 〔他動詞バ行下二段〕【ベ・ベ・ブ・ブル・ブレ・べヨ】 なびかせる。 | -安騎の大野に 旗すすき 小竹を押しなべ 草枕 旅宿りせす(万1-45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なへ [苗] | 〔名詞〕 ① 種子から発芽してまもない時期の草木。特に、人工的に栽培する植物が多い。 ② 稲の苗。さなえ。 |
春霞春日の里の植ゑ子水葱苗なりと言ひし枝はさしにけむ(万3-410) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なへ | 〔接続助詞〕上代語 一つの事柄と同時に他の事柄が存在・進行する意を表す。 ~するとともに。~するにつれて。~するちょうどそのときに。 〔接続〕活用語の連体形につく。 |
雲の上に鳴きつる雁の寒きなへ萩の下葉はもみちぬるかも(万8-1579) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 「なべ」 と濁音であったとする説もある。多く、格助詞「に」に付いた「なへに」の形で用いられる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なへに | 〔接続助詞〕《上代語》 [接続助詞「なへ」に格助詞「に」の付いたもの] 一つの事柄と同時に他の事柄が存在・進行する意を表す。 「~するとともに」、「~するにつれて」、 「~するとちょうどそのときに」。 |
-みあらかは 高知らさむと 神ながら 思ほすなへに 天地も -(万1-50) 黄葉の散りゆくなへに玉梓の使を見れば逢ひし日思ほゆ(万2-209) 鴬の音聞くなへに梅の花我家の園に咲きて散る見ゆ [對馬目高氏老] (万5-845) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なほ [尚・猶] | 〔副詞〕 ① 前と同じ状態で。やはり。依然として。 ② そのまま何もしないでいるさま。 ③ さらに。もっと。いっそう。④ なんといっても。 |
① ますらをや片恋せむと嘆けども醜のますらをなほ恋ひにけり(万2-117) ① 黙居りて賢しらするは酒飲みて酔ひ泣きするになほ及かずけり(万3-353) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なまよみの | 【枕詞】「甲斐(かひ)」 にかかる。 (かかり方未詳) | なまよみの 甲斐の国 うち寄する 駿河の国と こちごちの 国のみ中ゆ-(万3-322) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なみ [波・浪] | 〔名詞〕 ① 水面に立つ波。 ② でこぼこや起伏のあるものを波にたとえて」いう。 ③ (年とって肌に生じる) しわのたとえ。 |
① -荒磯面に 廬りて見れば 波の音の 繁き浜辺を しきたへの -(万2-220) ② 天の海に雲の波立ち月の舟星の林に漕ぎ隠る見ゆ(万7-1072) ③ -年ごとに鏡のかげに見ゆる、雪と波とを嘆き-(古今仮名序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なみ [並み] | 〔名詞〕 ① 並び。列。続き。② 同類。同列。その類。③ 共通の性質。共通の癖。 |
① -さはにあれども 山なみの よろしき国と 川なみの-(万6-1054) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 普通だ。世間並みだ。 |
若鮎釣る松浦の川の川なみの並にし思はば我れ恋ひめやも(万5-862) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なみ [無み] | 〔なりたち〕形容詞「無し」の語幹「な」+原因・理由を表す接尾語「み」 ないために。ないので。 |
-道行き人も ひとりだに 似てし行かねば すべをなみ 妹が名呼びて-(万2-207) 志賀の海女は軍布刈り塩焼き暇なみくしげの小櫛取りも見なくに(万3-281) -草枕 旅にしあれば ひとりして 見る験なみ 海神の-(万3-369) 若の浦に潮満ち来れば潟をなみ葦辺をさして鶴鳴き渡る(万6-924) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なみだ [波] | 〔名詞〕《上代は「なみた」 とも》涙。 | 朝日照る佐田の岡辺に群れ居つつ我が泣く涙やむ時もなし(万2-177) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なみだぐまし [涙ぐまし] | 〔形容詞シク活用〕 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 涙が自然にこぼれてうるようである。 |
妹と来し敏馬の崎を帰るさにひとりし見れば涙ぐましも(万3-452) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なみだぐむ [涙ぐむ] | 〔自動詞マ行四段〕目に涙を浮かべる。泣きそうになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なみたち [並み立ち] | 〔名詞〕並んで立つこと。 | -二神の 貴き山の 並み立ちの 見が欲し山と 神代より-(万3-385) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なみのうへ [波の上] | 〔名詞〕海上。海面。 | -楫の音しつつ 波の上を い行きさぐくみ 岩の間を い行きもとほり-(万4-512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なむ [並む] | 〔自動詞マ行四段〕 並ぶ。連なる。 |
松の木の並みたる見れば家人の我れを見送ると立たりしもころ (万20-4399) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞マ行下二段〕【メ・メ・ム・ムル・ムレ・メヨ】 並べる。 |
たまきはる宇智の大野に馬並めて朝踏ますらむその草深野(万1-4) -ももしきの 大宮人は 舟並めて 朝川渡る-(万1-36) -高光る 我が日の皇子の 馬並めて み狩り立たせる 若薦を-(万3-240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なむ | 〔なりたち〕[完了の助動詞「ぬ」の未然形「ぬ」+推量の助動詞「む」] ① その事態の実現を強く推量する意を表す。 「~てしまうだろう」「きっと~であろう」 ② その事態の実現への強い意志を表す。 「~てしまおう」「きっと~しよう」 ③ その事態の実現を強く望む意を表す。 「~てしまいたい」「~たいくらいだ」 ④ 当然・適当の意を表す。 「~するのがよい」「~すべきだ」 ⑤ 可能性に対する推量を表す。 「~することができよう」 ⑥ (多く「なむや」の形で、全体で) 勧誘・婉曲な命令を表す。 「~たらどうだ」「~てくれないか」 ⑦ その事態が実現したらと仮定する意を表す。 「~としたら」「~てしまったなら」 |
① 夕さらば潮満ち来なむ住吉の浅香の浦に玉藻刈りてな(万2-121) ① -ぬばたまの 夜床も荒るらむ [一云 荒れなむ] そこ故に -(万2-194) ① なかなかに人とあらずは酒壷に成りにてしかも酒に染みなむ(万3-346) ① 百伝ふ磐余の池に鳴く鴨を今日のみ見てや雲隠りなむ(万3-419) ① 明日香川行き廻る岡の秋萩は今日降る雨に散りか過ぎなむ(万8-1561) ② この世にし楽しくあらば来む世には虫に鳥にも我れはなりなむ(万3-351) ③ 海の底沖つ白波龍田山いつか越えなむ妹があたり見む(万1-83) ⑦ 妹が家に咲きたる梅のいつもいつも成りなむ時に事は定めむ(万3-401) ⑦ 恋ひ死なむ時は何せむ生ける日のためこそ妹を見まく欲りすれ(万4-563) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔終助詞〕他に対するあつらえの語で、相手の動作の実現を希望する意を表す。 ~してほしい。~してもらいたい。 |
足代過ぎて糸鹿の山の桜花散らずもあらなむ帰り来るまで(万7-1202) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔接続〕「紛らわしい語『なむ』の識別」。 a 花咲かなむ(花ガ咲イテホシイ) 未然形に付く「あつらえ」の終助詞 b 花咲きなむ(花ガ咲イテシマウダロウ) 連用形に付く、完了の助動詞「ぬ」の未然形「な」に推量の助動詞「む」の付いたもの。 c 花の咲くなむ待たるる(花ノ咲クノガ待タレル) 係助詞。 d わびぬれば身をつき草の根を絶えてさそふ水もあらばいなむとぞ思ふ ナ変動詞「いぬ」の未然形語尾「な」に推量の助動詞「む」の付いたもの。 接続の仕方から「a」と「b」は区別できる。 「c」は係助詞であるので、種々の語に付くが、連用修飾的機能の語に付いていることから識別できる。 「d」のように動詞の語尾の場合は、「なむ」を除いた上が一語となるかを考える。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なも | 〔係助詞〕(上代語):強く指示する意を表わす 〔接続〕活用語の連用形に付く。 |
何時はなも恋ひずありとはあらねども-(万12-2889) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔終助詞〕(上代語):他に対して願望の意を表わす 〔接続〕動詞の未然形に付く。 |
三輪山をしかも隠すか雲だにも心あらなも隠さふべしや(万1-18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔助動詞〕「らむ」の上代東国方言、推量の意を表わす | うべ児なば吾に恋ふなも立と月の流なへ行けば恋しかるなも(万14-3495) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なよたけ [弱竹] | 〔名詞〕細くしなやかな竹。若竹。「萎竹(なゆたけ)」とも。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なよたけの [弱竹の] | 【枕詞】「なゆたけの(萎竹の)」 なよ竹は、よくたわむので「とをよる」に、 また竹の縁から「よ(=節・夜・世)・ふし」にかかる。 |
秋山の したへる妹 なよ竹の とをよる子らは いかさまに 思ひ居れか-(万2-217) なゆ竹の とをよる御子 さにつらふ 我が大君は こもりくの-(万3-423) なよ竹のよながきうへに 初霜のおきゐて物を思ふころかな(古今雑下-993) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なら [奈良・寧楽] | 〔地名〕 ほぼ今日の奈良市にあたる。 古くは「添(そふ)」と呼ばれ、和珥(わに)一族の居住地であった。 のち春日氏や渡来人系の楢(なら)氏がこれを受け平城遷都まで続いた。 |
あをによし奈良の都は咲く花の薫ふがごとく今盛りなり(万3-331) 藤波の花は盛りになりにけり奈良の都を思ほすや君(万3-333) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-330 注『奈良の都』」】 原文「平城京」とある。「平」は「ならす(平らかにする)」で、奈良の地名は、平坦な地の意で、そこに設けられた都城だから「平城京」である。 和銅三年(710)三月十日に「始遷都于平城」(続紀)とある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ならし | 〔なりたち〕「なるらし⇒ならし」と転じたもの。 [断定の助動詞「なり」の連体形「なる」+推定の助動詞「らし」] ① 断定して推量する意を表す。 「~であるらしい」「~のようだ」「~であるにちがいない」 ② 断定の助動詞「なり」とほとんど同じ意味を表す。 中世以降の用法で、婉曲に表現して余情を深める。 「~である」「~だなあ」 |
① -百足らず 筏に作り 泝すらむ いそはく見れば 神からならし(万1-50) ① 武庫の海船庭ならしいざりする海人の釣船波の上ゆ見ゆ(万3-258) ① -かく行けば 人に憎まえ 老よし男は かくのみならし-(万5-808) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なら(の)やま [奈良山] | 〔地名〕[「平城山」ともかく] 平城京の北方に横たわる丘陵。 | -あをによし奈良の山の 山の際に-(万1-17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻第一」】 奈良市北部、京都府境いの丘陵地。この山を越えて山城へ出る道は、上ツ道の延長線にある奈良坂越え、中ツ道を辿る関西本線の線路にあたる地、下ツ道の延長線にある歌姫越えの三つがあった。飛鳥からは中ツ道を利用することが多い。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ならぶ [並ぶ] | 〔自動詞バ行四段〕 ① 一列になる。② 匹敵する。等しい。 |
我妹子に我が恋ひ行けば羨しくも並び居るかも妹と背の山(万7-1199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞バ行下二段〕 ① 並べる。連ねる。そろえる。② 匹敵させる。また、比べる。比較する。 |
① 馬ないたく打ちてな行きそ日並べて見ても我が行く志賀にあらなくに(万3-265) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なり | 〔助動詞ナリ型〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 「にあり」の約 ① 断定を表わす。「~である、~だ」 ② 「~にある、~にいる」 ③ 続柄を表わす。「~に当る、~である」 ④ 状態・性質を表わす。「~である」 〔接続〕体言・用言の連体形に付く。 用言の連体形に付く用例は上代にはなく、中古以降。 |
① 大和には鳴きてか来らむ呼子鳥象の中山呼びぞ越ゆなる(万1-70) ① うつそみの人なる我れや明日よりは二上山を弟背と我が見む(万2-165) ① 大君は神にしませば天雲の五百重が下に隠りたまひぬ(万2-205) ① 梅の花咲きて散りぬと人は言へど我が標結ひし枝ならめやも(万3-403) ② 嶋の宮上の池なる放ち鳥荒びな行きそ君いまさずとも(万2-172) ② 家ならば妹が手まかむ草枕旅に臥やせるこの旅人あはれ(万3-418) ② -高く貴き 駿河なる 富士の高嶺を 天の原-(万3-320) ② 今日もかも都なりせば見まく欲り西の御馬屋の外に立てらまし (万15-3798) ④ この世には人言繁し来む世にも逢はむ我が背子今ならずとも(万4-544) ④ -たわやめの 我が身にしあれば 道守が 問はむ答へを-(万4-546) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なり | 〔助動詞ラ変型〕【○・ナリ(ケリ)・ナリ・ナル・ナレ・○】 音とか声の意の「な(音)」 又は「ね(音)」 に「あり」 が付いて、 つづまったもの、という。 ① 音や声が聞こえることから推定する意を表わす。 「~のようだ、あれは~だな」 ② 周囲の状況から判断し推定する意を表わす。「~のようだ、~らしい」 ③ 世間の噂・人の話・故事などによる推定を表わす。「~だそうだ」 〔接続〕 ラ行変格活用を除く用言および助動詞の終止形に付く。 平安時代以降、ラ行変格活用をする語には連体形が付くが、上代には終止形に付いた。 |
① -み執らしの 梓の弓の 中弭の 音すなり 朝猟に 今立たすらし 夕猟に-(万1-3) ① ますらをの鞆の音すなり物部の大臣盾立つらしも(万1-76) ①「葦原の中つ国はいたくさやぎてありなり」(記・上) ① 我が背子が古家の里の明日香には千鳥鳴くなり夫待ちかねて(万3-270) ① 秋の野に人待つ虫のこゑすなり我かとゆきていざとぶらはん(古秋-202) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】断定の「なり」と伝聞推定の「なり」の違い- ① 断定の助動詞は連体形に、伝聞推定の助動詞は終止形に付く。 ただし、ラ変、四段動詞に「なり」が付く場合は、前後の意味から「断定」か「伝聞推定」かを判断しなければならない。 ② 伝聞推定の「なり」は、常に主語が対称・他称であって、自称ではない。また話し手の「聞く」行為と関係がある。 ③ 係り結びの場合にその形式が違う。伝聞推定の「なり」は、「係助詞+動詞+なる(又はなれ)」の形をとり、断定の「なり」は、「~に+係助詞+ある(又はあれ)」となる。 ④ 断定の「なり」は「にあり」の約と見られる。「万葉集」では断定の「なり」を「爾有」と書いて「ナリ」とよませている。 また伝聞推定の「なり」の語源は、はっきりしないが、断定の「なり」とは語源を異にすると思われる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なる [生る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 生れる。生じる。 ② 実をむすぶ。みのる。 |
① -行くちふ人は 石木より なり出し人か 汝が名告らさね-(万5-804) ② 玉葛花のみ咲きてならざるは誰が恋ならめ我は恋ひ思ふを(万2-102) ② 我妹子がやどの橘いと近く植ゑてし故に成らずは止まじ(万3-414) ② 冬こもり春へを恋ひて植ゑし木の実になる時を片待つ我れぞ(万9-1709) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なる [成る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 成立する。成就する。実現する。出来上がる。 ② (それまでとは違った状態やもの、地位などに) なる。 変化する。成長する。 ③ することが出来る。可能である。かなう。 |
② -知らぬ国 寄し巨勢道より 我が国は 常世にならむ 図負へる-(万1-50) ② -朝言に 御言問はさぬ 日月の 数多くなりぬれ そこ故に 皇子の宮-(万2-167) ② 山菅の実ならぬことを我に寄そり言はれし君は誰とか寝らむ(万4-567) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なる | 〔補助動詞ラ行四段〕 自然にそのような状態になる。 |
藤波の花は盛りになりにけり奈良の都を思ほすや君(万3-333) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なる [萎る・褻る] | 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 ① (衣類が) よれよれになる。糊気が抜け落ちる。着古す。 ② (道具などが) 古びる。古ぼける。使い古す。 |
① 須磨の海人の塩焼き衣の藤衣間遠にしあればいまだ着馴れず(万3-416) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なれば | 〔接続詞〕[断定の助動詞「なり」の已然形「なれ」+接続助詞「ば」] ① それだから。したがって。それゆえに。 ② (問いに対し答えて)それは。 |
① 妹も我も一つなれかも三河なる二見の道ゆ別れかねつる(万3-278) 〔「なれかも」は「なればかも」の約〕 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なれや | 〔成り立ち〕 断定の助動詞「なり」の已然形「なれ」+助詞「や」 ①「や」が疑問を表す場合。 「~だからなのだろうか」「~なのだろうか」 ②「や」が反語を表す場合。 「~であるのか(いや、そうではないのに)」 ③「や」が詠嘆を表す場合。 「~であることよ」「~だなあ」 【参考】 多く、和歌でみられる表現。 「や」を係助詞とする説と、終助詞とする説がある。 |
① うき草のうへはしげれる淵なれやふかき心を知る人のなき(古今恋一-538) ② 打ち麻を麻続の王海人なれや伊良虞の島の玉藻刈ります(万1-23) ② 山の際ゆ出雲の児らは霧なれや吉野の山の嶺にたなびく(万3-432) 【小学館「新編日本古典文学全集『万葉集巻第一-23』頭注】 ナレヤは疑問条件法、ナレバヤに同じだが、それよりも古格。ナレカという形もあるが、同じ疑問助詞でも、カが単純な疑問を表すのに対してヤは反語性を含むため、そんなこともなかろうに、というような余意が込められることが多い、そのため「霧なれや」(432)、「潮満てば入りぬる磯の草なれや」 (1398) など比喩的な用法もある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| に | 〔格助詞〕 ① 場所を表わす。~に、~で。② 時を示す。~(とき) に。 ③ 動作の帰着点を示す。④ 方向を示す。~(の方) へ。 ⑤ 動作・作用の結果、変化の結果を示す。~と。 ⑥ 動作の目的を示す。~ため。 ⑦ 原因・理由を表わす。~により。 ⑧ 受身の時、その動作の源を示す。 ⑨ 使役の時、その動作の目標を示す。⑩ 資格を示す。 ⑪ 手段と方法を示す。~で。 ⑫ 動作の対象を示す。 ⑬ 動作の拠り所を示す。⑭ 比較の基準を示す。~より。 ⑮ 比況を表わす。~のように。 ⑯ 同じ動詞を重ねて意味を強める。 ⑰ 場合・状況などを示す。⑱ 添加の意を表わす。~と、そのうえに。 ⑲ 身分の高い人を尊敬する意を表わす。~におかれても 〔接続〕 体言、または活用する語の連体形に付く。 「⑥・⑯」の場合は、連用形に付く。 〔語法〕 動作などの行われる時や場所などを表わすのが本来の意味で、 それから種々の用法が誕生したものと考えられる。 |
① -我が寝し 枕づく つま屋の内に 昼はも うらさび暮らし 夜はも-(万2-210) ① かはづ鳴く神奈備川に影見えて今か咲くらむ山吹の花(万8-1439) ② いにしへに恋ふる鳥かも弓絃葉の御井の上より鳴き渡り行く(万2-111) ② -思ひ居れか 栲縄の 長き命を 露こそば 朝に置きて 夕には-(万2-217) ② 妹が名は千代に流れむ姫島の小松がうれに蘿生すまでに(万2-228) ② 旅にしてもの恋しきに山下の赤のそほ船沖を漕ぐ見ゆ(万3-272) ② 妹が家に咲きたる梅のいつもいつも成りなむ時に事は定めむ(万3-401) ④「尾張に直に向へる尾津の前なる一つ松」(記中) ④ 家に来て我が屋を見れば玉床の外に向きけり妹が木枕(万2-216) ⑤ 我を待つと君が濡れけむあしひきの山のしづくにならましものを (万2-108) ⑤ 天の香具山 霞立つ 春に至れば 松風に 池波立ちて 桜花-(万3-259) ⑥ 人見ずは我が袖もちて隠さむを焼けつつかあるらむ着ずて来にけり(万3-271) ⑦ 我が背子を大和へ遣るとさ夜更けて暁露に我が立ち濡れし(万2-105) ⑦ 古りにし嫗にしてやかくばかり恋に沈まむ手童のごと [恋をだに忍びかねてむ手童のごと](万2-129) ⑦ 降る雪はあはにな降りそ吉隠の猪養の岡の寒からまくに(万2-203) ⑦ 春の野に若菜つまむと来しものを散りかふ花に道はまどひぬ (古春下116) ⑨ 淡路の野島の崎の浜風に妹が結びし紐吹き返す(万3-252) ⑩ 高円の野辺の秋萩な散りそね君が形見に見つつ偲はむ(万2-233) ⑪ -斎きの宮ゆ 神風に い吹き惑はし 天雲を 日の目も見せず-(万2-199) ⑫ 我が背子に我が恋ふらくは夏草の刈り除くれども生ひしくごとし (万11-2779) ⑮ 橘の蔭踏む道の八衢に物をぞ思ふ妹に逢はずして [三方沙弥](万2-125) ⑮ 大君は千歳にまさむ白雲も三船の山に絶ゆる日あらめや(万3-244) ⑮ あな醜賢しらをすと酒飲まぬ人をよく見ば猿にかも似る(万3-347) ⑮ 山高み白木綿花におちたぎつ瀧の河内は見れど飽かぬかも(万6-914) ⑰ -剣太刀 身に添へ寝ねば ぬばたまの 夜床も荒るらむ-(万2-194) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| に | 〔接続助詞〕 ① 逆接の確定条件を表わす。~けれども、~のに ② 事実を述べ、下に続ける。~と、~したところが ③ 原因・理由を表わす。~ので、~ために ④ 恒時条件を表わす。~する時はいつも ⑤ 添加の意を表わす。その上さらに 〔接続〕活用する語の連体形に付く。 |
① -天離る 鄙にはあれど 石走る 近江の国の 楽浪の-(万1-29) ① -見まく欲り我がする君もあらなくに何しか来けむ馬疲るるに(万2-164) ① -思ひ頼みて 天つ水 仰ぎて待つに いかさまに 思ほしめせか-(万2-167) ① 庭の面はまだ乾かぬに夕立の空さりげなく澄める月かな(新古夏-267) ② 衾道を引手の山に妹を置きて山道思ふに生けるともなし(万2-215) ③ 大船の泊つる泊りのたゆたひに物思ひ痩せぬ人の子故に(万2-122) ③ 風早の美穂の浦廻の白つつじ見れどもさぶしなき人思へば [或云 見れば悲しもなき人思ふに](万3-437) ④ -形見に置ける みどり子の 乞ひ泣くごとに 取り与ふる -(万2-210) ④ -入日なす 隠りにしかば そこ思ふに 胸こそ痛き 言ひもえず-(万3-469) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔語法〕接続助詞「に」は格助詞から派生したものである。 用言の連体形に付く格助詞の「に」は、その下の名詞「時」「所」などが言外に含まれたものと考えてよく、転用されたときは接続助詞と考えてもいい場合がある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| に | 〔終助詞〕 ① 他に対して願望する意を表わす。 ~して欲しい、~してもらいたい。「ね」に同じ ② ~のになぁ、~だぜ 〔接続〕 ①は文末の動詞の未然形に付き、 ②は文末の活用する語の終止形に付く。 〔語法〕①は上代に用いられ、②は近世に用いられた。 |
① ひさかたの天道は遠しなほなほに家に帰りて業を為まさに(万5-805) ② 高円の野辺の秋萩いたづらに咲きか散るらむ見る人なしに(万2-231) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| に | 断定の助動詞「なり」の連用形 ① ~であって ② 接続助詞「て」「して」を伴って中止の表現に用いる。「~で」 ③ 補助動詞「あり」「おはす」「候ふ」「はべり」を伴い、「~で」 |
① 伊勢の海の沖つ白波花にもが包みて妹が家づとにせむ(万3-309) ① なでしこがその花にもが朝な朝な手に取り持ちて恋ひぬ日なけむ(万3-411) ② 月やあらぬ春やむかしの春ならぬ我が身ひとつはもとの身にして (古恋五-747) ③ 我妹子を早見浜風大和なる[大和にある]我れ松椿吹かざるなゆめ(万1-73) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| に | 完了の助動詞「ぬ」 の連用形。 助動詞「き・けり・けむ・たり」、また、 接続助詞「て・して」などを伴った形で用いられる。 |
み立たしの島の荒礒を今見れば生ひざりし草生ひにけるかも(万2-181) 妻もあらば摘みて食げまし沙弥の山野の上のうはぎ過ぎにけらずや(万2-221) 三笠山野辺ゆ行く道こきだくも荒れにけるかも久にあらなくに(万2-234) 名にめでて折れるばかりぞ女郎花我おちにきと人にかたるな(古秋上-226) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| に | 〔上代語〕打消しの助動詞「ず」の連用形。~ないで。~ないので。 |
-為むすべの たどきを知らに 白栲の-(万5-909) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔参考〕「に」の用法は狭く、「知らに」「飽かに」「かてに」などに限定され、中古に入ると、用いられなくなる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| に [荷] | 〔名詞〕荷物。一例「荷前 (のさき)」の箱。 | 東人の荷前の箱の荷の緒にも妹は心に乗りにけるかも [禅師](万2-100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にあり | 〔成り立ち〕断定の助動詞「なり」の連用形「に」+ラ変補助動詞「あり」 「~である。~だ。」 |
石上布留の山なる杉群の思ひ過ぐべき君ならなくに(万3-425) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔成り立ち〕格助詞「に」+ラ変動詞「有り」 「~にある。~にいる。」 |
山越しの風を時じみ寝る夜おちず家にある妹を懸けて偲ひつ(万1-6) あをによし奈良にある妹が高々に待つらむ心しかにはあらじか (万18-4107) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にか | 〔なりたち〕[断定の助動詞「なり」の連用形「に」+係助詞「か」 ① (連体形の結びを伴って、「にかあらむ」「にかありけむ」の形で) ~で(あろう)か。~で(あっただろう)か。 ② (文末に用いられて、① の「あらむ」「ありけむ」などが省略された形で) ~であろうか。~であっただろうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にか | 〔なりたち〕格助詞「に」+係助詞「か」 ① 疑問の意を表す。「~に~か」 ② 反語疑問の意を表す。「~に~ か(いや、~ない)」 |
① いづくにか我が宿りせむ高島の勝野の原にこの日暮れなば(万3-277) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にきたつ [熟田津] | 〔地名〕歌枕。中古以降は「にぎたづ」 今の愛媛県道後温泉付近の船着き場。 松山市三津浜、同市和気町などの諸説がある。 |
熟田津に船乗りせむと月待てば潮もかなひぬ今は漕ぎ出でな(万1-8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にきたへ [和栲・和妙] | 〔名詞〕[中古以後は「にぎたへ」] 打って柔らかくした、神に供える布。また、織目の細かい布の総称。 |
-片手には 和たへ奉り 平けく ま幸くませと 天地の 神を乞ひ祷み-(万3-446) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にきたま [和魂・和霊] | 〔名詞〕[中古以後は「にぎたま」] 温和な神霊。=和御魂(にきみたま) |
大君の和魂あへや豊国の鏡の山を宮と定むる(万3-420) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にきはだ [和膚] | 〔名詞〕 《「にき」 は接頭語。中古以降は「にぎはだ」》柔らかな肌。やわはだ。 |
-靡かひし 嬬の命の たたなづく 柔肌すらを 剣太刀 身に添へ寝ねば-(万2-194) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にきぶ [和ぶ] | 〔自動詞バ行上二段〕【ビ・ビ・ブ・ブル・ブレ・ビヨ】 心が和らぐ。慣れ親しむ。くつろぐ。 |
大君の 命畏み 柔びにし 家を置き こもりくの 泊瀬の川に-(万1-79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にくし [憎し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① 嫌だ。気に入らない。不快だ。② 醜い。みっともない。見苦しい。 ③ 無愛想だ。つれない。④ むずかしい。奇妙だ。 ⑤ (すぐれていて「憎いほどだ」の意から) 感心だ。あっぱれだ。 ⑥ (動詞の連用形の下に付いて) ~するのが困難だ。~づらい。 |
① 紫のにほへる妹を憎くあらば人妻故に我れ恋ひめやも(万1-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にけり | 〔なりたち〕[完了助動詞「ぬ」の連用形「に」+過去助動詞「けり」] ① (「けり」が過去を表す場合) ~てしまった。~た。~たということだ。 ② (「けり」が何かに気づいたことや詠嘆を表す場合) ~いた(のだった)。~してしまったことだ。 |
① はだすすき久米の若子がいましける [一云 けむ] 三穂の岩屋は見れど飽かぬかも [一云 荒れにけるかも](万3-310) ② 我が船は比良の湊に漕ぎ泊てむ沖辺な離りさ夜ふけにけり(万3-276) ② ここにして家やもいづち白雲のたなびく山を越えて来にけり(万3-290) ② 古への古き堤は年深み池のなぎさに水草生ひにけり(万3-381) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にごる [濁る] | 〔自動詞カ行四段〕 ① (水・酒などが)不透明になる。濁る。 ② 邪念を持つ。煩悩にとらわれる。けがれる。 ③ 濁音になる。濁音にする。 |
験なき物を思はずは一坏の濁れる酒を飲むべくあるらし(万3-341) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にし | 格助詞「に」+副助詞「し」(「に」が下の連用修飾語になる) 「~に」「~によって」「~によって」「~で」 |
この世にし楽しくあらば来む世には虫に鳥にも我はなりなむ(万3-351) 妹が家に咲きたる花の梅の花実にし成りなばかもかくもせむ(万3-402) 白栲の袖折り返し恋ふればか妹が姿の夢にし見ゆる(万12-2949) 散る花の鳴くにしとまる物ならばわれ鶯に劣らましやは(古今春下-107) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にし | 断定の助動詞「なり」の連用形「に」+副助詞「し」 (下に「あり」などがきて、口語助動詞「で」に相当する意を表す) 「~で」 |
-草枕 旅にしあれば ひとりして 見る験なみ 海神の-(万3-369) 岩戸割る手力もがも手弱き女にしあればすべの知らなく(万3-422) とりとむるものにしあらねば年月をあはれあな憂と過ぐしつるかな (古雑上-897) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にし | 完了の助動詞「ぬ」の連用形「に」+過去の助動詞「き」連体形「し」 「~てしまった」「~た」「~してしまった」 |
ま草刈る荒野にはあれど黄葉の過ぎにし君の形見とぞ来し(万1-47) 大君の 命畏み 柔びにし 家を置き こもりくの 泊瀬の川に(万1-79) 我が里に大雪降れり大原の古りにし里に降らまくは後(万2-103) 難波潟潮干なありそね沈みにし妹が姿を見まく苦しも(万2-229) 古りにし嫗にしてやかくばかり恋に沈まむ手童のごと [恋をだに忍びかねてむ手童のごと](万2-129) 浅茅原つばらつばらに物思へば古りにし里し思ほゆるかも(万3-336) 秋風の吹きにし日より久方のあまのかはらにたたぬ日はなし(古秋上-173) 慕はれて来にし心の身にしあれば帰るさまには道も知られず(古今離別-389) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にしか | 〔完了の助動詞「ぬ」の連用形「に」+過去の助動詞「き」の已然形「しか」〕 ~てしまった。 |
-朝立ちいまして 入日なす 隠りにしかば 我妹子が 形見に置ける-(万2-210) -入日なす 隠りにしかば そこ思ふに 胸こそ痛き 言ひもえず-(万3-469) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にして | 〔なりたち〕[断定の助動詞「なり」の連用形「に」+接続助詞「して」] ~で。~であって。~でありながら。 |
君に恋ひいたもすべなみ葦鶴の音のみし泣かゆ朝夕にして(万3-459) 山吹の花色衣ぬしやたれ 問へどこたへず くちなしにして(古今雑体旋頭歌-1012) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にして | 〔なりたち〕[格助詞「に」+接続助詞「して」] ①(場所を表す)「~にあって」「~において」「~で」 ②(時を表す)「~で」「~のときに」 |
① 旅にしてもの恋ほしきに鶴が音も聞こえざりせば恋ひて死なまし(万1-67) ① 旅にしてもの恋しきに山下の赤のそほ船沖を漕ぐ見ゆ(万3-272) ① 旅にして物思ふ時に霍公鳥もとなな鳴きそ我が恋まさる(万15-3803) ① 家にして恋ひつつあらずは汝が佩ける大刀になりても斎ひてしかも (万20-4371) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にぞ | [奈良時代は「にそ」とも] ①〔断定の助動詞「なり」の連用形+係助詞「ぞ」〕 ~で。 ②〔格助詞「に」+係助詞「ぞ」〕 ~に。 |
① しきたへの枕ゆくくる涙にそ浮き寝をしける恋の繁きに(万4-510) ① 心なき鳥にぞありける霍公鳥物思ふ時に鳴くべきものか(万15-3806) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にて | 〔格助詞 (「格助詞「に」+接続助詞「て」)〕 ① 場所をさす。「~において」「~まで」 ② 時刻・年齢を表す。「~で」 ③ 状態・資格を表す。「~で」「~として」 ④ 手段・方法を表す。「~で」 ⑤ 材料を表す。「~で」 ⑥ 理由・原因を表す。「~のために」「~によって」 [接続] 体言・活用語の連体形に付く。 |
③ -よけくもぞなき うつそみと 思ひし妹が 灰にていませば(万2-213) 【参考】 現代語の「で」と同じと考えればよい。語源的には、 にて → んで(中世) → んで → で という発音の変化をたどり、現代語の「で」となった。「で」となって初めて用いられたのは「平家物語」で、それ以前はすべて「にて」である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にて | 〔成り立ち〕断定の助動詞「なり」の連用形「に」+接続助詞「て」 ①~であって。~という状態で。 ② (下に「あり」「おはす」「候ふ」「侍り」など存在を表す語を伴って) 断定を表す。「~である」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にて | 〔成り立ち〕 完了の助動詞「ぬ」の連用形「に」+接続助詞「て」 「~てしまって」「~てしまっていて」 |
梅の花咲きて散りなば桜花継ぎて咲くべくなりにてあらずや [藥師張氏福子] (万5-833) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| には [庭] | 〔名詞〕 ① (神事・狩猟・農作業・戦争など)物事の行われる場所。場。用地。 単独より、「狩庭(かりには)」など上に語を付して使うことが多い。 ② 家に付属した土地で草木や石で整えた物。庭。庭園。 ③ 海面。海原。④ 《近世語》土間。 |
① 飼飯の海の庭良くあらし刈り薦の乱れて出づ見ゆ海人の釣船(万3-257) ③ -明けぬとし 立ち騒くらし いざ子ども あへて漕ぎ出む 庭も静けし(万3-391) ③ -立ち騒くらし いざ子ども あへて漕ぎ出む にはも静けし(万3-391) ③ 庭清み沖へ漕ぎ出る海人舟の楫取る間なき恋もするかも(万11-2756) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| には 格助詞「に」、 接続助詞「に」 |
① 断定の助動詞「なり」の連用形に、係助詞「は」の付いたもの。 「~では」 ② 格助詞「に」に係助詞「は」の付いたもの。 「には」の「に」に従って、種々の意を表わす。 |
① 風流士に我れはありけりやど貸さず帰しし我れぞ風流士にはある (万2-127) ① 橘の嶋の宮には飽かねかも佐田の岡辺に侍宿しに行く(万2-179) ① -桜花 木の暗茂に 沖辺には 鴨つま呼ばひ 辺つへに あぢ群騒き-(万3-259) ① この世にし楽しくあらば来む世には虫に鳥にも我はなりなむ(万3-351) ② 大和には 群山あれど とりよろふ 天の香具山 登り立ち 国見をすれば-(万1-2) ② -我が大君の 朝には 取り撫でたまひ 夕には い寄り立たしし-(万1-3) ② -天離る 鄙にはあれど 石走る 近江の国の 楽浪の-(万1-29) ② あをによし奈良の家には万代に我れも通はむ忘ると思ふな(万1-80) ② 我が行きは久にはあらじ夢のわだ瀬にはならずて淵にもありこそ(万3-338) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にはたづみ [行潦・庭潦] | 〔名詞〕雨が降って、にわかに地上にあふれ流れる水。 | 「庭中にひざまづきし時、にはたづみ腰に至りき」(記下)に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】 「にはたづみ」 は、流れるものであることから「流る・川・行く」 にかかる。 |
み立たしの島を見る時にはたづみ流るる涙止めぞかねつる(万2-178) -あしひきの 山行き野行き にはたづみ 川行き渡り 鯨魚取り-(万13-3349) -遠音にも 聞けば悲しみ にはたづみ 流るる涙 留めかねつも(万19-4238) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にふのかは [丹生の川] | 〔名詞〕 | 丹生の川瀬は渡らずてゆくゆくと恋痛し我が背いで通ひ来ね(万2-130) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉野川の支流丹生川のこと。奈良県吉野郡大天井ヶ岳の北西方に発し、下市町長谷で丹生川上 (にうのかわかみ) 下社の前を過ぎ五条市で吉野川に注ぐ。 なお同郡川上村の丹生川上上社付近の吉野川、東吉野村の丹生川上中社付近の高見川とする説もある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にほどりの [鳰鳥の] | 【枕詞】 「にほどり」の習性から「潜(かづ)く」「なづさふ(=水ニ浮カブ)」「息長河(おきなわがわ)」「二人並びゐ」に、また地名「葛飾(かづしか)」にかかる。 |
にほ鳥の潜く池水心あらば君に我が恋ふる心示さね(万4-728) 思ひにしあまりにしかばにほ鳥のなづさひ来しを人見けむかも(万11-2498) にほ鳥の息長川は絶えぬとも君に語らむ言尽きめやも [古新未詳](万20-4482) -我れをばも いかにせよとか にほ鳥の ふたり並び居 語らひし-(万5-798) にほ鳥の葛飾早稲をにへすともその愛しきを外に立てめやも(万14-3404) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にほはす [匂はす] | 〔他動詞サ行四段〕 ① 染める。色づかせる。ほんのりと彩る。 ② かおらせる。香気をただよわせる。③ ほのめかす。暗示する。 |
① 引間野ににほふ榛原入り乱れ衣にほはせ旅のしるしに(万1-57) ① 秋の野をにほはす萩は咲けれども見る験なし旅にしあれば(万15-3699) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にほふ [匂ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 ① (草木などの色に)染まる。美しく染まる。 ② つややかに美しい。照り輝く。③ 栄える。恩恵や影響が及ぶ。 ④ かおる。香気がただよう。 |
① 草枕旅行く人も行き触ればにほひぬべくも咲ける萩かも(万8-1536) ② 紫のにほへる妹を憎くあらば人妻故に我れ恋ひめやも(万1-21) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【語義】 現代語では、「匂う」と書いて④の意で、または、「臭う」」と書いて、鼻に不快に感じる意で用いることが多いが、原義は「丹(に=赤い色)秀(ほ=物の先端など、抜き出て目立つところ)ふ(=動詞化する接尾語)」で、赤い色が表面にあらわれ出て目立つの意。 【「にほふ」という美しさ】 「源氏物語」の宇治十帖で活躍する薫の君と匂宮。 並び称される二人だから、「かをる」も「にほふ」も鼻で感じることをいう語だと思いがちだが、「にほふ」は「丹秀(にほ)ふ」で、美しさが照り輝くの意。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にも | 〔格助詞「に」の意味によって、種々の意味を表わす〕 ① ~においても。~でも。② ~からも。~にさえも。③ ~に対しても。 ④ ~であろうとも。たとえ~でも。⑤ 並列を表わす。 ⑥ 尊敬の意を表す。~におかれても。 |
① 神風の伊勢の国にもあらましを何しか来けむ君もあらなくに(万2-163) ① 神木にも手は触るといふをうつたへに人妻といへば触れぬものかも(万4-520) ④ よく渡る人は年にもありといふをいつの間にそも我が恋ひにける(万4-526) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にも | 東人の荷前の箱の荷の緒にも妹は心に乗りにけるかも [禅師](万2-100) 我が行きは久にはあらじ夢のわだ瀬にはならずて淵にもありこそ(万3-338) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻第二-100 注『にも』】文中、旧歌番号 「ニモ」の「ニ」は、「あきつ葉ににほへる衣」(10・2304) の「に」と同様に、「~ノヨウニ」の意味をあらわす助詞である(講義)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にる [似る] | 〔自動詞ナ行上一段〕【ニ・ニ・ニル・ニル・ニレ・ニヨ】 ① 形態や性質がほとんど同じように見える。 ② ~と見える。 |
① あな醜賢しらをすと酒飲まぬ人をよく見ば猿にかも似る(万3-347) ② -玉桙の 道行き人も ひとりだに 似てし行かねば すべをなみ-(万2-207) ② あな醜賢しらをすと酒飲まぬ人をよく見ば猿にかも似る(万3-347) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぬ [寝] | 〔自動詞ナ行下二段〕【ネ・ネ・ヌ・ヌル・ヌレ・ネヨ】 「いぬ」の「い」が脱落。「寝る・眠る・横になる」 |
大和恋ひ寐の寝らえぬに心なくこの洲崎廻に鶴鳴くべしや(万1-71) -奈良の都の 佐保川に い行き至りて 我が寝たる 衣の上ゆ-(万1-79) 今よりは秋風寒く吹きなむをいかにかひとり長き夜を寝(ね)む(万3-465) 塵をだにすゑじとぞ思ふ植ゑしより妹とわがぬる常夏の花(古夏-167) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぬ 「主要助動詞活用表」 | 〔助動詞ナ変型〕【ナ・ニ・ヌ・ヌル・ヌレ・ネ】 [ナ変動詞「往ぬ(いぬ)」が動詞の連用形に付いて約まったものという] ① 動作または作用が完結・存続する意。~てしまった、~てしまう ② 意味を強める。きっと~だ、たしかに~だ 「む」「べし」「らむ」を伴う ラ変動詞「あり」および「あり」の系統の語・形容動詞などに付く 〔接続〕活用語の連用形に付く。 古くはナ変動詞に付くことはなかったが、 中世以後には「死にぬ」などの例がある。 |
① ますらをや片恋せむと嘆けども醜のますらをなほ恋ひにけり(万2-117) ① 大船の泊つる泊りのたゆたひに物思ひ痩せぬ人の子故に(万2-122) ① 笹の葉はみ山もさやにさやげども我れは妹思ふ別れ来ぬれば (万2-133) ① 敷栲の袖交へし君玉垂の越智野過ぎ行くまたも逢はめやも [一云 越智野に過ぎぬ](万2-195) ① 大君は神にしませば天雲の五百重が下に隠りたまひぬ(万2-205) ① -隠りのみ 恋ひつつあるに 渡る日の 暮れぬるがごと 照る月の-(万2-207) ① 我が待たぬ年は来ぬれど冬草のかれにしひとはおとづれもせず(古冬-338) ② いざ子ども早く日本へ大伴の御津の浜松待ち恋ひぬらむ(万1-63) ② ますらをの心はなしに秋萩の恋のみにやもなづみてありなむ(万10-2126) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぬ 「主要助動詞活用表」 | 〔打消の助動詞「ず」の連体形〕未然形に付く |
梓弓引かばまにまに依らめども後の心を知りかてぬかも [郎女] (万2-98) ⇒「ぬかも」 人言を繁み言痛みおのが世にいまだ渡らぬ朝川渡る(万2-116) たけばぬれたかねば長き妹が髪このころ見ぬに掻き入れつらむか [三方沙弥] (万2-123) -あぢさはふ 目言も絶えぬ 然れかも あやに哀しみ ぬえ鳥の-(万2-196) 明日香川明日だに [さへ] 見むと思へやも [思へかも] 我が大君の御名忘れせぬ [御名忘らえぬ](万2-198) 来むと言ふも来ぬ時あるを来じと言ふを来むとは待たじ来じと言ふものを(万4-530) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【紛らわしい語「ぬ」の識別】 ① 春の色のいたりいたらぬ里はあらじ咲ける咲かざる花の見ゆらむ (古今春下-93) ② 潮満ちぬ。風も吹きぬべし。(土佐日記) ③ 契りおきしさせもが露を命にてあはれ今年の秋もいぬめり(千載和歌集・雑上) ④ 嘆きつつひとりぬる夜のあくるまはいかに久しきものとかは知る(拾遺和歌集・恋四) 「識別の方法」 「①」は打消の助動詞「ず」の連体形。動詞の「未然形」に接続していることから判断できる。 「②」は完了の助動詞「ぬ」の終止形。動詞の「連用形」に接続していることから判断できる。「京には見えぬ鳥なれば」(伊勢・9) の「ぬ」は、接続する動詞が下二段活用の「見ゆ」であり、未然形・連用形が同じ形なので接続からは判断できない。この「ぬ」は名詞「鳥」を修飾する連体形である。完了の「ぬ」の連体形は「ぬる」、打消しの「ず」の連体形は「ぬ」であるので、この場合は打消しの意味になる。 「③」はナ変動詞「いぬ」の活用語尾、「④」は下二段活用動詞「ぬ(寝)」の連体形の一部である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぬえことり [鵺子鳥・鵼子鳥] | 〔名詞〕小鳥の名。とらつぐみの異称。「ぬえ」「ぬえどり」とも。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】 「ぬえどり」の鳴き声が悲しげに聞こえる事から、「うらなく」にかかる。 |
-むらきもの 心を痛み ぬえこ鳥うら泣け居れば-(万1-5) -然れかも 一に云ふ [そこをしも] あやに哀しみ ぬえ鳥の 片恋づま-(万2-196) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぬか | 〔打消助動詞「ず」の連体形+係助詞「か」〕 ① (多く「~も~ぬか」の形で) 願望の意を表す。 ~ないかなあ。~であってほしい。 ② ~ないか。 |
① 我が命も常にあらぬか昔見し象の小川を行きて見むため(万3-335) ① ひさかたの雨も降らぬか雨つつみ君にたぐひてこの日暮らさむ(万4-523) ② かげろふのそれかあらぬか春雨の降る日となれば袖ぞ濡れぬる(古今恋四-731) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【参考】 「①」は上代特有の用法。万葉集では打消の意の「ず」「ぬ」などには漢字「不」が当てられることが多いのに、この「ぬか」にはその例がないところから、打消の意にとる意識がなかったとし、「ぬか」を一語として願望の助詞と見る説もある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぬかも | 〔上代語〕 [打消助動詞「ず」の連体形「ぬ」+係助詞「か」+終助詞「も」] (多く「~も~ぬかも」の形で) 願望の意を表す。 「~であってほしいなあ。~ないかなあ。」 |
吉野川行く瀬の早みしましくも淀むことなくありこせぬかも(万2-119) 梅の花今咲けるごと散り過ぎず我が家の園にありこせぬかも [少貳小野大夫] (万5-820) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぬかも | 〔上代語〕[打消助動詞「ず」の連体形「ぬ」+終助詞「かも」] 詠嘆の意を表す。 「~ないことよなあ。~ないなあ。」 |
-夜はも 夜のことごと 伏し居嘆けど 飽き足らぬかも(万2-204) はだすすき久米の若子がいましける [一云 けむ] 三穂の岩屋は見れど飽かぬかも [一云 荒れにけるかも](万3-310) 我が宿に咲きし秋萩散り過ぎて実になるまでに君に逢はぬかも(万10-2290) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぬきす [貫簀] | 〔名詞〕 細く削った竹を糸で編んだもの。手を洗う時、水が飛び散らないように、たらいなどの上にかける。 |
古人の飲へしめたる吉備の酒病まばすべなし貫簀賜らむ(万4-557) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぬく[貫く] | 〔他動詞カ行四段〕穴にさし通す。貫く。 | -角鹿の浜ゆ 大船に 真楫貫き下ろし いさなとり 海路に出でて-(万3-369) 我が宿の尾花が上の白露を消たずて玉に貫くものにもが(万8-1576) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぬく [脱く] | 〔他動詞カ行四段〕(上代は「ぬく」、中古末に「ぬぐ」と濁音化) 脱ぐ。 |
-手に巻き持ちて 衣ならば 脱く時もなく 我が恋ふる 君ぞ昨夜の夜 -(万2-150) 我妹子が形見の衣下に着て直に逢ふまでは我れ脱かめやも(万4-750) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぬさ [幣] | 〔名詞〕 ① 神に祈るときに捧げるもの。 古くは麻や「木綿(ゆふ)」などを供えたが、後にはそれで織った布や絹・紙なども用いた。 また旅行のときには、紙または絹の細かに切ったものを用い、道祖神の前にまいて奉った。 幣(へい・みてぐら)・和幣(にきて)・幣帛(へいはく)。 ② 贈り物。餞別。 |
① 在り嶺よし対馬の渡り海中に幣取り向けて早帰り来ね(万1-62) ① ちはやぶる神の社に我が掛けし幣は賜らむ妹に逢はなくに(万4-561) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぬばたま [射干玉] [諸注参照] | 〔名詞〕[「うばたま」「むばたま」ともいう] 「ひあふぎ (=草の名)」の実。黒くて丸い。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻第二-89 ぬばたまの」頭注】 「ぬばたま」は、アヤメ科の多年草「ひおうぎ (射干) の実。夏黄赤色に暗紅点を散らしたような六弁の花を開き、花後の蒴果 (さつか) が割れると光沢のある種子が現れる。 その濃黒色をもって比喩とした。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぬばたまの [射干玉の] | 【枕詞】「枕詞一覧」 |
居明かして君をば待たむぬばたまの我が黒髪に霜は降るとも(万2-89) 児らが家道やや間遠きをぬばたまの夜渡る月に競ひあへむかも(万3-305) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-302」 注『ぬばたまの』】 ここでは、夜にかかる枕詞。原文「野干子乃」とあり、檜扇(ひおうぎ)すなわち「ヌバタマ」を「射干」(『本草和名』)、「夜干」(延喜式) などと書いたが、音通の「野干」の字で書き、実(み)の意の「子」をつけた表記である。この檜扇の実は真っ黒なので「夜」にかかる枕詞となった。そのヌバタマという国語は、実は元来「黒い玉」の意であった。そのヌバはヌマ(沼)と同源で、それは「泥」の色であり、それは「黒」の色であった(佐竹昭広『万葉集万抜書』)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぬの [布] | 〔名詞〕 麻・からむし・葛(くず) などの繊維で織った織物の総称。絹と比べて目が粗い。 |
庭に立つ麻手刈り干し布さらす東女を忘れたまふな(万4-524) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぬる [濡る] | 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 濡れる。水などがつく。濡れる。 |
我が背子を大和へ遣るとさ夜更けて暁露に我が立ち濡れし(万2-105) あしひきの山のしづくに妹待つと我れ立ち濡れぬ山のしづくに(万2-107) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぬる | 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 (ひとりでに) 解ける。するするとゆるんでほどける。 |
嘆きつつますらをのこの恋ふれこそ我が結ふ髪の漬ちてぬれけれ(万2-118) たけばぬれたかねば長き妹が髪このころ見ぬに掻き入れつらむか [三方沙弥] (万2-123) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぬる「主要助動詞活用一覧」 | 完了の助動詞「ぬ」の連体形。 | 秋きぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる(古秋上-169) -朝言に 御言問はさぬ 日月の 数多くなりぬれ そこ故に 皇子の宮-(万2-167) 見渡せば明石の浦に燭す火のほにそ出でぬる妹に恋ふらく(万3-329) 世間は常かくのみと別れぬる君にやもとな我が恋ひ行かむ(万15-3712) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぬれ [濡れ] | 〔名詞〕① 濡れること。② 恋愛。情事。 | ① 雨降らば着むと思へる笠の山人にな着せそ濡れは漬つとも(万3-377) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ね | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ね [子] | 〔名詞〕 ① 十二支の一番目。②方角の名。北。 ③ 時刻の名。 今の午前零時頃およびその前後約二時間(午後11時頃から午前1時頃)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ね [音] | 〔名詞〕聞く人の耳にしみじみと訴える音。声。ひびき。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ね [根] | 〔名詞〕 ① 植物の名。②奥深いこと。奥深い部分。③根源。もと。 |
① 竹の根の根足(ねだる)宮(記下) ② 奥山の岩本菅を根深めて結びし心忘れかねつも(万3-400) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ね [寝] | 〔名詞〕寝ること。 | -剣太刀 身に添へ寝ねば ぬばたまの 夜床も荒るらむ -(万2-194) -敷栲の 手枕まきて 剣太刀 身に添へ寝けむ 若草の その嬬の子は-(万2-217) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ね [峰・嶺] | 〔名詞〕みね。山の頂上。 | 我が面の忘れむしだは国はふり嶺に立つ雲を見つつ偲はせ(万14-3536) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ね | 〔助動詞〕→「主要助動詞活用表」 | たけばぬれたかねば長き妹が髪このころ見ぬに掻き入れつらむか [三方沙弥](万2-123) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔打消し助動詞「ず」の已然形〕 | 翼なす あり通ひつつ 見らめども 人こそ知らね 松は知るらむ(万2-145) しらぬひ筑紫の綿は身に付けていまだは着ねど暖けく見ゆ(万3-339) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔終助詞〕《上代語》他人が自分の願いを聞き入れてくれる事を願う。 ① ~てください。~てほしい。 ② (「な~そね」の形で)~てほしくない。~ないでほしい。 [接続] 動詞と動詞型に活用する助動詞の未然形、および終助詞「そ」に付く。 【参考】 ① と同類の上代語の終助詞に「な」「に」がある。 →「主要助詞活用表」 |
①-この岡に 菜摘ます子 家聞かな 告らさね-(万1-1) ① 在り嶺よし対馬の渡り海中に幣取り向けて早帰り来ね(万1-62) ① 丹生の川瀬は渡らずてゆくゆくと恋痛し我が背いで通ひ来ね(万2-130) ① 鳥座立て飼ひし雁の子巣立ちなば真弓の岡に飛び帰り来ね(万2-182) ② 高円の野辺の秋萩な散りそね君が形見に見つつ偲はむ(万2-233) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ねがふ [願ふ] | 〔他動詞ハ行四段〕 [四段動詞「祈(ね)ぐ」の未然形+上代の反復・継続の助動詞「ふ」] ① 神仏に祈る。祈願する。② 望む。得たいと願う。念ずる。 |
① 今夜の早く明けなばすべをなみ秋の百夜を願ひつるかも(万4-551) ① 水泡なす仮れる身ぞとは知れれどもなほし願ひつ千年の命を(万20-4494) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ねになく [音に泣く] | 声を出して泣く。 | 岩が根のこごしき山を越えかねて音には泣くとも色に出でめやも(万3-304) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ねのみしなかゆ [音のみし泣かゆ] |
〔なりたち〕[名詞「音(ね)+副助詞「のみ」+強意の副助詞「し」+四段動詞「泣く」の未然形「なか」+上代の自発の助動詞「ゆ」」] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ただもう泣けてくる。 | -なにしかも もとなとぶらふ 聞けば 音のみし泣かゆ 語れば-(万2-230) -夕霧に かはづは騒く 見るごとに 音のみし泣かゆ いにしへ思へば(万3-327) 君に恋ひいたもすべなみ葦鶴の音のみし泣かゆ朝夕にして(万3-459) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ねのみなく [音のみ泣く] | 〔自動詞カ行四段〕声を立てて泣く。 | -男じもの 負ひみ抱きみ 朝鳥の 音のみ泣きつつ 恋ふれども-(万3-484) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ねば | 〔成立ち〕打消の助動詞「ず」の已然形「ね」+接続助詞「ば」 ① (「ば」が順接の確定条件を表わす場合) 原因・理由の意で用いられる。 ~ないので。~ないから。 ② (「ば」が恒常条件を表わす場合) ~ないと。~ないときは。 ③ (「ば」が逆接の意を表す場合。「も~ねば」の形で) ~しないのに。 |
① 朝日照る嶋の御門におほほしく人音もせねばまうら悲しも(万2-189) ① -剣太刀 身に添へ寝ねば ぬばたまの 夜床も荒るらむ-(万2-194) ① -侍ひえねば 春鳥の さまよひぬれば 嘆きも いまだ過ぎぬに-(万2-199) ① -玉桙の 道行き人も ひとりだに 似てし行かねば すべをなみ-(万2-207) ③ -いまだ過ぎぬに 思ひも いまだ尽きねば 言さへく 百済の原ゆ-(万2-199) ③ 筑紫船いまだも来ねばあらかじめ荒ぶる君を見るが悲しさ(万4-559) ③ 見まつりていまだ時だに変はらねば年月のごと思ほゆる君(万4-582) ③ 秋立ちて幾日もあらねばこの寝ぬる朝明の風は手本寒しも(万8-1559) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ねばふ [根延ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕「ねはふ」とも 根が張る。根が長くのびる。 |
礒の上に根延ふむろの木見し人をいづらと問はば語り告げむか(万3-451) 紫草の根延ふ横野の春野には君を懸けつつ鴬鳴くも(万10-1829) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ねもころ [懇ろ] | 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 「ねんごろ」の古形 こまやかに行き届くさま。 |
-里にしあれば ねもころに 見まく欲しけど やまず行かば-(万2-207) 思ふらむ人にあらなくにねもころに心尽して恋ふる我れかも(万4-685) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔副詞〕心をこめて。熱心に。 | かわづ鳴く六田の川の川柳のねもころ見れど飽かぬ川かも(万9-1727) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の [野] | 〔名詞〕 草や小低木の自生している広い平地。のはら。 |
妻もあらば摘みて食げまし沙弥の山野の上のうはぎ過ぎにけらずや(万2-221) 君がため春の野に出でて若菜つむわが衣手に雪は降りつつ(古今春上-21) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の [箆] | 〔名詞〕矢の、幹の部分。矢柄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の 「主要助詞活用表『格助詞』」 | 〔格助詞〕 ① 連体修飾語を作る。所有・所属・所在など種々の関係を示す。 ア 所有を表す。~の。 イ 所属を表す。~の。~のうちの。 ウ 所在を表す。~の。~にある。 エ 時を表す。~の。 オ 作者・行為者を表す。~の。 カ 材料を表す。~の。 キ 名称・資格を表す。~という。~である。 ク 性質・状態を表す。~のような。 ケ 下に「ごとし・やうなり・まにまに・からに・ゆゑに」などを伴って、その様子・状態を表す。 ② 主語を表す。~が。 ③ いわゆる同格の意を表す。~で。~であって。 ア 同一の体言または準体言を前後に用いる。 イ 後ろの体言または準体言が省略された形。 ④ 連体修飾の被修飾名詞が省略された形。「の」が体言の代わりに用いられる ⑤ 各種の連用修飾語的用法。 ア 「を」 に近い意味を表す。 イ 「と」 に近い意味を表す。 ウ 「例の」 形で用いる。 エ 比喩的表現に用いる。~のように。 ⑥ 枕詞・序詞の終わりであることを示す。~のように。 〔接続〕体言および体言に準ずるものに付く。 |
① ウ 秋の野のみ草刈り葺き宿れりし宇治の宮処の仮廬し思ほゆ(万1-7) ① ウ 石上布留の山なる杉群の思ひ過ぐべき君ならなくに(万3-425) ① カ 置きて行かば妹はま愛し持ちて行く梓の弓の弓束にもがも(万14-3589) ① キ -か寄りかく寄り 靡かひし 嬬の命の たたなづく-(万2-194) ① キ あをによし奈良の都は咲く花の薫ふがごとく今盛りなり(万3-331) ① ク 大君の命恐み大殯の時にはあらねど雲隠ります(万3-444) ① ケ 大君の命畏み大船の行きのまにまに宿りするかも(万15-3666) ① ケ -時ならず 過ぎにし子らが 朝露のごと 夕霧のごと(万2-217) ② 朝ぐもり日の入り行けばみ立たしの島に下り居て嘆きつるかも(万2-188) ② 朝日照る佐田の岡辺に泣く鳥の夜哭きかへらふこの年ころを(万2-192) ② -か寄りかく寄り 靡かひし 嬬の命の たたなづく 柔肌すらを-(万2-194) ② -隠りのみ 恋ひつつあるに 渡る日の 暮れぬるがごと-(万2-207) ② 黄葉の散りゆくなへに玉梓の使を見れば逢ひし日思ほゆ(万2-209) ② -辺つへに あぢ群騒き ももしきの 大宮人の 罷り出て-(万3-259) ③ ア 須磨の海人の塩焼き衣の藤衣間遠にしあればいまだ着馴れず(万3-416) ③ ア 逆言の狂言とかも高山の巌の上に君が臥やせる(万3-424) ③ ア 風交り 雨降る夜の 雨交り 雪降る夜は すべもなく-(万5-896) ⑤ エ -網の浦の 海人娘子らが 焼く塩の 思ひぞ焼くる 我が下心(万1-5) ⑤ エ もののふの八十宇治川の網代木にいさよふ波のゆくへ知らずも(万3-266) ⑥ -網の浦の 海人娘子らが 焼く塩の 思ひぞ焼くる 我が下心(万1-5) ⑥ -夕川渡る この川の 絶ゆることなく この山の いや高知らす-(万1-36) ⑥ 埴安の池の堤の隠り沼のゆくへを知らに舎人は惑ふ (万2-201) ⑥ 滝の上の三船の山に居る雲の常にあらむと我が思はなくに(万3-243) ⑥ 見渡せば明石の浦に燭す火のほにそ出でぬる妹に恋ふらく(万3-329) ⑥ -心いさよひ その鳥の 片恋のみに 昼はも 日のことごと-(万3-375) ⑥ 川の上のいつ藻の花のいつもいつも来ませ我が背子時じけめやも(万4-494) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の | 〔終助詞〕中世末以降の用法。文を言い切ったところに付く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のぎ [野木] | 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻三-295 頭注『野木の松原』」】 住吉の野木の松原遠つ神我が大君の幸行処(万3-298) 野木は「吉隠(よなばり)の野木」(二三三九)のそれと同じく野中の立木。原文は底本など仙覚本には「清江乃木笶松原」とあるが、原本には「清江乃野木笶松原」とあったとみて改める。 「笶」は矢竹を意味する名詞ノ(乙類)を借りた訓仮名。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のさかのうら [野坂の浦] | 〔地名〕 |
芦北の野坂の浦ゆ船出して水島に行かむ波立つなゆめ(万3-247) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1『付録地名一覧』」】 熊本県芦北郡内であろうが所在未詳。 同郡田浦町田浦、芦北町佐敷(さしき)など、諸説がある。 「水島」(二四五題)までは、田浦から一五キロメートル、佐敷から二五キロメートル離れている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のさき [荷前・荷向] | 〔名詞〕 年末に諸国から貢物の初穂や絹布を天照大神をはじめ諸神、および諸陵墓に献じたこと。 またその貢物。 |
東人の荷前の箱の荷の緒にも妹は心に乗りにけるかも [禅師](万2-100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のしま [野島] | 〔地名〕和歌山県御坊市南部の島。 また、張り出た海岸の地を呼ぶ称として各地にもある名称。 |
我が欲りし野島は見せつ底深き阿胡根の浦の玉ぞ拾はぬ [或頭云 我が欲りし子島は見しを](万1-12) 玉藻刈る敏馬を過ぎて夏草の野島の崎に船近づきぬ(万3-251) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
〔地名 野島の埼〕 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1『付録地名一覧』」】 兵庫県津名郡北淡町野島。淡路島の西側、北端から約四キロメートルの辺り。昔、野島の蟇(ひきの)浦に長い岬があったという説もある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のち [後] | 〔名詞〕 ① あと。つぎ。以後。② 子孫。③ 未来。将来。④ 死後。 |
① 我が里に大雪降れり大原の古りにし里に降らまくは後(万2-103) ③ 梓弓引かばまにまに依らめども後の心を知りかてぬかも [郎女](万2-98) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のど [長閑] | 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 のどか。穏やか。静か。 |
明日香川しがらみ渡し塞かませば流るる水ものどにかあらまし [一云 水の淀にかあらまし](万2-197) 畏きや 神の渡りは 吹く風も のどには吹かず 立つ波も おほには立たず(万13-3349) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のどか [長閑] | 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 [「のどやか」 とも] ① (天候などが) 穏やかなさま。うららか。のどか。〔春〕 ② 心静かでのんびりしているさま。 ③ 落ち着いているさま。平気であるさま。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のどけし [長閑けし] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① (天候・状態などが) 静かで穏やかなさま。うららかである。 ② (気持ちや性質などが) 穏やかである。ゆったりしている。 ③ のんびりしたさま。暇である。 |
久方の光のどけき春の日に しづ心なく花の散るらむ(古今春下-84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のとせがは [能登瀬川・能登瀬の川] |
所在不明。 一説に滋賀県坂田郡近江町大字能登瀬を流れる辺りの天野川をいうか。 |
さざれ波礒越道なる能登瀬川音のさやけさ激つ瀬ごとに(万3-317) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のなか [野中] | 〔名詞〕野原のなか。 | 磐代の野中に立てる結び松心も解けずいにしへ思ほゆ(万2-144) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のなかのしみづ [野中の清水] | 【歌枕】播磨(兵庫県)印南野(いなみの)にあったという清水。 「にしへの野中の清水ぬるけれどもとの心をしる人ぞくむ」 (古今・雑上)から、疎遠になった恋人・旧友のたとえに用いる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のび [野火] | 〔名詞〕春の初めに、新しい草が生えやすいように野原の枯草を焼く火。 | -さつ矢手挟み 立ち向かふ 高円山に 春野焼く 野火と見るまで 燃ゆる火を-(万2-230) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のへ | 《上代東国方言》[打消しの助動詞「なふ」の連体形・已然形「なへ」の転] ~ない。 |
うべ子なは我ぬに恋ふなも立と月のぬがなへ行けば恋しかるなも(万14-3495) 或本歌末句曰 「ぬがなへゆけど、わぬゆがのへば」 遠しとふ故奈の白嶺に逢ほしだも逢はのへしだも汝にこそ寄され(万14-3497) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のへ [野辺] | 〔名詞〕野のあたり。野原。 | 高円の野辺の秋萩いたづらに咲きか散るらむ見る人なしに(万2-231) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のぼす [上す・泝す] | 〔他動詞サ行下二段〕【セ・セ・ス・スル・スレ・セヨ】 ① 上へ移す。高い所へ上げる。のぼらせる。 ② 川を溯らせる。③ 召し寄せる。呼び寄せる。④ 地方から都へ行かせる。 ⑤ おだてる。 |
② -真木のつまでを 百足らず 筏に作り 泝すらむ いそはく見れば -(万1-50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞サ行四段〕 ① 上へ移す。高い所へ上げる。のぼらせる。② おだてる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のぼりたつ [登り立つ] | 〔自動詞タ行四段〕山や丘などの高い所に登って立つ。 | -とりよろふ 天の香具山 登り立ち 国見をすれば 国原は 煙立ち立つ-(万1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のぼる [上る・登る・昇る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 高い所、上の方へ行く。のぼる。また、(川の)上流へ行く。遡る。 ② 海や川から陸地に移る。③ 地方から都へ行く。 ④ 宮中へ参内する。貴人のもとに参上する。 ⑤ 官位・官職が高くなる。 |
① -上りいましぬ [一云 神登り いましにしかば] 我が大君-(万2-167) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【「のぼる」 と「くだる」】 下(低) から上(高) へ行くのが「のぼる」、上から下へ行くのが「くだる」 の原義であるが、都に対する地方、宮廷・貴人の邸(やしき) に対する臣下の邸、貴人のいる場所に対する臣下の居所などを上に対する下と見て、その間の行き来にも、広く用いる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のみ | 〔副助詞〕[基本義] 以前に述べた一つの事を強調。限定の意味を表す。~だけ。 ① 限定の意を表す。「~だけ」「~ばかり」 ② 限定し強調する意を表す。「特に」「とりわけ」「もっぱら」 ③ 強調する意を表す。 〔接続〕体言その他種々の語につく。活用する語には連体形につく。 |
① 玉葛花のみ咲きてならざるは誰が恋ならめ我は恋ひ思ふを(万2-102) ① -心もあらず そこ故に せむすべ知れや 音のみも 名のみも絶えず-(万2-196) ① -雲居なす 心いさよひ その鳥の 片恋のみに 昼はも 日のことごと-(万3-375) ② 隠りのみ居ればいぶせみ慰むと出で立ち聞けば来鳴くひぐらし(万8-1483) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のむ [飲む・呑む] | 〔他動詞マ行四段〕のむ。飲酒する。 | 験なき物を思はずは一坏の濁れる酒を飲むべくあるらし(万3-341) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のもり [野守] | 〔名詞〕 禁猟区などの野を守る番人。 |
あかねさす紫野行き標野行き野守は見ずや君が袖振る(万1-20) 〔縁語〕 「野守」は「標野」の縁語 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のらす [宣らす・告らす] | 〔なりたち〕[四段動詞「宣(の)る」の未然形「のら」+上代尊敬助動詞「す」] おっしゃる。 |
-み堀串持ち この岡に 菜摘ます子 家告らせ 名告らさね そらみつ-(万1-1) 否と言へど語れ語れと詔らせこそ志斐いは奏せ強ひ語りと言ふ(万3-238) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のる [乗る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ①(馬・車・船などに)乗る。 ② 霊魂などが乗りうつる。こころに取りついて離れなくなる。 ③ 道に沿って進む。 ④ 気乗りする。調子付く。 ⑤ [「載る」と書く]記載される。書き記される。 ⑥ 欺かれる。策略にのる。 |
① 塩津山うち越え行けば我が乗れる馬そつまづく家恋ふらしも(万3-368) ① 大船に妹乗るものにあらませば羽ぐくみ持ちて行かましものを (万15-3601) ② 白雲の絶えにし妹をあぜせろと心に乗りてここば愛しけ(万14-3538) ③ その道にのりていでまさば(記・上) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のる [宣る・告る] | 〔他動詞ラ行四段〕 言う。述べる。告げる。 |
-しきなべて 我れこそ座せ 我れこそば 告らめ 家をも名をも(万1-1) 大船の津守が占に告らむとはまさしに知りて我がふたり寝し(万2-109) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻第二-109 のらむとは」注】 旧訓「ツケムトハ」を童蒙抄に「ノラムトハ」と改訓。「ノル」は呪力ある発言をあらわし、「ツグ・イフ」などとは異なる。天皇の発言や占に関して用いられることが多い。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| は | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| は [葉] | 〔名詞〕草や木の葉。 | 奥山の真木の葉しのぎ降る雪の降りは増すとも地に落ちめやも (万6-1015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| は 主要助詞活用表「格助詞」 | 〔格助詞〕(上代東国方言) 格助詞「へ」の転。方角を表わす。「~へ」 〔語法〕「いえびと(家人)」が「いはびと」となるように、エ段の音がア段の音に変ったもの。 |
我が背なを筑紫は遣りて愛しみえひは解かななあやにかも寝む(万20-4452) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔係助詞〕ある事柄を他と区別して、あるいは特にとりたてて言う意。 ① 特に提示する意を表わす。(主語のように用いる) ② 特にとりたてて区別する。 ③ 強調する気持ちを表わす。「なんと~が」 〔語法〕 ⅰ:格助詞「を」に付く時は「をば」となる ⅱ:中世の用法で撥音「ん」の下にくるときは「な」、促音「っ」の下にくるときは「た」と発音する場合がある。 |
① 居明かして君をば待たむぬばたまの我が黒髪に霜は降るとも(万2-89) ① 真木柱太き心はありしかどこの我が心鎮めかねつも(万2-190) ① -羽易の山に 我が恋ふる 妹はいますと 人の言へば 岩根さくみて-(万2-210) ① 秋はきぬ紅葉はやどにふりしきぬ道ふみわけてとふ人はなし (古秋下-287) ② 夏の夜はまだよひながら明けぬるを雲のいづこに月やどるらん (古夏-166) ② いにしへに恋ふらむ鳥は霍公鳥けだしや鳴きし我が念へるごと (万2-112) ③ きみがため春の野にいでてわかなつむ我が衣手に雪はふりつゝ (古春上-21) 〔語法ⅱ〕-妻別れ 悲しくはあれど 大夫の-(万20-4422) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔参考〕「は」と「が」の違い 「は」は、それについている事物を他からはっきり区別する語で、主語を表わす格助詞ではない。 「が」は、主語を表わしたり、連体修飾を表わしたりする格助詞であり、それぞれ述語・被修飾語と密接に結びつくが「は」にはそのような働きがない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔接続助詞〕 順接の仮定条件を表わす。~ならば。 〔接続〕形容詞、及び打消しの助動詞「ず」の連用形に付く。 |
言清くいたくもな言ひそ一日だに君いしなくは堪へ難きかも(万4-540) 恋しくは形見にせよと我が背子が植ゑし秋萩花咲きにけり(万10-2123) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔語法〕 動詞の未然形に付く接続助詞「ば」と同じ用法。 なお、この「は」が「ば」と濁り、「~くば」「~ずば」と読まれるようになったのは近世初期からである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔終助詞〕感動・詠嘆の意を表わす。「~よ」 〔接続〕文末に付く。 |
降る雪はあはにな降りそ吉隠の猪養の岡の寒からまくに(万2-203) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ば [主要助詞一覧] | 〔接続助詞〕 [順接の仮定条件] 「~(する)なら・~だったら」 [順接の確定条件] ① 原因・理由 「~ので・~だから」 ② 単純接続 「~すると・~したところ」 ③ 恒常条件 「~するときはいつも・~すると必ず」 [並列・対照]並列的・対照的に前後を繋ぐ「~(し)て、一方」 〔接続〕 仮定条件 「未然形」+「ば」 確定条件 「已然形」+「ば」(並列・対照ふくむ) |
[順接仮定] 夕さらば潮満ち来なむ住吉の浅香の浦に玉藻刈りてな(万2-121) つれもなき佐田の岡辺に帰り居ば島の御階に誰れか住まはむ(万2-187) -やまず行かば 人目を多み まねく行かば 人知りぬべみ-(万2-207) 朝に日に見まく欲りするその玉をいかにせばかも手ゆ離れずあらむ(万3-406) [順接確定] ① -花散らふ 秋津の野辺に 宮柱 太敷きませば ももしきの-(万1-36) ① 外に見し真弓の岡も君座せば常つ御門と侍宿するかも(万2-174) ① -入日なす 隠りにしかば 我妹子が 形見に置ける みどり子の-(万2-210) ② たけばぬれたかねば長き妹が髪このころ見ぬに掻き入れつらむか [三方沙弥] (万2-123) ② み立たしの島の荒礒を今見れば生ひざりし草生ひにけるかも(万2-181) ③ -打橋に 生ひををれる 川藻もぞ 枯るれば生ゆる なにしかも-(万2-196) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔係助詞〕 係助詞「は」が格助詞「を」について濁音化したもの。 ⇒「をば」動作・作用の対象を強く示す意を表わす。 |
相見ずは恋ひざらましを妹を見てもとなかくのみ恋ひばいかにせむ(万4-589) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はかひ [羽交ひ] | 〔名詞〕 ① 鳥の両翼の先の重なり合うところ。 ② 羽、つばさ。 ③(比喩的に用いて)経営している店。 |
① 葦辺行く鴨の羽交ひに霜降りて寒き夕は大和し思ほゆ(万1-64) ① -逢ふよしをなみ 大鳥の 羽易の山に 我が恋ふる 妹はいますと-(万2-210) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はかる [計る・量る] | 〔他動詞ラ行四段〕 ① おしはかる。推量する。② 予想する。予期する。 ③ (量・重さ・長さなどを) 測定する。④ 相談する。 ⑤ 計画する。たくらむ。⑥ 機をうかがう。見てとる。 ⑦ 〔「謀る」 とも書く〕だます。 |
④ -千万神の 神集ひ 集ひいまして 神分り 分りし時に 天照らす 日女の命-(万2-167) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はぎ [萩・(芽)] | 〔名詞〕 ① 植物の名。秋の七草の一つ。紅紫色または白色の小さな花をつける。 古来、秋を代表する草花として和歌に多く詠まれた。〔秋〕 ② 襲(かさね)の色目の名。表は蘇芳(すおう)=紫がかった赤色、 裏は青で、秋に用いる。 |
① かくのみにありけるものを萩の花咲きてありやと問ひし君はも(万3-458) ① 萩の花尾花葛花なでしこの花をみなへしまた藤袴朝顔の花 (万8-1542) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-455 注『萩の花』」】 原文「芽子花」。万葉集には「萩」の字はなく、「芽子」「芽」の字を用いている。「萩」は中国では「よもぎ(蕭)」の意で、『新撰字鏡』に「萩、蒿蕭類也、波支(ハギ)又伊良(イラ)」とあるのを見ると、「ハギ」と訓むのは国訓であることが分かり、平安朝初期の頃からのことである。「芽子」は、『本草綱目』(巻十七) に「狼牙」の一名を「牙子」とするが、「はぎ」の一葉三片と似ていることから、牙子をハギに通じさせ、さらに芽子と書いたものという(山本章夫『万葉古今動植正名』)。さて、旧訓「ハギノハナ」を、略解に「ハギガハナ」とした。しかし「波疑能花(ハギノハナ)」(20・四五一五) の如く「ハギノハナ」と訓むべきで、「ハギガハナ」は「萩が花散るらむ小野の」(古今集4・二二四) などの中古人の語感によるものであろう(池上禎造「『梅が花』と『梅の花』」『万葉雑記』所収)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はく [着く・著く] | 〔他カ行〕 ① 四段 ②下二段【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】弓に弦を張る。 |
① 陸奥の安達太良真弓はじき置きて反らしめきなば弦はかめかも (万14-3456) ② 梓弓弦緒取りはけ引く人は後の心を知る人ぞ引く(万2-99) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はこ [箱・篋・筥] | 〔名詞〕物をおさめる器。多く、蓋と身からなる。 | 東人の荷前の箱の荷の緒にも妹は心に乗りにけるかも [禅師](万2-100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はし [端] | 〔名詞〕 ① へり。ふち。先端。② 家の外側に面している部分。特に縁側。 ③ 物事の端緒。発端。きっかけ。④ 一部分。断片。切れ端。 ⑤ 中間。中途半端。 |
⑤ 木にもあらず草にもあらぬ竹の節(よ)の はしに我が身はなりぬべらなり (古今雑下-959) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はし [愛し] | 〔形容詞シク活用〕 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 愛らしい。いとおしい。したわしい。 |
み吉野の玉松が枝ははしきかも君が御言を持ちて通はく(万2-113) -道だに知らず おほほしく 待ちか恋ふらむ はしき妻らは(万2-220) 愛しきかも皇子の尊のあり通ひ見しし活道の道は荒れにけり(万3-482) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はし [橋] | 〔名詞〕① 川などに架け渡した通路。② 殿舎に架け渡した橋状の渡り廊下。 | ① つれもなき佐田の岡辺に帰り居ば島の御階に誰れか住まはむ(万2-187) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はしきやし (はしきよし) [愛しきやし] |
「愛(は)し[= いとおしい]」と思う意から) 愛惜・嘆息・追慕などの感動を表わす。 ああ。ああ、いとしい。ああ、かわいそう。ああ、なつかしい。 |
-はしきやし 我が妻の子が 夏草の 思ひ萎えて 嘆くらむ 角の里見む-(万2-138) はしきやし栄えし君のいましせば昨日も今日も我を召さましを(万3-457) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はじむ [始む] | 〔他動詞マ行下二段〕【メ・メ・ム・ムル・ムレ・メヨ】 ① 新たに事を起こす。始める。 ②(「~よりはじめ(て)」~をはじめ(て)」などの形で) 「~を始めとする」「~を第一とする」 |
① -荒栲の 藤井が原に 大御門 始めたまひて 埴安の 堤の上に-(万1-52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はじめ [初め・始め] | 〔名詞〕 ① 最初。はじまり。物事の起こり。② 以前。前。 ③ 物事の順序の第一。また、最初の部分。 ④ 事の次第。事の一部始終。 |
天地の 初めの時の ひさかたの 天の河原に 八百万 千万神の-(万2-167) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はず [筈・弭] | 〔名詞〕 ① 弓の両端の弦をかけるところ。弓筈(ゆはず)。 ② 矢の上端の弦を受けるところ。矢筈(やはず)。はく。 |
-み執らしの 梓の弓の 中弭の 音すなり 朝猟に 今立たすらし 夕猟に-(万1-3) 【「万1-3」の「中弭は諸説があるが未詳】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はしりで [走り出] | 〔名詞〕「わしりで」とも。 家から走り出たところ。家の門に近い所。門口。一説に、山の裾を引いているいる姿。 |
- 我がふたり見し 走出の 堤に立てる 槻の木の こちごちの枝の-(万2-210) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はた [幡・旗] | 〔名詞〕 ① (仏教語) 仏・菩薩の威徳を示すための荘厳(しようごん=飾り付け) の道具の一つ。 法要や説法の時、境内に立てたり堂内に飾ったりする。幡(ばん)。 ② 装飾や標識として、朝廷の儀式や軍陣にかかげる旗。 |
② -ささげたる 幡の靡きは 冬こもり 春さり来れば 野ごとに-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はだ [肌・膚] | 〔名詞〕 ① 表面。② 皮膚。③ きめ。④ 気性。気だて。 |
① 「初土(はつに)ははだ赤らけみ」(記中) ② 蒸し衾なごやが下に臥せれども妹とし寝ねば肌し寒しも(万4-527) ② -心消失せぬ 若かりし 肌も皺みぬ 黒くありし 髪も白けぬ-(万9-1744) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はたこ | 畑子らが夜昼といはず行く道を我れはことごと宮道にぞする(万2-193) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻二-193 注 「はたこらが」」】 原文「八多籠良我」。金澤本・古葉略類聚鈔・紀州本・西本願寺本などに、「ハタコラカ」 とあったのを、流布本では「ヤタコラガ」 と改訓。代匠記(精選本) に、「ヤタコラカハ、タトツト通スレハ、奴等カト云ニヤ」 と説き、また「八ノ字ハ音訓共ニ用レハ、音ヲ取テハタコラカト読ヘキカ」 とも言う。 ここは橋本四郎「八多籠」(万葉九号) に古写本の訓と同様ハタコと訓み、畑子すなわち畑で働く者の意としたのによるべきだろう。 「八」 は音訓両用の仮名で、ハにもヤにも宛てられるが、あとに「t」あるいは「t∫」 頭子音を含む音仮名の続く場合に「ハ・」 の連合仮名として使われる(稲岡『万葉表記論』)。 ここも「八多(ハタ)」 と訓むのであろう。籠は子の借訓字、網子(アコ)・楫子(カコ) などの「コ」 と同じく或る仕事に従事する人をあらわす。 その場合、コは関係の深い物を示す名詞に接するのであり、「田子」(蜻蛉日記) という語も見られるように畑子も認められるだろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はたす [果たす] | 〔他動詞サ行四段〕 ① なしとげる。物事を終える。 ② 神仏への願がかなって、その願をとくためのお礼参りをする。願ほどきをする。 ③ 殺す。討ち取る。 |
① -結びてし ことは果たさず 思へりし 心は遂げず 白たへの-(万3-484) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はたすすき [旗薄] | 〔名詞〕[「はだすすき」とも書く] 穂が風に吹かれて旗のようになびいているすすき。[秋] |
夕去り来れば み雪降る 安騎の大野に 旗すすき 小竹を押しなべ 草枕(万1-45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】一説に「膚薄(はだすすき)」で穂が出る前の皮を被っているすすきの意ともいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はだすすき [はだ薄] | 【枕詞】[「はたすすき」とも] 「すすき」の縁で、「穂」「うら(=末、穂の先)」にかかる。 |
はだ薄久米の若子がいましける [一云 けむ] 三穂の岩屋は見れど飽かぬかも [一云 荒れにけるかも](万3-310) はだすすき穂には咲き出ぬ恋をぞ我がする玉かぎるただ一目のみ見し人ゆゑに (万10-2315) かの子ろと寝ずやなりなむはだすすき宇良野の山に月片寄るも(万14-3587) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はたのまねき [旗のまねき] | 〔名詞〕 【有斐閣「萬葉集全注巻二-199 注「ささげたる幡の靡きは」】 「指擧」 はササゲと訓む。サシアゲの約。旧訓サシアクルであったのを万葉考にササゲタルと改訓した。幡は軍防令の義解に「幡者旌旗惣名也」 という。 和名抄に「幡 波太」 とある。 当時のハタは縦に細長いのぼりのような形のものが多かったらしい。攷證に「さて、ここに幡のなびくを、火と見なしたる、思へば、この幡は、赤幡なりけん」 と記す。 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1」巻二-199 頭注「旗のまねき」】 マネキの原文「麾」 は指揮に用いる旗の義。ここは旗印を言うのであろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はたや [将や] | 〔副詞〕 〔なりたち〕副詞「はた」+疑問の係助詞「や」 (語感)未来について疑い、あるいは心配している感じ。 「もしかすると・・・か」「あるいは・・・か」 |
み吉野の山のあらしの寒けくにはたや今夜も我が独り寝む(万1-74) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻第一-74 原文『為当』」頭注】 原文「為当」は、もし、また、などの意の「為」と同じく、二つの物を並べて選択する場合に用いる中国の俗語的用法。「ヤ・・ム」(ますらをや片恋せむ) 【有斐閣「万葉集全注巻第一-74 「や・・・む」注】 「や・・・む」は、詠嘆の性格のこもる疑問推量を表わし、目下の自己の動作について、こんなにも~することか、という気持ちを表すことが多い。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はぢ [恥・辱] | 〔名詞〕 ① 面目を失うこと。侮辱を受けること。 ② 恥を知ること。名誉・体面を重んじること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はつ [泊つ] | 〔自動詞タ行下二段〕【テ・テ・ツ・ツル・ツレ・テヨ】 船が港に着いて泊る。停泊する。 |
大船の泊つる泊りのたゆたひに物思ひ痩せぬ人の子故に(万2-122) 照る月を雲な隠しそ島蔭に我が舟泊てむ泊 (とま) り知らずも(万9-1723) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はづ [恥づ・羞づ] | 〔自動詞ダ行上二段〕【ヂ・ヂ・ヅ・ヅル・ヅレ・ヂヨ】 ① 恥ずかしく思う。きまり悪く思う。恥じる。 ② 遠慮する。気がねする。 |
山守がありける知らにその山に標結ひ立てて結ひの恥しつ(万3-404) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はつせ [泊瀬・長谷] | 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 付録『地名一覧』」】 奈良県桜井市初瀬(はせ)を中心に宇陀郡榛原町の一部にかけての一帯。初瀬(はせ)川の流域で、東西に長い峡谷状の地形であるところから「長谷」とも書かれる。 大和から伊賀・伊勢に出る通路に当たる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はつせがは [初瀬川] | 〔地名〕[歌枕] 「泊瀬川」とも書く。 今の奈良県桜井市初瀬(はせ)を流れる初瀬川の古称。 大和高原から流出し、佐保川に合して大和川となる。 |
柔びにし 家を置き こもりくの 泊瀬の川に 舟浮けて 我が行く川の(万1-79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はつせやま [初瀬山] | 〔地名〕[歌枕] 「泊瀬山」とも書く。 今の奈良県桜井市初瀬(はせ)の地の周囲の山。 |
-都を置きて 隠口の 初瀬の山は 真木立つ 荒き山道を 岩が根-(万1-45) つのさはふ磐余も過ぎず泊瀬山いつかも越えむ夜は更けにつつ(万3-285) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はつせをとめ [泊瀬娘子] | 【有斐閣「萬葉集全注巻三-424 注『泊瀬娘子』」】〕 泊瀬に住む女で、石田王の愛人。「娘子」 の原文「越女」の「越」 は、「越乞(ヲチコチ)」(あちこち) の如き「ヲチ」 の音、またこのように「ヲト(乙類)」 の音に用いられている。だいたい二音仮名が歌の中に用いられる時は、「i」と「u」 に母音が集中するが、「ヲト」 のように「Ö」 がつくのは珍しい。「ヲ」の「オ列」に同化したためであろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はな [花] | 〔名詞〕 ① 草木の花。 ア:特に梅の花。イ:特に桜の花。 ② はなやかなこと。美しいこと。うるわしいこと。 ③ 栄えること。名誉。 ④ (花は咲いても実にならない意から) うわべだけで真実味のないこと。 ⑤ 露草の花からとった青い絵の具。 ⑥ 薄いあい色。縹 (はなだ) 色。花色。 ⑦ 芸人などに当座の賞として与えるもの。祝儀。心づけ。⑧ 生け花。 ⑨ 和歌・俳諧で、表現技巧をいう。 実 (=真情)に対応し、花実相そなわるものがすぐれた作とされた。 ⑩ 《能楽用語》(観客を引きつける) 芸の美しさ・魅力・はなやかさ。 |
① 橘は実さへ花さへその葉さへ枝に霜降れどいや常葉の木(万6-1014) ①「ア」人はいさ心も知らず古里は花ぞ昔の香ににほひける(古今春上-42) ①「イ」久方の光のどけき春の日にしづ心なく花の散るらむ(古今春下-84) ② 今の世の中、色につき、人の心、花になりけるより(古今仮名序) ④ 玉葛花のみ咲きてならざるは誰が恋ならめ我は恋ひ思ふを(万2-102) ④ 霞立つ春日の里の梅の花花に問はむと我が思はなくに(万8-1442) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【古典における「花」】 -古典において「花」という語は、特に「桜の花」の代名詞として使われた。 ただ「花」が「桜の花」の意味だけに使われるのは、中古の「拾遺集」のころであり、それ以前「古今集」「後撰集」では、「花」は「① イ」のように「桜の花」を指すほか、「① ア」のように「梅の花」を指す場合にも用いられた。 時代が下るにつれて、「花」=「桜の花」と、「花」と言えば、まず「桜」が思い出されるように、人々の生活の中で「桜」の占める位置が大きくなる。 現代語では「花」=「桜の花」の関係は、「花見」「花便り」のように、一部の複合語の中に残るだけである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はなたちばな [花橘] | 〔名詞〕 ① 橘の花。花の咲いた橘。時鳥が宿るとされ、また右掲の古今和歌によって昔を思い出させる縁(よすが)とされた。 ② 「襲(かさね)の色目」の名。表は朽ち葉、裏は青。四、五月ころ着用。 |
① さつきまつ花たちばなの香をかげば 昔の人の袖の香ぞする(古今夏-139) ① -ほととぎす 鳴く五月には あやめぐさ 花橘を 玉に貫き-(万3-426) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はなちどり [放ち鳥] | 〔名詞〕 ① 翼を切って放し飼いにした水鳥。 ② 祈願や死者の追善のため、籠のなかの鳥を放してやること。 |
① 嶋の宮まがりの池の放ち鳥人目に恋ひて池に潜かず(万2-170) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はなぢらふ [花散らふ] | 【枕詞】「秋津」にかかる。 稲の花が盛んに散る意で、豊かな稔りの秋を想起させる。 |
-御心を 吉野の国の 花散らふ 秋津の野辺に 宮柱 太敷きませば-(万1-36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はなつ [放つ] | 〔他動詞タ行四段〕 ① 《上代語》くずす。こわす。② 離す。手放す。 ③ 束縛を解く。自由にさせる。放し飼いにする。 ④ 追放する。流罪にする。 ⑤ (戸や障子などを)開け放す。開く。⑥ 遠ざける。 ⑦ 人手に渡す。売り払う。ゆずる。 ⑧ (火・光・声などを)発する。⑨ (矢などを)射る。射出する。 ⑩ 除く。さしおく。のけものにする。 ⑪ (「ことばをはなつ」の形で)思いのままに言う。放言する。 ⑫ 免職にする。解任する。 ⑬ (髻(もとどり)などを)あらわに出す。むき出しにする。 |
① 「またその畔(あ)を放つ」(神代紀) ② とこしへに夏冬行けや裘扇放たぬ山に住む人(万9-1686) ③ わたつみの沖に持ち行きて放つともうれむそこれのよみがへりなむ(万3-330) ③ いとはるるわが身は春の駒なれや のかひがてらに放ちすてつる(古今雑体-1045) ⑧ 「大臣(おほおみ)の宅(いへ)を囲み、火を放ちて焼く」(武烈紀) ⑨ -しのぎ羽を 二つ手挟み 放ちけむ 人し悔しも 恋ふらく思へば(万13-3316) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 現代語には「放す」というサ行の語があるが、タ行→サ行という変化をしたもので、類する語に「消つ」→「消す」、「ふたぐ」→「ふさぐ」などがある。 中世に変化したもの。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はなる [離る・放る] | 〔自動詞ラ行下二段活用〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 ① はなれる。遠ざかる。隔たる。 ② 別れる。縁が切れる。関係がなくなる。③ 逃げる。 ④ 官職を辞任する。免官となる。 |
① 北山にたなびく雲の青雲の星離り行き月を離れて(万2-161) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はにふ [埴生] | 〔名詞〕 ①「埴(はに)のある土地。また、埴。②「埴生の小屋(をや)」の略。 |
① 草枕旅行く君と知らませば岸の埴生ににほはさましを(万1-69) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻第一-69 埴(ハニ)」頭注】 「ハニ」は赤土・黄土の類。水酸化鉄。鮮やかな黄色で、これを焼いて酸化させたものが「べんがら」。帯黄赤色をなし、顔料に用いられる。 ただし、染料に使った確証はなく、摺染の料としたものか。―「フ」は生ずる所を示す。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はにふのをや [埴生の小屋] | 〔名詞〕[「はにふのこや」とも] 土で塗った粗末な家。 (一説に、「埴」をとるような低地にある家。みすぼらしい、粗末な家とも) |
彼方の埴生の小屋に小雨降り床さへ濡れぬ身に添へ我妹(万11-2691) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はにやす [埴安] | -使はしし 御門の人も 白栲の 麻衣着て 埴安の 御門の原に-(万2-199) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻二-199」 注『埴安』】 埴安は藤原宮の東、香久山の西北麓にあたる。 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻二-199 頭注「埴安の御門の原」】 埴安の池のほとりの高市皇子の宮殿前の広場。埴安の池はかつて香久山の西南部にあった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はにやすのいけ [埴安の池] | 〔地名〕上代、今の奈良県香具山の西側の麓にあった池。 | 埴安の池の堤の隠り沼のゆくへを知らに舎人は惑ふ(万2-201) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はぬ [跳ぬ・撥ぬ] | 〔自動詞ナ行下二段〕【ネ・ネ・ヌ・ヌル・ヌレ・ネヨ】 ① 飛び上がる。おどり上がる。② はじける。とび散る。 ③ その日の興業が終わる。 〔他動詞ナ行下二段〕 ① はね上げる。② (普通「刎ぬ」と書く) 首などを切り落とす。 ③ 一部分をかすめとる。上前をはねる。 |
〔他動詞ナ行下二段〕 ① ― いたくな撥ねそ 辺つ櫂 いたくな撥ねそ 若草の―(万2-153) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はは [母] | 〔名詞〕自分を生み育てた女性。女親。母親。 | 憶良らは今は罷らむ子泣くらむそれその母も我を待つらむそ(万3-340) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はばかる [憚る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 障害があって、行き悩む。進めないでいる。 ② はびこる。いっぱいになる。 〔自動詞ラ行四段〕恐れ慎む。遠慮する。 |
① -い行きはばかり 時じくそ 雪は降りける 語り継ぎ 言ひ継ぎ行かむ-(万3-20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ははのみこと [母の命] | 〔名詞〕「母」 の敬称。 | -たらちねの 母の命は 斎瓮を 前に据ゑ置きて 片手には-(万3-446) たらちねの母の命の言にあらば年の緒長く頼め過ぎむや(万9-1778) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はひ [灰] | 〔名詞〕灰。 | -なづみ来し よけくもぞなき うつそみと 思ひし妹が 灰にていませば(万2-213) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はひたもとほる [這ひ徘徊る] | 〔自動詞ラ行四段〕[「た」は接頭語] はい回る。=這ひ徘徊(もとほ)る。 | みどり子の這ひたもとほり朝夕に音のみそ我が泣く君なしにして(万3-461) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はふ [這ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 ① 腹這う。這うようにして進む。 ② 植物のつるなどが伸びてゆく。はびこる。 |
① -あかねさす 日のことごと 獣じもの い匍ひ伏しつつ ぬばたまの-(万2-199) ① -い這ひ拝め 鶉こそ い這ひもとほれ 鹿じもの い這ひ拝み-(万3-240) ② ちはやぶる神のいがきにはふ葛も秋にはあへずうつろひにけり (古今秋下-262) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はふ [延ふ] | 〔他動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 ① 引きのばす。張りわたす。 ② 思いをかける。心を寄せる。 |
① -墨縄を 延へたるごとく あぢかをし 値嘉の崎より-(万5-898) ② 谷狭み嶺辺に延へる玉葛延へてしあらば年に来ずとも [一云 岩つなの延へてしあらば](万12-3081) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はふくずの [這ふ葛の] | 【枕詞】 葛のつるが長くはってゆく状態から、 「遠長(とほなが)し」「後(のち)」「行くヘ」「絶えず」「下」「尋ぬ」 にかかる。 |
-延ふ葛の いや遠長く [一云 葛の根の いや遠長に] 万代に-(万3-426) 梨棗黍に粟つぎ延ふ葛の後も逢はむと葵花咲く(万16-3856) 大崎の荒礒の渡り延ふ葛のゆくへもなくや恋ひわたりなむ(万12-3086) 延ふ葛の絶えず偲はむ大君の見しし野辺には標結ふべしも(万20-4533) 藤波の咲く春の野に延ふ葛の下よし恋ひば久しくもあらむ(万10-1905) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はふつたの [這ふ蔦の] | 【枕詞】 蔦の先が分かれて伸びてゆくことから、 「おのがむきむき」「別れ」 にかかる。 |
-さ寝し夜は 幾だもあらず 延ふ蔦の 別れし来れば- (万2-135) -黄泉の境に 延ふ蔦の おのが向き向き 天雲の池- (万9-1808) -しなざかる 越道をさして 延ふ蔦の 別れにしより 沖つ波- (万19-4244) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はぶる [葬る] | 〔他動詞ラ行四段〕[「はふる」とも] ① 埋葬する。葬る。② 火葬にする。 |
-言さへく 百済の原ゆ 神葬り 葬りいまして あさもよし -(万2-199) -磐余を見つつ 神葬り 葬りまつれば 行く道の たづきを知らに-(万13-3338) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はま [浜] | 〔名詞〕 ① 海や湖に沿った平らな陸地。浜辺。 ② 囲碁で囲んで取った相手の石。上げ石。 |
① 大伴の御津の浜なる忘れ貝家なる妹を忘れて思へや(万1-68) ① 越の海の 角鹿の浜ゆ 大船に 真楫貫き下ろし いさなとり-(万3-369) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はまかぜ [浜風] | 〔名詞〕 浜に吹く風。 |
我妹子を早見浜風大和なる我れ松椿吹かざるなゆめ(万1-73) 淡路の野島の崎の浜風に妹が結びし紐吹き返す(万3-252) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はまのまさご [浜の真砂] | 浜にある砂。無数にあるもののたとえ。 | このたび、(歌を)集め選ばれて、山下水の絶えず、 浜の真砂の数多く積りぬれば(古今仮名序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はまべ [浜辺] | 〔名詞〕[古くは「はまへ」] 浜のほとり。 |
-廬りて見れば 波の音の 繁き浜辺を しきたへの 枕になして-(万2-220) 神風の伊勢の浜荻折り伏せて旅寝やすらむ荒き浜辺に(万4-503) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はままつ [浜松] | 〔名詞〕浜辺に生えている松。 | 磐白の浜松が枝を引き結びま幸くあらばまた帰り見む(万2-141) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はまゆふ [浜木綿] | 〔名詞〕草の名。ハマオモトの異称。暖地の海岸に自生する。葉が幾重にも重なるところから、「百重」「幾重」などを導く序詞に用いられる。また、葉が重なって茎を隔てているところから、幾重にも隔てるものの譬に用いられる。〔季語:夏〕 | み熊野の浦の浜木綿百重なす心は思へど直に逢はぬかも(万4-499) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はまをぎ [浜荻] | 〔名詞〕① 浜辺に生えている荻。〔季語:秋〕② 葦の別名。 | 神風の伊勢の浜荻折り伏せて旅寝やすらむ荒き浜辺に(万4-503) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はむ [食む] | 〔他動詞マ行四段〕 ① 食べる。飲む。 ②(俸禄や知行を)受ける。 |
① うつせみの命を惜しみ波に濡れ伊良虞の島の玉藻刈り食む(万1-24) ① 瓜食めば 子ども思ほゆ 栗食めば まして偲はゆ いづくより-(万5-806) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はも | 〔上代語〕【なりたち】係助詞「は」+係助詞「も」 文中に用いて、上の語を取り立てて示す。~は。 |
― 山科の 鏡の山に 夜はも 夜のことごと 昼はも 日のことごと ―(万2-155) ― あやに畏み 昼はも 日のことごと 夜はも 夜のことごと ―(万2-204) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔上代語〕【なりたち】終助詞「は」+終助詞「も」 文末に用いて、回想や愛惜の気持ちを込めた感動・詠嘆の意を表す。 ~よ。~なあ。 |
― 小野(をの)に燃ゆる火の火中(ほなか)に立ちて問ひし君はも―(記・中) 高光る我が日の御子の万代に国知らさまし嶋の宮はも(万2-171) 葦辺には鶴がね鳴きて湊風寒く吹くらむ津乎の崎はも(万3-355) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はや [早・速] | 〔副詞〕 ① 早く。急いで。さっさと。② 早くも。すでに。 ③ 他でもない。実は。 |
① 在り嶺よし対馬の渡り海中に幣取り向けて早帰り来ね(万1-62) ① 早来ても見てましものを山背の高の槻群散りにけるかも(万3-280) ② 昨日こそ年は果てしか春霞春日の山に早立ちにけり(万10-1847) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はやく [早く] | 〔副詞〕[形容詞「早し」の連用形から] ① すでに。とっくに。②昔。以前。③もともと。元来。 ④(多く助動詞「けり」を文末に伴って)驚いたことには。なんと実は。 |
②「はやく住けるところにて郭公(ほととぎす)のなきけるを聞きてよめる」 (古今夏-163詞書) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はやし [林] | 〔名詞〕① 樹木が群生しているところ。② 物事が多く集まっている所。 | ① -取り持てる 弓弭の騒き み雪降る 冬の林に [一云 木綿の林] -(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はやし [早し・速し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① 速度が速い。すばやい。 ②(時期的・時間的に)早い。③激しい。急である。 ④(香りが)鋭い。強い。 |
① いざ子ども早く日本へ大伴の御津の浜松待ち恋ひぬらむ(万1-63) ① 吉野川行く瀬の早みしましくも淀むことなくありこせぬかも(万2-119) [「早み(はやみ)」は「早し」のミ語法] ② 我妹子を早見浜風大和なる我れ松椿吹かざるなゆめ(万1-73) [「早見(はやみ)」は「早し」のミ語法] ② 朝烏早くな鳴きそ我が背子が朝明の姿見れば悲しも(万12-3109) ③ たぎつ瀬の早き心を何しかも人目つつみのせきとどむらむ(古今恋三-660) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はやひと [隼人] | 〔名詞〕[「はやと」とも] 上代、今の鹿児島地方に住んでいた種族。律令制下では、宮門の守護、行幸の先駆をし、大礼の日には「風俗(ふぞく)」の歌舞などを奏した。 |
隼人の薩摩の瀬戸を雲居なす遠くも我は今日見つるかも(万3-249) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はゆま [駅・駅馬] | 〔名詞〕〔「はやうま」の転〕 令制で、諸道の宿駅に備えてあった、公用の馬。伝馬(てんま)。=駅馬(えきば)。 |
左夫流児が斎きし殿に鈴掛けぬ駅馬下れり里もとどろに(万18-4134) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はゆる | 【武田祐吉萬葉集全註釈巻2-196 釋「干者波由流」1956年初版】 カルレバハユル。枯れればまた生える。上の川藻モゾのゾを受けて生ユルという。生ユルの原文波由流と書いてあるのは、假字づかいを證するものである。ここにも人生無常の意が寓せられているのであろう。以上第一段の第二節、石橋に生ヒ靡ケル玉藻モゾ絶ユレバ生フルと、打橋ニ生ヒヲヲレル川藻モゾ枯ルレバ生ユルとは、對句をなし、明日香川の水草について敍している。この一段は、次の段を引き起す序として構成されている。 【橘千蔭萬葉集略解巻2-196 寛政8〜文化9年(1796〜1812 刊】 タユレバオフルは、人死にて又歸らぬを言はむとてなり。ヲヲレルは、打橋の邊に生ひたる藻の靡くを言ふ。此爲は烏の誤りなるべし。卷六に、春べには花|咲乎遠里《サキヲヲリ》、また春されば乎呼理《ヲヲリ》爾ををりなどあまた有り。ヲヲリはタワミの意なり。 考の別記に委し。川藻モゾカルレバハユルも、詞を變へたるのみにて生ふるなり。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はらから [同胞] | 〔名詞〕母の同じ兄弟姉妹。転じて、一般に兄弟姉妹。 | -良しと聞かして 問ひ放くる 親族兄弟 なき国に 渡り来まして-(万3-463) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はらふ [払ふ・掃ふ] | 〔他動詞ハ行四段〕 ① 取り除く。除き去る。はたいて除く。掃除する。 ② 追い払う。先払いをする。③ 賊を討伐する。平定する。 |
③ -天の下 治めたまひ [掃ひたまひて] 食す国を 定めたまふと-(万2-199) ③ -天降りまし 払ひ平げ 千代重ね いや継ぎ継ぎに 知らし来る-(万19-4278) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はり [榛] | 〔名詞〕 「榛(はん)の木」の異名。 |
綜麻形の林のさきのさ野榛の衣に付くなす目につく吾が背(万1-19) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【「野榛」】 「野の榛」、「野」は格助詞の「の」ではなく、接頭語「さ」が付き、「野榛」になると思う。小学館「新編日本古典文学全集万葉集」のこの歌の頭注には、 「野榛」は、「ハリ」とも。ハリは、かばのき科「はんのき」の古名。秋熟したまつかさ状の実の煎汁に灰汁や鉄などの触媒を加えて褐黄色・褐色・紺黒色などさまざまな色の染料とした。 この榛の語に、三輪山神話の跡認(あとつな)ぎの小道具で同音語の「針」が隠されている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はりはら [榛原] | 〔名詞〕はんの木の生えている原。 | 間野ににほふ榛原入り乱れ衣にほはせ旅のしるしに(万1-57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はりめ [針目] | 〔名詞〕針の縫い目。縫った糸のあと。 | 我が背子が着せる衣の針目落ちずこもりにけらし我が心さへ(万4-517) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はる [春] | 〔名詞〕 ① 四季の一つ。陰暦で一月から三月までの季節。〔春〕 ② 新年。正月。新春。 |
① -堤に立てる 槻の木の こちごちの枝の 春の葉の 繁きがごとく-(万2-210) ① 佐保川の岸のつかさの柴な刈りそねありつつも春し来らば立ち隠るがね(万4-532) ① 春たてば花とや見らむ 白雪のかかれる枝にうぐひすの鳴く(古今春上-6) ① ほのぼのと春こそ空に来にけらし 天の香久山かすみたなびく(新古今春上二-2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はる [張る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 一面に広がる。② 芽が出る。芽ぐむ。③ 気負う。張り合う。 |
② 山背の久世の鷺坂神代より春は張りつつ秋は散りけり(万9-1711) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞ラ行四段〕 ① 広げる。のべわたす。ひっぱる。② 設ける。しかける。 ③ (気持ちを)緊張させる。④ 金をかけて勝負する。⑤ うつ。殴る。 |
① 天の原振り放け見れば白真弓張りてかけたり夜道は良けむ(万3-292) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はるがすみ [春霞] | 〔名詞〕春のかすみ 〔春〕 | ① はるがすみ立つを見捨てて行く雁は花なき里に住みやならへる(古春上-31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】 同音を重ねて「かすが」に、霞の立つのを「居る」というところから「たつ」「井(ゐ)」に、また霞が立って直接に物が見えない意から「よそに」にかかる。 |
春霞春日の里の植ゑ子水葱苗なりと言ひし枝はさしにけむ(万3-410) 春霞井の上ゆ直に道はあれど君に逢はむとた廻り来も(万7-1260) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はるけし [遥けし] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ①(空間的に)非常に遠い。ひどく離れている。 ②(時間的に)ずっと遠い。久しい。はるかである。 ③(心理的に)遠く隔たっている。心が遠く離れている。 【「とほし」と「はるけし」の違い】⇒「とほし」 |
② 人目ゆゑのちにあふ日のはるけくはわがつらきにや思ひなされむ (古今物名-434) ③もろこしも夢にみしかば近かりき思はぬ仲ぞはるけかりける(古今恋五-768) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はるくさの [春草の] | 【枕詞】 (若草が生い茂る意から)「繁(しげ)し」、 (冬枯れの野に芽生えることから)「いやめづらし」にかかる。〔春〕 |
春草の繁き我が恋大海の辺に行く波の千重に積もりぬ(万10-1924) -仰ぎて見れど 春草の いやめづらしき 我が大君かも(万3-240) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はるとりの [春鳥の] | - 侍ひえねば 春鳥の さまよひぬれば 嘆きも いまだ過ぎぬに 思ひも- (万2-199) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【比喩的枕詞】 [有斐閣「萬葉集全注巻二-199 注 『春鳥のさまよひぬれば』] 「春鳥の」は比喩的枕詞。サマヨフにかかる。原文「佐麻欲比奴礼者」とサマヨヒを仮名書きしている。 サマヨフは新撰字鏡の「※(喔の至が米)」に「呻吟」とも「佐万与不」「奈介久」とも注があり、また呻に「吟也歎也佐萬與不又奈介久」ともあるように嘆きの声を発することをいう。 巻二十にも「春鳥の声のさまよひ」(四四〇八) の例を見る。春の鳥のように嘆いているとの意。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はるの [春野] | 〔名詞〕春の野原。 | 巨勢山のつらつら椿つらつらに見つつ偲はな巨勢の春野を(万1-54) 藤波の咲ける春野に延ふ葛の下よし恋ひば久しくもあらむ(万10-1905) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はるはなの [春花の] | 【枕詞】 春の花が美しく咲く意から「にほえさかゆ・さかりに・」に、 春の花を愛でる意から「めづらし・貴(たふと) し」 に、 春の花の散る意から「うつろふ」などにかかる。 |
-春花の 貴くあらむと 望月の 満しけむと 天の下 食す国-(万2-167) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はるひ [春日] | 〔名詞〕春の日。春の一日。〔春〕 | ① 霞立つ 長き春日の 暮れにける わづきも知らず むらきもの 心を痛み-(万1-5) うらうらに照れる春日にひばり上がり心悲しも独し思へば(万19-4316) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はるひの [春日の] | 【枕詞】 春の日の「かすみ」から、同音を含む地名「春日(かすが)」にかかる。 | はるひの春日(かすが)の国に-(継体紀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はるひを [春日を] | 【枕詞】「はるひの」に同じ。 | 春日を 春日(かすが)の山の 高座の 御笠の山に 朝さらず-(万3-375) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はるべ [春べ] | 〔名詞〕[古くは「はるへ」] 春。春のころ。 | -夕宮を 背きたまふや うつそみと 思ひし時に 春へは 花折かざし-(万2-196) 難波津に咲くやこの花冬ごもり今は春べと咲くやこの花(古今仮名序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はるやま [春山] | 青々とした「春の山」の意。 用例歌(万1-52)「春山跡」の誤字説。 |
-青香具山は日の経の大御門に春山と茂みさび立てり畝傍のこの瑞山は- (万1-52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はろばろ [遥遥] | 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 「はろはろ」とも。遠く隔たっているさま。はるばる。 |
難波潟漕ぎ出る舟のはろはろに別れ来ぬれど忘れかねつも(万12-3185) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひ [日] | 〔名詞〕[原義は太陽] ① 太陽。また、日光。② 日中。昼間。 ③ (時間の単位としての) 日。一日。一昼夜。 ④ 時期。おり。時代。⑤ 天候。天気。空模様。 ⑥ 太陽の神としての天照大御神。 また、その子孫と考えられた天皇・皇子。 |
① -天の原 振り放け見れば 渡る日の 影も隠らひ 照る月の 光も見えず-(万3-320) ① なごの海の霞の間よりながむれば入日をあらふおきつしら浪(新古春一-35) ② 幾夜か寝つる日日(かが)なべて夜には九夜(ここのよ)日には十日を-(記中) ③ -その生業を 雨降らず 日の重なれば 植ゑし田も 蒔きし畑も-(万18-4146) ④ 黄葉の散りゆくなへに玉梓の使を見れば逢ひし日思ほゆ(万2-209) ④ 燈火の明石大門に入らむ日や漕ぎ別れなむ家のあたり見ず(万3-255) ⑤ 大君は千歳にまさむ白雲も三船の山に絶ゆる日あらめや(万3-244) ⑥ やすみしし 我が大君 高照らす 日の皇子 神ながら 神さびせすと-(万1-45) ⑥ 朝ぐもり日の入り行けばみ立たしの島に下り居て嘆きつるかも(万2-188) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひ [氷] | 〔名詞〕 ① こおり。氷室 (ひむろ) に貯蔵し、夏に用いた。 ② 雹 (ひょう) 。ひさめ。 |
- 栲の穂に 夜の霜降り 岩床と 川の氷凝り 寒き夜を-(万1-79) 我が衣手に 置く霜も 氷にさえわたり 降る雪も 凍りわたりぬ(万13-3295) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひ [檜] | 〔名詞〕ひのき。 | -真木さくひの板戸を押し開き-(継体紀) -田上山の 真木さく 桧のつまでを もののふの 八十宇治川に-(万1-50) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひ [火] | 〔名詞〕 ① 燃える火。ほのお。火炎。② あかり。ともしび。灯火。 ③ 炭火。おき。炭火などを急いでおこして、炭火を持って(廊下を)通っていくもの(冬の早朝に)とても似つかわしい。 ④ 火災。火事。⑤ のろし。 |
① さねさし相模(さがむ)の小野に燃ゆる火の火中(ほなか)にたちて-(記中) ② 見渡せば明石の浦に燭す火のほにそ出でぬる妹に恋ふらく(万3-329) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひ [非] | 〔名詞〕 ① 道理に合っていないこと。あやまり。不正。 ② 欠点。短所。③ 不利な立場にあること。④ 価値がないこと。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひ [緋] | 〔名詞〕 ① 濃く明るい朱色。緋色。律令制では、四位・五位の人の着用する、袍 (ほう) の色とする。 ② 緋色の練り絹。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひあい [非愛] | 〔名詞・形容動詞ナリ〕 ① 無遠慮であるさま。また、思いやりのないさま。 ② 危険なさま。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひかり [光] | 〔名詞〕① 光る事。輝き。② 栄え。光栄。花形。誉れ。③ 勢い。威光。 | -天皇の 神の皇子の 出でましの 手火の光りそ そこば照りたる(万2-230) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひかる [光る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 光を放つ。照る。輝く。 ② (容姿・才能などが)すぐれて見える。 |
① 夜光る玉といふとも酒飲みて心を遣るにあに及かめやも(万3-349) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -かみ [光る神] | ①〔名詞〕雷。雷神。光の神。〔夏〕 ② 【枕詞】雷が鳴りはためく意から、「なりはた」にかかる。 |
② -愛しき 我が妻離る 光る神 鳴りはた娘子 携はり-(万19-4260) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひきでのやま [引手の山] | 〔山〕所在未詳。 |
衾道を引手の山に妹を置きて山道を行けば生けりともなし(万2-212) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻二-212 注『引出の山』」】 引手の山は、大和誌に「在中村東呼曰竜王高聳人以為望」とあり、その竜王山は、現在も桜井市と天理市にまたがって、三輪山の北、巻向山の西北に並んでいるので、それを引手の山とする説が有力である。 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1巻二-212 頭注『引手の山』」】 二一〇歌の羽易ノ山と同じ山の別名か。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひきはなつ [引き放つ] | 〔他動詞タ行四段〕 ① 弓を引いて矢を放つ。② 引っ張って、離れ離れにする。引き離す。 ③ 間隔を置く。また、放ち書きにする。 |
① -聞きの恐く [一云 諸人の 見惑ふまでに] 引き放つ 矢の繁けく-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひきむすぶ [引き結ぶ] | 〔他動詞バ行四段〕 ① 引き寄せて結び合わせる。結ぶ。 ② (草庵を) 構える。 |
磐白の浜松が枝を引き結びま幸くあらばまた帰り見む(万2-141) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひく [引く] | 〔自カ行四段動詞〕 ① 退く。後退する。②(心が)ある方向に動く。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他カ行四段動詞〕 ① 引き寄せる。引っ張る。② 抜き取る。引き抜く。 ③ 取り除く。④ 盗み取る。⑤ 引き連れる。⑥ ひきずる。 ⑦ 長く線を書く。⑧ 張り渡す。⑨ のばして広げる。くり広げる。 ⑩ 平にならす。⑪ 撒き散らす。ばらまく。⑫ 弓を射る。 ⑬ 引用する。例としてあげる。⑭ 誘う。心ひく。促す。招く。 ⑮ ひいきにする。⑯ 物を与える。引き出物とする。 ⑰ 湯を浴びる。入浴する。⑱ 座を去る。退座する。 【参考「都引き」】 |
① -海を恐み 行く船の 梶引き折りて をちこちの 島は多けど-(万2-220) ② あしひきの岩根こごしみ菅の根を引かば難みと標のみそ結ふ(万3-417) ⑫ み薦刈る信濃の真弓我が引かば貴人さびていなと言はむかも [禅師] (万2-96) ⑫ み薦刈る信濃の真弓引かずして[強作留]わざを知ると言はなくに [郎女] (万2-97) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔自動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 引かれる。連れられる。 |
引け鳥のわが引け往(い)なば 泣かじとは汝(な)は言ふとも(記・上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひくまの [引馬野] | 〔地名〕 愛知県宝飯郡御津町御馬の地。音羽川河口付近の地で引馬神社がある。 豊川市為当町・静岡県浜松市北郊の曳馬町付近とする説もある。 |
引間野ににほふ榛原入り乱れ衣にほはせ旅のしるしに(万1-57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひごろ [日頃] | 〔名詞・副詞〕 ① 数日前。何日もの間。② 数日来。このところ。③ 平生。平常。ふだん。 【有斐閣「萬葉集全注巻四-487 注『日のころごろ』」】 中古語の「ヒゴロ」に当たる「ケノコロ」という語があったのではないか。その重複形か。ネモコロ(懇) の重複形が「ネモコロゴロ」 となるのと同じ語構成であろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひさ [久] | 〔形容動詞ナリ〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 時間の長いさま。久しいさま。 |
我が行きは久にはあらじ夢のわだ瀬にはならずて淵にもありこそ(万3-338) 月は日は変らひぬとも久に経る三諸の山の離宮ところ(万13-3245) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひざ [膝] | 〔名詞〕腿と脛の間の関節部。ひざ。 | -鹿じもの 膝折り伏して たわやめの おすひ取りかけ かくだにも-(万3-382) 膝に伏す玉の小琴の事なくはいたくここだく我れ恋ひめやも(万7-1332) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひさかたの [久方の] | 【枕詞】天に関係のある語にかかる。 「天 (あめ・あま)」「雨」「月」「雲」「空」「光」「夜」「都」など。 |
うらさぶる心さまねしひさかたの天のしぐれの流れあふ見れば(万1-82) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひさし [久し] | 〔形容動詞シク活用〕 【シカル・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 ① 長い時間が経ったさま。長い間である。 ② ある状態が長く続くさま。③ 久しぶりだ。 |
東の市の植木の木垂るまで逢はず久しみうべ恋ひにけり(万3-313) 「ひさしみ」の「み」はミ語法」 ② 天地と共に久しく住まはむと思ひてありし家の庭はも(万4-581) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひさなり [久なり] | 〔形容動詞ナリ〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 時間が長く経つ様子。久しい。 |
三笠山野辺行く道はこきだくも繁く荒れたるか久にあらなくに(万2-232) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひじり [聖] | 〔名詞〕 ① 徳の高い立派な人。儒教でいう聖人。 ② 高い徳で天下を治める人。天皇。③ その道に優れた人。達人。 ④ 徳の高い僧。聖僧。大徳(だいとこ)。 ⑤ 一般に僧。法師。 特に山中にこもり、また諸国をめぐって厳しい修行をする僧。 |
① 酒の名を聖と負せし古の大き聖の言の宣しさ(万3-342) ② 玉たすき 畝傍の山の 橿原の ひじりの御代ゆ-(万1-29) ③-柿本人麻呂なむ歌の聖なりける-(古今・仮名序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻第一-29 ひじり」注】 「ひじり」の原義は霊(ひ)を知る(支配する)人の意。「霊」と「日」は同源の語であるから、日(太陽の運行)を司る人... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひそか [密か・窃か] | 〔形容動詞ナリ〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 ① 表立たず、内密なさま。こっそり。 ② 私物化するさま。 |
【参考】 中古では、漢文訓読に用いる。和文の「みそか」に対応する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ひそかに) [竊かに] | 【有斐閣「万葉集全注巻第二-105、116 題詞原文「竊」注】 [105] 大津皇子竊下於伊勢神宮上来時大伯皇女御作歌二首 116歌の題詞にも見える。「霊異記訓注」などにより「ヒソカニ」と訓む。大津皇子が伊勢の大伯皇女を訪ねた時の皇女の作歌である。 この題詞に「竊かに」とあるのは、皇女が斎宮であったため、姉弟でも簡単に逢うことを許されなかったのを、忍んで逢いに行かれたことをあらわしているのだろう。 [116] 但馬皇女在高市皇子宮時竊接穂積皇子事既形而御作歌一首 既出 (105歌)。「日本霊異記上巻第三十四話の訓注に「宴嘿二合竊也」と見え、同第二十話には「宴嘿」に「比曽加尓之天」とある。 同義語に「ミゾカニ」があるが、上代における確例は見出せない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひつ [漬つ・沾つ] | 〔自動詞タ行四段〕 水につかる。ぬれる。浸る。 |
声はして涙は見えぬ時鳥わが衣手のひつを借らなむ(古今夏-149) 嘆きつつますらをのこの恋ふれこそ我が結ふ髪の漬ちてぬれけれ(万2-118) 雨降らずとの曇る夜のぬれ漬てど恋ひつつ居りき君待ちがてり(万3-373) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔自動詞タ行上二段〕【チ・チ・ツ・ツル・ツレ・チヨ】 水につかる。ぬれる。浸る。 |
-朝露に 玉裳はひづち 夕霧に 衣は濡れて 草枕 旅寝かもする-(万2-194) -道来る人の 泣く涙 小雨に降れば 白たへの 衣ひづちて 立ち留まり -(万2-230) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞タ行下二段〕【テ・テ・ツ・ツル・ツレ・テヨ】 水につける。ひたす。ぬらす。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひつき [日月] | 〔名詞〕① 太陽と月。② 日数月数。歳月。漬 | -高知りまして 朝言に 御言問はさぬ 日月の 数多くなりぬれ-(万2-167) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひづちなく [漬ち泣く] | 〔自動詞カ行四段〕涙を流して泣く。 | -天知らしぬれ 臥いまろび ひづち泣けども せむすべもなし(万3-478) -思ひはぶらし 臥いまろび ひづち哭けども 飽き足らぬかも(万13-3340) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひづつ [漬つ・泥つ] | 〔自動詞タ行四段〕 泥で汚れる。また、水にぬれる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひと- [一-] | 〔接頭語〕 ① 一つの、一度の、一回の、の意を表す。「一枝」「一目」。 ② ある、の意を表す。「一年(とせ)」「一夜(ひとよ)」。 ③ 全部、全体、~じゅう、の意を表す。 「日一日(=一日じゅう)」「一京」「一山」 ④ 少しの、わずかな、の意を表す。「ひと時」「一筆」。 |
① 験なき物を思はずは一坏の濁れる酒を飲むべくあるらし(万3-341) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひと [人] | 〔名詞〕 ① 人間。② 世間の人。世の人。③ 自分以外の人。他の人。 ④ 大人。成人。⑤ 立派な人。優れた人。 ⑥(特定の人をさして)あの人。意中の人。⑦ 身分。家柄。 ⑧ 人柄。性質。 |
① なかなかに人とあらずは酒壷に成りにてしかも酒に染みなむ(万3-346) ② 人見ずは我が袖もちて隠さむを焼けつつかあるらむ着ずて来にけり(万3-271) ③ 大船の泊つる泊りのたゆたひに物思ひ痩せぬ人の子故に(万2-122) ③ 人皆は今は長しとたけと言へど君が見し髪乱れたりとも [娘子](万2-124) ③ 山守はけだしありとも我妹子が結ひけむ標を人解かめやも(万3-405) ⑤-ひげ掻き撫でて 我れをおきて 人はあらじと 誇ろへど- (万5-896) ⑥ 磐代の岸の松が枝結びけむ人は帰りてまた見けむかも(万2-143) ⑥ わたの原八十島かけてこぎ出でぬと人には告げよあまの釣舟 (古今羈旅-407) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとおと [人音] | 〔名詞〕人のいる気配。人の来る音。ひとけ。 | 朝日照る嶋の御門におほほしく人音もせねばまうら悲しも(万2-189) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとごと [人言] | 〔名詞〕 他人の言う言葉。世間の噂。 |
人言を繁み言痛みおのが世にいまだ渡らぬ朝川渡る(万2-116) 人言を繁み言痛み逢はざりき心あるごとな思ひ我が背子(万4-541) 【参考 人言を繁み】「~を~み」は「ミ語法」。「~が~なので」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとつ [一つ] | 〔名詞〕 ① 一つ。一個。一歳。 ② そのものだけである事。単一。単独。 ③ 同じ物。同じこと。同じ所。同時。いっしょ。 ④ 第一。一番目。 ⑤ 時刻の数え方。一刻を四つに分けた最初の一区分。 ⑥ 一方。一面。 |
③ 妹も我も一つなれかも三河なる二見の道ゆ別れかねつる(万3-278) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔副詞〕 ① (下に打消しの表現を伴って)少しも。まったく。 ② 少し。ちょっと。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとづま [人妻・他妻] | 〔名詞〕 ① 他人の妻。② [他夫] 他人の夫。 |
① 紫のにほへる妹を憎くあらば人妻故に我れ恋ひめやも(万1-21) ② つぎねふ 山背道を 人夫の 馬より行くに 己夫し-(万13-3328) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとひ [一日] | 〔名詞〕 ① いちにち。② 一日中。終日。③ ある日。先日。④ 月の最初の日。朔日。 |
① 一日には千たび参りし東の大き御門を入りかてぬかも(万2-186) ① 一日には千重波しきに思へどもなぞその玉の手に巻き難き(万3-412) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとみな [人皆] | 〔名詞〕すべての人。 [参考「みなひと」] |
人皆の見らむ松浦の玉島を見ずてや我れは恋ひつつ居らむ(万5-866) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとめ [人目] | 〔名詞〕 ① 他人の見る目。はため。よそめ。 ② 人の出入り。人の往来。 |
①-見まく欲しけど やまず行かば 人目を多み まねく行かば-(万2-207) ① すみのえの きしによる波 よるさへや ゆめのかよひぢ 人目よぐらん(古今恋二-559) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとり [独り・一人] | 〔名詞〕 ① ひとり。単身。② 独身。 |
① 流らふる妻吹く風の寒き夜に我が背の君はひとりか寝らむ(万1-59) ① ふたり行けど行き過ぎかたき秋山をいかにか君がひとり越ゆらむ(万2-106) ① -声も聞こえず 玉桙の 道行き人も ひとりだに 似てし行かねば-(万2-207) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとり | 〔副詞〕自然に。ひとりでに。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとりね [独り寝] | 〔名詞〕相手がいなくて独りで寝ること。=独り臥(ぶ)し。 | ひとり寝て絶えにし紐をゆゆしみと為むすべ知らに音のみしそ泣く(万4-518) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひな [鄙] | 〔名詞〕田舎。都から遠い地方。 | 天離る鄙の長道ゆ恋ひ来れば明石の門より大和島見ゆ [一本云 家のあたり見ゆ](万3-256) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひなみしのみこ [日並皇子] | 〔名詞〕 | 日雙斯 皇子命乃 馬副而 御猟立師斯 時者来向(萬-49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注 巻第一-49 日並皇子の命」注】 日(天皇)に並ぶ皇子の命(みこと)の意。皇太子をいう普通名詞。実際には草壁皇子にだけいう。(私注:この書では、原文「日雙斯」を「ヒナミシ」の四文字で訓じている。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひのくま [檜前] | 〔地名〕 | 夢にだに見ざりしものをおほほしく宮出もするかさ桧の隈廻を(万2-175) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻二 175 注」】 ヒノクマは現在の明日香村大字檜前を中心とした一帯の地で、平田・野口・立部などにも及んでいた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひのたて [日の経] | 〔方角〕東。また、東西とも。 ⇔「日の緯(よこ)」 | -見したまへば 大和の 青香具山は日の経の 大御門に 春山と -(万1-52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【有斐閣「万葉集全注」での高橋氏文「本朝月令所引」】 「東西南北」を、それぞれ「日竪 (ひのたて)」「日横 (ひのよこ)」「陰面 (かげとも)」「背面 (そとも)」に当てている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひのみかげ [日の御蔭] | 「天の御蔭」の言い換え。 | -天知るや 日の御蔭の 水こそば つねにあらめ 御井のま清水(万1-52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひのみかど [日の御門・ 檜の御門] | 〔名詞〕 ① [日の御門] 皇居。朝廷。 ② [檜の御門] 檜(ひのき)造りのりっぱな宮殿。 |
①-鴨じもの 水に浮き居て 我が作る 日の御門に 知らぬ国 -(万1-50) ②-真木さく檜の御門新嘗屋(にひなへや)に-(記・下) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひのみこ [日の御子] | 〔名詞〕天皇、また皇子を敬っていう語。 | やすみしし 我が大君 高照らす 日の皇子 荒栲の 藤原が上に-(万1-50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひのもとの [日の本の] | 【枕詞】「大和(やまと)」にかかる。 | -水の激ぎちそ 日本の 大和の国の 鎮めとも います神かも 宝とも-(万3-322) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひのよこ [日の緯] | 〔方角〕西。また、南北とも。⇔「日の経(たて)」 | -この瑞山は 日の緯の 大御門に 瑞山と 山さびいます 耳成の-(万1-52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひむがし [東] | 〔名詞〕[古くは「ひむかし」] ひがし。 | 東の野にかぎろひの立つ見えてかへり見すれば月かたぶきぬ(万1-48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひめしま [姫島] | 〔地名〕 | 妹が名は千代に流れむ姫島の小松がうれに蘿生すまでに(万2-228) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1巻二-228 頭注『姫島』」】 現在の淀川河口辺りにかつてあった島の名。大阪市西淀川区の阪神電鉄本線と同・西大阪線との間にその町名が残る。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひも [紐] | 〔名詞〕物を結んだり、束ねたりなどするのに使う細長い縄状ののもの。 | 淡路の野島の崎の浜風に妹が結びし紐吹き返す(万3-252) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひら [比良] | 〔地名〕[歌枕] | 楽浪の志賀の [一云 比良の] 大わだ淀むとも昔の人にまたも逢はめやも [一云 逢はむと思へや](万1-31) 我が船は比良の湊に漕ぎ泊てむ沖辺な離りさ夜ふけにけり(万3-276) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今の滋賀県琵琶湖西岸の地名。比良山東側のふもと。比良の高嶺・比良の山は、比叡山の北に連なる山で、天台修験道の霊場であった。 「比良の暮雪」は近江八景の一つ。 「比良の港」は、滋賀県滋賀郡志賀町木戸から小松へかけての、比良山東麓一帯。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひらく [開く] | 1〔自動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 ① 咲く。ほころびる。② 始まる。起こる。③ 晴ればれとさわやかになる。④ 文明が進む。 2〔他動詞カ行四段〕 ① 開く。あける。② 解く。取り去る。 ③ 新しく始める。切り開いて盛んにする。 3〔自動詞カ行四段〕 ① あく。広がる。ひらく。② 幸運になる。盛んになる。 ③ 合戦や婚礼の時に「退く」「帰る」「退散する」などの語を忌み避け、その代わりに用いる語。 |
1-② 天地のひらけはじまりける時より出でにけり(古今仮名序) 2-① -天の原 岩戸を開き 神上り 上りいましぬ -(万2-167) 2-① 我が思ひを人に知るれや玉櫛笥開き明けつと夢にし見ゆる(万4-594) 2-① 久方の天の門開き高千穂の岳に天降りし皇祖の神の御代より-(万20-4489) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひりふ [拾ふ] | 〔他動詞ハ行四段〕《上代語》拾う。 | 家づとに貝を拾ふと沖辺より寄せ来る波に衣手濡れぬ(万15-3731) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひる [昼] | 〔名詞〕 ① 日の出から日没までの間。② 日中。正午。③ 昼飯。④ 物事の隆盛。ひる |
① 「畝傍山昼は雲とゐ(=雲が流レ動キ)夕されば風吹かむとぞ木の葉騒げる」(記・中) ① -雲居なす 心いさよひ その鳥の 片恋のみに 昼はも 日のことごと-(万3-375) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひる [干る・乾る] | 〔自動詞ハ行上一段〕【ヒ・ヒ・ヒル・ヒル・ヒレ・ヒヨ】 ① かわく。② 潮が引く。水が少なくなる。 |
① 村雨の露もまだひぬ槙の葉に霧立ちのぼる秋の夕暮れ(新古秋下-491) ② 潮干なば玉藻刈りつめ家の妹が浜づと乞はば何を示さむ(万3-363) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひろし [広し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① (面積や幅などが) 広い。広々としている。 ② すみずみまで行き渡っている。 ③ おおらかである。寛容だ。 ④ (一族が) 多い。栄えている。 |
① 千鳥鳴く佐保の川門の瀬を広み打橋渡す汝が来と思へば(万4-531) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふ ⇒「主要助動詞活用表」 | 反復・継続の助動詞「ふ」 [四段動詞の未然形に接続] | 秋の田の穂の上に霧らふ朝霞いつへの方に我が恋やまむ(万2-88) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふ [干・乾] | 〔自動詞ハ行上二段〕【ヒ・ヒ・フ・フル・フレ・ヒヨ】 ≪上代語≫「ひる (干る・乾る) に同じ」 |
あやに悲しみ明け来ればうらさび暮らし荒栲の衣の袖は干る時もなし-(万2-159) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふ [経] | 〔自動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 ① 時がたつ。年月が過ぎる。 ②(場所を)通って行く。通り過ぎる。 ③ 経験する。 |
① 白波の浜松が枝の手向けぐさ幾代までにか年の経ぬらむ [一云 年は経にけむ] (万1-34) ① しきたへの手枕まかず間置きて年そ経にける逢はなく思へば(万4-538) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふえ [笛] | 〔名詞〕 ① 横笛。笙(しよう)。篳篥(ひちりき)・尺八など、管楽器の総称。 ② 特に、横笛。 |
- 吹き鳴せる 小角の音も [一云 笛の音は] 敵見たる 虎か吼ゆると-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふかし [深し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① 水面や物の上部などから底までの距離が長い。深い。 ② 奥深い。奥まっている。 ③ (心や動作が)落ち着いている。(思慮・愛情などが)深い。 ④ 色や香りが濃い。⑤ 間柄が親しい。親密だ。 ⑥ 時・季節などがかなり経過している。夜がふけている。⑦ 多い。 ⑧ 程度がはなはだしい。はげしい。 |
① 我が欲りし野島は見せつ底深き阿胡根の浦の玉ぞ拾はぬ [或頭云 我が欲りし子島は見しを](万1-12) ⑥ 古への古き堤は年深み池のなぎさに水草生ひにけり(万3-381) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふかみる [深海松] | 〔名詞〕海底深く生えた海松(みる=海藻の一種) | 神風の 伊勢の海の 朝なぎに 来寄る深海松 夕なぎに 来寄る俣海松-(万13-3315) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふかみるの [深海松の] | 【枕詞】同音を重ねて「深む」「見る」にかかる。 | -靡き寝し子を 深海松の 深めて思へど さ寝し夜は-(万2-135) -浦廻には なのりそ刈る 深海松の 見まく欲しけど-(万6-951) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふかむ [深む] | 〔他動詞マ行下二段〕【メ・メ・ム・ムル・ムレ・メヨ】 深める。深くする。深く思う。 |
-靡き寝し子を 深海松の 深めて思へど さ寝し夜は-(万2-135) 奥山の岩本菅を根深めて結びし心忘れかねつも(万3-400) あひ見ねば恋こそまされ水無瀬川なにに深めて思ひそめけむ(古今恋五-760) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふきかへす [吹き返す] | 〔他動詞サ行四段〕 ① 吹き戻す。② 風が吹いて着物の袖や裾などをひるがえす。 |
采女の袖吹きかへす明日香風都を遠みいたづらに吹く(万1-51) 淡路の野島の崎の浜風に妹が結びし紐吹き返す(万3-252) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふきまどふ [吹き惑ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 (風が) ひどく吹く。吹き荒れる。 |
-渡会の 斎きの宮ゆ 神風に い吹き惑はし 天雲を 日の目も見せず-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふく [吹く] | 〔自動詞カ行四段〕 ① 風が起こる、風が渡る。 ② 嘯く。③ 水が湧き出る。 |
① 君待つと我が恋ひ居れば我が宿の簾動かし秋の風吹く(万4-491) 采女の袖吹きかへす明日香風都を遠みいたづらに吹く(万1-51) 我妹子を早見浜風大和なる我れ松椿吹かざるなゆめ(万1-73) -我が漕ぎ来れば 時つ風 雲居に吹くに 沖見れば とゐ波立ち-(万2-220) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふく [更く] | 〔自動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 ① 季節が深まる。たけなわになる。 ② 夜が深くなる。更ける。 ③ 年をとる。老いる。 |
① 秋更けぬ鳴けや霜夜のきりぎりすやや影さむしよもぎふの月 (新古今秋下-517) ② 我が背子を大和へ遣るとさ夜更けて暁露に我が立ち濡れし(万2-105) ③ ふけにけるわがみのかげをおもふまにはるかに月の傾きにける (新古今雑上-1534) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふく [葺く] | 〔他動詞カ行四段〕 ① (瓦・板・茅などで) 屋根を覆う。 ② 草木を屋根や軒にさす。 |
① 秋の野のみ草刈り葺き宿れりし宇治の宮処の仮廬し思ほゆ(万1-7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふくし [堀串] | 〔名詞〕後世「ふぐし」とも 竹または木の先をとがらせて作った、土を掘るへら。 |
篭もよ み篭持ち 堀串もよ み堀串持ち この岡に-(万1-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふくろ [袋・嚢] | 〔名詞〕① 布・皮・紙などでつくった、物を入れるふくろ。② 財布・巾着。 | ① 燃ゆる火も取りて包みて袋には入ると言はずやも智男雲(万2-160) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふじかは [富士川] | -つつめる海そ 富士川と 人の渡るも その山の 水の激ぎちそ 日本の-(万3-322) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻三 『付録 地名一覧』】 山梨・長野の県境に発し、山梨県西部を流れ静岡県に入り、岩淵を経て駿河湾に注ぐ。 富士山の北にある御坂山地以北の甲府盆地の水は集めるが、富士山周辺の水は大部分潤井川となって、ほとんどこれには関係がない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふじのたかね・ふじのやま [富士の高嶺・富士の山] |
天地の 分れし時ゆ 神さびて 高く貴き 駿河なる富士の高嶺を 天の原 -(万3-320) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻三 『付録 地名一覧』」】 万葉当時噴火し盛んに降灰していたことはこれを引いた歌や『続日本紀』の記事から知られる。万葉集では「不尽」と書き、「富士」と書くのは平安時代以降。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふす [伏す・臥す] | 〔自動詞サ行四段〕 ① 横になる。寝る。② うつぶす。うつむく。③ 隠れる。ひそむ。 |
① -夜はも 夜のことごと 伏し居嘆けど 飽き足らぬかも(万2-204) ① 蒸し衾なごやが下に臥せれども妹とし寝ねば肌し寒しも(万4-527) ② -あかねさす 日のことごと 獣じもの い匍ひ伏しつつ ぬばたまの-(万2-199) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞サ行下二段〕【セ・セ・ス・スル・スレ・セヨ】 ① 横にする。寝かせる。② うつむかせる。顔などを下へ向かせる。 ③ おし倒す。押さえつける。④ 隠す。ひそませる。 |
② 貫き垂れ 獣じもの 膝折り伏して たわや女の 襲取り懸け かくだにも(万3-382) ④ 主聞きつけて、かの道に夜ごとに人をふせて守らすれば(古今恋三-632詞書) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふすまぢを [衾道を] | 【枕詞】「ふすま」を引いてかけることから、「引き出」にかかる。 | 衾道を引手の山に妹を置きて山道を行けば生けりともなし(万2-212) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふせいほ [伏せ庵] | 〔名詞〕軒が低く、みすぼらしい家。= 伏せ屋 | -肩にうち掛け 伏廬の 曲廬の内に 直土に 藁解き敷きて-(万5-896) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふせや [伏せ屋] | 〔名詞〕→ ふせいほ。 | -倭文幡の 帯解き交へて 廬屋立て 妻問ひしけむ 葛飾の-(万3-434) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふたがみのたふときやまの [二神の貴き山の] |
-さはにあれども 二神の 貴き山の 並み立ちの 見が欲し山と-(万3-385) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-382 注『二神の貴き山の』」】 底本「明神之」 とあり、アキツカミノとあるが、童蒙抄に「筑波山はをつくば、めつくばといひて、二山相共に立ちならべる山と伝へ来りたり。よりて此明の字は、朋の字の誤りにて、とも神のとよめる義也」 と誤字説を出した。この誤字説により万葉考はフタカミノと訓んだ。これによるべきである。講義に「朋」 を「両」 の意に解し得ることを、漢書『食貨志』の蘇林の注や『詩経』の豳風(ひんぷう)七月の「朋酒」 の注に「両樽(ふたもたひのさけ)ヲ朋ト曰フ」 とあるのを例示している。山を「神」 と表現するのは富士山にも例(三一九) があった。「貴き山の」 の「ノ」 は「並み立ちの見が欲し山」 と同格であることを表す助詞。この種の例に「風雑(まじ)り 雨降る夜の 雨雑り 雪降る夜は」(5・八九二) ほかがある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふたかみやま [二上山] | 〔地名〕歌枕 ① 今の奈良県北葛城郡と大阪府南河内郡との間にある山。 二上山(にじょうさん)。 ② 今の富山県高岡市北部の山。月と紅葉の名所。 |
① うつそみの人なる我れや明日よりは二上山を弟背と我が見む(万2-165) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふたつ [二つ] | 〔名詞〕[[つ]は接尾語] ① 数の名。二。② 二歳。③ 二度。ふたたび。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -なし [二つ無し] | くらべるものがない。かけがえがない。 | いなだきにきすめる玉は二つなしかにもかくにも君がまにまに(万3-415) 二つなき恋をしすれば常の帯を三重結ぶべく我が身はなりぬ(万13-3287) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のうみ [二つの海] | 生と死の世界。 | 生き死にの二つの海を厭はしみ潮干の山を偲ひつるかも(万16-3871) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のみち [二つの道] | ① 忠と孝の道。 ② (「白氏文集」の「秦中吟(しんちゅうぎん)」の中の語から) 貧と富との二つの道。 貧家の女の品行と富家の女の品行。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふたはしる [二走る] | 〔自動詞ラ行四段〕「ふたゆく」と似た表現。 「ふたゆく」より一層目まぐるしく経過するように言ったもの。 |
我が君はわけをば死ねと思へかも逢ふ夜逢はぬ夜二走るらむ(万4-555) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふたみのみち [二見の道] | 〔地名〕 | 妹も我も一つなれかも三河なる二見の道ゆ別れかねつる(万3-278) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 『付録 地名一覧』」】 愛知県豊川市御油町と同市国府町との境で、東海道の本道(南寄り海沿い)と、浜名湖の今切の険を避けるために静岡県との境の本坂峠を越えて浜名湖北岸を行く姫街道とが別れる分岐点か。 一説に宝飯郡御津町広石の現在、浄宝寺という寺にある辻かとするものもある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふたゆく [二行く] | 〔自動詞カ行四段〕 ① 同じことを二度繰り返す。 ② 二つの心を持つ。両方に通じる。 |
① うつせみの世やも二行く何すとか妹に逢はずて我がひとり寝む(万4-736) ② 沼二つ通は鳥が巣我が心二行くなもとなよ思はりそね(万14-3547) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふたり [二人] | 〔名詞〕ふたり。 | 行くさには二人我が見しこの崎をひとり過ぐれば心悲しも [一に云ふ 見もさかず来ぬ](万3-453) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふち [淵] | 〔名詞〕水のよどんで深いところ。ふち。 | 我が行きは久にはあらじ夢のわだ瀬にはならずて淵にもありこそ(万3-338) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふぢえ [藤江] | 〔名詞〕 | 荒たへの藤江の浦にすずき釣る海人とか見らむ旅行く我れを(万3-253) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集『付録地名一覧』】 兵庫県明石市の西部藤江の地。沖に鹿の瀬と呼ばれる漁場がある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふぢごろも [藤衣] | 〔名詞〕[「ふぢころも」とも] ① 藤や葛の繊維で織った、粗末な着物。低い身分の者が着用した。 ② 喪服。特に麻で作った喪服。 【参考】 「①」はその織り方が粗いことから、「間遠(まどほ)」を、また褻(な)る(=ヨレヨレニナル)意から「馴る」を導く序詞を構成する。 |
須磨の海人の塩焼き衣の藤衣間遠にしあればいまだ着馴れず(万3-416) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふぢなみ [藤波・藤浪] | 〔名詞〕 ① 藤の花房が風になびくさまを波に見立てていう語。また、藤の花。 ② 藤原氏の称。 |
藤波の花は盛りになりにけり奈良の都を思ほすや君(万3-330) 恋しけば形見にせむと我がやどに植ゑし藤波今咲きにけり(万8-1475) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふぢなみの [藤波の・藤浪の] | 【枕詞】 藤つるがまつわりつくことから「思ひまつはり」に、 波が寄る意から「たち」「ただ」「よる」などにかかる。 |
-満ちてあれども 藤波の 思ひまつはり 若草の 思ひつきにし-(万13-3262) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふぢはら [藤原] | 〔地名〕 | やすみしし 我が大君 高照らす 日の皇子 荒栲の 藤原が上に 食す国を-(万-50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【有斐閣「万葉集全注巻第一-50 藤原が上に」注】 「藤原」は大和三山に囲まれる地の総称。藤原氏と関係が深いらしい。藤原遷都の陰には藤原氏の力がかなり大きく作用していよう。 【中央公論社「萬葉集注釈巻第一-50 藤原がうへに」注】 「藤井が原」(1・52)ともあるのを見ると、藤の木蔭に良い井水が出て、それを藤井と呼び、その辺りの野を「藤井が原」、また略して「藤原」と云つたのかと思はれる。 「うへ」は上の意。その原の上に宮殿を建設される意である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふと- [太-] | 〔接頭語〕[名詞・動詞に付いて] 大きく尊い、荘重なり、立派な、の意を添える。 |
【例】 「太祝詞」「太敷く」など |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふとし [太し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① 太い。太っている。肥えている。 ② 肝が太い。動じないでしっかりしている。 |
② 真木柱太き心はありしかどこの我が心鎮めかねつも(万2-190) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふとしく [太敷く] | 〔他動詞カ行四段〕[「ふと」は接頭語] ① 立派に立てる。「太知る」とも。 ② 天皇の徳を天下にしきほどこす。立派に世を治める。 |
①-花散らふ 秋津の野辺に 宮柱 太敷きませば ももしきの-(万1-36) ②-瑞穂の国を 神ながら 太敷きまして やすみしし 我が大君の -(万2-199) 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻第一-36 宮柱太敷きませば」頭注】 礎石を置かずに穴を掘って直接柱を立てる古代の建築様式を示す。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふなぎ [船木] | 〔名詞〕造船の材料の木。 | とぶさ立て足柄山に船木伐り木に伐り行きつあたら船木を(万3-394) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふなで [舟出] | 〔名詞〕舟で漕ぎ出すこと。出帆。 | 山川も依りて仕ふる神ながらたぎつ河内に舟出せすかも(万1-39) 芦北の野坂の浦ゆ船出して水島に行かむ波立つなゆめ(万3-247) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふなには [船庭] | 釣り船に適した漁場 | 武庫の海船庭ならしいざりする海人の釣船波の上ゆ見ゆ(万3-258) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふなのる [船乗る] | 〔他動詞ラ行四段〕船に乗り漕ぎ出す。船出する。 | 熟田津に船乗りせむと月待てば潮もかなひぬ今は漕ぎ出でな(万1-8) いづくにか舟乗りしけむ高島の香取の浦ゆ漕ぎ出来る舟(万7-1176) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふなはて [船泊て] | 〔名詞〕船が港に泊ること。船泊まり。 | いづくにか船泊てすらむ安礼の崎漕ぎ廻み行きし棚無し小舟(万1-58) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふなびと [船人] | 〔名詞〕① 船に乗り合わせている人。船客。② 船頭。船員。 | ② 住吉の得名津に立ちて見渡せば武庫の泊まりゆ出づる船人(万3-286) ② 風早の三穂の浦廻を漕ぐ舟の舟人騒く波立つらしも(万7-1232) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふね [船・舟] | 〔名詞〕ふね。 | かからむとかねて知りせば大御船泊てし泊りに標結はましを (万2-151) 沖つ波辺波立つとも我が背子がみ船の泊り波立ためやも(万3-248) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふね [槽] | 〔名詞〕① 水などを入れる器。水槽。② 馬のかいばおけ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふはやま [不破山] | 〔地名〕 | -背面の国の 真木立つ 不破山超えて 高麗剣 和射見が原の-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1 萬葉集巻二 頭注「不破山越えて」】 「天武紀」では天皇が伊勢国から美濃国に入ったように記してあり、天武天皇の行宮のある和射見が原は近江・美濃国境の山、不破山より東にある。 この前後の記述はそれと矛盾する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふみおこす [踏み起こす] | 〔他動詞サ行四段〕 ① 地を踏んで獣を驚かして狩り立てる。② おこす。再興する。 |
① -召し集へ 率ひたまひ 朝狩に 鹿猪踏み起し 夕狩に 鶉雉踏み立て-(万3-481) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふみたつ [踏み立つ] | 〔他動詞タ行下二段〕【テ・テ・ツ・ツル・ツレ・テヨ】 ① 地面を踏んで、鳥獣を驚かして追い立てる。 ② 踏みしめて立つ。 |
① -夕狩に 鶉雉踏み立て 大御馬の 口抑へ止め 御心を 見し明らめし-(万3-481) ① -朝猟に 五百つ鳥立て 夕猟に 千鳥踏み立て 追ふ毎に -(万17-4035) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふむ [踏む・践む] | 〔他動詞マ行四段〕 ① 足で抑える。踏みつける。 ② 踏み歩く。歩く。行く。訪れる。 ③ (多く「位をふむ」の形で) その地位につく。 ④ 舞う。技芸を演じる。 ⑤ 値段を見積もる。値踏みをする。 ⑥ 日を過ごす。 |
② 橘の蔭踏む道の八衢に物をぞ思ふ妹に逢はずして [三方沙弥](万2-125) ② 佐保川の小石踏み渡りぬばたまの黒馬の来夜は年にもあらぬか(万4-528) ② 岩根踏み夜道は行かじと思へれど妹によりては忍びかねつも(万11-2595) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふゆごもり [冬籠り] | 〔名詞〕[古くは「ふゆこもり」] 冬の寒さの厳しい間、動植物が活動を止め、土中や巣にこもること。 |
雪ふればふゆごもりせる草も木も春に知られぬ花ぞ咲きける(古今冬-323) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】「春」にかかる。 | 冬こもり春咲く花を手折り持ち千たびの限り恋ひわたるかも(万10-1895) -ささげたる 幡の靡きは 冬こもり 春さり来れば 野ごとに-(万2-199) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふらばふ [触らばふ] | -上つ瀬に 生ふる玉藻は 下つ瀬に 流れ触らばふ 玉藻なす -(万2-194) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻二-194 注「流觸經」】 「流觸經」 の三字、旧訓「ナカレフレフル」 であったのを、考に「ナカレフラヘリ」と改めたが、玉の小琴には「ナカレフラバヘ」 とした。 雄略記歌謡に「本都延能(ホツエノ) 延能宇良婆波(エノウラバハ) 那加都延爾(ナカツエニ) 淤知布良婆閇(オチフラバヘ)」 とあるのによる。 フラバフ(ヘ) は、「触ル」の未然形「触ラ」 に、接尾語「ハフ」 を添えた語(春日政治「成実論天長点続貂」 国語国文昭和八年一月) と考えられる。 「ナガレフラフ」 とも訓めるが(古義)、この長歌の各句の音数が五音七音に整えられていることも考えあわせて「ナガレフラバフ」とする。流れ触れている意か。 終止形で、文は切れる。あとの196歌の冒頭にも同様な明日香川の川藻の描写が見られる。あるいは河島皇子の御殿が明日香川の河畔にあったためか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふり [振り・風] | 〔名詞〕 ① 動作・ふるまい。② 姿・なりふり。③ そぶり。④ 習慣・風俗。 ⑤ (歌舞伎や舞踏で) しぐさ・所作。⑥ (音曲で) 曲調・節回し。 ⑦ ずれ・ゆがみ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ふり) | (接頭語) 動作を強調するための語。〔万葉集全注〕 「ふり起こし」「ふりたて」などと動詞に冠して動作を強める意に用ゐる接頭語。〔万葉集注釈〕 フリは他の動詞に冠して、勢いよくする意味を加えている。〔万葉集全註釈〕 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふりおく [降り置く] | 〔自カ行四段〕降り積もる。 | 富士の嶺に降り置く雪は六月の十五日に消ぬればその夜降りけり(万3-323) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふりおこす [振り起こす] | 〔他動詞サ行四段〕 ① 振り動かして起こす。振り立てる。 ② 気持ちを奮い立たせる。鼓舞する。 |
① ますらをの弓末振り起し射つる矢を後見む人は語り継ぐがね(万3-367) ② -妻別れ 悲しくはあれど 大夫の 心振り起し 取り装ひ-(万20-4422) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふりく 降り来 | 〔自動詞カ行変格〕【コ・キ・ク・クル・クレ・コヨ】 (雨・雪などが) 降って来る。 |
苦しくも降り来る雨か三輪の崎狭野の渡りに家もあらなくに(万3-267) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふりさく [振り放く] | 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 はるか遠方を仰ぐ。ふり仰ぐ。 |
振り放けて三日月見れば一目見し人の眉引き思ほゆるかも(万6-999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふりさけみる [振り放け見る] | 〔他動詞マ行上一段〕【ミ・ミ・ミル・ミル・ミレ・ミヨ】 はるかに仰ぎ見る。ふり仰いで遠くを見る。 |
あまの原ふりさけみればおおきみのみ命はながくあまたらしたり (万2-147) -天のごと 振り放け見つつ 玉たすき 懸けて偲はむ 恐くありとも-(万2-199) あまの原ふりさけみれば春日なるみかさの山にいでし月かも (古今羇旅-406) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふりまがふ [降り紛ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 見分けがつかないほどしきりに降る。 |
矢釣山木立も見えず降りまがふ雪に騒ける朝楽しも(万3-264) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 降って見分けにくくする。 |
くさもきもふりまがへたるゆきもよに はるまつうめのかをりぞする(新古今冬-684) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふる [旧る・古る] | 〔自ラ行上二段〕【リ・リ・ル・ルル・ルレ・リヨ】 ① 古くなる。年月を経る。② 年をとる。老いる。③ 古くさくなる。 |
① 浅茅原つばらつばらに物思へば古りにし里し思ほゆるかも(万3-336) ② 古りにし嫗にしてやかくばかり恋に沈まむ手童のごと [恋をだに忍びかねてむ手童のごと](万2-129) ③ 我が里に大雪古れり大原の古りにし里に降らまくは後(万2-103) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふる [降る] | 〔自ラ行四段〕雨、雪などが降る。また比喩的に涙が流れ落ちる。 〔参考〕和歌では「旧る」にかけて用いられることが多い。 |
-さやかに見れば 栲の穂に 夜の霜降り 岩床と-(万1-79) 居明かして君をば待たむぬばたまの我が黒髪に霜は降るとも (万2-89) 我が里に大雪降れり大原の古りにし里に降らまくは後(万2-103) 降る雪はあはにな降りそ吉隠の猪養の岡の寒からまくに(万2-203) 君がため春の野に出でて若菜つむわが衣手に雪は降りつつ(古春上-21) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふる [触る] | 〔自ラ行四段〕触る・触れる。 | 我妹子に触るとはなしに荒礒廻に我が衣手は濡れにけるかも(万12-3177) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔自ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 ① さわる・触れる。② 出逢う・関係する。③ 箸をつける・食べる。 ④ (多く「肌触る」の形で) 男女が親しみ会う・契る。 |
① 神木にも手は触るといふをうつたへに人妻といへば触れぬものかも(万4-520) ① うち靡く春さり来れば小竹の末に尾羽打ち触れて鴬鳴くも(万10-1834) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 広く知らせる・告げ知らせる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふる [振る] | 〔他動詞ラ行四段〕 ① 揺り動かす。ふる。② 神体などを移す。遷座する。 ③ 男女の間で、相手を振り捨てる。④ 入れ替える。置き換える。 |
① 石見のや高角山の木の間より我が振る袖を妹見つらむか (万2-132) ① かねさす紫野行き標野行き野守は見ずや君が袖振る(万1-20) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふるし [古し・故し・旧し] | 〔形容詞シク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① 遠い昔のことである。 ② 年を経ている。年功を積んでいる。年老いている。 ③ 古びている。また、珍しくない。 |
① 古の人に我れあれや楽浪の古き都を見れば悲しき(万1-32) ② 古への古き堤は年深み池のなぎさに水草生ひにけり(万3-381) ③ 鶉鳴き古しと人は思へれど花橘のにほふこの宿(万17-3942) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふるひと [古人・旧人] | 〔名詞〕[「ふるびと」とも] ① 昔の人。故人。② 老人。③ 以前からいる人。古参の人。④ 昔なじみの人。 ⑤ 古風な人。 |
① 妹らがり今木の嶺に茂り立つ嬬松の木は古人見けむ(万9-1799) ② 古人の飲へしめたる吉備の酒病まばすべなし貫簀賜らむ(万4-557) ④ かげろふのそれかあらぬか 春雨のふるひとなれば袖ぞぬれぬる(古今恋四-731) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふるへ [古家] | 〔名詞〕[「ふるいへ」の転] ① もとのすみか。② 古びた家。 |
① 我が背子が古家の里の明日香には千鳥鳴くなり夫待ちかねて(万3-270) ② 人言を繁みと君を鶉鳴く人の古家に語らひて遣りつ(万11-2809) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふるまひ [振る舞ひ] | 〔名詞〕① 行動。行為。 | -常なりし 笑まひ振舞 いや日異に 変らふ見れば 悲しきろかも(万3-481) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふるゆきの [降る雪の] | 【枕詞】 雪の性質や状態から「消(け)・白髪・いちしろし」 また、同音の「行(ゆ)き」にかかる。 |
道に逢ひて笑まししからに降る雪の消なば消ぬがに恋ふといふ我妹(万4-627) 降る雪の白髪までに大君に仕へまつれば貴くもあるか(万17-3944) 我がやどの君松の木に降る雪の行きには行かじ待にし待たむ(万6-1045) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -へ [-重] | 〔接尾語〕重なっている数を示す。 | 「八重(やへ)垣」「千重(ちへ)」「一重(ひとへ)」など 大君は神にしませば天雲の五百重が下に隠りたまひぬ(万2-205) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| へ [上] | 〔名詞〕(ふつう「~のへ」の形で)うえ。 | 韓国(からくに)の城(き)の上に立ちて(欽明紀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| へ [戸] | 〔名詞〕(戸籍上の一戸としての)いえ。民家。またそれを数える語。 | 秦人(はたびと)の戸の数総べて七千五十三戸(ななちへあまりいそあまりみへ (欽明紀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -へ [-辺] | 〔接尾語〕「べ」とも。 ~のあたり。~のほう。~のころなどの意を添える。 「沖辺」「末辺」「春辺」「山辺」など |
桜田へ鶴鳴き渡る年魚市潟潮干にけらし鶴鳴き渡る(万3-273) 大和辺に君が立つ日の近づけば野に立つ鹿もとよめてそ鳴く(万4-573) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| へ [辺] | 〔名詞〕 ① ほとり。あたり。 ②(沖に対して)海辺。 |
① -海行かば 水漬く屍 山行かば 草生す屍 大君の 辺にこそ死なめ- (万18-4118) ② -沖見れば とゐ波立ち 辺を見れば 白波騒く いさなとり 海を恐み-(万2-220) ② -罷りいませ 海原の 辺にも沖にも 神づまり- (万5-898) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| へ [家] | 〔名詞〕いえ。 | 妹が家に雪かも降ると見るまでにここだもまがふ梅の花かも[小野氏國堅] (万5-848) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| へ [舳] | 〔名詞〕船の前部。船首。へさき。⇔「艫(とも)」 | -夕潮に 船を浮けすゑ 朝なぎに 舳向け漕がむと-(万20-4422) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| へ ⇒「主要助詞一覧表」 | 〔格助詞〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| べし ⇒ 「助動詞活用表」 | 〔ク活用型助動詞〕推量。 【ベカラ・ベク(ベカリ)・ベシ・ベキ(ベカル)・ベケレ】 ① あるべき事の起こることを予想する (・・・しそうだ) ② ある程度確実な推測を表わす(きっと・・・だろう) ③ 予定の意を表わす (・・・することになっている) ④ 当然の意を表わす (・・・するがよい) ⑤ 可能または可能性を推定する意を表わす (・・・する事ができる) ⑥ 終止形を用いて強い勧誘・押し付けの意 (・・・する方がよい) ⑦ 終止形を用いて意志を表わす(・・・するつもりだ) ⑧ 必要・義務の意を表わす(・・・しなければならない) 〔接続〕 終止形に付く。ラ変には連体形に付く。 |
わが背子が来べき宵なりささががにのくものふるまひかねてしるしも (古今墨滅-1110) ③ 明日香川川淀去らず立つ霧の思ひ過ぐべき恋にあらなくに(万3-328) ④ 大和恋ひ寐の寝らえぬに心なくこの洲崎廻に鶴鳴くべしや(万1-71) ④ 験なき物を思はずは一坏の濁れる酒を飲むべくあるらし(万3-341) ⑥ 三輪山をしかも隠すか雲だにも心あらなも隠さふべしや(万1-18) ⑥ 我が聞きし耳によく似る葦の末の足ひく我が背つとめ給ぶべし(万2-128) ⑧ 石上布留の山なる杉群の思ひ過ぐべき君ならなくに(万3-425) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上代「べし」の語幹「べ」に理由・原因を表わす接尾語「み」がついて「べみ」の形が用いられた。 | ほととぎす鳴く羽ぶりにも散りぬべみ袖に扱き入れつ藤波の花 (万19-4217左注) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【「べし」の語源】 「べし」の語源は副詞「べ」だといわれている。当事者の意志を超えた道理・理由によって、当然・必然のことと考えられるようすだというのが原義であったらしい。 →「うべ」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| へそ [巻子] | 〔名詞〕つむいだ糸を環状に巻きつけたもの。=芋環(をだまき)。 | 綜麻形の林のさきのさ野榛の衣に付くなす目につく吾が背(万1-19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| へつかい [辺つ櫂] | 〔名詞〕(「つ」は「の」の意の上代の格助詞)岸辺を漕ぐ船の櫂。⇔ 沖つ櫂 | ―いたくな撥ねそ 辺つ櫂 いたくな撥ねそ 若草の ―(万2-153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| へつへ [辺つ方] | 〔名詞〕[「つ」は「の」の意の上代の格助詞。岸辺。 |
-桜花 木の暗茂に 沖辺には 鴨つま呼ばひ 辺つへに あぢ群騒き-(万3-259) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| へなみ [辺波] | 〔名詞〕岸辺または船べりに寄せる波。 | 沖つ波辺波立つとも我が背子がみ船の泊り波立ためやも(万3-248) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| べみ | 〔なりたち〕助動詞「べし」の語幹「べ」+原因・理由を表す接尾語「み」 《上代語》~そうなので。~にちがいないので。 |
-人目を多み まねく行かば 人知りぬべみ さね葛 後も逢はむと-(万2-207) 秋萩を散り過ぎぬべみ手折り持ち見れども寂し君にしあらねば(万10-2294) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【語法】 接尾語の「み」は、「山高み」のように形容詞の語幹(シク活用には終止形)に付いて原因・理由を表すが、形容詞型活用の「べし」でも同様の形となる。 多く「ぬべみ」の形で用いられる。中古では和歌に少々残存するだけである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほ [秀] | 〔名詞〕 高く秀でているもの。抜きんでて目につくもの。 他よりすぐれているもの。また、表面に現れているもの。 |
見渡せば明石の浦に燭す火のほにそ出でぬる妹に恋ふらく(万3-329) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほ [穂] | 〔名詞〕 ① 稲・すすきなどの、花や実の付いた茎の先。 ② やり・刀などの先。 |
① 秋の田の穂の上に霧らふ朝霞いつへの方に我が恋やまむ(万2-88) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほこすぎ [矛杉・鉾杉] | 〔名詞〕矛のような形の杉。 | 何時の間も神さびけるか香具山の桙杉が本に苔生すまでに(万3-261) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほし [星] | 〔名詞〕 ① (天の) 星。② 兜の鉢に並べて打ち付けた鋲の頭。 ③ 九星のうち、その人の生まれ年にあたるもの。また、その年々の吉凶。 運勢。 |
① 北山にたなびく雲の青雲の星離り行き月を離れて(万2-161) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほし [欲し] | 〔形容詞シク活用〕【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 ① 自分のものにしたい。欲しい。 ② そうありたい。望ましい。 |
-里にしあれば ねもころに 見まく欲しけど やまず行かば-(万2-207) ② -古き都は 山高み 川とほしろし 春の日は 山し見が欲し 秋の夜は-(万3-327) ② なでしこが花取り持ちてうつらうつら見まくの欲しき君にもあるかも(万20-4473) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほす [干す・乾す] | 〔他動詞サ行四段〕 ① 濡れたものをかわかす。② 涙をかわかす。泣くのをやめる。 ③ すっかり飲みつくす。 |
① 春過ぎて夏来るらし白栲の衣干したり天の香具山(万1-28) ② -白たへの 衣手干さず 嘆きつつ 我が泣く涙 有間山-(万3-463) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほだ [穂田] | 〔名詞〕稲の穂の出そろった田。 | 秋の田の穂田の刈りばかか寄りあはばそこもか人の我を言なさむ(万4-515) 秋の田の穂田を雁がね暗けくに夜のほどろにも鳴き渡るかも(万8-1543) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほっす [欲す] | 〔他動詞サ行変格〕【セ・シ・ス・スル・スレ・セヨ】[「ほりす」の促音便] ① 欲しいと思う。 ② (「~む(ん)とほっす」の形で)~したいと思う。 また、~しそうな状態である。 |
朝に日に見まく欲りするその玉をいかにせばかも手ゆ離れずあらむ(万3-406) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほととぎす [時鳥・杜鵑・霍公鳥・郭公] |
〔名詞〕 鳥の名。初夏に渡来し、秋に南方に去る。 巣をつくらず、うぐいすなどの巣に卵を生み、ひなを育てさせる。 夏を知らせる鳥として親しまれ、多くの詩歌に詠まれた。 「死出の田長 (たをさ) 」という異称から、冥途から来る鳥ともされた。 卯月鳥 (うづきどり)。 |
いにしへに恋ふらむ鳥は霍公鳥けだしや鳴きし我が念へるごと (万2-112) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほとほと [殆・幾] | 〔副詞〕[「ほとど」とも] ① もう少しで。すんでのことに。 ② おおかた。ほとんど。 |
① 帰りける人来れりと言ひしかばほとほと死にき君かと思ひて(万15-3794) ② 我が盛りまたをちめやもほとほとに奈良の都を見ずかなりなむ(万3-334) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほのか | 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 ① 音・形などが、かすかに聞こえたり見えたりするさま。 ② 色・光などがはっきりしないさま。 ③ わずかである。ほんの少しだ。 |
-うつせみと 思ひし妹が 玉かぎる ほのかにだにも 見えなく思へば(万2-210) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほのけ [火気] | 〔名詞〕 「火気(ほのけ)」の訓解釈。〔名詞〕 「火気(ほのけ)」の訓解釈。 | 縄の浦に塩焼く火のけ夕されば行き過ぎかねて山にたなびく(万3-357) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-354 注『塩焼く煙』」】〔この注釈書では、第二句を「しおやくけぶり」と訓む〕 原文「塩焼火氣」とある「火氣」を、古典全集に「伊勢志摩の海人の刀祢らがたく保乃介(ほのけ)」(神楽歌) とあるのを証に「ホノケ」と訓む。 『説文』(巻十) に「煙、火气也」 とあるから、まさにホノケでよいが、『新訳華厳音義私記経』に「煙、烟字同、気夫利(ケブリ)」 とあるので、通説に従い「ケブリ」 と訓んでおく、後にも「塩焼炎(シホヤクケブリ)」(三六六) の用字が見える。 【中央公論社・澤瀉久孝「萬葉集注釈巻三-354 訓釋『鹽焼くけぶり』」】〔この注釈書でも、第二句を「しおやくけぶり」と訓む〕 「けぶり」 は前(1・二) にあつたが「火気」 の文字を用ゐた事については講義に中村多麻氏が説文(巻十) に「煙、火气也」 とあるに注意された旨紹介されてゐる。 催馬楽、弓立歌に「伊世之末乃(イセシマノ) 安末乃止祢良可(アマノトネラガ) 太久保乃計(タクホノケ)」 とある。それは「火の気」 であり、今も文字通りホノケと訓んでもよい(5・八九二参照) が、「塩焼炎(シホヤクケブリ)」(三六六)、「焼塩煙(シホヤクケブリ)」(7・一二四六) の例と共に「ケブリ」と訓む。鹽焼く事は既(1・五)に述べた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほむき [穂向き] | 〔名詞〕実った穂が一方に靡いていること。 | 秋の田の穂向きの寄れる片寄りに君に寄りなな言痛くありとも(万2-114) 秋の田の穂向き見がてり我が背子がふさ手折り来るをみなへしかも (万17-3965) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほゆ [吠ゆ] | 〔自動詞ヤ行下二段〕【エ・エ・ユ・ユル・ユレ・エヨ】 ① (獣などが) 声を立ててなく。ほえる。 ② 声をあげて泣く様子をののしって言う語。泣きわめく。 ③ やかましく言う。どなる。 |
① -敵見たる 虎か吼ゆると 諸人の おびゆるまでに-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほりす [欲りす] | 〔他動詞サ行変格〕【セ・シ・ス・スル・スレ・セヨ】[「ほっす」の古形] 欲しがる.。望む。 |
いにしへの七の賢しき人たちも欲りせしものは酒にしあるらし(万3-343) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほる [欲る] | 〔他動詞ラ行四段〕願い望む。欲しがる。 | 我が欲りし雨は降り来ぬかくしあらば言挙げせずとも年は栄えむ (万18-4148) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほる [掘る] | 〔他動詞ラ行四段〕 ① (地面や木材などに) 穴をあける。ほる。 ② (地中にあるものを) 掘って取り出す。掘り出す。 |
① -斎ひ掘り据ゑ 竹玉を しじに貫き垂れ 鹿じもの 膝折り伏して-(万3-382) ① 馬酔木なす栄えし君が掘りし井の石井の水は飲めど飽かぬかも(万7-1132) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ま | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ま- [真] | 〔接頭語〕(名詞・形容詞などについて) 真実・正確・純粋・称賛・強調などの意を添える。 「真かなし」 「真木」 「真心」 「真清水」など |
三輪山の山辺真麻木綿短か木綿かくのみからに長くと思ひき(万2-157) 朝日照る嶋の御門におほほしく人音もせねばまうら悲しも(万2-189) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ま [間・際] | 〔名詞〕 ① (時間的に) あいだ。ひま。 ② (空間的に) あるものが位置するところ。また、物と物との間。隙間。 ③ 柱と柱との間。 ④ 家の内で、ふすま・屏風などで仕切られたところ。部屋。 |
① たれこめて春のゆくへも知らぬまに 待ちし桜もうつろひにけり (古今春下-80) ② -波の上を い行きさぐくみ 岩の間を い行きもとほり 稲日つま-(万4-512) ② み吉野の象山の際の木末にはここだも騒く鳥の声かも (万6-929) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まうす [申す] | 〔他動詞サ行四段〕《上代語「まをす」のウ音便》 ① 「言ふ・告ぐ」 の謙譲語。申し上げる。 ② 「願ふ・請ふ」 の謙譲語。お願い申し上げる。お頼み申し上げる。 ③ 「~(と)いふ・~(とよぶ)」 の謙譲語。~と申し上げる。 ④ 「す・なす」 の謙譲語。(何かを何かを)し申し上げる。してさしあげる。 ⑤ 「言ふ」 の丁寧語。申します。言います。 【参考】 「①」 の意では「聞こゆ」が一般的・日常的に用いられ、「申す」 に改まった男性的・古風な感じがあった。 |
① -やすみしし 我が大君の 天の下 申したまへば 万代に -(万2-199) ④ 堀江より水脈引きしつつ御船さすしづ男の伴は川の瀬申せ(万18-4085) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔補助動詞サ行四段〕[四段動詞「まうす」から] 動詞の連用形の下について謙譲の意を表す。 お~申しあげる。お~する。 【参考】 この用法では、他に「聞こゆ・奉る」があり、のち「参らす」も用いられた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まかす [任す・委す] | 〔他動詞サ行下二段〕【セ・セ・ス・スル・スレ・セヨ】 ① そのもののするがままにさせる。自由にさせる。ゆだねる。 ② 従う。 |
-みどり子の 乞ひ泣くごとに 取りまかす 物しなければ 男じもの-(万2-213) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まかぢ [真楫]す | 〔名詞〕「ま」 は接頭語。 楫(=かじ、櫓(ろ) や櫂(かい) など) の美称。 一説に、大型の船の左右に数対そろった楫とも。 |
越の海の 角鹿の浜ゆ 大船に 真楫貫き下ろし いさなとり-(万3-369) -桜皮巻き 作れる船に 真楫貫き 我が漕ぎ来れば 淡路の-(万6-947) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まがひ [紛ひ] | 〔名詞〕 ① 入り乱れて、見分けのつかないこと。 ② 見間違えるほど似せてあること。また、そうしたにせ物。 |
① あしひきの山下光る黄葉の散りの乱ひは今日にもあるかも(万15-3722) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まがふ [紛ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 ① 入り乱れて区別できなくなる。入りまじる。 ② 間違えるほどよく似ている。 ③ 見分けがつかなくなる。間違える。 |
① 妹が家に雪かも降ると見るまでにここだもまがふ梅の花かも(万5-847) ③ 桜花ちりかひくもれ 老いらくのこむといふなる道まがふがに(古今賀-349) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 ① 入り乱れさせて区別できないようにする。見失う。 ② 見間違える。聞き違える。思い違える。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まかなし [真愛し] | 〔形容詞シク活用〕[「ま」は接頭語] 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 いじらしい。いとしい。 |
うちひさす宮に行く子をまかなしみ留むれば苦し遣ればすべなし(万4-535) 置きて行かば妹はま愛し持ちて行く梓の弓の弓束にもがも(万14-3589) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まかりいづ [罷り出づ] | 〔自動詞ダ行下二段〕【デ・デ・ヅ・ヅル・ヅレ・デヨ】 ① 「出(い)づ」の謙譲語。退出する。さがる。 ② 「出(い)づ」の丁寧語。出て参ります。参上します。 |
① -宮人の 罷り出て 遊ぶ船には 楫棹も なくてさぶしも-(万3-259) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まかりぢ [罷り路] | 〔名詞〕死者の行く道。冥土への道。また、葬送の道。 | 楽浪の志賀津の児らが 罷り道の川瀬の道を見ればさぶしも(万2-218) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まがりのいけ [匂の池] | 嶋の宮まがりの池の放ち鳥人目に恋ひて池に潜かず(万2-170) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻二 170 注」】 嶋の宮の中の池を指す。舎人作歌(172) に「上の池なる放ち鳥」 と詠まれており、「匂の池」 という名が実際にあったとは思われない。人麻呂は池の形状によってこの名を創造したのであろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まかる [罷る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 命を受けて都から地方へ下る。赴任する。 ② 貴人の前から引き下がる意の謙譲語。退出する。おいとまする。 ③ この世から退く。死ぬ。 ④ (多く自己・自己側の者に用いて) 「行く」の丁寧語。まいります。 ⑤ 動詞の上に添えて、謙譲または丁寧の意を表す。 |
① 我が背子しけだし罷らば白栲の袖を振らさね見つつ偲はむ(万15-3747) ② 憶良らは今は罷らむ子泣くらむそれその母も我を待つらむそ(万3-340) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔語法〕 下二段他動詞「任(ま)く」(=官職ニ任ズル。赴任サセル) に対する自動詞として「任命されて任地に赴く」意が原義。それから、尊ぶべき所から出て卑しむべき所へ行く意で、出発点を高める「②」の用法が生じ、到着点を高める「まゐる」の対義語となった。中古には「まかる」は敬うべき相手に向かって、話し手や話し手側の者が行くことを改まって言う場合に使われ、「④」の用法が発達し、同様の来る意の「まうでく」の対義語となった。 「まかる」も「まうでく」も、勅撰集の詞書や物語の会話文などに多く用いられる。なお、出発点を高める謙譲語としては「まかづ」が用いられるようになって「まゐる」の対義語となった。 →「まうでく」「まかづ」 【参考】 中古、謙譲語の「まゐる」「まかづ」は下に「給ふ」を付けて「まゐり給ふ」「まかで給ふ」と言うのに対して、丁寧語の「まかる」「まうでく」にはそのような用法はない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まき [真木・槙] | 〔名詞〕[「ま」は接頭語] 立派な、良質の木。檜・杉・松などの常緑樹をいうが、特に檜の異名。 |
-隠口の 初瀬の山は 真木立つ 荒き山道を 岩が根-(万1-45) 真木の葉のしなふ勢能山しのはずて我が越え行けば木の葉知りけむ(万3-294) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まきのつまで [真木の嬬手] | 〔名詞〕杉や檜などの角だった、粗作りの木材。一説に、檜の丸太とも。 | -泉の川に 持ち越せる 真木のつまでを 百足らず 筏に作り-(万1-50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まきばしら [真木柱] | 【枕詞】真木柱は太いことから「太し」 にかかる。檜や杉材の柱。 | 真木柱太き心はありしかどこの我が心鎮めかねつも(万2-190) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まく [枕く] | 〔他動詞カ行四段〕 ① 枕とする。枕にして寝る。② 一緒に寝る。結婚する。 |
① かくばかり恋ひつつあらずは高山の磐根しまきて死なましものを (万2-86) ① 沖つ波来寄する荒礒をしきたへの枕とまきて寝せる君かも(万2-222) ② うちひさす宮の我が背は大和女の膝まくごとに吾を忘らすな (万14-3476) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まく [巻く・捲く・纏く] | 〔他動詞カ行四段〕 ① 長い物をぐるぐると巻く。巻きつける。(丸く)巻く。② 取り囲む。 |
-つむじかも い巻き渡ると 思ふまで 聞きの畏く-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まく [任く・罷く] | 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 ① 官職に任ずる。赴任させる。② 命じて去らせる。退出させる。 【参考】 萬葉集巻十八に四段活用の連用形の例が二例見られるが、後世の人の誤写といわれる。 |
① 土部(はじ)の職(つかさ)にまけ給ふ(紀・垂仁) ① -皇子ながら 任けたまへば 大御身に 大刀取り佩かし 大御手に-(万2-199) ② 姉は醜(みにく)しとおもほして、御(め)さずしてまけ給ふ(紀・神代) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まく [蒔く・撒く] | 〔他動詞カ行四段〕 ① (種子などを) 手から地面に落とす。まき散らす。 ② 蒔絵(まきゑ) をする。 |
① 我が宿に韓藍蒔き生ほし枯れぬとも懲りずてまたも蒔かむとそ思ふ(万3-387) ① ちはやぶる神の社しなかりせば春日の野辺に粟蒔かましを(万3-407) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まく | (上代語)未来の推量を表す。~だろうこと。~であるようなこと。 推量の助動詞「む」のク語法。 ⇒「む」語法 〔接続〕活用語の未然形に付く。 |
-我妹子が 里にしあれば ねもころに 見まく欲しけど やまず行かば-(万2-207) 草枕旅の宿りに誰が嬬か国忘れたる家待たまくに(万3-429) 梅の花散らまく惜しみ我が園の竹の林に鴬鳴くも(万5-828) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まくさ [真草] | 〔名詞〕[「ま」は接頭語] 草、特に屋根を葺くのに用いる「かや」「すすき」などをいう。 |
ま草刈る荒野にはあれど黄葉の過ぎにし君の形見とぞ来し(万1-47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まくさかる [真草刈る] | 【枕詞】「荒野」にかかる。 | ま草刈る荒野にはあれど黄葉の過ぎにし君が形見とぞ来し(万1-47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まくほし [まく欲し] | 〔なりたち〕推量の助動詞「む」のク語法「まく」+形容詞「欲(ほ)し」 ~(し)たい。~でありたい。 |
栲領巾のかけまく欲しき妹の名をこの勢能山にかけばいかにあらむ [一に云ふ 替へばいかにあらむ](万3-288) 老いぬればさらぬ別れもありといへばいよいよ見まくほしき君かな(古今雑上-900) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 「まくほし」が変化して平安時代の希望の助動詞「まほし」になったといわれるが、和歌では、平安時代に入っても用いられることがある。→「まほし」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まくら [枕] | 〔名詞〕 ① 寝るときに、頭をのせるもの。まくら。 ② 寝ること。宿ること。 「新枕(にひまくら)・草枕・旅枕」などの形で用いる。 ③ 枕のあたり。頭の方。④ かたわらに置いて事の拠り所とするもの。 |
② 玉藻刈る沖へは漕がじ敷栲の枕のあたり忘れかねつも(万1-72) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -べ [枕辺] | 〔名詞〕「まくらへ」とも。枕もと。 | -我がやどに みもろを立てて 枕辺に 斎瓮を据ゑ 竹玉を-(万3-423) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まくらづく [枕付く] | 【枕詞】枕を二つ並べて寝ることから、「妻屋(つまや=夫婦の寝室)」にかかる。 | -二人我が寝し 枕づく つま屋の内に 昼はも うらさび暮らし-(万2-210) -思ひ延べ 嬉しびながら 枕付く 妻屋のうちに 鳥座結ひ-(万19-4178) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まくらく [枕く] | 〔他動詞カ行四段〕[名詞「枕」を動詞化したもの] 枕にする。 | 大伴の高師の浜の松が根を枕き寝れど家し偲はゆ(万1-66) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まけ [任] | 〔名詞〕(下二段動詞「任(ま)く」 の連用形から) 官職に任ずること。特に、地方官に任命すること。 【参考】 多く「大君のまけのまにまに」の形で使われる。 |
物部の臣の壮士は大君の任けのまにまに聞くといふものぞ(万3-372) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まこと [真・実・誠] | 〔名詞〕 ① ほんとうのこと。真実。事実。真理。 ② いつわりのないこと。まごころ。成実さ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔副詞〕ほんとうに。じっさい。 | 聞きしごとまこと尊くくすしくも神さびをるかこれの水島(万3-246) たらちねの母を別れてまこと我れ旅の仮廬に安く寝むかも(万20-4372) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔感動詞〕ふと思い出したことを言う時の言葉。 「ああ、そうそう。ああ、そうだ。」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まさきく [真幸く] | 〔副詞〕[「ま」は接頭語] 幸せに。無事に。 |
磐白の浜松が枝を引き結びま幸くあらばまた帰り見む(万2-141) 我が命しま幸くあらばまたも見む志賀の大津に寄する白波(万3-291) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まさしに [正しに] | 〔副詞〕まことに。確かに。 | 大船の津守が占に告らむとはまさしに知りて我がふたり寝し(万2-109) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まさる [増さる] | 〔自動詞ラ行四段〕(数量や程度が) 増える。強まる。 | 都なる荒れたる家にひとり寝ば旅にまさりて苦しかるべし(万3-443) 我妹子を相知らしめし人をこそ恋の増されば恨めしみ思へ(万4-497) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まさる [勝る・優る] | 〔自動詞ラ行四段〕すぐれる。ひいでる。 | 賢しみと物言ふよりは酒飲みて酔ひ泣きするし優りたるらし(万3-344) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まし | 〔助動特殊型〕 ① もし・・であったとしたら・・だろうに。 ② 希望・願望・・だったらよかったろうに。 |
① 旅にしてもの恋ほしきに鶴が音も聞こえざりせば恋ひて死なまし (万1-67) ① 妹が家も継ぎて見ましを大和なる大島の嶺に家もあらましを [一云 妹があたり継ぎても見むに] [一云 家居らましを](万2-91) ① 高光る我が日の御子の万代に国知らさまし嶋の宮はも(万2-171) ① 妻もあらば摘みて食げまし沙弥の山野の上のうはぎ過ぎにけらずや(万2-221) ① ちはやぶる神の社しなかりせば春日の野辺に粟蒔かましを(万3-407) ① 悔しかもかく知らせませばあをによし国内ことごと見せましものを (万5-801) ② 見る人もなき山里の桜花ほかの散りなむ後ぞ咲かまし(古春上-68) ② 我を待つと君が濡れけむあしひきの山のしづくにならましものを (万2-108) ② 早来ても見てましものを山背の高の槻群散りにけるかも(万3-280) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔接続〕活用語の未然形につく。 〔語法〕未然形の「ましか」は「ば」を伴って仮定の意を表わすのに用い、已然形の「ましか」は「こそ」の結びとして用いられる。上代には未然形に「ませ」という形があった。「ませ」は中古以後も歌に用いられた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まして [況して] | 〔副詞〕① いっそう。もっと。② いわんや。いうまでもなく。 | -時じき時と 見ずて行かば まして恋しみ 雪消する 山道すらを-(万3-385) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ましじ 主要助動詞活用『まじ』 | 〔助動詞「まじ」の古形〕 ~ないだろう。~まい。~はずがない。 |
玉櫛笥みもろの山のさな葛さ寝ずはつひに有りかつましじ [玉くしげ三室戸山の] (万2-94) 直に逢はば逢ひかつましじ石川に雲立ち渡れ見つつ偲はむ(万2-225) 堀江越え遠き里まで送り来る君が心は忘らゆましじ(万20-4506) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まじふ [交じふ・雑じふ] | 〔他動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 まぜ合わせる。混合させる。 |
-玉に貫き [一云 貫き交へ] 縵にせむと 九月の しぐれの時は-(万3-426) 霍公鳥汝が初声は我れにもが五月の玉に交へて貫かむ(万10-1943) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まじる [交じる・混じる・雑じる] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① あるものの中に他のものが入り込む。また、まざる。 ② 人に立ちまじる。仲間にはいる。また、宮仕えする。 ③ (山や野に)分け入る。 |
① 今日今日と我が待つ君は石川の貝に [一云 谷に] 交じりてありといはずやも (万2-224) ① 残りたる雪に交れる梅の花早くな散りそ雪は消ぬとも(万5-853) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ます [増す・益す] | 〔自動詞サ行四段〕 ① 数・量が多くなる。増加する。 ② まさる。すぐれる。 |
② 秋山の木の下隠り行く水の我れこそ益さめ思ほすよりは(万2-92) ② 価なき宝といふとも一坏の濁れる酒にあにまさめやも(万3-348) ② 旅と言へば言にぞやすきすべもなく苦しき旅も言にまさめやも (万15-3785) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ます [増す・益す] | 〔他動詞サ行四段〕 ① 数・量を多くする。増加させる。 ② すぐれるようにする。まさらせる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ます | 〔助動詞四型〕「申す」からの転。相手に対する謙譲の意「~し申す」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔助動詞サ変型〕 【マセ・マシ・マス(マスル)・マス(マスル)・マセ(マスレ)・マセ(マセイ)】 「まゐらせさす」の略。 ① 動作を受ける相手に対する敬意を表わす。お~する。 ② 相手に対する丁寧・謙譲の意を表わす。~ます。 〔接続〕動詞の連用形に付く。 |
② -花散らふ 秋津の野辺に 宮柱 太敷きませば ももしきの-(万1-36) ② 打ち麻を麻続の王海人なれや伊良虞の島の玉藻刈ります(万1-23) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 ①と②が合流して、現代の丁寧語「ます」(サ変型)が現れた。 ②の活用はもともと下二段型であったが時代が新しくなるにつれて「サ変型」に移行している。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ます [座す・坐す] | 〔自動詞サ行四段〕 ①「あり」の尊敬語。 「いらっしゃる」「おいでになる」「おありになる」 ②「行く「来(く)」の尊敬語。 「いらっしゃる」「おいでになる」 |
① 外に見し真弓の岡も君座せば常つ御門と侍宿するかも(万2-174) ① 大君は千歳にまさむ白雲も三船の山に絶ゆる日あらめや(万3-244) ① -名付けも知らず 奇しくも います神かも 石花の海と-(万3-322) ② 我が背子が国へましなば霍公鳥鳴かむ五月は寂しけむかも (万17-4020) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ます | 〔補助動詞サ行四段〕(動詞の連用形に付いて)尊敬の意を表す。 「お~になる」「~て(で)いらっしゃる」 |
-ひじりの御代ゆ [或云 宮ゆ] 生れましし 神のことごと -(万1-29) -清御原の宮に 神ながら 太敷きまして すめろきの 敷きます国と-(万2-167) やすみしし我が大君の敷きませる国の中には都し思ほゆ(万3-332) ひととせにひとたび来ます君待てば宿かす人もあらじとぞ思ふ (古今羈旅-419) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ますみのかがみ [真澄の鏡] | きれいに澄み、はっきり映る鏡。 真澄鏡(ますかがみ・まそかがみ)。真澄み鏡。 |
-み墨の坩 我が目らは ますみの鏡 我が爪は み弓の弓弭-(万16-3907) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ますらを [益荒男・丈夫] | 〔名詞〕勇ましく立派な男・勇士・ますらたけを。⇔「手弱女(たをやめ)」 |
大夫の 出で立ち向ふ 故郷の -(万10-1941) ますらをの鞆の音すなり物部の大臣盾立つらしも(万1-76) ますらをや片恋せむと嘆けども醜のますらをなほ恋ひにけり(万2-117) 梓弓 手に取り持ちて ますらをの さつ矢手挟み 立ち向かふ-(万2-230) 嘆きつつますらをのこの恋ふれこそ我が結ふ髪の漬ちてぬれけれ(万2-118) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ますらをの [益荒男の] | 【枕詞】 「ますらを」が手結(=袖カザリ/たゆい) をつけたことから、 地名「たゆひ」 にかかる。 |
-我が漕ぎ行けば ますらをの 手結が浦に 海人娘子-(万3-369) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ませば~まし | 〔なりたち〕 反実仮想の助動詞「まし」の未然形「ませ」+接続助詞「ば」+~+反実仮想の助動詞「まし」 【参考】 主として上代に用いられ、中古以降は多く「ましかば~まし」が用いられた。 |
明日香川しがらみ渡し塞かませば流るる水ものどにかあらまし [一云 水の淀にかあらまし](万2-197) 我が背子とふたり見ませばいくばくかこの降る雪の嬉しくあらまし(万8-1662) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反実仮想を表す。事実に反することや、実現しそうにないことを仮に想定し、その仮定の上に立って推量、想像する意を表す。 もし~(た)なら、~(た)だろう(に) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まそかがみ [真澄鏡] | 〔名詞〕「ますかがみ」とも。「ますみのかがみ」に同じ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】 鏡の使いみち・状態などから、 「見る・みぬめ・清し・面影・照る・掛く・磨ぐ」などにかかる。 |
まそ鏡見飽かぬ君に後れてや朝夕にさびつつ居らむ(万4-575) まそ鏡敏馬の浦は百舟の過ぎて行くべき浜ならなくに(万6-1070) 織女し舟乗りすらしまそ鏡清き月夜に雲立ちわたる(万17-3922) 里遠み恋わびにけりまそ鏡面影去らず夢に見えこそ(万11-2642) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まそぼ [真赭・真朱] | 〔名詞〕(「ま」は接頭語) 「ますほ」とも。 ① 朱色の顔料にする赤色の土。辰砂(しんしや)。 ② 赤い色。多く、「真赭の糸・真赭の薄」の形で、すすきの穂が赤みを帯びたものをいう。 |
① 仏造るま朱足らずは水溜まる池田の朝臣が鼻の上を掘れ(万16-3863) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また [又・亦・復] | 〔副詞〕 ① もう一度。ふたたび。かさねて。② 同じように。やはり。 ③ その他。別に。 |
① 楽浪の志賀の [一云 比良の] 大わだ淀むとも昔の人にまたも逢はめやも [一云 逢はむと思へや](万1-31) ① 水伝ふ礒の浦廻の岩つつじ茂く咲く道をまたも見むかも(万2-185) ① 敷栲の袖交へし君玉垂の越智野過ぎ行くまたも逢はめやも [一云 越智野に過ぎぬ] (万2-195) ① 我が盛りまたをちめやもほとほとに奈良の都を見ずかなりなむ(万3-334) ③ これをおきて またはありがたし さ慣らへる 鷹はなけむと (万17-4035) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また | 〔接続詞〕 ① ならびに。および。② そして。それに。そのうえ。 ③ あるいは。もしくは。そうかと思うと。 ④ しかし。そうかといって。 ⑤(話題を変えるときに言う語) 「そして」「それから」「そこで」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まちかぬ [待ち兼ぬ] | 〔他動詞ナ行下二段〕【ネ・ネ・ヌ・ヌル・ヌレ・ネヨ】 [「かぬ」は接尾語] →「かぬ」 待っていることに堪えられなくなる。待ち切れなくなる。 |
荒礒やに生ふる玉藻のうち靡きひとりや寝らむ我を待ちかねて(万14-3584) 楽浪の志賀の辛崎幸くあれど大宮人の舟待ちかねつ(万1-30) 我が背子が古家の里の明日香には千鳥鳴くなり夫待ちかねて(万3-270) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まちざけ [待ち酒] | 〔名詞〕来客用に、長い時間をかけて作った酒。 | 君がため醸みし待酒安の野にひとりや飲まむ友なしにして(万4-558) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まつ [松] | 〔名詞〕 ① マツ科の常緑高木。 古くから神の宿る木とされ、長寿・繁栄・慶事・節操を表すものとして尊ばれた。 ②「松明(たいまつ)」の略。 ③「門松(かどまつ)」の略。新年を祝って家の門に立てる松。松飾り。 |
① 我妹子を早見浜風大和なる我れ松椿吹かざるなゆめ(万1-73) ① 八千種の花は移ろふ常盤なる松のさ枝を我れは結ばな(万20-4525) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まつ [待つ] | 〔他動詞タ行四段〕 ① 相手や物事の来るのを望む。意識する。 ② 相手や物事の来るのを用意して迎える。もてなす。 ③ 延期する。遅らせる。 |
① 熟田津に船乗りせむと月待てば潮もかなひぬ今は漕ぎ出でな(万1-8) ① 君が行き日長くなりぬ山尋ね迎へか行かむ待ちにか待たむ(万2-85) ① 鴨山の岩根しまける我をかも知らにと妹が待ちつつあるらむ(万2-223) ① 春日野に粟蒔けりせば鹿待ちに継ぎて行かましを社し恨めし(万3-408) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まつかぜ [松風] | 〔名詞〕松の梢にあたって吹く風。また、その音。多く琴の音にたとえる。 | 天降りつく 天の香具山 霞立つ 春に至れば 松風に 池波立ちて-(万3-259) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まつがね [松が根] | 〔名詞〕松の根。 | 大伴の高師の浜の松が根を枕き寝れど家し偲はゆ(万1-66) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まつがねの [松が根の] | 【枕詞】 同音を重ねて「待つ」に松の根が続く意から、「絶ゆることなく」にかかる。 |
-人に言ふ ものにしあらねば 松が根の 待つこと遠み-(万13-3272) -いや継ぎ継ぎに 松が根の 絶ゆることなく あをによし- (万19-4290) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まつちやま [真土山・待乳山] | 〔地名〕 ① [真土山]和歌山県橋本市の西にある山。 「南海道」の入り口にあたるため古来歌に詠まれ、多く同音の「待つ」にかける。 「真土の山」(歌枕) ② 東京都台東区の浅草本竜院の境内にある小丘。 頂上に聖天(=歓喜天)をまつる。江戸文学ゆかりの地。 |
① あさもよし紀人羨しも真土山行き来と見らむ紀人羨しも(万1-55) ① -あさもよし 紀伊路に入り立ち 真土山 越ゆらむ君は もみち葉の-(万4-546) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まつばら [松原] | 〔名詞〕一面に松の木が生えている原。 | 住吉の野木の松原遠つ神我が大君の幸行処(万3-298) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まつる [奉る] | 〔他動詞ラ行四段〕《上代語》 ① [「与ふ」「やる」などの謙譲語] 「差上げる」「たてまつる」 ② [「飲む」「食ふ」などの尊敬語] 「召し上がる」 |
① 心をし君に奉ると思へればよしこのころは恋ひつつをあらむ(万11-2608) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まつる [奉る] | 〔補助動詞ラ行四段〕《上代語》 [動詞の連用形の下に付いて、謙譲の意を表す] 「お~申し上げる」「お~する」 |
-神宮に 装ひまつりて 使はしし 御門の人も 白栲の 麻衣着て-(万2-199) 見まつりていまだ時だに変らねば年月のごと思ほゆる君(万4-582) -神下し いませまつりし 高照らす 日の御子は 飛ぶ鳥の-(万2-167) - あさもよし 城上の宮を 常宮と 高くしたてて 神なが -(万2-199) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻二-199 注「高くしまつりて」」】 -略、なお古典全集には「タカクシタテテ」という旧訓を採用しているが、これは「奉」を「タツ」と訓む点に難があろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まつる [祭る] | 〔他動詞ラ行四段〕 食物をさし上げたり、音楽を奏したりして、神霊を慰め、また祈願する。 |
我が祭る神にはあらずますらをにつきたる神そよく祭るべし(万3-409) 木綿懸けて祭る三諸の神さびて斎むにはあらず人目多みこそ(万7-1381) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まつろふ [服ふ・順ふ] | 〔四段動詞「奉(まつ)る」の未然形「まつら」に上代の反復・継続の助動詞「ふ」の付いた「まつらふ」の転。〕祭る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔自動詞ハ行四段〕従う。服従する。 |
「東の方十二道(とをまりふたみち) の荒ぶる神、 またまつろはぬ人どもを言向け(ことむけ) 和平(やは) せ」(記中) -召したまひて ちはやぶる 人を和せと 奉ろはぬ 国を治めと-(万2-199) -ちはやぶる 神を言向け まつろはぬ 人をも和し 掃き清め-(万20-4489) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 つき従わせる。服従させる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まで まで (真手) その「表記」 |
〔副助詞〕 ① 動作・作用の帰着点・終点を示す、~までに ② 動作・作用の及ぶ時間的・空間的な限界を示す、~くらいに ③ 動作・作用・状態の限度・程度の極端なことを示す、~ほど |
① 天飛ぶや鳥にもがもや都まで送りまをして飛び帰るもの(万5-880) ② 白波の浜松が枝の手向けぐさ幾代までにか年の経ぬらむ (万1-34) ② 大宮の内まで聞こゆ網引すと網子ととのふる海人の呼び声(万3-239) ② -里長が声は 寝屋処まで来立ち呼ばひぬ-(万5-896) ③ -つむじかも い巻き渡ると 思ふまで 聞きの畏く-(万2-199) ③ -立ち向かふ 高円山に 春野焼く 野火と見るまで 燃ゆる火を-(万2-230) ③ わが宿は道もなきまで荒れにけりつれなき人を待つとせしまに (古今恋五-770) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔終助詞〕「までに」とも。感動の意を表わす。なあ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| までに | 〔副助詞〕「まで」に格助詞「に」のついたもの ① 動作・作用の程度をはっきり表わす。「~くらいに、~ほど」 ② 動作・作用・状態の限度をはっきりと示す。「~ほどに」 |
① あさぼらけありあけの月と見るまでに吉野のさとにふれる白雪(古冬-332) ① -作れる家に 千代までに いませ大君よ 我れも通はむ(万1-79) ① -虎か吼ゆると 諸人の おびゆるまでに [一云 聞き惑ふまで] -(万2-199) ② 妹が名は千代に流れむ姫島の小松がうれに蘿生すまでに(万2-228) ② 我が宿の穂蓼古幹摘み生し実になるまでに君をし待たむ(万11-2769) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まとかた [円方] | 〔地名〕三重県松坂市の東部、東黒部町一帯の地。 『逸文風土記』に、「地形似的」とあり、地形より出た地名。 |
大丈夫のさつ矢手挟み立ち向ひ射る圓方は見るにさやけし(万1-61) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まどはす [惑はす] | 〔他動詞サ行四段〕「まどはかす」とも。《上代は「まとはす」》 ① 迷わす。悩ませる。心を動揺させる。 ② 混乱させる。区別をつかなくさせる。まごつかせる。 ③ ゆくえの知れないようにする。見失わせる。 |
② -聞きの恐く [一云 諸人の 見惑ふまでに] 引き放つ 矢の繁けく-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まどふ [惑ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕《上代は「まとふ」》 ① 心が乱れる。あれこれ思い悩む。分別を失う。 ② 迷う。さまよう。途方にくれる。③ あわてる。うろたえる。 ④ (動詞の連用形の下について) ひどく~する。 |
② 埴安の池の堤の隠り沼のゆくへを知らに舎人は惑ふ(万2-201) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まどほ [間遠] | 〔名詞・形動ナリ〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】[「まとほ」とも] ① (時間的・空間的に) 間が隔たること。 ② 網目や織目の粗いこと。 |
② 須磨の海人の塩焼き衣の藤衣間遠にしあればいまだ着馴れず(万3-416) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まどほし [間遠し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 「まとほし」とも。 (時間的・空間的に) 離れている。 |
児らが家道やや間遠きをぬばたまの夜渡る月に競ひあへむかも(万3-305) 昨夜こそば子ろとさ寝しか雲の上ゆ鳴き行く鶴の間遠く思ほゆ(万14-3543) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まなし [間無し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① 隙間がない。 ② 絶え間がない。暇がない。 ③ すぐだ。即座である。 |
① -枕辺に 斎瓮を据ゑ 竹玉を 間なく貫き垂れ-(万3-423) ② 波立てば奈呉の浦廻に寄る貝の間なき恋にぞ年は経にける(万18-4057) ② -時なくぞ 雪は降りける 間無くぞ 雨は振りける -(万1-25) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まにま [随・随意] | 〔名詞・副詞〕 事のなりゆきに従うこと。「~どおりに・~ままに」 |
大君の 行幸のまにま もののふの 八十伴の男と 出でて行きし-(万4-546) 去年の秋相見しまにま今日見れば面やめづらし都方人(万18-4141) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まにまに [随に] | 〔副詞〕[「ままに」の古形。] 事のなりゆきに任せるさま。「~ままに・~につれて」 |
梓弓引かばまにまに寄らめども後の心を知りかてぬかも(万2-98) もののふの臣の壮士は大君の任けのまにまに聞くといふものそ(万3-372) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まぬかる [免る] | 〔他動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 そのことの影響を受けないですむ。のがれる。まぬがれる。 |
-生ける者 死ぬといふことに 免れぬ ものにしあれば 頼めりし-(万3-463) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まの [真野] | 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 『付録 地名一覧』」】 〔A〕神戸市長田区東尻池町、西尻池町、真野町などの一帯。 〔B〕福島県相馬郡鹿島町。 昭和二十九年(1954)まで上真野村・真野村の名があった。 真野川が流れている。 |
〔A〕 いざ子ども大和へ早く白菅の真野の榛原手折りて行かむ(万3-283) 白菅の真野の榛原行くさ来さ君こそ見らめ真野の榛原(万3-284) 〔B〕 陸奥の真野の草原遠けども面影にして見ゆといふものを(万3-399) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-396 注『真野の草原』」】 真野は陸奥の行方郡に「真野、末乃(マノ)」(和名抄) とある。今の福島県相馬郡鹿島町。西の山の手に、もと上真野村、東の海岸寄りに真野村があった。真野川の流域が、草原をなしていたので、昔から有名であり、もう万葉時代から歌枕的地名として都人の知るところであったとみてよい。「草原」 の「草」 はクサ(これは雑草の意) ではなく、カヤ(茅・萱・薄などの総称) と訓む。雑草の原では名所にもならないからである。 【有斐閣「萬葉集全注巻四-490 注『真野の浦』」】 所在未詳。あるいは高市黒人夫妻が「白菅の真野の榛原」(3・二八〇、二八一) と詠み、また「真野の池の小菅の笠に逢はずして」(11・二七七二) とも詠まれた摂津のそれあという。摂津志矢田部郡に「真野浦、西尻池村ニ在リ」 とあり、それは神戸市長田区東部の東尻池町、真野町、西池尻町などの一帯に当たるという。浦とあることからも、その地が海岸近くの入江であったことが想像される。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まねし | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 《上代語》たびかさなる。数が多い。 |
-御言問はさぬ 日月の 数多くなりぬれ そこ故に 皇子の宮人-(万2-167) -やまず行かば 人目を多み まねく行かば 人知りぬべみ-(万2-207) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まへ [前] | 〔名詞〕 ① 前方。正面。表のほう。② 過ぎ去ったほう。もと。以前。昔。③ 前庭。庭先。④ 神や貴人を尊びはばかって、直接それとささずに言う語。神前。御前。 ⑤ 貴人の近くに出ること。 ⑥ (「~の前」の形で) 女性の名に付けて敬意を表す。⑦ (僧などの) 食事。 ⑧ 陰部。 |
① -母の命は 斎瓮を 前に据ゑ置きて 片手には-(万3-446) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まほし | 〔助動詞シク型〕【マホシ・マホシク(マホシカリ)・マホシ・マホシキ(マホシカル)・マホシケレド】 〔推量の助動詞「む」のク語法「まく」に形容詞「欲(ほ)し」の付いた「まくほし」の転。〕→「まくほし」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① 動作の主体の希望の意を表す。~たい。 ア 話し手と動作の主体が一致する場合。 イ 話し手と動作の主体が一致しない場合。 ② 他に対してその状態への希望の意を表す。~てほしい。 〔接続〕 動詞及び動詞型活用の助動詞の未然形に付く。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ままのいりえ [真間の入江] | 【有斐閣「萬葉集全注巻三-433 注『真間の入江』」】 真間は今日では内陸部にあるが、昔は入海になっていた。高橋虫麻呂歌集の「勝鹿の真間娘子を詠む歌一首并せて短歌」(9・一八〇七) に「浪の音の 騒く港の 奥城(おくつき)」 という表現によっても「可豆思加(カヅシカ)の麻万(ママ)の浦廻(ウラミ)を」(14・三三四九) とあるによっても、入海になっていたことがよく分かる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ままのてこな [真間の手古奈] | 〔人名〕[「てこな」は少女の意。「てごな」とも] 「万葉集」に歌われた伝説上の女性。下総(千葉県)葛飾郡の真間の里の娘で、絶世の美人で多くの男子に求婚されて悩み、入水してしまったという。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まゆみ [檀] | 〔名詞〕 ① 山野に自生する落葉亜高木。晩秋に紅葉する。 幹の外皮は青く艶があり、内面は白色または黄。 木質は強く弓を作るのに適する。また紙をつくる。 ②(檀弓・真弓)檀の木で作った丸木弓。 作り方によって「白檀弓「反檀弓」「小檀弓」など諸種がある。 |
① 南淵の細川山に立つ檀弓束巻くまで人に知らえじ(万7-1334) ② み薦刈る信濃の真弓引かずして強ひさるわざを知ると言はなくに(万2-97) ② 外に見し真弓の岡も君座せば常つ御門と侍宿するかも(万2-174) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻二 2-167」 注】 真弓の岡は、今の近鉄飛鳥駅の西で、高市郡高取町佐田にある。 諸陵式にも「真弓丘陵岡宮御字天皇、在大和国高市郡」 と見えるが、最近の発掘で従来岡宮天皇陵と考えられていた所から三百メートル北の東明神古墳が草壁陵として有力視されつつある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まよね [眉根] | 〔名詞〕[「まゆね」とも] 眉(まゆ)。 | 暇なく人の眉根をいたづらに掻かしめつつも逢はぬ妹かも(万4-565) -青柳の 細き眉根を 笑み曲がり 朝影見つつ 娘子らが-(万19-4216) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まよねかく[眉根掻く] | 眉がかゆくてかく。恋人に会う前兆、または、恋人に会いたいときのまじない。 | 月立ちてただ三日月の眉根掻き日長く恋ひし君に逢へるかも(万6-998) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まろぶ [転ぶ] | 〔自動詞バ行四段〕① ころがる。② 倒れる。 | -天知らしぬれ 臥いまろび ひづち泣けども せむすべもなし(万3-478) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まゐる [参る] | 1〔自動詞ラ行四段〕 ① 「行く・来(く)」 の謙譲語。参上する。 ア- (神社や寺に) 参詣する。参拝に行く。 イ- (身分の高い人、目上の人の所へ) 参上する。うかがう。 ウ- (身分の高い人、目上の人の所へ) お仕えする。出仕する。 ② 「行く・来(く)」 の丁寧語。参ります。 2〔他動詞ラ行四段〕 ① 「す・仕ふ」 の謙譲語。(何かを) してさしあげる。奉仕する。 ② 「飲む・食ふ・す」 などの尊敬語。召し上がる。(何かを) させなさる。 |
〔1-①-イ〕 一日には千たび参りし東の大き御門を入りかてぬかも(万2-186) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 「まゐる」 の対義語は、上代では「まかる」 だが、中古になると、「まゐる」 に対しては「まかづ」 が用いられるようになった。 「1-②」の場合は、身分の高い人、目上の人の所へではなく、必ずしも敬う必要がない場所に「行く・来」 の場合で、丁寧語と見る。 「2-②」の尊敬語としての用法は、「2-①」から転じたものであるが、その場合は、動作の為手(して)、受け手はだれかを、前後の文意から読み取って判断する必要がある。 『まゐる』と『まかる』 身分の高い人、目上の人など上位と見られる人の所へ「行く」 意の謙譲語が「まゐる」、そこから「退く」 意の謙譲語が「まかる」 の原義である。 この関係は「のぼる」 と「くだる」 の関係に似ている。なお、中古に下ると、「まゐる」 と「まかづ」、「まうづ」「まうでく」と「まかる」とが、それぞれ対応するようになる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まをす [申す・白す] | 〔他動詞サ行四段〕《上代語》[「まうす」の古形] 「言ふ」 の謙譲語。 申し上げる。 |
-秋去らば 帰りまさむと たらちねの 母に申して 時も過ぎ-(万15-3710) 否と言へど語れ語れと詔らせこそ志斐いは奏せ強ひ語りと言ふ(万3-238) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔補助動詞サ行四段〕《上代語》[「まうす」の古形] (動詞の連用形の下に付いて) 謙譲の意を表す。~申し上げる。 |
天飛ぶや鳥にもがもや都まで送りまをして飛び帰るもの(万5-880) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| み- | 〔接頭語〕 ①【御】尊敬の意を表す。 「御格子(みかうし)」「御国」「御位(みくらゐ)」「御世」 ②【御・美・深】美称、または語調を整えるときに用いる。 |
① み立たしの島を見る時にはたづみ流るる涙止めそかねつる(万2-178) ① つれもなき佐田の岡辺に帰り居ば島の御階に誰れか住まはむ(万2-187) ① 沖つ波辺波立つとも我が背子がみ船の泊り波立ためやも(万3-248) ② -苦しきものを み空行く 雲にもがも 高飛ぶ 鳥にもがも-(万4-537) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -み | 〔接尾語〕 ① 形容詞の語幹に付き、この後に続く「思ふ」「す」の内容を表わす連用修飾語をつくる。 ② 形容詞及び形容詞型に活用する助動詞「べし・まし・ましじ」の語幹について、原因・理由を表わす。多くは上に名詞と助詞「を」が来る。 「~なので、~だから」 ③ 形容詞の語幹について、名詞をつくる。 ④ 動詞または助動詞「ず」の連用形について重ねて用いられ、動作が交互に反復して行われることを表わす。[~み~み] |
① 玉桙の道の神たち賄はせむ我が思ふ君をなつかしみせよ(万17-4033) ② 山越しの風を時じみ寝る夜おちず家なる妹を懸けて偲ひつ(万1-6) -見まく欲しけど やまず行かば 人目を多み まねく行かば-(万2-207) ③ 古への古き堤は年深み池のなぎさに水草生ひにけり(万3-381) ③ 夏の野の茂みに咲ける姫百合の知らえぬ恋は苦しきものぞ(万8-1504) ③ 采女の袖吹きかへす明日香風都を遠みいたづらに吹く(万1-51) ④ -男じもの 負ひみ抱きみ 朝鳥の 音のみ泣きつつ 恋ふれども-(万3-484) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| み [-回・曲] | 〔接尾語〕(上一段動詞「回(み)る」の連用形から) 山・川・海などの入り曲がったところの意を表す。「~のあたり・~のめぐり」 【例:「浦み」「隈み」「里み」「島み」など】 |
大和恋ひ寐の寝らえぬに心なくこの洲崎廻に鶴鳴くべしや(万1-71) 後れ居て恋ひつつあらずは追ひ及かむ道の隈廻に標結へ我が背(万2-115) 夢にだに見ざりしものをおほほしく宮出もするかさ桧の隈廻を(万2-175) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミ語法) | 上代の語法で、「接尾語②」に相当する。 ② 形容詞及び形容詞型に活用する助動詞「べし・まし・ましじ」の語幹について、原因・理由を表わす。多くは上に名詞と助詞「を」が来る。 「~なので、~だから」〕 「名詞」+「間投序詞『を』」+「形容詞語幹」+「み」 「~を~み」 ~が~なので。 「ミ語法+ト」の形式 ① 主情的な意味を表す形容詞のミ語法の場合は、 「~だと思って・~ぶって・~がって」 ② 客観的な性質状態を表す形容詞のミ語法の場合は、 「~だというわけで」、いわゆる「~トテ」 |
我妹子をいざ見の山を高みかも大和の見えぬ国遠みかも(万1-44) 宵に逢ひて朝面無み名張にか日長き妹が廬りせりけむ(万1-60) 三津の崎波を恐み隠り江の舟公宣奴嶋尓(万3-250) あしひきの岩根こごしみ菅の根を引かば難みと標のみそ結ふ(万3-417) ① 賢しみと物言ふよりは酒飲みて酔ひ泣きするし優りたるらし(万3-344) ① あしひきの岩根こごしみ菅の根を引かば難みと標のみそ結ふ (万3-417) ② 霰降り吉志美が岳を険しみと草取りかなわ妹が手を取る(万3-388) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| み [見] | 〔名詞〕見ること。 | 香具山と耳成山と闘ひし時立ちて見に来し印南国原(万1-14) -明日香の 古き都は 山高み 川とほしろし 春の日は 山し見が欲し-(万3-327) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| み [身] | 〔名詞〕 ① からだ。身体。② 身分。また、身の上。身のほど。 ③ 自分。我が身。④ 命。⑤ 刀の鞘の中の刃。刀身。⑥ 中身。内容。 〔代名詞〕 自称の人代名詞。わたくし。われ。男性が用いた。 |
① -其を取ると 騒く御民も 家忘れ 身もたな知らず 鴨じもの-(万1-50) ① しらぬひ筑紫の綿は身に付けていまだは着ねど暖けく見ゆ(万3-339) ③ -たわやめの 我が身にしあれば 道守が 問はむ答へを-(万4-546) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| み [実] | 〔名詞〕① 果実。実ったもの。② 内容。中身。 [実ならぬ木には神がつく] しかるべきときに結婚しない女性には神がとりつき、一生結婚できなくなる。 |
① 妹が家に咲きたる花の梅の花実にし成りなばかもかくもせむ(万3-402) ② 住吉の浜に寄るといふうつせ貝実なき言もち我れ恋ひめやも(万11-2807) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉葛実ならぬ木にはちはやぶる神ぞつくといふならぬ木ごとに(万2-101) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みあらか [御舎・御殿] | 〔名詞〕[「み」は接頭語] 宮殿。御殿(ごてん)。 | -真弓の岡に 宮柱 太敷きいまし みあらかを 高知りまして-(万2-167) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みえぬ [見えぬ] | 〔なりたち〕 [下二段動詞「見ゆ」の未然形「見え」+打消の助動詞「ず」の連体形「ぬ」] ① 見えない。思われない。② 見かけない。見ることができない。 |
② 我妹子をいざ見の山を高みかも大和の見えぬ国遠みかも(万1-44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みかさやま [三笠山] | 〔名詞〕 | 御笠山野辺行く道はこきだくも繁く荒れたるか久にあらなくに(万2-232) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1巻二-232」付録地名一覧】 奈良市街東方、春日大社後方の円錐形の山。標高二八三メートル。真西から望めば春日山と区別がつかないが、北の若草山山頂などから見れば三輪山に似た山容が望まれる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みかのはら [三香の原] | 〔地名〕 天平十二年(740) 久邇京遷都以前に既にあった元明・聖武の離宮。宮跡は不明。鹿背山丘陵の北端、京都府相楽郡法花寺野(ほっけじの) の当たりか、という。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みかど [御門] | 〔名詞〕「み」 は接頭語。 ① 貴人の家の門の敬称。ご門。② 皇居。朝廷。 ③ 「帝」 とも書く。天皇に対する尊称。④ 天皇の治める国。 |
② ひさかたの天見るごとく仰ぎ見し皇子の御門の荒れまく惜しも(万2-168) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みかは [三河・参河] | 〔国名〕 | 妹も我も一つなれかも三河なる二見の道ゆ別れかねつる(万3-278) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知県豊川市の国府町と御油町との境で、東海道の本堂と姫街道(浜名湖の今切の難所を避けて、県境の本坂峠を越えて浜名湖北岸を行く道) との分岐点。 一説に宝飯郡御津町にある東海道の分岐点ともいう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みがほし [見が欲し] | 〔形容詞シク活用〕【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 見たい。見たいと思う。 |
-二神の 貴き山の 並み立ちの 見が欲し山と 神代より-(万3-385) 神からか見が欲しからむみ吉野の滝の河内は見れど飽かぬかも(万6-915) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みかも [水鴨] | 〔名詞〕水に浮かぶ鴨。 | -はしきやし 妹がありせば 水鴨なす ふたり並び居 手折りても-(万3-469) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みかりたたせる [御狩立たせる] | 【有斐閣「萬葉集全注巻三-239 注『御狩立たせる』」】 原文「三猟立流」とあり、旧訓ミカリニタタル、紀州本ミカリニタテルとあるが、代匠記にミカリタタセルと訓んだ。 「御獦立師斯(ミカリタタシシ)」(1・四九)、「馬並而(ウマナメテ) 御獦曽立為(ミカリソタタス)」(6・九二六)の例がある。「立たせる」のセは尊敬、ルは完了の助動詞。「立つ」は「御狩りに立つ(出発する)」の意とされるが、「御獦そ立たす」の例からは「に」の省略とは考えられない。この「立つ」は注釈に、他動詞四段で「催す」の意(「上つ瀬に 鵜川を立ち」 1・三八)とするのが正しい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みくさ [水草] | 〔名詞〕水中または水辺に生える草。みずくさ。 | 秋の野のみ草刈り葺き宿れりし宇治の宮処の仮廬し思ほゆ(万1-7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みくさ [御軍・皇軍] | 〔名詞〕「み」 は接頭語。「みいくさ」の転。天皇の軍隊の尊称。 | 霰降り鹿島の神を祈りつつ皇御軍に我れは来にしを(万20-4394) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みけむかふ [御食向かふ] | 【枕詞】 食膳の食品が向かい合っている、その中に、 「粟(あは)・蜷(みな)・味鴨(あぢ)・葱(き)」などがあることから同音を持つ「淡路(あはぢ)・南淵(みなぶち)山・味原(あぢふ)の宮・城上(きのへ)の宮」 にかかる。 |
-御食向ふ 淡路の島に 直向ふ 敏馬の浦の 沖辺には 深海松採り(万6-951) 御食向ふ南淵山の巌には降りしはだれか消え残りたる(万9-1713) -見まく欲りする 御食向ふ 味経の宮は 見れど飽かぬかも(万6-1066) -遊びたまひし 御食向かふ 城上の宮を 常宮と 定めたまひて-(万2-196) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みこ [御子・皇子・親王] | 〔名詞〕[「み」は接頭語] ① 貴人の子供の敬称。お子様。② 天皇の子。または孫。 ③ 親王として認められた天皇の子または孫。親王宣下を受けた皇子。親王。 |
② -皇子ながら 任したまへば 大御身に 大刀取り佩かし-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みこころを [御心を] | 【枕詞】御心を「寄す」の意で、「吉」にかかる。 | -山川の 清き河内と 御心を 吉野の国の 花散らふ-(万1-36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みこし [神輿・御輿] | 〔名詞〕[「み」は接頭語] ① 「輿」の敬称。天皇や貴人の乗る輿。 ② 神が乗っている輿。神輿(しんよ)。おみこし。 |
-和束山 御輿立たして ひさかたの 天知らしぬれ 臥いまろび-(万3-478) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みこと [命・尊] | 〔名詞〕[「み」は接頭語] ① 神や人を敬っていうときに付ける語。 ②〔代名詞〕対称の人代名詞。あなた。おまえ。 |
① -八千矛の神のみこと-(記上) ① 日並の皇子の命の馬並めてみ狩り立たしし時は来向ふ(万1-49) ② -か寄りかく寄り 靡かひし 嬬の命の たたなづく 柔肌すらを-(万2-194) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みこと [御言] | 〔名詞〕[「み」は接頭語] 神や天皇、または貴人のおことば。仰せ。 |
み吉野の玉松が枝ははしきかも君が御言を持ちて通はく(万2-113) -太敷きいまし みあらかを 高知りまして 朝言に 御言問はさぬ-(万2-167) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みこも [水菰・水薦] | 〔名詞〕水中に生えるまこも。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みこもかる [水薦刈る] | 【枕詞】「信濃」に懸かる。 |
み薦刈る信濃の真弓我が引かば貴人さびていなと言はむかも(万2-96) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みさき [岬] | 〔名詞〕海や湖で突き出た形の陸地。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みさきみ [岬回] | 〔名詞〕[「回」は湾曲した所の意の接尾語] 岬の周辺。岬の周り。 |
み崎廻の荒磯に寄する五百重波立ちても居ても我が思へる君(万4-571) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みさく [見放く] | 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 ① 遠くを眺める。遠くを見遣る。 ② 会って心中の思いをはらす。 |
①-見つつ行かむを しばしばも 見放けむ山を 心なく-(万1-17) ②-心には 思ふものから 語り放け 見放くる人目 乏しみと-(万19-4178) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みさご [鶚・雎鳩] | 〔名詞〕鳥の名。猛禽類で、海辺にすみ、水中の魚をとる。 | みさご居る磯廻に生ふるなのりその名は告らしてよ親は知るとも(万3-365) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-362 注『みさご』」】 原文「美沙」 の「沙」 は「イサゴ」 であるから、ミイサゴでミサゴの表記したもの。ミサゴは倭名抄に「雎鳩、雕(わし)ノ属ナリ。 好ク江辺ノ山中ニ在リテ、マタ魚ヲ食フ者也」 とある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みじか [短] | 〔形容動詞ナリ〕短い事。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みじかうた [短歌] | 〔名詞〕短歌。和歌の一体。五・七・五・七・七の三十一音からなる。 ⇔ 長歌・長歌(ながうた・ちやうか)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みじかし [短し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① 空間的に、二点間の距離が短いさま。 ア・長さが少ない。 イ・たけが低い。 ② 時間の短いさま。 ア・時間が十分にない。わずかである。 イ・(愛情など) が長続きしない。 ③ (思慮・分別などが) 足りない。劣る。 ④ せっかちだ。短気だ。 ⑤ 位が低い。身分が低い。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みじかやか [短やか] | 〔形容動詞ナリ〕短いようす。 ⇒ 短(みじか)らか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みじかゆふ [短木綿] | 〔名詞〕たけの短い木綿。 | 三輪山の山辺真麻木綿短か木綿かくのみからに長くと思ひき(万2-157) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みじかよ [短夜] | 〔名詞〕夏の短い夜。 | 霍公鳥来鳴く五月の短夜もひとりし寝れば明かしかねつも(万10-1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みす [見す] | 〔他動詞サ行四段〕 [上一段動詞「見る」の未然形「み」に上代の尊敬の助動詞「す」の付いたもの] 「見る」の尊敬語。ご覧になる。 |
御諸が上に登り立ち我が見せば(紀・継体) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞サ行下二段〕【セ・セ・ス・スル・スレ・セヨ】 ① 見せる。見るようにさせる。② とつがせる。結婚させる。 ③ 占わせる。④ 経験させる。 |
① 我が欲りし野島は見せつ底深き阿胡根の浦の玉ぞ拾はぬ [或頭云 我が欲りし子島は見しを](万1-12) ① -手折りても 見せましものを うつせみの 借れる身なれば 露霜の-(万3-469) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みそか [密か] | 〔形容動詞ナリ〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 人目につかないようにひそかにするさま。こっそり。 |
【参考】 漢文訓読では、「ひそか」が用いられる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みそかごころ [密か心] | 〔名詞〕人に知られたくない思いを隠した心。ひそかに恋する心。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みそぎ [禊] | 〔名詞〕 身にけがれや罪がのあるとき、また、祭りなどの神事のある前、川や海の水で身を洗い清めること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みそぐ [禊ぐ] | 〔自動詞ガ行四段〕みそぎをする。 | - 出で立ちて みそぎてましを 高山の 巌の上に いませつるかも(万3-423) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みたみ [御民] | 〔名詞〕〔「み」は接頭語] (人民は天皇のものという考えから)天皇の民。 |
御民我れ生ける験あり天地の栄ゆる時にあへらく思へば(万6-1001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みだる [乱る] | 〔自動詞ラ行四段〕 乱れる。入り交じる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞ラ行四段〕 ① 乱す。心を乱れさせる。思い悩ませる。 ② 騒ぎを起こす。秩序を乱す。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 ① 入りまじる。ばらばらになる。 ② あれこれと思い悩む。平静さを失う。 ③ 礼儀が崩れる。だらしなくなる。うちとける。 ④ 騒ぎが起こる。混乱する。 |
① 引間野ににほふ榛原入り乱れ衣にほはせ旅のしるしに(万1-57) ①-川しさやけし 朝雲に 鶴は乱れ 夕霧に かはづは騒く-(万3-327) ① こもりくの泊瀬娘子が手に巻ける玉は乱れてありと言はずやも(万3-427) ② 別れてもまたも逢ふべく思ほえば心乱れて我れ恋ひめやも [一云 心尽して] (万9-1809) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みち [道・路] | 〔名詞〕[「み」は接頭語。「ち」は道の意。] 海・陸を問わず人の通るところを言うが、転じていろいろ抽象的な意にも用いられる。 ① 陸または海で、人または船の通るところ。道路。航路。 ② 途中。③ 旅・外出。④ 地方。国。⑤ 人の行うべき道徳。義理。 ⑥ 教え、特に仏教・儒教の教義。⑦ 道理をわきまえること。思慮分別。 ⑧ 方向。方面。⑨ やり方。手立て。手法。⑩ わけ。道理。条理。 ⑪ すじ。秩序。⑫ 学問・芸能・武術などの専門。 |
① 橘の蔭踏む道の八衢に物をぞ思ふ妹に逢はずして(万2-125) ① 楽浪の志賀津の児らが [罷り道の川瀬の道を見ればさぶしも(万2-218) ③ 人やりのみちならなくにおほかたは行きうしといひていあ帰りなむ (古今離別-388) ④ 高志 (こし) のみちにつかはし(記中) ⑧ 世間の遊びの道にたのしきは酔ひ泣きするにあるべくあるらし (万3-350) ⑪ 奥山のおどろがしたもふみ分けて道ある世ぞと人に知らせむ (新古今雑中-1633) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みちのく [陸奥] | 〔地名〕[「道(みち)の奥(おく) の転」] 陸奥(むつ)・陸中・陸前・岩代(いわしろ)・磐城(いわき) の五か国をさす。 今の青森・岩手・宮城・福島の四県にあたる。 出羽を加え東北地方全体をさすこともある。「みちのくに」とも。 |
陸奥の真野の草原遠けども面影にして見ゆといふものを(万3-399) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-396 注『陸奥』」】 東北地方をいう。和名抄に「三知乃於久(ミチノオク)」 とあるが、上代では縮めてミチノクと言っていた。「美知能久(ミチノク)」(14・三四二七)、「美知乃久(ミチノク)」(14・三四三七) の仮名書きがある。「道の奥」 の意であるが、東山道の道の奥ということで命名されたもの。したがって、いわゆる「陸奥(むつ)国」 だけではなく、磐城・岩代・陸前・陸中を含めた奥州全体の称である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みちもり [道守] | 〔名詞〕道路や駅路を守る人。 | -我が身にしあれば 道守が 問はむ答へを 言ひ遣らむ-(万4-546) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みちゆき [道行き] | 〔名詞〕 ① 道を行くこと。旅行。道中。 ② 文体の一種。戦記物・謡曲・浄瑠璃などで、旅して行く道の叙景と叙情を記した韻文体の文章。縁語・序詞・掛詞などの技巧をこらした文章で、通常七五調をとる。道行き文。 ③ 歌舞伎・浄瑠璃などで、男女が連れ立って旅をしたり心中・駆け落ちをするさまを演じる所作。転じて、駆け落ちすること。または情死の場へ行くこと。 |
①-かへり見しつつ 玉桙の 道行き暮らし あをによし 奈良の都の-(万1-79) ① 若ければ道行き知らじ賄はせむ黄泉の使負ひて通らせ(万5-910) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みちゆきびと [道行き人] | 〔名詞〕通行人。旅人。 | -声も聞こえず 玉桙の 道行き人も ひとりだに 似てし行かねば-(万2-207) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みつ [満つ・充つ] | 〔自動詞タ行四段〕 ① いっぱいになる。 ②(願いや思いが)かなう。 ③(世の中に)広がる。知れ渡る。 ④ 満潮になる。また、満月になる。 |
① -四方の国には 人さはに 満ちてはあれど 鶏が鳴く 東男は-(万20-4355) ④ 夕さらば潮満ち来なむ住吉の浅香の浦に玉藻刈りてな(万2-121) ④ -夕されば 潮を満たしめ 明けされば 潮を干れしむ 潮さゐの-(万3-391) ④ 玉敷ける清き渚を潮満てば飽かず我れ行く帰るさに見む(万15-3728) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞タ行下二段〕【テ・テ・ツ・ツル・ツレ・テヨ】 ① 満たす。いっぱいにする。 ② 十分にする。かなえる。 【参考】 「自動詞四段」は、中古以降「上二段」にも活用する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みつ [御津・三津] | 〔名詞〕 難波(今の大阪市付近)の港。難波の津。大伴の御津などといわれた。 西海航路の基点で遣唐使などの発着した港。 特に尊んで「御津(みつ)」という。 |
いざ子ども早く日本へ大伴の御津の浜松待ち恋ひぬらむ(万1-63) 大伴の御津の浜なる忘れ貝家なる妹を忘れて思へや(万1-68) 潮干の三津の海女のくぐつ持ち玉藻刈るらむいざ行きて見む(万3-296) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みづ [水] | 〔名詞〕飲み水や、川・海・湖・池などの水。 | -鴨じもの 水に浮き居て 我が作る 日の御門に 知らぬ国 -(万1-50) 水(みな)伝ふ礒の浦廻の岩つつじ茂く咲く道をまたも見むかも(万2-185) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みつあひ [三つ合ひ] | 〔名詞〕三本の紐や糸を、撚り合せること。 | 我が持てる三つ合ひに搓れる糸もちて付けてましもの今そ悔しき(万4-519) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻四-516 注『三つ合ひに撚れる糸』」】 三本の糸を撚り合せた丈夫な糸。正倉院の衣服の縫糸は二本を撚り合せたいわゆる双子糸が普通、絹または麻の糸が用いられているという。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みづがき [瑞垣・瑞籬] | 〔名詞〕神社・皇居などの周囲にめぐらした垣根。=斎垣(いがき)・神垣。玉垣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みづがきの [瑞垣の・瑞籬の] | 【枕詞】 「瑞垣」に守り囲まれた神の意から「神」に、 「瑞垣」は朽ちることなく久しい時を経ているというところから「久し」にかかる。 |
娘子らが袖布留山の瑞垣の久しき時ゆ思ひき我は(万4-504) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みつき [貢・調] | 〔名詞〕[「み」は接頭語。のちに「みつぎ」] ①「租・庸・調」などの租税の総称。また献上物。 ②「服従」の印に地主神や一般民衆が天皇に献ずる物品 |
①-聞こし食す 四方の国より 奉る 御調の船は 堀江より-(万20-4384) ②-たたなはる 青垣山 山神の 奉る御調と 春へは 花かざし持ち-(万1-38) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みづしま [水島] | 〔地名〕 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1付録『地名一覧』」】 熊本県八代市植柳の西南部、球磨川の分流の一つである南川の河口にある周囲四〇メートル前後の岩山からなる小島。 今も島の南側からわずかながら水が湧き出ている。 「景行紀」に、天皇が葦北の小島で食事をとろうとして冷水を求めた際、神に祈ったところ崖の傍より寒泉が湧き出た、よって水島と称する、という伝説を載せる。 一説にこの水島の対岸の、今は陸地になっている大鼠蔵(おおそうぞう)島に擬するものもある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みつのさき [三津の埼] | 〔地名〕 | 三津の崎波を恐み隠り江の舟公宣奴嶋尓(万3-250) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1付録『地名一覧』」】 幾つかあったと思われる「難波の御津」のうちの、どれかの周辺にあった岬角か。 ミツは公的性格を持つ湊。「三津」と書かれることが多いが、「御津」が原義に近ろう。 四面を山に囲まれた大和国は外港を持たず、摂津国難波の地をもって国際・国内両便の発着所とした。 ただし、万葉時代でも地形の変動・交通の便などの理由で、南は現在の大阪市住吉区、北は中央区辺りまで転々としたことが想像される。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みつのはまべ [三津の浜辺] | 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 付録『地名一覧』」】 「難波の御津」の浜辺。万葉集にはその白砂青松の景を歌ったものがある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みづほのくに [瑞穂の国] | 〔みずみずしい稲穂の実る国の意〕日本の美称。 | -常闇に 覆ひ賜ひて 定めてし 瑞穂の国を 神ながら 太敷きまして-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みつみつし | 【枕詞】「久米(くめ=氏族ノ名)」 にかかる。 | みつみつし久米の若子がい触れけむ礒の草根の枯れまく惜しも(万3-438) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-435 注『みつみつし』」】 「稜威々々(ミツミツ)し」 の意か。イツ(勢いが激しいこと) に神秘的な意のミ(のちに敬語のミとなる) がついて「ミツ」 となったものであろう。 「イカ(厳)」-「ミカ」、「イマシ(汝)」-「ミマシ」 の類と思われる。 「美都美都斯(ミツミツシ) 久米の子」(記・10など) の如く、久米(くめ、平時は農耕、戦争には兵として従軍した勇武な氏族名) にかかる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みづやま [瑞山] | 〔名詞〕 若葉の瑞々しく生い茂った美しい山。神聖な山。 「瑞」は清らかで生き生きした様をいう形状言。 「瑞垣「瑞歯」「瑞穂」「瑞枝」など。 |
-畝傍の この瑞山は 日の緯の 大御門に 瑞山と 山さびいます-(万1-52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みと [水門] | 〔名詞〕川や海などの水の出入口。河口。海峡。 | 稲日野も行き過ぎかてに思へれば心恋しき加古の島見ゆ [一云 水門見ゆ](万3-254) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みとらし [御執らし] | 〔名詞〕「みたらし」とも。 「み」は「接頭語」、「とらし」は四段動詞「とる」の尊敬語「とらす」の連用形から。 手にお取りになるもの。転じて、貴人の弓の敬称。 |
-夕には い寄り立たしし み執らしの 梓の弓の-(万1-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みどりこ [嬰子] | 〔名詞〕[後世「みどりご」とも] 三歳くらいまでの子供。幼子。乳児。 |
-我妹子が 形見に置ける みどり子の 乞ひ泣くごとに 取り与ふる-(万2-210) -我妹子が 形見に置ける みどり子の 乞ひ泣くごとに 取り与ふ-(万2-213) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みな [皆] | 〔名詞〕 すべての事やもの。すべて。すべての物。残らず。 〔副詞〕 すべて。ことごとく。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みなか [み中] | 〔名詞〕[「み」は「接頭語] まんなか。 | なまよみの 甲斐の国 うち寄する 駿河の国と こちごちの 国のみ中ゆ-(万3-322) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みなそそく [水注く] | 【枕詞】「な」は「の」の意の上代の格助詞。 「臣(おみ)」「鮪(しび)」にかかる。 |
みなそそく臣のをとめ(記下) みなそそく鮪(=人名)の若子(わくご)を(武烈紀) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (みなそそく) [水激く] | 水が激しくぶつかり流れる意。 | -この山の いや高知らす 水激く 瀧の宮処は 見れど飽かぬかも(万1-36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みなづき [水無月・六月] | 〔名詞〕陰暦六月の異称。 | 富士の嶺に降り置く雪は六月の十五日に消ぬればその夜降りけり(万3-323) 六月の地さへ裂けて照る日にも我が袖干めや君に逢はずして(万10-1999) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みなと [水門・湊] | 〔名詞〕[「水(み)の門(と)」(=出入口)の意] 「な」は「の」の意の上代の格助詞 ① 河口など、川や海などの水の出入口。転じて、船の停泊するところ。 ② 行きつくところ。 |
磯の崎漕ぎ廻み行けば近江の海八十の港に鶴さはに鳴く(万3-275) 港の葦の末葉を誰れか手折りし我が背子が振る手を見むと我れぞ手折りし(万7-1292) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みなひと [皆人] 参考: ひとみな( 人皆) |
〔名詞〕すべての人。 | 我れはもや安見児得たり皆人の得かてにすといふ安見児得たり (万2-95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 意味の似た語に「人皆 (ひとみな)」がある。「人皆」は「世間の人は皆」の意を表し、「皆人」は、「その場の人は皆」の意で、両者を区別する説もあるが、それに合わない例も見られる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みにくし [見悪し・醜い] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 (様子が)見苦しい。みっともない。顔かたちがよくない。 |
あなみにく賢しらをすと酒飲まぬ人をよく見ば猿にかも似る(万3-347) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みにくやか [醜やか] | 〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 [形容詞「みにくし」の語幹に接尾語「やか」の付いたもの] いかにも醜く感じられるさま。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みぬめ [敏馬] | 〔地名〕 | 玉藻刈る敏馬を過ぎて夏草の野島の崎に船近づきぬ(万3-251) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1付録『地名一覧』】 神戸市灘区岩屋町付近。神戸港の東方に当たる。阪神電鉄岩屋駅の東南、阪神高速道路に面した所に敏馬神社がある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みね [峰・峯・嶺] | 〔名詞〕 ① 〔「み」 は接頭語〕山の頂。② 物の高くなったところ。 ③ 刀の背。=刀背(むね)。④ 烏帽子の頂。 |
① 青山の嶺の白雲朝に日に常に見れどもめづらし我が君(万3-380) ① 奈良山の嶺の黄葉取れば散る時雨の雨し間なく降るらし(万8-1589) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みふねのやま [三船の山] | 〔名詞〕 | 滝の上の三船の山に居る雲の常にあらむと我が思はなくに(万3-243) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集1 萬葉集地名一覧『三船の山』」】 奈良県吉野郡吉野町宮瀧の柴橋の上流右手に見える山。舟岡山とも呼ばれる。標高四八七メートル。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みほ [美保] | 〔地名〕所在未詳。 「三穂の岩屋」と同じ「みほ」か。 |
風早の美穂の浦廻の白つつじ見れどもさぶしなき人思へば [或云 見れば悲しもなき人思ふに](万3-437) 風早の三穂の浦廻を漕ぐ舟の舟人騒く波立つらしも(万7-1232) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みほのいはや [三穂の岩屋] | はだすすき久米の若子がいましける [一云 けむ]三穂の岩屋は見れど飽かぬかも [一云 荒れにけるかも](万3-310) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1付録『地名一覧』】 アメリカ村の名で知られる和歌山県日高郡美浜町の最西端、日ノ御崎の東、三尾漁港から更に東側の突角の後磯(うしろいそ)にある。 久米の穴と称する大きな岩窟がそれかという。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みほのうら [三保の浦] | 〔地名〕三保の岬で囲まれた静岡県清水市の入海。 | 廬原の清見の崎の三保の浦のゆたけき見つつ物思ひもなし(万3-299) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻三-296 頭注『清見の埼の三保の浦』」】 清見埼から三保の岬で最も近い先端の真崎まで三キロメートル。 清水の入海を隔てた二つの地名をノでつなぐことは表現として無理だが、清見埼から三保の浦を見つつというべきところを圧縮していったのであろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みまく [見まく] | [上一段動詞「見る」の、未然形「み」+推量の助動詞「む」のク語法「まく」] 見ること。見るであろうこと。 |
難波潟潮干なありそね沈みにし妹が姿を見まく苦しも(万2-229) 朝に日に見まく欲りするその玉をいかにせばかも手ゆ離れずあらむ(万3-406) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みまくほし [見まく欲し] | 〔動詞「見る」の未然形+意志の助動詞「む」のク語法「まく」+形容詞「ほし」〕 見たい。会いたい。 |
老いぬればさらぬ別れもありといへば いよいよ見まくほしき君かな(古今雑上-900) あしひきの山に生ひたる菅の根のねもころ見まく欲しき君かも(万4-583) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みまくほる [見まく欲る] | 見たいと思う。会いたいと思う。 | 見まく欲り我がする君もあらなくに何しか来けむ馬疲るるに(万2-164) 恋ひ死なむ時は何せむ生ける日のためこそ妹を見まく欲りすれ(万4-563) 見まく欲り恋ひつつ待ちし秋萩は花のみ咲きてならずかもあらむ(万7-1368) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みみ [耳] | 〔名詞〕 ① 聴覚の器官。耳。② 聞くこと。聞こえること。③ うわさ。評判。 ④ (耳に穴があることから) 針の穴。 |
① -鳴く鳥の 声も変らふ 耳に聞き 目に見るごとに うち嘆き-(万19-4190) ② 言に言へば耳にたやすし少なくも心のうちに我が思はなくに(万11-2586) ③ 我が聞きし耳によく似る葦の末の足ひく我が背つとめ給ぶべし(万2-128) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みみがのみね・みみがのやま [耳我の嶺・耳我の山] |
み吉野の耳我の嶺に 時なくぞ 雪は降りける 間無くぞ 雨は振りける(万1-25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注」第一-25番】注釈 吉野山中の一峰であろうが、どの山か未詳。金峰山 (きんぷせん) をあてたり、多武峯 (とおのみね) と吉野の境、今の細峠・龍在峠一帯をあてたりする説がある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みみなしやま [耳成山] | 〔地名〕[「耳梨山」とも書く] 今の奈良県橿原市にある山。 【歌枕】香具山・畝傍山とともに大和三山と言われている。 |
→大和三山 (香具山) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みもろ [御室・御諸・三諸] | 〔名詞〕[「み」は接頭語]「みむろ」とも 神の降臨して鎮座する所。神をまつる森や山や神座。後には、神社。 |
みもろの 神名備山に 五百枝さし しじに生ひたる つがの木の-(万3-327) -みもろを立てて 枕辺に 斎瓮を据ゑ 竹玉を 間なく貫き垂れ-(万3-423) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みもろのやま (みむろのやま) [御室山・三室山] |
〔地名〕[歌枕] ① 奈良県桜井市三輪にある三輪山。 ② 奈良県生駒郡斑鳩町にある神奈備山 (かんなびやま) 。 紅葉・時雨の名所。 【参考】御室山は「神のいます山」の意で、各地にある。 |
① 玉櫛笥みもろの山のさな葛さ寝ずはつひに有りかつましじ [玉くしげ三室戸山の](万2-94) ① みもろの神の神杉已具耳矣自得見監乍共寝ねぬ夜ぞ多き (万-156) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みや [宮] | 〔名詞〕[「御屋(みや)」の意] ① 伊勢神宮をはじめとする神社。 ② 皇居。御所。 |
② -石走る 近江の国の 楽浪の 大津の宮に -(万1-29) ② 大君は神にしませば雲隠る雷山に宮敷きいます(万3-236) ② うちひさす宮に行く子をまかなしみ留むれば苦し遣ればすべなし(万4-535) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みやこ [都・京] | 〔名詞〕[「宮処(みやこ)」の意] 皇居のある所。京。転じて首府。 |
昔こそ難波田舎と言はれけめ今は都引き都びにけり(万3-315) 沫雪のほどろほどろに降りしけば奈良の都し思ほゆるかも(万8-1643) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】「都引き」 「萬葉集全注巻三-312 注『都引き』 「都引き」とは都を引き移すことで、平城京の規模をまねて、建物などを少し移改築したりして、副都としての形を整えることをいうのであろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みやこぶ [都ぶ] | 〔自動詞バ行上二段〕【ビ・ビ・ブ・ブル・ブレ・ビヨ】 [「ぶ」は接尾語] 都らしくなる。都のふうをする。 |
昔こそ難波田舎と言はれけめ今は都引き都びにけり(万3-315) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みやぢ [宮路・宮道] | 〔名詞〕① 宮殿に通う道。② 神社に参拝する道。 | ① 畑子らが夜昼といはず行く道を我れはことごと宮道にぞする(万2-193) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みやで [宮出] | 〔名詞〕宮中を出ること。また、宮中に出仕すること。 | 夢にだに見ざりしものをおほほしく宮出もするかさ桧の隈廻を(万2-175) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みやばしら [宮柱] | 〔名詞〕皇居の柱。神社や宮殿の柱。 | -御心を 吉野の国の 花散らふ 秋津の野辺に 宮柱 太敷きませば-(万1-36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みやび [雅び] | 〔名詞〕[上ニ段動詞「雅 (みや) ぶ」の連用形から] 宮廷風であること。上品で優雅なこと。風雅。風流。 |
あしひきの山にしをれば風流なみ我がするわざをとがめたまふな(万4-724) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【文学理念】 「みやび」は、「をかし」「なまめかし」「あて」「らうたし」などとともに、平安時代の美的理念を表すことばであるが、「をかし」が一般的な美、「なまめかし」が優しく、しかも清新な、時には、官能的な美、「らうたし」が愛の上の美を表現するのに対し、「みやび」は「あて」と同じく、貴族的な美を表現している。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みやびを [雅男] | 〔名詞〕風流を解する男。 | 風流士と我れは聞けるをやど貸さず我れを帰せりおその風流士(万2-126) 風流士に我れはありけりやど貸さず帰しし我れぞ風流士にはある(万2-127) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みやま ① み山 ② 深山 ③ 御山 |
〔名詞〕 ① [「みは接頭語」] 山の美称。 ② 「深山」奥深い山。奥山。 ③ 「御山」 [「みは接頭語」] 天皇の墓。御陵。みささぎ。また、一般の墓の敬称。お墓。 |
① 笹の葉はみ山もさやにさやげども我れは妹思ふ別れ来ぬれば (万2-133) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みゆ [み湯・御湯] | 〔名詞〕[「み」は接頭語]温泉の美称。いでゆ。 |
- 岡に立たして 歌思ひ 辞思ほしし み湯の上の 木群を見れば-(万3-325) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みゆ [見ゆ] | 〔自動詞ヤ行下二段〕【エ・エ・ユ・ユル・ユレ・エヨ】 ① 目に映る。見える。② 会う。対面する。③ 来る。やって来る。 ④(人に)見られる。⑤ 人に見せる。⑥(女が)結婚する。妻となる。 ⑦ 思われる。感じられる。⑧ 見かける。見ることが出来る。 |
① 我妹子をいざ見の山を高みかも大和の見えぬ国遠みかも(万1-44) ① 矢釣山木立も見えず降りまがふ[雪に騒ける朝楽しも](万3-264)下二句未定訓 ① -振り放け見れば 渡る日の 影も隠らひ 照る月の 光も見えず -(万3-320) ① 稲日野も行き過ぎかてに思へれば心恋しき加古の島見ゆ [一云 水門見ゆ](万3-254) ① 天離る鄙の長道ゆ恋ひ来れば明石の門より大和島見ゆ [一本云 家のあたり見ゆ](万3-256) ④ もの思ふと人に見えじとなまじひに常に思へりありぞかねつる(万4-616) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現代語の「見える」にあたるが、受身・可能・自発の意を表す上代の助動詞「ゆ」の受身にあたるのが、「④」。 受身の表現を使役の表現に変えると「⑤」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みゆき [御幸・行幸] | 〔名詞〕[「御行(みゆ)き」の意] 天皇のお出まし。古くは、上皇、法皇、女院などの場合にも用いた。 天皇には「行幸」、それ以外には「御幸」の漢字を当てた。 → 御幸(ごかう)、行幸(ぎゃうがう) |
梓弓爪引く夜音の遠音にも君の御幸を聞かくし良しも(万4-534) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みゆき [御雪] | 〔名詞〕[「み」は接頭語] 雪の美称。 | -夕去り来れば み雪降る 安騎の大野に 旗すすき 小竹を押しなべ-(万1-45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みゆき [深雪] | 〔名詞〕深く降り積もった雪。[冬] | 降り積みし高嶺の深雪とけにけり清滝川の水の白波(新古春上-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みよ [御代・御世] | 〔名詞〕[「み」は接頭語] 天皇の治世の敬称。御治世。 | 玉たすき 畝傍の山の 橿原の ひじりの御代ゆ-(万1-29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みよしの [み吉野] | 〔地名〕[歌枕](「み芳野」とも書く。) 「み」は接頭語。吉野 (今の奈良県吉野郡) 地方の美称。 |
み吉野の 耳我の嶺に 時なくぞ 雪は降りける 間無くぞ 雨は振りける(万1-25) み吉野の高城の山に白雲は行きはばかりてたなびけり見ゆ(万3-356) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みる [廻る・回る] | 〔自動詞マ行上一段〕【ミ・ミ・ミル・ミル・ミレ・ミヨ】 「まわる・まわりめぐる」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みる [見る] | 〔他動詞マ行上一段〕【ミ・ミ・ミル・ミル・ミレ・ミヨ】 ① 目にとめる。目にする。眺める。 ② 見て判断する。理解する。③ 処理する。取り扱う。 ④ 試みる。ためす。⑤ 経験する。事件などに遭遇する。 ⑥ 会う。顔を合わせる。⑦ 異性と関係を持つ。夫婦になる。妻とする。 ⑧ 世話をする。面倒をみる。 |
① 妹が家も継ぎて見ましを大和なる大島の嶺に家もあらましを [一云 妹があたり継ぎても見むに] [一云 家居らましを] (万2-91) ① あかねさす紫野行き標野行き野守は見ずや君が袖振る(万1-20) ① 隼人の薩摩の瀬戸を雲居なす遠くも我は今日見つるかも(万3-249) ③ -山を茂み 入りても取らず 草深み 取りても見ず 秋山の-(万1-16) ⑥ たけばぬれたかねば長き妹が髪このころ見ぬに掻き入れつらむか [三方沙弥](万2-123) ⑥ 明日香川明日だに [さへ] 見むと思へやも [思へかも] 我が大君の御名忘れせぬ [御名忘らえぬ](万2-198) ⑥ 老いぬればさらぬ別れもありといへばいよいよみまくほしき君かな (古今雑上-900) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みわ [神酒] | 〔名詞〕神に供える酒。おみき。 |
哭沢の神社に三輪据ゑ祈れども我が大君は高日知らしぬ(万2-202) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みわたす [見渡す] | 〔他動詞サ行四段〕 遠く広く見やる。はるか遠くまで眺める。 |
住吉の得名津に立ちて見渡せば武庫の泊まりゆ出づる船人(万3-286) 見渡せば明石の浦に燭す火のほにそ出でぬる妹に恋ふらく(万3-329) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みわのさきさの [三輪の埼狭野] | 〔地名〕 |
苦しくも降り来る雨か三輪の崎狭野の渡りに家もあらなくに(万3-267) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 『付録 地名一覧』」】 和歌山県新宮市三輪埼町・佐野町。JR紀勢本線新宮駅から勝浦寄りに、三輪崎、紀伊佐野と、約二キロメートルを隔てて駅が並んでいる。 佐野はもと東牟婁郡三輪崎村の中に含まれていた。したがって三輪崎・狭野と並列したのではなく、大地名の下に小地名を続けたものと思われる。 【有斐閣「万葉集全注巻三-265」 注『三輪の埼』】 原文「神之埼」とある。「神」をミワと訓むのは、大和の大神(おおみわ)神社の「神(みわ)」に基づく。三輪の埼は新宮市三輪崎町及び佐野町一帯。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みわ(の)やま [三輪山] | 〔地名〕「三和山」ともかく。 | 三輪山をしかも隠すか雲だにも心あらなも隠さふべしや(万1-18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今の奈良県桜井市三輪の東部にある山。ふもとにこの山を神体とする大神(おおみわ)神社がある。「三諸の神奈備」と称され崇められてきた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| む 「主要助動詞表」 | 〔助動詞特殊型〕【○・○・ム(ン)・ム(ン)メ・○】 ① 推量を表わす。~だろう。~でしょう。 ② 意志を表わす。~う。~よう。 ③ 連体形を用いて仮定を表わす。~したとして~が。 ④ 已然形「め」が疑問の助詞「や」「が」を伴って反語の意を表わす 〔語法〕 「む」は、「ン」と発音されるようになり、それに伴って「ん」と表記されるようになった。 上代には未然形に「ま」という形があったと考えられるが、これは「降らまく」などの形でしか現れない。 〔接続〕活用語の未然形に付く |
① わがやどの池の藤なみさきにけり山郭公いつかきなかむ(古今夏-135) ① 大船の津守が占に告らむとはまさしに知りて我がふたり寝し(万2-109) ① 我が御門千代とことばに栄えむと思ひてありし我れし悲しも(万2-183) ① けころもを時かたまけて出でましし宇陀の大野は思ほえむかも(万2-191) ② 見れど飽かぬ吉野の川の常滑の絶ゆることなくまたかへり見む(万1-37) ②-作れる家に 千代までに いませ大君よ 我れも通はむ(万1-79) ② 後れ居て恋ひつつあらずは追ひ及かむ道の隈廻に標結へ我が背 (万2-115) ② 山吹の立ちよそひたる山清水汲みに行かめど道の知らなく (万2-158) ② 天地とともに終へむと思ひつつ仕へまつりし心違ひぬ(万2-176) ② 芦北の野坂の浦ゆ船出して水島に行かむ波立つなゆめ(万3-247) ② 人見ずは我が袖もちて隠さむを焼けつつかあるらむ着ずて来にけり(万3-271) ④ 玉葛花のみ咲きてならざるは誰が恋ならめ我は恋ひ思ふを (万2-102)(反語) ④ にほどりの葛飾早稲をにへすともその愛しきを外に立てめやも (万14-3404) -大空の月を見るがごとくにいにしへを仰ぎて今を恋ひざらめかも- (古今仮名序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むかし [昔] | 〔名詞〕 ① 過ぎ去った時。ずっと以前。 ②(「ひと昔」の形で)過去の二十一年。 三十三年。また十年を一期としていう語。 |
楽浪の志賀の [一云 比良の] 大わだ淀むとも昔の人にまたも逢はめやも [一云 逢はむと思へや](万1-31) 我が命も常にあらぬか昔見し象の小川を行きて見むため(万3-335) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むかしのひと [昔の人] | ① 昔の時代に生きた人。古人。 ② 亡くなった人。故人。③ 昔なじみの人。 |
① 岩屋戸に立てる松の木汝を見れば昔の人を相見るごとし(万3-312) ③ さつきまつ花たちばなの香をかげば 昔の人の袖の香ぞする(古今夏-139) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むかふ [迎ふ] | 〔他動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 ① したくして相手を待つ。②受止める、受け入れる。③出迎える。招く。 |
① 去年の春逢へりし君に恋ひにてし桜の花は迎へけらしも(万8-1434) ③ 君が行き日長くなりぬ山尋ね迎へか行かむ待ちにか待たむ(万2-85) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むかふ [向ふ・対ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 ① 向き合う、対座する。② 赴く、出かけて行く。③ 近づく、傾く。 ④ 当る、相当する。匹敵する。⑤ さからう、敵対する |
④ 直に逢ひて見てばのみこそたまきはる命に向ふ我が恋やまめ(万4-681) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むかぶす [向か伏す] | 〔自動詞サ行四段〕 はるか向こうの方に横たわる。また、伏しているように見える。 |
天雲の 向伏す国の もののふと 言はるる人は 天皇の 神の御門に-(万3-446) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むかへ [迎へ] | 〔名詞〕人を迎えること | 君が行き日長くなりぬ山たづの迎へを行かむ待つには待たじ(万2-90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むく [向く] | 〔自動詞カ行四段〕 ① その方向に向う。対する。 ② そのほうに進む。傾く。③ 適する。相応しい。 |
① 家に来て我が屋を見れば玉床の外に向きけり妹が木枕(万2-216) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 ① 向くようにする。向ける。 ②(神仏に)供え物をする。たむける。 ③ 服従させる。従わせる。 |
② 在り嶺よし対馬の渡り海中に幣取り向けて早帰り来ね(万1-62) ③-韓国を向け平らげて 御心を 鎮めたまふと -(万5-817) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むこのうみ [武庫の海] | 〔地名〕尼崎市から西宮市にかけての海岸を広くいう。 | 武庫の海船底ならしいざりする海人の釣船波の上ゆ見ゆ(万3-258) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むこのうら [武庫の浦] | 〔地名〕兵庫県西宮市と尼崎市の境を流れる武庫川河口付近の海の古称。〔歌枕〕 | 武庫の浦を漕ぎ廻る小舟粟島をそがひに見つつともしき小舟(万3-361) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むこのとまり [武庫の泊] | 住吉の得名津に立ちて見渡せば武庫の泊まりゆ出づる船人(万3-286) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 『付録 地名一覧』」】 武庫川の河口の船着き場。武庫川は現在は兵庫県尼崎市と西宮市の間を流れているが、当時はさらに東にかけて三角州を形成しつつ海に注いでいたという。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むささび [鼯鼠] | 〔名詞〕 動物の名。リスに似た姿で、木から木へ飛び移る。 四肢の間に被膜があり、四肢をひろげて樹間を滑空する。 |
むささびは木末求むとあしひきの山の猟夫にあひにけるかも(万3-269) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むし [虫] | 〔名詞〕 ① むし。主に昆虫類をいう。 ② 特に、秋鳴く虫の総称。まつむし・すずむしなど。 ③ 人の体内にいるという虫。 種々の病気を起こしたり、感情を高ぶらせたりするもとになるもの。 |
① この世にし楽しくあらば来む世には虫に鳥にも我はなりなむ(万3-351) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むしぶすま [苧衾] | 〔名詞〕「苧(からむし)」の繊維で織った夜具。 | 蒸し衾なごやが下に臥せれども妹とし寝ねば肌し寒しも(万4-527) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むす [生す・産す] | 〔自動詞サ行四段〕はえる。生じる。 | 川の上のゆつ岩群に草生さず常にもがもな常処女にて(万1-22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むす [噎す・咽す] | 〔自動詞サ行下二段〕【セ・セ・ス・スル・スレ・セヨ】 ①(物や煙等が喉につまって)むせる。 ② 悲しみで胸が一杯になる。 |
② 我妹子が植ゑし梅の木見るごとに心咽せつつ涙し流る(万3-456) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むすびまつ [結び松] | 〔名詞〕 誓いや願をかけたしるしに、松の小枝を結び合わせておくこと。 また、その松。 |
磐代の野中に立てる結び松心も解けずいにしへ思ほゆ(万2-144) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むすぶ [結ぶ] | 〔自動詞バ行四段〕固まる。まとまる。ある形になる。 〔他動詞バ行四段〕 ① 端と端をつなぎ合わせる。結ぶ。また、結び目をつくる。 ② 編んで作る。組んで作る。 ③ 生じさせる。かたちづくる。 ④ 約束する。言いかわす。 |
① 磐代の岸の松が枝結びけむ人は帰りてまた見けむかも(万2-143) ① 淡路の野島の崎の浜風に妹が結びし紐吹き返す(万3-252) ④ -新世に ともにあらむと 玉の緒の 絶えじい妹と 結びてし-(万3-484) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むた [共] | 〔名詞〕(助詞「の」「が」の下について) ~とともに。 | -風こそ寄せめ 夕羽振る 波こそ来寄れ 波のむた-(万2-131) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むだく [抱く] | 〔他動詞カ行四段〕だく。 | -男じもの 負ひみ抱きみ 朝鳥の 音のみ泣きつつ 恋ふれども-(万3-484) 上つ毛野安蘇のま麻むらかき抱き寝れど飽かぬをあどか我がせむ(万14-3422) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むつまし [睦まし] | 〔形容詞シク活用〕[動詞「睦(むつ)む」に対応する形容詞。近世以後「むつまじ」] 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 ① 親しい。親密である。仲が良い。② 慕わしい。なつかしい。 |
② -もみち葉の 散り飛ぶ見つつ むつましみ 我は思はず 草枕-(万4-546) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むなし [空し] | 〔形容詞シク活用〕 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 ① 実質がない。中になにもない。からである。 ② からだだけで中の魂がない。死んでいる。命がない。 ③ 事実無根である。事実がない。 ④ 無益である。あてどがない。かいがない。むだである。 ⑤ 無常である。はかない。 |
① 人もなき空しき家は草枕旅にまさりて苦しかりけり(万3-454) ④ 士やも空しくあるべき万代に語り継ぐべき名は立てずして(万6-983) ⑤ 世の中は空しきものとあらむとそこの照る月は満ち欠けしける(万3-445) ⑤ 世間は空しきものと知る時しいよよますます悲しかりけり(万5-796) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むね [胸] | 〔名詞〕 ① 胸部。② 胸の病気。③ 衣服の胸の部分。④ 心。思い。⑤ 短歌の第二句。 |
④ -入日なす 隠りにしかば そこ思ふに 胸こそ痛き 言ひも得ず-(万3-469) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むらさき [紫] | 〔名詞〕 ① 草の名。もと武蔵野に多く自生し、根は赤紫色の染料とした。紫草。 ② 染め色の名。「①」の根で染めた赤紫色。 |
① むらさきのひともとゆゑに武蔵野の草はみながらあはれとぞ見る (古今雑上-868) ② 韓人の衣染むといふ紫の心に染みて思ほゆるかも(万4-572) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考「色の代表『紫』」】 平安時代には、紫は色彩の中の代表であった。単に「濃き」「薄き」と言った場合でも、それは「紫」をさした。 また「色ゆるさる」「ゆるし色」ということばがあったように、一般の人が着ることを許されない高貴な色であった。 この紫を生かしたのが、「源氏物語」である。桐壺の更衣(桐の花は紫)、藤壺、さらにその「紫のゆかり」としての紫の上と、紫は理想の象徴として物語り全体をおおっている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むらきもの [群肝の・村肝の] | 〔枕詞〕「むらぎもの」とも。 臓器に、心が宿っていると考えたことから、「心」にかかる。 |
むらきもの心砕けてかくばかり我が恋ふらくを知らずかあるらむ(万4-723) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むらさきの [紫野] | 〔名詞〕紫草を栽培する御料地。 〔地名〕今の京都市北区紫野。大徳寺付近一帯の野原。朝廷の狩猟地。 |
あかねさす紫野行き標野行き野守は見ずや君が袖振る(万1-20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むらやま [群山] | 〔名詞〕群がって連なり続いている山。多くの山々。 | 大和には 群山あれど とりよろふ 天の香具山 登り立ち 国見をすれば-(万1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むる [群る] | 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 一か所に多くのものが集まる。群がる。 |
-鴨つま呼ばひ 辺つへに あぢ群騒き ももしきの 大宮人の 罷り出て-(万3-259) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むれゐる [群れ居る] | 〔自動詞ワ行上一段〕【イ・イ・イル・イル・イレ・イヨ】 群がってすわる。 |
朝日照る佐田の岡辺に群れ居つつ我が泣く涙やむ時もなし(万2-177) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むろのき [室の木・杜松] | 〔名詞〕杜松(ねず=木ノ名) の古名。 | 我妹子が見し鞆の浦のむろの木は常世にあれど見し人そなき(万3-449) 礒の上に立てるむろの木ねもころに何しか深め思ひそめけむ(万11-2493) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| め | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| め | 推量の助動詞「む」の已然形。 疑問の「や」「が」を伴って反語の意を表わす。 |
秋山の木の下隠り行く水の我れこそ益さめ思ほすよりは(万2-92) 玉葛花のみ咲きてならざるは誰が恋にあらめ我は恋ひ思ふを(万2-102) 大名児を彼方野辺に刈る草の束の間も我れ忘れめや(万2-110) にほどりの葛飾早稲をにへすともその愛しきを外に立てめやも(万14-3404) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| め | 〔係助詞〕(上代東国方言)⇒係助詞「も」 〔接続〕名詞・助詞、および活用する語の連体形・連用形に付く。 |
我妹子と二人我が見しうち寄する駿河の嶺らは恋しくめあるか(万20-4369) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| め [目] | 〔名詞〕 ① 目。まなこ。② まなざし。目つき。視線。③ 顔。目にうつる姿。 ④ 物と物との隙間。網目など。⑤ 出会い。境遇。状況。体験。 |
① 秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる(古今秋上-169) ③ 道遠み来じとは知れるものからにしかぞ待つらむ君が目を欲り(万4-769) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| め [牝・雌] | 〔名詞〕動植物のめす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| め [女・妻] | 〔名詞〕 [女] (「男」に対して) おんな。女性。 [妻] (「夫」に対して) 妻・夫人。配偶者。 |
臣の女の 櫛笥に乗れる 鏡なす 三津の浜辺に さにつらふ -(万4-512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| めかり [海布刈り・和布刈り] | 〔名詞〕わかめ(=海藻の名)を刈ること。〔春〕 | 志賀の海女は軍布刈り塩焼き暇なみくしげの小櫛取りも見なくに(万3-281) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| めかる [目離る] | 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 目が離れる。しだいに見えなくなる。離れていて会わなくなる。 |
佐保過ぎて奈良の手向けに置く幣は妹を目離れず相見しめとそ(万3-303) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| めこと [目言] | 〔名詞〕目で見、口で言う事。会うことと語る事。会って語り合う事。 | -あぢさはふ 目言も絶えぬ 然れかも あやに哀しみ ぬえ鳥の-(万2-196) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| めす [見す・看す] | 〔他動詞サ行四段〕 ①「見る」の尊敬語。御覧になる。 ②「治む」の尊敬語。お治めになる。 |
① -埴安の 堤の上に あり立たし 見したまへば-(万1-52) ① 愛しきかも皇子の尊のあり通ひ見しし活道の道は荒れにけり(万3-482) ② -皇子の尊 万代に 食したまはまし 大日本 久迩の都は-(万3-478) ② やすみしし 我が大君の 見したまふ 吉野の宮は 山高み-(万6-1010) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| めす [召す] | 〔他動詞サ行四段〕 ①「呼ぶ」「招く」の尊敬語。お呼びになる。お招きになる。 ②「取り寄す」の尊敬語。お取り寄せになる。 ③「飲む」「食ふ」「着る」の尊敬語。召し上がる。お召しになる。 ④「為す」の尊敬語。なさる。 |
① 東のたぎの御門に侍へど昨日も今日も召す言もなし(万2-184) ① -東の国の 御いくさを 召したまひて ちはやぶる 人を和せと-(万2-199) ① -もののふの 八十伴の男を 召し集へ 率ひたまひ 朝狩に-(万3-481) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| めす | 〔自動詞サ行四段〕「乗る」の尊敬語。(乗り物に)お乗りになる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 「めす」は動詞「見る」の未然形「み」に上代の尊敬の助動詞「す」の付いた形「みす」が音変化したもので、「見る」が原義。次第に「召す」に転意して用いられるようになったものと考えられる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| めす [召す] | 〔補助動詞サ行四段〕 [他の尊敬の動詞の連用形に付いて、尊敬の意を強める] お~になる。~なさる。 |
-いかさまに 思ほしめせか-(万1-29) -たかてらす ひのみこ いかさまに おもほしめせか-(万2-162) 遠くあれば一日一夜も思はずてあるらむものと思ほしめすな(万15-3758) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| めづらし [珍し] | 〔形容詞シク活用〕 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 ① 賛美すべきである。すばらしい。② 愛らしい。かわいい。 ③ 目新しい。清新である。④ めずらしい。めったにない。 |
① 人ごとに折りかざしつつ遊べどもいやめづらしき梅の花かも [大判事丹氏麻呂](万5-832) ② -望月の いやめづらしみ 思ほしし 君と時どき 出でまして-(万2-196) ② 難波人葦火焚く屋の煤してあれどおのが妻こそ常めづらしき(万11-2659) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| めにつく [目につく] | 「万葉集中」この語句は、「巻第一-十九番」でしか現れず、それを「古注」である鹿持雅澄「古義」の注釈を引用する。 【参考「古義」】 綜麻形の林のさきのさ野榛の衣に付くなす目につく吾が背(万1-19) 目爾都久 [メニツク] とは、その人の愛 [ウツク] しまるゝより見ぬふりしても常に目につき易きよしなり、七 (ノ) 卷に、今造斑衣服面就常爾所念未服友 [イマツクルマダラノコロモメニツキテツネニオモホユイマダキネドモ] ともよめり、 ただし、古語辞典での「目につく」という語が、項目として載るのは、学研「全訳古語辞典」で、その意味、用例は「源氏物語」となる。 【参考「学研全訳古語辞典」】 〔連語〕見て気に入る。 「少しまばゆく、艶にこのましきことは、目に付かぬ所あるに」(源氏物語-帚木) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| めや | 〔なりたち〕 [推量の助動詞「む」の已然形「め」+反語の終助詞「や」] 反語の意を表す。「~だろうか(いや、~ない)」 |
大君は千歳にまさむ白雲も三船の山に絶ゆる日あらめや(万3-244) 愛しき人のまきてししきたへの我が手枕をまく人あらめや(万3-441) うゑしうゑば 秋なき時やさかざらん 花こそちらめ ねさへかれめや (古今秋下-268) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| めやも | 〔なりたち〕[推量の助動詞「む」の已然形「め」+反語の終助詞「やも」〕 反語の意を表す。「~だろうか(いや、~でないなあ)」 |
紫のにほへる妹を憎くあらば人妻故に我れ恋ひめやも(万1-21) 楽浪の志賀の [一云 比良の] 大わだ淀むとも昔の人にまたも逢はめやも [一云 逢はむと思へや](万1-31) 敷栲の袖交へし君玉垂の越智野過ぎ行くまたも逢はめやも [一云 越智野に過ぎぬ](万2-195) 沖つ波辺波立つとも我が背子がみ船の泊り波立ためやも(万3-248) 価なき宝といふとも一坏の濁れる酒にあにまさめやも(万3-348) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| も | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| も | 〔係助詞〕 ① 並列を表わす。 ② 同種の事柄の一つをあげていう。「~もまた。においてもまた」 ③ 軽いものをあげて、言外に重いものを想像させる。「でも。~だって」 ④ 最小限の希望。「せめて~だけでも」 ⑤ 仮定してみる気持ち。「~でも、なりと」 ⑥ 主語などについて、和らいだ表現。 ⑦ 否定文に用いて、否定を強める。 ⑧ 推量・命令などの文に用いて、感情を添える。 [接続] 名詞・助詞および活用語の連体形・連用形に付く。 |
① 稲日野も行き過ぎかてに思へれば心恋しき加古の島見ゆ [一云 水門見ゆ](万3-254) ② 外に見し真弓の岡も君座せば常つ御門と侍宿するかも(万2-174) ② -剣太刀 身に添へ寝ねば ぬばたまの 夜床も荒るらむ -(万2-194) ② -川藻もぞ 枯るれば生ゆる なにしかも 我が大君の 立たせば-(万2-196) ③ -夕に立ちて 朝には 失すといへ 梓弓 音聞く我れも 凡に見し-(万2-217) ③ 大君は千歳にまさむ白雲も三船の山に絶ゆる日あらめや(万3-244) ③ 隼人の薩摩の瀬戸を雲居なす遠くも我は今日見つるかも(万3-249) ③ 生ける者遂にも死ぬるものにあればこの世にある間は楽しくをあらな (万3-352) ③ 大和辺に君が立つ日の近づけば野に立つ鹿もとよめてそ鳴く(万4-573) ④ -かくにあるらし 古も しかにあれこそ-(万1-13) ④ 妹が家も継ぎて見ましを大和なる大島の嶺に家もあらましを [一云 妹があたり継ぎても見むに] [一云 家居らましを](万2-91) ④ 妻もあらば摘みて食げまし沙弥の山野の上のうはぎ過ぎにけらずや(万2-221) ⑤ 吉野川行く瀬の早みしましくも淀むことなくありこせぬかも(万2-119) ⑤ 家に行きて何を語らむあしひきの山霍公鳥一声も鳴け (万19-4227) ⑦ 大名児を彼方野辺に刈る草の束の間も我れ忘れめや(万2-110) ⑦ 朝日照る佐田の岡辺に群れ居つつ我が泣く涙やむ時もなし(万2-177) ⑦ 東のたぎの御門に侍へど昨日も今日も召す言もなし(万2-184) ⑦ 朝日照る嶋の御門におほほしく人音もせねばまうら悲しも(万2-189) ⑦ あしひきの山道越えむとする君を心に持ちて安けくもなし(万15-3745) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| も | 〔接続助詞〕 ① 逆接の確定条件。「~のに。~けれども」 ② 逆接の仮定条件。「~ても。~とも」 [接続] 動詞・動詞型助動詞の連体形に付く。 |
① -大夫と 思へる我れも 草枕 旅にしあれば 思ひ遣る たづきを知らに-(万1-5) ② 来むと言ふも来ぬ時あるを来じと言ふを来むとは待たじ来じと言ふものを(万4-530) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| も | 〔終助詞〕 詠嘆(文末につく)。「~よ」「~なあ」 [接続] 文末、文節末の種々の語に付く。 |
-ももしきの 大宮ところ 見れば悲しも-(万1-29) 楽浪の国つ御神のうらさびて荒れたる都見れば悲しも(万1-33) 玉藻刈る沖へは漕がじ敷栲の枕のあたり忘れかねつも(万1-72) 玉櫛笥覆ふを安み明けていなば君が名はあれど吾が名し惜しも(万2-93) 我が御門千代とことばに栄えむと思ひてありし我れし悲しも(万2-183) 朝日照る嶋の御門におほほしく人音もせねばまうら悲しも(万2-189) 真木柱太き心はありしかどこの我が心鎮めかねつも(万2-190) 秋山の黄葉を茂み惑ひぬる妹を求めむ山道知らずも [一云 路知らずして](万2-208) 苦しくも降り来る雨か三輪の崎狭野の渡りに家もあらなくに(万3-267) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| も | 〔間投助詞〕 ① 詠嘆・感動を表わす。② 意味を強める。 [接続] 種々の語に付く。 |
① 安騎の野に宿る旅人うち靡き寐も寝らめやもいにしへ思ふに(万1-46) ① つのさはふ磐余も過ぎず泊瀬山いつかも越えむ夜は更けにつつ(万3-285) ① 我が命も常にあらぬか昔見し象の小川を行きて見むため(万3-335) ② 釧着く答志の崎に今日もかも大宮人の玉藻刈るらむ(万4-530) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もが | 〔終助詞〕《上代語》願望の意を表す。 ~があればなあ。~であればなあ。 〔接続〕 体言および体言に準ずる語、形容詞と助動詞の連用形、副詞、助詞「に」などに付く。 |
伊勢の海の沖つ白波花にもが包みて妹が家づとにせむ(万3-309) 都辺に行かむ船もが刈り薦の乱れて思ふ言告げやらむ(万15-3662) あしひきの山はなくもが月見れば同じき里を心隔てつ(万18-4100) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 係助詞「も」+終助詞「が」=「もが」、係助詞「も」+係助詞「か」=「もか」の変化したもの、などの説がある。 上代では、多く「も」を伴って「もがも」の形で用いられた。平安時代以降は「もがな」の形か、「も」の落ちた「がな」の形で使用された。→もがも・もがな・がな |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もがな | 〔終助詞〕[終助詞「もが」に、終助詞「な」が付いたも] 願望の意を表す。~があればなあ。~であればなあ。 〔接続〕 体言、形容詞の連用形、打消しや断定の助動詞の連用形「に」「と」につく。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 上代の「もがも」に代わって、中古以降に用いられた。「も」の落ちた「がな」も併用された。→もが・がな |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もがも | 〔終助詞〕[終助詞「もが」に、終助詞「も」が付いたも] 「願望の意(・・・であればなあ)」 〔接続〕 体言および体言に準ずる語、形容詞の連用形、副詞、断定の助動詞「なり」の連用形、助詞などにつく。 |
岩戸割る手力もがも手弱き女にしあればすべの知らなく (万3-422) -高飛ぶ 鳥にもがも 明日行きて 妹に言問ひ 我がために-(万4-537) 君が行く道の長手を繰り畳ね焼き滅ぼさむ天の火もがも(万15-3746) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】上代に「もが」と併用され「もがもな」「もがもや」「もがもよ」などの形になることが多い。中古以降は、「もがな」の形にとって代わられた。→もが・もがな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もころ [如・若] | 〔名詞〕(連体修飾語を受けて「如(ごと)」 と同じように用いられる。) よく似た状態であること。~(の)ように。~(の)ごとく。 |
-我が大君の 立たせば 玉藻のもころ 臥やせば 川藻のごとく-(万2-196) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もし [茂し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 草木が生い茂っている。 |
水伝ふ礒の浦廻の岩つつじ茂く咲く道をまたも見むかも(万2-185) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もぞ | ① 悪い事態を予測し、あやぶんだり、心配したりする意を表す。 ~するといけない。~したら大変だ。 ② 「も」 の意味を「ぞ」 で強めた言い方。~も。 |
② -人の言へば 岩根さくみて なづみ来し よけくもそなき-(万2-210) ② 立ちて思ひ居てもぞ思ふ紅の赤裳裾引き去にし姿を(万11-2555) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 ① は中古以降の用法。「柴の戸の跡見ゆばかりしをりせよ忘れぬ人のかりにもぞ訪(と)ふ」(正治二年百首) のように、よい事態を予測する意の用例もあるが、数は少ない。→「もこそ・ぞ」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もだ [黙] | 〔名詞〕 何もしないこと。また、黙っていること。沈黙。 |
黙居りて賢しらするは酒飲みて酔ひ泣きするになほ及かずけり(万3-353) - かつは知れども しかすがに 黙もえあらねば 我が背子が-(万4-546) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もだす [黙す] | 〔自動詞サ行変格〕【セ・シ・ス・スル・スレ・セヨ】 ① 黙る。口をつぐむ。 ② そのまま捨てておく。黙って見過ごす。 |
① 恥を忍び恥を黙して事もなく物言はぬさきに我れは寄りなむ [二](万16-3817) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もち [望] | 〔名詞〕 ① 「望月(もちづき)」の略。 ② 陰暦で、月の十五日の称。 |
② 富士の嶺に降り置く雪は六月の十五日に消ぬればその夜降りけり(万3-323) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【岩波書店「日本古典文学大系風土記 逸文『駿河国-富士雪』」】 富士ノ山ニハ雪ノフリツモリテアルガ、六月十五日(みなつきのもちのひ)ニソノ雪のキエテ、子ノ時ヨリシモニハ又フリカハルト、駿河国風土記ニミエタリト云ヘリ。 (萬葉集註釈巻第三) 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻三-320 頭注『六月の十五日に消ぬれば』」】 逸文『駿河国風土記』には、富士山に降り積もっている雪が六月十五日に消えて、子の刻以後にまた降りかわる、という古伝承を載せる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もちこす [持ち越す] | 〔他動詞サ行四段〕[なりたち:係助詞「も」+係助詞「ぞ」] ① 持って他へ移す。運ぶ。 ② そのままの状態で時日を過ごす。 |
① -泉の川に 持ち越せる 真木のつまでを 百足らず 筏に作り-(万1-50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もちづき [望月] | 〔名詞〕陰暦で、十五日の夜の月。満月。望(もち)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もちづきの [望月の] | 【枕詞】 満月に欠けているところがないことから「たたはし・足(た) れる」に、 また、美しいことから「めづらし」 にかかる。 |
-貴くあらむと 望月の 満しけむと 天の下 食す国 四方の人の-(万2-167) -見れども飽かず 望月の いやめづらしみ 思ほしし 君と時々 - (万2-196) -妹にしかめや 望月の 足れる面わに 花のごと 笑みて立てれば-(万9-1811) -いつしかも 日足らしまして 望月の 満しけむと 我が思へる-(万13-3338) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もつ [持つ] | 〔他動詞タ行四段〕 ① 手に取る。身に付ける。② 所有する。 ③(連用形の形で)用いる。使う。 ④ 心にいだく。心に思う。 ⑤ 保つ。維持する。 |
② 我が持てる三つ合ひに搓れる糸もちて付けてましもの今そ悔しき(万4-519) ③ 我が持てる三つ合ひに搓れる糸もちて付けてましもの今そ悔しき(万4-519) ③ あをによし奈良の山なる黒木もち造れる室は座せど飽かぬかも (万8-1642) ④ あしひきの山道越えむとする君を心に持ちて安けくもなし (万15-3745) ⑤ -選ひたまひて 大御言 [反云 大みこと] 戴き持ちて もろこしの- (万5-898) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もて [持て] | [「持ちて」の促音便「もって」の促音「っ」の表記されない形] (手に) 持って。 | -燃ゆる火を 雪もて消ち 降る雪を 火もて消ちつつ 言ひも得ず-(万3-322) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もと [本・元・原・旧・故・許] | 〔名詞〕 ① 根本。よりどころ。主とするところ。 ② 物事の起こるところ。原因。始まり。 ③ 根もと。④ 辺り。そば。⑤ ところ。住居。 ⑥(「末」に対して)和歌の上の句。 ⑦ 元金。資本金。⑧ 以前。昔。 |
① 何時の間も神さびけるか香具山の桙杉が本に苔生すまでに(万3-261) ④ 莫囂円隣之大相七兄爪謁気我が背子がい立たせりけむ厳橿が本(万1-9) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もと | 〔副詞〕以前に。さきに。 | もとありし前栽もいとしげく荒れたりけるを見て(古今哀傷詞書-853) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もとな | 〔副詞〕 ① 根拠もなく。理由もなく。② しきりに。やたらに。 |
① -なにしかも もとなとぶらふ 聞けば 音のみし泣かゆ 語れば-(万2-230) ② 我妹子が笑まひ眉引き面影にかかりてもとな思ほゆるかも(万12-2912) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もとむ [求む] | 〔他動詞マ行下二段〕【メ・メ・ム・ムル・ムレ・メヨ】 ① 手に入れようと探す。② 欲しいと願う。③ 買う。④ 招く。誘い出す。 |
① 秋山の黄葉を茂み惑ひぬる妹を求めむ山道知らずも [一云 路知らずして](万2-208) ① むささびは木末求むとあしひきの山の猟夫にあひにけるかも(万3-269) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もとほす [回す・徘徊す] | 〔他動詞サ行四段〕巡らす。回す。 | -奇しきものか 淡路島 中に立て置きて 白波を 伊予に廻ほし-(万3-391) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もとほる [回る・徘徊る] | 〔自動詞ラ行四段〕[多く動詞「立つ・這ふ・行く」などの連用形に付いて] 巡る。回る。徘徊する。 |
- 夕にいたれば 大殿を 振り放け見つつ 鶉なす い匍ひ廻り-(万2-199) -い行きさぐくみ 岩の間を い行き廻り 稲日都麻 浦廻を過ぎて-(万4-512) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もの- | 〔接頭語〕(形容詞・形容動詞などについて) はっきり言い表せないの意を表す。何となく。また、語調を整える。物。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もの [物] | 〔名詞〕 ① 物事。対象をはっきりと指示せず、漠然という。 ② ふつうのもの。一般の事物。③ 人。動物。④ 道理。 ⑤ (多く下に打消の語を伴って) 取り立てて言うべきほどの事柄。 ⑥ 飲食物。食事。⑦ 衣服。調度品。⑧ 楽器。 ⑨ 前後の関係から言わなくても解る物事を示す。 ⑩ 言語。言葉。 ⑪ 出かけて行く場所。ある所。 ⑫ 超自然的な力を持つ存在。鬼神。怨霊。物の怪。 ⑬ (形式名詞として)ある属性を有する実体や事柄を表す。 |
① かくばかり恋ひつつあらずは高山の磐根しまきて死なましものを(万2-86) ⑤ 験なき物を思はずは一坏の濁れる酒を飲むべくあるらし(万3-341) ⑥ 古の七の賢しき人たちも欲りせしものは酒にしあるらし(万3-343) ⑬ 世の中は空しきものとあらむとそこの照る月は満ち欠けしける(万3-445) ⑬ 世間は空しきものと知る時しいよよますます悲しかりけり(万5-796) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ものいふ [物言ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 ① 口をきく。口に出して言う。 ② 気の利いたことをいう。秀句・しゃれなどを言う。 ③ 男女が情を通わせる。 |
② 賢しみと物言ふよりは酒飲みて酔ひ泣きするし優りたるらし(万3-344) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ものおもふ (ものもふ) [物思ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕[「ものもふ」とも] 思い悩む。思い耽る。 |
大船の泊つる泊りのたゆたひに物思ひ痩せぬ人の子故に(万2-122) 浅茅原つばらつばらに物思へば古りにし里し思ほゆるかも(万3-336) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ものか | 〔終助詞〕[組成] 形式名詞「もの」+係助詞(終助詞的用法)「か」 ① 強い感動を表す。~ではないか。全く~ことよ。 ② 非難をこめた反問の意を表す。~ものであろうか。~ことがあろうか。 |
① 海神は 奇しきものか 淡路島 中に立て置きて 白波を-(万3-391) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ものこほし [物恋し] | 〔形容詞シク活用〕[「もの」は接頭語] 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 何となく恋しい。 |
旅にしてもの恋ほしきに鶴が音も聞こえざりせば恋ひて死なまし(万1-67) 旅にしてもの恋ほしきに山下の赤のそほ船沖を漕ぐ見ゆ(万3-272) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ものぞ [上代は「ものそ」とも] | 〔なりたち〕 形式名詞「もの」+係助詞(終助詞的用法)「ぞ」。 ① 強い断定の意を表す。~ものである。 ② (助動詞「む」の下に付いて) 強意を表す。~にちがいない。 |
① もののふの臣の壮士は大君の任けのまにまに聞くといふものそ(万3-372) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もののふ [物部・武士] | 〔名詞〕 ① 上代、朝廷に仕える多くの文官・武官。文武百官。 ② 武士。さむらい。つわもの。 |
① ますらをの鞆の音すなり物部の大臣盾立つらしも(万1-76) ① もののふの臣の壮士は大君の任けのまにまに聞くといふものそ(万3-372) ① 秋野には今こそ行かめもののふの男女の花にほひ見に(万20-4341) ②-たけき(勇猛な)もののふのこころをも、なぐさむるは歌なり(古今仮名序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もののふの [物部の・武士の] | 【枕詞】 「もののふ(=文武百官)」は数が多いことから、「八十(やそ」に、 また「八十氏川(やそうぢがは)」にかかることから地名「宇治(うぢ)」に、 「もののふ(=武士)」持つ「矢」から地名の「矢野」「矢田」、また「岩瀬」にかかる。 |
為むすべの たづきを知らに もののふの 八十の心を 天地に-(万13-3290) あをによし 奈良山過ぎて もののふの 宇治川渡り 娘子らに-(万13-3251) もののふの石瀬の社の霍公鳥今も鳴かぬか山の常蔭に(万8-1474) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ものを | 〔接続助詞〕 ① 逆接の確定条件を表す。「~のに」 ② 順接の確定条件を表す。「~ので・~だから」 〔接続〕活用語の連体形に付く。 |
① 早来ても見てましものを山背の高の槻群散りにけるかも(万3-280) ① かく故に見じと言ふものを楽浪の旧き都を見せつつもとな(万3-308) ① ぬばたまのその夜の梅をた忘れて折らず来にけり思ひしものを(万3-395) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔終助詞〕詠嘆の意を表す。「~のになあ・~のだがなあ」 〔接続〕活用語の連体形に付く。 |
我を待つと君が濡れけむあしひきの山のしづくにならましものを(万2-108) 富士の嶺を高み恐み天雲もい行きはばかりたなびくものを(万3-324) 陸奥の真野の草原遠けども面影にして見ゆといふものを(万3-399) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔参考〕 接助 ①と終助詞の識別はつきにくいが、省略も倒置もない文末に「ものを」がくれば、終助詞とすればよい。 接助 ①は「ものの」「ものから」「ものゆゑ」と意味・用法が似ているが、「を」が間投助詞であるところから、感動・詠嘆を表す場合が多く、そこから、「終助詞」の用法も生じている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もみぢ [黄葉・紅葉] | 〔名詞〕[上代は「もみち」] ① 秋、草木の葉が赤または黄に色づくこと。また、その葉。こうよう。 ②「紅葉襲(もみぢがさね)」の略。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【「黄」という色】 「万葉集」には「黄葉」と書いて「もみち」と読ませ、「黄泉」と書いて「よみ」と読ませるなど、「黄」の字が用いられてはいるが、色としての「き」の用例とみられるのは、 奥つ国領く君が染(ぬり)屋形黄染(ぬり)の屋形神が門渡る (万16-3910) の一例に過ぎない。ことばの上からいうと、「青し・赤し・白し・黒し」などの形容詞はあるが、「き」の形容詞はない。実際に「黄色のもの」がなかったというのではなく、「青し」と「赤し」とで広い範囲の色をさし、間に合わせることができたから。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もみぢば [黄葉・紅葉] | 〔名詞〕[上代は「もみちば] 秋に赤や黄に色づいた草木の葉。紅葉した葉。 |
-思ひし時に 春へは 花折かざし 秋立てば もみち葉かざし 敷栲の-(万2-196) 黄葉の散りゆくなへに玉梓の使を見れば逢ひし日思ほゆ(万2-209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もみぢばの [黄葉の・紅葉の] | 【枕詞】[上代は「もみちばの」] 紅葉は散りやすく色が変りやすいところから、「移り」「過ぎに」に、 その色から「朱(あけ)」にかかる。 |
見れど飽かずいましし君が黄葉のうつりい行けば悲しくもあるか(万3-462) ま草刈る荒野にはあれど黄葉の過ぎにし君が形見とぞ来し(万1-47) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もみつ [紅葉つ・黄葉つ] | 〔自動詞タ行四段〕上代語「もみづ」に同じ。 | 秋山にもみつ木の葉のうつりなばさらにや秋を見まく欲りせむ(万8-1520) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 上代はタ行四段活用であったが、中古以降、「もみづ」と濁音化し、ダ行上二段活用となる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もみづ [紅葉づ・黄葉づ] | 〔自動詞ダ行上二段〕【ヂ・ヂ・ヅ・ヅル・ヅレ・ヂヨ】 秋になって草木の葉が赤または黄に色づく。紅葉する。 |
雪ふりて年のくれぬる時にこそつひにもみぢぬ松も見えけれ(古今冬-340) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もも- [百-] | 〔接頭語〕数の百の意から、数の多いことを表す。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔例語〕「百枝(ももえ)・百日(ももか)・百草(ももくさ)・百種(ももくさ)・百隈(ももくま)・百箇(ももち)・百年(ももとせ)・百鳥(ももとり)・百重(ももへ)・百世(ももよ)・百夜(ももよ)」など。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もも [百] | 〔名詞〕百。また、数の多いこと。 | -我が二人見し 出で立ちの 百足る槻の木 こちごちに 枝させるごと-(万2-213) 百に千に人は言ふとも月草のうつろふ心我れ持ためやも(万12-3073) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ももしき [百敷・百磯城] | 〔名詞〕[枕詞「百敷の」がかかる「大宮」から意味が転じて] 皇居。宮中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ももしきの [百敷の・百磯城の] | 【枕詞】多くの石や木で造ってある意から「大宮」にかかる。 | -ももしきの 大宮ところ 見れば悲しも-(万1-29) ももしきの大宮人の熟田津に船乗りしけむ年の知らなく(万3-326) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ももたらず [百足らず] | 【枕詞】 百に足りないという意から、「八十(やそ)」「五十(い)」にかかる。 また、、「や」「い」から始まる、「山田」「筏(いかだ)」などにかかる。 |
百足らず八十隈坂に手向けせば過ぎにし人にけだし逢はむかも(万3-430) -真木のつまでを 百足らず 筏に作り 泝すらむ いそはく見れば-(万1-50) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ももち [百箇] | 〔名詞〕[「ち」は接尾語] 百。また、数の多いこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ももちだる [百千足る] | 〔自動詞ラ行四段〕 満ち足りている。十分に備わっている。「ももだる」とも。 |
千葉の葛野を見れば百千足る家庭(やには)も見ゆ国の秀(ほ)も見ゆ(記中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ももちどり [百千鳥] | 〔名詞〕 ① 多くの鳥。さまざまの鳥。百鳥(ももどり)。 ② 鶯の異称。 ③ 千鳥の異称。 |
ももちどりさへづる春は 物ごとにあらたまれども 我ぞふりゆく(古今春上-28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ももづた(と)ふ [百伝ふ] | 【枕詞】 数えて百に至る意から、「八十(やそ)」や「五十(い)」の音を持つ地名「磐余(いはれ)」にかかる。 また、多くの地を伝わって行く意から、地名「角鹿(つぬが)」「渡会(わたらひ)」に、 遠くへ行くときに用いた駅路の鈴の意から、「鐸(ぬて=上部に長い柄のある大型の鈴)」にかかる。 |
百伝ふ八十の島廻を漕ぐ舟に乗りにし心忘れかねつも(万7-1403) 百伝ふ磐余の池に鳴く鴨を今日のみ見てや雲隠りなむ(万3-419) 百伝角鹿の蟹-(記中) 百伝渡会県(わたらひあがた)の-(紀・神功) 百伝鐸響(ゆら)くも-(記下) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もものつかさ [百の官] | 〔名詞〕多くの役人。百官(ひゃっかん)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ももはがき [百羽掻き] | 〔名詞〕 鴫(しぎ=水鳥の名)が嘴で何度も羽をかくこと。 回数の多い物事のたとえにいう。 |
暁のしぎのはねがきももはがき 君がこぬ夜は我ぞかずかく(古今恋五-761) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ももへ [百重] | 〔名詞〕 数多く重なっていること。 |
み熊野の浦の浜木綿百重なす心は思へど直に逢はぬかも(万4-499) あしひきの山は百重に隠すとも妹は忘れじ直に逢ふまでに(万12-3203) [一云 隠せども君を思はくやむ時もなし] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ももよ [百夜] | 〔名詞〕多くの夜。 | -頼める今夜 秋の夜の 百夜の長さ ありこせぬかも (万4-549) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もや [母屋] | 〔名詞〕 家屋の中で中心となる所。 また、寝殿造りで、廂(ひさし=簀の子の縁の内側にある細長い部屋)に対して、その内側にある中央の部屋。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【発展】寝殿の構造 平安時代の貴族の邸宅で、主人の居間兼客間として用いられた南向きの建物を寝殿と呼ぶが、その寝殿の中心となる部屋が「母屋(もや)」であった。 母屋は「主屋(おもや)」の転であろう。母屋は、外側を「廂」、さらにその外側を一段低くなった「簀の子」がとりまき、廂と簀の子の境に格子がはめられるのが普通であった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もや | 〔間投助詞〕[係助詞「も」+間投助詞「や」] 感動を表す。 | 我れはもや安見児得たり皆人の得かてにすといふ安見児得たり(万2-95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もや | [係助詞「も」+係助詞「や」] ~だろうか。~も~だろうか。 「もや」の結び「あらん」が省略された形。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もやふ [舫ふ] | 〔他動詞ハ行四段〕船と船をつなぎ合わせる。船を岸につなぎとめる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もゆ [萌ゆ] | 〔自動詞ヤ行下二段〕【エ・エ・ユ・ユル・ユレ・エヨ】 草木などの芽が出る。芽ぐむ。 |
春は萌え夏は緑に紅のまだらに見ゆる秋の山かも (万10-2181) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もゆ [燃ゆ] | 〔自動詞ヤ行下二段〕【エ・エ・ユ・ユル・ユレ・エヨ】 ① 火が燃える。火がついて炎や煙がたつ。 ② 炎の揺らめくような光を放つ。 ③ 情熱が高まる。 |
① さねさし相模(さがむ)の小野に燃ゆる火の火中(ほなか)に立ちて問ひし君はも (記・中) ② -かぎろひの 燃ゆる荒野に 白たへの 天領巾隠り 鳥じもの-(万2-210) ② 埴生坂(はにふざか)我が立ち見ればかぎろひの燃ゆる家群妻が家のあたり (記下) ③ 心には燃えて思へどうつせみの人目を繁み妹に逢はぬかも (万12-2944) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もゆらに | 〔副詞〕[「も」は接頭語] 玉の触れ合って鳴るさま。ゆらゆらと。 |
ぬなとももゆらに、天の真名井に振りすぎて-(記上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もよ | 〔間投助詞〕[上代語・係助詞「も」✙間投助詞「よ」] 感動の意を表す。ねえ。ああ~よ。 〔接続〕種々の語につく。 |
篭もよ み篭持ち 堀串もよ み堀串持ち この岡に 菜摘ます子 家聞かな- (万1-1) おしていなと稲は搗かねど波の穂のいたぶらしもよ昨夜ひとり寝て(万14-3572) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もる [盛る] | 〔他動詞ラ行四段〕 ① 高く積み上げる。特に飲食物を器物に入れていっぱいにする。 ② 薬や酒などを飲ませる。 |
家にあれば笥に盛る飯を草枕旅にしあれば椎の葉に盛る(万2-142) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もろごひ [諸恋ひ] | 〔名詞〕互いに激しく思うこと。相思相愛。⇔「片戀ひ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もろひと [諸人] | 〔名詞〕「もろびと」 とも。多くの人びと。たくさんの人。 | -虎か吼ゆると 諸人の おびゆるまでに [一云 聞き惑ふまで] -(万2-199) 梅の花折りかざしつつ諸人の遊ぶを見れば都しぞ思ふ [土師氏御道](万5-847) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| や | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| や | 〔間投助詞〕 ① 感動・詠嘆。② 呼び掛けの意、「~よ」。③ 事物の列挙。 ④ 和歌で、上の語句を下の体言に結びつける。 ⑤ 和歌で、音の調子を整えるために添える。 〔接続〕 文節の切れめ、体言、活用語の連体形に付く。 文末に用いる場合、活用語には終止形につく。 |
① 燈火の明石大門に入らむ日や漕ぎ別れなむ家のあたり見ず(万3-255) 天飛ぶや雁を使に得てしかも奈良の都に言告げ遣らむ(万15-3698) 藤原の大宮仕へ生れ付くや娘子がともは羨しきろかも(万1-53) ⑤ 石見のや高角山の木の間より我が振る袖を妹見つらむか(万2-132) ⑤ 蒸し衾なごやが下に臥せれども妹とし寝ねば肌し寒しも(万4-527) ⑤ 春の野に鳴くや鴬なつけむと我が家の園に梅が花咲く[t師志氏大道](万5-841) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| や | 〔係助詞〕 ① 文中に用いられれば、 ア:疑いを表わす、イ:問いを表わす、ウ:反語の意を表わす ② 文末に用いられる場合 ア:問いを表わす、イ:反語の意を表わす 〔接続〕 種々の語に付く。活用語には連体形・連用形に付く。 上代では活用語の已然形にも付く。 |
① 古の人に我れあれや楽浪の古き都を見れば悲しき (万1-32) ① いにしへに恋ふらむ鳥は霍公鳥けだしや鳴きし我が念へるごと (万2-112) ① うつそみの人なる我れや明日よりは二上山を弟背と我が見む(万2-165) ① 雪こそば春日消ゆらめ心さへ消え失せたれや言も通はぬ(万9-1786) ①「イ」-けだしくも 逢ふやと思ひて [一云 君も逢ふやと] -(万2-194) ①「イ」-明しといへど 我がためは 照りやたまはぬ 人皆か-(万5-896) ①「ウ」-そこ故に せむすべ知れや 音のみも 名のみも絶えず-(万2-196) ② 「ア」-宜しき君が 朝宮を 忘れたまふや 夕宮を 背きたまふや-(万2-196) ② 「ア」 藤波の花は盛りになりにけり奈良の都を思ほすや君(万3-333) ② 「ア」 -我が泣く涙 有間山 雲居たなびき 雨に降りきや(万3-463) ②「イ」 今日来ずは明日は雪とぞ降りなまし消えずはありとも花と見ましや (古春上-63) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔語法〕この語を受けて終止する活用語は連体形をもって結ぶ。 ①の「ア」は特に推量の意を表わす助動詞「む」「らむ」「けむ」等とともに用いられる。 ①の「ウ」は、已然形について、疑いや反語の意を表わす用法。 ②は終助詞用法。文末にある場合、「や」は活用語の終止形に接続。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| や | 〔終助詞〕 ① 疑問の意を表す。 ~か。 ② 反語の意を表す。 ~(だろう)か(いや、~ない)。 〔接続〕 活用語の終止形・已然形に付く。 已然形に付くのは、「万葉集」に多く、中古でも和歌のみにみられる。 |
① 風吹けば波打つ岸の松なれやねにあらはれて泣きぬべらなり (古今恋三-671) ② 三輪山をしかも隠すか雲だにも心あらなも隠さふべしや(万1-18) ② 安騎の野に宿る旅人うち靡き寐も寝らめやもいにしへ思ふに(万1-46) ② 大伴の御津の浜なる忘れ貝家なる妹を忘れて思へや(万1-68) ② 大和恋ひ寐の寝らえぬに心なくこの洲崎廻に鶴鳴くべしや(万1-71) ② 大名児を彼方野辺に刈る草の束の間も我れ忘れめや(万2-110) ② 川風の寒き長谷を嘆きつつ君があるくに似る人も逢へや(万3-428) ② 妹が袖別れて久になりぬれど一日も妹を忘れて思へや(万15-3626) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻第二-117 「や~む」頭注】 ますらをや片恋せむと嘆けども醜のますらをなほ恋ひにけり 一人称に用いた「「ヤ~ム」は、現在の自分がしていることについて、こうも~することか、などと不甲斐なく思いながらどうすることもできない気持ちを表す語法。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| や [矢・箭] | 〔名詞〕 武具の一つ。 一方の端に羽を付け、他の端に鏃(やじり)を付け、弓の弦につがえて射るもの。 |
-聞きの恐く [一云 諸人の 見惑ふまでに] 引き放つ 矢の繁けく-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やきづ [焼津] | 〔地名〕 | 焼津辺に我が行きしかば駿河なる阿倍の市道に逢ひし児らはも(万3-287) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 『付録 地名一覧』」】 静岡県焼津市。静岡市の西南約一二キロメートル。日本武尊の伝説で名高い。 『続日本紀』天平宝字元年の条に「益頭郡」とある。『和名抄』では「益頭 末志豆(ましづ)」と読んでいる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やく [焼く] | 〔他動詞カ行四段〕 ① 火をつけて燃やす。② 思いをこがす。心を悩ます。 ③ 人をだます。おだてる。 |
① -野ごとに つきてある火の [一云 冬こもり 春野焼く火の] 風の共-(万2-199) ① -さつ矢手挟み 立ち向かふ 高円山に 春野焼く 野火と見るまで -(万2-230) ② 我が心焼くも我れなりはしきやし君に恋ふるも我が心から(万13-3285) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔自動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 ① 火がついて燃える。② 心が乱れる。思い焦がれる。 |
② -網の浦の 海人娘子らが 焼く塩の 思ひぞ焼くる我が下心(万1-5) ② 人にあはんつきのなきには 思ひおきて胸走り火に心焼けをり(古今雑体-1030) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やくも [八雲] | 〔名詞〕 ① 幾重にも重なっている雲。 ② (「①」の用例の須佐之男命の歌が、和歌の最初であることから) 和歌。 |
① 八雲立つ出雲八重垣妻籠みに八重垣作るその八重垣を(記上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -のみち [八雲の道] | (「八雲②」の意味から) 和歌の道。歌道。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -さす [八雲刺す] | 【枕詞】「出雲」にかかる。 | やくもさす出雲の児らが黒髪は吉野の川の沖になづさふ(万3-433) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -たつ [八雲立つ] | 【枕詞】雲が幾重にも立ちのぼる意から「出雲」にかかる。 | 八雲立つ出雲八重垣妻籠みに八重垣作るその八重垣を(記上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やしろ [社] | 〔名詞〕 ① 神が来臨する所。古代では、地を清め臨時に小屋などを設けて、神を迎えた。 ② 神社。 |
春日野に粟蒔けりせば鹿待ちに継ぎて行かましを社し恨めし(万3-408) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やす [痩す] | 〔自動詞サ行下二段〕【セ・セ・ス・スル・スレ・セヨ】 やせる。 |
大船の泊つる泊りのたゆたひに物思ひ痩せぬ人の子故に(万2-122) 我がゆゑに思ひな痩せそ秋風の吹かむその月逢はむものゆゑ(万15-3608) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やすし [易し・安し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ①【易し】 ア:やさしい。容易である。たやすい。 イ:手軽である。無造作である。簡単である。 ウ:(動詞の連用形に付いて) そうなる傾向がある。そうなりがちである。 ②【安し】 ア:安心である。安らかである。穏やかだ。落ち着く。気楽だ。 イ:品位が低い。軽々しい。 ウ:値段が安い。 |
①「ア」 何せむに命をもとな長く欲りせむ 生けりとも我が思ふ妹にやすく逢はなくに(万11-2362) ①「ア」 玉櫛笥覆ふをやすみ明けていなば君が名はあれど吾が名し惜しも (万2-93) 「やすみ」は「ミ語法」 ①「ウ」 月草のうつろひ易く思へかも我が思ふ人の言も告げ来ぬ(万4-586) ①「ウ」 思はじと言ひてしものをはねず色のうつろひやすき我が心かも (万4-660) ② 「ア」 -思ふそら 安けなくに 嘆くそら 苦しきものを み空行く-(万4-537) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やすのの [安の野] | 〔地名〕福岡県朝倉郡夜須町一帯の野。 | 君がため醸みし待酒安の野にひとりや飲まむ友なしにして(万4-558) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻第四-555 注『安の野』」】 神功前紀に、羽白熊鷲という賊を討伐し得て「我ガ心即チ安シ」 と皇后が宜しうたところからその地名が出た、という伝説を載せる。筑前風土記に「安野は、夜須郡の東小田村、四三鳴村、鷹場村、この三村の間、七板原という広き原原あり。方一里あり。これ、則、安野也」(攷證による) とある。大宰府址の東南約12km。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やすみしし [八隅知し・ 安見知し] | 【枕詞】「わが大君」「わご大君」にかかる。 | 高光る日の御子やすみししわが大君(記中) やすみしし 我ご大君の 高知らす 吉野の宮は(万6-928) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やすむ [休む] | 〔自動詞マ行四段〕 ① 休息する。② 安らかになる。平穏になる。③ 寝る。臥して寝る。 |
① -岩床と 川の氷凝り 寒き夜を 息むことなく 通ひつつ -(万1-79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やそ [八十] | 〔名詞〕[「そ」は十の意味] はちじゅう。また、数の多いことにいう。 |
磯の崎漕ぎ廻み行けば近江の海八十の港に鶴さはに鳴く [未詳](万3-275) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やそうぢかは [八十宇治川] | 〔名詞〕 枕詞「もののふの」がかかる、「やそうぢがは」は、「もののふ」が朝廷に仕える多くの文武百官であること、そして多くの部族に分かれていることから分流の多い「八十氏(やそうぢ)」と同音の「八十宇治川」と詠われた。 |
-真木さく 桧のつまでを もののふの 八十宇治川に 玉藻なす-(万1-50) もののふの八十宇治川の網代木にいさよふ波のゆくへ知らずも(万3-266) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集巻第三-264(旧歌番)」頭注】 八十宇治川-宇治川は山地より急傾斜で流下し、宇治橋下流付近から南西に向かって巨椋(おぐら)池に流入したが、そのおびただしい土砂堆積が槙島・向島など幾多の島州を作り、さらにその間に幾筋もの水路ができ、湖内とも河道ともつかない状態にあった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やそくま [八十隈] | 〔名詞〕非常にたくさんの曲がり角。「八十」はたくさん、の意。 | -泊瀬の川に 舟浮けて 我が行く川の 川隈の 八十隈おちず -(万1-79) -この道の 八十隈ごとに 万たび かへり見すれど いや遠に-(万2-131) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やちまた [八衢] | 〔名詞〕道が四方八方に分かれている所。 |
橘の蔭踏む道の八衢に物をぞ思ふ妹に逢はずして(万2-125) 橘の本に道踏む八衢に物をぞ思ふ人に知らえず(万6-1031)[125歌の異伝歌] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やつりやま [矢釣山] | 〔山名〕 |
矢釣山木立も見えず降りまがふ[雪に騒ける朝楽しも](万3-264)下二句定訓なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奈良県高市郡明日香村八釣の東北にある山。大原(小原)の東北にあたり東は桜井市に接する。この付近に新田部皇子の御殿があった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やど [屋戸・宿] | 〔名詞〕[「家 (や) 処 (ど)」の意、また「屋外 (ど)」の意とも] ① 家の敷地。屋敷のうち。家の構えのうち。庭先。 ② 家の戸。③ 旅先で泊ること。宿る所。旅宿。④ 住む所。家。自宅。 ⑤ 主人。あるじ。他人に対し、多く妻が夫をさしていう語。 ⑥ 遊女を呼んで遊ぶ家。揚げ屋。また、その主人。 |
① 我が背子が宿のなでしこ日並べて雨は降れども色も変らず(万20-4466) ② 人の見て言とがめせぬ夢に我れ今夜至らむ宿閉すなゆめ(万12-2924) ③ あしひきの山行き暮らし宿借らば妹立ち待ちてやど貸さむかも(万7-1246) ④ 君待つと我が恋ひ居れば我が宿の簾動かし秋の風吹く(万4-491) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考 「やど」と「いへ」】 類義語に「いへ」があり、古くは、ほぼ同様に用いられたが、平安以後「いへ」は散文に、「やど」は和歌に多用されるようになる。 なお、現代語の「宿(=旅宿)」の意では、「やどり」を用いた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やどり [宿り] | 〔名詞〕[四段動詞「宿る」の連用形から] ① 旅先で、宿泊すること。また、その場所。 ② すまい。家。③ とどまる所。また、とどまること。 |
① 草枕旅の宿りに誰が嬬か国忘れたる家待たまくに(万3-429) ① 海人娘女棚なし小舟漕ぎ出らし旅の宿りに楫の音聞こゆ(万6-935) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やどる [宿る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 旅先で泊る。宿泊する。② 住む。仮の住みかとする。③ とどまる。 ④ 映る。⑤ 寄生する。 |
① 安騎の野に宿る旅人うち靡き寐も寝らめやもいにしへ思ふに(万1-46) ④ あひにあひて物思ふころの我が袖にやどる月さへぬるるかほなる (古今恋五-756) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やな [梁・簗] | 〔名詞〕 川の瀬などに杭を打ち並べ、一か所だけ水が流れるようにあけて、そこに斜めに簀を敷いて流れ込む魚を捕らえる仕掛け。 |
この夕柘の小枝の流れ来ば梁は打たずて取らずかもあらむ(万3-389) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -うつ [梁打つ] | 杭を打って「梁」 を構え作る。 | いにしへに梁打つ人のなかりせばここにもあらまし柘の枝はも(万3-390) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やはす [和す] | 〔他動詞サ行四段〕和らげる。平和にさせる。服従させる。 | -御いくさを 召したまひて ちはやぶる 人を和せと 奉ろはぬ-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やへ [八重] | 〔名詞〕 八つに重なっていること。転じて幾重にも重なっていること。 また、そのようなもの。 |
-天雲の 八重かき別けて [一云 天雲の八重雲別けて] -(万2-167) 白雲の八重に重なる遠(をち) にても思はむ人に心へだつな(古今離別8-380) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やへぐも [八重雲] | 〔名詞〕幾重にも重なってわき立つ雲。八重棚雲(たなぐも)。 | -天雲の 八重かき別けて [一云 天雲の八重雲別けて] -(万2-167) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やべのさか [屋部坂] | 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集 『付録 地名一覧』」】 香久山の東部にあった坂の名か。その他に、奈良県磯城郡田原本町矢部(近鉄京都線笠縫駅西方)や奈良市西北部、秋篠寺のある一帯に擬する説もある。 『日本後紀』大同元年の条の「大宮に直に向かへる山部の坂」(霊異記下卅三十八話にも)の山部と関係があるか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やほよろづ [八百万] | 〔名詞〕きわめて数の多いこと | -天の河原に 八百万 千万神の 神集ひ 集ひいまして 神分り-(万2-167) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やま [山] | 〔名詞〕 ① 山。山岳。② 比叡山。また、そこにある延暦寺の称。 ③ 山の形に作ったもの。築山(つきやま)。 ④ 多く積み重なっていること。また、そのもの。 ⑤ 仰ぐべきもの。ゆるぎのない高いもの。頼りとするもの。 また、目標とするもの。 ⑥ 陵。山陵。墓。⑦ 物事の絶頂。物事のもっとも重要なところ。 ⑨「山鉾(やまぼこ)」の略。 |
① み吉野の山のあらしの寒けくにはたや今夜も我が独り寝む(万1-74) ① あしひきの山のしづくに妹待つと我れ立ち濡れぬ山のしづくに(万2-107) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまかげ [山影・山陰] | 〔名詞〕山の陰になること。」また、そのところ。 | 吉野なる夏実の川の川淀に鴨そ鳴くなる山影にして(万3-378) 春されば木の暗多み夕月夜おほつかなしも山蔭にして [一云 春されば木蔭を多み夕月夜](万10-1879) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまかは [山川] | 〔名詞〕山と川。また、山の神と川の神。 | 山川も依りて仕ふる神ながらたぎつ河内に舟出せすかも(万1-39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまごし [山越し] | 〔名詞〕① 山を越えること。② 山を越えた向こう側。 | 朝日影にほへる山に照る月の飽かざる君を山越しに置きて(万4-498) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまさぶ [山さぶ] | 〔自動詞バ行上二段〕【ビ・ビ・ブ・ブル・ブレ・ビヨ】 [「さぶ」は接尾語] 山が古びて、神々しいさまである。いかにも山らしい姿である。 |
-畝傍の この瑞山は 日の緯の 大御門に 瑞山と 山さびいます-(万1-52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やましな [山科] | 〔地名〕「山階」とも書く。 今の京都市東部の地名。京都から東国へ通じる門戸にあたる。 |
やすみしし 我ご大君の 畏きや 御陵仕ふる 山科の 鏡の山に ―(万2-155) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やました(やまもと) [山下 (山本)] | 〔名詞〕 山の下の方。山のふもと。また、山の茂みの下陰。 |
旅にしてもの恋しきに山下の赤のそほ船沖を漕ぐ見ゆ(万3-272) 秋萩にうらびれをれば あしひきの山したとよみ鹿のなくらん(古今秋上-216) 見わたせば山もとかすむ水無瀬川夕べは秋となにおもひけむ(新古今春上-36) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やましろ [山城・山背] | 〔地名〕旧国名。畿内五か国の一つ。今の京都府南部。 古くは「山背」「山代」と書いたが、桓武天皇の遷都のおり「山城」と改められた。 城州(じょうしゅう)。 |
早来ても見てましものを山背の高の槻群散りにけるかも(万3-280) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やますげ [山菅] | 〔名詞〕[「やますが」とも] ① 野生の菅(すげ)。② やぶらん(=野草ノ名) の古名。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やますげの [山菅の] | 【枕詞】 同音から「やまず」、葉の状態から「乱る・背向(そがひ)」、 山菅の実の意から「実」にかかる。 |
山菅のやまずて君を思へかも我が心どのこの頃はなき(万12-3069) 山菅の乱れ恋のみせしめつつ逢はぬ妹かも年は経につつ(万11-2478) 愛し妹をいづち行かめと山菅のそがひに寝しく今し悔しも(万14-3599) 山菅の実ならぬことを我に寄そり言はれし君は誰とか寝らむ(万4-567) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまたづ [山たづ・接骨木] | 「接骨木・庭常」(にはとこ)の古名。 落葉低木の名。四月ころ、白い花を開く。茎・葉・花は薬用となる。 接骨木の花。春 |
山たづと言へるは今の造木 (みやつこぎ) なり(記下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまたづの [山たづの] | 【枕詞】 「迎へ」に懸かる |
君が行き日長くなりぬ山たづの迎へを行かむ待つには待たじ(万2-90) -桜花 咲きなむ時に 山たづの 迎へ参ゐ出む 君が来まさば(万6-976) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまぢ [山路・山道] | 〔名詞〕 山の道。山道。 |
秋山の黄葉を茂み惑ひぬる妹を求めむ山道知らずも [一云 路知らずして](万2-208) 朝霧に濡れにし衣干さずしてひとりか君が山道越ゆらむ(万9-1670) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまつみ [山神・山祇] | 〔名詞〕[「つ」は「の」の意の上代の格助詞] 国津神の代表格。 山の神。山の霊。山を治めつかさどる神。 |
-たたなはる 青垣山 山神の 奉る御調と 春へは 花かざし持ち-(万1-38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまと [大和・倭] | 〔名詞〕 ① [地名] 旧国名。「畿内」五ヶ国の一つ。今の奈良県。倭州 (わしゆう) 。 ② 平安遷都まで歴代天皇の都があったところから、日本国の称。 やまとの国。 |
妹が家も継ぎて見ましを大和なる大島の嶺に家もあらましを [一云 妹があたり継ぎても見むに] [一云 家居らましを](万2-91) ① 大和には 群山あれど とりよろふ 天の香具山 登り立ち-(万1-2) ① これやこの大和にしては我が恋ふる紀路にありといふ名に負ふ背の山 (万1-35) ② いざ子ども早く日本へ大伴の御津の浜松待ち恋ひぬらむ(万1-63) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまとしま [大和島] | 〔名詞〕 (海上から島のように見えることから) 大和の国(奈良県)の山々。 大和の国を中心とした地域。「大和島根」とも。 |
天離る鄙の長道ゆ恋ひ来れば明石の門より大和島見ゆ [一本云 家のあたり見ゆ](万3-256) 名ぐはしき印南の海の沖つ波千重に隠りぬ大和島根は(万3-306) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまとしまね [大和島根] | 〔名詞〕 ① 日本国。② 「やまとしま」 に同じ。 |
-海神の 手に巻かしたる 玉だすき かけて偲ひつ 大和島根を(万3-369) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまとぢ [大和路・大和道] | 〔名詞〕 大和へ向かう道。 |
大和道の島の浦廻に寄する波間もなけむ我が恋ひまくは(万4-554) 大和道の吉備の児島を過ぎて行かば筑紫の児島思ほえむかも(万6-972) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまのあらし [山の嵐] | 〔名詞〕峰から吹きおろす風。 |
み吉野の山のあらしの寒けくにはたや今夜も我が独り寝む(万1-74) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまのしづく [山の雫] | 山中の樹木などからしたたり落ちる水滴。 「記紀歌謡」には見えず、「万葉集」でも、大津皇子と石川郎女との贈答歌にしか見えない。 |
あしひきの山のしづくに妹待つと我れ立ち濡れぬ山のしづくに(万2-107) 我を待つと君が濡れけむあしひきの山のしづくにならましものを(万2-108) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまのは [山の端] | 山を遠く眺めた時、山の上部の空に接する境目あたり。稜線。 | 見えずとも誰恋ひざらめ山の端にいさよふ月を外に見てしか(万3-396) あかなくにまだきも月のかくるるか山の端にげて入れずもあらなん (古今雑上-884) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまのま [山の際] | -あをによし 奈良の山の 山の際に い隠るまで-(万1-17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻第一-17」注】 「際 (ま)」は間。ほとり、境いなどの意をあてうる場合もある。 【小学館「新編日本古典文学万葉集巻第一-17番 頭注」】 山と山とが重なって見える部分。原文「山際」の「際」は、交わるの意。古本『玉篇』に「交会之間也」とある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまのまゆ [山の間ゆ] | 【枕詞】山の間から出るの意で、「出(い)づ」と同音の地名「出雲」にかかる。 | 山の際ゆ出雲の児らは霧なれや吉野の山の嶺にたなびく(万3-432) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまぶき [山吹] | 〔名詞〕 ① 植物の名。落葉小低木。晩春に黄色の花を開く。春 ② 襲(かさね)の色目の名。表は朽ち葉(=赤みをおびた黄色)、裏は黄色。 春に用いる。 ③ 「山吹色」の略。 |
① 山吹の立ちよそひたる山清水汲みに行かめど道の知らなく (万2-158) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまべ [山辺] | 〔名詞〕 山のほとり。「山の辺」とも。 |
山辺の御井を見がてり神風の伊勢娘子どもあひ見つるかも(万1-81) 春日野の山辺の道をおそりなく通ひし君が見えぬころかも(万4-521) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまみち [山道] | 〔名詞〕 ① 山中の道。山の道。 ② 仏道修行のため、山中の寺などに行く道。また、出家を志して行く道。 |
① -その雨の 間なきがごと 隈もおちず 思ひつつぞ来し その山道を(万1-25) ① -まして恋しみ 雪消する 山道すらを なづみぞ我が来る(万3-385) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やまもり [山守] | 〔名詞〕山を守る事。またその人。 | 山守がありける知らにその山に標結ひ立てて結ひの恥しつ(万3-404) 大君の境ひたまふと山守据ゑ守るといふ山に入らずはやまじ(万6-955) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やむ [止む] | 〔自動詞マ行四段〕 ① 続いていたものが、終りになる。止る。絶える。 ② 物事が中止になる。途中で行われなくなる。 ③ 病気が治る。苦痛や怒りなどが収まる。 ④ 命が終る。死ぬ。 |
① 秋の田の穂の上に霧らふ朝霞いつへの方に我が恋やまむ(万2-88) ① -絶ゆることなく ありつつも 止まず通はむ 明日香の 古き都は-(万3-327) ① 千鳥鳴く佐保の川瀬のさざれ波止む時もなし我が恋ふらくは(万4-529) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞マ行下二段〕【メ・メ・ム・ムル・ムレ・メヨ】 ① 続いていたことを、終りにする。やめる。 ② 病気や癖などを治す。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やむ [病む] | 〔自動詞マ行四段〕 病気になる。わずらう。 |
古人の飲へしめたる吉備の酒病まばすべなし貫簀賜らむ(万4-557) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞マ行四段〕 ① 病気におかされる。 ② 心配する。心を痛める。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やも | 《上代語》 〔係助詞〕係助詞「や」に係助詞「も」が付いたもの。 ① 反語の意を表す。~であろう(か)いや~ない。 ② 疑問の意を表す。~だろうか。~か。 〔接続〕種々の語につく。 |
① 士やも空しくあるべき万代に語り継ぐべき名は立てずして(万6-983) ② ここにして家やもいづち白雲のたなびく山を越えて来にけり(万3-290) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やも | 《上代語》 〔終助詞〕係助詞「や」に終助詞「も」が付いたもの。 ① 反語の意を表す。~であろう(か)いや~ない。 ② 疑問の意を表す。~か。 〔接続〕活用語の終止形・已然形に付く。 ①の反語の場合は、已然形につく。 |
① 楽浪の志賀の [一云 比良の] 大わだ淀むとも昔の人にまたも逢はめやも [一云 逢はむと思へや](万1-31) ② こもりくの泊瀬娘子が手に巻ける玉は乱れてありと言はずやも(万3-427) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やや [稍・漸] | 〔副詞〕 ① 物事が少しずつ進行することを示す語。 しだいに。だんだんと。ようやく。 ② 物事の程度をいう語。大小・長短・上下などのどれにもいう。 いくらか。少し。 |
② 児らが家道やや間遠きをぬばたまの夜渡る月に競ひあへむかも(万3-305) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やる [遣る] | 〔他動詞ラ行四段〕 ① 行かせる。進ませる。② 送る。届ける。 ③ 不快な気持ちを晴らす。なぐさめる。④ 逃がす。⑤ 導き入れる。 ⑥ 与える。取らせる。金を払う。 |
① 我が背子を大和へ遣るとさ夜更けて暁露に我が立ち濡れし(万2-105) ① うちひさす宮に行く子をまかなしみ留むれば苦し遣ればすべなし(万4-535) ③ 夜光る玉といふとも酒飲みて心を遣るにあに及かめやも(万3-349) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔補助動詞ラ行四段〕(動詞の連用形の下に付いて) ① その動作が遠くまで及ぼすことを表す。遠く~する。 ②(多く、下に打消の語を伴って)その動作を完全に行う意。 「すっかり~する。~しきる」 |
〔参考〕「やる」がこちらからあちらに動作が及ぶのに対し、あちらからこちらへ動作が及ぶ意を表す語に「おこす」がある。⇒「遣 (おこ) す」 ② -問はむ答へを 言ひ遣らむ すべを知らにと 立ちてつまづく(万4-546) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔参考〕「やる」がこちらからあちらに動作が及ぶのに対し、あちらからこちらへ動作が及ぶ意を表す語に「おこす」がある。⇒「遣 (おこ) す」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆ | 〔上代語、助動詞ヤ行下二型〕【エ・エ・ユ・ユル・ユレ・○】 ① 受身 「~れる」 ② 可能 「~ことができる」 ③ 自発 「自然に~れる」 〔接続〕四段・ナ変・ラ変動詞の未然形に付く |
① -か行けば 人に厭はえ かく行けば 人に憎まえ-(万5-808) ② 明日香川明日だに [さへ] 見むと思へやも [思へかも] 我が大君の御名忘れせぬ [御名忘らえぬ](万2-198) ② 堀江越え遠き里まで送り来る君が心は忘らゆましじ(万20-4506) ③ 一日こそ人も待ち良き長き日をかくし待たえばありかつましじ(万4-487) ③ 天離る鄙に五年住まひつつ都のてぶり忘らえにけり(万5-884) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔参考〕 「ゆ」は上代では「る」よりは用例が多く「る」より古い。中古になると「る」にとってかわられ、わずかに「聞こゆ・おぼゆ・あらゆる・いはゆる」などの語の一部分として残るだけとなる。 また「ゆ」が「思ふ・聞く」などに付く場合に、「思ほゆ・聞こゆ」などのように、未然形のア段音がオ段音になることがあり、一語の動詞として扱う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆ | 〔上代語、格助詞〕 ① 起点(動作の時間的・空間的な) 「~から・~以来」 ② 経由点(移動する動作の) 「~から・~を通って」 ③ 手段(動作の) 「~で・~によって」 ④ 比較の基準 「~よりも」 〔参考〕 同義の助詞に「ゆり・よ・より」があるが用例が少なく意味の違いは不詳。 「ゆ」が最も古く、中古に入ると「より」だけが用いられた。 |
① -奈良の都の 佐保川に い行き至りて 我が寝たる 衣の上ゆ-(万1-79) ① 天地の 別れし時ゆ 神さびて-(万3-320) ① 玉たすき 畝傍の山の 橿原の ひじりの御代ゆ-(万1-29) ② -渡会の 斎きの宮ゆ 神風に い吹き惑はし 天雲を 日の目も見せず-(万2-199) ② -継ぎきたる 那珂の港ゆ 船浮けて 我が漕ぎ来れば 時つ風-(万2-220) ② 三笠山野辺ゆ行く道こきだくも荒れにけるかも久にあらなくに(万2-234) ② 芦北の野坂の浦ゆ船出して水島に行かむ波立つなゆめ(万3-247) ② 天離る鄙の長道ゆ恋ひ来れば明石の門より大和島見ゆ [一本云 家のあたり見ゆ](万3-256) ② 田子の浦ゆうち出でて見れば真白にぞ富士の高嶺に雪は降りける(万20-4506) ③ 小筑波の茂き木の間よ立つ鳥の目ゆか汝を見むさ寝ざらなくに (万14-3414) ④ 人言はしましぞ我妹綱手引く海ゆまさりて深くしぞ思ふ(万11-2442) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆ [湯] | 〔名詞〕 ① 水を温めたもの。湯。 ② 入浴。湯浴みをすること。また、その場所。 ③ 温泉。いで湯。④ 薬湯。薬を煎じた湯。 ⑤ (忌み詞として)船中に浸み入ってたまった水。船湯。あか。 |
① さし鍋に湯沸かせ子ども櫟津の桧橋より来む狐に浴むさむ(万16-3846) ③ 神の命の 敷きいます 国のことごと 湯はしも さはにあれども -(万3-325) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆき [雪] | 〔名詞〕 ① 寒い日に空から降る白く柔らかい固まり。雪。 ② 白い色。また、白い物のたとえ。特に白髪。 ③ 紋所の名。「①」の結晶を図案化したもの。 |
① 新しき年の初めの初春の今日降る雪のいやしけ吉事(万20-4540) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆき [行き] | 〔名詞〕行くこと。進むこと。また、旅。 | 君が行き日長くなりぬ山尋ね迎へか行かむ待ちにか待たむ(万2-85) 我が行きは久にはあらじ夢のわだ瀬にはならずて淵にもありこそ(万3-338) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆぎ [靫] | 〔名詞〕[上代は「ゆき」] 矢を入れて背に負う武具。後世の箙(えびら)・胡簶(やなぐい)の類。 |
-梓弓 靫取り負ひて 天地と いや遠長に 万代に かくしもがもと-(万3-481) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆきあふ [行き合ふ・行き逢ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕偶然に出会う。出くわす。 | 玉桙の道に行き逢ひて外目にも見ればよき子をいつとか待たむ(万12-2958) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 交差させる。並び連ねる。 |
まなばしら(=セキレイ) 尾ゆきあへ-(記・下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆきかよふ [行き通ふ] | 〔自動詞カ行四段〕行き来する。通って行く。 |
-ひさかたの 天伝ひ来る 雪じもの 行き通ひつつ いや常世まで(万3-263) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆきく [行き来・往き来] | 〔自動詞カ変〕【コ・キ・ク・クル・クレ・コ(コヨ)】 行ったり来たりする。往来する。 |
あさもよし紀人羨しも真土山行き来と見らむ紀人羨しも(万1-55) 芦屋の菟原娘子の奥城を行き来と見れば哭のみし泣かゆ(万9-1814) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆきげ [雪消・雪解] | 〔名詞・自動詞サ行変格〕[「雪消(ぎ)え」の意] ① 雪解け。また、その時・所。② 雪解けの水。 |
① -まして恋しみ 雪消する 山道すらを なづみぞ我が来る(万3-385) ② -射水川 雪消溢りて 行く水の いや増しにのみ 鶴が鳴く-(万18-4140) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆきじもの [雪じもの] | 〔副詞〕[「じもの」は、~のようなものの意の接尾語] 雪のように。雪めいて。一説に、「雪」にかかる枕詞とも。 |
-ひさかたの 天伝ひ来る 雪じもの 行き通ひつつ いや常世まで(万3-263) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆきすぐ [行き過ぐ] | 〔自動詞ガ行上二段〕【ギ・ギ・グ・グル・グレ・ギヨ】 とどまらずに行き過ぎる。通過する。 |
稲日野も行き過ぎかてに思へれば心恋しき加古の島見ゆ [一云 水門見ゆ](万3-254) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆきはばかる [行き憚る] | 〔自動詞ラ行四段〕 阻まれて行くことが難しい。 |
み吉野の高城の山に白雲は行きはばかりてたなびけり見ゆ(万3-356) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆきみる [行き廻る] | 〔自動詞マ行上一段〕【ミ・ミ・ミル・ミル・ミレ・ミヨ】 巡って行く。 |
軽の池の浦廻行き廻る鴨すらに玉藻の上にひとり寝なくに(万3-393) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆく [行く・往く] | 〔自動詞カ行四段〕 ① 進み行く。通り行く。② 通り過ぎる。通過する。③ 去る。立ち退く。 ④ 年月が過ぎ去る。時が移り行く。⑤ 雲や水が流れ行く。流れ去る。 ⑥ 死ぬ。逝去する。⑦ 満足する。心が晴れる。 ⑧〔助動詞の連用形の下に付いて〕その動作が継続し進行する意を表す。 「いつまでも~し続ける。ずっと~する。だんだん~てゆく。」 |
ひさかたの天行く月を網に刺し我が大君は蓋にせり(万3-241) ① 梅の花咲き散る園に我れ行かむ君が使を片待ちがてら(万18-4065) ② 敷栲の袖交へし君玉垂の越智野過ぎ行くまたも逢はめやも [一云 越智野に過ぎぬ](万2-195) ② 稲日野も行き過ぎかてに思へれば心恋しき加古の島見ゆ [一云 水門見ゆ](万3-254) ② 明日の日はその門行かむ出でて見よ恋ひたる姿あまたしるけむ (万12-2960) ③ 嶋の宮上の池なる放ち鳥荒びな行きそ君いまさずとも(万2-172) ③ 衾道を引手の山に妹を置きて山道を行けば生けりともなし(万2-212) ③ 春かすみ立つを見捨ててゆく雁は花なき里に住みやならへる (古今春上-31) ④ 君が行き日長くなりぬ山たづの迎へを行かむ待つには待たじ(万2-90) [「④」は、「行く」の連用形で、「名詞法」となり、「旅」の意を持つ] ⑤ 秋山の木の下隠り行く水の我れこそ益さめ思ほすよりは(万2-92) ⑤ 吉野川行く瀬の早みしましくも淀むことなくありこせぬかも(万2-119) ⑥ 朝ぐもり日の入り行けばみ立たしの島に下り居て嘆きつるかも(万2-188) ⑧ 黄葉の散りゆくなへに玉梓の使を見れば逢ひし日思ほゆ(万2-209) ⑧ -祖の名も 継ぎ行くものと 母父に 妻に子どもに 語らひて-(万3-446) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆくさ [行くさ] | 〔名詞〕[「さ」は時・折を表す接尾語] 行くとき。行きしな。→ 来(く)さ・帰へるさ |
行くさには二人我が見しこの崎をひとり過ぐれば心悲しも [一に云ふ 見もさかず来ぬ](万3-453) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆくさくさ [行くさ来さ] | 行く時と来る時と。行き帰り。 | 白菅の真野の榛原行くさ来さ君こそ見らめ真野の榛原(万3-284) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻三-281 注『行くさ来さ』」】 サは元来、時間空間を通じてその方向をさす(講義)。 空間の「マ」をつけてサマ(様) となり、分量のダをつけてサダ(時間) となり、「a」と「i」との交替でシともなるから、シマ・シダの語もできる。シダは「帰りシナ、行きシナ」に通じる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆくとりの [行く鳥の] | 【枕詞】 飛んで行く鳥が先を争うことから「争ふ」に、また、群れをなして飛ぶことから「群がる」にかかる。 |
-立ち向ひしも 露霜の 消なば消ぬべく 行く鳥の 争ふはしに-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆくへ [行方] | 〔名詞〕 ① 進んで行く先。行くべき方向。また、行った先。 ② 将来。なりゆき。 |
② -日月の 数多くなりぬれ そこ故に 皇子の宮人 ゆくへ知らずも-(万2-167) ② 埴安の池の堤の隠り沼のゆくへを知らに舎人は惑ふ (万2-201) ② あまたあらぬ名をしも惜しみ埋れ木の下ゆぞ恋ふるゆくへ知らずて(万11-2732) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆくゆく(と) | 〔副詞〕 ① 心の苦しみが深まるさま。遠慮のないさま。 ③ 程度の進むさま。ずんずん。どんどん。 |
① 丹生の川瀬は渡らずてゆくゆくと恋痛し我が背いで通ひ来ね(万2-130) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆずゑ [弓末・弓上] | 〔名詞〕弓の上端。 | ますらをの弓末振り起し射つる矢を後見む人は語り継ぐがね(万3-367) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆたけし [豊けし] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 ① 豊かである。富栄えている。盛大である。 ② 余裕がある。ゆったりしている。広々としている。 |
② 廬原の清見の崎の三保の浦のゆたけき見つつ物思ひもなし(万3-299) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆつ | 〔接頭語〕「斎」の意。神聖、清浄の意を表わす。植物に冠する事が多い。 (一説には数の多いとする) 「ゆついはむら」「ゆつかつら」「ゆつつまぐし」「ゆつまつばき」 |
川の上のゆつ岩群に草生さず常にもがもな常処女にて(万1-22) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆづりは [弓弦葉・交譲木] | 〔名詞〕「ゆづるは」とも。 木の名。新しい葉が生長してから古い葉が落ちるのでこの名がある。 葉は新年のしめ縄や供え餅に添えて飾るのに用いる。[春] |
いにしへに恋ふる鳥かも弓絃葉の御井の上より鳴き渡り行く(万2-111) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆはず [弓筈・弓弭] | 〔名詞〕《「ゆみはず」 とも》 弓の両端の弓弦(ゆみづる) をかける部分。 |
-風の共 靡かふごとく 取り持てる 弓弭の騒き み雪降る-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆひ [結ひ] | 〔名詞〕 ① 結うこと。標(=しめ/標識)を結うこと。 ② 田植えなどのとき、互いに手伝い合うこと。また、その人々。 |
山守がありける知らにその山に標結ひ立てて結ひの恥しつ(万3-404) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆふ [夕] | 〔名詞〕夕暮れの頃。夕方。 【参考】 「ゆふ」は多く複合語として用いられ、単独には「ゆふべ」が使われた。 |
真土山夕越え行きて廬前の角太川原にひとりかも寝む(万3-301) -梓弓 手に取り持ちて 剣大刀 腰に取り佩き 朝守り 夕の守りに-(万18-4118) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆふ [木綿] | 〔名詞〕 楮の皮の繊維を蒸して水でさらし、細かく裂いて糸状にしたもの。 幣として榊などにかけた。 |
三輪山の山辺真麻木綿短か木綿かくのみからに長くと思ひき(万2-157) -取り持てる 弓弭の騒き み雪降る 冬の林に [一云 木綿の林] -(万2-199) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆふ [結ふ] | 〔他動詞ハ行四段〕 ① ゆわえる。むすぶ。しばる。 ② 髪を整える。③ 作り構える。組み立てる。 ④ 糸などでつづる。つくろう。 |
① かからむとかねて知りせば大御船泊てし泊りに標結はましを (万2-151) ② 嘆きつつますらをのこの恋ふれこそ我が結ふ髪の漬ちてぬれけれ (万2-118) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考「ゆふ」と「むすぶ」との違い】 「ゆふ」も「むすぶ」も紐状のものを組み合わせてつなげる意味では共通するが、「むすぶ」は離れているものを寄せ合わせてつなげる、つないで固定する意が強く、「ゆふ」は組み合わせて作り上げる、作り整える意味が強い。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆふかり [夕狩り] | 〔名詞〕(「ゆふがり」とも) 夕方の狩り。 | -朝猟に 今立たすらし 夕猟に 今立たすらし み執らしの 梓の弓の-(万1-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆふぎり [夕霧] | 〔名詞〕 夕方立ち込める霧。〔対義語:朝霧〕 |
-玉裳はひづち 夕霧に 衣は濡れて 草枕 旅寝かもする 逢はぬ君故-(万2-194) -思ひ恋ふらむ 時ならず 過ぎにし子らが 朝露のごと 夕霧のごと(万2-217) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆふけ [夕占] | 〔名詞〕(= ゆふうら) 夕方道端に立って往来の人の言葉を聞いて、吉凶を占うこと。また、その占い。 |
-杖つきも つかずも行きて 夕占問ひ 石占もちて 我がやどに-(万3-423) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆふさる [夕さる] | 〔自動詞ラ行四段〕 夕方になる。夕べが来る。 |
-玉限る 夕去り来れば み雪降る 安騎の大野に 旗すすき-(万1-45) 夕さらば潮満ち来なむ住吉の浅香の浦に玉藻刈りてな(万2-121) 夕されば小倉の山に鳴く鹿は今夜は鳴かず寐ねにけらしも(万8-1515) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【「さる」という動詞】 四段動詞「さる」は移動することで、「行く」意にも「来る」意にも用いる。 「来る」意のときは季節や時を示す語につき、「夕されば」「春されば」「秋されば」など、「已然形+ば」の形となることが多い。 また「来」と重ねて「春さり来れば」と用いることもある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆふだすき [木綿襷] | 〔名詞〕「木綿(ゆふ)」で作ったたすき。神事に用いる。 | -竹玉を 間なく貫き垂れ 木綿だすき かひなに掛けて-(万3-423) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【枕詞】 たすきは掛けて結ぶことから、「掛く」「結ぶ」 などにかかる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆふたたみ [木綿畳] | 〔名詞〕「木綿(ゆふ)」 をたたんだもの。神事に用いる。 | 木綿畳手に取り持ちてかくだにも我れは祈ひなむ君に逢はじかも(万3-383) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆふたたみ [木綿畳] | 【枕詞】 「木綿畳」を神に手向けるところから「手向け」 に、 また「手(て)」 と同音を含む地名「田上(たなかみ)」 にかかる。 |
木綿畳手向けの山を今日越えていづれの野辺に廬りせむ我れ(万6-1022) 木綿畳田上山のさな葛ありさりてしも今ならずとも(万12-3084) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆふづつの [長庚の・夕星の] | 【枕詞】 「ゆふづつ」 の空を渡るさまから「か行きかく行き」 に、 また、「ゆふづつ」 の現れる時刻から「夕べ」 にかかる。 |
-夏草の 思ひしなえて 夕星の か行きかく行き 大船の-(万2-196) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆふなぎ [夕凪] | 〔名詞〕夕方、海辺でしばらく風が吹きやむこと。 | -朝なぎに 水手の声呼び 夕なぎに 楫の音しつつ 波の上を-(万4-512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆふなみちどり [夕波千鳥] | 〔名詞〕 夕方、打ち寄せる波の上を群れ飛ぶ千鳥。 |
近江の海夕波千鳥汝が鳴けば心もしのにいにしへ思ほゆ(万3-268) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆふはな [木綿花] | 〔名詞〕 「木綿(ゆふ)」 の白さを花に見立てたものとも、その木綿で作った造花ともいう。 |
泊瀬女の造る木綿花み吉野の滝の水沫に咲きにけらずや(万6-917) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆふはなの [木綿花の] | 【枕詞】 木綿花は枯れないでいつまでも白く美しく栄える意から、 「栄(さか)ゆ」にかかる。 |
-木綿花の 栄ゆる時に 我が大君 皇子の御門を-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆふはふる [夕羽振る] | 夕方、鳥が羽ばたくように風や波が立つ。⇔ 「朝羽振る」 | -玉藻沖つ藻 朝羽振る 風こそ寄せめ 夕羽振る 波こそ来寄れ-(万2-131) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆふべ [夕べ] | 〔名詞〕上代は「ゆふへ」夕方・宵・暮れ方。⇔ 朝(あした) 「ゆふべ」は、一日を昼と夜に分けたときの、夜の時間の始まりで、「ゆふべ→よひ→よなか→あかつき→あけぼの→あした(朝)と続く。 「ゆふ」が「朝夕(あさゆふ)」「夕さりつ方」「夕されば」など、多く複合語中に用いられるのに対して、「ゆふべ」は単独で用いられる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆふやみ [夕闇] | 〔名詞〕陰暦二十日前後の、夕方まだ月が出なくて暗いころ。また、その時刻。 | -あしひきの 山辺をさして 夕闇と 隠りましぬれ 言はむすべ-(万3-463) 夕闇は道たづたづし月待ちて行ませ我が背子その間にも見む(万4-712) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆみとり [弓取り] | 〔名詞〕 ① 弓を手に取ること。弓を用いること。また、弓を射る人。 ② 弓術の上手なこと。また、その人。③ 武士。 |
① -任けたまへば 大御身に 大刀取り佩かし 大御手に 弓取り持たし-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆめ [努・勤] | 〔副詞〕 (禁止・打消しの語と呼応して) 強く禁止する意を表す。 決して。かならず。 つとめて。 |
我妹子を早見浜風大和なる我れ松椿吹かざるなゆめ(万1-73) 芦北の野坂の浦ゆ船出して水島に行かむ波立つなゆめ(万3-247) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆゆし [由由し・忌忌し] | 〔形容詞シク活用〕【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 ① (神聖で) 恐れ多い。慎まれる。② 不吉だ。忌まわしい。 ③ 素晴らしい。立派だ。④ ひどい。恐ろしい。⑤ はなはだしい。並々でない。 |
② ひとり寝て絶えにし紐をゆゆしみと為むすべ知らに音のみしそ泣く(万4-518) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【語誌語感】 名詞「斎(ゆ)」を重ねて形容詞化した語。 神聖なものは触れてはならない、美しすぎるものは、かえって不吉だ、といった心情から、「恐れ多い」「忌まわしい」などの意が生まれた。 中古以降は、良くも悪くも、単に程度が普通でないさまを表すようになった。「すばらしい」のか「ひどい」のか、文脈によって判断しなければならない。 連用形「ゆゆしく」は、程度のはなはだしさのみをいうことが多い。 用例の「ミ語法+ト」 は、~であるからとて、の意であるが、実際には「ト」は単に語調を整えるための働きが多い。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆゑ [故] | 〔名詞〕 ① 原因・理由・事情・わけ。② 趣・風情。③ 由緒・来歴・身分。 ④ 故障・さしつかえ。⑤ 縁故・縁。 ⑥ (体言、または用言の連体形の下に付いて) ア:順接的に原因・理由を表す。 「~のために・~が原因で・~によって」 イ:逆説的に原因・理由を表す。 「~なのに・~に関わらず・~のに」 |
⑥「ア」大船の泊つる泊りのたゆたひに物思ひ痩せぬ人の子故に(万2-122) ⑥「ア」我妹子がやどの橘いと近く植ゑてし故に成らずは止まじ(万3-414) ⑥「イ」紫のにほへる妹を憎くあらば人妻故に我れ恋ひめやも(万1-21) ⑥「イ」-夕霧に 衣は濡れて 草枕 旅寝かもする 逢はぬ君故-(万2-194) ⑥「イ」ひさかたの天知らしぬる君故に日月も知らず恋ひわたるかも (万2-200) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よ | 〔格助詞〕《上代語》 ① 動作・作用の時間的・空間的な起点を表す。「~から」 ② 動作・作用の経過する場所を示す。「~より」 ③ 比較の基準を示す。「~より」 ④ 手段・方法を示す。「~で」 〔接続〕体言に準ずるものに付く。[類語] 「ゆ・ゆり・より」がある。 |
① 天地の 遠き初めよ 世間は 常なきものと 語り継ぎ -(万19-4184) ① 我が背子を安我松原よ見わたせば海人娘子ども玉藻刈る見ゆ(万17-3912) ② さを鹿の伏すや草むら見えずとも子ろが金門よ行かくしえしも (万14-3551) ③ 上つ毛野伊奈良の沼の大藺草外に見しよは今こそまされ(万14-3436) ④ 鈴が音の早馬駅家の堤井の水を給へな妹が直手よ(万14-3458) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よ | 〔間投助詞〕 ① 詠嘆・感動を表す。「~よ」 ② 呼びかけを表す。 ③ 命令の意を強く確かめる。 ④ 強く指示する意を表す。 ⑤ 告示の気持ちを表す。 〔接続〕「③」は動詞・助動詞の命令形に、他は種々の語に付く。 |
① 篭もよ み篭持ち 堀串もよ み堀串持ち この岡に 菜摘ます子- (万1-1) ② -作れる家に 千代までに いませ大君よ 我れも通はむ(万1-79) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔参考〕一段活用・二段活用・カ変・サ変の命令形の活用語尾の一部となる「よ」も、この語から出たとする説がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よ [世・代] | 〔名詞〕[「節 (よ)」と同源で、区切られた期間・範囲の意] ① 人の一生。生涯。② 寿命。年齢。③ 治世の期間。時代。年代。代。 ④ 国を治めること。国政。⑤ ある時期。折。時。 ⑥ 人が集まって生活しているところ。また、そこの人々。世間。世の中。 ⑦ 仏教で説く、前世・現世・来世の三世。特に現世。⑧ 俗世間。浮世。 ⑨ 俗世間での欲望。⑩ 世間のなりゆき。時勢。時流。 ⑪ 身の上。境遇。身分。⑫ 男女の仲。夫婦の仲。⑬ 生活。渡世。実業。 |
① 人言を繁み言痛みおのが世にいまだ渡らぬ朝川渡る(万2-116) ① 立ちしなふ君が姿を忘れずは世の限りにや恋ひわたりなむ (万20-4465) ③ -年は百年(ももとせ) あまり、よは十継ぎになむなりにける (古今仮名序) ⑦ 生ける者遂にも死ぬるものにあればこの世なる間は楽しくをあらな (万3-352) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よ (よる) [夜] | 〔名詞〕日没から日の出までの間。よる。 【参考「よ」と「よる」の違い】 「よ」は「ひ」の対。「よる」は「ひる」の対。「よ」は多く複合語に用いられ、 また「明く」「更(ふ)く」「深し」などの主語として用いられる。 |
「新治筑波を過ぎて幾夜か寝つる日日(かが) 並(な)べてよには九夜(ここのよ)日には十日を」(記中) 流らふる妻吹く風の寒き夜に我が背の君はひとりか寝らむ(万1-59) 我が背子を大和へ遣るとさ夜更けて暁露に我が立ち濡れし(万2-105) 梓弓爪引く夜音の遠音にも君の御幸を聞かくし良しも(万4-534) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よく [良く・善く・能く] | 〔副詞〕形容詞「よし」の連用形「よく」から。「よう」とも。 ① くわしく。十分に。念入りに。②上手に。巧みに。 ③ 普通ではできないことをした場合にいう。「よくまあ」「よくぞ」。 ④ たいそう。非常に甚だしく。⑤ たびたび。ともすると。 |
① 淑き人のよしとよく見てよしと言ひし吉野よく見よ良き人よく見(万1-27) ① あな醜賢しらをすと酒飲まぬ人をよく見ば猿にかも似る(万3-347) ① 難波潟潮干のなごりよく見てむ家なる妹が待ち問はむため(万6-981) ③ よく渡る人は年にもありといふをいつの間にそも我が恋ひにける(万4-526) ④ 我が聞きし耳によく似る葦の末の足ひく我が背つとめ給ぶべし(万2-128) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よごもり [夜籠り] | 〔名詞〕 ① 夜が更けること。深夜。 ② 寺社に参詣し、一晩中こもって祈ること。 |
倉橋の山を高みか夜隠りに出で来る月の光乏しき(万3-293) 倉橋の山を高みか夜隠りに出で来る月の光乏しき(万9-1767) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よし [由・因] | 〔名詞〕[四段動詞「寄す」の連用形から。近づけ、関係づける物事の意] ① 物事のいわれ。由緒。由来。② 理由。わけ。③ 手段・方法。 ④ 趣。風流。優雅。奥ゆかしさ。⑤ 話しのおおむね。次第。趣旨。 ⑥ 縁。ゆかり。⑦ そぶり。ようす。 |
③ -せむすべ知らに 恋ふれども 逢ふよしをなみ 大鳥の-(万2-210) ③ 遠き山関も越え来ぬ今さらに逢ふべきよしのなきが寂しさ [一云 さびしさ](万15-3756) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よし [葦・蘆・葭] | 〔名詞〕「あし(葦)」に同じ。 「あし」の音が「悪(あ)し」に通じるのを嫌って言ったもの。→「あし」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よし [好し・良し・善し] | 〔形容詞ク活用〕【カラ・ク(カリ)・シ・キ(カル)・ケレ・カレ】 [本質的によいさま。最高度にすぐれているさま。 対象によって「①」から「⑨」の訳になる。「⑩」は補助形容詞。] ① 優れている。価値がある。よい。 ②(こころが)正しい。善良である。③ 美しい。きれいだ。 ④ 身分が高い。教養があり、上品である。⑤ 快い。楽しい。好ましい。 ⑥ 上手である。巧みである。 ⑦ 道理にかなって適切である。相応しい。好都合だ。 ⑧ めでたい。縁起がよい。⑨ 効果がある。効き目がある。 ⑩(動詞連用形の下に付いて)「~しやすい。」 |
① 飼飯の海の庭良くあらし刈り薦の乱れて出づ見ゆ海人の釣船(万3-257) ① 天の原振り放け見れば白真弓張りてかけたり夜道は良けむ(万3-292) ③ 淑き人のよしとよく見てよしと言ひし吉野よく見よ良き人よく見(万1-27) ③ 月夜よし川の音清しいざここに行くも行かぬも遊びて行かむ(万4-574) ④ 淑き人のよしとよく見てよしと言ひし吉野よく見よ良き人よく見(万1-27) ⑤ 梓弓爪引く夜音の遠音にも君の御幸を聞かくし良しも(万4-534) ⑤ 梅の花散らすあらしの音のみに聞きし我妹を見らくしよしも(万8-1664) ⑨ 周防なる磐国山を越えむ日は手向けよくせよ荒しその道(万4-570) ⑩ 一日こそ人も待ち良き長き日をかくし待たえばありかつましじ(万4-487) ⑩山里はもののわびしきことこそあれ世の憂きよりは住みよかりけり (古今雑下-944) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中央公論社「萬葉集注釈巻三-289 『訓釋「よけむ」』」】 「よけむ」は「よし」の未然形に「む」がついたもの。 上代の形容詞は已然形も「見まくほしけど」(二・二〇七) の如く、「け」の形が普通であつたが、未然形にまた「け」の形があつた(一・七四参照)。「け・く・し・き・け」といふ活用である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よし [縦し] | 〔副詞〕 ① (「よし」と言って仮に許す意から) 不満足であるが、仕方がない。 ままよ。どうなろうとも。 ② (下に逆接の仮定条件を伴って) たとえ。仮に。よしんば。万一。 |
① みさご居る荒磯に生ふるなのりそのよし名は告らせ親は知るとも(万3-366) ① 人皆は萩を秋と言ふよし我れは尾花が末を秋とは言はむ(万10-2114) ② 人はよし思ひやむとも玉葛影に見えつつ忘らえぬかも(万2-149) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よしの [吉野] | 〔地名〕 今の奈良県吉野郡吉野町一帯の地。 修験道の霊場があり、桜と南朝の史蹟で知られる。 |
-山川の 清き河内と 御心を 吉野の国の 花散らふ-(万1-36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻第一 36番 吉野」注】 「吉野の国」、「国」は人為によって定めた一定区域。大和 奈良の一部でありながら、とくに「国」と呼ばれる土地は、この吉野と泊瀬と春日と難波とに限られる。 いずれも格別な地域であると意識されていたことに基づく。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よしのがは [吉野川] | 【地名・歌枕】 奈良県大台ケ原山に発し、西北流して吉野山のふもとを流れる川。 和歌山県に出ると紀ノ川となり紀伊水道に注ぐ。 |
吉野川行く瀬の早みしましくも淀むことなくありこせぬかも(万2-119) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よしののみや [吉野の宮] | 〔名詞〕奈良県吉野郡吉野町宮瀧の離宮。 | み吉野の 吉野の宮は 山からし 貴くあらし 川からし さやけくあらし-(万3-318) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よしのやま [吉野山] | 〔地名〕奈良県吉野郡にある山。修験道の霊場・南朝の史跡・桜の名所などで知られる。〔歌枕〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よしや [縦しや] | 〔副詞〕[副詞「縦(よ)し」+間投助詞「や」] ① ままよ。どうなろうとも。まあまあ。 ② たとえ。よしんば。かりに。 |
② 吉野川よしや人こそつらからめはやく言ひてしことは忘れじ(古今恋五-794) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よしゑ [縦しゑ] | 〔副詞 (上代語)〕[組成 副詞「縦(よ)し」+上代間投助詞「ゑ」] ええ、ままよ。どうなろうとも。 |
たらちねの母にも言はずつつめりし心はよしゑ君がまにまに(万13-3299) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よしゑやし [縦しゑやし] | 〔上代語〕[組成 副詞「よしゑ」+間投助詞「や」+上代の間投助詞「し」] 「縦しゑ」の意を強める。 |
-人こそ見らめ よしゑやし 浦はなくとも よしゑやし- (万2-131) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よす [寄す] | 〔自動詞サ行下二段〕【セ・セ・ス・スル・スレ・セヨ】 ① 寄る。せまってくる。② 攻め寄せる。近づく。 |
① 沖つ波来寄する荒礒をしきたへの枕とまきて寝せる君かも(万2-222) ① 我が命しま幸くあらばまたも見む志賀の大津に寄する白波(万3-291) ① 大伴の名に負ふ靫帯びて万代に頼みし心いづくか寄せむ(万3-483) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞サ行四段〕《上代語》 近寄らせる。寄せる。よこす。 |
紀の国にやまず通はむ妻の杜妻寄しこせに妻といひながら [一云 妻賜はにも妻といひながら](万9-1683) -日の御門に 知らぬ国 寄し巨勢道より 我が国は 常世にならむ-(万1-50) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞サ行下二段〕【セ・セ・ス・スル・スレ・セヨ】 ① 近づける。寄せる。② 任せる。任ずる。委ねる。 ③ かこつける。関係づける。④ 心をかたむける。向ける。 ⑤ 贈る。寄付する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よすが [縁・因・便] | 〔名詞〕 ① (心身の) よりどころ。頼り先。 ② 頼りとする縁者(夫・妻・子など)。親類。 ③ 手づる。つて。仲介者。 ④ 手段。方法。 【語源】 「寄(よ)す処(か)」で、心身を寄せるところの意が原義。類義語「よるべ」は、心身の寄る所を表すのに対して、、「よすが」は、心身を寄せる手がかりをも表す。また、「ゆかり」は、主として人間関係や血縁を表す点に特徴がある。 |
① -言問はぬ ものにはあれど 我妹子が 入りにし山を よすかとぞ思ふ(万3-484) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よそ [余所] | 1〔名詞〕 ① 他の場所。遠い場所。② 直接関係のないこと。他人の事。別。他人。 2〔形容動詞ナリ活用〕【ナラ・ナリ(ニ)・ナリ・ナル・ナレ・ナレ】 打ち解けないさま。疎遠で冷淡なさま。 |
〔名詞〕 ① 家に来て我が屋を見れば玉床の外に向きけり妹が木枕(万2-216) ① -通ひけむ 君をば明日ゆ [一云 君を明日ゆは] 外にかも見む(万3-426) ① -天雲の 外のみ見つつ 言問はむ よしのなければ 心のみ-(万4-549) ② 鈴鹿山憂き世をよそに振り捨てていかになり行く我が身なるらん (新古今雑中-1611) 〔形容動詞ナリ活用〕 よそに見てかへらむ人に 藤の花はひまつはれよ 枝は折るとも(古今春二-119) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よそひ [装ひ] | 〔名詞〕① 取りそろえること。準備。したく。② 装飾。飾り。③ 晴れ着。装束。 | ① 水鳥の立たむ装ひに妹のらに物言はず来にて思ひかねつも(万14-3549) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よそふ [装ふ] | 〔他動詞タ行四段〕[「よそほふ」とも] ① 取りそろえる。準備する。② 身づくろいをする。飾る。 ③ 食器に食物を盛る。 |
① 年に装る我が舟漕がむ天の川風は吹くとも波立つなゆめ(万10-2062) ② 君なくはなぞ身装はむ櫛笥なる黄楊の小櫛も取らむとも思はず(万9-1781) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よそる [寄そる] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 自然に引き寄せられる。なびき従う。 ② 打ち寄せる。 ③ ある異性と関係があるとうわさされる。よ |
① -荒山も 人し寄すれば 寄そるとぞいふ 汝が心ゆめ(万13-3319) ② 白波の寄そる浜辺に別れなばいともすべなみ八度袖振る(万20-4403) ③ 山菅の実ならぬことを我に寄そり言はれし君は誰とか寝らむ(万4-567) ③ 新田山嶺にはつかなな我に寄そりはしなる子らしあやに愛しも(万14-3427) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よど [淀・澱] | 〔名詞〕[「よどみ」に同じ] | 真野の浦の淀の継橋心ゆも思へや妹が夢にし見ゆる(万4-493) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よとこ [夜床] | 〔名詞〕《「ゆとこ」 とも》夜に寝る床。 | -剣太刀 身に添へ寝ねば ぬばたまの 夜床も荒るらむ-(万2-194) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よどせ [淀瀬] | 〔名詞〕流れのゆるやかな浅瀬。水の淀んでいる瀬。 | 宇治川は淀瀬なからし網代人舟呼ばふ声をちこち聞こゆ(万7-1139) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よどみ [淀み・澱み] | 〔名詞〕流れのとどこおること。また、その所。淀(よど)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よどむ [澱む・淀む] | 〔自動詞マ行四段〕 ① 水の流れが、留まってとどこおる。 ② 物事がうまく運ばない。また、ためらう。よる |
① 楽浪の志賀の [一云 比良の] 大わだ淀むとも昔の人にまたも逢はめやも [一云 逢はむと思へや](万1-31) ① 吉野川行く瀬の早みしましくも淀むことなくありこせぬかも(万2-119) ② ねもころに思ふ我妹を人言の繁きによりて淀むころかも(万12-3123) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よなき [夜鳴き・夜泣く] | 〔名詞〕夜に鳥などが鳴くこと。また、乳児が夜眠らずに泣くこと。 | 朝日照る佐田の岡辺に泣く鳥の夜哭きかへらふこの年ころを(万2-192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よなばり [吉隠] | 〔地名〕 | 降る雪はあはにな降りそ吉隠の猪養の岡の寒からまくに(万2-203) 吉隠の猪養の山に伏す鹿の妻呼ぶ声を聞くが羨しさ(万8-1565) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「萬葉集全注巻二-203 注『吉隠の猪養の岡』」】 吉隠はヨナバリと訓む。旧訓ヨコモリであったのを、代匠記にヨナハリと改訓。坂上郎女作歌に「吉名張乃(よなばりの) 猪養山尓(ゐかひのやまに) 伏鹿之 嬬呼音乎 聞之登聞思佐」(万8・一五六五)と見える。現在は奈良県桜井市に吉隠という地名が残る。初瀬の東約二・五キロの伊勢街道上の地。猪養の岡は、その名が伝わらないが、その付近であったのだろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よのなか [世の中] | 〔名詞〕 ① 世間。社会。② 現世。この世。③ 天皇の治める世。御代(みよ)。 ④ 世の常。世間一般。世間なみ。⑤ 身の上。運命。境遇。 ⑥ 男女の間柄。夫婦仲。⑦ 世間の評判。名声。⑧ あたり。外界。自然界。 ⑨ (「世の中の・世の中に」の形で)この上ない。まったく。 |
① -頼めりし 児らにはあれど 世の中を 背きしえねば かぎろひの-(万2-210) ④ 世の中の女にしあらば我が渡る痛背の川を渡りかねめや(万4-646) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よばふ [呼ばふ] | 〔他動詞ハ行四段〕 [四段動詞「呼ぶ」の未然形「よば」に上代の反復・継続の助動詞「ふ」が付いて一語化したもの] ① 何度も呼ぶ。呼び続ける。 ② 言い寄る。求婚する。 |
-桜花 木の暗茂に 沖辺には 鴨つま呼ばひ 辺つへに あぢ群騒き ももしきの-(万3-259) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よひ [宵] | 〔名詞〕日没から夜中までをいう語。夜、また、夜に入って間もない頃。 | 宵に逢ひて朝面無み名張にか日長き妹が廬りせりけむ(万1-60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よぶ [呼ぶ] | 〔自動詞バ行四段〕声が響く。 | 大和には鳴きてか来らむ呼子鳥象の中山呼びぞ越ゆなる(万1-70) 月読みの光りを清み夕なぎに水手の声呼び浦廻漕ぐかも(万15-3644) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞バ行四段〕 ① 相手に自分を気付かせるために大声を出す。 ② 声を出して相手を来させる。③ 招く。招待する。 ④ 名づける。称する。 |
② 大宮の内まで聞こゆ網引すと網子ととのふる海人の呼び声(万3-239) ② 高圓の秋野の上の朝霧に妻呼ぶ壮鹿出で立つらむか(万20-4343) ④ たらちねの母が呼ぶ名を申さめど道行く人を誰れと知りてか(万12-3116) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よぶこどり [呼ぶ子鳥] | 〔名詞〕鳴き声が人を呼ぶように聞こえる鳥。今の郭公の異名か。 「古今伝授」の「三鳥(さんてう)」の一つ。 |
大和には鳴きてか来らむ呼子鳥象の中山呼びぞ越ゆなる(万1-70) 世の常に聞けば苦しき呼子鳥声なつかしき時にはなりぬ(万8-1451) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よみがへる [蘇る] | 〔自動詞ラ行四段〕[「黄泉(よみ)から帰る」の意] 生き返る。蘇生する。 | わたつみの沖に持ち行きて放つともうれむそこれのよみがへりなむ(万3-330) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よむ [読む] | 〔他動詞マ行四段〕 ① [読む] ア- 数を数える。 イ- (文章・詩歌・経文などを) 声を出して唱える。また、節をつけて唱える。 ② [詠む] 詩歌を作る。また、声を出して詩歌を唱える。 |
① ア 白たへの袖解き交へて帰り来む月日を数みて行きて来ましを(万4-513) ① ア 春花のうつろふまでに相見ねば月日数みつつ妹待つらむぞ(万17-4006) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よも [四万] | 〔名詞〕 ① 東西南北。前後左右。四方。 ② あちらこちら。いたるところ。あたり一帯。 |
「四万の国を安国と平らけく知ろしめすが故に」(祝詞) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| より | 〔格助詞〕 ① 動作・作用の時間的・空間的な起点を示す。~から。 ② 動作・作用の経過する地点を示す。~を通って。 ③ 動作・作用の手段、方法を表わす。~で。~によって。 ④ 比較の基準を表わす。~よりも。 ⑤ 一定の範囲を限定する意を表わす。~以外。 ⑥ 原因・理由を表わす。~ために。~によって。 ⑦ 即時の意を表わす。~やいなや。すぐに。 〔接続〕体言および活用する語の連体形に付く。 〔語法〕きわめて稀に形容詞の連用形や助詞にも付く。 |
① 天離る鄙の長道ゆ恋ひ来れば明石の門より大和島見ゆ [一本云 家のあたり見ゆ](万3-256) ① ひさかたの 天の原より 生れ来る 神の命 奥山の-(万3-382) ② いにしへに恋ふる鳥かも弓絃葉の御井の上より鳴き渡り行く(万2-111) ③ -馬より行くに 己夫し 徒歩より行けば 見るごとに -(万13-3328) ④ 秋山の木の下隠り行く水の我れこそ益さめ思ほすよりは(万2-92) ④ 賢しみと物言ふよりは酒飲みて酔ひ泣きするし優りたるらし(万3-344) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よりあひ [寄り合ひ] | 〔名詞〕 ① 寄り集まること。互いに接して一つになること。またその所。 ② 多くの人が一堂に会すること。会合。集会。 ③ 連歌・俳諧で、前句と付け句を付けること。 |
① -葦原の 瑞穂の国を 天地の 寄り合ひの極み 知らしめす-(万2-167) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よりく [寄り来] | 〔自動詞カ行変格活用〕【コ・キ・ク・クル・クレ・コヨ】 寄って来る。近づいて来る。 |
荒波に寄り来る玉を枕に置き我ここにありと誰か告げけむ(万2-226) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よる [夜] | 〔名詞〕 一日のうち、日没から夜明けまでの間。 |
夜光る玉といふとも酒飲みて心を遣るにあに及かめやも(万3-349) 旅にあれど夜は火灯し居る我れを闇にや妹が恋ひつつあるらむ(万15-3691) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よる [因る・由る・依る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 基づく。由来する。原因となる。 ② 従う。応じる。 ③ それと限る。定める。 |
① 大船を漕ぎのまにまに岩に触れ覆らば覆れ妹によりては(万4-560) ② -下つ瀬に 小網さし渡す 山川も 依りて仕ふる 神の御代かも(万1-38) ② 梓弓引かばまにまに依らめども後の心を知りかてぬかも [郎女](万2-98) ② 武蔵野の草葉もろ向きかもかくも君がまにまに我はよりにしを (万14-3395) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よる [寄る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 近寄る。接近する。② 集まる。寄り合う。 ③ 心が傾く。好意を寄せる。④ 頼る。依頼する。 ⑤ もたれかかる。寄りかかる。⑥(物の怪・霊などが)乗り移る。 ⑦ 寄進される。寄付される。 |
①-玉藻沖つ藻 朝羽振る 風こそ寄せめ 夕羽振る 波こそ来寄れ- (万2-131) ③ 今さらに何をか思はむうち靡き心は君に寄りにしものを(万4-508) ④-伊勢の海人も舟流したる心地して寄らむ方なく-(古雑体-1006) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よる [撚る・縒る・搓る] | 〔他動詞ラ行四段〕 (糸などを) 何本かねじり合わせて一本にする。ひねって絡みつかせる。よじる。 |
我が持てる三つ合ひに搓れる糸もちて付けてましもの今そ悔しき(万4-519) 浅緑糸縒りかけて白露を珠にもぬける春の柳か(古今春上-27) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔自動詞ラ行四段〕しわがよる。 | 蝉の羽のひとへに薄き夏衣 なれば縒りなんものにやはあらぬ(古今雑体-1035) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 よじれる。しわになる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よるひる [夜昼] | 〔名詞〕夜間と昼間。 | 畑子らが夜昼といはず行く道を我れはことごと宮道にぞする(万2-193) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よろし [宜し] | 〔形容詞シク活用〕【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 ① だいたいよい。まあよい。 ② 普通である。平凡である。当たり前である。 ③ 適当である。ふさわしい。似つかわしい。 ④ 結構である。すぐれている。好ましい。 |
① -草枕 旅を宜しと 思ひつつ 君はあるらむと あそそには-(万4-546) ④ -川藻のごとく なびかひの 宜しき君が 朝宮を 忘れたまふや-(万2-196) ④ 物皆は新たしきよしただしくも人は古りにしよろしかるべし(万10-1889) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よろしなへ [宜しなへ] | 〔副詞〕《上代語》 こころにかなって。よい具合に。ふさわしく。 |
背面の 大御門に よろしなへ 神さび立てり 名ぐはしき 吉野の山は(万1-52) よろしなへ我が背の君が負ひ来にしこの背の山を妹とは呼ばじ(万3-289) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よろづたび [万度] | 〔副詞〕何度も。たびたび。 | -我が行く川の 川隈の 八十隈おちず 万たび かへり見しつつ-(万1-79) -八十隈ごとに 万たび かへり見すれど いや遠に 里は離りぬ-(万2-131) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よろづよ [万代] | 〔名詞〕いつまでも続く世。万代。永久。永遠。 | あをによし奈良の家には万代に我れも通はむ忘ると思ふな(万1-80) 霍公鳥今し来鳴かば万代に語り継ぐべく思ほゆるかも(万17-3936) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よわたる [夜渡る] | 〔自動詞ラ行四段〕夜中に渡っていく。夜の間に過ぎていく。 | あかねさす日は照らせれどぬばたまの夜渡る月の隠らく惜しも(万2-169) ぬばたまの夜渡る月は早も出でぬかも海原の八十島の上ゆ妹があたり見む [旋頭歌也](万15-3673) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ら | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -ら [等] | 〔接尾語〕 ①(名詞・代名詞に付いて) ア:複数・親しみの気持ちなどを表す。 イ:謙譲の意を表す。 ウ:方向・場所を示す。 エ:語調を整える。 ②(形容詞の語幹((シク活用は終止形))に付いて)状態を表す名詞、 または形容動詞を作る。 |
① 「ア」- 黒髪敷きて 長き日を 待ちかも恋ひむ 愛しき妻らは(万20-4355) ① 「イ」憶良らは今は罷らむ子泣くらむそれその母も我を待つらむぞ(万3-340) ① 「ウ」-見し人をいづらと問はば語り告げむか(万3-451) ① 「エ」-思ひつつ 我が寝る夜らは 数みもあへぬかも(万13-3343) ② あな醜賢しらをすと酒飲まぬ人をよく見ば猿にかも似むらむ (万3-347) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| らし [動詞活用表] | 〔助動詞〕[推定・原因推定] ① ある根拠・理由に基づき、確信をもって推定する意を表す。 ~に違いない。きっと~だろう。 ② 明らかな事実・状態を表す語に付いて、 その原因・理由を推定する意を表す。~(と)いうので~らしい。 ③ 根拠・理由は示さないが、確信をもって推定する意を表す。 ~に違いない。きっと~だろう。 〔接続〕 活用語の終止形に付く。ただしラ変型活用の語には連体形に付く。 |
① 春過ぎて夏来るらし白栲の衣干したり天の香具山 (万1-28) ② 常止まず通ひし君が使来ず今は逢はじとたゆたひぬらし(万4-545) ② 我が背子がかざしの萩に置く露をさやかに見よと月は照るらし (万10-2229) ③ 験なき物を思はずは一坏の濁れる酒を飲むべくあるらし(万3-341) ③ み雪降る冬は今日のみ鴬の鳴かむ春へは明日にしあるらし (万20-4512) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 (1) 「らし」の語史 「らし」はおもに上代に用いられた語で、平安中期以降はおとろえ、和歌においては「らむ」に、散文においては「めり」にとってかわられた。 「らし」はある根拠・理由に基づいて推定するはたらきをする。 眼前の事実を根拠に推定する表現形式が「①」であり、眼前の事実に基づいてその奥にある原因・理由を推定する表現形式が「②」である。 夕されば(=夕方になると) 衣手寒し(事実・根拠) み吉野の吉野の山にみ雪降るらし 〔古今・冬〕 雄神川紅にほふ少女らし(=少女たちが) 葦付き採ると(理由) 瀬に立たす(事実) らし 〔万葉17-4045〕 (2) 連体形・已然形の用法 連体形と已然形は係助詞に対する結びとして用いられるだけである。 立田川色紅になりにけり山の紅葉ぞ今は散るらし 〔後撰・秋下〕 抜き乱る人こそあるらし白玉の間なくも散るか袖のせばきに 〔古今雑上〕 「らしき」は上代の係助詞「こそ」の結びとして、 香久山は畝火雄雄しと耳梨と相争ひき~古も然にあれこそうつせみも嬬を争ふらしき 〔万葉1・一三〕 のように用いられるが、上代では「こそ」の結びが形容詞型活用の語の場合、すべて連体形が用いられるので、これも連体形とされる。 (3) 「煮らし」 上代の用例では、上一段活用動詞の未然形あるいは連用形とみられる語形に付く場合がある。 春日野に煙立つ見ゆをとめらし春野のうはぎ(=植物の名) 採てみて煮らしも 〔万葉10・一八八三〕 (4) 「らし」がラ変型活用の用言および助動詞に付く場合、語尾の「る」が脱落して、「あらし」「けらし」「ならし」となることが多い。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -らく | 〔接尾語〕《上代語》 ① ~することの意を表す。 ② 連用修飾語になる。~することは。 ③ 文末にあって詠嘆を表す。~することよ。 |
① 桜花ちりかひくれも 老いらくのこむといふなる道まがふがに(古今賀-349) ② 里人の 我れに告ぐらく 汝が恋ふる うつくし夫は 黄葉の-(万13-3317) ③ 飫宇の海の河原の千鳥汝が鳴けば我が佐保川の思ほゆらくに(万3-374) ③ 草枕旅に久しくあらめやと妹に言ひしを年の経ぬらく(万15-3741) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔文法〕 形の上では、上二段・下二段・カ行変格・サ行変格・ナ行変格活用動詞の終止形、上一段活用動詞の未然形と考えられた形に付く。 また、助動詞「しむ」「つ」「ぬ」「ゆ」などの終止形と考えられた形にも付く。 上接の語を名詞化する働きがあり、中古以降は「おそらく」「老いらく」などの語にいわば化石化されて残り、現代に至っている。 接尾語「く」と補い合い、四段・ラ変の動詞、形容詞、助詞「けり」「り」「む」「ず」などには、「く」が付いて名詞化する。 この「らく」と「く」との複雑な接続を統一的に説明するため、接尾語の「あく」という語を想定して、上の語の連体形にこれが付いたとみる説があり、本書(旺文社全訳古語辞典 第三版)はこの説によっている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| らむ [動詞活用表] | ① 現在の事実について、想像・推量する。 ② 現在の事実について、その原因・理由を想像・推量する。 ③ 現在の事実について、その原因・理由を疑問を持って想像・推量。 ④ 他人から聞いたり読んだりしたという伝聞の意を表す。 ⑤「む」に同じく、ただその動作・状態を想像・推量する。 〔接続〕終止形 (ラ変型は連体形) に付く。 |
① わが背子は何処行くらむ奥つもの隠の山を今日か越ゆらむ(万1-43) ① ふたり行けど行き過ぎがたき秋山をいかにか君がひとり越ゆらむ (万2-106) ① 鴨山の岩根しまける我をかも知らにと妹が待ちつつあるらむ(万2-223) ① -剣太刀 身に添へ寝ねば ぬばたまの 夜床も荒るらむ-(万2-194) ① 荒たへの藤江の浦にすずき釣る海人とか見らむ旅行く我れを(万3-253) ② 春日野の若菜摘みにやしろたへの袖ふりはへて人の行くらむ (古春上-22) ③ ひさかたの光のどけき春の日に静心なく花の散るらむ(古春下-84) ④ 古に恋ふらむ鳥はほととぎすけだしや鳴きしわが念へるごと(万2-112) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| らゆ | 〔助動詞下二段型〕【ラエ(ヌ)・○・○・○・○・○】《上代語》 可能の意を表す。「~ことができる」「~られる」 〔接続〕 ナ行下二段活用の未然形に付く。 【参考】 中古の「らる」と意味用法は同じく、受身・可能・自発の意が考えられるが、「万葉集」あんど仮名書きのものでは「寝(ぬ)」「寝(い)ぬ」に接続した可能の用例しか見当たらない。平安時代には、漢文訓読語に稀に見られた。 |
大和恋ひ寐の寝らえぬに心なくこの洲崎廻に鶴鳴くべしや(万1-71) 妹を思ひ寐の寝らえぬに秋の野にさを鹿鳴きつ妻思ひかねて(万15-3700) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| り 「主要助動詞活用一覧」 | 〔完了・存続の助動詞〕【ラ・リ・リ・ル・レ・レ】 ラ変動詞「あり」が上接の動詞の語尾の母音と結合して「り」だけ残ったもの 〔基本義〕 すでにそういうことがあって、その事態の影響が、そこで述べようとしている時にまで及んでいるということを表す語。連用形の後に「て」をはさんでできた「たり」と同じ意味を表す。「~ている」「~てある」 ① 動作・作用の完了した意を表す。「~た」 ② 完了した動作・作用の結果が存続している意を表す。 「~ている・~てある」 〔接続〕四段活用の已然形とサ変の未然形につく。 |
① -我妹子が 形見に置ける みどり子の 乞ひ泣くごとに 取り与ふる-(万2-210) ② 風流士と我れは聞けるをやど貸さず我れを帰せりおその風流士(万2-126) ② あかねさす日は照らせれどぬばたまの夜渡る月の隠らく惜しも(万2-169) ② -偲ひ行かむ 御名にかかせる 明日香川 万代までに はしきやし-(万2-196) ② -風の共 靡かふごとく 取り持てる 弓弭の騒き み雪降る-(万2-199) ② 衾道を引手の山に妹を置きて山道を行けば生けりともなし(万2-212) ② 沖つ波来寄する荒礒をしきたへの枕とまきて寝せる君かも(万2-222) ② やすみしし我が大君の敷きませる国の中には都し思ほゆ(万3-332) ② み吉野の高城の山に白雲は行きはばかりてたなびけり見ゆ(万3-356) ② いなだきにきすめる玉は二つなしかにもかくにも君がまにまに(万3-415) 【語法】 四段・サ変以外には「たり」がつくが、時代が経つとともに四段・サ変にも「たり」のつく場合が多くなる。また、中古の仮名文では、未然形「ら」、已然形「れ」は「給へ」に付く形がほとんどである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 上代の特殊仮名遣いからみると、「り」の上の語が四段活用の已然形ではなく、命令形と同じであることから四段活用・サ変の命令形につくとする説もあるが、上代の例は動詞の連用形に「あり」のついた複合動詞が音の上で変化したものであって、助動詞として使われるのは中古以後であるとも考えられるので、接続は上述のようにした。 上代の「り」を助動詞とする説もある。上代には「吾(あ)がけ(着)る妹が衣の垢づく見れば」(万15-3689)、「玉梓(たまづさ)の使(つかひ)のけ(来)れば嬉しみと」(万17-3979) のように上一段やカ変に付いたものもあれば、東国方言では、「筑波嶺に雪かも降らるいなをかもかなしき児(こ)ろが布(にの)干さるかも」(万14-3365) のように、「り」の上のエ段の音がア段の音に変ったものもある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| る 「主要助動詞活用一覧」 | 〔助動詞下二段型〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 ① 受身。~れる。 ② 自発。自然に~れる。~ないではいられない。 ③ 可能。~ことができる。 ④ 尊敬。お~になる。~なさる。 〔接続〕四段・ナ変・ラ変の動詞の未然形につく。 |
① 昔こそ難波田舎と言はれけめ今は都引き都びにけり(万3-315) ① 天雲の 向伏す国の もののふと 言はるる人は 天皇の-(万3-446) ② 秋きぬと目にはさやかに見えねども 風の音にぞおどろかれぬる(古今秋上-169) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| れ | 受身・尊敬の助動詞「る」の未然・連用形 | 秋きぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞ驚かれぬる(古秋上-169) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完了の助動詞「り」の已然・命令形 | 秋さらば我が船泊てむ忘れ貝寄せ来て置けれ沖つ白波(万15-3651) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ろ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ろ | 〔間投助詞〕《上代語》 ① 感動を表す。「~よ」 ②(下に終助詞「かも」の付いた「ろかも」の形で、名詞または形容詞の連体形に付き)感動を表す。「~よ」「~なあ」 ③ 意味を強める。 〔接続〕「①」「③」は種々の語に付く。 |
① 荒雄らは妻子の業をば思はずろ年の八年を待てど来まさず (万16-3887) ① 草枕旅の丸寝の紐絶えば我が手と付けろこれの針持し(万20-4444) ②「百足らず八十葉の木は大君ろかも(仁徳紀) ② 藤原の大宮仕へ生れ付くや娘子がともは羨しきろかも(万1-53) ② -笑まひ振舞 いや日異に 変らふ見れば 悲しきろかも(万3-481) ③ 伊香保ろに天雲い継ぎかぬまづく人とおたはふいざ寝しめとら (万14-3428) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 品詞の分類に問題のある語で、「②」は「ろかも」の形で終助詞とする説、「ろ」を接尾語とする説などのほか、「①・③」のうちでも、あるものは接尾語とする説もある。 例歌「①」の「つけろ」のようなものは、現代の関東方言の命令形語尾となるものである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わ | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わ [我・吾] | 〔代名詞〕自称の人代名詞。私。 【参考】 上代には助詞「が」「を」「に」「は」等を伴って用いられたが、中古以後は、「が」を伴った「わが」の形で多く用いられる。 |
はしきやし栄えし君のいましせば昨日も今日も我を召さましを(万3-457) -水手ととのへて 朝開き 我は漕ぎ出ぬと 家に告げこそ(万20-4432) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わ- [我・吾・和] | 〔接頭語〕(人を表す名詞・代名詞に付いて) ① 相手に対する親しみの気持ちを表す。 ② 相手を見下げる気持ちを表す。 |
① 例「-御許(おもと)」「-殿」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わ | 〔間投助詞〕《上代語》 ① 呼び掛けに用いる。 ~よ。 ② 感動の意を表す。~よ。 〔接続〕 「①」は副詞「いざ」に付いたものと、終助詞「な」に付いた。右の用例のみ。 「②」は活用語の連体形に付く。 |
① -童ども いざわ出で見む こと放けば 国に放けなむ-(万13-3360) ① 鳰鳥(にほどり)の淡海(あふみ)の海に潜(かづ)きせなわ(=入ッテ死ノウヨ)(記・中) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わ | 〔終助詞〕終助詞「ば」が「わ」と発音されるようになり発音通りに書かれたもの。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わが [吾が・我が] | 〔代名詞「わ」+格助詞「が」〕 ① 「が」が連体格を示す助詞の場合 ア:私の。われわれの。 イ:その人自身の。自分の。 ② 「が」が主格を示す助詞の場合 私が。 |
①「ア」大船の津守が占に告らむとはまさしに知りて我がふたり寝し (万2-109) ①「ア」我が御門千代とことばに栄えむと思ひてありし我れし悲しも(万2-183) ①「ア」-なにしかも 我が大君の 立たせば 玉藻のもころ-(万2-196) ①「ア」我が命も常にあらぬか昔見し象の小川を行きて見むため(万3-335) ①「ア」-我がふたり見し走出の堤に立てる槻の木のこちごちの枝の-(万2-210) ①「ア」我が船は比良の湊に漕ぎ泊てむ沖辺な離りさ夜ふけにけり(万3-276) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わがおほきみ [我が大君・吾が大君] |
「わごおほきみ」とも。当代の天皇を敬っていう語。 今上(きんじょう)天皇。 |
やすみしし 我が大君の 朝には 取り撫でたまひ 夕には い寄り立たしし-(万1-3) 橘の下照る庭に殿建てて酒みづきいます我が大君かも(万18-4083) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わかくさの [若草の] | 【枕詞】 若草のみずみずしく美しいことから、「夫(つま)」「妻」 に、また新しく若々しいことから「にひ」などにかかる |
― 辺つ櫂 いたくな撥ねそ 若草の 夫の 思ふ鳥立つ (万2-153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わかごもを [若菰を] | 【枕詞】 若くて柔らかなまこも(=水草の名)を刈る意から、「狩り」にかかる。 |
- 馬並めて み狩り立たせる 若薦を 狩路の小野に 鹿こそば い這ひ拝め-(万3-240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わがせ [我が背] | 女性から夫・恋人などの親しい男性をいう語。〔=我が背子〕 | 我が背子は仮廬作らす草なくは小松が下の草を刈らさね(万1-11) 我が背子を大和へ遣るとさ夜更けて暁露に我れ立ち濡れし(万2-105) 沖つ波辺波立つとも我が背子がみ船の泊り波立ためやも(万3-248) 信濃道は今の墾り道刈りばねに足踏ましなむ沓はけ我が背(万14-3417) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わかる [別る・分かる] | 〔自動詞ヤ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 ① 分離する。別々になる。 ② 遠く離れて会いにくくなる。死に別れる。または、生き別れになる。 |
① 天地の 別れし時ゆ 神さびて 高く貴き 駿河なる 富士の高嶺を- (万3-320) ② 燈火の明石大門に入らむ日や漕ぎ別れなむ家のあたり見ず(万3-255) ② 妹も我も一つなれかも三河なる二見の道ゆ別れかねつる(万3-278) ② 衣手の別る今夜ゆ妹も我もいたく恋ひむな逢ふよしをなみ(万4-511) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 区別がつく、識別できる意の「わかる」は、四段活用の「わく(分く)」の未然形に、可能・受身・自発の助動詞「る」が付いたものとして、ニ語に分けた方がよい。 「その琴とも聞きわかれぬ(聞き分けることのできない)物の音ども、いとすごげに聞こゆ」 (源氏・橋姫) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わかれ [別れ] | 〔名詞〕 ① 別れること。離別。生別。死別。 ② ひとつの元から別れ出たもの。枝。分家。傍系。 |
① 我が背子にまたは逢はじかと思へばか今朝の別れのすべなかりつる(万4-543) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わきばさむ [脇挟む・腋挟む] | 〔他動詞マ行四段〕[「わきはさむ」とも] 脇の下にはさむ。 |
-取り与ふる 物しなければ 男じもの わき挟み持ち 我妹子と-(万2-210) 夕には 入り居嘆かひ 脇ばさむ 子の泣くごとに 男じもの 負ひみ抱きみ(万3-484) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わきばむ [脇ばむ] | 〔他動詞マ行四段〕いたわる。たいせつにする。いつくしむ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わぎも [吾妹] | 〔名詞〕《上代語》[「わがいも」の転] ⇔「吾が背 (わがせ)」 男性が、妻や恋人など親しい女性をいう語。私のいとしい女性。= 吾妹子 |
秋の雨に濡れつつ居ればいやしけど我妹が宿し思ほゆるかも(万8-1577) 風の音の遠き我妹が着せし衣手本のくだりまよひ来にけり(万14-3472) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わぎもこ [吾妹子] | 〔名詞〕[「わがいもこ」の転。「こ」は接尾語] ⇒「わぎも」、⇔「我背子 (わがせこ)」 【参考】 原形の「わがいもこ」は、「万葉集」に一例ある (20・4429)。 |
我妹子に恋ひつつあらずは秋萩の咲きて散りぬる花にあらましを(万2-120) 我妹子に猪名野は見せつ名次山角の松原いつか示さむ(万3-282) 我妹子が植ゑし梅の木見るごとに心咽せつつ涙し流る(万3-456) 葦垣の隈処に立ちて我妹子が袖もしほほに泣きしぞ思はゆ(万20-4381) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わぎもこに [吾妹子に] | 【枕詞】 「吾妹子」に「会ふ」意から、同音の「あふ」を含む「逢坂山 (あふさかやま)・近江 (あふみ) ・あふちの花・淡路 (あはぢ)」などにかかる。 |
我妹子に逢坂山のはだすすき穂には咲き出ず恋ひわたるかも(万10-2287) -逢坂山に 手向け草 幣取り置きて 我妹子に 近江の海の 沖つ波- (万13-3251) 我妹子に楝の花は散り過ぎず今咲けるごとありこせぬかも(万10-1977) -漕ぎて渡れば 我妹子に 淡路の島は 夕されば 雲居隠りぬ-(万15-3649) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わぎもこを [吾妹子を] | 【枕詞】 「吾妹子」を「見る」意から「いざみの山・早見の浜」などにかかる。 |
我妹子をいざ見の山を高みかも大和の見えぬ国遠みかも(万1-44) 我妹子を早見浜風大和なる我れ松椿吹かざるなゆめ(万1-73) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中央公論社「万葉集注釈巻第一-44 わぎもこを」訓釈】[文中、旧歌番号] 「我が妹」をつづめてワギモといふ。「和藝毛」(仁徳紀)、「和伎母 (ワギモ)」(万15-3764) など仮名書の例による。それに「子」をつけてワギモコといふこと「我が背」を「我が背子」ともいふに同じ。「和我伊母古我 (ワガイモコガ)」 (万20-4405) の如くワギイモコと云ひ、五音のところをわざわざ六音にした例があるが、それは防人の作一例であり、他の仮名書例はいづれもワギモとあるので、今もワギモコヲと訓でよい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わく [別く・分く] | 〔他動詞カ行四段〕 ① 区別する。分け隔てする。 ② 判断する。理解する。 |
② 廻り逢ひて見しやそれともわかぬ間に雲隠れにし夜はの月かげ (新古雑上-1497) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞カ行下二段〕【ケ・ケ・ク・クル・クレ・ケヨ】 ① 別々にする。区切る。 ② 草などを分けて行く。道をひらいて進んで行く。 ③ 物を分ける。分配する。 |
② -神の命と 天雲の 八重かき別けて [一云 天雲の八重雲別きて] -(万2-167) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わけ [戯奴] | 〔代名詞〕 ① 自称の人代名詞。卑下の意を表す。わたくしめ。 ② 対称の人代名詞。多くの場合、目下の者に対していう。おまえ。そち。 |
① 我が君はわけをば死ねと思へかも逢ふ夜逢はぬ夜二走るらむ(万4-555) ② 戯奴 [變云 わけ] がため我が手もすまに春の野に抜ける茅花ぞ食して肥えませ (万8-1464) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わごおほきみ [吾ご大王・我ご大君] |
〔「わがおほきみ」の転〕 「わがおほきみ」に同じ。 |
やすみしし 我ご大君 高照らす 日の皇子 荒栲の 藤井が原に―(万1-52) やすみしし我ご大君の大御船待ちか恋ふらむ志賀の唐崎 (万2-152) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わざ [業・態・技] | 〔名詞〕 ① 行い。動作。しわざ。② 仕事。勤め。③ 技術。技芸。 ④ 仏事。法要。⑤ ありよう。様子。⑥ 禍。祟り。害悪 |
① み薦刈る信濃の真弓引かずしてしひさるわざを知ると言はなくに [郎女] (万2-97) ⑤ 今のみのわざにはあらずいにしへの人そまさりて音にさへ泣きし(万4-501) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わざみがはら [和射見が原] | 【武田全註釈巻二-199 釋「和射見我原」】 和射見我原乃 ワザミガハラノ。美濃の國であろうが、所在未詳である。今の青野が原附近であろうという。 日本書紀天武天皇紀に、「天皇於茲、行宮興野上而居焉。(中略)戊子、天皇往於和蹔撿挍軍事而還」とある、和蹔 はこの和射見に同じ。 【有斐閣「萬葉集全注巻二-199」 注「狛劔 和射見我原乃 行宮尓 安母理座而」】 和射見が原は、関が原説(上だ秋成『胆大小心録』、大日本地名辞書) と青野が原説(伴信友『長等の山嵐』付録一) とあるが、土屋文明の『万葉紀行』に「天武天皇の行幸即ち野上宮は、吉野方の本営で、軍の総司令官とも申し上ぐべき高市皇子が、軍を率ゐて駐まられたのが「和蹔が原」 である。野上宮の跡はいづくに定むべきか、これ亦困難であらうが、現在東海道線垂井、関が原二駅の中間、下りの左側に、関が原町に属して野上の字が存して居るから、大体そのあたりと推定しても大過はあるまい。人麻呂の歌には野上の行宮のことを言はず、和蹔が原の行宮と歌つて居るのであるが、これは天皇がしばしば和蹔にも行幸せられ、軍をみそなはされたがためであらう。野上に本営があつて、一方之に対抗する近江方の軍は、志賀宮を本拠として、近江に勢力を持して居るとすれば、軍司令官の所在地たる和蹔は、両勢力の中心を結ぶ線上になければならぬ様に思はれる。関が原はその条件に適し、美濃から近江に進む要衝であることは言ふまでもない」 と言い、青野が原説に対しては「現在の野上より更に対抗勢力に反対に東へ五六キロも遠ざかつて居る青野説は都合が悪いやうに思はれる」 と、これをしりぞけている。青野が原説は山田講義や、茂吉評釈にも採られているが、古典大系に一説として付記されている程度で、最近の古典全集・古典集成などには見られない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わする [忘る] | 〔他動詞ラ行四段・下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 忘れる。記憶をなくす。 【参考】 四段活用はおもに上代に用いられた。 また、上代では四段活用の場合は、「意識的に忘れる」、下二段活用の場合は「自然に忘れる」「つい忘れる」の意に用いられたという。 |
[四段] 忘らむて野行き山行き我れ来れど我が父母は忘れせのかも (万20-4368) 人はよし思ひやむとも玉葛影に見えつつ忘らえぬかも(万2-149) [下二段] -其を取ると 騒く御民も 家忘れ 身もたな知らず-(万1-50) 大名児を彼方野辺に刈る草の束の間も我れ忘れめや(万2-110) 忘れ草我が紐に付く香具山の古りにし里を忘れむがため(万3-337) 草枕旅の宿りに誰が嬬か国忘れたる家待たまくに(万3-429) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わすれがひ [忘れ貝] | 〔名詞〕離れ離れになった二枚貝の片方。 これを拾うと、恋しい人を忘れられるという。 |
大伴の御津の浜なる忘れ貝家なる妹を忘れて思へや(万1-68) 和歌の浦に袖さへ濡れて忘れ貝拾へど妹は忘らえなくに [忘れかねつも] (万12-3189) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わすれぐさ [忘れ草] | 〔名詞〕「萱草(くわんざう=草ノ名)」の別名。 うれいを忘れる草といわれ、恋の苦しみを忘れるため、 垣根に植えたり下着の紐に付けたりした。 また、転じて、うれいを忘れさせるもの。忘るる草。 |
忘れ草我が紐に付く香具山の古りにし里を忘れむがため(万3-337) 忘れ草我が下紐に付けたれど醜の醜草言にしありけり(万4-730) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わた [綿] | 〔名詞〕① 繭から作る真綿。絹綿。② 木綿。もめんわた。 | ① しらぬひ筑紫の綿は身に付けていまだは着ねど暖けく見ゆ(万3-339) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わたす [渡す] | 〔他動詞サ行四段〕 ① ある場所から他の場所に移す。② (川や海などを) 越えさせる。 ③ (此岸から彼岸に行くのに、その間を横たわる煩悩を渡ることから) 浄土に行かせる。神仏の力で救う。④ またがらせる。岸から岸に架ける。 ⑤ 与える。授ける。⑥ 見せしめに、罪人に大路を通らせる。引き回す。 |
④ -上つ瀬に 石橋渡し 一に云ふ「石なみ」下つ瀬に 打橋渡す-(万2-196) ⑤ 明日香川しがらみ渡し塞かませば流るる水ものどにかあらまし [一云 水の淀にかあらまし](万2-197) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔補助動詞サ行四段〕(動詞の連用形の下に付いて) ある動作・行為がずっと及ぶ。広く~する。めいめい~する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わたつみ [海神] | 〔名詞〕[「海(わた)つ霊(み)」の意。 ① 海を支配する神。海神。 ② (海神のいる所の意から)海。大海。 |
① わたつみの沖に持ち行きて放つともうれむそこれのよみがへりなむ(万3-330) ① 海神のいづれの神を祈らばか行くさも来さも船の早けむ(万9-1788) ② 海神の豊旗雲に入日さし今夜の月夜さやけくありこそ(万1-15) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻第一-15】 「わたつみ」は「渡(わた)つ神(み)」で、渡ることに関して、支配権を握る神の意。「やまつみ」の対義語。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔補助動詞サ行四段〕(動詞の連用形の下に付いて) ある動作・行為がずっと及ぶ。広く~する。めいめい~する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わたなか [海中] | 〔名詞〕「わだなか」とも。海の中。海上。 | 在り嶺よし対馬の渡り海中に幣取り向けて早帰り来ね(万1-62) 名児の海を朝漕ぎ来れば海中に鹿子ぞ鳴くなるあはれその鹿子(万7-1421) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わたのそこ [海の底] | 【枕詞】[海の底の深いことから] 「奥 (おき)」の同音で、「沖」にかかる。 | 海の底沖つ白波龍田山いつか越えなむ妹があたり見む(万1-83) 海の底沖漕ぐ舟を辺に寄せむ風も吹かぬか波立てずして(万7-1227) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わたらひ [渡会] | 〔地名〕 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1巻二-199 付録『渡会』」】 伊勢国の郡名。現在の三重県伊勢市および渡会郡にあたる。 |
-渡会の 斎きの宮ゆ 神風に い吹き惑はし 天雲を 日の目も見せず 常闇に-(万2-199) 度会の大川の辺の若久木我が久ならば妹恋ひむかも(万12-3141) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わたり [渡り] | 〔名詞〕 ① 移動すること。移転。 ② 来訪すること。向こうからこちらへ来ること。 ③ 川や海を渡ること。また、渡し場。渡船場。 ④ 品物が外国から来ること。舶来。 ⑤「渡り者」の略。⑥交渉。掛け合い。 ⑦ 物の端から端までの長さ。差し渡し。直径。 ⑧(接尾語的に用いて)物事が全体にいきわたる回数を表す。 |
③ 在り嶺よし対馬の渡り海中に幣取り向けて早帰り来ね(万1-62) ③ 苦しくも降り来る雨か三輪の崎狭野の渡りに家もあらなくに(万3-267) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わたりのやま [渡りの山] | 〔地名〕 |
-大船の 渡の山の 黄葉の 散りの乱ひに 妹が袖 さやにも見えず-(万2-135) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1巻二-135 付録『渡りの山』」】 所在未詳。一説に島根県江津市渡津町、江の川の河口近くでS字カーブする川隈のうち下流に近い方の右岸にある標高174メートルの山かという。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わたる [渡る] | 〔自動詞ラ行四段〕 ① 海や川などを越えて行く。 ② 過ぎる。通る。行く。来る。移る。 ③ 年月が過ぎる。年月を送る。 ④ 一方から他方につながる。またがる。岸から岸に架かる。 ⑤ 広く通じる。広い範囲に及ぶ。 ⑥(多く「給ふ」「(させ)給ふ」とともに用いられて) 「あり」の尊敬語。「いらっしゃる」「おいでになる」 【語義】 「わたつみ」の「わた」と関連がある「①」が原義とみられる。転じて、ある一定の空間・時間を超えて他に及ぶ「②」から「③」の意で広く用いられる。 |
① -ももしきの 大宮人は 舟並めて 朝川渡り 舟競ひ-(万1-36) ① 人言を繁み言痛みおのが世にいまだ渡らぬ朝川渡る(万2-116) ① 佐保川の小石踏み渡りぬばたまの黒馬の来夜は年にもあらぬか(万4-528) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -わたる [-渡る] | 〔自動詞ラ行四段〕[動詞の連用形の下に付いて] ① 時間的に「ずっと~続ける」の意を表す。 【例語】 「逢ひわたる(=長いこと会い続ける)」 「在りわたる」「言ひわたる」「倦みわたる」「思ひわたる」 「恨みわたる(=恨んで月日を過ごす)」「聞きわたる」「偲びわたる」 「住みわたる」「解けわたる(=何度も解ける)」「嘆きわたる」 「悩みわたる(=苦しみながら過ごす)」「念じわたる(=念じ続ける)」 「待ちわたる」 ② 空間的に「一面に~」の意を表す。 【例語】 「明けわたる(=すっかり夜が明ける)」「霞わたる」 「凍りわたる(=一面に凍る)」「冴えわたる」「澄みわたる」 「立ちわたる」「這ひわたる」「見えわたる」 「萌えわたる(=一面に芽が出る)」「燃えわたる(=一面に燃える)」 「行きわたる(=あまねく及ぶ)」 |
① 万代に年は来経とも梅の花絶ゆることなく咲きわたるべし [筑前介佐氏子首] (万5-834) ② -つむじかも い巻き渡ると 思ふまで 聞きの畏く-(万2-199) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わづき | 未詳-区別の意のワキと、方法・状態の意のタヅキとが混線した語か。 「万葉集」中、用例の一首のみ。 |
霞立つ 長き春日の 暮れにける わづきも知らず(万1-5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わづかやま [和束山] | 京都府相楽郡和束町の地にある山。安積皇子の墓は同町白栖小字大勘定にあり、久邇京跡より東北約5キロメートル。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わる [割る・破る] | 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 ① 物がわれる。くだける。さける。② 分かれる。別れる。 ③ 分裂する。不和となる。④ 心が乱れる。⑤ (秘密などが) 露見する。 |
④ 高山ゆ出で来る水の岩に触れ割れてぞ思ふ妹に逢はぬ夜は(万11-2725) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔他動詞ラ行四段〕 ① くだく。やぶる。② 分け配る。割り当てる。③ 押し分ける。打ち破る。 ④ ことをわけて細かく言い聞かせる。 |
① 岩戸割る手力もがも手弱き女にしあればすべの知らなく(万3-422) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| われ [我・吾] | 〔人称代名詞〕 ① 自称の人名代名詞。わたくし。 ② その人自身。自分。 ③ 対称の人名代名詞。おまえ。あなた。そなた。 |
-松が根や 遠く久しき 言のみも 名のみも我は 忘らゆましじ(万3-434) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【「われ」「なれ」「おのれ」】 「われ」は、「わ(我・吾)」に接尾語「れ」が付いた形で、「あ(我・吾)」に「れ」の付いた「あれ」と同義である。また、、「な(汝)」に「れ」の付いた「なれ」と対応する。一人称にも二人称にも用いる点は、「おのれ」と同じである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゐ [井] | 〔名詞〕 ① 泉あるいは川から水を汲むところ。 ② 穴を掘って、地下水を汲み上げるようにしたところ。井戸。 |
① 春霞井の上ゆ直に道はあれど君に逢はむとた廻り来も(万7-1260) ② 馬酔木なす栄えし君が掘りし井の石井の水は飲めど飽かぬかも(万7-1132) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゐあかす [居明かす] | 〔他動詞サ行四段〕 起きたままで夜を明かす。徹夜する。 |
居明かして君をば待たむぬばたまの我が黒髪に霜は降るとも(万2-89) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゐなの [猪名野] | 〔地名〕 兵庫県伊丹市を中心に、尼崎市・川西市、更に大阪府豊中市の一部をも含む猪名川沿いの平野。 【有斐閣「萬葉集全注巻三-279 注『猪名野』」】 兵庫県伊丹市を中心に広がる風光明媚な猪名川流域の平野。 |
我妹子に猪名野は見せつ名次山角の松原いつか示さむ(万3-282) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゐる [居る] | 〔自動詞ワ行上一段〕【ゐ・ゐ・ゐる・ゐる・ゐれ・ゐよ】 ① 座る。しゃがむ。② とまる。とどまる。(波風が)おさまる。 ③ 住む。いる。④ 存在する。ある。⑤ ある地位につく。 ⑥ (水・つらら・草などが)生じる。 ⑦ (「腹がゐる」の形で)怒りがおさまる。 ⑧ (動詞の連用形または助詞「て」の下につく場合) 動作の継続や状態・結果の存続を表す。 |
① み崎廻の荒磯に寄する五百重波立ちても居ても我が思へる君(万4-571) ② つれもなき佐田の岡辺に帰り居ば島の御階に誰れか住まはむ(万2-187) ② 滝の上の三船の山に居る雲の常にあらむと我が思はなくに(万3-243) ② -淡路島 礒隠り居て いつしかも この夜の明けむと さもらふに-(万3-391) ③ みさご居る磯廻に生ふるなのりその名は告らしてよ親は知るとも(万3-365) ⑧ -身もたな知らず 鴨じもの 水に浮き居て 我が作る 日の御門に-(万1-50) ⑧ -夜はも 夜のことごと 伏し居嘆けど 飽き足らぬかも(万2-204) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【古語の「ゐる」】 現代語では「いる」と表記する。現代語の「いる」は、人・動物など生物の存在を表し、物など無生物の存在には「ある」が用いられると、主語の違いで区別されて使われているように思える。 これに対し、古語の「ゐる」は止って動かずじっとしているの意味を表す語で、現代語「いる」とは意味が異なっている。 しかし、現代語の「いる」も「渋滞の先頭にバスがいる」のように、無生物でも動いて行く物の存在にも用い、「いる」「ある」の違いは、動くと意識されるものの「いる」、動くと意識されないものの「ある」ということと考えられる。現代語の意味をこのように捉えることとで、古語の「ゐる」、現代語の「いる」の両者の違いも分かってくる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゑ | 〔間投助詞〕《上代語》 苦痛や悲嘆などの気持ちを添えて、詠嘆の意を表す。~よ。~なあ。 〔接続〕活用語の」終止形ほか、種々の語に付く。 【参考】 「よしゑ」「よしゑやし」「しゑや」 など、副詞・感動詞の一部にも用いられた。 |
山の端にあぢ群騒き行くなれど我れはさぶしゑ君にしあらねば(万4-489) 世の中は恋繁しゑやかくしあらば梅の花にもならましものを [豊後守大伴大夫](万5-823) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゑひなき [酔ひ泣き] | 〔名詞〕 酒に酔って泣くこと。「泣き上戸」。 |
賢しみと物言ふよりは酒飲みて酔ひ泣きするし優りたるらし(万3-344) 世の中の遊びの道にかなへるは酔ひ泣きするにあるべくあるらし(万3-350) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゑふ [酔ふ] | 〔自動詞ハ行四段〕 ① 酒や乗り物に酔う。② 中毒する。③ 心を奪われ、我を忘れる。 |
賢しみと物言ふよりは酒飲みて酔ひ泣きするし優りたるらし(万3-344) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゑまふ [笑まふ] | 〔四段動詞「笑(ゑ)む」の未然形+上代の反復・継続の助動詞「ふ」〕 ① 微笑む。② 花が咲く。花のつぼみがほころびる。 |
-常なりし 笑まひ振舞 いや日異に 変らふ見れば 悲しきろかも(万3-481) -心には 思ひほこりて 笑まひつつ 渡る間に 狂れたる 醜つ翁の-(万17-4035) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| を [牡・雄・男・夫] | 〔名詞〕 ① おす。雄花。② おとこ。男性。③ 夫。④ (陰陽) の陽。 |
① 高圓の秋野の上の朝霧に妻呼ぶ壮鹿出で立つらむか(万20-4343) ② -もののふの 八十伴の男を 召し集へ 率ひたまひ 朝狩に-(万3-481) ② -もののふの 八十伴の男と 出で行きし 愛し夫は 天飛ぶや-(万4-546) ③ 汝(な)をきてをはなし、汝(な)をきてつまはなし(記・上) ④ 陰(め)を分かれざりし時(神代紀) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| を | 〔格助詞〕目的語や場所・時間を表わす連用修飾語に用いる。 現代語の「を」とほぼ同じ。 ① ア 動作の対象を示す。~を イ 動作の相手となる対称を示す。~に。~と ウ 自動詞や形容詞の主格にあたる語句を対象として示す。~が ②(移動の動作に対して)起点・経過地点を示す。~を ③(時間的動作に対して)持続する時間を示す。~を ④(~を~に〔にて〕の形で)「~を~として」の意を表わす。 ⑤(〔寝(い)を寝(ぬ)〕〔音(ね)を泣く〕の形で)強調する。 〔接続〕体言・活用語の連体形に付く。 |
① ア 我を待つと君が濡れけむあしひきの山のしづくにならましものを(万2-108) ① イ -石見の海 角の浦廻を 浦なしと 人こそ見らめ - (万2-131) ① イ -頼めりし 児らにはあれど 世の中を背きしえねば かぎろひの-(万2-210) ① ウ -天雲を 日の目も見せず 常闇に 覆ひ賜ひて 定めてし-(万2-199) ① ウ ひとり寝て絶えにし紐をゆゆしみと為むすべ知らに音のみしそ泣く(万4-518) ② 夢にだに見ざりしものをおほほしく宮出もするかさ桧の隈廻を(万2-175) ② 川風の寒き長谷を嘆きつつ君があるくに似る人も逢へや(万3-428) ③ 長き夜をひとりや寝むと君が言へば過ぎにし人の思ほゆらくに(万3-466) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| を | 〔接続助詞〕 ① 軽い確定の逆接を表わす。~のに ② 軽い確定の順接を表わす。~ので ③ 軽く前後をつなぐ。~と、~が。 〔接続〕活用語の連体形に付く。 |
①-栂の木の いや継ぎ継ぎに 天の下 知らしめししを-(万1-29) ①- 隠口の 初瀬の山は 真木立つ 荒き山道を-(万1-45) ① 草枕旅行く君と知らませば岸の埴生ににほはさましを(万1-69) ① 風流士と我れは聞けるをやど貸さず我れを帰せりおその風流士(万2-126) ① 高照らす我が日の御子のいましせば島の御門は荒れずあらましを(万2-173) ① 一日には千たび参りし東の大き御門を入りかてぬかも(万2-186) ① -思ひ居れか 栲縄の 長き命を 露こそば 朝に置きて 夕には-(万2-217) ① -梓弓 音聞く我れも 凡に見し こと悔しきを 敷栲の 手枕まきて―(万2-217) ① 人見ずは我が袖もちて隠さむを焼けつつかあるらむ着ずて来にけり(万3-271) ② 君により言の繁きを故郷の明日香の川にみそぎしに行く(万4-629) ③ -かきのくづれよりかよひけるを- (古恋三詞書-632) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| を | 〔間投助詞〕 ①(文中に用いられた時)強調を示す。~ね ②(文末に用いられた時)感動・詠嘆を表わす。~なあ (〔~を~み〕の形で)「~が~ので」の意を表わす。 〔接続〕種々の語に付く。②は「もの・まし」に付くことが多い。 |
① 橘の蔭踏む道の八衢に物をぞ思ふ妹に逢はずして [三方沙弥](万2-125) ① 生ける者遂にも死ぬるものにあればこの世なる間は楽しくをあらな (万3-352) ② 我妹子をいざ見の山を高みかも大和の見えぬ国遠みかも(万1-44) ② かくばかり恋ひつつあらずは高山の磐根しまきて死なましものを (万2-86) ② 人言を繁み言痛みおのが世にいまだ渡らぬ朝川渡る(万2-116) ② -見まく欲しけど やまず行かば 人目を多み まねく行かば-(万2-207) ② 我妹子に恋ひつつあらずは秋萩の咲きて散りぬる花にあらましを (万2-120) ② 夢にだに見ざりしものをおほほしく宮出もするか佐日の隈廻を(万2-175) ② 朝日照る佐田の岡辺に泣く鳥の夜哭きかへらふこの年ころを(万2-192) ② 三津の崎波を恐み隠り江の舟公宣奴嶋尓(万3-250) ② ちはやぶる神の社しなかりせば春日の野辺に粟蒔かましを(万3-407) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| を [緒・弦・命] | 〔名詞〕 ① 糸、紐などの総称。② 弓、楽器などに張る弦。 ③(大切なものを繋ぎ止める意から)命。生命。 ④(~の緒、の形で)長く続く物事。 格助詞「を」に係助詞「は」のついた「をは」の濁音化したもの。 動作・作用の対象を強く示す意を表わす。 |
① 東人の荷前の箱の荷の緒にも妹は心に乗りにけるかも [禅師](万2-100) ① 世間は常かくのみか結びてし白玉の緒の絶ゆらく思へば(万7-1325) ② み薦刈る信濃の真弓引かずして弦はくるわざを知ると言はなくに (万1-97) ③ 己がをおほにな思ひそ庭に立ち笑ますがからに駒に逢ふものを (万14-3556) ④ 我が形見見つつ偲はせあらたまの年の緒長く我れも偲はむ(万4-590) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をか [丘・岡] | 〔名詞〕土地の小高くなったところ。 | 篭もよ み篭持ち 堀串もよ み堀串持ち この岡に 菜摘ます子-(万1-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をぐし [小櫛] | 〔名詞〕[「を」は接頭語] くし。 | 志賀の海女は軍布刈り塩焼き暇なみくしげの小櫛取りも見なくに(万3-281) 君なくはなぞ身装はむ櫛笥なる黄楊の小櫛も取らむとも思はず(万9-1781) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をさむ [治む] | 〔他動詞マ行下二段〕【メ・メ・ム・ムル・ムレ・メヨ】 ① しずめる。落ち着かせる。② 統治する。国などを治める。 ③ 建物などを造営する。修理する。管理する。 ④ 治療する。看護して病気をなおす。⑤ (「修」とも書く。) 整え正す。 |
② -高麗剣 和射見が原の 仮宮に 天降りいまして 天の下 治めたまひ-(万2-199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をさむ [収む・蔵む・納む] | 〔他動詞マ行下二段〕【メ・メ・ム・ムル・ムレ・メヨ】 ① しまっておく。所蔵する。収納する。 ② 取り入れる。収穫する。受け入れる。受領する。 ③ やり遂げる。終わりにする。④ 葬る。埋葬する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をし [鴛鴦] | 〔名詞〕おしどり(=水鳥の名)の古名。 雌雄離れずにいることが多いので、夫婦仲のよいことにたとえる。 |
人漕がずあらくもしるし潜きする鴛鴦とたかべと船の上に住む(万3-260) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をし [愛し] | 〔形容詞シク活用〕 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 かわいい。いとしい。 |
香具山は 畝傍を愛しと 耳成と 相争ひき 神代より-(万1-13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をし [惜し] | 〔形容詞シク活用〕 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 失うにしのびない。惜しい。残念だ。捨て難い。 |
玉櫛笥覆ふを安み明けていなば君が名はあれど吾が名し惜しも(万2-93) 大夫の靫取り負ひて出でて行けば別れを惜しみ嘆きけむ妻(万20-4356) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をじか [牡鹿] | 〔名詞〕牡の鹿。〔季語:秋〕 =小牡鹿(さをしか) | 夏野行く小鹿の角の束の間も妹が心を忘れて思へや(万4-505) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をすくに [食す国] | 天皇が統治なさる国。 |
-荒栲の 藤原が上に 食す国を 見したまはむと みあらかは-(万1-50) -大君の 命畏み 食す国の 事取り持ちて 若草の 足結ひ手作り- (万17-4032) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【有斐閣「万葉集全注巻第一-50 をすくに」注】 統治される国の意。「高天原」に対する「天の下」より、さらに政治性、社会性の強い語。「食す」は、「食ふ」の敬語。 統治者は諸国奏上の五穀を食べることで国々の領知を果たすという考えから、治めるの意になった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をちかた [彼方・遠方] | 〔名詞〕遠く隔たったほう。遠方(えんぽう)。⇔「此 (こ) の方」 | 雲をのみつらきものとて明かす夜の月よ梢にをちかたの山 (新古今雑上-1546) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をちかたのべ [彼方野辺] | 〔名詞〕遠くの方にある野。 | 大名児を彼方野辺に刈る草の束の間も我れ忘れめや(万2-110) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をちこち [彼方此方・遠近] | 〔名詞〕 ① 遠い方と近い方。あちこち。ここかしこ。 ② 未来と現在。 |
① -梶引き折りて をちこちの 島は多けど 名ぐはし 狭岑の島の-(万2-220) ① をちこちのたづきも知らぬ山中に おぼつかなくも喚子鳥かな(古今春上-29) ② 真玉つくをちこち兼ねて言は言へど逢ひて後こそ悔にはありといへ(万4-677) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をちの [越智野] | 〔地名〕【有斐閣「万葉集全注巻二-194 注『をちのおほの』】 越智野は、奈良県高市郡高取町越智を中心とする野。 -中略-大野は人里離れた荒野を言う。 |
-玉垂の 越智の大野の 朝露に 玉藻はひづち 夕霧に-(万2-194) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をつ [復つ・変若つ] | 〔自動詞タ行上二段〕【チ・チ・ツ・ツル・ツレ・チヨ】 もとにもどる。若返る。 |
我が盛りまたをちめやもほとほとに奈良の都を見ずかなりなむ(万3-334) いにしへゆ人の言ひ来る老人の変若つといふ水ぞ名に負ふ瀧の瀬(万6-1038) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をとこじもの [男じもの] | 〔副詞〕[「じもの」は接尾語] 男であるのに。男らしくもない。 | - 取り与ふる 物しなければ 男じもの わき挟み持ち-(万2-210) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をとめ [少女・乙女] | 〔名詞〕 ① 若い娘。未婚の女性。「をとめこ」とも。 ② 五節の舞姫。 |
① 嗚呼見の浦に舟乗りすらむをとめらが玉裳の裾に潮満つらむか (万1-40) ① -たづきを知らに 網の浦の 海人娘子らが 焼く塩の 思ひぞ焼くる(万1-5) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をとめ [処女] | 〔地名〕 | 処女を過ぎて夏草の茂る野島の埼で小屋がけして泊っているよわれわれは (万3-251左注) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【小学館「新編日本古典文学全集万葉集1『付録地名一覧』」】 兵庫県芦屋市および神戸市東部一帯の地をいうか。菟原(うない)処女(一八〇一)の伝説が生まれた地名であろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をは [尾羽] | 〔名詞〕鳥の尾と羽 | うち靡く春さり来れば小竹の末に尾羽打ち触れて鴬鳴くも(万10-1834) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をば | 〔格助詞「を」に係助詞「は」のついた「をは」の濁音化したもの〕 動作・作用の対象を強く示す意を表わす。 |
-取りても見ず 秋山の 木の葉を見ては 黄葉をば 取りてぞ偲ふ- (万1-16) -日女の命 [一云 さしあがる 日女の命] 天をば 知らしめすと-(万2-167) 我が君はわけをば死ねと思へかも逢ふ夜逢はぬ夜二走るらむ(万4-555) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をふ [終ふ] | 〔他動詞ハ行下二段〕【ヘ・ヘ・フ・フル・フレ・ヘヨ】 終える。終わらせる。終わりまでやる。 |
天地とともに終へむと思ひつつ仕へまつりし心違ひぬ(万2-176) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をぶね [小舟] | 〔「を」は接頭語〕小さな舟。 | 武庫の浦を漕ぎ廻る小舟粟島をそがひに見つつともしき小舟(万3-361) -葦刈ると 海人の小舟は 入江漕ぐ 楫の音高し そこをしも-(万17-4030) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をみな [女] | 〔名詞〕若い女。女性。古くは、美人。⇒「をんな」 | をみな先に言へるは良からずとつげ給ひき(記上) 詔 (みことのり) して曰 (のたま) はく、 『諸氏 (もろもろのうぢ) をみなを貢 (たてまつ) れ』とのたまふ(天武紀) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をや | 〔格助詞「を」+係助詞「や」〕 ① (「や」が疑問の意を表し) ~を~だろうか。 ② (「や」が反語の意を表し) ~を~だろうか (いや、~ない)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をや | 〔間投助詞「を」+間投助詞「や」。文末に用いる〕 ① 強い詠嘆の意を表す。~だなあ。~だよ。 ② (多く「いはんや~(において)をや」の形で) 程度の低い例をあげ、程度の高い物事を類推させる意を表す。 (まして) ~はいうまでもないことよ。の |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をり [居り] | 〔自動詞ラ変〕【ラ・リ・リ・ル・レ・レ】 ① 存在する。いる。ある。 ② 座っている。 |
① 妹が家も継ぎて見ましを大和なる大島の嶺に家もあらましを [一云 妹があたり継ぎても見むに] [一云 家居らましを](万2-91) ② -敷栲の 床の辺去らず 立てれども 居れども ともに戯れ -(万5-909) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔補助動詞ラ変〕 ① (動詞の連用形の下に付いて) 動作・状態の存続を表す。「~ている」 ② 他の動作をいやしめののしる意を表す。「~やがる」 |
① -心を痛み ぬえこ鳥 うら泣け居れば 玉たすき 懸けのよろしく-(万1-5) ① -なよ竹の とをよる子らは いかさまに 思ひ居れか-(万2-217) ① まそ鏡見飽かぬ君に後れてや朝夕にさびつつ居らむ(万4-575) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をりかざす [折り挿頭す] | 〔他動詞サ行四段〕(木の枝や花などを) 折って飾りとする。 | -うつそみと 思ひし時に 春へは 花折かざし 秋立てば-(万2-196) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をりふす [折り伏す] | 〔自動詞サ行四段〕 (手足を) 折り曲げて横になる。膝を折り曲げて身を伏す。 〔他動詞サ行下二段〕【セ・セ・ス・スル・スレ・セヨ】 折り曲げて横にする。折り倒す。 |
〔他動詞サ行下二段〕 神風の伊勢の浜荻折り伏せて旅寝やすらむ荒き浜辺に(万4-503) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をる [折る] | 〔自動詞ラ行四段〕 波などが折れるようにくずれる。波などが寄せてはかえす。 |
今日もかも沖つ玉藻は白波の八重をるが上に乱れてあるらむ(万7-1172) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をる [折る] | 〔自動詞ラ行下二段〕【レ・レ・ル・ルル・ルレ・レヨ】 ① 曲がる。曲がって行く。② 曲がって切れる。折れる。 ③ 気がくじける。服従する。負ける。 ④ 和歌で第三句(=腰の句)と第四句との続き具合が悪い。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をる [折る] | 〔他動詞ラ行四段〕 ① 曲げる。折り曲げる。② 折りとる。手(た)折る。③ 折りたたむ。 |
① -いさなとり 海を恐み 行く船の 梶引き折りて をちこちの-(万2-220) ① 秋の野に咲きたる花を指折りかき数ふれば七種の花 [其一](万8-1541) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をろがむ [拝む] | 〔自動詞マ行四段〕《上代語》おがむ。礼拝する。 | かしこみて仕へまつらむをろがみて仕へまつらむ(紀推古) -鹿こそば い這ひ拝め 鶉こそ い這ひもとほれ 鹿じもの い這ひ拝み-(万3-240) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ををし [雄々し] | 〔形容詞シク活用〕 【シカラ・シク(シカリ)・シ・シキ(シカル)・シケレ・シカレ】 男らしい。勇ましい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ををる [撓る] | 〔自動詞ラ行四段〕たわみ曲がる。いっぱいの葉や花で枝がしなう。 | -絶ゆれば生ふる 打橋に 生ひををれる 川藻もぞ 枯るれば生ゆる-(万2-196) -山辺には 花咲きををり 川瀬には 鮎子さ走り いや日異に-(万3-478) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| をんな [女] | 〔名詞〕[「をみな」の撥音便] ① (成人した) 女性。婦人。② 妻。恋人である女。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】 「をんな」「をみな」「をうな」は比較的若い女性をさし、年をとって老女になると「おんな」「おみな」「おうな」となる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||