巻第十七の最後の歌は天平二十年(748)正月の作であったが、巻第十八はそれから約二ヶ月後から始まっている。家持は橘諸兄の使者田辺福麻呂の来訪を受ける。福麻呂は家持と顔見知りであり、歌才の面で諸兄から認められていたとおぼしく、それより四年前のことか、元正太上天皇が諸兄の難波の邸に幸した時に詠まれた歌を記憶していて、家持に伝誦した。元正天皇はその前年暮頃から枕席安からず、間もなく崩ずることになる。そのことは万葉集に記されず、直接的影響はないが、これ以後、政局は少しずつ変化し始める。この前後、正確な日付は不明だが、一族であり掾であった池主が隣国越前の掾に転じ、後任に久米広縄が着任する。それでも越前から池主は家持に歌(4097〜4099)を詠み贈り、家持はそれに返歌(4100〜4103)を届けている。翌天平二十一年(749)二月、陸奥国から国産最初の黄金が出たことから、四月、天平感宝と改元する。その前から東大寺廬舎那仏の建立を進めそれに鍍金する黄金の不足を嘆いていた聖武天皇は、そのことを慶賀し、皇祖を初めとする諸神仏に感謝する詔書を発し、諸臣の功を称えたが、なかんずく大伴・佐伯二氏の忠誠を嘉賞し、「海行かば」の言立てまで引かれていることに感激して、「陸奥国に金を出だす詔書を賀く歌」(4118)を作る。その後半を引くならば次のごとくにある。
| ・・・大伴の 遠つ神祖の その名をば 大久米主と 負ひ持ちて 仕へし官 海行かば 水漬く屍 山行かば 草生す屍 大君の 辺にこそ死なめ かへり見は
せじと言立て 大夫の 清きその名を いにしへよ 今のをつづに 流さへる 祖の子どもぞ 大伴と 佐伯の氏は 人の祖の 立つる言立て 人の子は 祖の名絶たず
大君に まつろふものと 言ひ継げる 言の官ぞ 梓弓 手に取り持ちて 剣大刀 腰に取り佩き 朝守り 夕の守りに 大君の 御門の守り 我れをおきて
人はあらじと いや立て 思ひし増さる 大君の 御言のさきの 聞けば貴み 貴くしあれば |
佐保大納言家の当主たるべき身として、一族の者に呼び掛け、先祖の名誉を汚さないように努めよう、結束しよう、と訓諭するような語調になっている。この余韻でまた家持は、いずれの日か吉野行幸が行われるであろう、その日のための予作歌を作ることになる。それには比べられないが、題材が特異な点で無視できないのは、配下の尾張少咋という史生が、都に妻を持ちながら、遊女と同棲している、とのかどでこれに反省を促す、という趣旨の歌(4130〜4134)を詠み載せていることである。これが果たして重婚という罪に当るか否か疑問であるが、その歌の前文に「七出例」「三不去」「両妻例」などの法律条文を並べて大仰に構え、詰問・教諭する形で私行を指弾する内容の歌である。用語の上でも「父母を 見れば貴く 妻子見れば かなしくめぐし」とか「然にはあらじか」など、巻第五の山上憶良の「惑へる情を反さしむる歌」(804)からの借用であることは明らかで、筑前と越中との差こそあれ、共に儒教道徳の体現者たることを要求された国司の地位なればこその作品という意味で興味深い。しかし、これが当事者尾張少咋に対する訓戒のために作られたとは考えられず、単なる机上の作物として著したものではなかろうか。公務の傍ら、なんとしても四巻の継ぎ足し編纂を達成すべく、それも量の増大のみならず、質の上でもなるべく多彩な広がりを求めて、あえて家持はこのような小事件さえも事々しげに取り上げたのではないだろうか。 |
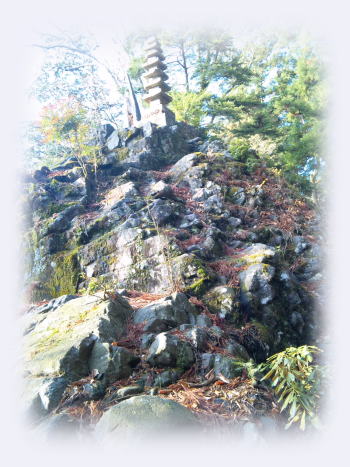 |