| 【歌意2916】 |
ひたすら恋慕いつづけて、
今はともかく、後には必ず逢えるだろうと、じぶんを慰める
その気持ちが、なかったなら
わたしは生きていることができるだろうか...できやしない
|
逢うこともなく、終る恋もある
しかし、人の普通の感情では、恋したら
せめて一度でも、逢いたい、語らいたい、と思うのではないか
そんな想いがあるからこそ、私は生きることができる
そう、詠者はいう
その通りだと思う
自分の想いを伝えることが叶わなくても
逢えさえすれば、少なくとも、少々の慰めにはなる
こんなに想い続けていたのだから、と...
「逢う」ことへの、命に等しい願望
命がけの「想い」があればこそ、「恋い慕う気持ち」は輝くものだ
ここに、もう一つの「のちもあはむと」がある
もっとも、ここに引く「のちもあはむと」は、
「ゆりもあはむと」と、訓じられている
掲題歌の「のちも」は「後裳」が原文だが、
次の歌は、「由利母」で、「ゆりも」と訓じているのは
ユリ科の植物の総称である「百合(ゆり)」と、
「後日・将来・のち」を意味する上代語の「ゆり」をかけている
| (庭中花作歌一首[并短歌])反歌(二首) |
| 佐由利花 由利母相等 之多波布流 許己呂之奈久波 今日母倍米夜母 |
| さ百合花ゆりも逢はむと下延ふる心しなくは今日も経めやも |
| さゆりばな ゆりもあはむと したはふる こころしなくは けふもへめやも |
| 天平感宝元年閏五月廿六日大伴宿祢家持作 |
| 巻第十八 4139 大伴宿禰家持 |
初句の「さゆりばな」は、同音の「後(ゆり)」にかかる枕詞、だとある
この枕詞から、必然的に「ゆり」が導かれたのだろうか
あるいは、第二句の「のちもあはむと」の語意に合わせ
語意が変わらなく、「さゆりばな」を添えることで、
「のち」を「ゆり」と詠いたかったのか...
現代の私がこの手法に触れれば、「技巧」的だなあ、と思ってしまうが
考えてみると、「のち」のことを、上代では「ゆり」とも言ったのなら
決して技巧を凝らした「ことば」ではなく
これも当然普通に詠み込まれた歌だということだろう
〔4139〕歌は、大伴家持の詠歌だが、その背景は後日採り上げよう
この歌の歌意、
小百合花の名のように、のちに必ず逢おう、と心中では思う
そのように思わなければ、一日たりとも過ごせやしない
この歌では「恋」とか「慕ふ」という語句はないが
柔らかさの中でも、「したはふる こころしなくは」で、
その覚悟を感じさせる
同じような手法の、次の歌も採り上げておく
この歌は、2013年7月15日に掲載しているが、ここで再掲する
| 又家持和坂上大嬢歌(二首) |
| 相聞 |
| 後湍山 後毛将相常 念社 可死物乎 至今日<毛>生有 |
| 後瀬山後も逢はむと思へこそ死ぬべきものを今日までも生けれ |
| のちせやま のちもあはむと おもへこそ しぬべきものを けふまでもいけれ |
| 巻第四 742 相聞 大伴宿禰家持 |
歌意、
そう、後瀬山というように、後に逢おうと思えばこそ
死ぬほどの辛さや苦しみを耐えて、今日まできたのだよ
この歌も、大伴家持の詠歌だ
先の「さゆりばな」「ゆりもあはむと」と同じように
「後瀬」原義は、「下流の瀬」だが、もう一つの意味もある
それは「のちに会う機会」という意味
後に逢える、という名の山のように、「のちもあはむと」
ここでも、「のちにあはむと」という言葉によって、
それに生きる支えを受けている
「のちにあはむと」とは...この時代の、生きるための「エネルギー」のようだ
|
|
掲載日:2013.10.01.
| 正述心緒 |
| 戀々而 後裳将相常 名草漏 心四無者 五十寸手有目八面 |
| 恋ひ恋ひて後も逢はむと慰もる心しなくは生きてあらめやも |
| こひこひて のちもあはむと なぐさもる こころしなくは いきてあらめやも |
| 巻第十二 2916 正述心緒 作者不詳 |
| 【2916】語義 |
意味・活用・接続 |
| こひこひて[戀々而 ] |
| こひこひ[恋ひ恋ふ] |
[他ハ上二・連用形]恋し続ける・ひたすら恋い慕う |
| て[接続助詞] |
[単純接続]~て・そして |
連用形につく |
| のちもあはむと[後裳将相常] |
| も[係助詞] |
[仮定希望]せめて~だけでも・~なりとも |
種々の語につく |
| む[助動詞・む] |
「推量意志・終止形」~よう・~つもりだ |
未然形につく |
| なぐさもる[名草漏] |
| なぐさもる[慰もる] |
[下二段「慰(なぐさ)む」の連体形「なぐさむる」の転、慰める |
| こころしなくは[心四無者] |
| し[副助詞] |
語調を整え、強意を表す |
体言につく |
| は[係助詞] |
[順接の仮定条件]~ならば |
| (形容詞型活用の連用形「く・しく」につき)順接の仮定条件を表す(「なく」は形ク・連用形) |
| いきてあらめやも[五十寸手有目八面] |
| あら[有り・在り] |
[補助動詞ラ変・未然形]~いる・~ある |
| めやも |
[反語]~だろうか(いや、~でないなあ) |
| 〔成立〕推量の助動詞「む」の已然形「め」+反語の終助詞「やも」 |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [も]『全集』より |
ここでの「も」は、この「後も逢はむ」という形の他に
「後も我が妻」(2432)、「後も我が松」(397)などとして現れることが多く
今すぐにでは無理だが、未来はきっと思い通りになる、という気持ちがある |
| |
| [あら] |
自動詞ラ変「有り・在り」は、「存在する・無事でいる・過ごす」などが本来の意味
この歌のように、「補助動詞」として、
助詞「て」(他に「つつ」)の付いた語の下について、動作・作用の存続の状態を表す |
|

 |
| 【歌意2918】 |
遠く、よその国まで求婚に来たが
まだ大刀の緒さえも解いていないのに
もう夜が明けてしまったようだ
随分、長く歩き通したものだ...ここまできたのだから...
|
「大刀の緒」を解くというのは、
その日の旅程を終え、寛ぐために、大刀を置く、ということなのだろう
そう、素人は思ってしまうが...
従って、その「緒も解かない」うちに、夜が明けるというのは
一日の行程としては、かなりの時間を要した、ということだ
やっと、目的の国に着いた、しかし気づけば
もうすっかり夜も明けてしまっている
もとより、何日も懸かるような遠さであれば
こんな夜通し歩き続けることもないだろう
おそらく、一日の行程としては、ぎりぎりのところのように思われる
大刀を携えてのことであれば、この男もそこそこの韋丈夫
その健脚を持ってしても、やはりこんな時間になってしまった
それほど、求婚する相手に、早く逢いたかったのだろう
普通であれば、きっとどこかで一晩泊って、
それからあくる日の朝にでも到着の予定ではなかったか
そして、こんなにしてまで、懸命に歩き通した
その成果を、何としても得たいものだ...その胸中は、そのことで一杯だろうな、きっと
この歌は、記紀にもその伝承があり
当然年代的には、それらが先行し、万葉の人々に詠い継がれた、というのだが...
私には、そうとも言い切れないものがある
こうした言い回し...「記紀」などの古歌謡が伝誦されて、というのは
必然的に、「記紀」の記載内容が、そのまま「古い」ことを前提としている
勿論、「記」はともかく、正史であるとされる「紀」だから
そのような一片の「疑念」は、取るに足らないことだが
冷静に考えてみれば、万葉歌の残された時代も
「記紀」が編纂された時代も、それほど大きく変わらない、ということだ
ある時点から、過去に遡って、いくらそれが「歴史」です、といわれても
それは「真の歴史」とは言えないと思う
同時代の積み重ねが、途切れることなく「継承」されること
それが、「歴史のシステム」ではないかと思う
今の私に、昔ほど「古代史」に熱が入らなくなったのも
その限界を知り、さらに「万葉集」に出逢えたからだ
過去に「真実」を探がす、のではなく
過去の時代の「人々の想い」に、惹かれ始めてしまった
少なくとも、7世紀以前の歴史は、残念ながら日本国に残る資料だけでは解らないだろし
その種の研究や論文は数多くあるので、下手に手を付ければ、より混乱してしまう
私には、万葉歌のような、人の「想い」に、
「歴史のひとかけら」でも想いを馳せられれば、それで充分だ
その作業にしても、おそらく生涯をかけても...終りは迎えられないだろうが...
掲題歌の作者のように、自分の歩いた行程を、
このように「歌」に残せる環境があった、そしてその頃の巷の歌謡にもあるように
同じような状況で、人はこうして詠ったのだろう、と
万葉の時代は、そんな時代でもあったのだ
このような歌が、伝承歌の類として広く詠われているとしたら
この歌の続編とか、あるいはイメージを重ねられる歌もるということだ
また、夢を見ることができる
|
|
掲載日:2013.10.02.
| 正述心緒 |
| 他國尓 結婚尓行而 大刀之緒毛 未解者 左夜曽明家流 |
| 他国によばひに行きて大刀が緒もいまだ解かねばさ夜ぞ明けにける |
| ひとくにに よばひにゆきて たちがをも いまだとかねば さよぞあけにける |
| 巻第十二 2918 正述心緒 作者不詳 |
| 【2918】語義 |
意味・活用・接続 |
| ひとくにに[他國尓 ] |
| ひとくに[人国・他国] |
(日本国内の)他の国・地方の国 |
| よばひにゆきて[結婚尓行而] |
| よばひ[婚ばひ・呼ばひ] |
求婚すること・結婚を求めて名を呼びかけること |
| たちがをも[大刀之緒毛] |
| が[格助詞] |
[連体修飾語・所有]~の |
体言につく |
| を[緒] |
糸・紐などの総称 |
| も[係助詞] |
(程度の類推)~さえも |
体言につく |
| いまだとかねば[未解者] |
| いまだ[未だ] |
[副詞]まだ |
| (下に打消しの語を伴って、その動作をするときがきていないことを示めす) |
| とか[解く] |
[他カ四・未然形]結び目をほどく |
| ねば |
「ば」が逆接の意の場合、「も~ねば」の形で 、
~しないのに・~しないうちに |
| 〔成立〕打消しの助動詞「ず」の已然形「ね」+接続助詞「ば」 |
| さよぞあけにける[左夜曽明家流] ぞ~ける〔係り結び〕 |
| さよ[小夜] |
「さ」は接頭語、夜 |
| ぞ[係助詞] |
[強調]~が (文中にある場合、まさにその物である、と強調) |
| あけ[明く] |
[自カ下二・連用形]夜が明ける・明るくなる |
| に[格助詞] |
[強調]~に 〔接続〕強調の場合は、動詞の連用形につく |
| ける[助動詞・けり] |
[詠嘆を込めて、今気づいた意]~たことよ |
連用形につく |
| 掲題歌トップへ |
|
 |

| 「しぬべきものか」...さときこころ、ことばにすれば... |
|
|
|
| 【歌意2919】 |
「ますらたけを」を自負していた、このわたしの
聡明でしっかりしていた精神、心構え
それも、今となっては、見ることもない
「恋」という、とんでもない奴のせいで
わたしは、死んでしまうにちがいない
|
男であっても、女であっても
その理性までも失わせてしまうのが「恋」
なるほど、この歌のように「擬人化」でもして恨みたくもなるだろう
この歌で面白いと思ったのは
男が、「ますらを」であることを自負しているような詠い振りだ
確かに、そんな「ますらを」と言われる自分でも、「恋の奴」には歯が立たない
それほど、「恋してしまう力」は、生半可なものじゃない、と言いたいのだろう
しかし、敵わぬ相手でも、命をかけて挑む姿もまた、真の「ますらを」ではないか
その意味では、この作者...もともとから「真のますらを」ではない、と
図らずも告白したようなものだ、と思う
このサイトでも、何度か持ち出したが 〔「古今集」サイト、もう何年も手付かず〕
『古今集』巻第十二・恋歌二・615 紀友則の歌を、私はいつも思いだす
| いのちやは なんぞはつゆの あだものを あふにしかへば をしからなくに |
| 古今集 巻第十二 恋歌二 615 紀友則 |
命なんて、何だというのだ
この俺の、露みたいな取るに足らない命なんぞ、
お前に逢えるなら、いつだってくれてやる
この表現、いかにも感情的で、まさに理性を失くした語の「想い」が伝わる
しかし、本当にそうだろうか
俺は「ますらを」だと言われていた、というよりも
俺の命なんて「露みたいに取るに足らない」ものだ、と言い切るほうが
私には、より「理性的」に思える
少なくとも、恋して感情を抑えられない「自分」を見詰めている
そして、何よりも惹かれるのは、そんな「俺」でも
「命よりもお前が大切だ」と、無茶振りを理性で訴えているのではないか
「恋に死にそうだ」という「元ますらを」よりも
一見粗野のように見える友則の激情こそが、
「狂人の理性」かもしれないが、グッと惹かれるものがある
江戸時代の国学の大家・賀茂真淵が提唱した「ますらをぶり」
その理想の歌集を『万葉集』としたということだが
この二首の比較においては、私には逆のように思えてならない
勿論、『万葉集』にも「狂人の如く、けれど理性を備え」た歌も多い
しかし、この掲題歌の、「ますらを」を自負した詠歌では
残念ながら、その「ますらをぶり」は感じられない
あるいは、ただただ「恋の威力・魔力」を詠いたかっただけなのかもしれないが...
|
|
掲載日:2013.10.03.
| 正述心緒 |
| 大夫之 聡神毛 今者無 戀之奴尓 吾者可死 |
| ますらをの聡き心も今はなし恋の奴に我れは死ぬべし |
| ますらをの さときこころも いまはなし こひのやつこに あれはしぬべし |
| 巻第十二 2919 正述心緒 作者不詳 |
| 【2919】語義 |
意味・活用・接続 |
| ますらをの[大夫之 ] |
| ますらを[益荒男・丈夫] |
勇ましく強く立派な男子・勇士 |
| |
枕詞「ますらをの」は、益荒男が「手結(たゆ)ひ」をしていることから同音の地名「たゆひ」にかかる |
| さときこころも[聡神毛] |
| さとし[聡し] |
[形ク・連体形]聡明だ・明敏だ・賢い・悟りが早い |
| こころ[心・情] |
精神・意識・感情・意志・心構え・思い遣り・情け・思慮 |
| も[係助詞] |
[強意](下に打消しの語を伴って)強める |
種々の語につく |
| いまはなし[今者無] |
| いまは[今は] |
(「今はもう限りだ」の意から) 今となっては ・もうこれまで |
| 〔成立〕名詞「今」+係助詞「は」 |
| なし[無し] |
[形ク・終止形]ない |
| 〔補助形容詞ク〕として、体言に続く係助詞の付いた形について、否定の意を表す、「~(で)ない」〔前句の「も」に呼応〕 |
| こひのやつこに[戀之奴尓] |
| こひ[恋] |
恋しく思うこと・心がひかれること・恋愛 |
| の[格助詞] |
[同格]~で・~であって |
体言につく |
| やつこ[臣・奴] |
人に使われる身分の低い者・相手を罵っていう語・下僕・臣下 |
| に[格助詞] |
[相手](動作の対象) ~に |
体言につく |
| あれはしぬべし[吾者可死] |
| べし[助動詞・べし] |
[推量・終止形]~そうだ・きっと~だろう・~にちがいない |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [やつこ] |
原文「奴」を見て、「やっこ」と言いたくなってしまうが
この当時では、「やっこ」ではなく、「やつこ」という
古語辞典によると、「やっこ」は、近世の語で、「やつこ」の転じたもの
江戸時代、武家に仕えた下男、中間、行列の先頭に立って、
槍・挟み箱などを持ち歩く役目の者
江戸時代初期では、侠客・男伊達の意があった「武家奴・旗本奴・町奴、など」
なお、掲題の「やつこ」には、この名詞の他に「人称代名詞」もあり
それは、自己の謙譲語として、「私・わたくしめ」などと用いられた |
| |
| |
|

|
| 【歌意2920】 |
ふだんから、いつもこんな風に恋悩んでいたら
苦しくて堪らない
せめて、ちょっとの間だけでも、
わたしのこころが、安らぐ配慮をしてほしい
|
昨日の歌〔2919〕といい、今日の歌といい
男の弱気を詠っている
「恋する辛さ」は、男でも女でも一緒だ、それも理解できる
しかし、決して相手に、その配慮を求めるものではない
自身で深く悩み沈めばいい...それが「恋」ではないか
賀茂真淵が「ますらをぶり」と、『万葉集』を評したのは、
こうした歌の内容ではなく、
ひょっとしたら、あまりにも率直な「男心」しかも、「弱き心」を隠すこともなく
飾り気もなしに、詠っていることを、言っているのだろうか
そうであれば、少しは納得できる
そもそも、私には、どうして「ますらをぶり」という『万葉集』に相対するかのように、
『古今集』などの平安時代の歌集に付けられる「たをやめぶり」という「言い方」も
何となく気になっている
「たをやめぶり」は、勿論「ますらをぶり」の対語になっており
平安時代の和歌の「優美で繊細な歌風」をいうらしいが
「和歌」というもの、そうした画一的な類別が出来るのだろうか
どの時代であっても、人の心に宿る「うたごころ」は一緒のはずだし
この時代は、こんな風潮だから、こうあるべきだ、ということもない
勿論、賀茂真淵は、そんなことは言ってはいない
結果的に、その時代に生み出された「和歌」が、
技巧を一層凝らし、優美さが鮮明に表現されているから、いうのだろうが
「歌風」の仕分けは、言ってみれば、万葉人と平安人の違い、とでも言い換えられる
それは、学問的には意味のあることであっても
...それはおかしい、と私は思う
音楽でいえば、バロックから古典派、ロマン派、民族楽派、近代、現代などと習うが
それは、決して「発展している」のではなく
そうした流れの中で、生み残された所産を、言っている
仮に、これが「発展、進化」だとでも言うのであれば
では、現代人は、バロック様式の音楽も、古典様式の音楽も作れないのか、となる
そんなことはない
今でも多くのバロックファンや、古典のファンはいる
そうした人たちが求める「感性」は、時代を超えている
「和歌」もそうではないか、と思う
技術的に「ますらをぶり」、「たをやめぶり」とするのではなく
その「歌そのもの」を仕分けするならまだ理屈に合う
現代において、『万葉集』が「ますらをぶり」を発揮している、というのなら
少なくとも、この昨日と今日の二首は...いや、もっとあるだろうが
一応、直近で採り上げたこの二首は、技術的には「たおやめぶり」と言えなくても
では、必然的に「ますらをぶり」か、とも言えないだろう
『万葉集』は、「ますらをぶり」の歌集
『古今集』などの平安期の歌集は、「たをやめぶり」の歌集という線引きは、気になる
歌論書『俊頼髄脳』を読んでいて、日々いろんな想いに捉われるが
「歌合」の様子を、少しは垣間見ることも出来た
初めて知った、その「歌合」
まさに、一首対一首の対決であり、判者がいて、その優劣をいう
さらに、その結果の理由も述べるのだが、これも時代の感性が大きく左右するだろう
私が、一番関心を持ったのは、「和歌」の位置付けだ
万葉の人たちにとって、こうした優劣を決するような意識はあったのだろうか
しかし、平安時代にはそれが「歌道」とでもいうべき重責を持つ
当然、「歌風」も変わってくるだろう
何だか...息苦しさを感じてしまう
『万葉集』と『万葉集以後』の「歌の世界」は、こうも違うのか、と
|
|
掲載日:2013.10.04.
| 正述心緒 |
| 常如是 戀者辛苦 シマシク毛 心安目六 事計為与 |
| 常かくし恋ふれば苦ししましくも心休めむ事計りせよ |
| つねかくし こふればくるし しましくも こころやすめむ ことはかりせよ |
| 巻第十二 2920 正述心緒 作者不詳 |
| 【2920】語義 |
意味・活用・接続 |
| つねかくし[常如是 ] |
| つね[常・恒] |
ふだん・通例・普通・当たり前 |
| かく[斯く] |
[副詞]このように・こんなに・こう |
| し[副助詞] |
語調を整え、強意を表す |
| 〔接続〕体言または活用語の連体形・連用形、副詞、助詞などにつく |
| こふればくるし[戀者辛苦] |
| こふれ[恋ふ] |
[他ハ上二・已然形]思い慕う・恋しく思う |
| ば[接続助詞] |
[順接の恒常条件](已然形+「ば」)~するときはいつも |
| くるし[苦し] |
[形シク・終止形]苦しい・痛みや悩みでつらい |
| しましくも[蹔(斬の下に足)毛] |
| しましく[暫しく](上代) |
[副詞]しばらくの間・少しの間・ちょっとの間 |
| 上代語「しまし(暫し)」の古形 |
| も[係助詞] |
[仮定希望]せめて~だけでも・~なりとも |
| 〔接続〕名詞、助詞、用言や助動詞の連体形と連用形など、種々の語につく |
| こころやすめむ[心安目六] |
| やすめ[休む] |
[他マ下二・未然形]安らかにさせる |
| む[助動詞・む] |
[推量・連体形]~だろう |
未然形につく |
| ことはかりせよ[事計為与] |
| ことはかり[事計り] |
事のはからい・処置・配慮・方策 |
| せよ[為(す)] |
[サ変・命令形]体言について様々な複合動詞をつくる |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [しましく]『全集』より |
「しばし」の古形「しまし」に同じ
「けだし⇒けだしく」「ただし⇒ただしく」と同類の派生形であろうが
例数は、「しまし」の二倍を超える
原文「蹔(斬の下に足)」(「暫し」に同じ)の一字であるが、
音数を考慮して「しましく」(+助詞で五音)にしている
と、『全集』の語注にあるのは、定形「五七五七七」の韻律にこだわると
少なくとも、恣意的に「訓」もその定形に合わしている、という解釈になる
『万葉集』では、原文一字で、一句を表現する場合も多いが
必ずしも、その作者の「訓」の追究だけとは限らず
このように、「和歌」の「確立された」形を前提にしている、とも感じられる |
|
 |
| 【歌意914】 |
山が高いから、こんなに激流となって流れる川瀬
まるで白木綿の花をその急流に滾らせたような風情だ
このような早瀬は、いつ見ても、飽きないものだと
感心してしまう
|
| 【歌意1111】 |
泊瀬川の急流に、白木綿の花が咲き乱れたかのように波立つそのさま
流れが早く、澄み切っているので
つい誘われるように見に来たわたしは...
|
| 【歌意1740】(再掲:2013年7月11日) |
山が高いので、白木綿の花が咲き
そして、激しく咲き落ちるようなその「夏身」の川門は
いつ見ても、飽きないものだなあ
|
「わた」が、実際に木になる「植物」だと、
この目で認識できたのは、昨日が初めてのことだ
奈良春日大社の「萬葉植物園」
行く度に、新たな発見をしてしまう
先日は、「ナンバンキセル」が、すすきに隠れるように開花しているのを偶然見かけた
そして、昨日は「わた」の...まさに「わた」そのものが、驚きを誘って目に入った
解説に拠ると、花が咲き終わって、実がなり
それが成熟して白い綿毛を持った種子が現れるとあるが
この綿毛に包まれた「中身」が種子なのだろう
指で挟んでみると、確かに「種子」の感触があった
そして、じっくり見ると、綿毛から透けて、幾つかの塊が見える
触った感じ、見た目...まさか、「わた」がこんな風に木になるとは...
新鮮な驚きと、自分の無知さを、思い知らされた
そして、ここで挙げた「三首」の歌
純粋な「わた」の歌ではなく、「白木綿」という、
「わた」から「ゆふ」に変身させて、その白く美しいさまを「木綿」として詠う
その重なる姿は、柔らかい美しさ、ではなく
「おちたぎつ」瀬の岩に砕ける白き飛沫...
そんなギャップがありながらも、思い浮かべる水飛沫が
今の私には、「白木綿」のように思えてくる
なるほど、万葉人の「美」への映像は、こうした「激しさ」をも
柔らかく、優しく「わた」のように昇華していくのだろう
激流に弾かれるように飛び交う飛沫...そのさまが「白木綿の舞」に映し出されるとか...
羨ましい感性だと思うに
この日、この植物園で、初めて中学校の修学旅行生の一団に出合った
若い彼らが、どんな風に「万葉の花々」を感じるのか
少々興味があったので、その会話を意識的に聞いてみた
残念ながら、ほとんどの生徒は、「万葉の花々」と言っても
それほど感慨を持って接する風には見えなかったが
単純に珍しい花とか、あるいは独特の威容を見せる「臥龍のイチイガシ」など
中学生らしい感嘆の声を聞くことはできた
そして、やはり「わた」のなる姿をを目の当たりにして
私と同じように指で触るその姿は...微笑ましかった
こうして、手に触れることが、マナーとしていいのか悪いのか
この場合、私には分からないが
心ある触れ方は、是非必要なことだと思う
「心ある触れ方」...花々を愛でる「心」があるのなら... |

|
掲載日:2013.10.05.
| 雑歌 / (養老七年癸亥夏五月幸于芳野離宮時笠朝臣金村作歌一首[并短歌])反歌(二首) |
| 山高三 白木綿花 落多藝追 瀧之河内者 雖見不飽香聞 |
| 山高み白木綿花におちたぎつ瀧の河内は見れど飽かぬかも |
| やまたかみ しらゆふばなに おちたぎつ たきのかふちは みれどあかぬかも |
| 巻第六 914 雑歌 笠朝臣金村 |
| |
| 雑歌 /詠河 |
| 泊瀬川 白木綿花尓 堕多藝都 瀬清跡 見尓来之吾乎 |
| 泊瀬川白木綿花に落ちたぎつ瀬をさやけみと見に来し我れを |
| はつせがは しらゆふはなに おちたぎつ せをさやけみと みにこしわれを |
| 【語義・歌意】 巻第七 1111 雑歌 作者不詳 |
| |
| 雑歌 (再掲:2013年7月11日) |
| 山高見 白木綿花尓 落多藝津 夏身之川門 雖見不飽香開 |
| 山高み白木綿花に落ちたぎつ夏身の川門見れど飽かぬかも |
| やまたかみ しらゆふばなに おちたぎつ なつみのかはと みれどあかぬかも |
| 【歌意】 巻第九 1740 雑歌 式部大倭 |
| 【914】語義 |
意味・活用・接続 |
| やまたかみ[山高三 ] |
| やまたかみ[常・恒] |
山が高いので |
| たかみ[形容ク・高し]、上代では語幹「たか」に「み」をつけて原因・理由を表す |
| しらゆふばなに[白木綿花] |
| しらゆふばな[白木綿花] |
白い木綿で造った造花、滝や波の白さにたとえる |
| に[格助詞] |
[状態・比況]~のように |
体言につく |
| おちたぎつ[落多藝追] |
| おちたぎつ[落ち激つ] |
[自タ四・連体形]飛沫をあげて激しく流れ落ちる |
| たきのかふちは[瀧之河内者] |
| たき[滝](上代「たぎ」) |
急流・早瀬・崖から流れ落ちる水・垂水 |
| かふち[河内] |
〔「かはうち」の転〕川が屈折して流れている所・谷間の流域 |
| みれどあかぬかも[雖見不飽香聞] |
| みれ[見る] |
[他マ上一・已然形]眺める・目に留める |
| ど[接続助詞] |
[逆接の恒常条件]たとえ~てもやはり |
已然形に付く |
| あか[飽く] |
[自カ四・未然形]あきあきする・満ち足りる |
| ぬ[助動詞・ず] |
[打消・連体形]~ない |
未然形に付く |
| かも[終助詞] |
[詠嘆・感動]~であることよ |
連体形に付く |
| 掲題歌トップへ |
| 【1111】語義 |
意味・活用・接続 |
| はつせがは[泊瀬川 ]〔歌枕〕今の奈良県桜井市初瀬を流れる初瀬川の古称 |
| しらゆふばなに[白木綿花]上、既出〔914〕 |
| おちたぎつ[落多藝追]同、既出 |
| せをさやけみと[瀬清跡]〔~を~み〕」語法、「~が~ので」 |
| せ[瀬] |
浅瀬・早瀬・機会・場所・その節 |
| さやけ[清けし] |
[形ク・語幹]澄み切っている・清くすがすがしい・冴えている |
| み[接尾語] |
(形容詞などの語幹について「~を~み」の形で)原因・理由 |
| と[格助詞] |
~と(きいたので) |
| みにこしわれを[見尓来之吾乎] |
| み[見る] |
[他マ上一・連用形]眺める・目に留める |
| に[格助詞] |
[目的]~のために |
「目的」は連用形につく |
| こ[来(く)] |
[自カ変・未然形]来る・行く・通う |
| し[助動詞・き] |
[過去・連体形]~た・~ていた |
「カ変」は未然形につく |
| われを |
間投助詞「を」で文末につく場合、感動・詠嘆を表す |
| 『全集』では「われを」止めの歌は、「~した私であることだ」の意の詠嘆の気持ち |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [たかみ] |
形容詞ク活用の語幹に、「み」を付ける「ミ語法」
「ミ語法」は、一般的に理由を表す |
| |
| [しらゆふばなに] |
「白木綿花」は、楮の皮を裂き、
その繊維を漂白した「ゆふ」の白く美しいさまを花に喩えていう
「に」は、名詞について、比喩を表す |
| |
| [たき] |
「滝(たき)」を古語辞典で引いてみると
上代では「たぎ」と言って、水が激しい勢いで流れる意の動詞「たぎつ」の派生語で、
急流のことをさしていたようだ
現代語の「滝」という概念は「たるみ(垂水)」といって区別していたと言う |
| |
| [歌枕] |
和歌によく詠まれる名所や特定の地名
平安時代中期までは広く和歌の歌語全般を指していたが
しだいに地名のみを指すようになった
後世、和歌によく詠まれる「名、歌詞・枕詞」などを記した本のことをいう
歌人のための手引書とも言われている |
| |
| [せ]旺文社古語辞典「せ」と「ふち」 |
「せ」は多義語であるが、
「世の中は何か常なるあすか川きのふの淵ぞ今日は瀬になる」<古今集 雑歌下・933>
のように「淵」に対して用いる場合は、川の浅くて人が徒歩で渡ることができる所をいう。水が澱んで深いところが「淵」である。 |
| |
| [さやけし]旺文社古語辞典〔参考〕 |
| 意味用法において「清(きよ)し」に近い語であるが、「清し」が対象そのものの汚れない様子を表すのに対して「さやけし」は対象に接して呼び覚まされるさわやかな感覚を表すという違いがある。具体的に言えば「さやけし」は汚れない清らかな自然に触れて感じるすがすがしさ、人間の矜持などの澄み切った心境などを表す。 |
| |
| [と] |
『小学館新編日本古典文学全集』の語注には、この格助詞「と」について、
「この『と』は目的意図を表す本来の働きがほとんど認められない用法」とあった
格助詞「と」は、確かに古語辞典を引くと、多くの用法があるが、
何かの対象物(この全集で言う「目的」)との関係が希薄だと言っているのだろうか
しかし、その用例の中でも「引用」では、
「人のことばや思うことなどを直接受けて、引用を表す」という用法もある
この用法では、当てはまらないのだろうか
もっとも、その場合では、初句からここまでを受けて、「だから」となってしまうが... |
| |
|
|
| 【歌意2921】 |
いいかげんな気持ちで、この私が想っているのなら
人妻だ、とまで言っているあなたのことを、
こんなに恋し続けているのでしょうか...
|
人妻への強烈な「恋心」の告白
巻第一・21 大海人皇子が額田王に答えたとされる歌を思いだす
| 雑歌/(天皇遊猟蒲生野時額田王作歌)皇太子答御歌 [明日香宮御宇天皇謚曰天武天皇] |
| 紫草能 尓保敝類妹乎 尓苦久有者 人嬬故尓 吾戀目八方 |
| 紫のにほへる妹を憎くあらば人妻故に我れ恋ひめやも |
| むらさきの にほへるいもを にくくあらば ひとづまゆゑに われこひめやも |
| 巻第一 21 雑歌 大海人皇子 |
紫草のように、美しいあなたを気に入らないと思っているのなら
どうして、人妻であるあなたなのに、
私は恋したりするのか...
この歌も、掲題歌も、その「男心」は同じだ
もっとも、〔21〕歌は、大海人皇子、後の天武天皇
しかも相手は額田王という前期『万葉集』中のヒーロー・ヒロインだ
その歌の通りの展開があったかどうかは、私には解らないが
かつては夫婦であったことが、仮に事実なら
この歌に籠もる情念は偽りではないだろう
ここでいう、「ひとづま」という概念は、
決して万葉時代が特殊な意味で使われてはいないことは、
敢えて「ひとづま」という、本来は立ち入ることの出来ない相手でさえ
こんなにも、恋してしまい、伝えるのは...「本気」なんだ、と訴えている
これは現代でも使われる手法だ
ドラマであっても、こうした非現実的な展開が、むしろ歓迎される
そこには、決して現実には「あってはならない」という「障壁」があり
それでも「恋してしまったら」と、その「悲劇性」が、人を惹き込む
現実と虚構の境をなくしているのが、「創作」であるはずだ
現実と思えば、「現実」であるし、虚構と思えば「虚構」として見ればいい
ただ、『万葉集』のようなはるか昔の「歌集」における「現実と虚構」は
その「真実」の究明よりも、その残された歌の「心」に想いを馳せるしかない
それが現実か虚構か、などというのは、まだそれを立証する手がかりがある可能性の範囲だ
勿論、大伴家持のように、一種の「歌物語」のようにも思える「私家集」的な歌群は
初期の『万葉集』から次第に、「残すため」の歌集への変貌が底辺にあるからだろう
家持の時代を中心に読む『万葉集』と、
たとえば柿本人麻呂や、この〔21〕歌のような前期『万葉集』とでは、
現代から思えば、同じ古代の歌であっても、当時では、やはり「隔世」の「歌」なのだろう
私自身も、久し振りに巻第一の歌に触れると、何だか懐かしくなってしまう
やはり...時代の「風貌」は、確実に感じることができる...僅か百年足らずであっても...
そう思うと、歴史上の「奈良時代」という百年足らずの「時代」は
その激動のエネルギーが、「歌」にも籠められている貴重な「時代」なのだろう |
|
掲載日:2013.10.06.
| 正述心緒 |
| 凡尓 吾之念者 人妻尓 有云妹尓 戀管有米也 |
| おほろかに我れし思はば人妻にありといふ妹に恋ひつつあらめや |
| おほろかに われしおもはば ひとづまに ありといふいもに こひつつあらめや |
| 巻第十二 2921 正述心緒 作者不詳 |
| 【2921】語義 |
意味・活用・接続 |
| おほろかに[凡尓 ] |
| おほろかに[凡ろか・形動] |
[連用形](「おぼろか」とも)いい加減なさま・おろそか |
| われしおもはば[吾之念者] |
| し[副助詞] |
語調を整え、強意を表す |
体言などにつく |
| 「~し~ば」という条件を表す句の中か、係助詞「も・ぞ・か・こそ」を伴う形が多い |
| おもは[思ふ] |
[他ハ四・未然形]思案する・恋しく思う・愛する |
| ば[接続助詞] |
[(未然形+「ば」)順接仮定条件]~だったら・~(する)なら |
| 〔接続〕順接の仮定条件は、活用語の未然形につく |
| ひとづまに[人妻尓] |
| ひとづま[人妻・他妻] |
他人の妻・〔他夫(ひとづま)〕他人の夫 |
| に[格助詞] |
[動作の対象]~に |
体言などにつく |
| ありといふいもに[有云妹尓] |
| といふ[と言ふ] |
~という |
| こひつつあらめや[戀管有米也] |
| つつ[接続助詞] |
[継続]~しつづけて |
連用形につく |
| あら[補動ラ変・未然形] |
[助詞「て・つつ」の付いた語の下に付いて] |
| |
動作・作用の存続の状態を表す「~いる・~ある」 |
| めや[反語] |
~だろうか(いや、~ない) |
| 〔成立〕推量の助動詞「む」の已然形「め」+反語の終助詞「や」 |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [といふ] |
「といふ」とそのまま古語辞典を引いても、勿論載っていない
現代語の「という」に同じであることは、歌意から理解できるが
古語を、どう理解するか...やはり古語辞典を引いてしまう
しかし、「といふ」では載っていないのであれば
やはり、格助詞「と」の「引用」の用法となるだろう
古語辞典によると、格助詞「と」の「引用」は、
「言ふ・問ふ・聞く・思ふ・見ゆ・知る」などの動詞へ続けて、
その内容を示す、とある
『全集』では、「形式的用法」と片付けている
もっと理解したかったので、『万葉集古義』の「訓」を捲ってみた
すると、「ありちふいもに」とある
「ちふ」を古語辞典で調べる
やっと、手がかりに辿り着いた
「ちふ」は古語辞典に載っており
「といふ、の転」とあり、参考として、次のような説明があった
「上代では『とふ』も用いられ、中古以降は「てふ」が用いられた」と
確かに、「ありとふいもに」という「訓」(中西進・全訳注)もある
『古義』『全訳注』の文字数は七文字で、字音からすれば、その方がいいと思うのだが
あえて字余りの句にしたのは、何か意味があるのだろうか |
|

|
| 【歌意2925】 |
いったい、いつまで生きられるというのか
こんなにも恋しつづけるなどとはせずに、
死んでしまえば、気も楽だろうに...
|
結句の「しなましものを」は
ほとんどの訳注での訓は「しなむまされり」「しぬるまされり」とある
『万葉集古義』でも「しなむまされり」という
「しなむ」とも「しぬる」とも、どちらとも訓は可能とあるが
ならば、それに続く「まされり」の異訓が、私にはまだ見つけられない
ただ、「しなましものを」という結句に触れたとき
何だか、この方が「和歌」の言葉としては、いいなあ、と思った
しかし、その「訓」が、何による出典かは、手元の資料では解らない
また今度明日香で調べよう
「まされり」と訓じれば、必然的にその結句の訳は「死んだ方がいい」となる
それは、原文「死上有」の語意から「死というものの方が上」という意味だろうか
しかし、「しなましものを」とすれば、
「ましものを」が、詠嘆の終助詞を伴うので
辛い恋心を嘆き、「死んだ方が気も楽だろうなあ」という意味合いになるのでは、と思う
「死んだ方がましだ」と言い切るより、
「死ねば、どんなにか楽だろう」と気弱く嘆く方が、しみじみとして胸にくる
私の拙い「古語解釈」など、笑われるかもしれないが
原文が、漢字という借用文字での「日本語」表記なので
好きなように読ませてもらえそうだ...もっとも、稚劣ながらも自分で調べることが前提だけど
それが、古典の醍醐味なのだ、と思う |
|
掲載日:2013.10.07.
| 正述心緒 |
| 何時左右二 将生命曽 凡者 戀乍不有者 死上有 |
| いつまでに生かむ命ぞおほかたは恋ひつつあらずは死なましものを |
| いつまでに いかむいのちぞ おほかたは こひつつあらずは しなましものを |
| 巻第十二 2925 正述心緒 作者不詳 |
| 【2925】語義 |
意味・活用・接続 |
| いつまでに[何時左右二 ] |
| いつ[何時] |
はっきりと定まらない日・日時を表す |
| までに |
程度・限度をはっきり表す、~までも |
| 〔成立〕副助詞「まで」+格助詞「に」 |
| いかむいのちぞ[将生命曽] |
| いか[生(い)く] |
[自カ四・未然形]生きる・命を保つ |
| む[助動詞・む] |
[推量・連体形]~(の)だろう |
未然形につく |
| ぞ[係助詞] |
[断定の疑問]~か〔接続〕体言、連体形、種々の語につく |
| おほかたは[凡者] |
| おほかたは[大方は] |
[副詞]ふつうは・一般には・通り一遍には |
| 〔成立〕名詞「おほかた」に係助詞「は」 |
| こひつつあらずは[戀乍不有者] |
| ずは〔上代語〕 |
~ないで・~せずに |
| しなましものを[死上有] |
| しな[死ぬ] |
[自ナ変・未然形] 命を失う・息が絶える・死ぬ |
| ましものを |
~していたらよかったのに |
未然形につく |
| 〔成立〕反実仮想の助動詞「まし」の連体形+詠嘆の終助詞「ものを」 |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [ずは] |
〔成立〕打消しの助動詞「ず」の連用形「ず」に、係助詞「は」
古語辞典より〔参考〕
この「ずは」の形を「ずば」という形と考えて、
打消しの助動詞「ず」の未然形に接続助詞「ば」のついたものである、とする説もある
しかし、この「ず」は連用形、「は」は濁音ではなく清音と考えるべきで、
係助詞とするのが普通である
ただし、「ずはこそ」と係助詞の「こそ」が「は」の下にくる点は説明がつかない
係助詞の「は」であれば、「こそは」となるのが普通だからである
中世には、「ずんば」という形が生じ、また近世には仮定条件からの類推で、
「ずば」という形も生れた |
|
|
| 【歌意2926】 |
いとしいと思うあの娘を、
夢に見て、その想いのままに目覚め、
指先で探ってみたけれども、
あの娘がいないことの、何と寂しくて悲しいことか
|
この歌、当時さかんに読まれていたと言われる、唐の小説『遊仙窟』の、
「即ち夢に十娘を見、驚き覚めて撹(かきさぐ)るに、忽然として手を空しくす」、
この情景を浮かべての詠歌とされている
『遊仙窟』を、私は読んだことはないが
万葉の人々が、多くの歌にその影響を見せているのは、
それも、当時の風俗としての大きな参考にはなるだろう
中国文学は、詩歌・小説などの歴史ある人類の宝だとは思うが
まだまだ、『万葉集』が終らない以上...なかなか手を付けられない
もっとも、古典文学を一律にかじってやろうとは思っていない
『万葉集』だからこそ、私がここまで続けられたことも事実だ
ただ、万葉の時代に、やはり影響のある何かしらの作品には、少なからず興味もある
いつか...『遊仙窟』も読んでみたいものだ
同じように、掲題歌と同じ一文を題材にして、詠んだ歌がある
大伴家持が坂上大嬢に贈った十五首の中の一首
この歌、2013年7月16日に掲載しているので、再掲になるが
その時点での、私の解釈も含めて、載せておく
歌の背景は、その頁を参考にしてほしい
| 相聞/更大伴宿祢家持贈坂上大嬢歌十五首 |
| 夢之相者 苦有家里 覺而 掻探友 手二毛不所觸者 |
| 夢の逢ひは苦しかりけりおどろきて掻き探れども手にも触れねば |
| いめのあひは くるしかりけり おどろきて かきさぐれども てにもふれねば |
| 巻第四 744 相聞 大伴家持 |
夢で逢うことは、こんなにも辛いことなのか
目を覚まして、手探りであなたに触れようとしましたが
あなたは、触れさせてくれませんでしたね |
このように、同じ文章を題材にしたものでも
その扱い方には、大きな違いがある
家持は、なまじっか夢で会ったからこそ
現実に、目覚め手探りしても、そばにいないことを
相手のためらいであるかのように、嘆いている...(あくまで私の感じ方)
そして、今日の歌〔2926〕は、相手の意思まで言及せず
ただただ、現実での一人寝の寂しさを嘆く
漠然とした「相手」を、読み手には感じさせるが
家持は大嬢という具体的な相手との相聞を描き
尚且つ、「おどろきて」と言って、あたかもその大嬢が不意に現れたかのように詠う
夢の中での出会いから、現実にそばにいるかのような、なかば半覚醒の状態だ
こんな風に、相手が具体的に読み手にも「知り得る」人であれば、
この基となった『遊仙窟』の一文も、より深く詠えるものかもしれない
夢の中では、逢いたいという願望の故もあれば
そうあっては欲しくない、という避けたい気持ちもあるものだと思う
そうした「避けたい」気持ちが、念じることによって、逆に強烈な「想い」に作用させる
妙な言い方だが、家持の「おどろきて」には
何か、そんな「ただならぬ」ものを...今、改めて感じてしまった
|
|
掲載日:2013.10.08.
| 正述心緒 |
| 愛等 念吾妹乎 夢見而 起而探尓 無之不怜 |
| 愛しと思ふ我妹を夢に見て起きて探るになきが寂しさ |
| うつくしと おもふわぎもを いめにみて おきてさぐるに なきがさぶしさ |
| 巻第十二 2926 正述心緒 作者不詳 |
| 【2926】語義 |
意味・活用・接続 |
| うつくしと[愛等 ] |
| うつくし[愛し・美し] |
[形シク・終止形]かわいい・愛らしい・いとしい |
| と[格助詞] |
[引用]~と(思う) 〔接続〕体言、体言に準ずる語につく |
| おもふわぎもを[念吾妹乎] |
| おもふ[思ふ] |
[他ハ四・連体形]考える・思う・愛する・恋しく思う |
| を[格助詞] |
[対象]~を |
体言につく |
| いめにみて[夢見而] |
| いめ[夢](上代語) |
〔「寝(い)目」の意か〕ゆめ |
| に[係助詞] |
[動作の対象]~に |
体言、活用語の連体形につく |
| み[見る] |
[他マ上一・連用形]目にする・理解する・会う |
| て[接続助詞] |
[単純接続]~て |
連用形につく |
| おきてさぐるに[起而探尓] |
| おき〔起く〕 |
[自カ上二・連用形]眠りから覚める・目覚める・起き出る |
| さぐる[探る] |
[他ラ四・連体形]指先などで触って、探し求めたりする |
| に[接続助詞] |
[逆接]~けれども・~のに |
連体形につく |
| なきがさぶしさ[無之不怜]〔「~が~さ」の用法〕 |
| なき[無し] |
[形ク・連体形]いない・存在しない・不在である |
| が[格助詞] |
[感動文の主語]~が・~の |
体言、活用語の連体形につく |
| さぶし[寂し・淋し] |
〔(上代語)・「さびし」の古形〕気持ちが塞いで楽しめない |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [~が~さ] |
接尾語「さ」の用法に、「~の~さ」「~が~さ」の形で文末に付き、感動の意を表す
誤訳としては、「~ことよ」 |
| |
| [が] |
「が」+形容詞語幹(シク活用は終止形)+接尾語「さ」の形で、感動文の主語を表す
この歌では、「なきがさぶしさ」の形容詞シク活用「さぶし」の終止形「さぶし」に、
接尾語の「さ」が付いている
例、「見るが悲しさ」、『見ることの悲しさよ』 |
|
 |
| 【歌意2927】 |
「妹」と言ったなら、馴れ馴れしくて恐れ多いことだ
しかしながら...そうはいうものの、
口に出してそう呼んでみたい、そんな「妹」ということばではないか...
|
「妹」は、一般的に妻とか恋人とか
特に愛しい女性に対して使う人称語だという
この作者は、近づきがたい「愛しい女性」に、
「妹」と呼べるほどの「仲」になりたい、と詠う
現代でも、「呼びかけ」の言葉で、その親密振りが想像できるが
よそよそしさを感じる言葉であっても、「親密さ」を確認できる言葉がある
そこには、「親密さ」以上に「尊敬」の気持ちが備わっている
だからこそ、「よそよそしさ」ばかり目立つことになるが
本当の意味での親愛の言葉には、多分にその「よそよそしさ」も含まれるものだと思う
いや含まれなければならないものだ、と私は思う
随分昔になるが、仏語で「tutoyer 君僕の仲で話す」という動詞を習ったとき
何だか妙な感じを抱いた記憶がある
自然に身につく概念として「君僕の仲」は頭に理解できても
それが、敢えて覚えなければならない「単語」で示めされると
より親密な仲というのは、言葉にしなければならないものなのか、と
「妹」と呼びかけてみたい...まさに「君僕の仲間」になりたい
しかも、単なる親しさではなく、「恋人」としての親密さでありたい、という
自分が想うだけなら、何の障害もない
しかし、それを言葉にするなら、当然相手の気持ちも思い遣らなければならない
「言葉にしたい」ということは、そういうことなのだ、と知らされる
恐れ多い、もったいない...何がそう思わせるのだろう
相手の身分なのだろうか
それとも、自分には相応しくない、と単に自虐的に言っているだけなのだろうか
恐れ多いことなどあるものか
本当に身分的な問題であれば、まず「妹」と呼べるほどの仲になりたいとは思わないだろう
現代の自由恋愛では想像もできないだろうが
おそらく、この当時の恋愛観は、かなり多くの仕来たりがあったことだろう
こうした気持ちを持ちえるのは、少なくとも「許される」相応の相手だったとは思う
見向きもされないほどの「高嶺の花」のような、存在の女性なのかもしれない
そうであれば、こうして詠うことも...一種の自分の心を慰めるだけの「きやすめ」だ
『万葉集』中に見られる多くの相聞には、
命がけもあれば、「きやすめ」としてこころを癒そうとするものなど
さまざまな「恋心」がある
この歌、一人で悲しみにくれる情景ではなく
仲間内で、意中の女性を想って、俺の気持ちは、こうなんだぞ、と勢いで言ってしまった
そんな「観」さえもする...男って、そうしたものだ...多分 |
|
掲載日:2013.10.09.
| 正述心緒 |
| 妹登曰者 無礼恐 然為蟹 懸巻欲 言尓有鴨 |
| 妹と言はばなめし畏ししかすがに懸けまく欲しき言にあるかも |
| いもといはば なめしかしこし しかすがに かけまくほしき ことにあるかも |
| 巻第十二 2927 正述心緒 作者不詳 |
| 【2927】語義 |
意味・活用・接続 |
| いもといはば[妹登曰者 ] |
| いはば[言はば] |
言ってみれば・言うならば・言ったなら |
| 〔成立〕四段「いふ」の未然形「いは」+接続助詞「ば」 |
| 未然形+「ば」で、「順接の仮定条件」~(する)なら・~だったら |
| なめしかしこし[無礼恐] |
| なめし |
[形ク・終止形]失礼だ・無作法だ・馴れ馴れしい |
| かしこし[畏し・恐し] |
[形ク・終止形]恐れ多い・もったいない・恐ろしい・怖い |
| しかすがに[然為蟹] |
| しかすがに[然すがに] |
[副詞](上代語) そうはいうものの・しかしながら |
| 〔副詞「然(しか)」にサ変動詞「為(す)」の終止形「す」、接続助詞「がに」のついたもの〕 |
| 〔参考〕中古以降は「さすが」が用いられた「さすがに」 |
| かけまくほしき[懸巻欲] |
| かけ[掛く・懸く] |
[他カ下二・未然形]口に出していう・話しかける |
| まくほしき[まく欲しき] |
~(し)たい・~でありたい |
未然形につく |
| 〔成立〕推量の助動詞「む」のク語法「まく」+形容詞「欲し」の連体形「ほしき」 |
| 「まくほし」は、古語で希望の助動詞「まほし」の古形、連体形「まくほしき」 |
| ことにあるかも[言尓有鴨] |
| こと[言] |
口に出していうことば・言葉・噂・評判 |
| ある[有り・在り] |
[補助動詞ラ変・連体形]状態・存在の表現を助ける |
| (形容詞・形容動詞の連用形、副詞、及び一部の助動詞の連用形の下につく) |
| かも[終助詞] |
[詠嘆・感動]~であることよ |
連体形につく |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [なめし]古語辞典より「なめし」の語感 |
「なめし」という語は、折り目を欠いた無作法な態度を非難する気持ちを表す言葉だが、
ただ怒っているだけではない
怒りの内には、多分に相手を軽蔑する気持ちが含まれてる
かなりはっきりした感情を表すので「源氏物語」などには用例が少なく、
いくぶんやわらかな語感の「なめげなり」という形容動詞が多く用いられている |
| |
| [かしこし]古語辞典より「語義パネル」 |
人間業とは思えない霊力に対し、恐れ敬う感じを表す「畏し・恐し」が原義で、
転じて中古以降「並外れた学識・才能などのあるさま」などの意の「賢し」になる |
| |
| [こと]古語辞典より「参考」 |
語源的には「言」と「事」は同じであったと考えられるが、奈良時代以降に分化した
しかし、奈良・平安時代の「こと」には、どちらにも解せるものが見られる |
|

|
右頁の記事は、若い頃から私の抱いていた、いや燻っていた、というべきもの
『万葉集』の「詠」は、本当に作者の「声なのか」という疑問に
少なからず光を当ててくれた書物に出会って、多くを参考にしながら書かせてもらった
これほど有名な歌であっても、尚も未だに手出しできなかったのは
あまりにも若い頃の衝撃...それは、江戸時代の学者の「訓」だった、という
私の「万葉人」への想いが打ち砕かれたような気がして...
しかし、賀茂真淵なりに、人麻呂は、こう訓じたに違いない、という信念があったのだろう
その真実は今となっては誰にも確認しようがない
...それが『万葉集』だ
今日の締めくくりとして、参考にした著書の一部の引用を載せる
【白石良夫著「古語の謎」より】第三章 幻の万葉語たち-江戸時代に生れた古代語
-(略)-、八世紀以前(上代)の日本人は漢字以外の文字を知らなかった。漢字はもともと中国語を表記するための文字であり、われわれの先祖はその漢字を借り、さまざまな工夫をして、自分たちの言葉である日本語を書き表した。『万葉集』48番の人麻呂歌の原文「東野炎立所見而反見為者月西渡」も、そういった工夫の跡をしめす漢字の連なりである。
ただ、48番歌で試みたような工夫は、上代の日本人にとって、きわめて特異な日本語表記法であったと考えなければならない。
そもそも最初の素朴な日本語表記者は日本人ではなく、中国大陸のひとたちであった。日本の固有名詞(人名や地名)を、かれらの文字である漢字でもって表記した。われわれもよく知っている「邪馬臺(ヤマト)」「卑弥呼(ヒミコ)」を表記したのは中国人であって、かの国の史書に残る日本語である。かれらは耳で日本語音を聞いて、それとおなじ発音の漢字をあてたのであった。
日本人も、その中国人にならって、日本語一音節に、それと共通する音を持つ漢字一字をあてるという方法で、みずからの言語を書き表した。日本語の「ア」を表記するのに「安」や「阿」などをつかい、「カ」を表記するのに「加」や「可」などをつかい「シ」を表すのに「志」「之」「斯」などをつかう。この場合、漢字の持っている意味は関係しない。日本語の「ココロ」を「許己呂」、「カハ」を「可波」、「サクラ」を「佐久良」と表記するごときである。
これら「安」-以下例語-などを真仮名といって、これが上代日本人の日本語表記のための最初の文字であった。
ところで、漢字の一字一字には、音を持つと同時に、意味をも持つ。すると、漢字にそれと同じ(似た)意味の日本語を当てて読むようになり、日本語に漢字を当てて書くようになる。「心」や「情」を「ココロ」と読み、「川」「河」を「カハ」、「桜」を「サクラ」と読む。日本語の「ココロ」を「心」「情」と書き、「カハ」を「川」「河」と書き、「サクラ」を「桜」と書く。「心」「情」を「ココロ」と読む、これをこんにち俗に「訓読(くんよ)み)」というが、この訓読みの知識をつかって、たとえば、「ウツセミ(この世の人)」を「打蝉」と書いたり、「ナツカシ(懐かし)」を「夏樫」、助詞の「カモ」や「ナガラ」を「鴨」「長柄」などと表記できるようになった。また「肉」という意味の「シシ」を「十六」という戯れの表記も編み出す(掛け算の四四十六から)。
だが、これら「打蝉」や「夏樫」「鴨」「長柄」「十六」は、ほとんど『万葉集』にのみ見られる表記法であって、上代一般におこなわれていたわけではない。48番歌のようなのが特異な日本語表記法であったとは、そういう意味であるが、常識で考えても、「ツキカタブキヌ」を「月西渡」と書くのは、文字の重要な役割である伝達機能を無視している。書き手の遊び心が書かせた表記であり、それが理解できる読み手がいてはじめて、コミュニケーションが成立する。書くほうも、読むほうも、どちらも習熟した漢字運用能力と秀逸な想像力、すなわち相当な高等技術を必要とする。48番歌の他の部分にしても、日本語で重要な「てにをは」(助詞や助動詞など)を隠されていて、素朴な日本語表記法とは言いがたい。
普通は、先のごとき真仮名でもって日本語は書かれた。そのことを、ここでしっかり確認しておきたい。この真仮名がもとになって、やがて平仮名・片仮名がつくられるのである。
以下の項で、それらの具体的な解説に入っていくのだが
ここまでの、著者の「心構え」は、いつも思っていることであり
しかし、ならば誰かに説明しみよ、といわれても
なかなか整理して述べられるものではない
まさに、「一を語るに、十を学ばなければ」としなければ、言えるものではない
私にとって『万葉集』は、やっと出逢えた生涯の「友」だが
それに相応しい自分を、常に意識しなければ、本当の理解は出来ないし
そのためには、死ぬまでも不断の継続が必要だろう
何しろ、私の性格では、ちょっと気が緩むと、一気に崩れてしまうから...
この白石良夫著「古語の謎」、エッセイのサイトで、その目次を紹介している
〔古語の謎〕
|


 |
掲載日:2013.10.10.
| 雑歌/((軽皇子宿于安騎野時柿本朝臣人麻呂作歌)短歌) |
| 東 野炎 立所見而 反見為者 月西渡 |
| 東の野にかぎろひの立つ見えてかへり見すれば月かたぶきぬ |
| ひむがしの のにかぎろひの たつみえて かへりみすれば つきかたぶきぬ |
| 巻第一 48 雑歌 柿本人麻呂 |
| 【歌意48】(通説) |
東の方の、野にかげろうの立つのが見えて
振り返って見ると、月は西に傾いている
|
この歌は、私が単純に『万葉集』に惹かれてしまった根本を、一変させてしまった歌だ
それまでの私の『万葉集』は、人麻呂の相聞に我が身を重ね
あるいは、挽歌に胸を震わせ、ときには子どもじみた共感を自負し
そんな『万葉集』の世界に浸っている自分を、誇らしく思っていた
無批判、無節操、解らないままに繰り出される「いにしへのことば」に振り回され
それでも、それが何故か心地よく私の心を支配してしまった
山に入り、深淵とする谷間、稜線で「風の音」、「風の声」、「風の香」だなどと
いかにもそんな感性が自分には備わっているのだ、と
今になって振り返れば、笑ってしまうような、いや恥ずかしくなるようなことを
真剣に嘯いていた自分がいた
まだ二十代の、染まり易く、弾け易い年頃だったとはいえ
山仲間同士で、いっぱしの「万葉論」を語り合い、
それが、お互いに「自分の居場所」はここだ、と言わんばかりの「山」が舞台だから
尚更、不敵・傲慢・曲解の極みの「万葉論」だった...はずだ
相聞の「泣ける」ような一首に触れると、街に降りて、それを使いたがる
相手がいようがいまいが、まさに「俺の心境は」などと、飲み屋で詠じ出す
そんな私、そして仲間を含めた「こころもろき若者たち」にとって
本当の意味の『万葉集』など、考えもしなかった
...その歌が、今日に残るその「訓」が、作者そのものの「詠歌」であることを
誰一人として疑わなかった
それから数年が経ち、その頃には、『万葉集』の周辺の研究書などにも目が渡り
万葉歌が、実際はすべて「漢字」表記であり、その訓には、異訓も少なからずある
そう知るようになり、今度はそちらに俄然興味が走る
そのとき出合った歌が、この掲題歌「ひむがしの...」だった
この歌が、どれほどの名歌なのか、それは私には解らない
表面的には、昇る太陽と沈もうとする月を映像にして
当時の、人麻呂が関わった政治的な情景の意味合いもあったのだろう
その深層にどこまで入り込めるかで、この歌の意味合いも違ってくるだろうが
そんなことよりも、はるかに大きく私に衝撃を与えたのは、
この、今日までも「訓」として伝えられている、
「ひむがしの のにかぎろひの たつみえて かへりみすれば つきかたぶきぬ」
これが、江戸時代の国学の大家賀茂真淵によって決定付けられた、ということだった
それまで、万葉の歌は、すべて詠者本人の「ことばそのもの」と思っていた私には
これ以上もない衝撃だった
それ以来私は、こうしたいわゆる「万葉研究史」的な方面にまで目が行くようになる
平安時代の天暦年間(947~957)、宮中の梨壺で
当時の代表的な学者、源順など五人(梨壺の五人といわれる)によって
初めて、二百年ほども前の『万葉集』に「訓」が付けられた
何故このような作業が行われたかといえば、
その頃、『万葉集』は、すでに読み難い「歌集」だった、ということだ
全文が漢字表記、しかも助詞すら表記されないものが多い
逆に考えてみれば解る
中国の古書に、たとえば当時の日本の様子を書き記したもの
「東夷伝倭人条」に登場する「卑弥呼」など、
この表記は、当時(記述された)の筆者が耳で確認した「音」を
自国の表記文字である漢字に当てはめて記したものだ
当時、実際に日本で「ひみこ」と呼んでいたのか、あるいは
中国で、「卑弥呼」をどう発音していたのか、そう考えれば
あくまでも「ひみこ」は便宜上の「人名」であって、
本来的な実存したかもしれない、当時の名「ひみこ」とは限らない
何しろ、違う言語を、自国の表記音に近いものを当てはめただけなのだから...
そこで、『万葉集』を振り返ると
単純に、漢字音だけを利用したのであれば、その解明は少しは楽だろうが
そうはいかなかった
漢字には、必ず「意味」が備わる
したがって、初めは「音」のみ借りて表記していた「日本語」も
次第にその「意味」に近い漢字を使いだすようになる
そのタイミングには諸説もあるだろうが、現実的には
その混在して使われている歌もかなりある
さらに、その漢字と日本語を、いかにも「戯」とするかのような「表記」まである
そうなってくると、やがて一般に広まり人々が使いだす「ひらがな」の世になると
そうした「漢字」の漢語表現以外の「表記」など、精確に読めなくなるだろう
現代でも、よく言われることだが
パソコン、そして携帯の文字を打つとき、
音は間違っていないが、表記される「漢字」が違う場合が多い
それを、間違いだと気づくことが殆どだが
それは、現段階でも、それらがまだ「現役」の「表記文字」だからだ
しかし、それらを使わなくなった時代に、仮に必要があってその文字を打つとき
誤表記であることすら解らなくなってしまうのではないか...
いや、現代でも、その傾向は少なからずあると思う
普段使い慣れていない漢字を表記するとき、候補に表示される「漢字」群の
どれが正しいのか、解らないときがあることも確かだ
このような状況(諸状況の一つ)が、天暦年間に危機感を持った朝廷、
このままでは、『万葉集』は誰にも読めなくなるだろう、というこの危機感が
「梨壺の五人」の役割になった
『万葉集』が一応の編集を終えてから二百年...
この二百年は、現代人が二百年前の江戸時代の文物を読みこなすことよりも
はるかに困難なことだった、と容易に想像できる
何しろ、表記する言語が、まったく「現代」とは違うのだから...
『万葉集』の歌意については、これにも異説も確かに多いが
それでも、「訓」の根本的な「相違」は、最終的には「歌意」にまで及ぼすだろうし
それが、長い間論じられてきたことも頷ける
しかも、詠歌の時代から、どんどん時代が離れていく現在でもなお...
江戸時代の、賀茂真淵以前には、どんな風に訓じられていたのだろうか
先に述べた梨壺で訓が付けられたのは、約四千首の短歌の殆どに付けられ、
これを「古点」という
しかし、現在この「古点」とみられる本(写本だろうが)は存在しない
この「古点」に次いで、付けられた「訓」が「次点」といわれ
それは、鎌倉時代の仙覚が訓を付けるまでの間、何代にも渡り付けられ、
その「次点」の数は三百数十首と言われている
この時期の写本を「次点本」といい、「桂本」をはじめ約十種の写本が残っている
そして、仙覚は残った読みにくい百ないし百五十首の歌に訓を付け、
これが「新点」とされ、寛元本系の神宮文庫本・細井本、
同文永本系の西本願寺本以下、京都大学本にいたる諸本は、
いずれも「新点」本の系統となる
参考程度の、それらの説明は、
このサイトの「諸本と注釈書について」(小学館・新編日本古典文学全集)
ここに、賀茂真淵以前の〔48〕について、載せてみる
| あづまのの けぶりのたてる ところみて かへりみすれば つきかたぶきぬ |
| 元暦校本〔元暦年間(1184年)の書写、訓読の跡がはっきりわかる現存最古の資料〕 |
鎌倉・室町時代にもなると、訓点のついた『万葉集』の資料、
そして万葉歌を採録した撰集なども多く残っており、
それらも〔48〕歌については、「あづまのの・・・」とある
江戸時代の初期になって、印刷技術が発達し、書物の出版物が商業活動の一環となる
そこで、『万葉集』も、慶長年間(1596~1615)に漢字本文だけの刊本が出版され
そのときの訓も、元暦校本とまったく同じで、
このことからも、鎌倉・室町時代を通じて、この訓が読み継がれていたことが解る
江戸時代最初の『万葉集』の全註釈は、北村季吟著『万葉拾穂抄』で、
その出版は貞享・元禄年間(1684~1704)で、そこに附された「訓」もまた、
元暦校本の「訓」と同じだ
この『万葉拾穂抄』が流布した元禄時代、
契沖という学僧が著した注釈書『万葉代匠記』が、この〔48〕歌の「訓」の契機となった
契機というのは、契沖自身は、この歌一首の訓を付けたのではなく
「あづまの」よりも、結句の「西」の対語として、「ひむかし」と訓でもいいのでは、
と提案している (他にも、「春」という提案も)
ここが重要なところで、それまでの説は師の説を受け継ぐ形で残されてきたが
ここで、契沖の試訓が、まったくそれらのしがらみにとらわれない、
自由な批判精神によるもの、といえることだ
これが、後の賀茂真淵の「訓」に繋がっていく
初句だけではなく、「かげろひ」も「つきかたぶきぬ」も
あらゆる語句への見直しが、これを契機に盛んになる
そして、契沖の学問を継承し、
多くの門人を抱える賀茂真淵(1697~1769)という当代の大学者が著した『万葉考』
そこで、この歌に、初めて現代に続く「訓」がみられるようになった
| ひむがしの のにかぎろひの たつみえて かへりみすれば つきかたぶきぬ |
| 万葉考 |
この『万葉考』で、賀茂真淵は、この歌の訓の解説をしている
引用は長くなるので、機会をみて載せるが
今、我々が目にする「人麻呂の名歌」と言われているこの歌
しかし、本当に人麻呂が詠ったのかどうか、それよりも賀茂真淵の「訓」が
「柿本人麻呂作」として伝わっている...それを知らなければならない
この賀茂真淵の「訓」で、それまでの「あづまのの けぶりのたてる・・・」は、
まるでなかったかのように消えてしまう
以後の注釈書の訓は、賀茂真淵の訓で統一されてしまう
| 加藤千蔭『万葉集略解』 |
岸田由豆流『万葉集攷証』 |
| 上田秋成『金砂』巻七 |
橘守部『万葉集檜嬬手』 |
| 富士谷御杖『万葉集燈』 |
鹿持雅澄『万葉集古義』 |
彼らは、賀茂真淵の弟子あるいは、その学閥に連なる学者たちだ
『万葉集攷証』の岸田由豆流は、真淵以前の訓を「いたく誤れり」として、
「『万葉考』の訓によるべきだ」と明言している
このように、私自身の契機ともなった〔48〕歌を採り上げて、
『万葉集』への私のこれまでの姿勢を今一度見詰めたかったので
今日は、長くなってしまった
この歌に限らず、『万葉集』の「訓」や「語解釈」には多くの異説がある
それは、根本的には、ただただ「表記」に拠るものだとは思うが
それと忘れてはいけないのは
梨壺で付けられた「訓」は、万葉時代から二百年も経過した時代の「訓」
ということは、多分に平安期の「古今集」のような詠い振りも影響あるのだろう、と
私には、その懸念も捨て切れないものがある
|
|
| 【歌意2928】 |
綺麗な「かつま」が合わさるように、逢おうと言ったのは、誰なのでしょう
こうやって逢っているときまでも、
あなたは、顔を見せてくれないのですね |
恋愛の、もっとも「恋愛らしいときめき」は
ひょっとすると、このような感じなのかもしれない
愛しい人に、逢えずにいる苦しさ、哀しさ
そして願いが叶って、いざ逢おうとするとき...あまりの「恥じらい」に、
顔を見せることもできない...
それは、自分も相手を見ることができない、ということだ
それまでの、「逢いたい」と思う気持ちは、何だったのだろう
しかし、顔を見せることが、願いを叶えることとは限らない
一目逢うことが、恋心を満たされるとは限らない
「眩しい」のだ
相手が眩しいだけではなく、自分の「恋心」までもが眩しくて
それを覆い隠して、気取られないようにする
その「眩しさ」こそ、恋の苦しさの原因であり、恋のときめきの正体ではないか
この歌に、「恋心」の原点を思う私は、単純かもしれないが
とても、新鮮な「恋歌」のように思える
作者は、勿論顔を見せてくれない人の相手方なのだが
顔を隠す所作を、咎めながらも、どこか優しく聞こえる
相手への思い遣りに満ちた歌だと思う
実際、言葉の表現だけを追いかけると、相手への非難のようにも感じられるが
歌というものは、根底にはどんな心境であろうと、「思い遣り」が「一片」はある
だからこそ、誰もが詠うことができるのではないだろうか
|
|
掲載日:2013.10.11.
| 正述心緒 |
| 玉勝間 相登云者 誰有香 相有時左倍 面隠為 |
| 玉かつま逢はむと言ふは誰れなるか逢へる時さへ面隠しする |
| たまかつま あはむといふは たれなるか あへるときさへ おもかくしする |
| 巻第十二 2928 正述心緒 作者不詳 |
| 【2928】語義 |
意味・活用・接続 |
| たまかつま[玉勝間 ]〔枕詞〕「あふ」「しま」にかかる |
「かつま」は竹の籠の意で、身と蓋が合うところから「あふ」に、
また、籠の目のしまっているところから、「しま」にかかる |
| あはむといふは[相登云者] |
| あは[逢ふ] |
[自ハ四・未然形]出逢う・対面する・来あわせる |
| む[助動詞・む] |
[意志・終止形]~つもりだ・~よう |
未然形につく |
| と[格助詞] |
[引用]「~と言って・~と思って」などの意で、あとに続く動作・状態の目的・状況・原因・理由などを示めす |
| 〔接続〕体言、体言に準ずる語につく |
| いふ[言ふ] |
[他ハ四・連体形]言葉で表現する・話す・言う |
| は[係助詞] |
[とりたてて言う・強調]~は |
| 〔接続〕名詞、助詞、活用語の連体形と連用形など種々の語につく |
| たれなるか[誰有香] |
| たれ[誰] |
[近世以降は「だれ」とも]不定称の人代名詞・だれ |
| なる[助動詞・なり] |
[断定・連体形]~だ・~である |
体言につく |
| か[係助詞] |
[疑問]~か・~だろうか |
体言につく |
| あへるときさへ[相有時左倍] |
| あへ〔逢ふ〕 |
[自ハ四・已然形]出逢う・対面する・来あわせる |
| る[助動詞・り] |
[完了・連体形]~ている |
已然形につく |
| とき[時] |
その場・一時・場合・おり・よい機会・好機 |
| さへ[副助詞] |
[添加]~までも |
| 〔接続〕体言・活用語の連体形・助詞などや、主語・目的語なども含め連用修飾語にもつく |
| おもかくしする[面隠為] |
| おもかくし[面隠し] |
〔おもがくし〕恥じたりして顔を隠すこと |
| する[為(す)] |
[他サ変・連体形]ある動作を行う・ある行為をする |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [第三句「か」と結句「する」] |
これは、一種の「係り結び」ではないかと思う
そうでなければ、私の乏しい知識では、結句が連体形で終る説明がつかない |
|
|
| 【歌意2930】 |
どうしたことだ、普通であれば、
なぜこんなに恋い慕い、苦しむことがあろうか
おそらく、そんなことはないだろう
これまでのように、逢えないことを嘆くような愚痴もいうことなく
愛しい人に寄り添って共に寝る年が、近いというのに...
もう少し待てば、それが叶うというのに... |
何故だろう...間もなく逢えるではないか
何故、そんなに恋の辛さに苦しむ
愛しく想う人と、間もなく逢える
そう思うだけで、日々の暮らしは明るくなる
普通は、そう思う...作者も、そう言っている
しかし、待ち遠しく思う時間は、人の想いを凝縮させることも事実だ
「時」は、まったく機械的に、無意思に刻み経過して行く
それでも、人の「待ち焦がれる想い」は、
その「時」を悪戯するかのように「奔放に解放つ」
その「奔放な時間」に振り回され
逢えるつもりの「日」が、永遠の彼方にも思えるのだろう
間違いなく、正確に訪れる「その日」ではなく
本当にやってくるのだろうか、と不安に押し潰されそうになる
手加減のしようのない「とき」も、
「恋い慕う」気持ちの前では、誰かに操られでもしているかのように振舞う
「なにかもこひむ」
この「なにかも」の語句が、とても不安感、焦りを際立たせてるように思える
そもそも、「なにかも」という「疑問」とか「反語」に繋がる語句を
続けて並べるのは、よほどのことではないか
勿論、「なに」は、理由を問う「疑問」であり、
「かも」は「反語」で、自問自答をしている
古典で、このような用法が珍しいのか一般的にあるものなのか、
私にはよく解らないが、少なくとも、『万葉集』中では、先ほど調べてみたら、
[巻第十一・2600]が一首あり、今日の掲題歌との二首だけだった
迂闊にも、その〔2600〕歌、〔2013年4月8日〕に採り上げている
しかし、その時の私の感想では、「なにかも」に特別な意識はなかった
一首全体の歌意として書いている
僅か半年前のことなのに、私自身も、『万葉集』への触れ方が違ってきている
当時は、細かい語句のことなど、あまり気にしなかったようだ
今何故、こうも「なにかも」が気になっているか、正直解らない
しかし、確実に『万葉集』にどっぷりと入り込んでしまっている私がいる
それは間違いないようだ
「なぜ今こんなに恋苦しむことがあろう...普通なら、そんなことはないだろう」
では、普通の状態ではない、ということなのだろうか...
「時の戯れこそ」...と思うのだが...
|
|
掲載日:2013.10.12.
| 正述心緒 |
| 大方者 何鴨将戀 言擧不為 妹尓依宿牟 年者近綬 |
| おほかたは何かも恋ひむ言挙げせず妹に寄り寝む年は近きを |
| おほかたは なにかもこひむ ことあげせず いもによりねむ としはちかきを |
| 巻第十二 2930 正述心緒 作者不詳 |
| 【2930】語義 |
意味・活用・接続 |
| おほかたは[大方者 ] |
| おほかたは[大方は] |
[副詞]普通は・一般には・通り一遍には |
| 〔成立〕名詞「おほかた」に係助詞「は」のついたもの |
| なにかもこひむ[何鴨将戀] |
| なに[何] |
[副詞](疑問)なぜ(~か)・なにゆえ(~か) |
| かも[終助詞] |
[反語]~(だろう)か(いや、~でない) |
| む[助動詞・む] |
[推量・終止形]~だろう |
未然形につく |
| ことあげせず[言擧不為] |
| ことあげせ[言挙げ] |
[他サ変・未然形]言葉に出してはっきり言う |
| ず[助動詞・ず] |
[打消し・終止形]~ない |
未然形につく |
| いもによりねむ[妹尓依宿牟] |
| より〔寄る〕 |
[自ラ四・連用形]近寄る・寄りかかる |
| ね[寝(ぬ)] |
[自ナ下二・未然形]眠る・寝る・男女が共寝する |
| む[助動詞・む] |
[推量・連体形]~だろう |
未然形につく |
| としはちかきを[年者近綬] |
| とし[年] |
季節・歳月・年齢 |
| ちかき[近し] |
[形ク・連体形](時間的・空間的・心理的に)近い |
| を[接続助詞] |
[逆接]~のに |
連体形につく |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [ことあげ] |
言わなくてもよいことを、口に出して言い立てること
この「ことあげ」を古語辞典で引くと、「名詞」と「他動詞サ行変格活用」がある
手持ちのどの辞書も、詳しく文法解説していないので、自分なりに考えてみた
まず、「ことあげ」が動詞だとすれば、その活用は「サ変」というので
その「サ変動詞」の活用形を考えてしまうが、「ことあげ」そのものではない
やはり、サ変動詞「為(す)」が、体言について複合動詞となるものだった
解ってしまえば、当たり前のように思えるのだが...そこは素人の文法解釈だから...
でも、少しずつ古語辞典の使い方が解ってきた |
|
 |

| 「ふたりして結びし紐」...たとえ擦り切れようと... |
|
|
|
| 【歌意2931】 |
あなたと一緒に結んだ紐だもの
わたし一人でだけで、それを解こうなんて、思いません
あなたに、じかに逢うまでは... |
| 【歌意1793】 |
愛しいあの人が結んでくれたこの紐、
どうしてわたしが解くことなどあろうか
切れるものなら切れてみよ
たとえ切れようとも、あなたに逢うまでは、決して解かないぞ |
『伊勢物語』三十七段に、〔2931〕と同じような想いの歌があるらしい
ちょっと、引いてみた
| 我れならで下紐解くなあさがほの夕影待たぬ花にはありとも |
| 二人して結びし紐をひとりしてあひ見るまでは解かじとぞ思ふ |
最初の歌が、男の歌で、それに女が返した歌が、まさに〔2931〕歌だった
使われている語句まで同じだ
『伊勢物語』は読んだこともないので、この「歌物語」どんな内容なのか解らないが
少なくとも、採り上げた歌に見る限り、「紐」を解く行為に関しては
万葉時代の俗信と同じものだとは解る
『万葉集』には、このような俗信ともいえる行為を詠ったものが多い
その意味を知っていないと、理解し辛い歌もあるだろう
恋人同士が紐を結び合い、固めのしるしとし、解けることを不吉と嫌った、とある
〔2931〕歌では、確かにそのように感じることが出来るが
〔1793〕歌は、少し違うようだ
男の紐を、結んでくれた「愛しい人」
ここでは、互いに結んだことは詠われていない
この歌は、笠朝臣金村歌集から載せられた長歌の反歌二首の内の一首
その長歌によると、詠者は役人で、気の進まない出張で旅に出たおり、
地方の里で、紐を解かずにごろ寝をすると、
自分の衣が随分よれよれになっていることに気づく
それを見て、この紐を結んでくれた「愛しい人」...妻だろう、きっと
その愛しい妻を思いだし、この「紐」に願を掛ける
自ら解くことなどするものか、妻が結んでくれたこの紐だから
たとえ、擦り切れても、決して解きはしない
最愛の妻を残し、旅する男の強い想いを込める歌ではないかと思う
俗信によるもの、と解するだろうが
それだけではないと思う
妻が「結んでくれた」紐...それを解くのは、「妻」であって欲しい
決して旅の惑いになど...と、
そう思うと、このような俗信も、
その発祥には、あまりにも人間らしい「まじない」めいたものがあったのかもしれない
以前にも書いたことがあるが、現代における和歌の解釈など
これまでの時代を重ねて研究されてきたほとんどの成果を基にしており
それをたたき台にして、新たな解釈がされている
いきなりこれまでの解釈をひっくり返すような新解釈などは、
よほど具体的な新資料が発見されない限り、かなり難しいものだと思う
この俗信にしても、現代の研究者たちが、探り当てたものではなく
そうした上古から断片的にでも残る資料に、基づくものだ
だからこそ、その「俗信」といわれるものが
どうして、こうも歌の世界に採り上げられるのか
和歌の類とは別の資料から、そうした世相が知り得るものなのか
それが気になってしかたない
逆に、和歌にこれほど多くの「俗信」が詠われており
他の資料では確認できなくても、こんなに詠われているのだから、
これは、間違いなく当時に多くの人が信じていった「まじない」の一種なのだ、と
そうも考えられるだろう
どうなのだろう
また調べたくなる事案が増えてしまった...楽しいことだけど
|
|
掲載日:2013.10.13.
| 正述心緒 |
| 二為而 結之紐乎 一為而 吾者解不見 直相及者 |
| ふたりして結びし紐をひとりして我れは解きみじ直に逢ふまでは |
| ふたりして むすびしひもを ひとりして あれはときみじ ただにあふまでは |
| 【語義・歌意】 巻第十二 2931 正述心緒 作者不詳 |
| |
| 相聞/((天平元年己巳冬十二月歌一首[并短歌])反歌) |
| 吾妹兒之 結手師紐乎 将解八方 絶者絶十方 直二相左右二 |
| 我妹子が結ひてし紐を解かめやも絶えば絶ゆとも直に逢ふまでに |
| わぎもこが ゆひてしひもを とかめやも たえばたゆとも ただにあふまでに |
| 右件五首笠朝臣金村之歌中出 |
| 【語義・歌意】 巻第九 1793 相聞 笠金村歌集出 |
| 【2931】語義 |
意味・活用・接続 |
| ふたりして[二為而 ] |
| して[格助詞] |
[人数・範囲]~で・~とともに |
| 〔接続〕体言及び活用語の連体形など体言に準じたものや格助詞「を」につく |
| むすびしひもを[結之紐乎] |
| むすび[結ぶ] |
[他バ四・連用形]紐を結ぶ・言いかわす・編んで作る |
| し[助動詞・き] |
[過去・連体形]~た・~ていた |
連用形につく |
| ひとりして[一為而] |
| して[格助詞] |
[人数・範囲]~で・~とともに |
| あれはときみじ[吾者解不見] |
| とき[解く] |
[他カ四・連用形]結び目をほどく |
| み[見る] |
[他マ上一・未然形]処理する・取り扱う・試みる・眺める |
| じ[助動詞・じ] |
[打消意志・終止形]~ないつもりだ |
未然形につく |
| ただにあふまでは[直相及者] |
| ただに[副詞] |
〔直に〕直接に・まっすぐに |
| |
〔徒に〕むなしく・何もしないで |
| |
〔唯に・啻に〕(下に打消・反語の語を伴い)ただ単に |
| まで[副助詞] |
[限度](動作・作用の及ぶ時間的・空間的な限度)~まで |
| 〔接続〕体言及び体言に準ずる語、動詞・助動詞の連体形、副詞や助詞など種々の語につく |
| は[係助詞] |
[強調]前の語句を強調すると思う |
| 〔接続〕名詞、助詞、活用語の連体形・連用形など種々の語につく |
| 掲題歌トップへ |
| 【1793】語義 |
意味・活用・接続 |
| わぎもこが[吾妹兒之 ] |
| ゆひてしひもを[結手師紐乎] |
| ゆひ[結ふ] |
[他ハ四・連用形]結ぶ・ゆわえる |
| て[助動詞・つ] |
[完了・連用形]~た・~てしまう |
連用形につく |
| し[助動詞・き] |
[過去・連体形]~た・~ていた |
連用形につく |
| とかめやも[将解八方] |
| とか[解く] |
[他カ四・未然形]結び目をほどく |
| めやも[反語] |
~だろうか(いや、~でないなあ) |
未然形につく |
| 〔成立〕推量の助動詞「む」の已然形「め」+反語の終助詞「やも」 |
| たえばたゆとも[絶者絶十方] |
| たえ[絶ゆ] |
[自ヤ下二・未然形]絶える・切れる |
| ば[接続助詞] |
[順接の仮定条件]~(する)なら・~だったら |
未然形につく |
| たゆ[絶ゆ] |
[自ヤ下二・終止形]絶える・切れる |
| とも[接続助詞] |
[逆接の仮定条件]たとえ~にしても |
終止形につく |
| ただにあふまでに[直二相左右二] |
| ただにあふまで |
上、〔2931〕既出 |
| に[格助詞] |
[時間を表す]~に・~の間は |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [たえばたゆとも] |
この語句は、「~(未然形)ば~(終止形)とも」で一種の慣用句だろう
「未然形+ば」で、順接の仮定条件、「終止形+とも」で逆接の仮定条件
『万葉集』中の用例でも、「散らば散るとも」「染まば染むとも」などがあり
この語句の下に「よし(縦し)」という言う副詞が略されている
この副詞「よし」の意味は、「不満足だが仕方ない・どうなろうとも」などがある |
|
|
| 【歌意2932】 |
やがて尽きるだろうこの命、
そのことは、何とも思いはしない
しかしながら...あなたに逢えなくなることこそが
わたしを、こんなにも嘆かせ、苦しめてしまう |
初句の原文「終命」を、多くの注釈書は「しなむいのち(死なむ命)」としている
私の手持ちの資料では、伊藤博校注『万葉集』に、「をへむいのち(終へむ命)」とあり、
その訓の方がいいのでは、と思う
ついでに、「しなむいのち」と訓じる集中の他の原文を探すと、一首だけあった
巻第十六・3833歌に、原文「将死命」を「しなむいのち」と訓じている
「終命」と「将死命」...この訓を、私は同じようにすべきではないと思う
どちらも、結果的には「あらがえない死」をいうものだろうが
「終命」には、はなから「死」を受け入れる自然体の姿勢を感じる
しかし「将死命」をイメージすると、何かに未練を引きづりながらも...
自らの「意志」を感じさせる
この歌では、「死」など怖くも思わない、ただあなたに逢えなくなることだけが...
少なくとも、これは「未練」ではなく、ましてや望むものでもない
ただただ、なるようになれ、あらがいはしない、と
敢えて未練といえば、あなたに逢えなくなることだ、それを気にしている、私は...
「しなむいのち」、『万葉集古義』もそう訓じており、そこに異訓の解説がないので
すでに「しなむいのち」の方が、その頃には定着していたのだろう
『全集』によると、『名義抄』に「終、シヌ」とあり、
更に、『古今集』恋歌二に「しぬるいのちいきもやする」(568)とあることで
「しぬる」とも訓じられる可能性にも言及している
「をへむいのち」の訓に可能性を見出す根拠は、
「仏足石歌」に「我が世(生涯)は終へむこの世は終へむ」と「をへむ」と訓じていることから
「をへむ」も可能性あり、としている
いずれにせよ、『万葉集』中ではなく、他の歌集あるいは資料からの推測がほとんどで
こうなれば、私のような素人に残された手段は
「字面」のイメージと、歌意に流れる「こころの響き」になるだろう
そして、私は...「をへむいのち」の方が、いい、と思った
作者のいう「終命」とは、どのような情況で詠ったのだろう
戦乱、処罰、病...
あるいは、単純に「命なんて、恋する気持ちに比べれば」ということか
いや、それは違うだろう
単に激しい「恋心」を言うのではなく
「死」は前提なのだと思う
目の前に、それがある
情況はともかく、そんな「死」を前にして
ひとつの心残りが、あなたに逢えなくなること、それが自分を苦しめている
現代と、当時の「死生観」を、ふと思ってみる...
|
|
掲載日:2013.10.14.
| 正述心緒 |
| 終命 此者不念 唯毛 妹尓不相 言乎之曽念 |
| 終へむ命ここは思はずただしくも妹に逢はざることをしぞ思ふ |
| をへむいのち ここはおもはず ただしくも いもにあはざる ことをしぞおもふ |
| 巻第十二 2932 正述心緒 作者不詳 |
| 【2932】語義 |
意味・活用・接続 |
| をへむいのち[終命 ] |
| をへ[終ふ] |
[他ハ下二・未然形]終える・終らせる・終りまでやる |
| む[助動詞・む] |
[推量・連体形]~だろう |
未然形につく |
| ここはおもはず[此者不念] |
| ここ[此処] |
[近称指示代名詞]事物・場所をさす・この点・このこと |
| ただしくも[唯毛] |
| ただし(くも)[但し(くも)] |
[接続助詞]もっとも・しかしながら・ひょっとしたら |
| 〔成立〕副詞「ただ」に副助詞「し」のついたもの |
| いもにあはざる[妹尓不相] |
| あは[逢ふ] |
[自ハ四・未然形]出逢う・逢う・対面する |
| ざる[助動詞・ず] |
[打消・連体形]~ない |
未然形につく |
| ことをしぞおもふ[言乎之曽念] |
| こと[事] |
行為・動作・事情・わけ・意味 |
| 用言、助動詞連体形につき、動作・作用・状態の名詞を作る「~すること・~であること」 |
| を[格助詞] |
[対象]~を |
体言、活用語の連体形につく |
| し[副助詞] |
[語調を整え、強意を表す]強める |
| 〔接続〕体言または活用語の連体形・連用形、副詞、助詞などにつく |
| ぞ[係助詞] |
[強調]主語または目的語を強調する〔係り結びの「係り」〕 |
| おもふ[思ふ] |
[他ハ四・連体形]思う・思い起こす・心配する・悩む |
| 係助詞「ぞ」を受けて、係り結びの「結び」として、連体形で終る |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [ただし(くも)] |
接続助詞「ただし」の二種の語意
①前の文に添えて、条件や例外などを言い出す語
「もっとも・とはいうものの・しかしながら」など
②前の文を受け、推量や疑問の内容を説くのに用いる
「あるいは・もしくは・ひょっとしたら」など
「ただしく」は、同じような用例として
「けだし⇒けだしく(も)」「しまし⇒しましく(も)」などにあるような派生語
「し」で終る三音節の副詞を五音句にあてようとして、
形容詞シク活用の副詞形にしたものの連想では、といわれる |
|
 |
| 【歌意2933】 |
か弱いこんな私でも、あなたと同じように
ちょっとの間でも、絶えることなく
きっとあなたに逢いたいと・・・、
あの娘なら、そう言うだろうと思う |
「か弱い私でも」、同じ気持ちで逢いたいと思うのか、
「か弱い私だから」、あなたと同じように思っていたいのか...
係助詞「は」には、「順接の仮定条件」で「~ならば」という用法もあるが
「仮定条件」とうのは、実際は「手弱女」ではない、ということだろうし
そうなると、この詠歌の全体の意味としてはそぐわない
敢えていうなら「確定条件」で、「~なので」とでもあればいいのだが、
この「係助詞」には、その用法はなかった
何故、このように「ここの部分」が気になったのかといえば
結句の解釈に随分悩んだからだ
それで、何か手懸りを、と読み直してはみたものの、やはり解らない
その結句「みてむとぞおもふ」
「みてむとぞおもふ」の「みてむ」だけで、「きっと逢いたいだろう」
誰が、そう思うのか...それは「手弱女」である女
そして「とぞ」は、更にそれを強調していう
最後の「思ふ」は、誰が「思う」のか...これで悩んでしまった
どの注釈書でも、やはり作者「手弱女」の女が、自身のことをそう思った、としている
しかし、逆の場合も考えられないか、と私は思う
「手弱女」の愛しい女性である、あの娘は、
自分も同じ気持ちで、絶え間なく逢いたいと・・・ここまでを、男が思ったのではないか
「とぞ」で一旦区切れると思う
それまでの「手弱女」の女の気持ちを察して、男は思う
仮に、通説であれば、最後の「思ふ」が、どうもしっくりこない
女が、客観的に冷静に自分をそう見詰めている、ということになる
自分は、こんな風に、思います、と
それでは、歌の余情が沸かない
少なくとも、私には響かない
男が、女...むしろ「娘」とイメージした方がいいのだろうが
あの娘なら、きっとこんな風に言うだろう、と「思う」
そう詠った歌ではないか
通説の下二句を拾い出してみると
「絶え間もなく逢いたいと思います」[中西進・全訳注]
「休む間とてなく逢いたく思います」[小学館『新編日本古典文学全集万葉集』]
「止む時なくあなたのお姿を見たいと思っています」[岩波『日本古典文学大系万葉集』]
など、これらが代表する解釈なのかどうか解らないが
取敢えず、この「二句」を読むと、私には不思議に思えてならない
「みてむ」で、自身の気持ちは吐き出しているのではないか
「てむ」が「強い推量」
きっと~だろう・~にちがいない
敢えて最後の「思ふ」を女の思いにするのなら
「僅かな間でも、ちょっとの間でも、逢いたいと思うに違いない」
そう訳した方が、より自然だと思う
「とぞ」があって「思ふ」が終りにくるから、上記のような日本語になったのだろう
一様に、「思います」と締めくくらなければ...と
私も、最初はそう訳してしまった
しかし、どう語順を遣り繰りしても、最後の「思ふ」がぴんとこない
だから、この「思ふ」が別人であったら、と
その方が、少なくとも歌の語を素直に訳せた
素人とは、恐ろしいものかもしれない
「盲蛇に怖じず」、まさにその通りだ
自分だけでも、そんな歌だと思うことにしよう
|
|
掲載日:2013.10.15.
| 正述心緒 |
| 幼婦者 同情 須臾 止時毛無久 将見等曽念 |
| たわや女は同じ心にしましくもやむ時もなく見てむとぞ思ふ |
| たわやめは おなじこころに しましくも やむときもなく みてむとぞおもふ |
| 巻第十二 2933 正述心緒 作者不詳 |
| 【2933】語義 |
意味・活用・接続 |
| たわやめは[幼婦者 ](「たをやめ」に同じ) |
| たわやめ[手弱女] |
か弱い女性・しとやかな優しい女性 |
| おなじこころに[同情] |
| おなじ[同じ] |
[形シク・終止形]同一である・等しい |
| しましくも[須臾] |
しましく[暫しく](上代語)
|
[副詞]しばらくの間 |
| やむときもなく[止時毛無久] |
| やむ[止む] |
[自マ四・連体形]絶える・続いていたものが終りに鳴る |
| も[係助詞] |
[強意](下に打消しの語を伴う場合) 強める |
| 〔接続〕名詞、助詞、用言や助動詞の連体形・連用形など、種々の語につく |
| みてむとぞおもふ[将見等曽念] |
| み[見(み)] |
[他マ上一・連用形]逢う・顔を合わせる・目にする |
| てむ(「てん」とも表記される) |
[強い推量]~にちがいない・(きっと)~だろう |
| 完了(確述)の助動詞「つ」の未然形「て」+推量の助動詞「む」〔接続〕連用形につく |
| とぞ |
[文中に用いて]「と」の受ける内容を強める |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [たわ(撓)] |
ここで「たわ」と使うからには、「たわ」の本来の意味にも関連があるだろう
「たわやめ」が「たをやめ」と同じだというが、
どうして「たわやめ」と訓じるようになったのだろう
原文「幼婦者」の「字面」が、そもそもの「たをやめ」を意味するのだろうか
「たわ」の本来の意味を引いてみる
形容動詞ナリ「たわ」は、「しなうさま・ゆがむさま・たわわ」
そこから、いかにも「しなうさまの女」、幼い子のように「たわむ女」が連想される
それで「たわ」と訓じたのかな
『万葉集古義』を捲ってみる
すると、雅澄は、本居宣長説を採用している
〔原文は「幼婦者」で、タハヤメハとよむのが普通。「幼婦者、穩ならず、本居氏、或人の説に、この三字は、紐緒之(ひものをの)の誤なるべし、古今集に、入れ紐の同じ情にいざむすびてむ、とあるに同じといへり、と云り、姑く此の説によりて訓つ」。〕
この誤写説、あるいは誤記説などは、私はあまり乗り気ではないが、
古今集の歌を採り上げて、その根拠としているのも、面白い
|
| |
| [おなじ] |
ここでも『万葉集古義』に、ついでに目を遣ると
「おやじ」と訓じている
「おやじ」は、上代語で「同じ」のことなので、
この「おやじ」と訓じる注釈書は珍しくない
ここで気になったのは、活用のことだ
「おなじ」であれば、「終止形」となる
古語辞典を引く
〔参考〕体言に接続する場合、和文では連体形「おなじき」より、
終止形「おなじ」を用いる方が多い、
「おなじき」は、漢文訓読体の文に多く使われる、とあった
|
|
 |

| 「日々、またあらたに」...つねのときめきか... |
|
|
|
| 【歌意2934】 |
日が暮れてしまえば、あなたに逢えるだろうと、
そう思うからこそ、日が暮れることが
いっそう喜ばしいものなのですよ |
日が暮れると、あの人がやってくる
だから、「夕べ」は、待ち遠しく嬉しいものだ
このような歌は、『万葉集』には随分とある
いってみれば、みんな類想歌のようなものだ
当時の結婚生活の慣習で、男が妻の実家に通う、と聞くが
生活の基が、このように夜に妻の実家に通うだけなら
実質的な普通の結婚生活なのでは、と思う
朝から夕刻まで仕事する
そして、夕べになると、妻のいるところへ帰る
それを「通う」というのだろうか
男は、自分の家を持っている...だから「通い婚」か
しかし、生活の実態は...何も夜だけやってくる、と言わなくても
夜には、男が仕事から帰ってくる
現代でも、有り触れた結婚生活の形だ
そこのところが、私にはよく分からない
あるいは、男が家業の仕事をしていて、日中は男の実家にいる
しかし、夜は妻のところで過ごす...ということか
それとも、当時の勤めは、割と早い時間に終り
男は一旦自分の家に戻る
そして、日が暮れたら...妻の実家に行く...ことかもしれない
私の勉強不足であることは否めない
いつも、この類の歌に接すると、こうした疑問が頭を過ぎる
詠歌の背景...もっと本腰を入れて勉強しなければ、とつくづく思う
いや、それだけではない
今日の歌、文法的にも、私にはかなり難しかった
理屈で通る意味になるためには、こうあるべきだ、と...
いったいいつになったら、古語辞典を必要としないで、読み得るのだろう
でも、こうして手間をかけるのも、また楽しいことだが....
ただ、夜更かしは、つらい |

|
掲載日:2013.10.16.
| 正述心緒 |
| 夕去者 於君将相跡 念許増 日之晩毛 □(変換表記できず)有家礼 |
| 夕さらば君に逢はむと思へこそ日の暮るらくも嬉しかりけれ |
| ゆふさらば きみにあはむと おもへこそ ひのくるらくも うれしかりけれ |
| 巻第十二 2934 正述心緒 作者不詳 |
| 【2934】語義 |
意味・活用・接続 |
| ゆふさらば[夕去者 ] |
| ゆふさら[夕さる] |
[自ラ四・未然形]夕方になる・夕べが来る |
| ば[接続助詞] |
[順接の仮定条件]~なら・~だったら |
未然形につく |
| 已然形に付くときは、順接の確定・恒常条件になる〔~ので・~だから・~すると必ず〕 |
| きみにあはむと[於君将相跡] |
| あは[逢ふ] |
[自ハ四・未然形]出会う・対面する |
| む[助動詞・む] |
[推量・連体形]~だろう・~よう |
未然形につく |
| と[格助詞] |
[引用]下に続く動詞の内容を示す |
連体形につく |
| おもへこそ[念許増]〔「おもへばこそ」に同じ〕(五音にするためだろうか) |
(ば)こそ
|
〔活用語の已然形について〕確定条件の強調を表す
~だからますます(~だ) |
| ひのくるらくも[日之晩毛] |
| くるらく[暮(く)る] |
[自ラ下二動詞「暮る」に接尾語「らく」で名詞化]
日が暮れること |
| も[係助詞] |
[感動・詠嘆]~もまあ |
| 〔接続〕名詞、助詞、用言や助動詞の連体形・連用形など、種々の語につく |
| うれしかりけれ[将見等曽念] |
| うれしかり[嬉し] |
[形シク・連用形]喜ばしい・快い・嬉しい |
| けれ[助動詞・けり] |
[過去・已然形]~たなあ・~たのだ |
連用形につく |
| 已然形で終るということは、第三句の「こそ」の係り結びなのだろうか |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [さる]「さる」という動詞 |
四段動詞「さる」は、移動する意味が原義であり
「行く」にも「来る」にも用いられる
「来る」意のときは季節や時を示す語につき、
「夕されば」、「春されば」、「秋されば」など「已然形+ば」の形になることが多い
また、「来る」と重ねて「春さりくれば」と用いることもある
今日の歌は、「ゆふさらば」で、「未然形+ば」、「仮定条件」の用法だ
原文「夕去者」を、「ゆふされば」なのか「ゆふさらば」なのか
どうやって見分けるのだろう...歌全体の歌意に合うか合わないか、なのだろうか
その疑問があったので、
『万葉集』中の「ゆふされば」「ゆふさらば」の原文を拾い出してみた
私の不充分な資料の中から、何とか探がし出すが、若干の数え間違いもあるかもしれない
| 【ゆふされば】 |
| 暮去者 (12) |
2-159/3-391/4-605/6-959/7-1156/9-1668/
10-1941,2169,2323/11-2604 |
| 夕去者 (6) |
2-138/3-357/6-918/8-1457/10-2218/11-2593 |
| 由布佐礼婆 (6) |
14-3534/15-3611,3688/17-3984,4027,4030 |
| 由布左礼婆 (2) |
15-3647,3649 |
| 夕者 (2) |
10-2099/11-2508 |
| 暮去者 (1) |
19-4231 |
| 【ゆふさらば】 |
| 暮去者 (3) |
2-121/4-747/19-4201 |
| 夕去者 (1) |
12-2934 |
「由布佐礼婆」「由布左礼婆」の表記であれば、
「ゆふされば」と客観的に訓じられると思うが、
その他の表記だと、どこに訓の使い分けがあるのか、すぐには分からない
「ゆふされば」は「已然形+ば」で「確定・恒常条件」
「ゆふさらば」は「未然形+ば」で「仮定条件」
当然解釈も違ってくるはずなのに...
勿論、歌全体の歌意というものもあるが、
それだと解釈の前に歌の意図が語られている、ということになり、不自然だ
確かに、テーマがあれば、それも可能だとは思うが
上表のように列挙しただけでは、さっぱり分からない
いずれ、それぞれの歌意を並べてみようと思う
当然、前後の語句とのつながりの問題もあるだろ牛...
さらには、作者の「書きくせ」もあるだろう(大伴家持が結構登場する)
古語の文法...例外はあるのだろうか...
いずれにしても、ここでは「順接の仮定条件」で訳すことになる
|
|
|
| 【歌意2935】 |
今このときも、今日にでもあなたに逢いたいと思うのに
人のうわさが、絶え間なくうるさいので
逢わないままに、ずっと恋い慕い続けるだけなのかなあ |
ただ想うだけじゃない
今すぐにでも、逢いたいと思う
その気持ちを、こうやって訴えるのなら
世間のうるさいうわさなど、何でもないではないか
目の前に、作者がいたら、私はそう言うだろう
気持ちは、少しの間も休むことなく恋い慕い続けているのに、
どうしても、世間の噂が気になって、などと
これでは、まったくの言い訳のようにしか思えない
本当は、そんなに逢いたいと思っているわけではない、と白状しているようなものだ
現代なら、現代に生きている私なら、そう考えてしまうだろう
しかし、この時代の「恋愛観」は、どうだったのだろう
「世間の噂」になることは、どうしても避けなければならないことだったのだろうか
「世間の噂」というのは、まともな「恋愛感情」を台無しにしてしまうほど
影響力があり、支障のあるものだったのだろうか
この歌の「こころ」が、偽りなく「我慢できないほど逢いたい」というものであっても
それにも勝る「世間の噂」という「大障害」なのだろうか
この時代の「恋愛観」あるいは「形」
昨日の「男が通う」恋というものも含め
やはり調べてみたくなった
これまで、時代の息づく「価値観」にはあまり気を向けなかったが
『万葉集』には、これでもか、というほど、このような歌が多い
「作者不詳」歌だからこそ、より実情に近いものだろうし
そうなれば、その世相も...やはり無視はできない
純粋に「うたごころ」を、と思っていても
その「こころ」を少しでも感じるためには、「時代観」は、やはり必要ということか
『万葉集』に馴染み始めた頃、やたらと「当時は何々の習慣」とか
その頃は、不必要な先入観だ、と気にもしなかったが
ならば、どうしてそのような「習慣」が解ってきたのか...
また、手探りから始めてみたい、と今は思いだしている
明日香の図書館があるから...
今、改めて思うと
大阪に来る前の「つくば時代」であれば、ここまで思いもしなかったことだろう
つくづく、こちらに住むようになって良かった、と思う
もっとも、大阪自体は、未だに馴染めないが... |
|
掲載日:2013.10.17.
| 正述心緒 |
| 直今日毛 君尓波相目跡 人言乎 繁不相而 戀度鴨 |
| ただ今日も君には逢はめど人言を繁み逢はずて恋ひわたるかも |
| ただけふも きみにはあはめど ひとごとを しげみあはずて こひわたるかも |
| 巻第十二 2935 正述心緒 作者不詳 |
| 【2935】語義 |
意味・活用・接続 |
| ただけふも[直今日毛 ] |
| ただ[唯・只] |
[副詞]程度副詞としての用法、たった今・ほんの |
程度副詞は、一般的に形容詞などを修飾するが、
数量・方向・時間を表す名詞を修飾する場合もある 〔「今日」を強調している〕 |
| きみにはあはめど[君尓波相目跡] |
| あは[逢ふ] |
[自ハ四・未然形]出会う・対面する |
| め[助動詞・む] |
[意志・已然形]~よう・~つもりだ |
未然形につく |
| ど[接続助詞] |
[逆接の確定条件]~けれども・~のに |
已然形につく |
| ひとごとを[人言乎] |
ひとごと[人言]
|
他人のいう言葉・世間のうわさ |
| を[間投助詞] |
[「~を~み」の用法]~が~ので (次の「しげみ」へ) |
| しげみあはずて[繁不相而] |
| しげみ[繁し・茂し] |
[形ク・語幹]絶え間ない・うるさい |
| 上代の語幹(シク活用は終止形)に接尾語「み」をつけて、原因・理由を表す用法 |
| あは[逢ふ] |
[自ハ四・未然形]出会う・対面する |
| ずて |
~ないで・~なくて |
未然形につく |
〔成立〕打消の助動詞「ず」の連用形「ず」+接続助詞「て」
〔参考〕おもに上代に用いられ、平安時代以降は和歌の用語として残った |
| こひわたるかも[戀度鴨] |
| こひ[恋ふ] |
[他ハ上二・連用形]思い慕う・恋慕する・想う |
| わたる[渡る] |
[自ラ四・連体形](動詞の連用形について)
時間的に「ずっと~続ける」の意を表す
空間的に「一面に」の意を表す |
| かも[終助詞] |
[詠嘆・感動]~であることよ |
連体形につく |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [昨日の歌〔2934〕の「ゆふさらば」] |
原文「夕去者」の訓が、どうしても気になり、今日調べてみた
すると、旧訓では「ゆふされば」とあったようだが、
『万葉集略解』橘千蔭〔寛政十二年(1800)成立〕で、この初句「夕去者」を、
「ゆふさらば」と改訓した、と『万葉集全注』(昭和58年刊行開始)に解説されていた
その理由として、
主文が「君に逢はむ」であるから「仮定条件」の「さらば」でなければ、といい
私も、同じような理由で「仮定条件」、つまり「さらば(未然形)」だと思う
これは、原文「夕去者」の訓として、全体の歌意にそくした、と
その手段・方法を教えてくれたようなものだ
やはり続く語句など、歌意に不自然さがなければ、訓、つまり解釈は決まるものだ、と
では、ここでまた疑問が生じる
何故、旧訓では「ゆうされば」だったのか、ということ
少なくとも、『万葉集略解』で、上述の説明をして改訓したのであれば
当初の解釈は、「確定条件」であったということになる
勿論、作者の意図が「確定条件」だった、というのではなく
『万葉集』に訓が付けられる時代、平安時代の学者たちの解釈が、そうだった
ということになってしまう
〔2934〕歌は、そのような解釈も成り立っていた、ということではないか
すると、『略解』が理由としてあげる「君に逢はむ」との関係が曖昧になる
同じく「已然形」の場合には「確定条件」だけではなく、「恒常条件」もある
意味は「~すると、必ず」となる
旧訓での解釈は、きっとそうだったに違いない
「夕方になれば、必ず逢えるだろう」...おそらく、そんな歌意として訓が付けられた
これで、少しは疑問が解けたかもしれない...少なくとも、私への説明には...
となれば、次の疑問
いや、疑問というより、改めて『万葉集』に訓をつける作業が至難のことだったか
それが現代においても、未だに研究対象として残るのだから
本当に、『万葉集』は、作者が詠じた「まま」に読めるなどとは
永遠に不可能なことなのだろうか...寂しいような嬉しいような...複雑な気持ちだ
|
|
|
| 【歌意2942】 |
これまでの私の人生で、「恋」というものに出逢ったこともなかった
だから、今まさに恋に夢中になっているこの「私の恋」は
こんなにも苦しくて辛いものなのか |
恋に初めて出逢う
異性にときめく心情を、初めて自覚する
やがて、この辛さこそ、「恋」というものだ、と気づいていく
だから、『万葉集』中にときどき使われる「こひ」の表記「孤悲」
この表記が、私にはとても印象深かった
まさに、これぞ「こひ」だ、と
この歌のように、「恋」に初めて出会い
そして、やがて様々な「恋」の形を詠う
人の最初にしか経験し得ない、新鮮な「芽生え」を感じられる歌だ
今日は、読んでいた本の中で、まさにこうした「物語」的な歌への意欲を知った
「日記」ブログにも書いたものだが
最近の私の「気掛かり」に、何とか光を当ててくれそうだ
ブログと重複するが、ここにコピーしてみる
著者は言う、
「一首それぞれの言語量は三十一文字の短詩形であるから、その情報量は少ない。けれども一首ずつの歌が集まって一つの歌群を成すと、それぞれの歌群の言語量は豊富さを獲得する。そしてさらにそれらの歌群をその意味内容に即して論理的に結び付けていくならば、たちまち巻十一、十二の歌々は一つの物語を成していることに気づかされるのであった。」
「その歌物語とは、それはこれから結婚しようとする未婚の少年少女たちが、互いに相逢おうとするところから始まり、その恋は家父長権を代行する母親の制止の下に置かれているけれども、遂にはその恋が許され、少年は男夫の資格を許されて女家に通い始める。しかしながら通い始めることが許されたからといって、その婚姻は直ちに成立するものではない。なぜならば男はまだ許されて女家に通い始めたばかりで、その時期ではその新しく始まった男の女家への通いに関し、「里人」は兎角いろいろ悪評を加えて妨げをなすことがあったからである。また幸いにしてそのような悪評、妨げがなくても、男は女家に通い始めて女に逢い始めたばかりであるから、通い逢い始めているうちに男女間の不和や不実が持ち上がり、それが原因で男が女家に足を向けることが稀になったり、まったく通う足が途絶えてしまったりすることもあった。このように古代では少年少女の恋が実って婚姻の成就に辿り着くまでには、さまざまな辛苦心労があり悲哀のあったことが、これら歌々の整序を通して偲ばれるのであり、そのことがこれら歌々の主題であるように察せられるのである。歌々はこのような当時の時代社会で考えられ得る限りの、さまざまな恋と婚姻上の悲喜劇を描いているように察せられる。」 |
この文章は、著書名「万葉集作者未詳歌巻の説明」...たしか、そうだった
著者・今井優 和泉書院発行
先日、明日香万葉文化館の図書室でコピーしたもので、表紙はコピーせず
その目次を見て、最近の私が感じている、「当時の婚姻」絡みの実情
その実情を、『万葉集』の「作者未詳歌」を理解することで深めようとしている
従来の積み重ねられた「通説」ではなく、『万葉集』そのものから
「歌物語」を通して浮かび出させることを試みている
久し振りに夢中になって読めそうな本だ
まだ読み始めたばかりだが、何しろ高価な本
先日は、250頁ほどコピーしてもらったが...
いつも通うたびに、コピーばかりしてもらい、厚かましいとは思っているが
それでも、まだまだ必要箇所は残っている
きっと、この先も続くだろう...職員さんたちには、ただただ感謝
そのコピーしてもらっている間には、明日香散策も十分出来るし
ますます明日香が「欠かせない古都」なっている
今日の歌ではないけど、こんな気持ちで「日々を過ごす」のは、辛いことだ
これほどまでに、読みたい本が...普通の図書館にないとは...
並行して、古書店めぐりも頻繁になりそうだ
この本にも書かれているように、
「作者未詳歌」をばらばらで読めば、確かに類想歌だらけに思うだろう
実際、毎日『万葉集』の頁を捲っていて
あれ、この歌、過去にも採り上げたような、と思うことが多い
しかし、未掲であることを知ると...どうしてこう似たような歌を、と思ってしまう
そのひっかかりも、これから紐解く楽しの中で、少しは解消できそうだ |
 |
掲載日:2013.10.18.
| 正述心緒 |
| 生代尓 戀云物乎 相不見者 戀中尓毛 吾曽苦寸 |
| 生ける世に恋といふものを相見ねば恋のうちにも我れぞ苦しき |
| いけるよに こひといふものを あひみねば こひのうちにも われぞくるしき |
| 巻第十二 2942 正述心緒 作者不詳 |
| 【2942】語義 |
意味・活用・接続 |
| いけるよに[生代尓 ] |
| いけ[生(い)く] |
[自カ四・已然形]生きる・命を保つ |
| る[助動詞・り] |
[完了・連体形]~ている・~てある |
已然形につく |
| よ[世・代] |
個人の一生涯・一生・世間・世の中・ある時期 |
| に[格助詞] |
(時間的に)~に 〔接続〕体言・活用語の連体形につく |
| こひといふものを[戀云物乎] |
| いふ[言ふ] |
[他ハ四・連体形]称する・呼ぶ・名付ける |
| もの[物] |
物事・もの |
| を[格助詞] |
[対象]~を・~に 〔接続〕体言・活用語の連体形につく |
| あひみねば[相不見者] |
あいみ[相見る]
|
[他マ上一・未然形]対面する・逢う |
| ねば[間投助詞] |
[順接の確定条件]~ないので・~ないから |
未然形につく |
| 〔成立〕打消しの助動詞「ず」の已然形「ね」+接続助詞「ば」(已然形+「ば」で確定条件) |
| こひのうちにも[戀中尓毛] |
| うち[内・中] |
心の中・(数量的に)一部分、その中 |
| にも |
~においても・~でも |
(格助詞「に」の意味により種々の意味を表する)
〔成立〕格助詞「に」+係助詞「も」 |
| われぞくるしき[吾曽苦寸] |
| ぞ[係助詞](上代では「そ」) |
[強調]~が・~を 〔係り結びの「係り」〕 |
| くるしき[苦し] |
[形シク・連体形]痛みや悩みでつらい・苦しい |
| 係助詞「ぞ」を受けて、連体形で結ぶ 〔係り結びの「結び」〕 |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [いけるよに] |
『万葉集全注』では、この「生ける代に」の「いける」は、
「生く」に、「あり」を添えたもの、「生きているの意」と語釈されている
続いて、生きているこの世でのことであるが、
生れてこの方、今までの自分の生涯の意、と
「生有代尓我はいまだ見ず言絶えてかく面白く縫へる袋は」<万葉集4・749>
この「いけるよに」に同じだと説明してあった
しかし、〔749〕歌を〔2013年7月20日〕に採り上げたときも、
私は、やはり今日と同じような文法解釈をしている
それで、不自然さを感じなかったからだ
ただし、〔749〕と、今日の〔2942〕歌の原文を比べてみると
〔749〕では、「生有代尓」で、今日の〔2942〕は「生代尓」
たしかに「有」という「字」に対して、
『万葉集全注』のような文法も感覚的には理解できる
では、今日の〔2942〕に「有」が使われていないので、
今日の歌こそが、先のような文法解釈で
〔749〕歌は、『万葉集全注』のような、「いく」「あり」なのだろうか
でも、その場合でも、この『全注』の筆者たちは、同じ、と言っている
『万葉集』中でも、「いけるよ」という訓のある原文は、
この二首しかない...他に手がかりはない
しかし「生く」の活用では、連用形「いき(四段・上二段)」であり、
接続する動詞「あり」に「いける」とはつながらない
他動詞「生く」であっても、「カ行下二段」で、その連用形は「いけ」となる
となると、「いくあり」が音便か何かの変化なのだろうか...
残念ながら、今の私の能力では、解らない
|
| |
| [生く] |
〔参考〕
「生く」の活用には、自動詞の場合には「カ行四段」と「カ行上二段」がある
ただし、四段活用はおもに中古までで、上二段活用は中世以降の用法
|
| |
| [こひといふものを] |
この句は字余りで、そうとしか訓めなかったのか、と思ったら
原文「恋云物」には、
「こひてふもの」〔旧訓・拾穂抄〕
「こひちふもの」〔童蒙抄・古義・井上新考〕
「こひとふもの」〔考・略解・口訳・岩波文庫新訓など〕
以上の注釈書などは、こうして字余りを解消している
ただし、通説では
「こひといふもの」〔定本・全註釈・古典大系〕に落ち着き
字余りを「よし」としている
源俊頼『俊頼髄脳』など歌論書に、「字余り」の決まりみたいな書いてあるかもしれない
|
| |
| [こひのうちにも] |
原文「恋中尓毛」の『万葉集全注』の説明は、
「こひのうちにも」〔旧訓・全註釈ほか諸注〕
「こひのなかにも」〔童蒙抄・考・折口口訳・井上新考・全釈・総釈・新校〕
ただし、総釈は、「うち」でもいいと言っている
「こふるうちにも」〔古義・釈注・新大系〕
澤潟注釈は「中」は「うち」とも訓むが「なか」と訓む方が通例だとする
この『全注』のいうこれらの一般的な解釈は、
「世の人のする様々な恋の中でも」
結句「われぞくるしき」に続き、「自分の恋が格別に苦しい」となる
『万葉集全注』では、この解釈に異を唱えているが...
「しかし、生れてこの方、恋というものに出逢ったことがないので、世間の恋の中で一番苦しいというのはおかしい」と
そして、実は『万葉集古義』が「こふるうちにも」と訓んだのはそれで、
「今自分が、恋しく思いつつある中にも」と解している
この解釈では、
折口口訳が、「こひのなかにも」と訓じ「恋をしながらも」、
私注が、「こひのうちにも」と訓じ「恋ひする中にも」とし、
古典大系が、「こひのなかにも」と訓じ「恋のただ中にいて」としている
こうして、様々な訓に触れてみると
『万葉集』を初めて手にする「諸本」によって
『万葉集』の世界観が違ってくるものだ、と思わざるを得ない
私は、その初めての時...その「訓」に「異訓」があるなどと
夢にも思わなかった
手にした「書」が、偶然にもその人の万葉観を形づくってしまう
それが、現代に於ける『万葉集』という歌集の宿命なのかもしれない
何しろ、今では全く使われなくなった「表記法」でしか
私たちには触れることができないのだから...
|
|
|
| 【歌意2945】 |
想ってもくださらないあなたですけれど、
それでも、このような「片恋」に、
わたしは恋い慕っています
あなたの姿を想いうかべて... |
この「恋歌」は、多くの注釈書で、それほど評価されていない
平凡だ、という
何故なのだろう
一途な想いに、率直さがないとでもいうのだろうか
自分を想ってくれない人に対してでも、
私は変わらず、想い続けています、というのは
率直な想いだろう
それとも、それが恋する人の、本当の気持ちであるはずがない
綺麗事過ぎる、というようなことなのだろうか
私は、もともと文法は苦手な方なので、自信を持って言うことではないが
この歌の語義を古語辞典で引いていて
どうも「注釈書」の解釈と言うのは、日本語としては難しいと思ってしまう
この歌の場合、第三句の助詞「に」と、結句の「すがたに」
第三句の「に」は、確かに接続からすると「格助詞」には違いない
しかし、ここで私なりに採り上げた「状態」の「~として」で、
何とか、「片想いの状態」を読み込めるが
本当は、接続助詞「に」で、逆接の確定条件とした方がいいのでは、と思えてしまう
「片恋であるのに・片恋ではあるけれども」
勿論、それでは接続する語が、連体形にならなければならず
「かたこひ」ではあてはまらない
だから、格助詞「に」として解釈するしかないのだが
歌意としては、逆説的な思いとして解釈するべきではないか、と思う
単純に「片恋に」としている解釈があるので、それでは不充分だと思うのだが...
結句の「すがたに」の訓には、旧訓には「すがたを」と言ったらしいが
私には、そのことよりも、「すがた」が気になった
どの注釈書でも、結句をその語句通りに「あなたの姿に」と
まるで余韻を残すかのような訳をつけているが
第四句の様々な訳語を使うのに対して、結句を単純に「あなたの姿に」で終らせている
その先に読む人が思い浮かべるものは何だろう
「すがた」が、いったいどのようなものなのか...
直訳では、確かに「あなたの姿に」で終らせ、余韻を残す手法なのだろうが
第四句から続く語句として読むと、歌意にはもっと丁寧な情景を出した方がいい
勿論、反語のように、敢えて言葉に出さなくても、通じることもある
しかし、この「すがた」という語では
説明なしに読み終えることは、出来ないのでは、と思う
そもそも、「すがた」と同じような語で「ありさま」「かたち」がある
| ありさま |
事物の様子や状態。人については容姿・態度をいう。 |
| かたち |
物の形状。人については容貌・顔立ちをいう。 |
| すがた |
服装を含む人の外見的印象・身なり。また、事物の風情や趣をいう。 |
この歌で女性がいうのは「すがた」だ
この三態を見ると、「すがた」というのは、現代的な感覚では、
女性が憧れる、あるいは見惚れる本来の「すがた」ではないような気もする
いや、男の本質よりも、その「身なり」...いわば外見的な見映え
その「すがた」を思い浮かべようとしている
そこから感じられるのは、それほど親しい間柄、もしくは近づき難いものがある
そうなると、先ほどの第三句の助詞「に」が苦もなく理解できる
この歌全体の歌意が、「片恋」だけど、あなたの姿を思い続けて慕う、というよりも
「片恋」その「状態」に、自分は「恋して」いる
あなたの姿を見ていると、そう思えます
そのような女性の気持ちが感じられる
だから、「片恋」といいながらも、そこに「悲哀」感はなく
結句の「すがた」を見、そして想いうかべることで満足している
「想い」のいっぱい詰まった歌ではなく
「恋」に恋する乙女のような純真さが詠われているように思えてならない
|
|
掲載日:2013.10.19.
| 正述心緒 |
| 不相念 公者雖座 肩戀丹 吾者衣戀 君之光儀 |
| 相思はず君はいませど片恋に我れはぞ恋ふる君が姿に |
| あひおもはず きみはいませど かたこひに あれはぞこふる きみがすがたに |
| 巻第十二 2945 正述心緒 作者不詳 |
| 【2945】語義 |
意味・活用・接続 |
| あひおもはず[不相念 ] |
| あひ[相][あひ-・接頭語] |
(動詞について)互いに・一緒に |
| おもは[思ふ] |
[他ハ四・未然形]思う・恋しく思う |
| ず[助動詞・ず] |
[打消・連体形]~ない |
未然形につく |
| きみはいませど[公者雖座] |
| いませ[坐す・在す] |
[上代尊敬の動詞「坐す」に接頭語「い」のついたもの]
[自サ四・已然形]「あり」の尊敬語、「いらっしゃる」 |
| ど[接続助詞] |
[逆接の確定条件]~けれども・~のに・~だが |
| かたこひに[肩戀丹] |
かた[片][かた-・接頭語]
|
(片一方の、の意を表す)「片恋」「片枝」など |
| に[格助詞] |
[状態・資格]~として |
体言、活用語の連体形につく |
| あれはぞこふる[吾者衣戀] |
| は[係助詞] |
[とりたて・主語]~は |
| ぞ[係助詞](上代では「そ」) |
[強調]~が・~を 〔係り結びの「係り」〕 |
| 他動詞ハ行上二段「恋ふ」の連体形「こふる」を、係り結びの「結び」とする |
| きみがすがたに[君之光儀] |
| が[格助詞] |
[所有]~の 〔接続〕体言、または活用語の連体形につく |
| すがた[姿] |
身なり・容姿・ありさま |
| に[格助詞] |
[相手・動作の対象]~に |
体言、活用語の連用形につく |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [きみはいませど] |
この語句の原文「公者雖座」の「旧訓」は「きみはませとも」であったのを
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕が、改訓した
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕も、それによった
しかし、『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕は「きみはまさめど」と訓み、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕、
『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年〕も、これに従う
原文「雖座」は「ませども」か「いませど」か、と定訓はない
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37成〕に、
この「雖座」は「不相念」につづくのであるから「相思はずます」とは続かず、
「います」と続くのが通例だと思う、とある
「まさめど」と訓むのは相手の男の心を言うのだから、「いませど」と断定的に言うより
「まさめど(まさむ)」と推量に言う方が穏当だという(万葉集総釈)
「まさめど」と訓むのは、
岩波文庫新訓・万葉集全釈〔鴻巣盛広、昭和5~10年〕・総釈・新校万葉集・定本万葉集
・評釈万葉集〔佐佐木信綱、昭和23~29年〕・万葉集私注〔土屋文明、昭和24~31年〕・日本古典文学大系万葉集〔岩波書店、昭和32~37年〕・日本古典文学全集万葉集〔小学館、昭和46年~50年〕・新潮日本古典集成万葉集〔新潮社、昭和51~59〕など
「いませど」と訓むのは、
万葉集全註釈〔武田祐吉、昭和23年~25年〕・万葉集評釈〔窪田空穂、昭和18~27年〕・注釈・講談社文庫・新編日本古典文学全集万葉集〔小学館、平成6~8年〕・
万葉集釈注〔伊藤博、平成7年~11年〕など
|
| |
| [あれはぞこふる] |
普通に係り結びであれば、「あれはこふる」でいい
それが「あれはぞこふる」...係助詞「は」と「ぞ」で係助詞を重ねている
これは、たんに「いっそう強調する」ということなのだろうか
「我はぞ恋ふる」のみの用例で、五首しかない
(『万葉集全注』では六首というが、私の資料では五首しか探し出せなかった)
| なきすみの ふなせゆみゆる あはぢしま まつほのうらに あさなぎに たまもかりつつ ゆふなぎに もしほやきつつ あまをとめ ありとはきけど みにゆかむ よしのなければ ますらをの こころはなしに たわやめの おもひたわみて たもとほり あれはぞこふる ふなかぢをなみ |
6-940 |
| うつせみの よのひとなれば おほきみの みことかしこみ しきしまの やまとのくにの いそのかみ ふるのさとに ひもとかず まろねをすれば あがきたる ころもはなれぬ みるごとに こひはまされど いろにいでば ひとしりぬべみ ふゆのよの あかしもえぬを いもねずに あれはぞこふる いもがただかに |
9-1791 |
| あひおもはずきみはいませどかたこひにあれはぞこふるきみがすがたに |
12-2945
|
| あしひきのやますがのねのねもころにあれはぞこふるきみがすがたを |
12-3065 |
|
|
|
| 【歌意2946】 |
網の目のようにしっかりと、
あなたを目に止めていないわけではないのですが、
お互いに、手を取り話もしないのは
本当に苦しく、辛いことなのです |
いつも見かける「想ひ人」
お互いの気持ちは、解らないのかもしれない
この歌の作者は、自分がこれほど恋い慕っていても
そばに寄り添って、手を取り合い、話しかけることもできない
その苦しさ、辛さを詠っているのだろうか
この歌の諸書での解釈は、さまざまだ
そばにいながら、決して親しく声を交わせない男の悲しみの歌、とか
同じ家にいて始終逢いながら、言い寄ってくれない苦しさを詠う女歌、とか
常にそばに見ながら、なかなか深い関係になれない辛さは、確かにあるものだ
例えば、幼馴染のような関係であっても、この歌は甘酸っぱい恋心を香らせてくる
兄妹のように無邪気に接していた頃を、思い出せばよけいに辛くなる
いつからか相手を「想い」始め、そこからこの「辛さ・悲しみ」は胸に貼り付いている
いつか気づいてくれるだろう、と...待つ歌のような気もする
右頁に載せた『万葉集古義』の「味沢相」の訓「うまさはふ」
「味」を「うま」と訓むことにも、その意味から抵抗はない
また「あぢ鴨」とする方が、漢字「味」の音を利用したことになる
古語辞典を引いたら、鴨の一種である「あぢ」を使った枕詞があった
「あぢむらの(あぢの漢字は、「有鳥」で一字)」
この枕詞の由来が「あぢがも」の群れが騒ぎ往来することから、
「騒く」「通ふ」などにかかる
原文は、「味村乃」4-488、「安治村」7-1303、「安治牟良能」20-4384
たしかに「味」という漢字も使っている
ほぼ同じ由来で生れたらしい「枕詞」
「あじむらの」は、三例しかないが、これは「あじの群」が本義なので
かかる語句もやはり違う
しかし、〔2946〕歌の「あぢさはふ」は、例外なく「味沢相」が原文だ
「あじ」、たくさんを意味する「沢」...やはり、そう訓じる方が自然なのかな
では、何故「うまさはふ」という訓を敢えて付けたのだろう
それが無性に気になっている
「あぢさは」のような、理解できる説明が、『古義』にあるのだろうか
今度の明日香行が楽しみになってきた
|
右頁からの続き
| [こととはなくも] |
旧訓は「とはれぬこと」を『万葉代匠記(初稿本)』では、「とはさることも」、
とも訓むべし、という
同じく『万葉代匠記(精撰本)』〔元禄三年(1690)成〕に、原文「不問」は、
「とはさる」と訓むべしと言っている
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕は
「こととはざるも」と訓む
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕に「こととはなくも」と訓んだ
本居宣長への門人田中道麿の質問解答書『万葉問聞抄』に、この句の訓みを、
道麿が「ことはざるも」か「こととはなくも」かと尋ねたのに対して
宣長は「こととはなくも」なるべし、と答えている
以来、この訓が定訓となる
ただ次の三書は「とはれぬことも」と訓じている
『定本万葉集』〔佐佐木信綱・武田祐吉が昭和十五年から同二十三年にかけて岩波書店から出した五冊本。西本願寺本を底本として校訂し、上段に原文、下段に読み下し文を並べてある。各冊とも末尾に校訂に関する別記を掲げる。〕
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年〕
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年〕
『全註釈』は、「こととふ」は熟語だから
「問事」とは書かないだろうと説明している
|
|
|
掲載日:2013.10.20.
| 正述心緒 |
| 味澤相 目者非不飽 携 不問事毛 苦勞有来 |
| あぢさはふ目は飽かざらねたづさはり言とはなくも苦しかりけり |
| あぢさはふ めはあかざらね たづさはり こととはなくも くるしかりけり |
| 巻第十二 2946 正述心緒 作者不詳 |
| 【2946】語義 |
意味・活用・接続 |
| あぢさはふ[味澤相 ]〔枕詞〕「目」「夜昼知らず」にかかる |
| めはあかざらね[目者非不飽](二重否定) |
| あか[飽く] |
[自カ四・未然形]十分満足する・満ち足りる |
| ざら[助動詞・ず] |
[打消・未然形]~ない |
未然形につく |
| ね[助動詞・ず] |
[打消・已然形]~ない |
未然形につく |
| たづさはり[携] |
たづさはり[携はる]
|
[自ラ四・連用形]互いに手を取る・連れ立つ・かかわる |
| こととはなくも[不問事毛] |
| こととは[言問ふ] |
[自ハ四・未然形]話をする・ことばをかける |
| なく[無し] |
[形ク・連用形]ない |
| も[係助詞] |
[強意]~も |
| 〔接続〕名詞、助詞、用言や助動詞の連体形・連用形など種々の語につく |
| くるしかりけり[勞有来] |
| くるしかり[苦し] |
[形シク・連用形]痛みや悩みで辛い・苦しい |
| けり[助動詞・けり] |
[詠嘆・終止形]~たことよ・~たことよ |
連用形につく |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [あぢさはふ] |
原文「味沢相」を、『万葉集古義』では「うまさはふ」と訓じる
この原文を用いる歌は、集中で五首あるが、
『古義』を除いて、どれも「あぢさはふ」だ
しかし、その『古義』でも、すべて「うまさはふ」かといえば、そうではなかった
今日の歌〔2946〕の他に、〔2560〕も、「うまさはふ」と訓じている
しかし、その他の三首については「あぢさはふ」と訓じているのは
単に「枕詞」としてではなく、語意をも添えてのことだろうか
これも、調べてみたいものだ
「枕詞」とは一応解釈されているが、その語義・かかりかたは未詳でもある
一つの例として、全五例中の四例が、次句で「目」に続くことから、
「目」にかかる、とされ
残りの一例は、「夜昼知らず」に続くので、「よるひるしらず」にかかる、という
僅かこの用例だけで、「枕詞」は成り立つものなのか、と意外な気もする
「目」にかかる「枕詞」としての由来に有力な説として、『冠辞考』では、
「あぢ鴨」が多く(サハニ)群れわたる意から、
「ムレ」のつづまった「メ」にかかるという
◆ 『冠辞考』〔賀茂真淵(1697~1769)、江戸中期の枕詞辞書、宝暦七年(1757)刊〕
この「枕詞辞書」は、記紀・万葉集の枕詞326語を五十音順に並べ、
その意義・出典・解説をつけたもの
また、井手至「枕詞『あぢさはふ』の背後」〔『国語国文』昭和32年七月〕に、
「さはふ」は遮る意の「さふ」に反復継続の「ふ」がついたもので
味鴨を遮りつづけるところから「網の目」の「目」にかかるというが
昭和58年より刊行の始まった『万葉集全注』では、この「鳥網の目」が、
何故、味鴨を捕るのに限定されるのか、納得いかない、としている
ならば、「うまさはふ」はどうなんだろう
どんな由来か『古義』の著者、鹿持雅澄の言葉を聞いてみたいものだ
「味」が「うまさけ・味酒」、
それに形容詞シク活用の「うまし・甘し、美し、旨し」には、「味がよい」と
このことから、「うまさはふ」も、それなりに想像は出来るのだが...
「味沢相 (あぢさはふ、うまさはふ)」の用例が少ないので
今日も表にしてみる
| |
諸注 |
万葉集古義 |
| 2-196 |
--- 定めたまひて あぢさはふ 目言も絶えぬ--- |
あぢさはふ |
| 6-947 |
あぢさはふ 妹が目離れて--- |
あぢさはふ |
| 9-1808 |
---哭のみ泣きつつ あぢさはふ 夜昼知らず ---
|
あぢさはふ |
| 11-2560 |
---早くな開けそあぢさはふ目が欲る君が--- |
うまさはふ |
| 12-2946 |
あぢさはふ目は飽かざらねたづさはり--- |
うまさはふ |
|
| |
| [めはあかざらね] |
旧訓は「めにはあけとも」で、
『万葉代匠記(初稿本)』〔契沖(1640~1701)、貞亨四年(1687)成〕に、
原文「非不飽」は「あかざるにはあらざれども」で、
それは「飽けども」の心だから意味をとってそう訓むのだという
この旧訓は、『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年〕』まで続いたが、
『新校万葉集』〔昭和十年から翌年にかけて出された注釈書「万葉集総釈」(楽浪書院)の付巻として収められた本文篇で、寛永本を底本にして、澤潟久孝・佐伯梅友が校訂を加えた。原文に平仮名傍訓がついている。後に創元社から改訂版が出版された〕に「めはあかざらね」と改訓され、岩波文庫新訓改訂版・大成本文篇はそれにより、『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年〕もこれによる
『大系』も『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37成〕も、以来諸注すべて、
この「めはあかざらね」と訓む
|
|
|

|
| 【歌意2947】 |
長い年月をかけて磨く、堀出したばかりの「璞」のように
いつまでつづくのであろうか
このわたしの恋心は...
いのちにも、限りがあるというのに... |
いつまでも恋し続ける
それが苦痛であるという、環境をいうのだろうか
お互いが求め合うものであれば、逆に「いつまでも続けたい」と、そう思うはずだ
それが、いつまで続くのか、と悲歎にくれたように詠うのは
片恋の「想い」なのだろう、きっと
この歌と同じと思われる心情を詠った万葉歌がある
「類想歌」、と言われるものだが、表現は違っても
確かに、その心情は...ほとんど同じだ
| 正述心緒 |
| 是耳 戀度 玉切 不知命 歳經管 |
| かくのみし恋ひやわたらむたまきはる命も知らず年は経につつ |
| かくのみし こひやわたらむ たまきはる いのちもしらず としはへにつつ |
| 巻第十一 2378 正述心緒 柿本人麻呂歌集出 |
このようにして、恋し続けるばかりで
いつこの命が終るかも解らないのに、年だけが過ぎてゆく...
ここでは「いのちもしらず」という
しかし、次の「としはへにつつ」こそが、この「いのち」の意味を教えてくれる
命の限界、寿命があるのに、それを管理できずに、年月は過ぎて行く
これだと、右頁に引き合いに出した、中西進著『万葉集全訳注』の解釈がすっきりする
掲題歌〔2947〕では、その「としはへにつつ」の役目を
原文の「寿(命)」の表記で、教えてくれているのではないか
「としはへにつつ」のその前提は、「命には限界」があること、つまり「寿命」だ
いつこの命が果てるとも解らないのに、
こんなことでいいのか、もっと積極的に行動できないのか...
そう自分へ叱咤しているのかもしれない
ただ単に、嘆くばかりではなく、それこそ「命がけであれ」と
掲題歌〔2947〕は、自身の行動力のなさが漠然と感じられるが
類想歌〔2378〕は、「かくのみし」と言っている
もっと深く、こんなことではいけない、と自分に言い聞かせる「何か」を思わせる
その「何か」が、たとえば「問答歌」のように、
この「巻第十一・十二」に潜んでいるかもしれない
「作者未詳歌」の件で、気の遠くなるような再構築の試みを知り
その視点で考えれば、今日の二首も、どこかにぴったりと填まる歌であると思う
|
右頁からの続き
[いのちしらずて] |
この句には、通説とは違う解釈もある
通常、この句を解釈すると、「命を知らないで」、
つまりここでいう「いのち」の原文「寿」は「寿命」のことだろうから
「命がいつまで続くのか知らないで」のような意味になると思う
しかし、異なる解釈を述べているのは、
「命に限りのあることも知らないで」と...少々理解しにくい解釈になっている
『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年〕』がそうだし、
岩波の『古典大系』もそうだ
「命の限りあることも知らずに」、と
また、もっと微妙に感じられるのは、中西進著『万葉集全訳注』
「命の生死も測り難く」...これは、限りある命を承知したものか、
あるいは、「命など眼中にない」ということなのか...日本語も難しい |
|
掲載日:2013.10.21.
| 正述心緒 |
| 璞之 年緒永 何時左右鹿 我戀将居 壽不知而 |
| あらたまの年の緒長くいつまでか我が恋ひ居らむ命知らずて |
| あらたまの としのをながく いつまでか あがこひをらむ いのちしらずて |
| 巻第十二 2947 正述心緒 作者不詳 |
| 【2947】語義 |
意味・活用・接続 |
| あらたまの[璞之 ]〔枕詞〕「年・月・日・春」などにかかる |
| としのをながく[年緒永] |
| としのを[年の緒] |
年の長く続くのを緒(=ひも)にたとえた語 |
| ながく[長し・永し] |
[形ク・連用形](空間的・時間的に)隔たりの大きなさま |
| いつまでか[何時左右鹿] |
いつ[何時]
|
はっきりと定まらない日・時を表す |
| まで[副助詞] |
[限度]~まで |
| 〔接続〕体言、体言に準ずる語、動詞・助動詞の連体形、副詞や助動詞など種々の語につく |
| か[係助詞] |
[疑問]~か・~だろうか |
| 〔接続〕体言・活用語・副詞・接続助詞などが主語・目的語・連用修飾語などにつく |
| あがこひをらむ[我戀将居] |
| をら[居り] |
[補助動詞ラ変・未然形]動詞連用形の下に付く |
| |
(動作・状態の存続を表す)~ている |
| む[助動詞・む] |
[推量・終止形]~(の)だろう |
未然形につく |
| いのちしらずて[壽不知而] |
| いのち[命] |
生命・寿命・一生・生涯・生命を支えるもの |
| しら[知る] |
[他ラ四・未然形]理解する・認識する・知る |
| ずて |
~ないで・~なくて |
未然形につく |
| 〔成立〕打消の助動詞「ず」の連用形「ず」+接続助詞「て」 |
| 〔参考〕おもに上代に用いられ、平安時代以降は和歌の用語として残った |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [あらたまの] |
「あらたまの」、いくら「枕詞」といえ、これまでその表記をあまり気にしていなかった
そして、その原文「璞之」を目にしたとき、枕詞に語訳は不必要なときもあるが
しかし、よく使われる表記ではないので、今回は調べてみたくなった
「あらたまの」を「安良多麻乃」などの「音表記」とか
あるいは「荒玉之」など、ある程度「意訳」しやすい表記ばかり慣れてしまって
「璞之」では、すんなり映像が浮んでこない
何しろ「璞」という「漢字」を知らなかったのだから...
勿論、古語辞典にも載っていない...「ハク・ホク・あらた」で引いても...
それで、漢和辞典で「璞」を引く
〔字義〕として、次のように説明してあった
| あらたま。堀り出したままで、まだ磨いていない玉。生まれつきのままで、真実で飾り気がない。 |
すると「荒玉」のような表記は、ちょっと重たくなるような...
もっとも、国語も苦手な私には、この「璞」の字義が、
万葉時代に、同じような解釈であったのかどうかは、解らないが...
ここでも、せっかくだから「あらたまの」の原文表記の用例を表にしてみる
| [璞]の表記 (七首) |
| 璞之 (四首) |
11-2414/2535/2539,12-2947 |
| 璞 (二首) |
10-2096/2144 |
| 荒璞能 (一首) |
17-4002 |
| 他の表記 (二十八首) |
| 荒玉之 (七首) |
3-446,8-1624,12-2903,13-3272/3338/3343,19-4268 |
| 荒玉乃 (五首) |
3-463,4-641,10-2209,12-3231,19-4272 |
| 安良多麻能(三首) |
15-3705/3713/3797 |
| 阿良多麻能(二首) |
5-885,20-4355 |
| 安良多麻乃(二首) |
17-4003,20-4432 |
| 安良多末能(二首) |
18-4137,20-4514 |
| 安良多末乃(一首) |
18-4140 |
| 荒玉能 (一首) |
19-4180 |
| 荒玉 (一首) |
4-593 |
| 荒珠 (一首) |
4-590 |
| 荒珠乃 (一首) |
10-2093 |
| 麁玉 (一首) |
11-2389 |
| 未玉之 (一首) |
12-2968 |
こうみると、「璞」の文字、結構使われていたのだ、と意外だった
これからは、枕詞の表記にも気をつけて触れたいものだ |
| |
|
|
| 【歌意2949】 |
白栲で愛しい人が作ってくれたこの衣の袖を、
折り返して恋しく想ったからなのか、
愛しい人の夢をこうして見ることができたのは... |
夢に現れれば、自分を想ってくれているから
また、逢える吉兆だともいい
恋しく想うと、夢に逢える...
こうした「夢」の歌も多くある
そこから、この時代の「俗信」であろう、と言われてはいるが
その「俗信」も、日本古来からのものなのか
あるいは、いつからか持ち込まれた大陸や半島の文献にもあるのか...
「俗信」と言っても、その由来が明確な場合もあれば
定かでない場合も多いだろう
現代においても、様々な「俗信」めいたものはある
起源も明確でなく、いつからか自然に、という意味での「俗信」なのだと思う
夢に、思いもしなかった意外な人が現れたりもする
そのとき、その意味は何だろう、何かも前兆なのかな、とか
人の「想い」は様々だろうが
愛しい人が現れたときは、無条件で「逢える」予兆だ、と思ってしまう
都合の悪い「夢」は、「夢だから」とあっさり片付け、
自分がときめくものに関しては、何かとこじつけようとする
夢に現れる人を「想う」歌を詠むこと自体が
「想うからこそ」詠う、という「相聞」の定型なのだから
その「想い方」に、「夢に見る」舞台を用意した
最近、そんな風にも思え出した
昨日の歌〔2947・2378〕のように、
その歌自体では「何か」という具体的な事柄が抜けているのは
その歌が、決して単独で詠われたものではなく、
一連の歌群の一首であることを、想像も出来るが
今日のように、「夢」が舞台だと
「夢」は、あくまで理屈ではなく、奔放な世界だから
脈絡もなく、「夢」にまつわる独詠歌のように感じられるのだろう
しかも、ほとんどの注釈書で、都合よく「俗信」を付け加えて、
歌意をほぼ決められた方向へ導こうとする
それも、「夢」は「夢だから、何があってもおかしくない」と
しかし、恋人同士の「夢語らい」には、そこには「俗信めいたものがある」
だから、このような歌が多い、という風に...
それにしては、その「俗信」にも、様々な「姿」があって
結局は、「俗信」という以前に、何故そんな心情を詠うのか
それを解する「手間」が抜けているようにも思える
私が、そんな大それたことなど言える能力もないが
このところ、出来る範囲での「注釈書」に接しているのも
その「心情」の一端に、触れることができるかもしれない、
という期待があることは確かだ
このスタイルで今後も続けると...
命の終える時まで『万葉集』づけになってしまいそうだ
まあ、それもいい
どうせ、先の短い残りの人生だから...
|

|
掲載日:2013.10.22.
| 正述心緒 |
| 白細布之 袖折反 戀者香 妹之容儀乃 夢二四三湯流 |
| 白栲の袖折り返し恋ふればか妹が姿の夢にし見ゆる |
| しろたへの そでをりかへし こふればか いもがすがたの いめにしみゆる |
| 巻第十二 2949 正述心緒 作者不詳 |
| 【2949】語義 |
意味・活用・接続 |
| しろたへの[白細布之 ]〔枕詞〕「衣・袂・袖・紐・帯」や、「雲・雪・波」にかかる |
| 白栲で衣服を作ることから衣料に、その色から「白」を連想する「雲」などにかかる |
| しろたへ[白栲・白妙] |
こうぞ(=木の名)の繊維で織った白い布・白い色・白いこと |
| そでをりかへし[袖折反]〔他動詞サ行四段「袖返す」の強調だと思う〕 |
| そで[袖] |
着物の両腕を覆う部分・古くは筒袖であったが、袖の形が変わるにつれ、たもとを言うようになった |
| をり[折る] |
[他ラ四・連用形]折り曲げる・手折る |
| [自ラ四・連用形](波などが)折れるように崩れる |
| かへし[返す・反す・覆す] |
[他サ四・連用形]ひるがえす・裏返す・ひっくり返す |
| こふればか[戀者香] |
こふれ[恋ふ]
|
[他ハ上二・已然形]思い慕う・恋しく思う |
| ば[接続助詞] |
[順接の確定条件]~ので・~だから |
已然形につく |
| 〔接続〕「已然形」+「ば」で、「順接確定条件」、「未然形」では「順接仮定条件」になる |
| か[係助詞] |
[疑問]~か・~だろうか |
| 〔接続〕体言・活用語・副詞・接続助詞などが主語・目的語・連用修飾語などにつく |
| いもがすがたの[妹之容儀乃] |
| が[格助詞] |
[連体修飾語・所属]~の〔接続〕体言、連体形につく |
| すがた[姿] |
衣服を身につけたようす・身なり・容姿 |
| の[格助詞] |
[主語]~が 〔接続〕体言、体言に準ずるものにつく |
| いめにしみゆる[夢二四三湯流] |
| し[副助詞] |
語調を整え、強意を表す |
| 〔接続〕体言または活用語の連体形・連用形、副詞、助詞などにつく |
| みゆる[見ゆ] |
[自ヤ下二・連体形]目に映る・見える・感じられる |
| 第三句の係助詞「か」の係り結びの「結び」で連体形で終る |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [格助詞「の」] |
格助詞「の」には、様々な用法があるが、この歌の場合
この句の「の」の解釈によって、歌意が大きく変わる
私は、「主語」の用法で解釈した方がいいと思う
「袖を折り返し」て恋ふるのは、作者自身だと...
幾つかの注釈書では、上三句「しろたへの そでをりかへし こふればか」を、
「妹」の行動だとし、従ってその「姿を」というように
この格助詞「の」を「連用修飾語的」に解している
そうなると、歌意そのものは、結句の「いめにしみゆる」だけが、
作者が主語である行為になる
諸注での違いを、表にしてみる
| 「袖を折り返し」て恋ふるのは作者 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| 『万葉集総釈』〔楽浪書院、昭和10~11年成〕 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37成〕 |
| 『万葉集釈注』〔伊藤博、平成7年~11年成〕 |
| 『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕 |
| 「袖を折り返し恋ひ」ているのは妹 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| 『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕 |
| 『日本古典文学全集』〔小学館、昭和50年成〕 |
| 『日本古典集成』〔新潮社、昭和51~9年成〕 |
| 『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕 |
| 『万葉集全訳注』〔講談社文庫、昭和58年成〕 |
| 『万葉集校注』〔角川ソフィア文庫、伊藤博校注、昭和60年成〕 |
この相違をみると、昭和以降にも、これほど拮抗しているとは思わなかった
しかも、岩波の「大系」と「新大系」では四十年余で、解釈も変わっている
それほど、文法的には難しい判断の、格助詞「の」なのだろう
私には、自分が袖を折り返したから、
恋しい「妹」の夢を見える、とした方が自然だと思うのだが...
『釈注』の言う、こちらがせつに相手のことを思えば、相手が夢に現れる、
との歌もあり、
それは、「袖を折り返し」て恋ふるから、そんな夢も見る、とすれば
やはり、袖を折り返すのは、作者であるのでは...
一応、主語が「作者」の解釈を「旧注」とし、
必然的に主語が「妹」を「新注」となるようだが
「旧注」ならば、やはり近世までの『古義』の解釈もそうだったのだろう...か |
| |
|
| 【歌意2951】 |
「恋」ということばを使うといつも、
有り触れた情けの薄い感じがしてならない
しかし、そうであっても
わたしは、決してあなたを忘れまい
たとえ、恋焦がれて、死ぬことになろうとも... |
現代でも、「薄っぺらな言葉」という表現はよく使う
本来なら、ときめくはずの「恋」ということばも
あまり頻繁に使うと、何だか本心ではないような、
ただ「気を引くだけ」のような気がしないでもない
それは、使う方でも、それを意識しているから
やはり、自然に口から言葉として漏れ出す「恋」でなければ
相手にも、その「恋心」は伝わらない
この万葉の時代、すでに現代と同じような感覚を持ち合わせていたことが意外だった
いや、そう思い込んでいた自分の浅はかな気持ちを、叱責されたような歌だ
そして、そうではあっても、やはり恋して伝える想いは...「恋」なのだ、と
むしろ「恋ひ死ぬ」という古語があることに
「恋」は生半可な想いではない「時代」だったのだなあ、と思い知らされる
恋焦がれて死ぬこと...それほどまでに「恋しい」想いを
こうして歌に詠めるのは、
それが現実であろうと、虚構であろうと
歌の中に、想いが詰まっていなければならない
その意味で、この歌の評価が、一般的にどうなのか解らないが
注釈書の一つを参考にすれば、『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕
「表現に屈折があって、ひとふしある歌になっている」とし、その文芸性を評価している
なるほど...「ひとふしある歌」ということだ
古語辞典で「ひとふし」を引いてみた
「一つの目立つ点・一点・一部分・一つのこと・一つの事件・音楽の一調子」ということだが
勿論、古語辞典の「古語」としての語意なので、
この注釈書が書かれた時代とは、まったく同じではないだろう
しかし、「ひとふし」を「古語」としてでなく、現代語として素直に聞けば
「音楽の一調子」的な、味のある歌、という風に思えてくる
では、どこがそうなのだろう
私が、最初に感じたような、「薄っぺらな言葉」という表現を使いながら
敢えて、それを自分も「言う」ことが、「ひとふし」なのだろうか...そうだと思う
しかし、そのことで「たとえ死ぬようなことがあっても」と覚悟を述べる
ありきたりの言葉だけど、命を捨てる覚悟はあるよ、と
案外、「言葉を尽くす」よりも、ありきたりの言葉で、
そこに「命さえも」と宣言することで、
本来の言葉の意味を「取り戻し」ているのではないだろうか...
もっとも、この最後の言葉「こひはしぬとも」が
ありきたりの言葉でないことを知ってもらわなければならないが...
そこで「恋ひ死ぬ」という動詞に、係助詞「は」を入れて
「恋ひ」を強調している...「恋ひ死ぬ」という動詞に、思い余って飽き足らず
「は」を挿入した...そう思いたい |
 |
掲載日:2013.10.23.
| 正述心緒 |
| 戀云者 薄事有 雖然 我者不忘 戀者死十万 |
| 恋と言へば薄きことなりしかれども我れは忘れじ恋ひは死ぬとも |
| こひといへば うすきことなり しかれども われはわすれじ こひはしぬとも |
| 巻第十二 2951 正述心緒 作者不詳 |
【注記】に〔657〕歌あり
| 【2951】語義 |
意味・活用・接続 |
| こひといへば[戀云者 ] |
| こひ[恋] |
恋しく想うこと・心がひかれること・恋愛 |
| と[格助詞] |
[引用]~と 〔接続〕体言、体言に準ずる語につく |
| 「~と言って・~と思って・~として」などの意で、後に続く動作・状態の目的・状況・原因・理由などを示す |
| いへ[言ふ] |
[他ハ四・已然形]言葉で表現する・話す・称する |
| ば[接続助詞] |
[順接の確定条件]~ので・~だから |
已然形につく |
| [順接の恒常条件]~するときはいつも・~すると必ず |
| 〔接続〕「已然形」+「ば」で、順接の「確定条件・恒常条件」 |
| うすきことなり[薄事有] |
| うすき[薄し] |
[形ク・連体形](愛情や思慮などが)深くない・薄情である |
| こと[事] |
(人のする)行為・動作・事情・わけ・意味 |
| [用言、助動詞の連体形について]動作・作用・状態の名詞をつくる「~すること・~であること」 |
| なり[助動詞・なり] |
[断定・終止形]~である・~だ〔接続〕体言、連体形につく |
| しかれども[雖然] |
しかれども[然れども]
|
[接続詞]そうではあるが・しかしながら |
| 〔成立〕ラ変動詞「しかり」の已然形「しかれ」に接続助詞「ども」 |
| 〔参考〕平安時代以降、漢文訓読体の文章に用いられた語、和文では「されども」がふつう |
| われはわすれじ[我者不忘] |
| わすれ[忘る] |
[他ラ下二・未然形]~忘れる・記憶をなくす |
| じ[助動詞・じ] |
[打消の意志・終止形]~まい・~ないつもりだ |
未然形につく |
| こひはしぬとも[戀者死十万] |
| こひはしぬ[恋ひ死ぬ] |
[自ナ変・終止形]恋焦がれて死ぬ |
〔参考〕ナ変動詞「恋ひ死ぬ」の間に、係助詞「は」が挿入されたもの
古代の複合動詞はその結合が緩く、助詞や副詞の挿入を許した |
| とも[接続助詞] |
[逆接の仮定条件]たとえ~にしても |
〔接続〕動詞・形容動詞・助動詞(動詞・形動型活用)の終止形、
形容詞・助動詞(形容詞型・打 消「ず」)の連用形につく
〔成立〕接続助詞「と」+係助詞「も」 |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [戀云者] |
『万葉集』中の「戀云者」の用例は、二首のみ
掲題歌〔2951〕と〔657〕
| 相見者 月毛不經尓 戀云者 乎曽呂登吾乎 於毛保寒毳 |
| 相見ては月も経なくに恋ふと言はばをそろと我れを思ほさむかも |
| あひみては つきもへなくに こふといはば をそろとわれを おもほさむかも |
| 巻第四 657 相聞 大伴駿河麻呂 |
お逢いしてから、まだ間もないのに
「恋しい」といえば、わたしのことをせっかちだと思われますか |
ただし、その訓〔657〕は、「こふといはば」
この「未然形」に「ば」で、順接の「仮定条件」なので、
この歌意もそれに従ってみる
これで思うのは、原文でしか知ることの出来ない『万葉集』だが、
歌全体の「意」の中で、自然と訓み方も定まっていくのだな、と
仮に、この〔657〕を「已然形」として「こふといへば」と訓むと、どうなる
「恋しいと言ったので、わたしのことをせっかちだと、思っていらっしゃるだろうなあ」
この場合、結句の「かも」は「疑問」ではなく、「詠嘆・感動」になる
これでも、意味はなすとは思うが...
ただし、この〔657〕は、作者大伴駿河麻呂が坂上郎女に返した三首の歌かも知れず
その一連の歌群の中で、判断しなければならないだろうから、
今日はこれ以上は、考えない...いずれ、にしておこう
ただ、ここで気がつくのは、原文の表記の訓、その訓点の作業は並大抵ではない
あらためて、そのことを知る
原文「戀云者」のこの〔2951〕での訓も、「こひといへば」、「こふといへば」
この二訓で、諸注が分かれる
「~といへば」の格助詞「と」は、その接続が「体言、体言に準ずる」とあるので
名詞「こひ」も、動詞「こふ」の終止形でつながるが
「恋」を名詞として扱うことの方が、
この歌の場合の、「引用の格助詞・と」が生かされていると思う
訳すときに、[「恋」といえば]と表記できるとすると、それも一目瞭然だろう
ただし、『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37成〕では、
この「恋」について、「恋」を名詞にすると抽象的な表現になり、ここはあなたを「恋ふ」という意味で、「恋ふ」と動詞にした方が適切だという
「あなたを恋ふ」と言ったなら...ということになるだろうが
私は、そうは思わない
「恋」という名を口にして、あなたに言ったなら...私は、そう思う
| 訓「こふといへば」 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕(こふとへば) |
| 『新校万葉集』〔沢潟久孝・佐伯梅友、昭和10~11年成〕 |
| 『定本万葉集』〔佐佐木信綱・武田祐吉、昭和15~23年成〕 |
| 『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕 |
他の諸注は、「こひといへば」という
「こふ」は、『万葉考』の賀茂真淵が唱えたものらしい |
| |
| [うすきことなり] |
『元暦校本・広瀬本・西本願寺本・神宮文庫本・細井本・紀州本・温故堂本』は、
「うすきことなり」と訓じたが、
『大矢本・京都大学本・寛永版本』は「うすきことあり」と訓む
これらの諸本は、「うすきことなり」と「うすきことあり」に分かれるが
『万葉考』が注釈書で唯一、「あさきことあり」と訓じた以外は
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕が、「古訓・うすきことなり」を採り
それが、現在の一般的な訓になっている
〔諸本と注釈書について〕 |
| |
| [われはわすれじ] |
「我者不忘」を、
『元暦校本・広瀬本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本・寛永版本』は、
「われはわすれす」と訓み、
『神宮文庫本・細井本・紀州本』は、「われはわすれし」と訓じた
『万葉集註釈』〔仙覚、文永六年(1269)成〕が最初「わすれじ」と改訓したのを
古訓の「わすれじ」に戻したのだと言われている
このことにより、
『万葉代匠記(初稿本)』〔契沖(1640~1701)、貞亨四年(1687)成〕以下の諸註釈書は
すべて、「われはわすれじ」と訓むようになる |
|
|
| 【歌意2952】 |
いっそのこと、死んだ方が心も穏やかになれるでしょう
日が昇るのも気づかず、また日が沈むことにも気づかないほどの私です
それほど私は、苦しんでいるのです |
恋をすると、周りが一切見えなくなる、という
この歌を読んでみると、確かに「誰も同じ想いなのだなあ」と思う
すべてを投げ出して「恋」だけに生きることができるのなら
たとえ相手がどう想おうと、人は懸命になれるだろう
しかし、「人が生きる」ということは、そうではない
ここでいう「日が昇り、日が沈む」ように、
そのサイクルの中で、多くのしがらみが「人」に纏わり付く
あまりにも苦しく切なく、その「日の昇ることも、沈むこと」も忘れてしまうほど...
そこには、生きるために用意されている「責務」さえも投げ棄てたい願望がある
ひたすら「想い」を続けることは、それを許してはくれない
ならば、「死」しかないのか
先日来、万葉の時代の「婚姻制度」を知りたいと、彼の書を読み続けているが
そもそも、男が女の家に通う習慣とか、よく目にする説明も
その根拠となるのは、やはり断片的にしか復元されていない、
『飛鳥浄御原令』や『大宝令』のようだ
そして「婚姻」についての現代解釈の基になるのは『養老戸令』だという
確かに、その中には、婚姻に関する「年齢規程」があり、
男は十五歳から、女は十三歳以上とされている
ただし、問題はそこからのことだった
この規程だけで、その年齢に達してさえいれば、
自由に結婚できるのか、と思えばそうではなかった
現代では想像もつかないが、そこで親が許せるのは、まず恋愛の開始だ
親を含めた親族が、様子をみるという
婚姻が、その地域の将来に欠かせないことは、そこから生産される農作物、
そして女であれば、機織の技術
それらが、地域の発展には欠かせない時代だった
だから、若い二人が恋仲になっても、その親族にとっては
二人が、十分な生産的な務めを果たしてくれるのかどうか...
その様子見の期間が、男夫の女家への通いだという説がいわれている
その様子が、『万葉歌』に多く詠われる、当人同士の想いを超えたところでの
親族、そして地域ぐるみでの「監視」めいたことへの「嘆き」になるのだという
この婚姻制度、確かに『戸令』などの制度を知ることはできても
その実体は、その資料の解釈に随分幅があり、そこから「研究」が始まっている
当時の先進国家「唐」の制度に倣うところから始まった国家創生
それは、あくまで「制度」の取り込みであって、
こうして資料を「史料」として解釈するのなら、はたして実態が伴っていたのかどうか...
『万葉集』を断片的に読めば、そうした背景でも頷けるものがある
しかし、「それは何故」と、どんどん遡って行けば、どうなるのだろう
「俗信」と言われている諸々の事象でも、勘ぐれば、それは大陸からの俗信であって
それを、『万葉集』に残せる階層の人たちの「知識」として「詠って」みた、
それだけのことかもしれない
現代でも、多くの法には解釈の幅があり、極端に真反対の解釈も起こり得る
ならば、万葉の時代の、言ってみれば「法律」が
そう書かれているからといって、それが実効されていた時代だとは言い切れないのでは...
私が読み始めた本が、どんな風に展開していくのか分からないが
最初に、当時の資料をによるしかない、と当然のことだが、
それを改めて知ったとき、現代と同じように...「解釈論」で終るのではないか、と危惧する
よく『万葉集』は、「一級の歴史資料」だとも言われる
確かに、「記紀」にはない記事も、『万葉集』の題詞や左注で知ることができ
あるいは、「記紀」を始めとする、他の資料の「裏付け」のような役割も期待されている
しかし、そうだろうか....
「和歌集」は、あくまで「和歌集」であり、そこには様々な「工夫」がある
「和歌集」らしくするための工夫は、厳格な歴史への補助にはならない
一片でも作為があれば、それは「参考」程度にしかならない
万葉の時代に、こんな「婚姻制度」が頒布されていた
それは、『万葉集』の歌の背景に、まさに合致する
だから、この「婚姻制度」を記した資料は、正確だ、ということにはならない
それを確実にするには、『万葉集』を歴史書として、研究しなければならないし
当時の制度が、どの階層で有効であったのか、まで証明しなければならない
和歌の一様な解釈どころの話ではない
そもそも、和歌には多分に脚色もあることが当たり前だし
だからこそ、多くの事象を「俗信があった」と括っている
その「俗信」の根拠を知ろうとすると、そこから「歴史」も学ばなければならなくなる
ただ、この「婚姻制度」の背景の中で、詠われる歌が、
多くの胸打つ「和歌」として、現代でも魅了しているのは事実だ
それを更に、当初の「形」に復元できるのなら、もっと奥深い「歌物語」に成り得る
「万葉集作者未詳歌巻の説明」を読んでいて、そう思った
まだまだ読み方が足りないはずだが
僅かであっても共感する考え方に触れると、やはり「やる気」は起こるものだ |
|
掲載日:2013.10.24.
| 正述心緒 |
| 中々二 死者安六 出日之 入別不知 吾四九流四毛 |
| なかなかに死なば安けむ出づる日の入る別知らぬ我れし苦しも |
| なかなかに しなばやすけむ いづるひの いるわきしらぬ われしくるしも |
| 巻第十二 2952 正述心緒 作者不詳 |
【注記】に〔3956〕〔719〕歌あり
| 【2952】語義 |
意味・活用・接続 |
| なかなかに[中々二 ] |
| なかなかに[なかなか] |
[形動ナリ・連用形]中途半端なさま・どっちつかずだ |
| しなばやすけむ[死者安六] |
| しな[死ぬ] |
[自ナ変・未然形]命を失う・息が絶える・死ぬ |
| ば[接続助詞] |
[順接の仮定条件]~(する)なら・~だったら |
未然形につく |
| 〔接続〕「未然形」+「ば」で、順接の「仮定条件」 |
| やすけ[安し] |
[形ク・上代の未然形「け」]安らかである・心が穏やかである |
| む[助動詞・む] |
[推量・終止形]~(の)だろう |
未然形につく |
| いづるひの[出日之] |
いづる[出づ]
|
[自ダ下二・連体形](表面に)現れる・(中から外へ)出る |
| ひ[日] |
[原義は太陽]太陽・日光・日中・天候・時期・一日 |
| の[格助詞] |
[主語]~が 〔接続〕体言、体言に準ずるものにつく |
| いるわきしらぬ[入別不知] |
| いる[入る] |
[自ラ四・連体形](日や月が)すっかり沈む・没する |
| わき[別き・分き] |
区別・けじめ・分別 |
| しら[知る] |
[自ラ四・未然形]わかる |
| ぬ[助動詞・ず] |
[打消・連体形]~ない |
未然形につく |
| われしくるしも[吾四九流四毛] |
| し[副助詞] |
語調を整え、強意を表す |
| 〔接続〕体言または活用語の連体形・連用形、副詞、助詞などにつく |
| くるし[苦し] |
[形シク・終止形]痛みや悩みでつらい・苦しい |
| も[終助詞] |
[感動・詠嘆]~よ・~なあ 〔接続〕文末・文節末の語につく |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [やすけむ] |
初めは「安けむ」で、助動詞「けむ」がついたものと思った
しかし、助動詞「けむ」は、活用語の連用形につくので、「やすけむ」とはならない
敢えて語をつくれば「やすかりけむ」...聞いたことがない
やはり古語辞典が役に立った
助動詞「けむ」は、上代では形容詞に付くことはなかったらしい
そこで例文として、「安けむ」は、形容詞「安し」の上代の未然形「やすけ」に、
助動詞「む」がつく、とあった
そのそも、上代の活用表などなく、その問題に出合わない限り、気づくこともなかった
いや、例文で「安けむ」が載っていなかったら、まだ理解できていなかったはずだ
今日の収穫かな
せっかくだから、「なかなかにしなばやすけむ」の上二句が同じ歌〔3956〕を載せる
平群氏女郎が、越中の大伴家持に贈った十二首のうちの一首
この作者の十二首のうち九首ほど〔書庫5〕と〔書庫6〕で採り上げている
ここで十首目となるが、ここでは感想は省く
| (平群氏女郎贈越中守大伴宿祢家持歌十二首) |
| 奈加奈可尓 之奈婆夜須家牟 伎美我目乎 美受比佐奈良婆 須敝奈可流倍思 |
| なかなかに死なば安けむ君が目を見ず久ならばすべなかるべし |
| なかなかに しなばやすけむ きみがめを みずひさならば すべなかるべし |
| (右件十二首歌者時々寄便使来贈非在<一>度所送也) |
| 巻第十七 3956 贈答歌 平群氏女郎 |
いっそのこと、死んだ方が心も穏やかになれるでしょう
あなたに、長くお逢いできないのでしたら
わたしには、もう何をしようにも、そのすべもありません |
|
| [いるわきしらぬ] |
原文「入別不知」は、旧訓「いるわきしらす」を、
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕が、「しらぬ」と改訓し、
それが定訓になっている
しかし、『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年〕、さらには
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕とが「いるわきしらに」と訓む
この場合の「に」は、打消助動詞「ず」の連用形「に」で、
次に「知らなくて~」、「知らないので~」と続くはずだが
『万葉集全訳注』の訳を読んでみると、
「いつ夜が明けいつ日が暮れるとも知らず私は辛いことよ」だ
この訳では、連用形「に」ではなく、終止形「ず」でいい、といわれている
連用形「に」で訳すのなら「苦しい」ことが「知らないので」が原因になってしまう
私も、連体形「ぬ」で、「知らないでいる私」とする方が、自然に訳せると思う
同じように、この語句を使った歌も載せておく
大伴家持が娘子に贈った歌七首のうちの一首
これも、他の一首〔723〕を〔書庫5〕に載せている
| (大伴宿祢家持贈娘子歌七首) |
| 夜晝 云別不知 吾戀 情盖 夢所見寸八 |
| 夜昼といふ別き知らず我が恋ふる心はけだし夢に見えきや |
| よるひると いふわきしらず あがこふる こころはけだし いめにみえきや |
| 巻第四 719 相聞 大伴家持 |
夜、昼という区別も分からないほどの私の恋心、
もしかしたら、あなたの夢に現れたのでしょうか |
ここでの「ず」は、打消しの助動詞「ず」の終止形だが
やはり、『万葉集全訳注』では、「しらに」と連用形「に」に訓じている
しかし、その解釈は、はっきりと区別している
「昼夜の区別も分からず」ではなく「昼夜関係なく」として...
では〔2952〕でも、同じように訳せば、と思うのだが、〔2952〕歌では
前述のように、「いつ夜が明けいつ日が暮れるとも知らず私は辛いことよ」となっている
いっそのこと、「日が昇ろうが沈もうが、思いも及ばない」くらいの訳であれば、と思う |
|
|
| 【歌意2953】 |
憂いを晴らす手立てなど、
今となっては私には何も残っていない
あの娘に逢わなくなって、
こんなに年が経ってしまったのだから...今更なんて... |
もう手立てもないほど、時が過ぎ去って...
それまでのこと、どんな気持ちで過ごしていたのだろう
この類想歌を、右頁に幾首か並べてみたが
語句こそ、その変化はあるものの、歌意においてはあまり変わらない
ということは、作者一人の「想い」ではなく
この時代の、このような環境下にある男もまた、多く
その世情を詠ったものとして、幾首も詠われた可能性もあるだろう
先日から読んでいる、万葉の時代の「婚姻制度」に
一つの可能性として、このような歌の背景を物語る当時の「法令」の解釈がある
当事者同士の意志だけではなく、その親や親族の意志をも必要とされる
そして、いわば婚約のような形で、二人が恋仲をオープンにしても
現代のように、自由に逢瀬は重ねられない
何故なら、娘の親族が男に対して観察するのは
立派に農耕などの「生産技術」を身に付けるかどうか...
それが、家族のため、そして村のためになるからだ
仮に、娘の親族から異論があれば、二人の意志には関係なく
この結婚は流れてしまう可能性も高い
今、この歌を読んでいて、男はまさにそんな状況に置かれているのではないか
ふと、そう思えてきた
大人同士の婚姻と違って、今で言う未青年同士の婚姻であれば
「何も手立てがなくて...」が大人の場合よりも、
親の承諾の要る婚姻であればこそ、ついことばに出てくるものだろう
婚姻規程では、男十五歳以上、女十三歳以上とあっても
また別の実態を推測させる資料からだと、実際は二十歳前後の婚姻の実態があるらしい
この点については、その前提がすべて推測なので、
「和歌」という世界の中でしか、同じように推測は続けられないが
婚姻可能年齢に達してから実際の結婚までの数年の期間が、
まさに男の試験期間とでもなるのだろうか
この間に、お互いの「想い」が続くにしても
その周囲から、異論が出始めたら...男は、なかなか女家に足を運べなくなる
初めの内は、あまり大きなこととは思っていなくても
それが長きに及ぶことにでもなれば、いっそう行くことは出来まい
「あいつは役に立たない奴だ」とでも周囲から言われれば
そうした制度がある以上、少年少女がそれに立ち向かうのは容易なことではないだろう
長く逢わないことが、既成事実になってしまうと
「想い」そのものも、実態のない観念的な「恋に恋する」ような意識になってしまう
だから、そんな自分を客観的に見詰めるような歌まで...先日目に触れたばかりだ
あるいは、周囲からは、もう「あいつは駄目だ」と言われていても
二人の気持ちは、どうしても抑えられず、人目を忍んで「逢瀬」を重ねる
これもまた、『万葉集』中には、よくみかける歌だ
そして、今日の歌のように、こうして詠んだあとに続くもの...
この歌に続く歌が、必ず詠われていると思う
手立てがなくなっても、想いが消えない以上は、死ぬしかないのか、とか
今の俺は認められなかったけど、何年かしたら、必ず認められるような男になる
だから、それまで待っていてくれ、とか
嘆くばかりでは、それこそ「和歌のための詠い」になってしまう
前に突き進む歌にも...触れてみたいものだ |
 |
掲載日:2013.10.25.
| 正述心緒 |
| 念八流 跡状毛我者 今者無 妹二不相而 年之經行者 |
| 思ひ遣るたどきも我れは今はなし妹に逢はずて年の経ぬれば |
| おもひやる たどきもわれは いまはなし いもにあはずて としのへぬれば |
| 巻第十二 2953 正述心緒 作者不詳 |
【注記】に〔2904〕〔2893〕〔2485〕〔3275〕〔2972〕歌あり
| 【2953】語義 |
意味・活用・接続 |
| おもひやる[念八流 ] |
| おもひやる[思ひ遣る] |
[他ラ四・連体形]憂いの気持ちなどを晴らす・気遣う |
| たどきもわれは[跡状毛我者] |
| たどき[方便](上代) |
「たづき・たつぎ」手段・方法・手掛かり・様子・見当・手立て |
| 〔参考〕古くは下に「なし・知らず」などの打消の語を伴った |
| も[係助詞] |
[強意](下に打消の語を伴って、強める) ~も |
| 〔接続〕名詞、助詞、用言や助動詞の連体形・連用形など種々の語につく |
| いまはなし[ 今者無] |
いまは[今は]
|
[今はもう限りだ、の意から]今となっては・もうこれまで |
| 〔成立〕名詞「今」+係助詞「は」 |
| いもにあはずて[妹二不相而] |
| ずて |
~ないで・~なくて |
未然形につく |
| 〔成立〕打消の助動詞「ず」の連用形「ず」+接続助詞「て」 |
| 〔参考〕おもに上代に用いられ、平安時代以降は和歌の用語として残った |
| としのへぬれば[年之經行者] |
| へ[経] |
[自ハ下二・連用形] |
| ぬれ[助動詞・ぬ] |
[完了・已然形]~てしまう・~てしまった |
連用形につく |
| ば[接続助詞] |
[順接の確定条件]~ので・~だから |
已然形につく |
| 〔参考〕「未然形」+「ば」だと、「順接の仮定条件」(~なら・~だったら)になる |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [念八流 跡状毛我者] |
旧訓では、諸本すべてに初句「念八流」の下に「跡」をつけて、その訓を、
「念八流跡、おもはると」としていたらしい
そして次の句では、当然「跡」がないので、「状毛我者」を「かたちもわれは」と訓じる
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕で、初めて「跡」を下に移して
「おもひやる あとかたもわれは」と訓べし、と説いている
これで初句「おもひやる」が、定訓になるが、第二句に考察がすすむと、
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕が、次の二首を用例とし、
「跡状」を「たどき」と訓むことを考え、これが定訓となった
| 思遣 為便乃田時毛 吾者無 不相數多 月之經去者 |
| 思ひ遣るすべのたどきも我れはなし逢はずてまねく月の経ぬれば |
| おもひやる すべのたどきも われはなし あはずてまねく つきのへぬれば |
| 既出、書庫10 巻第十二 2904 正述心緒 作者不詳 |
この苦しみを、どうにも紛らせる方法も、わたしには浮ばない
こんなにも長く、逢わない日々が続いたのだから... |
| |
立而居 為便乃田時毛 今者無 妹尓不相而 月之經去者
[或本歌曰 君之目不見而 月之經去者] |
立ちて居てすべのたどきも今はなし妹に逢はずて月の経ぬれば
[或本歌曰 君が目見ずて月の経ぬれば] |
たちてゐて すべのたどきも いまはなし いもにあはずて つきのへぬれば
[きみがめみずて つきのへぬれば] |
| 既出、書庫10 巻第十二 2893 正述心緒 作者不詳 |
立ったと思えば、また座って...そんな落ち着きもないことを繰り返し
何をしていいのか、今は為すすべがない
それも、あの娘に逢わずに、月日が経ってしまったものだから..
[或る本歌]あの人に逢えなくて、こんなにも月日が経ってしまったので... |
この用例から、「跡状」を「たどき」と考えたようだ
こうした歌意に沿うように、「跡状」の語は、次の例歌の原文からも伺える
| 大野 跡状不知 印結 有不得 吾眷 |
| 大野らにたどきも知らず標結ひてありかつましじ我が恋ふらくは |
| おほのらに たづきもしらず しめゆひて ありかつましじ あがこふらくは |
| 巻第十一 2485 寄物陳思 柿本人麻呂歌集出 |
広い野原に、その手段も意味さえも解らず標縄を張ってしまい
わたしの恋は、もうこのままではいられないだろう
|
|
| [としのへぬれば] |
旧訓「としのへゆけは」で、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕が初めて「としのへぬれば」と訓む
この訓を、『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕が、採り上げ
| 立而居 為便乃田時毛 今者無 妹尓不相而 月之經去者 |
| たちてゐて すべのたどきも いまはなし いもにあはずて つきのへぬれば |
| 巻第十二 2893 正述心緒 作者不詳 |
| 思遣 為便乃田時毛 吾者無 不相數多 月之經去者 |
| おもひやる すべのたどきも われはなし あはずてまねく つきのへぬれば |
| 巻第十二 2904 正述心緒 作者不詳 |
| 思遣 為便乃田付毛 今者無 於君不相而 年之歴去者 |
| 思ひ遣るすべのたづきも今はなし君に逢はずて年の経ぬれば |
| おもひやる すべのたづきも いまはなし きみにあはずて としのへぬれば |
| (反歌)今案 此反歌謂之於君不相者於理不合也 |
| 巻第十三 3275 相聞/反歌 作者不詳 |
この憂いを晴らす手立ても、今はもうなにもない
あなたに逢わずに、年がこんなにも過ぎてしまって... |
尚、この歌には左注があり、元の「長歌」では、「我妹子」を恋ふる男歌なのに
この反歌では「君に」となる、だから「妹に逢はず」というべき、とある |
こうして、「経去者」の訓が「へぬれば」とされ
『日本古典文学全集』〔小学館、昭和50年成〕・
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕・
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕などが、これに続いた
ただし、不思議に思うのは、岩波書店の
『古典大系』では、そもそもの「へぬれば」であったものが
その後の、『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕では
旧の『大系』の「へぬれば」を、「へゆけば」と改訓している
それほど、「訓」の研究は今も尚「いったりきたり」なのだろうか...
他に、『万葉集全注』〔伊藤博、昭和58年開始〕では
「経去者」は「へぬれば」であっても、
「経行者」は、「へゆけば」であるべき、としてる
そこは、岩波との違うところだ
この語句での類想歌を、もう一首挙げておく
| 虚蝉之 宇都思情毛 吾者無 妹乎不相見而 年之經去者 |
| うつせみの現し心も我れはなし妹を相見ずて年の経ぬれば |
| うつせみの うつしごころも われはなし いもをあひみずて としのへぬれば |
| 巻第十二 2972 正述心緒 作者不詳 |
まるで、現実ではない心持で、私はいる
あの娘に逢うこともなく、年が経ってゆくので... |
|
|

| 「いつはりを、よくする人」...しればまこと... |
|
|
|
| 【歌意2955】 |
わたしが、このいのちを永らえたいのは
うそを巧みにつく、あの人を
何とか取り押さえて、懲らしめたいくらいのことかなあ |
この歌、どんな解釈が可能なのか、随分悩んだ
まず、女性の恨みごとなのか、戯れなのか...
諸注を読み比べても、確信めいた解釈にはならない
それも当然だと思う
現代に生きる人の詠歌であれば、その辺りの胸中も聞き出せるだろうが
何しろ...はるか昔の「人」なのだから...
『万葉集総釈』〔各巻分担、楽浪書院、昭和10~11年成〕では、
「偽りをよくする人、は口先ばかりのお上手な人」、とし
また、『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕で解される、「作者は才気ある女」
さらに、『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕で、
「男に捨てられた女が、男に執り付いてやる為に生きてゐたいといふのであるが、凄味よりも辛辣な皮肉に聞こえるので、受け取った男はその意味で悚然たるものがあったろう。読者は軽いユーモアを感じて洒脱な年増女の風耒を想像するのである。」と評している
これらの註釈は、わりとこの作者の心情に、思い詰めた女の執念ではなく
懲りない男を、ちょっと懲らしめてやろう、だからそのために長生きしたい
あるいは、長生きすること自体が、男への「懲らしめ」になるだろう、と
私も、こうした側での解釈に思う
しかし、少し違うところもある
それは、「ばかり」という語義を、古語辞典で引き
その用例に触れたとき、他の注釈書とは違うイメージを感じてしまった
辞書の言う、「上代での、限定」つまり「~だけ」という用法は見られない、ということ
しかし、どの注釈書をみても、この歌の歌意は
「私が長く生きることを望むのは、うその巧みなあの人を捕まえたいだけだ」のような
そのためにだけ、「長生きしたい」と感じられる解釈になっている
私の受け方が不充分かもしれないが...
そして、古語辞典の解説を、そのまま根拠にするなら
この「ばかり」では、「限定」にならないのだから
もっと違うニュアンスにならなければならない、と思ってしまった
「捕まえたいことだけで」、生きたいのではなく
「捕まえたい、そんな程度のものなのかもしれない」、
それが、長く生きたいと思う理由なのですね、きっと
この歌の作者は、決して強い口調で男をたしなめてはいない
「うそが上手なんだから」と笑いながらいい
「そんなあなたを、懲らしめるために、長く生きてみたいのかもしれない」
そう呟かれたら、男には大変なインパクトがある
改心するかもしれないし、愛しさが増してくるかもしれない
右頁の「よく」で分かれる、作者の「心」
私は...好意的な解釈をしたい
うそつき、と男を恨む女の歌ではなく
「巧みなあなたのうそ」に、せいぜい気をつけて付き合っていきたいものです
そんな「大人の心」が感じられる歌だと思う
|
 |
掲載日:2013.10.26.
| 正述心緒 |
| 我命之 長欲家口 偽乎 好為人乎 執許乎 |
| 我が命の長く欲しけく偽りをよくする人を捕ふばかりを |
| わがいのちの ながくほしけく いつはりを よくするひとを とらふばかりを |
| 巻第十二 2955 正述心緒 作者不詳 |
【注記】に〔2921〕歌あり
| 【2955】語義 |
意味・活用・接続 |
| わがいのちの[我命之 ] |
| の[格助詞] |
[主語]~が〔接続〕体言および体言に準ずるものにつく |
| ながくほしけく[長欲家口] |
| ながく[長し・永し] |
[形ク・連用形]長い・(時間的に)隔たりの大きいさま |
| ほしけ[欲し] |
[形シク・(古い)未然形]そうありたい・ほしい |
| く[接尾語](上代) |
~することには・(文末で、詠嘆をあらわす)~することよ |
| 〔接続〕動詞の未然形、形容詞の古い未然形語尾「け・しけ」につく |
| 〔接続〕名詞、助詞、用言や助動詞の連体形・連用形など種々の語につく |
| いつはりを[ 偽乎] |
いつはり[偽り・詐り]
|
うそ・そらごと |
| よくするひとを[好為人乎] |
| よくする[能くす・善くす] |
[他サ変・連体形]手落ちのないようにする・巧みにする |
| とらふばかりを[執許乎] |
| とらふ[捕ふ・捉ふ・執らふ] |
[他ハ下二・終止形]しっかりと掴む・取り押さえる |
| ばかり[副助詞] |
[程度]~ほど・~ぐらい |
終止形につく |
| を[間投助詞] |
[感動・詠嘆]~なあ |
種々の語につく |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [我命之] |
ほとんどの諸注は、「わがいのちの」と訓むが、
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕は、この「之」について
「今本之と有はかなはず、古本に依って乎とす」という
「わがいのちを」と『万葉考』は訓む
そして、この訓を採るのが、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕だけで、「古本に従つ」としている
ただし、この「乎」とする「古写本」は現在、その存在は確認されていない
岩波文庫新訓が「わがいのちし」と訓じ、
『定本万葉集』〔佐佐木信綱・武田祐吉、昭和15~23年成〕及び、
『万葉集釈注』〔伊藤博、平成7年~11年成〕が、それに倣う
確かに「之」は「強意」の副助詞「し」に当てた例もあり、その一例を載せる
| 凡尓 吾之念者 人妻尓 有云妹尓 戀管有米也 |
| おほろかに我れし思はば人妻にありといふ妹に恋ひつつあらめや |
| おほろかに われしおもはば ひとづまに ありといふいもに こひつつあらめや |
| 既出 書庫11 巻第十二 2921 正述心緒 作者不詳 |
ここでは「之」は、強意の副助詞「し」の解釈になる
|
| |
| [接尾語「く」] |
上にくる語を名詞化するはたらきがあり、
中古では「言はく・思はく」などの特定の語として残り
この語の説明を、「ク語法」として単に、そう片付けられていたが
詳しい説明は、現代でも決め手がないらしい
ただし、この語の意味としては、三種の用法が使われている
①「~すること」の意を表す
②連用修飾語になる、「~することには」
③文末にあって詠嘆を表す、「~することよ」
この歌でも、この語に関しては、②や③の用法で揃っていない
|
| |
| [よくするひとを] |
この歌の解釈は、この語句にかかっていると思う
副詞「よく」、動詞「よくす」、どちらだろうと思ったが
この二語は、品詞が違うだけなのに、微妙にそのイメージが違う
副詞「よく」では、「念入りに」とか「上手に・巧みに」などのように
ある意味での肯定的な語義の他に、
「たいそう・非常に甚だしく」、「たびたび・ともすると」など、
相手に対して「否定的」な意味合いをも持つ
それに対して、動詞「よくす」は、
「十分にする・手落ちのないようにする」や「巧みにする・上手にする」と、
これは、肯定的というのか、好意的な解釈に感じられる
勿論、私の古語辞典が、詳細な語意を載せていないかもしれないが
幾つかの辞書を引いても、どれも同じだった
とすると、私には自然と、動詞「よくす」を採ってしまう
何しろ、この歌の歌意が、そのように思えるのだから...
表面的な「恨み」こそ、この作者の「無邪気な歌心」ではないだろうか
前の句から、「うそを上手に、巧みに言う人」となるが、
この「よく」あるいは「よくす」の解釈の仕方で、註釈書によっては
歌意に「情け」がこもらない歌にもなっている
例えば、
『新潮日本古典集成万葉集』〔新潮社、昭和51~59年成〕では、この「よく」を、
「程度や数量の甚だしさを言う」としており
それは、「うそ」の「程度の甚だしさ」を意味してしまう
それよりも、やはり「巧みに」とか「上手に」とした方が
それを笑いながらも、言葉では懲らしめようとする女性の「茶目っ気」がある
|
| |
| [とらふばかりを] |
原文「執許乎」の「執」について、
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕、そして
『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕は、「執」は「報」の誤りとして訓む
『略解』で橘千蔭は、「或人云、執は報の誤にて」とし、「むくゆばかりを」ならむ
そう「或人」が言うのを「さも有べし」と言っている (或人とは...)
『口訳万葉集』の折口信夫も、「報ゆ許りを」と訓み
「為返しをしてやりたい許りで、さう思う」と口訳している
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕は、「とらむばかりを」と訓んで、
「捕へむ為のみぞ、そいふ意とすべし」という
しかし、この『万葉集新考』の、
動詞「とらふ」が「とらむ」と活用することができないのでは、と思う
解釈の「捕へむ為」とするように「とらむ」ではなく助動詞「む」に接続するなら
「とらへむ」とならなければならないはずだ
これ以外の諸注では「とらふばかりを」と訓み
語意としては「その人を捕まえ、取り押さえて、こらしめよう」と解する
|
| |
| [ばかり] |
この語の「成り立ち」は、動詞「計る」の名詞形「はかり」とある
そして、その用法には二種類あり、
①おおよその範囲・程度
範囲 ~ごろ・~あたり
量 ~ぐらい・~ほど
程度 ~ほど・~ぐらい
及ばない程度 ~ほど・~ぐらい
強調 ~ほど・~ぐらい
②限定
~だけ・~だけだ・~にすぎない
この二種の用法も、①の「ほど」と②の「だけ」では、
その使用例に、時代的な違いがあり
上代では、②「限定」は見られないらしい
さらに、接続においても、①は終止形に付き、②の場合は「連体形」に付くのが多い
|
|
| 【歌意2956】 |
人目がうるさく、気になるものだから
あの娘にも逢えず、こうして心の中で恋しく想うこのごろだ |
万葉の時代の「婚姻制度」を、少しかじっただけなのに
この歌のような「男心」が、これまでに比べ、かなり深く感じられるようになった気がする
講談社文庫の『全訳注』では、このような歌の「妹」は
ほとんど「妻」と解釈している
勿論、「妹」には、「妻」もあるし「愛しい人」、恋人のような意味合もある
「妻」というと、とても限定されてしまって、「恋歌」として読む場合
その情感が一気に狭くなっていた
しかし、この歌のように、「逢えないでいる妻」もいることを
今読みかけの本で、知ることができた
その説が、どこまで正しいのか解らないが
状況的には、これまで私が、いつも疑問に思っていた「通い婚」の実態に近いもの
そう思えるほどの説得力がある
「妻」と解釈するのなら、それも確かに、この歌のような情況でなければならない
「妻」と呼べる相手がいるのに、「人目」を気にして、なかなか逢いに行くことができない
それは、まだまだ親族の監視の下、二人の仲が十分認められていないからだ
その「親族」も、「里人」たちが、いつしか加わる
小さな地域であれば、他人でも「親族」のようなものだ
その「里人」たちが、どんな風評を「親族」に言うかも解らず、
男は気軽に女の所へ通うことも出来ない
双方の親族が、無条件で認めているのであれば
こんな「歌」のような「せつなさ」もないのだろう
だから、男の立場からすれば、俺はまだまだ一人前に認められていない
そんな状態の中で、あの娘の所へなど...いくら結婚の許可はあったにせよ
いつ覆されるか...その不安の一杯に詰まった「詠歌」なのだろう
不思議なもので、一つの疑念が晴れたとき
歌の世界が、その「時代」を語っている重要な「証言」であることに
改めて教えられる
勿論、こうした「婚姻制度」が唐の文化からの倣いであったにせよ
その運営実体は、どこまで唐に倣ったものか...それも知りたいものだ
何しろ、形だけを先行させて「法令」を整備した国家創生の時代のことだから
それまでの実情にも、ある程度は配慮があったことだろうし...
やはり、『万葉集』の「奇跡」と思える所以は、
このような「未詳歌」の歌群の中に、あるのだ、と
つくづく思う
|
 |
掲載日:2013.10.27.
| 正述心緒 |
| 人言 繁跡妹 不相 情裏 戀比日 |
| 人言を繁みと妹に逢はずして心のうちに恋ふるこのころ |
| ひとごとを しげみといもに あはずして こころのうちに こふるこのころ |
| 巻第十二 2956 正述心緒 作者不詳 |
【注記】に〔1772〕〔2591〕歌あり
| 【2956】語義 |
意味・活用・接続 |
| ひとごとを[人言 ] |
| ひとごと[人言] |
他人の言うことば・世間の噂 |
| を[間投助詞] |
[~を~み]の形で、「~が~ので」 |
体言につく |
| しげみといもに[繁跡妹] |
| しげみ[繁し・茂し] |
[形ク・語幹]量が多い・絶え間ない・うるさい |
| と[格助詞] |
[引用]~と 〔接続〕体言、体言に準ずる語につく |
「~と言って・~と思って・~として」などの意で、
後に続く動作・状態・目的・状況・原 因・理由などを示す |
| あはずして[ 不相] |
して[接続助詞]
|
[「ずして」の形の場合]~(ない)で・~(なく)て |
〔参考〕打消の助動詞「ず」の連用形「ず」に、「して」がつき、「ずして」として使う
おもに、漢文訓読文や和歌に用いられた 〔接続〕助動詞の連用形につく |
| こころのうちに[情裏] |
| に[格助詞] |
[位置](空間的な場所をさす)~に・~で |
体言、連体形につく |
| こふるこのころ[戀比日] |
| こふる[恋ふ] |
[他ハ上二・連体形]思い慕う・恋しく思う・恋慕する |
| このころ[此の頃] |
近頃・近いうち・今頃・今時分 |
| 〔「このころ」は上代の訓で、「このごろ」と同じ〕 |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [人言 繁跡妹] |
この初句、第二句の原文「人言繁跡妹」は、『万葉集全注』〔伊藤博、昭和58年〕で、
「柿本人麻呂歌集歌」としている「巻第十一-2591」の「人事茂君」を、
「ひとごとを しげみときみに」とあり、その訓の根拠として、
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕が、
略体歌だから、『人麻呂歌集』の歌だとし、『柿本人麻呂歌集』に移している
確かに、助辞の表記のないこの一首は、
略体歌には違いないだろうが、通説にはなっていない
同じような考えで、
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕では、
「此の歌、人麻呂集の書体也。乱れてここにまじりたるなるべし」として
やはり、『柿本人麻呂歌集』の一首として扱い
もっと、直接的なのは、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕での扱い方だ
鹿持雅澄は、この歌の配列を変えている
ここ〔2956〕番目のところではなく、この巻第十二の目録に
本来ならば、「正述心緒の歌百十首」とあり、
「十首が人麻呂歌集で、それ以外の百十首」としているところを
「十一首が人麻呂歌集、それ以外百十首」の「計百十一首」としている
この〔2956〕歌を、『柿本人麻呂歌集』の一首と計算したからだ
ただし、ここで腑に落ちないのは、それでも「正述心緒の計百十首」との目録は
その内訳に異説があろうと、合計歌数には変わりないはずだと思うのだが...
これは、『古義』をもう一度明日香で確認しなければ...
そして『古義』では、この歌が、上述のように、
冒頭の「十首」の直後、〔2852~2861の十首〕の直後に置かれている
(だから、当然「正述心緒」の部立てで、その合計数は、変わらないはず)
明日香図書館の『古義』は、歌番号が付いていない本来の姿なので
鹿持雅澄が入れ換えた配列は、
現代のように番号が便宜上付されている書を見慣れていると
変更されたことに、まったく違和感を覚えない...普通に歌が並ぶ
ただ、その左注に、『略解』での見解を付け、移動した、とある
このことは、他の注釈書では、認めてはいない
それに、『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕の言う〔2591〕が、
他の諸注でも『柿本人麻呂歌集』歌とはされていないし
『古義』でも、〔2591〕については、〔2956〕のように移動はさせていない
つまり、『古義』では、その巻第十一の目録でも、〔2591〕は、「人麻呂歌集以外」
とされている...ややこしいが、一貫性がないように思う
ここに、その〔2591〕を載せる
| 正述心緒 |
| 人事 茂君 玉梓之 使不遣 忘跡思名 |
| 人言を繁みと君に玉梓の使も遣らず忘ると思ふな |
| ひとごとを しげみときみに たまづさの つかひもやらず わするとおもふな |
| 巻第十一 2591 正述心緒 作者不詳 |
人のうわさが、わずらわしいので
あなたに、大切な使いの者も遣れません
だから、あなたのことを忘れているとは、思わないでください |
|
| |
| [こころのうちに こふるこのころ] |
この下二句と同じ歌が、巻第九-1772
| (抜氣大首任筑紫時娶豊前國娘子紐兒作歌三首) |
| 石上 振乃早田乃 穂尓波不出 心中尓 戀流比日 |
| 石上布留の早稲田の穂には出でず心のうちに恋ふるこのころ |
| いそのかみ ふるのわさだの ほにはいでず こころのうちに こふるこのころ |
| 巻第九 1772 相聞 抜気大首 |
石上の布留の早稲田の穂とは違い
その表面には出ないで、この心の中で、
あなたを恋しく想うこのごろです |
言葉にはしないが、想いは心の中に秘めている
そのことを、早稲田の穂のように表面に出すのではなく
秘かな恋心を知ってほしい、そんな切ない気持ちなのだろう
この二句からなる想いの語句は、多く用いられているようだ
秘めた気持ちを詠う、慣用句なのかもしれない
『全注』では、こうした類想歌も、〔2956〕がその原形ではないか、としている
|
|
| 【歌意2957】 |
あなたがおくる、たまづさの使いを
今か今かと待っていたあの夜のこと...
その名残が今も消えずに、寝られない夜の多いことでしょう |
この歌には、類想歌として〔2593〕がある
| 正述心緒 |
| 夕去者 公来座跡 待夜之 名凝衣今 宿不勝為 |
| 夕されば君来まさむと待ちし夜のなごりぞ今も寐ねかてにする |
| ゆふされば きみきまさむと まちしよの なごりぞいまも いねかてにする |
| 巻第十一 2593 正述心緒 作者不詳 |
夕方になれば、あなたがいらっしゃるだろうと
待っていた頃の夜が、今もその頃の気分が残って...
寝ることもできないのです |
この歌も、「連体形止め」で終えている
余情をこめて一首を終らせているのだろう
すると、確かに〔2957〕と〔2593〕は、その語句の用法をみても、
同じ気持ちを詠った女歌のようだ
こうした、類想歌が、「巻」も離れ、配列も離れているのに、非常に近くに感じるのは、
やはり編纂時にうず高く積まれた資料(多分木簡類だろう)の仕分けの煩雑さを想像させる
すべてを手作業でしなければならない、編纂の過程で、
このような「類想歌」が実に多いことか...
ただし、語句が似通っているからといって、「重複」だとは限らない
この二首でも、一方は「使者」を待ち、もう一方は「愛しい人」本人を待つ
当然、その舞台は違うだろう
単に類想歌が、どちらかが「本歌」で、どちらかが「異伝」というわけでもないし
あるいは、似ている歌を「見逃した」とも限らないと思う
多くの注釈書が、この二首を「類想歌」と挙げるのは理解できるが
私には、もう一首...
これは、「類想歌」ではなく、この〔2957〕歌の「歌群」に入るような歌を想った
それは、昨日採り上げた、〔2591〕だ
| 正述心緒 |
| 人事 茂君 玉梓之 使不遣 忘跡思名 |
| 人言を繁みと君に玉梓の使も遣らず忘ると思ふな |
| ひとごとを しげみときみに たまづさの つかひもやらず わするとおもふな |
| 巻第十一 2591 正述心緒 作者不詳 |
人のうわさが、わずらわしいので
あなたに、大切な使いの者も遣れません
だから、あなたのことを忘れているとは、思わないでください |
この歌では、何とか「使者」を遣って、想いを伝えたいと思いながらも、それが叶わない
だから、「あなた」が勘違いしないか、と気にしている
そして、今日の〔2957〕は、「あなた」からの「使い」を待っている
これは、自分の方からは「使い」を遣ることができないが
「あなた」の方からの「使い」を、日々待っている
この二首の歌が、私には作者のように思えてしまう
そうなると、今日の「なごりそいまも」の語句は、時間的な経過を教えてくれる
私は、随分長く「使い」も遣れないけど、
でも、「あなた」からの「使い」もさっぱりです
私が、あなたのことを忘れた、と思っているのでしょうか
あるいは、順序は逆かもしれない
あなたからの「使い」もなく、待っているとなかなか寝つけない
かといって、私の方から「使い」を遣るには、周囲の情況から...それも難しい
この二首に、先の〔2593〕を含めた歌を並べてみると...
この女性が「苦しい想いを抱きながら、悶々としている」姿が凝縮されてくる
まさに目の前で、一人の女性が、「行き違いと、その不安」を嘆いている
それが一枚の絵のように、すべてを詰めて...浮んでくる
〔2957〕と〔2593〕の類想歌二首について
諸注の評を、並べてみる
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕は、
「〔2957〕が、〔2593〕より劣る」とする
『万葉集釈注』〔伊藤博、平成7年~11年成〕は、
「この歌〔2957〕の間接性と、かの歌〔2593〕の直接性と、いずれにあわれをより深く見るかは、人の好み」とし、「ともに感は深い」とする
ここでいう間接性、直接性というのは、たぶん「使者」を介する「間接性」と、
「本人その人」を直接待つ「直接性」なのだと思う
「待ちし夜のなごり」の語句にも、思いは様々だ
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕は、
「君の使が来なくなっても、なおそれを待っていた習慣」であり、同じように、
『新潮日本古典集成万葉集』〔新潮社、昭和51~59年成〕が、
「惰性的に待ち続けている昔の習慣」としている
『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕では、
「既に男と仲の途絶えた後も猶、楽しかった当時の追憶に生きている女心があはれである」と
これらの解釈では、女性の一方的な「未練の歌」だとしている
私には、そうは思えないが...
それは、先に述べたように...このような歌を単独で感じるよりも
そして、類想歌だからといって、同じように考えるよりも
その状況下で詠われた心情を、「映像」としてみれば
決して、一首だけの解釈はできないはずだ
その中から「切り取られた」一場面が、どれほど「歌」に広がりを与えてくれることか...
「もう終った恋」ではなく、長く途絶えなければならなかった事情を
女心から、男に知ってほしい
それが伝えられないからこそ...苦しんでいる
私が、「女心」などというのも、おかしなことなのだが... |
|
掲載日:2013.10.28.
| 正述心緒 |
| 玉梓之 君之使乎 待之夜乃 名凝其今毛 不宿夜乃大寸 |
| 玉梓の君が使を待ちし夜のなごりそ今も寐ねぬ夜の多き |
| たまづさの きみがつかひを まちしよの なごりそいまも いねぬよのおほき |
| 巻第十二 2957 正述心緒 作者不詳 |
【類想歌】〔2593〕歌
| 【2957】語義 |
意味・活用・接続 |
| たまづさの[玉梓之 ]〔枕詞〕「使ひ」「人」「妹」などにかかる |
| きみがつかひを[君之使乎] あなたが送る「使者」を |
| まちしよの[待之夜乃] |
まち[待つ]
|
[他タ四・連用形]人や物事が来るのを待つ |
| し[副助詞] |
語調を整え、強意を表すま |
| 〔接続〕体言、または活用語の連体形・連用形、副詞、助詞などにつく |
| なごりそいまも[名凝其今毛] |
| なごり[名残] |
(過ぎ去ったあと、なお)その気分・影響・面影など残ること |
| そ[其・夫] |
[中称の指示代名詞]そのこと・それ |
| いま[今] |
(過去・未来に対して)現在・新しいもの・新しいこと |
| も[係助詞] |
[強意](下に打消しの語を伴って) 強める |
| 〔接続〕名詞、助詞、用言や助動詞の連体形・連用形など、種々の語につく |
| いねぬよのおほき[不宿夜乃大寸] |
| いね[寝ぬ] |
[自ナ下二・未然形]寝る・眠る |
| 〔複合動詞〕名詞「寝(い)」と下二段動詞「寝(ぬ」とが複合したもの |
| ぬ[助動詞・ず] |
[打消・連体形]~ない |
未然形につく |
| おほき[多し] |
[形ク・連体形(連体形止め)]多い |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [たまづさの] |
枕詞「たまづさの」は、『万葉集』中、十三例
「玉」は「玉だすき」「玉櫛笥(たまくしげ)」「玉桙の」「玉葛」「玉藻」「玉裳」など、美しいものを比喩的にいう「接頭語」
玉で飾ったという意味で用いられる場合もある
「梓(あずさ)」は弓の材料として最良の木であった
梓の木で作った弓を「梓弓」という
カバノキ科の落葉高木、甲斐・信濃の山中に多く自生していた
古代の使者は梓の木を杖にしていたので「玉梓の」が「使」の枕詞になった、という
「使」は男女の恋の便りを届けることが多かったので、恋の相手の連想から「妹」のかけ、その用例は、集中に二首ある
| 玉梓の妹は玉かもあしひきの清き山辺に撒けば散りぬる |
| 巻第七 1419 挽歌 作者不詳 |
| 或本の歌に曰 |
| 玉梓の妹は花かもあしひきのこの山蔭に撒けば失せぬる |
| 巻第七 1420 挽歌 作者不詳 |
以上は、『万葉集全注』〔伊藤博、昭和58年〕の解説だが、
この解説によると、「使者は梓の木を杖にしていた」とある
しかし、『万葉集辞典』〔折口信夫、大正八年〕では、
「此木に書状を挿んで往来した処からつづけた」とあり、
『全注』では、『万葉集』の「使」は多く書状ではなく口頭で伝えた、
と『万葉集辞典』を否定している
私には、「口頭」で伝えることが、いかに困難であるか
その方が不自然に思えるのだが...
詠歌を書き写すことが出来ない「人々」であれば、「口頭」も当然だろうが
果たして、文字表記に縁のない「人々」にとっては
「使者」を遣ってまで「歌」の遣り取りをするのだろうか...
仮に、それがあり得るとすれば、その場合は確かに「口頭」での扱いではあるが...
|
| |
| [指示代名詞「そ」] |
上代で称する係助詞「そ」、以降では「ぞ」となるが、
その「係助詞」では、「なごり」を単に強調するだけのことだが
これが、指示代名詞「そ」であれば、
「なごり」、過ぎ去ったその「面影」や「気分」など
「そのこと」が、「今も」に続く、歌意の奥行きが深まると思う
それに、原文の「其」は、やはり「指示代名詞」を意味すると思う
仮に「係助詞」であれば「曾(そ・ぞ)」と多くは表記されたのではないか |
| |
| [おほし] |
上代語「おほし」と「多し」「多かり」 【古語辞典】より
上代では、「おほし」は「大し」とも書かれ、「数量が多い」「容積が大きい」「立派だ」「正式だ」などの意味があった。中古以降、数量的な多さは、形容詞「多し・多かり」を使い、容積の大きさには形容動詞「大きなり」を使うようになった。これが中世末期になると、さらに「多い」「大きい」と区別が明確になる。なお、中古までの和文では、終止形は「多かり」が一般的で、「多し」は漢文訓読語として使われた。
|
| |
| [おほき] |
ここで、形容詞「おほし」の連体形「おほき」で終ることに戸惑った
連体形で終るには、「係り結び」という用法があるが、
この歌では、「係り」となる「係助詞」がない
だから、もう一つの「終止法」ということになるのだろう
それは、「連体形止め」
詠嘆の気持ち・余情をこめて、文を終了する
|
|
 |
| 【歌意2958】 |
玉桙のある、その神聖な道で行き逢った
傍目でも、とても上品で美しいあの娘なのに
いつになれば、また逢えるだろう
そう思って待つことになるのだろうか |
通りすがりに見かけた、美しい娘
男は一目惚れしたのだろうが、近づくすべもなく
今度逢えるのも、いつのことなのか分からない
註釈書の中には、「それほど深い想い」ではないのだろう、としているものもあるが
私には、そうは思えない
どんな手段を使ってでも「逢いたい」と思うのが深い「想い」とは限らない
限りなく望みは薄くても、
たった一度の「ときめき」を、大切にしている男の気持ち
こうやって、「いつとかまたむ」といい、その心情を大切にしている男の気持ち
決して「薄き情け」の恋心ではない
可能性が少なければ少ないほど、それでも「想う」気持ちは
むしろ「深い」ものなのだと思う
きっと、今度出逢ったら、こう言おう、ああ言おう、と考えていることだろう
そして、もうどれだけ時が経ったことか...
最近のことではないとは思う、見かけたのは...
見かけてすぐであれば、また近いうちに出逢うかもしれず
この先、どれだけ待つのか、などとは思うまい
やはり、しばらくは...逢えなかったのだ
だから、この歌を詠う
この先、たとえ逢えないまま終ろうと...死んでしまおうと...
そんな歌も、『万葉集』の中には、あるかもしれない
何しろ、私にとっても、この「万葉の旅」は、まだまだ果てしなく続く
四千五百首余りの「歌」の中で、まだ六百首ほどしか「旅」を終えていない
どんな「歌」に出逢えるか...楽しみは尽きない
|

 |
掲載日:2013.10.29.
| 正述心緒 |
| 玉桙之 道尓行相而 外目耳毛 見者吉子乎 何時鹿将待 |
| 玉桙の道に行き逢ひて外目にも見ればよき子をいつとか待たむ |
| たまほこの みちにゆきあひて よそめにも みればよきこを いつとかまたむ |
| 巻第十二 2958 正述心緒 作者不詳 |
【注記】〔1880〕〔3727〕歌
| 【2958】語義 |
意味・活用・接続 |
| たまほこの[玉桙之 ]〔枕詞〕(「たまぼこの」とも) 「道・里」にかかる |
| みちにゆきあひて[道尓行相而] |
| に[格助詞] |
[位置](空間的な場所を表す)~に・~で |
| 〔接続〕体言、活用語の連体形につく |
| ゆきあひ[行き逢ふ] |
[自ハ四・連用形]偶然に出逢う・出くわす |
| て[接続助詞] |
[単純接続]~て・そして |
連用形につく |
| よそめにも[外目耳毛] |
よそめ[余所目]
|
よそながら見ること・それとなく見ること |
| |
はたから見たようす・他人の見る目・はため |
| にも |
~においても・~からも・~でも |
| 〔成立〕格助詞「に」に係助詞「も」、係助詞「に」の意味のよって様々な意味を表す |
| みればよきこを[見者吉子乎] |
| みれば[見れば] |
[順接の確定条件・単純接続]目にすると・目にしたところ |
| 〔参考〕已然形+接続助詞「ば」で、「順接の確定条件」 |
| よき[好し・良し・善し] |
[形ク・連体形]美しい・綺麗だ・上品である |
| を[接続助詞] |
[逆接]~のに |
連体形につく |
| いつとかまたむ[何時鹿将待] |
| いつ[何時] |
[代名詞]はっきりと定まらない日・時、どのとき・いつ |
| と[格助詞] |
[比較の基準]~と・~に対して〔接続〕体言、体言に準ずる語 |
| か[係助詞] |
[疑問]~か・~だろうか 〔「係り結び」の「係り」〕 |
| また[待つ] |
[他タ四・未然形]人や物事が来るのを待つ |
| む[助動詞・む] |
[推量・連体形]~だろう 〔「結び」〕 |
未然形につく |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [たまほこの] |
枕詞「たまほこの」は、『万葉集』中、三十七例あり
このうち「道」にかかるものが三十六例、「里」へは一例
原義及びかかりかたは未詳とされるが、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕の補注〔巻第一・79〕で、
「三叉路や部落の入り口に邪悪なものの侵入を防ぐために桙状の陽石を立てたのによるのではないか」という
ただし、岩下武彦『人麻呂歌集における枕詞の位相-タマホコノをめぐって-』
(『美夫君志』55号、平成九年10月)では、「桙」の一字に注目し、
「これで陽石をイメージすることは難しい」、「『桙』が木製だったとすると実用のものではなく「おそらく神事などに関わる儀礼的なものであったろう」といっている
|
| |
| [ゆきあひ] |
動詞「行き逢ふ」には、「自動詞ハ行四段」と「他動詞ハ行下二段」の活用がある
この歌では、その接続する活用から「自動詞四段」であることは間違いないが
「他動詞下二段」の場合は、意味合いが違ってくる
「行きあわせる・並べ連ねる・交差させる」となる |
| |
| [よそめ(にも)] |
「よそめ(にも)」は、『万葉集』中で、この歌を含め僅か三例しかない
| 朝東風にゐで越す波の外目にも逢はぬものゆゑ瀧もとどろに |
| 巻第十一 2726 寄物陳思 作者不詳 |
| 外目にも君が姿を見てばこそ我が恋やまめ命死なずは [一云 命に向ふ我が恋やまめ] |
| 巻第十二 2895 正述心緒 作者不詳 |
いずれも、外から見る意味で解釈されるのが一般的だ
ことさら、深い意味を探しだすこともないが、用例が僅か三首、というのが
珍しい「語句」なのかなあ、と思う
|
| |
| [いつとかまたむ] |
平安中期書写の校本『元暦校本』以下の諸本は、すべて「いつしかまたむ」と訓じていた
しかし、『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕が、
「いつとかまたむ、とも読へし」といい、
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕、
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕、
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕、そして
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕もその訓に倣う
ただし、『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕のみ旧訓だが
「いつとかまたむ」が、現段階での定訓になっている
原文の「鹿」を、「しか」ではなく「か」と訓じ、
その訓を用いて「と」を添える用例を二首載せる
| 朝霞 春日之晩者 従木間 移歴月乎 何時可将待 |
| 朝霞春日の暮は木の間より移ろふ月をいつとか待たむ |
| あさかすみ はるひのくれは このまより うつろふつきを いつとかまたむ |
| 既出、書庫-6 巻第十 1880 春雑歌 詠月 作者不詳 |
(あさかすみ)春の日が暮れてしまえば、
今度は木の間より垣間見せる月を、
いつかいつか、と待つのだろうか |
| |
| (竹敷浦舶泊之時各陳心緒作歌十八首) |
| 多可思吉能 多麻毛奈婢可之 己藝デ奈牟 君我美布祢乎 伊都等可麻多牟 |
| 竹敷の玉藻靡かし漕ぎ出なむ君がみ船をいつとか待たむ |
| たかしきの たまもなびかし こぎでなむ きみがみふねを いつとかまたむ |
| 右二首對馬娘子名玉槻 |
| 巻第十五 3727 各陳心緒作歌 玉槻 |
竹敷の玉藻を靡かせて、
漕ぎ出ようとするあたなの船の帰りが、
いつになるだろうかと、私は待ちましょう |
「鹿」を「か」でなく「しか」と訓めば、「いつしか」にはなる
「いつしか」の意味としても、「いつしかも」であれば「いつになったら~か」
のように、この掲題歌の歌意に沿うようにも思うが
「いつしかも」とは、間違いなくめない
でも「いつしか」でも、十分通用するような気もする
では「いつしか」と「いつとか」はどう違うだろう
「いつしか」は「副詞」であるが、「いつとか」となると、「と」と「か」がついたもの
その「と」と「か」の解釈を、どんな風にするのだろう
「格助詞」と「係助詞」にすることくらいしか私には思いつかないが
それでも、歌意を「いつしか」と大きく変わることはないと思うのだが...
江戸時代の契沖が、改訓するまでは、「いつしかまたむ」だったということは
少なくとも、より詠歌の時代に近い時代の「訓」を、否定しているのだから
どこかに、その時代の「名解釈」のようなものがあれば、と思う
|
|
|
| 【歌意2959】 |
恋しく思うこの気持ちを、
どうしても抑えることができず、思い余って
わたしは、あなたのことを「くち」にしてしまった
いうべきとこではなかったのに...つつしむべきことだったのに... |
この歌のように、よく聞く解説では、
「恋人の名前を口にだすことは忌むべきものとされていた」
「恋人の名を口に出せば、人に知られる危険があり」
「その名を知られ、その名に対して呪詛されたりする」
「直接その名の人物自身が害を受ける、と信じられていた」
このようなことが、岩波の『古典大系』には書かれている
勿論、多くの研究者たちの成果を基本にしているのだろうが
「恋人の名を出せば危険」という感覚では
そもそも「相聞歌」など詠えるものだろうか
作者不詳の歌では、具体名は知りようもないが
笠女郎にしても、家持にしても
更には万葉歌人として名の残る人たちが詠う「恋い慕う歌」が
仮に「忌むべき」ものだとすれば、相当な矛盾のように思えてしまう
先日来少しずつ理解しつつある当時の「婚姻制度」を思い浮かべると
まだ「その名」を公言するには憚れる情況だと思った方が、実にすんなり理解できる
それを踏まえて、この歌に触れると
若い恋人同士が、まだ親に言えないままに、つい他の人に漏らしてしまった
そのような情況ではないだろうか
「いむべきもの」という、それこそ「呪詛」に連想されてしまいそうな語句だけど
「名」を知られることが、「呪詛」を懼れての「いむべきこと」ではなく
「名を知られ」、二人の仲が裂かれることを「懼れ」たので「いむべきこと」だと思う
このことで、親に知られてしまい、もう逢えなくなるかも知れない
その「怖ろしさ」を、切々に詠っているのではないだろうか
まだ当時の「婚姻制度」を私が理解しているとは思わないが
何でもかんでも「俗信」だった、とか「習慣」だった、とかで片付けたくはない思いもある
当時は、大陸からの文化面での流入も多かったはずだ
そして、はるかに文芸的にも先進国であった「唐」の、
大衆に根付いている諸々の、それこそ創作的な「俗信」もまた
先進国では、「こういうものらしい」程度に伝わり、
それは、先進国の文化を摂取する中で、一様に受け入れられた可能性もある
勿論、日本の古来からの、「俗信」もあったろう
しかし、そうしたことが記されていたかもしれない「文献」そのものが、
日本には残っていない
これは、私の単なる思い付きのような観もあるが
俗信などという根拠は、多くはこうした『万葉集』などの訳し方に負うものも多いのでは、と
少なくとも、「婚姻制度」に見る、世相の泣き笑いも、
その「法令」が唐に倣ったものだと、『万葉集』以外からの資料からも見える
その「法令」をベースにすれば、「万葉歌」も、自ずと歌意の「綾」が見えてくる
そのような考え方で、今日の歌のように、「名を知られたくない」という情況が
何を意味するものか、もっともっと知りたいと思うようになった
|
 |
掲載日:2013.10.30.
| 正述心緒 |
| 念西 餘西鹿齒 為便乎無美 吾者五十日手寸 應忌鬼尾 |
| 思ひにしあまりにしかばすべをなみ我れは言ひてき忌むべきものを |
| おもひにし あまりにしかば すべをなみ われはいひてき いむべきものを |
| 巻第十二 2959 正述心緒 作者不詳 |
| |
| 或本歌曰 門出而 吾反側乎 人見監可毛 [一云 無乏 出行 家當見] 柿本朝臣人麻呂歌集云 尓保鳥之 奈津柴比来乎 人見鴨 |
| |
| 或本歌曰 |
| 門出而 吾反側乎 人見監可毛 [一云 無乏 出行 家當見] |
門に出でて我が臥い伏すを人見けむかも
[一云 すべをなみ出でてぞ行きし家のあたり見に] |
かどにいでて わがこいふすを ひとみけむかも
[一云 すべをなみ いでてぞゆきし いへのあたりみに] |
| 柿本人麻呂歌集云 |
| 尓保鳥之 奈津柴比来乎 人見鴨 |
| にほ鳥のなづさひ来しを人見けむかも |
| にほどりの なづさひこしを ひとみけむかも |
| 【2959】語義 |
意味・活用・接続 |
| おもひにし[念西] |
| おもひ[思ひ] |
[他ハ四・連用形]愛する・恋しく思う |
| に[格助詞] |
[強調]~に 〔接続〕「強調」では動詞の連用形につく |
| し[副助詞] |
語調を整え、強意を表す |
| 〔接続〕体言または活用語の連体形・連用形、副詞、助詞などにつく |
| あまりにしかば[餘西鹿齒] |
| あまり[余る] |
[自ラ四・連用形]程度を超える |
| にしか |
~てしまった |
連用形につく |
| 〔成立〕完了の助動詞「ぬ」の連用形「に」+過去の助動詞「き」の已然形「しか」 |
| ば[接続助詞] |
[順接の確定条件・単純接続]~すると・~したところ |
| 〔接続〕「已然形」+「ば」は、「順接の確定条件」 |
| すべをなみ[為便乎無美]「~を~み」の語法 「~が~ので」 |
すべ[術]
|
手段・方法・仕方 |
| なみ[無し] |
[形ク・語幹+接尾語「み」]ない |
| 〔接尾語「み」〕形容詞の語幹につき「~を~み」の形で、~ので・~から |
| われはいひてき[吾者五十日手寸] |
| てき |
~てしまった・確かに~した・~た |
連用形につく |
| いむべきものを[應忌鬼尾] |
| いむ[忌む・斎む] |
[他マ四・終止形]つつしむ・不吉として避ける |
| べき[助動詞・べし] |
[可能・連体形]~ことができそうだ・~ことができよう |
| 〔接続〕終止形に付く |
| ものを[接続助詞] |
[逆接の確定条件]~のに |
連体形につく |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [おもひにし] |
『元暦校本』で「おもふにし」と訓じ、『広瀬本』ほか『寛永版本』までの諸本は、
すべて「おもふにし」と訓じている
古註釈においては、『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕が、
「しのびにし」とも訓むべし、といい、「我慢に堪えかねての意」としたが、
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕が「おもふにし」とし、
それが定訓となった
近代では、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37成〕、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕までが続いているが
『塙本』が「おもひにし」と改訓し、それを
『日本古典文学全集』〔小学館、昭和50年成〕、
『新潮日本古典集成万葉集』〔新潮社、昭和51~59年成〕、
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕、
『万葉集釈注』〔伊藤博、平成7年~11年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕が、それに倣う
諸注の「おもうにし」は「思うにあまったので」と口訳し、
「おもひにし」は、「思ふ」の名詞形「思ひ」とする
しかし、格助詞「に」、副詞「し」を、それぞれ強意とするが
私は、それだと「名詞形」ではないと思う
格助詞「に」であれば、活用語の「連用形」に接続するので、名詞「思ひ」はおかしい
だから、動詞「思ふ」の連用形「思ひ」と説明すべきだと思う
|
| |
| [鬼尾(ものを)] |
原文の「鬼」を「もの」の借訓仮名として用いることは多い
「鬼」は魔物、不思議な力を持った霊威とされ、「もの」というらしい
『万葉集』中の用例を三首ほど、
| 天雲之 外従見 吾妹兒尓 心毛身副 縁西鬼尾 |
| 天雲の外に見しより我妹子に心も身さへ寄りにしものを |
| 巻第四 550 相聞 笠金村 |
| 殊放者 奥従酒甞 湊自 邊著經時尓 可放鬼香 |
| こと放けば沖ゆ放けなむ港より辺著かふ時に放くべきものか |
| 巻第七 1406 譬喩歌 寄船 作者不詳 |
| 朝東風尓 井堤超浪之 世染似裳 不相鬼故 瀧毛響動二 |
| 朝東風にゐで越す波の外目にも逢はぬものゆゑ瀧もとどろに |
| 巻第十一 2726 寄物陳思 作者不詳 |
これら三首は、後日採り上げたい |
| |
| [柿本人麻呂歌集云] |
ここで「左注」に「柿本人麻呂歌集」として、下三句を書き記しているが、
この歌は、上二句「おもひにしあまりにしかば」が、
『万葉集』中に、この〔2959〕を含めて三首あり、残りの二首の内の一首をいう
| 思ひにしあまりにしかばにほ鳥のなづさひ来しを人見けむかも |
| 巻第十一 2497 寄物陳思 柿本人麻呂歌集 |
| 思ひにしあまりにしかばすべをなみ出でてぞ行きしその門を見に |
| 巻第十一 2556 正述心緒 作者不詳 |
この二首も、後日に採り上げる
|
|
| 【歌意2960】 |
明日には、あなたの家の門の前を通っていくことになります
表に出て、見て下さい
わたしが、どれほど恋しく辛い想いをしているか
その姿を、はっきりと知ることができるでしょう |
意図してなのか、偶然なのか、明日は愛しい人の家の前を通ることになった
なかなか逢うこともなく、寂しさで打ちひしがれていた日々
そんな自分の姿を、是非あなたに見てもらいたい
どれほどあなたのことを、想い慕っていたのか、きっと解ってもらえる
男の、そんな叫びのうたかもしれないが
個人的には、そんな姿を見せて、どうするのか、と思ってしまう
そのような気持ちがあっても、「つらい想いに日々を過ごした」自分の姿など
...私には共感できない
ただし、私がこの歌に感じたことへの「想い」であって
作者の想いは別なのかもしれない
自分の「恋やつれ」を見せたいのではなく
単純に、家の前を通るから、外に出て見てくれ、と言っているのかもしれない
でも、そうであれば、自分がこんなにも「恋しい」という強調はなんだろう
やはり、自分が想うほど、相手には想われていない、そのことの嘆きなのだろう
この歌の「門」からの連想で、家持の歌を思い出した
好きな娘の家の田を見ようという口実で出かけたが、
その夜の月の美しさに、自身の気持ちを照れ隠すかのように詠うものだ
「門」という「語」は、どうもこのような歌によく使われるものらしい
注釈書の中には、今日の〔2960〕歌は、男の愛の偽らざることを女に言い送ったもの、
と評してはいるが、
どうして、家のぞばを通る自分の姿を見てくれ、ということが
愛の偽らざる気持ちになるのか、私にはわからない
それに、他の注釈書でも、概ねこの歌に対する評価をしかねているように思える
それこそ、この歌の「不思議な魅力」なのか、とも言えるのかもしれない
私は初めて知ったことだが、鎌倉時代前期に成ったとみられる擬古物語『住吉物語』に、
| 君が門今ぞ過ぎ行く出でて見よ恋する人のなれるすがたを」という歌があるらしい |
この「物語」中の歌は、『万葉集』の今日の歌である〔2960〕が本歌という
そして、『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕では、
「物語」の改作は「流麗優雅であるが」、「原型の素朴さには及ばない」という
ということは、この〔2960〕歌...後世にも、注目された歌だった、ということか
|
 |
掲載日:2013.10.31.
| 正述心緒 |
| 明日者 其門将去 出而見与 戀有容儀 數知兼 |
| 明日の日はその門行かむ出でて見よ恋ひたる姿あまたしるけむ |
| あすのひは そのかどゆかむ いでてみよ こひたるすがた あまたしるけむ |
| 巻第十二 2960 正述心緒 作者不詳 |
| 【2960】語義 |
意味・活用・接続 |
| あすのひは[明日者]〔明日には〕 |
| そのかどゆかむ[其門将去] |
| その[其の] |
話し手から少し離れた事物・人をさしていう語 |
| かど[門] |
門・門の辺り・門前 |
| ゆか[行く・往く] |
[自カ四・未然形]通り行く・通り過ぎる |
| む[助動詞・む] |
[意志・終止形]~う・~よう・~つもりだ |
未然形につく |
| いでてみよ[出而見与] |
いで[出づ]
|
[自ダ下二・連用形](中から外へ)出る・(表面に)現れる |
| て[接続助詞] |
[単純接続]~て・~そして |
連用形につく |
| みよ[見る] |
[他マ上一・命令形]目にとめる・目にする・見る |
| こひたるすがた[戀有容儀] |
| こひ[恋ふ] |
[他ハ上二・連用形]思い慕う・恋慕する |
| たる[助動詞・たり] |
[継続・連体形]~ている |
連用形につく |
| 〔成立〕接続助詞「て」にラ変動詞「有り」がついた「てあり」の転じたもの |
| すがた[姿] |
衣服を身につけたようす・身なり・容姿・服装 |
| あまたしるけむ[數知兼] |
| あまた[数多] |
[副詞]非常に・はなはだ・数多く・たくさん |
| しるけ[著し] |
[形ク・上代の未然形]きわだっている・はっきりしている |
| む[助動詞・む] |
[推量・終止形]~だろう |
未然形につく |
| 掲題歌トップへ |
【注記】
| [あすのひは] |
『元暦校本』以下の諸本では、すべて「あけむひは」と訓じていた
註釈書では、『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕が、「あすならば」と訓む
異色だと思ったのは、「田中道麿」の説
この歌を解釈しようとして、この「田中道麿」とう万葉学者を知った
人物紹介として、「世界大百科事典」の説明を載せる
たなかみちまろ【田中道麿】 1724‐84(享保9‐天明4)
江戸時代の万葉学者。通称庄兵衛,号は榛木翁。薙髪(ちはつ)後は道全と号す。美濃国多芸郡榛木村の農家に生まれる。おもに大坂,名古屋に居住。幼時から読書に親しみ神童の誉れが高かったという。初め大菅中養父(おおすがなかやぶ)に師事。のち本居宣長に入門,万葉研究に才を現した。宣長の万葉に関する著書中にはしばしば道麿の説が採用され,宣長の信頼は篤かった。著書に《撰集万葉徴》《万葉集答問書》《万葉集東語栞》など。
|
こうして「田中道麿」を採り上げたのは、
その試みに、「一つの考え方」のあり方を知ることができたからだ
彼の著書を含め、私は全く知らなかったが、調べればいろんなことが解る
その研究で目を引くのは、「古今集」に「万葉歌」が十一首採用されている、というもの
そのすべてが、「読み人しらず」であり、その「元歌」は、「万葉歌」では、という研究
それについての評価は、私には解らないが、
この歌〔2960〕に限っては、どうしても私なりに考えてみたかった
道麿は、その著書『万葉集問聞抄』で、
第二句の「其」字を、初句に付けて「あすはその」と訓み、
第二句「門将去」を「かどにゆきなん」と七音に訓
それを、師である本居宣長に問うたのを、宣長が承認し、
「第二句を カドマカリナン と訓むべし」と答えていること
しかし、この試訓は、現在には全く論じられることはない
道麿であろうが、宣長であろうが...今では、一考されることもなく、
そして、私たちの「万葉集」入門書の類では、知ることもない
この「訓」は、『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕において
その訓の右に小字で併記されているが、他のどの注釈書もこの訓は記さず
そこから、この併記は、宣長からの改訓の朱入れだったのだろう、と言われている
宣長の晩年、弟子の伊予八幡浜の野井安定の質問には、このことは採り上げていないので
現在での確認は出来ないのだろうが、
同じ流れを汲む鹿持雅澄、『万葉集古義』〔天保十三年(1842)成〕は、
「明日者」を「あすのひは」と訓じ、それが現代までも「定訓」になっている |
| |
| [こひたるすがた] |
私は初めて知ったことだが、「恋ふ」の原義というもの
『万葉集全注』〔伊藤博、昭和58年〕によると、
「愛する人に逢えなくて、その人を求めて苦しい思いをする」とある
そう言えば、表記でも「孤悲(こひ)」とすることがある
その場合の歌の意としては、やはり「悲しい恋」なのだと思う
その意味では、この歌の意としては、片恋ではないことは察せられるが
原義からすると、「恋」そのものに、「つらい想い」が表現されているのだろうか
だから、そんな恋苦しむ自分の「姿」を、しっかり見ることができるだろう、と...
|
| |
| [数知兼] |
諸注では、
『元暦校本』、『類聚古集』、『広瀬本』、『西本願寺本』が、「かすはしりけむ」の訓
『神宮文庫本』、『細井本』が、「あまたしるかね」の訓、
『紀州本』、『大矢本』、『京都大学本』以下『寛永版本』まで「あまたしるけむ」と訓
この「あまたしるけむ」が、定訓になっている
実際に、実作者の詠歌が、どんなものなのか
もう『万葉集』は...「歌はそこにあるのに...詠う姿が見えない」歌集なのだと
つくづく思う
|
| |
| [け] |
「活用語尾」、上代のク活用形容詞の活用語尾とされる
「未然形」、「已然形」の語尾として用例がある
|
| |
|
 |
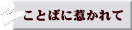  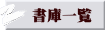  |




























