| 【歌意1900】 |
春になると、若葉を揺らせる枝垂れ柳の枝のように
わたしの心もしなうほど、どうにも揺れ動くのは
あの娘が、この心の内にすっかりとりついてしまったからだろうなあ |
枝垂れ柳が、春の風に吹かれるのは、
傍で見るには、とても爽やかな光景だ
しかし、想い人にとっては、そのしなう枝に、自身の「心」の落ち着きのなさを見出すのだろう
「とをを」に表現されるのは、
為すすべもなく、風任せ
しかし、枝垂れ柳がしなるのは、決して「風」のせいではない
秋萩や白橿が、「とををに」なるのとは違う
露や、雪といった「試練」に耐えているのではなく
枝垂れ、そして風に吹かれ揺れるのが、「枝垂れ柳」の本当の姿だ
ならば、「しだれやなぎの とををにも」という表現は、
それこそ、「春相聞」に相応しい「ときめき」の歌ではないかと思う
右頁の「注記」で取り上げた「いもはこころに のりにけるかも」の例歌では
そのどれもが、「のりにけるかも」の何か呪術的な、「私をこんなにさせて」の気持ちがある
しかし、この掲題歌が右の例歌と比較しても、「しだりやなぎの とをを」で、
自らこの「ときめき」を歓迎して詠っているような感じがする
比喩に用いる「しだりやなぎの とををに」が、他とは違って、
その本質を詠っているからだと思う
「紐」でもなく、穏やかなときもあるだろう「波」
そしてびっしり積み込まれた「葦荷」
「綱」に、人の手によって音を出す梶の「ゆっくりと次第に支配する音」
やはり「しだりやなぎ」は違う
そして、それがしなるのも、他とは違う
それが、「枝垂れ柳」であり、それでこそ「生きている証」と言える
だから、この歌の第四、五句の用い方は
こんなに一杯あの娘のことを思えるのが、楽しくてしかたない、とでも言うような歌だ
ちなみに、この歌が『西本願寺本』での配列では、次の「寄鳥」の題詞の次にあり
それを、現行のように「位置をここに訂する」旨の記号があるらしい
これは、明らかに単純なミスを後で訂正したことが伺えるものだが
改めて思うのは、諸本いや明治以前の注釈も含めて、
この四千五百首余りに及ぶ「歌集」が、現在のような歌番号もなく研究されていたこと
とてつもない作業だったと思う
ましてや、パソコンもない状況で、その検索などどんな方法で行ったのだろう
何度も何度も繰り返しての「確認」を怠らなかったのだろうが
それでも、気の遠くなるような作業だ
だから、配列の誤写も含めて、むしろこれほどその例が少ないとは、どうしても思えない
もっとも、それが系統本などによって、それぞれの伝本として残っているのだろうが
言ってみれば、該当する歌は一首なのに、異訓や異伝が多いのは
間違いなく伝本の写本の過程での誤写だろう
しかし、その正しい歌が...どれが正しいのか伝わっていない
『万葉集』の原本が存在しない以上、どうしても古写本を頼るしかなく
その古写本も、どこかの過程で「誤写」があったことなど、解りようがない
誰もが一様に同じような「歌意」をする歌もあれば、
その逆の歌意が出回っていても、誰も「それは違う」とは言い切れない
毎日のように、『万葉集』の頁を捲っているが
そこに書かれているのを、いつしか単純に「うたごころ」に触れるだけではなく
この「語」ならば、こんな風に訳せないか、とか大それたことまで考えている自分に気づく
素人の私に出来ることなど、専門家の淘汰された「解釈」あるいは、
そもそも話にならないほどのものかもしれないが
それでも、専門家だろうが素人であろうが、同じ語を、同じように目で拾えば
自分の心だけで『万葉集』を楽しむ分には、いいだろう、と自分に言い聞かせている
さらに、気をつけなければ、と以前は強く思っていたことがある
それは、現代人の感覚で読むだけではなく
当時の「感性」をも出来るだけ知らなければ、と
しかし、それはやはり手段の一つに過ぎない、と思うようになった
千数百年前の人の「こころ」を探っているわけではない
確かに、それほど古い人の「心」を知るのはいいことだし、興味もある
しかし、歌がこのように千数百年も残されているのは、決して「古い」からだけではないはずだ
現代人にも...古代に無関心な人でさえも、ときとして涙するような歌に出逢えるからだ
現代人である私が、現代人としても感じるからこそ、こうして伝えられている
そのことに、あまり気を遣わなかった
どうしても、「万葉人の心」と意識し過ぎていたのかもしれない
心に響く歌は、時代を越えて響き伝わるものだ
今更ながらに、『万葉集』の「大きさ」に気づく
|
| |





|
掲載日:2014.02.01.
| 春相聞 |
| 春去 為垂柳 十緒 妹心 乗在鴨 |
| 春さればしだり柳のとををにも妹は心に乗りにけるかも |
| はるされば しだりやなぎの とををにも いもはこころに のりにけるかも |
| (右柿本朝臣人麻呂歌集出) |
| 巻第十 1900 春相聞 柿本人麻呂歌集 |
【注記】〔1599・2319〕〔100・2431・2758・2759・3188〕
| 【1900】語義 |
意味・活用・接続 |
| はるされば[春去] 春になると・春になったので |
| しだりやなぎの[為垂柳] しだれ柳のこと |
| とををにも[十緒] |
| とををに[撓(とをを)] |
[形動ナリ・連用形]しなうさま・たわむさま・たわわ |
| も[係助詞] |
[並列]~も |
種々の語につく |
| いもはこころに[妹心] |
| は[係助詞] |
[とりたて]~は |
種々の語につく |
| のりにけるかも[乗在鴨] |
| のり[乗る] |
[自ラ四・連用形]のりうつる・とりつく |
| ける[助動詞・けり] |
[過去・連体形]~たのだ・~たことよ |
連用形につく |
| かも[終助詞] |
[感動・詠嘆]~であることよ |
連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [春去] |
この原文表記「春去」だけだと、順接の「仮定条件(~なら・~だったら)」と、
「確定条件(~ので・~だから・~すると・~したときはいつも)」の、
二通りの意味を考えなければならないが
その場合は、どちらで解釈すれば、他の語句との矛盾がないかを見つける
この歌では、結句の「のりにけるかも」が、詠嘆の含みもある過去の助動詞「けり」で、
春になったことが、すでに事実だとして詠われているので、
紛れもなく「確定条件」であり、その場合は四段動詞「去る」の「已然形」になる
ちなみに、「仮定条件」の場合の接続は、「未然形」になる |
| |
| [とををに] |
形容動詞「とをを」は、『万葉集』中に長歌一首を含めて六首ある
意味は、形容動詞「たわわ」(「たわたわ」の転)と同じで、しなう・たわむ様
しかし、「とをを」は詠われても、「たわわ」は詠われていない
唯一「えだもとををに」を「えだもたわたわ」と「或云」で伝える歌が一首あるだけだ
長歌を除く五首は、「秋萩」の「露」に「たわむ」とするのが三首で
掲題歌の「枝垂れ柳」の「心のしなるさま」を詠うのが一首
そして、白橿(しらかし、ブナ科の常緑高木)の、堅い枝を撓ませるほどの「雪」が一首
それぞれ、一首ずつ載せてみる
| 秋雑歌/大伴宿祢像見歌一首 |
| 秋芽子乃 枝毛十尾二 降露乃 消者雖消 色出目八方 |
| 秋萩の枝もとををに置く露の消なば消ぬとも色に出でめやも |
| あきはぎの えだもとををに おくつゆの けなばけぬとも いろにいでめやも |
| 巻第八 1599 秋雑歌 大伴宿禰像見 |
〔語義〕
「けなばけぬとも」は、下二段「消(く)」の連用形「け」に、
完了の助動詞「ぬ」の未然形「な」、そして順接仮定条件の接続助詞「ば」
その「けなば」で、「消えてしまうのなら」
続いて、「けぬとも」も、連用形「消(け)」に、完了助動詞「ぬ」の終止形「ぬ」
さらに、事実がそうであったり、そうなるのが確実な事柄について、
逆接の仮定条件で意味を強める接続助詞「とも」で、
「たとえ消えてしまうにしても」
「いろに」の、この場合の「いろ」は、顔色・素振り・表情、など
「いでめやも」の「めやも」は反語表現 |
〔歌意〕
秋萩の枝をたわわに撓らせる露も、やがては消えるように
消えてしまうのなら、いや、たとえ消えてしまうにしても
私は決してこの胸の内を、表に出したりしましょうか... |
| |
| 冬雑歌 |
足引 山道不知 白□○ 枝母等乎々尓 雪落者 [或云 枝毛多和々々]
(□=木偏に可、○=木偏に戈) |
| あしひきの山道も知らず白橿の枝もとををに雪の降れれば [或云 枝もたわたわ] |
あしひきの やまぢもしらず しらかしの えだもとををに ゆきのふれれば
[えだもたわたわ] |
| 右柿本朝臣人麻呂之歌集出也 但件一首 [或本云三方沙弥作] |
| 巻第十 2319 冬雑歌 柿本人麻呂歌集 |
〔語義〕
「やまぢもしらず」は、豪雪のため道筋も解らないようす
「しらかし」は、ブナ科の常緑高木で、非常に堅い木とされる
「ふれれば」は、四段「降る」の已然形「ふれ」に、
完了の助動詞「り」の已然形「れ」、そして逆接の確定条件の接続助詞「ば」、
「降っているので」 |
〔歌意〕
山路も、いったいどこにあるのか解らない
あの堅い「白橿」の枝までも撓むほどの、
ひどい雪が降っているのだから... |
秋萩の枝を撓ませる「露」と、白橿の枝までも撓ませる「雪」
しかし、これらの「とをを」を使っての表現は、
心の内を直接披露しているものではなく、あくまで「露」であり「雪」だ
秋萩の他の二首にしても、秋萩に使われる「とをを」はそうだと思う
そして、掲題歌の「とをを」となると
枝垂れる柳そのものを、作者の心と重ねて「とをを」としている
「とをを」が、唯一中心となった掲題歌だと思う
そしてこのことは、次句の「比喩」と比較しても、充分中心であることが伺える |
| |
| [いもはこころに のりにけるかも] |
「愛しいあの娘が、私の心にとりついてしまった」とは、
もうあの娘に夢中だ、他には何も考えられない、という意味なのだろう
『元暦校本』の付訓に、「いもがこころに のりにけるかも」とあり、
『万葉代匠記(初稿本)』〔契沖(1640~1701)、貞亨四年(1687)成〕など、
多くがそれに従っていたものの、
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕に、「いもは」と改め
以降は、これに倣う
『万葉語研究』(佐伯梅友)で、この点に触れ、詳細に吟味し
「けるかも」で結ぶ文においては「~が」ではなく「~は」というのが通例だと、いう
この「いもはこころに のりにけるかも」が、『万葉集』中に他に五例ある
| 相聞/(久米禅師娉石川郎女時歌五首) |
| 東人之 荷向篋乃 荷之緒尓毛 妹情尓 乗尓家留香問 [禅師] |
| 東人の荷前の箱の荷の緒にも妹は心に乗りにけるかも [禅師] |
| あづまひとの のさきのはこの にのをにも いもはこころに のりにけるかも |
| 巻第二 100 相聞 久米禅師 |
〔語義〕
「あづまひとの」には「あづまと」の訓もある・東国の人
「のさきのはこ」、「のさき」は「荷前」とも書き、毎年地方から朝廷に奉る貢物で「初穂」のことをいう
「篋」は、『和名類聚抄』に「波古」の訓がある
「にのをにも」は、荷物を括る紐のように |
〔歌意〕
東人が運ぶ荷物の箱を括る紐のように、
あなたのことが、片時も私の心から離れない |
| |
| 寄物陳思 |
| 是川 瀬々敷浪 布々 妹心 乗在鴨 |
| 宇治川の瀬々のしき波しくしくに妹は心に乗りにけるかも |
| うぢかはの せぜのしきなみ しくしくに いもはこころに のりにけるかも |
| (以前一百四十九首柿本朝臣人麻呂之歌集出) |
| 巻第十一 2431 寄物陳思 柿本人麻呂歌集 |
〔語義〕
「是」が、何故「うぢ」になるか、どの注釈書でも、「氏」と「同音」相通とある
そして、この「氏」が、日本語の同音「宇治」に当てられた、としている
「是」と「氏」が、同音相通とは?
漢和辞典で調べてみたら、「是」には「し」とも訓があった
つまり、この「し」が、「氏」のことなのだろう...そして「宇治」なのか
以前にも、この「是川」と「宇治川」を調べたことがあったが、
こうして何度も同じ事を繰り返し確認していくと、覚えやすい
「しきなみ」は、繰り返して寄せる波
「しくしくに」は、しきりに |
〔歌意〕
宇治川の瀬々の繰り返し寄せる波のように、
しきりに、そして次第に大きく、
あの娘は、私の心の中を占めてしまった |
| |
| 寄物陳思 |
| 大船尓 葦荷苅積 四美見似裳 妹心尓 乗来鴨 |
| 大船に葦荷刈り積みしみみにも妹は心に乗りにけるかも |
| おほぶねに あしにかりつみ しみみにも いもはこころに のりにけるかも |
| 巻第十一 2758 寄物陳思 作者不詳 |
〔語義〕
「あしにかりつみ」は、葦を刈り取って船に積み載せ...ここまでが「しみみに」の序
「しみみに」は、隙間もなく一杯に |
〔歌意〕
大船に、葦荷を隙間もないほど積むように、
あの娘は、私の心にずっしりと乗りかかってきた |
| |
| 寄物陳思 |
| 驛路尓 引舟渡 直乗尓 妹情尓 乗来鴨 |
| 駅路に引き舟渡し直乗りに妹は心に乗りにけるかも |
| はゆまぢに ひきふねわたし ただのりに いもはこころに のりにけるかも |
| 巻第十一 2759 寄物陳思 作者不詳 |
〔語義〕
「はゆま」は、「早馬(はやうま)」の約、『新全集』の補注では、
[律令制の確立に伴い、中央と諸国とを結ぶ幹線道路が必要となり、山陽道をはじめとする大・中・小各路が開かれ、その道々に約三十里(後世の五里)ごとに駅が設けられた。その駅には官吏の乗用にあてるため駅馬が飼われていた。ただしここは、河川を上下する舟の発着場を兼ねた水駅をさす。水駅は水路の舟行が長い中国大陸では重要だが、日本ではほとんど実用されなかった、とする説がある]という
「ひきふねわたし」は、この歌の歌意からすれば、川の両岸を綱を張って横断する渡し舟のようなもの、と思われる
「ただのり」の「ただ」は、じかに・まっすぐ、などの意味する副詞で、その渡しの「綱」のように、不可欠なことの喩えだろう、と思う
|
〔歌意〕
水駅の渡し場で、舟を引く大切な綱のように、
あの娘は、もう私の心から離れることもなく... |
| |
| 羇旅發思 |
| 射去為 海部之楫音 湯按干 妹心 乗来鴨 |
| 漁りする海人の楫音ゆくらかに妹は心に乗りにけるかも |
| いざりする あまのかぢおと ゆくらかに いもはこころに のりにけるかも |
| 巻第十二 3188 羇旅發思 作者不詳 |
〔語義〕
「いざり」は、漁のこと
「あまのかぢおと」は、操業中の梶のたてる音
「ゆくらかに」は、ゆらゆらと揺れ動く様・心の落ち着かない様 |
〔歌意〕
漁をする海人の梶の音が、ゆっくりと止むこともなく揺れるように
私の心にもあの娘が、沁み込んできた |
この「いもはこころに のりにけるかも」の歌は、どれもその比喩が伴っている
そして、その比喩を競うように...
勿論、それぞれの作者が他と競った訳ではないだろうが、
この語句を拾い出すと、同じようなパターンで、あたかも競い合ったような感じになる
「俺をすっかり虜にさせてしまったあの娘は」との「詠題」があったかのようだ
その深さを、それぞれが競い合う...まあ、そんなことはないだろうが
僅か六首の同句の用例で、どれも同じような詠い方であれば
この想いも、そう遠くはないと思う
「荷物の箱を括る紐」
「瀬々の繰り返し寄せる波」
「葦荷を隙間もないほど積む」
「舟を引く大切な綱」
「ゆっくりと止むこともなく揺れる」
そして、掲題歌の「枝垂れ柳のとをを」...
俺の心を、どんなに夢中にさせているか、
私ならどんな表現、譬をするだろう...いや、もう遠い昔の話だ、沸き起こりもしない |
| |
|
|
| 【歌意1901】 |
春になると、草むらに隠れ潜む百舌のように
たとえ姿は見えなくても、
わたしは眺めていよう...いとしいあなたの辺りを...
|
もず、という鳥は、いろんな説明を読んでみると
あまり愛嬌を感じないような書き方がしてある
そんな「鳥」を、比喩に使うのは、「もずの草ぐき」という行動の表現なのだろうか
秋から冬にかけ、人里近く現れて高い木に止り鋭く鳴き立てる鳥...
春先になると、山中へ移動するが、五月頃まで平地に残っているものは
その草原や潅木の間にいて、鳴くことも稀だ、とある
確かに、あそこにあの人がいる
ついこの前までは、あの人があそこにいた...
季節は移り変わって、もうあの人の姿も見ることは叶わない
しかし...私は、ずっと見ていたい
「もずの草ぐき」のように、見えなくても、あなたがいるのだから...
「もず」という印象から、妙な感じ方をしてしまった
その「あなた」というのは、本来は「近づいて」はいけない人なのかもしれない
だから、「もずの草ぐき」のように、見えないからこそ
私は、ずっと遠方からでも...あなたを見ていたい、と
さて、もう一つの「春之在者」(はるしあれば)かな
| 夏相聞 寄鳥 |
| 春之在者 酢軽成野之 霍公鳥 保等穂跡妹尓 不相来尓家里 |
| 春さればすがるなす野の霍公鳥ほとほと妹に逢はず来にけり |
| はるされば すがるなすのの ほととぎす ほとほといもに あはずきにけり |
| 巻第十 1983 夏相聞 寄鳥 作者不詳 |
〔語義〕
「すがる」は、蜂類の総称、主としてジガバチ類と、ベッコウバチ類をさすらしい
腰が細いところから、美しい女の形容の比喩に用いられたりしている
「なすのの」の解釈には、その幅が広い
「ほとほと」は、あやうく、もう少しで~するところであった、の意
|
〔歌意〕
春になると、「すがる」が飛び交い、「なすの」野にその音が満ちる
ほととぎすよ、おまえの名のように、「ほとほと」本当にあやうく
あの娘に逢わずに来てしまうところだった |
この歌、何故あやうく逢えずに来てしまうところだった、と詠うのか
その事情を伺うことができない
それに、「すがる」の飛び交う「野」のほととぎす、
この情況も、絡みつくこともない
唯一「ほとほと」「あはずきにけり」が、この歌のメッセージだとは解るが
その「ほとほと」を導く「ほととぎす」だとの説明が多い
でも、歌意としての「場面」が遮断されてしまうような「序」に、人は心を響かせるだろうか
音では繋がっても、場面を想い起こすのに、「なすの」「すがる」「ほととぎす」が...
「春之在者」の訓が「はるされば」で、僅か『万葉集』中の二首として選んだが
そもそも、初夏に渡来し、秋に南方へ去る「ほととぎす」を、「春之在者」というのも...
この二首で詠われる「もず」と「ほととぎす」
本来は、春には「見ることのない」鳥たちではないか
もずは「草潜き」、ほととぎすは、まだ「飛来していない」
そこに、二例しか使われていない表記「春之在者」
何となく、これに意味がありそうな気もするが...
ふと思いつくのだが、「はるしあれば」の「し」
これは「強意」を示し、語調を整える副助詞だ
「強意」...「春」を意識させている
「春なんだよ、今は」とでも言うように...
だから、秋から冬にかけて平地で鳴く「もず」も見えない
「ほととぎす」は、まだやって来ないはずなのに、もう来ている
だから、あやうくあの娘に逢えないところだったのに、お前のお陰で、逢えたのか、と
こんな風に感じれば、字余りであっても「はるしあれば」と詠いたくなる
そして、どちらも「寄鳥」で詠いながら、その季節感に異があるからこそ
「強意」の副助詞「し」がどうしても必要になるのではないだろうか
そうすると、「はるしあれば」こそ、作者と共に歌を響かせることができそうだ
|
| 【注記】 |
| [なすのの] |
この原文「成野之」の「成」は、その訓において「なる」「なす」と二種類あり
さらに、解釈においては、四種類ある
| 原文「成」と語意、訓「なる・なす」 |
|
| 動詞「鳴く・鳴らす」 鳴く |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕
『日本古典文学全集』〔小学館、昭和50年成〕
|
| 推定の助動詞「なり」~のようだ |
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕
『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕
『万葉集総釈』〔楽浪書院、昭和10~11年成〕
『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕 |
| 動詞「生(な)る」 生れる・生み育てる |
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕
『万葉集』〔伊藤博校注、角川文庫、平成10年18版〕
|
| 地名「那須」 |
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
『代匠記』
「成ハ鳴ニ借テ書ケリ-略-以翼鳴者ト云類ナレハ、ナルト云ヘリ」の朱書
『私注』
「ナルは、生まれ出る、実際は冬ごもりから出るのにしても、その飛びまはるのをかう見たのであらう」
『窪田評釈』(『全註釈・古典全集』も同じ)
「『なす』は、鳴らすの古語。-略-ここは羽を鳴らす意」
『古義』
「霍公鳥の春のころ巣立て鳴声は、かのスガルに似たる故にスガル如(ナス)霍公鳥といふ意につづきたるか」
『全釈』
「似我蜂のやうに痩せてゐる郭公の意であらう」
『古典集成』(角川文庫も倣う)
「なす、生じさせる。ここは、生み育てる、の意」
『注釈』
「『すがる』までを『なす』の序と見る。-略-さてその『成野』はどこであるか、といふ問題はなほ考へるべきところだと思ふが、私は下野国那須郡、那須嶽の麓、那須の湯の南に開けてゐる那須野ではないかと思ふ」
以上のように、これほどの解釈の相違があれば、
専門的な考察など、私には及びもつかない
ならば、素直に感じたままで、歌を読むしかないだろう
|
|
掲載日:2014.02.02.
| 春相聞 寄鳥 |
| 春之在者 伯勞鳥之草具吉 雖不所見 吾者見将遣 君之當乎婆 |
| 春さればもずの草ぐき見えずとも我れは見やらむ君があたりをば |
| はるされば もずのくさぐき みえずとも われはみやらむ きみがあたりをば |
| 巻第十 1901 春相聞 寄鳥 作者不詳 |
【左頁・春之在者】〔1983〕
| 【1901】語義 |
意味・活用・接続 |
| はるされば[春之在者] 春になると・春になったので |
| もずのくさぐき[伯勞鳥之草具吉] |
| もず[鵙・百舌] |
[鳥の名]秋に高い木に止って鋭く鳴く |
| ぐき[漏(く)く・潜(く)く] |
[自カ四・連用形]漏れる・間をくぐる |
| みえずとも[雖不所見] |
| とも[接続助詞] |
[逆接の仮定条件]たとえ~しても |
連用形につく |
| われはみやらむ[吾者見将遣] |
| みやら[見遣る] |
[他ラ四・未然形]遠くを望み見る・目を向ける |
| む[助動詞・む] |
[推量(意志)・終止形]~よう・~つもりだ |
未然形につく |
| きみがあたりをば[君之當乎婆] |
| をば |
格助詞「を」の働きを強調し、動作・作用の対象を強く示す |
| 〔接続〕体言、活用語の連体形につく〔成立〕格助詞「を」+係助詞「は」(「は」の濁音化) |
| 〔格助詞「を」は、動作の対象を示す、「~を」〕 |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [はるされば(春之在者)] |
この原文「春之在者」の訓、ちょっと興味があって調べてみた
そもそも、「はるされば」とする「訓」は、『万葉集』中二十六首ある
その原文で、最も多く使われているのが、「春去者」の十五首
以下に書き出すと、
「春去」、二首
「春避者」、一首(長歌)
「春去婆」、一首(長歌)
「春佐礼播」、一首(長歌)
「波流左礼婆」、一首(長歌)
「波流佐礼婆」、三首(内二首は「梅花三十二首」の宴)
そして、掲題歌の表記「春之在者」が二首
今日の「春之在者」以外は、「はるされば」と訓む他にはないだろう
勿論、昨日書いたように「はるさらば」とも訓み得る表記はある
万葉仮名表記以外は、どれもそうだろう
その場合は、他の語句との整合性で、歌意に矛盾が生じないかが手掛かりになる
ちなみに、未然形接続の「はるさらば」となれば、五首の例があり、
その表記も、「春去者」、「春去」がそれぞれ一首
他の三首は、いずれも万葉仮名で「佐良」の表記なので、間違いはない
すると、この「はるされば」で異訓が生じ得るのは、掲題歌を含めた「春之在者」
この二首が可能性としてはある
実際に、『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕では
この「春之在者」に、二首とも「はるしあれば」と「訓」をつけている
その理由は、『全註釈』を今度、明日香で調べるまで私には解らないが
当然、諸本あるいは注釈書の根拠があるはずだ
もっとも、この学者にとって「春之在者」の表記は、「はるしあれば」が当然だ、
ということなのだろうが、
初句の字余りを無視してでもそう訓じたい、というのは...
それに、それが他の書では見られないのは、どうしてなのだろう
また、「はるしあれば」と詠う歌は、『万葉集』にはない
「はるしあれば」の訓で、語を解釈すると
「し」は、強意を表する副助詞になるだろう
そして、「あれば」はラ変動詞「在り・有り」の已然形だ
「ば」は已然形に接続する接続助詞で、順接の確定条件
そうなると、定訓になっている「はるされば」と、解釈上は変わらない
ただ、「春」を強調する訓になるかどうか、そして、その語が入ることで、
「歌」としての「語調」はどうなのか、と言うことだろう
しかし、一番大きな違いもまた見逃せない
確かに、「大意」としては同じようなものでも、
「去る」と「在り」とはその個々の意味はかなり違う
これを踏まえて、この歌は訳すべきだと思う
字余りを極力避ける姿勢と、原文の表記を出来るだけ生かしたい...
そんな問題ではないとは思うが...それでしか、違いを付けられない
左頁に、「春之在者」のもう一つの歌を載せる
訓は、定訓に従うが、この表記の「二首」として、同時に味わってみたい |
| |
| [もず] |
「もず」は、秋から冬にかけて平地に姿を現し、鋭く鳴く
春夏は山中に移動し、雑木の繁みに巣を営む
「もずの早贄(はやにえ)」という語があるが、
捕獲した小動物を、木の枝などに刺して蓄える習性からきているらしい
『日本書紀』「仁徳天皇六十七年十月十八日条」に、
天皇の寿陵を築造する役民の中に、突然鹿が走り込んできて倒れ死んだのを、
怪しんで調べたところ、もずが耳から飛び去り、その耳の中を覗いて見ると、
その肉がもずに喰い裂かれていたという「百舌野耳原陵」の名の由来を伝えている |
| |
| [「とも」の接続] |
動詞・形容動詞・助動詞(動詞・形容動詞型活用)の終止形につくが、
形容詞・助動詞(形容詞型活用、それに打消の助動詞「ず」)の連用形につく
奈良時代の文献に特例が見られる
上一段動詞「見る」に接続する場合、
「終日(ひねもす)に見とも飽くべき浦にあらなくに」(万葉集巻第十八4061)のように、
「見とも」の形が表れる
これは、「見べし」「見らむ」の用例とともに、
動詞「見る」の接続の古い形を残したものといわれる
|
| |
|

|
| 【歌意1902】 |
かほ鳥が、しきりに止むこともなく鳴く春野
そこには、草もかなり生い茂ってびっしりと...
そのように絶える間もない「孤悲」をしているのだなあ
|
「こひもするかも」には、その情況によって、いろいろと感じることもできる
詠嘆には間違いないことだが、歓びに近いものなのか
あるいは、悲歎のくれる「孤悲」なのか...
ただ、『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕の解釈は、私には違和感がある
「かほ鳥の 絶え間なく鳴く 春の野の 草のように絶え間ない 恋さえもすることよ」
この係助詞「も」を、言外暗示「~さえも・~でも」として解釈している
「言外暗示」は、古語辞典では、程度の軽いものをあげて言外の重いものを暗に示す、とある
その通りに受止めるとすると、
かほ鳥がしきりに鳴くこと、草が隙間もなく生い茂る、
それにもまして「恋する」この気持ちが納まらない、とでもなってしまう
かほ鳥の絶え間もない鳴き声や、見事に生い茂った草根は、決して「軽い」ものではなく
同じように、それほど「私の想い」もまた、「止むことがない」となるはずだ
係助詞「も」のもともと意味である「添加」こそ、相応しいと思う
「そのように、私の恋もまた絶えることがない」
そして、本題に入れば、この作者は「歓嘆」だろうか、それとも「悲嘆」を詠うのか
いや、私にはどう沁み込んできたのだろうか
しきりに鳴く、ことは想いが募って決して止ることもない、と直感的に思う
しかし、「くさねのしげき」となると、その情景は、決して「明るい」ものじゃない
草根が、地中に根を張ることの意味を含み、
さらに「繁し」には、程度の甚だしいことから「わずらわしい」という意味もある
これが、この歌に用いられているということは
作者自身は、こんなに恋に苦しんでしまったことを「嘆いている」ように思える
何も、作者の想いを第一義として詮索することが目的ではなく
それがはっきり可能性のあるものならともかく、不明なものであれば
その歌は、自分にどう響いてくるのだろう、と
それが、若い頃には「古典」に背を向けていた私の、今の精一杯の接し方だ
この歌に、私がどうしても「孤悲」という文字を使いたくなるのは...
あの娘に、想いが届いていないのかもしれない
しかし、そんなことはどうでもいい
この想いは、いっときも止むことなく...
|

|
掲載日:2014.02.03.
| 春相聞 寄鳥 |
| 容鳥之 間無數鳴 春野之 草根乃繁 戀毛為鴨 |
| 貌鳥の間なくしば鳴く春の野の草根の繁き恋もするかも |
| かほどりの まなくしばなく はるののの くさねのしげき こひもするかも |
| 巻第十 1902 春相聞 寄鳥 作者不詳 |
| 【1902】語義 |
意味・活用・接続 |
| かほどりの[容鳥之] 既出〔書庫-13〕 |
| まなくしばなく[間無數鳴] |
| まなく[間無し] |
[形ク・連用形]絶え間がない・隙間がない・暇がない |
| しばなく[屡鳴く] |
[自カ四・連体形]しきりに鳴く |
| 「屡(しば)」は副詞で、しばしば・たびたび・しきりに、の意 |
| はるののの[春野之] 春の野の |
| くさねのしげき[草根乃繁] |
| くさね[草根] |
草のこと、地中に根を張っているので、草根という |
| しげき[繁し] |
[形ク・連体形]量が多い・しきりである・わずらわしい |
| こひもするかも[戀毛為鴨] |
| かも[終助詞] |
[詠嘆・感動]~であることよ 〔接続〕体言、連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [しばなく] |
この副詞「しば」が動詞について、「しきりに」や「しばしば」などの意味で修飾するが
古語辞典で、「しば鳴く」という語(動詞)があるように、
他にも、古語辞典の同じ頁に、「しば叩(たた)く」「しば立(た)つ」という動詞があった
副詞が動詞に付くような、一般的な形ではなく、一つの語として成り立っており
その語義も、単純に「副詞」としての意味を用いるだけではなく、
おそらく、その原義からの派生する新たな「語」となったような感じだ
たとえば、「しば叩(たた)く」は、副詞「しば」と動詞「叩く」とすれば
「叩く」の意味は、「水鶏(くいな、水鳥の名)が、戸を叩くような声で鳴く」の他、
「打って音を立てる・門戸を叩いて来訪を告げる・なぐる・ぶつ」なので、
「副詞+動詞」で、「しきりに打って音を立てる・しきりになぐる」程度の訳になる
しかし、他動詞カ行四段「しば叩く」の一語だと、
「しきりに瞬きをする・目をぱちぱちさせる」など、苦しみの表情を意味することが多い
勿論、「叩く」ことを繰り返しされれば、そんな意味にまで容易に想像はつくが...
「しば立つ」にしても、副詞「しば」と、数多くの意味のある動詞「立つ」では
その中の「音が高く響く」や、「波が立つ」などの意味に限定されている
自動詞タ行四段「しば立つ」は、「音が絶えず響く・波などがしきりに立つ」
もっとも、コンパクトな古語辞典という容量の制限のためかもしれない
本来は、もっと動詞の原義に対応した語義も載せられるのかもしれないが...
とにかく、何も一語にしなくても、と思ったものだが
それで、語義に変化があるものなら、当然のことだろう
ついでに言うと、「しば見る」という動詞もある
しかし、これは単純に「副詞+動詞」の関係で、新たな一語と言うのも首を捻る |
| |
| [こひもするかも] |
結句「こひもするかも」の用例は、『万葉集』中で、掲題歌を含めて七首
どれも同じような詠い方で、上の三、四句で「恋」を比喩する「序」になっている
| 結句「こひもするかも」 |
|
| 高座の御笠の山に鳴く鳥の止めば継がるる恋もするかも〔書庫-13〕 |
3-376 |
| をみなへし佐紀沢に生ふる花かつみかつても知らぬ恋もするかも〔書庫-6〕 |
4-678 |
| 言に出でて云はばゆゆしみ朝顔の穂には咲き出ぬ恋もするかも |
10-2279 |
| この山の嶺に近しと我が見つる月の空なる恋もするかも |
11-2680 |
| 君が着る御笠の山に居る雲の立てば継がるる恋もするかも |
11-2683 |
| 庭清み沖へ漕ぎ出る海人舟の楫取る間なき恋もするかも |
11-2756 |
この掲題歌も、かほ鳥が絶え間なく鳴くことと、
春の野に草が生い茂るさまを、作者の止むこともなく溢れる「想い」を籠めている
ちなみに、先日来少し引き始めた「古今六帖」にも、この歌は載っている
| かほとりの まなくしはなく はるののの くさねのしけき こひもするかな |
| 古今六帖第六 鳥 4486 |
先日も少し書いたが、平安時代、十世紀中頃、
その頃には、すでに『万葉集』は,
非常に読み辛い、あるいは読めない「和歌」となっており
梨壺の五人による、「訓読作業」が行われ、初めて『万葉集』に訓が点けられた
その頃の成立だろうと言われている「古今六帖」もまた、『古今集』や『後撰集』など
さらに、『万葉集』からは千首以上が載せられ、まさにその当時の万葉歌が、
どのように読まれていたのか、の手掛かりとも言われているが
それでも、現代に繋がる「訓」との違いもまた多い
私も、当初は「伝本」の相違からくるものだろう、と思っていたが
この歌の原文を見たとき、「戀毛為鴨」の「鴨」が、
どうして「かな」になるのだろう、「鴨」は、間違いなく「かも」だ、と思った
ならば、「古今六帖」の編者が、意図的に訓を変えたのだろうか
もしそうであれば、万葉歌から二百年を経て、その頃の「歌」の感覚から
「こうあるべきだ」という意味での「改訓」なのだろうか
それでは、やり過ぎだとは思うが、もう少し甘く考えれば
この時点で、原文が「鴨」ではない、また別の「伝本」(古写本)があったのかもしれない
「かも」は上代に使われた終助詞で、
「かな」は中古以降の、詠嘆の意味合いの強い終助詞だ
確かに、原文は「鴨」であっても、
あたかも翻訳するかのように「かな」と訓だのかもしれない |
| |
|
|
| 【歌意1903】 |
春になるといつもの長雨のせいで、
すっかり花も朽ちてしまった
昔、わたしが越えた、あの娘の家の垣根も
今はすっかり荒れてしまったなあ
|
作者が今佇むところは、かつていとしい人が住んでいた家
垣根の隙間から、何度も何度も通ったものだ
その家も、今は誰も住んではいない
長い間のこととて、雨風に晒され、
その垣根も、今はこんなに荒れ果ててしまっている
作者の往時の回想を詠ったものだと思う
「寄花」とあるからには、やはり「卯の花」に何か「想い入れ」があるはず
しかし、単純に「卯の花」をこの歌で解せば、「うのはなぐたし」
卯の花を腐らせてしまった...
こんな「寄花」を詠うだろうか
卯の花の開花は夏
そこから、「はるさればうのはな」と詠うのはおかしい、と多くの諸中では書かれているが
「卯の花」が「象徴」であれば、そして、それが「はるされば」に見合うものであれば
誰も異は唱えまい
古語辞典にあるように「うのはなくたし」が、一つの成語として使われたとしたら
「はるされば」に合わないこともない
しかし、「音」あるいは「訓」で「うのはな」を「はるされば」に続けるのは、
やはり「卯の花」は、「象徴」にしても、きっと意味があるはずだ
通説のように、垣間を何度も越えて傷めたことが主題であれば、何も「卯の花」でなくてもいい
それこそ「はるされば」に見合う「花」でいい
他に手掛かりを求めて、「くたす」を用いる残りの二首を見る
| (「老身重病經年辛苦及思兒等歌七首 [長一首短六首]」反歌) |
| 富人能 家能子等能 伎留身奈美 久多志須都良牟 キヌ綿良波母 |
| 富人の家の子どもの着る身なみ腐し捨つらむ絹綿らはも |
| とみひとの いへのこどもの きるみなみ くたしすつらむ きぬわたらはも |
| 巻第五 905 反歌 山上臣憶良 |
〔語義〕
「とみひと」、「とみ」が「豊かな財産・金持ち」なので、「金持ちの人」
「きるみなみ」の「みなみ」は「身無し」のことで、
「なみ」は「無し」の語幹「な」と、理由・原因の意の接尾語「み」
従って、「着る体がなくて(たりなくて)」となる
「くたしすつらむ」は「くたす」の連用形に、下二段「捨つ・棄つ」の終止形、
それに、現在推量の助動詞「らむ」の終止形
「きぬわた」は、「絹や綿」
「ら」は、複数の意を表す接尾語
「はも」は、上代語で、文末に用いた場合は、
回想や愛惜の気持ちを込めた感嘆の意を表し、「~よ・~なあ」 |
〔歌意〕
金持ちの家の子供たちが、衣類ばかりが多く、着る体が足りないので
腐らせて捨てていることだろう、絹よ綿よ、ああ |
| |
| 霖雨晴日作歌一首 |
| 宇能花乎 令腐霖雨之 始水邇 縁木積成 将因兒毛我母 |
| 卯の花を腐す長雨の始水に寄る木屑なす寄らむ子もがも |
| うのはなを くたすながめの みづはなに よるこつみなす よらむこもがも |
| (右二首五月) |
| 巻第十九 4241 霖雨晴日作歌 大伴宿禰家持 |
〔語義〕
「ながめ」は、「霖雨、長く雨が降り続くこと」をいう
「みづはな」は、「はなみづ」とも訓まれ、定訓がない
「始水」の語義は、出水の先端をいう
「はな」は、先頭・先端の意
「に」は原因・理由の格助詞「に」で、「~により・~によって」
「こつみ」は、木の屑、あくた、の類で、おびただしい推量のたとえ
「なす」は、上代の接尾語で、名詞につき、「~のように・~のような」の意
「よらむ」は、寄って来る・好意を寄せる意の四段「寄る」の未然形「よら」に、
推量の助動詞「む」の連体形「む」
「もがも」は、上代の終助詞で、終助詞「もが」に終助詞「も」がついたもの
願望の意を表す、「~があったらなあ・~であったらなあ」
|
〔歌意〕
卯の花を腐らすほどの五月の長雨で、
その「みづはな」に集まってくるごみのように、
私の周りに寄ってくるこは、いないのかなあ |
『万葉集』で「くたす」として使われている歌三首(含む掲題歌)での、「くたす」は
ここで私が知りたかった、『万葉集』で使われる「くたす」が、
原義「腐らせる」を離れて「傷める」の意が使われているかどうか
〔905〕では、金持ちの家の子どもたちの家では、あり余るほどの着物も
結局は使い切れずに、「腐れさせて」棄てる、ということであり
それは、放っておく、ともいえることだ
何も、使わないからといって、切り裂いたりなどの「傷める」行為ではないはずだ
そして、〔4241〕は、これは掲題歌に通じるものだが
しかし、この場合の表現が「うのはなをくたすながめ」とあるのは
「うのはなくたし」という一つの成語を、少々言い換えたものだと思う
基本的には、この歌は掲題歌と同じ用法で「くたす」を用いており
長雨による「傷め付けられ」た「卯の花」ではなく、
長雨そのもので「みづはなによるこつみなす」のような場面を起こし、
「くたす」単独での意味はなさない
唯一「うのはなくたし」として、この長雨(霖雨)を導いている
だとすれば、この成語「うのはなくたし」が使われているこの掲題歌は
作者が垣根を越えた為に「傷めた卯の花」ではなく、
それほどの長い雨、長い歳月を「象徴」しているものだと思う
「くたし」を、「傷める」と解する注釈書はどれも、その「歌意」に「雨」が出てこない
「傷める」と解釈したからには、それが「雨による」ものではなく、
垣根を越えて何度も出入りした故に、としか訳せないのだろうなあ、きっと |
| |
| 【注記】 |
| [ながめ] |
家持が赴任した越中での「卯の花」の盛りは関西より約半月遅いという
太陽暦の六月十日前後から、二十日頃までの間のことを言う
『新全集』は左注に「五月」とあることから、太陽暦で六月二十日に当たる旧暦の五月八日
その数日後の作だろうとしている
「霖雨(ながめ)」によって、卯の花が腐るほどに、と解し、必然としてその盛りを過ぎた頃か |
| |
| [なす] |
接尾語とする「なす」の例語は、以下の通りであり、稀に動詞の連体形につく
| 朝日なす |
蜾蠃(すがる)なす |
真珠(またま)なす |
| 巖(いはほ)なす |
着くなす(着くように) |
水鴨(みかも)なす |
| 垣穂(かきほ)なす |
翼なす |
水沫(みなわ)なす |
| 木屑(こづみ)なす |
常磐(ときは)なす |
雪なす |
| 獣(しし)なす |
錦(にしき)なす |
行くなす |
尚、枕詞と見られる以下の語「なす」も、同類と考えられる
| 馬酔木(あしび)なす |
鏡なす |
玉藻(たまも)なす |
| 入り日なす |
雲居(くもゐ)なす |
泣く子(なくこ)なす |
| 鶉(うづら)なす |
五月蝿(さばへ)なす |
闇夜(やみよ)なす |
| 績(う)み麻(を)なす |
|
さらに、動詞の連用形につく場合は、「ことさら~・特に~・いかにも~であるように~」の意
| 負ひなす |
聞きなす |
取りなす |
| 思ひなす |
着なす |
吹きなす |
| 書きなす |
為(し)なす |
見なす |
| 語りなす |
作りなす |
|
|
| |
|
掲載日:2014.02.04.
| 春相聞 寄花 |
| 春去者 宇乃花具多思 吾越之 妹我垣間者 荒来鴨 |
| 春されば卯の花ぐたし我が越えし妹が垣間は荒れにけるかも |
| はるされば うのはなぐたし わがこえし いもがかきまは あれにけるかも |
| 巻第十 1903 春相聞 寄花 作者不詳 |
【注記「くたし」左頁】〔905・4241〕
| 【1903】語義 |
意味・活用・接続 |
| はるされば[春去者] 春になると |
| うのはなぐたし[宇乃花具多思] |
| うのはな[卯の花] |
[別名うつぎ・(雪見草)]ユキノシタ科の落葉低木 |
| ぐたし[腐(くた)す] |
[他サ四・連用形]腐らせる・非難する・気落ちさせる |
| わがこえし[吾越之] |
| こえ[越ゆ] |
[自ヤ下二・連用形](ある場所・障害物などを)越える |
| し[助動詞・き] |
[過去・連体形](過去に直接経験した事実)~た・~ていた |
| |
〔接続〕連用形につく |
| いもがかきまは[妹我垣間者] |
| かきま[垣間] |
垣の隙間〔垣間(かいま・かきま)見る〕の様にも使われる |
| あれにけるかも[荒来鴨] |
| あれ[荒(あ)る] |
[自ラ下二・連用形]荒廃する・すたれる |
| に[助動詞・ぬ] |
[過去・連用形]~た・~てしまった |
連用形につく |
| ける[助動詞・けり] |
[過去(詠嘆)・連体形]~たなあ・~たのだ |
連用形につく |
| かも[終助詞] |
[感嘆]~であることよ〔接続〕体言、活用語の連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [うのはなぐたし] |
古語辞典に「うのはなくたし(卯の花腐し)」と、載っている
その意味は、長く降り続いて卯の花を腐らす意から「五月雨の異称」とある
では、五月雨は、というと、「陰暦五月頃、季語は夏、長雨・梅雨」とある
この歌で大きく分かれる解釈は、この「うのはなぐたし」を、
その一語として解釈するか、もしくは「卯の花」、「くたし」をそれぞれ解釈するか
それで歌の解釈が違う
多くの諸注で解釈されているのが、「卯の花」、「くだし」の直截的な解釈だ
その場合、「くたし」は腐らせる、という意味ではなく、
「損ねる・傷める」の意味になる
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕の補注で、次のような説明をしている
「くたす」は、「他動詞四段」で、「腐らせる・朽ちさせる」などの意があるが
補注によると、「自動詞上二段・朽(く)つ」の「他動詞形」とある
確かに、「朽つ」には「腐る・朽ちる・廃れる・衰える」などの意がある
だから、「くたす」がその他動詞だということは解る
現代でも、「朽ちる」といえば「朽ち果てる」というように、腐り廃れることだ
そこに「傷める」ような意味合いは、なかなか浮ばない
なのに、そこまで説明しておきながら、この『大系』では大方の注釈書と同じように
「卯の花をいためて」として歌意にしている
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕でも、
「くたす」は、腐らせることと、その「補注」にいいながら、やはり歌意は岩波と同じだ
さらに言えば、私が日頃手放すことのない『全注』にしてもそうだ
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕など、どれもまた
「くたす」を「腐らせる」意と説明しながらも、歌意では「傷める」とする
私は、『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕を開いたとき
その「うのはなくたし」の解釈の仕方が、もっともしっくりきた
この『講談社版』では、「腐らせる」意の「くたし」だとし、
「損ねる」ではない、としている
それだと、「うのはなくたし」が、五月雨の異称、長雨により腐れ朽ちた歌意になる
自分が垣根を越えて踏み荒し、傷めた卯の花ではない
卯の花が朽ち果てていることと、垣根を越えることとは、繋がっていないはずだ
「うのはなくたし」で、長年の歳月を想い、「わがこえしいもがかきね」は
その歳月の、その原点を回想している
この「くたす」を用いた万葉歌は掲題歌以外では二首ある
それを左頁に載せる |
| |
| [うのはな] |
五、六月頃、円錐花序を出して多くの白い五弁花を開く
幹が中空なので「うつぎ」といい、
「うのはな」は「うつぎのはな」の略された名と言われている
「うのはな」は、そもそも開花が「夏」であることから、
「はるさればうのはな」というのはおかしい、と
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕で
「妹カ家ノ卯花垣ヲ、度々我越シカハ、莟メル花ノソコナハレテ朽ルヲ云ヘリ」
と書かれ、さらには、
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕で「梅」の誤りだとか
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕では、本居宣長説を引用し、
「四月頃までも大やうに春といふぞ古意なる」と書く
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕でも、
「季節を厳密にいわずに春のものと見たのだろう」としている
しかし、一昨日の歌〔1983〕のように、「はるされば」の歌に「ほととぎす」もある
まだ飛来していないはずの「ほととぎす」
「部立て」に、あまり「厳格さ」がないのは感じているが
「歌」の中での「いい加減な季節感」は、ないと思う
だから、この「はるさればうのはな」も、その視点から感じたいものだ
|
| |
|


|
| 【歌意1904】 |
梅の花が咲き、そして散るあの庭園に
わたしは行こう
あなたが寄こす使者を、とても待ち切れなくて...
|
結句の「かたまちがてり」が、この歌の方向を決めるとすれば
この歌、もう結論は出ている、と私は思う
「がてり」の語義は、右の「語義」の表にも載せたが
これは、あくまで通常の「語義」であり、そのままこの歌を訳せば、
私にとって、とても味気ない歌に感じられてしまう
かといって、大胆な意訳など、そんな能力もない私が
手持ちの限られた注釈書ではあるが、その中に手掛かりを得られれば
もうそこから、私の「フリーハンド」だ
「がてり」の古語辞典通りの訳に従うなら、多くの注釈書が書くように
「使者をひたすら待ちながら、梅の花の咲き散る園へ行こう」となる
それでは、矛盾してしまう
「ひたすら待ちながら」と「われゆかむ」の「私は行こう」という意志には
直訳はともかく、歌を「心のことば」として感じるのであれば
「ひたすら待っていたのに、もう待ち切れなくて」、だから「私は行く」となるはずだ
さて、この歌には、もう一つ気にかかることがある
それは、「小異歌」と言われ、たった一文字だけが違う歌がある
| (于時期之明日将遊覧布勢水海仍述懐各作歌) |
| 宇梅能波奈 佐伎知流曽能尓 和礼由可牟 伎美我都可比乎 可多麻知我底良 |
| 梅の花咲き散る園に我れ行かむ君が使を片待ちがてら |
| うめのはな さきちるそのに われゆかむ きみがつかひを かたまちがてら |
| (右五首田邊史福麻呂 / 前件十首歌者廿四日宴作之 ) |
| 巻第十八 4065 宴席歌 田辺史福麻呂 |
〔語義〕
「がてら」は、上代の頻度では「がてり」が多く、その意味はほとんど同じとされる |
したがって、歌意もこの歌を〔1904〕の「小異歌」とすべての注釈書でいう以上、
まったく同じように訳されている
以前にも書いたが、原文の表記は同じ歌であっても、詠み継がれていくうちに
その使われる漢字は同じものとは限らず、
万葉仮名表記の歌が併行してあって、初めて、訓み下せることもあったようだ
この歌など、その例の一つだと思う
| 梅花 咲散苑尓 吾将去 君之使乎 片待香花光 |
1904 |
| 宇梅能波奈 佐伎知流曽能尓 和礼由可牟 伎美我都可比乎 可多麻知我底良 |
4065 |
もっとも、〔1904〕が難訓とは言われないし、その異訓もないので
〔4065〕歌がなくても支障はなかっただろうが
このように、仮に「難訓」とされるような歌があった場合、
どこからか...たとえば、訓点作業の部屋にうず高く積まれている木簡などから
それと同じ歌だと思われる「万葉仮名」表記の木簡が現れたとき
その作業に当たっている学者たちの歓喜は想像に難くないものだ
なるほど、この歌は、きっとこのように読むものだろう、と...
こうして、「小異歌」とされ『万葉集』に共に載せられることになるのだが
万葉仮名表記は作者が明記され、「借訓・借音」表記の方は「作者不詳」歌が多い印象がある
すると、「小異歌」というより、作者不詳の「借訓・借音」表記の歌を
後の歌人や学者たちが、訓み下したものではないかと思う
その可能性も充分あると思う
ただ、その説明が見当たらない以上、一般的にはこうした場合に言われるのが
古歌、誦詠歌の類で、貴族や官人に詠われたのだろう、と
そうかもしれないが、「小異歌」とされる歌の表記を比較すると
古歌を持ち出し、この歌はこんな風に詠むのだろう、と意見をいうような場景をも浮ぶ
ならば、今日の大きなテーマでもあった「がてり」もまた
その表記が「香光」「香花光」の他、万葉仮名で、
「我○里」(○=氐、低の人偏なし)〔17-3965〕
「我弖利 」〔1-81〕とあれば、
その歌の元歌に「香光」と表記された歌があったのかもしれない
こんな風に万葉時代の表記に想いを馳せると、自国の言葉の「文字」の偉大さを痛感する
もとは漢字を借りたにせよ、「ひらがな」という表記を得たのは、本当に素晴らしいことだ |
| |
| |


|
掲載日:2014.02.05.
| 春相聞 寄花 |
| 梅花 咲散苑尓 吾将去 君之使乎 片待香花光 |
| 梅の花咲き散る園に我れ行かむ君が使を片待ちがてり |
| うめのはな さきちるそのに われゆかむ きみがつかひを かたまちがてり |
| 巻第十 1904 春相聞 寄花 作者不詳 |
【注記】〔373・1219〕【左頁小異歌】〔4065〕
| 【1904】語義 |
意味・活用・接続 |
| うめのはな[梅花] |
| さきちるそのに[咲散苑尓] |
| さきちる[咲き散る] |
[複合語「咲いて散る」]既出、〔1838、2013年12月15日〕 |
| その[園・苑] |
果樹や草花などを植える庭園 |
| われゆかむ[吾将去] |
| む[助動詞・む] |
[推量(意志)・終止形]~よう・~つもりだ |
未然形につく |
| きみがつかひを[君之使乎] |
| が[格助詞] |
[連体修飾語・所有]~の〔接続〕体言、活用語の連体形につく |
| つかひ[使ひ・遣ひ] |
使いの者・召使・そばめ |
| かたまちがてり[片待香花光] |
| かたまち[片待つ] |
[他タ四・連用形]ひたすら待つ・一心に待つ |
| がてり[接続助詞] |
[他の動作をも兼ねて行う意を表す](上代語) |
連用形につく |
| |
~のついでに・~しながら |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [かたまちがてり] |
この句の「がてり」の原文表記「香花光」が気になる
そもそも、『万葉集』中の「がてり」のと詠われる歌は、六首ある
しかし、万葉仮名で表記される二首「見がてり」(1-81・17-3965)を除くと、
残りの「がてり」の表記は「香光」三首(3-373・7-1219・12-3183)、
そしてこの掲題歌の「香花光」の計四首となる
「光」が、「照(て)る」の訓としてよく使われるのは、かつて調べてみたことがある
だから「がてり」を、「香光」と当てる用法を、不思議とは思わないが
ならば、何故この掲題歌だけ「花」が加わるのだろう
『万葉代匠記(初稿本)』〔契沖(1640~1701)、貞亨四年(1687)成〕によれば、
「香花光の花は衍文なるへし」とし、これに倣う注釈書も多い
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕、
『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕など
「衍(えん)字」というのは、間違って入った不必要な文字、と一般的にされている
『代匠記』以降の主だった注釈書は、そんな風に解釈している
勿論、この「花」の役割に触れない注釈書も多い
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕や
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕などは、その立場を述べていないが
当然、「訓」や「歌意」に反映されるものではないので、問題にもされない
しかし、「花」を不必要ではなく、意味あるものとして捉える注釈書もある
いつも独創的な「訓」を見せてくれる一書
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕
それに、『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕は、
梅の花の美しさをあらわそうとして、特に「花」を用いたのだろう、と
いわば、「梅の花」を強調させたいがための用字だ、ということだ
この『新全集』では、この「衍字説」云々とは別に、この「がてり」の解釈にも及ぶ
この「がてり」に、「かねて」(あらかじめ・前もって、など)と同じような意味・用法
それを含め、「がてり」を「がて(難)」とも掛けて、歌意としている
この掲題歌の一般的な結句の解釈が「ひたすら待ちつつ」なのだが、『新全集』は、
「じっと待っていられなくて」とする
このような意味合いの解釈では、『講談社版』もそうだ
そこでは「がてり」が、「かてにあり(がてにあり)」の約したものか、として
その「かてに(がてに)」の「~できなくて・~しかねて」で訳している
これには、『新全集』と同じように、「がて(難)」の意を認める形となるものだ
そもそも「かてに」は、形容詞「難(かた)し」の語幹に、格助詞「に」のついた意と、
混同され、さらに読み方も「がてに」と濁音化されてきた、とされている
結句と言うのは、歌全体の歌意の方向を決めるものだと思う
だから、第四句までの流れを、この結句の解釈で大きく変えてしまう
左頁の、私の「歌意」に移る前に、何度も何度も読み直してみたいものだ
この「がてり」が「難」のニュアンスを含むものと『新全集』が挙げる二首は、
| 雑歌/阿倍廣庭卿歌一首 |
| 雨不零 殿雲流夜之 潤濕跡 戀乍居寸 君待香光 |
| 雨降らずとの曇る夜のぬるぬると恋ひつつ居りき君待ちがてり |
| あめふらず とのぐもるよの ぬるぬると こひつつをりき きみまちがてり |
| 既出〔書庫-6、2013年5月19日〕巻第三 373 雑歌 安倍朝臣広庭 |
〔歌意〕2013年5月19日時点の私の解釈
雨の降りそうなこの夜のように、
もう涙でくれています
こんなにもあなたを恋い
お待ちしながら... |
〔歌意〕2014年2月5日の解釈
雨も降らないでいるのに、この夜の一面の曇り空
べとつくようなその夜空は、まるでわたしの恋のように
思い切ることもなく...涙にくれて
あなたの訪れを、待ち耐えかねています
|
| |
| 雑歌 羈旅作 |
| 吾舟者 従奥莫離 向舟 片待香光 従浦榜将會 |
| 我が舟は沖ゆな離り迎へ舟方待ちがてり浦ゆ漕ぎ逢はむ |
| わがふねは おきゆなさかり むかへぶね かたまちがてり うらゆこぎあはむ |
| (右件歌者古集中出) |
| 巻第七 1219 雑歌 羈旅作 作者不詳 |
〔語義〕
「おきゆなさかり」は、沖を遠くへ行くな、岸から離れるな
「うらゆこぎあはむ」は、浦伝いを漕いで、逢おう、の意 |
〔歌意〕
この舟を遠く沖には漕ぎ出さないでくれ
わたしを迎える舟に...
わたしがその舟を、ひたすら待ちかねて
遠くはなれてしまわないように...
この浦伝いで、逢うつもりだから... |
なるほど、「難」のニュアンスを含んで訳してみたら、確かに歌意に不自然さはない
むしろ、通常の「~しながら」よりも、「~しかねて」の方が「歌」になっていると思う
〔373〕も以前は、「待ちながら涙する」ような歌意に感じたものだが、
「待つことが耐えられません」と詠う方が、切ない
〔1219〕もまた同じだ
迎えの舟を「待ちかねて」ゆえの、逸る気持ち...行き違いを心配する気持ちだ
しかし、迎えの舟の方が、わたしを「片待ちがてり」とも解せる
だから、浦伝いで逢うために、岸から遠く離れず、となるだろうか...
でも、それは私には、あまりしっくりこない
この情況を思い浮べるのに、作者の心情こそ率直であるべきで
相手の「気持ち」を思い、だから、と詠うのは想いの強烈さが弱まる |
| |
|
|
| 【歌意1906】 |
春の野に、かすみがたなびいている
花も咲き、あなたに逢えると待っていたのに、
こんなになっても...花が散ってしまうのに、
あなたは逢ってくれないのですね |
大方の注釈では、「かくなるまでに」が、花が咲きほこっているのに、と
それでもあなたは逢ってくれない、あなたに逢えない、とするが
私には、「花が咲いている」現在では、その時間的な深さが足りないと思う
それに、「咲いている花」を、今まさに美しくなっている自分にたとえてもいい
だから、逢いたい、逢ってくれるでしょう、のような大きな期待もする
しかし、あなたは来てくれない
こんなになるまで...咲きほこっていた花も散り始めているのに...
私だって、長く待ち過ぎて...今は綺麗な姿を見せられない
こんなになるまでも、あなたは私に逢いに来てくれないのですね
女の、愛しい男を待ちわびる、切ない歌だと思う
この歌の類想歌とされている歌三首
| 春相聞 問答 |
| 梓弓 引津邊有 莫告藻之 花咲及二 不會君毳 |
| 梓弓引津の辺なるなのりその花咲くまでに逢はぬ君かも |
| あづさゆみ ひきつのへなる なのりその はなさくまでに あはぬきみかも |
| 巻第十 1934 春相聞 問答 作者不詳 |
〔語義〕
「あづさゆみ(梓弓)」枕詞、弓を引くことから「引津」にかかる
「引津」は、福岡県糸島郡志摩町の岐志から船越にかけての入海とされる
「なのりそ」は、海藻の一種で、ほんだわらのこと
「はなさくまでに」は、掲題歌の「かくまでに」の「かく」が、
具体的に「咲く花」と示されている、その「かく」
ここでのこの語句の解釈にも様々あるが、現代語の「花が咲くまで」の意だと思う |
〔歌意〕
(あづさゆみをひく)引津の辺りに生えている、
「なのりそ」の花が、咲くまで
あなたとは逢えないのですね |
| |
| 秋相聞 寄水田 |
| 住吉之 岸乎田尓墾 蒔稲 乃而及苅 不相公鴨 |
| 住吉の岸を田に墾り蒔きし稲かくて刈るまで逢はぬ君かも |
| すみのえの きしをたにはり まきしいね かくてかるまで あはぬきみかも |
| 巻第十 2248 秋相聞 寄水田 作者不詳 |
〔語義〕
「たにはり」は、開墾して田を作り、の意
「まきしいね」は、蒔いた稲
「かくてかるまで」は、この「かくて」に誤字説を含め、諸説があり
いずれまた採り上げたいが、ここでは素直に「こうして刈り取るまで」とする
すると、結句もまたそれに見合った解釈にしなければならない |
〔歌意〕
住吉の岸を耕して田にし、そこに稲を蒔く
その稲を、こうして刈り取るまで、あなたに逢っていません
随分時が経ちましたね |
| |
| 秋相聞 寄花 |
| 吾屋戸尓 開秋芽子 散過而 實成及丹 於君不相鴨 |
| 我が宿に咲きし秋萩散り過ぎて実になるまでに君に逢はぬかも |
| わがやどに さきしあきはぎ ちりすぎて みになるまでに きみにあはぬかも |
| 巻第十 2290 秋相聞 寄花 作者不詳 |
〔語義〕
「やど」、ここでの「やど」は庭先の意味
「ちりすぎて」は、散ってしまって
「みになるまでに」は、そのままの意味だが、「ちりすぎて」と絡み、
これが結句の「きみにあはぬかも」に歌意を導く
掲題歌のように、曖昧な結句の解釈の理由にはならない
これを掲題歌に当てはめれば、花が散って実がなるまでの長い期間をさすからだ |
〔歌意〕
我家の庭先に咲いた萩の花が
散ってしまって、今、実になるまでのこんなにも長い間
あなたに逢っていないのですね、逢いたいものです
(ここは願望の終助詞「かも」だと思う) |
この三首のように、結句に同じ語を用いながらも
その前の情況で、歌意が違ってくる
どれも掲題歌の類想歌と言われながらも、純粋な「類想」歌となれば、
私には、三首とも微妙に違うと思う
掲題歌は、逢ってくれそうもない男への切なさを詠い、
〔1934〕は、「なのりそ」の花が咲けば、逢える希望がある
〔2248〕は、稲刈りという現実に沿えば、帰ってくる夫を待つものだろう
もうそろそろ逢えるだろうか、と半ば期待する
〔2290〕は、「かも」を感嘆の終助詞と考えれば、確かに類想歌にはなるだろうが
具体的な「花が咲き、散り、そして実がなっているのに」の長い間も逢っていないので
「逢いたい」気持ちを表現していると思う |
| |
| 【注記】 |
| [なのりそ] |
「なのりそ」は、「名告りそ(名を告げるな)」とも表記できるように、
和歌においては、「ほんだわら」とかけて用いられる |
| |
|
掲載日:2014.02.06.
| 春相聞 寄花 |
| 春野尓 霞棚引 咲花乃 如是成二手尓 不逢君可母 |
| 春の野に霞たなびき咲く花のかくなるまでに逢はぬ君かも |
| はるののに かすみたなびき さくはなの かくなるまでに あはぬきみかも |
| 巻第十 1906 春相聞 寄花 作者不詳 |
【左頁類想歌】〔1934・2248・2290〕
| 【1906】語義 |
意味・活用・接続 |
| はるののに[春野尓] |
| かすみたなびき[霞棚引] |
| さくはなの[咲花乃] |
| かくなるまでに[如是成二手尓] |
| かく[斯く] |
[副詞]このように・こんなに・こう |
| なる[成る] |
[自ラ四・連体形]成就する・実現する・変化する・可能である |
| までに |
[程度をはっきり表す]~くらいに・~ほどに |
| |
[限度をはっきり表す]~までも |
| 〔成立〕副助詞「まで」+格助詞「に」 |
| 〔接続〕体言、体言に準ずる語、動詞・助動詞の連体形、副詞や助詞など種々の語につく |
| あはぬきみかも[不逢君可母] |
| ぬ[助動詞・ず] |
[打消・連体形]~ない |
未然形につく |
| かも[終助詞] |
[詠嘆・感動]~であることよ 〔接続〕体言、活用語の連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [かくなるまでに] |
この歌もまた、一語の解釈が様々な歌意を生んでいる
この歌では、「かく」がそれにあたる
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕では、
「花の咲きほこる現在の状態をさす」とし、この語句を
「花がこんなに見事に咲くまでになっても(あの方はいっこうに逢ってはくださらない)」
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕も、「花が咲き満ちる」意だ
『万葉集』〔伊藤博校注・角川文庫、平成13年23版〕もまた「見事に咲く」意とする
ただし、『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕は、これを避け
「花が満開になっている状態なのか、散りかけている場合なのか、不明」とし、
この語句の解釈も「咲く花が、こうなるまでも」としている
このニュアンスは、「咲いていた花が、こんなに散ってしまうまで」になると思う
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕は、この〔1906〕が抜けている
原文と、訓み下し文は載っているが、この歌の補注と「大意」が載っていない
単純な脱落だと思う
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕では、「花が咲き盛るまで」とする
この『全注』のこの歌について述べられていることは、
『万葉代匠記(初稿本)』〔契沖(1640~1701)、貞亨四年(1687)成〕以下が、
「花が盛りになるまで」と解する説が多い、といい同じく倣ったものだ
その中で、紹介する『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕の、
「なる」を「実になる」意とし、「霞たち花咲きし頃逢ひしままにて、其花の実に成るまで逢はぬを嘆くなり」と解していることを載せている
しかし、その歌意に対して、「春の野に霞たなびき」の表現は無理があろう、とする
霞がたなびいている情景は、花が「かくなっている」今現在の情景描写だ、としている
さて、ここで今日、明日香の図書室でコピーしてきた
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕をみてみる
やはり、「現に花の盛りになっているのをいう」とあり、
「ナルは、実のなることをも言うが、春の歌だからそうではあるまい」と書いている
これは、上述の『略解』の説のことを言っているようだ
しかし、「春の歌」だから、というのは「実の成る」ことではない、との理由は通るが
春に散る花もある
それとも、よく言われるように、花の名前が明記されていないときは、
だいたい「梅か桜」というものだろうか
いや、春に咲く花は、春に散るのではないだろうか
だとすれば「実の成る」説は採れなくても、それを否定したからといって
答えは「咲く花」にはならないだろう |
| |
|

|
| 【歌意1908】 |
手折った梅の花を、
枝垂れ柳にちょうどよく折り混ぜ、
一緒にお供えすれば、
いとしいあの人に、逢えるのでしょうか |
手を尽して願掛けをする
といっても、出来ることと言えば、仏への供物の花として、梅と枝垂れ柳を献じることしか...
このように、花を仏に添えて、いとしい人との恋の成就を願うのは、
「供養」という語が、万葉集で唯一この歌だけであるなら、
他には、ないだろう、と思う
この時代には、仏教がかなり浸透しており
『万葉集』のこのような歌では、多くが「神」を詠うのに対して
「仏」への信仰心が、こうした「作者不詳」歌にまで伺えるのは、珍しいことだろう
もっとも、この「作者不詳」というのは、まったくの「不詳」ではないだろうが...
そして、官人や貴族たちの間での、仏教信仰と風流との融合も、指摘されてる
『全注』の説明では、
供花に代表的な春の景物で風流なものとされていた梅の花と枝垂れ柳、とあるが
その「代表的」な「花」を、詠歌に用いているのは、
これも、一種の形式的な表現なのかもしれない
この歌の「部立て」は、「春相聞寄花」なので、どうしても「梅と枝垂れ柳」に意識が向うが
「代表的な花」を、願掛けの「供花」として用意すれば、
恋も成就しようもの、というのだろか
文末に「かも」と、疑問の終助詞をつけている
「逢えるだろうか」という...
ここまですれば、逢えるだろう、の気持ちも
ここまですれば、本当にあえるのだろうか、と
そのどちらの気持ちも混じっているように聞こえる
となれば、「供養」の行為は、気安めほどの程度になってしまう
通説では、仏教信仰が浸透していることを伺わせる歌、ともされるが
そうであれば、もっとこの種の歌があってもいいはずだ
それは、何も「仏」に対してだけでなく、「神」へも同じことが言える
「神」に恋の成就を願掛けする歌は多いが、それ以上に多いのが
「神も仏」も抜きの、「もの」に寄せる恋のうただと言える
信仰心を基にした歌ではなく、当事者の「不安と歓び」こそが
『万葉集』の「相聞(恋歌)」の源泉だと思う
仏教信仰が浸透していた、とその背景をいうなら
この歌は、形式的な「供花」を用いた平凡な歌だと思うが
そこまでするけど、不安も付きまとうような「かも」であれば
やはり基本的には、これが『万葉集』の「相聞」なのだと思う
極端に言えば、無信心者が、藁をも掴む思いで行った「供養」かもしれない
だとすれば、よけいに切なくなる歌だと思う |
| |
| |


|
掲載日:2014.02.07.
| 春相聞 寄花 |
| 梅花 四垂柳尓 折雜 花尓供養者 君尓相可毛 |
| 梅の花しだり柳に折り交へ花に供へば君に逢はむかも |
| うめのはな しだりやなぎに をりまじへ はなにそなへば きみにあはむかも |
| 巻第十 1908 春相聞 寄花 作者不詳 |
| 【1908】語義 |
意味・活用・接続 |
| うめのはな[梅花] |
| しだりやなぎに[四垂柳尓] |
| に[格助詞] |
[相手(動作)の対象]~に〔接続〕体言、活用語の連体形につく |
| をりまじへ[折雜] |
| をり[折] |
何かが起こっている、また行われているちょうどそのとき |
| [折る] |
[他ラ四・連用形]折り取る・手折る |
| まじへ[交(ま)じふ] |
[他ハ下二・連用形]まぜ合わせる・混合させる |
| はなにそなへば[花尓供養者] |
| に[格助詞] |
[状態(資格)]~として〔接続〕体言、活用語の連体形につく |
| そなへ[供ふ] |
[他ハ下二・未然形]神仏や貴人などに、物を調えて差し上げる |
| ば[接続助詞] |
[順接の仮定条件]~(する)なら・~だったら |
| 〔接続〕動詞の未然形につけば、「順接の仮定条件」となる (「已然形」は、確定条件) |
| きみにあはむかも[君尓相可毛] |
| む[助動詞・む] |
[推量・連体形]~だろう |
未然形につく |
| かも[終助詞] |
[疑問]~だろうか・~か〔接続〕体言、活用語の連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [をりまじへ] |
古語においても、現代語においても、「をりまじへ(折り交じえ)」という語はなかった
「交じる」には、動詞について複合動詞を成すものが多いが、
私にとっては、「折り交じる」もその一つかと疑いもなく思っていたので
どんなに探しても見つからなかったことは、意外だった
ならば、「まじへ(交じふ)」は問題ないとして、「をり」とは何なのだろう
「機会・場合、季節・時候」と古語辞典に載っているが、これらの語釈では合わない
もう一つ語義として載っているのが、上表の語釈だ
「何かが起こっている、または行われているちょうどその時」に混ぜ合わせる
意味合いとすれば、そうなるだろう
いや、もっと単純に他動詞四段「折(を)る」の連用形だろう、きっと
梅の花を手折って、枝垂れ柳に混ぜる
あまりにも「をりまじり」という一語に拘り過ぎたかもしれない
|
| |
| [はなにそなへば] |
「そなへ」の原文「供養」は、仏語であり、
『万葉集』中でも、ここでしか使われていない
そして、その訓もまた幾つかある
主な書をあげると、
| 原文「花尓供養者」 |
諸本・諸注 |
| はなにそなへば |
『西本願寺本』
『萬葉集』〔桜楓社、昭和55年補訂版〕
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕
『万葉集校注』〔伊藤博、角川文庫、平成13年23版〕
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕
『萬葉集本文篇』〔塙書房・佐竹昭広、昭和38年成〕
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕 |
| はなにまつらば |
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕 |
| はなにくやうせば |
『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| はなにたむけば |
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)〕
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「そなへ」について、『集成』では、
「仏前には春の供花として柳・梅を手向(たむ)けることが多かった。『延喜式』(図書寮)にも、正月、最勝王経斎会堂の装束として「梅柳、雑(くさぐさ)ノ花」をあげている
これは、当然「供養」を「供ふ」としての解釈になる
そして、「まつら」とする『全註釈』は、
「供養者をタムケバと読む説があるが、本集ではタムケは、祭祀の一種であって、物を奉る意ではない。マツラバ、ソナヘバと読むのが穏やかだろう。マツルは、献る意である。字音で読んだかも知れないが、読み方が不明である。クヤセバか。」
「たむけ」が、神仏に幣帛(へいはく)・花・香などを供えること、
またその供え物と、古語辞典にはあるが、
『全註釈』のいう「本集では」の意味は、この『万葉集』では、とのことだろうか
そこで、面倒だが、また「たむけ」を拾い出してみる
すると、十七首あった (既出の歌としては、〔34・策略〕〔3752・悲話応答歌〕)
その殆どが、神仏に幣などを供え、旅の安全を祈願するなどの用例になっている
確かに、祭祀の一種と言われればそうだが、一方で幣帛などの「物」を「奉」っている
唯一例外と思われるのが、〔3752〕だと思う
この歌は、中臣朝臣宅守が、妻の狭野弟上娘子に贈答する歌だ
罪を問われ、護送される道中で、詠った四首のうちの一首
| 畏みと告らずありしをみ越道の手向けに立ちて妹が名告りつ |
巻第十五 3752 |
罪人となる身で、妻の名を呼ぶこともできない
しかし...
神を畏れ、名を告げずにここまで来たが、
越路の峠に差し掛かり、ついに堪え切れずに、妻の名を呼んでしまった
この「たむけ」は、「手向け」と「峠(たむけ」を掛けているはずだ
古語辞典でも、この「峠(たむけ)」で道祖神に「手向け」をすることから、
「山道を登り詰めたところ・峠」とも書いてある
この歌〔3752〕での「手向け」は、決して「物を奉る」ものではない
確かに一般的な「手向け」の意もあるが、物を奉ってはいない
では、『全註釈』がいうような「たむけ」は、「本集」であっても、
物を奉る意ではない、というのに該当するのは、十七首中、この一首になる
私の理解力が足りないかもしれないが、今の私の能力では...
「はなにたむけば」でも、何もおかしくはない、と思う
|
| |
|
|
| 【歌意1909】 |
秋になると、佐紀野に咲くをみなへし
今は、白つつじが咲いている
その名ではないが、あなたにとって知らぬこと、身に覚えのないことなのに
いろいろと言われた、わたしのいとしい人よ |
恋仲の二人を周囲がはやす歌は多い
しかし、実際にはそれほどでもない仲なのに、
周囲の思い違いに悩む歌もまた多い
この歌も、そちらに近いような気がする
いとしいあなたの「身に覚えのないこと」というのは、
作者の片恋を言うのだろう
いや、告白さえまだしていないのかもしれない
その心つもりがあっても、先行する周囲の評判に、臆する気配を感じる
ただ、救いがあるのは
相手が迷惑と思う様子が、感じられないことだ
少なくとも、自分の想いは、たとえ直接的なものではなくても
周囲から届いてはいようものを、その反応が伺えない
ひょっとしたら、無関心なのかもしれない
そんな想いを時折交えながら、この歌を詠う
「迷惑でしょうか、そうでないなら、歌を返して欲しいものです」
恋仲まで進展していなくても、噂は大きく伝わるものだ
生真面目に迷惑がるでもなく、かといって気にならないわけでもない
半ばもどかしく、半ば戸惑い
こうして詠うことで、作者の本当の気持ちが伝わることを、願う
「わがせ」には、女性から親しい夫、あるいは恋人に使う言葉だ
二人の関係が、すでにそんな関係であれば、
またこの歌の意味合いも違ってくる
仲の良い二人なのに、周囲ではあれこれと、あなたの知らない噂があります、と
いや、これは違うだろうな
すでに男の耳には、その噂は届いている
しかし、男にとっては、まったく身に覚えのないこと
いや、男には関係すらないことかもしれない
ならば、作者が伝えたい気持ちと言うのは...
私は、あなたを信じています
あなたは私を、信じてくれますね
「わがせ」と言えるほどの、すでに恋仲だとしたら
お互いが周囲の評判に惑わされず...
それぞれが思いもしない、知らないことで騒ぎ立てられても
お互いが信じ合っていれば...
それを心から願う歌なのかもしれない |
| |
| |



|
掲載日:2014.02.08.
| 春相聞 寄花 |
| 姫部思 咲野尓生 白管自 不知事以 所言之吾背 |
| をみなへし佐紀野に生ふる白つつじ知らぬこともち言はれし我が背 |
| をみなへし さきのにおふる しらつつじ しらぬこともち いはれしわがせ |
| 巻第十 1909 春相聞 寄花 作者不詳 |
【注記】〔678・1350・2111〕
| 【1909】語義 |
意味・活用・接続 |
| をみなへし[姫部思]〔枕詞〕「佐紀」にかかる |
| さきのにおふる[咲野尓生] |
| さきの[佐紀野] |
奈良市佐紀町を中心に、東は佐保に接し、西は西大寺まで及ぶ |
| おふる[生ふ] |
[自ハ上二・連体形]生ずる・生える・生長する |
| しらつつじ[白管自] |
| つつじ[躑躅] |
春から初夏にかけて紅・白などの花を開く・襲(かさね)の色目の名 |
| しらぬこともち[不知事以] |
| もち[以] |
[他四「持つ」の連用形「もち」が本]もって・によって・~で |
| いはれしわがせ[所言之吾背] |
| れ[助動詞・る] |
[受身・連用形]~れる |
未然形につく |
| し[助動詞・き] |
[過去・連体形]~た・~ていた |
連用形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [をみなへし] |
秋の七草の花の一つ、多年草
山野に自生し、晩夏から秋にかけて黄色の小さな花を、茎の先端に咲かせる
「をみな」が、古来「美女」という意味であり、
「をみなへし」は、美しい女性をたとえる歌として、よく詠われている
この歌では、この「をみなへし」を「枕詞」として、
「佐紀野(さきの)」にかかる、とする説と
原文が「咲野」(さきの)」であるので、「女郎花」が「咲く野」とする説がある
しかし、部立て「春相聞」であることから、
他に手掛かりがなければともかく、ここには「白つつじ」がある
秋の花「女郎花」が「寄花」ではなく、春の花「つつじ」が詠われたものだ
だから、女郎花が「咲く野」は、「秋には咲く女郎花」という意味であり
この歌では、直接的な意味を持つものではないが、
何故、ここで用いられているのかを考えると、
秋には女郎花の花が「咲く」この「野」を知らすためで
この「咲く」こそに、敢えて「をみなへし」を持ち出す意味があったのだと思う
そして、この「咲く」は、「佐紀、佐紀野」を「音」で導いている
「佐紀・佐紀野」を引き出すのに、何故「をみなへし」なのか、
「咲く」ことが必要であれば、他の花でも同じことだと思う
しかし、「をみなへし」...
これが「枕詞」だと認識しているから、今では不思議に思わないが
古語辞典の殆どが、「をみなへし」を枕詞としていない
だから、私のように古語辞典を頼りにこのような歌を解釈しようとすると
「をみなへし」と「さきの」が、どうしても曖昧にしか結びつかなくなってしまうだろう
単純に、女郎花ではなく、他の花でもいいではないか、と
その疑問を封じてしまうのが、まさに「枕詞」という便利な用法だ
「をみなへし」と「さき」をセットにすれば、悩まずに済む、と言うわけか
そして、この「さき」に「佐紀・佐紀野」に当てれば、立派な枕詞になる
と、不遜ながらに考えてしまった
殆どの注釈書が、「枕詞」と解し、「をみなへし さきのにおふる」としている中で、
手元で確認できる「さくの」としている注釈書は、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕がある
これらは、当然のことながら、「をみなへし」は枕詞ではなく、
「女郎花が咲く野」と解釈し、決して「佐紀野」とはならない
『全註釈』では、「女郎花が咲く野の、白いツツジのように」
『講談社文庫』では、「女郎花の咲く野に生える白つつじのような私」とする
なお、『大系』は、その「大意」で、この箇所の解釈を省いている
ここに共通するものは、「白つつじ」そのものの歌ではないことだ
「白つつじのように」としている
そもそも、『万葉集』中の「をみなへし」は十四首ある
そのうちの二首〔1538・1542〕は、秋の七草を旋頭歌風に並べたものだが
残りの掲題歌を除く十一首の内、掲題歌と同じような用法の枕詞と思われる歌が三首ある
| 相聞/(中臣女郎贈大伴宿祢家持歌五首) |
| 娘子部四 咲澤二生流 花勝見 都毛不知 戀裳摺可聞 |
| をみなへし佐紀沢に生ふる花かつみかつても知らぬ恋もするかも |
| をみなへし さきさはにおふる はなかつみ かつてもしらぬ こひもするかも |
| 既出〔書庫-6、2013年5月11日〕巻第四 678 相聞 中臣女郎 |
〔語義〕
「はなかつみ」は、水辺に生える草の名、野生の花菖蒲とも言われ、諸説がある
和歌においては、同音の「かつ」「かつて」を導きだす序詞として用いられている
「かつて」は、下に打消しの語を伴って、
「全然・決して・かねて・今まで一度も」の意の副詞 |
〔歌意〕
秋になると、女郎花が咲く佐紀沢の「花かつみ」のように
今まで一度も知らなかった恋も、するものです
(では、はなかつみ、にどんな含みがあるのか、今の私には解らない) |
| |
| 譬喩歌 寄草 |
| 姫押 生澤邊之 真田葛原 何時鴨絡而 我衣将服 |
| をみなへし佐紀沢の辺の真葛原いつかも繰りて我が衣に着む |
| をみなへし さきさはのへの まくずはら いつかもくりて わがきぬにきむ |
| 巻第七 1350 譬喩歌 寄草 作者不詳 |
〔語義〕
「まくずはら」の「ま」は美称、葛の原
「いつかもくりて」は、いつ手繰り採って
「わがきぬにきむ」は、私の衣として、着ることができるだろう |
〔歌意〕
女郎花の咲く佐紀沢の辺りの、美しい葛を
いつになったら、それを採って、衣にできるのだろう
(岩波の『大系』では、第二句を「おふるさはへの」とし、さきさはを否定している) |
| |
| 秋雑歌 詠花 |
| 事更尓 衣者不揩 佳人部為 咲野之芽子尓 丹穂日而将居 |
| ことさらに衣は摺らじをみなへし佐紀野の萩ににほひて居らむ |
| ことさらに ころもはすらじ をみなへし さきののはぎに にほひてをらむ |
| 巻第十 2111 秋雑歌 詠花 作者不詳 |
〔語義〕
「ことさら」は、「事改めてするさま・わざわざ・格別・特別」の意の形容動詞
さらに、副詞として、「わざと・故意に・とりわけ」もある
「すらじ」は、「摺り染めにする」意の四段動詞「摺る」の未然形「すら」に、
打消しの推量(意志)の助動詞「じ」の終止形、「摺り染めまい」となる
「にほふ」は、赤く色づく意が原義で、ここでは花の色が衣服に照り映える意
|
〔歌意〕
格別に、衣服を染めたりはすまい
(女郎花の咲く)佐紀野の萩に、見事に映えて染まっているのだから |
三首目は、枕詞でなくても、歌意に支障はないだろうが
「女郎花の咲く、佐紀野の萩」というのも、やや重たい気もする
やはり、「佐紀」のかかる枕詞とした方がいいと思う
ついでに言うが、「をみなへし」を、この三首目では「佳人部為」と表記している
先にも書いたように、「をみな」は「美女・佳人」の意であったのが原義であり
それが後に「女一般」を指すようになる
音変化して「をうな・をんな」に転じると、女の一般名称となってゆく
十四首の残りの八首は、「をみなへし」の花を詠ったもの
| 「をみなへし」そのものを詠った八首 |
花 |
所載巻 |
| をみなへし秋萩交る蘆城の野今日を始めて万世に見む |
秋萩と並立 |
8-1534 |
| 手に取れば袖さへにほふをみなへしこの白露に散らまく惜しも |
女郎花 |
10-2119 |
| 我が里に今咲く花のをみなへし堪へぬ心になほ恋ひにけり |
女郎花 |
10-2283 |
| 秋の田の穂向き見がてり我が背子がふさ手折り来るをみなへしかも |
女郎花 |
17-3965 |
| をみなへし咲きたる野辺を行き廻り君を思ひ出た廻り来ぬ |
女郎花 |
17-3966 |
| ひぐらしの鳴きぬる時はをみなへし咲きたる野辺を行きつつ見べし |
女郎花 |
17-3973 |
| をみなへし秋萩しのぎさを鹿の露別け鳴かむ高圓の野そ〔既出〕 |
秋萩と並立 |
20-4321 |
| 高圓の宮の裾廻の野づかさに今咲けるらむをみなへしはも |
女郎花 |
20-4340 |
|
| |
| [さきの] |
平城京の北方にあたり、聖武天皇の時代に騎射や曲水宴などが行われた松林苑や、
長皇子の佐紀宮などがあった
|
| |
| [もち] |
語義としては「もて(以て)」とした方がいいだろうが、
この用法で「もて」とするのは、『万葉集』中に、二首しか見えない
なお、「もて」と訓じているのは、
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕、
それに、『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕
ともに、「~で」と解釈している
古語辞典では、「以て(もて)」の方が載っており、「もち」単独では載っていなかった
その「以て」の解説では、「もちて」の転とし
手段、材料となるものを示す「~によって・~で」
動作のきっかけになるものを示す「~から・~がもとで」
特にある一つのことを強調して示す「~(を)もって」
|
| |
|
|
| 【歌意1910】 |
梅の花を、わたしは決して散らさない
(あをによし)奈良に住む、いとしい人が
何度も何度も訪れて来て、一緒に見られるように... |
この梅の花が、いとしい人を呼ぶ「まじない」のように詠う
梅の花さえ散らさないでいれば、あの人は、何度も何度もやって来る
そんな願い、いや強い意志を思い描くことができる
多くの注釈書では、特定の「いとしい人」ではなく
「平城」の人、つまり「みやこびと」を梅の花の観賞に誘っている解釈になっている
それが、おかしいのではなく
私にとっての、『万葉集』の「相聞」は、それでは平凡過ぎる
「想いを詠」う歌であれば、それは「いとしい人」への「相聞」であるはずだ
一般的な解釈では、
平城京周辺の土地の人が、梅の花を愛でるために、
「みやこびと」を招待するような歌になっている
私が、こんな「いとしい人」への解釈にしたいのも
テキストにした本が、「ならなるひとの」と訓を載せているからだと思う
勿論、今の私は、一つのテキストに拘ることもないし
そもそも、一冊のテキストに拘り、「万葉歌」を知りたいとは思わない
最初に頼るのは、やはり古語辞典や、その他の資料
そして、異訓が何故生じて、それはどんな根拠があるのか、など
拙いながらも、自分で「歌意」を求めている
それは、まったく見当外れの「歌意」になったりもするだろうが、
少なくとも、自分に響いてくる「歌」として受止めるには、「押付けの歌意」よりはいい
右頁に紹介したように、「平城之人」の訓が、
仮に「ならなるひとも」しかなければ、
私の受止め方も違っただろう
「訓点」の研究まで、私には理解する能力も無く
それぞれの批判などできやしないが、
「異訓」が、あるものなら、少なくとも自分なりの「選択」はできる
そして、この掲題歌に、「ならなるひとの」とすれば、「上掲の歌意」
「ならなるひとも」であれば、それこそ「いとしい人」と限定は弱いと思う
私は、梅の花を散らしませんから、都の人たちも、見に来てください
それこそ、大方の注釈書の歌意になる
勿論、「あなたも来てください」という含みはある
でも、それより「あなたに見せたいから」と「きつつみるがね」は詠っていると思う
この歌が、「相聞歌」として配列されていることに異論がなければ
一般的な、梅の花の観賞を招待する歌ではなく
やはり、「散らさない」という強い意志
それは、「あなたに何度も来て欲しいから」という強い想い、
そうであってこそ、「相聞歌」の切なさがこみあげてくる歌なのだと思う |
| |
|
掲載日:2014.02.09.
| 春相聞 寄花 |
| 梅花 吾者不令落 青丹吉 平城之人 来管見之根 |
| 梅の花我れは散らさじあをによし奈良なる人の来つつ見るがね |
| うめのはな われはちらさじ あをによし ならなるひとの きつつみるがね |
| 巻第十 1910 春相聞 寄花 作者不詳 |
| 【1910】語義 |
意味・活用・接続 |
| うめのはな[梅花] |
| われはちらさじ[吾者不令落] |
| ちらさ[散らす] |
[他サ四・未然形]ちりじりにする・ちらかす・言いふらす |
| じ[助動詞・じ] |
[打消推量・終止形]~ないだろう・~まい・~ないつもりだ |
| 〔主語が話し手の場合、打消の意志を表す〕〔接続〕未然形につく |
| あをによし[青丹吉]〔枕詞〕「なら」にかかる 〔上代、奈良に青土が出たことによる〕 |
| ならなるひとの[平城之人] |
| なる[助動詞・なり] |
[断定・連体形]~である・~だ〔接続〕体言、連体形につく |
| の[格助詞] |
[主語]~が 〔接続〕体言、体言に準ずる語につく |
| きつつみるがね[来管見之根] |
| つつ[接続助詞] |
[継続]~しつづけて |
連用形につく |
| がね[終助詞](上代) |
~のために・~のように・~であろうから |
連体形につく |
| (打消・意志・禁止・命令・願望)などの表現を受け、その理由・目的を表す) |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [青丹吉] |
常陸国風土記久慈郡河内里の条
「有らゆる土は、色、青き紺の如く、画に用ゐて麗し。俗、阿乎爾(あをに)といひ、或、加支川爾(かきつに)といふ。時に朝命の随に、取りたてまつる」とある
「よ」は、詠嘆・感動の間投助詞
「し」は、語調を整え、強意を表す副助詞「し」が、
詠嘆・感動の間投助詞「し」だという説もある
|
| |
| [ならなるひとの] |
原文の「平城之人」を、七音で訓じるには、「ならなるひとの」の他にも、
「ならなるひとも」など、幾つもの説がある
| 原文「平城之人」 |
諸本・諸注 |
| ならなるひとも |
『萬葉集本文篇』〔塙書房・佐竹昭広、昭和38年成〕
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕
『萬葉集』〔桜楓社、昭和55年補訂版〕
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕
『万葉集校注』〔伊藤博、角川文庫、平成13年23版〕
|
| ならなるひとの |
『西本願寺本』
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕
|
| みやこのひとも |
『元暦校本』 |
| ならのさとびと |
『万葉代匠記(初稿本)』〔契沖、貞亨四年(1687)成〕 |
係助詞「も」と、格助詞「の」は違う
原文が「平城之人」であれば、そこに「も」や「の」を断定はできない
歌意に沿って、矛盾無く読めるかどうか...
『全註釈』の説明の仕方が、素人には不満が残る
「-略-、之はノと読むのが普通であるが、音が足りないからナルとする」とある
|
| |
|
|
| 【歌意1911】 |
こんなことになるのだったら
どうして、山吹を植えたりしたのだろう
まさに、その名のように、この花を見ていると
決して止むこともなくて、
恋しく思うばかりではないか |
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕の「歌意」を載せてみる
「こんなに見に来てくれないのなら、植えなければ良かった
山吹のように、止む時もなく恋しいことを思うと」
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕もまた
「こんなことだったら、何のために山吹など植えたのであろうか
その名のように片時も止むことなく、恋に苦しみ続けることを思うと」
このように、この歌の「歌意」としては一般的に、
あなたに見せたくて植えた「山吹の花」が咲いたのに
あなたは来てくれない、という寂しさを詠ったものと解釈している
しかし、もう一つの感じ方もある
確かに、初めの内は、いとしい男の為に植えたのかもしれない
でも、「花が咲いたのに、来てくれないなら、植えなければよかった」ではなく
植えたこの「山吹の花」を見ていると、いっそう想いがつのり
それが止む時もなく、恋の苦しみへと誘う
こんなに自分を苦しめるのなら、山吹なんて植えなければよかった
どうして、植えたりなんかしたのだろう
歌中で、「あなたが来ないので」とは詠っていない
ただ、「かくしあらば」にすべてがこめられている
そして、その「かく」が第四・五句を言うものであり
だから、第二句の「なにかうゑけむ」と自身に問うている
問題は、その「問い」の答えだ
どうして植えたのだろう...
その解釈を、千数百年経ってもなお、誰も見つけることはできない
ならば、読む者が、それぞれの立場、環境で「自身に問う」てみればいい
「やまぶき」を、恋心の慰めに、と思っていたのに
逆に、いっそう想いがつのった、とする家持の歌がある
| (天平勝宝2年4月5日)詠山振花歌一首[并短歌] |
| 宇都世美波 戀乎繁美登 春麻氣テ 念繁波 引攀而 折毛不折毛 毎見 情奈疑牟等 繁山之 谿敝尓生流 山振乎 屋戸尓引殖而 朝露尓 仁保敝流花乎
毎見 念者不止 戀志繁母 |
| うつせみは 恋を繁みと 春まけて 思ひ繁けば 引き攀ぢて 折りも折らずも 見るごとに 心なぎむと 茂山の 谷辺に生ふる 山吹を 宿に引き植ゑて
朝露に にほへる花を 見るごとに 思ひはやまず 恋し繁しも |
| うつせみは こひをしげみと はるまけて おもひしげけば ひきよぢて をりもをらずも みるごとに こころなぎむと しげやまの たにへにおふる やまぶきを やどにひきうゑて あさつゆに にほへるはなを みるごとに おもひはやまず こひししげしも |
| 巻第十九 4209 詠山振花歌 大伴宿禰家持 |
〔語義〕
「はるまけて」の「まく」は、「その時期になる」意
「おもひしげけば」の「しげけ」は已然形、
上代語の形容詞の「順接」は、「仮定・確定」ともに「けば」で紛らわしく
使い分けを明らかにするために、
仮定は「~くは」、確定は「~ければ」と分化しつつあった
「こころなぎむ」の「なぎむ」は、上二段動詞「和(な)ぐ」で、
心が静まる・穏やかになる、の意
「にほへるはなを」の「にほふ」は、赤く色づく意で、
「を」は、ここでの文法の構成上は格助詞だが、意味合いとしては逆接になるだろう |
〔歌意〕
人の身であれば、恋というものは絶えないもので
春になり、その恋心がおさまらず、
手にとって折っても折らなくても、見るたびに心穏やかになろうと
木々の生い茂る谷辺に入り、その山吹を引いてきて庭に植え
朝露に色づき輝いているその花を見るたびに、
そんなことはしなければよかった、と
想いは止まず、恋しさはつのるばかりです |
| |
| 反歌 |
| 山吹乎 屋戸尓殖弖波 見其等尓 念者不止 戀己曽益礼 |
| 山吹を宿に植ゑては見るごとに思ひはやまず恋こそまされ |
| やまぶきを やどにうゑては みるごとに おもひはやまず こひこそまされ |
| 巻第十九 4210 反歌 大伴宿禰家持 |
〔歌意〕
やまぶきを、家の庭に植えては、見るたびに
想いは止まず、一層恋心がつのるばかりです |
これらの歌が、掲題歌の「想い」に通じるのは、言うまでもないと思う
この「山吹」もまた、恋しさを癒してくれるどころか
眺めることによって、一層想いがつのってしまう
この長歌とその反歌は、この前の歌〔4208〕に対する応答歌になるものだが
それは、今日の掲題歌の主題にならないので、この二首だけを採り上げた
〔4208〕をいつか採り上げる時には、この二首もまた再掲したいと思う
|
| |
|
掲載日:2014.02.10.
| 春相聞 寄花 |
| 如是有者 何如殖兼 山振乃 止時喪哭 戀良苦念者 |
| かくしあらば何か植ゑけむ山吹のやむ時もなく恋ふらく思へば |
| かくしあらば なにかうゑけむ やまぶきの やむときもなく こふらくおもへば |
| 巻第十 1911 春相聞 寄花 作者不詳 |
【左頁類想歌】〔4209・4210〕
| 【1911】語義 |
意味・活用・接続 |
| かくしあらば[如是有者] |
| かく[斯く] |
[副詞]このように・こんなに・こう |
| し[副助詞] |
語調を整え、強意を表す〔接続〕 |
〔接続〕体言、活用語の連体形・連用形、副詞、助詞などにつく
|
| 〔「~し~ば」〕中古以降の形で、条件を表す句の中か、係助詞「も・ぞ・か・こそ」を伴っ た形で用いられることが多い (副助詞ではなく間投助詞とする説もある) |
| ば[接続助詞] |
[順接の仮定条件]~(する)なら・~だったら |
未然形につく |
| なにかうゑけむ[何如殖兼] |
| なにか[何か] |
[疑問]どうして~か |
| うゑ[植(う)う] |
[他ワ下二・連用形]種子や根を土に埋める・植える・種を蒔く |
| けむ[助動詞・けむ] |
[推量・連体形]~たのだろう・~ていたのだろう |
連用形につく |
| (疑問語とともに用いて)過去の事実について、時・所・原因・理由などを推量する意を表す |
| やまぶきの[山振乃]〔枕詞〕「やむ」にかかる 〔類音によるもの〕 |
| やまぶき[山吹] |
落葉小低木、晩春に黄色の花を開く・襲(かさね)の色目の名 |
| やむときもなく[止時喪哭] |
| やむ[止む] |
[自マ四・連体形]続いていたものが終りになる・止る・絶える |
| も[係助詞] |
[強意]~も (下に打消しの語を伴う) |
| こふらくおもへば[戀良苦念者] |
| らく[接尾語] |
[上代語]~することの意を表す |
| ば[接続助詞] |
[順接の確定条件]~ので・~だから |
已然形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [かくしあらば(如是有者)] |
この「斯く」は、第四・五句の現在の「やむときもなく こふ」をいう
「恋い慕う気持ちが、止まないこの状態」を「『かく』しあらば」と表現するもの
この初句の六字...字余り
ほとんどの書が、「かくしあらば」とし、字余りに異訓を挿まないが
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕は、異訓を載せている
「かくしあらば なにか」までの訓を、「ことならば いかで」とする
その説明では、「義を得て」コトナラバとよむ。「ことが中にも、如之中(ことがなか)にて、此ノ如キ中にと云意なり」。
ちょっと、私の解釈では難しい
「義を得て」というのは、歌の「歌意」のことを言うのだろうか
こうした私の部分的な引き出しは、かえって混乱させてしまうものだろう
今度、きちんと読み直そう
ちなみに、初句の字余りをただした雅澄は、結句の「こふらくおもへば」の字余りも、
「こふらくもへば」としている...一応一貫性はある
もう一つ、素人ながら付け加えれば
字余りを、極力避けるとしたら、「かくあらば」ではまずいのだろうか
強意の副助詞「し」が省かれた訓にはなるが、第四・五句に具体的に述べているので
初句に、何も「強意」の語を加えなくても、そのように読めるだろうし
「如是」の文字においても、強調は感じられるはずだ
|
| |
| [なにか] |
「なにか」の「なに(何)」には、三つの品詞がある
| ①不定称の指示代名詞〔名前や実体の解らないものをさす〕 |
なにもの・なにごと |
| ②副詞〔疑問・反語を表す〕 |
なぜ・なにゆえ |
| ③感動詞〔念をおすために問い返す語〕 |
なんだって |
そして、それぞれに係助詞「か」がついて、「なにか」は微妙な違いを見せる
| ①〔疑問・反語〕(文末は連体形で結ぶ) |
なにが~か・なにを~か |
| ②〔疑問・反語〕(文末は連体形で結ぶ) |
なぜ~か・どうして~か |
③上の語または相手の言葉を打消し
反対のことを述べる |
どうしてどうして・いや、なあに |
この歌では、②の副詞「なに」に係助詞「か」がついたもの
|
| |
| [うゑ] |
植える意味の動詞「うう」という語、何だか初めて知ったような気がする
以前の私なら、古語辞典でこの語を引くのに苦労したはずだ
しかし、下二段活用の動詞に、少しずつ馴染み出したので
今回「うゑ」の「終止形」は、たぶん「うう」だろうと、すぐに気づいた
「据(す)う」と同じワ行の活用だ
[-ゑ・-ゑ・-う・-うる・-うれ・-ゑよ]
ちなみに、「ワ行下二段活用」の動詞は、「植(う)う・飢(う)う・据(す)う」の三語のみ
|
| |
| [こふらくおもへば] |
「おもへば」の「おもふ」は、古語辞典にも「もふ(思ふ)」として載っている
他動詞四段で、「思(おも)ふ」の「頭母音」の「お」が脱落した形だとある
意味は、勿論「おもふ」ことなのだが、
この歌のように、字余りとして訓まずに、「こふらくもへば」とする諸注もある
上に挙げた『古義』の他には、『萬葉集』〔桜楓社、昭和55年補訂版〕がある
残念なことに、
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕と、
『万葉集校注』〔伊藤博、角川文庫、平成13年23版〕、そして、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕は、
その「訓み下し文」に「思へば」としてあるので、
それが「おもへば」なのか「もへば」なのか解らない
おそらく、「思へば」と書くのは、「おもへば」と読ませるものなのだろう
仮に「もへば」と読ませるのであれば、「思」字を使わずに「もへば」とすると思う
|
| |
|
|
| 【歌意1912】 |
春になれば、水辺の草に降りる霜が、
たちまち消えてしまうように、
わたしの身もまた同じように消えてしまいそうです
でも、わたしは...あなたを、ずっと想い続けていたいのです |
自分の身を、たちまち消え行く「霜」に置き換えても
しかし「想い」だけは消えずに続けていきたい
この「霜」に寄せる想いをもっと考えれば
哀しい歌として、やるせなく響いてくる
それは、ずっと想い続けていたい、その願いさえも、
消え行く「霜」のように...消えてゆくのですね、と
「想い」が、観念的に消えるのではなく
「想う身」が、消えてしまう
恋慕う気持ちは、永遠に変わらず、と思っても
この身が消えてしまえば...せめて、この想いだけでも...
作者が、こうまで身を痛めるのは、当然のこととはいえ
どうにもならない「恋心」ゆえなのだろう
その「どうにもならない」恋だから、身をやつし、残った想いにすがるが
その「想い」さえも...
この「霜に寄せる歌」
まるで、「想う身」のはかなさを詠ってしまう「詠題」のように感じられてならない
『万葉集』中で、「詠題」としての雑歌「詠霜」や、相聞「寄霜」を詠った歌は
この掲題歌の他には二首しかない (他の「詠題」の中で分類されているものは数首ある)
| 秋雑歌 詠霜 |
| 天飛也 鴈之翅乃 覆羽之 何處漏香 霜之零異牟 |
| 天飛ぶや雁の翼の覆ひ羽のいづく漏りてか霜の降りけむ |
| あまとぶや かりのつばさの おほひばの いづくもりてか しものふりけむ |
| 巻第十 2242 秋雑歌 詠霜 作者不詳 |
〔語義〕
「あまとぶや」は、大空を飛ぶ意から、「雁」にかかる〔枕詞〕
「おほひば」は、ここでは雁の羽が、空を覆う情景をさしている
「いづく」は、「どこ(何処)」の意で、
場所についての不定称の指示代名詞、「く」は場所を表す接尾語
「か」は疑問の係助詞
「しものふりけむ」は、霜が降ったのであろうか
「けむ」は、疑問語と共に用いて、過去の事実について、
「時・所・原因・理由」などを、推量する意を表する
なお、疑問の係助詞「か」の係り結びの「結び」として、連体形で結ぶ |
〔歌意〕
大空を飛ぶ雁が、その翼を広げ空を覆うようにしているのに
その羽の何処が漏れて、この地上に霜を降らせたのだろうか |
| |
| 冬相聞 寄霜 |
| 甚毛 夜深勿行 道邊之 湯小竹之於尓 霜降夜焉 |
| はなはだも夜更けてな行き道の辺の斎笹の上に霜の降る夜を |
| はなはだも よふけてなゆき みちのへの ゆささのうへに しものふるよを |
| 巻第十 2340 冬相聞 寄霜 作者不詳 |
〔語義〕
「はなはだ」は、「ひどく・非常に」、「も」は強調の係助詞
「よふけて」を修飾している
「なゆき」の「な」は、下に続く活用語の動作を禁止する語
「ゆささ」の「ゆ」は、神聖な意を示す接頭語、
「ささ」は、神祭りに採り物として用いるものなので、特に神聖視されていた
「を」は、強調の格助詞だと思うが、歌の意味合いから、「逆接的」になる |
〔歌意〕
こんなにも遅く、夜が更けてからお帰りにならないでください
道端に見える笹の葉の上に、霜が降る夜なんですよ |
この二首、「霜のはかなさ」を詠ったものとは言い難い
自然現象の「霜」そのものだ
確かに、このように「霜」を詠題として詠った歌が少ないのは、
その「霜」に対する「心の映し」が、万葉の時代の人たちに感じられなかったのだろう
その意味では、掲題歌の「はかなく消えゆく霜」を詠うのは、珍しいことになる
その「霜」のはかなさと、「作者の身」のはかなさを詠っている
上述で、「霜」を詠題とする歌は、「想う身のはかなさ」を詠っているのだろうか、と思ったが
そうでもなかったことになる
現代に生きる私が、単純に霜や霧のような、どこか幻想的なものに抱くロマンとは
どうも違うような気もする
「雪」や「露」のような、視覚的に景観を一変させてしまうものではない「霜」
その想い入れは...詠題の数からしても、少ないものだったのだろう
|
| |
|
掲載日:2014.02.11.
| 春相聞 寄霜 |
| 春去者 水草之上尓 置霜乃 消乍毛我者 戀度鴨 |
| 春されば水草の上に置く霜の消つつも我れは恋ひわたるかも |
| はるされば みくさのうへに おくしもの けつつもあれは こひわたるかも |
| 巻第十 1912 春相聞 寄霜 作者不詳 |
【注記】〔1568〕【左頁「詠霜・寄霜】〔2242・2340〕
| 【1912】語義 |
意味・活用・接続 |
| はるされば[春去者]春になると・春になったので |
| みくさのうへに[水草之上尓] |
| みくさ[水草] |
水中や水辺に生える草 |
| おくしもの[置霜乃] |
| おく[置く] |
[自カ四・連体形]霜や露が降りる |
| けつつもあれは[消乍毛我者] |
| け[消(く)] |
[自カ下二・連用形]消える・なくなる |
| 〔参考〕この動詞の「連体形・已然形・命令形」の確かな用例は見当たらない、とされる |
| つつ[接続助詞] |
[継続]~し続けて |
連用形につく |
| も[係助詞] |
[やわらげ]~も (他のものを暗示する) |
| 〔接続〕名詞、助詞、用言や助動詞の連体形・連用形など種々の語につく |
| こひわたるかも[戀度鴨] |
| わたる[渡る] |
[補動自ラ四・連体形]動詞の連用形の下について、ずっと~続ける |
| かも[終助詞] |
[詠嘆・感動]~であることよ |
連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [みくさのうへに] |
この原文「水草之上尓」の「之」の訓を、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕では、「が」としている
しかし、その根拠について、充分とは思えない説明になっている
この歌の「類想歌」とされる一首〔1568〕を挙げ、それが掲題歌とほぼ同型なので、
そこに訓じられている「が」を倣っている
| 秋雑歌/日置長枝娘子歌一首 |
| 秋付者 尾花我上尓 置露乃 應消毛吾者 所念香聞 |
| 秋づけば尾花が上に置く露の消ぬべくも我は思ほゆるかも |
| あきづけば をばながうへに おくつゆの けぬべくもわは おもほゆるかも |
| 巻第八 1568 秋雑歌 日置長枝娘子 |
〔語義〕
「あきづけば」は、秋になると
「が」は、連体修飾語「所属」の格助詞
「おもほゆる」は、下二段「おもほゆ」の連体形で、「自然に思われる」が原義
「かも」は、詠嘆・感動の終助詞で、「~であることよ」 |
〔歌意〕
秋になると、尾花の上に置く露のように、
私の身もはかなく、消えてしまうように思えてしまいます |
確かに、この歌の「想い」は掲題歌と類想とされるものだと解る
さらに、その使われる語句もまた、似通っている
そして、『全註釈』でいうように、これほど似通った歌の第二句が、
「をばながうへに」の「が」が原文「我」の音で間違いないので
同じ形をとる掲題歌の「みくさのうへに」の原文「之」もまた、
「が」とするものだ、という
「之」を「が」とする歌も結構ある
しかし、こうした比較の仕方で、断じるのはよくないと思う
歌というのは、同型であっても、
少し助詞を変えたりして雰囲気を別のものにすることができるものだ
この掲題歌がそうだとも言い切れないが、
「の」ではなく「が」と詠む方が、
こんなにいい歌になる、というような説明が欲しかった
|
| |
| [みくさ] |
『万葉代匠記(初稿本)』〔契沖(1640~1701)、貞亨四年(1687)成〕に、
「水草と書たれとも、真草なり。唯春の草なり」とし、
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕では、
「水草ハ 水ハ只借テカケリ 春ニナリテモマタ霜ノ降比ハ、水草ハナキ物ナリ」とする
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕にも、「真草なり」としているが、
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕に、
「水草はその例のように、文字通りに見るべきやうで、必ずしも水中の草ばかりでなく、水辺の草で、芹の如きも冬から春まで茂ってゐるので、水草に霜の置く事は認められる」
「真草」とあるのは、「ま」が接頭語で、たんなる「草」のことをさすが、
一般的には、特に屋根を葺くのに用いる「かや」や「すすき」などをいう
『注釈』の言うのは、「水草」を文字通りに考えるべきだ、ということで
しかし「水草」というのは、何も「水中」の草とは限らず、
水辺に生える草のことも当てはまる、との見解だ |
| |
| [けつつもあれは] |
この句の訓は、「けつつもあれは」が定訓だとは思うが、異訓もある
しかし、その異訓「けにつつもあれは」では、字余りとなるので
どうしてもそう訓じなければならないのは、何故なのだろう
これもやはり、他の歌との用法を参考にしてのことなのだろうか
その場合の「に」は、完了の助動詞「ぬ」の連用形「に」なのだろうが...
まさに「消え入らんとしている様」をいうのだろうか
しかし、それなら「つつ」で重複してしまうような気もする
この「けにつつもあれは」と訓むのは、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕、
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕、
『萬葉集』〔桜楓社、昭和55年補訂版〕など |
| |
|
|
| 【歌意1913】 |
春霞が、山にたなびいて、ぼんやりと景色を霞ませているように
しっかりと見ることができずに、あの娘と逢ったので、
これからは、それがわたしの恋心を募らせていくのだろうか
(しっかりと見たはずなのに...) |
初々しさの感じられる「恋の歌」だ
まだ親密な恋仲ではなく、お互いが、恥じらいと自身への戸惑いを醸し出している
出逢って間もなくの逢瀬なのだろう
まるで、春霞に覆われるかのように、ぼんやりとして見える
これは、実際の逢瀬が、その情況だっただけでなく
むしろ、お互いが逢った時には、しっかりと見詰め合ったものかもしれない
しかし、一旦別れて思い出そうとすると、
その娘の顔や姿が、霞の中に沈んでしまう
大切なもの、いとしいものを失いたくない気持ちが強ければ強いほど
それは大きな不安となって、苦しめてしまう
あの「霞」の中でも、しっかり見ていたはずなのに、
どうして、こう思い出そうとすると、霞に隠れようとするのか...
この先、何度逢っても、こうして自分は恋に苦しむのだろうか...
この歌の類想歌がある
| 寄物陳思 |
| 香山尓 雲位桁曵 於保々思久 相見子等乎 後戀牟鴨 |
| 香具山に雲居たなびきおほほしく相見し子らを後恋ひむかも |
| かぐやまに くもゐたなびき おほほしく あひみしこらを のちこひむかも |
| (以前一百四十九首柿本朝臣人麻呂之歌集出) |
| 巻第十一 2453 寄物陳思 柿本人麻呂歌集 |
〔語義〕
「くもゐたなびき」の「くもゐ(雲居)」は、「雲がかかっている辺り、または雲そのもの」 |
〔歌意〕
香具山に雲がかかって、ぼんやりとしか山が見えない
そのように、はっきりと見ることが出来なかったあの娘を
あとで、いっそう恋い慕うことだろうか... |
この類想の歌
気持ちは掲題歌と同じだろうが、
表現の仕方が違う
掲題歌では、「春霞」が覆うのは、娘の姿だ
しかし、この類想歌の「雲」は、山を覆い隠している
これだと、むしろ娘の顔や姿を現実にしっかりとは見られなかったことが直観できる
そして、やはり掲題歌の「春霞」が、実際にはしっかりとその姿を見ていたはずなのに、
いざ思い出そうとすると、「霞」の中に...
「雲」は、遮ってしまうもの
しかし「霞」は、実体が見えそうで見えない
この掲題歌は、それほどの「恋の苦しさ」を予感させてしまう
|
| |

|
掲載日:2014.02.12.
| 春相聞 寄霞 |
| 春霞 山棚引 欝 妹乎相見 後戀毳 |
| 春霞山にたなびきおほほしく妹を相見て後恋ひむかも |
| はるかすみ やまにたなびき おほほしく いもをあひみて のちこひむかも |
| 巻第十 1913 春相聞 寄霞 作者不詳 |
【左頁「類想歌」】〔2453〕
| 【1913】語義 |
意味・活用・接続 |
| はるかすみ[春霞] |
| やまにたなびき[山棚引] |
| たなびき[棚引く] |
[自カ四・連用形]雲や霞などが横に長く引く |
| おほほしく[欝] |
| おほほしく[おほほし] |
[形シク・連用形]ぼんやりとしている・はっきりとしない |
| いもをあひみて[妹乎相見] |
| あひみ[相見る] |
[他マ上一・連用形]対面する・出逢う |
| て[接続助詞] |
[確定条件(原因・理由)]~ので |
連用形につく |
| のちこひむかも[後戀毳] |
| のち[後] |
あと・次・以後 |
| む[助動詞・む] |
[推量・連体形]~(の)だろう |
未然形につく |
| かも[終助詞] |
[疑問]~だろうか |
連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [はるかすみ やまにたなびき] |
この詠い出しに触れたとき、少し異質なものを感じた
和歌には、限られた文字数と言っても、かなり慣用句的な「語句」がある
「はるかすみ」が、枕詞でもあるが、この「やま」には掛かることはなく
「かすが・立つ・ゐ・おぼ・よそに」などにかかる
だから、おそらくこの「はるがすみ」は、第三句「おほほし」に掛かるのだろう
いや、そのことに違和感を抱いたのではなく、
「はるがすみ」と詠んだ歌を、無意識に口ずさんでしまったからだ
それは「はるやまに かすみたなびく」と...
山に霞が棚引いている様子を詠ったものなら、こちらの方が一般的だと思ったが
それでも、じっくり乏しい知識で考えてみた
そして、検索して「はるやまに かすみたなびく」など、一首もないことが分かった
何故なのか、掲題歌の詠い方より、自然に口に出すことができたのに...
ありそうな「語句」なのだが...見落としたのかな
こうした例を、幾つか拾い出してみた
「はるかすみ」は十八首あったが、次のように拾い出してみた
| 春霞たなびく山のへなれれば妹に逢はずて月ぞ経にける |
| 巻第八 1468 春相聞 大伴宿禰家持 |
| 後れ居て我れはや恋ひむ春霞たなびく山を君が越え去なば |
| 巻第九 1775 相聞 作者不詳 |
| 昨日こそ年は果てしか春霞春日の山に早立ちにけり |
| 既出〔書庫-13、2013年12月21日〕巻第十 1847 春雑歌詠霞 作者不詳 |
| 春霞たなびく今日の夕月夜清く照るらむ高松の野にし |
| 既出〔書庫-14、2014年1月13日〕巻第十 1878 春雑歌詠月 作者不詳 |
| 春霞立つ春日野を行き返り我れは相見むいや年のはに |
| 既出〔書庫-14、2014年1月19日〕巻第十 1885 春雑歌野遊 作者不詳 |
| 白雪の常敷く冬は過ぎにけらしも 春霞たなびく野辺の鴬鳴くも |
| 既出〔書庫-14、2014年1月25日〕巻第十 1892 春雑歌旋頭歌 作者不詳 |
| 春霞たなびく田居に廬つきて秋田刈るまで思はしむらく |
| 巻第十 2254 秋相聞寄水田 作者不詳 |
「はるかすみ」を一句(五音)として詠ったもの、
私が違和感を抱く方がおかしなことだった、ということだ
「かすみたなびく」が、つい普通の詠い方だと、思い込んでいた
|
| |
| [おほほしく] |
原文「欝」を「おほほし」とも訓むらしい
万葉仮名の表記を除けば、この「おほほし」の表記には、
「欝悒久」「欝」「不明」などがある |
| |
| [妹乎相見] |
この原文「妹乎相見」は、『元暦校本』などの「非仙覚本」に、
「妹乎相言」と表記されてはいるが、
その「訓」は「あひいひて」ではなく「あひみて」としているようだ
後に仙覚が、その訓を頼りにして「言」を「見」に意改したといわれている
一般的には、「妹ヲ相言ヒ」では、意も語も繋がらないとして
積極的に「妹乎相見」が底本とされるようになった |
| |
|
|
| 【歌意1914】 |
春霞が立ち始めた頃から...立春の頃からだろうか
それ以来、今日にいたるまでも
わたしの想いは、その春霞のように、とりとめもなく、絶えず続いています
心の奥底にある、この恋の想いが、こんなにも強くて...
(片想いでありながら) |
昨日の歌〔1913〕もそうだが、
霞に映す恋心というのは、どうも「片想い」の感じがする
この歌、一般的には、この「霞」が「立っ」た時から、とする「起点」にしているが
歌意を深く添えるのは、そんな場景の描写だけではなく
実際の「心」をも「映し」ているように思う
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕が、同じことを解説している
「鬱情を誘う春霞とともに、募った恋心を詠んだ歌」と
そのように読めば、前の歌と同じような「春霞」の役割が明確になる
この「春霞」に、「鬱情」を感じさせる歌がある
| 春相聞/大伴宿祢坂上郎女歌一首 |
| 情具伎 物尓曽有鶏類 春霞 多奈引時尓 戀乃繁者 |
| 心ぐきものにぞありける春霞たなびく時に恋の繁きは |
| こころぐき ものにぞありける はるかすみ たなびくときに こひのしげきは |
| 巻第八 1454 春相聞 大伴坂上郎女 |
〔語義〕
「こころぐき」は、形容詞「こころぐし」の連体形で、
「心が晴れ晴れしない・せつなく苦しい」の意
「~ぞ~ける」は、係り結びで、過去の助動詞「けり」の連体形「ける」で結ぶ |
〔歌意〕
心も晴れず、せつなく苦しいものでした
春霞のたなびくときに、恋心がこんなにもしきりに募るのは... |
「春霞がたなびくとき」に、恋心がこんなに募る
それは、「春霞」によって誘発された「鬱情」のように感じられる
私は、今まで「春霞」によって想起させられるのが、
「春の訪れ」だと思い込んでいたが
昨日から接している歌に、その「春の鬱情」とも言えるような「恋心」を感じてしまった
「春霞」が呼び起こすもの
それは、おおらかでのどかな「春」の一面と
思い通りにならない「恋」の苦しさを、それゆえに「かすむ」現象に重ねているかのようだ
特に掲題歌の「一云 かたもひにして」は、その念を強くする
これは「異伝」というのだろうが、作者あるいは作者以外の人が
この歌に相応しい、と付け加えたものかもしれない
|
| |
 |
掲載日:2014.02.13.
| 春相聞 寄霞 |
| 春霞 立尓之日従 至今日 吾戀不止 本之繁家波 [一云 片念尓指天] |
| 春霞立ちにし日より今日までに我が恋やまず本の繁けば [一云 片思にして] |
はるかすみ たちにしひより けふまでに あがこひやまず もとのしげけば
[かたもひにして] |
| 巻第十 1914 春相聞 寄霞 作者不詳 |
【左頁「連想歌」】〔1454〕
| 【1914】語義 |
意味・活用・接続 |
| はるかすみ[春霞] |
| たちにしひより[立尓之日従] |
| にし |
~た・~てしまった |
連用形につく |
| 〔成立〕完了の助動詞「ぬ」の連用形「に」+過去の助動詞「き」の連体形 |
| より[格助詞] |
[起点]~から (動作・作用の時間的・空間的な起点を表す) |
| けふまでに[至今日] |
| までに |
[限度をはっきり表す]~までも |
| 〔成立〕副助詞「まで」+格助詞「に」 |
| 〔接続〕体言、それに準ずる語、動詞・助動詞の連体形、副詞や助詞などの種々の語につく |
| あがこひやまず[吾戀不止] |
| もとのしげけば[本之繁家波] |
| もと[本・元・原・旧] |
根本・よりどころ・主とするところ |
| しげけ(れ)[繁し] |
[形ク・已然形]絶え間ない・しきりである |
| ば[接続助詞] |
[順接の確定条件]~ので・~だから |
已然形につく |
| [かたもひにして][片念尓指天] |
| かたもひ[片思ひ] |
[「かたおもひ」の転]男女二人の一方だけが相手を慕うこと |
| にして |
~で・~であって・~でありながら〔接続〕体言、連体形につく |
| 〔成立〕断定の助動詞「なり」の連用形「に」+接続助詞「して」 |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [たちにしひより] |
この「たち(立つ)」を解釈するのに、幾つかの場景が思い起こされる
春霞が立つ、といえば多くの歌にも詠まれているように
霞が棚引く様子が自然に思い浮かぶが、この歌については、少し違うような気がする
「立つ」を古語辞典で引くと、数多い語義の中で、
「季節などの始まり・季節が新たになる」という意味もある
この歌の歌意に即して、この「立つ」を解釈すれば、「立春」こそ合うと思った
何故なら、「より」が起点を表す格助詞なら、その「起点」は明確でなければ
全体の「強さ」が、薄らいでしまう、と思ったからだ
しかし、これまで、この「立春」と明確に解説している注釈書は一書しかない
勿論、私の知り得る範囲でのことだが...
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕が、「立春のこと」としている
その他の書は、「立つ」を「春という季節の始まり」としてではなく、
霞が「たなびく」さまを、場景として捉えている
| うち靡く春立ちぬらし我が門の柳の末に鴬鳴きつ |
| 既出〔書庫-13、2013年12月1日〕巻第十 1823 春雑歌詠鳥 作者不詳 |
| 月数めばいまだ冬なりしかすがに霞たなびく春立ちぬとか |
| (天平宝字一年12月23日) 巻第二十 4516 宴席歌 大伴宿禰家持 |
ここでいう「はるたちぬ」は、〔1823〕と〔4516〕とでは違う
〔1823〕は、草木がうちなびき、「春」になったようだ、鶯も鳴いている
そこに、「立春の日」を明確に意識はしていない
目の前の「春の気配」に、「春になったようだ」と感じ詠ったもの
〔4516〕においては、詠歌の日付もまた重要な根拠になっている
旧暦の12月23日、この日付は、まさに「立春の頃」とかみ合う
二至(夏至・冬至)と、二分(春分・秋分)を季節の中心とし
それぞれの中間に、四立(立春・立夏・立秋・立冬)をおいた、とされる
その「立春」が、年内にあることもあり、それによって、「年内立春」といったり、
年を越えての立春の「新年立春」といったりする
古今集の第一番など、それを知ることが出来る
さて、〔4516〕の年紀をいうなら、「年内立春」になるだろうか
この年の立春が、いつかわからないが、この日の前後であることは間違いないはずだ
「月」を読めば、まだ十二月、冬なのに、霞がたなびいている
やはり「立春」なのだなあ、と受け取ることもできる |
| |
| [しげけば] |
「しげけ」が、形容詞「繁し」の上代の活用形で已然形だと、どの書もいう
そして、上代の活用形では、未然形と已然形が同じなので
掲題歌のように「-けば」とあれば、仮定条件なのか、確定条件なのか
その判断は、歌意に沿ってするしかない、とのことだ
ここでは、確定条件の歌意になるので、「已然形」接続になる
普通の活用なら、「しげければ」になるだろうなあ、きっと
|
| |
|
|
| 【歌意1915】 |
ほんのりと頬を紅くした、あの美しい娘を想っているので
この春の霞がたなびく、春の明るい一日までも
心が乱れ惑い、この春日が暗く思われるほどに
わたしは、心から恋つづけているのだなあ |
陽光眩しい春の一日
そして、かすみもたなびく、のどかな春の一日
じっと野に、山に佇んでいても、そこには「明るい春の日」がある
しかし、その「明るい春の一日」を、
作者は、まるで晩秋のごとく、日が早々と沈んだ黄昏にしてしまう
一人の、美しい娘に恋をしてしまった
その時から、作者には「春」は季節感を無くしたようだ
暗くなる物理的な「一日」ではなく
「心を乱れ惑う一日」に、作者の季節になってしまった
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕の歌の評価に、引っかかるものがある
「『さ丹つらふ』『春日』と明るい紅色の印象に対して、『くれに恋ひ渡る』といっている点が対照的でおかしみがある。調べも明るく謡いものとしてよろこばれたものであろう」
何も、この歌に限ったことではないが、
こうした評価の仕方には、少々抵抗も感じている
何故なら、「謡いもの」という決め付け方はおかしい
実際には、そうかもしれないが、それは「演出物」として舞台裏を知った上で鑑賞しなさいよ
まるで、そう言われているような気がする
歌の表現は、出来上がったものに対して、それを受け取る人が、どう感じるかであり
それが「宴席歌」と明記されていなければ、
まず、実際の情景に即した解釈を試み、自身にどう受止めるか確かめる
そして、それが皆に歓ばれる「謡いもの」であろうがなかろうが
それを詮索する「意味」はないと思う
確かに、研究史としての「歌論」には必要な手段だろうが
純粋な「歌一首」の「こころ」を理解するのに、その舞台裏はいらない
「謡いものとしてよろこばれたものであろう」と言われたら
この歌から感じる、哀愁にうちしがれる姿が台無しだ
『万葉集』に限らず、「歌集」として幾世紀も経て残り伝えられてきた「歌」は
その「作歌」が作者自身で説明ができるもの以外は、
もう「歌」自体が唯一の「対照」になるものだ
そして、そのような歌は、何も舞台裏を知らなければ読めないものではなく
ただただ、「その一首」が、自分にどう響かせてきたか、それで充分だ
歴史書は、事実を書き記す義務と権利がある
それは普遍的な実証を伴うものだから、誰もが「史実」としての「歴史」を尊重する
しかし、古典の歌は、それとは違うと思う
厳密な意味での「事実」...作者の詠歌の「こころ」は、どこまでいっても推測だ
検証さへも、必要としない場合もあるだろう
よく、自作の解説を饒舌に語る「芸術家」がいるが
書(描)き上げた時点で、もう作者のエネルギーは果て、手さえも離れるものだと思う
何もいう必要はない
寡黙であるべきだ、と思う
それに触れる人が、どのように感じようが、それに応えてくれるのは...「作品」のみだ
だから、作者に解説を求めるのは、私には不思議なことであり
その「作品」から、何を感じたのか、何を感じるのか、
作品に触れた人自身が、「答え」を持っているはずなのに...
こうした「鑑賞」の仕方が、できるのも、『万葉集』ならでは、なのかもしれない
「古典」と呼ばれ、作者との時代の隔差が大きければいっそう自身の答えを意識させてくれる
以前にも書いたが、同じ歌でも、時が経てば、受止める感じ方も違う
それは、紛れもなく自分自身の「意識」の変化であり、あるいは「成長」なのだと思う
今、こうして毎日、万葉歌を鑑賞しているが
この私の歌の解釈を、私自身が何年か後に、また同じ歌をどのように感じるのか
それも、楽しみの一つになっている
|
| |
|
掲載日:2014.02.14.
| 春相聞 寄霞 |
| 左丹頬經 妹乎念登 霞立 春日毛晩尓 戀度可母 |
| さ丹つらふ妹を思ふと霞立つ春日もくれに恋ひわたるかも |
| さにつらふ いもをおもふと かすみたつ はるひもくれに こひわたるかも |
| 巻第十 1915 春相聞 寄霞 作者不詳 |
| 【1915】語義 |
意味・活用・接続 |
| さにつらふ[左丹頬經]〔枕詞〕「妹」にかかる |
| さにつらふ[さ丹つらふ] |
赤い頬をしている、という意 |
| 〔成立〕接頭語「さ」+名詞「丹(に)」+名詞「頬(つら)」+動詞を作る接尾語「ふ」 |
| いもをおもふと[妹乎念登] |
| と[格助詞] |
[引用(目的・原因)]~と〔接続〕体言、それに準ずる語につく |
| かすみたつ[霞立] 〔「春日」にかかる「枕詞」でもある〕 |
| はるひもくれに[春日毛晩尓] |
| はるひ[春日] |
春の日・春の一日 |
| くれ[暗(く)る] |
[自ラ下二・連用形]目の前が真っ暗になる・心が乱れ惑う |
| に[格助詞] |
[強調]~に |
連用形につく |
| こひわたるかも[戀度可母] |
| わたる[補動・渡る] |
[自ラ四・連体形]動詞の連用形の下について、ずっと~続ける |
| かも[終助詞] |
[詠嘆・感動]~であることよ |
連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [さにつらふ] |
この歌では、枕詞「さにつらふ」として用いられるが、
この語義から、そのまま接頭語のない「につらふ」として使われる歌もある
自動詞ハ行四段活用「丹(に)つらふ」上代語、赤く照り映える・美しい色をしている
| 我れのみやかく恋すらむかきつはた丹つらふ妹はいかにかあるらむ |
| 既出〔書庫-9、2013年8月4日〕巻第十 1990 夏相聞 寄草 作者不詳 |
| かきつはた丹つらふ君をいささめに思ひ出でつつ嘆きつるかも |
| 巻第十一 2526 正述心緒 作者不詳 |
これは、枕詞「かきつはた」が、「花のように美しい」意から、
「赤味を帯びて美しい」という「につらふ」に掛かっており
「につらふ」もまた、同様な意を含んで、
枕詞「さにつらふ」と同じく「妹・君」を修飾している |
| |
| [くれに] |
原文「晩尓」から、自動詞ラ行下二段動詞「暮(く)る」で、日が暮れる意かと思ったが
どの注釈書も「暗い」意の「暗(く)る」と解釈している
その理由も、歌意に沿えば納得する
春の日、といえば、希望に満ちた明るい「日」を思い浮かべるものだ
その「明るい日」であるはずの「春の一日」に、「暮れる」ではなく「暗い一日」と詠う
そうして、「暮れる」意が、歌意の流れに合わないことが解る
そこまでは、私にも解るが、やはり素人には「くれに」とする文法で立ち止ってしまう
何も一つずつ、何でもかんでも明らかにしなければ、先に進まない、というのではなく
このまま、理解できないでいると、
次の同じようなケースで、やはり立ち止ってしまうからだ
だから、出来るだけその都度、自身を納得させたい
また、また暫くして、忘れていようとも、そうやって何度も繰り返しているうちに
やがては、古語辞典も必要としないで、歌を読めるようになる、と信じているから
この歌の「くれ」の意味が、暗くなること、であるなら
既に「暮る」の名詞形「暮れ」が存在する
その名詞「暮れ」は、日が没して辺りが暗くなる頃、という意味だ
そこから、繋がるのが「暮れ」であり、「暗くなる」ことの名詞形「くれ」なのかな
上表の「語義」で、自動詞ラ行下二段動詞「暗る」の「連用形」としたが
それは、「くらくなる」という解釈に合わせて当てた
でも、実際は...名詞「暮れ」として、解釈では「(日が暮れて)暗くなること」
そこから、「明るい春の日」が、この「日が暮れて」のところを裏にしながら、
その対語となる「暗い日」を浮かび上がらせている
そう思う方がいいのかもしれない
ここでいう「暗い」という解釈は、「日が暮れる」ことから導く「暗い日」になる
だから、「日が暮れる」と、それが表に出ないように解釈し、なおそれを利用し、
「暗くなる」と理解すれば、次に繋がる格助詞「に」への接続も
名詞形でなくても、連用形で、その用法「強調」であれば無理なく繋がる
それに、動詞「暗る」には、「心が乱れ惑う」という意味があることも、また見逃せない
格助詞「に」の接続は、普通は「体言、活用語の連体形」に付くものだが
用法の一つ「強調」の場合は、連用形につく
「修飾語+動詞の連用形+格助詞「に」(強調)+動詞」の形だと思う |
| |
|
|
| 【歌意1916】 |
この限りある命...
わたしの里の山にたちこめる霞の、湧き立ちまた消える
そのように、たとえ立つとしても、また座るとしても
それは、わたしの命を託す、あなたのお心のままに |
私の命は、あなたの気持ち次第ですよ、と言うのだろうか
この歌で、ことさら「いのち」を持ち出すこともないだろうが
やはり、枕詞の「たまきはる」自体が、「命」を想起させるので
この歌の解釈に「命」を添える注釈書は多い
仮に、あっさり読もうと思っても
結句の「きみがまにまに」が、「愛情表現」の最大限のもので
そうすると、やはり「命を託す、命さえも、命なんか」のような歌意になってしまう
「無償の愛」になるのだろう
ただ、この歌の「詠題」として「寄霞」とされている割には
「無償の愛」の比喩として使われる「霞」の意味は何だろう、と思う
例外なくどの解釈でも、「立つ霞のよう」に「立つにしても座るにしても」と解し
この語の繋がりを、「立つ」という一点に決めている
そのために、第三句までを序詞としているので、これは便利な考え方だ
しかし、枕詞もそうだが、序詞のように多くの語句を要する中で
やはり、歌意にも自然に映し出される必要はあると思う
万葉の当時の作歌の手法が、どんなものか私には解らないが
「たつともうとも」が「たちてもゐても」と同じような「慣用句」というのなら
そのフレーズに自然に歌意も繋がるような(音だけではなく)「型」もあるでは、と思う
勿論、こんな風にすべての歌を一律に決め付けるのではなく
一首一首の「こだわり」は必要だ
だから、この歌の第三句までが「たつ」を起こす序詞だとしても
当然その歌意は結句に向けて解釈しなければならず
歌の意味が、最後にどう繋がって終るのか...
私には、「立つ霞のように」が解されるとしたら
それが、結句の「愛の深さ」にどうもしっくりとは繋がらない
比較したい歌がある
| たらちねの母にも言はずつつめりし心はよしゑ君がまにまに |
| 既出〔書庫-8、2013年7月20日〕巻第十三 3299 (3298の反歌) 作者不詳 |
母親にも言わずに胸の内に包み込んでいた、この想いを
もう、どうなっても構わない
あなたの心のままに...私は、ついて行きます
この歌は、掲題歌のように序詞としての「音」でつながる歌ではないので
結句の「きみがまにまに」まで、とても「想いの深さ」が流れている
この「きみがまにまに」が、このような使い方であれば、とても共感をもてる
しかし「きみがまにまに」という語の重さ、深さに比して
霞が立ちこめるは、どう解釈すれば、見合うのだろう
仮に、序詞としての「音」のつながりを考えず
「霞」という現象を、歌意の中で表現できないのだろうか...
「霞」は、霧と同じ現象とされる
平安時代の頃には、「春は霞」、「秋は霧」と表現されるようになったらしいが
霞や霧には、どんな想いがこめられているのだろう
天気の一現象として、詠われるのでも、その背景には
霞や霧への万葉人の「こころ」がある
微細な水滴が空中に浮遊して、
空や遠方などが、はっきり見えない現象、と古語辞典にはある
要は、「おぼろ」の状態だということだ
ぼんやりと霞んでいるさま・ぼうっとしてはっきりしないさま、と古語辞典にある
それが「立ちこめ」、「きみがまにまに」となる間に
何があるのだろう
幻想の中に作者を引き寄せる
実体のない「もの」の中に、作者を惑わせる
そんな悲観的なイメージしか、残念ながら私には浮んでこない
すると、この作者は、「覚悟」を持って詠ったものかもしれない
「かすみ」のように、底なしの奥深い「霧の中」に、私は飛び込んで行きましょう
そうすれば、あなたに逢えるのですね、と
あなたのお心のままに、というよりも
自分の方から、命をも惜しまない覚悟を示めしているのではないだろうか
そう感じられるとすれば、初句の枕詞「たまきはる」が、ぴったりの歌になる
「たまきはる」が、この一首しかかからない「我・吾」に使われ
序詞に惑わされることもなく、「かすみ」のイメージを浮かべれば
私の命なんて、どうせ限りのあるものです
どんなところへでも、私は行こうと思っています
こんな風にこの歌を感じると、例歌として持ち出した〔3299〕にも充分に見合うものだと思う
|
| |

|
掲載日:2014.02.15.
| 春相聞 寄霞 |
| 霊寸春 吾山之於尓 立霞 雖立雖座 君之随意 |
| たまきはる我が山の上に立つ霞立つとも居とも君がまにまに |
| たまきはる わがやまのうへに たつかすみ たつともうとも きみがまにまに |
| 巻第十 1916 春相聞 寄霞 作者不詳 |
| 【1916】語義 |
意味・活用・接続 |
| たまきはる[霊寸春]〔枕詞〕 |
| わがやまのうへに[吾山之於尓] |
| たつかすみ[立霞]霞が立ちこめる ここまでが、次句「たつ」への序 |
| たつともうとも[雖立雖座] |
| とも[接続助詞] |
[逆接の仮定条件]たとえ~にしても |
終止形につく |
| う[「居る」の古形] |
「居る」の、座る・しゃがむ意 |
| きみがまにまに[君之随意] |
| まにまに[随に] |
[副詞]事の成り行きに任せるさま・~に従って・~につれて |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [たまきはる] |
古語辞典では、かかる語として「命・うち・世」、それに「我(吾)」が挙げられているが
この語義そのものは、未詳とされている
「わ(我・吾)」に掛かる歌は、この一首のみで、「命」が一番多い
限りある命の意を含むものらしい |
| |
| [わがやまのうへに] |
原文「吾山之於尓」は、一般的なテキストである『西本願寺本』に拠るものだが
この原文には「異同」も幾つかある
| 「吾山之於尓」の異同 |
注釈書 |
| 五口山之於爾(いくやまのうへに) |
『万葉集改訓抄』〔荷田春満(1669~1736)〕 |
| 春山之於爾(はるやまのうへに) |
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
| 吾家之於爾(わぎへのうへに) |
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
これらは、「異訓」ではなく、原文そのものを異とするもの
従って、その訓もまた、定訓とは異なる
尚、原文をそのままとし、訓を違える書が、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕で、「わがやまのへに」とする
「七音」、そして「歌意」からも、決して無理ではないと思う
|
| |
| [たつともうとも] |
「たつともうとも」の表現は、この一首のみ
似た表現で「たちてもゐても」がある
その「ても」は、接続助詞「て」に、係助詞「も」で活用語の連用形に接続する
「たちてもゐても」の用例は、五首あるが、
その原文は、
| 三埼廻之 荒礒尓縁 五百重浪 立毛居毛 我念流吉美 |
巻第四・571 |
| 秋去者 鴈飛越 龍田山 立而毛居而毛 君乎思曽念 |
巻第十・2298 |
| 春楊 葛山 發雲 立座 妹念 |
巻第十一・2457 |
| 遠津人 猟道之池尓 住鳥之 立毛居毛 君乎之曽念 |
巻第十二・3103 |
| -佐射礼奈美 多知弖毛為弖母 己藝米具利- |
巻第十七・4017 |
掲題歌の原文「雖立雖座」の表記には、逆接の「雖」があるが
「たちてもゐても」の原文表記には、このような明確な逆接仮定条件はない
歌意に沿って、「逆接の仮定条件」(たとえ~しても)ともなる
しかし、「立っても座っても」という言い回しから、
「いつもいつも」と解されることになる |
| |
| [う] |
この「う」が終止形であることは、その接続から間違いではないが
いくつかの古語辞典では、「座る」という意味の動詞「う」が見つけられなかった
しかし、最後に頼った岩波古語辞典で、やっと見つけることができた
【う・居・坐】動詞「居(ゐ)る」が、古く上二段活用をした場合の「終止形」
さて、ここからが、私の「古語の寄り道」が始まった
「う」が終止形で、接続助詞「とも」に繋がって、一応納得はしたが
この「う」を元にする動詞「居(ゐ)る」を訓じた注釈が目に入ったからだ
一般的には、この歌の訓は「たちてもうとも」だが、
動詞「居(ゐ)る」をそのまま使って、「たちともゐとも」とする書がある
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕や、
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕がそれにあたる
『全注』に引用された解説を読むと、ちょっと首を傾げる
「動詞『居ル』は、上一段活用だから、助詞「トモ」が接続する時は、古くは「ヰトモ」となる。『美等母安久倍伎』(巻第十八・4061)の例である。」(脇屋眞一君説)
この例で使われた「美等母安久倍伎」は「見とも飽くべき」と訓じ、
「みとも」の使用例を、この掲題歌にあげたものだ
「古くは」というように、上一段活用「見る」の終止形は「見る」なのだが
かつては上二段の活用で、その終止形が「見(み)」であったことを言っている
これは、私にも理解できた
さらに、古語辞典での接続助詞「とも」の「文法」に目を通すと、
| 接続に関して、奈良時代の文献に特例が見られる。上一段活用の動詞「見る」に接続する場合、「終日(ひねもす)に見とも飽くべき浦にあらなくに」(巻第十八4061)のように「見とも」の形が表れる。これは「見べし」「見らむ」の用例とともに、動詞「見る」の接続の古い形を残したものと見られる |
「べし」にしても「らむ」にしても、それにつくのは「終止形」なので、
上一段「見る」の終止形が、古い形では上二段「見(み)」であることを説明し、
それが万葉歌にも見られる、としている
これも、理解できた
もっとも、この古語辞典の説明では、「見る」にそうした特例があるのか
あるいは、他にもあるのかは解り辛いが、現実的に「居る」もそう解釈しているので
このような、古い形においては、活用の変化を理解し、訓を得よう、ということだ
しかし、私が首を傾げたのは
「居る」の古い活用で、「ヰトモ」を導くなら
それが、「見とも」に倣った手法であることは明らかであり
ならば、その「古い」手法を取り入れるのなら、
「う」とすることこそ正しいのでは、と思う
「たつともゐとも」が、古形に倣ったというのが、どうしても腑に落ちない
古形に倣うのであれば「たつともうとも」が、最善の導き方だと思う |
| |
|
|
| 【歌意1917】 |
見渡してみると、この春日野一帯に霞が立ち込めている
あなたに逢いたいと想う一心からでしょうか
このような霞にさへ、あなたの姿を求めてしまいます |
最近、「寄霞」の歌を続けて読むが、
この「霞」という「語」に対する万葉人の「想い」が、
まだ私にはつかめていない
この歌を解すれば、いろいろとそのイメージは浮ぶ
これまでも、「霞」にはいろいろな「顔」を見てきた
この歌にも、幾つかの感じ方がある
「霞」そのものを、いとしい人が「居るところ」として、
いつも立ち込める「霞」のように、あなたの姿を映し出す
また、「霞」は、いとしい人を「おぼろの世界」に置かせる
あるいは、右頁の〔1876〕みたいに、実景の中に、景観を舞台とする歌
勿論、実景は多くの場合には有効だろうし、それも訳すことには意味あることだ
しかし、この掲題歌のように、実景に拘ると、歌意として訳すのに
非常に苦労することもある
語句通りに訳すなら、「その霞のように、あなたの姿を見たいと思う」になる
そうした抽象的な歌意を載せる注釈書も少なくない
では、この「霞のように」という「霞」には、何が込められているのだろう
この歌の解釈に、手掛かりに成り得る歌がある
| 相聞/(大伴坂上家之大娘報贈大伴宿祢家持歌四首) |
| 春日山 朝立雲之 不居日無 見巻之欲寸 君毛有鴨 |
| 春日山朝立つ雲の居ぬ日なく見まくの欲しき君にもあるかも |
| かすがやま あさたつくもの ゐぬひなく みまくのほしき きみにもあるかも |
| 巻第四 587 相聞 大伴坂上大嬢 |
〔語義〕
「あさたつくもの」までが、「ゐぬひなく」を起こす序詞とされる
「ゐぬひなく」は、雲や霞など動くべきものが動かずにあること
|
〔歌意〕
春日山に絶えずかかる雲
その雲のように、絶えず見詰めていたい、あなたなのです |
この歌では、はっきりと「ゐぬひなく」と詠っている
春日山にかかって、動こうとしない「雲」
そのように、絶え間なく(動くことなく)あなたを見詰めていたい
掲題歌と同じような表現だが、「霞」がどんな役割なのか解らないのと違い
この「雲」は、はっきりと解る...
だから、この歌を参考にして、
掲題歌もまた、多くの注釈書で「いつも立ち込める霞」としているのだろうか
もう一首、参考にしておきたい
| 寄物陳思 |
| 若月 清不見 雲隠 見欲 宇多手比日 |
| 三日月のさやにも見えず雲隠り見まくぞ欲しきうたてこのころ |
| みかづきの さやにもみえず くもがくり みまくぞほしき うたてこのころ |
| (以前一百四十九首柿本朝臣人麻呂之歌集出) |
| 巻第十一 2468 寄物陳思 柿本人麻呂歌集 |
〔語義〕
「くもがくり」までが、思うように見えない相手への三日月の雲隠りに喩えた序
「さやに」は、副詞「はっきりと・明らかに」
「みまくぞ」は、「みまく」が「見む」で、助動詞「む」のク語法
「ぞ」は、「強調」の係助詞で、係り結びの「係り」
結びは、「ほしき」で形容詞「欲し」の連体形
「うたて」は、副詞で、「嘆かわしい・ふつうでないさま」
|
〔歌意〕
三日月が、はっきり見えずに、雲に隠れている
だから尚更、あなたを見たい、逢いたい、と思って...
本当に嘆かわしいこの頃の私です |
この歌では、三日月を「いとしい人」に喩え、
その「いとしい人」を隠すようにかかる雲の故に
一層、その三日月を恋しがる、この頃の自分を、嘆いている
それは、「雲」が、「恋しさ」を募らせるものであり
先の歌〔587〕とは相反する用い方をしている
歌の語句における類似性は、確かに〔587〕にあるのだろうが、
「類想歌」とするなら、私は〔2468〕歌の方が、しっくりくる
勿論、「類想歌」とは言えないが、それでも「霞」のせいで一層想いがつのり
その「霞」にさえ、いとしい人の姿を求めてしまう
それは、この〔2468〕歌の「雲」故に、より「恋しさ」をつのらせることと同じ響きだと思う
|
|
| |
|
掲載日:2014.02.16.
| 春相聞 寄霞 |
| 見渡者 春日之野邊 立霞 見巻之欲 君之容儀香 |
| 見わたせば春日の野辺に立つ霞見まくの欲しき君が姿か |
| みわたせば かすがののへに たつかすみ みまくのほしき きみがすがたか |
| 巻第十 1917 春相聞 寄霞 作者不詳 |
【左頁(類想)】〔587・2468〕
| 【1917】語義 |
意味・活用・接続 |
| みわたせば[見渡者] |
| みわたせ[見渡す] |
[他サ四・已然形]遠く広く見やる・遥か遠くまで眺める |
| ば[接続助詞] |
[順接の確定条件]~すると・~したところ |
已然形につく |
| かすがののへに[春日之野邊]春日の野辺に |
| たつかすみ[立霞]霞が立ちこめる |
| みまくのほしき[見巻之欲] |
| まく[助動詞・む](上代) |
[未来の推量・ク語法]~だろうこと |
未然形につく |
| ほしき[欲(ほ)し] |
「形シク・連体形」自分のものにしたい・そうありたい |
| きみがすがたか[君之容儀香] |
| か[終助詞] |
[詠嘆・感動]~だなあ |
体言につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [みわたせば] |
第三句「たつかすみ」までが、第四句の「みまくほしき」にかかる序詞となる
かすみが立っていない日がないように絶えず、という意味でそうなるようだ
では、「霞」が何を象徴しているのだろう...
絶え間なく「霞」が立つことに、何を見ようとしているのだろう
こうした解説は、私には混乱ばかり生じさせてくる
単純に、「見渡せば」「見まくの欲しき」と音による導き方なのか...
似たような表現で、この三句までを詠った歌がある
| 見わたせば春日の野辺に霞立ち咲きにほへるは桜花かも |
| 既出〔書庫-14、2014年1月11日〕巻第十 1876 春雑歌 詠花 作者不詳 |
この歌では、霞の中に咲いて見える花は、桜だろうなあ、と
おぼろに立ち込める「かすみ」が実景として詠われたものだと思う
しかし、三句まで同じ表現を使いながら、掲題歌は違う結び方になっている
ここでの「かすみ」は、実景とするよりも、
そのような「おぼろげなスクリーン」に、あるいは
「かすみ」そのものに、いとしい人の姿を見出そうとしている
|
| |
|


|
| 【歌意1918】 |
あなたを、こんなに恋慕い苦しんでいるのに
今日は何とか一日を過ごすことが出来ました
でも、今日のように、
春ののどかな霞の立つ、明日の長い春の一日を、
どのように過ごせばいいのでしょうか |
春の一日は、何故か「のどかさ」と同時に「もの憂い」気分が漂う
恋の切なさを詠う歌でありながら、一日一日が流されるように過ぎている
そんな情景が感じられる
昨日より今日、今日より明日
明日より...
その日々付き纏う「せつなさ」は、行き着くところもなく、春の「霞」に仕舞われている
そこが、「秋のせつなさ」と、何となく違うような気もする
類想歌と言われる歌がある
| 正述心緒 |
| 戀管母 今日者在目杼 玉匣 将開明日 如何将暮 |
| 恋ひつつも今日はあらめど玉櫛笥明けなむ明日をいかに暮らさむ |
| こひつつも けふはあらめど たまくしげ あけなむあすを いかにくらさむ |
| 既出〔書庫-9、2013年8月5日〕巻第十二 2896 正述心緒 作者不詳 |
〔歌意〕
想い続けていますよ、今日も変わらずにね
しかし、その夢のように人に知られたとしたら
明日は、どう過ごしたらいいでしょう |
〔注〕
この歌意は、2013年8月5日時点の私の感じたそのままの転載になる
今思うと、かなりの意訳、いや意訳というより、「想い入れ」が感じられる「歌意」だ
当時、笠女郎と家持の表には出ない「相聞」に惹かれ...もっとも今でもそうだが
この「作者不詳歌」も、家持の「返歌」のように感じて解したものだ
ただ、今日新たに歌意を求めるのではなく
類想歌とされていることへの確認で、採り上げた |
「明日は、どう過ごしたらいいでしょう」...
この「気持ち」が、「類想歌」と言われるものなのだろう
しかし、その理由・原因となると、大きく違っていると思う
〔1948〕は、「恋の苦しさ」故に、日々を過ごすことが辛い
〔2896〕は、二人の仲を、人に知られてしまっては、この先どうして過ごせましょう
歌の語としては、確かに「類歌」と言える
しかし、「類想歌」にはならないと思う
これを類想歌というのなら、「悲恋」を詠う歌はすべて類想歌になるし
また、「満ち足りた」歌を詠うものは、それもすべて類想歌になる
詠われている「語句」と類する、ということと
詠われている「気持ち」が類することは違う
勿論、厳密な仕分けは不可能だとは思う
何しろ、「こころ」にその定義はないし、さらには「解釈」にも拠ることだろう
しかし、この二首のように、「一人苦しむ」歌と、
二人がそろって「どうしましょう」と嘆き悩む「心情」は、その「辛さ」は「類想」ではない
私は、そう思う |
|
| |

|
掲載日:2014.02.17.
| 春相聞 寄霞 |
| 戀乍毛 今日者暮都 霞立 明日之春日乎 如何将晩 |
| 恋ひつつも今日は暮らしつ霞立つ明日の春日をいかに暮らさむ |
| こひつつも けふはくらしつ かすみたつ あすのはるひを いかにくらさむ |
| 巻第十 1918 春相聞 寄霞 作者不詳 |
【左頁(類想)】〔2896〕
| 【1918】語義 |
意味・活用・接続 |
| こひつつも[戀乍毛] |
| つつ[接続助詞] |
[継続]~しつづけて |
連用形につく |
| も[係助詞] |
[言外暗示]~でも・~さえも |
| 〔接続〕名詞、助詞、用言や助動詞の連体形・連用形など、種々の語につく |
| けふはくらしつ[今日者暮都] |
| つ[助動詞・つ] |
[完了・終止形]~てしまった・~てしまう |
連用形につく |
| かすみたつ[霞立]霞が立ちこめる 〔枕詞〕「春日」にかかる |
| あすのはるひを[明日之春日乎] |
| いかにくらさむ[如何将晩] |
| いかに[如何に] |
[副詞]どのように・なぜ・どんなに |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [こひつつも] |
この歌の歌意を決める句だと思う
それは、この係助詞「も」をどう解釈するか...
ごく普通の係助詞「も」の用法は、「並列」と「添加」
恋慕いながら、今日も一日を過ごしてしまった
あるいは、逆接の接続助詞でも、歌意に矛盾はない
恋慕いながらも、今日一日は何とか過ごした、と言えば
こんなに恋慕って、切ないのに、何とか一日を過ごすことができた
これは、「逆接の確定条件」の接続助詞「も」といえる
しかし、この「も」が接続助詞であれば、その接続は、動詞・助動詞の連体形になる
ところが、この歌では、接続助詞「つつ」に付いている
そうなると、係助詞「も」で、似たような解釈が出来るのは「言外暗示」しかない
「~さえも・~でも」を用いれば、
こんなに苦しいほど恋しく想っていても、何とか一日を過ごすことができた、
というような感じなのだろうか
「添加・並列」か、「逆接」か...
|
| |
| [いかにくらさむ] |
この第五句を「いかでくらさむ」として、『古今六帖』には載せている
なお、第三句の異同「あかねさす」も併せて記す
さらに結句の「いかでくらさむ」を用いて、『赤人集』の第三句は「かすみつつ」とする
| こひつつも けふはくらしつ かすみたつ あすのはるひを いかでくらさむ |
| 古今六帖第一・天 630 |
| こひつつも けふはくらしつ あかねさす あすのはるひを いかでくらさむ |
| 古今六帖第一・天 271 |
| こひつつも けふはくらしつ かすみつつ あすのはるひを いかでくらさむ |
| 赤人集 195 |
この歌は、『拾遺和歌集』にも載せられているが、作者が「人麿」とある
| 恋つゝも今日は暮らしつ霞立(たつ)明日の春日をいかで暮らさん |
| 拾遺和歌集 巻第十一 恋一 695 人麿 |
こうして比べてみると、『万葉歌』の原文「如何将晩」が、
後には「いかで」と普通に訓まれていたように思える
古語辞典で、「いかに」と「いかで」を比べてみる
| いかに 〔如何に〕 |
[副詞]
状態や程度また理由などを疑い、推測するときに用いる
①どのように・どう
②どんなに(~だろう)・さぞ(~だろう)
③なぜ・なにゆえ
④どんなに・どれほど
感動を表す
⑤なんとまあ
[感動詞]
相手に呼びかける語
○おい・なんと・さて・もし
〔参考〕次注 |
| いかで 〔如何で〕 |
[副詞]
願望を表す
①なんとかして・どうにかして
疑問を表す
②どうやって・どのようにして・どういうわけで
反語を表す
③どうして(~か、いや、~でない)
〔参考〕
述部に助動詞「む・じ」、助詞「ばや・てしがな・にしがな」など、願望に関係する語がくるときは①、述部に助動詞「む・けむ・らむ・べし・まし」、助詞「ぞ・か」など、疑問・反語に関係する語がくるときは②または③の意となる |
この用法で考えれば、たしかに「いかに」の方が無理はないと思う
どちらも、似通った語義だが、「推測」する一点においては、やはり「いかに」だろう
明日の春の一日を、どうやって暮らすのだろう、と
|
| |
| [いかに] |
ここでは、副詞「いかに」としたが、
この語は形容動詞ナリ「いか(如何)」の連用形「いかに(いかなり)」ともされる
「どのようだ・どういうふうだ」の意の形容動詞「いかなり」は、
その終止形「いかなり」の用例がきわめて少なく、
連用形「いかに」、連体形「いかなる」の用例が多い
|
| |
|
|
| 【歌意1919】 |
わたしの、いとしいあの人が、間もなくやってくると思うと
どうしようもなく恋しくてたまらず
春雨が降るのも気づかずに、心乱れて
家を飛び出して、しまったのですよ |
この歌は、男歌か、あるいは女歌なのか、と決めかねているようだ
「男歌」だとすると、右頁の「誤字・誤写」説や、「背子」の用例など
その中でも、また幾つかのパターンがある
しかし、この歌の根本的な「居ても立ってもいられない」という気持ちを
どの場面で思い浮かべるのが自然かと言えば
首を長くして、心待ちにしている「人」を「待ち切れ」ずに
つい表に飛び出してしまった
少しでも、早く「いとしい人」に逢いたいが為に...
ここまでの「情景」を詠う歌は、そんなに珍しいことではないと思う
しかし、春雨が降っているのも気づかないで、と詠うところに、
その想いの深さや、激しさ、また切なさがある
そして、このような「心情」を、男が詠うものなのか、と考えてみる
勿論、有り得ないことではない
しかし、女がやって来るのを、今か今かと待ちかねて、雨にも気づかず飛び出す
そうした万葉時代の「行動」は、どうしても思いつかない
こうしたことが出来るのは、やはり通い婚の時代、
男がやって来るのを待ち切れなくて、と自然に思い浮かべてしまう
ただ、右頁の「誤字・誤写」説を採ると、その意味がまったく違ってくる
そして、その「誤字・誤写」説が間違いでなければ...
恋しい女に、どうしても逢いたくて
分別も無く家を飛び出し、女の家に向かったが
春雨が降っていることなど、まったく気づかなかった、と
こうした情況が、「吾妹子」であれば、そんな男の気持ちも理解できる
ただ、その前提に「誤字・誤写」を用意しなければならない
この時代に、男が女の家に行くことは普通のことだった
そこが前提となっての「誤字・誤写」説なのだろうか
そうすると、第二句の「こひてすべなみ」の主語は、男であり
雨の中を、懸命に女の家に向って走る男の姿が浮ぶ
時代の状況を思えば、確かに「誤字・誤写」説も、暴論とは思えないが
仮にそれが本当の歌の姿であっても、それが明確に検証されなければ
後の世まで伝わり残ってきた形に、できるだけ沿うのが「正しいこと」だと思う
何かを「誤字・誤写」と決めつけ、それが罷り通れば
オリジナルが残らない「歌」については、いくらでも恣意的な解釈が出来てしまう
多くの学者が支持する説が、無条件で正しい、とは思わない
少数であっても、感覚的な検証ではなく、物的な検証が充分であれば
「学閥」、権威主義に捉われない「説」も、真実を導き出す
そして、更に後世に向かい、それが多くの学者に支持され、「定説」になる
まだまだ『万葉集』は、すべてが解決している『歌集』ではない
だから、定説の持ち得ない歌も多くある
どんなアプローチで、その謎を解き明かすか、が学者の仕事だろう
そして、そんな専門的な知識を得る環境に無い私のような素人には、
単純に「自身の想い」を重ねられる「歌」を求めていくしかできないだろう
だから...手間の掛かることだが、自分で「語義」を確認しつつ鑑賞するしかない
誰しも、それぞれに『万葉集』には想い入れがある
だから、『私の万葉集』でいい
いとしい人が来るのを待ち切れずに、
雨にも気づかず、飛び出してしまった女の一途さが、私は好きなのだから...
|
|
| |
 |
掲載日:2014.02.18.
| 春相聞 寄雨 |
| 吾背子尓 戀而為便莫 春雨之 零別不知 出而来可聞 |
| 我が背子に恋ひてすべなみ春雨の降るわき知らず出でて来しかも |
| わがせこに こひてすべなみ はるさめの ふるわきしらず いでてこしかも |
| 巻第十 1919 春相聞 寄雨 作者不詳 |
【注記】〔576・3998〕
| 【1919】語義 |
意味・活用・接続 |
| わがせこに[吾背子尓]いとしい君が・いとしい君に |
| こひてすべなみ[戀而為便莫] |
| すべなみ[術無し] |
[形ク・語幹+接尾語「み」]どうしようもないので |
| はるさめの[春雨之]春の雨が |
| ふるわきしらず[零別不知] |
| わき[別き・分き] |
区別・けじめ・分別 |
| いでてこしかも[出而来可聞] |
| いで[出(い)づ] |
[自ダ下二・連用形](中から外へ)出る |
| て[接続助詞] |
[単純接続]~て・そして |
連用形につく |
| こ[来(く)] |
[自カ変・未然形]来る・行く・通う |
| し[助動詞・き] |
[過去・連体形]~た・~ていた |
カ変には特殊 |
| かも[終助詞] |
[詠嘆・感動]~であることよ |
連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [わがせこに] |
一般的には、「背子」を男とし、この歌は女が詠ったもの、とされている
しかし、これには諸説がある
あまり歓迎できないのが「誤字・誤写」説
男が、女の家を訪れる歌なので、「吾背子」ではなく「吾妹子」が妥当、とする説だ
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕が、「背は妹の字の誤れるならん」とし
それを支持する『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕も、
「背は、妹の誤るなるべし。と云る説によるべし」としている
こうした説に対して、『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕は、
「このままでよい。(中略)これは相手を訪問する為に出て来るのではなく、所在なさに出て来るのだから女であってよいのである」
この解説、私には何度も読まなければ理解できないところもある
つまり、男の訪問を待っている女が、じっとしていられなく、表に出た、ということか
これが、一般的に採られている解釈だ
また、『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕は、
「春雨の降っている中を、濡れながら夫の家に来て、言いわけとして云ってゐる歌」とする
いずれも、女歌であり、先の「誤字・誤写」説を否定している
もっとも、『万葉集評釈』は、女が男の家に恋しさのあまり、駆け込んだ、としてるが
第四句、結句を考えると、行動は頷ける
しかし、「何を言いわけ」としているのか、それが解らない
男歌、女歌とも決め難い、とする注釈書もある
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕がそれで、
「初句ワガ夫子ニとあるので、女子の作とされているが、男子どうしの場合でも、戀うということがあるから、決定はしがたい。」
確かに、「男から男」への歌、更にはそこに「恋(ひ)」を表記する歌がある
| 「沙弥満誓」⇒「大伴宿禰旅人」 |
| 相聞/(大宰帥大伴卿上京之後沙弥満誓贈卿歌二首) |
| 野干玉之 黒髪變 白髪手裳 痛戀庭 相時有来 |
| ぬばたまの黒髪変り白けても痛き恋には逢ふ時ありけり |
| ぬばたまの くろかみかはり しらけても いたきこひには あふときありけり |
| 巻第四 576 相聞 沙弥満誓 |
〔語義〕
「ぬばたまの」は、「黒髪」にかかる〔枕詞〕
「かはり」は、自動詞四段「かはる(変はる)」の連用形で、「前と変化する」
「しらけ」は、自動詞下二段「白(しら)く」の連用形で、「白くなる」
「ても」は、上の語句を逆説的に下に続ける、「~にもかかわらず・~のに」
「いたき」は、形容詞ク活用「いたし」の連体形で、「精神的に辛い」
「には」は、格助詞「に」と、係助詞「は」で、「~には」
「ありけり」は、ラ変動詞「有り」に、過去(詠嘆)の助動詞「けり」で、「ことよ」
|
〔歌意〕
(ぬばたまの)黒髪が、こんなに白くなっても
辛い恋には、出逢う時もあるのですね |
「痛き恋」というのは、勿論男女間の「恋」ではなく
沙弥満誓の大伴旅人への「思慕」が、言わせたものだと思う
| 「大伴宿禰池主」⇒「大伴宿禰家持」 |
| (題詞略)/(天平19年3月5日) |
| 和賀勢故邇 古非須敝奈賀利 安之可伎能 保可尓奈氣加布 安礼之可奈思母 |
| 我が背子に恋ひすべながり葦垣の外に嘆かふ我れし悲しも |
| わがせこに こひすべながり あしかきの ほかになげかふ あれしかなしも |
| 三月五日大伴宿祢池主 |
| 巻第十七 3998 贈答 大伴宿禰池主 |
〔語義〕
「すべ」は、「手段・方法」
「なかり」は、「無くあり」で形容詞「なし」の連用形中止法
「あしがきの」は、葦」を編んで作った「垣」、
「垣の内・垣の外」の意から「外」にかかる
「ほか」は、「よそ」の意味で、よそに離れていて、の意
「なげかふ」の「ふ」は、反復・継続の助動詞「ふ」の連体形
「し」は、語調を整えたり、強調する副助詞 |
〔歌意〕
いとしいあなたが「恋い」しくてどうしようもなく
(あしがきの)離れていて嘆き続けるばかりのわたしは、
本当に哀しいものです |
この歌には、大伴宿禰池主が、前日の四日に、「拙い思い」を申し述べ、
今朝(五日)はまたこのつまらぬ手紙であなたの耳目をけがします
そんな書き出しで始まる、大伴家持讃歌と言えそうな「題詞」が付いている
「山柿(山部赤人・柿本人麻呂)も、あなたの作品に比べれば物の数ではない」などと書く
それほどの敬愛の想いを、この歌で、あたかも「男女の恋愛関係」に擬え表現したものだ
このような詠い方もあるので、この掲題歌に諸説があるのも解る
でも、一般的な解釈による「女が待ち切れずに、面に飛び出す」
「はるさめの ふるわきしらず」の語句に、その「衝動的」な行為のリアリティを感じる
|
| |
| [すべなみ] |
形容詞「すべなし」は、どうしようもない・なす手段も無い、の意味で
その語幹「すべな」に、その原因・理由を表す接尾語「み」が付いたもの
多くは「~を~み」として用いられ、「山を高み」のように「山が高いので」だが
間投助詞「を」を省く場合もある
|
| |
|
|
| 【歌意1920】 |
この雨の中を、今更になって、
あなたは帰っていかないのでしょう
この雨は、あなたを帰すまいと、
私の気持ちのように降っているのですよ
その「春雨の心」を、わからないあなたではないでしょうから... |
人なら誰でも解する「春雨の心」と詠う
男が、女の家から帰ろうとすると
まるで、女の気持ちを察したかのように降る雨
「春の長雨」に触れて、女は強い味方を得たように男にいう
詠題の「寄雨」が、とてもしっくりくる
昨日の歌でも「誤字・誤写」説を載せたが
この歌にも、第二句の「きみはゆかじ」の「君」が「吾」の誤りだとする書がある
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕が、その書の中で
「本居宣長説」として紹介している
それに倣うかのように、『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕も採り入れる
昨日の歌と同じパターンだ
「きみはいゆかじ」を「あれはゆかじ」とすれば、どんな歌意になるのだろう
右頁の「注記」に書いたように、「話し手が主語」の場合になれば
この助動詞「じ」は、推量ではなく「打消の意志」になる
このような雨の中、今となっては、私は帰っては行くまい
春雨の心を、知らないわけではないのだから...
こうなれば、先に解釈した「女の気持ち」を、雨に寄せた歌ではなく
「男が、雨を理由に、帰るのを止めた」という明確な意思表示の歌だ
第三句「はるさめの」から結句までが、「男の帰らない理由」として持ち出されたものだ
これでも、歌意に矛盾はなく、歌としての一首を味わえる
しかし、昨日も書いたように、「誤字・誤写」説は、極論すれば
まったく別の歌を論じるようなものだ
むしろ、「異同歌」としてあっても、その歌は充分鑑賞できると思う
今日、古書店で一冊購入した「校本万葉集」
早速、この歌を引いてみた
すると、「翻刻版」というのだろうか、オリジナルを印刷した書だったので
整った活字に慣れてしまった私には、非常に読み辛い
もっとも、同じ「翻刻版」でも、『万葉集古義』よりは、解りやすいが...
この『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕、この歌の異訓ではないか
この書を見るまでは、この歌での「異訓」は、ほとんどなく
結句の「しらざらなくに」が、「しらずあらなくに」とあるぐらいで
その『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕、
『万葉集校注』〔伊藤博、角川文庫、平成13年23版〕がある
しかし、「しらざらなくに」は、「しらずあらなくに」を約して訓んだものなので
あまり気を引かなかった
その他に「異訓」があるようには思わなかったが、意外とあるものだ
まず、『校本万葉集』
「いまさらにきみはいゆくなはるさめのこころをひとのしらさらなくに」
この「ゆくな」は、動詞の終止形につき、強い禁止の意を表す終助詞「な」ではないか
同じような禁止の表現で、「な~そ」があるが、それよりも強い禁止だという
「春雨の心」を思えば、帰らないでください、となるのだろうか
この解説の「訓」の中で、諸本の異訓も詳しく書かれている
『類聚古集』では「えゆかし」
『元暦校本』では「な行そ」
『神宮文庫本』では「なゆきそ」
『西本願寺本・細井本』は「しらさるなくに」
なお、これには、「『西本願寺本』「る」ヲ消セリ。ソノ右ニ「ら」アリ」
この『西本願寺本』がテキストとして伝わっている
「諸説」においては
『万葉代匠記(初稿本)』〔契沖(1640~1701)、貞亨四年(1687)成〕が「キミハイユカス」
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕が、
「キミハイユカシ」又ハ「イマサシ」トモス
右頁の『略解』の「宣長説」も挙げている
面白いと思ったのは、「春雨之情乎(ハルサメノココロ)」を、
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕が、
「情ハ晴ノ誤カ」として、「ハルサメノハルルヲ」としているところだ
これだと、一体どんな「歌意」になるのだろう
この『校本万葉集』では、このように「諸本・諸注」の「訓」の異同を書き出しているが
それについての著者の「評価」はされていない
もっとも、学者にとっては、自分の解釈こそが「正しい」のだろうけど...
この歌もまた、『古今六帖』『赤人集』に載り、さらには『家持集』にもあると知った
| いまさらに きみはなゆきそ はるさめの こころをひとの しらさらなくに |
| 古今六帖 第一天 445 |
| いまさらに きみはよにこじ はるさめの こころをひとの しらさらなくに |
| 赤人集 雨に寄す 199 |
| けふさらに きみはなゆきそ はるさめの こころをひとの しらさらなくにこ |
| 家持集 早春 29 |
「赤人集」を除き、他では第二句を「なゆきそ」と訓じている
これは、『元暦校本・神宮文庫本』が用いられた、ということだろうか
もっとも、この当時では、原資料のオリジナルも残っていただろうし
現代でテキストとして広く使われている『西本願寺本』は、その大きな要因が、
全二十巻を伝本として残しているからで、平安時代から鎌倉時代にかけては
少なくとも、現代よりは資料には恵まれていたと思う
そのような環境の中で、「なゆきそ」と『万葉集』以外の「歌集」で訓まれたのは
やはり見逃せないことだとは思うが...
今回、偶然にも『校本万葉集』の古本を手に出来たが
明日香の図書館にすべて揃っていたにも関わらず、
今までその頁も捲ったことがなかった
これからは、また他の「巻」を古書店で見つけるまでは、明日香でも注意して見ておこう
そして、もっともっと多くの「諸注」に触れてみたいものだ
|
|
| |
|
掲載日:2014.02.19.
| 春相聞 寄雨 |
| 今更 君者伊不徃 春雨之 情乎人之 不知有名國 |
| 今さらに君はい行かじ春雨の心を人の知らざらなくに |
| いまさらに きみはいゆかじ はるさめの こころをひとの しらざらなくに |
| 巻第十 1920 春相聞 寄雨 作者不詳 |
【注記】〔1937〕
| 【1920】語義 |
意味・活用・接続 |
| いまさらに[今更] |
| いまさらに[今更に] |
[形容動詞ナリ・連用形]今となっては、もう必要がないさま |
| きみはいゆかじ[君者伊不徃] |
| い[接頭語](上代) |
動詞について、調子を整えたり意味を強めたりする |
| ゆか[行く・往く] |
[自カ四・未然形]去る・立ち退く |
| じ[助動詞・じ] |
[打消の推量・終止形]~ないだろう |
未然形につく |
| はるさめの[春雨之]春の雨が |
| こころをひとの[情乎人之] |
| ひと[人] |
人間・世間一般の人・他の人・(特定の人をさして)意中の人 |
| しらざらなくに[不知有名國] |
| ざら[助動詞・ず] |
[打消し・未然形]~ない |
未然形につく |
| なく[助動詞・ず] |
[打消し「ず」のク語法]~ないこと |
未然形につく |
| に[格助詞] |
[原因・理由]~によって・~により |
体言につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [いまさらに] |
形容動詞「いまさら」の語幹「いまさら」が副詞化して、
下に打消しや反語の表現を伴って用いることがある
この歌は、多く、否定的な気持ちを含む形容動詞の連用形だと思う
|
| |
| [接頭語「い」] |
接頭語「い」の例語
| い懸かる |
い掘(こ)ず |
い継ぐ |
い行き会ふ |
い別る |
| い隠る |
い副(そ)ふ |
い積もる |
い行き憚る |
い渡る |
| い通ふ |
い立つ |
い泊(は)つ |
い行き回(もとほ)る |
|
| い刈る |
い辿(たど)る |
い這(は)ふ |
い行き渡る |
| い組む |
い回(た)む |
い拾ふ |
い行く |
| い漕ぐ |
い繁(つが)る |
い触る |
い寄る |
|
| |
| [打消し推量「じ」] |
この助動詞「じ」には、「打消の推量」と「打消の意志」がある
推量の助動詞「む」の打消しに相当するのが、「打消の推量」となるが
この「じ」は、主語が話し手の場合には、「打消の意志」を表すことになる
この歌の場合、「きみは」とあるように、主語が、話し手(詠者)ではないので、
一般的な「打消の推量」だと言える |
| |
| [はるさめの こころ] |
この第三句「はるさめの」と、第四句の「こころ」として、
「はるさめのこころ」と訓むことになる
春雨を、人のように「有情」のものとして、用いたものだ
多くの注釈では、そのように解釈しているが、
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕では、「春雨」そのものの性質と解する
「春雨といふものの性質を、で、春雨は降り出すと容易に止まない物であることを」と
春雨の「有情」を詠った歌がある
| 春相聞 問答 |
| 吾妹子尓 戀乍居者 春雨之 彼毛知如 不止零乍 |
| 我妹子に恋ひつつ居れば春雨のそれも知るごとやまず降りつつ |
| わぎもこに こひつつをれば はるさめの それもしるごと やまずふりつつ |
| 巻第十 1937 春相聞 問答 作者不詳 |
〔語義〕
「こひつつをれば」は、「恋い続けていると」、「ば」は順接確定条件の接続助詞
「それ」は、詠者が恋い続けてい、ということをさす
「ごと」は、比況の助動詞「ごとし」の語幹で、「~のように」
「ふりつつ」は、「降り続けている」 |
〔歌意〕
いとしいあなたを想い続けていると、
この春雨が、あたかも私の恋心を知っているかのように、
私の想いに合わせて、止むこともなく絶えず降り続いています |
この歌に詠われる「春雨」は、あたかも「人」の用に扱われている
作者の恋しさを、思い遣るように、一途な想いの如く、降り続く
勿論、『窪田評釈』の言うように、「春雨」の「春の長雨」という性質もあるだろう
しかし、この歌ははっきりと言っている
「それもしるごと」と...
同じように掲題歌も考えていいと思う
|
| |
| [ひと] |
「ひと」には、上表のように、幾つかの意味があるが
多くの注釈書では、前の句(春雨の心)に対応する語として、
この「ひと」は普通の「人」だったら、この「春雨の気持ち」が解るでしょう、
と次の句に続く形になる
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕では、次のようにまで言っている
「春雨の降る心を、人として知らないことはないでしょう」という歌意にしている
その「評語」では、「人ノという方が、一般的になってよい」といい積極的な評価だ
勿論、「一般的な人」ならば、という前提であり
しかし、歌の中の語意として、
「世間の人は知っていることなので、あなたにも春雨の心が解りますね」と
言えるものだと思う
「ひと」の語義の中に、特定の人をさして「意中の人」というのがあるが
この歌で、「ひとの」が「きみの」であっても、
その前提を踏まえてのことであれば、「意中の人」として解してもいいのでは、と思う |
| |
| [しらざらなくに] |
これは「知る」の二重否定になり「知らないはずはないから」ということになる
そのため、助詞「に」には、
「なくに」として「~(し)ないことだのに」と解釈するのが普通だと思う
何故なら、その用法から「格助詞」「断定の助動詞『なり』の連用形」、
そして「接続助詞」などの諸説があり、「なくに」と用いて解釈した方が
すっきりする
ここでは、一応品詞を分けてみたが、そのままに解釈するのは、やはり難しかった
|
| |
|
|
| 【歌意1921】 |
春雨が、衣服を濡れ通すということがあるのでしょうか
もしも七日間降り続いたら
あなたは、その間の夜も、衣服が濡れるからといって
来ないつもりですすか |
春雨が、男の訪れを止めている原因だなんて
待つ身にすれば、そんなことは思いたくはないものだ
一日程度なら、まだいい
しかし、もし雨が長引けば...
その時でも...来られないのですか
ならば、私への想いなど、この雨にも劣るものなのでしょう
春雨が、いくら衣服を濡らすものであっても
体まで濡らせるものなのか
女の懸念が、男の口実に不満をつのらせる
なるほど、男の口実
でも、見え透いた口実は、愛情表現の裏返しでもあるとは思う
それに乗った振りをして拗ねてみるのも、親密な間でのことだ
こうした「雨を口実」と詠う一首と、実際に「雨を厭う」を載せる
| 相聞/大伴女郎歌一首 [今城王之母也今城王後賜大原真人氏也] |
| 雨障 常為公者 久堅乃 昨夜雨尓 将懲鴨 |
| 雨障み常する君はひさかたの昨夜の夜の雨に懲りにけむかも |
| あまつつみ つねするきみは ひさかたの きぞのよのあめに こりにけむかも |
| 既出〔書庫-9、2013年8月15日〕巻第四 522 相聞 大伴郎女 |
〔歌意〕2013年8月15日時点での歌意そのまま転載
いつもあなたは、雨を口実にしては、来てくださらない
なおさら昨夜の雨に遭って、もう懲りてしまわれたのでしょうね
これからは、来てはくださらないのでしょうか |
| |
| 秋雑歌/(藤原朝臣八束歌二首) |
| 雨障 常為公者 久堅乃 昨夜雨尓 将懲鴨 |
| 雨障み常する君はひさかたの昨夜の夜の雨に懲りにけむかも |
| あまつつみ つねするきみは ひさかたの きぞのよのあめに こりにけむかも |
| 既出〔書庫-6、2013年5月25日〕巻第八 1574 秋雑歌 藤原朝臣八束 |
〔歌意〕2013年5月25日時点での歌意をそのまま転載
ここにいると、春日山はどこにあるのか...
この雨につつまれ、さっぱり分からない
それに、この雨ではどこにも出て行けず、募るは恋しさばかりだ |
〔522〕のように、「雨」を恋の遣り取りに欠かせない歌もあれば
〔1574〕のように、「雨」を疎ましく思う歌もある
そして、私が掲題歌で感じたような雰囲気が、〔522〕にはある
この〔522〕歌に対して、後の人が「唱和」したとする歌がある
まさに、「雨の口実」が「恋」の遣り取りに欠かせないことを実感する歌だ
| 相聞/(大伴女郎歌一首 [今城王之母也今城王後賜大原真人氏也])後人追同歌一首 |
| 久堅乃 雨毛落<粳> 雨乍見 於君副而 此日令晩 |
| ひさかたの雨も降らぬか雨障み君にたぐひてこの日暮らさむ |
| ひさかたの あめもふらぬか あまつつみ きみにたぐひて このひくらさむ |
| 既出〔書庫-9、2013年8月15日〕巻第四 523 相聞 (作者不詳) |
〔歌意〕2013年8月15日時点での歌意そのまま転載
想いを察して、雨でも降ってくれないものだろうか
その雨を口実に、足止めをされ、
あなたと寄り添いながら、また一日を過ごせるのだけれど... |
〔522〕歌と〔523〕歌を取り巻くその環境には、
私も想い入れが深くある
それは、「書庫-9」で書いているが
ここでは、「雨を口実」とする点にだけ絞って載せてみた
「雨を口実」と言っても、その想いはこのように逆になる場合がある
だから、「口実」という語感だけで、歌のイメージを作るが
遠く離れて想う恋人同士であれば、この「口実」こそ、「恋の遣り取りの材料」のはずだ
それに、よく考えてみると、
「口実」として詠う場合は、必ずその対象となる歌がある
ということは、片恋に対して詠うものではないのは、確かなことであり
決して、切なさや哀しさを詠うものではない
掲題歌のように、あなたが何だかんだ言っても
春雨が衣服を通して、体まで濡らすなんて
実際に雨が何日も続いたら、どうするつもりなのですか
と、恨めしそうに男に詰問する無邪気な女の姿を想い起こしてしまう
子供だましのような「言いわけ」は、親密度の深さを感じさせるものだ
|
|
| |
|
掲載日:2014.02.20.
| 春相聞 寄雨 |
| 春雨尓 衣甚 将通哉 七日四零者 七日不来哉 |
| 春雨に衣はいたく通らめや七日し降らば七日来じとや |
| はるさめに ころもはいたく とほらめや なぬかしふらば なぬかこじとや |
| 巻第十 1921 春相聞 寄雨 作者不詳 |
【左頁『雨を口実』】〔522・1574・523〕
| 【1921】語義 |
意味・活用・接続 |
| はるさめに[春雨尓]春雨が |
| ころもはいたく[衣甚] |
| いたく[いたし] |
[形ク・連用形]程度が甚だしい・激しい |
| とほらめや[将通哉] |
| とほら[通る] |
[自ラ四・未然形]つきぬける・通じる |
| めや |
[反語]~だろうか(いや、~ない) |
未然形につく |
| 〔成立〕推量の助動詞「む」の已然形「め」に反語の終助詞「や」 |
| なぬかしふらば[七日四零者] |
| なぬか[七日] |
七日間 (古語辞典では、文字通りの意味) |
| し[副助詞] |
語調を整え、強意を表す |
| ふら[降る] |
[自ラ四・未然形]雨、雪などが降る・比喩で、涙が流れ落ちる |
| ば[接続助詞] |
[順接の仮定条件]~なら・~だったら |
未然形につく |
| なぬかこじとや[七日不来哉] |
| なぬか[七日](七夜) |
語義としては、上出と同じだが、「注記」のようにも考えられる |
| こ[来(く)] |
[自カ変・未然形]来る・行く・通う |
| じ[助動詞・じ] |
[打消の推量・連体形]~ないだろう |
未然形につく |
| とや (文末にある場合) |
[「~とやいふ」の略]~というのか・~というのだな |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [はるさめに] |
『元暦校本』『類聚古集』は、「はるさめの」とする
原文「尓(爾)」については言及されていないが、「の」とは訓めないと思う
ならば、この二書では「春雨」のみだったか、「春雨之」であったか...
|
| |
| [ころもはいたくとほらめや] |
この原文の異同も、『元暦校本』『類聚古集』で「こころはきみもしれるらむ」
こうなると、まったく別系統の「写本」のようにも思える
『元暦校本』は、この「しれるらむ」の「れる」の右に赭で「りた」とも記す
原文の異訓として、『細井本』は「ころもはいたくとをらぬや」
『京都大学本』は「ころもはいたくとほらめや」としながらも、その漢字の左に赭で、
「ころもはきみもしれるらむ」と記している
注釈書では、『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕が、原文「衣甚」を、
「ころもはなはだ」とする
なお、「甚」を『活字無訓本』では、「是」
その訓は、その資料が手元にないので、解らない
『類聚古集』では、「将」を「持」とするが、古写本の訓は、書き直しも多く
素人が目を通すと、混乱しかない...混乱しっぱなしだ |
| |
| [なぬか] |
この歌が、「七日間」と限定されるのではなく、
現実的な、ある程度の「長い期間」を言ったもの、とする
こうした用例は、幾つかの歌にも見える
そして、結句の「七日」は、先に一般的な「七日」を出したため、
この結句の「七日」には、限定された意味も加わる
その考え方なのか、理由は解らないが
「ななよ(七夜)」と訓む諸本・諸注もある
確かに、古語辞典でも、
「子どもが生れて七日目の祝いの夜」とともに「七夜(しちや)」ともある
この場合でも、先の「七日」が、「長い日にち」を言うのなら
当然この「七夜」も、同じように思わなければならない
しかし『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕では、その「評語」として、
「四・五句に七日の語を重ねたのが、ひどく利いている。これが歌の中心を成している。才気に富んだ表現である。五句を『七夜来ジトヤ』に作っているのもよい。しかしその方は一層技巧が勝つ。やはり七日の同語を重ねた方が古調である。」と称讃している
「ななよこじとや」の諸本は、『類聚古集・神宮文庫本』に見られ
多くのテキストの底本とされる『西本願寺本』はこれに拠っている
このことから、「仙覚本系統」には、「七日」を「七夜」にしているのだろう
これに倣った諸注として、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕、
『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕など
掲題歌は、底本に拠らず「七日」としている
勿論、現在では圧倒的にその訓が多いからだろうが
私は、『全註釈』のいうように、「七日」と「七夜」と対比させることが
一層の技巧とは思わないし、むしろ自然に並べられるべき表現だと思う
|
| |
| [とや] |
格助詞「と」に係助詞「や」
この「とや」が、「文中にある場合」には「~といふや」の略になり、疑問を表する
(掲題歌のように「文末にある場合」は「~とやいふ」の略で、伝聞を確かめる意)
その他、物語などの文末に用いて、「~ということだ・~とさ」との用法もある
参考例としては、「今昔物語集」などの説話文学によく見られる
この「今昔物語集」では、基本的に、
「今は昔」で始まり、「~となむ語り伝へたるとや」で終る |
| |
|
|
| 【歌意1922】 |
梅の花を散らすかのように春雨が、
長い間降り続いている
旅先にあるあなたは、
廬を造って、そこで雨を避けながら泊っているのだろうか |
花を散らせるほどに長く降り続く雨
旅先の「想い人」を心配してはいるが、きっと廬を造って雨宿りしているのだろう
そう自分に安心させようとしている
雨で足止めを強いられるのは、ときには歓迎することもある
女の家から、雨のため帰るに帰られないでしょう、と男を引き止める歌
この歌では、離れた状態での「足止め」を詠うもの
昨日の歌のように、「雨を口実」に通わないのではなく
「雨を口実」にしようも、それが「二人の仲」に影響を及ぼすものではない
ただただ、この長雨に、足止めされている「想い人」を案じている
そして、雨に濡れることなく、ちゃんと「廬」を手当て出来たのだろうか、と
今、このような「長雨」に対する感情は、歌に出来ないだろう
雨が降れば、「傘」を当然のように用意する
雨が降っても、旅先での過ごし方など、心配することもない
そうした現代に生きる私が、
この歌のように、雨がしきりに降り続いている情況で
相手のことを心配する気持ちが、何故素直に響いてくるのだろう
「新鮮」な感覚、というのだろうか
そう思うと、千数百年も前に生きる人たちの所作など、理解できないようで
しっかり理解、いや感じとして解る、ということなのだろうか
旅先の不具合を心配することは、いつの時代にもある
どんなに時代がハイテク機器に守られようと、
人々の「心配」するという「人間的」な感情は決して消えることはない
勿論、その背景はどんどん変わってくる
その中で、こうした歌が読み伝えられ、残るのは
時代がどうの、歴史がどうの、ではなく
人が何を精神の元として残していきたかったのか、
それぞれの時代で、こうした歌に触れる人たちの直観的な「責任感」なのかもしれない
現代のような、何かで足止めされても、確立された通信手段の恩恵で、
少なくとも、こうした相手のことを「思い遣る」精神というものが変革している
そこでは、「無事なのか」「影響はどうか」で終ってしまうものだが
万葉の時代の人々の歌に見られるように
その「心配」の中に、「想い」というものがこめらている
通信できない情況なのだから、なおさらその想いは強いはずだ
現代人が、こうした古典の歌集に「何かを感じる」のも
一つ一つの言葉が、想いをこめられたものであることを、
無意識の内に、感じ取っているからなのだろう
この歌も、『古今六帖』に載る
| うめのはな ちらすはるさめ おほくふる たひなるきみは いほりせるらむ |
| 古今六帖 第四 別 2428 |
元の『万葉集』歌との違いは、「いたくふる」が「おほくふる」
これは、原文をそのまま訓んだような形だ
梅の花を散らすほどの「多く降る雨」という感覚を、平安の人は理解していた、ということだ
勿論、それが結果的に「いたくふる」のように、「ひどく」の意味なのは承知している
しかし、中世以降に「多零」を「いたくふる」との意改で安易に訓むものではなく
原文の「多零」を尊重して訓む気持ちが、私には感じられる
「さはにふる」もまた、意訓ではない
古語辞典での「さは」は、「数多く・たくさん」とする副詞「さは」で、
この「多」を当てている
しかし、「さはにふる」と、その訓の万葉仮名の歌が一首もない以上
「多」を「さはに」と訓む他の歌の用例に沿ったものでしかない、ということになるのか
万葉仮名の「伊多久奈布里曾」(4246)、僅か三首の歌の中で、この歌一首の影響は大きい
|
|
| |




 |
掲載日:2014.02.21.
| 春相聞 寄雨 |
| 梅花 令散春雨 多零 客尓也君之 廬入西留良武 |
| 梅の花散らす春雨いたく降る旅にや君が廬りせるらむ |
| うめのはな ちらすはるさめ いたくふる たびにやきみが いほりせるらむ |
| 巻第十 1922 春相聞 寄雨 作者不詳 |
【注記】〔1874・1640・4246〕
| 【1922】語義 |
意味・活用・接続 |
| うめのはな[梅花] |
| ちらすはるさめ[令散春雨] |
| ちら[散る] |
[自ラ四・未然形](花や葉などが)散る |
| す[助動詞・す] |
[使役・終止形]~せる |
未然形につく |
| いたくふる[多零] |
| いたく[甚し] |
[形ク・連用形]程度が甚だしい・激しい |
| たびにやきみが[客尓也君之] |
| に[格助詞] |
[位置]~で・~に |
体言につく |
| や[係助詞] |
[疑問・係り結びの「係り」]~か 〔接続〕種々の語につく |
| いほりせるらむ[廬入西留良武] |
| いほり[廬] |
仮小屋に泊まること・旅先で仮の家にいること |
| せ[為(す)] |
[他サ変・未然形]ある動作を行う・ある行為をする |
| る[助動詞・り] |
[完了(継続)・連体形]~ている |
サ変は未然形につく |
| らむ[助動詞・らむ] |
[現在推量・連体形]今頃~ているだろう |
ラ変型は連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [うめのはな] |
『近衛本』では、「う」がなく「めのはな」
『万葉集』のテキストでは、一般的に「めのはな」はなく、
この古写本が、この歌のみ「めのはな」としたかどうか、今のところ私にはわからない |
| |
| [ちらすはるさめ] |
原文の「令散」を「ちらす」と訓むが、なるほど、と思った
『万葉集』の表記では、漢字を借訓・借音して訓まれるが、統一的な使用法ではないので
私など、よく混乱する
音を借りているだけなのに、それに気づかず、やたらと「意味」を考えたり...
この「令」は、漢和辞典にも「~しむ・~せしむ」として使役の助字とある
となると、「令散」が、「散らせしむ」の意だと、古典の苦手な私でも理解できる
こうした出会いには、嬉しさが伴うものだ
後段にも記すが、この歌には、この他にもこうした出会いがあり
私にとっては、楽しい「一首」になった |
| |
| [多零(いたくふる)] |
この原文「多」の異訓は、「さはに」
『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕に載り、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕も倣う
私も通説の「いたく」より「さはに」の方が適っていると思う
確かに、春雨が「多く降る」とする表記は、
多く降る雨の「激しさ」を思い起こさせるが、
「いたく」とする他の歌の用例では、「甚」が使われている
「多(さはに)」は、数の多さを甚だしく言う場合の使い方が多い
ならば、あまりにも多くの雨の降るつけるさま、を訓んだ方がいいのではないか、と思う
『万葉集』中での用例では、「いたくふる」は掲題歌の一首しかないが
「いたくなふりそ」という表現が三首ほどある
その「いたく」の表記を拾ってみた
| 春雑歌 詠花 |
| 春雨者 甚勿零 櫻花 未見尓 散巻惜裳 |
| 春雨はいたくな降りそ桜花いまだ見なくに散らまく惜しも |
| はるさめは いたくなふりそ さくらばな いまだみなくに ちらまくをしも |
| 既出〔書庫-14、2014年1月9日〕巻第十 1874 春雑歌 詠花 作者不詳 |
この「甚勿零」は、まさしく「激しく降らないでくれ」という意味だ
傷めつけるような激しを表現している |
〔歌意〕2014年1月9日時点での訳そのまま転載
春雨よ、そんなに激しく降らないでくれ
桜の花を、私はまだ見ていないのだから...
それなのに、散ってしまうのがとても残念だ |
| |
| 冬雜歌 / 舎人娘子雪歌一首 |
| 大口能 真神之原尓 零雪者 甚莫零 家母不有國 |
| 大口の真神の原に降る雪はいたくな降りそ家もあらなくに |
| おほくちの まかみのはらに ふるゆきは いたくなふりそ いへもあらなくに |
| 既出〔書庫-8、2013年7月2日〕巻第八 1640 冬雑歌 舎人娘子 |
| この「甚莫零」もまた、降る雪の激しさを直感させる |
〔歌意〕2013年7月2日時点での訳そのまま転載
(おほくちの)この真神の原に降る雪よ
そんなにひどく降らないでおくれ
家もないのだから...
|
この二首については、「甚」と表記している以上、
その激しさ故に、桜花が早々と散る心配をし、
「真神の原」の雪は、その降雪の多さをも含めて、「ひどく」という感覚にしたくなる
いずれも、「甚」の底にあるのは、「多」を含めたものをうかがうことが出来る
さらに、残りの一首は、万葉仮名なので、
「いたくなふりそ」と訓む手助けにはなっただろう
| (九月三日宴歌二首) |
| 許能之具礼 伊多久奈布里曽 和藝毛故尓 美勢牟我多米尓 母美知等里テ牟 |
| この時雨いたくな降りそ我妹子に見せむがために黄葉取りてむ |
| このしぐれ いたくなふりそ わぎもこに みせむがために もみちとりてむ |
| 右一首掾久米朝臣廣縄作之 |
| 巻第十九 4246 宴席歌 久米朝臣広縄 |
| 「伊多久奈布里曾」の訓は、間違いようもなく、こうした表現の確認になる |
〔語義〕
「みせむ」は、上一段動詞「見る」の連用形「み」に、
サ変動詞「為(す)」の未然形「せ」、そして推量(意志)の助動詞「む」
「てむ」は、完了(確述)の助動詞「つ」の未然形「て」に、推量の助動詞「む」で、
強い意志を表し「~てしまおう・(きっと)~しよう」 |
〔歌意〕
この時雨、そんなにひどく降るなよ
雨で散る前に、いとしい妻に見せたいので、
早く黄葉を採ってしまおう |
僅か三首の例としても「いたく」が「ふる」に修飾する語としては
その歌意に沿えば充分理解できる
異訓でいう「さはに」では、「さはにふる」でも、「さはにはふりそ」でも
その用例は一首もなかった
しかし、ならばどうして「甚」を使わないのだろう
『万葉集』での雨などが激しく降るような表現の仕方では、
「甚」の方が少ない用例とはいえ、有り触れた使い方ではなかったかと思う
それを、「多」で表現するのは、他の「さはに」が、「多さ」を意味し
この雨の場合でも、降雨量の「多さ」が結果的に「ひどく降る雨」を表現するのなら
この「多」は、「さはに」と訓む方が、素直ではないか、と思う
「いたくふる」のは、「梅の花を散らせるほどの激しい雨」
「さはにふる」のは、「絶え間もなく降り続き、梅の花も散ってしまうほどの雨」
単に、激しさを言うのではなく「多零」で、鬱陶しいほど降り続く雨のことを
表現したのかな、と思う
ちなみに、『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕では、
またも「誤字」説を採っている
「多は重の誤なるべし、草書よく似たり、さらばシキテフルと訓べし」と...
意味としては、幾重にも重ねるように降り続く雨のことなのだろうが、
やはり極力「誤字」説は、避けたいものだ
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕の「補注」に
「いたくの原文『多』は、雨量のおびただしさをしめす」と載せた上で、
その訓については「いたくふる」のままだ
その「補注」で、藤原宮第二十四次出土木簡の表記例を紹介している
『雪多降而甚寒』
ただ載せるだけで、何も解説もないし、その『新全集』の本旨ではないのだろうが
私なりに、拙いながらも「訓」をつけてみた
「多」と「甚」がともに表記されているので、面白い
「ゆきさはにふりて いたくさむし」
専門家が目にしたら、「いたく」ご立腹のことだろう
|
| |
| [たびにやきみが] |
素人がつい陥ってしまう、こうした「にや」のような語だ
私は、初めに「にや」と思ってその語義を調べた
その「にや」には、二つの「成立ち」がある
| 『にや』 断定の助動詞「なり」の連用形「に」+係助詞「や」 |
①(連体形の結びを伴って、「にやあらむ」「にやありけむ」の形で)
「~であろうか・~であっただろうか」
②(文末に用いられて①の結びの「あらむ」などが省略された形で)
「~であろうか」
③(はっきりわかっていることを、わざとぼかして遠回しにいう)
「~だろうか」 |
| 『にや』 格助詞「に」+係助詞「や」 |
①(疑問の意を表す)
「~に~か」
②(反語の意を表す)
「~に~だろうか(いや、~でない) |
これらを当てはめようとすると、私ではなかなかしっくり使えない
そんなときには、その「成立ち」を追って考えてみればいい
どちらも、「体言」に接続するので、その次の作業は、当然歌意に沿うかどうか
学校の授業なら、すぐに先生に質問するのだろうが、
今更ながらに、高校の古典授業に「睡眠時間」を当てていたことが、悔やまれる
そして、いっそのこと、「に」と「や」それぞれ元の形にして考えてみた
むしろ、その方が、私にはしっかり感じがつかめてくる
面倒だから、「にや」という語が古語辞典に載っていたので、そのまま使おう
などと考えていたけど、
最終的に、おそらくこうだろう、と採り得た解釈に出会ったときは
まるで難解なパズルを解いたようで、格別嬉しいものだ |
| |
| [いほりせるらむ] |
まず、現在推量の「らむ」は、第四句の係り結び「や」の「結び」にあたり、
「連体形」で終る
「いほり」は、簡単な小屋を造って旅寝をすることだが
「いほりせ」は、一般的に「いほりす」として使われ、その「未然形」になる
次の完了の助動詞「り」は、四段動詞には已然形につくが、
サ変動詞には「未然形」につく
この「る」は、その助動詞「り」の「連体形」
最後の現在推量の助動詞「らむ」は、終止形に尽くの基本となるが
助動詞「り」が「ラ変型」の活用であり、その場合には「連体形」つく
ここでも、「パズル」を解くような楽しみができた
もっとも正解かどうか、確かとは言えないが...
尚、小学館の『新全集』の「補注」によると、
原文「廬入」を、「いほり」の語源が「いほいり」と解した表記だとしている
|
| |
|
|
| 【歌意1923】 |
国栖たちが、春菜を摘むという司馬の野は、
その「しま」で想いを起こされて
何度も何度も、あなたのことが想われるこのごろです |
「国栖」が「万葉集中」では、この一首だけの歌だと言う
その「国栖」を使って、「春菜を摘む司馬の野」を詠うのは
「しばしば」につながる「幾度も幾度も」想い起こすあなたのこと
だとすると、「国栖」という古記にいう「都人」とは違った生活の習俗にも意味があるはずだ
私が、初めて「国栖(くず)」という名称を知ったのは、もう随分昔のことだ
学生の頃だったと思う
黒岩重吾「天の川の太陽」という小説で、その登場する吉野の人たちを知った
以後も、その「壬申の乱」を題材にした、能楽「国栖」を、
能楽の知識などないまま鑑賞した記憶がある
何しろ、当時の私は「万葉集」に絡む「古代史」にも夢中だったので
この種の「物語」は、何でも聞き、何でも見たものだ
この小説を読み、高市皇子や、舎人たちの生き様に感じ入ったのも事実であり
その頃、後の「公家政治」の「なよなよ」した世の中になる前の「豪族たちの時代」に
心を躍らせていた
だから、その頃の私にとって、大伴家持などの後期万葉の歌人たちではなく
『万葉集』といえば、柿本人麻呂や大津皇子、高市皇子などの時代だった
従って、「国栖」といえば、私には当然その時代の面影が浮び離れるものではない
その頃の「国栖」のイメージでは、近江朝廷から逃れるようにして吉野に下った大海人皇子、
その皇子に協力して血気を助けた「国栖」の人たち
能楽では、隠れるようにして吉野にいたこの皇子たちが、
国栖人に見つかり、匿ってくれという...何となく覚えている
その「国栖」が舞台の、この歌
いくら、「しばしば」を導く「国栖の司馬の野」だとは言っても
そこに、「国栖」ならではの思い入れがあって欲しい、と思う
作者が「国栖」を舞台にした「想い」は、いったい何だったのだろう
「国栖」の人たちは、古来より権力者、体制側に与しない人たちだと評されている
だから、大海人皇子を匿ったのだ、というようだが
それが、ある面で本質なら、この歌にだって、それが投影されない訳がない
作者も、「国栖」の人たちの古来からの習性は知っていたはずだ
そして、この歌を詠うのに、それを無視して、単に序詞のために使ったとは思えない
作歌の時期が、すでに太平の世であっても
「国栖」の野の先に見えるものは、少し前の「戦乱」まで思い起こせるだろう
「部立て」は、「春相聞」とされ、恋しい人を想うこのごろ、と訳せはするが
その「想う人」とは...飛鳥時代、奈良時代よりそれほど経っていない、「壬申の頃」
その当時のことを想い馳せているのではないだろうか
当時幼い娘だった作者が、その吉野の地に勇ましく戦い、過ごした人たちの中に、
「想い人」を見つけてもおかしくない
大海人皇子が戦乱に勝利し、また平穏な吉野に戻った時、
地元の老いた作者が思い出すのは
あの頃の「若者たち」...そして「想い人」
今、こうして何度も何度も、思い出されてしまう
それが「国栖」を舞台にした「序詞」の映像のように思えてならない
この歌も、後の歌集に「本歌」として使われている
| くにすこの わかなつまむと しめしのの しはしはわれを おほせわかせこ |
| 古今六帖 第一〔歳時〕49 |
| くにすらか わかなつまむと しめしのに あまのきみか よきりころほひ |
| 赤人集 一 202 |
| くすひとの わかなつむらむ しはののの しはしはきみを おもひそむらし |
| 夫木和歌抄 第一 214 読人不知 |
『古今六帖』は、『万葉集』とほぼ同数の和歌を採集しているが、
『万葉集』からも千首以上が載せられている
四千五百首余りの歌の中から千首ばかりが、選ばれたのだから、
少なくとも、万葉時代から二百年以上経ても、この歌は「霞むことはなかった」ということだ
それを、私は「国栖」に対するこの時代の人の「思い入れ」も少なからずあったのだと思う
当時の人たちにとって、「国栖人」たちは、天皇時代の立役者でもあったはずだ
それが、たとえ「序詞」として後の世に解されようとも、
この時代では大きな意味を持っていたと思う
能楽の「国栖」の作者も、世阿弥以前の古典的な「能」とされている
「国栖」が、単に「序詞」だけでは終らない何かを、教えているに違いない
|
|
| |



|
掲載日:2014.02.22.
| 春相聞 寄草 |
| 國栖等之 春菜将採 司馬乃野之 數君麻 思比日 |
| 国栖らが春菜摘むらむ司馬の野のしばしば君を思ふこのころ |
| くにすらが はるなつむらむ しまののの しばしばきみを おもふこのころ |
| 巻第十 1923 春相聞 寄草 作者不詳 |
| 【1923】語義 |
意味・活用・接続 |
| くにすらが[國栖等之] |
| くにす[国栖] |
奈良県吉野郡吉野町国栖辺り |
| はるなつむらむ[春菜将採] |
| らむ[助動詞・らむ] |
[推量(伝聞)・連体形]~ているという・~そうだ |
終止形につく |
| しまののの[司馬乃野之] |
| しまのの[司馬の野] |
地名の所在は不明、異訓がある |
| しばしばきみを[數君麻] |
| しばしば[屡] |
[副詞]たびたび・何度も |
| おもふこのころ[思比日] |
| このころ[此の頃] |
近頃・近いうち・今頃・今時分 |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [くにす] |
『日本書紀』応神紀「夫国栖者、其為人甚淳朴也。毎取山菓食、亦煮蝦蟆為上味、名曰毛瀰。其土、自京東南之、隔山而居于吉野河上。峯嶮谷深、道路狭巘。故雖不遠於京、本希朝来。然自此之後、屡参赴以献土毛。其土毛者、栗・菌及年魚之類焉」(十九年十月一日条)とあり、
生活習俗が異なることで知られていた
『古事記』(中)には「国主」と記されており、後世では「くず」とも呼ばれる
上記の記事によると、性質は純朴で、山の果実を採食し、蛙料理が美味しく、
たびたび難路を越えて参入し、栗・茸・鮎さどを献上したりしていた
「国栖」を詠った万葉歌は、この一首のみ
吉野宮滝から吉野川沿いに溯ってある浄見原神社に、国栖奏(くずそう)が伝わっている
|
| |
| [はるなつむらむ] |
「春菜」を「はるな」と訓むのが普通だと思うが、
何故か「わかな」と訓む書も多い
『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕にそれが見えるが、
本格的な注釈書としては、もっとも古い『万葉集註釈』〔仙覚、文永六年(1269)成〕、
これは私も知ったばかりだが、この注釈書は、別名『万葉集抄』とも言われているようだ、
しかし同じく『万葉集抄』と呼ばれるものに、『秘府本萬葉集抄』があるらしい
これは、仙覚以前の訓を知る上で、とても重要だと言われる資料らしい
この『秘府本萬葉集抄』を『校本』では「異伝」として載せている
その『秘府本萬葉集抄』には、
「國栖等之春菜將採司馬乃野之数君麻思背」
〔クスヒトノワカナツムランシメノヽノシハシモキミヲオモヒソムラシ〕と訓じられ
「クス人トハ吉野ノオクニクス人ト云夷ノオホヤケニモシラレタテマツラテカクレテ有ケルヲ神皇后又清原天皇ナトノオハシマシタリケルニミツケラレマイラセテアユト云魚ト菜ナトヲ進タリケル其ヲメシタリケルヲミテ悦テワラヒテクチヲタヽキテ笛ヲフキケルサレハワカナツムトハシル也サテ今ニイタルマテ節會ニハ其クス人フエタクミハマイリテ御菜ヲマイラスル也正月節會ニ必スマイリテワカナヲ進スルナリ 」(赤字はテキストとの異訓)
この解説は、前注記「くにす」の『日本書紀』で記されていることと同じ内容だが
この書で言う「わかな」というのは、歌で言う「はるな」を、
実際の「菜」としての「わかな」と言い換えただけのように思える
何故原文の「春菜」を「わかな」と訓じるのか、が書かれていない
だから、仮に最初の注釈書を重んじるばかりに「わかな」と訓むのは、
無批判で一つの説を鵜呑みにするようなものだ
もっとも、『万葉研究史』などは多くの書があり、私の理解は見当違いかもしれないが
今後は、それらにも触れてみたくなった
そして、「異訓」について言えば、「左頁」でも紹介する、
『古今和歌六帖(こきんわかろくぢょう)』(成立年代未詳だが、976~987年が有力らしい)
『赤人集』成立年時未詳(740年頃)
『夫木和歌抄(ふぼくわかしょう)』〔延慶三年頃(1310年頃)〕
これらの三つの「歌集」での掲題歌は、「異訓」というよりも、
この『万葉歌1923』を元歌にして歌い継がれたような気がする
「左頁」で載せる三首は、すべてが「わかなつむ」と詠む
原文の「春菜」がどうのこうのではなく、「歌」として「わかな」と詠んだと思う
|
| |
| [しまのの(司馬乃野)] |
『西本願寺本』が「しばのの」とするが、多くの注釈書は「しまのの」と訓む
「馬」を「ま:託馬野(たくまの)」や「め:敏馬(みぬめ)」などのように使用例はあっても
「ば」と詠まれた例がない、ということらしい
『講談社文庫本』では、「馬」を「漢音バ」の例がない、としている
実際の所は、私にも分からないが、このように「馬」が「ば」と詠まれないのは
当時ではあったのかもしれない
しかし、鎌倉末期の『西本願寺本』が、「ば」と訓むのは、
その頃には「馬」が「ば」とも訓まれるになっていた、ということなのだろうか
それとも、『万葉集』中に「ば」と詠まれた歌がない、というのも
そうした「訓読」がされていなかっただけなのだろうか
平安末期の『類聚古集』では、「しめのめ」と訓じられ、
それは、同じ時代の前述の『秘府本万葉集』や、
もっと古い『古今六帖』で使われている
多くの書に底本とされている『西本願寺本』による、「しばのの」とするのは
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕、
『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕、
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕など、比較的新しい注釈書だ
もっとも、この「しばのの」に拘るのは、もう一つ理由がある
この第三句までが、類音で次句「しばしば」を導く序詞とされていること
この解釈には、どの注釈書も異はない
だとすると、素人には、「しばのの」なら、「類音」ではなく「同音」の繰り返しであり、
「しばのの」方が、よりすっきりと「序詞」を説明できるじゃないか、と思うのだが、
これについては、『全注』が説明している
「シマノノ・シメノノ・シバノノの訓はいずれも可能性はあるが、類音の繰り返しによる序詞の例が珍しくないことよりすれば、集中の馬の用字例にもかない、シマ-シバの繰り返しの自然なシマノノ説によりたい。古義・私注・佐佐木評釈以下、現行注釈書の多くがこれを採っている。」
「同音」も「類音」も、同じようなものなのか...
珍しくない、という根拠も、おそらくその「珍しくない」とされる他の歌においては、
この掲題歌もまた、「珍しくない」側の一首になるだろうなあ、きっと
ついでに言えば、「しまのの」と訓む注釈書の中でも、
やはり同音の繰り返しによる「序詞」だとする書もある
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕、
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕、
そして『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕がそうだ
「しましまきみを」と訓む
『全註釈』の説明には、いくらなんでも首を傾げざるを得ない
「『馬』は、字音仮字として『マ』にも『メ』にも使用されている。ここは次に『シマシマ』とあるを引き起こすのだから『マ』として使っているのだろう。」
この後に、次の句の「しばしばきみを」という定訓を、
「しましまきみを」とする根拠が説明されているのなら、
一学者の見解として理解できるのだが、そのことには全く触れていない
あたかも第四句「しましまきみを」が、定訓であるかのように述べ、
だから、第三句の「しまのの」が正しい訓だ、と言っているかのようだ
もっとも、大学者になると、多くの論文が書かれており、
この「しましま」は既に発表済の説なのかもしれないが...
しかし、この『全註釈』だけで「注釈書」と銘打つ以上、解説不足だとは思う
それにしても「しましま」という語があるのだろうか...
|
| |
| [しばしば] |
原文「數(数)」には、古語辞典にも「かず」として、
「多数・いろいろ」の語義も載っている
だから、「しばしば」の「何度も・たびたび」の意にも繋がるものだが、
これを「しましま」と訓むには、私にはどうにも理解できない
どこで、繋がるのだろう
そもそも「しましま」という語義は、いったい何なのだろう
これも、岩波の古語辞典が頼りになった
その他の古語辞典では、「しばしば」は載っていても、
それが「しましま」に関連付けられるような記載はされていない
かろうじて、副詞「しまし」が、副詞「しばし」の「古形」とあり、
少々近づいたかな、と思ったが
しかし、「しばし」と「しばしば」では、意味がどうも繋がらない
「しばし」は、少しの間・ちょっとの間・しばらく、とあり
「しばしば」は、何度も・たびたび、とある
同じようで、やはり違う
諦めかけて、岩波の机上版を広げてみたら、「しばしば」に手掛かりがあった
「シバはシバシ(暫)のシバと同根。短い時間の意。従ってシバシバは、ちょこちょこと、が原義」とあって、「幾度も・何度も」と載せている
この説明だと、「しばし」の「ちょっとの間」を原義とする、「幾度も」の「しばしば」
ということになる
ならば、その「しばし」の「古形」である「しまし」もまた、同様に「しましま」となる
可能性とすれば、それしかないように思えるが、「しまし」は古形として存在しても
「しましま」という語そのものが、何も語られていない
しかし、この歌の「数」を、「しましま」と訓み得る可能性も、少なからずあった、
ということにはなると思う
現代感覚では「しましま」などとは、思いもつかない「語」そして「語感」だが、
この当時に、それが「語」として存在していなかった、とは言い切れない
「しましま」と訓む注釈書では、その説明が欲しいものだ
|
| |
|
|
| 【歌意1924】 |
春草が、盛んに繁るような私の溢れる想いは、
それが今では、もっと大きく溢れ
大海の幾重にも重なる波が、岸辺に押し寄せるように激しく
こんなにも、恋心が積もってしまった |
この歌の評価は、散々なものだ
一首のなかに、枕詞と序詞を歌い込んでいること
確かに、限られた文字数なのに、
定型ともいえる「詞」を多用するのはいいことではない
しかし、こうした枕詞や序詞というのは、
「ことば」以上にその情景を膨らませてくれるものだ
「繁き我が恋」を比喩する「春草の」
「千重」を起こす「大海の辺にゆく波の」
この対となるグループが、学者たちに不評らしい
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕では、
「二つの譬喩を使って構成しているが、その譬喩が、春草であり、大海であって、全然連絡のない別種のものを使っているのは、思想の分裂が感じられて、よくない。またその譬喩も平凡だが、内容も平凡である。」
また、『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕も同じように、
「短歌一首の中に枕詞と序詞を詠み込んでいる。しかも枕詞は春草で、序詞は大海の岸辺に寄せる波であるから、一首に統一性がなく、いたずらに形式的な感がある。」
この歌の作者が、この評を聞けば、どんな気持ちになるだろう
実際に、手抜きとまではいかないが、枕詞、序詞をその構成の殆どに使うのは
その内容以前に、ある程度のこのような評価にはなるだろう
しかし、私には作者がそんな気持ちで詠った歌には思えない
以上のような評価が一般的だが、それを踏まえての歌意を見ると、
素人の私でも、がっかりする
その最も落胆させられた注釈書の歌意は、岩波の『新大系』だ
「春草のような盛んな私の恋は、大海の岸に寄せる波のように千重に積もった」
こんな風に端的な訳し方だと、先の酷評のように、前句と後句がしっくり繋がらない
作者が詠ったのは、その「あいだ」のことのはずだ
岩波に限らず、先の『全註釈』も『全注』も同じような訳し方になっている
どうして、この「あいだ」の「想い」を歌意に表現しないのだろう
それが、解っていても、原文の表現にないから、ということなのだろうか
それは違うと思う
枕詞、序詞を使い込んだのは、確かにまずかったと思うが
ならば、どうしてそんな詠い方になったのか
その言葉に埋もれてしまった「想い」があるのだろうか
そんな気持ちで、訳して欲しかった
私が言う、この「あいだ」と言うのは
二つの譬喩の間のことだが、そこに深遠の淵に潜むように「詠われた想い」のことだ
初めの頃は、春草の繁るような、初々しい恋心だったのに
今では、大海の荒波が激しく岸辺に寄せるが如く心に撃ち響かせる
この気持ちこそ、作者の想いを...弾けさせた歌ではないか、と思う
春草の繁き、といえば、まだまだ静的な「淡い恋心」を思わせる
それが、「荒波」という言葉こそ使わなくても、「大海の」で「大海から千重に打ち寄せる」
それは、止むこともない「恋の想い」が幾重にも打ち寄せる
これは、スケール観一杯の表現だと思う
初恋の淡い慕情が、いつしか大海の絶えることのない波のように激しく...
これが平凡な歌だとは...
専門家の評価に私が太刀打ちなど出来やしないが
仮に、そうした注釈書で『万葉集』に親しむ以前の私のスタイルだったら
『万葉集』は、決して私に語りかけてはくれなかっただろう
思い上がった言い方だが、私だけの『万葉集』
私が、その一首から感じたものこそ、『私の万葉集』だ
押し付けられた歌の解釈ではなく、私が受止めた「感じ方」を
たった一人でも、しっかり受止めていきたいものだ
この歌も、『古今六帖』の載る
| はるくさの しけきわかこひ おほうみの かたゆくなみの ちへにつもりぬ |
| 古今六帖 第六草 3544 |
「かたゆくなみの」、旧訓(当時の訓)でも「佳作」として載せたのだから
どうして契沖は、「へにゆきなみの」としたのだろう
当時の研究資料に、きっかけがあったのだろうか...
|
|
| |
|
掲載日:2014.02.23.
| 春相聞 寄草 |
| 春草之 繁吾戀 大海 方徃浪之 千重積 |
| 春草の繁き我が恋大海の辺に行く波の千重に積もりぬ |
| はるくさの しげきあがこひ おほうみの へにゆくなみの ちへにつもりぬ |
| 巻第十 1924 春相聞 寄草 作者不詳 |
| 【1924】語義 |
意味・活用・接続 |
| はるくさの[春草之]〔枕詞〕「しげき」にかかる |
| しげきあがこひ[繁吾戀] |
| しげき[繁し] |
[形ク・連体形]草木が生い茂っている・たくさんある |
| おほうみの[大海] |
| おほうみ[大海] |
大きな海・織物や蒔絵の模様の名・海浦(かいぶ) |
| へにゆくなみの[方徃浪之] |
| へ[辺] |
(沖に対して)海辺・岸辺・ほとり・あたり |
| ちへにつもりぬ[千重積] |
| ちへ[千重] |
幾重にも重なっていること |
| つもり[積もる] |
[自ラ四・連用形]積み重なる・かさむ・量が増える・たまる |
| ぬ[助動詞・ぬ] |
[完了・終止形]~てしまう・~てしまった |
連用形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [はるくさの] |
枕詞「なるくさの」は、意外と少なく三首のみ
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕の評では、
繁茂する状態の比喩としては、「なつくさの」の方が相応しい、としながらも
むしろ繁茂した夏草のイメージと異なり、
若々しく柔らかなイメージが「春草の繁き」にはある、とする
『万葉集』中の「春草の」は、三首だが、「夏草の」は九首ある
|
| |
| [おほうみの] |
原文「大海」を、一般的には「おほうみの」とするが、
比較的新しい注釈書だと、「おほきうみの」としている
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕、
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕
『新全集』の「注」によれば、
「原文に『大海』とあり、オホウミと読むこともできるが、『於保吉宇美』(4515)の仮名書き例があり、『和名抄』にも〔溟渤、和名於保岐宇三〕とあるのによる」とある
訓み方としては、仮名書きのように「おほきうみ」とするのは解るが
実用的な「名称」と、「歌」で用いる「名称」とは違うこともあると思う
実際は「大海」を「おほきうみ」と言うのが日常の中で使われたとは思う
しかし、歌に詠う場合にはそうした「語」を、いかに「生きた歌の語」にするか
それも詠い手の「技」だと思う
「大海」を、歌として詠じるとき、「おほうみの」としたのは
その五音というリズムに合わせて調子も良いし、
あくまでも「おほきうみの」とする場合には、最後の「の」を詠わず、
「おほきうみ」のままでいいはずだ |
| |
| [へにゆくなみの] |
原文「方往浪之」の「方」を、旧訓では「へ」ではなく、「かた」とする
『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕は、「かたゆくなみの」としている
その場合の「かた」は、おそらく「潟(かた)」の意ではないかと思う
その「潟」の意味は、
「遠浅になっている海岸で、潮の干満によって見え隠れする所・干潟・浦・入り江」
この訓も、私には味わい深いものがある
まず、「へに」という場合の助詞「に」が、
「潟」では読まなくてスマートに詠える
歌で、あまり助詞を詠わないほうが、私は好きだ
日常の会話ではなく、歌には多くを略して多くを表現するものだ、と思っている
だから、「へにゆくなみの」よりも「かたゆくなみの」の方がいいと思うけど
どうして、「かた」は普及しなかったのだろう
「方」も「かた」と読めるし、無理はないと思うのだが...
『万葉代匠記(初稿本)』〔契沖(1640~1701)、貞亨四年(1687)成〕が、
その旧訓を、「へにゆくなみの」と改めた、ということらしい
さらに、『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕による、
「往」は「依」の誤り、とする説を採って、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕は、「へによるなみの」と訓む
|
|
|

|
| 【歌意1925】 |
まともに、あなたを見ることもできず
菅の根のように長い、この春の一日を、
恋しく想い続けるのでしょうか... |
結句の「かも」を、「詠嘆・感動」の終助詞とする訳ばかりだ
それは、初句の「おほほし」の解し方によるものだと思う
岩波『大系』「はっきりとあなたにお逢いできなくて」
岩波『新大系』「ぼんやりとあなたを見て」
小学館『新全集』「おぼろげにあの方を見て」
新潮『集成』「おぼろげにあなたをお見かけしたばかりに」
有斐閣『万葉集全注』「ほのかにあの方にお逢いして」
岩波が明快な訳語だとする、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕は「はっきりではなしに」
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕は、「ぼんやりとあなたを見て」
など、みな同じような訳なので、当然その結句も、同じようになるだろう
だいたいが、「詠嘆・感動」の「恋つづけることです」のようになる
私の「歌意」について書く前に、「類想歌」と言われる歌を載せる
| 春相聞 寄霞 |
| 春霞 山棚引 欝 妹乎相見 後戀毳 |
| 春霞山にたなびきおほほしく妹を相見て後恋ひむかも |
| はるかすみ やまにたなびき おほほしく いもをあひみて のちこひむかも |
| 既出〔書庫-15、2014年2月12日〕巻第十 1913 春相聞 寄霞 作者不詳 |
〔歌意〕2014年2月12日時点そのままの転載
春霞が、山にたなびいて、ぼんやりと景色を霞ませているように
しっかりと見ることができずに、あの娘と逢ったので、
これからは、それがわたしの恋心を募らせていくのだろうか
(しっかりと見たはずなのに...)
|
| |
| 寄物陳思 |
| 夕月夜 五更闇之 不明 見之人故 戀渡鴨 |
| 夕月夜暁闇のおほほしく見し人ゆゑに恋ひわたるかも |
| ゆふづくよ あかときやみの おほほしく みしひとゆゑに こひわたるかも |
| 巻第十二 3017 寄物陳思 作者不詳 |
〔語義〕
「ゆふづくよ」は、〔枕詞〕「あかときのやみ」にかかる
「あかときやみ」は、夜明けには月が没し、「暁闇(あかときやみ)」になる |
〔歌意〕
「夕月夜」が、まるで明け方の闇夜のようにぼんやりと、見た人なので
こんなにも私は、恋つづけているのだろうか |
この二首の「おほほし」は、自然現象の物理的な「不明瞭さ」がまずある
しかし、「想ひ人」をしっかり見られなかったのは
そのせいではなく、作者が「しっかりと見なかった」ことを
この「霞」や「暁闇」の現象に重ねているものだと思う
...そんな訳は、どの書も用いていないが
この既出の一首〔1913〕のときは、私の思い入れが強いのだろうなあ、と思ったものだ
しかし、今日の歌に触れて、その想いがいっそう強くなった
確信のようなものだ
それを更に後押ししてくれたのが、「孤戀」という表記になる
賀茂真淵が言うような、決して「誤写」ではない
「孤悲」のように「寂しさ」「悲しみ」を重ねてはいないが
はっきりと「孤独な恋」と作者は詠いたかったはずだ
ならば、その「孤独な恋」というものは、どんなものなのだろう
自分の意志に関わらず「ぼんやりと」や「おぼろげに」とか「ほのかに」ではなく
自分の意志を持って、「まともに」見ることの出来ない「想い人」なのだと思う
それほど「眩しい人」であれば、偶然にも見かけてしまったものの
とても見ることが出来ない
こんな調子では、この先もずっと恋つづけてしまうのではないか
「おほほし」には、「憂鬱である・心が晴れない」という意味もあるではないか
結句の「かも」が「詠嘆・感動」のでもいい
しかし、私にはそれだけでは収まらない作者の気持ちが響いてくる
「このまま...恋つづけることになるのか、孤独な恋に...」
決して「恋してしまったなあ」ではない
|
|
| |
|
掲載日:2014.02.24.
| 春相聞 寄草 |
| 不明 公乎相見而 菅根乃 長春日乎 孤悲渡鴨 |
| おほほしく君を相見て菅の根の長き春日を恋ひわたるかも |
| おほほしく きみをあひみて すがのねの ながきはるひを こひわたるかも |
| 巻第十 1925 春相聞 寄草 作者不詳 |
【左頁[類想歌]】〔1913・3017〕
| 【1925】語義 |
意味・活用・接続 |
| おほほしく[不明] |
| おほほしく |
[形シク・連用形]ぼんやりとしている・憂鬱である |
| きみをあひみて[公乎相見而]あなたに逢って |
| すがのねの[菅根乃]〔枕詞〕「長き」にかかる |
| ながきはるひを[長春日乎]長い春の一日を |
| こひわたるかも[孤悲渡鴨] |
| わたる[渡る] |
[自ラ四・連体形](連用形の下について)ずっと続ける、の意 |
| かも[終助詞] |
[詠嘆・感動]~であることよ |
連体形につく |
| [疑問]~か・~だろうか |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [おほほしく] |
原文「不明」...これを「おほほしく」と訓むのは、『万葉集』中で二首しかない
この掲題歌の他では、〔巻第十二-3017 左頁「類奏歌」〕がある
しかし、「不明」という表記においては、この二首を含めて四首がみえる
| 不明 公乎相見而(第一、二句) |
おほほしくきみをあひみて |
掲題歌 巻第十 1925 |
| 不明毛有寐鹿(第五句) |
あけずもあらぬか |
巻第十 2074 |
| 不明行哉(第五句) |
あけずもいかぬか |
巻第十二 2870 |
| 不明 見之人故(第三、四句) |
おほほしくみしひとゆゑに |
類想歌 巻第十二 3017 |
「あけず」と訓むのは、文字通りの原文の意味をいっている
それぞれが、その前句の「今夜」「夜等者」に続き「夜も明けず~」となる
そして、形容詞「おほほし」は、その歌意に沿えば、本来の「不明」にはならないが
明るくならず、はっきりしない、ぼんやり...とする語意の連想なのだろう
ただ、「おほほし」には、「憂鬱である・心が晴れない」とする意味もある
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕においては、
「今本ほのかにもと訓たれど、さてかなはず」として「おぼろかに」とし
さらに、『寛永版本』を底本とする『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕では、
「ほのかにも」としている
『神宮文庫本』は、その「不明」の左に「あかさりし」とある
|
| |
| [孤悲] |
私の好きな「万葉集の語」の中で、おそらくこの「語」に一番惹かれていると思う
幸せな恋もあるふだろう、夢のような恋もあるだろう
でも、『万葉歌』に相応しい「こひ」の響きは...「孤悲」に勝るものはない
ただし、この原文「孤悲」だが、『西本願寺本』では「孤戀」となっている
この校本を底本とする諸注でも、この箇所については、
『元暦校本・類聚古集・紀州本』の「孤悲」に拠る
「全歌の初めて」の注釈書と言われている、
『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕もまた、
その底本を『西本願寺本』としながらも、「孤悲」に改めているのは見逃せない
「孤戀」は「孤悲」の単純な誤写なのだろうか...
それとも、訓はともかく、「孤独な恋」という気持ちを「漢字」の表記にしたのか...
その場合でも、訓は「こひ」で間違いないと思う
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕で、真淵はいう
「今本、『孤戀』とあるは『悲』を誤れるなり。一本によりてあらたむ」と
「孤戀」の表記を、真剣に検証した上でのことなのだろうか... |
| |
|

|
| 【歌意1926】 |
梅の花が散ってしまえば、その花を見に来ていたあの娘だけど
それでも来てくれるのだろうか、もう来ないのだろうか
ずっと「待つ」しかない私は、まさに「松の木」ではないか
【意改】
あの娘が楽しみに見に来ていた梅の花が、散ってしまった
もう来てはくれないのだろうか
来るだろうか、来ないのだろうか、と待ち続ける私は
「松の木」にでもなったようだ |
この歌に限って、ということもないが、
テキストのままに一首を載せると、どうしてもその「語義解釈」でいいのか、と
しかし、取り敢えず書き出してみて、それから先には自分で語義を確認する
そんなことばかりしていると
ふと、「意訳」に過ぎるなあ、と反省することがある
もっとも、これまでにしても、通説は参考にはなるが
そのまま素直に私の心に打ち響いてくることはなかった
やはり、大御所であればあるほど、「他人の想い」の観が強くなる
かといって、自分の感じ方が正しい、と言うつもりもなく
あくまで、こんな風に読めば、私には素直に響く歌なんだけど...と謙虚に...
この歌にしてもそうだ
「意改」と書いたのは、そもそも「語義」からして改めなければ読めない解釈だ
第二句の訓にしても、さらに言えば、第三句の「わぎもこを」もそうだ
歌としては、読み得ても、「わぎもこ」の訪れを待つ、という歌は、
かなり珍しいといわれる
そこでいろいろな「解釈」が飛び出してくる
しかし、「わがせこを」の間違いではないか、というのは見たことがない
誤字説、誤写説もタブーではない「注釈書」に、
何故か、この「誤字・誤写」説は見られない
ということは、誰もが素直に、男が女の訪問を待つ歌、と受け入れていることになる
しかし、それでも、ではどうして、この「通い婚」の時代に
女の方から、男の家に行くのか、とまた論じられている
「歴史考証」の意味合いからすれば、それも重要なことだとは思うが
これが、「記録文書」ではなく「歌」だと言うことはもっと重視しなければならないはずだ
すべての歌が、「実景」を伴うものではなく
宴席歌のように、「歌」そのものを披露し合うことだってある
もっと言えば、「創作」も多くあると思う
この掲題歌が、創作かどうか解らないが
仮に「待ち続ける恋心」を詠題とするような一群でみれば、
それは男であろうと、女であろうと、問題ではなくなる
ただし、この時代に「男が女の訪れを待つ」ことが
いくら歌であろうと、理解されたかどうか、は別の問題としてあることは間違いないだろう
一般的に言われている、通い婚のスタイルばかりが「恋人」どうしの姿ではないだろうし
この歌に即して言えば、「恋仲」というのではなく
男の方が、一方的に恋い慕っているようにも思える
自分の家の見事に咲く梅の花を、
それが綺麗、だと言ってその季節になるとやって来ていた娘に、
男は、淡い慕情を抱いているのかもしれない
「恋仲」であれば、そんな季節に限らず、逢いたいから「逢う」、「逢いに行く」
それが自然に歌われるものだ
しかし「梅の花が散って」、もう来ないだろうか、などと言うのは
少なくとも、女の方から「恋」という認識ではないことになる
そこまで考えたら、「男が女の訪れを待つ」のも、当然あっていいことになる
この歌では、「待つ」と「松」を掛詞として用いていることから
技巧を競い合った「宴席歌」だという評価も多い
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕が、
「これは、女の方から男の家へ通って来るといふ仲だったのである。これは稀にはあることで、必ずしも格別のことではなかったのである」と評したのに対し、
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕は、
「やはり、個人的な歌としては、男が女の来訪をひたすら待つしかないというのは無理で、実用に供せられた歌ではなく、謡いものとしてその機知がよろこばれたものであろう」とする
このような、男女間の設定や、「謡いもの」あるいは「宴席歌」という固定された観念でしか
どの注釈書も論じていない
しかし、「男女間」が、普通の「恋仲」でなく、男の淡い「恋心」であった場合
何も無理することなく読めるし、感じられるような気もするのだが...
この歌、どちらが本歌なのか解らないが、『赤人集』に一首載せられている
| うめのはな さきてちりなは わかいもを とくみにこむと わかまつのきそ |
| 赤人集 まつによす 205 |
「とく」は副詞「疾く」だろうか
「はやく・すみやかに・さっそく」などの意味がある
梅の花が散ってしまいそうなのでさっそく見に来るだろう、
と、妹を待っている私は、まるで「松の木」ではないか
となるのだろうか...
|
|
| |
|
掲載日:2014.02.25.
| 春相聞 寄松 |
| 梅花 咲而落去者 吾妹乎 将来香不来香跡 吾待乃木曽 |
| 梅の花咲きて散りなば我妹子を来むか来じかと我が松の木ぞ |
| うめのはな さきてちりなば わぎもこを こむかこじかと わがまつのきぞ |
| 巻第十 1926 春相聞 寄松 作者不詳 |
| 【1926】語義 |
意味・活用・接続 |
| うめのはな[梅花]梅の花が |
| さきてちりなば[咲而落去者] |
| な[助動詞・ぬ] |
[完了・未然形]~てしまう・~てしまった |
連用形につく |
| ば[接続助詞] |
[順接仮定条件]~なら・~だったら |
未然形につく |
| わぎもこを[吾妹乎] |
| こむかこじかと[将来香不来香跡] |
| む[助動詞・む] |
[推量・終止形]~だろう |
未然形につく |
| か[係助詞] |
[疑問]~か・~だろうか |
| 〔接続〕体言・活用語・副詞・接続助詞などが主語・目的語・連用修飾語になるものにつく |
| じ[助動詞・じ] |
[打消の推量・終止形]~ないだろう |
未然形につく |
| と[格助詞] |
[引用]「~と言って・~と思って」などの意で、
あとに続く動 作・状態の目的・状況・原因・理由などを示めす |
| わがまつのきぞ[吾待乃木曽]「まつ」は、「我が待つ」と「松の木」の「掛詞」 |
| ぞ[係助詞] |
[断定]~だ |
| 〔接続〕体言、活用語の連体形・種々の助詞などにつく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [落去者(ちりなば)] |
原文に「去」と表記されている (「者」は後述)
一応、底本に異訓はないので、そのまま載せたが、
これが、随分気になって、データを拾い出してみた
既出は、〔1000、書庫-12〕〔1660、書庫-4〕、掲題歌は〔1926〕
| 原文「落去」を含む語句 八首(掲題歌を含む) |
| 黄葉之 落去奈倍尓 玉梓之 使乎見者 相日所念 (散りゆくなへに) |
2-209 |
| 梅花 開而落去登 人者雖云 吾標結之 枝将有八方 (咲きて散りぬと) |
3-403 |
| 如是為乍 遊飲與 草木尚 春者生管 秋者落去 (秋は散りゆく) |
6-1000 |
| 瞿麥者 咲而落去常 人者雖言 吾標之野乃 花尓有目八方 (咲きて散りぬと) |
8-1514 |
| 棹壮鹿之 来立鳴野之 秋芽子者 露霜負而 落去之物乎 (散りにしものを) |
8-1584 |
| 酒杯尓 梅花浮 念共 飲而後者 落去登母与之 (散りぬともよし) |
8-1660 |
| 梅花 咲而落去者 吾妹乎 将来香不来香跡 吾待乃木曽 (咲きて散りなば) |
10-1926 |
| 藤原 古郷之 秋芽子者 開而落去寸 君待不得而 (咲きて散りにき) |
10-2293 |
無益な試みだとは思うが、気になるものはしかたがない
この掲題歌を除く七首の中で、既出の二首だけが確信して述べる〔確述〕の意味になる
つまり、「秋には散る」、「散ってもかまわない」
しかし、その他の五首については、どれも「過去」もしくは「完了」の意を持つ
少ない用例とはいえ、「去る」という語感から、何となく「過去」を思い起こす
勿論、「あきさらば」などのように、仮定条件としての表記で「秋去者」はある
これとて、本来の「秋去者」は、「あきされば」と確定条件とする方が多く
「仮定条件」は少ない
歌意に即して解釈すれば、そう使わざるを得ないこともあるが
多くは、「確定条件」が普通だ
単純に原文「去者」だけを拾い出せば、九十八首ある
この場合の「者」を接続助詞「ば」とするので、その場合の「去」が
「未然形」の「仮定条件」か、「已然形」の「確定条件」なのか、だいたい解る
その「去」の「訓」だけを拾い出してみた 〔計98首〕
| 「確定条件」 |
「仮定条件」 |
| されば |
36首 |
なば |
11首 |
| ゆけば |
18首 |
さらば |
8首 |
| ぬれば |
10首 |
ゆかば |
6首 |
| いぬれば |
1首 |
いなば |
6首 |
| |
65首 |
|
31首 |
| 「者」を「係助詞」とする「去者」も二首ある |
| 去者不別 (行きは別れず) 11-2800 |
吾去者 (我が行きは) 9-1752 |
いや、「確定条件」が普通だ、と書いたが、確かに多いとは言え、
圧倒的というほどでもなかった
掲題歌〔1926〕は、一応「確定条件」の「なば」に入れている
何故こんなことをしたか、と言えば、「去」に拘ったからで
掲題歌のように定訓が「ちりなば」とすれば、その表記の用例は、
掲題歌一首の他は、万葉仮名で一首
残りの二首の「ちりなば」は、「落者」であり「去」がない
| 不手折而 落者惜常 我念之 秋黄葉乎 挿頭鶴鴨残 |
| 手折らずて散りなば惜しと我が思ひし秋の黄葉をかざしつるかも |
| 既出〔書庫-4、2013年3月9日〕巻第八 1585 秋雑歌 橘朝臣奈良麻呂 |
| |
| 春日野之 芽子落者 朝東 風尓副而 此間尓落来根 |
| 春日野の萩し散りなば朝東風の風にたぐひてここに散り来ね |
| 既出〔書庫-12、2013年11月29日〕巻第十 2129 秋雑歌詠花 作者不詳 |
そもそも、「ちりなば」の表現が少ない上に、その訓であっても
「落去者」を、「ちりなば」とするのは、掲題歌しかないことになる
この第二句を、「さきてちりぬれば」(字余りだが)、
あるいは「さきてちれれば」と訓めば、歌意の「切実さ」も増すように思えるのだが...
「散ってしまったら、あの娘は来るだろうか、来ないのだろうか」よりも、
「散ってしまったので、今は、来るだろうか来ないだろうか、と待つ〔松の木〕のようだ」とも解釈してみたくなる
先のことよりも、すでにその時が来て、落ち着かない様子の歌にはならないのかな |
| |
|
|
| 【歌意1927】 |
白真弓を、「今」張るというその春山に、
せっかく恋し合って暮らしていたのに
流れ行く雲のように、
私たちは別れてしまうのだろうか
戻って来はしない雲の、なんと辛いことだ
こんなに恋しているというのに |
妻あるいは恋人と別れて、旅に出る男の歌とされている
確かに、別れのいっときの寂しさはあるものの
永遠でない以上、その寂しさ、哀しみは
やがて、再会する日までの、辛い辛抱、ということになる
先の見える「辛さ」は、いくらでも耐えられる
しかし、それが二度と逢えないだろう、という予感があれば...
多くの注釈書が語るものは、
別れだというのに、切実な悲しみが感じられない、という評価の歌だ
それはそうだろう
仕事などの公用で旅に出るにしても、あるいは所用で家を空けるにしても
またそこに帰って来るような前提でこの歌を解せば
作者がどれほどいっときの寂しさを詠おうが
どこに、それを解釈する時に反映させられるのだろう
「惜別の情」を主題とするにも係わらず、一首に流れる気分は、ひろやかである
そんな評を『全注』はしているが、そこには「旅に向う」とする前提がある
仮に、『全注』を含め、諸注のいうような「切実さ」が欲しい、
それがあれば、もっと良い歌だ、となれば
そのような解釈にもなるはずだ
「ゆくくもの ゆきやわかれむ」が、それに当るのではないか、と思う
雲が流れ行く、そして私たちは別れて行く
この描写が、もう二度と逢えないかもしれない、という実景と情景を表現していると思う
流れる雲は、もう戻って来ることはない
果てしなく流れ、そして消えてゆく
この「旅」もそうだ、私は...もう二度とここには戻って来られないだろう
作者の時代が、まだ戦乱の時代なのか、あるいは権力闘争の渦中にあるのか
それは分からないが
人の心には、その深さを様々に表現できるものがある
「辛い」からこそ「淡々と」して詠い、しかしその描写に大きな意味を映すもの
声高に「悲しみ」を訴え、そのヴォリュームで、圧倒する歌
それは、言葉など要らない
ただただ「泣き崩れれば」、それが人に染み渡る
いずれも作者にとっては「切実」な心の歌のはずだ
しかし、その歌を聞くものが、あらかじめ「こうあるべきだ」と構えたら
それは、すべてにおいて「物足りなさ」を感じてしまうものではないだろうか
「行く雲の 行きや別れむ」に、どれほどの作者の慟哭が込められていようと
初めから永遠の別れを想定し得なかったら、
この句は...「別れを修飾する」表現でしかなくなってしまう
もう一つ、小学館の『新全集』が可能性として書いている、「今こそ我が世」が、
こんなにも愛し合っている私たちなのに、というような意味合いがあるとすれば
それは二人のどんな意志でも逆らうことの出来ない「強制的」なものがあるのだろう
この歌の、『古今六帖』一首と、『赤人集』に見える二首
| あつさゆみ いまははるやま ゆくくもの ゆきやわかれむ こひしきものを |
| 古今六帖 第一 天 520 (作者、前歌519と)おなじ人 |
『古今六帖』のこの歌は、作者「おなじ人」と明記されている
その「おなじ人」の意味は、前の歌「519」の作者と同じ作者、ということなのだろう
そこに書かれている作者は「人丸」
柿本人麻呂を「人丸」ともいうようだが...
| しらまゆみ いまはるののに ゆくくもの ゆきやわかれむ こひしきものを |
| 赤人集 第一 203/第二 84 |
| しらまゆみ いまはるのべに ゆくくもの ゆきやわかれむ こひしきものを |
| 赤人集 第三 94 |
どちらが本歌か解らないが...いや、私には解らない、ということであって
歌学会では、解決済みのことかもしれないが...
「春山」と「春野」の違いだと、どんな情景になるのだろう
山にかかり流れる雲は、その動きが視覚的にも明瞭だが
野で、空を流れ行く雲をみると、あまりその流れ行くさまを、はっきりと意識はできない
やはり「春山」の方が、描写的には「想い」がはっきりと表現されているような気がする
|
|
| |
 |
掲載日:2014.02.26.
| 春相聞 寄雲 |
| 白檀弓 今春山尓 去雲之 逝哉将別 戀敷物乎 |
| 白真弓今春山に行く雲の行きや別れむ恋しきものを |
| しらまゆみ いまはるやまに ゆくくもの ゆきやわかれむ こほしきものを |
| 巻第十 1927 春相聞 寄雲 作者不詳 |
| 【1927】語義 |
意味・活用・接続 |
| しらまゆみ[白檀弓]〔枕詞〕「春」にかかる |
| 白木の檀で作った弓・弦を弓に張る意から、春山にかける枕詞となる |
| いまはるやまに[今春山尓] |
| いま[今・副詞] |
すぐに・ただいま・まもなく・やがて |
| はるやま[春山] |
春の山、とする説と、「今春山」という固有名詞とする説がある |
| ゆくくもの[去雲之] |
| ゆく[行く・往く] |
[自カ四・連体形]通り過ぎる・去る・(雲や水が)流れ去る |
| ゆきやわかれむ[逝哉将別] |
| ゆき[行く・往く] |
[自カ四・連用形]同上 |
| や[係助詞] |
[疑問]~か〔係り結びの「係り」〕(「結び」は連体形「む」) |
| 〔接続〕種々の語につく・活用語には連体形・連用形につく・上代では已然形にもつく |
| わかれ[別る・分かる] |
[自ラ下二・未然形]別々になる・遠く離れて会いにくくなる |
| む[助動詞・む] |
[推量・連体形]~(の)だろう(係り結びの「結び」) |
未然形につく |
| こほしきものを[戀敷物乎] |
| こほしき[恋(こほ)し] |
[形シク・連体形]慕わしい・恋しい (「こひし」の古形) |
| ものを[終助詞] |
[詠嘆]~のになあ・~のだがなあ |
連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [いまはるやまに] |
「いま」という語に、不自然さがまず浮ぶ
なぜ「いま」と断りがいるのだろう、と思った
それは、たまたま先に知ることになった「人麿集」の歌によるのだろう
| しらまゆみ いそはのやまに ゆくくもの ゆきやわかれむ こひしきものを |
| 人麿集 第四 291 |
ここで訂正しておかなければならないが、
昨日のページで、「赤人集」に、昨日の掲題歌を本歌とした一首が、と書いて載せた
しかし、それは私の大きな思い込みで、実際はどちらが「本歌」なのか解らないはずだ
この「人麿集」も「赤人集」も、仮にその歌人名が実作者のことであれば
少なくとも、『万葉集』の編纂時には存在していたはずだ
ならば、どちらが古いのかは、この掲題歌の年紀が解らなければ断定できない
早速、昨日の頁は訂正しておいた
さて、本題に戻るが、この第二句「いそはのやまに」
『万葉歌』の「いまはるやまの」と比べると、私は「いそはのやまに」の方が好きだ
「いそはのやまに」の注釈書を知らないので、自分なりの解釈だが
「磯端の山に」ではないかな、と思う
「いそ」は、海岸などの波打ち際の岩の多いところ、と言う意味だが
私なりのイメージでは、その海辺でも湾のようになっていれば、
遠望する山は見ることができる
言ってみれば、海辺に立って、遠くの山を流れ行く雲の描写のように思える
そして「いまはるやまの」とすれば、同じ山にかかり流れ行く雲のことなのだが
やはり「いま」という言葉がしっくりこない
こうした情景を挿む歌というのは、語らずとも、常に「今」なのではないか
だから、くどく感じたのかもしれない
しかし、小学館『新全集』の補注に、思わず「そうか」と合点する「注」があった
「『今春山』は、今こそわが世の春と茂り立つ山、の意であろうが、地名説もある」と
「今春山」の地名説は、これまではあまり真剣に考えたこともなかった
しかし、この歌に、なぜ「いま」が使われなければならないか、大きな手掛かりになった
となると「今は春」は、実景だけでなく、今二人はこんなに恋し合っているのに、
というような「想い」がこめられていることになる
私も、その方がよく思えてきた
しかも、この「いま」は、次の句の「ゆくくも」にもかかる
|
| |
| [ゆきやわかれむ] |
『西本願寺本』という同じ底本を使っていても、表記こそ違わない場合でも
その訓になると、現代の諸注は、様々な校定を行って、ある意味での改変を行う
それほど、諸本や諸注の研究がすすみ、「底本」が絶対的なものではなくなっている
そんな時代なのだろう、と思う
勿論、従来より、絶対的な『万葉集』という書はなく
その時代時代において、多くの研究成果による書の刊行であり
『西本願寺本』が多く「底本」として用いられているのは、それが正しいからではなく
全二十巻を現在に残す「完本」だから、とも言える
由緒ある古来からの伝本にしても、断簡であったり、
幾つもの異同のある古写本であったり、
その性格としては、一貫性を求められる研究には、資料的な価値はあったとしても
それを、「底本」にするには「不充分」だったからだと思う
そして現代に至っては、注釈書が盛んになり始めた頃に比べ
多くの研究者たちが、『万葉集』の豊富な「研究成果」を共有する
決して、特異な分野の研究ではなくなっている
だから、「底本」は、何々としながらも
現代に於ける解釈上の成果から、改訓などが行われることは、必然だと思う
岩波の『新大系』の「凡例」に明記されている
「-文字の音と訓については、古音・古訓はなるべく避けて、慣用の音訓に従うことに「した」とあるが、この姿勢が現代の多くの注釈書のあり方なのだろう
『萬葉集』〔桜楓社、昭和55年補訂版〕が、その『西本願寺本』の原形を残すと思う
「底本」との異同は、刊行時点での知られる諸注は頭注に記し、
諸本の異同も、脚注に載せている
多くの書が「ゆきやわかれむ」と訓む中、
この桜風社『万葉集』では、この第四句を「ゆきかわかれむ」としている
疑問の係助詞「か」であり、歌意には影響はないが、
『西本願寺本』の訓は、そうだ、ということだ
|
| |
| [わかれ] |
区別がつく、識別ができる意の「わかる」は、
四段活用の「わく(分く)」の未然形「わか」に、
可能・受身・自発の助動詞「る」がついたものとして、二語に分けた方がいい、とされる |
| |
| [こほしきものを] |
これも、どの注釈書も「こひしきものを」としている
「こほし」は、「こひし」の古形なので、
その流れなら、「古形」を使わず、改める、という方針が見える
「ものを」には、「逆接と順接の確定条件」である「接続助詞」
それに、「詠嘆」の「終助詞」があり
その識別が難しい、とされている
大雑把に理解するとすれば、省略も倒置もない文末に「ものを」がくれば
それは詠嘆の「終助詞」と思えばいい |
| |
|
|
| 【歌意1928】 |
男らしさを見せるどころか、
この私が、恋しさのあまり、伏し、座り込み、
そして嘆息しながら造った柳の蘰
娘よ、どうかその蘰を挿してくれ |
俺が、こんな風にして作ったものなんだぞ、とでも言いたそうな詠い振りだ
実際、こうした贈り物に、謂れを付けることはあっても
男が女への贈り物で、このように「柄にもなく」というのは珍しいことだろう
「ますらを」という語は、男らしさ、勇ましさを形容する語でよく使われるが
自称する場合には、むしろ自嘲的な意味合いが多いという
そうだと思う
自分から「男らしさ」を詠うには、どうしてもそうなる
しかし、その気持ちを汲むかどうかは...
この歌では、相手の気持ちは伝わらないが
少なくても、「ふしゐなげきて」を深読みするなら、
特別には想われていないことが想像できる
この一首で、女心を射止めることが出来るかどうか...
それにしても、この有り触れた歌なのに
おそらく、こんなに考えさせられたのは...これまでなかったはずだ
歌意に悩んだのではなく
「文法」に悩んでしまった
昨日(2月27日)から、原稿を書き始めたが、
深酒で、仕切り直ししたお陰で
今は、自分なりの理解ができている
この歌、実際は今日(2月28日付け)だが、HPの検索の利便性を考えて
取り組んだ昨日の日付のままに掲載するが
この一日置いたことで、かなり考えることができた
昨夜、無理して何が何でも、とアップしていたら
自分でも理解できないまま、終らせていただろう
そして、この一首は、またいずれ出会うまで、真剣に考えることもなかった、と思う
その意味で、一日遅らせなければならなかった「深酒」に、感謝しなければならない
一番のブレーキは、結句の「かづらせわぎも」にあった
この「せ」が、助動詞ではなく、サ変動詞「為(す)」であることは間違いないのだが
その命令形であるべきなのに「せ」というのが...右の「注記」のごとく、だ
しかし、鹿持雅澄『古義』によって、救われた
「かづらけわぎも」とする方が、私には正しいと思う
それが、なぜ「せ」と定訓になったのか、今度はそれを調べなければならない
「せよ」であれば、まだ理解できる
「せ」とする理由が、私には解らない
語調の上から、こうした「よ」の省略が古代にはあったのかもしれないが
その説明も、手持ちの資料では見出せなかった
『拾穂抄』や『校本万葉集』では、「かづらせよわぎみ」とする以上
何らかの理由があって、「せ」になったのだろうし...
明日香...早く行きたいものだ
| ますらをの ふしゐなけきて つくりたる したりやなきの かつらせわきもこ |
| 古今六帖 第五 服飾 3161 |
| ますらをか ふしゐなけきて つくりたる したりやなきの かつらせよいも |
| 赤人集 204 |
「せ」、「せよ」
『古今六帖』は、『万葉歌』を採録するに当って、
10世紀終わり頃の編纂過程で「訓」まれ継いでいたものだろう
しかし「赤人集」は、その原文に、いつ「訓」がつけられたのだろう... |
|
| |


 |
掲載日:2014.02.27.
| 春相聞 贈蘰 |
| 大夫之 伏居嘆而 造有 四垂柳之 蘰為吾妹 |
| 大夫の伏し居嘆きて作りたるしだり柳のかづらせ我妹 |
| ますらをの ふしゐなげきて つくりたる しだりやなぎの かづらせわぎも |
| 巻第十 1928 春相聞 贈蘰 作者不詳 |
【注記】〔1856〕
| 【1928】語義 |
意味・活用・接続 |
| ますらをの[大夫之] |
| ますらを[益荒男] |
勇ましく、強く立派な男子・ますらたけを・勇士 |
| 地名の「手結(たゆひ)」にかかる〔枕詞〕もあるが、ここは普通に解釈するもの |
| ふしゐなげきて[伏居嘆而] |
| ふし[伏す・臥す] |
[自サ四・連用形]うつぶす・横になる・ひそむ |
| ゐ[居(ゐ)る] |
[自ワ上一・連用形]しゃがむ・とどまる |
| なげき[嘆く・歎く] |
[自カ四・連用形]嘆息する・悲しんで泣く・祈る |
| て[接続助詞] |
[単純接続]~て・そして |
連用形につく |
| つくりたる[造有] |
| つくり[作る・造る] |
[他ラ四・連用形]こしらえる・つくる |
| たる[助動詞・たり] |
[完了・連体形]~た・~ている |
連用形につく |
| しだりやなぎの[四垂柳之] |
| かづらせわぎも[蘰為吾妹] |
| せ[為(す)] |
[他サ変]ある動作を行う・ある行為をする |
| 〔参考〕かづらけわぎも |
| かづらけ[蘰く] |
[他カ四・命令形]つる草や草木の枝・花を蘰としてつける |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [ますらを] |
『万葉集』「相聞歌」中で詠われる「ますらを」の自称は、
その名に相応しくない現在の自分を、自嘲的に使う場合が多い
|
| |
| [つくりたる しだりやなぎの] |
原文「造有四垂柳」は、「四垂柳」を「したりやなぎ」と、ごく普通に読む
だから、「造有」を「つくりたる」と必然的に訓まざるをえなくなる
動詞の連用形「つくり」に、完了の助動詞「たり」の連体形「たる」
この原文は、古写本などを見ると、「造有四垂柳」のように区切りがない
もっとも、この歌に限らず、『万葉集』そのものが、「漢字」の羅列なので
注釈書あたりで、解釈上の便宜的な区切り方がされるようになったと思う
だから、今目にするどんな注釈書でも、原文を載せている書にしても、
「造有 四垂柳」と、定訓のように訓むのが自然になっているが、
可能性としては、「造有四 垂柳」と訓むことも出来る
「造有」を「つくりたる」とするよりも、
「造有四」を「つくれりし」と訓む方が、いいのではないか、と思う
小学館『新全集』も、同じことを指摘している、
ただし、あくまで可能性もある、と言う表現にとどめ、結局採用は定訓に拠る
四段動詞「つくる」の已然形「つくれ」に、完了の助動詞「り」の連用形「り」
「り」は已然形接続だから、問題ない
さらに、強意や語調を整えるための副助詞「し」(連用形につく)
この語感の方が、歌が綺麗に詠めるのではないかと思う
そうなると、では「垂柳」をどう訓む、ということになるが
『万葉集』中で「しだりやなぎ」を拾い出して見ると、
その表記は掲題歌を除き三首あった
| 春雑歌 詠柳 |
| 百礒城 大宮人之 蘰有 垂柳者 雖見不飽鴨 |
| ももしきの大宮人のかづらけるしだり柳は見れど飽かぬかも |
| ももしきの おほみやひとの かづらける しだりやなぎは みれどあかぬかも |
| 巻第十 1856 春雑歌 詠柳 作者不詳 |
〔語義〕
「ももしきの」は、「おおみや」にかかる〔枕詞〕
「かづらける」は、「かづら」を動詞化した四段「かづらく」の連用形「かづらき」に、動詞「あり」の連体形「ある」がついた「かづらきある」の約
「あく」は、「あきあきする・いやになる」
「かも」は詠嘆の終助詞 |
〔歌意〕
(ももしきの)大宮人が、蘰にしている「しだり柳」、
いつ見ても飽きないものだなあ、あの美しさは... |
| |
| 春去 為垂柳 十緒 妹心 乗在鴨 |
〔書庫-15〕10-1900 |
| 梅花 四垂柳尓 折雜 花尓供養者 君尓相可毛 |
〔書庫-15〕10-1908 |
「しだりやなぎ」の表記には、「垂柳」「為垂柳」「四垂柳」があり、
〔1908〕では、まさに同じ表記になるが、よく見ると、
その前の語句は「梅花」という名詞だ
その他は、〔1856〕が「有」、〔1900〕が「去」、
ただし「去」は「去為」で「さりし」とも訓める
掲題歌〔1928〕の前の語は「有」で、「有四」、接続の動詞の活用によるが、
「ありし」...この場合は「つくりありし」→「つくれりし」にもなりそうだ
以前は「為垂柳」「四垂柳」を、何も不思議に思わず「しだりやなぎ」と私は訓んだ
しかし、〔1856〕のように「垂柳」のみで「しだりやなぎ」と訓むなら
その過去の訓にも、〔1900〕「春去 為垂柳」→「春去為 垂柳」、
〔1908〕では、「梅花」で、名詞なので、「四垂柳」が「しだりやなぎ」だろうが、
掲題歌の場合は、「造有四」と「四」を動詞につけて訓むことができると思う
〔1856〕のように「垂柳」が「しだりやなぎ」と純粋に訓めるなら
以上の条件で、四首中三首が「垂柳」を「しだりやなぎ」と訓めることになる
「つくれりし しだりやなぎの」
未熟な、また無知な発想だとは解っていても、こんな風に考えることが楽しいものだ
|
| |
| [かづらせわぎも][かづらけわぎも] |
この「訓」が、どんなに調べても解らない
「せ」が「為」で、歌意からすれば、「蘰」をして欲しい、してください、しなさい
そんな意味なのだろうが、ならば命令形「せよ」と訓むのが本当ではないかと思う
多くの諸注が「せ」であり、その異訓は殆どないが
しかしながら、仙覚の校訂で最初に著された「寛元本」系統の校本を底本とする、
『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕が、「かつらせよわきも」とする
この注釈書は『神宮文庫本』の訓を基本にしているような感じがする
そして、この仙覚の最後の校訂(文永本)を基にした、『西本願寺本』の影響の強い、
『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕が、その中で
「かつらせよわきも」と、やはり訓んでいることだ
では、「せ」とするのは、どんな「諸本」だったのだろう
明日香での宿題が、増えるばかりだ
現代では、殆どの注釈書『西本願寺本』を底本としているが
勿論、盲目的な使い方ではなく、多くの諸本・諸注との交合もされている
ということは、「せ」と訓む諸本なり諸注が、ある時点からどうやって定訓になったのか
知りたいものだ
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕を見てみた
そこには第四句の「しだりやなぎの」の「の」を「そ」として、
「之は、曾の極草により誤れるなるべし」と、解らない説明があるが
それよりも、「せ」について、知りたかった
すると、「かづらけわぎも」...
何となく思い出した
そうだ、名詞「蘰」の動詞形で四段「かづらく」があった
その命令形であれば、「かづらけ」だ
命令形に拘るなら、この「かづらけ」の方が理解しやすい
|
| |
| [せ] |
何も理解できないままに、落ち着くことも出来ず
何とか、手掛かりでも、と思いながら手持ちの古語辞典やその他の書をひっくり返す
この「せ」が、「蘰」という体言についていることから、助動詞では有り得ず
どうしても、サ変動詞「為(す)」しか考えられない
とすれば、「せ」は未然形だし、命令形なら「せよ」だ
しかし、どの注釈書を見ても、「カヅラセは、蘰せよ、の意」とされる
歌の場合、上代の命令形で「よ」の省略があるのだろうか
それならそれで、そんな説明も欲しいところだ
苦し紛れに、命令形ではなく、終止形「す」としてみた
「かづらすわぎも」、これを当てはめれば
「しだり柳の蘰を、娘がする」、「わぎも」を文末に倒置して強調する
こうであれば、何も悩むこともないのだが...
でも、やはり「かづらけ」の方が、すっきりする
|
| |
|
|
| 【歌意1930】 |
春の山に咲く、アシビの花の「アシ」ではないが
「あし」とは思ってもいないあなたですもの
ええい、たとえ関係を噂されようと、構うものですか |
| 【歌意1931】 |
石上の布留の神社にある神木の杉
そんなに神々しく思われるほど年老いてしまった私が、
今更になっても、恋に出逢ってしまったのだろうか |
これは、「相聞」ではなく「問答歌」なので、
必ずしも当事者間で交わされた歌とは言えないが、
この『万葉集』の編者の演出は、この二首で見事な冴えを見せてくれる
実際の評価は解らないが、私には年の離れた男女間の、
戯れの「相聞歌」に聞こえる
夢中になるほどではないが、あの人となら、そんな噂も嫌ではない、という女
こんなに老いた私も、噂されれば、妙に「恋心」が騒ぎ出す、と返す男
ほのぼのとした、まさに「春らしさ」一杯の歌だと思う
一般的には、〔1931〕が「春」には相応しい訳でもないが、
「問答歌」とする組み合わせの中で、こうした配列になっている、
という「左注」〔右一首不有春歌而猶以和故載於茲次〕に従って
「真剣な恋歌」ではなく、「挨拶性の濃い」歌だとされている
あしびの花を、実際は「可憐な花」だとして万葉人は好んで詠む
だから、序詞として「あし」を重ねるために用いただけではなく、
そんな「素敵なあなたでしたら」と、むしろ噂も心地よく受け入れよう、
そんな気持ちの方が強いのかもしれない
そうすると、何も序詞の前提となる「あしからぬ」に拘る必要もなく
「にくからぬ」でも充分通用する
『全註釈』がいう「譬喩」がそうだ
「あしびの花」のように...
「馬酔木」を実際に見ると、白い玉の房が、清楚なそれでいて、逞しさは感じられる
そんな男への憧れなのだろうか
忍照 難波乎過而 打靡 草香乃山乎 暮晩尓 吾越来者 山毛世尓
咲有馬酔木乃 不悪 君乎何時 徃而早将見 |
| -山も狭に 咲ける馬酔木の 悪しからぬ 君を- |
| 右一首依作者微不顕名字 |
| 巻第八 1432 春雑歌 草香山歌一首 (長歌の一部) 作者不詳 |
| -山道も狭くなるほどに咲く馬酔木、そのように美しいのに荒々しくないあなたに- |
「あしび」と「あし(悪し)」は、ここでも「あし」を引き出す序詞として使われているが
しかし、「あしび」そのものの「花の房の力強い美しさ」もまた表現していると思う
| はるやまの あせみのはなの にくからぬ きみにはしへや よりぬともよし |
| 古今六帖 第六 木 4321 |
| はるやまの あせみのはなの にくからぬ きみにはしめや よかれはこひし |
| 夫木抄 第五 春五 1718 赤人 |
| はるやまの あせみのはなの にくからぬ きみにはしめや よかれはこひし |
| 赤人集 207 |
| いそのかみ ふるのかみすき かみさひて われやさらさら こひにあひにける |
| 古今六帖 第六 木 4279 |
やはり、岩波文庫の『新訓万葉集』から訓じられる「よそる」は、ここには見られない
|
|
| |

 |
掲載日:2014.02.28.
| 春相聞 問答 |
| 春山之 馬酔花之 不悪 公尓波思恵也 所因友好 |
| 春山の馬酔木の花の悪しからぬ君にはしゑや寄そるともよし |
| はるやまの あしびのはなの あしからぬ きみにはしゑや よそるともよし |
| 巻第十 1930 春相聞 問答 作者不詳 |
| 石上 振乃神杉 神備西 吾八更々 戀尓相尓家留 |
| 石上布留の神杉神びにし我れやさらさら恋にあひにける |
| いそのかみ ふるのかむすぎ かむびにし われやさらさら こひにあひにける |
| 右一首不有春歌而猶以和故載於茲次 |
| 巻第十 1931 春相聞 問答 作者不詳 |
| 【1930】語義 |
意味・活用・接続 |
| はるやまの[春山之]春の山に |
| あしびのはなの[馬酔花之]馬酔木の花の |
| あしからぬ[不悪] |
| あしから[悪し] |
[形シク・未然形]悪い・みっともない・不快である・荒々しい |
| ぬ[助動詞・ず] |
[打消・連体形]~ない |
未然形につく |
| きみにはしゑや[公尓波思恵也] |
| しゑや[感動詞] |
(断念や決意、または嘆息したりするときに発する) ええい |
| よそるともよし[所因友好] |
| よそる[寄そる] |
[自ラ四・終止形]自然に引き寄せられる・異性と関係を噂される |
| とも[接続助詞] |
[逆接の仮定条件]たとえ~にしても |
終止形につく |
| よし[縦(よ)し] |
[副詞]不満足であるが仕方ない・ままよ・どうなろうとも |
| 【1931】語義 |
意味・活用・接続 |
| いそのかみ[石上]石上の |
| ふるのかむすぎ[振乃神杉]布留の社の神木の杉 |
| かむびにし[神備西] |
| かむび[神ぶ] |
[自バ上二・連用形]年をとる・神々しくなる |
| にし |
~た・~てしまった |
連用形につく |
| 〔成立〕完了の助動詞「ぬ」の連用形「に」+過去の助動詞「き」の連体形「し」 |
| われやさらさら[吾八更々] |
| や[係助詞] |
[疑問]~か 係り結びの「係り」、結びは連体形「ける」 |
| さらさら[更々] |
[副詞]今更に・改めて・ますます |
| こひにあひにける[戀尓相尓家留] |
| こひ[名詞・恋] |
恋しく思うこと・心がひかれること・恋愛 |
| に[助動詞・ぬ] |
[完了・連用形]~てしまう・~てしまった |
連用形につく |
| ける[助動詞・けり] |
[過去(詠嘆)・連体形]~だなあ |
連用形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
[あしびのはなの あしからぬ]
「あしびのはなの」までの上二句が、同音の反復で「あしからぬ」を引き出す序、と
確かに、定訓になっているこの訓ではそうなるが、
この「あしからぬ」の異訓がある
『萬葉集』〔桜楓社、昭和55年補訂版〕は、「底本」を『西本願寺本』としながらも、
その「訓」については、『元暦校本』の「にくからぬ」とし、
『寛永版本』を「底本」とする『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕は、
この第二、三句を「つつしのはなの にくからぬ」としいる
この第二句の原文「馬酔木」は同じなのに「つつし」と訓むのは解らないが、
第三句は「にくからぬ」としているので、こうした訓では、
この一首に「序詞」は、認められないだろう
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕が、
「二句の馬酔をアシビと読むべしとするなら、アシカラヌと読むのが順当のようである」
とするが、「にくからぬ」と読むなら、「序詞」ではなく「譬喩」になる、という
「あしからぬ、にくからぬ」、似たような語だが、微妙に違うのだろうなあ |
| |
| [よそる] |
ラ行四段「寄そる」、初めてのような気がする
こんな言葉があったのか
古語辞典でも、「異性との関係を噂される」とするように
動詞一語で、そんな意味を表現できるとは思いもしなかった
「新訓」の「よそるともよし」が、定訓のようになっているが、
この「新訓」というのは、岩波文庫の『新訓万葉集』のことなのか
『新訓万葉集』〔岩波文庫、佐佐木信綱、1927年刊行〕
同じ著者が係わる『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕は1923年、
確かに、それよりも「新しい」とはいえるが...
最近の(戦後の)盛んに刊行される「全集」の類には、交合や校訂に、
この『新訓万葉集』は見ることもないので、名こそ「新訓」であっても
あまり用いられてはいないのかもしれない
しかし、この「新訓」が、『新訓万葉集』をさすのなら
「よそるともよし」は、それほど古くはない、ということになる
実際、『古今六帖』や『赤人集』など、左頁に載せるが、
その訓は、確かに違うものだし
「底本」として多くの注釈書に用いられる『西本願寺本』にしても、
その訓は、「よりぬともよし」だ
後世に大きな影響を与えている、
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕が、「よするともよし」
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕や、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕が、「よせぬともよし」
とすれば、その時代の「訓」に「よそるともよし」はなかったのだろう
やはり、この「訓」は『新訓万葉集』から、ということになるのか
...まだ百年も満たない、ということなのかな
しかし、『新校万葉集』〔沢潟久孝・佐伯梅友、昭和10~11年成〕、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕、
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕など
新しい注釈書になると、「よさゆともよし」が多く見えることになる
この場合の「寄さ」は、他動詞四段「寄す」の未然形だ
意味としては、「近寄らせる・寄せる・よこす」、そして受身の助動詞「ゆ」の終止形
こうした「訓」もまた、今後の「定訓」への道を進むのかもしれない
古語、といっても
言葉は永遠に生き続けているような気がする
「よそる」、確かに馴染みのない語だとは思うが、これもれっきとした「古語」だ
|
| |
| [いそのかみ ふるのかみすぎ] |
この二句の語句は、『日本書紀』〔顕宗天皇〕や『万葉集』などにも、
そのままの成句として使われている |
| |
| [かむびにし] |
「神々しい」から転じて「年老いた」の意味にもなるが
この異訓、『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕では、「かみひても」
これは、「神備西」の異同で、『寛永版本』による「神備而」とするものだろう
「西」と「而」のどちらかが誤写本ということか...似ているので、そうなるのだろう
同じ「神備而」を、『古義』は「かみさびて」とするが、その方が解りやすい
『神宮文庫本』が「かみひきも」
|
| |
|
|
 |
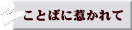  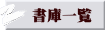  |








































