| 【歌意1862】 |
決して、鳥は食べたりはしないのだが...
実ならいざ知らず、でもその場合と同じように
縄を張りめぐらせて、守ってやりたい、と思わせるほど
何とこの梅の花は美しいのだろう |
襲いかかるかもしれない災難...
いや、普通では考えられないことだが
しかし、たとえ過剰だなどといわれようと
そうして守りたいという気持ちを、顕せるのなら
何の躊躇もなく、そうしてしまう
何故なのか...
それほど、「どうしても守りたい」という気持ちの強さが
理屈に勝ってしまうからだと思う
草木が、実をつける時期になると、
鳥たちの襲来から守るために、縄を張って守ることもあったという
それは、間違いなく予期できる「襲来」だから...
しかし、実もなく、ただただ「美しい花」に心を魅せられ
鳥など食べに来るわけないのに、「守ってやりたい」と思うのは
ある意味では、口実としての「守る」であって
「縄延」となると、「自分の領地、自分のもの」だという独占したい意識が潜在する
そんな風に解釈すると、あまり「きれい」には思えなくなるが
よく考えてみると、それこそ紛れもなく「恋」なのだろう、と思う
何かから守る、ということは
その何かを近づけないことにもなる...それは、「自分の心にだけ」持つ存在にすることだ
この歌、詠じた者が意識していなくても
傍で見る者にとっては、「恋すればこんなもの」と理解もあるだろうし
「大袈裟だな、そこまですると...偽善者だぞ」とも成り得る
こんな感じ方をしては、せっかくの万葉歌が...万葉人に叱られてしまう
右頁の注記「なははへて」を、もう一度考えてみたい
この歌の「歌意」に沿うならば、
動作としての「縄を張りわたす」ことが、
「しめ」が意味する「立ち入り禁止」にすることを目的にしているのだから
その「目的」こそ、作者が表現したかったことのはずだ
一見して、「美しい梅の花」と思ってしまうが
それをただ「美しい」と言って見るだけでは、心を揺さぶった主観的な歌にはならない
その「美しさ」は、「しめなは」を張りたくなるほど...作者にそう思わせるほどのもの、
そう思っていいはずだ
普段、この時期に「縄」を張りめぐらせたりしない...「実」ではないから...
それでも疑問は残る
その気持ちに従えば、「縄延」の表記ではなく、
「標刺(しめさす)」(三例)や「標指(しめさす)」(一例)と表記した方が、より明確だ
単純に「縄を張りわたす」だけの行為ではなく、心情的には「標刺」のはずなのに...
やはり、義訓や戯書の類なのだろう
単純な動作の表現で、その本当の意味を「知らせる」ことになる用法だ
「縄延」の漢字の意味から、連想して結びつくので「戯書」とは言わないだろうが
それこそ「寒過暖来(冬が過ぎて春が来る)」的な用法ではないかと思う
この歌、「寓意」ではないか、ともいう
私は「寓意」だと思う
そして「梅の花」こそ、「恋人」のこと
「守ってやりたい」「独占したい」と思う対象は...「恋人」が相応しい
|
| |
|
掲載日:2014.01.01.
| 春雑歌 詠花 |
| 打細尓 鳥者雖不喫 縄延 守巻欲寸 梅花鴨 |
| うつたへに鳥は食まねど縄延へて守らまく欲しき梅の花かも |
| うつたへに とりははまねど なははへて もらまくほしき うめのはなかも |
| 巻第十 1862 春雑歌 詠花 作者不詳 |
| 【1862】語義 |
意味・活用・接続 |
| うつたへに[打細尓 ] |
| うつたへに[副詞] |
(下に打消し・反語表現を伴って)決して・絶対に・ことさら |
| とりははまねど[鳥者雖不喫] |
| はむ[食む] |
[他マ四・未然形]食べる・飲む |
| ね[助動詞・ず] |
[打消・已然形]~ない |
| ど[接続助詞] |
[逆接の確定条件]~けれども・~のに・~だが |
已然形につく |
| なははへて[縄延] |
| なは[縄] |
わらや植物の繊維などをより合わせて作った細長い紐 |
| はへ[延ふ] |
[他ハ下二・連用形]引き伸ばす・張りわたす |
| て[接続助詞] |
[単純接続]~て・そして |
連用形につく |
| もらまくほしき[守巻欲寸] |
| もら[守(も)る] |
[他ラ四・未然形]見張る・番をする・(人目を)伺う・はばかる |
| まく[上代語] |
[推量の助動詞「む」のク語法]未来の推量を表す・~だろうこと |
| 〔成立〕推量の助動詞「む」の名詞化 〔接続〕活用語の未然形につく |
| ほしき[欲し] |
[形シク・連体形]自分のものにしたい・そうありたい |
| うめのはなかも[梅花鴨] |
| かも[終助詞] |
[詠嘆・感動]~であることよ 〔接続〕体言、連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [なははへて(縄延)] |
原文「縄延」は、この歌一首しか『万葉集』には用いられていない
しかし、「縄」を「なは」と訓むのが一般的だが、幾つかの注釈書では、「しめ」とする
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
『萬葉集』〔桜楓社、昭和55年補訂版〕などがそうだ
岩波は、『新体系』の方では、「なははへて」にしている
古語辞典で、「しめ」と「しめなは」の違いの説明を見つけた
| 「しめ」と「しめなは」 (旺文社・全訳古語辞典第三版) |
| 「しめ」は下二段動詞「しむ(占む・標む)」の名詞形である。「しめ」を設置する方法としては、草や枝をひき結んだり、わら・萱などでいわゆる「しめなは」を張ったり、杭を立てたりする。そこで、「しめゆふ」、「しめたつ」「しめさす」などの言い方が生れる。中古以降は「しめなは」は神域などの聖なる場所を示すものとして用いられ、それ自体に呪術的な威力を認める考え方も生れた。 |
では、動詞「しむ(占む・標む)」の意味は、何だろう、と調べてみる
「自分のものとする・自分の領地であるしるしをつける」
「敷地とする・その土地に住む」
「身に備える・心に持つ」
などの用法があった
「なは(縄)」が、単なる「物」としての名称であるのに対して
「しめ」は、その語だけで、多くの意味を示している
この歌で「なははへて」、「しめはへて」の訓を考えると
原文「縄」それ自体に「しめ」という訓は成り立たないと思う
しかし「細長い紐」(縄)を「張りわたす」(延)ことによって、「しめなは」にしてしまう
ということは、訓では「しめ」とは読めないが、作り上げた「場所」は「しめなは」だ
『万葉集』の表記する漢字には、「義訓」や「戯書」のように
本来の読み方とは違う用い方もある
では、「縄を張り巡らせ」て「しめ」を表現することも
そんな万葉の時代であれば、おかしなことではないはずだ
一般的なテキストから、掲題歌を上に挙げたが
この「なははへて」は、「しめはへて」の方が、いいのではないか、と思えてきた
このことについては、右頁で続きを書こう
|
| |
|
|
| 【歌意1863】 |
馬を並べ、手綱を綰く
その高の山辺を真っ白に彩り、目に鮮やかなのは
梅の花だろうか |
結句「うめのはなかも」は、昨日の歌〔1862〕の結句と同じだが
今日のこの語句は、「感嘆の終助詞」ではなく、「疑問の終助詞」だと思う
昨日は「美しい梅の花」だと認識し、それで「守りたい」気持ちを抱いた
今日は、「高」の山辺を馬を疾走させながら、山裾に彩る花の姿を想い起こさせる
だから、あの見事な彩りは、「梅の花なのかなあ」と少々確認気味に魅入っている
そんな感じのする歌だ
山裾の広い野原に、一面を鮮やかに彩る花の色
今、自分が走っているところからでは、その正体が分からない
きっと梅の花なんだろう、と思いながらも
見事に馬の手綱を操って駆け抜けて行く
美しく、高原の春風に描かれる「疾風」の香りが漂ってくる
|
| |
 |
掲載日:2014.01.02.
| 春雑歌 詠花 |
| 馬並而 高山部乎 白妙丹 令艶色有者 梅花鴨 |
| 馬並めて多賀の山辺を白栲ににほはしたるは梅の花かも |
| うまなめて たかのやまへを しろたへに にほはしたるは うめのはなかも |
| 巻第十 1863 春雑歌 詠花 作者不詳 |
【注記】〔280〕
| 【1863】語義 |
意味・活用・接続 |
| うまなめて[馬並而 ] |
| なめ[並む] |
[他マ下二・連用形]並べる |
| て[接続助詞] |
[並立]~て |
連用形につく |
| たかのやまへを[高山部乎] |
| たか[綰く](上代語) |
[他カ四・未然形]髪をかき上げる・手綱をあやつる |
| しろたへに[白妙丹] |
| しろたへ[白栲・白妙〕 |
こうぞ(木の名)の繊維で織った白い布・白い色・白いこと |
| にほはしたるは[令艶色有者] |
| にほはし[匂はす] |
[他サ四・連用形]染める・色づかせる・ほんのり彩る |
| たる[助動詞・たり] |
[完了・連体形]~ている・~てしまった |
連用形につく |
| は[係助詞] |
[題目](主語に当たる語句をとりたてて提示する)~は |
| 〔接続〕名詞、助詞、活用語の連体形・連用形などの種々の語につく |
| うめのはなかも[梅花鴨] |
| かも[終助詞] |
[疑問]~だろうか 〔接続〕体言、連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [うまなめて] |
この「うまなめて」を、高い山を馬で駆ける情景の連想から
「たか」(地名)とする「枕詞」だとする説や、そうでないとする説もあり
古語辞典でも、「枕詞」として載せていないものもある(載せていない方が多い)
そもそも枕詞の役割を充分理解していない私には、その判断はつくはずもないが
この歌に於いては、馬を操る意の四段動詞「たく」と、
地名とされる「たか」(京都府綴喜郡井手町多賀)にかけた「掛詞」とする説に拠りたい
その地名「高」を推定させる歌がある
| 雑歌/(高市連黒人覊旅歌八首) |
| 速来而母 見手益物乎 山背 高槻村 散去奚留鴨 |
| 早来ても見てましものを山背の高の槻群散りにけるかも |
| はやきても みてましものを やましろの たかのつきむら ちりにけるかも |
| 巻第三 280 雑歌 高市連黒人 |
〔語義〕
「はやきても」の「はや」は、「急いで・早く」が原義だが、
この歌意に沿うのは、「もっと早くに」のように、その時を逃がした悔恨がある
「みてましものを」の「て」は完了の助動詞「つ」の未然形
「まし」は反実仮想の助動詞「まし」の連体形で、「~たらよかった」
「ものを」は、逆接の詠嘆の意を含む終助詞で、「~のになあ」
「やましろの たかのつきむら」は、その原文「山背高槻村」から、
「山城の多賀(京都府綴喜郡井手町多賀)の槻の木群(こむら)」と推定されている
もっとも、古来よりこの「山背高槻村」の訓は難訓とされており
『万葉集難語難訓攷』に拠ったものが採用されている
「ちりにけるかも」は、槻(今のケヤキ)の黄葉が、散ってしまったことに気づいた感動 |
〔歌意〕
もっと、早く見に来ていればよかったのになあ...
山城の多賀のケヤキの美しい黄葉が、
もう散ってしまっているではないか... |
この歌で「たか(高)」が、掲題歌の「高」と同所と断定はできないが
少なくとも、「地名」としての「高」があり得た、ということにはなる
尚、「高」を形容詞ク活用「高し」の連体形「高き」として訓む注釈書もある
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕がそうだ 「たかきやまへを」
|
| |
|
|
| 【歌意1865】 |
能登川の、水底までも花色に輝かせるほどに
三笠の山は、見事に花に埋まっているなあ |
それほどまでに輝かせる花...その花は、どんな花なのだろう
桜、梅、あるいは山吹とも...
現代的な感覚では、川沿いに美しい並木を作るのは、「桜」が一番だろう
しかし、山を覆い尽くすほどの花となると、「梅」もいい
勿論、桜で覆われた山も見事だ
特に、吉野の桜は、山そのものが桜になってしまう
吉野から山並みを眺望すると、まさに桜の山に相応しい景観を目にする
梅は、桜より古くから愛でられていたように
街中の「梅林」といわれるごとく、整理された空間に映えるようだ
私の知識不足もあるだろうが、「梅林」は聞いても「桜林」は聞かない
山桜のように、街中から離れてこそ、それも言えるだろうが
「梅林」は、街中の庭園...しかも群生するように圧倒的な数を誇示する
桜で、吉野以外で圧倒的な群生とは、あまり知らない
桜は、一本一本んの美しさを愛でる気がする
この歌のように、水底までその輝きを映せるのは...「梅」ではないかと思う
三笠山を覆う梅の木々、花が能登川に映し込む
川辺の桜ではすぐにでも映し出せるだろうが...何しろ三笠山の花の木だから...
右頁の【注記】を、一部こちらに移す
| [さきにけるかも] |
ここでいう「咲く」花は、多くは「さくら」とされている
『万葉代匠記(初稿本)』〔契沖(1640~1701)、貞亨四年(1687)成〕に、「桜なるへし」
とされ、それ以来「さくら」をいうものと、一般的にされているが
この前歌〔1864、既出・書庫-5〕では「やまぶき」が詠われており
その関連性から、掲題歌も「やまぶき」ではないか、とする注釈書もある
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕が、それだが
私には、その「関連性」が、何を指すものか解らない
でも、頼りない手段でもあるが、一つの方法を試してみたくなった
時間の余裕のある今だからこそ、できることだ
それは、「咲」の表記で使われる、花の種類だ
勿論、花の種類が明記してあるのは問題ない
「咲」の表記だけで、「花の名」が明記されていない歌を探そうと思った
当然、「さく」が、すべて「咲」の表記とはならず、「万葉仮名」での表記もあるだろう
それに、「開」を「咲く」と当てる訓もある(ただし「開」は、一応カウントしてみたい)
でも、それはいずれ専門家の本でも探すとして、今は自分で出来ることをしてみたい
「光」の時と同じように、「テキスト」から「咲」を検索する
全部で、「208首」...なかなか多い
それを一首一首拾い出して確認する
この中で、長歌は三十六首あったが、それは外した...読み切るのが辛い
目当ての、「花の名」を伴わない歌の数は、「三十一首」(「開」も含む)
これだと、ある程度は潰していけそうだ
ちなみに、この作業の副産物で知り得たこと...
当然ながら、「花の種類とそれぞれの数」
まず、それを表にしてみた
| 「咲」表記にともなう「花の名」 |
| うめ |
42 |
をみなへし |
4 |
まつ |
1 |
| はぎ |
39 |
あしび |
3 |
あぢさゐ |
1 |
| さくら |
11 |
あさがほ |
2 |
つつじ |
1 |
| なでしこ |
9 |
つゆくさ |
2 |
つばき |
1 |
| やまぶき |
6 |
ねむのき |
2 |
ひめゆり |
1 |
| ふじ |
5 |
あふち |
1 |
不明三首 |
| うのはな |
5 |
あふひ |
1 |
精度は充分ではない
一首に複数の花の名を用いる歌もあるので、確かに厳密とは言えない(梅と柳とか)
それにしても、「梅」「萩」「桜」は、やはり多い
ただ、「花の名」を言わないでも「咲く花」が指す「花」を知りたいのだから
何も、多さだけが参考になるわけではない
勿論、多いことが「一般的に咲くと言えば」に通じるのは違いないが...
さて、いよいよ「三十一首」に取り掛かろう
この歌に限っては、季節が解るものは、外せる...何しろ「春雑歌」だ
それに、一般的なたとえ方で「花が咲くような」というような場合もあるだろう
それも外す
そして残った歌は、掲題歌を含めて五首になった
掲題歌〔1865〕以外の歌は、次の四首
| 春雑歌/尾張連歌二首 [名闕] |
| 春山之 開乃乎為里尓 春菜採 妹之白紐 見九四与四門 |
| 春山の咲きのををりに春菜摘む妹が白紐見らくしよしも |
| はるやまの さきのををりに はるなつむ いもがしらひも みらくしよしも |
| 巻第八 1425 春雑歌 尾張連[名闕] |
〔語義〕
「ををり」は、花が多く咲いて枝がたわみ、曲がること
「しらひも」は、白い紐
「みらくしよしも」の「みらく」は「見る」の名詞形で「見ること」 |
〔歌意〕
春山の、枝をたわませるほどに咲き満ちている木の下で
春菜を摘む愛しい娘の「白紐」を見るのは、気持ちのいいものだ |
| |
| 打靡 春来良之 山際 遠木末乃 開徃見者 |
| うち靡く春来るらし山の際の遠き木末の咲きゆく見れば |
| うちなびく はるきたるらし やまのまの とほきこぬれの さきゆくみれば |
| 巻第八 1426 春雑歌 尾張連[名闕] |
〔語義〕
「うちなびく」は、草木が伸びてなびくことから、「春」にかかる枕詞
「こぬれ」は、梢・木の枝の先
「さきゆく」は、四段動詞「咲く」の連用形「さき」、その動詞の連用形の下につき、その動作が継続・進行する意を表する四段動詞「行く」がついて、
「だんだん咲きて行く・いつまでも咲き続ける」などの意になる
「見れば」は、上一段「見る」の已然形「見れ」に、順接確定条件の接続助詞「ば」
「見たところ・見ると」 |
〔歌意〕
草木があんなに茂り、春が来たようだ
山の間の遠くに見える木々の梢に、
溢れんばかりに咲いているのを見ると |
| |
| 雑歌/獻舎人皇子歌二首 |
| 妹手 取而引与治 フサ手折 吾刺可 花開鴨 |
| 妹が手を取りて引き攀ぢふさ手折り我がかざすべく花咲けるかも |
| いもがてを とりてひきよぢ ふさたをり わがかざすべく はなさけるかも |
| 既出〔書庫-13〕巻第九 1687 雑歌 柿本人麻呂歌集 |
| |
| 春雑歌詠花 |
| 打靡 春避来之 山際 最木末乃 咲徃見者 |
| うち靡く春さり来らし山の際の遠き木末の咲きゆく見れば |
| うちなびく はるさりくらし やまのまの とほきこぬれの さきゆくみれば |
| 巻第十 1869 春雑歌詠花 作者不詳 |
〔1426〕歌の異伝歌
ここでは、結句が「咲往見者」となっている |
これらの、花の名を伴わない「咲く」をいう歌では、
どの注釈書も「さくら」を当てている
注釈書によっては、「さくら」を詠う歌は、その「名」を出さない場合が多い、ともある
さらに、「さくら」は「花の代表」だという、しかし、私の知識では、
「さくら」が名実共に「代表」といわれるのは平安時代からだと...認識している
万葉の時代の代表格、名を出さなくても「花が咲く」と言えば
それは「梅」ではないかと思うのだが、「梅」に言及した注釈書は見当たらない
それに、「さくら」がことさら詠われるのは
梅とは違って、その「潔い散り際」を詠うものも多いはずだ
「咲く花」というよりも、「見事に散っている」のが「さくら」だ
「花の代表」を受けても、「咲く花」としてではなく
「散る花」の「感嘆の対象」が「さくら」であるのだと思う
だから、「咲く花」で、名を伴わないのは、「咲いている美しい花」の代表
それは、「梅」ではないかと思う
それに、一例に過ぎないが、髪に挿す「花」もまた
私の印象では、「さくら」ではなく「梅」が相応しいような気がする〔1687〕歌
勿論、以上の歌すべてが「梅」だとは思わない
〔1425〕では、桜の木の下での春菜摘みがいいとは思う
しかし、同じ作者で連作でありながら、〔1426〕では、
春の訪れをいち早く知らせてくれる「花」としてみれば、それは「梅」になるだろう
ならば、その二首、題詞では「尾張連歌二首」とあるが、
同じ花を見て詠ったとは限らず、春の情景歌として詠ったものかもしれない
「さくら」を一首、「梅」を一首... |
|
| |
|
掲載日:2014.01.03.
| 春雑歌 詠花 |
| 能登河之 水底并尓 光及尓 三笠乃山者 咲来鴨 |
| 能登川の水底さへに照るまでに御笠の山は咲きにけるかも |
| のとがはの みなそこさへに てるまでに みかさのやまは さきにけるかも |
| 巻第十 1865 春雑歌 詠花 作者不詳 |
【注記】〔480〕【注記左頁】〔1425・1426・1687・1869〕
| 【1865】語義 |
意味・活用・接続 |
| のとがはの[能登河之 ] |
| のとがは[能登川] |
奈良県、春日山と高円山の間の地獄谷の渓流を源流とし、白毫寺町・能登川町を過ぎて岩井川に合流したのち、佐保川に注ぐ
〔犬養孝『万葉の旅』より〕 |
| みなそこさへに[水底并尓] |
| みなそこ[水底] |
水の底 〔「な」は「の」の意の上代の格助詞〕 |
| さへに |
~までもまあ~ことだ |
| 添加の副助詞「さへ」~までも、に助詞「に」のついたもの |
| 〔接続〕体言・連体形、連用形・助詞・(主語・目的語なども含め)連用修飾語にもつく |
| てるまでに[光及尓] |
| てる[照る〕 |
[自ラ四・連体形]光を放つ・輝く・(容貌や姿が)美しく輝く |
| までに |
~くらいに・~ほどに・~までも |
程度・限度の副助詞「まで」
~ほど・~くらいに・~まで、に助詞「に」のついたもの |
| 〔接続〕体言及び、体言に準ずる語、動詞・助動詞の連体形、副詞や助詞など種々の語につく |
| みかさのやまは[三笠乃山者] |
| みかさのやま[三笠山] |
春日山の西に連なる一峰、標高293メートル (現御蓋山) |
| さきにけるかも[咲来鴨] |
| ける[助動詞・けり] |
[過去・連体形]~たなあ(今まで気づかなかったことに気づいて) |
| |
〔接続〕連用形につく |
| かも[終助詞] |
[感嘆]~であることよ 〔接続〕体言、連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [さへに・てる] |
副助詞「さへ」は、ある事柄にさらに他の事柄が加わることを示す
この歌では、三笠山の花の輝きが、能登川の水底までも照らしている表現になる
ここで、「さへに」を持ち出したのは、
次の原文「光」の訓に関係あるかな、と思うからだ
この「光」を、どの注釈書も「てる(照る)」と訓んでいる
「光」を「ひかり」と訓じたり「照る」と訓じるルールがあるのかどうか
ふと、知りたくなった
そこで、パソコンのデータを「光」で検索すると、四十一首を拾い出した
その内訳は、「てる」と訓む歌が「十一首」、「ひかり」が「九首」だった
「光儀」を「すがた」と訓じるのが「十首」、長歌が「十一首」だが、これらは今は外す
「ひかり」の場合と、「照る」の場合と読み出したらなかなか前に進まず
止むを得ず、掲題歌に関係ありそうな手掛かりめいた歌を見つけたので
一応、その歌に絞ってみた
それが、次の〔480〕歌で、気になったのは、「光」の前に「さへ」があるからだ
掲題歌と、同じ形で使われている
もっとも、副助詞「さへ」単独と、
副助詞「さへに」(助詞「に」のついたもの)の違いはあるが...
解釈においては、大きな違いはないと思う
| 挽歌/((十六年甲申春二月安積皇子薨之時内舎人大伴宿祢家持作歌六首)反歌) |
| 足桧木乃 山左倍光 咲花乃 散去如寸 吾王香聞 |
| あしひきの山さへ光り咲く花の散りぬるごとき我が大君かも |
| あしひきの やまさへひかり さくはなの ちりぬるごとき わがおほきみかも |
| 右三首二月三日作歌 |
| 巻第三 480 挽歌 大伴宿禰家持 |
〔語義〕
「ちりぬる」は、花の散る姿に掛けた、皇子の死をいう |
〔歌意〕
この山全体までも輝かせていた花を、
散ってしまように感じさせる、「大君」よ |
この歌に注目したのは、原文「山左倍光咲花乃」が、
「水底并尓光乃尓」を思わせたからだ
「山までも輝かせる花」、「水底までも照らし輝かせる花」
似ているのに、この「光」の訓に「ひかり」と「てる」が違えて当てられている
この〔480〕は、旧訓では「光」を「てりて」と訓でいたのを、
『万葉集玉の小琴』〔本居宣長、安永八年(1779)成〕が、「ひかり」に改めた、とある
花が咲いて周囲が明るいさまを、
「光」の文字で「てる」、「ひかる」双方共に訓めるようだ
旧訓「やまさへてりて」とは、どんな解釈になるのだろう
接続助詞「て」の「添加」の「~て」なのか、
「補足・状態」の「~のさまで・~の状態で」となるのだろうか、
あるいは、「~のようにして」のような解釈なのだろうか
そして、接続助詞「て」であれば、次の語句「さくはなの」の補足になるのだから
「咲く花」が、「山までも照らすように輝いて」ということになるのだろう、きっと
これで語法的に支障なければ、「てりて」でもいいような気もするが、
本居宣長は、どんな根拠で、「やまさへひかり」に改めたのだろう
結局、「さへ」に関係するかもしれない、とするようなことではなく、
「光」自体が、どちらでも訓め、
その使い分けは、研究者のそれぞれの説を知るしかないことになるのだろうか
ついでに言えば、この〔480〕歌は、結句の「咲来鴨」を調べていて出合った歌だ |
| |
|
| [みかさのやま] |
現在の御蓋山(みかさやま、293メートル)のことだが、
三等三角点「三笠山」は、北隣の「若草山(342メートル)」にあるらしい
「若草山」は、三つの笠を置いた様なその山容から「三笠山」と混同された時期もあった
毎年一月に行われる「山焼き」は、この「若草山」の「のしば」を燃やして行われる
|
| |
|



|
| 【歌意1866】 |
(庭の)雪を見ていると、まだ冬のままだ
しかしながら、遠くの山を見れば、春霞が立って
それに、(庭の)梅も散り始めたようだ |
この「雪」は、「春霞」を手掛かりとして、山の雪だとする解釈がある
その場合でも降る雪なのか、残雪なのか解らないようだが
そもそも、「残雪」と認識して詠うのであれば、それは「冬の雪」なのだから
「しかすがに」という語は成り立たないだろう
降る雪、あるいは新雪を庭で見ており、そこにある梅の花も散り始めている景観が浮ぶ
しかし、遠くの山並みに目を遣れば、霞がたなびいて、春なのだけれども...
「いまだふゆなり」と断定して言っている
春霞が立ったり、梅が散り始めてはいるが、まだ「冬」だと言い切る
この時代でも、実際の季節感が、
暦上の季節とかみ合わないのを思わせる歌が結構多い
きっと、作者の心情もそうなのだろう
右頁の【注記】を書いていて、この掲題歌と同じ着想だと『岩波新大系』から
ふと思い巡らせたことがある
同じことを、逆に言う方法は、確かに語法としてはある
それは、言いたいことを「強調」するためでもある
しかし、今、その歌〔1838〕と、今日の掲題歌を並べて読んだとき
この二首は、『岩波』が引用して言うような
「逆にして言った」ものとは違うように思えてきた
むしろ、二首がセットで詠われた叙景歌のように思える
掲題歌〔1866〕で詠い、その結句は「うめはちりつつ」
その庭の梅が散り始めているのに、
しきりに白雪は降ってくる
それで、〔1838〕歌が続けて詠われる
散り始め、そしてすっかり花も散ってしまった
それなのに、雪が降りつづけ...
確かに今はまだ「冬」に違いないのに、春霞が立ち、梅の花が散る
この二首は、もともとは同時に詠まれたものかもしれない
同じ作者なのか、詠い合っているものなのか...
しかし〔1838〕は、「しらゆきにはに ふりしきりつつ」が主体とされ
〔1866〕は、「冬」だと言い切られているのに「うめはちりつつ」が主体とされた
この『万葉集』の編者は、目の前に積まれた万葉歌の資料(木簡だろうが)から
そうした部立ての仕分けで、この二首を離してしまったかもしれない
片や「詠雪」、片や「詠花」として
並べて読むと、その詠歌の空間が自然に重なり
だからこそ、二首の中で一首には「雪は庭に」と明言しているように思える
二首とも「庭」をいう必要はないのだから...
このように作者不詳の歌の魅力は、読み手がいろいろと想像できるところがいい |
| |

|
掲載日:2014.01.04.
| 春雑歌 詠花 |
| 見雪者 未冬有 然為蟹 春霞立 梅者散乍 |
| 雪見ればいまだ冬なりしかすがに春霞立ち梅は散りつつ |
| ゆきみれば いまだふゆなり しかすがに はるかすみたち うめはちりつつ |
| 巻第十 1866 春雑歌 詠花 作者不詳 |
【注記】〔1838〕
| 【1866】語義 |
意味・活用・接続 |
| ゆきみれば[見雪者 ] |
| ゆきみれば |
雪を見ると |
| いまだふゆなり[未冬有] |
| いまだ[未だ] |
[副詞](下に打消しを伴って)まだ・(今になってもなお続いていることを示す)今でも・まだ |
| なり[助動詞・なり] |
[断定・終止形]~である・~だ |
体言につく |
| しかすがに[然為蟹 ] |
| しかすがに[然すがに] |
(上代語)そうはいうものの・しかしながら |
副詞「然(しか)」にサ変動「為(す)」の終止形「す」、接続助詞「がに」のついたもの
中古以降は「さすがに」が用いられた |
| 〔接続〕体言及び、体言に準ずる語、動詞・助動詞の連体形、副詞や助詞など種々の語につく |
| はるかすみたち[春霞立] |
| うめはちりつつ[梅者散乍] |
| つつ[接続助詞] |
[余情](反復・継続の意で和歌の文末に用いられた場合は、後文を言いさして余情をこめる) ~ことだ 〔接続〕連用形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [ゆきみれば] |
他動詞マ行上一段「見る」の已然形「見れ」に、順接確定条件の接続助詞「ば」で、
「雪を見ると」の意になるが、この雪の状態が、人によって感じ方が違ってくる
「降っている雪」なのか、「残雪なのか」...
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕では、
第四句の「はるかすみたち」が言うのは、遠景のことだから、と「山頂の雪」と解釈する
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕は、
「雪」を冬の景物としての表現とし、「残雪」とし、
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕は、
『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕を引用し、
「(1838)を逆に言っただけで、内容にかはりはない。然しこの歌の雪は何処に降っているのか、明らかにされてゐない」と「注」に記している
「どこに降っているのか明らかにされてゐない」と言うのは、私には不思議に思える
昨日の「咲く花」が、何の花が咲くのか明らかにされていない、にも通じるものだ
しかし、そんな疑問には、今まで触れたこともなく、
「咲く花」が確かに歌意に解けこんでいる
この歌の「ゆきみれば」もまた、同じような解釈をすべきだと思う
どこの雪であろうと、「はるかすみ」と「散る梅」があるのだから
そこから、感じられるものがあるはずだ
〔1838〕歌と、逆に言っている、とうので、先月採り上げたその歌を、再掲してみる
| 春雑歌詠鳥(詠雪) |
| 梅花 咲落過奴 然為蟹 白雪庭尓 零重管 |
| 梅の花咲き散り過ぎぬしかすがに白雪庭に降りしきりつつ |
| うめのはな さきちりすぎぬ しかすがに しらゆきにはに ふりしきりつつ |
| 既出〔書庫-13〕巻第十 1838 春雑歌詠雪 作者不詳 |
〔歌意〕(2013年12月15日掲載時そのまま)
あんなに咲いていた梅の花が、今はすっかり散ってしまった
それなのに、白雪が
しきりに、とても尽きることもないように降りしきって... |
この〔1838〕歌を逆に言っただけで内容に変わりない、と『全釈』はいい、
それでいて、この雪はどこに降る雪なのかと明言されていないことを言っている
その『全釈』の「注」を引用した『岩波新大系』の解釈では、
「雪を見るとまだ冬だ。そうであっても、春霞が立って梅は散りつつある」の解釈
なるほど、所在不明のままの「雪」の解釈になっている
では、同じ内容だとわざわざ引用した〔1838〕歌を、『岩波新大系』はどう訳したのか
「梅の花は咲いて散ってしまった。それはそうであるが、白雪が庭に盛んに降っている」
ここでは、その雪は「庭」に降っている
勿論原文に「白雪庭尓」とあるのだから、「庭に降る」のは間違いではないが
同じような着想の歌の掲題歌〔1866〕であれば、「庭の雪」を思い描いてもいいはずだ
庭に残る、あるいは降る雪を見ると、いまだに「冬」だが
遠く山並みを見ると、春霞がたなびき、梅も散り続けている、の方がいいと思う |
| |
|
|
| 【歌意1867】 |
去年咲いた久木が、今咲いている
思いもしないこの時期に咲くとは...
むなしく散って地に落ちるだけだろうに...
誰にも見られることもなく... |
こんな解釈をする注釈書はないだろう
去年の対語として「今」とあれば、それは「今年」だろうし
花は、殆どの花は、毎年咲くものだ
だから、去年咲いた、と改めていうのも、不思議な気がする
私が思い浮かべたのは、
去年咲くべき時期に咲かなかった花が、今になって咲いている、そんな感じに似ている、と
この初句、第二句で受けたのは、そんな感じだった
しかし、「去年は咲いた」のだから、それを踏まえて感じられるのは
まだ、お前が咲く季節ではないのに...去年咲いたではないか
どうして今頃また咲くのか...誰も見る人もなく、むなしく散って行くだけだろうに...
唐突に、こんな風に思ったのではない
「久木」を古語辞典で引き、さらにこの歌での「久木」の解釈の諸説に触れたとき
この花は、「夏」に花開く、とあった
だから、誤字説も存在するのだが
仮に、この歌の部立ての「春雑歌詠花」を、間違いないものとすると
本来、夏に咲くべき花の「久木」が、「春である今咲いた」と言えるかもしれない
去年咲かないで、遅れて今、というのなら、「遅れた」ことへの「詠歌」になるだろう
しかし、去年咲いた上に、今この時期にまた咲くとは...
そんな、驚きと、誰にも知られず咲き散る哀れさが、上二句に表れていると思う
諸注のいくつかが述べるように、「去年愛しい人と見た花が、今年はいない」のであれば
「いたづらに つちにかおちむ」は、解釈することができない...私には
散る花を、「むなしく」とか「はなかく」、とか哀れむのは
一緒に見る人がいないからではなく、誰にも知られることもなく「咲いた」からだろう
その意味で、この歌は右頁の【注記】で採り上げた〔231・1871・3801〕とは違い
〔1677〕の部類になると思う
誰にも知られず、咲き、そして散るからこそ「いたづらに」であり
愛しい人と一緒に見られないので、「久木」に「いたづらに」とかけるのは合わないと思う
もっとも、今後も引き続く『万葉歌』との触れ合いの中で、
私のこんな想いを覆えす歌もあるかもしれないが...今は、素直に感じたままを残しておこう |



| |
| |
| 写真は「Wikipedia 「きささげ」]より拝借 |
|
掲載日:2014.01.05.
| 春雑歌 詠花 |
| 去年咲之 久木今開 徒 土哉将堕 見人名四二 |
| 去年咲きし久木今咲くいたづらに地にか落ちむ見る人なしに |
| こぞさきし ひさぎいまさく いたづらに つちにかおちむ みるひとなしに |
| 巻第十 1867 春雑歌 詠花 作者不詳 |
【注記】〔231・1871・3801・1677〕
| 【1867】語義 |
意味・活用・接続 |
| こぞさきし[去年咲之 ] |
| こぞ[去年] |
去年・昨年 〔名義抄〕「去年・昔歳 こそ」 |
| し[助動詞・き] |
[過去・連体形]~た・~ていた |
連用形につく |
| ひさぎいまさく[久木今開] |
| ひさぎ[楸・久木] |
[木の名]きささげ・(一説に)あかめがしわ、と言われる |
| いたづらに[徒 ] |
| いたずらに[徒らに] |
[形動ナリ・連用形]むなしい・はかない・なんの趣もない |
| つちにかおちむ[土哉将堕] |
| にか |
~であろうか・~であっただろうか〔接続〕体言・連体形につく |
| 〔成立〕断定の助動詞「なり」の連用形「に」に、係助詞「か」 |
| 〔係り結び〕係助詞「か」の働きで、連体形で結ぶ |
| む[助動詞・む] |
[推量・連体形]~(の)だろう |
未然形につく |
| みるひとなしに[見人名四二] |
| なし[無し] |
[形ク・終止形]いない・存在しない |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [ひさぎ] |
諸説があり、実際は未詳とされているが、しかし一般的には、
「あかめがしわ(タカトウダイ科)」か「きささげ(ノウゼンカズラ科)」などと言われている
共に落葉高木で、開花時期は「夏」なので、そこから「誤字説」もある
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕にいたっては、
「久木」は「足氷(あしび)」の誤字ではないか、と「木」と「氷」が似ているから、とし
「久木」は「馬酔木(あしび)」の借字とすべし、という
また、『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕では、「きささげ説」をとり
花がそれほど美しいものではなく、当時の人にもあまり親しまれていなかったので
編集者が春のものと誤ってここに入れたと考えることができる、としている |
| |
| [つちにかおちむ] |
原文「土哉将堕」は、一般的に「つちにかおちむ」と訓じられているが
「つちにやおちむ」と訓む注釈書もある
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕などがそれだ
ただし、同じ「岩波の大系」でも、
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕は、「つちにかおちむ」と訓じている
「や」も「か」も疑問の係助詞
どちらも「係り結び」の「係り」で、連体形で「結ぶ」 |
| |
| [みるひとなしに] |
「みるひとなしに」と訓む歌が幾つかあるが
その用いられる環境は、一様ではなく、解釈も様々みられる
『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕が言う解釈は、
「去年愛人と共にこの花を眺めた事実があったのだろう」とし、
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕もそれに倣う
そして、『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕もまた、
「去年咲いたときは共に眺める人があったのに、今年はそれがゐないという惆悵の情けをこめたものかと想像される」と言っている
これらの「想い」を同じにする歌が次の三首にあたる
| 挽歌/(霊龜元年歳次乙卯秋九月志貴親王薨時作歌一首[并短歌])短歌二首 |
| 高圓之 野邊乃秋芽子 徒 開香将散 見人無尓 |
| 高円の野辺の秋萩いたづらに咲きか散るらむ見る人なしに |
| たかまとの のへのあきはぎ いたづらに さきかちるらむ みるひとなしに |
| (右歌笠朝臣金村歌集出) |
| 既出〔書庫-6〕巻第二 231 挽歌 笠朝臣金村 |
〔歌意〕(2013年5月22日掲載時そのまま)
高円の野辺の秋萩は、空しく咲いては散るのだろうか...
もう見る人もいなくなった後なのに... |
| |
| 春雑歌詠花 |
| 阿保山之 佐宿木花者 今日毛鴨 散乱 見人無二 |
| 阿保山の桜の花は今日もかも散り乱ふらむ見る人なしに |
| あほやまの さくらのはなは けふもかも ちりまがふらむ みるひとなしに |
| 巻第十 1871 春雑歌詠花 作者不詳 |
〔語義〕
原文「佐宿木花者」には、諸説があるが、一応「さくら」とする
「ちりまがふらむ」は、「散り乱れているだろうか」
「みるひとなしに」、ここでの「みるひと」は、いつも「さくらの見事な散りさま」を見る人たちのことで、先の二首と同列 |
〔歌意〕
阿保山の、あの見事なさくらの花は、
今日あたり、散り乱れているであろうか
誰も見る人もいないのに... |
| |
| (中臣朝臣宅守与狭野弟上娘子贈答歌) |
| 和我夜度乃 波奈多知婆奈波 伊多都良尓 知利可須具良牟 見流比等奈思尓 |
| 我が宿の花橘はいたづらに散りか過ぐらむ見る人なしに |
| わがやどの はなたちばなは いたづらに ちりかすぐらむ みるひとなしに |
| (右七首中臣朝臣宅守寄花鳥陳思作歌) |
| 巻第十五 3801 贈答歌 中臣朝臣宅守 |
〔語義〕
「わがやどの」は、このときの中臣朝臣宅守の事情を考えると
自宅ではなく、「旅」の境遇にあることが知られているので
「やど」とは、その途中の宿舎の庭、あるいはその周辺だと言われている
しかし、結句の「みるひとなしに」を思うと、
どうしても、誰もいない都の自宅の庭のことに思えてしまう
「ちりかすぐらむ」は、「散り去っていることだろうか」 |
〔歌意〕
都の家の庭に咲く橘の花
今頃は、むなしく散り去っていることだろうか...
いまは、見る人もいなくて... |
こうして並べてみれば、ここでの「人」はある特定の人を言っている
秋萩を愛でた志貴皇子、もうその秋萩を見ることもないのに、秋萩は咲き、散る
いつも阿保山の見事に咲き、そして散る桜を、見る人が、いない
自分の家の庭に咲く橘の花、私は見ることもできないで...散る
こうした詠い方は、とてもせつないものだ
そして、もう一つは、不特定な「見る人」
目の前に起こっていること、作者は客観的に詠じるのだから
実質的には、誰も他に見る人がいない、と...
それが、次の歌の場合になるだろう
| 雑歌/(大寳元年辛丑冬十月太上天皇大行天皇幸紀伊國時歌十三首) |
| 風莫乃 濱之白浪 徒 於斯依久流 見人無 [一云 於斯依来藻] |
| 風莫の浜の白波いたづらにここに寄せ来る見る人なしに [一云 ここに寄せ来も] |
かざなしの はまのしらなみ いたづらに ここによせくる みるひとなしに
[ここによせくも] |
| 右一首山上臣憶良類聚歌林曰 長忌寸意吉麻呂應詔作此歌 |
| 巻第九 1677 雑歌 長忌寸奥麻呂 |
〔語義〕
「かざなしの」の原文「風莫」を「風早」の誤りとして、
「風が激しい」とする説もある
「風莫」であれば、それは「無風状態」のことを言うのだろう
『新大系』などは、「風早」とし、そんな激しい風にあおられて起つ白波の、
浜に寄せるのを、誰も見る人もいないのに、むなしいことだ、とするが
確かに、見る人もいないのに、風も激しく波を寄せることもないだろうに、と
そうした方が自然だろう...
しかし、「風早」のような情況での「白波」であれば、「いたづらに」ではない
それが起こる当然の荒々しさだから...
むしろ風もないのに、懸命に白波を浜に寄せいるのに
それでも「誰も見る人がいない」...それが「むなしい」のではないか |
〔歌意〕
風もなく、それでもこの浜に押し寄せる白波
それなのに、ここには誰も見にこない...むなしく寄せる白波だ |
この歌も、初句の「風莫」「風早」で、随分その意味が違ってくる
まさに、詠う者の「感性」を伺うに等しいことになる
いつかまた、じっくり読んでみたい
掲題歌〔1867〕は、この〔1677〕と同じ「想い」の歌だと思う
『全釈』などが言う、「愛しい人と、去年は見た」ではなく
第二句の「今開」が手掛かりになると思う |
|
|
|
| 【歌意1868】 |
(あしひきの)山の合間を、美しく照り輝かせて咲いている桜花
この降る春の雨に
舞うこともなく散ってゆくのだろうなあ |
見頃を終えた桜花なのだと思う
あとは、風に吹かれて、桜吹雪などと期待するのだが...
この降り続く雨に、そのように舞うこともなく、散ってゆくのだろう
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕の解説では、
第二句「やまのまてらす」が現在形で、第四句「このはるさめに」の「この」から、
「春雨は今降り出したと見える」と、その情況を描いてみせる
そうかもしれない、
降り出した雨に、山の合間に見え輝いていた「桜花」が散るのは惜しい
桜は、「咲く花」と「散る花」の二種類の楽しみ方が出来ると思う
その締め括りが、雨に打ち落とされて、では
何だか、切なくなる
この歌の類想歌とされるのが〔1561〕歌なのだが、
私には、その「うたごころ」は違うものだと思う
| 秋雑歌/故郷豊浦寺之尼私房宴歌三首 |
| 明日香河 逝廻丘之 秋芽子者 今日零雨尓 落香過奈牟 |
| 明日香川行き廻る岡の秋萩は今日降る雨に散りか過ぎなむ |
| あすかがは ゆきみるをかの あきはぎは けふふるあめに ちりかすぎなむ |
| 右一首丹比真人國人 |
| 既出〔書庫-8〕巻第八 1561 秋雑歌 丹比真人国人 |
〔歌意〕
明日香川が、めぐり流れる岡の秋萩は、
今日降っている雨で、散ってしまうのだろうか |
この「秋萩」は、「散るのを惜しむ」ものだ
しかし、掲題歌の「桜花」は
私には、その「散り方を惜しむ」ように思える
花のいのちとは、儚いもの
しかし、その「終え方」にまで人を魅了する花が、「さくら」という花
儚さをいとおしむばかりでなく、「いかに散るか」を期待される花
私だけかもしれないが...そう思う
|
|
掲載日:2014.01.06.
| 春雑歌 詠花 |
| 足日木之 山間照 櫻花 是春雨尓 散去鴨 |
| あしひきの山の際照らす桜花この春雨に散りゆかむかも |
| あしひきの やまのまてらす さくらばな このはるさめに ちりゆかむかも |
| 巻第十 1868 春雑歌 詠花 作者不詳 |
【左頁類想歌】〔1561〕
| 【1868】語義 |
意味・活用・接続 |
| あしひきの[足日木之 ]〔枕詞〕山にかかる |
| やまのまてらす[山間照] |
| ま[間] |
(空間的に)あるものが位置する所・間・隙間 |
| てら[照る] |
[自ラ四・未然形]光を放つ・輝く・(容貌や姿が)美しく輝く |
| す[助動詞・す] |
[使役・終止形]~せる |
未然形につく |
| さくらばな[櫻花 ] |
| このはるさめに[是春雨尓] |
| この[此の] |
(自分に最も近いものを指示する) この・このような
|
| 〔成立〕代名詞「此(こ)」に、格助詞「の」 |
〔参考〕現代語では一語の連体詞とするが、
古語では「こ」の下に他の助動詞も付くことから 、連語に扱う |
| に[格助詞] |
[原因・理由]~によって・~により |
体言につく |
| ちりゆかむかも[散去鴨] |
| ちり[散る] |
[自ラ四・連用形](花や葉などが)散る |
| ゆか[行く・往く] |
[自カ四・未然形](動詞の連用形の下について) |
| |
いつまでも~し続ける・だんだん~てゆく |
| む[助動詞・む] |
[推量・連体形]~(の)だろう |
未然形につく |
| かも[終助詞] |
[詠嘆・感動]~であることよ |
連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [ちりゆかむかも] |
原文「散去鴨」は、『西本願寺本』などによる「ちりゆかむかも」の他に
『類聚古集』『紀州本』に「ちりぬらぬかも」、
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕に「ちりにけんかも」、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕に「ちりにけるかも」などがある |
| |
|

|
| 【歌意1870】 |
雉の鳴く声が聞こえる、高円辺りの桜の花が
散りながらも、なお春風に流れるよう舞うのを見せてくれる
共に見る人がいたらいいのだが... |
雉の鳴き声、妻を求めて鳴く声を、自分の「すがた」に重ねる
高円の山辺では、その鳴き声もいっそう響く感じがする
その高円の「桜花」が、春風に揺られ、散り出した
しかし、それでもなお、その「散る舞いの姿」は、胸を打つほど素晴らしいのだろう
今この場に、共に見る人がいないのを...「雉」に重ねて「鳴(歎)いて」いる
この歌、「叙景歌」として感じ取るのも『全注』がいうような「絵画的」な風趣だろう
しかし、「絵画」では、雉の鳴き声は聞かれない
雉が鳴くことによって、「妻を求め」
「ちりてながらふ」桜花を、一緒に見る人がいない、いたらなあ、と感嘆する「情景歌」だ
写生的な歌も、確かにいい
しかし、限られた文字数で、韻を踏みながら描く世界は
「こころ」の「うつしごと」の方が、その奥行きを表現できる
言葉にすると、すべてが「限定される」
しかし、歌だけは違う
限られた言葉数にしながら、その広さ、奥行きに深遠な世界観を与えてくれる
もっとも、言葉の本来の目的は、その限定することにあるのだが
だからこそ、その表現する「道具」を駆使して、「無限」の世界を創り出す
そうでなければ、言葉を用いて「歌」だという意味がなくなる
一つの歌でも、様々な解釈を可能にするのは
それが、「言葉によって限定」されない「歌」であるからだ
言葉の相反する作用...改めて、その魅力を、こうして接する日々の万葉歌に感じている
|




|
掲載日:2014.01.07.
| 春雑歌 詠花 |
| 春雉鳴 高圓邊丹 櫻花 散流歴 見人毛我母 |
| 雉鳴く高円の辺に桜花散りて流らふ見む人もがも |
| きぎしなく たかまとのへに さくらばな ちりてながらふ みむひともがも |
| 巻第十 1870 春雑歌 詠花 作者不詳 |
【注記】〔1424・510〕
| 【1870】語義 |
意味・活用・接続 |
| きぎしなく[春雉鳴 ] |
| きぎし[雉子] |
[「きぎす」とも]きじ(鳥の名)の古名 |
| たかまとのへに[高圓邊丹] |
| さくらばな[櫻花 ] |
| ちりてながらふ[散流歴] |
| て[接続助詞] |
[逆接の確定条件]~のに・~ても
|
連用形につく |
| ながらふ[流らふ] |
[自ハ下二・終止形]流れ続ける・流れるように降り続ける |
| 〔下二段「流る」に上代の反復・継続の助動詞「ふ」が付いて一語化したもの〕 |
| みむひともがも[見人毛我母]〔慣用句的な表現になっている〕共に見る人がいたらなあ |
| がも[終助詞] |
[係助詞「も」について「もがも」の形で]願望の意を表す |
| |
~てほしい・~たらいいがなあ |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [きぎし] |
平地や低い山の林や草地に住む
春の繁殖期に、妻を求めて鳴くとされている
鶉と並んで代表的な狩猟鳥 |
| |
| [接続助詞「て」] |
この接続助詞「て」の解釈は、
まず例外なく「単純接続」や「補足の行われ方」で解釈するものばかりだろう
しかし私は、「逆接の確定条件」の方が、いいと思う
接続助詞「て」の用法は、
| 単純接続 |
~て・そして |
| 並立 |
~て |
| 確定条件 |
|
| 原因・理由 |
~ので |
| 逆接 |
~のに・~ても |
| 補足 |
|
| 行われ方 |
~て・~ようにして |
| 状態 |
~のさまで・~の状態で |
| 添加 |
~て |
そう思う理由は、この第四句「ちりてながらふ」の解釈の仕方にあると思う |
| |
| [ちりてながらふ] |
この接続助詞「て」を
上表の用法の「単純接続・並立・補足」などとして解釈するのが普通だと思う
「散る」、そして「流れ続ける」
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕の解釈では、
「桜の花が流れるようにしきりに散っている」としており
あたかも「補足」のような使い方になっているが
私の調べ方が足りないのか、古語辞典での接続助詞「て」の「補足」の解説では
「前の事態が、あとの事態の内容を補う関係で続くことを示す」とあり
その中での「行われ方」では、
「あとの動作の行われ方を示す」、とある
すると、その方法で「ちりてながらふ」を解釈すると
「散るようにして、流れつづける」になると思うのだが...私の理解不足かもしれない
敢えて「補足」に拘れば「流らへて散る」になるはずだ
そして、おなじく『全注』は、この語句と比較して、
巻第八〔1424〕の「流らへ散る」を引き合いに出し
それに比べて、この掲題歌〔1870〕は観察が細かく、表現も細密である、という
おそらく、歌意としての流れからは、「流らへ散る」が素直であり
しかし、その歌としての文学的な表現を求めたとき、
「散りて流らふ」の方が優れている、という意味なのだろう
それでも、こうした解釈以外にも、もう一つの可能性があると思う
「散って、流れる」「流れるようにして散る」は、当たり前過ぎる
仮に、歌としての表現に拘るのなら、私はこう感じたい
「散っても尚、その流れるような散り方」が素晴らしい...それが「さくら」なのだと
接続助詞「て」に、「逆接の確定条件」も用法としてある以上、これも可能だ
さらに言えば、元来この接続助詞「て」は、
完了の助動詞「つ」の連用形「て」から転化したものだとされている
接続助詞「て」も、助動詞「つ」も、ともに「連用形」につくので
この区別は、歌意から理解することになるらしい
この歌の場合、完了の助動詞「つ」の連用形「て」も考えられるだろうか
「散っている、流れるようにして」、「散ってしまった、流れるように...」
「ちりてながらふ」「ながらへちる」の醸し出す「歌」に惹かれて先ほどの〔1424〕歌
| 春雑歌/駿河釆女歌一首 |
| 沫雪香 薄太礼尓零登 見左右二 流倍散波 何物之花其毛 |
| 沫雪かはだれに降ると見るまでに流らへ散るは何の花ぞも |
| あわゆきか はだれにふると みるまでに ながらへちるは なにのはなぞも |
| 巻第八 1424 春雑歌 駿河采女 |
〔語義〕
「あわゆき(沫雪)」泡のように消えやすい雪
「はだれ」は、雪がはらはらと薄く降り積もるさま
「までに」は、程度をはっきり表す「~までに」
「ながらへちる」は、「流れるように降り散る」
「なにの」は、「どうのような」、「なんという」
「ぞも」(上代は「そも」)、疑問の語とともに用いられて、「いったい~だろうか」 |
〔歌意〕
沫のような「はだれ雪」、
そんなふうに、みまがうほどに流れ降り散るこの花は
いったい何という花なのだろうか |
この作者「駿河采女」は、出身が駿河国くらいしか現代には伝わらないようだが
『万葉集』には、この歌の他に、もう一首「駿河采女」作があり、私も好きな歌だ
| 相聞/駿河采女歌一首 |
| 細乃 枕従久々流 涙二曽 浮宿乎思家類 戀乃繁尓 |
| 敷栲の枕ゆくくる涙にぞ浮寝をしける恋の繁きに |
| しきたへの まくらゆくくる なみたにぞ うきねをしける こひのしげきに |
| 巻第四 510 相聞 駿河采女 |
〔語義〕
「しきたへの」は、枕詞で「枕」にかかる
「まくらゆくくる」の「ゆ」は「~より・~を通って」
「くくる」は、水中を潜行することにいうばかりでなく、
水が岩間を行く場合にも用いる
狭い間隙を窮屈そうに通り抜けることを意味する
「なみだにぞ」は、涙を水の流れ「川」にたとえている
「うきねをしける」の「うきね(浮き寝)」は、水に浮いて寝ること
「しける」は、サ変「為(す)」の連用形「し」に、
過去の詠嘆の助動詞「けり」の連体形「ける」
「しげき」は、絶え間ない、しきりに、の意の形容詞「しげし」の連体形「しげき」
それに、原因・理由の格助詞「に」
|
〔歌意〕
(しきたへの)枕を濡らして流れる涙
その涙川の中に、浮いて寝たのですよ
あまりの恋の激しさゆえに...
|
いい歌だと思う
涙で塗れた枕...水の上で寝られはしない
止め処もなく流れる涙
そんな中で、私は寝ようとしていた...それでも涙は流れ...
作者「駿河采女」が、この二首ともに同じ作者かどうかは分からないが
こう千何百年も経ては、「象徴的」な受け方でもいいと思う
「采女」は、天皇の後宮に貢進された地方豪族層出身の女性
大化改新の詔に、
「郡少領以上の姉妹及び子女にして形容端正なる者を貢物として差し上げるべき」
自由を束縛され、官人男子から遠ざけられて寂しく生きているかのような境遇を
万葉歌の幾つかある「采女」の歌から伺うことができる
この〔510〕でも、恋愛さえ許されない悲しい想いを、思わせる |
| |
| [がも] |
一般的に用いられる「もがも」を、係助詞「も」と「がも」に分けて終助詞としたもの
尚、上代の終助詞「もがも」は、終助詞「もが」に、終助詞「も」がついたもの
いずれの用法も、「願望」を表す |
| |
|
|
| 【歌意1873】 |
咲けよ、と春雨にうながされるように
そして、その春雨に抵抗することも敵わずに、
私の家の桜の花は、咲き始めてしまったなあ |
作者は、桜の花の開花を、待ち望んではいた
しかし、「春雨」にせかされるようにして「咲く」のは、不満があるらしい
自然に、桜自身の意志で咲かせたかった
そんな愛情がこもった歌だと思う
注釈書によっては、まったく逆の解釈もある
どれが正しいのかなど、解りようもない
自分が思い描く感じ方でいいと思う
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕の解釈に拠れば
「春雨に抵抗しきれずに、我家の庭の桜の花は、ようやく咲きはじめたよ」と歓迎している
「春雨」のお陰で、咲き渋っていた「開花」を感じている
この『全注』の解釈は、はっきりと解る
しかし、他の注釈書では、作者がどちらの気持ちで詠んだものか、その訳では解らない
急かされて、抵抗しきれずに「咲く」ことが
「見る側」の「情け」なのか「咲く側」の「情け」として詠うのか...
万葉人への「深読み」かもしれない
「あらそひかねてさくはな」を、せっかく頑張っていたのになあ、と感じられる万葉人
私は、その「こころ」を持つ万葉人の方が好きなんだけど
一般的には、どんな手段であっても、早く咲いてくれたことを、喜ぶものなのだろう
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕に、
「季節のおとずれに催されて、花の咲いたのを、アラソヒカネテと解釈しているのが特色である。その考え方には、植物を擬人化した気持ちがあり、若干のいやみが無いでもない。」とある
この「若干のいやみ」とは、擬人化した「さくら」へのことなのだろうか
もっと、抵抗してもいいじゃないか、と
それならば、「急かされて咲く花」の、
「ほら、やっと咲いたか」というような「咲き惜しみ」への「いやみ」ではなく
やはり、私と同じように「もっと頑張って欲しかった」としたいものだが...
それにしても、どの注釈書も何も語らない
「抵抗しきれず、やっと咲いてくれたか」と詠む歌なのか
「抵抗しきれず、咲いてしまったのか」と詠む歌なのか...
どちらとも採れる解釈ばかりだ
私は...「もっと頑張って欲しかった、桜よ」といってやりたい
|



|
掲載日:2014.01.08.
| 春雑歌 詠花 |
| 春雨尓 相争不勝而 吾屋前之 櫻花者 開始尓家里 |
| 春雨に争ひかねて我が宿の桜の花は咲きそめにけり |
| はるさめに あらそひかねて わがやどの さくらのはなは さきそめにけり |
| 巻第十 1873 春雑歌 詠花 作者不詳 |
【注記】〔2106・2120・2200〕
| 【1873】語義 |
意味・活用・接続 |
| はるさめに[春雨尓 ] |
| あらそひかねて[相争不勝而] |
| あらそひ[争ふ] |
[自ハ四・連用形]張り合う・抵抗する・言い争う・戦う |
| かね[接尾語・かぬ] |
[ナ行下二・連用形](動詞の連用形について)
~のが難しい・~ことが出来ない |
| 〔例語〕言ひかぬ・思ひかぬ・堪へかぬ・待ちかぬ・忘れかぬ・見かぬ、など |
| て[接続助詞] |
[順接の確定条件(原因・理由)]~ので
|
連用形につく |
| わがやどの[吾屋前之 ] 我家の前庭の |
| さくらのはなは[櫻花者] |
| さきそめにけり[開始尓家里] |
| そめ[接尾語・初(そ)む] |
[マ行下二・連用形](動詞の連用形について)
~はじめる・はじめて~ |
| 〔例語〕相見初む(互いに恋心を抱き始める)・言ひ初む・思ひ初む・恋初む・知り初む、など |
| にけり |
[完了の助動詞「ぬ」の連用形+過去の助動詞「けり」] |
| 〔「けり」が過去を表す場合〕 「~てしまった・~た・~たということだ」 |
| 〔「けり」が何かに気づいたことや詠嘆を表す場合〕「~ていた・~てしまったことだ」 |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [あらそひかねて] |
「春雨に争いかねる」というのは、春雨に抵抗できず、とか
その結果、止むを得ず、~してしまった、というような意味になる
この歌の「あらそひかぬ」とは、「春雨が桜の開花を促し、それに抵抗しきれず」だろう
「あらそう」表現で、この歌と同じように促された「草木」の歌がある
| 秋雑歌詠花 |
| 此暮 秋風吹奴 白露尓 荒争芽子之 明日将咲見 |
| この夕秋風吹きぬ白露に争ふ萩の明日咲かむ見む |
| このゆふへ あきかぜふきぬ しらつゆに あらそふはぎの あすさかむみむ |
| 巻第十 2106 秋雑歌 詠花 作者不詳 |
〔語義〕
「あらそふはぎの」は、白露に咲かまいと抵抗していた萩 |
〔歌意〕
この夕方になって、秋風が吹いてきた
白露に逆らって、花を開かせまいとしている萩も
明日は咲くのだろう...見てみよう |
| |
| 白露尓 荒争金手 咲芽子 散惜兼 雨莫零根 |
| 白露に争ひかねて咲ける萩散らば惜しけむ雨な降りそねそ |
| しらつゆに あらそひかねて さけるはぎ ちらばをしけむ あめなふりそね |
| 巻第十 2120 秋雑歌 詠花 作者不詳 |
〔語義〕
「ちらばをしけむ」は、散ったら惜しいことだろう
「あめなふりそ」は、禁止の「~な~そ」で、中の動詞の連用形が示す動作の禁止、
同じ禁止の「~な」の形にくらべ、婉曲な言い方になる
「ね」は、相手に対してその行為の実現を望む意 |
〔歌意〕
白露に抵抗しきれずに咲いた萩
早くも散ってしまえば、惜しいことだろう
雨よ、そうならないように、どうか降らないでくれ |
| |
| 秋雑歌詠黄葉 |
| 四具礼能雨 無間之零者 真木葉毛 争不勝而 色付尓家里 |
| しぐれの雨間なくし降れば真木の葉も争ひかねて色づきにけり |
| しぐれのあめ まなくしふれば まきのはも あらそひかねて いろづきにけり |
| 巻第十 2200 秋雑歌 詠黄葉 作者不詳 |
〔語義〕
「しぐれのあめ」は、「しぐれ」のこと
「まなくしふれば」の「まなく」は、「絶え間なく」、「し」は強意の副助詞
「ふれば」は、順接の確定条件「ば」で、「降っているので」
「まきのはも」の「まき」は、杉や檜のような良質の木材になる木のこと
「も」は、言外暗示の係助詞で、~さえも、他のものはもとより、の意
「にけり」は、上述、「~てしまった」 |
〔歌意〕
しぐれが、止むこともなく絶えずに降り続いているので
真木の葉までも、とても抵抗しきれず
とうとう色づいてしまった |
こうして、草木に関する「あらそひかぬ」を並べてみると
「白露」も「しぐれ」も、花などを早く散らせるだけでなく
その開花を促す働きとしても、万葉人は詠んでいることが解る
こうした発想は、早く咲けば、それだけ散るのが早い
結果的には、花が散るのを惜しむことからのものだ
開花を待ち望むあまりに、そんなに急かして咲かさないでくれ、
散るのが早くなるから...この心情、いいなあ、と思う |
| |
| [わがやどの] |
この語句には、以前にも考えさせられた
「わがやど」という場合、幾つかの環境が言われるのが万葉集だ
作者のそのときの事情も踏まえて、その「やど」の環境を推察する
この歌の場合の「わがやど」の原文は「吾屋前」
以前、私はこの表記なら「我家の前庭」とした方がいい、と書いている
その意味合いも当然含んでのことだろうが、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕は、「わがにはに」と訓む
そうした例は、他には私は知らない
『全註』では、「吾屋前」を、すべてそう訓むのかどうか解らない
いつか、確認したいものだ
それでも、今できることがある
一般的なテキストでの「わがやど」の表記例を拾い出してみた
| 「わがやど」の表記例 『万葉集』中、六十七首 (長歌四首は除く) |
| 吾屋戸 |
21首 |
万葉仮名 |
|
| 我屋戸 |
9首 |
和我夜度 |
8首 |
| 吾屋外 |
3首 |
和我屋度 |
2首 |
| 我屋前 |
2首 |
|
| 吾屋前 |
22首 |
今は、この表記の歌数だけを拾い出したが
勿論、その目的は、この「わがやど」のそれぞれの歌で描かれる場所が知りたい
以前は、単純に「屋前」だと「前庭」のイメージが容易だ、としたが
本当にそうなのかどうか...
それに、「家の前」つまり外かもしれない
「万葉仮名」はともかくとして、「屋戸」と「屋前」が、ほぼ半々
「屋戸」を「やど」と訓じるのは理解できる
しかし「屋前」を「やど」とするのは...「前」を「ど」とは訓めない
やはり、その漢字「前」に意味を持たせてのことだとは思うのだが...
いずれ一首ずつ、ただ描かれる場所だけに絞って、調べたいものだ |
| |
|
|
| 【歌意1874】 |
春雨よ、そんなに激しく降らないでくれ
桜の花を、私はまだ見ていないのだから...
それなのに、散ってしまうのが、とても残念だ |
春雨は開花を促し、今度は散らさんばかりに、降りしきる
まるで意志を持った、意地悪な「雨」のようで、
作者は懇願している、そんなに意地悪しないでくれ、と
桜の花の開花は短い
だから、一旦咲いた桜花を、じっくりと観賞できる期間は短い
雨ばかり降って...
ならば、この作者は、「春雨」と対話しているのではないか
「お前のせいで、桜の花を見られなかったら、どうしてくれる」
いや、違う
「私の、この気持ちを分かって欲しい、だからそんなに激しく降らないで」とか...
『万葉集』中で、部立てで扱われる「雨」は、
「春雑歌詠雨」が一首、「秋雑歌詠雨」が四首...
「春相聞寄雨」が四首、「秋相聞寄雨」が二首...
この「詠雨」「寄雨」は、いずれも巻第十の「春・秋」の季節感の中で詠われている
この他の「詠雨」「寄雨」は、
共に巻第七の、雑歌「詠雨」二首、譬喩歌「寄雨」二首のみで、これらは「季節」を詠わない
意外と、「雨」を詠む歌は少ない
掲題歌〔1874〕にしても、「春雑歌詠花」であり
勿論、「桜花」を愛でる歌には違いないが
しかし、この歌...私には、「雨」も大きな役割を担っているので、
「詠雨」でもいいのではないか、と思ってしまう
「春雨」の思惑一つで、変わるものなら、花を散らすような雨にはならないで欲しい
作者が対話している「春雨」こそ、この歌の主題ではないだろうか
こんなに切に願うのも、まだ桜花を見ていないのだから...と理解を求める
この歌もそうだが、昨日の歌〔1873〕でも、「春雨」を相手にしている
もっとも、昨日の歌は、その「春雨」に抗しきれずに「咲いた桜花」に心は向いているが
今日の「春雨」は、違う
まさに、作者の懇願する「相手」として詠われている
初句と第二句で一旦区切ると、もう少し分かりやすい
上二句が「春雨」へ懇願し、以下は自分の「心」を、「春雨」に訴えるかのようだ
これでは「桜花」は、「出演しない登場者」になっている
ならば、この歌...「詠雨」の方が、良さそうだ
部立てに、あまり拘りたくはないが...
実際、部立てそのものへの曖昧な仕分けも言われていることだし
私が、とやかくいうこともない
それにしても、「季節の雨」を詠った歌が、この巻第十の十一首だけとは...少ない |
| |
|
掲載日:2014.01.09.
| 春雑歌 詠花 |
| 春雨者 甚勿零 櫻花 未見尓 散巻惜裳 |
| 春雨はいたくな降りそ桜花いまだ見なくに散らまく惜しも |
| はるさめは いたくなふりそ さくらばな いまだみなくに ちらまくをしも |
| 巻第十 1874 春雑歌 詠花 作者不詳 |
| 【1874】語義 |
意味・活用・接続 |
| はるさめは[春雨者 ] |
| いたくなふりそ[甚勿零] |
| いたく[甚し] |
[形ク・連用形]甚だしい・ひどく |
| な~そ[禁止] |
[副詞「な」と終助詞「そ」の間の動詞連用形の動作を禁止] |
| |
~するな・~してくれるな |
| さくらばな[櫻花 ] |
| いまだみなくに[未見尓] |
| なくに |
~(し)ないことだのに・~(し)ないのに |
未然形につく |
| [助動詞「ず」の「ク語法なく」+助詞「に」] 〔ク語法は名詞化する語法〕 |
| ちらまくをしも[散巻惜裳] |
| まく[助動詞・む] |
[推量・ク語法]~てしまうだろうこと |
未然形につく |
| をし[惜し] |
[形シク・終止形]失うにしのびない・惜しい・残念だ |
| も[終助詞] |
[感嘆]~よ・~なあ 〔接続〕文末・文節末の種々の語につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [はるさめは] |
どの諸本も、「春雨者」とあるが、『類聚古集』には、原文「春乃雨者」とあり、
それを採り入れている注釈書が、『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕で、
「はるのあめは」と訓んでいる
尚、「はるのあめ」と訓む例は、三首あり
その原文はすべて「春之雨」なので、「春乃雨」は表記の面でも
さらに、韻で「はるのあめ」ならともかく「はるのあめは」とするのは、無理だろう
|
| |
| [いたく] |
形容詞ク活用「いたし」
究極に達する意のラ行四段動詞「いたる」と同根で、
究極に達する甚だしいさまを表すのが原義
その原義に近いのが「甚し」と漢字を当てるもので
「程度が甚だしい・激しい・非常によい・すばらしい」
そして、その「激しさ」が、肉体や精神に与える感じを表すのが、
マ行四段動詞「いたむ」を同根とする「痛し」となる
「(体に)痛みを感じる・(精神的に)苦痛である・つらい・いたわしい・いとしい」 |
| |
| [な~そ] |
禁止の終助詞「な」による表現と比べて穏やかな願望をこめた禁止の意を表す
上代には「な~」だけで多く用いられた
中古末期以降「な」が省略され、「~そ」のみの形で用いられることもあった
なお、「な~そ」については、この形で一つの終助詞とする説もある |
| |
| [なくに] |
打消しの助動詞「ず」の「ク語法」で、「ないこと」と名詞化されるが
問題は助詞「に」の扱いだ
格助詞、断定の助動詞「なり」の連用形、接続助詞などの諸説があるが
この歌の歌意からすると、格助詞ではなく、逆接の接続助詞に思える
「まだ見ていないのに、散るのは惜しい」というのだから、やはり逆接だろう
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕では、格助詞「に」としているが
その解釈は、接続助詞だ
もっとも、古語辞典によると、格助詞は体言に接続するが、接続助詞は連体形とされる
だから、文法的には「格助詞」というのだろうが、歌意は「逆説」しか考えられない |
| |
|
|
| 【歌意1875】 |
春になったので、やがて惜しくも散るだろう梅の花よ
もう少しの間、我慢して咲かずにいて欲しい
蕾のままでいて欲しいよ |
「春されば」を異訓の「春さらば」とすれば、こんな歌意になるだろうか
春になったら、咲いても、あとは散るばかりだ
まだまだ散らすのは惜しい
このまま蕾のままで、いてくれたらなあ
一般的な訓に従えば、表記のような歌意になると思うが
その場合、「梅の花」は、まさに開花時期を迎えた最中ということだろう
季節に促さられるようにして、やがて見事に咲き誇るのだろうが
散るときのことを思うと、つらいものだ
ならば、いっそのこと、蕾のままで、少しの間咲かずにいて欲しい
もっと、少しでも長く、お前を見ていたいのだ
しかし、そんな願望も空しく、梅の花は今にも咲きそう...残念なことだ
こうやって解釈すると、「詠花」と言っても、
「花の盛り」を愛でるのではなく
梅の木そのものを、芽吹いた状態から愛しむ気持ちが伝わってくる
しかし、「梅の花が咲き散る」ことを惜しむ、というより
これも異訓の「桜花」の方が、その「早く散る」を惜しむ気持ちが、
詠われるには相応しいような気もする
これは、個人的な感じ方になるだろうが、
「春になったので」、「桜」は、あっという間に咲いて、あっという間に散る
その寂しさを詠ったのではないか、と
多くに採り上げられているように、「梅の花」であれば
むしろ、初句の異訓「はるさらば」こそ、「梅の花」に似合う
「順接の仮定条件」だから、いくら部立てが「春雑歌」であっても
まだ春になっていないことになる
おそらく、「春去れば」とするのは、この部立て「春雑歌」が影響しているのではないだろうか
春の歌だから、「春になっていなければならない」と
だから、その前提があって「春去らば」とは訓まれなかった
そんな風に、私は考えてしまう
そして、「春去らば」と詠い出すのであれば、ここでこそ「梅の花」でなければならない
何しろ、まだ季節は「冬」
しかし、間もなく「春」はやってくる
「梅の蕾」もちらほら見え出した
でも...咲いてしまえば、散ってしまうのも惜しい
だから、そんなに急いで咲かなくても、少し我慢してくれないかなあ、と
部立てを重視するなら、「春去れば」と詠い出し、
でも「桜花」とすべきではないかな、と思う
しかし、何もいじらず、「春去らば」を異訓としないのなら、「梅花」
その方が、下手にいじらないのでいい
そして、この部立て「春雑歌」の曖昧さを指摘する方が、まだましではないだろうか
実際、部立てに対する評価はそんなものだし...
しかし不思議だとは思う
多くの注釈書が「春去れば」とし、「順接の確定条件」を採用しながら
その解釈では、何だか「仮定条件」のような歌意になっているのものもある
岩波の『新大系』では、「春になれば散るのが惜しい梅の花よ」
同じく旧の『大系』でも、「春になると散るのが惜しい梅の花よ」
『全注』は、中間的で、むしろ「恒常条件」として訳している
「春になると、いつも散るのが惜しまれる梅の花よ」...これは「春去れば」でも矛盾しない
まだまだ引き合いに出せれば、と思うが...大方はこんなものだ
『全注』のデータから思うこともある
四季分類の巻第八・十では、梅の花は、冬と春とに収められており
巻八では、、春の八首に対して、冬の梅は十五首
そのうち咲いていないものを除いても、春七首、冬十二首
冬の方が多い
ならば、この歌が「冬雑歌」で詠われたものであっても、何も不都合ではないはずだ
そうすれば「春去らば」と「梅の花」で、本当に何もいじることなく訓める
「部立て」...少なからず、影響している
|
| |
|
掲載日:2014.01.10.
| 春雑歌 詠花 |
| 春去者 散巻惜 梅花 片時者不咲 含而毛欲得 |
| 春されば散らまく惜しき梅の花しましは咲かずふふみてもがも |
| はるされば ちらまくをしき うめのはな しましはさかず ふふみてもがも |
| 巻第十 1875 春雑歌 詠花 作者不詳 |
| 【1875】語義 |
意味・活用・接続 |
| はるされば[春去者 ] |
| ちらまくをしき[散巻惜] |
| まく[助動詞・む] |
[推量・ク語法]~てしまうだろうこと |
未然形につく |
| をしき[惜し] |
[形シク・連体形]失うにしのびない・惜しい・残念だ |
| うめのはな[梅花 ] |
| しましはさかず[片時者不咲] |
| しまし[暫し](上代語) |
[副詞](「しばし」の古形)少しの間・ちょっとの間 |
| さか[咲く] |
[自カ四・未然形]花の蕾が開く・波頭が立つ・荒波が立つ |
| ず[助動詞・ず] |
[打消し・連用形]~ない |
未然形につく |
| ふふみてもがも[含而毛欲得] |
| ふふみ[含(ふふ)む] |
[自マ四・連用形]花が蕾んでいて、まだ開ききらない |
| て[接続助詞] |
[補足・状態]~のさまで・~の状態で |
連用形につく |
| 〔前句の連用形「ず」と、「ふふむ」の連用形「ふふみ」につながる〕 |
| もがも[終助詞](上代語) |
[願望]~であったらなあ・~であってほしい |
助詞などにつく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [はるされば] |
原文「春去者」は、「はるされば」、「はるさらば」と両方に訓める
しかし、その意味は違う
「已然形」につく接続助詞「ば」は、
「順接の確定条件・恒常条件」で「~ので・~だから・~するときにはいつも」
「未然形」につく接続助詞「ば」は、「順接の仮定条件」で「~なら・~だったら」
そして、掲題歌〔1875〕は、殆どのテキストで「はるされば」と訓じている、ところが
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕では、「はるさらば」とする
|
| |
| [うめのはな] |
初句に関わるのではないかと思うが、『大矢本』『京都大学本』の諸本や、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕など一部の注釈書では、
この第三句の「うめのはな」を、「さくらばな」としていることだ
初句の「れば」あるいは「らば」と、「花の名」については、「歌意」を通して左頁で書く |
| |
|

 |
| 【歌意1876】 |
この春日野の一帯を、見渡していると
春の霞が立つ中に、美しく照り輝いているのは
きっと、桜に違いないだろうなあ |
作者が詠おうと思った動機は、まさに春霞の中に、美しく輝く「桜花」だと思う
私も、その映像を思い浮かべることが出来る
「霞の中ににほへる桜花」...これほど美しい「春の景観」はないだろう
「かすみ」に心を奪われて、でも
「さくら」に心を奪われて、でもない
その双方が創り出す「美しい光景」を眼前にしたとき、作者は「歌ごころ」を衝き動かされた
この場所での、「桜花」はすでに知っていたこと
それを詠じるのは、「かすみ」に映えるからこそ、なのだと思う
そうであれば、結句の「かも」は、疑問ではなく「感嘆」であるはずで
それでも、「かすみ」に覆われているため、直に見るのではなく
「きっと、桜花の輝きなのだろう」と確信して詠っている
そもそも、この歌のような「~は~かも」という表現は、どのような気持ちがあるのだろう
根拠があって推測する場合が多いと思う
純粋な「疑問」であれば、「~は」に当るものを、むしろ否定的な表現ですると思う
たとえば、この歌のように「さきにほへるは」ではなく、
こんな歌はないだろうが、「ちりかふはなは」と「あちこちに散り乱れるのは」とあれば
その詠じる心の内は、散り乱れる花を「否定」したい気持ちがあり
その次句で「さくらばなかも」となれば
「かも」を疑問や反語の表現として感じることができる
「ちりかふはなは さくらばなかも」
「あんなに散り乱れている花は、桜花だろうか」...
たとえ、現実を知っていても、「疑問」で詠うことで心情的な「否定」を表現する
歌は...そんな「心の技」をも持っている、と思う
作者は、霞に輝く桜花の姿を...しっかりと見詰めているはずだ
勿論、感動して...
|
| |

|
掲載日:2014.01.11.
| 春雑歌 詠花 |
| 見渡者 春日之野邊尓 霞立 開艶者 櫻花鴨 |
| 見わたせば春日の野辺に霞立ち咲きにほへるは桜花かも |
| みわたせば かすがののへに かすみたち さきにほへるは さくらばなかも |
| 巻第十 1876 春雑歌 詠花 作者不詳 |
| 【1876】語義 |
意味・活用・接続 |
| みわたせば[見渡者 ] |
| みわたせ[見渡す] |
[他サ四・已然形]遠く広く見やる・はるか遠くまで眺める |
| ば[接続助詞] |
[順接確定条件・単純接続]~すると・~したところ |
| 〔接続〕動詞の「已然形」+「ば」は、順接の確定条件、その中の「単純接続」 |
| かすがののへに[春日之野邊尓〕春日野一帯 |
| かすみたち[霞立 ] |
| さきにほへるは[開艶者] |
| にほへ[匂ふ] |
[自ハ四・已然形]美しく染まる・艶やかに美しい・照り輝く |
| る[助動詞・り] |
[完了・連体形]~いる・~てしまった |
已然形につく |
| は[係助詞] |
[とりたて・題目]~は |
連体形につく |
| さくらばなかも[櫻花鴨] |
| かも[終助詞] |
[詠嘆・感動]~であることよ |
体言につく |
| |
[疑問]~か・~だろうか |
体言につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [にほふ(匂ふ)] |
『古語辞典「語義パネル」より』
現代語では、「匂う」と書いて表の④の意で、または、「臭う」と書いて、鼻に不快に感じる意で用いることが多いが、原義は「丹(に=赤い色)秀(ほ=物の先端など、抜き出て目立つところ)ふ(=動詞化する接尾語)」で、赤い色が表面にあらわれ出て目立つ意。
| ①(草木などの色に) 染まる・美しく染まる |
| ②つややかに美しい・照り輝く |
| ③栄える・恩恵や影響が及ぶ |
| ④かおる・香気がただよう |
『古語辞典「発展」より』
「源氏物語」の宇治十帖で活躍する薫の君と匂宮。並び称される二人だから、「かをる」も「にほふ」も鼻で感じることをいう語だと思いがちだが、「にほふ」は「丹秀ふ」で、美しさが照り輝くの意である。 |
| |
| [かも] |
終助詞「かも」を、「感嘆」と解釈するか、「疑問」と解釈するか
この歌の諸注の解釈も分かれている
「詠嘆・感動」ととるものは、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕などで
『全注釈』によると、「カモは、疑問の意から出発して、感動の意をあらわしている。作者は、桜の花であることをよく知って、詠嘆している」としている
「疑問」ととるものは、
『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕、
『万葉集総釈』〔楽浪書院、昭和10~11年成〕、
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕、
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕、
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕など
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕においては、
「詠嘆・感動」をとる、『全註釈』を理解しつつも、
「咲きにほへるは」の係助詞「は」に註目し、
その対応として終助詞「か」に幾分の疑問があると、解している
従って、疑問を若干抱きながらの詠嘆の解釈になっている
『全注』の歌意、
「眺めわたして見ると、春日野一帯には、霞がかかって、色美しく咲いているのは、桜の花であろうかなあ」 |
| |
|
|

| 「うぐひすの」...こづたひちらすうめのはな... |
|
|
|
| 【歌意1877】 |
早く夜が明けないものかなあ
うぐひすが、木の枝を伝え飛びながら
その体に触れて散る梅の花を
早く見たいものだ |
この歌の視点には、二つの受止め方がある
一つは、梅の枝を飛び交いながら、花を散らす、その眺め
もう一つは、何故そう「散る」花を急がせるほど期待するのか...
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕の評では、
「うぐいすの散らすところを見るといふのでは、余りいやな見方だ。散らす花を、散らさぬ前に見ようとの心であろうか。それにしても嫌味の歌たるをまぬがれぬ」としている
この考え方には、かなりの無理があると思う
「散らさぬ前に見よう」とする気持ちは、この歌をどう解釈しても伺えない
「いつしかも このよのあけむ」は、それに反する句だろう
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕の評では、
「この作者は、梅の花の散るのを惜しまないのみならず、鶯の木伝ひ散らすさまの面白さを想像して、夜明けを待ってゐるのである。物の趣には限界がない。かう云はれると同感し得る心が誰にもある」と言っている
この『評釈』の方が、この歌の作者が感じたものを、理解しようと試みている
これを受けて、『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕の「考」では、
「評釈のいうように、梅の花をうぐいすが木伝い散らすさまは面白く、まさに絵になる美しさといってよい。健康な美ではないかも知れないが、このような美を愛でる万葉人もいたわけである。散る花の美を詠んだ歌は前にもあった〔1870、書庫-14〕。それも単に花が散るだけではなくて、春の雉の鳴く声が響く中での落花であった。これは鶯の枝移りによって、はらはらと散る美である。繊細ではかなくあわれのこもった美である」
「散る花の美」を詠うものとすれば、このような解釈の仕方は妥当かと思う
しかし、私が感じた、何故そんなに「散る花」を見たいのか、という視点をとれば...
こんな符牒らしきことも考えることができる
それは、この巻第十「春雑歌詠花」の最初の歌〔1858、書庫-4〕がそれだ
| 春雑歌詠花 |
| 鴬之 木傳梅乃 移者 櫻花之 時片設奴 |
| 鴬の木伝ふ梅のうつろへば桜の花の時かたまけぬ |
| うぐひすの こづたふうめの うつろへば さくらのはなの ときかたまけぬ |
| 巻第十 1858 春雑歌詠花 作者不詳 |
〔歌意〕(2013年3月16日時点そのまま)
うぐひすが、いつものように、枝から枝へととび伝う...
もう梅の花も散り、桜の花が近づいてきたと言う知らせなのか |
この〔1858〕では、「梅の花が散る」とは、文字としては表現されていない
しかし、うぐいすが木伝うことで、「桜花」の時が近づいた、と言うのは
紛れもなく、うぐいすのその行為で、梅の花が散り、それは桜花を迎えるさまを教えている
この「春雑歌詠花」の最初の歌に、この歌を挙げて
そして、この「春雑歌詠花」の最後の歌に、掲題歌〔1877〕を挙げるのは
考え過ぎであっても、そして偶然であっても、一種の演出の効果がある
「うぐひすの木伝う」ことが、梅の花を散らす
それは、もう一つの言い方をすれば、「桜の花」の準備が始まった
いよいよ、桜の季節だなあ
夜が明け、うぐいすの木伝え、枝移りが見られれば、それも確認できる
そんな気持ちなのではないだろうか
梅の盛りは、もう充分に堪能することができた
さあ、次は「桜」でも...早く見たいものだ
この〔1858〕歌の心情を、もっと具体的に詠った歌がある
| (梅花歌卅二首[并序] / 天平二年正月十三日 萃于帥老之宅 申宴會也 于時初春令月 氣淑風和梅披鏡前之粉 蘭薫珮後之香 加以 曙嶺移雲 松掛羅而傾盖
夕岫結霧鳥封□而迷林 庭舞新蝶 空歸故鴈 於是盖天坐地 促膝飛觴 忘言一室之裏 開衿煙霞之外 淡然自放 快然自足 若非翰苑何以□情 詩紀落梅之篇古今夫何異矣
宜賦園梅聊成短詠) |
| 烏梅能波奈 佐企弖知理奈波 佐久良婆那 都伎弖佐久倍久 奈利尓弖阿良受也[藥師張氏福子] |
| 梅の花咲きて散りなば桜花継ぎて咲くべくなりにてあらずや[藥師張氏福子] |
| うめのはな さきてちりなば さくらばな つぎてさくべく なりにてあらずや |
| 巻第五 833 梅花歌三十二首 張福子 |
〔語義〕
「なば」は、完了の助動詞「ぬ」の未然形「な」に、接続助詞「ば」
未然形+「ば」で、「順接の仮定条件〔~なら・~だったら〕」
「つぎて」は、他動詞四段「継ぐ」の連用形、接続助詞「て」で「跡を継いで・続いて」
「さくべく」は四段「咲く」の終止形につく推量の助動詞「べし」の連用形「べく」で、
「咲くことになっている・咲くはずだ・咲くにちがいない」
「なりにて」は、自動詞四段「成る」の連用形「なり」に、
完了の助動詞「ぬ」の連用形「に」と接続助詞「て」で、「咲いてしまって」
「あらずや」は、「ない」の意の「あらず」に反語の「や」
|
〔歌意〕
梅の花が咲いて散ってしまったならば
桜の花が続いて咲くようになってないだろうか... |
この歌は、有名な大宰府での「梅花歌三十二首」の一首だが、
梅の花を愛でる宴席の中で、
梅が咲いて散ったあとの「桜」のことに言及しているのは異質なことだ
しかし、感じ方によっては、もう桜の花がそこまで開花を迫っている
梅の時期も、せめて桜の開花の準備が整うまで、散らずにいてくれよ、とも...
いずれにしても、掲題歌をも含め、
梅が散れば...確かに「散る花も美しい」が、
次は「さくら」という期待感がある歌だと思う
|
| |
|
掲載日:2014.01.12.
| 春雑歌 詠花 |
| 何時鴨 此夜乃将明 鴬之 木傳落 梅花将見 |
| いつしかもこの夜の明けむ鴬の木伝ひ散らす梅の花見む |
| いつしかも このよのあけむ うぐひすの こづたひちらす うめのはなみむ |
| 巻第十 1877 春雑歌 詠花 作者不詳 |
【左頁補注】〔1858・833〕
| 【1877】語義 |
意味・活用・接続 |
| いつしかも[何時鴨 ] |
| いつ[何時] |
[代名詞]はっきりと定まらない日、時を表す |
| し[副助詞] |
語調を整え、強意を表す |
| 〔接続〕体言、活用語の連体形・連用形、副詞・助詞などにつく |
| か[係助詞] |
[疑問]~か・~だろうか |
| 〔接続〕体言・活用語・副詞・接続助詞などが主語・目的語・連用修飾語のときつく |
| も[終助詞] |
[詠嘆・感動]~よ・~なあ〔接続〕文末、文節末になる |
| このよのあけむ[此夜乃将明〕 |
| む[助動詞・む] |
[推量・終止形]~(の)だろう |
未然形につく |
| 〔いつしか~む〕で、「いつになったら~だろう」 |
| うぐひすの[鴬之 ] |
| こづたひちらす[木傳落] |
| こづたひ[木伝ふ] |
[自ハ四・連用形]木から木へ、枝から枝へと飛び移る |
| ちらす[散らす] |
[他サ四・連体形]~ちらかす・落とす・発散させる |
| うめのはなみむ[梅花将見] |
| む[助動詞・む] |
[意志・終止形]~よう・~つもりだ |
未然形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [いつしかも] |
「いつしか」で始まる疑問文は、単に疑問の意だけではなく
その時になるのを早く、と待ち望む気持ちがこめられている場合が多い
従って、「早くして欲しい」と訳す注釈書も多い |
| |
|


 |
| 【歌意1878】 |
春霞がたなびいているいま
その中でも、淡く光輝いている夕月は
きっと清らかに澄み渡って照らしていることだろう...
あの高松の野であれば... |
我家から見えるのは、春霞に隠れながらも
ほのかに、その輝きを見せる「夕月」
この春霞も、きっと広く小高い「高松の野」であれば、
それほど「たなびく」こともなく
この「夕月」の輝きが、野原一杯に澄んだ美しさをみせていることだろう...
霞に隠れる「夕月」
霞ににじむ「夕月」
それらも、私はいいと思うのだが...
このような「月」を、「おぼろづき」と、確か言ったと思う
寒い冬から、暖かな「春」を迎えて
「朧月」の浮ぶ夜空は、「空の季節」を、改めて認識させるものだ
今日の歌「詠月」は、春の月を詠ったものだが
この部立て「春雑歌詠月」には、引き続き二首が詠われ
それぞれ「春」「春日」の語が使われ、まさに「春の月」
その他、この巻第十には、「秋雑歌詠月七首」、「秋相聞寄月三首」、「冬雑歌詠月一首」
そして巻第六に「月の歌」「初月の歌」として十首
「部立て」以外に詠まれた「月」も多いだろうが
「花」ほどにはなく、やはり「月」も意外と少なく感じる
万葉人にとって、目の前の「花」や「鳥」は、詠いやすくても
夜空に様々な形となって浮ぶ月を、
ある意味で「畏怖」の気持ちを持ち得ているのでは、と思う
|
| |

|
掲載日:2014.01.13.
| 春雑歌 詠月 |
| 春霞 田菜引今日之 暮三伏一向夜 不穢照良武 高松之野尓 |
| 春霞たなびく今日の夕月夜清く照るらむ高松の野に |
| はるかすみ たなびくけふの ゆふづくよ きよくてるらむ たかまつののに |
| 巻第十 1878 春雑歌 詠月 作者不詳 |
| 【1878】語義 |
意味・活用・接続 |
| はるかすみ[春霞 ] |
| たなびくけふの[田菜引今日之〕 |
| たなびく[棚引く] |
[自カ四・連体形]雲や霞などが、横に長く引く |
| ゆふづくよ[暮三伏一向夜 ] |
| づくよ[月夜] |
[「つく」は「つき」の古形]月・月の光・月夜・月の明るい夜 |
| きよくてるらむ[不穢照良武] |
| きよく[清し] |
[形ク・連用形]清らかである・澄んでいる |
| らむ[助動詞・らむ] |
[現在推量・終止形]今頃~ているだろう |
終止形につく |
| たかまつののに[高松之野尓] |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [ゆふづくよ] |
原文「暮三伏一向夜」を「ゆふづくよ」と訓むのは、
「づく」の「三伏一向」が、「戯書」の用法
朝鮮半島渡来の遊びで、「柶戯(チョボ)」というのがあり
四枚の小木片の采を擲げて、その上向きと下向きの数による「呼び名」
「三伏一向」は、「下向き三、上向き一」のことで
それを、「つく」といった
この「柶戯」から用いられた表記には、
他に「折木四(かり)」「諸伏(まにまに)」も、そうだという |
| |
| [きよく] |
原文「不穢」...
こうした語法が、好んで使われる人たちの階層とは、どんなところだろう
確かに、「不穢」は、「穢れのない」「穢さない・穢れない」の意であり
それはまた「清し」という意味になる
それで、この表記で「きよし」と訓ませているのは...
この頃の「流行」なのだろうか...この歌全体の表記の印象が、手の込んだものだ
こっちも意地悪く、その表記通りに訓じてみたくなる
「不」は、動詞を否定する漢字だから、「穢さない・穢れない」という意味になるだろう
すると、「けがさずてるらむ」、「けがれずてるらむ」...
う~ん、語調がまずいかな、やはり |
| |
| [たかまつののに] |
原文「高松之野尓」、この「高松」という地名が、一部の注釈書では問題になっている
ほとんどの注釈書では、「高松」は現在の奈良市東部の「高円」として解釈し
歌意でも、「高円」としているものが多い
しかし「高円」としながらも、「未詳」として「注記」しているものも多い
また「高松」を「たかまつ」ではなく、その表記のままで「たかまと」と訓じているのが、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕で、それには
「高松はタカマトとよむべし、松は言を転して借り用る例なり、高円(たかまと)なり」
とあり、『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕も同じくしている
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕は、少し違いがあり、
「たかまと」は同じように訓み、その後の「のに」を「ぬに」とする
これには「の」が「ぬ」と訓じられていたことも言われているので、
それに基づいた訓だとは思う
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕の見解では、
「当時タカマトをタカマツとも(ミモロ、マキモクをミモロ、マキムクともいひし如く)いひし故に高松と書けるにこそ」といい
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕など、幾つかの「補注」には
「マトのトは甲類toなので、ツtuと通用するともいう」としている
〔参考〕
はるかすみたなひく山のゆふつくよきよくてるらむたかまとの野に 古今六帖
はるかすみたなひくけふのゆふつくよきよくてるらむたかまつのやま 赤人集 |
| |
|
|
| 【歌意1879】 |
春になったので
茂った木々の枝葉で陰をつくる下闇に
おぼろげに夕月の光がさし...
ここ山陰にあって...
〔春になったので、木々の茂みの多さに、夕月夜〕 |
日も沈み、夕暮れから夜にかけて輝く月
しかし、春のせいか木々の生い茂るさまが圧倒的で
月もなかなか観賞できない
その木々の下を見遣れば、薄暗いところに、月のほのかな明かりが射している
まったく音のない世界が浮ぶ
静寂そのものだ
そうか...万葉の時代、夜はそんなものなのだろう
だから、山も川も生きて感じることができる
煌々と夜空に浮ぶ「月」
寂々と陰を落とす木々の下闇
そんな場面に自らを置けば、誰もが詩人になれる
月を見上げて詠う歌ではない
生い茂った木々の枝葉に邪魔されて、見えない月を
その微かな明かりを頼りに、木々の下闇をほのかに照らす情景...
「おほつかなし」と言うが、詠者はそれを楽しんでいる
もどかしいほど、何かを期待して見入ることが、楽しい
思うようにならない現実を、「おほつかなき」こととして受止めても
微笑ながら、「何とかしてくれ」と、月に言いすがる
静かに笑い...静かな夜には、静かな月と、静かな陰があれば...静かに微笑む
こうして飲む酒は、きっと美味しいのだろう
そして、何よりも大切なことは...一人の世界だ、ということだ
|
| |


 |
掲載日:2014.01.14.
| 春雑歌 詠月 |
| 春去者 紀之許能暮之 夕月夜 欝束無裳 山陰尓指天 [一云 春去者 木陰多 暮月夜] |
春されば樹の木の暗の夕月夜おほつかなしも山蔭にして
[一云 春されば木の暗多み夕月夜] |
はるされば きのこのくれの ゆふづくよ おほつかなしも やまかげにして
[はるされば このくれおほみ ゆふづくよ] |
| 巻第十 1879 春雑歌 詠月 作者不詳 |
【注記】〔1455・1956〕
| 【1879】語義 |
意味・活用・接続 |
| はるされば[春去者 ] 春になったので 〔已然形+接続助詞「ば」は順接確定条件〕 |
| きのこのくれの[紀之許能暮之〕 |
| このくれ[木の暗れ] |
木が茂って暗いこと、またその暗いところ |
| ゆふづくよ[夕月夜 ] |
| づくよ[月夜] |
[「つく」は「つき」の古形]月・月の光・月夜・月の明るい夜 |
| おほつかなしも[欝束無裳] |
| おほつかなし |
[形ク・終止形]はっきりしない・もどかしい |
| も[終助詞] |
[感動・詠嘆]~よ・~なあ |
文末、文節末の種々の語につく |
| やまかげにして[山陰尓指天] |
| にして |
[場所を表す場合]~にあって・~において・~で |
| 〔成立〕格助詞「に」+副助詞「して」、〔接続〕体言や連体形につく |
| 〔一云〕このくれおほみ[木陰多] 生い茂る木々の陰が多いこと |
| 〔み〕接尾語「み」の一用法で、形容詞の語幹について名詞化する、その状態である場所を表す |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [おほ(ぼ)つかなし] |
この「おほつかなし」という言葉が、『万葉集』中で僅か三例とは驚いた
そもそも、形容詞ク活用「おほつかなし」には、どんな意味があるのだろう
| 形容動詞「おぼろ」の「おぼ」に、「あはつか」「ふつつか」などの状態を表す「つか」、「いかにも~だ」の意を添える接尾語「なし」で、できていると見られる形容詞。対象がぼんやりしていてつかみどころがない感じ。 |
| ①はっきりしない・ぼうっとしている |
| ②気掛かりだ・心配だ・不安だ |
| ③よくわからない・疑わしい・不審だ |
| ④待ち遠しい・もどかしい |
この語義からしても、もっと使われていいような「語句」だと思うのだが...
その貴重な三首の歌の残りの二首を載せる
| 春相聞/笠女郎贈大伴家持歌一首 |
| 水鳥之 鴨乃羽色乃 春山乃 於保束無毛 所念可聞 |
| 水鳥の鴨の羽色の春山のおほつかなくも思ほゆるかも |
| みづどりの かものはいろの はるやまの おほつかなくも おもほゆるかも |
| 既出〔書庫-6・書庫-8〕巻第八 1455 春相聞 笠女郎 |
〔歌意〕書庫-6 (2013年5月6日時点のまま)
水鳥の羽色のような春山の
そこに立つ霞のように、私たちのことが
覚束なく思えてしまいます |
〔歌意〕書庫-8 (2013年7月7日時点のまま)
水鳥の羽の色のような、春山の色合い
そのように、はっきりとしない様は、
もどかしくて、不安で...
あなたのそんな気持ちに
私は、こころ穏やかに過ごせないのですよ |
| |
| 夏雑歌詠鳥 |
| 今夜乃 於保束無荷 霍公鳥 喧奈流聲之 音乃遥左 |
| 今夜のおほつかなきに霍公鳥鳴くなる声の音の遥けさ |
| こよひの おほつかなきに ほととぎす なくなるこゑの おとのはるけさ |
| 巻第十 1956 夏雑歌詠鳥 作者不詳 |
〔語義〕
「鳴くなる声」は、四段動詞「鳴く」の終止形に、
伝聞推定の助動詞「なり」の連体形「なる」で、
「鳴くのが聞こえる・鳴いているようだ」
「はるけさ」は、形容詞「はるけし」の語幹に、接尾語「さ」がつき
程度・状態の意を表す名詞をつくる
「はるけし」の意味は、空間的には、非常に遠い・ひどく離れていることであり
心理的には、心が遠く離れていることをいう
また、「~の~さ」の形で文末に用いて、感動の意を表す、「~ことよ」
|
〔歌意〕
今夜のように、あたり全体がぼうっとして薄暗いと
うぐいすの鳴く声が、ひどく遠くに聞こえるものだなあ |
あらためて、この「おほつかなし」を読んでみると、
どうしてもっと使われないのか、と不思議でならない
心のもどかしさを、実際の現象に重ねて表現できる語なのに...
|
| |
| [このくれおほみ] |
この句は、第二句の異伝として添えられているが、
この異伝に、実に多くの異訓があり、ある意味では、
本歌の原文「紀之許能暮之(きのこのくれの)」の訓や解釈に影響していると思う
その極端な例が、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕の雅澄の解釈だ
彼は、この『古義』で、こう述べている
「第二三の句、舊本には紀之許能暮之夕月夜、とあり、木之木暗之(きのこのくれの)と云なるべし、今は一云、春去者(はるされば)木陰多(こがくれおおき)暮月夜(ゆふづくよ)、とあるを用ふ、陰は隱の誤なり」とし、本歌そのものを、異伝の自説で訓んでいる
これは、あまりにも大胆過ぎる手法だと思う
『万葉集』には、このような「異伝」も多く、こうした例を作ると
すべての「異伝」について考察しなければならなくなり、
それは普遍的な歌集と言えなくなる
「異伝」はいくらすぐれていようと、「異伝」として解釈しなければならない、と思う
雅澄ファンとしては、残念でならない
本歌の原文には、異訓もないのだが、「異伝」の異訓には、少々思うところもある
[一云 春去者 木陰多 暮月夜]
この「木陰多」は、ほとんどの底本や古写本で使われており、
『古義』のいう「陰」は「隠」の誤写とするのは少ない
しかし、『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕に、「隠」とあるのを見つけた
その根拠として、『元暦校本』『広瀬本』及び、『仙覚抄』本文に「木隠多」とあり、
これに倣ったとしている
どうして、倣うほどのものか、と言えば
『後撰集』に「春くれば木がくれおほきゆふづくよおぼつかなしも花陰にして」(春中62)
が採用されており、「一云」の形に近い、ということのようだ
語句の検証ではなく、先例もしくは近い形で、判断するというのは、
少し違うような気がするのだが...
そして、訓にはたしかに様々あるが
名詞「木隠(こがく)れ」も動詞「木隠る」も、その意味は「木の陰に隠れる」こと
結局は、解釈上の違いはないはずだ
ただし、「歌」であるからには
その語調も大切なのだから、やはり拘るのだろう
最後に、これほど多くの異訓も珍しいので、挙げておく
| 〔木陰多〕 |
| このくれおほみ |
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕
『萬葉集本文篇』〔塙書房・佐竹昭広、昭和38年成〕
『萬葉集』〔桜楓社、昭和55年補訂版〕
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕
|
| きのかげおほみ |
『新校万葉集』〔沢潟久孝・佐伯梅友、昭和10~11年成〕 |
| このかげおほき |
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| このくれおほみ |
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| こかげのおほき |
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
こがくりおほみ
(木隠多) |
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕 |
| こかげをおほみ |
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕
『万葉集』〔伊藤博校注、角川文庫、平成10年十八版〕
|
|
| |
|
|
| 【歌意1881】 |
春の雨...濡れてもたいしたこともないだろうに
それに、小雨で止むことなく降り続く
少し休んだところで...なのに、雨を避けて物蔭に雨宿りか...
おかげで、妻の家に行く途中だというのに、
この日、一日を雨宿りで過ごしてしまった |
「春の雨」のたわいのなさを、何故こうも畏れるのか、と自分を責める
濡れたって、たかが知れている「春雨」ではないか
情けないおれだ...
違う、そんな風には思っていないだろう
「春の雨」が、どんな雨なのか承知して、「雨宿り」をしている
ということは、何故か解らないが、「春の雨」を時も忘れるほど見ていたかった
衝動的だったのかもしれない
よく考えれば、何のための「雨宿り」なのか、と
おれは、濡れることが嫌だったのではない、「春の雨」を見たかったのだ
それを、自分に確認させようとしている
雨に靄る山間にでも惹かれたのかもしれない
私も、明日香のような雰囲気を持つところでは
一番好きな景観が、この雨にけぶる姿だ
あちこちの山間から立ち上がる「もや」に、心を奪われたことも何度かある
そんなとき、濡れてしまう濡れたくない、と思うより
じっと佇んで眺めていたい、と思う気持ちの方が勝ってくる
当然そうなれば「雨宿り」でもしなければ、気持ちよく眺められるものではないだろう
妻の待つ家への道中、その途中であっても...心奪われるものには、我を忘れてしまう
|
| |

|
掲載日:2014.01.15.
| 春雑歌 詠雨 |
| 春之雨尓 有来物乎 立隠 妹之家道尓 此日晩都 |
| 春の雨にありけるものを立ち隠り妹が家道にこの日暮らしつ |
| はるのあめに ありけるものを たちかくり いもがいへぢに このひくらしつ |
| 巻第十 1881 春雑歌 詠雨 作者不詳 |
| 【1881】語義 |
意味・活用・接続 |
| はるのあめに[春之雨尓 ] |
| に[格助詞] |
[手段・方法]~で |
体言につく |
| ありけるものを[有来物乎] |
| ありける[連体詞] |
前に述べた・例の・さっきの、など前の状況をいう |
| 〔成立〕ラ変動詞「有り」の連用形「あり」に過去の助動詞「けり」の連体形「ける」 |
| ものを[接続助詞] |
[逆接の確定条件]~のに・~のだが |
連体形につく |
| たちかくり[立隠 ] |
| たちかくり[立ち隠る] |
[自ラ四・連用形]隠れる (「たち」は接頭語) |
| いもがいへぢに[妹之家道尓] |
| いへぢ[家路] |
家の方へ向う道・我家へ帰る道・帰路 |
| このひくらしつ[此日晩都] |
| くらし[暮らす] |
[他サ四・連用形]日を暮れさすことから、日の暮れるまで過す |
| つ[助動詞・つ] |
[完了・終止形]~てしまった・~しまう |
連用形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [はるのあめに] |
これまで、少しずつ古書店で買い集めていた諸本や注釈書
勿論、本文だけの訓に興味があるのだが
運よく見つけて手に入れた注釈書でも、最近は一通り開いてみる
すると、何の異訓もないような解りやすい「語句」でも
ときとして、えっ、と思うこともある
それが、この初句の「はるのあめに」にも言える
原文「春之雨尓」は、確かにその字数は「六文字」となる「はるのあめに」では不自然だ
しかし、やはり「はるのあめに」としか読めない
また誰かが「誤写」説でも唱えているのかな、と確認してみたが
不思議と、この初句についての異訓は何も語られていない
しかし、私の手持ちの本文の中で、唯一
『萬葉集』〔桜楓社、昭和55年補訂版〕が、「はるさめに」としていた
たしかに、そう詠いたくなるものだ
すると、原文表記は...誤写説がない以上、やはり「はるのあめに」だろう
|
| |
| [たちかくり] |
この「たち」は、動詞について意味を強める「接頭語」だが、
動詞「立つ」の意味が残る時には、「接頭語」にしない、と古語辞典にある
この「たちかくり」は、動詞「隠る」の連用形「隠り」で
私の素人考えだが、「たちかくりて」と同じ用法だろう
つまり、原因・理由の確定条件である接続助詞「て」が、
語調を整えるために省略されていると思う
しかし、それは文脈から理解できることなので、無理なく出来る省略だ...と、思う
具体的に言えば、前句の「ものを」が逆接の接続助詞で、その呼応する形だと思う
「春の雨であったのに、雨を避けて物蔭に隠れてしまったので」と、後に続く
ただ、この句もまた、一つの異訓があった
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕には、
「たちかくれ」と連体形になっている
その解釈は、「隠れていて」と平凡な解釈になっている
これでは、「隠り」の方が文法的にはいいのではないか、と思えてしまう
それでも、敢えて連体形にするのなら、連体形の「終止法」で解釈すべきだ
連体形で終る「係り結び」ではないのは、「係り」がないので明白だが、
連体形の終止法には、他に「詠嘆・余情」の表現としての「連体形止め」がある
そして、もう一つ「準体言法」というのがあり、
もともと連体形は「体言に準ずる語」だから、
一種の体言止めのような語感を持つことになる
『大系』には、そんな訳をつけて欲しかった...「隠れていたのは」
|
| |
|
|
| 【歌意1882】 |
今、すぐにでも行って、聞くことができればなあ
明日香川の、春雨によって水嵩が増し
激しく流れているその瀬音を...聞きたいものだ |
作者が、明日香川の水嵩が増して、急流になった瀬音を聞きたいと思うのは
ただ漠然とした、「瀬音」への関心だけではないだろう
雪解けの春の増水、春雨のもたらす増水
それらは、作者が幼い頃からずっと続いている現象だ
「瀬音」だけなら、春に限らずとも、季節折々癒してくれるし
「たぎつ瀬」というのが、作者自身の「春」を思い起こしているのかもしれない
毎日が、何の変化もなく過ぎて行く
それが人生だ、などと言ってはみても
明日香川の「たぎつ瀬」の「瀬音」を聴きながら見入っていると
何か力が沸いてくるような...
それは、遠い若い頃の自身のエネルギーかもしれない
そんなことを重ねた想いのような気がする
川の瀬音に惹かれる歌は結構ある
今の私に、真っ先に浮んでくるのは
明日香万葉文化館の地階にある「さやけしルーム」の入り口に書かれている歌だ
| 相聞/(大宰帥大伴卿被任大納言臨入京之時府官人等餞卿筑前國蘆城驛家歌四首) |
| 月夜吉 河音清之 率此間 行毛不去毛 遊而将歸 |
| 月夜よし川音清けしいざここに行くも行かぬも遊びて行かむ |
| つくよよし かはとさやけし いざここに ゆくもゆかぬも あそびてゆかむ |
| 右一首防人佑大伴四綱 |
| 既出〔書庫-10、2013年9月22日〕巻第四 574 相聞 大伴宿禰四綱 |
〔歌意〕(2013年9月22日時点の、そのまま)
月が美しい、川の瀬音も、なんと澄み切ってすがすがしいことか
さあ、こんな夜こそ、都に行くものも、残るものも
ここで、遊んで行こうではないか |
この歌が、文化館の「さやけしルーム」の入り口にあり、それを初めて読んだとき
まさに「さやけし」の語義そのままの気分になった
「澄み切っている」「清くすがすがしい」...
この歌は、今日の掲題歌と違って、
「かはとさやけし」とし、「たぎつせのおとを」と対をなしている
いろんな「瀬音」の惹かれ方がある
ついでに言えば、ここでは「音」は「と」と一般に訓じられている
「河音」かはと...
「湍音」せのおと...やはり「せおと」の方が、いいかもしれない
このような、どこがどう違えば、こう訓む、とかいうルールはあるのだろうか
まだ記憶できる程度の歌数ならともかく
『万葉集』の4500首に及ぶ膨大な歌集で、記憶には頼られない情況であれば
どうしても、客観的に用いられるルールがあるはずなのに...
それがないのも、また『万葉集』の魅力なのかもしれない
ただ、懸念があるのは、
ある時代の実力者...大歌人であったり、研究の権威者の説に無条件で倣うのは、
あまり気分のいいものではない
「無条件」でいいのは、私のような素人のすることで
しかしながら、それを後世へも普遍的な成果と目論むものならば...やはり「拘り」は必要だ
|
| |
|
掲載日:2014.01.16.
| 春雑歌 詠河 |
| 今徃而 聞物尓毛我 明日香川 春雨零而 瀧津湍音乎 |
| 今行きて聞くものにもが明日香川春雨降りてたぎつ瀬の音を |
| いまゆきて きくものにもが あすかがは はるさめふりて たぎつせのおとを |
| 巻第十 1882 春雑歌 詠河 作者不詳 |
【左頁】〔574〕
| 【1882】語義 |
意味・活用・接続 |
| いまゆきて[今徃而 ] |
| て[接続助詞] |
[単純接続]~て・そして |
連用形につく |
| きくものにもが[聞物尓毛我] |
| もの[物] |
物事・対象を明示せず漠然と言う |
| もが[終助詞](上代語) |
[願望の意を表す]~があればなあ・~であればなあ |
| 〔接続〕体言及び体言に準ずる語、形容詞と助動詞の連用形、副詞、助詞「に」などにつく |
| あすかがは[明日香川 ] |
| はるさめふりて[春雨零而] |
| て[接続助詞] |
[並立]~て |
連用形につく |
| たぎつせのおとを[瀧津湍音乎] |
| たぎつせ[激つ瀬] |
水が激しく流れる瀬・急流 |
| 〔あるいは、四段動詞「激つ」の連体形「激つ」に、名詞「瀬」〕 |
| を[格助詞] |
[対象]~を 〔接続〕体言、活用語の連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [もが] |
係助詞「も」+終助詞「が」(もが)、係助詞「も」+係助詞「か」(もか)の変化したもの
とする説がある
上代では、多く「も」を伴って「もがも」の形で用いられた
平安時代以降は「もがな」の形か、「も」の落ちた「がな」の形で使用された |
| |
| [たぎつせのおとを] |
この句の異訓もまた、字数から発生したのではないかな、と思う
異訓としている諸注は、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕(『新大系』は異訓なし)、
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕で、
その訓は「たぎつせのとを」とし、「音」を「と」としている
和歌という限られた文字数の韻を踏みながら、ときには工夫された詠み方もあると思う
「音」という表記で、川の瀬音を描き
しかし、和歌のルールとして、「音」を「おと」ではなく「と」と読ませる
この歌を声にして読むとき、「たぎつせのとを」の方が、いいのかもしれない
「たぎつせおとを」では、駄目なのかなあ
|
| |
|

|
| 【歌意1883】 |
春日野に、煙が立つのが見える
きっと、娘たちが春の野の嫁菜を摘んで
煮ているのだろう... |
野で若菜を摘み、その場で煮て、若者たちが食す習俗があったことが伺える
何も、この歌からだけではなく、他にも同じような記述がある
『万葉集』でいえば、巻第十六の〔3813~3824〕の「歌物語」の十二首
この物語については、既出〔書庫-5、十二首、2013年4月26日〕なので
そこに「歌物語」について書いているが
今は、そこの題詞にある、若者たちが煮物を共食する場景を知ることにある
| 昔、通称を竹取という翁がいて、春に丘に登ったときのこと、そこにはたまたま羹を煮ている九人の乙女がいた。それぞれのその美しさは、並べるものがないほどで、花のように美
しい乙女たちだった。その中の一人が、翁に気づき、からかうように呼び寄せ、火を吹いてくれと言うので、翁は言われるままに、その席に着いた。乙女たち
は、屈託なく楽しく興じているが、しばらくしてある娘が「誰なの、このおじさんを呼んだのは」とつっけんどんに言うので、翁は恐縮して、厚かましく同席さ
せてもらったこ罪滅ぼしに、歌でも詠って償わせてください、と申し出て、長歌一首と、反歌二首を詠じた。 |
こうした若者たちの、野原や丘で摘んだばかりの菜を煮る習俗というのは
ここにも珍しいとして書かれているのではないので、ごく普通のことだったようだ
ただし、若者に限る、というわけだ
どこからだろう...作者は自分の家から臨んでいるのか
それとも、出先で偶然立ち昇る煙を見たのか...
その煙が、いかにも春らしく、というのではないだろう
きっと、あそこでは若者たちが、摘んだばかりの嫁菜を煮て
楽しく語らっていることだろう...そんな郷愁を感じたと思う
確かに、「詠煙」という部立てのように
すべてが「煙」から起こっている
「煙」には、寓意的な意味もあるが、ここはあくまで「けぶり(けむり)」だ
しかし、その「煙」が運んできたものと言えば、かつては自分もそうだった、と
若い頃の楽しかった仲間たちとの語らいではなかったか
だから、この「詠煙」という『万葉集』中でも、この部立てはこの一首しかない
「詠煙」と「部立て」をしない、「煙」を詠ったものは確かにある
しかし、「詠煙」は、この一首だけ...
ということは、この「煙」が、語義としては一般的な煙にしろ
その及ぼす効果は、作者の「郷愁」にまで辿ってゆくことになる
だから、この一首が故に、「詠煙一首」というのは、人の生きてきた「幅」をも
しっかり感じられるものだ
勿論偶然だが、ここで挙げた「歌物語」の竹取翁の映像と、この歌が...繋がって見える
野原や丘などの語句の違いは、当然まったく関係ない歌として詠まれたものだから
何も辻褄を合わせる必要はない
創作もまた「歌」なのだから...
しかし、ここでの歌は...繋がっていると解釈しても、決して悪くはない、と思う
遠くで「煙」の立ち昇るさまを見て、竹取翁がつい足を向けてしまったのも
若者に交じっての自慢話を始めたことを思えば、よりいっそう計画的だったとも取れる
「煙」が若き自分を思い出させた、という歌として感じてしまった
|
|
 |
掲載日:2014.01.17.
| 春雑歌 詠煙 |
| 春日野尓 煙立所見 □嬬等四 春野之菟芽子 採而煮良思文(□=女偏に「感」) |
| 春日野に煙立つ見ゆ娘子らし春野のうはぎ摘みて煮らしも |
| かすがのに けぶりたつみゆ をとめらし はるののうはぎ つみてにらしも |
| 巻第十 1883 春雑歌 詠煙 作者不詳 |
| 【1883】語義 |
意味・活用・接続 |
| かすがのに[春日野尓 ] |
| かすがの[春日野] |
奈良市春日山麓一帯の地 |
| けぶりたつみゆ[煙立所見] |
| けぶり[煙・烟] |
けむり |
| みゆ[見ゆ] |
[自ヤ下二・終止形]見える・目に映る |
| をとめらし[□嬬等四 ]〔□は、女偏に「感」〕 |
| をとめら |
娘たち |
| し[副助詞] |
語調を整え、強意を表す |
| 〔接続〕体言または活用語の連体形・連用形、副詞、助詞などにつく |
| はるののうはぎ[春野之菟芽子] |
| うはぎ |
[嫁菜(よめな)のことで、古名をオハギ]が有力説 |
| つみてにらしも[採而煮良思文] |
| つみ[摘む] |
[他マ四・連用形](植物などを)つみとる |
| て[接続助詞] |
[単純接続]~て・そして |
連用形につく |
| に[煮る] |
[他ナ上一・連用形]水などを沸かして、中に入れた物を熱する
とくに、食物を鍋の中に水とともに入れ、加熱・調味して食べられるようにする |
| らし[助動詞・らし] |
[推量・終止形]確実な根拠に基づいて現在の事態を推定する
「~にちがいない・きっと~だろう」 |
| 〔接続〕活用語の終止形につき、ラ変には連体形につくが、ここでは連用形についている |
| も[終助詞] |
[感嘆]~よ・~なあ〔接続〕文末、文節末の種々の語につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [かすがの] |
若草山・御笠山の西麓に続く台地で、北は佐保川、南は能登川に至る範囲
平城京の東方郊外に位置し、大宮人の遊楽の地だったとされている |
| |
| [けぶり] |
名詞「煙(けぶり)」には、通常の「けむり」の他に、
「火葬の煙・火葬・死ぬことのたとえ」、「飯を炊くかまどの煙・転じて暮らし」、
「霞や新芽などが、煙のように棚引いたり、立ち上ったり、霞んで見えたりするもの」、
「地獄の業火の煙」と、煙り本体だけではなく、そこから派生する意味合いをもいう
古語辞典の〔「煙」と死〕の解説がある
「煙」が人の死を象徴するものとされるようになったのは、仏教とともに火葬の風習が一般化してからのことである。わが国の火葬の第一号は、歴史の記録によると、文武天皇四年(700)に亡くなった道昭という高僧だということになっているが、それ以前から、渡来人など仏教に帰依していた人々の間には広まっていたと考えられる。文芸作品においてはしばしば、人の死をはっきりとは言わないで、「煙」によって暗示することがある。
なお、この歌では、勿論一般的な「煙」のことだが
私は「名詞」の「煙」だと何の迷いもなく思ったが
辞書を引いてみると、自動詞ラ行四段動詞「煙(けぶ)る」もある
文法的には、動詞「立つ」に続くので、連用形「けぶり」でも不思議ではない
ただし、動詞「煙る」は、そもそも、「煙が立ち上がる」という意味なので
「けぶりたつ」と動詞を重ねることはない
|
| |
| [みゆ] |
現代語の「見える」にあたる動詞
ただし、「見る」と「見ゆ」の違いは、これも古語辞典から引いてみる
以前にも載せたことがあるが、再掲
〔「見る」と「見ゆ」〕
「見る」は他動詞、「見ゆ」は自動詞。「見ゆ」は「見る」の未然形に助動詞「ゆ」がついてできた語である。「ゆ」という助動詞は、上代に用いられ、受身・可能・自発の意を持っていた。だから、「見ゆ」は一語であるが、「見る」に、受身・可能・自発の意を添えた意味を持つと考えればよいことになる。 |
| |
| [うはぎ] |
『万葉集攷証』〔岸田由豆流、文政十一年(1828)成〕に、
「ウハギは今日ヨメナとも野菊ともいふものなるべし。ウとオと音かよへば、ウハギといふもオハギといふも同じ」とある
この「オハギ」というのも、大辞林などで引いてみると、「嫁菜の古名」と出ていた
この「古名オハギ」を知らないと、『攷証』の言うことが理解できなかっただろう
『和名抄』には、「野菜類食経云。薺蒿菜一名莪蒿。和名於波岐」とある
「ヨメナ」の名称は、若芽を食用とする類の中でもっとも美味で、
しかもやさしく美しいことによるという |
| |
| [らし] |
推量の助動詞「らし」の接続は、一般的に活用語の終止形につき、
ラ変動詞の場合には、連体形につくとされている
しかし、この歌での接続は、「煮る」の連用形となっており
この文法解釈にも、幾つかの見解がある
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕では、
「らし」の接続が「終止形・ラ変には連体形」というルールの他に
上一段動詞の場合には「連用形」につく、と解釈している
しかし、一般的に目に付くのは、上一段動詞「煮る」が、
かつては「煮(に)」が「終止形」であった名残ではなかったか、とするもの
その解りやすい説明が、『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕で言われている
「上一段活用の動詞の終止形は奈良朝より前の古い時期には、煮ル・見ル・着ルなどのルがなく、今日いう語幹のニ・ミ・キだけで終っていたらしい。推量のラシは終止形につくのでその語幹に直ちに接続した。そこでニラシという形が成立した」と書いている
この『旧体系』を受けて、『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕では、
「もと終止形であった可能性がある」としている |
| |
|
|
| 【歌意1884】 |
春日野の浅茅が生えている上で、
我ら親しい友たちと遊ぶ今日の楽しい日を、
忘れることがあるだろうか... |
この春雑歌の部立て「野遊」は、漢語との説明がある
そうなると、どうしても雰囲気的に、官人たちの興じた「宴席」を思うものだ
よほど楽しい一日だったことは、結句の「わすらえめやも」で伺える
若い頃の友人関係には、お互いの利害関係も少なく
無心になってお互いを信頼し、心を裸にして付き合えることができる
そんな「ひととき」を、実感させる歌だと思う
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕の「わすらえめやも」の解説には、
私も、そこからまた想いを派生させるものを感じた
その解説は、
「『忘れじ』あるいは、『忘らえぬ』という表現は、恋の誓いに最も多く、挽歌において死者を永遠にしのぶ誓いとしても、さらには土地賞めにも用いられているが、遊宴の楽しさをいう例は稀である」
なるほど、言われてみれば、通常の楽しさのなかから、この言葉を持ち出すのは異質だ
何故なら、その後においても、いくらでも無邪気に遊ぶことが可能であれば
ここで、まるで自分に言い聞かせるような「忘れるものか」などとは詠わないだろう
それは、それこそ挽歌に用いられような、もう二度とは起こり得ないことへの「誓い」に及ぶ
恋の誓い、というのもそうだろう
あなたの他に、愛する人はもうできないでしょう...この日を忘れません、というような...
そんな感覚で、この歌を読めば、仲間たちと無邪気に遊ぶ自身のなかに
ふと、堪え切れないなにかが沸き起こっている
こんな仲間たちと、この先もずっと一緒にいることができるのだろうか、と
いつ離れ離れになるかもしれず、一旦そのことを思いだすと
今このひとときが、とてつもなく大切な「ひととき」に思えてしまう
この先、何があろうと...この仲間たちと遊んだ、今日という日を
決して忘れはしない...忘れるもんか |
| |

|
掲載日:2014.01.18.
| 春雑歌 野遊 |
| 春日野之 淺茅之上尓 念共 遊今日 忘目八方 |
| 春日野の浅茅が上に思ふどち遊ぶ今日の日忘らえめやも |
| かすがのの あさぢがうへに おもふどち あそぶけふのひ わすらえめやも |
| 巻第十 1884 春雑歌 野遊 作者不詳 |
| 【1884】語義 |
意味・活用・接続 |
| かすがのの[春日野之 ] |
| かすがの[春日野] |
奈良市春日山麓一帯の地 |
| あさぢがうへに[淺茅之上尓] |
| あさぢ[浅茅] |
たけの低い茅萱(ちがや) |
| おもふどち[念共] |
| おもふどち[思ふどち] |
「おもひどち」ともいう、親しい者同士 |
| あそぶけふのひ[遊今日] |
| わすらえめやも[忘目八方] |
| え[助動詞・ゆ] |
[可能・未然形]~ことができる |
未然形につく |
| め[助動詞・む] |
[推量反語・已然形]~だろう(か)(いや、~ないだろう |
| 〔接続〕未然形に付く |
| 已然形「め」は、疑問の助詞「や・か」、反語の終助詞「やも」を伴って反語の意を表す |
| やも[終助詞] |
[反語]~(で)あろうか(いや、~ない) |
已然形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [あさぢ] |
「むぐら」「よもぎ」とともに、荒れ果てた場所の描写によく用いられる
「茅」は、イネ科の多年草
野山や道のほとりに、生える
丈の低い茅を「アサヂ」といい、
屋根の葺き草になるほどの大きさのものを「チガヤ」という
春に花穂の出たものを「ツバナ」という |
| |
| [あそぶけふのひ] |
この原文「遊今日」も、多くの異訓がある
一般的なテキストでは、「あそぶけふのひ」とされ、
「遊ぶ」は活用形による捉え方だが、
「今日」の表記に、「けふ・けふのひ・このひ」と分かれるようだ
| 原文「遊今日」異訓 |
| あそへるけふの |
『類聚古集』『古葉略類聚鈔』 |
| あそへるけふは |
『紀州本』、『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| あそふけふをは |
『西本願寺本』 |
| あそぶこのひの |
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| あそびしけふの |
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| あそぶけふのひは |
『定本万葉集』〔佐佐木信綱・武田祐吉、昭和15~23年成〕
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| あそびしけふは |
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| あそぶこのひは |
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕 |
| あそぶけふのひ |
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
これほどになると、「異訓」というより、まだ「未訓」の方が適している感じがする
「今日」を、「けふのひ」と定訓とする歌は幾つかあるが
それに、「万葉仮名」の訓が添えられているのかどうか、また明日香で探してみよう
ただ、「けふ」ではなく、「けふのひ」という「語」は確かに詠われてはいる
その万葉仮名は「介敷乃日」、「気布能比」などで確認できる
だから、「今日」と言う表記が「けふのひ」であっても、その音数からは妥当だと思う
もっとも、「遊ぶ」に強調の助詞「し」が表記されていれば、「けふ」としても自然だ
『親考』『私注』などは「けふ」で辻褄を合わせるが、
「春日野之」の「之(の)」や「浅茅之上尓」の「之(が)・尓(に)」の助詞は表記されている
だから「遊今日」を「あそびし」と訓むのは...無理じゃないかと思う |
| |
|
|
| 【歌意1885】 |
春霞の立つ春日野を
幾度も幾度も行っては帰り、帰っては行きを繰り返して
私たちは、決して途絶えることなく毎年...幾年も、逢い続けたいものだ |
春霞の春日野を景観として、毎年この季節に逢いましょう、逢いたいものだ
勿論、そこには、この景観も、共に眺めよう、という気持ちも籠められてはいるだろう
この「相見む」という語が、作者の気持ちをどのように表現したものか
それは推測でしか解らないが
多くの注釈書では、毎年共に眺めよう、と
その眺める対象が「春霞の春日野」であり、「相」で「一緒に」としている
そこに、「逢いましょう」という気持ちは表れないのだろうか
「共に眺める」ことが、すなわち「逢いましょう」になるとも言えるが
一般的な歌意だと、どうしても「毎年眺めに行こうな」と
親しい仲間内の約束事が中心になってくる
この部立て「春雑歌野遊」だから、そんな歌意であっても不自然さはないが
私は「相」に、何となく強烈な願望のようなものを抱いてしまう
右頁の「注記」で書いたように、接頭語「相」には強調のニュアンスもある
お互いに、忘れず毎年ここで逢いましょう
お互いに、幾度もこの春日野を行ったり帰ったりしてはいるものの
この春霞の季節の春日野で...逢いたいものです
その想いは、年毎に深まってゆくのでしょうね |
| |
 |
掲載日:2014.01.19.
| 春雑歌 野遊 |
| 春霞 立春日野乎 徃還 吾者相見 弥年之黄土 |
| 春霞立つ春日野を行き返り我れは相見むいや年のはに |
| はるかすみ たつかすがのを ゆきかへり われはあひみむ いやとしのはに |
| 巻第十 1885 春雑歌 野遊 作者不詳 |
| 【1885】語義 |
意味・活用・接続 |
| はるかすみ[春霞 ] |
| たつかすがのを[立春日野乎] |
| ゆきかへり[徃還] |
| ゆきかへり[行き帰り] |
行って帰ってきては、また行く、それを幾度も繰り返す |
| われはあひみむ[吾者相見] |
| あひみ[相見る] |
[他マ上一・未然形]対面する・会見する |
| む[助動詞・む] |
[推量・意志・終止形]~よう・~つもりだ |
未然形につく |
| いやとしのはに[弥年之黄土] |
| いや[弥・接頭語] |
いよいよ・ますます・いちだんと、の意を表す |
| としのは[年の端] |
毎年・年ごと |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [われはあいみむ] |
この語句「あいみむ」には、まさに表記のように「相対し見る」の意味がある
しかし、この語句の解釈にも、いろいろとある
単純に古語辞典に頼るなら、「顔を合わせる・対面する」と載っているが...
「相(あひ)」を接頭語として解釈すると、
その原義を用いて「一緒に・二人で・互いに」などとなる
そして、そこから転じて接続する動詞を強調する働きもする
| 「吾者相見」の語義解釈 |
注釈書 |
| 私は見よう |
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| 私は友と共に眺めよう |
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕 |
| 我々は集い逢おう |
『日本古典文学全集』〔小学館、昭和50年成〕
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕 |
| 我々は集い(共に見よう) |
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕 |
以上の注釈書などが、私には確認できるが
こうして見ても、「友と共に眺めよう」とする解釈が多い
『全注』の解説を読むと、時代別上代編に漢籍の「相」の字は、
「一緒に・互いに」の用法は、秦漢の頃から見えるが、『捜神記』などの小説類や、
『世話新語』『遊仙窟』などになると、「強調」の用法が多くなり
しかも、その中でも、原義を含むことが多いという
『万葉集』の「強調」の例としてあげられるものも、原義「一緒に」との区別は微妙で、
「向く・見る・別れる」のように、常に相手を伴う語に接しているのは、
原義を完全に払拭していないからだろう、としている
しかし、ここでの「あひみむ」が、何を対象としているのか
何を「見よう」としているのか、
それが読む者の感じ方で、この「あひみむ」の解釈も決まってくる
ほとんどの注釈書では、その対象を「春霞の立つ春日野」とし
「ともに見よう」と解釈している
『新・旧全集』と『講談社文庫』が、「見る」ことではなく「逢う」ことを重視している
私も、その解釈でこの歌を感じた方がいいと思う |
| |
| [黄土(はに)] |
この原文「黄土」の表記は、『万葉集』中六例あるが、
この歌では、単純にその「音」だけを借りている
「としのはに」は、「としのは」と助詞「に」になるので、
「はに」としての「語句」にはならない
「集中」の六例でも、この歌を除く他の五例は、すべて
| 岸乃黄土粉 「岸の黄土(はにふ)に」 |
6-937 |
| 岸乃黄土 「岸の黄土(はにふ)に」 |
6-1007 |
| 岸乃黄土 「岸の黄土(はにふ)を」 |
7-1150 |
| 岸乃黄土 「岸の黄土(はにふ)を」 |
7-1152 |
| 三津之黄土 「三津の黄土(はにふ)の」 |
11-2734 |
このように、「黄土」を「はにふ」と訓んでいる
その「はにふ」も、それぞれの歌意では、例外なく「埴生(はにふ)」と解され
古語辞典によると、「生(ふ)」はそれを産する所の意で、
「埴(はに)」は、黄赤色の粘土のこととし、「はにふ」はその産出地とされている
だから、この「黄土」の五例は、その実際の色、「埴生色」を表現したものだ
そこから、この掲題歌〔1885〕だけが、その音、「はに」を当てたことになる
よく考えてみると、あまりスマートな「借音」とは思えない
何しろ、語の区切り方が、自然じゃないから...
かといって、「いやとしの」+「はに」では、通じる「語」にはならない
自国の言葉の表記がないということは、本当に悲しいことだ |
| |
|
|
| 【歌意1886】 |
春の野に、心をのびのびとさせ、語り合いたいと
親しい仲間たちがやってきた今日のこの日は、
このまま暮れずにあってほしいものだ |
宮仕えの息苦しさを思わせるような歌だ
だから、こうして春の野に集まったこの日を
きままに、のびのびと過ごせる、この一日を
このまま暮れることもなく、終らせたくない強い願いが滲み出ている
これは、それほど日々の職務が、こうした若者たちに窮屈さを感じさせている傍証にもなる
たんに、この日が楽しい一日だから、というだけではなく
職場の緊張感や堅苦しさから解放された「開放感」を詠ったものだろう
勿論、「おもふどち」というからには、楽しい気の合った仲間たちなので
この一日も楽しいひとときであるには違いない
尚、類想歌の「秋の宴」を詠った一首を載せておく
| 秋雑歌/(橘朝臣奈良麻呂結集宴歌十一首) |
| 黄葉乃 過麻久惜美 思共 遊今夜者 不開毛有奴香 |
| 黄葉の過ぎまく惜しみ思ふどち遊ぶ今夜は明けずもあらぬか |
| もみちばの すぎまくをしみ おもふどち あそぶこよひは あけずもあらぬか |
| 右一首内舎人大伴宿祢家持 / 以前冬十月十七日集於右大臣橘卿之舊宅宴飲也 |
| 巻第八 1595 秋雑歌 大伴宿禰家持 |
〔語義〕
「すぎまく」は、盛りが過ぎる意の自動詞ガ行上二段「過ぐ」の未然形「すぎ」に、
上代語の未来の推量、「~だろうこと・~であろうようなこと」を表す「まく」
なお、この「まく」は、推量の助動詞「む」のク語法
「をしみ」の「み」は、原因・理由を表す接尾語
「あけずもあらぬか」は、掲題歌と同じ用法「~も~ぬか」 |
〔歌意〕
黄葉が過ぎ去ろうとしていることを惜しみ、
親しい者同士こうして集まった今夜、
このまま夜も明けないでほしい |
|
| |

|
掲載日:2014.01.20.
| 春雑歌 野遊 |
| 春野尓 意将述跡 念共 来之今日者 不晩毛荒粳 |
| 春の野に心延べむと思ふどち来し今日の日は暮れずもあらぬか |
| はるののに こころのべむと おもふどち こしけふのひは くれずもあらぬか |
| 巻第十 1886 春雑歌 野遊 作者不詳 |
【左頁類想歌】〔1595〕
| 【1886】語義 |
意味・活用・接続 |
| はるののに[春野尓 ] |
| こころのべむと[意将述跡] |
| のべ[延ぶ・伸ぶ] |
[他バ下二・未然形]のびのびさせる・きままにさせる |
| む[助動詞・む] |
[推量意志・連体形]~よう・~つもりだ |
未然形につく |
| と[格助詞] |
[比喩]~のように・~として〔接続〕体言、また準ずる語につく |
| おもふどち[念共]気の合った者同士・親しい者同士 「おもひどち」ともいう |
| こしけふのひは[来之今日者] |
| こ[来(く)] |
[自カ変・未然形]来る・行く・通う |
| し[助動詞・き] |
[過去・連体形]~た・~ていた〔接続〕連用形、カ変サ変は特殊 |
| けふのひは |
今日というこの日は |
| くれずもあらぬか[不晩毛荒粳] |
| くれ[暮る・昏る] |
[自ラ下二・未然形]日が暮れる・季節が過ぎる・年月が終る |
| も[係助詞] |
[仮定希望]せめて~だけでも・~なりとも |
| 〔接続〕名詞、助詞、用言や助動詞の連体形・連用形につく |
| ぬか[上代語] |
多く「~も~ぬか」の形で、詠嘆をこめた願望の意を表す |
| |
「~であって欲しい・~ないかなあ」 |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [こころのべむと] |
この「訓」には異訓がほとんどないので、
どの注釈書も、「心をのびのびさせようと」で、解釈は同じ
しかし、旧訓は「こころやらむと」とあって、これを重んじたのが鹿持雅澄だ
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕の「訓」について
| 原文は「意述將跡」で、旧訓は「こころやらむと」。現在では「こころのべむと」とよむのが普通。雅澄は「酒飲みて心を遣るに」(巻三)、「恋ふること心やりかね」(巻十一)、「見あきらめ心やらむと」(巻一九)などの例をあげて旧訓をよしとし、「述」は「遣」の誤字かとする。 |
と、『全注』は紹介している
現在の「定訓」となったのは、
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕に拠るものらしい
その中で、契沖は
| 赤人集の「こころのへむと」を引き、「赤人集字ニ当リテマサルベキ歟」とする |
ここでも、権威ある学者の「感性」が呪縛をかける
そもそも原文の「意将述跡」の「述」が、
「のびのびさせる・きままにさせる」意の、他動詞「のぶ(延ぶ・伸ぶ)」の「借訓」
ということらしいが、雅澄が誤字説を唱えたと同じように
逆に「述べる」意味では通じないのだろうか
「述べる」意となると、その語は、他動詞ハ行下二段「のばふ(述ばふ)」なので、
確かに、助動詞「む」に接続して訓むのであれば、未然形「のばへ」となって
字数からすれば、「こころのばへむと」と字余りになる
しかし、この日が暮れないように、と願うには、
通説の「気晴らし」だけではなく、
「親しい仲間同士」で「語らう」ひと時であってもいいのではと、思ってしまう
この「述」を使う意味が、そんな意味合いも含んでのことではないかと思う
|
| |
| [こしけふのひは] |
この歌の二首前の歌〔1854、既出 書庫-14〕にも書いたように、
〔1854〕「遊今日」を「あそびしけふは」とする『私注』
そして、今日の歌〔1856〕「来之今日者」を、「きたりしけふは」とする『私注』
この「きたりし」は、カ変動詞「来」の連用形「き」に、
その連用形に接続する完了の助動詞「たり」の連用形「たり」
そして、またその連用形に接続する、過去の助動詞「き」の連体形「し」というのだろう
そうしなければならないのは、やはり「今日」の訓を「けふのひ」ではなく、
「けふ」とするから、なのだと思う
尚、過去の助動詞「き」の接続の仕方では、通常は「連用形」だが
サ変とカ変動詞は特殊な接続になる
カ変動詞の場合、連用形につくのは「来(き)し方」の形で使われるのみで
他の場合には、未然形について「来(こ)し」となる
また、サ変動詞の場合は、連用形にはつかず、未然形について「せし」となる
|
| |
|
|
| 【歌意1887】 |
(ももしきの)大宮に仕える官人たちが
休みの時でもないだろうに、みんな梅を髪にかざして
ここに集められているのは...何事だろうか |
この部立て「春雑歌野遊」四首の最後の歌だが、
それまでと全く情景が違う
作者が詠うのは、「野に遊ぶ」若人たちの姿を「楽しげ」に感じてはいない
確かに、梅の花を髪に挿して集い遊んだ歌は多い
だから、その語句だけでも、「野遊」を思い浮かべるのは不自然ではないだろう
ならば、「暇あれや」とは、何なのだろう
通常の勤務時間内だからこそ、言える語ではないだろうか
「仕事が暇なのだろうか」
「休みの時間なのか」
そんな思いで、作者は官人たちの「興」を見て詠ったのだろうか
おそらく、長い間の研究の成果で、この訳が固定されたのだろうが...
こんな歌もある
この掲題歌とは、まったく逆の情況を詠ったとされるものだ
| 雑歌/(秋八月廿日宴右大臣橘家歌四首) |
| 百礒城乃 大宮人者 今日毛鴨 暇无跡 里尓不出将有 |
| ももしきの大宮人は今日もかも暇をなみと里に出でずあらむ |
| ももしきの おほみやひとは けふもかも いとまをなみと さとにいでずあらむ |
| 右一首右大臣傳云 故豊嶋采女歌 |
| 巻第六 1030 雑歌 豊島采女 |
〔語義〕
「けふもかも」は、添加の係助詞「も」~もまた、と
確定条件の疑問の係助詞「かも」~からか
「なみ」は、形容詞「無し」の語幹「な」に、原因・理由を表す接尾語「み」、ないので
「さとにいでずあらむ」には、原文に「里尓不去将有」もあり、訓も分かれるが、
田舎(おそらく本貫地)には、行かないだろう
疑問の係り結び「かも」の結びが、結句の連体形「む」 |
〔歌意〕
(ももしきの)大宮人は、今日もまた暇がないと言って
本貫の田庄へは行かないのであろうか |
勿論、すべての官人たちの事情が同じだとは言えないが
少なくとも、宮中の仕事が忙しく、なかなか田舎に帰ることもできないのだろう
そんな大宮人の様子を詠っている
今日のこの二首の「宮仕え」振りが、それぞれ違う姿で描かれている
こんな宮中での官人たちを詠う歌がある一方、野遊びに興じる官人たち...
しかし、〔1887〕には、何故その野遊びに興じる官人の描写がないのだろう
〔1887〕を詠った作者には、野遊びとは違った雰囲気を感じているのかもしれない
「何事かがあったのだろうか」と、作者の不安が「いとまあれや」になるのではないだろうか
季節や行事の事情もあり、仕事も一律ではないことは当然だろう、が
官人を象徴的に詠う歌として、私はこの二首をまったく逆の情況だとは思えない
「いとまあれや」、暇などないだろうに...同じような歌に聞こえる
そんなに忙しいのに、どうしてみんな集められているのだろう...、と
多くの注釈書が、「反語」の歌意にはならず「軽い疑問」とわざわざ質しているのが、
返って、「反語では何故いけないのか」と思ってしまった
尚、掲題歌は『和漢朗詠集』「春興」にも、
| ももしきの大宮人は暇あれや桜をかざして今日も暮らしつ |
そして、『新古今集』「春歌下104」にも、「題しらず 赤人」として
| 春歌下 題しらず |
| ももしきの おおみやびとは いとまあれや さくらかざして けふもくらしつ |
| 新古今集 巻第二 104 春歌下 赤人 |
「うめ」と「さくら」の違い
そして、結句の「ここにつどへる」と「けふもくらしつ」の違い
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕の解説では、
「ここにつどへる」よりも「けふもくらしつ」の方が、閑暇多い大宮人の、
春のもの憂い気分を出しているが、万葉的ではない、という
赤人とは、万葉歌人山部赤人だろうに...
『万葉的』な歌とは...率直さ、なのだろうか
ならば、歌意としても「反語」を基調にした方が、いいように思えるのだが...
|
| |
|
掲載日:2014.01.21.
| 春雑歌 野遊 |
| 百礒城之 大宮人者 暇有也 梅乎挿頭而 此間集有 |
| ももしきの大宮人は暇あれや梅をかざしてここに集へる |
| ももしきの おほみやひとは いとまあれや うめをかざして ここにつどへる |
| 巻第十 1887 春雑歌 野遊 作者不詳 |
【左頁】〔1030〕
| 【1887】語義 |
意味・活用・接続 |
| ももしきの[春野尓 ] 〔枕詞〕「大宮」にかかる (多くの石や木で作ってある意から) |
| おほみやひとは[大宮人者] |
| おほみやひと[大宮人] |
宮中に仕える人 (古くは清音だが、後に「おほみやびと」) |
| いとまあれや[暇有也] |
| いとま[暇] |
仕事などのない時間・休み・休暇・勤めを止めること |
| や[係助詞] |
[疑問]~か (係り結びの「係り」、「結び」は「つどへる」) |
| |
[反語]~だろうか、いや~でない |
| 〔接続〕種々の語につく・活用語には連体形、連用形につく・上代では已然形にも付く |
| うめをかざして[梅乎挿頭而] |
| かざし[挿頭す] |
[他サ四・連用形]草木の花や枝、造花などを髪や冠にさす |
| て[接続助詞] |
[並立]~て |
連用形につく |
| ここにつどへる[此間集有] |
| つどへ[集ふ] |
[他ハ下二・連用形]集める・寄せ集める |
| る[有り・在り] |
[自ラ変・連体形]過ごす・時が経過する・いる・その場にいる |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [いとまあれや] |
この頃の官人たちの勤務時間は、原則として六日に一日の割合で休日があった
早朝に出仕して、正午ころに退庁する決まりだったという
しかし、天皇に関係する宮内省や侍従などは、これに拘束されない、とする
また、写経所で臨時に大量の写経を行うような場合は、夜間も勤務した、とある
「あれや」は、「あればや」と同じく疑問条件
「已然形」+「や」は、「已然形」+「か」に比べて普通反語性が強く、
「そんなはずはないのに」の意となるが、
どの注釈書でも、この歌では、反語の意にはならず、「軽い疑問」だと説明している
しかし、どうして「反語の意」にはならないから、「軽い疑問」だと言えるのだろう
この歌、「反語の意」では解釈はできないのだろうか
| A |
大宮人たちは、今休みの時間だからなのか、
梅をかざしてここに寄り集まり時を過している
|
このような一般的な歌意だと、確かに「疑問」なのだが
反語では、訳せないのかなあ
| B |
大宮人たち、休みどきなのかな、そんなはずもないのに...ここに集めさせられて |
こう訳せば、だめなのだろうか
[A]の通常の解釈では、
「つどへる」を自動詞四段「つどふ」の「集まる・寄り合う」になる
そして、この「つどへる」を、四段の已然形「つどへ」とすると、
「る」は、動詞「あり」(連体形「る」)ではなく、
完了の助動詞「り」の連体形「る」としなければならない
[B]は、上表の〔語義〕に載せたように、他動詞下二段「つどふ」と、
自動詞ラ変「あり」を用いて、この歌を訳したものだ
一般的ではないが、私はそんな風に解釈した
勿論、それには私なりの根拠はある
それは、左頁に載せた例歌〔1030〕とともに、考えてみたい
なお、古語辞典から「つどふ」と「あふ」の解説を引用する
| 「つどふ」と「あふ」 |
| 多くのものが一箇所に集まる意を原義とするのが「つどふ」であり、二つのものが一つになる意を原義とするのが「あふ」である。軍団のように、あるまとまりが単位となって「つどふ」あるいは「あふ」こともある。「つどふ」の対義語は「あかる」、「あふ」の対義語は「わかる」である。 |
|
| |
|

|
| 【歌意1889】 |
すべてのものは、新しいのがよい
しかしながら、人間だけは、
そう年とって「古く」なった方が、いいんだぞ |
この初句の「物皆」は、『万葉集』でこの一首でしか使われていない
「人皆」は、何首かあるのだが...珍しい表現だと思う
次に続く、「人」を同じ土俵に立たせている
いや、「人は新しくない方が」といい、違うと詠うのだが
それは同じ土俵上での「差異」を言うに過ぎない
まあ、あまりそんなことには拘らない方がいいのかな
この歌、前の歌と「問答歌」のようにセットと考えられたり
同じ作者の連作と考えられたり、いろいろと解釈もできる
さて、自分に言い聞かせ馴染めるのは、どんな感じになるだろう
まず、前の歌〔1888〕は
| 春雑歌歎舊 |
| 寒過 暖来者 年月者 雖新有 人者舊去 |
| 冬過ぎて春し来れば年月は新たなれども人は古りゆく |
| ふゆすぎて はるしきたれば としつきは あらたなれども ひとはふりゆく |
| 既出〔書庫-13、2013年12月22日、12月31日〕巻第十 1888 春雑歌歎舊 作者不詳 |
この歌は、新春を迎えた喜びの中に、人が老いてゆく嘆きを詠んだ、という
そして、今日の歌〔1889〕は、「人は年を取って老いている方が、いい」という
確かに、問答歌のような掛け合いだ
ただ、春が来ることが、新しい年を迎え、「老いる」と詠う歌と
新しいものは、どれもいいことだ
しかし、人は新しいことよりも、老いて古い方がいい、というのは、
何か冒頭で言ったような「同じ土俵」とは違う気がする
「物と人」を「同じ土俵」としたことへは、妙な気持ちになるが
その比較ではなく、〔1888〕歌と、〔1889〕歌とを並べたとき
これは、決して同じ土俵ではない
だから、問答歌にはならない、と思う
何が違うのか...
老いることが、いいと言うのは、何度も「春」が来てというような「年」の積み重ねではなく
何かへの「想い」を深めることに主眼があると思う
その何かは、人それぞれあるものだろう
人であったり、物であったり...
その対象となるものへの「深まり」は、むしろ歓迎すべきことで
それを、「老いる」と表現しているのではないだろうか
何かへの「想い」の「深まり」は、年齢的な要素も確かにある
しかし、年齢に関わらず、「想い深め」て行くことこそ、
機械的に年を取るのではない「人」の「想いの深さ」のはずだ
その意味では、標題に「歎舊」とあるのは、相応しくない
前の歌〔1888〕に唱和して、おいおいそう歎くな、人って、そんなものじゃないぞ、
「歎舊」は〔1888〕の一首であって、この〔1889〕は、「人生讃歌」に向けられている
ただ、セットと言えば、やはりセットになるかな
注釈書の中には、前歌を若者が老人を揶揄した歌とし、
それを、いい返した老人の歌だとするものや
自らの嘆きを、自ら慰撫するための歌だとか...いろいろある
私の描く、素直な場景は、
老いた人が二人、片や新しき年を、また老いてしまうな、と歎き
横にいるもう一人の老人が、馬鹿言うな、老いてこその「人の魅力だ」と言っている
そんな場面を思い浮かべてみたくなる
|
| |


|
掲載日:2014.01.22.
| 春雑歌 歎舊 |
| 物皆者 新吉 唯 人者舊之 應宜 |
| 物皆は新たしきよしただしくも人は古りにしよろしかるべし |
| ものみなは あらたしきよし ただしくも ひとはふりにし よろしかるべし |
| 巻第十 1889 春雑歌 歎舊 作者不詳 |
| 【1889】語義 |
意味・活用・接続 |
| ものみなは[物皆者 ]すべての物は |
| あらたしきよし[新吉] |
| あらたしき[新たし] |
[形シク・連体形]新しい・新鮮である |
| よし[良し・善し・] |
[形ク・終止形]本質的によいさま・最高に優れているさま |
| 良い・正しい・美しい・好ましい・相応しい・縁起がよい・効果がある、など |
| ただしくも[唯] |
| ただしく[但しく] |
もっとも・とはいうものの・しかしながら |
| も[係助詞] |
[やわらげ]~も〔接続〕名詞・助詞・用言や助動詞につく |
| ひとはふりにし[人者舊之] |
| ふり[古る・旧る] |
[自ラ上二・連用形]年をとる・老いる・古くなる |
| にし |
~てしまった・~た |
連用形につく |
| 〔成立〕完了の助動詞「ぬ」の連用形「に」+過去の助動詞「き」の連体形「し」 |
| よろしかるべし[應宜] |
| よろしかる[宜し] |
[形シク・連体形]すぐれている・まあよい・だいたい良い |
| べし[助動詞・べし] |
[推量・終止形]~にちがいない |
ラ変型には連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [あらたしきよし] |
原文「新吉」を、「あらたまるよし」とする訓もある
『萬葉集本文篇』〔塙書房・佐竹昭広、昭和38年成〕、
『日本古典文学全集』〔小学館、昭和50年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕が、それだ
ただし、同じ出版社であっても、小学館の『新全集』、岩波の『旧体系』は、
一般的な「あらたしきよし」とする
刊行時期が違えば、解釈も変わるだろうが、「旧から新」、「新から旧」へと
その解釈の定説への「揺れ」というものを感じさせられる
題目「歎舊」の感覚を考えるのなら、「新旧」のテーマなので
「あらたしき」の方が、いいと思う
|
| |
| [あらたしき] |
平安時代以降は、「新(あら)たし」と「惜(あたら)し」とが混同され、
「新しい」意の場合も「あたらし」となった
|
| |
| [ただしく] |
「ただし」は、副詞「ただ」に副助詞「し」の付いたもので
前の文に添えて、条件や例外などを言い出す語 「もっとも・とはいうものの」
そして、もう一つの用法で、前の文を受け、推量や疑問の内容を説くのに用いる
「あるいは・もしくは・ひょっとしたら」
この「ただし」に副詞語尾「く」がついた形で、「ただしく」
例として言われるのが、「けだし」と「けだしく」の関係と同じという説明だ
また、接尾語「く」は、上代の用法で、「~すること」の意の他
連用修飾語として、「~することには」、
文末にあって、詠嘆を表し「~することよ」などがある
この接尾語「く」は、形の上では、四段・ラ変動詞の未然形、
形容詞の古い未然形語尾「け・しけ」の形につく
また助動詞「けり・り・む・ず」の未然形と考えられた形につき、
「けらく・らく・まく・なく」となり、助動詞「き」の連体形「し」につき、
「しく」などとなる
上接の語を名詞化する働きがあり、中古では「いはく・思はく」などの
特定の語として残り、いわば化石化され現代にも至っている
接尾語「らく」と補い合い、
四段・ラ変動詞以外の動詞には、「らく」がついて名詞化する
この「く」と「らく」との複雑な接続を統一的に説明するため、
「あく」という語を想定して、上の語の連体形にこれが付いたものとする説がある |
| |
| [ひとはふりにし] |
この原文にも、解釈がいくつかある
そもそも、オリジナルの『万葉集』には、句切れでは書かれていなかったはずだ
だから、この歌の第三句「唯」と、第四句「人者舊之」も
その原文では「唯人者舊之」と当然繋がっていたはずだ
そこで、幾つかの訓の解釈が起こる
「唯」に「人者」をつけて「唯人者」[ただひとは]としたのが、
『類聚古集』や『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕など
当然、第三句に「人者」が入るので、第四句は「舊之」となる
だから、第三句を「ただひとは」とした場合の第四句にもまた異訓が生じる
その場合の第四句は、
「ただひとは ふりたるのみぞ」は『類聚古集』の他に、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕
「ただひとは ふりぬるのみし」とするのが、『万葉代匠記』の他に、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕
そして、「唯」を「ただしくも」と訓み、
「人者舊之」を「ひとはふりにし」と提示したのが、
佐伯梅友「万葉集巻十僻案ニ題」(国語と国文学昭和十九年十二月)になる
それにより、この「唯」を「ただしくも」とする訓は、定説となっているが
第四句には、また異訓が残る
| ひとはふるきし |
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕 |
| ひとはふりゆく |
『萬葉集本文篇』〔塙書房・佐竹昭広、昭和38年成〕
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕
|
『新全集』が「ふりゆく」とするのは、その「補注」に、こう説明してある
「第四句原文の『旧之』の『之』、名義抄に「ゆく」の訓がある。この歌も表記が簡略なので、訓み下しに諸説がある。」
なるほど、「表記が簡略なので」...
それが、『万葉集』の「本来の姿」といえるものなのだろう
だとしたら、後に万葉仮名を駆使して、助詞まで間違うことなく表現した時代と違って
漢字の「借音・借訓」時代の『万葉集』は、一種の「メモ帳」的なものかもしれない
それを正しく訓めるのは「作者本人」だけ、といえるだろう
|
| |
| [助動詞「べし」の接続] |
推量の助動詞「べし」は、普通、活用語の終止形につく
しかし、ラ変型の活用語には、その連体形に付く
この歌の場合の形容詞「よろし」の連体形「よろしかる」の「かる」は、
その活用語尾が「ラ変型」であるので、「よろしかるべし」となる |
| |
|
|
| 【歌意1890】 |
住吉の里を、通っていたところ
まるで春の花のような、
この上もなく美しく心惹かれるあなたに
出逢えたことが... |
住吉の「里」が、宮仕えの作者の実家なのか、
あるいは、旅先の通り道なのか、具体的な説明はないが
この「いやめづらしききみ」と言うからには
暮らし馴染んだ「実家」であるよりも、旅の通りすがりの方がいいのかもしれない
旅の途中で、通り掛った住吉の里
思いもかけず、心惹かれる「あなた」に逢ってしまった
この「あなた」が、以前から顔見知りで、慕っていた「あなた」であれば、
まさか、あなたとここで逢おうとは、という偶然の出逢いに驚き歓んで詠ったものだろう
どの注釈書をみても、この「あなた」を漠然と描いている
旅先で見かけた「魅力的なあなた」なのか、
普段は、たとえば都などでも逢うことがあって、秘かに心惹かれていた「あなた」を
この住吉で、偶然逢ってしまった
その嬉しさは、普段見かける場面より、いっそう増すものだと思う
「きみ」といえば、上代では一般的に、女性が男を呼ぶときにいう語だが
中古以降は、男女間でも「きみ」と使われていたらしい
勿論、この歌が女の歌で、男と逢った歓びを詠ったものかもしれないし
男が、仕事で出張する旅の途中で、出逢った歌かもしれない
一応、歌意では男歌っぽく書いたが、
「めづらしき」は、なにも「美しく心惹かれる」に固守されるものではなく
現代語のように、「珍しい」という意味でもあるのだから
それこそ、「まさかこんなところで」と解釈したところで、おかしくはない
むしろ、その訳しかたの方が、
都では何気なく逢っていた「あなた」に、珍しいこともあるものだ、こんなところで...
とも言える
しかし、「懽逢」の「逢ふを懽ぶる」という作者の想いからすると
「珍しい」ことであると同時に「心惹かれるあなた」に逢った、と思いたいものだ
ちなみに、誤字と断じられた「得」を、そのまま訳せば...
第二句は「さとにえしかば」となるのだろうか
「え」は、他動詞ア行下二段「得(う)」の連用形で、
「里で、手に入れたのだから」、「春の花のような可愛いあなたに、逢えたのでしょう」
くらいの歌意にはなりそうだ
ただ、その場合、「何を手に入れたのか」と問われることが、欠点になるが...
|
| |
|
掲載日:2014.01.23.
| 春雑歌 懽逢 |
| 住吉之 里行之鹿歯 春花乃 益希見 君相有香開 |
| 住吉の里行きしかば春花のいやめづらしき君に逢へるかも |
| すみのえの さとゆきしかば はるはなの いやめづらしき きみにあへるかも |
| 巻第十 1890 春雑歌 懽逢 作者不詳 |
| 【1890】語義 |
意味・活用・接続 |
| すみのえの[住吉之 ] |
大阪市住吉区一帯の地・海上を支配する神である底筒之男・中筒之男・上筒之男の三神を祀る
住吉神社があり、住吉の御津があった |
| さとゆきしかば[里行之鹿歯] |
| さと[里] |
人家が集まっているところ・人里・(宮中に仕える者の実家) |
| ゆき[行く] |
[自カ四・連用形]通り行く・通過する・進み行く |
| しか[助動詞・き] |
[過去・已然形]~た・~ていた |
連用形につく |
| ば[接続助詞] |
[順接の確定条件・単純接続]~したところ |
已然形につく |
| はるはなの[春花乃]〔枕詞〕「いやめづらしき」にかかる |
| いやめづらしき[益希見] |
| いや[弥](接頭語) |
「いよ」の転、いよいよ・一段と・この上なく、などの意を表す |
| めづらしき[めづらし] |
[形シク・連体形]愛らしい・清新である・珍しい・滅多にない |
| きみにあへるかも[君相有香開] |
| あへ[逢ふ] |
[自ハ四・已然形]出逢う・対面する |
| る[助動詞・り] |
[完了・連体形]~ている・~てしまった |
已然形につく |
| かも[終助詞] |
[詠嘆・感動]~であることよ |
連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [さとゆきしかば] |
原文「里行之鹿歯」は、その底本では「里得之鹿歯」とあったものが、
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕により、「得」は「行」の誤字だろうとされ
それが、以降の定説になったらしい
それ以前の「得」を用いた「訓」は、どんなものだったろう...興味あるなあ
|
| |
| [めづらしき] |
「愛する・賛美する・心が惹きつけられる」の動詞ダ行下二段「愛(め)づ」に、
対応する形容詞で、現代語では、「めずらしい・滅多にない」の意に用いるが、古くは、
「賛美すべきである・すばらしい」
「愛らしい・かわいい」
「目新しい・清新である」
「珍しい・滅多にない」などがある
さらに、この動詞「愛づ」から派生する語に「めでたし」がある
これは、動詞「愛づ」の連用形「めで」に、
程度が甚だしい意の形容詞「いたし」のついた「愛(め)で甚(いた)し」の転と見られる
「はなはだ愛すべきだ」の意が原義となる
この「めでたし」の意味は、
「魅力的だ・心ひかれる」
「立派だ・見事だ・素晴らしい」
「祝う価値がある・慶賀すべきだ」となり、
確かに、「めづらし」の程度を更にアップさせたような意味になる
|
| |
|
|

| 「つきもいでぬかも」...さくらのはなのみゆべく... |
|
|
|
| 【歌意1891】 |
春日の三笠山、早く月が出てこないものかなあ
三笠山に月が出れば、この佐紀山に咲いている桜花が
その月明かりのもとで、とても綺麗に映えるだろうに |
奈良の佐保辺りを通って、佐紀の方面へは歩いたことがない
でも、佐保の佇まいを見ていると、佐紀もきっといいところなんだろうなあ、と想像してしまうこの歌のように、月明かりで「夜桜」を待ち望む「佐紀」の辺り...いいなあ、と思う
現代的にライトアップされた花見ではなく、
天空の月の明かりに映える桜、どんな風に見えるのだろう
私の乏しいイメージでは、桜のシルエットくらいしか思い浮かばないが
この万葉の当時には、人々を魅了するほどの「夜桜」が楽しめたのだろう
人工的な「灯かり」もなく、初めはシルエット程度の桜木も
次第に目が慣れてくると、日中見ている桜木と同じように見え出してくるのだろう
そんな「夜桜」を待つ人たちの想いが、この歌を詠わせている
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕には、
三笠山で月の出を待つのが平城京人の風流であった、と次の三首を紹介している
いつまでも出てこない月を歎いたり、
宴の杯に、その影を映したり...
ただ、掲題歌のように「月下の桜」とはいえないようだ
| 雑歌/安倍朝臣蟲麻呂月歌一首 |
| 雨隠 三笠乃山乎 高御香裳 月乃不出来 夜者更降管 |
| 雨隠り御笠の山を高みかも月の出で来ぬ夜はくたちつつ |
| あまごもり みかさのやまを たかみかも つきのいでこぬ よはくたちつつ |
| 巻第六 985 雑歌 安倍朝臣虫麻呂 |
〔語義〕
「あまごもり」は、〔枕詞〕三笠にかかる 他、〔異訓〕
「たかみかも」は、「やまをたかみ」の「~を~み」で、「~が~ので」となる
「くたちつつ」の旧訓は「ふけにつつ」
|
〔歌意〕
(あまごもり)の三笠の山が、
あんなに高いので、月が出てこない
夜は次第に更けてゆくというのに |
| |
| 雑歌/藤原八束朝臣月歌一首 |
| 待難尓 余為月者 妹之著 三笠山尓 隠而有来 |
| 待ちかてに我がする月は妹が着る御笠の山に隠りてありけり |
| まちかてに わがするつきは いもがきる みかさのやまに こもりてありけり |
| 巻第六 992 雑歌 藤原朝臣八束 |
〔語義〕
「かてに」の「かて」は、動詞の連用形について、
「~できる・~するに堪える」意を表す補助動詞「かつ」(下二段の活用)で、
その下に打消の助動詞「ず」の連体形「ぬ」及び古形の連用形「に」、
また打消の推量「まじ」の古形「ましじ」などについて、「かてぬ・かてに・かつましじ」
の形で用いられることが多い
ここでは、「かてに」で、「できない」の意になる
「わがする」は、「私が想う」ような気持ち
「いもがきる」は〔枕詞〕で、「三笠」にかかる
|
〔歌意〕
わたしがこんなに待ち切れないでいる月は
(妹が着る)三笠の山に、隠れていたんだなあ |
| |
| 雑歌旋頭歌 |
| 春日在 三笠乃山二 月船出 遊士之 飲酒坏尓 陰尓所見管 |
| 春日なる御笠の山に月の舟出づ風流士の飲む酒杯に影に見えつつ |
かすがなる みかさのやまに つきのふねいづ
みやびをの のむさかづきに かげにみえつ |
| 巻第七 1299 雑歌 旋頭歌 作者不詳 |
〔語義〕
「つきのふね」は、「船のような月」
「みやびをの」は、風流を愛する人たち |
〔歌意〕
春日の三笠山に、船のような月が出た
風流をこよなく愛する人たちの酒杯に
その影を映しながら... |
【補注】
「あまごもり」
『元暦校本』『類聚古集』などの古訓は「あまがくれ」
『西本願寺本』以下、仙覚系統諸本の訓は「あまごもり」
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕、『赤松万葉集創見』、
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕は、「あまごもる」
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕は、「あめごもり」
ここで面白いと思ったのは、『赤松万葉集創見』の見解だ
この書は、『万葉集創見』〔赤松景福〕のことで、調べてみたが、一切解らず
その情報は、『全注』によるもの
ただし、この著者・赤松景福の別の著作『続萬葉集古義』〔昭森社、昭和21年刊〕は
まだ古書として、紹介されてあったが、いつかは手に入れよう
そして、その『創見』の見解だが、『全注』が引用するには、
「是は雨隠る御笠と続く枕詞なれば、アマゴモルと連体に訓むべし。以下略」
といい、「雨に降り込められる三笠山」と解して、単に〔枕詞〕としてではなく
自動詞四段「雨隠る」の連体形の解釈をもしている
「三笠」にかかる〔枕詞〕であれば「あまごもり」のような「連用形」でもいいのだろう、と
しかし、ここでは、しっかり「雨に降り込められる三笠山」と解釈すべき、との主張らしい
確かに、歌意からすれば、そうとも受け取れるが...
「山を高み」でも、月の出の遅い理由にはなっている |
| |
| 「くたちつつ」 |
『万葉代匠記(初稿本)』〔契沖(1640~1701)、貞亨四年(1687)成〕の書き入れに、
「くだちつつ」とあり、『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕、
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕などがこれに従い
以来ほとんどの注釈書は、「くだちつつ」もしくは「くたちつつ」とする
自動詞四段「降(くだ)つ」は、原義は「衰える・傾く」だが
この歌の場合では、「日が傾く・夜が更ける・明け方に近づく」の意になる
自動詞下二段「更(ふ)く」は、形容詞「深し」と同根で、「夜が深まる」の意がある
「夜が更ける」とは、「夜が深まる」といえる
似たようなこの「くだつ」と「ふく」だが、
片や「明け方に近づく」、片や「夜が深まる」、この違いは大きい
しかし、原文に「夜者更降管」とあるので、悩ましいところだろう |
| |
|
掲載日:2014.01.24.
| 春雑歌 旋頭歌 |
| 春日在 三笠乃山尓 月母出奴可母 佐紀山尓 開有櫻之 花乃可見 |
| 春日なる御笠の山に月も出でぬかも 佐紀山に咲ける桜の花の見ゆべく |
かすがなる みかさのやまに つきもいでぬかも
さきやまに さけるさくらの はなのみゆべく |
| 巻第十 1891 春雑歌 旋頭歌 作者不詳 |
【左頁「月下の夜桜、でなくとも」】〔985・992・1299〕
| 【1891】語義 |
意味・活用・接続 |
| かすがなる[春日在 ]春日にある |
| みかさのやまに[三笠乃山尓] |
| つきもいでぬかも[月母出奴可母] |
| ぬかも[上代語] |
[「~ぬ~かも」の形で]願望の意を表す |
未然形につく |
| |
「~であってほしいなあ・~ないかなあ」 |
| 〔成立〕打消の助動詞「ず」の連体形「ぬ」+係助詞「か」+終助詞「も」 |
| さきやまに[佐紀山尓] |
| さけるさくらの[開有櫻之] |
| る[助動詞・り] |
[完了・連体形]~ている・~てしまった |
已然形につく |
| はなのみゆべく[花乃可見] |
| みゆ[見ゆ] |
「自ヤ下二・終止形」目に映る・見える・見ることができる |
| べく[助動詞・べし] |
[推量・連用形]~そうだ・~がよい・~ことができよう |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [みかさのやまに] |
春日山の西に連なる一峯、標高293メートル
三笠山に出る月を詠んだ歌は多い(左頁・1299)
和田嘉寿男「三笠の月、春日の月」(『万葉・その後』犬養孝博士古稀記念論集)には、
三笠山を春日山を含めた総称とするが、通説では現在の御蓋山だとする |
| |
| [さきやまに] |
「佐紀山」は、『万葉集』中では、この歌にだけ詠われる
他には、「佐紀沼」、「佐紀沢」、「佐紀野」などの名称がみられる
「佐紀」の地は、現在の佐紀町を中心に東は「佐保」に接し、
西は西大寺辺りまで及んでいたらしい
まさに平城京跡の北方とされる
|
| |
| [べく] |
この助動詞「べし」が連用形「べく」で終っている
連用形の「対偶中止法」かとも思った
それは、二つの文節が対等の関係にあるとき
下の対等語の打消・受身などの意味が上の対等語に及び
上の対等語が連用形の中止法をとることがある、
という古語辞典の説明で、合うのかな、と
しかし、この歌の場合、連用形の中止は下の対等語だから、合わない
さらに古語辞典を引いていると、「倒置法」にその手掛かりを見つけた
-(略)-短歌など韻文では、この倒置法が感情をこめた強調の表現として、
非常によく用いられる
文脈を捉える点では、語順を変えてみると明確になるが、
現代語に置き換える場合には、原文の語順を生かすようにする
例歌として、『古今集』の二首が載っていた
| これさだのみこの家の歌合によめる |
| つきみれば ちゞにものこそ かなしけれ わがみひとつの あきにはあらねど |
月を見ると、心が様々に乱れてもの悲しく感じることだ
自分一人だけに訪れてきた秋ではないのだけれど |
| 古今集巻第四 193 秋歌上 大江千里 |
| |
| 冬の歌とてよめる歌 |
| やまざとは ふゆぞさびしさ まさりける ひとめもくさも かれぬとおもへば |
山里は(都と違って、特に)冬が寂しさがまさって感じられることだ
人の訪れも絶え、草も枯れてしまうと思うと |
| 古今集巻第六 315 冬歌歌 源宗于朝臣 |
この例のように、掲題歌を解釈すれば、どうなるのだろう
旋頭歌下三句が、上三句と倒置されているのが解る
結句の「はなのみゆべく」は、「つきもいでぬかも」に修飾している
「花が見えるように、月が出てくれないかなあ」と通常文になるのを
歌の感情表現で、倒置する
「月が出てくれないかなあ、花が見えるように」と
そして、この連用形「べく」は、連用形の「名詞法」で「~もの」のようになり
「月が出る」に繋がると思う...
拙い私の解釈だけど、手持ちの資料からは、こんな推測しかできなかった
|
| |
|
 |

| 「しらゆきのつねしくふゆ」...すぎにけらしも... |
|
|
|
| 【歌意1892】 |
白雪が、いつも降り敷く冬も
やっと過ぎ去ったようだなあ
春霞のたなびく野辺に、
さらにうぐいすの鳴き声も聞こえてくるので... |
冬は、一面に白い雪景色
降り続く白雪に覆われ...
普段、作者のいるところは、そんな冬の景観を見せるところなのだろう
比較的に山あいにあり、冬は冬で、その景観を楽しむ
そして、そんな「冬」も...過ぎ去ってしまったようだ
野辺には、「春霞」がたなびいている
のみならず、うぐいすの鳴き声までも聞こえるではないか
春の訪れ...
現代では、冬が去り、春の訪れを実感する景物とはなんだろう
春も深まった、と思えばいきない「季節外れ」の雪が舞うこともある
昔ほど、こうした自然の風物による「季節感」を思わなくなったのも事実だ
学校など、新しい年度を迎えるのに、「春の陽気さ」を開始の時期にするのも
案外、それが「春」の実感になっているのかもしれない
すべてが、「さあ、今から始まるぞ」というように...
|
| |
| |
 |
掲載日:2014.01.25.
| 春雑歌 旋頭歌 |
| 白雪之 常敷冬者 過去家良霜 春霞 田菜引野邊之 鴬鳴焉 |
| 白雪の常敷く冬は過ぎにけらしも春霞たなびく野辺の鴬鳴くも |
しらゆきの つねしくふゆは すぎにけらしも
はるかすみ たなびくのへの うぐひすなくも |
| 巻第十 1892 春雑歌 旋頭歌 作者不詳 |
| 【1892】語義 |
意味・活用・接続 |
| しらゆきの[白雪之] |
| つねしくふゆは[常敷冬者] |
| つね[常・恒] |
同じ状態にあること・変わらないこと・いつも・ふだん |
| しく[敷く・領く] |
[自カ四・連体形]一面に広がる・一面に散らばる・重なる |
| すぎにけらしも[過去家良霜] |
| に[助動詞・ぬ] |
[完了・連用形]~てしまった・~てしまう |
連用形につく |
| けらし[助動詞・けらし] |
[過去推定・終止形]~たらしい |
連用形につく |
| 〔成立〕過去の助動詞「けり」の連体形「ける」+推定の助動詞「らし」、「けるらし」の転 |
| も[終助詞] |
[感動・詠嘆]~よ・~なあ |
| 〔接続〕文末、文節末の種々の語につく |
| はるかすみ[春霞] |
| たなびくのへの[田菜引野邊之] |
| の[格助詞] |
[所在]~の・~で |
体言につく |
| うぐひすなくも[鴬鳴焉] |
| も[終助詞] |
「感動・詠嘆」~よ・~なあ |
| 〔接続〕文末、文節末の種々の語につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [たなひくのへの] |
この語句の異訓は少なく、『萬葉集』〔桜楓社、昭和55年補訂版〕が、
「たなひくのへに」としているくらいだと思う
格助詞「に」も、空間的な位置を表す助詞なので、この歌の場合でも意味は同じだが
歌として詠まれるときの「の」と「に」の違いを思うことがある
「の」は、いかにも「歌」のための婉曲的な言い回しを感じることが出来るが
「に」では、他の用例ではともかく、「位置」の用例においては
どこか直截的で、会話中の普段の言葉のように響いてしまう
勿論、それは私の感じ方の浅いところだろうが、私は「の」の方がいい |
| |
| [うぐひすなくも] |
原文「鴬鳴焉」には、幾つかの異訓がある
| 原文「鴬鳴焉」 |
注釈書 |
| うぐひすなきつ |
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| うぐひすなくを |
『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕 |
| うぐひすなきぬ |
『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕
『万葉集総釈』〔楽浪書院、昭和10~11年成〕
|
さらに、多くの注釈書では、この「焉」を「助辞」としている
「助辞の焉」とは、どんな意味なのだろう
調べてみたら、漢文の文末に語調を整えるために添えられた文字のことらしい
一部の例を除けば、ほとんど「訓読」されることもない「文字」のことだ
「焉」そのものには、どんな意味があるのか...
音では「エン」、訓では、「いずくんぞ・なんぞ」など
確かに、漢文でしか訓むことのない「訓」なのだが
『万葉集』では二十八首に、この「焉」が使われているが
その殆どが、文末や文節末にあって、確かに「訓」らしきものはない
私には、精確なことは解らないが、一部「漢文調」の表現の中で、
確かに「訓」のあるものもあった、たとえば「ぞ」と訓むように...
でも、殆どは「訓」まない
だから、この歌の「焉」も、いわゆる「助辞」として、たんに語調を整える、ことか
いずれにしても、このことと、「異訓」は関係なさそうだ
ついでに、定訓の終助詞「も」でない上表の解釈でもしてみよう
| なきつ 〔完了の助動詞「つ」の終止形〕 |
鳴いてしまった |
| なくを 〔順接の接続助詞「を」〕 |
鳴いているので |
| なきぬ 〔完了の助動詞「ぬ」の終止形〕 |
鳴いてしまった |
私の未熟な解釈では、この程度なのだが
「なくを」であれば、この歌全体にも沿うような気もする
歌本来の持つ歌意では、下三句を事実として、上三句が推定されるのだから
この訓として、訳すのにはいいと思う
実際、このような歌意を本質としながらも、
その訓を感嘆の終助詞「も」としているため、中途半端な歌意が目立っていると思う
|
| |
|
|
| 【歌意1893】 |
家の前庭の毛桃の木の下に、
月明かりがさす
内心思っていたことが...喜ばしいことなのだが...
何となく不安もあって、このころは... |
この歌、結構有名らしい
「譬喩歌」とされているからには、何がどんな「譬」なのか
それを巡っての説が、多いという
少し紹介をしておく
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕は、
「上は下心といはん序なから、花の下の月はよろしきなり、その花の下のよろしきをわが下心(に)よき響きとせり」
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕は、上三句を序として
「シタニ、シタゴコロと音を繰返す表現をねらったのであらう」
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕は、
「春夜の佳景に接して、平常の鬱挹を散じた趣に歌っている」
『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕は、
「柔らかな和毛におほわれた桃の球が、月の光にくっきりと浮びあがってゐる。その美しい庭の眺めを、そのまま取り用ゐて譬喩としたもので、豊かな実をふくよかな少女の肉体に比してゐるのであらう」
この解釈は、『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕も支持している
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕は、
「この頃は、以前とは違って内心気持ちがよいというのが全体である」とし、上三句は、
「その気分の前に展けてゐる景で、それも同じく気分よく感じられるといふ範囲のものである」
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕は、この説が最も穏やかな解とする
もっとも具体的な説として、『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕では、
上三句を「娘の初潮を寓したものか」といい、「自分の娘が一人前になって、母としてこのごろ嬉しくて仕方がない」と、表面的な歌意の寓意として付け加えている
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕も、同じ解釈になっている
右頁の「注記」にも書いたように
『万葉集玉の小琴』〔本居宣長、安永八年(1779)成〕は、
第四句の「下心吉」を、本居宣長は「下心苦」の誤りと見て、「したなやましも」と訓む
岩波の『大系』によれば、宣長は「うたて」の意味を、悪い方の解釈に採ったものだとしている
そして、「うたて」の『万葉集』での用例は、「しきりに」くらいのもので、
必ずしも悪いことの場合に限らない、としている
確かに、誤字説を前提とした説には、無条件で賛同はできないが
岩波『大系』がいうような、「うたて」の解釈は、断定できないと思う
何故なら、宣長のいうような「気持ち」もあるからこそ、「譬喩歌」として
「したこころよし うたてこのころ」に、複雑な想いも込められているのではないか、と
母親が作者とすれば、『大系』のように素直に解釈もなるだろうし
父親が、あるいはそれに近い立場の「男」が作者であれば、「複雑な心境」でもある
私の上記の「歌意」は、そんな「男」の気持ちを基にして感じたものだ
この歌では、「毛桃」が、おそらく「少女」のことを言うものだろうが
「毛桃」を同じ譬で、「恋占い」のように用いた歌がある
| 譬喩歌寄木 |
| 波之吉也思 吾家乃毛桃 本繁 花耳開而 不成在目八方 |
| はしきやし我家の毛桃本茂み花のみ咲きてならざらめやも |
| はしきやし わぎへのけもも もとしげみ はなのみさきて ならざらめやも |
| 巻第七 1362 譬喩歌 寄木 作者不詳 |
〔語義〕
「はしきやし」は、「はしけやし」ともいい、「愛(は)し」(いとおしい)と思う意から、
「愛惜・嘆息・追慕」などの感動を表す
「ああ・ああ、いとしい・ああ、かわいそう・ああ、なつかしい」など
「もとしげみ」の「もとしげ(し)」は、根元の近くから出た小枝が多いことで、
接尾語「み」は形容詞「しげし」の語幹「しげ」について、原因・理由を表す
「~ので・~から」
「ざらめやも」は、打消の助動詞「ず」の未然形「ざら」に、
推量の助動詞「む」の已然形「め」+疑問の係助詞「やも」の反語表現 |
〔歌意〕
いとしい我家の毛桃は、
根元からの小枝が多く茂っているので
花だけ咲いて、実はならないなどということがあろうか... |
| |
| 譬喩歌 |
| 日本之 室原乃毛桃 本繁 言大王物乎 不成不止 |
| 大和の室生の毛桃本繁く言ひてしものをならずはやまじ |
| やまとの むろふのけもも もとしげく いひてしものを ならずはやまじ |
| 右一首寄菓喩思 |
| 巻第十一 2845 譬喩歌 作者不詳 |
〔語義〕
「むろふ」は、奈良県宇陀郡室生
「いひてし」は、「言ふ」の連用形「言ひ」に、
完了の助動詞「つ」の連用形「て」+過去の助動詞「き」の連体形「し」
「を」は軽い確定の順接を表す接続助詞「を」で、「~ので」
「ならずはやまじ」は、実を結ぶ意の「成る」と打消しの助動詞「ず」、
「は」は接続助詞「ば」に同じで、打消しの助動詞「ず」に接続する場合は「は」になる
「じ」は、打消しの推量・意志の助動詞「じ」の終止形
従って、「やまじ」は、「止むまい・終るまい」の意で強い意志を表している |
〔歌意〕
やまとの室生の毛桃の幹に、枝が多く茂りように、
それほど頻繁に言い寄ったので
この恋は必ずや成就させずにはいられない |
この「毛桃」が、「いとしい娘」であることは、充分伺える
「もとしげく」とは、それほど障害が多いということなのだろう
作者の想いが、娘に届かないとしたら、それは実を結ばないことになる
今日の掲題歌とは、「毛桃」の扱い方においては、表現の深さが違う
掲題歌は、「毛桃」にさす「月明かり」が発端で重要であるのにくらべ
この二首は、「毛桃」そのものの「実」、つまり「恋の実」の「成否」を言う
しかし、いずれも「毛桃」が、「いとしい娘」であることには、変わりはない
|
| |
|
掲載日:2014.01.26.
| 春雑歌 譬喩歌 |
| 吾屋前之 毛桃之下尓 月夜指 下心吉 菟楯頃者 |
| 我が宿の毛桃の下に月夜さし下心よしうたてこのころ |
| わがやどの けもものしたに つくよさし したこころよし うたてこのころ |
| 巻第十 1893 春雑歌 譬喩歌 作者不詳 |
【左頁・毛桃】〔1362・2845〕
| 【1893】語義 |
意味・活用・接続 |
| わがやどの[吾屋前之]我が家の庭 (屋前は、前庭もしくは家の前と訳したい) |
| けもものしたに[毛桃之下尓] |
| けもも[毛桃] |
バラ科の落葉小高木 |
| つくよさし[月夜指] |
| つくよ[月夜] |
月の光 |
| さし[射す・指す・差す] |
[自サ四・連用形]光が照り入る |
| したこころよし[菟楯項者] |
| したこころ[下心] |
心中の秘めた思い・内心・かねてのたくらみ |
| よし[好し・善し・良し] |
[形ク・終止形]快い・楽しい・好ましい・縁起がよい |
| うたてこのころ[菟楯頃者] |
| うたて[転(うたた)の転] |
[副詞]ますます・ひどく・いやになるほど |
| このころ[此の頃] |
(後、このごろ)近頃・近いうち・間もなく・今頃・今時分 |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [けもも] |
「毛桃」は、中国原産ともいうが、日本自生のものもあったらしい
春、桜に先駆けて淡紅色または白色の五弁の花を開く
夏に果実を結び、縄文時代から食用に供せられていたという
『万葉集』中での表記では、「桃の木一首」「毛桃三首」「桃の花一首」〔万葉の植物Ⅰ〕
以上に六首あり、他に題詞に見える「桃の花一首」
「毛桃」の掲題歌の他の二首〔1362・2845〕は、
その実を結ぶか否かを、恋の成否の譬喩として詠っている〔左頁〕
前川文夫「日本人と植物」に、
毛桃は、果実の表面にうぶ毛が一面にあることからの称で、大陸から渡来した品種という |
| |
| [けもものしたに 異訓] |
原文「毛桃之下尓」の異訓は、手持ちの諸注では、一書だけ見える
『萬葉集』〔桜楓社、昭和55年補訂版〕が、「けものがしたに」としている
この「が」は、格助詞の連体修飾語であり、同じ用法の「の」と同義だと思う
これも、他の同種の異訓のように、作者の原語を知り得ない以上
あとは、和歌としての「響き方」になるだろう
|
| |
| [したこころよし 異訓] |
ただ、一説だけ異を唱える説があった
『万葉集玉の小琴』〔本居宣長、安永八年(1779)成〕で、「したなやましも」とする
これに倣ったのが、『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
| [うたて] |
副詞「うたて」は、同じく副詞の「うたた」から転じた語で、
程度が進み過ぎて異常なさまに対する不快感から、
「異様に・気味悪く・不快に・情けなく・嘆かわしく」などの意が強い
「うたた」の語形は「うたうた」が詰まったもので、
更にそれが「うたて」に転じたとされる
|
| |
|


|
| 【歌意1894】 |
春山では、鶯たちが、友と鳴く鳴く別れるように
私たちも、泣き泣き別れるのですね
どうか、お帰りになる間も、
忘れないで想っていてください、私のことを |
相聞の歌には、多くの別れを詠うものが多い
またすぐに逢えるのに、ほんの少しの間も、別れが惜しい
そんな激しい想いをこめる歌など、
その想いの一途さが伝わるものだが
この歌は、感覚的には本当の「別れ」の歌のように思う
「泣き泣き別れる」とした表現に、その悲しみをこめ
読み終ったあとも、その余韻が残る
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕の解釈では、
「妻を求めて鳴く鶯のように、泣き別れて」としているが、
この「友鶯」と「鳴別」に、切なさが感じられない
他の「友鶯」の解釈では、「鶯たち」が、「鳴きながら友と別れる」ことを
次の「鳴別」で、恋人同士が「泣き泣き別れる」ことを教えてくれるが
『講談社』だと、妻を求めるために、友と別れる鶯と思えてしまう
その受止め方が間違いでなければ、この歌は下二句には繋がらない、と思う
|
| |
 |
掲載日:2014.01.27.
| 春相聞 |
| 春山 友鴬 鳴別 眷益間 思御吾 |
| 春山の友鴬の泣き別れ帰ります間も思ほせ我れを |
| はるやまの ともうぐひすの なきわかれ かへりますまも おもほせわれを |
| (右柿本朝臣人麻呂歌集出) |
| 巻第十 1894 春相聞 柿本人麻呂歌集 |
| 【1894】語義 |
意味・活用・接続 |
| はるやまの[春山] |
| ともうぐひすの[友鴬] |
| なきわかれ[鳴別]泣き泣き別れる |
| かへりますまも[眷益間] |
| ます[座す・坐す] |
[補助動詞サ変・連体形](動詞の連用形について)尊敬の意を表す
「お~になる・~て(で)いらっしゃる」 |
| 〔参考〕おもに上代に用いられ、中古以降は和歌にのみ見られる |
| ま[間] |
(時間的に)あいだ・ひま |
| も[係助詞] |
[並列]~も (言外のある事情と並列的に述べる) |
| 〔接続〕名詞、助詞、用言や助動詞の連体形・連用形など、種々の語につく |
| おもほせわれを[思御吾] |
| おもほせ[思ほす] |
[他サ四・命令形]「思ふ」の尊敬語・お思いになる |
〔成立〕四段「思ふ」の未然形「おもは」に、上代の尊敬の助動詞「す」で「おもはす」
その「おもはす」の転じたもの |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [はるやまの ともうぐひす] |
この原文「春山友鶯」も、定説となるまでの原文は、「春日野犬鶯」だった
多くの諸本(『紀州本』『西本願寺本』『大矢本』『細井本』『京都大学本』など)が、
「春日野犬鶯」としているのを、『類聚古集』に「春山野友鶯」」とあり、
そこから改稿説がとられ、今の通説に繋がる
旧訓では「かすかのに いぬるうくひす」と訓む
もともとは「春山」とあったのに、「野」が加えられ、
それが更に後に「春日野」と改められた、とする説による
従って、『類聚古集』の姿勢を、本来の表記だと、現在では通している
しかし、「友鶯」もまた、誤字説が多い
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕が、「本居宣長説」を所引し、
「犬は友の誤」といい、『類聚古集』説が定着したようだ
確かに、底本の「犬」に拘り、「いぬるうぐひす」との旧訓は、今では通らないが
「犬」を「哭」の誤りとする説もある
「犬」を「友」の誤りとするより、「哭」の誤りとした方が、あるいは妥当かと思う
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕が、「なけるうぐひす」
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕が、「なくうぐひすの」とする
「はるやまの」も「かすがのの」も、一応「場所」を示めすものなので
その違いの「質」は、気にならないが、
「友」と「犬(哭)」では、解釈も違ってくる
「友鶯」は、「鶯の連れ」の意味合いであり、
「犬(哭)鶯」は、「鳴いている鶯」が、次の句の「鳴く鳴く別れ」に滑らかに繋がる
仮に「犬」を誤字とするのなら、私は「友」より「哭」の方が可能性があると思う
勿論、「いぬる」も本来の語義解釈ですれば、
自動詞ナ変「往(い)ぬ」の連体形「いぬる」で、おかしくはないが...
「いぬるうぐひす」、殆どの学者たちは、この解釈を捨ててしまった
|
| |
| [眷益間] |
原文「眷益間」の「眷益(かへります)」は、「帰る」の敬語だが
「眷」を「かへる」と訓むのは、『名義抄』に「眷」を「かへりみる」とされている
なお、底本には「春眷」とあるのを、『細井本』などが「春」を消した、とある |
| |
| [思御] |
原文「思御」は、「御念」と同じ意味の表記で、敬語表現を示めした表記
|
| |
|
|
| 【歌意1895】 |
冬が終り、春に咲く花を
私は手に折って持ち、心に思います
幾度も幾度も命の果てるまで繰り返し
あなたのことを、恋い続けることでしょう |
相聞の歌に相応しい一途な想いが、「命の限り」と私に訓ませるほど...切ない歌だ
人麻呂歌集の歌なので、本人なのか採録した古歌なのか解りようもないが
私には「女歌」としてしか感じられない
どの注釈書でも、「男歌」として歌意を添えている
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕が、「春咲く花」を「女」の比喩とし
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕は、「その花のようなあの人」という
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕も、「花のような人」と解している
だから、春に咲く花を「手折り持つ」男が、幾度も幾度も繰り返し想い続ける
中には、右頁の「注記」でも書いたように、すでに手に入れた「女」とする書も...
私には、女が遠目でしか逢うことのない男に対する「想い」のような気がする
「ふゆごもり」が、冬の雪や寒さに閉ざされた場景と想いを思わせ
そして春になって、やっと花を「手折る」ことが出来た
「花」を「女性」と見立て、男歌と解釈するのだろうが
右の「注記」に引いたように、『新全集』の「手折り持ち」を察するなら
何も「花は女性」の喩えにすることもない
相手のことを偲ぶ、一つの行為なのかもしれない
男歌であろうが、女歌であろうが
異性を想う「作者」の、「距離」があるからこその「一途な想い」なのではないか、と思う
|
| |


|
掲載日:2014.01.28.
| 春相聞 |
| 冬隠 春開花 手折以 千遍限 戀渡鴨 |
| 冬こもり春咲く花を手折り持ち千たびの限り恋ひわたるかも |
| ふゆこもり はるさくはなを たをりもち ちたびのかぎり こひわたるかも |
| (右柿本朝臣人麻呂歌集出) |
| 巻第十 1895 春相聞 柿本人麻呂歌集 |
【注記】〔2375・2394・606〕
| 【1895】語義 |
意味・活用・接続 |
| ふゆこもり[冬隠]〔枕詞〕「春」にかかる |
| はるさくはなを[春開花] |
| たをりもち[手折以] |
| たをり[手折る] |
[他ラ四・連用形]手で折る |
| もち[持つ] |
[他タ四・連用形]手に持つ・身につける・所有する・心に思う |
| ちたびのかぎり[千遍限] |
| ちたび[千度] |
多くの・幾度も幾度も、を意味する表現 |
| かぎり[限り] |
限度・限界・最大限・極限・はて・(命の)終り |
| こひわたるかも[戀渡鴨] |
| わたる[渡る] |
[自ラ四・連体形](動詞の連用形について)ずっと~続ける |
| かも[終助詞] |
[詠嘆・感動]~であることよ |
連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [たをりもち] |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕では、
「冬隠春開花トハ、待々テヨキ程ニナレル人ニ喩ふ。手折以ハ、ソレヲ云ヒ靡ケテ我手ニ入ルルニ喩フ」とし、第四句の「千度の限り恋ひ渡るかも」で、すでに「我が手に入」れた女に対する思いという
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕でも、それに近い解釈だ
そこでは、「花を手折ることが女性と契る比喩になることが多い」と言っている
しかし、この歌は果たしてそうだろうか
私が抱いた感想では、第四句の「ちたびのかぎり」というのが、どうしても気にかかる
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕の「補注」では、
「たをりもち」は、相手を偲びながらの手すさびのわざ、とある
「てすさび(手遊び)」とは、手でする慰み、手慰み、と古語辞典にあるが
相手を偲びながら、とはどんな情況なのだろう
相手を「思い慕いながら」する、無意識の行為なのだろうか...心ここにあらず、と
|
| |
| [ちたびのかぎり] |
原文「千遍限」の「千遍」の表現は、『万葉集』中に十五例ある
うち、長歌一首を含めて、「ちたび」と訓じられるのが「十三首」
残り二首は、その歌意から「ちへ(千重)」と訓じられ、異訓もない
しかし、その「ちたび」の「かぎり」と言う表現は、この歌一首しかない
「限り」の持つ意味は、限界まで、や極限のような最大級の「程度」を言うもので
「ちたびのかぎり」の、その凄まじい「恋心」を感じずにはいられない
ならば、古語辞典に載るように、「(命の)終り」の意味合いも捨て難いものだろう
この「かぎり」が伴わない「千遍(ちたび・ちへ)」は他の歌から推測できる
| 正述心緒 |
| 心 千遍雖念 人不云 吾戀□ 見依鴨 □=女偏に「麗」 |
| 心には千重に思へど人に言はぬ我が恋妻を見むよしもがも |
| こころには ちへにおもへど ひとにいはぬ あがこひづまを みむよしもがも |
| 巻第十一 2375 正述心緒 柿本人麻呂歌集 |
〔語義〕
「こひづま」は、恋しく想う「女性」という |
〔歌意〕
心では、幾度も幾度も想うのだが、
人には言わない、この恋心
それほど愛しい私の「恋妻」に、逢える方法があればなあ |
| |
| 戀為 死為物 有者 我身千遍 死反 |
| 恋するに死するものにあらませば我が身は千たび死にかへらまし |
| こひするに しにするものに あらませば あがみはちたび しにかへらまし |
| (以前一百四十九首柿本朝臣人麻呂之歌集出) |
| 既述〔書庫-6、2013年5月5日〕巻第十一 2394 正述心緒 柿本人麻呂歌集 |
〔歌意〕(2013年5月5日時点そのまま)
恋すれば、死ぬものだと決まっていたら
私は、千度も繰り返し死んでいよう |
| [類歌] |
| 相聞/(笠女郎贈大伴宿祢家持歌廿四首) |
| 念西 死為物尓 有麻世波 千遍曽吾者 死變益 |
| 思ふにし死にするものにあらませば千たびぞ我れは死にかへらまし |
| おもひにし しにするものに あらませば ちたびぞわれは しにかへらまし |
| 既述〔書庫-6、2013年5月5日〕巻第四 606 相聞 笠女郎 |
〔歌意〕(2013年5月5日時点そのまま)
想うだけで、想うことが「死」ぬ、ということであるのなら
私は千度も繰り返し、繰り返し死んでいるのですね |
確かに、「何度も何度も」という表現は、切羽詰った想いには違いない
こうした例の「千遍」は、単に頻繁に、という「多さ」を表現するに留まる
しかし、この「千遍」に、「限り」がつくと
それは最大限の「切羽詰った想い」だと思う
であれば、多くの注釈書で訳されるような、「おだやか」な「多さ」だけではなく
まさに、「命果てても」、と思いたいものだ
ちなみに、「柿本人麻呂歌集」の〔2394〕と、「笠女郎」の〔606〕は
類想は勿論のこと、その語句までもほとんど同じだ
大きな違いと言えば、第四句「あがみちはちたび」と「ちたびぞわれは」
この語順の入れ替えが、〔2394〕の本歌を知る「笠女郎」の知性を伺わせる
|
| |
|
|

| 「きりにまとへるわれ」...うぐひすにまさり... |
|
|
|
| 【歌意1896】 |
春山の霧に、閉じ込められ迷う鶯でも
私以上に物思いなど、思い悩むことあるだろうか... |
「霧」に方向を見失う「鶯」
作者の、思い悩む姿に重ねて、なおかつ、それでもお前は、まだ「抜け出せる」ではないか
そんな自身の「深い霧」を詠う
通常「霧」が詠われるのは、秋と言われるが、それがまだ定着していない頃の歌だ、とされる
しかし、その一方で、「春の霧」にも、何かを暗示させるものがある、と思う
「秋の霧」に同じような歌を詠じたら、それは「霧」そのものが単独で映像化される
それが「春の霧」であれば、思いがけずにこんな目にあって、と落胆の気分も醸し出す
「霧」に閉じ込められ、いっときは方向を見失う鶯も
やがて、求める方向に飛び去って行くのだろう
しかし、自分にはそれが出来ない
どこへ向おうにも、この「春の霧」では、何も「見えない」
そのうちには、自分が向おうとしている先も、さらに「向おうとしている」ことさへも
自覚できなくなってしまいそうな歌だ
自分の恋の深さを、何かに比較して表現しようとするのは、『万葉集』の特徴と言うが
それに応えて、この歌を読み直せば、
その比較されるのは、「霧に方向を見失った鶯」ということになる
そして、その鶯は、やがて自由に飛び去れる「鳥」
その意味では、比較の「深さ」を競うのは物足りない
この歌を、もっと自分に深めるのは、やはり「春の霧」だろう
「鶯」は、その「春の霧」に添えられる「春の鳥」
作者が実際にどう感じて詠ったものか、解らないが
私が、この歌で共感を受けるのは...「思いがけず恋に悩む自身の姿」を詠っている
そう感じてしまう |
| |
 |
掲載日:2014.01.29.
| 春相聞 |
| 春山 霧惑在 鴬 我益 物念哉 |
| 春山の霧に惑へる鴬も我れにまさりて物思はめや |
| はるやまの きりにまとへる うぐひすも われにまさりて ものおもはめや |
| (右柿本朝臣人麻呂歌集出) |
| 巻第十 1896 春相聞 柿本人麻呂歌集 |
| 【1896】語義 |
意味・活用・接続 |
| はるやまの[春山] |
| きりにまとへる[霧惑在] |
| まとへ[惑ふ] |
[自ハ四・已然形]心が乱れる・迷う・途方にくれる・分別を失う |
| る[助動詞・り] |
[完了・連体形]~ている・~てしまった |
已然形につく |
| うぐひすも[鴬] |
| われにまさりて[我益] |
| まさり[勝る・優る] |
[自ラ四・連用形]すぐれる・ひいでる・ |
| [増る] |
(数量や程度が)ふえる・強まる |
| ものおもはめや[物念哉] |
| ものおもは[物思ふ] |
[自ハ四・未然形]思い悩む・思いに耽る (「ものもふ」ともいう) |
| め[助動詞・む] |
[推量・已然形]疑問の助詞「や」がついて反語になる |
| |
~だろうか(いや、~ないだろう) |
未然形につく |
| や[終助詞] |
[反語]~だろうか(いや、~でない) |
| 〔参考〕推量の助動詞「む・らむ」の已然形・終止形について、反語表現となる |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [ものおもはめや] |
この原文には、異訓が多い
掲題の訓は、旧訓とされているものだが
その他の訓も含めて、下表にする
| 原文「物念哉」 |
注釈書 |
| ものおもはめや |
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕
|
| ものおもはめやも |
『萬葉集本文篇』〔塙書房・佐竹昭広、昭和38年成〕
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕 |
| ものもはめやも |
『萬葉集』〔桜楓社、昭和55年補訂版〕
『万葉集』〔伊藤博校注、角川ソフィア文庫、平成10年18版〕 |
| ものおもふらめや |
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕 |
この巻の『柿本人麻呂歌集』の「相聞」はすべて「略体歌」で、
原文「物念哉」に異訓が多いのは、なるほど、と思う
この歌に訓を付けるようになった後の時代の、「和歌」の影響も大きいことだろう
「ものおもふ」が、「ものもふ」とも言われていたことが通説なら
「ものおもはめや」も、「ものもはめやも」も同じようなもので
この歌が、作者はどう詠じたのか、今ではどんな研究成果であっても、推測でしかない
語調や音数で、どちらが「和歌」らしく響くか...それぞれの人の感じ方に拠るだろう
ただ、『新全集』の「訓」は、それ以外の書で助動詞「む」とするのを、
同じ推量でも、現在推量の助動詞「らむ」の已然形「らめ」とし、
以下疑問の助詞「や」がついて反語としている
現在においての推量、ということで「~しているだろうか(いや、~ないだろう)」
この「らむ」は、終止形につくので、終止形「ものおもふ」となるが
字数からすれば、「ものもふらめや」に、何故しなかったのだろう
この『新全集』の「補注」では、『類聚古集』に、
「ものおもふらめや」とあるのに拠る、とある
このところだけを採り上げて判断するのは危険だが、では他の諸本は、何故駄目なのか
こうした採り上げ方、説明の仕方は、不充分だと思う
さらに、『後撰集』に見える「類想歌」として、
「あしひきの山したとよみ鳴く鳥もわがごとたえず物思ふらめや」(雑四・1300)をあげ
この第五句「物思ふらめや」も、それを支持する、とある
この「支持する」という意味は、『後撰集』でも、このような詠い方があるから、と
そんな意味なのだろうか
私には、『古今集』に次ぐ勅撰和歌集である『後撰集』のことは解らないが
少なくとも、この歌集は、10世紀の中頃に成立した、と言われる歌集であり
その頃の「歌風」が、『万葉歌』をすべて引き継いでいるならともかく
それは有り得ないので、『新全集』のいう「支持」の意味が、今の私には解らない
|
| |
|
|
| 【歌意1897】 |
家を出ると、いつも目の前に見えるあの丘
多くの枝を纏い茂って、咲いている花のように
実を結ばないではいられまい
必ず、その実を...この恋を成就させてみよう |
多くの説明にあるように、この歌は第四句までが結句への「序詞」という
まさに、結句の「ならずはやまじ」を、作者は「決意」している
この歌の前(1894~1896)までと併せ一連の作として、人の「恋心」を物語風に詠うものだ、と
そうかもしれない
別れがあって、永遠の想いがあって、深い霧に惑う「心」があって
そして、この歌で、大きな決意を詠う
そんな風に描けるのも、『柿本人麻呂歌集』という特殊な「歌集」の所以だろう
ただ、疑問も残る
この『万葉集』では、他の「歌集」からの出典される「歌」が
そのまま順番通りに掲載されているかどうか、だ
おそらく、『柿本人麻呂歌集』では、これらの歌が連作風には載っていないだろう
『万葉集』の編者が、意図的に配列したとも充分考えられることだ
連作と言うのであれば、当然同一人の作歌か、
もしくは、同じ席での「詠い合い」のようなものだろうが
その視点で見れば、とても同席もしくは同一人とは思えない
「歌意」を追えば、一人の「恋心」を物語風に作ることもできるだろうが...
あらかじめ知り得る「恋仲」でないかぎり、本来の「相聞」の遣り取りを
ここで見出すのは、難しいだろう
だから、この歌もまた、「恋歌の一首」として受止めたい
家の前の、いつもの丘に咲く花
決して見逃すことのない、その花は
まさに、いとしいあの人のこと
そして、やがて間違いなく実を成らすそれらの花のように
私は...私だって、この恋を必ず実らせてみせる |
| |
|
掲載日:2014.01.30.
| 春相聞 |
| 出見 向岡 本繁 開在花 不成不止 |
| 出でて見る向ひの岡に本茂く咲きたる花のならずはやまじ |
| いでてみる むかひのをかに もとしげく さきたるはなの ならずはやまじ |
| (右柿本朝臣人麻呂歌集出) |
| 巻第十 1897 春相聞 柿本人麻呂歌集 |
| 【1897】語義 |
意味・活用・接続 |
| いでてみる[出見] |
| いで[出づ] |
[自ダ下二・連用形]中から外に出る |
| て[接続助詞] |
[単純接続]~て・そして |
連用形につく |
| みる[見る] |
[他マ上一・終止形]目にとめる・眺める・目にする |
| むかひのをかに[向岡] |
| むかひ[向かひ] |
向かい合っていること・真正面・前方 |
| をか[丘・岡] |
土地の小高くなったところ・おか |
| もとしげく[本繁] |
| もと[本] |
根もと・原因・始まり |
| しげく[繁し・茂し] |
[形ク・連用形]量が多い・たくさんあること・茂っている |
| さきたるはなの[開在花] |
| たる[助動詞・たり] |
[完了・連体形]~た・~ている |
連用形につく |
| ならずはやまじ[不成不止] |
| なら[成る] |
[自ラ四・未然形]成就する・なる・変化する・成長する |
| ず[助動詞・ず] |
[打消・連用形]~ない |
| は[係助詞] |
[順接・仮定条件]~ならば |
連用形につく |
| 〔接続〕打消の助動詞「ず」について順接の仮定条件を表す・接続助詞「ば」と同じ |
| やま[止む] |
[自マ四・未然形]止る・絶える・物事が中止になる |
| じ[助動詞・じ] |
[打消の意志・終止形]~まい・~ないつもりだ |
未然形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [ならずはやまじ] |
この語句は、つい先日採り上げた〔2845〕(書庫-14、2014年1月26日)であり
その歌意もまた、「類想歌」として、この掲題歌に並ぶ
強い意志を持った言い方だ
似たような表現に「とらずはやまじ」、「いらずはやまじ」がある
| とらずはやまじ |
取らずにはおくものか |
巻第六 956 |
| 巻第七 1121 |
| 巻第七 1321 |
| いらずはやまじ |
入らずにいられようか |
巻第六 955 |
|
| |
|
|
| 【歌意1898】 |
霞の立つ春の、この長い一日を
ずっと想い続けて、まさに「恋い暮らし」
夜も更けてしまったのに...
いとしいあの人は、逢ってくれないのだろうか
逢って欲しいものだ |
昨日、私はこの巻の「春相聞」が〔1894〕から始まり
昨日の歌〔1897〕までの段階で、一連の「恋思い」の歌だと言われているようだ、と書いたが
どうも一般的には、〔1895~1898〕に、そんな説があるようだ
春相聞の最初の歌が入らないのは、「友鶯」としているからだろう、と思う
仮に、「犬鶯」あるいは「哭鶯」とすれば、その「恋心」は繋がってくる
でも、そもそも、一連の作歌とはあまり思いたくないので
今日も、この歌に集中したい
霞の立つ一日というだけで、何だかこの一日が「もやもや」としたすっきりしない
思い悩み、沈んだ気持ちの描写を受けるが、
春の「霞」では、それでも秋のような「感傷に耽る」ほどの重さはない
やはり、「はるのながひ」が、この切ない気持ちを浮き上がらせてくれる
そして、とうとう夜も更けてしまったのに
まだ、あの人と逢えないでいる
何とか、逢いたいものだ
他の注釈でいうように、夜も更けて、やっとあの人に逢えた
とする歓びよりも、未だに逢えない切なさが、
春霞のベールに包まれて、その「切なさ」を一層「もやもや」とした空間に誘い込んでくれる
この歌で感じられるもの、いや私が感じたいものは
春の優しい霞でさえも、自分の恋心を決して穏やかに包み込んではくれない
やはり、恋の辛さは...逢いたいと思うからこそ...これが、恋の辛さ、切なさなのか |
| |

 |
掲載日:2014.01.31.
| 春相聞 |
| 霞發 春永日 戀暮 夜深去 妹相鴨 |
| 霞立つ春の長日を恋ひ暮らし夜も更けゆくに妹も逢はぬかも |
| かすみたつ はるのながひを こひくらし よもふけゆくに いももあはぬかも |
| (右柿本朝臣人麻呂歌集出) |
| 巻第十 1898 春相聞 柿本人麻呂歌集 |
| 【1898】語義 |
意味・活用・接続 |
| かすみたつ[霞發]〔枕詞〕「春日」にかかる |
| かすみ[霞] |
微細な水滴が空中に浮遊して、空や遠方などがはっきり見えない様 |
| はるのながひを[春永日]日中の、長い春の一日の意 |
| こひくらし[戀暮]日中恋い続けて夕暮れを迎える意 |
| よもふけゆくに[夜深去] |
| ふけ[更く] |
[自カ下二・連用形](夜が)更ける・(季節が)深まる |
| ゆく[行く・往く] |
[自カ四・連体形]だんだん~ゆく |
| |
(動詞の連用形の下について、動作の継続・進行)の様 |
| に[接続助詞] |
[逆接]~けれども・~のに |
連体形につく |
| いももあはぬかも[妹相鴨] |
| も[係助詞] |
[強意](下に打消しの語を伴って)強める |
| 〔接続〕名詞、助詞、用言や助動詞の連体形と連用形など種々の語につく |
| ぬかも[上代語] |
(多く「~も~かも」の形で)願望の意を表す |
未然形につく |
| |
「~であって欲しいなあ・~ないかなあ」 |
| 〔成立〕打消の助動詞「ず」の連体形「ぬ」+係助詞「か」+終助詞「も」 |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、283語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
| [よもふけゆくに いももあはぬかも] |
略体歌の宿命といえるような、まさにこの第四、五句の「訓」
この異訓が、ざっと十例もある
内容が同じで、単に「訓」が違う、というのではなく
内容まで大幅に違ってきては、私など混乱してしまう
それぞれの「訓」で、歌意を想い、どちらが自分の気に入る[歌」になるか...
素人の、精一杯の関わり方だ
| 原文「夜深去」 |
諸本、諸注 |
| よもふけゆくに いももあはぬかも |
『日本古典文学全集』〔小学館、昭和50年成〕
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕
『萬葉集本文篇』塙書房・佐竹昭広、昭和38年成〕
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕
『万葉集』〔伊藤博校注・角川文庫、平成13年版〕
『萬葉集』〔桜楓社、昭和55年補訂版〕
|
| よのふけゆけば いもにあへるかも |
『紀州本・西本願寺本』他「旧訓」
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕
|
| よふかくゆきて いもにあへるかも |
『類聚古集・紀州本(左注)』 |
| よのふけぬれば いもがあへるかも |
『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
| よのふけぬれば いもにあへるかも |
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕 |
| よのふけぬるに いもにあへるかも |
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年〕 |
| よのふけゆきて いもにあへるかも |
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕
『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕
『万葉集総釈』〔楽浪書院、昭和10~11年成〕
『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
| よのふけゆかば いもにあはんかも |
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間成〕 |
| よもふけゆくを いもにあはぬかも |
『玉勝間』〔本居宣長随筆集、文化九年(1812)刊〕 |
| よふけてゆくに いももあはぬかも |
『新校万葉集』〔沢潟久孝・佐伯梅友、昭和11年成〕
尚、新版は『注釈』の訓によって改める |
「夜深去」の「訓」では、いずれも「夜が更ける」確定の事実だが
それが、「順接」か「逆接」かとなると、原文のこの「三文字」だけでは困難だ
略体歌の助詞(に・を・ば)表記は、ほとんどその表記がないので、
どうしても歌全体の歌意から逆に辿ることになる
その意味でも、結句の「妹相鴨」が、大きく意味、訓が分かれるのも頷ける
私が、掲題歌に採り上げた「よもふけゆくに いももあはぬかも」、
この「ゆくに」の「に」が「逆接」になるのは、結句で希求の「ぬかも」からくる
「夜も更けて行くのに、妹は逢ってくれないのかなあ、逢って欲しいものだ」
この場合の「かも」は、願望の終助詞になる
しかし、「よのふけゆけば いもにあへるかも」となると、
訳す上では、「夜も更けたので、妹に逢うことができた」という意味になる
「あへるかも」は、完了の助動詞「り」の連体形「る」に、詠嘆・感動の終助詞「かも」
確かに、逢えたことの感動、喜びを詠うものだ
このように、第四句の解釈と結句の解釈がリンクしているので
分けるとすれば、歌意はこの二例になると思う
尚、『万葉集』から約千首を載せている平安時代の私撰和歌集『古今和歌六帖』には、
| かすみたち なかきはるひを こひくらし よのふけゆけは いもにあへるかも |
| 古今和歌六帖 第五・雑思 2795 |
と、「旧訓」に倣って載せている
古い時代に、『万葉集』がいかに訓読されていたか、の手掛かりといえるようだが
少なくとも、その「古くから」と言うのが、
まさにこの時代に点けられた訓点のことだろう
だから、元の訓には違いないが、
『万葉集』に初めて訓が点けられた時代の『古今六帖』の所載歌なので、
それを引き合いに出すのも、おかしなことだが... |
| |
|
|
 |
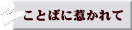  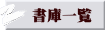  |












































