 |
| |
| |
| |
| |
| |
「たちばなの」...はなちるにはを...
|
| 『みむひとやたれ』 |
| 【歌意1972】 |
ホトトギスが来て、声を響かせて鳴いている
その庭で、鳴き声に唱和するように橘の花の散る風情を
一緒に見てくれる人は誰でしょう
あなたこそ、とお待ちしています |
|
| |
| |
解釈に二通り浮ぶ
意中の人に、この情緒ある景観を見せたい
何故なら、あなたこそこの風情を理解して、一緒に楽しんでくれるから...
そして、もう一つ考えられるのが
恋慕う気持ちとは関係なく、純粋にこの風情を解る人
せっかくの景観なのに、それを解せる人がいないものか
勿論、それが実現したら、その先には「恋慕う気持ち」が起こってくる予感は自覚している
このような微妙な気持ちの変化こそ、歌の言葉には出てこなくても
言外にその予感を思わせるこの一首だと思う
景観の視覚的な情景と、人の心ある姿を重ねて、動きある映像だけではなく
見えない「もの」を変化させ得る「本心」が詠われているのではないだろうか
初めから「意中の想い人」ではなく、今はどうなるか解らないが
あなたが、思いに違わぬ人であり、この景観に理解を見せる「心ある」人であるなら
それが「意中の人」として、
「それはあなたなんですよ」と、心に秘めているものかもしれない
あなたに、そうあって欲しい
そんなあなたを、恋慕うことができれば...
そうこの歌を詠める女性は、『全釈』の鴻巣盛広の言葉を借りれば
「言い方が上品」、と言っても過ぎることはないと思う
|
|
【赤人集 (三十六人集、撰藤原公任[966~1041])】
| 郭公なきてひゝかす橘の 花ちる山にすむ人やたれ |
| 私家集大成第一巻 新編増補[陽明文庫蔵「三十六人集」] 赤人Ⅲ 137 |
| ほとゝきすなきてひゝかはたちはなの はなちるやとにくる人やたれ |
私家集大成第一巻6 [書陵部蔵「三十六人集」) 赤人Ⅱ 125
|
| ほとゝきすなきてひゝかはたちはなの はなちるやとにくる人やたれ |
私家集大成第一巻5 [西本願寺蔵「三十六人集」] 赤人Ⅰ 245
|
【夫木和歌抄 (延慶三年頃[1310年頃]、撰勝間田長清)】
| ほととぎすなきとよむなるたちばなのはなちるさとをみん人もがな |
国歌大観第ニ巻16 巻第七 夏部一 橘 2671 従二位行家
|
【家持集 (三十六人集、撰藤原公任[966~1041])】
| ほとゝきすきなきとよむるたちはなの 花ちるにはをみる人もかな |
私家集大成第一巻 7 [西本願寺蔵三十六人集] 家持Ⅰ 夏歌 91
|
| ほとゝきすなきとよむなるたちはなの はなちるさとをみん人もかな |
私家集大成第一巻 8 [冷泉家時雨亭叢書『資経本私家集一』] 家持Ⅱ 夏歌 83
|
| ほととぎすなきとよむなるたちばなのはなちるさとをみん人もがな |
国歌大観第三巻 3 家持集[書陵部蔵五一〇・一二] 夏歌 83
|
|
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1972] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔ほとゝきすきなきとよますたちはなのはなちるにはを見ん人ひとやたれ 〕
霍公鳥來鳴響 之花散庭乎将見人八孰
|
| ほとゝきすきなき 郭公鳴橘ちる庭を心ありてみん人は誰ならんと也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
| |
霍公鳥來鳴響橘之花散庭乎將見人八孰
〔ホトヽキスキナキトヨマスタチハナノハナチルニハヲミムヒトヤタレ〕 |
| 落句の落著は君にこそあれなり、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
霍公鳥來鳴響橘之花散庭乎將見入八孰
〔ほとゝぎす、きなきならせる、たちばなの、はなちるにはを、みん人やたれ 〕 |
| 郭公も馴れきて、鳴きならして橘を散らせる此面白き庭を誰が來て見ん、來て見る人もがなと願ふ意也。心あらん人は來ても見よかしとの意をこめて也。又心ありて來て見はやさむ人は誰なるらんとの意にも見る也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
霍公鳥、來鳴響[キナキトヨマス]、橘之、花散庭乎、將見[ミム]人八熟[タレ]、 こはたれかはある君ならずしてはといふなり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
| |
霍公鳥。來鳴響。橘之。花散庭乎。將見入八孰。
〔ほととぎす。きなきとよもす。たちばなの。はなちるにはを。みむひとやたれ。 〕 |
橋の花散る庭を、君こそは來ても見るべき人なれと言ふなり。
參考 ○來鳴響(新)キナキトヨモシ。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔ホトヽギス。キナキトヨモス。タチバナノ。ハナチルニハヲ。ミムヒトヤタレ。〕
霍公鳥來鳴響橘之花散庭乎將見人八孰
|
歌(ノ)意は、霍公鳥の來鳴とよもすにつれて、橘花のちる庭の興あるさまを、來て見む人や孰なるぞ、君こそ來て見べき其(ノ)人なれとなり、
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔ほととぎす來なき響[トヨモシ]たちばなの花ちる庭を見む人やたれ 〕
霍公鳥來鳴響橘之花散庭乎將見人八孰 |
| 略解古義に第二句をキナキトヨモスとよみたれどトヨモシとよむべし。トヨモシテの意にて花チルにかゝれるなり。ミム人ヤタレとは君コソ來テ見メとなり |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
| |
霍公鳥來鳴きとよもす橘の、花散る庭を見む人や。誰 |
| |
子規が來て、鳴き響かせる橘の花の散る庭を、見に來てくれる人は誰だらう。さういふ心ある人は、あなたより外はない。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔ほととぎす 來鳴きとよもす 橘の 花散る庭を 見む人や誰〕
ホトトギス キナキトヨモス タチバナノ ハナチルニハヲ ミムヒトヤタレ
霍公鳥來鳴響橘之花散庭乎將見人八孰 |
霍公鳥ガ來テハ聲ヲ響カセテ鳴ク、私ノ家ノ橘ノ花ノ散ル庭ヲ見ニ來ル人ハ誰デセウ。アナタコソソノ人ダト思ヒマス。早クオイデ下サイマシ。
○將見人八孰[ミムヒトヤタレ]――見る人は誰かと、訊ねたのではなくて、誰にもあらず、君こそその人なれと言つたのである。
〔評〕 言ひ方が上品で、婉曲である。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔ほととぎす 來[き]鳴きとよもす、橘の 花散る庭を 見む人や誰[たれ]。〕
ホトトギス キナキトヨモス タチバナノ ハナチルニハヲ ミムヒトヤタレ
霍公鳥來鳴響橘之花散庭乎將見人八孰 |
【譯】ホトトギスの來て鳴き立てて橘の花の散る庭を、見ようとする人は誰でしよう。
【釋】霍公鳥來鳴響 ホトトギスキナキトヨモス。橘の花散る庭を修飾している。連體句。
花散庭乎 ハナチルニハヲ。ニハは屋前の廣場をいう。屋前をニハと讀むべき證の一つである。
將見人八孰 ミムヒトヤタレ。見よう人は誰か、君こその意に誘つている。
【評語】庭前の敍述は、類型的だが美しい。五句の誘いも、見ム人モガモなどの表現よりは、誘いの氣もちがよく出ている。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| |
〔ほととぎす来鳴きとよもす橘の花散る庭を見む人や誰〕
ホトトギス キナキトヨモス タチバナノ ハナチルニハヲ ミムヒトヤタレ
霍公鳥來鳴響橘之花散庭乎將見人八孰 |
【大意】ほととぎすが来鳴きさわぐ。それで橘の花の散る、吾が庭を見よう人は誰であらうか。
【作意】心の中に、見せたく思ふ人があり、其の人に贈る歌であらう。タレと歌つて居るが、意は君こそ見て欲しいであらうといふのである。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
| |
〔ホトトギス キナキトヨモス タチバナノ ハナチルニハヲ ミムヒトヤタレ〕
霍公鳥來鳴響橘之花散庭乎將見人八孰 (『元暦校本』) |
【口訳】霍公鳥が来て、声を響かせて鳴いてゐる、その橘の花の散る庭を見る人は誰でせうか。(君こそとお待ち申します。)
【訓釈】見む人や誰―代匠記に「落句ノ落者ハ君ニコソアルナリ」とある。「見む人もがもなどの表現よりは、誘ひの気持ちがよく出てゐる。」と全註釈にあるとほりである。
【考】赤人集「鳴きてひゝかは」「花散るやどにくる人やたれ」、流布本「鳴きてひゝかす」、家持集「来鳴きとよむる」「見む人もかな」、夫木抄(七、「橘」)「鳴きとよむなる」「花散る里を見む人もかな」従二位行家卿とある。 |
|
|
掲載日:2014.04.01.
| 夏雑歌 詠花 |
| 霍公鳥 来鳴響 橘之 花散庭乎 将見人八孰 |
| 霍公鳥来鳴き響もす橘の花散る庭を見む人や誰れ |
| ほととぎす きなきとよもす たちばなの はなちるにはを みむひとやたれ |
| 巻第十 1972 夏雑歌 詠花 作者不詳 |
【赤人集】〔137・125・245〕
【夫木抄】〔2671〕
【家持集】〔91・83〕
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1972】 語義 意味・活用・接続 |
| ほととぎす [霍公鳥] |
| きなきとよもす [来鳴響] |
| きなきとよもす [来鳴き響もす] |
[他サ四・終止形] 鳥が来て鳴き声を響かせる |
| 〔複合動詞〕カ変動詞「来(く)」の連用形「き」+四段動詞「響(とよ)もす」 |
| たちばなの [橘之] |
| はなちるにはを [花散庭乎] |
| みむひとやたれ [将見人八孰] |
| む [助動詞・む] |
[婉曲・連体形] ~とすれば、その |
未然形につく |
| や [係助詞] |
[反語] ~(だろう)か(いや、~でない) |
種々の語につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [む] |
推量の助動詞「む」には、連体形を用いて、「仮定・婉曲」の用法がある
この歌の場合が、そうだと思う
「見る人は誰だろう」と推し量るのであれば、それは通常の「推量の助動詞」だが
ここでは、「あなたに見て欲しい」という気持ちが滲み出ている
すると、反語表現と相成って、「見る人がいるとすれば、誰でしょう...あたなですよ」
そうやって婉曲に誘っている表現になる
このことは、なかなか当てはまる歌を見つけられないが
難しい用法の表現のようだ
古語辞典で、これを引いてみた
| |
助動詞「む」は、口語の「う」、「よう」にあたり、基本の意味として、「推量・意志(・意向)・勧誘」の三つを表す。他、「適当・当然」は、「勧誘」の、「反語」は「推量」の延長線上にあるものと考えられる。
「仮定・婉曲」は、口語の「う」のような用法で、まだ「実現していない動作・状態」についていうときに用いられるものである。口語で「明日来るときに...」などというところを、「明日来(こ)むときに...」というのである。適切な現代語がないので、訳出しない場合が多い。 |
訳出しない場合が多いとなると、歌意にその雰囲気や気持ちを籠めて解釈することになる
|
| |
| |
| |
| |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[本文]「霍公鳥 来鳴響 橘之 花散庭乎 将見人八孰」(「【】」は編集)
「ホトヽキス キナキトヨマス タチハナノ ハナチルニハヲ ミムヒトヤタレ」 |
| 〔本文〕 |
| なし |
|
| 〔訓〕 |
| キナキトヨマス |
『元暦校本・天治本』「きなきとよむる」
『神田本(紀州本)』「キナキトヨムル」
|
| ミムヒトヤタレ |
『類聚古集』「みる人やたれ」 |
| 〔諸説〕 |
| ○[キナキトヨマス]。『童蒙抄』「キナキナラセル」 |
|
【左頁資料について】
| 『万葉拾穂抄』 |
「心ありてみん人」がいい
「心あり」は、思い遣りがある、思慮分別がある、情趣を解する、などのことだ
そんな人にこそ、ホトトギスが鳴き橘散る庭を見て欲しい
それは「意中の人」を想いながらいうのだろう |
| 『万葉代匠記(精撰本)』 |
| 結句の本心は、それはあなたなんですよ、というもの |
| 『万葉集童蒙抄』 |
この風情ある情景を、誰か一緒に見てくれる人はいないのか、いてくれたらいいのになあ
心あらん人、とは「心ある人」の逆だろうが、そんな人が来ては、しっかり見なさい、とか少々情趣に落ち着かないが、心ある人は、この情景を気に入ってほめてくれる、そのような人は、誰なのだろうか、とそれこそ「まだ未ぬ恋人」を想うような乙女心だと言っているのかもしれない |
| 『万葉考』 |
だいたい、大方の歌でも、この真淵の時代辺りで、その「訓」の変化が多く見られる
この歌では、旧訓の「とよます」と訓むのも、この真淵までだ(荷田春満足は違うが)
以前にも書いたが、自動詞四段「とよむ」とするか、他動詞四段「とよもす」にするか、だろう
自動詞四段では「とよます」は未然形「とよま」に使役の助動詞「す」になる
だから、自動詞に使役の助動詞がついて、結果的には他動詞と同じ意味になるのだろう
となると、やはり語感をどう受止めるか、なのかもしれない
歌意は、あなたしかいませんよ、という |
| 『万葉集略解』 |
| 「君こそは来ても見るべき人なれ」、一緒にこの風情を解せるのは、あなたしかいないのだから... |
| 『万葉集古義』 |
| ホトトギスが鳴き響かせるにつれ、そのせいで橘の花が散る風情...前にそのような歌があった |
| 『万葉集新考』 |
| 橘の花が散る原因と思われるホトトギスの鳴き声ならば、と「とよもし」と訓み、「とよもして」の意で解釈している |
| 『口訳万葉集』 |
| 特になし |
| 『万葉集全釈』 |
| 「想い人」というよりも、「心ある人」の意味をかなり強く出している解釈だと思う |
| 『万葉集全註釈』 |
家の前の広場を「には(庭)」という、だから「屋前」と書いて「には」と訓むべき、という
この歌では関係ないが、「屋前」の訓に言及したもの
|
| 『万葉集私注』 |
| 特になし |
| 『万葉集注釈』 |
| 特になし |
|
|
|
| |

|
 |
| |
| |
| |
「くやしきときに」...あへるきみかも...
|
| 『ゆきちる、はなたちばな』 |
| 【歌意1973】 |
私の家の庭の橘の花は、もう散ってしまいました
こんなときにお出でになるなんて、
せっかくあなたがいらしてくださったのに、残念です。 |
|
| |
| |
表面的には、女はこうして男を迎えたのかもしれない
現代の注釈書では、どれも同じように、
いやむしろ次第に「想い人」から「友人」に訪問客が変化している
語義通りに訳すと、「想い人」であろうが、「友人」であろうが
咲きほこる橘の花を見せられなかったのは、残念です、となるだろう
しかし、古注釈書に触れられているような解釈は、素晴らしいと思う
歌の言葉の底に見えなくても感じられる「女心」を、読もうとしている
私の家なんか、こうやって花橘を愛でるくらいしか見映えのいいものはありませんよ
だから、本当に...
そう、残念に思うのは、橘の咲いているところを見せられなかったことではなく
何も自慢できない我家に、訪れてきた「あなた」への、
「自分自身の無念さ」があるのでは、と思う
そして、そこまで言外の想いを汲み取るのなら、もう少し深めたい
男は、橘が咲いていようが、散っていようが、そんなことお構いなしに
ただただ、女が恋しくてやってきた
男の「想い」と、もてなす手段がなくなった女の「無念さ」が、この歌では交錯している
宴席で詠まれた歌だろう、と言われている
だから、それに似つかわしい花を愛でる「想い」が
歌意として全面に押し出されているのかもしれない
しかし、以前にも書いたことがあるが
「宴席歌」だから、という理由は、有り得ない、と思う
宴席でこそ、男女の機微や、日常では見逃すようなことでも
それをドラマティックに詠えるものだし
少なくとも、作品として表に出たものは、もうその世界しか評価の対象にはならない
それが、どんな環境で作られたものなのか、というのは、別の課題になる
仮に宴席で、ほろ酔いの作者がこの歌を詠む
その歌の世界に、どこまで入っていけるか、だと思う
女は、橘の咲く庭を、想い人へのもてなしとして待っていた
男は、ただただ逢いたくてやって来た
そのすれ違いだからこそ、この歌は胸に響くのではないか、と思う
|
|
【赤人集 (三十六人集、撰藤原公任[966~1041])】
| 我やとの花たちはなはちりにけり くやしきことにあえる君かも |
| 私家集大成第一巻 新編増補[陽明文庫蔵「三十六人集」] 赤人Ⅲ 138 |
| 我やとの花たちはなはちりにけり くやしきことにあえる君かも |
私家集大成第一巻6 [書陵部蔵「三十六人集」) 赤人Ⅱ 126
|
| わかやとのはなたちはなはちりにけり くやしきことにあへるきみかも |
私家集大成第一巻5 [西本願寺蔵「三十六人集」] 赤人Ⅰ 246
|
|
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1973] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔わかやとの花たちはなはちりにけりくやしきときにあへる君かも 〕
吾屋前之花橘者落尓家里悔時尓相在君鴨
|
| わかやとの花たちはな 盛の時にも來あはてと也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
| |
吾屋前之花橘者落爾家里悔時爾相在君鴨
〔ワカヤトノハナタチハナハチリニケリクヤシキトキニアヘルキミカモ〕 |
| 時爾相在君とは、問來る人の悔しき時に相と云へる歟、花橘の盛に來ば見すべきを、落て後悔しき時に來たる人に我が逢へるとよめる歟、第八の遊行女婦[ウカレメ]が橘歌引合て見るべし、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
吾屋前之花橘者落爾家里悔時爾相在君鴨
〔わがやどの、はなたちばなは、ちりにけり、くやしきときに、あへるきみかも 〕 |
| とく來りなば、せめて橘をもゝてなしにせんに、あやしき宿なれば、いぶせき様を見する事の悔しきと也、 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
吾屋前之[ノ]、花橘者、落爾家里、悔時爾[クヤシキトキニ]、相在[アヘル]君鴨、 橘のちりて後來れるをかく云なり女歌なり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
| |
吾屋前之。花橘者。落爾家里。悔時爾。相在君鴨。
〔わがやどの。はなたちばなは。ちりにけり。くやしきときに。あへるきみかも。 〕 |
| 橘も散り過ぎたれば。君を待ち得しかひも無くて、くやしき時にも訪ひ來つるよとなり。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔ワガヤドノ。ハナタチバナハ。チリニケリ。クヤシキトキニ。アヘルキミカモ。〕
吾屋前之花橘者落爾家里悔時爾相在君鴨
|
| 歌(ノ)意は、契冲云、たちばなのにほひにこそ、いやしきやどもまぎれつれ、それさへ散過たるころ君がとへば、何のいふかひもなし、くやしき時にもきましつるかな、となり、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔わがやどの花橘はちりにけりくやしき時にあへる君かも 〕
吾屋前之花橘者落爾家里悔時爾相在君鴨 |
| アヘル君とは來リ訪ヘル君となり |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
| |
我が宿の花橘は散りにけり。悔《クヤ》しき時に、逢へる君かも |
| |
私の屋敷内の橘の花は、散つて了うたことです。殘念な時分に逢ひに來て下さつたあなたですこと。も少し早かつたらよかつたのに。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔吾がやどの 花橘は 散りにけり くやしき時に 逢へる君かも〕
アガヤドノ ハナタチバナハ チリニケリ クヤシキトキニ アヘルキミカモ
吾屋前之花橘者落爾家里悔時爾相在君鴨 |
私ノ屋敷ノ花橘ハ、今ハモウ散ツテシマヒマシタ。モツト早クオイデ下サレバヨイノニ、アナタハ殘念ナ時ニ、オイデナサツタモノデス。
○悔時爾相在君鴨[クヤシキトキニアヘルキミカモ]――悔しき時に君に逢へるかもと同意で、相在[アヘル]は君に逢つたので、君が悔しい時に逢つたのではない。
〔評〕 花橘が咲いたので、友の來るのを待つてゐたが、その友は花が散つた頃になつて、漸く訪ねて來たのを、遺憾とした歌である。三句切の爽やかな格調の作品である。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔わが屋前[には]の 花橘は 散りにけり。 悔[くや]しき時に 逢へる君かも。〕
ワガニハノ ハナタチバナハ チリニケリ クヤシキトキニ アヘルキミカモ
吾屋前之花橘者落尓家里悔時尓相在君鴨 |
【譯】わたしの庭の橘の花は散つてしまつた。殘念な時にお目にかかつたあなたです。
【釋】悔時尓 クヤシキトキニ。花が散つてしまつて殘念な時節に。殘念な時に君に逢つた意である。
【評語】賓客に橘の花を見せられなかつたことを殘念がつている氣もちがよく出ている。それほどに自然を愛していたのだ。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| |
〔吾が宿の花橘は散りにけり 悔しき時に逢へる君かも〕
ワガヤドノ ハナタチバナハ チリニケリ クヤシキトキニ アヘルキミカモ
吾屋前之花橘者落尓家里悔時尓相在君鴨 |
【大意】我が家の花橘は散つてしまつた。残念な時に会つた君かな。
【作意】花の盛りに来てくださればよかつたのに。散つた後に辛じて来られたと惜しむ心である。前の歌と連関して考へてもよい。巻八、(1492)の「君が家の花橘は成りにけり花の盛りに会はましものを」と同じ行き方である。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
| |
〔ワガヤドノ ハナタチバナハ チリニケリ クヤシキトキニ アヘルキミカモ〕
吾屋前之花橘者落尓家里悔時尓相在君鴨 (『元暦校本』) |
【口訳】私の家の花橘は散つてしまひました。残念な時にお会ひしたあなたよ。
【訓釈】悔しき時にあへる君かも―代匠記に「橘のにほひにこそ、いやしき宿もまぎれつれ。それさへ散過たる比、君がとへば、何のいふかひもなく、くやしき時にもきましつるよとなり」とある。
【考】君が家の花橘は成りにけり花なる時にあはましものを (8・1492) 遊行女婦
は「これに基づいたのであらう」と佐佐木博士評釈に云はれてゐる。
赤人集に「くやしきことに」、流布本「あへる君かな」。 |
|
|
掲載日:2014.04.02.
| 夏雑歌 詠花 |
| 吾屋前之 花橘者 落尓家里 悔時尓 相在君鴨 |
| 我が宿の花橘は散りにけり悔しき時に逢へる君かも |
| わがやどの はなたちばなは ちりにけり くやしきときに あへるきみかも |
| 巻第十 1973 夏雑歌 詠花 作者不詳 |
【赤人集】〔138・126・246〕
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1973】 語義 意味・活用・接続 |
| わがやどの [吾屋前之] |
| やど [宿・屋戸] |
家の敷地・庭先・前庭・家・自宅・一時寝るところ |
| はなたちばなは [花橘者] |
| ちりにけり [落尓家里] |
| に [格助詞] |
[強調] ~に |
| 〔接続〕通常は連体形につくが、「強調」の場合は「連用形」につく |
| けり [助動詞・けり] |
[過去(詠歎)・終止形] ~たことよ |
連用形につく |
| くやしきときに [悔時尓] |
| くやしき [悔し] |
[形シク・連体形] 残念だ・後悔される |
| あへるきみかも [相在君鴨] |
| あへ [逢ふ・会ふ] |
[自ハ四・已然形] ~出逢う・対面する |
| る [助動詞・り] |
[完了・連体形] ~ている・~てしまった |
已然形につく |
| かも [終助詞] |
[詠歎・感動] ~であることよ |
体言につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [やど] |
原文「屋前」を、どの書も例外なく「やど」と訓む
「やど」には、家の戸、家屋、庭先、
そして現代語的にも、旅先での一時的に泊るな「宿」などの意味がある
原文の「屋前」の字から、「やど」の意味の一つである「庭先」を浮かべるのが自然だと思う
勿論、歌意として、「庭先」でこそより意味が通ることもある
昨日の歌〔1972〕で、『全註釈』は、原文「花散庭乎」が「ハナチルニハヲ」と訓めるのを
「庭」は、「屋前の広場」のことで、すなわち「には」だから
語意として「屋前」を、「には」と訓める一つの「証」のようなものだ、と言っている
その時は唐突に「屋前」の漢字が出てきて、昨日の歌には関係ないものだ、と思ったものだが、次の歌、この掲題歌に使われる「屋前」を、事前に説明した、ということだ
「やど」という語が建物、あるいは広義でも、家の敷地内と言うのであれば、
『全註釈』がいう「屋前」については、「には」の方がいいと、私は思う
しかし、「屋前」を『万葉集』中で検索すると、三十四首あるが、すべて「やど」と訓む
諸本にも異訓のない語となれば、「には」と訓まれるのは、やはり難しいのだろう
|
| |
| [くやし] |
この語の「類語」は、よく使われるので、まとめておきたい
古語辞典によれば、[惜しむべき、という意味の形容詞語幹「惜(あたら)」の項目]
| |
| 中古以降、新しいの意の「あらたし」と混同して、「新しい」の意にも用いるが、本来は別後。惜しいの意の「あたらし」は、形容詞「惜(を)し」に押されてやがて用いられなくなるが、その語幹は「あたら青春を無為に過ごす」のように、「惜しいことに」の意の副詞、または「惜しむべき」の意の連体詞として、現代にも残っている。 |
| あたらし |
優れたものが失われるのを惜しむさま |
| くちをし |
物事が期待はずれで、がっかりするさま |
| くやし |
自分のした行為を反省して後悔するさま |
| をし(惜し) |
強い愛着を感じているものが、失われるのを惜しむさま |
|
| |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[本文]「吾屋前之 花橘者 落尓家里 悔時尓 相在君鴨」(「【】」は編集)
「ワカヤトノ ハナタチハナハ チリニケリ クヤシキトキニ アヘルキミカモ」 |
| 〔本文〕 |
| なし |
|
| 〔訓〕 |
| アヘルキミカモ |
『天治本』「ヘ」ハ何カヲ直セリ
|
| 〔諸説〕 |
| ○ |
|
【左頁資料について】
| 『万葉拾穂抄』 |
| 我が家の花橘、花盛りの時にきてくれれば、いいのに、と |
| 『万葉代匠記(精撰本)』 |
結句は、尋ねて来る人に残念な時に逢うなんて、花橘の盛りの時に来てくれれば...
巻第八の1492歌は、花が盛りの時に、あなたの家に行けばよかったのに、という歌で
契沖が云う様に、この二首は響き合うものがある |
| 『万葉集童蒙抄』 |
「いぶせき」は、むさくるしい、という意味でいうのかな
いらっしゃる時には、橘をもてなしにしようと思っているのに
橘が散ってしまっては、それもできず、このむさくるしい家を見せなければならないのは、残念だ
と言う意味に解釈しているのだろう |
| 『万葉考』 |
| 特になし |
| 『万葉集略解』 |
橘が散れば、待つ甲斐もない...だから、散るまでに来て欲しかったのに、かな
でも、それだとつれない気がする
結果的に同じ解釈になっても、荷田春満の方が健気でいい |
| 『万葉集古義』 |
| なるほど、契沖以降、春満も含めて、同じように橘の花で、みすぼらしい我家を少しでもよく見せたい女心、と捉えているようだ |
| 『万葉集新考』 |
| 特になし |
| 『口訳万葉集』 |
| 『古義』までの「女心」は表面に出さず、ただただ「橘の盛り」を見せたかった、というようだ |
| 『万葉集全釈』 |
| 橘の盛りを見せられなかったのが、残念だ、という気持ち |
| 『万葉集全註釈』 |
同上、特になし
|
| 『万葉集私注』 |
| 同上、特になし |
| 『万葉集注釈』 |
赤人集の流布本、「あへる君かな」とあるが、現存する赤人集三種は、いずれも「きみかも」だ
流布本とは、何を底本にして言うのだろう |
|
|
|
|
| |

|
 |
| |
| |
| |
| |
| |
「ちらまくをしも」...あめなふりそね...
|
| 『あめのしづくも』 |
| 【歌意1974】 |
見渡してみると、
向こうに広がる野辺のなでしこが、
雨に打たれて、散りそうなのが見えて、
それが惜しく思われてならない
もう降らないでくれ、雨よ |
|
| |
| |
「なでしこ」の漢字表記「撫子」
これから思い浮かべられるのが、「なでしこ」の語義の一つでもある、
「なでるようにかわいがっている子」という意
その語義が、この歌にかけられているかどうかは、解らないが
それほど可憐な花、ということだろうか
そして近代になって、「なでしこ」が散る、という表現に、
どこか似つかわしくない、評も出てきた
確かに、桜や梅のように、花が散るという風情ではない
「散る」光景そのものが、浮ばない
『新考』では、「見渡して見えるものではない」というが、私もそう思う
ならば、この歌で作者が「散るのを惜しむ」光景、とは
いったいどんな光景なのだろう
雨のせいで、野辺の景観が一変することが、視覚的に「惜しい」と言うものなのだろうか
その景観を損ねるような「雨」に対して、降らないで欲しい、と懇願する
そして、なぜかと言えば、こんなに可憐な「なでしこ」ではないか、
いじめないでくれ
そう心情的な想いが重なっているように思う
単なる景観を「惜しむ」だけではなく、上述の「撫子」の語義にもあるような
そんな「いとおしさ」が溢れている歌だと思う
原文表記に「石竹」が使われたのは、当時の「なでしこ」の一般的な用法だったかもしれない
「石竹(セキチク)」なら尚更、可憐で守ってやりたい「花」のように思える
この歌は、その歌意に苦しむところはないが
問題となるのが、結句の「行年」という表記を、どう訓むのか、だ
旧訓では「こそ」という
その旧訓「こそ」が「そね」に替わられたエピソードめいた話しが、調べていて解った
それは、江戸時代の伊勢神宮の祠官であり国学者であった荒木田久老(1747~1804)が、
万葉集の研究として著した、
『万葉考槻落葉』〔荒木田久老、寛政十一年(1799)成〕にあった
荒木田久老は、賀茂真淵の門に入り、同門の本居宣長とともに学んでいたが
宣長は、「古事記」を深めてゆき、久老は「万葉集」を深めていく
その二人の晩年になると、お互いの意見に対立が見られるようになった、という
この『槻落葉』に、
| 底本、古今書院1924年萬葉集叢書第四輯、久保田俊彦(島木赤彦)校訂の臨川書店1972年復刻本 |
大納言大伴卿(ノ)[旅人卿なるを、家持卿の父なれば、あがめて名いはぬは、卷の例なり。家持卿の家集也といへるはよし有。]歌、一首。
奥山之《オクヤマノ》。菅葉凌《スカノハシヌキ》。[山菅は、麥門冬也。しぬぐといふ言の意を考るに、自堪忍《ミツカラタヘシヌ》ぶを、しの び、しのぶといひ、他《ひと》のたへがたきを、是よりおしてするを、しのぎ、しのぐといふ。神代紀に、凌奪《シヌギウバフ》吾(ガ)高天原《タカマノハ
ラ》、とあるしぬぎ、即是にて、凌礫の字意也。さればこゝも、菅の葉をおしなびけて、降雪をいふ意となれれり。]零雪乃《フルユキノ》。消者將 惜《キエハヲシケム》。[今本に、けなばおしけむとあるも、きえの約め氣《ケ》なれば、さもよむべけれど、なとよむ字のなければ、きえはをしけむ
と訓たり。]雨莫零所年《アメナフリソネ》。[今本行年とありて、こそとよめるは、例なく、誤なるよし、本居氏いへり。雨《アメ》なふりそといふに、ねの 言をそへたるなり。ねは願のこと葉なり。]
|
雨莫零所年《アメナフリソネ》。[今本行年とありて、こそとよめるは、例なく、誤なるよし、本居氏いへり。雨《アメ》なふりそといふに、ねの 言をそへたるなり。ねは願のこと葉なり。]
この歌は、下段の資料にも引用される巻第三・302(旧国歌大観299)による、
おそらく「行年」についての初めての解説になると思う
ここでは、本居宣長提唱の「そね」を採ったことに関し、
「な~そ」の用法の歌意になることを前提に考え、そこに願望の終助詞「ね」が添えられた、と
しかし、「行」を単純に「誤」とするだけなので、後世にもさまざまな研究課題が残された
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕から探ってみると、
この〔302〕歌の項目で、次のような説明があった
| 〔302〕歌、「雨な降りそね」 文中の歌番号は「旧国歌大観」 |
| ナ~ソネの文型で、懇願的禁止表現。原文「雨莫零行年」とあり、その「行年」を旧訓にコソと訓んでいたのを、槻落葉に宣長説として「所年(そね)」と改め、攷証は「行年(こそ)」(去年「コゾ」からの連想で、「来莫「コソ」の意)としたが、「行年」はソネと訓むことに誤りはなく、しかしなぜソネと訓むのか未だに分からない。「行年」の「年」はネだから、「行」はソだとして、「来(コ)」に対する「行(ソ)」ではないかとする考え方もできないことはないが、「行(ソ)」の例がないので賛成を得難い。となると、「行年」ニ字でソネと訓む理由を考えればよいことを示している。思うにこうではあるまいか。「細竹刈嫌(シノナカリソネ)」(巻七・1276)の「嫌」をソネと訓ませることが参考になるのだが、「嫌」は憎むとか嫌うとかの意で、それをソネムと言ったこと、霊異記(上、第五話、興福寺本)や祟峻紀五年の古訓に見える。一方「行年」は過ぎ去った年齢を言うが、この「行年」という文字が「嫌う」印象を与えたのでソネムのソネと訓まれるようになったものか。享年(没年)の意に用いたのはいつのことか不明であるが、後にそういう意味になるということも、「行年」は語感として嫌われたのであろう。この「行年(そね)」の例は集中に四例ある。 |
『全注』の刊行は、その巻ごとに執筆者が違う
そして、叢書の冒頭にも述べられているように、全二十巻通しての同じ見解には拘らず
それぞれの執筆者が、自説を展開している
それが魅力の「万葉集注釈書」とも言えるので、
この第三(初版昭和五十九年)の執筆者西宮一民氏の上出の見解が、
そのまま掲題歌、巻十(初版平成元年・阿蘇瑞枝氏)の歌に当てはまるかどうか
それは分からないが、少なくとも、語句の訓に関しては、
このように誰もが明確な説明が、今も出来ない、と言うことが解る
現代の私たちは、そうした「ことば」を無意識に受け入れているが
このように、歌として残された「古語」を「訓」じようとする人々の「思想」を
古注釈書に触れると、よく知ることができる
私にとっては、とても面白い、とさえ思える
|
|
【夫木和歌抄 (延慶三年頃[1310年頃]、撰勝間田長清)】
| 見渡せばむかひの野べのなでしこのちらまくをしもあめなふりこそ |
| 新編国歌大観第ニ巻16[静嘉堂文庫蔵本]巻第九 夏部三 瞿麦 3485 よみ人しらず |
【和歌童蒙抄 (仁平年間[1151~54]頃、藤原範兼作[1107~1165])】
| みわたせばむかひののべのなでしこのちらまくをしもあめなふりこそ |
| 新編国歌大観第五巻293[古辞書叢刊<尊経閣本>] 第七巻 草部 瞿麦 556 |
|
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1974] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔見わたせはむかひののへのなてしこのちらまくおしもあめなふりこそ 〕
見渡者向野邊乃石竹之落卷惜毛雨莫零行年
|
| 見わたせはむかひのゝへ おしものもは助字也雨なふりこそはふり來たりそと也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
| |
見渡者向野邊乃石竹之落卷惜毛雨莫零行年
〔ミワタセハムカヒノノヘノナテシコノチラマクヲシモアメナフリコソ〕 |
| 無し |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
見渡向野邊乃石竹之落卷惜毛雨莫零行年
〔見わたせば、むかふのゝべの、なでしこの、ちらまくをしも、あめなふりこそ 〕 |
| 雨はなふり來そといふ義也。聞えたる歌也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
見渡者、向野邊乃[ムカヒノヽベノ]、石竹之[ナデシコノ]、落卷惜毛、 雨莫零行年[ナフリコソ]、 雨はふるなとねがへるなり行年は去年の意さればこぞの言もてこその辭にかり用たるなり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
| |
見渡者。向野邊乃。石竹之。落卷惜毛。雨莫零行年。
〔みわたせば。むかひののべの。なでしこの。ちらまくをしも。あめなふりそね。 〕 |
打向ふ所の野なり。行は所の誤なり。
參考 ○見渡(新)ミワタス「者」を衍とす ○行年(古、新)ソネ「所年」の誤とす。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔ミワタセバ。ムカヒノヌヘノ。ナデシコノ。チラマクヲシモ。アメナフリソネ。〕
見渡者向野邊乃石竹之落卷惜毛雨莫零行年
|
| 零行年は、本居氏云、行は所の誤にてフリソネなり、○歌(ノ)意は見わたせば、この向ひの野邊のおもしろき石竹の、雨ふらばやがて散失べきさまなるに、その散(リ)失べき事はさても惜や、いかで雨ふることなくて、あれかし、となるべし、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔見渡者[ミワタシノ]向野邊乃[ムカヒノノベノ]なでしこのちらまくをしも雨なふり行年[ソネ] 〕
見渡者向野邊乃石竹之落卷惜毛雨莫零行年 |
| 初二を從來ミワタセバムカヒノ野ベノとよみたれど瞿麦の散るは見渡して見ゆるものにあらねばミワタセバとよみてチラマクと照應せしむべきにはあらず。されば者を乃の誤としてミワタシノとよむべし |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
| |
見渡せば、向ひの野邊の撫子の、散らまく惜しも。雨な降りそね |
| |
見渡すと、向うの野にある撫子の花が、散りさうである。それがどうも殘り惜しい。雨よ降つてくれるな。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔見渡せば 向ひの野べの なでしこの 散らまく惜しも 雨なふりそね〕
ミワタセバ ムカヒノヌベノ ナデシコノ チラマクヲシモ アメナフリソネ
見渡者向野邊乃石竹之落卷惜毛雨莫零行年 |
見渡スト向フノ野原ニハ撫子ガ美シク咲イテヰルガ、アノ撫子ガ散ルノハ惜シイコトダヨ。雨ヨ、降ラナイデクレヨ。
○雨莫零行年[アメナフリソネ]――行年をソネとよむことについては、卷三の雨莫零行年[アメナフリソネ](二九九)參照。
〔評〕 野もせに美しく咲いた、瞿麥の花を惜しんで雨よ降るなと希つたので、やさしい内容と調子とを持つてゐる。卷三の奥山之菅葉凌零雪乃消者將惜雨莫零行年[オクヤマノスガノハシヌフルユキノケナバヲシケムアメナフリソネ](二九九)と似たところがある。。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔見渡せば 向ひの野邊の 石竹の、散らまく惜しも。雨なふりそね。〕
ミワタセバ ムカヒノノベノ ナデシコノ チラマクヲシモ アメナフリソネ
見渡者向野邊乃石竹之落卷惜毛雨莫零行年 |
【譯】見渡せば、向こうの野邊のナデシコが、散るのが惜しいことだ。雨よ降らないでくれ。
【釋】雨莫零行年 アメナフリソネ。行年は、ソネと讀むものの如くであるが、しか讀む理申はわからない。「雨莫零行年[アメナフリソネ]」(卷三、二九九)。
【標語】見わたした野邊に咲いているナデシコの、雨に逢つて散ることを惜しんでいる。野趣の愛すべきものを感じている。ナデシコの散るというのは、似合わないようだ。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| |
〔ミワタセバ ムカヒノヌベノ ナデシコノ チラマクヲシモ アメナフリコソ〕
見渡者向野邊乃石竹之落卷惜毛雨莫零行年 |
【大意】見渡す、向こうの野べの撫子の、散らうのは惜しい。雨よ降るなかれよ。
【作意】野べの撫子の、雨に衰へて行くのを惜しむ心である。ナデシコには今はチルは宛てまいが、此の頃はさうあらはしたと見える。ミワタセバは殆ど枕詞風に置かれてある。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
| |
〔見渡せば 向ひの野邊の なでしこの 散らまく惜しも 雨な零りそね〕
ミワタセバ ムカヒノノベノ ナデシコノ チラマクヲシモ アメナフリソネ
見渡者向野邊乃石竹之落卷惜毛雨莫零行年 (『元暦校本』) |
【口訳】見渡すと向こうの野辺に咲いてゐる撫子の散る事が惜しいよ。雨よ零らないでおくれ。
【訓釈】なでしこ―既出(3・408)
雨な零りそね―既出(3・299)。「行年」を旧訓コソとあるを略解にソネと訓んだに従ふべきことその條で述べた。『類聚古集』に「年」の字を「序」とあるは、コソの訓によつてソの仮名としたものかといふ事も既述。「行年」はソネの借訓の文字と思はれるが、なぜさう訓むかはまだわからない。
【考】夫木抄(九「瞿麦」)に旧訓のまま載せる。 |
|
|
掲載日:2014.04.03.
| 夏雑歌 詠花 |
| 見渡者 向野邊乃 石竹之 落巻惜毛 雨莫零行年 |
| 見わたせば向ひの野辺のなでしこの散らまく惜しも雨な降りそね |
| みわたせば むかひののへの なでしこの ちらまくをしも あめなふりそね |
| 巻第十 1974 夏雑歌 詠花 作者不詳 |
【夫木和歌抄】〔3485〕
【和歌童蒙抄】〔556〕
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1974】 語義 意味・活用・接続 |
| みわたせば [見渡者] |
| みわたせ [見渡す] |
[他サ四・已然形] 遠く広く見やる・はるか遠くまで眺める |
| ば [接続助詞] |
[順接の確定条件] ~すると・~したところ |
已然形につく |
| むかひののへの [向野邊乃] |
| むかひ [向かひ] |
正面の方向・正面・前面、また相手 |
| なでしこの [石竹之] |
| なでしこ [撫子・瞿麦] |
[秋の七草の一つ] 初秋に淡紅色の花を開く |
| ちらまくをしも [落巻惜毛] |
| まく |
推量の助動詞「む」のク語法、「~だろうこと」 |
| をし [惜し] |
[形シク・終止形] 失うにしのびない・惜しい・残念だ |
| も [終助詞] |
[感動・詠歎] ~よ・~なあ |
種々の語につく |
| あめなふりそね [雨莫零行年] |
| な~そね [終助詞] |
[懇願するの気持ちをこめた禁止] ~しないでほしい |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [なでしこ] |
「秋の七草」の一つである「なでしこ」が、
この夏雑歌に配されるのは、何故だろう...
「なでしこ」は、その表記が一般的に「撫子・瞿麦」とするが、
「唐撫子(からなでしこ)」である「石竹(せきちく)」を含めていうこともあるので、
この歌の表記が「石竹」になっているのだろうか
しかし、調べてみると、普通に「なでしこ」といえば「河原撫子(大和撫子)」のことらしい
枕草子「草の花は」に
| |
| 草の花はなでしこ。唐のはさらなり、大和のもいとめでたし |
とある
充分な理解とは言えないが、「大和のも」という言い方は
「唐撫子」と「大和撫子」は同格で扱っているのだな、と思う |
| |
| [まく] |
助動詞「む」の活用は、終始形「む」、連体形「む」、已然形「め」の三つだが
今日初めて知った「説」に、
本来はない「未然形」の「ま」を想定し、それに体言化接尾語「く」が付いたもの
というのがあった
確かに、接尾語「く」には名詞化する働きがあり、それで「ク語法」というのだが
現在でも、まだ確実な文法上の説明は難しいらしい |
| |
| [をし] |
昨日の歌〔1973〕に「くやし」があり、同じような意味合いの「語」として
この「をし」を含めて比較表を作った 〔1973、くやし〕 |
| |
| [な~そね] |
「そね」は、上代語で禁止の終助詞「そ」に、他に対する願望の終助詞「ね」のついたもの
それに、動詞の連用形の上について禁止を表す副詞「な」と組み合わさり
「な~そね」で、懇願する気持ちをこめた禁止を表現する
原文「行年」を「そね」と訓じていること、旧訓が「こそ」であり、
その現代での「訓」解釈を、左頁に紹介する |
| |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[本文]「見渡者 向野邊乃 石竹之 落巻惜毛 雨莫零行年」(「【】」は編集)
「ミワタセハ ムカヒノヽヘノ ナテシコノ チラマクヲシモ アメナフリコソ」 |
〔本文〕頭注に『和歌童蒙抄』
第七「ミワタセハムカヒノヽヘノナテシコノチラマクヲシモアメナフリコソ 同(万葉)第十アリ」とある |
| 「年」 |
『類聚古集』「序」
『神田本(紀州本)』下ニ小字「曽⊓」アリ【「⊓」が解らない、もっと幅がある】 |
| 〔訓〕 |
| ミワタセハ |
『元暦校本』「タ」ナシ。右ニ書ケリ。同筆カ。
『天治本』「ワ」ナシ。右ニ「わ」アリ
|
| ムカヒノヽヘノ |
『類聚古集』「むかひのゝへに」。墨ビテ「に」ヲ消セリ。ソノ右ニ墨「ノ」アリ『神田本(紀州本)』「ムカヘノヽヘノ」
『天治本』「むゐのゝへの」
|
ナテシコノ
チラマクヲシモ |
『細井本』「石竹之落」ノ左ニ「イハタケノヲチ」アリ
『神宮文庫本』漢字ノ左ニ「イハタケノ」アリ
『神宮文庫本』「チラマクオシモ」。「落」ノ左ニ「ヲチ」アリ
『類聚古集』「をしみ」。墨ニテ「み」ヲ消セリ。ソノ右ニ墨「も」アリ
『神田本(紀州本)・西本願寺本・細井本』「オシモ」
|
| 〔諸説〕 |
| ○[雨莫零行年アメナフリコソ]。『略解』「行」ハ「所」ノ誤。訓「アメナフリソネ」。 |
|
【左頁資料について】
| 『万葉拾穂抄』 |
文法の説明をしている
旧訓「こそ」だが、その用法は「な~そ(ね)」で、中古以降では「な」が省略されたらしいから
「ふり来たりそ」と当時の「禁止表現」で説明している
|
| 『万葉代匠記(精撰本)』 |
| 解釈なし |
| 『万葉集童蒙抄』 |
当時の旧訓「こそ」に「来そ」を当てている
原文の「行年」に倣ったものだろうか
「こそ」という訓は、そこからきているのかな
終助詞「こそ」には、「~てほしい」という希望の意味がある、「降らないでくれ」と... |
| 『万葉考』 |
「こそ」の訓の由来を説いている
「行年」は、「こぞ(去年)」の意味なので、その「音」を借りているものだ、という
だから、結句は「こそ」と訓むべきだ、と
荷田春満のいう「来そ」もそうだったのか、たぶん... |
| 『万葉集略解』 |
「所年」を「そね」と訓むのは、どんな説明があるのだろう
「行年」が「去年」の「音」を借りた説明の方が、私にはまだ理解出来る
歌意には、特筆なし |
| 『万葉集古義』 |
| 歌意には、特筆なし |
| 『万葉集新考』 |
実景に照らして、「見渡せば」は、おかしい、という
しかし、「みわたしの」となれば、どんな情景を浮かべられるのだろう |
| 『口訳万葉集』 |
| 歌意に特筆なし |
| 『万葉集全釈』 |
この注釈書は、全巻を持ち合わせていないので
著者が巻三で、どう説明しているか解らない
しかし、巻三の同じ原文を他の書で調べたので、左頁に載せる |
| 『万葉集全註釈』 |
「行年」を「そね」と訓むこと、これも解らないとする
なでしこの「散る」と言う表現も、似合わないようだ、と |
| 『万葉集私注』 |
| なでしこの散る、を「万葉時代」は、そう表現したものか、と |
| 『万葉集注釈』 |
| 「行年」の訓に、なおも理解出来ず |
|
|
|
|
| |


|
 |
| |
| |
| |
| |
| |
「はなたちばなは」...ちりにけむかも...
|
| 『長雨にうしなふ』 |
| 【歌意1975】 |
雨が上がりの晴れ間を待って、ふるさとの小高い岡から、
花橘の咲きほこる野辺を見たかったのに
この長雨、きっとその花橘も、散ってしまったことだろうなあ |
|
| |
| |
この歌もまた、歌意は解り易いようだが、その複雑さはかなりある
単純に、高い所から花橘を見たかった
しかし、雨のせいでなかなか「ふるさと」にいけなくて
むなしく時を過ごしていたので、そのふるさとの花橘も散ったのだろう
こう読めば、ふるさとを離れた作者が
そのふるさとを懐かしく思い、雨が上がって晴れれば
そこまで出向き、岡に登って美しい花橘でも眺めたい、
だのに...
こう読ませない語句が、「あままあけて」と「くにみもせむを」だ
古注釈から見ても、その解釈の流れがあるのではなく
同じ時代の解釈でも、その捉え方は違う
「あままあけて」という語は珍しいらしい
確かに、「あまま」という「語」はある
「雨の晴れ間」
感覚的には理解出来ても、「雨の晴れ間」というのは、どんな情況だろう
降っては止んで、の繰り返しの中での「晴れ間」のことだろうとは思う
しかし、「あけて」に続く
この動詞は右頁でも書いたが、他動詞なので
作者の意志が現れている
その意志と言うのが、「晴れるのを待って」になるはずだ
長雨が続く、その時々止む合間を待つのではなく
本格的に晴れ上がるのを待つ
そうでないと、ふるさとの岡など登れはしない
「くにみ」が、私も以前は思っていた為政者が国土の視察とか
役人が巡検に廻るとか、そんな意味合いではなく
ふるさとを眺望できる意味でも使われていたとすれば
いや、その意味でなければ、ここで「くにみ」という語に限らなくても
他の語では歌意を解することはできない
ましてや、「作者不詳」の歌だ
そうした私的な感慨に浸って詠える者が使える「国見」という語もまた
私のように思い込みの強い者には、すぐには素直な歌として読めなかったと思う
「国見」に拘るからこそ、多くの書でも言うように、巡検めいた役人仕事をいい
そのついでに、ふるさとに立ち寄るので、橘の花でも見たい
しかし、その巡検さえも、雨のせいでなかなか出発できない
ああ、もうふるさとの花橘も、散っているだろうなあ
これが「国見」から無意識の内に理解してしまう歌意の解釈だと思う
しかし、一般的ではないにしても
「国見」には、呪的な民族的行事もあった、とも言われている
古語辞典には書かれていないが、関連書にはそのことは仮説でもなく通じている
ならば、それに合わせることも可能だが...
それでも、私にはそれさえも余計なこととして思える
「国見」、「くにみ」をそのままに、ふるさとを眺望できるところでいい
その景観を見たくて、花橘の季節、ふるさとに行こう、と思っていたのに、生憎の長雨
雨上がりを待っていたら、随分むなしい時を過ごしてしまった
花橘も、散ってしまったことだろう...
「くにみ」のついでに、ふるさとの岡に登って、花橘を見たい、のではなく
花橘を見に、ふるさとの「岡から国見しよう」なのだと思う
結句の終助詞「かも」は「疑問」よりも「詠嘆」の方が、無念さが伝わる
|
|
| |
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1975] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔あまゝあけて国見もせんをふる里のはなたちはなはちりにけんかも 〕
雨間開而國見毛将為乎故郷之花橘者散家牟可聞
|
| あまゝあけて国見も 見安云あまゝあけては雨の晴たる空也愚案雨晴て我国見をもせはやと思ふに此比の雨に故郷の橘やちらんと也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
| |
雨間開而國見毛將爲乎故郷之花橘者散家牟可聞
〔アママアケテクニミモセムヲフルサトノハナタチハナハチリニケムカモ〕 |
| 國見は今は四方を見はるかすを云へり、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
雨間開而國見毛將爲乎故郷之花橘者散家牟可聞
〔あまゝあけて、くに見もせんを、ふるさとの、はなたちばなは、ちりにけんかも 〕 |
| あまゝあけては、雨の間を見て也。雨の霽れなば國廻りをもして、故郷へも廻らましをと也。雨降り續きし五月雨の頃、故郷などを思ひ出て詠めるならん |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
雨間開而[アメハレテ]、今本にあまゝあけてとよめるはわろしあめはれてと訓べし集中の例なり
國見毛將爲乎、故郷之、花橘者、散[チリニ]家牟可聞、
橘の散るばかりの事に國見など云べからずこは國見せん時に橘の咲てあらば興あらんに雨ふりこめて國見もせざる間に橘はちりなんかとをしめりさて此古郷は飛鳥藤原などの古京を云ならん、 |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
| |
雨間開而。國見毛將爲乎。故郷之。花橘者。散家牟可聞。
〔あままあけて。くにみもせむを。ふるさとの。はなたちばなは。ちりにけむかも。〕 |
アママアケテは雨の晴間なり。國見は橘にのみ懸かるに有らず。國見もせん時、橘も咲きて、興多からんに、雨降り續きて、國見もせず。故郷の橘も、いたづらに散らんと言ふなり。此故郷は、藤原か、飛鳥の古京を言ふなるべし。
參考 ○雨間開而(新)アメハレテ「間開」は「霽」の誤。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔アママアケテ。クニミモセムヲ。フルサトノ。ハナタチバナハ。チリニケムカモ。〕
雨間開而國見毛將爲乎故郷之花橘者散家牟可聞
|
| 國見[クニミ]は、一(ノ)卷三(ノ)卷などにも出て、既くいへり、○故郷[フルサト]は、飛鳥の故京か、いづれ故京なるべし、○歌(ノ)意は、雨の晴間もあらば、立出て國見をもせむ、それにつれて、飛鳥の故京の橘花をも見むとおもふ間に、雨のをやみなければ、空しくて打過る程に、故京の花橘はちり失にけむか、となり |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔雨間開而[ハレテ]國見もせむをふるさとの花橘はちりにけむかも 〕
雨間開而國見毛將爲乎故郷之花橘者散家牟可聞 |
| 初句を從來アママアケテとよみたれどさる辭あるべくもあらず。間開はおそらくは霽の一字を誤れるならむ。さらばアメハレテとよむべし○クニミモセムヲはここにては國見アリキモセムヲとなり。略解古義に國見を一處にゐて眺望する事と心得たるより此歌を釋き煩へり。フルサトといへるは飛鳥ならむ |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
| |
雨間[アマヽ]あけて、國見もせむを。舊里[フルサト]の花橘は、散りにけむかも |
| |
雨の晴れ間に登つて、野原を眺めようと思ふのに、さびれた在所なる飛鳥の橘の花は、もう散つて了うたことだらうか。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔雨まあけて 國見もせむを ふるさとの 花橘は 散りにけむかも〕
アママアケテ クニミモセムヲ フルサトノ ハナタチバナハ チリニケムカモ
雨間開而國見毛將爲乎故郷之花橘者散家武可聞 |
雨ガ降リ止ンダラ、舊都ノ景色ヲ見下ロシテ花橘ノ美シイ樣子デモ眺メヨウト思ツテヰタノニ、雨バカリ降ツテ居ルウチニ花橘ハ散ツタダラウナア。惜シイモノダ。
○雨間開而[アママアケテ]――雨間[アママ]は雨の止んだ間であるが、アママアケテといふのは一寸變つた詞である。意は雨霽れてと同じであらう。考にはアメハレテとよんでゐる。
○國見毛將爲乎[クニミモセムヲ]――國見は山の上などの高所から、下の平野を見下ろすこと。
○故郷之[フルサトノ]――故郷は舊都、飛鳥京であらう。
〔評〕 國見する岡の上から、花橘の白い花が散り過ぎて、最早見られないかと心配したのである。國見といつても、あのあたりの低い岡(恐らく雷岡)からであるから、里の花橘も見えるのである。新考に「國見アリキモセムヲとなり」として、故郷の中を見ながら歩くことに解いてゐるが、國見にはさういふ用例はあるまい。これも優美な、なつかしい歌である。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔雨間[あまま]關[か]けて 國見もせむを、故郷の 花橘は 散りにけむかも。〕
アママカケテ クニミモセムヲ フルサトノ ハナタチバナハ チリニケムカモ
雨間關而國見毛將爲乎故郷之花橘者散家武可聞 |
【譯】雨のやんだまをかけて、國見もしようのに、故郷の橘の花は、散つてしまつただろうか。
【釋】雨間關而 アママカケテ。雨と雨とのあいだを懸けて。雨のやんだまに。
國見毛將爲乎 クニミモセムヲ。クニミは、高い處に登つて國土を望見するをいう。天皇の國狀視察などに多く使われるが、ここは觀光に使われている。
故郷之 フルサトノ。フルサトは、住み古した里。何處ともわからないが、明日香だろう。
【評語】降り續いた梅雨のこやみを見て、故郷をおとずれようとして詠んでいる。永い雨のために、橘の花ももう散つてしまつたろうと推量している。故郷をなつかしむ心がよく出ている。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| |
〔アママアケテ クニミモセムヲ フルサトノ ハナタチバナハ チリニケムカモ〕
雨間關而國見毛將爲乎故郷之花橘者散家武可聞 |
【大意】雨間が晴れて、国見もしようものを、故郷の花橘は散つたことであらうか。
【作意】フルサトは、明日香であらう。そこに田庄など有する者の歌と見える。クニミは己が田庄を見廻ることであらう。その序に花橘も見ように、それは既に、雨が長く、時間がなかつたので散つたことであらうといふのである。初句は「雨間關而」とある本があり、アママカケテとも訓まれるが、アケテの方を取る。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
| |
〔アママアケテ クニミモセムヲ フルサトノ ハナタチバナハ チリニケムカモ〕
雨間關而國見毛將爲乎故郷之花橘者散家武可聞 (『元暦校本』) |
【口訳】雨の晴間をこしらへて国見もしようものを。故郷の花橘はもう散つてしまつたであらうかナア。
【訓釈】雨間あけて―「雨間」は雨の晴間で、「あけて」は雨の晴間をこしらへて、の意で、消極的に云へば雨の晴間を待つて、の意と同じになる。雨の止むのを待つ事を、「雨をやませて」といふのと同じである。(8・1491)
国見もせむを―「国見」は既出(1・2題)。高いところから平野を見渡すこと。
故郷の―考に「此故郷は飛鳥藤原などの古京を云ならん」とあるが当つてゐよう。
散りにけむかも―「武」の字、『元暦校本・類聚古集・紀州本』による。『西本願寺本』以降「牟」とする。
【考】『紀州本』にはこの歌を落し、(1974)の余白に別筆で記し、ここへ入れるべきしるしをつけてゐる。 |
|
|
掲載日:2014.04.04.
| 夏雑歌 詠花 |
| 雨間開而 國見毛将為乎 故郷之 花橘者 散家武可聞 |
| 雨間明けて国見もせむを故郷の花橘は散りにけむかも |
| あままあけて くにみもせむを ふるさとの はなたちばなは ちりにけむかも |
| 巻第十 1975 夏雑歌 詠花 作者不詳 |
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1975】 語義 意味・活用・接続 |
| あままあけて [雨間開而] |
| あまま [雨間] |
雨の晴れ間 |
| あけ [開く] |
[他カ下二・連用形] すきま・切れ目などを作る |
| て [接続助詞] |
[単純接続] ~て・そして |
連用形につく |
| くにみもせむを [國見毛将為乎] |
| くにみ [国見] |
山や岡の上に登って国土を眺めること |
| ふるさとの [故郷之] 一般的には平城遷都後の飛鳥旧京と言われている |
| はなたちばなは [花橘者] |
| ちりにけむかも [散家武可聞] |
| に [格助詞] |
[強調] ~に |
連用形につく |
| 〔接続〕格助詞「に」は体言、活用語の連体形に付くのが普通だが、強調の場合は連用形 |
| けむ [助動詞・けむ] |
[過去推量・連体形] ~ただろう・~ていただろう |
連用形につく |
| かも [終助詞] |
[詠嘆・感動] ~であることよ |
連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [あけて] |
この語句の「あけ」は、動詞「開く」のことだが
その動詞は、自動詞、他動詞で活用形が違う
| 動詞「開く」 |
| 自動詞カ行四段 |
閉じてあるものなどが開く・あく・すき間、切れ目などができる |
| 他動詞カ行下二段 |
閉じられているものなどを開ける・すき間、切れ目などをつくる |
初句の意味を考える以前に、文法上の用法で、どちらかが決まってしまう
接続助詞「て」には、連用形がつくので、
この動詞の連用形が「あけ」になるのは、下二段動詞になる
すると、初句の意味が、何となく簡単にはいかないような...
「雨間」の意味からすると、
自然に晴れ間がのぞくような感じなので、自動詞かと思っていたが
他動詞だとなると、作者が「晴れ間」を作るような意味になる
それは、どういうことだろうか...
「晴れ間」を作る、というのは現実的ではないので、考えられるのは
「晴れ間」を「待つ」ということなのだと思う
それに沿った訳し方にならなければ、この語句の意を感じられないと思う
|
| |
| [くにみ] |
どの古語辞典でも、天皇が高い所に登って、国土を望み見ること、という説明が最初にある
それしか書いていない古語辞典もあれば、豊穣を祈る儀礼も付け加える辞書もある
更には、「天皇」を「為政者」に置き換えて記するのは、親切なことだと思う
私も、「国見」とは天皇の巡検のようなものかと思っていたが
この掲題歌の「国見」と言う語、そしてこの歌の「作者不詳」、
それをも頭に入れて感じなければならないようだ |
| |
| |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[本文]「雨間開而 國見毛将為乎 故卿之 花橘者 散家牟可聞」(「【】」は編集、歌番は旧)
「アママアケテ クニミモセムヲ フルサトノ ハナタチハナハ チリニケムカモ」 |
| 〔本文〕頭注に『神田本(紀州本)』コノ歌ナシ。但〔1974〕ノ歌ノ下ニ別筆ニテ書キ底本ノ如キ位置ニ入ルベキ記号ヲ附セリ。コレニテ校ス。『西本願寺本・大矢本・京都大学本』訓ニ朱ノ合点アリ。 |
| 「開」 |
『類聚古集』「開【だと思うが崩れていて読みにくい】」
『神田本(紀州本)』下ニ小字「曽⊓」アリ【「⊓」が解らない、もっと幅がある】 |
| 「卿」 |
『神田本(紀州本)・西本願寺本・細井本・京都大学本・活字無訓本・神宮文庫本』「郷」
|
| 「牟」 |
『元暦校本・類聚古集・神田本(紀州本)・天治本・京都大学本』「武」 |
| 〔訓〕 |
| アママアケテ |
『元暦校本』「あまゝあきて」。「あき」ノ右ニ赭「ハレ」アリ。
『類聚古集』「あまゝわけて」。
『神田本(紀州本)』「アマハレテ」。漢字ノ左ニ「アマアケテ 江」アリ
『京都大学本』漢字ノ左ニ赭「アマハレテ」アリ
|
| クニミモセムヲ |
『類聚古集』「くにみもせむに」。墨ニテ下ノ「に」ヲ消セリ。ソノ右ニ墨「を」アリ
『神田本(紀州本)』「クニミモセンヲ」
|
| チリニケムカモ |
『類聚古集』「さきにけむかも」
『大矢本』「ニ」ナシ
『近衛本』底本ニ同ジ。但「ニ」ハ後筆カ
|
| 〔諸説〕 |
| ○[アママアケテ]。『万葉考』「アメハレテ」。 |
|
【左頁資料について】
| 『万葉拾穂抄』 |
また登場した「見安」、どうしてもその正体が解らず、いつもそこで止ってしまう
そして、何も解決しないまま、通り越せば、またお目にかかる
「見安」とは、誰なのか...この書を冒頭から読み直してみる
最初に現れるのは、巻第一の四番からだ
しかし、いきなり登場して、そこでも何も正体の手掛かりも掴めない
随所に現れる「見安」...辞書を片っ端から引いても見当たらない
思い余って、「見」と「安」を別々に引いて、組み立ててみた
そうなると、固有名詞ではなく、「見安」そのものの意味のようなものが、
おぼろげに見えて来る
それが確実に当っているか解らないが、少しは気休めにはなる
私が、現段階で出した「見安」の正体「らしき」ものは、
「見」の「見て思う・判断する」、そして「安」の「責任や困難がなく、気楽である」
この二つを底に置い著者の「意見」ではないのだろうか
もっとも、この著書には「愚案」というものも随所にあるので、
私の憶測もいい加減かもしれないが...暫くは、そう思っておこう
「あままあけて」が、すでに雨は止み今は晴れている、と解釈
|
| 『万葉代匠記(精撰本)』 |
| ここで言う「今は」というのは、万葉の時代は違った意味を持っていた、ということだろうか |
| 『万葉集童蒙抄』 |
「あままあけて」は、雨の合間、という解釈
「国見」という語については、単に巡検の意味合いに捉えているのかな |
| 『万葉考』 |
この解釈には、それまでにない新しさがある
国見をしようとしていたら、この雨...
国見もしない間に、橘の花も散ってしまうのか...
私が理解したこの解釈、結句は、巻第十五・3681の集中二例しかない「ちりにけむかも」
それに通じるもののように思える
単純に「散ってしまっただろうか」と言うのではなく
その〔3681〕のように、それほど空しく時を過ごしてしまう、という意味が強くなるものだ
雨のせいで、国見も遅れがちになり、橘の花も散るほどに時が...と
真淵の解釈は、そうではないかと思う
そして、「ふるさと」は「飛鳥藤原」のことだという
確かに万葉の時代の「古京」で該当するのは、「飛鳥藤原」だとは思うが
そうなると、「国見」の意味もまた、重たくなってくる、と思う |
| 『万葉集略解』 |
| 真淵の解釈を倣っている |
| 『万葉集古義』 |
| これも同じで、そのやはり真淵の影響は大きいのだろう |
| 『万葉集新考』 |
| 誤字説は解ったが、「国見」の理解は「歩くこと」か...私にはなかなか読み取れない |
| 『口訳万葉集』 |
この解釈では、この歌は一気に情況が変わってしまう
雨の続く晴れ間に、登って野原を眺めようと思うが...
すでに、作者は飛鳥にいて、このさびれた在所飛鳥の橘の花は、散ってしまったろうか、と
「国見」が単なる高いところからの眺望になっている |
| 『万葉集全釈』 |
ここでは、雨が上がって、晴れるのを待ってから、
旧都の花橘を高い所から見下すことが当初の目的だったように解釈する
それなのに、雨が降り続いているうちに、花橘は散ってしまうのだろう、惜しいものだ、と
私も、同じように解釈している
|
| 『万葉集全註釈』 |
| 明日香と思われる故郷を懐かしむ歌、と解釈している |
| 『万葉集私注』 |
「国見」する者を、故郷に「田庄」を持つ者として、
その様子を見るついでに花橘を見ようとするが、長雨のせいで、その機会を失い
花はもう散ってしまっただろう、と |
| 『万葉集注釈』 |
| 歌意に特筆なし |
|
|
|
|
| |

|
 |
| |
| |
| |
| |
| |
「わがまつあきは」...ちかづくらしも...
|
| 『望秋』 |
| 【歌意1976】 |
野辺には、もうこんなに、なでしこの花が咲いている
私が待ち遠しく思っている秋が、近づいているのだなあ |
|
| |
| |
作者の心に、詠う言葉そのままの「秋を待ち望む」気持ちが溢れている
深く詮索は無用、と言わんばかりの、素直な歌だと思う
だから、歌意を左右するような異訓もなく、
詠い伝わってきたのだと思う
少々専門家を困らせかねない簡明な歌だから
『全註釈』では、待ちかねた「秋」を「なでしこの美しさ」に寄せて
こんなに美しい花を咲かせる秋なんだから、とか
『私注』のように、「君が設ける」という表現は、
逆に言えば、簡明簡潔最も素直に心に響く歌心、と言うものではないか、と思う
ただし、『私注』のいう「君」を、「なでしこ」と私は解釈したので、そう思うのだが
実際は、別の意味の「君」を『私注』は言っているのかもしれないが...
もう一つ、『代匠記』の注釈で述べられている内容、私の理解不足もあるかもしれないが
季節の訪れを知るのに、こうした花が咲いたり、鳥の初声などを詠うことによって
その歓びや過ぎ行く季節を惜しむような心情、さらには
その鳥と逢わなくなって、花の散るのを知るとか...
「歌の表現」の仕方を、に少しばかり述べている
と、読めたつもりでいるが、どうも江戸時代の言葉というのは、解るようで解らない
古語辞典も、中心は「古語」だから、辞書ではなかなか江戸時代の表現をつかみにくい
|
|
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
| 野へみれはなてしこの花ちりにけり わかまつ秋はちかつきぬらし |
| 新編私家集大成-新編増補(陽明文庫蔵三十六人集) 140 |
| のへみれはなてしこの花ちりにけり わかまつあきはちかつきにけり |
| 新編私家集大成(書陵部蔵三十六人集) 127 |
| のへみれはなてしこのはなちりけり わかまつ秋はちかつきにけり |
| 新編国歌大観(西本願寺蔵三十六人集) 247 |
【後撰和歌集 [天徳ニ年(958)頃、宮中の梨壺(昭陽舎)、撰源順・紀時文・坂上望城等]】
| なでしこの花ちりがたになりにけりわがまつ秋ぞちかくなるらし |
| 新編国歌大観第一巻2 [日本大学総合図書館蔵本] 第四 夏 題しらず よみ人も 204 |
|
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1976] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔のへ見れはなてしこの花咲にけりわかまつ秋はちかつくらしも 〕
野邊見者瞿麦之花咲家里吾待秋者近就良思母
|
| のへみれはなてしこの 秋まつ心にて心明也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
| |
野邊見者瞿麥之花咲家里吾待秋者近就良思母
〔ノヘミレハナテシコノハナサキニケリワカマツアキハチカツクラシモ〕 |
| 後撰集には、なでし子の花散方に成にけり、我待秋ぞ近く成らしとよめり、今の歌と違へるやうなれど歌はかやうなる常の事なり、秋の物にしてよめる歌も多し、此卷下に至て雁の初聲を聞て芽子[ハキ]の咲とよめるに、又雁にあはじとにや聲を聞ては散ともよめり、萬此等に准らふべし、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
野邊見者瞿麥之花咲家里吾待秋者近就良思母
〔のべみれば、なでしこのはな、さきにけり、わがまつあきは、ちかづくらしも 〕 |
| 秋は千種の花咲かん野邊なれば、我待つ野邊ともよめるなるべし。よく聞えたる歌也。後撰、なでしこの花散かたになりにけり吾待つ秋ぞ近くなるらし。此歌などによりて詠める歟 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
野邊見者、瞿麥之花、咲家里、吾待秋者、近就[チカヅク]良思母、 意明なり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
| |
野邊見者。瞿麥之花。咲家里。吾待秋者。近就良思母。
〔ぬべみれば。なでしこのはな。さきにけり。わがまつあきは。ちかづくらしも。〕 |
| 記なし |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔ヌヘミレバ。ナデシコノハナ。サキニケリ。アカマツアキハ。チカヅクラシモ。〕
野邊見者瞿麥之花咲家里吾待秋者近就良思母
|
| 歌(ノ)意かくれたるところなし、瞿麥は、夏の末より、秋かけてさくものなれば、かくいへり、後撰集に、なでしこの花ちりがたに成にけりわが待秋ぞちかくなるらし、似たる歌なり、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔野邊みればなでしこの花さきにけりわがまつ秋はちかづくらしも 〕
野邊見者瞿麦之花咲家里吾待秋者近就良思母 |
| 記なし |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
| |
野邊見れば、撫子の花咲きにけり。我が待つ秋は近づくらしも |
| |
野を見ると、もう撫子の花が咲いたことだ。私の待ちうけた秋は、近寄つて來てるに違ひない。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔野べ見れば なでしこの花 咲きにけり 吾がまつ秋は 近づくらしも〕
ヌベミレバ ナデシコノハナ サキニケリ ワガマツアキハ チカヅクラシモ
野邊見者瞿麥之花咲家里吾待秋者近就良思母 |
野原ヲ見ルト撫子ノ花ガ咲イタヨ。コノ花ガ咲イタカラニハ、ワタシノ樂シミニシテ待ツテヰル秋ハ近クナツテ來タラシイヨ。嬉シイナア。
〔評〕三句切の、さつぱりした歌である。爽快な秋を愛した上代人の氣分が出てゐる。後撰集に「なでしこの花ちりがたに成りにけりわがまつ秋ぞ近くなるらし」とあるのは、これを少し改めたのであらう |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔野邊見れば なでしこの花 咲きにけり。わが待つ秋は 近づくらしも。〕
ノベミレバ ナデシコノハナ サキニケリ ワガマツアキハ チカヅクラシモ
野邊見者瞿麥之花咲家里吾待秋者近就良思母 |
【譯】野邊を見れば、ナデシコの花は咲いている。わたしの待つ秋は、近づくらしい。
【釋】瞿麥之花 ナデシコノハナ。ナデシコは、一九七〇の石竹に同じ。本集では、石竹、瞿麥兩用し、また牛麥花とも書いている。
【評語】ナデシコの花の咲くにつけて、秋の近づくのを喜んでいる。夏の暑さに堪えかねる心であり、また秋の花を愛する心でもあろうが、そうとはいわないで、ナデシコの花に寄せて美しい歌を成している。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| |
〔ヌベミレバ ナデシコノハナ サキニケリ ワガマツアキハ チカヅクラシモ〕
野邊見者瞿麥之花咲家里吾待秋者近就良思母 |
【大意】野べを見れば、撫子の花が咲いた。君が待ち設ける秋は、近づくらしい。
【作意】簡素で心持の通つた作である。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
| |
〔ノベミレバ ナデシコノハナ サキニケリ ワガマツアキハ チカヅクラシモ〕
野邊見者瞿麥之花咲家里吾待秋者近就良思母 (『元暦校本』) |
【口訳】野辺を見るとなでしこの花が咲いたよ。私の待つている秋が近づくらしいよ。
【訓釈】瞿麥の花咲きにけり―これもなでしこが夏から咲く例の一つである(3・408)。
【考】赤人集(流布本も)第三句「散りにけり」結句「近つきにけり」とある。
なでしこの花散り方になりにけりわが待つ秋ぞちかくなるらし (後撰集巻四) よみ人しらず
異伝とも見るべきものである。 |
|
|
掲載日:2014.04.05.
| 夏雑歌 詠花 |
| 野邊見者 瞿麦之花 咲家里 吾待秋者 近就良思母 |
| 野辺見ればなでしこの花咲きにけり我が待つ秋は近づくらしも |
| のへみれば なでしこのはな さきにけり わがまつあきは ちかづくらしも |
| 巻第十 1976 夏雑歌 詠花 作者不詳 |
【赤人集】〔140・127・247〕
【後撰和歌集】〔204〕
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1976】 語義 意味・活用・接続 |
| のへみれば [野邊見者] |
| みれ [見る] |
[他マ上一・已然形] 目にとめる・目にする・眺める |
| ば [接続助詞] |
[順接の確定条件] ~すると |
已然形につく |
| なでしこのはな [瞿麦之花] |
| さきにけり [咲家里] |
| に [助動詞・ぬ] |
[完了・連用形] ~てしまう・~てしまった |
連用形につく |
| けり [助動詞・けり] |
[過去(詠嘆)・終止形] ~たことよ・~ことよ |
連用形につく |
| わがまつあきは [吾待秋者] |
| ちかづくらしも [近就良思母] |
| ちかづく [近づく] |
[自カ四・終止形] 近寄る・接近する・時期が近くなる |
| らし [助動詞・らし] |
[原因推定・終止形] ~(と)いうので~らしい |
終止形につく |
| も [終助詞] |
[詠嘆・感動] ~よ・~なあ 〔接続〕文末、文節末の種々の語につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [なでしこのはな] |
この語句は、従来より「なでしこのはな」と訓まれていたのを、
最近の注釈書では、「なでしこがはな」とされ始めている
何がきっかけで、「改訓」がなされたのか解らないが
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波文庫校訂版、平成25年~〕、
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕、
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕辺りから、この訓が目立つ
しかし、この「改訓」についての、それぞれの「注記」では言及されておらず
唯一、小学館の『新全集』が、簡単に説明していた
| 『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕[なでしこがはな] |
| ナデシコは、連体格助詞として「ノ」より「ガ」をとる方が多い。原文に「瞿麦之花」とあり、その「瞿麦」は石竹の異名で、かわらなでしことは小異がある。 |
近年の他の注釈書すべてを見たわけでないので、これがきっかけとは思わないが
少なくとも、このような簡単な説明文すら他には載らないところをみると、
近年の訓は、「なでしこがはな」が、通説なのかもしれない
この『新全集』の「頭注」で、思わぬ文章に遭遇した
原文の「瞿麦」は「石竹」の異名で、かわらなでしことは「違う」という文章だ
あれっ、と思う
この歌のニ首前〔1974〕では、「石竹之」を、やはり「なでしこが」と訓じており
その訓もまた、今回と同じように従来は「なでしこの」が通っていた
だから、この歌で「が」に私が注目したという訳ではなく
私が、驚いたのは、この『新全集』の「なでしこ」の解説の仕方だ
〔1974〕では、原文「石竹」を「かわらなでしこ。秋の七種の一つ。」
〔1976〕では、原文「瞿麦」は「石竹」の異名で、「かわらなでしことは小異がある。」
「かわらなでしこ」と違うのなら、「瞿麦」の異名とはならない
「小異」というのは、どの程度のことをいうのか、説明は書いてなかった
|
| |
| |
| |
| |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[本文]「野邊見者 瞿麥之花 咲家里 吾待秋者 近就良思母」(「【】」は編集、歌番は旧)
「ノヘミレハ ナテシコノハナ サキニケリ ワカマツアキハ チカツクラシモ」 |
〔本文〕頭注に『類聚古集』前行ニ「ニ首無作者」アリ。ニ首ハコノ歌ト〔1970〕トヲ指セリ
赤人集「のへみれはなてしこのはなちりにけりわかまつ秋はちかつきにけり」 |
| 「麥」 |
『大矢本』「【判読出来ず】」消セリ。左ニ「麦」アリ
『近衛本』底本ニ同ジ |
| 「思」 |
『神田本(紀州本)』ナシ |
| 「母」 |
『類聚古集』「毛」 |
| 〔訓〕 |
| チカツクラシモ |
『類聚古集』「ちかつきにけり」。墨ニテ「きにけり」ヲ消セリ。ソノ右ニ朱「クラシモ」アリ
『神宮文庫本・細井本』「チカクツクラシモ」
|
| 〔諸説〕 |
| ○ |
|
【左頁資料について】
| 『万葉拾穂抄』 |
「心明」、この著者はよくこの語を使うようだ
|
| 『万葉代匠記(精撰本)』 |
後撰集の歌を引き出して、この歌の心を解説している
初雁の声を聞いて、秋萩が咲くというようなものだし... |
| 『万葉集童蒙抄』 |
秋は千種の花が咲く野辺だから、私は秋が好きなんだ、という
後撰の歌は、この歌を本歌にしているかもしれない、と |
| 『万葉考』 |
| 「意明」、真淵もこの語をよく使う |
| 『万葉集略解』 |
| 記なし |
| 『万葉集古義』 |
ナデシコは、晩夏から初秋にかけて咲くものなので、こういう歌が詠われたのだろう、とする
歌意については、有り触れているが、後撰集に似た歌がある、としている |
| 『万葉集新考』 |
| 記なし |
| 『口訳万葉集』 |
この訳では、「らし」を「推定」の解釈にしているが、
眼前にナデシコが咲いている明らかな事実に基づいているので、
「原因推定」の訳しかたの方がいいと思う |
| 『万葉集全釈』 |
待ち望む秋を、全面に出した解釈だ
|
| 『万葉集全註釈』 |
秋の待望を言葉に出さず、ナデシコの花に寄せて、美しい歌、という
初期の注釈書の時代と、その評価は大きく変わってきている |
| 『万葉集私注』 |
| 「君」とは、人のことではなく、「なでしこ」のことなのだろうか |
| 『万葉集注釈』 |
| 歌意に特筆なし |
|
|
|
|

| |
| 「あふちのはなは」...ちりすぎず... |
| |
| 『そのままで』 |
| 【歌意1977】 |
あふちの花、その名を聞くと、
いとしい妻に逢いたいと思わずにはいられない
だから、すっかり散ってしまうことなく、
今咲いているそのままで、
ずっといてほしいと、願っているよ |
| |
| |
「散り過ぐ」という語に、心情的な落ち着きを感じられる
咲く花は、散るものだ
散るからこそ、花は輝く
しかし、すっかり散ってしまっては、心惜しい花もある
それが、その名を心地よく響かせる「あふちの花」だ
「逢ふ」花だからこそ、お前だけはすべて散って終らせないでくれ
せめて、その名のように、「逢ふ」ことへの想いだけは、いつも心に留めておきたい
散るものと解っていても、散ってくれるな、と叫びたくなる時がある
しかし、「散り過ぐ」という語には、「散る」意味が多分にある
古語辞典では「すっかり散ってしまう」という言い方で載っていたが
そのかすかな「望み」、たとえ一輪の花でも残っておれば、
いとしい妻に、いつも逢いたいと忘れずに想えるものだ、と
あるいは、その一輪に、妻自身の面影を見出しているのかもしれない
逢いたい、ということは、その対象が「あふちの花」で想い起されるのなら
確かに、「あふちの花」自身を、「妻の面影」に見立ててもいいように思う
同じように「ちりすぐ」や、「いまさけるごと」、「ありこせぬかも」を用いた類想歌がある
この三語を用いれば、間違いなくその歌意は、同じものになるだろう
有名な梅花三十ニ首の宴席歌にある
| |
| 梅花歌(卅二首) |
| 烏梅能波奈 伊麻佐家留期等 知利須義受 和我覇能曽能尓 阿利己世奴加毛[少貳小野大夫] |
| 梅の花今咲けるごと散り過ぎず我が家の園にありこせぬかも[少貳小野大夫] |
| うめのはな いまさけるごと ちりすぎず わがへのそのに ありこせぬかも |
| 巻第五 820 梅花歌 小野老 |
〔語義〕
「わがへのそのに」は、本来は大宰帥大伴旅人の邸での宴席歌であるが、
この場合の客人たちは、ときに主人の立場になって詠うことも多く
この「わがへのその」と言うのは、当然作者の家ではなく、
主人である大伴旅人の家の庭のことになる
「その」は、塀で囲んだ中国風の庭、という |
〔歌意〕
梅の花、今咲いているそのままで、
すっかり散ってしまわないように、我が家の庭で
いつまでも咲いていてほしいものだ |
花が、「あふちの花」から「梅の花」に変わるので
当然、「わぎもこに あふちのはなは」という枕詞や掛詞のような深みはなくなるが
それでも「散り過ぐ」の語と、「いまさけるごと」、「ありこせぬかも」で、
散るのは構わないが、少しでもたとえ一輪でも残って、今のように咲いていて欲しい
その心情はよく伝わってくる
「ちりすぎず ありこせぬかも」...いい言葉だと思う |
| |
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
| わきもこかあふちの花はちり過て いもさけることありとかきく |
| 新編私家集大成-新編増補[陽明文庫蔵三十六人集] 141 |
| わきもこかあふちのはなは散にけり いもはきけるかことありとかきく |
| 新編私家集大成[書陵部蔵三十六人集] 128 |
| わきもこにあふちのはなはちりにけり きていもさけることありとかきく (本) |
| 新編国歌大観[西本願寺蔵三十六人集] 248 |
【古今和歌六帖 (成立年代未詳[永延元年(987年)か]撰、兼明親王あるいは源順が有力)】
| 我がやどにあふちのはなはさきたれどなにしもおはぬ物にぞ有りける |
| 新編国歌大観第二巻4 [宮内庁書陵部蔵五一〇・三四] 第六 あふち 4291 つらゆき |
|
|
掲載日:2014.04.06.
| |
| 夏雑歌 詠花 |
| 吾妹子尓 相市乃花波 落不過 今咲有如 有与奴香聞 |
| 我妹子に楝の花は散り過ぎず今咲けるごとありこせぬかも |
| わぎもこに あふちのはなは ちりすぎず いまさけるごと ありこせぬかも |
| 巻第十 1977 夏雑歌 詠花 作者不詳 |
【赤人集】〔141・128・248〕
【古今和歌六帖】〔4291〕
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
| 【1977】 語義 意味・活用・接続 |
| わぎもこに [吾妹子尓] [枕詞]「あふちの花」にかかる |
| あふちのはなは [相市乃花波] |
| あふち [楝・樗] |
[木の名] せんだん、初夏、薄紫の小さな花が咲く |
| ちりすぎず [落不過] |
| ちりすぎ [散り過ぐ] |
[自ガ上二・未然形] すっかり散ってしまう |
| いまさけるごと [今咲有如] |
| る [助動詞・り] |
[完了・連体形] ~ている・~てある |
已然形につく |
| ごと [如] |
[比況の助動詞「ごとし」の語幹] ~のように・~のようだ |
連体形につく |
| ありこせぬかも [有与奴香聞] |
| ありこせ [有りこす] |
[複合語・未然形] そうあってほしいと思う |
| ぬ [助動詞・ず] |
[打消・連体形] ~ない |
未然形につく |
| かも [終助詞] |
[感動・詠嘆] ~であることよ |
連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [あふち] |
枕詞の「わぎもこに」が、「あふ」を掛詞として、この「あふちのはな」にかかる
「あふち」はセンダン科の落葉高木
現在では「栴檀(せんだん)」と称するらしいが、
香木の「栴檀(せんだん)」とは別種とされる
本州中部以南の暖地に多く自生するが、植栽もされている
高さ、7~8mに達するものもある
五、六月頃、淡い紫色の美しい小花をつける
[万葉の植物Ⅱ あふち]
|
| |
| [ごと] |
比況の助動詞「ごとし」の語幹
連用修飾語となって、「~のように」、
述語となって、「~のようだ」、と用いられる
接続は、体言及び副詞「かく」「さ」に、助詞「の」がついたものや
活用語の連体形および代名詞「吾(あ)」「我(わ)」に助詞「が」が付いたものにつく
|
|
| |
| [ありこせぬかも] |
この語句をそのまま直訳すると、「そうであってくれないかなあ」
だから、「そうであってほしいものだ」となる訳だが、
助動詞「こす」が、上代語の、「あつらえ望む意」を表し「~てほしい・~てくれ」、
活用は、未然形「こせ」、終止形「こす」、命令形「こそ(こせ)」しかなく、
終止形「こす」は、禁止の助詞「な」を伴って、「~てくれるな」の意で用いられ、
命令形の「こせ」は、平安時代になって生じた形、とある
この「こす」の成立ちについては、
「おこす」の頭母音の脱落した形とも、
「来(こ)為(す)」かたとも、助詞「こそ」が活用したもの、とも諸説がある
接続は、動詞の連用形につく
|
| |
| |

|
| 掲題歌[1977]についての資料 |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「吾妹子爾相市乃花波落不過今咲有如有與奴香聞」
「ワキモコニ アフチノハナハ チリスキヌ イマサケルコト アリソハヌカモ」(「【】」は編集、歌番は旧) |
| 〔本文〕頭注に『類聚古集』本文ノ下ニ朱小字「無作者」アリ。 赤人集「わきもこにあふちのはなはちりにけりきていもさけることありとかきく 本」 |
| 「奴」 |
『類聚古集』「妹」。右ニ朱「珠○【○判読出来ず】」アリ
|
| 〔訓〕 |
| ワキモコニ |
『類聚古集』「わかいもに」
『細井本』「吾妹」ノ左ニ「ワカイモ」アリ
『神宮文庫本』「キ」ハ「カ」ヲ磨リ消セル上ニ書ケリ。「吾妹」ノ左ニ「ワカイモ」アリ
『大矢本』「ワカモコニ」「カ」ヲ朱ニテ消セリ。右ニ「キ」アリ
『近衛本』底本ニ同ジ
|
| チリスキヌ |
『元暦校本・類聚古集』「ちりすきす」
『神田本』「チリスキス」
|
| イマサケルコト アリソハヌカモ |
『元暦校本』「ソハヌカモ」ナシ。「こと」ノ右ニ赭「アラム」アリ
『類聚古集』「あるはたまかも」
『神田本』「アヘルイモカモ」
『西本願寺本』「アリソハヌ」モト青
『大矢本・京都大学本』「アリソハヌ」青。『京』漢字ノ左ニ赭「アヘイモカモ」アリ。赭ニテ右ノ訓ト入レ換フ可キヲ示セリ |
| 〔諸説〕 |
| ○[チリスキヌ]『代匠記(初稿本)』「チリスキス」。○[有與奴香聞アリソハヌカモ]『代匠記(初稿本)』「與」ハ「興」ノ誤。訓「アリコセヌカモ」。『童蒙抄』「アリタヘヌカモ」。『万葉考』「與」ハ「乞」ノ誤。 |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1977] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
| |
〔わきもこにあふちの花はちり過すいまさけることありそはぬかも 〕
吾妹子尓相市乃花波落不過今咲有如有與奴香聞
|
旧訓「ありそはぬかも」、諸本は殆どが「アリソハヌ」
まだこの時代では、「アリコセ」は訓まれない
「名はあふちもかひなし」とは、「あふち」と言う名も、
効き目がないようだ、と読めば
その前にいう「珍らかに有そはまほしき」という意味が、
何となく解るが...私には、ここは難しい |
| わきもこにあふちの 妹にあふと樗をそへて也散過す今咲し如く珍らかに有そはまほしきに名はあふちもかひなしと也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
| |
〔ワキモコニアフチノハナハチリスキヌイマサケルコトアリソハヌカモ
吾妹子爾相市乃花波落不過今咲有如有與奴香聞 |
底本そのままに「チリスキヌ」をあげ、
これは「チリスギズ」と伝写の段階での誤とする
「チリスギズ」「アリコセヌカモ」、現訓の基がこの書ということか |
落不過[六帖云、チリスキテ、]
發句は相坂山などつゞくる如くあふちと云はむためなり、腰句はチリスギズと讀べし、スギヌと有は傳寫の誤なるべし、落句は今の點叶はず、六帖にあらむいもかもとあるは讀かねて改けるにや、今按アリコセヌカモと讀べし、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
| |
〔わぎもこに、あふちのはなは、ちりすぎず、いまさけるごと、あり與ぬかも 〕
吾妹子爾相市乃花波落不過今咲有如有與奴香聞 |
「あふちの花」と詠いたいが為に「わぎもこに」と詠い出した、という解釈なのだろうか
そして、その「あふ」には、「珍らしき」という、ここではおそらく「愛らしい・かわいい」という意味も具わっている、ということなのだろ
今でも「あふち」を辞書で引くと「楝・樗」と引けるが、
「樗」は「ぬで」と訓むのか、そのことを憤慨している感じだ
やけに「あふち」に拘るのは、「わぎもこに」にかかるから、その掛詞としての重要性を言っているのかもしれない
「落不過」(チリスギズ)は、今を盛りということらしい
私は、「散り切らない」と感じた方がいいと思う
結句については、誤字説など、やたらと賑やかに書いているが
結局は、「歌によりて」というのは、歌意に沿って、決めなければならない、と言うことなのだろうかな |
相市 わぎも子にあふとうけたり。あふちの花と云はんとて、わぎも子にと詠出たり。珍らしきと云ふ意をも含めたるか。和名抄、草木部木類云、楝、玉篇云、〔音練〕本草云、阿布智、其子如榴類、白而黐〔可以浣衣者也〕今樗の字をあふちと讀ます、これはぬでと讀む字也。然るを何としてか、ぬでとあふちを取替たる事不審望。扨又今世に云ふ處のあふちは、俗に栴檀の木とも云也。此誤ども未考定也。楝の子如榴類、とあれば、今云栴檀とも不合也。落不過なれば今を盛と云ふ意也。よりて直に今咲ける如くとよめり
有與 ありたへぬかもと讀ませたるか。此通にてあらぬかもあれかしの意也。興の字の誤りにてこせぬか、おこすと讀む故さしすせ同音也。又た輿の字の誤り歟。これにても、こしぬかも、こしぬも、こせぬも同前也。なれ共字の儘にて、たへぬと讀みて義通ずれば、たへぬと讀ませたる義ならんか。此字は樣々に誤りたる事あまた有。歌によりて辨ふべき事也
|
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
| |
吾妹子爾、相市乃花波[アフチノハナハ]、落不過[チリスギズ]、今咲有如[サケルコト]、有乞奴[アリコセヌ]香聞、 |
結句の「與」を「乞」に改訓して歌意に合わせる |
相市は借字楝なり
初めの吾妹子はあふといはんのみ今本乞を与と誤れること既いふ如くなれば改むありこせぬのぬは後にたゞぬてふにてね又はなに通ひて今咲る如くありこそよとねがふ意なり
|
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
| |
〔わぎもこに。あふちのはなは。ちりすぎず。いまさけるごと。ありこせぬかも。〕
吾妹子爾。相市乃花波。落不過。今咲有如。有與奴香聞。 |
「ちりすぎず」とは、「いつも散らず」という意味なのかなあ
真淵説「與」は「乞」の誤説を継ぐ |
| 乞を與に誤れり。楝[アフチ]を妹に逢ふに言ひ懸けて、いつも散らずして、今咲きたる如く有れかしと願ふなり。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
| |
〔ワギモコニ。アフチノハナハ。チリスギズ。イマサケルゴト。アリコセヌカモ。〕
吾妹子爾相市乃花波落不遇今咲有如有與奴香聞
|
特に目新しい説なし |
| 吾妹子爾[ワギモコニ]は、枕詞なり、妹に逢(フ)といひかけたり、○有與奴香聞[アリコセヌカモ]は、嗚呼いかで有かし、と希望ふ意なり、○歌(ノ)意は、あふちの花は散失ずして、いつも今(ノ)目前に咲たる如く、嗚呼いかで常に有かしとなり、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
| |
〔(吾妹子に)あふちの花はちりすぎず今さけるごとありこせぬかも 〕
吾妹子爾相市乃花波落不過今咲有如有與奴香聞 |
どんどん「ちりすぎず」が、語感から遠のいていく感じがする |
| ワギモコニは枕辭なり。チリスギズは散ラデなり。四五は今サケル如クイツモ盛デアレカシとなり |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| |
吾妹子に樗[アフチ]の花は、散り過ぎぬ。今咲けるごと、ありこせぬか |
この解釈で、やっと少しは理解出来るようになった
「散ってしまわずに」や、「まるで今咲いたように」というニュアンスが、私には理解出来る
しかし、あの人の逢いに来る時分、というのが気に入らない
普段、なかなか逢うことも叶わないからこそ、
「あふちの花」に、その願いを託している歌だと思う |
| |
いとしい人に逢ふといふ名の樗の花は、何時迄も散つて了はずに居て、あの人の逢ひに來る時分には、まるで今咲いたやうにあつてくれゝば好いが。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
| |
〔吾妹子に あふちの花は 散りすぎず 今咲けるごと ありこせぬかも〕
ワギモコニ アフチノハナハ チリスギズ イマサケルゴト アリコセヌカモ
吾妹子爾相市乃花波落不過今咲有如有與奴香聞 |
「真っ盛り」...そうなのかなあ
待ち望む秋を、全面に出した解釈だ
〔評〕に余計な解釈が見られる
確かに、可憐な花には違いないが、「かういふ花を愛するのは、支那に倣ったのではなく、真の国民的趣味に出てゐるやうだ」と
万葉の時代のうたと、戦前の国民感情を重ね過ぎているように思う |
(吾妹子爾)楝ノ花ハイツマデモ落リ失セナイデ、今咲イテヰルヤウニ、眞盛デアツテクレナイカナア。
○吾妹子爾[ワギモコニ]――相市[アフチ]につづく枕詞。逢ふにかけてある。
○相市乃花波[アフチノハナハ]――アフチは楝、五月の頃、薄紫の可憐な花を開く。卷五(七八九)參照。
〔評〕 初夏の景物として、可憐な楝の花に目を附けたところがよい。かういふ花を愛するのは、支那に倣つたのでなく、眞の國民的趣味に出てゐるやうだ。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
| |
〔吾妹子に あふちの花は 散り過ぎず、今咲ける如 在りこせぬかも。〕
ワギモコニ アフチノハナハ チリスギズ イマサケルゴト アリコセヌカモ
吾妹子尓相市乃花波落不過今咲有如有與奴香聞 |
その名に願掛けて、あふちの花が散ってしまえば、逢えない
そんな感じをも受ける解釈になる
実際の解釈は違うだろうが、「逢う」と「あふち」を掛けるなら
その方がいいのかもしれない |
【譯】わたしの愛人にあう。そのオウチの花は、散つてしまわないで、今咲いているように、咲いていてくれないかなあ。
【釋】吾妹子尓 ワギモコニ。枕詞。吾妹子に逢うというので、アフチに冠している。
相市乃花波 アフチノハナハ。アフチは、オウチ科の落葉喬木、オウチ。五月頃淡紫色のちいさい花をつける。
有與奴香聞 アリコセヌカモ。コセは自分にそうなつてあらわれる意の助動詞で、多くは動詞アリに接續して使われている。
【評語】オウチの花のような目立たない花をも愛している。初句の枕詞も、なつかしみを出す上に役立つている。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
| |
〔吾妹子にあふちの花は散り過ぎず今咲ける如有りこせぬかも〕
ワギモコニ アフチノハナハ チリスギズ イマサケルゴト アリコセヌカモ
吾妹子尓相市乃花波落不過今咲有如有與奴香聞 ガマツアキハ チカヅクラシモ〕 |
「大意」では、「散りすぎずに」とあり、
これからは「盛り」とは汲めない
やはり、散りながらも、すべて散ってしまわないでくれ、という
そんな切ない想いがある歌だ |
【大意】ワギモコニ(枕詞)楝の花は散りすぎすに、今咲いてゐるままで、有つてくれないものだらうか。
【作意】楝の花を惜しむ心であるが、枕詞にも相当の重心がおかれてある。イモニアフのアフをアフチのアフに言ひつづけたのである。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
| |
〔吾妹子に あふちの花は 散り過ぎず 今咲ける如 ありこせぬかも〕
ワギモコニ アフチノハナハ チリスギズ イマサケルゴト アリコセヌカモ
吾妹子尓相市乃花波落不過今咲有如有與奴香聞 (『元暦校本』) |
この歌意もまた、同じように散り行く中でも
すべて散り終わらずに、の気持ちが籠もる解釈だと思う
盛りを願うのは、それこそ途方もない「願い」であるが
せめて少しは残って、そのまま咲いていて欲しい
そう願う歌だからこそ、惹かれると思う |
【口訳】吾妹子にあふ、といふ名の、あふちの花は、散つてしまはないで、今咲いてゐるやうにあつてはくれないかナア。
【訓釈】吾妹子に―吾妹子に逢ふ、と「あふち」の「あふ」をかけた枕詞
あふち―俗にせんだんといふ木(5・798)。九州、四国などの川の堤などに多く見かける。
ありこせぬかも―既出(2・119)。「与」の文字は前(1965)にもあつた。
【考】類歌。
梅の花今咲ける如散り過ぎず吾が家の園にありこせぬかも (5・816) 小野老
古今六帖(六「あふち」)「散り過ぎて」「あらむ妹かも」、赤人集「散りにけりきていもさけることありとかきく本」、流布本「わきも子か」「妹はきけるかこと有とかきく」とある。 |
|
|

| |
| 「ふぢはちりにて」...なにをかも... |
| |
| 『かざしもなくて』 |
| 【歌意1978】 |
春日野に、咲いていた藤の花は、もうみんな散ってしまって
これからは、なにをみ狩の人々は、手折って髪に挿すのだろうか |
| |
| |
歌意そのものは、単純な歌だと思う
もう髪や冠に挿頭す「花」もないのに、一体これからは何を、と
傍観者として気にかける人の詠う歌だ
そして、古注釈書より現在に至るまでも、ほとんどその意は変わらない
歌意に表現する言葉としては、五月五日の「薬狩」こそないが
基本的には、その行事に沿った歌だとされている
しかし、少なくとも下段の資料を見る限り、『全釈』以前では
その「五月五日」の「薬狩」とは一つも語られていない
私は、それが自然だと思う
勿論、「薬狩」かもしれないが、それが「藤の花が散った」とするのが根拠なら
確かにそうかもしれない
しかし、この歌の主眼は、花の失せた春日野で
狩をする人たちは、何をもって「挿す」のだろう、という
おかしいと思った
この行事が恒例であれば、決まって毎年同じような環境のはずだ
何も今に限って、藤が散ったわけでもないだろうし
それを不思議がる必要はない
だとすれば、この「御狩」は、通常の「狩」なのかもしれない
高貴な人に従って「狩」に出た大宮人たち
おそらく、その大宮人たちは、不満も多かったことだろう
せっかくの「狩」なのに、「かざす」花がないではないか、と
それを見遣って、都人たちは、どう思ったのだろう
ただでさえ、花の散った春日野
その荒涼とした風景の中で、狩にくりだす人たち
いっそう、その寂寥感を思ったのではないだろうか
大宮人たちの「かざし」を思い遣りながらも
寂しさのます春日野を、改めて知らされた作者、いや都人の想いなのだろう
私は、そう感じる
春日野辺りに、何度も藤を見に行ったことがある
勿論、藤だけが目当てではないが、植物園とか手入れされた場所ならそうでもないが
ただ野原に、ぽつんと残る藤もある
確かに、花の盛りは、その孤高の美しさもまた胸を打つが
この歌に触れて、その藤の散った後の光景を思い浮かべていた
何もない野原だ
花の季節は、次から次へとやってくる
しかし、私が見たその野原には、確かに藤が一箇所だけあった
それ以外には何もなかった
まさに、この歌の光景を浮かべてしまう
そこに、賑やかに「狩する人」が集まれば
何もないところでのそんな賑わいは...むしろ寂しいだけだろう
|
|
掲載日:2014.04.07.
| |
| 夏雑歌 詠花 |
| 春日野之 藤者散去而 何物鴨 御狩人之 折而将挿頭 |
| 春日野の藤は散りにて何をかもみ狩の人の折りてかざさむ |
| かすがのの ふぢはちりにて なにをかも みかりのひとの をりてかざさむ |
| 巻第十 1978 夏雑歌 詠花 作者不詳 |
【家持集】〔89・81〕
【赤人集】〔142・129・249〕
【古今和歌六帖】〔2320〕
【雲葉和歌集】〔255〕
【夫木和歌抄】〔2163〕
【新千載和歌集】〔180〕
【歌枕名寄】〔1778〕
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
| 【1978】 語義 意味・活用・接続 |
| かすがのの [春日野之] |
| ふぢはちりにて [藤者散去而] |
| ふぢ [藤] |
マメ科の落葉低木 |
| に [助動詞・ぬ] |
[完了・連用形] ~てしまった・~てしまう |
連用形につく |
| て [接続助詞] |
[確定条件(原因・理由)] ~ので |
連用形につく |
| なにをかも [何物鴨] |
| なに [何] |
[不定称指示代名詞] (名前や実体の解らない物事をさす) 何もの・何ごと |
| を [格助詞] |
[動作の対象] ~を(「かざす」対象として) |
体言につく |
| かも [係助詞] |
[疑問] ~か・~だろうか |
体言につく |
| 〔成立〕係助詞「か」に、係助詞「も」係り結びであり、その結びは連体形で終る、結句の「む」 |
| みかりのひとの [御狩人之] |
| み [接頭語] |
名詞について尊敬の意を俵す・尊称 |
| かり [狩り] |
山野で鳥獣を捕らえること・特に鷹狩 、また花・紅葉などを採集すること |
| をりてかざさむ [折而将挿頭] |
| をり [折る] |
[他ラ四・連用形] 折りとる・手(た)折る |
| かざさ [挿頭す] |
[他サ四・未然形] 草木の花や枝、造花などを髪や冠に装飾としてさす |
| む [助動詞・む] |
[推量・連体形] ~だろう 係り結びの「結び」 |
未然形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [かすがの] |
奈良市の若草山・御笠山の西麓に続く台地で、北は佐保川、南は能登川に至る範囲
大宮人の遊楽の地でもあり、そこでの遊興の歌が多く詠われている
|
| |
| [ちりにて] |
旧訓「ちりゆきて」も、無理なく訓めると思うが、
賀茂真淵が「去」を「いぬ」と訓じ、
その「ちりいにて」の「い」が略されて「ちりにて」とする
もともと、契沖の『万葉代匠記』でもその訓の可能性を述べてあったのを
真淵が確定させた感がある
以降、「ちりにて」が通訓となる
|
| |
| [ふぢ] |
山野に自生し、蔓性で右巻きに他の樹木などに巻きついて枝を伸ばす
葉は羽状複葉、花は四、五月頃紫色蝶形花の総状花序をなして垂らす
花序の長さは、三十センチから六十センチ、長いものは一メートルにもなる
変種に白色のものもある
その花房の揺れ動く様子から藤波とも呼ばれる
『万葉集』中二十四首、内十九首は(枕詞二例を含む)「藤波」と称している [万葉の植物Ⅱ ふじ]
|
|
| |
| [みかりのひとの] |
藤が散ってしまった、ということで
五月五日の「薬狩」と解するようだ
その「薬狩」に従う大宮人のこと
「薬狩」は、中国伝来の行事で、薬草を採り鹿の袋角を取るもの、とある
鹿の袋角は、「鹿茸(ろくじょう)」といい、陰干しにして補精強壮剤とされている
日本での行事の記録としては、推古紀十九年五月五日が初出で、
諸臣は礼装で参加したと伝えている
初めは、極めて儀礼性の強いものであったが、奈良遷都後は、遊楽的な趣が強くなっている
|
| |
|
| 掲題歌[1978]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
【家持集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041]) 】
| |
| かすかのゝふちゝりすきてなにをかも みかりのひとのをりてかさゝむ |
| 私家集大成第一巻7 [西本願寺蔵三十六人集] 家持Ⅰ 夏歌 89 |
| かすかのゝふちゝりは(て)(な)にをかも みるの(一字分空白)人のおも(り)てかさゝん |
| 私家集大成第一巻8 [冷泉家時雨亭叢書『資経本私家集一』] 家持Ⅱ 夏歌 81 |
| かすがののふぢちりはててなにをかもみかりの人のおも(り)てかざさん |
| 国歌大観第三巻3 [書陵部蔵五一〇・一二] 夏歌 81 |
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
| |
| かすか野ゝ藤はちりにきなにをかも みかりの人のおりてかさゝむ |
| 新編私家集大成-新編増補[陽明文庫蔵三十六人集] 142 |
| かすかのゝふちはちりにきなにをかも みかりの人のおりてかさゝむ |
| 新編私家集大成[書陵部蔵三十六人集] 129 |
| かすかのゝふちはちりにきなにをかも みかりのひとのをりてかさゝむ |
| 新編国歌大観[西本願寺蔵三十六人集] 249 |
【古今和歌六帖 [永延元年(987年)頃]撰、兼明親王・源順か
編国歌大観第二巻4 [宮内庁書陵部蔵五一〇・三四]】
| |
| かすがののふぢはちりゆくなにをかもみかりの人のとりてかざさん |
| 第四 かざし 2320 |
【雲葉和歌集 [建長六年(1454)]撰、藤原基家(~1093)
新編国歌大観第六巻11[内閣文庫蔵本・彰考館蔵本]】
| |
| かすが野のふぢはちりゆくなにをかはみかりのひとはをりてかざさん |
| 第三 春歌下 題不知 山辺赤人 255 |
【夫木和歌抄 [延慶三年頃(1310年頃]撰、勝間田長清 新編国歌大観第ニ巻16[静嘉堂文庫蔵本]】
| |
| かすが野の藤は散りにき何をかもみかりの人のをりてかざさん |
| 巻第六 春部六 藤花 題しらず、万十 人丸 2163 |
|
【新千載和歌集 [延文四年(1359)、二十一代集]撰、御子左入道大納言為定 (1293~1360)
新編国歌大観第一巻18 [宮内庁書陵部蔵 兼右筆「二十一代集」]】
| |
| 春日野の藤はちり行くなにをかはみかりの人のをりてかざさん |
| 第第二 春歌下 題しらず よみ人しらず 180 |
【歌枕名寄 [鎌倉時代頃、撰・澄月法師か [万治二年板本]】
| |
| 春日野の花はちり行きて何をかもみかりの人のをりてかざさん |
| 新編国歌大観第十巻181 巻第六 奈良篇 万十 御狩 1778 |
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「春日野之藤者散去而何物鴨御狩人之折而将挿頭」
「カスカノヽ フチハチリユキテ ナニヲカモ ミカリノヒトノ オリテカサヽム」(「【】」は編集、歌番は旧) |
| 〔本文〕頭注に、『類聚古集』訓ヲ附セズ 赤人集「かすかのゝふちはちりにきなにをかもみかりのひとのをりてかさゝむ」 |
| 「者」 |
『類聚古集』「石」
|
| 「去」 |
『神田本』「者」
|
| 「何」 |
『元暦校本』ナシ
『類聚古集』「向」
|
| 「御」 |
『類聚古集』「郷」
|
| 「挿」 |
『神田本』「○【判読出来ず】」
|
| 〔訓〕 |
| チリユキテ |
『元暦校本』ナシ。空白アリ。其処ニ赭「チリニキ」アリ
『神田本』「チリハテ」。「者而」ノ左ニ「スキ」アリ
|
| オリテ |
『元暦校本』「をりて」
『神田本・大矢本』「ヲリテ」
|
| 〔諸説〕 |
| ○[散去而チリユキテ]『代匠記(精撰本)』「チリニテ」トモス。『古義』「而」ハ「吉」ノ誤ニテ訓「チリニキ」カ。 |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1978] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
| |
〔かすかののふちはちりゆきて何をかもみかりのひとのおりてかさゝん 〕
春日野之藤者散去而何物鴨御狩人之折而将挿頭
|
確かに、「藤」の季語は「春」と書いてあった
上出の資料でも、「家持集」では「夏歌」の部で扱われているが、
その他では「春歌」として扱われている
藤が散って、五月五日の薬狩が年中の行事になっているのは、
藤の花盛りが「春」という認識だった、ということだろう
しかし、現実的には、この書でもあるように、
初夏にかけても鑑賞できたのだろう |
| かすかののふちは 藤は夏にも懸る物也されは夏のうたにかきつらねたり哥心は明也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
| |
〔カスカノノフチハチリユキテナニヲカモミカリノヒトノオリテカサヽム〕
春日野之藤者散去而何物鴨御狩人之折而將挿頭 |
原文は「ちりゆきて」と訓むのが、普通だと思うが
歌の場合、特別な訓になることも、よくあることだと思う
韻を合わせる為に口語とは違う訓や、
この歌のように、おそらく「七字」に調子をとる為のことだとも、
歌であれば、むしろ口語ではない「語」というのが
次第に認知されてゆくのだと思う |
| 散去而はチリニテとも讀べし、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
| |
〔かすがのゝ、ふぢはちりゆきて、なにをかも、みかりのひとの、をりてかざさん 〕
春日野之藤者散去而何物鴨御狩人之折而將挿頭 |
原文の意は「なにものを」「かも」となるのを
その語義を汲み、原文「何物」を「何を」とした、と説明する |
| 何物鴨 なにものをかもと云ふ意にて、義訓になにをかもとは讀ませたり。歌の意は聞えたり |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
| |
春日野之 藤者散去而[チリニテ] 何物[ナニヲ] 鴨御狩(ノ)人之[ノ] 折而將挿頭 |
原文「散去而」は「ちりゆきて」と訓じられていたものを、
先の契沖が提唱したように「ちりにて」と推し進める
しかし、ここでは解説のない契沖と違って、
「去」をナ変動詞「去(い)ぬ」とし、
その連用形「いに」で「ちりいにて」と訓み、
その「い」が略されて訓まれるのが「いにしへ」だとしている |
藤者散去而[チリニテ]、今本ちりゆきてと訓たれど去はいにてなればいを略てちりにてとよむぞいにしへなり
鴨御狩(ノ)人之[ノ] 折而將挿頭 は御狩などのあらんずる前に藤の花のちりしを惜みてよめるなり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
| |
〔かすがぬの。ふぢはちりにて。なにをかも。みかりのひとの。をりてかざさむ。〕
春日野之。藤者散去而。何物鴨。御狩人之。折而將挿頭。 |
真淵に倣う |
散リニテは散リイニテの略。
參考 ○藤者散去而〈代、考)略に同じ(古、新)フヂハチリニキ「而」を「吉」の誤とす。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
| |
〔カスガヌノ。フヂハチリニキ。ナニヲカモ。ミカリノヒトノ。ヲリテカザサム。〕
春日野之。藤者散去而。何物鴨。御狩人之。折而將挿頭。
|
「而」を、その草書体がよく似ている「爾(ニ)」と「吉」の誤とし、
その「吉(キ)」は現在の助詞だと言っているのだろうか
歌意が面白い
花は散り失せ、「さぶさぶしき野のさま」になっている
狩する人たちは、さて何を手折ってかざすのだろう、と |
散去而の而は、吉(ノ)字などの誤か、吉と爾と草書よく似たりチリニキとあるべし、吉[キ]は、さきにありしことを、今かたるてにをはなり、○歌(ノ)意は、春日野の藤(ノ)花は散失たり、今はなにをか、御獵の人の折て挿頭むぞ、さてもさぶさぶしき野のさまになりけり、となり、
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
| |
〔春日野の藤は散去而[チリニキ]なにをかも御狩の人のをりてかざさむ 〕
春日野之藤者散去而何物鴨御狩人之折而將挿頭 |
「而は吉字などの誤か」という、
その「など」に「爾」が含まれており、それは「爾吉」で、
「爾が而と誤とされ、吉は脱落した助詞」と、
私は、そう雅澄の解釈をしたが、そこまで具体的に述べていない
どうなんだろう |
| 古義に『而は吉(ノ)字などの誤か』といへるに從ひてチリニキとよむべし |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| |
春日野の藤は散りにて、何をかも、み狩りの人の折りてかざゝむ |
特になし |
| |
春日野の藤は散つて了つてゐるので、狩りに出た人々は、何をば簪しに折りとることであらう。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
| |
〔春日野の 藤は散りにて 何をかも み狩の人の 折りてかざさむ〕
カスガヌノ フヂハチリニテ ナニヲカモ ミカリノヒトノ ヲリテカザサム
春日野之藤者散去而何物鴨御狩人之折而將挿頭 |
「なにをかも」の「かも」を詠嘆の意を含む終助詞としているようだ
私には「疑問」の方が相応しいと思うが、この書の解釈では
「何をかざすのだろう」よりも、「何もなくなった春日野」が
主眼なのかもしれない
高貴な人の狩に従事しているので、
「薬狩」という大宮人たちの風趣は全面に出てこない |
春日野ノ藤ノ花ハモハヤ散ツテシマツテ、コレカラハ何ヲマア、御狩ニ來タ人ガ、折ツテ頭ニカザスデアラウカナア。花ノナクナツタ春日野ハ淋シクナツタ。
○藤者散去而[フヂハチリニテ]――舊訓にチリユキテとあるのは拙い。古義に散去吉[チリユキ]かとあるのも面白くない。代匠記精撰本による。
○御狩人之[ミカリノヒトノ]――天皇その他、高貴の方の狩に、扈從してゐる人を、御狩の人といつたのであらう。
〔評〕 大宮人の行樂の樣子がしのばれる。はつきりした歌である。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
| |
〔春日野の 藤は散りにて、何をかも 御狩の人の 折りて插頭さむ。〕
カスガノノ フヂハチリニテ ナニヲカモ ミカリノヒトノ ヲリテカザサム
春日野之 藤者散去而 何物鴨 御狩人之 折而將插頭 |
考えてみれば、この「狩」を、「薬狩」と決め付ける根拠は、
藤の花が散った後のこと、として「五月五日」を当てたのだろう
しかし、前出の『全釈』のように、
通常の高貴な人の狩に従事するだけのことかもしれないそ
しかし、すでに花は散ってしまった春日野で、
何をかざしにするのだろうか、と...
狩そして、花をかざす風雅さ...
この書では、薬狩と決め付けるが、
そうでなくてはいけないのだろうか |
【譯】春日野の藤は散つてしまつて、何をか、御狩の人が折つてかざすだろう。
【釋】藤者散去而 フヂハチリニテ。ニは完了の助動詞で、意を強調するに使われるが、ここなどは、散つてしまつてでよい。
御狩人之 ミカリノヒトノ。ミカリは、狩獵が宮廷の催しであるがゆえにいう。ミは、敬語の接頭語。
【評語】藤の花が咲いていたら、それを插頭にして狩に出で立つだろうが、今は花の無い季節であるので、そのさびしさが歌われている。この狩は、藥獵で、五月五日に行われるのを原則とする。藥獵に關する最古の文獻として知られている日本書紀の推古天皇の十九年五月五日の記事に、藥獵にいで立つ廷臣が、みな位階に應じて、金、豹尾、鳥尾などの髻華[うず]をつけたことが傳えられている。美的生活として知られる狩獵であつたのである。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
| |
〔春日野の藤は散りにて何をかもみ狩の人の折りてかざさむ〕
カスガヌノ フヂハチリニテ ナニヲカモ ミカリノヒトノ ヲリテカザサム
春日野之 藤者散去而 何物鴨 御狩人之 折而將插頭 |
他と比べて、特になし
ただ、「かも」が詠嘆の意を含む終助詞になっている |
【大意】春日野の藤は散つてしまつて、何をまあ、み狩の人は折つてかざしとすることだらうか。
【作意】初夏に行う薬狩は、実用よりは遊覧化されて居たと見えるから、狩人たる大宮人は美々しく装つて出で立つたのであらう。其の人達に呼びかける趣で、折角春日野の狩をされても、藤はもう散つてしまひました。何か美しいよいかざしの花が、ありますか、といふほどの心と見える。次の歌を予想して居ることが知られる。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
| |
〔春日野の 藤は散りにて 何をかも 御狩の人の 折りてかざさむ〕
カスガノノ フヂハチリニテ ナニヲカモ ミカリノヒトノ ヲリテカザサム
春日野之 藤者散去而 何物鴨 御狩人之 折而將插頭(『元暦校本』) |
「考」は参考になる |
【口訳】春日野の藤は散つてしまつて、これからは何をまあ、御狩をする人は、折つてさざしにする事であらう。
【訓釈】藤は散りにて―『元暦校本』「ふちは」の下三字の訓を缺き、そこに赭片カナでチリニキとあるを、『代匠記』に「チリニテトモ読ベシ」とし、『古義』にチリニキとし、「而は、吉ノ字などの誤か」と云ひ、『新考』それに従つた他は、チリニテが採られてゐる。ただ『考』に「去はいにてなればいを畧てちりにてとよむぞいにしへなり」といひ、『古典大系本』にも「ニは動詞イヌ(去)の連用形イニが、散りと複合してニとなつた形」とあるが、この「に」は完了の助動詞「ぬ」の連用形で、「物云はず来にて」(4・503)、「なりにてあらずや」(5・829)などの「にて」と同じと見るべきであらう。
何をかも―「何」の字『元暦校本』に無く、『類聚古集』「向」に誤るが、『紀州本』以後によ
御狩の人の折りてかざさむ―この「御狩」は冬から春に行はれた鳥獣を猟るものでなく、初夏に宮廷の行事として催された薬猟であつたから、前(1・20、21考)に述べたやうに、美しく着飾つたので、この句があると見るべきである。
【考】古今六帖(四「かざし」)「藤は散りゆく」、赤人集(流布本も)「藤は散りにき」、雲葉和歌集(三)には「藤は散りゆく何をかはみかりの人は」とあり、山辺赤人とし、家持集「藤散りすぎて」、夫木抄(六「藤花」)「藤は散りにき」人丸とあり、新千載集(二)には「藤は散り行く何をかは」とある。 |
|
|

| |
| 「さつきをまたば」...ひさしくあるべみ... |
| |
| 『ときはしらぬとも』 |
| 【歌意1979】 |
まだその時期ではないのに、
あの枝々に連なる花は、まるで五月の玉を貫くような姿をしている
卯の花の咲く五月、それまで待つことが出来なくて
私には、そう見えるようだ |
| |
| |
この歌、花のことに詳しくない私が、どれほど苦しんだことか...
もっと花の勉強をしなければ、と痛感する
そもそも、「卯の花」は「卯月」と言うくらいだから、「四月の花」と思っていた
勿論それも間違いではないようだが、必ずしも大正解、という訳でもないようだ
この『万葉集』中にも、五月に咲く花、と思わせる歌が幾つかある
下段の注釈書にも、その実例は載っているが、
それでも、敢えて「季語」とすれば四月の花と思って間違いなかった
しかし、この歌では、その難しさを思い知らされる
「ときならず」という初句を、無条件で「玉を貫く」五月とすれば
卯の花を実際に四月中に「玉を貫く」ことになり、何気なく読めば矛盾もない
それが、こんな大事に議論されていた歌だとは知らなかった
最近の注釈書では、卯の花が五月に咲く花のように解釈しているものが多くある
第三句と四句にかけての「うのはなの さつきをまたば」を
そのように解釈するのが、自然だということだ
しかし、第二句の「たまをぬける」が、それだと理解出来なかった
結局、『私注』の「季節のない玉」とか、
『注釈』の、「玉のような」とか、それまで通っていた「卯の花を玉として貫く」では
解決できなかった諸々の語義説明も、何とか理解はできた
さて、そこからの私の「歌意」なると
さらに、また悩ませることになる
卯の花を玉として貫くのは叶わないとすれば
どうして、そのような歌が詠われたのだろう、ということになる
随分昔...このHPを書き始めた頃、「万葉の植物Ⅱ」で、
昨日の歌〔1978〕と、この掲題歌〔1979〕を転載したことがある
その記事では、その二首が連作で扱われており
私も、そのときの歌意に触れながら、納得したものだった
そして、改めてその歌に触れ、自分でもう一度歌意をかみしめてみると、
昨日の歌の都人の視点が、藤の散った後の寂しい春日野であるのに対して
この掲題歌は、いかにも連作でその応えのように見えるが、
その視点と言えば、「玉を貫く」それが「薬玉」なのか「かざし」なのかは解らないが
少なくとも、「春日野の寂しい野原」に対する応答ではない、と思う
見立てでいいのであれば、卯の花や橘、藤などではなくても
「玉を貫く」ごとく見えるものはある
今、「かざし」にするような「花」がなくとも、
やがて、卯の花が咲くだろうが、その気持ちの表れなのか、
ふと目をやる木々の枝の、花々...それが「玉を貫ける」ように見えてしまう
早くかざしにしたい、というこの気持ちが、そう見せてしまったのだ
そんな歌のような気がしている
「さつきをまたば ひさしくあるべみ」という語句に
心から待ちきれない、もどかしさが現れているような気がしてならない
「ときならず」は、その「たまをぞぬける」の「習俗」でいいと思う
だから、五月の「薬玉」のことをさしていても問題はない
それが主眼ではなく、単に今の時期を言ったものだろう
多くの書が、「玉として貫く」ことに拘るが
実際に「薬玉」を作るなら、その「五月五日」を待てばいいので
その時まで待ちきれないから、卯の花、あるいは何かを「貫く」とするのはおかしなことだ
「五月五日」にこそ、意味があるのだから...
そうなると、「かざし」として早く手にしたい、という気持ちの方が理解出来る
その想いが強いからこそ、何かを「見立てて」しまった
この歌は、「玉」を用いて、時を設定し
その時を待ちきれない「気持ち」を「ときならず」で表現していると思う
その結果が、「何かが玉に見えて」、自分の気の焦りを詠い表現したものと、感じている |
|
掲載日:2014.04.08.
| |
| 夏雑歌 詠花 |
| 不時 玉乎曽連有 宇能花乃 五月乎待者 可久有 |
| 時ならず玉をぞ貫ける卯の花の五月を待たば久しくあるべみ |
| ときならず たまをぞぬける うのはなの さつきをまたば ひさしくあるべみ |
| 巻第十 1979 夏雑歌 詠花 作者不詳 |
【赤人集】〔143・130・250〕
【古今和歌六帖】〔81〕
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
| 【1979】 語義 意味・活用・接続 |
| ときならず [不時] |
| たまをぞぬける [玉乎曽連有] |
| (を)ぞ [係助詞] |
[目的語を強調] ~を 係り結びの「係り」 |
体言につく |
| る [助動詞・り] |
[完了・連体形] ~てしまった・~てしまう 「結び」 |
已然形につく |
| うのはなの [宇能花乃] |
| さつきをまたば [五月乎待者] |
| また [待つ] |
[他タ四・未然形] 人や物事が来るのを待つ |
| ば [接続助詞] |
[順接の仮定条件] ~(する)なら・~だったら |
未然形につく |
| ひさしくあるべみ [可久有] |
| ひさしく [久し] |
[形シク・連用形] 長い間である・ある状態が長く続くさま・久しぶりだ |
| べみ [助動詞・べし] |
[推量・語幹+「原因・理由」の接尾語「み」] ~ので |
連体形につく |
| 〔接続〕終止形につくが、ラ変動詞には連体形につく [「ある」はラ変動詞「あり」の連体形] |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [ときならず] |
ふさわしい時でない、という意味
下段『注釈書』資料の『新考』で、
| |
| 案ずるに上三句は卯花が枝にさき連れるを玉を貫けるに見立て、さて玉を貫くは五月のわざなればトキナラズといひサツキヲマタバヒサシカルベミといへるなり。 |
四月の花「卯の花」が、玉を貫くように見立てて、
「玉を貫くのは五月」なのに、という意味で「ときならず」を説明している
ただし、同じく下段の『全釈』では、卯の花は五月の花だとしている
第三句の「うのはなの」が、第四句の「さつき」に繋がると解釈する
この頃の注釈書は、随分と「卯の花」の解釈に拘っているようだ
確かに、歌意に影響するのであれば、それも当然だろうが...
この「ときならず」が、こうした「卯の花」の解釈によって、
季節のことであるのか、あるいは「五月五日の薬玉」の日のことをいうのか...
訓で「ときじくの」とする『私注』と、それに倣うのが、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
ただし同じ岩波書店の『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕や、
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕では、「ときならず」と訓む
しかし、いずれも「卯の花」の咲くのは五月と考えられている
いろいろ説があるようだが、「五月」なら、「ときならず」という初句との兼ね合いが...
|
| |
| [たまをぞぬける] |
これも重要な語句になる
この「玉を緒に通して連ねる」のは、「なに」だろう
四段「貫く」の已然形「ぬけ」に、完了の助動詞「り」の連体形「る」
これで「玉を緒に貫いてしまった、もしくは貫いている」になる
それが、「玉を貫く」のが五月のことであれば、卯の花は四月に咲いている
しかし、第三四句の「うのはなのさつきをまたば」であれば、
今貫いているのは、「うのはな」ではないことになる
どう考えても、四月の卯の花を、「ときならず たまをぞぬける」の方がいいと思うのだが
それとも、「うのはな」ではない、他の何かを暗示しているのだろうか
|
|
| |
| |

|
|
| 掲題歌[1979]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
| |
| ときならてたまをそぬけるこの花の あか月またはちりはてぬへし |
| 新編私家集大成-新編増補[陽明文庫蔵三十六人集] 143 |
| ときならてたまをそぬけるうのはなの あかつきはまたちりはてぬへし |
| 新編私家集大成[書陵部蔵三十六人集] 130 |
| ときならてたまをそぬけるうのはなの あかつきはまたひさしかるへし |
| 新編国歌大観[西本願寺蔵三十六人集] 250 |
|
【古今和歌六帖 [永延元年(987年)頃]撰、兼明親王・源順か
編国歌大観第二巻4 [宮内庁書陵部蔵五一〇・三四]】
| |
| 時ならぬ玉をぞぬけるうの花はさ月をまたば久しかるべく |
| 第一 うのはな 81 |
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「不時 玉乎曽連有 宇能花乃 五月乎待者 可久有」
「トキナラヌ タマヲソヌケル ウノハナノ サツキヲマタハ ヒサシカルヘク」(「【】」は編集、歌番は旧) |
| 〔本文〕頭注に、 赤人集「ときならてたまをそぬけるうのはなの あかつきはまたひさしかるへ」 |
| 「連」 |
『西本願寺本』「連【「連」の「車」の下の横棒が欠けている、誤字だろう】」直シテ「連」トセリ
|
| 「宇能花」 |
『類聚古集』「卯花」。右ニ朱「宇能花」アリ
|
| 〔訓〕 |
| タマヲソヌケル |
『類聚古集』「連有」ノ右ニ朱「ヌケル」アリ
|
| サツキヲマタハ ヒサシカルヘク |
『元暦校本』「さつきをまたはひさしかるへみ」
『類聚古集』「さつきをまたはひさしかるへし」。肩ニ朱「今案」アリ。「可久有」ノ右ニ朱「ヒサシカルヘシ」アリ
『神田本』「サツキヲマタハヒサシカルヘシ」
|
| 〔諸説〕 |
| ○[トキナラヌ]。『略解』「トキナラズ」補「トキナラヌ」ヲ可トス。○[ヒサシカルヘク]。『略解』「ヒサシカルベミ」 |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1979] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
| |
〔ときならぬ玉をそぬけるうの花のさつきをまたはひさしかるへく 〕
不時玉乎曽連有宇能花乃五月乎待者可久有
|
卯の花が、まるで「玉」のように枝に連なり、それが「玉を貫く」かのように見えるので、
「五月五日」の「薬玉」には、まだ待たなければならないが
この卯の花の姿を、そのように見立てて詠ったもの、と解釈 |
| ときならぬ玉をそ 五月にこそ薬玉はぬくへきに五月は待久しからんとてと也卯花の五月をまたす玉如咲と云心也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
| |
〔トキナラヌタマヲソヌケルウノハナノサツキヲマタハヒサシカルヘク〕
不時玉乎曾連有宇能花乃五月乎待者可久有 |
記述なし |
| 記なし |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
| |
〔ときならぬ、たまをぞぬける、うのはなの、五月を待ば、ひさしかるべき 〕
不時玉乎曾連有宇能花乃五月乎待者可久有 |
「卯の花」と「玉をぞ貫ける」で、それが「ときならぬ」
卯の花は四月の花、五月五日の菖蒲や橘でかずらにするのではなく
季節は違うが、卯の花で、そのかずらにした
では、「かずら」にする意味は何なのだろうか、読み取れなかった |
五月五日には、菖蒲の玉かづら橘を玉に貫くなど云ふ事ある故、卯の花は四月の物にて、既に卯月とさへ云へば、時ならぬとよめり。卯の花の五月とは續かぬ續きなれど、これは上にかづらうの花の玉をぞ貫けると云意也
不時とは、五月ならぬにより玉に貫けるを、卯の花を玉に貫けると也。卯の花をもて囃す意の歌也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
| |
不時[トキナラズ]、玉乎曾連有[ゾヌケル]、宇能花乃、五月乎待者、可久有[ヒサシカルベシ] |
五月に橘で玉を貫くのが習慣であるので、それを待ちきれなくて
四月の花、卯の花で玉を作ってみた、と読める歌 |
二三の句を上にして心得るにてうのはなのたまをぞぬけるなり
花實など糸はもとより藁の類にもつらぬくは後のわらはべもするわざなりさて玉にぬくはもはら橘にて五月の事なるよしは集中に見ゆさればうづきに卯の花を玉にぬき其手風より五月をまつを久しみてよめる歌なり、 |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
| |
〔ときならず。たまをぞぬける。うのはなの。さつきをまたば。ひさしかるべみ〕
不時。玉乎曾連有。宇能花乃。五月乎待者。可久有。 |
「玉を貫く」ことが、一般的に五月のことなので
四月に卯の花で「玉を貫く」から「ときならず」という |
上句一三二と次第して見るべし。時ならず卯花の玉を貫けると言ふ意なり。藥玉を貫くべき五月よりも先に四月に卯の花を玉に貫けば、時ナラズと言へり。橘の實樣の物ならで、唯だ結ひ束ぬるをも玉に貫くと言へり。
參考 ○可久有(考)ヒサシカルベシ(古、新)略に同じ。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
| |
〔トキナラズ。タマヲゾヌケル。ウノハナノ。サツキヲマタバ。ヒサシカルベミ。〕
不時玉乎曾連有宇能花乃五月乎待者可久有
|
この書で、「うのはなのさつき」と、初めて解釈が始まったのか
「卯の花の咲く五月」と...
しかし、その歌意になると、中途半端だ
だから、ここでいう「四月」には何をもって「玉を貫く」のだろう |
宇能花乃五月[ウノハナノサツキ]は、卯(ノ)花の咲(ク)五月の意にて、鶯の春といふと同例なり、○歌(ノ)意は、玉を貫とは、藥玉のことにて、其の五月にするわざなるを、これは五月を待ば、待久しからむとて、いまだ時ならねど、四月に玉をぞ貫る、となり、
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
| |
〔時ならず玉をぞぬけるうの花の五月をまたば久しかるべみ 〕
不時玉乎曾連有宇能花乃五月乎待者可久有 |
「卯花」は「卯月」の花、と明快にいい、古義説を否定する
結句「べみ」の接尾語「み」を「原因理由」の意味として、
「べきによりて」と意を説明している |
上三句一三二と次第して見べし。時ナラズ卯花ノ玉ヲヌケルといふ意也、藥玉をぬくべき五月よりも先に四月にうの花を玉にぬけば時ナラズといへり
抑ノに二種あり。たとへば花ノサクのノと花ノ枝のノとなり。千蔭はウノ花ノのノを花ノ枝のノとせるなれどこのノはかゝる處にては玉より下にはおくべからず。次に古義には
ウノ花ノ五月は卯花ノサク五月の意にて鶯ノ春(○本書一九二三頁)といふと同例なり
といへり。即ウノ花ノ五月ヲとつづけて心得たるなり。卯花は卯月の花なればウノ花ノ五月とはいふべからず。案ずるに上三句は卯花が枝にさき連れるを玉を貫けるに見立て、さて玉を貫くは五月のわざなればトキナラズといひサツキヲマタバヒサシカルベミといへるなり。さればウノ花ノのノは花ノサクのノにて主格の辭なり。ヒサシカルベミは待遠ナルベキニヨリテとなり
|
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| |
時ならず玉をぞ貫[ヌ]ける。卯の花の、五月を待たば久しかるべみ |
「卯の花」を「玉を貫く」実際の行為ではなく、
雨に打たれる卯の花が、その姿が「玉を貫く」ように見える
そう実景描写の解釈になっている |
| |
卯の花が雨を帶びて、玉を貫いてゐる。それが宛[アタカ]も五月の藥玉を拵へたやうに見える。ほんとうに卯の花が時ならぬ玉を通してゐることだ。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
| |
〔時ならず 玉をぞ貫ける 卯の花の 五月を待たば 久しかるべみ〕
トキナラズ タマヲゾヌケル ウノハナノ サツキヲマタバ ヒサシカルベミ
不時玉乎曾連有宇能花乃五月乎待者可久有 |
「卯の花」即「卯月」説を根拠の無いものとする
しかし、「卯の花の咲く五月」まで待てず
時節外れの薬玉をこしらえた、というのが、理解出来ない
それは、「卯の花」ではないということになるが... |
卯ノ花ガ咲ク五月マデ待ツテヰテハ待チ遠イノデ、私ハマダ早過ギタガ、時節ハヅレニ藥玉ヲコシラヘタヨ。
○玉乎曾連有[タマヲゾヌケル]――玉は藥玉であらう。略解には句を轉倒して、「時ならず卯の花の玉をぬけるといふ意也」とある。
○宇能花乃[ウノハナノ]――卯の花の吹く五月とつづくのである。卯の花は卯月即ち四月に咲くものだといふ説もあるが、卯月を卯の花の咲く月の意とするのは俗説で、何等根據がない。卯月即ち卯の花月とは考へられない。前に五月山宇能花月夜[サツキヤマウノハナヅクヨ](一九五三)とあるではないか。
〔評〕 歌の組立は簡單であるが、古來あまりむつかしく解する説が多い。蓋しこの歌が、詠花とある題には、しつくりふさはぬからであらう。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
| |
〔時ならず 玉をぞ貫ける。卯の花の 五月を待たば 久しかるべみ。〕
トキナラズ タマヲゾヌケル ウノハナノ サツキヲマタバ ヒサシカルベミ
不時玉乎曾連有宇能花乃五月乎待者可久有 |
折口信夫とやや情景は違うが、枝に連なる卯の花を、
「玉」に見立てて、まるで五月の薬玉のようだ、とする
ただ、後半の歌意がやはり中途半端な説明の意になっている |
【譯】その時でもなく玉を緒につらぬいている。卯の花が、五月を待つたら、久しいだろうから。
【釋】不時玉乎曾連有 トキナラズタマヲゾヌケル。五月には、玉につらぬくものだが、その時でないのに、玉を緒につらぬいている。卯の花が、枝に白く續いているのを説明している。
【評語】卯の花が、枝につらなつて咲いているのを、玉につらぬいたと見立てている。四月のうちに詠んだ作である。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
| |
〔時じくの玉をぞ貫ける卯の花の五月を待たば久しかるべみ〕
トキジクノ タマヲゾヌケル ウノハナノ サツキヲマタバ ヒサシカルベミ
不時玉乎曾連有宇能花乃五月乎待者可久有 |
前の歌〔1978〕に、何を手折ってかざしにするのか、という
それに対する答えとして解釈している
「卯の花」の解釈の重要さを訴えているかのような、
詳細な解説だと思う
前歌で、藤の花が散った春日野で、今度は卯の花を待てば
その咲く五月まではまだ先が長い
だから「季節にない玉」をかざしとして「貫く」
前歌の対の歌とすれば、通じるような気もする
そして、卯の花を五月の花とする説で、私が気になっていた
ならば、今貫いているのは、何の玉なのか、という疑問に
この書は応えてくれている
それが「季節のない玉」を貫いたのだ、と |
【大意】季節のない玉を、かざしとして貫きました。卯の花の咲く五月を待てば、時が久しくあらうので。
【語釈】トキジクノ 季節のない、何時もある意で、玉を修飾して居る。○タマヲゾヌケル 「何をかも折りてかざさむ」に対して、玉を貫いて、かざしとした意である。玉をかざしとすることは、「彦星のかざしの玉」(9・1686)とあつたので知られる。或は「連有」ツラケルと訓むべきかも知れぬ。ツラヌクと言ふから、「連」をヌクとしても通るし、又ヌクを直ちにツラヌキカザス意とすることも出来ようが、文字からすればツラクと訓みたいところである。なほ餘説に言はう。○ウノハナ サツキヲマタバ 卯の花は四月のものとされ、四月をウヅキと呼ぶのも、此の花によると言はれ、本集でも春の鶯に配したものもあるが、実際の花期は寧ろ五月の方に寄つて居る。ウヅキが種(ウエ)月を意味するといふ説の存する所以であらう。(1953)にも「五月山卯の花月夜」の句があつた。ウノハナノ サツキは前にも見えたウグヒスノハルと同工である。ウノハナをマツの主格と見るべきではない。マツの主格は省略されて居る作者ワレである。
【作意】前の歌に答へる形である。藤が散つて、かざしの花が無くなつたといふに答へて、藤につづく、卯の花をかざしに折りたいが、その咲く五月を待つたのでは、時が久しくなるから、季節にかかはらない玉を貫いて、かざしとして居るとの意である。藤と卯の花との間は、それ程距りはないと思ふが、事実に即いて言ふよりも、藤のなくなつた上は、玉にするといふのが、主意なのであらう。或は、時の花をかざすのが、古風であるのに、近来は、玉を用ゐるものが多くなつたのに対する、讃美、恐らくは反つて、諷刺の意があるのではないかと思ふ。玉をかざしとするのは、日本本来の習俗か、或は大陸の歩揺の如きものの模倣が、古来のカヅラの風俗と習合したのか、今は知るべき資料をもたない。カザシの花を金銀を以つて作ること、或はカザシ其の物も既に大陸風を加へて居るのではないかと推量するのは、全くの門外漢の思ひつきである。とにかく風俗上の詳しいことを知らないので何とも決しかねる次第である。
昭和二十六年、奈良付近に於ける藤と卯の花の開落の情況を上村孫作君が観察してくれたが、藤の開花は五月三日頃に始まり、五月十五日には殆ど全く終つて居る。卯の花は、五月十九日頃、やうやく咲き始め、二十五日頃から、本格的に花となり、三十日頃は盛りで、六月十日頃までは、咲きつづけた。大体藤と卯の花との間は、一週間前後、その盛りと盛りとの間は二十日位あると見てよい。私の現在住むのは山間部なので、両者とも後れたが、其の間隔は殆ど奈良付近と同じであつた。陰暦の月日は、季節に直接関係しないが、今二十六年の陰暦五月一日は陽暦六月五日と記されてある。天平十九年四月二十四日は陽暦六月十日であるが、その日の遊覧を二十六日即ち六月十二日に追和した大伴池主の布勢水海の叙景に「藤浪は 咲きて散りにき 卯の花は 今ぞ盛りと」(巻十七、三九九三)とあるのは、越中のことながら参考にはならう。フヂとウツギに就いては補巻「巻第十刊行に際して」「ウツギ問答」「ウツギの種類数々」を参照されたい。
【餘説】「連有」をツラケルと訓み、玉を頭部の装飾とする意、即ちカヅラケルと同義と見ることが出来れば、この(1975)の意味は一層的確になるであらうと思ふ。然しツラクと言ふ語は辞書にも上げてない。巻十八、(4136)の家持の作「あしひきの山の木末のほよ取りて可射之都良久波 千年ほぐとぞ」のツラクは、巻四、(485)の「阿可思通良久茂 長き此の夜を」のツラクと同じく、助動詞ツルの変化と説かれて居る。巻四の方はしばらく置いて、家持のカザシツラクは、カザシカヅラク意で、語を重ねたままで、助動詞ツルの意は加はつてないと見ることは出来まいか。カヅラクがカヅラを働かせた動詞として存在するなら、カヅラを構成するツラを働かせたツラクも存在してよいのではあるまいか。それが、此の家持の歌のツラクではあるまいか。信濃諏訪の方言にはツラヌと同義のツルク、及びツラナル意のツルクが現に存在する。古事記にはツララクが見える。そこでツラクといふ動詞が、ツラヌ又はカヅラクの意で存在するとすれば、ここの「連有」はツラケルで落ちつく訓とならう。巻十三、(三三二三)の「しなたつ 筑摩さぬかた 息長の 遠智の小菅 不連爾 い刈り持ち来 敷かなくに い刈り持ち来て」の「不連爾」はアマナクニと訓まれて居る。これは、サヌカタを地名と見、「不連爾」以下はすべて、小菅に関して歌ふところと見た故、菅にあたる如くにアマナクニの訓を得たものと思われる。しかしサヌカタは上の(1928)に注した如く、寧ろ蔓草と見えるので、「不連爾」はやはりツラカヌニと訓むべきであらう。蔓草(私案ではアケビの類)を刈り来ても頭のカヅラともせず、菅を刈り来ても、敷物ともせぬ如く、吾を妻としながら、愛撫することもせぬといふのが、巻十三の譬喩歌の本意の如く思はれる。「連」をヌクならともかく、アムと見るのは、疎遠な訓といはねばならぬ。但し、「連」をアムと訓むのは呂覽の注に連結也とあるのによつたとすれば、無理とはいへない。そのことについては巻二十、(四三三八)及び巻十三、(三三二三)の注参照。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
| |
〔時ならぬ 玉をぞぬける 卯の花の 五月を待たば 久しかるべみ〕
トキナラヌ タマヲゾヌケル ウノハナノ サツキヲマタバ ヒサシカルベミ
不時玉乎曾連有宇能花乃五月乎待者可久有 (『元暦校本』) |
だいたい『私注』の解釈に拠るものだと思うが、
さらに詳しく補完している
そして、多くの書が、実際に何かを玉として貫くのではなく、
古注の『拾穂抄』が原点であるかのように、「玉のような」とする
その解釈に落ち着いているようだ
その点は、『私注』とは異なる |
【口訳】まだその時でもないのに、薬玉を貫いたやうに花が咲いてゐる。卯の花が、薬玉を作る五月を待つたら待ち遠しいので。
【訓釈】時ならぬ玉をぞぬける―『拾穂抄』に「五月にこそ薬玉はぬくべきに五月は待久しからんとてと也。卯花の五月をまたず玉如咲と云心也」とある。「玉如咲」とあるが、「玉ノ如ク咲」の意だと思はれる。『古義』には、―中略[参照]―とある。『私注』はこの説に従ひ、初句をトキジクノと訓み、「季節のない玉を、かざしとして貫きました」と訳し、『古典大系本』もそれに従はれてゐる。『私注』には、―中略[参照]―とある。この作を前の作に答へたものとする説は新しい解釈であるが、この二句を作者が玉をかざしにしてゐると解くのは少し無理であらう。「卯の花の五月」を「卯の花の咲く五月」と解す説は『全釈』にも見え、「五月山 宇能花月夜 サツキヤマ ウノハナツクヨ」(1953)を例にあげてをられる。天平二十一年五月十日の家持の作に、「宇能花乃 佐久月多弖婆 ウノハナノ サクツキタテバ」(18・4089)とあるのを見ると卯の花は五月と考へられてゐたやうにも見えるが、又同じ人が天平二十年四月一日の作に「宇能花能 佐久都奇多知奴 ウノハナノ サクツキタチヌ」(18・4066)とあるのを見ると四月とも考へられる。『私注』に―中略[参照]―とある。これを神亀元年の旧暦に換算すると四月十八日頃咲きそめ二十四日頃から本格的に花となり、二十九日頃盛りで、五月十一日頃まで咲きつづけた、といふ事になる。私の今年の日記を見ると五月二十五日に咲きそめ、六月一日に盛りのところを次男に写真を写させた、とあり、奈良と京都との気温の差を考へると、やはり旧暦四月の終り頃には既に盛りになつてゐたと見てよい。だとすれば「卯の花の咲く五月を待つ」といふ事は当らない事が明らかであり、「五月を待つ」のは五日の薬玉を作る時を待つ意と解くべきである。即ち「卯の花の」の下の「の」は連体助詞でなくて主語を示す助詞である。『考』に、「二三の句を上下にして心得るにて」とある事が認められるが、この第三句はむしろ一二の句にも四五の句にもかかるので、これを散文に直せば三一二といふ順序になる。即ちはじめにあげた『拾穂抄』の説が簡単ながら正解と見るべきで、佐佐木博士の『評釈』に「卯の花のさきの方がまるく撓んで、こんもりと球状に花を綴つてゐるのを、大きな薬玉に見立てて、『玉をぞぬける』と詠んだのである」とあるが当つてゐよう。さて初句旧訓にトキナラヌとあるを『略解』以後トキナラズと改めた。その改訓も認められるが、前の「不時 斑衣服 トキナラヌ マダラノコロモ」(7・1260)と同じく、しひて旧訓を改めねばならぬとも思はれない。
五月を待たば久しかるべみ―右に述べたやうに「五月の玉」(8・1465)即ち薬玉に造られるのを待つたならば待久しからうから、の意。『元暦校本』にベミ。『類聚古集・紀州本(校本に誤る)』ベシ、『西本願寺本』以後ベクとあるが、ベミがよい(2・207)
【考】古今六帖(一「卯花」)に「卯の花は」「久しかるべく」、赤人集「時ならで」「あかつきはまたひさしかるべし」、流布本結句「ちりはてぬべし」とある。 |
|
|

| |
| 「はなちるさとに」...かよひなば... |
| |
| 『とよもさむかも』 |
| 【歌意1982】 |
橘の花が散っているあの里に
私が通って行ったら、
きっと、山ほととぎすが騒ぎ立てるだろうなあ |
| |
| |
この「譬喩歌」もまた、随分と諸説入り乱れて、
古注釈書から一つずつ読んでいけば、もうくたくたになってしまう
『童蒙抄』の荷田春満が書いているように、「此歌色々の聞様ありて、諸抄の説も不決」
まさに、その一語に尽きる
大方の解釈では、「花散る里」が、「女のいる家」であり、
「山ほととぎす」が、その女の周囲の人たち
だから、男が、その女のもとへ通うと、周囲の里人のやかましいこと...
そんな「譬喩歌」として普通に解釈されている
ただ、古注釈書の初めの頃は、そうではなかった
『拾穂抄』では、「花散る里」は、昔を偲ぶ形見も古ゆく宿となり
そこに行けば、亡き妻を偲ぶことを「山ほととぎす」の昼夜問わずの鳴き渡る声
ちょっと異質なのは、契沖の『代匠記』で、
元の「想い人」の名残を忘れられず、今となって其処に行けば
今住んでいる人がうるさく騒ぎ立てる
『私注』では、その「今住人」を、現在の妻だと解釈し引用している
言ってみれば、「三角関係」のような感じであり、この解釈も捨て難く
幾つかの注釈書でも、その可能性をほのめかしている
ただ、そうした解釈は、「譬喩歌」の性格上、
どれが最も相応しいか、などとは言えないものだ
読む人それぞれに、思い重ねる何かがあれば、当然それを得心するだろう
この『代匠記』で、私に思わぬ「寄り道」をしなければならないことがあった
それは、契沖がいう、「源氏物語」の「花散里」が、この歌に依るものだ、という件だ
へえー、この歌が、源氏物語に載っているのか、と思ったが
それは早とちりで、そもそも「源氏物語」の「花散里」が何なのか解らなかった
第十一帖の「巻名」であること、光源氏の妻の一人であることは、すぐ調べられた
しかし、「源氏物語」など手元にないので、そこから先には進めない
藁にもすがる思いで、「新編国歌大観」を引いてみる
まさか、「源氏物語」は載っていないだろうと思ったら
その所収されている「795首」の歌は全部載っていた
そこで、初めて「花散里」の意味が理解出来たし、その「帖」に載る「四首」もまた
興味深いものだった
この四首を読んだだけでも、少しはこの「物語」の雰囲気は感じられる
その三首目〔168〕に、この掲題歌と関連する歌があった
なるほど、これだ
そして、その歌に触れたとき、
平安時代の人の、この掲題歌への「感じ方」もまた、何となく理解出来たと思えた
橘の香りが懐かしいので、「花散る里」を訪ねた、ということだと思う
その前後の歌をみても、普段は通わないような、人里離れたような印象を受ける
単に物理的なその情況だけではなく
そこが、どんなにか光源氏の「想い安らぐところ」であったか...
そう思うと、私も平安の人と同じように「花散る里」をイメージしてしまう
「山ほととぎす」という、固有のほととぎすはいないと言われる
それでも「山」が冠せられるのは、やはり「花散る里」のイメージに繋がるものだ
人見知りするかのような、静かなところでひっそりと暮らす
そこに行くというのは、通う方も「覚悟」が必要だろう
追い返されるかもしれない
それでも、通っているうちに、次第に心を許してもらえることを信じて...
ここでいう「花散る里」の「譬」は自分なりの解釈は出来た
すると、「山ほととぎす」を、何に譬えるか...
「花散る里」のイメージからすると、その女の周囲というのは私には浮ばない
むしろ、通う男の周囲の者たちの方がピッタリする
あまり行かない方がいいよ、とか...
「山」のイメージから、どうしても「花散る里」と同じ場所を浮かべてしまうが
単に気難しい「外野の衆」でいいのではないかと思う
「花散る里」は、静かなところで、それこそ「人里離れたところ」
そんなところに通うなんて、いったいどんないい女がいるんだい、とでも言い立てられようか
そっとしていて欲しい「想い人」のこと、騒がれたくはないものだが...
|
|
掲載日:2014.04.09.
| |
| 夏雜歌 譬喩歌 |
| 橘 花落里尓 通名者 山霍公鳥 将令響鴨 |
| 橘の花散る里に通ひなば山霍公鳥響もさむかも |
| たちばなの はなちるさとに かよひなば やまほととぎす とよもさむかも |
| 巻第十 1982 夏雑歌 譬喩歌 作者不詳 |
【赤人集】〔146・137・257〕
【源氏物語古注釈書 [河海抄]「花散里」】〔1247〕
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
| 【1982】 語義 意味・活用・接続 |
| たちばなの [橘] 「橘の花散る里」は、美しい女のいる家を比喩したもの、という |
| はなちるさとに [花落里尓] |
| かよひなば [通名者] |
| かよひ [通ふ] |
[自カ四・連用形] 行き来する・男が女のもとに行く |
| な [助動詞・ぬ] |
[完了・未然形] ~てしまう・~てしまった |
連用形につく |
| ば [接続助詞] |
[順接の仮定条件] ~(する)なら・~だったら |
未然形につく |
| やまほととぎす [山霍公鳥] |
| とよもさむかも [将令響鴨] |
| とよもさ [響もす] |
[他サ四・未然形] 大きな声や音をたてる・鳴り響かす |
| む [助動詞・む] |
[推量・連体形] ~(の)だろう |
未然形につく |
| かも [終助詞] |
[詠嘆・感動] ~であることよ |
連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [たちばなの はなちるさと] |
「譬喩歌」として、それぞれの語句に、本意が譬えられて表現されているので
この初二句は、「美しい女のいる家」とされるのが似合う
しかし、それが「どんな女」なのか、が古来より諸説あり
「花散る里」の当初の解釈では、
『仙覚抄』に、「昔を偲ぶ形見の古い宿」とし、そこで鳴く山霍公鳥は、
「妻を恋しく思い鳴く」ものだとしている
『童蒙抄』の引用案では、山霍公鳥の馴れ難きことを言い
花散る里に絶えず通えば、やがて馴れてくれるものだろうか、という
『古義』に至っては、「多くの里人」の「想い人」であるので
自分が「花散る里」の女の所へ行けば、嫉妬で騒がれるだろう、と
面白いのは、契沖『代匠記』の説に、現代でもそれほど突飛でもなく言及されていることだ
「山ほととぎす」を、今の妻に見立てて、騒がれる、というのもまたいい
『私注』『注釈』で、少しは触れられており、
新しい注釈書では、
『新日本古典文学大系』〔岩波文庫校訂版、平成25年~〕にその意見が見える
そして何より、この「花散里」と言う語が、
源氏物語の巻名、及び光源氏の妻の一人として用いられ
その着想が、この歌になる可能性の指摘があることが、興味をそそられる
ならば、源氏物語の作者は、この歌をどんな「歌意」、イメージとして読んだのだろう...
思わぬ調べ物として、源氏物語の「花散里」を、俄仕込みで読んでみた
その第十一帖で、主人公が詠う歌、
そして下段の資料に載せたように、〔168〕の歌の背景、情景が
この掲題歌と重なってきた
決して、この歌の「花散る里」は、単に「美しい女がいるところ」というだけではない...
|
| |
| [やまほととぎす] |
通説では、花散里にいる女の周囲の人々の比喩とされる
だから、男が通うことで、やかましく鳴き騒ぐというのが
周囲の人々、里人たちの「言い騒ぐ」ことだと言われているが
これも、諸説がある
契沖などは、作者が行く「花散る里」は、昔なじみの女の名残があり忘れられずにいると
「山ほととぎす」、それが「今の妻」であるような解釈で、それが煩く騒ぎ立てる
「譬喩歌」なればこその、多様な解釈を見ることができる
|
|
| |

|
| 掲題歌[1982]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
| |
| 橘の花ちる里にかよひなは 山ほとゝきすひゝかさむかも |
| 新編私家集大成-新編増補[陽明文庫蔵三十六人集] 146 |
| たちはなのはなちるさとのかよひなは 山ほとゝきすひゝかさらむか |
| 新編私家集大成[書陵部蔵三十六人集] 137 |
| たちはなのはなちるさとにかよひなは 山ほとゝきすひゝかさらむかも |
| 新編国歌大観[西本願寺蔵三十六人集] 257 |
|
|
【源氏物語古注釈書四種の一つ[河海抄]「花散里」】
まさか私が「源氏物語」を紐解くことになろうとは...
いくら優れた古典の作品であろうと、興味もないものはどうしようもない
理屈ではなく、ただただ興味が湧かなかった
しかし、今日の掲題歌の「古注釈書」である『代匠記』を読むと
そこに、「源氏の花散里此歌に依れり」とあったので、見逃せなかった
そこから今日もまた苦労の船出が始まった
何しろ、全くの門外漢
「花散里」が、何のことなのかもさっぱり解らない
調べていく内に、それが巻名であり、人名で主人公の妻の一人ともあったので
ならば、すぐにでも解るだろう、と甘くみていた
私が求めたのは、この掲題歌が、その「巻名」というのであれば
契沖が言う、この歌の「譬え」られる底の部分が、少しは理解出来るかと思ったからだ
しかし、手元にあるのは「源氏物語」そのものではなく
かろうじて、古典以降の「全和歌」を収載している「新編国歌大観」のみ
物語としては、理解出来なくても、掲題歌との関係は解ると思った
この「国歌大観」には、「源氏物語」中の和歌795首が載せられている
その中での第十一帖「花散里」には、四首ほどあった |
| 新編国歌大観第五巻421 源氏物語 [本古典文学全集一二~一七] 第十一帖 |
| をち返りえぞ忍ばれぬほととぎすほの語らひし宿の垣根に |
光源氏 166 |
| ほととぎす言問ふ声はそれなれどあなおぼつかな五月雨の空 |
中川のほとりの女 167 |
| 橘の香をなつかしみほととぎす花散る里をたづねてぞとふ |
光源氏 168 |
| 人目なく荒れたる宿はたちばなの花こそ軒のつまとなりけれ |
麗景殿女御 169 |
|
勿論、この物語の原文には、歌番号はない
明治になってから「国歌大観・(改訂の)新編国歌大観」によって、初めてつけられた歌番号だ
これによって、『万葉集』などの「歌」も容易に検索出来るようになった
「源氏物語」第十一帖「花散里」の巻名の由来が、〔168〕歌に依るものであることは解った
この歌を理解すれば、万葉歌〔1982〕の解釈にも役立つだろう
そう思った矢先に、今度は万葉歌〔1982〕そのものが、
「源氏物語」の古注釈書に引用されていることを見つけてしまった
この「国歌大観(実際は新編国歌大観だが、便宜上)」は、私のような怠け者にとって
まさに決して手放せない「宝物」になってしまった
古今のどんな書物であろうと、そこに載せられた「和歌」は殆ど「国歌大観」に番号が付けられる
たとえ、「歌集」ではなく、その「歌論書」や「注釈書」の類でも、
そこに引用されている「和歌」はすべて載る
だから、「源氏物語」を知らなくても、そこに載っている和歌については
「795首」全部が載っていた...まるで「歌集」のように...
そして、今度はこの「源氏物語」の「古注釈書」に引用されている「和歌」もやはり
本編(源氏物語)に載る歌以外の「和歌」が、これも「歌集」のように載せられている
その中に、この掲題歌〔1982〕があった
この古注釈書そのものを読めないので、引用された「和歌」しか手掛かりはないが
きっと、その書の中では、「花散里」の由来を、万葉歌に求めているのではないか、と
これは容易に想像できる |
編国歌大観第十巻212 源氏物語古注釈書引用和歌 古注釈書四種 [河海抄「花散里」]
【内、[河海抄]南北朝期成立、四辻善成著 (底本、角川書店「紫明抄・河海抄)】 |
| 春風は花のあたりをよきてふけ心づからやうつろふと見ん |
1245 |
| 夜やくらき道やまどへる時鳥我がやどをしも過ぎがてになく |
1246 |
| 橘の花ちるさとにかよひなば山時鳥とよませんかも |
1247 |
| 橘郭公なきて日数をたち花の花ちる里に住む人やたれ |
1248 |
うぐひすの かひごのなかの ほととぎす ひとりむまれて しやがち
ちに にてはなかず しやがははに にてはなかず うのはなの さけ
る野べより とびかへり なきとよまし たちばなの 花をゐちらし
ひねもすに なけばききよし まひはせん とほくなゆきそ わがやど
の はなたち花に すみわたれとり |
1249 |
|
| いつか、必ず読もう |
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「橘花落里爾通名者山霍公鳥將令響鴨」
「タチハナノ ハナチルサトニ カヨヒナハ ヤマホトヽキス トヨマセムカモ」(「【】」は編集、歌番は旧) |
| 〔本文〕頭注に、『類聚古集』本文ノ下ニ小字「無作者」アリ。 赤人集「たひうた たちはなのはなちるさとにかよひなは山ほとゝきすひゝかさらむかも」 |
| 無し |
|
| 〔訓〕 |
| ハナチルサトニ |
『類聚古集』「落」ノ右ニ朱「チル」アリ
|
| カヨヒナハ |
『類聚古集』「かよひては」。漢字ノ右ニ朱「カヨヒナハ」アリ
『温故堂本』「カヨイナハ」
|
| トヨマセムカモ |
『類聚古集』「とよまさむかも」。「令響」ノ右ニ朱「トヨマサム」アリ
『神田本』「トヨマサムカモ」
|
| 〔諸説〕 |
| ○[トヨマセムカモ。『万葉考』「トヨモサンカモ」 |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1982] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
| |
〔たちはなの花ちるさとにかよひなはやまほとゝきすとよませんかも 〕
橘花落里尓通名者山霍公鳥将令響鴨
|
ここで言う「仙曰」というのが、やっと解った
これまでも、おそらく「仙覚抄」のことだろうとは、想像していたが今日、『万葉集註釈』の「考」に、『仙覚抄』に、として
この『拾穂抄』の「仙曰」の後に記述されている内容が書かれていた
これで間違いないことが確認できた
学生であれば、先生にすぐ質問して無駄な時間を無くせるのだが、
やはり若い頃の「睡眠時間の古典授業」は、そのつけが大きい
その『仙覚抄』では、初二句を
「昔を偲ぶ形見を古い宿に譬ふ」という」
「山郭公」は、妻恋して夜も昼も鳴き渡る譬のこと |
| たちはなの花ちる里 仙曰橘の花ちる里とは昔を忍ふ形見も古ゆく宿にたとふ山郭公とよませんとは妻戀して夜昼分す鳴渡るにたとふる也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
| |
〔タチハナノハナチルサトニカヨヒナハヤマホトヽキストヨマセムカモ〕
橘花落里爾通名者山霍公鳥將令響鴨 |
かつての恋人、妻だろうか、その名残を忘れられずに
今更になって、そこに通えば、今住む人に咎められて騒がれる譬
「源氏物語」の「花散里」は、この歌からの着想だろう、とする
|
| もと見し人の名殘を忘れずして今更に彼處[ソコ]にかよはゞ、今住人やとがめてさはがむと云意を喩へたるべし、源氏の花散里此歌に依れり、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
| |
〔たちばなの、はなちるさとに、かよひなば、山時鳥、將令響かも 〕
橘花落里爾通名者山霍公鳥將令響鴨 |
譬喩歌の宿命というか、本質というのか
この歌、いろいろの聞き様があり、諸抄の説も決まらない、という
先述の「昔の形見とか名残」や、「恋思う人と過ごす」ことを
里人に騒がれる、とか
「宗師」というのが解らないが、その説では
ほととぎすは、人里離れて、馴れ親しみ難き鳥だから、
橘の花散る里に通えば、慣れてくれるだろう、
だから思う人のところへ絶えず通えば、しまいには自分のことを、
思ってくれるだろう、と
「山霍公鳥」を人馴れない「女」とする
著者は、自分ではどの説がいいとかは決め難いので、
後の賢明な解釈を待つ、と言う気持ちか
結句の訓も含めて、決めかねている |
| 此歌色々の聞様ありて、諸抄の説も不決。一説、橘の花ちる里と詠めるは、昔を慕ふ形見もふりゆく宿に喩ふ也。山郭公どよませんと詠めるは、妻戀して夜晝分す鳴き渡るに喩ふるとの義也。一説、花ちる里に通ふをば、戀思ふ人の、時を過さむ事を惜みて、わが行通ふによせ、山時鳥どよませんとは、里もとゞろに云騷がれむかと喩へたりと也。表は郭公の通ふ也。時鳥の鳴どよます如く、われも人の許に通ふから、人の物云ひも有べければ、斯くよめるならんと也。宗帥見樣は、郭公は、人遠く馴れ親み難き鳥なれ共、橘の花散る里に通ひなば、馴れしめんかもと云ふ意にて、われも思ふ人の方へ絶えず通ひなば、終には馴れそまんかもと云ふ意と見る也。愚意何れとも決し難し。後賢可決也。此歌にては將令響の三字を、ならしめんと讀むは、宗師の案の意には叶ふべけれど、なきならしめんなど續く時は、ならすと云義も苦しかるまじき歟。只ならしめんとは、少し叶ひ難からんか。何れにても、ならす物一つ据ゑてよまざれば、いかゞに聞ゆる也。どよほすと云假名書あれば通例は、どよませんと讀むべきか。此差別は歌によりて見樣有べき也。初の一説は如何にとも心得難し。中の説と宗師の案と未だ何れとも愚意に落着せず |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
| |
橘(ノ)、花落里爾、通名者、山霍公鳥、將令響鴨[トヨモサムカモ] |
「秋萩を鹿の妻」というように、「橘を霍公鳥のあるじ」と...
橘の花散る里に通えば、霍公鳥が嫉み鳴き騒ぐ
それを表にして、この歌意は、
妹の里に通えば、その里人の噂が大変だ、とする |
| 秋萩を鹿の妻てふ如く橘を霍公鳥のあるじの樣にいへり然れば古今歌集に「あきはぎにうらぶれをれば足曳の山下とよみ鹿の鳴らん」とよめる類にて橘の花ちる里にかよはば霍公鳥のねたみて鳴とよめるをおもてにて妹が里にかよはゞ其里人のこちたくいひさわがんかとたとへたり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
| |
〔たちばなの。はなちるさとに。かよひなば。やまほととぎす。とよもさむかも〕
橘。花落里爾。通名者。山霍公鳥。將令響鴨。 |
簡明に注釈している
詠い出しは、妹の許へ通う譬、後半は人に騒がれる、という譬
「いもがり」は、妻・恋人など親しい女性の所へ、という意味 |
| 本は妹許[イモガリ]通ふに譬へ、末は人に言ひ騷がれんと言ふに譬へたり。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
| |
〔タチバナノ。ハナチルサトニ。カヨヒナバ。ヤマホトヽギス。トヨモサムカモ。〕
橘花落里爾通名者山霍公鳥將令響鴨
|
中山巌水の云うこととして、
多くの人の思う女のところに通えば、里中で言い騒がれる、の意
この歌で、『万葉集古義十巻之上 終』とある |
歌(ノ)意は、中山(ノ)嚴水云、霍公鳥のめでなつかしむ、橘の花ちりまがふ里に、吾かよひなば、ほとゝぎすのねたく思ひて、鳴さわぎなむかと云意にて、多くの人の思ひよする女に我(カ)かよひなば、里もとゞろにいひさわがむかと云に、たとへたり、
萬葉集古義十卷之上 終
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
| |
〔たちばなの花ちる里にかよひなば山ほととぎすとよもさむかも 〕
橘花落里爾通名者山霍公鳥將令響鴨 |
千蔭の説を採り、雅澄が引用する中山巌水の説を誤りとする
この二人の違いは、千蔭が明確な「恋人」の許へとしているのに対し
雅澄は多くの人が思い焦がれる「女」を、
自分が出し抜く、というのだろうか |
略解に、
本[モト]は妹許かよふにたとへ末は人にいひさわがれんといふにたとへたり
といへる如し。古義の釋は誤れり |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| |
橘の花散る里に通ひなば、山霍公鳥とよもさむかも 〔譬喩〕 |
「おせっかいな人々」とは、面白い言い回しだ
これは、千蔭説だろう
もっとも、『略解』の解釈は、真淵の解釈に依るものだと思う |
| |
橘の花の散つてゐる里に、始終出かけて行つたら、子規がやかましく鳴き立てることであらう。
(といふ風に、おせつかいな人々が、騷しく評判を立てることであらう。) |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
| |
〔橘の 花散る里に 通ひなば 山ほととぎす とよもさむかも〕
タチバナノ ハナチルサトニ カヨヒナバ ヤマホトトギス トヨモサムカモ
橘花落里爾通名者山霍公鳥將令響鴨 |
男に嫉妬して、霍公鳥が騒ぐ、里人が騒ぐ
この場合の「花散る里」は、「妹許」だろうか... |
楠ノ花ガ散ル里ヘ私ガ通ツテ行ツタナラバ、山郭公ガ聲ヲ響カセテ鳴キ騷グダラウカナア。ワタシガ女ノ所ヘ通ツテ行ツタラ、人ガ妬ンデ喧シク言ヒ騷グダラウカナア。
○橘花落里爾[タチバナノハナチルサトニ]――他の女に寓してある。卷八に橘之花散里乃霍公鳥片戀爲乍鳴日四曾多寸[タチバナノハナチルサトノホトトギスカタコヒシツツナクヒシゾオホキ](一四七三)ともある。
〔評〕 寓意も明らかで、譬喩歌としては無理がなく、よく出來てゐる。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
| |
〔橘の 花散る里に 通ひなば、 山ほととぎす 響さむかも。〕
タチバナノ ハナチルサトニ カヨヒナバ ヤマホトトギス トヨモサムカモ
橘花落里尓通名者山霍公鳥將令響鴨 |
この解釈は、多分に『童蒙抄』の言う「宗師」の説のようだ
「山ほととぎす」を、人里から離れた人馴れない「女子」とする
通えば、応じてくれるだろうか...と
霍公鳥が、鳴き騒ぐのではなく
自分に応じて鳴き声を立てるのだろうか、という |
【譯】橘の花の散る里に通つたなら、山ホトトギスは鳴き聲を立てるだろうかなあ。
【釋】將令響鴨 トヨモサムカモ。音を立てさせるだろうか。
【評語】山ホトトギスというのは、まだ人馴れない女子を譬えているのだろう。通つたら應ずるだろうかの意に解せられる。その女のいる處を、橘の花散る里と云つたのは、風情がある。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
| |
〔橘の花散る里に通ひなば山ほととぎすとよもさむかも〕
タチバナノ ハナチルサトニ カヨヒナバ ヤマホトトギス トヨモサムカモ
橘花落里爾通名者山霍公鳥將令響鴨 |
『略解』の解釈を無難としながらも、
契沖の設定にも趣向の面白さを感じている
契沖の『代匠記』の解釈など、あまり後続も見られないと思ったが
この『私注』も少しは惹かれるように
現代でも、岩波の新しい文庫本では、「三角関係か」とも言っている |
【大意】橘の花の散る里に、通つたならば、山ほととぎすが、鳴きさわぐことであらう。
【作意】譬喩歌であるから、其の本意は如何様にも配することが出来る。花散る里を、本見し人即ち昔なじみに、山ほととぎすを今住む人、即ち今の妻にあてる『代匠記』の解釈など、中々面白い。契沖は、源氏の花散里は、此の歌によると言つて居る。しかし、山ほととぎすの方を、ただ世間がさわぐと見る『略解』などの方が無難な見方ではあるまいか。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
| |
〔橘の 花散る里に 通ひなば 山霍公鳥 とよもさむかも〕
タチバナノ ハナチルサトニ カヨヒナバ ヤマホトトギス トヨモサムカモ
橘花落里尓通名者山霍公鳥將令響鴨 (『元暦校本』) |
千蔭の解釈に倣う
『仙覚抄』の昔の人を偲ぶ形見、とか『代匠記』の三角関係めいた解釈を、考えすぎだという
そうだろうか...
|
【口訳】橘の花の散る里に通つて行つたならば、山ほととぎすが鳴き立てる事であらうかナア。
【考】前にも「橘の花散る里」(8・1473)の句があつた。ここは『略解』に「本は妹許通ふにたとへ、末は人に言ひさわがれむと言ふにたとへたり」とあるやうな意味にとるべきであらう。『仙覚抄』に「タチバナノハナチルサトヽハ、ムカシヲシノブカタミモフリユクヤドニタトフ。ヤマホトトギストヨマセンカモトハ、ミジカヨヲアカシカネタルツマゴヒシテ、ヨルヒルワカズナキワタルニタトフ也」といひ、『代匠記』に「モト見シ人ノ名残ヲ忘レズシテ今更ニ彼處(ソコ)ニカヨハヾ、今住人ヤトガメテサハガムト云意ヲ喩ヘタルベシ」とあるなどは、少し考へ過ぎであらう。
赤人集に「ひゝかさらむかも」、流布本「ひゝかさらむか」とある。 |
|
|

| |
| 「こもらふときに」...あへるきみかも... |
| |
| 『おもひもかけず』 |
| 【歌意1984】 |
五月の山の、その橘の花の陰に籠もって
今頃は、ほととぎすもおとなしく鳴きもしない
私のように、ひっそりと人目をはばかり...
そんな籠もるばかりの私のところへ
あなたが来てくれた
あなてに逢えるなんて、なんと嬉しいことか... |
| |
| |
まるで「譬喩歌」のように、それぞれの語句に想いが重なる
決して、一様な解釈を求めるのは、この歌の魅力を半減させる
この歌を、また別の日に目にしたとき、きっと違う解釈をしてしまう
この僅か三十一文字に、どれほどの「歌意」が籠められることか...
第四句の訓を、「こもらふときに」として歌意を思うと
かつて都で恋仲であった男と、今は別れて山里に引き籠もった女の哀歌を思わせる
だから、思いもしなかった男の来訪に、詠わずにはいられなかった
花橘に、ほととぎすが「こもる」のは、
お前は、何故鳴いてくれないのか、と責める気持ちもあると思う
譬喩歌のように、その姿を自分に重ねて、もう多くのことは望むまい
こうやって静かに暮らせれば、と思う反面
夏になると、あんなに美しい鳴き声を聞かせてくれるほととぎすよ
私のように、籠もってないで、せめて少しなりとも、
美しいその声を、聞かせておくれ
そうでないと、せっかくの覚悟でここに「こもって」いるのに、
いっそう寂しさがこみ上げて来る
そんな心持の中で、あなたが来てくれた
五月の山の橘の花の中で、息を潜めているかのような、ほととぎすのごとき私のところへ...
人が、ほととぎすの鳴く声を求めて、山に入るように
あなたは、私に逢いたくて、お出でになったのですね
とても嬉しいことです
そこに居ることが解っていながら、その鳴き声が聞かれず山に入る人たち...
同じように、私がここに籠もっているからこそ、あなたは来てくれた
ともすれば、人知れず暮らす覚悟もあったものを... |
|
掲載日:2014.04.10.
| |
| 夏相聞 寄鳥 |
| 五月山 花橘尓 霍公鳥 隠合時尓 逢有公鴨 |
| 五月山花橘に霍公鳥隠らふ時に逢へる君かも |
| さつきやま はなたちばなに ほととぎす こもらふときに あへるきみかも |
| 巻第十 1984 夏相聞 寄鳥 作者不詳 |
【赤人集】〔148・139・259〕
【夫木和歌抄】〔8801〕
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
| 【1984】 語義 意味・活用・接続 |
| さつきやま [五月山] 固有名詞「五月山」とする説もあるが、一般的には「五月の山」 |
| はなたちばなに [花橘尓] |
| ほととぎす [霍公鳥] |
| こもらふときに [隠合時尓] |
| こもら [籠る・隠る] |
[自ラ四・未然形] 囲まれる・閉じこもる・ひそむ・隠れる |
| ふ [助動詞・ふ] |
[継続・連体形] ~しつづける |
未然形につく |
| あへるきみかも [逢有公鴨] |
| る [助動詞・り] |
[完了・連体形] ~ている・~てしまった |
已然形につく |
| む [助動詞・む] |
[推量・連体形] ~(の)だろう |
未然形につく |
| かも [終助詞] |
[詠嘆・感動] ~であることよ |
体言につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [こもらふときに] |
旧訓では、「かくらふときに」とある
「こもる」と「かくる」では、その動作の結果は同じようなものでも
動機においては、かなりの違いがある
だから、「かくらふ」と訓でいた時代では、
人目を憚って、ひっそりと暮らしていたのに、
そこに思いもかけず、あなたがやってきた
その悦びを詠ったもの、と解する
しかし、「こもる」の時代の解釈になると、
五月、霍公鳥が山に籠もって姿を見せなくなる、その季節
人里離れて暮らしている私のところへ、あなたがやってくるのですね、と
期待に胸を弾ませる気持ちの度合が強く感じられる
もっとも、初三句を第四句のこの「こもらふときに」にかかる「序」とした場合でも
そして、この第四句までを、霍公鳥が山に籠もる隠れる時期とする場合でも
この「こもらふときに」「かくらふときに」は、上にも下しも双方に掛かる語にはなる
近年の注釈書では、殆ど「こもらふときに」だが
その中でも、『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕だけは、
旧訓の「かくらふときに」を採っている
下段の資料以外では、『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕が
「人に知られないように恋の思いを外に出さないという意味の『こもり妻』の語があるように、ここの「こもらう時」も、家にじっとしているかいないかに係わりなく、二人の仲が知られないように逢わないでいる時に、の意であろう」
としている
|
| |
|
|
| 掲題歌[1984]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
| |
| さ月やみ花たちはなに時鳥 かけろふときにあへる君かも |
| 新編私家集大成-新編増補[陽明文庫蔵三十六人集] 148 |
| 五月やみはなたちはなにほとゝきす かつそふ時にあへるきみかも |
| 新編私家集大成[書陵部蔵三十六人集] 139 |
| さつきやみはなたちはなにほとゝきす かけそふときにあつるきみかも |
| 新編国歌大観[西本願寺蔵三十六人集] 259 |
【夫木和歌抄 (延慶三年頃[1310年頃]、撰勝間田長清)新編国歌大観第ニ巻16[静嘉堂文庫蔵本]】
| |
| さ月山花たちばなにほととぎすかくらふ時にあへるきみかも |
| 巻第廿 雑部ニ さつき山、摂津 題不知、万十 人麿 8801 |
|

|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「五月山 花橘爾 霍公鳥 隠合時爾 逢有公鴨」
「サツキヤマ ハナタチハナニ ホトヽキス カクラフトキニ アヘルキミカモ」(「【】」は編集、歌番は旧) |
| 〔本文〕頭注に、赤人集「さつきやみはなたちはなにほとゝきすかけそふときにあつるきみかも」 |
| 「合」 |
『類聚古集』「会【のような、判読出来ず】」
『神田本』「会【これも「冬」に近い感じで判読出来ず】」
|
| 〔訓〕 |
| カクラフトキニ |
『元暦校本』「らふ」ノ右ニ赭「ルヽ」アリ。「ら」ノ左ニ赭「ロ」アリ
『類聚古集』「かくらふときに」。「ろふ」ノ右ニ朱「ルヽ」アリ。「隠合」ニ右ニ墨「カクロフ」アリ
『神田本』「カクロフトキニ」
|
| 〔諸説〕 |
| ○なし |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1984] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
| |
〔さつき山花たちはなに霍公鳥かくろふときにあへる君かも 〕
五月山花橘尓 隠合時尓逢有公鴨
|
この「折ふし」、というのがこの歌の本質ではないかと思うが、
そのことには触れられていない |
| さつき山花たちはな さつき山は五月の山也かくらふは橘に隠るゝ心也此折ふし君にあふてうれしき心なるへし |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
| |
〔サツキヤマハナタチハナニホトヽキスカクラフトキニアヘルキミカモ〕
五月山花橘爾霍公鳥隱合時爾逢有公鴨 |
大伴書持の歌(新1485)で、橘を霍公鳥は友と解釈し、
霍公鳥が花橘に隠れるのは、逢っているからだ、
というのだろうか
すると「隠合」の解釈、当然決まってしまう
契沖は、おそらく「逢うべくして逢った二人」の悦びだとしているのだろう
「隠合」の表記に、そぐわないような気もする
|
| 第八に大伴書持が橘を霍公鳥の友と讀つるに、霍公鳥の橘にあひにあふ時我も亦君に相へりと悦てよめるなり、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
| |
〔さつきやま、はなたちばなに、ほとゝぎす、隱合時に、あへるきみかも 〕
五月山花橘爾霍公鳥隱合時爾逢有公鴨 |
春満の時代では、この「隠合」は旧訓で「かくらふ」とされていた時代だ
それに対して、春満は納得していない
そして、「五月山」を「五月の山」とするのは
そもそも、霍公鳥が五月の鳥なので、それで「五月山」を合わせたとしている
「五月山」という地名と判断しているが、他には見当たらない
歌意を理解は出来るものの、「隠合」の「詞」の解釈は解らない、としたまま |
| 此歌隱合の二字如何に共讀難し。印本諸抄物には、かくらふと讀みて、隱れたる時思ふ人に逢ふて、嬉しきと喩へたるなど云ふ説あれど、かくらふと云ひては歌の意聞え難し。五月山はたゞ五月の頃の山と云事と釋したれど、此も地名と見ゆる也。五月山といふ地名あるから、時鳥は五月をせんとするものから詠出たるなるべし。古今集にも、五月山梢を高み云々とよめる也五月の時節にあはせてよめる事也。なれば此歌の意は、五月の花橘の頃折にあひて、時鳥の橘にこもり隱れて鳴時節に、我も思ふ人に逢ひて、嬉しきと云意と見る也。然れ共隱合の二字かくらふと讀める義、詞の釋、濟み難き也。歌の意は右の如くにて大方聞えたれど、詞の意不濟也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
| |
花橘爾、霍公鳥、隱合時爾、 良布は留の延言 逢有[アヘル]公鴨、 |
「かくろへず」は、下二段「隠ろふ」の未然形「かくろへ」に、打消しの助動詞「ず」が付いたものだ
「かくろふ」の意味は、ひっそりと人目につかないようにする、
そして、隠れるなどを言うので、「かくろへず」は、「隠れないで」となる
霍公鳥は花橘に隠れてはいるが、私は隠れませんでしたよ、と
言っているのかな
それだと、「隠合」という語は、霍公鳥と花橘のことであり、
もう一つ「不隠合」という語が、必要になってくると思う
しかし、歌にそんな説明文めいたものは要らない
「隠合時爾」の「爾」が、逆接の接続助詞「に」の意味になれば歌意としては、この二人は「隠れず」という出逢いになる
と読んでしまったが、どうなのだろう |
| 霍公鳥は花橘にかくるなるにわれはかくろへずあへるをよろこべる意のみ |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
| |
〔さつきやま。はなたちばなに。ほととぎす。かくろふときに。あへるきみかも。〕
五月山。花橘爾。霍公鳥。隱合時爾。逢有公鴨。 |
この注釈を単純に読めば、五月に霍公鳥が花橘に宿る季節、
私もまた、あなたに逢えることが嬉しくてなりません
という、季節的な逢瀬のことを詠ったもの、としか読めない |
| 五月の橘に郭公の宿りする時、我も又君に逢へるを喜ぶなり。カクロフはカクルを延べ言ふなり。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
| |
〔サツキヤマ。ハナタチバナニ。ホトヽギス。カクラフトキニ。アヘルキミカモ。〕
五月山花橘爾霍公鳥隱合時爾逢有公鴨
|
これまでの注釈書では、人目を憚って控えていたのに、思いがけず逢った悦び、が語られていた
しかし、雅澄は
その思いがけずに逢った故に、思うことも語らうことが出来ず
それを「くやしや」としている
巻第十一(新2513)の歌を引き合いに出しているのは、「隠れる」情況で逢瀬を行った、ということを言ってる
しかし、女の方は、それを窘めている
そのことが、同じような解釈へとなったのだろうか |
歌(ノ)意、契冲は、橘にほとゝぎすのあひにあふとき、われも又君にあへりとよろこびてよめりと云り、今按(フ)に、此(ノ)歌も本(ノ)句は序にて、さてほとゝぎすは、橘の陰に隱れて鳴よしにいひて、隱合[カクラフ]を云む料とせるのみか、さて人目をしのび隱るゝをりに、思はず君にあひて、思ふ心を語らふ事も得爲ず、さても悔しやと云るか、十一に、皇祖乃神御門乎懼見等[スメロキノカミノミカドヲカシコミト]、從侍時爾相流公鴨[サモラフトキニアヘルキミカモ]、と云に似たり、
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
| |
〔さつき山花たちばなにほととぎすかくらふ時にあへるきみかも 〕
五月山花橘爾霍公鳥隱合時爾逢有公鴨 |
やはり、素人の私でも感じたように、『古義』の解釈を否定している
とは言っても、この歌は、はっきりと逢えた悦びが詠われたとも言い切れず、
私などは結句の「かも」でしか判断のしようがなかった |
古義に、
本(ノ)句は序にて……さて人目をしのび隱るゝをりに思はず君にあひて思ふ心を語らふ事も得爲ずさても悔しやと云るか
といへるは非なり。五月山ノ花橘ニ霍公鳥ノ隱レテ鳴ク頃シモウレシクモ逢ヘル君カナといへるなり
○上(二〇〇四頁)にもわがやどの花橘はちりにけりくやしき時にあへる君かも
とあり
○第二句と第四句との終の共にニなるが爲に調わろきなり |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| |
[訓なし] |
特になし |
| |
五月頃の山の花橘の陰に、子規が籠つて鳴く時分に、嬉しく君に逢ふことが出來た。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
| |
〔五月山 花橘に ほととぎす 隱らふ時に 逢へる君かも〕
サツキヤマ ハナタチバナニ ホトトギス カクラフトキニ アヘルキミカモ
五月山花橘爾霍公鳥隱合時爾逢有公鴨 |
明確に解釈していることは、
霍公鳥が花橘にいて鳴く頃に、あなたに逢いました、ということであり、決して自分も籠もっている最中にお逢いしたので嬉しい、とはならないこと
逢えたことは悦び、と解釈しているが、単純に霍公鳥の鳴く季節に、ということだ
花橘に隠れて、霍公鳥が「鳴く」と解釈したもの
それまでは、どちらかと言えば、
「隠れて鳴かない霍公鳥」の前提で、自分も「隠れて」としているような感じがしていたが...
下句に喜びの情が見える、というのは、
やはり「かも」の解釈をそう採ったのだろう |
五月ノ頃ノ山ニ、咲イタ花橘ニ、霍公鳥ガ姿ヲカクシテ鳴ク頃ニ、アナタニ逢ヒマシタヨ。
○隱合時爾[カクラフトキニ]――隱れてゐる時にの意であるが、木蔭で鳴いてゐること。わざわざ隱れてゐるのではない。
〔評〕 上句は序詞とも見られるが、さうではなく郭公が花橘に來鳴く頃に、人にあつたことを喜んだものであらう。下句には喜びの情が見えるやうである。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
| |
〔五月山 花橘に、ほととぎす 隱らふ時に、逢へる君かも。〕
サツキヤマ ハナタチバナニ ホトトギス カクラフトキニ アヘルキミカモ
五月山花橘尓霍公鳥隱合時尓逢有公鴨 |
これは、まさに作者自身も「隠れている」とする解釈
こうした歌にも、何故「隠れている」のか、の説明がきっとあるはずなのだが、三句までの描写が、霍公鳥と花橘の場合を借りて、の解釈になっている
でも、そこに「何故」を見ることは出来ない
霍公鳥が花橘に居るのは、この解釈では「鳴かない」とまでは言っていないが、「鳴かないで潜めている」感じになるだろう
それを、作者の「身を潜めている」ことへの「譬え」として言うのだと思う |
【譯】五月の山に、橘の花にホトトギスの隱れるように、かくれている時に、お逢いしたあなたですね。
【釋】五月山 サツキヤマ。五月の頃の山。
隱合時尓 カクラフトキニ。ホトトギスが橘の花に隱れる時に。橘の樹にホトトギスの來る時をカクラフ時と云つている。そのように自分が隱れている時に。
【評語】四句までは、この好季節にの意を、具體的に描き、それを利用して、自分の家にこもつている時を描いている。君に逢つた喜びが巧みに表現されている。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
| |
〔五月山花橘にほととぎすこもらふ時に会へる君かも〕
サツキヤマ ハナタチバナニ ホトトギス コモラフトキニ アヘルキミカモ
五月山花橘爾霍公鳥隱合時爾逢有公鴨 |
ここでようやく現在の定訓とも言える「こもる」で訓まれ始める
だから「隠れる」の意味合いが薄まり、実質的に「こもる」とも解されてきたこれまでの注釈にも、違和感はなくなる
「かくらふ」、もしくは「かくろふ」などは
どうしても、「隠れる」、「ひっそりと人目につかないように」などの意味になるが、「こもる」では、むしろ「閉じこもる」と言うような意味になり、その心持ちは違ってくる
勿論「こもる」にも、「隠れる」という意味はある
だから、表記上は「隠合」も使われるのだろうが
歌意に無理なく沿える訓であれば、「こもる」だと思う
現代の注釈書では、この「隠合」の訓だけでなく、その語義の検証にも随分手間をかけている |
【大意】五月の山にて、花橘にほととぎすのこもる時に、会つた君かな。
【作意】ほととぎすが橘にこもる五月の山で、会つた君を詠歎して居る。さうした事は存在しもするであらうが、歌は美化を加へた表現である。或は三句まではコモラフの単なる序であるかも知れぬ。それなら独り遠ざかつてゐる時に愛人の君が逢ひに来てくれたといふので、その方が自然であらう。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
| |
〔五月山 花橘に 霍公鳥 隱らふ時に 逢へる君かも〕
サツキヤマ ハナタチバナニ ホトトギス コモラフトキニ アヘルキミカモ
五月山花橘尓霍公鳥隱合時尓逢有公鴨 (『元暦校本』) |
「かくらふ」、「こもらふ」の例歌を引用しての検証
「こもる」だからこそ、「逢えたうれしさ」が滲み出るのだろう
|
【口訳】五月の山に花橘の咲くかげに霍公鳥がこもつてゐるやうに、外に出ずにこもつてゐる時にお逢ひ出来た君であるよ。
【訓釈】五月山―既出(1953)。
隠らふ時に逢へる君かも―旧訓カクラフとあり、諸注も多く従うつてゐるが、折口氏『口訳』、『新校』『私注』はコモラフとした。「春されば許奴礼我久礼弖(コヌレガクレテ)鶯ぞ鳴きていぬなる」(19・4239)や「櫻花 木晩窂(コノクレゴモリ) 貌鳥は 間無くしば鳴き」(6・1047)の例によればコモラフがよいやうに思はれる。さて『略解』に「五月の橘にほととぎすのやどりする時、我れも又君に逢へるをよろこぶ也」とあるのは、第四句までを、作者が君に逢うた時の実景と見たのであるが、『古義』には「今按フに此ノ歌も本ノ句は序にて、さてほととぎすは橘の陰に隠れて鳴よしにいひて、隠合(カクラフ)を云む料とせるのみか」とし、上三句を序として、第四句を作者の事としてゐる。もし前者の解によればカクラフといふ訓も考へられるが、その解によられた『全釈』に「霍公鳥ガ姿ヲカクシテ鳴ク頃ニ」と訳し、佐佐木評釈に、「霍公鳥がそれに隠れて頻りに鳴くこの季節に」と訳されてゐるやうに、「かくれる」よりもむしろ「鳴く」事の方が大切なのではなかろうか。それを「隠合」と云つたのは作者の事とかけたからではなからうか。さうだとすれば、
隠耳哉(コモリテノミヤ)戀ひ渡りなむ (6・997)
隠耳(コモリノミ)居ればいぶせみ (8・1479)
虚木綿の牢而座在者(コモリテマセバ) (9・1809)
物思ふと隠座而(2199)
許母里為底(コモリヰテ)君に戀ふるに (17・3972)
などその用例の極めて多い語として、ここはコモラフと訓むべき事が認められようと思ふ。即ち上三句は前の作同様、序であり、前のが同音くりかえしの序であるに対し、これは実景をそのまま序とした譬喩の序と見るべきだと思ふ。従つて「こもらふ」は右の用例が示してゐるやうに、外へも出ず、籠つてゐる時に思ひかけず君がいらつしてこんなうれしい事は無い、の意に解くべきである。『古義』に序としながらカクラフと訓んだ為に「人目をしのび隠るゝをりに、思はず君にあひて、思ふ心を語らふ事も得為ず、さても悔しやと云るか」と述べ、
皇祖の神の御門をかしこみとさもらふ時にあへる君かも (11・2508)
と云ふに似たり、と云つたのであるが、「こもらふ時に」となれば、思ひがけぬ来訪を喜ぶことになると思ふのである。
【考】赤人集に「さつきやみ」「かげそふときにあへるきみかも」、流布本「さつき山」「かつそふときにあへるきみかも」、夫木抄(廿「山」)旧訓のまゝ載せる。 |
|
|

| |
| 「ひとりしぬれば」...あかしかねつも... |
| |
| 『寂しき夜も』 |
| 【歌意1985】 |
ほととぎすが、来て鳴くこの五月は
夜も短くなったのに、
こうして一人で寝ていると、恋しさのあまり
寝付くこともできず、夜が長く思われて...
なかなか夜が明けないものだなあ |
| |
| |
恋する人がいると、昼も夜も思わずにはいられない
暮れたと思ったら、もう明け方だ、と思えるこの季節
それなのに、こうして想い慕って寝付かれずにいると
随分と、夜は長いものだ...夜明けが、なかなかやって来ない
この歌で、「きなくさつきの、みじかよ」は
単に、五月の夜の短くなった季節の説明的な意味合いで解釈するのが多い
勿論、この語句のあることで、結句の「あかしかねつも」が生かされると思う
しかし、平安期の様々な「歌集」に、「なくやさつきの、みじかよ」とばかりある
その訓に触れたとき、平安の人たちの感性を知らされたような気がした
原文では「来鳴」なので、現訓の方が当たり前のように思うが
それを、平安時代の人たちは「なくや」と訓んだ
「や」には疑問、反語の係助詞、終助詞だけでなく
感動・詠嘆の「間投助詞」もある
間違っているかもしれないが、私はそう想って詠んだ作者の気持ちの方が
とても心地よく響いてくる
上出の「歌意」は、現訓に即して書いたが
仮に「なくや」として解することが出来るのなら
| 【歌意1985】改 |
ほととぎすが鳴いているなあ、この五月の夜に...
短くなったはずの、この五月の夜も
お前の鳴く声を聞くと、いっそう想われてならなくなり
夜明けの、なんと遠いことか... |
少なくとも、私にはこちらの方がいい
「ほととぎす」が、生かされている
同じようなことを、下段の「資料」の『全註釈』にも感じた
そこでは、「ほととぎすなどの、鳴く夜だという気持ちは、味わうべきだ」と言っている
私も、そう思う
だからこそ、「なくや」の方がいいと思う
「きなく」では、どうしてもその「行動」に誘われてしまうが
「なくや」では、自分と同じような気持ちで鳴いている、と想いを浮かべることができる
それにしても、この歌が、とても多くの歌集に収載されているのには驚いた
それだけではなく、鎌倉初期の「千五百番歌合」の「判詞」にも引用されていること
そこでは、競い合った歌い手が、それこそ有名な歌の語句を繋ぎ合わせただけだ、と批判され
結局は負けているが
確かに「判詞」も、率直だが
歌い手自身もまた、この掲題歌の「なくやさつきの」の箇所を気に入っていたのだろう
藤原定家もまた、その秀歌集『八代抄』で、この歌を載せている
この万葉歌の、その原文表記の意識は無くなっているのかもしれないが
「なくやさつき」と「詠み継がれ」ていった時代には
さらに、それが「秀歌」とされていることなどを思うと
今更ながらに、「きなく」と改訓した動機が知りたいものだ
歌の「質」ではなく、あくまで「原文」に沿って、ということを、
その「誰か」は貫いたのだろうか
鎌倉時代、初めての注釈書(万葉集注釈、1296年)を著した「仙覚」あたりが、
そうなのかもしれない
それまでの手法と違って、古語に忠実、俗説になびかない性質だったことを教えられている
そう言えば、『万葉集註釈(仙覚抄)』一度は読みたいと思いながらも
まだ手をつけていない
これも明日香図書館で探してみよう |
|
掲載日:2014.04.13.
| |
| 夏相聞 寄鳥 |
| 霍公鳥 来鳴五月之 短夜毛 獨宿者 明不得毛 |
| 霍公鳥来鳴く五月の短夜もひとりし寝れば明かしかねつも |
| ほととぎす きなくさつきの みじかよも ひとりしぬれば あかしかねつも |
| 巻第十 1985 夏相聞 寄鳥 作者不詳 |
【柿本人麻呂歌集】〔173・30・241〕
【赤人集】〔148・139・259〕
【古今和歌六帖】〔2699〕
【三十六人撰】〔4〕
【和漢朗詠集】〔154〕
【拾遺和歌集】〔125〕
【悦目抄】〔5〕
【千五百番歌合判詞[引用]】〔1291右〕
【定家八代集】〔219〕
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
| 【1985】 語義 意味・活用・接続 |
| ほととぎす [霍公鳥] |
| きなくさつきの [来鳴五月之] |
| みじかよも [短夜毛] |
| も [係助詞] |
[言外暗示] ~さえも・~でも |
体言につく |
| ひとりしぬれば [獨宿者] |
| し [副助詞] |
語調を整えたり、強意を表する |
| ぬれ [寝(ぬ)] |
[自ナ下ニ・已然形] 眠る・寝る・横になる |
| ば [接続助詞] |
[順接の確定条件(恒常条件)] ~するときはいつも |
已然形につく |
| あかしかねつも [明不得毛] |
| あかし [明かす] |
[他サ四・連用形] ~夜を明かす・(何かをしながら)徹夜をする |
| かね [かぬ] |
[接尾ナ下二型・連用形] ~のが難しい、~ことができない、などの動詞を作る |
| 〔接続〕動詞の連用形につく |
| つ [助動詞・つ] |
[完了(強意)・終止形] 必ず~・確かに~・~てしまう |
連用形につく |
| も [終助詞] |
[感動・詠嘆] ~よ・~なあ |
種々の語につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [きなくさつきの] |
底本も含め、この語句現訓の「きなくさつきの」が定着しているが
それでも、平安時代の歌集に、この掲題歌が収載されているのは、
「なくやさつきの」という語句になっている
いつ頃から、現訓になったのか解らないが、確かに原文の表記では、
「きなく」と訓じる方が、素直には違いない
それでも、何故平安の多くの歌集には、「なくや」とされたのだろう
原文の表記から、その意を汲んで「なくや」としたのだろうか
その訓が、「平安時代」のスタイルだということだろうか...
|
| |
| [みじかよも] |
「短夜」という表現は、『万葉集中』でも、この一例だけ
秋の「長夜」という「観念」に対して、
五月の「短夜」という「観念」があったということだ
|
| |
|
| [あかし] |
「夜明け」の動詞で、他動詞「明かす」、自動詞「明く」がある
夜が明ける、という意味なら、自動詞下二段「明く」
夜を明かす、という意味なら、他動詞四段「明かす」だが
私は、てっきり「夜が明ける」意だと思い込んでいた
だから、どうしても次の「かね」と接続が出来ず、頭を抱えてしまったが
確かに、他動詞であれば、接続の問題はなくなる
しかし、よく考えてみれば
「夜が明け難い」という現象は、作者自身に由来するもので
自分が、夜明けを遅らせている、という解釈になる
自然の「夜明け」ではなく、自分にとっての「夜が長い」ということが
他動詞で表現することになるのだろう
|
| |

|
| 掲題歌[1985]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
【柿本人麻呂歌集】
| 新編私家集大成第一巻2 人麿Ⅰ 柿本人丸集[書陵部蔵「歌仙集」五一一・二] |
| 時鳥なくや五月のみしか夜も ひとりしぬれはあかしかねつも |
| 柿本人丸集下 173 |
| 新編私家集大成第一巻3 人麿Ⅱ 柿本集[書陵部蔵五〇一・四七] |
| ほとゝきす啼やさ月のみしか夜も ひとりしぬれはあかしかねつも |
| 柿本集 夏 30 |
新編私家集大成第一巻4 人麿Ⅲ 柿本人麿集
[冷泉家時雨亭叢書『素寂本私家集西山本私家集』] |
| ホトヽキスナクヤサツキノミシカヨモ ヒトリシヌレハアカシカネツモ |
| 柿本人麿集中 恋部 詠鳥 万十 241 |
| 新編国歌大観第三巻1 人丸集[書陵部蔵五〇六・八] |
| 郭公なくやさ月のみじか夜もひとりしぬればあかしかねつも |
| 人丸集下 173 |
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
| |
| ほとゝきすなくやさ月のみしか夜も ひとりしぬれはあかしかねつも |
| 新編私家集大成-新編増補[陽明文庫蔵三十六人集] 149 |
| ほとゝきすなくやさつきのみしか夜も ひとりしぬれはあかしかねつも |
| 新編私家集大成[書陵部蔵三十六人集] 140 |
| ほとゝきすなくやさつきのみしかよも ひとりしぬれはあかしかねつも |
| 新編国歌大観[西本願寺蔵三十六人集] 260 |
【古今和歌六帖 ([永延元年(987年)頃]撰、兼明親王・源順か)】
| 新編国歌大観第二巻4 [宮内庁書陵部蔵五一〇・三四] |
| ほととぎすなくやさつきのみじかよもひとりしぬればあかしかねつも |
| 第五 ひとりね 2699 |
【卅六人撰 (三十六人歌合、撰、藤原公任[966~1041])】
| 新編国歌大観 五巻267 |
| 郭公鳴くやさ月の短夜も独しぬればあかしかねつも |
| 三十六人撰 [書陵部蔵五〇一・一九] 人麿 4 |
【和漢朗詠集 (撰、藤原公任[966~1041])】
| 新編国歌大観第二巻 6 [御物伝藤原行成筆本] |
| ほととぎすなくやさつきのみじかよもひとりしぬればあかしかねつも人 |
| 倭漢朗詠集巻上夏 夏夜 154 人丸 |
【拾遺和歌集 (寛弘四年[1007年頃]撰、藤原公任[966~1041]か)】
| 新編国歌大観第一巻3 [京都大学附属図書館蔵本] |
| 郭公なくやさ月のみじかよもひとりしぬればあかしかねつも |
| 巻第二 夏 題しらず よみ人しらず 125 |
【説目抄 (作者不明、鎌倉後期成立)】
| 新編国歌大観第五巻332 [日本歌学大系四] |
郭公なくやさ月のみじか夜もひとりねたればあかしかねつつ
|
| 悦目抄 5 |
【定家八代集 (秀歌集、藤原定家[1162~1241])】
| 新編国歌大観第十巻177 [書陵部蔵二一〇・六七四] |
| 時鳥鳴くやさつきのみじか夜もひとりしぬればあかしかねつも |
| 巻第三 夏歌 拾少 219 読人不知 |
|
【新編国歌大観第五巻197 千五百番歌合[高松宮旧蔵本]】
| 解題 |
仙洞百首歌合とも。後鳥羽院主催の第三度百首を歌合にしたもの。各人の百首詠進は建仁元年(一二〇一)六月で、同二年九月に歌合にし判者一〇名が決定。建仁二年一〇月以降、翌年初頭に成立か。四季・祝・恋・雑にわけられ、詠者三〇名、千五百番、判者一〇名は歌合史上最大規模のもの。諸本は数系統に分けられるが、改訂を経たためであろう。
底本は現存最古の高松宮蔵の南北朝期写本とし、校訂本はおもに東京大学蔵長親(耕雲)本に拠った。
なお、底本の四五一番~六〇〇番までにのみ存する勝負判の注記は、編集方針上、本文中には省いたが、次のとおりである(数字は番数を示す)。 |
| 千二百九十一番 左 女房 |
| 二五八〇 かずかずにおもふこころはおほよどの松をうらむるなみのおとかな |
| 右 家隆朝臣 |
| 二五八一 あひにあひてものおもふころの夕ぐれになくや五月の山郭公 |
| |
左歌は、伊勢物語に、むかし、いせの国なる女にえあはぬ男、いみじううらみて、となりの国へいきければ、女、おほよどの松はつらくもあらなくにうらみてのみもかへるなみかな、とよめる歌の心をおもひて、かずかずにおもふ心はおほよどのとつづき、いみじうこそよまれてきこえ侍れ
右歌は、五句ながらおもしろくこそよみつづけられて侍るめれ、あひにあひてものおもふころのと侍る二句は伊勢が歌なり、夕ぐれにといふ腰句は斎宮女御の、さらでだにあやしきほどのゆふぐれにと侍る歌、なくやさ月のは万葉の、ほととぎすなくや五月のみじか夜もと侍る歌の一句、山郭公とはてたるは躬恒が歌に、くるるかとみればあけぬる夏の夜をあかずとやなく山ほととぎす、已上新歌とて一文字もわが詞侍らぬうへに、させる事侍らずや、古今に、夏山になくほととぎす心あらばものおもふわれにこゑなきかせそ、と申す
歌のこころにこそ、堂舎高危瓦有松と申す詩を法花経の四文字に久歩三文字を読と感じけるには不可似歟、然者為負 |
|
 |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「霍公鳥 来鳴五月之 短夜毛 獨宿者 明不得毛」
「ホトヽキス キナクサツキノ ミシカヨモ ヒトリシヌレハ アカシカ子ツモ」(「【】」は編集、歌番は旧) |
| 〔本文〕頭注に、赤人集「ほとゝきすなくやさつきのみしかよもひとりしぬれはあかしかねつも このうた人丸集にあり」 |
| 「明」 |
『類聚古集』コノ下「石」アリ
『大矢本』ナシ。右ニ書ケリ。本文中「者不」ノ間ニ「○」符アリ
『活字無訓本』「朋」
『近衛本』底本ニ同ジ
|
| 「得」 |
『神田本』「○【判読出来ず】」
|
| 〔訓〕 |
| キナク |
『元暦校本・類聚古集』「なくや」。『元』ソノ右ニ赭「キナク」アリ
『神田本』「ナクヤ」
『神宮文庫本・細井本』漢字ノ左ニ「ナクヤ」アリ
『京都大学本』漢字ノ左ニ赭「ナクヤ」アリ
|
| ヒトリシヌレハ |
『元暦校本』「人りしぬれは」
『西本願寺本・細井本』「ヒトリシ子レハ」。『西』「子」ノ右ニ「ヌ」アリ。『細』漢字ノ左ニ「ヒトリシヌレハ」アリ
『神宮文庫本』「ヒトリシネレハ」漢字ノ左ニ「ヒトリシヌレハ」アリ
|
| 〔諸説〕 |
| ○[ヒトリシヌレハ]『童蒙抄』「ヒトリ子ヌレハ」 |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1985] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
| |
〔ほとゝきすきなく五月の短夜もひとりしぬれはあかしかねつも 〕
霍公鳥來鳴五月之短夜毛獨宿者明不得毛
|
ひとりし、の「し」、かねつも、の「も」は助詞
朗詠集には、「なくやさつきの」とあることを言う
朗詠集に限らず、季吟までのこの歌の収載された歌集には、
どれも「なくやさつきの」が載っている
諸本でも、上の『校本』に「異訓」を載せるように、「なくや」を伝える書が多い |
| ほとゝきすきなく 独しのしかねつものも皆助字也朗詠にはなくやさつきのと有 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
| |
〔ホトヽキスキナクサツキノミチカヨモヒトリシヌレハアカシカネツモ〕
霍公鳥來鳴五月之短夜毛獨宿者明不得毛 |
『遊仙窟』の「實怨更長」、私にしては珍しく
漢字からこの歌の歌意も窺われる
このような情況の「心」というのは、結構あると思う
|
| ヒトリシのしは助語なり、遊仙窟云、昔日雙眠、恒嫌夜短、今宵獨臥、實怨更長、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
| |
〔ほとゝぎす、きなくさつきの、みじかよも、ひとりしぬれば、あかしかぬつも 〕
霍公鳥來鳴五月之短夜毛獨宿者明不得毛 |
この問題にしている「夜も」の「も」、
文法的には、名詞につく「係助詞」なのだが、
意味合いとしては、逆接の接続助詞のような解釈だと思う |
| 此歌は、たゞ短夜も一人ねぬれば、明しかねると云義迄に、郭公の來鳴く夏の夜もとよそへたる也。よもの意此歌にては少しうすき也。色々巧拙はあるべき事也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
| |
霍公鳥、來鳴五月之、短夜毛、獨宿者、明不得毛[アカシカネツモ]、 |
歌意の明白な歌だ、ということだろうが
どうもこの書では、歌の評価はしない方針のようだ |
| 歌の意かくるゝ事なし |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
| |
〔ほととぎす。きなくさつきの。みじかよも。ひとりしぬれば。あかしかねつも。〕
霍公鳥。來鳴五月之。短夜毛。獨宿者。明不得毛。 |
記述なし |
| 記なし |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
| |
〔ホトヽギス。キナクサツキノ。ミヂカヨモ。ヒトリシヌレバ。アカシカネツモ。〕
霍公鳥來鳴五月之短夜毛獨宿者明不得毛
|
暮れるやいなや、もう夜が明けるこの季節、と情景の説明に、
「一筋に人を戀しや戀しや」というのが踏み込んだ歌意の解釈になっている
この心持では、この季節でも、なかなか夜は明けてくれない |
歌(ノ)意は、暮るかと思へば、早明るやうなる、極めて短かき五月の短夜をさへも、唯獨宿をすれば、一(ト)すぢに人を戀しや戀しやと思ひて、たやすく明すことを、得せず、さても明がたしとなり、
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
| |
〔ほととぎす來なく五月のみじか夜も獨しぬればあかしかねつも 〕
霍公鳥來鳴五月之短夜毛獨宿者明不得毛 |
記述なし |
| 記なし |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| |
霍公鳥來鳴く五月の短夜も、獨りし寢れば、明しかねつも |
この季節を通して、いつも夜明けが長く感じるほど
一人寝の寂しさをいう |
| |
子規が來て鳴く五月頃の、夜の短い晩も、獨り寢するので、いつも夜明けを待ちかねることだ。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
| |
〔ほととぎす 來鳴く五月の 短夜も 獨しぬれば あかしかねつも〕
ホトトギス キナクサツキノ ミジカヨモ ヒトリシヌレバ アカシカネツモ
霍公鳥來鳴五月之短夜毛獨宿者明不得毛 |
『拾遺集』に載せたのも尤もだ、という
こうした「心情」の歌では、「秀歌」ということなのだろう
万葉以降の、多くの歌集にも、この歌は載せられている |
霍公鳥ガ來テ鳴ク五月ノ頃ハ誠ニ夜ガ明ケルノガ早イモノダガ、ソノ短イ夜デモ、一人デ寢レバ夜ガ明ケルノガ待チカネルヨ。
〔評〕 明朗な歌だ。拾遺集に載せたのも尤もである。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
| |
〔ほととぎす 來鳴く五月の 短夜も、ひとりし宿れば 明かしかねつも。〕
ホトトギス キナクサツキノ ミジカヨモ ヒトリシヌレバ アカシカネツモ
霍公鳥來鳴五月之短夜毛獨宿者明不得毛 |
原文の訓み方に、意をもって訓ませる、とは解り易い
確かに「不得」を「かねつ」とは訓めない
万葉集には、こうした用例が多くある
さらに、ほととぎすが「来て鳴く」を季節の象徴だけでなく
「鳴く夜」にも注目しなければ、という
その方が、いっそう「恋しさ」「寂しさ」が募るのだろう |
【譯】ホトトギスの來て鳴く五月の短い夜も、ひとりで寐るので、明かしにくいことだ。
【釋】明不得毛 アカシカネツモ。容易に夜が明けないの意である。不得は、ユズともカヌとも讀まれるが、これなどは、意をもつてカネツと讀まれる例である。
【評語】ひとり寐て、短い夏の夜も明かしかねる心である。ホトトギス來鳴クという短夜の敍述があつて、はじめて歌に生氣がある。その説明は平凡だが、ホトトギスなどの鳴く夜だという氣もちは味わうべきだ。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
| |
〔ほととぎす來鳴く五月の短夜も一人し寝れば明しかねつも〕
ホトトギス キナクサツキノ ミジカヨモ ヒトリシヌレバ アカシカネツモ
霍公鳥來鳴五月之短夜毛獨宿者明不得毛 |
「観念的すぎる」というのは、少し説明不足だと思う
真淵も言うように、とても解り易い歌だと思うのだが... |
【大意】ほととぎすの来て鳴く、五月の短い夜も、一人寝をすれば、明かしかねる。
【作意】観念的すぎる歌だ。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
| |
〔霍公鳥 來鳴く五月の 短夜も ひとりしぬれば 明しかねつも〕
ホトトギス キナクサツキノ ミジカヨモ ヒトリシヌレバ アカシカネツモ
霍公鳥來鳴五月之短夜毛獨宿者明不得毛 (『元暦校本』) |
この書では、関連する書を紹介しているのが有りがたいが、ただ一つ、
「夜半の目覚」だけは、捜し得なかった
物語の書であることは、調べて解ったが、どんな風に引用されたのか
その箇所を見つけられなかった
歌意に特筆はない
|
【口訳】霍公鳥が来て鳴く五月の短い夜も、ひとりでねると明しかねることよ。
【訓釈】ひとりしぬれば明しかねつも―「ひとりし」の「し」は強意の助詞。「不得毛」は「カネツモ」と訓む(1・30、72)。既出(1953)。
【考】『代匠記』に「遊仙窟」の「昔日雙眠、恒嫌夜短、今宵獨臥、實怨更長」を引いてゐる。
柿本集(下)、赤人集、古今六帖(五「ひとりね」)、卅六人撰、朗詠集などいづれも「鳴くやさつきの」とあり、赤人集に「このうた人丸集にあり」とし、卅六人撰も朗詠集も人丸とする。拾遺集(二)には「鳴くや五月の」「あかしかねつゝ」よみ人知らず、とある。「夜半の寝覚め」(四)に「鳴くや五月の短夜も明かしかねつゝ」とあるは拾遺によつたものであるが、千五百番歌合(十八)の千二百九十一番の判詞にも引用され、悦目抄にも見え、この歌が後世の歌人に愛誦された事が察せられる。 |
|
|

| |
| 「いもとあれとし」...たづさはりねば... |
| |
| 『構わぬ』 |
| 【歌意1987】 |
人の噂というものは、夏の野に生い茂っている草のように、
刈っても刈っても決してなくなるものではない
でも私は、たとえそんなに口やかましいことであろうとも、
愛しいあの娘と、必ず添い遂げるだろう
そのあとは、どうなろうと構わない
二人が、悔やまないように、何があっても「俺が守る」 |
| |
| |
この歌、心情的に二つの受け方があると思う
一つは、あの娘と添い遂げられるのであれば
世間で何を言われても構わない、という「強い願望」
結句の「仮定条件」の用い方では、この解釈が普通だと思う
そして、もう一つの気持ちとしては
周りがどう言おうが、あの娘は俺が守る
私たちのことは、誰にも邪魔させない
これは、多分に「思い入れ」を強くした感じだけのようだが
そうではない
普通の解釈では、相手の娘の気持ちが反映されない
勿論、作者の気持ちはそうかもしれない
まだ親しくもない相手に、唐突にアプローチをして
それで周囲からとやかく言われても、
この恋が実るのであれば...
逆の場合もある
「とやかく」言われかねない、というのは
決して似合いの二人、と言う意味ではなく、少なからずの事情が窺える
お前がどんなに恋慕っても、無理だよ
だって、あの娘は、というようなニュアンスだ
そして、それが「娘」についての芳しくない評判であれば
尚更、男がアプローチすることに、周囲は騒々しくなる
そんなことを考えて、俺は躊躇なんてしない
何があっても、あの娘は俺が傍にいて守ってやる
そんな「男の決意」のようなものが感じられる
『全釈』に、「男らしい表現」という評があった
そう感じ取れるのは、単に憧れ的な「願望」ではなく
命懸けで「添い遂げる」ということこそ、ぴったりの表現だと思う
右頁の類想歌『古今和歌集』の〔704〕歌
どんなに噂を立てられようと、離れて行ってしまった君に逢わないでいられようか
これは「女歌」だが、この想いもまた、深いところで通じていると思う
「夏ののしげく」が理由で、二人は離れ離れにさせられた、とも感じることが出来る
それでも、女の方からは、「逢いたい、逢わずにはいられない」
この歌と、掲題の万葉歌とが、私にはとても呼応しているように思えてならない
小野小町の歌で、結句「ずは」が、やはり仮定条件で、この万葉歌に心情的に沿う
「人言・さと人の事(言)」が、ここでは「明日香川」ということなのだろうか
誰にも止められず、「明日香川のように、流れるなら流れろ」と譬えて...
これも「女歌」だが、こうまでも「人の噂」など気にしない、という気持ちが
女の方に見えるのなら、それに対して男が気持ちを詠うとすれば
普通の解釈ではなく、そこには「そこまでの想い」がある女に対して、
やはり相当の覚悟があって初めて「詠える」ものだと思う
「たづさはりねば」という語句は、象徴であり
その語義に備わる意味としては、「添い遂げる」だと私は思う |
|
掲載日:2014.04.14.
| |
| 夏相聞 寄草 |
| 人言者 夏野乃草之 繁友 妹与吾師 携宿者 |
| 人言は夏野の草の繁くとも妹と我れとし携はり寝ば |
| ひとごとは なつののくさの しげくとも いもとあれとし たづさはりねば |
| 巻第十 1987 夏相聞 寄草 作者不詳 |
【柿本人麻呂歌集】〔64〕
【赤人集】〔151・133・253〕
【古今和歌六帖】〔3551〕
【拾遺和歌集】〔827〕
【和歌童蒙抄】〔550〕
【八雲御抄】〔202〕
[類想歌]
【古今和歌集】〔704〕
【玉葉和歌集】〔2807〕
【小町集】〔84〕
【風雅和歌集】〔1232/1222〕
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
| 【1987】 語義 意味・活用・接続 |
| ひとごとは [人言者] |
| ひとごと [人言] |
他人のいうことば・世間の噂 |
| なつののくさの [夏野乃草之] |
| しげくとも [繁友] |
| しげく [繁し・茂し] |
[形ク・連用形] 草木が生い茂っている・量が多い |
| とも [接続助詞] |
[仮定条件の強意] たとえ~でも |
| 〔接続〕動詞・形容動詞・助動詞は終止形に、形容詞は連用形につく |
| いもとあれとし [妹与吾師] |
| し [副助詞] |
語調を整えたり、強意を表する |
| たづさはりねば [携宿者] |
| たづさはり [携はる] |
[自ラ四・連用形] 互いに手を取る・連れ立つ・関係する・係わる |
| ね [寝(ぬ)] |
[自ナ下二・未然形] 眠る・寝る・横になる |
| ば [接続助詞] |
[順接の仮定条件] ~(する)なら・~だったら |
未然形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [ひとごと] |
評判・噂のことだが、『万葉集中』では、「良い評判」について詠ったものは少ない
ほとんどが、恋に係わり、その妨げになるような「噂」の意味で用いられている
『全注』によると、「人言」の「集中の用例」では三十首あるが、
その内の二十三首が「しげく・しげき」で受けている、という
草木の茂るように、鬱陶しさ・煩わしいさを籠めた用例といえる
|
| |
| [文末の接続助詞「ば」] |
仮定条件の接続助詞が文末にくる場合には、副詞「よし」などの語が省略されている
この歌の場合、「仮定条件」なので、それで結ばれると、
次に、「あとはどうなってもいい」ような限定された使い方になる
副詞「よし(縦し)」の意味は、
「よし」といって仮に許す意から、不満足ではあるが、しかたがない
ままよ、どうなろうとも、などの意がある
|
| |
|

|
| 掲題歌[1987]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
【柿本人麻呂歌集】
| 新編私家集大成第一巻2 人麿Ⅰ 柿本人丸集[書陵部蔵「歌仙集」五一一・二] |
| 人ことは夏のゝ草としけくとも 妹とわれとしたへさわりなは |
| 柿本人丸集下 64 |
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
| |
| ひとことはなつのゝ草のしけくとも 君とわれとはたつさはりなは |
| 新編私家集大成-新編増補[陽明文庫蔵三十六人集] 151 |
| ひとことはなつのゝくさはしけくとも いもとわれとしたつさはりなは |
| 新編私家集大成[書陵部蔵三十六人集] 133 |
| ひとことはなつのゝくさにしけくとも いもとわれとしたつさはりなは |
| 新編国歌大観[西本願寺蔵三十六人集] 253 |
【古今和歌六帖 ([永延元年(987年)頃]撰、兼明親王・源順か)】
| 新編国歌大観第二巻4 [宮内庁書陵部蔵五一〇・三四] |
| 人ごとはなつののくさのしげくともいもと我としたづさはりなば |
| 第六 草 夏の草 3551 |
【拾遺和歌集 (寛弘四年[1007年頃]撰、藤原公任[966~1041]か)】
| 新編国歌大観第二巻 6 [御物伝藤原行成筆本] |
| 人ごとは夏野の草のしげくとも君と我としたづさはりなば |
| 巻第十三 恋三 人麿 827 |
【和歌童蒙抄 (仁平年間(1151~54)頃、藤原範兼[1107~1165])】
| 新編国歌大観第五巻-293[古辞書叢刊<尊経閣本>] |
| ひとごとはなつののくさのしげくともいもとわれとしたづさはりなば |
| 第七巻 草部 夏草 550 |
【八雲抄 (文暦元年[1234]頃、順徳院[1197~1242]作)】
| 新編国歌大観第五巻-311 [日本歌学大系別巻三] |
| 人ごとは夏野の草のしげくともいもとわれとしたづさはりなば |
| 巻六 用意部 202 |
|
【類想歌】
【古今和歌集 ([延喜五年(905年)]撰、紀貫之[866~945]他)】
| 新編国歌大観第一巻-1[伊達家旧蔵本] |
この歌は、返しによみてたてまつりけるとなむ
さと人の事は夏ののしげくともかれ行くきみにあはざらめやは |
| 巻第十四 恋 704 よみ人しらず |
【玉葉和歌集 ([正和ニ年(1313年)]撰、京極為兼[1254~1332])】
| 新編国歌大観第一巻-14 [宮内庁書陵部蔵 兼右筆「二十一代集」] |
人のもとにつかはしける 小野小町
世の中はあすか川にもならばなれきみとわれとがなかしたえずは
|
| (陽明文庫蔵甲本巻第十一、一四九六の次) 異本歌 2807 小野小町 |
【小町集 (古今和歌集、後撰和歌集の小町関係歌の編集 [一部「三十六人集」])】
| 新編国歌大観第三巻-5 [陽明文庫蔵本] |
| 世の中はあすか川にもならばなれ君と我とがなかしたえずは |
| 見し人のなくなりしころ 84 |
【風雅和歌集 ([貞和五年(1349年)]撰、正親町公蔭[1297~1360])】
| 新編国歌大観第一巻-17 [九大附属図書館蔵本] |
| 世中はあすか川にもならばなれ君と我とが中したえずは |
| 巻十三 恋歌四 1232/1222 小町 |
|

|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「人言者 夏野乃草之 繁友 妹與吾 携宿者」
「ヒトコトハ ナツノヽクサノ シケクトモ イモトワレトシ タツサハリ子ハ」(「【】」は編集、歌番は旧) |
〔本文〕頭注に、和歌童蒙抄、第七「ヒトコトハナツノヽクサノシケクトモイモトワレトシタツサハリテハ 万葉第十ニアリ」
赤人集「さくらによす ひとことはなつのゝくさにしけくともいもとわれとしたつさはりなは」
八雲抄、第六「万葉集哥なとを本哥とかやうとしもなくてすこしをかへてよめるにほし 人ことな夏野の草のしけくともいもとわれとしたつさはりなはといふ哥をとりて(下略)」 |
| 「吾」 |
『元暦校本・類聚古集・神田本』コノ下「師」アリ
|
| 「携」 |
『元暦校本』「乃」墨ニテ消セリ。右ニ墨「携」アリ
|
| 〔訓〕 |
| タツサハリ子ハ |
『元暦校本』「つ」ノ右ニ赭「ツ」アリ。「ね」ノ右ニ赭「ナ」アリ
『類聚古集』「宿者」ノ右ニ朱「ナハ」アリ。「宿」ノ左ニ朱「子」アリ
『神田本』「タトサハリ子ハ」
『細井本』「タツサワリ子ハ」
『神宮文庫本』「タツサワリネハ」
|
| 〔諸説〕 |
| ○ナシ |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1987] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
| |
〔ひとことは夏野の草のしけくともいもとわれとしたつさはりねは 〕
人言者夏野乃草之繁友妹與吾携宿者
|
どんなに噂されようと、あの娘と添い寝できたら
あとは、どうなっても構わない |
| ひとことは夏のゝ草の 口さかなき人ことは夏草のことくしけくとも妹とそひねはよしよしと也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
| |
〔ヒトコトハナツノヽクサノシケクトモイモトワレトシタツサハリネハ〕
人言者夏野乃草之繁友妹與吾携宿者 |
吾とし、の「し」は強意の副助詞「し」
たしかに、上述の関連「歌集」に載せたように、
結句が「なば」となっているものばかりで、これを「宿」の字を忘れたのだろう、と断定しているが
上出の『元暦校本』や『類聚古集』には、その訂正めいた跡が感じられるものの、特に『類聚古集』では、「宿者」を「ナハ」そして朱で「子(ね)」と記している
平安、鎌倉時代の歌集が、この歌を収載したにせよ、ほぼその同時代の「校本」には、「宿者」もまた「ねは」との認識があったようだ
類歌の小町の歌、『玉葉歌集』にあるが、人の噂「人言」を「世間」は何と言おうと、と引用している |
| 吾トシのしは助語なり、落句の云ひ殘せる意はさもわらばあれなり、拾遺六帖人丸集並にたづさはりなばとあり、宿の字を忘たり、古今に、里人の言は夏野の繁くとも、かれ行君にあはざらめやは、玉葉に小町歌云、世間は明日香川にも成らば成れ、君と我とが中し絶ずば、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
| |
〔ひとごとは、なつのゝくさの、しげくとも、いもとわれとし、たづさはりねば 〕
人言者夏野乃草之繁友妹與吾携宿者 |
どんなに噂があろうとも、あの娘と添い遂げられるなら、
決して嫌なことではない |
| 人は如何に云ひ騷ぐ共、妹と我と携はりてねなば厭はじと也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
| |
人言者、夏野乃草之、 此之の下に如を入て心得べし 繁友、妹與吾[イモトワレトシ]、携宿者[タヅサハリネバ] |
「たづさはり」を「手」と「さはり」に分けたのかな
それで、本義は「たさはり」とし、「づ」は助詞とする
「さはり」の意味でもないだろうし、「てさはり」の感覚なのかもしれない |
| たづさはりは手さはりなりづは助字なり携の字はあてゝ書しのみ人言のしげきはいとはじとなり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
| |
〔ひとごとは。なつぬのくさの。しげくとも。いもとわれとし。たづさはりねば。〕
人言者。夏野乃草之。繁友。妹與吾。携宿者。 |
第二句の「なつぬのくさの」の後に「如し」の省略は明白であり、わざわざ言うまでもないと思うが、ここまで書けば、結句の「よし」の省略にも触れなければならない
『元暦校本』などに、「師」が補記されていることをいう |
| 草ノ如クと言ふを略き、携リネバヨケムと言ふをこめたり。元暦本、吾の下師の字有り。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
| |
〔ヒトコトハ。ナツヌノクサノ。シゲクトモ。イモトアレトシ。タヅサハリネバ。〕
人言者夏野乃草之繁友妹與吾師携宿者
|
類歌として、古今集の一首をあげる
そして、小町の一首には、その想いも同じものだ、という
この書の段階で、ようやくこの歌の「注釈」書らしさが出てきた |
本(ノ)句は、古今集に、里人の言は夏野のしげくともかれゆく君にあはざらめやも、とあり、○師(ノ)字、舊本にはなし、今は元暦本に從つ、○携宿者[タヅサハリネバ]、といひのこしたるは、よしやそれはさもあらばあれと、云意を含ませたるなり、小町(カ)歌に、世中はあすか河にもならばなれ君とわれとが中したえずば、とあるに似たり、○歌(ノ)意は妹と吾と、二人手を上りかはして宿たらば、夏野の草の繁きが如く、人言は繁くいひさわぐとも、よしやそれはさもあらばあれ、いとひはすまじきを、いかにもして、一(ト)すぢに相宿せまほしく思ふ、このごろぞ、となり、
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
| |
〔人言は[夏野の草の]しげくとも妹と吾としたづさはりねば 〕
人言者夏野乃草之繁友妹與吾携宿者 |
第二句「夏野の草の」が、「枕辞」と言うのは、七文字だから、「枕詞」とは言わずに「枕辞」というのだろうか
「枕辞」のことは知らなかった
大正時代には、「枕詞」のことを「枕辞」と言っていたのかも知れないし、あるいは「七字」用の用語かもしれない
調べてみよう
語順を、結句の次に余情を残す「ヨシヤ云々」は、第三句の「しげくとも」の下にこそ補い感じるべき、とする
それでも、歌意には影響はないと思うが
私の理解不足なのかもしれない |
| 第二句はシゲクの枕辭なり。結句の下にウレシカラムといふばかりの意を略せるなり。古義に『タヅサハリネバといひのこしたるはヨシヤソレハサモアラバアレと云意を含ませたるなり』といへるは非なり。さる意は第三句の下にこそ補ひてきくべけれ |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| |
人言は、野の夏草の繁くとも。妹と我としたづさはり寢[ネ]ば |
歌意に特筆なし |
| |
人の評判は、譬ひ夏野の草のやうに、うるさく立つても、いとしい人と自分とが、寄り添うて寢ることさへ出來れば、何でもない。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
| |
〔人言は 夏野の草の 繁くとも 妹と我とし 携はり寝ば〕
ヒトゴトハ ナツヌノクサノ シゲクトモ イモトワレトシ タヅサハリネバ
人言者夏野乃草之繁友妹與吾師携宿者 |
『新考』の「枕辞」を、やはり「枕詞」と解釈するのはよくない、としている
確かに、省略された「如し」を認めるのなら、「譬え」だと思う
男らしい表現...なるほど、と思う |
人ノ噂ハ夏ノ野ニ生エタ草ノヤウニ、澤山デモ、女ト私ト一緒ニ寢サヘスレバ、ソレデ何モ思フコトハナイ。人ノ惡ロナドカマフモノカ。
○夏野乃草之[ナツヌノケサノ]――これは譬喩である。繁[シゲク]の枕詞とするのはよくない。
○妹與吾[イモトワレトシ]――元暦校本に吾の下、師の字があるのがよい。
〔評〕 結句嬉しからむといふやうな餘情を含めてゐるのが、珍らしい形になつてゐる。男らしい強い表現である。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
| |
〔人言は 夏野の草の 繁くとも、妹と吾とし 携はり宿ば。〕
ヒトゴトハ ナツノノクサノ シゲクトモ イモトワレトシ タヅサハリネバ
人言者夏野乃草之繁友妹與吾師携宿者 |
周囲を気にするな、私たちの気持ちこそ一番大切なものだ
特にないが、「概念的」の意味が解らない |
【譯】人の言葉は、夏の野の草のように繁くあつても、あなたとわたしとが共に寐たらそれでよいのだ。
【釋】人言者 ヒトゴトハ。ヒトゴトは、他人の言。うるさい人の口である。
夏野乃草之 ナツノノクサノ。一句、譬喩の插入句。
携宿者 タヅサハリネバ。この下に、よしの如き語が省略されている。
【評語】思い入つた心が歌われている。譬喩はよくあてはまつているが、それだけに概念的に落ちている。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
| |
〔人言は夏野の草の繁くとも妹と吾とし携はり寝ば〕
ヒトゴトハ ナツヌノクサノ シゲクトモ イモトワレトシ タヅサハリネバ
人言者夏野乃草之繁友妹與吾師携宿者 |
周囲が喧しく、そんな情況であっても私たちは想いを貫こう、か |
| 【大意】世間の人の言葉は、夏野の草のしげき如く、しげきうるさくとも、妹と吾とで、手を取り合つて寝れば、それもかまはぬ。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
| |
〔人言は 夏野の草の 繁くとも 妹と吾とし 携はりねば〕
ヒトゴトハ ナツノノクサノ シゲクトモ イモトワレトシ タヅサハリネバ
人言者夏野乃草之繁友妹與吾師携宿者 (『元暦校本』) |
歌意に特筆はないが、
ここで「類歌」として挙げた小町の一首
おそらく、いろんな「歌集」に収載されてはいようが、
ここでいう「風雅集」では、「巻十四」ではなく「巻第十三」にあり、
「玉葉集」には、「異本歌」の巻に「陽明文庫蔵甲本巻第十一」の出典として載っていた |
【口訳】人の口は、夏野の草のやうに、繁くあらうとも、あの子と私と相携へて寝たならば―。
【訓釈】夏野の草の―夏の野の草の如く。
妹と吾とし携はりねば―「師」の字、『元暦校本・類聚古集・紀州本』による。『西本願寺本』以後落ちてゐる。「携はり」の事は前(2・210、4・728)に述べた。相携へて寝たならば、人の口がうるさくともかまわない、の意が省略された形である。
【考】古今六帖(六「夏の草」)「たづさはりなば」柿本集(下)「夏野の草と」「たづさはりなば」、赤人集「夏野の草に」「たづさはりなば」、流布本は柿本集と同じ。拾遺集(十三)「たづさはりなば」人麿とある。
類歌
さと人の言は夏野の繁くともかれゆく君にあはざらめやは (古今集巻十四) よみ人しらず
世の中はあすか川にもならばなれ君と我とが中したえずば (風雅集巻十四) 小町 |
|
|

| |
| 「かりはらへども」...こひのしげけく... |
| |
| 『くも、むげん』 |
| 【歌意1988】 |
近頃の、この私の溢れんばかりの恋心は
一体どうやったら収まるのだろう...
それは、刈り掃っても刈り掃っても、
追いつくようにすぐ生えてくる夏草のようだ
|
| |
| |
青空を見上げながら、こんな心境の歌を詠う
私なら、そんな情況で詠いたくなる
空には、無限の空間が広がるが、私の「こころ」には、そんな広大な余裕もない
だから、どんどん脹らむこの恋心を、何とかしなければ
切なくなる一方だ
刈り掃っても刈り掃っても、また同じように生えてくる夏草のように...
作者の「想い」は、それをどうしようとして、この歌を詠んだのだろう
勿論、その答えが解ってから詠んだのではない
ただ、一つの手掛かりはある
作者が無意識に(だと思う)用いた「かりはらへども」
譬としては、よく理解出来る表現だとは思う
しかし、「はらふ(掃ふ・払ふ)」の意味は、取り除くこと
除き去る、と言うのであれば、何となくこの「恋心」が鬱陶しく感じられる
そこに、刈り取る意の「刈る」が加わる
いくら、その後の「どんどん生える」意味を譬える語句であっても
「刈り掃う」というのは、その意味を思い出さなければならない、と思う
根こそぎ、刈り取る
そこまでしても、生えてくる夏草のように、「恋心」は収まらない
ようは、「忘れることなど出来ない」という歌になる
下段資料の、『万葉拾穂抄』の北村季吟は、
「夏草のかりてもおひしきるかことく忘んとしても戀の難忘と也」と述べている
おそらく、こんな具体的な解釈に及ぶのは、この書以外ないのでは、と思う
多くの書は、「夏草のように繁る恋心、刈っても刈っても、また生茂る」
その表記のままの解釈で終っている
それでは、古語辞典を持ち出せば、注釈書など要らなくなる
勿論、注釈書に頼ることではなく
「注釈書」と銘打つのであれば、その「歌意」こそ「表現されたもの」として述べなければ
本来の意味ではないように思う
だから、『拾穂抄』のような、一つの見方も、その賛否は別であって
その姿勢は大切だと思う
私も、何度も読み、語義を考えれば、
結果として、同じような思いに至った
この歌は、溢れんばかりの切ない恋心を、
何とか忘れようとして苦しむ人の歌ではないか、と
その思いに至ったもう一つのきっかけがある
それは、柿本人麻呂集に所載されている歌だ
この掲題歌と、どちらが本歌か解らないが、そこには「かりはつれども」とある 〔下段資料〕
「はつれ」は、自動詞タ行下二段「はつ」の已然形「はつれ」、その意味は
「終りになる・終る」など
そして、この歌のように、動詞の連用形について「補助動詞」の用法もある
その場合は、「~おわる」「すっかり~きる」の意を表す
だから、この柿本人麻呂歌集歌の場合、
「すっかり刈り掃いきる」のような意味合いになるはずだ
すると、人麻呂歌集歌では、
掲題歌の「かりはらふ」よりも、いっそう強いものを感じる
そこまでの想い、というのは
やはり、こんなに苦しいものなら、忘れたい...
すべてを忘れたいと思う気持ちが、この表現になったのではないかと思う
当然、この人麻呂歌集歌と、掲題歌はリンクしているはずだから
どちらが本歌かは別にしても、
この歌の本来の意味として、忘れられるものなら忘れたい
しかし、生茂る夏草のように、
どんなに刈り掃っても、次から次へと恋しさが募ってくる...
そんな風に読みたい歌だ
『万葉集中』に「かりはつ」という用例は、なかった
|
|
掲載日:2014.04.15.
| |
| 夏相聞 寄草 |
| 廼者之 戀乃繁久 夏草乃 苅掃友 生布如 |
| このころの恋の繁けく夏草の刈り掃へども生ひしくごとし |
| このころの こひのしげけく なつくさの かりはらへども おひしくごとし |
| 巻第十 1988 夏相聞 寄草 作者不詳 |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】〔66・405・234・64〕
【赤人集】〔151・133・253〕
【古今和歌六帖】〔3551〕
[類想歌]
【万葉集巻第十一】〔2779〕
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
| 【1988】 語義 意味・活用・接続 |
| このころの [廼者之] |
| このころ [此の頃] |
近頃・近いうち・まもなく・今頃 |
| こひのしげけく [戀乃繁久] |
| しげけく [繁けし] |
[形ク「繁し」のク語法] たくさんであること・しきりであること |
| なつくさの [夏草乃] |
| かりはらへども [苅掃友] |
| はらへ [掃ふ] |
[他ハ四・已然形] 取り除く・除き去る・追い払う |
| ども [接続助詞] |
[逆接の確定条件] ~けれども・~のに・~だが |
已然形につく |
| おひしくごとし [生布如] |
| おひ [生ふ] |
[自ハ上二・連用形] 生ずる・生える・生長する |
| しく [及く・若く] |
[自カ四・連体形] 追いつく・至りつく・匹敵する・肩を並べる |
| ごとし [助動詞・ごとし] |
[例示・終止形] たとえば~(の)ようだ |
連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [このころ] |
原文「廼者」は、「廼」が「この」という意味で、『万葉集注釈』によると
「『廼者』は漢書、元帝紀(三年)に『廼者火災降於孝武園館』とあり、この頃の意に用ゐる。」
とある
他の注釈書では、この出典には言及していない
確かに古語辞典で引いても
「廼」を「この」、もしくは「廼者」を「このころ」とは出ていない
『万葉集中』で、「この頃」という意で表記されるのは
「頃者・比日・比来・比者」などであり、「廼者」の表記は、この一首のみ
|
| |
| [かりはらへども] |
旧訓は「かりはらふとも」と言うのだろうか、江戸時代からの注釈書では
すでに「かりはらへども」が大勢になっている
契沖の『代匠記』や、『校本万葉集』で、「かりはらふとも」を知るくらいだ
それにしても「仮定条件」の「とも」と、「確定条件」の「ども」では、
その解釈も違うと思うのだが、「改訓」が、「改意」をした、ということになるのかな
それに、類想歌として巻第十一の〔2779〕を載せる注釈書も多いが、
その歌は、「かりそくれども」の表現になっている
原文「苅除十方」で「かりそくれども」の訓になり、
歌意が同じだからといって、下二段動詞「刈り除く(かりそく)」を当てはめた感も否めない
ただ、〔2779〕は、その「苅除」という原文にその動詞もあるが、
この掲題歌のように、「刈り掃う」という動詞は見当たらない
勿論、「刈る」と「掃う」の複合動詞だろうが
収載する後の歌集「古今六帖」では、「かりそぐれども」と訓んでいる
|
| |
| [おひしくごとし] |
これも前の句の原文が、類想歌の原文の表記だと解り易いのと同じで
この掲題歌の原文「生布如」よりも、この「訓」で語意を解するなら、
類想歌の原文「生及如」の方が、すんなり訓める
旧訓「おひしくがごと」とあるのを、『万葉集古義』が改訓したとあるが
そもそも「ごとし」という語を、その語幹「ごと」で終らせるのは中古の和歌に多いと言う
江戸時代の雅澄は、当時のその考証を知った上の改訓だったのだろうか
現訓は、普通に「ごとし」になるが
万葉の時代、「ごと」だったのかもしれない
この歌を収載している『柿本人麻呂歌集・赤人集・古今六帖』では、いずれも「ごと」だ
多くの積み重ねられた研究成果を駆使できる現代の専門家たちも、
「ごとし」が原文の訓だ、ということなのだろうが...
それでも、よく目にするのが
古注釈書の何と言う解釈に依り、それに従う、という現代の注釈書
やはり、まだまだ古注釈書も捨てたもんじゃない
|
| |
| [しく] |
原文「布」を、私がここで「及く」と採り上げたのは、
類想歌〔2779〕の原文「及」があるからだ
勿論、その語義は、『万葉考』や『万葉集略解』のような「及ぶ」という意味からではなく
もう一つの語義である「追いつく」という意味があったからだ
ところが、真淵や千蔭の「及ぶ」を否定した所に至ると
「及」の「しく」ではなく「頻」の「しく」を主張している
これは、近年の書にまで及んでいるが
それでも、現代の叢書の『万葉集』になると、
「及」の「しく」を、追いつく、の意で解釈し始めている
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波文庫校訂版、平成25年~〕、
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕などは、明確に「追いつく」と注記に書く
注記にはなく、「及」と「頻」を併せ持つような解釈もまた多い
似たような意味だが、やはりその違いは歌全体の歌意にまで及ぶ
|
| |
|
|
| 掲題歌[1988]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
【柿本人麻呂歌集】
| 新編私家集大成第一巻-2 人麿Ⅰ 柿本人丸集[書陵部蔵「歌仙集」五一一・二] |
| 此比の恋のしけくさ夏草は(のイ) かりはつれともおひしくかこと |
| 柿本人丸集下 66 |
| 新編私家集大成第一巻-3 人麿Ⅱ 柿本集[書陵部蔵五〇一・四七] |
| このころのこひのしけくは夏草の かりそくれともをひしくかこと |
| 柿本集 たひの歌 405 |
新編私家集大成第一巻-4 人麿Ⅲ
柿本人麿集[冷泉家時雨亭叢書『素寂本私家集西山本私家集』] |
コノコロノコヒノシケヽクナツクサノ
カリソ(ハラヘ)クレトモオヒシク(ケルラン)カコト |
| 柿本人麿集中 恋部 クサヲヨメル 万十 234 |
| 新編国歌大観第三巻- 1 人丸集(書陵部蔵五〇六・八)人丸集下 64] |
| このごろの恋のしげけん夏草のかりはつれどもおひしくがごと |
| 人丸集下 64 |
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
| |
| この比はこひしけらくの夏草の かりはらへともおひしけりつゝ |
| 新編私家集大成-新編増補[陽明文庫蔵三十六人集] 152 |
| 此ころのこひのしけらむ夏くさの かりはらへともおひしけること |
| 新編私家集大成[書陵部蔵三十六人集] 134 |
| このころのこひのしけらくなつくさの かりはらへともおもひけること |
| 新編国歌大観[西本願寺蔵三十六人集] 254 |
【古今和歌六帖 ([永延元年(987年)頃]撰、兼明親王・源順か)】
| 新編国歌大観第二巻4 [宮内庁書陵部蔵五一〇・三四] |
| このごろのこひのしげくて夏ぐさのかりぞくれどもおひしくがごと |
| 第六 草 夏の草 3552 |
|

|
【類想歌】
| |
| 寄物陳思 |
| 吾背子尓 吾戀良久者 夏草之 苅除十方 生及如 |
| 我が背子に我が恋ふらくは夏草の刈り除くれども生ひしくごとし |
| わがせこに あがこふらくは なつくさの かりそくれども おひしくごとし |
| 巻第十一 寄物陳思 2779 作者不詳 |
〔語義〕
「こふらく」の接尾語「らく」は、上出の語を名詞化する働きがある
「そくれ」は、「除き去る」の意の下二段動詞「ソク」の已然形
「ども」は逆接の確定条件の接続助詞、「~のに・~けれども・~だが」
(参考)、接続助詞「とも」は、逆接の仮定条件、「たとえ~にしても」
「しく(及く)」は、「追いつく・至りつく・肩を並べる」の意の四段動詞「しく」の連体形 |
〔歌意〕
あの人への、私の恋心は、
夏草を、いくら刈っても刈っても
後から後から追いつくようにして
茂ってくるようなものです |
この類想歌、掲題歌の「異伝」とみるべきだ、という評もある
その通りだと思う
使われている語句の多寡ではなく、その「想い」こそが、掲題歌と通じるものがある
それに、訓については、むしろ掲題歌よりも解りやすく
この歌を参考にして、掲題歌を訓じたのではないか、とさえ思える
現代的な感覚では、歌順はこちらの方が後だから、
掲題歌の方が先行している、と思うものだが
歌集には、詠まれた順に配列するよりも
題目順とか、あるいは、まとまった人の個人的な歌集からとか
様々な配列の仕方がある
まして、『万葉集』のような、オリジナルは一体どんな形体だったのか、と想像すると
決して精確な配しかたなど出来なかっただろう
だから重複歌もあるし、作者名の混乱も生じる
似たような雰囲気の歌があれば
どうしても訓まで無意識であっても、それを「訓」として採ってしまう
研究者には、それなりの手法があるのだろうが
完璧でないものを、完璧に再現することなど不可能に近い
いや、不可能と言ってもいいと思う
掲題歌が、初句「このころの」で、いつの間にか擁いてしまった恋心を思わせるが
この類想歌は、そんな時間的な言葉は俗っぽくとでもいいたげに
直接的な歌を投げ掛けるものだ
勿論、自身へ詠いかけているのは同じだが
相手の反応を窺いたいと願う気持ちも、感じられてくる
敢えてこの二首の違いを言えば、私にはそのように思われてくる
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「廼者之 戀乃繁久 夏草乃 苅掃友 生布如」
「コノコロノ コヒノシケヽク ナツクサノ カリハラフトモ オヒシクカコト」(「【】」は編集、歌番は旧) |
〔本文〕頭注に、和歌童蒙抄、第七「ヒトコトハナツノヽクサノシケクトモイモトワレトシタツサハリテハ 万葉第十ニアリ」
赤人集「さくらによす ひとことはなつのゝくさにしけくともいもとわれとしたつさはりなは」
八雲抄、第六「万葉集哥なとを本哥とかやうとしもなくてすこしをかへてよめるにほし 人ことな夏野の草のしけくともいもとわれとしたつさはりなはといふ哥をとりて(下略)」 |
| 「苅」 |
『京都大学本』「刈」 |
| 〔訓〕 |
| コノコロノ |
『京都大学本』「之」ノ左ニ赭「ハ」アリ。赭ニテ右ノ訓ト入レ換フ可キヲ示セリ
|
| カリハラフトモ |
『元暦校本・類聚古集』「かりそくれとも」。『元』「くれ」ノ右ニ赭「クレ」アリ
『神田本』「カリソクレトモ」。「苅掃」ノ左ニ「カリハラヘ」アリ
『西本願寺本・細井本・温故堂本・神宮文庫本』
『京都大学本』「掃」ノ左ニ赭「ソクレ」アリ |
| オヒシクカコト |
『万葉集古義』「オヒシクゴトシ」
|
| 〔諸説〕 |
| ○[カリハラフトモ] 『代匠記(精撰本)』「カリハラヘトモ」○[オヒシクカコト] 『万葉集古義』「オヒシクゴトシ」 |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1988] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
| |
〔このころの戀のしけゝくなつくさのかりはらへともおひしくかこと 〕
廼者之戀乃繁久夏草乃苅掃友生布如
|
「忘んとしても戀の忘れ難く」、
そうか、「刈る」とは「忘れよう」とすることなのか... |
| このころの戀のしけゝ 夏草のかりてもおひしきるかことく忘んとしても戀の難忘と也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
| |
〔コノコロノコヒノシケヽクナツクサノカリハラフトモオヒシクカコト〕
廼者之戀乃繁久夏草乃苅掃友生布如 |
訓に重点を置いた注釈
巻第十一の歌を似ている歌、と引用するが
いつものことながら、歌番号もない時代の比較検証は、
想像することもできないほど、大変だったと思う |
| 苅掃友をカリハラフトモとあるは誤なり、カリハラヘドモと讀べし、六帖にはかりそくれとも、人丸集にはかりはつれども、並に叶はず、第十一に吾せこに吾戀らくは夏草の、苅除[カリソクレ]ども生及如[オヒシクガゴト]、似たる歌なり、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
| |
〔このごろの、こひのしげけく、なつぐさの、かりはらへども、おひしくがごと 〕
廼者之戀乃繁久夏草乃苅掃友生布如 |
最後の記述が途切れているが、漢書を持ち出そうとしているのだろうか
確かに、万葉集中での「廼者」の表記は、この一首のみ |
| 此頃の戀のいや増しにまさる事は、夏草の苅り掃へ共ども、後より生ひ繁る如しと也。廼者の二字、此頃とよむ義は [以下注記ナシ] |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
| |
迺者之、戀乃繁久、夏草乃、苅掃友、生布如[オヒシクガゴト]、 |
「及く」を「およぶ」の意で解釈するよりも、「追いつく」の意の方がいいと思う
それとも、「生及く」で「およぶ」と解釈するのだろうか
現代語では、もう一つの語義の方が相応しい |
| おひしくは生及[オヨブ]なり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
| |
〔このごろの。こひのしげけく。なつくさの。かりはらへども。おひしくがごと。〕
廼者之。戀乃繁久。夏草乃。苅掃友。生布如。 |
この江戸時代では、「およぶ」という動詞の語義の中の「追いつく」が、一般的だったのかもしれない
「およぶ」といい、「追いつく」という意に、苦もなく理解出来る、ういうことなのだろう |
卷十一、わがせこにわがこふらくは夏草のかりそくれども生及[オヒシク]がごと、大かた同じ歌なり。オヒシクは、卷十一に書ける如く、及ぶ意。
參考 ○生布如(考)略に同じ(古、新)オヒシクゴトシ。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
| |
〔コノゴロノ。コヒノシゲケク。ナツクサノ。カリハラヘドモ。オヒシクゴトシ。〕
廼者之戀乃繁久夏草乃苅掃友生布如
|
「生布加」を、この書が「オイシクゴトシ」と訓み始めたようだ
それが現訓に至るのだが、それは当時(江戸時代)の文法解釈の一般的な理解の仕方ではないだろうか
万葉時代に即した解釈、訓もきっとあったはずなのに...
勿論、碩学の人ならば、当然それも理解してのことだろうが... |
繁久[シゲケク]は、繁くあるやうはと云意なり、○生布加は、オヒシクゴトシと訓べし、○歌(ノ)意はこのごろの戀しく思ふ物思ひの、繁くあるやうは、たとへば夏野の草の刈掃へども、やがて其(ノ)跡に重々に生繁るが如しとなり、十一に、吾背子爾吾戀良久者夏草之苅除十方生及如[ワガセコニアガコフラクハナツクサノカリハラヘドモオヒシクゴトシ]、大かた似たる歌なり
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
| |
〔このごろの戀のしげけく夏草のかりはらへども生布如[オヒシクゴトシ] 〕
迺者之戀乃繁久夏草乃苅掃友生布如 |
この書で、初めてこれまでの「およぶ」の意がつかめた
やはり、真淵や千蔭がいう「およぶ」は、少し意味が違うようだ
そして、「頻く(シク)」もまた、私の描いていた「及く(シク)」とは違う
でも、巻第十一の〔2779〕を引用するなら、「及く」だと思う
確かに意味合いはそれほどの違いはないが...
それにしても、雅澄の訓をこの書では無批判に従うようだが
こうした理論の受け入れる根拠を、他の書に述べる、ということもあるのだろうか
それとも、先人の「成果」の自説に違わないものは、そのまま採り入れることは、敢えてその理由は述べなくてもいいのかな |
シゲケクはシゲカル事ハとなり ○結句を舊訓にオヒシクガゴトとよめるを古義にオヒシクゴトシと改めたり。古義に從ふべし。卷十一にも
吾背子にわがこふらくは夏草のかりはらへども生及如
とあり。そのオヒシクほ生頻なり。略解に『及ぶ意』といへるは誤れり |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| |
此頃の戀ひの繁けく、夏草の刈りはらへども生[オ]ひ頻[シ]くがごと |
掃っても、次から次へと生えてくる
敢えて「頻(シ)」の表記をしているということは
それが、何度も何度も掃うのではなく
一度すべてを刈り掃っても、あっという間に生え頻る
それが溢れる恋心の表現になっている
何故掃うかと言えば、忘れたいからなのか、切ないからなのか、
それが、この歌の解釈の仕方、感じ方に係わってくると思う |
| |
此頃の焦れる心が、一杯になることは、ちようど夏草が刈り拂ふと、後からどんどんと續け樣に生えついで來るやうである。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
| |
〔この頃の 戀の繁けく 夏草の 苅りはらへども 生ひしくが如〕
コノゴロノ コヒノシゲケク ナツクサノ カリハラヘドモ オヒシクガゴト
廼者之戀乃繁久夏草乃苅掃友生布如 |
折口信夫や、この鴻巣盛広、さらには次にも続くが、
旧訓の「おひしくがごと」を受け入れている
ただ、刈っても刈っても、と解釈するなら
「頻」ではなく「及」の方がいいのではないか、と思う
「評」で、引用歌〔2779〕の異伝だろう、と言いながら
その歌では「及」なのに、この歌では「及」ではない、とするのは、矛盾を感じる |
コノ頃ノ私ノ戀シク思フ心ノ頻繁ナコトハ、丁度夏草ガ苅リ拂ツテモ苅リ拂ツテモ、後カラ後カラ頻リニ生エルヤウナモノダ。
○廼者之[コノゴロノ]――廼はスナハチ・ソノなどの意であるから、ここは廼者をこの頃の意に用ゐたのである。
○生布如[オヒシクガゴト]――舊訓を改めて古義にオヒシクゴトシとよんだのは從ひ難い。卷三の跡無如[アトナキガゴト](三五一)參照。生布[オヒシク]は生ひ頻く。頻りに生ふること。生ひ及く意ではない。
〔評〕 よく出來た歌だ。譬喩適切。民衆の歌らしい。卷十一の吾背子爾吾戀良久者夏草之苅除十方生及如[ワガセコニワガコフラクハナツクサノカリソクレドモオヒシクガゴト](二七六九)の異傳であらう。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
| |
〔この頃の 戀の繁けく、夏草の 苅り掃へども 生ひしくが如。〕
コノゴロノ コヒノシゲケク ナツクサノ カリハラヘドモ オヒシクガゴト
廼者之戀乃繁久夏草乃苅掃友生布如 |
四段動詞「頻く」は、度重なる・何度も繰り返えす、とある
そこから、自然と「刈り掃っても刈り掃っても」という言い方に導かれるのだと思うが
その動作に対してのことであれば、
同じく四段動詞「及く」の、追いつく、の方がいい
刈り掃うことと、また追いついて生えてくる
何度も何度もその繰り返し、
そんな歌だと思う |
【譯】この頃の戀の繁くあることは、夏草が苅り掃つても、あとからあとから生えるようだ。
【釋】戀乃繁久 コヒノシゲケク。シゲケクは、繁くあること。
生布如 オヒシクガゴト。オヒシクは、續いて生えるをいう。續々として生えるようだ。
【評語】譬喩が巧みだ。殊に夏草の續々として生えるという、活動態を敍しているのがよい。それで歌が生きている。戀の繁くあることに、夏草を配したこと自體は平凡だが、ちよつとしたところで違つてくる。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
| |
〔この頃の戀の繁けく夏草の苅り拂へども生ひしくが如。〕
コノゴロノ コヒノシゲケク ナツクサノ カリハラヘドモ オヒシクガゴト
廼者之戀乃繁久夏草乃苅掃友生布如 |
無難な歌意解釈 |
| 【大意】此の頃の戀の思いがしげく、夏草が、刈り掃つても、しきりに生ひ立つ如くである。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
| |
〔この頃の戀の繁けく夏草の苅りはらへども生ひしく如し〕
コノコロノ コヒノシゲケク ナツクサノ カリハラヘドモ オヒシクゴトシ
廼者之戀乃繁久夏草乃苅掃友生布如 (『元暦校本』) |
こうなると、「頻く」も「及く」も同じように、また併せ持った解釈の方がいいのかもしれない
そもそも、厳密な解釈をここに重点を置くのではなく、いや厳密にはこの併せ持つ意味こそ、本来の「歌意」なのかもしれない
しかし、この歌の解釈で想いたいのは
「溢れる恋心」を、どうするのか、ということだと思う
残念ながら、これまでの注釈書では、そこには至っていないと思う
|
【口訳】この頃の私の戀心の繁くあることは、夏草が刈り拂つても後から後から頻りに生えるやうなものである。
【訓釈】この頃の戀の繁けく―「廼者」は漢書、元帝紀(三年)に「廼者火災降於孝武園館」とあり、この頃の意に用ゐる。「繁けく」は繁くあること(2・199)
生ひしく如し―旧訓オヒシクガゴトを『古義』にオヒシクゴトシと改めた(3・351)。「しく」は頻る意(1837)
【考】吾が背子に吾が戀ふらくは夏草の刈りそくれども生ひしく如し (11・2769)
類歌といふよりも同歌の異伝と見るべきものである。
赤人集に「戀のしげらく」「おもひけること」、流布本「戀のしけらむ」「おひしけること」、
柿本集(下)「戀のしけらむ」「刈りはつれともおひしくかこと」、
古今六帖(六「夏の草」)「戀のしげくて」「刈りそくれども」とある。 |
|
|

| |
| 「はなたちばなを」...ぬかむとおもひて... |
| |
| 『かたよりなれど』 |
| 【歌意1991】 |
片縒りに私は糸を縒っています
でも、あなたの心に通したいのです
私の想いが、あなたにとどくように... |
| |
| |
ときどき思うことがある
「注釈書」が、どんな高名な学者が書いたものであろうと
その「歌意」の「日本語」に触れたとき
さっぱり「情感」がこもらない、とがっかりする時が、少なからずあることだ
「古語」という訳の性格上、どこまで「現代語風」に訳すべきなのか
確かに難しいことだと思う
あまりにも「現代語的」過ぎると、
「古歌」の味わいも失いかねない
かといって、「古語」をふんだんに用いたのでは、おそらく読み辛いだろう
江戸時代の注釈書を読むと、やはり同じように感じるのは
どの時代であっても、「注釈書」の役割の難しさは、変わらない、ということだ
しかし、解り切った「語義解説」で終らせるような「書」もまた不親切だ
万葉時代と江戸時代、
万葉時代と江戸時代と現代(近代)とでは、「古語」の捉え方も違う
だから、「古語」が「古語」であると認識できる現代よりも
それが「古語」といえるか、なかなか判断もつきかねない江戸時代の研究者たちの書では
その「語句」と同じように、作者の「心」を求めることも大切なのだが
むしろ「訓」の解釈に力が入れられているように思えてならない
勿論、『万葉集』という漢字表記の特殊な「和歌」であれば
「訓」に力を入れるのは理解出来るが、それが最終的な目的ではないはずだ
まず「訓」を整えてから、その先に進んでこそ「注釈書」なのだが...
この掲題歌もまた、様々な解釈ができる歌といえる
どれが正しいか、ではなく
どの解釈が、どうやって人に、あるいは自分に響いてくるのか...
研究者は、そうはいかないだろうが
私のような単なる「ファン」であれば、あくまで「自分本位」でいい
多くの書では、
片縒りが、「片思い」の譬えとし、
そんな私があなたの為に、蔓を作る花橘を貫く...片縒りの糸で...
それだけでも、ひたすら想いを詠う女心を理解出来る
そして、愛しい男の家の花橘に糸を通すことが出来れば
私の想いは成就する、というような歌意にもなる
ただ、もう一つ考えなければならないのは
「片縒り」が初句にあることの意味だと思う
「片思いなのに、あなたの為に」あるいは、
「片思いだから、何とか振り向いて欲しいから」とか、
まず、「片思い」であることが先行している
そんな中で、真淵の歌意には、ハッとさせられた
あなたを想って橘を貫こうと思っている
その私の気持ちが届いてくれれば、と思うが
あなたは、そうでもないようで...「私の縒る糸は、片縒り」なんだなあ...
このような解釈だと思う
いろいろな情況が、どれもいい響きで伝わってくるが
私のこの歌への感じ方は、決して女の「片思い」ではないと思う
これから、男に自分の想いを伝えようとしているのではないか、と
そこで、初句の「かたより」が気になり始めた
確かに「片糸(かたいと)」と同じような意味合いで、「片思い」の譬として用いられるが
必ずしもそうとは言えないと思う
『万葉集』中の「かたより」を調べてみたら、五例あった
そのうち、三例(114・1076・2251)は、意味合いとしては「片寄る」のもので
その表記も「114異所縁、1076片因爾、2251片縁」
この掲題歌の意味の「片縒る」は二例で
掲題歌の他は、4017(万葉仮名[可多与理])
その使われている語彙は、決して「片思い」のような意味ではなかった
長歌の一文だったが、白波を糸に見立てて玉藻を貫き、妻を想うものだった
「片思い」というよりも、むしろ離れている寂しさを詠う語のように思えた
ならば、この掲題歌の「かたより」も、「片思い」の先入観を捨てて思えば
もっと違う感じ方も出来るかもしれない
勿論、「片思い」の方が、歌の切なさが伝わっていい、というものかもしれないが
寂しさのあまり、想ひ人の家の花橘を玉に貫こう、とする女のいじらしさも
またいいものだと思う
|
|
掲載日:2014.04.16.
| |
| 夏相聞 寄花 |
| 片搓尓 絲ヲ曽吾搓 吾背兒之 花橘乎 将貫跡母日手 [ヲ、口偏に立刀] |
| 片縒りに糸をぞ我が縒る我が背子が花橘を貫かむと思ひて |
| かたよりに いとをぞわがよる わがせこが はなたちばなを ぬかむとおもひて |
| 巻第十 1991 夏相聞 寄花 作者不詳 |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】〔67・83・68〕
【赤人集】〔155・142・262〕
[類歌]
【万葉集巻第七】〔1344〕
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
| 【1991】 語義 意味・活用・接続 |
| かたよりに [片搓尓] |
| かたより [片縒り・片撚り] |
糸を縒るとき左右一方の向きにだけよりをかけること |
| いとをぞわがよる [絲ヲ曽吾搓] [ヲ、口偏に立刀] |
| ぞ [係助詞] 係り結び |
[強調] ~を [目的語を強調する場合、「を」につく] |
| よる [縒る・搓る・撚る] |
[他ラ四・連体形] 糸などを何本か捩じり合わせて一本にする |
| [係り結びの「結び」] |
| わがせこが [吾背兒之] |
| はなたちばなを [花橘乎] |
| ぬかむとおもひて [将貫跡母日手] |
| ぬか [貫く] |
[他カ四・未然形] 穴に通す・つらぬく |
| む [助動詞・む] |
[推量(意志)・連体形] ~よう・~つもりだ |
未然形につく |
| と [格助詞] |
[引用] ~と (~と思って、などの意) |
| 〔接続〕体言、体言に準ずる語につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [かたより] |
糸を縒るということは、二本の糸とか三本の糸を縒って丈夫にするもので
それを、一本の糸で縒るというの、「片思い」の比喩としては、ぴったりの表現だ
契沖の『代匠記』に、
「片搓ハ片思ノ譬、橘ヲ貫ハ、事ノ成譬ナリ」と言っている
この歌で言う花橘を貫くのに、心もとない「片縒り」の糸で通そうとは、
それほど実りの見込みの薄い恋であっても、ということなのだろう
巻第四〔519〕に「三つ合ひに搓れる糸」という表現があり、
それは三本の糸を縒ったものとされているが
小学館の『新編日本古典文学全集』の補注によると
「一般には二本撚り合わせた、いわゆる双子(ふたご)糸が用いられていたことが、正倉院の衣服の縫糸についての調査でも報告されている」とある
|
| |
| [わがせこが はなたちばなを] |
この語句と次の第四句には、二つの説があるようだ
「わが背子のかずらにするための花橘」と解する説
「わが背子の家の花橘」と解する説
前者は、
『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕、
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕、
『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波文庫校訂版、平成25年~〕、
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕、
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕など
後者は、
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕、
『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕、
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕、
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕など
私が確認できる資料では、同じ程度の分かれ方だ
ただ、近年の解釈では「前者」の方が多い
片想いを認識している女が、どちらの行動をするものか... |
| |
| [おもひて] |
「おもひて」と「もひて」の訓が並存している
「われ」と「あれ」みたいなものだと思う
歌意に影響のある訓解釈ではなく、実際はどんな詠い方・訓だったのか、
そんな観点から扱うべき問題だと思う
特に、「おもふ」も「もふ」も同じ他動詞ハ行四段なので、活用は同じ
単に、「おもふ」の頭母音「お」の脱落したものが、定着したものだ
だから、接続の違いで語を見分けるなどできず
後に万葉仮名で同じ歌が載せられていない限り、作者の実際の訓は解らないだろう
試しに、上の「注記」で近年までの注釈書の訓を確かめてみる
すると、岩波書店のニ書(新大系、新校訂文庫本)、小学館の「新全集」、講談社「全訳注」、
さらに、古注釈書のでは、上の「注記」には歌意がどちらとも採りかねたので載せなかったが
ここでは、はっきり明言している『童蒙抄』
この書では「母」は「おも」とも訓む、と例歌を引用している
しかし、それでも僅か五書しかなかった
この語は、よく使われるが、「おもふ」「もふ」の使い分けはないと思う
単に字数とか、あるいは万葉仮名表記であるとか、明確なものがなければ...
「もふ」が和歌の語として定着した資料でも探してみよう...あれば、だけど
|
|
|
| 掲題歌[1991]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
【柿本人麻呂歌集】
| 新編私家集大成第一巻-2 人麿Ⅰ 柿本人丸集 [書陵部蔵「歌仙集」五一一・二] |
| かたよりにいとをこそよれわかせこか 花たちはなをぬかんとおもひて |
| 柿本人丸集下 67 |
新編私家集大成第一巻-4 人麿Ⅲ
柿本人麿集 [冷泉家時雨亭叢書『素寂本私家集西山本私家集』] |
| カタヨリニイト(モ)ヲコソヨレワカセコカ ハナタチハナヲヌカムトオモヒテ |
| 柿本人麿集上 夏部 詠花 万十 83 |
| 新編国歌大観第三巻- 1 人丸集 [書陵部蔵五〇六・八] |
| かたよりにいとをこそよれわがせこがはなたちばなをぬかんと思ひて |
| 人丸集下 68 |
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
| |
| かたよりにいとをこそよれわがせこがはなたちばなをぬかんと思ひて |
| 新編私家集大成-新編増補[陽明文庫蔵三十六人集] 155 |
| かたよりにいとをこそよれわかせこか はなたち花をぬかんとおもひて |
| 新編私家集大成[書陵部蔵三十六人集] 142 |
| かたよりにいとをこそよれわかせこか 花たちはなをよかんとおもひて |
| 新編国歌大観[西本願寺蔵三十六人集] 262 |
|
【類歌】
| |
| 譬喩歌 寄草 |
| 紫 絲乎曽吾搓 足桧之 山橘乎 将貫跡念而 |
| 紫の糸をぞ我が搓るあしひきの山橘を貫かむと思ひて |
| むらさきの いとをぞわがよる あしひきの やまたちばなを ぬかむとおもひて |
| 巻第七 譬喩歌 寄草 1344 作者不詳 |
〔語義〕
掲題歌の語義を参考 |
〔歌意〕
私の縒っている、紫の糸で
(あしひきの)山の橘を玉に貫こうと思って... |
この歌は、「類想歌」ではなく、「類歌」だと思う
掲題歌の「かたより」という「片思い」を想起させる語が、ここにはない
動作・行動は掲題歌と同じだが、その動機には違いがあると思う
ただ、掲題歌の解釈の分かれる部分、「わがせこが はなたちばなを」だけと比較して
それを参考にするとすれば、
「あしひきの やまたちばな」は、まさに「その山にある橘」といえるので
掲題歌も、「吾が背子の家の花橘」といえるのかもしれない
でも、歌とは不思議なもので、
そう単純に当て嵌めるわけにはいかないものだ
その「動機」に、違いがあると
助詞に変化があるわけでもないのに、歌意が大きく向きを変えることもある
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「片搓爾 絲ヲ曽吾搓 吾背兒之 花橘乎 将貫跡母日手 【ヲ、口偏に立刀】」
「カタヨリニ イトヲシワカヨル ワカセコカ ハナタチハナヲ ヌカムトモヒテ」(「【】」は編集、歌番は旧) |
〔本文〕頭注に、『類聚古集』前行ニ「二首無作者」アリ。二首ハコノ歌ト〔1990〕トヲ指セリ。
赤人集「はなによす かたよりにいとをこそよれわかせこか花たちはなをよかむとおもひて」 |
| 「片」 |
『活字附訓本』「斤」 |
| 「搓」 |
『元暦校本』右ニ赭「【手偏ではなく行人偏】」アリ |
| 吾搓の「搓」 |
『元暦校本』右ニ赭「縒」アリ |
| 「背」 |
『類聚古集』コノ下「【判読出来ず】」アリ。但、墨ニテ消セリ |
| 「母日手」 |
『元暦校本・神田本』「母卑」。『元』「母卑」ノ間ニ赭「○」符アリ。ソノ右ニ赭「日」アリ。マタ本文ノ下ニ赭「或本曰字尤又手字草作」アリ。『神田本』下ニ小字「莫人日手
或本」アリ
『類聚古集』「貫手」 |
| 〔訓〕 |
| イトヲソワカヨル |
『元暦校本』「いとをこそよれ」
『類聚古集』「いとをこそわかよる」。朱ニテ「こ」ヲ消セリ
『神田本』「イトヲコソヨレ」。「吾搓」ノ左ニ「ワレヨル」アリ
|
| ハナタチハナヲ |
『元暦校本』「はなたちはなの」。「の」ノ右ニ赭「ヲ」アリ |
| ヌカムトモヒテ |
『元暦校本・類聚古集』「ぬかむとおもひて」
『神田本』「ヌカムトヲモヒテ」
『西本願寺本』「ヌカントモヒテ」
|
| 〔諸説〕 |
| ○ナシ |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1991] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
| |
〔かたよりにいとをそわかよるわかせこかはなたちはなをぬかんともひて 〕
片搓尓絲○曽吾搓吾背兒之花橘乎将貫跡母日手 ○[口+斗]
|
「もひて」の解説をする、と言うことは
この時代では、和歌に「もふ」という「語」は一般的ではない、ということなのだろう
「せこのため」に橘を玉に貫く
しかし、「かたより」の糸では、貫くことも難しいだろう
それでも、貫きたい、という気持ちは... |
| かたよりにいとをそ もひては思ひてなりせこかために橘を玉にぬかんと糸をよると也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
| |
〔カタヨリニイトヲソワカヨルワカセコカハナタチハナヲヌカムトモヒテ〕
片搓爾絲○曾吾搓吾背児之花橘乎將貫跡母日手 ○[口+立刀] |
この解釈は、ほかとは違って、部立てが「寄花」だから、橘の花を見て、それが「実」になったら玉に貫こう、というものらしい |
| 寄花歌なれば、此花橘は花の時見て實にならばぬかむと思ふなり、母日手は思ひての上略なり、片搓は片思の譬、橘を貫は事の成譬なり、第七に紫絲乎曾吾搓とよめる歌に似たり、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
| |
〔かたよりに、いとをぞわれよる、わがせこが、はなたちばなを、ぬかんとおもひて〕
片搓爾絲○曾吾搓吾背兒之花橘乎將貫跡母日手 ○[口+立刀] |
「花橘を貫く」というのは、恋した男を我が夫としたい、という譬だという
「かたより」の語の役目は、語られていない
巻第八に「母山」を「おも山」と読ませる、としているが
「母山」の表記は、唯一巻第九1736(新歌番)に「祖母山(おほばやま)」とある
「よそへ」は「たとえ」のこと |
| かたよりには、女子の片思の義に寄せたり。花橘をぬかんとは、男子を戀ひて、わが夫とせんと思ふに譬へたり。寄花歌なれば、橘の花を玉にも貫かんとのよそへ也。下の意は、夫にしてより逢はんと思ふとの意也。母日手の母を、おもとも讀む也。第八卷の歌、母山を、おも山と讀ませたるにて知るべし。もひてと云ふも、思ひてと云ふ義なれば何れにても同じ
|
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
| |
片搓爾[カタヨリニ]、絲叫曾吾搓[イトヲソワガヨル]、 こは糸を搓といふなり惣て糸はもろ手ならでかたかたへよるは常なり 吾背兒之[ガ]、花橘乎、將貫跡母日手[ヌカムトモヒテ] |
背子の家の橘を採って、玉に貫きたいと思ってはいても、背子はそれほど想ってはいてくれないので、「かたより」と詠った |
| 我背の橘とりて玉にぬきなんとおもひて糸をよるといへるにかたよりといへるは背はさばかりおもはぬをよせてよめるなり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
| |
〔かたよりに。いとをぞわがよる。わがせこが。はなたちばなを。ぬかむともひて。〕
片搓爾。絲○曾吾搓。吾背兒之。花橘乎。將貫跡母日手。 ○[口+立刀] |
おそらく、契沖、ひょっとして真淵もそうかもしれない「実」を玉とする説に対して、「花」を玉に貫く、というう |
カタヨリは片思に譬ふ。橘の實を貫くは常なるを、寄花なれば、是れは花を言へり。ヌカムト思ヒテは、事成さんと願ふ意なり。
參考 ○吾背兒之(新)セコガタメ「吾」を衍とし「之」の下に「爲」を補ふ。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
| |
〔カタヨリニ。イトヲソアガヨル。ワガセコガ。ハナタチバナヲ。ヌカムトモヒテ。〕
片搓爾絲○曾吾搓吾背兒之花橘乎將貫跡母日手 ○[口+立刀]
|
想ひ人の家の花橘を玉に貫く、というのは
それが出来れば、このかたよりの恋も、成就できる、という譬か |
歌(ノ)意は、吾(ガ)夫子が家の、うるはしき花橘の花を、玉に貫むと思ひて、敵對[アヒテ]なしに、からくして、絲を片搓[カタヨリ]にのみ吾(ガ)搓[ヨル]ぞとなり、契冲云、寄花(ニ)謌なれば、此(ノ)花橘は花を云り、母日手[モヒテ]は思[オモ]ひてなり、片搓[カタヨリ]と云るは、かた思ひのたとへなり、はなたちばなをぬくをば、事成(ル)にたとふるなり、
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
| |
〔片よりに絲をぞわがよる吾背子之[セコガタメ]花橘をぬかむともひて 〕
片搓爾絲○曾吾搓吾背兒之花橘乎將貫跡母日手 ○[口+リ] |
この『新考』の時代は、おそらく、「背子の家の花橘」が主流だったと思う
この『新考』辺りから、「背子の為に」が大きく唱えられるようになった
雅澄のいう一種の「まじない」めいた説は、否定する |
片ヨリニヨルとは絲を合せずしてよるをいふならむ。代匠記に『片搓は片思の譬』といひ古義に『あひ手なしにからくして』と辭を補ひて釋ける共に從ひがたし
○第三句を從來ワガセコガとよみさて古義に『吾夫子が家のうるはしき花橘の花を』と釋けリ。上(一九二八頁)にも妹ガ家ノ梅を妹之梅といへる例あれどここは吾背子之を爲背子之の誤としてセコガタメとよむべし。セコガタメを爲背子之とは書くまじきに似たれど下にもコヒヌベシを可戀奴と書けり。又卷七にもシメシヨリを從標之と書けり
○略解に寄花歌なれば花橘とあるは花をいへるなりと云へり |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| |
片縒りに絲をぞ我が縒[ヨ]る。吾が夫子[セコ]が花橘を貫[ヌ]かむと思ひて |
この解釈は、一般的な解釈には違いないが
「かたより」に縒る、という意味も欲しい |
| |
あなたに上げる花橘を通さうと思うて、絲を片方縒[ヨ]りに縒つてゐることだ。(かの人を思うて、片思ひに焦れてゐる。) |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
| |
〔片よりに 糸をぞ吾がよる 吾が背子が 花橘を 貫かむと思ひて〕
カタヨリニ イトヲゾワガヨル ワガセコガ ハナタチバナヲ ヌカムトモヒテ
片搓爾絲○曾吾搓吾背兒之花橘乎將貫跡母日手 ○[口+立刀] |
歌意で、せっかく「戀ガカナフヤウニト」とまで言うのだから
そのために、今は「かたより」でも、この糸を花橘に貫きたい、となれば、深まる歌意になると思うのに... |
私ハ私ノ愛スル男ノ家ノ橘ノ花ヲ糸ニ通サウト思ツテ、片一方ニバカリ糸ヲ搓ツテヰマス。私ハ戀スル男トノ戀ガカナフヤウニト思ツテ、片思ヲシテココロヲナヤマシテヰマス。
○片搓爾[カタヨリニ]――片搓は片方からばかり縒をかけること。片戀の意を持たせてある。
〔評〕 代匠記精撰本に「寄花歌なれば、花橘は花の時見て、實にならばぬかむと思ふなり」とあるが、花橘とあるからやはり花であらう。しかし橘は花のうちから實の形をなしてゐるので、その實を糸に貫くのであらう。片戀を寄せたものか。かなり工夫の多い歌である。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
| |
〔片搓りに 絲をぞわが搓る。わが夫子が 花橘を 貫かむと思ひて。〕
カタヨリニ イトヲゾワガヨル ワガセコガ ハナタチバナヲ ヌカムトモヒテ
片搓尓絲叫曾吾搓吾背兒之花橘乎將貫跡母日手 |
「釈」にいう、相手の男の心に貫こうとする
そこまでの解釈は、やはり「古注釈書」では当たり前のことだとしているのかもしれないが、「注釈書」の歌意としては、そう具体的な表現が欲しいものう |
【譯】一方よりに絲をわたくしはよつています。あなたの橘の花を、それにつらぬこうと思いまして。
【釋】片搓尓 カタヨリニ。カタヨリは、一方の向きにだけ絲に搓りをかけること。絲のよりは一方にきまつているが、ひたすらによる意に、特にいうのだろう。片思いの心をこれに寄せている。
花橘乎 ハナタチバナヲ。橘の花のつぼみを玉として絲につらぬこうというのであるが、それは譬喩で、相手の男の心をたとえている。
將貫跡母日手 ヌカムトモヒテ。特にモヒテを假字がきにしている。
【評語】橘の花を玉として緒につらぬいて愛した生活から生まれている歌である。片よりに搓ると云つたところが、ねらいである。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
| |
〔片よりに絲をぞ吾がよる吾が背子が花橘を貫かむともひて〕
カタヨリニ イトヲゾワガヨル ワガセコガ ハナタチバナヲ ヌカムトモヒテ
片搓爾絲叫曾吾搓吾背兒之花橘乎將貫跡母日手 |
特筆なし |
【大意】片絲よりに絲を吾がよる。吾が背子の花橘を貫かうと思つて。
【作意】ワガセコが花橘に、男の心を譬へ、カタヨリニ絲ヲヨルを、片思するに譬へたのであらうが、さう説明すれば殺風景な歌になつてしまふ。寄物の歌は、物を明らさまにせず、そこにいくらかの美感を保つ徳はあらう。カタヨリは、二本三本にせず、一本絲をよることであり、ワガセコガは男の家の、或は男から贈られたの意であらう。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
| |
〔片よりに 絲をぞ吾がよる 吾が背子が 花橘を 貫かむと思ひて〕
カタヨリニ イトヲゾワガヨル ワガセコガ ハナタチバナヲ ヌカムトモヒテ
片搓尓絲○曾吾搓吾背兒之花橘乎將貫跡母日手 ○[口+立刀] (『元暦校本』) |
片思いであるが故に、男の心に「糸を通したい」
それを、恋の成就を願うこと
私も、そのように感じられた
|
【口訳】片方からよりをかけて私は絲をよつてをります。あなたのお宅の花橘をそれで通さうと思つて。
【訓釈】片よりに絲をぞ吾がよる―片方からばかりよりをかけて絲をよる、といふので片戀の意をもたせた。
吾が背子が花橘を貫かむと思ひて―『拾穂抄』に「せこがために橘を玉にぬかんと糸をよると也」といひ、『代匠記』には「花橘ハ花ノ時見テ実ニナラバヌカムト思フナリ。・・・片搓ハ片思ノ譬、橘ヲ貫ハ事ノ成譬ナリ」といひ、『略解』には「橘の実を貫は常なるを、寄花なれば、これは花を言へり。ぬかむと思ひては、事成さむと願ふ意也」といひ、『古義』に「吾ガ夫子が家の、うるはしき花橘の花を、玉に貫むと思ひて」と訳し、『全釈』には「私ハ私ノ愛スル男ノ家ノ橘ノ花ヲ糸ニ通サウト思ツテ」と訳し、『古典大系本』には「あなたのかずらにする花橘を貫き通そうと思つて」とある。「橘を貫く」といふ事は「珠に貫くべく」(8・1478)の條で述べたやうに、薬玉につくる事にもなるが、また「菖蒲 花橘を 玉に貫き 蔓にせむと」(3・423)で述べたやうに、蔓につくる事にもなり、又「花橘を玉に貫き送らむ」(1967)の如く玉のやうに絲で通す事にもなる。そこで「吾が背子が」の解釈を「吾が背子の為」とすると前二者の解が考へられるが、「吾が背子の家の」と解すれば、あとの解が適切だといふ事になるのではなからうか。「吾が背子が為」といふのであれば、「花橘乎 為君 玉尓社貫(ハナタチバナヲ キミガタメ タマニコソヌケ)」(8・1502)といふ風に、『新考』には「為背子之(セコガタメ)」の誤字説を出されてゐるやうな事になるのではなからうか。「吾が背子が花橘」といふのは「妹之梅(イモガウメ)」(1856)と同じく、背子が家の花橘と解くのが自然であらうと思ふ。さうだとすれば、片搓が片思ひで、花橘は相手の男の心にたとへ、それを絲に通すといふ事は戀の成就にたとへたと見るべきではなからうか。
【考】前にあつた、
紫の絲をぞ吾が搓るあしひきの山橘を貫かむと思ひて (7・1340)
の下の句と同じ心で、それは山橘の実であり、これは橘の花である違ひがあるだけである。
赤人集に「いとをこそよれ」「よかむとおもひて」、流布本「ぬくとおもひて」、柿本集にも「絲をこそよれ」とある。 |
|
|

| |
| 「うきことあれや」...きみがきまさぬ... |
| |
| 『たづねて花に』 |
| 【歌意1992】 |
うぐいすが、何度も何度も往来するこの垣根にも
卯の花が咲いてるのに
さっぱりお出でにならなくなったあなたは、
何か気にかかることでもおありなのでしょうか
垣根に咲く卯の花のように、あなたのお出でをこんなにも待ち望んでいるのに
私への不快感からでしょうか... |
| |
| |
この歌の「うきこと」を、相手の身に何かあったのか、と心配することも考えられる
卯の花が、こんなに咲き、鶯も行き来するこの垣根です
何故、あなたは来ないのですか
そこから、一様に「うきこと」をどちらへの「うきこと」かと決める必要はないと思う
何も解らない情況であれば、いろんなことを考えてしまうものだ
だから、「うきこと」もまた
それこそ原文の「鶯之往来垣根」のように、作者の心も「往来」、つまり「揺れて」いる
そんな気がする歌のように思うし、私はその揺れる心として感じる方が
とても素直な感じ方だと思う
私のせい、なのか
それとも、何か「事故」でもあったのだろうか、と
「歌の心」を揺れ動かすことも、作者だけではなく
それを聞く者にも、心を共鳴させる味わいがある
歌の心を、作者と同じように共鳴できれば、たとえその解釈が違っていようと
「生きている歌」として、大切に「詠い」継がれていくものだと思う
古注釈書を含め、現在でも「うぐいす」を「ほととぎす」から改めたのだとか
「序」については、無理な訳は不要だとか言われているが
この「序」と言われている上三句は、単なる情景の描写ではなく
作者である女と、男との「想いの交差」が、すでにそこに詠われているように思う
これまでも、いらっしたではありませんか
何かあったのですか
ひょっとしたら...
そんな女の「心の揺れ」が、この序を舞台にするからこそ、詠われるものだと思う
|
|
掲載日:2014.04.17.
| |
| 夏相聞 寄花 |
| 鴬之 徃来垣根乃 宇能花之 厭事有哉 君之不来座 |
| 鴬の通ふ垣根の卯の花の憂きことあれや君が来まさぬ |
| うぐひすの かよふかきねの うのはなの うきことあれや きみがきまさぬ |
| 巻第十 1992 夏相聞 寄花 作者不詳 |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】〔68・29・44・69〕
【赤人集】〔156・143・263〕
【拾遺和歌集】〔1701〕
[類歌]
【万葉集巻第八】〔1505〕
【古今和歌集】〔976〕
【後撰和歌集】〔154〕
[注釈書引用歌]
【契沖『代匠記』】〔拾遺集89・小町集60〕
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
| 【1992】 語義 意味・活用・接続 |
| うぐひすの [鴬之] |
| かよふかきねの [徃来垣根乃] |
| かよふ [通ふ] |
[自ハ四・連体形] 往来する・男が女のもとへ行く |
| かき [垣] |
家屋敷などの周囲にめぐらす囲い・垣根 |
| 〔参考〕「垣根」というのは、「垣」の根元のことをいう |
| うのはなの [宇能花之] |
| うきことあれや [厭事有哉] |
| うき [憂し] |
[形ク・連体形] 煩わしい・いやだ・気にくわない |
| あれ [有り・在り] |
[自ラ変・已然形] ある |
| や [係助詞] |
[疑問] ~か 係り結びの「係り」 |
已然形につく |
| きみがきまさぬ [君之不来座] |
| まさ [座す・坐す] |
[自サ四・未然形] 尊敬語、いらっしゃる・おいでになる |
| ぬ [助動詞・ず] |
[打消・連体形] ~ない 係り結びの「結び」 |
未然形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [うき] |
いやになる意の四段動詞「倦(う)む」と同根と見られ、
ままならぬ思いに嘆き、いやになる感じをいう
|
| |
| [や] |
この語は「あれや」が「あればや」に同じ疑問条件法と言われる
「うきこと」があったからだろうか、ということになるだろう
ちなみに終助詞「ばや」は、接続助詞「ば」に係助詞「や」がついたもので
仮定条件の疑問「(もし)~だとしたら~(だろう)か」〔未然形に接続〕
確定条件の疑問「~ので~(なおだろう)か」〔已然形に接続〕 |
| |
|
|
| 掲題歌[1992]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
【柿本人麻呂歌集】
| 新編私家集大成第一巻-2 人麿Ⅰ 柿本人丸集 [書陵部蔵「歌仙集」五一一・二] |
| うくひすのかよふ垣ねにうの花の うきことあれや君かきまさぬ |
| 柿本人丸集下 68 |
| 新編私家集大成第一巻-3 人麿Ⅱ 柿本集 [書陵部蔵五〇一・四七] |
| ほとゝきすかよふかきねのうのはなの うきことあれやきみかきまさぬ |
| 柿本集 夏 拾 29 |
新編私家集大成第一巻-4 人麿Ⅲ
柿本人麿集 [冷泉家時雨亭叢書『素寂本私家集西山本私家集』] |
| ウクヒスノカ( ユキシ)ヨフカキネノウノハナノ ウキコトアレヤ君カキマサヌ |
| 柿本人麿集中 恋部 寄花 万十 44 |
| 新編国歌大観第三巻- 1 人丸集 [書陵部蔵五〇六・八] |
| ほととぎすかよふかきねのうの花のうきことあれや君がきまさぬ |
| 人丸集下 69 |
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
| |
| ほとゝきすかよふ垣ねのうの花の う(う)きことあれや君かきまさぬ |
| 新編私家集大成-新編増補[陽明文庫蔵三十六人集] 156 |
| ほとゝきすかよふかきねのうのはなの うきことあれや君かきまさぬ |
| 新編私家集大成[書陵部蔵三十六人集] 143 |
| ほとゝきすかよふかきねのうのはなの うきこと(あ)りやきみかま |
| 新編国歌大観[西本願寺蔵三十六人集] 263 |
【拾遺和歌集 (寛弘四年[1007年頃]撰、藤原公任[966~1041]か)】
| 新編国歌大観第一巻3 [京都大学附属図書館蔵本] |
| 郭公かよふかきねの卯の花のうきことあれや君がきまさぬ |
| 巻第十六 雑歌春 題しらず 人まろ 1071 |
|
【類歌】
[万葉歌]
| |
| 夏相聞/小治田朝臣廣耳歌一首 |
| 霍公鳥鳴く峰の上の卯の花の憂きことあれや君が来まさぬ |
| 霍公鳥鳴く峰の上の卯の花の憂きことあれや君が来まさぬ |
| ほととぎす なくをのうへの うのはなの うきことあれや きみがきまさぬ |
| 巻第八 夏相聞 1505 小治田朝臣廣耳 |
〔語義〕
「を」は、「峰・丘」山の高いところ、また山の小高い所・丘
初三句は、「卯の花」の「う」で、第四句の「うきこと」を起こす「序」
下二句は、掲題歌参照 |
〔歌意〕
ほととぎすが鳴く、あの峰の高いところの卯の花の、その「う」ではないが
何か「いやなこと」でもあったのでしょうか
あなたがお出でにならないのは...
|
[古今和歌集 ([延喜五年(905年)]撰、紀貫之[866~945]他)]
| 新編国歌大観第一巻-1 [伊達家旧蔵本] |
| 水のおもにおふるさ月のうき草のうき事あれやねをたえてこぬ |
| 巻第十八 雑歌下 976 みつね |
[後撰和歌集 (天徳ニ年[958]頃、宮中の梨壺[昭陽舎]、撰源順・紀時文・坂上望城等)]
| 新編国歌大観第一巻2 [日本大学総合図書館蔵本] |
| 第四 夏 ともだちのとぶらひまでこぬことをうらみつかはすとて |
| 白妙ににほふかきねの卯花のうくもきてとふ人のなきかな |
| 第四 夏 154 |
【注釈書引用歌】
[契沖『代匠記』]
|
| 山里の卯の花にうぐひすのなき侍りけるを 平公誠 |
| 卯の花をちりにしむめにまがへてや夏のかきねに鶯のなく |
| 拾遺和歌集巻第ニ 夏 89 |
|
| 山里の卯の花にうぐひすのなき侍りけるを 平公誠 |
| 卯の花をちりにしむめにまがへてや夏のかきねに鶯のなく |
| 小町集 60 |
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「鸎之 徃来垣根乃 宇能花之 厭事有哉 君之不来座」
「ウクヒスノ カヨフカキ子ノ ウノハナノ ウキコトアレヤ キミカキマサヌ」(「【】」は編集、歌番は旧) |
〔本文〕頭注に、『類聚古集』コノ歌ハ次ノ歌ノ後ニ書ケリ。
赤人集「ほとゝときすかよふかきねのうのはなのうきことありやきみかまさぬ」 |
| 「垣」 |
『類聚古集』「恒」 |
| 「宇能」 |
『類聚古集』「卯」 |
| 「君」 |
『神宮文庫本・細井本』「居」 |
| 〔訓〕 |
| キマサヌ |
『西本願寺本・細井本・温故堂本・神宮文庫本』「キマサス」。『西』「ス」ノ右ニ「ヌイ」アリ
|
| 〔諸説〕 |
| ○ナシ |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1992] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
| |
〔うくひすのかよふかきねのうの花のうきことあれや君か來まさぬ 〕
鴬之徃來垣根乃宇能花之厭事有哉君之不來座
|
上三句を「序」とする、というだけのこと |
| うくひすのかよふ 上句は序也うの花のはうきとうけんとて也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
| |
〔ウクヒスノカヨフカキネノウノハナノウキコトアレヤキミカキマサヌ〕
鸎之往來垣根乃宇能花之厭事有哉君之不來座 |
人麻呂歌集で「ほととぎす」としているので、後の歌集の採録では、その「柿本人麻呂歌集」から採録したという
下二句が、巻第八の小治田廣耳の歌と同じ、というのを
現代の私たちは、さりげなく聞いてしまうが
この当時の注釈書では、当然歌番号などなく、類歌など、他の歌との比較や引用など、大変な作業だっただろうと思う
鶯が、原文「往来」するという表現を、人が絶えず行き来する、との譬、と説明し、『拾遺集』のその題詞の「山里の...」を引用し、平公誠の歌を載せる
これは、春の鳥である「うぐいす」を、夏にも詠われていることを言ったもので、同じく小野小町の歌も載せている |
| 拾遺に發句をほとゝぎすとて入たるは人丸集に依れり、赤人集に入たるも同じ、此歌第八に小治田廣耳が霍公鳥鳴峯乃上[ウヘ]能云々、下三句彼に同じ、初の二句卯花に依て鸎のかよひ來るを絶ず人の問ひ來しに譬ふ、鸎は夏懸てもすめばなり、拾遺集云、山里のうの花に鶯の鳴侍りけるを、平公誠、卯花を散にし梅にまがへてや、夏の垣根に鸎の鳴、又小町集にうの花のさける垣根に時ならず、我ことぞ鳴鶯の聲、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
| |
〔うぐひすの、かよふかきねの、うの花の、うきことあれや、きみがきまさぬ 〕
鶯之往來垣根乃宇能花之厭事有哉君之不來座 |
ここも、同じように「春」のうぐいすも、「夏」でもいるのだから、と解釈
さらに、この歌の主題は「うのはな」なので、以前に述べた「うのはなくたし」との比較にも及んでいる
「あれや」を「あるらめや」という意、という
「らめ」は現在推量の助動詞「らむ」
語感から、同じ意になるなら、俗な言い方をしない、という方法論にも言及
上三句が「序」なので、意は無い、とするが
「かよふかきね」には、大きな意味があると思う |
鶯之 夏の歌に、鶯のとよめる不審なれど、鶯は夏までも居るものなれば通ふとも讀むべき也。此歌は卯の花を專によめる故詞のうつりよき故、鶯のとよめるなるべし。別に意あるに有べからず。此歌によりて、前の卯の花くたしの歌も、春も咲く花の樣に釋せる説あれど、此歌と前の歌の意は違ひある事也。此歌は、うと云詞の縁を、始め專らとよめる歌なれば、斯くもあるべき也
有哉 あれやと讀むは、手爾波不叶樣なれど、此等も雅言を用る也。あると云ふは俗に近し。あれやは穩かなる詞にて、あるらめやと云義也。同じ詞の意なれば、俗を遠ざけたる方可然也。何とぞさはりいとふ事有りてやと云意也。或抄に、こなたを厭ふてやなど云へる説は執るべからず。第八卷の歌にも、下の句全く同意の歌有。古今集雜下に躬恒歌にも、水の面に生ふる五月の浮き草のうき事あれやねをたえてこぬ、此もあれやとよめるを見るべし。鶯の通ふとは、人は來ぬ、鶯は通へ共と云ふ意と釋せるも不可然。只上の句には意無き也。うき事あれやと云はん迄の序也
|
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
| |
鶯之、往來[カヨフ垣根乃、宇能花之、 こゝまではうきといはん序なり
厭事有哉[ウキコトアレヤ]、 あればにやを略いふなりうぐひすのうの花のうきことゝつゞけたるも古へにておもしろし
君之不來座[ガキマサヌ] |
真淵の万葉集の「巻」の順番は、通常とは大きく違う
この巻十というのは、勿論「巻第八」のこと |
| (卷十二)に霍公烏鳴けるをのへのとありて下は同じ小治田廣耳と見えたりり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
| |
〔うぐひすの。かよふかきねの。うのはなの。うきことあれや。きみがきまさぬ。〕
鸎之。往來垣根乃。宇能花之。厭事有哉。君之不來座。 |
特筆なし |
| 鶯は來[ク]れども、君は我を憂しと厭ふ心有ればにや、君が來ぬとなり。卯花は、ウの言を言ひ出でん爲に設けたり。卷八、ほととぎす鳴をのうへの卯の花のとて、下全く同じ歌有り。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
| |
〔ウグヒスノ カヨフカキネノ ウノハナノ ウキコトアレヤ キミガキマサヌ〕
鸎之往來垣根乃宇能花之厭事有哉君之不來座
|
「うきこと」の対象のことをいう
作者のことを「何かいやなことでも」ということで、
自分ではなく「さきの人」の身に、何かあったのだろうか、
という意味ではない、という
歌意に特筆なし |
本(ノ)句は、厭[ウキ]と云む料の序なり、鸎は夏かけてもすむものなれば云り、さて八(ノ)卷に、霍公鳥啼峯乃上能宇乃花之[ホトヽギスナクヲノウヘノウノハナノ]、とて、未(ノ)句全(ラ)同歌あり、古今集雜(ノ)下躬恒(ノ)歌に、水のおもにおふる五月のうきくさのうきことあれやねをたえてこぬ、とも見ゆ、○厭事有哉[ウキコトアレヤ]は、我を厭ひて、うるさきものに思ふ事のあればにや、と云意なり、さきの人の身に、憂ことのあればにやと云にはあらず、まがふべからず、○歌(ノ)意は、吾を厭ひて、うるさきものに思ふ事のあればにや、このごろはすべて君が問來坐ぬ、となり、
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
| |
鶯のかよふ垣根のうの花のうき事あれや君が來まさぬ 〕
鶯之往來垣根乃宇能花之厭事有哉君之不來座 |
「序」には、意味をもたせないものなのだろうか
確かに、この上三句を一首全体の歌意の中に訳そうと思うのは無理がある
通常「序」の場合は、「~のように」とでも訳すが
この歌も、そして類歌の〔1505〕も、そんな訳しかたでは
おかしな日本語になってしまう
「~の卯の花のように」などと訳して、下二句に続くはずがない
だから、「序」として意味を持たせない、
すると、強引な訳に悩まされることもない...ということか
意味はあると思うけど... |
卷八(一五四二頁)なる
ほととぎすなく峯[ヲ]の上のうの花のうき事あれや君が來まさぬ
と第三句以下全く相同じ
○ウキ事アレヤは我ニ對シテオモシロカラヌ事アレバニヤとなり
○略解に『鶯はくれども君は我をうしといとふ心あればにや君が來ぬと也』といへるは誤れり。上三句は無意の序なるのみ |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| |
鶯の通ふ垣根の卯の花の、うきことあれや、君が來まさぬ |
序を背景の舞台としている訳しかただ
これも一つの方法だと思う |
| |
鶯が始終往來する、垣に咲いてゐる卯の花で、うるさい心配事でも起つたので、あの方が一向入らつしやらないのか。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
| |
〔鶯の 通ふ垣根の 卯の花の うき事あれや 君が來まさぬ〕
ウグヒスノ カヨフカキネノ ウノハナノ ウキコトアレヤ キミガキマサヌ
鸎之徃來垣根乃宇能花之厭事有哉君之不來座 |
物足りない
そして、「評」の拾遺集が「春の鳥、鶯を怪しんで、霍公鳥に改めた」とする解釈も、独断が過ぎる、と思う |
何カ私ニ對シテイヤダト思フコトガアルト見エテ、アノオ方ハオイデニナリマセヌ。サモナクバオイデニナル筈ダガ。
○鸎之往來垣根乃宇能花之[ウグヒスノカヨフカキネノウノハナノ]――厭[ウキ]といはむ爲の序詞。鶯が通つて來る垣根に咲く卯の花の。略解に「鶯はくれども君は我をうしといふ心あればにや君が來ぬと也」とあるのは考へ過ぎではあるまいか。
〔評〕 卷八の霍公烏鳴峯乃上能宇乃花之厭事有哉君之不來益[ホトトギスナクヲノウヘノウノハナノウキコトアレヤキミガキマサヌ](一五〇一)とよく似てゐるが、鶯の方がウの音を繰返す點に興味が多い。一體この歌は音調に重きを置いてゐるので、上句が皆ノの音で終へてゐるのも注意すべきである。拾遺集には第一句を郭公に改めて載せてある。蓋し春の鳥の鶯を卯の花に配するのを怪しんだのであらう。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
| |
〔鶯の 通ふ垣根の 卯の花の、うき事あれや、君が來まさぬ。〕
ウグヒスノ カヨフカキネノ ウノハナノ ウキコトアレヤ キミガキマサヌ
鸎之往來垣根乃宇能花之厭事有哉君之不來座 |
この歌意の表現が、日本語として不自然だと思うのだが
「序」に通常の解釈で、「~のように」と拘ったら、
確かにこんな日本語になる
こんな表現で、上句と下句がどうして繋がるのだろう |
【譯】鶯が往來をする垣根に咲いている卯の花のように、うい事があつてか、あなたがおいでなさらない。
【釋】宇能花之 ウノハナノ。以上三句、序詞。同音によつてウキを引き起している。
厭事有哉 ウキコトアレヤ。ウキコトは、いやな事、不都合、不愉快なこと。アレヤは、疑問の條件法。あなたが嫌うような覺えはないのだがと深く凝う心である。
【評語】同音を利用した技巧が、禍を成して、歌が浮調子になつている。鶯は、春の鳥とされているが、ここに卯の花に配してあるのは、描寫である。
【參考】類歌。
ほととぎす鳴く峰[を]の上の卯の花のうき事あれや君が來まさぬ(卷八、一五〇一)
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
| |
〔鶯の通ふ垣根の卯の花の厭き事あれや君が來まさぬ〕
ウグヒスノ カヨフカキネノ ウノハナノ ウキコトアレヤ キミガキマサヌ
鸎之往來垣根乃宇能花之厭事有哉君之不來座 |
この歌意の表現が、「訓の歌意説明」のようだが、ある意味では親切な表現だと思う
しかし、こうした「説明」は、「歌意」ではなく
歌の検証として書くべきことだと思う
この書では、類歌〔1505〕の「ほととぎす」を、「う」を重ねる技法で「うぐいす」に変えた、というが
歌とは、そうしたものなのだろうか... |
【大意】鶯の行き通ふ垣根の、卯の花の、ウの如く、ウキいやな事が有ればか、君が来られない
【作意】巻第八に小治田廣耳の「ほととぎす鳴く尾の上の卯の花の厭きことあれや君が来まさぬ」(1501)があつた。それもウの頭韻をねらつた作であつたが、此の作はウの音を更に増すために、ほととぎすをウグヒスと変えた。カヨフカキネも、カを重ねるのを意識してのことかも知れぬ。末梢技巧がやうやく重視される時代であるのを示すものだ。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
| |
〔鶯の かよふ垣根の 卯の花の うき事あれや 君が來まさぬ〕
ウグヒスノ カヨフカキネノ ウノハナノ ウキコトアレヤ キミガキマサヌ
鸎之往來垣根乃宇能花之厭事有哉君之不來座 (『元暦校本』) |
これも同じ手法での歌意になるが、そうした「序」の「定番」を駆使しても、歌の感動は沸き起こらないだろう
類歌〔1505〕を、その序の音調を主として改めたものかと思われる、と
「峯の上」の「ほととぎす」にも、
「かよふかきね」の「うぐいす」にも、それぞれに見合う意味を持たせることは出来ると思うのだが... |
【口訳】鶯のゆき来する垣根の卯の花ではないが、そのウという名の、うき事があるからか、君がいらつしやらない。
【訓釈】鶯のかよふ垣根の卯の花の―前にあつた。
霍公鳥鳴く峯(を)の上の卯の花のうき事あれや君が来まさぬ (8・1501)
の序を音調を主として改めたものかと思われる。
うき事あれや―前には「猒事」とあつたのをここでは、『元暦校本・類聚古集』、その他諸本すべて、「厭事」とある。イトフを「厭」(1955)とも「猒」(4・764)とも書いたやうに通用したものと思はれる。
【考】
赤人集「ほととぎす」「うき事ありやきみがまさぬ」、流布本、下句萬葉に同じ。
柿本集(下)「ほととぎす」、拾遺集(十六)「ほととぎす」人麿とある。
水の面におふるさ月のうき事あれやねを絶えて来ぬ [古今集巻第十八 みつね]
白たへににほふ垣根の卯の花のうくも来てとふ人のなきかな [後撰集巻四
も、類歌である。 |
|
|

| |
| 「こひやわたらむ」...かたもひにして... |
| |
| 『ちるもさく』 |
| 【歌意1993】 |
卯の花が咲くようには、
あの人への想いは、決して咲くことはない
あの人へ、想いが通じることは...ないだろう
こうやって、長い年月を想い続けていくのだろうか
とても哀しい片想いのままで... |
| |
| |
同じ言葉での表現であっても
その意味するところが、まったく逆になってしまう
この歌は、まさにそのような歌だ
「さくとはなしに」の一句では、
その解釈にも、様々な説がある
「咲く」の比喩を、作者の心とするか、相手の心とするか
さらに、この句を、次句の「あるひと」にどう繋げるか、でも大きく違う
しかし、そのいずれであろうと、「さくとはなしに」と「かたもひにして」の句から
この歌の切なさが、まるで溜息とともに聞こえてきそうだ
想ひ人が、自分のことを想ってくれない
それが、辛い「片想い」の原点だろう
それを、自分の心が「さくとはなしに」であれば
それが果たして「片想い」と言いきれるかどうか...
しかし、私は契沖のいう「しのびに戀る人」という感じ方が好きだ
片想いであることは充分承知している
それもとても辛いことだ
にも拘らず、恋慕っている自分は、どうしたらいいのだろう
このまま、告白しないで、辛い片思いのままを続けるしかないのか...
この解釈においては、契沖や千蔭が引用する〔1772〕歌と類想になると思う
しかし、圧倒的にこの解釈は少ない
どの書も、相手が振り向いてくれないことを「さくとはなしに」に重ねている
それが無理なく読めるから、多くの支持があるのだとは思う
私が思い描く「片恋」の歌に合わせて、この歌を眺めてみれば
振り向かないから「片恋」というよりも
「想い」を伝えられないからこそ、「片恋」でもある
決して、控え目な、とか気恥ずかしがって、とかではなく
その他にも、人に言えない「苦悩」を持って、相手を「想う」こともある
この掲題歌に、そんな気持ちを投影しても、無理は無いように思える
そう思うに至ったのは、下段に載せた「赤人集」にある
三種のどの伝本でも、第三句が「あた人」になっている
この「あた人」という意味は、
「心の変わりやすい人・浮気者」などのような意味の言葉だ
この「赤人集」と『万葉歌』のこの一首が、どんな関係なのか詳しくは解らないが
少なくとも、「赤人集」を撰した藤原公仁(966~1041)の時代の人は、
この掲題歌の「ある人」を「あた人」と解釈していた
そう解釈していたからこそ、撰集に載せる歌を「あた人」と「万葉歌」とは違いながらも
そのまま伝本通りに載せたものではないか、と思う
そうなると、この「片思ひ」の意味も少しは理解出来るのではないだろうか
それに、三種の伝本の中でも、西本願寺本では「こひわたるらん」とし
あたかも、第三者的な伝聞の詠い方をも載せている
この西本願寺本に拘ってみれば、
あんな浮気性の人に、恋してしまったとは、と解することも出来
その背景を、この掲題歌に当てはめるなら
どうせ実らない恋なのだ、このまま想い続けるだけで、何も求めまい
そんな想い方もできる
「さくともなしに」は、無心になって咲く花とは違って
私の想いが実ることもない、そんな恋心であっても
恋してしまったのなら、この「片恋」のまま...それもいい
恋してしまったのだから...
自身に疑問を投げ掛け、自身で解決させる
いや、解決というより「決意」のようなものだろう
『ちるもさく』という
咲く花は、必ず散る
ならば、散ることも、「咲く」といえる
散ることは、「咲いた証」なのだから...
「片恋」もまた、「恋した証」のはずだ
|
|
掲載日:2014.04.18.
| |
| 夏相聞 寄花 |
| 宇能花之 開登波無二 有人尓 戀也将渡 獨念尓指天 |
| 卯の花の咲くとはなしにある人に恋ひやわたらむ片思にして |
| うのはなの さくとはなしに あるひとに こひやわたらむ かたもひにして |
| 巻第十 1993 夏相聞 寄花 作者不詳 |
[収載歌集]
【赤人集】〔157・144・264〕
[古注釈書引用歌]
【万葉集巻第九】〔『代匠記・略解』1772〕
[資料]
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
| 【1993】 語義 意味・活用・接続 |
| うのはなの [宇能花之] |
| さくとはなしに [開登波無二] |
| と [格助詞] |
[比喩] ~のように 〔接続〕体言、体言に順ずる語につく |
| は [係助詞] |
[取立て(題目)] ~は 〔接続〕名詞、序詞、活用語など種々の語につく |
| あるひとに [有人尓] |
| ある [有り・在り] |
[自ラ変・連体形] 存在する・(人が)いる・(物・事・所などが)ある |
| に [格助詞] |
[相手(動作の対象)] ~に 〔接続〕体言、活用語の連体形につく |
| こひやわたらむ [戀也将渡] |
| や [係助詞] |
[疑問] ~か 係り結びの「係り」 |
種々の語につく |
| わたら [渡る] |
[自ラ四・未然形] 年月が過ぎる・年月を送る |
| む [助動詞・む] |
[推量(未来)・連体形] ~だろう 係り結びの「結び」 |
未然形につく |
| かたもひにして [獨念尓指天] |
| かたもひ [片思ひ] |
[「かたおもひ」の転] 男女二人の一方だけが相手を慕うこと・片恋 |
| にして |
~で・~であって・~でありながら 〔接続〕体言、活用語の連体形につく |
| 〔成立〕断定の助動詞「なり」の連用形「に」+接続助詞「して」 |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [うのはなの] |
ここで使われている「うのはなの」は、「咲く」の「比喩的枕詞」とする説がある
しかし、その枕詞的な用法は肯定しながらも、「枕詞では無い」というのが通釈らしい
単に、「咲く」を比喩的に「置いた」だけだと...
私には、それも枕詞の一つの用法だろうと思っていたので
あからさまに、それは違うと言われて、そうなのかなあ、と思った
ならば、「序詞」として用法では、歌意に反映されるので
それもいいとは思うが、この一句だけでは...
確かに「序詞」は、五音節が決まりの「枕詞」と違って、
その音節は自由で、「ある語」を引き出すための「五句」だが
この一句が、となれば、「枕詞」でもいいような気がする
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕で面白い解説があった
| |
| ―咲くをいうためには、何の花であってもよいはずであるが、特に卯の花といったのは、前歌に同じく「卯」が「憂」に通じるからであろう。「咲く」は相手の心が自分の恋心を受け入れることの比喩。人を恋い慕う気持ちを抱くことを「咲く」という言葉であらわした例に、巻十七〔3942〕がある。それは、大伴家持を慕う平群氏の女郎が自分の恋心を「もとな咲きつつ」言ったものであるが、これは「咲くとはなしにある」ので、相手が自分の恋心を受け入れようとしないのである。 |
この〔3942(新編国歌大観歌番号3964)〕は、[書庫-6]でも採り上げたが、
「もとな」は、「根拠もなく・しきりに・やたらに」の意を持つ副詞で、
平群氏女郎が、つれない家持に対して、
「とにかく、しきりに咲く...自分は想い続けている」ことをいうものだが
掲題歌の「咲く」は、相手が自分に振り向くことを譬えている
しかし、「咲くとはなし」...
だから、初句の「卯の花」の「う」が「憂」に通じるという解説も理解出来る
|
| |
| [さくとはなしに] |
上述の「注記」にも関連しているが、
ここでは、慣用句だと思う「~とはなしに」の用例を載せる
語意としては、「~ということもなく」の意になる
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕の頭注では、
「漕グトハナシニ・逢フトハナシニ」などの用例を挙げ、
『新日本古典文学大系』〔岩波文庫校訂版、平成25年~〕の注釈では、
「逢ふとはなしに・寄るとはなしに」と挙げた後、「自分のあり方をいう」としている
|
| |
| [や] |
この「や」については、どの書も触れていないので
当然のように、疑問の係助詞「や」だろうと思う
しかし、『全注』では、
「疑問の意を持つ『間投助詞』であるが、詠嘆性が強い」、としていた
ただ、古語辞典では、「間投助詞の文末用法を終助詞とする説もある」としている
疑問の意を表する助詞「や」と「か」の違い
疑問の助詞は「や」と「か」があるが、その違いには文法上の大きな違いがある
疑問とする点が、「や」ではその後に、「か」ではその前にくる
たとえば、疑問の意を表す語「いづこ」「なぞ」「たれ」などの位置を比較すると
| 係助詞「や」 |
| 春霞たてるやいづこみよしのの吉野の山に雪はふりつつ [古今集 春上 3] |
| 係助詞「か」 |
| 世の中は何か常なるあすか川きのふの淵ぞ今日は瀬になる [古今集 雑歌下 933] |
厳密な助詞の働きには、係助詞とか終助詞とか
あるいは、間投助詞など、どちらとも採れるような使い方もあるようだが
その文脈からも、判断されるようだ |
| |
| [かたもひ] |
書庫-17 [4月16日記事]で、「おもひ」と「もひ」のことを書いた
その中で、現代の注釈書に集中して「おもひ」と訓み、他はすべて「もひ」とあり
語義的にはその違いはないものの、何故新しい注釈書に「おもひ」が集中するのか
私には解らないままだった
結句が七字音という音韻のことで言えば「もひ」の方がいいのに、何故、と...
そして、この掲題歌
今度は、先の「おもひ」と訓じた注釈書も、唯一『講談社文庫』を除いて
「もひ」に訓じている
勿論、音韻の七字が守られているので、すんなり馴染める
岩波書店・小学館の訓は、何故違いがあるのか、説明があればなあ、と思うのだが...
仮に字数に七字を合わせることが優先されたのなら、先の歌は何故だろう、と思う
他の理由があれば、知りたいものだ
素人考えになるが、原文の「獨念」の表記にも影響があるのだろう、きっと
『童蒙抄』は、そもそもこれを「片思ひ」か「ひとりね」か、とか決めかねてもいるようだが
「一人想う」...二人が想う恋仲ではなく、片方の「ひとりが想う」とする意だとは思う
だから、やはり「片思ひ」が自然な受け方だとは思うが、「おもひ」か「もひ」か...
ちなみに、『京都大学本』では、「ヒトリオモヒニシテ」、九字とは...
|
| |
|
|
| 掲題歌[1993]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
| |
| 卯花のさくとはなしにあた人を 恋やわたらんかたおもひにて |
| 新編私家集大成-新編増補[陽明文庫蔵三十六人集] 157 |
| 卯花のさくとはなしにあた人の こひやわたらんかたおもひにして |
| 新編私家集大成[書陵部蔵三十六人集] 144 |
| うのはなのさくとはなしにあた人を こひわたるらんかたおもひにして |
| 新編国歌大観[西本願寺蔵三十六人集] 264 |
【古注釈書引用歌 [『代匠記・略解』]】
| |
| 相聞/(抜氣大首任筑紫時娶豊前國娘子紐兒作歌三首) |
| 石上 振乃早田乃 穂尓波不出 心中尓 戀流比日 |
| 石上布留の早稲田の穂には出でず心のうちに恋ふるこのころ |
| いそのかみ ふるのわさだの ほにはいでず こころのうちに こふるこのころ |
| 既出〔書庫-11、2013年10月27日〕巻第九 相聞 1772 抜気大首 |
〔歌意〕書庫-11より、当時の解釈のまま転載
石上の布留の早稲田の穂とは違い
その表面には出ないで、この心の中で、
あなたを恋しく想うこのごろです |
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「宇能花之開登波無二有人爾戀也將渡獨念爾指天」
「ウノハナノ サクトハナシニ アルヒトニ コヒヤワタラム カタオモヒニシテ」(「【】」は編集、歌番は旧) |
〔本文〕頭注に、 赤人集「うのはなのさくとはなしにあた人をこひわたるらむかたおもひにして」
『類聚古集』、前行ニ「巳下無作者」アリ。コノ「巳下」ハコノ歌及〔1988〕〔1973〕ヲ指セリ。 |
| 【爾指天の】「爾」 |
『類聚古集』ナシ |
| 〔訓〕 |
| カタオモヒニシテ |
『温故堂本』「カタヲモヒニシテ」
『京都大学本』「ヒトリオモヒニシテ」
|
| 〔諸説〕 |
| ○ナシ |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1993] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
| |
〔うの花のさくとはなしにある人にこひやわたらんかた思ひにして 〕
宇能花之開登波無二有人尓戀也将渡獨念尓指天
|
私を振り向いてくれそうもない人なのに
これからも想い続けてゆくのか...と嘆く解釈 |
| うの花のさくとは 卯花をこそ人は待こひめうの花のさくたくひにてなくある人に片思ひに待戀わたらんかと也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
| |
〔ウノハナノサクトハナシニアルヒトニコヒヤワタラムカタオモヒニシテ〕
宇能花之開登波無二有人爾戀也將渡獨念爾指天 |
初句の「卯の花」をことに強調しての「咲くとはなしに」
巻九の歌〔1772〕を引用して、「早稲田の穂には出ず」と詠める類とあるのは、最後の言葉を借りるなら「しのびに戀る人」ということだろう
決して自分から告白しないことらしい
「ある人」、「サクトハナシニ」の「人」であり、「或人」ではないことを言う |
| 開トハナシニとは發句をうの花の如くと意得べし、第九に布留の早田の穗には出ずとよめる類なり、腰の句は上に連ねて開とはなくてある人にと意得べし、或人にと云にはあらず、しのびに戀る人なり、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
| |
〔うのはなの、さくとはなしに、有人に、こひやわたらん、獨念爾指天 〕
宇能花乃開登波無二有人爾戀也將渡獨念爾指天 |
この解釈の「咲く」は、自分の想いが相手に伝わらず晴れ晴れとしない意味になっている 「思ひの晴るる事無し」
ここでも「ある人」の解釈に悩んでいる
他の「抄」では、「つれなき人」、宗師説は「現在の人」と言う意味で「有」という表記になっている、と説明する
しかし、春満は「現在の人」つまり「現人」となれば、目の前の人ということであり、同意しかねているようすだ
「我思ひの晴れぬ」とし「つれなく心強き人」を、自分だけが想い続けてゆくことを嘆く歌とする |
卯の花の咲くとはなしにとは、わが思ひの開くるを、花の咲くにたとへ、咲かぬを思ひの晴れぬに寄せたる意也。咲くとはなしになれば、思ひの晴るゝ事無しにと云意也
有人 此詞心得難し。或抄には、花の咲くとはなしに、ある人にとは、つれなき人にと云意と云へり。宗師の説現在の人と云ふ意にて、有の字を書きたるなるべし。然れどば現[ウツ]人にと云うて現とはまのあたりに見はれある人と云意、又先をほめたる意にもなる也。兩義愚意に不決。
獨念爾指天 此も諸抄印本等には、片思ひにしてと讀ませたり。獨のみ思ひ忍ぶの意なれば、片思ひと云義訓に讀ませたるか。獨り寢にしてとも讀むべければこれも決し難し。然れども一人ねにしてとは、はしなき一人ねの云出で樣なれば、片思ひの方可然らんか。歌の意は、卯の花の咲く如くに、花も咲き出でず、我思ひの晴れぬをも、つれなく心強き人に我のみ一人戀渡らんやと嘆きたる意也
|
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
| |
宇能花之、開登波、 句をきりて心得べし
無二[ナシニ]、有人二[アルヒトニ]、 さくとはなく有人にゝて思ひひらけて我方へよらざる人をいふなり
戀也將渡[ワタラン]、獨念爾指天[カタモヒニシテ]、
|
ここは「つれなき人」の解釈 |
| 他、なし |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
| |
〔うのはなの。さくとはなしに。あるひとに。こひやわたらむ。かたもひにして。〕
宇能花乃。開登波無二。有人爾。戀也將渡。獨念爾指天。 |
丁寧過ぎる説明
「さくとはなしに」は「つれなき人」であり、
「卯の花の咲かぬ」と言うにはあらず
ここでも、第九〔1772〕を引用する
要は「咲かない」ではなく「~のようには咲かない」ということだろう |
| 上句はつれなくて有る人に譬ふる詞なり。卯花の咲かぬと言ふには有らず、唯だ咲くと言ふまでへ懸かれる詞なり。卷九に、ふるのわさ田の穗には出ずと詠めるになぞらへて知るべし。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
| |
〔ウノハナノ。サクトハナシニ。アルヒトニ。コヒヤワタラム。カタモヒニシテ。〕
宇能花之開登波無二有人爾戀也將渡獨念爾指天
|
「有人」と「或人」の語義の説明、契沖説に倣うもの
歌意、特筆なし |
本宇能花之[ウノハナノ]は、開[サク]と云む料なり、無二[ナシニ]と云までには關らず、○開登波無二[サクトハナシニ]は、吾にあはむと思ふ心の、ひらけずしてある人になり、と岡部氏の云るが如し、さてこれは契冲も云る如く、咲(ク)とはなしにある、と云心につゞけて心得べし、有人は、或人と云義にはあらざればなり、○歌(ノ)意は、末(タ)吾にはあはむと思ふ心の、ひらけずしてある人を片思に無益[イタヅラ]に、他事なく戀しく思ひて、月日を送らむか、となり、
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
| |
〔うの花のさくとはなしにある人にこひやわたらむかたもひにして 〕
宇能花之開登波無二有人爾戀也將渡獨念爾指天 |
契沖・千蔭の引用する〔1772〕とは同例では無い、とする
「咲く」が相手の心か、自分の心か、と言う意味では、
確かに「同例」ではない
契沖は、「自分の心」で解釈し、この井上通泰は相手の心と解釈しているのだから...まさしく、相対するものだ
|
| ウノハナノは卯花ノ如クなり。サクは女の靡くをたとへたるなり。略解に卷九(一七九四頁)なるフルノワサ田ノ穗ニハイデズを例に引きたれど彼と此とは同例にあらず |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| |
卯の花の、咲くとはなしにある人に、戀ひや渡らむ。片思[モ]ひにして |
この解釈は、「や」を反語と見ているようだ
「片想いを続けていられようか...それは苦しいことだ、いっそ終りにしてしまおう」と |
| |
卯の花ではないが、莞爾ともせずにゐる人に、片思ひでゐて、焦れ續けて居ようか。いつそ思ひきつて了はう。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
| |
〔卯の花の 咲くとはなしに ある人に 戀ひや渡らむ 片思にして〕
ウノハナノ サクトハナシニ アルヒトニ コヒヤワタラム カタモヒニシテ
宇能花之開登波無二有人爾戀也將渡獨念爾指天 |
この解釈も「反語」になっている
それにしても、「反語」解釈になると、確かにその「想い」は投げやりに近いものになるのかもしれない
ここで、初めて「うのはなの」の役割を具体的に解釈している
しかし、「枕詞」でもいいと思うが... |
私ニ逢ハウト思フ心ガマダ(宇能花之)開ケナイデヰル人ニ、私ハ片思ヲシテ、戀ヒツヅケテヰルコトカヨ。ホントニバカラシイ。
○宇能花之[ウノハナノ]――開[サク]と言はむ爲に置いた、枕詞式用法であるが、眞の枕詞ではない。
○開登波無二[サクトハナシニ]――心の開けるとまでは行かぬこと。我を愛する心がまだ開けてゐないこと。この開といふ語は譬喩的に用ゐてあるのである。
〔評〕 寄卯花戀の歌で、特に卯の花を持つて來たのは、憂[ウ]といふ聯想があるからではあるまいか。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
| |
〔卯の花の 咲くとはなしに ある人に、戀ひや渡らむ。片念ひにして。〕
ウノハナノ サクトハナシニ アルヒトニ コヒヤワタラム カタモヒニシテ
宇能花之開登波無二有人尓戀也將渡獨念尓指天 |
なるほど、第二句と結句は、確かに重複する意味になる
しかし、反復するほど、辛い想いなのかもしれない |
【譯】卯の花の咲くようにはない人に、戀して過すことか。片思いであつて。
【釋】宇能花之開登波無二 ウノハナノサクトハナシニ。卯の花の咲くとは、譬喩で、先方の人が、自分に好意を持つことをたとえている。そのようになく。
戀也將度 コヒヤワタラム。ヤは、疑問の係助詞。ワタラムは、日を送るだろう。句切。
【評語】譬喩が巧みである。片思いに日を過そうとしている歎きが感じられる。但し五句は、説明し過ぎている。卯ノ花ノ咲クトハナシニアル人で、既に十分ではないか。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
| |
〔卯の花の咲くとは無しにある人に戀ひや渡らむ片思にして〕
ウノハナノ サクトハナシニ アルヒトニ コヒヤワタラム カタモヒニシテ
宇能花之開登波無二有人爾戀也將渡獨念爾指天 |
「うのはなの」を枕詞ではなく「序」といい、漫然と置かれている、というのは
きっと、枕詞のようで、一句をもって「序」とするには、中途半端だ、ということだと思う |
【大意】卯の花の咲くがごとく、咲くといふこともなく、即ち私に対する戀心をことばにも、行為にもあらはすこともなく有る人に、戀ひつづけることであらうか、片思であつて。
【作意】ウノハナノの序も、ただ漫然と置かれてある。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
| |
〔卯の花の 咲くとは無しに ある人に 戀ひや渡らむ 片思ひにして〕
ウノハナノ サクトハナシニ アルヒトニ コヒヤワタラム カタモヒニシテ
宇能花之開登波無二有人爾戀也將渡獨念爾指天 (『類聚古集』) |
この解釈は、卯の花がまだ咲かないように、というこれまでとは全く異なる解釈だ
「咲くとはなしに」という語意からすると、
この解釈は間違っていると思う
卯の花は咲いている、でもそのようなこともない「ある人」の意になるはずだ |
【口訳】卯の花がまだ咲かないやうに、私に心を許さうとはしてゐない人に、私は戀ひ渡る事であらうか。片思ひのままで。
【訓釈】卯の花の咲くとは無しに―「卯の花の」は咲くにつづけた枕詞式な用法であるが、譬喩的に用ゐたので枕詞ではない。「咲くとは無しに」とは、自分の心に応ずる心がまだ開けてゐない事をいふ。
【考】
赤人集「あた人を戀ひ渡るらむ」、流布本「あた人の戀ひや渡らむ」とある。 |
|
|

| |
| 「はなたちばなを」...みにはこじやと... |
| |
| 『にくくもあらめ』 |
| 【歌意1994】 |
私のことは、本当に気にそわないのでしょうが、
美しく咲いている私の家の橘の花を、是非見にいらしてください
それとも、見にお出でにならないおつもりですか |
| |
| |
この歌は、二人の関係が現在ではどのようなものなのか
それを思わせるのに、両極端の解釈が行われている
現代語に於ける「憎い」という意味合いには、
恨みを伴う気持ちが強くある
しかし、古語の「にくし」には、
気に入らない、不快だ、にしても、そこに積極的に「恨む」ような気持ちは感じられない
それに、「無愛想だ・つれない」というような、
「にくし」の起因を曖昧に感じさせる用例もある
これを、少なくとも現代語の「憎い」という感覚で読むと、
歌の意味としては、かなり不自然なものを感じてしまう
「恨み」を意に汲むような気持ちがありながら、
私をいくら「憎んで」だとしても、花見には来られますね、などというのだろうか
「憎む」ことで、それまでの関係がすべて暗転するはずだ
相手のことなど構っておれない
顔さえも見たくない
それが、現代に於ける「にくい」感覚ではないか、と思う
しかし、「女の優しさ」の歌だ、と解釈する書では、
それを強調する
私は、いくら嫌われても、憎まれても構わない
でも、あなたが楽しみにしていた「花見」にはどうぞいらしてください
それとて、来ないと言われるのでしょうか
これを、「優しさ」と解釈している
確かに、その気持ちであれば、せっかく楽しみにしていたものを
私への不快感で、それさえ取り止めになさらなくても、と
女は完全に一歩引いた気持ちを示している
そして、その逆の解釈もまたある
私には、いつもつれないあなたでも
我が家の花橘は、見にお出でになりますよね
それとも、それさえも「つれなく」されるのでしょうか...
この解釈になると、この歌の「動機」が、先の解釈より少しは穏やかになる
前者の、男から疎ましく思われた女心、ではなく
男はいつもと変わらないだろうが
問題は、そんな男に恋してしまった女の気持ちを詠ったものになる
自分が責められることをした訳ではなく
ただ男が振り向いてくれないことを嘆き
家の庭の花橘の咲くのを口実に、誘いかけてみる
それでも、男が来ない、というのであれば
もうはなから、自分にはこの恋を実らせる望みはない
この場合の「花橘」は、口実として用いられていることになる
前者のように、何らかの事情で男から恨みのような責めを受けたとすれば
ここでの「花橘」は、まったく独立した「花見」になるのだが
そんな「責め」を負う情況で、冷静に男に「花見」を誘えるなんて
私には、不自然過ぎる気がしてならない
「にくし」の語感は、現代人には一様だが
この歌の時代では、もっと幅のある「語」だったことが古語辞典から窺える
「気に入らない・不快だ」と「つれない」
この違いは、作者が想う相手の立場になれば、おのずと用例は決められるのではないか、と思う
積極的に女を避けると思うのであれば
女は、決して花見などに誘わないだろう
しかし、単につれないだけのことであれば
女は、覚悟を決めて花見に誘ってみようと決心する
多くの書が、前者の解釈であり、だから何故「憎まれる」のか解らないが、と前置きする
しかし、後者であれば、そんな前置きは要らない
あとは、自分がどう想われているか、確かめるだけだ
我が家の花橘を口実にして...
|
|
掲載日:2014.04.19.
| |
| 夏相聞 寄花 |
| 吾社葉 憎毛有目 吾屋前之 花橘乎 見尓波不来鳥屋 |
| 我れこそば憎くもあらめ我がやどの花橘を見には来じとや |
| われこそば にくくもあらめ わがやどの はなたちばなを みにはこじとや |
| 巻第十 1994 夏相聞 寄花 作者不詳 |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】〔69・31・81・292・70〕
【赤人集】〔158・145・265〕
【拾遺和歌集】〔1261〕
【古今和歌六帖】〔4259〕
[古注釈書引用万葉歌]
【万葉集巻第八】〔『新考・全釈・注釈』1456〕
【万葉集巻第十】〔『新考』1921〕[既出、書庫-15]
[資料]
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
| 【1994】 語義 意味・活用・接続 |
| われこそば [吾社葉] 〔強調〕私こそは [「こそ」は係り結びの「係り」] |
| こそば [複合係助詞] |
〔成立〕係助詞「こそ」に、係助詞「は」 |
| にくくもあらめ [憎毛有目] |
| にくく [憎し] |
[形ク・連用形] いやだ・気に入らない・無愛想だ・つれない |
| も [接続助詞] |
[逆接の確定条件] ~ても・~としても〔接続〕形容詞には連用形につく |
| あら [有り・在り] |
[自ラ変・未然形] 存在する・(人が)いる・(物・事・所などが)ある |
| め [助動詞・む] |
[推量・已然形] ~だろう 係り結びの「結び」 |
未然形につく |
| わがやどの [吾屋前之] 私の家の庭の |
| はなたちばなを [花橘乎] |
| みにはこじとや [見尓波不来鳥屋] |
| じ [助動詞・じ] |
[打消の推量・] ~ないだろう |
未然形につく |
| とや |
[疑問の意] ~というのか 〔接続〕体言、体言に準ずる語につく |
| 〔成立〕格助詞「と」+係助詞「や」 |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [こそば] |
係助詞「こそ」は、強調の意で、係助詞「は」も強調の意があるが
このような係助詞同士の使い方は、「は」にだけ見られる
そして、「こそ」と結合した場合は「ば」と濁音化する
係り結びの「係り」として、「こそ」の場合は、その結びは「已然形」となる
この歌では、第二句の「め」が結びで、推量の助動詞「む」の已然形
古語辞典より、
| 強調の意を持つ係助詞「は」と「ぞ・なむ・こそ」 |
「は」-「向こうは~だが、こちらは~である」と、ある物と対照して区別する
「ぞ・なむ・こそ」-「他の何物でもなく、まさにそれが~である」と特別に取り立てる |
| このため、「は」だけは、他の係助詞と重ねて用いることができる |
原文「社」を「こそ」と訓じるのは、未詳のようだ
|
| |
| [にくくもあらめ] |
歌の歌意に沿えば、この句は逆接の確定条件にならなければならない
しかし、この句には、初め接続助詞が解らなかった
やっと係助詞だと思い込んでいた「も」が接続助詞だったことに気づくが
最初に開いた古語辞典では、その接続は連体形になている
これには参った
「にくく」は形容詞「にくし」の連用形なので、接続できない
何とか例外でもあるかと、辞書を丹念に読むが、求めるものが見つからない
そして、二冊目の古語辞典で、運良く見つけることができた
接続助詞「も」は、基本的には「連体形」に接続するが
形容詞には「連用形」にもつく、とあった
これで、ほっとして先に進むことが出来た
「あらめ」の「め」は推量の助動詞「む」の已然形で、「こそ」の係り結びになる
この語句は「憎くはあらめど」という言い方もあり
これだと、かなり解り易い
「ど」は已然形に接続する逆説の確定条件
|
| |
| [とや] |
「とや」の用法は、二種類あり
文中にある場合、「~といふや」の略
文末にある場合、「~とやいふ」の略で、この歌の場合はこれに当る
従って、この「とや」の下に「言ふ」「する」の語が省略されている
語意は、伝聞を確かめる意で、「~というのか」と
特に物語などの文末に用いて、「~ということだ・~とさ」がある
この物語などに使われる例では、「今昔物語集」で、基本的に「今は昔」で始まり、
「~となむ語り伝えへたるとや」で終る
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
[古注釈書引用万葉歌]
| 【万葉集巻第八 1456】 |
| 春相聞 紀女郎歌一首 [名曰小鹿也] |
| 闇夜有者 宇倍毛不来座 梅花 開月夜尓 伊而麻左自常屋 |
| 闇ならばうべも来まさじ梅の花咲ける月夜に出でまさじとや |
| やみならば うべもきまさじ うめのはな さけるつくよに いでまさじとや |
| 巻第八 1456 春相聞 紀女郎 |
〔語義〕
「やみならば」は、「闇夜であれば」、「ば」は順接仮定条件
「うべ」は、(平安中期以降は「むべ」という) 肯定の意を表し
「もっともなことに・なるほど・いかにも」などの意味
「きまさじ」は、「来る」に、尊敬語の「ます」で「いらっしゃる・おいでになる」
それに、打消の推量の助動詞「じ」
「さけるつくよ」は、梅の花が「咲く月夜」
「いでまさじとや」の「とや」は疑問 |
〔歌意〕
闇夜であれば、お出でにならないことも、もっともなことです
しかし、こんなに梅の花が咲く、きれいな月夜なのですよ
それでも、お出でになりませんか |
| 【万葉集巻第十 1921】 |
| 春相聞 寄雨 |
| 春雨尓 衣甚 将通哉 七日四零者 七<日>不来哉 |
| 春雨に衣はいたく通らめや七日し降らば七日来じとや |
| はるさめに、ころもはいたく、とほらめや、なぬかしふらば、なぬかこじとや |
| 既出〔書庫-15、2014年2月20日〕巻第十 1921 春相聞 寄雨 作者不詳 |
|
|

|
| 掲題歌[1994]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】
| 新編私家集大成第一巻-2 人麿Ⅰ [書陵部蔵「歌仙集」五一一・二] |
| われこそはにくゝはあらめ我やとの 花たちはなをみにはこしとや |
| 柿本人丸集下 69 |
| 新編私家集大成第一巻-3 人麿Ⅱ [書陵部蔵五〇一・四七] |
| 我こそはにくゝもあらめわかやとの はなたちはなをみにはこしとや |
| 柿本集 夏 31 |
| 新編私家集大成第一巻-4 人麿Ⅲ [冷泉家時雨亭叢書『素寂本私家集西山本私家集』] |
| ワレコソハニクヽモアラメワカヤトノ ハナタチハナヲオ(ミイ)ルニハコシトヤ |
| 柿本人麿集上 春部 橘 寄花 万十 81 |
| 新編私家集大成第一巻-新編増補 人麿Ⅳ [冷泉家時雨亭叢書『詞林采葉抄人丸集』] |
| われこそはにくゝもあらめわかやとの」/はなたちはなをみにはこしとや |
| 人丸集 はなによす 十 292 |
| 新編国歌大観第三巻-1 [書陵部蔵五〇六・八] |
| われこそはにくくもあらめ我がやどの花たちばなはみにも(は)こじとや |
| 人丸集下 70 |
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
| |
| われこそはにくゝもあらめ我やとの 花橘をみにもこしとや |
| [人丸か集にいれり] 新編私家集大成-新編増補[陽明文庫蔵三十六人集] 158 |
| われこそはにくゝもあらめわかやとの はなたち花をみにはこしとや |
| 新編私家集大成[書陵部蔵三十六人集] 145 |
| われこそはきくゝもあらめわかやとの はなたちはなをみにはこしとや |
| [このうた人丸集にあり] 新編国歌大観[西本願寺蔵三十六人集] 265 |
【拾遺和歌集 (寛弘四年[1007年頃]撰、藤原公任[966~1041]か)】
| 新編国歌大観第一巻-3 [京都大学附属図書館蔵本] |
| 我こそはにくくもあらめわがやどの花見にだにも君がきまさぬ |
| 巻第十九 雑恋 題しらず 伊勢 1261 |
【古今和歌六帖 ([永延元年(987年)頃]撰、兼明親王・源順か)】
| 新編国歌大観第二巻-4 [宮内庁書陵部蔵五一〇・三四] |
| 我こそはにくくもあらめわがやどの花たちばなをみにはこじとや |
| 第六 木 たちばな 4259 |
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「吾社葉 憎毛有目 吾屋前之 花橘乎 見爾波不来鳥屋」
「ワレコソハ ニクヽモアラメ ワカヤトノ ハナタチハナヲ ミニハコシトヤ」(「【】」は編集、歌番は旧) |
〔本文〕頭注に、『神田本』頭書「抄」
赤人集「われこそはきくゝもあらめわかやとのはなたちはなをみにはこしとや このうた人丸集にあり」
[新増補本]頭注に、六帖、第六「われこそはにくゝもあらめわかやとの花たちはなをみにはこしとや」
|
| 「社」 |
『類聚古集』「祐」 |
| 「憎」 |
『活字無訓本』「惜」
『類聚古集・神宮文庫本』偏ハ直セリ。原字共ニ「増」カ |
| 〔訓〕 |
| ミニハコシトヤ |
『温故堂本』「ミニワコシトヤ」
『京都大学本』「ヒトリオモヒニシテ」
|
| 〔諸説〕 |
| ○ナシ |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1994] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
| |
〔われこそはにくゝもあらめわかやとのはなたちはなを見にはこじとや 〕
吾社葉憎毛有目吾屋之花橘乎見尓波不來鳥屋
|
私のことこそ、いやなんでしょう
だから、尋ねてきてくれない |
| われこそはにくゝも 我をこそにくみてとひ來さらめと也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
| |
〔ワレコソハニクヽモアラメワカヤトノハナタチハナヲミニハコシトヤ〕
吾社葉憎毛有目吾屋前之花橘乎見爾波不來鳥屋 |
自分が、想われていなくても、
我家の橘は見に来てくれないのですか
人麿集、赤人集は、本物なのだろうか、と疑念を持つ
この歌は、女歌のように思えるのだから...
拾遺集の伊勢では、花だけでも見に来て欲しい、ということかな |
| 吾こそはいとはしくも思はぬ吾宿に咲ける花橘をさへ見に來じとやすらむと橘にたよりてよめり、人丸集赤人集にもあれど、彼は不審なる物なり、歌のやう女のよめるなるべし、拾遺集雜戀に伊勢が歌、上は今と同じくて花見にだにも君が來まさずとよめるあり。 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
| |
〔われこそは、にくゝもあらめ、わがやどの、はなたちばなを、みにはこじとや 〕
吾社葉僧毛有目吾屋前之花橘乎見爾波不來鳥屋 |
私へのつれなさは承知しているが
花橘には恨みをかうことなどないのに
何故、来てくれないのか... |
| 我にこそつれなくとも、花橘をなど恨み給ふ事あらんや。何とて見には來り給はぬぞと恨みたる也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
| |
吾社葉、憎毛有目、吾屋前之、花橘乎、見尓波不來鳥屋、
|
訓も歌意も、注釈するまでの事はない、ということか |
| 意明なり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
| |
〔われこそは。にくくもあらめ。わがやどの。はなたちばなを。みにはこじとや。〕
吾社葉。僧毛有目。吾屋前之。花橘乎。見爾波不來鳥屋。 |
私を厭だと想うあまり、花橘さへ見には来ない
女歌だと、いう |
| 我を厭ふ餘りに、花橘をさへに見に來らじとやとなり。女の歌なり。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
| |
〔アレコソハ。ニクヽモアラメ。ワガヤドノ。ハナタチバナヲ。ミニハコジトヤ。〕
吾社葉憎毛有目吾屋前之花橘乎見爾波不來鳥屋
|
私がいやであれば、いつも来なくても仕方ない
それでも、私を恨んでも、花橘に罪は無い
だから見にお出でください
それでも来られないというのは、情けないことだ、と
後半の解説は、雅澄の心情なのだろう
このような歌を得られたのなら、どんな雨降りでも行くのに、と |
歌(ノ)意は、吾(レ)をばにくきものにおもほすらむなれば、常には來座ぬもことわりなり、よしや吾をこそにくゝはおもほすらめ、わがやどの花にまで罪あるべきよしなければ、この花たちばなのさかりをば、見に來ますべしと思ひしを、其をだに見には來ますまじさとにや、さりとはあまりに情なしとなり、
○契冲云、拾遺集伊勢が歌に、上の句今と全(ラ)おなじうして、花見にだにも君がきまさぬとよめり、ともにやさしきうたなり、これらのうたを得てば、まことに雨のふるひならば、みのもかさもしとゝにぬれて、まどひゆきぬべし
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
| |
〔吾こそはにくくもあらめわがやどの花橘を見には來じとや 〕
吾社葉憎毛有目吾屋前之花橘乎見爾波不來鳥屋 |
類想の歌を二首あげている
〔新歌番号1921〕
〔新歌番号1456〕
|
結句の格上(一九六九頁)なる七日シフラバ七夜コジトヤ又卷八(一五〇八頁)なる
やみならばうべも來まさじ梅の花さける月夜にいでまさじとや に似たり |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| |
われこそは憎くもあらめ。我が宿の花橘を、見には來じとや |
嫌われていても、花見は別なのだ、という感覚が
どの注釈書でも、この歌の底辺にはある
そして、詠う女としては、花見で再会できることに
一縷の望みを託している、ということなのだろう |
| |
成程私は憎う御座いませうけれども、私の屋敷の橘の花迄も、見に來まいといふお積りですか。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
| |
〔我こそは 憎くくもあらめ 吾がやどの 花橘を 見には來じとや〕
ワレコソハ ニククモアラメ ワガヤドノ ハナタチバナヲ ミニハコジトヤ
吾社葉憎毛有目吾屋前之花橘乎見爾波不來鳥屋 |
女の優しさ...
私のことはいいので、あなたがお楽しみにしている花見
気にしないで、いらっしてください
となるようだが、これは「優しい」歌だろうか
拾遺集の伊勢の歌、「模倣」としているが
そのままの歌だ
拾遺集という歌集の性格が解らないので、推測しか出来ないが
伊勢作、というより
伊勢が、万葉集の秀歌を撰んで自身の私的歌集に採録したのではないだろうか
「模倣」というのは、「伊勢作」と語ることだが
この時代の「歌集」には、とりわけ「私的」な性格の歌集はあったのだから... |
アナタハ私コソハ憎ククモアルダラウガ、私ノ屋敷ニ咲イテヰル花橘ヲ、見ニハイラルシヤラナイトイフノデスカ。私ニハ逢ヒニオイデナサラズトモ、花橘ヲ見ニハオイデナサリサウナモノデス。
〔評〕 女らしいやさしい、なつかしい歌である。卷八紀女郎の闇夜有者宇倍毛不來座梅花開月夜爾伊而麻左自常屋[ヤミナラバウベモキマサジウメノハナサケルツクヨニイデマサジトヤ](一四五二)に似て、更に詰問的な強い調子である。拾遺集に「われこそは憎くもあらめわがやどの花見にだにも君が來まさぬ」とある伊勢の作は、これを模倣したものであらう。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
| |
〔吾こそは 憎くもあらめ。わが屋前の 花橘を 見には來じとや。〕
ワレコソハ ニククモアラメ ワガニハノ ハナタチバナヲ ミニハコジトヤ
吾社葉憎毛有目吾屋前之花橘乎見尓波不來鳥屋 |
『全釈』では、「女の優しさ」、と感じ
この書では「嫌味」と感じている
「嫌味」と感じることは、即ち「未練」、ということだろう |
【譯】わたくしこそは憎くもあるでしよう。しかしわたくしの庭前の橘の花を見には來ないというのですか。
【釋】見尓波不來鳥屋 ミニハコジトヤ。見にこないというのか。トヤの下に、イフ、スルの如き語が省略されている。
【評語】かなり突つ込んで歌つている。初二句はすこしいや味に墮している。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
| |
〔吾こそは憎くくもあらめ吾が宿の花橘を見には來じとや〕
ワレコソハ ニククモアラメ ワガヤドノ ハナタチバナヲ ミニハコジトヤ
吾社葉憎毛有目吾屋前之花橘乎見爾波不來鳥屋 |
「憎い」とまで思うのであれば、男女の仲のこと、どんなに魅力的な催しがあっても、顔を合わせる気にはなれないだろう
万葉の時代に「にくし」は、現代の「憎い」という感覚よりも柔らかいものだ、という
そうであれば、現代語解釈で「憎い」という語は避けた方がいい私は、そう思う |
| 【大意】私こそは憎くもありませう。私の家の花橘までも、見に来まいと言ふのですか。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
| |
〔吾こそは 憎くもあらめ 吾がやどの 花橘を 見には來じとや〕
ワレコソハ ニククモアラメ ワガヤドノ ハナタチバナヲ ミニハコジトヤ
吾社葉憎毛有目吾屋前之花橘乎見尓波不來鳥屋 (『元暦校本』) |
「こそ」と「め」で逆説的に、と説明するが、それは、「~もあらめ」が
「~はあらめど」という意味であるということから、
私は、「も」こそ「逆接の接続助詞」だと思う |
【口訳】私こそは憎くもお思ひでせうが、私の家の花橘を見には来ないとおつしやるのでせうか。
【訓釈】吾こそは憎くもあらめ―「こそ」と已然形「め」との関係については前(1・1、4・674、731)にも述べたやうに、ここも「あらめど」と逆説的につづく意味がこめられてゐる。
【考】 赤人集「きくゝもあらめ」とし、「このうた人丸集にあり」とあり、流布本「にくくも」とあり、柿本集(下)「花たちはなは見にも来じとや」、古今六帖(六「たちばな」)に萬葉のまゝ載せる。
やみならばうべも来まさじ梅の花咲ける月夜に出でまさじとや (8・1452) 紀女郎
も類歌である。
われこそは憎くもあらめ我がやどの花見にだにも君が来まさぬ (拾遺集巻十九) 伊勢
も似た作である。 |
|
|

| |
| 「ふぢなみを」...きみはこじとや... |
| |
| 『くもになく』 |
| 【歌意1995】 |
ホトトギスが来て鳴き立てる岡の辺り、
そこの藤の見事な「藤波」を見には、
あなたは、来ないというのですか |
| |
| |
この歌と、昨日の歌〔1994〕が、同型同想とする注釈書は多い
確かに、下句だけ比べてみても、花橘と藤波の違いはあるが
その情感溢れる「花見」を、「それさえも」と意をこめて言う
〔1994〕の私の感じた歌意を再掲する
私のことは、本当に気にそわないのでしょうが、
美しく咲いている私の家の橘の花を、是非見にいらしてください
それとも、見にお出でにならないおつもりですか
相手を「花見」に誘うことに「花見」を持ち出すのが同じ手法だとは思う
しかし、それが「同想」と言えるか、となると
私は、そうは思わない
古注釈書に於いても、はっきりと「同想」とするものもあれば
違う、とする書もある
どうして、この二首が「同想」になるのか、私には解らない
おそらく、下句の類似性だけでなく
続けて配列されていることも、そう思わせるのだろう
『私注』など、「以上二首、花にことよせ人を誘ふ心持」といい
その二首とも「俗だ」としている
二首が並んでいるからこそ、こんな解釈になるのだと思う
しかし、歌のオリジナルは、果たしてこんな風に並んでいたのかどうか
それは解らないはずだ
編者が意図的に配したのかもしれないが
「詠歌」の段階では、決して同じ「情況」下だったとは限らないし
むしろ、私にはまったく関係ないところでの詠歌だと思う
その根拠...
合理的な、説明は出来ないが、少し意を強くして言えば
〔1994〕には、上句でその情況が詠われている
しかし、掲題歌〔1995〕では、「ほととぎすが来て鳴いている岡」と詠い出し
そこに見事な「藤波」もある
来ないてはないでしょう、こんな素晴らしい景観なのに...
前の歌〔1994〕と離れてこの歌を眺めれば
「私はともかく、せめてこの風情を」とは、どうしても感じられない
「ほととぎす」までも、この景観に花を添えるよう鳴いているのに...
この「ほととぎす」を、〔1994〕風に言えば、
「ほととぎすでも、この風情を求めてやってきたのに」とでも言えるかもしれないが
それでも、「私はともかく」などとは結びつかない
この掲題歌、むしろ別な歌での類想を思い浮かべてしまう
| |
| 夏雑歌 詠花 |
| 霍公鳥 来鳴響 橘之 花散庭乎 将見人八孰 |
| 霍公鳥来鳴き響もす橘の花散る庭を見む人や誰れ |
| ほととぎす きなきとよもす たちばなの はなちるにはを みむひとやたれ |
| 巻第十 夏雑歌 詠花 1972 作者不詳 |
| 歌意、そのまま転載 既出 [書庫-17、2014年4月1日] |
ホトトギスが来て、声を響かせて鳴いている
その庭で、鳴き声に唱和するように橘の花の散る風情を
一緒に見てくれる人は誰でしょう
あなたこそ、とお待ちしています |
この歌と、掲題歌が並んで配されていたら
今回の例のように、同じような解釈にはならないだろうか
ここでの「ほととぎす」は、「ほととぎすも花橘も」というように
この風情を、「あなた」に来て見て欲しい、と詠う
掲題歌では、結句が「疑問」になるので
詰問調に感じてしまうが、その本音は、この「類想歌」のように
「あなたにこそ、来て欲しいのですよ」と続くような気がする
どの書も、この二首を類想歌などとは書かない
私の、解釈が大変な間違いなのかもしれないが
でも、私にはこの二首の心情は...同じに思える
決して〔1994〕歌と「同型同想」ではない
|
|
掲載日:2014.04.20.
| |
| 夏相聞 寄花 |
| 霍公鳥 来鳴動 岡邊有 藤浪見者 君者不来登夜 |
| 霍公鳥来鳴き響もす岡辺なる藤波見には君は来じとや |
| ほととぎす きなきとよもす をかへなる ふぢなみみには きみはこじとや |
| 巻第十 1995 夏相聞 寄花 作者不詳 |
[類想歌]
【万葉集巻第十】〔1972〕
[資料]
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
| 【1995】 語義 意味・活用・接続 |
| ほととぎす [霍公鳥] |
| きなきとよもす [来鳴動] |
| とよもす [響もす] |
[他サ四・連体形] 鳴り響かす・大きな声や音をたてる |
| をかへなる [岡邊有] |
| をかへ [岡辺] |
[「をかべ・をかび・をかのべ」とも] 丘のほとり・丘のあたり |
| なる [助動詞・なり] |
[断定・連体形] ~にある・~にいる 〔接続〕体言、連体形につく |
| ふぢなみみには [藤浪見者] |
| ふぢなみ [藤波・藤浪] |
藤の長い花房が風に靡いている様子を波に譬えて言う語・藤の花 |
| み [見る] |
[他マ上一・連用形] 目にする・眺める・目にとめる |
| には |
~には [格助詞「に」の意味によって、種々の意味を表す] |
| 〔成立〕格助詞「に」に係助詞「は」 |
| 〔接続〕通常は体言、連体形だが、「目的・強調」の場合は、動詞の連用形につく |
| きみはこじとや [君者不来登夜] |
| じ [助動詞・じ] |
[打消の推量・] ~ないだろう |
未然形につく |
| とや |
[疑問の意] ~というのか 〔接続〕体言、体言に準ずる語につく |
| 〔成立〕格助詞「と」+係助詞「や」 |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [断定の助動詞「なり」] |
大まかな助動詞の「括り」では、「断定の助動詞」というが
「推量の助動詞」など同じように、この「断定の助動詞」にも、幾つかの用法がある
| 断定の助動詞「なり」 ナリ活用型 〔接続〕体言・連体形 |
| 未然形 |
連用形 |
終止形 |
連体形 |
已然形 |
命令形 |
| なら |
なり〔に〕 |
なり |
なる |
なれ |
なれ |
| 断定を表す |
~である・~だ |
| 存在を表す (場所などを表す語を受けて) |
~にある・~にいる |
| 資格を表す (親族関係を表す語を受けて) |
~である・~にあたる |
| (近世語)人名などを表す語を受けて「~という」の意を表す |
|
| |
| [複合助詞「には」] |
格助詞「に」と係助詞「は」とするほうが解り易いかもしれないが
古語辞典に「には」の用法が載っていたので、それに従う
係助詞「は」については、
小学館の『新編日本古典文学全集』の「注」に、次のように説明があった
|
| 係助詞「は」には、他のものと区別する働きがあり、この「は」は、私を見には来ないだろうが、この藤を見にだったら来ないこともなかろう、という気持ちで用いた |
|
| |
| [きみはこじとや] |
前の歌〔1994〕で、下句が「はなたちばなを みにはこじとや」とあるのを
ここでは、「ふぢなみみには きみはこじとや」と変形しているが、
〔1994〕では「見に来る」主語が省略されているだけで、
語句の意味としては、掲題歌と同じだと思う |
| |
|

|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「霍公鳥 来鳴動 崗部有 藤浪見者 君者不来登夜」
「ホトヽキス キナキトヨマス ヲカヘナル フチナミミレハ キミハコシトヤ」(「【】」は編集、歌番は旧) |
〔本文〕
|
| 「崗」 |
『類聚古集・神田本・西本願寺本・温故堂本・大矢本』「○【判読出来ず】」
『京都大学本』「岡」 |
| 「部」 |
『類聚古集・神田本』「邊」 |
| 「浪」 |
『類聚古集・京都大学本』「波」 |
| 〔訓〕 |
| ヲカヘナル |
『西本願寺本・細井本・神宮文庫本』「オカヘラル」
|
| ミレハ |
『類聚古集』「みには」
『神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本・神宮文庫本』「ミニハ」。『京都大学本』赭ニテ「レ」ヲ消セリ。ソノ右ニ赭「ニ」アリ |
| 〔諸説〕 |
| ○[フチナミミレハ]『代匠記(初稿本)』「フチナミミニハ」 |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1995] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
| |
〔ほとゝきすきなきとよますをかへなる藤なみ見れはきみはこしとや 〕
霍公鳥來鳴動岡部有藤浪見者君者不來登夜
|
藤の花ばかりに見惚れて、私の方へは向いてもくれない、と「恨み侘しき心」 |
| ほとゝきすきなき 郭公なく岡へに藤さきて面白きを君か見てあれは是にのみめてて我かかたへは來ましきとにやあらんと恨侘し心也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
| |
〔ホトヽキスキナキトヨマスヲカヘナルフチナミミレハキミハコシトヤ〕
霍公鳥來鳴動崗部有藤浪見者君者不來登夜 |
旧訓である「みれは」を改めたのがこの代匠記にいうことからだと思うが、その契沖自身が倣うとする「幽斎本」とは、どんな書なのだろう
前の歌〔1994〕の注釈でも、同じ「譬」があった
古義の雅澄が、契沖の言葉として書いていた
「雨の降る日ならば云々」と
この意味というのは、雨が降ったら、簑も笠も着させてでも来てください、という歌ということかな |
見者、[幽齋本云、ミニハ、]
第四の句今の本の點叶はず、幽齋本に依べし、上の歌と似て雨の降日ならば簑も笠も著てしとゞにぬれて人來さすべき歌なり、
|
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
| |
〔ほとゝぎす、きなきならせる、をかべなる、ふぢなみ見には、きみはこじとや 〕
霍公鳥來鳴動崗部有藤浪見者君不來登夜 |
前の歌〔1994〕と同じ意とする
霍公鳥も鳴き、藤も盛りの岡辺に
何故あなたはいらっしゃらないのか
「あはれ」かく面白き...しみじみと心を動かされるこの景色なのに、いらっしゃい、と念じる意 |
| 前の歌に同じき意也。郭公も鳴き藤も盛りの岡邊に、何とて君は來まさぬぞ。哀れかく面白き折の景色をも見に來給へかしと念じたる意也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
| |
霍公鳥、來鳴動[キナキトヨモス]、崗部有[ナル]、藤浪見者、君者不來登夜、
|
歌意明瞭
そうかなあ、いろいろあると思うけど... |
| 歌の意かくるゝ事なし |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
| |
〔ほととぎす。きなきとよもす。をかべなる。ふぢなみみには。きみはこじとや。 〕
霍公鳥。來鳴動。崗部有。藤浪見者。君者不來登夜。 |
どうしても前の歌〔1994〕の意と同じだ、という解釈が目立つ、ならば、この歌の底にある、来ないという理由もまた、
同じ解釈ということだろうか |
| 是れも右と同じ意なり。郭公すら來鳴きとよもす藤を、君は見には來らじとやと言ふなり。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
| |
〔ホトヽギス。キナキトヨモス。ヲカヘナル。フヂナミミニハ。キミハコジトヤ。〕
霍公鳥來鳴動崗部有藤浪見者君者不來登夜
|
ここでは、やはり「来ない」という動機に於いて、前の歌と同じかどうか判断せず、
ほととぎすまでも、やって来て鳴くほど興のあるこの岡辺
その藤浪を見にはいらっしゃらないのでしょうか、と |
| 歌(ノ)意は、ほとゝぎすさへ來鳴とよもして、いとゞ興ある此(ノ)岡邊の藤浪を、見には來ますまじとにや、となり、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
| |
〔ほととぎす來なきとよもすをかべなる藤浪見には君は來じとや 〕
格公鳥來鳴動崗部有藤浪見者君者不來登夜 |
その通りだと思う
下二句が同じ句だからといって、「一連の歌」とはならない
契沖がこの歌を「雨が降る日云々」と評すのを引用するが、その後の語「此叟風情に昧からず」とは、どんな意味だろう
「叟(おきな・ソウ)」の意味は、「おきな。老翁。」とある
この翁、風情に味からず...「味からず」は「味気なし」のことなのだろうか
「おもしろくない」とか「なさけない」とかの意味があるが...
|
前の歌と四五句相似たれば並べて出せるならむ。一聯の歌にはあらず
○契沖此歌を評して
雨のふる日ならば蓑も笠も著でしとどにぬれて人來さすべき歌なり
といへり。此叟風情に昧からず |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| |
霍公鳥來鳴きとよもす岡邊なる、藤液見には、君は來じとや |
雅澄以降、前の歌のような「恨み」を窺わせる訳はない
ここまでは... |
| |
子規が來て邊を響かして鳴く岡の邊の藤の花見には、あなたは來まいと仰つしやるのですか。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
| |
〔ほととぎす 來鳴きとよもす 岡べなる 藤波見には 君は來じとや〕
ホトトギス キナキトヨモス ヲカベナル フヂナミミニハ キミハコジトヤ
霍公鳥來鳴動岡邊有藤浪見者君者不來登夜 |
ここで、また「理由」らしき解釈が出る
前の歌と同型同想とは... |
霍公鳥ガ來テ聲ヲ響カセテ鳴ク、岡ノホトリニ美シク咲イテヰル藤ノ花ヲ見ニ、アナタハオイデナサラナイノデスカ。オイデナサツテハイカガデス。私ニ用ハナクトモ、藤ノ花ヲ見ニオイデニナリサウナモノデス。
〔評〕 前の歌と同型同想と言つてよい。郭公鳴き、藤の花咲く岡に、家居する人の作で、詰問的の力強い歌になつてゐる。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
| |
〔ほととぎす 來鳴き響す 岡邊なる 藤浪見には、君は來じとや。〕
ホトトギス キナキトヨモス ヲカベナル フヂナミミニハ キミハコジトヤ
霍公鳥來鳴動岡邊有藤浪見者君者不來登夜 |
前の歌よりは「おだやか」というも、やはり同型だという
確かに、同型には違いないが、「同想」だろうか
いくら「前より露骨ではない」といっても... |
【譯】霍公鳥の來て鳴き立てる岡邊の藤の花を見には、あなたはこないというのですか。
【釋】來鳴動 キナキトヨモス。連體句。岡を修飾している。
【評語】前の歌と同型で、前の歌のように露骨でなく、おだやかである。ホトトギスと藤の花との取り合わせもよい。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
| |
〔ほととぎす來鳴きとよもす岡べなる藤浪見には君は來じとや。〕
ホトトギス キナキトヨモス ヲカベナル フヂナミミニハ キミハコジトヤ
霍公鳥來鳴動岡邊有藤浪見者君者不來登夜 |
前と合わせてのこの二首、「花にことよせ人を誘ふ」
その通りだと思う
しかし、直接的にはそうであっても、その動機は違う、と思う |
【大意】ほととぎすが来て鳴き騒ぐ岡べの、藤の花を、君は見に来たくないと言ふのですか。
【作意】以上二首、花にことよせ人を誘ふ心持であるが、共に俗である。後者やや勝るか。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
| |
〔霍公鳥 來鳴きとよもす 岡邊なる 藤浪見には君は來じとや〕
ホトトギス キナキトヨモス ヲカベナル フヂナミミニハ キミハコジトヤ
霍公鳥來鳴動岡邊有藤浪見者君者不來登夜 (『類聚古集』) |
「考」を読むと、ある程度の評価を与えている歌だと思う
詰問的な下句の解釈が、結局この歌の動機を固定させてしまうが... |
【口訳】ほととぎすが来て鳴き立ててゐる岡邊の藤の花を見には、君はいらつしやないとおつしやるのでせうか。
【訓釈】岡邊なる藤浪―「岡」の字、『細井本』と版本とには「崗」とある。「部」の字、『類聚古集・紀州本』に「邊」とあるが、『西本願寺本』以後の諸本によつた。「部」は甲類で「邊」に同じく、もと「部」とあつたものを後に「邊」に改めたものと思はれる。「浪」の字、『類聚古集』と『京都大学本(校本に脱す)』とに「波」に作る。『紀州本』、『西本願寺本』その他による。「藤波」と書いた例他に見えない(1944、3・330)。
【考】『代匠記』に「上ノ歌ト似テ、雨ノ降日ナラバ、簑モ笠モ著デシトヾニヌレテ来(コ)サスベキ歌ナリ」といひ、『私注』には「以上二首、花にことよせ人を誘ふ心持であるが、共に俗である。後者やや勝るか」と、てきびしい |
|
|

| |
| 「なでしこの」...はなにさきでよ... |
| |
| 『こふればくるし』 |
| 【歌意1996】 |
人に知られぬよう、心の中でのみ恋慕うことは
こんなにも苦しいものだとは...
いつもあなたを見ることが叶うように
せめて、なでしこの花となって咲き出てください
それで毎朝、そっとあなたを見ることができます
恋は秘めたままでも、逢えずに想うことよりは
まだ心を落ち着かせられます |
| |
| |
「こもりのみ」の解釈
そして、「なでしこの花」と「咲き出よ」の解釈
この三句だけで、いろんな想いが交錯する
女歌だ、とか男歌だとかそんな詮索は無用だと思う
なでしこの花を「女」に譬える方が、確かにいいのかもしれない
だから、自然と男が、詠ったもの、という先入観が立ってしまう
この歌の歌意では、大きく二つの解釈があるが、
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕の解説で、紹介してみる
|
| [なでしこが花に咲き出でよ] 二句を隠喩として、『代匠記初稿本』が「なてしこのつほめるが、咲出ることく、今はおしあらはして、人にもしらせよ」の意とし、「朝な朝な見む」を「なてしこのうるはしきをみることく、紅顔を、日に日にみんといふなり」としたが、現在も「表向に恋をあらはせ」の意(全釈)、夫婦関係を結んでいる女がそのことを母に秘密にしているのを男が「母に打ち明けよ」という譬喩(窪田評釈)、「表にあらわして返事せよの譬喩」(全註釈)のように、二句を隠喩と解する説が多い。だが、巻四・四〇八、巻八・一四四八のように、恋人がなでしこの花であればよいのに、と詠んだ歌や、恋人になぞらえて心を慰めるために早くなでしこの花が咲いてほしいという歌などがあるから、ここも、『古典全集』が「なでしこの花となって咲け。毎朝見よう」と訳したようにとりたい。第五句との続き具合からいっても、この方が自然だと思われる。 |
おそらく、この他にも幾つかの試みはあると思うし、
注釈書では採り上げられない、『柿本人麻呂歌集』の、上三句では
「かけてのみこふれはくるしなてしこの」
この「かけて」の語義解釈など、私には全く思いつきでしかないが
それでも、その「歌集」では、「かけて」とされるのは何故か、ということを思うと
また、別な解釈に思い至ることができる
「かけて」は副詞で、「心にかけて」などの意がある
その成り立ちは、下二段動詞「掛(か)く」の連用形「かけ」に、接続助詞「て」
動詞「掛く」には様々な意味もあるが、心情的な語義を拾うなら
「心にとめる・心を託す・思う」という意味を持つ
そこから、副詞「かけて」の「心にかけて」となるのだろうが...
『柿本人麻呂歌集』は、いわゆる「古歌集」と言えるもので
『万葉集』に、約三百七十首ほど載せられている
しかし、その「歌集出」と、「人麻呂作」の歌が、作風に合わないものも認められ
「歌集」すべてが「人麻呂作」ではなく、古歌の採録もかなりある、という評価がある
私には、その真実は解らないし、その解決を目指すのは、別の問題だ
今回のように、私にとって気になることといえば
『万葉集』の編纂時には、すでに「古歌」として扱われていたこの「歌集」の、
この歌に、「かけて」とあることの事実だ
「かけて」が絶対的に訓として正しい、というのではない
当時の『柿本人麻呂歌集』も、当然のことながら、その表記は「漢字」
だから、万葉編纂時と、その条件は同じだろうし
後の時代に、これを「かけて」と訓むことが通っていた「何か」の根拠があったのか、
あるいは、そもそも『柿本人麻呂歌集』の訓は、いつどこで誰が成し得たのかも、
勉強不足で、私には解らない
しかし、少なくとも「かけて」と訓ませる「何か」はあった
現訓の「こもり」が、江戸時代の契沖が提唱したのは、
以降のどの注釈書にもあるが、巻第十六の、初二句に同句が現れ
その句に対して、訓を重ねるのなら、巻第十七の「万葉仮名」が窺われる
契沖だけではなく、多くの注釈書でも、そう述べている
「かけて」と「こもり」では、その受ける感じはまったく違うものだ
あくまで語感として、歌を聞いたときに擁くのは、
「かけてのみ」は、「気にばかりしていないで」のようになり
「かくりのみ」では、それこそ真淵なども言うように、「しのぶ、耐え忍ぶ」に通じる
その「語感」の影響もあるのだろうが、現代の解釈の主流は
上出に挙げた、『全注』を引用したように、「耐え忍ぶ恋心」がすべてになっている
なぜ、『柿本人麻呂歌集』で「詠われ」た「かけて」の「なぜ」を考えないのだろう
仮に、その「かけて」で歌意を考えると
| 柿本人麻呂歌集による、掲題歌〔1996〕改 |
| かけてのみこふればくるしなでしこのはなにさかなんあさなあさなみん |
こころに想うだけの恋など、苦しくてせつないものだ
なでしこの花のように、こころを和ませるように咲いて欲しい
そんなあなたを、私は毎朝見たいのに... |
「さきでよ」が「さかなん」とするが、この「なん(む)」は終助詞で、
他に対する願望(あつらえ)の意を表す「~してほしい・~てもらいたい」
私は、こんな風にしか解釈できないが
この歌は、掲題歌とまったく違う歌ではない
本来なら、『柿本人麻呂歌集出』とされてもいいほどの「一首」だ
しかし、その「左注」がないというのは
まさに、この初句の訓一つで、歌意がすっかり変わりかねないからなのかもしれない
「こもりのみ」と訓じられ始めたのが、江戸時代
私には、漢字表記の「隠耳」に拘り過ぎているように思われてならない
しかし、仮に「隠」の表記であっても、「こもる」という意味であれば
必ずしも、二人の関係に行き着くものとは限らないだろう
『柿本人麻呂歌集』の一首を、解釈すれば
心の優しい作者と、恋に悩む女(たぶん)の、ほのぼのとした
それでいて、甘酸っぱくせつない「作者の慕情」が、とても感じられる歌だと思う
そして、肝腎なことを書こうと思うが、
今に言われる解釈の一つ、あるいはそんな雰囲気を持たせるのは
やはり、初二句の「こもりのみ こふればくるし」、そしてその「原文」がある
「類想歌」と言われる巻第十六〔3825〕の、その題詞にどうしても思いがいく
| 昔者有壮士與美女也[姓名未詳] 不告二親竊為交接 於時娘子之意欲親令知 因作歌詠送 |
| 隠耳 戀者辛苦 山葉従 出来月之 顕者如何 |
| 〔題詞〕の訳 |
昔、一人の男と美女がいた[名は未詳]。両親に告げられもせず、二人は恋仲になった。
その時、少女は心の中で親に知らせたい、と思い、そこで歌を作って男に送った、その歌。 |
初二句の原文の類似性、そこからこの題詞の背景
これを読めば、どうしても掲題歌もまた、同じような環境で詠われたものかもしれない
いや、きっとそうだ、と思いかねない
勿論、それが正しいかもしれないが、でも「歌」として解釈はしなければならないし
「歌物語」であれば、この万葉の編者は、
この〔3825〕と掲題歌〔1996〕を並べて配するべきだったと思う
この〔3825〕の「左注」に、次のような説明がある
| 右或云 男有答歌者 未得探求也 |
| 〔左注〕の訳 |
右は、或は云う、男の答歌が有る、と
しかし、未だに探し求め得られていない |
ひょっとすると、この掲題歌が、その「左注」にいう、「男の答え歌」なのかもしれない
それが違うから、離れたところに配されたのではなく
万葉編纂時の大変さ、混沌とした膨大な歌の中からの編纂作業では
意図しなくて見逃した可能性だって有り得る
題詞の後に、〔3825〕〔1996〕と配されて載っていたら
間違いなく、誰もが「歌物語」のような「秘めた恋仲」として解釈したのだろう
|

|
掲載日:2014.04.21.
| |
| 夏相聞 寄花 |
| 隠耳 戀者苦 瞿麦之 花尓開出与 朝旦将見 |
| 隠りのみ恋ふれば苦しなでしこの花に咲き出よ朝な朝な見む |
| こもりのみ こふればくるし なでしこの はなにさきでよ あさなさなみむ |
| 巻第十 1996 夏相聞 寄花 作者不詳 |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】〔70・406・238・71〕
【赤人集】〔159・146・266〕
[類想歌]
【万葉集巻第十六】〔3825〕
【万葉集巻第十七】〔4034〕
【万葉集巻第三】〔411〕
【万葉集巻第八】〔1452〕
[資料]
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
| 【1996】 語義 意味・活用・接続 |
| こもりのみ [隠耳] |
| こもり [隠り・籠もり] |
隠れること・籠もること・社寺に泊り込んで祈ること・おこもり |
| のみ [副助詞] |
[限定] ~だけ・~ばかり |
| 〔接続〕体言・副詞・活用語の連体形・格助詞など連用修飾語となる種々の語につく |
| こふればくるし [戀者苦] |
| ば [接続助詞] |
[順接確定条件] ~すると・~したところ・~ので・~だから |
| 〔接続〕已然形に接続すれば「確定条件」で、未然形に接続すれば「仮定条件」 |
| くるし [苦し] |
[形シク・終止形] 痛みや悩みでつらい・くるしい |
| なでしこの [瞿麦之] |
| はなにさきでよ [花尓開出与] |
| に [格助詞] |
[状態(比況)] ~のように |
体言につく |
| でよ [出(い)づ] |
[自ダ下二・命令形] (表面に)現れる・(中から)外に出る |
| |
[他ダ下二・命令形] 外に出す・表す |
| |
[補動ダ下二・命令形] (動詞の連用形について)~て外に出る、出す |
| あさなさなみむ [朝旦将見] |
| あさなさな [朝なさな] |
[副詞「朝な朝な」の転] 毎朝・朝ごとに |
| む [助動詞・む] |
[推量(意志)・終止形] ~よう・~つもりだ |
未然形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [こもり] |
四段動詞「隠る・籠る」の連用形かと思ったが、
連用形では、次の副助詞「のみ」に接続しない
動詞「隠る」の名詞「隠り」となる
柿本人麻呂歌集では「かけてのみ」が初句になっているが
その「かけ」も、下二段動詞「掛く」の連用形「かけ」と、接続助詞「て」で、
副詞「かけて」を作る
「かけて」の意味は、「心にかけて」というので、原文「隠」の「意訳」になると思う
赤人集の職「ひとしれず」もまた、原文「隠耳」の意訳ではないかと思う
平安期に撰された「赤人集」は、その訓が本歌と違うのは
このような訓の曖昧なものは、平安期の解釈に基づいて訓まれたものかもしれない
しかし、『柿本人麻呂歌集』になるとそうは行かない
『万葉集』にも数多くの「人麻呂歌集出」とあるように、古くからある
しかし原文の「訓」の曖昧さは、また同じことだろう
同じ『万葉集』中に、同じような歌を「万葉仮名」で書かれていたら、
まずその訓を、当てはめるのだろうが...
|
| |
| [のみ] |
この副助詞「のみ」には、四つの用法がある
|
|
| 限定 |
~だけ・~ばかり |
| 強調 |
特に・とりわけて |
| 用言の強めこ |
~しているばかりである・ただもう~する・ひたすら~でいる |
| 限定して断定 |
~だけだ |
この掲題歌では、「限定」の用法だと思うが、
その語義の一つ「ばかり」とも、やや違う意味合いがある
|
| のみ |
他のいかなる事物もまじえず、ただそれだけがあることを示す |
| ばかり |
おおよその範囲や概数、物事の程度を示す。また、ある事態を、それ以上のものはない限度として示す。 |
|
| |
| [なでしこの] |
原文「瞿麦之」をほとんどの書は「なでしこの」と訓むが、
現代の注釈書である、
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波文庫校訂版、平成25年~〕、
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕、
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕などは、
その訓を「なでしこが」とする
この「が」は、格助詞で、「所属」となるはずだ
「~の」という意味になる
「なでしこの花」も、「なでしこが花」も同じ意味になるが、
「之」を「の」と訓む方が、素直だと思う |
| |
| [でよ] |
下二段動詞「出(い)づ」の命令形だが、
この動詞を「自動詞」とするか「他動詞」とするか、で解釈は違ってくる
その解釈を受けて、結果的には「補助動詞下二段」になるのだが
自動詞で解釈すると、「なでしこの花が、咲き出る」となり
他動詞での解釈は、「なでしこの花を、咲かせる」となる
これが、作者が相手に求める気持ちの違いとなる
「咲きなさい」「咲かせなさい」
それは、相手に毎朝逢えるように、隠れていないで、なでしこの花のように咲きなさい
あるいは、心の中に秘めていないで、その想いを、なでしこの花のように咲かせ、見せなさい
との違いになる |
| |
| |
| |
[万葉集類歌及び類想歌]
【巻十六 3825】
| 雑歌/昔者有壮士與美女也[姓名未詳] 不告二親竊為交接 於時娘子之意欲親令知 因作歌詠送 |
| 隠耳 戀者辛苦 山葉従 出来月之 顕者如何 |
| 隠りのみ恋ふれば苦し山の端ゆ出でくる月の顕さばいかに |
| こもりのみ こふればくるし やまのはゆ いでくるつきの あらはさばいかに |
| 右或云 男有答歌者 未得探求也 |
| 作者不詳 |
〔語義〕
「やまのはゆ」は、「山の端から」
「いでくるつきの」は、「出てくる月のように」
格助詞「の」が、「連用修飾語的用法」で「~のように」となる
「あらはさば」は、はっきり示す意の四段動詞「あらはす(顕す)」の未然形「あらはさ」
それに、順接の仮定条件の接続助詞「ば」で、「顕したら」
「いかに」は、副詞で、「どのように・どんなに(~だろう) |
〔歌意〕
心に秘めていたままでは、苦しいもの
山の端から出てくる月のようにはっきりと
想いを顕せてはいかがでしょう |
初二句は、掲題歌と同じで、相手の心を説明している
この歌では、「月が出て、その存在をはっきりと示す」
そして、掲題歌に重ねると、「なでしこの花が咲くように見映えがよく」となるが
掲題歌が命令形で詠っていることが、この歌との違いだ |
|
【巻十七 4034】
| (忽見入京述懐之作生別悲兮断腸万廻怨緒難禁聊奉所心一首并二絶) |
| 宇良故非之 和賀勢能伎美波 奈泥之故我 波奈尓毛我母奈 安佐奈々々見牟 |
| うら恋し我が背の君はなでしこが花にもがもな朝な朝な見む |
| うらごひし わがせのきみは なでしこが はなにもがもな あさなさなみむ |
| 右大伴宿祢池主報贈和歌 [五月二日] |
| 大伴宿祢池主 |
〔語義〕
形容詞「うらこひし」は、「うら(心の意)」から恋しい、あるいは何となく恋しい
「もがもな」は、願望の意を表す「~であったらなあ」[終助詞「もがな」+終助詞「も」]
|
〔歌意〕
心から慕わしいあなたは、なでしこの花であってほしい
そうなれば、毎朝いつも逢うことができるのに... |
結句は、「もがもな」の影響で条件法的な結びになると思う
この歌も、命令形ではない点を除けば
掲題歌と同じ心持にはなるだろうが
先の「類歌」〔3825〕とも違うのは、「こもりのみ」で修飾されていないことだ
だから、「なでしこの花」を「我が背」に重ねて逢いたい、というだけの歌だ |
|
【巻三 411】
| 譬喩歌 |
| 石竹之 其花尓毛我 朝旦 手取持而 不戀日将無 |
| なでしこがその花にもが朝な朝な手に取り持ちて恋ひぬ日なけむ |
| なでしこが そのはなにもが あさなさな てにとりもちて こひぬひなけむ |
| 大伴宿禰家持 |
〔語義〕
「もが」は、願望の終助詞で、「~であればなあ」
「こひぬ」は、打消しの助動詞「ず」の連体形「ぬ」で、恋しく思わない
「ひなけむ」の「なけむ」は、形容詞「無し」の未然形「なけ」に、推量の助動詞「む」 |
〔歌意〕
あなたが、なでしこの花であったらなあ...
そうであれば、毎朝手に取り持って、恋しく想わない日はないだろう
|
この歌は、上の歌〔4034〕と類想歌と言える
結句が二重否定になっている
ここも、毎朝逢いたいがための、「なでしこの花」として詠っている |
|
【巻八 1452】
| 春相聞 |
| 吾屋外尓 蒔之瞿麥 何時毛 花尓咲奈武 名蘇經乍見武 |
| 我がやどに蒔きしなでしこいつしかも花に咲きなむなそへつつ見む |
| わがやどに まきしなでしこ いつしかも はなにさきなむ なそへつつみむ |
| 大伴宿禰家持 |
〔語義〕
「まきし」の「し」は過去の助動詞「き」の連体形「し」で、「蒔いた」
「いつしかも」は、「いつになったら~か」の意
「なむ」は強意の係助詞で、その結びは連体形となり、
結句の「む」が推量の助動詞「む」の連体形で、「結び」となる
「なそへ」は、なぞらえる意の下二段動詞「なそふ」の連用形「なそへ」
「つつ」は、並行の接続助詞「つつ」で、「~とともに・~ながら」 |
〔歌意〕
我が家の庭に蒔いたなでしこは、いったいいつになったら咲くのだろうか
その花を、あなたに擬え、見たいものだ |
この歌は、上出の類歌のまるで解説のような歌になっている
いや、そんな歌がよく聞かれるので、私も蒔いてみよう、というのだろうか
まあ、そんなことはないだろうが、
今日挙げた類歌は最初の〔3825〕が「類想歌」と言えるもので
やはり、「こもりのみ」の歌意に及ぼす影響は大きい
しかし、他の三首でも「なでしこの花」を、相手の面影と重ねることは同じだ
その心で、掲題歌を解釈することも出来る
そして、別の解釈では、〔3825〕のように、「秘めた想い」を吐出しなさい、と
命令形なので、こんな解釈になるのは自然だろう |
|
| |
|
|
| 掲題歌[1996]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
[収載歌集]
【柿本人麻呂】
| 新編私家集大成第一巻-2 人麿Ⅰ 柿本人丸集[書陵部蔵「歌仙集」五一一・二] |
| かけてのみこふれはくるしなてしこの はなにさかなん朝なみん |
| 柿本人丸集下 70 |
| 同第一巻-3 人麿Ⅱ 柿本集[書陵部蔵五〇一・四七] |
| かけてのみこふれはくるしなてしこの はなにさかなんあさなみむ」四四 |
| 柿本集 たひの歌 406 |
| 同第一巻-4 人麿Ⅲ 柿本人麿集[冷泉家時雨亭叢書『素寂本私家集西山本私家集』] |
| カケテノミコフレハクルシナテシコノ ハナニサカナンアサナミム」 |
| 柿本人麿集中 恋部 寄草 万十 238 |
| 新編国歌大観第三巻-1 人丸集[書陵部蔵五〇六・八] |
| かけてのみこふればくるしなでしこのはなにさかなんあさなあさなみん |
| 人丸集下 71 |
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
|
| ひとしれすこふれはくるしなてしこの 花にさきてよあさなさなに |
| 新編私家集大成第一巻-新編増補 赤人集Ⅲ[陽明文庫蔵三十六人集] 159 |
|
| ひとしれすこふれはくるしなてしこの 花さきいてよあさなさなみん |
| 新編私家集大成第一巻-6 赤人集Ⅱ[書陵部蔵三十六人集] 146 |
|
| ひとしれすこふれはくるしなてしこの はなにさきてよあさなみん |
| 新編私家集大成第一巻-5 赤人集Ⅰ[西本願寺蔵三十六人集] あか人 はなによす 266 |
|
| ひとしれすこふれはくるしなてしこの はなにさきてよあさなさなみん |
| 新編国歌大観第三巻-2 赤人集[西本願寺蔵三十六人集] 266 |
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「隠耳 戀者苦 瞿麦之 花爾開出與 朝旦將見」
「カクシノミ コフレハクルシ ナテシコノ ハナニサキイテ アサナサナミム」(「【】」は編集、歌番は旧) |
〔本文〕頭注に、『類聚古集』本文ノ下ニ小字「無作者」アリ。赤人集「ひとしれすこふれはくるしなてしこのはなにさきてよあさなさなみむ」
|
| 「戀」 |
『大矢本』「変」消セリ。左ニ「恋」アリ
『近衛本』底本ニ同ジ |
| 「與」 |
『大矢本・京都大学』ナシ |
| 〔訓〕 |
| カクシノミ |
『類聚古集』「したにのみ」。
『神田本』「シタニノミ」。ソノ右ニ「カクレノミ 江」アリ。漢字ノ左ニ「ヒトシレス」アリ。
『京都大学本』「カクレノミ」
|
| ハナニサキイテ |
『類聚古集』「はなさきいてよ」
『神田本』「ハナニサキテヨ」
『西本願寺本・神宮文庫本・細井本・温故堂本』「ハナニサキイテヨ」 |
| アサナサナミム |
『類聚古集』「あさなさなみむ」
『神田本』「アサナサナミム」
『西本願寺本』下ノ「サナ」モト青
『陽明本・温故堂本』「アサケサナミム」。『陽』「サナ」青
『大矢本・京都大学本』下ノ「サナ」青。『京』「朝旦」ノ左ニ赭「アサナサナ」アリ |
| 〔諸説〕 |
| ○[カクシノミ]『代匠記(初稿本)』「シタニノミ」。『代匠記(精撰本)』「コモリノミ」。『万葉考』「シヌビノミ」。○[ハナニサキイテ]『童蒙抄』「ハナニサキテヨ」 |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1996] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
| |
〔かくしのみこふれはくるしなてしこの花にさきいてよ朝なさなみん 〕
隠耳戀者苦瞿麦之花尓開出與朝旦将見
|
この「かく」は、「心にかけて」という意味の「掛く」で、「し」は強意の副助詞、というところだろうか
「あひみすして戀れはくるし」は、まさに「人麻呂歌集」の「かけて」に通じるものかな |
| かくしのみこふれは しは助字也かくのみ也あひみすして戀れはくるしきに撫子とたに咲出よ毎朝みんと也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
| |
〔カクレノミコフレハクルシナテシコノハナニサキイテアサナサナミム〕
隱耳戀者苦瞿麥之花爾開出與朝旦將見 |
ここから、初句の訓「コモリノミ」が始まったようだ
契沖も、その根拠を万葉仮名での訓に基づいて、その語を提唱している |
戀者、[幽齋本云、コフルハ、] 開出與、[幽齋本云、サキイテヨ、]
第十六に隱耳戀者/辛苦[クルシ]云々、今の初二句と同じ、今按發句は共にコモリノミと讀べし、其故は第十七に大伴池主が長歌の中に己母理古非[コモリコヒ]、伊枳豆伎和多利[イキツキワタリ]云々、此初の一句今の二句に亘れり、
|
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
| |
〔かくしのみ、こふればくるし、なでしこの、はなにさきでよ、あさなさなみむ 〕
隱耳戀者苦瞿麥之花爾開出與朝旦將見 |
「花に咲き出よ」の、「思ひととのひ叶へよ」と解釈するのは、このままでは駄目だ、気持ちをはっきりさせよ、ということだろうか
ことがととのふ、ということはいつも目にする事ができる、と |
| かくしのみ は如此のみと云意を合みて也。しのびのみとも讀べけれど、如此のみと云意をふまへての意なるべし。花に咲き出よとは、思ひのとゝのひ叶へよと也。先をなでし子によせて、事の調ひなば目かれずも見んと也。朝なさな見んは飽ず馴れそひ見んとの意也
|
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
| |
隱耳[シヌビノミ]、 今本かくしのみと訓りさても聞ゆれどしのぶ意を得て借たれば訓をあらためつ
戀者苦、瞿麥之、花爾開出與、朝旦將見[アサナサナミム]、
|
〔1993〕の「さくとはなしに」の意とは、異なり、ここでは「相逢ん」...要は「二人の花を咲かせよう」となるか
「しぬ(の)び」とあることから、秘めた恋から、堂々と知らしめよう、とするものかもしれない |
| 上に開とはなしにといふとは異にてこゝはあらはれ出て相逢んといふなり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
| |
〔こもりのみ。こふればくるし。なでしこの。はなにさきでよ。あさなさなみむ。 〕
隱耳。戀者苦。瞿麥之。花爾開出與。朝旦將見。 |
「なでしこ」は、単に季節的に目の前にあった「譬え」に過ぎない、という
「かくれてばかりいないで」、顕われてきてくれ、そして逢おう、という |
コモリノミは、忍ビニノミなり。花ニ咲キ出ヨは、顯れ出ても逢ひ見んと言ふなり。ナデシコは唯だ時に有る物をもて譬ふるなり。
參考 ○隱耳(代、古、新)略に同じ(考)シヌビノミ。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
| |
〔コモリノミ。コフレバクルシ。ナデシコノ。ハナニサキデヨ。アサナサナミム。〕
隱耳戀者苦瞿麥之花爾開出與朝旦將見
|
「咲き出よ」は、人に知らせよ
そこに中心を置いた解釈
作者の為に顕われて、ではなく
秘めたることを、公にして、堂々と逢おう、ということだろうか |
隱耳は、コモリノミと訓べし、十六に隱耳戀者辛苦山葉從[コモリノミコフレバクルシヤマノハヨ]、出來月之顯者如何[イデクルツキノアラハサバイカニ]、とあり、
○歌(ノ)意は、契冲、しのびてこふればくるしきに、なこでしこのつぼめるが咲出るごとく、いまはおしあらはして人にもしらせよ、なでしこのうるはしきを見るごとく、紅顔を日に日に見むといふなり、朝旦といへるは、日ごとの意なり、といへり、
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
| |
〔こもりのみこふればくるしなでしこの花にさきでよあさなさな見む 〕
隱耳戀者苦瞿麦之花爾開出與朝旦將見 |
サキデヨが、公表せよ、ということは
単に姿を見せなさい、ではなく
二人の秘めた関係を、公にしよう、ということだろう
これが女歌だとすれば、煮え切らない男に対して、態度を迫っている歌になる
|
| コモリノミはシノビテノミなり。ハナニは花トにてやがてナデシコノ花ノ如クとなり。サキデヨは表向ニセヨといふことをたとへたるなり○これも女の歌なり
|
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| |
籠りのみ戀ふれば苦し。撫子の花に咲き出でよ。朝な朝[サ]な見む |
想いを、自分の心に仕舞っておくのは苦しいことだ
公にさえしてくれれば、それでいい
ここでいう「毎日毎日見ていよう」というのは
これも堂々と逢いましょう、という譬えになるのだろう |
| |
心中に籠[コ]めて焦れて居るのは、苦しいことだ。撫子の花ではないが、表面に表してさへ下されば、それで好いのだ。さうすれば、毎日々々見てゐように。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
| |
〔隱りのみ 戀ふれば苦し なでしこの 花に咲き出よ あさなさな見む〕
コモリノミ コフレバクルシ ナデシコノ ハナニサキデヨ アサナサナミム
隱耳戀者苦瞿麥之花爾開出與朝旦將見 |
秘めた恋心は苦しい、だからすっかり公表して逢いましょう
ここでは、二人の関係を全面に推す解釈になる
|
心ノ中ニ包ンデバカリ戀シテヰレバ辛イコトデス。イツソノコト瞿麥ガ花ト咲キ出ルヤウニ、外ニアラハシテ表向キニ戀ヲシナサイ。サウシタラ人目ナドニカマハズニ、毎朝毎朝逢ヒマセウ。
○隱耳[コモリノミ]――心の中に包み忍んでばかりの意。
○花爾開出與[ハナニサキデヨ]――花の如く咲き出でよの意で、即ち表向に戀をあらはせといふのである。
〔評〕 瞿麥の花に寄せた歌。結句/朝旦將見[アサナサナミム]にも寄せる意があらはれてゐる。卷十六の隱耳戀者辛苦山葉從出來月之顯者如何[コモリノミコフレバクルシヤマノハユイデクルツキノアラハサバイカニ](三八〇三)と似てゐる。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
| |
〔隱りのみ 戀ふれば苦し。なでしこの 花に咲き出でよ。朝な朝な見む。〕
コモリノミ コフレバクルシ ナデシコノ ハナニサキイデヨ アサナサナミム
隱耳戀者苦瞿麥之花尓開出與朝旦将見 |
こもってばかりいないで、なでしこの花のように
咲き出でてください
そうすれば、私も毎朝見ることができる
明確な解釈の相違点が表れ始めた
それまでは、やや中途半端な「注釈」が多かった
『全釈』辺りから、この歌の解釈上の相違点が見え始める |
【譯】心の中でばかり思つているのは苦しい。ナデシコのように、花に咲き出てください。毎朝見ましよう。
【釋】隱耳 コモリノミ。心の中でのみ。
瞿麥之 ナデシコノ。譬喩。ナデシコの如く。
花尓開出與 ハナニサキイデヨ。花として咲き出よというので、表にあらわして返事せよの譬喩。句切。
【評語】譬喩がよく當つている。ナデシコを點出したのも、相手にふさわしい。
【參考】類句、こもりのみ戀ふれば苦し。
こもりのみ戀ふれば苦し。山の端ゆ出で來る月の顯[あらは]さばいかに(卷十六、三八〇三)
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
| |
〔こもりのみ戀ふれば苦し撫子の花に咲き出でよ朝なさな見む〕
コモリノミ コフレバクルシ ナデシコノ ハナニサキデヨ アサナサナミム
隱耳戀者苦瞿麥之花爾開出與朝旦将見 |
これが、中途半端な解釈だと思う
花を咲かせるのは、相手のことだけなのか
それとも、二人が係わっての「秘めた関係」のことなのか |
【大意】奥にこめてばかり戀するのは苦しい。撫子の花の咲くごとく、外にあらはしなさいよ。それなら毎朝毎朝会ひませう。
【作意】幼いながら、よく聞える歌である。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
| |
〔隱りのみ 戀ふれば苦し 瞿麥の 花に咲き出でよ 朝な朝な見む〕
コモリノミ コフレバクルシ ナデシコノ ハナニサキデヨ アサナサナミム
隱耳戀者苦瞿麥之花爾開出與朝旦将見 (『元暦校本』) |
これも同じく、どっちなんだろう
あなたが秘めようとしるから、作者も堂々と逢うことはできない
そう解釈すれば、二人の「秘めたる関係」なのだが
こうした日本語の解釈では、単に相手が「こもりがち」だから、
逢うことができないのか、その関係がつかめない |
【口訳】外に表はさず忍んでばかりゐては苦しい。なでしこの花の咲き出るやうに、思ひを外に表はしておしまひよ。そしたら毎朝毎朝逢ひませう。
【訓釈】隱りのみ戀ふれば苦し―人目を忍んで心の中でばかり戀してゐると苦しい、の意。
瞿麥の花に咲き出でよ―瞿麥の花のやうに、外に表はしてしまへ、と云った。
【考】赤人集に「ひと知れず」とあり、流布本「花咲き出でよ」、柿本集(下)「かけてのみ」「花に咲かなむ」とある。
隠りのみ戀ふれば苦し山の端ゆ出で来る月のあらはさば如何に (十六・三八〇三)
も似た作である。
|
|
|

| |
| 「わがころもでの」...ふるときもなき... |
| |
| 『せきべつの』 |
| 【歌意1998】 |
夏草の露に分け入り濡れた衣を
着ているわけでもないのに、
私の衣の袖は、あなたへの想いで、乾く時がありません |
| |
| |
この歌は、おそらく解釈上の難点はなく
どの注釈書も、その「訓」解釈に重点を置いている
確かに、歌意は明白で、他には思いもしないが
驚いたのは、唯一の「男歌」とする書があったこと、それは
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕の解釈で
|
| 夏草の露を踏みわけて濡れた衣を、べつに着たおぼえはないのに、どうして私の衣の袖は、乾く間もないのであろうか。 |
とある
この歌意解釈の説明として、
「衣の袖が君恋しさに涙に濡れることを詠んだ」
「夏草の露別け衣 女の家に通う男が夏草の露をわけてゆくために濡れる衣」
「着けなくに 女は露別け衣を着るはずもないので、こう表現した」
この解釈の基本になるのが、詠われている「露別衣」の扱い方だ
実際に作者が着るものとして、それを詠うのであれば、女では着ないはずだから、男歌、だと
しかし、作者が着ることを言うのではなく、
夏草の露を分け入るのに用いる「露別衣」という、「比喩」として詠ったものであれば
女の涙と絡めて表現するのに、決して無理はないと思う
|
|
掲載日:2014.04.22.
| |
| 夏相聞 寄露 |
| 夏草乃 露別衣 不著尓 我衣手乃 干時毛名寸 |
| 夏草の露別け衣着けなくに我が衣手の干る時もなき |
| なつくさの つゆわけごろも つけなくに わがころもでの ふるときもなき |
| 巻第十 1998 夏相聞 寄露 作者不詳 |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】〔72・342・513・293・73〕
【赤人集】〔160・147・267〕
【古今和歌六帖】〔3291〕
【新古今和歌集】〔1374/1375〕
[資料]
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
| 【1998】 語義 意味・活用・接続 |
| なつくさの [夏草乃] 夏の草、「枕詞」のもあるが、ここは「露」を修飾する語 |
| つゆわけごろも [露別衣] 露の降りた草の中を分けて行くときに着る衣 |
| つけなくに [不著尓] |
| つけ [着く] |
[他カ下二・未然形] 接触させる・付着させる |
| なくに |
~(し)ないことだのに・~(し)ないのに |
未然形につく |
| 〔成立〕打消しの助動詞「ず」のク語法「なく」+格助詞「に」 |
| わがころもでの [我衣手乃] 私の衣の袖は |
| ふるときもなき [干時毛名寸] |
| ふる [干(ふ)・乾(ふ)] |
[自ハ上二・連体形] 乾く・水が少なくなる |
| も [係助詞] |
[強意] (下に打消しの語を伴って) ~も |
名詞につく |
| なき [無し] |
[形ク・連体形] ない |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [つゆわけころも] |
どの注釈書でも、この歌の最初の語解釈になる
「古注釈書」では、下段の「資料」でも説明するが
他の歌集を引いて、「そのようなもの」として多く説明している
『万葉集』中では、この歌のみに、この語が見られる |
| |
| [なくに] |
打消しの助動詞「ず」のク語法、格助詞「に」について、
連体形+「に」と同じ働きをし、逆接的接続となる場合が多い
|
| |
| [ふる] |
この歌の上二段動詞「干(ふ)」は、上代での訓で、
中古以降は上一段動詞「干(ひ)る・乾(ひ)る」となる |
| |
| [なき] |
「ふるときもなき」で、咄嗟に思ったのは、係助詞「も」と、その結びの連体形に「なき」
しかし、係助詞「も」は、係助詞「は」と同様に、結びの制約がなく、
基本的には「終止形」で終る
だから、この結句の「なき」が連体形で終るのは、
その連体形の「終止法」の一つである、「詠嘆・余情の表現としての連体形止め」になる |
| |
|
|
 |
| 掲題歌[1998]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
[収載歌集]
【柿本人麻呂】
| 新編私家集大成第一巻-2 人麿Ⅰ 柿本人丸集[書陵部蔵「歌仙集」五一一・二] |
かけてのみ(なつくさの)露わけ衣きぬものを なとわか袖のかはく時なき
|
| 柿本人丸集下 72 |
| 同第一巻-3 人麿Ⅱ 柿本集[書陵部蔵五〇一・四七] |
| 夏草のつゆわけころもきもせぬに なとわか袖のかはくときなき |
| 柿本集 たひの歌 [新古今集] 342 |
| 同第一巻-4 人麿Ⅲ 柿本人麿集[冷泉家時雨亭叢書『素寂本私家集西山本私家集』] |
ナツクサノツユワケコロモキモセヌニ ワカコロモテノヒルトキモナキ
(ナトワカソテノカハクヨモナキ) |
| 柿本人麿集中 恋部 寄露 万十 513 |
| 同第一巻-新編増補 人麿Ⅳ 人丸集[冷泉家時雨亭叢書『詞林采葉抄人丸集』] |
なつくさのつゆわけころもきもせぬに/わかころもてのひるときもなき
|
| 人丸集 つゆによす 十 293 |
| 新編国歌大観第三巻-1 人丸集[書陵部蔵五〇六・八] |
| 夏草の露わけ衣きぬものをなどかわが袖のかわく時なき |
| 人丸集下 73 |
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
|
| 夏草の露わけ衣きぬ物を わかころもてのかはくよもなき |
| 新編私家集大成第一巻-新編増補 赤人集Ⅲ[陽明文庫蔵三十六人集] つゆによす 160 |
|
| なつ草のつゆわけころもまたきぬに わかころもてのひるよしもなき |
| 新編私家集大成第一巻-6 赤人集Ⅱ[書陵部蔵三十六人集] はなによす 147 |
|
| なつくさのつゆわけころもまたき」五一ぬに わかころもてに(ハ)ひるよしもなし |
| 新編私家集大成第一巻-5 赤人集Ⅰ[西本願寺蔵三十六人集] あか人 はなによす 267 |
|
| なつくさのつゆわけごろもまだきぬにわがころもではひるよしもなし |
| 新編国歌大観第三巻-2 赤人集[西本願寺蔵三十六人集] はなによす 267 |
【古今和歌六帖 ([永延元年(987年)頃]撰、兼明親王・源順か】
|
| なつぐさのつゆわけごろもきもせぬにわがころもでのかわくときなき |
| 新編国歌大観第二巻4 [宮内庁書陵部蔵五一〇・三四] 第五 夏ごろも 3291 |
【新古今和歌集 ([1205年4月16日~1210年9月頃]撰、藤原定家[1162~1241]他)】
|
| なつぐさの露わけ衣きもせぬになどわがそでのかわく時なき |
| 新編国歌大観第一巻-8 [谷山茂氏蔵本]巻第十五 恋歌五 1374/1375 人麿 |
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「夏草乃露別衣不著爾我衣手乃干時毛名寸」
「ナツクサノ ツユワケコロモ キモセヌニ ワカコロモテノ ヒルトキモナキ」(「【】」は編集、歌番は旧) |
〔本文〕頭注に、『神田本』、頭書「抄」。マタ歌ノ下ニ「○○【判読出来ず】」アリ。何ノ字ノ異カ明ナラズ。
赤人集「なつくさのつゆわけごろもまたきぬにわかころもてに(ハ)ひるよしもなし」
|
| 「著」 |
『類聚古集』「春」墨ニテ消セリ。右ニ墨「著」アリ |
| 「爾」 |
『細井本・活字無訓本・神宮文庫本』ナシ |
| 〔訓〕 |
| ナシ |
|
| 〔諸説〕 |
| ○[ツユワケコロモ]『万葉考』「ツユワケシキヌ」。○[キモセヌニ]『略解』「ケセナクニ」 |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1998] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
| |
〔なつ草の露わけ衣きもせぬにわかころもてのひるときもなき 〕
夏草乃露別衣不著尓我衣手乃干時毛名寸
|
「つゆわけころも」の語義説明
「きもせぬに」は、他動詞カ行上一段「着る」の解釈 |
| なつ草の露わけ 露わけ衣は露をわけし衣也哥の心あきらけし |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
| |
〔ナツクサノツユワケコロモキモセヌニワカコロモテノヒルトキモナキ〕
夏草乃露別衣不著爾我衣手乃干時毛名寸 |
「雨衣」のような衣...
古今集の用いられる「山分衣」が山伏の衣だということで、そのような「衣」だろう、という
古今六帖では、確かに「夏ごろも」の部立てで載っている
新古今集では、「人麿」作として収載されている |
露分衣と分る衣を押て云歟、又露を分む爲に雨衣などの樣に別に用意する衣の名歟、又古今集に山分衣とよめるは山臥の衣と聞ゆれば、それていの衣の名にや、能味はへば押て名付たるにはあらじとぞおぼしき、六帖には夏衣の歌とせり、新古今は人丸集に依て入られ、家集又赤人集にもあり、
|
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
| |
〔なつぐさの、つゆわけごろも、きもせぬに、わがころもでは、ひるときもなき 〕
夏草乃露別衣不着爾我衣手乃干時毛名寸 |
この書で、ようやく「歌意」をいう
「恋に沈みて」...いい表現だと思う
袖ばかり濡れて...「露わけ衣なら、濡れるのもわかるが」
それも着ていないのに、涙で乾く時もない |
| 戀に沈みて、袖のみぬれて乾かぬとの意也。露わけ衣ならば、ぬるゝも理りならんを、それを着もせぬに涙にぬれてひる時もなきと也。山わけ衣など共讀めり。一本、不着爾と有。爾の字あるを爲是 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
| |
夏草乃、露別衣[ツユワケシキヌ]、 今本つゆわけごろもと訓るは誤なり末の句に衣手とさへあれば訓のあやまりをおもへ(奥人按に此歌三句にきもせぬにとあれば今本のまゝに露わけごろもとよむぞよろしつゆわけしきぬと訓てはきこえがたくおもはる)
不著爾[キモセヌニ]我衣手乃、干[ヒル]時毛/名寸[ナキ]
|
「つゆわけしきぬ」と、一語ではなく「衣」を修飾する語として訓んでいる
|
| 歌意記なし |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
| |
〔なつくさの。つゆわけごろも。きせなくに。わがころもでの。ひるときもなき。 〕
夏草乃。露別衣。不著爾。我衣手乃。干時毛名寸。 |
「きせなくに」、他動詞サ行下二段「着(き)す」の解釈
千蔭のいう「古言」とは、何だろう
普通の活用で解釈も可能なのに...
巻第四の「けせる」と引用しながら、「けせる」と訓まないのは
それも解らない
おそらく、その引用では「せ」を説明したものだろう
|
露を分けたる衣なり。キセナクニのセは、老イセヌ、絶エセヌなどのセに等しく古言なり。卷四、吾せこが盖世流[ケセル]衣など詠めり。
參考 ○露別衣(考・新)ツユワケシキヌ(古)略に同じ ○不著爾(考)キモセヌニ(古)ケセナクニ(新)キタラヌニ。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
| |
〔ナツクサノ。ツユワケコロモ。ケセナクニ。アガコロモテノ。ヒルトキモナキ。〕
夏草乃露別衣不著爾我衣手乃干時毛名寸
|
千蔭と同じ巻第四の語句を引用して、ここでは「けせる」とする
「何故に私の袖がこんなにも濡れているのか」
乾く間もなく、涙の流れる哀しさ... |
露別衣[ツユワケコロモ]は、契冲云、たゞ露をわけゆく衣なり、古今集に、山分衣[ヤマワケコロモ]とよめるとおなじこゝろにて、かれはおこなひ人の衣と聞ゆれば、すこしかはれり、
○不著爾、は、ケセナクニと訓べし、著てあらぬことなるをと云むが如し、四(ノ)卷に、吾背子之蓋世流衣之[ワガセコガケセルコロモノ]、十六に、伊呂雞[イロケ]奮本雅に誤、世流菅笠小笠[セルスガカサヲカサ]云々、古事記中(ノ)卷倭建命(ノ)御歌に、那賀祁勢流意須比能須蘇爾[ナガケセルオスヒノスソニ]云々、美夜受比賣(ノ)歌に、和賀祁勢流意須比能須蘇爾[ワガケセルオスヒノスソニ]云々、などあり、
○歌(ノ)意は、雞夏草の露分衣を取着たらば、さもあるべきことなるを其(ノ)露分衣を着てもあらぬことなるを、何故に、吾(カ)袖の乾間もなく沾たるらむ、げにさりとはつよき涙ぞとなり、
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
| |
〔夏草の露別衣[ツユワケシキヌ]不著爾[キタラヌニ]わが衣手のひる時もなき 〕
夏草乃露別衣不著爾我衣手乃干時毛名寸 |
契沖と同じように「山分け衣」を解釈しながら
ここでは、真淵のように、その衣の意味の方で訓をつけた
千蔭の「古言」に噛み付く
雅澄には、そもそも「けせる」という用法が適切でない、とし
「著」の下に「有」を補って訓んだようだ
|
第二句を從來ツユワケゴロモとよみたれどさてはナツ草ノといふこと衣までかかるが上に、かの古今集雜上なる
きよ瀧の瀬々のしらいとくりためて山わけ衣おりて著ましを
の山別衣の如く露を分くる料に特製したる衣をいへるなりともおぼえねば訓を改めてツユワケシキヌとよむべし
○第三句を舊訓にキモセヌニとよみ略解にキセナクニとよみて
キセナクニのセは老セヌ、タエセヌなどのセにひとしく古言なり
といへれどオイヌ、タエヌは自動詞にて上に承くる語なければ連用格を變じて名詞としてオイセヌ、タエセヌといふべけれど、キヌは他動詞にてこゝにては衣を承けたればキを名詞としてキセヌといふべからざる上に、キセヌといはば不令著とまぎれぬべし。又古義にはケセナクニとよみたれどキルをケスといふは人の上にいふことなり。案ずるに不著爾はキタラヌニとよむべし。或は著の下に有の字ありしをおとせるか
|
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| |
夏草の露分け衣/著[ケ]らなくに、我が衣手の干[ヒ]る時もなき |
歌意、特筆ナシ |
| |
夏草の露を分けた、著物を著てるといふ訣ではないのに、自分の袖は、乾く間もないことだ。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
| |
〔夏草の 露別衣 つけなくに 吾が衣手の ひる時もなき〕
ナツグサノ ツユワケゴロモ ツケナクニ ワガコロモデノ ヒルトキモナキ
夏草乃露別衣不著爾我衣手乃千時毛名寸 |
岩波書店の「新訓万葉集」(1927年)より、この訓が定着している
ただ、「着る」という単純な意味だけを考えれば、
「着る」「着す」の方がいいと思う
他動詞カ行下二段「着く」には、多くの意味もあり、その意味合いの幅は広いので...「着る」「着す」のが素直に読める
どうして「つく」に拘ったのだろう
|
夏草ノ茂ツタ中ノ露ヲ別ケテ行ケバ、着物ハ濡レルモノダガ、ワタシハ夏草ノ露ノ中ヲ別ケテ通ツタ着物ハ着テモヰナイノニ、ワタシノ着物ノ袖ハ乾ク間モアリマセヌ。コレハ皆ワタシガ、アナタヲ戀シク思ツテ流シタ涙デス。
○露別衣[ツユワケゴロモ]――夏草の露を押し分けて行く衣の意である。新考にツユワケシキヌとよんだのは考によつたものか。從ひ難い。
○不著爾[ツケナクニ]――舊訓キモセヌニとあるのは俗調でおもしろくない。略解にキセナクニとよんで「きせなくにのせは、老せぬ、絶せぬなどのせにひとしく古言なり。卷四、吾せこが蓋世流[ケセル]衣など詠めり」と言つてゐる。ケセルのセは敬語のスで四段活用であるから、これとは異なつてゐる。ここは新訓に從つてツケナクニと訓むことにした。
〔評〕 夏草の露分衣は優雅な詞である。これと吾が衣と對比して、おのづから譬喩になつてゐるのがおもしろい。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
| |
〔夏草の 露分け衣 著けなくに、わが衣手の 干る時もなき。〕
ナツクサノ ツユワケゴロモ ツケナクニ ワガコロモデノ フルトキモナキ
夏草乃露別衣不著尓我衣手乃干時毛名寸 |
結句を「ふるときもなき」と訓むのは、この辺りからだろうか
上代語としての訓を採っている |
【譯】夏草の露を分けて行く著物を著たのではないが、わたしの著物のかわく時が無い。
【釋】露別衣 ツユワケゴロモ。草葉の露を分けて行く衣服。
干時毛名寸 フルトキモナキ。フルは、動詞乾ル。上二段活でフルの形となる。涙でかわく時がないのである。
【評語】上三句の敍述が美しい。涙でかわく時がないという平凡な内容が、これで生きて感じられる。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
| |
〔夏草の露分衣著けなくに我が衣手の干る時もなき〕
ナツクサノ ツユワケゴロモ ツケナクニ ワガコロモデノ ヒルトキモナキ
夏草乃露別衣不著爾我衣手乃干時毛名寸 |
この「作意」の評は、あまりいいとは思わない
涙の乾かぬことを、「露分衣」であらわしただけ、と言うが
「露分衣」が、万葉集中の唯一の用例であり
決して有り触れた表現でないことから
この評は、理解出来ない |
【大意】夏草の中に着る露分衣も着ないのに、吾が衣の袖は乾く時もない。
【語釈】ツユワケゴロモ 草の露を分けて行く時、露よけに着る衣と見える。山の篶を分ける時に、山伏の着る、スズカケの如き次第と見える。
【作意】涙の乾かぬことを、露分衣を用ゐてあらはしただけである。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
| |
〔夏草の 露わけ衣 着けなくに 我が衣手の 干る時もなき〕
ナツクサノ ツユワケコロモ ツケナクニ ワガコロモデノ フルトキモナキ
夏草乃露別衣不著尓我衣手乃干時毛名寸 (『類聚古集』) |
歌意については、どの書も違うことはないが、
訓にこれほどの異訓があるとは、思わなかった
この「つく」のしても、それに見合う「語」を用例として引用したもので
他の訓でも、千蔭や雅澄が言うような「用例」を持ち出せば
この書の解釈だけが正しいとは言えない
何が正しいのか、ではなく
こんな風にも訓める、程度の受止め方をしたい
ただ、「つく」と訓むと...その語意解釈には曖昧さも残る |
【口訳】夏草の露を分けてゆく着物を着てはゐないに、私の着物の袖の乾く時もないことよ。
【訓釈】露わけ衣―夏草の露をわけてゆく着物で、露にぬれた着物である。
着けなくに―旧訓キモセヌニ、略解キセナクニ、新訓にツケナクニとした。「身著而(ミニツケテ)」(三・三三六)、「靑衿著(アヲクビツケ)」(九・一八〇七)などによる。身に著けないものを、の意。
干る時もなき―旧訓ヒルを新校にフルと改めた。上代は上二段(二・一五九)。君を戀ふる涙に乾く間が無いのである。上に係助詞のない連体形で止めた(二・一〇五)。従って上は「は」の助詞でなく「の」を用ゐた。
【考】古今六帖(五「夏衣」)「着もせぬに」「かわくときなき」、赤人集「またきぬにわがころもてに(ハ)ひりよしもなし」、流布本「きもせぬに我衣手のひるよしもなき」、柿本集「きぬものをなど我袖のかわく時なき」、新古今集(十五)「きもせぬに」下句柿本集と同じく、人麿とある。
|
|
|

| |
| 「わがそでひめや」...きみにあはずして... |
| |
| 『あめのこころ』 |
| 【歌意1999】 |
みなづきの強い陽射しのように、大地を焦がし裂けさせるときも
私の衣の袖は、乾くことがあるでしょうか、
あなたを戀しく思うこの気持ちで、涙で止め処もなく袖を濡らします
あなたにお逢いもできなくて... |
| |
| |
結句の「逢わないで」では、これほどの表現にはならない
やはり「逢うことが出来ないので」として初めて、その激しい哀しみの表現に合う
歌意としては、あまりにも解り易く、下手に「他の想い」を挟める余地もない
しかし、この表現が、ありきたりの慣用句的なものなのか
あるいは、作者のそれほどまでに激しい想いをいう手段として必要だったのか...
私には、このような表現では、かえって実感から遠ざかるもののように思えてならない
この数日、この歌に拘ってしまったのも
当初は、いかにも、という簡潔な解釈でもできると思ったものだが、
下段資料の澤潟久孝『万葉集注釈』を読んでいて、そこで出合った一冊の書
そのお陰で、じっくりかみ締めるようにこの歌を読み直してみた
「堤中納言物語」
私が、初めてこの書に触れたのは、もう二十年も前のことだ
山の友人が夢中になって読んでいたもので、その後に、それこそ「お前も読め」と
置いていった一冊の文庫本が、それだった
当時、万葉集と古代史を絡めて接していた「古典」だったので、
いわゆる「古典文学」そのものにはあまり興味もなかった
何となく読んではみたものの、まさに古典授業が苦手だった高校時代を思い出さされ
本気では読めなかった
ただ、この短編集の「虫愛づる姫君」が、やけに印象に残ったことは覚えていた
そして、この本のタイトルも、何故か決して忘れることはなかった
今回、『注釈』の中で、この本の一篇「逢坂越えぬ権中納言」に、
この掲題歌の「つちさへさけててるひにも」の表現があることを知り
どうしても、また読みたくなった
勿論、どんな情況で使われた語句なのか、そちらの興味の方が強かったことは確かだ
有り触れてはいない表現だとは思う
しかし、これほどの表現を、どんな「窮極」の環境下で使うのか
また、この掲題歌の歌意解釈にも参考になるかと思って...
ところが、そんな思いとは別に、つい読み耽った
私が、万葉集以外の「古典」を、本気で読み耽ったのは、
あまり記憶がない
「古典文学」そのものを、ようやく味わう気分になれた、そうなのかもしれない
全十篇の感想はここでは書くこともないが
簡単に、この書の意義を述べなければ、と思う
今から千年も前の時代、こうした短編集があったということの驚き
しかも、その内容が決して現代の感覚で陳腐なものではなく
人の心の「有様」を、素直に受け入れられた驚き
現代でもそうだが、長編物よりも短編の作品の方が、はるかに難しい
一語の無駄も厳しく吟味されてしまう
「物語」の内容だけではなく、文体やその主旨の簡潔であるが故の強靭さが必要だ
勿論、私は国文学者でも、その学究の者でもなく
単なる「万葉集ファン」、敢えて言えば「古語ファン」で、専門の知識など全くない
検証の方法論も知らない
ただ、心に響くかどうか...それを拠り所にしている
そのためには、押し付けの解釈ではなく、自分で語義は調べる
だから、多くの勘違いや、解釈不足はあるはずだ
それは、また時を経て、自分の感じ方に影響を与えるものだろうから
その時に、素直にまた感じればいい
そんな姿勢なので、言ってみれば、好きなように感じ、また書ける
この「堤中納言物語」の「逢坂越えぬ権中納言」
その舞台情況で、何故この掲題歌のような、あんな激しい語句が使われたのだろう
原文と現代語訳は、下段に載せたが、
どうして、この激しい語句が使われたのか、中々理解出来ない
タイミングは理解出来る
そして、多くの書にあるように、万葉歌にこんな表現がある、などというような引用ではない
唐突に、「つきさへわれててる日にも、袖ほすよな/\おぼしくづをるゝ」と出現する
「つき」という出だしが、原文引用の誤りかどうか、解らないが、紛れもなく「礼記月令」だ
どんなに逢うことを申し出ても、拒絶され
「文」の返事さえ来ない
立派な家柄に育ち、叶うものは何でも出来る「権中納言」
しかし、この恋してしまった「姫」には、何も出来ない
日々その想いを繰り返し思うことで、ついに決意する
その場面で使われた、この語句
暑い夏が来る、という時期を明かした後にすぐ...
ならば、とてつもないほどの「決意」でなければ、と誰もが想像する
この語句の役目は、そこまでのような気がする
確かに、それまでの権中納言とは違って、その取った行動は、大胆だった
しかし、私にはそこからの展開も面白く、つい本題を忘れてしまった
あまりの頑なな姫宮の反応...決して心を開かず
ただただ怯えている姿に、権中納言は、なすすべもなく
結局せっかくの決意も自ら放棄し、ただただ姫宮を安心させることだけに苦心する
言い訳、黙して見詰め合うだけ、その繰り返し...
最後の一文、
「うらむべき、かたこそなけれ、夏衣、うすきへだての、つれなきやなぞ」
こんな終り方など、私の乏しい知識では、想像もしていなかった
[誰も恨むことはできない 薄い夏衣の隔て一枚も越せないのなぜだ 私は...何もできない]
この結末に至る「程度」と、問題の「語句」との開きは大き過ぎる
辛く言えば、この「語句」は「慣用句的」な使い方でしかなかったのでは、と思う
漢籍の「文章」は、そのまま多くの「慣用句的」な使われ方をしている
ただ、表現が大きく、その背景が最上級の場合だと、
その表現に続き「期待」もまた大きくなる
それに見合うこの表現なのかどうか...
鹿持雅澄の『万葉集古義』
この解釈も興味を引く
一般には上三句で、一つの意味を持つ表現と解釈するが
この『古義』では、「みなづきの」が、それぞれ第二句と第三句に掛かるような感じもする
酷暑で、照りつける太陽のせいで大地が乾き裂ける、というのではなく
たとえ大地が裂けようと、またどんなに暑い日であろうと、と並列的だ
しかし、程度の軽いものを後半に置くはずもないか...これは私の考え過ぎだ
でも、「つちさへさけて てるひにも」が、慣用的な表現だったら
その軽重の判断は、私には出来ない
もっと違った、訳し方があるのかもしれない
|
|
掲載日:2014.04.23.
| |
| 夏相聞 寄日 |
| 六月之 地副割而 照日尓毛 吾袖将乾哉 於君不相四手 |
| 六月の地さへ裂けて照る日にも我が袖干めや君に逢はずして |
| みなづきの つちさへさけて てるひにも わがそでひめや きみにあはずして |
| 巻第十 1999 夏相聞 寄日 作者不詳 |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】〔73・407・74〕
【赤人集】〔268〕
【古今和歌六帖】〔107・274〕
【拾遺和歌集】〔825〕
[古注釈書引用歌]
【二条院讃岐集】〔51〕[万葉考]
[類想歌]
【万葉集巻第十ニ】〔2868〕
[歌物語]
【堤中納言物語】〔逢坂越えぬ権中納言〕
[資料]
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
| 【1999】 語義 意味・活用・接続 |
| みなづきの [六月之] |
| みなづき [水無月・六月] |
陰暦六月の称 |
| つちさへさけて [地副割而] |
| つち [土・地] |
大地・地上・土の上・土くれ |
| さへ [副助詞] |
[添加] ~までも |
| 〔接続〕体言・活用語の連体、連用形・助詞などにつく |
| さけ [割く・裂く] |
[自カ下二・連用形] 割れる・裂ける・切れて分かれる |
| て [接続助詞] |
[補足(状態)] ~のさまで・~の状態で |
連用形につく |
| てるひにも [照日尓毛] |
| てる [照る] |
[自ラ四・連体形] 光を放つ・輝く・美しく輝く |
| わがそでひめや [吾袖将乾哉] |
| ひ [干る・乾る] |
[自ハ上一・未然形] 乾く・水が少なくなる |
| め [助動詞・む] |
[推量・已然形] ~だろう |
未然形につく |
| や [終助詞] |
[反語] ~(だろう)は(いや、~ない) |
已然形につく |
| きみにあはずして [於君不相四手] |
| して [接続助詞] |
[「ずして」の形になる場合] ~(ない)で・~(なく)て |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [みなづき] |
陰暦では、四・五・六月の三ヶ月が夏で、
「土用・大暑」を含む六月は最も暑い時期だとされる
「水無月(みなづき)」という表記は、そのイメージからであり、それを訓んだもの
と、素人にも解る...多分 |
| |
| [つちさへさけて てるひにも わがそでひめや] |
下段資料で採り上げた、契沖『代匠記(精撰本)』に、礼記月令の、
「仲冬(ノ)之月、冰益々壯也、地始坼」をあげ
「痛ク日ノ照ニモ、痛ク寒キニモ、地ハ裂ルナリ」とし、
その過酷さの表現を利用しているようだ
『礼記(らいき)』の「月令」とは、全四十九篇の第六番で、
一年十二月の年中行事と天文や暦について論じたもの、とある
また、この篇の作者については、
秦の呂不韋が編纂させた『呂氏春秋』十二紀とほぼ同内容で、
『呂氏春秋』を引き写したものとされている
それはともかく、この表現が、
私にとっては、思わぬところへの「寄り道」になってしまった
「つきさへわれて照る日にも、袖ほすよなよなおぼしくづをるゝ」
このことを知ったのは、下段資料の澤潟久孝『万葉集注釈』だが
そこには、ただ「堤中納言物語『逢坂こえぬ権中納言』」にこの表現がある、とだけあった
だから、どうしても、その箇所がどんな情況で書かれているのか知りたくなって...
結局、読み通してしまった
そこでの表現は、大地も裂けるほどの「日照り」でも、
決して乾くことのない涙に濡れる袖...
では、その表現がどの程度の度合なのか...解釈にとても役立った
左頁に載せる
|
| |
| [てる] |
この語を一般的に訓み、その語義を浮かべると、
どうしても、この歌の歌意のような「過酷な暑さ」のイメージにはならない
この『万葉集』中での、「照る」は、
むしろ「美しい輝き」のような使い方が、多いのではないかと思う
| |
| 春の苑 紅にほふ桃の花 下照る道に 出で立つをとめ |
| 既出 [万葉の植物Ⅰ] 巻第十九 4163 |
| 見渡せば 向かつ峰(を)の上の 花にほひ 照りて立てるは 愛(は)しき誰(た)が妻 |
| 巻第二十 4421 |
これらの歌など、「下照る・照る」が美しく輝く意で用いられている
『記紀』に登場する天稚彦(あめわかひこ)の妃は「下照(したでる)姫」という
この掲題歌を、大地も干からびて裂けるような過酷な暑さでも、と譬えるのなら
そして、敢えて「照る」を使うのなら、「てりはたたく」という表現が合うと思った
その自動詞カ行四段動詞「てりはたたく(照り霹靂く)」は、
「日光が強く照りつけたり、雷鳴がとどろいたりする」という意味だ
しかし、それも違う、とやはり思い直した
確かに「酷暑」をいう表現で「照る」は気になったが
それは「つちさへさけて」という表現で充分だし、
涙で袖も乾かない、というのであれば「照る日」が「シニカルな象徴」表現のようにも思える
この「日」は勿論「太陽の」ことだが...それでも「涙が...」というような
|
| |
| [ひ] |
| この上一段動詞「ひる」は、昨日付け(22日)の、上代の上二段動詞「干(ふ)・乾(ふ)」と同じ |
| |
 |
| |
[類想歌]
【万葉集巻第十ニ 2868】
| 寄物陳思 |
菅根之 惻隠々々 照日 乾哉吾袖 於妹不相為
|
| 菅の根のねもころごろに照る日にも干めや我が袖妹に逢はずして |
| すがのねの ねもころごろに てるひにも ひめやわがそで いもにあはずして |
| 巻第十ニ 寄物陳思 2868 柿本人麻呂歌集出 |
〔語義〕
「すがのねの」は、「ねもころ」に掛かる〔枕詞〕
「ねもころごろ」は、こまやかに行き届くさま、の意の「ねもころ」の、
「ころ」を重ねた語で、「心をこめてするさま」
下三句、掲題歌参照
|
〔歌意〕
菅の根のように、こまやかに充分照る太陽の日にも、
乾くことがあるでしょうか、私の袖は...
妻に会うこともなくて... |
この類想歌の下三句は、ほとんど掲題歌と同じものだ
しかし、その「涙」の深さは、掲題歌の比ではない
掲題歌が、「酷暑」を最大限の表現で詠っているのに対して
この類想歌では、「酷暑」ではなく、一般的な「照る太陽」としか感じない
しかも、「つちさけて」に対応する「ねもころごろ」では、
ひょっとすると、違った情況を醸し出すのかもしれない、とも思ってしまう
|
| |
[古注釈書引用歌]
『万葉考』
【二条院讃岐集(成立不詳、作、二条院讃岐[1141~1217頃])】
|
| 我が袖はしほひにみえぬおきのいしの人こそしらねかわくまぞなき |
| 新編国歌大観第四巻- 12 [書陵部蔵五一一・二一] いしによするこひ 51 |
〔歌意〕[角川文庫、島津忠夫訳注「百人一首」]
あのお方のことを思って忍び音に泣き濡らす私の袖は、
潮干の時にも見えない沖の石のように、人は知らないでしょうが、
乾くひまとてございません |
この歌、掲題歌との関連は、真淵が比較して優劣をつけたことで知り得たが
私には、真淵のいうような「かざりたくみ」でも「意浅く」とは思わない
そもそも、優劣をつける「土俵」が違う
作者の二条院讃岐は、万葉の時代から四百年以上も後の人だ
更に言えば、その二条院讃岐から、真淵の時代まで、五百年以上も時を経ている
当然、その時代の「感性」というものがある
同じ歌集の中での比較、あるいは同時代での比較には意味があるだろうが
これほど時を経ていれば、何を基準に優劣をゆのだろう
この歌、『千載集』、定家の『八代抄』、
そして『百人一首』の基のなったと言われる『百人秀歌』にも収載されている
私も、いい歌だと思う |
|
|
| 掲題歌[1999]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】
| 新編私家集大成第一巻-2 人麿Ⅰ 柿本人丸集[書陵部蔵「歌仙集」五一一・二] |
みなつきのつちさへわれててる日にも 我袖ひめや妹にあはすして
|
| 柿本人丸集下 73 |
| 同第一巻-3 人麿Ⅱ 柿本集[書陵部蔵五〇一・四七] |
| みな月のつちさへさけててる日にも わか袖ひめやいもにあはすて |
| 柿本集 たひの歌 [拾遺和歌集] 407 |
| 新編国歌大観第三巻-1 人丸集[書陵部蔵五〇六・八] |
| みな月のつちさへさけててる日にも我が袖ひめやいもにあはずて |
| 柿本集下 74 |
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
|
みなづきのつちさへさけててる日にもわがそでひめやいもにあはずして
このうた人丸集にあり |
| 新編国歌大観第三巻-2 赤人集[西本願寺蔵三十六人集] 日によす 268 |
【古今和歌六帖 ([永延元年(987年)頃]撰、兼明親王・源順か】
| 新編国歌大観第二巻4 [宮内庁書陵部蔵五一〇・三四] |
| みな月のつちさへわれて照る日にも我が袖ひめやいもにあはずて |
| 第一 歳時部 夏 みな月 107 人丸或本 |
| つくばねの雲けふまでにてるひにもわが袖ひめやいもにあふまで |
| (類歌) 第一 歳時部 天 てる日 274 |
【拾遺和歌集 ([寛弘四年(1007年)頃]撰、藤原公任 [966~1041]か)】
|
| みな月のつちさへさけててる日にもわがそでひめやいもにあはずして |
| 新編国歌大観第一巻3 [京都大学附属図書館蔵本]巻第十三 恋三 よみ人しらず 825 |
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「六月之地副割而照日爾毛吾袖将乾哉於君不相四手」
「ミナツキノ ツチサヘサケテ テルヒニモ ワカソテヒヌヤ キミニアハスシテ」(「【】」は編集、歌番は旧) |
〔本文〕頭注に、『類聚古集』、本文ノ下ニ小字「無作者」アリ。
赤人集「日によす みなつきのつちさへさけててる日にもわかそてひめやいもにあはすして このうた人丸集にあり」
|
| 「爾」 |
『神田本』「出」 |
| 「乾」 |
『活字無訓本』「朝」 |
| 〔訓〕 |
| ワカソテヒヌヤ |
『元暦校本・類聚古集』「わかそてひめや」
『神田本・温故堂本・大矢本・神宮文庫本』「ワカソテヒメヤ」 |
| キミニ |
『元暦校本』「きみ」ノ右ニ赭「イモ」アリ
『類聚古集』「いもに」
『神田本』「イモニ」。漢字ノ左ニ「キミニ」アリ |
| 〔諸説〕 |
| ○ナシ |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1999] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
| |
〔みなつきのつちさへさけててる日にもわかそてひめやきみにあはすして 〕
六月之地副割而照日尓毛吾袖将乾哉於君不相四手
|
歌意は明瞭、拾遺集に入集している |
| みなつきのつちさへ 心は明也拾遺集に入 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
| |
〔ミナツキノツチサヘサケテテルヒニモワカソテヒメヤキミニアハスシテ〕
六月之地副割而照日爾毛吾袖將乾哉於君不相四手 |
禮記の表現の引用を指摘
結句の「於君」が、他の収載歌集では「いもに」という
この『代匠記』、この歌で巻十上を終える
元禄三年(1690) |
禮記月令云、[仲冬(ノ)之月、冰益々壯也、地始坼]痛く日の照にも痛く寒きにも地は裂るなり、於君を拾遺人丸集六帖並にいもにとあり、
萬葉集代匠記卷之十上
元禄三年三月廿二日抄之畢
|
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
| |
〔みなづきの、つちさへさけて、てる日にも、わがそでひめや、きみにあはずして 〕
六月之地副割而照日爾毛吾袖將乾哉於君不相四手 |
ここも「礼記月令」を引用し、「それ程に照る日」でも」とする
そして「戀侘ぶる事の甚だ切ないこと」を言う、と
或抄では、「てにをは」「を」に「於」を用いることが万葉集では多い、というが、どれも「に」と用いている、という |
| いたく照る日には、土乾きて割れ裂くる也。禮紀月令、仲冬之月冰益壯也、地始拆。寒天炎天共に到て盛なれば地裂くる也。それ程に照る日にも、思ふ人に逢はでは、袖のひる事あらんやと、戀佗ぶる事の甚切なる事を云へる也。於君と書きて、君にと讀ませたるをもて、於の字を上に据ゑて、にと讀ませたる證と知るべし。或抄に、手爾乎波のをに於を用ふる事當集にありと注せるは不考の義也。皆にと用ひたる也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
| |
〔六月之、地副割而[ツチサヘサケテ]、照日爾毛、吾袖/將乾哉[ヒメヤ]、於君不相四手[キミニアハズシテ、〕
|
前歌〔1998〕とともに、恋の涙に溢れる詠うものだ、とする、
何の工夫も凝らさずやり遂げられており、それでいて意は深い
後の世に
わが袖は汐千に見えぬ沖の石の人こそしらねかわく間もなし
という歌があり、とてもいい歌なのだが、この二首に比べると
巧みな表現を凝らしているが、その意は浅く、「心」がないことを見よ、という
この後の世の歌とは、二条院讃岐集51番の歌のことだろう、
その歌、定家の『百人秀歌』の一首94番にも撰されており、
決して平凡な歌ではない、と思うのだが、真淵は、万葉歌より
「浅い」とする
|
| 上の歌も、此歌もともに戀あまれる涙をよめれど何にたくめる事もなくとほりてあらはにして然も意はふかし後の世に「わが袖は汐千に見えぬ沖の石の人こそしらねかわく間もなし」てふは其頃の歌にはあらはにかくれたる事なくよき歌なるを此二歌にくらべてはかざりてたくみたればいともたがひて意あさくまことなきを見よ
|
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
| |
〔みなづきの。つちさへさけて。てるひにも。わがそでひめや。きみにあはずして。 〕
六月之。地副割而。照日爾毛。吾袖將乾哉。於君不相四手。 |
注釈なし
|
| みなづきの。つちさへさけて。てるひにも。わがそでひめや。きみにあはずして。月の名の事は、考の別記に委し。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
| |
〔ミナツキノ。ツチサヘサケテ。テルヒニモ。アガソデヒメヤ。キミニアハズシテ。〕
六月之地副割而照日爾毛吾袖將乾哉於君不相四手
|
あなたに飽きたなら、涙も止ろうが、何にもまして恋しや恋しや、と思えば、たとえ大地が引き裂かれ、六月の強い陽射しがあろうと、この涙に濡れる袖は、決して乾くこともないでしょう
(六帖には、結句「妹に逢わずて、とある)
六帖に限らず、古歌集では「妹に」となっている
歌意解釈、いい |
歌(ノ)意は、君にあひたらば涙もとゞまりて、おのづから乾[ヒ]もすべきなれど、君にあはずしては、他事なく戀しや戀しやと思へば、たとひ地さへ割裂[フレケ]て、つよく照六月の日影にほすとも、この涙にいみじく沾漬りたる吾(カ)袖は、乾はすまじとなり、(六帖には、終句、妹にあはずてとあり、)、
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
| |
〔みな月のつちさへさけててる日にも吾袖ひめや君にあはずして 〕
六月之地副割而照日爾毛吾袖將乾哉於君不相四手 |
注釈なし |
| 注釈なし |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| |
水無月の地[ツチ]さへ裂けて照る日にも、我が袖干めや。君に逢はずして |
歌意に特筆なし |
| |
六月の地さへも裂けて了ふ迄に、照つてゐる暑い日光にも、自分の袖は乾きさうではない。戀しい方に逢はずに、泣いてゐるので。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
| |
〔六月の 地さへ割けて 照る日にも 吾が袖ひめや 君に逢はずして〕
ミナヅキノ ツチサヘサケテ テルヒニモ ワガソデヒメヤ キミニアハズシテ
六月之地副割而照日爾毛吾袖將乾哉於君不相四手 |
「地さへ割けて」という表現は、この歌集ならでは、という
確かに漢籍からの引用だが、最上級の比喩を用いたのでは
他の表現が、どれもかすみはしないか
力強い、という評価...この表現のなせることだ
|
六月頃ノ日光ハ實ニ強クテ何デモ乾カスガ、地サヘ裂ケルヤウナ強イ六月ノ日光ニモ、アナタニオ目干カカラナイデハ、ワタシノ袖ハ乾キハシマセヌ。私ハアナタヲ思ツテ絶エズ泣イテヰルカラ、私ノ袖ハイツデモ乾きマセヌ。
〔評〕 力強い歌だ。地さへ裂けて照る日といふ語は、類のない珍らしいもので、雄勁な内容と調子とはこの集でなくては見られないものである。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
| |
〔六月の 地さへ割けて 照る日にも、わが袖乾めや。君に逢はずして。〕
ミナツキノ ツチサヘサケテ テルヒニモ ワガソデヒメヤ キミニアハズシテ
六月之地副割而照日尓毛吾袖將乾哉於君不相四手 |
特筆なし |
【譯】六月の土までも裂けて照る日にも、わたしの袖はかわかないでしょう。君に逢わないでは。
【釋】地副割而 ツチサヘサケテ、かわき切つて土地の裂けることを敍して、照る日を説明している。
【評語】上三句の烈日の敍述が強いひびきを持つている。これも、この三句で生きている作である。夏の烈日を歌つた歌として、集中珍しい作品である。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
| |
〔みな月の地さへ裂けて照る日にも吾が袖乾めや君に会はずして〕
ミナツキノ ツチサヘサケテ テルヒニモ ワガソデヒメヤ キミニアハズシテ
六月之地副割而照日尓毛吾袖將乾哉於君不相四手 |
「常識的」という
詠い方の直接的、というのが解らない
これほどの比喩は、直接では譬えられないものだ
あまりにも壮大になると、空虚さも感じてしまう
「常識的」というのは、そのことかもしれない |
【大意】六月の地までも裂けて強く照る日にも、吾が袖は乾かうか、乾きはしない。君に会はないで居て。
【作意】歌ひ方は直接であるが、常識的である。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
| |
〔六月の 地さへ裂けて 照る日にも 吾が袖干めや 君にあはずして〕
ミナヅキノ ツチサヘサケテ テルヒニモ ワガソデヒメヤ キミニアハズシテ
六月之地副割而照日尓毛吾袖將乾哉於君不相四手(『元暦校本』) |
「裂けて照る」と、「霜ふりて寒き」は、大きな違いがあると思う
「裂けるほどに強烈に照る」は、決して「裂けはしないが、そんな想像を絶する」というような気宇壮大な感覚だが、
「霜ふりて寒き」は、実際に肌で感じる「「霜の降る朝の厳しい寒さ」
それは、想像ではなく、体験していることを思い出させる表現だ
多くの「古歌集」に「妹に」と表現されているのは、オリジナルがそうだったからなのだと思う
「妹」を「君」にするのは、ひょっとすると万葉集の編纂時のことかもしれない
しかし、この歌の表現では、男がいいかねない気もするが
「君」になったことで、「女の切ない歌」になり、その表現とのギャップが大き過ぎる
「堤中納言物語」、この書のせいで、読み通してしまった |
【口訳】六月の、大地まで裂けるやうに照る日にも、私の袖は乾きませうか。君に逢はないで。【訓釈】六月の―「六月」夏をミナヅキと訓むこと前(三・三二〇)に述べた。
地さへ裂けて照る日にも―「裂けて照る」は「霜ふりて寒き」(一・六四)といふのと同じ云ひ方で、裂けるやうに、裂けるばかりに、強く照る、の意である。
【考】赤人集に結句「いもにあはずして」「このうた人丸集にあり」とある。柿本集(下)には「いもにみえずて」、同群書類従本と古今六帖(一「みな月」)とに「妹に逢はずて」とあり、後者人丸とあり、同書(一「てる日」)に「筑波ねの岩もとどろに」[妹に逢はずて」とあり、拾遺集(十三)―抄にも―「妹に逢はずして」とある。堤中納言物語(逢坂こえぬ権中納言)に「地さへ割れて照る日にも、袖ほすよなよな思しくづほるゝ」とある。
|
【堤中納言物語 堤中納言物語[京都大学附属図書館所蔵 『伴信友校蔵書』]】
| 逢坂越えぬ権中納言 [天喜三年(1055年)、小式部] [作者、成立年代ともに解っていないが、十篇の短編集の中で、唯一作者と成立年代が確認されている] |
| 伝本[京都大学附属図書館所蔵 『伴信友校蔵書』]原文 |
現代語訳 「平安古典を優しく楽しく」の[綺羅拾遺]のサイトより拝借
忠実な原文解釈ではない、とのことだが、素敵な解釈だと思い、
古典の苦手な私には、とても魅力的な解釈と感じた |
五月まちつけたる花橘のかも、むかしの人こひしう、秋のゆふべにおとらぬかぜに、
うちにほひたるは、をかしうも、あはれにも、思ひしらるゝを、
やまほとゝぎすもさとなれてかたらふに、三日月のかげほのかなるは、
をかしうしのびがたくて、れいのみやわたりに、おとなはまほしうおぼさるれど、
かひあらじとうちなげかれてあるわたりのなほなさけあまりぬるまでとおぼせど、
そなたはものうきなるべし、いかにせんと、ながめ給ほどに、
うちに御あそびはじまるをたゞいままゐらせ給へとて、くら人の少將參り給へり、
またせ給ふをなどそゝのかしきこゆれば、ものうながらくるまさしよせよなどの給ふを、
少將いみじうふさはぬ御けしきのさふらふは、たのめさせ給へるかたの、
うらみ申べきにやと聞ゆれば、かばかりあやしき身を、うらめしきまで思ふ人は、
たれかなどいひかはしてまゐり給ぬ、ことふえなどとりちらして、
しらべまうけてまたせ給ふなりけり、
ほどなき月もかくれけるを、ほしのひかりにあそばせ給、
このかたつきなくてむ上人などはねぶたげにうちあくびつゝ、
すさましけなるぞわりなき、御あそびはてゝ、
中納言中宮の御かたにさしのぞき給へれば、わかき人々こゝちよげにうちわらひつゝ、
いみじきかた人參らせ給へり、あれをこそなどいへば、
なにごとせさせ給ふぞとの給へば、あさてねあはせし侍るを、
いづかたにはよるらむとおぼしめすと聞ゆれば、あやめもしらぬ身なれども、
ひきとり給はんかたにこそはとのたまへば、あやめもしらせ給はざなれば、
みぎにはふようにこそはさらばこなたにとて、こざい將のきみおしとり聞えさせつれば、
御心もよるにや、かうおほせらるゝをりも侍けるはとて、にくからずうちわらひて、
いで給ぬるを、れいのつれなき御けしきこそわびしけれ、かゝるをりは、
うちもみだれ給へかしとぞみゆる、みきの人さらばこなたには、
三位中將をよせ奉らんといひて、殿上によびにやりきこえて、かゝる事の侍るを、
こなたによらせ給へとたのみ聞ゆると、
きこえさすれはことににも侍らぬ心のおよばむかぎりこそはとたのもしうの給ふを、
さればこそこの御心は、
そこひしらぬ恋ぢにもおりたち給なんと、かたみにうらやむも、宮はをかしきかこせ給、中納言さこそこゝろにいらぬけしきなりしかど、その日になりて、
えもいはぬねどもひきぐして參りたまへり、こざい相のつぼねにまつおはして、
心をさなくとりよせ給しか心ぐるしさに、わかわかしき心ちすれど、
あさかのぬまをたづねて侍、さりともまけ給はじとあるぞたのもしき、
いつのまに思ひよりける事にか、いひすぐすべくもあらず、みぎの少將おはしたんなり、いづこやいたうくれぬほどぞよからん、中納言はまだまゐらせ給はぬにやと、
まだきにいどましげなるを、少將の君、あなをこがまし、
御まへこそ御声のみたかくておそかめれ、かれはしのゝめよりいりいて、
とゝのへさせ給めりなどいふ程にぞ、かたちよりはじめて、おなじ人ともみえず、
はづかしげにて、などゝよこのおきな、ゝいたういどみ給ひそ、身もくるしとて、
あゆみいで給へり御としのほとぞ、廿に一二ばかりあまり給ふらん、
さらばとくし給へかし、見侍らんとて、人々まゐりつどひたり、
かた人”のてん上人、心/\にとりいづるねのありさま、
いづれも/\おとらずみゆるなかにも、ひだりのは、なほなまめかしきけさへそひて、
中納言のしいで給へる、あはせもてゆくほどにぢにやならんとみゆるを、
ひだりのはてにとりいでられたるねども、さらにこゝろおよぶべうもあらず、
三位中將、いはんかたなくまもりゐ給へり、ひだりかちぬるなめりと、
かた人”のけしき、したりがほに心ちよげなり、ねあはせはてゝ、うたのをりになりぬ、
ひだりのかうし左中弁、右のは四位の少將よみあぐるほど、こさい相君などいかに心つくすらんとみえたり、四位少將、いかにおくすやとあいなり、
中納言うしろみ給ほどねたげなり、左
君が代の、ながきためしに、あやめ草、ちひろにあまる、ねをぞひきける
なべてのと、たれかみるべきあやめ草、あさかの沼のねにこそ有けれ
との給へば、少將さらにおとらじものをとて
いづれとも、いかゞわくべき、あやめ草、おなじよどのに、おふるねなれば
との給ふほどに、うへきかせ給て、ゆかしうおほしめさるれば、
しのびやにてわたらせ給へり、宮の御覧ずる所によらせ給て、をかしきことの侍けるを、
などかつげさせ給はざりける、中納言三位などがたわるゝは、
たはふれにはあらざりけることにこそは、との給すれば、心によるかたのあるにや、
わくとはなけれど、
さすがにいどましげにぞなどきこえさせ給ふこさい將中將がけしきこそいみじかめれ、
いづれかちまけたる、さりとも中納言はまけじなどおほせらるゝや、
ほのきこゆらん、少將みすのうちうらめしげにみやりたるしりめも、
らう/\しくあい行づき人よりことにみゆれど、なまめかしうはづかしげなるは、
なほたぐひなげなり、むげにかくてやみなんも、なごりつれ/\”なるべきを、
びはのねこそこひしきほどになりにたれと、中納言、
弁をそゝのかし給へば、そのことゝなきいとまなさに、
みなわすれにてはべるものをといへど、のがるべうもあらずのたまへば、
はんしきてうにかひしらべて、はやりかにかきならしたるを、
中納言たえずをかしうやおぼさるらん、
わうごんとりよせてひきあはせ給へり、このよのことゝは聞えず、三位よこぶえ、
四位少將ひやうしとりて、くら人の少將いせの海うたひ給ふ、声まぎれずうつくし、
うへはさま/\”おもしろくきかせ給中にも、中納言は、かううちとけ、にいれてひき給へるをりはすくなきを、めづらしうおぼしめす、あすは御ものいみなれば、
よふけぬさきにとくかへらせ給とて、ひたりのねの中に、
ことにながきをためしにもとて、もたせ給へり、中納言參りてたまふとて、
はしのもとのさうびと、うちずんし給へるを、わかき人々は、
あかずしたへぬへくめできこゆ、かのみやわたりにも、
おぼつかなきほどになりにけるをと、おとなはまほしうおぼせど
いたうふけぬらんとうちふし給へれど
まどろまれず、人はものをやとぞいはれ給ける、又のひ、
あやめも引すぎぬれど、なごりにや、
さうぶのかみあまたひきかさねて
きのふこそ、ひきわびにしか、あやめ草、ふかきこひぢになりたちしまに
ときこえ給へれど、れいのかひなさをおほしなげくほどに、はかなくさつきも過ぬ、
つきさへわれててる日にも、袖ほすよな/\おぼしくづをるゝ、
十日よひの月くまなきに、宮にいとしのびておはしたり、
さい將の君にそうそく し給へれば、はづかしげなる御ありさまに、
いかできこえんといへど、さりとてものゝほどしらぬやうにやとて、
つまどおしあけたいめむしたり、うちにほひ給へるに、よそながらうつる心ちぞする、
なまめかしう、心ふかげに聞えつゞけ給ふことゞもは、おくのゑびすも思ひしりぬべし、
れいのかひなくとも、かくと聞つばかりの御ことの葉をだにとせめ給へば、
いざやとうちなげきているに、やをらつゞきていりぬ、ふし給へる所にさしよりて、
とき/\”は、はしつかたにてもすゞませ給へかし、あまりうづもれゐたるもとて、
れいのわりなきことこそ、えもいひしらぬ御けしき、
つねよりもいとをしうこそみたてまつりはべれ、
たゞひとこと聞えしらせまほしくてなん、野にも山にもとかこたせ給ふこそ、
わりなく侍るときこゆれば、いかなるにか、心ちのれいならずおほゆるとの給、
いかゞときこゆれば、れいは宮にをしふるとて、うごきたまふべうもあらねば、
かくなんきこえんとてたちぬるを、声をしるべにてたづねおぼしたり、
おぼしまどひたりさま心ぐるしければ、身のほどしらず、
なめげにはよも御覧ぜられじ、たゝ一ことをといひもやらず、
なみだのこぼるゝさまぞさまよき人もなかりける、
さいしやうの君いでゝみれど人もなし、
かへりこともきこえてこそいで給はめ、人にものゝ給なめりと思ひて、
しばしまちきこゆるに、おはせずなりぬれば、中々かひなきことはきかじなどおほして、いで給にけるなめり、いとをしかりつる御けしきを、われならばとや思ふらん、
あぢきなくうちながめて、うちをばおもひよらぬぞ、こゝろおくれたりける、
宮はさすがにわりなくみえ給ふものから、心つよくて、あけゆくけしきを、中納言も、
えそあらたち給はさりける心のほどもおぼししれとにや、わびしとおぼしたるを、
たちいで給べき心ちはせねど、見る人あらば、ことありがほにこそはと、
人の御ためいとをしくて、いまよりのちだにおぼししらずがほならば、心うくなん、
猶つらからんとやおぼしめす、人はかくしも思ひはべらじとて
うらむべき、かたこそなけれ、夏衣、うすきへだての、つれなきやなぞ
 |
|
「五月待つ花橘の香をかげば昔の人の袖の香りぞする」
よく知られた歌を心に思い浮べ、権中納言は五月の夕暮れに佇んでいた。山時鳥の声が聞こえ、三日月は空に浮ぶ。しかし、あの姫宮に心を奪われてから、権中納言の心が弾むことはない。
今日も姫宮の所を訪れてみようか、どうせまた逢ってもくれないのだろう、喜んでくれる他の女の所には、もう行く気もなくなっていた。
自分は一体何をしたいのだろう・・・
蔵人の少将がやってきた。
「内裏で管弦の宴が始まります。今すぐ御参上下さい。帝が権中納言をお待ちかねでございます。」
特に気乗りはしなかったが、帝のご機嫌をとっておくのも殿上人の勤めのひとつではないか。
「車をこちらへ。」
心のうちを気づかれたか。蔵人の少将に言われた。
「ご機嫌がよろしくないようですね。どこかの姫君とお約束hがあったのですか。さすが権中納言様ともなると周りが放っておかないですよね。」
権中納言は心の中で思った。そうだ、今日はあの姫宮を訪ねようとしていたのに、帝のお呼びで行けなくなったんだ。それで自分はこんなに気分が良くないんだ。
帝のお呼びがなかったところで、姫宮を訪れる勇気が自分にあっただろうか。そんな疑問を必死にかき消した。
「こんな私を思ってくれる女なんかいませんよ。」
適当な会話を少将と交わす。
それにしても、あの姫宮と約束があったら
・・・どんなにいいことだろう。
三日月はすぐに雲に隠れた。星の光のもとで、琴や笛を鳴らして、宴は続く。
「権中納言様がいらっしゃったわ。」
「あの件、権中納言様に味方になってくれるようお願いしてみたらどうかしら。」
女房たちの声が御簾越しに聞こえてきた。自分の噂話をされていると気づいた権中納言はそつなく声をかけることにした。
「何のお話ですか。」
「こんど左右に分かれて、菖蒲の根合わせをするんですよ。権中納言様はどちらの味方になって下さるのかしら。」
「物事のあやめを知らない私ですよ。引き取ってくれるだけでもありがたいです。」
「まあ、あやめもご存じないのならば、右方はきっといらないって言いますわ。是非私たち左方のお味方になって下さいな。」
「こんな風に誘っていただけることもあるなって嬉しいですね。」
根合わせの後見の約束をしてその場を立ち去る。女房との気の利いたやりとり。公卿としての必須科目だ。後ろの方でまだ声が聞こえて来る。
「権中納言様って、いつもまじめなのよね。もう少し遊んでくれてもいいのに。」
「あら、それが素敵なところじゃない。今をときめく方なのに、ちっとも威張ってなくて落ち着いているわ。」
女房の悪くない評判を聞いて、とりあえず権中納言は胸をなでおろす。実のところ、菖蒲の根合わせにはあまり興味がない。
どうやら右方の女房には、三位の中将が後見になったらしい。何かというと権中納言をライバル視する中将の大きな声が届いた。
「権中納言にはなんとしても負けられません。右方の女房の皆さん、私におまかせください。」
根合わせの主催者となる中宮が、おもしろがって聞いていた。
権中納言は物心ついた時から、当代一の公卿の父のもとで、大きな邸に暮らし、立派な貴族になれと育てられた。邸には、色よい除目を求める全国の受領からの贈り物でいっぱいだ。だから、根の立派な菖蒲を見つけることなど、権中納言にとって、いともたやすいことだ。
根合わせの日、権中納言は左方の小宰相の君のところへまず挨拶にでかけた。
「私なんかを味方にしていただいて、本当にすみません。どうしても勝たせてあげたくて、大人げなく安積沼まで出かけてこの菖蒲を取って参りました。」
知らないうちに、立派な根をさりげなく見つけて来るというのが女房たちにとってはスマートに映る。
一方、三位の中将もやってきた。相変わらずの大きな声で、右方の女房たちに声をかけている。
「根合わせの場所はどこですか。日が暮れないうちに始めましょうよ。おやおや、権中納言は遅刻かなあ。」
中将はいつものように権中納言に張り合おうとしている。右方にいる少将の君という女房が、苦笑いしながら中将に言った。
「ばかねえ、中将様、いつも口ばっかりなんだから。権中納言様は朝からそこにお待ちですわよ。」
権中納言は三位の中将と目が合った。どうもこの中将は苦手だ。まだ若く、さっきみたいに女房たちとも軽口を言いあえて、なんだかんだ言っても女房達に人気があるらしい。。つまりは、自分にないものを持っている。
少し言葉に詰まった後、それでも平然と権中納言はおどけてみせた。
「おやおや、私のような年寄りにあまりつっからないでくださいよ。ごほごほ。
根合わせが始まった。右方も左方もすばらしいが、やっぱり権中納言の菖蒲の方がより美しい。それでも引き分けにと皆が思いかけたその時、権中納言が最後に出した菖蒲の根の長さと美しさに誰もが息をのんだ。三位の中将も悔しい顔して黙り込んでしまった。
「さすが権中納言様だわ。」
賞賛の嵐、左方の勝ちが決まった。根合わせ後の歌会でも、権中納言の持ってきた菖蒲の根の美しさを誉める歌が左右を問わず女房たちから詠まれた。
帝もやってきた。中宮と話しをしている。
「こんなおもしろいことがあるならなぜ声をかけてくれなかったんだい。権中納言と中将が対決とはただのお遊びでは済まないだろう。」
「まあ、特に敵味方と分けたつもりはなかったのですよ。ただ、やっぱりお互い張り合っていらっしゃるようですわ。」
「それでどちらが勝ったんだい。まあ、どうせまた権中納言の勝ちだろうけどね。」
三位の中将が、この会話を聞いて、御簾の向こうから恨めしそうな目をしていた。
権中納言は、こういう時、場を読むのが上手い。まだお開きにはしたくないという周りの雰囲気を感じとっていた。
左中弁殿、琵琶など弾かれませんか。私の琴でお手合わせ願いたい。」
間もなく、三位の中将の横笛も加わり、小さな演奏会となった。
女房たちは夢心地だ。
「権中納言の和琴はなんて素敵なのかしら。」
帝も満足の様子。
「権中納言がこれほど惜しげもなく琴を披露するのは珍しいね。素晴らしい。」
繰り返される賞賛の声。権中納言にとって、決して珍しいことではない。最高の家柄、非のうちどころのない容姿、完璧な教養、望むものは全てかなうように見える。
けれども、権中納言の心は晴れない。権中納言が本当に望むもの、それは・・・
あの姫宮を始めて見たのはいつのことだったか。もう忘れてしまった。父を早くに亡くし後見もいないまま、独りで生きる強い眼差しを御簾越しに垣間見て、今まで会ったどの女にもない魅力を感じた。望めば周りが何でも叶えてくれた今までの権中納言の人生で、始めて自分から好きになった。けれど、それはもう誰も与えてくれない。文の返事も来ない。どんな歌の知識も、彼女には役に立たなかった。
「今日はもう訪れるには遅すぎる」
溜息をつくうちに、菖蒲の季節も過ぎ、夏が来る。
日照りでひび割れる大地も、権中納言の袖から零れる涙で濡れない日はない。
悩んでいるだけではだめだ。自分から行動しなくては。そう、昔の物語の主人公にもあったではないか。
・・・「光君」のように・・・
月がとっても明るい夜、意を決した権中納言は、姫宮の邸にお忍びで出かけてゆく。宰相の君という見知った女房がいるので、彼女へ姫宮に取り次いでもらうよう頼もうというのだ。
宰相の君も、権中納言が姫宮に思いを寄せていることは知っている。素晴らしい薫物の移り香に染まりそうな程の距離で、当世一の貴公子が想いを切々と語るのを聞き、何とも言えない表情をしている。
いつもみたいに、お返事頂けないのはわかっていますが・・・それでも、私がこういう想いでいるということを・・・そして、あの方の気持ちが知りたい・・私は・・・」
宰相の君は、困った顔をしている。いつものことだ。
「さあ、とにかくお伝えはいたしますが」
宰相の君が、姫宮の寝所へと戻っていく。その後ろ姿を見送りながら、権中納言は何かを心に決めた雰囲気をしているようだった。
「姫様、またいつものように権中納言様がいらしていますが。」
「そう」
「一言でも姫様の気持ちが聞きたいと、思い詰めていらっしゃる様子ですが・・」
「なんだか今日は気分が悪いわ」
「あの・・・」
「いつもあなたが代わりに返事をしてくれるのでしょう。お父様がいなくなった私に、何の用があるというの。」
「わかりました。権中納言様には、今おっしゃったことをそのままお伝えします。」
宰相の君が、姫宮の寝所を離れていく。権中納言に、この返事を伝えに行くためだ。しかし、宰相の君はその晩もう二度と権中納言に会うことはなかった。
「権中納言様、どこに行ったのかしら。いつものように、つれないお返事を聞くのが嫌でもう帰ってしまったのかしらね。」
「誰?」
そのころ、姫宮の少しおびえたような小さな声が聞こえた。権中納言は宰相の君と入れ替わりに姫宮の寝所にいた。宰相の君の後をつけてきたのだ。こうでもしないと、自分の想いは遂げられないと思って・・・。
権中納言は、姫宮を目の前にしていた。何度、夢で見たことだろう。ついにここまで来た。もう後には引けないはずだ。後は、無理にでも姫宮を自分のものにしてしまえばよい。昔から、物語にも歌にも詠まれている通りではないか。
しかし・・・。姫宮は、おびえながらも強い目をしていた。その目を見て、権中納言は動けなくなってしまった。
「何もしませんから・・・お言葉だけでも・・・」
望むものを目の前にしながら、変わらぬ繰り言。
「もし、今晩のことを他の人が聞いたら、私とあなたに何もなかったなんて誰も思わないのですよ。なぜ、これからもずっとこんな風に冷たくされなければいけないのですか。」
言い訳のような懇願にも、姫宮の返事はない。権中納言と姫宮はこうして見つめ合いながら、夏の短夜が過ぎていく。
誰も恨むことはできない
薄い夏衣の隔て一枚も越せないのなぜだ
私は・・・何もできない
|
|
|

| |
| 「みづさへにてる」...あまのがは... |
| |
| 『ほしもてらし』 |
| 【歌意2000】 |
天の川の、水面までも照り輝く美しく装いを凝らせた舟は
無事に向こう岸へ到着して、あの人は愛しい人と逢ったのだろうか |
| |
| |
この歌、勿論「七夕伝説」の「二星の逢瀬」に擬えたもので
言うまでもなく、牽牛と織女の年に一度の「逢瀬」を詠ったものだ
それを、作者が第三者の目で二人を見守る風に、その優しさが感じられる
年に一度、という極めてロマンティックな「逢瀬」だからこそ
第三者の視点でありながら、切なく同調して聞くことができるのだろう
「七夕伝説」が、日本で盛んにこのように歌われるようになったのは、
万葉集では、巻第十に集中する、「柿本人麻呂歌集」がよく挙げられる
そして、同じ頃の日本最古の漢詩文集と言われる「懐風藻」にもみられ
それは、本来の「七夕伝承」が、中国から少しずつ形を変えて日本に及び
尚且つ「漢詩」というそのスタイルが、中国の「漢詩」に倣ったものなら
いっそう顕著に、「詩文」として取り上げられる...と思っていたが、
むしろ、万葉歌ほどの発展はなかったような気がする
「懐風藻」については、あまり詳しいことは解らないが
少しばかり目にした「書」の中で、解り易かった「論文」があったので
「下段資料」に、このサイトで当分続く「七夕歌」に合わせて、継続して載せておく
今回の掲題歌に伴って、その表現やイメージに、
古注釈書の幾つかで、「懐風藻」の一文が引き合いに出されていた
その「詩」が、山田史三方の詩で、
何とか理解出来たつもりだが、そこから、この掲題歌とどんな類想があるのか
また時間がかかってしまった
漢詩の方では、織女が「艶やかな姿で、舟に乗」り、牽牛に逢いに行く
古注釈書で用いた「玲瓏映彩舟」が類想、というのは、この舟を鮮やかに彩るところであり
その実体は、織女の髪を美しく整え、しとやかな姿で玉を鳴らす
そんな「美しさ」が、乗る舟を彩に際立たせるものだ
しかし、この掲題歌では、ほとんどの注釈書で舟自体を艤装を凝らせ立派にしている、とする
それが、水面あるいは水底までも輝かせるほどに...
初めに、こうして「万葉歌」を読んでしまったので
どうしてもその解釈が第一義的になって、その先入観が先走ってしまうが
考えてみれば、「懐風藻」の解釈に沿っても、この掲題歌は読める可能性はある
実際、『童蒙抄』が、その中で、諸説に言及し、
舟に乗る者が、「織女」とする説も述べている
それは、他ではみられなかったが
あるいは、この「懐風藻」の「詩」を知っていて、その歌意を追ったのかもしれない
当然、万葉の時代には「漢詩」が隆盛であり、万葉歌よりも「懐風藻」の方が、
都では重んじられていたはずだ
その背景を考えれば、中国から伝わった「七夕伝説」の様々なパターンを熟知し
さらに、漢詩文にも長けた者がこのような万葉歌の七夕歌を口ずさみ
それが柿本人麻呂歌集に採録されたとしても、不思議ではない
そもそも、「七夕伝説」を題材にした万葉歌を詠える人たちは
ある程度の階層ではないかと思う
その伝来の背景で確かに、牽牛の農耕の行事とか、織女の家内作業のこととか
庶民的ではあっても、それが国の年中行事に発展するには、
決して庶民からだけの広まりではなかった、と思う
そんな有力者たちが、次第に「七夕」の「年に一度の逢瀬」にスポットを当て
何かにつけて「七夕歌」を題目にして詠い合う、というのも頷ける
そして、本来の姿から変化し、様々なパターンで「七夕伝説」が残されてきたと思う
この歌にしても、牽牛が舟に乗ることも自然に解釈でき
さらに、その逆に織女が舟に乗ることも、無理はない
そして、水面を輝かせるのが、舟自体もあり、織女の艶やかさに依るものもまた無理がない
だから、『童蒙抄』の荷田春満が、悩むように、諸説がとても多くあるのも理解出来る
私がこの歌で感じるのは、主人公の二人ではなく
その二人に注がれる、優しい眼差しで詠う作者の気持だ
牽牛を送り出し、その無事の到着を願い、さらに向こうでは織女と逢えたのだろうか、
と案じる気持ちが、私には伝わってくる
そこには、古注釈のいうような「競う」も「装う」もなく
ごく自然に、年に一度の逢瀬を、無事に成し遂げられることを願う気持ちがある
まだまだ、七夕歌は続くが、今回から始まる七夕シリーズ、私自身にとっても
「七夕」についての、いい勉強になりそうだ
お互いが天の川を行き来していた...それが、年に一度の逢瀬の姿に相応しいと思う
|

|
掲載日:2014.04.24.
| |
| 秋雑歌 七夕 |
| 天漢 水左閇而照 舟竟 舟人 妹等所見寸哉 |
| 天の川水さへに照る舟泊てて舟なる人は妹と見えきや |
| あまのがは みづさへにてる ふねはてて ふねなるひとは いもとみえきや |
| 巻第十 2000 秋雑歌 七夕 柿本人麻呂歌集出 |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】〔249〕
【赤人集】〔161・148・269〕
[古注釈書引用歌]
【懐風藻】〔大学頭従五位下山田史三方 53〕[万葉集全釈・評釈万葉集・万葉集注釈]
[資料]
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
【七夕】〔中華民国[国立成功大学、成大宗教與文化学報 第七期 論文]〕
| 【2000】 語義 意味・活用・接続 |
| あまのがは [天漢] |
| みづさへにてる [水左閇而照] 以下第四句まで「注記」 |
| さへ [副助詞] |
[添加] ~までも |
体言につく |
| に [間投助詞] |
[感動・強調] ~まあ~ことだ 〔接続〕副助詞「さへ」につく |
| てる [照る] |
[自ラ四・連体形] 光を放つ・輝く |
| ふねはてて [舟竟] |
| はて [泊つ] |
[自タ下二・連用形] 停泊する・船が港について泊る |
| ふねなるひとは [舟人] |
| なる [助動詞・なり] |
[存在・連体形] ~にある・~にいる |
体言につく |
| いもとみえきや [妹等所見寸哉] |
| と [格助詞] |
[動作の相手] ~と・~を相手にして |
体言につく |
| みえ [見ゆ] |
[自ヤ下二・連用形] 会う・対面する |
| き [助動詞・き] |
[過去・終止形] ~た・~ていた |
連用形につく |
| や [終助詞] |
[疑問] ~か |
終止形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [あまのがは] |
語儀的には「銀河」のことだが、歌に絡めれば「七夕伝説」の象徴と思う
数億以上の微光の恒星から成る帯状の星群を「天上の川」に見立てたもの
原文「天漢」は、『和名抄』巻一、天部・景宿類第一の、
「天河 兼名苑云一名天漢 今按又名河漢銀河也。和名阿萬乃加八」による
『万葉集』中の「天の川」の用字例は、万葉仮名を除けば「天川・天河・天漢」のみ
しかし、現存する日本最古の漢詩文集『懐風藻』では「金漢」、
他に『文選』には「雲漢・星漢」などの例を見る
何故「漢」の字を当てるかは、中国の川「漢水」によるもの、とする説がある |
| |
| [みづさへにてる ふねはてて ふねなるひとは] |
この三つ句は、諸説が多くて、いまだに定釈はみられない
一応、より新しい訓釈で載せる
まず、大きな相違点は、第二句から始まる
原文「水左閇而照」の「水」の次に「底」の字が脱落している、と契沖『代匠記』にいう
その根拠として、赤人集のこの一首が、
「あまのがはみなそこまでにてらすふねつひにふなびといもとみえずや」(左資料)とあり
それに倣って、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕では、
〔1865、書庫-14〕の「能登川の水底さへに照るまでに...」そして
〔7・1323〕、「大海の水底照らし...」を引用して、「底」の文字を加えた
ただし、現在でも普及する注釈書では、この訓はほとんどなく
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕が採っている
同じ岩波の『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕、
さらには『新日本古典文学大系』〔岩波文庫校訂版、平成25年~〕もまた、「底」はない
近代までの注釈書については、下段資料に載せる
ここで問題が続くのは、その「そこ」を訓じたときに、全体の訓に影響するということだ
現代の一般的な訓では、
「あまのがは みづさへにてる ふねはてて ふねなるひとは いもと(に)みえきや」だが、
「そこ」を加えることによって、
「あまのがは みなそこさへに てらすふね はてしふなびと いもにみえきや」
原文で比べると
「天漢 水左閇而照 舟竟 舟人 妹等所見寸哉」
「天漢 水底左閇而 照舟 竟舟人 妹等所見寸哉」
「底」の一字挿入で必然的に以下がずれてしまうが
訓としては、それでも成り立つのだから、不思議なものだ
今更ながらに思う
そもそも万葉歌の原文には、句の切れ目など無く、漢字がただただ連なっているだけだ
どこに切れ目があるかは、研究者のその判断に依らざるを得ないが、
この歌に限っては、それも難しいといえるのだろう
ただ、肝腎なことを言えば、脱字と解釈することから始めれば
その段階で、大きなハンディを背負いながら説明しなければならない
|
| |
| [なる] |
一般的に、「断定の助動詞」という「なり」の、「存在」の用法
その成り立ちは、格助詞「に」にラ変動詞「有り」のついた「にあり」の転じたもの
この掲題歌のように、「舟人」を、「舟にいる人・舟にある人」と解すれば
最も素直な訓み方になるが、『評釈万葉集』のように、
前の句の「竟」を「競」の誤字とすると、「ふなぎほひ(舟競)」、
そして「舟人」を、「競う」ことから「ふねこぐひと(舟漕ぐ人)」と訓ずることになる |
| |
| [と] |
現代の注釈書では、ほとんどこの「等」の訓に「に」を当てている
表記的には、旧訓以来の「と」で問題ないと思っていたが
岩波の『古典大系』が、動詞「見ゆ」は助詞「に」に受ける、ということから、
「と」ではなく「に」を採っている
その論理でいけば、どうして旧訓、いや近代までの注釈書までも「と」であるのだろう
私は、「と」が表記上だけではなく、その語感からも「歌」の助詞らしくていい、と思う |
| |
| |
| |
[古注釈書引用歌]
【懐風藻[天平勝宝3年(751年]編者不詳】
|
金漢星榆冷 銀河月桂秋 靈姿理雲鬢 仙駕度○流 [○さんずいに黄]
窈窕鳴衣玉 玲瓏映彩舟 所悲明日夜 誰慰別離憂 |
きんかん せいゆひややかに
ぎんが げつけいのあき
れいし うんびんををさめ
せんが くわうるにわたる
えうてうとして いぎよくをならし
れいろうとして さいしうにはゆ
かなしむところは みやうにちのよる
たれかべつりの うれひをはぐさめん
|
| 大学頭従五位下山田史三方 五言七夕 53 |
| 「語義」、「訳」は [小学館・新編日本古典文学全集 日本漢詩集]より |
〔語義〕
「金漢」、天の河
「星楡」、楡の木、あまた多くの星
「月桂」、月中にあるという桂の木、また月光
「霊姿」、優れた姿、織姫をいう
「雲鬢」、美しい髪 「鬢」は耳のそばの毛
「仙駕」、神仙の乗り物
「○流」、水の豊かな天の渡し場
「窈窕」、しとやかで美しい
「玲瓏」、さえてあざやかなさま
「彩舟」、美しい舟、織女星の乗り物天 |
〔訳〕
天の河のほとりには、楡の木かげに多くの星たちがきらきらとまたたいている
銀河のそばに輝く、月中の桂の木も秋になって色づいているようだ
今宵は、あでやかな織女星が美しい髪をととのえて、
仙人の乗り物に乗って、天の河の渡し場めざして進む
しとやかで美しい姿で、衣につけた玉を鳴らしながら渡って行き、
豪華な舟に、彼女の姿はすきとおる玉のように照り映えて美しい
ただ悲しいことに、明日の夜には牽牛星と別れねばならぬ
いったい誰が別離の憂いを慰めてくれるのだろう |
この詩は、陰暦七月七日の夜に牽牛・織女の二星が相会う「七夕伝説」を詠ったもの
「七夕伝説」は、「二星相会」の伝承が万葉集に多く詠まれているが、
その本来の「年中行事」と言われるものから、中国からどのように伝わったのか
その解説する書は多くある
その中で、私が出合った中華民国(台湾)の大学の論文に興味を引かれたので、
下段に、関係箇所を載せ、しばらくこのサイトで続く「七夕」では
そのまま掲載しておこうかと思っている
この「漢詩」と掲題歌とのことは、左頁に書く |
| |
|
|
| 掲題歌[2000]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】
| 新編私家集大成第一巻-4 人麿Ⅲ [冷泉家時雨亭叢書『素寂本私家集西山本私家集』] |
アマノカハミナソコマテニテラスフネ ツヰニフナ人クモニアハスヤ
|
| 柿本人麿集中 恋部 寄月 万十 249 |
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
|
| あまのかはみなそこまてにてらす舟 つひにふな人いもとみしあや |
| 新編私家集大成第一巻-新編増補 赤人集Ⅲ[陽明文庫蔵三十六人集] あきのさう 161 |
| あまのかはみなそこまてにてらす舟 つゐにふな人いもとみえすや |
| 同第一巻-6 赤人集Ⅱ[書陵部蔵三十六人集] 秋雑歌 148 |
| あまのかはみなそこまてにてらすふね つひにふなひといもとみえすや」 |
| 同第一巻-5 赤人集Ⅰあかひと[西本願寺蔵三十六人集] あきのさふのうた 269 |
| あまのがはみなそこまでにてらすふねつひにふなびといもとみえずや |
| 新編国歌大観第三巻-2 赤人集[西本願寺蔵三十六人集] あきのざふのうた 269 |
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「天漢水左閉而照舟竟舟人妹等所見寸哉」
「アマノカハ ミツサヘニテル フナワタリ フ子コクヒトニ イモトミエスヤ」(「【】」は編集、歌番は旧) |
〔本文〕頭注に、『元暦校本・類聚古集』、訓ヲ附セズ。『西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本』、訓ヲ朱書セリ。
赤人集「あきのさふのうた あまのかはみなそこまてにてこすふねつひにふなひといもとみえすや」
|
| 「舟」 |
『元暦校本・類聚古集』「丹」 |
| 「竟」 |
『温故堂本』「競」 |
| 舟人の「舟」 |
『元暦校本』「丹」 |
| 「寸哉」 |
『類聚古集』「木哉」。コノ下ニ字ヲ磨リ消セル痕アリ。ソノ痕ニ朱ノ○【表示できず】ヲカケ、ソノ右ニ朱「人」ヲ書ケリ
『神田本』「哉」ノ下ニ小字「武イ」アリ |
| 〔訓〕 |
| フナワタリ |
『神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本』「フナヨソヒ」 |
| フ子コクヒトニ |
『細井本』「フ子コフヒトニ」
『京都大学本』赭ニテ「ニ」ヲ消セリ。ソノ右ニ赭「モ」アリ |
| イモトミエスヤ |
『神田本・西本願寺本・細井本』「イモトミヘキヤ」
『温故堂本』「イモトミユキヤ」 |
| 〔諸説〕 |
| ○[アマノカハ]『万葉考』「アマツカハ」○[水左閉而照舟竟舟人ミツサヘニテルフナワタリフ子コクヒトニ]『拾穂抄』「フナヨソヒ」。『童蒙抄』師案「照」ノ下ノ「舟」ハ「丹」ノ誤ニテ訓「ミツサヘナカラテラセルニワタルフナヒト」トス。愚案「ミツサヘニテルフナヨソヒカチトルヒトニ」、又ハ「ミツサヘシカモテルフ子ヲコクフナヒトモ」。『万葉考』「竟」ハ「章」ノ誤ニテ訓「フナヨソヒ」トス。『万葉集古義』「水」ノ下「底」脱トシ訓「ミナソコサヘニヒカルフ子ハテシフナビト」トス○[イモトミエスヤ]『代匠記初稿本』「イモトミエキヤ」。『代匠記精撰本』「イモラ」トス |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [2000] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
| |
七夕歌九十八首 柿本朝臣人麻呂
〔あまのかは水さへにてるふなよそひふねこくひとにいもと見えきや 〕
天漢水左閇而照舟競[イいそひ]舟人妹等所見寸[イす]哉
|
牽牛の心になりてよめり
この歌は、第三者が気品のある舟が着くのを見て、
その乗っている人を牽牛と重ね、その妻と逢ったのだろうか、という歌意に解する
水さへも照り輝く舟、乗る人、七夕の年に一度の逢瀬に相応しい表現としているのだろう |
| あまのかは水さへに 七夕つめの舟渡りに水さへ照かゝやけは舟こく人にもさためて其かゝやく姿隠れあらしと也牽牛の心になりてよめり |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
| |
〔アマノカハミツサヘニテルフナワタリフネコクヒトニイモトミエスヤ〕
天漢水左閉而照舟竟舟人妹等所見寸哉 |
これまで、度々登場していた「幽斎」が、やっと解った
きっと、戦国武将の「細川幽斎(1534~1610)」のことだろう
歌人としても、当時の教養人として著名であり、
和歌に関する書も多かったはずだ
契沖がいう、「幽斎本」の実体は分からないが、
そこに「ミエキヤ」との訓があったのだろう
「ミエスヤ」とされていたのを、契沖は「ミエキヤ」と採る
舟を、豪華に着飾った舟、とでも解しているのだろうか
さらに、「いもら」では「相まみえ」の意が殺がれると思う |
所見寸哉、[幽齋本云、ミエキヤ、]
水サヘ照とは丹/塗[ヌリ]などの餝れる舟なり、舟人は牽牛なり、舟人とのみかけるは第三に舟公をふねこぐきみとよめるが如し、落句は幽齋本の點に依べし、今宵織女の牽牛に妻とて相まみえきやとなり、今按妹等はイモラとも讀べき歟、
|
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
| |
〔訓に、迷いがあるようだ 〕
天漢水左閉而照舟竟舟人妹等所見寸哉 |
諸説を並べ、思案にくれている
舟の人を織女とする説があること、意外だった |
此歌、諸抄の説、印本の假名等左の如くにて、其心得難し
牽牛の舟を飾りて渡れば、水さへに照る船わたりとは云ふ也。舟漕ぐ人は彦星にて、七夕つめの今宵彦星に妹なりとて、相まみえきやと云義と也。又一説、其輝く姿かくれなく、舟漕ぐ人にも妹と見えきやとの説也。如此説不一決也。舟人と書きて、舟漕ぐ人と讀む事も、義訓にて苦しからざるべきや。未考。下の妹と見えきやの説も、舟人を彦星として、相まみえきやと云説適ふべくや、決し難し。宗師説は
あまのかはみづさへながらてらせるにわたる舟人いもとみえきや
と讀みて、上の舟は丹の字なるべし。而と云字は日本紀などに、ながらと讀ませたれば、此歌にてもながらと讀むべし
所見寸哉 前の説の如く妹と相まみえきやと云意と也。愚意未決。水さへながらと云義心得難し。此句の意未甘心。又照らせるにいもと相まみえきやと云意も聞え難し。妹と見えきやと云事は、相まみえたるやと云義との説愚意不得心。妹に逢ひきやと云べきを、みえきやと讀める意聞えず。何とぞ見る見えと讀まで叶はぬ縁語言葉つゞきあらば、さもあるべしや。さも無きなれば、逢ひきやとか、妹を見つるやとか、聞き易く讀たきものなるに、見えきやとよめる意不打着也。何とぞ今一義見樣あらんか
竟の字一本に競の字に作れるも有。然れば、わたるとも訓じ難く、よそふとも訓み難し。あらそふとか、きそふと讀までは不可成也。なれば此歌まちまちの見樣ありて、如何に共決し難し。宗師の説も此歌の解は未得心也。羈案は
天のかはみづさへ [しかもてる舟をこぐ舟人をいもとみえずや・にてる船よそひかぢとる人もいもと見えきや]
此意は 水さへに照る美麗の飾り舟故、人も美女の躰に見ゆると也。是は織女の乘れる船と見る意也。彦星のつま迎船などよめば、彦星より迎へとる船と見る也。水さへ照ると詠出たるからは、此照ると云義の詮立べき歌と見る也。宗師の説にたがひ、先達の意にたがふ拙見其罪幾難逃けれど、愚意に不落ば、愚案を述ぶるのみ。然し竟の字よそふと讀み、こぐと讀む字義未考。古く讀ませたるに從ひて也。見えきやのやも助語とも見る也。此格當集其外古詠に何程もある事也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
| |
天漢[アマノカハ]、 あまの川と訓は後なり委は古事記を引て別記にいふ
水/左閉而照[サヘニテル]、船章[フナヨソヒ]、 今本章を竟としてふなわたりと訓たれど意とほらず字を誤るよりて考るに船竟二字は艤の一字にてふなよそひかとおもへれど字のちかければ暫章としてよそひと訓む、一本竟を競に作りてきそひとよめりされど水/左閉而照[サヘニテル]といへばよそひの方つゞきてきこゆ
舟入[フネコグヒトノ]、 彦星を云なり
妹等所見寸哉[イモトミエキヤ]、 |
真淵のいう「ふなよそひ」と言う漢字「艤」は、
「出船の準備をする」などの意味で、この歌では、その準備の如く艤装を施している、という意味だろう、そのため、
引き合いに出す「競」では、「ミヅサヘニテル」の解釈に沿わないのは明白だ
でも、「ふなよそひ」を導くのが「みづさへてるに」の為であるのは、安易過ぎる |
| 相見えきやなり寸は計利約やはよに通ひ妹はたなばたつ女をさしていふなり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
| |
七夕[ナヌカノヨヒ]
〔あまのがは。みづさへにてる。ふなわたり。ふねこぐひとに。いもとみえきや。 〕
天漢。水左閉而照。舟竟。舟人。妹等所見寸哉。 |
古本とは、何を指すのだろう
水底まで照らすほど装う舟...
|
古本、水の下底の字有り。然れば二三四の句、ミナソコサヘニ、テルフネノ、ハテテフナビトと訓むべし。水底まで照り渡るばかり装ひたる舟を言へり。舟人はやがて牽牛にて、イモは織女を言へり。ミエキヤは相マミエケリヤと言ふなり。
參考 ○水左閉而照(考)水サヘニテル(古、新)ミナゾコサヘニ「水」の下「底」を補ふ ○照舟竟舟人(考)フナヨソヒ、フネコグヒトノ「照」は上の句に付け「竟」を「章」と改む(古)ヒカルフネ、ハテシフナビト(新)テラスフネ、ハテシフナビト。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
| |
〔アマノガハ。ミナソコサヘニ。ヒカルフネ。ハテシフナビト。イモトミエキヤ。〕
天漢水底左閉而照舟竟舟人妹等所見寸哉
|
ここでも言う、「一本」とは...
「照舟」で、艤装の美しさを言うもの
「妹に」と「妹と」の感覚の違いを説明している
歌意には、特筆なし |
水底左閉而(底(ノ)字、舊本にはなし、今は一本に從つ、)は、ミナソコサヘニなり、
○照舟は、ヒカルフネと訓べし、艤[ヨソヒ]の美麗[ウルハシ]きをいへり、
○妹等所見寸哉[イモトミエキヤ]といへるは、妹と相見えきやと、問かけたる意にて、妹等[イモト]は、妹と共にといふほどにきくべし、妹に所見[ミエ]きやといへば、此方の容儀の、妹が目に所見[ミエ]きやとのみきこゆるを、妹等[イモト]としもいへるは、此方の容儀は妹に見え、彼方の容儀は吾に見ゆる謂なるを思ふべし、
○歌(ノ)意、舟人は彦星、妹は棚機女なれば、天(ノ)河の水底までひかるばかりに、装ひたる舟を泊[ハテ]し、その舟人の彦星は、棚機女の妹と相見えきやいかにと、かたへの人の問かけたる謂なるべし、
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
| |
〔あまのかはみなぞこさへに、てらすふね、はてしふなびといもとみえきや 〕
天漢水左閉而照舟竟舟人妹等所見寸哉 |
略解、古義の「そこ」への言及に倣う
やはり、万葉歌の用例を持ち出している
気になるのは、他動詞で「はてし」とすること
「し」は、過去の助動詞だから、
他動詞で同じ下二段になるのだろうか
「泊めさせて」と解釈するのだろう |
略解に
古本水の下底の字有。しかれば二三四の句ミナゾコサヘニテルフネノハテテフナビトと訓べし
といひ、古義にはミナゾコサヘニヒカルフネハテシフナビトとよめり。第二句は二書に從ふべし。上(一九三一頁)にもノト河ノ水底サヘニテルマデニとあり。次に第三句はテラスフネとよむべく第四句は古義の訓に從ふべし
○フナビトは牽牛、イモは織女なり。ミエキヤは相見エキヤなり。こゝのハテシは他動詞なり |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| |
天の川。水底[ミナソコ]さへに照る舟の、泊[は]てて、舟人、妹と見えきや |
水底までも輝かせる立派な舟
それを漕いで天の川を渡り、牽牛が織女に逢ったことだろう
歌意に初めて具体的な位置関係を取り込んでいる |
| |
天の川の水底迄も輝くやうな立派な舟が、向う岸に著いて、その舟の舟頭なる牽牛が、織女と逢うたであらう。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
| |
〔天の川 水底さへに 照らす舟 はてし舟人 妹とみえきや〕
アマノガハ ミナソコサヘニ テラスフネ ハテシフナビト イモトミエキヤ
天漢水左閇而照舟竟舟人妹等所見寸哉 |
歌意にいっそうの思い入れが見られる
校本万葉集で、「底」のある書が見えないが、赤人集にあるから、そうした書もあったと推測する
略解や古義がいう古本の存在は、やはり不明らしい
「竟」の意味は、調べてみなければ解らなかった
具体的に「対岸に着いて」というのは、「竟」の持つ「終」の意からだろうか
それとも、第三者が詠うのだから、その第三者のもとから出かけ対岸で、妹と相見えたのか、ということからの推測か
「竟」の意味が、もう一つしっくりこない
懐風藻の「玲瓏映彩舟」を重ねるが、この語句だけの類想だ
|
天ノ川ノ水ノ底マデモ照ラス程ノ美シイ舟ニ乘ツテ對岸ニ着イタ牽牛星トイフ舟人ハ、妻ノ織女星ト今夜一年ブリデ逢ツタデアラウカ。ドウデアラウ。
○水左閉而[ミナソコサヘニ]――舊本/水左閉而照[ミヅサヘニテル]とあるが、略解に「古本水の下底の字有り。然れば二三四の句みなそこさへにてるふねのはててふなびとと訓べし」とあるに從ふ。但し校本萬葉集に底の字ある本が見えないが、赤人集にこの歌を「あまのかはみなそこまてにてらすふねつひにふなひといもとみえずや」とあるから、底の字のある本もあつたのであらう。新訓に「水/障[サ]へて照る舟競ひ」とあるが、意が明らかでないやうである。ミナソコサヘニテラスフネは舟が美しく色どられてゐるので、水の底までも映ずるのである。而の字も異本はないが、丹などの誤であらうか。
○竟舟人[ハテシフナビト]――竟は温故堂本に競に作つてゐるので、新訓には上につづけて、フナギホヒと訓んでゐるが、他本は皆竟とあるのだから、竟としてよむ方がよいやうに思ふ。竟は竟而佐守布[ハテテサモラフ](一一七一)・年者竟杼[トシハハツレド](二四一〇)など、ハツとよむべき文字である。ハテシフナビトは對岸へ到着した舟人、即ち牽牛星のことである。
〔評〕 牽牛星の喜びを想像してゐる。懷風藻に見えた七夕の詩「玲瓏映彩舟」とあるのと同想である。七夕の歌がここに長歌短歌併せて一百九十八首に及んでゐるのは、如何にこの傳説が廣く行はれてゐたかを示すもので、これも當時流行した神仙思想と、同一傾向によるものと見るべきであらう。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
| |
〔天の河 水さへに照る。舟競ひ 舟こぐ人に 妹と見えきや。 〕
アマノガハ ミヅサヘニテル フナギホヒ フネコグヒトニ イモトミエキヤ
天漢水左閇而照舟競舟人妹等所見寸哉 |
「水左閉而照」は、織女が対岸に迎えに出ているから、という
これまでにない解釈だ
その前提があるからこそ、舟を競い漕ぐになるのだろうか |
【譯】天の川は水までも照り輝いている。船を競つて船こぐ人に、あれは妹と見えたか。
【釋】天漢 アマノガハ、漢は、天河をいい、一字だけでも使用されている。ここは熟字として天の字を添えている。銀河である。
水左閉而照 ミヅサヘニテル。 ミヅサヘニテル(西)、ミヅサヘテテル(新訓)、
水底左閉而照[ミナソコサヘニヒカル](古義)
諸説のある所である。而をニの假字に當てる例は、下に「然敍手而在[シカゾテニアル]」(卷十、二〇〇五)とある。水までも照つている由で、織女星が、川岸に出ているをいう。句切。
舟競 フナギホヒ。勢いよく船を進めるをいう。「舟競[フナギホヒ] 夕河渡[ユフカハワタル]」(巻一、三六)。これも人麻呂の作品である。
舟人 フネコグヒトニ。人麻呂集の習として、極端に字を節約するので、何とでも讀まれるが、フネコグヒトニあたりが無難であろう。舟こぐ人は、牽牛星をさす。牽牛皇が船をこいで天の川を渡るとする構想である。
妹等所見寸哉 イモトミエキヤ。イモトミヘキヤ(西)、イモラミエキヤ(代精)。河岸に出て水さえ照つている人は、妹と見えたかの意。ヤは、疑問の助詞。反語ではない。
【評語】七夕の歌は、その性質上、多くは題詠作爲の歌になるのは、やむを得ない。この歌も、そういう誇張のところがあるが、想像力はよく働いていて、一往天上の情景を描きなしている。
|
| 『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕 |
「評釈」私見 |
| |
天漢[あまのがは]水さへに照る舟競[ふなぎは]ひ舟こぐ人は妹とみえき |
歌意、従来と同じで特筆なし
でも、「競う」という語にする意味が薄れている
これだと、早く逢いたい一心で、競うように漕ぐ、となるが
わざわざ誤字説を用い出さなくても、と思う
敢えて言えば、
艤装を凝らし立派な舟に仕立てて出向いたことで、
「競う」の意味も含まれるのではないか、と思う
懐風藻の例の一文が、同想には違いないが、同じ七夕歌であれば
そこに、歌意の工夫もあった方がいいと思う |
【譯】天の河の水までが照るやうに、沢山の照り輝く美しい舟を競ひつつ、舟を漕いで行つた人―彦星は、妻なる織女と相逢うたであらうか。
【評】天の河を美しい舟を漕ぎ競うてゆく彦星の、晴れの舟出の喜を想像し、彦星が多くの従者を引き連れて行くといふ風に見立てて「舟競ひ」といつたのであらう。但、この歌、訓に諸説があつて決し難いので、解釈も一様ではない。
【語】○水さへにてる 懐風藻なる七夕の詩に「玲瓏映彩舟」とあると同想で、舟が彩られてゐるため、水まで照るやうなのをいふ。○舟こぐ人 牽牛星をさす。
【訓】○水さへに 白文「水左閇而」とある。而は「然叙手而在」(二〇〇五)によつてニと訓んだ。○舟ぎほひ 白文「舟競」は温故堂本によつた。他本は竟とあり、また赤人集に「天の河水底までにてらす舟つひに舟人妹とみえずや」とあるのを傍証とし、また巻十に「水底さへに(て)るまでに」(一八六一)の句もあるにより、「水」の下に「底」の字を脱したとして「天の川水底さへに照らす舟竟(は)てし舟人妹とみえきや」と読む説がある。 |
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
| |
〔天の川水さへに照る舟はてて舟なる人は妹と見えきや 〕
アマノガハ ミヅサヘニテル フネハテテ フネナルヒトハ イモトミエキヤ
天漢水左閇而照舟竟舟人妹等所見寸哉 |
歌意に特筆なし
語意の解釈にも特筆なし |
【大意】天の川が水まで光つて居る。船を泊めて、船の中に居る人は、織女と会いひましたか。
【作者及作意】七夕伝説のことは、巻八に注した。以下三十八首は、人麻呂歌集所出であるが、恐らくは大部分が奈良時代に入つての成立であらう。此の一首は訓釈に説の多いものであるが、かう訓んだ。牽牛が川を渡り、とまり船の中に居るところとして、もう織女に会つたかと問の形ながら、実は肯定する心持であらう。ミユを相会ふ意とすれば、一首はよく分る。「而」は「爾」に近い助辞なので「ニ」に用ゐた。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
| |
〔天の河 水底さへに 照らす舟 泊てし舟人 妹と見えきや 〕
アマノガハ ミナソコサヘニ テラスフネ ハテシフナヒト イモトミエキヤ
天漢水左底閇而照舟竟舟人妹等所見寸哉 (『元暦校本』) |
従来の訓釈の解説
この書は、これまでにも感じていたことだが
現代の注釈書が本来そのスタイルで書いてもいいものを、ほとんど自説を中心にしているので
その点においては、注釈書の「総合誌」のような役割を感じてしまう |
【口訳】天の河の水底までも照らすばかりの美しい舟、その舟を対岸に泊めた舟人は、妹と相見えたことであらうか。
【訓釈】水底さへに照らす舟―原文「水左閇而照舟」とあり、この歌、『元暦校本・類聚古集』に訓なく、『西本願寺本・陽明本・大矢本・京都大学本』は朱書してゐる。『紀州本・西本願寺本』、その他にミツサヘニテルとし、「舟」の下の「竟」を第三句に入れ、『紀州本・西本願寺本・細井本・陽明本』にフナヨソヒ、『大矢本・京都大学本』その他フナワタリとした。代匠記に「水サヘ照トハ丹塗(ニヌリ)ナドノ餝(カザ)レル舟ナリ。・・・但赤人集ニ天河水底マテニ照ス舟ツヰニ舟人妹ト見エキヤト意得ベキ歟」と云つた。略解に「古本水の下底の字有り。然れば二三四の句、みなそこさへにてるふねのはてゝふなびとゝ訓べし」とあり、古義にも「底ノ字、旧本にはなし、今は一本に従フ」とあるが、現存の古本には「底」の字は無い。しかし赤人集に「みなそこ」とあり、「さへに」の語に対しても単に「水」でなくして、「能登川の水底并尓照るまでに」(1861)のやうに「水底」であるべき事が認められよう。彦星の舟は「さ丹塗の 小舟もがも 玉纏の ま櫂もがも」(8・1520)とあるやうな華麗な舟だから、水面ばかりでなく、水底までも照らす舟と云つたのである。「而」をニと訓む事は、この先にも「然叙年而在(シカゾトシニアル)」(2005)とあり、日本書紀には「阿那而惠夜(アナニエヤ)」(神代紀上)、「比苔嗟破而(ヒトサハニ)」(神武紀)、「伊莽儴而毛(イマダニモ)」(同)などあり、字音弁証(上)に「韻鏡第八轉に収て、漢次音ジ、呉次音ニの音なり」とある。「而」は「広韻(七三)9に「如之切」集韻(同)「人之切」とあつて呉音ニである。「舟」の字、『元暦校本・類聚古集』に「丹」に誤る。『紀州本・西本願寺本』その他による。
泊てし舟人妹と見えきや―旧訓第二句ミヅサヘニテルと訓んだ為に「舟竟」を第三句として右に述べたやうにフナヨソヒ、フナワタリと訓み、新訓にはフナギホヒとし、新校にはフネハテテと訓み、「舟人」をフネコクヒトと訓み、新校にはフネナルヒトハと訓んだ。「平城之人(ナラナルヒト)」(1906)、「舟公(フネナルキミ)」(3・249)などによるとフネナルヒトハの訓は認められるやうで私もそこでこの「舟人」をフネナルヒトと訓んだが、第二三句を右に述べたやうにミナソコサヘニテラスフネと訓むと極めて自然にハテシフナビトといふ古義の訓に従ふべきであらう。増訂本新考に「こゝのハテシは他動詞なり」とある。「泊る」には井出君(『訓詁篇』)が云はれてゐるやうに、「千船湊(チフネノハツル)大わだの浜」(6・1067)の如く自動詞的なものと、「舟盡(フネハテテ)戕牁(かし)振り立てて廬せむ」(7・1190)の如く他動詞的なものがあり、ここは後者である。「妹等所見寸哉」は『西本願寺本・紀州本・細井本』イモトミヘキヤ、『陽明本』イモトミユキヤ、『大矢本・京都大学本』、版本イモトミエスヤ、拾穂抄などイモトミエキヤとし、代匠記に「イモラトモ読べき歟」ともいひ、新校にイモニと改め、井出君や古典大系本それに従はれ、「織女にその姿が見えたであろうか」と訳し、「『妹に逢つたか』と見るのは、『見ゆ』にまみえる、逢ふ等の意がないので不都合である」といはれた。「妹ら」の語は前(5・863、7・1121)にもあつたが、この場合適切とも思はれない。「妹等」二字をイモと訓む事は、この先にも「往来吾等須良(カヨフワレスラ)」(2001)、「吾等戀(ワガコフル)」(2003)などの「吾等」の例はいくつもあるのでそれに準じて、認める事も出来るやうであるが、事実に於いて「妹等」をイモと訓んだ例は他に一例もない。これに反し、「妹等」をイモトと訓んだ例は人麻呂集の作にも「古に妹等吾見(イモトワガミシ)」(9・1798)の例がある。即ちこの用字からはイモトミエキヤという古訓が最も穏かだといふ事になる。古典大系本には「見ユは・・・ト見ユという形は当時無く、・・・ニ見ユといつた」とあるが「と見ゆ」の例がこれ以外に無いからと云つてその語が認められないといふ事はできない。また「見ゆ」といふ語が普通「目に見える」の意に用ゐられて「逢ふ」意に用ゐられた例はないやうにも考へられるが、
玉かぎる髣髴所見而(ホノカニミエテ)別れなばもとなや戀ひむあふ時までは (8・1526)
は、やはり七夕の作であり、これはただ「目に見える」意でなく、現に古典大系本で「互いにほんのわずか会つただけで」と訳されてゐるのであるから、ここもトミエと訓んで、代匠記に「妹ト相見エキヤト意得ベキ歟」とあるに従ふべきである。
【考】評釈篇(下)に「一首は七夕伝説の牽牛織女をば現身世界の恋愛のやうに見立てて歌つてゐるところに妙味があり、結句の、『妹と見えきや』、即ち、『妹と相見(あいまみ)えきや』と云つてゐるところに妙味があるのである」とある。
赤人集に「みなそこまでにてらすふねつひにふなひといもとみえすや」、流布本「妹と見えすそ」とある。
懐風藻、大学頭従五位下山田史三方の五言七夕に
金漢星榆冷 銀河月桂秋 靈姿理雲鬢 仙駕度潢流
窈窕鳴衣玉 玲瓏映彩舟 所悲明日夜 誰慰別離憂
とある。
|
|
|

| |
| 「うらなげましつ」...すべなきまでに... |
| |
| 『まてと、きみへ』 |
| 【歌意2001】 |
ひさかたの天の川原で、
ぬえ鳥のように物悲しく、織女は歎き泣いておられる
私には、どうすることもできないのに
一年後...待っていてくれ、としか... |
| |
| |
通釈は、天の川原で、牽牛を待つ織女が忍び泣く姿を、第三者が詠ったもの、とされているが
私には、一首の歌に想いが凝縮されることを基本とすれば、
その歌意解釈には、どうしても馴染めないものがあった
そもそも、長年結句の「乏」を、
異例の「寂しさ故に」のような固定観念を植え付けられていたからだろう
その解釈が中心になり、年に一度の逢瀬を「寂しさ」で解釈していることへの不自然さがあった
「ともし(乏し)」には、「不充分・少ない」などの意があり、
そこから、おそらく「心を満たされない」とする意訳になったのだろうが
やはり私には満足できなかった
だから、時間は掛かったが、何度も何度も読み返し情況を浮かべては、こうだああだ、と...
「ともし」には、同じ訓で「羨し」という意もある
『古義』など少数だが、その解釈もあれば、
『新考』では、「乏」を「かなしき」と訓じて、従来の意を補充する形までになっている
後に、「乏諸手丹」を『全註釈』の澤潟久孝博士が「すべなきまでに」と改訓し、
それ、現在の定訓ともいえるようになっていると思うが
それでも、歌の歌意には、その「改訓」の真意が反映されていないと思う
解釈は、相変わらず従来のままが多く、ならばより一層不自然さが目立つのだが、と思う
「すべなきまでに」とすれば、その歌意はかなり定まってくる
「手段がない」、「どうしようもない」という意の結句が、どうして反映されないのだろう
それは、「寂しい」という従来からの固定観念に押さえつけられているからではないだろうか
「すべなきまでに」とした『全註釈』の解釈で、私が自然に理解出来たのが
その「評語」にある、「牽牛の気持ちになって詠んだものだろう」という記述だった
それが、それまで読んでいた他の書で満足できなかった私の苛立ちを、一気に解放った
その視点で読めば、もうこの歌の歌意は、自然と感じることができる
これまで、第三者が、天の川原で寂しさに歎き泣く織女の様を詠ったもの、とする
そんな「無機質」な観察ではなく
「すべなきまでに」が語るのは、牽牛の「想い」を推し量ったからではないか、と...
そして、そこから導き出されるのは...
牽牛が織女の待つ岸へ向かい、
その岸で織女が年に一度の逢瀬に、雅澄は「嬉しさ」で泣き、といい
他では、その他に類のない逢瀬の仕方に、忍び泣く織女を「あわれ」と見る情景を詠う
そんな解釈ばかりだが、どうしてそんな解釈になるのだろう
決して、そんな歌ではない
『全註釈』で、「すべなきまでに」と提唱した澤潟久孝博士までも、同じ解釈のままだ
それが腑に落ちないが、私が感じたのは
この「すべなきまでに」で見えて来る歌意解釈は、
牽牛と織女の、別れの場面だった
哀しみに暮れる姿を、どうしてどの書も「牽牛が来るのを待つ」と重ねるのだろう
幸せなひと時を過ごし、そして別れの時になる
岸から立ち去ってゆく牽牛は、岸に残り歎き泣く織女の姿を見て、
いたたまれなくなる...
それを、第三者がその空間に「逢瀬と別れの時間」を詠いこんだものだと思う
だから、牽牛にしてみれば、そんな歎き悲しむ織女に、
また一年後の逢瀬を待ってもらうしかない、そのもどかしさ、すべのなさ
その気持ちが、たっぷりと表現されている
このように解釈できれば、上句と下句の繋がりが私には理解出来る
そして、俗にいう「七夕伝説」...「二星の逢瀬」が、
その再会にばかり焦点を当てるのに対し、このような「別れ」の場面もあるのだ、と
そして、それは一年に一度の逢瀬を「嬉しく」思うか「少な過ぎて、よけいにせつなく」思うか
その違いを詠い分けているのに過ぎない
しかし、このような感じ方も、この歌には出来るとすれば
織女が歎き悲しむ姿を、ただただなすすべもなく立ち去るしか出来ない牽牛
そして、それを客観的であっても、第三者が目に映す感情の豊かさには
万葉人の「情感」を思わずにはいられない
私のような素人の万葉歌ファンが、何を求めて一首を読むのか...
それは、ただ一つしかない
その歌にこめられた「情け」を、自分がどう受止められるか
それは、紛れもなく自分自身を知ることになる
俺は、こんな男だったのか、と呆然とすることもあれば
俺にも、こんなところがあったのか、と気づかされてこともある
後の時代の、いわゆる「歌人」たちの儀式的な「歌合」とか
「歌道家」のための「歌」ではない、人間味溢れる「歌」が、『万葉集』には多くある
誰も作者の真意など訊くこともできない
だから、歌そのものに、何を感じるか...それが何百年も伝わり、残ってきた歌の「本意」だと思う
誰がどう感じようと、それで自分を知り得るならば、誰にも批判はできないはずだ
勿論、恣意的な語義解釈は論外だが、
だからこそ、私は「愛読書」を何冊もの「古語辞典」に拘ってしまう... |
|
掲載日:2014.04.25.
| |
| 秋雑歌 七夕 |
| 久方之 天漢原丹 奴延鳥之 裏歎座都 乏諸手丹 |
| 久方の天の川原にぬえ鳥のうら歎げましつすべなきまでに |
| ひさかたの あまのかはらに ぬえどりの うらなげましつ すべなきまでに |
| 巻第十 2001 秋雑歌 七夕 柿本人麻呂歌集出 |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】〔130〕
【赤人集】〔162・149・270〕
【夫木和歌抄】〔12848〕
[古注釈書引用歌]
【袖中抄】〔739〕
[資料]
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
【七夕】〔中華民国[国立成功大学、成大宗教與文化学報 第七期 論文]〕
| 【2001】 語義 意味・活用・接続 |
| ひさかたの [久方之] 〔枕詞〕「天」にかかる |
| の [格助詞] |
[枕詞・序詞の終り] 一般的には「~にように」 |
| あまのかはらに [天漢原丹] 天の河原で |
| ぬえどりの [奴延鳥之] 〔枕詞〕 「うらなく」にかかる |
| ぬえどり [鵺鳥] |
小鳥の名、とらつぐみの異称・想像上の怪鳥 |
| うらなげましつ [裏歎座都] |
| うらなげ [うらなげく] |
「注記」「心(うら)」と四段「歎く」の語幹 |
| 参考(うらなく) |
([自カ下二・連用形] しのび泣く・また心の中で自然に泣けてくる) |
| 参考(うらなけす) |
([自サ変・連用形は「うらなけし」]) 「うらなく」に同じ |
| まし [座す・坐す] |
[補動サ四・連用形] 動詞の連用形について、尊敬の意を表す |
| つ [助動詞・つ] |
[完了・終止形] ~てしまう・~てしまった |
連用形につく |
| すべなきまでに [乏諸手丹] |
| すべなき [術無し] |
[形ク・連体形] なすべき手段がない・どうしようもない |
| までに |
[程度をはっきり表す] ~くらいに・~ほどに |
| 〔成立〕副助詞「まで」+格助詞「に」〔接続〕体言及びそれに準ずる語 |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [ぬえどりの] |
「ぬえ(鵺)」という鳥に模しての「枕詞」は、「ぬえどりの」「ぬえこどり」の二つある
「ぬえ」という鳥そのものにも、「とらつぐみ」の異称の他に、
想像上の怪鳥とある
「怪鳥」とは、具体的に古語辞典に書かれている表現をすると
「頭は猿、からだは狸、手足は虎、尾は蛇、鳴き声はとらつぐみに似る」という
枕詞として使われる「ぬえどりの」は、
とらつぐみの鳴き声が歎いているように聞こえることから、
「のどよふ(細々と鳴く)」「うらなく」「片恋」にかかり
「ぬえこどり」の方は、
とらつぐみの鳴き声が悲しげに聞こえることから「うらなく」にかかる
どちらも似たような情況を表現しての「枕詞」だと思うが
万葉の時代には、その使い分けの明確な意識があったのだろうか
夜間に「ヒョーヒョー」と悲しく寂しげな声で鳴く鳥らしい
『万葉集』中では、「ぬえどりの」は六例あるがすべてが「枕詞」としての用法 |
| |
| [うらなげ] |
現代の殆どの注釈書では、上表の語義解説の「参考」にある「うらなく」とする
「うら泣く」で一語になるが、その原義は、まさに原文「裏歎」のように
「うら(心)」に、自動詞四段「歎(なげ)く」だと思う
定訓で訓めば、ここの句は「うらな(泣)けましつ」になるが、
どうしても、原文の「裏歎く」に惹かれるものがあり、
そうなると、この句の訓は「うらなげ(歎)きましつ」としたくなる
(下段資料の『万葉集新考』で、このことが詳細に検証されており、惹かれるものがある)
でも、それでは字数だけでなく、語感がやはりしっくりしないようだが...
だから、どれも「歎」の表記で「泣く」に訳すことになる
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕では、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕の補注を引用し、
この問題の整理をしているが、
『大系』は、「うらなげき」と訓むべきだが、やはり字余りが面白くないらしく
幾つかの用例を踏まえて、「うらなけ」としている
ここで、さらにややこしくなるのが、四段「泣く」と、下二段「泣く」となることだ
「うら」に続く四段「なく」であれば、「うらなき」となり
下二段「なく」であれば、「うらなけ」となる
それが、現代注釈書においても、違いが出ている
「うらなきましつ」とするのが、
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波文庫校訂版、平成25年~〕の両新大系
そして、『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕、
『万葉集校注』〔伊藤博、角川文庫、平成13年23版〕
「うらなけましつ」が、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕、
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕
古注釈については「下段資料」による
なお、鎌倉初期の歌学書「袖中抄」に、
この歌が載っていることを、幾つかの書がいう
下段の [古注釈書引用歌] に、紹介する
そこでは「歎(なげ)く」をそのまま用い、
しかしその字数の調整からなのか「つつ」につなげている
「うらなげきつつ」で、確かに字数は整うが
それでも、今度は尊敬の補助動詞「座す」が消えてしまう
この「袖中抄」は、当時ではかなり有力な「歌学書」とされており
その中で、この一首が、訓を違えて引用されているのは
まだ訓の不明な万葉歌の多かった時代、その「訳」に触れてみたい気持ちになった
「歎く」をそのまま使った訓解釈として、『万葉集新考』の見解は、参考になる
|
| |
| [すべなき] |
原文「乏」は、旧訓で「ともしき」と訓まれていた
下段の資料でも、その改訓がなされたのは、『万葉集注釈』の澤潟久孝博士で、
その著『万葉歌人の誕生』に依るものらしい
「乏」が「」と同じく「スベナシ」と訓み得ることが述べられている、という
それが、現在に至っている |
| |
| [までに] |
「までに」の「諸手(まで)」の訓については、
「義訓」の一種で、「真手」つまり「両手」を意味し
「左右手」、「二手」と表記して「まて(まで)」と訓むのと同じ |
| |
| |
[古注釈書引用歌]
『万葉代匠記』
【歌学書袖中抄(文治二、三年頃[1186,1187]作、顕昭[1130~1209])】
| 鎌倉初期の和歌注釈書。《顕秘抄》と題する3巻本もあるが、一般にはそれを増補したとみられる20巻本をさす。1186‐87年(文治2‐3)ころ顕昭によって著され仁和寺守覚法親王に奉られた。《万葉集》以降《堀河百首》にいたる時期の和歌から約300の難解な語句を選び,百数十に及ぶ和・漢・仏書を駆使して綿密に考証。顕昭の学風を最もよく伝え,《奥儀(おうぎ)抄》《袋草紙》とならぶ六条家歌学の代表的著作 |
| 新編国歌大観第五巻-299 袖中抄[日本歌学大系別巻二] |
久かたの天の河原にぬえ鳥のうらなげきつつともしきまでに
|
| 第十六 739 |
|
| |
|
|
| 掲題歌[2001]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】
| 新編私家集大成第一巻-4 人麿Ⅲ [冷泉家時雨亭叢書『素寂本私家集西山本私家集』] |
ヒサカタノアマノカハラニヌエトリノ ウチ(ラ)ナキシツモ(恋)シキマテニ
|
| 柿本人麿集上 秋部 七夕 万十 130 |
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
|
| ひさかたのあまのかはらにゐる鳥の うらひれおりて心くるしきまて」一〇 |
| 新編私家集大成第一巻-新編増補 赤人集Ⅲ[陽明文庫蔵三十六人集] あきのさう 162 |
| ひさかたのあまのかはらにぬ[る](ママ)とりの うらひれをりつくるしきまてに |
| 同第一巻-6 赤人集Ⅱ[書陵部蔵三十六人集] 秋雑歌 149 |
| ひさかたのあまのかはらにぬるとりの うらひ[をり](ママ)つくるしきまてに |
| 同第一巻-5 赤人集Ⅰあかひと[西本願寺蔵三十六人集] あきのさふのうた 270 |
| ひさかたのあまのかはらにぬるとりのうらびれをりつくるしきまでに |
| 新編国歌大観第三巻-2 赤人集[西本願寺蔵三十六人集] あきのざふのうた 270 |
【夫木和歌抄 (延慶三年頃[1310年頃]、撰勝間田長清)】
| 編国歌大観第ニ巻16[静嘉堂文庫蔵本] |
久方の天のかはらにぬえ鳥のうらびれ[おり](ママ)つくるしきまでに
|
| 巻第二十七 動物部 鳥 鵼 題不知 万十 赤人 12848 |
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「久方之天漢原丹奴延鳥之裏歎座津乏諸手丹」
「ヒサカタノ アマノカハラニ ヌエトリノ ウラナキマシツ トモシキマテニ」(「【】」は編集、歌番は旧) |
〔本文〕頭注に、『袖中抄』、第十六「万葉哥ニ ヒサカタノアマノカワラニヌエトリノウラナケキツヽトモシキマテニ」
赤人集「ひさかたのあまのかはらにぬえとりのうらひをりつくるしきまてに」
|
| 「久」 |
『類聚古集』ナシ。墨「○」符アリ。右ニ墨「久」アリ |
| 「歎」 |
『神田本』「欲」。左ニ「イ歎」アリ |
| 「津」 |
『元暦校本・類聚古集・神田本』「都」 |
| 〔訓〕 |
| ヒサカタノ |
『活字附訓本』「タ」ナシ |
| アマノカハラニ |
『大矢本』「アマノカワラニ」 |
| ヌエトリノ |
『神田本』「ヌヘトリノ」
『細井本』「ヌヱトリノ」 |
| ウラナキマシツ |
『元暦校本』「うらなけきしつ」。「ら」ノ右ニ赭「ラ」アリ。「つ」ノ右ニ赭「テ」アリ
『類聚古集』「うらなけきしつ」。「きしつ」ノ右ニ朱「サヽツ」アリ
『西本願寺本』「ナキ」モト青。「歎」ノ左ニ「フレ」アリ
『神田本』「ウラナケキシツ」。「欲座都」ノ左ニ「ナケマシツ 或本」アリ
『温故堂本』「歎」ノ左ニ「フレ」アリ
『大矢本・京都大学本』「ナキ」青 |
| トモシキマテニ |
『元暦校本』「も」ナシ。右ニ墨「も」アリ。「と」ノ下ニ墨「○」符アリ
『類聚古集』「ともなきまてに」
『神田本』「乏」ノ左ニ「トモナキ 或本」アリ |
| 〔諸説〕 |
| ○[ウラナキマシツ]『代匠記精撰本』「ウラナケマシツ」『童蒙抄』「ウラナキヲリツ」 |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [2001] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
| |
〔ひさかたのあまのかはらにぬえとりのうらなきましつともしきまてに 〕
久方之天漢原丹奴延鳥之裏歎[イふれ]座津乏諸手丹
|
ぬえ鳥の「うらなき」と表現し、そのもの悲しさを言うのだが
「よそ目にもともしき」というと、その解釈に悩んでしまう
心が満たされず、ということなのだろうが... |
| ひさかたのあまの ぬえ鳥のはうらなきといはん諷詞也七夕の妻戀て鳴てまし/\つらんよそめにも乏く悲き迄と也乏くはさひしき心也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
| |
〔ヒサカタノアマノカハラニヌエトリノウラナキマシツトモシキマテニ 〕
久方之天漢原丹奴延鳥之裏歎座津乏諸手丹 |
「袖中抄」のみが「歎」の原文そのものの「なげき」を表現するが、その「うらなげき」と「うらなき」は同じことだ、と言うのかな
結句の「ともしきまでに」は、珍しい為に、心引かれる、というような解釈だろうか
佳人の立派な姿よりは、少しうらぶれている様子が...というところ、その意味が、私の今の理解力では、なかなか掴めない |
裏歎は第一の軍王の歌に注せし如くウラナケと讀べし、袖中抄にはうらなげきつゝとあり、つゝこそ叶はねどなけとなげきとは具略の異のみにて替らず、落句はめづらしきまでになり、織女の歎くをめづらしと云はむは本意ならぬやうなれど、佳人も痛くゑみさかえてほこりがなるよりは少しうらぶれたる樣なるに艶なる所は添ひぬべし、マテニと云詞はさるへしと云ひはつるにあらぬ意なり、諸手と借てかけるも左右二手等に同じ、
|
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
| |
〔ひさかたの、あまのかはらに、ぬえどりの、うらなきをりつ、ともしきまでに 〕
久方之天漢原丹奴延鳥之裏歎座津乏諸手丹 |
「うらなきをりつ」は理解出来るが、なぜ「ともしき」なのか、その語義がすんなり結びつかなくて、この書でも「寂しい」とする意味をこの歌に当てているが、「乏」という表記はともかく、「ともし」と訓じて、「寂しい」は、やはり「満たされない」という意からなのだろう
第三者の視点と言う詠い方は、前歌と同じだが、実際にその姿を見て、その心の内まで推し量るのは、他に解釈のしようがなかったのだろうか |
| 久方の天の河原と云はん序也。戀ひわびをる事の久敷と云意をこめて也。ぬえ鳥のうらなきは、わがうら泣きと云意也。うらなくと云ふ序に、ぬえ鳥のとはよめり。此序詞は前にも毎度ありし也。うらなきとは、うらは發語にも云ひ、又忍びしほれて泣くと云ふ意にもよめる也。乏はともほしきと云意、此歌にては寂しき意也。左右の手と書きても、までと訓む、二手と書きても讀む義をもて、諸手と書きてまでと也。清濁は其義に從ひて讀む也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
| |
久方之、 冠辭
天漢原丹[アマツカハラニ]、奴延鳥之、 冠辭
裏歎座津[ウラナキマシツ]、乏諸手丹[トモシキマデニ] |
歌意を丁寧に書こうとするなら、この書のような簡潔だが本意を理解出来るものであるべきだ、と思う
「天の川」で、「一年に一度」の逢瀬を具体的に表現しているので、それがこれまでの習慣なのに、何故「ぬえ鳥」の「うらなく」ような悲しげな姿になるのだろう
それを「夜の遠き」を「わびましつ」という
この書での根本的な解釈は、「一年に一度の逢瀬」では、少ないと、歎いている、としているのだろう |
| 一年に一たび逢ます事の遠くすくなければ奴延鳥の如うらなきまして二星の逢夜の遠きをわびましつとなり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
| |
〔ひさかたの。あまのがはらに。ぬえとりの。うらなけましつ。ともしきまでに。 〕
久方之。天漢原丹。奴延鳥之。裏歎座津。乏諸手丹。 |
「年に一度の逢瀬」これが「ともし」と、珍しいまでの「恋」
「うらなけ」の用例は解る上句と下句の繋がり方に、これまでの書では、どれも述べていないのが、私には不満だ
|
卷一、卜歎居者[ウラナケヲレバ]、卷十七、宇良奈氣之都追[ウラナケシツツ]と有り。契沖云、トモシキマデニは、期かる戀は類ひ少なく、珍しきまでにと言ふなりと言へり。諸手は眞手、或は左右と書けるに同じ義なり。
參考 ○裏歎座津(代)ウラナケ (考)ウラナキマシツ (古)略に同じ、但し「ケ」濁る(新)ウラナゲキマシツ ○乏諸手丹(新)「哀」カナシキマデニ。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
| |
〔ヒサカタノ。アマノガハラニ。ヌエトリノ。ウラナゲマシツ。トモシキマデニ。〕
久方之天漢原丹奴延鳥之裏歎座津乏諸手丹
|
この歌意では、前の歌〔2000〕と一組のように、作者の視点が今度は、牽牛を待つ織女の側で詠われている感じだ
前歌〔2000〕が、牽牛を送り出した「天の川」の岸から、その到着した後のことを思い遣ったのに対して、この歌では、織女が、牽牛がやってくるのを待つ岸での様子を描く
しかし、従来の解釈のような「寂しさ」や「悲しみ」はない
それは、「歎き」を嬉しい時にも悲しいときにもつく「ため息」のようなものとし、さらに「ともし」を、確かにその語義の用法の一つである「うらやましい」とすることで、この歌は、一変した |
奴延鳥之[ヌエトリノ]は、枕詞なり、かくつゞくる謂は既く一(ノ)卷軍王(ノ)歌に委(ク)説り、
○裏歎[ウラナゲ]とは、裏は表の對にて、裏[シノヒ]に物することなり、歎[ナゲ]は、程無あはむと長き息をつきて歎美[ナゲク]よしなり、奈宜久[ナゲク]とは、喜しき事にも、哀しき事にも、嗚呼[アヽ]と長き息をつく事なり、
○乏諸手丹[トボシキマデニ]は、うらやましく思はるるまでにと云意なるべし 契冲、かゝるこひはたぐひすくなく、めづらしきまでにと云なり、と云るはいかゞ、
○歌(ノ)意は、外[ヨソ]に居て見やる人のうらやましく思はるゝまでに、天(ノ)河原に出立て、彦星の來まさむを、心に喜[ウレ]しく下待て、棚機女の裏[シノビ]に歎美[ナゲキ]座つるよ、と云ならむか、
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
| |
〔(久方の)あまのかはらに(ぬえどりの)裏歎[ウラナゲキ]ましつ乏[カナシキ]までに 〕
久方之天漢原丹奴延鳥之裏歎座津乏諸手丹 |
「うらなげき」への検証、まさに私が感じていたことと同じだった
私も、この説に手を挙げてしまう |
卷一軍王見山作歌にヌエコドリ卜歎居者とあり又此卷の下に
よしゑやしただならずともぬえ鳥の浦嘆/居[ヲリト]つげむ子もがも
又卷十七なる述戀緒歌にヌエ鳥ノ宇良奈氣之都追とあり。さて卷一なる卜歎居者を舊訓にウラナケヲレバとよめり。契沖は此訓に從ひて
奴要子鳥は子は添へたる字にて唯ヌエ鳥なり。ウラナケヲレバとは下なげく也。高く聲をも立ず喉聲にてつぶやくやうに啼鳥なれば我故郷を戀とて打うめかるゝに喩て云へり。後にも今のごとく喩てよめる歌多し。或點にウラナキとあるは同じ心なれど第十に七夕の歌の中に二首今と同じく歎の字を用、十七には奴要鳥能宇良奈氣之都追とあればウラナケなり
といひ、眞淵の冠辭考にはウラナキヲレバ、ウラナケマシツ、ウラナケシツツとよみて
こはかれが聲のかなしくうらめしげなるを人のをらびなくに譬ておけり。古事記にアヲヤマニヌエハナキとよみ給ふも物おもふ時に此聲を聞ていよゝ愁ましたまへる意なり○卷五にヌエ鳥ノノドヨビヲルニ云々これも哭にたとへたる意は右に同じ。さて裏嘆とかきノドヨビともいへるをもて或人は隱聲になく鳥ならんといひしを……よりておもふに和名抄に鵼怪鳥也とあれば梟などの類にて夜鳴ならん。且喉呼とも書るは隱聲なるにはあらでからごゑに鳴かたにていふ也けり。ウラ鳴は恨鳴也
といひ、おなじ人の萬葉考に
鵼のなく音は恨をらぶが如きよし冠辭考にいひつ。人のウラナキは下に歎くにて忍音をいへり。然れば鵼よりは恨鳴といひ受る言は下歎なり
といひ、宣長の玉(ノ)小琴には
卜歎居者 本のまゝ(○ウラナケ)に訓べし
といひ、略解にもウラナケとよめり。御杖の燈には『ウラナゲヲレバとよむべし』といへり。即ケを濁りてよめり。古義にも濁りてウラナゲとよみ、さて
卜歎、浦歎など書るはともに借字、裏歎と書るぞ正字にてしのびに歎きてあらはさぬを云り。……裏はウラガナシ、ウラグハシなどのウラと同意なり。歎は字(ノ)意の如し。さればケの言濁て唱べし(但し十七に宇良奈氣之都追と氣の清音の假字を用ひたるは正しからじ)
といへり。案ずるに眞淵の如くウラナキヲレバとよまば又ウラナキマシツ、ウラナキシツツとよまざるべからず。即此をウラナキとよみ彼をウラナケとよむべきにあらず。次にウラナクルといふ語あるべしともおぼえねば舊訓、契沖、宣長、千蔭の如くウラナケヲレバ、ウラナケマシツ、ウラナケシツツとよむべきにあらず。次にナゲキはもと長息の約なれば略してナゲとはいふべからず。されば御杖雅澄の如くウラナゲとよむべきにあらず。然らばウラナキヲレバとよむべきかといふに假字書なるを除きて三箇處ともに歎の字を書きて哭の字を書かざる事、卷十七に字良奈氣とかける氣はキとよみがたき事以上二つの理由によればウラナキともよむべからず。されば字のまゝにウラナゲキとよみて卷十七なる宇良奈氣之都追は氣の下に伎をおとせりとすべし。本集には濁音の語に清音の字をあてたる例少からざればゲに氣を宛てたるは訝るに足らず。又ウラナゲキとよめば四箇處ともに八言の句となれどこれはた疚しとすべからず。さてそのウラナゲキは裏歎にてかのノドヨビとおなじく呻吟の意なり。眞淵が恨鳴の意としたるは非なり。ウラミを略してウラといふべけむや○結句の乏は哀などの誤としてカナシキマデニとよむべし○この歌は織女のさまをよめるなり |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| |
久方の天の川原に、ぬえ鳥のうらなげましつ。ともしきまでに |
表記されている文字だけの「解釈」であり、面白味がない |
| |
天の川原で、眞底から、歎いて入らつしやる。他に比類のない程にひどく。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
| |
〔久方の 天の川原に ぬえ鳥の うらなげましつ ともしきまでに〕
ヒサカタノ アマノカハラニ ヌエトリノ ウラナゲマシツ トモシキマデニ
久方之天漢原丹奴延鳥之裏歎座津乏諸手丹 |
本当にこの歌の歌意を量るのに、確かに表現の「表」は一律になろうが、それを如何に読む者が感じるか、その一例を挙げるのが注釈書の役目の一つだと思う
しかし、こうした表面的な解釈というのは、語義説明だけで充分であり、何も「注釈書」と銘打つ必要はない
この歌を、このような解釈で終らせるから、「評」にいうように「優れた歌ではない」としてしまう
|
(久方之)天ノ川原デ、棚機ハ彦星ノ來ルノヲ待ツテ、コンナニ戀シガルノハ珍ラシク思ハレル程ニ、(奴延鳥之)心デ歎息シテヰル。
○奴延鳥之裏歎座津[ヌエトリノウラナゲマシツ――卷一に奴要子鳥裏歎居者[ヌエコトリウラナゲヲレバ(五)とあるのと同じで、奴延鳥之[ヌエドリノ]はウラナゲの枕詞。ウラナゲは心の中に歎くこと。この下にも奴延鳥浦嘆居[ヌエトリノウラナゲヲリト](二〇三一)とあり、卷十七に奴要鳥能宇艮奈氣之郡追[ヌエドリノウラナゲシツツ](三九七八)ともある。
○乏諸手丹[トモシキマデニ]――トモシは代匠記初稿本に、「かかるこひは、たぐひすくなく、めづらしきまでになり」とある意であらう。古義は羨ましきまでにの意とし、新考は「哀などの誤としてカナシキマデニとよむべし」とある。諸手をマデとよむのは、左右・二手をマデとよむのと同じで、兩手をマデといつたのである。
〔評〕 これは彦星を待ちわぶる、織女の状態を見てゐる、第三者の心を述べたものである。優れた歌ではない。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
| |
〔ひさかたの 天の河原に、ぬえ鳥の うら歎けましつ。すべなきまでに。〕
ヒサカタノ アマノガハラニ ヌエドリノ ウラナケマシツ スベナキマデニ
久方之天漢原丹奴延鳥之裏歎座津乏諸手丹 |
この書での新味といえば、作者が見ているだろう織女の歎き泣く姿ではなく、作者はその織女の姿を見る牽牛の気持ちになって詠った、とする点だ
であれば、どうして「あんなに嘆き悲しむ」のか、と詠う気持ちが理解出来る
第三者である作者が客観的に織女の姿を見て詠うだけでは、上句と下句の繋がり具合が、私には理解出来なかった
この解釈は、参考になる |
【譯】大空の天の川原で、ぬえ鳥のように、心で泣いておいでになつた。しかたのないまでに。
【釋】奴延鳥之 ヌエドリノ。枕詞。譬喩によつて、ウラナケに冠する。
裏歎座都 ウラナケマシツ。ウラナケは、心中に泣かれるの意。「奴要子鳥[ヌエコドリ] 裏歎居者[ウラナケヲレバ]」(卷一、五)、「奴延鳥[ヌエドリノ] 浦嘆居[ウラナケヲリト]」(卷十、二〇三一)、「奴要鳥能[ヌエドリノ] 宇良奈氣之都追[ウラナケシツツ]」(卷十七、三九七八)など。これは織女星のふるまいを敍している。句切。
乏諸手丹 スベナキマデニ。乏は、澤瀉博士の説に、スベナキと讀むべしとする。「及乏[スベナキマデニ]」(卷九、一七〇二)參照。諸手は、左右手、二手などと同じく、眞手の義をもつて、マデに當てて書いている。
【評語】織女星の上を詠んでいる。その牽牛星を慕つて歎いている樣の敍述である。牽牛星の心になつて詠んでいるのだろう。歎いているのを見て、たまらなくなつた情である。
|
| 『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕 |
「評釈」私見 |
| |
ひさかたの天漢原にぬえ鳥のうら歎けましつ羨しきまでに |
「ともし」の「うらやましい」とする語義を用いれば、このような解釈になるだろうが、では「うらなげく」は、これでいいのだろうか
牽牛が来るのを待ちかねて、「忍び音に泣いて」おられた、と
鹿持雅澄の解釈そのものだ |
【譯】天の河原にゐて、棚機は彦星の来るのを待ちかねて、忍び音に泣いてをられた、よそ目に見ても羨ましい仲と思はれるほどに。
【評】織女の彦星を待ち戀ふる様を想像して、その仲らひのこまやかさを読んだものであらう。結句は適切の用語といひ難く、解釈上、異説を生じてゐるが、古義の説が穏やかであらう。
【語】○ぬえ鳥の 枕詞。「ぬえこどり」(五)「うらなけをりて」(二〇三一)参照。
○ともしきまでに 外(よそ)にゐて見る人の羨しく思はれるまでと解する説(古義)、この「ともし」は珍しいの意とし、こんな戀はたぐひ少く珍しいまでにとする説(代匠記)、その他誤字説によつて、哀しきまでにとする説(新考)などがあるが、古義の説に従ひたい。 |
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
| |
〔ひさかたの天の川原にぬえ鳥のうら歎けましつともしきまでに 〕
ヒサカタノ アマノカハラニ ヌエドリノ ウラナケマシツ トモシキマデニ
久方之天漢原丹奴延鳥之裏歎座津乏諸手丹 |
これが、従来からの解釈のままで
私には、第三者が織女を見て描写するには不自然な表現だと感じていた
しかし、どうして『全註釈』のような解釈が誰もいないのだろう第三者が、織女のその「うらなげく」姿を、牽牛の気持ちを思って詠ったとすれば、その不自然さも解消されると思うのに... |
【大意】ヒサカタノ(枕詞)天の川原にヌエドリノ(枕詞)なくが如くに、心から歎いて居られた。淋しく思はれるほどに。
【作意】織女の悲戀を歌つて居るのである。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
| |
〔ひさかたの 天の河原に ぬえ鳥の うらなきましつ すべなきまでに 〕
ヒサカタノ アマノカハラニ ヌエトリノ ウラナキマシツ スベナキマデニ
久方之天漢原丹奴延鳥之裏歎座都乏諸手丹 (『元暦校本』) |
「歎」を「泣く」と同じ語義として解釈している時点で、『新考』の解釈に及ばない
|
【口訳】天の河原でぬえ鳥のやうに織女は下泣きに泣いてをられた。せんすべもない程に。
【訓釈】ぬえ鳥の―既出(2・196)。「ぬえこ鳥」(1・5)ともいふ。「うらなき」の枕詞。
うらなきましつ―「歎」を『元暦校本・類聚古集・紀州本』ナケキ、『西本願寺本(青)』以後ナキ、『代匠記』ナケとしたが、ナキと訓むべきこと前(1・5)に述べた。ナケと訓で下二段活用で自然に泣かれる意とする説が『全註釈』などにあり、『古典大系本補注』にも「解キ(他動詞)・解ケ(自動詞)、缺キ(他動詞)・缺ケ(自動詞)、放キ(他動詞)・割ケ(自動詞)など四段活用と下二段活用との対立がある際、下二段活用が自然可能の意味になるものは奈良時代にも例がすくなくない。従つて、ナケを、おのずと泣ける意にとることは差支えない」とある。しかし、前にも述べたやうに「泣く」の下二段は使役の意のものであり、右にあげた四段と下二段とは前者がいづれも他動詞であるが、「泣く」(十四・三三六二)、「浮く」(十七・三九九一)、「向く」(廿・四三九八)、「満つ」(十八・四〇五七)などは四段の方も自動詞であつて同じ例とはいひ難く、且つ今の場合など作者自身の事ではないのだからしひて所能の語に解くべき必要はないのである。即ち仙覚の改訓に従ひウラナキマシツと訓み、下泣きに泣いていらつしやる、の意に解くべきである。「都」の字、『元暦校本・類聚古集・紀州本』による。『西』以後「津」とある。
すべなきまでに―旧訓トモシキマテニとあり、諸注もそえに従つたが、「ともし」では少ない意(一八二〇)としても、羨しい意(一・五五)としても、心惹かれる意(二・一六二)としてもここに適切でない。ここは前の「及乏」(九・一七〇二と同じくスベナキマデニと訓むべきである。『増訂本全註釈』、『古典大系本』もこの私案に従はれてゐる。「諸手」をマデと訓ませたのはこれ一例であるが、「二手」(一九〇二)』、「左右手」(二三二七)と同様に用ゐたものである。
【考】赤人集に「ぬるとりのうらひをりつくるしきまでに」、流布本「ぬるとものうらひれをりつ」とあり。
夫木抄(廿七「鵼」)「うらひれをりつくるしきまでに」赤人とある。
|
|
|

| |
| 「すぎてくべしや」...こともつげなむ... |
| |
| 『おもひをのこし』 |
| 【歌意2002】 |
私が恋しく思っていることを、あの人は知っているだろうに、
舟が通り過ぎるように、何も残さず素通りをするなんて...
それはないではないか
せめて言伝だけでも伝えてほしいものを
この思いばかりを残して... |
| |
| |
この歌、「七夕」歌として、確かに配されているが
どうして「七夕」歌に見合うのか不思議でならない
古注釈書から何度も何度も、この歌の解釈を読むが
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕だけが、明確にそれを否定している
私も同じように思う
他の書では、まるで「牽牛」と「織女」の「片恋」であるかのような歌意も多く
そこに「年に一度の逢瀬」を、普通の男女の「相聞」と重ねる無理な解釈が多い
では、何故通常の「相聞歌」としないのだろう
その視点で解釈すれば、無理はなくなる
ただただ、「七夕歌」という部立てに、どうしても抑えられてしまうのか...
『万葉集』の部立ての分類には、かなりの曖昧さも指摘されている
そこをさんざんに突きながら、どうしてこの歌には、厳格に従うのだろう
この一首、部立てを除けば、どこにも「七夕」を必然とする「語句」はない
下段の「資料」で、古注釈書に歌意として受け入れられても、
その解説で、「彦星」や「織女」とされると...とても不思議な気がする
さらに、この歌の解釈には、大きく解釈の分かれるところが二箇所ある
一つは、「つま」という語の解釈
「七夕」歌ということを考えずにいうと、
この「つま」を「男」とするか「女」とするか...
「七夕」歌であっても、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕で言うように、
「ツマは、夫の意とする解もあるが、織女星のこととしても通ずるから、文字通りに解するのが順当である」
といい、その「男」か「女」かの解釈が二分されていることを、に当然のように述べているが、
これが、一般の「相聞歌」であれば、そうはならないと思う
「七夕伝説は」は、幾つかのパターンがあり、牽牛が天の川を渡ることも、
織女が天の川を渡ることも、どちらも詠われている
だから、『全註釈』のいうように、どちらを採っても、歌意は成り立つということだが
この歌の内容までもが、果たして「七夕」の歌に沿うものかどうか、と言えば
そこには疑問だらけだ
「年に一度の逢瀬」を、このような人間世界の「相聞」のように詠うものだろうか
少なくとも、この万葉の時代であっても、「七夕」は一首の儀式めいた催事でもあったはずだ
そこに求められるのは、あくまで「年に一度の逢瀬(催事)」であり、
そこからいくらバリエーションがあるにしても、まるで「片恋」のような展開にはならない
この掲題歌に感じられるのは、
| 2002改意 |
私(男)の恋心を、あなたはご存知のはずなのに、
まるで沖の船が目の前を行き交うように、素知らぬ顔をしておられる
そうやって、どんどん時が経つのに、あなたから何もご返事がありません
せめて、何らかの言伝なりとも、欲しいものです |
こうした内容であれば、むしろ「女」歌の方が似合うとされるかもしれないが
せめて、女からの「言伝」を待つ、というのは、私には男の願いの方が似合うと思う
言い方は語弊があるかもしれないが、逆の立場であれば
「言伝」ではなく、ほんの少しの間でも立ち寄っては、
はっきりとした返事を聞かせて欲しい、となる方が「歌」らしくなる
あくまで、これは私が感じたもので、それが一般的ではないことは承知している
しかし、その解釈は、少なくとも「牽牛と織女」の「年に一度の逢瀬」に合わせたりしない
それに、少なからず「つま」の「嬬」という表記は、数ある「つま」の表記の中で用いられ
その意味を無視はできないと思う
人麿集や赤人集では、「いも」と伝わっている
そこからも、私の恋心を知る「女」というのが、古集を覗けば解るのではないだろうか
もう一つの大きな解釈の相違点として、「片恋」のように解するのと
逆に、さっき逢ったばかりなのに、またすぐにでも逢いたい、とする解釈
それは『童蒙抄』が述べている
そして、真淵に至っては、その『万葉考』で、
「行く舟の」は、「わかれのとき」と解釈し
今年の「逢瀬」は終った、来年また逢おう、と
こうした解釈には、「七夕」歌の伝説の意味を反映させなければならないものを感じる
「牽牛と織女」が、相思相愛でありながら、年に一度しか逢えないので、悲恋物語になる
その前提があるから、このような解釈になってしまうのではないだろうか
そこに「こともつげなむ」(荷田春満は訓まず、真淵は「なく」とする)が薄らいでいる
つまり、また来年も逢おうと言うのだから、「言伝」は要らない、とでもいうように...
これが通常の「相聞歌」であれば、この結句こそ、大きな意味を持つものだと思うのに
その解釈を重視すれば、やはりこの歌が「七夕」歌に似つかわしくないことが理解出来る
雅澄の『万葉集古義』の解釈は、それ自体が一つのドラマのようだ
織女が、侍女たちをそばにおき、岸辺で牽牛の来る船を待つ
舟が行き過ぎるよに時が過ぎてゆく、それでも牽牛は来ない
侍女たちがいう、
遅れるなら、そのことを言伝に送ってくるものを
それがないと言うことは、きっと来るでしょう、と
そして、沖からこちらに向かってくる舟には、牽牛が乗っているのでは、と期待をこめて...
この侍女たちのさまを見て、織女が詠ったものと解釈している
なるほど、歌の解釈と言うのは、「字数」の制限があるものではない
このように、注釈しようことも、出来るものだと教えてくれる
この解釈と対照的なのが、『万葉集私注』といえるだろう
下段資料に、その「大意」はあるが、その歌意には、かなりの不満がある
織女が、まるで灯台のような存在になっている
舟にいる牽牛の視点から、岸辺にはっきりと織女を見る
だから、行く舟のように、素通りはできない、という
そこには、想いをそれぞれ持つ「男と女」の心が描かれていない
少々くどい解釈のような雅澄の方が、歌を丁寧に感じようとしている
一体、「たなばた」の歌とは...
『万葉集』だけでなく、以降にも多くの歌集に詠われる「七夕歌」
今は、まだそこまで手が回らないが、
いつか、必ず「全歌集の七夕歌」シリーズでも書いてみたいものだ
『万葉集注釈』の澤潟久孝博士は、この掲題歌と、
「人妻故に」との表現を持つ、次の歌を、「七夕」歌ではないとする
私も、同感だ
今日は、また繋ぎの歌で「一日一首」を書こうと思っていたが
昨日今日と、解釈を終えられたことで、そろそろ「万葉歌」に戻ろうと思う
このGW中に、何とか帳尻は合わせられそうだ
|
|
掲載日:2014.04.26.
| |
| 秋雑歌 七夕 |
| 吾戀 嬬者知遠 徃船乃 過而應来哉 事毛告火 |
| 我が恋を嬬は知れるを行く舟の過ぎて来べしや言も告げなむ |
| あがこひを つまはしれるを ゆくふねの すぎてくべしや こともつげなむ |
| 巻第十 2002 秋雑歌 七夕 柿本人麻呂歌集出 |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】〔526〕
【赤人集】〔163・150・271〕
[資料]
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
【七夕】〔中華民国[国立成功大学、成大宗教與文化学報 第七期 論文]〕
| 【2002】 語義 意味・活用・接続 |
| あがこひを [吾戀] 私の「恋心」を |
| つまはしれるを [嬬者知遠] |
| つま [夫・妻] |
妻、または恋人である男への呼称・夫、または恋人である女への呼称 |
| しれ [知る] |
[自ラ四・已然形] わかる・知る |
| る [助動詞・り] |
[完了・連体形] ~ている・~てある |
已然形につく |
| を [接続助詞] |
[逆接] ~のに (軽い逆接の確定) |
連体形につく |
| ゆくふねの [徃船乃] 〔枕詞〕「すぎ」にかかる |
| すぎてくべしや [過而應来哉] |
| すぎ [過ぐ] |
[自ガ上二・連用形] 通り過ぎる・時が過ぎる・経過する |
| て [接続助詞] |
[並立] ~て |
連用形につく |
| く [来(く)] |
[自カ変・終止形] 来る・行く・通う |
| べし [助動詞・べし] |
[推量(当然)・終止形] ~がよい・~が適当だ |
終止形につく |
| や [終助詞] |
[反語] ~(だろう)か(いや、~ない) |
終止形につく |
| こともつげなむ [事毛告火] |
| つげ [告ぐ] |
[他ガ下二・未然形] 知らせる・伝える |
| なむ [終助詞] |
[「なん」とも] ~てほしい・~てもらいたい |
未然形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [つま] |
私たちの馴染んでいる「つま」という語感は、男から女への呼称としているものだが、
万葉の時代は、女から男への呼称にも、用いられている
その一例が、巻第二の〔153〕倭大后の歌で、
|
| 挽歌 太后御歌一首 |
| 鯨魚取 淡海乃海乎 奥放而 榜来船 邊附而 榜来船 奥津加伊 痛勿波祢曽 邊津加伊 痛莫波祢曽 若草乃 嬬之 念鳥立 |
| 鯨魚取り 近江の海を 沖放けて 漕ぎ来る船 辺付きて 漕ぎ来る船 沖つ櫂 いたくな撥ねそ 辺つ櫂 いたくな撥ねそ 若草の 夫の 思ふ鳥立つ |
いさなとり あふみのうみを おきさけて こぎきたるふね へつきて こぎくるふね おきつかい いたくなはねそ へつかい いたくなはねそ わかくさの つまの
おもふとりたつ |
| 巻第二 153 挽歌 倭皇后 |
〔大意〕『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕より
淡海の海の遠く沖辺を漕いで来る舟よ
岸辺について漕いで来る舟よ
沖の櫂もひどく水を撥ねないでおくれ
岸辺の櫂もひどく水を撥ねないでおくれ
なつかしいわが夫の愛していた鳥が、
驚いて飛び立つから... |
こうした例からも、この掲題歌の「つま」を「牽牛」とし
「ゆくふね」をその牽牛が乗っている舟、と解する書が多い
しかし、古注釈書などでは、旧訓で「いも」と詠われており、
「人麻呂集」も「赤人集」も「いも」として詠っている
それは、必然的に、この「つま」に当るのが「女」である解釈に繋がってくる
だから、古注釈の多くは、「牽牛」の気持ちと見立て、
「織女」は、私の「恋心」を知っているはずなのに...としている
これは、先日の『懐風藻』山田三方の「五言七夕」のように、
織女が舟に乗ってやってくる、パターンと解しているものだ
|
| |
| [ゆくふねの] |
これを実景とするのは、
『万葉代匠記(初稿本)』〔契沖(1640~1701)、貞亨四年(1687)成〕、
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波文庫校訂版、平成25年~〕、
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕など
枕詞と解する注釈書は、古注釈書を除く現代の書では、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕、
『万葉集校注』〔伊藤博、角川文庫、平成13年23版〕などがある
実景の方が、一般的に解釈でも通りがいいようには思うが、
そもそも、この歌の解釈に「七夕」を当てるのは、どうも不似合いのように思える
年に一度の「逢瀬」と言えば、厳粛な儀式の要素も多分にある
それが、この歌の歌意に沿えば、少々俗っぽい感じがする
実景とすると、尚更その感が強くなる
私は、「枕詞」の方が、いいと思う
実景でなく、気持ちを表現したものだと思いたい
|
| |
| [べし] |
この助動詞は、その分類からすれば「推量」とされるが
用法に関しては、七つの用法がある
|
| 推量 |
~そうだ・きっと~だろう・~にちがいない・~らしい |
| 予定 |
~ことになっている |
| 当然 |
~はずだ・~にちがいない |
| 適当 |
~がよい・~が適当だ |
| 義務 |
~なければならない |
| 可能推定 |
~ことができそうだ・~ことができよう |
| 意志 |
~う・~よう・~つもりだ |
|
| 未然形 |
連用形 |
終止形 |
連体形 |
已然形 |
命令形 |
| べから |
べく <ベカリ> |
べし |
べき <ベカル> |
べけれ |
○ |
接続は、活用語の終止形につくが、ラ変型に活用する語には連体形につく
古くは未然形に「べけ」があったといわれる
助動詞「む」がついた「べけむ」が漢文調の文章ではしばしば用いられている
「なんぞたちまちに死ぬべけむや (死ぬはずがあるであろうか)」 [今昔物語九・三一]
また未然形に「べく」を認める説もある
「ゆく蛍雪の上まで往(い)ぬべくは(行くことができるならば)秋風吹くと雁に告げこせ」
[伊勢物語四十五]
のような「べくは」は仮定条件の表現だが、
「大納言佐殿、やがて走りついてもおはしぬべくはおぼしけれども(そのまま走って後についてもいらっしゃりたいとはお思いだったが)」 [平家物語十一・重衡被斬]
のような「べくは」は仮定条件の表現ではないので、
仮定条件の「べくは」の「は」を、
「ば」と同じように未然形につく接続助詞とみようとするもの
しかし、一般には、この「は」も係助詞とみて、「べく」を連用形としている
連用形「べく」は「べう」とウ音便になり、
連体形「べき」は「べい」とイ音便になることがある
「べい」は戦記物語に多く見られる
「ベカル」に「めり」「なり」がつくと、「べかるめり」「べかるなり」となり、
これが撥音便となって「べかんめり」「べかんなり」となる
この「ん」は表記されず「べかめり」「べかなり」と書かれることが多い
古くは、上一段動詞には、「見べし」「似べし」のように接続した
ひぐらしの鳴きぬる時は女郎花咲きたる野辺を行きつつ見べし(見るがいい) [万17・3973]
しろたへの波路を遠くゆきかひてわれに似べきは(私と同じ道を辿るはずの人は)誰ならなくに [土佐日記]
「べし」の語源は副詞「うべ」だという
当事者の意志を超えた道理・理由によって、
当然・必然のことと考えられるようすだというのが原義であったらしい
上の意味分類の他に、勧誘・命令などを立てることもあるが、
「適当」に準じると考えられている
|
| |
| [なむ] |
どの書にも、説明してあるのが、この原文表記「火」
これは、五行説の方位に「火」が「南」に当てられ、その訓が「なん・なむ」とするからだ
五行を四方に当てるとき、
「木は東」、「火は南」、「金は西」、「水は北」とされている
|
| |
|
|
| 掲題歌[2002]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】
| 新編私家集大成第一巻-4 人麿Ⅲ [冷泉家時雨亭叢書『素寂本私家集西山本私家集』] |
ワカコフルイモハヽルカニユクフネノ スキテクヤシヤコトモツケナン
|
| 柿本人麿集中 恋部 問答 526 |
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
|
| わかこふるいもははるかに行舟の わきてくへしやことつけなみに |
| 新編私家集大成第一巻-新編増補 赤人集Ⅲ[陽明文庫蔵三十六人集] あきのさう 163 |
| わかこふるいもははるかにゆくふねの すきてくへしやこともつてな(ママ)み |
| 同第一巻-6 赤人集Ⅱ[書陵部蔵三十六人集] 秋雑歌 150 |
| わかこふるいもはゝるかにゆくふねの すきてくへしやゝともつけなん |
| 同第一巻-5 赤人集Ⅰあかひと[西本願寺蔵三十六人集] あきのさふのうた 271 |
| わがこふるいもははるかにゆくふねのすぎてくべしやこともつけなん |
| 新編国歌大観第三巻-2 赤人集[西本願寺蔵三十六人集] あきのざふのうた 271 |
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「吾戀 嬬者知遠 徃船乃 過而應来哉 事毛告火」
「ワカコヒヲ イモハシレルヲ ユクフ子ノ スキテクヘシヤ コトモツケラヒ」(「【】」は編集、歌番は旧) |
〔本文〕頭注に、『元暦校本』、別行平假ノ字ノ訓ナク餘白アリ。其處ニ赭片假字ノ訓アリ。コレニテ校ス。『類聚古集』、訓ヲ附セズ。『西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本』訓ノ肩ニ朱ノ合點アリ。『京』赭ニテコレヲ止メタリ。赤人集「わかこふるいもはヽるかにゆくふねのすきてくへしやヽともつけなむ」
|
| 「者知」 |
『類聚古集』右ニ朱「或本云」アリ。
『京都大学本』赭頭書「○本知遠弥イ本」【○判読出来ず】アリ。「○」及「弥」ニ朱ノ合點アリ。頭書「弥イ本」ノ右ニ墨「イヤトヲ」アリ |
| 「告」 |
『類聚古集』「○【判読出来ず】」
『神田本』「苦」 |
| 〔訓〕 |
| ワカコヒヲイモハシレルヲ |
『元暦校本』「ワカコフルツコハイヤトホ」
『神田本』「ワカコフルツマハイヤトヲ」
『細井本』「嬬者」ノ左ニ「ツマハ」アリ |
| シキテクヘシヤコトモツケラヒ |
『細井本』「過而」ノ左ニ「コキテ」アリ。「ツケラヒ」ヲ「ツケラシ」トセリ
『京都大学本』赭ニテ「スキ」ヲ消セリ。ソノ右ニ赭「ヨキ」アリ。「應来哉事毛告火」ノ左ニ赭「キナムヤコトヲモツケヒ」アリ |
| 〔諸説〕 |
| ○[ワカコヒヲ]『万葉集略解』「ワカコフル」○[嬬者知遠イモハシレルヲ]『代匠記精撰本』「ツマハシレルヲ」、『略解』「知」ハ「弥」ノ誤。訓「ツマハイヤトホク」○[事毛告火コトモツケラヒ]『童蒙抄』「火」ハ「哭」ノ誤。訓「コトモツケナク」『補』「コトモツケナム」 |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [2002] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
| |
〔わかこひをいもはしれるをゆくふねのすきてくへしやこともつけらひ 〕
吾戀嬬者知遠徃船乃過而應來哉事毛告火
|
牽牛の心で詠う歌、との前提
ここでいう「舟のは過ぎて」は、時の経過をいうので、「枕詞」と解釈している
最後に言わんとしていることは、どんな意味なのだろう
時を過ぎて来られないなら、なぜ伝言さへも、、、
我が恋心は伝えてあるのに、ということか |
| わかこひをいもはしれるを 牽牛の心にてよめりゆく舟のは過てといはん諷詞也我戀る心を知なから時過て來へき事かは已に事も告たるにと也事も告らひはわかこふる事も告たるにとの儀也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
| |
〔ワカコヒヲイモハシレルヲユクフネノスキテクヘシヤコトモツケラヒ 〕
吾戀嬬者知遠往舩乃過而應來哉事毛告火 |
「嬬」を、それまでの「いも」ではなく「つま」と訓じたのは、
この契沖がいう『紀州本(神田本)』に基づくもの
その改訓により、この歌の心は、織女が定着してしまう
三四句は、「あらまし」、こうありたい、と言う願い
通り過ぎていかないでしょうね、ということだろう
結句の「事毛告火」を「コトモツケラヒ」と訓じるのは、ここに言う巻第九浦島子を詠める歌〔新1744〕に依るものだろう
そこには、「事毛告良比」と原文があり、「コトモカタラヒ」や「コトモノラヒ」などと訓まれている |
嬬者、【紀州本云、ツマハ、】
第二句の點は紀州の本の如く讀べきか、其故は此歌は織女になりて讀と見えたれば彦星を指てつまと云にや、三四句は兼てあらましに云なり、我方に渡り來む船の明ぬとて榜行て過なむ後又こぎ來べしや、相見ぬさきには言をだにも早く告よとなり、落句は第九に浦島子をよめる歌にも見えたり、
|
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
| |
〔わがこひを、つまはしれるを、ゆくふねの、すぎてくべきや、こともつげ火 〕
吾戀嬬者知遠徃船乃過而應來哉事毛告火 |
原文の「告火」を、「つげらひ」と訓むのは珍しい、とする
だから、この「火」については訓は避けているが、歌意はかなり明確に述べている
牽牛の歌とし、すでに逢瀬の後の歌で、年内にまた逢おうと、伝えてくれ、という
従来の、私の恋心を知っておりながら、月日は過ぎて行く、という説を否定している
宗師説としては、「火」を「哭」の誤字とし、織女が意図的に来ないので、告げない、という歌意になるのだろうか |
此火の字いかに讀まんか。印本等には、つげらひと讀ませたれど、語例無く珍しき言葉也。此歌諸抄の説まちまち也。彦星の歌にて、わが戀わびる心は、織女の知れる事なれば、こざ行船は過ぐるの序詞にて、一度逢事過ぎて、年の内に又逢ふべきや、言の葉をもつげよとの義也
又一説は、我戀心を知りながら、時過ぎて來べき事かは、わが戀ふ事も既に告げたるにと云ふの意と也。後の説は殊に聞え難し。宗師説は、わが戀を妹は知れるをかく過ぎ行て、又來るべきや、來るまじ。されば來べき共ことを告げなくと云意にて、火の字は哭の字の誤りなるべしと也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
| |
吾戀[ワガコヒヲ]、 吾は彦星なり
嬬者知遠[イモハシレルヲ]、 織女はしりてあるをなり
往船乃[ユクフネノ]、 別れの時をいふなるべし
過而應來哉[スギテクベシヤ]、 來ん年ならでは來べきやなり
事毛告哭[コトモノラナク] |
これも牽牛の歌とし、今年はすでに逢瀬も終り、
また来年、逢おう、と
だから、告げることもなく、としているようだ
『紀州本』の「つま」をとらず、「いも」とするなら、当然牽牛説になるだろう
いや、その為に「いも」の訓を採ったのかもしれない
「ゆくふねの」を別れの時をいう、というのは感心した |
| 事は借字にて今年別れては又こん年ならでこぬに、言ものらぬといふなり今本告火と有てつげらひとあるは字も訓も誤れり哭の畫の消しならん |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
| |
〔わがこふる。つまはしれるを。ゆくふねの。すぎてくべしや。こともつげなく 〕
吾戀。嬬者知[知ハ哭ノ誤]遠。往船乃。過而應來哉。事毛告火。[火ハ哭ノ誤] |
「哭」は、その意を言うのではなく、「なく(無く)」の借音としていることの具体的な注釈
これは「つま」を牽牛として解し、何も告げることなく、牽牛は去っていった、という歌意なのかな
初句の「わがこふる」は、「つま」にかかる連体形として訓む
|
知、一本彌に作るぞ善き。ツマハイヤトホクと訓むべし。火は哭の誤なるべし。イヌルを來ルと言ふ例有り。嬬は借れるにて、彦星を指す。彦星は舟漕ぎ出でて、言をも告[ノ]り給ふ事無くて、彌遠く唯だ過ぎに過ぎ行くはなさけ無し。さは過ぎ去[ユ]くべき事かはと言ふなり。
參考 ○吾戀(考)ワガコヒヲ (古)アガコヒヲ (新)略に同じ ○嬬者知遠(代)ツマハ(考)イモハシレルヲ (古、新)ツマハシレルモ ○事毛告火(考、古)略に伺じ(新)コトモツゲナム。
|
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
| |
〔アカコヒヲ。ツマハシレルヲ。ユクフネノ。スギテクベシヤ。コトモツゲナク。〕
吾戀嬬者知遠住船之過而應來哉事毛告火
|
雅澄も解釈に苦しんでいるようだ
歌意について、深読みの感もあるが、なるほど、と思う
時が過ぎるなら、そのことを伝えてこようものを、
それが無いということは、必ず来るものと、行き交う舟を、
牽牛が乗る舟か、と期待して付き添う女たちが言うのを、
それに応えて詠ったもの、とする
この説に従うなら、時を過ぎる意味合いから、
「ゆくふねの」は、枕詞かもしれない、と更に考える、という |
| 知(ノ)字、彌と作る本もあれど、舊本を宜とす、○事毛告火は、岡部氏云、火は、无か哭の誤なるべし、言[コト]も告無[ツグナク]の意なり、○歌(ノ)意、中山(ノ)嚴水、第一二の句はアガコヒヲツマハシレルヲと訓べし、嬬[ツマ]は彦星を云、徃船[ユクフネ]とは、たゞ天(ノ)漢を漕(キ)行(ク)舟にて、彦星の舟にあらず、過而[スギテ]は、時過而[トキスギテ]の意なり、わが待つゝ戀ることを、彦星はよく知給ひぬるを、舟の過徃[ク]ごとく時過て來ますべしやは、もし時過むとならば、事のよしを告來すべきに、しかしかと言もつげ來ずてあれば、時過て今更來座べきやうはなしといへるにて、かのこぎ行(ク)舟を見て、彦星の來り給ふにやと、つきそふ女どものいふに、こたふるさまなりといへりか、今按に此説の如くならば、往船之[ユクフネノ]は、たゞ天(ノ)漢の縁[チナミ]に、枕詞の如くに云るものともすべきか、なほ考(フ)べし、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
| |
〔吾戀[ワガコヒヲ]、嬬者知遠[ツマハシレルヲ]ゆく船のすぎて來べしや事毛告火[コトモツゲナム] 〕
吾戀嬬者知遠往船乃過而應來哉事毛告火 |
真淵、千蔭、雅澄の解釈批判から始まる
「なむ」は、ここから定着したのか...
「なく」とは、まったく語義解釈が変わってくる
歌意としては、織女が我が心を知りながら、
牽牛は通り過ぎようとするなんて、あるだろうか、と
|
略解には第二句の知を一本によりて彌の誤とし又結句の火を哭の誤と認めてワガコフルツマハイヤトホク……コトモツゲナクとよみ、さて
イヌルを來ルといふ例有。嬬は借れるにて彦星をさす。彦星ハ舟コギ出テ言ヲモノリ給フ事ナクテ彌遠クタダ過ニ過行ハナサケナシ、サハ過去ベキ事カハといふなり
といひ、古義には初二を舊訓(紀州本)によりてアガコヒヲツマハシレルヲとよみ結句を眞淵の説によりて コトモツゲナクとよみ、さて
中山嚴水、嬬は彦星を云。往船とはただ天漢を漕行舟にて彦星の舟にあらず。過而は時過而の意なり。ワガ待ツツ戀ルコトヲ彦星ハヨク知給ヒヌルヲ舟ノ過往ゴトク時過テ來マスベシヤハ、モシ時過ムトナラバ事ノヨシヲ告來スベキニシカジカト言モツゲ來ズテアレバ時過テ今更來座ベキヤウハナシといへるにてかのこぎ行舟を見て彦星の來り給ふにやと附添ふ女どものいふに答ふるさまなりといへり
といへり。嚴水は第三句を枕辭とせるにや然らずや。いとおぼつかなし。舟ノ過往ゴトク時過テと釋せるを見れば枕辭とせるにてカノコギユク舟ヲ見テ彦星ノ來リ給フニヤト附添フ女ドモノイフニといへるを見れば枕辭とはせざるなり。雅澄が
今按(フ)に此説の如くならば往船之はただ天漢のちなみに枕辭の如くに云るものともすべきか
といへるはた事理に明なる言とは稱しがたし。訓義辨證(下卷二四頁)には卷十三に二二火四[シナムヨ]吾妹とあるを例として結句をコトモツゲナムとよみ、さて
按に火は南の意に借たるにてツゲナムと訓べきなり。四句クベシヤはユクベシヤの意にて過テ往ベキ事カハ、暫時ハトドマリ給へ、セメテ吾オモフ言ナリトモ告知センモノヲといふなり
といへり。臨別の歌とせるは誤解なれど結句はげにツゲナムとよむべし。又初二は舊訓の如くワガコヒヲツマハシレルヲとよむべし。ユクフネノは枕辭にあらず。來ベシヤはユクベシヤにおなじ。此歌は織女になりてよめるにて
ワガカク戀フル事ヲ彦星ハヨク知レルヲ今天ノ河ヲ舟ニテユクトナラバ傳言ダニスベキヲ素通リニシテ往クベシヤ
といへるなり |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| |
我が戀ふる妻は、いや遠く、行く舟の過ぎて來べしや。言も告げなく |
ここまでの解釈になると、「七夕」の歌としては、かなり疑問も鮮明になってくる
これまでの書の解釈にしても、その感じはあったものの、この折口信夫の解釈では、「年に一度の逢瀬」である「七夕」歌の前提そのものが消えてしまう
確かに、「七夕」歌を、頭から外してしまえば
このように感じることも可能だろうと思う
その意味では、意義のある解釈だと思う |
| |
自分の焦れてゐる妻は、ちようど段々遠くへ行く舟のやうに、過ぎ去つて了うた後は、歸つて來る氣づかひはない。何の便りの言も、此頃はおこさない。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
| |
〔吾が戀を つまは知れるを 行く船の 過ぎて來べしや 言も告げなむ 〕
ワガコヒヲ ツマハシレルヲ ユクフネノ スギテクベシヤ コトモツゲナム
吾戀嬬者知遠往船乃過而應來哉事毛告火 |
この歌意を、七夕歌とせず、男女の仲を「天の川を行く船」に譬えていうのであれば、まさにぴったりの解釈だと思う
つまり、「彦星」でなく「夫」で充分であり、天の川を渡る船は、決して素通りなんてしない、だから、あなたも...
そう解釈したくなる文章だが、「彦星」と明記されているので、
それが残念だ
第三句を「枕詞」ではない、としているが
「彦星」を「つま(夫)」と解釈すれば、「序詞」になる
そもそも、「彦星」とするのは、この歌が[七夕」の部立てになっているからで、その部立てのいい加減さは、この歌集の特徴でもあるのに、と思ってしまう
|
私ガ戀フルコトヲ夫ノ彦星ハ知ツテヰルノニ、天ノ河ヲ行ク舟ガ、黙ツテ通リ過ギルトイフコトガアルモノデスカ。何トカ言傳シテモラヒタイモノデス。
○吾戀[ワガコヒヲ]――舊訓を略解にワガコフルと改めたのはよくない。
○嬬者知遠[ツマハシレルヲ]――舊訓イモハシレルヲとあるのはよくないであらう。略解に「知一本彌に作るぞよき。つまはいやとほくと訓べし」とあるのは、落ちつかない訓である。
○事毛告火[コトモツゲナム]――舊訓コトモツゲラヒとあるのではわからない。童蒙抄や略解に火を哭の誤としてコトモツゲナクとよんでゐるが、火は卷十三に二二火四吾妹[シナムヨワギモ](三二九八)とあり、火を方角に配すれば南に當るから、火を南に借りてナムと訓ませたのであらう。珍らしい用字法の一例である。
〔評〕 織女星の心になつてよんだものである。一寸難解の點もないではないが、右のやうに訓めば理義明白である。第三句を枕詞とする説はよくない。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
| |
〔わが戀を 嬬は知れるを、行く船の 過ぎて來べしや。言も告げなむ 〕
ワガコヒヲ ツマハシレルヲ ユクフネノ スギテクベシヤ コトモツゲナム
吾戀嬬者知遠往船乃過而應來哉事毛告火 |
この解釈では、中途半端な歌になってしまう
事情を告げよう、とするのは、何を、と
「釈」で、理解出来たのが、「つま」を夫の意とも言えるが、どちらで解釈しても通じるから、文字通りの解釈が順当という
それが、ここで最も共感できた
「嬬」という文字を何気なく使うにしても、敢えて使うにしても
そこには読む人に「女」を印象付ける |
【譯】わたしの戀を、妻は知つているのを、行く船が通り過ぎてくることはできない。事情も告げよう。
【釋】嬬者知遠 ツマハシソルヲ。ツマは、夫の意とする解もあるが、織女星のこととしても通ずるから、文字通りに解するのが順當である。
往船乃 ユクフネノ。牽牛星自身の乘つている船が。
過而應來哉 スギテクベシヤ。スギテは、通過して。ヤは反語。通過してくるべきではない。句切。
事毛告火 コトモツゲナム。コトは事情。火は五行の南方に相當するので、ナムの音に借りて書いている。「二々火四吾妹[シナムヨワギモ]」(卷十三、三二九八)。
【評語】牽牛星の心になつて詠んでいる。船に乘つて天の川を往來している意である。説明的で情趣に乏しい憾[うら]みがある。
|
| 『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕 |
「評釈」私見 |
| |
吾が戀を嬬は知れるを行く船の過ぎて来べしや言も告げなむ |
現代的には、もっとも理解し易い解釈だと思うが
もう「七夕」歌の面影はなくなっている |
【譯】私が恋しがつてゐることを、夫の彦星は知つて居られるのに、こんなに時過ぎていらつしやるべきではありませうか。おくれるならば言伝でもしていただきたいものです
【評】この歌も疑義があつて、解釈上異説があるのは、畢竟表現力が不充分といふ以外はない。
【語】○嬬 ここは借字で、夫のこと。彦星をさす。
○往く舟の過ぎて来べしや 夜が明けて行き過ぎて後又来るべきか云々と解する『代匠記精撰本』の説は牽強である。「往く舟の」は枕詞で、時過ぎて来べしやの意とする説(古義)が穏やかである。
○ことも告げなむ 「なむ」は他に希望する意を表はす助詞、随つて上の「告げ」は未然形である。
○ことも告げなむ 白文「事毛告火」で事は言の借り字。「火」は五行説により方角に配すれば南にあたるからナムと訓む説(訓義弁証)がよい。巻十三にも「死なむよ妹」を「二二火四吾妹」(三二九八)とある。旧訓ツゲラヒは義を成さず、「哭」と改めて、ツゲナクと訓む説もよくない。 |
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
| |
〔吾が戀ふる妻はしるきを行く船の過ぎて來べしや言も告げなむ 〕
ワガコフル ツマハシルキヲ ユクフネノ スギテクベシヤ コトモツゲナム
吾戀嬬者知遠往船乃過而應來哉事毛告火 |
「つまはしれるを」ではなく「つまはしるきを」にして
その解釈では、これまでの問題をなくしてしまった
我が恋心を知っている「つま」だからこそ、歌として魅力があったのに、これでは「つま」は単なる対象になってしまう
「つま」の気持ちを推し量って、自らの気持ちに揺らぐ歌だったはずなのに... |
【大意】吾が戀ひ思ふ妻、織女は、はつきり見えて居るのに、行く船の如く、ただ通り過ぎて来べきではあるまい。話をもしたいものだ
【作意】織女が光つて見えて居るのであるから、素通りすべきではないといふ、牽牛の立場で歌つたのである。ユクフネノは天漢を渡る牽牛の船であるが、時に臨んでの枕詞として見てもよい。「火」をナムと訓むのは、五行を方位にあてる時、火を南とするからである。一二句の訓はかくあらねばならぬ。補巻「巻第十刊行に際して」参照。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
| |
〔吾が戀を 夫は知れるを 行く船の 過ぎて來べしや 言も告げなむ 〕
ワガコヒヲ ツマハシレルヲ ユクフネノ スギテクベシヤ コトモツゲナム
吾戀嬬者知遠往船乃過而應來哉事毛告火 (『元暦校本』) |
『評釈万葉集』と同様に、これではまるで一般の相聞歌になる
そのことも、解説を読めば納得する
この書では、この歌を「七夕」とはみていない
だから、上の『評釈万葉集』が同じように解釈しながら、「彦星」と訳したのとは大きな違いがある
|
【口訳】私が戀しがつてる事を、あの方は知つていらつしやるものを、素通りをなさるつて法はありませんわ。せめて言伝だけでも伝えてほしいわ。
【訓釈】吾が戀を夫は知れるを―この歌、『元暦校本・類聚古集』に訓が無い。『元』には訓のところ二行分あけてあり、そこに赭筆片カナの訓がある。初句『元』『紀州本』にワカコフルを『西本願寺本』以後ワカコヒヲと改め、「嬬」を『西』以後イモとしたが、『紀』にツマとあるがよい。「嬬」は夫をもいふこと前(2・153、217)にあつた。ここもさうである。『代匠記』はじめ諸注はこの[夫」を彦星と見たのは七夕の作だと思つたからであるが、次に述べるやうにこれは人間同士の相聞の歌と見るべきである。
行く船の―これは「行く川の」(7・1119)、「行く水の」(9・1797)と同じく「過ぐ」の枕詞である。これを従来実景と見た為に七夕の作としたのであるが、それでは船が岸に添うて素通りしてしまふやうになり、七夕の歌としては得心がゆかない事になる。この作と次の作とは七夕の作ではないのを、「巻向の檜原に立てる春霞」(1813)が序であつて相聞の歌であるのを春の雑歌の中へ入れたやうに、これも「行く船の」を枕詞と考へずに七夕の歌に入れたと見るべきである(「人麻呂集の歌二つ」『古徑』三所収)。
過ぎて來べしや―「過ぎて」は素通りすること(6・1066)。「来」は、行くに同じ(1956)。「や」は反語。
言も告げなむ―『元暦校本・紀州本』にコトヲモツケヒ、『西本願寺本』以後コトモツケラヒとあつたのを『訓義弁証』(下)にコトモツケナムと改めた。「火」をナムと訓むのは、五行を四方に当てる時、木は東、火は南、金は西、水は北で、「南」と同様に用ゐたのである。「二二火四吾妹(シナムヨワギモ)」(13・3298)ともある。その「なむ」は希求の助詞(1964)。逢ふ事はかなはずとも、せめて言伝だけでもほしい、の意。
【考】赤人集に「わがこふる妹ははるかに」「こともつげなむ」、流布本「こともつてなみ」とある。
|
|
|

| |
| 「ひとづまゆゑに」...あれこひぬべし... |
| |
| 『とほくをしり』 |
| 【歌意2003】 |
赤ら顔の、美しい子よ、
お前をたびたび見ていると、
お前が人妻だと解っていながらも、
私は、恋してしまいそうだ |
| |
| |
この歌、「七夕」歌では、決して有り得ない、と思う
注釈書でも、そのことについては多く言われている
何しろ、「七夕」の「星合」...「年に一度の逢瀬」の意味合いが、全くない
それでも、こじつけるような注釈書はあるが、
この歌、どうして一般の「相聞歌」として読まないのだろう
訓にしても、諸説が多くあり、これだ、というものはない
勿論、そこが漢字表記でしか伝わらない特有のものなのだが
訓を違えても、歌意に於いては、大きく解釈を左右するものはない
だから、素直に読むことが出来るのだが
古注釈書以来のどの注釈書も、歌意に違いはないものの、
一つ、あれっ、と思う解釈があった
それは、『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕の「現代語訳」で、
| |
| あの美しい織姫さんを、私が度々見るやうだつたら、人の妻だとわかつてゐるが、その人の妻なる人の爲に、焦れることであらう。美しい人に。 |
この解釈、「人妻だからこそ」、想いが募る、とも感じられる
そもそも、「人妻故に」と言いながら、この種の歌を詠うのは
確かに、その底には、「人妻だからこそ」というニュアンスを感じないわけにはいかない
しかし、どの注釈書でも、そこに描かれる情景は、
「七夕歌」に模した場合では、
牽牛の妻である織女の美しい様を見て、地上の人間が恋してしまうほどだ、とされ
「七夕」歌としない、とするのは
人の妻であるのに、その美しさ故に、何度も見ていると、恋してしまいそうだ、と
「七夕歌」になれば、憧れであり、そうでなければ、「ならぬ恋心」の悲哀を詠うものになる
この歌が、一様に「七夕歌」でない、と言われるのは
やはり「人妻故に」という、「年に一度の逢瀬」の根本に係わるものだから
誰もが思うものだろう
そして、そこには「部立て」の混乱にこそ言及しなくても、
当然、「部立て」への信頼感が損なわれている
では、何故昨日の歌〔2002〕では、そのような議論に発展しなかったのだろう
明確な「語」があって、初めて「異」を唱える、と言うものなのだろう
その明確さが、この「人妻故」ならば
その語意を、もっと深く考えたくもなる
その矢先に触れた、折口信夫の「現代語訳」だった
人妻だからこそ、恋心が激しくなる
何故なら、「想い慕う」ことしかできないのだから...
どうにもならない、と結果が見えていることへの対処は二つある
一つは、潔く「諦める」こと
もう一つは、「諦めずに、奪い取ること」
振り返って見ると、歌として好ましく詠われるのは、「諦める」という「悲恋」なのだろうが
なかには、決意として、自分を奮い立たせる詠いっぷりもあるだろう
思い出されるのが、巻第一の、大海人皇子が、人妻でる額田王へ投げ掛けた歌だ 〔右頁〕
人妻であろうが、好きになってしまったら...
これは、堂々とした「宣言」ではないか、と思う
勿論、一般的にはこの歌は「遊興」の部類としてでしか取り合ってはいないが
何しろ、その相手が「天智天皇」なのだから、
絶対無二の存在者への本心とは受け取らないだろう
しかし、結果はどうなったのか...
「人妻故に」が、言葉として解釈できるのは、
「人妻だと解っていても」という、それでもどうしようもない気持ちをいうものだろう
その意味からすると、これを「七夕歌」とすれば、それこそ〔21〕歌のように、
多くの解釈通りの「遊興」めいたものになるが、
「七夕歌」でないとすると、すぐに理解出来る
もう一度、この歌を読み返してみる
「人妻故に 吾れ恋ひぬべし」...
これは、「故に」を逆接で解釈しようが、順接で解釈しようが
男の決意としては、「きっと、恋してしまうだろう」と宣言している
そうであれば、結果的に大海人皇子が詠ったように
周囲からどう思われようと、私は恋してしまう...「人妻であっても」...
「七夕歌」に見立てれば、牽牛が天智天皇であり、その妻である織女、額田王へは
誰も憧れでしか恋することはできないのだが
通常の「相聞歌」であれば、「人妻であっても、私は恋している」という
宣言に他ならない歌になる...〔21〕歌もそうだと、私は思っている
同じく〔3107〕も、やはり同様の歌としか思えない
|
|
掲載日:2014.04.27.
| |
| 秋雑歌 七夕 |
| 朱羅引 色妙子 數見者 人妻故 吾可戀奴 |
| 赤らひく色ぐはし子をしば見れば人妻ゆゑに我れ恋ひぬべし |
| あからひく いろぐはしこを しばみれば ひとづまゆゑに あれこひぬべし |
| 巻第十 2003 秋雑歌 七夕 柿本人麻呂歌集出 |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】〔138〕
【赤人集】〔164・151・272〕
【古今和歌六帖】〔139〕
[古注釈書引用歌(語句ではなく全文引用の歌)]
【万葉集〔見れば〕『万葉集注釈』】〔1655・2608(既出)〕
【万葉集〔人妻ゆゑに〕『万葉集略解・万葉集古義・代匠記・童蒙抄』】〔21(既出)・3107〕
[資料]
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
【七夕】〔中華民国[国立成功大学、成大宗教與文化学報 第七期 論文]〕
| 【2003】 語義 意味・活用・接続 |
| あからひく [朱羅引] 赤い色が広がる意 |
| いろぐはしこを [色妙子] |
| ぐはし [細い・美し] |
[形シク・終止形] 細やかで美しい・うるわしい |
| 〔この語句を「いろぐはしこを」とするなら「いろぐはしきこを」と訓むべき、と思う〕 |
| しばみれば [數見者] |
| 〔参考〕しば [屡] |
[副詞] しばしば・たびたび・しきりに |
| 〔参考〕「しば鳴く」「しば立つ」「しば見る」などのように動詞に冠して用いられることが多い |
| しばみれ [屡見る] |
[他マ上一・已然形] しばしば見る・たびたび見る |
| ば [接続助詞] |
[順接の確定条件] ~ので・~すると・~すると必ず |
已然形につく |
| ひとづまゆゑに [人妻故] |
| ひとづま [人妻・他妻] |
他人の妻 [他夫(ひとづま)として、他人の夫] |
| ゆゑ(に) [故] |
[体言、用言の連体形の下に付いて] |
| |
[順接的な原因・理由] ~のために・~が原因で・~によって |
| [逆接的な原因・理由] ~なのに・~にかかわらず・~のに |
| あれこひぬべし [吾可戀奴] |
| ぬ [助動詞・ぬ] |
[完了・終止形] ~た・~てしまう・~てしまった |
連用形につく |
| べし [助動詞・べし] |
[推量・終止形] ~そうだ・きっと~だろう |
終止形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [あからひく] |
赤い色を帯びている、という意から、「枕詞」として「日」「朝」「膚」にかかるが、
現代の多くの注釈書では、ここでは枕詞でなく、通常の修飾語として解している
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕は、
「色ぐはし子を」にかかる「枕詞」と明確に述べているが、
他では純粋な「枕詞」として解説していない
その懸念を持って解説しているのが、『新考』で、「准枕詞」という
古注釈書では、『万葉考』『略解』『全釈』『全註釈』『私注』『注釈』が「枕詞」とし、
『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕が、「枕詞」ではないとしている
|
| |
| [いろぐはしこを] |
原文「色妙子」を、「いろたへのこを」とか「しきたへのこを」とか古くは訓まれていたのを、
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕でも述べられている、
同著者の「万葉の古徑 三『注釈』」で、「いろぐはし」を提唱し、
それが現訓としは、広く支持されているようだ
「妙」も「くはし」と訓む例もある [巻第十三 3345 妙山叙(くはしき山ぞ)]
「花ぐはし」、「香ぐはし」、「名ぐはし」と同じ語の構成だとされるが
この「~ぐはし」が、例えば「枕詞」のような「語」であれば理解もし易いが
一般の修飾語であれば、「くはし」は形容詞であり、その活用からすれば
この歌の用法では「いろぐはしきこを」と、連体形にしなければならないと思う
名詞「いろ」には、色合い、色彩の他に、「美しさ・華やかさ・華美」の意味があり、
形容動詞「妙(たへ)」には、「神々しいほど優れている」のような意がある
だから、「いろたへなるこを」でも、字数を除けば支障はないだろうし
「しきたへの」となると、そもそも「枕詞」としての用法しかなく、
敢えて言えば、「敷物」の絡みだから、「色」を「しき」と訓むことは可能でも
この歌の歌意にはそぐわないものだ
「いろぐはし」「いろたへの」が、どちらも相応しく思える訓だと思うが
その活用に於いて、「枕詞」としても解釈を容認しなければ、混乱する
「枕詞」は、確かに訳すことのない「語句」が多いが、その語の語感で次の語を導くのだから
それも、訳すことはなくても、「序詞」のような、一種の修飾語だと思う
|
| |
| [ぬべし] |
完了の助動詞「ぬ」が、他の助動詞とともに用いられて、
「なむ」「なまし」「ぬべし」などの形になる場合、
推量・意志・可能などの意を、「確かに」「きっと」「必ず」の気持ちで述べる
|
| |
| |
| |
| |
| |
[古注釈書引用歌(語句ではなく全文引用の歌)]
【万葉集〔見れば〕『万葉集注釈』】
| 冬雑歌 大伴坂上郎女歌一首 |
沫雪乃 比日續而 如此落者 梅始花 散香過南
|
| 淡雪のこのころ継ぎてかく降らば梅の初花散りか過ぎなむ |
あわゆきの このころつぎて かくふらば うめのはつはな ちりかすぎなむ
|
| 巻第八 1655 冬雑歌 大伴坂上郎女 |
〔歌意〕
[引用する『注釈』では、「ふれば」とする]
泡のような、この頃の降り続く雪、
こうして降り続いたら、梅の初めの花は、
散ってしまうだろうか...
|
| 正述心緒 |
心乎之 君尓奉跡 念有者 縦比来者 戀乍乎将有
|
| 心をし君に奉ると思へればよしこのころは恋ひつつをあらむ |
こころをし きみにまつると おもへれば よしこのころは こひつつをあらむ
|
| 既出〔書庫-5〕巻第十一 2608 正述心緒 作者不詳 |
〔歌意〕
私のこころは、あなたに捧げているのですから
このまましばらくは、慕うだけにしておきましょう... |
【万葉集〔人妻ゆゑに〕『万葉集略解・万葉集古義・代匠記・童蒙抄』】
| (天皇遊猟蒲生野時額田王作歌)皇太子答御歌 |
紫草能 尓保敝類妹乎 尓苦久有者 人嬬故尓 吾戀目八方
|
| 紫のにほへる妹を憎くあらば人妻故に我れ恋ひめやも |
むらさきの にほへるいもを にくくあらば ひとづまゆゑに われこひめやも
|
| 既出〔書庫-11〕巻第一 21 大海人皇子 |
〔歌意〕
紫草のように、美しいあなたを気に入らないと思っているのなら
どうして、人妻であるあなたなのに、
私は恋したりするのか...
|
| 寄物陳思 |
小竹之上尓 来居而鳴鳥 目乎安見 人妻め尓 吾戀二来
|
| 小竹の上に来居て鳴く鳥目を安み人妻ゆゑに我れ恋ひにけり |
しののうへに きゐてなくとり めをやすみ ひとづまゆゑに あれこひにけり
|
| 巻第十ニ 3107 寄物陳思 作者不詳 |
〔歌意〕
しの竹の上に来て鳴く鳥は、目にもたやすく見えるので、
人妻であるに、私は恋してしまった...そんなに見えては... |
|
| |
|
|
| 掲題歌[2003]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】
| 新編私家集大成第一巻-4 人麿Ⅲ [冷泉家時雨亭叢書『素寂本私家集西山本私家集』] |
アカラヒテイロタエノコノカスミレハ ヒトツマユヘニワレコヒヌヘシ
|
| 柿本人麿集上 秋部 万十 138 |
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
|
| おほ空にたなひく雨のかすみは(ママ)人つまゆゑにわれわひぬへし |
| 新編私家集大成第一巻-新編増補 赤人集Ⅲ[陽明文庫蔵三十六人集] あきのさう 164 |
| おほそらにたなひくあめのかすみれは 人のつまゆへわれにあひぬへし |
| 同第一巻-6 赤人集Ⅱ[書陵部蔵三十六人集] 秋雑歌 151 |
| おほそらにたなひくあやめかすみれは ひとのつまゆゑいもにあひぬへし |
| 同第一巻-5 赤人集Ⅰあかひと[西本願寺蔵三十六人集] あきのさふのうた 272 |
| おほぞらにたなびくあやめ(ママ)かずみればひとのつまゆゑいもにあひぬべし |
| 新編国歌大観第三巻-2 赤人集[西本願寺蔵三十六人集] あきのざふのうた 272 |
『注釈』でも指摘しているように、初句を〔2005〕歌と混乱しているようだ
撰集の段階での作業の「確実性」を、現代感覚で見るのは、やはり無理というものだろう
【古今和歌六帖 ([永延元年(987年)頃]撰、兼明親王・源順か)】
| 新編国歌大観第二巻4 [宮内庁書陵部蔵五一〇・三四] |
あからひくいろたへのこのかずみれば人づまゆゑに我こひぬべし
|
| 第一帖 歳時部 秋 七日の夜 139 人丸 |
|
| |
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「朱羅引色妙子數見者人妻故吾可戀奴」
「アカラヒク シキタヘノコヲ シハミレハ ヒトツマコヱニ ワレコヒヌヘシ」(「【】」は編集、歌番は旧) |
〔本文〕頭注に、赤人集「おほそらにたなひくあやめかすみれは ひとのつまゆゑいもにあひぬへし」
|
| 「妙」 |
『類聚古集』ナシ。右ニ墨ニテ書ケリ。本文中「色子」ノ間ニ墨「○」符アリ |
| 「數」 |
『元暦校本』「数?【判読出来ず】」
|
| 「奴」 |
『元暦校本』「○【判読出来ず】」 |
| 〔訓〕 |
| アカヒラク |
『元暦校本』「あかこひく」。「こ」ノ右ニ赭「ラ」アリ
『神田本』「引」ノ左ニ「ヒキ江」アリ |
| シキタヘノコヲシハミレハ |
『元暦校本』「いろたへのこのかすみれは」
『類聚古集』「いろたつのこのかすみれは」。墨ニテ「つ」ヲ消セリ。ソノ右ニ墨「ヘ」アリ
『神田本』「イロタヘノコノカスミレハ」
『西本願寺本』「シキ」モト青。「色」ノ左ニ「イロ」アリ
『細井本』「色妙子數」ノ左ニ「イロタヘノコノカス」アリ
『温故堂本』「色」ノ左ニ「イロ」アリ
『大矢本・京都大学本』「シキ」青。『京』漢字ノ左ニ赭「イロタヘノコノカスミレハ」アリ |
| ヒトツマコヱニ |
『元暦校本』「ひとつまゆへに」
『類聚古集』「ひとつまゆゑに」
『神田本・温故堂本』「ヒトツマユヘニ」
『細井本』「ヒトツマユエニ」
『西本願寺本』「ヒトツマユヱニ」 |
| 〔諸説〕 |
| ○[アカラヒク]『童蒙抄』「アカモヒク」○[シキタヘノコヲ]『拾穂抄』「イロタヘノコヲ」、『童蒙抄』「ウツクシキ」又ハ「ウルハシキ」又ノ「マクハシキ」、『万葉集古義』「シキタヘノコヲ」ヲ可トス |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [2003] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
| |
〔あからひくいろたへのこをしは見れは人つまゆへにわれこひぬへし 〕
朱羅引色[イしき]妙子數見者人妻故吾可戀奴
|
いろたへの訓の由来を言っている
八雲抄の「あかき心」とは...
奥儀抄では、「紅のウスモノ」、色がめでたきを「いろたへ」
それを着る女は織女で、それを見るのは、牽牛ではなく第三者
星合を見る人の歌 |
| あからひくいろたへのこ 八雲抄奥儀抄いろたへとよむ類聚しきたへとよめり(枕床なとのやうに夜ぬる心云々不用之)八雲の御説に可随歟八雲云あからひくはあかき心也いろたへのこ好色物といへる奥儀抄に云あからは紅の羅[ウスモノ]也其色のめてたきをいろたへと云是をきたる女といへり是は織女の哥也愚案朱羅のすそひく容色絶妙の女子也しは見れはとはしはしばみれは也人つまゆへとは織女は牽牛夫あれは人つまと云星合みる人のよめるうたにして可心得
|
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
| |
〔アカラヒクシキタヘノコヲシハミレハヒトツマユヱニワレコヒヌヘシ 〕
朱羅引色妙子數見者人妻故吾可戀奴 |
語義の解釈で、「數見者」を年毎に見ることも、また一夜の中でも何度も見ることもいう
織女と牽牛は夫婦なので、作者が恋慕うことはないだろうに、たびたび見てしまうので、恋してしまいそうだ、となるのか
古今集のいう、逢いたいと思うことを人は嫌がるようだが、という意味なのかな
〔21〕と〔3107〕下句同様 |
色妙子、[六帖云、イロタヘノコ、]
朱羅引は第四に注す、色妙子はイロタヘノコと讀べし、匂[ニホ]ふ色の、妙なる子と織女を云なり、第十一にはあから引肌ともよめり、數見者とは年毎に見るをも亦一夜の中にもつくつくとまもるをも云べし、杜□[手偏+攵]が詩に臥見牽牛織女星と作るが如し、織女は牽牛の妻にて我思ひ懸べきにあらぬ物故に、しばしば見れば戀ぬべしとなり、古今集に見ても亦またも見まくの欲ければ、馴るを人は厭ふべらなり、此意を思ふべし、第一に天武天皇未太子にてましましける時の御歌の下句今と同じ、又第十二にも似たる下句あり、
|
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
| |
〔あかもひく、うつくしき子を、しば見れば、ひとづまからに、われこひぬべし 〕
朱羅引色妙子敷見者人妻故吾可戀奴 |
女の服に、「あから」と言うものは無いではないか、と「あかも(赤裳)」を挙げるが、その用例は「数え難し」と、有り過ぎる事なのか、捜し得ない、ということなのか
「しきたへのこ」とは、何と言う義なのか、というが、枕詞の「しきたへの」とはしないのだろうか
「色妙」の文字が、女子の通称なのだから、別な訓があるべき、とのこと
「うつくしき子」や、「まぐはしき子」などがあるが、一応として、「うつくしき子」としている
人妻故に、の句は、〔21・3107〕にもあり、同様
しかし、彦星が七夕女を見てよめる歌、とは...
七夕歌には、いろいろと解釈できる歌があり、この歌も、七夕歌ではなく、ただの恋歌であるが、七夕歌として読むようなこともある、というか
|
朱羅引 皆あからひくと讀ませたり。無下に不考の假名也。女服にあからと云ふ物ありや。うすものと讀む字故、あかもとは讀む也。赤裳也。句例あげて數へ難し。
色妙子 しきたへの子と訓ませたり。是も心得難し。しきたへの子とは何と云義にや。色妙の二字は、女子の通稱、美の字なれば賞讃の別訓あるべし。先づ美しき子と讀め共、日本紀等又遊仙窟など追而可考。美はしき子とか、まぐはしき子とか讀むべきか。うつくしき子と計りには決すべからず
人妻故に 世の中の人の妻なるべき子なるからと云義第一卷にても注したり。第十二卷にも人妻故にわれ戀にけりと云歌有、皆同じ意也。彦星の七夕女を見てよめる歌と見る也。七夕の歌は其身になり思ひやり色々によめる也。此歌七夕の歌と不聞共、只戀の意をよみて、七夕の意通る歌もある也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
| |
朱羅引、 冠辭
色妙子[シキタヘノコヲ]、 冠辭考色栲の條にくはし
數[シバ]見者、 しきたへよりいひくだせり
人嬬/故[ユヱニ]、吾可戀奴[ワレコヒヌベシ] |
あからひく、を枕詞とする
「敷栲」は、単に敷物の関連でのみ使うのは堅苦しい
「敷栲の妹」のように、美しく和やかな女という意としている
この歌が、七夕の歌でなく、
ここに紛れて入れられたもの、と判断している |
此歌/七夕[ナヌカノヨ]の歌にあらずまぎれてここに入しなるべし
【○眞淵云色妙は借字子は女を云にて敷栲の妹と云に同しさて敷細布てふ敷は物の繁くうつくしきをいひ細布はよき絹布を云古語女のうつくしく和[ナゴ]やかなるに譬なり或本にいろたへと訓しは誤れり神祇令の集解に敷和者宇都波多也云云敷は絹布の織目の繁き意和はなごやかなる意にて美織[ウツハタ]なり敷は下に敷事にのみ思ふはかたくるし |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
| |
〔あからひく。しきたへのこを。しばみれば。ひとづまゆゑに。われこひぬべし 〕
朱羅引。色妙子。敷見者。人妻故。吾可戀奴。 |
真淵の説に倣う
ここに配するのは、誤ってのこと
七夕歌ではない、とする
|
アカラヒク、枕詞。シキタヘノ子に冠らせたるは、アカネサス君、ニツカフ妹など言ふに等しく、アカラヒク子と懸かりて、紅顔を言ふ。さてシキタヘとは、色妙は借字にて、敷細布[シキタヘ]の意なり。數キは物の繁く美くしきを言ひ、細布もよき絹布を言ふ古語にて、女の美くしく、和[ナゴ]やかなるに譬へたる語なりと翁言はれき。冠辭考に委し。シバミレバは、シバシバ見レバなり。人妻故に云云は、卷一、紫のにほへる妹をにくくあらば人嬬故[ヒトヅマユヱ]にわれこひめやもと有るに同じく、人の妻なる物をと言ふ義なり。此歌七夕の歌と聞えず、誤りてここに入りたるなるべし。
參考 ○朱羅引(古)アカラビク「ヒ」を濁る(新)「ヒ」清む ○色妙子(代)イロテヘノコヲ(考、古)略に同じ(新)イロタヘナルコ ○數見者(古)略に同じ(新)シバミナバ。
|
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
| |
〔アカラビク。シキタヘノコヲ。シバミレバ。ヒトヅマユヱニ。ワレコヒヌベシ。〕
朱羅引色妙子數見者人妻故吾可戀奴
|
「あからひく」の語義の解説から始まる
巻第二の〔222〕は、確かに「色妙乃」と表記し「しきたへの」と訓むの通常だが、その掛かる語が「枕」であるので、「しきたへの」としても、不思議ではない
雅澄は、それを「美しい子」にも当てようとしたのかな
「しきたへの」という枕詞は、やはり「美しい」という「敷物関連」に使われるものだろう
人妻故には、同じように先例の二首を挙げている
「奴」の字の用字へのイメージについて言っているが、他に同様の用例があるので、と
歌意は、七夕の歌とせず、作者が人妻と知りながらも恋する心情を詠ったもの、とする |
朱羅引[アカラヒク]は、朱[アカ]ら光[ビカル]の縮れるにて紅顔[ニホヘルカホ]を云なるべし、雁[ラ]にそへ言なり、既く四(ノ)卷に出づ、
○色妙子は、十三にも、日本之黄楊乃小櫛乎抑刺[ヤマトノツゲノヲクシヲオサヘサス]、刺細子彼曾吾孋[シキタヘノコハソレゾワガツマ]、とあり、刺細は敷細[シキタヘ]の誤なれば、ここも舊本にシキタヘとよめるよろし、(イロタヘとよむはわろし)、二(ノ)卷に色妙乃枕等卷而[シキタヘノマクラトマキテ]、とあるをも、考(ヘ)合(ス)べし、色[シキ]は重浪[シキナミ]の重[シキ]にて、妙[タヘ]は、徴妙[クハシクタヘ]なる謂ならむ、美女を稱ていふなるべし、(袖中抄に、崇徳院御製、たへの子がよとでのすがた見てしより/しえ[本ノマヽ]が命は逢にかへてき、とあり、
○人妻故[ヒトヅマユヱニ]は、人妻なるものをの意なり、一(ノ)卷に、紫草能爾保敝類妹乎爾苦久有者[ムラサキノニホヘルイモヲニククアラバ]、人嬬故爾吾戀目八方[ヒトヅマユヱニアレコヒメヤモ]十二に、小竹之上爾來居而鳴鳥目乎安見人妻姤爾吾戀二來[シヌノウヘニキヰテナクトリメヲヤスミヒトヅマユヱニアレコヒニケリ]、これら同體なり、
○可戀奴は、コヒヌベシなり、奴(ノ)字は、いかゞしき用樣なれど、かくかけること集中前後に例あり、既くいへり、
○歌(ノ)意は、人妻なれば、いかに戀しく思ひても、益なき事とは思ひながら、紅顔の美女をたびたび見れば、見る度に心うつりて、なほ止ことを得ずして、戀しく思ふべしとなるべし、
(六帖に、此(ノ)歌をいろたへの子のかずみれば、と載たるは誤なり、)
さて此(ノ)歌、七夕によめるものとしも聞えず、此間に収たるにやあらむ、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
| |
〔あからひく色妙子[イロタヘナルコ]しば見者[ミナバ]人妻ゆゑにわれこひぬべし〕
朱羅引色妙子數見者人妻故吾可戀奴 |
「アカラヒク」が、その掛かり方から、純粋な枕詞ではなく、准枕詞だとすべき、という
「いろたへなるこ」それは、「いろぐはし」にも通じるが、文法上の連体形の語法を述べている
「みなば」とは「仮定条件」をいうのだろう、そうでないと、「こひぬべし」に照応しないというが、何故だろう
|
アカラヒクは集中にアカラヒク日モクルルマデ、アカラヒク朝ユクキミヲ、アカラヒクハダモフレズテとあり。日と朝とにつづきたるは純粹の枕辭なれど肌につづきたるとこゝなるとは准枕辭と認むべし。アカクニホフといふ意とおぼゆ(古義にはヒを濁りてアカビカルの約とせり)
○第二句を舊訓にシキタヘノコヲとよめるを契沖はイロタヘノコヲに改め眞淵、千蔭、雅澄は舊訓に從へり。さて冠辭考には
アカラヒクシキタヘノコヲ云々こは子につづけて上の赤ネサス君てふに同じ。色妙は借字にて下に擧るシキタヘノ妹といふに同じく敷細布てふ意也。さてその敷は物の繁くうつくしきをいひ細布もよき絹布をいふ古語にて女のうつくしく和[ナゴ]やかなるに譬へたる語也
といひ、古義には
シキタヘノコは十三にもヤマトノツゲノヲグシヲオサヘサス刺細(ノ)子(ハ)ソレゾワガツマとあり。刺細は敷細の誤なればここも舊本にシキタヘとよめる、よろし。二卷に色妙乃枕トマキテとあるをも考合べし。シキは重浪[シキナミ]のシキにてタヘは微妙なる謂ならむ。美女を稱ていふなるべし
といへり。色妙をシキタヘノとよみて子にかゝれりとせむには枕辭と認めざるべからず。既にアカラヒクといふ枕辭を戴き更にシキタヘノといふ枕辭を戴くべきならむや思ふべし。これのみにてシキタヘノとよむべからざる事明なれば其上は云ふにも及ばざる事なれど尚云はむに冠辭考に例として引けるシキタヘノ妹は卷二に敷妙ノ妹ガタモトヲとあるを云へるにてそのシキタヘノは眞淵自も[シキタヘノの下に]『こは語を隔てタモトにつづく』といへるにあらずや。又古義に卷十三なる
みなのわた、かぐろき髪に、眞木綿もち、あざねゆひ垂り、やまとの、つげの小櫛を、おさへさす、刺細の子は、それぞわがつま
の刺を敷の誤として今の例とせるは妄とも妄なり。刺はおそらくは腰の字の誤ならむ。なほ彼處に至りていふべし。然らば契沖の如くイロタヘノ子ヲとよむべきかと云ふに語法上イロタヘノ子とはいふべからず。宜しくイロタヘナル子とよむべし。さて初二はレナヰノ色ウツクシキ子といへるなり
○シバは屡なり。見者を從來ミレバとよみたれどミナバとよまではコヒヌベシと照應せす。人妻ユヱニは人ノ妻ナルニとなり(卷七【一三八二頁】參照)
○此歌は略解古義にいへる如く元來七夕の歌にあらざるがまぎれてこゝに入れるなり |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| |
あからひく敷栲[シキタヘ]の子を屡[シバ]見れば、人妻故に、我戀ひぬべし |
この解釈で、意表を突かれた
「人妻だからこそ」、恋焦がれる、という意味だ |
| |
あの美しい織姫さんを、私が度々見るやうだつたら、人の妻だとわかつてゐるが、その人の妻なる人の爲に、焦れることであらう。美しい人に。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
| |
〔あからひく 敷妙の子を しば見れば 人妻ゆゑに 我戀ひぬべし 〕
アカラヒク シキタヘノコヲ シバミレバ ヒトヅマユヱニ ワレコヒヌベシ
朱羅引色妙子數見者人妻故吾可戀奴 |
歌意に特筆なし
ここでも巻第二の〔222〕を引用するが、
その引用は誤りだと思う
織女の美しさに見惚れた歌として、七夕歌としても、間違いとは言えないとするが、
根本的な「牽牛と織女」の「年に一度の逢瀬」の舞台が、大きく変質してしまう
有り触れた、人妻への「恋心」の歌なのに...
|
顔色ノ赤イ美シイ女ヲ度重ネテ見ルト、アレハ人ノ妻ダノニ、私ハ思ガ加ハツテ戀シク思フデアラウ。
○朱羅引[アカラヒク]――枕詞。赤ら引く。赤らは赤ら橘などの赤らであらう。ひくは光る、輝くなどの意か。この枕詞は朝・日・月・肌などにもつづいてゐるが、ここに色妙子[シキタヘノコ]につづいたのは、顔の色の赤く輝く意であらう。
○色妙子[シキタヘノコヲ]――イロタヘノコヲと訓む説もあるが、卷二に色妙乃枕等卷而[シキタヘノマクラトマキテ](二二二)とあるによれば、イロタへはよくないやうである。シキタヘは古義に「色《シキ》は重浪[シキナミ]の重[シキ]にて妙[タヘ]は微妙[クハシクタヘ]なる謂ならむ。美女を稱ていふなるべし」とあるのに從はう。
○數見者[シバミレバ]――屡々見れば。
○人妻故[ヒトヅマユヱニ]――人妻だのに。この故には、ダノニ、ナルモノヲなどの意で、集中に多い。
〔評〕人妻を戀ふる歌である。七夕の歌らしくないが、朱羅引色妙子[アカラヒクシキタヘノコ]を織女に見たのであらう。織女の美に見とれた人の歌として、七夕の歌と見られないことはない。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
| |
〔赤らひく 敷妙の子を しば見れば、人妻ゆゑに 吾戀ひぬべし。 〕
アカラヒク シキタヘノコヲ シバミレバ ヒトヅマユヱニ ワレコヒヌベシ
朱羅引色妙子數見者人妻故吾可戀奴 |
歌意に特筆なし
「しきたへ」を譬として言うのは、訳しようがないからだろう
では、どうしてストレートに修飾語として「いろぐはし」にしないのだろう
「いろたへ」の語が他に見えない、とあるが、用例が一例というのも珍しいことではない
第三者が、織女の美しさを詠うものとしているが、
それだけであれば、確かに「七夕」歌の外伝のようにも思える
しかし、「人妻故に」となれば、その様子は違ってくるのではないだろうか |
【譯】赤らんでいる美しい子を度々見れば、人妻であるのに、わたしは戀をしそうだ。
【釋】朱羅引 アカラヒク。枕詞。ラは接尾語で、赤ラ孃子、赤ラ小船などいう。ヒクは、色の行き及んでいるをいう。朝、日、月、肌などに冠しているが、ここは容顔の紅潮している意に冠している。
色妙子 シキタヘノコヲ。シキタヘは、緻密な織物をいい、ここは譬喩として、和柔の子の意をあらわしている。「布細乃[シキタヘノ] 宅乎毛造[イヘヲモツクリ]」(卷三、四六〇)などの用法に通うものがある。イロタヘノコヲ(拾穗)の訓のあるのは、赤ラヒクの句に引かれたものであるが、イロタヘの語は、他に見えない。
人妻故 ヒトヅマユヱニ。織女星は、牽牛星の妻であるから、第三者の立場としてヒトヅマと言つている。ユヱニは、その原因をいい、それだのにの意をあらわす。人妻であるのだのに。
吾可戀奴 ワレコヒヌベシ。奴は、字音假字として書き添えてある。
【評語】第三者として織女星の美を歌つている。赤ラヒクシキタヘノ子という特殊な敍述が、その美しさをよく描いている。
|
| 『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕 |
「評釈」私見 |
| |
あからひくしきたへの子を屡見れば人妻ゆゑに吾戀ひぬべし |
歌意、語釈特筆ナシ |
【譯】顔の色のあかく美しい、やはらかい織物のやうなあの女をしばしば見ると、人妻であるその女に、自分は牽きつけられて戀しくなつてしまひさうである。
【評】これは七夕の歌ではなく、人妻を戀ふる歌がまぎれこんだものとも思はれるが、「あからひくしきたへの子」は織女のことで、彦星以外の男の星が、織女の美しさに見とれたものと考へられるもする。
【語】○あかひらく 赤みを帯びて血色のよいこと。ここは枕詞といふべきではない。「六一九」参照。
○しきたへの子 美しい女。「しき」は重浪(しきなみ)の重(しき)「たへ」は微妙(くはしたへ)といふ説もあるが、「しきたへ」は多く袖、衣、などにかけた枕詞として用ゐられてをり、しなやかで織目のしげくある織物の意と思はれるので、「しきたへの子」は、敷妙のごとく美しい女と見る方がよいとの説によつた。
○人妻ゆゑに 他人の妻である女のゆゑに。ここは後世の如く、人妻であるのにとも解し得る。 |
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
| |
〔あからひくしき細布の子を屡見れば人妻ゆゑに吾戀ひぬべし 〕
アカラヒク シキタヘノコヲ シバミレバ ヒトヅマユヱニ ワレコヒヌベシ
朱羅引色妙子數見者人妻故吾可戀奴 |
牽牛の妻である織女を、人間界の人の憧れとしての歌、と |
【大意】赤い色を引き美しい、精巧な布の如き子、織女を、しばしば見れば、人妻たる織女であるのに、吾は戀ひ思ふであらう。
【語釈】アカヒラク 枕詞。赤みを帯びた意で用ゐられるが、ここなどは普通の修飾語と見てよい。
○シキタヘノコ シキタヘは細い布の意である。「刺細子」(巻十三、三二九五)はサスタヘノコ或はサシタヘノコと訓むべきことは、そこの注に言ふが、共に精巧なる織物の感覚と、女子の肌の感覚の連合により、成立した語であらう。美女をいふのである。
○シバミレバ シバシバ見れば。
○ヒトヅマユヱニ 人妻の為にだが、人妻であるのにとなる語勢で、いつもあらはれる語である。
【作意】牽牛の妻と定められた織女を見る、人間の心持を歌つたのである。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
| |
〔あからひく 色ぐはし子を しば見れば 人妻故に 吾戀ひぬべし 〕
アカラヒク イログハシコヲ シバミレバ ヒトヅマユヱニ ワレコヒヌベシ
朱羅引色妙子數見者人妻故吾可戀奴 (『元暦校本』) |
「いろぐはし」が、初めて提唱され、今では多くの書でも採られているが、純粋な枕詞としてされていない以上、その文法的には、疑問もある
「くはし」が形容詞なら、「子」にかかる連体形「くはしき」にならなければ、と思う
「いろぐはし」を枕詞とすれば、「子」にかかるのも理解出来るが、まだそれは通じてないようだ
しかし、似たような語の用例では、実質的な枕詞と言ってもいいような気がする
|
【口訳】紅顔の美女を、こんなに度々見てゐると、この人妻ゆゑに自分は戀ひしくなつてしまふであらう。
【訓釈】あかひらく―枕詞(4・619)。赤い色をしてゐる、の意。
色ぐはし子を―『元暦校本・類聚古集・紀州本・京都大学本(左に赭)』イロタヘノコノ、『西本願寺本(青)』以後シキタヘノコヲとしたが、「しきたへの」はいづれも枕詞でここには適切でない。私はイロクハシコヲと訓むべきでないかと述べ、井出君の『訓詁篇』と『古典大系本』とに採られてゐる。「浦妙山曾(ウラグハシヤマゾ)」(十三・三二二二)、「朝日奈須 目細毛(マグハシモ)」(十三・三二二四)、「名細寸(ナグハシキ) 稲目乃海」(三・三〇三)、「香具波之君(カグハシキミ)」(十八・四一二〇)、「花細(ハナグハシ) 葦垣越尓 直一目 相見之兒」(十一・二五六五)など、特に「名くはし」「香くはし」「花くはし」の例があるから「色くはし」もあつてよいと考へたのである。井出君は「宇良具波之(ウラグハシ)」(十七・三九九三)、「可具波志伎(カグハシキ)」(廿・四三七一)など濁音仮名「具」が用ゐられてゐるからイログハシと濁つて訓む事を注意されてゐる。紅顔の色の美しい少女、の意。これをシキタヘノと訓んで、前の「行く舟」を牽牛の舟と考へたやうに、織女と結びつけて七夕の歌とするに至つたのでないかとも考へられるが、これはただの人の世の戀の歌である(「人麻呂集の歌二つ」『古徑』三所収)。
しば見れば―『元暦校本・類聚古集・紀州本・京都大学本(左に赭)』カスミレバを『西』以後シバミレバと改めた。『新考』に「ミナバとよまではコヒヌベシと照応せず」とあるが、シバミナバと訓んでは概念的な叙述歌になつて感動の無いものになる。
淡雪のこのころ継ぎてかく降れば梅の初花散りか過ぎなむ (8・1651)
心をし君に奉ると思へればよしこのころは恋ひつつをあらむ (11・2603)
などの例を見てもわかるやうに、「しば見る」のは仮定ではない。現にしばしば見てゐるのである。見ない方がよいのかとも思ふけれども見ないでをれないのである。機会が与へられる―実は機会をつくつてゐるのかも知れないが―まゝにしばしば見てゐるのである。それが現実なのである。この現実に対して将来を案ずるのだから「しばしば見れば」でなければならない。「しば見れば」であればこそ作者のどうにもならない「なげき」がにじみ出て来るのである。これを七夕の歌としてはこの句も意味をなさない事になるのである。
人妻故に吾戀ひぬべし―この句も『拾穂抄』に「人つまゆへとは織女は牽牛夫あれば人つまと云 星合みる人のよめるうたにして可心得」と云ひ、諸注もいろいろ述べてゐるが、ただ『万葉考』に「此哥七夕の哥にあらず まぎれてこゝに入しなるべし」に従へばこの歌は右に述べたやうにすなほに解けるのである。人妻故に戀におちてしまふであらう、の意である。
【考】古今六帖(一「七日の夜」)「いろたへの子のかずみれば」、赤人集には「おほそらにたなひくあやめかすみれは人のつまゆゑいもにあひぬべし」、流布本「たなひくあめの」「人のつまゆく我にあひぬべし」とある。初句は(2001)より紛れたものか。
|
|
|
 |
 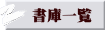  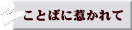 |











































