| 【歌意1932】 |
「さぬかた」は、たとえ実にはならなくても
どうか、花だけは咲いて見せてほしい
私の苦しい恋心を、何とか慰めたいのですよ |
| 【歌意1933】 |
「さのかた」は、もう実になってしまったので
いまさら春雨が降って、花が咲くことなどあるでしょうか... |
「実」を結ぶことが、恋の成就をいうものだと、この歌は前提にしている
確かに、その前提でこそ、「はなのみにさきてみえこそ」という語が生きてくる
だから、「答歌」の「みになりにしを」と断るのは、解り切ったことを返した詠歌だ
そうだろうか
おそらく、「問歌」は男だろうが、「人妻に求愛」しているのではなく
理屈抜きに、どうにも抑えることが出来ないこの気持ちを
何とか、鎮めようともがいており
せめて、姿だけでも見ることが出来たら、
やがて、私の気持ちも収まるでしょう、と言い聞かせているものだと思う
それでも、重ねて言う女の歌は、男には辛いものなのだろう
「いまさらにはるさめふりて」...
どうして、今になって...もう、遅いのですよ
どんなに花を咲かせようと、雨が降っても
もう実になっているのでは、手遅れじゃないですか
どうして、今更...
もっと早く仰っていただければ...
これが女の気持ちではないかな、と思う
多くの注釈が、人妻への求愛を、人妻故に拒否した「問答歌」とするが
これは、「求愛」の歌ではなく
結婚することが、男の事情で叶わなかったが
だけど、せめて姿だけでも、見たいものだ...そうやっと本心を伝えた歌だと思う
「人妻故に拒否した」のは事実だが
その重さ以上に感じられるのは、
「私も逢えば抑えられません」という気持ちもあるのではないだろうか
「花を咲かすことはできない」
この花を咲かせる行為には、女が相手に想いを伝える表現にもなる
だから、すでに「実」も成ったので、「咲かせたくても咲くことができない」
『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕にいう
「さのかたはみになりにしを 花にさきて見えよといへるをいひのかれんとて一たひみになりにし物を今更に又春雨ふりて花さかんや已に花ちりみになりし木は二たひさくへきやうなしとの心なるへし」
「言い逃れんとて」...嫌な表現だ
「花に咲く」表現で、想いを綴る歌がある
| (平群氏女郎贈越中守大伴宿祢家持歌十二首) |
| 麻都能波奈 花可受尓之毛 和我勢故我 於母敝良奈久尓 母登奈佐吉都追 |
| 松の花花数にしも我が背子が思へらなくにもとな咲きつつ |
| まつのはな はなかずにしも わがせこが おもへらなくに もとなさきつつ |
| 右件十二首歌者時々寄便使来贈非在一度所送也 |
| 既出〔書庫-6、2013年5月10日〕巻第十七 3964 平群氏女郎 |
〔歌意〕
松の花は、あなたにとっても「花の数」には入れないのでしょうが
いくらあなたが想ってくださらなくても
私は、その松の花のように、しきりに咲き続けています
|
掲題歌とは、その「花に咲く」ということの意味においては
同じものだと思う
「散る」のではなく、「咲く」、「咲きたいけど、咲かせることはできない」
何故なら、「花」が「想い」であり、「咲く」ことが「想いを伝えること」なのだから...
| さのかたは みにならすとて はなにのみ さきてなみえそ こひのさくらを |
| 赤人集 209 |
| さのかたは みになりにしを いまさらに はるさめふりて はなさかむやは |
| 赤人集 210 |
〔209〕、何だか雰囲気が違う
格助詞「とて」は、幾つか用法もあるが、「理由・原因」の「~からといって」ではどうだろう
「さのかたは、実には成らないからと言って」
「さきてなみえそ」の「なみえそ」は、「な~そ」の禁止形だが
「みえ」は下二段「見ゆ」の連用形だ
その「見ゆ」の意味は、「見える・会う・見られる、など」
ならば、どんな解釈になる
掲題歌の「さきてみえこそ」と、どうみても逆の表現になっている
その前の句に「はなにのみ」と、これも掲題歌と違う
掲題歌では、「はなのみに」で、「せめて花だけでも」のような意味になるだろうが、
この『赤人集』の「はなにのみ」では、「花だけを」としたくなる
ここまで通すと、「さきかたは、実には成らないからといって、花だけを見せないで」
要は、実に成らないのなら、花も見せないでくれ、ということか
結句の「こひのさくらを」が解らない...さくらの花を、恋心に見立てているのだろうか
だから、成就しない「恋の桜花」なら、咲かないで欲しい
〔210〕では、結句が助動詞「む」の終止形「む」に、反語の終助詞「やは」で、
意味は、掲題歌と変わらない
「問歌」で、恋の成就も出来ないのなら、花だけ咲かせて見せないでくれ、といい
「答歌」で、すでに結婚してしまっているので、花も咲かせられません、という
これでも、一応「問答歌」にはなっている
しかし、『万葉歌』のように、通説とする男の求愛を、拒否する女、というよりも
どうせ、どうにもならない「恋」なのだから、あなたの姿は見たくない、辛いだけだ
それはそうでしょうけど、一度成った実に、もう花は咲きませんよ、と「頷き返す」女
こんな解釈すると、ますます自分の能力のなさに愕然としてしまうが
もっと時間をかけて勉強しよう
|
|
| |
|
掲載日:2014.03.01.
| 春相聞 問答 |
| 狭野方波 實尓雖不成 花耳 開而所見社 戀之名草尓 |
| さのかたは実にならずとも花のみに咲きて見えこそ恋のなぐさに |
| さのかたは みにならずとも はなのみに さきてみえこそ こひのなぐさに |
| 巻第十 1932 春相聞 問答 作者不詳 |
| 狭野方波 實尓成西乎 今更 春雨零而 花将咲八方 |
| さのかたは実になりにしを今さらに春雨降りて花咲かめやも |
| さのかたは みになりにしを いまさらに はるさめふりて はなさかめやも |
| 巻第十 1933 春相聞 問答 作者不詳 |
【左頁〔花に咲く〕】〔3964〕
| 【1932】語義 |
意味・活用・接続 |
| さのかたは[狭野方波]植物説、少数ながら地名説もある |
| みにならずとも[實尓雖不成] |
| とも[接続助詞] |
[逆接の仮定条件]たとえ~にしても |
| 〔接続〕動詞・形容動詞・助動詞の終止形、形容詞・助動詞「ず」の連用形につく |
| はなのみに[花耳] |
| のみ[副助詞] |
[限定]~だけ・~ばかり |
| に[格助詞] |
[よりどころ]~に |
体言につく |
| さきてみえこそ[開而所見社] |
| こそ[終助詞] |
[希望]~てほしい |
連用形につく |
| こひのなぐさに[戀之名草尓] |
| なぐさ[慰] |
苦しさ・悲しさを慰めるもの・慰め |
| に[間投助詞] |
[感動・強調]~になあ・~のであるよ |
体言につく |
| 【1933】語義 |
意味・活用・接続 |
| さのかたは[狭野方波] |
| みになりにしを[實尓成西乎] |
| にし |
~た・~てしまった |
連用形につく |
| 〔成立〕完了の助動詞「ぬ」の連用形「に」+過去の助動詞「き」の連体形「し」 |
| を[接続助詞] |
[順接]~ので |
連体形につく |
| いまさらに[今更] |
| いまさらに[今更] |
[形動ナリ・連用形](多く否定的な気持ちを含み)
今となっては、もう必要のないさま |
| はるさめふりて[春雨零而] |
| て[接続助詞] |
[単純接続]~て・そして |
連用形につく |
| はなさかめやも[花将咲八方] |
| めやも |
[反語]~だろうか(いや、~でないなあ) |
未然形につく |
| 〔成立〕推量の助動詞「む」の已然形「め」+反語の終助詞「やも」 |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
[さのかたは]
地名説が、どこで語られているか解らないが、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕は、「狭野方」を
植物名のように、「狭野方は、實に成らないでも...」としているが、
地名説もある、と次の根拠を紹介している
「師名立 都久麻左野方 息長之 遠智能小菅-」〔巻第十三 3337〕の
「都久麻左野方」(つくまのさのかた)の「左野方」が、
「狭野方」に同じで、滋賀県坂田郡だろうと
その地名説はいう、と
しかし、第二句の「みにならずとも」に続く語としては、「植物」の方が合理的だ
『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕の注釈では、
「さのかたはみにならす 狭野方は春花さく木也仙覺はさのかたはさねかたきといふ事にて藤の一名を云といへり但類聚萬葉に春木のねふりさねきの中 にさのかたを書つらねて藤とは別所に書入られたりたとひさのかたはさねかたきといふにても必藤はかりさるへくもあらねは藤の説信用しかたし見安にも仙説に
したかへりけれと蔵玉等の異名にも八雲抄等にも見えさる異名定かたき事にや哥の心はみにならすともとは人にあはぬ事をよそへいへるにや前にも其心あるかこ
としたとひあはすともま見えたにせよ戀しき慰めにせんといへり」
季吟は、仙覚が、「さのかた」は「藤の一名」だというが、
「藤とは限らない」としている...私の未熟な読解力ではそう読める
この『拾穂抄』は、仙覚の説を紹介しながら、この歌の歌意を書いているが
それは、ここでは語らない
また、『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕は、その解説の中で、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕の見解を書いている
「私注は続日本後記嘉祥二年三月条に枕詞ヒサカタノに『瓠葛』とあることからカヅラのことをカタとも呼んだことを述べ、サネカヅラ・サナカヅラとの音の類似性からサノカタもサネカヅラと同義の語の音の転訛したものと考えて、アケビを指しているとした。私注がアケビとしたのは、仙覚抄にいう藤は藤波の称呼が広く行われていたと見えることと、アケビも花が美しく開花期が晩春であることからなので、アケビと断定する根拠は少し弱いが、花の美しい蔓草の一種ということは認めてよいだろう。」
と述べ、多くの注釈書に推定されるように、「あけび」が有力だとする |
| |
| [こひのなぐさに] |
上二段動詞「和(な)ぐ」は、「心が静まる・心が穏やかになる」を意味するが
その動詞「なぐ」に、接尾語「さ」が付いたもので体言化するものだが
この歌のように「こひのなぐさ」の形で「~の~さ」は、感嘆の意にもなる
「恋心が、慰められるよ」
|
| |
| [いまさらに] |
「いまさらに」は形容動詞ナリ活用の連用形だが、
この語幹「いまさら」が副詞化して、副詞「いまさら」の形で、
下に打消しや反語の表現を伴っていることもある
この歌の場合も、副詞「いまさら」で、結句に反語の「めやも」として解釈できる
が、そうなると、「に」をまた解釈しなければならないので、
ここは「形容動詞」でいいと思う |
| |
|

|
| 【歌意1934】 |
(梓弓を引く)引津のほとりに生えている、
その「なりその花」が咲くまで、
逢わない、と言うあなたは、
咲かない花を待つとは...逢うことはできないのですか |
| 【歌意1935】 |
川面に生える、数多く(いつ)の「藻」の「花」咲く、というように、
いつもいつでも、いらしてください、いとしいあなた
その時期でないなどというのでしょうか、
いえ、そんな「いけない時」などないのですよ |
この二首を、素直に読めば、だいたい上のような歌意になると思う
しかし、これでは、何となくちぐはぐな「問答歌」だ
「問い」と「答え」には、あまり綺麗になっていない
勿論、『万葉集』の「問答」の性格からすれば
「相聞」の「掛け合い」のような「響き合い」は、ないだろう
しかし、それをぴったり演出された「問答歌」に出合うと
その見事な編集に、喝采したくなるのだが、
この二首について言えば、「響き合う」ことはない
この「恋の歌」を「問答」とするには、どちらかを「男」として読まなければならない
〔1934〕で、結句に「あはぬきみかも」と言えば、「女歌」だろうし
〔1935〕についても、第四句に「きませわがせこ」とあるのは、やはり「女歌」だ
もともと、関連のない歌だとは解るので、辻褄合わせに二首を持ち出したのであれば
〔1934〕歌を、詠み直して載せればよかったものを、と思う
何故なら、この〔1934〕歌は、巻第七旋頭歌(右注記)の詠み変えのように言われている
ならば、どうせ同じような作業をするのなら、どうして意改しなかったのだろう
次のような「例」あるいは、「手段」が実際にある
| あづさゆみ ひきつのへなる なのりそも はなはさくまで いもあはぬかも |
| 歌経標式 |
これは、「男歌」にする為に、詠み直したもののように思える
実際は、違うかもしれないが
〔1934〕に沿って解釈すると
「なりその花が咲くまで、逢わないという妹よ」
それだと、〔1935〕の解釈が、ぴったり合う
「そんなことはありません、『いつもの花』が咲くように、いつもいつでも来てください」
また、『古今六帖』には、『万葉集』の旋頭歌〔1283〕と短歌〔1934〕の関係のように
| あつさゆみひきつりにあるなのりそのはな とるましにあはすあらめやなのりそのはな |
| 古今六帖 第五 雑体 2521 |
| あつさゆみ ひきつのへなる なのりその いつれのうらの あまかかるらむ |
| 古今六帖 第三 水 1844 |
そして、『夫木抄』にも、
| あつさゆみ ひきつへにある なのりその はなとるまてに あはさらめやも |
| 夫木抄 第二十六 雑八 12029 人麿 |
どちらも、『万葉集』の「問答」を想定したものではなく
だから「詠い変えた」ものではないと思うが、
少なくとも、このような「男歌・女歌」不明の「歌」への改訓があるのなら、
『万葉集』編集時にでも、あってもよさそうに思える
ただ、『赤人集』をみると、「問答」ではなく、同じ「詠題」で歌を並べただけのこと
そんな気もしてくる
| あつさゆみ ひきつへきやは なつくさの はなさかぬまて あはぬきみかな |
| 赤人集 211 |
| かはかみの いつものはなの いつもいつも きませわかせこ たえすまつはた |
| 赤人集 212 |
どちらも、「女歌」だが、『万葉集』が、「問答」の詠題に敢えて配列したのは間違いないが
こうして、「無題」で並べてみると、
『万葉集』でも有り触れた、配列に思えてくる
だから、『万葉集』が、「問答」にしたのであれば、その意図に沿った「詠い変え」が、
あるべきではなかったか、と思う
最後に、〔1935〕の重出歌となる〔494〕も参考までに載せておく
ただし、この歌では、作者が明記されている
| 相聞/(吹芡刀自歌二首) |
| 河上乃 伊都藻之花乃 何時々々 来益我背子 時自異目八方 |
| 川上のいつ藻の花のいつもいつも来ませ我が背子時じけめやも |
| かはのへの いつものはなの いつもいつも きませわがせこ ときじけめやも |
| 巻第四 494 相聞 吹芡刀自 |
『歌経標式』のように、「問答」らしく「詠い変え」するか
あるいは、原文のまま「男」とか「女」とか現実的な「恋心」ではなく
「観念的」な「人の想い」を「問答」の掛け合いに仕立てているものなのか
それにしては、原文通りだと、双方の想いに「焦点」が合わないように思えてならない
|
| |



 |
掲載日:2014.03.02.
| 春相聞 問答 |
| 梓弓 引津邊有 莫告藻之 花咲及二 不會君毳 |
| 梓弓引津の辺なるなのりその花咲くまでに逢はぬ君かも |
| あづさゆみ ひきつのへなる なのりその はなさくまでに あはぬきみかも |
| 既出〔書庫-15、2014年2月6日〕 巻第十 1934 春相聞 問答 作者不詳 |
| 川上之 伊都藻之花乃 何時々々 来座吾背子 時自異目八方 |
| 川の上のいつ藻の花のいつもいつも来ませ我が背子時じけめやも |
| かはのへの いつものはなの いつもいつも きませわがせこ ときじけめやも |
| 巻第十 1935 春相聞 問答 作者不詳 |
【注記〔旋頭歌〕】〔1283〕【左頁〔重出歌〕】〔494〕
| 【1934】 |
既出〔書庫-15、2014年2月6日〕 |
| あづさゆみ[梓弓]〔枕詞〕「引」にかかる |
| ひきつのへなる[引津邊有] |
| なのりその[莫告藻之]「ホンダワラ」という名の海藻の一種で、花は咲かない |
| はなさくまでに[花咲及二]咲かない花を、咲くまでに、と言うのは、永遠に、ということか |
| あはぬきみかも[不會君毳] |
| 【1935】語義 |
意味・活用・接続 |
| かはのへの[川上之]川面に |
| いつものはなの[伊都藻之花乃] |
| いつ[いつ] |
「接頭語」勢いが盛んである・神聖なものなどに付ける |
| 〔いつも〕「いつ藻」とする固有名詞説や、多くのとする「五百(いつも)」なども言う |
| いつもいつも[何時々々]いつでも |
| きませわがせこ[来座吾背子] |
| ませ[座(ま)す] |
[補動サ四・命令形]お~になる |
連用形につく |
| (動詞の連用形について、尊敬の意を表す) |
| ときじけめやも[不會君毳] |
| ときじけ[時じ] |
[形シク・未然形]その時期でない・時節に関係ない |
| 〔古い活用〕「ときじ」の未然形は「ときじから」だが、古い活用の未然形「ときじけ」 |
| めやも |
[反語]推量の助動詞「む」の已然形「め」+反語「や」+詠嘆「も」 |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】(諸本諸註釈書の解説の場合『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年〕拠)
| |
[ひきつのへなる]
「引津」は、福岡県糸島郡志摩町の岐志から船越にかけての入海とされている
遣新羅使人たちが引津の亭で詠んだ歌七首が、巻第十五にある
幾つかの「異訓」が見られる
「ひきつべにある」『元暦校本』の「交合」違いによる別系統の『元暦校本』(元赭)
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕
「ひきつのへにある」
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕
《古注釈の引用》
『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕
「あつさゆみひきつのへなるなのりその花さくまてにあはぬきみかも 」
「あつさ弓ひきつのへ 梓弓はひきといはん枕詞也引津は筑前名所也此哥類聚には引津べにあると和シなのりそのと和せり仙点は引津のへなると和シなのりそかと
和して濱成式の訓といへり式の点はさもあるへしひきつとは井をいふつるへをひくゆへなといへる仙抄の儀更に信用しかたし引津は此集第七に人丸の旋頭哥にも
梓弓引津のへなるなのりその花ともあり名所也」
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕
「あづさゆみひきつのべなるなのりそのはなさくまでにあはぬきみかも」
「引津邊 第七卷の旋頭歌にも出たり。なのりその名物の所歟。第七卷の歌も此歌の如く、なのりその花を詠めり。此引津邊は攝津の國と云傳へたり。紀州と云説
も有。証明追而可考。第十五卷にも、引津邊は出たり。國所追而可決。なのりその花は、つぼみて細く咲ものか。又年を經て、ひねゝば花咲かぬものか。此
歌の意程へて咲ものと聞ゆる也。追而可考也 」
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕
「引津邊有《ベナル》、莫告藻之、花咲及二《マデニ》、不曾《アハヌ》君毳、」
「(卷十五)到筑前國志麻郡云云とありて其次に引津亭舶泊之(此間に夜或 は日の字を脱せり)作歌七首とありこれにあはせ見れば引津は筑前の地名なり引津の邊のゝは辭にて引津の方《ベ》なり野にあらず(卷七)旋頭歌に『梓弓引津
邊有莫告藻之花摘まではあはざらめやも名のりその花』とありいづれかまことなるらんしらず 」
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕
「(梓弓)引津の邊なるなのりそ之《ノ》花さくまでにあはぬ君かも 」
「略解には誤りて引津邊有の津の下に野の字を加へたり。卷七(一三六五頁)に(1978) 梓弓引津の邊なるなのりその花、及採あはざらめやもなのりその花 とありて及採を從來ツムマデニとよめるを採を咲の誤としてサクマデニとよむべき由其歌の處にていひつ。略解に卷七なるといづれかもとならむといへれど旋頭歌の第六句に意義あるを思へば旋頭歌の方もとなる事明なり○第三句の之は略解の如くノとよむべし(舊訓と古義とにはガとよめり)
」
『拾穂抄』は、この「引津」は筑前の引津と断定し、
『童蒙抄』は、大阪北部の摂津だろう、とする
『万葉考』は、巻第十五で、筑紫の館四首、筑前の韓亭六首、
その次に、「引津亭七首」なので、その流れから筑前の引津とする
『新考』は、「古注釈」とは言えないだろうが、
『略解・古義』について言及しているので、載せた
そして、それぞれが巻第七の旋頭歌にも言及している
| 雑歌 旋頭歌 |
| 梓弓 引津邊在 莫謂花 及採 不相有目八方 勿謂花 |
| 梓弓引津の辺なるなのりその花 摘むまでに逢はずあらめやもなのりその花 |
あづさゆみひきつのへなるなのりそのはな
つむまでにあはずあらめやもなのりそのはな |
| (右廿三首柿本朝臣人麻呂之歌集出) |
| 巻第七 1283 雑歌 旋頭歌 柿本人麻呂歌集 |
〔語義〕
「なのりそ」は、「ホンダワラ」という名の海藻の一種で、花は咲かない
「あはずあらめやも」は、反語で
「逢わないというのだろうか、いや逢うだろう」 |
〔歌意〕
(梓弓引く)引津のほとりに生える「なのりそ」の花よ
その花を摘むまでは、逢わないというのでしょうか...
いや、お逢いしましょう...花は咲かないのですから
だから、「名は告らさないでください」、なのりその花よ |
この旋頭歌〔1283〕が、短歌〔1934〕に纏められた、という説が強いが
確かに似通った語句だとは思う
しかし、その「歌意」となると、随分と違う |
| |
| [あはぬきみかも] |
「かも」が「詠嘆・感動」の終助詞なのか、「疑問」の終助詞なのか...
「逢わないと言うあなたなのですね」
「あなたは、逢わないと言うのですか」
本来の独立した一首であれば、「詠嘆・感動」の終助詞として読み
その嘆きは、自己で完結してもよさそうなものだが
こうした「問答歌」として演出されれば、「問いかけ」のような「疑問」が自然だろう
その「疑問」として読むならば、旋頭歌〔1283〕のような「歌意」にも合致する
「咲くことのない花が、咲くまで」などと、なかなか逢えない「あなた」に、
女の方は、嘆くだけではなく、その次の行動を心に感じさせることが出来る |
| |
| [かはのへの] |
この語句の異訓を拾い出しても、歌意に影響はないだろう、と思ったが
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕の注釈が興味深かった
「川上の いつものはなの いつもいつも きませわがせこ ときじかめやも」
「此歌問答の標題あれば、其意をもて見るべき歟。然らば、引津邊の歌は男の歌、此歌は女の答歌と見ゆる也。始めの歌は名のりそをもて喩へ、これはいつもをもて和へたり。前歌に不會君と詠かけし故、こなたには時わかず待佗れど、そこに來まさぬとの意、いつにても來りまさば、あはん時をわくべき事にはあらずとの答也。此歌第四卷吹黄刀自が二首の歌の一首にて、二度茲に出たる也
川上 これを川かみと讀める事心得難し。前に釋せる如く、川かみと讀みては、其所に限る意不得心。前に讀める如く、川づらとか、川のべとか讀むべき也
伊都藻之花 これはいつもと云藻一種有と聞ゆる歌也。さにはあらず。前にも第四卷ふき刀自が歌に出たり。いつもの花と云事をよめり。此歌同歌也。然るに、此いつもの花とは、何の藻を云事にや。尤も八雲等にも只藻の事と有。然らばいつと云へるは、いかなる事にや。此伊都とよめる意知れず。下のいつもいつもとよめらん爲に、いつもとよめると云ひても、何とぞ云べき譯無くては、云出られぬ事也。此義に付ては宗師深き考案ある事也。先いつもと云義は、五十百と云義と心得て、數々の事を云たる義と知る也。伊勢物語にも、つゝゐつの井筒とよめる歌につきても論有事にて、其義は彼物語にて傳ふべし。いつもと云事を、數の多き事と云義は、五つ十百と重ねて云たる義也。又五十をいとも云。つは初語にて五十もゝと云事也。神代紀を始め、五百津と云事、數限りの無き數々の事に云たる義と、古來より傳へ來れども、數多き事を五百に限りて云へる義不濟六百も七百も有べき事を、五百に限れる義不審ある事也。こゝをもて考へ見れば、五十をいと古語に云來れるから、いとは五十の義、ほとは百のことにて、一數に限らず、五つより十、十より百と云意にて數々の義を云たる詞也。八百萬抔云は夥しき事なれ共、此義はいやほよろづと云義にて、八の字は書たると見えたり。然れば此歌のいつもの花とは、數々の藻の花と云義と見る也。五百をいほと云ほは濁音と見るべし。濁音なれば、も也。もは百の義也。神代紀岩戸の所の、五百津のすゞの八十玉串と云も、數々のすゝ竹に、いや玉を貫たれて天神に奉ると云の義也。此歌の、いつもの花とよめるは、何時々々とよまん爲迄の序詞也。いつもいつもは、不斷に時をもわかず來り給へ、相ま見えんと云義也。不會君かもと云かけられたる故、裏を返して答へたる歌也。此歌は第四卷に出たる吹黄刀自の歌を、二度贈答によりてか此處に出せり」
この『童蒙抄』で、一気にこの歌の歌意全体を眺めることになったが、
まず、詠題に「問答」とあるので、その趣旨で鑑賞しなければならない、とする
前歌〔1934〕は「男歌」と解し、この〔1935〕は「女歌」とするべきだという
こうした問題が言われるのも、問歌〔1934〕の結句が、
「あはぬきみかも」では、あたかも「女歌」のように思えるものだが、
「問答歌」として鑑賞するには〔1934〕は、「男歌」とすべきだ、ということだ
これは、左頁でも書くが、そうした解釈は多い
次に、「かはのへの」と訓むべき根拠が書いてある
そして、「いつものはな」に及ぶと、他の注釈書にはない詳細な検証がみられた
一般に、『万葉歌』を自分の心に響かせ鑑賞するだけなら、
細かい理屈は必要ないのだが、
その「ことば」の意味を少しずつでも理解していくと
また違った万葉人の「想い」に触れることができる
今の私は、まさにそんな「味」...「甘味」を知ってしまった
...だから、毎晩こんなに苦労しているのだろうが...それでも楽しい
『神宮文庫本』による「かはかみの」
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕など
『類聚古集』による「かはのうへの」
『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕、
「かはのうへのいつもの花のいつもいつもきませわかせこときわかめやも 」
「かはのうへの(かみのイ)いつもの 八雲御抄にいつもの花只藻を云也と有見安同義也哥の心は一二句はいつもいつもといはん諷詞也前の哥になのりその花さくまてにあはぬといふに答ていつもの花のいつもいつも時わかす來てあひ給へと也」
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕など
|
| |
| [ときじけめやも] |
この異訓、上述の『拾穂抄』が「ときわかめやも」
『神宮文庫本』が、「ときつかめやも」
『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕が、「ときおかめやも」
『童蒙抄』が、「ときじかめやも」 |
| |
| [ときじけ] |
形容詞「ときじ(時じ)」を初めて知った
「じ」は、形容詞をつくる「接尾語」で、打消しの意を含む、とある
形容詞のシク活用であれば、未然形は「ときじから」なのだが
初めは、「ときじ」に「け」、「めやも」かと思った
「ときじ」を古語辞典で拾っても、
その活用で「ときじけ」など見つけられなかったからだ
「めやも」が、推量の助動詞「む」の已然形「め」なので、当然接続は「未然形」になる
しかし、「ときじ」の未然形は見つからない
また最後に開いた岩波の古語辞典、そこでやっと「ときじけ」を見つけた
古い活用の「未然形」と書いてあり、それを見つけた時は、本当にホッとしたものだ |
| |
|
|
| 【歌意1936】 |
春雨が、こんなに絶え間もなく降り続いて
私が恋しく想う、あの人の顔さえも、
来て見させてはくれないのですね |
| 【歌意1937】 |
私のいとしい人のことを、想い続けていると、
この春雨が、私のこの絶え間のない想いを知っているかのように
同じように、止むこともなく絶えず降り続いています |
この「問答」における「春雨」を、漠然と「降る雨」として思えば
この二首は、本当に「噛み合うことがない歌」になる
〔1936〕でいう「春雨」は、この雨のせいで、恋人が逢いに来てくれない辛さ恨めしさを詠う
では、〔1937〕は...
歌の語義だけを追いかけていけば、
「春雨」は、「私」の恋い続ける気持ちを知り、
それと同じように、絶え間なく降る続けることを描写している
これは、何だろう
女のもとへ逢いに行きたいのだが、この雨のせいで逢いに行くこともできない
「春雨」が、知っているのは、男の絶え間ない恋心
いや、そうだとすれば、この「春雨」は、その男の恋心を、「邪魔」していることになる
「逢いになど行かせない」
「それもしるごと」
その男心を知っているかのように、とすれば
どうしても、「春雨」は「逢いに行かせない」となってしまう
そのために、お前と同じように、降り続けているのだぞ、と
だから、この「春雨」を「無情の雨」と解する注釈書ばかりだ
しかし、このような「問答」があるのだろうか
「雨のために来てくれないのですね」と問い
「私の想い続ける気持ちを知る春雨が、同じように降り続ける」と答える
このままだと、「春雨」は「悪者」扱いにされてしまう
そうなのだろうか
『万葉考』に、気になる解釈が載っている
| 吾妹子に我戀しぬびつゝたえぬ涙とともに春雨のやまず降ぬるは吾思ひをしる如くふるとなり |
この解釈は、自分がいとしい人に恋い慕い続け、絶えず涙に暮れているのを、
この春雨は、その気持ちを知って、同じように泣いてくれている
まさに、春雨が「涙雨」のように...
こんな解釈ではないだろうか
しかし、そうであれば、男が女のところに行けないのは、
「春雨」のせいではなく、ただただ「深い恋心」のせいだということになる
そのせいで、「涙雨」となるを知らず、女は「春雨」のせいで来てくれない、というのか
こんな解釈をすると、この「問答歌」は、少し異質な響き合いをしている
無難な解釈は、確かに「無情の雨」とすることだが
それでは、「春雨」が「やまずふるふる」「やまずふりつつ」が同質のものであり
尚且つ、「それもしるごと」が、片方にだけ「擬人化」されているようになる
この「春雨」は、男の気持ちを「知り」、「涙雨」として「降り続い」ている
二首の歌の「春雨」には、そんな「性質」がある
しかし、女はそれを知らず、男はそれを知っている
この背景でこそ、「春雨」を介する二人の仲を味わえるのではないか、と思う
| はるさめの やますふりおちて わかこふる わかいもひさに あはぬころかな |
| 赤人集 213 |
| わきもこを こひつつをれは はるさめの たれもるとてか やますふりつつ |
| 赤人集 214 |
これだと、どちらも「男歌」だ
【異訓】
| [1936]異訓 |
注釈書 |
| はるさめは やまずふるふる あがこふる ひとのめすらを あひみせなくに |
『萬葉集』桜楓社 |
| はるさめの やまずふりふり わがこふる ひとのめすらを あひみせなくに |
『万葉集全註釈』 |
| はるさめの やまずふるふる わがこふる ひとのめすらを あひみしめなく |
『日本古典文学大系』 |
| はるさめは やまずふるふる わがこふる ひとのめすらを あひみせさらむ |
『万葉拾穂抄』
『校本万葉集』
|
| はるさめの やまずふりふる わがこふる ひとのめすらを あひみせしめず |
『万葉集童蒙抄』 |
| はるさめの やまずふりつつ わがこひは ひとのめすらを あひみせざらむ |
『万葉考』 |
| はるさめの やまずふりつつ わがこひは ひとのめすらを あひみしめなく |
『万葉集新考』 |
| はるさめの やまずふりつつ わがこふる ひとのめすらを あひみせざらむ |
『口訳万葉集』 |
| [1937]異訓 |
注釈書 |
| わぎもこに こひつつをれば はるさめは それもしるごと やまずふりつつ |
『萬葉集』桜楓社 |
| わぎもこに こひつつをれば はるさめの そもしるごとく やまずふりつつ |
『口訳万葉集』
『万葉集全註釈』
|
| わきもこに こひつゝをれは はるさめの かれもしること やますふりつゝ |
『万葉拾穂抄』
『万葉考』
『万葉集古義』
『校本万葉集』
|
| わぎもこに こひつゝをれば はるさめの ひともしるごと やまずふりつゝ |
『万葉集童蒙抄』 |
|
| |

|
掲載日:2014.03.03.
| 春相聞 問答 |
| 春雨之 不止零々 吾戀 人之目尚矣 不令相見 |
| 春雨のやまず降る降る我が恋ふる人の目すらを相見せなくに |
| はるさめの やまずふるふる あがこふる ひとのめすらを あひみせなくに |
| 巻第十 1936 春相聞 問答 作者不詳 |
| 吾妹子尓 戀乍居者 春雨之 彼毛知如 不止零乍 |
| 我妹子に恋ひつつ居れば春雨のそれも知るごとやまず降りつつ |
| わぎもこに こひつつをれば はるさめの それもしるごと やまずふりつつ |
| 既出〔書庫-15、2014年2月19日〕巻第十 1937 春相聞 問答 作者不詳 |
【異訓〔左頁下段〕】
【赤人集〔左頁〕】
| 【1936】 |
意味・活用・接続 |
| はるさめの[春雨之]春の雨が |
| やまずふるふる[不止零々] |
| ふる[降る] |
[自ラ四・終止形](雨・雪などが)降る・(比喩的に)涙が流れる |
| あがこふる[吾戀]私が恋しく想う |
| ひとのめすらを[人之目尚矣] |
| ひとのめ[人の目] |
恋しく想う人の顔 |
| すら[副助詞] |
[強調]~までも・~でさえも |
| 〔接続〕体言、活用語の連体形、副詞、助詞などにつく |
| を[間投助詞] |
強調を示めす |
| あひみせなくに[不令相見] |
| あひみ[逢ひ見る] |
[他マ上一・連用形]対面する・逢う |
| せ[為(す)] |
[他サ変・未然形]ある行為を行う・ある行為をする |
| なくに |
~(し)ないことだなあ |
未然形につく |
| 〔成立〕打消しの助動詞「ず」のク語法「なく」+助詞「に」 |
| 【1937】語義 |
意味・活用・接続 |
| わぎもこに[吾妹子尓]私がいとしく想うあなたを |
| こひつつをれば[戀乍居者] |
| をれ[居れ] |
「自ラ四・已然形」ある・いる・座っている |
| ば[接続助詞] |
[順接の確定条件]~すると・~したところ |
已然形につく |
| はるさめの[春雨之]春雨が |
| それもしるごと[彼毛知如] |
| それ[其れ] |
[中称の指示代名詞]そのこと・そのもの |
| も[係助詞] |
[並立・添加]~も・~もまた |
| ごと[如] |
(比況の助動詞「ごとし」の語感)~のように |
連体形につく |
| やまずふりつつ[不止零乍]絶え間なく降る続いている |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| |
[はるさめの]
|
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕の注釈では、
「春雨は毎日々々無2晴間1降りふる」から、来るべき人も来ない、と
この「春雨」に、歌全体の「寂しさ」の「基」があると解釈しているようだ |
| |
| [ふるふる] |
『新訓万葉集』〔岩波文庫、佐佐木信綱、1927年刊行〕は「ふりふり」
現在の語法では、「ふりふり」になるが、奈良時代では、
動作や状態の継続を表すとき、動詞の終止形を重ねた
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕で、真淵は
「不止零零《ヤマズフリツヽ》、 今本此零々をふるふると訓せりこは乍を零に誤りしと本居宣長はいへれど今考るに零零のまゝにてふりつゝと訓が古意ならん」とし、
宣長が「零々」を「乍」の誤りとしたのに異を唱え、
「零々」のままで「ふりつつ」と訓ませた
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕も、その「ふりつつ」で訓み、
「零零を舊訓にフルフルとよめるを宣長は零乍の誤としてフリツツとよみ古義は舊訓に從へり。今いふフリフリを古くはフルフルといへどそはフリナガラといふ義にてこゝにかなはざる上に答歌にも不止零乍とあれば宣長の誤字説に從ふべし」
このように、『万葉集新考』は、真淵のように「ふりつつ」としながらも、
原文をそのまま用いた真淵と違って、その語義から「ながら(乍)」、すなわち「つつ」
宣長の誤字説をとっている
『元暦校本』の「ふりふる」とするのは、
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
| [ひとのめ] |
『万葉考』に、「紀(斉明)中大兄皇子命の君がめをほりとよませ給へるは御母天皇の御かほを見まほしませ給ふなり古へは人に逢まくほるをめをほるなどいひしなり」と述べ、
人の顔を見たい、つまり逢いたい、ということを、
「めをほる」(「ほる」は欲しい)としている
|
| |
| [あひみせなくに] |
この結句の異訓は、幾つかあり
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕では、
「結句を舊訓にアヒミセザラムとよめるを雅澄はアヒミセナクニに改めたり。宜しくアヒミシメナクとよむべし。アヒミシメナクは相見セヌコトカナと云はむに似たり」とし、
旧訓で「あひみせざらむ」とあるのを、
『古義』の雅澄が「あひみせなくに」に改めた、とある
現在、広く訓まれている「訓」は、『古義』の改訓によるものなのか...
しかし、この『井上新考』は「あひみしなめく」とする
旧訓は、『万葉拾穂抄』を始め『万葉考』、『校本万葉集』、
そして『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕がある
『新考』の「あひみしなめく」は、岩波の『日本古典文学大系』がそれによる
|
| |
| [わぎもこに] |
『神宮文庫本』では、「吾妹」の左に「わかせ」とある
これは、「女歌」を伺わせるものだが、
とすると、前歌を、「男歌」と想定してのことなのだろうか
しかし「ひとのめ」というと、女から男のことへの表現のような気もするが... |
| |
| [それもしるごと] |
この「それも」は、「わぎもこ」に対する絶え間もない恋心のことで、
春雨が、「そのこと」を知り、同じように「絶え間なく降る」こと
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕に、
「彼毛を從來カレモとよめれどソレモとよむべし。さて三四は春雨モ知ルゴトといふべきを言足らぬが故にソレを挿めるなり。ソレ、ソノ、を加へて言數を滿せる例は集中に多し、又彼の字をソノ、ソなどよめる例はた集中に見えたり。地名にも彼杵と書きてソノキとよむ例あり」
異訓として、原文「彼毛(かれも)」に即した「訓」がある
『類聚古集』によるもので、『万葉拾穂抄』『万葉集古義』『校本万葉集』
『万葉考』「彼毛知如《カレモシルゴト》、 雨をさして彼とはいへり」
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕、「ひともしるごと」
「彼毛 そこもと讀めり。誰れもとも讀むべけれど、ひともと詠めるは、春雨の日と云詞の續き也。畢竟妹も知れる如くと云意也。われかれと云彼なれば、義訓にそこも共誰れもとも讀むべき也。春雨の晴れず降るから、雨にさへられて得出行かぬと答へたる也」
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕では、「そもしるごとく」
「彼は『黒駒 厩立而 彼乎飼(そをかひ)』〔第十三、3292〕、『抑刺 々細子 彼曽吾妻(それぞわがつま)』〔第十三、3309〕の如く、ソ、ソレと読まれている。指示の代名詞であるが、さす所には疑いがある。春雨をさすとされており、春雨みずからが事情を知る如くであろう。」
これは、用字の例から「彼」を「そ、それ」と訓む可能性をいう
|
| |
|
|
| 【歌意1938】 |
思ってもくれないあの娘に、
わけもなく...しきりに、(菅の根のように)長い春の一日一日を
恋しく思って暮らすことになるのか |
| 【歌意1939】 |
春になると、真っ先に鳴く鳥である鶯のように、
誰よりも早く、初めに私に声を掛けてくださったあなたを、
私は、その想いを大切にし、待っていましょう |
| 【歌意1940】(1938の類歌、あるいは異伝なのか対の歌はない) |
私のことなど、想ってくれそうもないあの娘なのに
玉の緒のように、長い春の一日を、思い暮らすことだ |
「問答」とされながらも、この三首は、〔1940〕が孤立している
もっとも、〔1938〕の類想歌と見做され、ここに並列されたのかもしれない
あるいは、本来はこの次の「答歌」があったかもしれない
しかし、類想歌であることには間違いなく
恋しいと想っている「娘」が、自分のことを「想ってくれない」
あるいは、「想ってくれそうもない」などと悲観的に詠うのが同じくする
小さい点を挙げれば、〔1938〕は、「疑問の詠嘆」で終るが
〔1940〕は、連体形止めと同じような終り方で、強調の詠嘆の感じがする
しかし、〔1938〕は「あひおもはぬいも」で断定的だが
〔1940〕は、「あひおもはずあらむこ」と、現在推量「らむ」で表現されており
娘の態度を図りかねている心象表現になっている
いずれにしても、〔1938〕と〔1940〕は「問歌」になるだろう
この「問歌」だけを読めば、作者の独り相撲の観が強く感じられるが
続く「答歌」を読むと、そうでもないことが分かる
男は、娘に声を掛けていることになる
そして、娘の方は、最初に声を掛けてくれた男を大切に思い
次の誘いを待っている、と想像できる
しかし、男の方はそう受け取らない
自分のことを「想ってくれない」と落ち込んでいる様子だ
よほど、娘の応対が素っ気なかった、ということだろう
態度では、素直に想いを見せられなくても
実際は、心をときめかして待っている
この先の展開が知りたいものだ
この「問歌」の類想歌がある
| 相聞/(山口女王贈大伴宿祢家持歌五首) |
| 不相念 人乎也本名 白細之 袖漬左右二 哭耳四泣裳 |
| 相思はぬ人をやもとな白栲の袖漬つまでに音のみし泣くも |
| あひおもはぬ ひとをやもとな しろたへの そでひつまでに ねのみしなくも |
| 巻第四 617 相聞 山口女王 |
〔語義〕
「そでひつまでに」は、四段動詞「ひつ」は、水に漬かったようにびっしょり濡れる意「ねのみしなくも」は、声に出して泣くこと |
〔歌意〕
想ってくれない人のことを、わけもなく
(しろたへの)袖も濡れるほど、声に出して泣くことか |
| |
| 寄物陳思 |
| 相不念 有物乎鴨 菅根乃 懃懇 吾念有良武 |
| 相思はずあるものをかも菅の根のねもころごろに我が思へるらむ |
| あひおもはず あるものをかも すがのねの ねもころごろに わがもへるらむ |
| 巻第十二 3068 寄物陳思 作者不詳 |
〔語義〕
「ねもころごろ」は、「ねんごろ」の古形「ねもころ」の重複中略形、
「丁寧」の意で、「こまやかに行き届くさま」「熱心に」
「わがもへるらむ」は、字余りになるが「わがおもへるらむ」とする訓も多い
第二句の「かも」が、結句の「らむ」に呼応して、「どうして~だろう」となる |
〔歌意〕
想ってもくれない人を、(菅の根の)ねもころのように、
どうしてこうも熱心に私は想っているのだろう |
自分のことを想ってもくれない人...
そのことを、理屈で考えずに、ただ声を出して泣く
そして、もう一首は、同じように想ってくれない人を、どうしてこんなに恋い慕うのか、と
少なくとも、この二首は同質ではない
同じような「語句」が使われているので、「類想歌」とされるのだろうが
「類歌」であって、「類想歌」ではないと思う
しかし、本人が思い込んでいる現実を、受け入れていることにおいては
〔617〕と掲題の「問歌」は「類想歌」だとは思う
【古今六帖】
| はるされは まつなくとりの うくひすの ことさきたてて きみをしまたむ |
| 古今六帖 第六 鳥 4406 (本歌、万葉歌1939) |
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの) |
| [1938] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔あひ思はぬいもをやもとな菅のねのなかきはる日をおもひくらさん〕 |
| あひ思はぬ妹をや 是より三首問答也心は明也 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
〔あひおもはぬ 妹をやもとな すがのねの ながきはるひを おもひくらさん〕 |
| 此もとなは、果敢なき事を云たる意也。本の無き浮不定る事をもとなと云へば、果敢なき事にも通ふなるべし。諸抄の説の通り、由なきと云事にも、此所は叶
へ共、よし無きと云義を、もとなと云へる義不濟ば、その義とも決し難き也。もとなと云事は兎角根本の無き浮たる事不定事を云たる義と見るべし。こゝも
われのみ獨果敢なくも、春の長き日を戀暮さんやと嘆たる歌也。菅の根とは長きと云はん序也。これは男のよみて贈れると聞えたり |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
〔相不念《アヒオモハヌ》、妹哉《イモヲヤ》、本名《モトナ》、菅根之、長春日乎、念晩牟〕 |
| おもはぬ妹を戀るがよしなきにながき春日を戀くらさんかとなげくなり |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔相念はぬ妹をやもとな(すがのねの)ながき春日をおもひくらさむ〕 |
妹ヲヤのヤはオモヒクラサムと照應せり。さればクラサムの下に引下げてクラサムカと直して心得べし。妹ヲヤのヲはナルニのヲなり。一本にアヒオモハズアルラム兒ユヱとあると卷四に
相おもはぬ人をやもとなしろたへの袖ひづまでにねのみしなかも
とあるとを合せ見て心得べし
ハルビヲはクラサムにかゝれり。されば一首の意は
相念ハヌ妹ナルニ心ノ外ニ其ヲ思ヒテ長キ春日ヲ暮サムカ
となり |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔あひおもはぬ いもをやもとな すがのねの はなぎはるひを おもひくらさむ〕 |
【訳】思つていないあなたなのに、心から菅の根のような長い春の日を思つて過すことだろうか
【釈】妹哉本名 イモヲヤモトナ。妹ヲヤ念ヒ暮ラサムと続く。ヤは、疑問の係助詞。モトナ、副詞。切に、心から。五句の念ヒ暮ラサムを修飾する。
【評語】この長い春の日を、片思いに過ごすことかと歎いている。格別の歌ではない。問の歌である。 |
| [1939] |
| 『万葉拾穂抄』 |
| |
〔はるされはまつなくとりの鴬のことさきたてしきみをしまたん〕 |
| はるされはまつなく 序哥也上句はことさきたてしといはんとて也ことさきたてしとは夫の方より先いひをこせたるをいふ也日本紀第一曰 如何婦人反先言乎
《イカンソタヲヤメノカヘツテコトヲサイタテンヤ》とある詞也あひおもはぬとはの給へと我はさやうにいひをこせられし君をまたん相思はぬにはあらすと也
|
| 『万葉集童蒙抄』 |
| |
〔はるされば、まづなくとりの、うぐひすの、ことさきだちし、せなをしまたん〕 |
| 春になれば、諸鳥の囀聲をもてはやす中に、鶯獨り己が春ぞと、諸鳥に先だちて鳴聲を、人にも被賞もの故、先づ鳴鳥とはよめり。既に前の歌にも、鶯の春に
なるらしとさへ詠みて諸鳥の中に、わきてもてはやさるゝ春鳥故、かくも詠めり。春鳥と書きて鶯とも義訓せる也。よりて先鳴鳥とは讀めるならん。その如く、妹に早く言を云通はせし人を待たんと云意也。早く思ひを表せし人を、せなとし待たんと答へたる也。第四卷に、こと出しは、誰がことにあるかと詠める意と、此こと先だちしと云ふ同じ意也 事先立之 神代紀上卷云、〔如何婦人反先言乎。〕此古語もあるから、かくこと先だちしとは詠めり。相思はぬと讀みたるから○にては無く、誰彼とわくべきにはあらねど、先に言通はせし人をこそ相思ふて、せなともして待たんと也。是等はかけ放れたる贈答格也 |
| 『万葉考』 |
| |
〔春去者、先鳴鳥乃、鶯之、事先立之《コトサキダテシ》、君乎之將待〕 |
是も鶯の春とつゞけしと同じつづけがらにて雪のうちより鳴諸鳥に先だち聲を出すをあげて下に言さきだてしといはん序とせり
事は借字言なり
はやくいひ出し頃の契にたがはず其君を待んと云なり(卷十二)に「こと出しはたが言なるか小山田のなはしろ水の中よとにして」ともよめり |
| 『万葉集新考』 |
| |
〔春さればまづなく鳥のうぐひすの事先立之《コトサキダチテ》、君をし待たむ〕 |
略解に第四句をコトサキダチシとよみて
春鳥の中に鶯はことにとく來鳴けばコトサキ立といはん序とせり。心は言出初シ君ヲ待ミンといふ也。卷四、言出シハタガコトナルカ小山田ノナハシロ水ノ中ヨ
ドニシテ、神代紀如何婦人反先言乎《コトサキダチシ》といひ古義には舊訓に從ひてコトサキダテシとよめり。案ずるに事は如の借字にて卷八(一六二一頁)なる
あしひきの山下とよみなく鹿の事ともしかもわがこころづま
の事にひとし。次に先立之の之は弖の誤としてサキダチテとよむべし。即アヒオモハヌ妹ヲヤ云々といへるに對して我ヨリ先ンジテ君ヲ待タムといへるなり。第二句のトリノは鳥ナルといふ意なり
|
| 『万葉集全註釈』 |
| |
〔はるされば まづなくとりの うぐひすの ことさきだちし きみをしまたむ〕 |
【訳】春になるとまず鳴く鳥である鶯のように、早く言葉をおかけになつたあなたをお待ちしましょう。
【釈】春去者 先鳴鳥乃 鴬之 ハルサレバマヅナクトリノウグヒスノ。以上譬喩で、次の言先立チシを引き起こしている。 事先立之 コトサキダチシ。コトは言。言葉がまず言い出された意で、他の人よりも先に言い寄つたことをいう。
【評語】譬喩が巧みである。言先立チシ君ヲシ待タムというのも、よく言い得ている。 |
| [1940] |
| 『万葉拾穂抄』 |
| |
〔あひおもはすあらんこゆへに玉のをのなかきはる日をおもひくらさく〕 |
| あひおもはすあらんこゆへ くらさくはくらさん也此哥は又夫のはしめいひし哥を少詞をかへてとかくあひおもふましき妹なるこゝろをいへるなるへし |
| 『万葉集童蒙抄』 |
| |
〔あひおもはず、あらんこゆゑに、たまのをの、ながきはるひを、おもひくらさく〕 |
| 前の歌と同意にて男子の詠みかけたる歌也。此答無をは一首脱せるか。前は菅のねの序詞をよみ、此は玉緒の序詞の違ばかり也。歌の意に違ふ事無ければ、同歌同作故定めて擧たるか
|
| 『万葉考』 |
| |
〔相不念《アヒオモハズ》、將有兒《アラムコ》故(ニ)、玉緒(ノ)、長春日乎、念晩久《オモヒクラサク》、〕 |
| 末の句佐久約須にてくらすなりこの三首は問答ともなしその上終の此歌は三首のはじめの歌の變にて或本の歌ならんを今本にはならべ書たり亂書のまゝならんとおもへば例によりて小書とす又此上の二首も問答とある標にあはねど挽歌などのまぎれ入しとは別にて春の雜歌に春ならぬも有例にならへり |
| 『万葉集新考』 |
| |
〔あひおもはずあるらむ兒ゆゑ(玉の緒の)長き春日をおもひくらさく〕 |
略解古義にいへる如く上なるアヒオモハヌといふ歌の傳のかはれるなり。別の歌にあらず。されば上なる歌の次に或本歌曰または一云として掲ぐべきなり
兒ユヱは子ナルニなり。クラサクはクラス事ヨとなり |
| 『万葉集全註釈』 |
| |
〔あひおもはず あるらむこゆゑ たまのをの ながきはるひを おもひくらさく〕 |
【訳】思つていないだろう人なのだのに、玉の緒のような長い春の日を思い暮らすことだ。
【釈】玉緒 タマノヲ。枕詞。絶ユ、継グなどにも冠するが、往々長シにも冠している。
念晩久 オモヒクラサク。クラサクは、暮らすこと。
【評語】前の「あひ念はぬ妹をやもとな」の歌の類歌として載せたもので、春サレバの歌に対する答えではないだろう。長い春の日を思うということが、類型になつている。思ヒ暮ラサクと、現にそうしている意に歌つたのがよい。 |
|
|
掲載日:2014.03.04.
| 春相聞 問答 |
| 相不念 妹哉本名 菅根乃 長春日乎 念晩牟 |
| 相思はぬ妹をやもとな菅の根の長き春日を思ひ暮らさむ |
| あひおもはぬ いもをやもとな すがのねの ながきはるひを おもひくらさむ |
| 巻第十 1938 春相聞 問答 作者不詳 |
| 春去者 先鳴鳥乃 鴬之 事先立之 君乎之将待 |
| 春さればまづ鳴く鳥の鴬の言先立ちし君をし待たむ |
| はるされば まづなくとりの うぐひすの ことさきだちし きみをしまたむ |
| 巻第十 1939 春相聞 問答 作者不詳 |
| 相不念 将有兒故 玉緒 長春日乎 念晩久 |
| 相思はずあるらむ子ゆゑ玉の緒の長き春日を思ひ暮らさく |
| あひおもはず あるらむこゆゑ たまのをの ながきはるひを おもひくらさく |
| 巻第十 1940 春相聞 問答 作者不詳 |
【注記】〔4514〕【注記(比較1938・1939)】〔778・779〕
【類想歌】〔617・3068〕
【古今六帖】〔4406〕
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 【1938】語義 |
意味・活用・接続 |
| あひおもはぬ[相不念] |
| あひおもは[相思ふ] |
[他ハ四・未然形]互いに思う・思い合う |
| ぬ[助動詞・ず] |
[打消・連体形]~ない |
未然形につく |
| いもをやもとな[妹哉本名] |
| を[格助詞] |
[対象]~を |
体言につく |
| や[係助詞] |
[詠嘆的疑問]~か〔係り結び〕 |
種々の語につく |
| もとな[副詞] |
理由もなく・根拠もなく・しきりに・やたらに |
| すがのねの[菅根乃]〔枕詞〕「ながき」にかかる |
| ながきはるひを[長春日乎]長い春の一日を |
| おもひくらさむ[念晩牟] |
| おもひくらさ[思い暮らす] |
[他サ四・未然形]恋しく思って日を暮らす |
| む[助動詞・む] |
[推量・連体形]~だろう〔係り結び〕 |
未然形につく |
| 【1939】語義 |
意味・活用・接続 |
| はるされば[春去者]春になると |
| まづなくとりの[先鳴鳥乃] |
| まづ[先づ] |
「副詞」初めに・先に |
| の[格助詞] |
[連体修飾語・資格]~という・~である |
体言につく |
| うぐひすの[鴬之]うぐいすのように ここまで〔序詞〕 |
| の[格助詞] |
[枕詞・序詞の終り]~のように |
体言につく |
| ことさきだちし[事先立之] |
| こと[言] |
口に出して言うこと・ことば |
| さきだち[先立つ] |
[自タ四・連用形]真っ先に起こる・先んずる |
| し[助動詞・き] |
[過去・連体形]~た |
連用形につく |
| きみをしまたむ[君乎之将待] |
| を[格助詞] |
[対象]~を |
体言につく |
| し[副助詞] |
語調を整え、強意を表す |
| 〔接続〕体言、活用語の連体形・連用形、副詞、助詞などにつく |
| 【1940】語義 |
意味・活用・接続 |
| あひおもはず[相不念] |
| ず[助動詞・ず] |
[打消・連用形]~ない |
未然形につく |
| あるらむこゆゑ[将有兒故] |
| ある[有り・在り] |
[自ラ変・連体形]ある・いる・存在する |
| らむ[助動詞・らむ] |
[現在の原因推量・連体形]~のだろう |
| 〔接続〕基本は終止形に付くが、ラ変型には連体形につく |
| ゆゑ[故] |
[逆接的な理由・原因]~なのに〔接続〕体言、連用形の下につく |
| たまのをの[玉緒]〔枕詞〕「ながき」にかかる |
| ながきはるひを[長春日乎]長い春の一日を |
| おもひくらさく[念晩久]「く」はク語法・連体止めと同じで詠嘆をこめる |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [まづなくとりの] |
鶯は、春一番に鳴くことから、「春告鳥」とも「春鳥」ともいわれている
そのことを詠った一首
| (十二月十八日於大監物三形王之宅宴歌三首) |
| 安良多末能 等之由伎我敝理 波流多々婆 末豆和我夜度尓 宇具比須波奈家 |
| あらたまの年行き返り春立たばまづ我が宿に鴬は鳴け |
| あらたまの としゆきがへり はるたたば まづわがやどに うぐひすはなけ |
| 右一首右中辨大伴宿祢家持 |
| 巻第二十 4514 宴席歌 大伴宿禰家持 |
〔語義〕
「あらたまの」は、〔枕詞〕、「年」にかかる
「ゆきがへり」は、「旧年が行き、新年が再び来る」
「はるたたば」、四段「立つ」の未然形「たた」に、順接の仮定条件「ば」で、
「春になったら」 |
〔歌意〕
新しい年になって春になったなら
まず初めに、我家で鳴いてくれ |
春を知らせる使者を、我家の庭先で迎えたい
春を待ち焦がれ、鶯の鳴き声を待つ
鳴けば...春を知る
|
| |
| [ことさきだちし] |
この語句の解釈には、二通りが考えられる
一つは、「先に声をかけてきた君」
もう一つは、「他の人に先立って言葉をかけてきた君」
前者を解釈するのは
『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕、
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕、
「決して相思はぬのではない、云ひ出されたのがあなただから、そなたのから更に第二の言動をお待ち申してゐるだけよ、と云った」
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕では、「大意」のあとに
「ひたすら待つと下手に出ることで、先に言い出したくせに、あなたこそ不実だと切り返した歌」とする
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕は、「先に言葉に出したあなた」で、『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕も含めて、これらは同じだと思う
左頁の「古諸注」では、『拾穂抄』が、「夫の方より先いひをこせたるをいふ也」とする
後者の方は、左頁の『童蒙抄』、『万葉考』、『全註釈』があり
さらには、『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕、
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕が採っている
私も、うぐいすが、何よりも先んじて「春」を告げることを喩えているのであれば
「他の人に先立って、言葉をかけた君」とする方が、いいのではないかと思う
尚、この「問答歌」の「ことさきだち」と、類想歌ではないが
とても似通った「相聞歌」がある
| 相聞/大伴宿祢家持贈紀女郎歌一首 |
| 鶉鳴 故郷従 念友 何如裳妹尓 相縁毛無寸 |
| 鶉鳴く古りにし里ゆ思へども何ぞも妹に逢ふよしもなき |
| うづらなく ふりにしさとゆ おもへども なにぞもいもに あふよしもなき |
| 巻第四 778 相聞 大伴宿禰家持 |
〔語義〕
「うづらなく」、〔枕詞〕「ふる・ふりし」にかかる
「ふるにしさと」は、当時の久邇京からみた旧都奈良のこと
「ゆ」は、起点の「格助詞」で、「~以来」
「おもへども」は、「思っているのですが」
「なにぞ」は、下に述べる語句についてその理由を疑う副詞、「何故・何ゆえ」
「あふよしもなき」の「よし」は、「手段・方法」 |
〔歌意〕
(うづらなく)今は、旧都となってしまった奈良の都以来、
あなたのことを思ってはいるのですが、
どうして、あなたに逢う機会が、逢う手段がないのでしょう |
| |
| 相聞/紀女郎報贈家持歌一首 |
| 事出之者 誰言尓有鹿 小山田之 苗代水乃 中与杼尓四手 |
| 言出しは誰が言にあるか小山田の苗代水の中淀にして |
| ことでしは たがことにあるか をやまだの なはしろみづの なかよどにして |
| 巻第四 779 相聞 紀女郎 |
〔語義〕
「ことで」は、「言」+「出(い)で」の約、「言い出し」
「たがことなるか」は、「誰の言葉なのか」
「をやまだ」は「を」が美称で、「やまだ」は、主に清水の湧出する場所
日照りでも、水田を涸れさせないようにすることが必要なので、そのような場所
この表現は、結句の「なかよど」の比喩の序とされている
「なはしろみづ」は、稲の苗を育てるの苗代に引く水
「なかよどにして」、「なかよど」が空いての訪れて来なくなることを、
水が途中で留まって流れなくことの喩え |
〔歌意〕
最初に言葉を掛けたのは、どなたでしょう
それなのに、山田の苗代水のように滞って、
来てくださらないのは... |
似ていると言えば、「最初に仰ったのは」ということくらいだが
この例歌でいう「ことでし」は、当事者間のことが確実であり
掲題歌のように、何よりも早く鳴く鶯、との喩えがない
だから、逆に言えば、その「うぐひすの喩え」があることで
「誰よりも早く、言葉をかけてくれた君」とした方が、心に響く
尚、この異訓も多く、左頁でも「旧訓」は「ことさきたてし」が目立つ |
| |
[こと]
|
語源的には「言」と「事」は同じであったと考えられるが、奈良時代以降、分化した
しかし、奈良・平安時代の「こと」には、どちらにも解せるものが見られるという |
| |
| [あるらむこゆゑ] |
旧訓は、ほとんどが「あらむ(ん)こゆゑ」だ(左頁)
ラ変動詞「あり」の未然形「あら」に、推量の助動詞「む」
掲題歌のような訓だと、「あり」の連体形「ある」に「現在」の原因推量「らむ」
その違いがある |
| |
|

|
| 【歌意1941】 |
立派な男子が、明日香古京へ向かう、その神名備山に
夜が明けると、柘の小枝で、
さらに夕方になると、小松の梢で、
里の人たちが聞いて恋しく思うほどに、
また、その山彦が返ってくるほどに、
ほととぎすは、妻を恋い慕っているようだ
こんな夜中だというのに、鳴いて... |
| 【歌意1942】 |
旅にあって、ほととぎすが、妻を恋い慕っているらしく
神名備山で、こんな夜更けに鳴いているのが、
私にも同じように思われて、淋しいことだ |
ほととぎすが、夜鳴きするのを
ふと都に残してきた妻のことを思わせて、しんみりと聞き入っている
「ますらを」と、自称するのは、自嘲気味に言うのだと、最近書いたが
日中、どんなに気張っていても
夜になると、孤独感は募るものだ
そこに、ほととぎすの鳴き声までも、妻恋いの自身の境遇に重なってしまう
「ますらを」、「ふるさと」...
この語には、他の旅にはないものがある
「ますらを」は、気丈な男だろうし、
この歌での「ふるさと」は、「明日香古京」だという
寂しさを醸し出す、鄙の地への「旅」ではない
勿論、一旦都が遷都してしまえば、古京がどれほど廃れるのか
『万葉歌』にも多く詠われているように、想像はつく
都の建造物の移築が行われ、遷都と同時に、旧都は荒廃する
そのことを思えば、「鄙の地」への旅以上に、いっそう「寂しさ」があるのだろう
そんな「古京」への「旅」(公務だろうが)は、この「ますらを」振りの男でさえ
ほととぎすの鳴き声に、「妻恋」を誘われてしまう
だからこそ、この歌に響く「寂寥感」が、無条件に伝わってくるのかもしれない
古京の寂寥感ではなく、男の心に映し出される「寂寥感」が...
『全註釈』が、この「反歌」の逸話を載せている
初めは、『新古今和歌集』に選ばれた一首だったのが、
『後撰集』に入っていることが解り、他の歌と差し替えた、と...
こうした「逸話」の類は、いったいどんな「書」に書かれているのだろう
それもまた興味のもてるものだ
いつか、探してみよう
【夫木抄】
| ますらをの いてたちむかふ ふるさとの かみなひやまに あけくれは つみのさえたに ゆふされは |
| 夫木抄 巻第三十雑十 14244 読人不知 |
| たひにして つまこひすらし ほとときす かみやひやまに さよふけてなく |
| 夫木抄 巻第二十雑二 8357 読人不知 |
【後撰集】
| たひねして つまこひすらし ほとときす かむなひやまに さよふけてなく |
| 後撰集 巻第四 夏 187 読人不知 |
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの) |
| [1941] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔ますらおに いてたちむかふ ふるさとの かみなひ山に あけくれは つみのさ枝に ゆふされは こまつかうれに さと人の きゝこふるまて 山ひこの こたふるまてに ほとゝきす つまこひすらし さよなかになく〕 |
ますらおにいてたち向ふ 大夫は武士也軍なとに立向へはたちむかふの諷詞によめり此故郷は飛鳥の古京をいふなるへし
あけくれは 明もてくれは也柘の枝松の梢なとに朝夕なく心也 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
〔ますらをに、出たちむかふ、ふるさとの、神なび山に、あけくれば、つみのさえだに、ゆふされば、こまつがうれに、さとびとの、きゝこふるまで、やまびこの、こたふるまでに、ほとゝぎす、つまこひすらし、さよなかになく〕 |
此ますらをに出立向ふと云事、諸抄の説、ものゝふ勇者の軍に出立向ふ如く、故郷の飛鳥と、神南山と相對してあると云義にて、只立向ふと云はむ爲の序詞と釋し來れり。詳ならぬ義なれ共、未だ考案出でざれば、先古説に隨ふ也。立向ふものは丈夫ならず共、外の事にもあるべき義、且ますらをにと讀めるも不審也。をとあらば、凡てのますらをにかゝるべし。丹とありては、丈夫に外の者の立向ふ事に聞ゆる也。何が立向ふ義歟委しからぬ也
柘之左枝 前にある柘の木の事也
若末爾 うれと讀む。義をもて書けり。松の若芽の末の事也。うれうらとは木の枝の末を云古語也。答響は二字合せて答ふると讀む也
歌の意は、朝夕夜かけて不v絶郭公の鳴くは、妻戀こそすらめ、夜晝をもわかず鳴と云義也。柘の木松のうれ意ある歌にあらず。只當然の節物景色を其儘に詠める也
|
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
〔 丈夫丹《ニ》、出立向《イデタチムカフ》、 是を契冲は軍に出立向ことゝいへれど丈夫丹と云から軍にといふまではなし事遠し(卷一)に丈夫之得物矢手挿立向射流圓方波云云(卷二十)あらしをのいほさ手狹むかひ立かなるましづみ云云是らは的に向なり(同卷)に(長歌)あづまをのこは伊田牟可比《イタムカヒ》かへり見せずて又其下にけふよりはかへりみなくておほ君のしこの御楯刀伊○[泥/土]《ミタテトイデ》多都吾例波など
を思ふにこゝの丈夫丹云云といふも丈夫どち立向ふ勢ひをおもひて丈夫爾の言を冠辭とせしならんさて出立向は我家を出立て向はるゝ故郷の神なび山なればさ云のみ〕 |
故郷之、 飛鳥郡
神名備山爾、明來者、柘之左枝爾《ツミノサエダニ》、 桑の類なり
暮去者、小松之宇末爾《ガウレニ》、里人之《ノ》、聞戀麻由《キヽコフルマデ》、山彦乃、答響萬田《コタヘスルマデ》、 今本萬田をまでにと訓たれどそも假字なれば假字の下に字はそへられず依てあらたむ
霍公鳥、都麻戀爲良思、左夜中爾鳴《ナク》 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔大夫丹《マスラヲノ》 出《キ》たちむかふ 故郷の 神名備山に あけくれば 柘《ツミ》のさえだに ゆふされば 小松がうれに 里人の ききこふるまで 山彦の 答響《アヒトヨム》まで ほととぎす つま戀すらし さ夜中になく〕 |
一二句を舊訓にマスラヲニイデタチムカフとよみたれどさては意通ぜざれば或人は大夫丹を走出丹《ハシリイデニ》の誤とし(略解に據る)雅澄は丹を乃の誤と
してマスラヲノとよめり。ハシリイデニイデタツとはいふべきならねば雅澄の説の方まされり。さるにてもイデタチムカフといふこと穩ならず。イデタツは門より出づる事なればなり。雅澄も自安んぜざる所ありきと見えて
さてイデタツは男女にかぎるべからぬが如くなれども男は日々に外に出、女は内にのみこもり居て常に出る事なき故に取分てマスラヲノイデタチムカフといへるにやあらむ
といへり。案ずるに出は來の誤字にてマスラヲノキタチムカフならむ。マスラヲは作者自云へるなり。さて來タチムカフとすれば作者は他郷に住める人、もとの
如く出タチムカフとすれば作者は此里に住める人なり。其いづれとするが穩なるべきかは反歌と對照して思定むべし○フルサトは飛鳥にて神名備山は雷岳なり。ツミは野桑なり。答響は契沖に從ひてアヒトヨムとよむべし(略解にはコタヘスルとよめり)。さてアケクレ
バ、ユフサレバといひてサヨナカニナクとは収むべからず。又ツミノサエダニ、小松ガウレニを受くる辭なかるべからず。さればおそらくはホトトギスの次に來ナキトヨモシ、旅ナガラなどの二句おちたるならむ |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔ますらをの いでたちむかふ ふるさとの、かむなびやまに、あけくれば つみのさえだに、ゆふされば こまつのうれに、さとびとの ききこふるまでに、やまびこの こたふるまでに、ほととぎす つまごひすらし。さよなかになく〕 |
【訳】勇士が出で立つて向う所の、古い里の神名備山に、夜が明けてくればツミの枝に、夕方になれば小松の枝先に、里人の聞いて慕うまでに、山の木だまの返事をするまでに、ホトトギスが妻恋をするらしい。夜中に鳴いている。
【構成】段落は無く、全篇一文である。
【釈】大夫之出立向 マスラヲノイデタチムカフ。作者自身が出かけてきたことを叙して、故郷の神名備山を修飾している。故郷之 フルサトノ。古くなった里である意で、明日香の里をいう。神名備山尓 カムナビヤマニ。カムナビ山は明日香の神名備で、もと飛鳥神社のあつた山。今この飛鳥神社のある山は、後に移した地である。柘之左枝尓 ツミノサエダニ。ツミは樹名。野生のタワ。小松之若末尓 コマツノウレニ。ウレは、文字通り若い枝葉の末である。聞恋麻田 キキコフルマデニ。古くキキコフルマデと読んでいるが、下の答響萬田をコタフルマデニと読むに合せては、ニを加えて読むのが順当である。田をデニに当てて書いている。ホトトギスの声を聞いてまた聞きたく恋い慕うまでにの意である。山彦乃 ヤマビコノ。ヤマビコは、山の木だま。反響を擬人化して、山男がいて返事をするようにいう。答響萬田 コタフルマデニ。答響は、熟字として書いている。山彦だから答に重点をおいてコタフルと読むが、響を重視すれば二字でトヨムルである。
【評語】故郷の神名備山のホトトギスを叙して、感じのよい歌である。但し、明ケクレバ、暮サレバと、朝夕に分けて述べ、それを受けて、サ夜中ニ鳴クというのは、突然で、不調和である。 |
| [1942] |
| 『万葉拾穂抄』 |
| |
〔たひにしてつまこひすらしほとゝきすかみなひやまにさよふけてなく〕 |
| たひにしてつまこひ 長哥のつまこひすらしさよ中になくとよめるを反《カヘ》してよめり旅にしてとよめるは蜀魂もと蜀の望帝なりし旅行を好みて途中にうせたりし霊魂なれは故郷こひて不如歸となく其故に旅にしてとよめり此哥後撰集に入 |
| 『万葉集童蒙抄』 |
| |
〔反歌 後撰に入也
たびにして、つまこひすらし、ほとゝぎす、かみなみやまに、さよふけてなく〕 |
郭公の旅にて己が故郷の妻を戀ふらし、夜ともわかず鳴くは、獨り音をやうし共思ひて鳴らんとの意なるべし。蜀望帝旅行を好んで途中にて終り、その亡魂故不如歸と鳴鳥となりし故、客にしてとよむとの説有
右古歌集中出 此注者の時代迄は、古歌集と云書もありて、世にもてはやしたりと見えたり。今は世に絶えて一紙一葉も無き事也 |
| 『万葉考』 |
| |
〔客《タビ》爾爲而、妻戀爲良思、霍公鳥、神名備山爾、左夜深而鳴、〕 |
| 調のとゝのひたる歌なりこともなく打となへたるによく調ふぞかたき |
| 『万葉集新考』 |
| |
〔たびにして妻ごひすらしほととぎす神なび山にさよふけてなく〕 |
| 作者を他郷の人として子規モ我如ク旅ニシテ妻戀スラシといふ意とせむ方哀深からずや |
| 『万葉集全註釈』 |
| |
〔たびにして つまごひすらし。ほととぎす かむなびやまに さよふけてなく
右、古歌集中出
【釈】古歌集 フルキウタノシフ。巻の二以下しばしが出ている。奈良時代初期ごろの作品を集めているが、誰の集ともわからない。巻七、および九に見える古集との同異も問題になる。〕 |
【訳】旅にあつて、妻に恋うているらしい。ホトトギスは、神名備山で、夜中に鳴いている。
【釈】客尓為而 タビニシテ。ホトトギスが旅にあつての意だが、作者が旅先なので、鳥に託してこの句がある。
【評語】旅に出て妻恋しているのを、ホトトギスが妻恋をして鳴くと歌つている。これは情景よく一致して情趣のゆたかな作である。新古今和歌集撰進の時、はじめこの歌がはいつていたが、既に後撰和歌集にはいつていることを発見して他の歌ととりかえたという挿話を伝えている。 |
|
|
掲載日:2014.03.05.
| 夏雑歌 詠鳥 |
| 大夫之 出立向 故郷之 神名備山尓 明来者 柘之左枝尓 暮去者 小松之若末尓 里人之 聞戀麻田 山彦乃 答響萬田 霍公鳥 都麻戀為良思 左夜中尓鳴 |
| 大夫の 出で立ち向ふ 故郷の 神なび山に 明けくれば 柘のさ枝に 夕されば 小松が末に 里人の 聞き恋ふるまで 山彦の 相響むまで
霍公鳥 妻恋ひすらし さ夜中に鳴く |
| ますらをの いでたちむかふ ふるさとの かむなびやまに あけくれば つみのさえだに ゆふされば こまつがうれに さとびとの ききこふるまで やまびこの あひとよむまで ほととぎす つまごひすらし さよなかになく |
| 巻第十 1941 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
| 反歌 |
| 客尓為而 妻戀為良思 霍公鳥 神名備山尓 左夜深而鳴 |
| 旅にして妻恋すらし霍公鳥神なび山にさ夜更けて鳴く |
| たびにして つまごひすらし ほととぎす かむなびやまに さよふけてなく |
| 右古歌集中出 |
| 巻第十 1942 夏雑歌 詠鳥 右古歌集中出 |
【夫木抄】〔14244・8357〕
【後撰集】〔187〕
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 【1941】語義 |
意味・活用・接続 |
| ますらをの[大夫之]勇ましく強く立派な男子・勇士 |
| いでたちむかふ[出立向] |
| いでたち[出で立つ] |
[自タ四・連用形]出かける・出て行ってそこに立つ |
| むかふ[向かふ] |
[自ハ四・連体形]出向く・赴く・近づく |
| ふるさとの[故郷之]古くなった里の意で、ここでは明日香古京 |
| かむなびやまに[神名備山尓] |
| 神名備山は、神霊の籠もる山、ここでは明日香古京の神名備山で、その比定には諸説がある |
| あけくれば[明来者]夜が明けてくると |
| つみのさえだに[柘之左枝尓] |
| つみ |
樹名で、野生のクワ |
| さえだ[小枝] |
木の枝・小枝 「さ」は接頭語 |
| に[格助詞] |
[位置]~で 〔接続〕体言、活用語の連体形につく |
| ゆふされば[暮去者] 夕方になると |
| こまつがうれに[小松之若末尓] |
| こまつ[小松] |
小さな松 |
| うれ[末] |
「うら」の転で、木の枝や葉の先端・梢 |
| さとびとの[里人之] その里に住んでいる人々が |
| ききこふるまで[聞戀麻田] |
| ききこふる[聞き恋ふ] |
[他ハ上二・連体形]聞いて恋しく思う・期待し耳を傾ける |
| まで[副助詞] |
[程度]~ほど・~くらい |
連体形につく |
| やまびこの[山彦乃]山のこだま 返事をする、という擬人化で用いている |
| あひとよむまで[答響萬田] |
| あひ[相] |
[接頭語]動詞について、一緒に・互いに・語調を整える |
| とよむ[響む・動む] |
[自マ四・連体形]鳴り響く・響きわたる |
| ほととぎす[霍公鳥]鳥の名・初夏に飛来し、秋に南方に去る・夏を知らせる鳥、という |
| つまごひすらし[都麻戀為良思 ] |
| つまごひ[妻恋ひ・夫恋ひ] |
夫が妻を妻が夫を恋しく思うこと・雌雄が互に恋し慕うこと |
| す[為(す)] |
[他サ変・終止形]ある動作を行う・ある行為をする |
| らし[助動詞・らし] |
[推定・終止形]~らしい |
終止形につく |
| さよなかになく[左夜中尓鳴]「さ」は語調を整える「接頭語」で、真夜中に鳴いている |
| 【1942】語義 |
意味・活用・接続 |
| たびにして[客尓為而] |
| にして |
[場所を表す]~にあって・~において~で |
体言につく |
| 〔成立〕格助詞「に」+副助詞「して」 |
| つまごひすらし[妻戀為良思]前歌同じ |
| ほととぎす[霍公鳥]前歌同じ |
| かむなびやまに[神名備山尓]前歌同じ |
| さよふけてなく[左夜深而鳴] |
| ふけ[更く] |
[自カ下二・連用形](夜が)更ける・年をとる・老いる |
| て[接続助詞] |
[逆接の確定条件]~のに・~ても |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [ますらをの] |
底本とする『西本願寺本』は、原文「大夫丹」(ますらをに)だが、
『元暦校本』『類聚古集』が、「大夫之」と表記しており、
「ますらをの」が採られている
左頁の「資料」でも、『万葉集新考』において、『略解』や『古義』などをあげ
その見解を述べているが、古くからの「諸本」については、どの見解も、断定はできない
ただ、真淵以前の注釈書では、「丹(に)」が普通に訓まれていたことが解る
|
| |
| [こまつ] |
平安時代になると、正月の最初の子(ね)の日に、
野で若菜を摘み小松を引き抜いて長寿を祈る行事が行われた
これを「小松引き」または「子の日の遊び」というらしい
この万葉歌の時代は、奈良時代...
|
| |
| [ききこふるまで~あひとよむまで] |
この対を為す語句に、幾つかの異訓がある
『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕が載せる本文は、
「ききこふるまで~こたふるまでに」
これは、「麻田」を「まで」と訓み、
「万田」を「までに」と訓むことの理由が欲しくなる
『全註釈』が、「万田」を「までに」と訓むのだから、「麻田」も「までに」と訓むのが、
順当だというのは、説明にはならないと思う
「あひとよむ」が「こたふる」とするのは、
原文「答響」の「意」で訓むか「音」で訓むか、のことだと思うが
旧訓は「こたふる」が殆どだ
しかし、近年の注釈書は、逆にほとんど「あひとよむ」とする
|
| |
[さよふけてなく]
|
ほととぎすは、早朝から鳴く鳥とあり、夜鳴くこともある、とあった
このほととぎすの「鳴く」習性を、作者が意図的に用いたのかどうか...
この「ふけて」の助詞「て」の解釈に、大きく影響すると思う
夜、鳴くことが驚くことでもなければ、この逆接の意味にはならない
単純に、夜更けにほととぎすが鳴いている、となってしまう
しかし、この歌の歌意に沿って、妻を残しての旅先
その妻恋しさに、「夜なのに」、「夜になっても」ほととぎすが鳴きやまない
それが「妻恋しくて」なかなか寝付けない作者の心情であれば
やはり、この接続助詞「て」は、「逆接」の意味で解釈したくなる |
| |
|

 |
| 【歌意1943】 |
ほととぎすよ、おまえのその美しい「はつこえ」を、
このわたしにくれないかなあ
端午の節句の「五月の玉」の、緒を通すとき
おまえの初声も一緒に通そうと思う
まじないが効くだろうよ、きっと |
春のうぐいす、夏のほととぎす
その季節に、初めてその鳴き声を聞くと、思わず立ち止ってしまう
現代では、わざわざその「初声」を聞くために
山にまで行くことはないが
当時では、「初声」を求めて山里に入るのも、普通のことだったのだろう
花が咲いたり、雪が降ったり
目で見える季節感と違って、
鳥の鳴き声、というものは、人と同じだ
その季節が来たことを、人と同じように感じ取って、鳴く
ただ、この歌や、類想歌のように
ほととぎすの初声を、「五月の玉」の緒と混ぜて通す、というのは
どんな意味がこめられているのだろう
それが解らないと、この歌を解したことにはならない、と思う
言葉通りの抽象的な、「初声」を愛でることではないはずだ
類想歌もそうだが、「五月の玉」に「貫く」と詠っている
「五月の玉」の意味は、調べていて解った
諸説もあるが、一般的には「薬玉」とされ、また邪気を封じるものともされている
何となく、その関わり合いに想像はつくが...
また調べなければならない宿題が増えてしまった
明日香...早く行きたい
もう少し仕事が落ち着いたら、有休とって行かなければ...
【夫木抄】
| ほとときす なくはつこゑは われきかむ くさつきのやま さやぬきいてむ |
| 夫木抄 巻第二十 雑二 8569 赤人 |
| ほとときす なくはつこゑは われにかも さかつきやまの さしてなくかも |
| 夫木抄 巻第二十 雑二 8569 赤人 |
【赤人集】
| ほとときす なくはつこゑは われきかむ さつきのたまに まきてぬきてむ |
| 赤人集 221 |
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1943] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔ほとゝきすなかはつこゑはわれにかもさつきのたまにましへてぬかん 〕
霍公鳥汝始音者於吾欲得五月之珠尓交而将貫 |
| ほとゝきすなか初声 われにかもはわか物にもかな也郭公のこゑを薬玉にぬかんの心 |
| 『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕 |
| |
霍公鳥汝始音者於吾欲得五月之珠爾交而將貫
〔ホトヽキスナカハツコヱハワレニカモサツキノタマニマシヘテヌカム 〕 |
| 於吾欲得は我に得させよの意なり、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
霍公鳥汝始音者於吾欲得五月之珠爾交而將貫
〔ほとゝぎす、ながはつねをば、あれにかな、さつきのたまに、まじへてぬかん 〕 |
| 五月之珠爾交而將貫 郭公の聲を賞美して、五月にもてはやす藥玉の事を兼ねて、もてあそびものにせんと也。聲をぬかるべきものならねど、ケ樣に詠める事歌の風雅也。歌は、幼く跡無き樣に、詞を安らかに詠むを專とす。玉に交へて聲をぬかんとはあまり跡無き事の樣なれど、かくはよまれぬもの也。聲を賞愛の意を云はずしてあらはせる也。畢竟珍しきものと賞翫せんの意也
|
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
〔霍公鳥、汝始音《ナガハツコヱ》者、於吾欲得《ワレニコソ》、 われに得させよとなり五月之珠爾《サツキノタマニ》、交而將貫《ヌカン》〕 |
| さつきの珠は蘆橘の實を糸してつなぎて玉緒などの如くする手進《テスサミ》と見えたりさて玉緒と云は首玉手玉足玉などの遺れる手風なりけり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕 |
| |
霍公鳥。汝始音者。於吾欲得。五月之珠爾。交而將貫。
〔ほととぎす。ながはつこゑは。われにもが。さつきのたまに。まじへてぬかむ。〕 |
郭公の初聲を、吾が物にせん由もがな、玉に交へぬかんとなり。
參考 ○於吾欲得(古、新)ハナニモガ「吾」を「花」の誤とす。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔霍公鳥《ホトヽギス》。汝始音者《ナガハツコヱハ》。於吾欲得《ハナニモガ》。五月之珠爾《サツキノタマニ》。交而將貫《マジヘテヌカム》。〕 |
| 於吾欲得は、吾は、もしは花などの誤にはあらざるべきか、さらばハナニモガと訓べし、もとのまゝにては心ゆかず、○歌(ノ)意は、霍公鳥よ、汝がめづらしく鳴その初音が、形ある花にてもがなあれかし、さらば五月の藥玉に貫交へて、玩ぶべきに、と云るならむ、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔ほととぎすながはつこゑは於吾欲得《ハナニモガ》、五月の玉にまじへてぬかむ〕
霍公鳥汝始音者於吾欲得五月之珠爾交而將貫 |
古義に
於吾欲得は吾はもし花などの誤にはあらざるべきか。さらばハナニモガと訓べし。もとのまゝにては心ゆかず
といへり。此説に從ふべし。サツキノ玉は藥玉なり。卷八にも
ほととぎすいたくななきそながこゑを五月の玉にあへぬくまでに
とあり |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔ほととぎす 汝が初聲は 我にもが 五月の珠に 交へて貫かむ〕
霍公鳥《ホトトギス》 汝始音者《ナガハツコヱハ》 於吾欲得《ワレニモガ》 五月之珠爾《サツキノタマニ》 交而將貫《マジヘテヌカム》 |
霍公鳥ヨ、オマヘノ初音ハソレヲ、私ノモノトシテ取リタイモノダ。サウシタラ、ソノ聲ヲ、五月ノ藥玉ニ交ゼテ、糸ニ通シテ玩ビ物ニシヨウ。
○於吾欲得《ワレニモガ》――古義に吾を花の誤として、ハナニモガとよんでゐるが、花では却つてわからない。
〔評〕 卷八の霍公鳥痛莫鳴汝音乎五月玉爾相貫左右二《ホトトギスイタクナナキソナガコヱヲサツキノタマニアヘヌクマデニ》(一四六五)と同想で、子供らしく詠んだのである。他に卷十七(四〇〇七)、卷十九(四一八九)などに類想が見えてゐる。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔ほととぎす 汝(な)が初声(はつこゑ)は 吾(われ)にもが。五月(さつき)の珠(たま)に まじへて貫(ぬ)かむ〕
霍公鳥 汝始音者 於吾欲得 五月之珠尓 交而将貫 |
【訳】ホトトギスよ、お前の鳴く初声は、わたしに欲しいものだ。五月の珠にまぜて緒につらぬこう。
【釈】於吾欲得 ワレニモガ、我に得させよの意。句切り。五月之珠尓 サツキノタマニ。サツキノタマは、薬包にさげる玉。「霍公鳥 痛莫鳴 汝音乎 五月玉尓
相貫左右二」(巻八1465)参照。
【評語】その年になつて始めて鳴くホトトギスの声を愛する心で歌っている、ずいぶん風流がついている内容である。ホトトギスは、ちようど五月の頃に鳴くので、その声を五月の珠につらぬこうというのは、類想があつて前からある歌によつたのだろう。 |
|
|
掲載日:2014.03.06.
| 夏雑歌 詠鳥 |
| 霍公鳥 汝始音者 於吾欲得 五月之珠尓 交而将貫 |
| 霍公鳥汝が初声は我れにもが五月の玉に交へて貫かむ |
| ほととぎす ながはつこゑは われにもが さつきのたまに まじへてぬかむ |
| 巻第十 1943 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【注記[初声]〔4195〕
【類想歌】〔1469〕
【夫木抄】〔8569・8806〕
【赤人集】〔221〕
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 【1943】語義 |
意味・活用・接続 |
| ほととぎす[霍公鳥] |
| ながはつこゑは[汝始音者] |
| な[汝] |
[対称の人名代名詞]おまえ・あなた |
| 自分より目下の者や親しい人に対して用いる |
| はつこゑ[初声] |
[初音(はつね)と同じ]鳥や虫などの、その年、その季節にはじめて鳴く声。とくに、鶯やほととぎすの鳴く声をいう |
| われにもが[於吾欲得] |
| に[格助詞] |
[相手(使役の対象)]~に |
体言につく |
| もが[終助詞](上代語) |
[願望]~があればなあ・~であればなあ |
| 〔接続〕体言、体言に準ずる語、形容詞と助動詞の連用形、副詞、助詞「に」などにつく |
| さつきのたまに[五月之珠尓] |
| まじへてぬかむ[交而将貫] |
| まじへ[交(ま)じふ] |
[他ハ下二・連用形]混ぜ合わせる・混合させる |
| ぬか[貫く] |
[他カ四・未然形]穴に通す・つらぬく |
| む[助動詞・む] |
[推量(意志)・終止形]~よう・~つもりだ |
未然形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [はつこゑ] |
その季節になってはじめて鳴く鳥の声を「初音」というが、
ふつうは、鶯やほととぎすの場合をさすことが多い
鶯だったら陰暦一月、ほととぎすだったら、陰暦五月
当時の貴族たちは、初音を聞くためにわざわざ山里まで出かけたりした
一方で、「忍び音」という言い方もある
本格的な季節が来る前の鳴き声をいい、それもまた愛でていたようだ
| (廿四日應立夏四月節也 因此廿三日之暮忽思霍公鳥暁喧聲作歌二首) |
| 常人毛 起都追聞曽 霍公鳥 此暁尓 来喧始音 |
| 常人も起きつつ聞くぞ霍公鳥この暁に来鳴く初声 |
| つねひとも おきつつきくぞ ほととぎす このあかときに きなくはつこゑ |
| 巻第十九 4195 暁喧声歌 大伴宿禰家持 |
〔語義〕
「つねひとも」は、「世の常の人」で、まして自分は、の気持ちがある
「おきつつきくぞ」は、「起きつづけてきく」、「ぞ」は断定の係助詞
「あかとき」は、上代語で、「明時(あかとき)」の意、中古以降は「あかつき」
「夜明け前・未明」
「きなく」は、四段「来鳴く」の連体形で、「来て鳴く」 |
〔歌意〕
世の中の、普通の人でも、起きつづけていて、聞くものだ
ほととぎすが、この「あかつき」に来て鳴く
その初めての鳴き声を |
世間の常の人、普通の人であっても、ほととぎすの初声は特別なものだという
だから、作者もその「初声」を聞こうとする
|
| |
| [われにもが] |
異訓は少ないが、原文「於吾欲得」の「欲得」の訓に、その時代の慣用的な用例が伺える
多くの「われにもが」の、「もが」と、その「欲得」を当てているが、
この「欲得」の表記を拾い出してみると、『万葉集』中に、二十八首ある
語の前に「裳」や「毛」がついて「もがも」となる場合もあれば、
「欲得」だけで、「もがも」と訓じられてもいる
その「もが」「もがも」は、いずれも終助詞になるが、
二首だけ、違った「訓」があった
それは、上代の助動詞下二段動詞「こす」で、
相手に動作の実現を希望する意、「~てほしい・~てくれ」だ
「もが」の、「願望」の意を、相手に乞う形になると思うが
この原文「欲得」を、その意において用いながら、
訓では「こす」の「命令形(こせ・こそ)」とする注釈書がある
古くは、『万葉考』(左頁「資料)に見え、
新しくは、『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕に載る
『万葉考』は「われにこそ」、『新全集』は「われにこせ」だが、いずれも「命令形」だ
『新全集』の説明では、
「『ワレニモガ』と読む説は、ニモガのニが必ず断定の助動詞ナリの連用形であるべき点で成り立たず、ワガニモガと読みワガ物ニ…、と解する説もあるが、「於」を断定のニに用いた例がない。「欲得」を「こす」と読むことは、形式的用法だが、マサキクアリコソを『真好去有欲得(1794)』と書いた例から類推して成立しよう」と書いてある
多くの諸注が「われにもが」とするなかで、
「われにこそ・われにこせ」が他に見えないので、
「欲得」の二十八首を、もう一度見てみたら
二十八首中で、僅か二首だけの助動詞「こす」としての使用は、
「好去有欲得」(マサキクアリコソ、9-1794)
「無有欲得」(ナクアリコソ、13-3302)
確かに、ラ変動詞「あり」の連用形「あり」に接続する助動詞「こす」と言える
だから、「もが」と同じ意を持つ「こす」であれば、
動詞に付く場合に「こす」となるのは理解できるが、
その他の二十六首は、体言や助詞についている
だからこそ「もが」とされていると思う
この掲題歌も、「われに」であり、決して動詞の「連用形」ではない
『新全集』は、この「に」が断定の助動詞「なり」の連用形「に」だとすれば、
「於吾」を「われに」とする「於」が「に」となるはずで、そのような用例がなく、
だから成り立たないのだ、と
しかし助詞「に」に「もが」は接続する、と古語辞典には載っているが...
では、「に」と訓むことに、初めから問題があった、ということなのだろうか
他にも「かな・かも・をば」などがあるが、左頁の「資料」の載せる
|
| |
| [さつきのたま] |
「五月の玉」を「橘の実」とする説を採るのが、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕とする
他は、薬玉として、麝香・沈香・丁子などの香料を袋に入れ、
菖蒲や蓬、あるいは橘の蕾などをつけ、五色の糸を垂したもの、と解している
|
| |
[まじへてぬかむ]
|
類想歌と言われ、ほととぎすの鳴き声を、
「五月の玉」に混ぜて、緒に通す意味の歌がある
| 夏雜歌 / 藤原夫人歌一首 [明日香清御原宮御宇天皇之夫人也 字曰大原大刀自 即新田部皇子之母也]類 |
| 霍公鳥 痛莫鳴 汝音乎 五月玉尓 相貫左右二 |
| 霍公鳥いたくな鳴きそ汝が声を五月の玉にあへ貫くまでに |
| ほととぎす いたくななきそ ながこゑを さつきのたまに あへぬくまでに |
| 巻第八 1469 夏雑歌 藤原夫人 |
〔語義〕
「いたく」は、形容詞「いたし」の連用形から派生した副詞「いたく」で、
「ひどく・非常に・はなはだしく」、そして下に打消しの語を伴って「それほど」
「な~そ」は、禁止を表す
「あへぬく」は、四段「合へ貫く」の連体形「あへぬく」で、合わせて通す
「まで」は、限度の副助詞で、「~まで」 |
〔歌意〕
ほととぎすよ、そんなに鳴くな
お前の声を、「五月の薬玉」にまぜて、緒に通すまでは...
その後は、いくら鳴いても構わないから... |
「五月の玉」自体に、邪気を封じる呪術的な意味合いがあるが
その薬玉に「ほととぎすの声」を通す、という表現には、
どんな意味があるのだろう
単純に、「ほととぎすの鳴き声」を愛しんで、常に携行したいからなのだろうか
それとも、「初声」を「玉」に通すという願掛けのようなものがあるのだろうか... |
| |
|
|
| 【歌意1944】 |
朝霞がたなびいている、この野辺に
(あしひきの)山のほととぎすは、
いったいいつになったらやって来て、鳴くのだろうか
早く来て鳴いて欲しいものだ |
この野辺から、彼方に見える山裾まで、
何も遮るものがないような、そんな景色が現れてくる
点在する美しい樹木、山に霞がたなびく
あとは、ほととぎすが、この野辺にやって来て、
鳴くのを待つだけだ
のどかに、酒でも飲みながら、彼方の山でも見入っているかのようだ
人の多い人里では、どこからともなくやってくるほととぎすなのだろう
しかし、こうやって心待ちに出来る情景歌を詠えるのは
やはり、山に対峙する場景が必要だと思う
山、そして野辺を挟んで作者がいる
自然そのものの舞台が、語らずとも目に見えてくる
昨日の歌のように、「初声」を待っているのだろうか...
このような「舞台」とは違う、ほととぎすを待つ歌がある
| 夏雑歌 / 志貴皇子御歌一首 |
| 神名火乃 磐瀬之社之 霍公鳥 毛無乃岳尓 何時来将鳴 |
| 神奈備の石瀬の社の霍公鳥毛無の岡にいつか来鳴かむ |
| かむなびの いはせのもりの ほととぎす けなしのをかに いつかきなかむ |
| 巻第八 1470 夏雑歌 志貴皇子 |
〔語義〕
「かむなびの いはせのもり」神のよりつく所であるイハセの杜
「けなしのをか」、「毛無し」は草木の生えていない地だが、
ここでは固有名詞かもしれない |
〔歌意〕
神奈備の磐瀬の杜に鳴くほととぎすは、
いつになったら、この「毛無の岡」に来てなくのだろうか
早く来て鳴いてくれないだろうか |
この歌の「いはせのもり」がそうなのかどうか、解らないが
「岩瀬の森」という「歌枕」がある
今の奈良県生駒郡斑鳩町竜田が比定されている
そこにある森は、呼子鳥、ほととぎす、それに紅葉の名所と知られている
そのことからすると、この歌のほととぎすは、
その「いはせのもり」で鳴いているのだが、いつになったら
作者のいる「けなしのをか」に来てくれるのか、と
すでに、「いはせのもり」での鳴き声は聞こえているのだろう
今度は、こっちだぞ、と急かしているようだ
何やら順番待ちのようで、その点では掲題歌とは違う
情景としては、掲題歌のように、野辺を挟んで彼方に見える山を見ながら
いまかいまかと、待つほととぎすの「来鳴く」心情の歌の方が好きだ
【赤人集】
| あさきりの たなひくのへの あしひきの やまほとときす いつきてかなく |
| 赤人集 222 |
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1944] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔あさかすみたなひくのへに足引のやまほとゝきすいつかきなかん 〕
朝霞棚引野邊足檜木乃山霍公鳥何時來将鳴 |
| あさかすみたなひく 心は明なるへし |
| 『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕 |
| |
朝霞棚引野邊足檜木乃山霍公鳥何時來將鳴
〔アサカスミタナヒクノヘニアシヒキノヤマホトヽキスイツカキナカム 〕 |
| 初の二句夏に入てもまだ程なき意あり、下句は古今集に我宿の池の藤浪咲にけりと云歌と同じ、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
朝霞棚引野邊足檜木乃山霍公鳥何時來將鳴
〔あさがすみ、たなびくのべに、あしびきの、やまほとゝぎす、いつかきなかん 〕 |
| これは郭公を待歌にて、春の頃よりも待居し意をこめて、朝霞とは詠めるなるべし。尤霞は夏も立なれど、下の心をこめたるならん。野邊と云て、山時鳥とよめるを、手にしたる歌也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
〔朝霞、棚引野邊(ニ)、足檜木乃、 冠辭 山霍公鳥、何時來將鳴、〕 |
| かくるゝ事なし |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕 |
| |
朝霞。棚引野邊。足檜木乃。山霍公鳥。何時來將鳴。
〔あさがすみ。たなびくのべに。あしびきの。やまほととぎす。いつかきなかむ。〕 |
| 古へ霞、霧、ともに時を定めず詠めり。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔朝霞《アサカスミ》。棚引野邊《タナビクヌヘニ》。足檜木乃《アシヒキノ》。山霍公鳥《ヤマホトヽギス》。何時來將鳴《イツカキナカム》。〕 |
歌(ノ)意は、この霞のたなびく野邊に、山ほとゝぎすは、いつか來て鳴べきぞとなり、古今集に、わがやどの池の藤浪さきにけり山ほとゝぎすいつか來なかむ、末(ノ)句全(ラ)同じ、
○此(ノ)歌は、春よみし歌と聞えたれば、春(ノ)部に入べきなれど、霍公鳥を主としてよめる歌なるゆゑに、此間に載たるなるべし、下にいたりて、夏の相聞に、春之在者酢輕成野之《ハルサレバスガルナスヌノホトヽギス》、とある歌、又これに同じ、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔朝霞たなびく野邊に(あしひきの)山ほととぎすいつか來なかむ〕
朝霞棚引野邊足檜木乃山霍公鳥何時來將鳴 |
春に限りてカスミといふは後の事なり。いにしへは時に拘はらずいひき。卷八にも
霞たつあまの河原に君まつといかよふ程に裳のすそぬれぬ
とあり。古義に
此歌は春よみし歌ときこえたれば春部に入べきなれど霍公鳥を主としてよめる歌なるゆゑにこゝに載たるなるべしといへるは從はれず。さていにしへカスミといひしは薄霧にこそ |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
朝霞 たなびく野邊に あしびきの 山ほととぎす いつか來鳴かむ〕
朝霞《アサガスミ》 棚引野邊《タナビクヌベニ》 足檜木乃《アシビキノ》 山霍公鳥《ヤマホトトギス》 何時來將鳴《イツカキナカム》 |
朝靄ガ棚引ク野ノアタリニ、(足檜木乃)山郭公ハ何時ユナツタラ來テ鳴クダラウカ。早ク鳴イテクレ。
○朝霞《アサガスミ》――朝の靄である。後世ならば郭公の頃、霞とは詠まない。
〔評〕 簡明な歌である。下句は古今集「わがやどの池の藤浪さきにけり山ほととぎすいつか來なかむ」と同じである。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔朝霞 たなびく野辺に、 あしひきの 山ほととぎす いつか来鳴かむ。〕
朝霞 棚引野邊 足桧木乃 山霍公鳥 何時来将鳴 |
【訳】朝霞のたなびいている野辺に、山のホトトギスは、いつになつたら来て鳴くだろう。
【釈】何時来将鳴 イツカキナカム。イツカは、何時か、早くと思う意である。
【評語】すなおな表現である。朝霞のたなびく野辺にホトトギスを待つ心が、純な叙述であらわされている。 |
|
|
掲載日:2014.03.07.
| 夏雑歌 詠鳥 |
| 朝霞 棚引野邊 足桧木乃 山霍公鳥 何時来将鳴 |
| 朝霞たなびく野辺にあしひきの山霍公鳥いつか来鳴かむ |
| あさかすみ たなびくのへに あしひきの やまほととぎす いつかきなかむ |
| 巻第十 1944 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【類歌】〔1470〕
【赤人集】〔222〕
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1944】語義 |
意味・活用・接続 |
| あさかすみ[朝霞]朝、かかる霞 |
| たなびくのへに[棚引野邊] |
| たなびく[棚引く] |
[自カ四・連体形]雲や霞などが横に長く引く |
| あしひきの[足桧木乃]〔枕詞〕「やま」にかかる 集中では最も多く使われている枕詞 |
| やまほととぎす[山霍公鳥]山にいるホトトギス、また単にホトトギス |
| いつかきなかむ[何時来将鳴] |
| いつか[何時か] |
[未来のある時点についての疑問]いつになったら~か |
| [過去のある時点についての疑問]いつの間に~か |
| [反語]いったい、いつ~か(いや、そんなことはない) |
| 〔成立〕代名詞「いつ」+係助詞「か」 |
| きなか[来鳴く] |
[自カ四・未然形]来て鳴く |
| む[助動詞・む] |
[推量(意志)・終止形]~よう・~つもりだ |
未然形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [あさかすみ] |
「かすみ」は、『万葉集』でも、圧倒的に「春」の季節を詠ったものが多い
しかし、万葉の当時は、季節に拘わらず詠われているとする説が有力だ
左頁の「資料」を見ても、江戸時代の注釈書では、
「かすみ」を春の景物としながらも、
「ほととぎす」を待つ歌だから、「夏雑歌」に入れたもの(『古義』)、としたり
『新考』のように、「春に限りてカスミといふは後のことなり」という注釈書も多い
この原文「霞」を、『元暦校本』だけが「霧」としている
|
| |
| [たなびくのへに] |
異訓のほとんどないこの歌で、おそらく唯一の「異訓」が、この「野辺」の「の」だろう
左に挙げた「諸注」でも、『古義』と『全釈』が「ぬへ」としている
この「野」を「ぬ」と訓むのは、江戸時代のある時期からのものらしい
用例として、江戸時代から近代にかけて、
「偲ぶ(シヌブ)」「楽しく(タヌシク)」「凌ぐ(シヌグ)」「角(ツヌ)」、
そして「信濃(しなぬ)」「上野(カミツケヌ)」などがあるが
これらの訓の基になったのが、江戸時代のある時期における学者たちの提唱ゆえ、という
「奴」「努」「怒」「弩」の一群の真仮名が、中世から江戸時代初期にかけて、
「の」と読まれていたことへの反省があり、
これらは「ぬ」の音を表記している仮名ではないのか、と言われ始め、
大学者たちの説得力ある論証の結果、上代語音「ぬ」に当てられた仮名という学説が、
定説となっていった
初めの頃は、論証の手続きに近代的実証主義が貫かれていた、とされ
それが、大きな説得力を持ち「ヌ説」が拡がっていった、といわれているが
しかし、次第に、何でもかんでも「の」と読むべきところまで「ぬ」となり
戦前の学者たちの間では、この上代語音「ぬ」を、誰も疑うことがなかったらしい
勿論、「ぬ」と読むべき表記はあるが、江戸時代の流行のような観があったようだ
戦後になって、著名な古代語学者・大野晋氏によって、その説が否定されるまで
『万葉集』のような漢字表記の歌集には、特に江戸時代からの注釈書においては
「ぬ」などの訓は多い
|
|
 |
|
| 【左、資料補注】 |
『代匠記』の「夏に入ってもまだ程なき意あり」というのは、
「あさかすみ」と「ほととぎす」の関係をいうのだろうか |
| |
| 『童蒙抄』もまた、「郭公を待歌にて、春の頃よりも待居し意をこめて、朝霞とは詠めるなるべし」 |
| |
『万葉考』の「冠辞」は、「枕詞」のこと
ついでに言えば、『仙覚抄』では「詞書」といっている
「かくるる事なし」とは、特に書くこともない、と言う意味なのだろうか |
| |
| 『略解』において、この時代の注釈書としては珍しく「時を定めず詠めり」とある |
| |
『古義』は、「春」の歌だろうけど、ほととぎす、を主とするので、ここに載せられている、としている
これには、夏相聞の一例をあげて、その根拠としている |
| |
『親考』は、『古義』の説を否定する
この注釈書は、『略解』や『古義』の説に、かなりの批評を用いているが
時代的に、その頃の影響を大きく与えていた「諸注」だったからだろう |
| |
| |
| |
|
 |
| 【歌意1946】 |
ほととぎすの、鳴く声を聞きましたか
卯の花が、咲いて散ったこの岡で、
葛を引いている娘さん |
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕では、
単に、ほととぎすの鳴き声を聞きましたか、と娘に尋ねたのではなく
葛を引く作業が、ほととぎすの声を招き寄せるだろうとして詠ったものでは、という
その根拠になるのが、ほととぎすを勧農の鳥とする歌があるから
この歌も、同じではないだろうか、と
その勧農の歌ではないか、あるいはそのような意味合いも考えられる歌ではないか、という
その歌が、家持の歌だ
| (廿四日應立夏四月節也 因此廿三日之暮忽思霍公鳥暁喧聲作歌二首) |
| 霍公鳥 来喧響者 草等良牟 花橘乎 屋戸尓波不殖而 |
| 霍公鳥来鳴き響めば草取らむ花橘を宿には植ゑずて |
| ほととぎす きなきとよめば くさとらむ はなたちばなを やどにはうゑずて |
| 巻第十九 4196 暁喧聲作歌 大伴宿禰家持 |
〔語義〕
「きなきとよめば」、やって来て鳴き響き渡れば
「とよめ」は下二段の未然形で、仮定条件になる
「くさとらむ」は、「草を取ろう」
「やどにはうゑずて」、「家の庭には植えないで」
「ずて」は、「~ないで・~なくて」 |
〔歌意〕
ほととぎすが、里までやって来て、鳴き響かせるようになったら
田の草取りでもしよう
家の庭に、花橘を植えないで... |
まるで、ほととぎすの鳴き声を合図にするかのように、
田の草取りをしよう、という
だから、後の時代に「ほととぎすが勧農の鳥」とされる習慣が
ここに見られる、というものだ
「花橘」を植えないで、と言うのは、そんな暇もないだろう、ということなのか
それとも、「花橘」を植えることが、ほととぎすを誘うことだったのか、よく解らないが、
仮に花橘を、そうした誘いの「道具」に使うのであれば
「田の草を刈る」というのは...
早くその作業を済ませたいからなのか
しかし、あまりしっくりこない
それでは、ほととぎすが来れば、もう花橘には用はない、というのだろうか
そもそも、掲題歌の「卯の花」のように、
ほととぎすは「花橘」に誘われるものなのだろうか
花橘を植えようと思っていたけど、
ほととぎすがやって来て鳴き出したら
やはり、田の草刈を始めなければ、という時期的な「勧農」の習慣とした方が
何となく合うのかな
掲題歌の歌意は、その「勧農」の習慣を背景にすれば
葛引く娘さん、もうほととぎすがやって来て、鳴いたのだね
だから、農作業をしているんだね、という意味なのだろう
【夫木抄】
| ほとときす なくこゑきくや うのはなの さきつるをかに たくさひくいも |
| 夫木抄 巻第八 夏二 2800 人麿 |
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1946] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔ほとゝきすなくこゑきくやうの花のさきちるをかにたくさひくいも 〕
霍公鳥鳴音聞哉宇能花乃開落岳尓田草引○嬬 [○女+咸] |
| ほとゝきすなくこゑ 見安云田草引は手にて草引く也又田のくさとも云愚案田草引いもは子規の声を聞やと也 |
| 『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕 |
| |
霍公鳥鳴音聞哉宇能花乃開落岳爾田草引○嬬 [○女+感]
〔ホトヽキスナクコエキクヤウノハナノサキチルヲカニタクサヒクイモ 〕 |
| 田草引は。草取なり、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
霍公鳥鳴音聞哉宇能花乃開落岳爾田草引○嬬 [○女+感]
〔ほとゝぎす、なくこゑきくや、うのはなの、さきちるをかに、たぐさ引いも 〕 |
| 霍公鳥は、卯の花によると云來れば、卯の花の咲散る折に、草取る妹はいか計り時鳥を聞くやと羨みても聞え、又田草引とよめるは、卯の花の咲散る頃、岡べに
時鳥鳴らん面白き景色を、賤女も聞知るや、心無き賤は知らずやあらんと、心を深く詠める歌共聞ゆる也。唯一通に見ば、何の意も無く聞えたる歌なれど、聞人の情によりては、深くも淺くも聞ゆる歌也。又われは五月ならねば聞かぬを、うの花の咲散る折なれば、田草引女も、此處には聞つるやと詠める共聞ゆる也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
〔霍公鳥、鳴音《コヱ》聞哉、宇能花乃、開落《サキチル》岳爾、 岡の山田なり、田草引○嬬[○女+感]《ヒクイモ》、〕 |
| (無記) |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕 |
| |
霍公鳥。鳴音聞哉。宇能花乃。開落岳爾。田草[草ハ葛ノ誤]引○嬬[○女+感]。
〔ほととぎす。なくこゑきくや。うのはなの。さきちるをかに。くずひくをとめ。〕 |
源康定主《ヌシ》の説、草は葛の誤なりと有るぞよき。集中クズを田葛と書けり。さて葛引く女を呼びかけて問ふさまなり。
參考 ○田草(考)説も訓も無し(古、新)「葛」の誤とす。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔霍公鳥《ホトヽギス》。鳴音聞哉《ナクコエキクヤ》。宇能花乃《ウノハナノ》。開落岳爾《サキチルヲカニ》。田草引○嬬[○女+感]《クズヒクヲトメ》。〕 |
| 田草、略解云、源(ノ)康定主の説に、草は葛の誤なりとあるぞよき、○歌(ノ)意は、卯(ノ)花のちりとぶ岳に、葛根を引(キ)取(ル)をとめ子よ、汝等も、あのほとゝぎすの鳴なる音を聞つるや、となり、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔ほととぎすなくこゑきくやうの花のさきちるをかにくずひくをとめ〕
霍公鳥鳴音聞哉宇能花乃開落岳爾田草引○嬬 [○女+感] |
| (無記) |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
ほととぎす 鳴く聲聞くや 卯の花の 咲き散る岳に 葛引くをとめ〕
霍公鳥《ホトトギス》 鳴音聞哉《ナクコヱキクヤ》 宇能花乃《ウノハナノ》
開落岳爾《サキチルヲカニ》 田草引○嬬[○女+感]《クズヒクヲトメ》》 |
卯ノ花ガ咲イテ散ル岡デ、葛ノ蔓ヲ引イテヰル少女ヨ、オマヘハ郭公ノ鳴ク聲ヲ聞クカドウダ。
○田草引○嬬[○女+咸]《クズヒクヲトメ》――舊訓タクサヒクイモとあるのを、略解に「源康定主説、草は葛の誤也と有ぞよき。集中くずを田葛と書り」といつて、訓をクズヒクヲトメと改めてゐる。卷七の劔後鞘納野葛引吾妹《タチノシリサヤニイリヌニクズヒクワギモ》(一二七二)、眞田葛原何時鴨絡而我衣將服《マクズハライツカモクリテワガキヌニキム》(一三四六)などによれば、誤字説がよいやうである。又この葛は夏衣に縫ふ葛布を織る爲に、蔓を引くのである。今も葛布の料にする葛糸を採取する爲に、葛蔓を苅るのは、五月頃に行ふさうである。葛根を採る爲とするのは當らない。
〔評〕 卯の花は郭公の宿りともいはれる花である。今、卯の花が眞白に咲き滿ちた岡の上で、葛蔓を引いてゐる里の少女に對して、郭公の鳴く聲を聞くかと呼びかけたのは、郭公を待つ人の心であらう。下の問答の歌に宇能花乃咲落岳從霍公鳥鳴而沙渡公者聞津八《ウノハナノサキチルヲカユホトトギスナキテサワタルキミハキキツヤ》(一九七六)あるのは似た歌であるが、その意味を以でこれを解釋しようとするのはよくない。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔ほととぎす 鳴くこゑきけや、 卯の花の 咲き散る岡に くさひくをとめ。〕
霍公鳥鳴音聞哉宇能花乃開落岳爾田草引○嬬 [○女+感] |
【訳】ホトトギスの鳴く声を聞いてか、卯の花の咲き散る岡で、草を引いている娘子よ。
【釈】鳴音聞哉 ナクコエキケヤ。キケヤは、已然条件法。ホトトギスの鳴く声を聞いて、時節のきたのを知る意である。聞哉は、従来多くキクヤと読んでいたが、この形の多くの用例は、已然条件法に読むべきものである。助詞ヤの表意文字としての表示は、哉が多く、耶が少々あるだけである。哉は、感動および疑問の意の字で、ヤの意味もまたその辺にあるものと察せられる。
【評語】ホトトギスが、農事を催し立てるという諺をもとにしているらしい。田草を引くわざが詠まれているのが注意される。枕の草子にある「ほととぎす、おれ、かやつよ、おれ鳴きてこそ、われは田植うれ」という民謡は、ホトトギスが鳴いて田植の季節になつたことを歎いたもので、このような歌が古くから行われていたのだろう |
|
|
掲載日:2014.03.08.
| 夏雑歌 詠鳥 |
| 霍公鳥 鳴音聞哉 宇能花乃 開落岳尓 田葛引○嬬 [○女+感] |
| 霍公鳥鳴く声聞くや卯の花の咲き散る岡に葛引く娘女 |
| ほととぎす なくこゑきくや うのはなの さきちるをかに くずひくをとめ |
| 巻第十 1946 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【類歌】〔4196〕
【夫木抄】〔2800〕
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1946】語義 |
意味・活用・接続 |
| ほととぎす[霍公鳥] |
| なくこゑきくや[鳴音聞哉] |
| きく[聞く・聴く] |
[他カ四・終止形]聞いて心に思う・聞き入れる |
| や[終助詞] |
[疑問]~か 〔接続〕終止形・已然形につく |
| うのはなの[宇能花乃]ユキノシタ科の落葉低木、初夏に白い鐘状の五弁の花を円錐状につける |
| さきちるをかに[開落岳尓]咲いて散る岡に |
| くずひくをとめ[田葛引○嬬 [○女+感]] |
| くず[葛] |
山野に自生するつる草、秋に紫色の蝶形の花を開く、秋の七草の一つ |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [ほととぎす] |
鳥の名、「時鳥・杜鵑・郭公・子規」とも表記される
初夏に渡来し、秋に南方に去る、巣を作らずうぐひすなどの巣に卵を生み、
ひなを育てさせる
夏を知らせる鳥として親しまれ、多くの詩歌に詠まれている
|
| |
| [なくこゑきくや] |
どの注釈書も「なくこゑきくや」だが、『全註釈』だけが「きけや」としている
その説明は、左の本文にあるが、「已然形」に読むべきというのが、
一般的な終助詞「や」の接続に合わないので、あれっ、と思ったが
それは、係助詞「や」のことだった
終助詞「や」であれば、已然形にも自然と接続し、
しかも『万葉集』に多く見られる、とあった
なるほど、接続上は問題ないわけだ
すると、解釈の仕方になるだろうが...
違いとなれば、『全註釈』によれば、「ホトトギスの鳴く声を聞いてか」で、
その鳴き声に急かされて、もしくは、それを合図に、というような解釈になっている |
| |
| [うのはな] |
『万葉集』中に、二十四首詠われているが、
そのうち十八首が、ほととぎすとの組み合わせで詠われている
|
| |
| [くずひくをとめ] |
この原文「田葛」は、底本ではどれも「田草」とあり、
旧訓では「たくさ」と訓まれていた (左頁「童蒙抄」の頃までがそうだと思う)
次代の真淵の『万葉考』では、この箇所の訓には触れられていないが
その学派の流れである橘千蔭が、『略解』に中に、誤字説を載せる (左頁)
「草を引く」とはいわないらしい
そうだろうなあ、「草を刈る」だろう
「葛」は、「引く」というので、確かにこの誤字説は、現代に受け入れられたのだろう
この『略解』以降、多くの検証もあっただろうが、「葛」に落ち着いている
しかし、その中にあって、『全注釈』は、「くさひく」としている
あくまで、原文に拘ったものなのだろうか
その説明がないので、そう思うしかない
さらに言えば、もっと原文(誤字説以前の「田草」)に忠実な注釈書がある
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕がそれで、
「たくさひく」と訓んでいる
|
| |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】 |
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
もっとも、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
今日の一首において、この『校本万葉集』の面白かった
[本文]
「霍公鳥 鳴音聞哉 宇能花乃 開落岳尓 田草引○嬬 [○女+感]
「ホトトキス ナクコヱキクヤ ウノハナノ サキチルヲカニ タクサヒクイモ」
[本文]「霍公鳥 鳴音聞哉 宇能花乃 開落岳尓 田草引○嬬 [○女+感]
「ホトトキス ナクコエキクヤ ウノハナノ サキチルヲカニ タクサヒクイモ」 |
〔本文〕
|
「鳴」。『西本願寺本』ナシ。右ニ書ケリ。本文中「鳥音」ノ間ニ「○」符アリ。
「聞」。『元暦校本』「開」墨ニテ消セリ。右ニ墨「聞」アリ。
「乃」。『元暦校本』ナシ。右ニ書ケリ。本文中「花開」ノ間ニ墨「○」符アリ。
「開落」。『神田本(紀州本)』「落開」。但「開落」トスベキ記号ヲ符セリ。
「女偏に感」。『元暦校本』『類聚古集』「女偏に咸」
(『拾穂抄』は、これに拠ったものだろう) |
| 〔訓〕 |
「ナクコエキクヤ」。
|
『元暦校本』『類聚古集』「なくこゑきくや」。
『元暦校本』下ノ「く」ノ右ニ赭「ク」アリ。
『神田本(紀州本)』『西本願寺本』『細井本』『京都大学本』「ナクコヱキクヤ」。
『西本願寺本』「コヱキク」は何カヲ直セリ。 |
| 「サキチルヲカニ」。 |
『類聚古集』「さきちるをたに」。朱ニテ「た」ヲ消セリ。ソノ右ニ朱「カ」アリ。 |
| 〔諸説〕 |
「田草引○嬬[○女+感]」。「タクサヒクイモ」。
『略解』「草」ハ「葛」ノ誤ニテ訓「クズヒクヲトメ」トスル(源廉定説)ヲ可トス。 |
このように、歌の解説ではなく、表記の校合を目的とした「校本」は、さらに『万葉集』の魅力を教えてくれるものだ |
| |
| |
| |
| 【左、資料補注】 |
『童蒙抄』の、ほととぎすは、卯の花に寄るので、その卯の花の咲き散り岡で
草を「取る」娘は、どれほどほととぎすの鳴き声を聞けるのか、と羨ましく思っている
それに、通り一遍で聞けば、何ともない歌だが
聞くものの気持ち次第で、深くも浅くも聞こえるとは、踏み込んだ言い方だなあ、と思う |
| |
『略解』のこの引用が、それ以降の定訓となったのだから、
それ以前にも「草を引く」とは言わない、疑念はあったものなのだろう
しかし、やはり大御所が持ち出さなければ、流れは向かない、ということか
先人の大学者である「賀茂真淵」でさえ、
「田草」には言及していないし、訓もつけていない
この時代の雰囲気が、何となく伝わってくるような「誤字説」だ
勿論、安易な「誤字説」は慎むべきだが、その誤字説が後世に残るということは
それが時代時代の検証に耐え得るものだった、と言うことなのだろう |
| |
『古義』で、「葛根」と言う
「葛」は、つるからは葛布(くずふ)を製し、根からはでんぷんを採る、とあった
だから、「引」を字句通りに解釈するなら、やはり「葛」なのだろう
「葛根」を「引く」こそ、ぴったりなのだが
ふと思う
逆は誰も考えなかったのだろうか
「引」が「刈」の誤字で、あるいは「引」であっても「かる」と訓ませた、とは... |
| |
| 『略解』において、この時代の注釈書としては珍しく「時を定めず詠めり」とある |
| |
『古義』は、「春」の歌だろうけど、ほととぎす、を主とするので、ここに載せられている、としている
これには、夏相聞の一例をあげて、その根拠としている |
| |
『親考』は、『古義』の説を否定する
この注釈書は、『略解』や『古義』の説に、かなりの批評を用いているが
時代的に、その頃の影響を大きく与えていた「諸注」だったからだろう |
| |
|
|
| 【歌意1947】 |
月が、こんなに美しく輝く夜だから
鳴くホトトギスの姿を、見たいものだ
お前のために、私は草も取り、素敵な舞台を用意したぞ
誰か来て、一緒に見られればいいのだが... |
「みむひともがな」という語句の歌は、幾つか目にしている
想い人と一緒に見たいものだ、とか
言ってみれば、それが叶わない願いのような意味合いも感じられるが
以前と違って、今の私は、多くの注釈書に触れることが出来るようになったので
その解釈に、正直驚いている
知れば知るほど、結局何が肝腎なのだろうか、と自問してしまう
無論、知らないより、知っていた方がいい
ただ、そこに「何がこめられてるのか」という、いっそうの面倒な作業が加わる
今のところ、それも心地よいが...いつまで続けられるかな
この歌が、昨日の歌〔1946〕と問答の歌という説も強くあるが
意味合いから、それも可能だと思う
しかし、その判断は、少なくともこの歌集の編者が演出していない以上
それが「正しい」として議論することもないと思う
この歌の魅力は、美しい月夜に鳴くホトトギスを
誰と見たいか、とかいうよりも
その舞台を俺は用意してやったぞ
だから、ここで鳴いてくれ、と懸命になった作者の「想い」にあると思う
その中で、せっかく舞台を用意したのだから、
想い人でも来てくれないかなあ、と気持ちに期待感が出てくる
『講談社文庫本』や『全註釈』で解釈されるように、
そんな自分を、誰か見てくれないかなあ、という意にも通じるかもしれない
しかし、それは結果として思うことであって、
何よりも、まず月夜の素敵な舞台を作ったこと、
それは、月明かりに美しく鳴くホトトギスのため
それが、大きな気持ちを占めている
それにしても、一首にこめられた想いは
作者一人ではなく、多くの人がそれぞれに感じられる、いいものだ、と思う
【赤人集】
| つききよみ なくほとときす みむとおもふ わかこころのこと みむひともかな |
| 赤人集 229 |
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1947] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔月夜よしなくほとゝきすみまくほりわかさをとれる見んひともかな 〕
月夜吉鳴霍公鳥欲見(見まほしみ)吾草取有見人毛欲得 |
| 月夜よしなく郭公 さをとれるは草を採也 |
| 『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕 |
| |
月夜吉鳴霍公鳥欲見吾草取有見人毛欲得
〔ツキニヨシナクホトヽキスミマクホリワカサヲトレルミムヒトモカナ 〕 |
發句はツキヨヽミと讀べし、吾草取有はワレクサトレリとも讀べし、草をサヲと點ぜるは書生の誤なり、第十八に霍公鳥こゆ鳴度れ燈を、月夜になぞへ其影もみむとよめる如く、聲を聞は更なり、月夜に飛渡る影をも見むとの意に隱ろふ草を取拂ふなり、第十九十七右に、霍公鳥來鳴響者《トヨマバ》草等良牟、花橘乎屋戸爾波不殖而、今の歌をもて家持のよまれたるなり、
草、[官本云、クサ、] |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
月夜吉鳴霍公鳥欲見吾草取有見人毛欲得
〔つきよゝし、なくほとゝぎす、みまくほし、わがくさとるを、見る人もがな 〕 |
| 吾草取有 わがさを取れると讀ませたれど、第十九卷に、草取らんとよみたり。あれ草取れりとか、草とるをとか讀べし。此歌の意は、月も清く折から郭公鳥も
鳴夜頃なれば、戀慕ふ人をも見まくほし、若しや訪來んかと、われはかく庭の草をも刈拂ふて待居るを、訪來て見る人もがなと詠める也。月よき夜、鳴く時鳥の音に催されて、思ふ人をも待居る情さも有べき也
|
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
〔月夜吉《ツクヨヨシ》、鳴霍公鳥、欲見、吾草取有《ワカクサトレル》、 庭を掃しなるべしさて此夜のさま親き友がきなどに見せまくほりしなり見人毛欲得《ミムヒトモガモ》、〕 |
| 此歌上の歌のこたへにあらず、 |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕 |
| |
月夜吉。鳴霍公鳥。欲見。吾草取有。見人毛欲得。
〔つくよよみ。なくほととぎす。みまくほり。わがくさとれる。みむひともがも。〕 |
是れは郭公を見んとて、庭草を掃きて待つ意かとも聞ゆれど、穩かならず。宣長云、吾は今の誤にて、イマクサトレリなり。草トルは凡て鳥の木の枝にとまり居る事なり。見マクホリは、郭公が月を見まくほりて、今木の枝にゐるを、來て見ん人もがななり。卷十九、ほととぎすきなきとよまば草とらむ花橘をやどにはうゑずてと詠めるも、郭公の來てとまるべき橘を植ゑんと言ふなりと言へり。此十九の歌も末句誤字有るべし。猶そこに言はん。
參考 ○月夜吉(代、古、新)略に同じ(考)ツクヨヨシ ○欲見(考、新)略に同じ(古)ミガホレバ ○吾草取有(代)ワレクサトレリ(考)ワガクサトレル(古)イマクサトレリ(新)ワレクサトレリ ○見人毛欲得(新)ミムヨシモガモ「人」を「由」の誤とす。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔月夜吉《ツクヨヨミ》。鳴霍公鳥《ナクホトヽギス》。欲見《ミガホレバ》。吾草取有《イマクサトレリ》。見人毛欲得《ミムヒトモガモ》。〕 |
| 欲見吾草取有、本居氏、吾は今の誤にて、イマクサトレリなり、草取とは、凡て鳥の木の枝にとまり居ることなり、欲見《ミマクホリ》は、ほとゝぎすが、月をみまくほりて、今木の枝にゐるを、來て見む人もがななり、十九に、ほとゝぎすきなきとよまば草とらむ花橘をやどにはうゑずて、とよめるも、ほとゝぎすの來てとまるべき、橘をうゑむと云なりといへり、中山(ノ)嚴水云、此(ノ)歌、大方は本居翁の説の如し、但し欲見は、霍公鳥が、月を見まくほりする意に説れたるはいかゞなり、欲見は、ミマホレバとよむべし、見まくほりすればなり、鳴霍公鳥を見まほしと思ひて見やりたれば、草取て鳴居たるを見出したるなりと云り、その意ならばミガホレバとよむべし、ミマホレバとよまむは、後(ノ)世の詞づかひなり、凡て見まくほし、聞まくほしなど云べきを略きて、見まほし、聞まほしと云類は、古言の用格にあらず、)さてこゝは、欲見者とありしを、もしは者(ノ)字の脱たるにもあらむか、さて霍公鳥のすがたを見まくほりする歌、十八にも、霍公鳥《ホトヽギス》を、登毛之備乎都久欲爾奈蘇倍曾能可氣母見牟《トモシビヲツクヨニナソヘソノカタモミム》、八(ノ)卷に、鳴霍公鳥見曾吾來之《ナクホトヽギスミニソワガコシ》、などあり思(ヒ)合(ス)べし、〔頭註、「哥袋西園寺、目に見れど草とる鷹のふるまひは云々、祐則、くれぬるかつかれにかへるはしたかの草とる道も見えぬばかりに、などあり、これ又木居に同じく鷹のつかれて、草に落てやすむを云、」〕○歌
(ノ) 意は、月がよく照たる故に、この月影には、霍公鳥のすがたも見ゆべきなれば、いかにぞして、そのすがたを見まほしと思ひて、見やりたれば、今木の枝にとまりて鳴て居を、唯獨見むはくち惜ければ、いかで來て見む人もがなあれかし、となり、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔月夜よみなくほととぎす欲見《ミマクホリ》、吾草取有《ワレクサトレリ》、見人《ミムヨシ》もがも 〕
月夜吉鳴霍公鳥欲見吾草取有見人毛欲得 |
三四を略解にミマクホリワガクサトレルとよみ、さて宣長の説を擧げて
「吾は今の誤にてイマクサトレリなり。草トルは凡て鳥の木の枝にとまり居る事也。ミマクホリはほとゝぎすが月を見まくほりて今木の枝にゐるを來て見ん人もが
な也。卷十九ホトトギスキナキトヨマバ草トラン花橘ヲヤドニハウヱズテとよめるもほとゝぎすの來てとまるべき橘をうゑんといふ也といへり」
といへり。古義には三四をミガホレバイマクサトレリとよみ、さて
「中山嚴水云。此歌大方は本居翁の説の如し。但し霍公鳥が月を見まくほりする意に説れたるはいかがなり。欲見はミマホレバとよむべし。見マクホリスレバなり。なくほとゝぎすを見まほしと思ひて見やりたれば草取て鳴居たるを見出したるなりと云り。その意ならばミガホレバとよむべし。さてこゝは欲見者とありしを、もしは者(ノ)字の脱たるにもあらむか」
といへり。案ずるに欲見は舊訓の如くミマクホリとよみ第四句は契沖に從ひてワレクサトレリとよみ、結句は人を由の誤としてミムヨシモガモとよむべし。
「月夜ニナク子規ノ影ノ地上ニウツルヲ見ムト欲シテ庭前ノ草ヲ取除キタリ。イカデ見ム由モガナ」
といへるなり。卷十九なる
「ほととぎす來なきとよまば草とらむ花たちばなを屋戸爾波不殖而 」
は此歌に據れるにて結句は不を省きてヤドニハウヱテとよむべし |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔月夜よみ 鳴くほととぎす 見まくほり 吾が草取れり 見む人もかも〕
月夜吉《ツクヨヨミ》 鳴霍公鳥《ナクホトトギス》 欲見《ミマクホリ》 吾草取有《ワガクサトレリ》 見人毛欲得《ミムヒトモガモ》 |
月ガヨイ夜ナノデ、鳴ク霍公鳥ヲ見タイト思ツテ、私ハ今木ノ下ニ生エテ居ル草ヲ取ツテヰル、一人見ルノハ惜シイカラ、共ニ見ル人ガアレバヨイガナア。
○吾草取有《ワガクサトレリ》――舊訓ワガクサトレルとあるが、宣長は吾を今の誤としてイマクサトレリと改めてゐる。その解について略解に、これはほととぎすを見むとて、庭草を掃て待意かともきこゆれど穩ならず。宣長云、「吾は今の誤にて、いまくさとれり也、草とるは凡て鳥の木の枝にとまり居る事也、見まくほりは、ほととぎすが月を見まくほりて、今木の枝にゐるを來て見ん人もがな也、卷十九ほととぎすきなきとよまば草とらん、花橘をやどにはうゑずてとよめるも、ほととぎすの來てとまるべき橘をうゑんといふ也といへり。」とあるが、清水濱臣は「兩説ともに非なり、草とるは手とりにすることにて、此歌は霍公鳥を手とらまへにせし事、十九の歌は杜宇の多く來鳴くならば手とりにせむとおもふ故に中々に橘をばうゑじとなり。さるよしは永久四年百首鈴虫、顯仲、鈴むしの聲を鈴かと聞からに草とるたかそおもひしらるる、又、兼昌、みかり野になく鈴虫をはしたかの草とりて行く音かとぞきく、此意にて知るべし。さて草とるは空とるといふ詞の對語にて、空とるは飛鳥の空にてものをとるを言ふなり。是もおなじ百首、野行幸、仲實、あかねさすみかりの小野にたつきぎす空とるたかにあはせつる哉、又、忠房、そらとらぬたかはあらじなみかり野に雲の上人あはすと思へば」といつてゐる。古義も大體宣長説に賛同してゐるが、郭公の鳴くべき月夜に、草を苅りつつ待つてゐるだけの意ではあるまいか。なほ攻究を要する。
〔評〕意味が明らかでないので、許はむつかしいが、右のやうに解すれば全く田舍人の歌である。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔つくよよみ なくほととぎす みまくほり われくさとれり みむひともがも〕
月夜吉 鳴霍公鳥 欲見 吾草取有 見人毛欲得 |
【訳】月がよいので、鳴くホトトギスを見たいと思つて、わたしは草を取っている。誰か見る人がほしいなあ。
【釈】月夜吉 ツクヨヨミ。 月がよさにホトトギスを見たいと思つての意に、見マクホリを修飾している。
吾草取有 ワレクサトレリ。ワガクサトレル『元暦校本』。ワカサヲトレル『西本願寺本』。ワレクサトレリ『万葉代匠記(初稿本)』。ワガクサカレリ『改』。ワガクサトルヲ『万葉集童蒙抄』。今草取有(イマウサトレリ)『万葉集略解(宣長説)』。
諸説があるが、ほとんど問題にするに足りない。
見人毛欲得 ミムヒトモガモ。自分の草を取っている働きぶりを見る人もあれと願うのである。
【評語】ホトトギスを愛する文雅と、草を取る実生活との交錯しているおもしろさがある。但し草を取るというのが、事実どの程度に生活を写しているかは、別の問題である。 |
|
 |
掲載日:2014.03.09.
| 夏雑歌 詠鳥 |
| 月夜吉 鳴霍公鳥 欲見 吾草取有 見人毛欲得 |
| 月夜よみ鳴く霍公鳥見まく欲り我れ草取れり見む人もがも |
| つくよよみ なくほととぎす みまくほり われくさとれり みむひともがも |
| 巻第十 1947 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【赤人集】〔229〕
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1947】語義 |
意味・活用・接続 |
| つくよよみ[月夜吉] |
| よみ[良し] |
形ク・語幹「よ」+接頭語「み」](原因・理由を表すミ語法)~ので |
| なくほととぎす[鳴霍公鳥]ホトトギスが鳴く |
| みまくほり[欲見] |
| みまく |
上一段「見る]の未然形「み」に、意志の助動詞「む」の「ク語法」 |
| ほり[欲(ほ)る] |
[他ラ四・連用形]願い望む・欲しがる |
| われくさとれり[吾草取有] |
| とれ[取る・採る] |
[他ラ四・已然形]採集する・つかむ・とりあげる |
| り[助動詞・り] |
[完了・終止形]~ている |
已然形につく |
| みむひともがも[見人毛欲得] |
| みむ |
「見る」の未然形「み」に、推量の助動詞「む」の連体形「む」 |
| もがも[終助詞] |
[上代語](願望)~があったらなあ・~であったらなあ |
| 〔成立〕終助詞「もが」に、終助詞「も」 〔成立〕体言、体言に準ずる語に付く |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [つくよよみ] |
この訓が、古くは「つきよよし」とされていたことは、左の資料からもわかる
そして、いつ頃から「つくよよみ」となったのか...
『略解』の頃から、この訓が定着しているようだ
「つきよ」、「つくよ」はともかく、「よし」と「よみ」では、
その意味合いも変わってくる
旧訓で「よし」であったのを、「よみ」が定着した、というのは
この歌の歌意に沿った「訳」が、「よみ」を導いたのだろうか
月がとても綺麗なので...「つくよよみ」
月夜が、とても綺麗だ...「つくよよし」
これは第三句の「みまくほり」にかかる句なので、
「みまくほり」、なぜ見たいのか、
月の光のもと、ホトトギスの鳴く姿でも見ることができたら、ではないだろうか
それだと、「原因・理由」の接尾語「み」が相応しいはずだ
だから、「つくよよみ」では、そのような「歌意」にならなければおかしい
|
| |
| [みまくほり] |
この「異訓」はとても多い
今まで「欲見」を「みまくほり」と解ったつもりで訓じていたが
こうして訓がつけられるまでも、やはり多くの検証があったのだ
しかし、この訓は、随分初期の頃からそう訓まれてもいる
本格的な注釈が行われ始める江戸時代頃から、むしろ賑やかになったような観もある
『古義』の注釈は、読んでいて面白かった
ほととぎすが、月を見たい、とすれば「みまくほり」だが...と
有り得ないことではないだろうが、そんな発想、いったいどうやって思いつくのだろう
|
| |
| [われくさとれり] |
これも異訓の多い句だが、たんに同義の訓の違いで誰にもすぐに理解できる
そんな「異訓」ではなく、その「訓」そのものに、驚かされることもある
「くさ」と訓むのは普通のことだが、「さを」と古くから訓があるのは
その「さを」が、当時としては一般的に用いられた「語」だということだろう
しかし、『校本万葉集』(下段)でも、載せてあるが、「くさ」とする「諸本」が多い
ただし、「草」に「サヲ」と別記することからも、
「草」を「さを」というのは、かつてはあったのだろう、と言うことだと思う
多くの底本となっている『西本願寺本』が「サヲ」となれば、
その「さを」が、どんな文献から採られたものなのか、誰も気にしないものなのか
とは言っても、私が知らないだけで、それは常識かもしれないが...
しかし、古語辞典に「さを」は、いくら探しても見つからなかった |
| |
| [みむひともがも] |
これは、異訓の問題ではなく、解釈の問題が大きい
確かに、異訓もあるが、この語句の解釈が大きく二つに理解できる
「誰か一緒に見てくれる人がいて欲しいなあ」と、
「こうしている自分を見てくれる人がいて欲しいなあ」
普通に考えられるのは、前者の方で、その解釈をする注釈書も多いが、
ならば、どうして後者のような解釈が起こり得るのだろう
もっとも解りやすい書が、『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕だ
「月が美しいので鳴き飛ぶ霍公鳥の姿を見たいと思い、私は野に草をとっている。この愛着を、誰か見てほしい」
『全註釈』では、その「釈」で、『講談社文庫』と同じように、
「自分の草を取っている働きぶりを見る人もあれと願うのである」と言っている
私など、仮にこのような解釈に出合わなかったら、何の疑いもなく
従来の解釈だと思うだろう
かといって、後者の解釈に、「その通りだ」とも言えないものがある
この意表を突くような解釈のお陰で、従来の解釈に、
少しでも合理性や、共感を求めたい、と思う気持ちが沸いたのも事実だ
|
| |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日~] |
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
[本文]「月夜吉 鳴霍公鳥 欲見 吾草取有 見人毛欲得」
「ツキヨヨシ ナクホトトキス ミマクホリ ワカサヲトレル ミムヒトモカナ」 |
| 〔本文〕 |
| 「鳥」 |
『京都大学本』ナシ。左ニ書ケリ。本文中「公欲」ノ間ニ「○」符アリ |
| 「吾」 |
『類聚古集』「吉」墨ニテ消セリ。右ニ墨「吾」アリ |
| 「毛」 |
『類聚古集』ナシ。右ニ朱ニテ書ケリ。本文中「人欲」ノ間ニ朱「○」符アリ |
| 〔訓〕 |
| ミマクホリ |
『元暦校本・類聚古集』「みまくほし」 |
| 『神田本(紀州本)』「ミマクホシ」 |
| 『西本願寺本』「クホリモト」青 |
| 『細井本・神宮文庫本』「ミマクトリ」 |
| 『大矢本・京都大学本』「クホリ」青 |
| 『京都大学本』漢字ノ左ニ赭「ミマクホシ」アリ |
| 『近衛本』「ミマクナリ」。「クナリ」青 |
| ワカサヲトレル |
『元暦校本・類聚古集』「わかくさとれる」 |
| 『神田本(紀州本)・細井本・京都大学本・神宮文庫本』「ワカクサトレル」。「草」ノ左ニ「サヲ」アリ。『神田本(紀州本)』「レル」ハ「リ」ヲ削リテ書ケリ。『細井本』「草」ノ左ニ「サヲ」。『京都大学本』「クサ」青 |
| 『西本願寺本』「サヲ」モト青。『大矢本』「サヲ」青 |
| ミムヒトモカナ |
『元暦校本』「みるひともかも」。「る」ノ右ニ赭「ム」アリ |
| 『類聚古集』「みむひともかも」 |
| 『神田本(紀州本)』「ミルヒトモカモ」 |
| 〔諸説〕 |
| ○「ツキヨヨシ」。『万葉代匠記(初稿本)』「ツキヨヨミ」 ○「欲見、ミマクホリ」。『改』「ミマホシミ」。『万葉集古義』「ミガホレハ」ヲ可トシ「見」ノ下「者」脱カトス。 ○「吾草取有、ワカサヲトレル」。『万葉代匠記(初稿本)』「ワカクサトレル」又ハ「ワレクサトレリ」。『改』「ワカクサカレリ」。『万葉集童蒙抄』「ワカクサトルヲ」トモス。『万葉集略解』宣長「吾」ハ「今」ノ誤訓「イマクサトレリ」 |
|
| |
| 【左、資料について】 |
『拾穂抄』
「さをとれる」は「草を採也」という
この歌に関しては、この語義解釈のみであり
この時代では、まだ多くの検証すべきものある、との認識が少なかったのだろうの |
| |
『代匠記』
この説明に、私は混乱している
「草」を「さを」とするのは間違いだ、としながら
どうして、この訓では、「わかさをとれる」としているのだろう
私の入力ミスなのだろうか
これも、明日香図書館での宿題だ
それとも、従来の「訓」を載せておいて、
それに対する批評が説明されているのだろうか... |
| |
『童蒙抄』
この時代の、注釈書として、この歌への、
やっとまともな「注釈」がつけられていると思う
それに、この解釈は、前述の「一緒に見たい」ではなく、
「月も清く折から郭公鳥も 鳴夜頃なれば、戀慕ふ人をも見まくほし、若しや訪來んかと、われはかく庭の草をも刈拂ふて待居るを、訪來て見る人もがなと詠める也」と、
雰囲気もいい夜なので、恋慕う人が来てくれないかなあ、
こうして草を取って待っているのに、とも汲み取れる解釈だ |
| |
『万葉考』
ここにいう、「此歌上の歌のこたへにあらず、」というのは
前歌との問答歌で、その「答歌」ではないか、とする説があり
そのことへの真淵の見解を言うものだ
この時代に、この「問答歌」説、結構強かったのだろうか |
| |
『略解』
この時代の大御所と言われる人たちの見解が、
その後の学者たちの指針になったのは間違いないことだが
宣長の説に対して、千蔭は訓はともかく、その解釈にあたっては、同調している
ほとんどの注釈が、霍公鳥を見るために庭を綺麗にするという前提にたいし
宣長の言う、ほととぎすが、木に止ることを「草とる」などと理解し、
木に止まって鳴くのを、誰か来て見ないものか、と解釈している
おそらく、この解釈は、他には見られないだろう |
| |
『古義』
雅澄は、千蔭よりさらに宣長に寄る解釈を見せる
訓について、「吾」を「今」の誤りとする宣長説を採り、
歌意は、それに基づくものだ
ただし、「みまくほり」については、自身の独創かと思う |
| |
『万葉集新考』
これもまた独創的な解釈をしている
千蔭や雅澄の解釈を挙げ、しかしその前提の宣長説を、その検証もなく
ただ「案ずるに」で自説に導くだけだ
そして、歌意は、
「月夜ニナク子規ノ影ノ地上ニウツルヲ見ムト欲シテ庭前ノ草ヲ取除キタリ。イカデ見ム由モガナ」と、ほととぎすの地上に落ちる月影を見るために、草を取り除く、としている
確かに、草が生い茂っていては、霍公鳥の影など、地上には映らないだろう |
| |
『万葉集全釈』
これも、宣長説から始まる、千蔭や雅澄の解釈に、異論を唱えているが、
「草とる」の意が「手にする」とする一般的な語義解釈から、霍公鳥を手にする
そんな解釈も有り得る、としている
しかし、結局は、霍公鳥の泣く夜に、草を刈っているだけの意ではないだろうか、
と落ち着く、その「評」で、
「意味が明らかでないので、許はむつかしいが、右のやうに解すれば全く田舍人の歌」
とし、言葉の表現以上の意味が解らない、ということらしい
|
| |
『万葉集全註釈』
この書のポイントは、『講談社文庫本』と同じく、
草をとっている自分を、誰か見てくれないかなあ、とする点にある
『講談社文庫本』もそうだが、この『全註釈』もまた、異訓はない
それでいて、このような解釈の有り様は、一つの方法としては
原点に還ってみるのもいいのかなあ、と
原点、と言っても、万葉の時代に、と言うのではなく
注釈書が出始めた頃の時代、その頃の人たちが
この歌を、どのように感じていたか
少なくとも、現代のように人の価値観や趣向が多様化している時代ではないだろうから
そんな情報過多に踊らされずに解釈されていた時代...時に振り返ることも必要だ
意識しなくても、どうしても現代人には「現代的な感性」があるのだから... |
| |
|
|
| 【歌意1948】 |
藤の花が、散るのを惜しむからだろう
ほととぎすが、今城の丘を
鳴きながら、越えて行く姿が見えるようだ
寂しそうな鳴き声ではないか... |
丘の近くで、藤の花が散りそうな季節を憂鬱そうに眺めやる
そんな作者の心に共鳴するかのように、ホトトギスが鳴きながら
丘を越えて行く
いや、鳴き声しか聞くことは出来ないのだが
自分が藤の花への惜別を想うとき、ホトトギスもまた
同じように、散るを惜しむ気持ちを感じさせる
ホトトギスが『万葉集』中に詠われるのは、154首
花との取り合わせでは、橘の花が最も多い
そして、卯の花、あやめ...
藤の花は、その次で僅か五首となる
一説では、「藤」は晩春の花であり、早く散るので、その詠い合わせが少ないのだろう
そう言われている
まるで、桜のような「花の命」だが、
桜花に、人は多くの思い入れを擁くように
藤にもまた同じように擁くのだろう
しかし、掲題歌のように、
ホトトギスの、同じような心情を重ねて詠うとなれば
確かに、二者が重なる時期としては、短い
ホトトギスが「鳴きて越ゆなり」...つまり去っていくのか
そして、「藤の花」も、その命を終らせようとする
春の丘にあって、一つの季節の終りに、鳥と花の去り行く想いを
作者は感じ取ったものだろう
あたかも、自身までもが...過ぎ去る季節のように...
【赤人集(成立年時未詳[740年頃])】
| ふちなみの ちらまくをしき ほとときす いまきのをかに なきてこゆらむ |
| 赤人集 224 |
【夫木抄(ふぼくしょう、延慶三年頃[1310年頃])】
| ふちなみの ちらまくをしき ほとときす いまきのをかに なきてゆくらむ |
| 巻第二十一 雑三 9138 赤人 |
【歌枕名寄(うたまくらなよせ、嘉元元年頃[1303年頃])】
| ふちなみの ちらまくをしみ ほとときす いまきのをかに なきてこゆなり |
| 巻第三十三 南海道一 8555 |
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1948] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔ふちなみのちらまくおしみほとゝきすいまきのをかをなきてこゆなり 〕
藤浪之散卷惜霍公鳥今城岳叫鳴而越奈利 |
| ふちなみのちらまく 今城岳《イマキノヲカ》八雲抄紀伊 |
| 『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕 |
| |
藤浪之散卷惜霍公鳥今城岳○[口偏+立刀]鳴而越奈利
〔フチナミノチラマクヲシミホトヽキスイマキノヲカヲナキテコユナリ 〕 |
| 今城岳大和なり、第九に注するが如し、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
藤浪之散卷惜霍公鳥今城岳○[口偏+立刀]鳴而越奈利
〔ふぢなみの、ちらまくをしみ、ほとゝぎす、いまきのをかを、なきてこゆなり 〕 |
| ふぢなみは 藤の花を直に詠めり。前にも有。時鳥の藤の花になれ來て鳴かんに散なば疎かるべしとて、散なんことを惜める也。今城岳は大和也。第九卷に注せり。こゝは時鳥の今來ると云に詠みかけたり |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
〔藤浪之、散卷惜《ヲシモ》、霍公鳥、今城岳叫《イマキノヲカヲ》、〕 |
| 今城は大和國高市郡紀(雄略)に新韓《イマキ》又紀〈齊明)に今來と見えたり今本に○[口偏+立刀]とあるは叫の誤なり叫吉弔切驕去聲呼也、鳴而越奈利、 |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕 |
| |
藤浪之。散卷惜。霍公鳥。今城岳○[口偏+立刀]。鳴而越奈利。
〔ふぢなみの。ちらまくをしみ。ほととぎす。いまきのをかを。なきてこゆなり〕 |
| 今城は大和高市郡なり。ほととぎす今來と言ふ心に續けたり。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔藤浪之《フヂナミノ》。散卷惜《チラマクヲシミ》。霍公鳥《ホトヽギス》。今城岳○[口偏+立刀]《イマキノヲカヲ》。鳴而越奈利《ナキテコユナリ》。〕 |
| 今城(ノ)岳は、大和(ノ)國高市(ノ)郡にあり、九(ノ)卷に註す、○歌(ノ)意は、この藤の花は、程なくちり失べきに、もし散失てあらむ跡に來たらば、いかにくち惜からむとて、霍公鳥の、今城の岳を今鳴て越るなりとなり、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔藤浪のちらまくをしみほととぎす今城のをかをなきてこゆなり 〕
藤浪之散卷惜霍公鳥今城岳○[口偏+刂]鳴而越奈利 |
| 今城は大和の地名なり。略解に『ホトトギス今來といふ心につづけたり』といひ、古義にも今城ノ岳ヲ今鳴テ云々と釋けるは非なり。いひかけにあらず。もし今來テ今城ノといふべきをつづめたるならむにはただ今城ノ岳ニナクナリといふべく、コユナリとまではいふべからず。さて今城(ノ)岳《ヲカ》は藤の多かりし處とおぼゆ |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔藤浪の 散らまく惜しみ ほととぎす 今城の岳を 鳴きて越ゆなり〕
藤波之《フヂナミノ》 散卷惜《チラマクヲシミ》 霍公鳥《ホトトギス》 今城岳○[口偏+立刀]《イマキノヲカヲ》 鳴而越奈利《ナキテコユナリ》 |
藤ノ花ガ散ルノヲ惜シガツテ、郭公ハ今城ノ岡ヲ鳴キナガラ飛ビ越シテ行クヨ。
○今城岳○[口偏+立刀]《イマキノヲカヲ》――今城の岳は大和國高市郡、今は吉野郡に編入されてゐる。寫眞は辰己利文氏寄贈。卷九に妹等許今木乃嶺《イモラガリイマキノミネニ》(一七九五)とあるのは異なつてゐる、この地名を今來にかけて、霍公鳥が今來て、今城の岳を鳴いて越えるやうに、略解・古義に解してゐるが、かけ言葉らしい語調になつてゐない。
〔評〕 今城の岡は藤の花の多いところと見えるが、作者がそのほとりにゐて、それを觀賞してゐる時に、霍公鳥の聲を聞いてよんだのであらう。優しい氣分の作である。
|
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔ふじなみの ちらまくをしみ、 ほととぎす いまきのをかを なきてこゆなり〕
藤浪之 散巻惜 霍公鳥 今城岳叫 鳴而越奈利 |
【訳】藤の花の散るのを惜しんで、ホトトギスは、今城の岡を鳴いて越えて行く。
【釈】藤浪之 フヂナミノ。 フヂナミは、ここではその花をいう。今城岳叫 イマキノヲカヲ。今城の岡は、奈良県吉野郡。吉野川のその郡内での西端の右岸にある。高市郡を古く今木郡と言ったのは、新しい宮の造営された地の意であつて、イマキは新宮をいう。そのある岡で、明日香にその名の岡があるかもしれない。叫は、訓假字としてヲに使用されている。
【評語】ホトトギスが藤の花の散るのを惜しんで鳴くように歌つているのは、梅花の散るのを惜しんで鶯が鳴くというのと同様の手段だ。歌は平易で、今城の岡の初夏の情景が描かれている。 |
|

 |
掲載日:2014.03.10.
| 夏雑歌 詠鳥 |
| 藤浪之 散巻惜 霍公鳥 今城岳○ 鳴而越奈利 ○[口偏+立刀] |
| 藤波の散らまく惜しみ霍公鳥今城の岡を鳴きて越ゆなり |
| ふぢなみの ちらまくをしみ ほととぎす いまきのをかを なきてこゆなり |
| 巻第十 1948 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【赤人集】〔224〕
【夫木抄】〔9138〕
【歌枕名寄】〔8555〕
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1948】語義 |
意味・活用・接続 |
| ふぢなみの[藤浪之] |
| ふぢなみ[藤波・藤浪] |
藤の花房が風に靡いている様子を波に見立てていう語・藤の花 |
| ちらまくをしみ[散巻惜] |
| ちらまく[散らまく] |
四段「散る」の未然形「散ら」に、助動詞「む」のク語法 |
| ほととぎす[霍公鳥] |
| いまきのをかを[今城岳○]○[口偏+立刀] |
| いまき[今城] |
[地名]奈良県吉野郡大淀町今木、京都府宇治市彼方の離宮山とも |
| なきてこゆなり[鳴而越奈利] |
| こゆ[越ゆ] |
[自ヤ下二・終止形]越える・通り過ぎる・上回る |
| なり[助動詞・なり] |
[伝聞推定・終止形]~ようだ・~のが聞こえる |
終止形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [ふじなみ] |
藤の花、その花房が風に揺れるさまを波に見立てていう
藤は、蔓性の落葉樹、マメ科
山野に自生し、他の木などに右巻きに巻きついて幹を伸ばす
葉は奇数羽状複葉、四、五月頃紫または白色の蝶型の花が総状花序をなして垂れ下がる
花房は30~90センチくらい、秋になると豆果がなる
藤蔓の繊維で布を織り作業着などに用いられ「藤衣」と称された
|
| |
| [いまきのをか] |
この地は、大方推定はされるが、「未詳」とする書もある
仮に、現在の吉野郡大淀町今木付近の岡、とすると
飛鳥藤原の地から吉野へ入るコースの一つ、吉野口迂回コースの途中にあたる |
| |
| [いまき] |
近年の注釈書である、
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕も、
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕もまた、
この「いまき」が「今来た」と、地名の「今城」の掛詞だとは解していない
ただし、同様の「全集本」でも、
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕は、「今来」と「今城」を
はっきりと、その「歌意」に載せている
しかし、江戸時代の『童蒙抄』などにも見られるように、
その時代では、「掛詞」だと解する当時の諸注が多いのでは、と思う
『略解』『古義』がそうだが、
大正年間の『新考』になると、その解釈を否定し始める
『全釈』では、掛詞らしい語調になっていない、と一蹴する
書もある |
| |
| [なり] |
伝聞推定の助動詞「なり」の、本来の意味は、
音や声が聞こえることから、推定する意になる
古語辞典を引くと、「なり」の語源が載っていた
「なり」は、「めり」が視覚で推定する意を持つのと対照的に、聴覚で推定する意を表す。「なり」に付く動詞は、上代では、音に関連しているものがほとんどなので、「なり」の語源は、「音(ね)」または「鳴る」の「な」に「あり」が付いたものではないかと推定されている。この、音を手掛かりに推定する「~のが聞こえる」のような意がもととなって、「~そうだ・~ということだ」の伝聞を表す意が生じ、「なり」の付く動詞も音に関連のないものが現れたと考えられる。
「平家物語」<巻六>にある今様の名手大納言資賢の逸話は、この「なり」の伝聞的意味と「き」の経験的意味とを対照させた話しとして有名である。一時信濃に流されていた資賢が、許されて帰京した際、後白河法皇の前で信濃に縁のある今様を歌ったときのことである。
『大納言拍子取って、[信濃にあんなる木曽路川]といふ今様を、これは見給ひたりしあひだ(=ご覧になったので)、[信濃にありし木曽路川]と歌はれけるぞ、時に取っての高名なる」《平家物語六・嗄声》
実際に自分が木曽川を見ていたので、伝聞の「あんなる」を経験の回想の「ありし(「し」は「き」の連体形)」に変えたというのである。 |
|
| |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日~] |
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
[本文]「藤浪之 散巻惜 霍公鳥 今城岳○[口偏+刂] 鳴而越奈利」
「フチナミノ チラマクヲシミ ホトトキス イマキノヲカヲ ナキテコユナリ」 |
| 〔本文〕 |
| 「浪」 |
『元暦校本・類聚古集』「波」 |
| 〔訓〕 |
| チラマクヲシミ |
『神田本(紀州本)』「み」ノ右ニ「キ江」アリ。「惜」ノ左に「モヲシ」アリ |
| 『西本願寺本・細井本・神宮文庫本』「チラマクオシミ」 |
| イマキノヲカヲ |
『元暦校本』「いまきのをかに」。「に」ニ朱ノ合点アリ。ソノ右ニ赭「ヲ」アリ |
| 『西本願寺本・細井本・神宮文庫本』「イマキノオカヲ」 |
| ナキテコユナリ |
『元暦校本』「なきて○◎」。「○」ノ右ニ「こゆ」アリ。「○◎」ノ左ニ赭「スクナリ」アリ
|
| 『細井本・神宮文庫本』「ナキテコエナリ」 |
| 『西本願寺本』「オキテコユナリ」 |
| 〔諸説〕 |
| ○今城岳○[口偏+刂] 『万葉考』「『口偏+刂』」ハ「叫」 |
|
| |
| 【左、資料について】 |
『拾穂抄』
ここで「今城岳《イマキノヲカ》八雲抄紀伊」とあるのは、
十三世紀鎌倉時代の順徳天皇が当時の歌論を集大成した歌論書「八雲抄」のことだろう
私は、全くその知識はないが、この記し方は、
その歌論書には、今城岳に「イマキノヲカ」の訓がある、と言う意味なのだと思う |
| |
『代匠記』
この巻九は、〔1799〕歌のことで、『代匠記』でのその歌の注釈を載せる(【】は編集)
| 【挽歌 / 宇治若郎子宮所歌一首】 |
| 妹等許今木乃嶺茂立嬬待木者古人見祁牟 |
イモラカリイマキノミネニナミタテルツママツノキハフルヒトミケム
|
| いもらがり いまきのみねに しげりたつ つままつのきは ふるひとみけむ |
| 【巻第九 1795(国歌大観) 挽歌 宇治若郎子】 |
| 茂立、〔官本、茂或作並、〕 |
| 發句は妹が許へ今來たと云意におけり、今木の嶺は大和國高市郡なり、齊明紀云、四年五月皇孫建王薨、今城谷上起殯而收、天皇不忍哀、傷慟極甚、詔群臣曰、萬歳千秋之後、要合葬於我陵、輙作歌曰、伊磨紀那屡《イマキナル》、乎武例我禹杯爾《ヲムレガウヘニ》、倶謨娜尼母《クモダニモ》、旨屡倶之多々婆《シルクシタタバ》、那爾柯那○柯武《ナニカナゲカム》、又云、十月幸紀温湯、天皇憶皇孫建王愴爾悲位、乃口號曰、耶麻古曳底《ヤマコエテ》、于瀰倭○留騰母《ウミワタルトモ》、於母之樓枳《オモシロキ》、伊麻紀能禹知播《イマキノウチハ》、倭須羅○麻自珥《ワスラユマジニ》、欽明紀云、七年秋七月倭國今來郡言云々、此外雄略紀皇極紀孝徳紀等に見えたり、新の一字をもイマキとよめり、昔三韓の人の徳化を慕ひて渡り來けるをおかせ給へる故に此名あり、一説に紀伊國と云説ある故に今慥かに和州なる證を出せり、茂立は今按シゲリタツと讀べし、嬬待木とは松の木とのみ云ひては字の足らねばかくは云へり、石上袖振川と云類なり、古人見祁牟とは稚郎子皇子の宮所は唯跡をのみ申傳ふるに、今木嶺の松は昔の人もかくこそ見けむを今も替らずして茂りて立るよと感概を起すなり、又は皇子の宮の中より御覽ぜられけむと云意にや、 |
契沖は、『日本書紀』既述の「イマキ」を持ち出して、「いまき」が大和国という
そして、この歌〔1799〕でいうように、掲題歌の「イマキ」もまた、ということだろう
それに、この時代の常識なのかもしれない、「いまき」は掛詞と認識されている
|
| |
『童蒙抄』
この解釈は、現代の解釈とは違うようだ
ホトトギスは、藤の花が散ると疎になるので、散ることが惜しまれる、というのだと思う
先の『代匠記』をそのまま継いだように、〔1799〕に用例をいい、やはり掛詞とする |
| |
『万葉考』
真淵も、それまでの注釈書を引き継ぐかのように、
『日本書紀』から「いまき」を比定する
しかし、これまでと違うのは、「イマキノヲカヲ」の「ヲ」の原文誤字説を唱えたこと
『校本万葉集』にもあるように、この「叫」は、真淵説から始まったようだ |
| |
『略解』
この注釈書も、「当時の定説」を簡単に記しているだけだ |
| |
『古義』
雅澄の解釈に、何だか初めて「ホトトギス」の「心情」が述べられたのではないだろうか
勿論、それまでも同じような気持ちは認識されていただろうが
注釈書に、はっきりと書かれていたものではなかった
曖昧な表現や、「いまき」の比定だけに言及したり...
この藤の花が散るのは、惜しいといって、今ホトトギスが、鳴き越えて行く
そう、惜しい、と思うのが、「ホトトギスの心情」だと、はっきりと述べられている |
| |
『万葉集新考』
この注釈書の最大の魅力は、ことごとく『略解』や『古義』を批評することにあるようだ
この『新考』の時代は、巨人・真淵の流れを汲む千蔭や雅澄が、
再検証される時代だったのだろうか
井上通泰は、「いまき」には同意しながらも、「掛詞」には、はっきりと理由を述べる
「今来て、今鳴く」ならば「越ゆ」の表現はおかしい、と
「イマキノヲカニ ナクナリ」
確かに、言われてみれば...そんな気もする |
| |
『万葉集全釈』
前述したが、掛詞の語調になっていない、との評
そして、ホトトギスが、藤の花の散るのを惜しむ、という解釈
大正昭和頃の、こうした江戸時代の解釈への否定が、
今の定説になっていったのかもしれないが、
何故、そうなのか、その説明は、こうした注釈書では無理なのだろうか
もっと違う分野の、たとえば「歌学」の分野とかでないと
注釈書の範囲では、語り切れない、ということなのだろうか
|
| |
『万葉集全註釈』
なるほど、鶯が梅の花の散るのを惜しみ鳴く...歌を詠う者は
こうした感情移入が優れている
鳥と花の詠い合わせには、ホトトギスや鶯ばかりではなく
そのような意識を持って、読むことも必要なのかな、と気づかされる |
| |
|
|
| 【歌意1949】 |
朝霧が、幾重にも山間に立ち込めるように
多くの峯を翔け抜けて、ホトトギスが
卯の花の咲く辺りを通ってやって来て
鳴きながら、そこもまた飛び去ってしまった
(また戻ってくるだろうか) |
最後に「(また戻ってくるだろうか)」という言葉は、語ることもないものだ
しかし、待ち望んでいたホトトギスが、やっと訪れて、過ぎ去ってしまった
作者の根底にある気持ち、いやこの歌に触れた者の気持ちとしては
また来るのを、待っているぞ、と伝えることが、本意だったように思う
この気持ちがなければ、それこそ「叙景歌」で終ってしまう
よく、ホトトギスと卯の花は、もっとも似合う取り合わせだ、と言われる
だから、実景かどうか解らないが
ここに「卯の花」を用意したことで、その「風物」としての役割は果たしている
しかし、「こえきぬ」とか「こゆらし」、あるいは「こえけり」とするのは
そこで、終らないことを詠っている
『評釈』のような感傷こそ、過ぎるかもしれないが
それに近いものがあってもいいと思う
山を幾重も越えて、やって来る
卯の花が咲く野辺も越えて、飛び去ってゆく
目を閉じ、この歌を諳んじると、とてつもない奥行きのある空間が浮んでくる
人がいる里をも飛び去って、翔け抜けてゆく
あんなに待ち焦がれていたのに、そんな気配りなどお構いなしに...
だから、一つの枠には収まらない、広さ、奥行きを感じてしまう
これと対照的な歌が、下に載せる【赤人集】の一首だ
この歌では、山を越えてやって来たホトトギスが、
卯の花の繁みに隠れ、鳴く声だけが聞こえてくる
おそらくそんな歌意だと思う
ここでは、ホトトギスは、飛び去るのでもなく
その一時的な終着点を、卯の花の辺りにしている
「赤人集」と「万葉歌」との関係は、私には解らないが
どちらかの歌を基にして、新しく創作したことは理解できる
しかも、その歌意を、大きく変えて...
私でも感じられることは、この「赤人集」の歌であれば
それこそ、やっと里にホトトギスがやって来て、今鳴いているぞ
と、多くの書が言うように「ほととぎすが、ようやく訪れた歓びを詠った」ものだろう
しかし、掲題歌の「万葉歌」は、
そんな「待ち人」の気持ちなど斟酌しない
ほととぎす自身が、確かに叙景歌のように描かれるのだが
そこには、「待ち人」をも巻き込んで、大きな空間を見せてくれる
どちらがいい歌か、などとは解らないが
どちらが好きな歌か、と問われれば、
私は、「万葉歌」の方がはるかに好きだ
【赤人集(成立年時未詳[740年頃])】
| あさきりの やへやまこえて ほとときす うのはなかくれ なきこえくなり |
| 赤人集 225 |
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1949] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔あさきりのやへ山こえてほとゝきすうのはなへからなきてこゆらし 〕
旦霧八重山越而霍公鳥宇能花邊柄鳴越來 |
| あさきりのやへ山越て 卯花へからは卯花の邊よりといふ也 |
| 『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕 |
| |
且霧八重山越而霍公鳥宇能花邊柄鳴越來
〔アサキリノヤヘヤマコヱテホトヽキスウノハナヘカラナキテコユラシ 〕 |
| 一二句のつゞき上に旦霞八重山と云に同じ、宇能花邊とは卯花のほとりなり、越來は今の點叶はずコエケリと讀べし、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満・信名、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
旦霧八重山越而霍公鳥宇能花邊柄鳴越來
〔あさぎりの、やへやまこえて、ほとゝぎす、うのはなべから、なきてこえきぬ 〕 |
| 旦霧の八重山越えて 前に朝霞共よめる意に同じ。幾重もの山を越えて也。卯の花になれ來るもの故、越來る山も卯の花の咲たるあたりより鳴來ると也。何の意無き歌也
|
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
〔旦霧(ノ)、上に同言あれば是も霞ならんかされど既いふ如く霧は秋とのみおもへるは後なれば朝霧と云も嫌なし 八重山越而、霍公鳥、宇能花邊柄《ベカラ》、今本宇を字に誤る一本によりて改つ
鳴(テ)越來《コエキヌ》、」 越來を今本にこゆらしと訓るは誤なり〕 |
| |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕 |
| |
旦霧。八重山越而。霍公鳥。宇(宇ヲ字ニ誤ル)能花邊柄。鳴越來。
〔あさぎりの。やへやまこえて。ほととぎす。うのはなべから。なきてこえきぬ。〕 |
朝ギリノも、上の朝霞の如く、ヤヘと言ふへ懸かる枕詞なり。是れは霧は霞の字の誤なるべし。ウノ花ベカラは、卯花の咲きたる方よりと言ふなり。
參考 ○旦霧(古)アサガスミ「霧」を「霞」の誤とす(新)アサギリノ ○八重山越而(新)ヤヘヤマコユル「而」を衍とす ○鳴越來(代)コエケリ(考)略に同じ(古)ナキテコユ「成」ナリ(新)ナキテコユラシ「來」を「良之」の誤とす。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔旦霧《アサカスミ》。八重山越而《ヤヘヤマコエテ》。霍公鳥《ホトトギス》。宇能花邊柄《ウノハナヘカラ》。鳴越來《ナキテコエキヌ》。〕 |
| 旦霧は、本居氏云、霧は霞の誤なり、○宇能花邊柄《ウノハナベカラ》は、卯(ノ)花の咲るあたりをと云が如し、柄《カラ》は從《ヨリ》と云に同じ、十一に、守山邊柄《モルヤマヘカラ》、同卷に、直道柄《タヾチカラ》、十三に、自此巨勢道柄《コヨコセチカラ》、同卷に、此山邊柄《コノヤマヘカラ》、十四に、安受倍可良《アズヘラ》、十七に、乎可備可良《ヲカビカラ》、などあり、又古今集に、浪(ノ)音の今朝から殊にきこゆるは、又かのかたにいつからさきに渡りけむ、又浪の花おきからさきてちりくめり、拾遺集に、紅葉に、衣の色はしみにけり、秋の山からめぐり來し間に、かげろふの日記に、去年から山こもりして侍るなる、枕冊子に、このたびやがて竹のうしろから舞出て云々、などあるも、みな徒《ヨリ》と云に同じ、又催馬樂本滋に、毛止之介支支比乃名加也萬牟加之與利牟加之加良名乃不利己奴波《モトシゲキキビノナカヤマムカシヨリムカシカラナノフリコヌハ》、伊萬乃與乃太女介不乃比乃太女《イマノヨノタメケフノヒノタメ》、とあるにて、加良《カラ》と與利《ヨリ》とは、同意なるを知べし、また歩《カチ》よりと云ことをも落窪物語に、かちからといへり、さてこゝの柄《カラ》は輕くて、乎《ヲ》と云辭に通はしたり、○來は、草書の成を來と見て誤しものなり、ナリとよむべし、○歌(ノ)意かくれたるところなし、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔(旦霧《アサギリノ》)八重山越《ヤヘヤマコユル》而〔□で圍む〕ほととぎすうの花邊から鳴越來《ナキテコユラシ》 〕
且霧八重山越而霍公鳥字能花邊柄鳴越來 |
上にアサガスミヤヘ山コエテヨブコドリといへる歌あるによりて略解には『霧は霞の誤なるべし』といひ、古義も此説に從ひてアサガスミとよみ、訓義辨證下卷(二五頁)には
此歌霧にてもきこえぬにはあらねど猶此上にアサガスミヤヘヤマコエテヨブコドリとあると全く同じつづきの歌なれば霞とせんこそよからめ。されど各本皆霧とありて霞とかける本はあることなし。故按ふに文字をば此まゝにてカスミとよむべきにや。然いふは承暦三年の鈔本金光明最勝王經音義といふ書に霧〔音武、加須美〕とあればなり。本集卷二に秋ノ田ノ穗ノヘニキラフアサ霞とあるも霧をカスミといへり。古へ霧と霞とは言の上にては春秋共に通はしいへることあれば文字もまた通はしかけるなるべし
といへり。上なる歌と同一ならざるべからざる理由なし。字のまゝにアサギリノとよみて可なるにあらずや ○結句を舊訓にナキテコユラシとよめる を契沖はコエケリに改め、略解はコエキヌに改め、古義は來を成の誤字としてコユナリとよめり。いづれにしても上に越而といひて更に越とはいふべきにあらず。案ずるに越而の而を衍字、來を良之などの誤として
あさぎりのやへやまこゆるほととぎすうのはなべからなきてこゆらし
とよむべし ○カラはヨリに同じ。古義にヨリの意なる例又ヨリと對用せる例を擧げたり。さればウノハナベカラは山中ノ卯ノ花ノホトリヲといふ意なり ○且は旦、字は宇の誤なり
|
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔朝霧の 八重山越えて ほととぎす 卯の花べから 鳴きて越え來ぬ〕
旦霧《アサギリノ》 八重山越而《ヤヘヤマコエテ》 霍公鳥《ホトトギス》 宇能花邊柄《ウノハナベカラ》 鳴越來《ナキテコエキヌ》 |
(旦霧)八重ニ重ル山ヲ飛ビ越シテ、郭公ハ卯ノ花ノ咲イテヰルアタリヲ鳴イテ、飛ビ越シテ來タ。
○旦霧《アサギリノ》――前に旦霞八重山越而《アサガスミヤへヤマコエテ》(一九四一)とあるのと同じく、この旦霧は枕詞である。しかし略解に、霧を霞の誤であらうとあるのはよくない。猥に改むべきでない。○鳴越來《ナキテコエキヌ》――舊訓ナキテコユラシ、代匠記初稿本ナキテコエケリとあるが、又一にナキテコエキヌとしてある。古義に來を成の誤としてナキテコユナリとしたのは獨斷にすぎる。
〔評〕 第四句の宇能花邊柄《ウノハナベカラ》で、歌が全く優美化されてゐる。第二句と第五句とに越《コエ》を用ゐたのは故意か偶然か。重複の嫌がないでもない。
|
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔あさぎりの やへやまこえて ほととぎす うのはなべから なきてこえけり(きぬ)〕
旦霧 八重山越而 霍公鳥 宇能花邊柄 鳴越来 |
【訳】朝霧の幾重にもかかつている山々を越えて、ホトトギスは、卯の花の咲いている邊を通つて、鳴いて越えて行つた。
【釈】旦霧 アサギリノ。枕詞。実景を直に枕詞に利用している。前の「旦霞(アサガスミ) 八重山越而(ヤヘヤマコエテ)」(1941)と同手段。その條参照。
宇能花邊柄 ウノハナベカラ。カラもユと同じく、それを経過しての意に使つている。卯の花邊は、今作者のいる処である。但しその用例は、いずれも邊もしくは道のような、地理上の名辞に接続している。これが初出であるが、集中九例あり、ユに比べて口語なので、多く使われなかつたのだろう。「人祖(ヒトノオヤノ) 未通女兒居而(ヲトメゴスヱテ) 守山邊柄(モルヤマベカラ) 朝々(アサナサナ) 通公(カヨヒシキミガ) 不来哀(コネバカナシモ)」(巻第十一、2360)、「直道柄(タダヂカラ) 吾者雖来(ワレハクレドモ)」(同、2618)。
鳴越来 ナキテコエケリ。 ナキテコエケリ(代匠記、初)、ナキテコエキヌ(同)。四句をよく吟味すればコエケリの方がよいようだ。
【評語】朝霧のかかつている山々を、ホトトギスの鳴いて越えて来て、そうして今卯の花の咲いているあたりを越えたことを歌つている。これも情景のよく描かれている作である。 |
|
| |
| 【上、資料について】 |
『古義』
この時代前後、真淵や千蔭など、積極的な「訓」の考察の時代のように感じられ
その中でも、この雅澄の見識は、私には心地よい
しかし、それが独善的な、と否定される評価もまた多い
学者であればこそ、そのような批評もあるのであって
しかし、素人がそれほど掘り下げて一首を鑑賞するのでなければ
結局は、それぞれが独善的になってしまうものだ
この頃の、こうした注釈書には、とにかく安易な「誤字説」「誤写説」が多く
その点だけは、私も素直に受け入れられない
ただ、この一首の解説でも解るように、雅澄の取り組み方は、
かなり広範な照査を行っている
その点が、同時代の他の学者との違いだと思う
今日、古書店からネットで注文した『万葉集古義』全十巻が届いていた
大正三年の再版本だが、その古色然とした風格に、圧倒された
確かに、汚れも目立つが、それが一層の「風格」を醸し出している
頁を捲る...いい香りがする(ような気がする)
不思議なものだ
以前の、それもほんのつい最近までの私なら
このような文体の本は、読む気にもならなかっただろう
しかも、おそらくまともに理解も出来なかったはずだ
しかし、今はどの頁を開いても、かなり理解できるような気がしている
実際、声に出しては、すらすらとは読めないだろうが、
目で追いかけても、難解だと思うところは、今のところなかった
もっとも、まだ数ページのことだけど...
さて、楽しみが「目の前」にあるのも、いいものだ |
| |
『万葉集新考』
ここでも、『略解』『古義』を俎上にして、注釈の展開をする
大正時代の学者にとって、やはり『略解』や『古義』は、
最も基本にすべき「注釈書」なのだろう
それらを、認めるか否定をするか、そんな時代だったような気がする
ここで、『古義』が「霧」のままで、「かすみ」と訓むことの理由が解った
雅澄は、宣長が云うには「霧」は「霞」の誤字だから、とまでは言うが
では「霧」の表記で「かすみ」と訓むことには言及していない
この『新考』で、その根拠も推察できる |
| |
『万葉集全釈』
「略解に、霧を霞の誤であらうとあるのはよくない。猥に改むべきでない」この姿勢がいい
また、「古義に來を成の誤としてナキテコユナリとしたのは獨斷にすぎる」
どうも、それまで大きな影響を与えてきた『略解』や『古義』への、その独断的な姿勢に
ようやく現代に繋がるような考証の仕方が始まったようだ
|
| |
『万葉集全註釈』
この書の歌意は、『評釈』に倣ったかのように、
ホトトギスが、越え来て、過ぎ去ってしまった、という
卯の花が咲いているのは、今作者がいるところ
それが従来の解釈とは違う
だから、その卯の花の辺りからも、過ぎ去ってしまった、ということになる
「四句をよく吟味すればコエケリの方がよいようだ」という「吟味」とは
このような「歌意」が前提になっているのではないか、と勘ぐってしまう |
| |
|
掲載日:2014.03.11.
| 夏雑歌 詠鳥 |
| 旦霧 八重山越而 霍公鳥 宇能花邊柄 鳴越来 |
| 朝霧の八重山越えて霍公鳥卯の花辺から鳴きて越え来ぬ |
| あさぎりの やへやまこえて ほととぎす うのはなへから なきてこえきぬ |
| 巻第十 1949 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【赤人集】〔225〕
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1949】語義 |
意味・活用・接続 |
| あさぎりの[旦霧] 〔枕詞〕「八重」にかかる |
| やへやまこえて[八重山越而]朝霧が「八重」に立ち込める、「幾重」にも重なり合う山並み |
| ほととぎす[霍公鳥] |
| うのはなへから[宇能花邊柄] |
| から[格助詞] |
[経由点]~を通って・~を |
体言につく |
| なきてこえきぬ[鳴越来] |
| き[来(く)] |
[自カ変・連用形]来る |
| ぬ[助動詞・ぬ] |
[完了・終止形]~た・~てしまう・~てしまった |
連用形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [あさぎりの] |
原文「旦霧」、既出〔書庫-13、2013年12月4日〕の歌〔1945〕では、
初句、第二句「旦霞 八重山越而」(あさかすみ やへやまこえて)の「旦霞」に、
「霞」と「霧」の諸本、諸注があり、大方は「旦霧」に従っている、と書いた
確かに、この掲題歌と「霞」、「霧」の違いだけの初句、第二句なので
どちらが本来の歌なのか解らないが、一つの拠り所として、
この掲題歌が、〔1945〕の場合と違って、
例外なくどの古写本でも「霧」としていることから、では〔1945〕が誤写だろう、と
それに、「霞」は、「春」に詠ったものが圧倒的に多く、「あさぎり」が受け入れられた
ただ、「古写本」そのものも、またオリジナルを幾度も写本を繰り返したものであり
結局は、確定できないものは、原文そのままに訓むべきだと思う
そのことは、〔1945〕のところでも書いたが、
この掲題歌に限っては、まったくそんな問題もなく、そろって「旦霧」だ
ただ、やはり「霧」という「語」が、「秋」だということで、「霞」の誤写説もある
それを言えば、「霞」だって「春」だ
さらに、この時代には、
「春は霞、秋は霧」という観念も定着していなかった、とされている
左の「資料」で、面白い経緯が知られる
真淵の『万葉考』で、「霧」は「秋」というが、そう思うのは後のことだ、といい
しかし、その流れを汲む千蔭『略解』や、
また『古義』においては、本居宣長が「霧」は「霞」の誤りだ、とその説を採っている
さらに次代の井上通泰『新考』で、
明治時代の国文学者・木村正辞『訓義辨證』(下卷)の解釈を持ち出していることだ
この学者は、『万葉集美夫君志』〔木村正辞、明治34~44年成〕を著しているが
私はまだ目にしたことがない
だから、左のように、「霧」の表記のままでも「かすみ」と訓める、とする解釈が
単に宣長あたりから引き継いだことだろうしか想像できない者にとって
このよう検証して『古義』は「霧」を「かすみ」と訓んだものか、と
具体的に、知ることができた
|
| |
| [から] |
この語は、「より」と似た意味を持つが、中古までは「より」の方が多く使われた
「から」は中世以降さかんに使われ、現代に至っている
この二つの差は、「より」には比較の基準の用法があるからだ
だから、形容詞・形容動詞とともに用いられるのは、「より」に限られる
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕には、
石垣謙二「助動詞の歴史的研究」をあげ、「から」は「まにまに」の意に近い、とする
その歌意では、殆どの注釈書が「経由点」で解釈している中、
「卯の花の咲いている辺りに沿って...」
副詞「まにまに」の語義は、事の成り行きに従うこと・~のままに、とあるので
卯の花が咲いている辺りを、単に通過するのではなく、
その咲く辺りに従って、鳴きながら飛んでいる、という意味を持たせたのだろう
しかし、この岩波の叢書の前の、『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕では、
従来の「経由点」そのままの歌意を載せている
私の感覚では、同じ出版社の叢書の『新大系』であれば、
ある程度の方向性があると思っていたが、それは大きな勘違いだった
そもそも、この40年の隔たりがある叢書では、全く別の「注釈書」と考えるべきだった
勿論、校訂者もすっかり変わっている
ただ、同じく岩波の新たな「注釈書」が最近「文庫本」で出ており
それは、『新大系』の「新校訂版」で、校訂者も同じだ
まだ全巻揃っていないが、今のところ半年サイクルで出版されており
今年の一月に第三(巻九~十二)の出版があり、第四は、七月らしい
文庫本版では、講談社(中西進)と同じように本格的な注釈書になりそうだ
早速、この歌を確認してみたら、
『新大系』に挙げられていた「助動詞の歴史的研究」には触れられておらず
微妙にその歌意も曖昧になっていた
|
| |
| [なきてこえきぬ] |
原文「鳴越来」の「来」は、回想の助動詞「けり」にあてる例も多くある
そのことから、「鳴きて越えけり」と訓む説もある
左の『万葉代匠記(精撰本)』では、定訓を載せたあと、
「越來は今の點叶はずコエケリと讀べし、」と述べている
ただし、その根拠は説明されていない
「こえけり」として解釈すると、「超えてしまった」になるのではないだろうか
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕が、
「渡り鳥であるほととぎすの、この土地を去らねばならぬ時のあはれを云った歌」とし、
「ほととぎすは八重山を越して遠く去るのであるが、その時には、深い縁を持ってゐる卯の花の咲いてゐる辺りを通って、名残を惜しんで鳴いた上で、八重山を越えて去ったといふのである」
ぐっとくる魅力的な解釈だ
しかし、本当にそう読めるのだろうか
その前提は「けり」とした場合に限るのだから、
「こえきぬ」が「こえけり」と決まらなければ、受け手の創作になってしまう
『全註釈』では、「けり」としながらも「きぬ」を別訓で書いている
そして、結果だけを述べているが、
「四句をよく吟味すればコエケリの方がよいようだ」としている
その、どんな「吟味」なのか、書かれていないのは、残念だ
私のような単純な者なら、歌意を先ほどの『万葉集評釈』の方がいいので
そうする、と書いただろうが...
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕
契沖が「こえけり」と訓んだものの、旧訓に「なきてこゆらし」とあったのを、
『略解』辺りから「なきてこえきぬ」が次第に定着し始めたようだ
さらに、井上通泰『新考』に書かれているように、単純に「誤写」を言うのではなく、
「いづれにしても上に越而といひて更に越とはいふべきにあらず」として
「なきてこゆらし」とすべきとの主張もある
あらためて思うのだが、こうした「古注釈書」のスタイルが
様々にある、ということだ
内容のことではなく、「スタイル」のこと...書式のようなものだ
まず「定訓」とされているような「訓」を載せ
それから、「自説」を述べる
じっくり読まないと、勘違いしてしまう
安易な拾い読みは、なるべく避けなければならない |
| |
| |
| |
| |
| |
| 【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日~] |
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
[本文]「且霧 八重山越而 霍公鳥 字能花邊柄 鳴越来」
「アサキリノ ヤヘヤマコヱテ ホトトキス ウノハナヘカラ ナキテコユラシ」 |
| 〔本文〕 |
| 「且」 |
『神田本(紀州本)・西本願寺本・細井本・大矢本・京都大学本・天治本・神宮文庫本』「旦」 |
| 「重」 |
『元暦校本』「里」墨ニテ消セリ。右ニ墨「重」アリ |
| 「字」 |
『元暦校本・類聚古集・神田本(紀州本)・西本願寺本・細井本・大矢本・京都大学本・無・附・天治本・神宮文庫本』「宇」 |
| 「柄」 |
『大矢本』「栖」。
『近衛本』底本ニ同ジ |
| 〔訓〕 |
| アサキリノ |
『類聚古集』「あさきりに」 |
| ヤヘヤマコヱテ |
『元暦校本・類聚古集・天治本』「やへやまこえて」。
『神田本(紀州本)・西本願寺本・大矢本・神宮文庫本・京都大学本・附』「ヤヘヤマコエテ」 |
| ウノハナヘカラ |
『天治本』「うのはなかへゝ」。「かへゝ」ヲ消セリ。右ニ「へから」アリ。 |
| コユラシ |
『元暦校本』「○◎」。「○」ノ右ニ「こゆ」アリ。「○◎」ノ左ニ赭「スクナリ」。
『類聚古集』「すくなり」。
『神田本(紀州本)』「コユナリ」。「ナリ」ノ左ニ「クル」アリ。漢字ノ左ニ「スクラシ」アリ。
『細井本』「コヱラシ」。
『神宮文庫本』「コエラシ」
|
| 〔諸説〕 |
| ○且霧、アサキリノ。『古義』本居氏「霧」ハ「霞」ノ誤。訓「アサカスミ」。○字能花邊柄、『略解』「字」ハ「宇」ノ誤。○鳴越来、ナキテコユラシ。『代匠記(初稿本)』、「ナキテコエケリ」。又ハ「ナキテコエキヌ」トス。『古義』、「来」ハ「成」ノ誤。訓「ナキテコユナリ」。 |
|
| |
| |
| 【左、資料について】 |
『拾穂抄』
旧訓となる「なきてこゆらし」
この「こゆらし」、下二段「越ゆ」も終止形
現在推量の助動詞「らし」
「こえきぬ」と違うのは、鳴き声を聞くことで、
ホトトギスがやって来たのを確信して思うこと
「なきてこえきぬ」は、あたかも鳴きながらやって来たホトトギスを見たかのようだが、
見えた、ことよりも、すでに鳴き声が来たことを教えてくれてる
訳すとなると、同じようなものだが
これが「歌」であれば、作者も、聞き手も、その人の持つ感性次第、ということか
後に言われるようになる「けり」とは、意味がまるで違ってくる |
| |
『代匠記』
契沖は、「こえけり」と読むべし、という
回想の助動詞「けり」を用いるには、表記上の問題をクリアしなければ、と思う
いくら、「来」が、「けり」に当てられることが少なくない、と言っても
原文の「鳴越来」を素直に見れば、「ないて、こえて、きた」が自然だ
「来」を「けり」と訓む歌を、拾い出しても、「にけり」の用法が多い、と思う
ならば「こえにけり」でもなるのかな
いずれにしても、回想の助動詞には違いないのだから
今、やって来た、とはならない
『評釈』が言うように、越えて来はしたが、もう行ってしまった、のような意味合いだ
|
| |
『童蒙抄』
あっさりとした評価になっている...「何の意無き歌」
単なる叙景歌だと言うのだろうか
前述の思い入れたっぷりの『評釈』のような受け手もあれば、
このようにあっさりと読み過ごす評価もある |
| |
『万葉考』
「こゆらし」を否定するが、何故否定できるのか、そうした説明は
この時代には、それほど厳密に問われることもなかったのだろうか
それとも、四千五百首に及ぶ万葉歌を、それぞれ詳細に注釈付ける余裕もなかったのか
自著における「注釈書」は、結論だけを載せ、
その説明は、別の「書物」にでも載せるのが普通だったのかな
一首一首ごとの説明ではなく、
同じように「定義付ける」必要に応じて、その種の解説書みたいなものが... |
| |
『略解』
訓の解説が重視されている一首になっている
ただし、当時に知られる「訓」の網羅であって、あまりその評価には及んでいない |
| |
| |
|

|
| 【歌意1950】 |
決して、木を高くなど植えたりしない
ホトトギスは、そんな高い木に止り鳴くものだ
そうやって、鳴き響き渡る声を聞くと
どうしても恋心が抑え難くなり、辛くなる
(だから、高い木など植えるものか) |
この歌、他に解釈のしようがないと思っていたが
意外と、別な解釈も出来るものだ
賀茂真淵が、『万葉考』で「意明なり」と述べたことがすべてだ、と思っていたのに...
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕は、
この「恋」を、ホトトギスへの想いと解釈している
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕は、
「時鳥への執心の強さを逆説的に述べた歌」と、歌意の後に付け足している
ホトトギスの鳴き声に、心を癒される、だからホトトギスを大切に思うのだろうが
仮にその想いがあるのであれば、高い木を植えず
ホトトギスがやって来て鳴かないようにする、というのは
何か矛盾しているのでは、と思う
その声を聞きたいからこそ、ホトトギスを愛でるのであって
それが辛いから、というのは...
それが、恋する人へのことであれば、解らなくもない
ホトトギスと違って、双方の想いが交錯するからこそ
その「恋」しさが、常に揺れ動く
しかし、ホトトギスへの「愛着」は、そんな想いではなく
「癒される」ことを望んでのことなのだから
逆に言えば、癒されることを望まない、と言うことになってしまう
それとも、ホトトギスを、「想い人」に重ねて詠ったのだろうか
ならば、普通の解釈でもいいはずだ
癒されるはずのホトトギスの鳴き声に、「想い人」への恋心がさらに増して...
これが、もっとも素直なこの歌の感じ方だと思う
『代匠記』、『全釈』に引用された、大伴坂上郎女の「ほととぎす」の歌
| 夏雜歌 /大伴坂上郎女霍公鳥歌一首 |
| 何奇毛 幾許戀流 霍公鳥 鳴音聞者 戀許曽益礼 |
| 何しかもここだく恋ふる霍公鳥鳴く声聞けば恋こそまされ |
| なにしかも ここだくこふる ほととぎす なくこゑきけば こひこそまされ |
| 巻第八 1479 夏雑歌 大伴坂上郎女 |
〔語義〕
「なにしか」は、「どうして~か・なぜ~か」
「ここだく」は、「こんなにも多く・こんなにもひどく」
「こひこそまされ」は、「こそ~まされ」の係り結びで、「こそ」は已然形で結ぶ |
〔歌意〕
どうして、こんなにもひどく恋しいのだろう
(なのに)ホトトギスの鳴く声を聞くと、恋しさがいっそうつのってしまう |
この歌は、確かにホトトギスの声を聞くと、恋心がいっそうつのる、と言うものだろうが
その点では、『全註釈』がいう、ホトトギスの「感傷を誘う鳥」という固定概念も解る
しかし、この下二句は、掲題歌や、この坂上郎女のように、
慣用句かどうか解らないが、何首か詠われている
しかし、雁であったり、決してホトトギスの「固定概念」とは決められないと思う
また、この歌では、まず「何故こんなに恋しいのか」と詠っている
それは、ホトトギスに誘発されたものではなく
作者のこの時の想いや辛さを背景にしており
そこに、本来なら癒される鳴き声のホトトギスが、鳴くものだから
よけいに、その想いが増してしまった
だから、ホトトギスが「感傷の鳥」とは言えないはずだ
もっとも、『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕は、
ホトトギスの鳴く声を、どうしてこんなにも待ち望むのか、という
これは、これまでのような解釈と違って、ホトトギスの鳴く声に、
人恋しさが、よけいにつのるばかりなのに、と重点を置いている
しかし、次の歌では、まさにホトトギスの鳴く声そのものが「辛い」という
| 夏雜歌/弓削皇子御歌一首 |
| 霍公鳥 無流國尓毛 去而師香 其鳴音手 間者辛苦母 |
| 霍公鳥なかる国にも行きてしかその鳴く声を聞けば苦しも |
| ほととぎす なかるくににも ゆきてしか そのなくこゑを きけばくるしも |
| 巻第八 1471 夏雑歌 弓削皇子 |
〔語義〕
「なかるくに」は、「なくあるくに」の約、「あることがないくに」が直訳
「てしか」は、願望の助詞
|
〔歌意〕
ホトトギスのいない国があれば、行きたいものだ
その鳴く声を聞くと、心が苦しくてしかたないから... |
こう見ると、〔1479〕と〔1471〕の違いがはっきりする
そして、古注で引用する歌が、〔1479〕だけであれば
この掲題歌もまた、同じような「想い」の歌だと思われているのではないか、と思う
つまり、ホトトギスに対して、私がこんなに恋に悩んでいるのに
そんな美しい歌声で歌わないでくれ、よけいに辛くなる
〔1471〕を引用するなら、ホトトギスの鳴き声が、あまりにも人恋しさを誘うので
ホトトギスが来て鳴けないように、そんな高い木は植えない、となる
現代では、どちらでも読む者が自分に素直に感じられる方でいいと思うが
少なくとも、近世までの学者には、前者のように感じられたのだろう
尚、現代の注釈書も多くは、その前者の方に倣っているのが多い
【赤人集(成立年時未詳[740年頃])】
| こかくれて いまそきくなる ほとときす なきひひかして こゑまさるらむ |
| 赤人集 226 |
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1950] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔こたかくはかつて木うへしほとゝきすきなきとよみて戀まさらしむ 〕
木高者曽木不殖霍公鳥來鳴令響而戀令益 |
| こたかくはかつて木うへし 木をこたかくはかつてうへしと也 |
| 『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕 |
| |
木高者曾木不殖霍公鳥來鳴令響而戀令益
〔コタカクハカツテキウヱシホトヽキスキナキトヨミテコヒマサラシム 〕 |
| 令響而はトヨメテと讀べし、トヨミテと點ぜるは令の字に應ぜず、落句は第八に坂上郎女が歌に霍公鳥鳴聲きけば戀こそ益れとよめる意なり、顧况詩云、庭前有箇(ノ)長)松樹、半夜子規來(リ)上(テ)啼 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
木高者曾木不殖霍公鳥來鳴令響而戀令益
〔こだかくは、かつきはうゑじ、ほとゝぎす、きなきならして、こひまさらしむ 〕 |
| 曾木 これをかつて木植ゑしと讀ませたれど、かつて木植ゑしとは不穩詞也。かつ木はと讀べし。此歌はわれに思ひのあるから、霍公鳥の鳴音にいとゞ思ひの増すから、今よりは霍公鳥の宿りとなる木は植ゑじと、郭公をわが思ひあるから疎みたる歌也。疎みながらも、霍公鳥の音を哀れに感嘆せるから、如此よめる意をこめたる歌也
|
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
〔木高者《コダカクハ》、曾木不殖《カツテキウヱジ》、霍公鳥、來鳴令響《キナキドヨメテ》、戀令益《コヒマサラセリ》、」〕 |
| 意明なり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕 |
| |
木高者。曾木不殖。霍公鳥。來鳴令響而。戀令益。
〔こだかくは。かつてきうゑじ。ほととぎす。きなきとよめて。こひまさらしむ。〕 |
| トヨメテは、トヨマセテを約め言ふなり。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔木高者《コタカクハ》。曾木不殖《カツテキウエジ》。霍公鳥《ホトヽギス》。來鳴令響而《キナキトヨメテ》。戀令益《コヒマサラシム》。〕 |
| 曾《カツテ》は、此《コヽ》は俗に堅《カタ》く、或は毛頭などいふ意なり、さてこの言は、初句の上にうつして心得べし、曾《カツテ》木高く木を殖ることはせじといふ意なり、○歌(ノ)意は、木高く木を殖ることは堅くせじ、いかにとなれば、木高く木を殖るときは、ほとゝぎすの其木に來棲て、常に鳴響て、人を戀しく思ふ心を、益らしむればなり、となり、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔木《コ》だかくはかつて木うゑじほととぎす來なきとよめてこひまさらしむ 〕
木高者曾木不殖霍公鳥來鳴令響而戀令益 |
| カツテは決シテなり。されば初二は決シテ高キ木ハ植ヱジとなり。子規は好みて高き木にとまりて鳴くが故にしかいへるなり。結句の上に我ヲシテといふことを加へて聞くべし |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔木高くは かつて木植ゑじ ほととぎす 來鳴きとよめて 戀まさらしむ〕
木高者《コタカクハ》 曾木不殖《カツテキウヱジ》 霍公鳥《ホトトギス》 來鳴令響而《キナキトヨメテ》 戀令益《コヒマサラシム》 |
丈ノ高イ木ハ決シテ私ハ植ヱマイ。何故ナレバ高イ木ヲ植ヱテ置クト、霍公鳥ガ來テ鳴イテ、聲ヲ響カセ人ヲ戀シク思フ心ヲ増サシメルカラ。
○曾木不殖《カツテキウヱジ》――カツテは、すべて、決して、全くなどの意。○戀令益《コヒマサラシム》――我をして人を戀しく思ふ心を、増さらしむといふのである。
〔評〕 戀に惱める人の歌だ。もとより郭公を嫌ふのではない。何哥毛幾許戀流霍公鳥鳴音聞者戀許曾益禮《ナニシカモココダクコフルホトトギスナクコヱキケバコヒコソマサレ》(一四七五)と似たところがある。
|
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔こだかくは かつてき植ゑじ。 ほととぎす 来鳴きとよめて 恋まさらしむ〕
木高者 曽木不殖 霍公鳥 来鳴令響而 戀令益 |
【訳】木高くは決して木を植えまい。ホトトギスが来て鳴いて、恋をまさらせる。
【釈】曽木不殖 カツテキウヱジ。カツテは、決して、全く、すべてなどの意で、下はかならず打消しで受ける。「常者曾 不念物乎」(ツネハカツテ オモハヌモノヲ、巻第七、1069)、「名者曾不告 恋者雖死」(ナハカツテノラジ コヒハシヌトモ、巻第十二、3080)。句切。
来鳴令響而 キナキトヨメテ。トヨメテは、とよましめて。音を立てさせて。
【評語】ホトトギスの声が感傷を誘うものとして取り扱われている。ホトトギスが樹梢に来て鳴きたてるというのである。その鳥の概念が固定している作だ。 |
|
| |
| |
|
掲載日:2014.03.12.
| 夏雑歌 詠鳥 |
| 木高者 曽木不殖 霍公鳥 来鳴令響而 戀令益 |
| 木高くはかつて木植ゑじ霍公鳥来鳴き響めて恋まさらしむ |
| こだかくは かつてきうゑじ ほととぎす きなきとよめて こひまさらしむ |
| 巻第十 1950 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【用例歌】〔1479・1471〕
【赤人集】〔226〕
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1950】語義 |
意味・活用・接続 |
| こだかくは [木高者] |
| こだかく [木高し] |
[形ク・連用形] 梢が高い・木立が高い |
| は [係助詞] |
[とりたて(題目)] ~は 係り結びの「係り」 |
連用形につく |
| かつてきうゑじ [曽木不殖] |
| かつて [曾(かつ)て・嘗て] |
[副詞] (下に打消の語を伴って)全然・決して・今まで |
| じ[助動詞・じ] 係りの結び |
[打消(意志)・連体形]~ないつもりだ |
未然形につく |
| 前に付く動詞「植(う)う」は、ワ行下二段で、未然形は「うゑ」 |
| ほととぎす [霍公鳥] |
| きなきとよめて [来鳴令響而] |
| きなき [来鳴く] |
[自カ四・連用形] 来て鳴く |
| とよめ [響(とよ)む] |
[他マ下二段・連用形] 鳴り響かせる |
| て [接続助詞] |
[確定条件(原因・理由)] ~ので |
連用形につく |
| こひまさらしむ [戀令益] |
| まさら [増さる] |
[自ラ四・未然形] (数量や程度が)増える・強まる |
| しむ [助動詞・しむ] |
[使役・終止形] ~せる・~させる |
未然形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [かつて] |
男性語で、平安時代には、「源氏物語」や「枕草子」などの女流作品には出てこない
なお、近世以降には「かって」と促音にも発音されるようになった
|
| |
| [とよめ] |
現代の注釈書では、ほとんどが「とよめ」となっており
その語義は、他動詞下二段活用の連用形で、「鳴り響かせる」
しかし、左頁の資料を見ると、
旧訓は、どうも自動詞四段活用の連用形「とよみ」だったようだ
その語義は「鳴り響く・響き渡る・騒ぎ立てる」
細かな違いは解らないが、大まかに感じられるのは
他動詞で「とよめ」だと、ホトトギスが「鳴く声」そのものを、
客観的に見ているような感じになり
自動詞で「とよみ」とすると、ホトトギスが、
「鳴き響かせる姿」を見詰めているような気がする
でも、素人にはその違いが正当かどうか、解らない
いずれにしても、古くは「とよみ」だったようだ
『万葉考』の真淵は「どよめ」と濁らせているが、
これは古語辞典によれば、中古末期頃から「どよむ」と言われていたようで
この歌の場合、これもその時代だろうし、真淵はそれを厳格に採用したのだろうか
|
| |
|
| |
| 【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記] |
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
[本文]「木高者 曽木不殖 霍公鳥 来鳴令響而 戀令益」
「コタカクハ カツテキウヱシ ホトヽキス キナキトヨミテ コヒマサラシム」 |
| 〔本文〕 |
| 「木」 |
『元暦校本』「木」に「`」 |
| 「響」 |
『大矢本・京都大学本』「音」。赭ニテ消セリ。『京都大学本』、赭頭書「響」アリ |
| 〔訓〕 |
| カツテキウヱシ |
『天治本』「いまはきはうへ□」。末尾ノ字ヲ消セリ。右ニ「し」アリ。
『類聚古集』「いまはきはうゑし」
『神田本(紀州本)』「イマハキウヘシ」
『西本願寺本』「カツテ」モト青
『細井本』「曾」ノ左ニ「イマハ」アリ
『京都大学本』「曾木」ノ左ニ赭「イマハキ」アリ『神宮文庫本』「カツテキウエシ」。「曾」ノ左ニ「イマハ」アリ。
|
| キナキトヨミテ |
『元暦校本』「なきとよまして」。「な」ノ上ニ墨ニテ「○」符アリ。右ニ「き」アリ。「なき」ノ「き」ヲ墨ニテ消セリ。訓ノ右ニ赭「ナキテトヨミテ」アリ。「ま」ノ左ニ赭「メハ」アリ
『天治本』「きなきとよめは」 |
| コヒマサラシム |
『神田本(紀州本)』「コヒマサラマシ」
『天治本』「こひまさらしを」。「を」ヲ消セリ。下ニ「も」アリ
|
| 〔諸説〕 |
| ○カツテキウヱシ。『改』「イマハキウヱシ」。『童蒙抄』「カツキハウヱシ」。○キナキトヨミテ。『万葉代匠記(初稿本)』「キナキトヨメテ」。『改』「キナキトヨマセテ」。『童蒙抄』「キナキナラシテ」。 |
|
| |
| |
| 【左、資料について】 |
| |
今日の掲題歌は、どの「古」注釈書も大きく違わないので、
書かれていることも、割と平易なものだった |
『拾穂抄』
歌意はなく、初二句だけを載せており、語意の説明になる
このような扱い方が、この時代のこの歌に対する一般的な評価だったのだろう
それは、『万葉考』の真淵で際立つ |
| |
『代匠記』
ここで、旧訓とも言える「とよみ」ではなく、「とよめ」にその理由を述べる初出になる
そして、大伴坂上郎女の歌〔1479〕を引用するが、左頁にその歌を載せる
|
| |
『童蒙抄』
訓に関して、「かつて木植ゑし」を、「かつて木は植ゑし」を主張する
そして、この歌の「想い」の「主」を挙げるのは、後の注釈書への影響も大きいと思う
|
| |
『万葉考』
「意明なり」とは、述べるまでもなく、明らかなことだ、と解釈していいのかな
|
| |
『略解』
千蔭の言う「とよませて」とは、四段「とよむ」の未然形「とよま」に、
使役の助動詞「す」の連用形「せ」のことを言うのだろう |
| |
『古義』
この「かつて」を初句の上にうつして言うを心得よ、というのは
まさに「解説書」らしい説明だと思う
|
| |
『万葉集新考』
結句に「われをして」を加えて聞くべし、ということは
他にも「恋の想いをさらにかきたてる」何かが、伺えるからかもしれない
だから、それは「作者」だと断ってその意を固める意図だと思う
思い過ごしかもしれないが、これまでホトトギスの鳴き声を聞くと
人恋しさが一層つのるから、とする見方が多かったが
すでに、別な解釈、「ホトトギスそのものへの想い」とする解釈もあるからだ |
| |
『万葉集全釈』
「恋に悩める人の歌」という
あくまで、ホトトギスの鳴き声が、よけいに人恋しさをつのらせる、という解釈
|
| |
『万葉集全註釈』
ホトトギスが感傷を誘う鳥、という概念が固定している歌
そうなのかなあ、と思ってしまう
そのことと、一般に「勧農」の鳥、という概念は矛盾するように思える
あるいは、そうした固定された概念は必要ないのかもしれない
ホトトギスを詠う、作者それぞれの「想い」があった方がいい |
|

|
| 【歌意1951】 |
なかなかお逢いすることも出来ない人なのに
やっとこうして逢うことが出来たこの夜だから
ほととぎすよ、他の時ならともかく
今、このときこそ、私たちのために、鳴いてほしい |
「想い人」との特別な夜を、ほととぎすの鳴き声で大切な「とき」にしたい
そんな切な願いが詠われている
なかなか逢うことが出来ない人とは、身分や立場の事情があってのことか
古語辞典で「あひかたき」という語を見ると、そんな説明があった
改めてその「語」を意識すると
この「あひかたき」と使う意味こそ、深い想いを伝えてくるように思える
待ち望んで長い間待っていた人
いつ鳴くか、と心待ちにしているホトトギス
「想い人」と「ホトトギス」が同体化したこの歌は、
今この時こそ、もっとも大切な瞬間、ひととき、だと感じるものだ
ホトトギス、鳴いてくれ
注釈書のニ書に引かれた大伴宿禰書持の歌
| 夏雜歌/(大伴書持歌二首) |
| 我屋戸前乃 花橘尓 霍公鳥 今社鳴米 友尓相流時 |
| 我が宿の花橘に霍公鳥今こそ鳴かめ友に逢へる時 |
| わがやどの はなたちばなに ほととぎす いまこそなかめ ともにあへるとき |
| 巻第八 1485 夏雑歌 大伴宿禰書持 |
〔語義〕
「あへるとき」は、掲題歌と同じ完了(存続)で、「逢っているとき」
|
〔歌意〕
わが家の庭に咲く花橘に、ホトトギスよ、
今この時こそ来て鳴いてくれないか
こうして、大事な友に逢っている時なのだから |
この歌が、『全釈』の鴻巣盛広に言わせると、掲題歌を「焼き直し」したものだろう、という
それにしては、掲題歌に比べ「想い」の深さがないような気がする
「焼き直し」したのなら、その歌意を汲んで、もっと切実な気持ちになると思う
「想い人」と「友」の違いがあるにせよ
その歌意を想うなら、それこそ「最後の語らい」を予感させるような場面とか
あるいは、よくここまで来てくれたな、とかいうような雰囲気があって欲しい
だから、私は「類想歌」とは思わない
「類歌」には違いないが...
この掲題歌の「想い」と〔1485〕の「想い」は、その響き方がまったく違う、と思う
【赤人集(成立年時未詳[740年頃])】
| あひかたき きみにあへるとき ほとときす ことときよりは いまこそなかめ |
| 赤人集 227 |
【古今和歌六帖(こきんわかろくぢょう、成立年代未詳[永延元年(987年)か])】
| あひかたき きみにあへるよ ほとときす ことときよりも いまこそなかめ |
| 古今和歌六帖 巻第六 鳥 4451 |
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1951] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔あひかたききみにあへるよ霍公鳥ことときよりはいまこそなかめ 〕
難相君尓逢有夜霍公鳥他時從者今社鳴目 |
| あひかたき君に 他時よりかく稀なる君にあふ夜こそなかめといへるなるへし |
| 『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕 |
| |
難相君爾逢有夜霍公鳥他時從者今社鳴目
〔アヒカタキキミニアヘルヨホトヽキスコトトキヨリハイマコソナカメ 〕 |
| 無記 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
難相君爾逢有夜霍公鳥他時從者今社鳴目
〔あひがたき、きみにあへるよ、ほとゝぎす、あだしときゆは、いまこそなかめ 〕 |
| よく聞えたる歌也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
〔難相、君爾逢有夜《アヘルヨ》、霍公鳥、他時從者《コトヽキヨリハ》、今社鳴目《イマコソナカメ》、」 〕 |
| 右に同じ |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕 |
| |
難相。君爾逢有夜。霍公鳥。他時從者。今社鳴目。
〔あひがたき。きみにあへるよ。ほととぎす。あだしときゆは。いまこそなかめ。〕 |
他《コト》時に鳴かんよりは、斯く稀に逢へる夜に、來鳴けかしとなり。
參考 ○君爾逢有夜(新)キニアヘルヨゾ「曾」又は「焉」の脱とす ○他時從者(考)コトトキヨリハ(古)アダシトキヨハ、又は、コトトキヨリハ(新)略に同じ。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔難相《アヒガタキ》。君爾逢有夜《キミニアヘルヨ》。霍公鳥《ホトヽトギス》。他時從者《アタシトキヨハ》。今社鳴目《イマコソナカメ》。〕 |
| 他時從者は、マタシトキヨハとも、コトトキヨリハともよむべし、○歌(ノ)意、かくれたるところなし、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔あひがたき君にあへる夜△《ヨゾ》ほととぎすあだし時ゆは今こそなかめ 〕
難相君爾逢有夜霍公鳥他時從者今社鳴目 |
| 第二句はキミニアヘル夜ゾとあらではととのはず。夜の下に曾、焉などの字をおとしたるならむ |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔逢ひがたき 君にあへる夜 ほととぎす こと時よりは 今こそ鳴かめ〕
難相《アヒガタキ》 君爾逢有夜《キミニアヘルヨ》 霍公鳥《ホトトギス》 他時從者《コトトキヨリハ》 今社鳴目《イマコソナカメ》 |
容易ニ逢フコトノ出來ナイアナタニ、今夜久シブリデ逢ツタガ、郭公ヨ、他ノ時ヨリハドウゾ今夜コソナイテクレヨ。二人デオマヘノヨイ聲ヲ聞イテ樂シムカラ。
○他時從者《コトトキヨリハ》――童蒙抄アダシトキユハとあり、略解もそれに倣つてゐるが、舊訓に從つて置く。他は集中他辭《ヒトコト》(五三八)、他妻《ヒトツマ》(一七五九)などヒトとよんだ例は多いが、コト又はアダシの用例は見えない。しかしここはヒトとはよむべくもないから、コトがよいであらう。
〔評〕 卷八の大伴家持の歌、我屋前乃花橘爾霍公鳥今社鳴米友爾相流時《ワガヤドノハナタチバナニホトトギスイマコソナカメトモニアヘルトキ》(一四八一)は、蓋しこれを燒直したものであらう。
|
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔あひがたき きみにあへるよ、 ほととぎす ことときよりは いまこそなかめ。〕
難相 君尓逢有夜 霍公鳥 他時従者 今社鳴目 |
【訳】容易に逢い難い君に逢つた夜だから、ホトトギスは、ほかの時よりは、今こそ鳴くべきだ。
【釈】他時従者 コトトキヨリハ。コトトキは、他の時。ヨリは、比較をあらわしている。
【評語】人と共にホトトギスの声を賞翫しようとする心である。酒宴の席などでの作であろう。一往の座興に詠まれている。
【参考】類想。
わが屋前(には)の花橘にほととぎす今こそ鳴かめ。友に逢へる時(巻第八、1481、大伴の家持) |
|
| |
| |
 |
掲載日:2014.03.13.
| 夏雑歌 詠鳥 |
| 難相 君尓逢有夜 霍公鳥 他時従者 今社鳴目 |
| 逢ひかたき君に逢へる夜霍公鳥あたし時ゆは今こそ鳴かめ |
| あひかたき きみにあへるよ ほととぎす あたしときゆは いまこそなかめ |
| 巻第十 1951 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【類歌】〔1485〕
【赤人集】〔227〕
【古今和歌六帖】〔4451〕
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1951】語義 |
意味・活用・接続 |
| あひかたき [難相] |
| あひかたき [逢ひ難し] |
[形ク・連体形] 逢うことが困難である・逢いにくい |
| 相手の身分や立場、その他の事情からの場合が主 |
| きみにあへるよ [君尓逢有夜] |
| あへ [逢ふ] |
[自ハ四・已然形] 出逢う・来合わせる |
| る[助動詞・り] |
[完了(存続)・連体形]~ている |
已然形につく |
| ほととぎす [霍公鳥] |
| あたしときゆは [他時従者] |
| あたし [他し・異し] |
[接頭語(形容詞とも)](名詞について) 別の・異なっている |
| ゆ [格助詞] |
[比較の基準] ~よりも |
体言につく |
| は [係助詞] |
[目的語] 特に~を |
種々の語につく |
| いまこそなかめ [今社鳴目] |
| こそ~め [係り結び] |
[「係助詞「こそ」+助動詞「む」の已然形「め」] |
| 「こそ~め」の強調は、相手に対しての勧誘の語法 「~してほしい」 |
種々の語につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [きみにあへるよ] |
異訓はないが、左頁の『新考』は、強調の係助詞「ぞ」の脱落では、という
|
| |
| [あたし] |
古語辞典では「あだし」と濁音で載るが、古くは「あたし」とも記されている
この「あたし」を、旧訓では「こと」と訓まれている
しかし、本格的な注釈書が行われる時代に、「あたし」、「こと」は、
併行して訓まれていたことが左の「資料」から伺える
現在では、殆どの注釈書が「あたし」だが、
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕、
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕、
『万葉集校注』〔伊藤博、角川文庫、平成13年23版〕は、「こと」を採り
「ことときよりは」と訓んでいる『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕は、原文「他時」を、
『名義抄』で「他 アタシ」、『日本書紀』の傍訓にも「他 アタシ」が多い、とする
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕では、
「ことときよりは」も紹介しながら、「あたし」を採っている
さらに、「あたし」が「あだし」と使われ出すのは、室町期からだとしている
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕は、
この「あたし」は、形容詞シク活用だとし、終止形を連体格に用いた例しかない、という
左頁の『全釈』は「他」の字が、例をあげて「ヒト」と訓む例は多くあるが、
「こと」や「あたし」と訓む例がないとしている
しかしこの歌の場合、「ひと」と、歌意にならないので、
「こと」、「あたし」を当てるなら、との説明で「こと」を採る
|
|
|
| |
| 【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記] |
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[本文]「難相 君尓逢有夜 霍公鳥 他時従者 今社鳴目」
「アヒカタキ キミニアヘルヨ ホトヽキス コトヽキヨリハ イマコソナカメ」 |
| 〔本文〕 |
| 「他」 |
『類聚古集』「化」【の「ヒ」に横棒もう一本追加】(【】は編集) |
| 「社」 |
『西本願寺本』「杜」。但、「社」ニ直セリ |
| 「目」 |
『天治本』「【字、不明瞭】」。右ニ「目」アリ (【】は編集) |
| 〔訓〕 |
| アヘルヨ |
『神田本(紀州本)』「アヘルヨハ」
|
| コトヽキヨリハ |
『元暦校本・類聚古集』「ことをりよりは」 |
| イマコソナカメ |
『京都大学本』「イマコソハナカメ」。「ハ」ハ赭書セリ
|
| 〔諸説〕 |
| ○コトヽキヨリハ。『童蒙抄』「アタシトキユハ」。『古義』「アタシトキヨハ」。 |
|
| |
| |
| 【左、資料について】 |
『全釈』及び『全註釈』で類想歌として引用されている〔1481(新1485)〕の歌、
この作者を大伴家持と記されているが、明らかに弟の「大伴宿禰書持」の間違いだ |
『拾穂抄』
この書の「歌意」は、「あひかたき」の語義の解説をしただけのような感じだ
当時、一首ごとの歌番などはないので、どの歌も全力で注釈を付ければ
長い間の執筆期間、混乱をしかねない
平易な唱は、出来るだけ簡潔にするのだろう
真淵が、いい例だ |
| |
『代匠記』
歌意は載らず、訓のみ
|
| |
『童蒙抄』
「よく聞こえたる歌」とは、有り触れた歌、ということかな
|
| |
『万葉考』
「右に同じ」もまた、昨日の歌で、この歌の前歌〔1950〕の「意明なり」と言うのだろう
|
| |
『略解』
この『略解』の、それぞれの歌の最後に、[異訓」が載せられているが、
「(新)」は、一体どの「書」を指すのだろう
たとえば、今日など「曾」を持ち出すのは、『新考』かと思えるが
それでは、時代がはるかに合わないし...
今度の土曜日、明日香で『略解』をじっくり見てみよう
〔2014年3月19日記事で、解決を見る〕 |
| |
『古義』
原文「他時從者」の訓み得る可能性だけを述べ、「歌意」については
「かくれたるところなし」とは、広く承知で難しくない、という意味かな
|
| |
『万葉集新考』
第二句の「よ」は「夜」の下に「曾」が脱落しているのでは、とだけ書く
そもそも『新考』は、その緒言において、次のように書いている
「余は元來書を見し事多からず。萬葉註釋書中此書を作るに當りて一讀せしは
圓珠庵契沖の代匠記
賀茂眞淵の考〔著者の原著は 一、二、十一、十二、十三、十四のみ〕
著者の原著は 一、二、十一、十二、十三、十四のみ
本居宣長の玉の小琴(卷四まで)
荒木田久老の槻の落葉(卷三のみ)
富士谷御杖の燈《アカシ》(卷一のみ)
加藤千蔭の略解《リヤクゲ》
香川景樹の○[手偏+君]解稿本(卷四まで)
鹿持雅澄《カモチマサズミ》の古義
近藤芳樹の註疏(卷三まで)
木村|正辭《マサコト》博士の美夫君志《ミブクシ》(卷二まで)
以上十書のみ。」
この注釈書が成ったのが昭和二年のこと
その当時の万葉関連の書が、どれほどあったのかは解らないが
でも、この著者が『万葉集新考』を書き上げるのに目を通したのは、以上の十書、とある
この中で、今採り上げている「巻第十」を読むとすれば、
なるほど契沖、真淵、千蔭、雅澄しかない
その中に、井上通泰が「曾」があったはずだ、という何かの根拠があった
しかし、『代匠記』も、『略解』また『古義』にそれらしく述べたところはない
となると、万葉関連以外の書からの考察なのだろうか
|
| |
『万葉集全釈』
注記「あたし」のところでも書いた「他」
そして、作者の名は間違いながらも、〔1485〕歌は、
この掲題歌の焼き直したものと、推察している
|
| |
『万葉集全註釈』
「酒宴の席」での座興の一首
そのような「評価」というのは、私には理解できない
この歌に限らず、たとえば少々現実離れしていると、すぐ「酒宴の席」が持ち出される
しかし、それは歌の「評価」に必要な見方なのだろうか
『万葉歌』は、多くの創作が詠われているものだとは、私も思う
それは「歌」だから、何も不思議なことではない
だから、創作なのか、実景、実想なのかを論じるのは「注釈書」の立場ではないはずだ
この歌の内容を、素人が感じる手掛かりを教えてくれる、そうあるべきもので
「座興の一首」となれば、読む者を純粋な「歌の世界」から遠避けてしまう
たとえは適当ではないかもしれないが、
ある映画に感動しても、これは「映画」だから、「作られたものだから」と
そう言っているようなものだ
こうした注釈書のあり方は、あまり好きになれない |
| |
|
|
| 【歌意1952】 |
木々の生い茂った「夕闇」は、いっそう暗いものだ
それなのに、ほととぎす
どこに棲み処を、とでもいうのか
こんな暗がりを、鳴きながらな飛んでいくのだ |
ホトトギスが、夜も鳴く鳥だとは、『万葉歌』でも知ることが出来る
実際に、夜も鳴くのかどうか解らないが
歌に詠われる「夜鳴きのホトトギス」は、何かしらの「意味」を負っているはずだ
この歌にしても、その底には、「夜なのに、何故鳴く」という不審感からきている
叙景歌として、そうした風変わりな景観を詠ったものだと感じてもいいだろうし
もう一歩進めて、まあ明るくなるまで待てよ、というお節介を言うのもいい
そんな解釈が、『万葉集親考』にあった
多くの注釈書が、有り触れた内容のように書いているが
ふと振り返れば、
どの人も同じように、自身の行動を起こし、
あるいはその振る舞いに接し、首を傾げるケースがあるものだ
決して、作者の意図は何だったのか、というものではなく
それぞれが、どのようにも感じられる「広がり」を詠ったものだ、と思えば
この「ほととぎす」が、「夕闇」に鳴きながら飛び行くのを
「焦って無茶をするなよ」と自分に言い聞かせるように感じる聞き手もいることだ
先の『万葉集親考』が、おそらくそうだろう
この歌は、こんな意味なんだぞ、と
これが正解だというものではなく
解釈する人の、感じたその背景には、同じような想いがあったのだろう
私は、この歌に詠われる光景を想い浮かべて
懸命に何かをしている、あるいはしようとする者へ
それを見た者は、何を自身へ投影させるのか
傍観者なのか、積極的に係わろうとするのか...
そして、少なくとも、この詠われている「目と耳」の持ち主は、
「どんな理由か解らないけど、明るくなるまで待った方がいいぞ」と
そんな気持ちをこめて、見ている
「いづくをいへと なきわたるらむ」
この語句の中に、『親考』の井上通泰は、声を掛けざるを得なかったのだろう
そうした歌の感じ方が出来るのは
注釈書の初期の時代の人たちには、なかったのだろうか
『全註釈』で、
「何処を家というあたり、巧みだが、ホトトギスの上を推量しているのは、作り歌たるを免れない」としているのを、
私は、だからこそ、いいのではないか、と言ってしまった
【赤人集(成立年時未詳[740年頃])】
| こかくれて ゆふく○なるを ほとときす いつこをいへと なきわたるらむ |
| 赤人集 228 |
『赤人集』の底本(あるかどうか解らないが)を知らないので、
テキストをそのまま載せたが、
第二句の「○」は、私が付記したもので
このテキストでは「ゆふくなるを」と「万葉歌」でいう「ゆふくれ」の「れ」がなかった
これも明日香で、明日調べよう
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1952] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔このくれのゆふやみなるに 一云なれは 霍公鳥いつこをいへとなきわたるらし 〕
木晩之暮闇有尓 有者 霍公鳥何處乎家登鳴渡 |
| このくれの夕やみ 此暮の夕やみは重ね詞のやうにいへり又は木の下茂りてくらきを木の暮と云とそ |
| 『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕 |
| |
木晩之暮闇有爾 [一云有者] 霍公鳥何處乎家登鳴渡良哉
〔コノクレノユフヤミナルニホトヽキスイツコヲイヘトナキワタルラム 〕 |
| 良哉、[官本、哉改作武、] 哉は云までもなき誤なり、武に作るべし、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
木晩之暮闇有爾 [一云有者] 霍公鳥何處乎家登鳴渡良哉
〔このくれの、ゆふやみなるに、ほとゝぎす、いづこをやどと、なきわたるらん 〕 |
| 木晩之 前にも注せり。夏の木立の茂りて陰囁くなりたる義をば、木陰暗き夕暗なるにと云義也。家はやと讀べし。哉は武の誤りなるべし 一云有者 或説には夕暗なればとあると也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
〔木(ノ)晩之《クレノ》、暮闇有爾《ユフヤミナルニ》、 木晩は木茂りて小《ヲ》闇きに夕べ殊更なれば云、一云有者《ナレバ》、霍公鳥、何處《イツコ》乎家登、鳴渡良武、 〕 |
| 今本に武を哉に誤る假字はむとあり哉をむと訓ことなし |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕 |
| |
木晩之。暮闇有爾。(一云有者)霍公鳥。何處乎家登。鳴渡良哉。[哉ハ武ノ誤]
〔このくれの。ゆふやみなるに。ほととぎす。いづくをいへと。なきわたるらむ。〕 |
コノクレは木の下闇を言ふ。哉は武の誤なり。一本の有者《ナレバ》も、ナルニと同じ意なる古言の例なり。
參考 ○暮闇有爾(考、新)略に同じ(古)クラヤミナルニ。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔木晩之《コノクレノ》。暮闇有爾《クラヤミナルニ》。霍公鳥《ホトトギス》。何處乎家登《イヅクヲイヘト》。鳴渡良哉《ナキワタルラム》。〕 |
| 有爾、舊本に、一云有者と註せり、ナレバにても、ナルニの意になれば、同じことなり、○武(ノ)字、舊本哉に誤れり、契冲説に從て改つ、○歌(ノ)意は、木闇く繁り合(ヒ)たる暮闇《クラヤミ》の夜なれば、物のあやめも見えわかぬに、ほとゝぎすは、何處をさして己が家として鳴わたるらむ、となり、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔このくれの暮闇《ユフヤミ》なるに[一云なれば]ほととぎすいづくを山となきわたるらむ 〕
木晩之暮闇有爾[一云有者]霍公鳥何處乎家登鳴渡良哉 |
| コノクレは木陰なり。暮闇を古義にクラヤミとよめれど舊訓の如くユフヤミとよむべし。卷四(七七七頁)に夕闇ハ路タヅタヅシ、卷十一にも夕闇ノコノハガクレル月マツガゴトとあり○第四句はイヅクヲオノガ家トとなり。ココニトドマレカシといふ意を含めり○哉は武の誤なり |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔木のくれの ゆふやみなるに 一云、なれば ほととぎす 何處を家と 鳴き渡るらむ〕
木晩之《コノクレノ》 暮闇有爾《ユフヤミナルニ》[一云有者《ナレバ》] 霍公鳥《ホトトギス》 何處乎家登《イヅクヲイヘト》 鳴渡良哉《ナキワタルラム》 |
木ガ深ク茂ツテ暗ク、ソノ上夕方ノ闇トナツタノニ、郭公ノ鳴クノガ聞エルガ、ドコニアル自分ノ家ニ歸ラウト思ツテ、鳴イテ飛ンデ行クノダラウ。暗クテ方向モ分ラナイデ嘸困ルデアラウ。
○暮闇有爾《ユフヤミナルニ》――古義にクラヤミナルニとあるが、暮は多くヨヒ・ユフとよんでゐる。爲暮零禮見《シグレフレミム》(二二三四)の例も(224)あるが、クラとよんだのはないから、舊訓のままにしておく。殊にここは夕暮の景らしく思はれる。○一云有者――これはユフヤミナレバといふ異傳であるが、おもしろくない。○鳴渡良哉《ナキワタルラム》――哉は元暦校本に武とあるのがよい。
〔評〕夕暮の森などで聞く、郭公の聲をあはれんだので、前の旦霞八重山越而《アサガスミヤヘヤマコエテ》(一九四一)と似たところがある。
|
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔このくれの ゆふやみなるに、一は云ふ なれば。ほととぎす いづくをいへと なきわたるらむ。〕
木晩之 暮闇有尓 [一云 有者] 霍公鳥 何處乎家登 鳴渡良武 |
【訳】木の茂つて暗い夕闇だのに、ホトトギスは、何処を家として鳴いて行くのだろう。
【釈】木晩之 コノクレノ。 コノクレは、木の繁茂して暗いこと。
暮闇有尓 ユフヤミナルニ。 クラヤミナルニ(古義)。暮闇はクラヤミとも読まれるが、暮の字は、集中多くユフ、ヨヒと読まれている。またクラヤミの語は、「晩闇跡(ユフヤミト) 隠益去礼(カクリマシヌレ)」(巻三、460)の晩闇をクラヤミと読む説があるだけである。ユフヤミは「夕闇者(ユフヤミハ) 路多豆多頭四(ミテタヅタヅシ)」(巻四、709)、「夕闇之(ユフヤミノ) 木葉隠有(コノハゴモレル) 月待如(ツキマツガゴト)」(巻十一、2666)がある。
一云有者 アルハイフ、ナレバ。第二句がユフヤミナレバとあるとすると、ナルニの方が通りがよい。
何處乎家登 イヅクヲイヘト。何処を、わが行くべき家として。
【評語】暗い空にホトトギスの鳴いて行くのを詠んでいる。何処を家というあたり、巧みだが、ホトトギスの上を推量しているのは、作り歌たるを免れない。 |
|
| |

|
掲載日:2014.03.14.
| 夏雑歌 詠鳥 |
| 木晩之 暮闇有尓 [一云 有者] 霍公鳥 何處乎家登 鳴渡良武 |
| 木の暗の夕闇なるに [一云 なれば] 霍公鳥いづくを家と鳴き渡るらむ |
| このくれの ゆふやみなるに[なれば] ほととぎす いづくをいへと なきわたるらむ |
| 巻第十 1952 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【赤人集】〔227〕
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1952】語義 |
意味・活用・接続 |
| このくれの [木晩之] 〔枕詞〕もあるが、ここではそうでない |
| このくれ [木の暗れ] |
木が茂って暗いこと、またその暗い所・木の暗れ闇 |
| ゆふやみなるに [暮闇有尓] 一云 なれば [一云 有者] |
| ゆふやみ [夕闇] |
月齢十六日以後の日没から月の出まで、しばらく暗い時間帯 |
| なる [助動詞・なり] |
[断定・連体形]~である・~だ |
体言につく |
| に [接続助詞] |
[逆接]~のに・~けれども |
連体形につく |
| なれば [接続詞] [有者] |
[順接]それだから・したがって |
体言につく |
| 〔断定の助動詞「なり」の已然形「なれ」に接続助詞「ば」のついたもの〕 |
| ほととぎす [霍公鳥] |
| いづくをいへと [何處乎家登] |
| いづく [何処] |
[場所についての不定称の指示代名詞] どこ |
| 「いづこ」の古形・上代では「いづく」のみが用いられ、中古以降は両形が併用された |
| と [格助詞] |
[比喩] ~として・~のように |
体言につく |
| なきわたるらむ [鳴渡良武] |
| なきわたる [鳴き渡る] |
[自ラ四・終止形] 鳴きながら飛んでゆく |
| らむ [助動詞・らむ] |
[現在推量(疑問)・終止形] ~ているのは何故だろう |
| 〔現在の事実について、その原因・理由を疑問を持って推量する |
終止形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
この歌、珍しく最近のどの注釈書も異訓はなく、異訓となると、古注釈に見えるだけだ
確実に誤字と見られる「哉」も、「武」に落ち着いている
異訓がなければ、その歌意にも、大きな違いはない
|
| |
| |
| 【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記] |
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[本文]「木晩之 暮闇有尓 [一云 有者] 霍公鳥 何處乎家登 鳴渡良哉」
「コノクレノ ユフヤミナルニ ホトヽキス イツコヲイヘト ナキワタルラム」 |
| 〔本文〕 |
| 「登」 |
『天治本』「【字句不明瞭】」。消セリ。右ニ「登」アリ。 |
| 「渡」 |
『元暦校本』「度」 |
| 「哉」 |
『元暦校本・大矢本・京都大学本・天治本・神田本(紀州本)』「武」。
『類聚古集』墨ニテ消セリ。右ニ墨「武」アリ |
| 〔訓〕 |
| コノクレノ |
『京都大学本』漢字ノ左ニ赭「コカクレ」アリ。赭ニテ右ノ訓ト入レ換フ可キヲ示セリ
|
| ユフヤミナルニ |
『元暦校本』「ゆふやみあるよ」。「よ」ノ右ニ墨「に」アリ。
『類聚古集』「ゆふやみあるに」
|
| 有者 |
『西本願寺本・大矢本・京都大学本』右ニ朱「ナレハ」アリ。
『細井本・』右ニ「ナレハ」アリ。
『神宮文庫本』右ニ「ナレハ」アリ。朱ノ上ニ墨ヲ重ネテ書ケリ |
| イツコヲイヘト |
『元暦校本』「いつくこをいへと」。「つくこを」ノ右ニ赭「ツコヲ」アリ。『神田本(紀州本)』「イツコヲイヱト」 |
| 「渡」 |
『元暦校本』「度」 |
| ナキワタルラム |
『類聚古集』「なきわたらるらむ」。墨ニテ上ノ「ら」ヲ消セリ |
| 〔諸説〕 |
○イツコヲイヘト。『童蒙抄』「イツコヲヤトト」。
○鳴渡良哉。『代匠記(初稿本)』「哉」ハ「武」ノ誤 |
|
| |
| |
| 【左、資料について】 |
| |
『拾穂抄』
「このくれ」と「ゆふやみ」の重ね言葉
それほど、「暗さ」が強調されている、ということなのか
下の二句を、際立たせるために...と、私は都合よく解釈している
何しろ、「重ね言葉」といいながら、それがどんな意味合いなのか触れていないので
この著者の言外の思いを想像するしかない |
| |
『代匠記』
この時代の「官本」が、どんな種類の書を指すのか解らないが、
その「官本」にても、原文「哉」を誤字とし「良」に改作していることを書いている
「哉は云までもない誤なり、武につくるべし」は、誰も異論はないだろう
|
| |
『童蒙抄』
数少ない「異訓」だが、「家」を「や」と訓むなら、
いっそ、「やど」とした方が、実際的なのに
「や」と読むべし、とは中途半端な気がする
もっとも「家」を「やど」と訓む例がなく、
語義の上から「やど」と訓じたのかもしれないが
現代の注釈書に比べると、その必要とする対象者の違いがよく解る
|
| |
『万葉考』
この書も、これまでの書のように、「哉」を「武」の誤字と指摘したに過ぎない
|
| |
『略解』
「一云」の「なれば」が、「なるに」と同じ意となる古言とは、
当時の解釈は、そうなのだろうか
少なくとも、『略解』以前に、主な注釈でこの歌の歌意を載せたものは、
私はまだ見ていない...あるかもしれないし、ないかもしれない
前述のような主な書では、「歌意」ではなく、語義や誤字の指摘で済ませている
「なれば」と「なるに」が「同じ意」というのは
「なれば」の用法は、已然形「なれ」に「ば」なので、語法上確実に順接の確定条件だ
それは、間違いない
問題は、その同じ意味で「なるに」を解釈する、ということだ
接続助詞「に」には、逆接も順接も、接続助詞「ば」と違って語法上での見極めではなく
その前と後の事態との意を明確に捉えて、解釈することになる
この歌の姿は、
「暗闇の中を、家を求めてなのか、鳴きながら飛んでいる」ほととぎす
それを、「なるに」を「逆接」で解釈すると、
「暗くなったのに、どこを棲み処と捜し求めて、鳴きながら」となり
「順接」、つまり「なれば」と同じ意とすれば
「暗くなったので、どこが棲み処かと、慌てて捜して鳴きながら」...
私は、本歌は「逆接」で解釈し、しかし「一云」では、「順接」の異伝もあるぞ
そんな編集かと思っていたが、千蔭は、同じ意だとしている
「一本の有者《ナレバ》も、ナルニと同じ意なる古言の例なり。」
しかし、この言い方だと、
「なれば」もまた「逆接」で、「古言の例」と言いたげな感じもする
そういえば、現代の叢書の中でも、
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕は、
「異聞の『なれば』は、逆接の【なるに】に同じ」と書いている
やはり、『略解』の言う「古言」の例として、あるのかな
|
| |
『古義』
この雅澄もまた、「なれば」が「なるに」と同じなのだろう、という
それと、「ゆふやみ」を、この書だけは「クラヤミ」と訓む
なぜそう訓むのか、説明はない
ただし、これまでの注釈書のパターンを見ていると
新しく著される本には、必ずと言っていいほど、かつての書の「異訓」に対して
その理由らしきものを推察している
不思議なのは、ならばどうしてその当時には、それが語られることが少ないのだろう
|
| |
『万葉集新考』
「暮闇を古義にクラヤミとよめれど舊訓の如くユフヤミとよむべし」
何故、旧訓に従うべきか、知りたかった
そうでないと、どの書も第四句を「いへ」もしくは「やど」としているのに
この書では、「山」としている
勿論、ホトトギスの「棲み処」をいう「家」が、「山」だと解釈してのことだろうが
それは、「訓」をそのように「解釈」すべきもので、
「訓」自体を解釈するとなると、また違った検証の仕方が必要になる
『古義』の「くらやみ」を、旧訓に従うべし、と言うのなら
この「山」は、「いへ」と訓むのだろうか
〔これは、やはりミス入力だった、15日付けに訂正を載せた〕
ただ、この書において、ようやく「歌意」への「らしさ」が書かれているように思える
暗がりでの「たづたづし」(おぼつかない・はっきりしない)さまを理由に、
ここに留まって、明けるのを待て、と解釈している
|
| |
『万葉集全釈』
「一云有者――これはユフヤミナレバといふ異傳であるが、おもしろくない。」
この気持ち、解る
これだと、「なれば」と「なるに」が真逆の意を為すものと理解できる
どちらの「意」が「心地よい」のか、それは人それぞれだろうが
少なくとも、「本歌」を解釈するのであれば、この著者の姿勢はいいと思う
ここで、『古義』における「くらやみ」の強引さを指摘しているが
それがどう評価されているのか、他には言及した書を知らないので
どうなのだろう
|
| |
『万葉集全註釈』
「一云有者 アルハイフ、ナレバ。第二句がユフヤミナレバとあるとすると、ナルニの方が通りがよい。」
「通りがよい」というのは、「意」に適っている、ということだろうか |
| |
|
|
 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 「けさのあさけに」...なきつるは... |
| 『あさいかねけむ』 |
| 【歌意1954】 |
ほととぎすの、今朝早くに鳴く声を、
あなたはお聞きになりましたか
それとも、まだおやすみだったでしょうか
(一緒に聞きたいと思っていましたが...) |
|
| |
| |
この歌の現訓は、「古注釈書」の流れを追いかけてみると
鹿持雅澄の『古義』によるものだと解る
以降の注釈書が、この雅澄の訓に異を唱えていない
この歌の表面的な「歌意」は、まさに多くの注釈書が述べるようなもので
他愛のない遣り取りの一つに思えるが、
さらに何故このような問い掛けめいた歌を詠うのか
それを、これらの表面的な「歌意」から感じ取るのは、難しいのだろうか
それとも、あまりにも容易なことなので、書くまでもない、とするものなのか
「歌意」が平面的で、まさに読んだまま、と言うのであれば
それこそ、これまでお数多くの「注釈書」が、その書法を用いたように
何も「全歌の注釈書」にしなくてもいい、そう思える
全四千五百余首から、「註釈」に値するものを選び出し「抄」とでもすべきだ、と思う
そうした「注釈書」は、数多くある
しかし、敢えて「全歌」を載せるのなら
可能な限り、作者の心情が私たちに見せるものをもっと拾い出して欲しい
素人には、それも叶わないが、何しろ研究者であれば、そうした目的が必要ではないだろうか
この歌、単純に「朝のホトトギスの鳴く声を、聞いたのか、朝寝坊してたのか」
と、詠うだけでなく
「こんなに心地よく鳴くホトトギスの声、一緒に聞きたかったですね」
そんな気持ちもあった、と解釈すれば
少なくとも、「歌集」で載せられる「歌」として少しは輝くのでは、と思う
どんな「歌集」でも、後世に残る歌となれば
その一首の「意味」には、私たちが日々日常で、口すさむ「鼻歌」とは違う何かがある
勿論、作者の意など本当のところまで解るものではないが
だからこそ、ある程度の自由さで、自分に感じさせることも出来る
それでこそ、長年残り伝わってきた「歌集」の「一首」だと言える
この歌、作者と君がどんな関係なのか、と詮索する気はないが
歌に感じれば、自然と「共に聞きたかった」と思う、女の想いが伝わる
賀茂真淵の「朝影」という言葉を借りれば、いっそう、そのイメージハ重なってくる |
| |
| |
| |
【訂正】
〔3月14日付け〕で、右頁の「資料について」の『万葉集新考』の中で
その訓について「家」を「山」としてあることに、不思議に思いながらも、
そのことについて意見を書いてしまった
私のテキストの入力ミスだったので訂正しておく『右頁万葉集新考』
|
| |
| |
【赤人集(成立年時未詳[740年頃])】
| ほとときす けさのあさきり なきくるを きみはえきかす いやはねつらむ |
| 赤人集 230 |
|
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1954] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔霍公鳥けさのあさけに鳴つるはきみきくらんかあさいぬらんか 〕
今朝之旦明尓鳴都流波君将聞可朝宿疑将寐
|
| 霍公鳥けさのあさけ きみきゝしにやもし朝いして聞すやと也 |
| 『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕 |
| |
霍公鳥今朝之且明爾鳴都流波君將聞可朝宿疑將寐
〔ホトヽキスケサノアサケニナキツルハキミキクラムカアサイカヌラム 〕 |
| 官本には此歌を次に置、次の歌を此に置けり、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
霍公鳥今朝之旦明爾鳴都流波君將聞可朝宿疑將寐
〔ほとゝぎす、けさのあさけに、なきつるは、きみきくらんか、あさいかしぬる 〕 |
疑 は、うたがふと云字故義をもて歟と讀む也
將寐 將は、しとも、すとも、めとも所によりて讀む字也。寐は借訓也。いぬると讀字故、ぬると云詞に借り用て讀べし。此朝に誰が方よりの歸さにや、鳴く霍公鳥の哀れも一方ならぬ音を、戀慕ふ人のいかにや聞給へるや、朝いをやして、かく哀れむべき聲をも聞かでや過し給はんと思ひやれる也。朝いかぬらんと讀ませたれど、さは詠める句例無し。又詞の義も六ケ敷也。朝いかしぬると讀めば、何の義も無く義安也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
〔霍公鳥、今朝之旦明爾《ケサノアサケニ》、 旦明は朝開と書く如く借字にて朝影なりくはしくは(卷一)の長歌の下に見えたり鳴都流波、君將聞可《キクラムカ》、朝宿疑將寢《アサイカヌラム》、」 〕 |
| 【訓じながら、意を述べる】(「【】」は編集) |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕 |
| |
霍公鳥。今朝之旦明爾。鳴都流波。君將聞可。朝宿疑將寐。
〔ほととぎす。けさのあさけに。なきつるは。きみききけむか。あさいかぬらむ。〕 |
朝ケは朝明なり。君は聞きけんか、若くは朝寢《アサイ》して聞かざりしかと問ふなり。疑は義を以て歟の言に用ひたり。
參考 ○君將聞可(考)キミキクラムカ(古、新)略に同じ ○朝宿疑將寐(考)略に同じ(古、新)アサイカネケム。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔霍公鳥《ホトヽギス》。今朝之旦明爾《ケサノアサケニ》。鳴都流波《ナキツルハ》。君將聞可《キミキヽケムカ》。朝宿疑將寐《アサイカネケム》。〕 |
| 末(ノ)句キミキヽケムカアサイカネケムと訓べし、(キミキクラムカアサイカヌラムとよみては、鳴都流波《ナキツルハ》とあるにかなはず、)○歌(ノ)意は、今朝ほのぼの明に霍公鳥の初音もらして鳴つるをば、君は聞けむか、又は朝宿して聞ずにありけむか、となり、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔ほととぎすけさのあさけになきつるは君將聞可《キミキキケムカ》、朝宿疑將寐《アサイカネケム》 〕
霍公鳥今朝之且明爾鳴都流波君將聞可朝宿疑將寐 |
| 四五を舊訓にキミキクラムカ、アサイカヌラムとよめるを略解に第四句のみキミキキケムカに改め、古義には結句をもアサイカネケムに改めたり。古義に從ふべし。ネタリケムをネケムともいふべければなり○且は旦の誤なり |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
| |
子規が今朝の夜の引き明け方に鳴いたのは、あなたはお聞きなさつたでせうか。それとも、今頃未朝寢をして入らつしやるのでせうか。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔ほととぎす 今朝の朝けに 鳴きつるは 君聞きけむか 朝いあか寐けむ〕
霍公鳥《ホトトギス》 今朝之旦明爾《ケサノアサケニ》 鳴都流波《ナキツルハ》 君將聞可《キミキキケムカ》 朝宿疑將寐《アサイカネケム》 |
郭公ガ今朝ノ夜明ケ方ニ鳴イタノハ、アナタハアノ聲ヲ聞イタダラウカ、ソレトモ朝寢ヲシテヰマシタカ。ドウデスカ。
○朝宿疑將寐《アサイカネケム》――舊訓アサイカヌラムとあるが、古義の訓に從ふ。上に鳴郡流《ナキツル》とあり、君將聞《キミキキケム》と訓んでゐるのだから、ここもネケムとしなければならない。
〔評〕 おほやうな上代人らしい歌で、多少の滑稽味も感ぜられる。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔ほととぎす けさのあさけに なきつるは、 きみききけむか。 あさいかねけむ。〕
霍公鳥 今朝之旦明尓 鳴都流波 君将聞可 朝宿疑将寐 |
【訳】ホトトギスが、今朝の夜明けに鳴いたのは、あなたはお聞きになつたのでしょうか。それとも朝寝をなさつたでしょうか。
【釈】朝宿疑将寐 アサイカネケム。アサイは、朝の睡眠。疑の字を、カに当てて書いている。
【評語】第五句が率直で、さすがに萬葉集らしい。相手を揶揄している気もちもあるのだろう。 |
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| |
〔ほととぎす けさのあさけに なきつるは きみききけむか あさいかねけむ〕
霍公鳥 今朝之旦明尓 鳴都流波 君将聞可 朝宿疑将寐 |
【大意】ほととぎすが、今朝の朝あけに鳴いたのは、君は聞いたであらうか、それとも朝寝をして居たであらうか。
【作意】少しく嫌味を感じさせる。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
| |
〔ほととぎす けさのあさけに なきつるは きみききけむか あさいかねけむ〕
霍公鳥 今朝之旦明尓 鳴都流波 君将聞可 朝宿疑将寐 (『元暦校本』) |
【口訳】霍公鳥がけさの夜明けに鳴いたのはあなたはお聞きになつたでせうか。それともまだ朝寝をしてをられたでせうか。
【訓釈】君聞きけむか朝いか寐けむ-旧訓キミキクラムカアサイカヌラムとあるを古義に「鳴都流波(ナキツルハ)とあるにかなはず」として、キキケム、ネケムと改めたによる。「朝い」は朝寝(1・46)。
【考】赤人集に「けさのあさきり鳴きつるを君はえ聞かずいやはねつらむ」、流布本「君まだ聞かず」とある。桐火桶には「君聞くらむか朝ねやすらむ」とある。 |
|
| 契沖『万葉代匠記』の言う、「官本」とは |
| 今注する所の本は世上流布の本なり、字點共に校合して正す所の本は一つには官本、是は初に返して官本と注す、八條智仁親王禁裏の御本を以て校本として字點を正し給へるを、中院亞相通茂一卿此を相傳へて持給へり、水戸源三品光圀卿彼本を以て寫し給へるを以て今正せば官本と云彼官庫の原本は藤澤沙門由阿本なり、奥書あり、二つに校本と注するは飛鳥井家の御本なり、三つに幽齋本と注するは阿野家の御本なり、本是細川幽齋の本なれば初にかへして注す、四つに別校本と注するは、【正辭云、以下文缺く按ずるに水戸家にて校合せるものを云へるなるべし、】五つに紀州本と注するは紀州源大納言光貞卿の御本なり、此外、猶考がへたる他本あれど煩らはしければ出さず、三十六人歌仙集の中に此集の中の作者には人麿赤人家持三人の集あり、共に信じがたき物なれど古くよりある故に引て用捨する事あり、又六帖に此集より拔出して撰入たる歌尤多し、又代々の勅撰に再たび載られたる歌多し、見及ぶに隨て引て互に用捨せり、 |

|
掲載日:2014.03.15.
| 夏雑歌 詠鳥 |
| 霍公鳥 今朝之旦明尓 鳴都流波 君将聞可 朝宿疑将寐 |
| 霍公鳥今朝の朝明に鳴きつるは君聞きけむか朝寐か寝けむ |
| ほととぎす けさのあさけに なきつるは きみききけむか あさいかねけむ |
| 巻第十 1954 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【赤人集】〔230〕【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1954】語義 意味・活用・接続 |
| ほととぎす [霍公鳥] |
| けさのあさけに [今朝之旦明尓] |
| あさけ [朝明] |
[「あさあけ」の転] 明け方・早朝 |
| 「あかとき」よりも遅い早朝、明け方 |
| なきつるは [鳴都流波] |
| なき [鳴く] |
[自カ四・連用形] (鳥・虫・獣が)声を出す |
| つる [助動詞・つ] |
[完了・連体形] ~てしまった |
連用形につく |
| は [係助詞] |
[とりたて(目的語)] 特に~を |
連体形につく |
| きみききけむか [君将聞可] |
| きき [聞く] |
[他カ四・連用形] 聞いて心に思う・聞き知る |
| けむ [助動詞・けむ] |
[推量(過去)・終止形] ~たのだろう |
連用形につく |
| か [係助詞] |
[疑問] ~か・~だろうか |
| 〔接続〕体言・活用語・副詞・接続助詞などが主語・目的語・連用修飾語ならばつく |
| あさいかねけむ [朝宿疑将寐] 「か」は「係り結び」の「係り」、「けむ」は連体形「結び」 |
| あさい [朝寝] |
朝寝(あさね) |
| 朝眠ることを「あさい」といい、その対語は「夜寝(よい)」の夜眠ること |
| か [係助詞] |
[疑問] ~か・~だろうか |
| ね [寝(ぬ)] |
[自ナ下二・連用形] 眠る・寝る・横になる |
| けむ [助動詞・けむ] |
[推量(過去)・連体形] ~か・~だろうか |
連用形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
この歌、珍しく最近のどの注釈書も異訓はなく、異訓となると、古注釈に見えるだけだ
確実に誤字と見られる「哉」も、「武」に落ち着いている
異訓がなければ、その歌意にも、大きな違いはない |
| |
| 『きみききけむか』 |
旧訓では、「きくらん(む)か」、
これは、諸本が例外なく「きくらん(む)か」としているので、
春満の『童蒙抄』の時代までは、どの注釈書も「きくらん(む)か」とする
雅澄『古義』が、提唱した「ききけむか」が、今日の定訓になっている
この二者「きくらむか」、「ききけむか」の語意上の違いは、なんだろう
「きくらむか」は、四段「聞く」の終止形に、現在推量の助動詞「らむ」
活用の連用形につく「けむ」が、過去推量の助動詞なので、当然歌意には影響するだろう
雅澄のいう、「なきつるは」に適わず、というのは、
完了の助動詞「つる」の意味を、動作の「完了」とすれば、過去になる、ということなのだろう
同じ完了の助動詞でも「たり」は、動作が継続している意もあるが、
ここは確かに、継続ではなく、完了だ
雅澄のいう、「なきつるは」に適うとすれば、やはり「けむ」となるだろう
それでも、現在推量の「らむ」を解釈するなら、
「君」が、朝のほととぎすの声を、聞いただろうか、それともまだ寝ていて聞かなかったのか
という現在までの作者の疑問推量の継続、だということになる
この「らむ」が、『童蒙抄』や「『万葉考』当たりまでしか知ることは私には出来ないが
春満の歌意は、そんな内容だと思う |
| |
| 『あさいかねけむ』 |
原文の「朝宿」は、『万葉集』中、二例しかないが、
これを「あさい」と訓むのは、この掲題歌一首のみ
もう一つの「朝宿」は、第十一、2583の「朝宿髪」で、「あさねがみ」との訓が殆どだ
「あさねがみ(朝寝髪)」、朝起きたままの乱れた髪、という「語」もある
「あさい」は、「あさね」とも言うらしいので、
ここは、注釈者が、どちらが語調、語感で似合うのか、の判断だろう
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕は、
この〔2583〕歌を「あさいかみ」としているが
古注釈では、「あさねかみ」ばかりだ
「けむ」については、前の句で述べたことと同じ理由になると思う
雅澄以前は、「らむ」が主体となっている
季吟の場合は、「疑」を、最後に訓むが、他は語順通り |
| |
| |
| |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[本文]「霍公鳥 今朝之且明尓 鳴都流波 君将聞可 朝宿疑将寐」
「ホトヽキス ケサノアサケニ ナキツルハ キミキクラムカ アサイカヌラム」
(「【】」は編集) |
| 〔本文〕 |
| 「且」 |
『元暦校本・類聚古集・西本願寺本・細井本・神宮文庫本』「旦」。
『神田本(紀州本)』「【字句不明瞭】」 |
| 「明」 |
『神田本(紀州本)』「【字句不明瞭】」 |
| 「波」 |
『類聚古集』「者」 |
| 〔訓〕 |
| アサケニ |
『元暦校本』「あさあけに」 |
| キミキクラムカ |
『元暦校本』「きみきけらむか」。「み」の右下ニ赭「ヤ」アリ。「け」ノ右ニ赭「ク」アリ。
『西本願寺本』「キミキクランカ」 |
| アサイカヌラム |
『元暦校本』「あさいやすらむ」。「す」ノ右ニ赭「ヌ」アリ。
『類聚古集』「あさいやぬらん」。
『西本願寺本』「アサイカヌラン」 |
| 〔諸説〕 |
| ○キミキクラムカ。『古義』「キミキキケムカ」。○アサイカヌラム。『童蒙抄』「アサイカシヌル」。『古義』「アサイカネケム」 |
|
【左、資料について】
| 『万葉拾穂抄』 |
万葉の時代の歌を訳した、江戸時代の言葉を、また訳さなければ理解できないなんて、
まったく日本の言葉の難しさには、泣かされる
言葉の変化というのは、いきなり語義が変わるものではなく、長い間に変化していくものだ
季吟の時代から、三百数十年の今日、解るようで解らない
同じことが、この季吟の時代の人にも言えるだろう
三百年、四百年も前の時代の「和歌」...苦労したと思う
この季吟の歌意を、そのまま訳すのではなく、現代的に感覚で掴めば
「ほととぎすの明け方の鳴き声、あなたは聞きませんでしたか、朝寝で、聞かなかったでしょうか」と言うことだろう |
| 『万葉代匠記(精撰本)』 |
ここでも、契沖は「官本」という
以前から、その「官本」とは、いったいどんな書なのか、と気になっていたが
十五日の明日香図書館で、ようやくその手掛かりを見つけた
いずれ、こうした「古注釈書」の補足は、別頁に設けなければ、と思うが
今日は、その「官本」に言及した箇所だけを、左下段に載せておく
多分、公家と武家における万葉集の校合を為した由緒ある「書」ということだろう
この「官本」において、この歌は次の歌と順序が入れ替わっている、という
その歌順で載せる「校本」は、『元暦校本・類聚古集』など
この点は、どの書でも言っており、『西本願寺本』などを「底本」とする書では、
『国歌大観』の番号に基づけば、「1949(掲題歌)・1951・1950」の順だが、
「1950・1949(掲題歌)・1951」になるように「印」が付記されている
そうなれば、『元暦校本・類聚古集』などの順と一致することから
原本では、それが正しかっただろう、とされる
何しろ、もともと「歌番」など無い『万葉集』、歌順の異同が全く無い、と思う方に無理がある
|
| 『万葉集童蒙抄』 |
「疑」の語義から、「歟(か)」と訓むことをいう
「将」は「し」とも「す」とも「め」とも場合によって読める字、らしい、知らなかった
「ぬらむ」と訓む句例がないので、「しぬる」か
ただ、この注釈書で、「君」が「恋い慕う人」と初めて見えた |
| 『万葉考』 |
「朝影」とは、どんな意味になるのだろう
古語辞典では「朝、鏡や水に映る姿・朝日に照らされて映る影が細いことから、身の細った姿」
真淵は、その語意を持って、この歌を解釈した、ということになるのか
ここで、「巻一の長歌」というのが、この時代の実情を教えてくれる
何度も言うように、この時代には、本来の『万葉集』の姿であって、明治時代に便宜上付けられた「歌番号」などなかったから、「万葉集中」の引用など、具体的に言うには、それこそ引用する歌そのものを載せなければならない
そんなとてつもなく面倒な時代に、四千五百首余りの歌に注釈をつけるのは、気の遠くなるような大変なことだ
ただただ、頭を下げるしかない |
| 『万葉集略解』 |
「疑」については、『童蒙抄』そのままに継承し、「君將聞可」は、『古疑』に同調するが
結句の「らむ」は、そのままにする |
| 『万葉集古義』 |
この雅澄の「訓」が、現在の定訓となるものだ
たった「なきつるは」に適わず、というだけで、その後の多くに影響を与えている
このように、当時の「権威」への「挑戦」のようなもの、今読んでいる『古疑』の「翁傳」、
なるほどなあ、と思う |
| 『万葉集新考』 |
第四、五句の旧訓を、『略解』は第四句だけを『古疑』に改めているのを、訝しんでいるようだ
前日のこの「項目」で、「家」を「山」と表記したこの著を、
原文の「家」をその語意から「山」に導いたのか、と少し批判的に書いたが、
やはり、私の「テキスト」への入力ミスだった
明日香図書館で、幾つかの『万葉集新考』を開いてみたら、いずれも「家」だった
素人の入力ミス、だからと言っても、それに基づいて自分の感想を言うのだから
愚かなミスをしたものだ
校訂まで時間をかける必要も無い、とは思っているが
こうした単純ミスは、ただただ「恥ずかしい」 |
| 『口訳万葉集』 |
今日から、初めてこの「口語万葉集」を載せる
これとて、もう百年も前の著書になる
明治大正の歌人学者の感性を、教えてもらうことになる |
| 『万葉集全釈』 |
第四句までは、当時の解釈を継承し、
その意味で、結句も当然のように「けむ」が自明だ、というなら
私の拙い知識では、それなら歌意の「どうですか」というのは余分ではないか
疑問の問い掛け自体は、現在推量に基づくことになるので、「らむ」でもいいような気がする
いや、ひょっとすると、歌意としては、それがいいのかも知れない
だとすれば、『略解』の訓が、もっとも自然になるような気がしてきた |
| 『万葉集全註釈』 |
第五句が率直で万葉集らしい、と評している
そこが率直である、というのは、この作者と「君」の関係を言外に言っていることになる
親しい者同士、思い遣る歌で相聞歌でない、とする『講談社文庫本』の訳し方と共通する |
| 『万葉集私注』 |
歌意は過不足なく平易に述べるが、その「作意」において、嫌味を感じさせる、という
これも、やはり『全註釈』や『講談社文庫本』の背景と同じ気がするが
ただ、「嫌味」を感じさせる、というのなら、あまりの「親しさ」故に、「朝寝坊していたのか」
と、「愚かな奴だ」などと言い放っている感じ方なのだろう |
| 『万葉集注釈』 |
「桐火桶」、初めて知る「歌集」の名だが、
藤原俊成のエピソードに、その名がであることは解った
この『注釈』は、一首ごとに、その校本の出典を記しているが、『元暦校本』とあるのは
その原文も、訓も、合わない気がする
それとも、この注釈書の底本は『元暦校本』でありながらも
著者の校合の結果、改めたと解釈するべきなのかな
また調べなければならなくなった
|
|
|
|
|
 |
| |
| |
| |
| |
| |
「なきとよもせば」...はなはちりつつ...
|
| 『鳴き散らせるホトトギス』 |
| 【歌意1953】 |
ほととぎすが、花橘の枝にとまって
鳴き響かせるので、そのせいなのか
花が、しきりに散り続けて... |
|
| |
| |
ホトトギスが、橘の枝にとまって、鳴き響かせる
すると、花橘の花がその鳴き声のせいで、はらはらと散って...
これは、花が散るのを惜しむ歌なのか
あるいは、それほどに響き渡るほどの、「ホトトギスの鳴く声」に感嘆している歌なのか...
散るのを惜しむ歌となれば、ホトトギスに対して、もう少し諌めるような詠い方もあるだろう
かと言って、「散る花」さへも「許容」する「美声」に聞き入っているのだろうか
「散る花」、必ずしも、儚く切ないものとは限らないだろう、と思う
むしろ、その景観も優れた「美意識」に入るのではないだろうか
そして、ここでは、その更なる強力な参加者がいる
ホトトギスの鳴く声に、重なるようにして花橘が散る
私は、とても気に入っている
「散る花」の視覚的な景観に、ホトトギスの姿鳴き共演が、いかにもドラマティックだ
「桜吹雪」というではないか
「桜」には、「風」がよく似合う
「散る花橘」には、「鳴くホトトギス」が似合うかもしれない
同じように、ホトトギスが鳴いて、花橘を散らす歌がある
この歌の場合は、どうなのだろう
| 夏雑歌 大伴村上橘歌一首 |
| 吾屋前乃 花橘乎 霍公鳥 来鳴令動而 本尓令散都 |
| 我が宿の花橘を霍公鳥来鳴き響めて本に散らしつ |
| わがやどの はなたちばなを ほととぎす きなきとよめて もとにちらしつ |
| 巻第八 1497 夏雑歌 大伴宿禰村上 |
〔語義〕
「きなきとよめて」の「とよめ」は、他動詞下二段の連用形、「来て鳴き響かせて」
「もと」は、木の元
「ちらしつ」は、他動詞四段の「散らす」の連用形「散らし」に完了の助動詞「つ」
他動詞の「散らす」には、「ちらかす」というような嫌悪感のような意味合いがある
自動詞四段の「散る」だと、一般的な「花や葉などが散る」意味なので、
この違いから、この作者には、ホトトギスによって「散らされた」不満を感じる |
〔歌意〕
わが家の庭の花橘に、
ホトトギスがやって来て、その鳴き声を響かせたので
花橘は、木の下に散ってしまったではないか |
これだと、主役は「花橘」であり、ホトトギスは「悪役」を演じさせられている
そう読むのが普通なのかもしれない
では、掲題歌も、そう読むべきなのだろうか
しかし、「つつ」でこの歌は終っている
接続助詞「つつ」が文末に用いられる場合、その後に続くであろう語句を略し、
余韻を持たせる働きをするらしい
この「つつ」の後に、何を感じられるのだろう
言葉に表さなくても、見惚れてしまう「光景」が、そこにはあったのではないだろうか
散る花に合わせて、ホトトギスの鳴き声が響く
新しい発見でもしたかのように、感嘆の言葉を、詰まらせてしまう
私なら、そうすると思う
|
【赤人集(成立年時未詳[740年頃])】
| ほとときす はなたちはなの えたにゐて なきしひひけは はなはちりつつ |
| 赤人集 231 |
|
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1953] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔ほとゝきす花たちはなの枝にゐてなきとよませは花もちりつゝ 〕
霍公鳥花橘之枝尓居而鳴響者花波散乍
|
| ほとゝきす花橘の 心明也此哥此次の項に入 |
| 『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕 |
| |
霍公鳥花橘之枝爾居而鳴響者花波散乍
〔ホトヽキスハナタチハナノエタニヰテナキトヨマセハハナハチリツヽ 〕 |
| 【無記】 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
霍公鳥花橘之枝爾居而鳴響者花波散乍
〔ほとゝぎす、はなたちばなの、えだにゐて、なきならすれば、花はちりつゝ 〕 |
| 響者 これは集中あまたある義也。宗師案は、鳴なれたると云意をこめ、又詞の續きも、なきならと續く處よければ、凡てならすと讀むべしと也。然れ共どよめばと云ふ假名書あれば、どよむれば共讀べけれど、先づ此歌などは、橘になれそひなく意と見るべき歌なれば、斯く讀む也。花になれむつれて鳴くから、花も散るとよめる歌也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
〔霍公鳥、花橘之、枝爾居而、鳴響者、《ナキドヨマセバ》、花波散乍、」 〕 |
| かくるゝ事なし |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕 |
| |
霍公鳥。花橘之。枝爾居而。鳴響者。花波散乍。
〔ほととぎす。はなたちばなの。えだにゐて。なきとよもせば。はなはちりつつ。〕 |
| 參考 ○鳴響者(考)ナキトヨマセバ(古、新)略に同じ。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔霍公鳥《ホトヽギス》。花橘之《ハナタチバナノ》。枝爾居而《エダニヰテ》。鳴響者《ナキトヨモセバ》。花波散乍《ハナハチリツヽ》。〕 |
| 歌(ノ)意、かくれたるところなし、此は聲の響に、花の散をいへるなり、花を居散しとも、又は羽觸《ハフリ》に散すなどいへることも多し、みな同類なり、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔ほととぎす花橘の枝にゐてなきとよもせば花はちりつつ 〕
霍公鳥花橘之枝爾居而鳴響者花波散乍 |
| トヨモスは上なるキナキトヨメテのトヨムルにおなじ |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
| |
霍公鳥花橘の枝に居て、鳴きとよもせば、花は散りつゝ |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔ほととぎす 花橘の 枝にゐて 鳴きとよもせば 花は散りつつ〕
霍公鳥《ホトトギス》 今朝之旦明爾《ケサノアサケニ》 鳴都流波《ナキツルハ》 君將聞可《キミキキケムカ》 朝宿疑將寐《アサイカネケム》 |
郭公ガ花橘ノ咲イタ枝ニトマツテ、鳴キ聲ヲ響カセテ鳴クト、ソノ聲ノ響デ花ガ散ツタ。
〔評〕 ありのままの歌で、繪のやうな情景である。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔ほととぎす はなたちばなの えだにゐて、なきとよもせば、はなはちりつつ。〕
霍公鳥 花橘之 枝尓居而 鳴響者 花波散乍 |
【訳】ホトトギスは、花の咲いている橘の枝にいて鳴き声を立てれば、花は散つている。
【釈】鳴響者 ナキトヨモセバ。鳴いて声を立てれば。
【評語】ホトトギスが、橘の枝にとまつて鳴くと、花がほろほろとこぼれる。美しい素直な歌で、ホトトギスを描写しているのがよい。なお以下二首の順序は、古本系統による。それで番号は通行本によつて附けられているから順になっていない。 |
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| |
〔ほととぎす はなたちばなの えだにゐて なきとよもせば はなはちりつつ〕
霍公鳥 花橘之 枝尓居而 鳴響者 花波散乍 |
【大意】ほととぎすが、花橘の枝に居て、鳴きさわげば、花は散りに散る。
【作意】模様化された自然である。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
| |
〔ほととぎす はなたちばなの えだにゐて なきとよもせば はなはちりつつ〕
霍公鳥 花橘之 枝尓居而 鳴響者 花波散乍 (『元暦校本』) |
【口訳】ほととぎすが、花橘の枝に居て、鳴き立てると花はしきりに散つて...。
【訓釈】鳴きとよもせば-「とよもす」は既出(6・1057)。他動詞下二段の「とよむ」と同じ。
【考】赤人集「なきしひゞけば花ちりつゝ」、流布本「下にねて」「鳴きしひらけば花は散りつゝ」とある。この歌の順序は、『元暦校本・類聚古集(2・75)・紀州本・大矢本・京都大学本』による。『西本願寺本』は(1951)の次に別筆で紙の端に書き、更に(1948)の次へ入れるべきしるしをつけてゐる。『細井本』と版本とには次の歌の次にある。これは『西本願寺本』によつて(1948)の次へ入れるべきを(1949)の次へ誤って入れたものと思はれる。『元暦校本・類聚古集』等に従つて今改めた。『古典大系本』にはこの順序の事誤つて注せられてゐる。 |
|
| 契沖『万葉代匠記』の言う、「官本」とは |
| 今注する所の本は世上流布の本なり、字點共に校合して正す所の本は一つには官本、是は初に返して官本と注す、八條智仁親王禁裏の御本を以て校本として字點を正し給へるを、中院亞相通茂一卿此を相傳へて持給へり、水戸源三品光圀卿彼本を以て寫し給へるを以て今正せば官本と云彼官庫の原本は藤澤沙門由阿本なり、奥書あり、二つに校本と注するは飛鳥井家の御本なり、三つに幽齋本と注するは阿野家の御本なり、本是細川幽齋の本なれば初にかへして注す、四つに別校本と注するは、【正辭云、以下文缺く按ずるに水戸家にて校合せるものを云へるなるべし、】五つに紀州本と注するは紀州源大納言光貞卿の御本なり、此外、猶考がへたる他本あれど煩らはしければ出さず、三十六人歌仙集の中に此集の中の作者には人麿赤人家持三人の集あり、共に信じがたき物なれど古くよりある故に引て用捨する事あり、又六帖に此集より拔出して撰入たる歌尤多し、又代々の勅撰に再たび載られたる歌多し、見及ぶに隨て引て互に用捨せり、 |
|
掲載日:2014.03.16.
| 夏雑歌 詠鳥 |
| 霍公鳥 花橘之 枝尓居而 鳴響者 花波散乍 |
| 霍公鳥花橘の枝に居て鳴き響もせば花は散りつつ |
| ほととぎす はなたちばなの えだにゐて なきとよもせば はなはちりつつ |
| 巻第十 1953 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【類歌】〔1497〕【赤人集】〔231〕【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1953】 語義 意味・活用・接続 |
| ほととぎす [霍公鳥] |
| はなたちばなの [花橘之] |
| はなたちばな [花橘] |
花の咲いている橘の木 |
| えだにゐて [枝尓居而] |
| なきとよもせば [鳴響者] |
| なきとよもせ [鳴き響もす] |
[他サ四・已然形] 鳴き響かせる〔他マ下二動詞と同じ〕 |
| ば [接続助詞] |
[順接の確定条件(単純接続)] ~すると・~したところ |
| 〔接続〕已然形につく (未然形につけば、仮定条件になる) |
| はなはちりつつ [花波散乍] |
| つつ [接続助詞] |
[余情] ~ことだ |
連用形につく |
| 〔文末に用いると〕反復・継続の意で、余情を残した詠嘆表現 「つつ止め」 |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| 『はなたちばな』 |
橘はミカン科の常緑小高木で、今日の「こみかん」に当るようだ
その実の美味しいことは、『常陸国風土記』[香島郡]や、
『続日本紀』[天平八年(736)十一月]にも記されている |
| |
| |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[本文]「霍公鳥 花橘之 枝尓居而 鳴響者 花波散乍」
「ホトヽキス ハナタチハナノ エタニヰテ ナキトヨマセハ ハナハチリツヽ」 (「【】」は編集) |
| 〔本文〕 |
| 「波」 |
『大矢本・京都大学本』ナシ
|
| 〔訓〕 |
| エタニ |
『神宮文庫本・細井本』「ヱタニ」 |
| ナキトヨマセハ |
『類聚古集』「なきひゝかせは」
『元暦校本』「とよませ」ノ右ニ赭「ヒヽカセ」アリ
|
| アサイカヌラム |
『元暦校本』「あさいやすらむ」。「す」ノ右ニ赭「ヌ」アリ。
『類聚古集』「あさいやぬらん」。
『西本願寺本』「アサイカヌラン」 |
| 〔諸説〕 |
| ○ナキトヨマセハ『童蒙抄』「ナキナラスレハ」。 |
|
【左、資料について】
| 『万葉拾穂抄』 |
「心明也」、これも語ることもない、ということか
この歌は、掲載順序のことを、どの注釈書でも述べている |
| 『万葉代匠記(精撰本)』 |
「とよませ」が、解らない
この頃は、まだ「とよもせ」とは訓みはなく、「とよませば」となる動詞は四段しかないので
そうなると、「せ」は何だろう
「とよませば」と訓じて、その歌意を書いてある「古註釈書」、まだ出合っていない
いずれも、言わないでも解るだろう、の方式だ
|
| 『万葉集童蒙抄』 |
この書で、「どよめば」という仮名書きに言及しているが、それは自動詞なので、
他動詞の「どよむれば」だろうことも言うのに
まだ「とよもす」という他動詞四段には及んでいない |
| 『万葉考』 |
ここで、この大御所は、旧訓に立ち返る
中古末期頃から、「とよむ」は「どよむ」に使われるようになる、とされているので
真淵は、それを実践的に訓んだのだろう |
| 『万葉集略解』 |
この当たりから、現訓の姿が現れる
以降、現在にいたるまで、この訓が通っている
その背景は知ることもできないが、「とよむ」ではなく「とよもす」の語の方が
自然と文法上の不具合がなくなるからだろう、と自惚れてみる |
| 『万葉集古義』 |
| 特記なし |
| 『万葉集新考』 |
| 特記なし |
| 『口訳万葉集』 |
| 特記なし |
| 『万葉集全釈』 |
| 特記なし |
| 『万葉集全註釈』 |
| 特記なし |
| 『万葉集私注』 |
| 特記なし |
| 『万葉集注釈』 |
特記なし
|
|
|
|

 |
 |
| |
| |
| |
| |
| |
「うれたきや」...とはいうものの...
|
| 『思い遣る気持ちを』 |
| 【歌意1955】 |
なんとも残念ではないか、愚かにも...ホトトギスよ
今この時こそ、たとえ声が嗄れようと
やって来て鳴くべきなのに...そうして欲しいものだ |
|
| |
| |
この私の「歌意」には、テキスト通りの語意を忠実には汲み取っていないのかもしれない
しかし、ヒントはあった
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕が、その書で語ったように
私の為に鳴くものではないことは、充分承知している
だから、やって来て鳴いてくれ、と言っても、いい迷惑だろうが
その後は、どこへでも好きなところへ行けばいい
おそらく、こんなふうにこの歌を解釈する書は、他にはないだろう
それに、春満は、その前提として「うれたきや」ではなく「よしゑやし」としている
確かに、「うれたきや」では、こんな解釈は難しいだろう
でも、どの書でも、うんざりするような、ホトトギスへの罵り
感情的に、それが受け入れられない、という理由で
理屈に合わない歌意を強引に持ち出すことは、確かによくない
しかし、本当にそうとしか読めないのだろうか
もう一つ、手掛かりがあった
それは、逆説的な「思い遣り」と私が感じた解釈だ
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕、その歌意は
「仕様のないばかほととぎすだ この今こそ声も嗄れるほどに 来鳴きとよもせばよいのに」
これは、他の書と同じようにホトトギスを罵っているようには思えない
現代的に解釈すれば、
「今がそのチャンスなのに、どうして鳴かない 愚か過ぎやしないか」
「せっかく、お前の鳴き声を、皆楽しみにしているのに、もったいないじゃないか」
「皆に称讃されるチャンスだったのにな」
そんなふうにも感じられる、『新全集』の「歌意」だと思う
ホトトギスを案じて、残念がる
こうした言い方は、今でもよくあることだ
他の書では、今鳴いてくれないことに、腹を立て、
自分の楽しみが削がれ、尚且つ面目を失ったかのような歌意が目立つ
しかし、「よしゑやし」とする春満は、ちょっと違うにしても
現代の定訓で、同じように訳しても、『新全集』の歌意であれば
それは、「お前のためだったのに」という「思い遣り」が感じられた
実際は、そのような「意」を含んだ上での「歌意」なのかどうか解らない
しかし、私にはそう感じられたし、
その前提に、荷田春満の「思い入れ」たっぷりな解釈があったからだろう
それにしても、人間って、本当に勝手なものだ
|
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1955] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔よしえやしゆく霍公鳥今こそはこゑのかるかにきなきとよまめ 〕
慨哉四去 社者音之干蟹來喧響目
|
| よしえやしゆく郭公 よしよし今こそ声かるる迄にもなかめいつなくへきと也 |
| 『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕 |
| |
慨哉四去霍公鳥今社者音之干蟹來喧響目
〔ヨシエヤシユクホトヽキスイマコソハコヱノカルカニキナキトヨマメ 〕 |
| 此初二句の點大きに誤れり、ウレタキヤシコホトヽギスと讀べし、神武紀云、慨哉大丈夫云々、委は第八夏相聞家持の長歌の中に今の二句あるに付て注せしが如し、音之干蟹は音のかるゝかと思ふばかりにと云意なり、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
慨哉四去霍公鳥今社者音之干蟹來喧響目
此歌は、上二句のよみ樣未決。諸抄にも兩義に釋せり。何れか是ならん。宗師説の讀樣は〔よしゑよしゆくほとゝぎすいまこそは聲のかるかにきなきならさめ
〕
|
斯く讀む意は、己がさ月と今こそは聲のかるゝ計りにも、きなきならすらめ。なれば何處へ行ともよしやいとはじと、外へ行くをも今は厭はじとの意と也。拾穂抄には、よしよし今こそ聲のかるゝ迄に鳴かめ、いつ鳴べきにやと云意と注せり。予未だ得心せず。一説、慨哉四去、これは第八卷にも有詞にて、うれたきやしこ郭公と云ひて、郭公を戒め罵りたる詞と見て、歌の意は、聲のかるゝ程にも鳴き盡さで、よくもあらぬしこ時鳥と云ふ意と也
愚案、よしゑやしと讀むならば、よしゑやしいぬ郭公今社者聲の干蟹きなきどよめばと如此讀む意は、今こそはよしやいぬる共、よしや聲もかるゝにてもあら
ん、いか計り來鳴きどよめたれば、今は聲もかれたらんに、いぬる共よしやとよめるか。聲のかるかには、聲のかるゝ計りに來鳴きどよめたればと云ふ意と、聲もかれぬるかと云ふ意を兼ねてよめるならんかし
此説は、慨哉の字、日本紀の字、四去霍公鳥と云事も、前に句例あれば、かく讀まれまじきにもあらず。殊に、慨哉四の三字、よしゑやしと讀む義も、少し心得
難し。又ゆく郭公は、あてども無くゆくと詠める意も心得難ければ、うれたきやしこ、とよめる義可然らんか。然れ共歌の注は心得難し。とくと聞えたる共不覺。愚案は、うれたきやとよめるは、待てどつれなき餘りうれたきやと卑しめ罵しりて、今こそは聲のかるゝ計りにも來鳴ど
よますらめものをと、時鳥を待ちて叱りたる歌と見る也。右の聞き樣何れか是ならん。宗師の説に違ふ事いかゞなれど、予得心無ければ愚案を云ふ也。第八卷の長歌、いかといかと中畧わがもるものを宇禮多伎や志許霍公鳥〔以下畧〕 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
慨哉《ウレタキヤ》、四去霍公鳥、 今本慨哉四をよしゑやしと訓たるは誤れり既記(神武)に慨を于黎多棄《ウレタキ》と訓りよりて訓も句も改むさてうれたきはうしふれいたきてふ約たる謂なり四以下二の句にてほとゝぎすを詈て醜ほとゝぎすといふ(卷十三)に忘草をしこ草と詈りたる歌もありはつかに鳴をにくみしなり 今社者、音之干蟹《コヱノカルカニ》、 聲のかるゝまでになり
來喧響目《キナキドヨマメ》、」 どよまめは麻米の約米にて來鳴とよめと令《オホス》る辭なり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕 |
| |
慨哉。四去霍公鳥。今社者。音之干蟹。來喧響目。
〔うれたきや。しこほととぎす。いまこそは。こゑのかるかに。きなきとよまめ。〕 |
| 神武紀、慨哉此云于黎多棄加夜《ウレタキカヤ》、一二の句は他にのみ鳴くを罵りて言へり。シコは、シコノシコ草など言ふに同じく醜なり。卷八長歌に、宇禮多吉志許霍公鳥曉のうらがなしきにおへどおへどと詠めり。さて三の句よりは吾家に來りて聲の限り鳴くべき事なるをと言ふなり。カルカニは聲のカルルバカリニなり。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔慨哉《ウレタキヤ》。四去霍公鳥《シコホトヽギス》。今社者《イマコソハ》。音之干蟹《コヱノカルガニ》。來喧響目《キナキトヨマメ》。〕 |
| 本(ノ)二句は、八(ノ)卷長歌にありて、そこに委(ク)註り、○歌(ノ)意は、今こそ鳴べきをりなれば、音のかるゝばかりに、來鳴ともすべきを、來鳴ずあるは、慨《ウレタ》く惡《ニク》き醜霍公鳥《シコホトヽギス》なる哉と、なくべきをりに鳴ざるを、惡罵《ニクミノリ》ていへるなり、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔うれたきやしこほととぎす今こそはこゑのかるがに來なきとよまめ 〕
慨哉四去霍公鳥今社者音之干蟹來喧響目 |
| ウレタキヤのヤは助辭にてウレタキはシコホトトギスにかかれり。イヤナホトトギスメといはむが如し。子規のなかぬを罵りていへるなり。語例は卷八家持の長
歌(一五四七頁)にあり○カルガニは嗄ルバカリなり。上なるキナキトヨメテの例によればこゝはキナキトヨメメといふべきなれど、かく來ナキトヨマメともいひなれしなり。トヨムはヒビク、トヨムルはヒビカスにて自他の別あるなり
|
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
| |
うれたきや。醜《シコ》霍公鳥。今こそは、聲の嗄《カ》るがに、來《キ》鳴きとよまめ |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔うれたきや 醜ほととぎす 今こそは 聲の嗄るがに 來喧きとよまめ〕
慨哉《ウレタキヤ》 四去霍公鳥《シコホトトギス》 今社者《イマコソハ》 音之干蟹《コヱノカルガニ》 來喧響目《キナキトヨマメ》 |
ホントニ腹ガ立ツヨ、ロクデモナ郭公ヨ。ドウシテ鳴カナイノダラウ、今コソハ鳴クベキ時ダカラ、聲ガ枯レル程モ、此處ヘ來テ鳴ケバヨイニ。
○慨哉《ウレタキヤ》――卷八の宇禮多伎也志許霍公鳥《ウレタキヤシコホトトギス》(一五〇七)と同樣で、歎かはしいよの意であるが、ヤは切宇ではなく下につづいてゐる。○音之干蟹《コヱノカルガニ》――聲の嗄れるほどにの意。
〔評〕 可愛さあまつて憎さ百倍、來鳴かぬ郭公を罵つてゐる。右にあげた卷八のものと、句は同じで心は異なつゐてる。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔うれたきや しこほととぎす。いまこそは こゑのかるがに きなきとよまめ。〕
慨哉四去霍公鳥今社者音之干蟹來喧響目 |
【訳】腹立たしいいやなホトトギスだ。今こそ声の枯れるまで、来て鳴き立てるべきだのに。
【釈】慨哉 ウレタキヤ。ウレタキは、心痛しで、歎かわしい意。その連体形。ヤは、感動の助詞。「慨哉、此云于黎多棄伽夜(ヲバフウレタキカヤト)」(日本書紀、巻の三、神武天皇)、「宇礼多伎也(ウレタキヤ) 志許霍公鳥(シコホトトギス)」(巻八、1507)。四去霍公鳥 シコホトトギス。シコは、ホトトギスを悪く言つている。音之干蟹 コヱノカルガニ。カルガニは、嗄れるほど、嗄れるくらい。
【評語】宴会遊覧などの席で、ホトトギスの鳴かないのを恨んでいる。愛するあまり、その鳴かないのを罵倒したのが特色であるが、歌としては騒々しくなっている。時の興を助けるには足りよう。 |
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| |
〔うれたきや しこほととぎす いまこそは こゑのかるがに きなきとよまめ〕
慨哉四去霍公鳥今社者音之干蟹來喧響目 |
【大意】嘆かはしいことかな。悪いほととぎすめ、今こそ、声の嗄る程に鳴きさわげばよいのに。
【作意】ほととぎすの声の乏しいのを憎んで、責めたてる心持と見える。前の(1947)に似た場合だが、それよりも、感じ方が粗く、更に劣る。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
| |
〔うれたきや しこほととぎす いまこそは こゑのかるがに きなきとよめめ〕
慨哉四去霍公鳥今社者音之干蟹來喧響目 (『元暦校本』) |
【口訳】歎かはしい、いやなほととぎすよ。今こそ声の嗄れるばかりに、来て鳴き立てればよいのに
【訓釈】慨きや醜霍公鳥―「慨哉」は神武紀に「此云于黎多棄伽夜(ウレタキカヤ)」とあり、前にも「宇礼多伎也(ウレタキヤ) 志許霍公鳥(シコホトトギス)」(8・1507)ともあつて、ウレタキヤシコホトトギスと訓む。この「慨きや」は「かしこきや」(2・155、9・1800)などと同じく次を修飾する。
声の嗄るがに来鳴き響めめ―「がに」は既出(2・199)。ばかりに、程に。旧訓トヨマメを新校にトヨメメとしたのは、この「とよむ」は自動四段でなく他動下二段である(1828)から、その未然形「とよめ」に推量の「む」がついたもので、上の「こそ」を受けて「め」と已然形になつたので、鳴き立てればよいのに、一向鳴きもしない、の余意があつて、初二句の歎声となつたわけである。
【考】この作ウレタキヤシコの訓は代匠記にはじめて訓まれたので、アハレナリ(元)、オシヱヤシ(類)、ヨシヱヤシ(紀)などと訓まれてゐたので、従つて後の歌集には採られてゐない。 |
|
| 契沖『万葉代匠記』の言う、「官本」とは |
| 今注する所の本は世上流布の本なり、字點共に校合して正す所の本は一つには官本、是は初に返して官本と注す、八條智仁親王禁裏の御本を以て校本として字點を正し給へるを、中院亞相通茂一卿此を相傳へて持給へり、水戸源三品光圀卿彼本を以て寫し給へるを以て今正せば官本と云彼官庫の原本は藤澤沙門由阿本なり、奥書あり、二つに校本と注するは飛鳥井家の御本なり、三つに幽齋本と注するは阿野家の御本なり、本是細川幽齋の本なれば初にかへして注す、四つに別校本と注するは、【正辭云、以下文缺く按ずるに水戸家にて校合せるものを云へるなるべし、】五つに紀州本と注するは紀州源大納言光貞卿の御本なり、此外、猶考がへたる他本あれど煩らはしければ出さず、三十六人歌仙集の中に此集の中の作者には人麿赤人家持三人の集あり、共に信じがたき物なれど古くよりある故に引て用捨する事あり、又六帖に此集より拔出して撰入たる歌尤多し、又代々の勅撰に再たび載られたる歌多し、見及ぶに隨て引て互に用捨せり、 |
 |
掲載日:2014.03.17.
| 夏雑歌 詠鳥 |
| 慨哉 四去霍公鳥 今社者 音之干蟹 来喧響目 |
| うれたきや醜霍公鳥今こそば声の嗄るがに来鳴き響めめ |
| うれたきや しこほととぎす いまこそは こゑのかるがに きなきとよめめ |
| 巻第十 1955 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1955】 語義 意味・活用・接続 |
| うれたきや [慨哉] |
| うれたき [うれたし] |
[形ク・連体形] 嘆かわしい・腹立たしい・いまいましい |
| や [間投助詞] |
[感動・詠嘆] ~だなあ |
連体形につく |
| しこほととぎす [四去霍公鳥] |
| しこ [醜] |
頑固なもの・醜いものをあざけり罵っていう語 |
| いまこそは [今社者] 「こそ」は、「係り結び」の「係り」 |
| こそ [係助詞] |
[強調] ~こそ |
| 〔接続〕終助詞・間投助詞を除き、殆どの品詞につく |
| は [係助詞] |
[強調] 他の係助詞と重ねて用いることができる |
| こゑのかるがに [音之干蟹] |
| かる [嗄る] |
[自ラ下二・終止形] 声がしわがれる |
| がに [接続助詞] |
[程度・状態] ~のように・~ほどに |
| 〔接続〕動詞の終止形及び完了の助動詞「ぬ」の終止形につく |
| きなきとよめめ [来喧響目] 助動詞「む」の已然形「め」は、係り結びの「結び」 |
| とよめ [響む] |
[他マ下二・未然形] 鳴り響かせる |
| め [助動詞・む] |
[適当・当然・已然形] ~のがよい・~はずだ |
未然形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [うれたき] |
形容詞「うれたし」は、「心痛し(うらいたし)」の転じたもの
原文「慨哉」を旧訓では、「よしえやし」「よしゑよし」であったのを、
契沖『代匠記初稿版』で、初めて「うれたきや」と訓み、
真淵以降では、「うれたきや」となる
左頁の『万葉集註釈』【考】のところで、
契沖の訓で初めて用いられた、とするので、この「うれたきやしこ」という歌は、
『万葉集』以降契沖の時代まで見られない、というようなことが書いてある
|
| |
| [しこ] |
「醜(しこ)」は、本来みにくいものをいう語
転じて、不快感・嫌悪感を覚える対象を罵って用いた
|
| |
| [係助詞「は」] |
他の係助詞「ぞ」「なむ」「こそ」とは少し異なった強調の意味を持つ
「は」―「むこうは~だが、こちらは~である」と、ある物と対照して区別する意識の強調
「ぞ・なむ・こそ」―「他の何物でもなく、まさにそれが~である」と特別に取り立て、強調
このため、「は」だけは、他の係助詞と重ねて用いることができる
ただ、この歌の場合、新しい註釈書では、どれも「いまこそば」、と「は」が「ば」としている
しかし、原文が「者」なので、係助詞には間違いないと思う
何故、「いまこそば」になるのだろう
懸命に古語辞典を読み漁ったが、係助詞「は」に濁点がついて「ば」になるのは、
格助詞「を」について、「をば」になるくらいしかないと思っていたが... |
| |
| [とよめめ] |
「こそ~め」の語法は、相手に対して希求の「~してほしい」
旧訓では、「とよまめ」一辺倒で、
それは自動詞四段「とよむ」の未然形「とよま」として訓んでいる
それを、『新校万葉集』〔沢潟久孝・佐伯梅友、昭和10~11年成〕が、
他動詞下二段「とよむ」の未然形「とよめ」としたが、それでも暫くは、
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕など、旧訓に拠っていた
それが、『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕以来、
『新校』訓に拠ることになった
そもそも、自動詞四段「とよむ」と他動詞下二段「とよむ」の違いは、
古語辞典で比較すると、
自動詞「鳴り響く・響き渡る」
他動詞「鳴り響かせる」
相手に、望むことであれば、この場合、他動詞でなければ意味をなさないように思う
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[本文]「慨哉 四去霍公鳥 今社者 音之干蟹 来喧響目」
「ヨシエヤシ ユクホトヽキス イマコソハ コヱノカルカニ キナキトヨマメ」 (「【】」は編集) |
| 〔本文〕 |
| 「之」 |
『西本願寺本』コノ下「○」符アリ。ソノ右ニ字ヲ書キテ磨リ消セル痕アリ
|
| 「喧」 |
『京都大学本』「【私には判読できず】」
|
| 「目」 |
『元暦校本』ナシ。但、墨ニテ書加ヘタリ
|
| 〔訓〕 |
| ヨシエヤシユクホトヽキス |
『元暦校本』「あはれなりよもにさりにしほとゝきす」。本文ト訓トノ行間ニ赭「ヲシヱヤシ(アハレナリ)ユクホトヽキスイマコソハヲトノカレカニキナキトヨマメ」アリ
『類聚古集』「○しゑやしゆくらむほとゝきす」。墨ニテ「らむ」ヲ消セリ【「○」判読できず】
『神田本(紀州本)』「ヲシヘヤシユクホトヽキス」
『神宮文庫本・細井本』「エ」ナシ。「慨哉」ノ左ニ「オシヱ」アリ
『大矢本・京都大学本』「ヨシヱヤシユクホトヽキス」。『京都大学本』「慨哉」ノ左ニ赭「ヨシヨヤシ」アリ
『西本願寺本』「慨哉」ノ左ニ「ヲシヱヤシ」アリ
|
| イマコソハ |
『元暦校本』「ハ」ナシ |
| コヱノカルカニ |
『元暦校本』「コヱニ」ヲ「○の」トセリ。「カルカニ」ナシ【「○」判読できず】
『類聚古集』「○とのかれかに」【「○」判読できず】
『神田本(紀州本』「コヱノカレカニ」
『西本願寺本』「コエノカルカニ」
『神宮文庫本・細井本』「コヱノヤカニ」。「于」ノ左ニ「カレ」アリ
『京都大学本』「于」ノ左赭「カレ」アリ |
| キナキトヨマメ |
『元暦校本』ナシ |
| 〔諸説〕 |
○ヨシエヤシ。『代匠記(初)』「ウレタキヤ」。『童蒙抄』「ウレタシヤ」。○ユクホトヽキス。『代匠記(初)』「シコホトヽキス」
○キナキトヨマメ。『童蒙抄』「キナキナラサメ」。 |
|
【左、資料について】
| 『万葉拾穂抄』 |
「よしゑやし」の意味は、「たとえどうあろうとも」だが、
そうなると、今こそたとえ声が嗄れようと鳴くべきだろう、
一体いつ鳴くのだ、と季吟は解釈している
ただ、「ゆくほととぎす」をどう解釈したのか、私には解らない |
| 『万葉代匠記(精撰本)』 |
契沖は、旧訓をまず挙げて、そこに異を挿む
この歌が、初めて「うれたきや しこほととぎす」と訓まれた註釈書だ
『日本書紀』に、同じ語句があることをいい、『万葉集』中にも、大伴家持の長歌の一文をいう
この程度の頻度で、「だから」と言うのも不思議だが、
この時代当たりに本格的な万葉集の註釈が始まることを思えば
それ以前に諸本や註釈書の「抄」などで訓まれていたことを、一気に「改訓」する気運が高まった
そういうことだろうか
まさか、「改訓ありき」ではないと思うが、
確かに「万葉歌」の不明瞭な「訓」が「野放し状態」であったこと、
そのことへの義憤なのだと思いたい
|
| 『万葉集童蒙抄』 |
さあ、今こそ鳴いてくれ、その痕は何処へ行こうと構わない、という意味なのかな
そして『拾穂抄』の解釈を「予未だ得心せず」と否定しているようだ
つまり、大方の書が、肝腎な時に鳴かない霍公鳥を罵る解釈であるのに、
この荷田春満は、あくまでほととぎすに鳴いてくれよ、と懇願する姿勢を崩していない
そして、表記論も展開している
「慨哉」、「四去霍公鳥」という表記は、先のような例があるから、解らないでもない、と
しかし、「慨哉四」を「よしゑやし」と読める可能性も確かにありそうだが...、とする
どうも春満は、「よしゑやし」と「うれたきや」では、まったく違った歌意になることを言っている
そして私には、この註釈を充分理解できる読解力はないが、
春満は「うれたきや」という語で、ほととぎすを、ののしる歌ではない、としている感じがする
|
| 『万葉考』 |
真淵は、やはり「日本書紀」の使用例を持ち出して、「うれたきや」が正しいとしている
「慨哉」であり、「慨哉四」を「よしゑやし」と訓むのは、
「日本書紀」の「慨」を「于黎多棄《ウレタキ》」とあるので、「四」はやはり違う、と |
| 『万葉集略解』 |
| 真淵に倣いながらも、万葉歌の例を持ち出して、「うれたきやしこほととぎす」を主張する |
| 『万葉集古義』 |
| どうしても、「うれたきや」と訓めば、歌意はほととぎすを罵る歌になる |
| 『万葉集新考』 |
歌意は当時の大方の意と同じだが、「とよめめ」に言及しているのが、珍しい
『新校万葉集』の訓のまだ出ていない時期ではないだろうか
通泰は、中途半端な扱い方をしているが、自動詞他動詞の違いを指摘しているのは
これからの本格的な訓への兆しだ |
| 『口訳万葉集』 |
| 特記なし |
| 『万葉集全釈』 |
もう、この頃になると、すっかり「うれたきや」が定着している観がある
従って、その歌意もまた、いっそうきつい言葉で語られている
「ホントニ腹ガ立ツヨ ロクデモナイ郭公ヨ」 |
| 『万葉集全註釈』 |
| ここも同じくきつくホトトギスを罵っている |
| 『万葉集私注』 |
同じく、ホトトギスが鳴かないことへの罵り
鳴かないことを、責め憎んでいる、という |
| 『万葉集注釈』 |
この註釈書で、ようやく「とよめめ」が訓として登場した
それも当然だろう、著者は、「とよめめ」を提唱した『新校万葉集』と同じ著者なのだから
しかし、以降この訓が多く採られるということは
自動詞他動詞の厳密な使い分けが、検証された、ということなのだろう |
|
この一首までの三首〔1954・1953・1955〕3月15日付けで書いているが
その底本である『西本願寺本』に基づけば、歌の順序が〔1954・1955・1953〕になる
一説では、初句が「霍公鳥」が続くので、書写の混乱があっただろうとも言われている
何しろ、当時は「歌番号」など付いてはいないので、こうした混乱も多かったようだ
先日明日香でコピーした『註釈』のその頁に、『西本願寺本』の写真が載っていたので
ここに載せておく 〔最後の三首〕 |
|
| |
|
|
|
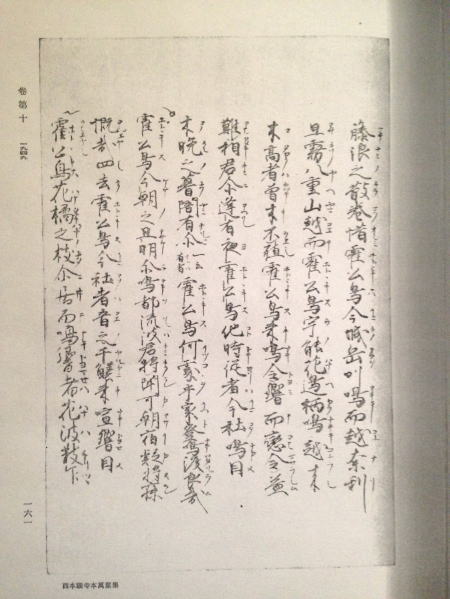 |
| |
|
|
|
|
 |
| |
| |
| |
「うのはなづくよ」...きけどもあかず...
|
| 『帰り来て鳴け』 |
| 【歌意1957】 |
五月の山に、卯の花が咲き、そして月が美しく照る夜、
ホトトギスの声は、いくら聞いても、その美しさに飽きることがない
今、飛び去ったホトトギスよ
また帰り来て、鳴いてくれないだろうか |
|
| |
夜のしじまに、月明かりに照らされる卯の花とホトトギス
しかし、月と卯の花は、そのまま今宵も共に過ごせるが
ホトトギスは、しばらく聞き惚れさせておいて
今は飛び去ってしまった
せっかくの美しい夜ではないか
もう一度、戻ってきて鳴いてくれ...この夜のために...
夜なくホトトギスは、幾つか詠われているが
実際に、夜に鳴くものかどうか...
その意味からすると、様々な註釈書で論議される「卯の花月夜」のが、
後に、歌語として詠われるような契沖や橘千蔭の説の方が現実的だろう
卯の花が白く咲き乱れ、まるで月に照らされているかのように、とする方が馴染む
しかし、「歌」には、こうした「現実」とは違う「情景」もまたある
それは、目の前に見える光景だけを詠う作者もいれば
自分の心の中に思い描く姿を、何かに託して詠う人もいるはずだ
ここでは、「卯の花月夜」がそれではないかと思う
ここに「ほととぎす」を鳴かせることで、この美しい「月夜」が生れた
だから、初句三句の評価が、それをどう思うかで分かれると思う
名詞(体言止め)を三句並べることで、新鮮さをいう学者もいれば、
平面的になる原因をいう学者もいる
私は、出来るだけ助詞を使わない方が、歌としては強烈だと思っているので
それが出来た歌には、思わず手を叩いてしまう
助詞は、受け手が心の中で響かせる方が、より感動するのではないだろうか
この歌の初句三句、何度も声に出して読むと、それだけでその光景が大きく迫ってくる
こうした歌、確かに重たくも感じる危険性はあるだろう
しかし、それは裏を返せば
それだけ受け手の心に、響くということだ
いい歌だと思う
できれば、ホトトギス
もう一度帰りに鳴き声を聞かせてほしいものだ
この素敵な夜を...
|
【赤人集(成立年時未詳[740年頃])】
| さつきやま うのはなつくよ ほとときす なけともあかす またもなかなむ |
| 赤人集 232 |
【新古今和歌集(1205年4月16日~1210年9月頃)】
| さつきやま うのはなつきよ ほとときす きけともあかす またなかむかも |
| 新古今和歌集 巻第三 夏 193 読人不知 |
【夫木抄(延慶三年頃[1310年頃])】
| さつきやま うのはなつきよ ほとときす きけともあかす またなかむかも |
| 夫木抄 巻第二十 雑二 8800 人麿 |
【歌枕名寄(嘉元元年頃[1303年頃])】
| さつきやま うのはなつきよ ほとときす なけともあかす またなかむかも |
| 歌枕名寄 巻第十六 摂津四 4491 |
|
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1957] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔さつき山うの花つきよ霍公鳥きけともあかす又なかんかも 〕
五月山宇能花月(つく)夜 雖聞不飽又鳴鴨
|
| さつき山うの花 五月比の山の卯花の白妙なる月夜をいふ也 |
| 『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕 |
| |
五月山宇能花月夜霍公鳥雖聞不飽又鳴鴨
〔サツキヤマウノハナツキヨホトヽキスキケトモアカスマタナカムカモ 〕 |
宇能花月夜、[赤人集云、ウノハナツクヨ、]
五月山は此下にもよめり、唯五月の山なり、名所にあらず、春山、秋山、彌《ヤ》生山など云が如し、古今集にも五月山梢を高み郭公、鳴音空なる戀もするかなとて各其時をよめり、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
五月山宇能花月夜霍公鳥雖聞不飽又鳴鴨 〔さつきやま、うのはなづきよ、ほとゝぎす、きけどもあかず、またなかんかも 〕
|
| 五月山 諸抄には、地名とはせず、やよひ山共よめる歌あれば、只五月の頃の山とよめる義と云へり。完師案は、卯花月夜とよめるは卯月の事にて、此歌五月山の地名、卯の花月夜とよめる取合せ上手の作と也。五月は時鳥の、己が五月とさへ詠みて鳴きふるす月也。卯月は珍しき也。五月山にて卯月に聞く處、珍しく飽かすと詠める處面白きと見る也。又鳴かんかもは、尚鳴けと願ふ意也。此歌新古今に入たり |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
五月《サツキ》山、 五月山は地の名にあらず五月の頃の山を云(卷八)に佐伯山とあるも字の誤にて五月山なるべき事はその卷にくはしくいふあはせ見るべし
宇能花月夜《ヅクヨ》、 五月の始までも卯の花の殘り咲たる夕月夜に霍公鳥をきゝてあかずおもへるなり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕 |
| |
五月山。宇能花月夜。霍公鳥。雖聞不飽。又鳴鴨。
〔さつきやま。うのはなづくよ。ほととぎす。きけどもあかず。またなかぬかも。〕 |
| サツキ山、地名に有らず、五月の頃の山なり。ウノ花ヅク夜は、卯花の盛りなるは、月夜の如く見ゆるを言へり。ナカヌカは、ナケカシと願ふ詞。モは添へたる詞なり。不鳴と書くべきを略き書けるは集中例多し。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔五月山《サツキヤマ》。宇能花月夜《ウノハナツクヨ》。霍公鳥《ホトヽギス》。雖聞不飽《キケドモアカズ》。又鳴鴨《マタナカヌカモ》。〕 |
| 五月山《サツキヤマ》は、地(ノ)名にあらず、たゞ五月ごろの山を云、古今集にも、五月山梢を高みほとゝぎすなく音そろなる戀もするかな、と見ゆ、○宇能花月夜《ウノハナツクヨ》は、卯(ノ)花の月のしろく照たるを云なるべし、(契冲は、うの花のさかりなるが月夜の如く見ゆるをいへり、といへれど、いかゞ、後(ノ)世には、しか心得てよめる歌おほかめれど、此歌なるは然にはあらじ、○又鳴鴨《マタナカヌカモ》は、いかで又もなけかしと希へるなり、○歌(ノ)意は、五月ごろの山の卯(ノ)花に、白く照たる月夜に、霍公鳥の鳴て過行なる聲の、聞どもあかず面白きに、いかで又もかへり來てなけかし、となり、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔五月山うの花月夜ほととぎすきけどもあかず又なかぬかも〕
五月山宇能花月夜霍公鳥雖聞不飽又鳴鴨 |
| ウノ花ヅクヨは古義にいへる如く卯花に月のさしたるをいへるなり。略解に『卯花のさかりなるは月夜の如く見ゆるをいへり』といへるは非なり。五月ノ山ノ卯
花月夜ニ子規ノナクヲキキシカドといふべきをテニヲハを略して上三句共に體言どめにしらべなしたる、範とはすべからず。キキシカドといふべきを現在格にてキケドモといへる、これも今は許されねど集中には例多し。マタナカヌカモは又ナケカシとなり。略解に『不鳴と書べきを略き書
るは集中例多し』といへれどセヨカシの意なるヌカモに不の字を添へて書けるは中々に集中に例なし(六二七頁及一九五二頁參照) |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
| |
五月《サツキ》山、卯の花月夜《ヅクヨ》、霍公鳥。聞けども飽かに、又鳴かぬかも |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔五月山 卯の花月夜 ほととぎす 聞けども飽かず また鳴かぬかも〕
五月山《サツキヤマ》 宇能花月夜《ウノハナヅクヨ》 霍公鳥《ホトトギス》 雖聞不飽《キケドモアカズ》 又鳴鴨《マタナカヌカモ》 |
| 五月ノ頃ノ山ニ、卯ノ花ガ盛ニ咲イテヰル月夜ニ、霍公鳥ノ鳴ク聲ヲ聞イタガ、アマリヨイ聲ナノデ聞キ飽キナイ。モツト鳴カナイカナア。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔さつきやま うのはなづくよ、ほととぎす きけどもあかず。またなかぬかも。〕
五月山宇能花月夜霍公鳥雖聞不飽又鳴鴨 |
【訳】五月の山の卯の花の月夜に、ホトトギスは、聞いても飽きない。またも鳴かないかなあ。
【釈】五月山 サツキヤマ。五月の山で、山名ではない。宇能花月夜 ウノハナヅクヨ。卯の花の咲いているのに月光の照つている夜。又鳴鴨 マタナカヌカモ。マタナカムカモ(『元暦校本』)、マタナカヌカモ(『略解』)。ヌに当る字を省いている。
【評語】美しい情景である。初三句の名詞を重ねた手法は、「淡海の海夕浪千鳥」(巻三、266)の類で、印象的である。 |
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| |
〔さつきやま うのはなづくよ ほととぎす きけどもあかず またなかぬかも〕
五月山宇能花月夜霍公鳥雖聞不飽又鳴鴨 |
【大意】五月の山卯の花の咲く月夜、ほととぎすを聞いても飽くことがない。又鳴いて欲しいものである。
【語釈】ウノハナヅクヨ 卯の花の月の差して居る夜の意であらう。気の利いた造語と見られるが、かうした造語は浅くなりがちである。
【作意】名詞を畳みかけた句法は注意を引く。但し、歌が平面的になつてしまつたのは、其為とも言へる。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
| |
〔さつきやま うのはなつくよ ほととぎす きけどもあかず またなかぬかも〕
五月山宇能花月夜霍公鳥雖聞不飽又鳴鴨 (『元暦校本』) |
【口訳】五月の山に卯の花の咲いた月夜にほととぎすが鳴くが、その声をいくら聞いても飽かない。また鳴かないかナア。
【訓釈】五月山―五月の頃の山。山の名前ではない。
卯の花月夜―卯の花の咲いている月夜。「月夜」は単に月の事をいふのが通例であるが、今いふ月夜の意味にも用ゐられるやうになつた(4・735)。代匠記に「卯花のさかりなるか、月夜のごとくみゆるをいへり」とあるは当らない。私注に「気の利いた造語とも見られるが、かうした造語は浅くなりがちである」と注意されてゐる。
又鳴かぬかも―旧訓マタナカムカモを略解にマタナカヌカモと改めたのがよい。新校にマタモナカヌカモとしたのは願望の意になる「ぬか」には上に「も」の助詞を置くのが通例(1954、3・332)だからであるが、ここは下に「も」があるので字余りの例外をつくってまで「も」を入れる必要は無い(2・119)。
【考】私注に「名詞を畳みかけた句法は注意を引く。但し、歌が平面的になつてしまつたのは、其為とも言へる」とある。
赤人集(流布本も)下句「鳴けどもあかずまたも鳴かなむ」、新古今集(三)旧訓のまま載せる。
|
|
| 契沖『万葉代匠記』の言う、「官本」とは |
| 今注する所の本は世上流布の本なり、字點共に校合して正す所の本は一つには官本、是は初に返して官本と注す、八條智仁親王禁裏の御本を以て校本として字點を正し給へるを、中院亞相通茂一卿此を相傳へて持給へり、水戸源三品光圀卿彼本を以て寫し給へるを以て今正せば官本と云彼官庫の原本は藤澤沙門由阿本なり、奥書あり、二つに校本と注するは飛鳥井家の御本なり、三つに幽齋本と注するは阿野家の御本なり、本是細川幽齋の本なれば初にかへして注す、四つに別校本と注するは、【正辭云、以下文缺く按ずるに水戸家にて校合せるものを云へるなるべし、】五つに紀州本と注するは紀州源大納言光貞卿の御本なり、此外、猶考がへたる他本あれど煩らはしければ出さず、三十六人歌仙集の中に此集の中の作者には人麿赤人家持三人の集あり、共に信じがたき物なれど古くよりある故に引て用捨する事あり、又六帖に此集より拔出して撰入たる歌尤多し、又代々の勅撰に再たび載られたる歌多し、見及ぶに隨て引て互に用捨せり、 |
|
掲載日:2014.03.18.
| 夏雑歌 詠鳥 |
| 五月山 宇能花月夜 霍公鳥 雖聞不飽 又鳴鴨 |
| 五月山卯の花月夜霍公鳥聞けども飽かずまた鳴かぬかも |
| さつきやま うのはなづくよ ほととぎす きけどもあかず またなかぬかも |
| 巻第十 1957 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【赤人集】〔232〕【新古今和歌集】〔193〕【夫木抄】〔8800〕【歌枕名寄】〔4491〕
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1957】 語義 意味・活用・接続 |
| さつきやま [五月山] 固有名詞ではなく、「五月の山」とされる |
| さつき [五月・皐月] |
陰暦五月の称 |
| うのはなづくよ [宇能花月夜] 卯の花の咲いている月夜 |
| ほととぎす [霍公鳥] |
| きけどもあかず [雖聞不飽] |
| ども [接続助詞] |
[逆接の確定条件] ~けれども・~のに |
已然形につく |
| あか [飽く] |
[自カ四・未然形] 飽きあきする・厭になる・充分満足する |
| またなかぬかも [又鳴鴨] |
| なか [鳴く] |
[自カ四・未然形] (鳥・虫・獣が)声を出す |
| ぬかも [上代語] |
[願望] ~てほしいなあ・~ないかなあ |
未然形につく |
| 〔成立〕打消しの助動詞「ず」の連体形「ぬ」+係助詞「か」+終助詞「も」 |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [うのはなづくよ] |
多くの註釈書が、この「語句」を「新しい造語」だとし、「新鮮だ」と評している
この語句が、新しい表現だとは知らなかった
『新日本古典文学大系』〔岩波文庫校訂版、平成25年~〕では、
「『卯の花月夜』は、後世卯の花が一面に白く咲くのを、月の光に見立てる歌語となっている」
と書かれており、実景だけではなく「月夜」の美しさまでも、同時に想わせる
そのように言われる「うのはなづくよ」で、もう一つの「卯の花」を思い出した
それは、「うのはなくたし」という語だ
この「うのはなくたし」は、長く降り続いて卯の花を腐らすことから、
「五月雨」の異称とされているものだ
同じように、「卯月」として今日でも普通に称する「四月」も、「卯の花月」という
「卯の花」の項目で岩波古語辞典を引けば、「うのはなづくよ」が載っていた
実景の語義と、「うのはなくたし」と同じように、
「卯の花が白く咲いて、月夜のように見えること」とある
|
| |
| [あかず] |
中古以降は、四段動詞「飽く」は、その未然形「あか」に、
打消しの助動詞「ず」がついた「あかず」の形で用いられることが多い
古語辞典で、その「飽かず」を引いてみた
満足する意の動詞「飽く」(カ行四段)は、満足し過ぎていやになる、飽きる意にも用いる。
「満足する意の」①満足しないで・物足りなく・名残惜しく
「飽きる意の」②飽きないで・厭になることなく |
|
| |
| [なかぬかも] |
旧訓は「なかむかも」
これは、推量・意志の助動詞「む」の連体形「む」の用法となり、
上代語「ぬかも」の打消しの助動詞「ず」の連体形「ぬ」と違うように思えるが、
意味は同じになるようだ
勿論、「同じ」という註釈書はないが、その場合は、
願望の終助詞「かも」のはずだ
だから、意味としては同じになると思う
しかし、「ぬかも」がその一語で「願望」を表すとは言え、
「成り立ち」の「ぬ」が打消しの助動詞なのに、
どうして、「してほしくないなあ」
となると、係助詞「か」が、「反語」ということになる
打消しを受けて、「鳴かないのかなあ、いや鳴く」と、そしてその願望...
そうとしか私の理解力では浮ばない
原文に訓に相当する「不」の表記が無いのは
その理由は解らないが、
「願望のヌカモ」の場合には「不」の表記されないことも多い、という
しかし、これについては、下段の註釈書の説明にも書くように、
いろいろとあるようだ |
| |
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[本文]「五月山 宇能花月夜 霍公鳥 雖聞不飽 又鳴鴨」
「サツキヤマ ウノハナツキヨ ホトヽキス キケトモアカス マタナカムカモ」 (「【】」は編集) |
| 〔本文〕 |
| 「鳥」 |
『類聚古集』ナシ |
| 〔訓〕 |
| ウノハナツキヨ |
『元暦校本』「うのはなさかり」。「さかり」ノ右ニ赭「ツキヨ」アリ
|
| イマコソハ |
『元暦校本』「ハ」ナシ |
| ホトヽキス キケトモアカス マタナカムカモ |
『神宮文庫本・細井本』以上ナシ
『元暦校本』「あかす」ノ「す」ノ右ニ赭「ヌ」アリ
『大矢本』「ナカムカモ」ヲ「ナカムカム」トセリ |
| 〔諸説〕 |
| ○ウノハナツキヨ。『略解』「ウノハナツクヨ」。○マタナカムカモ。『略解』「マタナカヌカモ」。 |
|
【左、資料について】
| 『万葉拾穂抄』 |
歌の文言通りの注釈...この時代、まだ本腰の「注釈」とは言えないようだ
語義解釈が中心となっているような気がする |
| 『万葉代匠記(精撰本)』 |
契沖が、本格的な注釈の始まりと言われるが、さすがに全歌を通しての注釈は困難だったと思う
これも、通り一遍の解釈に過ぎない
|
| 『万葉集童蒙抄』 |
ここで「完師案」を持ち出しているが、「完師」が何を意味しているのか、まだ私には解らない
きっと、荷田春満の「師匠筋」なのだろう
『童蒙抄』の頭から読まなければ、解らないのかもしれない...辛い
その完師の説として、他の書が「五月山」を地名としないのに、
「卯の花月」が「卯月(四月)」なので、四月に詠っているといい、従って「五月の頃」ではなく
この「五月山」は、山の名前だ、ということなのだろう
しかし、霍公鳥は「五月」の鳥、「卯月」は珍しい、と言っている
「五月山にて卯月に聞く」、それが面白い、と...
と、下手な読解力で、心もとないが、そんな記述だと思う
|
| 『万葉考』 |
ここでも、やはり「語義解釈」に重点を置いている
しかも、巻第八に「佐伯山」とあるのも、真淵は「五月山」の誤字だといい、
そのことは、巻八に詳細を述べていることを書いている
その歌を探して見たら、巻第八ではなく、第七1259(新1263)に「佐伯山」とあり、
真淵は、それを「サツキ」と訓じている
「五月山卯能花月夜とありこは佐付山とかけるを佐伯山と見たるにてはなき歟佐伯山に用なき意に見ゆるなり 」
でも、それに倣うのは、『古義』くらいではないか
『略解』では、その〔1259〕について、「サツキ」かもしれない、としている |
| 『万葉集略解』 |
「卯の花月夜」を、ただ月の夜、としないで、
卯の花の盛りが、月夜のように見える、と言っている
後世に「歌語」として詠われたと言われる一端を、ここにも見られると思う
また、原文に「不鳴」の「不」がないのも、集中例は多い、としている
「なかむかも」から「なかぬかも」への改訓も、この当たりからだろうか |
| 『万葉集古義』 |
「卯の花の月夜」を、雅澄は実景として、卯の花に白く月が照る夜、とし
契沖が解釈した、という卯の花の盛りが、月の照る如く、という説を、
この歌の場合は違う、という
確かに、後世には、そのような歌意で多くの歌が詠われていることを述べているが、
この歌は、違う、と
この『古義』で注目したいのは、ホトトギスが「鳴いて過ぎ行き」、また帰りに「鳴いてくれ」と
それまでの注釈には見られないような具体的な描写を言っていることだ |
| 『万葉集新考』 |
この書では、「卯の花月夜」を『古義』に倣って、月が卯の花に照る実景とし、
契沖、千蔭説を、否定している
さらに多くの現代の註釈書で言われている、初句からの三句が、
名詞だけで詠われていることに意外と評価が高いのだが
この井上通泰は、範としてはいけない、と批判的だ
また「なかぬかも」の「不」についての語法で、『略解』の説を否定している
確かに、「不」は省略ではなく、意味としてはその方がすっきりとする
「ぬ」は打消しであっても、「ぬかも」が願望の語意であるのなら、それでいい
でも、「なかぬかも」を「なけかし」、念を押す「かし」の意だとすると
また少し意味合いが違うような気もするが... |
| 『口訳万葉集』 |
| 特記なし |
| 『万葉集全釈』 |
| 特記なし |
| 『万葉集全註釈』 |
初三句の名詞を重ねている表現を、印象的だという
それが、美しい情景を効果的に演出しているのだろうか |
| 『万葉集私注』 |
「卯の花月夜」が気の利いた造語だ、といいながらも、浅くなりがちだ、と言う表現は
一般的にはそうなのだが、この造語もそのようだ、ということかな
そして歌が平面的、というのも、岩波の『新大系』では、引用している |
| 『万葉集注釈』 |
願望の意となる「ぬかも」だが、古語辞典では、多くの場合「も~ぬかも」だという
だから、『新校』に「マタモナカムカモ」としたのを理解はしても、字数の面で、
「なきぬかも」がいい、と『略解』の改訓を誉めている |
|
|
|
|
 |
| |
| |
| |
| |
| |
「はなたちばなの」...つちにおちむみむ...
|
| 『散る花へ』 |
| 【歌意1958】 |
ほととぎすよ、来て枝に止って鳴いてくれないか
我家の庭の花橘が、そろそろ散るぞ
おまえのその鳴き声の美しい響きや、羽音を添えて
花橘の最期の「華姿」を見たいものだ |
|
| |
| |
「落つ」という語の意味には、木の葉や花が散る、という意味もあるので
この漢字「落」で、「ちる」と訓まれることも多くある
だから、旧訓「落つ」で、後に「散る」となった、というのものではなく
「おつ」も「ちる」も、同じように読み手の感性で訓まれてきたと思う
では、私はどう訓めば自分の心に響かせられるか...
交互に読み返しながら、「おちむみむ」「ちらむみむ」、さらには「ちるもみむ」と
まるで呪文のように、諳んじていた
感覚的には、雅澄の「ちるもみむ」が最も心地よかったが、
では、それが「正しい」というものではない
それに、私は「正しいもの」を求めていたわけでもない
日本語表記の混沌としていた万葉の時代、
現代に於いて作者の唯一の表現が、何であったか、などと誰にも解ることはない
江戸時代から始まった本格的な注釈にしても
当時における実証的な検証が、多分に「感性」に拠るものであったことも想像できる
何しろ、原資料そのものに、幾つもの古写本の不整合があるのだから...
「落ちる」と「散る」
同じ言葉の意味があっても、私はその使い方で、「主客」が変わると思う
「落ちる」と言えば、この歌に当てはめると
「ホトトギスのせいで、花橘が散らされる、だから、その光景を見たいから」と私は感じる
「散る」とすれば
「やがて散る花橘、ホトトギスよ、早く来て鳴けよ、間に合わないぞ」と
あくまで、「散る」は「花橘」の「花の寿命」によって起こるもので
「散る」という言葉が、「咲き散る」というように、一体となった印象を受ける
勿論、ここにホトトギスを登場させるのは、本質ではなくなるが
その「ホトトギス」が登場することで、どの註釈書も、
ホトトギスの鳴く声や羽音で「散る」花橘を見たい、としているのではないだろうか
ホトトギスを、花橘の「最期の命」に添えるものとして感じることが
この歌を読むときに、私は最も美しい景観を目にすることが出来ると思う
註釈書がようやく本格的になされ始めた江戸時代、
それまであまり顧みられなかった『万葉集』に対して、
一体どのような経緯のもと、それが始まったのだろう
そんな疑問がしばらく拭えず、
かといって私自身があまり真剣に、それを知りたかったわけでもなく
今日まで何年も過ごしてきた
それが最近になって、当初の「歌だけを感じたい」と思う姿勢から
いろんな註釈書に触れるようになって、その古注釈書の時代の人たちと
現代人は、何が違うのだろう、と漠然と考えるようになってきた
これまで、現代の注釈書ばかり貪り読み、それで満足していたのが
ふと気づくと、それもやはり、この江戸時代に始まった「注釈書」から、
独立しているわけでもなかった
確かに継続されている「感性」だった
一般の図書館で目に触れるのは、たとえば
岩波の『大系』であり、小学館の『全集』、新潮社の『集成』など
叢書の中の「万葉集」だった
それに加えて、様々な出版社が刊行する万葉関連の「書」
多くの「書」に触れれば触れるほど、「古注釈書」の存在が大きく聳えて見える
ならば、それも読んでやろう、いや読みたくなった、というべきだ
そんな気持ちから、古書店巡りが始まり、明日香の図書館でも採り上げる歌を中心に
そのコピーを繰り返してきたが...
今になって、やっとその一つに、どうしてもっと早く目を通さなかったのだろう
そんな後悔を起こさせるほどの書に出合った
それは、橘千蔭『万葉集略解』...
当初、私は『略解』そのものに触れていると思っていた
しかし、必要な箇所の歌の注釈を読むと、そこに書かれている「補注」めいた記事、
「参考」とされる記事のことだが、千蔭の時代に合わない別の注釈書の引用が目に付き
それが気になって、今回のことに思い知らされたのだが
先日手に入れた『万葉集古義』と違って、この『略解』は、叢書の中の「書」であり
当然、内容はそのまま復元されていても、「補注」は編者の行うもの
それに惑わされて、時代が合わないのを悩み続けていたことに、気づかされた
改めて、そのことを理解した上で読むと、
不思議と「江戸時代の注釈書事情」が頭に入っているので、語そのものに抵抗感がなくなった
「語」の理解は、その「語」を使う時代の背景、環境を知れば、より効率的にできるもの
こんなことは、これを専門とする研究者や学生たちにとっては当たり前のことだろうが
素人が、自分の好みや思い込みで行っていることなので、
やはり遠回りばかりしてしまう
でも、それもまた楽しいものだ
せっかくだから、その「注釈書の黎明期」とも言える文言を、
この叢書「日本古典全集」『万葉集略解』〔1926年、与謝野寛・晶子、正宗敦夫〕から抜粋する
ここに語られていることで、当初の注釈書の環境が、よく解る
| 『萬葉集略解解題』(抜粋)[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛・晶子・正宗敦夫] |
| 一、万葉集の注釈書で全部を通じて完成したものは割合に少ない。著者の順序から云って、先ず北村季吟(西暦1624~1705)の『万葉集拾穂抄』、僧契沖(1640~1701)の『代匠記』、加藤千蔭(1734~1808)のこの『万葉集略解』、鹿持雅澄(1791~1858)の『万葉集古義』ぐらゐの物である。賀茂真淵(1697~1769)の『万葉考』は、『賀茂真淵全集』には二十巻全部出ては居るが、是れは厳密に云へば完本では無い。さて以上の本にて徳川時代に開板に成つたものは『拾穂抄』と此の『略解』の両種に過ぎなかった。(明治大正に至つて万葉集全部の講説を完成せられたのは、参考として本書に引きたる井上通泰先生の『万葉集新考』二十巻があるのみである。)然し『拾穂抄』は余り古学の開けぬ折の著述で有るから、万葉集を研究する人人はどうしても『略解』に拠らねばならなかつた。其後明治になつてから『代匠記』も『古義』も共に活版に成つたが、猶簡明にして要を得た此の『略解』は捨てられず、否、近来の如く万葉集の歌が広く人人に読まれる様になれば、殊に歌学専門家ならぬ人が一通り万葉の歌を知らうとするには此の『略解』ぐらゐ便利なものは無いので、益益人人の書架に置かれるやうに成つて、今は活版本も種種出来て居るやうである。 |
| (二項略) |
| 一、本書の奥書に「此万葉集略解すべて三十巻寛政三年二月十日より筆を起こして同八年八月十七日に稿成れり。さてあまたたび考へ正して同十二年正月十日までにみづから書き畢りぬ。橘千蔭」と有るに由つて、其の成立の年代は明らかであるが、閉門は寛政元年の事であるから其の寛政三年までは材料を集めたり、友人にも相談したりなどして、いよいよ原稿らしい原稿を書きかけたのが即ち寛政三年二月であらう。寛政八年(1796)巻一より巻五まで一帙上梓し、其後文化(1811)九年までに数回に亘りて開板せられたのである。猶帝室博物館に略解関係書簡集が二巻有る。是れを見れば略解の成立が知られる。 |
| 一、此書が深い学問も無い千蔭に由つて是れだけに出来たのは、真淵の説を受け継いだからでもあり、村田春海(1746~1811)にも随分助けられたからでもあらうが、第一に本居宣長(1645~1716)の助成の功を挙げなければなるまい。千蔭は原稿が出来ると伊勢の宣長に送って一一異見を聞いた。宣長は又自説を惜しげも無く書き加へて送り返したのである。是れが確かに『略解』をして数等好い注釈書たらしめた所以である。 |
| (一項略) |
| 一、『略解』は、実を云へば根本的に筆を加へて今の進歩した学説を取り入れた其の改訂本が世に出てもよゐのであるが、其れは今我我の目的では無い。然し此儘では此書一冊で万葉集の一通りを知りたいと思ふ人人には不足が有る。それで参考として『万葉集代匠記』、『童蒙抄』、『万葉集古義』、『万葉集新考』等の訓の異同を掲げる事にした。此訓も実を云ふと『万葉集古義』の訓として出て居ても其れは『万葉集古義』に取り用ひた訓であつて、雅澄自身の訓で無いのが多いのである。旧訓を復活したのも有れば宣長の説や久老の説も有る。其れを『古義』が取り用ひたのが『古義』の訓として掲げられて有るわけで、一一基本拠を明らかにしては無い。それは実用本位で有るからと、且つは『校本万葉集』などに拠つて専門的に知りたい人は別にしることが出来るからである。此書の参考は唯だ是に由つて其処に訓の異同の有る事を一目に知り得る為めに添へたのである。猶『代匠記』は元来本文は無くて説の有る事だけを書いた書で有るから、説のないのは旧訓でよいのであるとも云へるが、本書にはその説の有るのみを掲げた。『考』はよき考へは大体此書に採集せられて有るし、又完成した本でも無いから、大体にとどめて、『古義』と『新考』との訓に重きを置いた。 |
| 一、参考に掲ぐべき訓の異同の内でも「~オモフ、~もふ」(思)とか、「アレ、ワレ」(吾、我)とか「ワガ、アガ」(吾、我)などは一一挙げて無い。実は仮字書き以外のは如何に訓んで居たか、作者はどう詠んだのか、今日確実には知られぬ事であるから、読者の考へに任すより外偽方が無い。又「囘、廻」を「ミ」と訓ますのは『古義』や『新考』は総てさうである。大抵は挙げて置いたが、かあkる類は或は脱漏が有るかも知れぬ。初めには必ず挙げて置いた筈であるから、類推して欲しい。 |
| (以下略) |
これも、いずれ別頁に載せるまでは、下段に残しておく
|
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1958] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔ほとゝきすきゐてもなくか我宿の花たちはなのつちにおちんみん 〕
霍公鳥來居裳鳴香吾屋前乃花橘乃地二落六見牟
|
| ほとゝきすきゐて 郭公のゐる故に橘のおちぬへきを声を聞落花をみんとなるへし |
| 『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕 |
| |
霍公鳥來居裳鳴香吾屋前乃花橘乃地二落六見牟
〔ホトヽキスキヰテモナクカワカヤトノハナタチハナノツチニオチムミム 〕 |
| 鳴香は鳴かななり |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
霍公鳥來居裳鳴香吾屋前乃花橘乃地二落六見牟
〔ほとゝぎす、來居も鳴香、わがやどの、花橘の、地二ちらんみん 〕 |
| 此歌二つの聞き樣有。此本の通りにては、時鳥の來り居て鳴から、橘の地に落ちんを見んとの意に見ゆる也。宗師案は、來りて鳴かぬと見る也。奴香の奴を脱したると見る也。然らば花橘もあだに散らんを見むに、來ても鳴かぬとよめる歌と見る也。地の字もつちにと讀むと、あだと他の字の誤と見る兩義也。つちと云ふ假名書き、土の字を書ける歌もあれば、此もつちと讀べきか。尤歌によりては、他の字の誤りとも見るべき事也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
霍公鳥、來居裳《キヰモ》鳴奴香、今本奴を脱せし事しるしよて補ふ 吾屋前《ニハ》乃、花橘乃、地二《ツチニ》落六《ム》見牟、 花たちばなをちらすを見んといふなり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕 |
| |
霍公鳥。來居裳鳴香。吾屋前乃。花橘乃。地二落六見牟。
〔ほととぎす。きゐてもなくか。わがやどの。はなたちばなの。つちにおちむみむ。〕 |
| ナクカは鳴クカモの略。宣長云、六見牟は左右手の誤か。オツルマデと訓むべしと言へり。さ無くては上にナクカと言ふに叶はず。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔霍公鳥《ホトヽギス》。來居裳鳴香《キヰモナカヌカ》。吾屋前乃《ワガヤドノ》。花橘乃《ハナタチバナノ》。地二落六見牟《ツチニチルモミム》。〕 |
| 來居裳鳴香は、キヰモナカヌカと訓べし、いかで來居ても鳴(ケ)かしの意なり、○落六見牟は、六は文(ノ)字などの誤にて、チルモミムなるべし、此(ノ)下に吾屋戸之麻花押靡置露爾《ワガヤドノチバナオシナベオクツユニ》、手觸吾妹兒落卷毛將見《テフレワギモコチラマクモミム》、とあり、考(ヘ)合(ス)すべし、(略解に、六見牟は、左右手の誤にて、ツチニチルマデニなるべしといへるは強解なり、)○歌(ノ)意は霍公鳥は、いかで吾(カ)庭の花橘の枝に來居ても鳴(ケ)かし、さらば羽觸や聲の響などに、その花のちるを見べきにとなり、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔ほととぎす來居裳鳴香《キヰモナカヌカ》わがやどの花橘のつちに落六見牟《チラムミム》〕
霍公鳥來居裳鳴香吾屋前乃花橘乃地二落六見牟 |
| 弟二句を舊訓にはキヰテモナクカとよめり。古義の如くキヰモナカヌカとよむべし。來居テモ鳴ケカシとなり○落六見牟を宣長の『落左右手の誤 か。オツルマデと訓べし』といへるは鳴香のナカヌカとよむべきに心附かざりし爲なり。雅澄が落六を落文の誤としてチルモとよめるもよろしからず。もとのまゝにてチラムミムとよむべし。子規のなく頃恰花橘の散るを子規の散らすやうに當時の歌人のいひならひし事卷八(一五四九頁)にいへる如し |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
| |
霍公鳥來坐《キヰ》ても鳴くか。我が宿の花橘の地《ツチ》に散らむ、見む |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔ほととぎす 來ゐも鳴かぬか 吾がやどの 花橘の 地に落ちむ見む〕
霍公鳥《ホトトギス》 來居裳鳴香《キヰモナカヌカ》 吾屋前乃《ワガヤドノ》 花橘乃《ハナタチバナノ》 地二落六見牟《ツチニオチムミム》 |
郭公ガ今、吾ガ宿ノ花橘ニ來テ宿ツテ鳴ケヨ。アノ吾ガ宿ノ庭ノ花橘ガ、郭公ノ羽風デ散ツテ地ニ落チ散ルデアラウノヲ見ヨウ。
○來居裳鳴香《キヰモナカヌカ》――舊訓キヰテモナクカとあるが、前の歌の結句に倣つて、ナカヌカと訓まねば意が通じない。來居ても鳴けよの意である。これを舊訓に從つた爲に、宣長は結句を地二落左右手《ツチニオツルマデ》と改めてゐるが、もとよりよくない。
〔評〕 郭公の羽風に散る、花橘の美しさを思ひやつたので、優美な歌である。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔ほととぎす きゐもなかぬか。わがにはの はなたちばなの つちにちらむみむ。〕
霍公鳥來居裳鳴香吾屋前乃花橘乃地二落六見牟 |
【訳】ホトトギスは、来てとまつて鳴かないかなあ。わたしの屋前の橘の花の、地上に散るのを見よう。
【釈】來居裳鳴香 キヰモナカヌカ。キヰテモナクカ(『元暦校本』)。
來居裳鳴奴香(キヰモナカヌカ)(『童蒙抄』)。ここにも打消に当る字が省略されている。句切。
【評語】前出の「花橘の枝に居て」(1950)の歌のような、ホトトギスが橘の樹にとまつて鳴くのを願つている。作り設けた歌であるのは勿論である。 |
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| |
〔ほととぎす きゐもなかぬか わがやどの はなたちばなの つちにちらむみむ〕
霍公鳥來居裳鳴香吾屋前乃花橘乃地二落六見牟 |
【大意】ほととぎすが来てとまつて鳴いてほしい。それで、吾が家の花橘の、地に散らうのを見よう。
【作意】(1950)に比するに、表現の間接なため、感銘が弱い。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
| |
〔ほととぎす きゐもなかぬか わがやどの はなたちばなの つちにおちむみむ〕
霍公鳥來居裳鳴香吾屋前乃花橘乃地二落六見牟 (『元暦校本』) |
【口訳】ほととぎすが来てとまつて鳴かないかナア。吾が庭前の花橘の地に散るのを見よう。
【訓釈】来居も鳴かぬか―旧訓キヰテモナクカを、『童蒙抄』に、「宗師案は、来りて鳴かぬと見る也。奴香の奴を脱したると見る也」としたのは「ぬ」を単なる打消と見た誤で、『古義』がこのままキヰモナカヌカと訓み、前の「鳴鴨(ナカヌカモ)」と同様と見たのがよい。願望になる「ぬか」は「不」の文字を用ゐないこと前(7・1287)に述べた。
地に落ちむ見む―「落六」を旧訓オチムとしたのを『童蒙抄』にチランとした。前に「土哉将堕(ツチニヤオチム)」(1863)、「地尓落目八方(ツチニオチメヤモ)」(6・1010)の例があるが、ここは「花橘之・・・花波散乍(ハナハチリツツ)」(1950)、「花橘乎 地尓落津(ツチニチラシツ)」(8・1509)の例により、チラムと訓む方がよいやうにも思へる。しかしさう訓むと字余の例外となる。ここは「都知尓於知米也母(ツチニオチメヤモ)」(19・4223)などと同じく、オの単独母音を含む八音の結句として「ツチニオチムミム」と訓むべきである。 |
|
| いずれ別掲で頁を設けるまで、ここに補記として載せておく |
| 契沖『万葉代匠記』の言う、「官本」とは |
| 今注する所の本は世上流布の本なり、字點共に校合して正す所の本は一つには官本、是は初に返して官本と注す、八條智仁親王禁裏の御本を以て校本として字點を正し給へるを、中院亞相通茂一卿此を相傳へて持給へり、水戸源三品光圀卿彼本を以て寫し給へるを以て今正せば官本と云彼官庫の原本は藤澤沙門由阿本なり、奥書あり、二つに校本と注するは飛鳥井家の御本なり、三つに幽齋本と注するは阿野家の御本なり、本是細川幽齋の本なれば初にかへして注す、四つに別校本と注するは、【正辭云、以下文缺く按ずるに水戸家にて校合せるものを云へるなるべし、】五つに紀州本と注するは紀州源大納言光貞卿の御本なり、此外、猶考がへたる他本あれど煩らはしければ出さず、三十六人歌仙集の中に此集の中の作者には人麿赤人家持三人の集あり、共に信じがたき物なれど古くよりある故に引て用捨する事あり、又六帖に此集より拔出して撰入たる歌尤多し、又代々の勅撰に再たび載られたる歌多し、見及ぶに隨て引て互に用捨せり、 |
|
掲載日:2014.03.19.
| 夏雑歌 詠鳥 |
| 霍公鳥 来居裳鳴香 吾屋前乃 花橘乃 地二落六見牟 |
| 霍公鳥来居も鳴かぬか我がやどの花橘の地に落ちむ見む |
| ほととぎす きゐもなかぬか わがやどの はなたちばなの つちにおちむみむ |
| 巻第十 1958 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1958】 語義 意味・活用・接続 |
| ほととぎす [霍公鳥] |
| きゐもなかぬか [来居裳鳴香] |
| きゐ [来居る] |
[自ワ上一・連用形] 来てじっとしている・来てとまっている |
| も [係助詞] |
[強意] ~も (下に打消しの語を伴う) |
連用形につく |
| ぬか [上代語] |
[願望] (多く「~も~ぬか」の形) ~ないかなあ |
| 〔成立・接続〕打消の助動詞「ず」の連体形「ぬ」+係助詞「か」 |
未然形につく |
| わがやどの [吾屋前乃] |
| はなたちばなの [花橘乃] |
| つちにおちむみむ [地二落六見牟] |
| おち [落つ] |
[自タ上二・未然形] (木葉や花が)散る・落ちる・落花する |
| む [助動詞・む] |
[推量・連体形] ~だろう |
未然形につく |
| み [見る] |
[他マ上一・未然形] 目にとめる・眺める・目にする |
| む [助動詞・む] |
[推量(意志)・終止形] ~だろう・~よう |
未然形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [きゐもなかぬか] |
旧訓は「きゐてもなくか」だが、「~も~ぬか」が願望の意を持つというのなら
この「鳴くか」の「か」は何だろう
疑問の「か」になるだろうが...「鳴くだろうか」なのか
『童蒙抄』は、歌の字句通りでは、ホトトギスがやって来て鳴くから、花橘が地に落ちる
それを見たい、とする歌だとしながらも、「宗師」なる者の「案」を載せている
「宗師案」では、「鳴かぬ(鳴かない)」といい、
打消しの「ぬ(奴)」が脱落している、と指摘する
でも、「ぬか」と訓めば、願望になるのだから...
そうか、この解釈では、やって来て鳴きはしない、だから鳴いて欲しい、となるのかな
『万葉考』も「奴」が落ちている説、
そして、『略解』は、「鳴くか」は、「鳴くかも」の略
さらに千蔭は、この「なくか」を、
宣長説の「結句六見牟を左右手(まで)」と見合いにする意義を紹介している
「なかぬか」に落ち着くのは、『古義』当たりからだと、左の資料から伺える
|
| |
| [つちにおちむみむ] |
この「おちむみむ」、初めて知る語法のように思う
「おちむ」と「みむ」、どちらも助動詞「む」の終止形だと思ったが
きっと、以前も知った「準体言法」ではないかと思う
連体形の意味や性質を持ちながら、体言として用いられる語法だ
歌意からすると、「おちむ」がそれに当ると思う
「つちに落ちるところ」を「みたい」
それにしても、この字余りの語感は、あまり綺麗な感じがしない
|
| |
| |
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[本文]「霍公鳥 来居裳鳴香 吾屋前乃 花橘乃 地二落六見牟」(「【】」は編集)
「ホトヽキス キヰテモナクカ ワカヤトノ ハナタチハナノ ツチニオチムミム」 |
| 〔本文〕 |
| なし |
|
| 〔訓〕 |
| キヰテモナクカ |
『元暦校本』「て」ノ右ニ赭「テ」アリ
『神田本(紀州本)』「キヰテナクカモ」
|
| オチムミム |
『元暦校本』「おつるみむ」。「つる」ノ右ニ赭「チム」アリ
『神田本(紀州本)』「ヲチムミム」 |
| 〔諸説〕 |
| ○来居裳鳴香、キヰテモナクカ。『童蒙抄』師案「鳴」ノ下「奴」脱ニテ訓「キヰモナカヌカ」トス。○地ニ落六見牟、ツチニオチムミム。。『童蒙抄』師案「地」ハ「他」ノ誤ニテ訓「アダニオチムミム」トモス。『略解』宣長「六見牟」ハ「左右手」ノ誤ニテ訓「ツチニオツルマデ」カ。『古義』「六」ハ「文」ナドノ誤ニテ訓「ツチニチルモミム」トス。 |
|
【左、資料について】[近い内に、それぞれの註釈書の性格や緒言を、別掲予定]
| 『万葉拾穂抄』 |
| この解釈は、歌の言葉通りであり、まだ本格的な「注釈」ではないようだ |
| 『万葉代匠記(精撰本)』 |
契沖のいう「鳴香」は「鳴かな」という
この「な」は、願望の終助詞「な」、ということだろう
ただし、その訓に「なくか」と当てているのは、表記の面からも説明して欲しかった
|
| 『万葉集童蒙抄』 |
この時代に、まだ本格的な「註釈書」がなかったはずで、
考え方によっては、それまで混沌としていた万葉集の訓に、あらゆる可能性があったことを
この書では、他の書に比べて知ることができるような気がする
誤字説や、脱落、異なる解釈の披露など、
後の註釈書に「『童蒙抄』では」と度々散見できるのは、
この書に、それだけ当時の「異説」が多く語られているからだと思う
じっくり読みたい「註釈書」には違いない
ここでも、歌意に二通り有り得ることを述べている |
| 『万葉考』 |
歌意に特筆することはないが、この『万葉考』よりもむしろ、
『賀茂真淵全集』に語られていることが多いらしい
だから、後の千蔭にしても雅澄にしても
そもそも、この時代に参考とすべき本格的な註釈書がなく
どうしても、真淵や宣長の万葉集の解釈を参考にするとすれば
その学説は、こうした『全集』や『随筆』などから引用されているものも多くなる
だから、よほど深く検証しなければならない歌でないのなら
いくら万葉集の註釈書として有名な、この『万葉考』であっても
そこで語られるものは、結構あっさりしているように思えてならない
|
| 『万葉集略解』 |
「なくか」は、「なくかも」の略、という
その場合の「かも」は、「感嘆」なのか「願望」なのか、その説明が、やはり欲しいものだ |
| 『万葉集古義』 |
『略解』で、宣長の説を述べたのを、この『古義』は、強引な解釈だ、という
このように、この時代には、当時の学者が唱えていた学説を、
自説のように記する風潮があった、と思える節がある
実際は、誰々は、と前置きしながらも、それについて否定も賛同もしなければ
著者が、同じように考えているのかどうか、解らないまま後の読者は誤解することもあるだろう
この雅澄が『略解』に言及したこの例でも、確かに『略解』には宣長説を明記しているが、
それが後には千蔭も同じように、と理解されていたのかもしれないだ
こうした「註釈書」の黎明期とも言えるこの時代を、左頁に少し書いておきたい
結句の「ちるもみむ」は「六」が「文」の誤だとし「も」と訓むが
それは、「おちむみむ」や「ちらむみむ」と助動詞「む」を重ねる語感よりも
「ちるもみむ」なら、この「も」は係助詞の係り結びになり、その結びが「みむ」と連体形になる
確かに、この方が無理のない「語感」に思える
「おち」は未然形、同じ用法で「散る」を使うなら未然形の「ちら」
「も」とするなら、連体形の接続なので、「散る」
だから、そう読むために「も」にしなければならなかった、というように私は感じたが
なかなか賛同者はいないようだ
やはり安易(かどうかは解らないが)な誤字説、というのは、よほどの根拠がない限り難しいだろう
|
| 『万葉集新考』 |
またここでも「鳴けかし」の意、と出ているが、
この「鳴けかし」は、何度も辞書を引かなければなかなか理解できない
たまたま連日のことなので、今回は理解できたつもりでいるが、
文末について、強く念を押す意味の終助詞「かし」
活用語の終止形や命令形につく
だから、「鳴けかし」は命令形についたもので「鳴けよ」という意味になるだろう
『古義』の訓に、また『略解』に、それをたたき台にして自説を展開するのは
当時の「註釈書」の環境を知れば、仕方ないことだ |
| 『口訳万葉集』 |
| 特記なし |
| 『万葉集全釈』 |
訓は「ぬか」で、その解釈は、雅澄や井上通泰のいうような「鳴けかし」、
まさにその語義通りの歌意だ
さすがに、この時代の頃になると、現代に近くなるので、私でも少しは読み易い「文」になる
「評」がいい |
| 『万葉集全註釈』 |
花橘が、ホトトギスの鳴き声や羽音で散る光景を望む
だから、ホトトギスよ、来てくれ、という気持ち
普通の解釈だ |
| 『万葉集私注』 |
| これも他と同じような普通の解釈 |
| 『万葉集注釈』 |
歌意の解釈は有り触れていても、「奴」の脱落を用い出さず、『古義』のように
願望の「ぬか」は、打消の語を表記しない語法をいう
それに、前にも感じたことだが、「字余りの規則」が、やはり存在することを伺える
漠然と語調がどうのこうのではないらしい
独学で調べるには、あれもこれも、と欲張ってはいけない、とは思うが
やはり、早急に調べたいものだ |
|
|
|



|
 |
| |
| |
| |
| |
| |
「かづらにせむひ」...こゆなきわたれ...
|
| 『厭う時無し』 |
| 【歌意1959】 |
ほととぎすよ、お前のその鳴き渡る声は、いつも歓迎している
いつだって来ていいのだぞ
でも、出来ることなら、菖蒲を蘰にする日に合わせて
ここを鳴きながら飛んで欲しい
そうしてくれよ、ほととぎす |
|
| |
| |
いつでも厭わず来訪を歓迎する
しかし、出来ることなら...こうした懇願の仕方と言うのは
間違いなく、この日が「特別な日」ということだ
しかも、人と思うような都合に合わせられるものとは違う
だからこそ、「懇願」になってしまう
多くの注釈書が、端午の節句に菖蒲を蘰にする日、として
その日が格別、めでたい日なので
お前が、その花を添えてくれ、ということだろう
重出歌では、酒席の歌として福麻呂が詠じている、としているが
その歌が、万葉仮名で、訓には問題なく
だから、この掲題歌もまた、意訳すると同じようになるので
そう訓まれている、との発想なのだろうが
どうせ想像を発揮させるのなら、また他の舞台も用意できる
そもそも、菖蒲には匂いがあまりにも強烈ということで
邪気を祓ったり、疫病を除いたり、そんな信仰めいた習俗があったようだ
その日が、確かに端午の節句かも知れないし
あるいは、橘千蔭が言うように「五月の末日頃」かもしれない
しかし、漠然と解釈してもいいではないか、と思う
何かのお呪いをするのなら、それにいっそうの力を注ぎ込まんがために
折りよく、ホトトギスが鳴き渡ってでもくれれば
その効力はさらに強くなるのではないか、と
初二句で、いつでも歓迎する、と言うのは
本来は、ホトトギスの鳴く声を鑑賞するのが当たり前のことなのだが
今度は、その場合と違うので、どうか協力してくれないか、と
鳴き声の鑑賞は、それこそいつでも望むこと
でも、菖蒲を蘰にする日は、違うものなのだよ、ホトトギスよ、頼む
そんな風にも、思える歌だと思う
「いとふときなし」が、私にそう思わせてくれた
|
【赤人集(成立年時未詳[740年頃])】
| 時鳥いとふときなくあやめ草 かさらむひよりこゝになかなん |
| 夏雑歌 詠鳥 陽明文庫本 125 |
| ほとゝきすいとふときなくあやめくさ かさゝむ日よりこゝになかなん |
| 夏雑歌 詠鳥 書陵部本 247 |
|
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1959] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔霍公鳥いとふときなしあやめ草かつらにせん日こゆなきわたれ 〕
厭時無菖蒲蔓将為日從此鳴度礼
|
| 霍公鳥いとふ時なし 菖蒲をかつらにする事前に注こゆはこゝより也端午に鳴渡れと也 |
| 『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕 |
| |
霍公鳥厭時無菖蒲蘰將爲日從此鳴度禮
〔ホトヽキスイトフトキナシアヤメクサカツラニセムヒコユナキワタレ 〕 |
此歌第十八に田邊福麻呂再誦す、
|
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
霍公鳥厭時無菖蒲蘰將爲日從此鳴渡禮
〔ほとゝぎす、いとふときなし、あやめぐさ、かづらにせん日、こゝになきわたれ 〕 |
| 時鳥はいつをとわかず珍しけれど、わきて五月五日の菖蒲の蘰かけし日、相共に鳴渡りたらんは、いか計り面白く珍らしからんと也。いとふ時なしとは、いつにても厭ふ時日は無けれ共と云意也
|
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
霍公鳥、厭時無《イトフトキナシ》、 いとふ時はなけれどもの意なり
菖蒲《アヤメグサ》、蘰(ニ)將爲日《セムヒ》、 續紀(聖武)に天平十九年五月五日太上天皇詔曰昔者五日之節常用菖蒲爲蘰比來已停此事從今而後非菖蒲者勿入宮中と見えたりかつらにせん日は五月五日をいふなり
從此鳴度禮《コユナキワタレ》、こゝより鳴渡れなり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕 |
| |
霍公鳥。厭時無。菖蒲。蘰將爲日。從此鳴渡禮。
〔ほととぎす。いとふときなし。あやめぐさ。かづらにせむひ。こゆなきわたれ。 〕 |
| いつとても厭ふ時は無けれども、同じくは五月末日の頃ここに鳴き渡れかしとなり。菖蒲カヅラは、續紀天平十九年五月、太上天皇詔に、昔は五日節菖蒲もて縵とせり。比來已に此事やむ、今より後菖蒲縵有らずして、宮中に入る事なかれと有り。卷十八に、田邊史福麻呂が歌とて再び載せたり。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔霍公鳥《ホトヽギス》。厭時無《イトフトキナシ》。菖蒲《アヤメグサ》。蘰將爲日《カヅラニセムヒ》。從此鳴度禮《コヨナキワタレ》。〕 |
| 從此鳴度禮《コヨナキワタレ》は、此處を鳴度れの意なり、集中に多き詞なり、○歌(ノ)意は、霍公鳥の聲を、いつは聞(カ)じと厭ふ時なければ、常に聞まほしき中にも、菖蒲を蘰に製りて、頭に飾らむ日は、わきて興あれば、をりをたがへず、此處を鳴て度れ、となり、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔ほととぎす厭時《イトフトキ》無《ナシ》あやめぐさかづらにせむ日こゆなきわたれ〕
霍公鳥厭時無菖蒲蘰將爲日從此鳴度禮 |
| 略解に『いつとてもいとふ時はなけれども同じくは五月五日の比こゝに鳴わたれかしと也』と釋せり。さては第二句に辭足らねば厭時無はイトフトキナシならで
外によみやうあるべきかとも思へど卷十八に此歌の重出せるに伊等布登伎奈之と假字書にしたればなほイトフトキナシとよみて略解の釋の如く心得べし |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
| |
霍公鳥厭ふ時なし。菖蒲草《アヤメグサ》蓮《カヅラ》にせむ日、茲《コ》ゆ鳴き渡れ |
| |
子規は、何時でも聞くに心持ちの好いものだが、その中にもとり分け、菖蒲《アヤメ》をば頭に纏ひつけて遊ぶ、五月節供の日に、茲《コヽ》即我が家を鳴いて通れ。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔ほととぎす 厭ふ時なし あやめぐさ 蘰にせむ日 こゆ鳴き渡れ〕
霍公鳥《ホトトギス》 厭時無《イトフトキナシ》 菖蒲《アヤメグサ》 ※[草冠/縵]將爲日《カヅラニセムヒ》 從此鳴度禮《コユナキワタレ》
|
郭公ハ何時來テ鳴イテモイヤト云フ時ハナイ。シカシ同ジ鳴クナラ、菖蒲ヲ頭飾ノ蘰ニスル五月五日ノ頃ニ、此處ヲ鳴イテ通リナサイ。
○厭時無《イトフトキナシ》――郭公の鳴く聲を聞くのを、否と言つて嫌ふ時はないの意。○菖蒲蘰將爲日《アヤメグサカヅラニセムヒ》――五月に菖蒲を蘰としたことは蒲草玉爾貫日乎《アヤメグサタマニヌクヒヲ》(一四九〇)、その他用例が多い。
〔評〕 この歌は卷十八に保等登藝須伊等布登伎奈之安夜賣具佐加豆良爾勢武日許由奈伎和多禮《ホトトギスイトフトキナシアヤメグサカヅラニセムヒコユナキワタレ》(四〇三五)とあり、田邊史福麿とあるのは、彼が古歌を誦したものであらう。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔ほととぎす いとふときなし あやめぐさ かづらにせむひ こゆなきわたれ〕
霍公鳥厭時無昌蒲蘰將爲日從此鳴度禮 |
【訳】ホトトギスは、厭うべき時は無い。アヤメを蘰にする日に、ここを通つて鳴いて行け。
【釈】厭時無 イトフトキナシ。何時として厭う時とては無い。句切。この下に、しかし特にの如き意を含めている。
昌蒲蘰將爲日 アヤメグサカヅラニセムヒ。五月五日に、アヤメを蘰に作る。その日をいう。昌蒲は、菖蒲に同じ。アヤメ。五月の節供に使うアヤメは、サトイモ科のショウブで、葉茎根に香気がある。アヤメ科のアヤメの名を、葉の形に似ているショウブに移したのだろう。
從此鳴度禮 コユナクワタレ。コユは、ここを通つて。
【評語】五月の節供に当つて、ホトトギスの声を望んでいる。アヤメの蘰とホトトギスの取り合わせが、五月らしい気分を作っている。後に田邊の福麻呂の誦詠したという歌中に重出しているのは、古歌を誦詠したのだろうか。なおその伝来には問題があるから、その條参照。
【訳】重出。
保等登藝須 伊等布登伎奈之 安夜賣具左 加豆良尓藝武日 許由奈伎和多礼 (巻十八、4035)
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| |
〔ほととぎす いとふときなし あやめぐさ かづらにせむひ こゆなきわたれ〕
霍公鳥厭時無菖蒲蘰將爲日從此鳴度禮 |
【大意】ほととぎすは厭ふ時はない。別けてもあやめ草をかづらにする日、五月五日に此所を鳴きわたれよ。
【作意】一二句は理に泥みすぎよう。コユはここを通つての意である。天平二十年三月二十三日、巻十八(4035)に田邊福麻呂が新作と共に此の歌と前の(1900)を誦して居る。ただこれ等二首だけで福麻呂と本巻との関連を考へるまでの資料とはなり兼ねよう。しかし、その前後の家持福麻呂等の作風は、大体この前後の諸作と相通ずる所が少なくないとは言ひ得るであらう。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
| |
〔ほととぎす いとふときなし あやめぐさ かづらにせむひ こゆなきわたれ〕
霍公鳥厭時無菖蒲蘰將爲日從此鳴度禮 (『元暦校本』) |
【口訳】霍公鳥はいつ聞いても厭はしく思ふ時は無い。しかし同じくは菖蒲を蘰にする五月五日にここを鳴いて飛び渡れよ。
【訓釈】霍公鳥厭ふ時無し―「保等登藝須 伊等布登伎奈之 ホトトギス イトフトキナシ」(18・4035)とあつて、「厭」をイトフと訓む事問題は無い。(4・764)
菖蒲蘰にせむ日―「菖」の字、『元暦校本・類聚古集(2・48)』に「昌」とあり、「蒲」の字、『元暦校本・類聚古集・神田本(紀州本)』に「○/草冠に補」と見られる字になつており、それが原本の文字かと思われること前(3・423)に述べた。菖蒲を五月五日の節句に蘰にする事もそこで述べた。
こゆ鳴き渡れ―「こゆ鳴き渡る」(8・1476)ともあつた。「こゆ」は、ここを。
【考】この作巻十八(4035)に重出。流布本赤人集に「いとふ時なく」「かさゝむ日よりこゝに鳴かなむ」とある。 |
|
|
掲載日:2014.03.20.
| 夏雑歌 詠鳥 |
| 霍公鳥 厭時無 菖蒲 蘰将為日 従此鳴度礼 |
| 霍霍公鳥いとふ時なしあやめぐさかづらにせむ日こゆ鳴き渡れ |
| ほととぎす いとふときなし あやめぐさ かづらにせむひ こゆなきわたれ |
| 巻第十 1959 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【赤人集】〔陽明文庫本125〕〔書陵部本247〕
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1959】 語義 意味・活用・接続 |
| ほととぎす [霍公鳥] |
| いとふときなし [厭時無] |
| いとふ [厭ふ] |
[他ハ四・連体形] 厭だと思う・うとましく思う・嫌う |
| なし [無し] |
[形ク・終止形] ない |
| あやめぐさ [菖蒲] |
| かづらにせむひ [蘰将為日] |
| かづら [鬘] |
上代、つる草や草木の枝・花などを髪に巻き飾りにしたもの |
| せ [為(す)] |
[他サ変・未然形] ある動作を行う・様々な他の他動詞の代用 |
| む [助動詞・む] |
[推量(意志)・連体形] ~よう・~つもりだ |
未然形につく |
| こゆなきわたれ [従此鳴度礼] |
| こ [此・是] |
[近称の指示代名詞] これ・・ここ [自分に近い事物や場所] |
| ゆ [格助詞] (上代語) |
[経由点] ~から・~を通って |
体言につく |
| 同義の助詞に「ゆり・よ・より」があるが、用例が少なく、意味の違いは未詳 |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [いとふ] |
「いとふ」は、単に不快に思うのみならず、それに顔をそむけ避けようとすることをいう
|
| |
| [なし] |
ここで使われる「無し」は、逆説的な意味で解釈されている
当然、歌意からそう考えられるのだろう
初二句で、「霍公鳥よ、いつ来ても厭なことは無い」で、本来は文は成立している
しかし、下三句「菖蒲草を蘰にする日、ここを鳴きながら飛んで行け」の「文」がある
この二つの「文」を繋げるには、逆接の「けれども、でも、だが」というのかな
それが、最も解りやすい「歌意としての表現」が、新潮社の『集成』だ
「時鳥よ、いつ飛んで来て鳴いてくれてもいっこうかまわない。けれども、同じなくことなら、菖蒲の蘰を作るこの日に、ここを鳴いて渡っておくれ。」
この解釈に沿えば、何の違和感も起こらない
しかし、小学館の『新全集』の「歌意としての表現」には、中途半端な気がする
「ほととぎすよ 嫌な時などないぞ あやめぐさを 蘰にする日に ここを鳴いて行け」
このままでは、二つの「文」の接続が「順接・だから」とも充分に思えてしまう
確かに、この『新全集』でも、その表現された歌意を理解するには、
「菖蒲草を、蘰にする日が、どんな日なのか」を知っていることが前提になるものだ |
| |
| [あやめぐさ] |
ここでいう「あやめぐさ」は、現在の「菖蒲」のことで、
池や沼などに群生するサトイモ科の常緑の多年草のこと
葉は向き合って叢生し、初夏、淡黄緑色の小花を密集した円柱状の花穂にして出す
根・茎・葉など全体から独特の強い匂いを発し、
これが邪気を祓い、疫病を除くと言われている
|
| |
| [かづらにせむひ] |
あやめを蘰にする日は、端午の節句五月五日とされる説が強い
『続日本紀』天平十九年(747)五月五日の条」に、太上天皇(元正天皇)が、
「昔、五月の節には菖蒲を用ゐて蘰とす。このころすでにこの事を停む。今より後、菖蒲の鬘に非ざる者をば宮中に入るることなかれ」と詔したことが伝わっている
これは、昔は節句の日に、菖蒲の鬘を用いて宮廷に出仕していたものが、
この頃は、それが廃れてしまっている
今から、菖蒲の鬘を用いないものは、宮廷に出仕させない、と言っているものだ
しかし、こうした宮廷の外では、どうだったのだろう
その強い匂いが、邪気を祓い、疫病を除くとなれば、
「廃れる」ことなどなかったのでは、と思う
この日に「ほととぎす」の鳴き渡ることを望むのは、
市井の人たちの、そんな生活習慣に欠かせないことだったような気がする
でも、それが「五月五日」と断定できるものかどうか...
|
| |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[本文]「霍公鳥 厭時無 菖蒲 蘰将為日 従此鳴度礼」(「【】」は編集)
「ホトヽキス イトフトキナシ アヤメクサ カツラニセムトヒ コユナキワタレ」 |
| 〔本文〕 |
| 「無」 |
『類聚古集』「无」 |
| 「菖」 |
『元暦校本・類聚古集』「昌」 |
| 「将」 |
『類聚古集』右ニ墨「○【私には判読できず】」アリ |
| 「従」 |
『神田本(紀州本)・類聚古集』「徒」 |
| 「鳴」 |
『元暦校本』「口」ノ部分ハ後ノ加筆ナリ。原字ハ「嶋」カ「鳥」カ未詳 |
| 〔訓〕 |
| イトフトキナシ |
『元暦校本』「あくときもなし」。赭ニテ「も」ヲ消セリアリ
『神田本(紀州本)』「厭時」ノ左ニ「アクトキ」アリ
『西本願寺本』「イトフ」モト青
|
カツラニセムトヒ
コユナキワタレ |
『元暦校本』「かさむひよりきてなきわたれ」。「かさむひより」ノ右ニ赭「カツラセムヒモ」アリ。「ひ」ノ右ニ墨「コヽイ」アリ
『類聚古集』「かつらせむひもこゝなきわたれ」
『神田本(紀州本)』「カツラニセンヒコヽニナキワタレ」
『西本願寺本・細井本・大矢本・京都大学本・活字附訓本・神宮文庫本』「ト」ナシ
『西本願寺本』「コユ」モト青。
『細井本』「従」ノ左ニ赭「ヨリ」アリ
『近衛本』「コユ」墨 |
| 〔諸説〕 |
| ○カツラニセムトヒコユナキワタレ。『童蒙抄』「カツラニセムヒコヽニナキワタレ」。『古義』「コヨナキワタレ」。 |
|
【左頁資料について】
| 『万葉拾穂抄』 |
| 特に無し |
| 『万葉代匠記(精撰本)』 |
重出歌を記す
歌番のないこの時代に、同じ歌を見つけ出す方法とは、どんなものだったのだろう
そちらの方に、興味が湧く
|
| 『万葉集童蒙抄』 |
| 「いとふときなし」に「いとふときなけれども」と解釈をつける |
| 『万葉考』 |
同じく「なけれども」と語意をいい、
さらに続日本紀を引用し、この歌の「かつらにする日」は、五月五日だ、としている
この歌と、続日本紀の記事を関連付けての断定は、おかしい
確かに、端午の節句に鬘を付けることは、公的な記録に載ってはいるものの
それと、この歌が無条件で結びつくことにはならない
|
| 『万葉集略解』 |
千蔭は、「五月の末日の頃」としている
その根拠は何だろう
ただし、無条件で「五月五日」としないのは、いいと思う |
| 『万葉集古義』 |
| 菖蒲を鬘にする日は、興も湧くので、ほととぎす、お前も鳴いて渡れよ、 |
| 『万葉集新考』 |
千蔭が、鬘をする日を五月五日にしている、というが、それは続日本紀の記述を述べたに過ぎない
千蔭は、「五月の末日頃」と言っていると思うが...
「いとふときなし」の他の訓を試みようとするが
重出の万葉仮名の訓が、やはり大きく影響しているようで、この訓に落ち着いている |
| 『口訳万葉集』 |
| 特に無し |
| 『万葉集全釈』 |
重出の万葉歌が万葉仮名で表記されて、
当然同じような訓をこの歌に当てはめることになるのだろうが
こうした関係の歌は多く見られる
それぞれ独立した「一首」となっているのは、単に表記上の理由だろうか
それとも、この掲題歌は、他に訓まれていて
それを、後の田邊福麻呂が、この歌はこう詠むのだ、と詠じたものかもしれない
『万葉集』には、同じ歌とされながら、表記上の形の違いで重出するようだが
仮に、同じ訓であれば、『万葉集』の編者は、この「歌集」に載せるだろうか
あるいは、載せるにしても、あの歌は、こう訓むものだ、と左注にでもあれば、と思う |
| 『万葉集全註釈』 |
著者は、やはりこの歌と重出歌との伝来に、問題あり、としている
まだ、その項を参照していなので、またコピーしに明日香に行かなければならなくなった |
| 『万葉集私注』 |
この掲題歌と福麻呂との関係...
問題にしている学者も多いようだ
ただ、数が少ないのは、どうしても「確証」にまではいけないだろう
すると、永遠に残される問題...それこそが、万葉集の本質かもしれない |
| 『万葉集注釈』 |
調べてからのことだが、菖蒲を鬘にする日が、五月五日であることが決まりごとのように
多くの書に書かれているが、それが続日本紀以外の文献からであれば、確かに有効だろう
もっとも、鬘にする日とホトトギスの鳴き渡る日が、特別な日なので
行事のある五月五日に、妥当だと思わせるものは、確かにある
ただ、鬘にする日が、他の意味がないのかどうか... |
|
|
|
|
 |
| |
| |
| |
| |
| |
「なきてかくらむ」...なきひとおもほゆ...
|
| 『不如帰去』 |
| 【歌意1960】 |
ほととぎすよ、鳴きながら大和に向かうのか
その鳴く声を聞くたびに、亡くなった愛しい人が思い偲ばれ、
帰りたい、と鳴くように聞こえてならないよ |
|
| |
| |
いにしへから、人々が「ほととぎす」に託した「想い」
花を愛でたり、季節を思い起こしたり...
しかし、この歌のような強烈な託し方は、他の鳥にはない
冥土と往来出来る「ほととぎす」
「しでのやまこえてくる」という歌語が、あまりにも印象的過ぎる
歌の言葉には、詠う人、聞く人、それぞれに違う意味も有り得る
花との詠み合わせで風情を感じたりするのも、鳥ならではだ
まさか、そのような歌に、「しでのたをさ」を想起することはないだろう
やはり、一首の中に「亡き人」のような語があるからこそ
風流の鳥が、一変して「しでのたをさ」になる
中国の故事や、日本の民間伝承を知ると、
その鳴き声に、魂の叫び、という現代的な言い回しを連想する
「叫び」というほどの荒々しいものではなくても
心の底から湧き上がる「想い」、しかも「後悔の念」の強い想いが
美しい鳴き声もまた一変させる
亡き人を偲ばせる、と言いながら
その彼の声には、「また戻りたい」という切ない願いが籠められている
それを汲みながら、多くの人は、「ほととぎす」を愛している
「亡き人」をこそ、最も逢いたい人と、誰もが思うのだから...
|
【赤人集(成立年時未詳[740年頃])】
| やまとにはなくて聞らん時鳥 なかなくことになに人おもほゆ |
| 夏雑歌 詠鳥 陽明文庫本 126 |
| やまさとになきてきつらんほとゝきす なかなくことのなきもおもほゆ |
| 夏雑歌 詠鳥 書陵部本 115 |
| やまとにはなきてきつらんほとゝきす なかかくことのなきもおもほゆ |
| 夏雑歌 詠鳥 西本願寺本 235 |
【拾遺和歌集(寛弘四年[1007年頃])】
| 生みたてまつりたりける親王の亡くなりて、又の年、郭公を聞きて |
| 死出の山越えて来つらん郭公恋しき人のうへ語らなんやま |
| 巻第二十 哀傷 1307 伊勢 |
|
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1960] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔やまとにはなきてかくらむ霍公鳥なかなくことになき人おもほゆ 〕
山跡庭啼而香将來 汝鳴毎無人所念
|
| やまとにはなきてか なきてかくらんは鳴てや來らんと也四手の山より來る鳥といへはなき人を思ひ出るにや |
| 『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕 |
| |
山跡庭啼而香將來霍公鳥汝鳴毎無人所念
〔マトニハナキテカクラムホトヽキスナカナクコトニナキヒトオモホユ 〕 |
郭公を聞てなき人を思こと第八に石上堅魚のよめる歌に注するが如し
|
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
山跡庭啼而香將來霍公鳥汝鳴毎無人所念
〔やまとには、なきてかくらん、ほとゝぎす、ながなくごとに、なきひとおもほゆ 〕 |
| 山跡庭 此五文字心得難し。前にも、やまとには鳴きてかくらん喚子鳥きさの中山なきてこゆ也と云ふ歌有。此意とは、歌の意異なり。是は他國に居 て、故郷の大和を慕ひて詠める歌として見れば、何の義も無く聞ゆれど、只いづ方にて詠める共無くては聞え難き歌也。諸抄の説は、なき人を思ひ出て詠めるにや。しでの山より來ると云から、山とゝは、山外に鳴きてやくらんとの説なれど其意不詳。愚案は、庭と云ふ字、從と云字の
誤りたるか。然らば四手の田長とも詠み、蜀公の亡魂とも云來れ共、迷途の鳥など俗諺もあれば、上古も云ふらしたる事にて山跡は、よもと也。當集に同音通を用ふる事、歌毎にあれば、よもとより嶋きてか來つると云歌歟。さなくては下の句の意いかに共不濟也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
山跡(ニ)夜、啼而香將來、霍公鳥、汝鳴毎、無人所念、」 此歌は挽歌なれど郭公をよむ故に此歌にまぎれ入しなりよりて小字とすこゝに山跡といふは大名を云ならんさて山跡にありし人のなきをおもふか又なき人を葬《ヲサメ》しゆゑをいふか
|
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕 |
| |
山跡庭。啼而香將來。霍公鳥。汝鳴毎。無人所念。
〔やまとには。なきてかくらむ。ほととぎす。ながなくごとに。なきひとおもほゆ。 〕 |
| 人をうしなひて後詠めるなるべし。卷八、旅人卿の妻大津郎女みまかりし時、石上堅魚の歌に、ほととぎす來鳴とよもす卯の花の共にやこしと問はましものをと詠めるも、亡き人と共に來りしやと言ふにて、昔より郭公にさる事言ひ習はせしと見ゆ。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔山跡庭《ヤマトニハ》。啼而香將來《ナキテカクラム》。霍公鳥《ホトヽギス》。汝鳴毎《ナガナクゴトニ》。無人所念《ナキヒトオモホユ》。〕 |
| 鳴而香將來《ナキテカクラム》は、啼て行らむかの意なるを、こゝは大和の方を内にして、來《ク》と云り、倭爾波鳴而與來良武呼兒鳥象乃中山呼曾越奈流《ヤマトニハナキテカクラムムヨブコトリキサノナカヤマヨビソコユナル》、とあるに同じ、○歌(ノ)意は、あの霍公鳥は、大和の方に鳴て行ならむ歟、その聲を聞て、大和の方には愛らむかしらず、我は汝(カ)鳴音を聞ごとに、なくなりし人の上の、戀しくおもはるゝよとなり、此歌は、霍公鳥の音に感じて、なくなりし人をおもひてよめるなり、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔やまとにはなきてか來らむほととぎすながなくごとに無人《イヘビト》おもほゆ〕
山跡庭啼而香將來霍公鳥汝鳴毎無人所念 |
卷一にも
やまとにはなきてか來らむよぶこどりきさの中山よびぞこゆなる
とあり○ヤマトニハのハは輕く添へたるのみ。クラムはユクラムにおなじ。旅先にてよめるなり○無人は家人の誤ならむ |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
| |
大和には鳴きてか來らむ。霍公鳥汝が鳴く毎に、亡《ナ》き人思ほゆ |
| |
子規よ。お前は大和へ鳴いて行くのだらう。お前が鳴く度毎に、大和に居た、死んだ人のことが思ひ出される。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔大和には 啼きてか來らむ ほととごす 汝が鳴く毎に なき人おもほゆ〕
山跡庭《ヤマトニハ》 啼而香將來《ナキテカクラム》 霍公鳥《ホトトギス》 汝鳴毎《ナガナクゴトニ》 無人所念《ナキヒトオモホユ》
|
大和ノ方ヘハ郭公ガ今啼イテ行クノダラウ。アチラノ人ハオマヘノ聲ヲ聞イテ、面白ク感ズルダラウガ、ワタシハオマヘガ鳴ク度ゴトニ、死ンダ人思ヒ出シテ悲シンデヰル。
○啼而香將來《ナキテカクラム》――鳴きてか行くらむに同じ。この初二句は卷一に倭爾者鳴而歟來良武呼兒鳥象乃中山呼曾越奈流《ヤマトニハナキテカクラムヨブコドリキサノナカヤマヨビゾコユナル》(七〇)とある。
〔評〕 郭公と死人との關係が詠まれてゐるやうである。旅にあつて亡き人を思つた歌か。卷八の大伴旅人の妻が死んだ時、石上竪魚朝臣が詠んだ老公鳥來鳴令響宇乃花能共也來之登問麻思物手《ホトトギスキナキトヨモスウノハナノトモニヤコシトトハマシモノヲ》(一四七二)を合はせて考ふべきである。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔やまとには なきてかくらむ。 ほととぎす ながなくごとに なきひとおもほゆ。〕
山跡庭啼而香將來霍公鳥汝鳴毎無人所念 |
【訳】大和には鳴いてか来ることだろう。ほととぎすよ、お前が鳴く度に、死んだ人が思われる。
【釈】山跡庭啼而香將來 ヤマトニハナキテカクラム。大和では、ホトトギスが、鳴きながらか来ることだろう。作者は他の地にいて、大和の有様を想像推量している。句切。「倭尓者
鳴而歟来良武 呼兒鳥 象乃中山 呼曽越奈流 ヤマトニハ ナキテカクラム ヨブコドリ キサノナカヤマ ヨビゾコユナル」(巻一、七〇)。
【評語】ホトトギスの鳴く声に死んだ人を思つている。それと同時に故郷の恋しさも描かれている。哀情のこもつた歌だ。ホトトギスの鳴く頃に旅にあつて妻を失った大伴の旅人あたりの作だろう。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| |
〔やまとには なきてかくらむ ほととぎす ながなくごとに なきひとおもほゆ〕
山跡庭啼而香將來霍公鳥汝鳴毎無人所念 |
【大意】大和の方へ鳴いて行くのであらう。ほととぎすよ、お前の鳴く度に、亡き人が思はれる。
【作意】一二句は巻一、(七〇)の黒人の句を取つたのである。下の句としつくりしないのは、其の為であらう。故人追憶の心である。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
| |
〔やまとには なきてかくらむ ほととぎす ながなくごとに なきひとおもほゆ〕
山跡庭啼而香將來霍公鳥汝鳴毎無人所念 (『元暦校本』) |
【口訳】大和へは鳴いて行くことであらう。ほととぎすよ、お前が鳴くごとに亡くなった人が思はれる。
【訓釈】大和には鳴きてか来らむ―黒人の作(1・70)に同じ句があつた。ここはそれを採つたもので、他郷にあつて都を思つてゐる人の言葉であらう。
【考】赤人集「なきてよつらむ」「なかなくことのなきもおもほゆ」、流布本「山里になきて待つらむ」「なかなこくとの」とある。 |
|
 |
掲載日:2014.03.21.
| 夏雑歌 詠鳥 |
| 山跡庭 啼而香将来 霍公鳥 汝鳴毎 無人所念 |
| 大和には鳴きてか来らむ霍公鳥汝が鳴くごとになき人思ほゆ |
| やまとには なきてかくらむ ほととぎす ながなくごとに なきひとおもほゆ |
| 巻第十 1960 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【拾遺集和歌集】〔1307〕
【赤人集】〔陽明文庫本126〕〔書陵部本115〕〔西本願寺本235〕
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1960】 語義 意味・活用・接続 |
| やまとには [山跡庭] |
| に [格助詞] |
[位置] ~に・~で |
体言につく |
| は [係助詞] |
[とりたて(題目)] ~は |
種々の語につく |
| なきてかくらむ [啼而香将来] |
| か [係助詞] |
[疑問] ~か・~だろうか |
| 〔接続〕体言・活用語・副詞・接続助詞などが主語・目的語・連用修飾語などの場合につく |
| く [来] |
[自カ変・終止形] 来る・行く |
| らむ [助動詞・らむ] |
[現在推量・連体形] 今頃~しているだろう |
終止形につく |
| 係助詞「か」の「結び」 |
| ほととぎす [霍公鳥] |
| ながなくごとに [汝鳴毎] |
| ごと [毎] |
[接尾語] (多く「に」を伴って)~のたびに・毎~・どの~も |
| なきひとおもほゆ [無人所念] |
| おもほゆ [思ほゆ] |
[自ヤ下二・終止形] しのばれる・自然に思われる |
| 四段「思ふ」の未然形「おもは」に上代の自発の助動詞「ゆ」の付いた「おもはゆ」の転 |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [やまとには] |
この初句の解釈が、随分と様々にされていることに、驚いた
この「に」が場所を表す「位置」もあれば、方向を表す「行く先」もある
現代でも、「やまとには」と普通に使えば、次に続く語句で判断するしかないが...
|
| |
| [なきてかくらむ] |
この句が、悩ましいところだ
前句と絡めて、
小学館の『新全集』では、「大和では、もう鳴いて来たのか」
岩波の『大系』では、「大和には、今頃鳴いて行っているであろうか」
岩波の『新大系』では、「大和には、鳴きながら来ていることだろうか」
新潮の『集成』では、「家郷大和には、もう時鳥が来て鳴いていることであろうか」
講談社文庫の『全訳注』では、「今、大和には死者の霊を運んで来て鳴いているだろうか」
最も新しい校訂本である、岩波文庫の『新校訂版』は、「大和で鳴いてから来たのだろうか」
カ変動詞「来」には、「来る・行く」ともあるので、
現代語的に「来る・行く」どちらも解釈できるだろうが、上記の解釈例は、
現代でもなお、この解釈の決定的な「解」がないことを示めしている
しかし、それは作者の意を求める「正解」を示めそうというのではないだろう、と思う
この歌のように、時代と共にその語句の持つ意味合いもまた、変わり得る
それは、後の世代が、歌を読み感じるのは
過去の時代の「歌心」ばかりではなく
現代に投影される自身の「心」でもあるはずだ
研究者が、当時の作者の「意」を求めるのは当然のことだが
何も私たちまで付き合う必要はない
今の自分が、この歌をどう感じるか、だと思う
この「注記」では、客観的な語句の解説に努めなければならないが
上記の例でも解るように、共通するのは、おそらく作者が現在のその場で
ホトトギスの鳴く声を聞いている、と言うことだろう
そして、それが「大和からやって来たホトトギス」なのか、
あるいは、この鳴き声を聞いて「大和でも、ホトトギスが鳴いている」のだろうか、と
そのどちらかの立場を前提にした歌の歌意を述べているものだ
そして、その背景にある「ホトトギス」という鳥のこと...
次の項目で書くことにする |
| |
| [ほととぎす] |
これまで、「ほととぎす」の歌は多く載せてきたけど
この歌の「ほととぎす」は、その意味合いが違う
この歌のように、この鳥の鳴き声で「亡き人」を思うのは
「ほととぎす」が冥土と行き来できる「鳥」である、と認識しているからだ
左頁に、「拾遺和歌集」の一首を載せたが、その題詞に
「生みたてまつりたりける親王の亡くなりて、又の年、郭公を聞きて」とある
この掲題歌と通ずるところがある
中国の『太平寰宇記』『蜀王本紀』などに、蜀の望帝が、鼈霊に譲位した後、
再び帝位につくことを願いつつ果たさず没したのに同情した蜀の人が、
ほととぎすの鳴き声を不如帰去(フジョキキョ 帰りたい)と聞き、
望帝の魂がほととぎすに化して飛来する、と言ったことが伝承されているようだ
私は、読んでいないが、この「不如帰」という現代では使われることもある表記
この当たりから伝わったものだろうか
日本の伝承でも誤解で弟を殺してしまった兄が、死んでからホトトギスになり
「オトトコヒシ」と鳴く、というものがあるらしい
この歌で、ホトトギスの声を聞き、亡き人を偲ぶ、というのは
このような大陸からの伝承が、基にあるのだろう
契沖『代匠記』を読んでいて、このホトトギスに言及した箇所で、
「しでのたをさ」と異名があることを知った
古語辞典で引いてみると
| しでのたをさ [ホトトギスの異名] |
| 語源は「賎(しづ)の田長」で、田植えの時期を告げる鳥の意であったが、音の類似から「死出」に結び付けて、「死出の山」を越えて来る鳥と解されるようになった、という説がある |
ホトトギスが、「勧農」の鳥と認識される元は、この異名の「賎の田長」にあったのか
ただ、そのさらに根本的な、なぜ「ほととぎす」と言われるようになったのか、
それを、私はまだ知らない
|
| |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[本文]「山跡庭 啼而香将来 霍公鳥 汝鳴毎 無人所念」(「【】」は編集)
「ヤマトニハ ナキテカクラム ホトヽキス ナカナクコトニ ナキヒトホモホユ」 |
| 〔本文〕 |
| 「将」 |
『類聚古集』「持」右ニ墨「【ニ字判読できず】」アリ |
| 「無」 |
『神田本(紀州本)・類聚古集』「无」 |
| 〔訓〕 |
| ホモホユ |
『元暦校本・類聚古集』「おもほゆ」
『神田本(紀州本)・西本願寺本・細井本・大矢本・京都大学本』「オモホユ」
|
| 〔諸説〕 |
| ○ |
|
【左頁資料について】
| 『万葉拾穂抄』 |
この書を持っていないので、総論的な性格というものが解らないが
この歌の注釈で「四手の山より来る鳥といへば」とあるのは、
ホトトギスが「四手の山から来る鳥」とする認識が、現代の私たちが思いもつかないほど
ごく自然に思われていた、ということなのだろうが
となると、これまでの「ほととぎす」の鳴き声を待ちわびる歌など
その背景は、少なからず考えるべきだったような気がする
具体的に、「亡き人」のような語があって、初めてこうした語義の解釈になるのかな
左頁に載せた「拾遺集」の「しでのやまこえてきつらんほととぎす」...なるほど、と思う |
| 『万葉代匠記(精撰本)』 |
ここに引用されるのは、大伴旅人の妻・大伴郎女が亡くなり、朝廷から弔問の使者として大宰府に遣られて詠じた歌、巻第八1472(1476)のことを言う
契沖は、その歌の注で述べたように、としているので、別記に載せた
その中で、私は初めて「しでのたをさ」というホトトギスの異名を知った
|
| 『万葉集童蒙抄』 |
ここで最初に語られている疑問が、まさに私もそう感じていたところだ
だから、上の「注記」にも述べたように、曖昧な解釈になってしまう
ただ、「蜀公」とか「四手の田長」とか、この時代の人の博識には驚かされる
「やまと」は「よもと」...要は「冥土」から来る鳥、と解釈しなければ、下句に意味が繋がらない
そんなところだろうか |
| 『万葉考』 |
初句に使われる「夜」、「庭」を「夜」と書き直している
この「異同」について、他の書ではまったく触れられていないので、私はてっきりミスかと思った
しかし、1906年刊行の吉川弘文館『賀茂真淵全集第三巻』には、間違いなく「夜」とされている
真淵の『万葉考』は、[万葉集]の「巻」番号と付け方が随分違うので、
該当歌を見つけるのに本当に苦労する
歌意はともかく、「山跡夜」、「山跡」と「夜」の間に片仮名で小さく「ニ」とあるので
「やまとに」までは訓めるが、「夜」に訓がない...知りたい
|
| 『万葉集略解』 |
| 千蔭も、石上堅魚の歌を引用し、昔より、ホトトギスの「さる事いい習わし」をいう |
| 『万葉集古義』 |
雅澄は「しでのたをさ」を全面に出していないように思える
大和の方へ、鳴きながら飛んで行くホトトギスの声を聞いて
その地には、すでに亡くなった愛しい人がいたので、この声で思いを馳せ偲ぶ |
| 『万葉集新考』 |
この書も「しでのたをさ」をさらに薄めている
いや、「無」を「家」の誤字とすることで、「しでのたをさ」は消えている
ホトトギスの鳴き声に、望郷の思いを起こされた、とする解釈のようだ |
| 『口訳万葉集』 |
どの書にも共通するが、大和に鳴きながら行く、あるいは来る、というのは
それが詠われることこそ、意味があるものだと思う
だから、来る行くは別にして、亡き人を思い出させる、とする意味に対して
『新考』のような解釈よりも、この書のような解釈が一般的だと思う |
| 『万葉集全釈』 |
この解釈は、これまでの「ほととぎす」を詠んだ歌の意をも含んだ、贅沢な解釈だ
大和に鳴きながら向かうホトトギスは、都人にすれば、待ち望んだ「鳴き声」なのだろうが
作者にとっては、亡き人を思い出させる、辛いものだ、と
でも、それでは一つの歌として、想いが拡散されてしまう
「想い」は絞れば絞るほど、その強さが際立つ
でも、この書のこうした感じ方も、なかなか出来ないものだ |
| 『万葉集全註釈』 |
この著者は、この掲題歌を、大伴旅人の作の可能性を言っているが
同じような背景は、数多くあるに違いない
歌の作風からそう思ったのだろうか
それとも、単なる「心情面」から... |
| 『万葉集私注』 |
| 歌意、特筆なし |
| 『万葉集注釈』 |
| 歌意、特筆なし |
|
|
|
|
 |
| |
| |
| |
| |
| |
「ちらまくをしみ」...きなきとよもす...
|
| 『をしむれど』 |
| 【歌意1961】 |
卯の花が、そろそろ散る頃だ、惜しいことだ
そう私が思っているので、
ホトトギスが、やたらと野山を慌しく鳴き声を響かせながら飛翔している
その煩わしさが、どうも気になって仕方ない
ホトトギスもまた、同じような気持ちで、惜しんでいるのだろうか
そうでなくても、私と一緒に卯の花の散るさまを、惜しみながら見よう |
|
| |
| |
この頁の作り方は、まず右の頁から書いていく
「掲題歌」その語義、「注記」...
「古注釈書」の資料は、時間があるときに普段から入力しているので
該当歌に及ぶと、もう一度読み返す
そうしなければ、右頁の「資料について」を書くことが出来ない
語義を書きながら、「注記」では、歌意に参考になれば、と補足していくが
その段階で、私の「歌意」はほぼ出来上がっている
これは、右頁を書き終えて、左頁の「歌意」からスタートするとき
比較的、スムーズに進められるのだが...
今回は、それが出来なかった
というのも、右頁の「資料について」を書き進めている内に
少しずつ疑問が湧いてきたからだ
一種の洗脳のようなもので、「古注釈書」が一律な解釈に満ちていると
自然と、そう思うようになってしまう
それはいけない、だから語義も自分自身で調べよう、と始めたことなのに
その初心がいつの間にか失われつつあった
確かに、有り触れた歌意になると、どの注釈書も、その語義や訓に重点を置く
それは仕方ないことだ
歌意に重点を置けば、ほとんど使われる言葉が一致してしまう
だから、自分では「古注釈書」に慣らされている、とは思わないで
結局、歌意は同じだな、という程度の認識で最近は書いていたが
この歌、やはり引っかかった
卯の花が散るのを惜しんで、ホトトギスが、鳴き響き渡る、という
『私注』においては、「擬人法」の手段だとする
それは、ホトトギスの気持ちを思って、詠った、とすることか
いや、私が読みながら思ったのは、この光景を見ている作者自身のことだ
散るのを惜しんで、ホトトギスが野山を行ったり来たり、などとは
その行為に正当な理由とは思えない
勿論、「擬人法」と言ってしまえば、それも通る
何しろ、作者と会話も出来ない「鳥」だから、
作者が「擬人化」して思ったことを詠う、いい方法だとは思う
しかし、ここに詠われている最も強い「惜しむ」気持ちは、
ホトトギスではなく、詠う人の気持ちではないだろうか
卯の花も散ってしまうなあ、寂しくなる
それにしてもホトトギスの奴、私が散りそうな花を惜しんでいるのに
あんなに忙しなく、野山を飛翔しているなんて...
そうか、お前も...いや、お前は私の気持ちに付き合おうとしているのか
だったら、少し大人しく卯の花を名残惜しんでくれ
ホトトギスが飛翔するのは、客観的な実景として詠われている
それを、作者が受止める気持ちは、どのような解釈でもできる
「惜しみ」の「み」が、原因・理由の接尾語で、それがホトトギスのことに当てられるが
仮に、それが作者の気持ちであれば、その気持ちはこの歌には表出せず
私は、惜しんでいるので、そんなに翔けているホトトギスよ、一緒に惜しもう
というような気持ち...その方が、私には「惜しみ」と言う語と
ホトトギスが野山を飛翔する行為が、結びつくような気もする
|
【赤人集(成立年時未詳[740年頃])】[別掲載赤人集ついて]
| 卯花のちらまくほしき時鳥 のにて山にていれよなきこす |
| 夏雑歌 詠鳥 陽明文庫本 127 |
| うのはなのさくまておしきほとゝきす 野にいて山にいておれよなきす |
| 夏雑歌 詠鳥 書陵部本 114 |
| うのはなのさくまてをしきほとゝきす のにてやまにてをれよきけす (本) |
| 夏雑歌 詠鳥 西本願寺本 234 |
【家持集[歌仙歌集の一つ]藤原公任(966~1041)の撰)】[別掲載家持集について]
| 卯花の散らまく惜しき時鳥野にも山にも鳴きとよむかも |
| (底本[群書類従]) [新国歌大観夏歌90] |
| 卯花の散らまく惜しみ郭公野にも山にも鳴きとよむかも |
| (国歌大観、木村正辞・井上頼国監修、紀元社書店、1925年) 国歌大観 夏歌111 |
|
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1961] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔うのはなのちらまくおしみ霍公鳥野にいてやまに入きなきとよます 〕
宇能花乃散卷惜 野出山入來鳴令動
|
| うのはなのちらまく 卯花の盛になかんとて山野に出入鳴動《トヨム》と也 |
| 『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕 |
| |
宇能花乃散卷惜霍公鳥野出山入來鳴令動
〔ウノハナノチラマクヲシミホトヽキスノニイテヤマニイリキナキトヨマス 〕 |
第四の句ノニデヤマニイリと讀べし、
|
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
宇能花乃散卷惜霍公鳥野出山入來鳴令動
〔うの花の、ちらまくをしみ、ほとゝぎす、野にも山にも、きなきならせる 〕 |
| 野出山入 義をもて書きたると見れば、野にも山にもと讀む也。尤、野にで、山にり、きなき共讀べけれど、意同じければ、義をもて野にも山にもとは讀む也
|
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
宇能花乃、散卷惜《ヲシミ》、霍公鳥、野出山入《ノニデヤマニリ》、來鳴令動《キナキトヨマス》、歌の意かくるゝ事なし |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕 |
| |
宇能花乃。散卷惜。霍公鳥。野出山入。來鳴令動。
〔うのはなの。ちらまくをしみ。ほととぎす。のにでやまにいり。きなきとよもす。 〕 |
| 郭公が卯の花を惜むさまに詠めるなり。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔〔宇能花乃《ウノハナノ》。散卷惜《チラマクヲシミ》。霍公鳥《ホトヽギス》。野出山入《ヌニデヤマニリ》。來鳴令動《キナキトヨモス》。〕 |
歌(ノ)意は、卯(ノ)花は、程なく散失べき樣に見ゆれば、その散失なむことを、霍公鳥の深く惜て、或は野に出、或は山に入など、とにかくして鳴とよもすならむ、となり、
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔うの花のちらまくをしみほととぎす野出《ヌニデ》山入《ヤマニリ》きなきとよもす〕
宇能花乃散卷惜霍公島野出山入來鳴令動 |
| 舊訓に野ニデ山ニイリとよめるを古義にヤマニリとよめり。ニにイの韻あればヤマニリとよみても可なり |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
| |
卯の花の散らまく惜しみ、霍公鳥、野山にかよひ、來鳴きとよもす |
| |
卯の花の散るのが惜しさに、子規が野や山の間を出没往來して、あちこちで鳴いて、あたりを響かして居る |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔卯の花の 散らまく惜しみ ほととぎす 野に出山に入り 來鳴きとよもす〕
宇能花乃《ウノハナノ》 散卷惜《チラマクヲシミ》 霍公鳥《ホトトギス》 野出山入《ヌニデヤマニイリ》 來鳴令動《キナキトヨモス》
|
卯ノ花ガ散ルノヲ惜シンデ、霍公鳥ハ野ニ出タリ山ニ入ツタリシテ、コノ邊ニ來テ聲ヲ響カセテ鳴イテヰル。
○野出山入《ヌニデヤマニイリ》――野山に出入して郭公が、治躍して鳴く有樣である。
〔評〕 卯の花の咲く野山を翔りつつ鳴く郭公の樣が、生生と詠まれてゐる。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔うのはなの ちらまくをしみ ほととぎす のにいでやまにいり きなきとよもす〕
宇能花乃散卷惜霍公島野出山入來鳴令動 |
【訳】卯の花の散りそうなのを惜しんで、ホトトギスは、野に出たり山にはいつたりして、来て鳴き立てている。
【釈】來鳴令動 キナキトヨモス。令動は、響かせる、音を立てさせる意。動だけで、トヨムに当てたと思われる例は、案外多い。
【評語】ホトトギスが、卯の花の散りそうなのを惜しんで鳴くというのは、類型的だが、この歌では、野ニ出デ山ニ入リの句が、特殊の句で、これで一首が生きている。ホトトギスがいかにも散るのを惜しんで往来するような様が描かれている。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| |
〔うのはなの ちらまくをしみ ほととぎす ぬにでやまにいり きなきとよもす〕
宇能花乃散卷惜霍公島野出山入來鳴令動 |
【大意】卯の花の散るのが惜しく、ホトトギスが、野にで、又山に入り、来て鳴きさわぐ。
【作意】例の擬人法であるが、煩瑣な歌だ。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
| |
〔うのはなの ちらまくをしみ ほととぎす のにでやまにいり きなきとよもす〕
宇能花乃散卷惜霍公島野出山入來鳴令動 (『元暦校本』) |
【口訳】卯の花の散ることを惜しんでほととぎすは野に出たり山にはひつたりして、来て鳴き立ててゐる。
【訓釈】野に出山に入り―旧訓ノニイデヤマニイリを代匠記にノニデヤマニイリと改めた。イデと訓んでもイの単独母音が二つあるから九音になる事も許される(1・7)が、「出で」は「宇良尓低尓家里(ウラニデニケリ)」(14・3374)、「己登尓氐尓思可(コトニデニシカ)」(14・3497)などデとも訓まれてゐるのでここはノニデとして八音に訓むがよい。
【考】上三句同想の作が前(1944)にもあった。
赤人集「さくまで惜しき」「のにてやまにてをれよきけす本」とあり、流布本「のにいで山にいてをれかなきかす」、
家持集「ちらまく惜しき」「野にも山にも鳴きとよむかも」とある |
|
|
掲載日:2014.03.22.
| 夏雑歌 詠鳥 |
| 宇能花乃 散巻惜 霍公鳥 野出山入 来鳴令動 |
| 卯の花の散らまく惜しみ霍公鳥野に出で山に入り来鳴き響もす |
| うのはなの ちらまくをしみ ほととぎす のにいでやまにいり きなきとよもす |
| 巻第十 1961 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【赤人集】〔陽明文庫本127〕〔書陵部本114〕〔西本願寺本234〕【家持集】〔90(111)〕
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1961】 語義 意味・活用・接続 |
| うのはなの [宇能花乃] |
| ちらまくをしみ [散巻惜] |
| ちら [散る] |
[自ラ四・未然形] (花や葉などが)散る |
| まく [助動詞・む] |
[推量・ク語法] ~であろうようなこと |
| 〔上代語・未来の推量〕〔接続〕活用語の未然形につく |
| をし [惜し] |
[形シク・終止形] 失うにしのびない・惜しい・残念だ |
| み [接尾語] |
[原因・理由] ~ので・~から |
終止形につく |
| 形容詞、形容詞型助動詞の語幹につくが、シク活用には「終止形」につく |
| ほととぎす [霍公鳥] |
| のにいでやまにいり [野出山入] 野山を飛び翔っているさま |
| きなきとよもす [来鳴令動] |
| きなきとよもす [来鳴き響くもす] |
[複合動詞四・終止形] 鳥が来て鳴き声を響かせる |
| 〔成立〕カ変動詞「来(く)」の連用形「き」+四段「鳴く」の連用形「なき」+四段「響もす」 |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [ちらまく] |
旧訓も含め「ちらまく」と訓むのは、間違いのないことだが
『細井本』に「ちりまく」との異訓を、『校本万葉集』は伝えている
上代語で未来の推量「まく」は、助動詞「む」の「ク語法」とされ、
その接続は、助動詞「む」と同じく「未然形」になる
だから、四段「散る」の未然形「ちら」に接続し「ちらまく」となる
しかし、「ちりまく」では、連用形接続だ
『細井本』は、あまり評価されていない古写本のようなので、誤記なのかな
それとも、当時の活用で、こうした「併用」も許容されていたのかなあ
|
| |
| [のにいでやまにいり] |
原文「野出山入」、表記を見ただけでも、「野に出て山に入って」とすぐ浮ぶ
まさに表記が「語意」を表わしているが、これを「歌」として「訓」をつけるとなると
結構難しいものだろう
現代の注釈書での訓は、そうした苦労の流れの中で落ち着いたものだが、
何よりその苦労が伺われるのが、「九字」という珍しい「字余り」になっていることだ
左の古注釈を見ると、
『童蒙抄』で「のにもやまにも」といい、「七音」に収まり、
それで決まるのかな、と思えば賀茂真淵の「のにでやまにり」が唱えられる
その後、千蔭『略解』が旧訓に戻ったものの、
今度は、雅澄『古義』が当時「の」を「ぬ」と訓むべき、という風潮のもと、
「ぬにでやまにり」とし、一応字余りは避けられ
その後も、「やまにり」を井上通泰が、その『新考』で、
「ニにはイの韻がある」と解説して、「やまにいり」は「やまにり」も可能だとした
これは、通常の「ことば」を、あくまで「歌語」として作り変えた、ということだ
それは、字余りを極力避ける、ということで、私は悪いこととは思わないが、
後世に、どれだけ評価されるか、と言うことになると思う
評価されなければ、定訓としては残らない...資料としては残るだろうが...
さらに、折口信夫『口訳万葉集』では、「のやまにかよひ」
まさに字余りを避け、語意を表面的には通している
しかし、その「歌意」を見ると、「のやまにかよひ」が、実に深く汲み取られており
それでは、もう少し「訓」に工夫があればなあ、と感じてしまう
その後の訓にも、その流れというのは一定ではなく、
行つ戻りつ、の感がある
ただ、「七字」という先訓もありながら、
「八字」「九字」もまた取り入れられているのは、珍しいことだと思う
字数もさることながら、出来る限り表記に忠実に訓む、という姿勢かな |
| |
| |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[本文]「宇能花乃 散巻惜 霍公鳥 野出山入 来鳴令動」(「【】」は編集)
「ウノハナノチラマクヲシミホトヽキスノニイテヤマニイリキナキトヨマス」 |
| 〔本文〕 |
| |
|
| 〔訓〕 |
| チラマクヲシミ |
『西本願寺本』「チラマクオシミ」
『細井本』「チリマクオシミ」
|
| ノニイテヤマニイリ |
『神田本(紀州本)』「テ」ノ下ニ「ヽ」ヲ削レル痕アリ。
『京都大学本』漢字ノ左ニ赭「ノイテヤマイリ」アリ。 |
| キナキトヨマス |
『元暦校本』「す」ノ右ニ赭「セ」アリ
『京都大学本』「令動」ノ左ニ赭「トヨメス」アリ |
| 〔諸説〕 |
| ○ノニイテヤマニイリ。『代匠記(精撰本)』「ノニデヤマニイリ」。『童蒙抄』「ノニモヤマニモ」。 |
|
【左頁資料について】
| 『万葉拾穂抄』 |
| 卯花の盛りに鳴こう、と山野に出入り...散る間際が、盛りというのでこう言うのだろう |
| 『万葉代匠記(精撰本)』 |
原文表記を、忠実に訓むと、こうなると思う
それが、「歌語」に相応しいかどうか、まだ問われない時代なのかな
ここで「のにいで」を「のにで」と訓むなら、
「やまにいり」も「やまにり」でも良さそうだと思うが...
|
| 『万葉集童蒙抄』 |
訓ではないが、「山にり」と言葉が使われている
「山に入り」という言葉は、普通に「やまにり」という音としてあったのだろうか |
| 『万葉考』 |
歌意は明白としているが、「とよます」は、「とよもす」の古形なのだろうか
使役の助動詞「す」なら、四段「とよむ」の未然形「とよま」について「鳴き渡らせる」だろうが
それでも、歌意は通じる
|
| 『万葉集略解』 |
| 特に無し |
| 『万葉集古義』 |
雅澄は、ホトトギスの心情を汲み上げようとしに歌意に書き込んだ
この説明に基づき、「野に出、山に入り」が、尋常でないことが伝わる |
| 『万葉集新考』 |
「ぬ」はともかく「ぬにでやまにり」と七字ですっきり訓むことを、「歌」の基本としている
このように、真淵以来の流れが、尊重されている |
| 『口訳万葉集』 |
これまでの訓は、語義解釈がほとんどだが、折口信夫は『口訳』と名に違わず、
歌意だけに心掛けている
注釈書、というより、ある歌人であり学者でもある人の、「歌の感じ方」を知ることが出来る書だ |
| 『万葉集全釈』 |
「評」にもいうように、確かに生き生きとして詠われているのだろうが、
それは、必ずしも「元気な姿」とはならない
散るのを惜しんで、慌しく今が見納め、と「もがき」にも似た様子のことだ、と思う
それを「生き生きと」と言えるかどうか... |
| 『万葉集全註釈』 |
そもそも、古い順に注釈書を読んできたものの、ここで少し気づいたことがある
散る卯の花を惜しむ、という気持ちが、野に山に、慌しく飛翔することと、
あまり結びつかないのではないか、と
歌の表現だけで、そう読まざるを得ないのは解るが
逆に言えば、ホトトギスが卯の花の散るのを惜しむ、というのは
作者、いや注釈者の主観で葉無いか、と思えてきた |
| 『万葉集私注』 |
| 歌意、特筆なし |
| 『万葉集注釈』 |
| 「音韻」の扱い方を、もっと知りたくなるような注釈だと思う |
|
|
|

|
 |
| |
| |
| |
| |
| |
「つねにふゆまで」...すみわたるがね...
|
| 『そのために』 |
| 【歌意1962】 |
橘の木をたくさん植えて林にしよう
この樹が好きなほととぎすがやってきて、
その冬まで、美しい鳴き声を聞かせてくれるように
そうやって、毎年々々聞かせて欲しいから... |
|
| |
| |
特別な想いを巡らせなくても、この歌の歌意は、大方このようだと思う
だから、『童蒙抄』の荷田春満の歌意に接したとき、まったく思いもよらなかった解釈なので
そこで、しばらく考え込んでしまった
このような解釈は、江戸中期の人たちに、どんな風に受け取られたのだろうか
理論的でない、合理性がない、無理な懇願だ、とでも言われたのだろうか
しかし、そんな解りきった「無茶」を「うたごころ」と解せることも
「歌だからこそ」とも言えるのではないかと思う
そもそも、「たちばなの はやしをうゑむ」という語句が、それを物語っている
よし、これから詠う歌は、「夢物語」だぞ、と宣言しているかのようだ
荷田春満のように解釈して初めて、この初二句が生きてくるのかもしれない
そうでないと、ありきたりの解釈では、「はやしをうゑむ」は、
あまりにも大事過ぎる
私には、まったく思いもしなかったが、
歌として詠むなら、その意味で感じた方がいいのかもしれない
お前の好きな橘の木を、いっぱいいっぱい、
それこそ林みたいにたくさん植えるぞ
そうしたら、ホトトギスよ、もう帰らなくても
ここにずっと住むことが出来るじゃないか
ここで過ごす四季もいいものだぞ
俺も、お前の鳴き声を、ずっと聞いていたいから... |
|
【赤人集(成立年時未詳[740年頃])】[別掲載赤人集について]
| たち花のはやしとそ思時鳥 つねにすみたるかもなし |
| 夏雑歌 詠鳥 陽明文庫本 128 |
| たちはなのはやしをうへむほとゝきす つねに冬まてすみわたるへく |
| 夏雑歌 詠鳥 書陵部本 118 |
| たちはなのはやしをうゑむほとゝきす つねふゆまてすみわたるかな |
| 夏雑歌 詠鳥 西本願寺本 238 |
|
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1962] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔橘のはやしをうへん霍公鳥つねに冬まて住わたるかね 〕
橘之林乎殖 常尓冬及住度金
|
| 橘の林をうへん 祇曰住わたるかねとはかにといふ詞也愚案橘は常磐木なれは冬まての栖によせあるにや |
| 『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕 |
| |
橘之林乎殖霍公鳥常爾冬及住度金
〔タチハナノハヤシヲウヱムホトヽキスツネニフユマテスミワタルカネ 〕 |
| 佐度金は住度歟になり、禰と爾と通ぜり、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
橘之林乎殖霍公鳥常爾冬及住度金
〔たちばなの、はやしをうゑて、ほとゝぎす、つねにふゆまで、すみわたるかに 〕 |
| 住渡れかなと乞たる意也。橘は常磐木なれば、時鳥も四季共に住渡れかしと愛するあまりに、願ひたる歌也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
橘之、林乎殖《ウヱン》、霍公鳥、常爾冬及《マデ》、住度金《スミワタルガネ》、がねはかにといふに同じ |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕 |
| |
橘之。林乎殖。霍公鳥。常爾冬及。住度金。
〔たちばなの。はやしをうゑつ。ほととぎす。つねにふゆまで。すみわたるがね。 〕 |
| 卷九、ほととぎすを詠める長歌に、わがやどの花橘に住わたれとりとも詠めり。ガネは後をかねて言ふ詞。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔橘之《タチバナノ》。林乎殖《ハヤシヲウヱム》。霍公鳥《ホトヽギス》。常爾冬及《ツネニフユマデ》。住度金《スミワタルガネ》。〕 |
林乎殖は、ハヤシヲウヱムと訓べし、(略解にハヤシヲウヱツとよめるは誤なり、)○住度金《スミワタルカネ》は、住わたるが料にの意なり、度《ワタル》は、月日を經度る謂なり、九(ノ)卷に、詠霍公鳥歌の末にも吾屋戸之花橘住度鳴ワガヤドノハナタチバナニスミワタリナク》と云り、(鳥は鳴(ノ)字の畫の滅たるなるべし、)(十九)に、霍公鳥雖聞不足網取爾獲而奈都氣奈可禮受鳴金《ホトヽギスキケドモアカズアミトリニトリテナツケナカレズナクガネ》、とも見ゆ○歌(ノ)意は、霍公鳥の夏より冬まで來り棲て、月日を經度りて、常にさらず鳴べきがために、橘の林を殖生し置むぞとなり、
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔橘の林を殖《ウヱム》ほととぎす常に冬まですみわたるがね〕
橘之林乎殖霍公鳥常爾冬及住度金 |
| 第二句は舊訓の如くウヱムとよむべし(略解にはウヱツとよめり)。ツネニといひて更に冬マデといへるなり。ガネはベクなり |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
| |
橘の林を植ゑつ。霍公鳥、常に、冬まで棲み渡るがね |
| |
子規は橘の花が好きだといふので、橘を林程植ゑた事だ。夏ぎりでなく、何時の年も、冬迄ぢつとして棲み續けるやうに。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔橘の 林を植ゑむ ほととぎす 常に冬まで 住みわたるがね〕
橘之《タチバナノ》 林乎殖《ハヤシヲウヱム》 霍公鳥《ホトトギス》 常爾冬及《ツネニフユマデ》 住度金《スミワタルガネ》
|
ワタシハ霍公鳥ガ始終冬マデモココニ住ンデヰル爲ニ、橘ノ林ヲワタシノ屋敷ニ植ヱヨウ。
○林乎殖《ハヤシヲウヱム》――略解にハヤシヲウヱツとあるが、舊訓による。○住度金《スミワタルガネ》――ガネは料に、爲に。
〔評〕橘に郭公が宿るものとして、詠んだ歌は他にも多い。卷九の長歌にも吾屋戸之花橘爾住度鳥《ワガヤドノハナタチバナニスミワタレトリ》(一七五五)とあつた。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔たちばなの はやしをうゑむ。ほととぎす つねにふゆまで すみわたるがね〕
橘之林乎殖霍公鳥常爾冬及住度金 |
【訳】橘の林を植えよう。ホトトギスがいつも冬まで住みつくだろう。
【釈】林乎殖 ハヤシヲウヱム。木を多く植えよう。句切。
【評語】ホトトギスが橘を愛して落ちつくだろうというのである。橘とホトトギスとの取り合わせが、既に成立している。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| |
〔たちばなの はやしをうゑむ ほととぎす つねにふゆまで すみわたるがね〕
橘之林乎殖霍公鳥常爾冬及住度金 |
【大意】橘の林を植えよう。そしたら、ほととぎすが、変わらずに、冬までも住みつづけるであらう
【作意】ほととぎす愛惜の歌であるが、まはりくどい感じ方が嫌味に近い。しかし、此の時代には
既にかういふ物の考方を、風流として居たのであらう。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
| |
〔たちばなの はやしをうゑむ ほととぎす つねにふゆまで すみわたるがね〕
橘之林乎殖霍公鳥常爾冬及住度金 (『元暦校本』) |
【口訳】橘の林を植えよう。霍公鳥がいつも冬まで住みつづけるやうに。
【訓釈】橘の林を植ゑむ―旧訓ウヱムを略解にウエツとしたが、古義に「誤なり」と云つてゐるやうに旧訓のままでよい。「幣はせむ 遠くな行きそ 吾がやどの 花橘に 住み渡れ鳥」(9・1755)とも、
霍公鳥聞けども飽かず網捕りにとりてなつけな離れず鳴くがね (19・4182) 家持
ともある。
住み渡るがね―「がね」は既出(1906)。
【考】上三句同想の作が前(1944)にもあった。
赤人集結句「すみわたるかな」、流布本「林の中に」「住み渡るべく」、夫木抄(7「橘」)結句「すさみたるがね」とある。 |
|
|
掲載日:2014.03.23.
| 夏雑歌 詠鳥 |
| 橘之 林乎殖 霍公鳥 常尓冬及 住度金 |
| 橘の林を植ゑむ霍公鳥常に冬まで棲みわたるがね |
| たちばなの はやしをうゑむ ほととぎす つねにふゆまで すみわたるがね |
| 巻第十 1962 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【赤人集】〔陽明文庫本128〕〔書陵部本118〕〔西本願寺本238〕【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1962】 語義 意味・活用・接続 |
| たちばなの [橘之] |
| の [格助詞] |
[連体修飾語(材料)] ~の |
体言につく |
| はやしをうゑむ [林乎殖] |
| はやし [林] |
木が群生している所・物事の多く集まった所 |
| うゑ [植(う)う] |
[他ワ下二・未然形] 植える・種をまく |
| む [助動詞・む] |
[推量(意志)・終止形] ~よう |
未然形につく |
| ほととぎす [霍公鳥] |
| つねにふゆまで [常尓冬及] |
| つねに [常] |
[形容動詞ナリ・連用形] 永久・同じ状態にあること |
| まで [副助詞] |
[限度]~まで |
体言につく |
| すみわたるがね [住度金] |
| わたる [渡る] |
[接尾語的用法四・連体形] ずっと続けるの意になる |
| がね [終助詞] (上代語) |
~のために・~のように |
連体形につく |
| 打消・意志・禁止・命令・願望などの表現を受けて、その理由や目的を表す |
| 〔参考〕和歌にしか使われないく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [たちばな] |
植物の名、こうじみかん
常緑樹で、香りの高い白い花をつける。果実はみかんに似て小さく、酸味が強い。
季語は「秋」とされるが、「橘飾る[春]・橘の花[夏]」とする
ホトトギスと共に和歌に多く詠み込まれている
| さつきまつ はなたちばなの かをかげば むかしのひとの そでのかぞする |
| 古今和歌集 巻第三 夏歌 139 よみひとしらず |
陰暦五月を待って咲く橘の花の香り
それをかぐと、昔親しんだ人の袖の香りがする
橘には、そんな「昔の人」を思い起こさせる「花」としても詠われている
そこに、「しでのたをさ」と異名を持つホトトギスとの組み合わせ
強烈だと思う
|
| |
| [はやし] |
この語の原義は「生ヤシ」だと書いてあった
何となく、「生える・生えてくる」の意味のサ変動詞「生えす」から
そのイメージが湧いてくる |
| |
| |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[本文]「橘之 林乎葅 霍公鳥 常尓冬及 住度金」(「【】」は編集)
「タチハナノハヤシヲウヱムホトヽキスツ子ニフユマテスミワタルカ子」 |
| 〔本文〕 |
| |
|
| 〔訓〕 |
| ウヱム |
『神田本(紀州本)』「ウヘム」
『細井本』「ウヱハ」
|
| スミワタルカ子 |
『神田本(紀州本)』「テ」ノ下ニ「ヽ」ヲ削レル痕アリ。
『京都大学本』漢字ノ左ニ赭「ノイテヤマイリ」アリ。 |
| キナキトヨマス |
『元暦校本』「ね」ノ右ニ赭「ニ」アリ
『類聚古集』「すみわたるかに」。「金」ノ右ニ朱「カニ」アリ
『京都大学本』「スミワタレカナ」 |
| 〔諸説〕 |
| ○ハヤシヲウヱム。『古義』「ハヤシヲウヱツ」トスル(略解)ヲ否トス。ノニデヤマニイリ」。 |
|
【左頁資料について】
| 『万葉拾穂抄』 |
「祇曰」とは何だろう
人の名前か、それとも「祇」には「国津神」といって地元の神の意があるし...
人の名であれば、平家物語に出てくる「祇王」...まさか、そんなことはないか
しかし、何であれ、ここでは面白いことを発見した
「住わたるかね」とは「住わたるかに」という言葉なんだという
私たちが、古語に触れたとき、この古語は、現代語の「何々」という
それで、意味が解ることになるが
この言い回しだと、万葉時代の歌の「かね(がね)」は、「かに(がに)」のことだ、と言っている
確かに、古語辞典でも終助詞「がに」は、上古の「がね」が転じたもので、
歌でしか使われてなく、しかも中古に入ってからは「がに」しか使われなくなっている
そして、橘は常緑木なので、冬までの「巣」は、
「よせ」は「うしろだて」や「世話をする人」なので、「任せておけ」と言うことなのだろうか |
| 『万葉代匠記(精撰本)』 |
よく解らない
佐度金は「住度歟」...「歟」は疑問ではないか
「すみわたるか」となるのかな
|
| 『万葉集童蒙抄』 |
橘は常緑木だから、ホトトギスも四季に亘って共に住んでくれ、と懇願している、と解釈
この解釈は、とても珍しいと思う
ホトトギスの好きな橘の樹を植えるのだから、「冬の間」も我慢してそこにいてくれ、という |
| 『万葉考』 |
特に無し
|
| 『万葉集略解』 |
「うゑつ」は、完了の助動詞「つ」、
植えよう、ではなく、植えてしまった、と解釈しているようだ |
| 『万葉集古義』 |
| 歌意に特筆はないが、『略解』の「うゑつ」を誤、という |
| 『万葉集新考』 |
「つねに」と言って、さらに「ふゆまで」ということを、不具合でもあるのだろうか
この「つねに」は、確かに「永久に」とか「変わらず同じように」とする意味だが、
この書は、それが矛盾だ、と言っているのだろうか
それとも、いつまでもずっと住ついて欲しい、せめて冬までは、と言外に訳しているのかな
しかし、「つねに」は矛盾しない
冬まで住めるようにするから、毎年「同じように変わらず」でいいはずだ
井上通泰も、そう言っているのだと思うが、
この箇所の注釈では、説明が足りないと思う
全体の歌意がないので、尚更明確な語意が必要だと思うのだけど... |
| 『口訳万葉集』 |
| 「うゑつ」、お前の為に植えたのだから、冬までじっとそこに居て、何年でもそこを棲み処としてやって来てくれ |
| 『万葉集全釈』 |
| 定説に従う歌意で、毎年やってきても、冬までは居られるように橘の樹を植えよう、とする |
| 『万葉集全註釈』 |
| 歌意、特筆なし |
| 『万葉集私注』 |
| 歌意、特筆なし |
| 『万葉集注釈』 |
| 歌意、特筆なし |
|
|
|
|
 |
| |
| |
| |
| |
| |
「あまばれの」...くもにたぐひて...
|
| 『こゆなきわたる』 |
| 【歌意1963】 |
雨もあがり、名残の雲も、
急ぐようにして春日の方へ流れている
そんな雲に添うように、ほととぎすは、
鳴きながら、この上を飛び翔けて行く、春日の方へ... |
|
| |
| |
幾つかの書に見るように、私も梅雨晴の空を思い浮かべていた
梅雨の雨あがりは、普通の「雨あがり」と違って
とても「瑞々しい」感じがする
一日の中での「梅雨」のあがりではなく
長い梅雨が、漸くあがった「雨あがり」だ
何だか、「梅雨明け」の異称として「あまあがり」という語があってもいいような気がする
もっとも、「梅雨晴」を、どう解釈するか、人それぞれ想いは違うだろうが...
このところ、この「詠鳥」で、ホトトギスの歌ばかり触れており
そのホトトギスの、さまざまな「顔」を知ることになった
この歌でも、この鳥が、曇り空や雨の中によく鳴く、という習性を教えてくれた
だから、普通の「晴れ間」ではなく、「雨あがりの晴れ」だからこそ
この歌の「瑞々しさ」が感じられ、さらにホトトギスの鳴き声が
その透明感に満ちた空間に響き渡るような情景を思わせてくれる
春日、春日山、春の日、
様々なイメージが沸き起こる
『童蒙抄』の荷田春満は、
「悲の意にて、声高くかすかなる」であってもいいではないか、という
雅澄が「歌意かくれたるところなし」とは、随分違う
人が一首に出逢うとき、その瞬間のその人の「想い」が、共鳴するのだろう
|
|
【赤人集(成立年時未詳[740年頃])】[別掲載赤人集について]
| あまはれの雲まにたくひ時鳥 かすかをさしていまなきわたる |
| 夏雑歌 詠鳥 陽明文庫本 129 |
| あまはれの雲間にたくふほとゝきす かすかをさしていまなきわたる |
| 夏雑歌 詠鳥 書陵部本 119 |
| あまはれのこむまにたくひほとゝきす こすかをさしていまなきわたる |
| 夏雑歌 詠鳥 西本願寺本 239 |
|
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1963] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔あまはりの雲にたくひて霍公鳥かすかをさしてこゆなきわたる〕
雨霽之雲尓副而 指春日而從此鳴度
|
| あまはりの雲に 見安云あまはりは空のはるゝなり |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
| |
雨○[日+齊]之雲爾副而霍公鳥指春日而從此鳴度
〔アマハリノクモニタクヒテホトヽキスカスカヲサシテコユナキワタル 〕 |
| 雨○[日+齊]、【校本、○[日+齊]或作霽、】 鳴度、【官本、度作渡、】 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
雨○[日+齊]之雲爾副而霍公鳥指春日而從此鳴度
〔あめはれし、くもにたぐひて、ほとゝぎす、はるひをさして、こゝゆなきわたる〕 |
| 「○[日+齊]」 此字、はるゝと讀む義未孝。霽の字の誤り歟。通じても書歟。歌の意は聞えたる通也。こゝよりと指す處は、作者の居所より、はるひと云所へ向つて鳴き行と也。春日は、かすがにても有るべきか。然れ共雨晴れてと詠出たるから、同じ地名にても晴るゝ日に鳴渡ると云意をこめて、はるひをさしてとは詠む也。古詠ともに、はるひとかすがと相まじりてわき難き歌多し。然れ共歌の意を疎かに見來れるより、押なべてかすがとのみ讀み來れ共、歌の言葉續く言葉の縁につきては、はるひと讀までは不叶歌共有。尤此歌も悲の意にて、聲高くかすかなると云意にても有らんか。宗師の意は、はるゝ日にと云意也
|
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
霽之《アマバリノ》、今本雨○[目+齊]なりとあるは誤なり霽の一字を二字としたるなり霽はのちにもゆふばれと訓て雨のはれたるをいへればなり ○[目+齊]は字書に見えずよりてよしこせのあまばりの訓をたすけて二字を一字とす婆利の利は禮に通ひてあまばれなり
雲爾副而《タグヒテ》、たぐひといふ言のもとはたてならぶてふ語をはぶきつゞめていふ言なりされば其意得て副の字をも用たり
霍公鳥、指春日而《カスガヲサシテ》、從此鳴渡《コユナキワタル》、 |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
| |
雨霽之。雲爾副而。霍公鳥。指春日而。從此鳴度。
〔あめはれし。くもにたぐひて。ほととぎす。かすがをさして。こゆなきわたる。 〕 |
| 雨晴れて、春日山の方へ歸る雲に添ひて、郭公の鳴き行くを詠めり。霽を今本○[日+齊]と有れど、字書に見えず。一本に依りて改む。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔雨霽之《アメハレシ》。雲爾副而《クモニタグヒテ》。霍公鳥《ホトヽギス》。指春日而《カスガヲサシテ》。從此鳴度《コヨナキワタル》。〕 |
雨霽之は、霽(ノ)字、書本には臍と作り、今は拾穗本に從つ、アメハレシと訓べし、○雲爾副而《クモニタグヒテ》は、雲に傍てと云が如し、雨のはれゆきし、なごりの雲にそひての謂なり、○歌(ノ)意かくれたるところなし
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔雨はれし雲にたぐひてほととぎす春日《カスガ》をさしてこゆなきわたる〕
雨晴之雲爾副而霍公鳥指春日而從此鳴度 |
初句は雨晴レテ山ニ歸ル雲ニといふべきを略せるなり。タグヒテは一ショニなり
○[日+齊]は晴又は霽の誤ならむ |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
| |
雨晴れし雲にたぐひて、霍公鳥、春日《カスガ》をさして、茲《コ》ゆ鳴き渡る |
| |
雨が晴れたので、山の方へ歸る雲と竝んで、子規が春日山をさして、此邊を鳴いて通ることだ |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔雨はれし 雲にたぐひて ほととぎす 春日をさして こゆ鳴き渡る〕
雨○[日頁齊]之《アメハレシ》 雲爾副而《クモニタグヒテ》 霍公鳥《ホトトギス》 指春日而《カスガヲサシテ》 從此鳴度《コユナキワタル》
|
雨ガ晴レテ春日山ヘ歸ツテ行ク雲ト一緒ニ霍公鳥ガ春日山ヲ指シテ、飛ビナガラ此處ヲ鳴イテ通ル。
〔評〕 雨晴の西風につれて、雲が東の方、春日山をさして、足速く移動してゐる。それと一緒に郭公も春日山を指して、此處を鳴き過ぐるといふので、梅雨晴らしい、すがすがしい歌である。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔あめはれし くもにたぐひて、ほととぎす かすがをさして こゆなきわたる〕
雨○[日+齊]之雲爾副而霍公鳥指春日而從此鳴度 |
【訳】雨あがりの雲に伴なつて、ホトトギスが、春日をさして、ここを通つて鳴いて行く。
【釈】雨○[日+齊]之雲爾副而 アメハレシクモニタグヒテ。雨の晴れあがると共に、その雲に伴なつて。
指春日而 カスガヲサシテ。作者は、多分奈良の京にいるだろう。そこで西から空が晴れて行つて、東方の春日の方へ雲が移動する。それにつれてホトトギスも春日をさして行くというのである。
【評語】雨後のホトトギスを詠んで、よい描写がなされている。梅雨ばれの情景がよく窺われる
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| |
〔あめはれし くもにたぐひて ほととぎす かすがをさして こゆなきわたる〕
雨○[日+齊]之雲爾副而霍公鳥指春日而從此鳴度 |
【大意】雨の晴れた雲と一緒になって、ほととぎすが、春日を目ざして、此所を通つて鳴いて行く。[○[日+齊]」は巻第八、(一五六九)にもあり、字書にない。[霽]の誤だらうと言はれるが、此の集には字書に見えぬ字が往々見えることは、上来見えた。唐代の俗字かも知れぬ。
【作意】よく物を見て居るやうだが、平面的である。クモニタグヒテは言ひ過ぎて居る。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
| |
〔あめはれの くもにたぐひて ほととぎす かすがをさして こゆなきわたる〕
雨○[日+齊]之雲爾副而霍公鳥指春日而從此鳴度 (『元暦校本』) |
【口訳】雨あがりの雲に伴つてほととぎすが春日の方へここを鳴き渡つてゐる。
【訓釈】雨霽の―「日+齊」の字、『類聚古集』に「晴」とあり、『紀州本』頭書「晴イ」とあるが他の諸本「日+齊」とあり、前(8・1569)に述べたやうに、それを原本の文字と認め、「霽」と同意に用ゐたものと思はれる。『元暦校本』に「アマハレノ」、『類聚古集・紀州本』その他「アマハリノ」、『童蒙抄』に「アメハレシとし、諸注多く従つてゐるが、これは「霜干(シモカレノ」(1846)と同様名詞とし、『元暦校本』に従つて「アマハレノ」と訓み、雨あがりの、と解すべきものと思ふ。
【考】赤人集に「あまはれのこむまにたくひ」「こすかをさしていま鳴きわたる」、流布本「雲間にたくふ」「かすかをさして」とあり、夫木抄(八「郭公」)「雨はれし」として人丸とある。 |
|
|
掲載日:2014.03.24.
| 夏雑歌 詠鳥 |
| 雨○之 雲尓副而 霍公鳥 指春日而 従此鳴度 [○日+齊] |
| 雨晴れの雲にたぐひて霍公鳥春日をさしてこゆ鳴き渡る |
| あまばれの くもにたぐひて ほととぎす かすがをさして こゆなきわたる |
| 巻第十 1963 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【赤人集】〔陽明文庫本129〕〔書陵部本119〕〔西本願寺本239〕
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1963】 語義 意味・活用・接続 |
| あまばれの [雨〇之] (〇=日+齊) 雨あがりの |
| くもにたぐひて [雲尓副而] |
| たぐひ [類ふ・比ふ・副ふ] |
[自ハ四・連用形] 添う・一緒に行動する・つりあう |
| ほととぎす [霍公鳥] |
| かすがをさして [指春日而] |
| かすが [春日] |
春日という地名のようだが、春日山とする固有名詞説もある |
| こゆなきわたる [従此鳴度] |
| こ [此・是] |
[近称の指示代名詞] これ・・ここ [自分に近い事物や場所] |
| ゆ [格助詞](上代語) |
[経由点] ~から・~を通って |
体言につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [あまばれの] |
原文「雨」に続く字が、江戸時代の注釈書の時代から、読めないとされている
多くは、「霽」の字を当てて、「晴れ」と解釈しているが
この「日+齊」の字は、歌の歌意からすると、
「晴」の語義を持つ字だと、今のところ読まれている
1603年に長崎で刊行された、日本語をポルトガル語で解説した「日葡辞書」
この辞書は、中世の日本語が、どんな音韻体系を持っていたか理解できるものらしい
そこに「Amabare 雨の後、晴れた穏やかな天気」とあるようだ
つまり、「あまばれ」という語が、存在していたことになるが
『万葉集』では、この歌一首のみの用例となっている
注釈書が盛んになった時代では、「あまばれ」という「語」の存在は理解できても
だからと言って、万葉の時代に、その「語」が使われていたかどうか
それは、解らないと思う
左頁に載せる「赤人集」にも、確かに「あまはれ」とは訓まれてはいるが
この「赤人集」を編纂したのは、平安時代の藤原公任(966~1041)で、
当然赤人の歌は漢字だったのだから、平安時代の学者による「訓」ということになる
現代の訓は、「あまばれの」通っているが、少し前の注釈書や
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕などは、
少し前までは、同じように訓まれていた「あめはれし」の訓を採っている
|
| |
| [かすがをさして] |
多くは、「春日の方へ」、と目指す方面が「春日」だと解釈するが、
最近の注釈では、岩波の新校訂文庫版も、「春日山」だとしている
漠然と方角をいう「かすが」と、行く先を限定させる「春日山」
どちらが、いいのだろう
原文では解りようもないが、「歌」としてみれば、
「春日の方を目指す」のような詠い方が、私は好きだ
「雨あがり」というのだから、と『童蒙抄』の解釈の仕方には、理解できる
「晴るゝ日」もまたいい |
| |
| |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[本文]「雨○之 雲尓副而 霍公鳥 指春日而 従此鳴度 [○日+齊]」(「【】」は編集)
「アマハリノクモニタクヒテホトヽキスカスカジサシテコユナキワタル」 |
| 〔本文〕 |
| 「日+齊」 |
『類聚古集』「晴」
『神田本(紀州本)』頭書「晴イ」アリ。コノ字ノ異ナラン。
『大矢本・京都大学本』「日+齊」
|
| 「而」 |
『京都大学本』ナシ |
| 〔訓〕 |
| アマハリノ |
『元暦校本』「あまはれの」
『大矢本』「アメハリノ」 |
| クモニタクヒテ |
『元暦校本』「くもゐにそひて」
『類聚古集』「くもにたくひの」墨ニテ「の」ヲ消セリ。ソノ右ニ墨「テ」アリ |
| コユナキワタル |
『元暦校本・類聚古集』「なきわたるなり」。『元』上ノ「な」ノ右上ニ赭「コヽ」アリ。「なり」ヲ赭ニテ消セリ
『神田本(紀州本)』「ナキワタルナリ」。漢字ノ左ニ「コヽニナキワル江」アリ
『西本願寺本』「コユ」モト青
『細井本』「従」ノ左ニ「コユ」アリ
『大矢本・京都大学本』「コユ」青。『京』「従此」ノ左ニ赭「コヽニ」アリ |
| 〔諸説〕 |
○[アマハリノ]『代匠記初稿本』「アマハレノ」。『童蒙抄』「『日+齊』ハ『霽』ノ誤カ」。訓「アメハレシ」。『万葉考』「雨『日+齊』」ハ「霽」ノ誤。
○[カスカヲサシテ]『童蒙抄』「ハルヒヲサシテ」。 |
|
【左頁資料について】
| 『万葉拾穂抄』 |
「あまはり」は、空の晴るる、という
雨の後の、というべきだと思う
また解らない「見安」...、その[見安」が云う、とは当時の学者なのか |
| 『万葉代匠記(精撰本)』 |
初句の「日+齊」の字を、この『代匠記』の校訂者も手こずっているようだ
それは、後のことでも同じだが、どの書も「字書」にないといい、「晴れ」の意を採っている
|
| 『万葉集童蒙抄』 |
これも「日+齊」を、晴れる意の「霽」の誤か、という
「春日」の解釈の仕方、説明の仕方がいい |
| 『万葉考』 |
「たぐひ」に、語源をいう
「たてならぶ」、おそらく「たちならぶ」のことだと思う
とすると、もともとの原義は「一緒に並ぶ」ということになる
そこから、添う、となるわけだ
その時代における「注釈書」は、その時代の人たちを相手にするものなので
この「たぐふ」は「たちならぶ」が語源なんだよ、と教えていることになる
|
| 『万葉集略解』 |
千蔭も、何かの書に基づいて「霽」に改めている
つまり、歌意を「晴」としなければ、この歌が成り立たない、ということなのだろう |
| 『万葉集古義』 |
歌意は明白、と
雨の後の晴れる空、名残の雲、というのがいい |
| 『万葉集新考』 |
| 特筆はなし |
| 『口訳万葉集』 |
| 特筆はなし |
| 『万葉集全釈』 |
梅雨晴の歌、と感じ取る
確かに、そんなイメージの歌だと思う |
| 『万葉集全註釈』 |
| 特筆はなし |
| 『万葉集私注』 |
この書では、その評価で「平面的」という言葉をよく目にする
やはり歌人の目なのだろう
「くもにたぐひて」が言い過ぎだとは、そうなのかなあ
『万葉集』には「字書」に見えない字が往々にしてある、と
「唐代」の俗字かもしれない、となると
当時そんな「俗字」までも日本に伝わっていたのだろうか |
| 『万葉集注釈』 |
「赤人集」で「あまはれの」と載っているのは、その訓の傍証のつもりなのだろうか
しかし、その訓がつけられ、「赤人集」に載ったのは、
万葉最後と言われる年代から二百年の後のことだから、
その平安時代に「あまはれの」とは確かに訓まれたのだろうが... |
|
|
|
|
 |
| |
| |
| |
| |
| |
「ものもふと」...いねぬあさけに...
|
| 『すべもなきまま』 |
| 【歌意1964】 |
哀しくて、もの思いにうちしおれて眠られず
明け方を迎えてしまった
こんなに早くから、ホトトギスが鳴きながら
我が家の上を飛び渡ってゆく
哀しくてたまらない気持ちにさせて... |
|
| |
| |
古くからの注釈書を眺めていると、
まず作者自身が何かにかられて「物思い」に沈んでいる
その結果、眠られずに迎えた朝方のホトトギスの鳴き渡る声、
お前は、何も悩み事は無いのか...一層辛く、物悲しくなったよ
そんな解釈が、自然と読み込まれてくる
しかし、他に「物悲しく鳴く」ホトトギスに誘われて、一層物悲しくなった、と
ホトトギスと共鳴するかのように、物思いに沈み込む
一枚の情景としては、少し凝ったものになるのだろうか
物思いの原因は語られなく、だからどの注釈もそこには及ばないが
「物思い」がホトトギスと共鳴する、
あるいは誘発されて一層の「物悲しさ」を募らせるなら
野暮だと思いながらも、
どうして眠られないほどの「物思い」なのだろう、と思ってしまう
『全釈』では、深い意味の言葉ではないのかもしれないが
「眠られないのではなく、眠らなかった」との言い方で解釈している
その場合なら、普通に鳴き渡るホトトギスの鳴く声を、
「悲しくて何とも仕様がないほど」とは感じられないだろう
やはり、その作者の心の底には、「深い」哀しみがあって、
それで、眠られなかった...いや、「眠らなかった」というのだろう
どの情景を採っても、作者が「物悲しさ」に打ち萎れて夜を明かしたことには
想像も難しくはない、と思う
「物悲しさ」...愛しい人を想ってのことだろうか
夜も寝れずに想う人とは、自分に振り向いてくれない「人」のことかもしれない
そして、鳴きながら飛び行くホトトギスに、その人の「面影」を重ねたのかもしれない
ホトトギスには、多くの「顔」がある
この歌の場合、悲しみに沈む自身に、美しく鳴き渡る声が、恨めしく
それで、「すべなきまでに なきわたる」にもなるだろうし
愛しい人を失って、その「人」が、ホトトギスと共に、彼方へ去って行く...
そんな情景を思い浮かべるとしたら、
この歌の詠まれる前の「気持ち」が、詠われなくても、この歌に籠められている
そんな歌ではないかな、と思う |
|
【赤人集(成立年時未詳、撰、藤原公任 [966~1041])】[別掲載赤人集について]
| 物おもふといねぬあさけの時鳥 我ころもてにきたりをりつゝ |
| 夏雑歌 詠鳥 新編私家集大成-新編増補(陽明文庫蔵三十六人集) 130 |
| ものおもふとねさるあさけのほとゝきす わかころもてにきなきをりつゝ |
| 夏雑歌 詠鳥 新編私家集大成(書陵部蔵三十六人集) 116 |
| ものおもふとねざるあさけにほととぎすわがころもでにきなきをりつつ |
| 夏雑歌 詠鳥 新編国歌大観(西本願寺蔵三十六人集) 236 |
|
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1964] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔物おもふといねぬあさけに霍公鳥なきてさわたるすへなきまてに 〕
物念登不宿旦開尓 鳴而左度為便無左右二
|
| 物おもふといねぬ いねぬあさけはねすして明せし朝也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
| |
物念登不宿旦開爾霍公鳥鳴而左度爲便無左右二
〔モノオモフトイネヌアサケニホトヽキスナキテサワタルスヘナキマテニ 〕 |
左度、【官本、度作渡、】
發句はモノモフトと讀べし、第十五に殊に此詞多し、皆於を略して毛能毛布とあり、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
物念登不宿旦開爾霍公鳥鳴而左度爲便無左右二
〔ものもふと、いねぬあさけに、ほとゝぎす、なきてさわたる、すべなきまでに〕 |
| 物思ふとて夜をいねざりし朝にと云ふ義也。すべ無き迄とは、愈物思ひの催されて、いかにせん方も無きと、郭公の聲に益々我思ひの増したる意也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
物念登《モノモフト》、不宿旦開《イネズアサゲ》爾、霍公鳥、鳴而左度、爲便無《スベナキ》左右二、 さ渡るのさはことおこす語なり歌の意は物もひにいねがてなるにまして郭公の聲のものがなしくきこゆればせんすべなきまでおもはるとなり、 |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
| |
物念登。不宿旦開爾。霍公鳥。鳴而左度。爲便無左右二。
〔ものもふと。いねぬあさけに。ほととぎす。なきてさわたる。すべなきまでに。 〕 |
| 物思ひに寢《イネ》ざりし夜の明方なり。サワタルのサは發語にて、鳴き渡るなり。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔物念登《モノモフト》。不宿旦開爾《イネヌアサケニ》。霍公鳥《ホトヽギス》。鳴而左度《ナキテサワタル》。爲便無左右二《スベナキマデニ》。〕 |
歌(ノ)意は、さなきだに、物思ひしげくて、得寐入ずして、起明したる夜の朝開なるを、せむ方なきまで、いよいよ物思(ヒ)をまさらせて、霍公鳥の鳴て飛度るよ、となり、
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔物もふといねぬあさけにほととぎすなきてさわたるすべなきまでに〕
物念登不宿旦開爾霍公鳥鳴而左度爲便無左右二 |
| イネヌアサケニは夜スガライネヌ曉ニとなり。サワタルのサは添辭、スベナキマデニは得堪ヘヌマデニなり |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
| |
物思ふと寢ねぬ朝明《アサケ》に、霍公鳥、鳴きてさ渡る。すべなき迄に |
| |
物を考へこんで、寢もしない夜の引き明け方に、子規が鳴いて空を通つて行く。それを聞いてゐると、やる瀬なくて爲方がない程に。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔物もふと いねぬ朝明に ほととぎす 鳴きてさわたる すべなきまでに〕
物念登《モノモフト》 不宿旦開爾《イネヌアサケニ》 霍公鳥《ホトトギス》 鳴而左度《ナキテサワタル》 爲便無左右二《スベナキマデニ》
|
物ヲ思ツテ眠ラナカツタ夜明ケ方ニ、霍公鳥ガ、悲シクテ何トモ仕樣ガナイホドニ、ココヲ鳴イテ通ルヨ。
○鳴而左度《ナキテサワタル》――鳴いて通る。サは接頭語。
〔評〕 感傷的な、あはれな歌。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔ものおもふと いねぬあさけに ほととぎす なきてさわたる。 すべなきまでに〕
物念登不宿旦開爾霍公鳥鳴而左度爲便無左右二 |
【訳】物を思うと寐ない朝あけに、ホトトギスが鳴いて過ぎて行く。何とも致し方のないまでに。
【釈】不宿旦開爾 イネヌアサケニ。寐なかつた夜あけに。
鳴而左度 ナキテサワタル。サは、接頭語。句切。
爲便無左右二 スベナキマデニ。自分の心が、ホトトギスの声に催されて、何ともしかたのないまでに。
【評語】ホトトギスの声が哀愁を誘うことを詠んでいる。感傷的な歌である。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| |
〔ものもふと いねぬあさけに ほととぎす なきてさわたる すべなきまでに〕
物念登不宿旦開爾霍公鳥鳴而左度爲便無左右二 |
【大意】物思をするとて、寝ない朝明に、ほととぎすが鳴いて通つて行く。仕方ないまでに。
【作意】スベナキマデニは、物思しての朝明なので、ほととぎすを聞いて、特にスベナク感ずるのであらうが、やはり言ひすぎに聞こえる。マデが悪いのであらう |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
| |
〔ものもふと いねぬあさけに ほととぎす なきてさわたる すべなきまでに〕
物念登不宿旦開爾霍公鳥鳴而左度爲便無左右二 (『元暦校本』) |
【口訳】物思ひをして寝ない夜明にほととぎすが、鳴いて通つてゆく。その声を聞くとせんすべもない思ひのせられるまでに。
【訓釈】鳴きてさ渡る―「さ」は接頭語。鳴いて飛び渡る。
すべなきまでに―既出(9・1702)。
【考】赤人集に「ものおもふとねざる朝けに」「わがころもてになきをりつゝ」とあるは次の歌の後半と混同したものと思はれる。 |
|
 |
掲載日:2014.03.25.
| 夏雑歌 詠鳥 |
| 物念登 不宿旦開尓 霍公鳥 鳴而左度 為便無左右二 |
| 物思ふと寐ねぬ朝明に霍公鳥鳴きてさ渡るすべなきまでに |
| ものもふと いねぬあさけに ほととぎす なきてさわたる すべなきまでに |
| 巻第十 1964 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【赤人集】〔陽明文庫本129〕〔書陵部本119〕〔西本願寺本239〕
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1964】 語義 意味・活用・接続 |
| ものもふと [物念登] |
| ものもふ [物思ふ] |
[自ハ四・連体形]「ものおもふ」の転 思い悩む・思いに耽る |
| と [格助詞] |
[引用] 後に続く動作・状態の目的・状況・原因・理由などを示す |
| いねぬあさけに [不宿旦開尓] |
| いね [寝(い)ぬ] |
[自ナ下二・未然形] 寝る・眠る |
| あさけ [朝明] |
「朝明け」の転、明け方・早朝 |
| ほととぎす [霍公鳥] |
| なきてさわたる [鳴而左度] |
| さ [接頭語] |
[名詞・動詞・形容詞について] 語調を整えたり意味を強めたりする |
| |
[名詞について] 「若々しい」の意を添える |
| すべなきまでに [為便無左右二] |
| すべなき [術無し] |
[形ク・連体形] なすべき手段がない・どうしようもない |
| までに |
[程度をはっきり表す] ~くらいに・~ほどに |
| |
[限度をはっきり表す] ~までも |
| 〔成立〕副助詞「まで」+係助詞「に」 〔接続〕体言、体言に準ずる語などにつく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [ものもふ] |
「ものもふ」が、「ものおもふ」の転じた「語」であることは
少なからず、日常の言葉だけではなく、「歌語」としてもその必要性はあったと思う
三十一字の制約の中に、語義を失わずに、韻を整える
「歌語」には、「歌」でしか使われない「語」も多くあるはずが
この「ものもふ」が、それに当てはまるかどうか解らないが
少なくとも、「ものおもふ」と訓じたら、「登」がある以上、「六字」の字余りになる
ならば、「ものもふと」と訓む方が、歌の調子からはいいのではないかと思う
まったく語義が変わってしまうのではなく、あくまで「韻」のことだから...
しかし、この歌の訓には、「ものもふ」と「ものおもふ」が、
古注の時代から現代までも併用されている
「ものもふ」とする近世までの注釈書は
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕、
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕、
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕、
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕、
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕、
『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕などで、
さらに現代に於いては、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕、
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
『万葉集校注』〔伊藤博、角川文庫、平成13年23版〕、
『新校訂万葉集』〔岩波文庫版、平成25年~刊行中〕がある
「ものおもふ」と訓む注釈書は、
『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕が古く、他は近代になって、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕、
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕、
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕などがそうだ
数の上からでは、圧倒的に「ものもふ」だが、
気になるところは、新しい注釈書に限ってみると、「ものおもふ」が多くなっている
特に、多くの読者がいる大手の叢書の『万葉集』では、一様に「ものおもふ」だ
もう一つ気になるのは、岩波の書籍について
『大系』と『新大系』では、その校注者が違うので、解釈の相違は理解でき
だから、別の注釈書と考えた方がいいのだが、
最近、文庫本で出た『新校訂』版は、『新大系』とまったく同じ校注者なのに
その訓が分かれる
「研究の成果」を新しさに見るのなら「ものもふ」になるのだろうか
「登」がある初句を、敢えて字余りにせずに「ものもふと」としては
何故いけないのだろう
ちなみに、『西本願寺本』を底本とする『新編国歌大観[万葉集]』では、
その「解題」を読むと、本文の右に、「西本願寺本」による訓をつけ、
さらに本文の左に、現代の万葉学の立場で、妥当と思われる訓をつけた、とある
それによると、「西本願寺本」の訓は、「ものおもふ」だが、
現代では、「ものもふ」と訓む立場になっている
『寛永版本』を底本とする『校本万葉集』は、「ものおもふ」とする
|
| |
| [いね] |
名詞「寝(い)」と下二段動詞「寝(ぬ)」とが複合したもの
名詞「い」は、単独では用いられず、助詞を介して動詞「ぬ」とともに、
「いのね(寝)らえぬに」「いもね(寝)ず」などの句として用いられる
また「熟寝(うまい)」「安寝(やすい)」などの語をつくる |
| |
| [接頭語「さ」] |
①「語調」や、「強調」の「さ」の例語として
「さ霧・さ遠し・さ鳴る・さ寝(ね)・さ乱・さ百合・さ夜・さ小舟(をぶね)・さ青(を)」など、
②「若々しさ」の意を添える「さ」には、「さ苗・さ乙女」などがあり、
表記としては、①には「小」、②には「早」の字を当てることがある
|
| |
| |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[本文]「物念登 不宿旦開尓 霍公鳥 鳴而左度 為便無左右二」(「【】」は編集)
「モノオモフト イ子ヌアサケニ ホトヽキス ナキテサワタル スヘナキマテニ」 |
| 〔本文〕 |
| 「旦」 |
『活字無訓本』「且」
|
| 「開」 |
『類聚古集』「【崩し字、読めず】」 |
| 「左」 |
『神田本(紀州本)』「臣」 |
| 「無」 |
『類聚古集』「无」
『細井本・活字無訓本』「為」 |
| 〔訓〕 |
| モノオモフト |
『元暦校本』「フ」ナシ。右ニ墨「フ」アリ。
『神田本(紀州本)』「モノヲモフト」 |
| イ子ヌアサケニ |
『神田本(紀州本)』「イ子ヌアサアケニ」
『細井本・京都大学本』「イ子スアサケニ」 |
| スヘナキマテニ |
『類聚古集』「為便无」ノ右ニ朱「セムスヘナキ」アリ |
| 〔諸説〕 |
| ○[モノオモフト]『代匠記精撰本』「モノモフト」。 |
|
【左頁資料について】
| 『万葉拾穂抄』 |
「物思うといねぬ」の語意解釈、「いねぬあさけ」は、眠らずして明ける朝
江戸時代には、こうした語句に、説明がいるのだろうか
「いねぬあさけ」が、この江戸時代の当時、「古語」として語意説明が必要だった、ということか |
| 『万葉代匠記(精撰本)』 |
契沖が用いる底本に「モノオモフト」とあるのを、著者契沖は「モノモフト」読むべし、とある
第十五に、この語が特に多く、どれも「お(於)」を略して「毛能毛布(ものもふ)」とする根拠、
それで、「ものもふ」が古語として、また歌語として詠われていることが定着している、ということなのだろう
|
| 『万葉集童蒙抄』 |
| ホトトギスの鳴く声が、いっそう「物思い」を深める |
| 『万葉考』 |
真淵は、ホトトギスの声こそが、物悲しく聞こえ、それで我が身にも響く、としているようだ
|
| 『万葉集略解』 |
| 特に筆べきはなし |
| 『万葉集古義』 |
| 物思いで寝られなく、明け方になると、ホトトギスが一層その思いを増させて飛び去って行く |
| 『万葉集新考』 |
著者は、「イネヌアサケ」を、寝ることの出来ない「未明」あかつき、だという
これまで、「あさけ」を、明け方、早朝と解している書ばかりだが、「あかつき」とは...
でも、「あさけ」と「あかつき」は、やはり違うと思うし、ホトトギスの飛び渡る声も、
「未明」ではなく「明け方」の方が、物思いに耽った深さを引き出すのにはいいと思う |
| 『口訳万葉集』 |
| 特筆はなし |
| 『万葉集全釈』 |
ホトトギスの声が、悲しくて何ともやるせないほどに聞こえる
物思いで、眠られなかった、のではなく「眠らなかった」とする |
| 『万葉集全註釈』 |
| ホトトギスの声が、哀愁を誘う、とする |
| 『万葉集私注』 |
| 語義の解釈が厳しい |
| 『万葉集注釈』 |
| 赤人集の歌に、指摘されている次の歌との混同、その通りだと思う |
|
|
|
|
 |
| |
| |
| |
| |
| |
「きみにきせよと」...われをうながす...
|
| 『袖に鳴きて』 |
| 【歌意1965】 |
私の衣をあの人に与えて着せなさいと、
霍公鳥が、まるでそう言っているかのように鳴いて、
私に催促します
ここに来て居つきながら、ずっと... |
|
| |
| |
この歌、私もこれまでの中で、一番頭を抱えた歌だったのだが
同じように、古注の時代から現代に至っても、やはり同じように大変な歌だったようだ
決して、私がその同じレベルだというのではなく
専門家たちが、あっさり解決しようが、あるいは頭を抱えようが
そんなことはお構いなしに、「古語辞典」を片手に自分の解釈を組み立てるものだが
その語義を拾い出しても、文章にしにくいことが、この歌にはあった
意味が通じないからだ
勿論、表向きは、ホトトギスの鳴き声が、この歌のベースにはある
戯れで詠う歌として、洒落てはいると思う
だから、字句通りに解釈しても、「戯れ歌」として片付ければ、それで済む
しかし、ただ一点、「領袖」という漢字表記が目に留まる
そこから、この歌での「苦闘」が始まった
中国の三国時代の後、「晋」という国が興るが
その後の唐の時代に、その「晋」の歴史を記した史書「晋書」(646年成)がある
そこに「領袖」という語の由来が語られている
巻四十一「列伝第十一」[魏舒伝]が、その出典らしい
「領袖」とは「えりとそで」が原義らしいが、衣のもっとも目立つところから
集団を率いる「長」となる人物のことをいう
唐の時代の書物となると、多くの文物が遣唐使によって持ち込まれたことから
万葉の時代の人たちにも、その語の由来は理解できたはずだ
勿論、この歌は偶然「えりとそで」を詠っているのかもしれないが
「領」も「袖」も、この歌でホトトギスが係わる必然性が薄いと思う
ならば、「領袖」という意味を、歌心に解して詠ったのではないかとも思ってしまう
和歌としての「音韻」に拘ることなく、ひょっとして「漢文調」の歌だったのかもしれない
助詞が多用されているので、確かに和歌には違いないが
その表記の語義には、「漢語」を多分に用いた歌だとしたら
「領袖」も捨てきれないと思う
右頁にも書いたが、現在私たちが目にするどんな『万葉集』の普及本も、
「領」を「領」として「うながす」とか「しらせる」、
「袖」を「袖」として、文字通りの衣類を指しているが
その大前提が、表面的な歌を作るための「戯れの歌」であることも
その本質には、誰も「とんでもない発想」だと思いもしなかったかもしれない
ホトトギスの「きぬきせよ」とか「ころもきせよ」とかに聞きなす鳴き声を戯れに用いて
ここを平和に治めたいなら、あなたの財産を、皆に分け与えなさい
...そんな夢想もしてみたかった
万葉の当時、内衣と言われる「肌着」は、男女の違いはなかった、という
だから、この歌も、それに合わせるかのように
女から男へ、贈りなさい、というような「意」というものが自然と思われたのだろう
この歌、本当に頭の痛い歌だった |
|
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1965] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔わかきぬを君にきせよとほとゝきすわれをしらせて袖に來ゐつゝ 〕
吾衣於君令服與登霍公鳥吾乎領袖尓來居管
|
| わかきぬを君にきせよ 此哥の義諸抄に注しもらして知人希なり今口訣別注也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
| |
吾衣於君令服與十霍公鳥吾乎領袖爾來居管
〔ワカキヌヲキミニキセヨトホトヽキスワレヲシラセテソテニキヰツヽ 〕 |
| 於を乎に用る事以前既に注せり、但吾衣をワガコロモと讀て發句とし、於君をキミニとも讀べし、吾乎領とは我に知らせてにて心を著るなり、尋常の鳥だに袖に來居る物にあらず、まして霍公鳥は人に馴ぬ鳥なれば此は夏衣を竿に懸干《ほ》せる其袖に來居てと云なるべし、さるにても君に著せよと知らすると云意いかにとも得がたし古今集にも韓《カラ》紅の振《フリ》出てぞ鳴と讀て霍公鳥は血に啼なれば、人に贈て著せば袖のみ紅深きを見てあはれと思ふべしと我を助る意に袖に來居て啼よと、戀する人の思ひ廻らさぬ事なう物思ふが、折しも衣に霍公鳥の居たるを見てよめるにや、せめてかくばかりも驚かし置て後の人を待に侍り、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
吾衣於君令服與登霍公鳥吾乎領袖爾來居管
〔わがきぬを、きみにきせよと、ほとゝぎす、われをしらせて、そでにきゐつゝ〕 |
此歌いかに共心得難き歌也。時鳥の袖に來居る事あるべき事にあらず。諸抄にも釋し難き由注して、口釋など云て遁れたり宗師某は左の如し
かりごろもせこにつけよとほとゝぎすかりをしらせてそでにきゐつゝ
予未得心。何とぞ誤字脱字あらんか。せこにつけよと讀みて、かりをしらせてと云義聞え難し。言葉の縁等は無餘義聞えたれど、全体の歌の趣意書樣心得難し。宗師の説は、郭公の音を、我思ふ人に告げよとおのが居所を知らせて、既に來居つゝとの義也。此來ゐつゝもと云義も聞え難し。鳴くとか、來鳴くとあらば、知らせてと云意も聞えたれ、只來居つゝと計りは心得難し。君につけよと云ふ義も、下の句と首尾せぬ樣なれば、誤字脱字有べき也。かりと云ふには所と云字を多く書きて、吾と云字を訓借に書ける事も、集中に稀なれば、此も不打着。兎角、別訓脱字の後案を待のみ。領袖爾の三字何とか別訓あらんか
|
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
吾衣、於君令服與登[キミニキセヨト]、 今本吾衣於の三字をわがきぬをと訓たれど於はてにをはに下におくべき字にあらずこは於君[キミ]と訓せんとておける事しるければ誤りしるしよりて句も訓もあらためつ 霍公鳥、吾干領[ワカホスキヌノ]、〔契冲は竿にかけてほしたる衣の袖を云歟されど君にきせよと吾にしらする心得がたしといへり今本誤字多を考得ざる故なり撰要抄云君は霍公鳥を指吾乎領は吾をしらせてと訓べしと云り奥人おもふに吾にしらせてとはいふべきにわれをしらせてとはちと不穩聞ゆ領は承上令下謂之領と有は吾をうながしと可訓〕今本吾乎領とありてわれをしらせてと訓たれど歌の意とほらず字も訓も誤れりとす領は衣一領などいひて衣の事にいへばきぬと訓べし日下部高豐云乎は干の誤なりこをよしとして改つさて歌の意は竿にかけほしたる袖に郭公の來居て鳴を其衣を君にきせよと鳴といへるなり 袖爾來居管[キヰツヽ]、 |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
| |
吾衣。於君令服與登。霍公鳥。吾乎領。袖爾來居管。
〔わがころも。きみにきせよと。ほととぎす。われをしらせて。そでにきゐつつ。 〕 |
| 契沖云ワレヲシラセテとは、我に心を付けてなり云云。是れは竿に懸けて干せる衣などを言ふにや、然《サ》るにても、君ニキセヨト知ラスルと言ふ心を得ずと言へり。翁は、乎は干の誤にて、領は衣一領など言へば、キヌと訓むべければ、ワガホスキヌノ云云なるべし。此歌、懸け干したる衣《キヌ》の袖に來ゐて鳴くと言はんより外無しと言はれき。とかくに四の句誤字有るべし。猶考ふべし。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔アガコロモ。キミニキセヨト。ホトヽギス。アレヲウナヅキ。ソデニキヰツヽ。〕
吾衣於君令服與登霍公鳥吾乎領袖爾來居管
|
吾乎領は、岡部氏この歌、末(ノ)句意得がたし、契冲云、常の鳥だに、袖に來居るものにあらぬうへに、ことにほとゝぎすは、人なれぬ鳥なれば、これは竿にかけてほせる衣などを云にや、さるにても、君にきせよとしらするといふこゝろをば得ず、といへり、又こゝに高豐と云人、乎は于(ノ)字かと云り、此(ノ)二(ツ)を合せて、乎は竿(ノ)字として、義訓にホスとよみ、領は、衣一領と云を以て、是もキヌと訓べしさらばワガホスキヌノならむか、又末に、鳴毛の字を落せしかと云一説あり、それによらば、吾竿領袖爾來居管鳴毛《ワガホスキヌニキヰツヽナクモ》、ならむか、猶考(フ)べしと云り、(以上岡部氏説、)中山(ノ)嚴水、領は頷の誤なるべし、ワレヲウナヅキなるべし、吾乎《ワレヲ》は、我爾《ワレニ》といふ意の古言なり、さて頷は、うなづきてしらする意にて、霍公鳥の鳴とき頭の動くが、頷くが如くなれば云るなり、さて袖は契冲云る如く、竿にかけて、ほせる衣なるべしと云り、(以上嚴水(ノ)説、)ウナヅクは、中昔の物語に、往々見えたる詞なり、古言なるべし、源氏物語帚木に、さは侍らぬかといへば、中將うなづく、と見えたる類なり、○歌(ノ)意は、吾(カ)衣を君に服せ奉れよと、吾に頷《ウナヅキ》しらせて、吾竿にかけてほしたる衣の袖に、來居つゝ鳴ならむといふか、
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔わがころも君にきせよとほととぎす吾乎領[ワレヲウナガス]、袖に來居つつ〕
吾衣於君令服與登霍公鳥吾乎領袖爾來居管 |
第四句を舊訓にワレヲシラセテとよみ、古義に中山嚴水の説に從ひて領を頷の誤としてアレヲウナヅキとよめり。なほ後にいふべし○契沖は
尋常の鳥だに袖に來居るものにあらず。まして霍公鳥は人に馴ぬ鳥なれば此は夏衣を竿に懸干せる其袖に來居てと云なるべし。さるにても君ニ著セヨト知ラスルと云意いかにとも得がたし
といひ、眞淵は右の説に枝を添へて
四句の乎は干の誤にて領は衣一領などいへばキヌと訓べければワガホスキヌノ云々なるべし。此歌かけほしたる衣の袖に來ゐてなくといはんより外なし
といひ、雅澄は中山嚴水の説を擧げて
領は頷の誤なるべし。ワレヲウナヅキなるべし。吾乎は吾爾といふ意の古言なり。さて頷はうなづきてしらする意にて霍公鳥の鳴とき頭の動くがうなづくが如くなれば云るなり。さて袖は契沖云る如く竿にかけてほせる衣なるべし
といへり。案ずるにこは子規の形を摺れる衣を人に贈るとて子規ガ吾袖ニトマリツツ此衣ヲ君ニ贈レト我ヲ云々スといへるなり。第四句の領は今の通用としてウナガスとよむべし。孝德天皇紀に凡京毎坊置長一人四坊置令一人とありて令をウナガシとよめり。又仁德天皇紀十年に百姓不領とあるをウナガサレズシテとよみ大寶令に國郡領造、付領訖、國司領送などあるを皆ウナガシとよめり。又天武天皇紀十四年に周芳《スハウ》ノ總令とあるはやがて總領にて欽明天皇紀四年に百済郡令とあるはやがて郡領なり。否總領郡領などは寧總令郡令と書くべきなり。かゝればいにしへ令と領とは通用せしなり。はやく續日本紀考證卷二大寶元年正月相樂郡令の下に
郡令見欽明紀。令即領字。古或以音近借用之。天武記有周防總令所。即總領所也。案令領通用。通雅楊子曰。君子純終領聞。○[赤+おおざと偏]京謂。即令聞
又同年四月田領の下に
貞觀三年二月田券有田領紀(ノ)直《アタヒ》牧成。案欽明紀云。十七年秋七月云々以葛城山田(ノ)直瑞子爲田令(田令此云舵豆歌○[田+比])。田領即田令
と云へり |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
| |
吾が衣君に著せよと、霍公鳥、我が干す衣[キヌ]の袖に來坐[ヰ]つゝ |
| |
自分が干して居る著物を、早くあの方にお上げなさい、と其著物の袖の邊に來乍ら、催促して鳴いてゐるやうだ。(思へばもう、衣更への時期にもなつて來た。) |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔わがころも きみにきせよと ほととぎす われをうしはき そでにきゐつつ〕
吾衣於君令服與登霍公鳥吾乎領袖爾來居管
|
私ノ着物ヲアナタニ着セヨト、霍公島ガワタシヲ指圖シテ、着物ノ袖ニ、來テトマツテヰル。
○吾衣《ワガコロモ》――舊訓ワガキヌヲとある。○吾乎領《ワレヲウシハキ》――舊訓ワレヲシラセテ、考は乎を干に改めてワガホスキヌノ、古義は領を頷としてワレヲウナヅキ、新考はワレヲウナガスと訓んでゐる。領は集中シラスともウシハクとも訓んであるが、新訓に從つてウシハクとよむことにした。改字説は感心しない。殊に頷に改める事は無理であらう。頷は集中に見えない文字である。ウシハキと訓んで、吾を支配し、指圖しての意と解するがよいであらう。
〔評〕 分らぬ歌であるが、言葉通りに解して右の通りにして置いた。契沖が言つたやうに、郭公は袖などに來て鳴くものではないが、近く來て鳴いたのを戯れて、かうよんだのではあるまいか。新考に郭公の形を摺れる衣を、人に贈るとてよんだものとしたのは當るまい。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔わがころも きみにきせよと、ほととぎす われをうしはき そでにきゐつつ。〕
吾衣於君令服與登霍公鳥吾乎領袖爾來居管 |
【訳】わたしの著物を、あなたにお著せなさいと、ホトトギスが、わたしを占領して、袖に來ております。
【釈】吾衣 ワガコロモ。ワガキヌヲ(元)、ワガコロモ(代初)。衣は、キヌヲともコロモとも読まれるが、ヲに當る字が無いから、コロモと讀む。ここでは、作者の著ている衣服である。
吾乎領 ワレヲウシハキ。 ワレヲシラセテ(西)、ワレヲウナガス(新考)、ワレヲウシハキ(新訓) 吾干領《ワガホスキヌノ》(考)、吾乎頷《アレヲウナヅキ》(古義) ウシハキは、領有する意。「奧國《オキツクニ》 領君之《ウシハクキミガ》 染屋形《シメヤカタ》」(卷十六、三八八八)の領もウシハクと讀む。
【評語】衣服に添えて人に贈つた歌だろう。ホトトギスを持ち出したのは風雅である。ホトトギスの聲が、人を催すように感じられることが働いている。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| |
〔わがきぬを きみにきせよと ほととぎす われをうながす そでにきゐつつ〕
吾衣於君令服與登霍公鳥吾乎領袖爾來居管 |
【大意】吾が衣を君に着せよと、ほととぎすが、吾を促がす。袖に来て居て。
【語釈】ウナガス 井上氏新考の訓である。「領」は「令」に通じ、地方官の令、領をウナガシと呼ぶからであると説明された。地方官をウナガシと呼ぶのも、百姓を督促する意からであらう。
【作意】ほととぎすが、吾が衣を、君に贈つて着さすやうにと、袖にとまつて、吾を促したてるといふ一つのフィクションである。ほととぎすの模様のある衣を、贈るなどと考へる必要はない。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
| |
〔わがころも きみにきせよと ほととぎす われをうながす そでにきゐつつ〕
吾衣於君令服與登霍公鳥吾乎領袖爾來居管 (『元暦校本』) |
【口訳】私の着物をあなたに着せよと、ほととぎすが私を促します。私の袖に来て居て。
【訓釈】吾が衣―旧訓ワガキヌヲ、[代匠記]に「わかころもきみにともよむべし」とある。この歌、於(ニ)、与(ヨ)、登(ト)、乎(ヲ)、尓(ニ)、と助詞が記入されてゐるので、ここはコロモと訓むべきかと思はれる。
吾をうながす袖に来居つゝ―「吾乎領」を『類聚古集・紀州本・京都大学本(左に赭)』ワカケヨソヒノ、『西本願寺本』以後ワレヲシラセテとあり、『代匠記』に「尋常ノ鳥ダニ袖ニ来居ル物ニアラズ。マシテ霍公鳥ハ人ニ馴ヌ鳥ナレバ此ハ夏衣ヲ竿ニ懸干セル其袖ニ来居テト云ナルベシ。サルニテモ君ニ着セヨト知ラスルト云意、イカニトモ得ガタシ」といひ、『万葉考』には「吾干領」とし「領は衣一領などいひて衣の事にいへばきぬと訓べし。日下部高豊云乎は干の誤也。こをよしとして改つ。歌の意は竿にかけほしたる袖に郭公の来居て鳴を其衣を君にきせよと鳴といへるなり」といひ、『古義』には「中山巌水、領は頷の誤なるべし、ワレヲウナヅキなるべし、吾乎(ワレヲ)は、吾尓(ワレニ)といふ意の古言なり、さて頷は、うなづきてしらする意にて、霍公鳥の鳴とき頭の動くが、頷くが如くなれば云るなり、さて袖は契沖云る如く、竿にかけて、ほせる衣なるべしと云り」とあるが、増訂本新考に「案ずるにこは子規の形を摺れる衣を人に贈るとて子規が吾袖ニトマリツツ此衣ヲ君ニ贈レト我ヲ云々スといへるなり。第四句の領は令の通用としてウナガスとよむべし。孝徳天皇紀に凡京毎坊置長一人四坊置令一人とありて令をウナガシとよめり。又仁徳天皇紀十年に百姓不領とあるをウナガサレズシテとよみ大宝令に国郡領送、付領訖、国司領送などあるを皆ウナガシとよめり。又天武天皇紀十四年に周芳(スハウ)ノ総令とあるはやがて総領にて欽明天皇紀四年に百済郡令とあるはやがて郡領なり。否総領郡領などは寧総令郡令と書くべきなり。かゝればいにしへ令と領とは通用せしなり」と述べ、続日本紀考證巻ニ大宝元年正月相楽郡令の條と同年四月田領の條に領令通用の事を述べてゐる事を引いてゐる。新訓にはウシハキとし、全釈それに従ひ「吾を支配し、指図しての意と解するがようであらう」とし、全註釈は「ウシハキは、領有する意」といひ、「わたしを占領して、袖に来て居ります」と訳されてゐるが、この場合はウシハクよりウナガスの方が適切だと思はれる。問題はほととぎすが袖に来居るといふ点で、契沖以来干してある着物の袖と云つたり、新考の如く、子規の形を採った着物と云つたりする事になつたりするのであるが、
| ほととぎす鳴きつる方を眺むればただ有明の月ぞ残れる (千載集巻三) 後徳大寺実定 |
の如き歌がほととぎすの代表的な歌だと考へられるやうになると、「袖に来居る」といふやうな事は考へられない事になるけれども、萬葉では、
| 吾がやどの花橘を霍公鳥来鳴きとよめて本に散らしつ (8・1493) |
| 橘の林を植ゑむ霍公鳥常に冬まで住み渡るがね (1958) |
| 霍公鳥来鳴きとよもす橘の花散る庭を見む人や誰 (1968) |
の如く、今日の鶯の如く庭前に見る歌のある事を思ふと、平安京と奈良の京と僅かの違ひのやうであるが、ほととぎすと人間との親しみはその間に相当のへだたりがあつたと見るべきではないかと私は考へるのである。
| 折りつれば袖こそにほへ梅の花ありとやここに鶯の鳴く (古今集巻一) よみ人しらず |
が認められるやうに、このほととぎすの歌も認められるのではなからうか。
【考】赤人集に、前の歌の前半とこんどうされてゐる事その條で述べた。 |
|
|
掲載日:2014.03.26.
| 夏雑歌 詠鳥 |
| 吾衣 於君令服与登 霍公鳥 吾乎領 袖尓来居管 |
| 我が衣君に着せよと霍公鳥我れをうながす袖に来居つつ |
| わがころも きみにきせよと ほととぎす われをうながす そでにきゐつつ |
| 巻第十 1965 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1965】 語義 意味・活用・接続 |
| わがころも [吾衣] 私の着物 |
| ころも [衣] |
着物・衣服 |
| きみにきせよと [於君令服与登] |
| きせよ [着す] |
[他サ下二・命令形] 着せる・身につけさせる |
| ほととぎす [霍公鳥] |
| われをうながす [吾乎領] |
| うながす [促す] |
[他サ四・終止形] せきたてる・催促する |
| そでにきゐつつ [袖尓来居管] |
| すべなき [術無し] |
[形ク・連体形] なすべき手段がない・どうしようもない |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [ころも] |
平安時代の仮名文では、衣服のことを言うときはふつう「きぬ」を使い、
「ころも」は歌語として使われた、と古語辞典にある
その説明では、この初句が「わがころも」であることに矛盾はないが
古注釈の初期の頃は「わがきぬを」と訓まれていた
それを、賀茂真淵が原文の「於」に注目し、「吾衣於」は「わがきぬを」ではなく、
「吾衣」と、「於」を「於君」と第二句に入れて改訓したのが、
現代に繋がっているようだ
だから、真淵以前では「わがきぬを」と訓まれる事が普通であったと思うが
その上で、古語辞典を読めば、それが「一説」ではなく、定まったものであるなら
万葉の時代は、「わがころも」になるだろう
もっとも、平安時代の「きぬ」が、万葉時代は「ころも」と呼ばれ、
それが平安時代では「歌語」として残り、日常では「きぬ」とされた、
と解釈してのことだけど...
さらに、真淵は助詞の語法にも言及しているので、
原文「於」をどうしても初句に入れられなかったことが、大きな理由にもなっていると思う
それでも、現代の注釈書の中にも、「わがきぬを」はある
『新編国歌大観』を始め、『私注』『角川文庫本』... |
| |
| [われをうながす] |
旧訓「われをしらせて」
この「知らす」ということであれば、「われに」となると思ったら、
案外そこが歌語の難しいところだ
助詞の使い方が、現代語とはまるっきり違う
もっとも、日常の語であれば、歌はその独特の響きを失うこともあるだろうが...
それにしても、この歌、
初句の「ころも」とか「きぬ」の異訓は、歌意が変わるわけでもなく
結局は、読む人の「感性」にも多く拠るものだろうが
この「うながす」にいたっては、随分と賑やかな論争があるようだ
近世の以降の多くの学者が、「領」という語義を、日本書紀などを引き出し
かなり詳細に述べている
今のところ、井上通泰が訓んだ「うながす」の語意が当てられているが
過去に溯っては、相当苦労していることが窺える
荷田春満足などは、「領袖爾」の三文字、別訓はないのか、と歎いている
真淵は、「領」は「衣の襟」のことだと解釈している
そこから「きぬ」という「訓」に辿り着くわけだが...
原文を見て、すぐに気づいたことがある
「領袖」という言葉だ
単純に、衣の「エリとソデ」のことだが、「衣」にとっての重要な部分と言うことで
そこから転じて、今日で言う「リーダー」のような意味合いも持っている
中国唐の時代に、「晋代の歴史」を書いた『晋書』が出典だと本にはあった
すでに万葉の時代には、この言葉も知られているのでは、と思う
「領袖」を一語とみると、通説の「吾乎領」、「袖爾」と句切りはおかしくなる
そうしているからこそ「われをうながす(あるいは、しらせて) そでに」となる
「万葉歌」の原文は、どこで句切りがあるか解らない
漢字がただただ続けて並べられている
だから、通説のような句切りが、絶対かどうか、解らない
しかし「領袖」が一語であれば、「領袖爾(に)」を春満が歎いた問題の糸口になると思うが
では、どうやって訓を当てれば、歌になるのか...解らない
語義を失わず、訓めること...
「吾乎領袖爾」は、格助詞「を」の「~を~に」の語法にもなる
「~を~として」...「私を領袖として」
こんな風に思えば、突飛もない発想は浮ぶ
私のこの衣、霍公鳥が、君に与えなさい、という
私が領袖として、ここに来て居続けるならば... |
文末の接続助詞「つつ」は、条件法とか言う語法はなかったのかなあ
まあ、こんな発想もまた自由だ
しかし、訓めなければ、はじまらない
「領袖」は、「かしら」という「万葉語」にもなりそうだが...
でも、竿に干す衣に、霍公鳥が来て、とか
古注釈でも、発想の豊かな解釈は結構あるものだ |
| |
| |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[本文]「吾衣 於君令服与登 霍公鳥 吾乎領 袖尓来居管」(「【】」は編集)
「ワカキヌヲ キミニキセヨト ホトヽキス ワレヲシラセテ ソテニキヰツヽ」 |
| 〔本文〕 |
| 「服」 |
『京都大学本』「月+艮」
|
| 〔訓〕 |
| キミニキセヨト |
『元暦校本』「ヨフ」ナシ。右ニ墨ニテ書ケリ
『類聚古集』「きみにきせむと」。「む」ノ右ニ朱「ヨ」アリ
『神田本(紀州本)』「キミニキセムト」 |
ワレヲシラセテ
ソテニキヰツヽ |
『元暦校本』「わかけきそひのそてにきゐつゝ」
『類聚古集』「わかけきそひのそてにきゐるか」。「るか」ノ右ニ朱「ツヽ」アリ
『神田本(紀州本)』「ワカケヨソヒノソテニキヰツヽ」
『西本願寺本』「ワレヲシラセテ」モト青
『細井本』「吾乎領」ノ左ニ「ワカケヨソヒノ」アリ
『大矢本・京都大学本』「シラセテ」青。
『京都大学本』漢字ノ左ニ赭「ワカケヨソヒテニキヰツヽ」アリ |
| 〔諸説〕 |
| ○[ワカキヌヲ]『代匠記初稿本』「ワカコロモ」。『改』「カリコロモ」。○[キミニキセヨト]『改』「セコニキセヨト」。○[吾乎領]「ワレヲシラセテ」。『改』「カリヲヨソヒニト」。『童蒙抄(師案)』「カリヲシラセテ」。『万葉考』「乎」ハ「干」トスル(日下部高豊)ヲ可トス。訓「ワガホスキヌノ」。『古義』「中山巌水説「領」ハ「頷」ノ誤。訓「ワレヲウナヅキ」。○[袖爾来居管]「ソテニキヰツヽ」。『童蒙抄』「スデニキヰツヽ」。『古義』「岡辺氏説」「管」ノ下「鳴毛」脱トシ「袖爾」ヲ上ノ「領」ト合セテ「キヌニ」ト訓ジ「来」以下ヲ「キヰツヽナクモ」ト訓ズ。 |
|
【左頁資料について】
| 『万葉拾穂抄』 |
意味が解らない
「諸抄」というのは、こうした「万葉集解釈」の書のことだろうか
「注しもらして」「知る人稀なり」...何となく解るが、この時代の「注釈書」の性格を知りたい |
| 『万葉代匠記(精撰本)』 |
初二句を、別の訓もある、とするものだろう
「吾乎領」と「領」を「知らせる」とする解釈
さらに、霍公鳥の現実の「鳥」としての捉え方から、理屈に合わないことをいう
竿に「干す」衣に、来て止る、と現実的な解釈だが、これが歌だと言うことを思えば...
|
| 『万葉集童蒙抄』 |
荷田春満も、お手上げのようだ
それほど、この歌を解するのは難しいのだろう |
| 『万葉考』 |
原文の句切り方に、初めて及んだものだと思う
それまで、初句三字「吾衣於」を「わがきぬを」と訓まれていたのを、
「於」は次句に付けている
|
| 『万葉集略解』 |
第四句「吾乎領」が、どうにもならないようだ
当時の学説(「乎」は「干」の誤、「領」は「きぬ(衣)」)に耳を傾けながらも、なおも考察が必要としている |
| 『万葉集古義』 |
ここでも「吾乎領」が大きな難題として書かれているが、霍公鳥の鳴く時の仕草が、あたかも頷くような擬態を表し、「領」は「頷」の誤だという説まで持ち出すも、多くの「仮説」を前提にすれば、そもそも本歌でなくなってしまうこと、客観的に読んでいると、よく解る
結局、最後に「歌意」として書かれているのも、一応もっともらしいが、解釈においては、他の書とそれほど変わらないものだ |
| 『万葉集新考』 |
この「書」で、初めて「領」を古典席に沿った解釈を試みている、と思う
『日本書紀・続日本紀』の引用から、「領」は、「うながす」意を言うのだとする
少なくとも、そうした検証が為されれば、それを覆すには、それ以上の検証結果が必要になる
過去の感覚的な「訓」解釈とは、大きく違ってきている
安易な「誤字」説は、やはり避けたいというのが、本当の学者の姿だろう |
| 『口訳万葉集』 |
歌人・折口信夫としては、「歌らしく」情景を解釈したいのだろうが、
こうした解釈...どれも同じような解釈にはなるが、それで意味が通るのかどうか...
「歌意」の中での表現にはならないが、結局はどの注釈書でも
霍公鳥が「きぬきせよ」「ころもきせよ」という鳴き声に似ていることが、大前提の歌としている
だから、歌の主眼は、そこに重きを置き、「歌意」を試みるところから始まっているかのようだ |
| 『万葉集全釈』 |
問題の第四句「吾乎領」の「領」を、支配する意の「ウシハク(領く)」としている
『新訓万葉集』〔岩波文庫、佐佐木信綱、1927年刊行〕に基づいてるようだが、
「領」という「字」だけの語義を考えれば、それも言えるだろう
すると、「作者・霍公鳥・君」の関係が、歌に似つかわしくなくなってしまうと思う
「評」にもあるように、「歌」としては、とても難しい一首だと思う
ただ、字句通りに読めば、訓の解釈は別にして、一応の「文」にはなる |
| 『万葉集全註釈』 |
| 解釈はともかく、「注釈書」としては、私にはもっとも解り易かった |
| 『万葉集私注』 |
| 特になし |
| 『万葉集注釈』 |
この注釈書は、基本的にそれまでの諸注を引用して是非を検討している性格だと思う
だから、自説に至っても、どれが適切なのか、と結ぶ形であり、
その検証は過去の検証の結果を引用している
やはり、新しくなればそれだけ多くの情報が詰め込まれるものだが、
古注釈書の網羅だけに留まらず、更に深めていくことも忘れてはいない
いい書だとは思う |
|
|
|


|
 |
| |
| |
| |
| |
| |
「いまかながくる」...こひつつをれば...
|
| 『古き馴染みの人』 |
| 【歌意1966】 |
昔なじみのホトトギスよ、やっと来てくれたのだなあ
私が、お前を懐かしがって思っているので、
こうやって恋しく思っていたから
お前は来たのだろうか... |
|
| |
| |
歌の難しさを、最近つくずく感じてしまう
その歌に、何を求めるか、という読む人の姿勢が一番大切だとは思うが
『万葉集』を解釈しようと、詠われた当時からはるかに時を経て行われた解釈
当然、作家本人の「声」はなく、伝え語られてきた「訓」や、外国語の「表記」
作家の意図を、あるいは「歌の心」を追い求めるのは、学者として当然のことだ
しかし、私のような素人には、その一首から受ける「何か」が自分に与える「感動」だと思う
とは言っても、勝手気ままに解釈などすれば、「歌」の本来の意味を侮辱することになる
だから、最低限の語義解釈は行っておきたいと願って始めたものだが
今、気づくと、随分深入りしてしまったような気もする
何も知らなければ、その範囲での解釈で済んだものを
少し別な見方があるのか、と知れば
それを追いかけたくなる
結局、今していることは、それぞれの一首が、どんな風に古来から受止められてきたか...
その中に、私が感じた「うたごころ」があるのか...
頷き、あるいは首を振り...
それでも、様々な解釈を一首ごと接してくると、
普段の私なら、思いも及ばない感じ方をしてしまうこともある
それが、自分の「成長」だと信じて...今は邁進しよう
人生を終えるまで、続けられるものに、こうして出逢えたのだから...
この掲題歌は、最近の注釈書に接すると、待ち焦がれた想い人との出逢いを
ホトトギスの、懐旧の情けを起こさせる、という「顔」に
巧みに歌に取り入れたかのように訳されている
しかし、この歌を初めて一読し、さらに何度も読み返して感じたのは
この歌に、「恋しく想う人」が、やって来た、とするようには思えなかった
どうしても「汝」という「語」が気になって
「恋しく想う人」を、「汝」という「歌」は、私には「歌らしく」ないように思える
「せこ」「いも」「きみ」など、聞きなれた呼称がある
それが決まりではないことは理解出来るが、
この歌で、どうして「汝」を「霍公鳥」とは思えないのだろう
そう思って、古注を読んでいくと、むしろ「古注釈書」では、
「汝」は「霍公鳥」としている「書」が断然多い
しかも、いろいろと用例なども駆使して、その検証にも時間を割いていることが解る
現代の書になればなるほど、すでに確立された「訓」や「解釈」のおかげで
読むものには、当たり前の「解釈」のように感じられるが
当初においては、凄まじいほどの「注釈」への情熱だったと思う
そんな中で、どこかで解釈が変わり、定訓なり通釈が変わるのであれば
その時点で、原点に匹敵するほどの「情熱的」な「検証」がなければ、と思う
その点を置いたままで、結果だけを「万葉集の注釈」として公表されれば
当然、素人では、たまたま手にした「注釈書」が、唯一無二の「万葉解釈」になり
そこから、自分の感性にどう響くかが始まる
そもそも、語義解釈は必要であっても、歌意の解釈は、必ずしも...と思っている
語義を理解した上で、自分なりに感じることができれば、と思う
ただ、その語義解釈こそが、もっとも厄介な作業だということは
このところ読み出した「古注釈書」をみても、よく解った
それこそ、江戸時代の先人が行ったこの作業は、一生を掛けるほどの作業だったのだろう
「万葉歌四千五百首」、ずべての語義解釈など、自分で拙いながらも行ってみて
その難しさがよく解る
有斐閣『全注』は、最も新しい注釈書の一つだが、
以前少しばかり言葉を交したことのある、その巻第十ニの筆者、小野寛博士は
その時、感慨深げに言われた...この巻第十ニに、十八年費した、と
その苦労の実体が、どこか江戸時代の「注釈作業」にたぶってくるを
だから、私も出来るだけ、個々の歌を大切にしたいと思う
話しは、掲題歌に戻る
あくまで、私の受けるこの一首だが、語義をある程度理解した上で、
掲題上出の歌意のように、お前の鳴き声を聞きたいと
ずっと恋しく想っていたので、やっと来てくれたのだな、と
|
|
【赤人集(成立年時未詳、撰、藤原公任[966~1041])】
| かむへひと時鳥をやまれにみむ いまやなかきくこひつゝおれは |
| 新編私家集大成-新編増補(陽明文庫蔵三十六人集) 131 |
| こんつひとほとゝきすをやまれにみん いまやなつきてこひつゝおれは |
| 新編私家集大成(書陵部蔵三十六人集) 117 |
| こむ□ひとほとゝきすをやまれにみむ いまやなへてにこひつゝをるは |
| 新編国歌大観(西本願寺蔵三十六人集) 237 |
|
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1966] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔もとつ人霍公鳥をやまれに見んいまやなかくる戀つゝをれは 〕
本人霍公鳥乎八希将見今哉汝來戀乍居者
|
| もとつ人霍公鳥をや 本人はもとの人也源氏若菜卷にもある詞也哥心は今汝か來る事戀まちつゝをれは稀なる鳥なれはもとの人もまれに見たらんと也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
| |
本人霍公鳥乎八希將見今哉汝來戀乍居者
〔モトツヒトホトヽキスヲヤマレニミムイマヤナカクルコヒツヽヲレハ 〕 |
| 本人とは昔の妻をも云ひなき人をも云ふ、此は郭公の聲を昔より聞馴て云なり、鳥けだ物草木までも人とは讀習なり、後撰集に待人は誰ならなくに郭公とよめるも郭公を指て待人と云へり、此集に鴈をも遠津人とよめり、されば本人と思ふ霍公鳥なればまれにやは見む、あかずこそきかまほしきを待つゝをるに、今ややうやう、汝が來る、初て聲の聞ゆるはとよめる歟、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
本人霍公鳥乎八希將見今哉汝來戀乍居者
〔本人、ほとゝぎすをば、まれにみん、今哉汝くる、こひつゝをれば〕 |
| 人 此二字心得難し。當集に此本[モト]つと云事、時鳥の歌に何首もありて、いかゞしたる事と云ふ釋先達も注せず。只時鳥の聲を、もとより聞きなれたれば、時鳥をさして本つ人と注せり。鳥獣をも人と云事、古詠に多き事なれば、こゝも時鳥を指して云へるとの説有。又もとの人、古人の事と云説もありて、確に定まれる正説不決也。古事などありて、時鳥を、もとつ人とよめる事にもあらば、時鳥の事に見る方、義安かるべし。然れ共其譯なければ、本つ人と云義いかに共釋し難し。宗師案は、みやこ人と云義なるべしと也。國の本と云は王都なれば、みやこ人と云義訓と見るべしと也。歌の意、都人は時鳥を稀に見るらめ。山里なれば、戀をれば今やなが來るとの意と也。予未得心。歌の意、とくと首尾聞え難し。如此にては、山里にてよめる歌と理りて見ざれば聞えざらんか。今やなが來ると云ふも少しむづかしからんか愚案は、何とぞ古事ありて、もとつ人とは時鳥の冠辭なるべし。然らば只時鳥をや今偶々も見ん、既に戀ひつゝをりてなれくればと云意ならんか。只作者の、時鳥今や稀に見んと云意ならんか。今哉汝來も、今やなれくると讀みて、馴れ來るの意をこめて詠めるならんか。戀ひつゝをれば今はなれ來て、時鳥を稀にも見んとの歌と聞ゆる也。又本人は昔人と云義か。昔の人も時鳥稀にや見つらん、今やのやは助語の格あれば、只今汝が來れと云ひて、戀つゝをれば、久しく待戀ひし心を云へるか。是にても不打着也。本人は時鳥の冠辭と見る方の義は最も安き也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
本人[モトツヒト]、霍公鳥乎八[ヲヤ]、 こはほとゝぎすをさしてもとつ人といふなり年毎に待戀居るものなればしか云又霍公鳥を故友などいふ事もありすべて時鳥のみならず(卷五)には「遠つ人かり路の池」とよめるも雁を人に譬なり
希將見[ネギテミン]、 今本希將見をまれに見んと訓るはあしゝよりてねぎて見んとよめり希はこひねぐ意なればなり
今哉汝來[イマヤナガコム]、 今本ながくると訓るはてにをはたがひて意をなさすよりてあらためつ
戀乍居者、 歌の意は郭公をこひしたしみつゝ居ははやこよとねぎてだにも見んさらば今や郭公のこんを云るなり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
| |
本人。霍公鳥乎八。希將見。今哉汝來。戀乍居者。
〔もとつひと。ほととぎすをや。めづらしく。いまやながこし。こひつつをれば。 〕 |
郭公を指してモトツ人と言へり。集中遠つ人鴈がきなかむと詠める遠ツ人は、鴈を言へるにひとし。ヤはヨヤの事なりと宣長言へり。呼びかくる詞なり。
參考 ○霍公鳥乎八、希將見(新)「霍公鳥」と「希將見」と入りかはる、メヅラシキヲヤホトトギスとす。希將見(考)ホギテミム(古)略に同じ ○今哉汝來(考)イマヤナガコム(古)略に同じ(新)ナキヤナガコシ「今」を「吟」とす。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔モトツヒト。ホトヽギスヲヤ。メヅラシク。イマヤナガコシ。コヒツヽヲレバ。〕
本人霍公鳥乎八希將見今哉汝來戀乍居者
|
本人[モトツヒト]は、契冲、むかし相しれる友をもいひ、又昔の妻をも云ことなり、こゝはほとゝぎすの聲を、もとよりきゝなれたれば、むかしの友とおもひて、かく云るなり、鳥獣草木までも、人とはよみならひたり、後撰集に、待人はたれならなくにほとゝぎす、おもひのほかになかばうらみむ、これもほとゝぎすをさして、待人と云り、第十二に、遠つ人かりぢの池とつゞけたるは、遠より來る鴈と云心に云り、第十七にも、遠つ人かりがきなかむと云り、源氏物語若菜下に、御猫どもあまたつどひはべりにけり、いづらこのみし人はと尋て、みつけたまへりともありと云り、
○霍公鳥乎八[ホトヽギスヲヤ]は、やよほとゝぎすとよびかけたる意なり、乎八[ヲヤ]は八與[ヤヨ]と云むが如し、
○歌(ノ)意は、昔の友にてある、やよほとゝぎすよ、汝にあひたしと戀しく思ひつゝ居れば、待しかひありて、めづらしく今來りしや、といふならむか、
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔もとつ人、霍公鳥乎八[メヅラシキヲヤ]、希將見[ホトトギス]、今哉汝來[ナキヤナガコシ]、こひつつをれば〕
本人霍公鳥乎八希將見今哉汝來戀乍居者 |
略解古義にホトトギスヲヤメヅラシクイマヤナガコシとよみ、さて略解に
ほとゝぎすをさしてモトツ人といへり。集中[卷十七]トホツ人雁ガ來ナカムとよめるトホツ人は雁をいへるにひとし。ヲヤはヨヤの意也と宣長いへり。呼かくる詞也
といひ、古義に
歌の意は昔の友にてある、やよほとゝぎすよ、汝にあひたしとこひしく思ひつゝ居れば待しかひありてめづらしく今來りしやといふならむか
といへれど二三の句と今哉といふことゝ穩ならず。よりて案ずるに霍公鳥と希將見と入りかはり又今哉は吟哉を誤れるならむ。されば
もとつ人、希將見乎八、霍公鳥、吟哉汝來こひつつをれば
にてメヅラシキヲヤホトトギスナキヤナガコシとよむべし。上にもヨブコドリ吟八汝來《ナキヤナガコシ》とあり○さてヲヤはニ(名詞を受くればナルニ)にかよふヲに無意義のヤの添へるにて當時行はれし一種の辭ならむ。卷四(七一五頁)なる
相おもはぬ人をやもとなしろたへの袖ひつまでにねのみしなかも
又上(一九七九頁)なる
相念はぬ妹をやもとなすがのねのながき春日をおもひくらさむ
のヲヤも今のヲヤとおなじきか。即ヤはナカモ、クラサムの下にめぐらして見べき疑辭にはあらで無意義の助辭なるか。こはなほ研究すべし〇一首の意は
古キナジミハユカシキヲアハレナル子規ヨ、ワガコヒツツヲレバ汝ハ鳴イテ來タカ、ヨクゾ鳴イテ來タ
といへるならむ |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
| |
舊[モト]つ人[ビト]霍公鳥をや稀に見む。今や汝[ナ]は來し。戀ひつゝをれば |
| |
古馴染の子規よ。お前をば客人として待遇[アシラ]はう。私が焦れてゐたので、今お前が來てくれたのか。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔本つ人 ほととぎすをや めづらしみ 今か汝が來る 戀ひつつをれば〕
本人霍公鳥乎八希將見今哉汝來戀乍居者 |
ワタシガ昔馴染ノ友達ノ郭公ヲ珍ラシイノデ戀ヒ慕ツテ居ルト、丁度今オマヘガヤツテ來ル。ホントニナツカシイ鳥ダ。
○本人[モトツヒト]――昔馴染の人の意で、次の句の霍公鳥のことである。卷十七に雁を遠つ人と稱し、登保都比等加里我來鳴牟等伎知可美香物[トホツヒトカリガキナカムトキチカミカモ](三九四七)とあるのに似てゐる。
○霍公鳥乎八[ホトトギスヲヤ]――ヲは結句につづいてゐる。ヤは呼びかけていふのでヨの意である。古義に「乎八[ヲヤ]は八與[ヤヨ]と云むが如し」とあるのは當るまい。
〔評〕 本人[モトツヒト]は卷十二(三〇〇九)・卷二十(四四三七)にも用ゐてあるが、ここのは用法が變つてゐて面白い。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔もとつひと ほととぎすをや めづらしみ、いまやながくる。こひつつをれば。〕
本人霍公鳥乎八希將見今哉汝來戀乍居者 |
【訳】昔なじみの人であるほととぎすをか珍しがつて、今にもかあなたがくるだろう。恋い慕つているので。
【釈】本人 モトツヒト。昔なじみの人の意で、ホトトギスは、前年から知り合いであるからいう。霍公鳥乎八希將見 ホトトギスヲヤメヅラシミ。ホトトギスをめずらしく思つてか。希将見は、義をもつてメヅラシに当てている。ヤは、疑問の係助詞で、メヅラシミがこれを受けている。
今哉汝來 イマヤナガクル。ヤは、疑問の係助詞。句切。
戀乍居者 コヒツツヲレバ。作者が、歌中の汝に対して恋いつついるのである。
【評語】二個の疑問條件法を使つて構成して、時鳥の来鳴く頃に人を待つ心が描かれている。今にもくるだろうかと待つ心がよく出ている。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| |
〔もとつひと ほととぎすをば めづらしむ いまやながくる こひつつをれば〕
本人霍公鳥乎八希將見今哉汝來戀乍居者 |
【大意】古いなじみのほととぎすをば、会いたいと思つて居る今、まあお前が来るよ。恋ひ恋ひて居れば。
【語釈】モトツヒト 古なじみである。ほととぎすの毎年来るのを言つたのである。
○ホトトギスヲバ 『童蒙抄』に見える訓である。「八」をバに宛てる例は巻十七、(三八九六)一に云ふに見えるだけで、それも余り確かとは言へないが、ここはヤと訓み疑問としたのでは、意をなさぬ。或いはヤを軽い感動と見れば、意味も通り、文字の方の難は除かれるが、次にもヤが来るので、バの方が自然なことは自然である。
○メヅラシム 会ひたいと思ふ。イマにつづく連体法に読む。メヅラシミと中止法ではやはり意をなさぬ。
○イマヤナガクル ヤは疑問でなく感動と見る方が自然であらう。ナはほととぎすと見なければ、やはり意をなさぬ。
【作意】少し無理ながら、此の訓で一応理解出来よう。メヅラシムとコヒツツの重複はあるが、さして気になるまい。擬人もそれほど苦にならぬ歌である。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
| |
〔もとつひと ほととぎすをば めづらしむ いまやながくる こひつつをれば〕
本人霍公鳥乎八希將見今哉汝來戀乍居者 (『元暦校本』) |
【口訳】古馴染みのほととぎすをばめづらしく思つてゐる今、お前はやつて来るよ。私がお前を恋しく思つて居ると。
【訓釈】本つ人霍公鳥をばめづらしみ―「本つ人」は「古人尓者(モトツヒトニハ) 猶不如家利(ナホシカズケリ)」(12・3009)、「母等都比等(モトツヒト) 可気都々母等奈(カケツツモトナ) 安乎祢之奈久母(アヲネシナクモ)」(20・4437)とあり、昔なじみの人であるが、『代匠記』に(私補注・その項参照)―中略―とある。私(著者)は前にもこの「もとつ人」を作者の古馴染ととつてはどうかと述べたことがあつた。さうすると第四句の「汝」と同じだといふ事になるが、「本つ人」と「汝」と打合ひがどうもよくないやうに思ひ、「遠つ人雁が来鳴かむ」(17・3947)とある例をも思ふと、この「本つ人」は、本つ人であるほととぎすと解くべきやうに思はれる。「霍公鳥乎八」を諸本諸注に「ホトトギスヲヤ」と訓んで異説を見なかつたのであるが―中略―私注にヲバと改めた。「八」の字はヤ又はハと訓むのが通例であるが、バと訓むのはめづらしい。しかし「をや」とすれば、「山矣邪(ヤマヲヤ)今はよすがと思はむ」(3・482)、「相思はぬ人乎也(ヲヤ)もとな」(4・614)、「淺乎也(アサキヲヤ)心深めて吾が思へるらむ」(7・1381)など、その「や」はいづれも反語乃至詠歎の意をもつたものであり、この場合に適切でなく、第四句の「哉」と重なる事も穏やかでなく、「宇伎底之乎礼八(ウキテシヲレバ)」(17・3896一云)の例に従つてヲバと訓む方が穏やかだと思ふ。「希将見」をメヅラシと訓むこと前(8・1548)に述べた。ただ略解にメヅラシクと訓み、新訓にメヅラシミと訓み改めてその訓が行はれるに至つたが、私注にはメヅラシムと訓んで次の「今」につづく連体形だとする。その新訓に従ふべきだと考へる。その事、次に述べる。
今や汝が来る恋ひつヽ居れば―旧訓イマヤナガクルを考にナガコム、略解にナガコシとした。解釈としては『代匠記』に(私補注・その項参照)といひ、「汝」をほととぎすとし、諸注多く従つたが、『全註釈』に「今にもかあなたが来るだらう」と訳し、「作者が、歌中の汝に対して恋ひつつ居るのである」とし、佐佐木博士の評釈や古典大系本では、それに従はれた。上を諸注の如くメヅラシミと訓み、「汝」をほととぎすだとすると、第三句は第五句へつづく事になる。―中略―即ちこの自然な解釈を成立させる為に前後の訓み方を調へる事が第一の道であるといふ事になる。だとすれば第三句のメヅラシミではこの句へつづかないのだから、私注の如くメヅラシムと訓で、めづらしく思ふ今こそお前がやつて来るよ。そのお前を恋しく思つてゐると、と解くべきものであらう。即ち私注に「ヤは疑問でなく感動と見る方が自然であらう」とあるやうに、詠歎の「や」と見るべきで、古典大系本に、カと訓で疑問に解かれていゐるのは当らないといふ事になる。ただ「めづらしみ」といふ例は前(2・196)にもあつたが、「めづらしむ」といふ言葉の例のないところに疑問が残るのである。
【考】「本つ人」と「霍公鳥」と「汝」との解釈にいろいろの説があり、右にあげた他にも新考には もとつ人希將見乎八霍公鳥吟哉汝 メヅラシキヲヤ ホトトギス ナキヤナガコシ
の誤とする説や、佐伯梅友君の、
霍公鳥本人乎八希將見今哉汝來 ホトトギス モトツヒトヲヤ メヅラシミ イマヤナガコシ
の誤とする説などもあるが、右に述べたやうに私注の新訓により契沖以来の解釈にかへるべきものだと考へる。
赤人集に、
こむ□ひとほとゝきすをやまれにみむいまやなへてにこひつゝをるは
流布本「もとつ人」「いさやなつきてこひつゝをれば」とある。 |
|
|
掲載日:2014.03.27.
| 夏雑歌 詠鳥 |
| 本人 霍公鳥乎八 希将見 今哉汝来 戀乍居者 |
| 本つ人霍公鳥をやめづらしみ今か汝が来る恋ひつつ居れば |
| もとつひと ほととぎすをや めづらしみ いまかながくる こひつつをれば |
| 巻第十 1966 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【赤人集】〔131・117・237〕
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1966】 語義 意味・活用・接続 |
| もとつひと [本人] 〔「つ」は「の」の意の上代の格助詞〕 |
| もとつひと [元つ人] |
元からの知り合い・昔馴染み |
| ほととぎすをや [霍公鳥乎八] |
| をや [文末に用いて] |
[強い感動・詠歎の意] ~だなあ |
| 〔成立〕間投助詞「を」+間投助詞「や」 |
| めづらしみ [希将見] |
| めづらしみ [珍し] |
[形シク・語幹+ミ語法] 珍しい・滅多にない・愛すべきさま |
| いまかながくる [今哉汝来] |
| か [係助詞] |
[疑問] ~か・~だろうか 〔係り結び〕 |
体言につく |
| な [汝] |
[対称の人名代名詞 お前・あなた |
| 自分より目下の者や親しい人に対して用いる |
| くる [来(く)] |
[自カ変・連体形] 来る・行く・通う 〔係り結びの「結び」〕 |
| こひつつをれば [戀乍居者] |
| つつ [接続助詞] |
[継続] ~しつづけて |
連用形につく |
| をれ [居り] |
[自ラ変・已然形] いる・居る・存在する |
| ば [接続助詞] |
[順接の確定条件] ~ので・~だから・~すると |
已然形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [もとつひと] |
この歌でいう「昔なじみ・旧知」というのは、
毎年やって来る、ホトトギスのことをいうようだ |
| |
| [いまかながくる] |
この原文「今哉汝来」には、
「イマヤナガクル」「イマカナガコシ」「イマヤナガコシ」など、
旧訓以来、未だに決定的な訓はないらしい
「汝」にしても、「恋い待っていた人」とする説や、
「霍公鳥」とする説とに分かれている
左頁の「資料」にも、古注以来、様々な説があるが、その他に
「恋い待っていた人」
『万葉集評釈』〔窪田空穂、昭和18~27年成〕、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波文庫校訂版、平成25年~〕、
『日本古典文学全集』〔小学館、昭和50年成〕、
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕、
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕など、
この解釈が、現代では主流のようだ
「霍公鳥」
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕、
と、古注以外では、圧倒的に前者が多い
私は、感覚的に「汝」という「呼称」は、ホトトギスを指していると思う
毎年やって来るホトトギス、今年は珍しく私は待ち焦がれている
今、お前はやって来るだろうか、こうして恋しく待っているのだから...
と解釈するのは、自然だと思う
これには、第三句の「めづらしみ」が、滅多に来ない「待っている人」を言うのか
今年は、私は珍しく、お前を、と「ホトトギス」のことを相手にして言うのか
どちらにも思いは通じそうだけど...
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕の歌意は、
「昔なじみのほととぎすを懐かしんで 今あなたが来たのか 恋しく思っていたところへ」
ここでの「あなた『汝』」は、「恋しく思う人」のこと
霍公鳥は、懐旧の情を起こさせる「鳥」としても詠われているので
それに合わせるかのようなタイミングを解釈に用いている
霍公鳥の鳴く声を懐かしんで、今あの人が来るだろうか...
でも、そうなると、結句との繋がりが不自然に思える
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕の歌意が、
「昔の人をなつかしがらせる霍公鳥を、なつかしいと思う今こそ、お前は来るだろうか、恋しく思っていると。」
この「お前『汝』」は、「霍公鳥」をいう
あれこれと考えると、この「汝」は確かに、厄介な「語」だ
しかし、直感的にこの歌を思うとき、「汝」は「霍公鳥」だろう
|
| |
| |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[本文]「本人 霍公鳥乎八 希将見 今哉汝来 戀乍居者」(「【】」は編集)
「モトツヒト ホトヽキスヲヤ マレニミム イマヤナカクル コヒツヽヲレハ」 |
| 〔本文〕 |
| |
|
| 〔訓〕 |
| ホトヽキスヲヤ マレニミム イマヤナカクル |
『元暦校本』「乎八希将見」ノ右ニ朱「ヲヤマレニミム」アリ。汝来ノ右ニ朱「ナカクル」アリ
|
| コヒツヽヲレハ |
『西本願寺本・細井本・神宮文庫本』「コヒツヽオレハ」 |
| 〔諸説〕 |
| ○[マレニミム]『万葉考』「子ギテミシ」。『略解』「メツラシク」。『補』「メツラシミ」。○[イマヤナカクル]『万葉考』「イマヤナガコム」。『略解』「イマヤナガコシ」。 |
|
【左頁資料について】
| 『万葉拾穂抄』 |
| 「汝」は、「霍公鳥」だと思うが、今お前が来ることを恋しく待っていれば、その稀なる故に、昔なじみにもまた珍しく逢えるだろう、という解釈だろうか |
| 『万葉代匠記(精撰本)』 |
「もとつひと」が、「昔の妻」や「亡き人」とか、具体的な情景をまず想い起させるが、この歌は、後撰集を引用し、「霍公鳥」もまたそれに当てはまることを言っている
その前提での解釈となれば、恋し待っているので、お前は来るのか、と、「汝」も「霍公鳥」だ
|
| 『万葉集童蒙抄』 |
契沖の説に沿うような解釈、
宗師案を挙げ、「もとつひと」を都人」とも解釈しているが、自分は「霍公鳥」だと言っている「もとつひと」「汝」、それぞれの立場を、都の人が「霍公鳥」を「まれにみむ」などと推測している説など、この当時から誰もが悩まされる歌だったようだ |
| 『万葉考』 |
「希将見」の訓、ネギテミンの「ネギ」は、
「希」を「請い望む・希望する」の意の「願(ねが)ふ」から導いたものだろうか
パソコンで「こいねがう」と打ち込んでみたら「希う」と表示された
これには驚いた
今まで、使った語ではないので、勿論当初からの「登録語」のはずだ
日本語の表記にも、まだ多くの知らない「語」があること、思い知らされた
「今哉汝来」の文法に、問題あり、と改訓したことを言うが、「コム」
「来」の未然形「こ」に、推量の助動詞「む」の連体形
助詞に問題ありというが、どう「問題あり」なのか解らない
|
| 『万葉集略解』 |
| 特になし |
| 『万葉集古義』 |
これまでの諸注で、「この語は、こんな意味だよ」とはあっても、
この歌の歌意全体を訳したのは、ここで初めてではないだろうか
契沖の語義解釈を用いつつ、訓にいくらか異訓を持ちながらも
この歌意の「文」は、そのまま今でも通用するものだ
昔なじみのホトトギスよ、お前に逢いたいと恋しく思いながら居たら、
その待った甲斐もあって、珍しいことに今来たよ、というのだろうか |
| 『万葉集新考』 |
これほどの改訓というか、異同というか、かなり大胆な説をいう
しかし、歌の歌意にすれば、雅澄の解釈を踏襲するものだ
「ヨクゾ鳴イテ来タ」...これがいい |
| 『口訳万葉集』 |
| このように「口語」で、直に歌を味わうと、いっそう「汝」が霍公鳥であるのが自然に思える |
| 『万葉集全釈』 |
| 特になし |
| 『万葉集全註釈』 |
「汝」が「思い人」、自分が昔馴染みの霍公鳥を思っているので、「恋し人」も、それに合わせて、来てくれるだろうか、との解釈は、
歌の技巧のような用法なのかもしれない |
| 『万葉集私注』 |
「語感」的に、「や」が二つ重なる「音」を懸念しているが、第四句の「や」は
現在の訓では「か」が多く、そうしたことが「か」に繋がったのかもしれない |
| 『万葉集注釈』 |
| 第三句「希将見」の訓に、他の注釈書以上の検証を行うが、結論「めずらしむ」を導いても、その例が他にはないことに疑問を残している |
|
|
|
|
|
|
|




|
 |
| |
| |
| |
| |
| |
「かくばかり」...あめのふらくに...
|
| 『なほなくらむ』 |
| 【歌意1967】 |
これほどにひどく雨が降っているけれども
卯の花がこんなに美しく咲き誇っている山で、
霍公鳥は、やはり鳴いているだろうか
お前には、雨が似合う |
|
| |
| |
この歌の「眼」の要素は、二つあると思う
一つは、勿論ホトトギスが、雨中でも鳴いているかもしれない、と思わせる「卯の花の美しさ」
そしてもう一つは、作者の見る「咲く卯の花」ではなく、
雨中でも厭わず鳴くであろう、「ホトトギス」の気持ち
ホトトギスが、雨中も厭わずに、むしろ好むようにして鳴くことを思わせる歌もあった
先日の〔1963〕では、「あまばれ」の瑞々しく晴れる空を飛翔する姿を見た
今度は、雨中の「ホトトギス」
うぐいすのような、春ののどかさに映える鳥と違って
このホトトギスのは、どこか計り様のない魅力を感じる
多くの注釈書では、雨中のホトトギスを求めるあまり、
その舞台として、卯の花の咲く山をセットする
だから、雅澄のように雨中を厭わず、卯の花に誘われて、とでもなるのだろう
中途半端な解釈するよりは、ホトトギスと卯の花が関連付けられていいと思う
しかし、「なほ」という語は、「鳴く」にかかり、
それでも鳴く、という「それでも」は、「雨中」のことを言うのだろうか
確かに、不自然さはそこになく、「こんなにひどい雨なのに」と思うのがいいのかもしれない
ただ、「人から」見た「雨中」でも、「ホトトギスから見える雨中」は違うかもしれない
先の「あまばれ」の中を飛び行くホトトギスを思う
あの時のホトトギスは、春日の方へ流れる雲に添うようにして飛んで行った
ならば、雨雲を追いかけて飛ぶ姿もまた、ホトトギスのもう一つの「顔」ではないか
雨中でも「なほかなくらむ」は、卯の花の美しさは人の「想い」であって、
ひょっとすると、人から見える雨の中の卯の花が美しく、
ホトトギスも同じように見惚れて鳴くのだろうか、と
私は、違うような気がする
だから、卯の花の誘われるようにして鳴く解釈を全面的に出している『古義』を除けば
他の注釈書では、あまりホトトギスと卯の花を結びつけて解釈していない
そして、情景描写として客観的な言い回しが目立っている
そうすると、先ほどまで理解出来なかった『全釈』の「評」も、何となく解るような気がする
「雨中に山の郭公を思ひやつたので、卯の花山が美しい。」
雨中のホトトギスを思えば、ふとそこの卯の花の美しさが浮んだ、と
この著者・鴻巣盛広博士の全般に渡る万葉解釈は残念ながら私にはまだ未達だが
最近毎日、目にしていて、ときどき言葉足らずと思いながらも、
後になって、なるほど、と思うことがある
この歌の「評」も、その一つだと思う
|
|
【赤人集(三十六人集の一つ、撰藤原公任[966~1041])】
| かくはかり雨のみふるをほとゝきす 此花山になをやなく覧 |
| 新編私家集大成-新編増補(陽明文庫蔵三十六人集) 132 |
| かくはかりあめのふるをやほとゝきす うのはなやまになをやなくら |
| 新編私家集大成(書陵部蔵三十六人集) 120 |
| かくはかりあめのふるをやほとゝきす うのはなやみになほやなくらん |
| 新編国歌大観(西本願寺蔵三十六人集) 240 |
【夫木和歌抄(延慶三年頃[1310年頃]撰勝間田長清) 静嘉堂文庫本】
| かくばかりあめのふる日をほととぎすうの花山になほやなくらん |
| 新編国歌大観第ニ巻 16 巻第八 夏部二 郭公 (家集、万10) 2747 赤人 |
【玉葉和歌集(正和ニ年10月[1312年]撰京極為兼[1252~1332])】
| かくばかり雨のふらくにほととぎすうの花やまに猶かなくらん |
| 新編国歌大観第一巻 14 巻第三 夏歌 318 人麿 |
【歌枕名寄(嘉元元年頃[1303年頃]撰伝澄月)】
| かくばかり雨のふらくにほととぎすうの花やまに猶かなくらん |
| 新編国歌大観第十巻 181 巻第ニ十九 越中国 7564 人丸 |
|
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1967] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔かくはかり雨のふらくに霍公鳥うのはなやまに猶かなくらん〕
如是許雨之零尓 宇之花山尓猶香将鳴
|
| かくはかり雨のふらく かく雨のふるに卯花山に猶なくやらんと也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
| |
如是許雨之零爾霍公鳥宇之花山爾猶香將鳴
〔カクハカリアメノフラクニホトヽキスウノハナヤマニナヲカナクラム〕 |
| 宇之花山は卯花のさける山を押て名付るなり、名所にあらす、もみぢする山を紅葉の山とよめるが如し、第十七に大伴池主が越中にてよめる長歌に、見和多勢婆宇能波奈夜麻乃保等登藝須とよめる故に越中と云説あれど、又同卷家持も越中守にての長歌に宇乃花乃爾保弊流山乎余曾能未母、布里佐氣見都追云々、是山の名ならぬ證なり、此卷に前にも後にも宇能花乃開落岳とよみ、又宇能花邊ともよめり、此歌人丸集にもなきを玉葉には何に依てか作者を定られけむ、おぼつかなし、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
如是許雨之零爾霍公鳥宇之花山爾猶香將鳴
〔かくばかり、あめのふれるに、ほとゝぎす、うのはなやまに、なほかなくらん〕 |
| よく聞えたる歌也。雨の降るにも卯の花山には聲かれず嶋くらんと也。此歌玉葉には、人丸の歌にして入れられたり |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
如是計、雨之零爾[フラクニ]、良久約るなり、霍公鳥、宇之花山爾、猶香將鳴[ナクラム]、 |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
| |
如是許。雨之零爾。霍公鳥。宇之花山爾。猶香將鳴。
〔かくばかり。あめのふらくに。ほととぎす。うのはなやまに。なほかなくらむ。 〕 |
| フラクはフルを延べ言ふなり。卯(ノ)花山は地名に有らず。卯花の咲きたる山を言ふ。斯く雨の降るをも厭はで、猶郭公は鳴くやらんと言ふなり。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔カクバカリ。アメノフラクニ。ホトヽギス。ウノハナヤマニ。ナホカナクラム。〕
如是許雨之零爾霍公鳥宇之花山爾猶香將鳴
|
零爾[フラクニ]は、フルニの伸りたるなり、降ことなるにの意なり、○宇之花山[ウノハナヤマ]は、名處にあらず、卯(ノ)花の咲たる山と云り、もみちしたる山を、紅葉の山と云に同じ、十七大伴(ノ)池主(ノ)長歌に、見和多勢婆宇能婆奈夜麻乃保等登藝須[ミワタセバウノハナヤマノホトトギス]云々、とも見えたり、○歌(ノ)意は、霍公鳥は、かくばかり雨のつよくふれば、雨やどりなどして、大かたは隱(リ)居らむを、卯(ノ)花の咲たる面白き山にて、雨のふることをもいとはで、なほ止ずに鳴らむか、となり、
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔かくばかり雨のふらくにほととぎすうの花山になほかなくらむ 〕
如是許雨之零爾霍公鳥宇之花山爾猶香將鳴 |
| フラクニはフルニを延べたるなり |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
| |
かくばかり雨の降[フ]らくに、霍公鳥、卯の花山に尚か鳴くらむ |
| |
こんなに迄雨が降つてゐるのに、子規が卯の花の咲いてゐる山に、今日らでも、鳴いてゐるであらうか。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔かくばかり 雨のふらくに ほととぎす 卯の花山に なほか鳴くらむ〕
如是許雨之零爾霍公鳥宇之花山爾猶香將鳴 |
コンナニ雨ガ降ルノニ霍公鳥ハ、卯ノ花ノ咲イテヰル山デ、ヤハリ鳴イテヰルノダラウカ。ドウダラウ。
○字之花山爾[ウノハナヤてマ]――卯の花の咲いてゐる山で、山の名ではない。卷十七に宇能波奈夜麻乃保等登藝須[ウノハナヤマノホトトギス](四〇〇八)とあるのも同じ。
〔評〕 雨中に山の郭公を思ひやつたので、卯の花山が美しい。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔かくばかり あめのふらくに、 ほととぎす うのはなやまに なほかなくらむ。〕
如是許雨之零爾霍公鳥宇之花山爾猶香將鳴 |
【譯】これほどに雨が降るのに、ホトトギスは、卯の花の咲いている山で、やはり鳴いているのだろうか。
【釋】雨之零尓 アメノフラクニ。フラクは、降ること。
宇乃花山尓 ウノハナヤマニ。卯の花の咲いている山に。「宇能婆奈夜麻乃[ウノハナヤマノ] 保等登藝須[ホトトギス]」(卷十七、四〇〇八)。
【評語】雨中のホトトギスを想像して詠んでいる。卯の花山は、ちよつと氣のきいた造語だ。雨中ホトトギスを思う心が、この句で生きて描かれている。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| |
〔かくばかり あめのふらくに ほととぎす うのはなやまに なほかなくらむ〕
如是許雨之零爾霍公鳥宇之花山爾猶香將鳴 |
【大意】これほど雨が降るのに、ほととぎすが、卯の花の山に、なほつづけて鳴くのであらうか。
【作意】雨中のほととぎすを聞いて居る歌である。ウノハナヤマニは、卯の花の咲いて居る山にの意であるが、立ち入りすぎた句であらう。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
| |
〔かくばかり あめのふらくに ほととぎす うのはなやまに なほかなくらむ〕
如是許雨之零爾霍公鳥宇乃花山爾猶香將鳴 (『元暦校本』) |
【口訳】こんなにも雨の零るのに、ほととぎすは卯の花の咲く山に、やはり鳴いてゐる事であらうか。
【訓釈】雨の零らくに―「零らくに」は零ることなるに。「く」は「暮さく」(1936)の「く」に同じ。
卯の花山になほか鳴くらむ-「乃」の字、『元暦校本・類聚古集・紀州本』による。『西本願寺本』以後「之」とある。「卯の花山」は「宇能波奈夜麻乃(ウノハナヤマノ) 保等登藝須(ホトトギス)」(17・4008)ともあつて、卯の花の咲いてゐる山。固有名詞ではない。「なほか」の「か」は疑問。
【考】赤人集「雨のふるをや」「うのはなやみになほやなくらむ」流布本下句萬葉に同じ。夫木抄(八「郭公」)「雨のふる日を」「なほや鳴くらむ」赤人とあり、玉葉集(三)には萬葉のまま、作者を人麿とする。 |
|
|
掲載日:2014.03.28.
| 夏雑歌 詠鳥 |
| 如是許 雨之零尓 霍公鳥 宇乃花山尓 猶香将鳴 |
| かくばかり雨の降らくに霍公鳥卯の花山になほか鳴くらむ |
| かくばかり あめのふらくに ほととぎす うのはなやまに なほかなくらむ |
| 巻第十 1967 夏雑歌 詠鳥 作者不詳 |
【赤人集】〔132・120・240〕
【夫木和歌抄】〔2747〕
【玉葉和歌集】〔318〕
【歌枕名寄】〔7564〕
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1967】 語義 意味・活用・接続 |
| かくばかり [如是許] |
| かくばかり [斯くばかり] |
これほどまでに・こんなにも |
| 〔成立〕副詞「斯く」+副助詞「ばかり」 |
| あめのふらくに [雨之零尓] |
| ふらく [降る] |
[自ラ四・未然形+ク語法] 雨・雪などが降る |
| に [接続助詞] |
[逆接] ~けれども・~のに |
連体形につく |
| 〔参考〕「格助詞」とする書があるが、歌意に沿えば「逆接」が適切だと思う |
| ほととぎす [霍公鳥] |
| うのはなやまに [宇乃花山尓] 卯の花が美しく咲いている山 |
| なほかなくらむ [猶香将鳴] |
| なほ [尚・猶] |
[副詞] やはり・依然として・さらに・何と言っても |
| か [係助詞] |
[疑問] ~か・~だろうか (係り結びの「係り」) |
| 〔接続〕体言・活用語・副詞・接続助詞など主語・目的語・連用修飾語などにつく |
| らむ [助動詞・らむ](結び) |
[現在推量・連体形] 今頃~ているだろうか |
終止形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [うのはなやまに] |
この「語」は、『万葉集』でも、ニ首しか用いられていなくて、「造語」と言われている
もう一首は、大伴池主の歌で、巻十七・4032(長歌)がある
新潮社の『集成』では、「詩的造語」と言っている
それほど、「万葉歌」の中では、新鮮な響きを持つのだろうか
このように、他に用例がないと、「造語」とか「固有名詞」とか考えるものなのだろうが
契沖が、「紅葉する山」を「紅葉の山」というようなものだ、と念を押すなど
そんな「固有名詞的」な捉え方もあった、ということだろう
新しい語というのは、時代が経てば、それが一般名詞なのか固有名詞なのか
確かに解りにくいこともあると思う |
| |
| [なほ] |
現代語では、「今もなお恋しく思う」、「日が経つとなお恋しくなる」のように、
「やはり」とか「さらに」の意で用いるが、
古くは、否定されかけているものを改めて肯定する気持ちや、
無視されがちなものを改めて取り上げる気持ちをこめて用いる、
「それでもやはり」、「何と言っても」などの用法が多い |
| |
| |
| |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[本文]「如是許 雨之零爾 霍公鳥 宇之花山爾 猶香将鳴」(「【】」は編集)
「カクハカリアメノフフクニホトヽキスウノハナヤマニナヲカナクラム」 |
| 〔本文〕 『類聚古集』本文ノ下ニ小字「無作者」アリ |
| 「零」 |
『神田本(紀州本)』「【部首「雨」無し】部ハモトノヲ削リテ書ケリ |
| 「之」 |
『類聚古集・神田本(紀州本)・天治本』「乃」 |
| 〔訓〕 |
| フフクニ |
『類聚古集』「ふれるに」。「零」ノ右ニ朱「フレル」アリ
『神田本(紀州本)・西本願寺本・細井本・大矢本・京都大学本・神宮文庫本』「フラクニ」
『天治本』「ふとくに」。「とく」ノ右ニ「らく」アリ
|
| ウノハナヤマニ |
『天治本』「うのはなやまに」。「う【崩れている】」ノ右ニ「う」アリ
|
| ナヲカナクラム |
『類聚古集』「将鳴」ノ右ニ朱「ナクラム」アリ
『大矢本』「ナホカナクラム」 |
| 〔諸説〕 |
| ○ |
|
【左頁資料について】
| 『万葉拾穂抄』 |
| 「卯花山」と書いているのは、敢えて解釈を保留にしたのだろうか |
| 『万葉代匠記(精撰本)』 |
「卯の花山」に言及しているのは、先の『拾穂抄』を意識してのことかもしれない
「人麻呂歌集」にはないのに、「玉葉和歌集」に「人麿作」として載るのがおかしい、という |
| 『万葉集童蒙抄』 |
有り触れた歌、との評価
「玉葉和歌集」に「人麿」の歌として入集していることをいう |
| 『万葉考』 |
特になし
|
| 『万葉集略解』 |
「ふらく」が、動詞「ふる」の名詞化されたものだという
ここでも、「卯の花山」が、固有名詞ではないとの念の入れようだ
ホトトギスは、こんな雨でも嫌がらずに、鳴くのだろうか、と |
| 『万葉集古義』 |
契沖や千蔭の「言」を用いるが、やはり注釈書となれば、先人の「説」をどう判断、あるいは解釈して検証するか、ということだろう
しかし、さすがに歌意では、一歩踏み込んだものを見せている
こんなに雨がひどくては、雨宿りをするものなのに、卯の花が美しく咲いているから、
雨宿りもしないで、鳴いているのだろうか、と |
| 『万葉集新考』 |
| 特になし |
| 『口訳万葉集』 |
| 特になし |
| 『万葉集全釈』 |
「評」の意味が、あまりしっくりこない
雨中の山のホトトギスを思い遣ったので、卯の花山が美しい、と
この意味は、雅澄がいうような、雨中でもなくホトトギスが、卯の花の美しさに惹かれて、
という意味なのだろうか |
| 『万葉集全註釈』 |
雨中のホトトギスが、何故鳴くのか、には積極的に言及していない
雨中のホトトギスを思う気持ちが、その背景に卯の花山を想起させたかのようだ |
| 『万葉集私注』 |
「うのはなやまに」が、立ち入り過ぎた句、
それがあるからこそ、雨中のホトトギスの説明にもなると思うのに、厳しい |
| 『万葉集注釈』 |
| 特になし |
|
|
|
|
|
|
|


|
 |
| |
| |
| |
| |
| |
「にほひこそ」...しまのはりはら...
|
| 『あきまたずとも』 |
| 【歌意1969】 |
私のいとしいあの娘が、衣を摺り染めにするので、
美しい色に照り映えて、香気を醸し出してくれ、島の榛原よ
秋にならなくても、今がその時なんだぞ |
|
| |
| |
この歌の歌意は、どの書も大きな違いはないと思う
いとしい娘が、衣を摺るので、まだ秋にはなっていないので
榛原では目立つこともない樹林だろうが
何とか、染物の手助けを頼む、という気持ちなのだろう
確かに、美しく見映えのいい染料の材料であれば
いいものが仕上がると思う
だから、季節的に早いと思いながらも、懇願する
「はりはら」と「はぎのはら」とする説が並立しているようだが
私の乏しい想像力でも「萩の原」というのはイメージが湧かない
山辺とか、あるいは古い寺院のような建物があるところとか...
「萩原」、あることはあるだろうが、イメージが湧かない
それに「衣摺る」とセットで考えれば、「萩」説は難しいと思う
「榛」を「摺る」記事は、天武紀にもあるように、行われていることだ
問題は、「あきたたずとも」に手掛かりを求める説明があることだ
それだと、「にほひ」もまたその実体を確定しなければならなくなる
やはり、素直に読むべきだと思う
音から「はり」と「はぎ」が通じるから、というのは
もっとも安易な解釈だと思う
それなら、『略解』に噛み付いた井上通泰の『新考』の方が、
まだ語義の理解を深めようとするので、読む気にもなれる
しかし、この歌をよく読んで見ると
季節を待たずに、染料の材料をいうのは、作者の思い込みなのかもしれない、と思う
どうしても、この「榛」で「摺る」、あるいは「摺りたい」というのは
いとしい娘の希望ではなく、作者の強い希望のような気がする
どうせ「ころもすり」をするのなら、いいものを作らせたい
そろそろ秋になるが、何とか「島の榛原」よ
今、その花を咲かせて、あの娘に使わせてやってくれ
そんな親心のような感じかもしれない
もっとも、娘への思い遣り、とするのは、
どの注釈書でも同じことだと思う
それを、前提にしての「島の榛原」への懇願だ
娘が希望した「ハンノキ」なのか、どうかは解らないが
「ハンノキ」で「摺る」染物を、男は心待ちにしているのかな
|
|
【赤人集(三十六人集の一つ、撰藤原公任[966~1041])】
| おもう覧心も空ににほひぬと しまのはしはみあきたゝねとも |
新編私家集大成-新編増補(陽明文庫蔵三十六人集) 134
|
| おもふらんこゝろもすらににほひぬと のはしはみ秋たゝねとも |
新編私家集大成(書陵部蔵三十六人集) 122
|
| おもはくのこころもあきににほひぬと ときのはしばみあきたたねども |
新編国歌大観(西本願寺蔵三十六人集) 242
|
【袖中抄(文治三年頃[1187年頃]著、顕昭)】 『世界大百科事典』より
鎌倉初期の和歌注釈書。《顕秘抄》と題する3巻本もあるが、一般にはそれを増補したとみられる20巻本をさす。1186‐87年(文治2‐3)ころ顕昭によって著され仁和寺守覚法親王に奉られた。[万葉集]以降[堀河百首]にいたる時期の和歌から約300の難解な語句を選び、百数十に及ぶ和・漢・仏書を駆使して綿密に考証。顕昭の学風を最もよく伝え、[奥儀(おうぎ)抄][袋草紙]とならぶ六条家歌学の代表的著作
| 袖中抄第十三「万葉云(中略)オモフコノコロモスラムニニホヒセヨシマノハクハラアキタヽスト」、第二十「オモフコノコロモスラムニヽホヒセヨ嶋(シマ)ノ榛原(ハキハラ)アキタヽストモ」 |
|
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1969] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔おもふこの衣すらんに匂ひせよしまのはきはら秋たゝすとも〕
思子之衣将摺尓尓保比與嶋之榛原秋不立友
|
| おもふこの衣すらんに 思ふとは思ひ人也嶋萩原名所にや |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
| |
思子之衣將摺爾爾保比與島之榛原秋不立友
〔オモフコノコロモスラムニニホヒセヨシマノハキハラアキタヽストモ〕 |
| 發句は古風の例に依てオモフコガと讀べし、腰の句は袖中抄にも今の點の如くあれど勢、世等の字もなし、以前注せし如く與は集中にこそと讀べき處お枚ければ今も然讀べきなり、島は第五に奈良[ナラ]路なる島の木立とよめる處なり、榛の木は秋に至て皮を剥て染るが色のよき歟、木竹を伐にも秋に至らざればよからねばさも侍るべし、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
思子之衣將摺爾爾保比與島之榛原秋不立友
〔おもふこの、きぬにすらんに、匂ひてよ、しまのはりはら、あきたゝずとも〕 |
| 爾保比與 これをにほひてよと讀ませたり。凡て集中に假名書に、手爾乎波の詞を添へて讀ませたる事甚不考の事也。訓字には添へらるべけれど、一字假名書に添る事はならぬ義也。讀様又誤字の考案なくて、諸抄等にも此誤りあまた也。此てよと讀ませたるも如此にては讀難し。此は南の字の誤り歟。宗師案は、乞の字なるべし。与の字と見誤りて乞を與に書きたるから、かく誤りたるならんと也。既にてよと假名を付けたれば、乞の字いでと讀みて、集中に願ひ乞ふ事にも用ひたる例數多なればこゝも匂へと願ひ乞ふ義なれば、乞の字を、てよと讀ませたると見ゆると也。榛ははぎと通じて、秋賞翫するもの故、既に秋不立ともと詠めり。木榛は夏花咲くものなれ共、はぎ、はり同じ言葉故、秋萩になぞらへて、斯く詠めるなるべし。嶋のはぎ原は大知の地名也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
思子之[オモフコガ]、衣將摺爾[スラムニ]、爾保比乞、 今本乞を與と見てにほひせよと訓れどさ訓んには世の歌に當る字なしこはおもへる子か衣にすらんに匂へとこへるにてこそとよむべきなり
島之榛原[ハイバラ]、 橘(ノ)島(ノ)宮同地にて大和國高市郡なり
秋不立友、
是は夏咲るを見てよめるにあらずまた花なきを乞てよむなり或人榛にて秋萩ならずと云は僻事榛は借字なり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
| |
思子之。衣將摺爾。爾保比與。島之榛原。秋不立友。
〔おもふこが。ころもすらむに。にほひこそ。しまのはりはら。あきたたずとも。 〕 |
乞を與に誤れるなり。ニホヒコソはニホヘカシと願ふ詞。島は高市郡の地名。榛は既に出づ。秋タタズトモと詠めるは、秋に成りて、此木の皮は剥ぐなるべし。
參考 ○榛原(考)ハギハラ(古、新)略に同じ。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔オモフコガ。コロモスラムニ。ニホヒコソ。シマノハリハラ。アキタヽズトモ。〕
如是許雨之零爾霍公鳥宇之花山爾猶香將鳴
|
零爾[フラクニ]は、フルニの伸りたるなり、降ことなるにの意なり、○宇之花山[ウノハナヤマ]は、名處にあらず、卯(ノ)花の咲たる山と云り、もみちしたる山を、紅葉の山と云に同じ、十七大伴(ノ)池主(ノ)長歌に、見和多勢婆宇能婆奈夜麻乃保等登藝須[ミワタセバウノハナヤマノホトトギス]云々、とも見えたり、○歌(ノ)意は、霍公鳥は、かくばかり雨のつよくふれば、雨やどりなどして、大かたは隱(リ)居らむを、卯(ノ)花の咲たる面白き山にて、雨のふることをもいとはで、なほ止ずに鳴らむか、となり、
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔おもふ子が衣すらむににほひこそ島の榛原秋たたずとも 〕
思子之衣將摺爾爾保此與島之榛原秋不立友 |
ハリに榛をかけるは借字にてこゝのハリは萩なり(三七頁及一〇〇頁參照)。略解に『秋に成て此木の皮は剥なるべし』といへるは誤りてハンノ木と思へるなり○ニホヒコソはニホヘカシにて花サケカシとなり。此句を見てもハンノ木にあらざるを知るべし○島は大和高市郡の地名なり。卷七(一三四八頁)なる
時ならぬまだらのころもきほしきか島のはり原時にあらねども
といふ歌の處にくはしく云へり |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
| |
思ふ子が衣摺[ス]らむに、匂ひこそ。島の榛原。秋立たずとも |
| |
いとしい人の著物に摺らうと思ふのだから、咲き出してくれ。此島の榛の原の榛よ、今は末秋になつてはゐないけれども。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔オモフコガ コロモスラムニ ニホヒコソ シマノハリハラ アキタタズトモ〕
思子之衣將摺爾爾保比與嶋之榛原秋不立友 |
秋ニナレバ萩ノ花ハ咲クモノダガ、島ノ萩原ハ秋ニナラヌ夏ノ今デモ、私ノ愛スル女ノ着物ヲ染メル爲ニ、咲イテクレヨ。
○爾保比與[ニホヒコソ]――このコソは希望の辭。與をコソと訓ませるのは集中に例が多い。誤字とするのはわるい。卷七の我告與[ワレニツゲコソ](一二四八)參照。
○島之榛原[シマノハリハラ]――島は草壁皇子の島の宮のあつたところか。然らば大和高市郡の島庄である。
〔評〕 三句切になつてゐるのが注意される。秋不立友[アキタタズトモ]とあるのが、榛でなくて萩の歌らしい。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔オモフコガ コロモスラムニ ニホヒコソ シマノハリハラ アキタタズトモ〕
思子之衣將摺尓々保比與島之榛原秋不立友 |
【譯】思うあの子の著物を摺ろうから咲いてくれ。島のハギ原は、秋にならないでも。
【釋】思子之 オモフコガ。オモフコは、わが思うその人をいう。
々保比與 ニホヒコソ。ニホヒは、色に出ることで、花の咲くをいう。コソは願望の助詞。句切。
島之榛原 シマノハリハラ。シマは、水に臨んだ地をいう。ハリハラは、ハギの原。
秋不立友 アキタダズトモ。タツは、物の始まるにいうが、秋立つは、暦の上で云い始めたのであろう。
【評語】まだ秋にならないのに、ハギの花の咲くことを望んでいる。思フ子ガ衣摺ラムという所に手段がある。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| |
〔オモフコガ コロモスラムニ ニホヒコセ シマノハリハラ アキタタズトモ〕
思子之衣將摺爾爾保比與島之榛原秋不立友 |
【大意】思ふ子の衣を染めるように、色立てよ。島の榛の木は、秋が立たなくとも。
【作意】榛の木の染色に適するやうになるのは、秋冬の候なので、かう歌つたのであらうか、それとも単にニホフといふ言葉の上でか。オモフ子は、文学的に想定されただけのものであらう。シマノハリハラは、明日香のシマであらう。巻ニ、(一七九)、巻七、(一三一五)に見えた。ハリは榛の木説を取ったが、此の歌では萩説の方が無難に聞こえようか。それも言葉の上だけのこととすれば、論拠にはならない。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
| |
〔オモフコガ コロモスラムニ ニホヒコソ シマノハリハラ アキタタズトモ〕
思子之衣將摺尓々保比與島之榛原秋不立友 (『元暦校本』) |
【口訳】思ふ人の着物を擢る為に実が色づいておくれ。島の榛原がまだ秋が立たないでも。
【訓釈】衣摺らむににほひこそ―「摺」の字、『紀州本』に「○」[判読出来ず]とあるは「揩」から誤つたものであらう。原本は「揩」であつたものと思はれる(4・675)。「にほひこそ」は榛の実の色づく事を求めたので、榛の実の摺染である事が知られる。「こそ」は希求の助詞(4・613)。「与」は「乞」と同じくコセ、コソなどと訓まれること前(4・546)に述べた。
【考】赤人集に、
思はくのころもあきにゝほひぬとときのはしはみあきたゝねとも
とあり、流布本「おもふらむ心も空に」「しまのはしばみ」とある。 |
|
|
掲載日:2014.03.29.
| 夏雑歌 詠榛 |
| 思子之 衣将摺尓 々保比与 嶋之榛原 秋不立友 |
| 思ふ子が衣摺らむににほひこそ島の榛原秋立たずとも |
| おもふこが ころもすらむに にほひこそ しまのはりはら あきたたずとも |
| 巻第十 1969 夏雑歌 詠榛 作者不詳 |
【赤人集】〔134・122・242〕
【袖中抄】〔歌学書〕
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1969】 語義 意味・活用・接続 |
| おもふこが [思子之] |
| おもふこ [思ふ子] |
いとしく思う子・恋人 |
| ころもすらむに [衣将摺尓] |
| すら [刷る・摺る] |
[他ラ四・未然形] [注記] |
| む [助動詞・む] |
[推量・連体形] ~だろう・~よう |
未然形につく |
| に [接続助詞] |
[順接(原因・理由)] ~ので・~ために |
連体形につく |
| にほひこそ [々保比与] |
| にほひ [匂ひ] |
[自ハ四・連用形] つややかに美しい・照り輝く |
| こそ [終助詞] |
[希望] ~てほしい・~てくれ |
連用形につく |
| しまのはりはら [嶋之榛原] |
| しま |
奈良県高市郡明日香村島の庄か、という |
| はり [榛] |
「はんのき」(木の名)の異名 |
| あきたたずとも [秋不立友] |
| たた [立つ] |
[自タ四・未然形] (年月や季節などが)始まる |
| ず [助動詞・ず] |
[打消・連用形] ~ない |
未然形につく |
| とも [接続助詞] |
[逆接の仮定条件] たとえ~にしても |
連用形につく |
| 〔接続〕基本は終止形につくが、助動詞「ず」には「連用形」につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [する] |
模様をほった型木の上に染料をつけ、布を上にあてて模様を染め出す
版木で印刷する
この歌の場合、秋に熟した榛の果実を黒焼きにし、その黒灰で摺染にした
黒の模様摺りができる
『日本書紀』[天武紀朱鳥元年正月]に、高市皇子に榛摺の御衣三具他を賜たことが見える
|
| |
| [にほひ] |
初めは、名詞「にほひ」で、係助詞「こそ」かと思ったが
それでは、結ぶ「語」がなく、やはり動詞「匂ふ」しかなかった
そうなると、「こそ」は、終助詞「こそ」になる
| 語義パネル 旺文社・古語辞典 |
| 現代語では「匂(にお)う」と書いて④の意で、または「臭う」と書いて、鼻に不快を感じさせる意で用いることが多いが、原義は「丹(に=赤い色)秀(ほ=物の先端など、抜き出て目立ち所)ふ(動詞化する接尾語)」で、赤い色が表面に表れ出て目立つ意 |
| ①(草木などの色に)染まる・美しく染まる |
| ②つややかに美しい・照り輝く |
| ③栄える・恩恵や影響が及ぶ |
| ④かおる・香気がただよう |
ここでは、「榛原」に対する「語」なので、①、②かと思うが
こうした歌の「語」は、どれか一つを決めるのではなく
これらの意味合いを含んで、一つの語で表現するものかもしれない |
| |
| [はり] |
「はんのき」はWikipediaで調べた、以下引用
| |
日本、朝鮮半島、ウスリー、満州に分布する。日本では全国の山野の低地や湿地、沼に自生する。樹高は15~20m、直径60cmほど。湿原のような過湿地において森林を形成する数少ない樹木。花期は冬の12-2月頃で、葉に先立って単性花をつける。雄花穂は黒褐色の円柱形で尾状に垂れ、雌花穂は楕円形で紅紫色を帯び雄花穂の下部につける。花はあまり目立たない。果実は松かさ状で10月頃熟す。葉は有柄で長さ5~13cmの長楕円形。縁に細鋸歯がある。良質の木炭の材料となるために、以前にはさかんに伐採された。材に油分が含まれ生木でもよく燃えるため、北陸地方では火葬の薪に使用された。近年では水田耕作放棄地に繁殖する例が多く見られる。
はんのきが密集する地域では、花粉による喘息発生の報告がある。 |

画像:Wikipedia
|
|
| |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[本文]「思子之 衣将摺爾 爾保比與 島之榛原 秋不立友」(「【】」は編集)
「オモフコノ コロモスラムニ ニホヒセヨ シマノハリハラ アキタタズトモ」 |
| 〔本文〕[頭注に「袖中抄の訓を載せている] |
| 「将」 |
『類聚古集』「持」 |
| 「摺」 |
『神田本(紀州本)』「○【判読出来ず】」
『天治本』「指」 |
| 「爾」第三句 |
『元暦校本・類聚古集・神田本(紀州本)・西本願寺本・細井本・大矢本・京都大学本・天治本・神宮文庫本』「ヽ【くりかえし】」
『近衛本』底本ニ同ジ |
| 「比」 |
『元暦校本』ナシ |
| 〔訓〕 |
| オモフコノ |
『神田本(紀州本)』「ヲモフコノ」
|
| コロモスラムニ |
『元暦校本』「ころもにすらん」。右ニ赭「キヌニスラムニ」アリ
『神田本(紀州本)』「コロモニスラムニ」 |
| 〔諸説〕 |
| ○[オモフコノ]『万葉代匠記(精撰本)』「オモフコガ」○[爾保比與ニホヒセヨ]『代匠記(初稿本)』「比」ノ下「世」脱トス。『童蒙抄宗師案』「與」ハ「乞」ノ誤ニテ訓「ニホヒテヨ」カ。愚案「與」ハ「南」ノ誤カ。『万葉考』「與」ハ「乞」トスルヲ可トシ「ニホヒコソ」トス○[シマノハキハラ]『略解』「シマノハリハラ」。 |
|
【左頁資料について】
| 『万葉拾穂抄』 |
「嶋萩原」とし、「名所」なのか、と
ということは、「榛」を「はんのき」ではなく「萩」と見立てていることになる |
| 『万葉代匠記(精撰本)』 |
「おもふこが」を、「古風」というのは、「古風の何」に倣ったのだろう
ここで、私も初めて知った鎌倉初期の歌学書「袖中抄」、
この「袖中抄」は、『校本万葉集』の頭注にあって、
初めて調べてみたが、詳しいことはわからない
そこに「セヨ」とあるのを、契沖は、「勢・世」の字もなく、
「與」は「こそ」と読むべき、との主張
「榛」は秋になって皮を剥がして染める色にする、だから「あきたたずとも」の歌になる
そう言っているのだと思う |
| 『万葉集童蒙抄』 |
「てにをは」の助詞は、「訓」では訓むべき、といっているのかな
「與」が「南」の誤字とか、「乞」の誤りとか、
「南」はともかく「乞」の「願い乞う」という意は理解出来る
「榛」は「萩」と通じて、とあるのは、何だろう
おそらくその「音」のことを言うのかもしれない
「しまのはぎはら」と訓んで、大和の地名としている |
| 『万葉考』 |
真淵は、歌意から「與」を「乞」にしたのだろう
明日香の橘の島の宮同地...橘寺から石舞台周辺、島の庄と呼ばれている
今でも歩くと、万葉の時代も少しはイメージが湧いてくる |
| 『万葉集略解』 |
| 「あきたたずとも」の解釈が、理解出来ない |
| 『万葉集古義』 |
「島」を比定するのに、やはり江戸時代では、奈良の都は「いにしへ」なのだな、と痛感する
この雅澄の歌意は、もっとも素直に読める解釈だと思う |
| 『万葉集新考』 |
「はり」は「萩」とし、千蔭がいう秋に成って皮を剥ぐというのは、ハンノキのこと
秋に「花咲く」という句の解釈で、ハンノキではあり得ない、「萩」だとする
でも、「萩」だとすると、「ころもする」という意味とは、どう関連するのだろう
「榛」は染料としても使われることが解る、
しかし「萩」は... |
| 『口訳万葉集』 |
| 特になし |
| 『万葉集全釈』 |
| 「あきたたずとも」から、「榛」ではなく「萩」だとしてるが、これは「あきたたずとも」の解釈が不充分だと思う |
| 『万葉集全註釈』 |
この解釈も「萩」を衣摺る材料として、秋にならなくても咲いてくれ、というのだろうか
「はりはら」が「ハギの原」というのは、古語辞典では「ハンノキの原」とあるので、他に「ハギの原」ともする文献があるのかな |
| 『万葉集私注』 |
| せっかく、素直な解釈だと思ったのに、「萩説」も無難か、というのは... |
| 『万葉集注釈』 |
| 特になし |
|
|
|
| |
|
 |
| |
| |
| |
| |
| |
「かぜにちる」...はなたちばなを...
|
| 『しのひつるかも』 |
| 【歌意1970】 |
風に散る橘の花を、この袖で受止めています、
それを、あなたとの「想いの証」として、大切にし
いつも、おしのびしたいのです |
|
| |
| |
この歌、映像の「一コマ」を観ているような気持ちになる
ただし、ナレーションも入らず、ただただ風に散る花橘のもとに、袖を置く女性...
この映像から、何を感じるか、
それが江戸時代からずっと論じられて、尚も今日に至って「通釈」といえるものがない
多くの注釈書に見えるように、「訓」にも様々あり
確かに、その「訓」によっては、歌意も違ってくる
ただ、思い浮かべる映像に、違いはないはずだ
袖に受ける「花びら」を、これほどの「想い入れ」とするなら
亡くなった愛しい人、だと思いたい
しかし、花橘そのものが「思い出」なのではなく
こうして「あなた」と一緒に佇んだ、この場所こそが「思い出」の場所であり
そこに、風に舞い落ちる「花橘」を、それこそ「あなた」が寄こしてくれたものだ、と
だから、袖に受止め、後生大事に「偲ぶ」ことにしよう
私には、そんな情景が浮ぶ
歌を、何の為に解釈するのか...
古くからの「注釈書」では、確かに「注釈書」のスタイルが確立されていなかった
だから、どんな目的で「注釈」があったのか、充分理解は出来ないが
一首の歌を解する以前に、一語ごとの「語義」の解釈が目的のように感じることもある
それが次第に「歌」として「注釈」が試みられるようになっている
今、目にすることが出来る「歌の解釈」は、そうした流れの中で、
常に先駆者の研究を叩き台にして存在している
下段の近世・近代までの「注釈書」も、
それ以前の「注釈書」を評価し、あるいは批判し、著されている
だから、現代に於いては、その時代とは比較にならないほどの「資料」が存在する
それが、常にいいことだとは思えないが、「研究者」としては、ありがたいことだろう
私が、最近になって「古注釈書」に興味を持ち出したのも、
何も研究のためではない...そんな教育を受けてはいないし
むしろ、だからこそ好き勝手に眺められる
そして、何よりも「語りたい」事実と言うのは
古い注釈書は、決して古くはない、ということだ
その当時の人が、その歌をどう「感じた」のか、
それは、文法や語義の解だけで、説明が終わるのではない
その当時の人々の、「感性」が、現代の私にもとても魅力的に感じられることだ
だから、新しい書ほど、その研究成果が反映されており、有意義な書だ、とはならない
毎日採り上げる「万葉歌」が、後世の「歌集」に採り上げられると
それも決まって、この頁に載せるようになった
異訓、表記の異同など、その時代時代の人たちの「万葉歌」の受止め方があるはずだ
勿論、間違って伝えられている歌もあるだろし
歌意に感ずるところがあり、少々アレンジして後の「歌集」に採録されているものもある
その「感ずるところ」が、私には興味が尽きない
少し生意気に言えば、今こうして私が書いているこのHPもまた
万葉の時代から、千二百五十年を経て、「今の私が感じる」ことを書いている
当然、平安以降のそれぞれの人たちとは、感じ方も違うだろう
知らず知らずの内に、「機械文明」というあまりにも便利で現代では欠かせない環境の中で
「古人」の「想い」に、どこまで理解出来るか解らないが
すべてを裸で歩くことを思って目を閉じれば
偉い人も、近所の人も、みんな同じ「一個の人間」だということが解る
だからかもしれない
「歌人」が、その「歌の良し悪し」を競い合う時代に、なかなか興味が湧かないのは...
今のところ、「万葉歌」に、「歌の良し悪し」ではなく、「詠わざるをえない」歌として
私を他の「歌集」に向かわせないものがあるのは、
そんな環境の中で詠われ、編された「歌集」だから、といえる
正直言えば、そもそも私のような「文学」とは無縁だった者が
何故こうも『万葉集』に惹かれるのか...
『万葉集』だけが、どうして特別なのか...
いつか、もっともっとじっくり考える時が来ると思う
|
|
【赤人集(三十六人集の一つ、撰藤原公任[966~1041])】
| 風にちるはなたち花を袖にうけて 君がためにとおもひぬる哉 |
新編私家集大成-新編増補(陽明文庫蔵三十六人集) 135
|
| かせにちるはなたちはなをてにうけて きみかみためとおもひけるかな |
新編私家集大成(書陵部蔵三十六人集) 123
|
| かせにちるはなたちはなをてにうけて きみかためとおもひつるかな |
新編国歌大観(西本願寺蔵三十六人集) 243
|
【夫木和歌抄(延慶三年頃[1310年頃]、撰勝間田長清)】
| かせにちる はなたちはなを そてにうけて きみかみためと おもひけるかな |
編国歌大観第ニ巻16 (万10) 巻第七 夏部一 橘 2677 人丸
|
【新拾遺和歌集(貞治三年[1364年]、撰藤原(二条)為明[1295~1364])】
| 風にちる花たちばなを袖にうけて君がためにと思ひけるかな |
新編国歌大観第一巻19[(宮内庁書陵部蔵 兼右筆「二十一代集」)]巻第三夏 245 赤人
|
|
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1970] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔かせにちる花橘を袖にうけてきみかみためとおもひつるかも〕
風散花橘○[口+斗]袖受而為君御跡思鶴鴨
|
| 風にちる花橘を 心明也きみかみためはみせんためと也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
| |
風散花橘○[口+立刀]袖受而爲君御跡思鶴鴨
〔カセニチルハナタチハナヲソテニウケテキミカミタメトオモヒツルカモ〕 |
| 爲君御跡、此書やう不審なり、君御處、或は御爲[ミタメ]君と書けむを傳寫を經て今の如くなれる歟、此君と云は夫君なるべし、君が爲とはたき物するやうなるを云歟、袖に受留て見せむと思ふを云歟 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
風散花橘○[口+立刀]袖受而爲君御跡思鶴鴨
〔かぜにちる、はなたちばなを、そでにうけて、きみがみためと、おもひつるかも〕 |
| 聞えたる歌也。爲君御と書たるは、珍らしき書樣なれど、當集いか程も如此の例あれば、君がみ爲と讀むべき也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
風(ニ)散、花橘叫[ヲ]、 叫は既にいふ如くなれば字を改
袖受而[ソデニウケテ]、爲君御跡[キミオハセリト]、 おはしますとなりおはせりはそこに人の居給ふをも又來り給ふをも古へよりいへば何れにても聞ゆこはむかしの人の袖の香ぞするてふ意なり今本きみに見せんとゝよめるは誤れり見せんとよむべき字もなくさ讀みては歌の意もとほらず
思鶴鴨、 |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
| |
風散。花橘○[口+立刀]。袖受而。爲君御跡。思鶴鴨。
〔かぜにちる。はなたちばなを。そでにうけて。きみがみためと。おもひつるかも。 〕 |
契沖云、橘の散るを袖に受くるは、爲(ニ)君薫衣裳と言ふに同じ心なるべしと言へり。君御爲跡と有りつらんを、誤りて君の上へ爲の字の入りしなるべし。
參考 ○爲君御跡(代)「君御爲」か「御爲君」か(考)キミオハセリト(古)「君御爲跡」キミガミタメト(新)タテマツラムト ○思鶴鴨(古)シヌビツルカモ(新)略に同じ。
|
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔カゼニチル。ハナタチバナヲ。ソデニウケテ。キミガミタメト。シヌヒツルカモ〕
風散花橘○[口+立刀]袖受而君御爲跡思鶴鴨
|
君御爲跡[キミガミタメト]を、舊本に、爲君御跡と作[ア]るは混れたるなるべし、今改つ、○思鶴鴨に、シヌヒツルカモとよむべし、○歌(ノ)意は、君が來座て愛べき花なれば、其(ノ)花橘の風にちるををしみて、せめて袖に受入て置てだに見せむとて、君を慕ひつるかな、となり
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔風にちる花橘を袖にうけてたてまつらむとおもひつるかもも 〕
風散花橘○[口+リ]袖受而爲君御跡思鶴鴨 |
第四句を舊訓にキミガミタメトとよめり。さて契沖は
君御爲或は御爲君とかきけむを傳寫を經て今の如くなれる歟
といひ、略解には
君御爲跡と有つらんをあやまりて君の上へ爲の字の入しなるべし
といひ、古義には君御爲跡と改めて
舊本に爲君御跡とあるはまぎれたるなるべし。今改めつ
といへり。キミガミタメトといふべき處にあらねば然よむべきにあらず。案ずるにタテマツラムトとよむべし。即タテマツルを戲に爲君(ノ)御(ト)とかけるなり○思は舊訓の如くオモヒとよむべし。古義にシヌビとよめるは第四句を誤り訓みてそれに合せむと試みたるなり |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
| |
風に散る花橘を袖にうけて、君が御爲[タメ]と思ひつるかも |
| |
風に散る橘の花をば、袖にうけとめて戀しいお方の著物を匂はせる爲に、使はうと思うたことだ。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔風に散る 花橘を 袖に受けて 君がみ跡と しぬびつるかも〕
カゼニチル ハナタチバナヲ ソデニウケテ キミガミアトト シヌビツルカモ
風散花橘○[口+立刀]袖受而爲君御跡思鶴鴨 |
風ニ吹カレテ散ル橘ノ花ヲ袖ニ受ケ入レテ、ソノ花ビラヲ見テ此處ハアナタガ曾テオイデナサレタ所ダト思ツテ、アナタヲナツカシク思ヒマシタヨ。
○爲君御跡[キミガミアトト]――舊訓キミガミタメトとあり、代匠記精撰に君御爲跡又は御爲君跡の誤としてゐる。略解・古義は君御爲跡説を採つてゐる。新考はもとのままでタテマツラムトとよんでゐるが、ここは新訓に從つておいた。
○思鶴鴨[シヌビツルカモ]――これも舊訓オモヒツルカモであるが、古義の訓によつた。
〔評〕 第四句を右のやうに訓むと、或人の舊宅又は縁ある地に赴いて、詠んだことになる。上句になつかしい優雅な感じがあらはれてゐる。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔風に散る 花橘を 袖に受けて、君が御跡[みあと]と 思[しの]ひつるかも。〕
カゼニチル ハナタチバナヲ ソデニウケテ キミガミアトト シノヒツルカモ
風散花橘叫袖受而爲君御跡思鶴鴨 |
【譯】風に散る橘の花を袖に受けて、あなたの御跡として慕つたことでした。
【釋】爲君御跡 キミガミアトト。キミガミタメト(元)、キミオハセリト(考)、タテマツラムト(新考)
君御爲跡[キミガミタメト](代精)/御爲君跡[キミガミタメト](代精)
爲は、トシテの意に使つているのだろう。君の殘した跡としての意で、その人の舊宅などで詠んだものでもあろうか。
【評語】思う人の高風をなつかしむ心がよく出ている。橘の花を袖に受けた風情が、まことにその高風を傳えるにふさわしい。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| |
〔風に散る花橘を袖に受けて君に着せむと思ひつるかも〕
カゼニチル ハナタチバナヲ ソデニウケテ キミニキセムト オモヒツルカモ
風散花橘○[口+リットウ]袖受而爲君御跡思鶴鴨 |
【大意】風に散る花橘を袖に受けて、橘の香のしみた衣をば、君に着させようと思つたことかな。
【語釈】キミニキセムト 「爲君御跡」は訓に説のある句である。「御」は衣、食のことを言ふので、ここは「衣」の意に用ゐたと見得る。尤も「御」は天子に言ふのが本来であるが、転じて、一般の敬語として、用ゐたものと見える。「爲君御」を、「君の衣服と為す」意味によつてキミニキスと訓む。「跡」はトの仮字である。(一九六一)のキミニキセヨトを思ひ合はさせる。補巻「巻第十刊行に際して」参照。
【作意】袖に受けた花橘の香のかぐはしきによつて、自らのみ着るのには惜しい。いとしき君に着せようと思つたといふのである。勿論文学的誇張は加へられてあるが、割合に自然に聞こえる。四五句キミガミアトト オモヒツルカモも考へ得られる訓であらう。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
| |
〔風に散る花橘を袖に受けて君が御跡[ミアトト/ミタメト]しのひ[オモヒ]つるかも〕
カゼニチル ハナタチバナヲ ソデニウケテ キミガミアトト/ミタメト シノヒ(/オモヒ)ツルカモ
風散花橘○[口+リットウ]袖受而爲君御跡思鶴鴨 (『元暦校本』) |
【口訳】風に散る花橘を袖に受けて、その花を見ながら、個々はあなたがおいでになつたおあとだとあなたをお偲び申したことよ。
【訓釈】君が御跡としのひつるかも―旧訓にキミガミタメトオモヒツルカモとある。代匠記に「君御處、或は御爲[ミタメ]君と書けむを傳寫を經て今の如くなれる歟」といひ、古典大系本には「恐らくキミガタメという場合に『爲君』と書くので、この場合も、為の字を最初に書いたのであろう」とある。さうも考へられるが、「君がみため」の解釈がどうもおちつかない。拾穂抄に「みせんためと也」と訳し、古典大系本には「あなたに差上げようと思つたことでした」とあるが、「君がみためと思ふ」の訳としてはどうも適訳だとは思へない。考にはキミオハセリトと訓み、「こはむかしの人の袖の香ぞするてふ意なり」と云つたが、この訓は無理であらう。新考には「案ずるにタテマツラムトとよむべし。即ちタテマツルを戯に爲君御とかけるなり」云つたが、やはり無理だと思はれる。私注にはキミニキセムトと訓み、「『御』は衣、食のことを言ふので、ここは『衣』の意に用ゐたと見得る。尤も『御』は天子に言ふのが本来であるが、転じて、一般の敬語として、用ゐたものと見える。『爲君御』を、『君の衣服と爲す』意味によつてキミニキスと訓む」とあるもやはり同様だと思はれる。新訓にはキミガミアトトシノヒツルカモとした。それだと「爲は、トシテの意に使つてゐるのだらう」と全註釈にあるやうな事になる。これだと全釈に「或人の旧宅又は縁ある地に赴いて、詠んだことになる」と云はれてゐゑやうな意味になる。今迄あげた説のうちでは比較的穏やかであり、安藤氏の総釈でも従はれてゐる。しかし「爲」の用字もさる事ながら、どうもこの訓釈にもまだおちつきかねるものがある。なほ後考を俟つべきものと思はれる。
【考】赤人集に、「てにうけてきみがみためとおもひつるかな」流布本「思ひぬるかな」、桐火桶に「君がかたみと思ひけるかも」、夫木抄(七「橘」)「思ひけるかな」人丸とあり、新拾遺集(三)「君がためにと思ひけるかな」赤人とある。 |
|
|
掲載日:2014.03.30.
| 夏雑歌 詠花 |
| 風散 花橘○ 袖受而 為君御跡 思鶴鴨 [○口+リットウ] |
| 風に散る花橘を袖に受けて君がみ跡と偲ひつるかも |
| かぜにちる はなたちばなを そでにうけて きみがみあとと しのひつるかも |
| 巻第十 1970 夏雑歌 詠花 作者不詳 |
【赤人集】〔135・123・243〕
【夫木抄】〔2677〕
【新拾遺抄】〔245〕
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1970】 語義 意味・活用・接続 |
| かぜにちる [風散] 風に吹かれて散る |
| はなたちばなを [花橘○] (○口+リットウ) 橘の花 |
| そでにうけて 袖受而] |
| うけ [受く] |
[他カ下ニ・連用形] 受止める・支える・受け入れる |
| て [接続助詞] |
[単純接続] ~て・そして |
連用形につく |
| きみがみあとと [為君御跡] |
| み [御] |
[接頭語] 美称、または語調を整えるときに用いる |
| あと [跡] |
[「足処(あと)の意] 形見・痕跡 |
| しのひつるかも [思鶴鴨] |
| しのひ [偲ぶ] (上代しのふ) |
[他バ四/上ニ・連用形] 思い慕う・なつかしむ |
| つる [助動詞・つ] |
[完了・連体形] ~~てしまう・~てしまった |
連用形につく |
| かも [終助詞] |
[詠歎・感動] ~であることよ |
連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [きみがみあとと] |
原文「為君御跡」は、旧訓「キミガミタメト」
その後、様々な訓が試みられているが、左頁の「古注釈書」が参考になる
現訓は、『新訓万葉集』〔岩波文庫、佐佐木信綱、1927年刊行〕に拠るもの
「為」の解釈が、『全註釈』のいうように、「として」というのであれば、
現訓の方が、いいと思う
|
| |
| [しのひつるかも] |
「しのぶ」は、上代では「しのふ」と読まれていた、と古儀辞典にある
濁音の表記が、厳密にされるようになったのは、いつ頃からだろう
こうした例は、よくあることだ
原文「思鶴鴨」の「思ひ」が、現代でもその違いが解る「偲ひ」と解されるのは
表記上の当時の限られた「漢字」の中で、今ほど厳密な違いを考慮せず用いられた
そんな気がしている
だから、原文は「思」だから、この歌の訓は「おもひつるかも」とは限らないはずだ
歌全体の歌意から、「偲ぶ」が適切だと思われれば、少なくとも現代文では
その使い分けを行っても、おかしくないと思う
為君御跡」は、旧訓「キミガミタメト」
その後、様々な訓が試みられているが、左頁の「古注釈書」が参考になる
現訓は、『新訓万葉集』〔岩波文庫、佐佐木信綱、1927年刊行〕に拠るもの
「為」の解釈が、『全註釈』のいうように、「として」というのであれば、
現訓の方が、いいと思う
|
| |
| |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[本文]「風散 花橘○ 袖受而 爲君御跡 思鶴鴨 [○口+リットウ]」(「【】」は編集)
「カセニチル ハナタチハナヲ ソテニウケテ キミカミタメト オモヒツルカモ」 |
| 〔本文〕【[頭注に『類聚古集』訓ノ下ニ小字「六首無作者」アリ。六首ハ以下四首及「1971」ノ五首ヲ 指スナラン。]】 |
| 「口+刂」 |
『神田本(紀州本)』「乎」 |
| 「爲」 |
『神田本(紀州本)』ナシ |
| 〔訓〕 |
| ソテニウケテ |
『西本願寺本』「ケ」ハ何カヲ直セリ
|
| キミカミタメト |
『神田本(紀州本)』「カ」ハ「ニ」ノ上ニ書ケリ
『天治本』「きみかためにと」 |
| 〔諸説〕 |
| ○[爲君御跡キミカミタメト]。『万葉代匠記(精撰本)』「君御爲跡」又ハ「御爲君跡」ノ誤。『万葉考』「キミオハセリト」。○[オモヒツルカモ]『古義』「シヌヒツルカモ」。 |
|
【左頁資料について】
| 『万葉拾穂抄』 |
「心明」という語は、知らなかったが、「明らかな心」「心明らかな」と言う意味だろう
であれば、この歌は心の穏やかな歌、と言うことだろうか
現代に至るまでも、「御跡」の意味するところが、定まっておらず、「君が為す、御跡」
その「御跡」とは、「跡」が形見とか痕跡となる意味なので、「君の形見を為す」、
なかなか難しい
この書では、「みせんため」としている
それは、「見せようと」という解釈なのだろうか |
| 『万葉代匠記(精撰本)』 |
「爲君御跡」の写本過程での誤写の可能性を指摘している
「君」が「亡き夫」で、散る花橘を袖に受けて、思い出に浸りながら、「君」に見せよう |
| 『万葉集童蒙抄』 |
「爲君御」の三字で「きみがみため」、要は「きみのために」「あなたとして」だろう
すると、形見のような意味合いのある「跡」を、散る花橘として、君に偲ぶ、ことか |
| 『万葉考』 |
袖に受けた花橘を、「君」に見せよう、という解釈は間違いで、
袖に受けた「花橘」こそ「君」という解釈 |
| 『万葉集略解』 |
| 契沖説を採る |
| 『万葉集古義』 |
これは、原文「爲君御跡」の写本の混乱で、「君御爲跡」が正しいので、それに改める、とする、
「君」が愛し親しんだ花橘だから、せめてその風に散る花を袖に受け入れて、「君」を思い慕う
「君」が、亡き人なのか、あるいは普段はなかなか逢えない人なのか解らない
しかし、「しのぶ」とここで訓じたのは、「なつかしむ」意味からも
亡き人を随分前に失った哀しみ、それを時を経て、「心穏やか」に偲ぶということだろうか |
| 『万葉集新考』 |
「キミガタメト」と訓まんばかりの「改訓」を批判し、「爲君御」は、その意から「タテマツル」であり、表記の異同よりも、意味合いから訓じている
さらに、雅澄が結句を「シノブ」とするのは、そもそも第四句の誤訓が原因であり、旧訓が適当とする |
| 『口訳万葉集』 |
思いもつかなかった解釈だ
散る花橘を袖に受け入れたのは、
いとしい「君」の着物に、花橘の香を匂わせるために、使おうと思った、とは... |
| 『万葉集全釈』 |
風に散る花橘を、今見ているここは、愛しい人が、かつてそれを見た処
そう思うと、懐かしく思い出される
「きみがみあとと」は、「跡」を、そのときの痕跡として言うのだろう |
| 『万葉集全註釈』 |
原文の字句通りの訳し方になると思う
この歌を、ここでは作者が「愛しい人」と思う「君」の「高風」に思いを馳せていることだろう
確かに、素敵な詠歌になる
「御跡」の解釈があれば、もっと踏み込んだ「偲び方」で解釈されたと思うが
ここがもっとも難しいところなので、曖昧になっている |
| 『万葉集私注』 |
折口信夫の解釈を倣ったような歌意
『口訳万葉集』では語義解釈はないので、ここで何故あんな解釈になったのか、知ることができる「跡」は助詞として扱っているようだ
「作意」で、「きみがみあとと おもひつるかも」も否定できない、とするが、
その場合の「語釈」で述べる説明は、単に花橘を袖に受け入れ、香気を匂わすのは、
「君」に着せようというのではなく、その「香気」に満ちる「着物」そのものが、
「君」だという解釈になるのだろう |
| 『万葉集注釈』 |
「爲君御跡」の故に、その訓、歌意ともに結論をもたない
情景は素直に浮ぶだろうが、その情景と「訓」が、落ち着かない、と言うことだろうか |
|
|
|
| |
|



|
 |
| |
| |
| |
| |
| |
「かぐはしはなたちばな」...まつといふも...
|
| 『みつれて、あのこは』 |
| 【歌意1971】 |
香りのよい花橘を、玉のようにして糸に貫き
いつも私に送ってくるあのいとしい娘は、
この頃、そんな気配もなく、音沙汰もないが、
病でやつれ伏せているのではないだろうか |
|
| |
| |
このような歌に触れると、日本語の難しさ
いや、「和歌」の難しさに思い知らされる
限られた文字数の中で、意味を明確に発信することは、確かに難しい
それに、時には「曖昧な」情景を想起させる手法だってある
しかし、この歌の解釈には、その「曖昧さ」が一首の「場面」を逆転させる
連想させる情景の曖昧さではなく、「場面」が全く逆になってしまうのが、
まさにこの歌だ
私が、こんな風に行き詰まったときにすることは
やはり、一切の語義の先入観を捨て、無心に何度も何度も音読することにしている
この歌も、今日一日で、何度口ずさんだことか...
そして、帰宅してから目にした契沖の『代匠記』
その書に「答え」があるわけではないが、一つの方法を示唆してくれた
「将送妹者」の「将送」を上の句につけ、「妹者」を下の句につけて読む可能性、だ
そこで、手掛かりとして、この一首の「二つの構文」の組み合わせで考えることが出来た
契沖のいうように、「将送妹者」を上の句と下の句に分けると
「香りのいい花橘を玉に貫き送るだろう、送ろうとする」と、
「妹はやつれ疲れはてている」
後半は、「感嘆」か「疑問」か、まだこの段階では決めかねていない
この第四句を分けずに読むと、
「香りのいい花橘を玉に貫き、送る妹は、やつれ疲れはてている」
この組み合わせを意識して、また何度も音読してみる
すると、さらに自問することになってしまった
香りのいい花橘を玉として糸に通すのは、何の為に...
それが解れば、誰がその作業をしているのか、何となく理解出来そうだ
何の為に、花橘を玉にして糸に通す
残念ながら、私の手元に、「習俗」に関する適当な書がないので
詳しくは解らない
解らないながらも思いつくのは、香気漂う花橘を玉として飾りをつくる
それは、男が女に贈るものなのか
それとも、女が男に贈るものなのか
この歌の解釈で、男が送るとするのは、やつれた妹に見舞いの意が強いようだ
そして、女が送るとするのは、芳しい香りを放つ花橘で作った玉飾りを
いつもその季節になると男に送り届ける
それが、今はないので、病気なのか、と訝しく思い心配する
まず、見舞いとして「贈る」物というのは、私には馴染めない
見舞い、あるいはいつも贈っていたが、今は病気らしいなあ、となっても
それには、もっと他の手段もある
決して、この歌のような行為が唯一無二ではない
しかし、毎年届いていたものが途絶える、病気なのか、と心配するのは
まさに、この歌のようにしか詠えない
その方が、いつも気にかけているわけではないが、決して疎かにはしていない
こんなに心配させて...
詠わずにはいられない心情が窺えると思う
江戸時代頃の人たちは、そのようにこの歌を解釈していた
それが現代に近づけば、次第に「見舞い」めいた形、
あるいは、贈ろうとしたら、そのとき久し振りの「様子」を知って気にやんだ...
上述したように、二つの構文を作れば、
その結句は疑問の係助詞しかないように思える
詠歎としては、どうしても分けることができない
そして、第四句を分けずに読み連ねても、他の注釈書がいうような詠歎では決してない
詠歎で読みようがない
「私が送ろうとするお前は、やつれ果てているのだなあ」などとなるはずがない
どちらに読んでも「疑問」であれば、二つに分けて読める方が自然だし
それだと、何によって「病気」を知るか、と言えば
いつもの「花橘の玉飾り」が届かないから、だとする方が、意味を為すと思う
|
|
【赤人集(三十六人集の一つ、撰藤原公任[966~1041])】
| かうはしき花たちはなをはなにぬひて おちこむいもをいつとかまたん |
新編私家集大成-新編増補(陽明文庫蔵三十六人集) 136
|
| かくはしきはなたち花をはなにぬひ おちこんいもをいつとかたのむ |
新編私家集大成(書陵部蔵三十六人集) 124
|
| かくはしきはなたちはなを花にぬひ おちこんいもをいつとかまたん |
新編国歌大観(西本願寺蔵三十六人集) 244
|
|
【資料〔近代までの注釈書〕】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [1971] |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
| |
〔かくはしき花たちはなを玉にぬきをくらんいもは見つれてもあるか 〕
香細寸花橘乎玉貫将送妹者三礼而毛有香
|
| かくはしき花たち花 かくはしきはかうはしき也榊葉のかをかくはしみ等神楽哥にも讀し詞也仙曰見つれてとはおさなゝゝしといふ詞也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
| |
香細寸花橘乎玉貫將送妹者三禮而毛有香
〔カクハシキハナタチハナヲタマニヌキオクラムイモハミツレテモアルカ〕 |
| 發句は仙覺抄に古點はかのほそきと有けるを今の如く改めたる由なり、但赤人集にはかぐはしきとあり、今の世にかうばしきと云詞なり、くとうとは同韻にて通ずる故にかうばしと云波を和の如く云と、濁て讀とは表裏なる事なれど、語勢に依て然るなり、應神紀の御製に云、伽愚破志波那多智麼那、辭豆曳羅波比等未那等利云々、第四の句は將送を上に連て句とし、妹者を下に連ても讀、又只讀連ねても意得べし、三禮而は第四に注せり、 |
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕 |
| |
香細寸花橘乎玉貫將送妹者三禮而毛有香
〔かぐはしき、はなたちばなを、たまにぬき、おくらんいもは、みつれてもあるか 〕 |
かぐはしき 匂はしきと賞めたる詞也。今俗にかうばしきと云ふに同じ
三禮而毛有香 物思にやつれ疲れてあらんやと慰めの爲に贈らんと也。前にも、みつれにゝゝと詠めるみつれと同じ |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
| |
香細寸[カクハシキ]、花橘乎、玉貫、將送[オクラン]妹者、三禮而毛有香[ミツレテモアルカ]、
みつれは羸[ミツレ]なり痩おとろへたるなり(卷十一)に「三禮二見津禮かたもひをせん」とあり橘の花さけはいつも玉にぬきおくるなるにわれにおくりこさぬは妹のやまひにみつれてもあるかといふなりこは相聞の歌なり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
| |
香細寸。花橘乎。玉貫。將送妹者。三禮而毛有香。
〔かぐはしき。はなたちばなを。たまにぬき。おくらむいもは。みつれてもあるか。 〕 |
クハシはすべて褒むる詞。卷四。三禮二見津禮[ミツレニミツレ]片もひをせむと詠めり。紀に羸をミツレと訓む。ここは所送[オクレル]と言はず。將送と言へるは。病みてつかれ居る時故に。贈り不來歟と言ふなるべし。
參考 ○將送妹者(考、新)略に同じ(古)オコセムイモハ。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
| |
〔カクハシキ。ハナタチバナヲ。タマニヌキ。オコセムイモハ。ミツレテモアルカ。〕
香細寸花橘乎玉貫將送妹者三禮而毛有香
|
香細寸[カクハシキ]は、薫のよきを云言なり、橘に多くよむことなり、○三禮[ミツレ]は病羸[ヤミツカ]るゝを云、四(ノ)卷下に出て委(ク)云り、○歌(ノ)意は馥[カグハ]しき橘花を、玉に貫まじへて、いつものごと、吾に賚[オコ]し示し示すべきに、さもなきはおもふに其(ノ)妹は、日者[コノゴロ]病羸[ミツレ]てあるにてもあらむか、といふならむ、
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
| |
〔かぐはしき花橘を玉にぬき將送[オクラム]妹はみつれてもあるか 〕
香細寸花橘乎玉貫將送妹者三禮而毛有香 |
將送は舊訓にオクラムとよめり。略解は此訓に從ひて
こゝはオクレルといはずオクランといへるは病てつかれ居る時ゆゑに贈り不來歟といふなるべし
といひ、古義にはオコセムとよみ改めて
いつものごと吾におこし示すべきにさもなきはおもふに其妹はこのごろ病羸[ミツレ]てあるにてもあらむかといふならむ
といへり。將送をオコセムとはよみがたければ、なほオクラムとよみて送來ラム妹ノ送來ラヌハの意とすべし ○ミツレは卷四に
ますらをとおもへる吾やかくばかりみつれにみつれ片もひをせむ
とあり。弱る事なり(七八一頁參照) |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
| |
香[カグ]はしき花橘を玉に貫[ヌ]き、贈らむ妹は、みつれてもあるか |
| |
好い匂ひの橘の花を、藥玉に通して、邪氣拂ひに贈らうと思ふいとしい人は、ひどく病み衰へてゐることよ。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
| |
〔かぐはしき 花橘を 玉に貫き 送らむ妹は みつれてもあるか〕
カグハシキ ハナタチバナヲ タマニヌキ オクラムイモハ 三ミツレテモアルカ
香細寸花橘乎花橘乎玉貫將送妹者禮而毛有香 |
薫ノ良イ橘ノ花ヲ玉トシテ糸ニ通シテ、アノ女カライツモ送ツテヨコスノダガ、今年ハマダ送ツテ來ナイノハ、送ツテヨコスベキアノ女ハ、病氣デモシテヰルノデハナイカ。心紀ナコトダ。
○三禮而毛有香[ミツレテモアルカ]――ミツレは身羸[ミヤツレ]の略であらうといふ。病んでつかれてゐること。卷四に三禮二見津禮片思男責[ミツレニミツレカタモヒヲセム](七一九)とある。
〔評〕 花橘を玉に貫く頃、妹よりの消息が絶えたのを、病氣かと心配したのである。第四句は此方から妹に送ることと解してはいけない。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
| |
〔かぐはしき 花橘を 玉に貫き、 送らむ妹は みつれてもあるか〕
カグハシキ ハナタチバナヲ タマニヌキ オクラムイモハ ミツレテモアルカ
香細寸花橘乎玉貫將送妹者三禮而毛有香 |
【譯】香氣のよい橘の花を玉として緒に貫いて送つてあげよう。そのわが妻は病み疲れているのだ。
【釋】將送妹者 オクラムイモハ。贈つてやろうとする妹はで、妹の方へ五月になれば、花橘を送つたものと見える。
三禮而毛有香 ミツレテモアルカ。ミツレは、身の病み疲れるをいう。「三禮二見津禮[ミツレニミツレ] 片思男責[カタオモヒヲセム]」(卷四、七一九)。アルカは、感動の語法。
【評語】五月になつて橘の花を送ろうとして、愛人の病んでいるのを悲しんで詠んでいるのだろう。橘の花を愛して、玉の緒にもした人々の生活が窺われる。
|
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
| |
〔かぐはしき 花橘を 玉に貫き 送らむ妹は みつれてもあるか。〕
カグハシキ ハナタチバナヲ タマニヌキ オクラムイモハ ミツレテモアルカ
香細寸花橘乎玉貫將送妹者三禮而毛有香 |
【大意】香よき花橘を五月の薬玉に貫いて、送らうと思ふ妹は、やつれてあることであらうか。
【作意】五月の薬玉を贈物にするにつけて、相手のやつれてあるのを心配するのである。しばらく疎遠にした為であらう。ミツルは衰へやつれる意である。少しうるさい感じ方だ。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
| |
〔かぐはしき 花橘を 玉に貫き 送らむ妹は みつれてもあるか〕
カグハシキ ハナタチバナヲ タマニヌキ オクラムイモハ ミツレテモアルカ
香細寸花橘乎玉貫將送妹者三禮而毛有香 (『元暦校本』) |
【口訳】香りのよい花橘を玉のやうに絲に通して送つてよこすいとしい人は、此の頃病みやつれてゐる事であらうか。
【訓釈】かぐはしき―古点カノホソキを仙覚抄にカクハシキと改めた。「くはし」は前(1851)にもあつた。精妙の意(1・52)。香のすぐれていること。「かうばし」に同じ。
送らむ妹はみつれてもあるか―「みつれ」はやつれ疲れる意(4・719)。童蒙抄に「物思にやつれ疲れてあらんやと慰めの為に贈らんと也」といひ、考に「橘の花さけばいつも玉にぬきおくるなるにわれにおくりこさぬは妹のやまひにみつれてもあるかといふ也」とあり、「送らむ」をみづからの意とする説と、妹が送り来らむはずとする説と両説が行はれてゐる。全釈に「花橘を玉に貫く頃、妹よりの消息が絶えたのを、病気かと心配したのである。第四句は此方から妹に送ることと解してはいけない」とある。連体形の「む」にも意志表示をするものもあるが、「おくらむ妹」の如き例はいづれも推量の意を持つので、ここはみづからの意ではないのである。浅見徹君「絶えむの心わが思はなくに―陳述をめぐる問題―」(萬葉第三十三号、昭和三十四年十月)、寺崎(旧姓森井)蘭夫人の「『む』の性格―推量意志のあらわれ方―」(女子大国文第十五号、昭和三十四年十月)参照。
【考】赤人集に「花にぬひおちこむ妹をいつとかまたむ」、流布本「おちこむ物をいつとかたのまむ」とある。 |
|
|
掲載日:2014.03.31.
| 夏雑歌 詠花 |
| 香細寸 花橘乎 玉貫 将送妹者 三礼而毛有香 |
| かぐはしき花橘を玉に貫き贈らむ妹はみつれてもあるか |
| かぐはしき はなたちばなを たまにぬき おくらむいもは みつれてもあるか |
| 巻第十 1971 夏雑歌 詠花 作者不詳 |
【赤人集】〔136・124・244〕
【資料】〔近代までの注釈書〕
| 【1971】 語義 意味・活用・接続 |
| かぐはしき [香細寸] |
| かぐはしき [芳し・馨し] |
[形シク・連体形] 香りがよい・心がひかれる・美しい |
| はなたちばなを [花橘乎] |
| たまにぬき [玉貫] |
| ぬき [貫(ぬ)く] |
[他カ四・連用形] 穴に通す・つらぬく |
| おくらむいもは [将送妹者] |
| おくら [贈る・送る] |
[他ラ四・未然形] 物を贈る・案内する・時を過ごす |
| む [助動詞・む] |
[推量(意志)・連体形] ~だろう・~しよう |
未然形につく |
| みつれてもあるか [三礼而毛有香] |
| みつれ [羸る] |
[自ラ下二・連用形] やつれる・疲れ果てる |
| ても |
「て」で受けた語句の意味を「も」で強めながら下に続ける |
| |
「~ても・~て・~てまあ」 |
連用形につく |
| 〔成立〕接続助詞「て」+係助詞「も」 |
| か [係助詞] |
[疑問] ~か・~だろうか |
連用修飾語につく |
| [終助詞] |
[詠歎・感動] ~だなあ |
連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
【注記】
| [かぐはしき] |
「香(か)細(くは)し」からつくる、「細し」は、繊細な美しさを表す語
橘の花の香りのよさは、早くから注目されていたらしく、
記紀歌謡にも、「かぐはし花橘」(記43・紀35)とある
古点「カノホシキ」とあるのを、仙覚がその『仙覚抄』で「かくはしき」と改めたことが、
契沖の『代匠記』に見える
|
| |
| [たまにぬき] |
橘の花を玉として糸に通すことを言うのだろうか
既出[1943、2014年3月6日]に、「五月の玉」を詠った一首がある
その「五月の玉」は、「橘の実」とする説、単に薬を詰め込んだ「薬玉」とする説
この歌では、「橘の花」を、その玉としている
香気を漂わせる洒落たアクセサリーなのだろう
|
| |
| [おくらむいもは] |
この歌の解釈が大きく分かれる語句になる
「花橘の玉」を「送ろう」というのは、作者である「男」なのか
それとも「妹」なのか
二つの解釈では、結句の意味合いまでも違ってくる
「男」であれば、愛する妻へ、美しく香りのよい花橘を玉にした「飾り」を贈り
「みつれて」の解釈を「病い」の一種だとすれば、それを見舞う形になり
男は、女の体調のすぐれないのを気に掛けている
「花橘の玉」は、それに対する「見舞い」のような感じになる
そして、この場合の結句の「か」は、詠歎・感動の終助詞「か」だと思う
そして、「妹」であれば、
いつもこの季節になると、「花橘の玉」で作った「飾り」を送ってくる「妹」なのに
未だにそれが届かないのは、「みつれて」いる「妹」なのだろうか
この場合の結句の「か」は、文末に用いられる場合の、疑問の係助詞「か」になるだろう
左頁の「古注釈書」を含め、主な「注釈書」では
「男が送る」とする書として、
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕〔資料〕、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕〔資料〕、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕〔資料〕、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕、
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕、
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕
「女が送る」とする書は、
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕〔資料〕、
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕〔資料〕、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕〔資料〕、
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕〔資料〕、
『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕〔資料〕、
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕〔資料〕
「不明」
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕
このように並べてみると、この歌の当初の理解は、
いつも妹が、「花橘を玉」とした贈りものを送ってくるのに、まだ来ないのは
「病気」なのではないか、と気にかける男の歌として解釈している
それが、少なくとも、左頁の「資料」の流れからみると、
『私注』辺りから、「男が送る」解釈になってきているように思う
語義解釈、古語の文法、用例の検証、それらの成果、ということだろうか
近年での『注釈』の解釈は、異質なのだろうか、
自説とは違う大勢の中で、何だか喝采を送りたくなる
なお、「不明」とした『代匠記』には、
第四句の「将送」を上の「玉貫」に繋げ、「妹者」は下の「みつれ」に繋げてもいい、
そう書いてあるので、私の曖昧なで拙い理解力では、
「玉に貫いて送ろう」、と「いもはみつれているだろう/なあ(あるいは「か」)
の二つの文になるのだが、そうなると「玉」を貫くのは「男」になる
しかし、ただ読み連ねても「意得」とあるので、
その読み連ねると、どうなんだろう、と悩ましくなる
契沖の解釈は、私には解らなかった
|
| |
| [ても] |
この歌では、「強調」の意になると思うが、
他にも意を持つ語となる
| |
| ①接続助詞「て」で受けた語句の意味を、係助詞「も」で強めながら下に続ける |
| ②「も」の働きで、上の語句を逆説的に下に続ける [~ても・~にもかかわらず・~のに] |
| ③逆接の仮定条件を表す [たとえ~しても・~たとしても] |
|
| |
| |
| |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが
その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく
その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、
もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが
かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、
それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[本文]「香細寸 花橘乎 玉貫 将送妹者 三禮而毛有香」(「【】」は編集)
「カクハシキ ハナタチハナヲ タマニヌキ オクラムイモハ ミツレテモアルカ」 |
〔本文〕【[頭注に】『釈日本紀』巻第二十四「裏書云香細寸 花橘乎 玉貫 万葉集第十」
赤人集「かくはしきはなたちはなを花にぬひおちこむいもをいつとかまたむ」 |
| 「香」 |
『類聚古集』「【香の崩れた字】」 |
| 「将」 |
『元暦校本』「【日のような字に寸】」 |
| 〔訓〕 |
| カクハシキ |
『元暦校本』「このほそき」。「こ」ノ右ニ赭「カ」アリ
『類聚古集・天治本』「かのほそき」
『神田本(紀州本)』「カノホソキ」
『神宮文庫本』「香細」ノ左ニ「カノホソキ」アリ
『細井本』漢字ノ左ニ「カノホソキ」アリ
『西本願寺本』五字モト青
『大矢本・京都大学本』「クハシキ」青。『京都大学本』漢字ノ左ニ赭「カノホソキ」アリ
|
| タマニヌキ |
『西本願寺本』「タマニヌク」但、「ク」ヲ消セリ。ソノ右ニ「キ」アリ
『神宮文庫本・細井本』「タマニヌク」 |
| オクラムイモハ |
『神田本(紀州本)・西本願寺本・細井本・神宮文庫本・近衛本』「ヲクラムイモハ」 |
| ミツレテモアルカ |
『元暦校本』「ツ」ナシ。右ニ赭「タ」ヲ書ケリ
『類聚古集・天治本』「みたれてもあるか」
『神田本(紀州本)』「ツ」ナシ・「而」ノ左ニ「トモ」アリ
『京都大学本』赭ニテ「ミツレ」ヲ消セリ。ソノ右ニ赭「ミレ」アリ。「三禮而」ノ左ニ赭「ミツレニモ」アリ |
| 〔諸説〕 |
| ○[カクハシキ]。『仙覚(万葉集註釈)』古点「カノホソキ」。新点「カクハシキ」。 |
|
【左頁資料について】
| 『万葉拾穂抄』 |
| 特になし |
| 『万葉代匠記(精撰本)』 |
初句の改訓が、『仙覚抄』で為されたことをいう
古点の「かのほそき」、古語辞典で調べたら、
「香(か)」の「細(ほそ)き」から「かぐはし」という「語」が生まれているので、
単純に、幅が細いなどの意の「ほそし(細し)」よりも、
細やかで美しい、などの意のある「くはし(細し)」に改められたことが知られる
ただ、第四句の語義解釈に曖昧さが残る |
| 『万葉集童蒙抄』 |
江戸時代、古語の「かぐはし」が、当時の俗語で「かうばし」と同じと、いう
古語「かぐはし」が転じたものだと思う
この書では、物思いにやつれ疲れる妹に、慰めの為に「花橘を玉」とする「飾り」を贈ろうと解釈 |
| 『万葉考』 |
| 花橘の玉を貫く飾りを送ってこないのは、「病気」ではないかと懸念する |
| 『万葉集略解』 |
「所送オクレル」ではなく「将送オクラム」は、
なるほど、そこに歌意の根本がある、としたのだろうか
「オクラム」が純粋な「推量」であり「意志」ではない、と言うのは
送ってこれないのは、病のためなのか、といたいのだろう |
| 『万葉集古義』 |
「かぐはし」と言う語、「橘」によく使われているのか...初めて知った
歌意に、具体的な情況を起こしている
「いつものごと」...妹が季節になるといつも送ってきたものが、途絶えているのは、
「やつれ疲れて」いるからだろう... |
| 『万葉集新考』 |
雅澄の訓に異を唱えるが、歌意は倣う
みつれ」を、巻四の一首を引用し「弱ること」、つまり疲れ果てること、というものか |
| 『口訳万葉集』 |
この書は、訓と解釈しかないが、おそらく作者は、愛しい妹の病み衰えていることを懸念し、
邪気払いに「花橘」を薬玉にして送ろう、というのだろうか |
| 『万葉集全釈』 |
解釈の言葉に、次第に具体性が見えるのは、それだけ充分な「歌意」がなかったからだと思う
このような明確な解釈が、現代の叢書の中には生かされていない節もある |
| 『万葉集全註釈』 |
「オクラムイモハ」が、贈ってやろうとする妹、としている
玉を貫いて「オクラム」とするのだから、その玉を貫くのは、という問題の解釈が必要になる |
| 『万葉集私注』 |
相変わらず、辛口だ
「少しうるさい感じだ」とは...
そう思う理由は、きっと相手に気を遣うために贈り物をしようとする男の立場をいうからであり
妹が、自分のせいでやつれ疲れているのが、事実であれば、鬱陶しいな、という感じ方なのか
それとも単に、歌としての「語法」や「語意」に「うるささ」を感じたのかな |
| 『万葉集注釈』 |
| 「おくらむ」の両説を並べ、自らは「妹が送る」と述べる |
|
|
|
| |
|
 |
 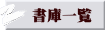  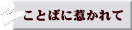 |





































