 |
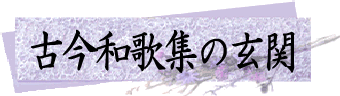
|
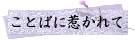
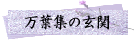 |
古今和歌集1111首のなかで、ほぼ一割を占める歌人、紀貫之.。この歌集の成立に大きく関わった歌人、紀貫之。明治三十一年、正岡子規は「歌よみに与ふる書」のなかで、「貫之は下手な歌よみにて古今集はくだらぬ集に有之候。其貫之や古今集を崇拝するは誠に気の知れぬことなどと申すものゝ、実は斯く申す生も数年前迄は古今集崇拝の一人にて候ひしかば今日世人が古今集を崇拝する気味合は能く存申候。云々」
正岡子規以前にも、与謝野鉄幹が同じような考えを持っていた。しかし彼らは、一様に新しい和歌の機運を盛り上げることになるが、これほどまで古い旧態依然とした歌風を否定したにもかかわらず、その原点を「万葉集」にもとめる。
そもそも、写生的な「万葉集」だということが大きな誤りだと思うのだが、明治後半の和歌革新運動は、和歌そのものを文芸にまで認知させてしまった。それほどまでに凄まじい攻撃にさらされながらも、古今和歌集以降の歌集の基礎となったことは、言うまでもない。極端に言えば、狂歌のような洒落歌も、古今和歌集の「誹諧歌」や「物名歌」などにみることが出来る。
古今和歌集は一時期不遇を甘受したけれども、その遊び心と、ときに情熱的な響きは、万葉人から百数十年経てより一層人間味が溢れている。
このホ−ムペ−ジでは、出来るだけ歌番号順に日々一首ごと掲載して行こうと思う。
|
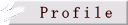 |
エッセイの部屋へリンク |
|
幼き頃の子どもたち、山の想い出写真 |
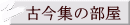 |
古今和歌集の撰者たち |
紀友則、紀貫之、凡河内躬恒、壬生忠岑 |
各巻の巻頭歌を掲載 |
|
仮名序 |
全文:出典・岩波文庫 |
|
| |
歌集 |
ある日の採り上げた歌、解説・感想 |
|
| |
真名序 |
全文:出典・岩波文庫 |
紀淑望 記 |
| |
掲載歌目次 |
本サイトに採り上げた歌の一覧 |
2013年2月現在、12首 |
| |
作者Profile |
本サイト掲載歌作者の解説 |
2013年2月現在、7名 |
| |
書庫巻第一 |
巻第一春歌上の本サイトで掲載した歌の感想記録 |
2013年2月現在、7首 |
| |
書庫巻第六 |
巻第六冬歌の本サイトで掲載した歌の感想記録 |
2013年2月現在、1首 |
| |
書庫巻第九 |
巻第九羈旅歌の本サイトで掲載した歌の感想記録 |
2013年2月現在、1首 |
| |
書庫巻第十六 |
巻第十六哀傷歌の本サイトで掲載した歌の感想記録 |
2013年2月現在、2首 |
| |
書庫巻第十八 |
巻第十八雑歌下の本サイトで掲載した歌の感想記録 |
2013年2月現在、1首 |
| |
古今全歌集 |
古今和歌集全20巻掲載
本サイト掲載歌については、「私的古語辞典」添付(予定) |
2013年2月現在、巻第一完了 |
| |
異本所載歌 |
現在の古今和歌集は、一般には定家の貞応二年書写本だが、他にも数々の書写本があり、その中には貞応二年書写本に掲載されていない和歌もある。各書写本より、それらを採録・感想。 |
28首採録。嘉禄本(底本)、道家本、亀山切、御家切、基俊本、昭和切、元永本、筋切、清輔本、伝藤原為家筆雅俗山荘本、寸松庵色紙、関戸本、高野切、善海所伝本、伝藤原為相筆静嘉堂本、唐紙巻子本古今集、志香須賀本、曼殊院本古今集、以上18書写本。 |