
| |
| 「あきたつまつと」...いもにつげこそ... |
| |
| 『ときをおそれ』 |
| 【歌意2004】 |
天上の安の川の渡し場に
私は、舟を浮かべて、今か今かと秋になるのを待っている
その早く逢いたい、という気持ちを、妻に知らせてほしい |
| |
| |
素直に読めば、どうしてもこのような解釈になるのだろう
まだ、逢瀬の許された「時」でもないのに、
私は待ち遠しくて、もういつでも天の川を渡れるように準備している
そのことを知らせることで、私の想いを解ってほしい、と願っている
今日、幾つかの「七夕」に纏わる本を広げてみた
そして、短い文章だったので、その箇所を熟考してみたが、
改めて、「七夕伝説」のパターンの多様性を知る
万葉歌に見られる、「七夕歌」は、これまでここで採り上げた歌を中心に考えれば
大方の天海は知られている
それは、牽牛(彦星)が、天の川を渡って、織女のところへ行くものだ
しかし、中国からのオリジナル...かどうか解らないが、その逆もある
右頁の〔織女と牽牛(伝説)〕のエピソードを知ると
織女が、天の川を渡る
雨の日は天の川の水かさが増して、渡河できず
その哀しむ姿を、地上の人は雲の合間から、眺める
そして、「かささぎの橋」は、確かに「万葉歌」にも詠われている
これらが、形を変えて日本で定着したにせよ
伝来された「まま」の物語を、多くの人は決して忘れてはいないだろう
万葉歌が詠まれた時代は、まさに、この伝承が伝えられる時代の最中だ
ということは、すべて「七夕」の題目で、同じパターンで解釈するのもおかしなものになる
それが、織女が渡河する、という話しなら理解出来るが
あたかも、牽牛の渡河がオリジナルの如く定着しているのは...
その見方で、〔2002、書庫-17〕を読み直してみるのも、興味深いものがある
勿論、私はその歌が「七夕歌」とは思わないので、
七夕伝承に合わせることではないが、少なくとも
「七夕」の数々のエピソードに潜む「人間世界」の「感情的」なところを
牽牛と織女の関係に見立てて「詠う」ことには、何ら制約もないはずだ
その「型」を取り払ったからこそ、
「七夕伝説」もどきの「人間讃歌」の「歌」があるのだと思う
「七夕伝説」という「型」に捉われていたら、おそらく面白味も感動もない歌ばかりだろう
掲題歌に戻るが、「いつでも渡河出来る」ことを伝えてくれ、というのは
よく考えれば、「余計な」説明なのではないか、と思えてくる
年に一度の逢瀬であれば、その時期が近づけば、無条件でそう思うもの
敢えて、知らせる「意味」というものが、この歌に詠われているのだろうか
深読みにもならないかもしれないが、この「ふねうけて」という意味
単に「舟を浮べて」なのだろうか
それ以上の思考が伴わないのは、当然その舟に乗って、牽牛が渡河する、という前提にある
私は、それが「余計な」説明だと感じてしまった
では余計でなく、この語句に「意味を持たせる」なら、それはどうなるのだろう
牽牛が、迎えに行く舟ではないのだろうか
織女の舟は、岸辺の沖合いまでしか来ない
私は、いつでも迎えに行ける準備は出来ている、
そう伝えてくれ、と言ってるようにもみえる
そもそも、俺は秋になればすぐにでも舟を漕ぎ出せる、
そんなことを「伝えてほしい」というものだろうか
七月七日の逢瀬に、違わぬ準備というものは、言わなくてもいいものだ
その信頼感は、互いに持っている
では、何を伝えてほしい、と...
こちらの準備は出来ている、お前は大丈夫か、やって来れるのか、と
その返事を求めるための「いもにつげこそ」のように思えてならない
この歌に、「七夕色」を強く感じるのは、やはり「あきたつまつと」だろう
この季節が、いや、この「とき」こそが、二人にとっては言うまでもなく
最も大切な「とき」であり、
不測の事態をやたらと思いがちの「ひととき」になる
待ち望むものが、近づけば近づくほど、その「ふあん」もまた
「歓び」と同じように「増大」して行くものだろう
だから、俺は準備はできた、お前は大丈夫か
「何とか無事に来てくれよ」と、「懼れ」の気持ちも多分にあるのだろう、と思う
|
|
掲載日:2014.05.03.
| |
| 秋雑歌 七夕 |
| 天漢 安渡丹 船浮而 秋立待等 妹告与具 |
| 天の川安の渡りに舟浮けて秋立つ待つと妹に告げこそ |
| あまのがは やすのわたりに ふねうけて あきたつまつと いもにつげこそ |
| 巻第十 2004 秋雑歌 七夕 柿本人麻呂歌集出 |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】〔128〕
【赤人集】〔165・152・273〕
【続古今和歌集】〔308〕
[資料]
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
【七夕】〔中華民国[国立成功大学、成大宗教與文化学報 第七期 論文]〕
【織女と牽牛】〔講談社学術文庫「星の神話・伝説」野尻抱影〕
| 【2004】 語義 意味・活用・接続 |
| あまのがは [天漢] |
| やすのわたりに [安渡丹] 安の川の渡し場 |
| ふねうけて [船浮而] |
| うけ [浮く] |
[他カ下ニ・連用形] 浮かべる・浮くようにする |
| あきたつまつと [秋立待等] |
| あきたつ [秋立つ] |
[自タ四・連体形] 秋になる・立秋になる |
| まつ [待つ] |
[他タ四・連体形] 人や物事が来るのを待つ |
| と [格助詞] |
[引用(~と言って)など、後に続く状況を示す] ~と |
| 〔接続〕体言、体言に準ずる語につく |
| いもにつげこそ [妹告与具] |
| つげ [告ぐ] |
[他ガ下二・連用形] 知らせる・伝える |
| こそ [終助詞] |
[希望] ~てほしい |
連用形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [やすのわたりに] |
安の川は、記紀神話で高天原にある川とされている(古事記上巻・日本書紀第一巻)
天の川を神話上の高天原の安の川と同一視している
「安の川」についての詳しい記述は、古注釈書に多くあり、下段資料では
どの注釈でも、述べている
『略解』では、「天河」の一名、としている
『新考』は、中国の伝説と、我が伝説の「天の安河」伝説が似ているので、相混じて、とする
『全釈』では、天の川の渡舟場を「安の渡」といい
『評釈万葉集』では、天の河の渡河地点の名、
など、いろいろと解釈があるが、
基本的には高天原の安の川と、中国伝承の「七夕伝説」から、
それを習合して用いたことを説明している
|
| |
| [あきたつまつと] |
四段動詞「あきたつ」と、四段動詞「まつ」を、並列で格助詞「と」が受けると思う
どちらの動詞も連体形であり、並列でしか考えられない
そう思っていたが、旧訓「あきたちまつと」に触れて、
その解釈を考えている内に、「秋立つ」が単独ではこの歌の意に沿うことは不自然だ、
と思うようになった
まず「あきたち」は、「待つ」にかかる連用形の用法となる
文法上はともあれ、その解釈としては、「秋になり、待つ」ではおかしい
「秋になるのを待っている」のが、この詠うところだ
だとすれば、「秋になるのを」という名詞化された語句になるのが自然だ
四段動詞「秋立つ」の連体形で、「体言に準ずる語」にはなるのだろう
だとすれば、最初に思った「並列」というのもおかしい
きっと「秋になるのを待つ」とする連体修飾語になるのだろう
こうして、その旧訓を否定するのが、『新考』などで、「あきたつ」を名詞的な解釈とし、
「秋になる」のを「待つ」という
「秋立つ」が、「秋になる」という名詞であれば、それにこしたことはないが
不幸にも、私の持つ古語辞典では、動詞としか載っていなかったが
古注釈の幾つかが述べるように、「秋になるのを待つ」の意で考えれば、と思う
|
| |
| [こそ] |
原文「與具」について、諸説がある
「與」の一字で、「こそ」という例もある
だから、「具」は添字になる、とか
「具」は「其」の誤字だとか...
すでに「與具」で決着がついていると思うが、こうした訓釈の変遷を見るのも面白い
特に、『万葉集注釈』の説明は興味深かいものがある |
| |
| |
 |
| |
| |
[織女と牽牛(伝説)] 講談社学術文庫「星の神話・伝説」野尻抱影
|
織女は、こと座のベーガ、牽牛は、わし座のアルタイルの中国名ですが、この二つの一等星が、天の川を隔てて瞬き合うさまは、正に一対の夫婦星で、世界にもまれな七夕伝説が中国に生まれたのも、自然に思われます。
織女は天帝の娘で、天の川の東の岸に住み、父のいいつけで明けても暮れても「機」を織っていました。その布は雲錦といって、五色にてり輝き、眩しいほど美しいものでしたが、織女はそれを織るので、髪を結う暇もなく、化粧をすることも忘れてしまいました。
やがて天帝も娘を不憫に思って、天の川の西に住む牽牛という若者とめあわせました。すると、織女は新しい生活の愉しさに、はた織りをなまけて、化粧にばかり身をやつすようになりました。それで天帝は腹を立てて、織女を再び東の岸へ連れ戻し、一年に一度、七月七日の夜だけ、天の川を渡って、夫に会うことを許してやりました。
こうしてその日に雨が降ると、天の川の水かさが増すために、織女は川を渡ることができないので、目のいい人には雲を通して、二つの星が天の川の両岸で、哀しげに五色に煌くのが見えるといいます。
その夜、カササギが、天の川の中に翼をならべて橋となり、織女を渡してやるというので、日本でも、これを『かささぎの橋』といって歌に詠みました。
中国では唐の時代から七月七日の夕べを七夕(しちせき)といって、織女牽牛を祭り、女たちが、針仕事や、琴や、文字などが上手になるように祈りました。
この伝説と祭りとが、遣唐使や留学生によって日本へ伝わり、織女には、はた織りの女神の名をあててタナバタ(棚機)とよび、牽牛は、男の星の意味でヒコボシ(彦星)とよび、また、オリヒメ、ウシカイボシともいいました。そして七夕と書いて、『タナバタ』と読むようになりました。 |
|
| |
|
|
| 掲題歌[2004]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】
| 新編私家集大成第一巻-4 人麿Ⅲ [冷泉家時雨亭叢書『素寂本私家集西山本私家集』] |
アマノカハヤスノワタリニフネウケテ」アキタチマツトイモニツケコソ
|
| 柿本人麿集上 秋部 万十 七夕 128 |
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
|
| あまの河やすのかはらに舟をうけて 秋たち待といもにつけよとて |
| 新編私家集大成第一巻-新編増補 赤人集Ⅲ[陽明文庫蔵三十六人集] あきのさう 165 |
| あまのかはやすのかはらにふねうけて 秋をまつとはいもつけよとて」 |
| 同第一巻-6 赤人集Ⅱ[書陵部蔵三十六人集] 秋雑歌 続古今 152 |
| あまのかはやすのかはらにふねうけて」五二秋にまつとはいもにつけよとて |
| 同第一巻-5 赤人集Ⅰあかひと[西本願寺蔵三十六人集] あきのさふのうた 273 |
| あまのがはやすのかはらにふねうけて秋にまつとはいもにつげよとて |
| 新編国歌大観第三巻-2 赤人集[西本願寺蔵三十六人集] あきのざふのうた 273 |
【続古今和歌集 ([文永二年(1265年)、同三年3月12日竟宴]撰、藤原為家[1198~1275]他)】
| 新編国歌大観第一巻-11 続古今和歌集[尊経閣文庫蔵本] |
あまのがはやすのかはらにふねうけて秋かぜふくといもにつげこせ
|
| 第四 秋歌上 308(/310) 山辺赤人 |
|
| |
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「天漢安渡丹舩浮而秋立待等妹告與具」
「アマノカハ ヤスノワタリニ フ子ウケテ アキタチマツト イモニツケヨク」(「【】」は編集、歌番は旧) |
〔本文〕頭注に、赤人集「あまのかはやすのかはらにふねうけて 秋をまつとはいもつけよとて」
|
| 「浮」 |
『類聚古集』ナシ。右ニ墨ニテ書ケリ。本文中「舩而」ノ間ニ墨「○」符アリ |
| 〔訓〕 |
| フ子ウケテ |
『元暦校本』「ふねをうけて」。赭ニテ「を」ヲ消セリ |
| アキタチマツト |
『元暦校本』「ち」ノ右ニ赭「ツ」、「つ」ノ右ニ赭「チ」アリ
『類聚古集』「あきたつまてと」
『神田本』「アキタツマツト」
|
| イモニツケヨク |
『元暦校本』「いもにつけこそ」
『類聚古集』「いもにつけうよく」。「う」ノ右ニ朱「ヲ」アリ
『神田本』「與具」ノ左ニ「コフ江」アリ |
| 〔諸説〕 |
○[秋立待等アキタチマツト]『万葉集略解』「秋」ハ「我」ノ誤ニテ訓「ワカタチマツト」トスル(宣長説)ヲ可トス、『万葉集古義』「アキタツマツト」トスル(岡部氏)ヲ否トス
○[妹告與具イモニツケヨク]『童蒙抄』「與」ハ「眞」ノ誤ニテ訓「イモニノラマク」トス、『略解』「與具」ハ「乞其」ノ誤。訓「イモニツゲコソ」。 |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [2004] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
| |
〔あまのかはやすのわたりに舟うけて秋たちまつと妹につけよよく 〕
天漢安渡[イかはら]丹船浮而秋立待等妹告[イつけよく]与具
|
日本神話の高天原の「安の河原」と伝来の「七夕伝説」の習合をいう |
| あまのかはやすのわたり やすのわたりやすのかはらともいふ天河原也八雲抄云あまの河やすのかはらは天照大神の隠れいまし給ひし所也諸神祈給ひし所なりこれ故[コ]人ノ説人不ル知事也正説也云々愚案是童蒙抄の説也奥に注日本紀ニ曰ク閉[サシテ]岩戸[イハトヲ]而/幽居[コモリマシヌ]焉/故[カレ]六合之内[クニノウチ]常闇[トコヤミニシテ]而不知晝夜之相代[ヒルヨルノアヒカハルワキヲ]于時[トキニ]八十萬神[ヤソヨロツカミ]曽[カツテ]合[ツトヒテ]於/天安河邊[アマノヤスノカハラニ]計[ハカラフ]其[ソノ]可[ヘキ]祷[イノル]之[ノ]方[サマヲ]と有此所歟告よよく類聚の和也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
| |
〔アマノカハヤスノワタリニフネウケテアキタチマツトイモニツケヨク 〕
天漢安渡丹舩浮而秋立待等妹告與具 |
「與具」を「こそ」と訓む例は、どの書も巻十三の「マサキクアリコソ」を引用するが、この時代の古語の検証と言うのは、こうした用例があるかないか、が基本なのだろうか |
安渡も天河の名なり神代紀云、于時八十萬神/會合[ツトヒテ]於天安河邊計其可祷之方、落句の與具は好く妹に告よとなるべし、第十三にも眞福在與具と云落句あり、
|
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、信名、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
| |
〔記ナシ 〕
天漢安渡丹船浮而秋立待等妹告與具 |
「具」が「眞」の誤字説
「安渡」を古語拾遺から「八湍」と広い出し、そのイメージを大きくさせる
訓には、及んでいない
|
| 與具を誤字と見ず、よくと讀めり。告げよくと云詞あらんや。眞の字の誤りにて妹にのらまく也。此等は極めたる誤字也。告げまくも、のらまくも同事也。船うけてと上に有から、縁語にのらまくとは讀べきか。安渡は、神代記諸神集會の所、畢竟高天原とふて、同所天上の義也。古語拾遺に八湍と書けるを正義と見るべし。いくせもの川にて廣大の河原也。さしすせそ通音の古語にて、やせともやすとも稱し來れり |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
| |
天漢[アマノガハ]、安渡丹[ヤスノワタリニ]、 古事記に天安川原とあるは都の地名なりかく云は古事記の考にくはしく云此歌にて安渡といふは天津銀河の事なりそれを彼地名の安川原にとりなしてよめるなり
船浮而、我立待等[ワレタチマツト]、
【今本云/秋立待等妹告與具[アキタチマツトイモニツゲヨヨク]】今本秋立待等とある秋は我の誤ならんと橘千蔭がいへるによるべし
妹告乞[イモニツゲコソ]、 |
「天漢」と「安渡」という和漢混在の趣をいう
「秋」を「我」の誤字とする
「與具」を「乞」とする
その詳細は、別の「巻」にあるようだが、真淵のいう巻順は、
万葉の巻順とは違うので、調べるのに手間が掛かる |
| 今本與具とあるは誤なり(卷三)に其誤るよしはくはしく云 |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
| |
〔あまのがは。やすのわたりに。ふねうけて。あきたつまつと。いもにつげこそ。 〕
天漢。安渡丹。船浮而。秋立待等。妹告與具。 [與具ハ乞其ノ誤] |
誤字をこれだけ立てると、どうも馴染めない
|
ヤスノ渡、則ち天河の一名なり。神代紀、八十萬神會合於天安河邊云云と有り。宣長云、秋は我の誤なり。ワガタチマツトなりと言へるぞ善き。與具は乞其の誤なるべし。告コソは告ゲヨカシと願ふ詞なり。卷十三、眞福在與具[マサキクアレコソ]と有るも、在乞其の誤なる事しるければ、共に誤れるなり。
參考 ○秋立待等(考)「我」ワレタチマツト(古)アガタチマツト(新)アキタツマツト。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
| |
〔アマノガハ。ヤスノワタリニ。フネウケテ。アガタチマツト。イモニツゲコソ。〕
天漢安渡丹船浮而秋立待等妹告與具
|
第四句の訓解釈で、岡部氏説、否定し宣長説に従う
何故「秋」を「我」の誤字としなければならないのか
それが解らない
巻十三の「マサキクアリコソ」の用例があるにも係わらず、どうして誤字説なのか、と疑問を持つる
秋を待っているこの気持ちを、どのようにして伝えようか、と |
安渡[ヤスノワタリ]は、安河[ヤスカハ]の渡なり、古事記に、是以八百萬(ノ)神、於天(ノ)安河之河原神集々而云々、(書紀にも、天(ノ)安河邊とあり、古語拾遺に、天八端河原[アメノヤセノカハラ]、とありて、名(ノ)意は彌瀬河[ヤセカハ]なるべし、
○秋立待等は、岡部氏、アキタチマツト訓はわろし、アキタツ待[マツ]トとよむべし、秋の立(ツ)を待の意なりと云り、本居氏、秋は、我の誤にて、アガタチマツトなりと云り、
○妹告與具は、イモニツゲコソにて、いかで妹につげよかしと希ふなり、(與具は乞其の誤なりと略解に云れど、)十三にも、眞福在與具[マサキクアリコソ](とあれば、誤とは決めがたし、)其(ノ)義は未(タ)思(ヒ)得ず、猶考(フ)べし、
○歌(ノ)意は、天の安河の渡に船を浮べて、吾(ガ)立て今か今かと待て居るよしを、いかで棚機女に告よかし、となり、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
| |
〔あまのかは安のわたりに船うけて秋立《アキタツ》まつと妹につげこそ〕
天漢安渡丹船浮而秋立待等妹告與具 |
この第四句の注釈が、もっとも解り易かった
|
支那傳説の銀河と我傳説の天(ノ)安河と相似たる所あればわざと相混じてアマノカハヤスノワタリニといへるなり。ワタリは渡津なり
○第四句を舊訓にアキタチマツトとよみ、眞淵は立をタツとよみ改め、宣長は秋を我の誤としてワガタチマツトとよめり。さて略解古義共に宣長の説に從へり。案ずるにこは眞淵の説に從ふべし。ワガタチマツトとよまむに待つべきものをいはでは物足らず又タチは不用なればなり。アキタツマツトとよみて秋ノ立ツヲ待テリトの意とすべし。さてこは風雲などにおほせたるなり
○與具は與其の誤、與のみにてコソとよむべきを更に其を添へたるか。其をソに借れる例は卷四にイヅクノコヒ其[ゾ]イヅレノイモゾとあり。下にもそれとおぼゆる例あり |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| |
天の川。安のわたりに舟/浮[ウ]けて、秋立つ待つと、妹に告げこそ |
雅澄が、思案している気持ちを伝える手段を、ここでは、その手段ではなく気持ちを優先させている
「こそ」の解釈では、そうなるだろう |
| |
自分は、天の川即天の安川のわたり場に、舟を浮べて、秋の來るのを待つてゐる、といとしい人に告げてくれ。(牽牛の心持ちを歌うた歌。) |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
| |
〔天の川 安の渡に 船うけて 秋立つ待つと 妹に告げこそ 〕
アマノガハ ヤスノワタリニ フネウケテ アキタツマツト イモニツゲコソ
天漢安渡丹船浮而秋立待等妹告與具 |
「具」を、添字とすれば、誰もが引用する巻十三さへも「其」の誤字ではないか、と疑問を持つ
用例を根拠とするだけなら、こうした論理も成り立つ |
天ノ川ノ安ノ渡[ワタリ]ニ船ヲ浮ベテ、ワタシハ秋ガ來ルノヲ待ツテヰルト、ワタシノ妻ノ織女ニ告ゲテクレヨ。
○安渡爾[ヤスノワタリニ]――天の川の渡舟場を安の渡といつたのである。古事記に「是以八百萬神於天安河之河原神集集而[ココヲモテナホヨロヅヨノカミアメノヤスノカハラニカムツドヒツドヒテ]」とあり、天上の川を天の安川といつたのを移して七夕傳説に取り入れ、天の川の名としたものである。
○秋立待等[アキタツマツト]――秋の來るのを待つてゐるとの意、舊訓にアキタチマツトとあるのはわるい。宣長が秋を我の誤としてワガタチマツトいつたのも從ひがたい。
○妹告與具[イモニツゲコソ]――與具は略解に乞其の誤とあるが、與は遊飲與[アソビニモコソ](九九五)・相見與[アフトミエコソ](二八五〇)などのやうに一字でコソと訓む字であるから、それにソを添へたものであらう。さう見れば具は其[ソ]の誤ではあるまいか。卷十三の眞福在與具[マサキクアリコソ](三二五四)も同樣に考へたい。
〔評〕 牽牛が織女を待ちわびる心を述べたもの。神代卷の高天原の安の河を、銀河に移したのはおもしろい。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
| |
〔天の河 安の渡りに 船浮けて、秋立つ待つと 妹に告げこそ。 〕
アマノガハ ヤスノワタリニ フネウケテ アキタツマツト イモニツゲコソ
天漢安渡丹船浮而秋立待等妹告與具 |
「安渡」は天の安の川の「渡河点」
「與具」の「具」を、「備え」の義で意味を持たせる
全体的に、いい解釈だと思う |
【譯】天の河の安の渡りに船を浮かべて、秋になるのを待つていると、妻に告げてください。
【釋】安渡丹 ヤスノワタリニ。高天の原にある川の名を、天の安の川という。それでここに安の渡りと云つている。ワタリは、渡るべき處。
秋立待等 アキタツマツト。アキタツは秋になるをいう。七月になるのを待つのである。
妹告與具 イモニツゲコソ。與具をコソに當てて書いている。略解に乞其の誤りとし、なお具を其の誤りとする説が多い。與は一字だけでもコソに當てて使用してあり、その意は、與えよの義によるものと思われる。よつて更に具を添えて、與えそなえよの義で使つているのだろう。「眞福在與具《マサキクアリコソ》」(卷十三、三二五四)。
【評語】牽牛の意に代つて詠んでいる。平明な内容の歌であつて、情熱に乏しい。
|
| 『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕 |
「評釈」私見 |
| |
〔あまのがは やすのわたりに ふねうけて あきたつまつと いもにつげこそ 〕
天漢安の渡に船浮けて秋立つ待つと妹に告げこそ |
彦星が、年に一度の逢瀬を待ちわびて、早く天の川を渡ろうとする歌、とする
誰に伝える手段を頼むのか、は解らないとするが、こうした歌では、問題ないはずだ
訓釈には、不充分なところがあると思う |
【譯】天の河の安の渡に船を浮べて、秋の来るのを待ちわびてゐると、自分の妻に告げてくれ
【評】彦星の歌で、船に乗つて秋の立つのを待つとは、年に一度逢ふ瀬を許された七月七日を待ちわびて、早く天の河を渡らうとする意である。妻は勿論織女のことであるが、その織女に告げてくれといふのは、誰に向つて頼むのか明らかでない。風雲にほせるのであらうと新考は云つてゐる。尚、安の渡は、古事記の高天原なる天の安の河から出たもので、日本の神話中の地名と、七夕伝説とが混じあつたのが面白く思はれる。
【語】○安の渡 天の河の渡河地点の名。神代紀に「干時、八百萬神、会合於天安河邊、計其可禱之方。」とあるのを、七夕伝説に融合させたものとおもはれる。
○浮けて 浮かべて。「浮け」は下二段活用。
○告げこそ 「こそ」は願望の助詞。
【訓】○告げこそ 白文「告與具」で、諸本皆この通りであり、巻第十三にも「眞福在與具」とあるが、ともに訓みがたい。略解は「告乞其」の誤といつてゐるが、二字にわたる改訂に従ひたい。「與」をコソと訓む例は、「九九五」「二八五〇」にもある。「具」は「其」を誤つたもので「二〇八九」に具穂船の例もある。「與」の一字でコソと訓み「其」を添へたものかとも思はれる。旧訓は字面に即してツゲヨク、元暦校本はこのままで「つげこそ」と訓み、略解は文字を前記の如く改めてツゲコソと訓んでゐる。 |
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
| |
〔天の川安の渡りに船浮けて秋立つ待つと妹に告げこそ 〕
アマノガハ ヤスノワタリニ フネウケテ アキタツマツト イモニツゲコソ
天漢安渡丹船浮而秋立待等妹告與其 |
特筆なし |
【大意】天の川の安の渡りに船を浮べて、秋の立つのを待つて居ると、妹、織女に告げて欲しい。
【語釈】ヤスノワタリ ヤスは天安河で日本の神話に、高天原にあるものとするのであるが、其を天漢伝説と習合させて、天漢をヤスノカハと呼ぶことは、下の(二〇三三)にも見える。即ち天漢の渡渉点、天津と同じ意に用ゐて居る。○ツゲコソ コソは「與」だけで足りるが、「其」を添へたのである。「其」は本には「具」とあるが、誤なことは下の(二〇八九)によつても知られる。
【作意】牽牛の立場の歌である。天の川の渡りに船を浮べて、秋になつたらすぐ渡るやうに待つて居ると、対岸の織女に告げて欲しいといふのである。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
| |
〔天の河 安の渡に 船浮けて 秋立つ待つと 妹に告げこそ 〕
アマノカハ ヤスノワタリニ フネウケテ アキタツマツト イモニツゲコソ
天漢安渡丹船浮而秋立待等妹告與具(『元暦校本』) |
この歌で、一番問題になるのが「具」の誤字あるいは、その訓の用例になるだろうが、この書の説明は、非常に解り易いる
|
【口訳】天の河の安の渡し場に船を浮べて秋の立つのを待つてゐると妹に告げておくれ。
【訓釈】天の河安の渡に―「安の渡」は古事記(上)に「是以八百萬神、於天安河之河原神集集而」とあり、神代紀(上)にも「干時八十萬神曾合於天安河邊、計其可禱之方」ともあつて、我が国の神話で高天原にある安の河原を支那から伝はつた七夕伝説の天の河の渡し場の名としたものである。この先に「八千戈 神自御世
(ヤチホコノ カミノミヨヨリ)」(2002)などといふのと同じく人麻呂らしい所作である。
船浮けて―「浮け」は四段自動の「浮く」を下二段他動にしたので、浮べて、の意。
秋立つ待つと―『元暦校本・西本願寺本』などアキタチマツとあるが、『紀州本』にタツマツとあるがよい。旧暦七月は秋であり、七夕は七月七日であるから、秋立てばやがて織女に逢へるから秋の立つのを待つてゐると、云つたのである。
妹に告げこそ―「与具」を『紀州本・西本願寺本』などヨクとあるが、『元』にコソとあるがよい。『考』に「乞曾」、略解に「乞其」の誤としたが、「与」はコセ、コソと訓むこと前(4・546、6・995)に述べた。「与」一字でコソと訓めるわけであるが、ここはソを示す為に「具」の字を添へたものと思はれる。然るに「具」はグの仮名に用ゐられる字である溜めに、略解の如く「其」の誤字だといふ説がある。「具」と「其」とは似てゐるやうであるが、この誤字例のたしかなものがない。『元』に「其里人」(13・3272)とあるが、「其」が「具」に近い字になつてゐる一例に過ぎない。然るにソと訓むべきところに「具」の字を用ゐたもの「具穂船乃(ソホフネノ)・・・本葉裳具世丹(モトハモソヨニ)」(2089)、「眞福在与具(マサキクアリコソ)」(13・3254)などいくつもあるので、これらをすべて誤字と認めることはどうであらう。ソナフのソを採つたものか、「行年」を「ソ(行)ネ」と訓むやうに「与具」はコソと訓むべきものと思はれる。ソナフのナフはアキナフ、イザナフなどのナフとすれば、ソだけを採る事は一層認めやすいと橋本四郎君も云はれてゐる。(2113)参照。
【考】赤人集に「やすのかはらに」「秋にまつとは妹につけよとて」、流布本「秋をまつとは」とあり、続古今集(四)「秋風吹くと妹につげばや」山辺赤人とある。
|
|
|

| |
| 「あまのかはぢを」...なづみてぞこし... |
| |
| 『ながゆゑに』 |
| 【歌意2005】 |
大空を自由に行き来している私でさへ、
今回ばかりは...あなたに逢うために、
こんなに苦労してしまったよ
天の川を渡る幾多の障害...あなたへ逢うのに降りかかる多くの障害を
こうやって、克服して、やって来たのです |
| |
| |
この歌、多くの注釈書での歌意を読んでいて、
自在に空を翔ける者が、どうして「天の川」を苦労してやってくるのか
その不自然な訳に随分悩まされてしまった
これは、勿論「七夕歌」なので、空を自在に翔けることも
天の川を渡河することも、ファンタジーの中の「実景」とすることが出来るが
「なづみてぞこし」という語に感じられるのは、
それこそ、『私注』の評を借りれば、「余りに人間過ぎる」と言える
ならば、その「人間」の立場で読めばいいのではないか
何でも思い通りに、事を為すことが出来る私なのに
あなたに逢うのは、とてつもない「幾多の試練」がある
でも、私は怖気づかない
何があっても、この「試練」の「天の川」を渡って
あなたのもとへ行く
歌の言葉通りでは、訳にするのが難しいが
「七夕伝説」を象徴的に背景として、愛しい人のところへ行く姿だと思う
下段資料の「私見」でも何度も感じた、そのもどかしさ、「人間」であれば、なるほど、と思う
|
|
掲載日:2014.05.04.
| |
| 秋雑歌 七夕 |
| 従蒼天 徃来吾等須良 汝故 天漢道 名積而叙来 |
| 大空ゆ通ふ我れすら汝がゆゑに天の川道をなづみてぞ来し |
| おほそらゆ かよふわれすら ながゆゑに あまのかはぢを なづみてぞこし |
| 巻第十 2005 秋雑歌 七夕 柿本人麻呂歌集出 |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】〔129〕
【赤人集】〔166・153・274〕
【古今和歌六帖】〔144〕
[資料]
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
【七夕】〔中華民国[国立成功大学、成大宗教與文化学報 第七期 論文]〕
【織女と牽牛】〔講談社学術文庫「星の神話・伝説」野尻抱影〕
| 【2005】 語義 意味・活用・接続 |
| おほそらゆ [従蒼天] |
| ゆ [格助詞] |
[経由点] ~から・~を通って |
体言につく |
| かよふわれすら [徃来吾等須良] |
| かよふ [通ふ] |
[自ハ四・連体形] 往来する・男が女のもとに行く |
| すら [副助詞] |
[類推] ~でさえ・~だって |
体言につく |
| ながゆゑに [汝故] |
| ゆゑ(に) [故] |
[体言、連体形の下について] ~のために・~よって |
体言につく |
| あまのかはぢを [天漢道] 天の川の渡り瀬を |
| なづみてぞこし [名積而叙来] |
| なづみ [泥む] |
[自マ四・連用形] 行き悩む・難渋する・悩み煩う |
| て [接続助詞] |
[補足(状態)] ~のさまで・~の状態で |
連用形につく |
| ぞ [係助詞] |
[強調] ~が 係り結びの「係り」 |
種々の語につく |
| し [助動詞・き] |
[過去・連体形] ~た 係り結びの「結び」 |
| 〔接続〕通常連用形につくが、カ変「来(く)」には未然形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [ゆ] |
旧訓は「に」だが、契沖が「ゆ」を提唱し、大方が従う
同じような解で、雅澄が同義で上代語の「よ」と訓むが、
それは、やはり経過点の格助詞「を」に通じるとしているので
そうなれば、一般的な「ゆ」の方が、相応しいと思う
しかし、「経過点」というよりも、この歌の歌意には、
大空を自在に飛び翔ける、とする意味があるので
「経過点」と言うよりも、「を」の方がしっくりくるかもしれない
次の句「かよふ」にも、自然につながる「を」だとは思う
|
| |
| |
[織女と牽牛(伝説)] 講談社学術文庫「星の神話・伝説」野尻抱影
|
織女は、こと座のベーガ、牽牛は、わし座のアルタイルの中国名ですが、この二つの一等星が、天の川を隔てて瞬き合うさまは、正に一対の夫婦星で、世界にもまれな七夕伝説が中国に生まれたのも、自然に思われます。
織女は天帝の娘で、天の川の東の岸に住み、父のいいつけで明けても暮れても「機」を織っていました。その布は雲錦といって、五色にてり輝き、眩しいほど美しいものでしたが、織女はそれを織るので、髪を結う暇もなく、化粧をすることも忘れてしまいました。
やがて天帝も娘を不憫に思って、天の川の西に住む牽牛という若者とめあわせました。すると、織女は新しい生活の愉しさに、はた織りをなまけて、化粧にばかり身をやつすようになりました。それで天帝は腹を立てて、織女を再び東の岸へ連れ戻し、一年に一度、七月七日の夜だけ、天の川を渡って、夫に会うことを許してやりました。
こうしてその日に雨が降ると、天の川の水かさが増すために、織女は川を渡ることができないので、目のいい人には雲を通して、二つの星が天の川の両岸で、哀しげに五色に煌くのが見えるといいます。
その夜、カササギが、天の川の中に翼をならべて橋となり、織女を渡してやるというので、日本でも、これを『かささぎの橋』といって歌に詠みました。
中国では唐の時代から七月七日の夕べを七夕(しちせき)といって、織女牽牛を祭り、女たちが、針仕事や、琴や、文字などが上手になるように祈りました。
この伝説と祭りとが、遣唐使や留学生によって日本へ伝わり、織女には、はた織りの女神の名をあててタナバタ(棚機)とよび、牽牛は、男の星の意味でヒコボシ(彦星)とよび、また、オリヒメ、ウシカイボシともいいました。そして七夕と書いて、『タナバタ』と読むようになりました。 |
|
| |
|
|
| 掲題歌[2005]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】
| 新編私家集大成第一巻-4 人麿Ⅲ [冷泉家時雨亭叢書『素寂本私家集西山本私家集』] |
オホソラニカヨフワレソラナレユヘニ アマノカハラヲナツミテソクル
|
柿本人麿集上 秋部 万十 七夕 129
|
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
|
| そらよりもかよふわれさえなれゆへに あまの河みちなつみてそきつる |
新編私家集大成第一巻-新編増補 赤人集Ⅲ[陽明文庫蔵三十六人集] あきのさう 166
|
| そらよりもかよふわれすらなれゆへに あまのかはみちなつみてそくる |
同第一巻-6 赤人集Ⅱ[書陵部蔵三十六人集] 秋雑歌 続古今 153
|
| そらよりもかよふわれすらたれゆゑに あまのかはみちなけきてそくる |
同第一巻-5 赤人集Ⅰあかひと[西本願寺蔵三十六人集] あきのさふのうた 274
|
| そらよりもかよふわれすらたれゆゑにあまのかはみちなげきてぞくる |
新編国歌大観第三巻-2 赤人集[西本願寺蔵三十六人集] あきのざふのうた 274
|
【古今和歌六帖 ([永延元年(987年)頃]撰、兼明親王・源順か)】
| 新編国歌大観第二巻4 [宮内庁書陵部蔵五一〇・三四] |
おほぞらをかよふ我すら何故にあまのかはらをなづみてぞくる
|
| 第一 歳時部 秋 七日の夜 144 人丸 |
|
| |
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「從蒼天往來吾等須良汝故天漢道名積而叙來」
「オホソラニ カヨフワレスラ ナレユヱニ アマノカハチヲ ナツミテソクル」(「【】」は編集、歌番は旧) |
〔本文〕頭注に、赤人集「そらよりもかよふわれすらたれゆゑにあまのかはみちなけきてそくる」
|
| 「蒼」 |
『温故堂本』「倉」 |
| 「天」 |
『神田本』「『会』の下『云』が『小』」 |
| 〔訓〕 |
| カヨフワレスラ |
『温故堂本』「カヨウワレスラ」 |
| ナレユヱニ |
『元暦校本』「ふれゆゑに」。「ふれ」ノ右ニ赭「ナカ」アリ
『類聚古集』「なかゆゑに」
『神田本・温故堂本・京都大学本』「ナレユヘニ」
『細井本』「ナレユエニ」
|
| アマノカハチヲ |
『元暦校本』「あまのかはらを」。「らを」ノ右ニ赭「タチ」アリ
『類聚古集』「あまのかはらは」
『神田本』「アマノカハラヲ」
『細井本』漢字ノ左ニ「アマノカハラハ」アリ
『京都大学本』「漢道」ノ左ニ朱「カハラヲ」アリ。ソノ上ニ赭「本」アリ |
| ナツミテソクル |
『元暦校本』「くる」ノ右ニ赭「ユク」アリ
『類聚古集』「なつみてそゆく」
『神田本』「来」ノ左ニ「ユク」アリ |
| 〔諸説〕 |
○[オホソラニ]『代匠記精撰本』「オホソラユ」
○[ナレユヱニ]『童蒙抄』『略解』「ナガユヱニ」
○[ナツミテソクル]『万葉考』「ナツミテソコシ」 |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [2005] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
〔おほそらにかよふわれすらなれゆへにあまのかはちをなつみてそくる 〕
從蒼天徃來吾等須良汝故天漢道名積而叙來
|
大空を自由に行き来できるのに、織女の為に天の川を苦労してやって来た、とする説明が、理解出来ない
天の川は、自由に翔けられるところではない、ということなら解るが、その解説は、どこにもない |
| おほそらにかよふわれ 七夕の心に成てよめり天人なれは大空を自由なるへき身なから戀つまゆへにあまの河の道をなつみくると也戀になやむ心也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
〔オホソラニカヨフワレスラナレユヱニアマノカハチヲナツミテソクル 〕
從蒼天往來吾等須良汝故天漢道名積而叙來 |
「おおそらより」とすべきを、「古風にあらず」として「おおそらゆ」とする
六帖の「あまのかはら」は、「道」の字を漏らした、と
引用する、巻十五は〔3405新番号3423〕、その訓「かはぢ」を言う |
發句を六帖にはおほそらをとあれど共に從を蒼天の上に置けるに叶はざる歟、赤人集にそらよりもとあるは叶へども古風にあらず、オホソラユと和すべきにや、天漢道を六帖にはあまのかはらをとあれど道の字を漏せり、赤人集にはあまのかはみちとあれど、第十四にも可美都氣乃乎度能多杼里我可波治爾毛云々、此今の點と叶へり、
|
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、信名、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
〔おほぞらに、かよふわれすら、なれゆゑに、あまのかはぢに、なづみてぞくる 〕
從蒼天徃來吾等須良汝故天漢道名積而叙來 |
牽牛織女、どちらの歌だとしても、天空を自在に翔けることが出来るに、そこに「恋の悩み」を被らせている
苦労してやって来た、というのは、その意味なのだろう
言葉通りに訳せば、「自在に翔けることができるのに、どうして」となるので、この解釈には納得できる
|
| 彦星織女何れの歌にしても、大空に通ふと讀むべき也。天上の人にして云へば也。空天を通ふ通力自在の身なれ共、戀路には悩み嫌ふもの故、天の河路に今夜汝に逢はんとてなづみこしと也。彦星織女の二星の内になりてよめる也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
從蒼天[オホソラユ]、 今本おほぞらにとあるは誤なりしかよみては從はあまれり
從來吾等須良[カヨフワレスラ]、
汝故[ナレユヱニ]、
天漢道[アマノカハラヲ]、名積而叙/來[コシ]、 |
「なづみ」の語義注釈、「いたづきなやみこしぞ」は、「いたづく」は上古「いたつく」で、骨を折る、患う、疲れる、などの意があり、やはり、「苦労してやって来た」というよりも、「思い悩みながらもやって来た」とする解釈なのだと思う |
| なづみは既に云如くいたづきなやみこしぞといふなり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
〔ほそらゆ。かよふわれすら。ながゆゑに。あまのかはぢを。なづみてぞこし。〕
從蒼天。往來吾等須良。汝故。天漢道。名積而叙來。 |
特筆無し
|
彦ボシに成りて詠めり。汝は織女を指す。
參考 ○汝故(考)ナレユヱニ(古、新)略に同じ。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
〔オホソラヨ。カヨフアレスラ。ナガユヱニ。アマノガハヂヲ。ナヅミテゾコシ。〕
從蒼天往來吾等須良汝故天漢道名積而叙來
|
「従」の訓について、起点・経過点の格助詞「を」として訓む
この歌意の解釈は、いつものことながら雅澄らしく、深読みになる
大空を自在に翔けてあなたの所へ行けるのだが、あなたが何処で私を迎えに来ているか分からない、だから最も険しい「天の川の道」を通って、やって来た、ということだろう
しかし、この歌意では、「天の川の道」が、どこに通じるかと言えば、織女のところであり、ならば他のどの道を通ろうとも、その目的地は解っているはずだ
この解釈のように、織女がどこに迎えにきているか解らない、と言うのであれば、「天の川の道」でも、同じではないか、と思う |
從蒼天[オホソラヨ]は、大空をと云が如し、從[ヨ]は、例の輕く乎[ヲ]といふに通へり、
○歌(ノ)意は、大空を飛廻りては、汝が何處に出來て、吾を迎ふと云事が、たどたどしきによりて、飛行自在の吾さへも、汝が河門に出て、待つゝあるらむと思ふが故に、他所をばたどらずて、天(ノ)河道を辛うして艱難[なづ]み來しとなり、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
〔蒼天[オホゾラ]ゆかよふわれすらなが故に天漢道[アマノカハヂヲ]なづみてぞこし〕
從蒼天往來吾等須良汝故天漢道名積而叙來 |
歌意に、自在に空を翔けることが出来るのに、敢えて苦労して逢いに来たことが、その偽りのない愛情の証だ、とでもいうようだ
|
牽牛が織女に告ぐる趣なり。第四句を舊訓にアマノカハミチとよみ、契沖は卷十四にカミツケノヲドノタドリノ可波治ニモとあるを例としてアマノカハヂヲとよめり。契沖の訓に從ふべし。卷二
(三一三頁)に川瀬ノ道とあるも同意なり
○ナヅミテはナヅサヒテにひとし(卷九[一七六二頁]參照)。一首の意は
大空ヲ飛ブ通力アル我ナレド汝ニ心底ヲ見セムトテ辛苦シテ天ノ川瀬ノ道ヲ渡ツテ來タ |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| 大空ゆ通ふ我すら、汝[ナ]が故に、天の川路[カハヂ]をなづみてぞ來し |
「天の川の道」の険しさが、どこかの書にでも伝えられているのだろうか
単に、二つの星を隔てる意味だけではなく、一種の「聖域」のように...「天の川」は、そんな「川」なのかもしれない |
| 自分は星だから、空を往來することが出來るのだ。その自分でさへも戀しいお前の爲に、天の川の渡り瀬を、難澀しながらやつて來た事だ。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
〔大空ゆ 通ふ我すら 汝が故に 天の川路を なづみてぞ來し 〕
オホゾラユ カヨフワレスラ ナガユヱニ アマノカハヂヲ ナヅミテゾコシ
從蒼天往來吾等須良汝故天漢道名積而叙來 |
初二句に興味がある、という
珍しい表現、ということなのだろう |
空ヲ飛ンデ通フコトノ出來ルワタシダガ、ソレデスラ、今夜ハ空ヲ飛バズニ〕、アナタ故ニ天ノ川ノ道ヲ、苦シイ思ヒヲシナガラ歩イテ來マシタ。
○從蒼天往來吾等須良[オホゾラユカヨフワレスラ]――大空を飛び通ふことの出來る我すらにの意で、星は空を飛ぶので、牽牛の心になつてかくいつたのである。
○名積而叙來[ナヅミテゾコシ]――ナヅムは骨折り苦しむこと。
〔評〕 牽牛が天の川路に行き惱む辛勞を、織女に訴へる趣で、一二の句に興味がある |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
〔蒼天ゆ 通ふ吾すら、汝がゆゑに 天の河路を なづみてぞ來し。〕
オホゾラユ カヨフワレスラ ナガユヱニ アマノガハヂヲ ナヅミテゾコシ
從蒼天往來吾等須良汝故天漢道名積而敍來 |
巻十四〔3425新番号3444〕を単に逆だとせず、この本歌にも通じるものがあると思うのだが...
労苦を織女に訴える、というのが、果たして... |
【譯】大空を通つて往來するわたしなのだが、あなたゆえに、天の川の道を骨をおつてきた。
【釋】從蒼天往來吾等須良 オホゾラユカヨフワレスラ。星は天空を飛行することのできるものとしている。オホゾラユは、大空を通つて。
名積而敍來 ナヅミテゾコシ。ナヅミテは、苦勞して、骨を折つて。
【評語】織女ゆえに苦勞して天の川の道を通う牽牛の心が詠まれている。勞苦を織女に訴える形になつている。初二句の敍述が特殊で、そういう者だがの意があらわれている。「淺/小竹[しの]原 腰なづむ。空は行かず 足よ行くな」(古事記三六)の趣である。「上つ毛野安蘇の川原よ石ふまず空ゆと來ぬよ。汝が心/告[の]れ」(卷十四、三四二五)はこの逆である。
|
| 『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕 |
「評釈」私見 |
〔蒼天ゆ通ふ吾すら汝がゆゑに天漢路をなづみてぞ來し〕
オホゾラユ カヨフワレスラ ナガユヱニ アマノガハヂヲ ナヅミテゾコシ
從蒼天往來吾等須良汝故天漢道名積而叙來 |
これも、労苦を訴え、そこまでして、逢いに来た、とする
しかし、この歌意には従来のようなそれだけの説明ではなく、「歩き悩む」という気持ちが伴っている
『童蒙抄』や『万葉考』に通じるところがある |
【譯】空を飛んで通ふことの出来る自分でさへも、そなたゆゑに、天の河の道を、歩き悩みつつたどつて来たのである。
【評】彦星が、大空を自在に飛行して得る身でありながら、戀なればこそ、馴れぬ河を渡つて来るといふ辛酸を、織女に向つて訴へたのである。固より條理にあてはまらぬところはあるが、幼くて可憐な想像である。
【語】○大空ゆ 「ゆ」は「より」の義であるが、「鄙の長道ゆ戀ひ来れば」(1155)、「空ゆと来ぬよ」(3425)等のやうな用法もあつて、動作の行はれる範囲を動的に示すもの、即ち「を通つて」の意。
○なづみてぞ来し 苦労をして、辛うじてやつと来たの意。
【訓】○蒼天ゆ 白文「従蒼天」で、旧訓オホゾラニ。今、代匠記精撰本に従ふ。
○汝がゆゑに 白文「汝故」で、旧訓ナレユヱニ。今、略解に従ふ。
○なづみてぞ来し 白文「名積而叙来」旧訓ナヅミテゾクル。今、考の訓を採る。 |
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
〔蒼天ゆ通ふ吾すら汝がゆゑに天漢路をなづみてぞ來し〕
ミソラヨリ カヨフワレスラ ナレユヱニ アメノカハヂヲ ナヅミテゾコシ
從蒼天往來吾等須良汝故天漢道名積而叙來 |
「余り人間にしてしまひ過ぎた」というように、上句と下句のギャップが大きく、意味がスムーズに繋がらないことを言うのだろう |
【大意】大空を通つて来る私でさへも、お前の為には、天の川の川路を、骨折つて来た。
【作意】牽牛の立場である。空を通ふのは、易々見えるかも知れないが、途中に天の川があつて、それを越えねばならぬ。が、それもお前の為に、骨折つて来たといふのである。余り人間にしてしまひ過ぎた。初句は古くからオホゾラニであつたのを代匠記にニをユとした。しかしオホゾラの例は集中にはない。ここも多きに従ひミソラとすべきだらう。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
〔大空ゆ かよふ吾すら 汝が故に 天の河道を なづみてぞ來し 〕
オホソラユ カヨフワレスラ ナガユヱニ アマノカハヂヲ ナヅミテゾコシ
從蒼天往來吾等須良汝故天漢道名積而叙來(『元暦校本』) |
従来の歌意をなぞるが、それで理解出来るのだろうか
|
【口訳】大空を往き来する自分でも、そなた故に天の河の道を難儀をしながらやつて来たよ。
【訓釈】大空ゆ通ふ我すら―「蒼天」は『元暦校本・類聚古集』その他諸本諸注にオホソラとある。アヲゾラとも訓めるわけであるが、萬葉にアヲソラの語無く、古今以後の勅撰集にもオホソラの語のみある。ここは星の事であるからアヲソラは適切でないであらう。星は大空を移動するので彦星になつての作である。
汝が故に―『元』フレユヱニ、『元』(右に赭)、『類』ナガ、『西本願寺本』その他ナレとある。「吾故」をワガユヱと訓むかワレユヱと訓むかといふに、ワレユヱの例は「和礼由恵尓(ワレユヱニ)思うひわぶらむ妹が悲しさ」(15・3727)の一例があるだけで、「賤吾之哉(イヤシキワガユヱ) ますらをの あらそふ見れば」(9・1809)、「和我由恵尓(ワガユヱニ)思ひなやせそ」(15・3586)など他はすべてワガユヱであり、「汝故」は「何如汝之故跡(ナゾナガユヱト)問ふ人も無し」(11・2620)の一例があるばかりで他に仮名書例は無いが、「吾故」の例に準じてナガユヱと訓むべきであらう。「汝」は即ち織女である。
なづみてぞ来し―旧訓ナヅミテゾクルを『考』にコシと改めた。「なづみ」は既出(1813、2・210)。
【考】古今六帖(一「七日の夜」)「何故に天の河原を」、赤人集「そらよりも」「たれゆゑにあまのかはみちなけきてそ来る」、流布本「なれゆへにあまのかはみそなつみてそ来る」とある。
|
|
|

| |
| 「ひとしりにけり」...ともしづま... |
| |
| 『いま、かけるとき なにがあろうとも』 |
| 【歌意2006】 |
八千戈の神がおられたはるかな昔から、
なかなか逢うことも叶わない人のことを、
世間の人たちに、知られてしまったなあ
私が、それほど長い間、想いを告げてきたからだろう |
| |
| |
この歌、「七夕歌」として、牽牛の心を詠ったとされる
しかし、いつものことながら、これを「七夕伝承」と言えるのだろうか
「部立て」に「七夕」とあるので、確かに「七夕」をベースに解釈したくはなる
でも、この歌でそれを持ち出せるのは、「人知りにけり」ではないだろうか
下段資料の『評釈万葉集』の解釈が、その前提に相応しいと思った
自分が、こんなに長い間想い続けてきたので、
今では多くの人に知られてしまった
この箇所を、「七夕伝承」が、多くの人に知られる事実とすればいい
長い時を経て、知られ渡った「恋心」
それは、決して嘆くようにして言うのではなく
自分の想いが、こうも長く続いているのか、という自身への共感もあるはずだ
しかし、人は決断しなければならない
今までが、あまりにも長きに渡る「想い」であれば尚更
「堂々」と恋仲であることを知らせたい、そう思うべきだ
「しりにけり」の「けり」という過去の助動詞には、詠嘆の気持ちがこめられている
「ここまできたら」と、自分を「翔けさせる」何かを感じ始めたのではないだろうか
これまで、積極的にかどうか解らないが、人に知られることを躊躇っていたとしたら
やはり、この「けり」は、「ともしつま」にしてはいけない、という気持ちの芽生えのはずだ
ここでいう「ともしつま」は、多くの解釈のように、滅多に逢うことが叶わない妻、
だから、年に一度の逢瀬」などとは、本当に「珍しい」という理解の仕方だが
「七夕」に捉われるのも、せいぜいそこまでだろう
ここからは、「人間界」の「想い」を「告げる」行動を、実際にしなければならない
何があろうとも、「想い」を実らせ、「ともしつま」から本当の「妻」へ...
この歌とは別の一首が、同じ「柿本人麻呂歌集」から『万葉集』に載っているが、
その左注を読むと、別な歌というより、同じ歌だと思える [右頁2484]
或本歌、と伝え、下句が、この掲題歌と同じだ
とすれば、その歌を元にして、「七夕」の伝承を取り入れたかのように思える
そして、その歌で詠われる表現は、まさに「人間界」の「想い」であり
恋しい妻のことを、人に知られてしまった、「ためらい」がある
そこが「人」としての「悩ましき」姿でもあるのに、
それを「七夕歌」とすると、いかにも、というように
「やちほこのかみのみよ」が詠われ、「ともしつま」が添えられる
そう、「いかにも」だ
残念ながら、私にはかなりの「意訳」でもしない限り、
この掲題歌には、胸を響かせることはなかった
しかし、おそらく「本歌」である〔2484〕に触れた途端、
この掲題歌もまた、「甦ってきた」
「七夕」に擬えたのではなく
「七夕」に秘めて詠ったものなのだ、という感じがした
このところ、毎日のように、「七夕歌」とされる「万葉歌」に触れているが
まだまだ「万葉歌人」(後の本格的な「歌人」ではなく)の「七夕」に重ねる「人」の歌に、
追いつけないでいる
人間的であればこそ、「悠久の時」という「ことば」を、つい欲しがるものだ
「七夕歌」...そこに「人の現実と夢」を、今後も感じてゆくと思う
|
 |
掲載日:2014.05.05.
| |
| 秋雑歌 七夕 |
| 八千戈 神自御世 乏○ 人知尓来 告思者 [○女偏に麗] |
| 八千桙の神の御代よりともし妻人知りにけり継ぎてし思へば |
| やちほこの かみのみよより ともしづま ひとしりにけり つぎてしおもへば |
| 巻第十 2006 秋雑歌 七夕 柿本人麻呂歌集出 |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】〔139〕
【赤人集】〔167・154・275〕
【和歌童蒙抄】〔138・524〕
[古注釈書引用歌]
【柿本人麻呂歌集】〔373〕
【夫木抄】〔4015〕〔万葉集古義・万葉集注釈〕
[古注釈書「万葉集」引用歌]
【万葉集】〔2484〕〔万葉集注釈〕
[資料]
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
【七夕】〔中華民国[国立成功大学、成大宗教與文化学報 第七期 論文]〕
【織女と牽牛】〔講談社学術文庫「星の神話・伝説」野尻抱影〕
| 【2006】 語義 意味・活用・接続 |
| やちほこの [八千戈] |
| かみのみよより [神自御世] |
| より [格助詞] |
[起点] (動作・作用の時間的、空間的な起点 ~から |
体言につく |
| ともしづま [乏○] [○女偏に麗] |
| ともし [乏し] |
[形シク・終止形] 少ない・稀な |
| ひとしりにけり [人知尓来] |
| ひと [非と] |
世間の人・他人 |
| けり [助動詞・けり] |
[過去・終止形] ~たのだ・~たなあ |
連用形につく |
| つぎてしおもへば [告思者] |
| つぎ [継ぐ・続ぐ] |
[他ガ四・連用形] 継続する・保つ・受け伝える |
| 〔参考〕 [告ぐ] |
[他ガ下二] 知らせる・伝える |
| て [接続助詞] |
[確定条件(原因)] ~ので |
連用形につく |
| し [副助詞] |
語調を整えたり、強意を表したりする |
助詞などにつく |
| おもへ [思ふ] |
[他ハ四・已然形] 愛する・恋しく思う |
| ば [接続助詞] |
[順接の確定条件] ~ので・~だから |
已然形につく |
| 〔接続〕通常連用形につくが、カ変「来(く)」には未然形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [やちほこのかみ] |
古くは、大国主命の別名とされる (古事記上巻・日本書紀第一巻)
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕に、
|
| 万葉集では、物事の起源の古いことを説明しようとして、この神の名を引くことが多い。これも七夕伝説を日本神話と融合させて解する一例。 |
とある
|
| |
| [ともしづま] |
形容詞「ともし」として、名詞「つま」に掛かるものであれば、
連体形の「ともしき」になるはずだが、
「ともしづま」と言う語が、一つの慣用的な名詞になっているのだろう
殆どの書では、「逢う事の少ない妻」「めったに逢う事の出来ない妻」などの意と解する
そんな状況なので「恋する妻」ということになるのだろう
原文「つま[女偏に麗]」を、
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕では、
| |
| 原文「孋つま[女偏に麗]」は、『後漢書・皇后紀』その李賢注に「[女偏に麗]も亦た「儷[人偏に麗(レイ・ならぶ)]なり」とある。「儷」に同じく配偶者、妻の意。 |
とある |
| |
| [助動詞「けり」] |
この過去の助動詞は、今まで気づかなかった事実に、気がついて述べる意を表す
他にも、以前から現在まで続いている事柄や伝承を回想する意や、
詠嘆の意をこめて、これまであったことに気づいた意を表したりする
|
| |
| [つぎ] |
原文は「告」だが、この表記で、続ける意の「継ぐ」をも掛けている表現
「おもひをつげれば」と「告ぐ」の意味で単純に思いたくもなるが、
何しろ「やちほこのかみのみよ」が詠い出しなので、
やはり「継ぐ」の意味になるのだろうか...
でも、それは時間的な表現であり、「おもひをつげれば」とすると、
そこに、更に「恋しく思い続けている」表現がはっきりすると思うのだが...
確かに[表記」は「告」でも、
「継ぐ」は四段動詞で、助詞「て」にかかる連用形「つぎ」は成り立つが、
「告ぐ」だと、下二段動詞となり、その連用形は「つげ」なので
「告ぐ」の意味での、訓「つぎ」にはならないだろう
敢えて「告ぐ」の意味として訓ませるなら、「おもひをつげれば」になると思う
|
| |
| |
[古注釈書「万葉集」引用歌]
【万葉集】〔2484〕〔万葉集注釈〕
|
| 寄物陳思 |
| 路邊 壹師花 灼然 人皆知 我戀□[女偏に麗] [或本歌<曰> 灼然 人知尓家里 継而之念者] |
道の辺のいちしの花のいちしろく人皆知りぬ我が恋妻は
[或本歌曰 いちしろく人知りにけり継ぎてし思へば] |
みちのへの いちしのはなの いちしろく ひとみなしりぬ あがこひづまは
[いちしろく ひとしりにけり つぎてしおもへば] |
| (以前一百四十九首柿本朝臣人麻呂之歌集出) |
| 巻第十一 2484 寄物陳思 柿本人麻呂歌集出 |
〔語義〕
「いちしのはな」は、未詳
「いちしろく」は、甚だしい意の接頭語「いち」に、顕著であるの意「しろし」で、
明白である、はっきりしている
|
〔歌意〕
みちばたの、いちしの花のように、いちしろく、
世間の人は皆知ってしまった
私の恋妻のことを
[或本歌<曰>]
はっきりと、人に知られてしまったなあ
ずっと、思い続けていたからなあ... |
この歌は、類想歌だと思う
どちらも、「柿本人麻呂歌集」からの歌だが、
かたや「七夕」のモチーフを背景に採録、もしくは人麻呂自身が詠っており
この類想歌では、「七夕」とは無縁の「羈旅発思」の部立てになっている
旅の途中で、道端の「いちしのはな」を見て、
恋しい人への慕情が、こんなにもはっきりと知られているのだろう、と詠ったものだ
こうした、世間の人へ知られることへの「抵抗感」、あるいは「気まずさ」とは... |
| |
| |
[古注釈書引用歌] 〔『万葉集古義・万葉集注釈』〕
【夫木和歌抄(延慶三年頃[1310年頃]、撰勝間田長清)】
| 編国歌大観第ニ巻-16 [静嘉堂文庫蔵本] |
| 天の川くらしかねたるともしづまわたりをいそぐぬさたむくなり |
巻第十 秋部一 七夕 建長八年百首歌合 前大納言顕朝卿 4015
|
|
| |
[織女と牽牛(伝説)] 講談社学術文庫「星の神話・伝説」野尻抱影
|
織女は、こと座のベーガ、牽牛は、わし座のアルタイルの中国名ですが、この二つの一等星が、天の川を隔てて瞬き合うさまは、正に一対の夫婦星で、世界にもまれな七夕伝説が中国に生まれたのも、自然に思われます。
織女は天帝の娘で、天の川の東の岸に住み、父のいいつけで明けても暮れても「機」を織っていました。その布は雲錦といって、五色にてり輝き、眩しいほど美しいものでしたが、織女はそれを織るので、髪を結う暇もなく、化粧をすることも忘れてしまいました。
やがて天帝も娘を不憫に思って、天の川の西に住む牽牛という若者とめあわせました。すると、織女は新しい生活の愉しさに、はた織りをなまけて、化粧にばかり身をやつすようになりました。それで天帝は腹を立てて、織女を再び東の岸へ連れ戻し、一年に一度、七月七日の夜だけ、天の川を渡って、夫に会うことを許してやりました。
こうしてその日に雨が降ると、天の川の水かさが増すために、織女は川を渡ることができないので、目のいい人には雲を通して、二つの星が天の川の両岸で、哀しげに五色に煌くのが見えるといいます。
その夜、カササギが、天の川の中に翼をならべて橋となり、織女を渡してやるというので、日本でも、これを『かささぎの橋』といって歌に詠みました。
中国では唐の時代から七月七日の夕べを七夕(しちせき)といって、織女牽牛を祭り、女たちが、針仕事や、琴や、文字などが上手になるように祈りました。
この伝説と祭りとが、遣唐使や留学生によって日本へ伝わり、織女には、はた織りの女神の名をあててタナバタ(棚機)とよび、牽牛は、男の星の意味でヒコボシ(彦星)とよび、また、オリヒメ、ウシカイボシともいいました。そして七夕と書いて、『タナバタ』と読むようになりました。 |
|
| |
|
|
| 掲題歌[2006]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】
| 新編私家集大成第一巻-4 人麿Ⅲ [冷泉家時雨亭叢書『素寂本私家集西山本私家集』] |
ヤチホコノカミノミヨヽリトモシツマ ヒトリ(ママ)ニケリツキテシオモヘハ
|
柿本人麿集上 秋部 万十 七夕 139
|
| 類歌〔2484〕の出典 |
| ミチノヘノイチシノハナノイチシロク 人ミナシリヌワカコヒツマト |
| 柿本人麿集中 恋部 羈旅発思 万十一 373 |
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
|
| やちほこの神の御代よりいもゝなき 人をしらせにきたりつけしは |
新編私家集大成第一巻-新編増補 赤人集Ⅲ[陽明文庫蔵三十六人集] あきのさう 167
|
| やちほしの神のみよゝりいもゝなき 人としらせにきたりつけしも |
同第一巻-6 赤人集Ⅱ[書陵部蔵三十六人集] 秋雑歌 続古今 154
|
| やちをしのかみのみよゝりいもゝなき ひとゝしらせしきたりつけゝん |
同第一巻-5 赤人集Ⅰあかひと[西本願寺蔵三十六人集] あきのさふのうた 275
|
| やちを(ママ)しのかみのみよよりいももなきひととしらせしきたりつげけん |
新編国歌大観第三巻-2 赤人集[西本願寺蔵三十六人集] あきのざふのうた 275
|
【和歌童蒙抄 (仁平年間(1151~54)頃、藤原範兼[1107~1165]】
|
| やちとせのかみのみよよりともしづまひとしりにけりつげてしおもへば |
新編国歌大観第五巻293[古辞書叢刊<尊経閣本>] 第ニ巻 時節 秋 七夕 138
|
| やちほこのかみのみよよりともしべのひとしりにけりつぎておもへば |
新編国歌大観第五巻293[古辞書叢刊<尊経閣本>] 第六巻 仏神部 神 524
|
|
|
 |
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「八千戈 神自御世 乏○ 人知尓来 告思者 【○女偏に麗】」
「ヤチホコノ カミノミヨヽリ トモシツマ ヒトシリニケリ ツキテシオモヘハ」(「【】」は編集、歌番は旧) |
〔本文〕頭注に、和歌童蒙抄第二「ヤチトセノカミノミヨヽリトモシツマヒトシリニケリツケテシヲモヘハ 万十ニアリヤチトセトハ八千歳トカケリ(中略)トモシツマトハ乏□【女偏に麗】トカケリ」
第六「ヤチホコノカミノヨリトモシヘノヒトシリニケリツキテヲモヘハ 万十ニ有」
赤人集「やちをしのかみのみよゝりいもゝなき ひとゝしらせしきたりつけゝむ」
|
| 「戈」 |
『西本願寺本』「【戈】の右肩の点なし」 |
| 「自」 |
『元暦校本』「冃【こんな感じ】」 |
| 「乏」 |
『類聚古集』「之【の崩した感じ】」。墨ニテ「乏」ニ直セリ |
| 〔訓〕 |
| カミノミヨヽリ |
『元暦校本』下ノ「ミ」ナシ。右ニ墨「ミ」アリ |
| トモシツマ |
『神田本』「トモシヘノ」。「□【女偏に麗】」ノ左ニ「ツマ江」アリ
『京都大学本細井本』「ツマ」ノ右ニ赭「江本」アリ。漢字ノ左ニ赭「トモシヘノ」アリ
|
| ツキテシオモヘハ |
『元暦校本』「つきてゝみれは」。「ゝみれ」ノ右ニ赭「シヲモヘ」アリ
『類聚古集』「つけてしおもへは」
『神田本』「ツケテオモヘハ」
『西本願寺本』下ニ貼紙別筆「告ツキテシ古本同イ本又同」アリ。「イ本」「古本」ニ各朱ノ合点アリ
『細井本』「ツキテシヲモヘハ」
『京都大学本』「ツケテシオモヘハ」。「テシ」ノ右ニ赭「江本」アリ。「告」ノ左ニ赭「ツキ」アリ。頭書赭「江本告ツケテシ」アリ |
| 〔諸説〕 |
| ○[乏□【女偏に麗】]『童蒙抄』「□【女偏に麗】」ハ「嬢」ニ作ルヲ可トス。『古義』大神景井、「乏」ハ「自」ノ誤カトス |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [2006] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
〔やちほこのかみのみよゝりともしつまひとしりにけりつけてしおもへは 〕
八千戈[イ歳とせの]神自御世乏□[女偏+麗]人知尓來告思者
|
「和歌童蒙抄」には、「やちとせ」とある
そこに、「やちほこのかみ」のような「神」は表現されていないが、
具体的に悠久の「いにしへ」を印象付ける「やちとせ」と、神話の時代を表現して、その「ふるさ」を表現する違いはあるが、どちらも、それほど古くから、という意味だ
この書では、「告ぐ」の意味で解しているので、訓は、必然として連用形「つげ」になる |
| やちほこの神のみよ 此哥童蒙抄にはやちとせのかみと有てやちとせとは八千歳とかけり其神とさしたる事見えす只久しき心をよめるなりともしつまとは乏□[女+麗]とかけりあふ事すくなきつまと云也告てしとは告てといふ也云々愚案此童蒙抄の説やちとせの儀をいへる可用之歟但才の字歳の字本の異あるなるへし仙本類聚等にはやちほこと有やちほこの神口訣あり |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
〔ヤチホコノカミノミヨヽリトモシツマヒトシリニケリツキテシオモヘハ 〕
八千戈神自御世乏□[女+麗]人知爾來告思者 |
先の「拾穂抄」もそうだが、結句の「告思者」を「継ぐ」の意ではなく、「告ぐ」の意で解するのが、やはり自然だと思う
そうなれば、当然その活用の違いから連用形「つげ」になるのだろうが
私には、それもまだ不充分に思われる |
告思者、【官本云、ツケテシオモヘハ、】
八千戈神は第六に注しつ、落句はツゲテシモヘバと讀べし、しは助語なり、或はツゲテオモヘバとも讀べし、
|
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、信名、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
〔やちほこの、かみのみよより、ともしづま、ひとしりにけり、告思者 〕
八千戈神自御世乏□[女+麗]人知爾來告思者 |
ここでいう、「神代の昔より今に人知りて」とし、七夕の年に一度の逢瀬のことを言うのであれば、「告思者」の意が、より困難になる
この書では、「訓釈」を述べない...難しいのだろう
それでいながら、歌意については、「神代の昔より人々知りたる苦しき思の恋心」という
結句を明確に解さず、一首の歌意を読めるのだろうか
|
やちほこの神 前にも注せり。卷第六に見えたり。大己貴神を奉v稱也。遠く久しき神世よりと云はんとて也。八千戈の神に意あるにあらず
乏□[女+麗] 珍しきつめ戀わびる妻と云ふ義也。乏しきものは少く珍しき意をもて、ともし妻共云へる也。□[女+麗]、一本に孃とあり。然るべし。又一本儷に作る心得難し。孃は少女の通稱也
告思者 此句心得難き句なれ共、古來よりつぐるとおもへば共、つげてしもへば共訓みて、抄物の意、世々人知りて云つぎ來りて、神代の昔より今に人知りて、七夕に逢ふ習とはなれるとの意と釋せり。今少し聞きおほせ難き意也。告げてし思へばと云ひて、さは聞え難し。告思者の三字何とぞ別訓あらんか。告の字苦の字にて、苦しきこひはと讀まんか。苦しきもひはと讀みて、年に一夜逢瀬の乏しき妻を戀慕ふ事は、神代の昔より人々知りたる苦しき思の戀路と云意にも見ゆる也。童蒙抄に八千戈を八千歳と云へるは心得難し。久しき事を云はんとて、八千歳の神とよめるとは難心得説也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
八千|戈[ホコノ]、神自御世[カミノミヨヽヨリ]、 八千戈神は大穴持神の一名なり古く久しき事にいはんためなり
乏□[女+麗][トモシヅマ]、 一本孃と有
人知爾來、苦思者[ネモコロモヘハ] |
「告」を「苦」の誤とし、「ねもころ」...副詞の「ねもころ」だろうか
「こころをこめて」とか「熱心に」などの意があるが、形容動詞の「ねもころ」では、連用形の「ねもころに」となるだろうし、改訓で、ますます「意」が難しくなった |
【奥人按に告苦字をかくは誤しかされどもありこせのまゝたすけ告思者[ツゲテオモヘバ]とよまるれば改ず有なむその義はつげの計を延れは伎弖となる故借て書るならむ】
今本告思者とありてつぎてしもへばと訓り告は苦の誤しるかれば字も訓も改む神の御世より久しくねもごろにおもへるともし妻なれば人もしりにけりと隔句によめりさて外になくおもふ妹をともし妻といふ將かゝるたぐひは皆彦星織女となりてよめると見るべし此歌も前の歌も彦星になりてよめるなり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
〔 やちほこの。かみのみよより。ともしづま。ひとしりにけり。つぎてしおもへば。〕
八千戈。神自御世。乏孋。人知爾來。告思者。 |
「つぎ」の訓の接続に、「告ぐ」であれば「つぎ」ではなく「つげ」になるとおもうのに、どうして「つぎ」と訓めるのだろう
引用している「イヒツギユカム」も「カタリツギ(ユカム)」も、「ゆく」という動詞に接続するから、というのだろうが、「いひつげゆかむ」「かたりつげゆかむ」ではないのだろうか
|
八千戈神は、大己貴命にて、三輪の大神なり。卷六、八千桙の神の御世より百舟の云云、トモシヅマは、たまたま逢ひて珍しみ思ふ意、告ギは借れるにて、意は繼ぎなり。卷三、長歌、語告/言繼將往[イヒツギユカム]も、カタリツギと訓むべければ、ここもツギと訓めり。孋は文選左太沖詩に、伉儷不安宅、張銑が註に、伉儷謂妻也と有り。儷、孋、同韻にて、古へ通じ用ひしならんと、濱臣は言へり。
參考 ○告思者(代)ツゲテシモヘバ、又は、ツゲテオモヘバ(考)「苦」ネモゴロモヘバ(古、新)ツギテシモヘバ。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
〔ヤチホコノ。カミノミヨヨリ。トモシツマ。ヒトシリニケリ。ツギテシモヘバ。〕
八千戈神自御世乏□[女+麗]人知爾來告思者
|
この「歌意」の意味するところは、「年に一度の逢瀬」を七夕として、誰もが知っている、ということになるだろう
では、「七夕歌」として詠う、多くの歌の中に、「一途な想い」とは異なる展開もあるのは、どうしたことか |
八千戈(ノ)神は、大穴牟遲(ノ)神のことなり、六(ノ)卷にもよめり、既くいへり、
○乏孋(孋字、拾穗本には儷と作り、)とは、年に一度ならでは、相見る事なければ、見る事の稀に乏しき妻と云なるべし、夫木集に天(ノ)河くらしかねたるともし妻わたりをいそぐぬさ手向らむ、とあり、さて略解(ニ)云孋は、文選左太冲(カ)詩に、伉儷不安宅、張銑(カ)註に、伉儷(ハ)謂妻(ヲ)也、とあり、儷孋同韵にて、古(ヘ)通(ハシ)用ひしならむと清水(ノ)濱臣云り、〔頭註、【大神景井云、乏孋は、自灑の誤にはあるまじくや、乏灑と云ることおぼつかなし、】〕孋/告思者[ツゲテシモヘバ]は、繼而思[ツギテオモ]へばにて、之[シ]は、その一(ト)すぢなるよしを思はする辭なり、〔頭註、【古事記博、苦思者、苦字、今本は告と誤れり、今は師の考に依て引、】〕
○歌(ノ)意は、神代より今に至るまて繼きて、織女を一すぢに戀しく思へば、人目を隱[シノ]ばむとしてもしのび得ず、吾(カ)戀妻なりと云ことを、世人皆よく知にけりと云ならむ、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
〔八千戈の神の御世よりともしづま人しりにけり告思者[ツギテシモヘバ]〕
八千戈神自御世乏□[女+麗]人知爾來告思者 |
「ともしづま」を「ゆかしき妻」と解するのは、理解出来る
「告ぐ」の活用に言及したので、てっきり我が意を得たり、と思えば、別の解釈で、上古には四段「告ぐ」があったのではないか、とする
せっかく、句順を変えてまで意を分かり易くしようとしているのに...
|
初二はただ遠キ昔ヨリといはむにひとし(卷六【一一八四頁】參照)。さて
ともし嬬人しりにけり八千矛の神の御世より告思者
と句をおきかへて心得べし。トモシヅマはユカシキ妻なり。卷八(一六二一頁)にもナク鹿ノ、如トモシカモワガココロ妻とあり。略解に
トモシヅマはたまたま逢てめづらしみおもふ意といひ、古義に
年に一度ならでは相見る事なければ見る事の稀に乏しき妻と云なるべし
といへるは非なり
○結句を舊訓にツギテシオモヘバとよみ略解に
告は借れるにて意は繼也。卷三長歌語告もカタリツギと訓べければこゝもツギとよめり
といへり(古義にもツギテシモヘバとよめり)。げに卷三(四一五頁)山部赤人望不盡山(2029)歌に語告イヒ繼ユカムとありてカタリツギとよむべくおぼゆ。但告の今の活は下二段にてツギとはたらかねばツギに告の字を借るべくはあらず。よりて思ふに告[ツグ]はいにしへ四段にはたらきしならむ。一説に告は苦の誤にてネモコロニモヘバなりといへれど八千矛ノ神ノ御世ヨリを受けたればツギテといはむ方まさるべし
|
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| 八千桙[ヤチホコ]の神の御世より、ともし妻[ヅマ]人知りにけり。つぎてし思[モ]へば |
なるほど、連作の中の一首か...そうかもしれない |
| 大昔の八千桙の神の居られた時代から、しきりなく思ひ續けてゐるので、たまにしか逢はない妻をば、人が悟つて知つたことだ。(此歌一首では牽牛の歌とも、七夕に詠んだ歌とも思はれないが、多くの聯作の中の一首と見れば、意味は明らかである。) |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
〔八千戈の 神の御世より 乏しづま 人知りにけり 繼ぎてし思へば
ヤチホコノ カミノミヨヨリ トモシヅマ ヒトシリニケリ ツギテシオモヘバ 〕
八千戈神自御世乏孋人知爾來告思者 |
特筆なし |
八千戈ノ神ノ昔ノ御代カラ、ワタシガ絶エズ戀シク思ツテヰルノデ、ワタシノ愛スル妻ヲ、人ガ知ツテシマツタヨ。
○八千戈神自御世[ヤチホコノカミノミヨヨリ]――八千戈神は大國主神の別名、一〇六五參照。
○乏孋[トモシヅマ]――トモシはここでは、なつかしく愛する意。トモシヅマは織女を指す。
○告思者[ツギテシオモヘバ]――告はツゲをツギに轉じ、繼に借り用ゐたのである。
〔評〕 牽牛星の心を述べてゐる。織女が自分の妻なる由が、世人に知れ渡つてゐることを言つたので、一二五三四と句を次第して見るべきであらう。一二の句は卷六にも見えた句だが、支那傳來の説話を日本化してゐるのが作者の工夫である、 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
〔八千戈の 神の御世より、ともし嬬 人知りにけり。繼ぎてし思へば。〕
ヤチホコノ カミノミヨヨリ トモシヅマ ヒトシリニケリ ツギテシオモヘバ
八千戈神自御世乏孋人知尓來告思者 |
「ともし」の解釈が、「滅多に逢えない」という意ではなく、他には類がないほど愛せられる、としているが、それでも語釈としては、従来の解釈になっている
「告ぐ」は、上古では「継ぐ」と同語で、四段として使われていたのが、残ったのだろう、と
こうなれば、訓はともかく、近年になってここの解釈は「告ぐ」ではなく「継ぐ」になってきたようだ
「愛する妻を人に知られたくない」とする作者たちの心、とするが、
それと「七夕伝説」は結びつかないような気がする |
【譯】八千戈の神の御代から、愛している妻を、人が知つている。續いて思つているので。
【釋】八千戈神自御世 ヤチホコノカミノミヨヨリ。八千戈の神は、大國主の神の別名と傳える。遠い神代から。「八千桙之[ヤチホコノ] 神之御世自[カミノミヨヨリ]」(卷六、一〇六五)。
乏嬬 トモシヅマ。トモシは、類すくなく愛せられる意の形容詞。ここは逢うことのまれな妻の意に織女星のことをいう。(卷十、二〇〇四參照)。
告思者 ツギテシオモヘバ。動詞告グは、下二段活として解されているが、ここにはツギの音に借りている。「語告[カタリツギ] 言繼將往[イヒツギユカム]」(卷三、三一七)の例もある。これは告グはもと繼グと同語で、四段に使用されていたので、かような用法が殘つたのだろう。
【評語】七夕の事の起原は、神代にありとする思想から、この歌を詠んでいる。これも牽牛の心になつて詠んでいる。愛する妻を人に知られたくないと思う作者たちの心が、牽牛の語を借りてあらわされている。初二句のかかりは、大がかりで、いかにも天上の戀らしい表現である。
|
| 『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕 |
「評釈」私見 |
〔八千戈の神の御世より乏し□[女偏に麗]人知りにけり繼ぎてし思へば〕
ヤチホコノ カミノミヨヨリ トモシヅマ ヒトシリニケリ ツギテシオモヘバ
八千戈神自御世乏□[女+麗]人知爾來告思者 |
自分が、こんなにも長い間想い続けているので、
多くの人に知られてしまった
そのように、この伝承は日本でも、古くから伝わっている、ということを詠った、とする |
【譯】遠い八千戈の神の御世から、自分のいとしい妻を、人は知つてしまつたことである。自分が絶えず思ひつづけてゐるので
【評】七夕の伝説の古さ、人口に言ひはやされることの久しさから、その戀の長久を、彦星が歎じてゐるのである。八千戈の神、即ち大国主命の御代よりと歌つて、大陸伝来の説話を日本化したのが、作者の機智である。
【語】○八千戈の神 大国主命の別名。「1065」参照。
○ともしづま いとしく懐かしい妻の意で、ここは織女をさす。
○継ぎてし思へば ずつと続いて戀ひ慕つてゐるので |
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
〔八千戈の 神のみ世より 乏し妻 人知りにけり 繼ぎてし思へば
ヤチホコノ カミノミヨヨリ トモシツマ ヒトシリニケリ ツギテシオモヘバ 〕
八千戈 神自御世 乏孋 人知爾來 告思者 |
この歌の成立に関して、「人間界のことも心の底にあって」とあるが、
私は、逆だと思う
「万葉集」の部立てが「七夕」なので、それが第一義とされているようだが、「七夕」に似つかわしくない歌も結構ある
むしろ、敢えていうなら「人間界」の歌だからこそ、気宇壮大な語を用いてしまうものだ
かなり古くから恋慕っているので、みんなに知られてしまった、とする歌が基本だと思う |
【大意】八千戈の神のみ世から、会ふことの稀な妻を、人が知つてしまつた。つづけて戀ひ思へば。
【語釈】ヤチホコノ カミノミヨヨリ ヤチホコカミは即ち大国主命である。遠い世からの意に、ヤチホコカミを持ち来つたのである。(2000)のヤスノワタリにも見えるやうに、日本神話と中国伝説の習合と見ることが出来る。七夕歌の中にはなほ幾つかの例をあげることが出来よう。
○トモシツマ 会ふことの稀なる妻と解すべきである。一年に一度のみしかあはぬ織女を言つて居る。
【作意】牽牛の立場である。遠い古から、会ふことの稀な妻ではあるが、戀ひ思ふのは引きつづいてであるので、人に知られてしまつたの意とすべきだ。此のあたりの歌は、多くは、人間界のことも心の底にあつて、そこから成立したのであらう。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
〔八千戈の神の御世よりともし□[女偏に麗]人知りにけりつぎてし思へば〕
ヤチホコノ カミノミヨヨリ トモシヅマ ヒトシリニケリ ツギテシオモヘバ
八千戈神自御世乏□[女+麗]人知爾來告思者(『元暦校本』) |
歌意に特筆はないが、諸注の解説は、いつものことながらありがたい
|
【口訳】八千戈の神の遠い御世から、逢ふ事の稀な妻を、人は知つてしまつたよ。絶えずひきつづいて思つてゐるので。
【訓釈】八千戈の神の御世より―「八千戈の神」は大国主の神(6・1065)。七夕伝説の遠い昔を、我が国の神話の神の御世より、と云つたのは、前に「安の渡」(2000)と云つたのと同じやり口である。
ともし妻―『拾穂抄』に「あふ事すくなきつまと云也」とある。『古義』にも「年に一度ならでは、相見る事なければ、見る事の稀に乏しき妻と云なるべし」といひ、
天の河くらしかねたるともし妻わたりをいそぐぬき手向くなり (夫木抄巻十「七夕」)
をあげてゐる。『新考』に、
「ともし妻人しりにけり八千戈の神の御世より告思者
と句をおきかへて心得べし。トモシヅマはユカシキ妻なり」といひ、『全釈』にも「トモシはここでは、なつかしく愛する意」とし、「一二五三四」と句を次第して見るべきであらう」とあるが、この「ともし」は、夫木抄の場合と同様、初二句へつづくものと見るべきもので、従つて「乏し」の原義によつたもので、稀にしか逢はないのだから人にも知られないであられようと思ふにかかはらず、人に知られてしまつたよ、といふのである。
つぎてし思へば―「告」をツギと訓み「継ぎ」の意に借りた例は前(3・317)にあり、そこで述べた。自分が久しい前からたえず思うてゐるので、といふので「人知りにけり」の理由を述べたものである。
【考】同じく人麻呂集の歌に、
路の邊のいちしの花のいちしろく人皆知りぬ我が戀妻を [或本歌云 いちしろく人知りにけり継ぎてし思へば] (11・2480)
とあり、さうした人間界の思ひを七夕の上に移し他ものである。
赤人集に「やちをしの」「いももなきひととしらせしきたりつけけむ」、流布本「やちしほの」「人としらせにきたりつけしも」とある。
|
|
|

| |
| 「いしまくらまく」...あまのかはらに... |
| |
| 『こよひもまた』 |
| 【歌意2007】 |
私がいつも恋しく思っている、
あの美しく紅に染まる頬の妻は、
今夜も私を待ち、天の川の河原で、石を枕に寝ているのであろうか |
| |
| |
「こよひもまた」、とする感覚には、
いつもと同じように、とする意味合いがある
しかし、この歌を「七夕歌」として読むと、
その「いつも」とは、一年前になるものと思った
でも、しばらく眺めていると
そうとも限らない
この一年の間、毎晩私への思慕で、それこそ河原の石を枕にして一人寝しているのではないか
それを思い遣っての歌のようにも思えた
本来ならば、決まった日、七月七日にしか逢えないものを、
そうやっていつも河原で待ちわびる、というのは
普通に考えれば、有り得ないものだ
では、「こよひもか」の解釈が違うのだろうか
「今夜もまた~か」ではなく...いや、この語釈には間違いはないはずだ
ただ、同じ語釈でも、歌意としては違った意味合いになることがある
この歌も、その用法なのかもしれない
近年の注釈書で、「こよひもか」を、「ともに過ごせる今宵」なので、
急いで駆けつけよう、という解釈が見られる
そこには、勿論自分が遅れることで、寂しい想いをさせてはいけない、という気持ちと
作者自身の、早く逢いたい、という想いもある
この掲題歌、一度読み、また読み返し...
そんなことを繰り返していたら、勿論この一首だけではないが
初めに感じたこととは違う感じ方もしてくる
この歌を、敢えて「七夕伝説」から外してみる
男は、愛しい妻の処へ、向かっているのだろうか...
「こよひもか」という語句に、何か別な想いを感じてくる
逢いたくても逢えない二人
そんな情況が浮んできた
「いつ逢おう」と、その約束があったにしても
この二人には、逢える環境が整っていない
男の方が、まだ結婚を許してもらえないかもしれないし
あるいは、「ならぬ恋」なのかもしれない
だから、「いつになるか解らないが、必ず迎えに行く」とする誓いの歌であるかもしれない
そう考えたら、一般的に立場を変えて詠われたような歌とされる、
次の一首が、見事に呼応してきた
この掲題歌とは、立場を変えただけではなく、「相聞歌」ではないか、と
[類想歌〔相聞歌〕]
|
| 秋雑歌/(山上臣憶良七夕歌十二首) |
| 久方之 漢瀬尓 船泛而 今夜可君之 我許来益武 |
| 久方の天の川瀬に舟浮けて今夜か君が我がり来まさむ |
| ひさかたの あまのかはせに ふねうけて こよひかきみが わがりきまさむ |
| 右神亀元年七月七日夜左大臣宅 |
| 巻第八 1523 秋雑歌 山上臣憶良 |
〔語義〕
「ひさかたの」は、「あま」にかかる枕詞
「うけて」の「うけ」は、浮かべる、意の下二段動詞「浮く」の連用形「うけ」
「わがり」の「がり」は、「~のもとへ」
「まさ」は、「あり」の尊敬語で、
「いらっしゃる、おいでになる」の意の四段動詞「ます」の未然形
「む」は推量の助動詞「む」の連体形 疑問の係助詞「か」を受けて連体形で結ぶ
|
〔歌意〕
(ひさかたの)天の川の川瀬に舟を浮べて、
今夜には、あなたは私のところへ、
来てくださるでしょうか |
勿論、この歌が本当の意味での、掲題歌との「相聞歌」とは思われないが
しかし、その歌意を掲題歌と立場を変えての「類想歌」とすると
そこから、上述の解釈になってしまった
ずっと待ち続ける女の姿
一年に一度の逢瀬、などと「七夕伝説」として読むには、
その「待つ心情」が、あまりにも「切ない」ものだ
やって来ることを、何の疑いを持たずに、待ち焦がれていようものを
「来てくれるだろうか」と言うのは、あまりにも人間界の「相聞歌」過ぎる
そして、「待つこと」は、決してゴールの見えるものではなく
このまま逢瀬を果たせずに生涯を終えることだってある
そんな不安があるからこそ、「こよひかきみが」と詠い、今夜にはあなたが、と訳せる
それは、いつもただただ待ち続ける姿を思わせる
それを知ったとき、掲題歌の「男の心情」が見えてきた
男が思い遣っている相手の女が、そのような心持であるのなら
男の置かれている立場は、逢いに行きたくても、すぐには行けない環境なのだ、と
掲題歌が「あまのかはら」と詠うのは、
本来約束されている、年に一度の逢瀬の渡し場を表現することで
簡単に逢いに行けないところだけど、という情景を思わせてくれる
だから、男は「今夜も河原の石を枕にし」一人寝をする「愛しい人」を思い遣る
その二人の仲を、客観的に見詰められるのは
当事者ではなく、周囲の人たち...
その意味で、「七夕」の関連する「語句」を用いて
舞台を俯瞰できるようにした二首になるのではないか...
「七夕伝説」をモチーフに詠うものではないが
その「七夕伝説」があるからこそ、この二首の呼応する二人の関係に辿り着けた
当時の人たちの、「七夕伝説」へ求める意味というのは、
いったい、どんなものだろう...
|
|
掲載日:2014.05.06.
| |
| 秋雑歌 七夕 |
| 吾等戀 丹穂面 今夕母可 天漢原 石枕巻 |
| 我が恋ふる丹のほの面わこよひもか天の川原に石枕まく |
| あがこふる にのほのおもわ こよひもか あまのかはらに いしまくらまく |
| 巻第十 2007 秋雑歌 七夕 柿本人麻呂歌集出 |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】〔450〕
【赤人集】〔155・276〕
【和歌童蒙抄】〔144〕
[類想歌〔相聞歌〕]
【万葉集】〔1523〕
[古注釈書「万葉集」引用歌]
【万葉集】〔1591・2569・3478〕〔万葉集注釈〕
[資料]
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
【七夕】〔中華民国[国立成功大学、成大宗教與文化学報 第七期 論文]〕
【織女と牽牛】〔講談社学術文庫「星の神話・伝説」野尻抱影〕
| 【2007】 語義 意味・活用・接続 |
| あがこふる [吾等戀] |
| にのほのおもわ [丹穂面] |
| に [丹] |
赤土・黄味を帯びた赤色・赤色の顔料 |
| ほ [穂・(秀)] |
[稲] 稲・すすきなどの、花や実の付いた茎の先・槍、刀などの先 |
| |
[秀] 目立って優れていること・表面に出ること |
| おもわ [面輪] |
顔の輪郭・顔 |
| こよひもか [今夕母可] |
| こよひ [今宵] |
今晩・今夜・(夜が明けてから)前の日の夜のことをいう・昨夜・昨晩 |
| もか |
[疑問・詠嘆の意] ~もまた~だろうか |
名詞につく |
| 〔成立〕係助詞「も」に係助詞「か」 |
| あまのかはらに [天漢原] |
| いしまくらまく [石枕巻] 石を枕にして寝る |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [あがこふる] |
原文の「吾等」の「等」が気になっていた
殆どの注釈書では、この「等」についての「注」はない
「が」とも訓めないだろうし、
それでも何故どの書も「あが(わが)」と当たり前のように訓めるのかだろう...
古注釈書の『童蒙抄』に、
|
| 吾等 印本等には、わがこふるとも讀ませたり。同意なれ共、等の字を書たれば、わらと訓みて、ラリル同音なれば、われ戀ふると云義と見るべし。然れば等の字虚字にならぬ也。集中吾等と二字に書きて、われとか、わがとか讀ませたる歌多し |
この書に溯るまで、なかなか「疑問」が解けなかった
もっとも、これが学問的に正しいかどうかは、私には解らない
ただ言えることは、私のように、理解出来ずに、悩む者にとっては
それが、まったく触れられずにあることで、妙に不安になるものだが
この書のお陰で、同じような疑問を挙げていたことに、ホッとする
それにしても、「等」を「ら」と訓み、その「ラリル同音」から「われ戀ふる」と解釈させ
さらに、その常用的な語として「わが戀ふる」に落ちつくさまは、少し懲り過ぎている、と思う
|
| |
| [にのほのおもわ] |
何しろ、原文が「丹穂面」だ
助詞が略されている
「丹穂」は、比較的訓み得ると思うが、
『全註釈』が言うように、「丹穂」を、動詞「にほふ」に当てている用例があり、
そこから「にほへるおもわ」と訓む
鎌倉時代の僧仙覚(出生は定かではないが、1203~1272年が有力)が、
「万葉歌」に初めて訓みを点けた「古点」では、「にほへるいもは」つるのようだ
しかし、「にのほの」が定着するのは、それほど時を経ずのことであり
後にも、この句に異訓を見るのは、むしろ「面」の方になったと思う
| 古語辞典解説 |
| 「ほ」 |
| 物の先端など、抜き出て目立つところをいうのが「秀(ほ)」の原義。稲・すすきなどの、花や実の付いた茎の先をいうときには「穂」を当てるが、語源は同じ。「ほのほ(災)」は「火の秀」であり、「にほふ(匂ふ)」は「丹秀ふ」であると考えられる。 |
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕に、その用例として
秋に、木の葉が美しく黄葉することを、「丹の穂にもみつ」(巻第十三〔3280〕)、
との用例を挙げている 〔既出、書庫-8 (2013年7月1日)〕
「面」を「おもわ」とか「おもは」などと訓まれ
真淵は「おもと」と訓み、井上通泰『新考』は「おもて」と訓む
千蔭や雅澄辺りから、「おもわ」が通訓になってきた、と思う
「おもわ」については、具体的な用例として、
多くの書が、巻第十九〔4193長歌〕の「自註」を引く
| 巻第十九 4193 為家婦贈在京尊母所誂作歌一首[并短歌] 大伴家持 |
| ―潜取云 真珠乃 見我保之御面― [御面謂之美於毛和] |
| ―かづきとるといふ しらたまの みがほしみおもわ― [御面はみおもわと謂ふ] |
しかし古注釈書では、「おもわ」以外の訓の「万葉集」の用例も幾つか述べている
|
| |
| [こよひもか] |
『童蒙抄』に「年に一度の今宵もか」と訳す
そのように解すると、「今年もまた」という意味になるが...
以降では、『古義』が言うように、軽い歎息を含めたような「も」と扱う解が多くなるが
『注釈』では、二種類の「こよいもか」を述べている
掲題歌の歌意に沿う例として下段〔古注釈書「万葉歌」引用歌〕の〔1591・2569〕をあげ、
掲題歌と違う意味合いの「こよひもか」に、〔3478〕をあげている |
| |
| [こよひ] |
古くは日没から一日が始まると考えられていたので、
夜が明けてから、昨夜のことを言った、とされる
|
| |
| [いしまくらまく] |
この訓、旧訓は「イソマクラマク」とされていたが、
この歌には、すでに「河原」という語があり、そこにまた「磯(いそ)」とすれば、
重複してしまうので、古くは『代匠記』にも提唱された、「いはまくらまく」に改められた
しかし、それでも『注釈』などでは、「いは」は高山の岩に「まくら」として使われるが、
河原に対しては、「いし」と訓む方が自然だとされる
ただし、『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕は、
「いはをまく」とはいうが、「いしをまく」とは言わない、とし「いはまくらまく」とする |
| |
| |
[古注釈書「万葉集」引用歌]
【万葉集】〔1591・2569・3478〕〔万葉集注釈〕
|
| 秋雑歌/(橘朝臣奈良麻呂結集宴歌十一首) |
| 足引乃 山之黄葉 今夜毛加 浮去良武 山河之瀬尓 |
| あしひきの山の黄葉今夜もか浮かび行くらむ山川の瀬に |
| あしひきの やまのもみちば こよひもか うかびゆくらむ やまがはのせに |
| 右一首大伴宿祢書持( / 以前冬十月十七日集於右大臣橘卿之舊宅宴飲也) |
| 巻第八 1591 秋雑歌 大伴宿禰書持 |
〔語義〕
「あしひきの」は、「山」にかかる枕詞
「うかびゆくらむ」は、黄葉が川の瀬に流れてゆく、「らむ」は現在推量で、
「今ごろ~しているだろ」う
「やまがは」は、山の中の「川」
(「か~らむ」は、係り結び)
|
〔歌意〕
(あしひきの)山の黄葉は、今夜もまた
浮んでは流れて行くのだろうか、山川の瀬に... |
|
| 正述陳思 |
| 夜干玉之 妹之黒髪 今夜毛加 吾無床尓 靡而宿良武 |
| ぬばたまの妹が黒髪今夜もか我がなき床に靡けて寝らむ |
| ぬばたまの いもがくろかみ こよひもか あがなきとこに なびけてぬらむ |
| 巻第十一 2569 正述陳思 作者不詳 |
〔語義〕
「ぬばたまの」は、「くろかみ」にかかる枕詞
「ぬらむ」は、完了の助動詞「ぬ」の終止形「ぬ」に、現在推量の助動詞「らむ」で、
「~ているだろうる・~てしまっただろう」
(「か~らむ」は、係り結び)
|
〔歌意〕
(ぬばたまの)黒髪を、今夜もまた
私のいない床になびかせて、
あなたは、寝ていることだろうか |
『万葉集注釈』で引用するこの二首は、掲題歌の「こよひもか」と同じだという
歌意としては、「今夜もまた」とするのは次の一首も同じだとは思うが、
根本的な違いと言うのは、この二首には「まさにこのとき」のことを詠っている
そこが、次の一首との違いなのだろう
〔3478〕では、そこには雅澄のいう「軽い歎息」の気持ちが込められている
雅澄の言う、「ともに」への「感動・詠歎」の「も」だ
|
| 東歌 相聞 |
| 伊祢都氣波 可加流安我手乎 許余比毛可 等能乃和久胡我 等里弖奈氣可武 |
| 稲つけばかかる我が手を今夜もか殿の若子が取りて嘆かむ |
| いねつけば かかるあがてを こよひもか とののわくごが とりてなげかむ |
| 巻第十四 3478 東歌 相聞 作者不詳 |
〔語義〕
「いねつけば」の「つけ」は、杵や棒の先などで打つ、
または打って押しつぶす意の四段動詞「つく」の已然形「つけ」で、
順接の確定条件「ば」に繋がる
「かかる」は、ひびやあかぎれが切れる、意の四段動詞「かかる」の連体形
「とののわくご」の「との」は、地方の豪族や首長階級の有力者で、
「わくご」は、その子、「若君」
一般的には、「わくご」は年の若い男の美称とされる
(「か~む」は、係り結び)
|
〔歌意〕
稲を舂(つ)くと、いつもあかぎれが切れる私の手を、
今夜も若君は、手にとって嘆かれるだろうか |
|
| |
| |
[織女と牽牛(伝説)] 講談社学術文庫「星の神話・伝説」野尻抱影
|
織女は、こと座のベーガ、牽牛は、わし座のアルタイルの中国名ですが、この二つの一等星が、天の川を隔てて瞬き合うさまは、正に一対の夫婦星で、世界にもまれな七夕伝説が中国に生まれたのも、自然に思われます。
織女は天帝の娘で、天の川の東の岸に住み、父のいいつけで明けても暮れても「機」を織っていました。その布は雲錦といって、五色にてり輝き、眩しいほど美しいものでしたが、織女はそれを織るので、髪を結う暇もなく、化粧をすることも忘れてしまいました。
やがて天帝も娘を不憫に思って、天の川の西に住む牽牛という若者とめあわせました。すると、織女は新しい生活の愉しさに、はた織りをなまけて、化粧にばかり身をやつすようになりました。それで天帝は腹を立てて、織女を再び東の岸へ連れ戻し、一年に一度、七月七日の夜だけ、天の川を渡って、夫に会うことを許してやりました。
こうしてその日に雨が降ると、天の川の水かさが増すために、織女は川を渡ることができないので、目のいい人には雲を通して、二つの星が天の川の両岸で、哀しげに五色に煌くのが見えるといいます。
その夜、カササギが、天の川の中に翼をならべて橋となり、織女を渡してやるというので、日本でも、これを『かささぎの橋』といって歌に詠みました。
中国では唐の時代から七月七日の夕べを七夕(しちせき)といって、織女牽牛を祭り、女たちが、針仕事や、琴や、文字などが上手になるように祈りました。
この伝説と祭りとが、遣唐使や留学生によって日本へ伝わり、織女には、はた織りの女神の名をあててタナバタ(棚機)とよび、牽牛は、男の星の意味でヒコボシ(彦星)とよび、また、オリヒメ、ウシカイボシともいいました。そして七夕と書いて、『タナバタ』と読むようになりました。 |
|
| |
|
|
| 掲題歌[2007]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】
| 新編私家集大成第一巻-4 人麿Ⅲ [冷泉家時雨亭叢書『素寂本私家集西山本私家集』] |
ワカコフルニホヘルイモハコヨヒカモ アマノカハラニイソマクラマク
|
柿本人麿集中 恋部 寄草 万十 450
|
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
|
| わかこひにほにあけてみむこよひ我 あまのつはしの今はうしまと |
同第一巻-6 赤人集Ⅱ[書陵部蔵三十六人集] 秋雑歌 続古今 155
|
| わかこひにほひあひてみむはこよひわか あまのつはしのいはかしまつと」(本) |
同第一巻-5 赤人集Ⅰあかひと[西本願寺蔵三十六人集] あきのさふのうた 276
|
| わがこひ〔 〕にほひあひてみむはこよひわがあまのつはしのいはかし |
新編国歌大観第三巻-2 赤人集[西本願寺蔵三十六人集] あきのざふのうた 276
|
【和歌童蒙抄 (仁平年間(1151~54)頃、藤原範兼[1107~1165])】
| 新編国歌大観第五巻293[古辞書叢刊<尊経閣本>] |
わがこふるにほへるいももこよひかもあまのかはらにいそまくらまく
|
第ニ巻 時節 秋 七夕 144
|
|
|
| |
| |
 |
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「吾等戀丹穗面今夕母可天漢原石枕卷」
「ワカコフル ニノホノオモハ コヨヒモカモ アマノカハラニ イソマクラマク」(「【】」は編集、歌番は旧) |
〔本文〕頭注に、和歌童蒙抄第二「ワカコフルニホヘルイモヽコヨヒカモアマノカハラニイソマクラマク 同(万十)ニアリ
赤人集「わかこひにほひあひてみむはこよひわか あまのつはしのいはかしまつと 本」 |
| 「夕」 |
『類聚古集』ナシ |
| 「石」 |
『元暦校本』「立【のような、判読出来ず】」。右ニ墨「石」アリ |
| 〔訓〕 |
| ニノホノオモハ |
『元暦校本』「にほへるいもは」。「へ」ノ右ニ赭「フ」アリ
『類聚古集』「にほくるいもは」。「いもは」ノ右ニ朱「オモハ」アリ
『神田本(紀州本)』「ニホヘルイモハ」
『西本願寺本』「ホノオモハ」モト青
『京都大学本』漢字ノ左ニ赭「ニホヘルイモハ」アリ |
| コヨヒモカモ |
『元暦校本』「こよひかも」
『神田本』「コヨヒカモ」
『類聚古集』「こよひもか」
『西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本・活字附訓本』「コヨヒモカ」
|
| 〔諸説〕 |
| ○[ワカコフル]『童蒙抄』「ワラコフル」○[ニノホイオモハ]『仙覚抄』古点「ニホヘルイモハ」。新点「ニノホノオモハ」○[コヨヒモカモ]『代匠記精撰本』「コヨヒモカ」○[イソマクラマク]『代匠記精撰本』「イハマクラマク」、『万葉考』「イハマクラカン」、『古義』「イソマクラマカム」 |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [2007] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
〔わかこふるにのほのおもはこよひもかあまのかはらにいそまくらまく 〕
吾等(イをら)戀丹穂(古にほつる)面(いもは)今夕母可天漢原石枕卷
|
仙覚が「面」を「いも」と訓じたのか、それとも誤字としたのか、「いも」としている |
| わかこふるにのほのおも 童蒙抄にはにほつるいもはと和せり古点なり但仙曰此哥第二ノ句古点にはにほへるいもはと點す其和あたらすにのほのおもはといへる也見安云にのほのおも紅顔也愚案/丹穂[ニホ]をにほへるとはへるをよみつけて也たとへは此卷に犬鴬をいぬるうくひすとよみ十緒をとをゝにもと和すたくひにや面をいもとよむはおといと五音通る故にや又古本新本の文字のかはりも知かたし卒尓に古点を不[ス]當[アタラ]と云へからさるにやされと新点も年久しく傳へ來たれはしはらく其まゝに和し侍り哥の心は匂へる妹にてもにのほのおもにても牽牛の心に成て織女をいへるなるへしいそまくらまきて我をこよひも待かねけんとなるへし或説にのほ丹は紅顔也穂はそれと顕るゝ心也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
〔ワカコフルニノホノオモハコヨヒモカモアマノカハラニイソマクラマク 〕
吾等戀丹穗面今夕母可天漢原石枕卷 |
七夕の前夜、一人寝の織女を思い遣る、とする |
牽牛になりてよめり、第二の句はニノホノオモワと讀べし、第九の玉名娘子をよめる歌に第十九を引て注するが如し、織女の紅顔なり、毛詩云、顔如(シ)渥丹(ヲ)、腰句の點モの字を餘せるは書生の誤なり、石枕はイハマクラと點ぜる然るべし、此は七夕より前の夜、織女の待らむ意を牽牛の思ひやるなり、
|
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、信名、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
〔わらこふる、にのほのおもは、こよひもか、あまのかはらに、いはまくらまく 〕
吾等戀丹穗面今夕母可天漢原石枕卷 |
初句の「わらこふる」は、原文の漢字をそのまま訓んだようだが、その根拠を含めても、理屈としては、間違っていないと思う
しかし、他に続く書がない
「面」は、その容姿ではなく、「妹」と同じだと解釈すべき、とする
「こよひもか」は、年に一度の今宵ということで、そのことが「今宵も」なのか、それとも「相手が待ちわびて河原で一人寝するの」ことを言うのか、解らない
|
吾等 印本等には、わがこふるとも讀ませたり。同意なれ共、等の字を書たれば、わらと訓みて、ラリル同音なれば、われ戀ふると云義と見るべし。然れば等の字虚字にならぬ也。集中吾等と二字に書きて、われとか、わがとか讀ませたる歌多し
丹穗面 織女をさして賞美して、丹のほのと讀む也。面とは面躰を云には有べからず。妹と云義と同じにて、乳おもなど共云へば、女子をさして云たる義と見る也。今宵もかと詠めるは、年に一度の今宵もか。石枕卷は、まかんの意なるべし。二星を思遣りて察して詠める歌歟。わらこふると云ふは、廣く云たる意か。さなくては彦星の歌と見る也。然らば面はと讀まんか。 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
吾等戀[ワガコフル]、
丹穗面[ニノホノオモト]、 丹穗の穗はをの如く唱ふべしこはさにつらふなどいへるに同じく艶やかに色づきいでたるかほばせをいふよし冠辭考に委し
今夕母可[コヨヒモカ]、 可は疑の辭なり
天漢原爾[アマノカハラニ]、石枕/卷[マカム]、 |
結句を推量とするのは、疑問の「か」なのだから、歌意に沿えばそうなる |
| 今本いはをいそと訓たれど既川原とあればしかよむべからねばあらたむ末の句まくとよみこせたれども歟と疑たればまかんと訓べし |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
〔わがこふる。にのほのおもわ。こよひもか。あまのがはらに。いそまくらまく。〕
吾等戀。丹穗面。今夕母可。天漢原。石枕卷。 |
結句の訓「いそ」を、即ち「石」というのは、
何故、石の意なのか、と述べていない
「石」であれば、「いし」や「いは」と訓む方が適切だと思う
|
彦星に成りて詠めり。ニノホノオモワは、卷十九、御面謂之(ヲ)美於毛和と自註有り、紅顔を言ふ。イソはここは則ち石なり。
參考 ○石枕卷(代)イハマクラ(考)石枕マカム(古、新)イソマクラマカム。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
〔アガコフル。ニノホノオモワ。コヨヒモカ。アマノガハラニ。イソマクラマカム。〕
吾等戀丹穗面今夕母可天漢原石枕卷
|
ここでの「も」の解釈は、係助詞の用法の中でも、「添加」の「~もまた」ではなく、「感動・詠嘆」の「~もまあ」としている
石枕を、略解の注と同じように、「石を枕にする」の意という
そして、年に一度の逢瀬を、一緒に過ごそう、と...その「もか」の用法だ |
丹穗面[ニノホノオモワ]は、紅顔を云、五(ノ)卷にも、爾能保奈酒意母提乃宇倍爾[ニノホナスオモテノウヘニ]、とあり、さて十九に、御面謂之/美於毛和[ミオモワト]、と註したれば、面(ノ)字ヲモワとよむこと見然[フラハ]なり、
○今夕母可コヨヒモカ]の母[モ]は、輕く添て歎息を含せたる辭なり、昨日母今日母[キノフモケフモ]などの母[モ]とは別なり、可[カ]は疑辭なり、
○石枕[イソマクラ]は、石を枕にするを云、
○歌(ノ)意は、吾(カ)一年を經[ワタ]りて戀しく思ひし紅顔の女と、天(ノ)河原に石枕を共に纏て、嗚呼今夜相宿せむかとなり、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
〔わがこふる丹穗[ニノホ]の面[オモテ]こよひもかあまのかはらに石枕卷[イソマクラマカム]〕
吾等戀丹穗面今夕母可天漢原石枕卷 |
「も」については、古義の解釈に倣う
「いそ」に「大石」の意があったとは...
|
ニノホは赤土ノニホヒなり。面を舊訓にオモハとよめるを略解古義にオモワに改めたれどオモワは顏の輪廓なればオモテとよむべし。さてニノホノオモテはやがて紅顏なり。卷五(八六一頁)にもニノホナス、オモテノウヘニ、イヅクユカ、シワカキタリシとあり
〇二三の間にソノ人トといふことを挿みてきくべし。コヨヒモカのモは助辭にてコヨヒカといはむにひとし
○石枕は舊訓の如くイソマクラとよむべし。イソは大石なり(卷九【一七三三頁】參照)。結句は古義に從ひてイソマクラマカムとよむべし |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| 我が戀ふる丹[ニ]のほの面[オモ]わ、今宵もか、天の川原に岩枕/枕[マ]く |
その「今夜」こそが、この歌の解釈の「ポイント」なのに... |
| 自分が焦れてゐる織女星の美しい顔が、今夜あたりは、私(牽牛)を待ちかねて、天の川原で、石を枕として寢ることであらう。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
| 〔無記〕 |
この歌意解釈に従えば、相手に対して、心変わりしていないか、との不安も若干感じられる
やはり、「もか」とするので、結句は「まかむ」になるはずを、「まく」と断定しているのは、その解釈を知りたいものだ
しかし、文法上は「まく」も連体形で支障はない |
ワタシノ戀シク思ツテヰル美シイ紅顔ノ織女ハ、今夜コソハ天ノ川原ニ石ヲ枕ニシテ、一年ブリデワタシト寢ルデアラウカ。アア嬉シイ。
○丹穗面[ニノホノオモワ]――ニノホは赤い色の秀でて美しいこと。面はオモワと訓むがよからう。新考にはオモテとある。卷五に爾能保奈酒意母提乃宇倍爾[ニノホナスオモテノウヘニ](八〇四)あるが、卷十九には御面謂之美於毛和(四一六九)と自註があるから、オモワでよい。
○石枕卷[イソマクラマク]――石枕は代匠記精撰本・考・新訓などに、イハマクラとよんであるのもわるくはないが、ここは舊訓によらう。この句は上にコヨヒモカとあるから、イソマクラマカムと結ぶべきところであらうが、斷定的にマクとしたのであらう。
〔評〕 第三句の今夕[コヨヒ]は何日のこととも解し得るが、七日の夕のこととして、牽牛の心になつてよんだ歌とすべきであらう。少しく感覺的の傾向がある。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
〔わが戀ふる にほへる面わ、今夕もか 天の河原に 石枕纏く。〕
ワガコフル ニホヘルオモワ コヨヒモカ アマノガハラニ イハマクラマク
吾等戀丹穗面今夕母可天漢原石枕卷 |
旧訓「にほへる」に依るのは、動詞「にほふ」の表記に「丹穂」が見あっれるからだ、という
ここでいう「強意」とは...係助詞「も」の「強意」の用法では、下に打消しの語を伴うものだ、と思っていたが...「添加」「感動・詠嘆」、そしてここに「強意」が加わった
「強意」とすると、『全釈』で述べている歌意に通じるものもある
打消しの語こそないが、その解釈は「不安」も混じる |
【譯】わたしの思つている美しい顔の子は、今夜は、天の河の河原で、石を枕に寐るであろうか。
【釋】丹穗面 ニホヘルオモワ。ニノホノオモワとも讀まれる。これは「爾能保奈須[ニノホナス] 意母提乃宇倍爾[オモテノウヘニ]」(卷五、八〇四)とあるを根據としている。しかもまた一方には、同じく人麻呂集所出の歌に「著丹穗哉[シルクニホハバヤ] 人可知[ヒトノシルベキ]」(卷七、一二九七)の如く、丹穗を動詞ニホフに當てて書いたと見られるものがあり、また丹穗日、丹穗比など、活用形を送つた例は更に多數である。よつてここもニホヘルオモワと讀むを妥當とすべきである。織女の美貌をいい、その主である織女星をいう。
今夕母可 コヨヒモカ。モは強意に添える。今夜はかである。
石枕卷 イハマクラマク。イハマクラ、石の枕。マクは、枕をする意。牽牛星と逢わないで、ひとり寐るさま。
【評語】織女が、夫を待ちわびて、天の川原で寐るだろうという意の歌で、牽牛星になつて詠んでいる。別れていて戀う心が描かれている。
|
| 『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕 |
「評釈」私見 |
〔吾が戀ふる丹のほの面今夕もか天漢原に石枕纏く〕
ワガコフル ニノホノオモワ コヨヒモカ アマノカハラニ イハマクラマク
吾等戀丹穗面今夕母可天漢原石枕卷 |
「も」は「詠歎」...それは、一年振りで、また逢えることを悦んでいうものだろう
引用歌〔1519新番号1523〕は、私は類想歌だと思う
いや、むしろ呼応する「相聞歌」のようにすら思える |
【譯】自分が戀しく思ふあの美しい顔色の織女は、今宵しも、天の河原に石を枕として、寝てゐることであらうか。
【評】天の河原に待つ織女の面影を想像しつつ、ひた急ぐ彦星の心の焦躁がよく現れてゐる。「ひさかたの天の河原に船うけて今夜か君が我がり来まさむ」(1519)とは、男女互いに立場をかへた趣である。
【語】○丹のほの面 丹の秀の面なる我が妻織女の義。「丹のほ」は赤い色の著しく美しいことで、即ち血色美しい顔。「八〇四」参照。面はオモテとも訓めるが、巻十九の長歌(四一六九)の自註に「御面謂之美於毛和」とあるに従ふ。
○今夕もか 今晩かまあの意。「も」は詠歎「か」は疑問の助詞で結句に呼応する。
【訓】○丹のほの 白文「丹穂」ニホヘルとよむ説もある。○石枕 旧訓イソマクラ。今、『代匠記精撰本』による。 |
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
〔吾が戀ふる丹の穂の面今宵もか天の川原に石枕まく〕
ワガコフル ニノホノオモワ コヨヒモカ アメノカハラニ イシマクラマク
吾等戀丹穗面今夕母可天漢原石枕卷 |
「詠歎」の「も」が、ことさら強調されているような歌意解釈だ
この歌のような情況では、「~もまあ」とする訳は適切ではないように思う
「わが」の「吾等」の表記を、用字上の「癖」にしている
『童蒙抄』のような注釈が欲しかった |
【大意】吾が戀ひ思ふ、紅の面の織女は、今夜まあ、天の川原で、石枕を枕とすることであらうか。
【語釈】ニノホノオモワ ニノホは紅の美しい色であらう。紅の美しい織女の顔を言つたのである。ニホヘルオモワとも訓まれる。
○ワガを「吾等」としたのは、吾々人間がといふ心をこめたやうにも見えるが、(二〇一四)の例の如きは単なる用字上のクセであらう。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
〔吾が戀ふる 丹のほの面わ 今宵もか 天の河原に 石枕巻く〕
ワガコフル ニノホノオモワ コヨヒモカ アマノカハラニ イシマクラマク
吾等戀丹穗面今夕母可天漢原石枕卷(『元暦校本』) |
この解釈を読むと、年に一度の逢瀬の時期が、そこまで来ている
あの人は、今ごろ私を待ちわびて、一人寝をしているのだろうか
早く行かなければ、という気持ちをこめている
だから、「こよひもか」の解釈で、『古義』などが言うような「ともに」ではなく
その「こよひ」は、まだ相手のところへ到達していない時期の「今夜」ということを
二つの解釈の引用をして、「こよひもか」の語釈を比較している
|
【口訳】私が戀ひ慕つてゐるくれなゐの面輪の人(織女)は今夜も天の河原で、河原の石を枕にして、ひとりでねてゐることであらうか。
【訓釈】丹のほの面わ―『元暦校本・類聚古集・紀州本』にニホヘルイモハ(『類』ヘをクに誤る)、『類』イモハの右に赭オモハとし、『西本願寺本』以後ニノホノオモハ(ホ以下青)とある。『代匠記』オモワと改めた。「紅(くれなゐ)の 一ニ云フ丹の穂なす 意母提乃宇倍尓(オモテノウヘニ)」(5・804)とあり、オモテとも訓めるが、「望月之 満有面輪二(タレルオモワニ)」(9・1807)ともあり、「見我保之御面(ミガホシミオモワ)」に「御面謂之美於毛和(ミオモワ)」(19・4169)と自注してゐるところを見ると「面」をオモワと訓んだ方がよいであらう。織女を紅の美しい面輪と云つた。
石枕巻く―旧訓イソマクラマクとあり、『代匠記』に「別校本云、イハマクラ」とあり、「イハマウラ點ゼル然ルベシ」といひ、『万葉考』にも「今本いはをいそと訓たれど既に川原とあればしかよむべからねばあらたむ」とある。その意味は「石」をイソと訓むこと前(3・359)にも述べたが「磯」の義をもつたもので、次の作に「荒磯巻而寐(アリソマキテネム)」とある場合はイソでよいが、既に「河原」とあるからまた「磯」とあつては重複するといふのである。それならばイハがよいかといふに「高山の磐根四巻手(イハネシマキテ)」(2・86)、「鴨山の磐根之巻有(イハネシマケル)」(2・223)などイハを枕にする事もあるが、それは山の岩であつて、河原に対してはむしろ「魚釣らすとみ立たしせりし伊志遠多礼美吉(イシヲタレミキ)」(5・869)、「安蘇の河原よ伊之布麻受(イシフマズ)」(14・3425)などとあるやうにイシと訓む方が自然ではなからうか。「木枕(コマクラ)」(2・216)、「「草枕」(1・5)、「手枕(タマクラ)」(2・217)、「薦枕」(7・1414)などと共に、私注にイシナクラと訓まれたのに従ひたく思ふのである。なほ『考』に「まくとよみこせたれども歟と疑たればまかんと訓べし」とあるが、マカムと訓むと単独母音節のない八音になつて字余例の例外になるから、『全釈』に「マカムと結ぶべきところであらうが、断定的にマクとしたのであらう」とあるやうに、マクと訓んでよい。
【考】『代匠記』に「此ハ七夕ヨリ前ノ夜、織女ノ待ラム意ヲ牽牛ノ思ヒヤルナリ」いひ、『童蒙抄』には「今宵もかと詠めるは、年に一度の今宵もか。石枕巻くは、まかん、の意なるべし」と云つた。その後の諸注を見るに、前説によるもの甚だ少なく、後説が多く行はれてゐる。たとへば佐佐木博士は「天の河原に待つ織女の面影を想像しつつ、ひた急ぐ彦星の心の焦燥がよく現れてゐる」といひ、
ひさかたの天の川瀬に船泛けて今夜か君が我許(わがり)来まさむ (8・1519)
をあげ、「男女互に立場をかへた趣である」と云はれてゐる。七夕の歌に「こよひ」とある場合はこの先にも(2037、2040、2049、2060、2073、2079、2080)などいづれも七日の夜の事をさしてゐるが、今の場合「丹の穂の面わ」といひ、「天の河原に石枕巻く」あるのを、「わたしと共に」といふやうな言葉を入れて解くべきであらうか。右に引用された作は「君が我許」とあつて、君を待つ吾がはつきり示されてゐるが、ここは「丹の穂の面わ」がただ「石枕巻く」とだけあるのである。第一、二星が石を枕にする事があらうとも、これを「石枕巻く」といふであらうか。また「まかむ」ではなく「まく」である事も今巻いてゐると見るべきではないか。即ちこの「こよひもか」は、
稲つけばかがる吾が手を許余比手可(コヨヒモカ)殿の若子がとりて歎かむ (14・3459)
の「今夜」ではなくて、
あしひきの山のもみち葉今夜毛加(コヨヒモカ)浮びゆくらむ山川の瀬に (8・1587)
ぬば玉の妹が黒髪今夜毛加(コヨヒモカ)吾が無き床に靡きて宿(ね)らむ (11・2564)
の「今夜」である。二星が逢ふ七日の「今夜」ではなくして、織女がひとりでねてゐる「今夜」であり、「巻く」の下に助動詞を加へるならば、「む」でなくて「らむ」であるべきである。
赤人集に「わがこひにほひあひてみむはこよひわがあまのつはしのいはかしまつと本」とあり、流布本「ほにあけてみむ」「いまはこしまと」とある。
|
|
|

| |
| 「きみまちかてに」...ありそまきてねむ... |
| |
| 『かはもにかくれ』 |
| 【歌意2008】 |
わが夫に、なかなか逢うことのできないあの子は、
夫の舟が入って来るはずの湊に佇み、
今夜こそは、と思いながら
荒磯を枕に寝ることであろう
夫の舟が、やがてこの船着き場にやって来るのを、待ちかねて... |
| |
| |
「七夕歌」とは、厄介なものだ
物語が生れたのは、たった一つの「伝承」なのに、
それを題材にして、どれほどの歌が詠われているのだろう
そうした伝承は、ところも、ときも変わると、次第に元の物語から遠ざかるものだ
私は、最近接するようになった「七夕歌」を読み進めているうちに
いろんな展開がある中で、一つだけ変わらないものがある、と知った
それは、「年に一度の逢瀬」という、
これこそ「七夕歌」としての、部立ての基本になるのでは、と思うことだ
極端に言えば、それ以外の要素は、「彦星」も「織女」も下手に固有名詞を使わず
「男女間」の「相聞歌」として感じることが、
その歌の「歌意」を素直に感じられる、と思えるようになった
この掲題歌、詠い手が、彦星、織女、第三者、などと
様々な諸説が古来より多くあるが、それは「助詞」の扱い方だけではなく
「七夕伝説」という、どうしてもその「呪縛」を解放つ意識がないことで
自ら、混乱を招いているような気もする
「ともしむ」、あるいは「ともし」という語を用いることで、
そこには「七夕伝説」を、モチーフにした条件はクリアされており
その「滅多に逢うことのない」二人の「想い」を、いかに歌で表現するか、
その視点で、読めたら、と思う
「年に一度」に限らず、何年も逢うことの叶わない二人は、
決められた「とき」に、約束された「逢瀬」が出来る
それが、間もなくやって来る
その背景の中で、この歌で詠われる「想い」というのは、
まだ「約束の日」ではないのに、やがてやって来る「夫」を待つに耐えかねて
まだ早い「船着き場」に足を運び、「まだ見えぬ船」を待つ
「きみまちかねて」という表現は、普通の「相聞歌」では有り触れた語句だと思うが
「七夕伝説」をモチーフにしているからこそ、
まだ「その日」でもないのに、「いてもたってもおられず」という「深く切ない」気持ちになる
(天の)河原の「荒磯」という表現には、疑問もあるが、
それも、「七夕伝説」を背景に詠ったことで、そう思われてしまうだろう
しかし、「七夕伝説」でなければ、この歌の舞台は、「海の岸辺」と、
すんなり訳せられていたと思う
だから、ここにも、「年に一度の逢瀬」...「なかなか逢うことのできない二人」を表現している
「約束の日」ではなくても、一日でも早く逢いたいと思う気持ちを、
「河原に寝てまでも待っている」...その想いを詠ったものであれば、
幾つかの諸注で、「第三者」が詠ったもの、と解するのは、
その「気持ち」を汲んでいない、と思う
当事者、勿論「待つ女」の詠ったものだと思う
それにしても不思議に思う
この歌、「柿本人麻呂歌集」出とあるが
「私家集大成」でも「国歌大観」でも、その「柿本人麻呂歌集」に、
この歌を見つけられなかった
現存の伝本以外に、「柿本人麻呂歌集」というものが、存在していたということだろうか
|

|
掲載日:2014.05.07.
| |
| 秋雑歌 七夕 |
| 己□ 乏子等者 竟津 荒礒巻而寐 君待難 [□女偏に麗] |
| 己夫にともしき子らは泊てむ津の荒礒巻きて寝む君待ちかてに |
| おのづまに ともしきこらは はてむつの ありそまきてねむ きみまちかてに |
| 巻第十 2008 秋雑歌 七夕 柿本人麻呂歌集出 |
[収載歌集]
【赤人集】〔168・156・277〕
[資料]
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
【七夕】〔中華民国[国立成功大学、成大宗教與文化学報 第七期 論文]〕
【織女と牽牛】〔講談社学術文庫「星の神話・伝説」野尻抱影〕
| 【2008】 語義 意味・活用・接続 |
| おのづまに [己□] [□女偏に麗] |
| ともしきこらは [乏子等者] |
| ともしき [乏し] |
[形シク・連体形] 少ない・貧しい・(珍しいために)飽きない・うらやましい |
| こ [子・児] |
(親に対して)子ども・幼子・人を親しんで呼ぶ語(男から愛する女にが多い) |
| ら [等] |
[接尾語] (名詞・代名詞について) 複数・親しみの気持ちなどを表す |
| はてむつの [竟津] |
| はて [泊(は)つ] |
[自タ下二・未然形] 船が港に着いて泊る・停泊する |
| む [助動詞・む] |
[推量・連体形] ~だろう |
未然形につく |
| つ [津] |
船の停泊所・船着き場・渡し場・港 |
| ありそまきてねむ [荒礒巻而寐] |
| ありそ [荒磯] |
[「あらいそ」の転] 岩の多い、荒波の寄せる海岸 |
| まき [枕(ま)く] |
[他カ四・連用形] 枕とする・枕にして寝る・一緒に寝る・結婚する |
| て [接続助詞] |
[補足(行われ方)] ~て・~ようにして |
連用形につく |
| ね [寝(ぬ)] |
[自ナ下二・未然形] 眠る・寝る・横になる・また、場面や文脈によって、男女が共寝する意にもなる |
| む [助動詞・む] |
[推量・連体形] ~だろう |
未然形につく |
| きみまちかてに [君待難] |
| かてに(がてに) |
~できなくて・~しかねて |
連用形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [おのづまに] |
この「訓」で、「自分の夫」と解釈している現代の注釈書は多い、しかし
『拾穂抄・童蒙抄 おのがつま』、『略解 しがつまの』、『全註釈 おのがつま』そして、
『新考 おのづまを』は、初二句を「妻」もしくは「妻の立場」とする
『万葉考 おのがつま われまちかねて』『口訳 おのづまの われまちがてに』に至っては、
その流れから、結句の「君」を「吾(我)」に改めてさえいる
現訓「おのづまに」では、自然と織女が「夫(つま)」を待つ歌意に沿うことになるが
従来は、以上のような「訓」でも、「つま」を、「織女」としていたようだ
|
| |
| [ともしき] |
形容詞シク活用「乏し」の連体形、
この語も、〔2006〕で「ともしづま」として使われている
そのときは、名詞「つま」にかかりながらも、終止形の使い方だったのが
この掲題歌では、文法上のルールーに沿って、連体形「ともしき」として
名詞「子ら」を修飾している
ここで新たに知ったのが、四段動詞「ともしむ(乏しむ)」だ、
その連体形で訓めば、「ともしむこらは」となり、
それは、本居宣長の説のようだが、『略解』で、それに触れ、
さらに、『古義』では、それに基づいて改訓している、他に、
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕、
『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕、
『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕、
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕など、近年の注釈書は続くが、
現代の「万葉集の叢書」としては、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕が唯一倣っており、
他はすべて「ともしき」とする
尚、四段動詞「ともしむ」は、
上二段動詞「ともしぶ」と同義であり、その語義は、「羨ましく思う・珍しく思う」とある
「ともしづま」の場合と違って、「ともしきこら」とするのは、
決して「なやましい」訓というわけではないが、
旧訓「ともしき」から近年になって「ともしむ」が定着し、
さらに現代では「ともしき」と、旧訓に戻る...
それほど、時代に影響される、ということなのだろうか...
下段資料の『注釈』の「訓釈」に、
|
| 略解に宣長の説としてトモシムコラハとあり、新考それによりオノヅマヲと改めた。新校にはオノヅマニトモシキとした。「ともしむ」にしても「ともしき」にしても、その「ともし」は、前の「ともし妻」(二〇〇二)やこの先の「乏しむべしや」(二〇一七)などの「ともし」と同じく、逢ふ事稀で心惹かれる意である。 |
とあるように、動詞「ともしむ」でも形容詞「ともし」でも、
歌意にすれば、同じだということなのだろう
|
| |
| [はてむつの] |
旧訓は「あらそひつ」、そして何とか工夫を凝らして訓もうとするのが、
契沖『代匠記』では、「船竟津」と、「船」が脱落しており「フネハテツ」
真淵『万葉考』は、旧訓では歌意にならない、とし
「竟」の漢字を「立」と「見」に分け「タチテミツ」と訓む
そして、歌意を満足させるためなのか、結句の「君」を「吾」に改めている
『略解』の千蔭は、真淵説に沿いながらも、宣長の「訓、ハツルツノ」に賛同しているようだ
現訓の「はてむつの」を提唱したのは、
『万葉集古義』の鹿持雅澄になる
|
| |
| [ありそまきてねむ] |
「ありそ」は「あらいそ」の転じた訓なので、
古くは「あらいそ」と訓んだとする古注釈もあるが、
その結句を含めたこ訓に、理解出来ないものがある
北村季吟『拾穂抄』、契沖『代匠記』に「あらいそまきて ねまくまちかね」
「寐」を結句につけて「寐君待難ネマクマチケネ」とするが、
確かに語意としては理解出来ても、訓釈において、無理があるようだ
ただし、契沖は、後の訓に影響を及ぼす「アリソマキテネム」の可能性も言っている
現在、「ありそまきてぬ」と七音で訓む書と、
「ありそまきてねむ」と、字余りながらも訓む書が併用されている
「ありそまきてぬ」の「ぬ」は、寝る意の下二段「寝(ぬ)」の終止形
その訓を採っている書は、
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕、
『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕、
『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕、
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕、
そして、現代の注釈においては、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波文庫校訂版、平成25年~〕、
ただし、岩波文庫本では、「ありそまきてねむ」説も紹介している
「ありそまきてねむ」は、字余りではあるが、「寝」に推量の助動詞「む」がつき
歌意としては、私は必然だと思う
この訓を採っている書は、
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕、
『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕、
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕、
『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕、
『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕、
『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕、
『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕、
そして、現代における「注釈書」としては、
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕、
『万葉集校注』〔伊藤博、角川文庫、平成13年23版〕、
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕
小学館の
『完訳日本の古典 万葉集』〔小学館、昭和59年初版〕、
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕では、
「ありそまきていぬ」と訓む
この「いぬ」は、そこでは説明はないが、私の拙い解釈では、
名詞「寝(い)」と、下二段「(ぬ)」とが複合した、とされる、
自動詞ナ行下二段「寝(い)ぬ」だろう
その語義は、寝る、眠る
名詞「寝(い)」については、古語辞典の説明によると、
単独で用いられることはなく、助詞を介して動詞「寝(ぬ)」につく、とある
その助詞が付かなくて「複合動詞」になったのではないか、と思う
しかし、いづれにしても、「終止形」で終る歌意ではないはずだ |
| |
| [かてに(がてに)] |
その「なりたち」は、
「できる・耐える」意の上代の下二段補助動詞「かつ」の未然形「かて」に、
打消の助動詞「ず」の上代の連用形「に」がついたもの
本来は、「かてに」と清音で読むが、
次第に形容詞「難(かた)し」の語幹に、格助詞「に」の付いた意と混同され、
読み方も「がてに」と濁音化した |
|
| |
|
|
| 掲題歌[2008]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
[収載歌集]
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
|
| おのかいもなしとはきゝつわれいてこ 待てねよ君まつにとめたし |
新編私家集大成第一巻-新編増補 赤人集Ⅲ[陽明文庫蔵三十六人集]あきのさう 168
|
| をのかいもなしとはきゝつてにまきて またきゝてねよきみまさにとなし |
同第一巻-6 赤人集Ⅱ[書陵部蔵三十六人集] 秋雑歌 156
|
| おのかいもなしとはきゝつてにまきて またきてねよきみさまにとかなし(本) |
同第一巻-5 赤人集Ⅰあかひと[西本願寺蔵三十六人集] あきのさふのうた 277
|
| おのがいもなしとはききつてにまきてまたきてねよきみさまにとかなし |
新編国歌大観第三巻-2 赤人集[西本願寺蔵三十六人集] あきのざふのうた 277
|
|
[織女と牛(伝説)] 講談社学術文庫「星の神話・伝説」野尻抱影
|
織女は、こと座のベーガ、牽牛は、わし座のアルタイルの中国名ですが、この二つの一等星が、天の川を隔てて瞬き合うさまは、正に一対の夫婦星で、世界にもまれな七夕伝説が中国に生まれたのも、自然に思われます。
織女は天帝の娘で、天の川の東の岸に住み、父のいいつけで明けても暮れても「機」を織っていました。その布は雲錦といって、五色にてり輝き、眩しいほど美しいものでしたが、織女はそれを織るので、髪を結う暇もなく、化粧をすることも忘れてしまいました。
やがて天帝も娘を不憫に思って、天の川の西に住む牽牛という若者とめあわせました。すると、織女は新しい生活の愉しさに、はた織りをなまけて、化粧にばかり身をやつすようになりました。それで天帝は腹を立てて、織女を再び東の岸へ連れ戻し、一年に一度、七月七日の夜だけ、天の川を渡って、夫に会うことを許してやりました。
こうしてその日に雨が降ると、天の川の水かさが増すために、織女は川を渡ることができないので、目のいい人には雲を通して、二つの星が天の川の両岸で、哀しげに五色に煌くのが見えるといいます。
その夜、カササギが、天の川の中に翼をならべて橋となり、織女を渡してやるというので、日本でも、これを『かささぎの橋』といって歌に詠みました。
中国では唐の時代から七月七日の夕べを七夕(しちせき)といって、織女牽牛を祭り、女たちが、針仕事や、琴や、文字などが上手になるように祈りました。
この伝説と祭りとが、遣唐使や留学生によって日本へ伝わり、織女には、はた織りの女神の名をあててタナバタ(棚機)とよび、牽牛は、男の星の意味でヒコボシ(彦星)とよび、また、オリヒメ、ウシカイボシともいいました。そして七夕と書いて、『タナバタ』と読むようになりました。 |
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「已孋乏子等者竟津荒礒卷而寐君待難」
「オノカツマ トモシキコラハ アラソヒツ アライソマキテ 子マクマチカネ」(「【】」は編集、歌番は旧) |
〔本文〕頭注に、『元暦校本』別行平仮字ノ訓ナシ。余白アリ。漢字ノ右ニ赭片仮字ノ訓アリ、コレニテ校ス。『類聚古集』訓ヲ附セズ。『西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本』訓ノ肩ニ朱ノ合点アリ。但『京』 赭ニテコレヲ止メタリ。
赤人集「おのかいもなしとはきゝつてにまきて またきてねよきみさまにとかなし(本)」 |
| 「乏」 |
『類聚古集』「之」。墨ニテ消セリ。右ニ墨「乏」アリ |
| 「寐」 |
『京都大学本』「寝」 |
| 〔訓〕 |
| オノカツマ |
『元暦校本・神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本』「ヲノカツマ」
|
| アラソヒツ |
『元暦校本・神田本』ナシ
『西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本』五字朱。『矢』漢字ノ左ニ「ワタリシツ」アリ。
|
| 子マクマチカ子 |
『京都大学本』漢字ノ左ニ赭「ヌルキミマタナ」アリ
|
| 〔諸説〕 |
| ○[オノカツマ]『代匠記精撰本』「オノツマノ」『童蒙抄』「ナカヲトメ」又ハ「ナカツマ」○[トモシキコラハ]『略、宣長』「トモシミコラハ」○[竟津アラソヒツ]『代匠記初稿本』「竟」ノ上「舟」脱カトシ訓「フ子ハテツ」トス。『童蒙抄』「アラソツノ」。『万葉考』「竟」ハ「立見」ノ誤。訓「タチテミツ」。『略解、宣長』「ハツルツノ」『古義』「ハテムツノ」 |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [2008] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
〔をのかつまともしきこらはあらそひつあらいそまきてねまくまちかね 〕
己□[人偏+麗]乏子等者競(イきほひつ)津荒礒卷而寐君待難
|
おそらく、原文「竟」を、「あらそひ」と訓むことで「競」の意と解釈しているので、表記にも、それが反映されたのだろう
一刻も早く逢いたい、と心を急かせる気持ちの表現なのだろうが、
その「あらそひまつ」のは「妻」のことであり、
従って「をのかつま ともしきこら」は「妻」となる |
| わをのかつまともしきこらは あらそひつとはあふせを早くと心に爭ひまつ也或はきほひつゝと和す同義也つまにあふ事のともしき子らはきほひつゝ天河のあらいそをまくらにまきてねまく事をまちかねてと也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
〔オノカツマトモシキコラハアラソヒツアライソマキテネマクマチカネ 〕
已□[女偏+麗]乏子等者竟津荒礒卷而寐君待難 |
この歌意解釈は、妻(織女)が夫(牽牛)の船を、天の河原で待ち詫びていると、やっと船が停泊したものの、宿に帰るの時間も惜しんで、荒磯を枕にして、共に寝ましょう、としているようだ
ここで、下二句の改訓の可能性も言っている |
發句は以前注せし如くオノツマノと讀べし、織女に成て牽牛を指なり、子と云も牽牛なり、乏已□[女偏+麗]子等者[コラハ]と云意なり、竟津は今按船竟津にてフネハテツなりけむ船の落たるにや、若は津[ツ]は竟[ハテ]つと讀て竟ると云用の詞に体の舟を、持たせたる歟、下句の點もおぼつかなし、アリソマキテネムキミマチカテニと讀べきか、意は天川原に立出て待に侘はつる比やうやう舟を泊つれば宿へ歸る間も遲し、唯此荒礒を枕として諸共に臥さむとなり、
|
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、信名、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
〔おのがつまともしきこらはあらそつのあらそまきてぬせこをまたなん 〕
己□[女偏+麗]乏子等者竟津荒磯卷而寢君待難 |
宗師案として、ある本には「竟」を「競」とあることを言う
それが旧訓「あらそひ」の根拠なのかもしれない
初句を「汝が女(ながをとめ)」として訓釈できるならば「長少女(ながをとめ)」は、七夕では天女なので、神代の昔より伝わる不絶夫婦の語らいある女、という意に擬えば、「ながつま」という語義にも通じるのでは、という
歌意解釈は、なかなか複雑で、私にはきちんと理解出来ない
ただ、作者の立場を「織女」としている
初句は自身のことをいい、第二句は夫牽牛との、滅多に逢うことのない逢瀬をいう
結句は、それゆえに「きみ」ではなく「せこ」と訓み直している
しかし、どのようにも解釈は可能だ、として後世にその役目を望んでいるようだ
|
此歌も色々見樣ある歌也。尤印本諸抄の通の假名附けにては、歌にても連歌にても無き讀み樣也。宗師案は竟の字一本に競の字也。正本なるべし。よりて左の如く讀み解也
おのがつまともしきこらはあらそつのあらそまきてぬせこをまたなん
おのが妻とは、彦星の織女をさして、打つけにわが妻と云義也。ともしきは賞して也。
あらそ津は、荒磯の津に、荒き石を枕として寢ん彦星を、今宵も/\と待つらんと云意也
己□[女偏+麗]此をながをとめとも讀みて、織女の通稱に云へるか共見ゆる也。ながをとめは、長少女にて、七夕は天女なれば、神代の昔より今に不絶夫婦の語らひある女子なるから、通稱に云ひて汝が女と云意によせて、ながをとめとか、なが妻とか讀む義もあらんか。次下の歌にも、天地等別れし時より共有。自の津に、荒き石を枕として寢ん彦星を、今宵も/\と待つらんと云意也己□[女偏+麗]、ながをとめと義訓に讀まるべき也。日本紀によの長人と云古語有。武内大臣を賞し給ふ御言葉也。なれば天地開けし時より今に不絶七夕つめなれば、斯くよめる意も計り難し。次の歌の意別而長女と讀めば、歌の意も聞ゆる也
愚案、此歌は織女の歌にして見るべきか。然らば君待難を、せこまちがたにと讀みて、背子を待ち兼ねての意に見るべしや。まちがてとは、かねてと云義に毎度よむ詞也。然らば上のおのが妻乏しきとは、夫の乏しきからと云ふ意にて、彦星に逢ふ事の珍しく乏しき我等は、あらそつの荒き磯に出て石を枕として、君を待ち兼ねてぬると詠める意にも見ゆる也。荒磯をまきてぬる脊子を待たんと云意少し心得難し。荒磯をも卷きて、背子を待つと云意は、聞安からんか。然ればおのがつめ乏しき子らとよめる意兩義也。夫にともしき我と云ふ、自身を云ふ意、我妻の乏しき女と云意との違ひ、又下の寢の字の見樣、我夫を待ち兼ねてぬると云意と、荒磯にぬる夫を待たんと云意との差別有。後賢の人可辨也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
己□[女+麗][オノガツマ]、
乏子等[トモシキコラハ]、
立見津[タチテミツ]、
荒磯卷而寐アリソマキテネム]、
吾/待難[マチカテニ]、 |
この解釈の特筆は、「竟」を「立見」の二字に分けていることだ
旧訓の「あらそひつ」では、織女が誰と共寝を「争う」のか、というが
「共寝」を、あらそう、と解しているので、そうなるのかな
歌意では、牽牛が逢瀬の夜を心待ちにしているように、織女も私を待っているだろう、
「待ちかねて、立って見ながら」荒磯を枕に寝ることだろう...「らん」は現在推量だろうが... |
| 今本此歌字も訓もいと誤れり三の句一本競今本竟とありてともにあらそひつと訓たれど織女の誰とともねをあらそはんよしもなく歌の意もとほらねば竟は立見の二字の一字となれりとす末の句の訓も誤れりよりて改む歌の意は彦星の逢夜をまつ心からともしづまも吾をまちがてに立見つゝありそをまくらとしてぬるならんとなり今本吾を君に誤れるならんと黒生か云へるによるべし たれども歟と疑たればまかんと訓べし |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
〔しがつまの。ともしきこらは。たちてみつ。ありそまきてねむ。きみまちがてに。〕
己孋。乏子等者。竟[竟ハ立見ノ誤カ]津。荒磯卷而寢。君待難。 |
真淵説をかなり採り入れているが、宣長の説にも魅力を感じている様子だ
その「ハツルツノ」は、少なくとも「あらそひつの」よりは、「船」という客観的な事象が対象なので、その方が理解し易い
|
一二の句は織女を指す。竟津、アラソヒツと訓みたれど由無し。竟は立見二字の一字に成れるにて、天の河原に立たぬ日は無しと言ふ意なるべしと、翁言はれき。宣長云、竟津、ハツルツノと訓むべし。さて一二の句はオノガツマ、トモシムコラハと訓み、四の句アリソマキテヌと訓むべしと言へり。猶考ふべし。
參考 ○己孋(代)オノヅマノ(考、古)オノガツマ(新)オノヅマヲ ○乏子等者(考)略に同じ(古、新)トモシムコラハ ○竟津(代)フネハテツ(考)略に同じ(古、新)ハテムツノ ○荒礒卷而寐(代、考、新)略に同じ(古)アリソマキテヌ。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
〔オノガツマ。トモシムコラハ。ハテムツノ。アリソマキテヌ。キミマチカテニ。〕
己孋乏子等者竟津荒礒卷而寐君待難
|
訓にも、不自然さがなくなり、この辺りから、この歌の「心持ち」が見え始めてきたように思える
「はてむつの」は、この雅澄から訓まれているが、その元になったのは、
きっと宣長の「はつるつの」だろう |
己孋(孋(ノ)字、拾穗本には儷と作り、)は、オノガツマと訓べし、岡部氏、孋一本に孃とあり、何れにてもあるべしと云り、さて孋は借字にて、彦星を己夫[オノガツマ]の云ならむ、
○乏子等者は、トモシムコラハと訓べし、さて乏子等[トモシムコラ]とは、己が夫の彦星に逢(フ)ことを、稀に乏しめる子等と云にて、その子等は棚機女なり、
○竟津は、ハテムツノと訓べし、竟津[ハテムツ]とは、彦星の舟の將[ム]竟[ハテ]天(ノ)河の津と云なるべし、
○歌(ノ)意は、夫(ノ)君を待に堪難にして、その夫(ノ)君の彦星の將竟津の、荒磯をやがて枕にして、棚機女の宿(ル)と云るにや、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
〔オノヅマノ トモシムコラハ ハテムツノ アリソマキテネム キミマチカテニ〕
己□[女+麗]乏子等者竟津荒磯卷而寐君待難 |
第二句を「ともしむ」と言わなければ、歌にならない、ということか
それで、「ともしむ」と訓むなら、初句を「おのづまの」に訓むべきだ、というのか
宣長は「おのがづま」「ともしむこらは」とあり、それも悪くない、と
しかし「おのがづま」と「おのづまの」どちらであっても、
その初二句では、牽牛が織女のことを言っている
そうなると、作者は牽牛の立場で詠っていることになり、
結句に「君待ちかねて」と、今度は織女の気持ちになって詠う
結句が「織女」であれば、やはり初二句も「織女」が詠う立場として「夫(つま)」になるのか...は、第二句の解釈が変わってくると思うが...
牽牛が、織女の想いを感じて、詠った歌なのだろうか
|
初二を舊訓にオノガツマトモシキコラハとよみたれどトモシムといはでは語脉とほらず。略解にはシガツマノトモシキコラハとよみたれど己をシガとよむべからざる事は卷九(一七四七頁)にいへる如し。宜しくオノヅマヲトモシムコラハとよむべし。宣長はオノガツマトモシムコラハとよめり。それもあしからず。トモシムはユカシガルにてやがて戀ふるなり。子ラは織女を指せり
○第三句を舊訓にアラソヒツとよみ眞淵が立見津の誤としてタチテミツとよめる共に由なし。宣長はハツル津ノとよめり。更に一歩を進めて古義の如くハテム津ノとよむべし。君ガ舟ノ泊テム津ノとなり。終の意なる竟[ハテ]を泊[ハテ]に借れるなり。卷七(一二八三頁)にも大御舟竟而サモラフとあり又上(二〇一八頁)にも竟[ハテシ]舟人妹ト見エキヤとあり
○第四句を宣長がアリソマキテヌとよみ雅澄が之に從へるはわろし。略解の如くアリソマキテネムとよむべし
○マチガテニは待敢ヘズにて即待兼ネテなり。君といへるは牽牛なり。此歌は第三者としてよめるなり。織女になりてよめるにあらず |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| 己[オノ]妻のともしき子等は、はてし津の荒磯[アリソ]枕[マ]きて寢[ヌ]。我待ちがてに |
真淵と同様に、初句を「織女」とすれば、結句は「われ」にせざるを得ないだろう |
| 自分の妻に逢ふこと稀々な懷しいいとしい人、即あの織女星は、今夜舟の著いた川口の荒い石濱を枕として、寢てゐることだらう。この私(牽牛)を待ちかねて。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
〔おのが夫 乏しむ子らは 泊てむ津の 荒磯まきて寝む 君待ちがてに〕
オノガツマ トモシムコラハ ハテムツノ アリソマキテネム キミマチガテニ
己孋乏子等者竟津荒礒卷而寐君待難 |
初句「私の夫、牽牛」、第二句「ともしむこら」の「こら」は「織女」、と
「評」にもあるように、確かにこの歌の訓には、一貫性がなく
詠み手の立場に振り回されてしまう
結句の「きみまちがてに」であれば、「きみ」と言うからには、織女が夫のことを待ちわびて詠ったであろうが、自らを「ともしむこら」となれば、それも不自然であり、この書のように、第三者が織女の気持ちを詠ったとするのも、頷ける |
自分ノ夫ヲナツカシガル織女トイフ女ハ、夫ノ彦星ヲ待チカネテ、ソノ舟ガ着ク天ノ川ノ船着場ノ荒磯ヲ枕トシテ寢ルデアラウ。
○己孋[オノガツマ]――舊訓による。略解にシガツマノとあるのはよくない。孋の字を用ゐてあるが、夫の彦星のことである。
○乏子等者[トモシムコラハ]――舊訓トモシキコラハとあるが、略解の宣長説による。ともしむはなつかしむこと。子等は織女を指す。
○竟津[ハテムツノ]――舊訓アラソヒツとある。代匠記初稿本、竟の上、舟の字脱として、フネハテツとよんでゐる。考には竟を立見の二字として、タチテミツとよんでゐる。略解の宣長説はハツルツノとしてゐるのもよいが、古義にハテムツノとあるのに從はう。
○荒礒卷而寐[アリソマキテネム]――略解に從つた。古義にはアリソマキテヌとある。これは宣長説によつたのである。
〔評〕 古來訓法が統一せられないで、意味もいろいろに解せられる。併し、右のやうに訓めばあまり無理もないやうだ。第三者が織女の有樣を想像したものである。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
〔おのが孋 ともしき子らは、泊てむ津の 荒礒枕きて寐む。君待ちがてに。〕
オノガツマ トモシムコラハ ハテムツノ アリソマキテネム キミマチガテニ
己孋乏子等者竟津荒礒卷而寐君待難 |
結句は、「夫である私を待ちかねて」と訳さなければ、文章に無理がある
だから、真淵などは「吾」に改訓さえした
「評語」に、この歌の訓の難しさが滲み出ている |
【譯】わたしの妻である逢うことの稀なあの子は、この船の行く先の船つき場で、荒礒を枕にして寐るだろう。夫を待ちかねて。
【釋】己孋 オノガツマ。自分の妻。嬬の字を使用しているので、やはり織女星のことと解すべきである。
乏子等者 トモシキコラハ。トモシムコラハ(略、宣長)。トモシキコラは、二〇〇二のトモシヅマに同じ。逢うことのまれな妻。
竟津 ハテムツノ。
アラソヒツ(西) アラソツノ(童) ハツルツノ(略、宣長) ハテムツノ(古義) 舟竟津[フネハテツ](代初) 立見津[タチテミツ](考)
牽牛の船の泊てむ津のであろう。
君待難 キミマチガテニ。キミは、自分すなわち牽牛を、織女の立場から云つている。
【評語】牽牛に代つて、織女の有樣を想像して詠んでいるが、五句の、君待チガテニの句には混雜が感じられる。但し訓法にもなお問題があり、まだ正しく讀まれていないのだろう。
|
| 『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕 |
「評釈」私見 |
〔己が夫乏しむ子等は泊てむ津の荒礒枕きて寐む君待ちがてに〕
オノガツマ トモシムコラハ ハテムツノ アリソマキテネム キミマチガテニ
己孋乏子等者竟津荒礒卷而寐君待難 |
第三者の視点で、詠われたとする
確かに『全釈』でもいうように、そう訓まなければ、訳すことに多くの説明文が必要となってしまう |
【譯】夫の彦星を懐かしがつてゐるあの織女は、夫の舟が着く天の河の船着場の荒磯を枕にして、寝ることであらう。その懐かしい夫を待ちかねて。
【評】彦星を待ち焦がれる織女星に同情を寄せた歌であるが、修辞が稚拙佶屈で、趣致に乏しい作である。
【語】○己が夫 自分のをつと、彦星のこと。○乏しむ子等 「ともしむ」は愛しなつかしむ意。「子等」は織女をさす。「ら」は口調の為の接尾辞、複数ではない。○泊てむ津の 彦星の船が着く筈の天の河の船着場の意。
【訓】○己が夫乏しむ 白文「己孋乏」。オノヅマニトモシム、又トモシキとよむ説もある。○泊てむ津 白文「竟津」で、代匠記は「竟」の上に「舟」の脱と見、万葉考は「竟」を「立見」の誤としてゐる。旧訓アラソヒツでは意を成さず、代匠記及び考は脱字説により、フネハテツ、タチテミツなど訓んだが、このまま古義の如くハテムツニと訓むのがよい。 |
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
〔己が夫ともしむ子等は泊てむ津の荒礒枕きて寐む君待ちがてに〕
オノガツマ トモシムコラハ ハテムツノ アリソマキテネム キミマチガテニ
己孋乏子等者竟津荒礒卷而寐君待難 |
「全体がうるさい想像といへばいへる」とは、「七夕伝説」をモチーフにする以上、それは当然だと思う。すべてが「想像」の「感情」であり、「年に一度の逢瀬」を、どんな風に料理するか、それを競う歌なのだから... |
【大意】己が夫を稀に会ふものと珍しみ思ふ織女は、船の着くべき港の、荒い磯を枕として寝るであらう。君、牽牛を待ち切れないで。吾
【作意】これも第三者としての歌である。オノガツマを妻として、織女に当てるのはやはり無理であらう。尤も全体がうるさい想像といへばいへる。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
〔己夫を 乏しむ子らは 泊てむ津の 荒礒巻きて寝 君待ちかてに〕
オノヅマヲ トモシムコラハ ハテムツノ アリソマキテヌ キミマチカテニ
己孋乏子等者竟津荒礒卷而寐君待難(『元暦校本』) |
字余例、というのが私の勉強不足で、よく理解出来ていない
当然、何でもかんでも「字余り」を認めるよりは、出来るだけ「語調」は守った方がいいに決まっているのだが、「訓」を「語調」に拘り過ぎると、解釈に影響も有り得るだろう
もっとも、その中から、和歌らしい「語」というものもあることは間違いない
|
【口訳】自分の夫にめつたに逢へずに戀しがつてゐる織女は、夫の船の着く港の荒磯を枕にしてねてゐることであらう。君を待ちかねて。
【訓釈】己夫を乏しむ子らは―「孋」は「嬬」(1・13)と同様、夫の意味にも用ゐる。この作、『元暦校本』に訓二行分余白あり、漢字に赭片カナの訓あり、『類聚古集』も訓が無い。『元・紀州本・西本願寺本』その他ヲノカツマトモシキコラハとあり、略解に宣長の説としてトモシムコラハとあり、新考それによりオノヅマヲと改めた。新校にはオノヅマニトモシキとした。「ともしむ」にしても「ともしき」にしても、その「ともし」は、前の「ともし妻」(二〇〇二)やこの先の「乏しむべしや」(二〇一七)などの「ともし」と同じく、逢ふ事稀で心惹かれる意である。
泊てむ津の―『元・紀・』訓なく、『西(赭)』アラソヒツ、『京都大学本』(左ニ―校本に「赭」とあるは誤)ワタリシツとあり、略解に宣長説としてハツルツノとし、古義にハテムツノとしたのがよい。彦星の舟の泊てむ河津の、の意。
荒礒巻きて寝 君待ちかてに―旧訓アライソマキテネマクマチカネを代匠記に「アリソマキテネムキミマチカテニト読ベキカ」とした。童蒙抄にマキテヌとし、宣長や古義など従つた。現在の諸家ネムを採つてゐるが、マキテネムとすれば字余例の例外になるので、、前のイソマクラマクと同じく、ヌと訓んで、「寐らむ」の意にとるべきではなからうか。「かてに」は既出(2・95)。
【考】これも前の作と同じくまだ逢はぬ夜の思ひを述べたものである。
赤人集に「おのがいもなしとはきゝつてにまきてまたきてねよきみさまにとかなし本」とあり、流布本に「またきゝてねよ君まさにとなし」とある。
|
|
|

| |
| 「おのがつま」...しかぞかれてあり... |
| |
| 『かれればこそ、いとしけれ』 |
| 【歌意2009】 |
天と地が別れ、この世界が創られたはるかな昔から、
私は、わが妻とこのように別れ別れに暮らしている
それゆえに、妻に逢える唯一の秋を、ひたすら待っている...、この私は |
| |
| |
この歌の旧訓に、第四句「然叙手而在」を「シカゾテニアル」とあり
その訓釈によると、天地開闢以来、「妻を手中」にし、
こうして、年に一度の逢瀬「秋」を待つ、という
そのような歌意に、私は響くものがない
その場合の「妻」は、いくらこの歌が、「男(彦星)」の視点であっても、
「男」の気持ちしか現れてこない
「天地開闢」以来、という壮大な「想い」を、
「手」と義を用いることで、台無しにしているように思えてならない
だから、『童蒙抄』で「年」でなければ、意をなさない、
とでもいうような解釈に、私も魅せられた
このような誤字説は、むしろ「歌」を、甦らせる
しかし、「七夕」の歌だから、その「年」の用例が示めすように
必然的に「年に一度の逢瀬」が、浮び
さらに、その「一度の逢瀬」も、「よし」とするのか、「物足りない」とするのか
初句のスケール感から言えば、中途半端だと思う
ならば、一気に「干」の誤字説で、「離(か)る」意をこめた「しかぞかれてあり」こそ
初句のスケールを有効にする「語」ではないか、と思う
「年に一度の逢瀬」など、二の次、三の次のことで
離れ離れになっているからこそ、許された「年に一度の逢瀬」に、
「男」は、その「秋」を待つ、と詠える
それは、同じような環境に置かれる「女」にとっても同じだと、
この歌の「つま」を「夫」の意に用いても、決して不自然ではない
「手中」などと解せば、決して同じ感覚では訳せないだろう
そして、何故「離れ離れ」になり、どうして「年に一度の逢瀬」が許されるのか
そこに「七夕」伝説を前提にした「詠歌」と言えるものがあるが
これまで、多くの「七夕歌」に触れていても
その前提でさえ、まったく辻褄が合わないケースもあった
こうした「七夕」の部立てを用いながらも、その一部を利用し
その分、説明めいた語句を省けるのは、歌詠みとしては、ありがたいのだろう
しかし、本来は「悲恋」であるはずの「七夕」伝説を、
もっとストレートに詠う歌に、出合いたいものだ
この後も、まだまだ「七夕」歌は続くが、その期待も充分あるように思える
何しろ、天上界の物語から、いつの間にか、人間界の「恋物語」になっているのだから...
純粋な「七夕」の歌、いったいどれほどあるのだろう
いつか、本気で「七夕」歌に取り組んでみたいものだ
| |
[注釈書「万葉歌」引用歌]
【万葉集注釈】
| 秋雑歌 七夕 |
| 年之戀 今夜盡而 明日従者 如常哉 吾戀居牟 |
| 年の恋今夜尽して明日よりは常のごとくや我が恋ひ居らむ |
| としのこひ こよひつくして あすよりは つねのごとくや あがこひをらむ |
| 巻第十 2041 秋雑歌 七夕 作者不詳 |
〔語義〕
「としのこひ」は、一年にわたった恋
「つく」は、上二段動詞で、「終る・終りになる・果てる・消え失せる・なくなる」の意「あすよりは」は、この「七夕歌」を前提にすれば「七月八日」のこと
「つねのごとく」、は「いつものごとく」で、
係助詞「や」は、疑問だろうか、あるいは「か」と訓んで「詠嘆」かもしれない
「をら」は、動詞の連用形につくラ変の補助動詞「居り」の「未然形」で、接続する動詞の動作・状態の存続を表す、「~ている」
「む」は、推量の助動詞「む」の連体形、「や」の係りに対して、係り結びの「結び」 |
〔歌意〕
この一年で、想いが募りに募った恋を、今夜二人で燃え尽して、
明日からは、またこれまでと同じく、私は恋しい想いに苦しみながら暮らすことであろう |
|
| 年丹装 吾舟滂 天河 風者吹友 浪立勿忌 |
| 年に装ふ我が舟漕がむ天の川風は吹くとも波立つなゆめ |
| としによそふ わがふねこがむ あまのがは かぜはふくとも なみたつなゆめ |
| 巻第十 2062 秋雑歌 七夕 作者不詳 |
〔語義〕
「としによそふ」は、一年にわたって「装う」、つまり準備を一年かけて、となる
「装ふ」は、衣装を身につけることや飾りつけること
「なゆめ」の、「な」は禁止を表す助詞で、
「ゆめ」は、禁止の「な」に呼応して強く禁止する意を表す |
〔歌意〕
一年にわたって準備をして整えた我舟を漕ぎ出そう
天の川よ、たとえ風が吹いても、お前は決して波を立たせるなよ |
「万葉集注釈」で、この二首を引用して、第四句の「年」の含む意味合いを説明している
そして、この引用歌でも分かるように、「年」には「一年の事」とするのは、
「七夕」ならでは、とも言えるもので、
そのために「年」を引っ張ってきたような気もする
さらに、次の二首も、掲題歌の「年而在 トシニアリ」を解釈するために引用する
| 秋雑歌 七夕 |
| 年有而 今香将巻 烏玉之 夜霧隠 遠妻手乎 |
| 年にありて今か巻くらむぬばたまの夜霧隠れる遠妻の手を |
| としにありて いまかまくらむ ぬばたまの よぎりこもれる とほづまのてを |
| 巻第十 2039 秋雑歌 七夕 作者不詳 |
〔語義〕
「としにありて」は、「一年を経てようやく」の意
従って、「年に一度」の意味に繋がるものだ
「いまかまくらむ」は、「いま、枕にしているだろうなあ」で、
この「いま」が、まさに[七夕当夜」をさしているので、
「いまか」の「か」は、疑問ではなく、詠嘆の終助詞になると思う
「よぎりこもれる」の「こもれる」は、
「囲まれる・包まれる」意の四段「隠(この)る」の已然形「こもれ」に、
完了の助動詞「り」の連体形「る」で、結句を修飾している |
〔歌意〕
一年を経て、今ようやく(彦星は)枕にしているであろう...
(ぬばたまの)夜の霧に包まれて、遠く離れ住む妻(織女)の手を... |
| (七夕仰觀天漢各陳所思作歌三首) |
| 等之尓安里弖 比等欲伊母尓安布 比故保思母 和礼尓麻佐里弖 於毛布良米也母 |
| 年にありて一夜妹に逢ふ彦星も我れにまさりて思ふらめやも |
| としにありて ひとよいもにあふ ひこほしも われにまさりて おもふらめやも |
| 巻第十五 3679 七夕 遣新羅使 |
〔語義〕
この歌での「としにありて」は、「一年で・一年に」というような意味合いになるだろう
その一年で、「一夜」に繋がる
「まさる」は、量的な増加
「おもふらめやも」は、現在推量「らむ」の已然形に、反語の終助詞「やも」がつき
「思うだろうか、いや思わない」となる |
〔歌意〕
一年で一夜だけしか妹に逢えない彦星でも、
この私以上に、これほどの思いをしていないだろう |
「としにあり」とすることで、「年に一度」の想いが更に強まっている
「七夕」歌の場合の「年」は、このような用法なのだろう、きっと
次の引用歌は、掲題歌の結句の文末「吾は」の用例を載せている
| 相聞/(柿本朝臣人麻呂歌三首) |
| 未通女等之 袖振山乃 水垣之 久時従 憶寸吾者 |
| 娘子らが袖布留山の瑞垣の久しき時ゆ思ひき我れは |
| をとめらが そでふるやまの みづかきの ひさしきときゆ おもひきわれは |
| 巻第四 504 相聞 柿本人麻呂 |
〔語義〕
「をとめらがそで」は、その「振る」という行為から、
「ふるやま」を起こす「序」となる
そして、「袖振る」と「布留山」の「ふる」が「掛詞」になる
「みづかき」は、「みずみずしい」という原義を持つ「杜」
「ゆ」は、動作の時間的・空間的な起点を表す上代の格助詞で、「~から・~以来」 |
〔歌意〕
おとめらが、袖を振るという名の布留山の
瑞垣のみずみずしく厳かな久しい前から、思っていたのです、私は |
| (當所誦詠古歌) |
| 多麻藻可流 乎等女乎須疑弖 奈都久佐能 野嶋我左吉尓 伊保里須和礼波 |
| 玉藻刈る処女を過ぎて夏草の野島が崎に廬りす我れは |
| たまもかる をとめをすぎて なつくさの のしまがさきに いほりすわれは |
| 柿本朝臣人麻呂歌曰 敏馬乎須疑弖 又曰 布祢知可豆伎奴 |
| 巻第十五 3628 古歌 遣新羅使 |
〔語義〕
「たまもかる」は、「をとめ」にかかる枕詞
そして、この歌での「をとめ」は、地名とされる
[契沖は「処女塚」のあるところを、やがて「をとめ」とのみいうようになった、とする]
「なつくさの」は、「野」にかかる枕詞
「いほりす」は、四段動詞「廬(いほ)る」の連用形「いほり」に、
ある動作を行う、ある行為をする意の他動詞サ変「為(す)」の終止形で、
「仮の宿りをすること」 |
〔歌意〕
「処女塚」のあたりを過ぎて、野島が崎に、仮の宿りをする、この私は |
この引用歌で説明しているのは、第四句「しかぞとしにあり」で句切りするのではなく
結句の「あきまつ」までを一文として、「吾者」の前で切ること
多くは、第四句で句切り、「あきまつわれは」とするが
この引用歌の例に見るように、「吾者 ワレハ」の前で活用語の終止形となり
そこで文は終り、「倒置法」のごとく「吾者」と終らせる |
|
|
掲載日:2014.05.08.
| |
| 秋雑歌 七夕 |
| 天地等 別之時従 自□ 然叙年而在 金待吾者 [□女偏に麗] |
| 天地と別れし時ゆ己が妻しかぞ年にある秋待つ我れは |
| あめつちと わかれしときゆ おのがつま しかぞかれてあり あきまつわれは |
| 巻第十 2009 秋雑歌 七夕 柿本人麻呂歌集出 |
[収載歌集]
【赤人集】〔169・157・278〕
[注釈書「万葉歌」引用歌]
【万葉歌】〔2041・2062・2039・3679・504・3628〕[万葉集注釈]
[資料]
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
【七夕】〔中華民国[国立成功大学、成大宗教與文化学報 第七期 論文]〕
【織女と牽牛】〔講談社学術文庫「星の神話・伝説」野尻抱影〕
| 【2009】 語義 意味・活用・接続 |
| あめつちと [天地等] 天と地とに |
| わかれしときゆ [別之時従] |
| わかれ [別る・分かる] |
[自ラ下二・連用形] 分離する・別々になる・死に(生き)別れる |
| し [助動詞・き] |
[過去・連体形] ~た |
連用形につく |
| ゆ [上代、格助詞] |
[起点] ~から・~以来 |
体言につく |
| おのがつま [自□] [□女偏に麗] |
| おのが [己が] |
私の・自分自身の・私が・自分自身が・各自が |
| 〔成立〕代名詞「おの」(普通「おのが」の形で、私・我)に、格助詞「が」 |
| しかぞかれてあり [然叙年而在] |
| しか [副詞] |
[前述されたことをさして] そのように・そのとおりに |
| ぞ [係助詞] |
[強調] ~が・~を 〔接続〕種々の助詞などにつく |
| かれ [離(か)る] |
[自ラ下二・連用形] 離れる・遠ざかる・間をおく |
| て [接続助詞] |
[補足(状態)] ~のさまで・~の状態で |
連用形につく |
| あり [有り・在り] |
[補動ラ変・終止形] ~いる・~ある |
| (助詞「て・つつ」の付いた語の下につき、動作・作用の存続の状態を表す) |
| あきまつわれは [金待吾者] 「金」は五行説を四季に配すると、「秋」は「金」になるらしい |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [わかれ] |
この歌のような意味での「別る」を言う場合は、この下二段動詞だが、
「区別がつく・識別できる」意の「わかる」は、
四段活用の「わく(分く)」の未然形「わか」に、可能・受身・自発の助動詞「る」がつくとするその二語に分けた方がいい、と古語辞典にある
〔例文〕
|
| その琴とも聞きわかれぬ(=聞き分けることのできない)物の音ども、いとすごげに聞こゆ |
| 源氏物語〔橋姫〕 |
|
| |
[しかぞかれてあり] |
諸本の多くは、「然叙手而在」で、旧訓「シカゾテニアル」と訓だ
しかし、下段資料の如く、
『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、享保年間(1716~35)成〕が、「手」を「年」の誤りとし、
「カクソトシナル」と訓んで以来、現在では「年」が一般的に用いられているが、
その過程では、「手」の誤字説も含め、この句全体が、幾つもの訓が試みられている
「シカチギリタル」[「叙」を「取」の誤字とし、「取手」を『遊仙窟』の訓「契」と解釈]
『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕
「シカゾタノミテ」[「手」を「恃(たの)む」の誤字、「在」は衍字とする解釈]
『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕
「シカゾトシニアル」
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕、
『完訳 日本の古典』〔小学館、昭和59年成〕、
『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕、
『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕
「シカゾトシニアリ」
『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕
「カクゾトシニアル」
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕、
『新日本古典文学大系』〔岩波書店、平成15年成〕
『新日本古典文学大系』〔岩波文庫校訂版、平成25年~〕
しかし、私が気に入っている訓は、次の訓になる
「しかぞかれてあり」
『新潮日本古典集成』〔新潮社、昭和51~59年成〕、
『万葉集校注』〔伊藤博、角川文庫、平成13年23版〕が採り入れている
この説は、やはり「手」を誤字とするものだが、
「手」として強引な解釈をすれば、歌意に「妻として手中」にあるようなイメージになる
『古義』の解説にみても、積極的な解釈にはならない注釈書が多い
この「手」を、「干」の誤字としたのが、
稲岡耕二「『然叙手而在』私按―両用仮名『而』の訓読―」国語と国文学昭和四十年二月、
この「干」は、訓を借りて、「離(か)る」を表現したものだと思う
ここに、「離る」を用いると、随分初句からの理解が容易い
『注釈』の説明では、七夕で詠われる「年」は、「年に一度の事」であり、
「年」こそ、ここでは相応しい、と言わんばかりだが
「干(離る)」こそ、初句の深さ、奥行きから窺えば、ぴったり、だと私は思う
そして、もう一つの問題が...いや、私には難しい文法上の理解について
この句には、手をやかされた
「ぞ」は、係助詞であり、その係り結びの「結び」は、当然「連体形」になる
しかし、「あり」を連体形で終らせるのなら、「ある」であるべきだ
だから、旧訓「シカソテニアル」の「アル」は連体形で結ばれている
そして、新訓にしても、「トシニアル」が得られる
では、この「かれてあり」は、「かれてある」ではないか、と思った
しかし、古語辞典を読み直すと、やっと理解出来た...と思う
|
| 「ぞ」を受けて連体形で結ばれるはずの語に、「に・を・とも・ども・ど・ば」などの接続助詞が付くと、接続助詞の支配を受けて結びが消滅して、条件句となって下文に続いていく。 |
この説明の中で、掲題歌の「て」は載っていないが、「~などの接続助詞」なので
私には、「て」も問題なく含まれると解釈している
そして、旧訓「手」や、あるいは「年」とした場合には、「あり」が結びの動詞になるが
「離る」の場合は、それが「結び」の役目をする「動詞」になるので
上記の説明のように、接続助詞の「支配」を受けて、「結び」が流れている
接続助詞「て」には、動詞の連用形が付くので「かれて」の「かれ」は連用形
ついでに、簡単な「係り結び」の由来の一つを書いておく
強調として、その訳し方は様々だが
本来、たとえば「降る雪」として、「雪」を修飾する連体形「降る」
これを強調すれば、その用法は「雪ぞ降る」で、連体形で終っている
私には、この説明が一番説明し易い
|
| |
| |
| |
| |
| |
[織女牛(伝説)] 講談社学術文庫「星の神話・伝説」野尻抱影
|
織女は、こと座のベーガ、牽牛は、わし座のアルタイルの中国名ですが、この二つの一等星が、天の川を隔てて瞬き合うさまは、正に一対の夫婦星で、世界にもまれな七夕伝説が中国に生まれたのも、自然に思われます。
織女は天帝の娘で、天の川の東の岸に住み、父のいいつけで明けても暮れても「機」を織っていました。その布は雲錦といって、五色にてり輝き、眩しいほど美しいものでしたが、織女はそれを織るので、髪を結う暇もなく、化粧をすることも忘れてしまいました。
やがて天帝も娘を不憫に思って、天の川の西に住む牽牛という若者とめあわせました。すると、織女は新しい生活の愉しさに、はた織りをなまけて、化粧にばかり身をやつすようになりました。それで天帝は腹を立てて、織女を再び東の岸へ連れ戻し、一年に一度、七月七日の夜だけ、天の川を渡って、夫に会うことを許してやりました。
こうしてその日に雨が降ると、天の川の水かさが増すために、織女は川を渡ることができないので、目のいい人には雲を通して、二つの星が天の川の両岸で、哀しげに五色に煌くのが見えるといいます。
その夜、カササギが、天の川の中に翼をならべて橋となり、織女を渡してやるというので、日本でも、これを『かささぎの橋』といって歌に詠みました。
中国では唐の時代から七月七日の夕べを七夕(しちせき)といって、織女牽牛を祭り、女たちが、針仕事や、琴や、文字などが上手になるように祈りました。
この伝説と祭りとが、遣唐使や留学生によって日本へ伝わり、織女には、はた織りの女神の名をあててタナバタ(棚機)とよび、牽牛は、男の星の意味でヒコボシ(彦星)とよび、また、オリヒメ、ウシカイボシともいいました。そして七夕と書いて、『タナバタ』と読むようになりました。 |
|
| |
| |
| |
| |
| |
 |
|
|
| 掲題歌[2009]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
[収載歌集]
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
|
| あめつちとわけし時よりわかいもに そひてしあれはかねて待我 |
新編私家集大成第一巻-新編増補 赤人集Ⅲ[陽明文庫蔵三十六人集]あきのさう 169
|
| あめつちとわけしときよりわかいもに そひてしあれはかねをまつかな」一八 |
同第一巻-6 赤人集Ⅱ[書陵部蔵三十六人集] 秋雑歌 157
|
| あめつちとわけしときよとわかいもと そひてあれはかねてまつわれ(本) |
同第一巻-5 赤人集Ⅰあかひと[西本願寺蔵三十六人集] あきのさふのうた 278
|
| あめつちとわけしときよりわがいもとそひてしあればかねてまつわれ |
新編国歌大観第三巻-2 赤人集[西本願寺蔵三十六人集] あきのざふのうた 278
|
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「天地等別之時從自□然叙手而在金待吾者」【□女偏に麗】
「アメツチト ワカレシトキユ オノカツマ シカソテニアル アキマツワレハ」(「【】」は編集、歌番は旧) |
〔本文〕頭注に、『元暦校本』別行平仮字ノ訓ナシ。余白アリ。漢字ノ右ニ赭片仮字ノ訓アリ、コレニテ校ス。『類聚古集』訓ヲ附セズ。『西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本』訓ノ肩ニ朱ノ合点アリ。但『京』 赭ニテコレヲ止メタリ。
赤人集「あめつちとわけしときよとわかいもとそひてあれはかねてまつわれ(本)」 |
| 「自」 |
『元暦校本』「目」。『類聚古集』「白」 |
| 「手」 |
『神田本』「乎」 |
| 〔訓〕 |
| アメツチト |
『元暦校本』「アメ」蝕シテ存セズ
|
| ワカレシトキユ |
『元暦校本・神田本』「ワケシトキヨリ」
『京都大学本』「從」ノ左ニ赭「ヨリ」アリ。赭ニテ右ノ訓ト入レ換フ可キヲ示セリ
|
| オノカツマ |
『元暦校本・神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本』「ヲノカツマ」
|
| シカソテニアルアキマツワレハ |
『元暦校本』以上ナシ
『神田本』「シカソテニアル」ナシ
『西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本』「シカソテニアル」朱
|
| 〔諸説〕 |
| ○[ワカレシトキユ]『童蒙抄』「ワカレシヨヨリ」○[オノカツマ]『童蒙抄』「ナカヲトメ」又ハ「ナカツマ」○[然叙手而在シカソテニアル]『童蒙抄』「手」ハ「年」ノ誤。訓「カクソトシナル」。『万葉考』「叙」ハ「取」ノ誤。訓「シカチキリタル」○[アキマツワレハ]『童蒙抄』「アキマツカリハ」 |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [2009] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
〔あめつちと別れし時ゆをのかつましかそ手にある秋まつわれは〕
天地等別之時從自□[□人偏+麗]然叙手而在金待吾者
|
第四句の「手」を、実像としての「手を握る」心持ち、とするのだろうか
「秋」は「逢瀬」のとき、その[秋」を待つ...七夕らしい解釈だ |
| あめつちと別れし時ゆ 見安云しかそ手にあるは吾妻を手ににきりたる心也愚案/混沌[コントン]天地と剖[ワカレ]し時より己か妻は手に入て逢瀬の秋まつと也秋まつわれはとはわれは逢瀬の秋まつとの心也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
〔アメツチトワカレシトキユオノカツマシカソテニアルアキマツワレハ〕
天地等別之時從自□[□女偏+麗]然叙手而在金待吾者 |
天地開闢よりの古くから、織女は私の妻だと決まっている、ということか
赤人集の結句は「金待」を「秋待つ」と解釈せず「かねをまつかな」と訓でいることに、どんな解釈で、そう訓んだのか、と疑問を述べている |
然叙手ニ在とは我妻と領するなり、牽牛と成て織女を指なり、赤人集に落句かねをまつかなと有はいかに意得てよめりけむ、
|
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、信名、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
〔あめつちとわかれしよゝりながをとめかくぞとしなる秋まつがりは 〕
天地等別之時從自□[□女偏+麗]然叙手而在金待吾者 |
この歌も、諸抄の解釈の多さを言う
この時代で、「手」を「年」の誤字だとする説を提唱しているが、それが受け入れられるのは、後世のことになる
「年」の語義として、「豊年」、つまり「秋」だという
「がり」という訓も、自称の詞だというが、これは受け入れられていない
「吾者」は、やはり「われは(あれは)」だろう
|
此歌も印本諸抄の意にては如何に共通じ難し。先づ、しかぞてにあると云ふ義歌詞にあらず。義も又如何に共通ぜず。宗師案は、手の字は年の字の誤字と見る也。扨此自□[女+麗]も長をとめとか長妻とか讀まんと也。上に天地と詠出たれば、長久の意をよめると聞ゆ。自の字は、ながくと讀めば、ながと借訓に讀まるゝ也。汝とはわれをも自語に云へば、長と己とを兼ねて也。年と云ふは豐年の義也。稻をとしと云故、年なるとは豐年の事を云也。稻の熟し調ひたる秋を待つと云義也。下の意にい寢る事のなる秋を待と云意をこめてか。諸抄の説は天地の別れし時より、我手に入れたる織女なれば、秋毎に逢ふ事を待つとの意と釋せり。然れ共しかぞてにあると云詞歌には無き詞也。宗師の讀樣は左の如し
あめつちとわかれしよゝりながをとめかくぞとしなる秋まつがりは
がりとは自稱の詞也。年あると讀むから、年は稻の義、稻は刈取ると云事あれば、その縁ある言葉にかりとは讀む也
總ての意は、織女にかく障り無く年毎に逢ふ事は、年なると同前の義、彦星の意には悦の意也。よりて年なる秋を待つとの義迄の歌と見る也。七夕の夜織女に逢ひて喜べる歌と見る也。よりてかくぞとよめる也 |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
天地等、別之時從、自孃[オノガツマ]、
然取手而在[シカチギリタル]、 今本取を叙に誤り訓もよしなければ改取手を契と訓は遊仙窟によれり契たるの多は弖阿の約なり
金待吾者[アキマツワレハ]、 |
随分大胆な解釈になっている
「手を取る」は、「男女の契り」か、久し振りに「遊仙窟」の名を聞いた
「取手」が、遊仙窟で「契」と訓まれる、というが...
「契たる」の「多」は、「てある」の約だという |
| 今本の訓はよしなしこは秋まつわれは妹としか契りおけりといひ天地のわかれし時より手に取てある秋とつゞけて契の久しきを云ならん |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
〔あめつちと。わかれしときゆ。おのがつま。しかぞてにある。あきまつわれは。〕
天地等。別之時從。自孋。然叙手而在。金待吾者。 |
第四句を誤字があるだろう、とし、解釈が難しい、とする
契沖の解釈には、再考が必要だ、とする
|
四の句誤字有らん、解き難し。契沖は、シカゾテニアルは、天地分れしより、織女は己が妻と定りて、斯くぞ手に有るなりと言へり。猶考ふべし。
參考 ○自孋(考、古)略に同じ(新)オノヅマト ○然叙手而在(新)シカゾタノミテ「手」を「恃」の誤「在」を衍とす。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
〔アメツチト。ワカレシトキヨ。オノガツマ。シカゾテニアル。アキマツアレハ。〕
天地等別之時從自孋然叙手而在金待吾者
|
副詞「しか」の解釈の説明を詳しく述べる
歌意解釈は、契沖の説に沿いながらも、結句に具体的な訳を与えている |
自孋[オノガツマ](孋(ノ)字、拾穗本には儷と作り、)契冲云、彦星になりて、たなばたを云なり、
○然叙手而在[シカゾテニアル]は、天地はやく割判[ワカ]れしより、織女はおのが妻とさだまりて、かくぞ我(カ)手にあるなりと、これも契冲云り、今云、右の説の如く然[シカ]は如此[カク]といふ意に聞べし、(然[シカ]と如此[カク]とは、彼[ソレ]と此[コレ]との差ありて、もとより表裏の辭ながら、又相通はしてきく例あり、そのくはしき理は、既くいへり、彼[ヒト]の然[シカ]と云は、此[コヽ]の如此[カク]、此[コヽ]の然[シカ]と云は、彼[ヒト]の如此[カク]なる謂よりいふことなり、たゞ何となく心まかせに、通はし云るにはあらず、各その前後の語勢の趣によることなり、と知べし、)
○金待吾者[アキマツアレハ]とは、むかしよりさだまれることれば、七日の夜はあはむと、まつなりと、これも同人云り、
○歌(ノ)意は、天地の割判[ワカ]れし時より、織女は自(カ)妻とさだまりて、如此[カク]我(カ)手にあるなれば、その、相見む初秋の七夕を、吾は待ぞと云なるべし、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
〔天地とわかれし時ゆ白□[女偏+麗][オノヅマト]、然叙手而[シカゾタノミテ]在金[アキ]まつ吾は〕
天地等別之時從自□[□女偏+麗]然叙手而在金待吾者 |
旧訓では、その歌意が理解出来ず、とするか
千蔭が、第四句に誤字があるようだ」とするのは率直でいい、というようだ
「手」を「恃」の誤字、「在」を衍字として訓まない
|
| 三四を從來オノガツマシカゾテニアルとよみたれどさては何の意ともきこえず。略解に『四の句誤字あらん。解がたし』といへるは率直なり。案ずるに手を恃などの誤字、在を衍字としてオノヅマトシカゾタノミテとよむべし。シカゾはカクゾなり |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| 天地[アメツチ]と分れし時ゆ、己[オノ]夫[ヅマ]と、しかぞ手にある。我が待つ君は |
通説の牽牛、織女の立場を変えての解釈をしている
しかし、何故結句「吾者」を「君者」に入れ換えてまで、そう解釈するのだろう |
| 渾沌とした物質が、天と地とに分れた時分から、牽牛星をば、自分の夫として、ちやんと自分の手の中の物としてゐる。その私が待つてゐる所のお方(牽牛)は。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
〔天地と 別れし時ゆ おのがつま しかぞ年にある 秋待つ我は〕
アメツチト ワカレシトキユ オノガツマ シカゾトシニアル アキマツワレハ
天地等別之時從自孋然叙年而在金待吾者 |
助詞「と」が、「天と地」の対等な分離を表現するのだろうか
第四句、略解の疑念を、「有り得る」とするが、やはり「年」に改めている
「手」を「年」に改めながら、その歌意には「手中」をいう
しかし、従来の天地開闢以来、織女は妻として私の手中になる、という解釈、私には馴染めない
そうであれば、年に一度の逢瀬を、
「待つ」という言葉に繋がるのだろうか... |
天地開闢ノ時カラ、ワタシノ妻トシテ、織女ハカウシテ手ノ中ノモノトナツテヰル。デ、ワタシハ妻ニ逢ヘル秋ヲカウシテ待ツテヰル。
○天地等別之時從[アメツチトワカレシトキユ]――卷三の不盡山の歌には天地之分時從[アメツチノワカレシトキユ](三一七)とあつたが、ここは同意ながら、天と地とが相分離したやうに云つたものである。
○然叙手而在[シカゾテニアル]――略解に「四の句誤字あらむ、解しがたし」とあるが、このままで分らぬことはない。織女を妻として手に入れてゐるといふのである。
○金待吾者[アキマツワレハ]――金を秋に用ゐたのは五行を四季に配すれは、金が秋に當るからである。
〔評〕彦星の心を述べたもので、二星の契の古く久しいことがよまれてゐるのは、前の八千戈神自御世[ヤチホコノカミノミヨヨリ](二〇〇二)、後の乾坤之初時從[アメツチノハジメノトキユ](二〇八九)などと同樣である。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
〔天地と 別れし時ゆ、おのが孋 然ぞ手にある。秋待つ、吾は。〕
アメツチト ワカレシトキユ オノガツマ シカゾテニアル・モチタル アキマツワレハ
天地等別之時從自孋然敍手而在金待吾者 |
「日本書紀」に語られる「開闢説」より、「人麻呂歌集歌」の古さをいい、そこでのこの歌の表現に、注目している
「開闢説」という思想は、古くから日本にあった、とは言えても、日本固有の思想とは言い切れないだろう
訓法に疑義が存在する...それは、「人麻呂歌集」を、どうみなすのか、によるだろう |
【譯】天と地と別れた時からこの方、わたしの妻は、かようにきまつているのだ。わたしは秋を待つている。
【釋】天地等別之時從 アメツチトワカレシトキユ。太古に天と地と一體であつたものが、やがて天と地と分かれた。その時からこのかた。むかし天と地とが分かれたというのは、日本書紀の開闢説で、大陸の哲學説によるものとされている。この歌は、人麻呂歌集所出で、日本書紀結集以前の作と考えられるが、當時既に、天地の初めに關して、かような思想が存在していたことを語つている。このような思想が、古くから日本にもあつたのだろう。ユは、その時からしてこなたへ。
然敍手而在 シカゾテニアル。シカソテニアル(西)
然取手而在[シカチギリケル](考)
然敍恃而[シカゾタノミテ](新考)
諸説があり決定しかねる。而をニの音に借りたことは、前出一九九六の歌のほかに確たる例が無く危まれる。手而在を、義をもつてモチタルと讀むべきか。かようにわが妻としてある意。句切。
金待吾者 アキマツワレハ。金は、五行の一で、季節の秋に當るので、借り用いている。アキマツで切る。
【評語】八千戈ノ神ノ御世ヨリの歌と同じく、大がかりに天地の初めから説いているのが、七夕の歌らしい所である。牽牛星に代つて読んでいるが、訓法に疑義が存するのは遺憾である。
|
| 『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕 |
「評釈」私見 |
〔天地と別れし時ゆおのが孋然ぞ手に在る秋待つ吾は〕
アメツチト ワカレシトキユ オノガツマ シカゾテニアル アキマツワレハ
天地等別之時從自孋然敍手而在金待吾者 |
そもそも、大陸伝来の「七夕」伝説が、もう万葉歌の解釈には、何の影響もなくなってしまった、というような注釈だ
大陸の「七夕説話」は、悲恋だと思う
しかも、それが日本に伝わったと推測されるのは、遣唐使の頃
やはり、日本にはその古くから類する伝承があった、ということだと思う
それに伝来の「七夕伝説」が重ねられ、優れた「歌物語」を作っていった、と私は思う |
【譯】天と地と相別れた遠い昔から、織女は自分の妻として、かうして自分の掌中にある。であるから、やがて妻に逢へる秋を楽しみに待つてゐるのである、自分は。
【評】七夕の歌は、多くはその悲戀を憐む同情を基調としてゐるが、これは趣を異にして、彦星の心の平安を歌つてゐる。なるほど年に一度の逢瀬しか許されないといふことは、悲しい戀には相違ないが、しかし又一面から見れば、永久にわたるその契の固いこと、安定してゐることを思はせるのである。この歌は全体に快活の響があり、「秋待つ吾は」にも、安んじて秋を楽しむ感じが受け取られる。
【語】○天地と別れし時ゆ 天地開闢の遠い昔から。○然ぞ手に在る このやうに自分の妻として定つてゐるの意。
【訓】○秋まつ吾は 白文「金待吾者」。「金」は、五行を四季に配すれば金が秋に当るからである。 |
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
〔天地と別れし時ゆおのが妻然ぞ手にある秋待つ吾は〕
アメツチト ワカレシトキユ オノガツマ シカゾテニアル アキマツワレハ
天地等別之時從自孋然敍手而在金待吾者 |
「しかぞてにある」が、「近々にある」意だとする
当然、その「しかぞてにある」は、
「秋の逢瀬ができる七月七日」に決まっているのだから
手の届く近さにありながら、その窮屈さには、
歌意を添えるのも、無理が必要だ |
【大意】天と地との別れた古の時から、己が妻は、この如く手の届く近さにある。会ふべき秋を吾は待つ。
【作意】牽牛の立場である。シカゾテニアルは近々にある意であらう。従つて、秋になりさへすれば、容易に会へる意をあらはしたのであらう。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
〔天地と 別れし時ゆ 己が妻 然ぞ年にあり 秋待つ吾は〕
アメツチト ワカレシトキユ オノガツマ シカゾトシニアリ アキマツワレハ
天地等別之時從自孋然叙年而在金待吾者(『元暦校本』) |
どうしても、「天地開闢」以来の「妻」だから、が無条件で受け取られているが
何故、そう言わなければならないのか、
そして、何故「天地開闢」以来なのに、年に一度の逢瀬に甘んじて秋を待つのか...
結局、この近代までの「注釈書」の最後にきても、
そのことには触れられることはなかった
この書でもそうだが、「訓」や「語釈」が中心であり、
この歌は、「どんな意味を持つのか」のような注釈書を望むのは、
別の研究分野なのかもしれない
ここで解説する [しかし手を相携へてむつみ交してゐる世の常の夫婦乃至しのびづまならばさうも云へようが、天の河をへだてて年に一度の七夕つ女の交情を「手にある」といふ事はおちつかない] と述べるのは、まさに私も同感であり、
「天地開闢以来」の妻を、年に一度しか逢うことができない、ということを「手中」にある、とは言えないだろう、と思う
|
【口訳】天と地と別れた時より私の妻に対して、こんなにして一年をあり経て秋を待つてゐるよ。私は。
【訓釈】天地と別れし時ゆ―前に「天地之分時従 アメツチノ ワカレシトキユ」(3・317)とあつた。この先に「天地跡別之時従 アメツチト ワカレシトキユ」(2092)とある。天は天、地は地と別れた時から、の意。
然ぞ年にあり秋待つ吾は―第四句原文「然叙手而在」とあり、『元暦校本・類聚古集・紀州本』に訓なく、『西(朱)』以後シカゾテニアルとし、『代匠記』に「然叙手ニ在トハ、我妻ト領ズルナリ」とあり、現代の諸家も疑を存しつゝ、多くこの訓釈によられてゐる。しかし手を相携へてむつみ交してゐる世の常の夫婦乃至しのびづまならばさうも云へようが、天の河をへだてて年に一度の七夕つ女の交情を「手にある」といふ事はおちつかない。『万葉考』には「然取手而在シカチギリタル」の誤とし、『新考』には「然叙恃而シカゾタノミテ」の誤としたがいづれも穏やかでない。『童蒙抄』に「しかぞてにあると云ふ義歌詞にあらず。義も又如何に共通ぜず。宗師案は、手の字は年の字の誤字と見る也」とする説は、「○」と「○」(【入力不能】)と草体は極めて接近してゐて誤字説としては最も認めやすい説である。但、「年と云ふは豊年の義也。稲をとしと云故、年なるとは豊年の事を云也。稲の熟し調ひたる秋を待つと云義也」とあるはむつかしすぎる解釈で、この年は、
年之戀[トシノコヒ]今夜盡して明日よりは常の如くや吾が戀ひ居らむ (2037)
年丹装[トシニヨソフ]吾が舟こがむ天の河風は吹くとも浪立つなゆめ (2058)
など七夕の歌にいくつもある「年」は一年の事であり、
年有而[トシニアリテ]今か巻くらむぬば玉の夜霧こもりに遠妻の手を (2035)
等之尓安里弖[トシニアリテ]一夜妹にあふ彦星もわれにまさりて思ふらめやも (15・3657)
の「年にあり」と同じで、「一年をあり経て」の意にとれば極めて自然に解釈が出来ると思ふ。「而」をニと訓む事は前(1996)に述べた。シカゾトシニアルアキマツワレハと訓んで、第四句で切り、「秋待つ」を「吾」の修飾とする事も出来、又第四句で切り、「秋待つ」で切るといふ事も考へられるが、「吾は」の結句は、
をとめらが袖ふる山の瑞垣の久しき時ゆ思ひき吾は (4・501)
玉藻刈るをとめを過ぎて夏草の野島が崎にいほりす吾は (15・3606)
の如く、「吾は」の上で切つて、第四句で切る例は少く、ここはシカゾトシニアリと訓んで下へつづけ、こんなにして一年をあり経て秋を待つことよ。自分は。と解くべきものと思はれる。(「人麻呂集訓詁二題」国語国文 第廿巻第一号、昭和廿六年一月)。「金」を秋とすること前(1・7)に述べた。
【考】赤人集に「わけしときよとわがいもとそひてあれはかねてまつわれ 本」、流布本「わけし時よりわか妹にそひてしあれはかねをまつ哉」とある。
|
|
|

| |
| 「ことだにも」...つげにぞきつる... |
| |
| 『われもまた』 |
| 【歌意2010】 |
彦星は、歎き泣きくれている妻に、
ことばさえも告げずに、いってしまった
それほど、妻である織女星の歎かれる姿を見るのが
苦しいからだろう |
| |
| |
参考解釈として、幾つか載せてみる
| 『万葉集全訳注』〔中西進・講談社文庫、昭和58年成〕 |
彦星は、嘆いておられる妻に、せめてことばだけでもと告げに来た。
見ていると苦しいので。 |
| 『万葉集全注』〔有斐閣、昭和58年~平成18年成〕 |
彦星は、嘆いておられる妻のもとに、
せめて言葉を伝えるだけでもと、やって来た。
織女星の嘆いている様子を見るのが辛くて。 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
彦星ハ嘆カス妻ニ(相寝ル事ハカナハズトモ)話ナリトモセムトテ来ツ、
見ネバツラキニヨリテ |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
男星なる牽牛星が、思ひこんで嘆息をついて居られる
相手の妻なる織女星は、只語だけをば、人に言付けておこせた
あへば却って苦しいので。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
彦星は歎いてゐられる妻に、せめて慰めの言葉だけでも通じようとやつて来たことよ。
見てゐると苦しいので。 |
これらは、多くの注釈書の解釈パターンを比較しようとするために載せたものだ
折口信夫の解釈は、彼自身の歌人としての本領発揮といえるだろう
自由闊達な歌意解釈が、いつも楽しめる
井上通泰の解釈もまた、改訓に力を注いだ甲斐もあって、
独特の解釈となっている
他の「中西進全訳注・全注・注釈」が、もっとも多くの解釈として見られる
だから、それが「通説」と言えるものだとは思うが、
これらの「通説」には、大きな矛盾がある
その矛盾を表現させることなく、このような解釈にせざるを得なかったのは...
何故、織女星が歎いているのか、そのことには触れられていない
ただ、日本に馴染んで、すでに変質してしまった「七夕伝説」を想像するなら
年に一度の決められた「逢瀬」だけではなく
本当は、その「七夕」以外の日にも、逢いたくて、歎き泣いている
それ以外には、その「歎く」理由が考えられない
そのことに言及している古注釈書も多い
しかし、それを歌意に表現してしまうと
この歌意解釈では、随分おかしなことになってしまう
「逢いたくて歎いている織女星」のもとへ
せめて慰めの言葉だけでも掛けようと、彦星がやって来る
それは、「逢う」ことの実現であり、「言葉だけでも」という理由が意味をなくしてしまう
『新考』や『口訳』では、その矛盾を解消させることに解釈を絞った感じだ
しかし、もう一つの解釈も可能だということを、岩波の「古典大系」の補注では述べている
異訓をことさら主張するのではなく
文法上の採り得る解釈として、「試案」を載せている
ただ、その歌意解釈では、
別れの日の、二星の苦しみの葛藤が描かれてきて
通説とは、まったく違う解釈になる
それに躊躇などするものではないが、敢えてその歌意を文字にしようとすると
不思議と「これでいいのかなあ」と立ち止ってしまう
しかし、通説での矛盾を感じたまま、それをこの歌の「こころ」だとは、
どうしても思えない
そして、訓をいじることなく、歌意を解釈してみれば
やはり、その「試案」には惹かれるものがある
「七夕」を詠ったものだからこそ、躊躇う解釈になるのだろうが
しかし、そこに詠われている「男」の「思い遣り」は
これが、万葉時代の人たちが描いていた「七夕」に係わる「二星」、
つまり恋人同士の、「歌」に詠われる一コマではないだろうか、と思える
七夕には、大陸伝来の本来の姿を詠ったものばかりではなく
人間世界の「悩み多き」さまざまな情況を、
逆に「七夕」へと差し込んだ、と考えられそうだ
その意味で、次に引用する「参考歌」の長歌は、
まさに、万葉歌に詠われる「七夕」伝説を国産化したような
諸々の情況を、凝縮したような歌になっている
ある部分を拾い出せば、そんな歌もあったなあ、といくつも数えることが出来る
案外、この山上憶良の長歌が、多くの七夕歌の「もと歌」なのかもしれない
| |
| |
| |
| |
[参考「万葉歌」]
| 秋雑歌 七夕/(山上臣憶良七夕歌十二首) |
| 牽牛者 織女等 天地之 別時由 伊奈宇之呂 河向立 思空 不安久尓 嘆空 不安久尓 青浪尓 望者多要奴 白雲尓 渧者盡奴 如是耳也 伊伎都枳乎良牟
如是耳也 戀都追安良牟 佐丹塗之 小船毛賀茂 玉纒之 真可伊毛我母 [一云 小棹毛何毛] 朝奈藝尓 伊可伎渡 夕塩尓 [一云 夕倍尓毛] 伊許藝渡
久方之 天河原尓 天飛也 領巾可多思吉 真玉手乃 玉手指更 餘宿毛 寐而師可聞 [一云 伊毛左祢而師加] 秋尓安良受登母 [一云 秋不待登毛] |
| 彦星は 織女と 天地の 別れし時ゆ いなうしろ 川に向き立ち 思ふそら 安けなくに 嘆くそら 安けなくに 青波に 望みは絶えぬ 白雲に 涙は尽きぬ
かくのみや 息づき居らむ かくのみや 恋ひつつあらむ さ丹塗りの 小舟もがも 玉巻きの 真櫂もがも [一云 小棹もがも] 朝なぎに い掻き渡り
夕潮に [一云 夕にも] い漕ぎ渡り 久方の 天の川原に 天飛ぶや 領巾片敷き 真玉手の 玉手さし交へ あまた夜も 寐ねてしかも [一云 寐もさ寝てしか]
秋にあらずとも [一云 秋待たずとも] |
| ひこほしは たなばたつめと あめつちの わかれしときゆ いなうしろ かはにむきたち おもふそら やすけなくに なげくそら やすけなくに あをなみに のぞみはたえぬ しらくもに なみたはつきぬ かくのみや いきづきをらむ かくのみや こひつつあらむ さにぬりの をぶねもがも たままきの まかいもがも [をさをもがも] あさなぎに いかきわたり ゆふしほに [ゆふべにも] いこぎわたり ひさかたの あまのかはらに あまとぶや ひれかたしき またまでの たまでさしかへ あまたよも いねてしかも [いもさねてしか] あきにあらずとも [あきまたずとも] |
| (右天平元年七月七日夜憶良仰觀天河 [一云帥家作]) |
| 巻第八 1524 秋雑歌 七夕 山上臣憶良 |
| 長歌は基本的には、積極的に採り上げないので、岩波文庫新版を転載する |
〔歌意〕
彦星は織女と、天と地が分かれて以来、(いなむしろ)天の川に向かい合って立ち、思う心は安らかでないのに、嘆く心も安らかでないのに、青波に隔てられて対岸は全く見えない。白雲に遮られて涙も枯れてしまった。こんなふうにため息ばかりついていられようか、こんなふうに恋い焦がれてばかりいられようか。赤く塗った小舟が欲しいものだ<一本に「小棹が欲しいものだ」と言う>。朝の凪に漕いで渡り、夕べの潮に<一本に「夕にも」と言う>。漕いで渡り、(ひさかたの)天の川原で、(天飛ぶや)領巾を下に敷いて、玉のような美しい手を互いにさし交わして、幾晩も寝たいものだ<一本に「眠りたいものだ」と言う>。秋の七夕ではなくても<一本に「秋の七夕を待たないでも」と言う>。 |
| 岩波文庫新版の「語釈」 |
彦星の気持を思いやって詠う。冒頭の四句、中国から伝えられた牽牛と織女の伝説を、天地開闢以来のものと言う。天と地が分かれたように、二星も別れ別れになったという含意もあるか。「かくのみや」以下は、彦星の立場になって詠う。
この長歌と反歌には詩文表現の影響が濃厚である。特に整然とした隔句対の駆使は六朝詩文の影響を思わせる。「青波(あをなみ)」は、「漢語『蒼波』」の訓読語。「望みは絶えぬ」も、漢語「望断」の翻訳語。眺望が遮られて、対岸の織女が見えないことを言う。また「涙は尽きぬ」も漢語「涙尽」の和らげ。「緘書(かんしょ)して還使を待ち、涙は尽く白雲の天」(初唐・上官儀「王昭君」。
第五句の「いなむしろ」は「川」の枕詞。係り方未詳。「かくのみや息づく居らむ」は、憶良の881に既出。「いかき」「い漕ぎ」のイは接頭語。「領巾片敷き」の「片」は、ここでは語調を整える言葉。 |
|
|
|
掲載日:2014.05.09.
| |
| 秋雑歌 七夕 |
| 孫星 嘆須□ 事谷毛 告尓叙来鶴 見者苦弥 [□女偏に麗] |
| 彦星は嘆かす妻に言だにも告げにぞ来つる見れば苦しみ |
| ひこほしは なげかすつまに ことだにも つげにぞきつる みればくるしみ |
| 巻第十 2010 秋雑歌 七夕 柿本人麻呂歌集出 |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】〔149〕
【赤人集】〔170・248〕
[参考「万葉歌」]
【万葉歌】〔1524〕
[資料]
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
【七夕】〔中華民国[国立成功大学、成大宗教與文化学報 第七期 論文]〕
【織女と牽牛】〔講談社学術文庫「星の神話・伝説」野尻抱影〕
| 【2010】 語義 意味・活用・接続 |
| ひこほしは [孫星] |
| なげかすつまに [嘆須□] [□女偏に麗] |
| なげか [歎く・嘆く] |
[自カ四・未然形] 嘆息する・悲しんで泣く・嘆願する |
| す [助動詞・す] 上代 |
[軽い尊敬、親愛の意・連体形] ~なさる・お~になる |
未然形につく |
| ことだにも [事谷毛] |
| こと [言] |
口に出して言うこと・ことば・うわさ |
| だにも |
[最小限の一事をあげて強調する意] せめて~だけでも |
体言につく |
| 〔成立〕副助詞「だに」+係助詞「も」 〔「添加」の意として、「~さえも」もある〕 |
| つげにぞきつる [告尓叙来鶴] |
| つげ [告ぐ] |
[他ガ下二・連用形] 知らせる・伝える |
| に [格助詞] |
[目的] ~のために |
連用形につく |
| ぞ [係助詞] |
[強調] ~が・~を 〔接続〕体言、連体形、種々の助詞などにつく |
| き [来(く)] |
[自カ変・連用形] 来る・行く・通う |
| つる [助動詞・つ] |
[完了・連体形] ~てしまう・~てしまった・~た |
連用形につく |
| みればくるしみ [見者苦弥] |
| ば [接続助詞] |
[順接の確定条件] ~ので・~すると・~したところ |
已然形につく |
| くるし [苦し] |
[形シク・終止形] 痛みや悩みで辛い・苦しい |
| み [接尾語] |
[形容詞、助動詞について原因・理由を表す] ~ので・~から |
| 〔接続〕形容詞、助動詞の語幹につくが、形容詞シク活用には、「終止形」につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [ひこほしは] |
「ひこ(彦)」とは、本来「男子の美称」のことであり、
この歌の場合も、「男性の星」と一般的に解するものもある
原文「孫」を、「ヒコ」と訓むのは、下段資料『注釈』にも述べられているが、
「倭名抄(二)」に、「孫 和名无麻古(ムマコ)、一云比古(ヒコ)」とある
|
| |
| [す] |
通常の尊敬の助動詞「す」ではなく、上代に於ける助動詞「す」の活用となる
私も初めは、この「す」を尊敬の「す」と解釈して、その「つま」にかかるのは、
連体形「する」ではないか、と思ったが、
たとえば、巻第一の〔1〕でも詠われた「摘ます児」などの、「す」でも、
その活用は連体形であり、もう一度古語辞典を開いて見ると、
同じ尊敬の助動詞「す」でありながら、上代に於いては、四段活用であった
通常の尊敬の助動詞「す」は、下二段活用なので、
この歌では、上代の「尊敬の助動詞」として訓まなければならない
|
| |
| [こと] |
「言」と「事」
原文では「事」の表記だが、語源的には同じであった、と考えられている
それを窺わせる考え方で、
上代の信仰では「言霊(ことだま)」の語の通りことばにすることで、
事象が発生すると考えられ、この二語の区別はつけ難かった
それが奈良時代以降、分化したとされる
ただし、奈良・平安時代の「こと」には、
どちらにも解せるものが、見られるらしい
|
| |
| [つげにぞきつる] |
『新編日本古典文学全集』〔小学館、平成8年成〕では、その頭注で、
「告げに」は、「告げむと」の言い換え、だとしている
確かに、助詞「に」の働きにある「目的」なので、理解出来る
格助詞「に」は、一般的な接続は、「体言、活用語の連体形」につくものだが、
多くの用法の中で、「目的、~のために」、「強調、~に」の場合は、動詞の連用形につく
係助詞「ぞ」は「係り結び」の「係り」で、
その結びは、完了の助動詞「つ」の連体形
『日本古典文学大系』〔岩波書店、昭和37年成〕では、その「大意」では
大方の解釈に相違は見られないが、
この歌、難解で諸説がある、といい、次の試案を「補注」で挙げている
| 告げにぞ来つる |
| 告げにのニを普通、助詞のニと解している。しかしこれを否定のズの連用形と見ることもできるのではないか。告げにぞは、告げずにの意と解するのである。その結果、「彦星は別れを嘆く織女星に、言葉だけもかけずに別れて来た。織女星を見ると苦しいから」との意になる。一試案として記しておく。 |
この「試案」は、従来から解されている矛盾をかなり解消していると思う
その矛盾、というのは、左頁に書く
|
| |
| [接尾語「み」] |
古語辞典によると、原因、理由を表す用法は、上代の語法とされるが、
平安時代以降も和歌には用いられている、とのこと
よく使われる、「~を~み」の「を」は、間投助詞で、
「山高み白木綿花に落ち激つ滝の河内は見れど飽かぬかも」 (書庫-11 巻六 914)
「君に恋ひいたもすべなみならやまの小松が下に立ち嘆くかも」(書庫-6 巻四 596)
のように、「を」が省かれることもある、また
「逢ふことも涙に(逢うこともないので、その悲しみの涙に)浮ぶ我が身には死なぬ薬も何にかはせむ」(竹取物語 ふじの山)
のように、「を」の省かれたところに係助詞の「も」が入り、
「涙」の「なみ」に「無み」をかけて「~も~み」の形になるような
見分けのつきにくい例もある |
| |
| |
| |
[織女牛(伝説)] 講談社学術文庫「星の神話・伝説」野尻抱影
|
織女は、こと座のベーガ、牽牛は、わし座のアルタイルの中国名ですが、この二つの一等星が、天の川を隔てて瞬き合うさまは、正に一対の夫婦星で、世界にもまれな七夕伝説が中国に生まれたのも、自然に思われます。
織女は天帝の娘で、天の川の東の岸に住み、父のいいつけで明けても暮れても「機」を織っていました。その布は雲錦といって、五色にてり輝き、眩しいほど美しいものでしたが、織女はそれを織るので、髪を結う暇もなく、化粧をすることも忘れてしまいました。
やがて天帝も娘を不憫に思って、天の川の西に住む牽牛という若者とめあわせました。すると、織女は新しい生活の愉しさに、はた織りをなまけて、化粧にばかり身をやつすようになりました。それで天帝は腹を立てて、織女を再び東の岸へ連れ戻し、一年に一度、七月七日の夜だけ、天の川を渡って、夫に会うことを許してやりました。
こうしてその日に雨が降ると、天の川の水かさが増すために、織女は川を渡ることができないので、目のいい人には雲を通して、二つの星が天の川の両岸で、哀しげに五色に煌くのが見えるといいます。
その夜、カササギが、天の川の中に翼をならべて橋となり、織女を渡してやるというので、日本でも、これを『かささぎの橋』といって歌に詠みました。
中国では唐の時代から七月七日の夕べを七夕(しちせき)といって、織女牽牛を祭り、女たちが、針仕事や、琴や、文字などが上手になるように祈りました。
この伝説と祭りとが、遣唐使や留学生によって日本へ伝わり、織女には、はた織りの女神の名をあててタナバタ(棚機)とよび、牽牛は、男の星の意味でヒコボシ(彦星)とよび、また、オリヒメ、ウシカイボシともいいました。そして七夕と書いて、『タナバタ』と読むようになりました。 |
|
| |
| |
| |
 |
|
|
| 掲題歌[2010]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】
| 柿本人麿集 私家集大成第一巻(冷泉家時雨亭叢書『素寂本私家集西山本私家集』) |
| ヒコホシヲナケカスイモカコトタニモ ツケニソキツルミレハクルシミ |
柿本人麿集上 秋部 七夕 [万十] 149
|
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
|
| ひこほしのうらむるいもかことたにも つけにそきつるわれはくるしみ |
新編私家集大成第一巻-新編増補 赤人集Ⅲ[陽明文庫蔵三十六人集]あきのさう 170
|
| ひこほしかうらむるいもかことたにも つけにそきつるけふはくるしも |
同第一巻-6 赤人集Ⅱ[書陵部蔵三十六人集]秋雑歌 柿本人丸歌とそ[玉葉]人丸歌云々 248
|
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「彦星嘆須□[女+麗]事谷毛告余叙來鶴見者苦彌」【□女偏に麗】
「ヒコホシノ ナケカスイモカ コトタニモ ツケニソキツル ミレハクルシミ」(「【】」は編集、歌番は旧) |
| 〔本文〕頭注、無し |
| 「彦」 |
『元暦校本・類聚古集・神田本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本』「孫」 |
| 「余」 |
『元暦校本・類聚古集・神田本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本』「尓」 |
| 〔訓〕 |
| ヒコホシノ |
『元暦校本』「ひさかたの」ソノ右ニ赭「ヒコホシヲ」アリ
『類聚古集』「ひこほしを」
『神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本』「ヒコホシヲ。『西』「ヲ」ノ右ニ「ノイ」アリ
|
| ツケニソ |
『神田本』「ツケニウ」
|
| クルシミ |
『類聚古集』「くるしも」。墨ニテ「も」ヲ消セリ。ソノ右ニ墨「み」アリ
『神田本』「ミ」ノ右ニ「モ」アリ
|
| 〔諸説〕 |
| ○[ヒコホシノ]『代匠記初稿本』「ヒコホシハ」○[ナケカスイモカ]『代匠記初稿本』「ナケカスイモニ」『略解』「ナケカスツマニ」○[告余叙来鶴ツケニソキツル]『代匠記精撰本』「余」ハ「爾」ノ誤。『童蒙抄』「余」ハ「荼」ノ誤カトモス」。訓「ノレトソキツル」 |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [2010] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
〔ひこほしのなけかすいもかことたにもつけにそきつる見れはくるしみ〕
孫星嘆須□[人偏+麗]事谷毛告余叙來鶴見者苦弥
|
この詠歌の作者は、牽牛と織女の二星を世話する「使い人」という
「いもかこと」という解釈なのかな...
要するに、「いものこと、織女星の事」
心苦しい、とはその二星を見ての作者の気持ち、ということか |
ひこほしのなけかす 二星の中の使なとの心にてよめり
牽牛のあはてなけきする織女のありさまをたに告しらせにそ來る二星のさまみれは心苦くてとの心なるへしいもか事とは織女をいへ |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
〔ヒコホシノナケカスイモカコトタニモツケニソキツルミレハクルシミ〕
彦星嘆須□[女+麗]事谷毛告余叙來鶴見者苦彌 |
幽斎とは、戦国時代から江戸初期にかけて活躍した、武将であり、歌学者の細川幽斎のことだろう
その本によると、「孫」は「彦」のことと言っている
「余」が「爾」の誤字というのは、当時では当然のように受け入れられていたのかもしれない
初二句を、「いもが」ではなく「いもに」と提唱しているのが、後世にも影響している
それによって、『拾穂抄』のいう「使者」ではなく、彦星の詠歌であるとする...たぶん |
彦星、[幽齋本、彦作孫、] 告余叙、[別校本、余作爾、]
今按初の二句ヒコボシハナゲカスイモニと讀べし、さらずして今の點のまゝにては牛、女の間に使する者ありてそれが詞のやうにて聞ゆるにや、但やがて下に妹傳速告與とよめるも上に秋立待等妹告與具とよめるも使の意なり、二星の事は風情の寄來るに任せて讀[ヨム]習なればさも有べきにや、余は尓を誤れる歟、第十八にも此違ひあり、尓と爾と同字なれば別校本よし、
|
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、信名、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
〔ひこぼしのなげきすいもにことだにものれとぞきつる見ればくるしみ 〕
彦星嘆須□[女+麗]事谷毛告余叙來鶴見者苦彌 |
諸説の多さに嘆く
「使者の作」、そして「彦星自身の作」では、
彦星が、対岸から織女の嘆く姿を見て、そのを見るのが苦しいから、天の川を渡ってくる解釈
それらを同意しかねる、としている
七夕の夜の歌ではなく、過ぎてからの歌だ、と具体的に言及
私には、充分な理解が出来ていないと思うが、この書では、
彦星が、七夕を過ぎてもう逢えないのなら、せめて言葉だけでも言い交したい、と
彦星の使者が織女に伝えたのを、織女がそれを見て、苦しんだ歌ではないか
となれば、この書での結句の想いは織女の苦しみなのだから、
織女作という立場なのかな...難しい
|
此歌も如何に共解し難し。諸抄の説も一定せず。一説は、二星の間の使の詠める意と見ると有。一説は、彦星の自身に來りて織女物をだに云はんとて來つるとの義、向ひの岸よりよそ目に嘆くを見れば苦しきから、天川を渡りて來るとの意と釋せり。如何に共聞え難し。宗師案も不決也。琴の義をよせてよめる歌か。七夕の夜の歌には有べからず。七夕過ぎては逢ふ事ならねば、見れば苦しみと詠たるならんづれと、告余叙來鶴と云ふ詞如何に共解し難く、尤余の宇爾の字の誤又茶の字の誤などにても讀み解樣不濟也。後案を待つのみ。押而釋せば一説の、抄物の意の如く二星の使になりてよめる意に見れば
ひこぼしのなげきすいもにことだにものれとぞきつる見ればくるしみ
彦星のなげきすは、彦星のうつくしみ慕ひ思ふ妹にと云義也。歎きすとは愛しうつくしむ妹と云意也。諸抄の意は彦星を歎かし、悲しまする妹が事をと云意は不合義也。其意から彦星をとよめり。彦星を嘆かすと云詞如何に共あるべきに、愚案の讀み樣にては、愛しうつくしむ妹と云義と、又慕ひ悲しむ意とを兼ねて嘆きすとは讀む也
事谷毛 逢ふ事は七夕夜過ぎぬれば、成難かるべければ、せめて言葉をだにも云ひ交せよと、使に來つる彦星の戀慕ひ歎くを見れば、苦しきにと云意ならんか共見る也
|
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
彦星(ノ)、嘆須孃[ナゲカスイモガ]、 なけかすの加は伎麻の約
事谷毛、 事は借字言なり
告爾叙[ツゲニゾ]來/鶴[ツル]、 今本の余は爾の誤
見者苦彌[ミレバクルシミ]、 |
恋慕って、七夕でもないので、逢えないことを嘆くのは、彦星という立場だ
織女が、使者を立てて言葉を送った、と言う解釈なのだろうか |
| 彦星のなげきますを見ればくるしきに織女の言をだにつげに來つるといふはなげきをなごめんとなり此だにはさへの如し輕く見るべしさてこは七夕にあらず其前後などよめるならん |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
ひこぼしの。なげかすつまに。ことだにも。つげにぞきつる。みればくるしみ。 〕
彦星。嘆須孋。事谷毛。告余[余ハ尓ノ誤]叙來鶴。見者苦彌。 |
彦星の嘆きを見るも苦しい、他人の言伝など、第三者の見据える二星か |
元暦本、彦を孫に作る。彦星の歎きを見るも苦しければ、他人の言傳を告げに來りしとなり。余は尓の誤なり。
參考 ○彦星(代、古、新)ヒコボシハ(考)略に同じ ○嘆須孋(代)ナゲカスイモニ(考)ナゲカスイモガ(古、新)略に同じ ○告余釦來鶴(新)ノラムトゾキツル「余」を「等」の誤とす ○見者苦彌(新)ミズバクルシミ「見」の上に「不」を補ふ。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
〔ヒコホシハ。ナゲカスツマニ。コトダニモ。ツゲニゾキツル。ミレバクルシミ。〕
彦星嘆須孋事谷毛告爾叙來鶴見者苦彌
|
旧訓「なげかすいも」だが、やはりこの表記は「つま」と読みたいものだ
彦星の気持ちを、第三者が詠ったものとする |
彦星は、契冲云、ヒコホシハと訓べし、
○嘆須孋(孋(ノ)字、拾穗本には儷と作り、)は、ナゲカスイモニと訓べし、嘆く妹になり、とこれも契冲云り、今云、孋は、ツマニとよみて然るべし、嘆須[ナゲカス]は、奈宜久[ナゲク]の伸りたるにて、嘆き賜ふ妻にと云ほどの意なり
○爾(ノ)字、舊本には余に誤れり、今は古寫本に從つ、
○歌(ノ)意は、つまこひに嘆き賜ふを、よそめに見ればくるしさに、そのなげき賜ふ織女に、物をなりとも告なぐさめむとてぞ、彦星は天(ノ)河を渡りきつるとなるべし、これも彦星に擬てよめるなり、
|
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
〔彦星はなげかすつまにことだにも告余叙來鶴[ノラムトゾキツル]見者苦彌[ミズバクルシミ]
彦星嘆須□[女+麗]事谷毛告余叙來鶴見者苦彌 |
第四句の訓「ノラムトゾキツル」は、「ことだにも」を受けるのであれば、
「ツゲムトゾキツル」の訓ではおかしい、と言うようだ
「ことだにものらむ」は、「話なりともせむ」...何となく解るような感覚ではある
巻九1744、水江浦島子の長歌の一節に「ことものらひ」とあることを参照セヨ、と言うが
その浦の島子の歌の「こと」は、「事情」のことだと思う
単に、言葉を掛けることではなく、事情を語ることであり、
この〔2010〕の「つげにぞきつる」とは、違うと思うのだが...
結句の「みればくるしみ」では、意は通じないとする
「みずばくるしみ」では、逢えないと苦しいので、やってきた、という歌意になる
|
初句を舊訓と略解とにはヒコボシノとよみ契沖と雅澄とはヒコボシハとよめり。後者に從ふべし
○第四句を舊訓にツゲニゾキツルとよみ又異本に余を爾に作れるによりて契沖以下皆余を爾の誤とせり。案ずるにコトダニモを受けたればツゲムトゾキツルとあらざるべからず。否ノラムトゾキツルとよむべし。されば余を等の誤とすべし。コトダニモノラムは話ナリトモセムとなり。卷九詠水江浦島子歌(一七四四頁)にチチハハニコトモノラヒとあると參照すべし
○結句を從來ミレバクルシミとよみたれどさては意通ぜず。宜しく見の上に不の字を補ひてミズバクルシミとよむべし
〇一首の意は
彦星ハ嘆カス妻ニ(相寢ル事ハカナハズトモ)話ナリトモセムトテ來ツ、見ネバツラキニヨリテ
といへるなり |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| 牽牛[ヒコボシ]の嘆かす妻が、言[コト]だにも告げにぞ來つる。見れば苦しも |
「あへば却て苦しいので」とは、すでに人間世界の「恋物語」だ
彦星は、こんなにも想いやっているのに、織女星が逢ってくれず、ただ「言伝」だけを送ってよこした...辛い描写だ |
| 男星なる牽牛星が、思ひこんで嘆[タメ]息をついて居られる、相手の妻なる織女星は、只語だけをば、人に言[コト]づけておこせた。あへば却て苦しいので。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
〔彦星は 嘆かすつまに 言だにも のりにぞ來つる 見れば苦しみ〕
ヒコホシハ ナゲカスツマニ コトダニモ ノリニゾキツル ミレバクルシミ
孫星嘆須孋事谷毛告余叙來鶴見者苦彌 |
歌意、通説と変わりはない
「告」を「のり」として置こう、と根拠もなく訓む、
『新考』の結句の説を、「妄」としている
確かに、続く者がいない
しかし、それをいうなら、折口信夫の説の方が、もっと異質な解釈だとは思うのだが... |
彦星ハ自分ヲ思ツテ、嘆イテヰル妻ニ、ソノ樣子ヲ見ルト苦シイノデ、セメテ言葉ダケデモ、言ヒ慰メヨウト思ツテ、言ヒニ來マシタ。
○告余叙來鶴[ノリニゾキヅル]――告は集中ノリともツゲともよんであるが、ここはノリとして置かう。余は元暦校本・類聚古集、その他の古本多くは爾に作つてゐるから、その誤に違ひない。
〔評〕 彦星の心を第三者が側から述べたものである。新考に結句を不見者苦彌[ミズバクルシミ]と改めたのは妄であらう。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
〔彦星は 嘆かす孋に、言だにも 告げにぞ來つる。見れば苦しみ。〕
ヒコボシハ ナゲカスツマニ コトダニモ ツゲニゾキツル ミレバ(ミネバ)クルシミ
孫星嘆須孋事谷毛告尓敍來鶴見者苦弥 |
これも通説に違わない
「みればくるしみ」が、何故変なのだろう
「釈」では、それに沿っての解釈を添えながら、一方では『新考』説を採るのだろうか
私は、「みれば」も「みずば」も、どちらも歌意としてはおかしくないので
ならば、敢えて表記の無い「不」を持ち出さない方がいいと思う |
【譯】牽牛星は、歎いている妻に、言葉だけでも告げに來たのだ。見ると苦しいので。
【釋】嘆須孋 ナゲカスツマニ。ナゲカスは嘆クの敬語法。
見者苦弥 ミレバクルシミ。見ると苦しいのでというのは、變であるから、打消の字はないが、ミネバであるかもしれない。
【評語】牽牛星は、今はただおとずれをするだけに來たのだという内容で、七日の夕以外の夜について歌つている。これは第三者として、取り扱つている。
|
| 『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕 |
「評釈」私見 |
| 〔彦星は嘆かす孋に言だにも告げにぞ來つる見れば苦しみ〕 |
ここでいう、明らかな矛盾というのは、「告げに来た」とする前に、
「見れば苦しい」ことをいうのだろうか
それは、「告げに来て」初めて、その「苦しみ」を見るので、
その「苦しみ」を見ることが理由にはならない、と言うことなのだろうか
「嘆かす」の理由は、それこそ「歌」として籠められた「ファンタジー」ではないか
逢えないからこそ、苦しみ嘆いている
『新考』の歌の矛盾を回避せんがための「不」は、軽々に賛同できない、とする |
【譯】彦星は嘆いて居られる妻に、慰めの言葉だけでもと思つて、それを言ひに来た。妻の様子を見ると苦しいので。
【評】織女に対する彦星の暖かい思ひやりを第三者が詠んだものであるが、條理が徹しない憾がある。特に「告げにぞ来つる」の行動と「見れば苦しみ」の条件とは明かに時間的矛盾であり、「歎かす」の理由も曖昧である。要するに拙作であらう。
【語】○歎かす 「歎く」の敬語であるが、ここは親愛の心持を表はす。○見れば苦しみ 歎くのを見てゐるのが苦しいのでの意。『新考』に「不」を補つて「見ずは苦しみ」と解したのは、前後に感じられる矛盾を除く意図に出たと思はれるが、それは軽々には賛し難い。
【訓】○告げにぞ 白文「告爾叙」。告はノリとも訓める。「爾」を通行本「余」に作るは誤。『元暦校本』によつて訂す。 |
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
〔彦星は嘆かす妻に言だにも告げにぞ來つる見れば苦しみ〕
ヒコボシハ ナゲカスツマニ コトダニモ ツゲニゾキツル ミレバクルシミ
孫星嘆須孋事谷毛告爾敍來鶴見者苦彌 |
歌意、通説で特筆無し
しかし、人間界の「人」が、二星の行動を見やって、というのなら
もっとそれに沿うような「歌意解釈」でもいいのではないか、と思う |
【大意】彦星は、嘆かれる妻に、言葉だけでも告げに来た。嘆くのを見れば苦しいので。
【作意】人間界から牽牛が、織女の嘆きを見て、言葉をかけに来たと、二星の行動を見やつての歌である。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
〔彦星は 歎かす妻に 言だにも 告げにぞ來つる 見れば苦しみ〕
ヒコボシハ ナゲカスツマニ コトダニモ ツゲニゾキツル ミレバクルシミ
孫星嘆須孋事谷毛告尓敍來鶴見者苦彌(『元暦校本』) |
この歌意解釈も通説に倣う...
近年の歌意解釈は、どれも一様に彦星が、逢えないで嘆く織女星に、せめて声だけでもかけて慰めようと...
ここに、一番の矛盾を感じるが、そうではないのだろうか...
むしろ、そのように織女が逢えなくて嘆く姿を見るのが苦しい、というのなら
せめて声だけでもかけてやりたい、と逢いに行く、と解釈するより
古注釈書に多く解されている、「使者」に言付けを託すのが自然だろう
第三者が、見て詠う、というのもおかしい
第三者が見るのは、織女星を慰めるために天の川を渡る彦星なのだから
その渡河自体で、完結するのではないか
何も「ことだにも」と語ることはない
岩波の「試案」を、用例的になのか、文法的になのか否定しているが...
|
【口訳】彦星は歎いてゐられる妻に、せめて慰めの言葉だけでも通じようとやつて来たことよ。見てゐると苦しいので。
【訓釈】彦星は―「孫」の字、『細井本』と版本とに「彦」とあるが、『元暦校本・類聚古集・紀州本』その他による。「孫」をヒコと訓むこと前(5・810序)に述べた。『倭名抄(二)』に「孫」「和名无麻古(ムマコ)、一云比古(ヒコ)」とある。
歎かす妻に―「す」は敬語(1・1)。織女が逢へないで歎いてゐるのをいふ。
言だにも告げにぞ來つる―「告尓」の「尓」の字、『西本願寺本・細井本』と版本に「余」に誤る。『元・類』以下一致した訓であるが、『童蒙抄』にノレトゾ、『新考』に「告等(ノラムト)ゾ」、『新訓』にノリニゾと改めたが、「のる」と「つぐ」との相違は前(2・109、3・317)に述べた如く、「事毛告良比(コトモノラヒ)」(9・1740)の一例があるが、「許登都礙夜良牟(コトツゲヤラム)」(15・3640)、「許登都礙夜良武(コトツゲヤラム)」(15・3676)などいづれもツゲムであり、「事太尓不告(コトダニツゲズ)」(3・443)と同じく旧訓により、「事」は「言」の意で、夫婦のちぎりを結ぶ事は出来ずとも、せめて言葉だけでも通じようとやつて来た、と解すべきである。従つてこれも七日の夜の事ではない。七夕の一年ただ一度の逢瀬に対する惻隠の心が、いろいろの空想を逞しくして、かうした歌となつたのである。『古典大系本補注』に「告げに」の「に」を打消の「に」として「彦星は別れを嘆く織女星に、言葉だけもかけずに別れて来た」といふ「一試案」を出してをられるが、打消の「に」はこの先にも「飽足尓(アキタラニ)」(2009)があり、そこでも述べるが、「にぞ来つる」などとつづく例は無く、七夕の歌だから七日の夜の歌と解しようとするところからさうした案も出るのであるが、右に述べたやうに、人間世界の事に移した自由な空想歌と見ればよくわかるのである。
見れば苦しみ―川をへだてて織女の歎いてゐるさまを見てゐると苦しいので、の意。
【考】流布本赤人集に「ひこぼしがうらむる妹が」「けふは苦しも」とある。
|
|
|

| |
| 「へだてておきし」...みなしがは... |
| |
| 『しらとりわたり』 |
| 【歌意2011】 |
(ひさかたの)天空のしるしを創るため、
水のない川を、二人を別つために天と地の間に置いた
それを取り決めた神代が、私はとても恨めしく思われる |
| |
| |
この歌を、「七夕歌」として読めば、
当然その解釈は、神代の時代に置かれた「天の川」によって
牽牛と織女は、年に一度の逢瀬しか、許されなくなった、となる
そのことが、語らずとも前提になっている...それが「七夕の歌」といえるものだ
そして、多くの注釈書もまた、「天の川」は「あまつしるし」として置かれた、という
「あまつしるし」という語義に、「天上にある境界線」という意味もある
それを「水無川(みなしがは)」を「天の川」として置いたのだから、
一見何ともないように思えてしまうが、
どうして天空に、境界線が置かれる必要があったのだろう
そして、この歌では、そこから年に一度の逢瀬は許されているなどと、少しも語られていない
「万葉歌」の七夕歌には、様々な展開がある
ならば、語られないことを、既知のように認めて解釈してしまっては
その歌の解釈に、中途半端な気持ちを抱くことになってしまうのではないか、と思う
まず、語られていることから、解を試み
そこにどうしても埋められない「言葉」が必要であれば、
語られていない「言葉」を当てはめ、それで解釈が成り立つかどうか...
だから、私がよくする方法は、「部立て」に捉われず読んでみて
ああ、これは「何々」のことを詠ったものか、とか
「何々」のことにしては、理解するのが難しい、とか
そんなアプローチも、必要だと思っている
この歌、「あまつしるし」「みなしがは」「かみよしうらめし」という語がある
「あまつしるし」を「天上の境界縁」とするのは無理はなかった
そして、「みなしがは」も、「天の川」と一般的に言われているのも、無理はない
しかし、結句の「かみよしうらめし」というのが、どうしても引っかかる
このところ採り上げている「万葉歌」で、
「やちほこのかみ」とか「あめつちと わかれしときゆ」などの表現があった
その表現のように、創造の時からの「伝承」を意図しているものだが
その言い方に倣うとすれば、この「あまつしるし」というのは、
「天上界」に限る必要もないのではないか
しかも、「年に一度の逢瀬の保障」など、どこにも語られていない
ただただ、そうした「水無川」という「境界線」を設けた「神代を恨む」
絶対に、行き来できないところ
それ故に、「恨む」
七夕歌なら、たとえ七月七日しか逢えないとしても
そのたった一日のために、「生きていける」と前向きな想いを持てる
しかし、その逢えるという「保障」がなければ、
当然、死ぬほどの「恨み」にはなるだろう
何故なら、どんなに想っていても、逢うことは叶わないのだから...
この歌、七夕伝説の舞台を使って、二度と逢うことも出来ない恋人の嘆きを詠っている
そんな風にも思えてきた
「あまつしるし」というのは、天上の境界線という、
初めから「天の川」を想定してのものではなく、
「地上と天上を分つものとして、みなしがはを置いた」と解釈したい
それなら、「天の印」という表現に、具体的な実像が見えてくる
この「みなしがは」によって、「天と地が分けられた」
それにより、地上の男(便宜上であり女でもいい)は、
天上の女に逢うことも出来ない
逢いに行く手段が、地上の男にはない
男は、「人間」として、地上に残された
逆に、天上に居る女もまた、地上に降りる手段を持たない
年に一度の逢瀬どころか、永遠に逢うことも出来なくなった二人だ
天も地も、神が治めていた「神代」
その時代に、行き来できた二人も、何が原因なのか
天と地の間に、水無川が置かれ、別れ別れにされてしまった
地上の男は、その「水無川」を置いた「神代」の治世を恨む
天上の女は、ひょっとすると、男が何とか手段を講じて天上まで来てくれるかもしれない
そんな儚い望みを、何度も何度も夢見ているのかもしれない
大陸伝来の「七夕伝説」に、多くの日本化された展開が許されるのなら
このように、一つの歌からもまた、「悲恋」を展開させることもできる
余談になるが、右頁の「引用歌」〔2827・2828〕の「みなせがは」を解せば
この別れ離れになった二人の「想い」は、
逢うことの叶わぬ、「川」の伏流のように、いつまでも続くものだろう
だからこそ、いっそう哀しみが残る
いつしか、天上の女は、「しらとり」を手懐けて、
地上の男の所に、やって来るのかもしれない
年に一度と言わず、人間界に生きることを覚悟して...
私は、そう応援したくなる...だから、想いは大切にしてくれ、と
| |
| |
 |
| |
|
|
掲載日:2014.05.10
| |
| 秋雑歌 七夕 |
| 久方 天印等 水無川 隔而置之 神世之恨 |
| ひさかたの天つしるしと水無し川隔てて置きし神代し恨めし |
| ひさかたの あまつしるしと みなしがは へだてておきし かみよしうらめし |
| 巻第十 2011 秋雑歌 七夕 柿本人麻呂歌集出 |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】〔571〕
【古今和歌六帖】〔2764〕
【八雲御抄】〔113〕
[引用「万葉歌」]
【みなしがは】〔2827・2828〕
[資料]
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
【七夕】〔中華民国[国立成功大学、成大宗教與文化学報 第七期 論文]〕
【織女と牽牛】〔講談社学術文庫「星の神話・伝説」野尻抱影〕
| 【2011】 語義 意味・活用・接続 |
| ひさかたの [久方] 〔枕詞〕天に関係のある語にかかる |
| あまつしるしと [天印等] |
| あまつしるし [天つ印] |
天上にある境界線、天の川をさす・皇位のしるし |
| と [格助詞] |
[比喩] ~として |
体言につく |
| みなしがは [水無川] 水の無い川の意から、天の川をさす |
| へだてておきし [隔而置之] |
| へだて [隔つ] |
[他タ下二・連用形] 間に物を置いて遮る |
| て [接続助詞] |
[補足(行われ方)] ~ようにして・~て |
連用形につく |
| おき [置く] |
[他カ四・連用形] その位置に置く・据える・設ける |
| し [助動詞] |
[過去・連体形] ~た・~ていた |
連用形につく |
| かみよしうらめし [神世之恨] |
| かみよ [神代] |
神々が国を治めたという神話時代 |
| し [副助詞] |
語調を整え、強意を表す |
| 〔接続〕体言、または活用語の連体形・連用形、副詞、助詞などにつく |
| うらめし [恨めし] |
[形シク・終止形] 恨みに思われる・残念である |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [あまつしるしと] |
『記紀』には、「天つ神」の直系子孫としての証拠の品、とあり
皇位の印、として用いられる語だが、
この歌では、「天上にある境界線として」との意になる
ただし、この語の持つ意味を拡げて思えば、「越境禁止」の境界線となることから
この「あまつしるし」を用いたということは、
「結界」のような「絶対的」な「境界線」になるのだろう
|
| |
| [みなしがは] |
この語は、「水無瀬川(みなせがわ)」として訓まれることもあり、
実際に、旧訓では殆ど「みなせがわ」と訓んでいる
しかし、古語辞典では、この二語には明確な違いの部分もある
「みなしがわ」では、その「水の無い川」の状態から、「天の川」を表現するが
「みなせがわ」では、本来の意となる「水の無い川・伏流の河川」の意を持つ
この歌の歌意に沿うものであれば、「みなしがは」と訓むものだろう
そうであれば、象徴としての「川」なので
幾つかの注釈書で「矛盾」というような「舟を漕いで渡る」
という解釈もおかしくない
「みなせがわ」の用例で、私の気に入っている歌、「問答」の二首を載せる
この場合の「みなせがは」は、勿論天の川ではない
| 巻第十一 問答 |
| 浦觸而 物莫念 天雲之 絶多不心 吾念莫國 |
| うらぶれて物な思ひそ天雲のたゆたふ心我が思はなくに |
| うらぶれて ものなおもひそ あまくもの たゆたふこころ わがおもはなくに |
| 2827 作者不詳 |
〔語義〕
「うらぶる」の「うら」は「心」の意で、侘しく思う・悲しみに沈む
「ものなおもひそ」は、禁止表現の「~な~そ」で、物思いをするな
「あまくもの」は、雲が漂うことから「たゆたふ」にかかる「枕詞」
ただし、単なる「枕詞」ではなく、「たゆたふ」雲の実景としても表現されている
「たゆたふこころ」は、「思い迷って定まらない心・ためらう」
「なくに」は、「~(し)ないことだから・~(しない以上は)」 |
〔歌意〕
そんなに悲しみに沈み、物思いをしないでくれよ
天雲のように漂うような浮気心を、私は持っていないのだから |
|
| 浦觸而 物者不念 水無瀬川 有而毛水者 逝云物乎 |
| うらぶれて物は思はじ水無瀬川ありても水は行くといふものを |
| うらぶれて ものはおもはじ みなせがは ありてもみづは ゆくといふものを |
| 2828 作者不詳 |
〔語義〕
「じ」は、打消の推量の助動詞「じ」だが、主語が話し手の場合は、打消の意志を表す
「みなせがは」は、本来の「伏流」の意味を用い、表面はさりげなく装いながら、
心の中では絶えず思っている自分の気持ちを喩えたもの
「ありても」は、現在の状態を保っていることで、「みづはゆく」と続き、
その伏流水のように、人に知られず思い続けていることをいう
「といふものを」は、間投助詞「を」の文末用法で、詠嘆を表す |
〔歌意〕
悲しみに沈んで、物思いなどしていません
水瀬川のように、その水は人目にはつかないで流れる、というではありませんか
私の心も、人目にはつかないで... |
|
| |
| [おく] |
動詞「置く」の「自動詞」は、霜や露が降りる、などの意味になるが、
「他動詞」の場合は、一般的に現代でも使われる意味になる
ただし、古語辞典を読んでいて、もう一つの用法を知った
それは、「補助動詞」としての用法だ
動詞の連用形や、連用形に助詞「て」の接続したものについて
「あらかじめ~する」、「かねて~(て)おく」という意もあることを、知る
|
| |
| [かみよ] |
記紀神話の天地開闢から神武天皇治世の前まで、を「神代」という
「かむよ」とも訓む
|
| |
| [うらめし] |
「うらめし」は、動詞「うらむ」に対応する形容詞
他動詞上二段「うらむ」、他動詞四段「うらむ」は、
| 上二段 |
| ① 恨みに思う・不満に思う・憎く思う |
| ② 恨みごとを言う・不平を言う |
| ③ 恨みを晴らす・しかえしをする |
| ④ 悲しむ・嘆く |
| ⑤ (自動詞的な用法で、虫や風などが)悲しげに音をたてる |
| 四段 |
| 上二段の①と同じく、恨みに思う・不満に思う・憎く思う |
「うらむ」の語源として、「心(うら)見る」が考えられ、
上代では上一段活用であったようだ
そして、中古になり上二段、近世になって四段に活用して、現代に至る
語源とされる「心見る」は、確かに「うらみ」そのものが「こころ」に発するものなので
何に対して「うらむ」のかではなく、
自分の心を「見詰め」る行為なのかもしれない |
| |
| |
| |
[織女牛(伝説)] 講談社学術文庫「星の神話・伝説」野尻抱影
|
織女は、こと座のベーガ、牽牛は、わし座のアルタイルの中国名ですが、この二つの一等星が、天の川を隔てて瞬き合うさまは、正に一対の夫婦星で、世界にもまれな七夕伝説が中国に生まれたのも、自然に思われます。
織女は天帝の娘で、天の川の東の岸に住み、父のいいつけで明けても暮れても「機」を織っていました。その布は雲錦といって、五色にてり輝き、眩しいほど美しいものでしたが、織女はそれを織るので、髪を結う暇もなく、化粧をすることも忘れてしまいました。
やがて天帝も娘を不憫に思って、天の川の西に住む牽牛という若者とめあわせました。すると、織女は新しい生活の愉しさに、はた織りをなまけて、化粧にばかり身をやつすようになりました。それで天帝は腹を立てて、織女を再び東の岸へ連れ戻し、一年に一度、七月七日の夜だけ、天の川を渡って、夫に会うことを許してやりました。
こうしてその日に雨が降ると、天の川の水かさが増すために、織女は川を渡ることができないので、目のいい人には雲を通して、二つの星が天の川の両岸で、哀しげに五色に煌くのが見えるといいます。
その夜、カササギが、天の川の中に翼をならべて橋となり、織女を渡してやるというので、日本でも、これを『かささぎの橋』といって歌に詠みました。
中国では唐の時代から七月七日の夕べを七夕(しちせき)といって、織女牽牛を祭り、女たちが、針仕事や、琴や、文字などが上手になるように祈りました。
この伝説と祭りとが、遣唐使や留学生によって日本へ伝わり、織女には、はた織りの女神の名をあててタナバタ(棚機)とよび、牽牛は、男の星の意味でヒコボシ(彦星)とよび、また、オリヒメ、ウシカイボシともいいました。そして七夕と書いて、『タナバタ』と読むようになりました。 |
|
| |
|
|
| 掲題歌[2011]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】
| 柿本人麿集 私家集大成第一巻-4(冷泉家時雨亭叢書『素寂本私家集西山本私家集』) |
| ヒサカタノアメノシルシトミナシカハ ヘタテヽヲキシカミヨノウラミ |
柿本人麿集中 恋部 覊旅発思 万十 571
|
【古今和歌六帖 ([永延元年(987)頃]撰、兼明親王・源順か)】
| 新編国歌大観第二巻-4 [宮内庁書陵部蔵五一〇・三四] |
| ひさかたのあめのしるしとみなしがはへだてておきしかみよのうらみ |
第五 雑思 物へだてたる 2764 人丸
|
この歌集の部立て「物へだてたる」に、「水無川」への解釈が含まれている
【八雲御抄 (文暦元年[1234]頃、順徳院[1197~1242]作)】
| 新編国歌大観第五巻-311 [日本歌学大系別巻三] |
| ひさかたのあまのおしでとみなしがはへだてておきし神よのうらみ |
巻三 時節部 113
|
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「久方天印等水無河隔而置之神世之恨」
「ヒサカタノ アマノシルシト ミナセカハ ヘタテヽオキシ カミヨノウラミ」(「【】」は編集) |
| 〔本文〕頭注、『八雲抄』、第三「万十 ひさかたのあまのをしてとみなしかはへたてておきし神代のうらみ」 |
| 「河」 |
『元暦校本・類聚古集・京都大学本』「川」 |
| 〔訓〕 |
| アマノシルシト |
『元暦校本』「あめのしるしと」。「しるし」ノ右ニ赭「ヲシテ」アリ
『類聚古集』「あめのをしてと」
『神田本』「アメノヲシテト」
『細井本』漢字ノ左ニ「アメノヲシテト』トアリ
『京都大学本』赭ニテ「マ」ヲ消セリ。ソノ右ニ赭「メ」あり。「印」ノ左ニ赭「ヲシテ」アリ
|
| ミナセカハ |
『元暦校本』「みなしかは」
『類聚古集』「みてしかは」
『神田本』「ミナシカハ」
『西本願寺本』左ニ貼紙別筆「ミナシ古点又イ本同此御本若アヤマルん」アリ
『京都大学本』「水無」ノ左ニ赭「ナレ」アリ。赭ニテ右ノ訓ト入レ換フ可キヲ示セリ
|
| オキシ |
『神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本』「ヲキシ」
|
| カミヨノウラミ |
『元暦校本』「よ」ナシ。但右ニ墨「よ」アリ。同筆カ
『類聚古集』「かみよのうらに」
|
| 〔諸説〕 |
| ○[アマノシルシト]『代匠記初稿本』「アマノオシテト」、『万葉考』「アマツルシト」○[ミナセカハ]『万葉集管見』「ミナシカハ」○[カミヨノウラミ]『童蒙抄』「カミヨシウラメシ」 |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [2011] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
〔ひさかたのあまのしるしとみなせ河へたててをきし神世のうらみ〕
久方天印[イをして]等水無瀬[古みなし天河名]河隔而置之神世之恨
|
「あまのしるし」の説明を述べた後、「みなせがは」の由来を言うが、
この書では「水無瀬河」との表記を用いている
水の無い川をおき、年に一度だけしか渡られないことを決めた神世への恨み |
| ひさかたのあまのしるし 玄天に銀河の明らかなるは印のあさやかなるやうなれはあまのしるしと云也イをしてといふも印の心也みなせ河は古点みなし河と和して類聚萬葉等にあり八雲抄天河の所にみなし河水只の折彼川に水のなきかと有此河を中に隔てゝ年に一夜ならては逢せぬ神世の恨ふかしと也神世のうらみとはかみよゝりかく定めをきしうらみといふ心也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
〔ヒサカタノアマノシルシトミナセカハヘタテヽオキシカミヨノウラミ〕
久方天印等水無河隔而置之神世之恨 |
「印」は「しるし」、「おして」とも読める、という
「おして」とは、無理に、しいて、の副詞「おして」なのかな
それに、立ちはだかる、の意の四段動詞「押し立つ」の連用形...
要は、「結界」のような意味合いを持たせることなのだろうか
それなら「印」という表記も理解し易いが...
八雲抄に「おして」と訓み、この歌を載せるのは、そんな歌意を含んでいるとの解釈なのだろう
「みなしかは」の表現にも解釈を示めす |
天印等、[六帖云、アメノシルシト、] 水無河、[六帖云、ミナシカハ、八雲御抄同此、官本又點亦同、]
八雲御抄に天印をあまのおしてとよませ給ひたるは古點なるべけれど、下の長歌に久方乃天驗常氐云々此今と同じきを、印はしるしともおしてともよめど、驗はおしてとよまねば彼を以て此を證するに今の點當れるにや、水無瀬河はミナシガハとよめる然るべき歟、但津國の水無瀬河をも第十一には水無河とかけり、河内の天河の名も空に通へば水無瀬河も亦空に通はして名付たるにやあらむ知べからねば左右なう定がたし、古事記云、且其天尾羽張(ノ)神者逆塞上(テ)天安河之水(ヲ)而塞(テ)道居、故佗神不得行云々、此に依れば水無河とは云ひがたかるべきを、神變は測がたければ下界の水の如くなる水のなき意に名付たるにや六帖には物へだてたると云に入れたり、
|
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、信名、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
〔ひさかたの、あめのしるしと、みなしがは、へだてゝおきし、神よしうらめし 〕
久方天印等水無河隔而置之神世之恨 |
本来の「川」の呼称であれば「水無瀬川」とある方が一般的で、その地名もある
ただし、天上の地名を移したものであれば、天上に「水」は無いものであり、
その義から、「天の川」のことと訓ませる、のか、と述べている
天上の定法、という言葉を持ち出しているのは、「七夕伝説」が神代の時代から
すでに決められている「年に一度の逢瀬」を中心としていることを言うのだろう
この書から、結句の「うらめし」が通説とされているようだ
それまでは、名詞「うらみ」で結んでいた
|
| 水無河 一本水無瀬河と有。不可然か。然し今國土にも水無瀬河と云ふ地名あるは、天上の地名を移したるか、たゞ天上の川故、水無河と書て義訓にあまの川と讀ませたるか。又神代紀、天のやす河にあるいほつ岩村となると云古語によりて皆石の河と云ふ義の略語にて、みなしとは云へるか。此等の義は何れとも外に證據なければ極め難し。所見の證明に從ふ也。歌の意は、天上の定法とて、七夕の昔より天の川を中に距てゝ、年に一度ならでは逢ふ事ならぬ掟の、その初めし神代の昔今更恨めしきとの意也。恨はらしとも讀まんか
|
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
久方(ノ)、 冠辭
天印等[アマツシルシト]、水無[ミナシ]河、 天漢をさしてたゝちにみなし川といふなり
隔而/置之[オキシ]、神世之恨[カミヨシウラメシ]、 |
珍しく平易な解釈 |
| 此歌は久方の天とつゞけ下してその言のしるしと天漢てふものを神世より定めおかして二星の逢瀬をへだて年に一夜のみなるがうらめしといふなり |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
〔ひさかたの。あまつしるしと。みなしがは。へだてておきし。かみよしうらめし。〕
久方。天印等。水無河。隔而置之。神世之恨。 |
ここで注目したのが、「みなせがは」ではなく「みなしがは」と訓んで、
その訓なればこそ「天漢(天の川)」の義と言っていることだ
やはり、「みなせがは」では、一般的な呼称になってしまう、という解釈なのだと思う |
| 此末長歌にも、天驗と定てしと有り。今本ミナセガハと訓みたれど、元暦本ミナシガハと有るに據るべし。即ち天漢の義なり。 |
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
〔ヒサカタノ。アマツシルシト。ミナシカハ。ヘダテテオキシ。カミヨシウラメシ。〕
久方天印等水無河隔而置之神世之恨
|
多くの書が、「ひさかたのあまつしるしと」の訓をいうとき、「この下の長歌にも」という
その長歌とは、この巻第十「秋雑歌 七夕」の最後の「長歌(反歌一首あり)」(2096)のことで
確かに、そこでも「久方乃 天驗常(アマツシルシト)」と訓まれている
それが「印」「験」を「しるし」と訓ませる根拠のようだ
気になるのは、「八雲抄」に採首されていることを、ことさら言うのが
何故だろう、と思う
歌意については、特筆すべきものはない |
天印等[アマツシルシト]は、此(ノ)下長歌にも、天驗常[アマツシルシト]とあり、
○水無河(無の下、拾穗本には瀬(ノ)字あり、)は、元暦本にミナシガハとよめり、八雲御抄にもしかよませ給へり、それによるべし、則(チ)天(ノ)河の事なり、實に、水の無(キ)河のよしに云るなり、
○歌(ノ)意は、天(ノ)河を天つ□[片+旁]示[シルシト]隔に置て、一年に一度ならでは、相見る事のかなはぬやうに、定めたりし神代が、一(ト)すぢに憾[ウラ]めし、となり、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
〔あまつしるしと水無[ミナシ]河へだてておきし神世しうらめし]
久方天印等水無河隔而置之神世之恨 |
「畫」は「画」の旧字体だとは思うが、その意とするのは、区画などからくる「境界線」かな
それを「しるし」と解することになるのだと思う
ここでも言う「あまのおしで」、この「おしで」とは、一体何だろう
|
アマツシルシのシルシは畫なり。莊子人間世に畫地而趨とあり孫子虚實に雖畫地而守之云々とあり文選の西京賦に畫地成川とあるシルシなり。こゝに天印とかき下なる長歌に天驗とかけるは共に借字なり。後世の歌にアマノオシデとよめるはこの天印を誤讀せるなりと契沖及濱臣(答問雜稿)おどろかせり
○ミナシ何といへるは天上の河なればしか云へるにや。ミナシ河は卷四に水瀬川、卷十一に水無瀬川と書きたればミナセ河ともいひしなり(アナシ河をアナセ河ともいふ如く)。但こゝは水無と書きたればミナセとはよみがたし |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| 久方の天つ標[シルシ]と、水無[ミナシ]川隔てゝおきし、神代しうらめし |
この解釈で、『新考』の「畫」が理解出来るが、しかしどんな「区切り」なのか、
ただ、水の無い川を置いた、というのでは、歌意を掴めないだろうに
このような歌意解釈に出合うと、そもそも七夕伝説が、どこまで既知のことで、
どこまで大前提として詠われるのが許されるのか、と考えてしまう |
| 天の區劃[クギリ]として、水のない天の川を隔てとして据ゑ置かれた、神代のことが恨しい。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
〔久方の 天つしるしと 水無河 隔てて置きし 神代し恨めし〕
ヒサカタノ アマツシルシト ミナシガハ ヘダテテオキシ カミヨシウラメシ
久方天印等水無川隔而置之神世之恨 |
「みなしがは」を、単に「天のしるし」という解釈では、「天の川」そのものの説明だけになってしまうが、どれも、同じことを書いている |
久方)空ノシルシトシテ、水ノ無イ天ノ川ヲ流シテソレデ我等二人ノ間ヲ、隔テテ置イタ神代ガ恨メシイ。
○天印等[アマツシルシト]――天の標として。次の長歌に天地跡別之時從久方乃天驗常定大王天之河原爾[アメツチトワカレシトキユヒサカタノアマツシルシトサダメテシアマノカハラニ](二〇九二)とあるのも同じ。
○水無河[ミナシガハ]――前に引いた長歌に天之河原爾[アマノカハラニ]とある通り、これは天の河を指してゐる。下界から見れば水が見えないので、水無川[ミナシガハ]といふのであらう。舊訓はミナセガハとある。
〔評〕 これは二星の心になつて詠んでゐる。悠久な、しかも逢瀬の尠い戀を悲しんでゐる。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
〔ひさかたの 天つ印と、水無し河、 隔てて置きし 神代し恨めし。〕
ヒサカタノ アマツシルシト ミナシガハ ヘダテテオキシ カミヨシウラメシ
久方天印等水無川隔而置之神世之恨 |
「これが天のしるしだ」と、少しはより実感できる解釈になっている
七夕伝説を、ことさら神話の時代からあるような演出に仕立てなければならないのだろうか |
【譯】これが天のしるしだと、水の無い川を隔てに置いた神代がうらめしい。
【釋】天印等 アマツシルシト。これが天である特徴として。天の川の横たわつていることをいう。
水無川 ミナシガハ。水の無い川。天の川をいう。天上の川だから水無シ川という。船で渡るという思想とは矛盾している表現である。
隔而置之 ヘダテテオキシ。牽牛と織女とのあいだに隔てておいた。
【評語】遠い神代に、天上でも天の川を隔てに置いたのだとしている。山川などが神代に作られたとする傳説を、天上にも持ち出したものである。これも七夕の傳説であるだけに、神代を出したのである。當事者に代つて詠んだ歌とも取れる。 |
| 『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕 |
「評釈」私見 |
| 〔ひさかたの天つ印と水無川隔てて置きし神代し恨めし〕 |
二人の逢瀬の「年に一度の」の制限を、言うのに、「天のしるし」であることが、
どうしても私には理解出来ない
勿論、その「天のしるし」の表現の本当の意味を知ればいいことなのだが...
どの書も、そこまで親切ではない
「水の無い川」をどうやって渡るか...「空想のつばさをはせてゐるのはおもしろい」という |
【譯】天上のしるしとして、水の無い天の河を、私たち二人の間に隔てて置いた神代が恨めしいことである。
【評】これは第三者としての歌ではなく、彦星か織女かの心になつての作である。天の河を隔てて夫婦交会の難いのを歎くあまりに、「神代し恨めし」と、運命を恨むことになつた。素朴な上代人の心に、この伝説の及ぼした悲哀の切実さが想像される。しかも大陸の伝説に、「神代」と日本化したのは注意すべきである。「水無」といふのは、下界から見た感じでいうのであらうか。天の川を船して渡り、或は渡舟にのつてわたり、或はかちわたりし、此の歌のごとく、水の無き川と様々に空想のつばさをはせてゐるのはおもしろい。
【語】○天つしるしと 彦星と織女とを隔てる天上での標としての意。下にも「久方の天つ験と定めてし天の河原に」(二〇九二)とある。 |
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
〔ひさかたの天つ印と水無し川へだてて置きし神世し恨めし。〕
ヒサカタノ アマツシルシト ミナシガハ ヘダテテオキシ カミヨシウラメシ
久方天印等水無川隔而置之神世之恨 |
「しるし」は「シメ」だという
確かに、意味としては同じようなところもある
要は、区画を示し、人の立ち入りを禁じるための標識のことだ
だから、水無しの川は、「天の川」として、立ち入り禁止の「川」ということになる
この解釈こそ、歌全体の解釈に沿うものだと思うが
しかし、その中から、年に一度の「逢瀬」が許されている、というのは
「七夕伝説」を持ち出す以上、必然なのかもしれない
しかし...どこにも、「年に一度の逢瀬を認める」など、表現されていないのだが... |
【大意】ヒサカタノ(枕詞)天の界の標として、水無川を、間をへだてて置いた、神世がうらまれる。
【語釈】アマツシルシト シルシはシメと同じで、境界標の意である。「印」は直ちにシメと訓まれる字故、アメナルシメトとも訓みたい所であるが、下の(二〇九二)にも「天験」をアマツシルシとあるので、旧来の訓をとるが、意は述べた如くである。
○ミナシガハ 水の無い川であるが、天の川をかう呼んだのである。
【作意】人間界より見て、天の川をシメとして、隔てられて居る、二星の運命を、同情して居る心持である。カミヨを言つたのは、それが古い時代であるだけの意である。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
〔ひさかたの 天つしるしと 水無し川 隔てて置きし 神代し恨めし〕
ヒサカタノ アマツシルシト ミナシガハ ヘダテテオキシ カミヨシウラメシ
久方天印等水無川隔而置之神世之恨(『元暦校本』) |
ここでいう「標識といふ程の意に用ゐたものと思はれる」には納得し難い
天の川が天上という空想の「川」なら、舟で渡る、という行為もまた、空想の「渡河」だから
矛盾と言うのはおかしい
|
【口訳】天上のしるしとして水の無い川を、中にへだてて置いた神代が恨めしいことよ。
【訓釈】天つしるしと―この先にも「天地と 別れし時ゆ ひさかたの 天験常(アマツシルシト) 定めてし 天の河原に」(2092)とある。「しるし」は前(3・338)に述べたやうに「效験」の意に用ゐる例が多いが、ここは「永代尓[ナガキヨニ] 標将為跡[シルシニセムト] 遐代尓[トホキヨニ] 語将継常[カタリツガムト]」(9・1809)とあるのと同じく、標識といふ程の意に用ゐたものと思はれる。
水無し川―天上の川だから水が無い川と云つたので、舟で渡るといふ考とは矛盾する事になる。
神代し恨めし―「神代」と云つたのは「八千戈の神の御代より」(2002)といふのと同じである。
【考】古今六帖(五「物へだてたる」)「あめのしるしと「かみよのうらみ」とある
|
|
|

| |
| 「とほくとも」...はやくつげこそ... |
| |
| 『たよりをまちて』 |
| 【歌意2012】 |
暗い夜霧に包まれて、いっそう遠くに感じられる妻よ
だから尚更、お前からの「たより」を待ち遠しく思っているので
早く寄こしてくれ |
| |
| |
たとえば、遠くに見えるものでも、
見えている限りは、心理的には「近く」と感じる場合がある
逆に、近くにあっても、この歌のように「夜霧」に包まれていれば
その心理としては、「遠く」に感じるものでは...
この歌、単に実景の描写ではなく
そんな心理的な「遠く」を表現しているのではないか、と思う
実景描写ではなく、その心理を背景に詠い、いかに「妹」が遠くにいるのか...
確かに、「たより」を待つのだから、実際も遠いのだろうが
ここで、ふと気になることに思い当たる
「たより」を「待つ」ということは、
「逢いたいのに、そう簡単に逢えない」のだから、ということなのだろう
この歌を、素直に言葉に従って解釈しようとすると
単に「遠い」から、簡単に逢えない、とでも言いたいようなのだが
その為に、「宵霧隠」と表現する必要はないのでは、と
もっとも、この語句には助詞が表記されていないので
「よぎりこもりて」とも、「よぎりかくれて」とする一方、
「よぎりにこもり」や、「よぎりにかくれ」など訓釈はいろいろできる
「よぎりに」とする契沖の訓は、後に続くものはいないが、
現代になって、幾つかの叢書の「万葉集」、
例えば小学館の「古典全集」(新旧とも)、岩波の「新古典大系」、新潮社の「古典集成」など
その訓を採用している
和歌として、どちらがいいのか、私には解らない
しかし、語感としては、口語に近い「夜霧に」とするよりも、
この助詞を詠まない方が、私は好きなのだが
何しろ、歌そのものが漢語のように「宵霧隠」なのだから、
本当に詠われた「訓」というのは、誰にも正解は探し出せないだろう
ただ、この歌で私が気になるこの部分は、
その助詞の位置で、随分歌意が変わりそうだ、と感じたからだ
一応、現代の訓に従って、解釈はしている
しかし、助詞「に」がなかったら...
勿論、それは旧訓などでも、そう訓むのだから、表面的には歌意に大差はないのだろうが
私が感じるのは、「よぎりに」の場合では、
まさに、自然現象の「よぎり」であり、実景描写に成り得る
そして「よぎり」で「こもりて」や「かくりて」などと続けば
それは自然の実景描写ではなく、「遠く」を表現しているのではないか、と
先に書いたように、「遠い」から逢えない、だから「たより」が欲しい
実際に「遠い」のであれば「よぎりこもりて」と言うのだと思う
そして、本当は近くなのに、「遠い」と表現しなければならない事情がある
その場合に「よぎりにこもりて」が相応しいと思う
そうなると、現代の叢書をテキストにしている現状では
この歌は「本当は近いのに、遠く」と詠う何か、を探ることになる
近いのに「たより」を待つなどと言うのは、
その上、ただ「待つ」のではなく、「早く告げこそ」と、催促までしている
この段階で、それが遠くであろうと、近くであろうと、「七夕」伝説の背景の意味はない
年に一度の逢瀬に、どんなに不満があろうと、それに従うからこそ、
その「悲恋」に多くの人が惹き付けられる
それが、この歌のように、形振り構わず「便りを寄こせ」と言えば、
そこに、どうして「二星の悲恋」を見ることが出来るのだろう
この歌、柿本人麻呂歌集に載る歌だが、
その「歌集」の伝本の一つには、「恋部 相聞」とある
万葉集には、柿本人麿歌集から多くの歌が載せられているが
この「人麻呂歌集」歌、万葉の編者の勘違いで「七夕」の部立てに配されたのかもしれない
私は、その方がいいと思う
古注釈書には、部立て通りに、牽牛と織女の物語として歌意解釈しているものもあるが
それは、たんに「男女の個名」としては意味があり
「七夕」の主人公と、たまたま名前が同じだ、と皮肉っぽく受止めている
話しを戻そう
「近い」のに、「夜霧に包まれ」、その居場所も見当がつかないほど遠くに感じられる
お前の消息が解らないのは、これほど苦しいことなのか
どうか、私を安心させる「たより」を、早く届けてくれ、と思える歌でもある
| 改意【歌意2012】 |
この夜霧につつまれ、いとしい妹は、いったいどこにいるのだろう
心配で、これほど落ち着かないとは...
どこにいようとも、「つてごと」を早く寄こしてくれ
私を安心させてくれ、妹よ |
何が原因で、この情況になったのか
それは、また想像を膨らませることのできる「相聞」ならではのことで
折に触れて、気ままに考えてみよう
いろんなことが浮んでくるかと思う
勿論、この歌と相関をなす一首もあるかもしれない...そこに、理由を思わせるような一首が...
|
|
掲載日:2014.05.11
| |
| 秋雑歌 七夕 |
| 黒玉 宵霧隠 遠鞆 妹傳 速告与 |
| ぬばたまの夜霧に隠り遠くとも妹が伝へは早く告げこそ |
| ぬばたまの よぎりにこもり とほくとも いもがつたへは はやくつげこそ |
| 巻第十 2012 秋雑歌 七夕 柿本人麻呂歌集出 |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】〔471〕
【赤人集】〔159・280〕
[資料]
【掲題歌資料】〔校本万葉集及び近代までの注釈書〕
【七夕】〔中華民国[国立成功大学、成大宗教與文化学報 第七期 論文]〕
【織女と牽牛】〔講談社学術文庫「星の神話・伝説」野尻抱影〕
| 【2012】 語義 意味・活用・接続 |
| ぬばたまの [黒玉] 〔枕詞〕夜や黒髪など、黒いものや暗いものにかかる |
| よぎりにこもり [宵霧隠] |
| こもり [籠る・隠る] |
[自ラ四・連用形] 囲まれている・隠れる・ひそむ・閉じこもる |
| とほくとも [遠鞆] |
| とほく [遠し] |
[形ク・連用形] 遠い・疎遠だ・気が進まない・縁が薄い |
| とも [接続助詞] |
[逆接の仮定条件] たとえ~にしても 〔接続については、「注記」〕 |
| 〔成立〕接続助詞「と」に係助詞「も」 |
| いもがつたへは [妹傳] |
| つたへ [伝へ] |
伝言・ことづて・たより |
| はやくつげこそ [速告与] |
| はやく [速し・早し] |
[形ク・連用形] (時間的に)早い・(速度が)速い・すばやい |
| つげ [告ぐ] |
[他ガ下二・連用形] 知らせる・伝える |
| こそ [終助詞] |
[希望] ~てほしい |
連用形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
| [ぬばたまの] |
「万葉集中」で、万葉仮名の表記を除けば、
「黒玉・烏玉・烏珠・野干玉・夜干玉」などの用字例がある
和名抄巻二十、「射干一名烏扇 射音夜 和名 加良須阿布岐」とあり、
射干は野干と通じるので、「ヌバタマ」は、烏扇の実のこととされる
「烏扇」は、「ヒオオギ」ともいい、アヤメ科の多年草
高さは50~100センチ、葉は剣状で檜扇を開いたような形に重なり並ぶ
夏に、黄赤色で内側に暗紅色の斑点のある六弁の花をつける
その黒色の球形の種子を「ヌバタマ」といったものといわれる
一般に、万葉集では「ぬばたまの」で訓み揃えられているが
人麻呂歌集歌や赤人集などでは、「むばたまの」と詠われているのが残る
古語辞典を引くと、「むばたま」も、「ぬばたま」に同じと書かれている
また、『元暦校本』や『神田本』など、「うはたまの(うばたまの)」とあり、
『拾穂抄』では「うはたまの」と訓むが、
これも、その表記は「烏羽玉の」であり「烏玉」が当てられ
古語辞典でも、「ぬばたまの」の転じたもの、と載っている
|
| |
| [とも] |
接続助詞「とも」の接続に関しては、
動詞・形容動詞・助動詞(動詞・形容動詞型活用)の終止形、
形容詞・助動詞(形容詞型活用・打消の「ず」)の連用形につく
鎌倉時代以降は、動詞・形容動詞・助動詞(動詞・形容動詞型活用)の連体形につく場合もある
|
| 古語辞典より |
| 接続に関して、奈良時代の文献に特例が見られる。すなわち、上一段活用の動詞「見る」に接続する場合、「終日(ひねもす)に見とも飽くべき浦にあらなくに」(万18・4061)のように「見とも」の形が表われる。これは「見べし」「見らむ」の用例とともに、動詞「見る」の接続の古い形を残したものと見られる。 |
|
| [いもがつたへは] |
原文「妹傳」を、旧訓は「いもしつたへは」とある
この「し」は、おそらく強意を表す副助詞「し」だと思う
「愛しい妹から」を強調して、その「伝言」ということだと思う
これを、「いもが」と訓み始めたのは、契沖からで
それでも、この第四句は「イモガツカヒハ」と、
「伝言」をもたらす「使者」にと、意訳している
さすがに、その訓を継ぐ書は見当たらないが
「訓」ではなく「訳」であれば、確かにその「意」だ
『古義』では、集中でも「伝言(ツテゴト)」の用例があり、
この歌も、それに倣って「言」が脱したものと解釈し、「イモガツテゴト」と訓む
この訓は、その後の幾つかの注釈書でも採られてはいるが、一過性のようだ
|
| |
| |
| [こそ] |
終助詞「こそ」は、係助詞「こそ」から変化したとする説と、
希望の助動詞「こす」の命令形として扱う説とがあるが、定説はないようだ
|
| |
| |
 |
| |
[織女牛(伝説)] 講談社学術文庫「星の神話・伝説」野尻抱影
|
織女は、こと座のベーガ、牽牛は、わし座のアルタイルの中国名ですが、この二つの一等星が、天の川を隔てて瞬き合うさまは、正に一対の夫婦星で、世界にもまれな七夕伝説が中国に生まれたのも、自然に思われます。
織女は天帝の娘で、天の川の東の岸に住み、父のいいつけで明けても暮れても「機」を織っていました。その布は雲錦といって、五色にてり輝き、眩しいほど美しいものでしたが、織女はそれを織るので、髪を結う暇もなく、化粧をすることも忘れてしまいました。
やがて天帝も娘を不憫に思って、天の川の西に住む牽牛という若者とめあわせました。すると、織女は新しい生活の愉しさに、はた織りをなまけて、化粧にばかり身をやつすようになりました。それで天帝は腹を立てて、織女を再び東の岸へ連れ戻し、一年に一度、七月七日の夜だけ、天の川を渡って、夫に会うことを許してやりました。
こうしてその日に雨が降ると、天の川の水かさが増すために、織女は川を渡ることができないので、目のいい人には雲を通して、二つの星が天の川の両岸で、哀しげに五色に煌くのが見えるといいます。
その夜、カササギが、天の川の中に翼をならべて橋となり、織女を渡してやるというので、日本でも、これを『かささぎの橋』といって歌に詠みました。
中国では唐の時代から七月七日の夕べを七夕(しちせき)といって、織女牽牛を祭り、女たちが、針仕事や、琴や、文字などが上手になるように祈りました。
この伝説と祭りとが、遣唐使や留学生によって日本へ伝わり、織女には、はた織りの女神の名をあててタナバタ(棚機)とよび、牽牛は、男の星の意味でヒコボシ(彦星)とよび、また、オリヒメ、ウシカイボシともいいました。そして七夕と書いて、『タナバタ』と読むようになりました。 |
|
| |
|
|
| 掲題歌[2012]についての資料 関連歌集については、[諸本・諸注 その他の歌集] |
[収載歌集]
【柿本人麻呂歌集】
| 柿本人麿集 私家集大成第一巻-4(冷泉家時雨亭叢書『素寂本私家集西山本私家集』) |
| ムハタマノヨルヒハカクレトホクトモ イモシツタヘハヽヤクツケコヨ |
柿本人麿集中 恋部 相聞 万十 471
|
【赤人集 ([三十六人集]撰、藤原公任[966~1041])】
| 新編私家集大成第一巻-6 赤人集Ⅱ[書陵部蔵三十六人集] |
| むはたまのよるくもくもりくらくとも いもかことをははやくつけてよ |
秋雑歌 159
|
| 新編私家集大成第一巻-5 赤人集Ⅰあかひと[西本願寺蔵三十六人集] |
| むまたまのよるひるくもりくらくとも いもかことはゝやくつけてよ」五三 |
あきのさふのうた 280
|
| 新編国歌大観第三巻-2 赤人集[西本願寺蔵三十六人集] |
| むまたまのよるひるくもりくらくともいもがことばははやくつげてよ |
あきのざふのうた 280
|
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」]
[本文]「黒玉宵霧隠遠鞆妹傳速告與」
「ヌハタマノ ヨキリコモリテ トホクトモ イモシツタヘハ ハヤクツケコヨ」(「【】」は編集) |
| 〔本文〕頭注、赤人集「むまたまのよるひるくもりくらくともいもかことはゝやくつけてよ」 |
| 「霧」 |
『京都大学本』「○【判読出来ず】」。消セリ。頭書「霧」アリ |
| 「速」 |
『類聚古集』「造」
『神田本』「迭」 |
| 「告」 |
『類聚古集』コノ下「丙?【判読出来ず】」アリ。但墨ニテ消セリ |
| 〔訓〕 |
| ヌハタマノ |
『元暦校本』「うはたまの」。「う」ノ右ニ赭「ム」アリ
『類聚古集』「むはたまの」
『神田本』「ウハタマノ」
『大矢本・京都大学本』「ヌ」青。『京』赭ニテ「ヌ」ヲ消セリ。ソノ右ニ赭「ウ」アリ
|
| ヨキリコモリテ |
『元暦校本・類聚古集』「よるきりかくれ」
『神田本』「ヨルキリカクレ」
『大矢本・京都大学本』七字青。『京』漢字ノ左ニ赭「ヨルキリカクレ」アリ
|
| トホクトモ |
『神田本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本』「トヲクトモ」
|
| イモシツタヘハ |
『元暦校本』「いもしへたへは」。「し」ノ右ニ赭「マツ」アリ。上ノ「へ」ノ左ニ墨「ツ」アリ
|
| ハヤクツケコヨ |
『神田本』「ハヤクツケヽヨ」
『西本願寺本・細井本・温故堂本』「ハヤクツケテヨ」
『京都大学本』「告與」ノ左ニ赭「ツケテヨ」アリ
|
| 〔諸説〕 |
○[妹傳イモシツタヘハ]『代匠記初稿本』「イモガツカヒハ」、『童蒙抄』「イモカカシツキ」、『万葉考』「イモカツタヘハ」、『万葉集古義』「傳」ノ下「言」脱トシ訓「イモガツテゴト」トス
○[速告與ハヤクツケコヨ]『代匠記精撰本』「ハヤクツケコソ」、『万葉考』「與」ハ「乞」ノ誤。訓「ハヤクツゲコセ」 |
【近代までの注釈書の掲題歌】
| 中世、近世、近代の注釈書 (私の範囲で確認できたもの・文中歌番はそのままの旧国歌大観) |
| [2012] |
各注釈書への、私的解釈 |
| 『万葉拾穂抄』〔北村季吟、貞享・元禄年間(1684~1704)成〕 |
[拾穂抄]私見 |
〔うはたまのよきりこもりてとをくともいもしつたへははやくつけてよ〕
黒玉宵霧隠遠鞆妹傳速告與
|
「霧こめて遠さかる」とは、霧に遠くへ追い遣られるような「現実感」がある
「うばたまの夜霧」が、たんに枕詞「うばたま」を用いただけではなく
それだけで「実景」のようにイメージできるのは、この枕詞の優れたところだと思う
「ぬばたま」を「うばたま」と用いるのは、『元暦校本』のオリジナルによるのだろうか |
| うはたまの夜霧 霧こめて遠さかるとも妹か消息は早く告よと也 |
『万葉代匠記(精撰本)』〔契沖、元禄三年(1690)成〕[萬葉集代匠記惣釋 僧契冲撰 木村正辭校]
|
「代匠記」私見 |
〔ヌハタマノヨキリニコモリテトホクトモイモシツタヘハハヤクツケコヨ〕
黒玉宵霧隱遠鞆妹傳速告與 |
なるほど、「妹傳」を義訓として解釈したのか...
それにしても「妹傳」の表記、確かにこれを訓ませるのは
いくつもの訓釈があるだろうが
この歌の場合、その語釈でもっとも可能性の高いのは「妹の伝言」なのだから
「義訓」はともかく、その意が外れなければ
どれが正しいとは、言えないものだ |
妹傳は義訓してイモガツカヒハと讀べきにや、與はコソと訓べし、
|
| 『万葉集童蒙抄』〔荷田春満、信名、享保年間(1716~35)成〕 |
「童蒙抄」私見 |
〔ぬばたまの、よぎりこめつゝ、とほくとも、いもが傳、速つげてよ 〕
黒玉宵霧隱遠鞆妹傳速告與 |
訓も歌意も、諸説が多く、決めかねている様子だが、宗師案の「傳」を「傅」とし、
「かしづき」とする説を出している
「かしづき」とは、「大切に世話をすること・大切に養い育てること」の意であり
その「者」を使って、「妹」に早く来て欲しい、と伝えてくれ、と
著者自身は、通説に寄ろうとしているようだが、まだ決め難し、としている
|
| 此歌も諸抄の説不決。妹傳とは使の事共注し又使の義共釋せり。宗師案、傳の字にて、かしづきと讀むべしと也。夜霧こめて遠く共、かしつきのもの、妹に早く出ませと告げよとの意に見る也。速は疾と讀みて、早く出立よと、とく告げよと願ふ意と也。愚意未決。妹がたより、つ手はと云方然るべからん。とくと告げよとは、とく出立よと告げよとの義と云ひては、言葉を入れて、とくと告げよと云ふ義と釋せねば成難し。便りつ手と見れば、妹の方よりの傳ふる事、便を早く滯らせず、こなたに告げよと見る也。尚後案を待つのみ |
| 『万葉考』〔賀茂真淵、宝暦十年(1760)成〕 |
「万葉考」私見 |
黒玉(ノ)、 冠辭
霄霧隱[ヨギリコモリテ]、 遠といはん序なり
遠鞆、妹傳[イモガツタヘハ]、速告乞[ハヤクツゲコセ] |
「黒玉」が枕詞(冠辞)であることは、解るが、何と訓むのか、そこには及んでいない
「つたへてふ」は、「伝えてという」こと、それが古くはなかった、というのだろうか
この注釈の部分、私には読み難い
真淵の解釈で、唯一私にも何を言っているのか解るのが、
「與」は「乞」の誤りだ、と主張しているところ
「こせ」は、上代の助動詞「こす」の命令形で、他に対して、あつらえ望むこと
もっとも、助詞「こそ」が活用したものとする説もあるので、
真淵の説が、表記はどうあれ、語義においては歌意に沿うものと思う |
| つたへはのちも言づてなど云が如しさてつたへてふ言古くはきこえず末の句終の乞を今本與に誤る事前に云が如し此歌も七夕に限らず |
| 『万葉集略解』〔橘千蔭、寛政十二年(1800)成〕[日本古典全集刊行会、1926年、与謝野寛他] |
「略解」私見 |
〔ぬばたまの。よぎりごもりて。とほくとも。いもがつたへは。はやくつげこせ。〕
黒玉。宵霧隱。遠鞆。妹傳。速告與。[與ハ乞ノ誤] |
「いもがつたへは」以下の解釈には特筆はないが、真淵は「七夕歌」に限らないとしているのにこの千蔭は、彦星、織女を自然と用いている
すでに、七夕の舞台設定にはなり得ていない歌意なので
ことさら、二星を出す必要はないと思う |
妹ガツタヘハは、織女より言を傳へたらば、疾く其意を告げよかしとなり。与は乞の誤なり。
參考 ○宵霧隱(考、古)略に同じ(新)ヨギリガクリテ ○妹傳(代)イモガツカヒハ(考)略に同じ(古、新)イモガツテゴト「傳」の下「言」を補ふ ○速告與(代)コソ(等)略に同じ(古、新)ハヤクツゲコソ。
|
| 『万葉集古義』〔鹿持雅澄、天保十三年(1842)成〕 |
「古義」私見 |
〔ヌバタマノ。ヨキリコモリテ。トホクトモ。イモガツテゴト。ハヤクツゲコソ。〕
黒玉宵霧隱遠鞆妹傳言〔○で囲む〕速告與
|
この書で、「傳」を「つたへ」の語義から「つてごと(伝言)」と提唱したが、
実際に「傳」それ自体が「つてごと」の義なので、「妹傳」表記を
いかに歌らしく訓むか、と苦心したのだろう
ここまで、どの書も、下句ばかりに力を入れているが、上三句の解釈も、また気になる
雅澄の「たとひ夜霧に隠りて、いとど吾が居るあたりの遠く隔てありとも」が、
この歌で、やっと歌全体の解釈に及んだ書となったような気もする |
妹傳言の言(ノ)字、舊本になきは、脱たるなるべし、イモガツテゴトと訓べし、
○速告與[ハヤクツゲコソ]は、いかで速く告よかし、と云意なり、與(ノ)字、コソとよみて、希望辭とすること、集中前後に例多し、
○歌(ノ)意は、たとひ夜霧に隱りて、いとど吾(ガ)居(ル)あたりの、遠く隔てありとも、織女の傳言をば、いかで速く告よかしと、織女の使を待わびて、彦星のよめる謂なり、 |
| 『万葉集新考』〔井上通泰、大正4~昭和2年成〕 |
「新考」私見 |
〔(ぬばたまの)宵霧隱[ヨギリガクリテ]、遠くとも妹傳△[イモガツテゴト]はやくつげこそ]
黒玉宵霧隱遠鞆妹傳速告與 |
ここで引用する、万葉歌の語句「ヨギリガクリテ」は、新歌番号2039であり、その原文は「夜霧隠」のことだ
しかし、その訓を「ヨギリガクリテ」と訓まなければならない、とするのは独断過ぎる
ただし、「道が夜霧に隠れて」という「意」とする立場なら、頷ける
漢字表記の「隠」にも、「こもる」と「かくる」があるが、その語義はやはり違うものだ
わざわざ「道」字を略しているとは、よほど「夜霧」の役割に拘っているようだ
|
略解古義にヨギリゴモリテとよみたれど下なるヌバタマノ夜霧隱トホヅマノ手ヲはヨギリガクリテとよまざるべからねばこゝもヨギリガクリテとよむべし。道ガ夜霧ニ隱レテといふ意なり
〇道といふことを略せるなり
〇さて霧に隱れたりとも道の遠近はかはるべからねど霧たてば道たどたどしくて恰道の遠きが如くに時費ゆればしばらく借りてトホクトモといへるなり
○第四句を舊訓にイモガツタヘハとよめるを古義に言の字のおちたるなりとしてイモガツテゴトとよめるは卓見なり。卷十九なる長歌にも玉桙ノ、道クル人ノ、傳言ニ、吾ニ語ラク云々とあり |
| 『口訳万葉集』〔折口信夫、1916~17年成〕 |
「口訳」私見 |
| ぬば玉の夜霧/籠[コモ]りて遠くとも、妹が傳言[ツテゴト]早く告げこそ |
『新考』以来、第二句の訓釈だけでなく、その語意においても注目している
この書では「こもり」とする立場だ |
| 夜霧に籠められて、間は遠く隔つて居ても、織女[オリヒメ]からの逢はうといふ傳言が、早くやつて來てくれ。 |
| 『万葉集全釈』〔鴻巣盛広、昭和5~10年成〕 |
「全釈」私見 |
〔ぬば玉の 夜霧がくりて 遠くとも 妹が傳へは 早く告げこそ〕
ヌバタマノ ヨギリガクリテ トホクトモ イモガツタヘハ ハヤクツゲコソ
黒玉宵霧隱遠鞆妹傳速告與 |
ここでも第二句を『新考』の見解に沿って解釈している
その手法、根拠を同じとしている
『古義』の「伝(言)」として「つてごと」と解するのは、
「伝言」という漢語をそのまま訓んだのだろうか
そして、その意としては同じとしながらも、真淵説を採っている
この「評」に、首を傾げた
「七夕の伝説としては少し変つてゐるようだ」とあるが
万葉集で詠われる「七夕歌」は、どれも変わっているように、私には感じられるのだが... |
(黒玉)夜ノ霧ガ立チコメテ、ワタシノ居ル所ガソコカラ遠クトモ、ワタシノ妻ノ織女ノ言傳は、速クワタシニ知ラセテクダサイ。
○黒玉[ヌバタマノ]――夜の枕詞。八九參照。
○宵霧隱[ヨギリガクリテ]――舊訓はヨギリコモリテとあるが、下に烏玉之夜霧隱遠妻手乎[ヌバタマノヨギリガクリニトホヅマノテヲ](二〇三五)とあるから、ガクリとよむべきであらう。
○妹傳[イモガツタヘハ]――古義に傳の下、言を補つて、イモガツテゴトをよんでゐる。ここは考による、意はツテゴトに同じ。
〔評〕 彦星が織女からの、使を待ちわぶる心を述べてゐる。七夕の傳説としては少し變つてゐるやうだ。 |
| 『万葉集全註釈』〔武田祐吉、昭和23年~25年成〕 |
「全註釈」私見 |
〔ぬばたまの 夜霧隱りに 遠くとも 妹が傳言 早く告げこそ。〕
ヌバタマノ ヨギリガクリニ トホクトモ イモガツテゴト ハヤクツゲコソ
黒玉宵霧隱遠鞆妹傳速告與 |
「傳」の字だけで「つてごと」と読むのだろう、としているが
「傳(伝)」は、確かに、何を伝えるかといえば「言」を伝えるのだから...
しかし、「傳」は果たしてそうだろうか
例えば、言葉にしなくても、伝えられる「想い」というものがある
ここで、第二句のことを、かなり重要視してはいないだろうか... |
【譯】くらい夜の霧にこもつて遠いにしても、妻の傳言は早く告げてください。
【釋】宵霧隱 ヨギリガクリニ。ヨギリゴモリテ(西)。夜の霧の中に隱れて。
妹傳 イモガツテゴト。
イモシツタヘハ(元)
イモガツカヒハ(代初)
イモガツタヘハ(考)
――――――――――
妹傳言《イモガツテゴト》(古義)
妹からの傳えごとは。イモは織女星をさす。傳の字だけで、ツテゴトと讀むのだろう。
【評語】牽牛星に代つて詠んでいる。織女星のもとから使の來る場合を想像している。初二句に若干の描寫がある。早く妻の傳言を聞きたいと思う心は、相當に感じられる。 |
| 『評釈万葉集』〔佐佐木信綱、昭和23~29年成〕 |
「評釈」私見 |
〔ぬばたま夜霧隱りて遠くとも妹が傳は早く告げこせ〕
ヌバタマノ ヨギリガクリテ トホクトモ イモガツタヘハ ハヤクツゲコセ |
ここでも、他の万葉歌の訓を引用し、「だから、ここもそう訓める」式の訓釈だが
少なくとも、万葉仮名での歌でない限り、その手法はよくないと思う
それに、「七夕歌」という大前提をそのまま認めているようで、
万葉編纂の当時、それほどきちんと「古歌集」の整理仕分けが出来たのだろうか、と
「部立て」への疑念は少なからずある
この歌、どんな風に読んでも、「七夕」伝説をモチーフにしたとは思えない |
【譯】夜霧が立ちこめ、その上自分のゐるところは遠くても、いとしい妻の伝言は、早く自分に聞かせてくれ。
【評】地上の恋人同士のやうに、彦星が織女からの文使を待ちわびてゐる心を叙べたもので、当時七夕伝説が様々に詠まれ、形を変へて想像されてゐたことが知られる。
【語】○ぬばたまの 「夜」にかかる枕詞。「八九」参照。
○妹が伝 妻即ち織女からの伝言の意。
○告げこせ 告げて下さいの意。「こせ」は「一一九」参照。
【訓】○がくりて 白文「隠」。ガクリニとよむ説もある。
○つたへは 白文「伝」。巻十二に「何の伝言(つてごと)」(三〇六九)、巻十九に「伝言に吾に語らひ」(四二一四)とあるにより、ここも「イモガツテゴト」と読む説もある。
○告げこせ 白文「告與」。ツゲコソと読む説もある。 |
| 『万葉集私注』〔土屋文明、昭和24~31年成〕 |
「私注」私見 |
〔ぬばたまの夜霧ごもりて遠けども妹が傳は早く告げこそ〕
ヌバタマノ ヨギリゴモリテ トホケドモ イモガツタヘハ ハヤクツゲコソ
黒玉宵霧隱遠鞆妹傳速告與 |
第二句は、実景としている注釈書が多くあるが、
それだと下句への続き方が、どうしてもしっくりしない
第二句、もっと「意味」のある語句だと思うのだが... |
【大意】ヌバタマノ(枕詞)夜霧の中にこもつて、遠くはあるけれども、妹(織女)の言伝は、早く告げて欲しい。
【作意】牽牛の立場としても、又人間の立場で同情して居るとも見られる。 |
| 『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕 |
「注釈」私見 |
〔ぬば玉の 夜霧こもりて 遠くとも 妹が傳へは 早く告げこそ〕
ヌバタマノ ヨギリコモリテ トホクトモ イモガツタヘハ ハヤクツゲコソ
黒玉宵霧隱遠鞆妹傳速告與(『元暦校本』) |
「霧」は、「こもる」とするのが一般的のようだ
古注釈書で、「こもりて」としているのは、やはりそれなりの当時の適切な解釈だったのだろう
赤人集の「よるひるくもり」とあるのを紹介しているが、
柿本人麿歌集は、「ヨルヒハカクレ」とするなど、さらに「七夕」という部立てではなく
「恋部 相聞」の中の一首となる
元歌は、「七夕歌」ではなかったのを、万葉編者が、「七夕」に配したのが意図的なのか、
あるいは単なる「相聞」を、間違ってここに並べたのか...
|
【口訳】夜霧にこもつて遠くあらうとも、妹が伝言は早く伝へてほしい。
【訓釈】ぬば玉の―夜の枕詞(2・89)。「黒玉」と書いた例、人麻呂歌集に二つ(7・1101)。
夜霧こもりて―『元暦校本・類聚古集・紀州本・京都大学本(左に赭)』にヨルキリカクレとあるを、『西本願寺本』以後ヨキリコモリテとしたが、『新考』にガクリテとして以来
その訓が行はれ、『全註釈』にガクリニ、折口氏『口訳』と『私注』にヨギリゴモリテとあるのみであるが、霧に対しては「こもり」が例であり、旧訓に従つてコモリテと訓むべき
こと前(4・509)に述べた。
遠くとも―『元』以後諸本諸注にトホクトモとあつたのを『私注』と『古典大系本』とにトホケドモと改められたが、ここは「よどむとも」(1・31)と同じく、たとへどんなに遠く
あらうとも、の意で、トホクトモの古訓を改める必要はない。「とも」をうけて「こそ」で結んだ例は「目耳谷[メノミダニ] 吾耳見乞[ワレニミエコソ] 事不問侶[コトトハズト
モ]」(7・1211)があつた。
妹が傳へは早く告げこそ―旧訓イモシツタヘハを『代匠記』に「イモガツカヒハト読ベキニヤ」といひ、『万葉考』にイモガツタヘハとした。『古義』には「妹伝言[イモガツテゴ
ト]の「言」の脱したものとした。「何伝言[ナニノツテゴト]」(12・3069)、「道来人之[ミチクルヒトノ] 伝言尓[ツテコトニ] 吾尓語良久[ワレニカタラク]」(19・4214)など
あるからその脱字説も認められるが、ツタヘと訓んで伝言の意に解く事も出来よう。「与」をコソと訓むこと前(2000)に述べた。
【考】赤人集に「むまたまのよるひるくもりくらくともいもかことははやくつけてよ」、流布本「むは玉のよる雲くもり」「妹かことはを」とある。
|
|
|
 |
 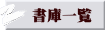  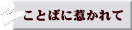 |


















