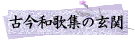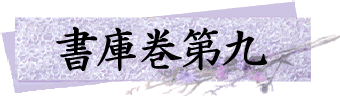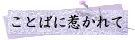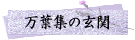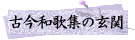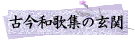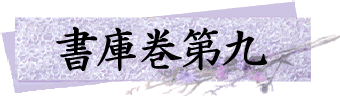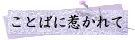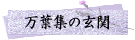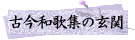|
2004年6月12日 古今和歌集巻第九
羈 旅 歌
唐土にて月を見てよみける 安倍仲麿
406 天の原ふりさけみれば春日なるみかさの山にいでしつきかも
この歌は、「昔なかまろを唐土にものならはしにつかはしたりけるに、あまた
の年をへて、え帰りまうでござりけるを、この国より又つかひまかりいたりけ
るにたぐひて、まうできなむとていでたちけるに、明州といふところの海辺に
て、かの国の人むまのはなむけしけり。よるになりて月のいとおもしろくさし
いでたりけるを見て、よめる」となむかたりつたふる。
故国から遠く離れた地で、月を眺める
故郷で見た月も、この月も同じものなのだ、と郷愁に駆られる
それは、何も月に限ったことではないが
この仲麿の郷愁は、我々の郷愁の域を超えている
淡々とした口調は、返って仲麿の慟哭を察してしまう
717年、吉備真備らとともに遣唐留学生として入唐
玄宗皇帝の寵を受け、そのまま唐に...
その年月は、753年に遣唐使藤原清河の来唐、そして誘われての帰朝まで続く
その帰路、蘇州江で満月を眺めて望郷の念に駆られて詠んだといわれる
しかし、その後の遣唐使団の船が難破し安南に漂着し
仲麿は再び唐に戻る
在唐54年、仲麿は帰国できないまま、唐土で死ぬ
「あまのはら ふりさけみれば」という表現は、「綺語抄」に「あまのはら おほぞらをいふ。
ふりさけみれば ふりあおいでみればといふ事也」としてこの歌をあげ、教長、顕昭、定家たちの
古注がつく、古語。
仲麿は、間もなく故国の地に立てると思い、あらためて大空を振り仰いだのだろう。折りしも満
月、故郷の三笠山で眺めた、あの月なのか...。もうすぐ、故郷なのだ。36年ぶりの想いが籠もる。
|
|