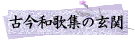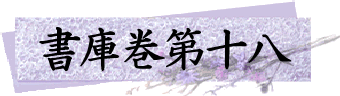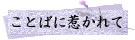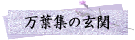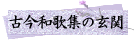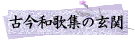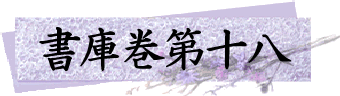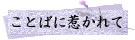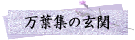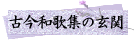|
2004年6月26日 古今和歌集巻第十八
雑 歌 下
貞観御時、「万葉集はいつばかりつくれるぞ」と問はせ給ひければ、よみて奉りける
文屋有季
997 神無月時雨降りおける楢の葉の 名におふ宮の古言ぞこれ
清和天皇の貞観年間(859〜77)に、「万葉集はいつごろ編集されたのか」と問われた
万葉集の成立年代に触れた最古の記録として有名な歌といえる
ただし、定家本以外の諸本には
たとえば清輔本での第四句「ならのみやこ」、顕昭本「ならのみかと」とある
「みかと」であれば、平城天皇のことを意味する
十月の時雨は、色づいた「楢(なら)」の葉に降り注ぐといわれます
万葉集は、その木と同じ名を持つ「奈良」の宮の時代の古歌なのです
万葉集の編纂(厳密には掲載歌の最終時期)は、貞観年間から百数十年をさかのぼるが
半世紀ばかり前に平城京から平安京への遷都があった
その平城京の時代の和歌集を「古言(古歌)」という
すでにこの貞観年間では、万葉集は「古歌」との認識になっている
しかも、天皇さえ、その成立の詳細を知らない
現代の私たちが、同じく百数十年前のことを思うとき
確かに江戸時代の中後期を、学んだこととして思い浮かべる
しかし、実感はとしての捉えかたは出来ない
これほど様々なメディアが浸透している現代の我々でさえ...
それを思えば、万葉集の採録歌は実に四、五百年間(諸説が多い)にも及ぶ
どんなに頭を柔軟にしても
そのように長期に渡る「歌集」の編纂など、思いもつかないのが普通だろう
ましてや、数々の言語の入り混じった時代のことを思うと
今更ながらに、万葉集の特異性を考えさせられる
|
|