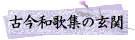
|
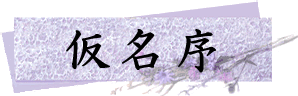
|
|||||||||
|
岩波文庫 種・葉など植物に喩えて言う 「言の葉は」は歌 「言ひだせるなり」は それが歌なのだ 「かはづ」は河鹿、春の鶯に対して秋のものとして言う 「天の浮橋・・・」はイザナギ・イザナミ神話 「久方の天」高天ヶ原 「「あらがねの地」地上 「唐の歌」 漢詩 「そへ歌」 六義の風 「かぞへ歌」六義の賦 「思ひつく身のあぢきなさ」深く心を奪われる我が身 「なずらへ歌」六義の比 「たとへ歌」六義の興 「よむとも・・・」 思いの数を数えても数え切れない 「ただごと歌」六義の雅 「いかばかり・・・」 どんなにあなたの言葉が嬉しいことか 「いはひ歌」六義の頌 「三葉四葉」殿造りの素晴らしい様子 「今の世の中・・・」 華美になり、人の心が浮薄になったから、表立った場所には出されなくなった 「さざれ石」343 「筑波山」1095 「喜び身に過ぎ」865 「富士の煙」534・1028 「松虫の音」200 「高砂」909・908 「住江」905・906 「男山」889 「女郎花の」1016 「鏡の影に」460 「草の露」860 「水の泡」827 「昨日は」888- 「松山の」1093 「野中の水を」887 「秋萩の」220 「暁の」761 「呉竹の」958・957 「吉野川」828 「正三位柿本・・・」 人麻呂は持統・文武時代で、正史には記録がない 「竜田川」283 「むめの花」334 「ほのぼのと」409 「春の野に」万葉集 「和歌の浦」万葉集 僧正遍昭以下六人を 六歌仙と言う 「このほかの人々・」 たくさんいるが、自分の歌のみを歌だと思って、歌の本当の様を知らないであろう |
仮名序全文 和歌は、人の心を種として、万の言の葉とぞなれ李ける。世の中にある人、事・業しげきものなれば、 心に思ふ事を、見るもの聞くものにつけて、言ひいだせるなり。花に鳴く鶯、水に住むかはづの声を聞け ば、生きとし生けるもの、いづれか歌を世混ざりける。力も入れずして天地を動かし、目に見えぬ鬼神を もあはれと思はせ、男女のなかをもやはらげ、猛き武士の心をもなぐさむるは、歌なり。 この歌、天地の開けはじまりける時より、いで来にけり。天の浮橋の下にて、女神男神となりたまへることを 言へる歌なり。然あれども、世に伝はることは、久方の天にしては下照姫に始まり、下照姫とは、あめわかみこ の妻なり。兄(瀬宇土)の神のかたち、丘谷にうつりてかがやくをよめるえびす歌なるべし。これらは、文字の数も定ま らず、歌のやうにもあらぬことどもなり。あらがねの地にしては、すさのをの命よりぞおこりける。ちはやぶる 神世には、歌の文字も定まらず、すなほにして、言の心わきがたかりけらし。人の世となりて、すさのを の命よりぞ、三十文字あまり一文字はよみける。すさのをの命は、天照かみなり。女と住みたまはむとて、出雲の 国に宮造りしたまふ時に、その処に八色の雲のたつを見て、よみたまへるなり。や雲立つ出雲八重垣妻ごめに八重垣作るそ の八重垣を。 かくてぞ、花をめで、鳥をうらやみ、霞をあはれび、露をかなしぶ心・言葉おほく、様々になりける。遠 き所もいでたつ足もとより始まりて年月をわたり、高き山も麓の塵土よりなりて天雲たなびくまで生ひのぼ れるごとくに、この歌も、かくのごとくなるべし。難波津の歌は帝の御初めなり。おほさざきの帝、難波津にて、 皇子ときこえけるとき、東宮をたがひに譲りて、位につきたまはで三年になりにければ、王仁といふ人のいぶかり思ひて、 よみたてまつりける歌なり。「この花」はむめの花をいふなるべし。安積山の言葉は采女のたはぶれよりみて、葛城王 を、陸奥へつかはしたりけるに、国の司事おろそかなりとて、設けなどしたりけれど、すさまじかりければ、采女なりける 女の、かはらけとりてよめるなり。これにぞ、おほきみの心とけにける。この二歌は、歌の父母のやうにてぞ、手習ふ 人のはじめにもしける。 そもそも、歌の様六つなり。唐の歌にも、かくぞあるべき。その六種の一つには、そへの歌、おほさざき の帝をそへたてまつれる歌、 難波津に咲くやこの花、冬ごもり今は春べと、咲くやこの花 と言へるなるべし。 二つには、かぞへ歌、 咲く花に思ひつくみのあぢきなさ、身にいたづきのいるも知らずて と言へるなるべし。これは、ただごとに言ひて物にたとへなどもせぬものなり。この歌、いかに言ヘルにかあらん。その 心得がたし。五つにはただごと歌と言へるなん、これにはかなふべき。 三つには、なずらへ歌、 君に今朝あしたの霜のおきていなば、恋しきごとに消えやわたらん と言へるなるべし。これは、物にもなずらへて、それがやうになんあるとやうに言ふなり。この歌、よくかなへりとも見 えず。「たらちめの親のかふこのまゆごもり、いぶせくもあるか、妹にあはずて」かやうなるや、これにはかなふべからん。 四つには、たとへ歌、 わが恋はよむとも尽きじ、荒磯海の浜の真砂はよみ尽くすとも と言へるなるべし。これは、万の草木鳥けだものにつけて、心を見するなり。この歌は、隠れたる所なむなき。されど、 はじめのそへ歌と同じやうなれば、すこし様をかへたるなるべし。「須磨のあまの塩やく煙、風をいたみ、思はぬ方にたな びきにけり。」この歌などや、かなふべからん。 五つには、ただごと歌、 いつはりのなき世なりせば、いかばかり人の言の葉うれしからまし といへるなるべし。これは、事のととのほり正しきをいふなり。この歌の心、さらにかなはず。とめ歌とやいふべからん。 「山桜、あくまで色を見つるかな、花ちるべくも風ふかぬ世に」 六つには、いはひ歌。 この殿はむべも富みけり、さきくさの三葉四葉に殿造りせり と言へるなるべし。これは、世をほめて神に告ぐるなり。この歌、いはひ歌とは見えずなんある。「春日野に若菜つみつ つ万世をいはふ心は、神ぞ知るらん」、これらや、すこしかなふべからん。おほよそ、むくさにわかれん事は、えあるまじき 事になん。 今の世の中、色につき、人の心、花になりにけるより、あだなる歌はかなき言のみいでくれば、色好みの家に 埋もれ木の人知れぬ事となりて、まめなる所には、花すすきほにいだすべき事にもあらずなりにたり。その初 めを思へば、かかるべくなむあらぬ。いにしへの世々の帝、春の花の朝、秋の月の夜ごとに、さぶらふ人々を めして、事に付けつつ歌をたてまつらしめたまふ。あるは花をそふとて便なき所にまどひ、あるは月を思ふと てしるべなき闇にたどれる心々を見たまひて、さかし、おろかなりと、知ろしめしけむ。然あるのみにあらず 、さざれ石にたとへ、筑波山にかけて、君をねがひ、喜び身に過ぎ、楽しび心に余り、富士の煙によそへて人 を恋ひ、松虫の音に友をしのび、高砂・住江の松も相生ひのやうにおぼえ、男山の昔を思ひいでて、女郎花の 一時をくねるにも、歌をいひてぞなぐさめける。また、春の朝に花のちるを見、秋の夕ぐれに木の葉の落つる をきき、あるは、年ごとに鏡の影に見ゆる雪と波とを嘆き、草の露、水の泡を見て、我が身をおどろき、ある は、昨日は栄えおごりて、時を失ひ、世にわび、親しかりしもうとくなり、あるは、松山の波をかけ、野中の 水をくみ、秋萩の下葉をながめ、暁の鴫の羽がきを数へ、あるは、呉竹のうき節を人に言ひ、吉野川をひきて 世の中を恨み来つるに、「今は、富士の山も煙たたずなり、長柄の橋も造るなり」と、聞く人は、歌にのみぞ 心をなぐさめける。 いにしへよりかく伝はるうちにも、奈良の御時よりぞ広まりにける。かの御代や、歌の心を知炉示したりけ む。かの御時に、正三位柿本人麻呂なむ、歌の聖なりける。これは、君も人も身をあはせたりといふなるべし。 秋の夕べ竜田河に流るる紅葉をば、帝の御目には錦と見たまひ、春の朝吉野の山の桜は、人麻呂が心には雲か とのみなむおぼえける。又、山の辺の赤人といふ人ありけり。歌に、あやしく妙なりけり。人丸は赤人が上に 立たむ事かたく、赤人は人麻呂が下に立たむ事かたくなむありける。奈良の帝の御歌、「竜田川もみぢ乱れて流る め り、渡らば錦中や絶えなん」。人麻呂、「むめの花それとも見えず、久方の天ぎる雪のなべて降れれば」「ほのぼのと明 石の浦の朝霧に島隠れゆく舟をしぞ思ふ」。赤人、「春の野にすみれつみにとこし我ぞ、野をなつかしみ一夜ねにける。」「 和歌の浦に潮みちくれば、潟をなみ、葦辺をさして鶴鳴き渡る」この人々をおきて、又、すぐれたる人も、呉竹の世 々にきこえ、片糸のよりよりに絶えずぞありける。これよりさきの歌を集めてなむ、万葉集と名づけられた りける。 ここに、いにしへのことをも歌の心をも知れる人、わづかに一人二人なりき。然あれど、これかれ、得たる 所・得ぬ所、たがひになむある。かの御時よりこの方、年は百年あまり、世は十継になん、なりにける。いに し へのことをも歌をも、知れる人よむ人、多からず。今この事を言ふに、官位高き人をば、たやすきやうな れば入れず。そのほかに、近き世にその名きこえたる人は、すなはち、僧正遍昭は、歌のさまは得たれども誠 すくなし。たとへば、絵にかける女を見て、いたづらに心を動かすがごとし。「浅みどり糸よりかけて、しら露を 玉にもぬける春の柳か」「蓮葉の、にごりにしまぬ心もて、何かは露を玉と欺く」「嵯峨野にてむまより落ちてよめる、名に めでて折れるばかりぞ、をみなへし、我おちにきと人に語るな」 在原業平は、その心あまりて言葉たらず。しぼめる花の、色なくてにほひ残れるがごとし。「月やあらぬ、春 や昔の春ならぬ、我が身一つはもとの身にして」「おほかたは月をもめでじ、これぞこの積もれば人の老いとなるもの」「ね ぬる夜の夢をはかなみ、まどろめば、いやはかなにもなりまさるかな」 文屋康秀は、言葉はたくみにて、そのさま身におはず。いはば、商人のよき衣きたらんがごとし。「吹くから に野辺の草木のしをるれば、むべ山風をあらしといふらむ」「深草の御国忌に、草深き霞の谷にかげかくし照る日のくれし今日 にやはあらぬ」 宇治山の僧喜撰は、言葉かすかにして、初め終わりたしかならず。いはば、秋の月を見るに、暁の雲にあへる がごとし。「わが庵は都のたつみ、しかぞ住む、世を宇治山と人はいふなり」よめる歌多く聞こえねば、かれこれを通 はしてよく知らず。 小野小町は、いにしへの衣通姫の流なり。あはれなるやうにて、強からず。言はば、よき女の悩めるところ あるに似たり。強からぬは、女の歌なればなるべし。「思ひつつぬればや人の見えつらん、夢と知りせばさめざらまし を」「色見えで移ろふものは、世の中の人の心の花にぞありける」「わびぬれば身をうき草の根を絶えて、誘ふ水あらばいな んとぞ思ふ」。衣通姫の歌、「わがせこが来べきよひなり、ささがにのくものふるまひかねてしるしも」 大伴黒主は、そのさまいやし。いはば、薪負へる山人の、花のかげに休めるがごとし。「思ひいでて恋しき時は 初雁のなきてわたると、人は知らずや」「鏡山いざたち寄りて見てゆかむ、年へぬる身は老いやしぬると」 このほかの人々、その名きこゆる、野辺に生ふるかづらのはひ広ごり、林にしげき木の葉のごとくに多かれ ど、歌とのみ思ひて、そのさま知らぬなるべし。 かかるに、今、天皇の天下知ろしめすこと、四時ここのかへりになんなりぬる。あまねき御慈愛の波、八州 のほかまで流れ、ひろき御恵みのかげ、筑波山の麓よりもしげくおはしまして、万の政務をきこしめすいとま もろもろの事を捨てたまはぬあまりに、「いにしへの事をも忘れじ、古りにし事をも興したまふ」とて、「今 もみそなはし、後の世にも伝はれ」とて、延喜五年四月十八日に、大内記紀友則、御書の所の預り紀貫之、前 の甲斐の少目凡河内躬恒、右衛門の府生壬生忠岑らに仰せられて、万葉集の入らぬ古き歌、自らのをもたてま つらしめたまひてなん。それが中に、梅をかざすより始めて、ほととぎすを聞き、紅葉を折り、雪を見るにい たるまで、又、鶴亀につけて君を思ひ人をも祝ひ、秋萩夏草を見て妻を恋ひ、逢坂山にいたりて手向けを祈り、 あるは、春夏秋冬にも入らぬ種々の歌をなん、えらばせたまひける。すべて千歌二十巻、名づけて「古今和歌 集」といふ。かく、この度集めえらばれて、山下水の絶えず、浜の真砂の数多く積もりぬれば、今は飛鳥川の 瀬になる恨みもきこえず、さざれ石の巌となる喜びのみぞあるべき。 それ、まくらことは、春の花にほひすくなくして、空しき名のみ秋の夜の長きをかこてれば、かつは人の耳 に恐り、かつは歌の心に恥ぢ思へど、たなびく雲のたちい、鳴く鹿の起きふしは、貫之らがこの世に同じくむ まれて、この事の時にあへるをなむ、喜びぬる。人麻呂なくなりにたれど、歌のこととどまれるかな。たとひ、 時移り事去り、楽しび哀しびゆきかふとも、この歌の文字あるをや。青柳の糸絶えず、松の葉のちり失せずし て、まさきのかづら長く伝はり、鳥のあと久しくとどまれらば、歌のさまを知り、ことの心を得たらん人は、 大空の月を見るがごとくに、いにしへを仰ぎて今を恋ひざらめかも。 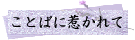 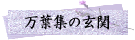 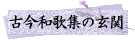 |