|
|
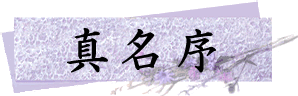
|
|||||
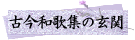
|
||||||
|
真名序全文 古今和歌集序 紀淑望 夫和歌者、託其根於心地、発其華於詞林者也。 それ 和歌は、その根を心地に託け その花を詞林に発くものなり。 人之在世、不能無為、思慮易遷、哀楽相変。感生於志、詠形於言。是以逸者其声楽、怨者其吟悲。 可以述懐、可以発憤。 人の 世にある、無為なること能はず、思慮遷り易く、哀楽あひ変る。感は志に生り、詠は言に形る。 ここをもちて、逸する者はその声楽しく、怨ずる者はその吟悲し。もちて懐を述べつべく、もちて憤を 発しつべし。 動天地、感鬼神、化人倫、和夫婦、莫宜於和歌。 天地を動かし、鬼神を感ぜしめ、人倫を化し、夫婦を和ぐること、和歌より宜しきはなし。 和歌有六義。一曰風、二曰賦、三曰比、四曰興、五曰雅、六曰頌。 和歌に六義あり。一に曰く 風、二に曰く 賦、三に曰く 比、四に曰く 興、五に曰く 雅 六に曰く 頌。 若夫春鶯之囀花中、秋蝉之吟樹上、雖無曲折、各発歌謡。物皆有之、自然之理也。 かの 春の鶯の花中に囀り、秋の蝉の樹上に吟ふがごとき、曲折なしといへども、各歌謡を発す。 物皆これあり、自然の理なり。 然而神世七代、時質人淳、情欲無分、和歌未作。逮于素戔烏尊、到出雲国、始有三十一字之詠。 今反歌之作也。其後雖天神之孫、海童之女、莫不以和歌通情者。 然れども、神の世七代は、時質に人淳うして、情欲分かつことなく、和歌いまだ作らず。 素戔烏尊の出雲の国に到るに逮びて、始めて三十一字の詠あり。今の反歌の作なり。その後天神 の孫、海童の女といえども、和歌をもちて情を通ぜずといふことなし。 爰及人代、此風大興、長歌短歌旋頭混本之類、雑躰非一、源流漸繁。譬猶払雲之樹、生自寸苗之煙、 浮天之波、起於一滴之露。 爰に人の代に及びて、この風大きに興る。長歌・短歌・旋頭・混本の類、雑体一にあらず、源流 漸く繁し。譬へば、なほ、雲を払ふ樹の寸苗の煙より生り、天を浮ぶる波の一滴の露より起るが ごとし。 至如難波津之什献天皇、富緒川之篇報太子、或事関神異、或興入幽玄。但見上古歌、多存古質之語、 未為耳目之翫、徒為教戒之端。 難波津の什を天皇に献り、富緒川の篇を太子に報へしが如きに至りては、或いは事神異に関り、 或いは興幽玄に入る。但し、上古の歌を見るに、多くの古質の語を存し、いまだ耳目の翫とせず、 徒に、教戒の端とせり。 古天子、毎良辰美景、詔侍臣預宴筵者献和歌。君臣之情、由斯可見、賢愚之性、於是相分。所以隋 民之欲、択士之才也。 古の天子、良辰美景ごとに、侍臣の宴筵に預金る者に詔して和歌を献らしむ。君臣の情、これに よりて見つべく、賢愚の性、ここにおきて相分る。民の欲ひに隋ひて、士の才を択ぶ所以なり。 自大津皇子之初作詩賦、詞人才子慕風継塵、移彼漢家之字、化我日或之俗。民業一改、和歌漸衰。 大津皇子の初めて詩賦を作りしより、詞人、才子 風を慕ひ塵に継ぎ、かの漢家の字を移して、我 が日域の俗を化す。民の業 一たび改りて、和歌 漸く衰へぬ。 然猶有先師柿本大夫者、高振神妙之思、独歩古今之間。有山辺赤人者、並和歌仙也。其余業和歌者、 綿々不絶。 然れども、なほ 先師柿本の大夫という者あり、高く神妙の思ひを振りて古今の間に独歩せり。山 辺の赤人といふ者あり、ともに和歌の仙なり。その余の 和歌を業とする者、綿々として絶えず。 及彼時変澆漓、人貴奢淫、浮詞雲興、艶流泉涌、其実皆落、其華孤栄、至有好色之家、以此為花鳥之 使、乞食之客、以此為活計之謀。故半為婦人之右、雖進大夫之前。 かの、時は澆漓に変じ 人は奢淫を貴ぶに及びて、浮詞雲のごとく興り、艶流泉のごとく涌き、そ の実皆落ち、その花ひとり栄えて、好色の家にはこれをもちて花鳥の使とし、乞食の客はこれをも ちて活計の謀とすることあるに至る。故に、半ば婦人の右となり、大夫の前に進めがたし。 近代、存古風者、纜二三人。然長短不同、論以可弁。 近き代に、古風を存する者はわづかに二三人なり。然れども、長短同じからず、論じてもちて弁ふ べし。 華山僧正、尤得歌躰。然其詞華而少実。如図画好女、徒動人情。 花山の僧正は、尤も歌の体を得たり。然れども、その詞、花にして実すくなし。図画の好女の 徒 らに人の情を動かすごとし。 在原中将之歌、其情有余、其詞不足。如萎花雖少彩色、而有薫香。 在原の中将の歌は、その情余りありて、その詞足らず。萎める花の 彩色少なしといへども、薫香 あるがごとし。 文琳巧詠物。然其躰近俗。如賈人之着鮮衣。 文琳は巧みに物を詠ず。然れども、その体俗に近し。賈人の鮮かなる衣を着たるがごとし。 宇治山僧喜撰、其詞華麗、而首尾停滞。如望秋月遇暁雲。 宇治山の僧喜撰は、その詞は華麗にして、首尾停滞せり。秋の月を望むに、暁の雲に遇へるがごとし。 小野小町之歌、古衣通姫之流也。然艶而無気力。如病婦之着花粉。 小野の小町が歌は、古の衣通姫の流なり。然れども、艶にして気力なし。病める婦の 花粉を着けた るがごとし。 大友黒主之歌、古猿丸大夫之次也。頗有逸興、而躰甚鄙。如田夫之息花前也。 大友の黒主が歌は、古の猿丸大夫の次なり。頗る逸興ありて、体甚だ鄙し。田夫の 花の前に息めるが ごとし。 此外氏姓流聞者、不可勝数。其大底皆以艶為基、不知和歌之趣者也。 この外に氏姓流れ聞ゆる者、あげて数ふべからず。その大底は皆、艶をもちて基とし、和歌の趣きを 知らざる者なり。 俗人争事栄利、不用詠和歌。悲哉々々。雖貴兼相将、富余金銭、而骨未腐於土中、名先滅世上。適為後 世被知者、唯和歌之人而巳。何者、語近人耳、義慣神明也。 俗人争でか栄利を事として、和歌を詠ずることを用いざる。悲しきかな、悲しきかな。貴きこと相将 を兼ね、富は金銭を余せりといへども、骨いまだ土中に腐ちざるに、名まづ世上に滅えぬ。適後世に 知らるる者は、唯和歌の人のみ。いかにとなれば、語は人の耳に近く、義は神明に慣へばなり。 昔平城天子、詔侍臣令撰万葉集。自爾来、時歴十代、数過百年。其後、和歌弃不被採。雖風流如野宰相 軽情如在納言、而皆以他才聞、不以漸道顕。 昔、平城の天子、侍臣に詔して万葉集を撰ばしむ。それより来、時は十代を歴、数は百年を過ぎたり。 その後、和歌 棄てて採られず。風流 野宰相の如く、軽情 在納言の如しといへども、皆、他の才 をもちて聞え、この道をもちて顕はれず。 陛下御宇于今九載。仁流秋津洲之外、恵茂筑波山之陰。淵変為瀬之声、寂々閇口、砂長為巌之頌、洋々 満耳。思継既絶之風、欲興久廃之道。 (伏して惟ひみれば)陛下の御宇今に九載なり。仁は秋津洲の外に流れ、恵は筑波山の陰よりも茂詞。 淵の変じて瀬となる声、寂々として口を閉ぢ、砂の長じて巌となる頌、洋々として耳に満てり。既に 絶えたる風を継がむことを思ほし、久しく廃れたる道を興さむことを欲ほす。 爰詔大内記紀友則、御書所預紀貫之、前甲斐少目凡河内躬恒、右衛門府生壬生忠峯等、各献家集并古来 旧歌、曰続万葉集。於是重有詔、部類所奉之歌、勒為二十巻、名曰古今和歌集。 爰に、大内記の紀友則・御書所の預紀の貫之・前の甲斐の少目凡河内の躬恒・右衛門の府生壬生の忠 岑等に詔して、各に、家の集、ならびに古来の旧歌を献らしめ、続万葉集といふ。ここにおきて、重 ねて詔あり、奉るところの歌を部類し、勒して二十巻とし、名づけて古今和歌集といふ。 臣等、詞少春花之艶、名竊秋夜之長。況哉、進恐時俗之嘲、退慙才芸之拙。適遇和歌之中興、以楽吾道 之再昌。嗟乎、人丸既没、和歌不在斯哉。于時延喜五年歳次乙丑四月十五日、臣貫之等謹序。 臣等、詞は春の花の艶少きに、名は秋の夜の長きを竊めり。況むや、進みては時俗の嘲を恐れ、退き ては才芸の拙きを慙づるを。適和歌の中興に遇ひて、もちて吾が道の再び昌りなることを楽しぶ。嗟 乎、人麻呂既に没して、和歌ここにあらずや。時に延喜五年歳の乙丑に次る四月十五日 臣貫之等 謹みて序す。 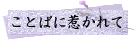 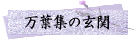 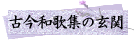
|