| |
| 「なつそびく」...夜更けの、海の風に... |
| |
| 『再度、万葉への想いを』 |
| 【歌意3362】 |
〔なつそひく〕海上潟の沖合いの砂州に船を停めてみよう
もうすっかり夜が更けてしまった
慌てて帰ることもない、夜の海の上も...いいものだ
|
| |
| 【はじめに】 |
ここを遠ざかってから、すでに半年以上も経つ
早く再開させようと、気持ちを急かしながらも、
やはり、仕事の忙しさを言い訳してしまう
何とかYahooブログ「一日一首」で、ごまかしてきたが、
結局一時凌ぎの「和歌解釈」では、十分な味わいも出来ず、どうしてもこの「場」が必要だった
「万葉集」に魅せられて、それに特化したHPなのだから、
素人の私でも、こんな資料があれば、と欲を出して、自分を追い込んでしまった
しかし、その気持ちは間違いではないと思う
確かに、深くを掘り下げての解釈は無理だが、少なからずの疑問を埋めてくれる資料は、
以前に比べていくらかは揃えられた
そして、後は再開する強い意志を持つことだけだったのだが、
ようやく、踏ん切りがついた
しかし、基本的には「一日も欠かさず」という姿勢を持っていたいので、
どうしても、日々更新の手間を効率よくする手段を用いなければならない
その為には、今まで「何に」手間取っていたのか、を考えると
どうしても、「古注釈書」に対する「思い入れ」が強過ぎた
これさえ省けば、といつも考えていたが...
「古注釈書」の魅力は、その解釈の古さなど、決して問題にならず
逆に、当時の人たちの「万葉集」に対する感じ方を知ることになり
とても欠かせないものだった
現代解釈の書で言えば、
「岩波書店『新日本古典文学大系』」
「小学館『新編日本古典文学全集』」
「新潮社『新潮日本古典集成』」
「有斐閣『萬葉集全注』」
他にも、講談社本や岩波文庫本、角川文庫本など、参考にしたい書は揃えた
しかし、それでも、鹿持雅澄「万葉集古義」や橘千蔭「万葉集略解」などに惹かれて揃え
少しずつでも他の「古注釈書」まで揃えつつある
何故かと言えば、現代の学者が到達した最新の解釈が、
すべて「万葉集」の魅力を語っているとは思えないからだ
藤原濱成「歌経標式」や、源俊頼「俊頼髄脳」などもまた、とても魅力的な書だ
古典和歌を解釈しようと思えば、いくらでも手段はある
手っ取り早く、最新の解釈で「歌意」に触れ、感動を味わうのも一つだし、
拙いながらも、自分で語意を拾い集め、自分の感性に響く歌を探すのも一つの方法だ
それに「歌意」は決して「普遍」的なものではない
その歌に接した自分自身の「環境」もまた、大きく影響する
それを楽しむのも、古典和歌の魅力だと思う
特に「万葉集」のように、現代でも多くの難訓が残り、定釈もない歌は多い
難訓であるのは、言うまでもなくその表記にある
助詞を伴わない表記の歌を、どれほど推測で補おうとも、
何かを拠り所にして解釈するには、やはり「助詞」が欠かせないものであり
その部分が「推測」に近いものであればあるほど、そこからまた様々な解釈が派生する
その「宿命」を、「万葉集」は持っている
だから、だと思う
それまでの「訓解釈」が中心だった時期を、画期的に変えた江戸時代の契沖
そこから一気に「万葉集」に精気が伴ってきたように思えてならない
時代が下れば、それだけ先達の研究が重ねられ、一層の理解も進む
しかし、一つの歌に籠められているのは、紛れもない「人の心」だ
どんなに一語一語が、より作歌当時の作者の意に近づいたとしても、
それを感じる人たちは、現代人である我々も含め、随分と違う「感性」をベースにしている
「古典和歌」が蘇えるのは、必ずしも「より正しい」と思う解釈だからではなく
その歌に接した人たちが、自分にどう受け止めることができるか、
その味わい方が、私は個人的に楽しむのには大切だと思う
だから、古典に全く縁遠い私が、ここまで入り込めるのは、
使われた「古語」を探し出し、そして調べ、自分なりに理解し、一つの歌を「かみしめる」
その結果が、どれほど通釈と違っていても、それで味わう歌には、一種の感慨もある
学者や研究者のように、正解を求め、それを積み重ねて広める役目は、私にはない
あくまで、自分が感じられた「歌」に、自分自身の「心のあり方」を学び、楽しむ
無責任だからこそ、ずっと続けられるもの...それが、個人の生き甲斐に成り得る
この休止期間中、「一日一首」で採り上げていた「万葉歌」の歌意解釈が、ここで追いつかず
苦し紛れに「萬葉外伝」と称し、少しでも「万葉歌」との縁絡みで「一日一首」は続けていた
しかし、「万葉歌」の解釈は、ここが中心でなければ、という強い気持ちが消えず
ここに立ち戻るまでの間、最近での「拾遺和歌集」をはじめ、
幾つかの「歌論書」や「歌集」の「歌」を採り上げ、大雑把な解釈に自身を満足させていた
でも、それが半年以上も続くと、次第に「万葉集」の素晴らしさが再認識させられてくる
そして、新年度となり、私の仕事の環境も少しは変化したので、
この機会を逃せないと思った
極力、手間の掛かる作業は不定期にし、
とにかく、「一日一首」で採り上げた「万葉歌」の「歌意解釈」を、ここに載せるスタイル
何とか、それを守っていきたい
【歌意解釈】
さて、そろそろ掲題歌の解釈に入ろうと思う
再開に当って、選んだのが、この「巻第十四」
実は、「巻第十五」を予定していたのだが、ふと「東歌」ばかりのこの巻にした
名も無き作者の「東国」からの「歌」を、順番に扱っていこうと思う
私の夢は、万葉全歌の「私的解釈」だ
少しでも寿命が尽きるまでに書き上げるには、これまであまり馴染まなかった「巻」を、
積極的に取り組んで「意思」を持続させたい
思えば、中断する前は、「巻第十」を歌番号順に採り上げ、それもまだ三百首ばかり残している
ちょうど「七夕歌」の最中だった
時期的に、気分転換にはいいはずだ
「海上潟」の沖合いの砂州に船を停めよう、というのは、
それが、生活の生業となる「漁船」ではないことを、江戸時代の賀茂真淵や橘千蔭は主張する
この巻の巻頭の五首の内、初二首と末一首が、「東ぶりならず」ということらしくて、
そこから官人である「京人」の利用する「官船」だという
しかし、その「京人」であれば、「東国」としなくて、「東国にて詠める歌」などのような、
よくある題詞がついても良さそうだ
地名はともかく、沖合いの砂州に、船を停めて...
確かに漁師であるなら、その日常的な行為に、
また日常的な感慨を詠うのもどうなのだろうか、と思う
詠うことが、「詠わざるを得ないほど」の心の非日常的なことであるのなら、
ここで砂州に船を停めて、夜が更けることに感嘆の表現をすることは、
私も、「漁師」たちの船ではないと思う
しかし、だからと言って、それが「東人」ではなく「京人」に決め付けられるのも、
少し抵抗がある
真淵や千蔭の説に、真っ向から異を唱えたのが、鹿持雅澄だ
「甚偏なる論なり」といい、
「古への東人も、雅言をよく学び得たる人は、猶京人の作にも、立ち遅れざりしなり、かかればここの初二首、末一首のみならず、凡て東歌の中に京人のと異なることなきが多かるは、さる故にこそありけれ」
とは言っても、これもまた「作者不詳」故に、その「歌風」だけで述べたものであり、
雅澄の主張が、決して根拠のあるものとも思えない
だから、私がこの歌の解釈に当って考えたいのは、「東国の歌」、つまり「東歌」ということと、
右頁の注記「なつそびく」で採り上げた「笠間時朝」の一首を参考にしたい、と思った
もっとも「笠間時朝」の時代は、この万葉歌から約五百年後の人だ
現代から五百年前、というほどの大きな変革はないにしても、かなりの時代差がある
それでも、私が注視したかったのは、その歌にある
| なつそびくうなかみがたに舟とめてなみよりいづる月をみるかな |
この歌は、波間より昇ろうとする「月」を観賞するために、船を停めている
情景が、掲題歌とほぼ同じだが、その「意志」は明らかに違う
ただ、それこそ「京人」とか「東人」とかの見方ではなく、
五百年間の「東人」の向かってきたものだ
確かに、笠間時朝は初期鎌倉時代の人、
万葉の時代の「都と東国」の環境とは、格段の違いがあるのだろう
しかし、「歌」はどうだ
「なつそびく」という「枕詞」が使われているのは、そのあまり使われることの無い「枕詞」
それが、この鎌倉時代の時朝に詠わせている
それは、初三句から窺わせる情景が、万葉の時代からこの地で語り、
あるいは口誦されていることなのだと思う
「京人」が掲題歌を詠ったものであれば、その時代から五百年経った鎌倉時代に
時朝が同じような情景に用いるほど口誦されているとは思えない
勿論、他の多くの「東歌」にもほとんど詠われていないことから、言い切れないものもあるが、
少なくとも、万葉の時代の三首の内二首は、
〔3399〕が、「東国武蔵国(万葉の時代東京湾に面している)」で、
〔掲題歌3362〕が、「東国上総国」、
残り一首の〔1179〕が羈旅歌で、「千葉」を詠ったものとされる
「うなかみ」という地名や「うなひ」という海辺を伴うものが、「東国」の歌であるのは、
無理なく考えられるが、長歌〔3269〕は「いのち」にかかり、その歌の場所は不明だ
しかし、この長歌に伴う「反歌」に、
| 巻第十三 3271 反歌 |
| 直に来ずこゆ巨勢道から石橋踏みなづみぞ我が来し恋ひてすべなみ |
| ただにこず こゆこせぢから いしばしふみ なづみぞわがこし こひてすべなみ |
| 或本以此歌一首為之紀伊國之 濱尓縁云 鰒珠 拾尓登謂而 徃之君 何時到来歌之反歌也 具見下也 <但>依古本亦<累>載茲
|
とあり、その歌意は、
真っ直ぐには、あなたのところへは行かずに、
「ここから来い」という「巨勢道」を通って、岩瀬を踏みあなたを探して私は来た
恋しくてたまらなくなったので... |
ここで「巨勢道」という、大和から紀国へ向かう道の名が出てくる
当然これだと「東国」ではなく近畿の歌でも、その長歌に「なつそびく」が詠われたことになる、
しかし、長歌〔3269〕には、やはり地名らしいヒントもなく
この「反歌」で使われた「巨勢道」にしても、想像をかなり逞しくすれば
本来通る必要はない「巨勢道」を通らせる、と言うのは
大和から、東国へ向かう遠回りの道中を言うものかもしれない
「東国」に赴任している男が恋しくて、
女は「この巨勢道」を通れ、という苦労の象徴で、恋しさを詠ったものかもしれない
もっとも、その時代の大和から東国へのルートが、どんなものなのか分からないから、
この長歌と反歌には、深入り出来ない
ただ、「なつそびく」が「いのち」にもかかる「枕詞」であるので、
そうであれば、もっと「万葉集」でも用いられてもよさそうなのに、という疑問は残る
最初の手掛かり、笠間時朝の一首に戻るが、
「波より出づる月」とすれば、東の海辺になるのか
いや、今の市川市周辺の江戸川河口周辺でも、波間から昇る月は見られるかもしれない
やはり...分からない
ただ、時朝が「出づる月」に心を癒されたように、
「海上潟」の砂州で「船を停め」た掲題歌の作者は、
求めて「夜更けの静寂さ」を感じたのではない
結句「さ夜更けにけり」という言い方は、気づけばもう夜も更けてしまった、という気持ちだ
勿論、夜も更けたので、砂州に船を停めようとしたのだろう
「夜の海の、何と静かなことか」と感傷に浸れるような雰囲気の歌には思えない
夜も更けたので、船を停めよう、というのが自然だと思う
夜が更けても、船を走らせることも普通にあることなのかどうか、
本当はそれを知りたい
夜が更けたからと言って、潟の砂州に船を停めずに帰港することもあることなら
折角の静かな夜の海なのだから、慌てて帰らなくても、この砂州でのんびり夜風を浴びよう、
そんな歌意にもなるだろう
それが作者の気持ちであれば、真淵や千蔭がいうような、「京人」の風流かもしれないが
しかし、都人にとって、夜の海は...まして海の上では、平常心ではないのでは、と思う
仮に「京人」だとしても、もうすっかり「東国」の風に馴れ親しんだ者なのだろう
夜更けの海の上を、感嘆して詠うのは、「今ではすっかり東人」か、本来の「東人」のはずだ
|
|
掲載日:2015.04.04
| |
| 東歌 |
| 奈都素妣久 宇奈加美我多能 於伎都渚尓 布袮波等杼米牟 佐欲布氣尓家里 |
| 夏麻引く海上潟の沖つ洲に船は留めむさ夜更けにけり |
| なつそびく うなかみがたの おきつすに ふねはとどめむ さよふけにけり |
| 右一首上総國歌 |
| 巻第十四 3362 東歌 作者不詳 |
| 【3362】 語義 意味・活用・接続 |
| なつそびく [夏麻引く] 枕詞 |
| 「うなかみ」「うなひ(海辺)」、また「いのち」にかかる |
| うなかみがたの [海上潟の] |
現在の千葉県市原市辺りの東京湾岸の砂州
また「海上」という地名は、かつて銚子市の西、利根川南岸の「海上郡海上町」があった |
| おきつすに [沖つ洲に] |
| つ [上代連体格助詞] |
位置・所在などの意を表し、連体修飾語をつくる「~の・~にある」 |
| す [洲・州](中州・砂州) |
海・川・湖などの中に、土砂が積もって水面に現れた所 |
| ふねはとどめむ [船は留めむ] |
| とどめ [留む・停む] |
[他マ下二・未然形] とどめる・引き止める |
| む [助動詞・む] |
[推量意志・終止形] ~しよう・~したい |
未然形につく |
| さよふけにけり [さ夜更けにけり] |
| さよ [小夜] |
[注記] |
| ふけ [更く] |
[自カ下二・連用形] 時が経つ・(夜が)更ける・(季節が)深まる |
| に [助動詞・ぬ] |
[完了・連用形] ~てしまう・~てしまった |
連用形につく |
| けり [助動詞・けり] |
[過去、詠嘆・終止形] ~た・~だなあ |
連用形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
[なつそびく]
この「枕詞」とされる「なつそびく」は、「万葉集中」でも、四首ほどしか表れない、
掲題歌の「うなかみ」は、他に、
巻第七 1179「夏麻引く海上潟の沖つ洲に鳥はすだけど君は音もせず」
「うなひ」にかかるのは、同じく巻第十四東歌で、
巻第十四 3399「夏麻引く宇奈比をさして飛ぶ鳥の至らむとぞよ我が下延へし」
「いのち」にかかるのは、長歌の一文の中で用いられ、
巻第十三 3269「-夏麻引く 命かたまけ 刈り薦の-」
「記紀」や「風土記」には、見えない、ということらしい
それに、この「なつそびく」を、その他の「歌集」を探しても、
出典をこの「万葉集」とする〔1179〕が、小異もあるが「綺語抄・五代集歌枕」に、
また同じく「掲題歌〔3362〕」が「和歌童蒙抄・五代集歌枕・歌枕名寄」に、
〔3399〕の「うなひ」は、「歌枕名寄」に、それぞれ収載されているが、
これらの「万葉歌」と異なるのが、一首だけあり、その収載歌集が、
「前長門守時朝入京田舎打聞集」という初めて目にする歌集だ
| 前長門守時朝入京田舎打聞集 |
| 東撰六帖に入る歌四十七首 後藤壱岐前司基政撰雑 |
| 雑/ 海 |
| 七六 なつそびくうなかみがたに舟とめてなみよりいづる月をみるかな |
| 「前長門守時朝入京田舎打聞集(書陵部蔵五〇一・二八二)」(新編国歌大観解題より) |
本集は、晩年の自撰と考えられ(私家集大成福田秀一氏解題参照)、詞書中の最後の日付が正元元年(一二五九)八月十五夜であるので、それ以降、時朝没の文永二年(一二六五)二月九日以前の成立となろう。
時朝は、藤原氏北家道兼流宇都宮一流、塩屋朝業(信生)の二男。元久元年(一二〇四)五月五日生。文永二年(一二六五)二月九日没、六二歳。常陸笠間の領主となり、笠間氏の祖、従五位上(一説下)左衛門尉・長門守。仁治三年(一二四二)の大嘗会に検非違使を務める。和歌に執心し、関東各地の歌会で活躍した他、中央歌人とも和歌を通じて交流し、いわゆる宇都宮歌壇の主要歌人の一人であった。また、仏法を厚く信じ、多くの仏像を寄進するなど文化的活動に熱心であった。続後撰集以下に計三首採られている。 |
東国を中心に活躍した時朝の歌、「掲題歌」と違う一首とは言っても、
その情景には「月」の視点が加わるだけなのだが、
「月夜の美しさ」か「夜の静寂さ」という惹かれる情景への違いはある
上二句も、それほど多くは詠われておらず、
「東歌」に伝わる歌が「本歌」なのかもしれない
「枕詞」としてかかる語の説明として、
「夏麻引く」というのは、夏麻を引いて苧(お)に績(う)む<糸を作る>、
あるいは夏麻を引き抜く畝(うね)の意で、「海」の「う」や類似音の「うな」にかかる
それに、夏麻を引いて作る「糸」の意で、「命」の「い」にかかる、と説明があった
鹿持雅澄の「万葉集古義『枕詞解』」に、
「夏麻は借り字で、魚釣緡挽(ナツソビク)」とあった
魚を釣る、ということは、〔巻第五-873 山上憶良〕を例としてあげ、
| 足姫神の命の魚釣らすとみ立たしせりし石を誰れ見き [一云 鮎釣ると] |
「魚釣(ナツ)る」と言うことは、まさにこの歌のように、
「釣緡(ツリソ)」を「魚釣緡(ナツリソ)」という
「釣竿(ツリザヲ)」も「魚釣竿(ナツリザヲ)」の例を出して補強する
そして「リ」音は、「活用言(ハタラキコトバ)」として、省かれるとし、
「ナツリソ」が「ナツソ」になる説明をしている
同様に、古事記など多くの用例を出して「ビク」を解説するが、
釣竿を用いての「魚釣り」ではなく、
「延縄」のように「曳く」ことで「魚釣り」と絡めている
何しろ、この「万葉集古義」、歌番号もなく例歌は殆ど原文だけで引用しているので
探すのにひと苦労だ、
この「枕詞」、この辺で止めておこう
[海上潟]
上記の語義解説では、市原市辺りの東京湾岸の砂州、と言い
仮に「うなかみ(海上)」という地名であれば、
「海上郡(かいじょうぐん)海上町(うなかみまち)」が、千葉県東部、銚子市辺りにあった
市原市と銚子市周辺では、どうも現代感覚では合致しないが、
古くは、東京に隣接する市川市辺りが、「市原・海上」の二郡に分かれていて、
旧市原郡三和町に「海上村」の旧名があった、という
この掲題歌が、左注通り「上総国」の歌であれば、「海上潟」は旧海上郡の海岸となり、
「潟」の意味からすれば、東京湾に面した現在の五井、姉崎辺りの、
「遠浅」の海岸だと言うことになる
[とどめ(とどめむ)] 〔参考〕
自動詞ラ行四段「とどまる」
① 同じ所に変らずにある・とまる
② 中止になる
③ 宿泊する・滞在する
④ あとに残る
他動詞マ行上二段「とどむ」
とどめる・おさえる
ここでは未然形に接続する推量の助動詞「む」なので、
その接続から、活用が「下二段」になり、「とどめる・引き止める」になる
[さよ]
接頭語「さ」は、二通りの用法があり
① 名詞、動詞、形容詞に付いて語調を整えたり、意味を強めたりする
〔例語〕
さ霧、さ遠し、さ鳴る、さ寝(ぬ)、さまねし、さ身、さ乱る、さ百合、
さ夜、さ青、さ躍(をど)る、さ小舟(をぶね)など...
② 名詞に付いて「若々しい」の意を添える
〔例語〕
さ苗、さ乙女
「さ」は「小」とも書く
[過去の助動詞「けり」]
過去の助動詞「き」との違いは、
過去の直接体験や、信じられる過去の事柄を回想して表現する「き」と違って
「気づきの助動詞」とも言われる「けり」は、
① 今まで気づかなかった事実に、気が付いて述べる意
「~たのだ・~たなあ」
② 人づてに聞き知った過去の事実を、伝聞として述べる意
「~たという・~たそうだ・~たとさ」
③ 以前から現在まで続いている事柄や伝承を回想する意
「~た・~たのであった」
④ 詠嘆の意をこめて、これまでにあったことに今、気づいた意
「~たことよ・~ことよ」
|
| |
|
| |
 |
| |
 |
| |
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」(今日の歌には無し)]
[本文]「奈都素妣久 宇奈加美我多能 於伎都渚爾 布禰波等杼米牟 佐欲布氣爾家里」 右一首上総国歌
「ナツソヒク ウナカミカタノ オキツスニ フ子ハトヽメム サヨフケニケリ」 右一首上総(カツサ)国歌(「【】」は編集) |
| 頭注 |
「類聚古集」本文ノ下ニ小字「上総」アリ。「古葉略類聚鈔」主文ヲ訓交リニ書ケリ。下ニ小字「上総」アリ。
「和歌童蒙抄」第三「ナツソヒクウナカミカタノオキツスニフ子ハトヽメムサヨフケニケリ 万葉十四ニアリ」 |
| 〔本文〕 |
| 奈都素妣久 宇奈加美我多能 於伎都 |
『古葉略類聚鈔』以上訓ヲ主文トセリ。「ウミカミ」ノ右ニ「宇奈加美(ウナカミ)」アリ。
|
| 加 |
『類聚古集』モトノ字ヲ磨リ消シテ書ケリ。
『京都大学本』「賀」。 |
| 渚 |
『類聚古集・古葉略類聚鈔』「【サンズイが不明瞭】」。 |
| 爾 布禰波等杼米牟 佐欲布氣爾家里 |
『古葉略類聚鈔』以上訓ヲ主文トセリ。 |
| 等 |
『神田本(紀州本)』ナシ。左ニ書ケリ。本文中「波杼」ノ間ニ〇符アリ。 |
| 杼 |
『西本願寺本・細井本・神田本(紀州本)・温故堂本』「【木偏が手偏】。 |
| 〔訓〕 |
| ウナカミカタノ |
『古葉略類聚鈔』「ウミカミカタノ」。
|
| オキツスニ |
『類聚古集』「をきつせに」。墨ニテ「せ」ヲ消セリ。ソノ右ニ墨「を」アリ。
『古葉略類聚鈔』「ヲキツヲニ」。
|
|
|
 |
| 【歌意3363】 |
葛飾の真間の浦のあたりを
漕ぎ進んで行く船の、その乗客たちが立ち騒いでいる
きっとこの先には、荒い波が立っているのだろうなあ
|
| |
この歌の作者の視点は、どこに向けられているのだろう
船の行く方向に、ただならぬ気配を感じさせはするが、
この詠いっぷりから、それほどの切羽詰った動揺は見られない
ここでいう「船人」は、船を漕いでいる「船員」たち、と解釈されている
しかし、「船人」には、その「乗客」をも意味を持つ
だから、別の見方も可能になる
乗客たちが、甲板で潮風に当っていると、
船の進む先に、白い波の立つ様子を見つける
その波を、作者は実際に見ることなく、騒ぎだけで推測する
操船のことなど、まったく知識もないし、
航海中の「船員」たちの経験に基づく振る舞いなど知りはしないが、
作者が詠うような、他所事のような「騒ぎ」に、仮に船員たちであれば、
そんな振る舞いが起るのだろうか
海のことは、俺たちに任せておけ、というような「船員」たちの自負もあるはずだ
どれほどの「なみたち」か、作者の表現でしか想像できないが
プロの船員たちが「騒ぐ」ほどの「波立つ」感じはしない
であれば、不安に慄く「乗客」たちの「騒ぎ」の方が、理解は出来る
ただ、そこで引っかかるのが、「漕ぐ船の船人騒ぐ」という語句だ
連体修飾語の格助詞「の」には、確かに多くの意味もあるが、
その一つに、「作者・行為者」もある
その場合、「漕ぐ船の」だけで、「船人たちが漕いでいる船の」もまた成り立つと思う
この格助詞「の」には、その行為者を含むのだから、
「漕ぐ」という行為は、必然的に文字に表れない「船人」含んでいることも考えられる
そして、続く「船人騒く」こそが、「騒ぐ人」が誰なのか、を示している
この「船の乗客」だと思う
「船員たちが漕ぐ」船の、その「乗客」たちが、
船の進路に白く波立っているのを見て不安気に騒いでいる
その気配を感じた作者は、
「ああ、きっと波が立っていて、みんなあんなに騒いでいるんだなあ」と詠う
勿論、こうしてのんびり構えて詠えるのも、
それが決して「船員」たちの動揺でないこと知っているので、
彼らは、無事に乗り切ってくれるだろう、という信頼があるからだろう
船員たちが「騒ぐ」のであれば、
こうした詠嘆の「らしも」などと詠えるものだろうか...
私が、古典文法など自信を持って言えるものではないが、
仮に作者に「不安がる」気配があるのなら、「らしも」ではなく
活用語の終止形に付く、疑問の終助詞「や」を使った方がいいはずだ
「波立つらしや」...大きな波でも立っているのだろうか...
|
| |
 |
| |
|
掲載日:2015.04.05
| |
| 東歌 |
| 可豆思加乃 麻萬能宇良未乎 許具布祢能 布奈妣等佐和久 奈美多都良思母 |
| 葛飾の真間の浦廻を漕ぐ船の船人騒く波立つらしも |
| かづしかの ままのうらみを こぐふねの ふなびとさわく なみたつらしも |
| 右一首下総國歌 |
| 巻第十四 3363 東歌 作者不詳 |
| 【3363】 語義 意味・活用・接続 |
| かづしかの [葛飾の] |
| 「葛飾」は、下総国の郡名 |
| ままのうらみを [真間の浦廻を] |
| 「真間」は、現在の千葉県市川市真間の辺り |
| うらみ [浦廻・浦回] |
海岸の曲がりくねった所、湾、浦回(うらわ)・原文「宇良未」 |
| こぐふねの [漕ぐ船の] |
| ふなびとさわく [船人騒く] |
| ふなびと [船人] |
船に乗り合わせている人・船客・船頭・船員 |
| さわく [騒ぐ] |
[自ガ四・終止形] 上代は「さわく」
騒がしくする・忙しく立ち働く・騒動が起きる・動揺する |
| なみたつらしも [波立つらしも] |
| たつ [立つ] |
[自タ四・終止形] 生じる・起る・立ちこめる |
| らし [助動詞・らし] |
[現在推量・終止形]
~にちがいない・~というので~らしい |
終止形につく |
| も [終助詞] |
[感動、詠嘆] ~よ・~なあ |
種々の語につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
[葛飾(かづしか)]
和名抄「加止志加」、
「万葉集中」では「勝鹿・勝牡鹿」、仮名書き例は「加豆思加・加豆思賀・可都思加」
現在の江戸川流域で、江戸時代に入る前後の慶長年間に、この江戸川を、
武蔵と下総の国境としたが、それ以前はこの流域は「下総国」という
現在の地名としても、その名残がある、
江戸川の西側の南部が「東京都葛飾区」、北部が「埼玉県北葛飾郡」、
江戸川の東側「千葉県東葛飾郡・野田市・松戸市・船橋市」
[真間]
古代では、東京湾がこの辺りまで湾入し、真間は江戸川(旧太田川)の河口に臨み、
入江をなしていた、と思われている
[宇良未(うらみ)]
この表記は、「西本願寺本」や「類聚古集」などの諸本すべての原文では、
「宇良末(うらま)」とされている
だから、「宇良末」の訓を「うらま」とするのが一般的だったが、
それに異を唱えたのが、鹿持雅澄だ
その注釈書「万葉集古義」には、
| 鹿持雅澄「万葉集古義」萬葉集古義十四卷之上 |
| 宇良未[ウラミ](未ノ字、舊本末に誤、今改、)は、浦回[ウラミ]なり、 |
もっとも、この「誤記説」は、雅澄以前の鎌倉時代の校本である「古葉略類聚鈔」に見える
この雅澄の提唱以来、「宇良末(うらま)」は、「宇良未(うらみ)」に改められ定着する
現代の書では、ほとんど「うらみ」とするが、私の知る限り、一書が「旧訓」のままだ
それは有斐閣「萬葉集全注」で、「宇良末」の表記を用い、勿論その訓は「うらま」とする
ただし、一般的には雅澄の誤記説が通っている、とする
| 有斐閣「萬葉集全注巻第十四」水島義治(巻ごとに執筆者が異なる) |
| 「浦ま」の原文「宇良末」は、西本願寺本、類聚古集、その他の諸本に異同がなく、訓も「ウラマ」であるが、古義が「末は未の誤り」として以来、「ウラミ」とする本が多い。 |
ただし、雅澄の提唱ばかりでなく、近年では約二十年ほど前に発見された「広瀬本」、
それに「宇良未」の表記があることから、そのことを明記しての「宇良未」説が、
一般的に使われている
[らし] 〔活用語の終止形に付くが、ラ変型活用の語には連体形に付く〕
助動詞「らし」の三つの意味
① 推定 ある根拠・理由に基づき、確信を持って推定する意
「~にちがいない・きっと~だろう」
② 原因推定 明らかな事実・状態を表す語について、その原因・理由を推定する意
「~(と)いうので~らしい」
③ 推定 根拠・理由は示さないが、確信を持って推定する意
「~にちがいない・きっと~だろう」
〔古語辞典による「らし」の語史〕
| 古語辞典「らし」の語史 |
「らし」はおもに上代に用いられた語で、平安中期以降はおとろえ、和歌においては「らむ」に、散文においては「めり」にとってかわられた。
「らし」はある根拠・理由に基づいて推定する働きをする。眼前の事実を根拠に推定する表現形式が「①」であり、眼前の事実に基づいてその奥にある原因・理由をを推定するのが「②」である。
「夕されば衣手寒し〔事実=根拠〕み吉野の吉野の山にみ雪降るらし」古今集・冬
「雄神川(をかみがは)紅にほふ少女らし葦付き採ると〔理由〕瀬に立たす〔事実〕らし」 万葉集巻第十七 4045 |
|
| |
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」(今日の歌には無し)]
【3363】
[本文]「可豆思加乃 麻萬能宇良末乎 許具布禰能 布奈妣等佐和久 奈美多都良思母」 右一首下総国歌
「カツシカノ ママノウラマヲ コクフ子ノ フナヒトサワク ナミタツラシモ」 右一首下総国歌(「【】」は編集) |
| 頭注 |
「類聚古集」本文ノ下ニ小字「下総」アリ。「古葉略類聚鈔」主文ヲ訓交リニ書ケリ。下ニ小字「上総」アリ。
「和歌童蒙抄」第五「カツシカノマヽノウラマヲコクフ子ノフナヒトサワクナミタツラシモ 同(万葉)十四ニアリ」 |
| 〔本文〕 |
| 可豆思加乃 |
『古葉略類聚鈔』以上訓ヲ主文トセリ。
|
能宇良末乎許具布禰能 布奈妣等佐和久
奈美多都良思母 |
『古葉略類聚鈔』以上訓ヲ主文トセリ。
|
| 〔訓〕 |
| フナヒトサワク |
『古葉略類聚鈔』「フナ人サハク」。
|
| 〔諸説〕 |
| 〇麻萬能宇良末乎、ママニウラマヲ[古葉略類聚鈔]「末」ハ「未」ノ誤訓、「ママノウラミヲ」 |
|
|
 |
| 【歌意3364】 |
筑波山の新しい野蚕の繭で作った、着物はあるのです
でも...それでも、私はあなたのお召し物が訳もなく着たくてなりません
それほど、あなたが恋しいのです
|
| |
上代の人たちの間で、恋しい相手の着物を着たい、というのは、
その相手の魂を乞うことだという
また、相手からの愛情を得たい、と意味することらしい
この歌の率直さは、歌でこそ「率直」だと言うものの
実際は、面と向かってなかなか言い出せない奥ゆかしさも感じさせる
いろいろな注釈書で、この「相手」を、都から下ってきた「官人」だとか、
東国の農民の歌謡だから、素朴な歌だ、とか言われているが
官人説は、当然「御衣」の実体がそうなのだ、と言うのだろう
立派な「お召し物」だと...
また農民歌謡での相手となれば、その相手の着ている物が、どんな物であれ、
恋する人の「着物」は、「御衣」なのではないか、と思う
それに私自身は、この歌の背景にあるのは、「歌垣」が欠かせない、と思う
春、秋の二季で知られる筑波嶺の歌垣
そこで、右頁の虫麻呂が詠うような「無茶振り」があるにしても
新しい出会いがあってもいいはずだ
何しろ、大掛かりな「歌垣」と言われる「筑波嶺の歌垣」らしい
かなり広範囲なところから、人が集まる
その中で芽生えた「恋」も多かったはずだ
「官人説」だと、離れている二人の雰囲気も自然と歌に滲み出てはくるが、
同じ「東国人」同士であっても、あちこちから人が集まるのであれば、
やはり離れている様子は感じられる
しかし、何も当人同士が、離れていなくてもいい
同じ村の村人でもいいし、「歌垣」で、初めて懇意になった、としてもいい
いつも遠くからであっても見ることは出来る
しかし、こうして「歌垣」で知りあったのだから、もっともっと愛情を求めてしまう
私は、遠く都から赴任してきた相手、またいつかは都に帰るという相手よりも
身近でありながら、歌垣までなかなか近づけなかった相手に、
歌垣で一気に燃えるような恋心を抱いた歌だと思う
「あやに」という言葉が、そう思わせてくれる
今まで堪えていたのは、何だったのだろう、と
あの「歌垣」の一夜が、そのきっかけになった
この歌に、「歌垣」を絡めるのは、よくないかもしれない
しかし、「筑波嶺」が使われている以上、当時の「筑波嶺」には、
そんな意識が潜在しているのではないか、と思えてしまう
勿論、すべての「筑波嶺」という語が、そうだと言うのではない
純粋に景観として、その舞台が「筑波嶺」もある
ただ、恋しく思う「歌」には、どうしても「歌垣」が...ちらついてしまう
|
|
掲載日:2015.04.06
| |
| 東歌 |
| 筑波祢乃 尓比具波麻欲能 伎奴波安礼杼 伎美我美家思志 安夜尓伎保思母 |
| 筑波嶺の新桑繭の衣はあれど君が御衣しあやに着欲しも |
| つくはねの にひぐはまよの きぬはあれど きみがみけしし あやにきほしも |
| 或本歌曰 多良知祢能 又云 安麻多伎保思母/ たらちねの、又 あまた着欲しも |
| (右二首常陸國歌) |
| 巻第十四 3364 東歌 作者不詳 |
| 【3364】 語義 意味・活用・接続 |
| つくはねの [筑波嶺の] |
| 「筑波嶺(つくはね)」茨城県つくば市の秀峰(双耳峰)筑波山 |
| にひぐはまよの [新桑繭の] |
| にひ [新-] |
[接頭語] 名詞に付いて「新しい、初めての」の意 |
| ぐは [桑] |
「桑子(くわこ)」、「蚕(かいこ)」の異称 |
| まよ [繭] |
蚕の「繭(まゆ)」の古形 |
| きぬはあれど [衣はあれど] |
| あれど |
「~はあれど」の形で、「~はともかくも・~はさておき」 |
| 〔成り立ち〕ラ変動詞「有り」の已然形「あれ」に、接続助詞「ど」 |
| きみがみけしし [君が御衣し] |
| みけし [御衣] |
「み」は接頭語、「けし」は動詞「着る」の尊敬語「着(け)す」の連用形の名詞化で、「着物の敬称・お召し物」 |
| し [副助詞] |
語調を整え、強意を表する |
| あやにきほしも [あやに着欲しも] |
| あやに [副詞] |
言いようもなく・わけもなく・むしょうに |
| き [着る] |
[他カ上一・連用形] 衣類を身につける・着る・身に受ける |
| ほし [欲し・形容詞] |
[シク活用・終止形] 欲しい・望ましい |
| も [終助詞] |
[感動・詠嘆] ~よ・~なあ |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
[筑波嶺]
八溝山系、西側に男体山(標高871m)と東側に女体山(標高877m)のピークを持つ双耳峰
常陸風土記にも見られるように、歌垣(嬥歌カガヒ)としても有名な山だ
常陸国に赴任し、そこを舞台とした伝承を多く詠んだ「高橋虫麻呂」の万葉歌に、
| 巻第九 雑歌 1763 高橋虫麻呂歌集 |
| 登筑波嶺為□歌會日作歌一首[并短歌](□は「擢」の手偏が、女偏) |
鷲住 筑波乃山之 裳羽服津乃 其津乃上尓 率而 未通女壮士之 徃集 加賀布の歌尓 他妻尓 吾毛交牟 吾妻尓 他毛言問 此山乎 牛掃神之 従来
不禁行事叙 今日耳者 目串毛勿見 事毛咎莫
[□歌者東俗語曰賀我比] (□は「擢」の手偏が、女偏) |
| 鷲の住む 筑波の山の 裳羽服津の その津の上に 率ひて 娘子壮士の 行き集ひ かがふかがひに 人妻に 我も交らむ 我が妻に 人も言問へ この山を
うしはく神の 昔より 禁めぬわざぞ 今日のみは めぐしもな見そ 事もとがむな [歌垣は、東の俗語に賀我比と曰ふ] |
| わしのすむ つくはのやまの もはきつの そのつのうへに あどもひて をとめをとこの ゆきつどひ かがふかがひに ひとづまに われもまじらむ わがつまに ひともこととへ このやまを うしはくかみの むかしより いさめぬわざぞ けふのみは めぐしもなみそ こともとがむな |
| (右件歌者高橋連虫麻呂歌集中出) |
| 中西進「万葉集全訳注原文付」訳 |
| 鷲の住む筑波の山の裳羽服津の、その泉のほとりに、つれだって女や男が集まり、歌を掛け合う「かがひ」で、他人の妻に私も交わろう。わが妻に他人もことばをかけよ。この山をお治めになる神が、昔から禁じない事だ。今日だけは監視をするな。咎め言もするな。 |
実におおらかな情景が浮ぶ
何故、「昔から禁じない事」なのか、常陸国風土記に、それらしきことが書いてある
人の寄り付かない西の富士山に対して、東の筑波山には、
多くの人が集まり、飲食や歌を歌い合う「場」に、昔の「神」がした、という
この掲題歌は、直接的には「歌垣」の場面ではないが、
筑波山麓に住む男女が交わす恋心を、その背景にしてもいいと思う
[新桑繭]
私は、普通に予断なく読み解釈すると、
「新しい桑の葉で育てた蚕の繭」と思ったが、この箇所は、他にも読み取り方があった
接頭語の「にひ(新)」が、「桑(桑の葉)」ではなく、「桑繭」まで及び、
その「桑繭」こそ、「桑子(野蚕の異名)」であり、「新しい蚕」を指し、
また、接頭語「にひ」が、「繭」そのものを指し、「新しく作られたばかりの繭」など...
一首では、この「新桑繭(尓比具波麻欲)」が修飾するのは「衣」であり、それぞれ、
「新桑の葉で飼った繭で織った着物」(岩波書店「日本古典文学大系」)、
「新しい野蚕(くわご)」(万葉集全釈 鴻巣盛広 昭和5~10年成)では、次のように書いている
| 「万葉集全釈」鴻巣盛広 昭和5~10年成 |
| 桑繭[クハマヨ]とは野蠶[クハゴ]の異名で、和名抄に、「桑繭。唐韻云、久波萬由桑上繭即桑蠶也」とあり、桑樹に野生する蠶である。その形、家蠶に同じく、暗褐色で尾角が黄褐色を呈してゐる。恐らくこれが家蠶の原種であらうと言はれてゐる。繭は七八月頃作り、灰褐色又は黄帶色である。これから粗惡な絹糸を得る。從來この句を春蠶とする説と、桑の春の若葉を以て飼つた蠶とする説との、二に分れてゐるやうであるが、家蠶としては初句の筑波禰乃[ツクバネノ]が理解されないから、筑波山に野生する桑蠶と解すべきである。 |
つまり、「若い桑の葉」と「春の蚕」の二説を承知し、筑波山に「野生する」桑蚕と解釈
そして、残る説として、
「新しくとれた蚕の繭」(万葉集全註釈 武田祐吉 昭和23~25年成)の解説
| 「万葉集全註釈」武田祐吉 昭和23~25年成 |
| ニヒグハマヨノ。ニヒは、新で、繭を修飾し、そのあらたに收穫されたものであることを示す。クハマヨは、桑によつて飼育した蠶の繭。蠶を桑子という。全釋(私注、鴻巣盛広)は、倭名類聚鈔に「桑繭、唐韻(ニ)云(フ)、蟓/久波萬由[クハマユ]桑上繭即桑繭也」とあるによつて、野蠶としている。そうとすれば、初句は、その採取した場處をいうことになる。しかし別傳に、タラチネノ新桑繭ノともあるのを見れば、やはり母が養う蠶の繭として解釋されていたのであろう。またニヒは、あらたに収穫された意であつて、これも春桑によつて飼育したと見るのは當らない。 |
と言うが、「にひ(新)」にあらたに収穫された、とする意があるのもまた頷ける
[あれど]
この「複合語」は、それ自体が定釈となる語意をもつのかもしれない
だとすると、ここでの「あれど」は、「有る」に、逆接の確定条件の接続助詞「ど」を、
普通に解釈した方が、歌意に見合った訳が出来そうだ
[みけし(御衣)]
ここで、面白い対比がある
「新桑繭の衣」と、この「君が御衣」だ
いくら出来たての繭にしても、新しい桑の葉云々だとしても、
それは、「野蚕」から仕上げたもの
しかし、「君が御衣」というには、その表現「みけし」という以上、立派なものだろう
たとえ、実体はそうでなくても、「御衣」という表現が、「新桑繭の衣」の対語であれば
作者の「心情」がかなり「立派な衣」にさせているのだと思う
[きほし]
動詞の連用形が、形容詞と複合した語は多い
この「着欲し」も、「着ることが欲しい」で「着たい」となるが、
たとえば、「万葉歌」でもよく使われる「見まく欲し」などのように、
形容詞「欲し」の前に、動詞は直接付かず「まく欲し」で、「~したい・~でありたい」、
となるのが一般的だが、
この掲題歌のように「着る」という動詞に直接付くのは、
唯一、「着欲(きほ)し」だけのようだ
ちなみに、「まく欲し」の「まく」は、推量・意志の助動詞「む」のク語法
|
| |
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」(今日の歌には無し)]
【3364】
[本文]「筑波禰乃 爾比具波麻欲能 伎奴波安礼杼 伎美我美家思志 安夜爾伎保思母 或本歌曰 多良知禰能 又云 安麻多伎保思母 」 (右ニ首常陸国歌)
「ツクハ子ノ ニヒクハマユノ キヌハアレト キミカミケシシ アヤニキホシモ タラチ子ノ アマタキホシモ」 (右ニ首常陸国歌)(「【】」は編集) |
| 頭注 |
「類聚古集」本文ノ下ニ小字「常陸」アリ。「古葉略類聚鈔」主文ヲ訓交リニ書ケリ。下ニ小字「常陸国」アリ。
「和歌童蒙抄」第六「ツクハ子ノニヰクハマユノキヌハアレトキミカケシカヤカニキホシモ 万葉十四ニアリ」 |
| 〔本文〕 |
| 筑波禰乃 |
『古葉略類聚鈔』以上訓ヲ主文トセリ。
|
| 乃 |
『類聚古集』「能」。 |
| 爾 |
『大矢本』ナシ。上ニ書ケリ。本文中「乃比」ノ間ニ〇符アリ。
|
| 比 |
『古葉略類聚鈔』「庇」。
|
| 具波 |
『古葉略類聚鈔』以上訓ヲ主文トセリ。
|
| 奴 |
『類聚古集』「努」。 |
| 杼 |
『神田本(紀州本)・温故堂本』「□」【「□は手偏に予】 |
| 思志 |
『類聚古集』「志思」。墨ニテ「思志」トスベキ記号を附セリ。 |
| 安夜爾伎保思母 |
『古葉略類聚鈔』以上訓を主文トセリ。
|
| 〔訓〕 |
| ニヒクハマユノ |
『古葉略類聚鈔』「ニヒクハマヨノ」。「欲」ノ左ニ「ユ」アリ。
|
| キヌハアレト |
『類聚古集』「ヌ」ナシ。右ニ墨「ぬ」アリ。
|
| 〔諸説〕 |
| 〇ニヒクハマユノ[代匠記初稿本]「ニヒタハマヨノ」 |
|
|
 |
| 【歌意3365】 |
古里の筑波嶺には、雪が降っているのだろうか
辺り一面を白く染めて...いや、その白さは、雪ではなく
その寒さの中でも、いとしいあの娘が健気に乾す晒なのかもしれないなあ
-懐かしいつくばよ、いとしいあの娘よ-
|
|
昨日以来、この歌の描かれる情景を考えてみた
降りしきる雪、私としては、この上もなく魅力的な景観を醸し出しているが
私も、長い間つくばに住んでいたが、筑波山麓での雪景色は滅多に見られない
勿論、古代の気象環境がどうだったのかは、私には分からないが、
なかなか、そのイメージは浮ばない
しかし、右頁に書いたように、
江戸時代に書かれた注釈書は、どれも「雪景色」を実景としている
万葉の時代ではなく、江戸時代といえば、当然「つくば」は身近なところで、
本当に、そんな描写が無理なく受け入れられたのだろうか...
「雪」の白さ、と
広範囲に渡って乾される「晒」の白さ
仮に、実景が「雪」だとすれば、それで理解出来るのは、
「雪が降るなんて、滅多にないこと」なのに、
まるで「いとしいあの娘が、晒を乾しているのを」想い起させてくれる
それは、この地、つくばにいる作者にとって、遠く離れたところに居る「いとしい娘」になる
そして、実景が「晒」であれば、
見渡す限りに、晒が乾してある
「曝布」という字面から、一面の「白さ」が想像できる
こうした俯瞰的な言い方は、筑波山の上の方からの見方になるのだと思う
そうであれば、少なくとも平地より高いところにいる作者が、
そこに雪が降っているかどうか、何も考え悩むこともない
自分のいるところに、雪がなければ、当然その平地とは言わないまでも、
その麓に雪が降っているのかどうか、すぐに解ることだ
初句「筑波嶺に」の格助詞「に」は、
下から見上げた「筑波山の峰」ではなく、同じ「位置」の格助詞であっても、
「筑波嶺で」という、その峰から麓を眺望すれば、その「白さ」に目がゆき
まるで、雪でも降ったのだろうか、いやそんなことはないだろう、
この峰にいる私の周辺には、その気配もないのに、と言えるかもしれない
ならば、あの「白い」ものは、何だろう...晒なのか、
では、私が愛しいと思っている、あの娘も、その中に混じって、
晒を乾しているのだろうなあ、と
雪が実景とすれば、そこに敢えて「白さ」を重ねる「晒」を詠うのは、
どうもしっくりこない
逆なら、私でも理解出来る
「この曝布は、まるで雪のようじゃないか」と
そこから、「寒さ」が感じられ始め、
この寒空の下で、健気に晒を乾す、いとしいあの娘、と恋心を募らす
それとも、この歌には、他に作者の「意図」があるのだろうか
現代の注釈書の歌意解釈を読み並べても、
あまり興味の惹かない文章になっているのは、
歌の表面的な語意解釈に捉われ過ぎているのではないだろうか
雪ではないことは、当然作者も解り切っていることだと思う
勿論、私がそう感じただけで、作者には本当に迷いがあったのかもしれない
しかし、その解り切った上での「いなをかも」だ
作者の意図を詮索するのは、必ずしも求めなければならないものとは思わないが、
「雪と晒」に目が奪われてしまって、それであんな現代の注釈書のような、
本当に味気ない表現に、しかもどの本も、同じなのは、
語意が解り易いから、そうなるのだろうが
その「解り易い」ことこそ、心情を解するには、とても難しくなる
この歌、まさにその例だと思う
「雪と晒」が、やはり気になる
決して「たとえ歌」ではないだろう
しかし、解り切ったことを敢えて知らないように詠うのは、
そのまま歌意解釈すれば、本当につまらない訳になってしまう
その実例を、現代書に見たのだから...
私は、「雪も晒」も実景ではないと思う
「雪」というのは、当然冬から春にかけての「景観」だ
その底にあるのは、季節的な「冷たさ」...寒さになる
その冷え冷えとする景観を「懐かしむ場所」に作者はいる
今、季節は「冬」なのに、「雪は降っているのだろうか」と
そして、その「雪」から連想される白い「晒」
きっと、私の想い人は、その寒さの中でも、「晒」を乾しているに違いない
そんな「望郷の歌」のようにも思えてしまう
そのきっかけが、「校本万葉集」の頭注で見つけた、鎌倉初期の歌学書「袖中抄」だ、
そこに書かれているのは、この歌を収載し、「是は常陸防人が歌也」とあった
| 袖中抄巻第十五 |
| 常陸防人 |
| 六六〇 つくばねにゆきかもふらるいなてかもかなしきころがにぬほさるかも |
第三句「いなてかも」は、平安末期の「類聚古集」に見える古訓だが、仙覚が否定し、
その訓は消えてしまったような感もある
しかし、ほぼ同時代の「袖中抄」に載るこの小異歌が、その実体は分からないが
「常陸防人歌」とされて伝わっているのを、他の諸本では言及されていない
単純に、「万葉集」に「防人歌」として分類されていないからなのだろうか
しかし、「防人歌」は、そのすべてが採録されたわけではない
それが故に、漏れたものでも、このように「東歌」として、載せられた可能性もある
「常陸防人」が、詠ったものが、「防人歌」として採用されず、
しかし、誰かの意趣に沿って、「東国の歌」でいこう、となったかもしれない
仮に、「根拠」のある「常陸防人歌」であれば、
「望郷の歌」にはぴったりの歌になるはずだ
|
| |
| |
| |
 |
|
| |
|
| |
|

|
|
掲載日:2015.04.07
| |
| 東歌 |
| 筑波祢尓 由伎可母布良留 伊奈乎可母 加奈思吉兒呂我 尓努保佐流可母 |
| 筑波嶺に雪かも降らるいなをかも愛しき子ろが布乾さるかも |
| つくはねに ゆきかもふらる いなをかも かなしきころが にのほさるかも |
| (右二首常陸國歌) |
| 巻第十四 3365 東歌 作者不詳 |
| 【3365】 語義 意味・活用・接続 |
| つくはねに [筑波嶺に] |
| 「筑波嶺」前歌〔3364注記参照〕(つくはね)」茨城県つくば市の秀峰(双耳峰)筑波山 |
| に [格助詞] |
[位置] ~で・~に |
体言、連体形に付く |
| ゆきかもふらる [雪かも降らる] |
| かも [複合語] |
[疑問の係助詞「か」に、強意・感動の係助詞「も」]
疑問の意を表し、「係り結び」として、文末の活用語は連体形になる |
| ふら(ふれ) [降る] |
[自ラ四・已然形] 雨・雪などが降る、また比喩的に涙が流れ落ちる |
| る [助動詞・り] |
[完了、存続・連体形] ~ている |
四段の已然形、サ変の未然形につく |
| いなをかも [否をかも] |
| いなをかも |
そうではないのだろうか、違うのだろうか |
| 〔成り立ち〕感動詞「いな」+間投助詞「を」+疑問の係助詞「かも」 |
| かなしきころが [愛しき子ろが] |
| かなしき [愛し] |
[形容詞シク・連体形] かわいい・いとおしい |
| ころ [子ろ] |
「子ら」の意で、「ろ」は東国語特有の接尾語 |
| にのほさるかも [布乾さるかも] |
| にの [布(ぬの)] |
「ぬの」の東国訛り |
| ほさる(ほせる)[乾す] |
[他サ四・已然形] 濡れたものを乾かす 「さ」は上記「降る」と同じ |
| かも [複合語] |
[注記参照] |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
[かも]
二種の終助詞と、係助詞がある
| 助詞「かも」の用法 |
終助詞
〔終助詞「か」に終助詞「も」〕 |
詠嘆・感動 |
~であることよ |
終助詞
〔係助詞「か」に終助詞「も」〕 |
①疑問 |
~か・~だろうか |
| ②反語 |
~だろうか、(いや、~でない) |
| ③願望 |
~てほしいなあ・~ないかなあ |
係助詞
〔係助詞「か」に係助詞「も」〕 |
①疑問 |
~か・~だろうか |
| ②確定条件の疑問 |
~からか |
古語辞典の文法解説では、
「かも」の用法は複雑であるが、基本は「か(終助詞・係助詞)+も(終助詞・係助詞)なので、「か」の用法に準じて判断すればよい。文末に用いられている場合は、疑問か詠嘆か、全体の文意で判断する。
主に上代に用いられた助詞で、「詠嘆・感動」は中古以降「かな」にとって代わられ、その他の用法は衰えていった。また「係助詞②」の已然形に接続するのも上代特有の用法である |
私には、「かも」の基本である「疑問」だけではなく、
たとえ「疑問・反語」の文意であっても、
和歌であれば、そこに「詠嘆」の気持ちも少なからずある
そう思いたい
[ふらる]
文法的には、完了の助動詞「り」は四段動詞の已然形「れ」に接続するので、
「降れる」となるが、ここを「東国方言」と言うらしい
小学館「新編日本古典文学全集」の注記の解説では、
| 小学館「新編日本古典文学全集『万葉集』」 |
| 降ラルは中央語の降レルに当る東国語形。中央語の「e」が、東国語の「a」に対応することがあり、特に置ケリ・狙ヘリなどの動詞の連用形+「アリ」の約音形(完了態)が置カリ・狙ハリなどという形になる傾向がかなり一般的。第五句の「乾サル」も「乾セル」の東国語形。 |
「東国語」を理解しないと、これから先、この「東歌」の表現に、
文法的に混乱してしまいそうだ
[いなをかも]
一般的な解釈として、ここに解り易い注釈がある
それは、鹿持雅澄の「万葉集古義」の注釈だ
| 「万葉集古義」 鹿持雅澄 天保十三年(1842)成 |
| ○伊奈乎可母[イナヲカモ]は、否歟諾歟[イナカヲカ]と云が如し、母[モ]は歎息ノ辭なり、(俗に、さうであるまいか、さうであらうか、と云に、こゝは同じ、)十一に、相見者千歳八去流否乎鴨我八然念待公難爾[アヒミテハチトセヤイヌルイナヲカモアレヤシカモフキミマチガテニ]、 |
「俗に」というくだりは当然理解出来るが、その前の「否歟諾歟[イナカヲカ]と云が如し」に、
そのような表記を目の当たりにすると、この「いなをかも」が、すんなり頭に入る
「否」か「諾」か...「イナは否定、ヲは諾の応答詞」、判断に迷う気持ちの表現だ
しかし、その表現から「いなをかも」と、どう連携するのかは、雅澄も書いていないので、
これが唯一の解釈とも言い切れないだろう
それに、この歌の情景には、この「いなをかも」の解釈如何で、まったく別の場面が現れる
一つは、筑波山に降る雪景色を見て、詠ったもの
もう一つは、まるで雪かと見紛うほどの、あちこちに乾せる「白布」
現代解釈では、殆どが後者の、
「筑波山麓辺りに、まるで雪が降ったかと見紛うほどに、賑やかに白い晒が乾してある」
という情景に解釈している
しかし、古くからの注釈書を見ると、注釈者の直感的なものや、
調奉にある「曝布」を手掛かりにした見据え方をしている
| 降りしきる雪を、実景として解釈している注釈書 |
| 「雪ヲ見テ興ジテヨメル歟」 [契沖「代匠記」 |
| 「是は本雪なるを、布に見なしたり、常陸よりは曝布の調[ミツギ]奉る事、續紀に見ゆ、然れば多く見なれし物にたとへたるなり、」 [賀茂真淵「万葉考」] |
| 「本は雪なるを、布と見なして詠めり。常陸よりは、曝布の調[ミツギ]奉る事續紀に見ゆ。然れば多く見慣れし物に譬へたるなり。」 [橘千蔭「万葉集略解」] |
| 「實は筑波山に雪の零るを見て、よめるなるべけれど、表には、雪のふれるか、いな然[サ]にてはあるまじきか、然にてあらむか、もし然[サ]にてあらずば、美しき女が布を干[ホシ]たるにてあらむか、さても見事のけしきや、と打見たるまゝに、疑ひて云るとなり、(初メには、雪のふれるならむかとおしはかり、中には、雪にてあらむか、其レにはあるまじきかと疑ひ、終には、布ほせるならむかと、おもひはかりたるさまにて、いとをかしきこゝろばえなり、略解に、曝布にたとへたるなり、と云るは、いさゝかたがへり、」 [鹿持雅澄「万葉集古義」] |
| 「筑波山頂に降つた雪を見て、愛する女が織りあげた布を乾したのではないかと、ふと思つたのである。筑波山麓に住む若い衆の謠つた歌であらう。織布にいそしんでゐた常陸少女の樣も偲ばれるし、又夢寐にもその少女を忘れ得ぬ男の氣分も出てゐる。」 [鴻巣盛広「万葉集全釈」 |
| 「山の雪の白くかかったのを見て詠んだ歌」 [武田祐吉「万葉集全註釈」] |
などがあるが、「万葉考」と「略解」の記述には、ほとんど変わりがなく、
おそらく千蔭が師匠に倣ったものではないか、と思う
異質なのは、雅澄の解釈だ
雪を実景と見て詠ったものだ、としながらも、彼自身が見立てたように、
「否歟諾歟[イナカヲカ]と云が如し」と、第三句「いなをかも」に忠実であろうとする
従って、作者自身の「決めかねる」迷いの心情を詠ったもの、という解釈のようだ
盛広は、語釈でいう、「否ヲ」の「ヲ」は嘆辞のみ、といい、
「古義に「香歟諾歟[イナカヲカ]と云が如し」とあるのは、その意を得ない、という
これが普通の解釈だとは、思う
近代に入ると、どうだろう
| 雪かと見紛うばかりの、曝布 |
| 「雪景色を歌ったものではなく、筑波山麓の聚落の生業として、白布を雪とまがふまで干し並べる、殷賑のさまを歌ったものであることは、言ふまでもない」[土屋文明「万葉集私注」 |
| 同じ立場で、「歌意解釈」を載せる [現代語では、どれも文章としては同じだ] |
| 「筑波嶺に雪でも降ったのかな、違うかな いとしいあの娘が、布を晒しているのかな」 [小学館「新編日本古典文学全集『万葉集』」] |
| 「筑波嶺に雪が降ったのかな、いや違うかな いとしいあの娘さんが布を晒しているのかな」 [岩波書店「新日本古典文学体系『万葉集』」] |
| 「筑波嶺に雪が降っているのかな。いや、違うかな。愛しいあの娘が布を乾しているのかな。」 [新潮社「新潮日本古典集成『万葉集』] |
| 「筑波嶺に雪が降っているのかなあ。いやそうではないのかなあ。かわいいあの娘が、布を乾しているのかなあ。」 [有斐閣「萬葉集全注」] |
小学館の歌意解釈では、はっきりとは分からないが、その頭注に、
「筑波山麓辺り一面雪が降ったかと見紛うほどに白布を乾してある景を詠んだ、布晒の歌」、
とあるのは、この歌意解釈の「文意」を、そう読まなければならない、ということだろう
これは、同じことが岩波書店の叢書にも言える
それに、上述の雅澄がいう「否歟諾歟[イナカヲカ]」のように、
「ヲ」を間投助詞とせず、「諾、応答詞」とし「否(いな)と諾(を)」とするのが、
小学館と新潮社なのだが、解釈上の文言には、どんな工夫が見られるだろうか、と思ったが
現代日本語解釈では、むしろ背景が語られずにいる
それぞれの「注」を読んで、
たとえば新潮社は「曝布の賑々しさを詠んだ歌、国見歌か」ということで、
どちらの立場なのか理解出来る、といった具合だ
そんな注をつけるくらいなら、歌意解釈に反映させればいいのに、と思う
解りづらいのが、講談社「中西進『万葉集全訳注原文付』」で、
文言は、現代注釈書と余り変らないが、その注記で、
「筑波山の白さに興じた民衆歌」という
その「白さ」が雪なのか、曝布なのか、なのに...
[かなしき(愛しき)]
「かなし」という形容詞には「愛し」という表記と、「悲し・哀し」の表記がある
「愛し」の場合は、上記のようにあるが、「悲し・哀し」の場合は、
「かわいそうだ、心がいたむ」などの意が、中心となる
そもそも、「かなし」の原義は、
人事に対しては情愛が痛切で胸がつまる感じ、
自然に対しては深く心を打たれる感じを表す、とある
「かわいがる」意のサ変動詞「かなしうす・かなしくす」
「かわいいと思う、悲しく思う」意の四段動詞「かなしがる・かなしぶ・かなしむ」が派生する
|
| |
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」(今日の歌には無し)]
【3365】
[本文]「筑波禰爾 由伎可母布良留 伊奈乎可母 加奈思吉兒呂我 爾努保佐流可母 」 右ニ首常陸国歌
「ツクハ子ニ ユキカモフラル イナヲカモ カナシキコロカ ニノホサルカモ」 右ニ首常陸国歌(「【】」は編集) |
| 頭注 |
「京都大学本」前ノ歌ノ右ノ行間ニ朱ノ注文アリ。上ノ「本」一字赭。「本第三句伊奈乎可母或本漢字伊奈乎可母其意殊勝々々」右ノ注を墨ニテコノ歌ノ行間ニ引キテ墨ニテ次ノ注アリ。「私此哥注□」【□不明瞭】
「類聚古集」本文ノ下ニ小字「常陸」アリ。
「袖中抄」第十五「万葉哥云 ツクハ子ニユキカモフラルイナテカモカナシキコロカニヌホサルカモ 是ハ常陸防人カ哥也」 |
| 〔本文〕 |
| 伎 |
『類聚古集』「岐」。
|
| 母 |
『類聚古集』「毛」。 |
| 乎 |
『類聚古集』【「手」のような「乎」のような流れる字】。モトノヲ磨リ消シテ書ケリ。
|
| 爾 |
『類聚古集』「企」。
『西本願寺本・温故堂本』頭書「企」アリ。
『大矢本・京都大学本』左ニ〇符アリ。頭書「企イ」アリ。「京都大学本」赭ニテ頭書ヲ消セリ。
|
| 〔訓〕 |
| イナヲカモ |
『類聚古集』「いなてかも」。
|
| カナシキコロカ |
『京都大学本』「兒」ノ左ニ赭「ラ」アリ。赭ニテ右ノ訓ト入レ換フ可キヲ示セリ。
|
| ニノホサルカモ |
『類聚古集』「きぬほさるかも」。
『細井本』「ニヌホサルカモ」。
『西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本』「爾努」ノ左ニ「キヌ」アリ。「京都大学本」赭ニテ「キ」ヲ消セリ。赭ニテ「ヌ」ト右ノ訓ト入レ換フ可キ記号ヲ附セリ。
|
| 〔諸説〕 |
| 〇伊奈乎可母、イナヲカモ、[仙覚抄]「乎」ヲ「手」ニ作リ「イナテカモ」ト訓ズル本ヲ否トシ、「乎」ニテ「イナヲカモ」ト訓ズルヲ可トス。〇ニノホサルカモ、[仙覚抄]「ニヌホサルカモ」。 |
|
|
 |
| 【歌意3366】 |
信濃の須我の荒野にたたずみ、都への望郷を募らせてはいたが、
ここで、またほととぎすの鳴く声を聞くと、いつものことだが
あゝ、今年もその時が過ぎてしまったのだなあ...
いつになったら、京へ帰ることが叶うのか、
もうそれは、夢ということなのか、この荒野を見ていると...
|
| |
信濃の人(あるいは、信濃に赴任している官人)が、「ほととぎす」を詠う
よく言われることだが、この歌は「都の雅」の伝統を継いだ「歌」であり、
この巻第十四の「東歌」に配せられていること自体が、
「信濃」という「旅先」での詠歌になり、決して「東国人」の歌とは思えない、とする
では、「東歌」の定義はなにか、ということになるだろうが、
単純に考えれば、「東国人」が、その「感性」で詠うからこそ「東歌」なのだろう、と
私はそう思うのだが、本格的な注釈が始まった頃からでも、諸説に分かれている
信濃に赴任している都の官人が、ほととぎすの季節を教えてくれる鳴き声で、
帰任の時期に思いを馳せる
あるいは信濃の人が、旅に出ている想い人のことを思って、詠う
これだけでも、その作者の立場は随分と違ってくる
さらに、農耕の時期、田植えの時期を知らせるほととぎすの鳴き声で
一年が過ぎ去ったことへの感慨、とか...
しかし、この説には、条件は同様であるはずなのに、なぜ「東歌」では他に詠われないのか
それが疑問に残る
このように「とき」に対する詮索が、歌意解釈の中心になっているようにも見えるが
「すがのあらの」と、結句の「けり」をみれば、私にはもう少し違った情景が見えてしまう
「東歌」に「ほととぎす」が他に詠われないことは、
確かに「東国人」には一般的な鳥ではないのかもしれない
いや、「ほととぎす」自体が一般的ではあっても、
「和歌」の中に「歌語」として詠み込むこと、
それが「東国人には一般的ではない」とすれば、
他への出現はなくて、都人の感性が窺い見える、という見解も理解出来る
ただ、私はそれが何故「東歌」なのか、ということに引っかかる
単に「信濃」で詠われた、からなのか
それであれば、「羈旅歌」でいいのでは、と思う
右頁に、語意の資料として、普通に拾い出せる解釈を並べたが
そこから汲み取れるこの歌に想いを重ねれば、
先ほど書いた「すがのあらの」と「けり」で、とても重苦しい気分になる
私の感じたままであれば、作者は確かに「都人」だと思う
しかし、ただこの「信濃」に赴任しているのではなく
何かの事情で、流れ着いた「人」ではないか、と思う
その「何か」には、それはそれで、また色々な想像も出来るが
この歌に似合うのは、
もう二度と「都」に戻れないかもしれない「地、信濃」であること
そう印象を持たせる「すがのあらの」だ
「あらの」の語意は、人けのない寂しいところであり、
それが実景であろうが、そうでなかろうが
作者には、信濃にいる自分の「前途」は「荒野」に思われてならない
そこで、季節になると「ほととぎす」の鳴き声を聞く
それは、都での出来事、とりわけ「人事」のような自身にも関わる「噂話」かもしれない
それを、毎年のように聞いては、それが報われずに今日まで至っている
一種の「諦観」の心境のようなものだ
「ほととぎす」が、都人特有の「雅」さで用いられ、それでも「荒野」に呼応するのは、
「都の噂話」を、その時期に鳴くほととぎすに重ねたのだろう
接続助詞「ば」を「恒常条件」で解釈すれば、それが適う
さらに、文末の「けり」に、今年もまたか、という気持ちを滲ませる
こんな風に解釈すれば、作者が置かれている立場、環境が容易に想像できる
そもそも「とき」に関して、多くの解釈が試みられている
ひと言も、その具体的な表現がないにも関わらず、だ
であれば、私のような、その「とき」に絡めての想像だって可能なはずだ
| 赴任地信濃から都への帰任を思わせる「時」 |
| 賀茂真淵「万葉考」 |
旅に在てとく歸らんことを思ふに、ほとゝぎすの鳴まで猶在をうれへたるすがたも意も、京人の任などにてよめりけん |
| 橘千蔭「万葉集略解」 |
旅に在りて疾く歸らん事を思ふに、郭公の時まで猶在るを愁ひたる意も、歌の調も、京人の任などにて詠めりけん |
| 鴻巣盛広「万葉集全釈」 |
(既説を並べ、その上で)京人の歌として、歸るべき時期の遲れたのに驚いたものとしよう |
| 夫を旅に出した妻の帰って来るのを待つ「時」 |
| 新潮社「古典集成」 |
賦役などで旅にある夫が帰ると約束した時期か |
| 井上通泰「万葉集新考」 |
時スギニケリの時を眞淵は歸ルベキ時とし雅澄は逢ハムト契リオキシ時とせり。夫の歸り來べき時なるべし |
| 会うべき「時」、契りし「時」 |
| 鹿持雅澄「万葉集古義」 |
春の末かぎりに逢むと人に約り置しを、得逢ずして、夏來て霍公鳥の音に驚きて、彼が鳴を聞ば、契りし時はや過にけり |
| 農耕の時期、田植えの時期 |
| 契沖「代匠記」 |
落句は、時の至ると云意なり、第六に時のゆければ都と成ぬとよめるを思ふべし、霍公鳥は農を催ほす鳥なればさる心などにてもかくはよめる歟 |
| 単なる「時・暦日・季節」 |
| 武田祐吉「万葉集全注釈」 |
時節の過ぎたことを詠嘆している。この時は、京に歸るべき時期と解せられるが、なお季節の移つたことを嗟嘆したものとも見るべきである |
| 岩波書店「新古典大系」 |
〔歌意〕
信濃の国の須我の荒野でホトトギスの鳴く声を聞くと、もう時節は過ぎ去ってしまったなあ |
| 小学館「新編古典全集」 |
トキスグは、ほととぎすの鳴く声を写した語、とし、「聞きなし」に興味の中心がある歌
だから歌意の上から、この「時」がいかなる場合をさしたかの詮索は無用 |
| 中西進「万葉集全訳注」 |
何の「時」にしろ、「時期」をいう。荒野ではほととぎすを聞く事によって喚起される時間の経過、帰京時の遅延とか、死別後の月日の経過とか(荒野は埋葬の野、ほととぎすは懐旧の鳥)。地方官人の愛誦歌だったろう |
| 有斐閣「萬葉集全注」 |
荒野に鳴くほととぎすの声に、季節の推移の速さをハッと気づいた気持ちが「けり」によって表現されているのである。ただし、、季節の推移の速さに驚くのは、その底にたとえば旅にあって、帰るべき時を契った家郷を思う心情が存するかもしれない。あるいは賦役などで旅にある夫の帰って来るのを待っている故かもしれない |
このように、最後の「単なる時・暦日・季節」の解釈例では、
それがもっともらしく「歌意」を理解させてはいるが、
それは錯覚だと思う
小学館の解釈説明は、とても惹きつけず、それを親切に説明したのが、
中西進「万葉集全訳注」や「萬葉集全注」になるだろうが、
この説明は、限られた文字数、言葉の中に籠められた「歌意」を感じ取る役目を、
私には放棄しているように思える
勿論、それぞれ読む人が感じるべき「和歌」というものだが
少なくとも、研究者が公に「歌意」らしく「論じる」のであれば
その研究者の「感性」というものを全面に出してこその、
万葉学者の「歌意解釈」ではないかと思う
そこに、なかなか「万葉歌」の語意解釈まで手が回らないファンが、
「万葉歌」の魅力を探し求めているはずなのに...
結局上述の仕方だと、単に「古語」解釈でいいことになる
その歌を、自分はどう感じたのか...
私のような素人が、浅い調べ方で受ける「歌意の感情」ではなく、
深いところで感じさせる「何か」を、示して欲しいものだ
私が、何度も何度も読み返して浮ぶその情景...
荒野という「寂寥感」の中に佇む、おそらく左遷人事を思わせる京の官人の姿がある
帰京への想いを抱きながらも、また今年も、その季節は過ぎ去ってしまったのか、と
この一首に使われている「語」には、切ない「哀しみ・諦観」が感じられてならない
|
|
掲載日:2015.04.11
| |
| 東歌 |
| 信濃奈流 須我能安良能尓 保登等藝須 奈久許恵伎氣婆 登伎須疑尓家里 |
| 信濃なる須我の荒野に霍公鳥鳴く声聞けば時過ぎにけり |
| しなのなる すがのあらのに ほととぎす なくこゑきけば ときすぎにけり |
| 右一首信濃國歌 |
| 巻第十四 3366 東歌 作者不詳 |
| 【3366】 語義 意味・活用・接続 |
| しなのなる [信濃なる] |
| 「信濃」東山道十三ヶ国の一つ、今の長野県 |
| なる [助動詞・なり] |
[断定、存在・連体形] ~にある・~にいる |
連体形に付く |
| すがのあらのに [須我の荒野に] |
| すが [須賀] |
[地名] 諸説があるが、所在未詳
|
| あらの [荒野] |
人けのないさびしい野、荒れるに任せてある野 |
| ほととぎす 東歌唯一の「ほととぎす」を詠う |
| なくこゑきけば [鳴く声聞けば] |
| ば [接続助詞] |
[已然形接続で順接の確定条件] 〔接続関係を含め注記参照〕 |
| ときすぎにけり [時過ぎにけり] |
| とき [時] |
「時」の語意には、色々とある 〔注記参照〕 |
| けり [助動詞・けり] |
[過去、気づき・終止形] 〔注記参照〕 |
連用形に付く |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
[信濃]
別称「信州」
『延喜式』によれば、国の等級は「上国」にあたる
国府は当初、上田市常入、後に松本市本郷に移転
訓において、「シナヌ」とする書も多い
現代叢書では、小学館「新編日本古典文学全集」くらいだが、
江戸時代の書では、以前読んだ本で、一種の「流行」だったような記憶がある
ただ、『和名抄』に「之奈乃」とあり、諸本の多くは「シナノ」としている
[すが(須賀)諸説]
筑摩郡苧賀(ソガ)郷曾加(当時の国府、松本市西方一帯)、
小県郡真田町菅平、
西筑摩郡菅村、など
[ほととぎす]
「万葉集」で、一番詠われている鳥は、この「ほととぎす」だ
題詞に見えるものを除けば、156首ある
次いで多いのが「雁」の63首、「うぐいす」の51首なので、
いかに「ほととぎす」が愛されている鳥なのか、と感じさせるが...
それにも関わらず、「東歌」での「ほととぎす」は、この掲題歌の一首だけ
ここにも、この歌の鍵がありそうだ
[接続助詞「ば」]
「未然形」に接続する「順接の仮定条件」もあるが、
ここでは「已然形」接続なので、「順接の確定条件」になり、
その「順接の確定条件」は、次のように用いられる
| 已然形接続の「順接の確定条件」 |
| 原因・理由 |
~ので・~だから |
| 単純接続 |
~すると・~したところ |
| 恒常条件 |
~するときにはいつも・~すると、必ず |
この歌の歌意に相応しい解釈は、私には「恒常条件」のように思える
ああ、また一年が過ぎ去ったのか、という自身の感慨を深める歌だとしたら...
一応、今のところは、そんな風に思えるが、まだ全体の語意を読み込んでいないので、
私なりの結論は、左頁に書こう
[とき]
この歌を解釈する上での、もっとも大きな「語」は、
この「とき」にあると思う
この「とき」を、どう思い描くかで、一首の趣が違ってくる
まず、「とき(時)」の語意を、古語辞典で引いてみた
| 古語辞典「とき(時)」 |
| ① |
月日の移り行く間・時間 |
| ② |
一昼夜を区分した時間の単位・一昼夜を二時間ずつに十二等分して、一時(いっとき)とし、そのそれぞれに十二支を配した。また江戸時代、民間では日の出・日の入りを基準として昼夜にわけ、それぞれを六等分する実用的な時法も行われた |
| ③ |
時代・治世 |
| ④ |
季節・時候・時節 |
| ⑤ |
場合・おり |
| ⑥ |
時勢・世のなりゆき |
| ⑦ |
よい機会・好機 |
| ⑧ |
そのころ・当時 |
| ⑨ |
その場・一時・当座 |
| ⑩ |
勢いがあり、盛んな時期・羽振りのよいおり |
おそらく、この「古語辞典」には載らない「時の概念」もあると思う
それらは、上出の語意から派生するものでなければならないが
それを感じ取るのも、それぞれの時代で歌を楽しむ人たちの「心」になるはずだ
[助動詞「けり」]
この助動詞「けり」については、「一日一首」の「萬葉外伝『なかりけり』」で、
随分拘って採り上げたものだ
一応、「過去の助動詞」とされるものに「き」と「けり」がある
その違いを述べた箇所だけを、大雑把にここに転載すれば、
| 「一日一首」の「萬葉外伝『なかりけり』」2015年1月7日記事 |
「き」は、現在とは断ち切られた過去の事実について述べる
① 過去に直接経験した事実または過去にあったと信じられる事実を回想していう意を表す 〔~た・~ていた〕
② (平安末期以降の用法) 動作が完了して、その結果が存続している意を表す
〔~ている・~てある〕
これに対して「けり」は、現在と関連した過去の事実について述べる
① 今まで気付かなかった事実に、気がついて述べる意を表す
〔~たのだ・~たなあ〕
② 人伝に聞き知った過去の事実を伝聞として述べる意を表す
〔~たという・~たそうだ・~たとさ〕
③ 詠嘆の意をこめて、これまであったことに今、気付いた意を表す
〔~たことよ・~ことよ〕
他、「けり」は、過去の事を今気付いた、というような用法から
「気づきの助動詞」とも言われている
そして、「けり」の肝心な用法と言えば、
動作や存在を表す語に付いた場合や、文中で用いられた場合は、
確かに「過去」の意を表し、また物語の文に用いられたものは
その多くが「過去」を表現している
そこで、「き」と使い分けられるのが、「直接体験か否か」となる |
|
|
 |
| |
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」(今日の歌には無し)]
【3366】
[本文]「信濃奈流 須我能安良能爾 保登等藝須 奈久許恵伎氣婆 登伎須疑爾家里」 右一首信濃国歌
「シナノナルスカノアラノニホトヽキスナクコヱキケハトキスキニケリ」(「【】」は編集) |
| 頭注 |
「類聚古集」本文ノ下ニ小字「信濃」アリ。
|
| 〔本文〕 |
| 婆 |
『類聚古集』「波」。
|
| 〔訓〕ナシ |
| 〔諸説〕ナシ |
|
|
 |
| |
| 「あらたまの」...わかれのとき、なきくずれるを.... |
| 【歌意3367】 |
麁玉の伎倍の林で、泣き崩れるお前を立たせ...
このままでは、私はとても行けそうにない
さあ、お前の方から、ここを離れておくれ
私を...もう行かせてくれないか
|
| |
この歌の情景を思い浮かべるのは、
男が旅立つ時に、妻である女が見送りに「伎倍」の林のところまで見送った場面、
私は、そう感じた
そこまでは、多くの書のように、おそらく自然に解釈できるのだろう
「立てて」と言う語が、四段動詞ではなく「下二段動詞」なので、
立たせるとか、立ち止まらせる、などそこで何かがあることを思わせる
哀しみで崩れる妻を「立たせる」、あるいは「もうここまででいいから」と、
しかし、「ゆきかつましじ」の語釈で、「このまま行けそうにない」とすれば
それは、「妻のあまりの哀しみの姿」を目の当たりにするからだろう
そんな姿を目の前で見れば、どの時代の男だって、なかなか立ち去ることはできない
「いをさきだたね」の「寐乎」を、「寝ること」や「共寝をすること」などと解釈するが、
私には、ここまでの情景を思い遣っていくと、どうしてもそんな解釈にはなれない
すると、都合よく、とでも言いたくなるような鹿持雅澄の解釈に目が行った
それは自説ではなく、
先人「本居氏」(本居宣長の養子の太平なのか、宣長なのか)の説らしいが、
雅澄は、「古義」の中で、「太平」と「本居氏」を使い分けているようなので、
きっと宣長だろうと思う
それに宣長の養子になった太平自身も、宣長の学説を継承しているのだから、
少なくとも、その周辺ではこの「寐乎」が「寐毛」の誤記という認識は普通だったのだろう
雅澄が、簡単にその説を採ったというのではなく、
この上句と下句、結句の繋がり方に、「違和感」があったからだと思う
それ以前の解釈では、右頁に真淵や千蔭などの説を挙げたが、
本格的な注釈書の始まりである契沖の「代匠記・精撰本」では、
真淵と同じような解釈になっている
| 契沖「万葉代匠記・精撰本」 |
| 奈乎多氐天は汝を立てゝなり、立は立待なり、由吉可都麻思自は雪が積[ツ]ましゝにて雪が多く降積て侘しからむなり、落句は寢を先立[サキタテ]ねとなり、冬の此道を隔たる所から伎倍に住女の許へ通ふ男の伎倍の林に汝が立待らむに雪が積て侘しからむ、唯先立て寢よ今到りて諸共に寢むずるぞと云意なり |
上句の場面を、根本的に現代解釈とは違えて「逢瀬の場面」としなければ、
この解釈は成り立たない
現代注釈書では、そんな解釈はないが、「雪」と「寝」を前提とするなら、
当然契沖や真淵の解釈も妥当になってくる
ただ、それでは「なをたたせて」という語句が、死んでしまう
やはり、別れの場面で、泣き崩れる「妻」だからこそ、
その妻を抱えるようにして立たせ、諭すようにここを離れてくれ、という
そんな妻の姿を見れば、男はもう動くことも出来ない
現代注釈書の中でも、「萬葉集全注」は、その解説の中で、
| 妻が伎倍の林まで送ってきて、別れ際にまた「寝ることを先立たせてくれ」とはどういうことなのか |
と疑問を持つ、
しかし、『万葉集注釈』〔澤潟久孝、昭和32~37年成〕の見解を引用し
| これに対して注釈が、私注に「林中に男女相会ふ趣と見える」とあることも「肯けるのであり、その地方の民謡とすれば、むしろその方が自然だと云える」 |
としている
そうなれば、結句の唐突感も払拭されたかのような記述だった
当然、この「全注」に限らず、多くの現代注釈書は、結句に異同は少ない
これも「東歌」という「東国」ならではの理解の仕方が、そうさせているのだろう
確かに、「東国」は都周辺からみれば「異郷」の地かもしれない
しかし、「和歌」という一応の文化的な「詠い」を残している以上、
何から何まで「東国だから」という括り方もよくない
「民謡」と言ってしまえば、それが「和歌」であっても同じものなのか
いや、「民謡」という背景に純然と備わる感情的な諸々のものが、
「和歌」という、一つの形を持った「文化」に昇華されているはずだ
私は、基本的には「誤字説」には、滅多に従わないことにしている
それを認めれば、どんな歌でも恣意的な解釈が可能だ
しかし、この掲題歌のように、「いね」と「いも」を違えることによって、
「民謡」に見える、などと条件説明をつけなくても、
素晴らしい一首になることもある
これは、秀歌を望むが故に、いわば添削後の非オリジナルの歌だ、というのではなく
「秀歌」かどうかの問題とは違う
限られた「文字数」「語調」から、読む人々が感じられるのが「和歌」であれば
むしろ「いね」ではなく「いも」であるべきだし、
「いも」に固守するのであれば、「民謡」歌として全面的に評価すればいい
この掲題歌、「あらたま」という地名、そして「遠江国」であるのなら、
東国と言っても、関東とは違って随分と都には近い
それでも、郷里を離れる人たちの旅立ちは、これほどの「切ない別れ」なのか
それを思うと、関東以北の人たちの「別れ」は、本当に今生の別れと思うものなのだろう
東歌も防人歌も、重なる心情が多いと思う
一つの歌集に、こうした趣向があるのも、また「万葉集」の魅力の一つなのだろう
|
|
掲載日:2015.04.12
| |
| 東歌相聞 |
| 阿良多麻能 伎倍乃波也之尓 奈乎多弖天 由伎可都麻思自 移乎佐伎太多尼 |
| あらたまの伎倍の林に汝を立てて行きかつましじ寐を先立たね |
| あらたまの きへのはやしに なをたてて ゆきかつましじ いをさきだたね |
| (右二首遠江國歌) |
| 巻第十四 3367 東歌相聞 作者不詳 |
| 【3367】 語義 意味・活用・接続 |
| あらたまの [麁玉の] |
| 「麁玉」遠江国の郡名、今の浜松市、浜北辺り |
| きへのはやしに [伎倍の林に] |
| きへ [伎倍] |
[地名] 「あらたま」を郡名とすれば「きへ」は地名となる
|
| はやし [林] |
木の群生している所・比喩的に、多くの物が集まっている所 |
| なをたてて [汝を立てて] |
| な [汝・対称の人代名詞] |
自分より目下の者や親しい人に対して用いる、「おまえ・あなた」 |
| を [格助詞] |
[対象] ~を |
体言に付く |
| たて [立つ] |
[他タ下二・連用形] 立たせる・立ち止まらせる |
| て [接続助詞] |
[補足・行われ方] ~ようにして・~て |
連用形に付く |
| ゆきかつましじ [行きかつましじ] |
| かつ [補助動詞] |
[タ下二・終止形] ~できる・~に耐える |
| ましじ [助動詞・まじ] |
[打消し推量・終止形]「まじ」の古形「~できまい・~はずがない」 |
| いをさきだたね [寐を先立たね] |
| い [寐・睡] |
寝ること・睡眠 |
| を [格助詞] 〔注記〕 |
[対象] ~を |
体言に付く |
| さきだた [先立つ] |
[自タ四・未然形] 真っ先に起る・先んずる |
| ね [終助詞] |
[上代語] ~てください・~てほしい |
未然形に付く |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
[あらたま(麁玉)]
この表記は、「万葉集」巻第二十の「防人歌」にも見える
| 巻第二十 4346 (天平勝寳七歳乙未二月相替遣筑紫諸國防人等歌) |
| 和我都麻波 伊多久古非良之 乃牟美豆尓 加其佐倍美曳弖 余尓和須良礼受 |
| 我が妻はいたく恋ひらし飲む水に影さへ見えてよに忘られず |
| わがつまは いたくこひらし のむみづに かごさへみえて よにわすられず |
| 右一首主帳丁麁玉郡若倭部身麻呂 |
| ( 二月六日防人部領使遠江國史生坂本朝臣人上進歌數十八首 但有拙劣歌十一首不取載之) |
題詞は、「天平勝宝七年乙未二月に、交代して筑紫に派遣された諸国の防人たちの歌」
この歌の作者は、「麁玉郡出身の主帳である若倭部身麻呂」
左注は、「二月六日、遠江国で防人の輸送を仕切る部署の書記官坂本朝臣人上が、薦めた防人たちの歌は十八首だが、拙劣な歌十一首があり、それは載せなかった」、とある
この「防人歌」、笠女郎を扱った〔2013年4月30日付けの記事〕で、
傍証の例歌として、一応扱っている
本格的な解釈は、いずれ、ということになる
「あらたまの」と聞くと、すぐに「枕詞」を思い浮かべるが、
「万葉集中」で、「あらたまの」とあるのは三十六首、
しかし、この掲題歌の他に次の一首は、「枕詞」ではなく、
「あらたまのきへ」とする地名が一般的だ
| 巻第十一 2535 正述心緒 |
| 璞之 寸戸我竹垣 編目従毛 妹志所見者 吾戀目八方 |
| あらたまの寸戸が竹垣網目ゆも妹し見えなば我れ恋ひめやも |
| あらたまの きへがたけがき あみめゆも いもしみえなば あれこひめやも |
| 作者不詳 |
勿論、この〔2535〕の「あらたまの」も「枕詞」とする注釈書は多いが、
その場合には、「きへ」に掛かる理由が、明らかにされていない
「枕詞」としての「あらたまの」は、
「年・月・日・春」などにかかり、そこに「新しい・新たな」の意が汲み取れる
ただし、「きへ」が、それに適えば「枕詞」としても用いられるだろうが、
掲題歌のように、「あらたまのきへ」が、地名として成り立っている以上、
この〔2535〕もまた、地名とした方がいいと思う
ただし、あくまで「きへ」を普通名詞とすれば、
「柵戸(城塞を守る民」や「伎戸(古代帰化人の機織伎人の民戸)」とも考えられるらしい
それでも、枕詞「あらたまの」にかかる語というのには、難しいと思う
[きへ]
「万葉集中」に、「きへ」が「地名」とはっきり分かる歌は、ないと思う
この掲題歌にしても、上述の注記「あらたま」のところで書いたように、
普通名詞の「きへ」も考えられるからだ
この歌は「相聞」の一首であり、その対となる歌が、
次の〔3368〕の「きへひとの」が、「きへの地に住む人」とした方が自然だと思うので、
そうなると、掲題歌の「きへ」もやはり「地名」の「きへ」なのだろう
[はやし(波也之)]
原文「波也之」を、木の群生する「林」とするのが歌意の上でも問題ないが、
有斐閣「萬葉集全注」に面白い解釈があった
本歌解釈は、「林」だが、他の解釈として、民俗学的な一考も載せている
| 有斐閣「萬葉集全注 巻第十四 水島義治著」[この全集は各巻執筆者が違う] |
「はやすの名詞形から出た語。『はやす』は『はなす』と近い語で、分霊を殖やし、分裂させること」、「古代には木の枝を伐って之に分霊を移す行事があった。今も旅立ちに際して村境の塞側で去る者留まる者が、木を伐って魂分割(タマハヤシ)の式をするのである」
(高崎評釈) |
確かに、この民俗学的な情景が、掲題歌の底にあっても、不思議なことではない
[かつましじ]
補助動詞「かつ」、助動詞「ましじ」いずれも上代語の終止形で、活用語の終止形に付く
「かつ」の語法は、動詞の連用形の下に付いて、
下に助動詞「ず」の連体形「ぬ」及び古形の「連用形「に」、
また助動詞「まじ」の古形「ましじ」など打消しの語を伴って、
「かてぬ」「かてに」「かつましじ」の形で用いられることが多い
「ましじ」の語法は、「敢(あ)ふ」「得(う)」「堪(た)ふ」「克(か)つ」など、
可能の意を持つ下二段動詞、あるいは可能の助動詞「ゆ」に付くことが多い
[い(寐・睡)]
単独では用いられず、助詞を介して動詞「ぬ(寝)」とともに、
「いの寝らえぬに」「いも寝ずに」などの句として用いられる
また、「熟寝(うまい)」「安寝(やすい)」などの語を作る
[を 原文「乎」]
一般的には、この「を」は、格助詞として解釈され、「寝ることを」となるが
それでは、この歌の意味を成さない、というのが、鹿持雅澄だ
そう思って、この歌の定釈...これもまた諸説があるが、それは下三句の情景によるだろう
その定釈を読み直してみると、確かに不自然さはあるし
いや、現実的に定釈では、あまりにも「情緒」が無さ過ぎる
いかにも「率直な万葉集」とはいえ、あるいは「素朴な東歌」とはいえ...
雅澄は、その著「万葉集古義」で言う
| 鹿持雅澄「万葉集古義十四之上」 |
| ○移乎佐伎太多尼[イモサキダタネ]は、稻掛ノ太平云、乎ノ字は毛の誤なるべし、妹先立[イモサキダヽ]ねなり、○歌ノ意は、本居氏、これは男の旅立行時、妻の伎倍[キヘ]の林まで、送リ來ぬるを別るゝ時、男のよめるなりと云る如し、伎倍[キヘ]の林に、汝を立留らせ置て別れ行カば、さても得行あへじ、妹も立チとまらずして、前立てゆけかし、さらば吾も共に行むぞ、となるべし、 |
「稻掛ノ太平云」の「稻掛太平」とは、本居宣長の養子になる「稻掛太平」のこと
雅澄は、その「誤字説」を引用して、「共に寝よう」ではなく、
「お前(いも)がそこを立ち去らないなら、私は行くことができない、だから先に行ってくれ」
というような解釈だと思う
もっとも、「共に行むぞ」というのが、
別れるのではなく「行動を共にする」とも考えられるが、
私の読解力では、「同じように私も行くから」くらいしか思いつかない
しかし、この雅澄の歌意解釈には、上記の「乎」と「毛」の誤字説だけでなく、
第四句「由伎可都麻思自」の「自」も「目」の誤字とし、「ゆきかてましも」とする
補助動詞「かつ」の未然形「かて」に、推量の助動詞「まし」、
そして詠嘆の終助詞「も」の構文になる
でも「可都」を「かつ」と終止形に訓むことは問題ないが、未然形の「かて」、
「都」を「て」とは訓めないはずだ
「自(じ)」を「目(も)」にしたため、未然形接続の助動詞「まし」だから、
「都」を「て」にしなければならなかった、としたら、かなりの無理がある
ただ、歌意については、定釈よりも「別れの情緒」が気持ちよく残る
この雅澄の時代を少し遡れば、真淵「万葉考」、千蔭「略解」なども同様の誤字説だが、
彼らは、そもそもが第四句「由伎可都麻思自(ユキカマシモ)」の語釈を、
「雪が積もりし也」とし、その歌意を、真淵はそのまま確信し、
千蔭は、師匠はそう言うけれど、とその解釈に自ら改意の記述をしている
| 「万葉考」「略解」の歌意解釈 |
○万葉考
男の來て伎倍の林に立待と告しに、女はいまだ母のゆるさねば、ねやへ入がたき間に、雪のふれば其林に積らんには堪じ、吾より先だちてね屋へ入ふして、待たまへといひやれるなり
〇略解
歌の意は、男の來て、伎倍の林に立ち待つと告げしに、女は未だ母の許さねば、閨へ入れ難き間に雪の降れば、其林に積らんには堪へじ。吾より先立ちて閨へ入り臥して待ち給へと言ひ遣れるなりと翁の説なり。されどすべて「イ」と言ふは眠る方に言ひて、臥す事を「イ」と言はざれば、此説いかにぞや。宣長云、是れは男の旅立ち行く時、妻の伎倍の林まで送り來ぬるを、別るる時の男の歌なり。きべの林に汝を立ちとまらせ置きて、別れ行く吾はえ行きやらじ。汝も立ち留まらずして、先立ちて行けかし。吾も共に行かんと言へるなり。「ユキガツマシモ」は、行キガテマシモなりと言へり。さて伊勢人稻掛大平が説に、移乎は、移毛[イモ]の誤なるべしと言へり。斯くては、いと穩かに聞ゆ |
江戸時代の「万葉観」の面白さを垣間見ることができる
ただし、それが古いから現代では否定される、というものではない
あくまで、歌には「情感」を持たなければならないのだから、それはいにしへ人も、
また江戸の人であろうが、現代人であろうが、どの時代でも言えることだ
|
|
| |
| |
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」(今日の歌には無し)]
【3367】
[本文]「阿良多麻能 伎倍乃波也之爾 奈乎多氐天 由吉可都麻思自 移乎佐伎太多尼」 (右二首遠江国歌)
「アラタマノキヘノハヤシニナヲタテヽユキカツマシヽイヲサキタタニ」(「【】」は編集) |
| 頭注 |
「類聚古集」本文ノ下ニ小字「遠江」アリ。
|
| 〔本文〕 |
| 天 |
『類聚古集』「々」。右ニ朱「天」アリ。
|
| 吉 |
『西本願寺本・神田本・温故堂本・大矢本・京都大学本』「伎」。左ニ「吉又一本如此吉也」アリ。上ノ「吉」一字赭ナリ。
|
| 可 |
『大矢本』ナシ。頭書「可」アリ。本文中「伎都」ノ間ニ〇符アリ。
|
| 太 |
『類聚古集』ナシ。
|
| 〔訓〕ナシ |
| 〔諸説〕 |
| 〇由吉可都麻思自、ユキカツマシヽ、「万葉考」「自」ハ「目」ノ誤訓「ユキカツマシモ」。〇移乎佐伎太多尼、イヲサキタタニ、「略解」稻掛太平説、「乎」ハ「毛」ノ誤ニテ訓「イモサキタヽニ」トス。「古義」「イモサキタタ子」。 |
|
|
 |
| 【歌意3368】 |
それにしても、ここの人たちの暮らし振りは、何と裕福なことか
普段使っている斑模様の布団には、綿が多く入ってるじゃないか
「遠江国」での任期を終え、都に帰ると言うのに
いささか、残念な気持ちでならない
あの娘の「綿衾」に、あのままずっと入っていれば良かったかもしれないなあ
あんなに、別れを悲しんでいるのだから...
|
| |
歌物語であれば、この歌の前に、
どうして、そんな風に思うのか、情況の場面があるだろう
この一首を単独で解釈すれば、それでも大まかに二通りにはなる
①「きへひと」が使っている「斑模様の布団」には、綿が沢山入っている、と聞く
そんな恋しいあの娘の「斑の布団」に、入ってくれば良かったなあ...
②「きへひと」の使う「斑模様の布団」には、綿が沢山入っている
その綿のように、私もあの娘の布団に一杯時間を掛けて入ってくれば良かったなあ...
一般に、上三句が、「入り」を起こす「序詞」と言われている
「序詞」であれば、その解釈は「②」が中心となるだろうが、
そんな心地良い「布団」であれば、とすると、「①」も成り立つ
しかし、どちらの場合でも、この歌を詠む前の情況が気になる
このように思い始めたら、どうしても、まず「きへ」という言葉に引っかかってしまう
何故なら、憶良の「貧窮問答歌」(右頁)に引用される「斑衾」というのが、
非常に高級品であると印象を持ってしまうが、
そんな代物を日常の生活で使用している「きへひと」、
あるいは「きへ」と言われる人たちは、決して「東国農民」のイメージにはならない
そしてもっとも大きな疑問と思われるのが、「きへひと」という概念が、
はたしてどこまで知られていたのだろうか、ということだ
庶民の生活に比べ、かなり裕福な「斑衾」を使うなど、
誰でも、その存在を承知していると思っていたが、そうでもなかった
まず、「きへひと」という語句は、この「万葉集」にこの一首、
しかも他の「歌集」で詠われているのが、それも一首
「きへ」が「地名」とすれば、「きへひと」もまた、同類になるのだから
「きへ」及び「きへひと」と詠われる歌が、
この「万葉集東歌相聞の二首」と、他に一首と言っても、次のような内容なので、
実質的に「きへひと」と言うのは、その
やはり、この二首には強い関連性があると思うのが自然のはずだ
鎌倉初期の「六百番歌合」という、「歌合」ではもっとも知られている中に、
判者、藤原俊成の「判じ」がある
| 「六百番歌合」(左大将家百首歌合) 藤原良経、建久四年(1193) |
| 「冬部 冬朝」 ○伊利奈麻之母乃[イリナマシモノ] |
廿二番 左持 有家
五八三 きへひとのまだらぶすまはいたまよりしもおくよはのなにこそ有りけれ |
右 中宮権大夫
五八四 さゆるよはあづまをとめもいかならむ風もたまらぬあさでこぶすま |
右申云、きへ人不審、陳云、見万葉集、左申云、無申事
判云、左歌、きへ人前前申す事には侍れど、万葉集に見えたりといへれば閉口する事は不可然事也、万葉集にもとりいでて可宜事をよむべきなり、右歌、あさでこぶすまなど万葉集の風情なるべし、左も、まだらぶすま霜おく心など、ゆゑなきにあらざるべし、持と申
すべくや |
詳しくは解らないが、「きへひと」という語は、「万葉集」に見えること、といい
それは、この時代でも珍しく、そして「きへひと」が一体どんな「ひと」なのか、
そんな感じを抱かせている
確かに、どの文献(私の資料なんて、たかが知れているが)にも、
「きへひと」についての詳しい記述はない
ただ、憶良が引用した一文を参考にすると、「綿を入れる」ことが高級な代物であり
その「斑衾」を「きへひと」は使っていることを思えば
確かに、普通に考えられる「東国の人々」とは違う
当然、「万葉集」に「遠江国歌」とあるのは、他の「東国歌」と何も変らない装いだ
しかし「東国歌」がどれもそうだとは思わないが
この相聞の二首については、「東国=田舎」を思わせない
いや、「田舎」であってもいい
しかし、中央の権威が行き届いている「田舎」ではなく
その「国」自体に、何かしらの魅力を際立たせているかのようだ
「万葉集編者」の意図するものが、私には解らないが
その万葉の時代においてさえも、目立つことのない「きへひと」たちの、
それでいて「裕福」な暮らし振りを思わせる「歌」を垣間見せている
「六百番歌合」の左方、有家の歌「きへひとの まだらぶすま」という語句は、
それが「万葉時代」から伝わっている一種の伝説のようなものなのかもしれない
歌意解釈に向かう前に、もう一つ考えたい「訓釈の仕方」がある
それは、右頁でも触れた鹿持雅澄の訓解釈に、
「此ノ下に、安比太欲波佐波太奈利努乎[アヒシヨハサハダナリヌヲ]、とよめり」とし、
これは、同じく巻第十四の一首、
| 「万葉集古義第十四之上 東歌相聞 (新編国歌大観歌番号 三四一三) |
| 乎豆久波乃 祢呂尓都久多思 安比太欲波 佐波太奈利努乎 万多祢天武可聞 |
| 小筑波の嶺ろに月立し間夜はさはだなりぬをまた寝てむかも |
| をづくはの ねろにつくたし あひしは さはだなりぬを またねてむかも |
雅澄は、「古写本」などで、「佐波太爾」があることも言っているが、
それだと、「さはだ」という副詞が、
まるで形容動詞の「連用形語尾『に』」のような働きをしているかのような解釈だと思う
文法的に「さはだに」と言えるかどうか、私には解らないが
小学館「新編日本古典文学全集」では、「佐波太尓」そのまま「さはだに」と載せている
雅澄が、掲題歌の訓「さはだ」の引用に、この歌を用いたのは解るが、
結局この歌にしても、底本となる「西本願寺本」は「佐波太尓」であり、
「元暦校本」や「広瀬本」では「佐波太」としている
そして、おそらく賀茂真淵「万葉考」を始め、その一門の言う「太」と「爾」の誤字説も、
そこから発生したのではないか、と思えてしまう
確かに「さはだに」とするなら、「さはに」とした方が、文法的には理解出来る
この〔3413〕を読んでいたら、この歌もまた大きな解釈の問題を含んでいた
ここでは、本格的には書かないが、いずれこの「東歌」を続けていけば、そのとき書ける
それまでは、我慢しよう
とにかく、この掲題歌の歌意解釈に入らなければ...
「きへひと」が、単なる「東国の人」である意味だけではなく
何かを暗示させるかのような「人々」であるなら、
前歌〔3367〕を踏まえるべきだし、そのためには、私が感じた〔3367〕の解釈を、
もう一度見つめ直さなければならない
その記事で、前歌〔3367〕を、次のように解釈した
麁玉の伎倍の林で、泣き崩れるお前を立たせ...
このままでは、私はとても行けそうにない
さあ、お前の方から、ここを離れておくれ
私を...もう行かせてくれないか
ここでは「きへ」が、何も特別な様子は感じられない
しかし、〔3368〕になると、その印象は一変する
だから、その一変した印象で、逆に〔3367〕歌を読まなければならない、と思う
前歌で、男は「きへ」の女と別れる場面だった
別れを悲しみ、泣き崩れる女を抱え起こし立たせる
さあ、もう家に帰って休みなさい
このままでは、私もここを去れないではないか、と
そして、今日の掲題歌〔3368〕
男は、やっとの思いで、女と別れ、悲しみを堪え「きへ」を立ち去る
それにしても、ここの人たちの暮らし振りは、何と裕福なことか
普段使っている斑模様の布団には、綿が多く入ってるじゃないか
「遠江国」での任期を終え、都に帰ると言うのに
いささか、残念な気持ちでならない
あの娘の「綿衾」に、あのままずっと入っていれば良かったかもしれないなあ
あんなに、別れを悲しんでいるのだから...
[2015年4月18日追記] 〔Yahooブログ「一日一首」記事〕
この歌の解釈、また改めて考えてみた
防人歌を読むと、また「いにしへの舞台」が広がる
|
|
掲載日:2015.04.14
| |
| 東歌相聞 |
| 伎倍比等乃 萬太良夫須麻尓 和多佐波太 伊利奈麻之母乃 伊毛我乎杼許尓 |
| 伎倍人のまだら衾に綿さはだ入りなましもの妹が小床に |
| きへひとの まだらぶすまに わたさはだ いりなましもの いもがをどこに |
| 右二首遠江國歌 |
| 巻第十四 3368 東歌相聞 作者不詳 |
| 【3368】 語義 意味・活用・接続 |
| きへひとの [伎倍比等乃] |
| ここでの「きへ」も前歌同様、麁玉郡の「きへ」と思う |
| まだらぶすまに [萬太良夫須麻尓] |
| まだら [斑] |
[名詞・形動] 色・濃淡などが混じっていること、また、その様 |
| ふすま [衾・被] |
寝るときに上に掛ける「夜具」、掛け布団、かいまきなど |
| わたさはだ [和多佐波太] |
| わた [綿] |
真綿や絹綿 |
| さはだ [副詞] |
たくさん・多く (「だ」接尾語とされる) |
| いりなましもの [伊利奈麻之母乃] |
| いり [入る] |
[自ラ四・連用形] 中に入る・入って行く・時間、時期になる |
| な [助動詞・ぬ] |
[完了・未然形] ~てしまった |
連用形に付く |
| まし [助動詞・まし] |
[反実仮想・連体形] ~たらよかった |
未然形に付く |
| もの [終助詞] |
[逆説的な詠嘆] ~のになあ・~のだがなあ |
文末に付く |
| いもがをどこに [伊毛我乎杼許尓] |
| をどこ [小床] |
「を」は、語調を整える接頭語で、寝床のこと |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
[まだらぶすまに]
この時代は、「敷布団」はなく、「茣蓙、蓆」などを敷いて寝ていた、という
この歌の「斑衾」が、当時の人たち、この場合の「きへひと」にとって、
どの程度の「財産価値」があるのか、興味がわく
有斐閣「萬葉集全注」の「斑衾」の説明では、
| 種々の色を濃く淡く斑に染めた、おそらくは麻布か木綿、しかも綿の沢山入った夜具=掛布団。-(中略)-斑衾は到底、憶良の貧窮問答歌に「綿もなき布肩衣の海松(みる)のごとわわけ下れるかがふのみ肩に打ち懸け」と歌われたのに似ていたと思われる東国農民の手にすることの出来る代物ではなかった。 |
この引用文の憶良の「貧窮問答歌」は、「万葉集巻第五-八九六」の一節だが、
その描写にある「綿もない、海藻のように、ばらばらと垂れ下がっている布肩衣」という、
その「貧窮」振りを語る「衣」のように、
東国の農民は同じように「綿の入っていない」代物を用いていた、
「斑衾」のような高級品は、手に出来ない、という説明なのだろう
とすると、掲題歌の「斑衾」は、随分高価な夜具、ということになり、
「きへひとの まだらぶすまに」の解釈に大きく関わってくる
[わた]
「真綿」繭を引き伸ばして作ったもの、主に屑繭から取る
「絹綿」真綿の一種で、屑綿のケバで作ったもの
現在の「木棉綿」ではない、とされている
「棉」が天竺人によって、日本にもたらされたのが延暦十八年(799)のこと
従って、奈良時代に「わた」と言えば「真綿か絹綿」ということになる
[さはだ]
賀茂真淵「万葉考」で、「わたさはだ」の「太」は、「尓」の誤字で、「わたさはに」とする
確かに「さはに」が一般的な「副詞」なのだろうが、
鹿持雅澄は、その著「万葉集古義」で、次のように言う
| ○和多佐波太[ワタサハダ]は、綿多[ワタサハダ]なり、佐波太[サハダ]は、多[サハ]と云に同じ、(岡部氏が、太は爾の誤なり、と云るはあらず、)此ノ下に、安比太欲波佐波太奈利努乎[アヒシヨハサハダナリヌヲ]、とよめり、さて此までは、衾に綿を入るを云て、入といはむ料の序なり、 |
岡部氏とは、賀茂真淵のことで、この誤字説は、「万葉考」のことを言うのだろう
雅澄は「わたさはだ」を「綿多」という漢字を当てているが、
まるで、初期万葉集の表記を「訳」すかのようだ...この場合、逆なのだが...
この「古義」の言う
「此ノ下に、安比太欲波佐波太奈利努乎[アヒシヨハサハダナリヌヲ]、とよめり」
この歌を調べてみたら、それがまた「大回り」してしまうきっかけになってしまった
このような引用の仕方が、正しくないことは、素人でも解るのだが...
この件は、左頁で書くことにする
[いりなましもの]
この語句は、ひとつずつの「語」を解釈し、そこから語意を理解しなければならない
「中に入る」の四段動詞「いり」は容易だが、「な」「まし」「もの」、
まさに助詞のオンパレードだ
「な」は、完了助動詞「ぬ」の、「まし」は、反実仮想の助動詞とも言われている推量助動詞、
「もの」は、詠嘆の終助詞
| 推量の助動詞「まし」 接続:未然形 |
| ① |
a.「ませば~まし・ましかば~まし」の形で事実に反することを仮に想像し、仮想する
「もし~たなら~ただろうに」 |
b.「未然形+ば」など仮定条件句を受けて、仮定の上に立って仮想する
「~ただろうに」 |
| ② |
単独で用いて、仮定の条件を含んでの仮想
「~たらよかった」 |
| ③ |
「いかに・なに・や」など疑問の意を表す語とともに用いて、決断しかねる意
「~たらよいだろう・~たものだろう」 |
| ④ |
[中世語] 単なる推量の意 「~う・~よう・~だろう」 |
ややこしいのは、「まし」だけだと思う
この語句を、基本通りに解せば、「入ってしまったら良かったなあ」となり、
その気持ちとなるのは、「入れなかったことが残念だ」、ということだろう
[終助詞「もの」]
この終助詞には「逆説的な詠嘆」と、単なる「詠嘆」の意味があるが、
反実仮想「まし」について、「~のになあ・~のだがなあ」の残念がる気持ちの嘆息になる
その語意においては、やはり終助詞である「ものを」と同じだ
この用例に対する言及が「古義」に見られる
| 鹿持雅澄「万葉集古義十四之上」 |
| ○伊利奈麻之母乃[イリナマシモノ]は、入なまし物をなり、物をといふべきを、物[モノ]とのみ云ること、古歌に例多し、既く云り、 |
原文七文字になるのは、「ものを」では字余りのために調整したのだろうか
でも、「いりなましものを」と訓じた方が、字余りでもいいように思えたが、
そこで歌が終れば、終助詞「ものを」だったのかもしれない
|
 |

|
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」(今日の歌には無し)]
【3368】
[本文]「伎倍比等乃 萬太良夫須麻爾 和多佐波太 伊刹奈麻之母乃 伊毛我乎杼許爾」 右二首遠江国歌
「キヘヒトノマタラフスマニワタサハタイリナマシモノイモカヲトコニ」(「【】」は編集) |
| 頭注 |
「類聚古集」本文ノ下ニ小字「遠江」アリ。
「古葉略類聚鈔」主文ヲ訓交リニ書ケリ。下ニ小字「遠江国」アリ。
|
| 〔本文〕 |
| 比等 |
『古葉略類聚鈔』「人」。
|
| 乃萬太良夫須麻爾 |
『古葉略類聚鈔」以上訓ヲ主文トセリ。
『類聚古集』「乃」ヲ「能」トセリ。
|
| 萬 |
『神田本』「万」。
|
| 和 |
『神田本』偏ハモトノヲ削リテ書ケリ。
|
| 佐 |
『温故堂本』左ニ〇符アリ。
『西本願寺本・温故堂本』頭書「伎イ」アリ。
|
| 伊利奈麻之母乃伊毛我乎杼許爾 |
『古葉略類聚鈔』以上訓ヲ主文トセリ。
|
| 刹 |
『類聚古集・西本願寺本・細井本・神田本・温故堂本・大矢本・京都大学本・活字無訓本・活字附訓本「利」。
|
| 乃 |
『温故堂本』ナシ。右ニ書ケリ。本文中「母伊」ノ間ニ〇符アリ。
|
| 杼 |
『神田本・温故堂本』(【不明瞭、「木偏を手偏か】)。
|
| 〔訓〕ナシ |
| ワタサハタ |
『温故堂本』「ハタサハタ」。
『西本願寺本・温故堂本』「佐」ノ左ニ「キ」アリ。 |
| イモカヲトコニ |
『類聚古集』「いもかおとこに」。 |
| 〔諸説〕 |
| 〇和多佐波太、ワタサハタ、「万葉考」「太」ハ「尓」ノ誤。訓「ワタサハニ」。〇伊刹奈麻之母乃、「代匠記初稿本」「刹」ハ「利」ノ誤。 |
|
|
 |
| |
| 「あまのはら」...せかす時を、暮れに染めさず.... |
| 【歌意3369】 |
大空に聳えるような富士の山を見ながら、
この山が夕暮れに染まるとき、それを過ぎてしまったら、
今日は、あの娘には逢えない気がする
私を信じて待っているあの娘、
それを違えた、と思われれば...もう二度と逢ってくれないかもしれない
|
| |
ここに、面白い仮説がある
契沖の「万葉代匠記」が、「しばやま(之婆夜麻)」の解釈で、
| 万葉代匠記精撰本 契沖 元禄三年(1690) |
| 之婆夜麻とは俗に柴刈[カル]山を云ひ或は芝[シバ]のみ生る山を云、柴山は去聲によび芝山は上聲に呼べり、柴刈る山は草木とも云はず皆刈拂ひ、芝山は本より木などの生ひぬを云へば富士の半腹より上つ方には草木もなきを右の二つの内に譬へて云歟、又しばとは繁きを云へば半腹より下つ方のしげきをしげ山と云歟、慈圓、天の原ふじの煙の春の色の霞になびく曙の空、定家卿此歌を取て天の原寓士のしば山しばらくも烟絶せず雪もけなくにと讀たまへり、己能久禮能とは此暮歟、若之婆夜麻はしげ山の意ならば木の晩にて春夏のあはひに相見むと期りしを其期の移りなむとすればおぼつかなく思ふ心歟 |
「しば」を「柴(シバ)」と解せば、
それは山野に生える小さな雑木、またその枝を切って薪にしたり垣根を作ったりするもの
「しば」を「萊草(シバ)」と解せば、(おそらく契沖の言う「芝」だと思う)
荒地や道端などに生える雑草、しばくさ(萊草)となる
契沖が、「代匠記」で述べるのは、
「しばやま」の意味を、「柴」と「芝」の違いで解釈するには、
その見分け方を、「声調(音の高低で意味を区別する)」によって解るとするが、
文字しか残らない「和歌」に、それを求めるのは不可能なことだ
しかし、同じ「しば」にその解釈によって大きく歌意全体が影響するのなら、大切なことだ
しかも「しば」を「繁る」の「しげ山」であれば、中腹より下方を「しげ山」と言うか、と
右頁の「新古今和歌集」の慈円の一首を引用し、それを藤原定家が、
定家卿此歌を取て「天の原寓士のしば山しばらくも烟絶せず雪もけなくに」と讀たまへり
慈円の一首を「本歌」として、と言っている
よく解らなかった
私の拙い解釈では、当面は富士の「しば山」噴煙も絶えず、雪も消えない、と
この意味は、「しば山」を、定家がどんな解釈をしたのか、を教えているのか
慈円は、「しば山」という語は使っていない
しかし、定家がその慈円の一首に想を得て、「しば山」にしている
そこには、春の霞になびく「富士のけぶり」を鑑賞しているさまが窺えそうだ
それを、「富士のしば山」と定家は詠っているのかもしれない
となると、「しげ山」のような、木々の生い茂った樹林帯ではない、中腹より上方になる
契沖が述べるのは、「しばやま」の解釈を、「しげやま」の如く「樹林帯」とすると、
この掲題歌の第三句「このくれの」が掛詞如何に関わらず「木の暗の」で、不自然ではないが
仮に、定家の解釈をそのまま当てはめれば、「木の暗の」を読むのは困難であり
すると、掛詞ではなく「此の暮れ」の解釈が得られる
藤原定家や慈円の一首への解釈が、私が誤釈でなければ、の話だが
やはり自信はあまりない
ただ、契沖の悩む姿こそが、いくら素人であっても、和歌を楽しむための、
私が求めて止まないものだ、とは言える
実際、多くの注釈書では「しば山」については、詳細を書かず
「木の暗の」としたり「此の暮れの」、あるいは双方の掛詞としている
しかし、「しば山」に対する一つの見解がある以上、
それをどう読み取るかもまた、歌意解釈には欠かせない
確かに、「此の暮れの」では、「ふじのしばやま」と、どうやって繋げればいいのだろう
案の定、橘千蔭「万葉集略解」では、こう解釈している
| 万葉集略解 橘千蔭 |
| シバ山は、麓は柴のみ繁ければ言へり。コノクレは、木之暗なり。さしもの富士の麓なれば、道も遠く、柴の小暗き夜道を辿るに、夜更けなば、妹が持つ時の違ひて、逢ひ難くや有らんと、心を遣りて急ぐさまなり、宣長云、上二句は、コノクレの序のみなり。木之暗は此暮に言ひ懸けたるなりと言へり |
歌意はともかく、「しば山」は麓の「柴」の繁みのことを言っている
それで得られる「歌意」に、何も不自然さはない
ただし、千蔭はこの箇所で、本居宣長の説を引用している
「木の暗」は「此の暮」の掛詞としている
これに対して、掛詞と採らないのが「古義」だ
しかし、やはり「しばやま」を千蔭と同じように「柴山」とする
| 万葉集古義 鹿持雅澄 |
| ○不自能之婆夜麻[フジノシバヤマ]は、富士之柴山[フジノシバヤマ]なり、富士の半より下の、小木の生しげりたる處を云、○己能久禮能[コノクレノ]は、木之暗之[コノクレノ]なり、(本居氏の、上ノ二句は、このくれの序のみ、木之暗[コノクレ]を、此暮[コノクレ]にいひかけたるなり、と云るはわろし、木之暗を、此ノ暮にいひかくるやうのことは、古風にあらず、) |
「しばやま」を「柴山」とするのなら、
「此の暮」との掛詞とするのもいいような気がするが、
雅澄は、それを「古風にあらず」と言う
近代に入り、この歌の作者が男だとか女だとか、いろいろと解釈も多いようだ
ただもっともらしく思えるのは、「木の暗」とする注釈書がほとんどで、
掛詞で何とか、約束の時に間に合いそうもない焦燥感を描写している
その前提になるかのように、「しばやま」が「柴山」になっているのが、
私には少々不満が残る
契沖の発想、そして定家の一首、そこに振り返り見るものはないのだろうか
上述したように、「しばやま」を、中腹より上方とすれば、
千蔭が言うような、木々の下闇の小暗き夜道を、女のところへ行けるのだろうか、という
そんな男の歌にはならない
ただし、「此の暮」では、それも可能だ、
何故なら、日が暮れるまでに着きたい、そうでないと、もうあの娘に逢えない気がする
ただ「日の暮れる」ことを懼れている
では、その場合の初二句「あまのはら ふじのしばやま」は、どんな役割になるのだろう
何も、そこを歩くのではない
日が暮れれば、当然西日が富士の山肌に照り返し、猶予のなさを教えてくれる
その「時」という観念の、「視覚的」な対象を、
「ふじのしばやま」は担っているのではないだろうか
そして第四句「ときゆつりなば」の「とき」が、それを言っている
掛詞にしろ、そうでないにしろ、「このくれ」を「木の暗」とするのは、
一般的な「時」の経過には必要のないことだ
掛詞説であれば、まだ理解出来るが
「木の暮」だけの解釈では、時に関係なく「木の下闇」なのだから...
ならば、「此の暮」とすると、「あまのはら ふじのしばやま」が、「時」の象徴になり
それを見ながら、男はひたすら女のもとへ向かう
「木の下闇」などの小道具は必要はない
大空に聳える富士をそばに感じながら、「時」に急かされて、男は女のもとへ向かう
暮れて夜にでもなれば、もうあの娘は、自分のことなど待ってはいないだろう
そうなれば、二度とは逢えない
そんな焦燥感に怯えながら...
|
|
掲載日:2015.04.19
| |
| 東歌相聞 |
| 安麻乃波良 不自能之婆夜麻 己能久礼能 等伎由都利奈波 阿波受可母安良牟 |
| 天の原富士の柴山この暗の時ゆつりなば逢はずかもあらむ |
| あまのはら ふじのしばやま このくれの ときゆつりなば あはずかもあらむ |
| (右五首駿河國歌) |
| 巻第十四 3369 東歌相聞 作者不詳 |
| 【3369】 語義 意味・活用・接続 |
| あまのはら [安麻乃波良] |
| 〔枕詞〕「富士」「ふりさけ見る」などにかかる |
| ふじのしばやま [不自能之婆夜麻] |
| しばやま [柴山] |
山野に自生する雑木の生えている山、雑木の樹林帯 |
| このくれの [己能久礼能] |
| このくれ [木の暗] |
木の下闇の夕暮れ時 |
| ときゆつりなば [等伎由都利奈波] |
| とき [時] |
時刻の「時」や、季節の「時」で、解釈にも影響する |
| ゆつり [移る] |
[自ラ四・連用形] 経過する・移る 連用形に付く |
| な [助動詞・ぬ] |
[完了・未然形] ~てしまう・~てしまった |
連用形に付く |
| ば [接続助詞] |
[順接の仮定条件] ~なら・~だったら |
未然形に付く |
| あはずかもあらむ [阿波受可母安良牟] |
| かも [係助詞] |
[疑問] ~か・~だろうか |
体言、連体形に付く |
| む [助動詞・む] |
[推量・連体形] ~だろう 係り結びの連体形 |
未然形に付く |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
[あまのはら]
「枕詞」としての「あまのはら」が、「ふじ」にかかる「万葉集」での用例は、
この一首しかない
資料などで、よく引用されるのが、山部赤人の次の歌の「題詞」だ
| 万葉集巻第三 雑歌 320 山部赤人 |
| 山部宿祢赤人望不盡山歌一首[并短歌] |
天地之 分時従 神左備手 高貴寸 駿河有 布士能高嶺乎 天原 振放見者 度日之 陰毛隠比
照月乃 光毛不見 白雲母 伊去波伐加利 時自久曽 雪者落家留 語告 言継将徃 不盡能高嶺者今 |
| 天地の 別れし時ゆ 神さびて 高く貴き 駿河なる 富士の高嶺を 天の原 振り放け見れば 渡る日の 影も隠らひ 照る月の 光も見えず 白雲も い行きはばかり
時じくぞ 雪は降りける 語り継ぎ 言ひ継ぎ行かむ 富士の高嶺は |
| あめつちの、わかれしときゆ かむさびて たかくたふとき するがなる ふじのたかねを あまのはら ふりさけみれば わたるひの かげもかくらひ てるつきの ひかりもみえず しらくもも いゆきはばかり ときじくぞ ゆきはふりける かたりつぎ いひつぎゆかむ ふじのたかねは |
厳密に言えば、「ふじ」に掛かるのではなく「ふりさけみれば」に掛かる
しかし、この題詞「望不盡山歌」が、
「あまのはら」と言う大空高く聳え立つ意で、「ふじ」を捉えているのは理解出来る
「ふじ」に掛かる枕詞となると、一首のみの「万葉集」よりも、以降の方によく見かける
| 新古今和歌集巻第一 春歌上 33 前大僧正慈円 |
| 百首歌たてまつりし時 |
| 天の原ふじのけぶりの春の色のかすみになびくあけぼのの空 |
| |
| 拾遺愚草上 藤原定家 |
| 内裏百首 恋二十首 不尽山 |
| あまの原ふじのしば山しばらくもけぶりたえせず雪もけなくに |
| |
| 賀茂翁家集巻第一 哀傷歌 274賀茂真淵 |
六月十四日はこぞ暉昌が身まかりし日なれば、としごろのむつびわすれがたきに、
たよりにつけていひつかはしける |
| 天の原ふじの高嶺の白雪のきえぬる時と聞くぞかなしき |
しかし、私が最初に思い浮かべる「あまのはら」の歌は、やはり「安倍仲麻呂」の一首だ
| 古今和歌集巻第九 羈旅歌 406 |
| もろこしにて月を見てよみける 安倍仲麿 |
| あまの原ふりさけ見ればかすがなるみかさの山にいでし月かも |
この歌は、むかしなかまろをもろこしにものならはしにつかはしたりけるに、
あまたのとしをへてえかへりまうでこざりけるを、このくにより又つかひまか
りいたりけるにたぐひてまうできなむとていでたちけるに、めいしうといふ所
のうみべにてかのくにの人むまのはなむけしけり、よるになりて月のいとおも
しろくさしいでたりけるを見てよめるとなむかたりつたふる |
長年の遣唐留学生として唐に居たが、やっと帰国の船に乗れることになり、
明州の海辺で、当地の人たちが別れの宴を開いてくれたときに、詠ったとされる
結局、この遣唐使船の帰国は、暴風に遭い、難破という形で再び唐に漂着する
そこでまた仲麻呂は唐の官吏として、唐で客死したとされる
奈良県桜井市の安倍文殊院に、仲麻呂の歌碑がある
鹿持雅澄「万葉集古義枕詞解巻之一」によれば、
| あまのはら (ふじのしば山) |
| 下河辺ノ長流燭明抄ニ云、是はことなる子細なし、かの山のきはめて高ければ、其いただきの天に及ぶ心にていへるなり、此ノ集第三に、駿河有 布士能高嶺乎 天原 振放見者云々、都氏富士山ノ記云、富士山者在駿河国、峯如削成、直聳而屬リ天ニ、とかけり、竹取物がたりにも、天に近き山をもとめて、不死の薬をやかせ給はむとて、此ノ山にのぼせて、やかせ給ふ、と云り、 |
とある
富士山の、天にも及ぶ高きを連想させる「あまのはら」としているのが、解りやすい
[しばやま]
「しば」の意からすると、どうしても高峰、霊峰とされる「富士」の「麓の丘陵」を浮かべる
多くの書は、富士山麓の樹林帯としているが、勿論そうであるにしても、
「しば」の意味には、歌意解釈上の大きな受け取り方がある
左頁で取り上げたい
[このくれ]
木が繁ってその下が暗いことで、「此の暮」を掛けた「掛詞」とされる
しかし、「掛詞」とせず解釈する注釈書もある
[ゆつり]
動詞「ゆつる」は、動詞「うつる」と同じ漢字表記をするが、
その意味合いは、微妙に違う
「うつる」は、状態が変化するなど、紅葉が散る、というような意味がある
「ゆつる」は、主に時間が過ぎる、などの経過をいう
|
| |
| |
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」(今日の歌には無し)]
【3369】
[本文]「安麻乃波良 不自能之婆夜麻 巳能久礼能 等伎由都利奈波 阿波受可母安良牟」 (右五首駿河歌)
「アマノハラフシノシハヤマコノクレノトキユツリナハアハスカモアラム」(「【】」は編集) |
| 頭注 |
「類聚古集」本文ノ下ニ小字「駿河」アリ。
「古葉略類聚鈔」主文ヲ訓交リニ書ケリ。下ニ小字「駿河」アリ。
|
| 〔本文〕 |
| 安麻乃波良 不自能之婆夜麻 己能久礼能 |
『古葉略類聚鈔』以上訓ヲ主文トセリ。
|
| 乃 |
『類聚古集』「能」。右ニ朱「乃」アリ。
|
| 婆 |
『神田本』「波」。
|
| 夜 |
『神田本』ナシ。左ニ書ケリ。本文中「波麻」ノ間ニ〇符アリ。
|
| 麻 |
『京都大学本』ナシ。右ニ書ケリ。本文中「夜巳」ノ間ニ〇符アリ。
|
| 都 |
『古葉略類聚鈔』ナシ。
|
| 波 |
『温故堂本』「婆」。
|
| 阿波受可母安良牟 |
『古葉略類聚鈔』以上訓ヲ主文トセリ。
|
| 〔訓〕 |
| トキユツリナハ |
『古葉略類聚鈔』以上七字ナシ。
|
| 〔諸説〕ナシ |
|
|
 |
| |
| 「ふじのねの」...惚れて通えば、千里も一里.... |
| 【歌意3370】 |
富士山の、その果てもなく遠く続く長い山路の先にいる、
いとしい女に逢いたい、と思うのだから、
いくら私たちの間に、立ちち塞がるように聳える富士の嶺であっても、
私には、少しも厄介には思えず、苦しいとも思えず、やって来たよ
|
| |
この歌の基に流れる感傷は、
どんな苦労も、愛しいもののところへ通うのであれば、
それが「千里が一里」などと言うように、何でもないことだ
自分に言い聞かせる歌でもあり、
相手にその「呻吟ぶ」ような労苦を知らせよう、あるいは知って欲しい、とする歌だと思う
この歌の解説に、あまりにも似合うと見られているからなのか、
「都々逸」の一首に次の歌がある
都々逸の歌を「一首」というのか「一句」と言うのか、
それとも、他に呼び方があるのか解らないが...
| 古謡 駿河 |
| 惚れて通えば 千里も一里 逢えずに帰れば また千里(作者不詳) |
しかし、「都々逸」という「七・七・七・五」の音数律を大成したとされるのが、江戸末期
この歌は、確かに「音律数」では、「都々逸」の定型詩になっているが
「古謡駿河」とあるように、本来駿河国に詠われる「古謡」を、
口語の「都々逸」風に、「定型詩」化させたものではないか、とも思える
何故なら、掲題歌の「通釈」とされる歌意解釈に、あまりにもその歌意が合致するから...
「故事ことわざ事典」で、この「惚れて通えば」を引いて見ると、
| 「惚れて通えば千里も一里」 |
恋人に会いに行くためなら、千里もの遠い道のりでも一里にしか感じないほど、苦にならない。自分が好きな人のために、自分が好きですることは、どんな苦労も苦に感じないというたとえ。
俗謡の詞では後に「逢わずに戻ればまた千里」と続けて言い、千里もの道のりを歩いて恋人に会いに来ても、恋人が留守だったならまた千里の道を歩いて帰る、という意味。 |
この「解説」が、そのまま掲題歌の歌意解釈にしてもいいほどに、
その心情は同じものだ、と言える
そこまで考えたら、「駿河国の古謡」と言うのも、
あるいは、掲題の「万葉歌」も、その元は同じものなのかもしれない
一つは、万葉の人によって、「五・七・五・七・七」の形で詠い継がれ、
もう一つは、不定形ながら、その地域の「古歌謡」のように、残されて...
それが、きちんとした形の、「都々逸」風に伝わっていく...
私の、気ままな想像になってしまうが、
その可能性があるとすれば、この掲題歌には、「古謡」の後半の
「逢えずに帰れば、また千里」に相当する「万葉歌一首」もあるのかもしれない
そう思ったら、次の〔3371〕に何となく...
いや、先走らず、今回はこの掲題歌を鑑賞しよう
「富士の嶺の」が、右頁のような「何か」を籠める気配のないことが感じられるが、
ひょっとすると、結句の「けによばずきぬ」に関係しているのかもしれない
この結句についての現代での大方の解釈は、右頁に列挙したが、
私には、その最後に書いたように、「よぶ」という語意にも気に掛かるものを感じている
一般的に「よぶ(呼ぶ)」は、呼びかける、招く、などの意があり、
その意味合いで結句を解釈すると、
「け」が「日」であれば、「日々呼ばれもしないのに、招かれもしないのにやって来た」
となり、それは「どんなに遠く離れていようと、じっと待ってなんかいられるものか」
に通じ、それがどんなに過酷な山路である「富士の山路」であろうと、苦しいとは思わない
「富士の嶺」は、二人を遠く引き離し「遮る」象徴のようにも思える
空に聳えたち、恋人同士の前に立ちはだかる「壁」のように...
そんな意味にはならないだろうか
「け」を「気」や「息」とすると、「呼びかけることもない、大声で何かを言うこともない」
それが前提になり、「気配も立てずに、お前の所へやって来た」
それは、「どんなに過酷な山路でも、お前がそこにいると思えば、何事もないかのように」
そして、「お前に逢うためであったなら、私はどんなことも苦とは思わない」
これもまた、やけに通じてしまう解釈になってしまう
しかも、これらの無謀な解釈をすれば、
先の「都々逸」風の「惚れて通えば千里も一里」に、とてもぴったりだ
通釈だけでこの歌を感じ取ろうとすれば、
「富士の果てしなく長く遠い山路」を舞台とし、
その先にいる「愛しい女に、逢いたいが為」に、「私はこんな苦労もしている」が、
そんなことは苦にもならない、と
その苦労を知らせるために詠っている
しかし、「よぶ」と解釈すれば、「日」や「気・息」どちらであっても、
まず、「逢いに行きたい」という気持ちが先行する
その気持ち故に、「千里も一里」と作者には感じられる
だから、心底「苦労」とは思わず、
「じっとしていられようか」とか「何事もないかのように、平然と山路を歩く」
目の前に聳える富士の嶺のような「鬱陶しいもの」さえも、何でもないことだ、と
それは決して、自分の、そこまでして逢いに行くのだ、という「苦労話」ではなく
あの女のところに行くには、富士の山路を行けばいいのか、
ならば、どんなに遠くて過酷な山路であっても、行くことにしよう、と言ってやってきた
それが、逆に「一途で激しい想い」を潜ませている、と感じることが出来る
諸書の解釈で、どれほど過酷な山路でも、いとしい「妹の所へ」行くのだ、と思えば、
何日も掛かる行程を一日で行く、とか
「日を置かずに」、すぐにでも逢いに行く、
あるいは、過酷な山路でも、息を切らすことなく、呻き立てることもなく行く、など
それらはすべて、「愛しい妹の所へ」行くのであれば、当然の事であり、
むしろ、「遠くて過酷な山路」という認識を捨て、
逢いに行くこと、それ自体に、迎えた「妹」が、「こんな過酷な山路を」と感嘆する
そんな歌であって欲しい、と願望する思いの歌意解釈になってしまった
|
|
 |
| |
|
 |
|
掲載日:2015.04.21
| |
| 東歌相聞 |
| 不盡能祢乃 伊夜等保奈我伎 夜麻治乎毛 伊母我理登倍婆 氣尓餘婆受吉奴 |
| 富士の嶺のいや遠長き山道をも妹がりとへばけによばず来ぬ |
| ふじのねの いやとほながき やまぢをも いもがりとへば けによばずきぬ |
| (右五首駿河國歌) |
| 巻第十四 3370 東歌相聞 作者不詳 |
| 【3370】 語義 意味・活用・接続 |
| ふじのねの [不盡能祢乃] |
| ね [峰・嶺] |
みね、山の頂上 あるいは、山そのものを言う |
| いやとほながき [伊夜等保奈我伎] |
| いや [感動詞] |
(驚いたり、嘆息したりするときなどに発する声) いやあ、いやはや |
| とほながき [遠長し] |
[形容詞シク・連体形] 遠くはるかである・永久である |
| やまぢをも [夜麻治乎毛] |
| をも [複合助詞] |
〔格助詞「を」に係助詞「も」が付いたもの〕
目的・対象を,さらに広くとりたてる意 |
| いもがりとへば [伊母我理登倍婆] |
| がり [許(接尾語)] |
~のもとへ・~のいる所に |
| とへ [問ふ・訪ふ] |
[他ハ四・已然形] 尋ねる・聞く・気遣う・訪問する |
| ば [接続助詞] |
[順接の確定条件] ~ので・~だから |
已然形に付く |
| けによばずきぬ [氣尓餘婆受吉奴] 注記にて、幾つかの語句全体の説を紹介する |
| け [諸説あり] |
[注記] |
| 〔によぶ [呻吟ぶ]〕 |
[自ハ四] あえぐ・うなる・うめく 「によふ」とも言う |
| 〔よぶ [呼ぶ]〕 |
[他バ四] 大声で何かを言う・呼びかける・招く・招待する |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
[(富士の)ね(峰)]
「ね(峰)」、山の峰と聞くと、私はごく自然に、その山頂を思い浮かべる
勿論、それが現代の感覚であることは承知している
この歌のように「山頂」では、「富士山の高き嶺」ほど「険しく」とするのだろうか
そうなると、この歌の主体は、富士裾の「山道」が、確かに生きてくる
「ふじのね」という語を使う歌は結構あるが、比較的多く目にするのが、
「ふじのね」で、「ふじのけぶり」、噴煙のことを導いている
そう言えば、山の名に「嶺(ね)」を付ける歌に「筑波嶺(つくばね)」があるが、
これは、それ自体が「山の名前」になる
この掲題歌のように「ふじのね」の「の」が入れば、
何だか「嶺」を強調するかのようにも思えてしまうが、では「ふじね」と言う語があるのか、
と、言うと...なかった
やはり、単純に「筑波嶺」のように「富士の嶺」で、固有名詞とした方がいいのかな
でも、万葉の当時から「霊峰」とされているのだから、
何かの「象徴」めいた用い方もあるはずだ
例えば、上述のように、「ふじのね(富士の嶺)」で、その山頂から立ち昇る噴煙のような...
「人丸集」に、東海道十五ヶ国「するが」に、次のような歌がある
| 人丸集 東海道十五ヶ国 |
| するが |
| 二四七 ふじのねの たえぬおもひを するからに ときはにもゆる 身とぞ成りぬる |
この歌の「ふじのね」は、勿論「富士山」そのものだが、
その名を出して、「たえぬおもひを」というのは、
現在は休火山だが、当時は活動していたとされる富士山が、
「噴煙」を常に山頂から立ち昇らせている光景が浮ぶ
その絶えることなく吹き上がる「噴煙」に、作者の「絶えぬ想い」を重ね、
なおも「ときは」、この場合は「名詞」ではなく、形容動詞「ときは」の連用形だと思うが、
常緑樹の「葉」のように、いつまでも変らぬ情熱的に燃える身に、なってしまった
私は、このような「ふじのね」が、単に山の名前という固有名詞だけではなく
特に「富士山」のような当時でも、おそらく際立った特別な存在だった山に、
「ふじのね」で、「その山頂から立ち昇る噴煙」のような意味も備わっているような気がする
| 古今和歌集 巻第十九 雑体 |
| きのめのと |
| 一〇二八 ふじのねのならぬおもひにもえばもえ神だにけたぬむなしけぶりを |
| 新古今和歌集 巻第十二 恋歌二 |
| 家隆朝臣 |
| 一一三二 ふじのねの煙も猶ぞたちのぼるうへなきものはおもひなりけり |
[がり]
人を表す体言、あるいは体言に相当する語について用いる
〔参考〕
「行く・通ふ・遣(や)る」などの移動を表す動詞とともに用いられる
上代には、体言に付き接尾語として用いられたが、
後に、格助詞「の」を介し、形式名詞のように用いられた
[とへば]
「『と言へば』の略」と「と」を格助詞とする、それが一般的な解釈になる
その場合は、「~と、言うのだから・~と思うので」のような解釈になり
前の語「いもがり」を「引用」する用法になる
上記「語意解説」の「問ふ・訪ふ」と、その意を解すれば似たようなものだが、
「いもがり」は、あくまで「いものいるところに」という目的になる語句であり、
そこに「訪ねる」という表現を、「とへば」に籠めると思う
もっとも、引用の格助詞「と」で、
「いもがり」自体が、作者を「訪ねさせる魅力的な」表現とすれば、
それも歌意解釈には支障がないと思う
[け]
この歌では、「け」の意の一つ「日(け)」、上代語「日(ひ)」の複数形で、
二日以上の期間を指し、「日々・日数」の意味がある一方、
「気(け)」として、「気持ち・気分・様子・気配」などの意もある
この歌の「け」は、原文の万葉仮名「気」なので、
だからと言って、確実に「気」(借音だから)だとは言い切れないものがある
その一例が、次の歌だ
| 巻第二 相聞 八五 磐姫皇后 |
| 相聞 難波高津宮御宇天皇代 [大鷦鷯天皇 謚曰仁徳天皇] 磐姫皇后思天皇御作(歌四首) |
| 君之行 氣長成奴 山多都祢 迎加将行 待尓可将待 |
| 君が行き日長くなりぬ山尋ね迎へか行かむ待ちにか待たむ |
| きみがゆき けながくなりぬ やまたづね むかへかゆかむ まちにかまたむ |
勿論、これが正しい「訓釈」であるとすれば、のことだが...
この「け」の解釈には、
どうしても結句「けによはずきぬ」全体の解釈に及ばなければならない
その他にも「け」という「音」の「語」(名詞)には、幾つかある
「卦」陰陽道で、易の算木に現れる象
それが天地間いっさいの変化を表したものとして、吉凶を占う、八卦の基本
「怪」不思議なこと、怪しいこと、たたり、もののけ
「故」ため、せい、ゆえ
「食」食物、飯、または食事
「笥」容器、特に飯を盛るのに用いる器
「褻」ふだん、日常
「褻」についての〔参考〕
| 「褻(け)」と「晴れ」参考 古語辞典より |
| 私的で日常的な事柄を「褻」、公的で非日常的な事柄を「晴れ」と区別して、対立的に捉えた。これらのことばは歌論用語としても使われ、和歌が詠まれる場によって、日常(褻の歌)と、非日常(晴れの歌)に分けて考えようとした。現代では「晴れ」が「晴れ着」「晴れ舞台」などに残る。柳田国男に始まる民俗学では、この言葉を学術用語として用い、衣食住などの生活全般を説明しようとした。 |
他、「接頭語」や形容動詞「異」などの解釈もある
接頭語「気(け)」は、動詞・形容詞・形容動詞について、
「~のようすである・~の感じだ・何となく~だ」の意になる
その用例として、
「気恐ろし」「気劣る」「気すさまじ」「気高し」、などがある
[けによばずきぬ]
「万葉集」注釈諸書でも、この訓釈には、幾つかの解釈があり、定説はない
「け」の諸説については、注記前項「け」を参照
「日(け)に・及(よ)ばず」とする書
ただし、その訓釈でも、二通りの解釈が可能になる
一つは、「その日の内に」であり、もう一つは「日もあけずに、すぐにまた」の意だ
〔その日の内に〕
鴻巣盛広 「万葉集全釈」 一日かからずして
武田祐吉「万葉集全註釈」 幾日もかからないで
新潮社「日本古典集成」 足どり軽く、その日のうちに
講談社文庫「万葉集全訳注原文付」 一日もかからずに
〔日もあけずに、すぐにまた〕
岩波書店「日本古典文学体系」 日数もおかずに
「け・呻吟(によ)ばず」とする書
この場合の「け」は、接頭語になる
橘千蔭「万葉集略解」宣長説 け長きのけにて、來經(キヘ)也。さればこは時刻を移さず
土屋文明「万葉集私注」 呻(うめ)き立てもせずに
有斐閣「萬葉集全注」 少しも苦しいとは思わず
「息(け)・呻吟ばず」とする書
賀茂真淵「万葉考」息つきうめく物なるを、妹がもとへ行と思へば、やすく來りつといへり
鹿持雅澄「万葉集古義」常は息づき呻吟(サマヨヒ)て...(中略)...、息づき呻吟ハずして
岩波書店「新日本古典文学大系」 喘ぐこともなく
小学館「新編日本古典文学全集」 造作なく
窪田空穂 「万葉集評釈」 呻き声も立てずに
佐佐木信綱 「評釈万葉集」 息づきうめくこともなく
変った解釈では、契沖「万葉代匠記初稿本」に、
ケを霧とし、ヨバズを迷はずと解し、「霧にも迷はずして來ぬるとなり」
① 名詞「日(け)」・格助詞「に」・動詞「及(よぶ・よふ)」
② 接頭語「け」・動詞「呻吟(によぶ・によふ)」
そして、私がはっきり出来ないのが、「息」を「け」と音することだ
③ 名詞「息(け)」・「呻吟(によぶ・によふ)」
この「③」の「息」は、「気」に通ずるものだとは、想像できる
小学館の注記にも、「ケ」は「息」のことと書いてあるが、
その音が、何故「息」なのかは、書かれていない
拙い想像を用いれば、「息遣い」が、「気配を漂わせる」に通じることからなのかもしれない
以上の説が、ほとんどの注釈書でいずれかが扱われているが、
「①」の「及ぶ」について、「及ぶ」の意である「およぶ」に、私は引っかかっている
原文「餘婆受」だから「よばず」と訓じるのだろうが、
「よぶ」が、どうして「及ぶ」の意になるのだろう
単純に「よぶ」という四段動詞では駄目なのだろうか...
|
| |
| |
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」(今日の歌には無し)]
【3370】
[本文]「不盡能禰乃 伊夜等保奈我伎 夜麻治乎毛 伊母我理登倍婆 氣爾餘婆受吉奴」 (右五首駿河歌)
「フシノ子ノイヤトホナカキヤマチヲモイモカリトヘハケニヨハスキヌ」(「【】」は編集) |
| 頭注 |
「類聚古集」本文ノ下ニ小字「駿河」アリ。
「古葉略類聚鈔」主文ヲ訓交リニ書ケリ。下ニ小字「駿河国本ノマヽ」アリ。
|
| 〔本文〕 |
| 不盡能祢乃伊夜 |
『古葉略類聚鈔』以上訓ヲ主文トセリ。
|
| 奈我伎 夜麻治乎毛 伊母我理登倍婆 氣爾餘 婆受吉奴 |
『古葉略類聚鈔』以上訓ヲ主文トセリ。
|
| 婆 |
『類聚古集・神田本』「波」。
|
| 〔訓〕 |
| フシノ子ノ |
『古葉略類聚鈔』「フシノ子ヤ」。「ヤ」ヲ消セリ。ソノ右ニ「ノ」アリ。
|
| ヤマチヲモ |
『古葉略類聚鈔』「チ」ナシ。
|
| イモカリトヘハケニヨハスキヌ |
『類聚古集』「いもかりとうへはけによはふけぬ」。
|
| 〔諸説〕ナシ |
|
|
 |
| 【歌意3371】 |
霞がかかっていることを承知で、それでもその富士の山路にやって来たなら、
その霞のせいで、どちらに向かって歩けばいいのか、解るだろうか
きっと私を待っている娘は、私がどこから来るのか、と待ちわび嘆き悲しむことだろう
そのまま、逢えずにいたなら...
|
| |
第三句の「わがきなば」で、この歌の作者の位置を推し量る
カ変動詞「来(く)」には、現代的には「来る」の用法だが、
古語辞典では、「行く・通う」との語意もある
そして、ここでの解釈は、その「行ってしまったなら」とするのが殆どだ
私も、「駿河古謡」を知らなかったら、同じように解釈していただろう
遠望する富士の霞、娘と別れて、あの霞の中の山路を行けば、
娘は、自分を霞の中に見失って、見るべき方向も定まらず嘆き悲しむだろう、と
惚れて通えば、千里も一里
逢えずに帰れば、また千里
前半の「惚れて通えば...」は、前歌〔3370〕そのものでないか、と思ったものだ
そして、「駿河古謡」と言うからには、
少なからず後半の「逢えずに帰れば...」の意を汲んだ「万葉歌」もまた、
この「東歌駿河国」にありそうな気がしていた
そんな先入観で、この歌に接してみると...
霞がかかっている「富士のやまび」、作者はその真っ只中に居る自分を想像している
定釈となっている女と別れて、霞のかかる富士の山路に向かうのではなく
「わが来(き)なば」、「女に逢うためにやって来たなら」とすれば、どうなのだろう
その視界も塞ぐ霞のせいで...この「かすみゐるふじ」
富士山のような独立峰の、その気象条件を私は知らないが、
江戸時代の学者で、橘千蔭「万葉集略解」に、
| 万葉集略解 橘千蔭〔寛政十二年(1800)成〕 |
| 霞居るなり。山備は山方なり。イヅチは何道なり。男は富士の麓へ別れて來居る事有る時、然か別るれば、富士は雲霞の立つ事常なれば、方も知られずして、吾が方を見んにも、何方を向きてか歎かんとなり。古へ雲、霧、霞を相通はして言へば、霞と言ふも、時は指すべからず。 |
歌意解釈は通釈になるが、江戸時代の人の、富士に対する認識を垣間見ることができる
何も科学的な根拠はないけど、「富士は雲霞の立つ事常なれば」と断定しているのは、
富士の山路を行く困難さをも、それが要因の一つなのかもしれない
前歌〔3370〕で、「ふじのねの」と詠われ、その山路の過酷さも厭わない、と
そこに、「かすみゐる」とは詠われはしないが、
「富士山」そのものに、「ふじのね」とか「かすみゐる」の特別な「何か」を籠めて...
仮に、富士山には常に「霞がかる」ような、
そしてその延々と続く「山路」を行交うことが、
まるで吹雪の収まることのない、冬の山のように、
道標も整備されていず、行く方向さえも迷わせる「山路」であれば...
第三句「わがきなば」を上述の解釈に基づけば、
娘に逢うために、その富士の「霞」の中に来てしまったのなら、
無事にその「山路」を歩き通せるのだろうか、と
そして、娘は男をその山路に見出すことなく、「いづちむきてか」もまた、
四段動詞「向く」が、定釈に言うどちらを「向いて」ではなく、
「その方向へ向かう」や「その方へ進む」とする本来の語意の方が相応しく思えてくる
[逢えずに帰れば、また千里]
この霞がかった富士の山路で、どの方向へ向かって行けばいいのか...
きっと娘は、霞の切れるところにいて、作者が現れるのを待っていることだろう
しかし、娘にしても同じことだ
この霞に覆われた「山路」の中で、男を迎えにいくことなど出来ない
男は来ない、そして娘も動けない
そのもどかしさに、嘆き悲み泣いている女のことを想っての歌のような気もする
このまま、行き違い、あるいは娘のところへ辿り着くことも出来ず
傷心のまま帰るとするのは、「逢えずに帰れば、また千里」の「古謡」の実感が湧いてくる
仮定条件法を用いているので、実際には男はまだ娘のところへは向かっていない
しかし、もし「かすみゐる 富士のやまび」に遭遇でもしてしまったら...
その不安が、男の決断を迷わせる
とすれば、この詠歌の動機は、何だろう...
いや、何としてでも娘のところへ...
男に「迷い」などない、たとえ「かすみゐる 富士のやまび」であっても、と言うことだろう
|
|
掲載日:2015.04.26
| |
| 東歌相聞 |
| 可須美為流 布時能夜麻備尓 和我伎奈婆 伊豆知武吉弖加 伊毛我奈氣可牟 |
| 霞居る富士の山びに我が来なばいづち向きてか妹が嘆かむ |
| かすみゐる ふじのやまびに わがきなば いづちむきてか いもがなげかむ |
| (右五首駿河國歌) |
| 巻第十四 3371 東歌相聞 作者不詳 |
| 【3371】 語義 意味・活用・接続 |
| かすみゐる [可須美為流] 霞がかかっている |
| ゐる [居る] |
[自ワ上一・連体形] (波風が)おさまる・(氷・草などが)生じる |
| ふじのやまびに [布時能夜麻備尓] |
| やまび [山傍] |
山のめぐり、山のまわり |
| わがきなば [和我伎奈婆] |
| き [来] |
[自カ変・連用形] 来る・行く・通う |
| な [助動詞・ぬ] |
[完了・未然形] ~た・~てしまう・~てしまった |
連用形に付く |
| ば [接続助詞] |
[順接の仮定条件] ~(する)なら・~だったら |
未然形に付く |
| いづちむきてか [伊豆知武吉弖加] |
| いづち [何方・何処] |
〔「ち」は場所を表す接尾語〕どの方角・どちら(方向についての不定称) |
| むき [向く] |
[自カ四・連用形] その方向に向かう・対する・その方に進む・傾く |
| て [接続助詞] |
[単純接続] ~て・そして |
連用形に付く |
| か [係助詞] |
[疑問] ~か・~だろうか 〔接続〕体言・活用語・副詞・接続助詞など |
| いもがなげかむ [伊毛我奈氣可牟] |
| なげか [嘆く・歎く] |
[自カ四・未然形] 嘆息する・悲しんで泣く・祈る |
| む [助動詞・む] |
[推量・連体形] ~だろう 前句「か」の「結び」 |
未然形に付く |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【注記】 |
[霞居る]
この語句の意味合いとしては、「霞がかかっている」、となる
枕詞「かすみたつ」と言えば、あたかも「霞」が、沸き起こるかのような描写になるが、
「かすみゐる」の「ゐる」には、「とどまる・(波風)がおさまる」の語意があり、
それによって、たんに「霞が発生する」ような情況ではなく、
その「霞」が、「富士」を覆い、そこに「居る」を思わせる語には違いない
「かすみたつ」という語は、「万葉集」中に十六首あるが、
掲題歌の他は、「かすみゐ(可須美為)」という、一首しかない
| 万葉集巻第十四 東歌相聞 3406 |
| 筑波祢乃 祢呂尓可須美為 須宜可提尓 伊伎豆久伎美乎 為祢弖夜良佐祢 |
| 筑波嶺の嶺ろに霞居過ぎかてに息づく君を率寝て遣らさね |
| つくはねの ねろにかすみゐ すぎかてに いきづくきみを ゐねてやらさね |
| (右十首常陸國歌) |
これは、「霞がかかっている」実景と言うよりも、山の嶺に纏わりつく「霞のように」と、
確かに上二句で、「すぎかてに」を導く序詞の用法だ
[いづちむきてか]
この不定の方向を示す代名詞は、「万葉集中」に三例あり、
その内の二首が「東歌」に詠われている
そして、「東歌」にはもう一首、「いづち」の訛ったもの、と言われる「いづし」がある
| 万葉集巻第十四 東歌相聞 3493 |
| 宇恵太氣能 毛登左倍登与美 伊デ弖伊奈婆 伊豆思牟伎弖可 伊毛我奈氣可牟 |
| 植ゑ竹の本さへ響み出でて去なばいづし向きてか妹が嘆かむ |
| うゑだけの もとさへとよみ いでていなば いづしむきてか いもがなげかむ |
掲題歌の「いづちむきてか」と、この訛りと言われる「いづしむきてか」
その次の結句も同じ「いもがなげかむ」なので、この語句は、東国のある地域で、
慣用句的に使われる「別れのとき」の気持ちを表現しているかもしれない
とは言っても、「いづち(し)むきてか いもがなげかむ」は、
この二首しか詠われていないので、「慣用句的」と言うのも...
ただ、同じ「東歌」での表現と言うのが、気になるところだ
|
| |
 |
| |
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」(今日の歌には無し)]
【3371】
[本文]「可須美為流 布時能夜麻備爾 和我伎奈婆 伊豆知武吉氐加 伊毛我奈氣可牟」 (右五首駿河歌)
「カスミ井ルフシノヤマヘニワカキナハイツチムキテカイモカナケカム」(「【】」は編集) |
| 頭注 |
「類聚古集」本文ノ下ニ小字「同上」アリ。「駿河」ニ同シ。
「和歌童蒙抄」第八「ミサコ井ルフシノヤマヘニワカキナハイツムキテカキミカナケカム 万葉十四ニアリ」
|
| 〔本文〕 |
| 婆 |
『類聚古集・京都大学本』「波」。
|
| 〔訓〕 |
| イツチムキテカ |
『類聚古集』「いつちむきてか」。
|
| 〔諸説〕 |
フシノヤマヘニ[代匠記初稿本]「フシノヤマヒニ」。補「フシノヤマヘニ」ヲ可トス。
|
|
|
 |
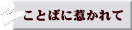  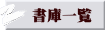  |