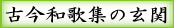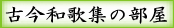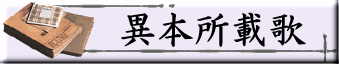
|
古今和歌集のテキストとして、一般的に広く採用されているのは、定家の貞応二年書写本だが、他にも数々の書写本があり、その中には貞応二年書写本に掲載されていない和歌もある。このページでは、それらを取り上げてみたい。 「歌番号」は、「古今和歌集1111首」からの連番としているが、異本の中での「位置」は、(B)を番号に付記することによって、その歌番号の次に置かれていることをしめす。 歌意は、「日本古典文学全集」(小学館)によるものだが、少しずつでも時間を作って自分の感じたままの想いを追記していこうかと思っている。 なお青字は、このページで掲載した歌の諸本をしめす。 |
| 歌番号 | 位置 | 和 歌 | 掲 載 諸 本 |
| 1112 | 仮名序 | 安積山かげさへ見ゆる山の井の浅くは人を思ふものかわ | 嘉禄本(底本) |
|
安積山の美しい姿が、澄んだ清水に映っている。清水は浅いと言うが、私の心がそのように浅いと言うのでしょうか。 この歌は伊達家旧蔵の定家自筆本の「仮名序」に、藤原為家(?)によって挿入され、その後は嘉禄本系統の定家本のみに見られる。「万葉集-3829」に「浅き心を我が思はなくに」とある。その題詞と「大和物語-155段」から、かつて采女であった女性が、葛城王に対して詠んだ歌と伝えられている。嘉禄本は、貞応二年本の底本で異本には当たらないが、その貞応二年本に掲載されていなので、作者を記さず、ここに掲載する。 |
|||
| 1113 | 20B |
題しらず 読人しらず 明日よりは若菜摘まむと片岡のあしたの原は今日ややくらむ |
道家本、亀山切、御家切、基俊本、昭和切 |
|
題知らず 読人知らず 片岡のあしたの原で野焼きの煙が上がっている。明日から若菜摘みでもしようと気が急いているのだろう。 「拾遺集-18」では、柿本人麻呂作歌とある。 |
|||
| 1114 | 80B |
桜の花の水に散るを見て つらゆき ゆくみづに風の吹きいるる桜花消えず流るる雪かとぞ見る |
元永本、筋切、清輔本、亀山切、 伝藤原為家筆雅俗山荘本 |
|
桜の花びらが、流れに散るのを見て 紀貫之 風が水の流れに桜の花を散らしている。雪が消えもしないで流れていくさまに似ている。 |
|||
| 1115 | 82B |
雲林院にまかりて桜の散りけるによめる つらゆき 雪と見て濡れもやすると桜花散るに袂をかづきつるかな |
清輔本、亀山切、 伝藤原為家筆雅俗山荘本 |
|
雲林院に参って桜が散っているのを見て詠んだ歌 紀貫之 まるで雪のように舞い散る桜を見て、雪かと見間違える。だから雪なら濡れるだろう、と思わず袂をかぶってしまった。 |
|||
| 1116 | 103B |
寛平御時后の宮の歌合の歌 つらゆき 月影も花もひとつに見ゆる夜は大空をさへ折らむとぞする |
元永本、筋切、伝藤原為相筆静嘉堂本、 基俊本、寸松庵色紙 |
|
寛平御時后宮歌合の歌 紀貫之 今夜は月の光も満開の桜も白一色に見渡される夜だから、手を伸ばして花の枝を折っているうちに、うっかり空までも折りそうになる。 この歌は題詞にいう「寛平御時后宮歌合」には見当たらない。「古今和歌六帖」には貫之の歌として掲げられる。 |
|||
| 1117 | 236B |
朱雀院の女郎花合によみて奉りける 読人しらず 女郎花なき名や立ちし白露の濡衣をのみ着てわたるらむ |
元永本、関戸本 |
|
朱雀院女郎花合に詠んで奉った歌 読人知らず かわいそうなおみなえしは、浮いた評判を立てられたのだろう、野原で一面に白露に濡れているのが、その濡れ衣というわけなのだろう。 この歌は元永本などで「朱雀院女郎花合」(「亭子院女郎花合」に同じ)の歌とするが、現存の同女郎花合にはない。 |
|||
| 1118 | 253B |
題しらず 読人しらず わが門の早稲田の稲も刈らなくにまだき移ろふ神奈備の森 |
元永本、筋切、高野切、伝藤原為相筆静嘉堂本 基俊本、善海所伝本、 |
|
題知らず 読人知らず 我が家の前の、早稲を作る田では稲刈りもまだ始らないのに、こんなに早くから神奈備の森では木々が色づき始めた。 |
|||
| 1119 | 408B |
題しらず 読人しらず 息長鳥猪名野を行けば有馬山夕霧たちぬ明けぬこの夜は |
元永本、筋切、唐紙巻子本古今集 |
|
題知らず 読人知らず 早暁に宿を出て広い猪名野をここまで歩いてきたら、向こうに見える有馬山には霧が立ちこめている。夜もしらじらと明けそめた。 |
|||
| 1120 | 532B |
題しらず 読人しらず 落ち激つ川瀬に浮かぶうたかたの思はざらめや恋しきものを |
元永本、関戸本、清輔本、志香須賀本 |
|
題知らず 読人知らず 流れ落ちてわきかえる川の流れに浮かぶ水の泡は、はかなく消えていく。私のあの人に対する思いもはかないものだろうが、どうして思わないでいられるだろうか。本当に恋しいのだもの。 |
|||
| 1121 | 739B |
題しらず 読人しらず 真鶴の葦毛の駒や汝がぬしのわが前行かば歩みとどまれ |
清輔本、志香須賀本 |
|
題知らず 読人知らず いつもあの人を乗せてきてくれる葦毛の馬よ。お前さんの主人が私の家の前を通るときには、きっと立ち止まっておくれ。あの人が素通りしないように。 |
|||
| 1122 | 751B |
題しらず 読人しらず 須磨の海人の塩焼衣なれぬればうとくのみこそ思ふべらなれ |
元永本、清輔本 |
|
題知らず 読人知らず 須磨の漁師の塩焼きの着物は、着ならされて古びているという。私はあの人に馴れすぎたせいか、あの人は私がいやになったようだ。 |
|||
| 1123 | 758B |
題しらず 読人しらず 言出しは誰ならなくに小山田の苗代水の中よどみする |
元永本、清輔本、基俊本 |
|
題知らず 読人知らず 最初に申し出たのは誰でもない、あなたですよ。それなのに山田の苗代水が途中で止められて淀むように、今になって足踏みをなさるとは。 この歌は「万葉集-779」(言出しは誰が言なるか小山田の苗代水の中淀にして)の類歌。 |
|||
| 1124 | 761B |
衣通姫の帝にたてまつる歌 とこしへに君もあへむやいそなとり沖の玉藻も寄るときどきに |
元永本、清輔本 |
|
衣通姫が允恭天皇に差し上げた歌 いつまでもあなたさまのお気持ちが変わらないことでしょうか。沖を流れている海の藻でも岸に寄ってくるときがあるのに、あなたさまが私に寄っていらっしゃらないはずはありません。 この歌は「日本書紀」巻第十三にある歌(とこしへに君もあへやもいさなとり海の浜藻の寄るときときを)の類歌。 |
|||
| 1125 | 762B |
題しらず 読人しらず 年経れば心やかはる秋の夜の長きも知らず寝しはなにとき |
清輔本、基俊本、志香須賀本 |
|
題知らず 読人知らず 年が経ったのであなたの心が変わったのでしょうか。長いといわれる秋の夜の長いことにも気がつかずに、二人が共に寝たのはいつだったのかしら。 |
|||
| 1126 | 845B |
諒闇の年、冷泉院の桜を見てよめる 尚侍広井女王 心なき草木といへどあはれなり今年は咲かずともにかれなむ |
志香須賀本 |
|
天皇の喪に服している年に、冷泉院に植えてある桜を見て詠んだ歌 広井女王 この桜は人情を解さない草木ではあるが、なんとなく悲しそうである。今年はたぶん咲かないで枯れてしまうのだろう。私が帝の喪が過ぎてからこの御所を離れるのと運命をともにして。 |
|||
| 1127 | 870B |
兵衛府生より左近将監にまかりわたりて、舎人どもに酒賜びけるついでによめる ただみね 柏木の森のわたりをうち過ぎて三笠の山にわれは来にけり |
元永本、志香須賀本、曼殊院本古今集 |
|
兵衛府生から左近将監に栄進して、近衛の舍人たちに帝のお酒を下賜された時に詠んだ歌 壬生忠岑 兵衛府でのお勤めをすませました私は、このたび皆さまのおられる近衛府にお勤めすることになりましたが大変喜んでおります。 |
|||
| 1129 | 932B |
屏風の絵をよみあはせて書きける 読人しらず 秋来れば萩の古枝も花咲きぬわが身のみこそかくて過ぎぬれ |
基俊本 |
|
屏風の絵に合わせて我が心境を詠んだ歌 読人知らず 秋が来たので萩の古い枝にも花が咲いている。しかし、私の身分だけは、不幸にして悲しくもこのままで過ぎてしまいそうである。 |
|||
| 1130 | 954B |
おなじ文字なき歌 読人しらず 沖つ波うち寄する藻にいほりして行方さだめぬわれからぞこは |
元永本、志香須賀本 |
|
同じ文字を二度使わない歌 読人知らず 沖の波が打ち寄せる海草に付着して、行方定めず流れるのが「われから」である。どこにでも仮の家を結び、我から求めて行方定めぬ生活をするのがこの私である。 この歌は、原本での位置により、出家者の作と思われる。 |
|||
| 1131 | 945B |
雲林院にてよめる 惟喬親王 さわぎなき雲の林にいりぬればいとど憂き世の厭はるるかな |
志香須賀本 |
|
雲林院で詠んだ歌 惟喬親王 雲の中のようにもめごと一つない雲林院にはいってしまうと、苦しい世の中が世間で暮らしている時よりもいっそういやになってくることよ。 |
|||
| 1132 | 1010B |
題しらず みつね 真澄鏡そこなる影にむかひゐて 見る時にこそ知らぬ翁に会ふ心地すれ |
元永本、志香須賀本 |
|
題知らず 凡河内躬恒 きれいに澄んだ鏡の中のわが姿にじっと向かい合って座って見ていると、それがかつての私だったとはとうてい思われず、まるで見も知らぬ老人に会っているような心地がする。 この歌は藤原公任の「新撰髄脳」などで旋頭歌の例として上げ、「拾遺集-565」では読人知らずとする。 |
|||
| 1133 | 1047B |
題しらず 読人しらず 逢はなくに夕占を問へば幣に散るわが衣手はつけもあへなくに |
志香須賀本 |
|
題知らず 読人知らず 今夜は逢えないと思うものの、とにかく占ってみようと夕方の辻に立ってみた。そして袖をさんざん切って幣にして散らしたので、袖には継ぎの当てようがなくなった。 この歌は「万葉集-2632」(逢はなくに夕占を問ふと幣に置くに我が衣手はまたそ継ぐべき)の類歌。 |
|||
| 1134 | 1060B |
題しらず 読人しらず 心こそ心をはかる心なれ心のあたは心なりけり |
志香須賀本 |
|
題知らず 読人知らず ちょっとしたところに現れる人の心遣いというものこそ、その本心を推し量る要点となるものでる。人の心をそこなうものは、その人自身がもっている心の弱さであるのだ。 |
|||
| 1135 | 1068B |
人の牛を使ひけるが死にければ、 その牛のぬしの許によみて遣はしける 源宗于娘 わが乗りし事をうしとや思ひけむ草葉にかかる露の命を |
元永本、筋切、志香須賀本 |
|
よその人の牛を借りて使ったところがそれが死んでしまったので、牛の持ち主に詠んで贈った歌 源宗于娘 私が車を引かせましたことを憂しと思って死んだのでしょうか。草葉にかかった露のように、草ばかりを食べて死んだはかない動物の命でございました。 この歌は「後撰集-1130」、「大和物語-百九段」などにある。「後撰集」の作者表記は「閑院のご」となっている。 |
|||
| 1136 | 1068C |
題しらず 読人しらず いかにして恋を隠さむ紅の八入の衣捲り手にして |
元永本、志香須賀本、基俊本 |
|
題知らず 読人知らず どのようにしてこの私の恋を隠そうかしら。そうだ、涙で何度も染まって真っ赤になった袖を捲り上げて、人に見られないようにすればいい。 |
|||
| 1137 | 1068D |
題しらず みつね 照る月を弓張りとしもいふことは山の端さしていればなりけり |
元永本、志香須賀本、基俊本 |
|
題知らず 凡河内躬恒 空に輝くあの月を、なぜ弓張りというか、とのお尋ねにお答えします。それは今、ご覧のとおり、山の端を目掛けて誰かが射るからなのでございます。 この歌は「大和物語-百三十二段」などによれば、醍醐天皇に献じられたものである。 |
|||
| 1138 | 1086B | 美濃山に繁の生ひたる玉柏豊の明かりにあふがうれしさ | 志香須賀本、基俊本、伝藤原為家筆雅俗山荘本 |
|
美濃国の山にびっしりと生い茂っていた美しい柏の葉が、はるばると都に上がってきて、帝のご宴会のお役に立っているとは、われわれ美濃の者どもにとってなんと嬉しいことであろう。 「催馬楽」に類歌(美濃山に繁に生ひたる玉柏豊明に会ふが楽しや)がある。仁明天皇の大嘗会の風俗歌とする説もあるが、むしろ陽成天皇の時の悠紀(第一に斎忌を捧げる国郡)である美濃から奉ったものであろう(大嘗会の風俗については、巻第二十が参考になる)。「古今六帖」巻第二で、この歌を大友黒主の作とするのは疑わしい。なお、この歌以下三首は巻第二十所載の歌だから、作者名を付さない。 |
|||
| 1139 | 1089B | 陸奥国やいてはいくつよまねども我こそ知れれ四十あまりは | 基俊本 |
|
陸奥には「やいて」がいくつあるか、一つ二つと数えてみないでも、私はちゃんと知っている。四十いくつかあるのだよ。 |
|||
| 1140 | 1100B |
寛平御時、八幡の宮にまゐりて奉る歌 祈りくる八幡の宮の岩清水よろづ世までにつかへまつらむ |
志香須賀本、基俊本 |
|
宇多天皇の御代に、岩清水八幡宮に勅使が参拝して奉納したお歌 帝の御代の繁栄をお祈りして八幡宮の神域から湧き出る岩清水は、万年ののちまでも涸れつきることなく、君にお仕えすることであろう。 |
|||