| 【歌意3378】 |
相模嶺の山々が見えなくなり、これほど遠くにやってきて
次第に薄れかけて来る妻のことが想われ、故郷を思わせる「山々」もここまでなのか、と
妻の名を呼んでみれば、泣けて泣けて仕方がない |
| 【或本歌 歌意3379】 |
あなたの故郷の武蔵嶺の山々が、あなたを見えなくさせてしまった、
私のことを次第に忘れて行くだろうあなたのことを想うと、
ついその名を口に出しては、声をあげて泣き崩れる私なのです |
| |
この二首、二年前の2013年3月15日〔書庫-4〕で採り上げている
当時のこの記事を読み直してみると、いかにも上辺だけの理解だったかを、知ることになる
この二首にしても、無条件で「相聞歌」として受け入れ、
では何故、というところまで踏み込んでいない
そう、「では何故」本歌があって、「或本歌」なのか、と
この頃は、まだ「古注釈書」の類には慣れていなかった
だから、一通りの「注釈書」に目を通して、大まかな「歌意」を理解したつもりになり、
そこから、不遜にも自分の「万葉集」への考え方を書き綴っている
今読み返して、ひどく気恥ずかしくなってしまう
勿論、今の私だって、それほどの変化はない
決して充分とは言えない取り組み方をし、情けなくもそれで満足している面もある
ただ、「古注釈書」に触れることの大切さが、以前よりは格段と理解出来ることは成長だと思う
この二首、「相模国」と「武蔵国」に分けられて収載されても、
本来はおかしくないはずだ
「武蔵嶺」は、やはり「武蔵国」の「山」であり、
どんなに、語句が似通っていようと、「万葉集」の通常の部立てでは、
用いられた「語句」によって、分類されることの方が多い
しかし、この「相模国」の収載歌に、何故「武蔵国」の「武蔵嶺」が載せられるのか、
それを考えれば、必然的にこの二首が「相聞関係」にあることが想像できる
出立する男と、それを見送って残される妻の「切ない歌」だ
この出立が、「防人」としてなのか、あるいは官吏としての、有り触れたものなのか、
「防人歌」とされていない以上、それは漠然としているが、
「ねしなくな/ねしなくる」と詠われていることからも、
かなり辛い別れだったことが、理解出来る
私が、この歌に触れた当初、何の疑いもなく「相聞」と思ったのは、
その決定的な「語句」は、本歌の「いも」と、或本歌の「きみ」だった
あまり深い考えもなく、「あっ、男と女の歌なんだなあ」と単純に思ってしまった
いや、今でもそれで間違いないと思っている
「きみ」という語は、上代と日本史では区分される「万葉の時代」では、
女性が男を呼称するときに使われる一般的な「語」だったとある
中古以降は「男女」の区別なく用いられるようだが、少なくとも「万葉の時代」は、
「きみ」は、男をさしていたことになる
それを、安易にと言えば、確かに安易なことだが、
それで、この二首に何ら不自然さが伺えないことが、一つの証にはなるのだが、
敢えて言えば、ではどうして「相聞二首」ではなく、「本歌・或本歌」なのか、と
以前、「駿河国」の歌群に、「いづのたかね」という「伊豆国」の歌が、「或本歌」にあった
その時は、何となくとしか感じられなかったが
今では、この二首に触れて、はっきりと理解出来る
本来は「相模国」の歌群である本歌だ
しかし、唱和する相聞歌でありながら「或本歌」とするのは、
それは、「武蔵嶺」のせいではないか、と
その「勘国」のルールを不必要に守らんが為に、「或本歌」とした
そうとしか考えられない
本歌の作者が、初句で詠う「相模嶺」は、「相模国の嶺」だ
そこで、何故作者は唐突に「妻を激しく想う」のか
故郷を離れて、その途中で望郷の念に駆られたのなら、「相模嶺」の重要性は薄まる
しかし、私はその「相模嶺」にこそ、ここでなければならないものを感じている
それは、「或本歌」で妻が詠う「武蔵嶺」に関係がある
東国から西へ旅することを前提とすれば、
この男の出立は、「武蔵国」となる
そこを旅立ち、「相模国」に辿り着き、男は「ねしなくな」と詠う
何故だろう...次第に忘れかけてくる、妻を思い出したからか、
では、何故その場所で、思い出すことになるのか...
「武蔵嶺」は、秩父の山々、という説が強い
山に囲まれた、故郷のイメージがある
男の旅は、その「武蔵国」から、「相模国」に入り、そこで「相模嶺の小峰」を眺望する
それは、出立したときから、ずっと見慣れた「山々」を、ここで終らせることになるからだろう
「相模嶺の小峰」は、際立った山である現在の「大山」だと比定されるが、
そんな固有の山ではないような気がする
「小峰」と言うのが、どうして固有の山をさすのか、その必然性はない
「相模国」にやってきて、それまで故郷の「山々」のように見慣れた景色が、
これからは見られなくなる
だからこそ、男はそこで立ち止って「泣くほどの」哀しみを詠う
「小峰(山々)」を振り返れば、必ず故郷に通じていた
それが今後は見えなくなる...「小峰」は、故郷、いや妻そのものなのだろう
次第に忘れて来る「妻の名」は、この「小峰」から遠ざかるように、と重ねられる
男は、声をあげて、泣き過ごす
これほどまでの恋しさを、その道中の「景色」が募らせている
男の故郷「武蔵国」では、もう二度と逢えないかもしれない、と思う妻が
「武蔵嶺の小峰(山々)」を振り返りもせず旅立って行った男を想う
本歌「忘れ来る」も、或本歌「忘れ行く」も、その動詞「忘る」は、
四段動詞「忘る」ではなく、下二段動詞「忘る」だ
それは、上代では「自然に忘れる」「つい忘れる」の意味合いがある
長旅で、想いも次第に薄くなりがちだった男が、
ふと故郷を思わせる山並みから遠ざかり始めると、泣きたくなるほど妻を思い出すことになる
妻は、それを思い遣って、きっと私のことを忘れつつあるのだろう、と気に掛け
思わず口について男の名を出す
それが、こんなにも切なく悲しいものなのだ、と思い知る
「忘れ行く」と言うのは、妻が男の心情を推し量って言うものだろう
自分のことではない
自分のことであれば、「忘れ来る」としなければならない
有斐閣「万葉集全注」では、この「忘れ行く」を、次のように解釈している
| 「万葉集全注」巻第十四 有斐閣 水島義治 昭和61年 |
| 私のことを思い出すまいとして歩いているに違いない |
これでは、下二段動詞ではなく、意識的に忘れる、という意になる四段動詞「忘る」だ
しかし、四段活用は主に上代で使われたもの、とされているので
「忘れ行く」のような語法もあったのだろう
それでも、「私のことを思い出すまい」と言うのは、かあんり主観的になってしまう
本歌が「(作者自身が)次第に(妻の事を)忘れて来る」と言うのに対して、
或本歌では「(妻)は、男が次第に(私の事を)忘れて行く」とした方がいいと思う
ここまで、「きみ」を上代の慣習の通りに「男」としたが、
数は少ないが、「妻の事」を「君」とする歌もある、という
その場合、よく引用されるのが、次の「万葉歌」だ 〔万葉の植物-Ⅱ〕
| 巻第二十 4376 防人歌 丈部鳥 |
| (天平勝寳七歳乙未二月相替遣筑紫諸國防人等歌) |
| 美知乃倍乃 宇万良能宇礼尓 波保麻米乃 可良麻流伎美乎 波可礼加由加牟 |
| 道の辺の茨のうれに延ほ豆のからまる君をはかれか行かむ |
| みちのへの うまらのうれに はほまめの からまるきみを はかれかゆかむ |
右一首天羽郡上丁丈部鳥
(二月九日上総國防人部領使少目従七位下茨田連沙弥麻呂進歌數十九首 但拙劣歌者不取載之) |
〔通釈〕
道のほとりのうまら(ノイバラ)の枝先にはう豆のように、吾にからみまつわる君に別れて行くことであろうか |
この「きみ」を、「妻」や「娘」としか採りようのないことだ、という
確かに、通常の男への「きみ」では、歌の情感がなくなる
上代では「男への呼称」が一般的であっても、後に「男女いずれへも」ということであれば、
この万葉の時代に於いてでさへ、「君」が「女」を呼称することも有り得ない事ではないだろう
掲題歌の「君」を、この「女」として解釈し、
そうなると、本歌、或本歌ともに「同一作者」が、同じ気持ちを
地名や部分的な「小異」を駆使して、
「この本歌には、こんな別伝もある」と左注に添えられたことも考えられる
しかし、仮にそれが「或本歌」の実情であっても、
もう少し捻って考えることも出来る
何故なら、「万葉集」の編者は、随所に「演出」を見せてくれる
勿論、そう感じるのは私だけかもしれない
そして、その「演出」を考えれば、この「別伝」を、
「武蔵国」の若者が、「相模国」を通って西国に行く過程での作者の気持ちを、
悲哀に満ちたドラマの「一コマ」として「創作」している、と
それは、作者自身の思惑かもしれないし、万葉編者なのかもしれない
「相模国」に収載されながら、「武蔵国」をも視野に入れる手法は、
「本歌」では、扱い難いのかもしれない
だから「或本歌」として、「武蔵国」の妻の歌を載せ、
「相模国」を旅行く「男」に唱和させ、並べるための手段「或本歌」なのかもしれない
|
| |
| |

|
| |
 |
| |
|
掲載日:2015.06.07
| 巻第十四 3378 東歌相聞 作者不詳 |
| 東歌相聞 |
| 相模祢乃 乎美祢見所久思 和須礼久流 伊毛我名欲妣弖 吾乎祢之奈久奈 |
| 相模嶺の小峰見そくし忘れ来る妹が名呼びて我を音し泣くな |
| さがむねの をみねみそくし わすれくる いもがなよびて あをねしなくな |
| (右十二首相模國歌) |
| 或本歌曰 3379 |
| 武蔵祢能 乎美祢見可久思 和須礼遊久 伎美我名可氣弖 安乎祢思奈久流 |
| 武蔵嶺の小峰見隠し忘れ行く君が名懸けて我を音し泣くる |
| むざしねの をみねみかくし わすれゆく きみがなかけて あをねしなくる |
| |
| 【3378】 語義 意味・活用・接続 |
| さがむねの [相模祢乃] |
| さがむね [相模嶺] |
「さがむ」の訓については、「注記」 |
| をみねみそくし [乎美祢見所久思] |
| をみね [小峰] |
「を」は「接頭語」、嶺は山の峰 |
| みそくし [見退くし] |
上一段動詞「見る」の連用形「み」と、四段動詞「退く」の連体形「そく」に、語意を整えたり、強意を表す副助詞「し」 |
| わすれくる [和須礼久流] |
| わすれくる [忘れ来る] |
次第に忘れてくる |
| いもがなよびて [伊毛我名欲妣弖] |
| が [格助詞] |
連体修飾語所有の「~の」 |
体言、連体形につく |
| あをねしなくな [吾乎祢之奈久奈] |
| を [間投助詞] |
[感動・詠嘆] ~なあ〔注記・終助詞「な」〕 |
種々の語につく |
| ねしなく [哭し泣く] |
[注記] 「声をあげて泣く」意の「哭(ね)泣く」の慣用表現 |
| な [終助詞] |
[感動・詠嘆] ~なあ・~なことだなあ |
終止形につく |
| 【或本歌 3379】 語義 意味・活用・接続 |
| むざしねの [武蔵祢能] 秩父の山々をさす、と言われているが、詳細は解らない |
| むざし [武蔵] |
東海道十五国、関東八国の一つ |
| をみねみかくし [乎美祢見可久思] |
| かくし [隠くし] |
[他サ四・連用形] 見えないようにする・見て見ぬ振りをする |
| わすれゆく [和須礼遊久] 本歌の「忘れ来る」の対語と思う |
| きみがなかけて [伎美我名可氣弖] |
| きみ [君] |
「上代」と呼ばれる「万葉の時代」であれば、女性が男に呼びかける語 |
| かけ [掛く・懸く] |
[他カ下二・連用形] 心にとめる・思う・口に出していう |
| あをねしなくる [安乎祢思奈久流] |
| ねしなくる [哭し泣く] |
[注記] 「ねしなく」 「ねしなく」の連体形止め |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【3378】注記 |
[「さがむ」の訓]
「相模」は、万葉の時代までは「さがむ」と呼ばれていたようだ
だから、平安以降の書では、「相模」を「さがみ」とするのが一般的で、
「万葉集」の「相模」を平安以降の呼称「さがみ」と訓じて収載する歌集は多い
この「さがむ」を提唱し始めたのは、鹿持雅澄「万葉集古義」からだと思う
それまでの注釈書では、どれも「さがみ」と訓じている
問題は、何故「さがむ」と訓じられるのか、ということだ
| 「万葉集古義」 鹿持雅澄 天保十三年(1842)成 |
| 相模禰[サガムネ]は、今大山とて、雨降ノ神社のある山なるべしと云り、さて和名抄には、相撲ハ佐加三[サガミ]とあれども、其は後に轉れる唱ヘにて、古ヘは佐我武[サガム]と呼しなり、古事記に、相武[サガムノ]國と書り、摸ノ字を書るも、ムの假字なり、又東遊の一歌に、左加安无乃於禰[サガアムノオネ]とあるも、相摸の峯といふことなるべし、と本居氏云り、 |
「和名類聚抄(和名抄)」に「相摸はサガミ」とあるのを、
雅澄は、それは後の時代に伝えられた「唱」だとする
「和名抄」は、承平年間(931~938年)に、「梨壺の五人」として知られる源順が編纂した
名詞を漢語で仕分けして、それに日本語を対応させるのに「万葉仮名」を用いている
平安時代の源順の編纂だから、当然平安時代以前の語彙やその「音」などが載せられるが、
だとすると、掲題歌の「相模」は、「和名抄」の編纂時期には、
すでに「さがみ」として呼び慣らされていた「地名」ということになる
だから、ほとんどの「歌集」や「古注釈書」に於いても、「さがみ」が通訓となる
しかし、そこに「古事記」の表記「相武」や「佐賀牟」を引用し、
それを「万葉歌訓釈」に用いたのは、この雅澄以降ということになるだろう
そして、現代ではそれが定説になってる
[さがむね]
この「嶺」について、賀茂真淵は、その「万葉考」で、次のように言う
| 「万葉考」 賀茂真淵 宝暦十年(1760)成 |
| 相摸禰乃乎美禰[サガミネノヲミネ]、今大山とて雨降[アブリノ]神社の在山をいふべし、乎美禰は重ね云て、調べの文[アヤ]と爲なり、乎は發言にて乎筑波などの如し、 |
この歌の「相模嶺」が、前述の「古義」にも言うように、
「万葉考」で唱えられ、以降の「大山」説が定着している
この「大山」は、標高1246メートルで、
「雨降(アフリ)山」「阿夫利山」などの呼称もある
この「万葉考」では、「さがみねのをみね」の「をみね」を、
「調べの文」とする
それは、接頭語「を(小)」の、「単に語調を整える」ということなのだろうか
接頭語「を」は、「細かい、小さい」などの意を表すが、
ある注釈書では、「親愛」のような気持ちを具える接頭語でもある、とし
ただ語調を整えるだけではなく、接頭語「お(御)」の語意をも匂わせている
しかし、原文の「乎」は、後の「ヲ」の略体字とされるように「を」なのだから、
私には、「相模嶺の小峰」の語意は、
相模の連山の中で、作者がことさら愛着を持つ比較的「小さい」山なのではないか、と思う
だから、「大山」ではないような...
それに、「をみね」と詠われる「万葉歌」は、この二首以外に、他には見当たらない
[みそくし]
原文「見所久思」を「みそくし」と訓み、「見退くし」と当てるのがごく自然な解釈だと思う
諸本もすべてが「所」だが、この語句には、諸説が多い
もっとも、その「諸説」と言うのは、「訓釈」を言うのではなく
「所」が「可」の誤写、あるいは「見過(す)ぐし」の東国訛り説などだ
最初に「見退くし」として歌意に不自然さがなければ、これらの諸説も考慮しなければ、と思う
四段動詞「退(そ)く」は、離れる、遠ざかる意がある
「みそくし」となるには、上一段動詞「見る」の連用形「み」、
四段動詞「退(そ)く」の連体形「そく」、
語調を整えたり、強意を表す副助詞「し」からなる
「見る」は、「目にとめる・目にする・眺める」などがあり、
「退く」は、「離れる・遠ざかる」、
そうなると、「みそく」は「目にとめて離れる」意味合いになる
「し」を、過去の助動詞「き」の連体形「し」かとも思ったが、
その助動詞は、「連用形」に接続するので、やはり副助詞「し」になる
一説の「所」を「可」としたものは、
「みかくし」と訓むことになり、「見隠し」
四段動詞「隠す」の連用形「かくし」で、「隠す」の意味は、「見えないようにする」
そうなると、「みかくし」は、「見ても見えないようにする」ということになるのだろうか
「見させない」と言うことだろう
東国訛りか、とする「見過ぐし」では、
四段動詞「過(す)ぐす」の連用形「すぐし」で「みすぐし」となり、
一般的に「時を過ごす・暮らす」や、動詞の連用形について、「~て時を過ごす」になる
この場合の「みすぐし」であれば、「見て時を過ごす」と言うことだろう
以上を解りやすく表にすると、
| 「見所久思(みそくし)」の異説 |
| 「所」は「可」の誤りで「見隠し」 |
| 岩波書店「新・旧日本古典文学大系」 |
見ぬふりをして |
| 中西進「万葉集全訳注原文付」 |
隠してしまうように山のかなたに |
| 小学館「日本古典文学全集」 |
ある物に背を向けてそれを見ないようにする |
| 「みそくし」は、「みすぐし」の東国訛りで「見過ぐし」とする |
| 契沖「代匠記」 |
見て暫忘來れども |
| 賀茂真淵「万葉考」 |
見過しつゝ遠く來て、久しく見えざれば |
| 橘千蔭「万葉集略解」 |
ミソグシは、見過シにて、遠く來つる由を言ふのみ |
| 鹿持雅澄「万葉集古義」 |
見所久思[ミソグシ]は、見過[ミスグ]しなり |
| 土屋文明「万葉集私注」 |
見過ぎ行きて |
| 鴻巣盛広「万葉集全釈」 |
見ながら過ぎて来て、もう見えなくなつたので |
| 武田祐吉「万葉集全註釈」 |
ミソクシは見過クシ。見て遠ざかる。 |
意表を突かれたのが、新潮社の「新潮日本古典集成」だ
その訓釈の表記では「見退くし」を当てて、次のように訳している
| 新潮社「新潮日本古典集成」 |
| 相模嶺のあの峰を見捨てるようにして、忘れよう忘れようとしてやって来たのに、今更あの娘の名なんか呼んで、この私を泣かせてくれるな |
このように、「見退くし」を、単に「見て遠ざかる」程度の解釈ではなく、
「見捨てるようにして、忘れよう忘れようとしてやって来たのに」とするのは、
小学館「新編日本古典文学全集」にも見られるように、
「退くす」を、「しりぞく・そきへ」など離れる意の「そく」からの派生語とみて、
「振り返りたい気持ちを断ち切って行くさま」の解釈をする
そうなると、「退く・す」の「す」は「為(す)」ということなのかな
文法的には「そく」の連用形「そき」に「す」、「をみねみそきし」で、
「し」が過去の助動詞「き」の連体形でも通用するが、
それであれば、「すぐす」の方が、まだすっきりする
派生語として「そくす」という語が存在していたのだろうか...
[ねしなく]
四段動詞「ねなく」、「声をあげて泣く」の意に、
「ね」を強調する副助詞「し」が添えられたもの
[終助詞「な」]
多くの注釈書が、「禁止」の終助詞「な」として、「泣かせるな」と解釈する
「泣く」が、自動詞四段であれば、「泣くな」だが、それでは意味が通じない
他動詞下二段の終止形「泣く」で「泣かせる」、「泣かせるな」となる
問題は、何故「泣かせられる」のか、どんな環境でそうなるのか、だが
作者を「泣かせない」とするには、「同行者」の存在が必要となる
だから、古注釈書を始め、そのような解釈も多い
しかし、ここに「同行者」が現れるのは、切なさの要因が外的なものとなって、
私には、味わいが薄れてしまう
ここに「な」を「感嘆」の気持ちで味わってこそ、孤独な旅人の切なさが滲み出て来る
そうなると、必然的に、「あをねしなくな」の「を」は、
対象の格助詞「を」ではなく、間投助詞の「を」になるべきだと思う
【或本歌 3379】
[むざし]
これも、本歌の「さがむ」と同様に、古くは「むざし」と濁音で呼ばれていた、とするが
少なくとも、現代目にする「万葉集」の諸々の本では、「むざし」とされている
しかし、「さがむ」のように、それが唱えられたのは、やはり雅澄の「古義」からだ
| 「万葉集古義」 鹿持雅澄 天保十三年(1842)成 |
| 武藏禰[ムザシネ]は秩父[チヽブ]山をいふなるべし、武藏は、武射志[ムザシ]と射[ザ]を濁り唱フなり、なほ次にいふ、 |
| 次にいふ [3374(新3391)]「万葉集古義」 鹿持雅澄 天保十三年(1842)成 |
| 武藏[ムザシ]は、牟射志[ムザシ]と射[ザ]を濁るべし、(今は清てのみ唱れども、ひがことなり、)此ノ下にも牟射志野[ムザシヌ]と書キ、古事記にも、牟射志[ムザシノ]國と書り、又藏ノ字を用たるも、濁音の故なり、 |
雅澄の時代は、「野」を「ヌ」と訓じることが主流であったので、
ここでは、「ぬ」については書かない
古義以前では、万葉の時代を過ぎて、いつ頃からか「むさし」と呼ぶようになり、
それが現代までも定着はしているのだが、
上述の「さがむ」もそうだが、確かに「古事記」などの文献ではそうだと言える
そして、その「古事記」が編纂されたのも、まさに「万葉の時代」なのだから、
「万葉集」が無条件で「むざし」と訓まれるのも頷ける
「万葉集東歌武蔵国」に、「或本歌一首」を含め、十首の歌があり、
その中で「武蔵」の原文表記があるが、現代ではすべて「むざし」と濁る
これも、「古義」の影響だろうし、同時代の「古事記」などの例に倣うべき、という発想だろう
雅澄は言う、「武蔵」の「蔵」の字を当てるのは、「濁音」が故のことだと...頷ける
[わすれゆく]
本歌で「忘れ来る」と詠った作者は、自身が次第に残した妻の事を忘れて「来る」ことを言うが、
ここでの「忘れ行く」は、第三者が「忘れて行く」ことと感じたい
この第三句だけでも、「本歌」と「或本歌」は、相聞関係にある二首だと思う
[連体形止め「ねしなくる」]
連体形の終止法の一つで、「詠嘆・余情」の表現とされる
|
| |
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」
【3378】
[本文]「相模禰乃 乎美禰見所久思 和須禮久流 伊毛我名欲妣氐 吾乎禰之奈久奈」(右十二首相模國歌)
「サカミ子ノヲミ子ミソクシワスレクルイモカナヨヒテワヲ子シナクナ」 |
| 頭注 |
「類聚古集」本文ノ下ニ小字「相模」アリ。
「古葉略類聚鈔」主文ヲ訓交リニ書ケリ。下ニ小字「相模」アリ。 |
| 〔本文〕 |
| 模 |
『元暦校本・細井本・古葉略類聚鈔・神田本・温故堂本・大矢本・京都大学本』「摸」。
|
| 乃 |
『類聚古集』「能」。
『古葉略類聚鈔』訓ヲ主文トセリ。
|
| 和須禮久流 伊毛我 |
『古葉略類聚鈔』以上訓ヲ主文トセリ。
|
| 之 |
『類聚古集』ナシ。
|
| 〔訓〕 |
| ヲミ子ミソクシ |
『元暦校本』「く」ノ右ニ墨「ク」アリ。
『西本願寺本・温故堂本・大矢本』「所」ノ左ニ「カ」アリ。
|
| イモカナヨヒテ |
『西本願寺本・温故堂本』「欲」ノ左ニ「モ」アリ。 |
| ワヲ子シナクナ |
『元暦校本』「われをねしなくな」。
『類聚古集』「われをねなくな」アリ。
『古葉略類聚鈔』「ワレヲ子シナクナ」。 |
| 〔諸説〕 |
| 〇サカミ子ノ、[万葉集古義]「サカム子ノ」。 |
| 【或本歌 3379】 |
[本文]「或本歌曰 武蔵禰能 乎美禰見可久思 和須禮遊久 伎美我名可氣氐 安乎禰思奈久流」
「 ムサシ子ノヲミ子ミカクシワスレユクキミカナカケテアヲ子シナクル」 |
| 頭注 |
「元暦校本」訓ヲ附セズ。
「古葉略類聚鈔」主文ヲ訓交リニ書ケリ。
「西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本」訓ヲ朱書セリ。
|
| 〔本文〕 |
| 或 |
『京都大学本』赭ノ合点アリ。
|
| 歌 |
『古葉略類聚鈔』ナシ。
|
| 曰 |
『古葉略類聚鈔』「云」。
|
| 能 |
『古葉略類聚鈔』訓ヲ主文トセリ。
|
| 和 |
『類聚古集』ナシ。右ニ墨ニテ書ケリ。本文中「思須」ノ間ニ墨〇符アリ。 |
| 遊 |
『西本願寺本』ナシ。右ニ書ケリ。本文中「禮久」ノ間ニ〇符アリ。 |
| 伎美我 |
『古葉略類聚鈔』以上訓ヲ主文トセリ。
|
| 可気氐 |
『古葉略類聚鈔』以上訓ヲ主文トセリ。
|
| 氐 |
『元暦校本』「恵」。右ニ墨「弖」アリ。 |
|
|
 |
| 【歌意3380】 |
いとしい私の夫を、大和へ旅立たせて、
無事に帰郷できるように、と
夫を送り出した足柄山の「神憑る」杉の木立に、日々通い
想いを募らせながらも、待ち祈る...
どんなに月日が過ぎようと...神の杉の木の間よ |
| |
私が、「万葉歌」を読むとき、まずその情景を思い浮かべることに努める
それが、そのまま胸に響くものであれば、その歌意解釈は、私なりに受け入れられる
しかし、この歌のように、第三句「まつしだす」の語意に、見当もつかなかった当初は、
さっぱり、その情景など浮びもしなかった
確かに、その第三句を除けば、どの語句も謎はない
だから、大まかな解釈には辿りつけられるだろう、と思っていたのだが
逆に、他の四句が、その有り触れた語句のせいで、ますます第三句の解釈如何に掛かってきた
ほとんどの注釈書が、夫を大和へ送り出し、
その無事の帰郷を、足柄山の杉の木の間に立って待つ、とか、
「木の間」は、その一つの舞台にすぎない、かのような解釈だ
「まつしだす」を、私が理解出来ない間は、
漠然と、夫の帰りを杉木立に立って待っている妻、そんなイメージが何の迷いもなく浮んできた
もっとも、「まつしだす」の語意に、何も正解は見つけられないが、
古注釈書に触れていると、現代的な解釈よりも、
より人の心に染みるような解釈の試みを見ることになる
「意訳」になるのか、あるいは強引な「誤字説」を用いるのか、
このような「難訓」に遭遇すると、必ずと言っていいほど、そのパターンに出合う
現代的な解釈では、そこを無難に通そうと、「未詳」のまま「まつしだす足柄山の」とするが、
そこが、研究者が表現する限界になるのだろう
確固たる裏付けや傍証がなければ、簡単に「語意解釈」には及ぶこともない
だから、古注釈書の類の、一個人の見解に近いスタイルを通す著書にも魅力は褪せない
この歌の歌意解釈に至る過程で、私自身もあっちへ行ったり、こっちへ来たり、と
随分彷徨った
その流れは、「一日一首」で日々綴っているが、
6月8日〔萬葉集巻第十四 東歌相聞 わがせこを 1〕から始まって、
昨日(6月20日)〔萬葉集巻第十四 東歌相聞 わがせこを 9〕まで引きずってしまった
ようやく、昨日にこの歌意解釈に辿りつけたが、この「HP」の書き始めが一週間前
結局、解ったつもりで書き始めては、壁にぶつかる、その繰り返しで、
今更ながらに、古典和歌の難しさや、その深さに酔いしれた...そう、酔いしれた
昨日までの私の感覚で、この一首が、「祈りの日々」の歌に行き着いたのは、
そんなに突飛なことではないと思う
むしろ、「まつしだす」という難解な語句に惑わされて、
なかなか気づくことのなかった「すぎのこのまか」に籠められた想いを、
時間が掛かったからこそ、そこまで行けたのだ、と思う
「杉」や「木の間」という平凡な語句であっても、
その用例には、やはり特別なものがあった
いや、作者はそんな意図はなかったのかもしれない
しかし、上述の「歌意解釈」のように読み取れる含みも、決して否定はできないと思う
「杉の木」という、特殊な「樹木」の意味、
そして「木の間」と言う、よく考えれば、とても魅力的な「視覚効果」を使い
平易な言葉では、表現すれば陳腐になってしまいがちな「祈り」の気持ちを、感じ取れる
この歌も、これまでの歌と同じように、
また数年もすれば、私には違った受止め方になることだろう
ただ今の私が、あちこち彷徨った挙句に受け入れられる「歌意解釈」に出合ったのは、
とても大切なことだと思う
歌を詠じるのも、その人のその時の感性ならば、
歌を感じ取るのも、その人のその時の感性になる
「万葉集」に触れただけで、上代の万葉人たちの心を感じ取ることは不可能だ
その時代背景も、人々の慣習や風俗にも、決して充分な知識があるわけではない
だから、「万葉人」との会話を求めると言っても、
決して、私自身が「万葉人」に擬えて日常の会話のように談笑する、というのではない
あくまで、現代人である私が、その拙い調べ方であっても、あくまで自身の手で掘り起こす
その「知識」でもって、「万葉人」と会話する
逆に言えば、万葉人から教えられることの方が、きっと多いはずだ
何も、上代はこうだったよ、というその時代を偲ばせるものではない
万葉人の心にあるもの、それがいかに現代人でも胸に響かせられるのか、ということを...
大和国へ夫を送り出す、と言うことは
「律令体制下」での「賦役」のことだと思う
諸国の役民たちは、無事にその賦役期間を終えても、
果たして、どれだけの人が念願の故郷へ帰ることができたのだろう
資料の「和銅三年正月十六日の詔」に、
| 和銅三年正月十六日の詔 (710年) |
| 「諸国の役民、郷に還る日、食糧絶え乏しく、多く道路に飢ゑて、溝に転填す。その類少なからず。」 |
また、「天平宝字三年五月の詔」では、
| 天平宝字三年五月の詔 (759年) |
| 「此の頃聞けり、三冬の間に市辺餓人多しと。其の由を尋問するに皆云へり、諸国の調脚郷に還る事を得ず、或は病に因りて憂苦し、或は粮無くして飢寒すと。」
|
「調脚」というのは「貢調」を運ぶ脚夫のことで、疲労困憊、そしてついに道に斃れ、
溝(谷)に墜ちて死ぬ、その屍の多さを特筆している
それほど、「賦役」は過酷なものだったことが解る
だから、掲題歌のように、夫をその賦役で送り出した妻は、
とにかく無事に帰ってくることを、祈らずにはいられないのだろう
|
| |
 |
|
 |
| |
| |
|
掲載日:2015.06.14
| 巻第十四 3380 東歌相聞 作者不詳 |
| 東歌相聞 |
| 和我世古乎 夜麻登敝夜利弖 麻都之太須 安思我良夜麻乃 須疑乃木能末可 |
| 我が背子を大和へ遣りて待つしだす足柄山の杉の木の間か |
| わがせこを やまとへやりて まつしだす あしがらやまの すぎのこのまか |
| (右十二首相模國歌) |
| 【3380】 語義 意味・活用・接続 |
| わがせこを [和我世古乎] |
| せこ [背子] |
「せ」はもと、女性が兄・弟・夫等の男性を親しんで呼んだ語 |
| やまとへやりて [夜麻登敝夜利弖] |
| やり [遣る] |
[他ラ四・連用形」行かせる・送る・不快な気持ちを晴らす |
| て [接続助詞] |
[単純接続] ~て・そして |
連用形につく |
| まつしだす [麻都之太須] 注記参照 |
| あしがらやまの [安思我良夜麻乃] |
| すぎのこのまか [須疑乃木能末可] |
| すぎ [杉] |
スギ科の常緑高木・古来、神木とされ、建築用材、酒樽に用いられた |
| このま [木の間] |
木々の間 |
| か [終助詞] |
[感動・詠嘆] ~だなあ |
体言、連体形につく |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【3380】注記 |
[せこ]
「こ」は、親愛の情を表す接尾語
| 用例歌「せこ」 一般的には、女性から男性へ呼ぶ語「兄子・夫子・背子」 |
| 兄弟を |
我が背子を大和へ遣るとさ夜更けて暁露に我れ立ち濡れし 巻ニ 105 |
| 大伯皇女が、弟・大津皇子を |
| 夫を、また恋人を |
我が背子はいづく行くらむ沖つ藻の名張の山を今日か越ゆらむ 巻一 43 |
| 當麻真人麻呂妻が、夫を |
| 男性同士も |
沖つ波辺波立つとも我が背子が御船の泊り波立ためやも 巻三 248 |
| 石川大夫(宮麻呂/君子)が、長田王を |
[やり(遣り)]
この「やる」が、こちらからあちらに動作が及ぶのに対して、
あちらからこちらへ動作が及ぶ意を表す語に、「遣(おこ)す」がある
その「遣(おこ)す」は、他動詞サ変下二段と四段があり、
「こちらへ送ってくる・よこす」の意を持つ
上代・中古は下二段活用だったが、室町時代頃から四段活用が見え、
近世に四段活用が一般的となる
[まつしだす]
この語句に、随分と振り回される
古注釈書では、様々な解釈が試みられており、それも楽しいことだ、と思ったものの
では、自分なら、どんな風に解釈すればいいのか、となると唸ってしまう
「万葉の時代」の「東国語辞典」めいたものが、手元にあればなあ、と痛感する
「まつしだす」の原文「麻都之太須」は、その訓自体は、「まつしだす」「まつしたす」だろう
しかし「太」は、「濁音」で訓むべき、というのが正論らしい
もっとも古い注釈書である仙覚の「万葉集註釈(仙覚抄)」では、
| 「万葉集註釈(仙覚抄)」 仙覚 文永六年(1269)成 |
| したすとはしたはひまといふ詞すはすみかなりわかせこをやまとへやりてまつあひだのすみかといふ心なり |
この解釈が、後の鹿持雅澄「万葉集古義」の「令待慕(まちしたはす)」に繋がると思う
しかし、仙覚と雅澄の決定的な違いは、その「主語」にある
諸説は、以下のようにある
| 「麻都之太須」訓釈の諸説 |
| 仙覚抄 |
したはひま(下延ふる間、なのか)、心中に深く恋しく思う |
| 代匠記 |
翳(まぶし)立つ、猟師が獲物を待受けて自分の身を隠すためのもの、都部誤字説 |
| 童蒙抄 |
松し如(な)す、然ればまつの如くと云義にて、人を待つに云ひかけて、杉の木間なれ共松の如くなるかなと云義と也 |
| 万葉考 |
まつしだす、麻都は松なり、之は助辭、太須は奈須にて如の意 |
| 古義 |
待つ慕はす、されば夫の方より吾を待慕はしむる謂に云るなるべし 童蒙抄批判 |
| 鴻巣全釈 |
まつしだす、「待つ時[シタ]し」の訛音と見られないであらうか |
| 土屋私注 |
松し立つ、松の立ててある |
| 岩波大系 |
都之は都々の誤で、待ちつつ立つの意か |
| 新潮集成 |
松時立す(まつしだたす)の約か、私が待つのは松ならぬ、足柄山の杉木立か |
| 中西全訳注 |
「待つ間(しだ)す(為)」か、 |
現代の古典叢書で岩波書店の「新日本古典文学大系」や小学館「新編日本古典文学全集」は、
明確な訓釈をしていない「『まつしだす』足柄山の」とするのが叢書の限界なのだろう
その点、新潮社の「新潮日本古典集成」は、踏み込んだ解釈になっている
[すぎ[杉]]
「万葉歌」で、「杉の木」を詠うその多くは、神木としての「木」となる
その用例歌として、二首をあげる
| 巻第三 425 挽歌 丹生王 |
| 石田王卒之時丹生王作歌一首[并短歌] |
| 石上 振乃山有 杉村乃 思過倍吉 君尓有名國 |
| 石上布留の山なる杉群の思ひ過ぐべき君にあらなくに |
| いそのかみ ふるのやまなる すぎむらの おもひすぐべき きみにあらなくに |
| 巻第九 1777 相聞 柿本人麻呂歌集 |
| 獻弓削皇子歌一首 |
| 神南備 神依板尓 為杉乃 念母不過 戀之茂尓 |
| 神なびの神寄せ板にする杉の思ひも過ぎず恋の繁きに |
| かむなびの かみよせいたに するすぎの おもひもすぎず こひのしげきに |
| (右三首柿本朝臣人麻呂之歌集出) |
杉には、「神が憑いている」こととして、「すぎ」を語句とすれば
必然的に、その想いの深さ、重さを比較できてしまう
ならば、この掲題歌の「杉の木の間」と言うのも
単純に「杉木立」の「樹間」と考えるべきではない
[このま(木の間)]
「木の間」のイメージは、鬱蒼とした樹林帯で、
その木々の間から、垣間見る場景を思い浮かべる
まるで、カメラの連写を思わせる
それを、歌の中で表現すれば、幾つかのそれに似合う「万葉歌」に出逢う
そもそも、「木の間」と言う語は、有り触れているようで、
実際にはそれほど多くは詠われていない
「万葉集」では、掲題歌を含めて十首ばかりだ
「木の間」らしさを、もっともアクティヴに詠ったものに、家持の二首がある
| 巻第八 1499 夏雑歌 大伴家持 |
| 大伴家持霍公鳥歌(二首) |
| 足引乃 許乃間立八十一 霍公鳥 如此聞始而 後将戀可聞 |
| あしひきの木の間立ち潜く霍公鳥かく聞きそめて後恋ひむかも |
| あしひきの このまたちくく ほととぎす かくききそめて のちこひむかも |
| 巻第十七 3933 大伴家持 |
| 橙橘初咲霍公鳥飜嚶 對此時候タ不暢志 因作(三首)短歌以散欝結之緒耳 |
| 安之比奇能 山邊尓乎礼婆 保登等藝須 木際多知久吉 奈可奴日波奈之 |
| あしひきの山辺に居れば霍公鳥木の間立ち潜き鳴かぬ日はなし |
| あしひきの やまへにをれば ほととぎす このまたちくき なかぬひはなし |
| (右四月三日内舎人大伴宿祢家持従久邇京報送弟書持) |
「このまたちくく(連体形)」「このまたちくき(連用形)」に、その「連写」の様を見る
自動詞四段「立ち潜く(たちくく)」は、間をくぐる、くぐり抜ける、という意を持つ
樹間を、縫うように飛び渡る「ほととぎす」
「木の間」が、まるでコマ送りのように飛翔の様を強調させる
掲題歌には、このようなアクティヴな「木の間」は窺えないが
一つの共通するものがある
それは、その場景の一場面ではなく、「木の間」で仕切られた「空間」を強調していることだ
他に「このまより」とする語句も多い
柿本人麻呂は、「木の間」にて「袖を振り」妹に見せようとする
| 巻第二 132 相聞 柿本人麻呂 |
| 柿本朝臣人麻呂従石見國別妻上来時(歌二首[并短歌]反歌二首) |
| 石見乃也 高角山之 木際従 我振袖乎 妹見都良武香 |
| 石見のや高角山の木の間より我が振る袖を妹見つらむか |
| いはみのや たかつのやまの このまより わがふるそでを いもみつらむか |
これも「木の間」でなければ、しんみりとした風情にならない
開けた山路から、袖を振るよりも、
「木の間」のその姿こそ、別れを一層際立たせられると思う
そして何より、「木の間」の幽玄さを思わせる歌がある
それは、「木の間」より現れる「いでくる月」だ
| 巻第七 1089 雑歌詠月 作者不詳 |
| 妹之當 吾袖将振 木間従 出来月尓 雲莫棚引 |
| 妹があたり我が袖振らむ木の間より出で来る月に雲なたなびき |
| いもがあたり わはそでふらむ このまより いでくるつきに くもなたなびき |
山の端に昇る月ではなく、「木の間」から現れる「月」だ
このことで、作者の位置が想像できる
山路に差し掛かって、これからは、鬱蒼とした樹林に、妹の住む家の辺りも遮られる
その前に、最後の一瞥を試みる
注釈書によっては、妹の家の辺りを照らす「月明かり」を望む歌ともあるが、
私は、やはり山路の作者の辺りを照らすための「月明かり」だと思う
嘱望する「月明かり」が、「木の間」より現れる、というのが、
視界の途絶えた「闇」にあって、まるでスポットライトを浴びせられるかのように映える
「木の間」から射し込む「月明かり」を、一身に浴びた作者が、妹に向かって一瞥の袖を振る
だから、その月に、雲は棚引かないで欲しい...
|
| |
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」
【3380】
[本文]「和我世古乎 夜麻登敞夜利氐 麻都之太須 安思我良夜麻乃 須疑乃木能末可」(右十二首相模國歌)
「ワカセコヲヤマトヘヤリテマツシタスシシカラヤマノスキノコノマカ」 |
| 頭注 |
「類聚古集」本文ノ下ニ小字「相模」アリ。
「古葉略類聚鈔」主文ヲ訓交リニ書ケリ。下ニ小字「相模」アリ。 |
| 〔本文〕 |
| 和我世古乎夜麻登敞夜利氐 |
『古葉略類聚鈔』以上訓ヲ主文トセリ。
|
| 安思我良夜麻乃須疑乃木能末可 |
『古葉略類聚鈔』以上訓ヲ主文トセリ。
|
| 〔訓〕 |
| シシカラヤマノ |
『元暦校本・類聚古集』「あしからやまの」。
『西本願寺本・温故堂本・大矢本』「所」ノ左ニ「カ」アリ。
|
| イモカナヨヒテ |
『古葉略類聚鈔・西本願寺本・細井本・神田本・温故堂本・大矢本・京都大学本』「アシカラヤマノ」。 |
| スキノコノマカ |
『元暦校本・類聚古集』「すきのきのまか」。「元暦校本」下ノ「き」ノ右ニ赭「コ」アリ。
『古葉略類聚鈔』「スキノ木ノマカ」。
『西本願寺本・大矢本・京都大学本』「コ」青。 |
| 〔諸説〕記ナシ |
|
|
 |
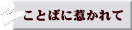  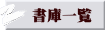  |