| 【歌意3372】 |
あの娘と、添い寝したのは、ほんの少しの間なのに、
この恋心は、富士の高嶺に鳴り続く、まるで「鳴沢」のように
激しく、そして止むこともない
|
| 【歌意3373】或る本の歌に曰く |
愛しいと思っている娘と、確かに共寝するにはしたのだが、
あの娘のその「評判」は、なるほど、確かに「伊豆の高嶺の鳴沢」のようだったなあ
|
| 【歌意3374】一本の歌に曰く |
逢ったのは、ほんの束の間で、玉の緒の短さにも及ばないのに、
恋しく思う気持ちは、あの富士の高嶺に雪が降ったとしても、
それは決して止むことなく続くことだ...
富士の鳴沢を収められないように...
|
| |
【3372】
本歌結句の「なるさはのごと」...、「鳴沢のようだ」と解釈にはなるが、
では、その「鳴沢」とは、どんなものなのか、と考えずにはいられない
これまでの幾つかの解釈(右頁)を大別してはみたが、
一つ興味深い根拠があった
それが、右頁の解釈群の「ハ」になる「富士山の大沢崩れ」だ
他の解釈「イ・ロ」が、多分に感覚的な発想を基にしているかのように感じられるが、
「ハ 富士山の大沢崩れ」は、ある地誌の記述にヒントを得ている
それが、明治時代後期に出版された、日本で初めての全国地誌「大日本地名辞書」だ
しかも、それが個人による編纂というのも、凄いことだと思う
勿論、そこでの記述が和歌の歌意解釈の「作者の意図」を語るものではないが、
仮にそれを採用して一首をイメージすると、それがごく自然に描き詠われるものだと思えるなら
それも、一つの大きな拠り所にはなる、と思う
この「大日本地名辞書」に、次のような一節がある
| 「大日本地名辞書」吉田東伍 元治元年(1864)-大正七年(1918) |
| 一滴の水なしと雖、磊塊の石の流下すること、水のごとく混々止まず、激衝して轟鳴を発する遠雷をきくが如し、古人「小寝(サヌ)らくは、玉の緒ばかり恋ふらくは」と比興せるも以あり」 |
この一文が、なぜ掲題歌の「大沢崩れ」に結びつくのか、ということになるが、
この著書の特徴は、それまでの地誌に見られるように、
書き残されている膨大な古典の資料を多く引用し、厳しい史料批判も行っている
そして、その「土地」に関係ある「和歌」や「漢詩」も、載せられており
上述の一節で、編者は「鳴沢は大沢崩れ」のことだ、と主張している
私は詳しく知るものではないが、富士には「崩壊谷」と呼ばれるところがあって
頂上から五合目付近(標高2200メートル)までの幅平均約500メートル、深さ約150メートル、
年に20万立方米の土砂が崩壊流失しているところらしい
富士山は孤立峰故にだと思うが、四方八方に「沢」を広げ、
それは、千年以上も前から「土砂崩壊」が続いており、
その最大のものが、「大沢崩れ」だと言われる
この推定を基にする歌意解釈では、「なるさはのごと」は、その「大崩落の如し」となり、
「激しい恋心」を言うものだろうが、「大崩落」と「激しい恋心」が似合うものだろうか、
そんな奇妙な気持ちにもなる
この詠歌の時代、「鳴沢」が「富士の大沢崩れ」を連想させるものなのかどうか、
それよりも、「鳴沢」が、一般的な「沢」の激流を指すものに収まらず
そこに、当時の富士の頂から、噴火によって延々ともたらす「溶岩様」の譬えの方がいいと思う
| 万葉集略解 橘千蔭 寛政十二年(1800)成 |
| 末は鳴澤の鳴り轟くを、思の涌き返るに譬ふるなり。フジノ鳴澤は嶺上に穴有りて、昔は水有り火有りて、相たたかふに、涌き返る音高かりしと言へり。延暦十二年、又貞觀の比にも甚[イタ]く燒けて、後火も騰らず、水も湛へねば、涌く事も無く、烟も絶えて、其後寶永には、山の半ばへ燒け出でたり。 |
| 万葉集古義 鹿持雅澄 天保十三年(1842)成 |
| 思ヒの、鳴澤の鳴さわぐごとく湧キ返る、となり、鳴澤は、此ノ山のいたゞきに大なる澤有リて、むかし山のもゆる火の氣[ケ]と、其ノ澤水と相對て、常にわき返り、鳴響む音の高かりしゆゑに、鳴澤といへるとぞ、 |
ともに「富士山頂の噴火口」説を採る注釈書だが、
万葉時代の、富士の「沢筋」の激しさを「鳴沢」と言う根拠を、一応語っている
右頁の「イ 轟き流れる渓流・渓谷」では、「なるさはのごと」と譬える印象が弱い気がする
この情景に近い想いを感じられる一首がある
右頁でも「なるさはのごと」で採り上げた、宗尊親王の一首だ
| 瓊玉和歌集巻第八 恋歌下 三七二/柳葉和歌集巻第四 恋 六〇一 宗尊親王 |
| したむせぶおもひをふじのけぶりにて袖のなみだはなるさはのごと |
心の中では、ひたすらむせび泣くこの想いは、
富士の「煙」(噴煙だと思う)で、どうにも止らなく袖を濡らす涙のようで、
それはまるで、あの激しく鳴り止まることもない「鳴沢」のようだ
私には、そんな風に感じられる歌だと思う
ここで詠われる「なるさはのごと」は、紛れもなく「噴煙」と関連付けられる
静かに想いを秘め、むせび泣くような姿なのに、
それが袖を濡らすまでの激しい想いの発露...
掲題歌の作者とは、意識はまるで逆だが、顕れる現象は、同じものだと思う
【3373】
この本歌には「或本歌曰〔3373〕」と「一本歌曰〔3374〕」が添えられている
当然、本歌の「異伝歌」だということなのだが、
この〔或本歌曰〕をみてみると、そうなのかなあ、と思わずにはいられない
本歌の作者の心情では、愛しい娘と共寝したのは、「ほんの短い時間」
それなのに、富士の「鳴沢」のように激しくも止むことなく恋心が募る
そして、この「或本歌曰」となると、
愛しいと思っている娘と、確かに共寝するにはしたのだが、
あの娘のその「評判」は、まるで「伊豆の高嶺の鳴沢」のようだったなあ
これでは、「鳴沢」に譬える意味がどうなのかなあ、と思う
本歌の「なるさは」とは、かなり違っている
男が、可愛いと評判の娘と、実際に共寝をした
その感想が、本歌のように「止むことのない激しい恋心」だと、回想するのはおかしい
では、この歌の「なるさは」とは、どう解釈すればいいのだろう
契沖の「万葉代匠記」に、次のような注釈がある
| 「万葉代匠記精撰本」 契沖 元禄三年(1690)成 |
| 伊豆の高根の鳴澤とは走湯なるべし |
これが正しいかどうか解らないが、少なくとも「富士の鳴沢」とは違う認識がある
そして、その「走り湯」というのは、
奈良時代の養老年間(717~724)に発見された、今でも有名な源泉らしい
調べるとその「走湯温泉」、往時には一分間に約900リットルもの源泉が海岸に流れていた、と
その様を想像すると、まるで地獄谷のような激しい湯煙を立てて流れているのが窺える
これは、「恋心の止まぬ激しさ」を譬える本歌の「なるさは」とは違って、
この「温泉」と言う、その「有名な評判」のことを譬えているのではないか、と思う
「さならくは いづのたかねの なるさはなすよ」
評判の高い、伊豆の走り湯のようだよ、と詠嘆の気持ちが、そこにあるのだから...
ちなみに、橘千蔭「万葉集略解」には、この歌について、次のように言う
「万葉集略解」 橘千蔭 寛政十二年(1800)成
|
奴良久の下、波一本に無く、奈良久の上、一本佐の字有り。此歌は、右の歌を誤り傳へたる物にて、解くべからず。
|
「右の歌」と言うのは、本歌のことであり、
誤写によって生まれた「歌」を、「或本歌」としているので、
改めて解釈する必要はない、と書いてある
これは、鹿持雅澄「万葉集古義」でも、同様に書かれている
そこまで考えてみると、
この「或本歌」を、本歌の「異伝」と言うのは、やはりおかしい
まったく別の意図を感じる詠歌だと思う
これは、大したことではないだろうが、名所を詠った「歌枕」の歌を集めた「歌枕名寄」、
そこに、この「或本歌」が、二首載っている
「歌枕名寄」巻第廿 駿河国 鳴沢 萬十四 一本云
|
| 五一八一 まかなしみ ぬらくはしけらく さならくは いづのたかねの なる沢なすよ |
「歌枕名寄」巻第廿 伊豆国 伊豆高嶺 萬十四
|
五二九六 まかなしみ ぬらくはしけみ さならくは いづの高ねの なるさはなすよ
|
「駿河国 鳴沢」で、「或本歌」、もっとも「歌集」では「一本云」とあるが、
もう一つは「伊豆国 伊豆高嶺」で、「或本歌」の「小異伝歌」
第二句の「しけみ」と、原因・理由を表現する「ミ語法」を用いている
それくらいの「差」でしかないが、気になるのは、その扱い方だ
「駿河国 鳴沢」に、「一本云」として「万葉集十四」に載っているよ、というのは解る
しかし、その小異歌を、今度は「伊豆国 伊豆高嶺」として、ここに載せている
と言うことは、本来は「伊豆国」の歌として収載されていた歌だったのかもしれない
それが、万葉集編纂のときに、「駿河国」に紛れ込んだ
「ク語法」の多用さや、「なるさは」という共通する「語感」から、
そのようにして紛れ込んだ、と考えてもいいのではないか、と思う
歌意についても、その詠歌の心情はまったく違っており、
「或本歌」とするには、どうしても首を傾げてしまう
【3374】
これこそ、本歌の想いを、「鳴沢」から「降る雪」に変えて伝わるものだと思う
想いそのものは、同じだ
そして、この「降る雪」で解ることがある
本歌で「なるさは」を単に「激しくも止むことのない渓流」のごとく理解したが、
ここで「降る雪」に描かれる姿は、必ずしも吹雪のような激しい降雪ではない
ただただ、降り続き止むこともない雪舞だ
吹雪であれば、いっときのものだ、と思い込んでしまう
しかし、深々と降りゆく雪というような表現もあるように、
激しさよりも、内面的に耐え忍びながらの、それこそ宗尊親王の、
「したむせぶおもひをふじのけぶりにて袖のなみだはなるさはのごと」この歌が重なってくる
「或本歌」とか「一本歌」という表現の意図が何だろうか、と考えてしまう
同じような語句であるが故の、類想歌になるのか、
それとも、語句はそれほど似通ってはいなくても
想いは、紛れもなくおなじものだ、とか...
「類歌」「類想歌」と使い分けることが、やはり必要だと思う
そして、この「一本歌」は、私なりに「類想歌」であり、
決して、本歌の「一本歌」として扱うものではない、と思う
では、「激しさ、止むことのない」鳴沢の譬と、
「深々と、静かに降り続く」雪の譬は、どう繋がるのだろう
同じ想いを詠ったとすれば、表現こそ違っていても、必ず共通するものがあるはずだ
一見して、「動と静」の違いを見せる「本歌と一本歌」
逢ったのは、玉を貫く短い緒にさえも及ばないほどなのに、
この恋心は、富士の高嶺に降り続ける雪のようだ
この「富士の高嶺に降り続く雪のよう」という意味、
それが、「激しさ」ではなく「深々とした静けさ」であるべきなのに
どうしても、「類想歌」とならなければならないとしたら...
こんな表現がある、
「寝ても覚めても」、「年がら年中」、「何があっても」...「四季を通じていつも」
これらも、「激しくも、止むことなき想い」だ
ならば、本歌でいう「なるさはのごと」が、噴火の名残をいい、
「降る雪」は、どんなにかそれを鎮めようとしても、決してそれを収めることはできない
しかし、それでも「止むことなく」雪は降り続く
言ってみれば、富士の高嶺の「鳴沢」が、収まるまでは何があろうと降り止まぬ雪
止むことのない降雪
この「降雪」が、ことさら「想い」の継続性を見せてくれるのは、
何といっても、激しさを残す富士の高嶺の「鳴沢」があるからこそではないか
こうして考えてみれば、「本歌」と「一本歌」は、「異伝歌」ではなく
この二首で、想いをいっそうの強さで表現している
例えば、古今和歌集の一首
| 「古今和歌集」巻第十三 恋歌三 |
題しらず 読み人しらず
|
| 六七三 あふことは 玉の緒ばかり 名の立つは 吉野の川の たぎつ瀬のごと |
この歌などは、ほんの少ししか逢っていないのに、
世間の噂になってしまって、その大きさと言ったら、
まるで吉野川の、激しい流れのようだ、という
掲題歌に擬えてみると、
束の間の逢瀬なのに、噂だけは「鳴沢」のようだ、と言える
ここに、その「噂」を打ち消そうとする「降る雪」があるが、
それでも、手に負えず、「噂」が収まらないように、
それを打ち消そうとする「降雪」も、続かざるを得ない
そうやって、「古今和歌集」には詠わない「続編」が、
この掲題歌では、「一本歌曰」として続いている
掲題歌の三首、「或本歌」はその流れに沿わないが、
「本歌」と「一本歌」の二首は、「想いの相乗効果」的な響き合いがあると思えてくる
|
|
掲載日:2015.05.02
| 巻第十四 3372 東歌相聞 作者不詳 |
| 東歌相聞 |
| 佐奴良久波 多麻乃緒婆可里 古布良久波 布自能多可祢乃 奈流佐波能其登 |
| さ寝らくは玉の緒ばかり恋ふらくは富士の高嶺の鳴沢のごと |
| さぬらくは たまのをばかり こふらくは ふじのたかねの なるさはのごと |
| (右五首駿河國歌) |
| 或本歌曰 3373 |
| 麻可奈思美 奴良久波思家良久 佐奈良久波 伊豆能多可祢能 奈流佐波奈須与 |
| ま愛しみ寝らくはしけらくさ鳴らくは伊豆の高嶺の鳴沢なすよ |
| まかなしみ ぬらくはしけらく さならくは いづのたかねの なるさはなすよ |
| 一本歌曰 3374 |
| 阿敝良久波 多麻能乎思家也 古布良久波 布自乃多可祢尓 布流由伎奈須毛 |
| 逢へらくは玉の緒しけや恋ふらくは富士の高嶺に降る雪なすも |
| あへらくは たまのをしけや こふらくは ふじのたかねに ふるゆきなすも |
| 【3372】 語義 意味・活用・接続 |
| さぬらくは [佐奴良久波] |
| さ [接頭語] |
[注記] |
| ぬ [寝(ぬ)] |
[自ナ下二・終止形] 眠る・場面や文脈によっては男女の共寝する |
| らく [接尾語] 上代語 |
[注記] |
| たまのをばかり [多麻乃緒婆可里] |
| たまのを [玉の緒] |
玉を貫く紐・期間の短い事のたとえ、少し、しばらく・命 |
| ばかり [副助詞] |
[程度・範囲] ~くらい・~ほど |
| こふらくは [古布良久波] |
| らく [接尾語] 上代語 |
上接の語を名詞化する |
| ふじのたかねの [布自能多可祢乃] |
| たかね [高嶺・高根] |
高い峰 |
| なるさはのごと [奈流佐波能其登] |
| なるさは [鳴沢] |
[注記] |
| ごと [助動詞・ごとし] |
[比況・語幹] ~のように・~のようだ [注記] |
| 【3373】 |
| まかなしみ [麻可奈思美] |
| ま [接頭語・真] |
(名詞・形容詞などに付いて)真実・正確・純粋・称讃・強調などの意
〔例語〕真心・真かなし・真木・真清水など |
| かなし [愛し] |
[形容詞シク・終止形] かわいい・いとおしい |
| み [接尾語] |
[ミ語法] ~ので・~から 〔接続〕形容詞シクの終止形に付く |
| ぬらくはしけらく [奴良久波思家良久] |
| ぬ・らく |
上出 |
| し [為] |
[他サ変・連用形] ある動作を行う・ある行為をする |
| けら [助動詞・けり] |
[過去(回想)・未然形] ~た・~たのであった |
連用形に付く |
| く [接尾語] 上代語 |
上接の語を名詞化する |
| さならくは [佐奈良久波] |
| さ [接頭語] |
[上出] |
| ならく [鳴る] (ク語法) |
[自ラ四「なる」・未然形「なら」+「ク語法」] 鳴り響くこと |
| いづのたかねの [伊豆能多可祢能] 諸説あるが、天城山が有力 |
| なるさはなすよ [奈流佐波奈須与] |
| なす [接尾語] 上代語 |
~のように・~のような |
| よ [間投助詞] |
[詠嘆・感動] ~よ |
種々の語に付く |
| 【3374】 |
| あへらくは [阿敝良久波] |
| あへ [逢ふ] |
[自ハ四・已然形] 出逢う・逢う |
| ら [助動詞・り] |
[完了・未然形] ~ている・~てしまった |
已然形に付く |
| く [接尾語] 上代語 |
[上出] |
| たまのをしけや [多麻能乎思家也] |
| しけ [及く・若く・如く] |
[自カ四・已然形] 及ぶ・匹敵する |
| や [終助詞] |
[反語] ~(だろう)か(いや、~でない) |
| こふらくは [古布良久波] 上出、恋することは |
| ふじのたかねに [布自乃多可祢尓] |
| ふるゆきなすも [布流由伎奈須毛] |
| なす [為す・成す] |
[他サ四・連体形]行う・する・あるものを他のものの代わりに用いる |
| も [接続助詞] |
[逆接の仮定条件] ~としても・~ても |
連体形に付く |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【3372 注記】 |
[接頭語「さ」]
① 名詞・動詞・形容詞に付いて、語調を整えたり意味を強めたりする
〔例語〕
さ霧・さ鳴る・さ寝(ぬ)・さまねし・さ身・さ乱る・さ百合・さ夜・さ青(を)・さ小舟(をぶね)
② 名詞に付いて、「若々しい」の意を添える
〔例語〕
さ苗・さ乙女(をとめ)
「参考」①には「小」、②には「早」をあてることが多い
[接尾語「らく」]
上代語の接尾語「らく」の用法は三つ
① ~することの意
② (連用修飾語になる) ~することには
③ 文末にあって詠嘆を表す・~することよ
古語辞典の「文法参考」では、次のように述べ、
| 上代の接尾語「らく」 |
形の上では、上二段・下二段・か行変格・サ行変格・ナ行変格活用動詞の終止形、上一段活用動詞の未然形と考えられた形に付く。また助動詞「しむ・つ・ぬ・ゆ」などの終止形と考えられた形にも付く。
上接の語を名詞化するはたらきがあり、中古以降は「おそらく・老いらく」などの語にいわば化石化されて残り、現代にいたっている。接尾語「く」と補い合い、四段・ラ変の動詞、形容詞、助動詞「けり・り・む・ず」などには、「く」が付いて名詞化する。この「らく」と「く」との複雑な接続を統一的に説明するため、接尾語の「あく」という語を想定して、上の語の連体形にこれが付いたとみる説がある |
また、有斐閣「万葉集全注巻第十四」では、詳しく解説する
| 「万葉集全注巻第十四」「らく」について 水島義治 |
| 「らく」は「く」と同じく準体助詞。ただし、「く」が四段・ラ変の未然形、形容詞「-ケ・-シケ」の形(やはり未然形)および助動詞「り」の未然形と、「ず・む・けり」の、それぞれの古形未然形(「な・ま・けら」)、「き」の連体形に付く〔散らく・有らく・/安けく・惜しけく/(逢ひ)らく/(鳴か)なく・(散ら)まく・(言ひ)けらく/(思ひ)しく〕のに対して、「らく」は上一段の未然形と上二段・下二段・カ変・サ変および助動詞「しむ・ゆ・つ・ぬ」などの終止形に付く〔見らく/恋ふらく・老ゆらく・来らく・ずらく/(思は)しむらく・(思ふ)ゆらく・(かざし)つらく・(更け)ぬらく〕。このように、「く」と「らく」は接続の仕方は異なるが、「こと」という意味を表す点は同じである。普通は上接の活用語を体言化する接尾語として扱われているが、もし接尾語とすれば、これが付いた、「恋ふらく」なり「有らく」なりを一語の体言と認めなければならぬことになる(言うまでもなく、接尾語という品詞は存しない)ので、語法的処理としては、「く」「らく」を一つの助詞として扱い、これを準体助詞とすることが穏当であろう。活用語に「く」「らく」の付いた形を「ク語形」、またそのような語法を「ク語法」という。 |
[たまのを]
玉と玉との間に見える細い紐の短さから、ごく短いことの譬えに用いられる
また、「命」のことをも言うのは、
玉を首にかけて魂を身に繋いでおく緒の意からのものだ、という
[副助詞「ばかり」]
動詞「計る」の名詞形「ばかり」が基
おおよその「範囲・程度」の「~ごろ・~ぐらい・~ほど」や、
「限定」の「~だけ・~だけだ・~にすぎない」など
〔接続〕
「範囲・程度」を表すときは終止形に付き、「限定」を表すときは連体形に付くことが多い
[なるさは]
この「なるさは」の現代表記「鳴沢」は、
よく知られる「鳴き砂」のようなイメージがあり、
この結句「なるさはのごと」は、まさに「沢が鳴り止まないようだ」、と言うのだろう
比況の助動詞「ごとし」の語幹が文末で終る用法は、珍しいらしい
「なるさはのごと」で検索してみると
次のように、いろいろな歌集で収載されてはいるものの、掲題歌と并せ三首しかない
| 掲題歌本歌「なるさはのごと」七集 |
和歌童蒙抄第三「地儀部・沢」、
五代集歌枕上「九 沢 なるさは 駿河」、
袖中抄第七、和歌色葉中巻、色葉和難集第七、
歌枕名寄巻第廿「駿河国 鳴沢」
雲玉集「恋部」 |
掲題歌或本歌曰 小異歌「なるさはのごと」二集
まかなしみぬよらくはしけよらくさなよふくは伊豆のたかねのなるさはのごと
|
袋草紙下巻、
袖中抄第七、
|
したむせぶ思ひをふじの煙にて袖のなみだはなるさはのごと 二集
|
瓊玉和歌集巻第八「恋歌下」、
柳葉和歌集巻第四 「恋」、
|
これらから、「鳴沢」という称名が、
「駿河国」もしくは「富士山」を眺望できる所と関係があることは想像がつく
そして、「なるさはのごと」を端的に古注釈書の類でも、現代の注釈書でも、
地名ではなく、激しく流れる渓谷の「鳴り止まぬ」表現として解釈している
上表の中に、室町時代後期の歌集「雲玉集」があるが、
この歌集は、古くは「万葉集」の歌などの注釈も試みた特異な歌集として知られ、
この掲題歌についても、次のように書いている
雲玉集(衲叟馴窓編)
三八八 さぬらくは玉のをばかりこふらくは富士の高ねのなるさはのごと
|
さぬらくは、すこしねたる事なり、玉のをは、みじかきなり、なるさはは、おびたたしき事なり、雪の消えて春夏のころ、さはのごとくおつる意なり、在所は北の麓なり、なるさと申すは、いさごの事なり、俊成卿の歌に、さみだれは高ねも雲のうちにしてなるさぞふじのしるしなりける、とよみ給ひしを、なるさはを下略してなるさとばかりよめるとて、その比なるさの大夫と名をつけて天下一の感応人をだにわらひし、俊頼朝臣又作者に一人の名をとられし人をも玉ぐしのはの歌により、みがくれのすけと申せしとかや、万葉以来の歌仙たちいづれも一のあやまりみな悉くしるしたる事はあれど、俊成卿つひにあやまりなしと申す人をもあだなをつけ奉りし、まして此比の事よき名はとらじ、せめてはぢをもかきて世に名を聞えばやと存ずれども、その恥をまことにたださん人おぼつかなし、片掌声無と申せば、かたてをふらば人ききつけんや、うしろ事をば申すなれど、その友にあふ時は秘しつつみて、やうありげになずらへぬれば何の曲かあらむ、なれば思ひつづけてしるしおき申すをや富士のかぐや姫の事、日本記注に欽明天王、詞林最要には桓武天王、何れも不審に存ずる、欽明は聖徳太子の御祖父、かの姫と契りて後思ひにしづみ給ひし、不死の薬やけしより内院の煙たつと申す、太子、黒駒にめして彼山にのぼり御あとを問見給ひし、
赫姫内院へ帰りて御門へ不死薬まゐらせ給ふ時、御歌
三八九 今はとてあまのはごろもきる時ぞ君をあはれとおもひいでぬる
-以下略-
|
この歌集、私の理解が十分ではなく、
この後にもまるで物語風に和歌を繋げているかのように思える
それは、もっとじっくり考えたいものだが、取り敢えず「室町時代後期」の歌壇では、
「なるさは」を、上述のように考えている
また、「なるさ」を「いさご」とか...「いさご」は、「砂」のこととある
そして現代で解釈されている、この掲題歌の「なるさは」という実体は、
大体次の三つに分かれての解釈になっている
これも、有斐閣「万葉集全注」の注釈から引用する
| 「なるさは」(鳴沢/奈流佐波) [万葉集全注巻第十四 水島義治] |
| 〔イ〕轟き流れる渓流・渓谷 |
「万葉集新考」 井上通泰 大正4年~昭和2年成
「万葉集全釈」 鴻巣盛広 昭和5年~10年成
「万葉集全註釈」 武田祐吉 昭和23年~25年成
「万葉集私注」 土屋文明 昭和24年~31年成
「万葉集注釈」 澤潟久孝 昭和32年~37年成
「万葉集全訳注」 中西進、講談社文庫 昭和58年成
「万葉集全注巻第十四」 水島義治、有斐閣 昭和61年成
「新日本古典文学体系『万葉集』」 岩波書店 平静15年成
|
| 〔ロ〕富士山頂の噴火口 |
「仙覚抄」 仙覚 文永六年(1269)成
「万葉集管見」 下河辺長流 寛文年間(1661~1673)成
「万葉代匠記」 契沖 初稿本貞亨四年(1687)、精撰本元禄三年(1690)成
「万葉集童蒙抄」 荷田春満 享保年間(1716~1735)成
「万葉考」 賀茂真淵 宝暦十年(1760)成
「万葉集略解」 橘千蔭 寛政十二年(1800)成
「万葉集古義」 鹿持雅澄 天保十三年(1842)成
「万葉集評釈」 窪田空穂 昭和18年~27年成
|
| 〔ハ〕富士山の大沢崩れ 『大日本地名辞書』の影響(左頁で触れてみたい) |
「評釈万葉集」 佐佐木信綱 昭和23年~29年成
「日本古典文学大系『万葉集』」 岩波書店 昭和37年成
「日本古典文学全集『万葉集』」 小学館 昭和50年成
「新潮日本古典集成『万葉集』」 新潮社 昭和51年~59年成
|
こうして解釈の流れを見ていると、古くは「富士山の噴火口」説が主流であったものが、
近現代では、「沢の轟き流れる激しさ」や、富士西側の剣ヶ峰と雷岩の間の崩壊谷のこと、など
その解釈は、ある方向へ進みながらも、決してこのようにはっきりとは色分けできないものだ
古説の「富士の噴火口」にしても、その激しさに主眼を置けば無理はないし、
「轟き流れる渓谷」や「大沢崩れ」の凄まじさもまた、「恋の想い」の譬えに、おかしくはない
[助動詞「ごとし」の語幹「ごと」]
その接続は、体言および副詞「かく」「さ」に助詞「の」が付いたものや、
活用語の連体形および代名詞「吾(あ)」「我(わ)」に助詞「が」が付いたものに付く
〔参考〕
連用修飾語として、連用形「ごとく」が使われるが、
中古の和文調の文章では、「ごとく」はあまり用いられず、
語幹だけの「ごと」が多く用いられた
〔例〕
「前栽の露は、なほかかる所も同じごときらめきたり」<源氏物語・夕顔>
(植え込みの草木の露は、やはりこんな所でも、同じように光り輝いている)
|
| 【3373 注記】 |
|
[かなし]
この「かなし」の原義は、「古語辞典」によると
人事に対しては、情愛が痛切で胸がつまる感じ、
自然に対しては、深く心を打たれる感じを表すもの、とある
「かわいがる」意のサ変動詞「かなしうす」「かなしくす」、
「かわいいと思う・悲しく思う」意の四段動詞「かなしがる」「かなしぶ」「かなしむ」は派生語
表記される「漢字」では、「愛し」、「悲し・哀し」がある
当然、「かわいい・いとおしい」の意であれば「愛し」と表記し、
「かわいそうだ・心がいたむ」の意であれば「悲し・哀し」と表記される
[接尾語「み」]
接尾語「み」には、幾つかの用法があるが、
この歌では、「~(名詞)を~み」で、原因・理由「~ので・~から」に当る用法だと思う
ただし、初句の「まかなしみ」では、「~(名詞)を」に当る語句が省かれているが、
それは容易に「いもを」と補えることができるからだと思う
形容詞及び形容詞型の助動詞の語幹(シク活用には終止形)に接続する
[接尾語「く」]
上述の接尾語「らく」とも重複するが、その接続に違いがある
| 上代の接尾語「く」 |
形の上では、四段・ラ変動詞の未然形、形容詞の古い未然形語尾「け・しけ」の形に付く。また助動詞「けり・り・む・ず」の未然形と考えられた形に付き、「けらく・らく・まく・なく」となり、「き」の連体形「し」に付き「しく」などとなる。
上接の語を名詞化するはたらきがあり、中古では、「いはく」「思はく」などの特定の語として残り、いわば化石化され現代にも至っている。接尾語「らく」と補い合い、四段・ラ変以外の動詞には、「らく」が付いて名詞化する。この「く」と「らく」との複雑な接続を統一的に説明するため、「あく」という語を想定して、上の語の連体形にこれが付いたとみる説がある |
[接尾語「なす」]
名詞、まれに動詞の連体形に付く
〔例語〕
朝日なす・巌(いはほ)なす・垣穂(かきほ)なす・木屑(こつみ)なす・獣(しし)なす・着くなす(着くように)・翼なす・常磐なす・錦なす・真珠(またま)なす・水鴨(みかも)なす・水沫(みなわ)なす・雪なす・行くなす
〔参考〕
枕詞とみられる以下の語の「なす」も同類と考えられる。「朝日なす」などは枕詞ともみられ、
その境界ははっきりしない
馬酔木なす・入り日なす・鶉なす・績み麻(うみを)なす・鏡なす・雲居なす・五月蝿(さばへ)なす・玉藻なす・泣く子なす・闇夜なす |
【3374 注記】
[特になし] |
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」(今日の歌には無し)]
【3372・3373・3374】
[本文]「佐奴良久波 多麻乃緒婆可里 古布良久波 布自能多可禰乃 奈流佐波能其登」 (右五首駿河歌)
「サヌラクハタマノヲハカリコフラクハフシノタカ子ノナルサハノコト」(「【】」は編集) |
| 頭注 |
「類聚古集」本文ノ下ニ小字「駿河」アリ。
「袖中抄」第七「サヌラクハタマノヲハカリコフラクハフシノタカ子ニナルサハノコト」
「和歌童蒙抄」第三「サヌラクハタマノヲハカリコフラクハフシノタカ子ノナルサハノコト 万葉十四ニアリ」
|
| 〔本文〕 |
| 婆 |
『大矢本』「波」。
|
| 古 |
『西本願寺本』「右」。直シテ「古」トセリ。
|
[本文]「或本歌曰 麻可奈思美 奴良久波思家良久 奈良久波 伊豆能多可禰能 奈流左波奈須與」 (右五首駿河歌)
「 マカナシミヌラクハシケラクナラクハイツノタカ子ノナルサハナスヨ」(「【】」は編集) |
| 頭注 |
「類聚古集」訓ヲ附セズ。
「西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本」訓ヲ朱書セリ。
「袖中抄」第七「万葉或本哥云 マカナシミヌラクハシケ、〇クサヌラクハイツノタカ子ノナルサハノコト」 |
| 〔本文〕 |
| 或 |
『京都大学本』赭ノ合點アリ。
|
| 波 |
『細井本・活字無訓本』ナシ。
|
| 久 |
『類聚古集・西本願寺本・細井本・神田本・温故堂本・大矢本・京都大学本・活字無訓本』コノ下「佐」アリ。
|
| 左 |
『類聚古集・西本願寺本・神田本・温故堂本・大矢本・京都大学本』「佐」。
|
| 〔訓〕 |
| ヌラクハシケラク |
『細井本』「ヌラクシケラク」。
|
| ナラクハ |
『西本願寺本・細井本・神田本・温故堂本・大矢本・京都大学本』「サナラクハ」。
|
| ナルサハナスヨ |
『京都大学本』「ナルサハノスヨ」。
|
| 〔諸説〕 |
〇[万葉考]コノ歌削ル。〇奴良久波思家良久 奈良久波、ヌラクハシケラクナラクハ[万葉集古義]「奴良久波」ノ「波」ハナキヲ可トシ、「家」ハ「末」ノ誤トス。訓「ヌラクシマラクサナラクハ」。
|
[本文]「一本歌曰 阿敞良久波 多麻能乎思家也 古布良久波 布自乃多可禰爾 布流由伎奈須毛」 (右五首駿河歌)
「 アヘラクハタマノヲシケヤコフラクハフシノタカ子ニフルユキナスモ」(「【】」は編集) |
| 頭注 |
「類聚古集」訓ヲ附セズ。
「西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本」訓ヲ朱書セリ。
「袖中抄」第七「万葉或本哥云(中略)又一本云 アヘラクハタマノヲシケヤコフラクハフシノタカ子ニフルユキノコト」 |
| 〔本文〕 |
| 一 |
『京都大学本』赭ノ合點アリ。
|
| 歌 |
『類聚古集』ナシ。
|
| 敞 |
『細井本・大矢本』「敝」。
|
| 〔諸説〕 |
〇[万葉考]コノ歌削ル。〇阿敞良久波[万葉集略解]「敞」ハ「敝」ノ誤。
|
|
|
 |
| 【歌意3375】 |
駿河の海の磯辺に、あんなにしっかりと生えている「はまつづら」のように、
私はあなたを、心から頼りにしているのです、
そのために、私は逢うことも許してくれない母の心に、背いてしまいました
〔一に云う「親に背いてしまった〕
|
| 遊び心で【歌意3375】改 |
駿河の海の磯辺、まるでそこの岩場に守られて、輝くように美しく、
その見映えの良い「はまつづら」のように、母の心優しい想いの中で育った私、
今は、こんなにもあなたを信頼し、心を寄せているのです
母親に、これほど反対されながらも...
|
| |
「磯辺」と言うのは、「浜辺」と違い、石や巌の多い荒々しい岸辺をイメージさせる
そこに生える「はまつづら」と言うのは、そこに強固にしがみつく「蔓」を言うのだろうか
母親の意に背いてまで、愛しい男との恋の成就を願った女の歌
「はまつづら」という植物、その実体は諸説があるようで、私には分からないが
海岸の「砂地」に多く生える、「ハマゴウ」、「ハマハヒ」とか
あるいは、たんに海岸に生えている「蔓草」を言うものなのか、など...
この上三句が、序詞とされているなら、当然次句に影響させなければならない
その及ぼすものが、「母の言いつけに背いてまでも、あなたを信じて」となるので
ならば、「はまつづら」の意味するところは、
その「作者の心」ということになる
そして、「ははにたがひぬ」のだから、よほどの「葛藤」があったのだろう
その葛藤は、どんな表現で詠われているのだろう、とやはり気になるのが、
「磯辺」と「「はまつづら」だ
「はまつづら」のように、強固に...石や巌に寄り添って...
実際、「はまつづら」が、「砂浜」ではなく、「磯辺」のごつごつした場所であれば、
その心地良いはずの「母親の庇護」の下にいる娘の環境が、いっそう理解し易い
その母親の元を離れことになり、こうした険しい「磯辺のはまつづら」になりたい、と
その意味では、「磯辺」と「浜辺」は、はっきりと区別された方がいい
波打ち際を、総じて「浜辺」ということもあるだろうし、
「はまつづら」という名の、曖昧な植物にしても、
確かに、実景を思い浮かべるのは、少なからず現代的な感覚に頼らざるを得ないが
荒々しい石や巌の多くある岸辺に、「蔓草」のしっかり這い広がる姿こそが、
上二句の、それほど母親から「許される恋」と猛反対されている「心の姿」だ
また母親に「守られ、大切にされて育った」環境を際立たせるものだ
そんな自分の置かれている環境でも、あなたのことを忘れられません、
母親に、反対されても、この「磯辺のはまつづら」のように
私はあなたを信じてついていきたい
この女の心が、通釈としての一途な恋心を、母の意に背いてまでとする歌意解釈になる
しかしここで、滅多にしないことだが、一つの試みをしてみた
右頁の「注記」にも書いたように、この歌をもう少し脚色させることを思いついた
勿論、オリジナルを蔑ろにするのではなく、あくまでも「可能性」として、との「遊び心」だ
よく古注釈書などに見る、「万葉集」の本格的な「注釈」には、
それまで十分な研究資料がないこともあって、随分と「誤字・誤写」説が見かけられる
確かに、研究資料のベースが乏しければ、一体何が正しいものなのか、
その判断は、なかなか難しいものだ
さすがに現代に至っては、そうした「誤字・誤写」説を新たに用いることはほとんどないが
この掲題歌、素人だからこそ、気づいたことだと思う
それは、第二句の「おしへにおふる」だ
この解釈は、まず間違いなく、通釈のように「磯辺に生えている」だろう
ただ、この「音」だけを頼りに「訓」むと、「おしへにほふる」も有り得るのでは、
そう思ってしまった
「音」の「~におふる 尓於布流」と「にほふる 尓保布流」の、
「格助詞(に)+動詞(生ふ)」を「動詞(にほふ・匂ふ)」とするには、
「於」が「保」の誤写もしくは誤字でなければならない
「匂う」の万葉表記には「尓保布/仁保布/薫/丹保布/丹穂經/丹覆/仁寶布」があり
この「保」の一時違いで、語意が変わる
その基本的には、ないはずの「誤字」を、当てはめてみると、
こんな歌意解釈になると思う
| 遊び心で【歌意3375】改 |
駿河の海の磯辺、まるでそこの岩場に守られて、輝くように美しく、
その見映えの良い「はまつづら」のように、母の心優しい想いの中で育った私、
今は、こんなにもあなたを信頼し、心を寄せているのです
母親に、これほど反対されながらも...
|
「本歌」と、勝手な「誤字」説を用いた「改」での大きな違いは、
「はまつづら」の用い方にある
「本歌」の「はまつづら」は、「作者の男への強固で一途な気持ち」の表現であり、
「改」の「はまつづら」となると、「母親に愛され育まれた慈しみの環境」の表現になる
勿論、こんな試みなど無用なことなのだが、ふと思った
これまで、多くの古注釈書で、「これは何々の誤字、誤写」という表現に出合うと、
そんなに根拠も十分でないのに、感じ方だけで言い切れるのだろうか、という疑問
しかし、たまたまこの掲題歌のように、声に出して読んでいると、
あれ、「にほふる」でも、歌意に矛盾はないぞ、と思ってしまった
なるほど、古人の言う「誤字・誤写」説と言うのは、
この私が感覚的に抱いたよりも、もっと深いところで感じ取ったものなのだろう
そして、試みに解釈してみる
それが、無理のないことであれば、さらに検証をして「誤字・誤写」説を唱える
確かに、私のようなレベルでははるかに及ばないものの、
一概に「誤字・誤写」説の選択も否定はできないものだ、と少しは理解出来た
この掲題歌に数日間触れていると、また寄り道の中で、こんな歌に出合った
| 万代和歌集巻第九 恋歌一 法橋顕昭 |
不逢恋といふことを
|
一八四九 あふことはさてもなぎさのはまつづらくるにつけてぞ袖はぬれける
|
| 万代和歌集巻第十二 恋歌四 法橋顕昭 |
遇不逢恋のこころを
|
二三九九 いきてなぞのちのつらさをなげくらむあふにかへてしいのちならずや
|
〔1849〕歌は、「はまつづら」を調べていて出合った歌だ
その題詞の「不逢恋」、これは「逢はざる恋」というのか「逢はずて恋」と言うのか...
ここでの「「なぎさのはまつづら」もまた、気になるところだが、今回は手が回らない
そして〔2399〕歌、「遇不逢恋」は、「遇ひて逢はざる恋」と訓む
これは、一度は逢ったものの、それ以降逢うことが困難になった恋心という
ならば「不逢恋」は、一度も逢っていないで、恋をしてしまった、ということなのだろうか
〔2399〕歌の下二句、「逢うことと引き換えに、捨てた命じゃないか」という語句は、
私の好きな「古今和歌集友則歌」の
「命やはなにぞは露のあだ物を逢ふにしかへば惜しからなくに」を彷彿させ、
こうした言い回しが、恋歌としてよく用いられていることが分かる
|
|
掲載日:2015.05.08
| 巻第十四 3375 東歌相聞 作者不詳 |
| 東歌相聞 |
駿河能宇美 於思敝尓於布流 波麻都豆良 伊麻思乎多能美 波播尓多我比奴
[一云 於夜尓多我比奴] |
| 駿河の海おし辺に生ふる浜つづら汝を頼み母に違ひぬ [一云 親に違ひぬ] |
するがのうみ おしへにおふる はまつづら いましをたのみ ははにたがひぬ
[おやにたがひぬ] |
| (右五首駿河國歌) |
| 【3375】 語義 意味・活用・接続 |
| するがのうみ [駿河能宇美] 現在の駿河湾・駿河は静岡県中、東部を占める旧国名 |
| おしへにおふる [於思敝尓於布流] |
| おしへ [磯辺(いそへ)] |
「磯」は、石・巌の多い岸 |
| おふる [生ふ] |
[自ハ上ニ・連体形] 生ずる・はえる・生長する |
| [にほふる〔匂ふ〕] |
[自ハ四・連体形] 注記 |
| はまつづら [波麻都豆良] 浜辺に生える蔓草 |
| いましをたのみ [伊麻思乎多能美] |
| いまし [汝] 上代語 |
[対称の人代名詞] あなた・おまえ |
| たのみ [頼む] |
[他マ四・連用形] 頼みにする・あてにする・信用する・信頼する |
| ははにたがひぬ [波播尓多我比奴] |
| たがひ [違ふ] |
[自ガ四・連用形] くい違う・背く・従わない |
| ぬ [助動詞・ぬ] |
[完了・終止形] ~てしまう・~てしまった |
連用形に付く |
| [おやにたがひぬ 〔一云 於夜尓多我比奴〕] |
| 一に云う 親に背いてしまった |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【3375 注記】 |
[おしへ]
「磯辺(いそへ)」の東国訛りとして、
「おしへ」、「おすひ」が、それぞれ一首ずつ「万葉集」に詠われている
「おしへ」は、掲題歌で、「おすひ」は、同じ巻第十四「東歌相聞下総国」一首
| 万葉集巻第十四 東歌相聞 3403 下総国 |
可豆思賀能 麻萬能手兒奈我 安里之可婆 麻末乃於須比尓 奈美毛登杼呂尓
|
| 葛飾の真間の手児名がありしかば真間のおすひに波もとどろに |
かづしかの ままのてごなが ありしかば ままのおすひに なみもとどろに
|
| (右四首下総國歌) |
「おしへ」の場合は、母音が前後入れ替わる形があるようで、その例として、
| 万葉集巻第十四 東歌相聞 3513 下総国 [目録 未勘国相聞往来歌百二十首寄物陳思] |
於曽波夜母 奈乎許曽麻多賣 牟可都乎能 四比乃故夜提能 安比波多我波自
|
遅速も汝をこそ待ため向つ峰の椎のこやでの逢ひは違はじ
|
おそはやも なをこそまため むかつをの しひのこやでの あひはたがはじ
|
この「こやで」は「小枝(こえだ)」のやはり東国訛りらしい
「おしへ」に共通するのは、母音の前後入れ替わりで、
「osife→isofe」と「koyade→koyeda」となる
ただし、「おすひ」には当てはまらないようだ
「おすひ」を古語辞典で引くと、一般的な「おすひ」は、
「おすひ(襲)」と書いて、
上代の衣服の一種、頭からかぶって衣服の上から全身を包むようにらした長いきれ、
とある
このことに、それらしく言及した注釈書は唯一武田祐吉の「万葉集全註釈」だけだ
| 「万葉集全註釈」武田祐吉 昭和23~25年成 |
[於思敝尓於布流 オシベニオフル]
オシベはオスヒベで、礒邊であろう。オスヒは、ある上に重ねる意である。「麻末乃於須比爾[ママノオスヒニ] 奈美毛登杼呂爾[ナミモトドロニ]」(卷十四、三三八五[旧番号])。
|
このように、記述の〔3403〕歌を引き合いに出して、
「おしべ→おすひべ→おすひ」を導き、また「おすひ」については、
まさに古語辞典に収録されている「襲(おすひ)」の語意そのものをイメージさせる
「磯(いそ)」には、石や巌の多い岸、という意味があるが、
その「磯辺」と言うのは、数多く重ねるように「石や巌」がある「岸辺」と言うことだろうか
「浜辺」が、海や湖に沿った「平地」に対する「語」だと思う
「万葉集」には、約二百四十首の「東歌」が収載されているが、
「磯辺(いそへ)」の東国訛りとして「おしへ」、「おすひ」がこの二首だとすれば
それは、他の資料からの手掛かりだろう
「東歌」に限らず、「万葉集」全歌中でも、他には見つけられない
そればかりか「いそへ」もしくは「いそべ」もまた、「万葉集」では詠われていない
それが、私には意外に思えた
だとすれば、「万葉の時代」には、後の「いそへ」ではなく、
「おしへ」や「おすひ」が、現代で言う「磯辺」を言った可能性もあるのでは、と思う
[〔参考「にほふる」〕]
この歌での第二句「おしへにおふる」は、その表記「於思敝尓於布流」から、
「磯辺に生ふる」、磯辺に生える」となるのが当然だが、
ここで、少し遊び心を持って、古注釈書によく見られる「誤写説」を試みた
「於」を「保」の誤写として、この第二句を訓釈すると、「磯辺匂ふる」になる
この「匂ふ」の語意は、次のようになる
① 草木などの色に染まる・美しく染まる
② つややかに美しい・照り輝く
③ 栄える・恩恵や影響が及ぶ
④ かおる・香気がたたよう
「にほふ」の原義は、「丹(に・赤い色)」「秀(ほ・物の先端など抜き出て目立つところ)」に、
「ふ(動詞化する接尾語)」で、
赤い色が表面にあらわれ出て目立つ意味をいう
従って、「視覚的」に感じるのが、本来の意味だ
この掲題歌に「磯辺に生ふる」と通釈で味わうのは必要なことだが、
仮に強引な誤写説を用いて...もっとも、誤写説、というのは、強引なものだが...
「磯辺匂ふる」としても、歌意解釈が楽しめそうだ
|
 |
| |
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」(今日の歌には無し)]
【3375】
[本文]「駿河能宇美 於思敝爾於布流 波麻都豆夜 伊麻思乎多能美 波播爾多我比奴 [一云 於夜爾多我比奴] (右五首駿河歌)
「スルカノウミオシヘニキフルハマツヽライマシヲタノミハハニタカヒヌ [一云 オヤニタカヒヌ] |
| 頭注 |
「類聚古集」本文ノ下ニ小字「駿河」アリ。
「古葉略類聚鈔」主文ヲ訓交リニ書ケリ。下二小字「駿河」アリ。 |
| 〔本文〕 |
| 駿河能宇美 |
『古葉略類聚鈔』以上訓ヲ主文トセリ。
|
| 敝 |
『類聚古集・古葉略類聚鈔・西本願寺本・細井本・神田本・温故堂本・大矢本・活字無訓本』「敞」。
『京都大学本』「倍」。
|
| 於布流 波麻都豆良夜 |
『古葉略類聚鈔』以上訓ヲ主文トセリ。
|
| 夜 |
『類聚古集・西本願寺本・細井本・神田本・温故堂本・大矢本・京都大学本・活字無訓本』「良」。
|
| 波播爾多我比奴 |
『古葉略類聚鈔』以上訓ヲ主文トセリ。
|
| 一云於夜爾多我比奴 |
『類聚古集・古葉略類聚鈔・西本願寺本・細井本・神田本・温故堂本・大矢本・京都大学本』以上小字トセリ。
|
| 奴 |
『古葉略類聚鈔』訓ヲ主文トセリ。
|
| 〔訓〕 |
| オシヘニオフル |
『類聚古集』「をしへにおふる」。
『古葉略類聚鈔』「ヲシヘニヲフル」。
『神田本』「ヲシヘニオフル」。
|
| オヤニタカヒヌ |
『類聚古集』ナシ。
『古葉略類聚鈔』「オヤニタカヒ」ナシ。
『西本願寺本・大矢本・京都大学本』以上七字朱書セリ。
『西本願寺本』「ヲヤニタカヒヌ。 |
| 〔諸説〕 |
| 〇波麻都豆夜[代匠記初稿本]「夜」ハ「良」ノ誤。〇一云[万葉考]「一云於夜爾多我比奴」ノ九字削ル。 |
|
|
 |
| 【歌意3376】 |
伊豆の海に、立つ白波のように、
絶え間なく途切れずに想っていこうとしているのに、
だから、あなたの心を乱れさすことなどあるだろうか、いやないだろう
|
| 或る本の歌に曰はく |
(伊豆の海に湧き立つ)白雲のように、途絶えながらも、
それでも想い続けていこうと思うからからでしょうか、
それで、こんなにも心が乱れ始めてしまったのでしょうか
|
| |
まず、この「別伝」との関係に、とても興味を引かれた
本来、左注に述べる「或本歌曰」と言えば、この歌は、こうとも伝わっている、というように、
収載歌そのものに、別な語句を用いた伝誦があることをイメージする
しかし、それであっても、同じ歌であることには変わりなく、
単に「伝わり方の違い」というに過ぎないものだ
この掲題歌と「或本歌」の場合は、私にはどうしても「同じ歌」の「異伝」には思えなかった
しかし、5月13日付けの「一日一首」で、私は次のように書いた
| 「一日一首」2015年5月13日記事 |
-略-
しかし、「万葉集」では、その出典が明らかでない「或本歌」とか「一本歌」も多い
少々懐疑的な見方をすれば、この掲題歌も、
「いづのうみに たつ」までがよく使われる語句で、
その後に「しらくも」や「しらなみ」などが慣用句のようになるのかな、とも思った
そして、調べてみて意外なことに
「いづのうみ」と詠った歌は、すべての「和歌」でも十五首しかない
しかも、「万葉集」には、この掲題の一首だけだった
さらに言えば、「いづみのうみに たつ」と詠うのは、慣用句どころか、
掲題歌以外では、一切詠われていなかった
そうであれば、この掲題歌と「或本歌曰」は、やはり同じ元歌なのだろう
そして、その歌意は...これほども違うとは...
-略-
|
この「HP」サイトの書き始めが、5月11日なのだが、(現在5月17日)
それ以来、何度も読み直しては書き、書いてはまた読み直し...
結局、「一日一首」の方が、先行して方針付けをしてしまった形だが、
上の記事のように、この語句の用いられ方を考えると、どうしても一般的な用法でもなく
であれば、同じ本歌、もしくは「同じ背景」をベースにした「相聞歌」のように感じられた
しかし、同じ一つの歌の「異伝」とするには、どうしても歌意がそう思わせない
真っ先に気になったのは、結句の本歌「みだれしめめや」、別伝「みだれそめけむ」だ
この一つの句で、当初から違和感が拭えなかった
本歌の「みだれしめ」は、使役助動詞「しめ」を用いている
それは、「みだれさせる」ということであり、作者が相手に対する行為をいうものだ
そして、別伝の「みだれそめ」は、「みだれはじめる」といい、それは作者本人の状態になる
勿論、創作の立場からであれば、一人で「問答歌」のような「相聞」を擬えることもあるだろう
しかし、そうであれば、何も「別伝」だと言うまでもなく、二首を並べて「問答歌」でもいい
それを、あたかも「本歌」は一首であるが、異伝として、こんな歌としても伝わっている、
そう「万葉集編者」は記している
この巻第十四は、「東歌」揃いの「巻」なのだが、
以前「駿河国歌」で見たような、たとえば「ふじのたかね」のような、
その語句に「こめられた」特別な「何か」が、この歌にあるのだろうか
初句の「いづのうみに」の「語句」だけが、[東歌伊豆国」の分類に関わっているだけだ
しかし、以下の語句は、お互いの気持ちを伝えながらも、相手を思い遣る、まさに「相聞」で、
ことさら「伊豆の海に」に、意を向ける内容でもないように思える
思い起こせば、前の「駿河国」の或本歌「まかなしみ」〔3373〕の第四句が、
「いづのたかねの」とあった
富士山から南に見れば「駿河の海」であろうし、
南東に見れば「伊豆の海」となり、同じキーワードとなった「なるさは」というのも
「ふじのなるさは」を連想させ、「駿河国歌」に紛れ込んだ
私は、この前の記事で、「伊豆国歌」である〔3373〕が、
「駿河国歌」に紛れ込んだもの、と書いているが、
そもそも、そこで「或本歌曰」という別伝は、
その歌意にいくらか似通ったところからのものだと思っている
そんな目で、「万葉歌」を眺めれば、いくらでも似通った歌はある
そして、掲題歌のように「いづのうみに」だけで「伊豆国歌」の分類なのであれば、
その歌意がどうあれ、〔3373〕の「いづのたかねの」は、やはり「伊豆国歌」であるべきだ
そして、掲題歌のように、初句から第二句にかけての「いづのうみに たつ」の同句だけで、
以下の内容に対比させられる語句があるにしても、
それが「異伝」なのか「相聞」なのか、検証出来ることはいくらでもあるはずだ
さて、掲題歌の歌意に取り掛かろうと思うが、
作者は、二人の仲をこのまま途切れることなく続けていこうと思っている
だから、あなたの心を乱れさすことなどあるだろうか、いやないでしょう
これは、自分がこんなにも思っているのだから、
何も思い悩んだりせずにいてくれ、ということだろう
伊豆の海に、常に立つ白波のように、決して途切れることもなく想い続けている
その想いを、理解して欲しい、とでも言うのだろう
或本では、本歌の「白波」が「白雲」に変わって、しかしこれも同じように
途切れることなく、絶え間なく想い続けていこうと思うからから
それで、こんなにも心が乱れてしまったのだろうか、となる
この二つの歌意には、「異伝歌」とすれば、少々の歌意の変化はあるだろうが
これほど、その主体がはっきりと違うとなれば
歌そのものが、まったく別人の歌である方が自然に思えてくる
しかも、あまりにもその情景の近い関連性に、ますます「相聞」を思わせてくる
男歌、女歌などの考慮はせずに歌意を書いたが、
「相聞歌」の二人の遣り取りとすれば、或本歌が「女の気持ち」であり、
それを慰めようとして、本歌の「男の気持ち」になるのでは、と思う
とすれば、まず「或本歌」が詠われ、その後に「本歌」が詠われたのではないかな、と
しかし、こうした歌意解釈は、あくまで結句の「みだれしめめや」の「しめ」を、
使役の助動詞「しむ」と解釈した場合のことであり、
少々気にはなっていたので、古注釈書を開いてみた
すると、古注釈書どころか、近代の注釈書においても、
「しめ」は、或本歌の「そめ」と同じで、その「そめ」の訛りとして解釈されている
契沖は、その著「万葉代匠記」で
| 又注の或本の落句を思ふに志と曾と通ずれば志米は曾米にて將亂初哉[ミダレソメヽヤ]と云へる歟、此も人と我とに亘るべき事は上の如し、 |
と書いている
左注の或本歌に「そめ」とあるので、本歌の「しめ」は「そめ」に通じるのではないか、と
また「万葉集略解」の橘千蔭は、本居宣長の説として
「宣長云、結句ミダレ初メメヤならん。」を書き
鹿持雅澄も「万葉集古義」で、
「美太禮志米梅楊[ミダレシメメヤ]は、將亂始[ミダレソメ]哉[ヤ]なり、」とする
戦後の注釈書でも、武田祐吉「万葉集全註釈」において
| 「万葉集全註釈」武田祐吉 昭和23~25年成 |
[美太禮志米梅楊 ミダレシメメヤ]
亂レ始メムヤで、思い亂れることはないだろう。あだし心を持つことはしない意である。 |
では、現代訓で使役の助動詞「しむ」としたのは、どこからなのだろう
手持ちの資料を探しても、いずれも当然の如く「使役」で訓釈している
勿論、私もその「音」から、「しめ」は「使役しむ」と疑いもしなかった
しかし、「しむ」が東国訛りで「そむ」のこととされていたことも、無視はできない
ならば、左注の「或本歌」で「そめ」と訛らずに表記されるのも、また合点がいかない
同一人の詠歌であれば、それは有り得ないが、
これは...別人とすれば、有り得ることなのかもしれない
そして、私など明らかに「別人の交わす相聞歌」だとは思っているが...
現代注釈書で、気づいたのだが、
「白波」と「白雲」に、少なからずの違いを見せている
「白波」は、あくまで「白波のように絶え間なく、途切れる事のない」を比喩としているが、
「白雲」については、「白雲のように途絶えがち」とするのが多い
そこに、本歌の「異伝」としての帳尻を合わせているかのように、私には映る
この本歌と異伝歌、様々な関係の解釈が行われている
しかし、私が感じたような、まず「或本歌」が詠われ、
その後に、あたかもその相手を慰めるかのように詠う「本歌」と感じた解釈は、
唯一、折口信夫「東歌疏」が、そのように書いている
| 折口信夫 「東歌疏」 |
| 或本の方が、相手方の心のゆるみを咎めたのに対して、本文の歌が、それに答へて、決してさうでないと誓ったもの |
残念ながら、この書はまだ持っていないので、その前後を含めた確認は出来ないが
折口信夫、と言えば、「口訳万葉集」しか持っておらず、
しかも、かなりその解釈は独特な想念みたいなものがあるので、あまり開くこともなかった
しかし、「東歌疏」で、このように言うのであれば、いくらか私の感じ方に近いのかな、と
その歌意解釈を開いてみた
| 折口信夫 「口訳万葉集」 |
| 伊豆ノ海に立つ白波の、ありつゝもつぎなむものを。亂れ初めゝや |
伊豆の海に立つてゐる波が、始終立つてゐるやうに、此儘で、二人の間を續けてゆかう、と思うてゐるのに、もうそんなに、心がわきへ散りかける、といふことがあるものか。(と男をとがめた歌。)
|
一説に、「伊豆ノ海に立つ白雲の、絶えつゝも、つがむともへや、亂れ初めけむ」とある。
(此は、男の答へた歌であらう。)伊豆の海に立つ雲ではないが、きれても復、仲を續けよう、と私が思うてゐる爲かしてやら、こんなに亂れかけたことなのだらう。
|
これだけでは、よく理解出来ないが、
少なくとも、男と女の「乱れ初め」に関わる「問答」であるのは窺える
それに、使役ではなく「しむ」を「そむ」としているからこそ、
男は、女が思い悩む理由に考え及ぶことになる
仮に使役「しむ」であれば、或本歌の「女の気持ち」に対して、
男は「本歌」で、それを窘めている、俺はこんなにも想い続けているのに、と
私は、そんな「相聞歌」であって欲しい、と思っている
|
|
掲載日:2015.05.11
| 巻第十四 3376 東歌相聞 作者不詳 |
| 東歌相聞 |
| 伊豆乃宇美尓 多都思良奈美能 安里都追毛 都藝奈牟毛能乎 美太礼志米梅楊 |
| 伊豆の海に立つ白波のありつつも継ぎなむものを乱れしめめや |
| いづのうみに たつしらなみの ありつつも つぎなむものを みだれしめめや |
| 右一首伊豆國歌 |
| 或本歌曰 |
| 之良久毛能 多延都追母 都我牟等母倍也 美太礼曽米家武 |
| 白雲の絶えつつも継がむと思へや乱れそめけむ |
| しらくもの たえつつも つがむともへや みだれそめけむ |
| 【3376】 語義 意味・活用・接続 |
| いづのうみに [伊豆乃宇美尓] 「伊豆」は、静岡県東部と伊豆諸島を含めた旧国名 |
| たつしらなみの [多都思良奈美能] |
| たつ [立つ] |
[自タ四・連体形] 生じる・起る・立ちこめる |
| しらなみ [白波] |
大きな音を立てたり砕けたりして、白く泡立つ波 |
| ありつつも [安里都追毛] |
| あり [在る] |
[自ラ変・連用形] 存在する・(物・事・所などが)ある |
| つつ [接続助詞] |
[反復] ~し、また~して・~ては~して |
連用形に付く |
| も [係助詞] |
[添加] ~もまた |
種々の語に付く |
| つぎなむものを [都藝奈牟毛能乎] |
| つぎ [継ぐ] |
[他ガ四・連用形] 続ける・継続する・保つ・持ち続ける |
| な [助動詞・ぬ] |
[完了・未然形] ~てしまう・~てしまった |
連用形に付く |
| む [助動詞・む] |
[推量意志・連体形] ~だろう・~つもりだ |
未然形に付く |
| ものを [接続助詞] |
[逆接の確定条件] ~のに |
連体形に付く |
| みだれしめめや [美太礼志米梅楊] |
| みだれ [乱る] |
[自ラ下二・未然形] あれこれ思い悩む・平静さを失う |
| しめ [助動詞・しむ] |
[使役・未然形] ~させる |
未然形に付く |
| めや [複合助詞] |
[反語] ~だろうか(いや、~ないだろう) |
未然形に付く |
| 〔成立〕推量の助動詞「む」の已然形「め」+反語の終助詞「や」 |
| 【或る本の歌曰はく】 語義 意味・活用・接続 |
| しらくもの [之良久毛能] |
| たえつつも [多延都追母] |
| たえ [絶ゆ] |
[自ヤ下二・連用形] 途絶える・切れる・縁が切れる |
| つがむともへや [都我牟等母倍也] |
| つが [継ぐ] |
[他ガ四・未然形] 上述 |
| む [助動詞・む] |
[推量意志・終止形] 上述 |
未然形に付く |
| と [格助詞] |
[引用] 後に続く動作・状態の目的・原因など |
体言に準ずる語に付く |
| もへ [思ふ] |
[他ハ四・已然形] 「おもふ」の「お」の脱落した形、おもう |
| や [係助詞] |
[疑問] ~か |
已然形に付く |
| 〔接続〕活用語には、連体・連用形に付くが、上代では已然形にも付く |
| みだれそめけむ [美太礼曽米家武] |
| みだれ [乱る] |
上述 |
| そめ [初む] |
[接尾マ下二・連用形] 動詞の連用形に付いて、~はじめる |
| けむ [助動詞・けむ] |
[過去推量・連体形] ~ただろう・~たのだろう・~ていたのだろう |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【3376】注記 |
[伊豆の海に]
伊豆半島の西岸は、駿河湾に面しているので、「駿河の海」とでもいえる
だから、「伊豆の海」というのは、伊豆半島の東岸を言うものだと思うして、
[接続助詞「つつ」〕]
この接続助詞は、上代においては多く用いられたものだが、
中古以降は、次第に「ながら」にとって代わられたらしい
「つつ」の用法は基本的には「反復・継続」の意味だが、その「反復」と「継続」には、
その付く語による、少しばかりの違いがある
| 接続助詞「つつ」の基本的用法「反復」と「継続」の違い |
反復(上述)
|
「取る」などのように、瞬間的な動作を表す語に付く場合 |
継続(~しつづけて)
|
「思ふ」などのように、状態を表す語に付く場合 |
この接続助詞には、他にも「単純接続・逆接・余情」などの用法もある
[しらくもの]
「白雲」に、ことさら特別な語意はないようだ
古語辞典にも「白雲」としては載らず、「しらくもに」として、「古今和歌集」に、
| 古今和歌集 巻第四 秋上 119 読み人知らず |
| 白雲に 羽うちかはし 飛ぶ雁の 数さへ見ゆる 秋の夜の月 |
とあり、この「しらくもに」は、「とぶ」に掛かるとされる
そして、「枕詞」として「しらくもの」があるが、
この謂れは、雲が湧き上がったり、消えたり、山にかかったりすることから、
「立つ」にかかり、またその「たつ」の同音から、「竜田山(たつたやま)」、「絶ゆ」、
それに、山にかかることから「かかる」などに掛かる
この掲題歌の場合、一つの「句」においての「しらくもの」ではないので
枕詞ではなく、「しらくもの 絶えつつも」の実景を言うのだろう、と思う
|
| |
| |
 |
| |
| |

|
| |
 |
| |
| |
 |
| |
| |
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」(今日の歌には無し)]
【3376】
[本文]「伊豆乃宇美爾 多都思良奈美能 安里都追毛 都藝奈牟毛能乎 [美]太禮志米梅楊」
「イツノウミニタツシラナミノアリツヽモツキナムモノヲミタレシメメヤ」 |
| 頭注 |
「類聚古集」本文ノ下ニ小字「伊豆」アリ。 |
| 〔本文〕 |
| [美] |
『西本願寺本』ナシ。右ニ書ケリ。本文中「乎太」ノ間ニ〇符アリ。以上訓ヲ主文トセリ。
|
| 〔訓〕 |
| ツキナムモノヲ |
『西本願寺本・温故堂本』「都藝」ノ左ニ「トケ」アリ。
|
| ミタレシメメヤ |
『類聚古集』「みたれしめしや」。 |
| 〔諸説〕 |
| 〇ミタレシメメヤ、[補]「ミタレソメメヤ」 |
[本文]「或本歌曰 之良久毛能 多延都追母 都我牟等母倍也 美太禮曽米家武」 右一首伊豆国歌
「 シラクモノタエツヽモツカムトモヘヤミタレソメケム」 |
| 頭注 |
「類聚古集」訓ヲ附セズ。
「西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本」訓ヲ朱書セリ。 |
| 〔本文〕 |
| 或 |
『京都大学本』赭ノ合点アリ。 |
| 〔訓〕 |
| タエツヽモ |
『細井本』「タヘツヽモ」。
『温故堂本』「タヱツヽモ」。
|
| ミタレソメケム |
『細井本』「ミタレソメケン」。 |
| 〔諸説〕 |
| 〇[万葉考]二行小字欄外ニ移ス。〇之良久毛能、シラクモノ[代匠記精撰本]「之良久毛能」ノ上「多都」ノ二字脱カ。 |
|
|
 |
| 【歌意3377】 |
足柄山のあちこちに仕掛けられた罠のように、
身動きの取れなくなった、この私の不遇さを気に掛けて
この娘は、私を慰めるために、添い寝してくれる |
| |
作者である、男に
何があったのかは、この一首からでは解らない
しかし単純な、これまで解釈されているような「率直な愛」ではないことが、
まず感覚的に私の頭に浮んだ
勿論、使用頻度の極めて少ない「かなるましづみ」や、
声に出して読んでも馴染めない「ころあれ」という表現など、
その躓くところが、容易には理解出来なかった
毎日のように、この「語句」を諳んじたり、古語辞典を何度も何度も引き、
また「漢和辞典」や「国語辞典」など、結構私にしては熱心に関わった
それほど、通釈にはしっくりとこないものを感じていた、と言うことなのだろう
もとより、「かなるましづみ」については、諸説も多く、
それぞれが「なるほど」と思わせるものだ
しかし、共通するのは、「騒々しさ」と「静けさ」
その「相対的な関係」に、歌意解釈が随分と分かれている
その手掛かりを「さすわな」としても、
では、その「わな」によって、何を語るのか、で違ってくる
ある書では、「罠」に掛かった獲物は、一時死に物狂いで「騒ぐ」ものだが、
やがて、その運命を受け入れ、あるいは「死」を受けて、「静か」になる
また、ある書では、「さすわな」を「人の噂」譬え、
その噂の騒々しい中でも、「静かな間をはかって」娘と寝る、とか
獲物を待つ間、静かに息を潜めて、「罠」を見守る、とするような...
この「しづみ」自体に、「鎮む・静む」の語意を前提とした解釈ばかりだ
そうであるなら、確かに上述のような歌意解釈は、どれであっても十分なものだと思う
もっとも、「和歌」としての味わい方次第にもなるだろうが...
その場合、結句の「ころあれひもとく」に向かって、何の情感もなく一直線に詠われる
しかし、私に「しづみ」という「語」に、立ち止ってしまった
「かなるましづみ」のような、聞き慣れない語句ならともかく
この聞き慣れない「語句」を、何とか理解しようともがいている最中に、
下二段動詞である「鎮む・静む」の活用で、「しづみ」があるのだろうか、
そんな疑問にぶつかってしまった
結果的には、その疑問から、私自身が納得できる「歌意解釈」になったと思う
「しづみ」を、四段動詞「沈む」の連用形で理解すれば、当然その語意から、
通説では歌意が纏められなくなる
そして、何気なく感じていた「ころあれ」と言う「感覚」もまた、馴染めなかった
そこで「ころが」とも有り得ることを知ると、
そこから、一気にこの歌の「歌意解釈」に至ることができた
この作者の男が、どんな訳があって「仕掛けられた罠」に怯えているのか
それは、いくらでも推測できるが、今一つの可能性を言えば、
「官吏」としての、不手際があった為に、謹慎の身なのかもしれない
あるいは、「防人」に絡むことかもしれない
そのような情況を感じさせる「万葉歌」も、あるかもしれない
ただ、通説だけでこの歌を理解していたら、
「東国」歌、大方に形容される「率直な性愛」表現の歌、で終ってしまう
そうした先入観を持たなくても、多分に恣意的な語意解釈はあるだろうが、
歌の本質かもしれないと、思えるような感じ方もできる
東国の人が、何も掛け値なしの「純朴」な表現しかできない、とする必要はない
この掲題歌のように、自身のことで「うちしおれる」姿を、娘に慰められる
そんな歌だって、「純朴」でありながらも、
そこには「都人」に決して劣らない、「喜怒哀楽」の「悩ましさ」を秘めていることを知る
補記として、以下に古注釈書や近代の注釈書の、「かなるましづみ」解釈をまとめてみる
| 契沖 代匠記 |
| 可奈流麻之豆美は第二十に防人が歌にもよめり、鹿鳴間枕[カナルマシヅミ]なり、鹿を捕むと蹄を刺て守り居る者の鹿の鳴て依り來るなど屏息して靜まりて待如く |
| 賀茂真淵 万葉考 |
| 可奈流麻下豆美[カナルマシヅミ]、 罠の小機[ハゼ]のはづるゝ間を、かなくる間といふを略きて、かなる間といへり、卷二十の防人歌に、阿良之乎の、伊を箭たばさみ、立向ひ、可奈流麻之豆美、伊□[デ、泥/土]□[テ、氏/一]曾あがくる、てふも均し、しづみは、その間を靜めてにて、いと暫のひまを竊なり |
| 橘千蔭 略解 |
| カナルマは、羂のこはぜの外るる間を、かなぐる間と言ふを略きて、カナルマと言へり。卷二十、防人歌に、あららをのいを箭[サ]たばさみ立向ひ可奈流麻之豆美[カナルマシヅミ]いでて(いねて)ぞあがくると言ふも等し。シヅミは、其間を靜めてにて、いと暫しのひまを竊[ヌス]むなり |
| 鹿持雅澄 古義 |
| 可奈流麻之豆美[カナルマシヅミ]は、囂鳴間靜[カナルマシヅミ]なるべし、可奈流[カナル]は、囂く鳴響をいふべし、字鏡に、□ハ加萬加万志[カマカマシ]、□[犬三つ]ハ加方加万志[カマカマシ]、又常に加志万志[カシマシ]とも加万妣須志[カマビスシ]とも云、俗にやかましとも云り、二十ノ卷に、阿良之乎乃伊乎佐太波佐美牟可比多知可奈流麻之都美伊□[泥/土、デ]弖登阿我久流[アラシヲノイヲサダハサミムカヒタチカナルマシヅミイデテトアガクル]、 |
| 鴻巣広盛 全釈 |
可奈流麻之豆美[カナルマシヅミ]
代匠記には鹿鳴間沈[カナルマシヅミ]とし、鹿を捕へむと係蹄を刺して守り居る者が、鹿が鳴いて依り來る程屏息しで靜まつて待如くの意としてゐるが、鹿鳴間[カナルマ]の解は無理であらう。考は「わな小機[コハゼ]のはづるる間をかなくる間といふを略きてかなる間といへり」と解いて、「いと暫のひまを竊むなり」と言つてゐる。古義は「可奈流は囂く鳴響をいふべし」と述べて、囂しき音をしづめてと解してゐる。卷二十に阿良之乎乃伊乎佐太波佐美牟可比多知可奈流麻之都美伊□[泥/土、デ]弖登阿我久流[アラシヲノイヲサタバサミムカヒタチカナルマシヅミイテテトアガクル](四四三〇)とあり、卷四に珠衣乃狹藍左謂沈家妹爾物不語來而思金津裳[タマキヌノサヰサヰシヅミイヘノイモニモノイハズキテオモヒカネツモ](五〇三)、この下に安利伎奴乃佐惠佐惠之豆美伊敝能伊母爾毛乃伊波受伎爾□於毛比具流之母[アリキヌノサヱザヱシヅミイヘノイモニモノイハズキニテオモヒグルシモ](三四八一)とあるのと比較すると、かまびすしく鳴る音を鎭めてと解釋すべきもののやうである。即ち人の立ち騷ぐのが鎭まるのを俟つての意であらう。
|
| 武田祐吉 全註 |
可奈流麻之豆美 カナルマシヅミ。
カナルマは、諸説があり、物音の騷がしい間の意に取るものが多いが、どうしてそういう意味になるのか明解はない。これは斯ニアル間で、カナルの否定の語が、カナラズ(必)である。意は、かくある間で、ちよつとのあいだである。「阿良之乎乃[アラシヲノ] 伊乎佐太波佐美[イヲサタバサミ] 牟可比多知[ムカヒタチ] 可奈流麻之都美[カナルマシヅミ] 伊□弖登阿我久流[イデテトアガクル]」(卷二十、四四三〇)の用例がある。シヅミは靜まつて、物音を立てず。「安利伎奴乃[アリギヌノ] 佐惠々々之豆美[サヱサヱシヅミ](卷十四、三四八一)。 |
| 折口信夫 口訳万葉集 |
| 足柄山のあちら側や、こちら側に澤山かけてある、罟ではないが、其罟に、獲物がうまくかゝつた樣に、うまく二人のみとが適ふ迄の間、ぢつと靜かに、いとしい人も、自分も、下裳の紐を打ち解いて、寢てゐる。 |
現代の注釈書も、大方はこれらの範囲を出ないが、
岩波書店の「新日本古典文学大系」は、この「語句」の解釈を保留している
| 新日本古典文学大系 岩波書店 |
| 足柄山のあちこちに仕掛ける罠のように、「かなるましづみ」私は自ら下紐を解く |
| 「かなるましづみ」は、防人歌にも「荒し男のいをさ手挟み向かひ立ちかなるましづみ出でてとあが来る」(4430)とあるが、難解である。現代語を保留する。「許呂安礼」は、「ころ我」、即ち、「許呂」を自分からの意に解する。 |
「ころ」の解釈はともかくとして、結句を導く解釈になる「かなるましづみ」を、
どうして保留とするのか解らない
この語句を保留すれば、当然結句もまた、「保留」されなければ、筋が通らない
まだまだ、十分とは言えないが、
この掲題歌に関しては、私なりのこれまでの「東歌」に付けられたイメージの払拭にはなった、
そんな一首になったような気がする |
| |
| |

|
 |
| |
 |
| |
| |
|
掲載日:2015.05.24
| 巻第十四 3377 東歌相聞 作者不詳 |
| 東歌相聞 |
| 安思我良能 乎弖毛許乃母尓 佐須和奈乃 可奈流麻之豆美 許呂安礼比毛等久 |
| 足柄のをてもこのもにさすわなのかなるましづみ子ろ我れ紐解く |
| あしがらの をてもこのもに さすわなの かなるましづみ ころあれひもとく |
| (右十二首相模國歌) |
| 【3377】 語義 意味・活用・接続 |
| あしがらの [安思我良能] |
| あしがら [足柄] |
相模国の西部、神奈川県足柄上郡・足柄下郡の総称 |
| をてもこのもに [乎弖毛許乃母尓] |
| をてもこのも [彼面此面] |
向こう側とこちら側・あちらこちら |
| さすわなの [佐須和奈乃] |
| さす [射す・差す・指す] |
[他サ四・連体形] 仕掛ける・張り渡す・設備する |
| わな [罠] |
鳥獣を生け捕りにする仕掛け・紐などを輪の形にしたもの |
| かなるましづみ [可奈流麻之豆美] |
| この「語句」には、随分思いを巡らせた、その流れは「一日一首」に書いた |
| ころあれひもとく [許呂安礼比毛等久] |
| ころ [子ろ・児ろ] |
[上代東国方言] 人、特に女性を親しんで呼ぶ語、「ろ」は接尾語」 |
| あれ [我・吾] |
[自称人代名詞] 私・われ |
「古語辞典」は掲載歌を基本に、と思っているが、なかなか実行できず未完、継続中
「枕詞一覧」もやっと載せることができた
ただし、「かかり方の理由」は「古語辞典」からのみなので、
今後は「詳説」に触れ次第補充してゆく
その点でも不充分であるし、載せた語数においても、284語と、およそ言われている半分程度だ
しかし、一応その都度古語辞典を引っ張り出さない程度の気安さにはなる |
| 古語辞典 |
文法要語解説 活用形・修辞 |
活用語活用法及び助詞一覧 |
活用形解説 |
枕詞一覧 |
| |
| 【3377】注記 |
[あしがら(足柄)]
足柄山を、慣用的に「あしがら」と呼ばれていたらしい
足柄山は、特定の山頂ではなく、南足柄市西辺と静岡県駿東郡小山町との境をなす連山
[をてもこのも]
「をちおも(遠面)このおも(此面)」の転じたもの
掲題歌では、山の斜面あちこちに、ということになる
[さす]
「罠をさす」という使い方が、現代では一般的ではないとに思うが、
「罠を仕掛ける」という意味のはずだ
「さす」という語を古語辞典で引くと、五種ほどあった
何故、調べたのか、と言えば、どの漢字表記が使われるのか興味があったからだ
多くの書では、「ひらがな」で「さす」とするが、中には「刺す罠の」もある
そこに、気になるものを感じてしまったからだ
[他動詞四段「さす」]
| 射す・差す・指す |
| ① 事物をさし示す |
a 指さす
b 目ざす・向かう
c それと確かに定める・指定する
d 指名する・任命する
e 示す・指摘する |
| ② 手でさし上げる |
a かざす・かざして身をおおう
b 肩でかつぐ |
| ③ 物を設ける |
a しかける・張りわたす・設備する
b 庵をつくる
c 帯・ひもなどをしめる・結ぶ |
| ④ 物を前方へさし出す |
a 杯をさし出す・酒をすすめる
b 舞などで、手を前へさし出す
c 碁で、石を置く・将棋で駒を動かす |
| 注す・点す |
| ① 加える・つぐ |
| ② 灯をかかげる・ともす |
| ③ 印をおす |
| ④ 入れてまぜる |
| ⑤ 色どりをする・色をつける |
| 刺す |
| ① つきさす |
| ② 棹で水底をついて船を進める |
| ③ もちざおで鳥などを捕らえる |
| ④ 毒虫が針で刺す・毒蛇などがかむ |
| ⑤ 縫う |
| ⑥ 糸・紐・串などで貫き通す |
| ⑦ 針でからだに入れ墨をする |
| 挿す |
| ① 間にはさみこむ・帯の間に入れる |
| ② 髪にさす |
| ③ さし木をする |
| ④ 細長いものを容器に入れる |
| 鎖す |
| ① 門戸をとざす |
| ② かぎをかける |
これらの中で、「罠」にもっとも関係ありそうな「表記」とすれば、
上表「射す・差す・指す」の「④」が適切だとは思うが、では、その漢字は何を使うのだろう
「罠をさす」など、ほとんど使わない言葉なので、
どんな漢字を使うのか、考えたこともなかった
やはり、訓釈では、「ひらがな」表記がいいのだろう
そして、この歌、「さすわな」の他の歌の用例に倣って、
「鳥網」を張ったりする「さす」から、「罠を張る」意味になるのかなあ
| 巻第十七 3939 十六年四月五日獨居平城故宅作歌(六首) 大伴家持 |
| 保登等藝須 夜音奈都可思 安美指者 花者須具登毛 可礼受加奈可牟 |
| 霍公鳥夜声なつかし網ささば花は過ぐとも離れずか鳴かむ |
| ほととぎす よごゑなつかし あみささば はなはすぐとも かれずかなかむ |
| 巻第十七 3940 十六年四月五日獨居平城故宅作歌(六首) 大伴家持 |
| 橘乃 尓保敝流苑尓 保登等藝須 鳴等比登都具 安美佐散麻之乎 |
| 橘のにほへる園に霍公鳥鳴くと人告ぐ網ささましを |
| たちばなの にほへるそのに ほととぎす なくとひとつぐ あみささましを |
| (右六首歌者天平十六年四月五日獨居於平城故郷舊宅大伴宿祢家持作) |
ここで言う「あみさす」は、網を張り巡らせて「捕える」こととなる
そうなると、上表「刺す」の「③」に近いものを感じもするが、
それだと、積極的な「捕獲」の意志であり、
この掲題歌のような、「かなるましづみ」との併用となると、少し違うような気もする
いずれにしても、「さす」という語が、「仕掛け」に対する一つの手段である事は解る
[わな]
この「罠」の語意に、勿論「仕掛け」であることは知ってはいたが、
「紐などを輪の形にしたもの」とあるのには、驚いた
まだ何も浮んではこないが、結句の「紐解く」に、思わず飛んでしまった
現代語では、「罠」は獣をおびき寄せて捕まえる仕掛けであり、人を欺く計略の意だが、
その「字義」を見ると、本来は「つりいと・あみ(網)」とある
そして、もとの意とは...「紐などを丸く輪にしたもの」とある
[かなるましづみ]
万葉集のブログ「一日一首」で、この「語句」についてのこれまでの関わりを書いたが、
〔2015年5月19日、20日、22日〕
ようやく手掛かりらしきものを得て、今日はこの語句を踏まえての歌意解釈になる
私が感じた結論と言えば、「しづみ」は、通釈などで多く解されている「鎮む・静む」ではなく
四段動詞「沈む」の方だ、
それだと、次のような語意のニュアンスを得られる
自動詞四段「しづむ(沈む)」の連用形「しづみ」
① 水中に没する・水中に沈む
② 身分・官位が下がる・不遇である・落ちぶれる
③ 罪・苦界などに陥る・死者の霊が成仏できない
④ 気がふさぐ・うちしおれる
⑤ 重い病気にかかる・まわずらう
私は、「②・④」の意で、この歌を解したいと思う
そして、その理由になるのが、「かなるま」なのだが、
この「か」が、接頭語「か」であれば、「なる」を強調することになる
では、「動詞」の「なる」とは...
私は、「罠」などの仕掛けから多くの書が連想する「鳴る」ではなく、
生じる意の「生る」や、それまでと違った状態になる「成る」に近いものだと思う
「かなるましづみ」は、
「このような状況に置かれ、気が塞ぎもし、うちしおれるほどだ」には思えないだろうか
そして、「このような状況」というのが、
あちこちに「張り巡らされている『罠』のようなもの」
それが、何なのかは解らないが、作者の境遇にとっては非常に不利なものなのだろう
[あれ(安礼)]
この原文「安礼」を人称代名詞「わたし」の意である「我・吾」と訓釈しているが、
「娘と私は、ともに紐を解く」では、この結句の唐突感が、いなめない
通説である、騒々しい中での「束の間の静けさ」において、二人は愛し合おうというものだ
古注釈書を含めても、ほとんどの書が結句をそう解釈している
しかし「ころあれ」という表現に、どうしても馴染めない
結句までの状況を浮かべると、この結句の描写は、たんに求め合う「娘と私」だけであり
素朴と言えば、確かに素朴だが、
よく言われる、率直過ぎるほどの表現が「東歌」に多い、という認識が、
このような解釈をも、当たり前のように通しているのかもしれない
そこで、「ころあれ」という一般的に書けば「娘私」という表現は、
本当によく使われる表現なのかどうか...手持ちの乏しい資料から、探してみたが
どうしても他には見当たらない
「ころ」が「子ら・児ら」の親しみを籠める接尾語「ら」の東国語だとしても
それを踏まえて探しても見当たらない
そこで出合ったのが、井上通泰の「万葉集新考」の一文だった
| 万葉集新考 井上通泰 大正四年~昭和二年成 |
| ○結句はコロガヒモトクの誤ならむ。許呂我とありしを誤りてコロアレとよみ終に許呂安禮と書けるにあらざるか〇四五の意は夜更ケ人靜マリテ始メテ女ノ下紐ヲ解クといへるならむ |
ここで言うのは、「許呂我」と「万葉集」の「原資料」にはあるものを、
「万葉集編集」の時代に、編者が「ころあれ(許呂安礼)」と訓み、それを収載したのか、
訓点作業の際には、もとより、「原資料」ではなく、成立している「万葉集」なので、
「許呂安礼」を「こころあれ」と訓を点け、それが定着してのでは、と
仮に「万葉集編集」の時代の「原文資料」に「許呂我」とあったとすれば、
「ころが」とも訓めるはずだ
「ころがひもとく」であれば、字余りもなく、それまでの四句の意味に無理なく通じる
「かなるましづみ」の状況の中で、娘がうちしがれる作者を愛おしみ、慰めようとする
そんな光景が浮んでくる
ただし、この「ころが」と解釈することの根拠は何もない
だから、井上通泰は提起にとどまり、
他には唯一小学館の「新編日本古典文学全集」で、通釈を採りながらも
| 新編日本古典文学全集 小学館 平成八年成 |
| あるいは、原資料に『許呂我紐解』などとあって、コロガヒモトクと読むべきところを誤読したものか (入力者注:万葉集の編者の誤読か、という) |
と、その注記に書いている
確かに、「万葉集」の「原資料」が確認されない限り、
「安礼」の訓の本となった「我」が本当に表記されていたのかどうか、
諸本も、一旦「安礼」と訓を付けられた「訓釈」を、覆せるほどの「原資料」がなかった、
だから現代では、「原資料」に触れられず、平安・鎌倉時代の「訓点」の「テキスト」でしか、
あたかも、それが「万葉集原本」のように錯覚してしまうが、
「現万葉集」であっても、その本となる「原万葉集」は、あったのだから、
この「ころあれ」の問題は、珍しく、そこに行き着いてしまう、と思う
もっとも、そう大騒ぎしているのは、私だけなのだろうが
上述のように、それぞれの語句の解釈を通じて、
「ころが」の方が、私にはこの歌の味わいを深めてくれると思う
このようなケースは、きっと多くあるだろうが、
残念ながら、私には何も気づくことなく「素通り」することばかりだろう
ただ、たまたまだが、この掲題歌の「かなるましづみ」と「ころあれひもとく」の関係に、
少なからずの不自然さを感じた結果が、この自分自身の解釈に至ったことは、
やはり嬉しいものだ
勿論、誤解も語釈もあるだろうが、自分で調べた結果、というのを、
何よりも、大切にしたい
いずれ、この歌に再度立ち返るとき、どんな感じ方になるか、これも楽しみだ
|
| |
|
|
【『校本万葉集』〔佐佐木信綱他、大正12年成〕の面白さ】[2014年3月8日記]
先日手にした『校本万葉集』、復刻版なので、なかなか読み辛いところもあるが、その内容は、確かに面白い
「注釈書」のような、歌の解説ではなく、その歌の本来の表記の姿を出来るだけ復元しようとする書では、もっとも新しいものだと思う
とはいえ、それでもまだ昭和になる前の書だから、古さはあるのだろうが、かと言って、それ以降の書が、注釈に重きを置いているばかりで
こうした「諸本」の校合を広く行い、それが中世の頃の「校本」に次ぐ形で刊行されたのは、素人の私でも嬉しいものだ
底本は、広く用いられている『西本願寺本』ではなく、『寛永版本』としている
[諸本・諸注については、「諸本・諸注、その他の歌集」(今日の歌には無し)]
【3377】
[本文]「安思我良能 乎□毛許乃母爾 佐須和奈乃 可奈流麻之豆美 許呂安禮比毛等久」(右十二首相模國歌) 【□:氏/一】
「アシカラノヲテモコノモニサスワナノカナルマシツミコロアレヒモトク」 |
| 頭注 |
「元暦校本」本文缼ケテ存セズ。訓ノミ存セリ。
「類聚古集」本文ノ下ニ小字「相模」アリ。
「古葉略類聚鈔」主文ヲ訓交リニ書ケリ。下ニ小字「相模」アリ。 |
| 〔本文〕 |
| 能 |
『古葉略類聚鈔』訓ヲ主文トセリ。
|
| □(氏/一) |
『類聚古集』「〇(人偏に弖)」。
|
| 佐須和奈乃 |
『古葉略類聚鈔』以上訓ヲ主文トセリ。
|
| 許呂安禮比毛等久 |
『古葉略類聚鈔』以上訓ヲ主文トセリ。
|
| 〔訓〕 |
| アシカラノ |
『古葉略類聚鈔』「ア」蝕シテ存セズ。
|
| サスワナノ |
『細井本・温故堂本』「サスハナノ」。 |
| カナルマシツミ |
『元暦校本』「る」ノ右ニ墨「ル」アリ。 |
| コロアレヒモトク |
『元暦校本』「あれともとく」。「あ」ノ上ニ墨〇符アリ。ソノ右ニ墨「ころ」アリ。上ノ「と」ヲ墨ニテ消セリ。ソノ右ニ墨「ひ」アリ。
『古葉略類聚鈔』「コヽロアレヒモトク」。 |
| 〔諸説〕 |
| 〇ナシ |
|
|
 |
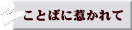  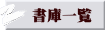  |