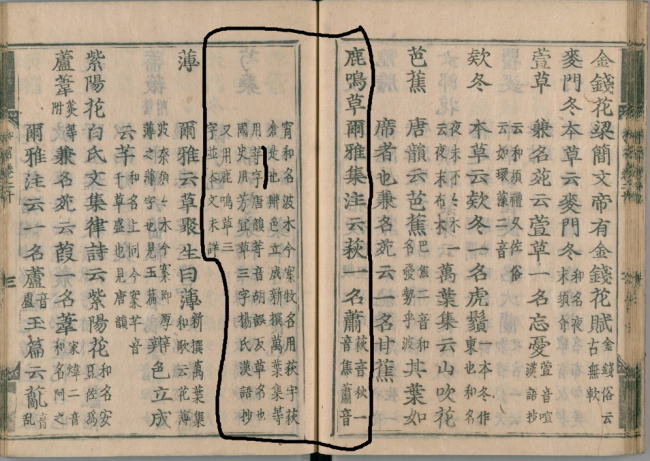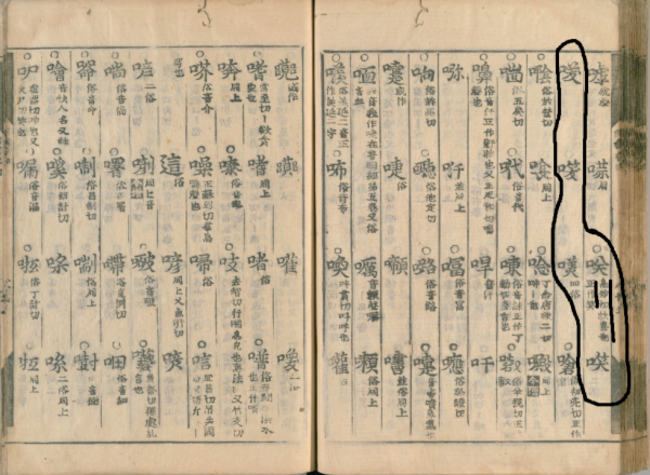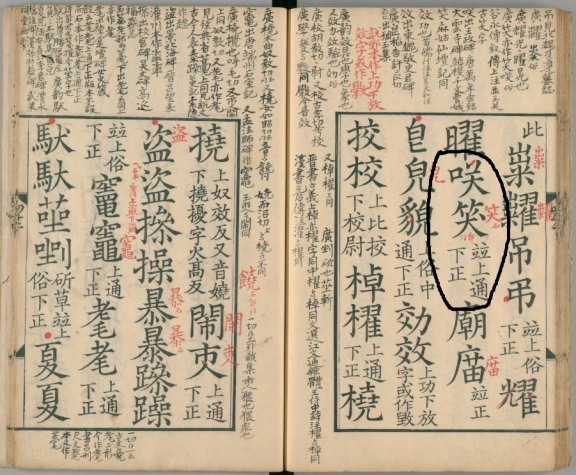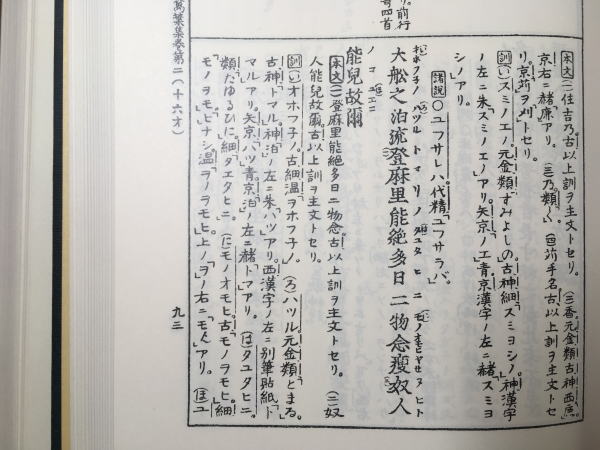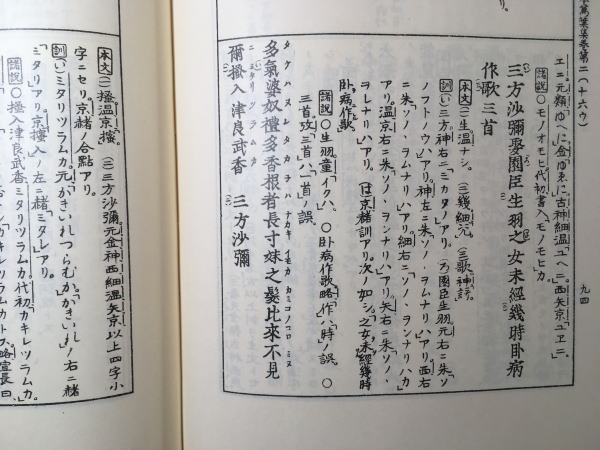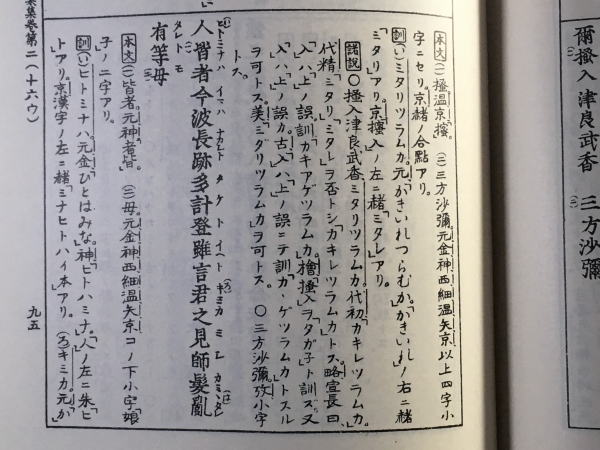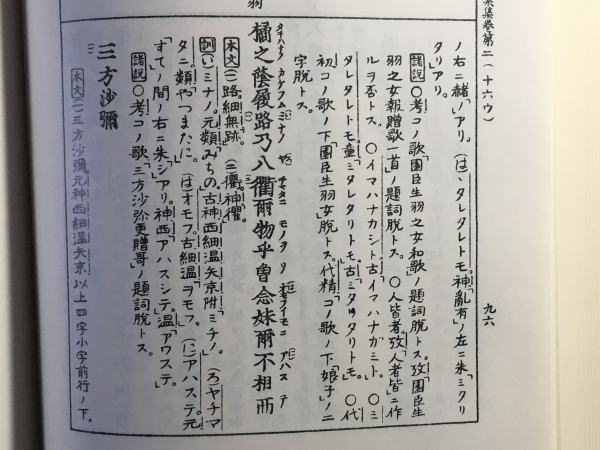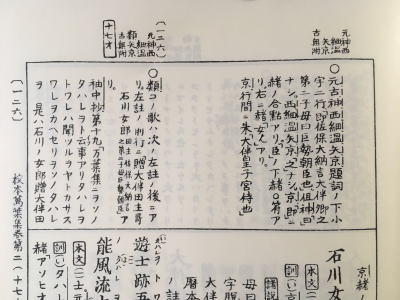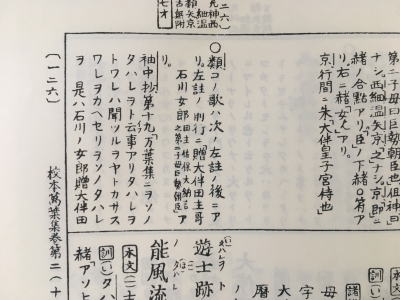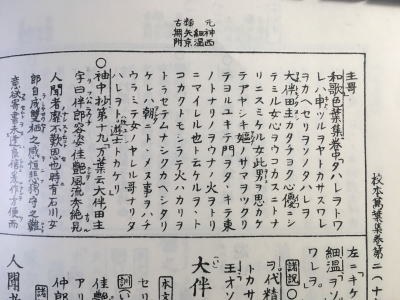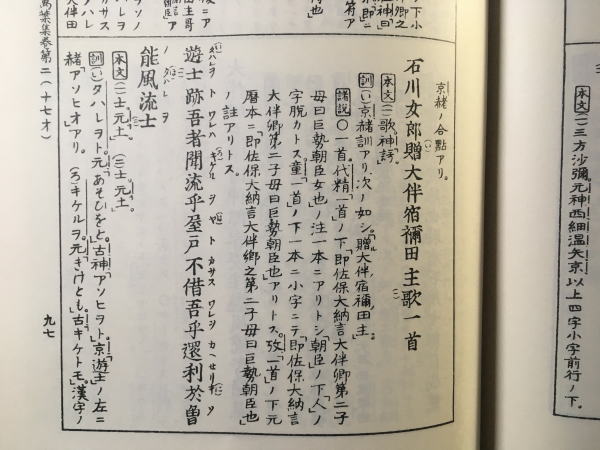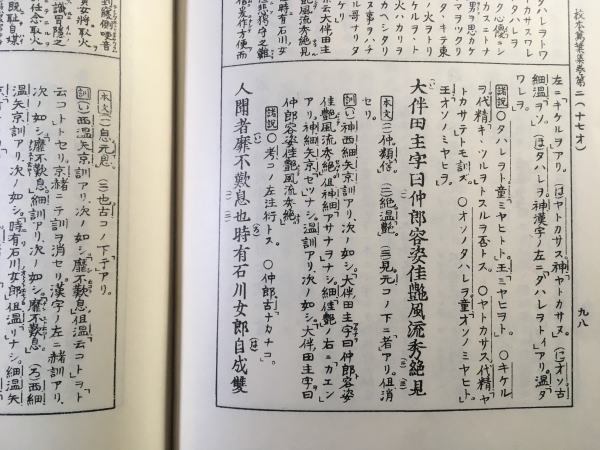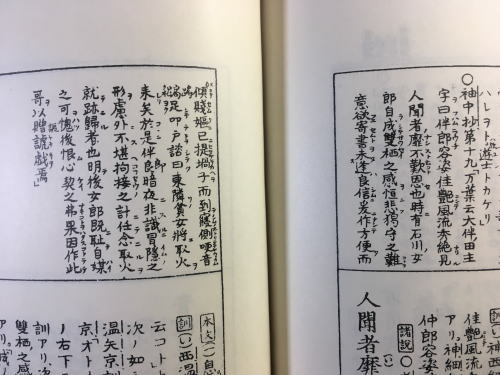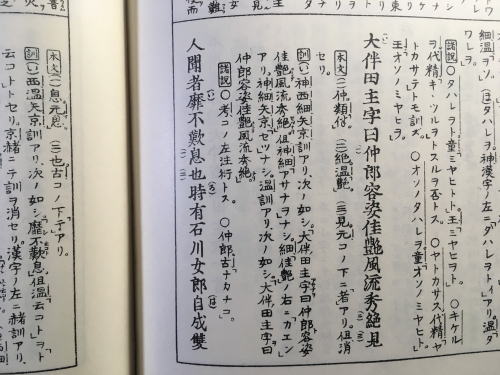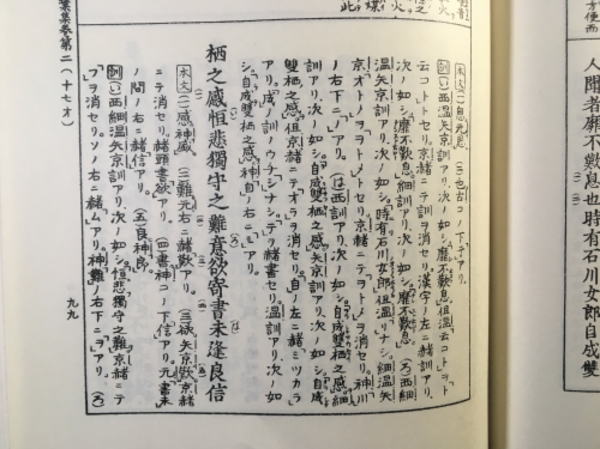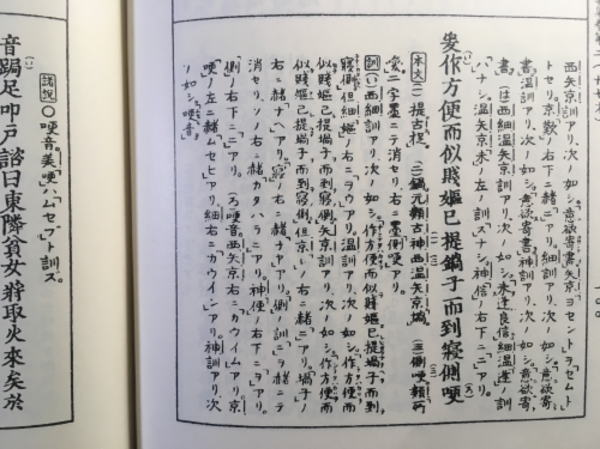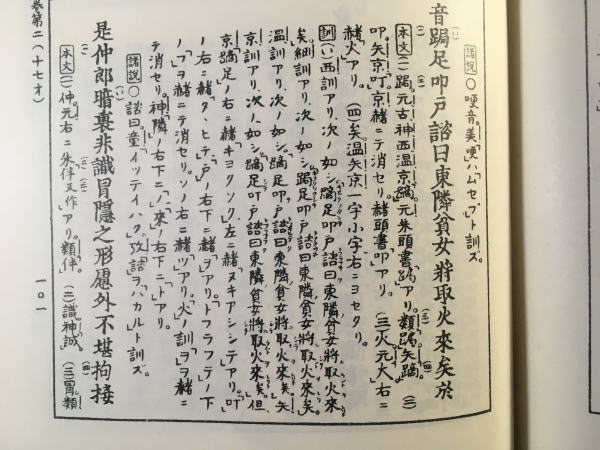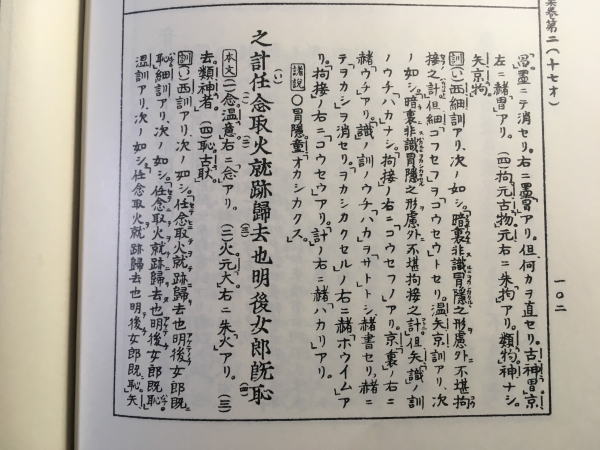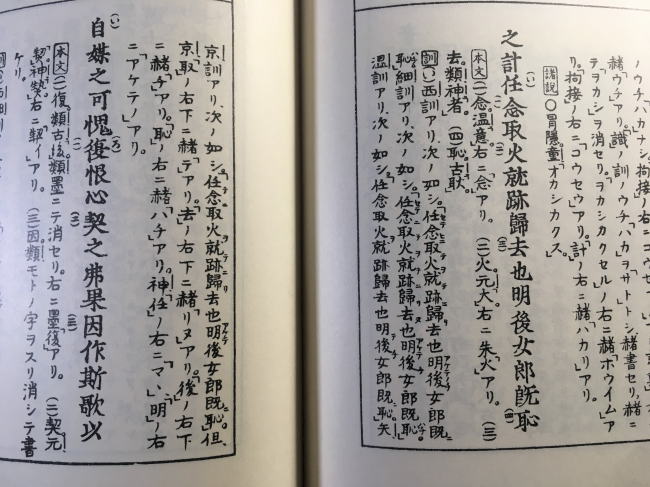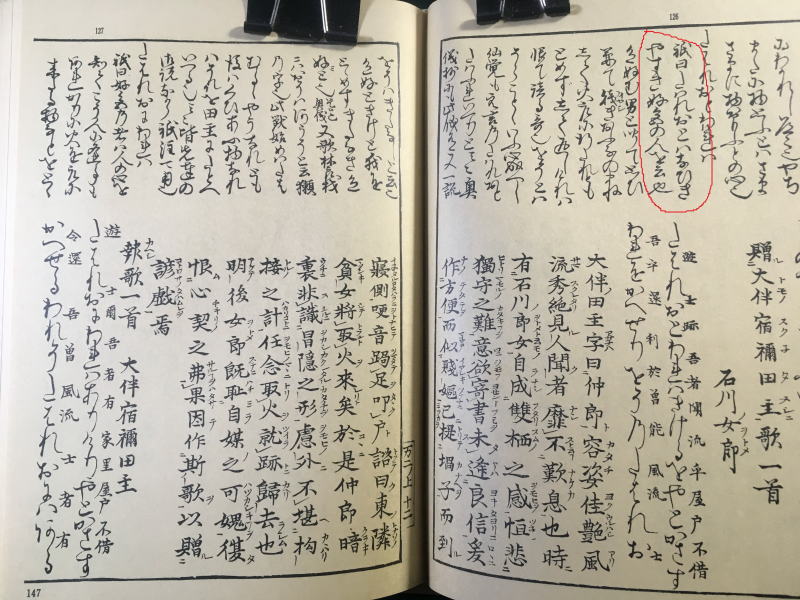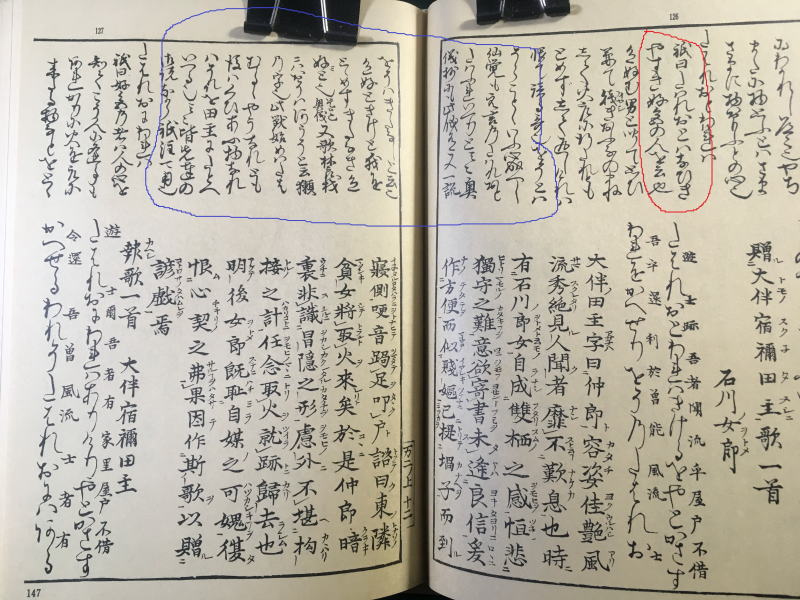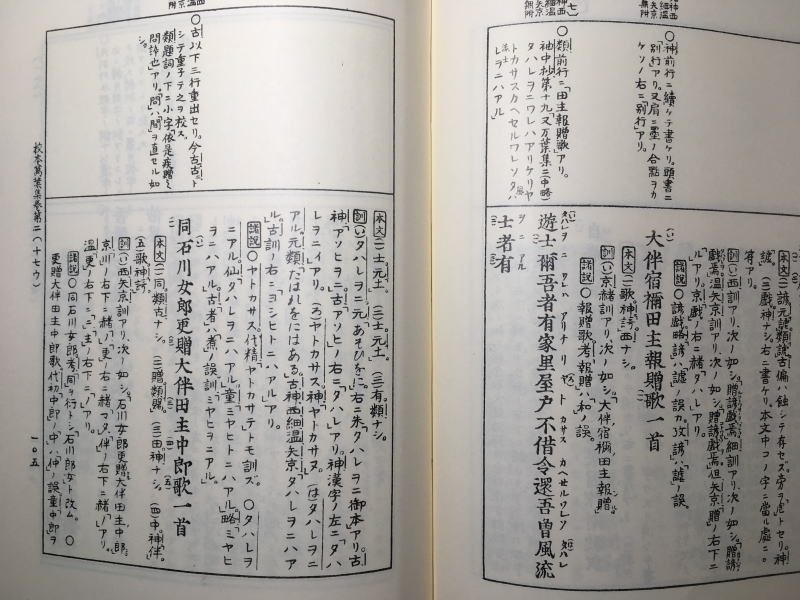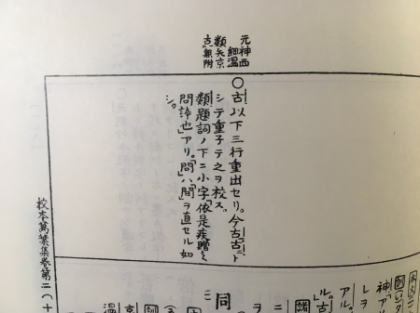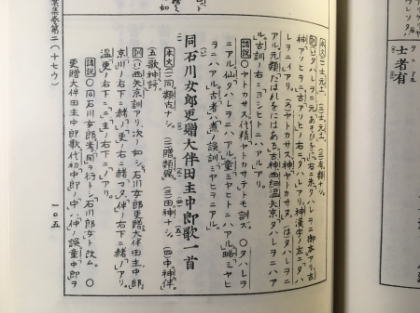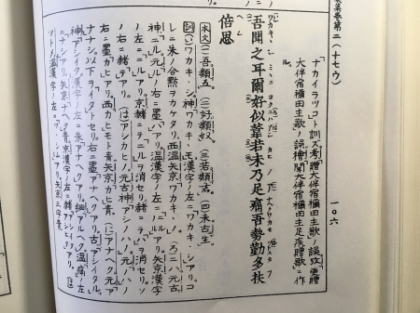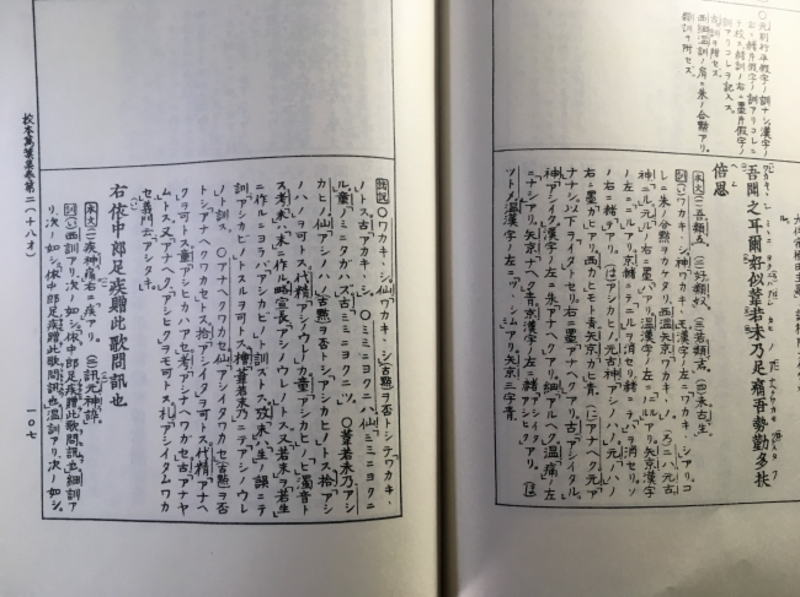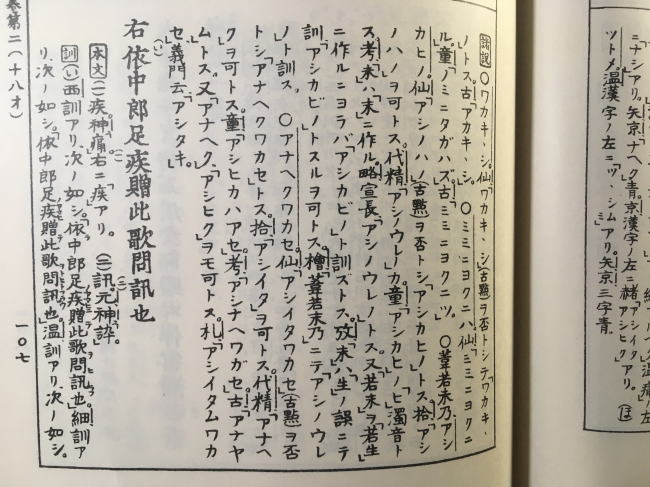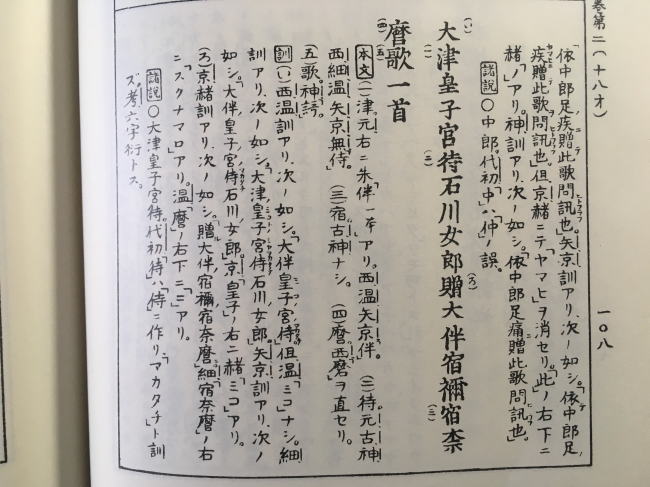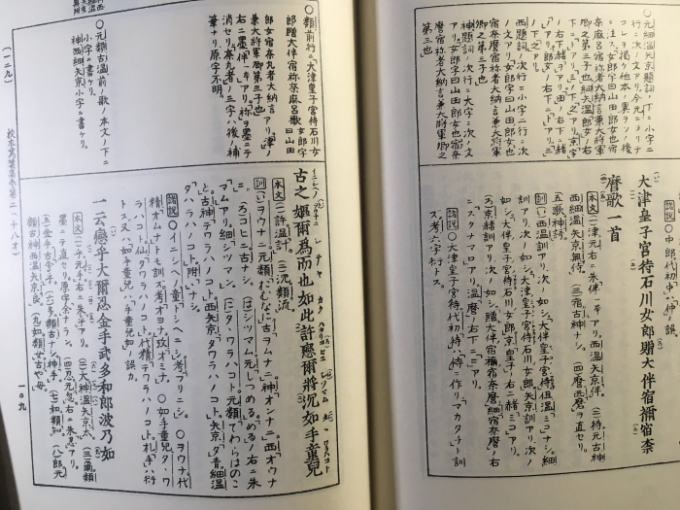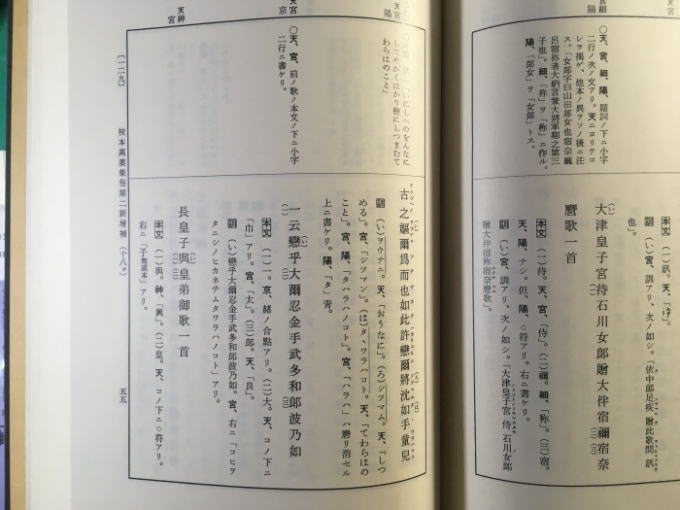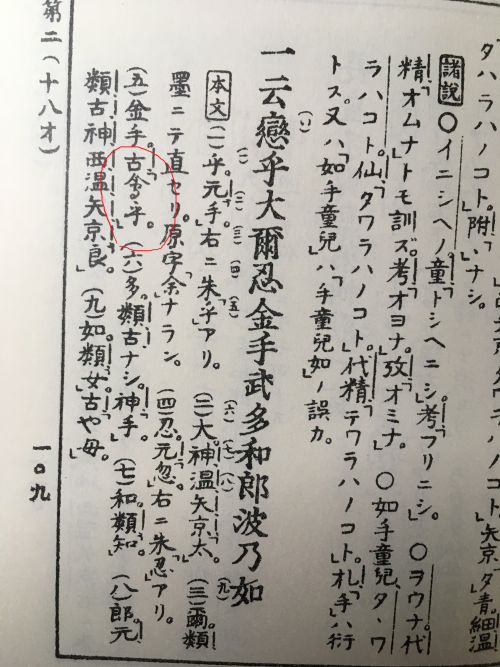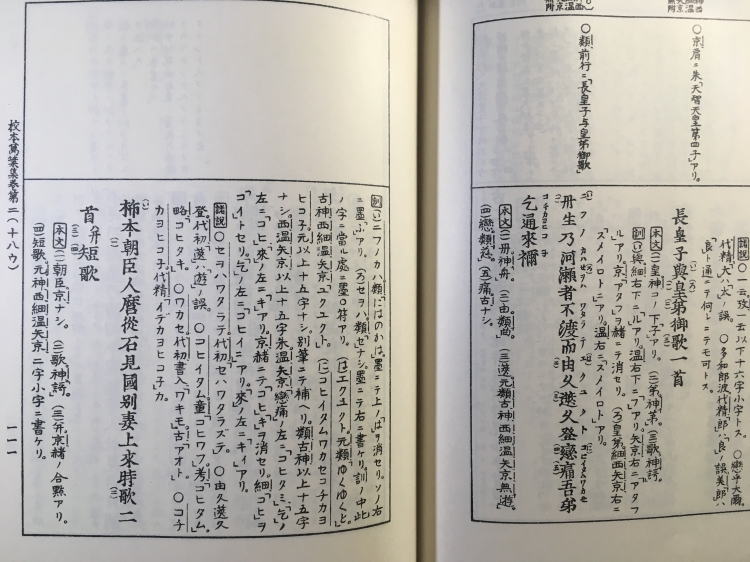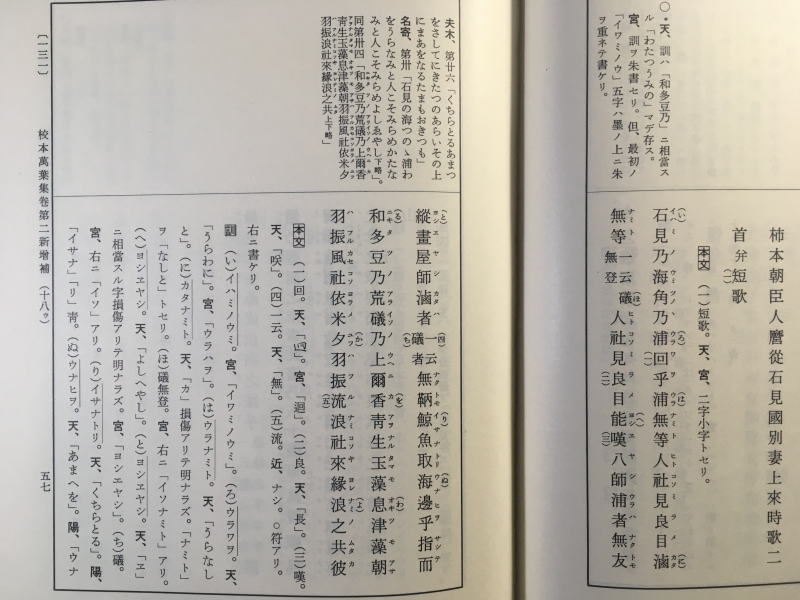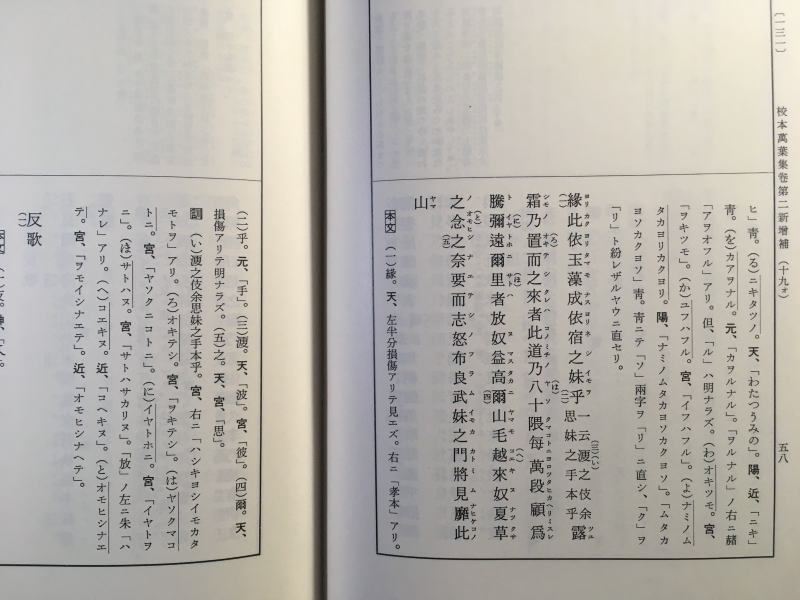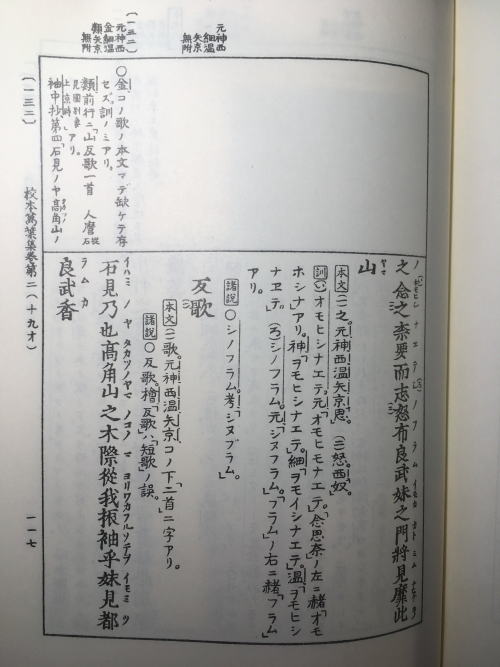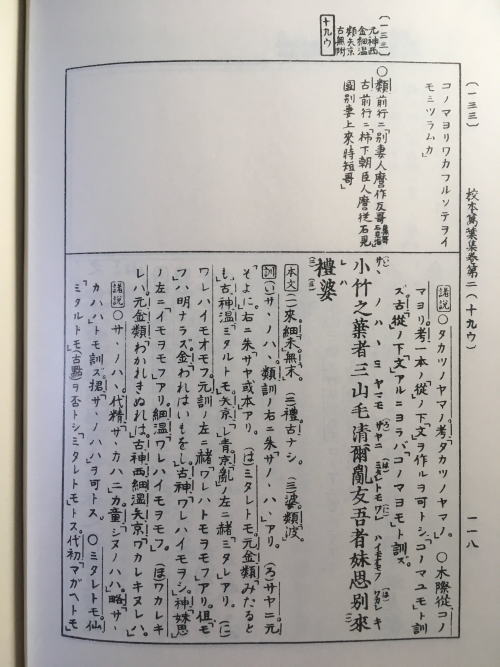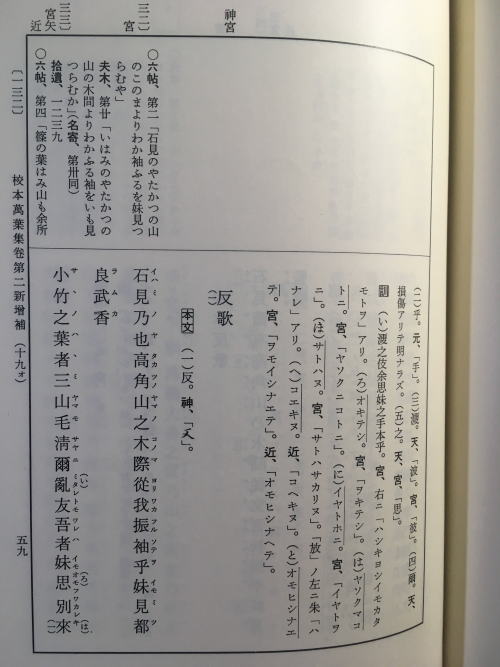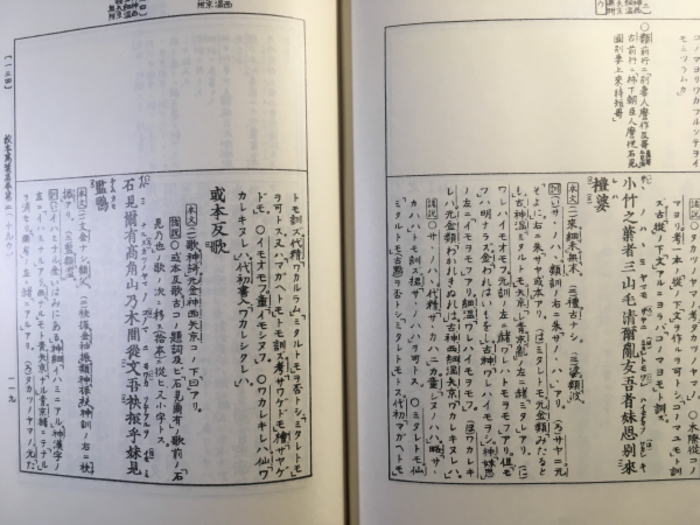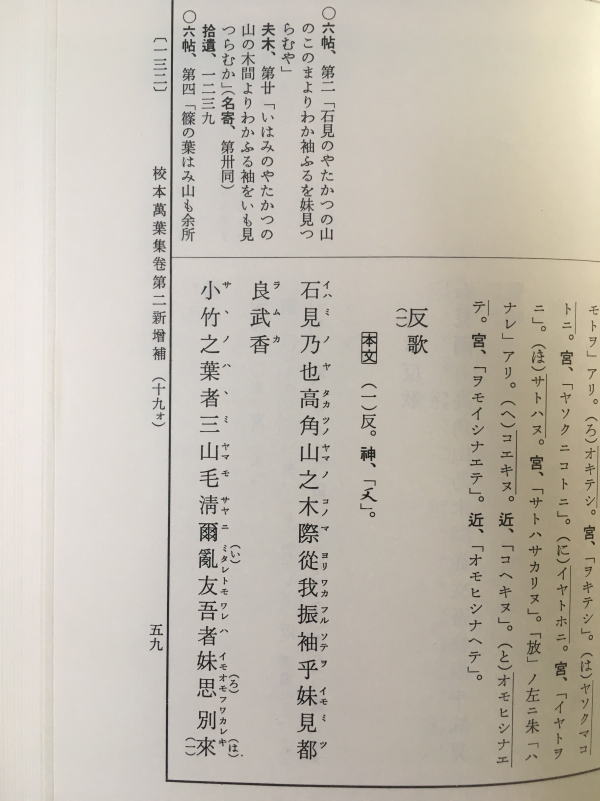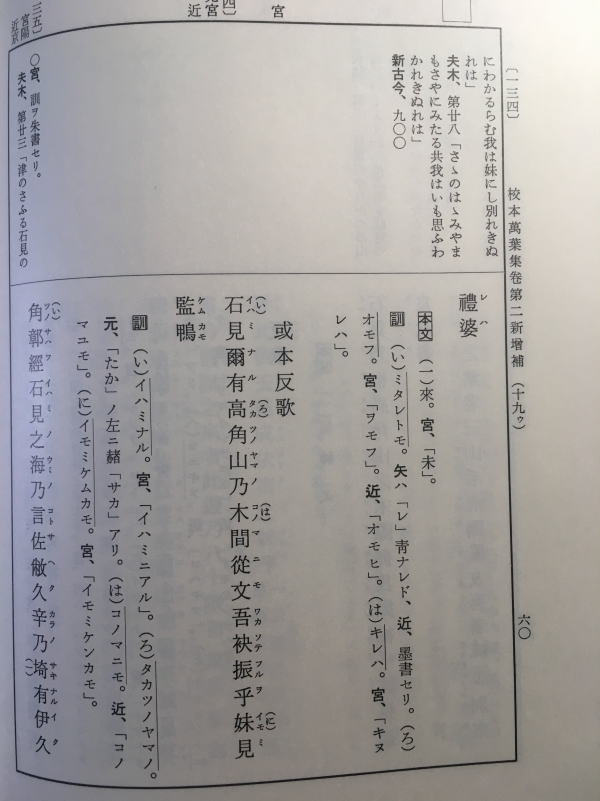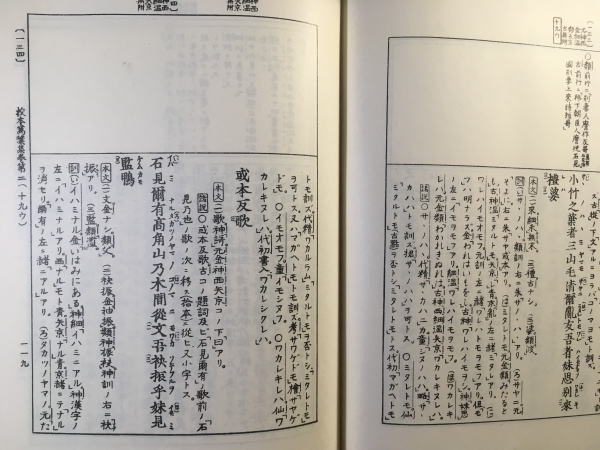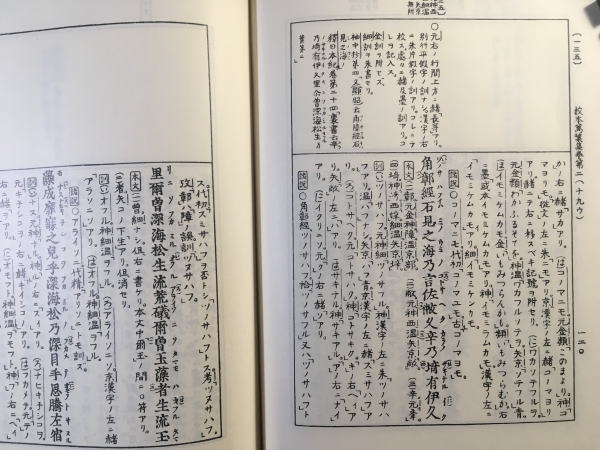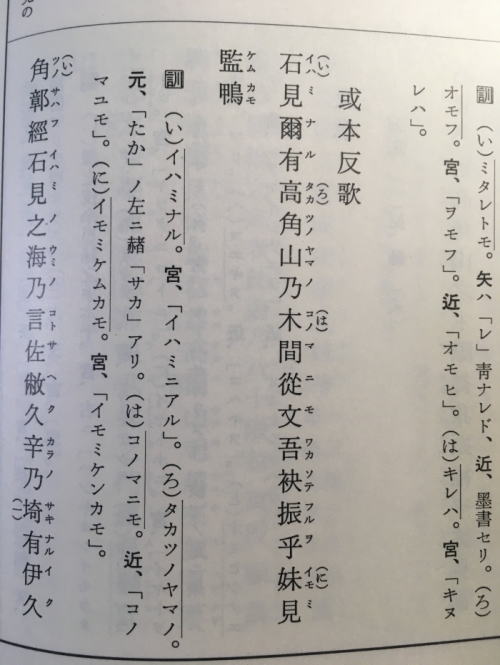| 歌番号 | 語句 | 諸注 | 諸注引用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巻第二 85 | 磐姫皇后「四首」 | 新全集 | 磐姫皇后が仁徳天皇と衝突し、嫉妬し抵抗したという伝えは、多少内容に差があるが記紀に詳しく記されており、その一部はこの後「90」の左注にも引かれている。これは皇后が有力豪族葛城氏の出身といわれることと関係があろう。記紀によれば磐姫は功臣武内宿禰の孫、葛城襲津彦 (かつらぎのそつびこ) の娘ということになっており、その襲津彦の子息たちは、巨勢 (こせ)・蘇我・平群 (へぐり)・紀 (き) など諸豪族の祖となっている。葛城氏は五世紀では天皇家に対抗できる勢力を有していた。以下の四首は本来別々の歌で、しかも作者不明の伝誦歌であったのが、いつの間にか磐姫皇后の伝説に結び付けられ、その作と見なされるようになったのであろう。編纂者はその所伝を尊重する立場を守った。もす皇后の歌であったら、巻第一の冒頭の雄略天皇の歌より百年以上時代が遡り、万葉集中最古の歌となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 題詞によれば五世紀の仁徳朝の歌で、万葉集中最も古い作となる。しあkし、帰らぬ夫を迎えに行こうか、それとも待ちつづけようかと去就に迷っている女性の心情を、あとの三首 (86~88) とともに短歌四首の連作として歌っていることからすれば、連作の創始された人麻呂の時代以後に作られたものと考えるほうが、自然である。あえて推測を加えるなら、この「85歌」は允恭記の軽大郎女の歌 (君が行きけ長くなりぬ山たづの迎へを行かむ待つには待たじ) またそれに近い歌に手が加えられ、磐姫に仮託されたものであろう (稲岡「磐姫皇后の歌」『万葉集を学ぶ』第二集)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 左注 「山上憶良臣類聚歌林載焉」 |
全注 | 原文「右一首歌山上憶良臣類聚歌林載焉」。この左注は、類聚歌林に八十五歌と同じ歌を磐姫皇后作として載せており、八十六歌以下は載せられていなかったことを示す (伊藤博「舒明朝以前の万葉歌の性格」『万葉集の構造と成立』上)。類聚歌林は、中国の芸文類聚などを手本に編纂された歌集。当時の宮廷に残された伝誦歌や行幸に関する歌などを集め、作者や作歌事情を説明したものと推定され (高野正美「類聚歌林」古代文学昭和四十一年十二月)、その編纂は養老五年以後と考えられる (澤瀉久孝「山上憶良の生涯と作品」春陽堂『万葉集講座』第一巻)。憶良がそのころ宮廷内で記録した磐姫伝承歌はこの一首のみであって、その後、三首 (86~88) が加えられ、四首連作の形が整えられたのかもしれない。なお、このことについては「88歌」の〔考〕に述べる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 後「90歌」に載せる允恭記に見える作も、その所伝の如く衣通王の作と断ずべきかどうかは疑問であるが、ともかく今の作よりは古いものであり、その伝誦歌としては第三句「山たづの」といふ枕詞であつたものが、磐姫皇后の御作として記録される頃には「山たづね」と改められたものであり、下句も「迎へを行かむ待つには待たじ」の方が表現も内容も直線的で素朴で原歌と認むべきものである。かたがたこの作は仁徳天皇の御代頃まで溯り得るものではない。この事は次々の歌についても考へられるところであり、くはしくは「伝誦歌の成立」
(『作品と時代』所収) を参照せられたい。 (左注について)憶良の類聚歌林は既に (1・6、7などの左注) 出てゐる。それにただ「載す」とあつて、作者の事を書いてゐないのは、類聚歌林も今と同じ所伝であつたものと思はれる。その事は「90歌」の左注によつても知られる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 巻第二の巻頭歌として磐姫皇后の古歌四首が揚げられた。同皇后作と伝えられる伝承歌四首である。左注には、類聚歌林にこの歌が載っていると記す。作者名が異なっていれば、その旨明記するはずである。類聚歌林にも、磐姫皇后の作として載せてあったのだろう。「類聚歌林」は既出 (六番左注)。「山尋ね」の語、他に用例が無い。「90所引」、古事記下 (允恭)、衣通王 (そとおりのおおきみ) の歌「やまたづの」が原形であろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 86 | ずは | 新全集 | この「ずは」は上代語法の中で最も難しい問題の一つ。三十例ばかりあるうち、その多くは「マシ (モノ) ヲ」のような仮想表現と呼応し、「ずは」の上に甚だ望ましくない現在の事実を示し、下にそれよりはましだと思う事柄を述べるという形をとる。本居宣長は、これを「ンヨリハ」の意と解し、「恋ひつつあらずは」は「恋つつあらんよりは」であるとした。これに従う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 「ズ」は打消の助動詞の連用形、「ハ」は清音で、強調の助詞。恋をしつづけていないで、の意 (橋本進吉『上代語の研究』)。本居宣長の詞の玉緒には、こうした「ズハ」を「~んよりは」と解しているが、「ズハ」に選択や仮定条件の意味が含まれるわけではなく、前後の句との関係によると見られる。この歌の場合、恋する現実の苦しみから脱出することを志向する内容なので、宣長の訳語も妥当する (尾上圭介「ずは」『万葉集を学ぶ』第二集)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 「恋ひつつあらずは」の「ずは」は、打消の助動詞「ず」の連用形に係助詞「は」の加わった形 (橋本進吉『上代語の研究』)。文法的意味は「ず」の強意であるが、「ましを」などと呼応する場合、文脈的意味としては、「~んよりは、むしろ」のような訳語が該当する。「我妹子に恋ひつつあらずは秋萩の咲きて散りぬる花にあらましを」 (120) 、「後れ居て恋ひつつあらずは紀伊の国の妹背の山にあらましものを」 (544)、「かくばかり恋ひつつあらずは石木にも成らましものを物思はずして」 (722)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 「ずは」については宣長が「~よりはといふ意也」 (言葉の玉のを七の巻) と云つてよりその説が一般に認められてゐたが、語法上なぜさういふ解釈に到達するかに疑義があり、それについて橋本進吉博士は「奈良朝語法研究の中から」
(国語と国文学第二巻第一号、大正十四年一月『上代語の研究』所収) に於いて、「す」はやはり打消の助動詞「ず」で、それに助詞「は」を加へたものでその「は」は「過ぎは行けども」「善くはあらず」「賜ふべくはあれど」などの「は」と同じくそれを省いても上の語の意味機能は少しも変化を受けないものとされ、宣長の解釈のあたらない例として、 立ちしなふ君が姿を和須礼受波 (ワスレズハ) 世の限りにや恋ひわたりなむ(20・4441) の歌をあげ、これは上総国の朝集使大掾大原真人今城が京に立つ時、郡司の妻女等が餞に詠んだ歌で、この「ずは」を「んよりは」と解しては意味をなさず、と云つて「ずは」即ち「何でなくば」と解してもあたらない。これは「忘れず」「忘れずして」の意としてはじめて意味が通ずる。しかも多くの場合、宣長の云つたやうに、「んよりは」と解してあたつてゐる如く見えるは、同じやうな思想を表はす相似た二つの表現法があるからで、 (甲) 汽車で行かないで船で行くがよい。 (乙) 汽車で行くより船で行くがよい。 の如く、内容は相似でゐるが表現法が違つてゐる。宣長はそれを混同したので、「ずは」は「甲」の場合で、 たまきはる命に向ひ戀従者 (コヒナムユハ) 君が御船の楫柄にもが(8・1455) の「戀ひむゆは」は「戀ひむよりは」の意で、「乙」の場合である。「甲」の方には打消の語によつて一方を捨てて他を採る意味が認められるが、「乙」のやうに「ゆ」「より」などの語によつて比較選択の意味は示されてゐない。「ただ『寧』といふ語を添へて解釈すれば、歌全体の思想に存する、一方を斥けて他を撰ぶ意趣を十分に明にして、一層適切な解釈が得られるといふまでである。」と述べられてゐる。これで確かに「ずは」の語法は説明されたが、比較の意は無いと云ひながら「ずして」だけでは意味がはつきりせず、「寧」といふ言葉を補はねばならぬところに何となく釈然としかねるものが感じられる。それが為になほ異論も出てゐて、大岩正仲氏の「奈良朝語法ズハの一解」 (国語と国文学第十九巻第三号唱和十七年三月)、濱田敦君の「上代願望表現について」 (国語と国文学第二十五巻第二号昭和二十三年二月)、「肯定と否定」 (国語学第一集、昭和二十三年十月)など、前者は「ナイナラバ」即ち仮定条件法の「ズハ」と同じだと見、後者は「あらば」 といふ肯定の仮定条件句と同じでないかといふ説であり、それらに対して吉永登氏は「奈良朝特殊語法『ずは』について」 (国文学第三号昭和二十六年二月) の論で、橋本博士の「甲」 注のの表現形式は万葉時代を下限としてほろび、今日では「甲」に相当する表現形式は存在しないので、語法としては博士の説明に根拠を認めながら、口訳としては「んよりは」によるべき事を述べられてゐる。なる程意訳としてはさういふ感がせられるが、ともかく万葉では「ずは」と「ゆは」「よりは」との両様の表現法が行はれてゐるので、両者の間に区別があつてよい。私は先年、この「は」は詠歎の意の強いもので、口訳すれば「何々しないでサ」といふ風に云へば、「寧」といふ語を補う事もなく、しかも言外に「よりは」の余意が感じられるのではないか、といふ事を述べた事があつた (昭和十四年秋、京都大学月曜講義月、『万葉雑記』所収「余情」) が、ともかく、余意としては「いつその事」とか「ままよ」とかいふ思ひ入つた歎きがもめられてゐると考へられる。なほこの「ずは」については、はやく黒澤翁満の言霊のしるべ (中篇下) にも見え、橋本博士自身もその後また「上代の国語に於ける一種の『ずは』について」 (『上代語の研究』所収) を書かれてをり、翁満の「ははいと軽し」と「は」を軽視してゐる点に訂正を加へ、「ずは」に常に「は」を伴ふのは、上の連用修飾語を特に提示して之に注意を向けしめる為であらうと述べられてゐる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 87 | 萬代日 (までに) | 新大系 | 「萬代日」の「日」の仮名使用は、万葉集にこの一例しかない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 「日」は「ニチ」の「ニ」を音仮名として用ゐた。集中唯一の例であるが、上の「萬」「代」もいづれも音仮名である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 原文「萬代日」は音仮名の表意性をも利用した書き方。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 88 | 朝霞 (あさがすみ) | 全注 | 霞は万象名義に「赤黄雲」、新撰字鏡に「胡加反平赤雲」とあるように、中国では赤雲をあらわす文字であるが、常陸風土記行方郡の条に香澄里を「霞郷」とも記していて、カスミに宛てたことがわかる。水滴が空中にただよって視界をおぼろにする状態で、アサカスミは、朝霧というのにほぼ等しい。万葉集では後世のように霞が春、霧が秋のものと季節的に固定していないので、秋の霞が詠まれる場合もある。ここまで上三句は序詞。霧のかかって晴れない状態を、恋の思いに心のむすぼれた状態の比喩としている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 「朝霞」-朝霧。「キリ」と「カスミ」とは必ずしも区別なく用いた。晴れぬ思いの鬱陶しさを霞の晴れやらぬさまにたとえた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 春には霞、秋には霧といふのが通例であるが、当時には二三例外がある。「霞立 (カスミタツ) 天河原尓 (アマノカハラニ)」 (8・1528)、「朝霞 (アサカスミ) 鹿火屋之下尓 (カヒヤガシタニ) 鳴蝦 (ナクカハヅ)」 (10・2265)。なほ霞と霧の区別は「旦霧隠 (アサキリゴモリ)」 (4・509) の條参照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 春は「霞」、秋は「霧」という大体の区別は万葉集に認められるが、時には秋にも「霞」ということがある。「霞立つ天の河原に」 (8・1528)。ここは「秋の田の穂の上に霧らふ朝霞」によって恋のいぶせきが続くことを譬え、その霞が晴れ、君に会うことができて、私の恋が止むのは何時ころなのかと嘆く。「このままにあたら朧霧のよも晴れじ」 (宗祇畳字百韻) の「朧霧」という漢語がほぼ該当する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何時邊乃方二 (いつへのかたに) |
全注 | 〔注〕 難解な語句。原文「何時邊乃方ニ」を「イヅベノカタニ」と読み、「何れの方」と解する考 (賀茂真淵「万葉考」) の説によるものが多いが、代匠記 (精撰本) に「邊ノ方トハ、渺々ト見エ渡ル田ノ、其ノカタハラナリ。哥ノ心ハ、君ニ久シクアハテ我胸ニ思ノ満タルハ、朝霞ノ田面ニ棚引アヘルカコトシ。サレト、霞ハカタヘニ晴行コトモアルヲ、イツカ我モソノコトク胸ノ晴テ戀ノ止ンソトナリ。」と記すのは、「何時」と「への方」とをそれぞれ時間・空間をあらわす語として分けて解するものである。また、野中春水は「邊」を「ユフベ」「ハルベ」の「ベ」と同じく時をあらわす名詞と考え、「方」も「明け方」「夕方」のように時をあらわす例があるので、「イツヘノカタ」で何時頃という意をあらわすと考えた (「『何時邊乃方』考」万葉八号) 。右の三説のいずれが正しいか、判断は難しい。最近の注釈書でも、古典大系 (岩波書店) は「万葉考」の説、澤瀉注釈 (中央公論社「万葉集注釈) と古典全集 (小学館) は契沖説、古典集成 (新潮社) には野中春水説が採られていて定まらない。巻第十九の「-霍公鳥 伊頭敝能山乎 (イヅヘノヤマヲ) 鳴可将超 (ナキカコラム)」(19・4195) に「イヅヘノヤマ」があり、「イヅヘノカタ」ならば現在の「どちらの方」に近い言葉として認められるので、「考」の説によるのが穏やかと思われるが、「何時邊」を「イヅヘ」と訓むには、借訓字の第二音節の清濁に関する一般的な傾向 (西宮一民「上代語の清濁」万葉三十七号、鶴久「万葉集における借訓仮名の清濁表記」万葉同上) に照らし疑問も持たれる (「考」の条に詳説)。「何時」を「イツ」と訓み、時の不定称とすると、「へ」を頃の意の名詞としても、助詞の「ノ」から「方」につながる「イツヘノカタ」という表現が落ち着かないし、また「イツ」と「ヘノカタ」を分ける説は、小刻みな表現になり過ぎて (注釈) 、納得しかねるようだ。いずれにしても問題があるわけで、三説のなかでは、「万葉考」の「何れの方」説により、何時を「イヅ」の借訓字とし、第二音節の清濁表記の違例とする方が歌としての難点は少ないように思われる。「何時邊 (イヅヘ)」で、「何時」という時間的な意味をも暗示した表記例と考えておきたい。 〔考〕 西宮一民・鶴久の研究によると (〔注〕に引用した文献参照) 、上代語を借訓文字で記す場合、万葉人たちは表記語の第二音節以下の清濁と、借訓文字の訓の清濁とを原則的に一致させるように注意しているらしい。たとえば朝入 (アサリ) ・鶴寸 (タヅキ) は、それぞれ餌を探し求めること、手掛かりとなることを表す語であって、アサリ・タヅキの第二音節以下と、朝 (アサ) ・鶴 (タヅ) という借訓字の「サ・ヅ」の清濁は原則的に等しい。それに従えば「何時邊」を「イヅヘ」とは訓み難いのであるが、例外も皆無ではないので違例としておくことにする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 〔何時邊の方に我が戀やまむ〕訓釈 原文「何時邊乃方二」とあるを考にイヅベノカタニと訓み「何れの方に云也」と云つて以来、諸注これに従ひ、「邊」をへと清むものと然らざるものとに別れたが、「何時」をイヅと訓んで、考の解釈に従つてゐる点では一致してゐると云つてよい。然るに代匠記には「イツ邊ノ方ニ」とし、「邊ノ方トハ、渺々ト見エ渡ル田ノ、其カタハラナリ」と解し、、「霞ハ、カタヘニ晴行コトモアルヲ、イツカ、我モソノゴトク、胸ノ晴テ戀ノ止ンゾトナリ」と釈してゐる。即ち「何時」はその文字通り時間に、「邊乃方」は場所方角に、解いたので、その前説を支持して更に新見を示したものに野中春水君の「『何時邊乃方』考」 (万葉第八号、昭和二十八年七月) がある。氏はこの句を時間的なものにとるべき理由として、 (一)「我が戀やまむ」といふ句は、 わたつみの海に出でたる飾磨川絶えむ日にこそ吾が恋やまめ(15・3605) あらたまの五年経れど吾が恋の跡なき恋のやまずあやしも(11・2385) などの例に見られるやうに、必ず時間の概念がつきまとつてをり、それが自然である事、 (二)前三首には「再び相逢ふことを期待してゐる心境」が説かれてをり、その連作として「わが戀やむ時」はいつ頃であらうかと反問し、嘆息するのは当然の勢である事、 (三)集中「何時」と書かれたもの五十余例、常にイツと訓み、時間的なもので、「伊豆久欲利 (イヅクヨリ)」 (5・802)、「何所行良武 (イヅクユクラム)」 (1・43)、「伊豆知武伎提可 (イヅチムキテカ)」 (5・887) などの場所、方角を示すイヅとは一線を画してゐる事に注意し、まづ「何時」をイツと訓み、時間を示すものとし、更に「邊」も、通例としては場所に用ゐるが、「いにしへ」「ゆふべ」「春べ」など時にも用ゐられ、従つて「何処邊 (イヅクベ)」 (13・3277) に対して「何時邊 (イツベ)」といふ語が成り立つても不思議でなく、「いつごろ」の意になる。又「方」の方も方角を示すのが普通であるが、「明け方」「朝方」など時に用ゐる例があり、集中にも「夜中乃方」 (7・1225) の例があるから、「方」を時間的なものと考へ得る余地もあり得る。そしてその「へ」と「かた」との結び付きについては、「於伎敝能可多 (オキベノカタ)」 (15・3624) の例があり、それは方角場所の例であるが、時間の場合にも可能である。以上が野中君の論の要旨であるが、その前半、即ち「何時」をイツと訓み、時間の意に解く説は、従来の説を明快に訂したものと思はれる。しかし後半、即ち「邊乃方」もまた時間と解する事はどうであらうか。推論としては認められるが存在の実証のないところにいささか疑問が残されてゐる。そこにあげられた例は皆場所のものであつて、時間のものではない。「春べ」「夕べ」はたしかにあるのだから、「いつべ」もあり得るといふところまでは推定として認められる。しかしその推定のうへに、更に「べの方」といふ推定の語を重ねるといふ点がどうであらうか。「夜中乃方」の「方」を時間に見る事は疑はしく、他に集中「方」を時間に用ゐた例はない。仏足石の歌に、 於保美阿止乎 美尓久留比止乃 伊尓志加多 知与乃都美佐閇 保呂夫止曽伊布 乃曽久止叙伎久 (オホミアトヲ ミニクルヒトノ イニシカタ チヨノツミサヘ ホロブトゾイフ ノゾクトゾキク) とある、その「いにし方」は時間である。しかしこれは今日も用ゐる「過ぎにし方」などと同じく、うなづけるものであるが、「春べの方」といふ風な例は無い。従来の一句全体を場所的に解釈する説に対して一句全体を時間的に解するといふ事は、徹底した新見のやうであるが、「いつへの方」を全部時間と見る事は実証の無い事であり、これはやはり代匠記の説そのままへ復帰すべきではなからうか。「何時」は時である。「邊の方」は所である。「邊」は「奥見者 跡位浪立 邊見者 白浪散動 (オキミレバ トヰナミタチ ヘミレバ シラナミサワク)」 (2・220) の「邊」である。奥 (沖) と相対して用ゐられる場合が多いが、「風高 邊者雖吹 (カゼタカク ヘニハフケドモ)」 (4・782)、「大海 方往浪之 (オホウミノ ヘニユクナミノ)」 (10・1920) などの如く「邊」とだけ用ゐられる場合もある。雲や霧を海にたとへる事は古今東西に例のある事であるが、その霧のさ中を「おき」と呼び、次第に薄れゆくはてを「へ」と呼ぶ事は十分考へられる事である。代匠記に「田ノ其カタハラナリ」とあるは少し適切を缼いて誤解のおそれがある。霧の消え果るところである。即ち朝霧のいづこをはてとも知られぬやうに立ちこめてはゐるが、いつかはしの方へ流れゆきて晴れ渡るやうに、といふのである。と同時にあやめもわかぬ戀のさ中を「おき」にたとへ、戀のはつるところを「へ」にたとへる事も認められるところだと思ふ。即ち戀のやむ彼岸が「邊の方」である。「いつ」は戀のやむ時であり、「への方」は戀のやむ状態である。その二つをうけて「我が戀やまむ」と云つたと見るのである。ただその二つに分けたところ、やや小刻みに過ぎ、特にこの一首のおほらかな声調にふさはない難があるやうに見える。「いついづこへ」といふ風な意であればまだよい。「いつ」と云つて「邊の方」とことわつたところに難があるとも見られよう。その点なほ考慮の余地があらうと思ふが、従来の如く一句全体を場所方角に見ればこそ、井上氏新考の如く「将息 (ヤマム)」は「将遣 (ヤラム)」の誤といふ疑も起こるのであり、右の如く見れば四五句の結び付きは極めて順調になる。集中「おもひ」を「やる」と云つた例はあるが、「戀」を「やる」と云つた例はない。「戀」に「なぐ」とあるもの二例、「すぐ」とあるもの二例、「盡す」とあるもの六例、「やむ」とあるもの十七例。今はその最も用例の多い「やむ」が用ゐられたものと見るべきである。さてその「やむ」といふのは思ひが遂げられて戀が消えるといふのか、ただ思ひ忘れるといふのか、作者はそこまでは云つてゐないのである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 89 | 居明而 (ゐあかして) | 全注 | 「ヰル」が元来坐っている状態をいう語であるが、ここは閨に入って寝ず、戸外で夜を明かすことを「ヰアカス」と言ったんであろう。古典全集に「居明カスがすわったまま夜を明かす意であるとすれば、この歌の作者は霜に降られて外にすわっていたことになる。おそらく、八十七の歌の初句を部分的に差し替えた結果、このような矛盾が生じたのであろう。」と記すのは、「ヰル」の意味を限定しすぎるのではあるまいか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 居明して-「乎里安加之 (ヲリアカシ) 許余比波能麻牟 (コヨヒハノマム)」 (18・4068) といふ仮名書例があるので、「ヲリアカシテ」と訓む説もあるが、「座待月 (ヰマチヅキ)」 (3・388)、「花乎居令散 (ハナヲヰチラシ)」 (9・1755) の如く「ゐー」とつづくと思はれる例があるから、「ヰアカシテ」と訓んでよい。閨 (ネヤ) に入らずに、かうしてこのまま居て待つこと。霜云々とあるから端近いところに腰かけなどしてゐると見てもよいだろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 初句「をりあかして」は、「ゐあかして」とも訓み得るが、後者の場合は「座ったまま夜を明かして」の意となるので、前者の訓を採る。本居宣長は、「居り明かす」の語について、「大かた此たぐひの居 (をり) は、ただ一わたり軽くつねに云ふとはかはりて、夜寝ずに、起きて居 (ゐ) る意也、軽く見るべからず」 (玉勝間十四・夜寝ず起きてゐるを居 (をり)と云へる事 ) と指摘している。「居りあかしも (乎里安加之母) 今夜は飲まむほととぎす明けむ朝は鳴き渡らむそ」 (4068)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぬばたまの | 新全集 | 黒、夜などの枕詞。「ぬばたま」はアヤメ科の多年草ひおうぎ (射干) の実。夏黄赤色に暗紅点を散らしたような六弁の花を開き、花後の蒴果 (さつか) が割れると光沢のある種子が現れる。その濃黒色をもって比喩とした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 「ぬばたま」は集中「野干玉」「夜干玉」とも書かれてゐるので、本草和名に「射干」に「一名烏扇」とも注し、「和名加良須阿布岐 (カラスアフキ)」とあつて、あやめ科の植物で葉の重なり開いた状、檜扇の形に似てゐるので今は「ひあふぎ」と呼ぶ、その実を「ぬば玉」と云つたらしく、色が黒いので「黒」「夜」などの枕詞とした、といふのが従来の説であつた。然るに、 烏玉 間開乍 貫緒 縛依 後相物春 (11・2448) (ヌバタマノ アヒダアケツツ ヌケルヲモ ククリヨスレバ ノチアフモノヲ) の條で引用するやうに、私注に、その「烏玉」を「草の実とも思はれぬ。黒い珠玉の意であらう。」といひ「ヒアフギの実をヌバタマといふのは、反つて第二次的稱呼であるかも知れぬ。数多い枕詞としてのヌバタマノも黒真珠などから来たと考へるのが、自然にも思はれる。」といひ、その後佐竹昭廣君は「古代日本語に於ける色名の性格」 (国語・国文第二十四巻第六号昭和三十年六月) の中で、「烏扇の実」が最初からヌバタマと云はれてゐたのなら、桑の実をクハコ、鰒の玉をアハビタマといふやうに、烏扇そのものはヌバと呼ばれさうなはずであるが、さういふ事実は認められない。一方ヌバタマは「黒玉」「烏玉」と書かれてゐる。それを従来は野干玉が黒いからと説明したのであるが、それは逆で、「黒玉」がヌバタマの語の本義で、烏扇の実も黒いからヌバタマと呼ぶやうになつた、シラタマが白い玉の義であるが、また真珠をも呼ぶやうになつたのと同じである、とし、そのヌバの語原は「m-b」音の交替が国語史を通じて活発に行はれてゐるところからヌマ (沼) と結びつける事が出来る。そしてそのヌマは「何となく濁つて泥深い気持ちをたたえて」をり、その「《泥》とか、もしくはその周辺の意味が、色彩的に黒ずんだ感を常に視覚上の印象として、人に与えるところ」があると云ひ、《泥》を表はす語が、次第に《黒》を表はす語となるので、アイヌ語にも《黒》を意味する「Nupur」といふ形容詞があり、一方「Nupki」《泥だらけになる、濁水の如く濃厚になる》の「ki」の語尾を除くと「Nup」といふ名詞となり、「Nupur」の語幹と同じものと認められる、などといふ例証があげられてゐる。委しくは同君の論を参照せられたく、沼と黒との関係についてはなほ異論もあらうが、佐竹君も云はれてゐる如く、上代にクロタマの語が見当たらないところを見ると、黒玉の事をヌバタマと云つたと思はれ、それが「ぬば玉」の本義と思はれる。ただ白玉が「真珠」 (16・3814、19・4169) と書かれてゐるものになるとその文字通り真珠をさす事になつたやうに、特に「野干玉」「夜干玉」と書かれてゐるものの多いところを見ると当時既に烏扇の実をヌバタマとも呼ぶに至つてゐた事は認められる。参考の為にその用字例をあげると(仮名書は記紀に3、万葉に22)、
この用字例から「ぬば玉」はたしかに黒い玉、それもただ黒いといふのではなく、後世も「濡れ烏」といふ言葉もあるやうに、烏の濡れ羽を思はせる美しい黒い玉を「ぬば玉」と呼ばれるに至つてゐた-それは薬草として当時の人達には今の人よりもはるかに親しまれてゐた事は、典薬式のあちこちにも、名の見える事によつても認められる-ので、単なる黒玉の義訓としてよりも、やはり烏扇の実とも考へて用ゐられるに至つたと解釈すべきであらう。人麻呂及び人麻呂集の用字と家持のそれとが対照的になつてゐる事も注意されてよい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霜者零騰文 (しもはふるとも) |
全注 | 全注訓釈〔しもはふれども〕 原文「霜者零騰文」。「シモハフルトモ」とも訓む (佐佐木評釈・窪田評釈・私注・古典全集・古典集成など)。「騰」は万葉集では普通濁音ド (乙) の仮名として用いられる。本巻に「顧みすれ騰」 (2・131、135) 、「深めて思へ騰」 (2・135) などがあるが、例外的に清音ト (乙) の仮名としても用いられる (巻2・5・17・20など)。「念へる碁騰 (ゴト)」 (2・112)、「騰遠依 (トヲヨル)」 (2・217) などが本巻にも見える。ただしそれらは、あくまでも例外で、濁音仮名の用例を主とするから、人麻呂の「恐有騰文」 (2・199) を「恐かれども」と訓むのと同様に、ここも「シモハフレドモ」とするのが穏やかだろう。逆接で霜は降りているけれど、も意。「フルトモ」と訓んでも、同じく確定条件に解するのが良いと思われる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 結句「霜は降るとも」の原文「騰」は濁音ドの仮名であることが多いが、清音トを表す例もある〔2・112参照〕。また、接続助詞「とも」は普通は仮定条件を表すが、「志賀の大わだ淀むとも」 (1・31) や「待ちかねて内には入らじ白栲の我が衣手に露は置きぬとも」 (11・2688) など、既定の事実を仮定的に表現することがある。万葉集には、右の「2688」の他にも、「君待つと庭のみ居ればうちなびく我が黒髪に霜そ置きにける」 (12・3044) の如く、男の訪れを露霜に濡れながら待ち続ける女の心を歌うことが多く、古今集にも、「君来ずは寝屋へも入らじ濃紫わが元結に霜は置くとも」 (恋四) などとある。そのような類型に属する歌と理解される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 左注右一首古歌集中出 | 注釈 | 古歌集といふ名が、巻七、九、十一などに見える。これを一つの定つた歌集と見る説もあるが、わからない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 「1267・1270・1938」などにも見える。特定の歌集名か、単なる古い歌集をいうか不明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 左注に引く「古歌集」の名は、162題詞細注、巻七 (1267・1270)・巻十 (1938)・巻十一 (2367) の左注にも見える。如何なる歌集であったか、不明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 「古歌集について」 古歌集は、万葉集編纂の資料となった歌集の一つ。巻ニのほか、七・九・十・十一の諸巻にも見え、長歌・短歌・旋頭歌を含んでいる。歌の内容や性格から持統朝以後奈良朝初期にかけての歌を集めたものと推測されるが、編者や歌集の体裁など未詳。巻七・九に見える「古集」と同じものであったかどうかも明らかでない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 90 | 題詞・左注について | 注釈 | 題詞「古事記曰。軽太子奸軽太郎女。故其太子流於伊豫湯也。此時衣通王 不堪戀慕而追徃時歌曰」 これは「85歌」の作の参考として允恭記を引用したものである。但原文のままの引用ではない。記には「天皇崩之後。定木梨之軽太子、所知日継、未即位之間、姧其伊呂妹軽大郎女」とあつて、軽太子は允恭天皇の御子、皇太子に定まつてゐたのであつた。そして軽大郎女 (諸本に「太」とあるが、古事記に「大」とあるによるべきである) はその同母妹で、衣通王の名についても、允恭記のはじめのところに「軽大郎女、亦名衣通郎女。」とし、注して「御名所以負衣通王者、其身之光、自衣通出也。」とある。衣通王を古今集の序には「そとほりひめ」とあるのでソトホリとも訓まれてゐるが、応神記に「登富志郎女 (トホシノイラツメ)」とも「藤原之琴節 (コトフシ) 郎女」ともあると今の衣通王とを記伝 (三十二、三十四) に同人とし、その「コトフシ」は「ソトホシ」と相通ずる音であると述べて「衣通は、曽登富志 (ソトホシ) と訓べし、」と云つてゐるのに従ふ。 左注「右一首歌古事記与類聚歌林所説不同歌主亦異焉」 これは右 (90歌) の作が、古事記には允恭記の物語として軽大郎女の作とし、類聚歌林で (85歌) の作を仁徳天皇の皇后の御作としてゐる事を注意したもので、それについて更に次の如く日本書紀を引用したのである。 「因檢日本紀曰難波高津宮御宇大鷦鷯天皇廿二年春正月天皇語皇后納八田皇女将為妃 時皇后不聴 爰天皇歌以乞於皇后云々」 現存日本書紀には「語皇后」の下に「曰」の文字があるのみで、他は同文である。 「八田皇女」は応神天皇の皇女。菟道稚郎子皇子 (ウヂノワキイラツコノミコ) の同母妹。即ち仁徳天皇には異母妹である。「聴」前田家本に「ウケユルサズ」と傍訓す。 「卅年秋九月乙卯朔乙丑皇后遊行紀伊國到熊野岬 取其處之御綱葉而還 於是天皇伺皇后不在而娶八田皇女納於宮中時皇后 到難波濟 聞天皇合八田皇女大恨之云々」 現存の書紀には「紀伊国」を「紀国」とし、「取」の上に「即」あり、「葉」の下に「葉此云箇始婆 (カシハ)」の注があり、「大恨」の上に「而」がある。 「御綱葉」は古事記に御綱柏とある。三津野柏 (造酒司式)、御角柏 (皇太神宮儀式帳) とも書かれてゐる。三角柏の意と云はれてゐるが、今の柏でなく、うこぎ科のかくれみので、その葉は倒卵形であるが、五裂又は三裂のものがあるので、それを云つたものであらう。神事に酒を盛るに用ゐる。 「亦曰 遠飛鳥宮御宇雄朝嬬稚子宿祢天皇廿三年春三月甲午朔庚子 木梨軽皇子為太子 容姿佳麗見者自感 同母妹軽太娘皇女亦艶妙也云々 遂竊通乃悒懐少息 廿四年夏六月御羮汁凝以作氷 天皇異之卜其所由 卜者曰 有内乱 盖親々相奸乎云々 仍移太娘皇女於伊豫者 今案二代二時不見此歌也」 「遠飛鳥宮」は後の飛鳥宮 (1・22標題) などとほぼ同じ。「雄朝嬬稚子宿禰天皇」とは允恭天皇である。 「二十三年」以下允恭記の文である。春三月が諸本多く「正月」とあるが、金澤本などに「三月」とあるが正しい。現存書紀には「立木梨軽皇子」とある。「太娘」 (二つとも) は紀に「大娘」とあるが正しい。「羮汁」の上に「御膳」あり、「仍移」以下「則流軽大娘皇女於伊予」とある。「二代云々」とは右の仁徳、允恭両帝の御代に万葉のこの作を載せない事を云つたのである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 〔原古事記についての新説〕 前の「85歌」に酷似した歌が古事記に見えるので、類歌として注記したものである。ただし、引用文も歌の表記も現存古事記と異なっている。当該の部分を古事記から摘記すれば、次の通り。 未即位之間、姧其伊呂妹軽大郎女而歌曰、(中略) 故、其軽太子者流於伊余湯也。亦将流之時、歌曰 (中略)、故後亦不堪戀慕而追往時歌曰、 岐美賀由岐 気那賀久那理奴 夜麻多豆能 牟加閇袁由加牟 麻都尓波麻多士 (キミガユキ ケナガクナリヌ ヤマタヅノ ムカヘヲユカム マツニハマタジ) 此云山多豆者是今造木者也 巻二の引用は、古事記の文章を要約した上、「中略」の部分に挿入されている歌及び文を省略し、一字一音の音仮名表記の歌謡を正訓字主体表記に改めているのである。これは万葉集の編纂者の書き改めと見られよう(注釈)。これを現存古事記よりも前の形、しなわち「天武本古事記」からの引用ではないかとする説も提出されたのであるが (西宮一民「古事記の成立」『論集古事記の成立』)、神野志隆光の批判もあるように (「『万葉集』に引用された『古事記』をめぐって」『論集上代文学』第十冊)、この注から、原古事記の体裁を推定することはできない。
〔注記の時期〕 類聚歌林によると「85歌」は磐姫皇后作であるが、その類歌の「90歌」は古事記に軽大郎女作となっており、作歌事情も甚だ異なっているので、編者が不審を抱き、書紀を検し、仁徳紀にも允恭紀にもこのような歌の見えないことを記したのである。「85歌」の注とともに、類聚歌林や書紀の成書化以後の注であることは言うまでもない。巻二の原型成立を元明朝とする説 (伊藤博『万葉集の構造と成立』下) が正しいとすれば、それ以後の作と考えられる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 91 | 家母有猿尾 (いへもあらましを) |
全注 | 鏡王女の家もあったらよいものを、の意。この「家」を、作者天智天皇の家とするか、鏡王女の家とするか、説が分かれる。代匠記 (初稿本) は「大しまみねにおはしまさましをなり」と記すのをはじめ、江戸時代の諸注はほとんど前者 (天智説) であったが、木村正辞の「万葉集美夫君志」に後者 (鏡王女説) とし、講義にも「これを繰返と見ずしては上下の打合都合せず」と評してから、後者に同調する注者も多い。最近では、古典大系 (岩波書店) ・注釈 (澤瀉久孝) ・古典全集 (小学館) など後説であり、わずかに全註釈 (武田祐吉) と古典集成 (新潮社) が前説によっている。ここでは、作者が大島の嶺の眺められる場所にいて、「妹が家を継ぎて見ましを」と歌ったものと考えられ、「妹が家も」の「モ」を、「ヲモ」
(添加) の意とすれば、大島の嶺の見えるのに加えて、妹の家も見えたらよい、と解するほうがよいだろう。そうすると、講義や茂吉秀歌の言うように、第二句と第五句は、密接な関連を持ち、同じ内容の繰返しに近いものになる。 異伝「家居らましを」 この家は、作者の家。巻十九に「谷近く伊敝波乎礼騰母 (イヘハヲレドモ)」 (19・4209) とある。「家居る」の主語は天智天皇となる。『万葉古徑』に「家居る」の語だけについて言えば他人にも自分にも用いるが、上句との関係から「見む」と「家居る」の主語を別々に考えることが無理なので、この異伝では、作者の「家居る」ことを意味すると記されている通りであろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 異伝「家居り」は、家を造り、そこに住むこと。主語は作者の天智天皇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | この「家」を従来作者、即ち天皇の家と解釈してゐたが、講義にこの作は上二句と下三句と二段落より成り、同意の繰返しであるから、上の「妹が家」と下の「家」とは同じものでなければ上下相応しないとして、下の「家」も「妹が家」とせられたのに従ふべきである。従つて大島の嶺は、作者のゐるところより眺められる山でなければならない。然るにもし作者が近江の大津宮に居られたのだとすると大和の山は眺められない。そこで題詞の條で述べたやうに作者の位置を難波の地だとすると大和境の生駒、二上、葛城、金剛の山々が見渡される事になつて、そのうちに大島の嶺を求めればこの歌は極めて適切に解釈する事が出来る。今大島といふ名の山はないが、攷証に日本後紀の大同三年九月十九日の條に、 いかに吹く風にあればか於保志萬(オホシマ)の尾花の末を吹き結びたる の歌のある事に注意し、その作者平群朝臣賀是麿が大和平群郡の人と思はれるから、この大島も「平群郡なるべし」と云つてゐる。平群郡といふのは今の生駒郡の一部で、生駒山の南につづく信貴山の東麓、竜田川に至るあたりである。それで今大島の名は残つてゐないが、その邊に大島といふ地があり、その山の頂を大島の嶺と云つたとすると、それは今の信貴山、あるいはそのあたりの一峯といふ事になる。これは単なる推定に過ぎないが、かう考へるとこの歌は無理なく解く事が出来るので私按として提出する (『古徑』三所収「『大島嶺』攷」参照)。 異伝「家居らましを」 「妹があたりつぎても見むに」とある方には第五句もかうあるといふので、家居をしてをらうものを、の意で、本文の「家もあらましを」といふのと似てゐるが、少し云ひ方が違つてゐる。講義にはこれも「意は大略異なることなし」と云つて、やはりこれもその家が妹の家と考へられてゐるやうである。しかし本文のやうであれば「家」が主格になつてゐて、家があつたら、といふのであるから、その家を-といふ事になり、「妹が家もつぎて見ましを」のくりかへしになるが、「家居らましを」では「家」が主格でなく、「家居る」主があるわけであり、その主は自分でも人でもよいわけで、「梅花 開有岳邊尓 家居者 (ウメノハナ サケルヲカヘニ イヘヲレバ)」 (10・1820) といふのは作者であり、「谷可多頭伎氐 家居有 君之聞都々 (タニカタヅキテ イヘヲレル キミガキキツツ)」 (19・4207) は相手であるが、今の場合は右に述べた如く、上の句から一つづきの文になつてゐるので、もし「居る」の主格を鏡女王だとすると、上の句の「見る」の主格とあはぬ事になり、一つの文で中途から主格が違ふ事になる。これは本文の場合上の句と下の句との「家」が同じ鏡女王に家と見るべきと同じく、一云の場合は「見る」と「居る」との主を共に作者と見るべきである。即ちこの御作は本文によれば、山の上に妹の家を眺めようといふのであり、一云によれば作者が山の上に家居して妹のあたりを眺めようといふのである (『古徑』一所収「『家もあらましを』と『家居らましを』」参照)。かういふ風に解釈を異にした二つの作が並存したので、その両作の解釈を可能ならしめる為にも大島嶺といふのが、作者の位置からも、妹の位置からも眺められるやうな山、即ち右に述べたやうな推定が必要だと考へられる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猿尾 (ましを) | 注釈 | 「猿」を「ましら」と云ふ事は、 哀哉檜原杉原風さびてましらも鳥もかしましきさへ (拾玉集巻五) などあつて、誰も知るところであるが、紫式部集に、
とあり、色葉字類抄 (中) にもマシとあつて、古くは「まし」とのみ云つたものと思はれ、今の助動詞「まし」の借訓に用ゐたのであるが、その「猿」の連想から「尾」の文字を用ゐて戯書風な借字とした。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 「まし」は、現在そうでないことを、 ~ならばと仮想し、その上で推量するので、自ずから希望の意となる。助動詞「まし」に「猿」の字を当てた例、後出 (120・510)。「猿尾」は戯書的表記。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 92 | 題詞「和(御)歌」について | 全注 | 題詞原文「鏡王女奉和御歌一首」。元暦校本・紀州本・西本願寺本など、この後に「鏡王女又曰額田姫王也」の十字を小書きするが、金澤本・大矢本によって削る。前歌に対して、王女のお答え申し上げた歌である。ここに鏡王女の歌を「御歌」と記すのは、巻二の額田王作歌
(155に「作歌」とある) の扱いとは違った王女の地位を示していると思われる。 〔考〕和ふる歌 万葉集では「和歌」「報歌」のいずれも「コタフルウタ」と読まれるが、両者の内容には相違がある。「報歌」が、贈歌と対等の立場で正面からぶつかり合い、しっぺ返しの意味の強いものが多いのに対して、「和歌」は、もとの歌をあくまでも主としつつ従の立場で添い合わされ、心情的にもとの歌に近似し共鳴する内容のものが多い (橋本四郎「幇間歌人佐伯赤麻呂」『上代の言語と文学』)。この鏡王女の「和歌」も、天皇の御製に対して反撥しぶつかり合うわけでなく、それを受けて並行的に近似した感情を歌い上げている。人目につきやすい大島の嶺に家があったらよいのにという天皇の歌に対し、人目に立たず流れてゆく水を比喩とする王女の歌からは虔ましい人柄まで想像されてくるようだ。なお講談社文庫に、この贈答の作意を「宮廷の奉仕をおえて本郷へ退出する時の挨拶歌」と記し、顕宗記の置目老媼の場合と同じと言う。興味深い想像であるが、近江の置女の場合と同じように考えられるかどうか、問題であろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | ここに御歌とあり、御歌とあるは皇子・皇女までに限られてゐる例に反するやうに見えたので、誤字説が行はれたり、「御歌に和へ奉る」と訓まれたり、してゐたが、(中略) 鏡女王を舒明天皇の皇女とすれば、この題詞のままでよい事になる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御念従者 (おもほすよりは) |
全注 | 「御念」の二字を「ミホモヒ」と訓むことが広く行われてきたが (旧訓をはじめ、最近の注釈書では窪田評釈・佐佐木評釈・私注・古典大系・講談社文庫など)、しかし、「御念」を「ミオモヒ」と訓む例は集内になく、「物莫御念」 (1・77)、「御念八君」 (3・330) のように「オモホシ(ス)」の例ばかりだし (全註釈)、また「ミオモヒヨリハ」と訓むと句中に単独母音を含む七音句となり、結句の準不足音不足音句の数少ない例となる。木下正俊「準不足音句考」 (『万葉集語法の研究』) によると、巻二の準不足音句は「安見兒衣多利 (ヤスミコエタリ)」 (2・95)、「妹尓不相而 (イモニアハズテ)」 (2・125)、「真浦悲毛 (マウラガナシモ)」 (2・189)、「待乍将有 (マチツツアラム)」 (2・223) と、この「御念従者」のみであり、しかもそのうち「125歌」は「イモニアハズシテ」、「223歌」は「マチツツアルラム」と改訓しうるものである。したがって、この場合も「オモホスヨリハ」と訓み、準不足音句となるのを避ける方が良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 〔われこそ増さめ思ほすよりは〕 原文「益目」「御念」とあるので、「ワコソマサラメ」「オモホサムヨハ」と訓む説などがある。講義に「ます」は量の加はる意、「まさる」は比較していふ語、とあるが、それは現在の通例であつて、本来はさうした区別はない。 旅にして物思ふ時に霍公鳥もとなな鳴きそ安我古非麻左流 (アガコヒマサル) (15・3781) の如く、「まさる」と云つて「増す」「募る」など量の加はる意に用ゐられた例が最も多く集中約三十例。 年にありて一夜妹に逢ふ彦星も和礼尓麻佐里弖 (ワレニマサリテ) 思ふらめやも (15・3657) のやうに、「まさる」と云つて比較に用ゐたもの約二十例。 逢はずして恋ひわたるとも忘れめやいや日に異には思益等母 (オモヒマストモ) (12・2882) の如く、マスと訓んで「増す」の意に用ゐたと思はれるもの約十例。 宇陀の野の秋萩しのぎ鳴く鹿も妻に恋ふらく我者不益 (ワレニハマサジ) (8・1609) のやうに、マスと訓んで比較の意に用ゐたと思はれるもの三例あまり。従つて今もマスと訓んで、比較の意にとる事不都合でなく、声調の上からワレコソマサメの訓を採る。これに対してワガコソと訓む説もあつた。これは下の「御念」をミオモヒと訓めば、それに対してワガオモヒの省略と見るのであるが、「御念 (ミオモヒ)」といふ言葉が先にあつて、それを受けて「わが」といふのであればうなづかれるが、突然「わがこそ」といふのは不自然であり、従ひ難い。さてワレコソと訓むとまたミオモヒでは語法にかなはないといふ事になる。「君がお思ひになりますよりは」といふ風の言葉であるべきだと考へられる。元暦校本に、「みおもひよりは」とした右に朱筆で「御本云オモホスヨリハ」とあり、古義に「オモホサムヨハと訓べし、自将御念者の意なり」としたのはそこを考へての事と思はれる。しかし「御念」を動詞として訓む事は何となくおちつかず、ミオモヒとした方がはつきりするやうにも思はれる。そこで「当時の思考論理をそれ程までに考へるにもあたるまい」 (私注) とも考へられ、語法の無理は時々ある (2・99) 事ゆえ、ミオモヒと訓んでもよささうに思はれ、さてこそミオモヒの訓が今日では定説と考へられるやうになつてゐるのである。しかし又ここで、も一つ考へられる事は、ミオモヒヨリハと訓むとこの句は「オ」といふ単独母音節を含む七音の結句といふ事になる。然るに木下正俊君の調によると、結句にア行音を中間に含む七音句は極めて少なく、その場合は大抵八音句になるのが例だといふ事である。この調査は尊重すべきものだと私は考へる。たとへば従来ア行音を含む七音句と認められてゐたもので八音に訓み改むべき例がいくつもある。「妹尓不相而 (イモニアハズシテ)」 (2・125)、「待乍将有(マチツツアルラム)」 (2・223)、「淵有乞 (フチニシアリコソ)」 (3・335)、「莫思吾背子 (ナオモヒワガセコ)」 (4・538)、「令還念者 (カヘサクオモヘバ)」 (4・631) など従来いづれも七音に訓まれがちであつたが、右の如く八音に改めらるべきものである。それを思ふと今もミオモヒヨリハと中間にオ音を含む七音の結句は少し軽すぎる感がせられ、そこで右にあげた元暦校本に引く御本の訓や古義の訓が改めても一度かへりみられるといふ事になる。「御念」をミオモヒと訓む事は極めて当然な訓み方で、問題がないやうに思はれるが、集中の実例を調べると、「み思ひ」といふ言葉は他に一例も無くて、「御念」の文字をオモホシ、オモホスなどと訓んだ例は既に前に「御念食 (オモホシメセ)」 (1・29)、「物莫御念 (モノナモノホシ)」 (1・77) があつたし、この巻にも「御念食 (オモホシメセ)」 (2・167) があり、また「御念八」 (3・330)、その他がある。これは「念 (オモフ)」の場合に限らず「御」を敬語の動詞の表記にした例は、「御食而肥座 (メシテコエマセ)」 (8・1460)、「神思将御知 (カミシシラサム)」 (12・3100)、「御見多麻波牟曽 (メシタマハムゾ)」 (19・4228) などいくつも例のある事である。かういふ事実を見ると今の「御念」もオモホスと訓む方が通例に従ふ事になる。そして又用言に「よりは」をつづけたものとしては「物言従者 (モノイフヨリハ)」 (3・341)、「将待従者 (マツラムヨリハ)」 (11・2831)、「故布登伊敷欲利波 (コフトイフヨリハ)」 (18・4080) などがある。かういふ風に考察してくると、オモホスヨリハといふ訓み方こそ最も自然な訓み方だといふ事になる。これならば中間にア行音を含まぬ七音句となり、「吾こそまさめ」に対する語法としても無理がない事になる。但、結局ア行音を含む七音句が無いわけではなく、現に「真浦悲毛 (マウラカナシモ)」 (2・189)、「宮敷座 (ミヤシキイマス)」 (3・235或本)、「用伊母祢奈久尓 (ヨイモネナクニ)」 (5・831) の如きも少しはあるのだから、今もミオモヒヨリハが絶対に不可だといふのではない。しかしオモホスヨリハと較べる時には、右に述べたやうに、後者を穏当とすべきであると私は考へる。即ち元暦校本以前の古本の古訓にかへし、君が思ひになるよりは、と解くのである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 93 | 題詞中「娉」用例 | 新大系 | 万葉集の題詞・左注に用いられる「娉 (よばふ)」字は、他に五例見える。「96題詞・101題詞・407題詞・528左注・3788題詞」 いずれも求婚する意。説文解字に「娉、問也」とある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 君名者雖有 吾名之惜裳 (きみがなはあれど わがなしをしも) |
注釈 | [訓釈] この句は、君が名の立つはともかくとして、我が名の立つ事の惜しさよ、といふやうな意に解くべきだとは感ぜられるが、これに類する「~はあれど~」がいろいろあり、その語法上の説明としてはまだ定説と認むべきものが無い。それについて佐伯梅友博士に「みちのくはいづくはあれど」 (『万葉語研究』所収) がある。 みちのくはいづくはあれどしほがまの浦こぐ舟の綱手かなしも (古今集巻20-1088) を、古今集遠望に「奥州ニハドコニモカシコニモ面白イ所ハオホクアレドモ、中デモ此塩竃ノ浦ヲ、アレ綱手デ船ヲ引テユクアノケシキガ、ドウモイヘタ物デハナイ、オモシロイコトヂヤワマア。」と訳され、それが通説になつてゐるが、それだとその「あれど」の「あり」は「ここに何々がある」といふ「存在」の「あり」になるわけだが、これは「かなしくあり」などの「陳述」の「あり」と見るべきものであり、又「いづくも」とあれば右の解釈でよいが、「いづくは」として、「あれど」とあるのだから、下の塩竃の「かなしも」と反対に、「いづくはかなしからずあれど」即ち「他のどこも面白くないがといふ意未になるのではなからうか。」と述べられ、その例として(一)今の歌や、 (二) 妹とありし時者安礼杼毛(トキハアレドモ)別れては衣手寒きものにぞありける (15・3591) (三) 故郷の飛鳥者雖有(アスカハアレド)あをによし奈良の明日香を見らくしよしも (6・992) (四) 筑波嶺の新桑繭の伎奴波安礼杼(キヌハアレド)君が御衣しあやに着欲しも (14・3350) なども同じやうに解釈すべきものだとし、今の歌の場合は「あれど」の上に「惜しからず」の語を、(二)の場合は「寒からず」の語を、それぞれ省略されたものとせられた。誠に語法の説明としては論理のよく通つた説であるが、歌の解釈としては何となく風情の乏しいものになる憾がある。そこで大濱巌比古君は「いもとありしときはあれども」 (万葉第十五号、昭和三十年四月) で、これらの「あり」はいづれも存在の「あり」であるとし、(二)の例は「妹と一緒だつた時としてあるが」と訳し、(一)も「君が名」と「吾が名」とのそこに存在する二者の比較から「吾が名」に就いての述懐がなされるので、やはり存在の「あり」と見なければなるまい、とし、「みちのく」の歌は、「みちのくは名所は何所何所とはあるが、同じ名所でもとりわけて塩竃の浦は、浦こぐ舟のつな手をまつて最も趣きがあるよ」となる、と云はれてゐる。そして存在の「あり」が陳述の「あり」と紛れて考へあっれるのは「具体的な地名とか着物とかいふものについては『あり』の存在性がそのまま把握され易く、時とか名とかいづくとかいつた抽象的なものについては、存在性が主題の抽象性の影響を受けて抽象化され、一見して陳述性の如き錯覚を『あり』に与えることによるのであらう。」と述べられてゐる。これは佐伯君の少し割り切り過ぎたと思はれるところを是正されようとしたもので、「みちのく」の解釈など注意すべき見解であるが、すべてを「存在」とされる点にまた行き過ぎがあるのではなからうか。殊に「(三)・ (四)」の場合については両君とも「はあれど」の点にのみ拘泥され過ぎた憾があるやうに私は見るので、それについてはそれらの作の條で私見を述べる事にするが、少なくも今の歌の場合は佐伯君の説明が当つてゐると考へる。ただ「惜しからず」といふやうな言葉を補つて訳するといふ事は穏かでなく、作者ははじめからそれを云つてはゐないのであり、もし相手が「私の名はどうでもよいのですか」と聞きかへしたら、「何もどうでもいいと云つてるのではありませんワ。~あれど、と云つただけよ」とほほゑむつもりであらう。さればこそ相手は「さねずはつひに」 (2・94) といふ事にもなるのではなからうか。現代語には「あれど」といふ言葉がない為に、それはそれとして、とか、ともかくとして、とか云ひかへてみるのであるが、ほんとはそれも野暮つたい冗言といふ事になるのではなからうか。「名し」の「し」は強意の助詞。「も」は詠歎の助詞。 [考] 「わが名惜しも」といふのはエゴイストの考のやうで、 我が名はも千名(ちな)の五百名(いほな)に立ちぬとも君が名立たば惜しみこそ泣け (4・731) 坂上大嬢 といふのが女心らしいやうに思はれる。そこで四五句の「君」と「吾」とが入れ替わるべきだといふ説 (代匠記、その他) もあり、既に早く古今六帖には、 玉櫛笥覆ふを安み明けゆかば我が名はありとも君が名し惜しも (第五「名を惜しむ」) とあり、同書 (五) 「たまくしげ」の條には第三句「明けたらば」とし、四五句また右の如くなつてゐる。しかし「君が名立てば惜しみこそ」と泣いたのは、後にその歌を贈つた家持の貞淑な妻となつた坂上大嬢であり、「吾が名し惜しも」と云つたのは右に述べたやうな身分の鎌足に対して、皇太子の寵も得てゐられた鏡女王である。「吾が名し惜しも」で不都合はない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 「~ハアレド」は、「ふるさとの飛鳥はあれど」 (6・992) や「筑波嶺の新桑まよのきぬはあれど」 (14・3350) などのように、「~はともかく」の意で、下句の内容を強調する表現である
(注釈・古典全集など)。代匠記に「吾が名は千名の五百名に立ちぬとも君が名立たば惜しみこそ泣け」 (4・731坂上大嬢) の歌をあげ、古今六帖に「我が名はありとも君が名惜しも」というかたちでこの歌ののせられていることを引いて、「君」と「我」とが入れ替えられたものと推測したのは
(略解など同説)、恣意的に過ぎる。なお結句の「惜裳」を西本願所本などに「惜毛」と伝えているが、金澤本・元暦校本などの本文による。 [考] 相聞歌と歌垣の歌 求婚の歌の源流は歌垣の掛け合い歌に求められる。歌垣の求婚問答には、女から男に問い掛けられる場合と、男から問い掛ける場合と二種類あって、前者は、婿選び型で、女の方に主導権があり、一般には母系制社会のもので、父権制社会では身分の高い家の娘が婿を選ぶ場合に限られるのに対し、後者は父権制社会における嫁選びの方法だったという (土橋寛『古代歌謡全注釈』93頁)。この歌は、「わが名し惜しも」と、求婚を柔らかく拒む歌であるが、「あけていなば」とも言われていて、「王女は拒んだにもかかわらず帰ろうとせず、夜明けまでも居そうなので、帰りを促す心で」歌われたものとも (窪田評釈)、「すでに女の家に通って居る場合」の歌とも (私注)、受け取られる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 94 | 題詞「報贈」 (こたへおくる) |
注釈 | 「報贈」を童蒙抄に「こたへおくるとよむべし」と云つてゐる。「報」は今日では「報知」「通報」などとしらせる意に用ゐる事が多いが、辞書に「復也酬也答也」とあつて、報歌 (226題、その他) などいづれも和歌と同様に用ゐられてゐる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 「内大臣藤原卿報贈鏡王女歌一首」。「贈」を紀州本・温故堂本・大矢本・京都大学本に「賜」とするが、「贈」が正しい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詠歌の背景 | 新全集 | 鏡王女は天智天皇の愛を失いかけた時に、藤原鎌足から求愛されたのであろう。「93歌」は王女自らの一存で諾否が答えられない立場と戸惑いが歌われており、この「94歌」は鎌足のひたむきだが、相手の都合を顧慮しない身勝手な態度がむき出しの形で詠まれている。このあと王女は鎌足の正室となる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 将見圓山乃 (みもろのやまの) |
全注 | 原文「将見圓山」は旧訓「ミムマトヤマ」であったが、童蒙抄に「ミムロノヤマ」と改訓、さらに講義に「ミモロノヤマ」と改めた。講義にその理由を「『将見圓』は字のままによめば、『ミムマロ』といふべきに、これをここに用ゐたるは、『ミモロ』の『モ』は『ム』にもあらず、『マ』にもあらず、いづれにもつかぬ中間音の『モ』なりしが故にわざとかかる書きざまをなしたりしなるべし」と説く。なお問題が残るが、「ミモロノヤマ」という訓に従う。三輪山のこと。異伝の三室戸山も同じ山をさすのだろう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 「ミモロ」の原文「将見圓」は、それを「ミムマロ」の約と解した表記。-「ミモロ」は「ミムロ」ともいい、神のいます所を意味する語。「カムナビ」と同格のように現れることが多く、その「カムナビ」はもと出雲族の祖神大国主を祭った所と考えられ、万葉のそれは大部分三輪山及び明日香の神奈備をさす。ここも三輪山をいうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 原文「将見圓」をもと「ミムマド」と訓んでゐた。「圓」は集中「マド」と訓むのが通例であるが、さういふ名の山がない。圓はマロと訓んだ例は他にないが、圓と通じて用ゐられる「丸」は「マロ」と訓んだ例 (9・1787) がある。従つて圓もマロと訓み得ると考へられるが、「ミムマロ」といふ山の名もなく「ミムロ」又は「ミモロ」はあるので、そのどちらかだと思はれる。もし「ミムロ」と訓むのだと「マロ」の「マ」を省略した形になる。「面
(オモ)」とか「荒 (アラ)」とかいふ風に上が母音である場合にはその母音を略して「モ」「ラ」と訓む事があるが、さうでない場合「マ」を略する例がない。講義には「ミモロ」の「モ」は「ム」にもあらず「マ」にもあらざる中間音の「モ」であつたからかういふ書き方をしたので、「ア」韻と「ウ」韻との中間の韻は「オ」韻であるから、さう認めてよいと述べられてゐる。姑くその説により「ム」「マ」合して「モ」の表記としたとする。さてその「みもろ」は「御室 (ミムロ)」といふに近く、神のいますところ、神を祭るところの義と思はれ、あちこちにその名があつてよいわけであるが、山の名としては、 三毛侶之(ミモロノ)その山なみに子らが手を巻向山は継ぎのよろしも (7・7093) とあつて、その次の歌に「味酒 三室山 (ウマサケ ミムロノヤマ)」とあり、又その次に「三諸就 三輪山見者 (ミモロツク ミワヤマミレバ)」ともあつて、今の三輪山 (1・17) を又「ミモロ」とも「ミムロ」とも云つたと考へられ、その事は「三室山 石穂菅 (ミムロノヤマノ イハホスゲ)」 (11・2472) に「一云、三諸山之 石小菅 (ミモロノヤマノ イハコスゲ)」とある事によつても明らかであるが、雄略記の三輪のところに「美母呂」とあり、集中でも「三室」とあるは右の引用に二例と今の作の或本歌に「三室戸」とあるのみで、他は「味酒之 三毛侶乃山 (ウマサケノ ミモロノヤマ)」 (11・2512)、「三諸乃 神能於婆勢流 泊瀬河 (ミモロノ カミノオバセル ハツセガハ)」 (9・1770) などいづれも「ミモロ」とある。即ちこの事実と右に述べた表記法と照合して、今は「ミモロ」と訓み、三輪山の事と見るべきである。尤も「モ」と「ム」とは集中に通用の例〔「名草漏」 (4・509)〕もあり、「モ」とも「ム」ともはつきりしない音が行はれてゐたかとも考へられる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「さ寝」語釈 | 全注 | 「『さ寝』という語は、上代にあっては結婚という語と同意であって、後世とは語感を異にしていた」 (窪田評釈) と想像する人もあるが、人麻呂作歌の「さ寝し夜は いくだもあらず」 (2・135) の例から知られるように、直接男女の共寝をあらわしたと見てよい。「サネ」の「サ」は接頭語であるが、ちょっとという意味ではないようだ (口訳)。岩崎良子「さ寝考」 (上代文学昭和五十八年四月) には、万葉集において接頭語「サ」を伴うことばの殆どは、「さよ・さよなか」を除き古今集に受け継がれてゆかないことを指摘している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「ありかつましじ」 | 注釈 | あり得られないだらう、の意。「かつ」は「得」「堪ふ」「敢ふ」などの意の下二段活用動詞で、「ましじ」は「倭須羅庾麻旨珥 (ワスラユマシジ)」 (斉明紀)、「由吉可都麻思自 (ユキカツマシジ)」 (14・3353) などの仮名書例もあり、否定推量の助動詞で、用言の終止形に続き、「かつましじ」となつて、堪へられないであらう、の意となる。原文「有勝麻之目」とあつて「アリガテマシモ」と訓まれてゐたが、元暦校本・類聚古集には「目」の字「自」とあるに注意し、橋本進吉博士「『がてぬ』『がてまし』考」 (国学院雑誌明治四十三年九、十、十一月第十六巻第九、十、十一号『上代語の研究』所収) を発表、右の如く訂正せられた。「かつ」の事は次の歌の條でも述べる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「たまくしげ」 枕詞繰返しの妙 |
注釈 | 〔注釈【考】〕 贈歌と同じ「玉くしげ」といふ枕詞を用ゐてゐるのは、「1・20」の作「紫草」を「1・21」の和歌の初句にくりかへしてゐるのと同じ技巧である。又その「20」の作者が「野守は見ずや」と歎き、今また「明けていなば」と歎じたに対し、「われ戀ひめやも」、「ありかつましじ」と酬いた二人の男性 (大海人皇子・藤原鎌足) が、当時の日本の歴史に偉大な役割を演じた人である事を見逃してはならない。斉藤茂吉氏が、この作を「端的で身体的に直接でなかなかいい歌である。身体的に直接といふことは即ち心の直接といふことで、それを表はす言語にも直接だといふことになる」 (『秀歌』) と云はれてゐる言は同感至極である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 95 | 「采女 (うねめ)」とは | 注釈 | 「采女」は天皇の御膳の事その他の奉仕する宮中の女官。既出 (1・51)。「安見兒」はその采女の名。伝未詳。「娶」は「メトリシ」と訓み、古義には歌詞により「エシ」と訓んでゐる。采女と通ずる事などは禁じられてゐた事 (2・217参照) であり、それを鎌足は賜はつたので、その時に喜びのあまりに詠んだものと思はれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 采女は天皇に対する服属のしるしとして諸国から貢上された美女であり、上級貴族たちにとっても禁忌の存在だった。「皆人の得難にすといふ」は、多くの恋敵をしりぞけて勝利者となった喜びのようにも聞かれるが、禁忌の采女をとくに許されて得たことを誇っているのだろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皆人 (みなひと) | 釈注 | 第三句の「皆人」が「皆さん」の意で、「人皆」という語が世間の人一般を抽象的にさすのに対し、ある限定された範囲の人をさす語であることを思えば、一首は宴の座でうたわれたもので、集う人びとに、 おれはまあ安見児を得たぞ。お前さんたちが手に入れられないと言っている、この安見児をおれは我ものとしたぞ と誇示したのであろう。世にも美しい娘子安見児を傍らに置いて、得意満面、酒を酌む鎌足の姿が浮んでくるような歌である。よろこびはそれ自体が歌である。ことさらうたう必要がない。そのためか、「万葉集」には、よろこびを奏でた歌はきわめて少ない。一首はそのめずらしいよろこびの歌の一つである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 皆人乃は、人皆乃とありしを下上に誤れるなり、かれヒトミナノと訓つ、こは皆人とも、人皆ともいふべき事と、誰も一 (ト)わたりは、思ひをる事なれども、熟考 (フ)るに、凡て皆てふ言は、某皆と、のみ云て、皆某といはむは、古語の體にあらずなむ、かれ集中の例を檢 (フ)るに、五 (ノ)卷に、比等未奈能美良武麻都良能 [ヒトミナノミラムマツラノ] 云々、十四に、比等未奈乃許等波多由登毛 [ヒトミナノコトハタユトモ] 云々、(これらは假字書なれば、さらに動くまじきなり、)又此 (ノ)下に、人皆者今波長跡 [ヒトミナハイマハナガミト] 云々、五 (ノ)卷に、人皆可吾耳也之可流 [ヒトミナカアノミヤシカル] 云々、六 (ノ)卷に、人皆乃壽毛吾母 [ヒトミナノイノチモアレモ] 云々、又、人皆之念息而 [ヒトミナノオモヒヤスミテ]云々、九 (ノ)卷に、人乃皆 [ヒトノミナ](皆乃を下上に誤か、)如是迷有者 [カクマドヘレバ] 云々、十卷に、人皆者 [ヒトミナハ] 芽子乎秋云 [ハギヲアキトイフ] 云々、十一に二ところ、人皆知 [ヒトミナシリヌ] 云々、又、世人皆乃 [ヨノヒトミナノ] 云々、又、里人皆爾 [サトヒトミナニ] 云々、十二に、人皆如去見耶 [ヒトミナノユクゴトミメヤ] 云々、又、人皆之 [ヒトミナノ](皆舊本皆人之に誤、今は元暦本に據て引、)笠爾縫云 [カサニヌフチフ] 云々、又十(ノ)卷に、物皆者新吉 [モノミナハアラタシキヨシ] 云々、古事記に、國土皆震 [クニツチミナユリキ] 云々、高天原皆暗 [タカマノハラミナクラク]、(上卷) 國皆貧窮 [クニミナマヅシ]、(下卷) 書紀竟宴歌に、倶娑幾微儺擧都夜謎豫斗底 [クサキミナコトヤメヨトテ] などある例なるを、(唯四卷に、皆人乎宿與殿金者 [ネヨトノカネハ]、七 (ノ) 卷に皆人之戀三吉野 [コフルミヨシヌ]、八 (ノ) 卷に、皆人之待師宇能花 [マチシウノハナ] などある皆人も、ともにみな、人皆とありしを、下上に誤れるなるをしるべし、且此 (ノ) 集には、字の顛倒 [イリチガヒ] いと多かること、上にもいへるごとくなるを考てよ、) 今までこの論せし人のなかりしは、いかにぞや、(但し古今集よりこなたのには、いづれも皆人とよみたれども、そはまづおきて、今は古きにつきていふのみぞ、) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 古義に「人皆の」の誤とあるが、「比等未奈能 (ヒトミナノ)」 (5・862) などの例もあり、「皆人之」 (7・1131、8・1482) の例もあつて、二様に用ゐられたものと思はれる。「人皆は」
(2・124) 参照。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 万葉集では、特定の集団に属するすべての人を指す場合に、「ミナヒト」と言い、不特定多数の人々を広く指す場合には「ヒトミナ」と言って区別しているらしい (伊藤博「釈万葉」『万葉集研究』第五集)。ここではその場に居合わせた人を言う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「かてに」の濁音化 「がてに」 |
全注 | 「カテニ」は語源的に耐える意のカツ (下二段活用) の未然形に、否定の助動詞「ズ」の古形「ニ」が接したものと考えられる。「行過勝尓 (ユキスギカテニ)」(3・253) 「待勝尓 (マチカテニ)」(9・1684) などと書かれているのは、そうした語原意識が失われた結果であり、それとともに「カタシ (難)」という形容詞の語幹「カタ」に助詞「ニ」をともなった「難尓」との間に一種の混淆を生じたらしい。「難尓」は「君待ち我弖尓」(5・859) などの例により、「ガテニ」と訓むのが正しいようだ (岩波書店「日本古典文学大系本 485歌」補注) 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大系 | 〔485歌補注〕より 「カテニ」は普通、耐える意の「カツ (下二段活用)」の未然形に、否定の「ズ」の古形「ニ」が接続して成立した語と説かれている。語源的な説明としてはそれで正しいものと考えられるが、注意すべきことは、奈良時代の人々が、一般に果たしてそのような意識、つまり、「ニ」は否定の「ズ」の連用形なのだという意識をもっていたかどうかということである。否定の「ズ」とか「ヌ」とかは、万葉集の訓仮名表記の部分では (字音仮名ばかりで書いてあるところは別として) 不、莫の文字で書くのが通例で、不や莫を用いないのは、願望の「ヌカ」「ヌカモ」の場合である。これは、「ヌカ」「ヌカモ」という助詞全体で一語と意識されていて、それを語源にさかのぼって、否定の「ズ」の連体形「ヌ」に助詞「カモ」の接続した形と言う意識が無かった結果、不や莫の字をその部分にあてなかったものと考えられる。それと同様のことが、「カテニ」の場合にも起こっている。すなわち、「行過勝尓 (ユキスギカテニ)」 (巻三・253)、「待勝尓 (マチカテニ)」 (巻九・1684) というような例があるのは、「ニ」が否定の「ズ」の連用形であることを忘れた (あるいは知らない) 表記と見られるのである。さらに、表意的な文字として勝の他に、難が用いられている。「得難尓為 (エガテニス)」 (巻二・95)、「待難尓為 (マチガテニスレ)」 (巻四・629) などの例がそれである。このような表記の例は十二例に及び、決して少ないということはできない。「難尓」という表記は「カタシ」という形容詞の語幹「カタ」に助詞「ニ」がついたもので、一種の混淆 (コンタミネーション) の結果である。これを何と訓んだかについては、恐らく「ガテニ」と訓んだのではないか。 「春されば我家の里の川門には鮎子さ走る君待ち我弖尓(がてに)」 (巻五・859) 「相見ては千年やいぬるいなをかも我れやしか思ふ君待ち我弖尓(がてに) [柿本朝臣人麻呂歌集出也]」 (巻十四・3470) の二例の存在が、その証となる。 つまり「カテニ」という言葉は、元来は「カツ」の未然形「ズ」の連用形がついて成立したが、奈良時代ではその語源意識は失われ、「カテニ」は「ガテニ」に移行しつつあり、「ガテニ」でひとまとまりとして意識されていた。その意識の形成は、否定の「ニ」の一般的衰退、「難(カタ)し」という意味・語形の類似する語の存在という事情が密接な関係を持っていたということである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 96 | みこもかる | 全注 | 原文「水薦苅」を古点に「ミコモカル」、仙覚の新点に「ミクサカル」とあったのを、童蒙抄に「ミスズカル」と改訓。以後「ミスズカル」も広く行われたが、集内に「疊薦」 (11・2777、2995) 、「薦枕」 (7・1414) 、「苅薦之」 (3・256、11・2765など) が見えるほか、二五六歌の異伝に「可里許毛能」 (15・3609) の仮名書があり、さらに記紀歌謡にも「多多美許母」 (記31、91)、「擧慕摩矩羅」 (紀94歌) の例があり、「薦」を「コモ」と訓むことが分かる。万象名義に「席」、新撰字鏡には「菰」の注がある。「コモ」は湖沼に生える稲科の多年生草木。「ミコモ」の「ミ」は水の意か。「ミコモカル」で、信濃にかかる枕詞。掛かり方は未詳であるが、信濃国に薦が多く珍しかったので、信濃の枕詞としたとも言う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 信濃の枕詞。信濃は湖沼が多く、菰のはえてゐるところが多いからと思はれる。「玉藻かる敏馬」 (3・250) の類である。「み」は接頭語 (『古徑』二「『水薦苅』攷」参照)。「薦」を古写本いづれも「□(蔧の草冠の下に广のある字)」と書く。当時の古文書も同様である。倭名抄に「薦」は「東韻云、薦 作甸反古毛、席也」とし、「菰」は「本草云、菰一名蒋 上音孤 下音将、古毛」とあり、菰と薦の関係は、葛(かづら)と蘰(かづら)との関係と同様であるが、集中では菰とあるべきをすべて薦と書かれてゐる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信濃の真弓 (しなののまゆみ) (しなぬのまゆみ) |
全注 | 信濃国からは梓弓を多く産出した。万葉集の梓は一名「ヨグソミネバリ」と呼ばれる落葉高木で、甲州や信州に多い。弓材に適しており、それで作られた弓(梓弓)
が朝廷に献上された。続日本紀に「文武天皇大宝二年二月己未甲斐国献梓弓五百張以充大宰府」、「同年三月甲子信濃国献梓弓一千二十張以充大宰府」などとあるのは、「ヨグソミネバリ
(別名ミヅメ)」を材としたものである(白井光太郎「梓弓の材について」『万葉学論纂』)。「マユミ」の「マ」は接頭語。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 信濃の国から産する弓。「ま」は美稱。弓の材になるので檀 (マユミ) と呼ばれる木があるが、ここは弓をさしたもので、信濃より弓を産した事は、續紀大宝二年三月の條に「甲午 (二十七日) 信濃国献梓弓一千二十張。以充大宰府」とあり、臨時祭式に「凡甲斐。信濃両国所進祈年祭料雑弓百八十張。甲斐国。槻弓八十張。信濃国。梓弓百張。 並十二月以前差使進上。」などともあつて、特に梓弓を多く産したらしい。初二句は「引く」といふ為の序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うまひとさびて | 注釈 | うま人は「うまし」 (1・2) の語幹に「人」をつづけたもので、日本書紀には「君子」 (顕宗紀)、「搢紳」 (同)、「良家子」 (欽明紀) をウマヒトノコと傍訓されてをり、 あさりする海人の子どもと人は云へど見るに知らえぬ有麻必等能古等(うま人の子と) (5・853) とあると対照すると「良家子」をウマヒトノコと訓ませた事の穏やかである事が認められ、「うま人」とは身分のある人、貴人の意と思はれる。「さび」は既出 (1・38)。貴人ぶる。お上品ぶること。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 原文「宇真人佐備而」。佐を西本願寺本に作とするが、元暦校本・金澤本・類聚古集による。ウマヒトは「宇摩比等」 (紀28歌)、「子麿臂苔」 (紀46歌)、万葉集にも「有麻必等」 (5・853) とあり、ヒは清音。身分の高い教養ある人の意。サビはヲトメサビ、オキナサビなど、そのものらしく振舞う意味の接尾語。貴人ぶって。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「不欲 (いな)」 | 注釈 | いやといふであらうか。「か」は疑問。「も」は詠歎の助詞。「いな」の原文「不欲」は義訓である。陽明本に「知」、流布本に「言」とあるは「欲」の草書「(変換不能)」より誤つたもので、「言」の草書「(変換不能)」とは特に誤りやすい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 97 | 原文諸説 「強作留」・「強佐留」 他、誤字説 |
全注 | 原文、西本願寺本に「強作留行事乎」とあり、元暦校本・金澤本・類聚古集・紀州本には「強佐留行事乎」とある。旧訓はそうした原文により「シヒサルワサヲ」と訓だが、契沖は、「強」を「弦」の誤字、「佐」は西本願寺の「作」を正字とし、「弦作留行事乎」を「ツルハクルワザヲ」と訓むべしとした (代匠記初稿本)。真淵はこれを受け、「ヲハグルワザヲ」と改訓。その後、山田講義に「ヲハクルワザヲ」と改訂されたのが、現在までのもっとも優れた訓である。一方、澤潟注釈には、金澤本「強佐留行事乎」の本文に従い、「シヒザルワザヲ」の訓が採られている。それに従う注釈書もあるが (講談社文庫)、打消しの「ザル」を「佐留」と記すのは、「佐」が清音仮名なので無理があると思われるし、「草武左受」 (1・22)、「安波射良米」 (15・3741) のように仮名表記語に接続する場合はともかく、「不強」を、「強佐留」と書かねばならぬ理由は見出し難い。全註釈に「アナサルワザヲ」としたのはその点の無理を避けたものだが、類聚名義抄に「強」に「アナガチニ」の訓があるから「アナ」とも訓めると考えているのも、強引に過ぎるようだ。やはり真淵や講義のように、「ヲハクルワザヲ」が穏やかか。弓には平城弓絃をはずしておき、射る前に弦をつけるので、「みちのくのあだたら真弓つらはけて引かばか人の吾を言なさむ」 (7・1329)とも歌われている。この歌でも、「引く」前の段階を問題にしているものと思われる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 「強作留」-底本原文のまま。元暦校本や金澤本などの古写本には「強佐留」とある。誤字説もあるが、文字通り「シヒサル」と読み、相手に強く迫ったりわざと気弱いふりをしたりする巧妙な恋の駆け引きを意味すると考えるべきか。-この歌には難訓があるが、前後から判断して、あなたは意気地なし、本気で誘惑する気があるのか、と誘いかけたものか- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 第四句の原文は諸本とも「強作留行事乎」。「強」は「弦」の誤りであろう (代匠記初稿本)。訓み方は、『講義』の「ヲハクルワザヲ」に従う。弓に弦を張ることを「はく」 (下二段動詞) といった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 |
「強ひざるわざを知るとはいはなくに」- 強ひるとは「いなと云はば強ひめやわが背」 (4・679) とあるによつて明らかなやうに、強引にせまる事である。従つて強ひざるわざとは、強引にせまる事をしないのである。上の「引かずして」の意をもう一度強く繰り返した形である。私の心を誘はうともなさらず、強ひてともおつしやらないでゐて、その事を「知る」といふのは理解してゐること、わかる事、即ち御自身で強い意志表示をなさらないでゐて、「いなといはむかも」などと勝手にきめておいでになるがそんな事がわかりますか、といふのである。「云はなくに」は云はぬことなるに、の意。「なくに」は既出 (1・75) 。以上に述べたやうな事を誰も云ひはしないにナア、といふのである。原文「強佐留」の「佐」西本願寺本以後の諸本「作」となつてをり、代匠記に「強」を「弦」の誤として「ツルハクル」と訓み、考にはその誤字説によつて「ヲハクル」と訓み、弓絃を懸けることだとし、以後その説が殆ど定説のやうになつている。ただ増訂本全註釈には類聚名義抄に「強」を「アナガチニ」と訓じてゐるから「強」を「アナ」と訓み、「アナ」は驚歎の意をあらはし、「ああ、引きもしないでさような業を我は知るとは言わないの意」とある。「佐」と「作」とは行書体が似てをり、両方とも「サ」の音に用ゐられてゐるので、どちらからどちらへ誤つたとも云ひかねるやうであるが、「作夜深而 (サヨフケテ)」(7・1143) の如く諸本に「作」とあるものは二三にすぎず、古写本にのみ「作」とある例「作美乃山 (サミノヤマ)」(2・221) の如きも二三あるが、「サ」の音を表するには「佐」を用ゐる事が通例であり、「佐日之隈回 (サヒノクマミ)」(2・175) の如きは古写本は皆「佐」であつて刊本のみが「作」とあり、「佐」が一ニ本にのみ「作」となつてゐる例 (5・803、14・3371、その他) 十例にも及んでをる。現に前の歌「宇真人佐備而」の「佐」も西本願所本のみ「作」となつてをり、今の場合また「作」とあるは西本願寺本にはじまるといふ事は、この二つの「作」を並べてみて、このあたりに誤字の因があるやうに思はれ、いよいよ「佐」が原本の文字と考へられる。さうだとすれば、「ヲハクル」などと訓む事は二字も誤字を作る事にになり、そんなにしひて誤字説を考へたり又古語拾遺を引合に出したりする迄もなく、私はこの原本の文字のまま、右の如く解く事が出来ると思ふ。むしろなぜこの解を考へつかれないか不審にたへないのである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一首「寓意考」 | 全注 | 寓意について- 第四句を「ヲハクルワザヲ」と読む注釈書の中にも、その寓する意味に関しては諸説があり、一致しない点が多い。まず第二句までを序詞と見るか否かで諸注の解は異なっている。前歌と同じく弓を引くことと相手を誘うこととを掛詞にしているのだが、下句も隠喩になっており、一首全体が比喩の歌とも見られるのである (佐佐木評釈など)。しかし、及び腰で、本気になって迫りもしない相手に対して、痛烈なシッペ返しをしたものとすれば、「あなたは『信濃の真弓吾が引かば』などと言われるけれど、引くどころか、弓弦の張り方さえ御存知ないのではないかしら」と揶揄を返したものと思われる。下句の寓意が何かは、あまり問題ではなく、久米氏の男性を弦の張り方さえ知らないと揶揄することに作者の意図はあったようだ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 98 | 「随意」古訓、仮名書例 | 注釈 | 「まにまに」は「保志伎麻尓麻尓 (ホシキマニマニ)」 (5・800) の如き仮名書例があり、「随意」は義訓の用字である。「大王乃 美許等能麻尓末 (オホキミノ ミコトノマニマ)」 (20・4331) の如くマニマとも云ひ、今のまゝに、と同じ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 「マニマニ」は原文「随意」とあるように、相手の心のままに従う意。「元暦校本・類聚古集」などの古写本に「ココロニ」と訓まれていたが、「西本願寺本・紀州本」など「マニマニ」とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 99 | 「引く人は後の心を 知る人そ引く」表現の違和感 |
注釈 | 「引く」の意は前同様。引く人は作者自身である。行末の事をわきまへてゐる人が引く、といふので、「引く人は」と云つて「知る人ぞ引く」といふのは語法が整はず、井上氏新考に「シリテコソヒケなどあるべきなり」とあるは尤もであるが、かうした物いひは今の人も不注意になすところであり、このまゝに、むしろ「引く人は」と云ひながら「知る人ぞ」とくりかへしたところに作者のきほひ込んだ心が示されてゐると見るべきである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】第三句の「引く人は」に対して、「シルヒトソヒク」という結びは、呼応が不正確である。講義に「『梓弓都良絃取波気引人』は後の心を知る人なり。かく後の心を知る人ぞ人を引くといへるなり」と言う。 【考】[文の捩じれ] 第四首目は、禅師の歌で、直接には九八歌に対する答えであるが、「弦緒取はけ」の句があるのは、九七歌をも意識し、郎女の二首にこの一首で答えた形になっている。〔注〕の項にも触れたとおり「~人は」を受け「知る人そ」で終わるのが文法的には正確なのだが、そこに「後の心を知ればこそ引け」という気持ちが重ね合わされ「引く」を再び繰り返す形になっている(古典全集頭注)。講義に説かれるような文法的に正しい形では第三者的な表現にとどまるところであるが、将来をかけてあなたを深く思うからこそ誘うのだという気持ちを重ねて強調したために生じた文形の捩じれである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 「引く人は後の心を知る人そ」という表現と「引く人は後の心を知ればこそ引け」という表現とが混線した変則的な言い方。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 100 | 「東人之」訓釈 | 注釈 | 東国の人の意であるが、「あづま」はまた「ゐなか」の意にも用ゐられる。天孫の降臨は高千穂の峯であり、海道東征によって、我が国の文化は西より東へ進んでをり、後世も「あづまえびす」と云はれるやうに東国が邊鄙の代名詞のやうに用ゐられたものと思はれる。倭名抄(一)に「邊鄙」に「阿豆万豆(アヅマヅ)」(真福寺本には阿豆末豆アヅマヅ) と訓み「今案俗用東人二字其義近矣」と注してゐる。類聚名義抄 (注、中) にはアツマトとし、右下にヒトと添へられてをり、アヅマヅはアヅマドの訛りとして、今の「東人」もアヅマドと訓む説も行はれ、古写本にはアヅマヅとある。タビビトがタビトに、フミヒトがフフビトになる訓でこれもアヅマビトがアヅマドになつたとも考へられるが、タビト、フビトの場合は、同音または同韻の語が略されてヒトひとはそのまま残つてゐるが、アヅマドの場合は、ヒトが音便でウトとなり、更にそのウが省略された事になるので、前者をもつて傍証とする事は出来ない。或いはこの「ド」「ヅ」は人の略でなくて處の意ではなかつたらうか。「寐屋戸 (ネヤド)」(5・892)、「多知度 (タチド)」(14・3546)、「久麻刀 (クマト)」(20・4357)、「隠處 (コモリド)」(11・2443)、「隠津 (コモリヅ)」(11・2794)」 などが参照せられる。ともかく、今は上代に確実な例が見出されないかぎり、アヅマヒトと訓むが穏やかであらう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】東国の人。名義抄にアツマトの訓があり、右下にヒトと書き添えられている。アヅマヒトがアヅマトとも言われたことを示す。短歌の初句における字余りは稀なので、ここではアヅマトと訓む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 101 | 枕詞・修飾語 「たまかづら」 |
注釈 | 【訓釈】「実」の枕詞-美夫君志に「早田(わさだ)の穂には出でず」(9・1760) の類だと云つたのに対し、井上新考には、この歌のみで云へば穏当な説であるが、答歌に至つて忽窮するから、玉葛は実のならぬ又は実のなり難いものだと述べられている。小清水卓二氏の『萬葉植物』ではあぢさゐに似た花束状の美しい花がついて、実は普通出来ない「ごとうづる (つるでまり、つるあぢさゐ)」の事だとされてゐる。それだと「実ならぬ」につづく事になり、答歌の「花のみ咲きて」にも好都合であるが、玉葛は「絶ゆる事なく」(3・324、6・920)、「いや遠長く」(3・443) ともつづき、又「山高み谷邊にはへる玉葛」(11・2775) ともあつて、つるでまりのやうな一種の植物と断定する事は穏やかでない。玉は玉藻、玉松などの玉と同じく美稱で、かづらは、さねかづら、くそかづら、ひかげのかづら、くずなど、すべて蔓のある植物の総稱で、花の咲くもあり、咲かぬもあり、実の成るもあつて、「絶ゆる事なく」とも「遠長く」とも「花」とも「実」ともつづけたと見るべきで、前 (93、94) の「玉くしげ」が「おほふ」とも「み」ともつづけたやうに、今も「み」とも「花」ともつづけたので、共に枕詞として用ゐたので、歌意に直接関係せしめてゐるのではない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】原文「玉葛」。葛は新撰字鏡に「加豆良」の注があり、「カヅラ」と訓む。万葉集のタマカヅラについてゴトウヅル・ビナンカヅラなどがあげられているが、一種の植物に限定するのは困難で蔓性植物の総称とするのが穏当のようである (松田修『万葉植物新考』)。タマは呪力あるものを表す接頭語。この歌のタマカヅラを枕詞とする説が多くの注釈書に見られるが (佐佐木評釈・全註釈・注釈・古典全集・古典集成など)、そうは言い切れない。カヅラには雌雄異株で、花の咲かぬものも実の成らぬ木もあるし、樹木に霊のより着く話も見られるから (〔考〕の条参照)、実質的な修飾語と解されるだろう。私注に「実の成らない例として、玉葛を上げて歌つたものであらう」と注しているのが正しい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「みならぬき」 | 注釈 | 【考】男に靡かうとしない女を、実の成らぬ木によせたので、作者の云ひ寄るのに、つれなく、こはごはしくもてなしてゐたら神のとりつくところになつて、いよいよ人げなく恐ろしいものになつてゆくだらうと云つたのである。「実ならぬ木に神がつく如くすでに附いて居るものがあるのであらう」といふ嫌味と解せられないでもないが、源氏物語総角に大君が薫大将に心の染まぬを許した言葉にも「世の人のいふめる、怖ろしき神ぞつき奉りつらむ」ともあつて、右に述べたやうな意味にとるべきである。(4・522) 参照。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「実ならぬ木には」 花だけ咲き実の成らぬものとしてゴトウヅルをあげる人もあるし (小清水卓二「万葉の植物」大成第八巻)、ビナンカヅラの雑木を念頭に置いての表現と考える人もある (私注補正稿)。雑木には花は咲くが実は成らないので、ふさわしいかもしれない。相手の不実を責める気持ちをこめた表現である。 【考】「神仏が憑りつく木の話」 この歌は、表面は実の成らないタマカヅラのことのみを歌っているように見えるのだが、もちろん歌の心は、恋にあり、求婚にある。実ならぬ木は、安麻呂の求愛に応じようとせぬ郎女を喩えたもので、そういう木には恐ろしい神がつくと、おどしているのである。木に神仏が憑りつく話としては、今昔物語の「天狗、現仏坐木末語第三」(巻二十) が思い合わされる。「今ハ昔、延喜ノ天皇ノ御代ニ五条ノ道祖神ノ在マス所ニ、大キナル不成柿ノ木アリケリ。其ノ柿ノ木ノ上ニ、俄ニ仏現ハレ給フ事有ケリ」という。これは真の仏が現じたのではなく、天狗であって、大臣に正体を見破られてしまうのであるが、こうした邪神の乗り移る話は、万葉集の時代にもあっただろう。安麻呂はそれにかこつけて、郎女を嚇して自分に靡かせようとしたのである。なお、「神そ着くといふ」は、「吾が事の成らぬところを見ると、君には実ならぬ木に神がつく如く、すでに附いて居るものがあるのであらう」 (私注) という意味にも解せられなくはないが、容易に靡かない女性を誘う悪口歌として、既述のように解する方が良いと思われる。雄略記の「三諸の 巌橿が本 ゆゆしきかも 橿原処女」は三諸の神の社の神聖な橿の木が忌みはばかられるように近寄りがたい橿原の乙女よの意で、近づき難い美女に対する悪口歌であり、女を誘う歌である (土橋寛『古代歌謡全註釈』)。近世以後にも、「お寺の前の玉椿、取りたくても、高く手が届かぬ」 (山梨県、盆踊り盆踊歌)、「成るか見て来いお寺のささげ、花は咲いても実ははならぬ」 (愛知県・盆踊歌) など、類例は少なくない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 古来、実の成らない木は、神聖視され、様々の伝承が伴っていた。「今は昔、延喜の天皇の御代に、五条の道祖神の在ます所に、大きなる不成ぬ柿の木有けり。其の柿の木の上に、俄かに仏現はれ給ふ事有けり」 (今昔物語二十ノ三)。「根本中堂へ参る道、賀茂河は河広し、観音院の下がり松、生 (な) らぬ柿の木人宿 (ひとやどり)、禅師坂、滑石水飲四郎坂、雲母谷、大岳蛇の池、阿古也の聖が立てたりし千本の卒塔婆」 (梁塵秘抄 312)。「西坂本の麓に実ならぬ梨有り。是を徳一和尚御覧じて、一首をかくぞ詠じ玉ひける。「草も木も仏に成ると云ふ山の麓にならぬ梨もこそあれ」と詠み玉ひければ、伝教太師御返歌に、「草も木も仏になると云ふ山のならぬ梨こそ本の仏よ」 (諸国一見聖物語)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 102 | 原文「花耳開而」 | 全注 | 【注】「花耳開而 (はなのみさきて) 不成有者 (成らざるは)」 原文「開」は、「サキ」と訓む。「咲」を「サク」に宛てる例は、初期万葉歌・人麻呂歌集歌に見えない。ビナンカヅラの花だけ咲いて実がならない、そのように結ばれることのない恋は、の意。花とは言葉の巧みなこと、実は心の誠実さのたとえで、言葉ばかり巧みで、実のない心のことをあらわす (講義など)。東大寺諷誦文稿に「不信人ハ花開テ実成ラヌ樹ノ如シ」とある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 葛の中でもサネカヅラは雌雄異株、雄株は花だけで結実はないという。男の歌では枕詞であった「玉葛」を、ここでは実のならない木に取り成した。春秋左氏・文公五年に、実行を伴わない言葉を「華にして実ならず」と言う。東大寺諷誦文稿に「不信人は花開(さ)きて実成らぬ樹の如し」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「誰恋尓有目」訓釈 〔たがこひならめ〕 〔タガコヒニアラメ〕 |
新全集 | 疑問語「たが」があって文末を已然形で止めると、「見えずとも誰恋ひざらめ」(3・393) のように反語を表す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「め」といふ推量助動詞「む」の已然形でうけてゐるのが不審なやうであるが、「孰不戀有米 (タレコヒザラメ)」(3・393) の如く、上の疑問の言葉をうけて「め」と結んだので、この「め」は「めや」の「や」が省略されたやうな形で、反語的な用法になつてゐる。即ち、あなたは私が実にならぬやうにおつしゃるが、実にならぬ戀は誰の戀であらうか。あなた以外の誰の戀でもありはしない、と云つたのである。 「ニアラメ」はつづめて「ナラメ」とも訓んだであらう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 103 | 原文「大雪落有」 | 全注 | 【注】「大雪落有 (オホユキフレリ)」 原文「大雪落有」。万象名義に零に注して「雨零・落」と言い、新撰字鏡ニモ、「力丁反餘雨也降也落也随也」とあって、「落・零・降」の三字が共に「フル」の意味に用いられたことを知る。「降れり」の「り」は、存在もしくは完了を表す助動詞。「降ッタ」と完了形で訳している注釈書も多いが、この歌の下句や、あとの藤原夫人の歌との照応を考えると現に降っている意味とする方が (注釈・講談社文庫など) ふさわしいかもしれない。 【考】「奈良の雪」 奈良や飛鳥地方では、めったに大雪が降ることはなかったらしい。天平十八年正月に降った雪は数寸であったが、橘諸兄をはじめ多数の大宮人たちが太政天皇の中宮西院に参候して歌を賦しているし、天平勝宝五年正月十一日のの雪は、積もること一尺二寸だったので、家持が「珍しく降れる大雪」(19・4285) と歌を詠んでいる。この贈答歌の場合、どれほどの雪かわからないが、珍しく降った雪に興じて、大原にいる夫人のところに歌が贈られたのである。「吾が里に大雪降れり」には誇張があるだろうし、親しみやユーモアもこめられている。「吾が里」に対して夫人の住む所を指して「大原の古りにし郷に降らまくは後」と歌ったのは、「フレリ・フリニシ・フラマク」という、「フル」の繰り返しの音律の効果もあって、即興の戯歌にふさわしい明るい雰囲気を強めている。この歌によると、大原と清御原とは空間的にかなり隔たっているように思われるが、実際は直線距離にして一キロほどに過ぎない。それを大げさに対照したため、下句の「降らまくは後」がいっそう諧謔感を強めている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 104 | 原文「於可美(おかみ)」 | 注釈 | 【訓釈】「於可美(おかみ)」 神代紀上、一書に伊弉諾尊が火神を斬られた劔の血から生まれた神「號曰闇龗(クラオカミ)」とあつて、「龗此云於箇美(オカミ)、音力丁反」と注されてゐる。豊後風土記、直入(ナホリ)郡球覃(クタミ)郷の條に「天皇行幸之時、奉膳之人、擬於御飲、令汲泉水、即有蛇龗」とあつて「謂於箇美」と注してゐる。水を司る龍神である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「龗に言ひて」 オカミは神代紀に「龗此云於箇美(オカミ)」とある。玉篇に「龗力丁切龍也又作靈神也善也」と見え、また「龗同上」と記している。新撰字鏡には「龗」を「龍字」と注しているように、龗は龍神をあらわす文字であり、水神を意味した。また、日本で水神をあらわす語が「オカミ」であった。水神に頼んで、の意。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「令落(ふらしめし)」 | 注釈 | 【訓釈】「令落(ふらしめし)」 「しめ」は使役の助動詞「しむ」の連用形。「万葉考」に「フラセタル」とあるが、当時使役の助動詞「す」「さす」はまだ十分発達せず、又タルに相当する「有」の文字もないので「シメシ」と訓む方がよく、下の「し」は過去の助動詞。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「降らしめし」 原文「令落」を「フラシムル」と訓む説(童蒙抄・全註釈)、「フラセタル」とする説(万葉考・攷証・檜嬬手・口訳)もあるが、講義に言うように、「タル」は、「有」「在」などの文字がないので無理な訓だし、文字から言えば「フラシムル」が良いが、第五句の「散りけむ」と合わない感じがあるので、結局「フラシメシ」に落ち着かざるを得ない。過去の助動詞「シ」の読み添えは、他に例がある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「雪之摧之」、「摧」考 (ゆきのくだけし)」 |
注釈 | 【訓釈】「雪のくだけし」 代匠記に「摧ハ物ノ摧タルカタハシノ意ナリ」と云ひ、拾穂抄に「しは助字也」と云つてゐるやうに、「くだけ」は碎片の意の名詞とし、「し」は強意の助詞と解する説があり、それに対して「万葉考」には「此之(シ)は之毛(シモ)の略」と云ひ、「攷證」に「之(シ)は過去のしにて、しがといふ意に心得べし」と云ひ、「くだけ」を動詞と見る説があり、講義には後説について「『クダケシモノ』の意にて『シ』までにて体言の取扱をなせりと考へたる人多けれど、さにあらじ」と云ひ、以後の諸家また多く前説を採るに至つた。精考には後説を「大いなる誤である」と断じ、金子氏評釈にも「し」を「過去の助動詞と見てはならぬ」とある。しかしなぜ間違ひかを説明しないで「大いなる誤」といひ「見てはならぬ」と云はれても承服する事は出来ない。 たしかなる使を無みと 情乎曾(ココロヲゾ) 使尓遣之(ツカヒニヤリシ) 夢所見哉(イメニミヱキヤ) (12・2874) この「之(シ)」は「過去の助動詞」であつて似た語法であるが、上に「曾(ゾ)」があつて一旦ここで切れてゐるから今と同様には見難い。 吾妹子に恋ひてすべ無み白たへの 袖反之者(ソデカヘシシハ) 夢所見也(イメニミヱキヤ) (11・2812) は「は」といふ助詞が添へられてゐて「袖かへしし」は講義の所謂「体言の取扱」をなしたものである事明瞭である。今はその「は」とか「が」とかの助詞が省略されたと見れば同様の語法と見る事が出来る。 古郷のならしの丘のほととぎす 言告遣之(コトツゲヤリシ) 何如告寸八(イカニツゲキヤ) (8・1506) に至つては、その間に助詞がなくして今と全く同様の語法と見るべきである。即ち「くだけ」を動詞とし「し」を時の助動詞と見る事は、集中に現に用例のある語法であつて誤と断ずべきではない。むしろ疑問は前説の「くだけ」といふやうな名詞の存在を認めるかどうかといふ点である。「くだく」の語は、 -我胸者 破而摧而 鋒心無 (ワガムネハ ワレテクダケテ トココロモナシ) (12・2894) -君之摧 情者不持 (キミガクダカム ココロハモタジ) (10・2308) の如く下二段活のものも四段活のものも集中に数例をあげる事ががが出来るが、いづれも動詞であつて名詞として用ゐられたものがない。その事は上代の散文んび於いても同様である。中古の物語に於いても管見に入るところ同様である。後世の辞書について見ても、クタク又はクダクの動詞は夥しいが、クダケの名詞は殆ど見あたらない。類聚名義抄にはクタク、クダクの訓をつけた漢字四十宇餘字に及んでゐるが、クダケは「屑」(法、下)にクダクとし、その下のクの右にケと書添へたもの一つあるに過ぎない。字鏡集に至つてはクタクの訓を附した漢字九十字にあまり、クタケとあるものは「□(米偏に靡)」の一字のみであるが、それも慶永本のみで、寛元本、白川本にはそれも「クタク」となつてゐるやうである。更にここに注意せられる事は、字鏡集には「クタケコメ」と訓んだ文字「糏」、「□(米偏に乞)」、「□(米偏に上に一下に山)」の三字、「クタケヨネ」と訓んだ文字「粞」一つあり、それらの文字の間に右の「□(米偏に靡)」のある事である。即ちこの事実から推察すると、かりに應永本のクタケといふ言葉の存在を認めるとしても、それは一般的な「くだく」といふ動詞の名詞形ではなくして、特に「くだけ米」(コメ又はヨネ)の省略語としての「くだけ」だと考へられる。この事は我々の「くだけ」といふ語感とも一致するといふ事になる。「くだく」といふ動詞に対して「くだけ」といふ名詞があり得るといふ事は論理的には正しい。しかしすべての動詞の連用形が名詞として存在するには限らない。いつも述べるやうに言葉の存在には実証が重んぜられる。然るに「くだけ」といふ名詞は右に述べたやうに上代にも中古にも実際に用ゐられたものを私はまだ見ない。語感といふものは今を以つてそのまま上代にあてはめる事は出来ないが、「雪がくだける」といふ言葉は今も云ひ得る言葉であるが、「雪のくだけ」といふ事は云はない。今より二十数年前この語の口訳に困つて私は「かけら」と訳したが、雪のかけらは益々へんてこであつて、雪をガラスやかき餅とまちがへてるやうで、語感の相違といふ事で説明し乍らも、心の底で落ちつき得ないものを感じつつ今日に至つた。それが右にあげた字鏡集のクダケの例-この他に「□(石偏に未・クダケイシ)」がある-を見るに及んではじめて釈然としたのである。即ち(一)「くだけし」といふ風な用言を主語とした例が集中にある事、(二)「雪のくだけ」といふやうな語は古今に例を見出し得ない事、(三)「くだけ」の語を見出した時には我々の語感と一致するものとして用ゐられてゐる事、この三つの事実から前説は認めがたく、後説こそ正しい解釈であると私は考へる。雪のくだけたのが、の意である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「雪の摧けし」 原文「雪之摧之」。摧は霊異記下巻十四話にクタケの訓注を見るので、「ユキノクダケシ」と訓むことに誤りはなかろうが、「シ」を強意の助詞と解するか、過去の助動詞と解するかで説が分かれている。代匠記に「摧ハ物ノ摧タルカタハシノ意ナリ」(精撰本)と言うのは前者で、講義にこれを引用し、クダケの体言的なことと、シは強意の助詞である事を説いたのをはじめ、金子評釈・茂吉評釈・佐佐木評釈・窪田評釈・全註釈・古典大系・古典全集など多くの注釈書に受け継がれている。これに疑義を呈したのは澤瀉注釈で、動詞に過去の助動詞シを加えた形が一文の主語や目的語になった例を万葉集に見うることと、雪ノクダケといった語の例を他に求め難いことなどを理由に、「摧け・し(過去)」であると主張されている。古典集成・講談社文庫などが、この説による。澤瀉説の特徴は、クダケという名詞の例が文献に見当たらぬこと及びわれわれの語感でも雪にクダケとは言わないことを重視している点にある。ただし、動詞連用形が名詞として使われることは一般的に認められるし、限られた文献上に無いからと言ってクダケが名詞として使われなかったとは言い難いので、代匠記や講義の説を完全に否定することはできないのである。天皇の歌った「大雪」に対し、わたしの所では水神に頼んで本格的な大雪を降らせた、その雪の砕片があなたのところに飛び散ったのでしょうという、その対照を「クダケ」で明らかにし、「シ」という助詞で強調したかとも解されて、助詞説には捨て難い魅力がある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「塵(ちり)」 | 全注 | 【注】 原文に「散り」を「塵」と記するのは、借訓表記であるが、「塵」字の持つ表意性をも利用している。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 自分の里の雪には「降る」の語を用い、相手側の雪には「散る」の語を用いている。「散り」の表記に「塵」の字を当てたことも、多分に意識的であろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 105 | 「題詞」写本 | 校本 | 大津皇子竊下於伊勢神宮上来時大伯皇女御作歌 〔本文〕 「大」、神田本「火」。「伯」、金沢本「泊」。「歌」、元暦校本・金沢本・神田本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本、コノ下ニ「二首」ノ字アリ。 〔訓〕京都大学本、赭訓アリ。次ノ如シ。「竊ニ下於伊勢神宮上来ル時大伯ノ皇女ノ」。 温故堂本、「竊」ノ右下ニ「ニ」アリ。 細井本、「大伯」ノ右ニ「ヲホクノ」アリ。 〔諸説〕代匠記精撰本、「歌」ノ下ニ「二首」ノ字アルヲ可トス。 童蒙抄、「オホツノミコヒソカニイセノカンノミヤニクダリテノホリキタルトキオホキノスメヒメノミツキリノウタ」ト訓ズ。 万葉考、「竊下」ヲ「シヌヒクダリテ」、又「上来時」ヲ「ノホリキマストキ」ト訓ズ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | 目録には御作歌二首とあり、ありぬべき事なり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 題詞原文「竊」 | 全注 | 「竊」 「116歌」の題詞にも見える。霊異記訓注などにより「ヒソカニ」と訓む。大津皇子が伊勢の大伯皇女を訪ねた時の皇女の作歌である。この題詞に「竊かに」とあるのは、皇女が斎宮であったため、姉弟でも簡単に逢うことを許されなかったのを、忍んで逢いに行かれたことをあらわしているのだろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 題詞の「窃(ひそ)かに」は、皇子の伊勢行がこの(本文既述)謀反事件に関わるものとして理解されていたことを示すのであろう。(「新大系」本では、「竊」ではなく「窃」を当てているが、訓は同じ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 万葉集の題詞・左注でこの字を用いてある場合(90左注・109題詞・116題詞など)必ず男女の秘事に関する記述が見られる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「遣(やる)」 | 全注 | 【注】「大和へ遣ると」 「ヤル」は、遠くへ行かせるとか、物を与える、気を晴らすなどの意をあらわす動詞。ここは行かせる意。 うち日さす宮に行く子をまがなしみ留むれば苦し聴去(やれ)ばすべなし (4・532) -時の盛りを とどみかね 過し野利(やり)つれ- (5・804) などのように、手離したくないのに行かせてしまう意味が強い。ここも大和へ帰したくはないのに行かせるという気持ちがこめられている。 【考】 〔注〕にも触れたとおり、「大和へ遣る」には、愛する者を引き留めたい気持ちや、遠くへ手放す不安がこめられている。夜更けから暁方まで茫然と立ち尽くしていた皇女の、鶏鳴によって我にかえられた時の心境を想像させて、あわれ深い作である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「大和へやると」 都のある大和の国へかへしてやるとて、の意。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 「遣る」-行かせる。強制的語気が感じられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「鶏鳴(あかとき)」 | 注釈 | 【訓釈】「鶏鳴露尓(あかときつゆに)」 暁は仮名書例「安香等吉(アカトキ)」(15・3627)、「安可等伎(アカトキ)」(15・3641)などとあり、「アカトキ」と訓む。「明時(アカトキ)」の意で、それが轉じて「アカツキ」になつたのであるが、ここに原文「鶏鳴」とあり、又「五更」(8・1543、10・2213、その他)ともあつて、一番鶏の鳴く頃、春分、秋分時の午前四時、即ちまだ暗いうちをさしたものと思はれる。推古紀十九年の五月五日兎田野の薬獵に「鶏鳴(アカトキ)」に集合して「會明(アケボニ)」に出発する旨の記事がある。従つて暁露といふのは朝露といふより夜露と云つた方がふさわしいものである。夜露に濡れて弟皇子を見送られる姿である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「暁露に」 原文「鶏鳴」を「アカトキ」と訓む。「暁」(7・1263)、「五更」(12・3061)とも、「安可等伎」(15・3641)とも書かれている。「五更」は午前四時ころをさすので、「アカトキ」は夜明け前のまだ暗い時、文字通り一番鶏(どり)の鳴く時分をあらわすと見られる。推古紀十九年の「取鶏鳴時集于藤原池上、以會明乃往之」の「鶏鳴時」に「アカトキ」、「會明」に「アケボノ」の古訓がある。アケボノは夜がほのぼのと明けようとするところで、アカトキよりも後の時刻をさす。第三句「さ夜ふけて」で夜のふけたことをあらわし、この第四句では夜明けに近づくまでの時の経過を表現している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 「暁露」-「アカトキ」に置く露。「アカトキ」は「アカツキ」の古形。原文「鶏鳴」は『新撰字鏡』にも「鶏鳴、丑時」とあり、一番鶏が鳴く時刻という意味だが、実際は夜明けに程遠い深夜の午前二時前後をいう。『日本書紀』には九月九日天武崩御、同二十四日大津謀反、十月二日逮捕、翌三日処刑、とある。この伊勢下向はその九日間のことで、この歌が詠まれたのは恐らく九月三十日未明、月のないアカトキであったろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「吾立所霑之」諸訓 | 注釈 | 【訓釈】「吾立所霑之(わがたちぬれし)」 上に「ぞ」「や」「か」などの係詞がなくて「ぬれし」と連体形で結んだ例は古くは、 阿斯波良能 志祁志岐袁夜之 須賀多々美 伊夜佐夜斯岐弖 和賀布多理泥斯 (神武記) (アシハラノ シケシキヲヤニ スガタタミ イヤサヤシキテ ワガフタリネシ) ともあり、この先にも「我二人宿之(ワガフタリネシ)」(109)とあり、詠歎の意をこめて結ぶ場合に用ゐられる。また連体止であるから、上に「が」の助詞が用ゐられる例で「ワガ」と訓み、「ワレ」ではない(佐伯君『萬葉語研究』所収「萬葉集の助詞二種」参照)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「吾が立ち濡れし」 原文「吾」は「ワレ」とも訓めるが(古訓・拾穂抄など)、末尾を連体形で止める文においては「人妻児ろをいきに和我須流」(14・3539)、「萱畳いやさやしきて和賀布多利泥斯」(記)のように、「ワガ」であることが確かめられるので(佐伯梅友「万葉集の助詞二種」『万葉語研究』)、「ワガタチヌレシ」と訓む。「ヌレシ」を西本願寺本など「□(占を古)之」とするが、元暦校本・類聚古集・金沢本に「霑之」とあるのが正しい。「霑」は万象名義に「濡」の注があり、「濡・潤」などに通ずる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校本 | 「吾立所霑之(ワカタチヌレシ)」 元暦校本・金沢本・類聚古集「われたちぬれぬ」。元暦校本、下ノ「ぬ」ノ右ニ朱「シ御本」あり。 神田本「タレタチヌレハ」。「吾」ノ左ニ朱「ワカ」あり。「ハ」ノ右ニ「ヌィ」アリ。「之」ノ左ニ「シイ」アリ。 温故堂本「ワカタテヌレシ」。 京都大学本「吾」ノ左ニ赭「ワレ」アリ。「所霑之」ノ左ニ赭「ヌレヌ」アリ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 「吾立所霑之(あがたちぬれし)」 「109歌、我二人宿之(わがふたりねし)」の頭注で、〔我が二人寝し-ワ・ワレは単数形ア・アレに対して複数を表すことが多い。-〕 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 106 | 原文「二人行杼」字余り考 | 新大系 | 初句原文は「二人行杼」。「フタリユケド」と訓むと字余りの規則に外れるが、「行(ゆ)く」の語を含む場合は、時に例外がある。「家に行きて(由伎弖)」(795)、「出て行きし(由伎斯)」(890)、「手に巻きて行かむ(由可牟)」(4007)など。一方に「いく」という語形もあったので、「行」の字を「イク」と訓むこともあり得る。「見つつゆかむ(由可牟)を置きていかば(伊加婆)惜し」(3990)は、「いく」が字余りを避けるための言い換えであることの明らかな例である。ここは「二人ゆけど、ゆき過ぎがたき」と訓でおく。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「去過難寸」 | 注釈 | 【訓釈】「二人行杼 去過難寸 秋山乎」(二人行けど行き過ぎ難き秋山を) 「難き」は今も用ゐる「難し」の連体形で、意味は前にあつた「がてに」(95)、「がてぬ」(98)と似てゐるが、それは前述のやうに、可能の意の動詞に打消の助動詞がつづいたもので、後には用ゐられなくなつたものであり、「難し」は、困難な、むつかしい、などの意の形容詞である。しかもその両者が混同される傾向の当時はやく認められる事既に(95)述べておいたが、口語に訳する場合、両者共に「かねる」といふ言葉を用ゐるにしても、本来別のものであるといふ認識の上に立つべきものだと思ふ。従つてこの三句も、「二人で連立つて行つても行き過ぎ難い秋山」、といふので、それは秋山が何となく物さびしく、わびしいものであるといふ心がこめられてゐる事がわかる。私注に「寧ろ秋山の趣深いのに引かれて行きすぎかねるといふのがほんとではあるまいか。『行きすぎがたし』といふ集中の例も必ずしも困難である為といふ風にはなつて居ない。」とあり、注意すべき新見のやうであるが、これも「難し」と「かてに」との混同によつたものと思はれる。 稲日野(いなびの)も 去過勝尓(ユキスギカテニ) 思へれば心恋しき加古の島見ゆ (3・253) は私注にいふ「趣深いのに引かれて行きすぎかねる」例であるが、そこには「かてに思ふ」とあつて「難き」ではない。「行き過ぎ難き」の例は集中ここ一例のみである。また作意から云つても秋山に心ひかれるのであるならば「二人行けど」といふ語が生きて来ない。これはやはり従来の解釈でよい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「行き過ぎ難き秋山を」 原文「去過難寸秋山乎」の「去」を「ユキ」と訓む。「去」は玉篇に「丘盧反離也往也」とあり、「往」に通ずる。「離」にも近く、ある場所を離れてゆく場合に用いられることが多い。「行き過ぎ難き」は淋しく恐ろしくて容易に通り過ぎがたいことを言う。秋山の趣深さにひかれて行き過ぎかねると解する説も見られるが (私注) 、それでは初句の「二人行けど」が生きないだろう。「難寸」は「カタキ」と清音に訓む。「カタシ」と「カテニ」については「95歌」の〔注〕参照。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 「二人行けど行き過ぎ難き」 二人でいたわりつつ行っても通過困難な。速総別王(はやぶさわけのおおきみ)・女鳥(めとりの)王の駆落ち(→385)などを暗示するか。 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 〔以下「巻第三-385」歌に関して〕 柘枝仙が歌三首 霰降り吉志美が岳をさがしみと草取りかなわ妹が手を取る 「頭注」一部 『古事記』仁徳天皇の条に天皇の弟速総別王が女鳥王と愛の逃避行をした際に詠んだという歌に、「梯立(はしたて)の倉梯(くらはし)山を険しみと岩かきかねて我が手取らすも」というのがあり、『肥前国風土記』にも「杵島曲(きしまぶり)」という曲名で、「霰降る杵島が岳を険しみと草取りがねて妹が手を取る」とある。これらの先後関係は不明。この歌も男女の駆落ちの民謡が「仙柘枝(やまびめつみのえ)が歌」に組み合わされたものか。 「本文左注」 「右一首或云 吉野人味稲与柘枝仙媛歌也 但見柘枝傳無有此歌」 〔右の一首、或いは云はく、吉野の人味稲(うましね)、柘枝仙媛(つみのえやまびめ)に与ふる歌なり、といふ。ただし、柘枝伝(しゃくしでん)を見るに、この歌あることなし。〕 「柘枝伝補注」 柘枝仙媛に関する伝記的小説。漢文的潤色を受けた文体で書かれた某官人の述作か。柘枝伝説はその具体的内容を明らかにしないが、柘の枝が吉野川の漁夫味稲の梁掛かって美女と化し、やがて味稲と同棲したが、遂に昇天したという筋かと思われる。『懐風藻』や『続日本後紀』所載の長歌などに見え、その間内容に多少の差があるが、もとは白鳥処女伝説の一種で、これに中国渡来の神仙思想をからませたものと言われる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「如何」諸訓 | 注釈 | 【訓釈】「いかにか君がひとり越ゆらむ」 「イカニ」を旧訓「イカデ」とし、諸注多くそれに従つてゐたが、山田博士の「奈良朝文法史」に「いかで」の語は「続日本後紀」、仁明天皇の嘉祥二年三月の條の長歌に「四方之国 隣皇波 百嗣尓 継云止毛 何弖加(イカデカ) 等久有牟」とあるが文献に見える最初であつて、集中の「如何」「何如」等を「」イカデ初と訓むは当たらない、と述べられてゐるに従ふべきであり、「伊可尓可阿我世武(イカニカアガセム)」(5・795)、「伊可尓可和可武」(5・826)などの仮名書例に従ひ、童蒙抄に「イカニ」とあるによるべきである。攷證に「武」の上に「良」が脱したものとしてゐるが、「春立下(ハルタツラシモ)」(10・1812)の如きも「ラ」が訓添になつてゐるから、今も訓みそへて「ラム」と訓む。既に山道にある君を思ひやられ、現在推量として、どのやうにして、ひとり越えてをられる事であらう、と云はれてゐるのである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「いかにか君が」 原文「如何君之」の「如何」を旧訓「イカデ1と訓み、代匠記ほか江戸時代の諸注のほとんどがそれによっているが、童蒙抄に「いかにか」とし、講義にそれを受けて、イカデは万葉集に仮名書きが見えず、おそらく平安時代に入ってから生じた語であろうと説いた。同じ山田孝雄の『奈良朝文法史』によれば、イカデの語は、続日本後紀に、仁明天皇の嘉祥二年三月の歌に、「何弖加等久有牟(イカデカヒトシクアラム)」とあるのが文献に見える最初の例である。イカニは、どのようにと状態を問うのに対し、イカデは、なぜという理由を問うのであって、意味の上からも、ここはイカニでなければならない。「伊可尓可阿我世武(イカニカアガセム)」(5・795)、「礼久礼等伊可尓可由迦牟(クレクレトイカニカユカム)」(5・888)などの仮名書き例を見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「獨越武」諸訓 | 全注 | 【注】「ひとり越ゆらむ」 原文「獨越武」を「ヒトリコエナム」と訓む説もある (万葉考・古義・略解など)。戦後の注釈書では、佐佐木評釈および全註釈に「ヒトリコユラム」と「ヒトリコエナム」の両訓を併記し、前者が現代の山行の状態を推量する意味であるのに対し、後者は、これから越えようとする様を思いやる意味になると説いている。「コエナム」も、一説として可能性を認められたのであろう。「越武」をどう訓むべきか。「越(良)武」とも、「越(奈)武」とも記されていないので、講義に言うように文字面からは決定し難いのである。ただし、前歌との関係から言えば、夜更けて弟を見送り、そのまま闇の中に立ち続けた皇女が、暁の露に濡れつつ、いまごろ弟は秋山を越えているだろうと想像して詠まれたものとする方が、これから越えようとしている状態と解するより遥かにまさるようだ。てゐるから、今も訓みそへて「ラム」と訓む。既に山道にある君を思ひやられ、現在推量として、どのやうにして、ひとり越えてをられる事であらう、と云はれてゐるのである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 107 | 未詳の枕詞「あしひきの」 | 註釈 | 有抄云、山ヲアシヒキトイフニ、四義アリ。一ニハ、三方ノ沙弥カ、惡日ニ山ヲコヱケルニ、大雪ニアヒテ、ミチヲウシナヒタリケルトキ、アシヒキノ山チモシラスシラカシノエタモタワヽニユキノフレヽハト詠レケレハ、アシヒキ [キヒィ] タルユヘニ、アシヒキト云也。二ニハ、推古天皇山ニイリテ、カリシ給シニ、御足ニクヒヲフミテナヘキテヒキ給ヒケルヨリ、山ヲ、アシヒキトイフ。日本記ニミヱタリト云々。三ニハ、天竺ニ、一角仙人卜云仙人、額ニ一ノ角アリ。鹿ノ足ナリ。道力 [通力カ] ハアリケレトモ、雨フリテ山ノミチノスヘリケルニ、タフレテ足ヲソコナヘリ。アシヲヒキシニヨリテ、足ヒキトイヘリ。委見智度倫第十七云々。四ニハ、昔天地サケワカレテ、日本土泥、イマタ、カタマラサリシトキ、人ミナ山ニアリケリ。トカクアリキケルニ、アトノアリケレハ、日本ヲ山アトヽイヒキ。ヤマトヽイフコレナリ。山ヘオリノホリスルハ、アシヲヒクニ似タレハ、アシヒキトイフ也。四義ノ中ニ、第四ノ義ヲモチヰルヘシトイヘリ。アシヒキノ義、イヒナシ、ヒトツニアラス。カヤウニコトノヲコリサマサマニイヒノベラレヌレハ、コノウヘニハ、ミヱタラン義ヲ尺シアラハシテモ、ヨシナキカタハヘルヘケレトモ、コトニヲイテ、アマタノ義モツネノコト也。又コノ歌ノミチモ、イマノヨハカリニカキルヘカラス。過去遠々、末來永々カキリモアルヘカラス。然ルニコノタヒニカキリテ、イフヘキコトノアラハレスシテ、ヤミナンコトモウラミナキニアラス。イマノヨヒト、コトニマコトノユヱヲサトラサルコト、ミツノタカラ、アキラカニテラシミタマハムコト、カナシキニヨリテ、ミヱサトリタル義ヲアラハスヘシ。カツハ、サキノ四義、アマタアルニハニタレトモ、タヽソノオコリヲ、イヒカヘタルハカリ也。三方ノ沙弥カ、フカキ雪ニミチマヨヒテ、アシヒ [ヲィ] キケルトイフモ、天竺ノ一角仙人カ、雨フリニ山ミチニタフレテ、アシヒキケルトイヘルモ、推古天皇ノ御事モ、ヌ日本ノ士泥イマタカタマラサリケルトキ、山ニオリノホルカ、足ヲヒクニ似タリケレハトイフモ、タヽ由縁ヲイヒカヘタルハカリ也。アシヲヒク義コレ一義也。ウルハシクアマタノ義トモイフニタラス。山ヲアシヒキトイフコトハ、ヤトイフハタカキ義、マトイフハホムル義、マトカナリトイフ詞也。カクルコトナク、トヽノホリタルヲ、マトカナリトイフ。然ルニ山齋 [アシヒ] トイフ木、コトニサカへタル木也。コノ木昔筑紫 [ツクシ] ノカタニオホカリケリ。コトニサカフル木ナルカユヱニ、此集ノ第七卷ノ歌ニハ、アシヒサ [ナィ] ス、サカヱシキミカ、ホリシヰノト、ヨソヘヨメリ。山ハタカクマトカナレハ、山ヲイヒイテムトスル諷詞ニ、アシヒキトヲケル也。アシヒトイフ木ナレハ、アシヒキトイフ、タトヘハ、サクラヲ、サクラ木トモイヒ、カシハヲ、カシハキトモイフカ如シ。山齋ハ、アシヒナリ。然レハ、山齋トカキテ、ヤマト訓スルモ此義也。此道ノ賢哲、イカテカ覺悟セサランヤ。源順等モ、存知シタリケルナルヘシ。カツハ、住吉玉津島明神、宜 [・ヘシ] クv垂タマフ2知見ヲ1焉。天平二年庚年 [マヽ] 冬十一 [二ィ] 月、太宰師 [帥ィ] [ダサイノソツ] 大伴卿、向京上道之後、還入故郷家作家三首中云、與妹爲而二作之 [イモトヰテフタリツクリシ] 、吾山齋者 [ワカヤマハ] 、木高繁成家留鴨 [コタカクシケクナリニケルカモ] 云々。但此義、我門弟ニアラスシテ、サカシサタテム者ノ、謗家ノ器量トナリヌヘカラン人ニ、ユメユメキカシムヘカラス。有抄云、山ヲアシヒキトイフニ、四義アリ。一ニハ、三方ノ沙弥カ、惡日ニ山ヲコヱケルニ、大雪ニアヒテ、ミチヲウシナヒタリケルトキ、アシヒキノ山チモシラスシラカシノエタモタワヽニユキノフレヽハト詠レケレハ、アシヒキ [キヒィ] タルユヘニ、アシヒキト云也。二ニハ、推古天皇山ニイリテ、カリシ給シニ、御足ニクヒヲフミテナヘキテヒキ給ヒケルヨリ、山ヲ、アシヒキトイフ。日本記ニミヱタリト云々。三ニハ、天竺ニ、一角仙人卜云仙人、額ニ一ノ角アリ。鹿ノ足ナリ。道力 [通力カ] ハアリケレトモ、雨フリテ山ノミチノスヘリケルニ、タフレテ足ヲソコナヘリ。アシヲヒキシニヨリテ、足ヒキトイヘリ。委見智度倫第十七云々。四ニハ、昔天地サケワカレテ、日本土泥、イマタ、カタマラサリシトキ、人ミナ山ニアリケリ。トカクアリキケルニ、アトノアリケレハ、日本ヲ山アトヽイヒキ。ヤマトヽイフコレナリ。山ヘオリノホリスルハ、アシヲヒクニ似タレハ、アシヒキトイフ也。四義ノ中ニ、第四ノ義ヲモチヰルヘシトイヘリ。アシヒキノ義、イヒナシ、ヒトツニアラス。カヤウニコトノヲコリサマサマニイヒノベラレヌレハ、コノウヘニハ、ミヱタラン義ヲ尺シアラハシテモ、ヨシナキカタハヘルヘケレトモ、コトニヲイテ、アマタノ義モツネノコト也。又コノ歌ノミチモ、イマノヨハカリニカキルヘカラス。過去遠々、末來永々カキリモアルヘカラス。然ルニコノタヒニカキリテ、イフヘキコトノアラハレスシテ、ヤミナンコトモウラミナキニアラス。イマノヨヒト、コトニマコトノユヱヲサトラサルコト、ミツノタカラ、アキラカニテラシミタマハムコト、カナシキニヨリテ、ミヱサトリタル義ヲアラハスヘシ。カツハ、サキノ四義、アマタアルニハニタレトモ、タヽソノオコリヲ、イヒカヘタルハカリ也。三方ノ沙弥カ、フカキ雪ニミチマヨヒテ、アシヒ [ヲィ] キケルトイフモ、天竺ノ一角仙人カ、雨フリニ山ミチニタフレテ、アシヒキケルトイヘルモ、推古天皇ノ御事モ、ヌ日本ノ士泥イマタカタマラサリケルトキ、山ニオリノホルカ、足ヲヒクニ似タリケレハトイフモ、タヽ由縁ヲイヒカヘタルハカリ也。アシヲヒク義コレ一義也。ウルハシクアマタノ義トモイフニタラス。山ヲアシヒキトイフコトハ、ヤトイフハタカキ義、マトイフハホムル義、マトカナリトイフ詞也。カクルコトナク、トヽノホリタルヲ、マトカナリトイフ。然ルニ山齋 [アシヒ] トイフ木、コトニサカへタル木也。コノ木昔筑紫 [ツクシ] ノカタニオホカリケリ。コトニサカフル木ナルカユヱニ、此集ノ第七卷ノ歌ニハ、アシヒサ [ナィ] ス、サカヱシキミカ、ホリシヰノト、ヨソヘヨメリ。山ハタカクマトカナレハ、山ヲイヒイテムトスル諷詞ニ、アシヒキトヲケル也。アシヒトイフ木ナレハ、アシヒキトイフ、タトヘハ、サクラヲ、サクラ木トモイヒ、カシハヲ、カシハキトモイフカ如シ。山齋ハ、アシヒナリ。然レハ、山齋トカキテ、ヤマト訓スルモ此義也。此道ノ賢哲、イカテカ覺悟セサランヤ。源順等モ、存知シタリケルナルヘシ。カツハ、住吉玉津島明神、宜 [・ヘシ] クv垂タマフ2知見ヲ1焉。天平二年庚年 [マヽ] 冬十一 [二ィ] 月、太宰師 [帥ィ] [ダサイノソツ] 大伴卿、向京上道之後、還入故郷家作家三首中云、與妹爲而二作之 [イモトヰテフタリツクリシ] 、吾山齋者 [ワカヤマハ] 、木高繁成家留鴨 [コタカクシケクナリニケルカモ] 云々。但此義、我門弟ニアラスシテ、サカシサタテム者ノ、謗家ノ器量トナリヌヘカラン人ニ、ユメユメキカシムヘカラス。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 足日木乃 [アシヒキノ] (木ノ字、仙覺註本には來と作り、) は、山 [ヤマ] の枕辭なり、(日の言清て唱フべし、古言清濁考に委ク出ツ、) さてこの詞の意、昔來 [ムカシヨリ] くさぐさ説あれど、皆あたらず、(それが中に、近キ頃本居氏古事記傳に、阿志比紀 [アシヒキ] は足引城 [アシヒキキ] にて、足 [アシ] は山の脚 [アシ]、引 [ヒキ] は長ク引キ延たるを云、城 [キ] とは凡て一構 [ヒトカマヘ] なる地を云て、此レは即チ山の平なる處を云、其は周リに限ありて、自 [オノヅカラ] 一トかまへなればなり、されば足を引たる城の山、といふつゞけなりと云るは、舊説どもより見れば、こよなくすぐれて、古意を得たるに似たれども、なほよく思ふに、山の周リに限ありとて、一トかまへのものとせむは、いさゝけなる小山などこそあらめ、千里 [チヘ] 百疊 [モヽヘ] 奧域 [オクカ] も知ぬ大山をば、いかでか、一トかまへのものとはすべからむ、狹小 [チヒサ] く倚 [カタヨ] りたる、思ヒ量リをはなれて、考へ見ずは、廣大無偏 [ヒロクオホキ] なる古ヘ人の心詞には、協ふべきことにあらずなむ、かく今までの説どもの、信がたきによりて、余 [オノレ] 年月かにかくに、おもひめぐらして、今やうやうに、一ノ義を思ひ得たり、) まづ阿志 [アシ] は伊加志 [イカシ] にて、(伊加 [イカ] の切阿 [ア]、) 茂檜木之 [イカシヒキノ] と云なるべし、茂 [イカシ] とは茂穗 [イカシホ]、茂彌木生 [イカシヤクハエ]、また重日 [イカシヒ]、嚴矛 [イカシホコ]、伊加志御代 [イカシミヨ] などの茂 [イカシ] にて、此 [コヽ] は檜の木の茂み榮えたるを稱美 [ホメ] て、茂檜木 [イカシヒキ] とは云るならむ、(地ノ名に葦城 [アシキ]、葦穗山 [アシホヤマ] などいふも、もしは、茂城 [イカシキ]、茂穗 [イカシホ] の義にはあらざるにや、然る意ならば、伊加志 [イカシ] を切て、阿志 [アシ] と云る例ともなるべし、) かくて檜をば、今ノ世には檜之木 [ヒノキ] とのみ呼 [イヘ] ど、古ヘは比伎 [ヒキ] とそいひけむ、都婆伎 [ツバキ] といふも、もとは都婆 [ツバ] と云けむを、(都婆市 [ツバイチ] を、海石榴市 [ツバイチ] と書るをも思ヒ合スべし、) 其を都婆乃木 [ツバノキ] と云ハずして、都婆伎 [ツバキ] と云る例をも合セ思ハべし、さるは集中に、この枕詞を、足檜木とも多く書るを、七ノ卷また十一に三處、十二に二處までに、足檜 [アシヒキ] とも書たるを合セ思フべし、(比伎 [ヒキ] と呼しならずは、檜の一字を、かくあまた所に、ヒキに用ふべき謂 [ヨシ] なし、) かくて山に屬くは、茂檜木 [イカシヒキ] の生樹 [ヒタテ] る山、と云意にいひかけたるものなり、さてしからば、生 [オフ] とか樹 [タツ] とかいふ言なくては、足はぬごと思ふめれど、其は白浪之濱 [シラナミノハマ]、白管之眞野 [シラスゲノマヌ]、炎之春 [カギロヒノハル](これら白浪のよする濱、白管の生る眞野、炎の燎る春の意なり、) などやうに云ること、枕詞にはあまた見えたれば妨なし、かくて山には數種 [クサグサ] の木あれば、檜をのみ云むは、いとかたくなしとおもふ人もあるべけれど、しからず、さるは檜は、諸木 [キヾ] の長上 [ツカサ] にして、此を眞木 [マキ] とも稱へ云て、その長上 [ツカサ] なる檜を云ヘば、其餘 [ソノホカ] の諸木 [キヾ] は、皆自 [オノヅカラ] 其ノ中にこもれることなればなり、(集中に、眞木之立荒山 [マキノタツアラヤヤ] とも、眞木立山 [マキタツヤマ] ともよめるをも思フべし、) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「あしひきの」 山の枕詞。「き」の文字原文に「木」とあり、記紀の例も「紀」又は「木」とある。いづれも「乙類」の仮名である。然るに又「曳」「引」の文字を用ゐたものが人麻呂集その他に見える。それによると四段活用動詞の連用形だから、その「き」は「甲類」の仮名であるはずである。この事はこの枕詞の原義がはやくわからなくなつてゐて、人麻呂時代には原義とは違つた解釈を勝手に試みたものでないかと思はれる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「あしひきの」 山の枕詞。語義・かかり方未詳。→ 「466歌」 以下「466歌」頭注 「あしひきの」-原文「足日木乃」とあり、このようにキに乙類の仮名を用いたものが82例あり、一方「足引」「足曳」などと記し、これらは四段の連用形を表し、そのキが甲類のものが20例ある。「足疾乃」 (670) などの例もごく一部にあり、それらは足を引く、足が不自由だ、などと解され、後者の傍証となるが、すべて二次的な民間語源を反映した表記とみるべきであろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 「あしひきの」は山に掛かる枕詞。語義未詳。相聞の歌では、女が男の訪れを待つのが普通であり、男が女を、しかも山中で待つということは尋常ではない。皇子と郎女の間の特殊な事情を窺わせる。題詞の「石川郎女」は、同じ頃、草壁皇太子と関係のあった石川女郎 (110題詞) と同一人であり、大津皇子としては、草壁皇太子の愛する女性を奪う行為であった。「109題詞」にも「大津皇子の窃かに石川女郎を婚きし時に」とある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「やまのしづくに」 | 全注 | 【注】「山のしづくに」 「ヤマノシヅク」は、山の岩角や木の葉、木末などから落ちるしずくを言うと思われる。記紀歌謡に見えず万葉集でもこの贈答歌に見られるのみの珍しい語。「山露」という中国詩の表現の翻読語きあもしれないが、未詳。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 山之四付二 [ヤマノシヅクニ](之ノ字、拾穗本には乃と作り、) は、山の草木よりしただる滴 [シヅク] になり、(金葉集に、戀しさを妹しるらめや旅宿して、山のしつくに袖ぬらすとは、) 十九に、足日木之山黄葉爾四頭久相而將落山道乎公之越麻久 [アシヒキノヤマノモミチニシヅクアヒテチラムヤマヂヲキミガコエマク] とあり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四句原文「沾」 | 全注 | 【注】「吾立ち濡れぬ」 原文「沾」は、西本願寺本に「沽」とあるが、金沢本・細井本・京都大学本による。万象名義には「薄」とあるのみだが、新撰字鏡には「霑字」の注が見え、「ヌル」と訓む。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 108 | 原文「吾乎待跡」旧訓 | 全注 | 【注】「吾を待つと」 旧訓「ワレヲマツト」であったが、万葉考に「アヲマツト」とした。「阿袁麻多周良武」 (5・890)、「安乎麻知可祢弖」 (14・3562) など集内の仮名書きによっても「アヲマツト」と訓むべきだろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | 吾乎待跡君之沾計武足日木能山之四附二成益物乎 [ワレヲマツトキミカヌレケムアシヒキノヤマノシツクニナラマシモノヲ] 「吾」は「わ」とひと文字にも讀べし、下にさもよめり、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二句原文「沾」 | 全注 | 【注】 「沾」を元暦校本・紀州本・西本願寺本・大矢本に「沽」とする。金沢本・細井本・温故堂本・京都大学本に「沾」とあるのが正しい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 109 | 題詞原文〔注〕 | 注釈 | 「大津皇子竊婚石川女郎時津守連通占露其事皇子御作歌一首」 「女郎」を金澤本に「郎女」とある。前二首の題詞によるとこれも郎女とあるが正しいやうに見える。しかし郎女をまた女郎と書いたとも思はれるので、もと「女郎」とあつたのを金澤本は前二首の題詞に習つてさかしらに改めたとも考へられる。金澤本はこの巻については最も古い写本ではあるが、文字の字体なども必ずしも原本の字体に拘泥しないところが見えるので、今は、この本以外の諸本すべて「女郎」とあるを改める事はさし控へる。檜嬬手別記には、女郎とは今も遊女を呼ぶやうに、昔も遊行女嬬に用ゐた名で、もとは郎女と女郎とは違つてゐたのではないか、といふ説が述べられてゐるが、これは推測の説にすぎず、下にも見られるやうに同人を郎女とも女郎とも書いたと考へる。 「津守連通」は和銅七年正月に正七位上より従五位下に、同十月には美作守になつてゐる。養老五年正月二十七日の詔に「文士武士。国家所重。醫卜方術。古今斯祟。冝擢於百僚之内。優遊学業、堪為師範者。特加賞賜、勸勵後生」とあつて、陰陽道の中でこの人も絁十疋、絲十絇、布二十端、鍬二十口を賜はつてゐる。七年正月には従五位上に叙せられてゐる。この作のなされた時は、右の恩賞を賜はつた時よりも更に三十五年許も前、年少気鋭の頃であつた事が察せられる。津守は攝津の住吉の津を守る職名が姓となつたもので、新撰姓氏録、攝津国神別、天孫の條に津守宿祢があり、和泉国神別、天孫の條に津守連がある。今は後者で、天火明命 (アメノホアカリノ) の男、天香具山 (アメノカゴヤマ) の後とある。 題詞の下に、金澤本、元暦本、紀州本には小字で「未詳」の文字がある。後人の注かと思はれる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 「大津皇子竊婚石川女郎時津守連通占露其事皇子御作歌一首 [未詳]」 「竊」-既出。105歌題詞。「石川女郎」-金沢本にのみ「石川郎女」とある。それによれば前歌の石川郎女にも一致し、正しいように思われるが、110歌の題詞にも「石川女郎」と記され、そこでは金沢本・元暦校本・紀州本・西本願寺本など古写本のすべてが「女郎」で一致しているから、女郎とも郎女とも記したと見るべきであろう。金沢本の「郎女」こそ前の題詞にひかれて、後人がさかしらに改めたものと考えられる (注釈)。なお中国では、「女郎」は男子のように才能ある婦人、もしくは未婚の少女を意味する称であり (八木沢元『游仙窟全講』)、「郎女」という称は無いらしい。他人の子を呼ぶ敬称「郎子」からの連想によってイラツメをあらわすために作られた和製の熟字か。「婚」-古事記に「欲婚稲羽之八上比賣」「其女須勢理毘賣出見為目合而相婚還入」「故相感共婚供住之間」など多くの例を見る。それらはマグハヒ・ヨバヒ・アヒなどに相当し、文脈によって読みわけられるようだ。万葉集の歌中には「結婚 (ヨバヒ)」 (9・1809、12・2906)、「左結婚 (サヨバヒ)」 (13・3310)の例を見るが、この題詞の場合は、すでに交渉を持ったのちのことなので、アフと訓むのが適切と思われる。 「津守連通」-和銅七年正月に従五位下となり、美作守を経、養老七年正月に従五位上に昇った陰陽道の大家。その占によって大津皇子と石川女郎との関係が暴露された時、皇子の作られたのが109歌であるという。「注」-題詞下に、金沢本・元暦校本・紀州本には「未詳」の小字注がある。何を未詳とするのか明確ではない。あるいは巻一の額田王歌 (7) と同様、作歌の時期に関して不審が抱かれたのであろうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「津守之占尓」異訓 | 全注 | 【注】「津守が占に」 旧訓「ツモリノウラ」で、佐佐木評釈・全註釈・古典大系・注釈なども同訓であるが、窪田評釈・私注・古典全集・桜楓社本・古典集成・講談社文庫などは「ツモリガウラ」と訓む。助詞「ガ」と「ノ」の違いについては、青木伶子「奈良時代における連体助詞『ガ』『ノ』の差異について」(国語と国文学昭和二十九年三月) にも記されているように、「ガ」に親愛・軽侮のこめられる場合があるので、ここは「ガ」の方が相応しい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「将告登波」旧訓 | 童蒙抄 | 大船之津守之占爾將告登波益爲爾知而我二人宿之 [おほふねの、つもりのうらに、のらんとは、まさしにしりて、わがふたりねし] 將告登波 古本印本ともに、つげんとはとよめり。しかれども第一卷の雄略天皇の御歌にて註せるごとく、つぐると云古語をのるともいひしなれば、こゝは大船のとよみ出し給ひて、しかもうらにとあれば、うらへにのると浦に乘との義をよせてよみ給ふ歌なれば、告はのるとよむべき也 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「のらむとは」 原文「告」とあつて旧訓に「ツゲム」とあつたのを童蒙抄に「ノラム」と改めたに従ふべきであるが、「うらへにのると浦に乗るとの義をよせて」とあるは従ひがたい。「告」の字は「われ旅なりと於妹告社 (イモニツゲコソ)」 (10・2249) の如く「ツグ」と訓むべきものもあり、「父母に事毛告良比 (コトモノラヒ)」 (9・1740) の如く「ノル」と訓むべきものもあるが、「ツグ」の例は、 ほととぎす鳴くと人都具 (ツグ) [17・3918] 都の人に都気 (ツゲ) まくは [20・4473] いまだ見ぬ 人にも都気 (ツゲ) む [17・4000] の如く、知らせる、通知する、報告する、など、伝達の意に用ゐられてをり、「ノル」の方は、 み越道の多武氣(峠・手向け)に立ちて妹が名能里 (ノリ) つ [15・3730] 石ふまず空ゆと来ぬよ汝が心能礼 (ノレ) [14・3425] まさでにも乃良 (ノラ) ぬ君が名占に出にけり [14・3374] の如く、打ち明けるとか、宣言するとか、いふ意に用ゐられてをり、それらを較べて今の場合は「ノル」の方が適切であり、殊に、 夕占問ひ占正謂 (ウラマサニノレ) [11・2506] 夕占にも占尓毛告有 (ウラニモノレル) 今宵だに [11・2613] の如く占の場合には「ノル」の語が用ゐられてゐるやうに思はれるので、今は「ノラム」と訓む。占に顯さうとは、の意。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「益為尓知而」諸訓 | 代匠記 | 「盆爲爾知而」 (まさしにしりて) マサシニは正しくなり、西行もまさしに見えてかなふ初夢と、立春の歌によまれたり、汝が占にあらはされむとは、我心の占にも兼て正しく知ながら、思かねて云初て逢つるぞと、不爭して讀たまへり、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 童蒙抄 | 「盆爲爾知而」 (まさしにしりて) まさしにのしは助語也。まさしくしりてといふ意地。此爲の字少心得がたけれど、先は助語に見るべき也。爾の字もしくは久の字具抔のあやまりにてあらんか。まさしくしりてとあればやすき也 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 「益爲爾知而」(カネテヲシリテ) 益爲爾知而は、益爲爾の三字は、必 [キハメ] て誤字なり、(岡部氏が、益爲爾 [マサシニ] は正 [マサ] しになりといへれどいかゞ、さらば直に益爲久 [マサシク] とこそいはめ、西行が立春の歌に、まさしに見えてかなふ初夢とよめるは、今の御歌の誤字によりてよめるなれば、證とするにたらず、又略解に、本居氏の説とて、爲 [シ] は氐の誤ならむと云て、十四の卷に、武藏野のうらへかたやき麻左氐 [マサテ] にも、とあるを據とせれど、かの十四なる麻左氐 [マサテ] は、同卷に、可良須等布於保乎曾杼里能麻左低爾毛伎麻左奴伎美乎許呂久等曾奈久 [カラストフオホヲソドリノマサテニモキマサヌキミヲコロクトソナク] ともありて、麻左氐 [マサテ] は眞實 [マサネ] の意なり、略解に、まさては正定 [マササダ] の意ならむ、と云るもあらず、麻左氐 [マサテ] に告 [ノル] は、俗にあり樣 [ヤウ] 有體 [アリテイ] に告 [ノル] といふことにて、麻左氐 [マサテ] の詞皆然り、されば占に、眞實に告たることにこそいはめ、こゝはそれとは意かはりて、占に告むことを、豫心に知リ居たるよしなれば、さは云べからざるをや、かれ強て嘗試 [コヽロミ] にいはゞ、) 益は兼の誤、兼益草書似たり、爲は而の誤、爲而草書似たり、爾は乎の誤、乎を□[乎の草書] の草書に作ときは□[尓の草書] に混ひ易し、さらば兼而乎知而 [カネテヲシリテ] なり、乎 [ヲ] はことをおもく思はする助辭なり、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「正しに知りて我が二人寝し」 (まさしにしりてわがふたりねし) 類聚名義抄「正」 (佛、上) に「マサ(ニ)シ」とあり、「適」 (佛、上)、「的」 (佛、中)、「期」 (同) などに「マサシ」の訓がある。代匠記に「マサシニハ正シクナリ。西行モマサシニ見エカナフ初夢ト立春ノ歌ニヨマレタリ」とあるが、山家集巻頭の歌は「まさしく」とあつて「マサシニ」といふ語は見えない。「まさし」の形容詞は「心のうらぞまさしかりける」 (古今集、十四)、新撰字鏡 (三) 「□(言偏+當)」に「万佐之支己止 (マサシキコト)」ともあるが、「まさしに」といふ用例はなく、他の形容詞についてもかういふ例は見当たらない。「見る人無しに」「こぐ人無しに」などの「無しに」はあるが、今の場合と同じものではない。今の「まさしに」は、まさに、まさしく、と同じ意に用ゐられたものである。「我が二人寝し」は前の「吾が立ちぬれし」 (105) と同じく連体止にしたもので、正しく承知の上で二人で寝たことであるよ、の意。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「正しに知りて」 原文「益為」は借訓。「マサシニワ」は、たしかにの意の副詞と見られる。「マサシ」という形容詞の語幹 (マサ) に「ニ」の付いた「マサニ」と同じ意味と思われるが、シク活用形容詞の終止形に、「ニ」をともなう形は珍しい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「まさしに」 まさしく。マサシは占いの確かなことを表す。ただし、シク活用形容詞の基本形が助詞「ニ」をとった例はない。「君なしに」 (458) などからの連想で生まれた語形か。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 第四句、諸本原文の「益為尓」は、「マサシニ」と訓まれて来たが、シク活用の形容詞の語幹に助詞「に」の接続した例は皆無なので、「尓」を「久」の誤字と見て、「マサシク」と訓む説に拠っておく。「此に於て正しく知るを」 (法華経玄賛・淳祐古点)。草壁皇太子の愛する人と通じ、発覚しても昂然としている皇子の態度は、懐風藻の「性頗る放蕩、法度に拘はらず」の評に適っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 110 | 題詞原文「尊贈賜」諸写本 | 注釈 | 「日並皇子尊贈賜石川女郎御歌一首 [女郎字曰大名兒也]」 「日並皇子尊」は既出 (1・49)。「贈」の文字、金澤本、紀州本などには無い。目録にも「賜」とのみある。天皇の場合は「賜」の一字が用ゐられ (91・103の如く) てゐるが、その他の場合は「贈」とのみ (107) あるのが通例で、「贈賜」とあるはここと坂上郎女が大嬢への作 (4・723) の題詞にあるのみで、その場合も元暦校本と紀州本とは「贈」の文字がない。しかしその作の左注にも「報賜」とあるのを見るとその「贈」もあつたものと見た方がよいであらう。即ち天皇の場合には「賜」と書き、その他の場合は目上の人より目下の人への場合に「贈賜」と敬語を添へたと見るべきであらう。注の「大名兒也」の四字刊本にないのは脱したもので、古写本すべてにあるによるべきである。「字 (アザナ)」については古義に「漢国には、姓氏名字號の五ツありて、自稱には、かならず名をいひ、人より呼には、必ズ字を稱ヒ・・・此方にて阿邪名 (アザナ) と云しは、唯に名のかはりに、人より呼料にて、漢人の字とは異れども、亦其ノ様大かたは似たるものなるゆゑに、字と書るなり」とあるやうに、本名の他に用ゐられた呼び名である。この注によつてこの女郎を前の石川女郎と別人とする説 (美夫君志) などもあるが、これは歌の句の説明の為に加へられたもので、前の石川女郎と別人たる事を示すものではない。この事なほ「129歌」の題詞の條で述べる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 「日並皇子尊贈賜石川女郎御歌一首」 「尊贈」の二字金澤本にない。元暦校本・金澤本・古葉略類聚鈔・紀州本・西本願寺本など「女郎字曰大名兒也」の八字小字にて記す。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初句「大名兒」諸訓 | 注釈 | 【訓釈】「大名兒」(オホナコ) 金澤本等の古写本には「オホナコカ」とあり、西本願寺本以後は「オホナコヲ」とし、この訓が今日も一般に行はれてゐる。仙覚抄に「加古点者、オホナコヤと点ス。オホナコガ、クサヲカリタツニ似タリ。イカガサルコト侍ルベキ。オホナコヲトイフベシ・・・」と述べ、代匠記にはそれを批評して「古点モ押照ナニハヲ、押照哉ナニハトモ云ヤウノ詞ニテ、ヤニ心ナケレバ悪カラズ。又呼懸ル意ニテサモ侍ルベシ。又唯四モジニヨミテモ、大名兒ヨト云意ニテ苦カラジ」と云つてゐる。按ずるに仙覚抄に「ヤ」とあるは、「カの誤写で、原本には「カ」とあつたのではないか。現存の古写本は右に述べたやうに「カ」とあつて、「ヤ」とあるものなく、又「ヤ」であれば契沖の言のやうに解釈に不都合なく、間投詞と見る事が出来るからである。即ち古訓には「オホナコカ」とあつたのを仙覚が「オホナコヲ」と改めたと見るべきである。それを契沖は仙覚抄の誤写に気づかず「ヤ」でもよいぢやないか、又「オホナコ」だけでも悪くはあるまい、と云つたのである。しかしそれに注意する人は殆どなく、仙覚の改訓が行はれる事になつたのであるが、新訓萬葉集に代匠記によつて「オホナコ」の四音の訓が採られ、全註釈に「大名兒よと呼び掛ける語法である」と云ひ、佐佐木博士の評釈にも「四字の句で呼びかけて歌はれたのが珍しく」といひ、「ヲ」を訓みそへぬがよい、と述べられてゐる。「オホナコヲ」と訓む事が定説のやうになつてしまつてゐる今日、代匠記の説によつて四音に訓む事には抵抗を感ずるのが多くの人の気持ちであらうと思う。しかしここには「ヲ」の表記がない。巻一、二には助詞の表記が省略されてゐない場合が多い事は (1・45、79) にも述べたが、この前後を見ても「吾勢□ [□ 示偏に古] 乎 (ワガセコヲ)」 (105)」、「大船之 (オホフネノ)」 (109)、「古尓 (イニシヘニ)」 (111) の如く、表記がある。名詞と名詞を結ぶ「の」はその名詞間の結合が密接な場合省略される事があるが、主客を決する「が」「を」の如き助詞を省略した例はこのあたりには見当たらない。「吾乎待跡 君之沾計武 (アヲマツト キミガヌレケム)」 (108) の如きを見ても、「オホナコヲ」と訓ませるつもりならば「大名兒乎」とあるが当然であるが、現存諸本ににその文字がないのみならず、古写本に「カ」とあり (もし仮に仙覚抄が誤写でないとすれば「ヤ」といふ事になり) 古今六帖 (五「忘れず」) には「オホナリノ」、夫木和歌抄 (二十四「河」) には「オホカハノ」とあつて、仙覚が改訓した迄のものに「ヲ」とあるものを見ないといふ事は、現存の写本以外のものにも「乎」の文字のなかつた事を考へさせる。だからもし脱字だとすれば、編纂前か、編纂後間もない頃に落ちたと見るべきであらうが、さうまで考へて「オホナコヲ」と訓まねばならないか。「オホナコヲ」とすれば調子が整ひ、意味も通じやすくなるとは誰も考へる。しかし初句四音の例は前にも「ウネメノ (1・51)」があり、それももとは「タワヤメノ」「タヲヤメノ」などと訓まれてゐたが、今は「ウネメノ」と訓まれて異論が出ないやうになつてゐる。今の場合も「オホナコ」が先入感になつてゐる為に「ヲ」を削る事に抵抗を感ずるのであるが、四音ではいけないといふ積極的な理由はない。たとへば今に類似の固有名詞の初句四音の例をあげれば、 伊夜彦 (イヤヒコ) おのれ神さび青雲のたなびく日すら小雨そほふる (16・3883) の如きも旧訓には「イヤヒコノ」とあつたが、「イヤヒコ」と四音に訓まれること諸注に一致するところである。だから今の場合、解釈としていづれが妥当であるかを考へる方が根本だといふ事になる。「大名兒を」と訓めば第二、三句は第四句にかかる挿入的序詞となつて、初句は結句につづく事になる。それは後世のものとしては別にあやしむに足らぬものであるが、萬葉としては異例である。萬葉の序は、初、二句又は三句に置かれるのが普通であり、それでなくば第三、四句に置かれるのが例である。第二、三句の序といふのは異例であるが、これは明らかにその異例であつて、しかも初句が結句につづくといふ萬葉としては珍しいものである。尤も初句より結句へといふ例は、 今日もかもおきつ玉藻は白浪の八重折るが上に乱れてあるらむ (7・1168) 行き行きてあはぬ妹故久かたの天の露霜にぬれにけるかも (11・2395) の如きがある。だから「大名兒を」として結句につづけるといふ事が認められないわけではないが、萬葉としては極めて異例な形である。それを「オホナコ」と四音に訓めば、右に引用の代匠記に苦シカラジと云つてゐるやうに、珍しいものでなく、「ほととぎす間しましおけ」 (15・3785)、「わらはども草はな刈りそ」 (16・3842)、の如く集中にいくらも例のあるものとなり、初句で一旦切れた形になるから、二、三句の序は異例ながら、挿入的なものではなく、一、二、三句の序詞をもつたものに準じた形となる。その上にこの歌は「大名兒」を第三者としての独詠歌ではなく、「大名兒」を相手として贈られた作であるから、「大名兒を吾忘れめや」といふよりも「大名兒よ-」といふ直接な表現の適切な事はいふまでもない。恋ひする人にとつて思はず口に出るその人の名がまづ呼びかけられたのである。初句は表記のままに「オホナコ」と四音に訓むべきであらう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「大名兒」(オホナコ) 初句は、原文「大名兒」で旧訓「オホナコヲ」であったが、「オホナコ」と読む注釈書も少なくない (佐佐木評釈・窪田評釈・全註釈・注釈など)。助詞「ヲ」を略した古体の表記に通ずるものと見て、「オホナコヲ」と訓む説 (古典大系・私注・古典全集・古典集成) も有力であるが、「ヲ」の読み添えは本巻では人麻呂作歌のみに見られるので、ここは「オホナコ」と四音に訓む。また、「オホナコヲ」は呼びかけを示すか、それとも目的格であるかも説が分かれている。類歌「夏野行く牡鹿の角の束の間も妹が心を忘れて思へや」 (4・502)、「紅の浅葉の野らに刈る草の束の間も吾を忘らすな」 (11・2763) などの例もあるが、「オホナコ」であれば呼び掛けだろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 初句、原文は「大名児 」。助詞「を」補読して「大名児を」と訓み、結句「われ忘れめや」の客語と解する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 大名兒 [オホナコヲ] は、第四ノ句の次に置て心得べし、(略解に、岡部氏の説によりて、大名見は、其ノ女を崇めてのたまへるなり、とあれど、然る例なし、みだりごとなり、女郎ノ字とあるは、動かぬことなり、さてまた、名姉 [ナネ] 名兄 [ナセ]、又大名持 [オホナモチ] など名 [ナ] をもてほめごととせしは、古ヘの常なりと云るも、おしあてなり、那姉 [ナネ] 那兄 [ナセ] などいふ類の那 [ナ] は、名の義にはあらず、大名持 [オホナモチ] の名も同し、くはしくは別に考あり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | 此發句、古点は大名兒ヤ、仙覺此を嫌て今の点に改らる、古點も押照なにはを押照哉なにはとも云やうの詞にて、〔や〕に心なければ惡からず、又呼懸る意にてもさも侍るべし、又唯四もじによみても、大名兒よと云意にて苦からじ、六帖忘ずと云題に、〔大なかの〕とあるぞ心えがたき、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「彼方」訓 | 注釈 | 【訓釈】 「彼方」は「こもりくの 初瀬の川の 乎知可多尓(ヲチカタニ) 妹らは立たし」 (13・3299) の仮名書例により「ヲチカタ」と訓む。「越方人迩 (ヲチカタヒトニ)」 (10・2014) とも書かれてゐる。「彼此 (ヲチコチ)」の「をち」で、あちらの方の野辺に刈るかやの、の意で、かやの一つまみの意の束を「束の間」とつづけた序である。「草」を「カヤ」と訓む事にいては前 (1・10) に述べた。必ずしも屋根を葺くかやばかりをさすのでなく、草の代表としての薄の類をさしたものと見てよい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「刈草乃」諸本訓 | 校本 | 「刈草乃 (カルカヤノ)」 元暦校本・金澤本・類聚古集「かるくさの」。 古葉略類聚鈔・神田本「カルクサノ」。 大矢本・京都大学本「カヤ」青。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 111 | 題詞原文「贈与」考 | 注釈 | 「贈与」の語はここの他には巻十六 (3806) の左注に「贈与其夫也」とあるのみであるが、この語に対しても前の歌の「贈賜」の語が認められ、「贈」を衍字と見るよりは「賜」「贈賜」「贈与」の書きわけがせられてゐると考へるべきであらう。目録には金澤本等には前の歌と同様「賜」とあり、元暦本等には「贈」とのみあるは、いづれも例の少ないままに後に勝手に削つたものと思はれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「戀」考 | 注釈 | 【訓釈】「戀ふ (こふ)」 「戀ふ」といふ語は今日の「愛する」といふ語と同じではなく、何かに「心惹かれる」「ひきよせられる」気持ちである。従つて「吾妹兒尓 (ワギモコニ) 戀乍不有者 (コヒツツアラズハ)」 (120) 、「君尓戀 (キミニコヒ)」 (3・456) の如く、「に戀ふ」といふのが通例である。それが後には「を戀ふ」とも用ゐるやうになつたが、集中にも「風」「月」などの無生物には「を戀ふ」の例がある (4・489参照)。今は過ぎ去つた時に対して心が惹かれてゐるので、「去にし方 (いにしへ)」といふ「古」の語の本義に対して、「に戀ふ」と正しい用ゐ方がされてゐるわけである。「伊敝尓古非奴 (イヘニコヒヌ) 日は無し」 (15・3670) といふ例があるが、これは「家人」といふに近いものであり、結局人間以外に「に戀ふ」と用ゐられた例は、これと次の作の二つの「古」があるだけである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 動詞「恋ふ」は、その対象を格助詞「に」で示す。「我妹子に(尓)恋ひつつあらずは」 (120)、「韓亭 (からとまり) 能許 (のと) の浦波立たぬ日はあれども家に(尓)恋ひぬ日はなし」 (3670)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「弓絃葉のみ井」考 | 童蒙抄 | 【和歌童蒙抄巻五】 「イニシヘヲコフルトリカモヨロツハノミ井ノウヘヨリナキワタリユク 万葉ニニアリヨロツハトハ弓弦葉トカケリ」(校本萬葉集頭注) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「弓絃葉のみ井の上より」 「ゆづるは」は正月の神事などにその葉を使用する「交譲木 (ゆづりは)」の事で、「弓絃葉のみ井」は、そのゆづりはの木の傍にあつた井戸を云つたものと思はれる。「み井」は藤原のみ井 (1・53) と同じく吉野の宮の用水となつた名水をたたへて「み」の美稱を加へたもの。今その跡はわからないが、離宮阯と思はれる宮瀧の北の山麓に近い神社の境内に今も古い良い井戸がある。そのあたりであらうか。- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「弓絃葉の御井の上より」 「ユヅルハ」は、とうだいぐさ科の常緑高木で、今ユズリハと言う。その葉の新旧入れ変わりが著しく目立つための名 (『牧野新日本植物図鑑』)。ユヅルハのミヰはおそらくその木の傍にあった井の名であろう。吉野宮の近くかと思われるが、現在のどこに当たるか不明。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「鳴濟遊久」諸本・諸注 | 校本 | 「鳴渡遊久 (ナキワタリユク)」 〔本文〕鳴、西本願寺ナシ。但、右ニ書ケリ。本文中「従渡」ノ間ニ「〇」符アリ。 渡、元暦校本・金澤本「濟」。元暦校本、右ニ朱「渡戓夲」アリ。 〔諸説〕鳴渡遊久、萬葉集美夫君志「渡」ヲ「濟」ニ作ルモ可トス。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「鳴き渡りゆく」 「渡り」の原文、金澤本・元暦校本二本に「濟」とあり、他の諸本は「渡」となつてゐる。元暦校本には右に赭で「渡或本」とある。「濟」の文字は前 (90 左注) に「難波濟」がある。いづれでも訓は同じであるが、、「濟」を通用の「渡」に改めたものかと思はれる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「鳴きわたりゆく」 「ワタル」は、一方から他方へ移動することをあらわす動詞。離宮近くの御井の上を鳴きながら飛んでいったのであろう。原文「鳴濟遊久」の「鳴」は西本願寺本に無く、右側に補われている。元暦校本・金澤本・紀州本などによる。次の「濟」は、西本願寺本・紀州本などに「渡」とあるが、元暦校本・金澤本による。「濟」は、万象名義に「子悌子礼反渡・益・成」と注され、新撰字鏡にも「子細反去渡也・益也・成也」とあって、渡と同義に用いられたことが知られる。古事記には、百濟の国名表記にのみ用いられているが、日本書紀には、「瀬田濟」 (神功紀) 「難波濟」 (仁徳紀) などにも見え、「濟此ニ云フ和多利ト」 (景行紀) の訓注もあって、「ワタリ」と訓んだことがわかる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 112 | 題詞原文「従倭京進入」考 | 校本 | 題詞「額田王奉和歌一首」 【頭注】 元暦校本・金澤本・西本願寺本・大矢本・温故堂本・細井本・京都大学本、題詞ノ下ニ小字「従倭京進入」アリ。 細井本、「京」ノ右ニ「重イニ」アリコレニ朱ノ合点ヲカケタリ。京都大学本、「倭」ニ赭ノ合点ヲカケタリ。 神田本、題詞ノ下ニ小字「従倭京近入」アリ。 類聚古集、前行ニ「額田王奉和」アリ。 〔訓〕 京都大学本赭訓アリ、次ノ如シ。「額田ノ王奉ル和シ。」 〔諸説〕 「一首」 萬葉集美夫君志、「一首」ノ下ニ「従倭京進入」アルヲ可トス。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 「従倭京進入」の注は刊本にはないが古写本にはすべてあり、「110歌」の題の注の場合と同様、刊本には脱したものと思はれる。「倭京」は飛鳥京か藤原京か不明であるが、後者とすれば、持統八年以後となる。前者ではなからうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 原文「額田王奉和歌一首」。題詞下に、元暦校本・金澤本・西本願寺本・大矢本・温故堂本・細井本・京都大学本に小字「従倭京進入」とある。この小字注は、額田王が吉野にいたのでなく、吉野行幸時に倭京に留まっていて作歌したことを示している。前の弓削皇子の歌も、王の歌も文字に書かれて贈られたものであり、それが額田王を感動させたことは、あとの歌から推察されよう。なお、「倭の京」は浄見原宮か藤原宮か判断は難しいけれども、「天武紀」に「倭京」とあるのは明日香京のことだし、藤原遷都は持統八年十二月なので、それ以前の作とすれば明日香京を指すと考えられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「従倭京進入 」 (わきょうよりたてまつりはいる) 「孝徳紀」「天智紀」「天武紀」などに見え、難波や近江など大和以外の地から飛鳥京一帯をさしていう。ここは吉野 (後に監[げん]が置かれ、一般に大和の外と考えられた) から飛鳥浄御原宮をさしていったのであろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「霍公鳥」表記例 | 注釈 | 【訓釈】「霍公鳥」 (ホトトギス) 「霍公鳥」は巻十七 (3914) に「思霍公鳥歌」と題して「保登等藝須(ホトトギス) 今し来鳴かば」とあり、又同じ巻 (3983) に「立夏四月既經累日而由(ナホ)未聞霍公鳥(ホトトギス)喧云々」と題して「保登等藝須(ホトトギス) 月たつまでに 何か来鳴かぬ」とあつて、ほととぎすの意に用ゐた事明瞭であるが、他の書には見あたらない。我が国では新撰字鏡 (八) に「鴞」と「郭公鳥」とに「保止々支須(ホトトキス)とし、倭名抄 (七) には「鸕□(糸偏と旁鳥の間に婁)鳥」[私注:漢字変換出来ず、倭名類聚抄で確認する]に「保度々岐須 (ホトトキス)」 [私注:右写真では「保度々木須」]として、唐韵を引いて「今之郭公也」とあるのみならず、既に新撰萬葉集に「郭公鳥」とあるから平安朝初期から郭公鳥又は郭公が用ゐられてゐたものと思はれる。郭公の文字は支那で用ゐられてをり-ほととぎすではないが-その「郭」と「霍」と同音の字であるから通用したものと思はれる。しかも集中では仮名書以外はすべて (百二十三例) 「霍公鳥」で統一せられてゐるところを見ると、一日本人のはじめたものと見るよりも、今日漢籍に「霍公」の文字を見出し得ないが、当時萬葉人の読んだ彼の地の通俗書に「郭公」をまた「霍公」と書いたものがあつたと見るべきではなからうか。しかも支那では郭公は「クワクコウ」であり、鳴き声によつた文字と思はれるが、日本では「ほととぎす」に宛てた為に、「霍」の本字「靃」に「飛声也雨而雙飛者其声靃然」と注されてゐるやうな意味を感じて-サクに咲、フルに零を宛てたやうに-「郭」よりも「霍」の方にほととぎすの表記文字としてのふさはしさを感じて、「霍公鳥」の方を採用したものと考へるべきではなからうか。萬葉動物考に、十王経を引いて閻魔法王の許にある無常鳥が化して「鸕□(糸偏と旁鳥の間に婁)鳥」となり、「別都頓宜壽 (ヘツトトンギス) と鳴く」とあるに注意し、「時鳥の鳴声を聞くと、聞き方によつてはホットントギスと聞かれぬでもない」として鳴声から由来した名称とされてゐるやうに、和名は鳴声によるものと見るべきである。 暁に名告り鳴くなる霍公鳥いやめづらしく思ほゆるかも (18・4084) 大伴家持 他にも「名告り鳴くなべ」 (18・4091) とある。さてこの第三句は、上の「鳥は」を受けて「霍公鳥であらう」と述語として結ぶ形になつてゐるやうであるが、下の句に対してはまた主語のやうな形になつてをり、ここで切れるのではなく、「霍公鳥にして」といふやうな意に解すべきである。 倭名類聚鈔 巻第十八羽族類第二百三十 孳尾附出
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「霍公鳥」 (ホトトギス) 「ホトトギス」を「霍公鳥」と記す例は、上代文献中万葉集にしか見えない。同音の「郭公」は中国では「カッコウドリ」を表す。日本でも新撰萬葉集には「夏之夜之臥歟砥為礼者郭公鳥 (ナツノヨノフスカトスレバホトトギス)」 (上巻) のように「ホトトギス」をあらわす例が見られるから、同音の「霍公鳥」も中国で「郭公」に用ゐられ、それによって日本でも「ホトトギス」を意味するようになったのではないかと言う (注釈)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「盖」訓釈 | 校本 | 「古爾 戀良武鳥者 霍公鳥 盖哉鳴之 吾戀流其騰」 (イニシヘニ コフラムトリハ ホトトキス ケタシヤナキシ ワカコフルコト) 〔本文〕 「盖」 元暦校本・神田本、「葢」。元暦校本朱ニテ消セリ。右ニ朱「葢」アリ。 〔訓〕 「ケタシヤナキシ」 元暦校本・金澤本、「ましてやなきし」。 元暦校本訓ノ右ニ朱「ケタシヤナキシ」アリ。ソノ下ノ「シ」ノ右ヨリ朱「礼□」アリ。下ノ字ノ下半ハ裁断セラレテ明ナラズ。 類聚古集、「けたしやこやなき」。墨ニテ「こや」ヲ消シテ「き」ノ右下ニ「シ」ヲ書ケリ。 神田本、「マシテヤナキシ」。「盖」ノ左ニ「ケタシイ」アリ。 京都大学本、「鳴」ノ左ニ赭「ナカ」アリ。 〔諸説〕 「ケタシヤ」 万葉童蒙抄、「アカスヤ」トモ訓ズ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「盖 (けだし)」 「けだし」は新撰字鏡 (一) に「儻」に注して「設也若也辟(口が言偏)也倜也 太止比(タトヒ)又 介太志(ケダシ)」とあり、もしや、或いは、などの意。集中「盖」の字 (刊本には「蓋」の文字も書かれてゐるが、古写本はいづれも「盖」とある。「盖」は正字通に俗蓋字とある。説文 (一) には「葢」とある) が多く用ゐられてゐるが、「若」もケダシと訓まれたと思はれる例 (11・2653、12・2929) がある。仮名書は「和我世故之 (ワガセコガ) 気太之麻可良婆 (ケダシマカラバ)」 (15・3725)、「気太志久毛 (ケダシクモ) 安布許等安里也等 (アフコトアリヤト)」 (17・4011) とあつて、「けだしく」とも用ゐられ、この形は後世用ゐられなくなつた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「けだしや鳴きし」 「蓋」は万象名義に「掩・上・裂・辞」とあるが、訓点において「ケダシ」と訓まれる例が多い。「ケダシ」は、もしかしたら、ひょっとしてなど、疑問の気持ちを伴いながらの推量を表わす語。その語源を「気甚 (けいた) し」とする説があるが、不詳(吉田金彦「副詞『けだし』の語源について」『訓点語と訓点資料』六十輯)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「吾念流碁騰」訓釈 | 校本 | 「古爾 戀良武鳥者 霍公鳥 盖哉鳴之 吾戀流其騰」 (イニシヘニ コフラムトリハ ホトトキス ケタシヤナキシ ワカコフルコト) 〔本文〕 「戀」 元暦校本・類聚古集・神田本、「念」。 「其」 元暦校本、「碁」朱ニテ消セリ。右ニ朱「基イ其」ヲカケリ。金澤本、「基」。類聚古集、「碁」。神田本、「碁」 (私注:金澤本・類聚古集・神田本、漢字判別困難) 〔諸説〕 「吾戀流其騰」 万葉集攷証、「其」ヲ「基」に作ルヲモ可トス。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「吾念流碁騰 (ワガモヘルゴト)」 第五句「思ふ」の原文、西本願寺本以下には「戀」とあつて、従来「ワカコフルコト」と訓まれてゐた。然るに金澤本、元暦校本、類聚古集、紀州本、の諸本いづれも「念」とある。これらの古本がいづれも同様であるといふ事は、これによるべきものと思はれる。ただこれらの諸本も訓は「コフル」とある為にやはりそれが正しいのではないかといふ気がせられるかと思ふが、これは「わが思へるごと」といふ言葉が、これらの古本の写された王朝の歌人の耳にはいささか抵抗を感じさせ、原本の文字をおほよそに訓んで、「ワガコフルゴト」とし、その訓が流通するに及んでは、遂に原文をも改めるに至つたと見るべきである。「石激 (イハハシル)」 (8・1418) を「イハソソク」と訓んで、後に「石灑」と改め、「七日不来哉 (ナヌカコジトヤ)」 (10・1917) を「ナナヨコジトヤ」と訓んで、「七夜不来哉」と改めるに至つた (『古径』三参照) のと同じ例である。「念」は「コフ」と訓んだ例他になく、今は「念流」で「オモヘル」と訓むべきであるが、「モヘル」とも訓まれたかと思ふ。「思ふ」は「戀ふ」とは同じでないが、「念」の文字が用ゐられてゐるやうに (『古径』二、一四六、七頁参照)、深く思ひ入ることで、この場合の如きは「戀ふ」といふに近く、自分が一途に思ひつづけてをるやうに、といふので、第四句へかかる倒置句の形である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「我が思へるごと」 原文、西本願寺本に「吾恋流其騰」とあるが、金澤本・元暦校本・紀州本・類聚古集に、「吾念流碁騰」とあるのによる。自分 (額田王) が古を懐かしく思っているように、ホトトギスも古を恋うて鳴いているのだろう、の意。注釈に「これらの古本 (稲岡注、金・元・紀・類) がいづれも同様であるといふことは、これによるべきものと思はれる。ただこれらの諸本も訓は「こふる」とある為にやはりそれが正しいのではないか、といふ気がせられるかと思ふが、これは『わが思へるごと』といふ言葉が、これらの古本の写された王朝の歌人の耳にはいささか抵抗を感じさせ、原本の文字をおほよそに訓んで、「ワガコフルゴト」とし、その訓が流通するに及んでは、遂に原文をも改めるに至ったと見るべきである」と記すのは、誤写の原因を推測して詳しい。あるいは、上句に「恋ふらむ鳥は」と歌われ、前歌にも「恋ふる鳥かも」と見えたため、それに引かれて「吾が恋ふるごと」という語句を生じたと単純に考えられもしよう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「我が思へるごと 」 (あがおもへるごと) わたしがあなたの父君天武天皇をお慕いしているように。原文は底本などに「吾恋流・・・」とあるが、元暦校本をはじめ非仙覚本系全古写本に「吾念流・・・」とあるのによる。「恋」とあるのは、字余りを回避した中古の仮名訓「わがこふるごと」に合わせた仙覚の改変本文で、信じ難い |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 113 | 題詞原文 「蘿(こけ)・柯(え)」 |
代匠記 | [從吉野折取蘿生松柯遺時額田王奉入歌一首] 和名云、辨要決云、松蘿、一名、女蘿、【和名、萬豆乃古介、一云、佐流乎加世、】六帖云、逢ことをいつか其日と松の木の、苔の亂て物をしぞ思へ、元輔集云、松の苔千年を兼て生ひ茂れ、鶴のかひこの巣とも見るべく、遺は贈と同訓歟、下に遣近江の遣を誤て、遺に作たれば、今も遣を誤て遺に作れるにや、此端作の詞、上を承る故に、弓削(ノ)皇子と云はざれども、奉入と云に、意顯はれたり、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 從吉野云々は、弓削皇子の、吉野にて松(カ枝を折て、京都にとゞまれる、額田(ノ)王のもとへ、御詞など副て遣はされたるたなり、(女君の公へ參らする文を、苔づいたる松の枝につけし事、かげろふの日記に見えたり、此類なり、)さて上の題詞をうけつぎたる故、弓削(ノ)皇子とはいはざれども其(レ)と知(ラ)れたり〔頭注【源氏物語若紫に、鞍馬寺の僧都より、五葉の枝に物つけて、源氏君に贈れること見え、松風に、鳥を萩の枝につけやるを、源氏君に奉り、行幸に、雉を木の枝に附て、おくれることも見え、伊勢物語にも、梅のつくり枝に雉をつけて、奉りしこと見えたり、凡て木(ノ)枝に物つけて、人におくる起本にや、〕 折(ノ)字、類聚抄にはなし、 蘿は、古計 [コケ] なり、下に子松之未爾蘿生萬代爾 [コマツガウレニコケムスマデニ]、三(ノ)卷に、梓椙之本爾蘿生左右二 [ホコスギノモトニコケムスマデニ] などあり、委くは品物解に出、(六帖に、逢ことをいつか其(ノ)日と松の木の苔の亂て物をこそ思へ、元輔集に、松の苔千年を兼て生茂れ鶴のかひこの巣とも見るべく、) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 「蘿」は本草和名 (上) に「松蘿一名女蘿」とあつて和名「末都乃古介 (マツノコケ)」とある。倭名抄には「唐韵云蘿 [魯何反、日本紀私記云、蘿比加介] 女蘿也、雜要決云、松蘿一名女蘿、 [萬豆乃古介、一云佐流乎加世]」とある。「ひかげ」は別 (19・4278参照) で、ここに「蘿」とあるは右の両書に「松蘿」とあり「マツノコケ」とあるもので、一云「佐流乎加世 (サルヲカセ)」とあるやうに、今もさるをがせと呼び、深山の松などの古木に付着して絲屑のやうな形で垂れ下がつてゐるもの。「柯」は説文に「斧柄也」とあるが、玉篇にまた枝也ともあつて、枝の意。吉野から「さるをがせ」のからみついた松の枝を贈られたので、その主の名が略されてゐるが、前二首とのつづきとして、これも同じく弓削皇子と思はれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 原文「従吉野折取蘿生松柯遣時額田王奉入歌一首」 「蘿・柯」 「蘿」は和名抄に「松蘿」を「万豆乃古介」と注するように「コケ」、「柯」は玉篇に「枝」、万象名義・新撰字鏡に「割多反法也枝也茎也」とあるように、枝や茎をあらわす。ここは松の枝。弓削皇子が吉野から苔の生えた古い松の枝を折り取ってそれに文をつけて額田王に送った時、額田王が歌を返したのである。当時、消息文を運ぶ使は、梓の木の枝を持ち、それに文を挿んで往来したと想像される (折口辞典)。この場合は、梓のかわりに古い松の枝を使ったのであろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 「蘿」は「サルオガセ」。松の梢から糸屑のように垂れ下がった苔である。「蔦と女蘿と、松柏に施す」 (詩経・小雅・頍弁)。その毛伝に「女蘿 は兎糸、松蘿なり」と言う。また「千年の松、下に茯苓有り、上に兎糸有り」 (淮南子・説山訓)、「葉は千年の蓋を繞る」 (陳・劉刪「賦松上軽蘿詩」・芸文類聚・女蘿) と、「蘿」 (女蘿・兎糸) は松の千年の寿命を顕示するものと考えられていた。「小松がうれに蘿生すまでに」 (228) の「蘿」も同じ。額田王を慶賀する詞がその松の枝に結び付けられていたので、「君がみ言を持ちて通はく」と詠んだのであろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本文「三吉野乃玉松」異同 | 校本 | 「三吉野乃 玉松之枝者 波思吉香聞 君之御言乎 持而加欲波久」 (ミヨシノノ タママツカエハ ハシキカモ キミカミコトヲ モチテカヨハク) 〔頭注〕神田本、コノ歌行間ニ書ケリ。別筆カ。コレニテ校ス。 類聚古集、前行ニ「従吉野折取蘿生松柯遣時額田王奉入哥」 和歌童蒙抄第七、「ミヨシノノ タママツノエハ ハシキカモ キミカミコトヲ モチテカヨハム」 〔本文〕 第四句「持」、温故堂本右ニ「待(マイテ)イ」アリ。 〔訓〕 「タママツカエハ」 元暦校本・金澤本・類聚古集、「たままつのえは」。神田本、「之」ノ左ニ「ノ」アリ。温故堂本、「タママツカヱハ」。 「ミコト」 類聚古集、「(画像参照)」墨ニテ「(画像参照)」ヲ消セリ。ソノ右ニ墨「み」アリ。 「カヨハク」 類聚古集、「かよはく」。 〔諸説〕 「玉松之枝者」 萬葉集玉小琴、「玉」ハ「山」ノ誤。万葉集攷証、「玉」ニテ可」トス。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「玉松之枝者」 | 注釈 | 【訓釈】「玉松が枝は」 「玉の小琴」に「玉松と云こと、此外に例なし、玉の字は山の誤也」とある。玉の草体が山にまぎれる事は十分認められ、誤字説としてはうなづかれるが、玉江、玉衣など集中には一例だけのもの珍しくなく、上代には玉の美称が多いのであるから、弓削皇子よりの御消息と共に贈られた松に玉といふ美称を加へる事は当然であつて誤字と見るべきでない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「玉松」(タママツ) 「玉」は接頭語。「玉藻」 (131、194など)、「玉床」 (216) などの例を見る。古事記にも「玉垣・玉盞(たまうき)」などがある。タマはもと霊力・霊魂を意味する語であったが、それが接頭語として用いられ、美称化した。ここでは「玉梓」 (207) と同じく、相手の言葉 (歌) を運んできたものとして、とくに親しみをこめて呼んだのであろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「はしきかも」考 | 注釈 | 【訓釈】「はしきかも」 「はしき」は、「波之伎和我勢故 (ハシキワガセコ)」 (19・4189)、「波之伎都麻良波 (ハシキツマラハ)」 (20・4331) の仮名書例に対して、「愛伎妻等者 (ハシキツマラハ)」 (220) があり、又「波之吉也思 (ハシキヤシ)」 (7・1358) に対して「愛也思 (ハシキヤシ)」 (6・986) があり、「愛」の漢字の意に相当する形容詞である事がわかる。愛すべきかなの意。「かも」は詠歎。ここで句が切れる。しかし、「波之吉可聞 皇子之命乃 (ハシキカモ ミコノミコトノ)」 (3・479) の如き例があるので、全註釈には「第四句の修飾句とも解せられる」と注意されてゐる。当時には「かしこきや」の「や」の如く、下の句の修飾としてつづく形容詞の連体形について、間投助詞的に用ゐられた「かも」があつたやうに見える (199参照) ので、今の「かも」もさういふ用法だと見られない事もないが、この「はしきかも」を第四句の修飾とする時には、第二句の「玉松が枝は」が結句の「かよはく」につづく事になる。然るに佐伯君の「萬葉集の助詞二種」 (『萬葉語研究』所収) で述べられてゐるやうに所謂「く」の延言につづく場合は「が」「の」の助詞を用ゐるといふ例に反する事になり、「はしきかも」にかかるとすれば、同じく同君の述べられてゐるやうに「は」の助詞をうけるといふ法則に適ふ事になる。即ちこの第三句は第二句の述語と見るべきであり、ここで句切となる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「はしきかも」 「ハシキ」は「シク活用」の形容詞「ハシ」の連体形。記歌謡に「吾がはし妻」 (59歌) と見え。万葉集にも、「波之伎都麻」 (20・4331) とあるように、いとしい、かわいいの意。「愛伎妻等者 (ハシキツマラハ)」 (220)、「愛妻之兒 (ハシキツマノコ)」 (4・663) のように「愛」の字を宛てているのが、表意的表記の例。この歌、三句切。澤瀉注釈に、萬葉集に確実な三句切の例は第一期になく、ここに始めて見えることを記している。これは注意されてよいだろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 114 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「穂向乃所縁」 | 注釈 | 【訓釈】「秋田之 穂向乃所縁 異所縁 (アキノタノ ホムキノヨレル カタヨリニ)」 第二、三句旧訓に「ホムケノヨスルカタヨリニ」とあつたのを代匠記に「ホムキノヨレル」かと云つてから、その説が多く行はれてゐたが、定本萬葉に「ホムキノヨリノコトヨリニ」と改め、その別記に「所は被役の意味を有する字であるが、それが訓読に現れない場合は多く」と云つてその例をあげ、「所縁」を「ヨリ」と訓み、全註釈には「異の字をカタと読むべくも無い。ここは別の方に寄る意であるから、文字通りコトヨリニと読む。」と説明され、更に大野晋氏は第三句を「コトヨリノ」と訓み、そのコトはカタと同義とされた。その理由として大野氏 (「萬葉集訓詁断片」萬葉、第三号昭和二十七年四月) は「奈良時代の音韻組織を見るに、本来の陰性母音はオ列乙類の母音〔ӧ〕であつたと考へられるが、これらの母音には、陽性母音のうちア列母音〔a〕と母音交替して、同義語を構成する造語法があつた。」として、 kikasu 聞 kikösu、 tawawa 撓 tӧwӧwӧ、 fadara 斑 fӧdӧrӧ、 ana 間投 ӧnӧ などの例をあげ、かかる語例は約四十を数へるとして、kӧtӧ~kata といふ対応が考へられ、従つて「『異』は『異』の意味を表すものでなく、音のみを借りたものであつて、『片 (カタ)』」と同義を示すのではあるまいか。『片 (カタ)』とは『兩 (マ)』に対して『一』を意味する。『片寄り』は一方に寄ることである。『異所縁 (コトヨリノ)』も同じく一方に寄ることであると考へられる」と述べ、上三句を序とされてゐる。この三句の訓詁を決する参考となるべきものは諸注にも引用されてゐるやうに、 秋田之(アキノタノ) 穂向之(ホムキノ)所依 片縁 吾者物念(ワレハモノオモフ) 都礼無物乎(ツレナキモノヲ) [10・2247] の上三句である。この類歌の第二句は同じものと思はれる。武田、大野両氏ともにこれを無造作に「ホムキノヨリノ」と訓まれてゐるが、これはさう訓めるであらうか。右に述べたやうに別記には「所」の字を訓まぬ例ニ三あげられてゐるが、その例にはなほ問題がある。「所」の字は受身、敬意などをあらはす場合に用ゐられるのが通例であるが、時に特殊な用例もある事前 (1・10) にも述べた如く、「所縁」「所依」を「ヨレル」と連体格に訓むのであれば、他にも例があるものとして認める事が出来る。しかし単にヨリと訓むのであれば何の為に「所」の字をわざわざ加へる必要があらう。「ヨリノ」と訓むつもりならば、「所」の字などをまぎらはしく加へる手間で、「之」「乃」などの文字を下へ加へるべきであらう。「秋田之 穂向乃」と「ノ」の表記がされてゐるに対して、ここに「所縁」とあるのを「ヨリノ」と訓むのは、その二つの「ノ」の用字に対しても不審であらう。特に巻十の場合「秋田之 穂向之所依 片縁」とある事は、「ヨレル」と「ヨリ」と区別したもので、これを「アキノタノ ホムキノヨレル カタヨリニ」と訓むべき事は、殆ど常識として認むべき事だと思ふ。さてさうだとすれば、今の第二句もまた「ホムキノヨレル」と訓む事は殆ど決定的と云つてよい。問題は第三句にある。旧訓カタヨリニであり、攷證に「義訓なり」と簡単にすませてゐるが、講義に「その據は未だ明らかならず」といふ疑問が出たり、武田博士」などの如くコトヨリといふ説が出たりするのは、諸家多く「異」と「所縁」とをわけて見る為に生じたものであり、さうすれば第一「縁」を「ヨリ」と訓むのは、右に私が述べたところからも当然不都合だといふ事になる。その不都合や諸家の疑問は、この句を「異所」と「縁」とにわけて見る事によりすべて解決するのでないかと私は考へる。上に「所縁」とある為にこの句も「所縁」とつづけて見られるのであるが、「所」の字は「何所」「彼所」「他所」などと下につづけても用ゐられること現に集中にも例のある事であり、殊に「他所」 (20・4459左注) といふ語に対して「異所」といふ用字も認められると考へる。「異」といふ一字として考へると、武田、大野両氏の如く、カタの用例が無い、コトだといふ事にもなるが、「異所」といふ二字として考へれば必ずしもコトに執着する必要はなく、もつと大まかに、攷證の所謂義訓が考へられよう。殊に「異」の文字は集中で「別 (べつ)」とか「違 (ちが)ふ」とかいふ意味ばかりでなく、「日異 (ヒニケニ)」とも「日殊 (ヒニケニ)」とも書かれてゐるやうに、「殊」とか「特異」とかいふ意味にも用ゐられてゐるので、ある特殊な一方へよる事を「異所縁」と書いたと考へられるのでなからうか。巻十には「片縁」と書かれてゐるが、これも「片方縁」とも書かれてもよいわけで、その「片方縁」の意味を「異所縁」と書いたと見れば、これを「カタヨリ」と義訓する事は十分認められる事ではなからうか。即ちこれを当時カタヨリとして伝誦してゐたればこそ、巻十の追随歌も生まれたのであつて、この二首の第三句はやはりぴつたり合ふべきものと見るのがすなほな見解であらう。しかし、「異所縁」といふ表記法はまぎらはしい為に、巻十の記録者は「片縁」といふ簡単明瞭な書き方をしたのであり、我々はその筆録者の親切にたすけられて「異所縁」をカタヨリと訓むべきものだと考へる。さてカタヨリと訓むべきだとすれば稲穂がかたよつてゐるやうに、自分の心も片よりに君の方へ--とつづくのだから第二句までが序であつて、第三句は歌の本意となり、従つて「カタヨリニ」と訓むべきである。武田博士が「ホムキノヨリノ」の「の」が「の如く」ととつて、「そのやうに違ふ方へ」とつづけられてゐるのは無理だと大野氏は批難し、大野氏は「コトヨリノ」と訓んで、今のも巻十のも第三句までを序としてをられるが、「片寄り」の語は右に述べたやうに歌の本意に入るべきものであり、殊に巻十の場合の如き「吾は物思ふつれなきものを」だけでは意を盡さないのであり、「物思ふ」に「片寄りに」といふ修飾の句があつてこそ「つれなきものを」の句とも対応して歌意を全くするものである。「よれる」といふやうな連体格でつづく序は少ないが、 橘の本に道踏む-やちまたに物をぞ思ふ (6・1027) 浅茅原小野にしめ結ふ-空事もいかなりと言ひて (11・2466) 妹があたり我が袖振らむ-木の間より出で来る月に (7・1085) などの例があつて、今の場合も「稲穂の片寄つてゐるやうに」の意の序詞と見る事に少しも不都合はない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「秋の田の穂向き」 秋に稲穂が実って穂先の一方に向くことを言う。巻十七の家持作歌に「秋の田の穂向き見がてり我が背子がふさ手折りける女郎花かも」 (3943) とあるのは、稲の実り工合を見る事を歌っている。窪田評釈に「穂は熟して重くなると、自然に傾くし、折からの風で、同じ方角に向かうものである」と言う。第二句まで、「片寄りに」にかかる序詞。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「異所縁」諸訓 | 古義 | 異所縁は、舊本にカタヨリニと訓たる宜し、十ノ卷ノ歌見べし、さて片縁 [カタヨリ] は、純一 [ヒタムキ] に係をいふ、拾遺集に、まねくとて立もとまらぬ秋ゆゑにあはれかたよる花すゝき哉、後拾遺集に、夕日さすすそ野のすゝき片よりにまねくや秋を送るなるらむ、金葉集に、風吹ば柳の糸の片よりに靡くにつけて過る春哉、朝まだき吹來る風にまかすれば、片よりしける青柳の糸、詞花集に、風吹ば藻鹽の烟片よりに靡くを人の心ともがな、夫木集に、春風にしだり柳のかたよりに君になびけば國ぞ榮えむ、現存六帖に、鶉ふす小野の茅生は霜枯てをれば片より風さわぐなり、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「片寄りに」(かたよりに) 旧訓「カタヨリニ」。「コトヨリニ」と訓む説もある (定本・全註釈・古典大系など)。「異」は、集内に仮名として用いられるほか、「日に異に」の「ケ」、「異(ケ)しき心」のケシキなどを表す場合に多く使われている。「紫草を草と別く別く伏す鹿の 野者殊異為而(ノハコトニシテ) 心は同じ」 (12・3099) の「殊異」は「コトニ」と詠むのであろうが、「殊」と「異」とを重ね用いた特殊な表記。「殊」を「特別に」の意味で用いた例は「橡の解き洗ひ衣のあやしくも殊(こと)に着欲しきこの夕かも」 (7・1314) などに見られるから、「殊異」は、殊を借訓字、異を表意字として組み合わせた書き方なのであろう。こうした集内例からすると、万葉時代に「異」を「コト」と訓む正訓が定着していたかどうか、疑わしい。古事記の本文を見ても、異心・異奇など、「ケシキ」とか「アヤシキ」と訓むと思われる例がほとんどで、安康記の「各異作仮宮而宿」を「オノモオノモコトニカリミヤヲツクリテヤドリマス」と訓めば、異=コト (ニ) の数少ない例となる。右のようなことを記したのは、武田全註釈に、「異の字をカタと読むべくもない。ここは別の方に寄る意であるから、文字通りコトヨリニと読む」とし、古典大系本に「原文、異はコトと訓む。コトは、同じの意」と注されていて、文字からすれば「コトヨリニ」と訓むのが当然のように考えられていることに、多少疑問を覚えるからである。大野晋の「万葉集訓詁断片」 (万葉三号) にコトとカタとは同義語をつくる対応とされ、「『異』は『異』の意味を表すものでなく、音のみを借りたものであって『片(カタ)』と同義を示すのではあるまいか」と記されているのは、「異」を借訓字と見る説で、古典大系本頭注のもととなる考え方を示す。が、万葉集や古事記における「異」の用例は、異がコトの借訓字として利用されうるほど慣用された跡を見せてくれないのである。「異所縁」をコトヨリニと訓む説の弱点は、「所」の扱い方にもある。「コトヨリニ」ならば「異縁尓」と記せばすむのに、「所」があるのは、なぜか。その点を明確に指摘したのは澤瀉注釈であろう。「所」の字は受身、敬意などをあらわす場合に用いるのが通例で、この歌の第三句はカタヨリニ、コトヨリニのいずれに読むにしても、「所縁」をヨリニとするのは不都合である。「所」はむしろ上の「異」と合わせて「異所」と「縁」とに分けて考えるのが良い。「異所」は義訓で「カタ」に宛てたものであって、「異所縁」は「カタヨリニ」と訓むべきだろう、と澤瀉は言う。万葉集に「異」一字で「コトと訓ませる例の他にないことと、異をコトと訓むと「所縁」を「ヨリニ」とは訓み難いことと、併せてコトヨリニという全註釈および古典大系本の訓がこの歌に適しない理由となるであろう。澤瀉注釈に言うとおり「異所縁」で「片寄りに」を表したと見られる。単純に「片縁」と記さなかったのは、古典全集に「高市皇子と別な人という気持ちの反映か」と注するような理由からかも知れない。類歌に、「秋の田の穂向きの寄れる片縁吾は物思ふつれなきものを」 (10・2247) がある。その場合は、つれない相手をひたすら思うので「片縁 (カタヨリニ)」という第三句の表記は「異所縁」とは置き換え難いだろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「異所縁」(カタヨリニ) 原文「異所縁」は高市皇子とは別な方へという気持ちで書いたものかという。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「言痛有」訓 | 注釈 | 【訓釈】「言痛くありとも」(コチタクアリトモ) 「言痛くあり」は「言痛 (こといた) くあり」の約で、痛くは甚しくの意。人の口が繁くうるさくともの意。「許知痛美 (コチタミ)」 (116) ともあり、「事痛」は「コチタ」と訓まれ、旧訓に「コチタカリ」とし、童蒙抄に「コチタクアリ」とした。旧訓も悪くないが、「言痛者 (コチタクハ)」 (7・1343) などの例により、ア行音を含む八音の結句 (92、125、参照) と認める。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「言痛かりとも」(コチタカリトモ) 「コチタシ」は、人の口のうるさいことをあらわす。あとの「116歌」に「許知多美 (コチタミ)」の仮名書きが見える。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 115 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 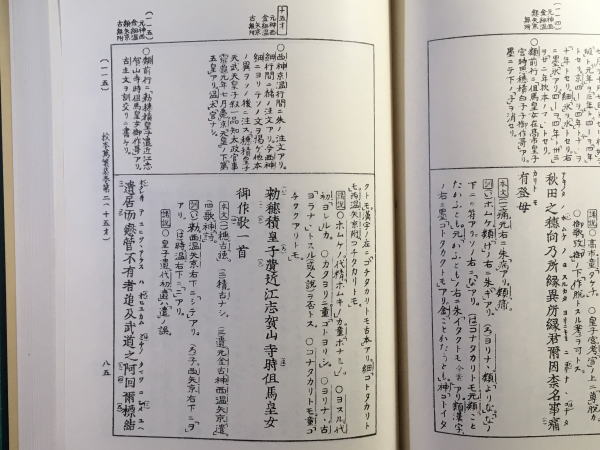 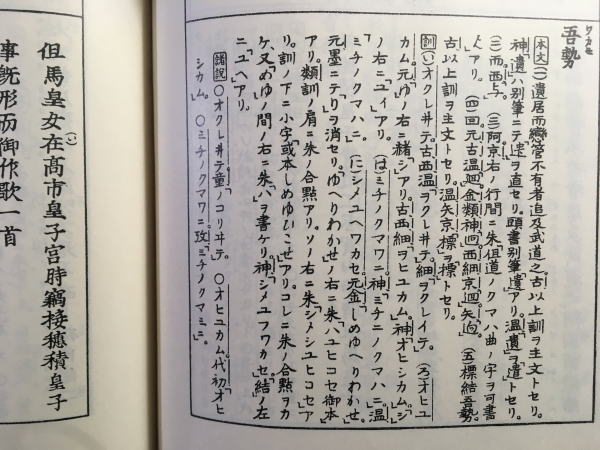 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「題詞」解釈 | 注釈 | 【題詞】「勅穂積皇子遣近江志賀山寺時但馬皇女御作歌一首」 「志賀山寺」は扶桑略記、天智七年の條に「正月十七日、於近江国志賀郡建崇福寺」とある崇福寺であり、続紀大宝元年八月の條に「甲辰 (四日)。太政官処分。近江国志我山寺封。云々 とあり、又天平十二年十二月の條に「乙丑 (十三日)。幸志賀山寺禮佛。」ともある。大津宮の西北、山の裾にあつた。京都の北白川より山中越又は滋賀峠越と云はれる道を大津市の北部南滋賀町に下りる少し手前に二つの谷をへだてて堂塔の阯が現存してゐる (今の新道よりはやや北にあたる)。勅してこの寺へ遣はされたといふ事について、「万葉考」には「左右の御哥どもを思ふに、かりそめに遣さるる事にはあらじ、右の事顯れたるに依て、此寺へうつして、法師に為給はんとにやあらん」とあり、「攷證」には「持統文武の御代、たえずこの皇子の位を昇し、封をも益したまひし事ありしにて、法師にとて遣はされしにはあらぬをしるべし。案るに、造立の事か、またはさるべき法会などありて、勅使に遣はされしなるべし。」とある。いづれも確証の無い事であるが、前者の推定によるべく、しかも法師にとまで限るはあたらない。もののまぎれにいつまでもかかづらふ事はやまと心ではない。一時の勅勘によつて暫くこの寺に籠られたのであらう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【題詞】「勅穂積皇子遣近江志賀山寺時但馬皇女御作歌一首」 -「志賀山寺」 「志賀の山寺」 崇福寺を指す。扶桑略記の天智七年の条に「正月十七日、於近江国志賀郡建崇福寺」と見える。大津宮西北の山裾に建てられたという。続紀の大宝元年八月の条に「近江国志我山寺ノ封、起庚子年計満卅歳」、天平十二年十二月の条には「乙丑幸シテ志賀山寺ニ禮ス佛ヲ」とあるが、穂積皇子の派遣については史書には見えず、目的も年次も不明である。真淵の「万葉考」に「左右の御哥どもを思ふに、かりそめに遣さるる事にはあらじ、右の事顯れたるに依て、此寺へうつして、法師に為給はんとにやあらん」と勅勘説を記したのを受け、澤瀉注釈には基本的にこの真淵説によるべきであるとしつつ、「法師にとまで限るはあたらない。もののまぎれにいつまでもかかづらふ事はやまと心ではない。一時の勅勘によつて暫くこの寺に籠られたのであらう」と言う。一方、岸本由豆流の「攷證」には「持統文武の御代、たえずこの皇子の位を昇し、封をも益したまひし事ありしにて、法師にとて遣はされしにはあらぬをしるべし。案るに、造立の事か、またはさるべき法会などありて、勅使に遣はされしなるべし。」と、勅勘説を否定。山田講義にも「これも亦証なきことなれど或はこの方ならむ」と言う。断定はし難いけれども、「勅~遣時」という題詞から「勅勘」を読み取ることは困難だし、また、後の歌 (116) の題詞に「事既に形 (あら) はれて作らす」とあるのを重視すれば、編者は少なくともこの「115歌」について、二人の関係が顕われた後の歌とは考えていなかったと推定されよう。したがって何らかの用件により勅使として派遣されたと考えられる。一説に、持統四年四月十三日の仏事と関連する近江朝鎮魂のための派遣と言う (渡瀬昌忠「人麻呂の宮廷詩の場」国文学昭和五十一年四月)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「崇福寺」 天智七年 (668) 近江京守護のために創建された勅願寺。大津市滋賀里 (しがさと) 町西方の山腹に遺跡がある。穂積皇子が志賀山寺に遣わされた理由は不明。但馬皇女との恋愛が露顕し、勅勘によって追放され一時僧となったとする説、造営あるいは法会などのための勅使として派遣されたとする説などがある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「遺居而」訓釈 | 古義 | 遺居而 [オクレヰテ] は、遺[ノコ] され居リての意なり、八ノ卷に、難波邊爾人之行禮波後居而春奈採兒乎見之悲也[ナニハヘニヒトノユケレバオクレヰテハルナツムコヲミルガカナシサ]、九ノ卷に、後居而吾戀居者白雲棚引山乎今日香越濫[オクレヰテアガコヒヲレバシラクモノタナビクヤマヲケフカコユラム]、十七に、無良等理能安佐太知伊奈婆於久禮多流阿禮也可奈之伎[ムラトリノアサダチイナバオクレタルアレヤカナシキ]、古今集離別ノ歌に、限りなき雲居のよそに別るとも、人を心に後[オク] らさむやはなどあり、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「後れ居て」(オクレヰテ) 原文、西本願寺本に「遺居与」とあるが、元暦校本・金澤本・類聚古集に「遺居而」とあるのによる。「遺」は万象名義に「与・贈・加」、玉篇佚文にも「贈也」と見える。「送」「贈」の意の「オクル」も「何かを放ちやること」を表わし、あとに残される意の下二段動詞「オクル」と同源だろうと言われるが、小島憲之「万葉集用字考証実例 (一)」 (『万葉集研究』第二集) に、この「115歌」の「遺」について、同義の「贈 (オクル)」から、同音「後 (オクル)」に当てたものではないかと説かれている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「追及武」訓釈 | 代匠記 | 腰の句オヒユカムと点ぜるは誤れり、及は日本紀にも、此集の未にもシクとよみたれば、オヒシカムと、点ずべし、おひつく心なり、仁徳紀に、皇后の八田ノ皇女の御事を恨給て、御舟にて直に山背へ越させ給たる由帝聞食て、鳥山[トリヤマ] と云舍人を急て御使に遣はさるゝ時の御歌に、山城に、急げ鳥山、いしけしけ、吾思ふ妹に、いしき逢むかも、いは發語の詞にて、しけは皆追付けとのたまふなり、しきるも同じ、天武紀上に、騎士[ウマイクサ]、繼踵[シキリテ]而進之といへり、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「追ひしかむ」(オヒシカム) 旧訓に「オヒユカム」とあつたのを、代匠記に「夜麻斯呂迩(ヤマシロニ) 伊斯祁登理夜麻(イシケトリヤマ) 伊斯祁伊斯祁(イシケイシケ)」 (仁徳記) を引用し、その「イ」は發語で「シケ」は「及」の字に相当し、追付けの意であるとして、今も「オヒシカム」と改めた。その説に従ふべきである。「及」の字は「千遍敷及 (チヘシクシクニ)」 (11・2552) とも「千重敷々 (チヘシクシクニ)」 (11・2437) とも書かれて集中「シク」と訓まれてゐる事が多い。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「追ひ及かむ」(オヒシカム) 旧訓「オヒユカム」を代匠記 (初) に「オヒシカム」と改訓。「シク」は及ぶ、追いつく意。神代記に「追斯伎」とある。平安時代になると、「シク」の用法が固定してゆくのに対し、「オヨブ」が、ある点に届くとか、届こうとするなどの意にも拡がった用例を見るようになる。「ム」は、意志を示す助動詞。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「阿廻」の「阿」 | 全注 | 【注】「道の阿廻」(ミチノクマミ) 「阿」は玉篇に「毛詩、成楽在阿、伝曰 (曲) 陵日阿」とあり、曲がった岡の意 (小島憲之「万葉集用字考証実例 (一)」)。新撰字鏡にも「於可反椅也美也棟也曲也近也雅也岳也此也」と見える。ここでは曲つまり曲がり角を表す。「クマ」について、井出至「万葉人と隈」(『万葉集研究』第八集) に、名義抄の「隈 (クマ)サグル」「曲 (マガルクマ) メグル」「岳 (ヲカ) 山ノミチ クマ」「阿 (クマ) マタ」などの例をあげ、「隈」は曲所を意味し、外側から見ると、その曲がりくねった箇所は「かど」をなすところ、内側から見るとそこは「くま」をなし、「すみ」となるという。「ミチノクマミ」は巻第五に「道乃久麻尾」(5・886) ともある。「ミ」は接尾語的な名詞で出入湾曲した地形を表す語に接し、その周辺や場所などを指す。語源は、曲がりめぐる意の動詞 (上二段活用)「ム」の連用形「ミ」かとも言う (時代別)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「標結」(しめゆふ) | 注釈 | 【訓釈】「標結へわが背」(シメユヘワガセ) 「標結ふ」は「為誰可(タガタメカ) 山尓標結(ヤマニシメユフ)」(154) の如く、人のはひらぬやうに標縄を結ひめぐらす事にもいふが、ここはしるしをつける事である。標はめじるし。 大伴の遠つ神祖(かむおや)の奥つ城は 之流久之米多底(シルクシメタテ) 人の知るべく(18・4096) の例もある。「わが背」は穂積皇子をさす。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「標結へ吾が背」(シメユヘワガセ) 「標」は万象名義に「夫 (末か)・書・顛」とあり、和名抄に「シメ」の注が見える。「シメ」は、占有することをあらわす動詞「シム」の名詞形。自分の所有であることを示したり、道の標識としたりするために、草の葉を結び、「シメナハ」を張り、あるいは印をつけたりした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「115歌」類歌考 | 全注 | 【考】「類歌と115歌の特徴」 「恋ひつつあらずは~」という句を含む歌は万葉集に二十首近くを数える。そのうち半数はこの「115歌」と同じく第二句が「恋ひつつあらずは」であるし、初句に「後れ居て」とある歌も、「後れ居て恋ひつつあらずは紀の國の妹背の山にあらましものを」 (4・544、笠金村)、「後れ居て恋ひつつあらずは田子の浦の海人にあらましを玉藻刈る刈る」 (12・3205) の二首を見る。類歌性に富んだ歌の形であるが、右にあげた「544歌」や「3205歌」と比較してみると、但馬皇女の歌の第三句「追ひ及かむ」と結句の「標結へ」は、「妹背の山にあらましものを」「田子の浦の海人にあらましを」などよりも、よほど切実と言えよう。現実性の乏しい「妹背の山」や「田子の浦の海人」となることを仮想的に表現するのと異なり、志賀の山寺へ遣された君を追って行きたいという熱情を表わしているからであろう。また佐佐木評釈に指摘されているように、第五句が「標結へ」と「吾が背」に分かれているため、「一層追ひ立てられるやうな切迫した感情」が表現されたとも言えるだろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 116 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 【頭書】 「題詞」 京都大学本、肩ニ朱「天武天皇皇女」アリ。 「本文」 類聚古集、前行ニ「但馬皇女在高市皇子宮竊接穂積皇子事既形而御作哥」アリ。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「題詞」解釈 | 注釈 | 【題詞】「但馬皇女在高市皇子宮時竊(ひそかに)接穂積皇子事既形(あらはれ)而御作歌一首」 この題詞の冒頭のところ既に前にあるところをくりかへしてゐるのは、資料を異にしてをり、集の編者が纂序にあたり原本の題詞のままによつたものであらう。 「接」は説文 (十二) に「交也」とある。廣韻 (五) にも「交也持也合也會也」とある。 「形」は現の意。「アラハレ」と訓む。「形而」の下に目録には「後」の字がある。代匠記に「有ヲ以テヨシトスベシ。此ニは脱セルナルベシ」とし、以後の諸注多く補つてゐる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【題詞】「但馬皇女在高市皇子宮時竊(ひそかに)接(あひ)穂積皇子事既形(あらはれ)而御作歌一首」「竊・接・形」 「歌」字、西本願寺本にないが、元暦校本・金澤本・紀州本などによって補う。この題詞によれば、但馬皇女の高市皇子の宮に住まいされていた時の歌で、「114歌」の題詞の表現と重複するところがある。注釈に「114歌」と「116歌」とが異なる資料から採取され、巻二の編纂時に原資料の題詞のまま入れられたのであろうと言う。 〔竊〕既出 (105歌)。日本霊異記上巻第三十四話の訓注に「宴嘿二合竊也」と見え、同第二十話には「宴嘿」に「比曽加尓之天」とある。同義語に「ミソカニ」があるが、上代における確例は見出せない。 〔接〕万象名義に「子葉反會・□□持・合」とあり、新撰字鏡に「子□反支也持也引也跡也交也會也対也」と注されている。「交」は「人妻に、吾も交らむ」 (9・1759) の例のように「マジハル」とも訓まれるが、男女関係を広くあらわす「アフ」とも訓まれるので、ここは「交・会・接」に通ずる訓としてそれによっておく。 〔形〕万象名義 (巻二之一) に「胡□反見・掌容・常・象」、名義抄に「見」・「示」などとともに「アラハル」の訓がある。穂積皇子との関係の露顕した時に皇女の作られたのが「116歌」であるという。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「己世尓」異同 | 代匠記 | 「人事乎繁美許知痛美巳母世爾未渡朝川渡 (ヒトコトヲシケミコチタミオノカヨニイマタワタラヌアサカハワタル)」(一首解釈) 人コトは他言なり、腰の句、現点字に叶はず、六帖においのよにとあるもまた同じ、其上、此時共に盛におはしまして、互に戀かはしたまへば、老の世と云べき理なし、字に任てイモセニと四文字に讀べし、下句は此集よそにも、朝川わたる、夕川わたるなどよめり、古今に人目つゝみの高ければ、川と見ながらとよみ、まだきなき名の立田川、渡らでやまむ物ならなくに、などよめる、皆男女の中を川に喩て、ならぬをば渡らぬに喩へ、成をば渡るに喩ふ、然れば纔に逢といへども、妹背と云ばかりにもあらぬ墓なき事により、まだ渡らぬ川を既に渡れりといはむやうに云さはがるゝが佗しき事と、譬て讀せたまへるなり、朝川渡は速くより事の成やうの意なり |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 「人事乎 [ヒトゴトヲ]。繁美許知痛美 [シゲミコチタミ]。己母世爾 [イケルヨニ]。未渡 [イマダワタラヌ]。朝川渡 [アサカハワタル]」 己母世爾、(こはいと通 [キコエ] 難けれど、母ノ字、類聚抄古寫本幽齋本拾穗本等になきに從ば、オノガヨニなるべきか、略解にも、母は我の誤にて、おのがよになりしかといへり、又飛鳥井本六條本等には、母の下に登ノ字ありて、イモトセニと訓り、殊と夫になり、又契冲は、此ノ一句を、本のまゝにて、イモセニと訓べしと云り、また略解に宣長云、爾は、川か河か水かの字のの誤にてイモセガハならむかと云りとあり、いづれも古風めかず、又妹兄 [イモヤ ]を己母世 [イモセ] と書むことも、此ノ御歌にてはいかゞ、又岡部氏が、己母世爾 [オノモヨニ] は、己之世 [オノガヨ] になり、此ノ母 [モ] は之 [ガ] に通ふ、すべて乃毛加 [ノモカ] の三ツは、言便のまにまに、何にもいふなりと云るは、いとをさなき考ヘなり、さて、己世爾 [オノガヨニ] とは、己が生來しこのかたの世にといふ意か、されどおぼつかなし、) 今按に己母は、生有と書るを、草書より誤寫せるにや、さらば生有世爾は、イケルヨニと訓べし、四ノ卷に、生有代爾吾者未見事絶而如是□(立心偏+可)怜縫流嚢者 [イケルヨニアハイマダミズコトタエテカクオモシロクヌヘルフクロハ]、また十二に、生代爾戀云物乎相不見者戀中爾毛吾曾苦寸 [イケルヨニコヒチフモノヲアヒミネバコフルウチニモアレソクルシキ]、などあるに同じきを思ふべし、生有 [イケル] は生てあるなり、來世 [コムヨ]のことは知ず、わが生てある現世 [ウツシヨ] には、未 [タ] あはざりしとつゞく意なり、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「己世尓」(オノガヨニ) 原文流布本には「己母世尓」とあるが、金澤本と細井本との他、元暦校本・類聚古集・古葉略類聚鈔・紀州本等の古写本いづれも「母」の文字が無い。尤も陽明本、京大本等には「己」と「世」との間に印あり、頭書に「母イ」とある。しかしまた京大本の頭書は朱で消し右に青で「无」とある (この事校本に脱してゐる。序にしるしておく)。金澤本にも訓は「おのがよに」とあつて、恐らく「母」は衍字であらう。ただなぜかういふ衍字が加はつたかといふ疑問が抱かれるが、「母」と「世」と字体が似てゐる為に「世」が「母」に誤り、「己母尓」といふ本と「己世尓」といふ本とが生じて、更に「己世(母)尓」といふ形の本となり、それが本文にくり入れられた (16・3867参照) と見るべきではなからうか。おのが生涯にまだ経験しないといふ意である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「己世尓」(オノガヨニ) 「ヨ」は生涯・時代・世の中などをあらわす語。ヨの乙類。ここは生涯、一生の意。自分の生まれてから今までを省みて「オノガヨ」と言ったもの。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「朝川渡」考 | 全注 | 【注】「朝川渡る」(アサカハワタル) この「アサカハワタル」に『詩経』の渡河の詩や六朝の雲漢詩の影響を見、渡河を現実の河わたりというより、恋の冒険を意味しているとする説もある (松本雅明「詩経と万葉集」文学昭和四十六年九月)。たしかに万葉集には、「世の中の女にしあらば吾が渡る痛背の川を渡りかねめや」 (4・643、紀女郎) のように概念化した渡河の表現も見られるが、この「116歌」をそのように解すべきかどうかは疑問だろう。代匠記に「男女ノ中ヲ川ニ喩テ、ナラヌヲハ渡ラヌニ喩ヘ、成ヲハ渡ルニ喩フ」 (精撰本) と記し、橘守部の「檜嬬手」に「今日迄知らぬ世のうき瀬を渡りて潔身し給ふよしなるべし」とあるのも、同様に、概念的に解しすぎるものと思われる。私注に「『朝川渡る』が突然に見えるので注釈家が苦しんだのであるが、之を事実と見れば分かりにくい句ではない」と言う通りに解すべきであろう。「アサカハ」は文字通り、朝の川をあらわす語である。ただし澤瀉注釈に「ここは特に人目にたたぬ夜明けと見るべきであらう。今の都会人は朝ね坊が多くなつて午前九時や十時を朝と考へたりするのであるが『暁と夜烏鳴けど』 (7・1263) の句もあつて、皇女の身であるが、人目を忍ぶためにまだ夜の明けきらぬ川を渡られる事があつたと見るべきで、さればこそ『おのが世に未だ渡らぬ』の句もうなづかれる事ににならう」と説くのは、問題を残すと思われる。同じ注釈の口訳に「未明の川を渡ること」とし、古典集成にも「事露れて世間がうるさいので、女の身でありながら未明の川を渡って逢いに行く」と、ほぼ同様な口訳を見る。これらは、「朝川渡る」という結句を人目を避けようとした皇女の行為と解するもので、古典大系に「人目をさけて朝早く川を渡るというなれぬことをしたのが、特殊な感動を与えたのであろう」と注されているのも同じ。右にあげた注釈・古典大系・古典集成などの解釈は、現在の通説と言ってよいものである。これらに従って読んでも、女性の身でありながら朝の川を渡って帰るという烈しい行動を歌った印象的な一首と言える。ただ「朝川渡る」を、人目につかない未明の徒歩と解する右のような通説は、万葉集の「朝川」を、わたしたち現代の読者の側に引き付け過ぎたものと言うべきかもしれない。「朝川」は、万葉集のこの他の歌では、決して未明の人目につかぬくらがりを意味しない。人麻呂の吉野賛歌に「船並めて朝川渡」ると歌われているのは、朝の光の溢れる大宮人たちの船遊びを想像させようし、坂上郎女の「・・・佐保川を 朝川渡り 春日野を そがひに見つつ・・・」 (3・460) も、暁方の暗闇を歌っているわけではない。それらの「朝川」の用例こそ「朝」の自然な用法を示すものではないかと思われる。別稿 (「但馬皇女の歌」明日香昭和五十二年一月) にも記したように、アサは昼を中心とする言い方で昼の時間区分の最初に位置し、「ユフベ→ヨヒ→ヨナカ→アカツキ→アシタ」という夜中心の時間区分に対している。アシタとアサとは、実質的に重なるところがあるが、アシタは夜の時間区分に属する故に、夜の明けてゆく意識を濃くまといつかせていると言われる (大野晋『日本語の年輪』)。アサは昼の時間帯の最初なので、明るいイメージが強い。万葉集の「朝川」に未明の印象の乏しいのも、その意味では当然と思われる。古代には妻問い婚であり、妻問いする男たちは暗いうちに女の家から帰るのが常であった。「明けぬべく千鳥しば鳴く白栲の君が手枕いまだ飽かなくに」 (11・2807) などと歌われているのは、そうしたアカトキの別れであり後朝 (きぬぎぬ) の別れである。後代の「有明けのつれなく見えし別れより暁ばかり憂きものはなし」 (古今・625) の歌やさらに後の『宝物集』に「更け行く鐘明け行く鳥の声を聞くにも、いとど心惑ひて睦言つきせざるを暁の別れと申すなり」と記されているのも、アカツキ(アカトキ) の別れである。アサやアカトキについて右のようなことを考えながら但馬皇女の「116歌」を読むと、通説のように人目を忍んで朝川を渡ったとは受け取り難いだろう。暁の川ならともかく、すっかり明けてしまって日の光も眩しいほどの朝川を皇女は渡ったのである。女の身で男の許へ通ったというだけでも、尋常なことではないのに (茂吉秀歌)、但馬皇女は人目を避けようもない朝の川を渡って帰ったと歌っている。朝の光に刺すような恥じらいを皇女は感じたかと思われるが、その一方で人目や人言の呪縛をようやく離れえた自分を意識したのではなかったか。その意識が「己が世に未だ渡らぬ」という詞句を選ばせたものとも思う。「ア・サ・カ・ハ・ワ・タ」ルというア段音の連綴には、人言の垣を越えた爽やかささえ感じられるようだ。 【考】「恋と人言」 「人言を繁み言痛み」という一、二句を「朝川渡る」に掛かるものと解するのが通説であるが、「朝川」を既述のように理解すると、人目を避けて未明の川を渡ったとは受け取りえない。一、二句は「己が世に未だ渡らぬ」に掛かるのであって、世間の人の噂を気にして、いままで渡りえなかった「朝川」を、今渡るという、決断と行為の歌として理解される。題詞に「事既に形はれて」と記されているのは、巻二の編者もこの歌の「朝川渡る」に皇女の「ひらき直り」を感じ取っていたことを想像させよう。「114歌」に、ひたすらに靡き寄りたいという願望が歌われ、次の「115歌」にはさらに積極的に君を追って行こうとする意志が歌われたのちに、この「朝川渡る」の歌が並べられたのは、巻二編者の構成意識によるだろう。人目や人言に抗いながら恋情のままに生きようとする女性の内面的なドラマを思わせる配列と言ってよい。 なお、万葉集のなかで、人目や人言の煩わしさを嘆いた歌は約180首にのぼる。人目・人言は、恋する男女にとって最大の障害だった (伊藤博『万葉集相聞の世界』)。そのため、 人言を繁み言痛み逢はざりき心あるごとな思ひ我が背子 (4・538) 人言を繁み言痛み我妹子に去にし月よりいまだ逢はぬかも (12・2895) のように、逢う瀬もとだえがちだったらしい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 人目を忍んで、朝川を渡らねばならない事情があったのであろう。窪田『評釈』は、「高市皇子の宮から、夜明けに脱出されてのことと思われる」という。「114・115歌」、いずれも皇女の気迫を感じさせる。「君によりなな言痛くありとも」(114)、「追ひ及かむ道の隅廻に標結へわが背」(115)。この歌も、結句「朝川渡る」と言い切ったところが強い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 117 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 【頭書】 「題詞」 西本願寺本・神田本、肩ニ朱ノ注文アリ。細井本、肩ニ赭ノ注文アリ。「舎人皇子天武天皇子叙一品」 京都大学本、肩ニ朱ノ注文アリ。「天武天皇々子一品」 「本文」 袖中抄第一「万葉第二云 マウラヲヤカタコヒセムトナケヽトモ鬼(ヲニ)ノ益卜雄(マスウラヲ)ナホコヒニケリ」
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「大夫哉」古写本 | 全注 | 【注】「大夫や」(マスラヲヤ) 原文「大夫」を金澤本に「丈夫」とし、温故堂本に「〔丈の右肩に点〕夫」とする。童蒙抄に「大の字は丈の字のあやまりたるか。大の字の下に丈の字を脱したるか。日本紀神武巻に慨哉大丈夫とあり。又皇極紀には丈夫とあり。これともに不審也。此集は多分日本紀の文字を用ゐて書きたれば、皇極紀に従てかきたるか。此集中みな大夫とかけるは丈夫の二字をあやまりたるなるべし。」と言う。たしかに「大夫」を「丈夫」と伝える写本もあって、-金澤本には、巻二の「大夫」のうち三例を「丈夫」としている-問題となるが、多数の古写本の伝えるように、「大夫」を原字と認めるべきである。単に立派な男子というのではなく、律令官人としての自負をこめた言葉であり、字面であったと思われる (『万葉集の作品と方法』参照)。「マスラヲヤ」の「ヤ」は反語。 【考】「万葉集のマスラヲについて」 万葉集にマスラヲの例は六十例余りを数える。そのうち四十五例、つまり三分の二以上が「大夫」と記されている。上田正昭「社会と環境-ますらを論を中心として-」 (解釈と鑑賞昭和三十四年五月) は、マスラヲの基本的性格を官僚貴族と規定する川崎庸之 (「大伴三中の歌」文学昭和二十二年一月)・西郷信綱 (『日本古代文学』) の説を承け、「治むる大夫」の姿にこそマスラヲの意識を支えるものがあったと記しているが、人麻呂以後、とくに奈良時代の歌におけるマスラヲに大夫的性格を指摘することは正しいであろう。ただし、上田氏が「大夫」を官職名の大夫と結び付けて理解しているのは疑問である。『時代別国語大辞典』には、官名の大夫などとは関係なく、大丈夫の意で用いられた表記かと記している。山田孝雄講義に、遊仙窟中の「大夫」を例として、 「マスラヲ」の義に「大夫」の字面を用ゐたるは、漢籍にては遊仙窟を見る。されば、支那にても「大夫」を「大丈夫」の意に用ゐしを見る。(巻一・五番歌の項) と記すのも、大夫=大丈夫と見る方向のものである。別稿 (「軍王作歌の論」国語と国文学昭和四十八年五月) に詳述したように、こうした考え方はかなり広く認められているのかもしれないが、次のような理由から従いがたい。第一に、講義の説のように「大夫」を「大丈夫」の意で用いたものが、中国にあるのかどうか、という点。講義に引く遊仙窟の例は、 大夫巡(リ)二麦隴(ヲ)一、処子習(ツ)二桑間(二)一。 大夫(ハ)存在(ス)二行迹(ヲ)一、慇懃(ニ)為(セ)二数来(ルコトヲ)一 の二か所に見えるが、いずれも主人公の張郎をさす。八木沢元『遊仙窟全講』によれば、これらの「大夫」は「官位ある者」を意味するという (185参照)。諸橋の『大漢和辞典』にも官名・爵位のほか、ひろく官位ある者の称としての「大夫」などをあげているが、「大丈夫」を意味する「大夫」は見えない。その点で、講義に、「支那にても『大夫』を『大丈夫』に用ゐしを見る」と記しているのは、疑問である。第二に、中国に見られずとも、日本で「大丈夫」を略して「大夫」と記したと考えることは可能であろうが、その場合には、なぜ「丈夫」でなく官名等と紛らわしい「大夫」としたのか、説明を要する。万葉集に、「大夫」を「大丈夫」と記した例が見られるのならともかく、そうした例はないし、日本書紀の「大丈夫」 (神武即位前紀) にマスラヲの古訓が見えるようであるが、それをそのまま万葉時代に遡らせ、しかも「丈」字を略した「大夫」を認めるには、「大丈夫」の例が乏ししぎるだろう (書紀の中で、「大丈夫」は右掲の一例のみ)。上田正昭等が「大夫」の字面のままにマスラヲの原義を探ろうとしたのは、方向として正しかったと思われる。周知の通り、「大夫」には、五位以上の称としての用例がある。万葉集にも「山上憶良大夫」「粟田大夫」「田口益人大夫」などとあるのは、これを和訓すればマヘツキミとなるのであろう。歌詞に見える「大夫」が、これと直接関わるのでないことは、人麻呂作歌や虫麻呂歌集の例によっても察せられる。結論から言えば、先掲の遊仙窟の「大夫」の例などと同じく、広く官職を有する者の意の「大夫」が万葉集の歌詞に見える「大夫」と深い関連を持つのであろう。 [大夫の嘆き] この歌について私注に「ひたごころをそのまま歌つた趣である」と記すが、窪田評釈に「我は丈夫(ママ)で、女々しき心をもつまいと思っているが、それをもたらされてしまったと、ただそれだけをいわれたのみで、相手に対しては、直接の訴えは一語もまじえていないものである。これは相手に対して、高く地歩を占め、また親しみをもっていての上の訴えだからである」と言う。〔注〕にも触れた通り、マスラヲとは本来剛強の男を意味する語であった。女々しい行為とか涙を拒む強さを持つのがマスラヲだと意識されたのである。万葉集に多く「大夫」と記されているのは、律令制度の官人一般にその呼称を広く及ぼした後の文字表記であるが、官僚としての自負も感じられる。そうしたマスラヲが次第に風流意識を深めてゆくのが奈良時代で、女性に対する男子一般の称に近いマスラヲの例をも見えるようになる。この歌の場合は、まだ古いマスラヲ意識を感じさせよう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「や~む」語法 | 新全集 | 【頭注】「ますらをや片恋せむ」 ますらおたる者が片恋のごとき女々しいわざをすることか。マスラヲ→5。一人称に用いた、ヤ~ムは、現在自分がしていることについて、こうも~することか、などと不甲斐なく思いながらどうすることもできない気持ちを表す語法。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「鬼乃益卜雄」訓 | 注釈 | 【訓釈】「醜のますらを」 原文「鬼」の文字は、 萱草(わすれぐさ)垣もしみみに植ゑたれど 鬼之志許草(シコノシコクサ)なほ恋ひにけり (12・3062) 慨(うれた)きや 四去霍公鳥(シコホトトギス)今こそは声の嗄(か)るがに来鳴きとよめめ (10・1951) などの例を対照して「シコ」と訓み、嘲罵の意の語と考へられる。神代紀上に「泉津醜女(ヨモツシコメ)を注して「醜女此云二志許売(シコメ)一」とあり、記伝六には「鬼」を「シコ」と訓む事について「こは醜ノ字の偏を略(ハブク)るか、又醜女(シコメ)の意を得て鬼とは書クか、」とあり、倭名抄(一)「醜女」の條に「日本紀私記云、醜女 [志古女]或説黄泉之鬼也」とあるによつて、黄泉の鬼の意で、鬼をシコと訓んだと見る説もあるが、鬼が「しこ」ではなく、醜女 (即ち黄泉の鬼) が「しこめ」なのであつて、シコは醜一字に相当するものであり、それは孝徳紀大化五年の條に高田醜雄の醜に注して「此云二之渠(シコ)一」とあるによつても明らかである。従つて「鬼」は「醜」の通用文字としてシコと訓んだと見るべきである。さてその「醜」は今は「ミニクシ」と訓まれてゐるが、説文 (九) には「可惡也」とあつて、必ずしも見た目の貌(かたち)についてのみの言葉でなく、その点は現在の我々の用法としても頷けるところであり、「しこ」は我々が今俗語として用ゐる「イヤーナ」、といふやうな意とも見る事が出来よう。「にくし」(1・21)、「あし」(8・1428参照)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「醜のますらを」(シコノマスラヲ) 「鬼」の字、古点に「「オニ」と訓まれていたが、仙覚抄に「シコ」と訓む。「醜」を「シコ」と訓むのは、孝徳紀大化五年の条に「高田醜雄」の「醜」に「此云之渠」の注があるので確かめられる。「鬼」は、その「醜」の偏を略したか、または「醜女」の意味で「鬼」と書いたか (古事記伝六) と推定されているが、講義には「醜を略して鬼とせる例はいまだ知らねば『醜女』の意にて鬼を用ゐしならむ」と言う。澤瀉注釈にも「鬼」を「醜」の通用文字として「シコ」と訓んだと見ているが、「通用文字」である証明はない。古典全集の頭注に「原文『鬼』は醜の意」とするのは、小島憲之『上代日本文学と中国文学』中巻に「『鬼』(醜に同じ) 」とあるのと等しく、そのいずれにも「鬼=醜」の根拠は記されていない。あるいは、 萱草吾が下紐につけたれど〔鬼乃志許草〕ことにしありけり (4・727) 萱草垣もしみみに植ゑたれど〔鬼之志許草〕なほ恋ひにけり (12・3062) などの例と、神代紀の注「醜女此云志許女」などを対照し、「鬼=醜」を帰納したか。「鬼」を「シコ」と訓むことと、「シコ」が自嘲の意であることは間違いないと考えられるが、「鬼=醜」の証明はまだ十分でなく後考にまつ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「醜のますらを」 シコは醜いものを言う語。ここは自己嫌悪して言った。原文「鬼」は「醜」に通用させたもの。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 【脚注】「しこのますらを」 「しこ」は罵りの言葉。原文「鬼」の字は、漢語「鬼」「鬼子」が罵る語に用いられることによる表記であろう。「しこのしこ草(鬼乃志許草)言(こと)にしありけり」(727)、「しこのしこ草(鬼之志許草)なほ恋ひにけり」(3062)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 118 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 【頭書】 「本文」 金澤本、訓ナシ。元暦校本、本文ト訓トノ行間ニ朱「御本云 ナケキツヽマスラオノコヒシケヽレハコソワカヽユヒノヒチテヌレケレ」
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「嘆管」異同 | 全注 | 【注】「嘆きつつ」 原文、西本願寺本・紀州本などの「歎管」とあるが、元暦校本・金澤本に「嘆管」とあるのによる。新撰字鏡に「呻」に注して、「舒神反吟也歎也左万与不又奈介久」とあり、呻・吟・歎を「ナゲク」とか「サマヨフ」と訓んだことが知られる。嘆は万象名義に「勅且(旦)反□・吟・傷」とあり、また歎は「他且反美・吟・息・謡哥吟」(巻三之一)とあって、嘆は歎に通ずる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「戀礼許曽」異同 | 注釈 | 【訓釈】「ますらをのこの恋ふれこそ」 元暦校本などに「マスラヲノカクコフレコソ」とあるが、西本願寺本に「マスラヲノコノ」とあるによる。原文「戀礼」が元暦校本、紀州本、細井本と版本とに「戀乱」とあり、紀州本に左に「コヒミタレ」とある。もし「乱」の文字によらば、上を「マスラヲノ」と訓み「コヒミタレコソ」とつづける事になるが、それでは句割になつて調子も整はず、金澤本、西本願寺本その他の古写本に「礼」とあり、「益荒丁子(マスラヲノコ)」(9・1801) の用例があり、「大夫」二字を「マスラヲノコ」と訓んだと思はれる例 (19・4187) もあるから西本願寺本によるべきである。「ノコ」の文字陽明本などに青になつてをり、仙覚の改訓かと思はれる。「恋ふれこそ」は「恋ふればこそ」の意 (1・23参照)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「恋ふれこそ」 已然形に係助詞「コソ」の付いた形。「コフレバコソ」の意。山田講義に、「この『コフレ』は已然形にしてここは下の句に対して条件を示すものなるが、かかる場合に今ならば、接続助詞『ば』を添ふべきにこれを添へざるは古語の一格なり。而してその条件と下の句との結合、はた思想上の強度を支配するためにその已然形の下に係助詞『ぞ』『こそ』等を添ふることも亦古語の一格なり」と言う。なお「戀礼許曽」の「礼」を「乱」と記した写本も見える。そのこと〔考〕の条に述べる。 【考】「戀礼許曽と戀乱許曽」 題詞に「和へ奉る歌」とあるように、前の舎人皇子の歌を受け、前歌の意に合わせて歌われている。「嘆きつつますらをのこの恋ふれこそ」という上三句は、皇子のことばの繰返しに近いもので、掛け合い唱和の伝統を受け継ぐと言えようが、娘子には、皇子の恋情にこたえようとする気持ちがある。第三句の「戀礼許曽」を元暦校本・紀州本・細川本などの「戀乱許曽」とする。それが正しいとすれば、「マスラヲノコヒミダレコソ」と訓むべきであろう。私注 (土屋文明万葉集私注) は「コヒテミダレバといふ例もあり、其他コヒとミダルは屡連合される語である。コヒとミダレが二句に分属するけれども、そこは休止なしに続く句法であるから句割れにはならない」として、「戀乱許曽 (コヒミダレコソ)」」の本文によっている。元暦校本・紀州本などの伝える本文だから、特に注意されなければならないが、巻第四の、 吾背子我如是戀礼許曽ぬばたまの夢に見えつついねらえずけれ(4・639)[旧歌番号] は、この「118歌」と類想である上、「戀礼許曽」の表記まで一致していて、「礼」の書き添えの意義を推測させるところを持つ。すなわち「コフレコソ」は已然形に「コソ」の接する形で、「バ」を補って解すべきところであり、「礼」のない場合は訓読に異説を生みやすいが、「戀礼許曽」と記すと、この五音の訓は明確になる。「118歌」の「礼」にもそうした表記上の配慮を読みとることができるだろう。それに、「戀乱許曽」の本文によれば、代匠記初稿本や童蒙抄の訓のように、「コヒミダレコソ」と訓むことになろうが、「ミダル」は万葉集には自動詞の四段活用の仮名書例がなく、当時すでに下二段活用になっていたと推定される上に (澤瀉久孝「み山もさやにさやげども」『万葉古径(一)』)、「刈りのみ刈りて乱てむとや」(11・2837) 、「柳の糸を吹き乱」(10・1856) の「乱」を「ミダリ、ミダル」と訓む場合は他動詞であるから、「コヒミダレバコソ」の意味の「コヒミダレコソ」を認める証例とはしがたい。したがって「戀乱許曽」は「戀礼許曽」の誤写から生じた本文の訛伝であったと考える。詳細は拙稿「万葉集訓詁存疑」(『論集上代文学』第十三冊) 参照。 なお。茂吉編『万葉集研究 上』に土屋文明の次のような評を見る。 ・・・舎人娘子は如何なる人か知られないが、巻一に大宝ニ年に三河国に行幸の時の歌があり、序歌ではあるが力量ある詠風を示して居る。さう言へば巻ニに皇子に和へる歌も幾分皇子を圧倒して居る観がある。殊に巻八の歌は一首に感動が溢れて居て、意吉麿の「苦しくもふり来る雨か神の崎狭野のわたりに家もあらなくに」(3・265) との前後は知り難いけれども、歌は寧ろ立ち勝って居るやうに感ぜられる。巻ニ、巻四に見える舎人吉年は女性であって、その歌は注意されるべきものであるが、事によつたら、この舎人娘子と記されてあるのと同一人ではないかと私は想像して居る。・・・ 同感されるところが多いが、舎人吉年と舎人娘子を同一人とすることにはなお問題が残るであろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「恋ふれこそ」 恋フレバコソに同じ。上代語では、已然形が「バ」を伴わずに順接確定条件 (その大半は理由格) を表すことがある (135「入日さしぬれ」・471「山隠しつれ」など)。これに「コソ」がついたものが「然にあれこそ」(13)、「依りてあれこそ」(50)の類。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文写本異同「吾結髪乃」と 「吾髪結乃」 |
注釈 | 【訓釈】「吾結髪乃」(ワガユフカミノ) 原文「髪結」とあり、金澤本には訓を欠き、元暦校本以下諸本に「ユフカミ」と訓み、ただ紀州本のみ「カミユヒ」とあ 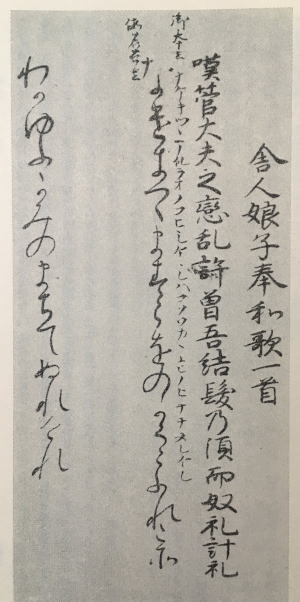 り、左に「ユフカミ」と「モトユヒ」との両訓がある。元暦校本には本文「結髪」とあるので全註釈にはそれにより、「ひぢてぬるぬるするのは髪であつて、もとゆひでは無い」として旧訓に従つた。但し、元暦校本には朱で、「髪」を「結」の上に移すべきしるしをつけてゐる。それにより「結髪」を筆者の誤写とすれば「ユフカミ」と訓むべき証が無い事になる。一方「カミユヒ」の語は皇太神宮儀式帳に「御加美結紫糸八條〔長條別三尺〕」
(新宮遷奉御装束用物事) といふ例があり、「モトユヒ」は同じ儀式帳に「紫御結糸二條〔長四尺〕」 (荒祭宮遷奉時装束) などと見え、倭名抄(六)
にも「孫愐切韻云、鬠〔音活、毛度由比〕、以レ組束レ髪也」とあり、古今六帖 (五「もとゆひ」) にこの歌を収めて、既に「もとゆひ」とし、長流の管見以後「モトユヒ」と訓むべき説が一般に行はれてゐる。「もとゆひ」の語は、 り、左に「ユフカミ」と「モトユヒ」との両訓がある。元暦校本には本文「結髪」とあるので全註釈にはそれにより、「ひぢてぬるぬるするのは髪であつて、もとゆひでは無い」として旧訓に従つた。但し、元暦校本には朱で、「髪」を「結」の上に移すべきしるしをつけてゐる。それにより「結髪」を筆者の誤写とすれば「ユフカミ」と訓むべき証が無い事になる。一方「カミユヒ」の語は皇太神宮儀式帳に「御加美結紫糸八條〔長條別三尺〕」
(新宮遷奉御装束用物事) といふ例があり、「モトユヒ」は同じ儀式帳に「紫御結糸二條〔長四尺〕」 (荒祭宮遷奉時装束) などと見え、倭名抄(六)
にも「孫愐切韻云、鬠〔音活、毛度由比〕、以レ組束レ髪也」とあり、古今六帖 (五「もとゆひ」) にこの歌を収めて、既に「もとゆひ」とし、長流の管見以後「モトユヒ」と訓むべき説が一般に行はれてゐる。「もとゆひ」の語は、 君来ずはねやへも入らじこ紫わがもとゆひに霜はおくとも (古今集巻十四) などの歌によりしたしまれた言葉である為にこの訓に疑がもたれなかつたのであるが、集中には他に見えず、管見に「もとゆひとはいふともただ髪のこと也」と云ひ、代匠記や古義もそれに従つてゐるやうに、髪そのものをさしたもののやうに思はれる。さうだとすれば「カミユヒ」と訓むならばともかく、わざわざ「モトユヒ」と義訓してまで髪の事とするよりも、やはり結髪とあるべきもので、元暦校本の「結髪」は誤写ではないと考へる。元暦校本には上の「戀礼」も「戀乱」と誤つてゐるにかかわらず、訓は「こふれこそ」と正しくなつてをり、今は本文も「結髪」とあり、訓も「ゆふかみ」とあつて、本文も訓も正しいものを伝へてゐるのだと私は考へる。「髪」を「結」の上におくべき朱のしるしをつけてゐるのは、本文の文字を筆写した人が誤写に気づいて訂正したものではなく、本文の左に朱で「御本云」として片カナの訓が書き込まれてをり、「結髪」に相当するところは複製本によれば「ワカヽユヒノ」とあるらしく、これは「カミユヒ」の「ミ」が落ちたのかと思はれ、その訓によつて、その訓を書き入れた人が同じ朱筆で本文にも右のしるしをつけたものと認むべきだと私は推定する。元暦校本の朱筆の訂正の中にはさかしらな加筆もある事前 (1・2「龍」を「籠」とす) にも述べたところであり、今もそれであり、その加筆を除いた「結髪」こそ正しい姿を伝へたもので、それを原本の形と認むべく、諸本の訓に「ゆふかみ」とある事はそれを証してゐるともいへるであらう。 【右写真は「元暦校本萬葉集」】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「吾結髪乃」(ワガユフカミノ) 原文、西本願寺本・紀州本・金沢本等に「吾髪結乃」とある。元暦校本には「吾結髪乃」とあり、朱で「髪」を「結」の上に移す印を付けてる (複製本でははっきりしないが、結髪の右に弧線が見えるのがそれか。校本万葉集に「朱ニテ入レ換フベキ記号ヲ附セリ」とあるによる)。他の写本には「髪結乃」となっているので、判断は難しい。ただし、元暦校本の別提訓には「わかゆふかみの」と訓まれており、西本願寺本その他の傍訓にも「ワカユフカミノ」と見える。西本願寺本には墨で記されており、古訓であることがわかる。校本万葉集に新増補せられた神宮文庫本でも同様である。紀州本の本文右に「ワカカミユヒノ」、左に「ワカユフカミノ」と「ワカモトユヒ」と二行の訓が見えるのは、それらの中で特殊である。これら三様の訓のうち、「モトユヒ」は、「髪結」「結髪」いずれの本文によるにしても考え難い訓である。全註釈に「ひぢてぬるぬるするのは髪であつて、もとゆひではない」と言うのも、もっともであるが、文字としても、「髪結」や「結髪」を「モトユヒ」とは訓み難い。澤瀉注釈に、歌意から、ここは髪そのものをさしたように思われる所で、「わざわざモトユヒと義訓してまで髪の事とするよりも、やはり結髪とあるべきもので、元暦校本の『結髪』は誤写ではない」と考えられているのが正しいだろう。元暦校本に、「髪」を「結」の上におくべき朱の印の見えるのは、本文の筆写者が誤写に気付いて訂正したわけではなく、本文左に「御本云」と仮名訓を書き入れた人が朱筆で本文にも右の印をつけたのであろうと言う。これは、元暦校本の傍訓書き入れと、本文右のしるしとの関係を見事に説いていると思う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「漬而奴礼計礼」訓釈 | 注釈 | 【訓釈】「漬而奴礼計礼」(ヒヂテヌレケレ) 「ひづ」は潰り濡れる意。「袖潰左右二(ソデヒヅマデニ) 哭耳四泣裳(ネノミシナカモ)」 (4・614) などの例がある。集中には仮名書きの例はないが、「袖ひぢてむすびし水」 (古今集、一) などの例により「漬」を「ヒヅ」と訓む。後には上二段にも用ゐられてゐるが、萬葉では「ヒヅマデ」とあつて四段活用である。「ぬる」は「伊波為都良(イハヰツラ) 比可婆奴流奴流(ヒカバヌルヌル)」 (14・3378) と「伊波為都良(イハヰツラ) 比可婆奴礼都追(ヒカバヌレツツ)」 (14・3416) とを照合し、又「多気婆奴礼(タケバヌレ) 多香根者長寸(タカネバナガキ) 妹之髪(イモガカミ)」 (123) の用例とくらべあはす時、濡れるの意ではなく、ずるずるとすべり解けることと見られる。即ち髪がしめりを帯びて解けてくる事で、人に恋ひせられると眉が痒くなつたり、くしやみをしたり、紐が解けたり (11・2408参照) するやうに、結髪も解けるといふ事が信じられてゐたのであらう。上の「こそ」をうけて「けれ」と結んだ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「漬而奴礼計礼」(ヒチテヌレケレ) 「漬」は万象名義 (巻五之三) に「似□(夾+刂)反浸・漚」とあり、「浸」は玉篇佚文に「沈溺也漬也」と見える。万象名義には、「濡」に「潤漬」、「潤」に「微湿・浸・餝・益・湿」の注もあって、「漬」に「濡・潤・浸」、とくに「浸」に近い意味のあることが知られる。万葉集に「袖さへ所漬せむすべもなし」 (12・2953) とあるのは、ヌレテ・ヒチテ両様に訓めるが、他の「漬」が「人にな着せそ霑れは漬跡裳」 (3・374)、「白妙の袖漬左右二ねのみし哭くも」 (4・614)、「白妙の袖漬左右二哭きし思ほゆ」 (11・2518) のようにヌルでなくヒツに宛てた例ばかりであるところからすれば(「埿漬」でヒヅチを表す例もあるが)、2953も「袖さへひちて」とするのが穏やかかもしれない。なお、ヒチのチは清音。名義抄 (図書寮本) の「漬」にヒチテとある。古今集巻一の「袖ひちてむすびし水のこほれるを~」という貫之歌の場合も、高松宮本などに清点がつけられていると言う。ヒツは四段活用の動詞。ぐっしょり濡れる意。ここでは、大夫の嘆きの息が霧となって濡れたと考えられている (古典集成)。万葉集にはヒヅツという動詞も見える。ヒツに近い意味の語と解されるが「比豆知」 (17・3969) と仮名で書かれ、また「土打」「埿打」などとも記され濁音を含んでいて、別語。ヌレは、集内に仮名書き例のみの語。「たけば奴礼たかねば長き妹が髪」 (123)、「入間路のおほやが原のいはゐづら比可婆奴流奴流吾にな絶えそね」 (14・3378)、「上毛野かほやが沼のいはゐづら引かば奴礼つつ吾をな絶えそね」 (14・3416) など。他に巻十四の3501歌。水に濡れる意味のヌルが、巻二、巻三、巻四など訓字主体表記の巻に沾・潤・湿など、すべて正訓字で書かれていて、仮名書きがないのと対照的である。123歌の「奴礼」と同様、この「奴礼」も水に濡れるのではなく、ズルズルほどける意味に解するのが正しい。ケレは係助詞コソの結びで已然形。髪がぬれてほどけた事実の理由を、今始めて覚ったという気持ちをあらわす。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「漬而奴礼計礼」(ひちてぬれけれ) ヒツは水に漬かったようにびっしょり濡れる意。→ 370歌「濡れて漬てど」。ヌルはひとりでに緩んで解けること。結んだ下紐や結った髪がひとりでに解けるのは相手が自分の事を思っているしるしと考える俗信があったか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 【脚注】「漬而奴礼計礼」(ひちてぬれけれ) 人に思われると結った髪がほどけるという俗信があったのであろう。反対に、結った髪をわざと解いて逢うことを祈る歌もある。「ぬばたまの我が黒髪を引きぬらし乱れてなほも恋ひわたるかも」 (2610)。「ぬれ」は下二段動詞。束ねた髪がほどける意。→ 123歌。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 119 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 弓削皇子思紀皇女御歌四首 芳野河 逝瀬之早見 須臾毛 不通事無 有巨勢濃香問 (ヨシノカハ コクセノハヤミ シハラクモ タユルコトナク アリコセヌカモ) 【頭書】 「題詞」 京都大学本、肩ニ朱「天武天皇皇子」 古葉略類聚鈔、前行ニ「弓削皇子思紀皇女御作哥四首中」アリ。但「作」ヲ消セリ。 題詞ノ左右ニ小字「紀皇女天武天皇女母同穂積皇子叙一品朱鳥元年遣伊勢神宮勝宝三年薨 集第二云紀皇女竊嫁高安王被責時作此哥高安王降同伊与国守入哥ニ□」
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拾穂鈔 | よしのかはゆくせのはやみしはらくもたゆることなくありこせぬかも 芳野河逝瀬之早見須臾毛不通事無有巨勢泥香問 〔よしのかはゆくせの 序哥也ありこせぬとは有來ぬと云心也心は絶間なく有來らぬかと也來よといはんため也〕
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「逝瀬之早見」訓釈 | 古義 | 逝瀬之早見[ユクセノハヤミ] は、逝瀬[ユクセ] が早き故にの意なり、さてこの之は、必ス乎[ヲ] とあるべき處なるを、かくいへるは、甚めづらし、この例は、外に見當らず、(美[ミ] の辭ノ例、總論に云るを照シ見べし、)若シは之は、乎ノ字を寫誤れるにはあらざるか、又は見は借リ字にて、早水[ハヤミ] の意にてもあらむか、また類聚抄には見ノ字なし、これによらば、ハヤクと訓べし、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「ユクセノハヤミ」 形容詞の語幹に「み」のついた用例は「心を痛み」 (1・5)、「都を遠み」 (1・51) の如く、上に「を」の助詞を用ゐる例であるのに、ここには「の」とあるので誤字説なども行はれてゐるが、「波祢蘰 今為妹之 浦若見 (ハネカヅラ イマスルイモガ ウラワカミ)」 (11・2627) の例もあり、「山高み」 (3・324、その他) の例もあり、必ずしも「を」の助詞を用ゐるに限らないから、誤字とすべきではない。この「早み」を体言とする説(講義、その他) もあり、それも一つの解釈であるが、右の「妹がうら若み」や「山高み」はそれでは解釈出来ないのであり、「心を痛み」の如きは「を」の助詞を用ゐるべき事が今も認められるが、その條でも述べておいたやうに、次第に「を」の意義が忘れられ、右にあげた例のように「を」を用ゐなかつたり「の」「が」が用ゐられたりするやうになつたと考へられる。ゆく瀬が早くありて、の意である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「ユクセノハヤミ」 「逝」は万象名義に「視制反往・去・行・乃」とあり、「ユク」と訓む。論語の「逝者如斯夫」(ゆくものはかくのごときかな) を思わせる用字。「ユクセノハヤミ」は「ユクセヲハヤミ」と同義とする注釈書もあり、それらによれば「はねかづら今する妹がうら若み」(11・2627) などと同じく、流れてゆく瀬が早いので、の意になる (講義・注釈など)。しかし、それでは次の句との関係もしっくりせず、一首を譬喩として「吉野川の流れる瀬が早くて、暫く淀む事がないやうに」 (注釈) と解するにしても、譬喩であることが歌詞から察せられないだろう。「早み」を名詞とみて、上二句を比喩的な序詞と解する方が正しいのではあるまいか (古典大系・古典全集・古典集成など)。後者によれば、「ユクセノハヤミ」は、流れの早い所をあらわす。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「逝瀬之早見」(ゆくせのはやみ) 早ミはミ語法で名詞となった語。速い所の意。→ 73 (早み浜風)。淀むことのないものの比喩。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 【脚注】「逝瀬之早見」(ゆくせのはやみ) 第二句の「早み」は、流れの早い所の意。「泊瀬川早み(速見)早瀬をむすび上げて飽かずや妹と問ひし君はも」(2706) の「早み」も同じ。「藤の繁み」 (4207) の「繁み」も同様。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「須臾毛」訓 | 古義 | 須臾毛は、シマシクモと訓べし、十五に、思未志久母見禰婆古非思吉[シマシクモミネバコヒシキ]、又、之末恩久母伊母我目可禮弖安禮乎良米也母[シマシクモイモガメカレテアレヲラメヤモ] などあり又シマラクモとも訓べし、十四に、思麻良久波禰都追母安良牟乎[シマラクハネツヽモアラムヲ]、(志婆之[シバシ]、志婆良久[シバラク] など云フは、後ノ世なり、) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 須臾毛[シマシクモ] ――シバラクモ・シマラクモの訓もあるが、シマシクモがよからう。之麻思久母比等利安里宇流[シマシクモヒトリアリウル] (三六〇一)・思末志久母見禰婆古非思吉[シマシクモミネバコヒシキ](三六三四)などの例がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「須臾毛」(シマシクモ) 原文「須臾」は「思末志久母 見祢婆古非思吉 (シマシクモ ミネバコヒシキ)」 (15・3634)、「安比太之麻思於家 (アヒダシマシオケ)」 (15・3785) などの例により「シマシク」と訓む。「思麻良久波 祢都追母安良牟乎 (シマラクハ ネツツモアラムヲ)」 (14・3471) の例により、「シマラク」とも訓めるが、それは東歌の一例のみであるから、用例の多いに従ふ。「シバラク」の語例はない。意は須臾の文字の如く、暫くの義。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「須臾毛」(シマシクモ) 「シマシク」は「思末志久」(15・3634)、「之麻思久」 (15・3601) など仮名書きが見え、「之末時 (シマシ)」 (19・4206) の形もある。「人事 蹔吾妹」 (11・2438) は、「ヒトゴトハ シマシソワギモ」と訓むのであろう。「須臾」は玉篇佚文に「俄頃也」と見える。「俄頃」は、瞬時をあらわす語。集内では、「須臾者勿散乱曽」 (137)、「須臾者有待」 (10・2088) のように、「シマシク・シマシ」に宛てられている。「シマシク」は副詞。「シバラク」は奈良時代には見られず、平安朝以後の語形と推測されている (時代別)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 【脚注】 しましくの原文「須臾」は漢語。「しまし」と訓むべき「須臾」 → 667・753・2088.第二句の「早み」は、流れの早い所の意。「泊瀬川早み(速見)早瀬をむすび上げて飽かずや妹と問ひし君はも」(2706) の「早み」も同じ。「藤の繁み」 (4207) の「繁み」も同様。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「不通」訓 | 代匠記 | 不通をタユルとよめるは義訓なり、今按、末に至て不行とも不逝とも書て、ヨトムとよめれば、今もヨトムとも和すべきか、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 不通事無[ヨドムコトナク] は、凝滯[トヾコホ] る事なくと云むが如し、余藤牟[ヨドム] は、水の淀むをいふが本にて、何にても物の滯るを云、不通とかきて、余藤牟[ヨドム] と訓べき處は、集中に甚多し、不行[ヨドム] 、不逝[ヨドム] なども見えたり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「不通事無」(ヨドムコトナク) 旧訓にタユルコトナクとあつたが、代匠記に「ヨドムトモ和スベキカ」とあるやうに、「奈奈勢能與騰波 與等武等毛 (ナナセノヨドハ ヨドムトモ)」 (5・860) と「河余杼能 不通牟心 (カハヨドノ ヨドマムココロ)」 (12・3019) とを照合し、今の場合も上の「早み」をうけてヨドムと訓むべきである。停滞することなく、の意。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「不通事無」(ヨドムコトナク) 原文「不通」を「ヨドム」と訓む。巻第十二の「あらひきぬ取替河の河余杼不通牟心思ひかねつも」(12・3019) は、同音反復の序歌と思われ、第四句は「ヨドマムココロ」と訓むものと推定される。また、 湊入之 葦別小船 障多 今来吾乎 不通跡念莫 港入りの葦別け小舟障り多み今来む我れを不通と思ふな(12・2998) 慇懃 憶吾妹乎 人言之 繁尓因而 不通比日可聞 ねもころに思ふ我妹を人言の繁きによりて淀むころかも(12・3109) などの「不通」も「ヨドム」であろう。流れる水の停滞する意から、男女の仲のとどこおる状態を「ヨドム」と言ったものと思われる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 120 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉集の「はぎ」表記 | 注釈 | 【訓釈】「秋芽之」(アキハギノ) 萬葉にはまだ「萩」の文字が見えず、「萩」に相当する文字として「芽」又は「芽子」の字が用ゐられている。新撰萬葉集にも「芽」とある。倭名抄 (十) には鹿鳴草の文字で掲げられてゐる。「萩」の文字は「秋の草」の意で、「椿」 (1・54) の場合同様、漢字としての「萩」とは別の国字と見るべきものである。漢字の萩は説文 (一) に「蕭也」とあつて「よもぎ」の類である。新撰字鏡 (七) に萩の字をあげて「蒿蕭類也、波支(ハキ)又伊良(イラ)」とあるは、昌泰、延喜の頃、既に「はぎ」に萩の字を用ゐた事が知られると共に、なほ漢字との混同があつて、用字の整理がなされてゐず、その後も「鹿鳴草」とも書かれてをり、それ以前は芽子又は芽と書かれてゐたものと思はれる。倭名抄には萬葉集などに「□」(ほとんど「芽」字だが、下のオの部分が、寸のようになっている。上掲写真) とかかれてゐたやうに記され、類聚名義抄(儈、上) にも「□」(同上) に「ハギ」の訓が見え、「□」(同上) の文字についての探求などもなされてゐるが、現存萬葉集について見るに、紀州本には「□」(同上) の字が用ゐられてゐるが、金澤本、元暦校本、類聚古集、藍紙本 (9・1790)、天治本 (13・3324)、などいづれも「芽」 とあるので、「□」(同上) は「芽」より転じたもので「□」(同上) の字についての探求はこの場合無用だと思はれる。「芽子」の文字については『動植正名』に、本草綱目 (十七) に狼牙の一名を「牙子」とし、保昇の注に「苗似二蛇苺一而厚大」とある (正名には苗を葉に改む) に注意し、「はぎも亦一葉三片なる、狼牙蛇苺と異なるなし。故に古へ牙子字を、はぎに仮用たるならむ。牙芽相通ずるをもて、更に牙を改め、芽に作れるものか。」と云つてゐる。郭公を霍公鳥としてほととぎすに用ゐたやうに、牙子を芽子として「はぎ」に用ゐたものと思はれる。萩は集中にその名の詠み入れられた作百四十一首、植物名中最も多く用ゐられている。ここにはじめて見え、第二期の作には少なく、奈良朝に入つての作が多い。花の時期により、「秋萩」とあるものが多く、七十八例を数える。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「秋芽之」(アキハギノ) 「秋萩の」-万葉集では「ハギ」を表わすのに「芽」、「芽子」の字を用いている。「芽」は万象名義 (巻四之一) に「語嘉反萌・始・・・」、新撰字鏡に「萌也始也」とあるように植物の萌え出ることをあらわす。「ハギ」は古株から芽を出すからの用字で、「ハギ」の名も生え芽 (キ) の意で、やはり古い株から芽を出すのでこの名がついたものと言われる。「ハギ」の漢名は胡枝花 (松田修『万葉植物新考』)。新撰万葉集に、「白露之、織足芽之下黄葉」 (上巻秋歌) 、「秋芽之、花□(手偏+斥) 介里」(同上、以上原撰本) とも見える。「萩」は、秋の代表的な草花の意で後に使われた文字。新撰字鏡 (巻七) に「七由反・・・波支又伊良」とあるので、平安時代にはすでに用いられていたことがわかる。万葉集に「ハギ」を詠む歌は「141首」に達し、草木類の第一位。巻第八、巻十にとくに多く。時代的には奈良遷都以後の作に多い。「ハギ」は現在は「ヤマハギ」「ミヤギノハギ」「キハギ」「ミヤマハギ」などに分類されているが、古く「ハギ」と呼ばれたのが「ヤマハギ」で、万葉の「ハギ」もそう解して支障ないと言われる (松田前掲書)。高さ二メートル内外の落葉性低木で、秋に紅紫色の花をつける。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 【脚注】「秋芽之」(あきはぎの) 万葉集に萩を詠む歌は百四十一首。その四分の一以上が花の散り過ぎることに言及し、平安朝以後の萩の歌が下葉の紅葉や露を好んで主題とするのとは傾向を異にする。「萩」の字は万葉集にはまだ登場しない。新撰万葉集も「芽」の字である。「白露之織足須芽之下黄葉 (しらつゆのおりたすはぎのしたもみち)」 (上・秋)。「秋芽之花開丹芸里 (あきはぎのはなさきにけり)」 (同上)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「咲」表記 | 注釈 | 【訓釈】「□而散去」(サキテチリヌル) 「□字、上掲の校本萬葉集写真を参照 本文(ニ、咲)」 「咲」の字を「サク」と訓む事は本集にはじまる。古事記には「咲」の字「八百萬神共咲」(神代記) をはじめ六例、いづれも「笑ふ」の意に用ゐられてゐる。干禄字書 (下右写真参照)に「咲」は「笑」通用とあり、龍龕手鑑には「下左写真参照」を俗字とし、「写真参照」を正字として「欣喜也」とある。類聚名義抄 (佛、中) にも「咲笑」を上通下正とし「ワラフ、ヱム」と訓し、「四字変換困難」を俗字としてゐる。即ち「咲」は「笑」の通用文字で「笑ふ」の義であるが、我が国ではこの作の頃から「さく」の意に用ゐたものである。集中では「さく」の意に「開」の字を用ゐた例九十六、「咲」を用ゐたもの七十例で、まだ「開」の方が多い。今の場合は細井本と諸版本とには「咲」とあるが、金澤本、元暦校本等の古写本には「変換困難(下左図俗字の四番目)」とある。しかし他の場合は桂本 (4・675、786)、天治本 (13・3266) なども「咲」とあり、今も元暦校本には「変換困難(下左図俗字の四番目)」の右に朱で「咲」とあるので、原本は「咲」であつたかとも考へられるが、琱玉集 (十四) にも「其妻始□(口偏に哭の上の口二つの代わりに竹冠)」など「□(口偏に哭の上の口二つの代わりに竹冠)」の字が屡見えるので、「俗字四番目」とも「俗字二番目」とも「咲」とも書く事があつたものであらう。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「□而散去」(サキテチリヌル) 「□字、上掲の校本萬葉集写真を参照 本文(ニ、咲)」 「咲・□ (口偏+笑) ・笑」は、『金石異体字典』によれば通用字。また、金澤本・元暦校本などに見える「□ (援の手偏を口偏にする)も類聚名義抄 (仏・中) によると、「笑」の俗字。「咲・□ (援の手偏を口偏にする)」を花のサクに用いた例は、初期万葉歌・人麻呂歌集歌・人麻呂作歌に見えず、すべて「開」と書かれている。また、古事記には「サク」の語はないが、「咲」を「ワラフ」の表記にあてていると見られ、「懐風藻」の釈智蔵の「五言、花鶯を翫す一首」に「含香花笑叢」とあるのも「花叢に笑 (ゑ)まふ」と訓まれる (古典大系本の訓による)。こうした「咲・笑」の用法から、笑を「サク」に宛てる用法を生じていったものと思われる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「花尓有猿尾」訓 | 注釈 | 【訓釈】「花尓有猿尾」(ハナニアラマシヲ) 花であらうものを。「ましを」は既出 (1・67、69)。「猿尾」の文字についても既述 (91)。「ニアラ」は「ナラ」とも訓まれてをり、実際の発音はそれに近いものかと思ふが、例の母音を含む八音として「ニアラ」とする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 121 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 暮去者 塩満来奈武 住吉乃 淺香乃浦爾 玉藻苅手名 (ユフサレハ シホミチキナム スミノエノ アサカノウラニ タマモカリテナ) 【頭書】 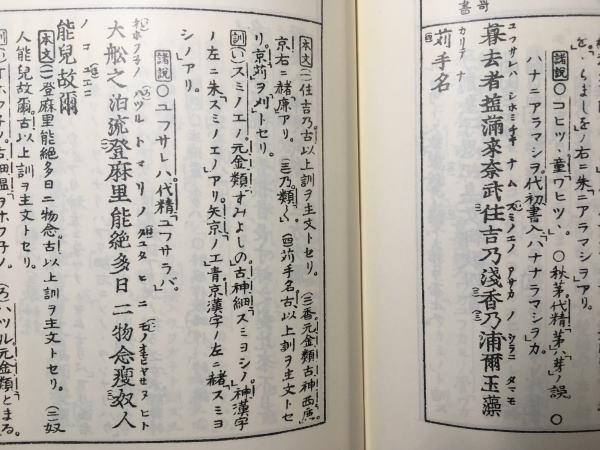 類聚古集、前行ニ「弓削皇子」アリ。 古葉略類聚鈔、前行ニ「弓削皇子思紀皇女御作哥四首中」アリ。主文ヲ訓交リニ書ケリ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「暮去者」訓 | 代匠記 | 暮去者塩滿來奈武住吉乃淺香乃浦爾玉藻苅手名 [ユフサレハシホミチキナムスミノエノアサカノウラニタマモカリテナ] 淺香、[幽齋本、香作レ鹿、] 此發句の心別に注す、今按塩滿來ナムとは、後をかけて云詞なれば、發句をユフサラバと和すべし、此歌は譬喩なり、夕塩の滿來れば玉もの刈られざるごとく、程過なば障出來て逢がたき事もありぬべし、塩干の程に玉藻刈やうに早逢ばやとなり、第六之二十二紙、第七之十四紙に似たる歌あり、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 童蒙抄 | 暮去者鹽滿來奈武住吉乃淺香乃浦爾玉藻苅手名 ゆふされば、しほみちきなん、住のえの、あさかのうらに、たまもかりてな 淺香の浦 攝津國住吉なり。淺香とよめるに意味あり。上にゆふさればとよみたまふ故、下に朝の意をこめて淺香の浦とはよめる也。古詠のおもしろきと云はかやうのところ也。たゞふまへなく淺香の浦をよみ出たるにはあらず |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 暮去者 [ユフサラバ]。鹽滿來奈武 [シホミチキナム]。住吉乃 [スミノエノ]。淺香乃浦爾 [アサカノウラニ]。玉藻苅手名 [タマモカリテナ]。 暮去者 [ユフサラバ] は、暮にならばの意なり、上に委く云り、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「夕さらば」 夕方になつたなら。「さらば」は既出 (1・84)。旧訓「サレバ」であつたが、下に「なむ」とあるから代匠記にサラバと改めたによる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「暮去者 塩満来奈武」(夕さらば潮満ち来なむ) 初句「暮去者」を旧訓に「ユフサレハ」と訓み、童蒙抄などそれによっていたが、代匠記 (精撰本) に「塩満来ナムトハ、後ヲカケテ云詞ナレハ、発句ヲユフサラハト和スヘシ」と改訓した。「夕去らば君にあはむと」 (12・2922)、「暮去らば・・・君をなやませ」 (19・4177) などと同様に「ユフサラバ」と訓む。潮満ち来なむのナムは、ナが完了、ムが推量の助動詞。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類歌について | 注釈 | 【考】 潮の満ちて来ない先に藻を刈らうといふので、女を藻にたとへた譬喩歌である。潮の満ちるは単に何かの支障とも「よする浪音高きかも」 (11・2730) の如き連想による人言の立つに喩へたとも見られよう。 時つ風吹くべくなりぬ香椎潟(かしひがた)潮干の浦に玉藻刈りてな (6・958) 時つ風吹かまく知らに阿胡(あご)の海の朝明(あさけ)の潮に玉藻刈りてな (7・1157) の如き類歌があるが、それには今の如き譬喩の意はない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【類歌について】 代匠記 (精撰本)に「此哥ハ譬喩ナリ。夕塩ノ満来れは、玉モノ刈ラレサルコトク程過ナハ障出来テ、逢カタキ事モ有ヌヘシ。塩干ノ程ニ玉藻刈ヤウニ、早逢ハヤトナリ。」とあるのは、要を得た説明と思われる。ただし、佐佐木評釈・窪田評釈などの指摘するように、題詞を除けば行楽の歌と見られる。類歌の、 時つ風吹くべくなりぬ香椎潟(かしひがた)潮干の浦に玉藻刈りてな (6・九五八) 時つ風吹かまく知らに阿胡(あご)の海の朝明(あさけ)の潮に玉藻刈りてな (7・一一五七) は、どちらも譬喩歌ではない。四首を現在見るように配列したのが編者によるとすれば、もともとは旅の歌であったことも考えられよう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 122 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 大船之 泊流登麻里能 絶多日二 物念痩奴 人能兒故爾 (オホフ子ノ ハツルトマリノ タユタヒニ モノオモヒヤヤせヌ ヒトノコユエニ) 【頭書】 類聚古集、前行ニ「弓削皇子」アリ。 古葉略類聚鈔、主文ヲ訓交リニ書ケリ。前行ニ「弓削皇子思紀皇女御作哥四首中」
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「泊流登麻里能」訓釈 | 代匠記 | 大舩之泊流登麻里能絶多日二物念痩奴人能兒故爾 [オホフネノハツルトマリノタユタヒニモノオモヒヤセヌヒトノコユヱニ] 舟を泊るをハツルと云は古語なり、六帖には、とまるとまりとあれど、集中に類多き古語に付べし |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 大船之 [オホブネノ]。泊流登麻里能 [ハツルトマリノ]。絶多日二 [タユタヒニ]。物念痩奴 [モノモヒヤセヌ]。人能兒故爾 [ヒトノコユヱニ]。 泊流登麻里能 [ハツルトマリノ] とは、船の行キ到 [ツキ] て泊る處を、登麻里 [トマリ] といひて、さてその泊には、浪のゆたゆたと動搖 [タユタ] ふよしにて、絶多日 [タユタヒ] をいはむ料の序とせるなり、泊 [トマリ] は三ノ卷に、六兒乃泊從 [ムコノトマリユ] 、十五に、可良等麻里 [カラトマリ] などあり、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「泊流登麻里能」(ハツルトマリノ) 「泊」は万象名義 (巻五之三) に「菩各反止・船」と見え、玉篇佚文に、「今篇舟上於岸曰泊」ともある。巻十五に「毛母布祢乃 波都流対馬 (モモフネノ ハツルツシマ)」 (3697) の仮名表記も見えるので、「ハツル」と訓む。「流」は語尾の一部を補記したもの。「トマリ」は船着き場。「等万里」(9・1732)、「大御船 泊之登万里」(151) の仮名書きの他、「吾が船泊てむ停知らずも」(7・1224)、「近江の海 泊八十あり」(13・3239)、「吾が船泊てむ留知らずも」(9・1719) のように「停・泊・留」と記された場合もあり、名義抄には、「泊」に「トマリ」の訓を見る。「ハツルトマリノ」の「ノ」は「ニオイテ」の意。以上二句 (オホフネノ ハツルトマリノ)、序詞。次の「タユタヒニ」にかかる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「たゆたひに」語釈 | 代匠記 | タユタヒは末に猶豫不定とかけり、とやせむかくやせむと定得ぬ心なり、大舟に寄て此集に多此詞を云へるは、諺にも事の行かぬるを、大舟こぐやうに喩とて云ごとく、順風などなければ礒へも寄がたく、奥へも出しがたくてもてなやむを、思ひの成がたく、さりとて、え思ひやまずして有程に喩るなり、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 絶多日二 [タユタヒニ] は、物のゆたゆたと動くを、由多布 [ユタフ] とも、由多比 [ユタヒ] とも(布 [フ] 比 [ヒ] は活用、)いふ故、體言に、由多比 [ユタヒ] ともいへり、又それに、多 [タ] の言ををへて、多由多布 [タユタフ]、多由多比 [タユタヒ] と云るなり、さてこゝは、上よりの連は、船の泊 [ハツ] るとまりの、浪のゆたゆたと動く意にて、物念とうけたるは、心 [ムネ] うち動 [サワ] ぐよしなり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「たゆたひに」 「たゆたふ」は「今者不相跡 絶多比奴良思 (イマハアハジト タユタヒヌラシ)」(4・542)、「海原 絶塔浪尓 (ウナバラノ タユタフナミニ)」 (7・1089) の例の如く、動揺すること。「大船 猶預不定見者 (オホフネノ タユタフミレバ)」 (196) の用字例もある。今はその名詞形で、心の動き落ち着かぬ状態で、の意。「ゆたにたゆたに」(7・1352) 参照。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「たゆたひに」 「タユタフ」は「吾が背子が心多由多比(タユタヒ)」 (4・七一三)、「夏草の 思ひ萎えて 夕星の か行きかく行き 大船の 猶預不定(タユタフ)見れば」(一九六) のように、安定しない様子や、決心がつかず躊躇している状態をあらわす。ここでは大船が港でなお動揺してとどまらぬ状態 (古典大系) を、恋のために心の安定しないありさまの譬喩としている。講義に代匠記説を受け、「昔の大船は順風などなくば、沖へも出しがたく、さりとて邊にもよりがたく、波の上にゆらゆらとして、定まらず、しかも出づるにも入るにもとかく手間どるものならばいふ」と説くのは歌の表現から離れ過ぎるようだ。窪田評釈に「大船は小舟と違って、たやすく岸に着けられず、水上に動揺する意」と説いているのも、どうであろうか。「大船の」は「思ひ頼む」の比喩的枕詞として多く用いられているように、本来安定しているはずのものである。しかもそれが港に入っていながら動揺することを表現しているので、思ひもかけぬ恋にとらわれた気持ちを伝えるものとなる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 【脚注】「たゆたひ」 「たゆたひ」は人目を気にして会うことを躊躇逡巡すること。「常やまず通ひし君が使ひ来ず今は逢はじとたゆたひ(絶多比)ぬらし」(542)。もの思いに痩せるという表現は万葉集に数例見えるが、詩にも離居の悲しみに痩せることを言う。「相去ること日々に已に遠く、衣帯日々に已に緩(ゆる)し」 (「古詩十九首」・文選二十九)、「寛帯君を思ふが為なり」 (蕭麒「詠衵複」・玉台新詠十) など。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「物念痩奴」訓釈 | 注釈 | 【訓釈】「物念痩奴」(モノモヒヤセヌ) 物思ひをしてやせた、の意。「もの」と「思ふ」と直接つづいた場合は「妻戀尓(ツマゴヒニ) 物念人(モノオモフヒト)」 (10・2089)、「如吾(ワガゴトク) 物念可毛(モノオモヘカモ)」 (10・2137) の二例以外は「物念者(モノモヘバ)」(3・333)、「物念跡(モノモフト)」(4・613)、「物念時尓(モノモフトキニ)」(8・1579)、「客尓物念(タビニモノモヒ)」(10・2163) など「念」を「オモフ(ヒ)」と訓むと字余りになる場合にのみ用ゐられてゐる。字余りになつても「オ」の単独母音節であるから不都合はないわけではあるが、「オ」を省略すればいづれも五音七音になる場合に用ゐられてをり、仮名書例は「毛能毛布等(モノモフト)」(15・3708)、「母能毛波受(モノモハズ)」(15・3760)、「毛能毛布等伎尓(モノモフトキニ)」(15・3780)、「物能毛比豆都母(モノモヒヅツモ)」(14・3443)、「毛乃母比毛世受(モノモヒモセズ)」(20・4425) などすべて「モノモフ(ヒ)」のみである事を見ると「もの」と直接つづく場合は「オ」が省略されるのが通例になつてゐたものと思はれる。殊に今の場合は「妹尓不相而(イモニアハズシテ)」(125) の條で述べるやうに、第四句である点から云つても七音句が適当なのである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「ひとのこゆゑに」語釈 | 代匠記 | 人ノ子とは、親の手に有をも人妻をもいへど、今歌にては、廣く我手に入らぬ人と心得べきか、異母の御妹を指てのたまへばなり、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 人能兒故爾 [ヒトノコユヱニ] は、人の兒なるものをの意なり、俗に、人の兒ぢやに、といはむがごとし、人能兒 [ヒトノコ] は、多く他妻をいへり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「人の子故に」 「人の子」を「人妻」と同じと見る説と「子」は愛称で単に「人」といふくらゐの意と見る説とある。 比登乃兒乃(ヒトノコノ)かなしけしだは浜洲鳥あなゆむ駒の惜しけくもなし (14・3533) の如きは後者の説によるべきやうにも思はれるが、 あしひきの山川水の音に出でず人之子姤(ヒトノコユヱニ)恋ひわたるかも (12・3017) 小竹(しの)の上に来居て鳴く鳥目をやすみ人妻姤尓(ヒトツマユヱニ)われ恋ひにけり (12・3093) をくらべると、「人の子」と「人妻」とは殆ど同じ意に用ゐられてゐるやうに見える。しかも一方、 息(いき)の緒(を)にわが息づきし妹すらを人妻なりと聞けば悲しも (12・3115) 人妻とあぜかそを云はむしからばか隣の衣(きぬ)を借りて着なはも (14・3472) あずの上に駒を繋ぎてあやほかど人妻子ろを息にわがする (14・3539) の如きは「人妻」といふ意識が実にはつきりと出てゐて作者のこの語を用ゐた所以がうなづけるのであるが、人の子の方にはさういふところがない。実質に於いては人妻と認めてさしつかへないと思はれるが、作者がはつきり人妻と云はずに人の子と云つたところに「語の選択」が行はれてゐるやうに見える。その作者の用語の精神を尊重すべきだと思ふ。今の場合も同様である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「人の子故に」 「ヒトノコ」を「人妻」とする説もあるが (古義)、代匠記に「広ク我手ニ入ラヌ人ト心得ヘキカ」、万葉考に「まだ得ぬほどなれば他の児といふべし」と記すのが正しいだろう。巻十八の家持作歌には、「人の子は 祖の名絶たず 大君に まつろふものと」 (4094) のように、人妻とまったく関わりない例を見る。澤瀉注釈に指摘するように、 あしひきの山川水の音に出でず人之子姤(ヒトノコユヱニ)恋ひわたるかも (12・3017) 小竹(しの)の上に来居て鳴く鳥目をやすみ人妻姤尓(ヒトツマユヱニ)われ恋ひにけり (12・3093) などを見ると、「人の子」と「人妻」とは殆ど同じ意味に用いられるように思われるが、 息(いき)の緒(を)にわが息づきし妹すらを人妻なりと聞けば悲しも (12・3115) 人妻とあぜかそを云はむしからばか隣の衣(きぬ)を借りて着なはも (14・3472) などには人妻という意識がはっきり出ている。「人の子」の場合も実質的に人妻と認めてさしつかえないと思われるが、作者が「人の子」と言ったところに意義を認めるべきであろうと言う。まだ自分の手に入らない状態を、人のものである、つまり「人の子」と言ったのではあるまいか。「ユヱニ」は、そのためにの意。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「人の児故に」 人ノ児は他人の妻だとか親がかりの身とかをいう。ここは紀皇女をさす。巻第三の挽歌425の左注に、この歌が紀皇女の薨後山前(やまさきの)王が石田(いはた)王に代わって詠んだものであることを記す。これによれば紀皇女は石田王の妻などであったのでないか。この当時紀皇女は少女で、生母蘇我大蕤娘(そがのおおぬのおとめ)の膝下にあったので、親の監視厳しい娘と解すべきかとする説もある。ユヱニ → 21「人妻故に」。ここも逆説的な用法になりかけている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考「古義の歌意解釈」 | 古義 | 御歌ノ意は、他妻なれば、いかに思ふとも益なきものを、なほ得堪ずして、むねうちさわぎつゝ、戀しく思ふものおもひに、このごろは、身もおとろへ痩ぬるよとなり、さてこの一首によれば、紀ノ皇女は、既く人に娶 [エラ] れ賜ひしを、弓削ノ皇子の、思 [ノ] ばしゝにや、(三ノ卷にて見れば、紀ノ皇女は、石田ノ王に嫁賜ひしか、詳には知がたし、さらば右の、暮去者 [ユフサラバ] 云々の御歌を贈リたまひしとは、別時にて、後に作ませるかとも思はるれども、すべて古ヘ、他妻 [ヒトツマ] 人之兒 [ヒトノコ] など云るは、打はれて、他妻とさだまれるに、かぎりたることにはあらで、他人に心かよはすごときをも、なべて云ることなれば、此もまことに、皇女の他妻と、さだまれるを、のたまへるにはあらで、此方にうときは、他人に、心かよはし給ふ故ならむ、さる他人の妻なるものを、とわざとのたまひて、皇女を切 [セマ] らせて、さて裏 [シタ] には、はやく我カ方に、なびき賜はむことを、おもほせるにもあるべし、) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 123 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 【題詞】 三方沙爾娶園臣生羽之女未經幾時□(原文目偏+卜)病作歌三首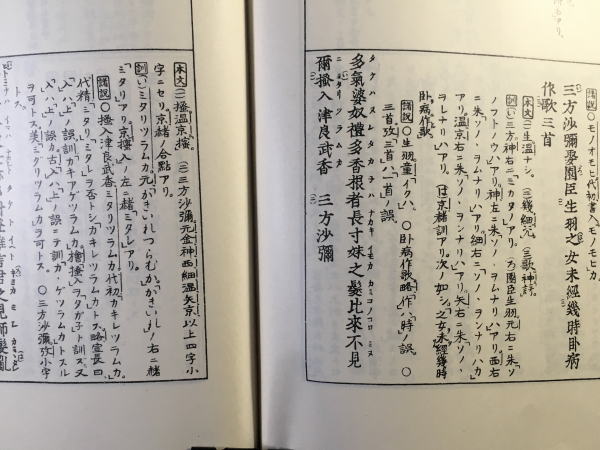 〔本文〕多氣婆奴禮 多香根者長寸 妹之髪 此来不見爾 掻入津良武香 [三方沙爾] (タケハヌレ タカ子ハナカキ イモカカミ コノコロミヌニ ミタリツラムカ) 〔頭書〕元暦校本、朱頭書「所名」アリ。 西本願寺本・神田本・温故堂本・京都大学本、肩ニ朱「所名」アリ。 細井本、肩ニ「所名」アリ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「三方沙弥と園臣生羽」考 | 全注 | 題詞訓 三方沙弥(みかたのさみ)、園臣生羽(そののおみいくは)の女(むすめ)を娶(ま)きて、未だいくばくの時も経ず、病に臥して作る歌三首 〔三方沙弥〕 伝未詳。攷證に「三方は名、沙爾は僧なりしほどの官也。姓氏録、その外の書にも三方といふ氏の見えざるにても三方は氏ならざるをしるべし。又沙爾満誓を四四十一丁に満誓とかけるにても三方は名ある事明けし」と言い、三方を氏でなく名としたが、山田講義にこれを否定し、「満誓沙弥は満誓は俗名にあらねば、これを沙弥の上に冠するは然るべき事にして後までも屡見る所なり。然れども三方の如き俗名をその上に冠せる例を知らず。又笠沙弥の如く氏を上にせるは例稀ならず。これらによらば、三方は氏なるべく考へられる」と記す。真淵の万葉考には、三方を氏、沙弥を常人の名としたが、講義に言うように、ここは普通の沙弥、つまり十戒を受けて未だ修行熟せず、比丘となるまでの男子を指した称と見るべきであろう。攷證のように、僧の官とするのは理由のないことと言わねばならない。続日本紀延暦三年正月に従五位下を授けられた三方宿禰広名の例があり、また続紀天平十九年十月に春宮少属御方大野の例もある。だから講義や注釈の言う通り、三方氏の男子で沙弥であったものと解すべきだと思われる。ただし具体的に誰を指すかは未詳。 〔園臣生羽〕 伝未詳。園臣は、応神紀二十二年九月の条に「以二苑縣一封二兄浦凝別一。是苑臣之始祖也」とある「苑臣」と同氏であろう。「生羽」は童蒙抄に「イクハ」と読んだのが正しいか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「たけば」語釈 | 注釈 | 【訓釈】「多氣婆」(たけば) 「たく」は「小放尓(ヲハナリニ) 髪多久麻庭尓(カミタクマデニ)」 (9・1809)、「振別之(フリワケノ) 髪乎短弥(カミヲミジカミ) 青草(アヲクサヲ) 髪尓多久濫(カミニタクラム)」 (11・2540)、「未通女等之(ヲトメラガ) 織機上乎(オルハタノウヘヲ) 真櫛用(マクシモチ) 掻上栲嶋(カカゲタクシマ)」(7・1233) などと用ゐられ、取上げ束ねる意と思はれ、次の句に「多香根者(タカネバ)」とあつて、「たけ」は四段活用の已然形である事が知られる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「多氣婆」(たけば) 「たく」は「小放りに 髪多久までに」 (9・1809) とも歌われるように、髪などを束ね結うこと。「振分けの髪を短かみ青草を髪に多久らむ」 (11・2540) の例もある。当時女性の髪は、童女期には現在のおかっぱのようにしていたが、やや長ずると、放り髪と言って、後方へ垂らした。さらに婚期に達すると、髪を上げて結ったのであり、女の成年のしるしであった。伊勢物語に「くらべこし振分け髪も肩すぎぬ君ならずして誰かあぐべき」の歌が見える。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「此来」訓釈 | 注釈 | 【訓釈】「比来」(このころ) 「このころ」の用字として「比日」(二十例)、「比来」(十一例)、「頃者」(八例)、「比者」(六例)、「日来」(10・2175) などの文字が見える。今の原文「比来」も当時の支那の俗語と思はれる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「比来」(このころ) 「比来」は、霊異記上巻第四話に訓註の見える「比頃 (コ) 乃 (コ) 呂」と同じく、「コノコロ」と訓む。巻第三に「間なく比来大和し思ほゆ」(359) ともある。王羲之の『東書堂帖』に「比来遅々、終不可也」など見えるように法帖類に多い表現で、万葉人も恐らく王羲之などの法帖によったのではないかと言われる (小島憲之『上代日本文学と中国文学』中巻八百三十四頁)。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「比来」(このころ) 原文「比来」は漢籍の俗語的用法。「比」「比日」などに同じ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 【脚注】「比来」(このころ) 「このころ」の原文「比来」は漢語。「比来天下奢靡し、転た相ひ倣効す」 (三国志・魏・徐邈伝)。→ 359・767・1011題詞など。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「掻入」訓釈 | 代匠記 | 多氣婆奴禮多香根者長寸妹之髪比來不見爾掻入津良武香 [タケハヌレタカネハナカキイモカカミコノコロミヌニミタリツラムカ] 三方沙彌 掻入を今はミダリと点じ、六帖には、みだれとあり、今按ことはりは明なれど、しかよむべきやう心得がたし、カキレと讀て、かきいれと心うべきか、入は収る義なれば掻上て結なり、第二十に、あしびの花を袖にこきれなと讀るは、袖にこき入むななり、其外コキレとあまたよめり、此に准ずべし、本点によらば、我煩て久しく相見ぬ程打嘆て髪をさへあげずして、亂てか有らむとなり、今按の意は、結も物うく長きも煩らはしければ、纔にそゝげたる髪を掻入れてや有らむなり、女は髪を先とするものなれば、髪を云に、かたちつくり皆籠れり、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 多氣婆奴禮 [タケバヌレ]。多香根者長寸 [タカネバナガキ]。妹之髪 [イモガカミ]。比來不見爾 [コノゴロミヌニ]。掻入津良武香 [カカゲツラムカ]。三方沙彌 [ミカタノサミ]。 掻入津良武香、(掻ノ字、古寫本に、□ [手偏+蜜] とかけるは、いかゞ、)入は上ノ字の誤にて、カヽゲツラムカなるべし、と本居氏云り、信に然り、十六に、橘寺之長屋爾吾率宿之 [タチバナノテラノナカヤニアガヰネシ]、童女波奈理波髪上都良武可 [ウナヰハナリハカミアゲツラムカ] となり、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「掻入」(カキレ) 「掻入」の二字を元暦校本に「カキイレ」と訓んでゐるが、右に赭で「ミタリ」とし、金澤本その他の諸本はいづれも「ミタリ」とある。古今六帖に収めたものには「ミタレ」とある。代匠記には「今按カキレト読ベキカ」として、「カキイレ」を略して「カキレ」といふは、「袖尓古伎礼都(ソデニコキレツ)」(19・4192) などの「コキレ」が「コキイレ」の略であると同様として、「ソソケタル髪ヲ掻入レテヤ有ラム」と解してゐる。宣長は「入」を「上」の誤として、「カキアゲ」と訓み、古義にはそれにより「カカゲ」と訓み、その他諸説が出てゐるが、旧訓に「ミタリ」とあり、次の意に「乱有」とあるにより、「ミタリ」又は「ミタレ」と訓む説としては、美夫君志に「掻は騒の通用の字にて、ミダルとも訓べき文字なり、呉志の陸凱伝に、所在掻擾更(ニ)為二煩苛一とある掻は、すなはち騒(ノ)字の意にて用ゐたるなり、韻會に、騒俗作レ掻とある是なり、玄応音義巻十三賢愚経第九巻に、騒騒、経文従レ手作レ掻とあるも、二字通用なるが故なり、又廣雅釈詁にも説文にも騒(ハ)掻也とあれば、ミダリと訓べき文字なること、もとよりなり」とし「乱る」の四段活用であつた事を主張されてゐる。「入」を「リ」の仮字とした例として「五百入(イホリ)」(7・1238)、「登能雲入(トノグモリ)」(12・3012) があげられてゐる。講義にも同様の説が述べられ、「入」の字が「レ」の仮名には用ゐられない事は武田博士も「用言の後部を音声とする萬葉仮字」(アララギ 第三十巻第二号、昭和十二年二月) で述べられてをり、もし「掻」を騒の通用として「ミダリ」と訓むならば「乱る」は四段活用といふ事になる。しかし、「乱る」の語はもとは四段であつたとしても、当時は既に下二段に転じてゐたと思はれ (133参照)、その点既に従ひがたく、また「掻」の字は集中の用例約二十、いづれも「掻く」の意に用ゐられて「騒」と通用のもの他になく、別に騒の文字はあるが、これも「サワク」であつて「ミダル」の例がない。一方「掻」は「掻撫 (カキナデ)」(6・973) の例もあり、右に引用したやうに「掻上(カカゲ)」の例もある。かう考えると結局代匠記の説にかへるべきである。即ち乱れ下る髪を掻き上げ束ね入れてつくろつてゐるであらうか、の意。代匠記に従ひ「コキレ」の例により「カキレ」と訓んだが、イの母音をそのままに八音と見るもよいであらう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「掻入津」(かきれつ) 「カキレツ」は「カキイレツ」の約。「掻入」の二字を、古写本に「ミタリ(レ)」と訓んだのを代匠記に「六帖ニハ、ミタレトアリ。今按コトワリハ明ナレト、シカヨムヘキヤウ意得カタシ。・・・今按カキレト読ヘキカ。カキイレヲ略シテカキレトヨムヘキ故ハ、第二十二、アシヒノ花ヲ袖ニコキレナト読ルハ袖ニコキ入ムナナリ。其外コキレトアマタヨメリ」(精撰本) と訂したのによるべきだろう。「掻」の字は集中二十例、いずれも「掻く」の意に用いられている (注釈)。「カキレツは乱れほつれている髪を、櫛をもって掻き入れておさめ」(全註釈)たのを言うのであろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「かきいれ」考 | 全注 |
【考】「掻きれつらむか」 結婚後、間もなく男が病臥して通えなくなったときの歌である。新妻は、放り髪のまま結婚したものと思われる。その髪上げをするのは、夫の役目であったらしい (講義)。ところが、男が病臥したために、長い髪はそのままになってしまった。あるいは、窪田評釈に言うように、三方沙弥も髪上げを試みたのかもしれない。妻が幼くて、それをするだけに髪が伸び切っていなかったために、十分にはできなかったのであろう。「タケバヌレタカネバナガキイモガカミ」は、そのように放り髪としては長すぎ、と言って、束ねるには短すぎる状態を歌ったものか。十分に髪上げをすることができなかったために、結婚前と変わらず、束ね髪に整えられていないのを気がかりに思っての作である。結句の「掻きれつらむか」は、ほつれ乱れた髪を掻き上げ整えただろうかと、その整えた状態を願ってのことと解されるが (佐佐木評釈・古典大系・全註釈・注釈など)、これを「わが物との標を結いきれず」に、「妙齢な、まだ夫のいない女という状態が、人の目に立つ者となったろうかというので、思慕というよりは、それを内にこめた、不安の情の方を主としての語」 (窪田評釈) とするものもある。そこまで言い切れるかどうか、問題である。また、当時、夫が幼な妻の髪上げをする風習や、再び逢うまでは髪型を改めない風習などがあって、「相手が人妻になったことを懸念したものか」 (古典集成) とする説も見え、講談社文庫にも、「もう誰かがかき入れて束ねてしまったろうか」とあって注目される。伊勢物語の二十三段に、「くらべこし振分け髪も肩すぎぬ君ならずして誰かあぐべき」とあり、髪を「あげる」ことが、人の妻となることと同義に表現されているので、古典集成のような考えも出されるわけであるが、伊勢物語の場合は「君ならずして誰かあぐべき」とあって、その意味は明瞭であるのに対し、三方沙弥の「このころ見ぬに掻きれつらむか」は、そこまで含意したものと思われぬふしも見える。「掻きれ」は「髪あげ」、「かかげ」などとは異なるのであって、とくに「掻きれ」と詠まれているのは、乱れた髪を櫛で整えているだろうか、と言いたいためで、自分以外の男性によって髪上げが行われたのではないかという不安を表に出して歌っているわけではないと思われる。そう考えると、次の娘子の返歌がよく理解されるはずである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 124 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 人皆者 今波長跡 多計登雖言 君之見師髪 乱有等母 [娘子] (ヒトミナハ イマハナカシト タケトイヘト キミカミシカミ ミタレタレトモ) 【頭書】 金澤本、コノ歌ノ訓「キミカミシカミ」以下缼ケテ存セズ。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「人皆者」訓考 | 童蒙抄 | 人皆者今波長跡多計登雖言君之見師髪亂有等母 娘子 ひとみなは、今はながしと、たけといへど、きみかみしかみ、みだれたりとも 娘子 印本には此二字を脱せり。古本には注せり 人皆者 奧に至つてかながきにもひとみなはとかきたれは、義訓にはあるべからず。意はみな人はと云義也。しかるを上古は如レ此人みなはとよめること古風の一躰なり |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「人皆者」(ヒトミナハ) 原文「人皆者」が、元暦校本と紀州本とには「人者皆」とある為に「ヒトハミナ」と訓む説もあるが、「人は皆」と「人」と「皆」との間に助詞を入れるのは平安朝以後の作に見るところで、それによって音調をなめらかにやはらかくしたものであるが、萬葉では「人皆者」(10・2110)、「比等未奈能」(5・862) などの如く「人皆」とつづけて「は」「の」の助詞を下へつづける例となつてゐる。流布本に「人乃皆」(9・1738) とある一例があるが、それも藍紙本その他の古写本には「人皆乃」とあつて、それが古い形を伝へるものと見るべきであり、今の場合も金澤本その他には「人皆者」とありながら、その金澤本に訓は「ヒトハミナ」とある事は、筆写の時代の影響を示すもので、さうした訓がもととなつて、元暦校本・紀州本の如き本文も生じたと見るべきである (8・1418、10・1917参照)。意味は「人は皆」といふのと同じと見ればよい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「人皆者」(ヒトミナハ) 原文、金澤本・西本願寺本など「人皆者」であるが、元暦校本・紀州本に「人者皆」とある。古典大系・全註釈は、それによって「ヒトハミナ」と訓む。集内の「ヒトミナ」の例は、「人皆か 吾のみやしかる」(5・892)、「人皆知りぬ」(11・2468、2480)、「人皆の」(5・862、6・928、9・1738、12・2843、3064) などあり、また、巻第十に、 人皆は萩を秋と言ふよし我れは尾花が末を秋とは言はむ (2110) の例も見えて、「ヒトミナハ」の方が正しいのではないかと思われる。童蒙抄に「ヒトミナハ」を「古風の一躰」と言う。澤瀉注釈に、「ヒト」と「ミナ」の間に、助詞を入れて「ヒトハミナ」と言うようになったのは平安時代以後のことで、「音調をなめらかにやはらかくしたものである」と記す源氏物語に、 人は皆花にこころをうつすらむ独りぞ惑ふ春の夜のやみ (竹河) 人は皆いそぎ立つめる袖の浦にひとり藻塩をたるる海人かな (早蕨) とあるし、更級日記にも、 人は皆春にこころを寄せつめりわれのみや見む秋の夜の月 と見える。金澤本・元暦校本・紀州本の「ヒトハミナ」の付訓は、こうした後代の表現の影響を受けており、また、その付訓がもとになって、元暦校本・紀州本のような本文を生じたのであろうという注釈の推定に同意される。また、集内の「人皆」と「皆人」について、前者が不特定多数の人を指すのに対し、後者は、限定された特定範囲の人を指すことばであったろうとする伊藤博の指摘も注目される (「釈万葉」『万葉集研究』第五集)。ここも、、特定の場に集った人を指すわけではない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大系(岩波) | 【訓及び大意】 人者皆 今波長跡 多計登雖言 君之見師髪 乱有等母 娘子 ひとはみな いまはながしと たけといへど きみがみしかみ みだれたりとも 人は皆、今はもう長くなった、掻き上げなさいと言いますが、あなたの御覧になった髪ですもの、(乱れてはいますが) たとえ乱れていても (そのままにしてあります)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系(岩波) | 【訓及び歌意】 人皆者 今波長跡 多計登雖言 君之見師髪 乱有等母 娘子 ひとみなは いまはながしと たけといへど きみがみしかみ みだれたりとも 人は皆、もう長くなったと言い、結上げなさいと言いますが、あなたが御覧になった髪は乱れていてもいいのです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「今波長跡と多計登」釈 | 古義 | 人皆者 [ヒトミナハ]。今波長跡 [イマハナガミト]。多計登雖言 [タケトイヘド]。君之見師髪 [キミガミシカミ]。亂有等母 [ミダリタリトモ]。 娘子 [イラツメ]。 ○今波長跡は、イマハナガミトと訓べし、(ナガシと訓 [ヨメ] るは非なり、)長 [ナガミ] は、俗に、長さにと云むが如し、跡 [ト] は、助辭なり、凡て恐美等 [カシコミト] 、賢美等 [サカシミト] 、難美等 [カタミト] 、無美等 [ナミト] 、忌々美等 [ユヽシミト] 、怪美等 [アヤシミト] 、歡美等 [ウレシミト] 、繁美等 [シゲミト] 、深美等 [フカミト] 、多美等 [オホミト] 、廣美等 [ヒロミト] 、乏美等 [トモシミト] など、美 [ミ] の辭の下にある等 [ト] は、皆助辭の例なり三ノ卷に、雖戀效矣無跡辭不問物爾者在跡 [コフレドモシルシヲナミトコトヽハヌモノニハアレド] とあるを、十三に、雖思印乎無見 [オモヘドモシルシヲナミ] 云々言不問木雖在 [コトトハヌキニハアレドモ] とあると、全同趣なるにて、跡 [ト] の助辭に、ことに意なく、あるもなきも、大かた異なることなきを知べし、されど語ノ勢を、助けたもつ爲には、此 [コゝ] のごとく、この助辭なくて叶はぬことなり、(たゞいたづらのものとのみは、思ふべからず、) なほ委きことは、總論に云り、披キ見て知ルべし、 ○多計登雖言 [タケトイヘド] は、今は髪の餘りに長きに過たる故に、總 [タゲ] よと人皆は云ヘどもなり、さて古ヘの女は、十四五歳と成ルまでは、髪を垂てあるを、童放 [ウナイハナリ] とも、童兒 [ウナヰコ] ともいふを、十四五歳の頃より後には、髪いと長く成レる故、男して髪を總揚 [タキアグ] るを、髪揚 [カミアゲ] といへり、 る。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「波長跡 多計登雖言」(いまはながしと たけといへど) 「今は長し」といひ、「たけ」といふけれど、の意。「と」を二つ重ねる例に「世間乎 宇之等夜佐之等 於母倍杼母 (ヨノナカヲ ウシトヤサシト オモヘドモ)」 (5・893)、「家ゆ出でて 三年の程に 垣もなく 家滅目八跡(イヘウセメヤト) この箱を 開きて見てば もとのごと 家者将有登(イヘハアラムト) 玉櫛笥 少し開くに」(9・1740) などがある。髪がもうながくななつたと云ひ、また結ひ上げなさいとも云ふけれど、の意である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「今波長跡 多計登雖言」(いまはながしと たけといへど) 「ナガシト」「タケト」と助詞「ト」を重ねた表現は、「世の中を憂しとやさしと思へども」 (5・893) などにも見える。この場合は、初句「ヒトミナハ」を受け、さまざまに言う人の多いことをあらわす効果もある。髪が今は長くなったと言う人もあるし、束ねなさいと言う人もあるけれど、の意。古義に、「イマハナガシト」を非として、「イマハナガミ」と訓んだのは、後句との論理的なつながりを強めたものであるが、「長跡」を「ナガミト」と訓むのは無理である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「きみがみしかみ」考 | 全注 | 【注】「君之見師髪」(きみがみしかみ) かつてあなたの見た髪。三方沙弥の歌に「妹が髪」と歌われているのを受けて、それはあなたの御覧になった髪であると言う。第三句の「~イヘド」との関連で、「君が見し髪ゆゑに」の意味が含まれる。なお古代における「見る」ことの意義については、土橋寛『古代歌謡と儀礼の研究』に詳しい。土橋によれば、「見る」ことは古代においては単なる感覚的行為ではなく、生命や霊魂にかかわる行為であった。花や青葉を見る事によって、花や青葉の生命力はその人に転移されるし、また逆に人から花や青葉へのタマの転移も見る事によって行われた。つまり、見られたものが見た人のタマを宿す形見としても意識されたのである。この歌の「キミガミシカミ」にも、そうした古代的な観念を読み取ることが可能であろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結句原文「乱有等母」訓注 | 全注 | 【注】「乱有等母」(みだれたりとも) 「乱れたりとも」-結句を旧訓に「ミタレタレトモ」としたが、童蒙抄に、「みだれてありとも也。『てあ』の約言なれば、みだれたりともよむべし」と訂正した。それが正しいであろう。「等母」の「ト」は清音。講義に、「ドモ」とよむと、「トモ」とよむとによって、歌意が頗る異なると言う。「ドモ」と訓めば「上の『イヘド』といふ語に勢同じくして文勢収捨すべからざるなり。これは『トモ』といふ仮説条件としていふ語にすべし。この『トモ』は仮説条件を否定して下に接する意なれば、たとひ乱れてありとも君がみし髪なれば、そのさまをかふるに忍びず。そのままにあらむとなり」と説く。詳しい説であるが、「トモ」と訓んでも、確定条件を表わす場合のあることは、「ささなみの志賀の大わだよどむとも昔の人にまたも逢はめやも」(1・31) の例から知られる。古典大系の補注に「31歌」の「ヨドムトモ」について、次のように記しているのを揚げておきたい。 //トモは普通、単純な仮定を表現するとされている。しかし、佐伯梅友博士が、修辞的仮定と名づけられたような一種の用法がある。それは、既定の事実が眼前にあるにも関わらず、それを仮定の事実のようにして表現するものである。この歌でも、志賀の大わだが淀んでいるのは事実である。それをあたかも仮定のようにして、決して昔の人と再会できないということを強調するわけである。この修辞的仮定では、下に反語・推量などが来るのが普通である。// 右の文中に引かれている佐伯梅友博士の説は、『万葉語研究』所収の論文「淀むとも考」に見られる。そこでは、 忍坂の大室屋に人さはに来入り居り人さはに入り居りとも・・・(記) 白玉は人に知らえず知らずともよし知らずとも我れし知れらば知らずともよし(6・1018) などの例をあげ、いずれも前に事実が述べられ、その上で「たとえそうであっても」という気持ちが歌われている。こうした「とも」の用法は、修辞的仮定として理解されるもので、「志賀の大わだ淀むとも」の場合も同様であることが述べられている。佐伯論文に、この「124歌」がとりあげられているわけではないが、この歌の「乱れたりとも」も、修辞的仮定として解されるであろう。「人皆は今は長しとたけと言へど」が、「乱れ」を示唆する表現になっているのである。大系本の「124歌」の頭注には、とくに説明はないが、〔大意〕に、「あなたの御覧になった髪ですもの、(乱れてはいますが) たとい乱れていても (そのままにしてあります) 」と記されており、「トモ」を修辞的仮定として理解したことが知られる。古典全集の頭注に「仮定条件だが、ここは確定的な場合に用いた用法。下に、私は掻き入れたりはしません、の意を含む」あるのも同様である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 125 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 橘之 蔭履路乃 八衢爾 物乎曽念 妹爾不相而 [三方沙彌] (タチハナノ カケフムミナノ ヤチマタニ モノヲソオモフ イモニアハステ) 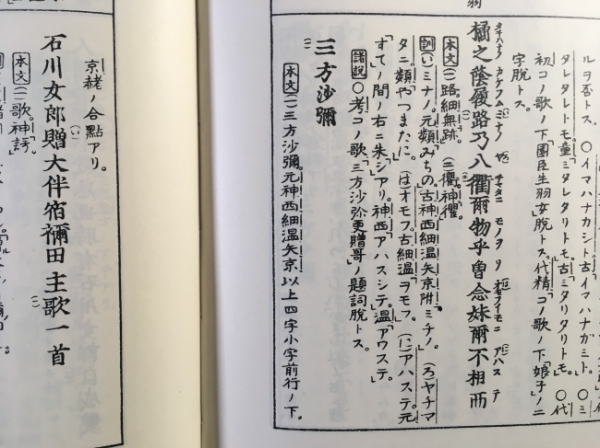 【頭書】 類聚古集、前行ニ「三方沙□(方+尓)」 古葉略類聚鈔、前行ニ「三方沙弥娶園臣生羽之女未絶幾時臥病哥三首中三方□」 〔本文〕 路、細井本・活字無訓本「跡」。 衢、神田本「□(衢の亍なし)」。 〔訓〕 ミナノ、 元暦校本・類聚古集「みちの」。 古葉略類聚鈔・神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・ 京都大学本・活字附訓本「ミチノ」。 ヤチマタニ、 類聚古集「やつまたに」。 オモフ、 古葉略類聚鈔・細井本・温故堂本「ヲモフ」。 アハステ、 元暦校本、「すて」ノ間ニ右ニ朱「シ」アリ。神田本・西本願寺本「アハスシテ」。 温故堂本「アワステ」。 〔諸説〕 万葉考、コノ歌「三方沙弥更贈哥」ノ題詞脱トス。 【三方沙彌】 元暦校本・神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本以上四字小字前行ノ下。 京都大学本赭ノ合點アリ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「たちばなのかげふむみちの」 | 注釈 | 【訓釈】「橘の蔭ふむ路の」(タチバナノ カゲフムミチノ) 橘は垂仁紀九十年の條に「春二月庚子朔。天皇命二田道間守(タジマモリニ)一。遣二常世国(トコヨノクニ)一。令レ求二非時香菓(トキジクノカグノミ)一。〔香菓。此云二箇俱能未一〕 今謂レ橘是也」とある。古事記にはその田道間守が帰つた時には天皇は既に崩御の後であつたので、御陵にその木実を擎げ「常世国之 登岐士玖能迦久能木実(トキジクノカクノコノミ)持チテ参上 (マヰノボリ) 侍リ」と「叫哭死也(オラビシニキ)」とある。倭名抄(九)に「太知波奈(タチハナ)」とある。街路樹として果樹を植ゑられた事は雄略紀十三年に「餌香市辺(エカノイチベノ)橘本」とあり、類聚三代格(七)に載せる天平宝字三年六月の乾政官符に、 應三畿内七道諸国駅路兩邊遍種二菓樹一□ (上に「古」、下に又) 右東大寺普照法師奏壮偁。道路百姓来去不レ絶。樹在二其傍一。足レ息二疲乏一。夏則就レ蔭避レ暑。飢則擿レ子噉レ之。伏願。城外道路兩邊栽二種菓子樹木一者。奉勅。依レ奏。 とあり、また延喜式の雑式にも「凡諸国駅路邊植二菓樹一。令三往還人得二休息一。若無レ水處。量レ便掘レ井」ともあり、本集にも「東の市の植木」 (3・310) ともあるによつて察することが出来る。さうした街路樹となつてゐる橘の木蔭を踏んでゆく道の意で、應神記にも「蒜(ひる)摘みに 我が行く道の かぐはし 花橘は」とある。以上二句は次の八衢の序。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「橘」「蔭履む路の」(タチバナノ カゲフムミチノ) 〔橘〕 タチバナは、今いうタチバナ (一名カラタチバナ、ヤブコウジ科) ではなく、コミカン (一名コウジミカン) 類をさす古名と言われる(松田修『万葉植物新考』)。万葉集内に六十八首の歌に詠まれている。ここでは街路樹として植えられていることを詠む。平城京の大路に街路樹の植えられてあったことは、「東の市の植木の木垂るまで逢はず久しみうべ恋ひにけり」 (3・310) などでわかるし、柳のあったことは「春の日に張れる柳を取り持ちて見れば京の大路思ほゆ」 (19・4142) からも想像される。藤原京にもおそらく街路樹が植えられたのであろう。橘は、その中の一種か。 〔蔭履む路の〕 蔭は日陰。履は霊異記上巻 (第十二話) に「履不万□」の訓注があり「所履」を「フマル」と訓んでいる。新撰字鏡にも「践」に「履也」と見える。万葉集では、「履をだに はかず行けども」 (9・1807) という「履(クツ)」の例のほか、「朝猟に 鹿猪履起之」 (6・926)、「妹が将レ履地にあらましを」 (11・2693) など、フムに宛てたものが十一例ある。以上二句まで、次のヤチマタにかかる序詞。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「橘の影踏む道の」(タチバナノ カゲフムミチノ) 「橘」-みかん科の常緑小高木。今日の、こみかんに当たると思われる。果物の最上として珍重された。 「影踏む道の」-木が地上に影を落とし、往還の人がそれを踏んで通る道の。街路樹とみる説もあるが、藤原京に橘など果樹の街路樹があったか否か、疑わしい。以上、八衢を起こす序。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 【脚注】「橘の陰踏む道の」(タチバナノ カゲフムミチノ) 複数の道路の交差する巷(ちまた)には、市が立ち、そこには目標となる樹木が植えてあった。 → 310。 椿の木の植えられた市は「海石榴市(つばきち)」と呼ばれた。「海石榴市の八十の衢に」 (2951、3101)。この歌もそうした市の一つと思われるが、どこの市に当たるか、不明。上二句は「八衢」の序詞。巻六に、「橘の本の道踏む八衢に物をそ思ふ人に知らえず」 (1027) とあり、左注に「或る本に云く、三方三方沙弥、妻苑臣(そののおみ)に恋ひて作りし歌なりといふ」と伝える。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「八衢」語釈 | 全注 | 【注】「やちまた」 「チマタ」は、道 (チ) の分かれたところ (マタ) の意。「衢」は新撰字鏡に「路四達也」とあり、霊異記上巻 (第一話) の「衢」に「知万太」の訓注を見る。「ヤチマタ」は、多くの方向に道の分岐するところを言う。神代紀の「天八達之衢」を和訓すれば「アメノヤチマタ」となる。この「ヤチマタニ」は、上の句とのつながりでは、「~道の四方に枝分かれする所」を意味するが、下句へはそれを比喩として、あれこれと迷い易い状態を表現している。この歌の三句までを比喩と解する説も見えるが (佐佐木評釈・全註釈など)、巻六にある類歌「橘の本に道履み八衢にものをそ思ふ人に知らえず」 (6・1027) から推測すれば、二句までが第三句にかかる序と解されよう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「妹尓不相而」訓釈 | 注釈 | 【訓釈】「妹尓不相而」(イモニアハズシテ) 金澤本は前の訓下し第四句以下逸してをり、元暦校本・類聚古集・古葉略類聚鈔などの諸本も版本も「イモニアハズテ」とあるが、元暦校本には、右に朱筆で「シ」の書入れがあり、紀州本と西本願寺本とには「スシテ」とあるところを見ると、はやく両訓を存したものと思はれるに、管見に入るところ、折口氏の口訳にのみ「ズシテ」とある他は、諸注すべて「ズテ」と訓んで「ズシテ」の約とするのみでするのみで、訓の収捨決定については殆ど何も言が費されてゐない。これは「岐美尓安波受弖(キミニアハズテ)」 (15・3777) といふ如き仮名書例のある事と「瀬者不渡而(セハワタラズテ)」 (130)、「妹尓不恋而(イモニコヒズテ)」 (7・1208)、「曲不見而(ヨクミズテ)」 (10・1925)、「襴之不相而(スソノアハズテ)」 (11・2619)、「蓑笠不蒙而(ミノカサキズテ)」 (12・3125) などの如く「而」を「テ」とのみ訓む例が多い事によつて、「不相而」を「アハズテ」と訓むべきは考慮の余地なきものと考へられた為ではなからうか。しかし「ズテ」の仮名書例と「ズシテ」の仮名書例とを較べると、前者よりむしろ後者が多いのであるが、「而」の読例は「テ」の方が多いやうに見え、殊に打消の「ず」を受けない場合は「而」を「テ」と訓む事が通例であり、「此間為而(ココニシテ)」 (3・287)、「獨為而(ヒトリシテ)」 (3・366) の如く「シテ」と訓む場合は「シ」の表記があり、「直獨而(タダヒトリシテ)」 (3・460) の如きは稀有の例と云つてもよい程であり、「馬數而(ウマナメテ)」 (1・4)、「良跡吉見而(ヨシトヨクミテ)」 (1・27)、「春過而(ハルスギテ)」 (1・28) の如き動詞を直接うける場合に至つては当然「テ」とのみ訓まれてゐる事申すまでもない。さうした用字例を見馴れてゐる為に「ず」を受ける場合も「テ」と訓むこと論に及ばぬと思はれて来たのかと考へられるが、「風毛吹額(カゼモフクヌカ) 波不立而(ナミタテズシテ)」 (7・1223)、「梅花開(ウメノハナサク) 含不有而(フフメラズシテ)」 (8・1648) の如きは、従来異論を見ないやうに「ズシテ」と訓むべきものである。殊に今と同じく、 今は吾は死なむよ吾妹不相而(わぎもアハズシテ) 思ひ渡ればやすけくも無(12・2869) の如き「不相而」を「アハズシテ」と訓んだ例は他にも三例(12・2882、2980、3107) をあげる事が出来る。即ちこの例によれば「妹尓不相而」は「イモニアハズシテ」と訓むベき事が認められるのみならず、 (1) 云ひつつも後こそ知らめとのしくもさぶしけめやも 吉美伊麻佐受斯弖(キミイマサズシテ) (5・878) (2) みな月の土さへさけて照る日にも我が袖干(ひ)めや 於君不相四手(キミニアハズシテ) (10・1995) (3) 波の間ゆ見ゆる小島の浜久木久しくなりぬ 君尓不相四手(キミニアハズシテ) (11・2753) (4) 玉の緒の絶えたる恋の乱れには死なまくのみぞ 又毛不相為而(マタモアハズシテ) (11・2789) (5) 菅の根のねもころごろに照る日にも干めや我が袖 於妹不相為(イモニアハズシテ) (12・2857) の諸例はいづれも句の中間に母音を有する字余り句であり、(5)に「而」の文字無く、「為」とだけあるのは、人麻呂集の通例として表記を省略したもので、「シテ」の「テ」は訓添と見るべく、「イモニアハズシテ」と訓むべき事は疑問の余地ないものであり、従つて今もまた同様に訓むべき事が考へられる。しかもなほ念の為に借問すると、 (6) 剣太刀名の惜しけくも我れはなし 君尓不相而(キミニアハズテ) 年の経ぬれば (4・616) (7) 思ひ遣るすべのたづきも今はなし 於君不相而(キミニアハズテ) 年の経ぬれば (13・3261) (8) うつせみの世やも二行く何すとか 妹尓不相而(イモニアハズテ) 吾がひとりねむ (4・733) (9) 春霞たなびく山のへなれれば 妹尓不相而(イモニアハズテ) 月ぞ経にける (8・1464) (10) 思ひ遣るたどきも我れは今はなし 妹二不相而(イモニアハズテ) 年の経行けば (12・2941) の如きは諸注に一致してゐるやうに、「キミニアハズテ」、「イモニアハズテ」と訓むべきものではないか、それと同じく今もしひて字余りに訓むに及ばないではないか、といふ反問のあり得る事である。だがその答えは、(1)-(5) はいづれも結句であり、(6)-(10) はすべて第四句である事を云へば足るであらう。即ち以上の事実を総合すれば、「不×而」は「-ズテ」とも「-ズシテ」とも訓んでさしつかへなく、句の位置に従つて音数に過不足のないやうに取捨すべきであるが、結句の場合は、集中に例の多いやうに、句中に単独母音を含むものは八音になつても「-ズシテ」とすべきもののやうである。(92)参照。今の場合また「イモニアハズシテ」と訓み改める事が用例に適ふばかりでなく、それによつて第四句の原因を示す倒置句としての結句の声調が萬葉らしい姿に帰つたと云へよう。 【考】 巻六に載せられた、 橘の本に道踏む八衢に物をぞ思ふ人に知らえず (6・1027) は、今の作が伝誦の間に変形したものと考へられる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「妹尓不相而」(イモニアハズシテ) 結句「妹尓不相而」を「イモニアハズテ」と七音に訓む説と、「イモニアハズシテ」と八音に訓む説とがある。古写本にも類聚古集・古葉略類聚鈔などに「アハズテ」、紀州本・西本願寺本には「アハスシテ」と訓まれており、元暦校本には「あはすて」の「すて」の間に、右に「シ」の朱記が見える。童蒙抄・代匠記・万葉考・古義など江戸時代の諸注には「アハズテ」とあり、明治以後の注釈書も、多くそれに従っている。折口口訳のみ「ズシテ」と見えることは、澤瀉注釈に指摘するとおりで、最近の注釈書でも、大系本には「ズテ」、古典全集と古典集成には「ズシテ」説が採られている。澤瀉注釈に言及されているように、江戸時代以降の諸注の大部分が「ズテ」説によっているのは、「伎美尓安波受弖」 (15・3777) という例のあることや、「而」を「テ」と訓むのがごく普通であることなどにもとづくと思われる。しかし、 海の底沖漕ぐ舟を辺に寄せむ風も吹かぬか波立てずして(7・1223) 十二月には淡雪降ると知らねかも梅の花咲くふふめらずして(8・1648) のように、「ナミタテズシテ」「フフメラズシテ」と「シ」に相当する文字のない場合でも、訓み添えの疑いない例もある。「今は吾は死なむよ吾妹不相而思ひわたればやすけくもなし」 (12・2869)、「まそ鏡見飽かぬ妹に不相而月の経ぬれば生けりともなし」 (12・2980) など、従来異論なく「不相而」を「アハズシテ」と訓まれてきた。特に第五句の場合は「久しくなりぬ君尓不相四手」 (11・2753)、「干めや我が袖妹に不相為」 (12・2857) のように字余りの八音句として訓まれている。従って、今の「125歌」の場合も「イモニアハズシテ」と句中に単独母音を含む字余り句として訓む方が正しいであろう。澤瀉注釈の論拠とするのは、「不相而」と書いて「アハズシテ」と訓む確実な例の存することと、「イモニアハズテ」と訓むと句中に単独母音を含みながら七音で、いわゆる準不足音句になることの二点と言ってよい。準不足音句については木下正俊『万葉集語法の研究』に詳論がある。それによれば、短歌の各句の準不足音句は、第二句と第四句に圧倒的に多く。反対に第一、三、五句には極端に少ない。その理由は明らかにしえないが、とりわけ第五句においては音数不足を忌避する傾向が強いようである。そこで、第五句に関し訓詀のさいに改訓の余地のあるものは積極的に読み改めることも必要と思われる。その観点から「125歌」の「妹尓不相而」と「12・2991歌」の「異母二不相而」を見ると、これを「イモニアハズシテ」と訓み、「シ」を補読するのが自然である。従って「イモニアハズシテ」と読む。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 126 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 〔題詞〕 石川女郎贈大伴宿禰田主歌一首 【頭書】 元暦校本・古葉略類聚鈔・神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、題詞ノ下小字二行「即佐保大納言大伴卿之第二子母曰 巨勢朝臣也」。 但神田本、「曰」ナシ。西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「之」ナシ。京都大学本、「即」ニ赭ノ合点アリ。「臣」ノ下赭〇符アリ。右ニ赭「女□」アリ(下写真[1]参照)。 京都大学本、行間ニ朱「大伴皇子宮侍也」 〔本文〕 歌。神田本「謌」。 〔訓〕 京都大学本、赭訓アリ、次ノ如シ。「贈ル大伴ノ宿禰ノ田主ニ」。 〔諸説〕 〇一首。代匠記精撰本、「一首」ノ下「即佐保大納言大伴卿第二子母曰 巨勢朝臣女也」ノ注一本ニアリトシ「朝臣」ノ下「人」ノ字脱カトス。童蒙抄、「一首」ノ下一本ニ小字ニテ「即佐保大納言大伴卿第二子母曰 巨勢朝臣也」アリトス。攷證、「一首」ノ下元暦校本ニ「即佐保大納言大伴卿之第二子母曰 巨勢朝臣也」ノ註アリトス。 〔本文〕 遊士跡 吾者聞流乎 屋戸不借 吾乎還利 於曽能風流士 (タハレヲト ワレハキケルヲ ヤトカサス ワレヲカヘセリ オソノタハレヲ) 【頭書】 類聚古集、コノ歌ハ次ノ左註ノ後ニアリ。左註ノ前行ニ「贈大伴田主哥石川女郎 田主佐保大納言之第二子母巨勢朝臣」アリ。 袖中抄、第十九「万葉集ニヲソノタハレヲト云フ事アリタハレヲトワレハ聞ツルヲヤトカサスワレヲカヘセリヲソノタハレヲ 是ハ石川ノ女郎贈大伴田主哥」 和歌色葉集、巻中「タハレヲトワレハ申ツルヲヤトカサスワレヲカヘセリヲソノタハレヲ 大伴田主カタチヨク心優ニシテミル女心ヲウコカスニトナリニスミケル女此男ヲ思カケテアヤシキ嫗(ヲウナ)ノサマヲツクリテヨルユキテ門ヲタタキテ東ノトナリノヲウナノ火ヲトリニマイレル也ト云ケルヲヲトコカクトモシラテ火ハカリヲトラセテムナシクカヘシタリケレハ朝(アシタ)ニトトメヌ事ヲハチウラミテ女ノヤレル哥ナリタハレヲト。遊士トカケリ」
(遊)士。元暦校本「土」。(風流)士。元暦校本「土」。 〔訓〕 タハレヲト。元暦校本「あそひをと」。古葉略類聚鈔・神田本「アソヒヲト」。京都大学本「遊士」ノ左ニ赭「アソヒオ」アリ。 キケルヲ。元暦校本「きけとも」。古葉略類聚鈔「キケトモ」。漢字ノ左ニ「キケルヲ」アリ。 ヤトカサス。神田本「ヤトカサヌ」。 オソ。古葉略類聚鈔・細井本・温故堂本「ヲソ」。 タハレヲ。神田本、漢字ノ左ニ「タハレヲトイ」アリ。温故堂本「タワレヲ」 〔諸説〕 タハレヲト。童蒙抄「ミヤヒトト」。万葉集玉小琴「ミヤヒヲト」。 キケルヲ。代匠記精撰本「キキツルヲ」トスルヲ否トス。 ヤトカサス。代匠記精撰本「ヤトカサテ」トモ訓ズ。 オソノタハレヲ。童蒙抄「オソノミヤヒト」。万葉集玉小琴「オソノミヤヒヲ」。
〔左注〕 大伴田主字曰仲郎 容姿佳艶風流秀絶 見 【頭書】(頭書全文写真[3]) 袖中抄巻十九「万葉云大伴ノ田主字ヲ曰フ伴郎(ハムラウチ)容姿佳艶ニシテ風流秀絶ナリ見ル人聞者ノ靡不歎恩セ也時ニ有石川ノ女郎自ラ成シテ雙栖(サウセイ)之感ヲ恒ニ悲ブ猲守之難コトヲ意欲フニ寄セムト書ヲ未タレ逢ハ良信(シム)ニ爰ニ作ナシテ方便タ而傾ニテ賤嫗(セムク)ニ已ニ提堝子ヲ而到テ寝側哽音跼足シテ叩テ戸ヲ諮シテ曰ク東隣リノ貧女将ニ取火ヲ来レリ矣於是(ココニ)伴良(郎)暗夜ニ非ス識ルニ隠(イム)之形ヲ慮外ニ不堪ヘ拘接(コフセウ)之計ニ任テ念ニ取ル火ヲ就テ跡ニ帰ル者也明後女郎既ニ耻テ自媒(ハイ)之可ヲ愧(ハツ)後恨ム心契(ケイ)之弗果因作(ナキコトヲハタスコト)作テ此テ哥ヲ以贈諕戯(ケキキ)ヲ焉」
〔本文〕 仲。類聚古集「□」(上写真[3]参照)。絶。温故堂本「艶」。見。元暦校本、コノ下ニ「者」アリ。但、消セリ。 〔訓〕 神田本・西本願寺本・細井本・大矢本・京都大学本、訓アリ。次ノ如シ。「大伴ノ田主字(アサナ)ヲ仲郎ト容姿佳艶ニシテ風流秀絶(セツナリ)。伹、神田本・細井本「アサナヲ」ナシ。細井本「佳艶」ノ右ニ「カエン」アリ。神田本・細井本・大矢本・京都大学本「セツ」ナシ。温故堂本、訓アリ、次ノ如シ。「大伴ノ田主字ヲ曰仲郎容姿佳艶ニシテ風流秀絶ナリ」。 〔諸説〕 万葉考。コノ左注衍トス。 仲郎。古葉略類聚鈔「ナカチコ」。 〔左注〕 人聞者靡不歎息也 時有石川女郎 自成雙 〔本文〕 息。元暦校本「□」(上写真[3]参照)。 也。古葉略類聚鈔、コノ下「亍」アリ。 〔訓〕 靡不歎息。西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本、訓アリ、次ノ如シ。「靡シ不云コト歎息」。伹、温故堂本「云コト」ヲ「ト云コト」トセリ。京都大学本、赭ニテ訓ヲ消セリ。漢字ノ左ニ赭訓アリ、次ノ如シ。「靡不歎息(□)」(下写真[4]参照)。細井本、訓アリ、次ノ如シ。「靡不歎息(□)」(写真[4]参照)。 時有石川女郎。西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、訓アリ、次ノ如シ。「時ニ有リ石川ノ女郎(オトメト云モノ)」。伹、温故堂本「リ」ナシ。細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「オトメ」ヲ「ヲトメ」トセリ。京都大学本、赭ニテ「ヲトメ」ヲ消セリ。神田本、「川」ノ右下ニ「ノ」アリ。 自成雙。西本願寺本、訓アリ、次ノ如シ。「自(ヲ)ラ成シテ雙栖(サウセイ)之感ヲ」。細井本、訓アリ、次ノ如シ。「自(ヲ)成シテ雙栖(サフセイ)之感」。大矢本・京都大学本、訓アリ、次ノ如シ。「自(オラ)成シテ雙栖ノ之感ヲ」。伹、京都大学本、赭ニテ「オラ」ヲ消セリ。「自」ノ左ニ赭「ミツカラ」アリ。「成」ノ訓ノウチ「シ」ナシ。「テ」ヲ赭書セリ。温故堂本、訓アリ、次ノ如シ。「自ラ成テ雙栖之感ヲ」。神田本「自」ノ右ニ「ミ」アリ。 〔左注〕 栖之感恒悲獨守之難 意欲寄書未逢良信 〔本文〕 感。神田本「□」(下写真[4]参照)。 難。元暦校本、右ニ赭「歎」アリ。 欲。大矢本・京都大学本「歎」。京都大学本、赭ニテ消セリ。赭頭書「欲」アリ。 書。神田本、コノ下「信」アリ。元暦校本「書未」ノ間ノ右ニ赭「信」アリ。 良。神田本「郎」。 〔訓〕 恒悲獨守之難 。西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、訓アリ、次ノ如シ。「恒ニ悲フ獨守之難ヲ」。京都大学本、赭ニテ「フ」ヲ消セリ。ソノ右ニ赭「ム」アリ。神田本「難」ノ右下ニ「ヲ」アリ。 意欲寄書。西本願寺本・大矢本・京都大学本、訓アリ、次ノ如シ。「意ニ欲寄(ヨセント)書ヲ」。大矢本・京都大学本「ヨセント」ヲ「セムト」トセリ。京都大学本「歎」ノ右下ニ赭「ニ」アリ。細井本、訓アリ、次ノ如シ。「意ニ欲寄ント書ヲ」。温故堂本、訓アリ、次ノ如シ。「意欲ス寄書ヲ」。神田本、訓アリ、次ノ如シ。「意ニ欲ニ寄ト書ヲ」。 未逢良信。西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、訓アリ、次ノ如シ。「未タ逢ハ良信ニ」。細井本・温故堂本「逢」ノ訓「ハ」ナシ。温故堂本・大矢本・京都大学本、「未」ノ左ノ訓「ス」ナシ。神田本、「信」ノ右下ニ「ニ」アリ。
〔左注〕 爰作方便而似賎嫗 己提鍋子而到寝側 哽 〔本文〕 提。古葉略類聚鈔、「□」(上写真[4]参照)。 鍋。元暦校本・類聚古集・古葉略類聚鈔・神田本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本「喎」。 側 哽。類聚古集「□□」(上写真[4]参照)二字墨ニテ消セリ、右ニ墨「側哽」アリ。 〔訓〕(上写真[4]のように、判読しづらい) 作方便而似賎嫗 己提堝子而到寝側。西本願寺本・細井本、訓アリ、次ノ如シ。「作方方便(ナシテタハカリ)ヲ而似ラ賤嫗ニ已□提堝子(□)ヲ而到テ寝側(子ヤノカタハラニ)」。但、細井本「嫗」ノ右ニ「ヲウ」アリ。温故堂本、訓アリ、次ノ如シ。「作テ方便(タハカリ)ヲ而似セテ賎嫗 己レ提堝子ヲ而到テ寝ノ側ニ」。大矢本・京都大学本、訓アリ、次ノ如シ。「作シテ方便(タハカリ)ヲ而似テ賎嫗(ク)ニ 己レ提ケテ堝子ヲ而到テ寝ノ側ニ」。但、京都大学本「レ」ノ右ニ赭「ニ」アリ。「堝子」ノ右ニ赭「ナヘ」アリ。「寝」ノ右ニ赭「子ヤ」アリ。「側」ノ訓「ニ」ヲ赭ニテ消セリ、ソノ右ニ赭「カタハラニ」アリ。神田本「便」ノ右下ニ「ヲ」アリ。「側」ノ右下ニ「ニ」アリ。 哽音。西本願寺本・大矢本・京都大学本、右ニ「カウイム」アリ。京都大学本「哽」ノ左ニ赭「ムセヒ」アリ。細井本、右ニ「カウイン」アリ。神田本、訓アリ、次ノ如シ。「哽(ムセヒ)音ヲ」。 〔諸説〕 哽音。万葉集美夫君志、「哽」ハ「ムセブ」ト訓ズ。 〔左注〕 音跼足叩戸諮曰 東隣貧女将取火来矣 於 〔本文〕 跼。元暦校本・古葉略類聚鈔・神田本・西本願寺本・温故堂本・京都大学本、「□」(下写真[5]参照)。元暦校本、朱頭書「□」(同)アリ。類聚古集「□」(同)。大矢本「蹢」。 叩。大矢本・京都大学本、「叮」。京都大学本、赭ニテ消セリ。赭頭書「叩」アリ。 火。元暦校本「大」右ニ赭「火」アリ。 矣。温故堂本・大矢本・京都大学本、一字小字、右ニヨセタリ。 〔訓〕 跼足叩戸諮曰 東隣貧女将取火来矣。西本願寺本、訓アリ、次ノ如シ。「蹢足(キヨクソクシテ)叩戸諮(トフラフテ)曰ク 東隣ノ貧女将ニ/シテ取ラント火ヲ来レリト矣」。細井本、訓アリ、次ノ如シ。「跼足叩(キヨクソクシテ)戸諮(トフラフテ)曰 東隣ノ貧女将ニ/シテ取ント火ヲ来レリ矣」。温故堂本、訓アリ、次ノ如シ。「蹢足叩テ戸諮(トフラヒテ)曰ク 東隣ノ貧女将ニ/シテ取ト火ヲ来レリト矣」。大矢本・京都大学本、訓アリ、次ノ如シ。「蹢足シテ叮戸諮(トフラフテ)曰ク 東隣ノ貧女将ニ/シテ取ラムト火ヲ来レリト矣」、但、京都大学本「蹢足」ノ右ニ赭「キヨクソク」、左ニ赭「ヌキアシシテ」アリ。「叮」ノ右ニ赭「タタヒテ」、「戸」ノ右下ニ赭「ヲ」アリ。「トフラフテ」ノ下ノ「フ」ヲ赭ニテ消セリ。ソノ右ニ赭「ツ」アリ。「火」ノ訓「ヲ」ヲ赭ニテ消セリ。神田本「隣」ノ右下ニ「ノ」、「来」ノ右下ニ「ト」アリ。 〔諸説〕 諮曰。童蒙抄「イツテイハク」。攷證「諮」ヲ、「ハカル」ト訓ズ。 〔左注〕 是仲郎 暗裏非識冐隠之形 慮外不堪拘接 〔本文〕 仲。元暦校本、右ニ朱「伴又作」アリ。類聚古集、「伴」。 識。神田本「誠」。 冐。類聚古集「□」(下写真[5]参照)墨ニテ消セリ。右ニ墨、「冐」アリ。但、何カヲ直セリ。古葉略類聚鈔・神田本、「□(上に田、下に日)」(下写真[5]参照)。京都大学本、左ニ赭「□(上に田、下に日)」(同)アリ。 拘。元暦校本・古葉略類聚鈔、「物」。元暦校本、右ニ朱「拘」アリ。類聚古集、「□」(同)。神田本、ナシ。大矢本・京都大学本、「拘」。 〔訓〕 暗裏非識冐隠之形 慮外不堪拘接。西本願寺本・細井本、訓アリ、次ノ如シ。「暗裏(クラキウチニ)非ス識ルニ冐(ヲカシ)隠(カクルル)之形ヲ慮外ニ不堪拘接(コウセフノ)之計(ハカリコト)」。但、細井本、「コフセフ」ヲ「コウセウ」トセリ。温故堂本・大矢本・京都大学本、訓アリ、次ノ如シ。「暗キ裏ニ非ス識(ハカルニ)冐隠(ヲカシカクセル)之形ヲ慮外ニ不堪拘接之計(コトニ)」。但、大矢本、「識」ノ訓ノウチ「ハカ」ナシ。「拘接」ノ右ニ「コウセフノ」アリ。京都大学本、「裏」ノ右ニ赭「ウチ」アリ。「識」ノ訓ノウチ「ハカ」ヲ「サト」トシ、赭書セリ。赭ニテ「ヲカシ」ヲ消セリ。「ヲカシカクセル」ノ右ニ赭「ホウイム」アリ。「拘接」ノ右ニ「コウセウ」アリ。「計」ノ右ニ赭「ハカリ」アリ。 〔諸説〕 冐隠。童蒙抄、「オカシカクス」。
〔左注〕 之計 任念取火就跡歸去也 明後女郎 既恥 〔本文〕 念。温故堂本、「□(意の日が田)」(上写真[5]参照)。右ニ「念」アリ。 火。元暦校本、「大」。右ニ朱「火」アリ。 去。類聚古集・神田本、「者」。 恥。古葉略類聚鈔、「耿」。 〔訓〕 西本願寺本、訓アリ、次ノ如シ。「任セテ念ヒニ取テ火ヲ就テ跡ニ歸リ去也 明後(アケテノチ)女郎 既ニ恥(ハチル)」。細井本、訓アリ、次ノ如シ。「任セテ念ニ取テ火ヲ就テ跡ニ歸リ去ヌ也 明(アケテ)後チ女郎 既恥(ハチ)」。温故堂本、訓アリ、次ノ如シ。「任念取火ヲ就跡歸去也 明テ後チ女郎 既ニ恥」。大矢本・京都大学本、訓アリ、次ノ如シ。「任テ念ニ取火就跡歸去也 明(アケテ)後女郎 既ニ恥」。但、京都大学本、「取」ノ右下ニ赭「テ」アリ。「去」ノ右下ニ赭「リヌ」アリ。「後」ノ右下ニ赭「チ」アリ。「恥」ノ右ニ赭「ハチ」アリ。神田本、「任」ノ右ニ「マヽ」、「明」ノ右ニ「アケテノ」アリ。 〔左注〕 自媒之可□(愧の上「甶」が「田」) 復恨心契之弗果 因作斯歌以 〔本文〕 復。類聚古集・古葉略類聚鈔、「□」(上写真[5下]参照)。類聚古集、墨ニテ消セリ。右ニ墨「復」アリ。 契。元暦校本、「□(契の下「大」が「火」)」。神田本、「□(契の「刀」が「丸」、下の「大」が「火」)」。右ニ「□(上「生・刀」、下「廾」)イ」アリ。 因。類聚古集、モトノ字ヲスリ消シテ書ケリ。 〔訓〕 自媒之可愧。西本願寺本・細井本、訓アリ、次ノ如シ。「自(ミ)ノ媒ノ之可キヲ愧(ハツ)」。 温故堂本・大矢本・京都大学本、訓アリ、次ノ如シ。「自(ミ)媒ノ之可ヲ愧」。但、京都大学本「ミ」ノ下ニ赭「ツカラノ」アリ。「愧」ノ右ニ赭「ハツ」アリ。 復恨心契之弗果 因作斯歌。西本願寺本、訓アリ、次ノ如シ。「復恨テ心ノ契之(チキリノ)弗果(サルヲハタサ) 因作テ斯歌」。細井本、訓アリ。次ノ如シ。「復恨テ心ニ契之(チキリノ)弗ルヲ果(ハタサ) 因作テ斯歌ヲ」。温故堂本、訓アリ。次ノ如シ。「復恨テ心ノ契ノ之弗ルヲ果サ 因テ作斯歌」。大矢本・京都大学本、訓アリ、次ノ如シ。「復恨テ心ノ契之(チキリノ)弗ルヲ果 因作テ斯歌」。但、京都大学本、「復」ノ右ニ赭「マタ」アリ。赭ニテ「ルヲ」ヲ消セリ。ソノ右ニ赭「サルコトヲ」アリ。「歌」ノ右下ニ赭「ヲ」アリ。神田本、「弗」ノ右下ニ「コトヲ」アリ。 〔左注〕 贈諺戯焉 〔本文〕 諺。元暦校本、「□(謔の七の下が「ヒ」)。類聚古集、「諕」。古葉略類聚鈔、偏ハ蝕シテ存セズ。旁を「□(元暦校本と同じ)」。神田本、「譃」。 戯。神田本、ナシ。右ニ書ケリ。本文中コノ字ニ當ル處ニ「〇」符アリ。 〔訓〕 贈諺戯焉。西本願寺本、訓アリ、次ノ如シ。「贈ル諺(コトワサノ)戯(タワフレヲ)焉」。細井本、訓アリ、次ノ如シ。「贈ル諺(コトハサノ)戯(タハフレヲ)焉」。温故堂本・大矢本・京都大学本、訓アリ、次ノ如シ。「贈諺(コトワサノ)戯ヲ焉」。但、大矢本・京都大学本、「贈」ノ右下ニ「ル」アリ。京都大学本、「戯」ノ右ニ赭「タハレ」アリ。 〔諸説〕 諺戯。万葉集略解、「諺」ハ「譃」ノ誤カ。攷證、「諺」ハ「謔」ノ誤。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「遊士 (みやびを)」訓・注 | 拾穂抄 | たはれおとわれはきけるをやとかさすわれをかへせりをそのたはれお 遊士跡吾者聞流乎屋戸不借吾乎還利於曽能風流士 たはれおとわれは 祇曰たはれおとはなひきやすき好色の人を云也色好む男と聞て思ひ兼て賤きおふなのまねして火取に行たれともとめずして返しけれは恨て讀る哥也をそとはそらことゝいふ心成へし仙覺も空言のたはれおとたはふれいへりと云々奥儀抄にも此儀有又一説をそはきたなしと云也色好ときけと我をとゝめすきたなき色好ミと也是迄奥儀又歌林良材にはおそは河うそと云獺の字也此獣始めはたはむるゝやうなれとも後はくひあふ物なれはそれを田主にたとへいへる也皆先達の御説なから祇注可用之
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | 遊士跡吾者聞流乎屋戸不借吾乎還利於曾能風流士 [タハレヲトワレハキケルヲヤトカサスワレヲカヘセリオソノタハレヲ] タハレヲとは、好色の人の風流なるを云 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 遊士跡 [ミヤビヲト]。吾者聞流乎 [アレハキケルヲ]。屋戸不借 [ヤドカサズ]。吾乎還利 [アレヲカヘセリ]。於曾能風流士 [オソノミヤビヲ]。 遊士跡 [ミヤビヲト]、本居氏云、遊士風流士を、師の、みやびとゝ訓れたるにつきて、猶思ふに、さては宮人と聞えて、まぎらはし、然ればみやびをと訓べし、此(ノ)稱は男に限れり、八卷に、をとめらがかざしのために遊士のかづらのためと云々、是をとめにむかへていへれば、必(ス)をといふべきなり、(舊本に、此 (レ)をタハレヲとよめるは、よしもなきひがことなり、岡部氏が、六(ノ)卷に、諸大夫等集2左少辨、云々家1宴歌とて、うなはらのとほき渡(リ)を遊士の遊ぶをみむとなづさひそ來し、てふ歌の左に、右一首云々、蓬莱仙媛所v作嚢縵爲2風流秀才之士1矣と書り、此(ノ)遊士風流秀才は、其(ノ)會集の、大夫たちをさすなるを、戯男といはゞ、客人になめし、かゝれば、何處にても、みやびとゝよむべし、といへり、) 跡 [ト] は常 [ツネ] の語(リ)辭なり、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「遊士」(ミヤビヲ) 原文「遊士」を元暦校本・紀州本等には「アソビヲ」とし、類聚古集 (15・56) 以下旧訓には「タハレヲ」としたのを「玉の小琴」に「ミヤビヲ」と改めた。「みやび」の語は集中仮名書の例は「梅の花夢に語らく美也備多流 (ミヤビタル) 花と吾思ふ」 (5・852) とある一例のみであるが、語義は「鄙び」「都び」 (3・312) などと同様「宮び」、即ち宮廷風といふやうな意で、粗野、卑俗の反対で、教養のある、風雅を解する者を「みやびを」と云つたものと思はれる。「遊士」は漢語としては遊子と同じく旅人の意に用ゐられるやうであるが、ここでは風雅の遊を楽しむ事の出来る人の意で用ゐたもので、他の例 (6・1016、7・1295、8・1429) と共にいづれも「ミヤビヲ」と訓むべきものと思はれる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「遊士」(ミヤビヲ) 「ミヤビヲ」の原文「遊士」。元暦校本・紀州本など、「アソビヲ」、類聚古集に「タハレヲ」と訓まれていたが、宣長の「万葉集玉の小琴」に「遊士風流士を、『万葉考』に『みやびと』と訓れたるにつきて、猶思ふに、さては宮人と聞こえてまぎらはし、然れはみやびをと訓へし、此称は男に限れり」と、「ミヤビヲ」の訓を提示した。同書欄外に「羽倉御風モミヤビヲト訓リトゾ」とあり羽倉御風にすでに同訓のあったことが知りられる (御風の論は未見)。この歌の初句に「遊士」とあり、結句に「風流士」とあるのは、同語を表記を変えて繰返したものと思われ、遊仙窟の古訓に「風流」を「ミヤビヤカナリ」と訓む例も見えるので、宣長の言うように「ミヤビヲ」と訓むのが適切だろう。巻四に「あしひきの山辺に居れば風流無み吾がするわざをとがめたまふな」(712・坂上郎女) とある、その「風流」も「ミヤビ」と訓む。なお、中国で風流と言う場合、晋代以後には、「① 個人の道徳的風格」、「② 放縦不羈」、「③ 官能的頽廃性」を帯びたなまめかしさ、などの意を表す (古典全集本頭注)。126歌では「①」に近い意味で使われている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「遊士」(ミヤビヲ) [「ミヤビ」+「ヲ(男)」]。「ミヤビ」は「ミヤ (宮廷)」を動詞に活用させた「ミヤブ」(上二段) の名詞形。「ヒナ (鄙俗)ビ」の対。原文は第一句のは「遊士」、第五句のは「風流士」と書かれている。「風流士」は漢籍に例があるが、「遊士」は風流を求めて遊ぶ男子の意で、万葉人の新造語か。中国における「風流」の意味は時代によって変遷があり、晋代以後、「① 個人の道徳的風格」、「② 放縦不羈」、「③ 官能的な頽廃性」を帯びたなまめかしさ、などと推移した。この「126・127」における「ミヤビ」の語の使用にも、田主と石川女郎との間で微妙な相違がある。田主が伝統的な風流「①」の解釈をとっているのに対して、女郎は風流「③」の延長とも言うべき、『遊仙窟』など唐代小説類に多い好色的な意味に解釈している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 【脚注】「遊士」(ミヤビヲ) [初句「みやびを」の原文「遊士」は漢語]。「海原の遠き渡りをみやびを (遊士) の遊ぶを見むとなづさひそ来し」(1016)。和語「みやびを」は「宮びな男」、即ち宮廷風・都会的に洗練された男をいう。結句の原文「風流士」の「風流」は、遊仙窟の古訓に、「ミヤビカ」(真福寺本)、「ミヤビヤカ」(醍醐寺本) とある。漢語「風流」は、超俗脱俗を中心的な意味として、高潔・洒脱・放逸・好色の意までを含む。この歌では、漢語「風流」の意味と和語「みやびを」とを重ねて「色好みの男」の意。次の歌 (127) では、節操高潔の人の意を「みやびを」に重ね用いた。[初句「みやびを」の原文「遊士」は漢語]。「海原の遠き渡りをみやびを (遊士) の遊ぶを見むとなづさひそ来し」(1016)。和語「みやびを」は「宮びな男」、即ち宮廷風・都会的に洗練された男をいう。結句の原文「風流士」の「風流」は、遊仙窟の古訓に、「ミヤビカ」(真福寺本)、「ミヤビヤカ」(醍醐寺本) とある。漢語「風流」は、超俗脱俗を中心的な意味として、高潔・洒脱・放逸・好色の意までを含む。この歌では、漢語「風流」の意味と和語「みやびを」とを重ねて「色好みの男」の意。次の歌 (127) では、節操高潔の人の意を「みやびを」に重ね用いた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「聞流乎(きけるを)」訓・注 | 代匠記 | 遊士跡吾者聞流乎屋戸不借吾乎還利於曾能風流士 [タハレヲトワレハキケルヲヤトカサスワレヲカヘセリオソノタハレヲ] 袖中抄に、聞流乎を、きゝつるをとよめり、同じ意ながら今の点に付べし、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「屋戸不借(やどかさず)」訓・注 | 代匠記 | 遊士跡吾者聞流乎屋戸不借吾乎還利於曾能風流士 [タハレヲトワレハキケルヲヤトカサスワレヲカヘセリオソノタハレヲ] 不借は、今案カサデとも和すべし、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「屋戸不借」(ヤドカサズ) 集中では「やど」を「屋前」とも書き、さういふ意味に用ゐられる事が多い (3・384参照) がここは「やどり」、宿所の意に用ゐれてゐる。集中では、貸すも借りるも「借」の字が用ゐられている。「貸」の文字は集中に見えない。左注にあるやうな事情で大伴田主が相手にならなかつた事を云つたのである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「屋戸不借」(ヤドカサズ) 「ヤド」には大別して三種の意味がある。① 家の庭や家のある所をさす場合、② 家 (建物) そのものをさす場合、③ 宿、旅先などで宿る所をさす場合、の三種。ここでは「③」の意味。「カル」を「借」と記す例が霊異記下巻第三十五話の訓注に見えるが、万葉集では「衣借すべき」 (1・75)、「宿借らば」 (7・1242) のように、「カス」にも「カル」にもいずれにも用いられている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「屋戸不借」(ヤドカサズ) 「やど貸さず」-「やど貸す」は、他人を泊める意。ヤド借ル・ヤド貸スという場合のヤドの「ド」の仮名には甲乙両類が用いられている。その理由については、意味の点で動詞「ヤド(乙)ル」との混同によるものか、単なる音韻上の混乱か不明。ここは原文に「屋戸」とあり、甲類が現れている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「於曽能風流士(おそのみやびを)」訓・注 | 拾穂抄 | たはれおとわれはきけるをやとかさすわれをかへせりをそのたはれお 遊士跡吾者聞流乎屋戸不借吾乎還利於曽能風流士 たはれおとわれは 祇曰たはれおとはなひきやすき好色の人を云也色好む男と聞て思ひ兼て賤きおふなのまねして火取に行たれともとめずして返しけれは恨て讀る哥也をそとはそらことゝいふ心成へし仙覺も空言のたはれおとたはふれいへりと云々奥儀抄にも此儀有又一説をそはきたなしと云也色好ときけと我をとゝめすきたなき色好ミと也是迄奥儀又歌林良材にはおそは河うそと云獺の字也此獣始めはたはむるゝやうなれとも後はくひあふ物なれはそれを田主にたとへいへる也皆先達の御説なから祇注可用之
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | 遊士跡吾者聞流乎屋戸不借吾乎還利於曾能風流士 [タハレヲトワレハキケルヲヤトカサスワレヲカヘセリオソノタハレヲ] オソノタハレヲは、此おそと云詞につきて先達の説々あり、一には獺の戯によす、二には、きたなきたはれをと罵る意、三には、僞のたはれをと云意、以上三義、事舊たれば委は出さず、往て見るべし、先獺戯は和名云、獺、【音脱、和名攷證曾、】今は於曾なれば、假名既にたがへる上に、袖中抄に、獺戯の下に云、又萬葉におそのたはれをと云事ありとて、今の歌を引て終に云、今云をそのたはれを、おとのたはれを紛ぬべければ、記し侍るなり、かゝれば、似たる事の本來別義なり、次に、きたなきをおそと云も假名違へり、其故は此集第十四に、烏とふ於保乎曾杼里とよめり、是大にきたなき鳥と云心なるに、乎曾とかければなり、奥義抄云、或人云、ひむがしの國の者は、虚言をばをそごとと云なり、さればそら色好みとよめるにこそとも申す、仙覺抄云、虚言のたはれをと戯れいへりけるなり、此は右の説と同じ、されど虚言を於曾と云所以を出さゞれば事たらず、今云、今の世僞を云をうそつくと申は、奥義抄のをそにや、うはをにもおにも通ず、口をひそめて聲を出すを嘯 [ウソフク] と云ひ、うそを吹とも云へば誠なき言もそれがやうになんあれば、うそ云とも、うそつくとも云にや、つくは吐の字なり、此義の用否は後の人定むぺし、今案右の外に兩義あり、一には、第十二に、山城の石田の杜に心おぞく手向したれば妹に逢がたき、此心おぞくと云に鈍の字をかけり、又第九に浦島子をよめる歌の反歌に、常世邊 [トコヨベ] に住べき物を釼太刀 [ツルギタチ] さが心から於曾也この君とよめるも太刀によせて心おぞしと云へり、源氏物語の、蓬生橋姫などにも心遲といへり、かゝれば心のにぶくて我方便をとくも意得ぬたはれをなりと戯て罵るにや、二つには、古語拾遺に、天鈿女命の下に注して云、古語、天乃於須女 [オズメ]、其神強捍猛固(ナリ)、故(ニ)以爲レ名、今(ノ)俗 [クニコト] 強女謂二之於須志 [オズシ] 一、此縁也、源氏東屋 [アツマヤ] に、めのと、はたいと苦しと思て、物つゝみせず、はやりかにおぞき人にて云云、注に、おずきとよむ、恐しき人と云事なりといへり、かゝれば、源氏にいへるおぞきは、古語拾遺の於須志なり、今も男女を別ずおそろしき人と云心に、おぞき人とも云合へり、されば、風流にはあらで、こはくおそろしき人と云にや、此中に注の意を以撰ぶに、心鈍と云義、能叶ふ歟、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 於曾能風流士 [オソノミヤビヲ] は、於曾とは、波夜 [ハヤ] の反對にて、世にさがしく、すぐれたる人を、はやき人と云(ヒ)、おろかにおとれる人を、おそき人といへば、こゝは、愚鈍 [オロカ] の風流士 [ミヤビヲ] ぞと云るなり、九(ノ)卷浦島(ノ)子を作る歌に、常世邊可住物乎釼刃已之心柄於曾也是君 [トコヨヘニスムベキモノヲツルギタチシガコヽロガラオソヤコノキミ] 、また十二に、山代石田杜心鈍手向爲在妹相難 [ヤマシロノイハタノモリニコヽロオソクタムケシタレバイモニアヒガタキ] 、と活かしても云り、(源氏物語蓬生橋姫などの卷にも心おそくと云ることあり、)時節などに、遲速 [オソハヤ] といふも、本同言なり、(十四の、可良須等布於保乎曾杼里 [カラストフオホヲソドリ] 、とある乎曾 [ヲソ] 、又獺 [ヲソ] のことなどを、思ひよせたる説は、於 [オ] 乎 [ヲ] の假字の、異 [カハリ] あることをだに、えしらねば、いふにも足ず)、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「於曾能風流士」(オソノミヤビヲ) 「おそ」は遅しの語幹。鋭敏の反対。にぶいこと。愚鈍なこと。気のきかないこと。ここの原文「風流士」は元暦校本以下すべて「タハレヲ」とあつたが、「遊士」同様玉の小琴に「ミヤビヲ」と改めたによる。巻六に「遊士」 (1016) とあつて、その左注に「風流秀才之士」とあつて遊士と風流士とを同様に扱つてゐることが察せられる。なほ「風流無三(ミヤビナミ)」(4・721) の例がある。 【考】 伊勢物語 (第一段) うゐかうふりの條の結末に「むかし人はかくいちはやきみやびをなんしける」とある、その「みやび」の意に近く用ゐられたもので、この相手はいちはやきみやびの出来ない、おそのみやびをだと罵つたのである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「於曾能風流士」(オソノミヤビヲ) オソは、形容詞オソシの語幹で、集内に「於曽早も汝をこそ待ため」 (14・3493) のような遅い意味の場合と「汝が心から於曽やこの君」 (9・1741) のような愚鈍の意味の場合がある。ここは後者。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 127 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 【題詞】 大伴宿禰田主報贈歌一首 〔頭書〕神田本、前行ニ續ケテ書ケリ。頭書ニ「別行」アリ。又肩ニ墨ノ合点ヲカケソノ右ニ「別行」アリ。 〔本文〕歌。神田本、「謌」。西本願寺本、ナシ。 〔訓〕京都大学本、赭訓アリ、次ノ如シ。「大伴ノ宿禰ノ田主報ン贈ル。」 〔諸説〕報贈歌。万葉考、「報贈」ハ「和」ノ誤。 【本文】 遊士爾 吾者有家里 屋戸不借 令還吾曽 風流士者有 (タハレヲニ ワレハアリケリ ヤトカサス カヘセルワレソ タハレヲニアル) 〔頭書〕類聚古集、前行ニ「田主報贈歌」アリ。 袖中抄、第十九「又万葉集ニ(中略)タハレヲニワレハアリケリヤトカサスカヘセルワレソタハレヲ(風流士)ニハアル」 〔本文〕(第一句)士。元暦校本「土」。(第五句)士。元暦校本「土」。 (第五句)有。類聚古集、ナシ。 〔訓〕タハレヲニ。元暦校本「あそひをに」。右ニ朱「タハレヲニ御本」アリ。朱頭書「所名」アリ。古葉略類聚鈔・神田本「アソヒヲニ」。古葉略類聚鈔、「アソヒ」ノ右ニ「タハレ」アリ。神田本、漢字ノ左ニ「タハレヲニイ」アリ。 ヤトカサス。神田本「ヤトカサヌ」。 タハレヲニアル。元暦校本・類聚古集「たはれをにはある」。古葉略類聚鈔・神田本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本「タハレヲニハアル」。古葉略類聚鈔、訓ノ右ニ「ヨシヒトニハアル」アリ。 〔諸説〕 ヤトカサス。代匠記精撰本「ヤトカサテ」トモ訓ズ。 タハレヲニアル。仙覚抄「タハレヲニハアル」。童蒙抄「ミヤヒトニハアル」。略解「ミヤヒヲニハアル」。古義「者」ハ「煮」ノ誤。訓「ミヤヒヲニアル」
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「遊士尓(みやびをに)」訓・注 | 古義 | 遊士爾 [ミヤビヲニ]。吾者有家里 [アレハアリケリ]。屋戸不借 [ヤドカサズ]。令還吾曾 [カヘセシアレソ]。風流士者有 [ミヤビヲニアル]。 風流士者有を、舊訓タハレヲニアル、とあるを思へば、者は、煮[者の下に火]ノ字の誤にぞあるべき、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「遊士尓(ミヤビヲニ)」 この「みやびを」は道徳的風格のある者を意味する。その点で石川女郎の歌(126歌)とは異なるわけで、その相違を意識しながら田主は自分こそ真の「みやびを」だと歌い返しているのである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】遊士尓(みやびをに) 田主にとっては、「風流」とは俗につかず高邁な生き方を貫くことでだった。(続くケリに) このケリは詠嘆的用法で、自媒女を撃退した自分こそミヤビヲであった、と再確認した気持ちを表す。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「令還(かへしし)」訓・注 | 注釈 | 【訓釈】「令還吾曽 風流士者有」(カヘシシワレゾ ミヤビヲニハアル) 旧訓に「カヘセル」とあるが井上新考に「過去に云ふべき處なればカヘセルにてはかなはず。カヘシシとよむべし」とあるに従ふべきである。古義には「カヘセシ」としたが、「かへす」は四段活用であるから「セシ」ではいけない。前の歌に「カヘセリ」とあるのをそのままうければ「カヘセル」とあるべきやうにも思へるが、先方にみれんを持つ女には、帰されたのはなほ今のことであり、つつぱなした男にとつては、帰したのはもはや今に縁のない過去のことである。だから前者は「カヘセル」であり、後者は「カヘシシ」であつて両者の気持ちは生かされると云へるのではなからうか。「ル」と訓でも「シ」と訓でも訓添になるが、完了の「ル」は表記されてゐる場合が多いので、その意味でも「シ」と訓む方がふさはしい。古義に原文「者」を「煮」の誤として「ニ」と訓んだが、美夫君志に「者」は「ニハ」と「ニ」を訓添へる例 (162、210) があると云つてゐるのが正しい。上の「ゾ」をうけて「アル」と結んだのである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「令還吾曽 風流士者有」(カヘシシワレゾ ミヤビヲニハアル) 「帰しし」の原文「令還」。旧訓「カヘセル」で、童蒙抄・代匠記・万葉考などみなそれによっていたが、「万葉集古義」に「カヘセシ」と改め、井上通泰新考に、「過去に云ふべき処なれば「カヘセル」にてはかなはず、カヘシシとよむべし」として、「カヘシシ」と改訓した。澤瀉注釈に、これについて「『かへす』は四段活用であるからセシではいけない。前の歌にカヘセリとあるのをそのままうければカヘセルとあるべきやうにも思へるが、先方にみれんをもつ女には、帰されたのはなほ今のことであり、つつぱなした男にとつては、帰したのはもはや今に縁のない過去のことである。だから前者はカヘセルであり、後者はカヘシシであつて両者の気持ちは生かされると云へるのではなかろうか」と注している。「両者の気持」に関する部分は、それだけでは決定的な論拠たりえないが、注釈には、表記の面から、次のようにも記されている。「『ル』と訓んでも『シ』と訓んでも訓添になるが、完了の『ル』は表記されてゐる場合が多いので、その意味でも『シ』と訓む方がふさわしい」。この指摘は正しいと思われる。すなわち過去の助動詞「キ (シ)」の読み添えは巻第二でも「令落シ雪」 (104)、「左宿シ夜」 (135)、「相シ日」 (209、219) などに見られるが、完了の助動詞「リ (ル)」は「大雪落有」 (103)、「吾念流碁騰」 (112)、「聞流乎」 (126)、「吾乎還利」 (126)、「大夫跡念有」 (135)、「野中尓立有」 (144)、「君之結有」 (146)などのように書かれるのが普通で、読み添えは「生リ跡毛無」 (212)、「生ル刀毛無」 (215) という、人麻呂作歌の「イケリ(ル)」の場合に限られる。この石川女郎と田主の贈答歌でも「聞流」「還利」と記されており、「カヘセル」なら「令還流」と記すのではないかと思われるので、「カヘシシ」と訓む。既述の「ミヤビヲ」の意味に関連することだが、女郎作歌では屋戸を貸し快く交渉を持ってくれるような「ミヤビヲ」と聞いていたのに、その条件に反して自分を帰すような無風流なことをしたその時点を焦点として歌われているために「カヘセリ」と完了形になるのが自然である。これに対し田主の作は、女郎の作に対する報歌であり、女郎の「吾を帰せり」と歌っているときはすでに過去のことであるから、「カヘシシ」と過去形に歌うのは当然と考えられる。なお、この「宿貸さず帰しし吾」は、宋玉の好色賦の「三年、至今未許也」に対応すると言う(小島憲之『上代日本文学と中国文学』中)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 128 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 【題詞】 同石川女郎更贈大伴田主中郎歌一首 〔頭書〕古葉略類聚鈔、以下三行重出セリ。今、古一、古ニ、トシテ重子テ之ヲ校ス。 類聚古集、題詞ノ下ニ小字「依是疾贈□問□(言偏に卆)」訊也」アリ。「問」ハ「間」ヲ直セル如シ。 〔本文〕同。類聚古集・古葉略類聚鈔、ナシ。 贈。類聚古集、「賜」。 田。神田本、ナシ。 中。神田本、「伴」。 歌。神田本、「謌」。 〔訓〕西本願寺本・大矢本・京都大学本、訓アリ、次ノ如シ。「石川女郎更贈クル大伴田主ノ中郎ニ」。京都大学本、「川」ノ右下ニ赭「ノ」、「更」ノ右ニ赭「マタ」、「伴」ノ右下ニ赭「ノ」アリ。 温故堂本、「更」ノ右下ニ「ニ」、「主」ノ右下ニ「ノ」アリ。 〔諸説〕同石川女郎。万葉考、「同」ヲ衍トシ「石川郎女」ト改ム。 更贈大伴田主中郎歌。代匠記初稿本、「中郎」ノ「中」ハ「仲」ノ誤。童蒙抄、「中郎」ヲ「ナカイラツコ」ト訓ズ。万葉考、「贈大伴宿禰田主歌」ノ誤。万葉集攷證、「更贈大伴宿禰田主歌」ノ誤。万葉集檜枛、「聞大伴宿禰田主足疾贈歌」ニ作ル。
【本文】 吾聞之 耳爾好似 葦若未乃 足痛吾勢 勤多扶倍思 (ワカキヽシ ミヽニヨクニハ アシカヒノ アナヘクワカセ ツトメタフヘシ) 〔頭書〕元暦校本、別行平假字ノ訓ナシ。漢字ノ右ニ赭片假字ノ訓アリコレニテ校ス。赭訓ノ右ニ墨片假字ノ訓アリコレヲ記入ス。 古葉略類聚鈔ニ、訓ヲ附セズ。 西本願寺本・細井本・温故堂本、訓ノ肩ニ朱ノ合點アリ。 類聚古集、訓ヲ附セズ。 〔本文〕吾。類聚古集、「五」。 好。類聚古集、「奴」。 若。類聚古集、「□(吉に近い、下写真参照)」。 未。古葉略類聚鈔、「生」。 〔訓〕ワカキヽシ。神田本「ワカキヽモ」。漢字ノ左ニ「ワカキヽシ」アリ。コレニ朱の合點ヲカケタリ。西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「ワカキヽノ」。 ニハ。元暦校本・古葉略類聚鈔・神田本、「ニル」。元暦校本、「ル」ノ右ニ墨「ハ」アリ。温故堂本、漢字ノ左ニ「ニル/ノル」アリ。大矢本・京都大学本、漢字ノ左ニ「ニル」アリ。京都大学本、赭ニテ「ニル」ヲ消セリ。赭ニテ「ハ」ヲ消セリ。ソノ右ニ赭「テ」アリ。 アシカヒノ。元暦校本・古葉略類聚鈔・神田本、「アシノハノ」。元暦校本、「ノハ」ノ右ニ墨「カヒ」アリ。西本願寺本、「カヒ」モト青。大矢本・京都大学本、「カヒ」青。 アナヘク。元暦校本、「アナ」ナシ。以下ヲ「イタ」トセリ。右ニ墨「アナヘク」アリ。古葉略類聚鈔、「アシイタル」。神田本、「アシイタ」。漢字ノ左ニ朱「アナヘク」アリ。細井本、「アルヘク」。温故堂本、「痛」ノ左ニ「ナシ」アリ。大矢本・京都大学本、「ナヘク」青。京都大学本、漢字ノ左ニ赭「アシイタ/アシヒク」アリ。 ツトメ。温故堂本、漢字ノ左ニ赭「ツツシム/・・・ミ」アリ。大矢本・京都大学本、三字青。 〔諸説〕ワカキヽシ。仙覚抄、「ワカキヽシ」(古點)ヲ否トシテ「ワカキヽノ」トス。万葉集古義「アカキヽシ」。 ミミニヨクニハ。仙覚抄「ミミニヨクニル」。童蒙抄「ノミニタガハズ」。万葉集古義「ミミニヨクニツ」。 葦若未乃、アシカヒノ。仙覚抄「アシノハノ」(古點)ヲ否トシ「アシカヒノ」トス。拾遺集、「アシノハノ」ヲ可トス。代匠記精撰本、「アシノウレノ」カ。童蒙抄「アシカヒ」ノ「ヒ」濁音トス。万葉考、「未」ハ「末」ニ作ル。万葉集略解、宣長、「アシノウレノ」トス。又「若末」ヲ「若生」ニ作ルニヨラバ「アシカビノ」ト訓ズトス。万葉集攷證、「末」ハ「生」ノ誤ニテ訓「アシカビノ」トスルヲ可トス。万葉集檜枛、「葦若末乃聞ニテ「アシノウレノ」ト訓ス。 アナヘクワカセ。仙覚抄、「アシイタワカセ」(古點)ヲ否トシ「アナヘクワカセ」トス。拾遺集、「アシイタ」ヲ可トス。代匠記精撰本、「アナヘク」ヲ可トス。童蒙抄、「アシヒカハアセ」。万葉考、「アシナヘワガセ」。万葉集古義、「アナヤム」トス。又「アナヘク」、「アシヒク」ヲモ可トス。万葉集略解礼記、「アシイタムワカセ」、義門云、「アシタキ」。
【左注】 右依中郎足疾贈此歌問訊也 〔本文〕疾。神田本、「痛」右ニ「疾」アリ。 訊。元暦校本・神田本、「□(言偏に卆)」。 〔訓〕西本願寺本、訓アリ、次ノ如シ。「依ラ中郎足ノ疾(ヤマヒ)ニ贈テ此歌ヲ問ヒ訊ラフ也」。 細井本、訓アリ、次ノ如シ。「依中郎足ノ疾(ヤマヒ)贈テ此歌ヲ問(トヒ)訊(トフ)ラウ也」。 温故堂本、訓アリ、次ノ如シ。「依中郎足ノ疾ニ贈テ此歌問ヒ訊(トフ)ラフ也」。 大矢本・京都大学本、訓アリ、次ノ如シ。「依テ中郎足ノ疾(ヤマヒ)ニ贈テ此歌ヲ問ヒ訊(トフ)ラフ也」。但、京都大学本、赭ニテ「ヤマヒ」ヲ消セリ。「此」ノ右下ニ赭「ノノ」アリ。 神田本、訓アリ、次ノ如シ。「依中郎足痛ニ贈此歌問ヒ訊ラフ也」。 〔諸説〕中郎。代匠記初稿本、「中」ハ「仲」ノ誤。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 題詞「同」について | 注釈 | 「同」の字、類聚古集 (十二・卅八) と古葉略類聚鈔 (四・ニウ) とに無く、目録もないので考 (万葉考) に衍字としてゐるが、類聚古集などは名の如く類聚されたもので、前の歌から離されて収められてゐるから、「同」の字を削つたのは当然であり、現に古葉略類聚鈔にはこの歌 (四・廿三オ) 重出し、そこには前の二首につづけてあげられてゐて「同」の字が加へられてゐる事を見ても原本にあつたことがわかる。特にこの字を加へたのは歌の内容が前二首とは別のものである為に同名異人と見られる事もあり得るところから、やはり同人同時の作である事を示す為に「同」の字を加へ、「更贈」としたものと思はれる。右の左注には「仲郎」とし、「中郎」とある。通用したものと思はれる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「吾聞之 耳尓好似」訓・注 | 註釈 (全文注) |
吾聞之 耳尓好似 葦若末乃 足痛吾勢 勤多扶倍思 [ワカキゝシ ミヽニヨクニル アシカヒノ アナヘクワカセ ツトメタフヘシ] 此歌、古點ニハ、ワカキヽシ、ミヽニヨクニル、アシノハノ、アシイタワカセ、ツトメタフヘシト點セリ。ソノコトハ不分明。ヨリテ、少々是レヲ和シカヘタリ。ワカキヽシ、ミヽニヨクニハ、アシカヒノ、アナヘクワカセ、ツトメタフヘシ。此歌ヲハ、右依 (テ) 二中郎足 (ノ) 疾 [トキニ] 一贈 (リ) 二此歌 (ヲ) 一問訊 [トヒトフ] 也。トイヘリ。第三句、葦若末乃トカケルハ、アシカヒ也。葦芽トイフハ、アシノツノクミオヒタルナリ。アナヘクトイフハ、アシヲイタミテヒク也。アシカヒハ、葦ノ苗ナレハ、アナヘクトイフコトハノ、葦苗ニカヨヘハ、ヨソヘヨメル也。ツトメタフヘシトイヘルハ、ツヽミタマウヘシ也。ワカキヽノ、ミヽニヨクニハトハ、アシヲヤムトキコユル、ワカキヽノコトク、マコトナラハ、ツヽシミタマヘト、ヨメル也。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | 初の二句は、古点のまゝに、ワガキヽシ、ミヽニヨク似ルと讀べきか。其故は、吾聞シとは兼て脚氣ありと聞なり、耳ニヨク似ルとは火を乞に行て見たる時聞し如くなるなり、又好と云に當て、聞に似ばと云は少叶はずや、耳とは音を開所なればきゝに能く應ずると云はんが如し、第十一に、ことにいへば耳に輙しとよめる耳の如し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 (全文注) |
吾聞之。耳爾好似。葦若末 [末ヲ今未ニ誤] 乃。足痛吾勢。勤多扶倍思。 [わがききし。みみによくにば。あしかびの。あしなへわがせ。つとめたぶべし。] アシカビノ枕即。和名抄、蹇阿之奈閇と有り。吾キキシ耳ニヨク似バとは、吾聞が如くならばと言ふをかくいへり。卷十一、戀といへば耳にたやすし。ツトメは紀に自愛の字をツトメと訓みたるが如し。タブベシは給フベシなり。未は末の誤りにて義訓なり。宣長云、若末をカヒとは訓み難し。卷十長歌に、小松之若末爾と有るはウレと訓めれば、ここも葦ノウレノと訓みて、足痛はアナヘクと訓まんか。蘆芽はなゆるものにあらず、一本若生と有るに據らば、カビと訓むべしと言へり。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 吾聞之云々は、アガキヽシミヽニヨクニツと訓べし、(ヨクニバとよめるは、甚わろし、) 吾聞しが如くにありつ、といふことを、かく云るはおもしろし、吾 (カ) 耳に聞しに、好 (ク) 似つと云が如し、今の人ならば、兼てわが聞しに似たり、など云べきを古人ならでは、かくは得いはじ、耳 [ミヽ] は、十一に、言云者三三二田八酢四 [コトエイヘバミヽニタヤスシ]、と云る(耳に輙 [タヤス] しなり、) に同し、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「吾聞之 耳尓好似」(ワガキキシ ミミニヨクニテ) 原文「好似」二字を古訓に「ヨクニル」とあつたのを、仙覚抄に「ヨクニハ」と改め「ワガキキノゴトク、マコトナラバ」と解したが、代匠記には再び「ニル」にかへして「吾聞シトハ兼テ脚気アリト聞ナリ。耳ニヨク似ルトハ火ヲ迄ニ行テ見タル時聞シ如クナルナリ。又好ト云ニ当テ、聞ニ似バト云ハ少叶ハズヤ」と云つてゐる。この場合の「耳」は「言に云へば耳にたやすし」 (11・2581) とあり、今も早耳とか耳学問とかいふやうに、聞く事であるから「耳に好く似る」とは聞いた通りに近い意である事は認められ、「ニバ」と訓む事は代匠記に云つたやうに従ひがたいが、(1) 「ニル」と云つてそこで切るか、(2) 「連体形」として下へつづけるか、(3) 古義に改めたやうに 「ニツ」さと訓むか、或いは別に訓釈があるか、といふ点に問題がある。(1) だと「私が聞いた通りである」といふ事になり、その二句が下三句と相対する事になるが、この初二句は果たしてさうした独立した句として据ゑらるべきものであらうか。今と同じく枕詞を第三句とした作を集中に求めると総数約二百四十首。そのうち、 吾が背子はいづく行くらむ 奥つ物名張の山をけふか越ゆらむ (1・43) の如く第二句で切れるもの壓倒的に多く、約九十を数へる。しかしそのうちで第二句を動詞の終止形で止めたものは極めて少ない。 我が園に宇米能波奈知流(ウメノハナチル) ひさかたの天より雪の流れ来るかも(5・822) 黒牛の海 紅丹穂経(クレナヰニホフ) ももしきの大宮人しあさりすらしも(7・1218) の如きがそれであるが、これらの初二句は下三句と相対して立派に独立した句としての存在が認められるけれども、「吾が聞きし耳によく似る」といふ句をそれと同様に見られるであらうか。同じくここで切るとしても「耳によく似つ」と云へば、少しは実感が出て力がこもる。古義がこの改訓を試み、井上、金子、土屋の諸氏-土屋氏にはこの句の内容について異説がある。その事は後に述べる-が、、従はれた所以もそこにあると思ふ。だが、それも、 妹が門 去過不勝都(ユキスギカネツ) 久方の雨も零らぬか其を因(よし)にせむ (11・2685) 思へども念毛金津(オモヒモカネツ) あしひきの山鳥の尾の長きこの夜を (11・2802) などに較べると、やはり「ニル」と訓んだ場合に云つたのと大差のない事が認められよう。それにしても「ニツ」と訓めば「ツ」は訓添へる事になるが、「ツ」の訓添は集中に極めて乏しい。「結之情 忘不得裳 (ムシビシココロ ワスレカネツモ)」 (3・397) の如きは「痛情者 不忍都毛 (イタキココロハ シノビカネツモ)」 (3・472) と相対照して「ツ」の訓添といふ事が認められるが、「似」一字を「ニツ」と訓む事には大きな不安がある。また「耳に好く似てゐた」、「聞いた通りであつた」といふ意味を「耳によく似つ」といふべきかにも疑がある。「つ」は問題の助動詞であるが、まづ「た」、「てゐる」と訳してあたる語であつて、「であつた」、「てゐた」と訳してふさはしい例は見当たらないからである。以上の如く考察すると、(1) (3) 両説とも従ひがたく、講義に「この『ニル』は終止の用法にあらずして連体として、下の『吾勢』に対しての限定をなす格たるなり。その意はわがかねて噂に聞きし所の如くにあるわが兄といふなり。」と云ひ、全註釈に「連体形とするを可とする。」とある所以が-両書には理由は説明されてゐないが-うなづけるやうに思ふ。だが、中に枕詞を挿んだ連体形といふものは集中に数首あるに過ぎず、 吾を待つと君がぬれけむ (あしひきの) 山のしづくにならましものを (108) ともし火のかげにかがよふ (うつせみの) 妹がゑまひし面かげに見ゆ (11・2642) 消残りの雪にあへ照る (あしひきの) 山橘をつとに摘みこな (20・4471) の如きであるが、これら第二句と第四句との連結が極めて自然であつて、疑の余地なきものであるが、「耳によく似る (あしかひの) 足ひくわがせ」では「足ひく」へつづくか、「わがせ」へつづくかもあいまいであり、調もぎこちない。やはり落ち着かないことは、(1) (3) と同様である。さうした例の少ない、あいまいな接続と考へないで、も少し自然な訓み方がなからうか。「耳によく似る」といふ言葉がはじめに述べたやうに「聞いた通りに近い」といふ意味の語として認めるとしても、かうした言葉は独立した句として、終止や連体の形で用ゐられる言葉ではなくて、本来条件句又は修飾句として「ば」とか「て」とかいふ言葉を下につづけて「聞いた通りだつたら」とか「聞いた通りで」とかいふ風に用ゐられる句ではないだろうか。さう考へて再びかへりみられるのは仙覚が「耳に好く似ば」と訓んだ事である。彼が「ニル」を「ニバ」と改めたのは、さうしたこの語の用法に敏感であつた為だと云へるのではなからうか。一首の型式としても第三句に枕詞を用ゐたものには、 みもろづく 三輪山見者(ミワヤマミレバ) 隠りくの初瀬の桧原思ほゆるかも (7・1095) 命をし 麻多久之安良婆(マタクシアラバ) ありぎぬのありて後にも逢はざらめやも (15・3741) の如く「ば」でうけたもの集中に十七例の多きを数へる。仙覚が「ニバ」と訓んだ意図は十分うなづく事が出来る。これならば、(1) (2) (3) のどの説よりもすなほに、一首の歌として立派に成立する事が出来る。ただ、代匠記に注したやうに、今の場合は田主を訪問した後であるといふ点で、「似ば」といふ未然がおちつかない。とすれば、おちつくところは、おのづからにして、「耳によく似て」となるのではなからうか。 窓越しに 月臨照而(ツキオシテリテ) あしひきのあらし吹く夜は君をしぞ思ふ (11・2679) 久かたの王都乎置而(ミヤコヲオキテ) 草枕旅ゆく君をいつとか待たむ (13・3252) 第二句を「て」でうけて枕詞を挿んで下の句へつづく例は集中になほ十例を数へる。「都をおきて-旅ゆく君」、「耳によく似て-足ひくわが背」。聞いた通りで、足を患つていらつしやるあなた。極めて自然におちつくのではなからうか。「ツ」の訓添が極めて少ない事は右に述べたが、「テ」の訓添は「道行人毛 獨谷 似之不去者 (ミチユクヒトモ ヒトリダニ ニテシユカネバ)」(207)、「秋山 始黄葉尓 似許曾有家礼 (アキヤマノ ハツモミチバニ ニテコソアリケレ)」 (8・1584) の如く「似」といふ言葉についてだけでも二つまであげる事が出来る。「似」一字を「ニテ」と訓む事は十分に認められる。即ち「ワガキキシミミニヨクニテ」と訓み、私が聞いてゐた言葉に、どうやら間違ひがなくて、と解いて不都合はないやうである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「吾聞之 耳尓好似」(ワガキキシ ミミニヨクニル) 耳はここでは耳で聞いたこと、噂。「好似」を元暦校本・古葉略類聚鈔・紀州本の訓の付訓に「ヨクニル」とし、代匠記などもそれによっているが、古義には「ヨクニツ」とする。最近の注釈書でも前者によるものが多いが (全註釈・窪田評釈・佐佐木評釈・古典大系・古典全集・古典集成・桜楓本・講談社文庫など)、新考・金子評釈・私注には後者 (ヨクニツ) を採り、注釈は諸説を詳細に検討し、「ヨクニテ」という新訓を提示している。「ヨクニル・ヨクニツ・ヨクニテ」という三種の訓の内、文字に即してもっとも無理のないのは「ヨクニル」であろう。「ヨクニツ」は、「ツ」の読み添えを必要とする点で、可能性が乏しい。「ツ」の読み添えは、万葉集内に例の少ないものであって (注釈)、とくに巻一・巻二にはまったく見えない。したがって、他の面から確かな根拠が提示されるのでないかぎり、認め難い訓と言わなければならないし、その上無理な読み添えを認めたとしても「吾が聞きし耳によく似つ」は二句切になって、「葦のうれの足痛く吾が背」との関係がやや不安定な感じを与えるのは、やはり「ニツ」説に疑問を抱かせるものと思われる。このことは【考】の条にも触れる。その点で、「ヨクニテ」は可能性のある訓と言える。注釈に「窓越しに 月臨照而(ツキオシテリテ) あしひきのあらし吹く夜は君をしぞ思ふ」 (11・2679) と、「久かたの王都乎置而(ミヤコヲオキテ) 草枕旅ゆく君をいつとか待たむ」 (13・3252) の二首をあげ、第二句を「て」で受け、枕詞を挟んで下句に続く例は多いので、この歌も「耳によく似て-足痛く吾が背」と読み、噂に聞いた通りで、足を患っているあなたと解釈したらどうだろうかと言っているのは、「テ」の訓み添えが巻一・巻二に見られるだけに、可能性のある訓と思われる。注釈に「ヨクニテ」を採用したもう一つの理由は「ヨクニル」と訓み、あとの「アシヒクワガセ」にかかる連体形と解した場合に、「おちつかない」と感じられる点にある。中に枕詞をはさんだ連体形は万葉集に数例見られる。 吾を待つと君がぬれけむ (あしひきの) 山のしづくにならましものを (108) ともし火のかげにかがよふ (うつせみの) 妹がゑまひし面かげに見ゆ (11・2642) 消残りの雪にあへ照る (あしひきの) 山橘をつとに摘みこな (20・4471) などであるが、これらは「第二句と第四句との連結が極めて自然」なものと思われるのに対し、「耳によく似る (葦のうれの) 足ひくわがせ」では、「足ひく」へ続くのか「わがせ」へ続くのか曖昧であり、調べも「ぎこちない」と評されている。しかしながら、注釈に強調されているほど、「中に枕詞を挿んだ連体形」の例が少ないかどうかは、疑問である。注釈の調査は短歌の例に限られているようだから、長歌の場合を含めて「枕詞を挿んだ連体形」を探してみると、人麻呂作歌に限っても、数例にとどまらない。しかもそれが各種の枕詞にわたっているから、きわめて一般的に見られる表現であったと思われる。 ・・・霞立ち 春日の霧れる ももしきの 大宮所 見れば悲しも(1・29) つのさはふ 石見の海の 言さへく 幸の埼なる 海石にそ 深海松生ふる・・・(135) ・・・天雲の 八重かき別きて 神下し いませまつりし 高照らす 日の皇子は・・・(167) ・・・久方の 天つ御門を かしこくも 定めたまひて 神さぶと 磐がくります やすみしし 吾が大君の・・・(199) ・・・吾妹子と 二人吾が宿し 枕づく 嬬屋の内に 昼はも うらさび暮らし・・・(210) ・・・敷栲の 手枕まきて 剣太刀 身に副へ寝けむ 若草の その夫の子は・・・(217) ・・・馬なめて み狩り立たせる わかこもを 獦路の小野に ししこそは い這ひ拝め・・・(3・239) 右のようにモモシキノ・コトサヘク・タカテラス・ヤスミシシ・ワカクサノ・ワカコモヲなど、多様な枕詞をここに見ることが出来る。短歌に例が少ないのは、おそらく形式上の制約があるためで、枕詞を挿んで連体修飾語と被修飾語の結ばれること自体は、とくに問題のないことだったと思われる。したがって、そうした面から「耳によく似る葦のうれの (葦かびの) 足痛く吾が背」を否定することは不可能である。それに「耳によく似る葦のうれの (葦かびの) 足痛く吾が背」を、「雪にあへ照るあしひきの山橘」などよりも、調べの「ぎこちない」表現と言えるかどうかも疑わしいだろう。注釈に「耳によく似る」が「葦のうれの (葦かびの)」に掛かるか、「足痛く」に掛かるか曖昧と記されているのも、むしろ曖昧な受け取り方のために「ぎこちない」表現という感じが強められたところがありはしないかと思う。「耳によく似る」は、第三句の「足痛く吾が背」に掛かるのであり、その間にアシと同音のアシノウレノ (アシカビノ) が挿入されていると考えるなら曖昧さは薄らぎ、「ぎこちなさ」もあまり感じられなくなるのではあるまいか。「耳尓好似」という本文を文字に即して読んだ場合に、もっともすなおな読み方は、「ミミニヨクニル」という古写本にも見られる訓である。読み添えもないし、ただ文字のままに読み下せば「ミミニヨクニル」と読まれるから、ヨクニテより尊重されるべきである。最近の諸注の多くがこの訓を採用しているのは当然とも言えよう。なお、次句「葦若末乃」の訓にも関連するので、次項参照。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「葦若末乃」訓・注 | 註釈 | 此歌ヲハ、右依 (テ) 二中郎足 (ノ) 疾 [トキニ] 一贈 (リ) 二此歌 (ヲ) 一問訊 [トヒトフ] 也。トイヘリ。第三句、葦若末乃トカケルハ、アシカヒ也。葦芽トイフハ、アシノツノクミオヒタルナリ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拾穂抄 (全文注) |
わかきゝしみゝによくにるあしのはのあしいたわかせつとめたぶへし 吾聞(仙きくの)之耳爾好似葦(仙あしかひの)若未乃足痛仙(あなへく)吾勢勤多扶倍思 わかきゝし (の) みゝによく 仙曰古点詞不分明によりてかく和しかへたり第三第四ノ句あしかひのあなへくわかせあしかひとは芦の角くみ生たる也あなへくといふはあしをいたみてひく也、芦芽 [アシカヒ] は芦の苗 [ナヘ] なれはあなへくと云詞の芦苗にかよへはよそへよめる也つとめたぶへしとはつゝしみ給ふへし也我きゝのみゝによく似はとは足を痛むと聞ゆる我聞のことくならはつゝしみ給へとよめる也愚案古点あしのはのあしいたわかせといふを詞不分明といふ事不審芦の葉のとは足いたといはん枕詞常の躰也あしいたは足いたむわかせこつゝしみつとめよといへるなるへし仙説あなへくもさもあるへけれと芦苗にかよふなといふ儀いりほかにてあるへくもあらぬ事にや只可レ用二古点一歟 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | アシカビは、神代紀には、葦牙とかけり、又はあしつのと云、和名云、菼[草冠に炎]【音、毯、和名、阿之豆乃、】蘆之初生也、六帖に、蘆つのゝ生てし時に天地と、人とのしなは定まりにけり、諺に草木の芽 [メ] の出るをめかびと云も、同詞を重て云なり、今按第十夏雜歌の初の長歌に、小松がうれと云々、若未と書たれば、アシワカノと讀べきか、歌仙家集の中に元眞、難波のあしわかとよめり、葦の若きをやがて體になして呼なり、譬ば童の名に某若と云がごとし、あしかびは、纔に萠して角ぐむ程を云、あしわかは、水を出もし出もせぬ程を云べければ、若未とかける意これなるべき歟、第十に、吾宿の萩の若未長、此下の三字を、ワカタチと点ぜり、此には今按の義あり、彼處に至て注すべし、若未の二字彼に同じ、葦牙よりは長じて後なる事准じて知べし、註釈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 葦若未乃 [アシノウレノ] 葦若未乃 未ノ字、類聚抄には生と作 [ア] り、) は、足痛 [アナヤム] の枕詞なり、本居氏、これは、若生とある本によらば、あしかびと訓べし、葦の若芽は、かたからず、なよなよとしたる物なるゆゑに、足痛 [アナヤム] に、冠らせつらむ、又未は、末の誤にてもあるべし、十ノ卷に、小松之若末爾 [コマツガウレニ] 、ともあればなり、これによらば、葦のうれのとよむべし、又同卷に、芽之若末長とあるは、はぎのうれながし、とよむべし、若末長を、ワカナヘと訓ては字にかなはず、なへを、末長と書べき由なきをや、右の如く、若末と云こと、二ツ例あれば、こゝもあしのうれの、なるべくやあらむ、冠辭考の説は、これかれ誤れりと云り、既く水戸侯の釋にも、アシノウレノと訓たまへり、字も末と作り、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「葦若末乃」(アシカビノ) 原文「末」の字元暦本以下多く「未」とある。然るに「小松之若末 (コマツガウレ)」 (10・1937) の例があり、「未」と「末」とは古写本の一部には混同してゐる事があり、今も類聚古集 (12・卅八)、及び古葉略類聚鈔 (四・二ウ) に載せられたものは「未」とも「末」とも見られる字になつてゐるので、「未」は「末」の誤と見てよからうと思ふ。さてこの句古訓に「アシノハ」とあつたのを仙覚が「アシカヒノ」と改めた。古事記神代巻に「如二葦牙(アシカビノ)一因二萌騰之物一而成 神名宇麻志阿斯訶備比古遲神」とあり、神代紀上にはその神の名を「可美葦牙彦舅尊 (うましあしかびひこぢのみこと)」とあり、それよつて葦牙を「アシカビ」と訓み、葦の芽生をいふのは問題のないところで、仙覚はそれによつたものと思はれるが、右に引用した巻十の例はたしかに「ウレ」と訓むべきものである為に、宣長は-略解に引用-「アシノウレノ」と訓み改め、以後の諸家多くそれに従ふ事となつた。しかしまた古葉略類聚鈔 (四・廿三オ) に再び載せられたものには「末」の字「生」となつてゐるので、宣長はそれによればまた「アシカヒノ」とも訓むべしと云つてゐる。「葦若生」であればたしかに「葦芽」と同様に見られるやうであるが、それは現存のただ一本、それも二つの記載の一方のみといふのであるから、直ちにそれによるとするには躊躇が感ぜられる。しかしかりに「葦若末」とあつても「アシカビノ」と訓めはしないか。若末をウレと訓んだ例はあるにしても、いつも必ずさう訓まねばならぬとは限らない。「幾許」は「ココダ」とか「ココダク」とか訓む例 (220、4・658、その他) が多いが、また「イクバク」と訓む例 (8・1658) もあるやうに、芽の事を「若末」と書いたとも考へる事が出来る。私注にも「アシカビでなくアシノウレであらうといふのは、あまりに字面になづみ過ぎる。葦芽、葦若末は同語をあらはすものと見るべきだ。枕詞であるから伝来ある語を用ゐたと見るのが穏当だ。」とある。この「枕詞であるから云々」の語は私の深く同感するところであり、私はこの語の枕詞としての二つの特質について次に小見を述べる。まづ第一に枕詞としての接続の形式であるが、この枕詞は次の句の「アシ」と同音繰返しの枕詞と思はれるが、その点「あしかびの」としても「あしのうれの」としても同様であるが、「あしかび」であれば一語と見られ、「あしのうれ」であれば「あし」と「うれ」とのニ語を「の」で結んだものとして、次の句の「アシ」との接続が前者に比してややもの遠い感を与える。枕詞や序詞のくりかへしの接続の場合、その句の句頭の語をくりかへすものと句中の語をくりかへすものとあり、たとへば、 (1) 深海松の 深めて思へど (135) (2) ありきぬの ありて後にも (15・3741) (3) 群鳥の 群立ち行かば (9・1785) (4) あしほ山 あしかるとがも (14・3391) の如きものと、 (5) 葦の根の ねもころ思ひて (7・1324) (6) 玉の小琴の ことなくば (7・1328) (7) 小松がうれの うれむぞは (11・2487) の如きとがある。前者がすべて一語の形であり、「の」「が」の助詞を挿むものがすべて後者であるとは限らない。「しののめのしのひてぬれば」 (11・2754) の如きものもないではない。しかし大体かう云つて右の如き区別のある事は認められるとすれば、殊に右にあげた「(4) (5) (7)」の如き例と較べあはす時、アシの語に冠する枕詞としては「あしのうれの」よりも「あしかびの」の方が適切である事は十分にうなづけるであらう。更に第二には枕詞の音数の考察であるが、枕詞といふものは五音を常態とするが、古くは四音のものが少なくなかつた。人麻呂の頃に至つて次第に五音に整へられた (『作品と時代』七四-七六頁参照) が四音のものはなほ少し残されてゐた。しかし六音のものはこの頃まで見当たらない。六音の枕詞は集中に「牡牛乃 (コトヒウシノ)」 (9・1780 蟲麻呂集)、「翼酢色之 (ハネズイロノ)」(4・657 坂上郎女、12・3074)、「伊毛我伊弊尓 (イモガイヘニ)」 (17・3952)、「和我伊能知乎 (ワガイノチヲ)」 (15・3621)、の如きもので、極めて少なく、殊に時代が新しく、第三期以後と見てよい。従つてもし「アシノウレノ」と訓めば当時としては異例である。尤も字余りとしても、他の数例いづれも、中間に単独母音節を交へてのものであるから、音調の上からはその存在は許される。しかし右に述べた接続上の異例に加へて、音数上の異例をつくつてまで「アシノウレノ」と訓むよりは、むしろ「若末」を記紀の「牙」と同様に見、「アシカビノ」と訓む方がおだやかではなからうか。しかもこの句には本文にも異同のある事右に述べた如く、私は疑を存しつつも仙覚の新訓を尊重する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「葦若末乃」 (アシノウレノ) 「葦若末乃」の「末」の字、元暦校本以下に「未」とあるが、「末」が正しい (稲岡「万葉集巻ニ訓詁存疑(一)」『論集上代文学』第十二冊)。旧訓「アシノハノ」を仙覚抄に「アシカヒノ」と改訓した。童蒙抄・攷証など同訓。古義・略解に「本居氏 (云)」「宣長云」として「アシノウレノ」と訓んでいるが、この訓は「玉の小琴」などに見えず、宣長全集の中で確かめえない。私注には「葦牙、葦若末は同語をあらはすもの」として「アシカビノ」の訓を採る。注釈も、六音の枕詞は万葉集第三期以後に見られること、同音反復の枕詞は、「深海松の 深めて思へど」「ありきぬの 在りて後にも」のように「の」の前に来る語は一語であるか、もしくは「小松がうれの うれむぞ」や「葦の根の ねもころ」のように後出の名詞を繰り返す形が一般であることなどを理由として、「アシノウレノ」を否定し、「アシカビノ」説による。確かに「アシカビノ」ならば五音で形も整えられるように思われるが、別稿 (「万葉集巻ニ訓詁存疑(一)」『論集上代文学』第十二冊) にも詳述したとおり、字余りの問題は「アシノウレノ」のように句中に単独母音を含む場合、単純に音数のみでは判断しえないし、語を隔てての反復も、枕詞でなく序詞の中に「荒磯越し外行く波の外心」 (11・2434、人麻呂歌集)、「秋柏潤和川辺のしののめの人にはしのび君にあへなく」 (11・2478、同上) のように見られるので、決定的な論拠とはし難いだろう。「葦若末乃」を文字に即してすなおに読めば「アシノウレノ」となることは、「夕されば 小松之若末に」 (10・1937) を「コマツガウレ」と訓まれることによって裏付けられよう。その上、「アシカビ」は「葦のかつがつ生初たるを云」 (記伝) う古語と思われるのであり、国土創成の神話への連想や、萌えあがる生命力の印象をともなっていたと考えられる。古義引用の宣長説に「葦芽はかたからずなよなよとしたる物なるゆゑに、足痛に冠らせつらむ」と言うように「足痛」に冠する枕詞としては、そうした神話的なエネルギーを印象する語よりも「アシノウレノ」の方がふさわしいであろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「足痛」訓・注 | 註釈 | アナヘクトイフハ、アシヲイタミテヒク也。アシカヒハ、葦ノ苗ナレハ、アナヘクトイフコトハノ、葦苗ニカヨヘハ、ヨソヘヨメル也。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 足痛は、アナヤムと訓べし、十四に、比登乃兒乃可奈思家之太波々麻渚杼里安奈由牟古麻能乎之家口母奈思 [ヒトノコノカナシケシダハヽマスドリアナユムコマノヲシケクモナシ]
とあり、(これに依ば、直に安奈由牟 [アナユム] とも訓べけれども、此は東語なれば、定マりたる古言のまゝに、今は安奈夜牟 [アナヤム] 、と訓むぞ宜しき、抑モ奈夜牟
[ナヤム] と云言は奈與夜可 [ナヨヤカ] 、奈與奈與 [ナヨナヨ] 、奈由流 [ナユル] 、奈夜須 [ナヤス] 、など云と同くて、もと軟弱
[ナヨヤカ] なるよしの言なれば、葦若末乃 [アシノウレノ] 、といふよりの屬 [ツヾキ] に、よくかなへり、又舊本に、アナヘクとよめる、是もあしからじ、(史記呉ノ大伯世家に、公子光、佯
[イツハリテ] 爲 [マネシテ]二足疾 [ナヘク] 一、入二于窟室ニ一、左傳に、光僞テ足族 [ナヘク] と見ゆ、又官本に、アシヒクと訓り、枕詞の足引 [アシヒキ] を、足病 [アシヒキ] とも書たれば、さも訓べし、略解に、あしなへとよめるは、太 [イミ] じく惡し、吾勢 ワガセ] と體言につゞきたれば、必ス用言に訓ずては、協はぬことなり、) 和名抄に、説文ニ云、蹇ハ行テ不レ正也、阿之奈閇 [アシナヘ]、此云二那閇久 [ナヘクト] 一、靈異記に、攣ハ、氐奈幣 [テナヘ]、躄ハ、阿志那倍 [アシナヘ]、字鏡に、癖ハ、腹内ノ癖病、足奈戸 [アシナヘ] とあり、那閇久 [ナヘク]
も、上の那夜牟 [ナヤム] と、本ト同言なり、但し然らば、那延久 [ナエク] とあるべきに、假字違へるは、いかにといふに、(丹波康頼神遺方に、阿師奈衣
[アシナエ] とあれど、假字亂れて後の書なれば、それはたのみがたし、) 凡て本は同言ながらも、夜伊由延 [ヤイユエ] にも、波比布閇 [ハヒフヘ]
にも通はして、活用 [ハタラケ] る言あり、萎をも、志那延 [シナエ] とも、志那閇 [シナヘ] とも、云るにて、意得べし、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「足痛」(アシヒク) 原文「足痛」を古点に「アシイタ」とあつたが「アナヘク」と仙覚抄に改めた。京都大学本には本文の左に赭筆で「アシイタ」と並べて「アシヒク」ともあるので、それも古訓と思はれる。万葉考には「アシナヘ」とし、岡本保孝の略解礼記には「アシイタム」とし、古義には「アナヤム」としたが、講義に「痛」には「蹇」の義がないとあるやうに、「ナヘ」とか「ナヘク」とかは従ひ難く、又「アナヘク」や「アナヤム」では枕詞の「アシ」との接続も不明になる。「アシイタム」は文字通りの訓ではあるが、講義に「足疾乃 (アシヒキノ)」 (4・670)、「足病之」 (7・1262) の用例のある事と今の左注に「足疾」とある事とに注意し、左注の場合は体言に今の場合は用言にしたものとして、古訓の一に返されたのに従ふべきである (講義には「新考の説によりて」とあるが、新考の初版本にはアシヒクとあつたが、増訂本にはまたアシナヘに変更されてゐる)。森本治吉博士の『新見』には「あしひきの」の「キ」は乙類の仮名だから「ひき」は上二段活用の動詞であるはずで「ひく」とはならずとし、又「痛」には「アナ、イタ」の訓はあるが、「ヒク」とは訓めないとして、「アシイタキ」と訓まれてゐるが、「あしひきの」の「キ」は甲乙混用されてをり (『作品と時代』六五頁-六八頁参照) 「足疾」「足病」の場合などは甲類即ち四段活用と認むべきものであり、又説文 (七) には「疾」にも「痛」にも共に「病也」とあつて両者を同訓とする事を少しも妨げない。「疾」を「ヒキ」と訓んだのもただ一例だけであり、「痛」も他に訓例がなくとも「疾」に準じて「ヒキ」とも「ヒク」とも訓む事は十分認められる。即ち「アシヒク」と訓で足を患つてゐるわが背、の意に解する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「足痛」 (アシヒク) 原文「足痛」を仙覚は「アナヘク」、万葉考に「アシナヘ」、古義に「アナヤム」と訓んだが、講義には、枕詞「アシヒキノ」を「足疾乃」 (4・670)、「足病之」 (7・1262) と記す例のあることから「病=疾=痛」と認め、「アシヒク」とした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「勤多扶倍思」訓・注 | 古義 | 動多扶倍思 [ツトメタブベシ] (倍ノ字、類聚抄に、信とあるは誤なり、思字、拾穗本には、之と作り、) は、契冲、勤 [ツトメ] は、日本紀に自愛とかきて、つとめとよめりといへり、(余云、舒明天皇ノ紀に、慎テ以自愛 [ツトメヨ] 矣、) 多扶 [タブ] は、たまふなり、土佐日記に、我國には、かゝる歌をなむ、神代より神もよみたび云々、同書定家ノ卿本に、楫取又曰く、ぬさには御心のいかねば、御舟も行ぬなり、なほうれしと思ひたぶべきもの、たいまつりたべといふ、平家物語に、木曾が、皷判官にあひて、抑々わ殿を、皷判官と云は萬ツの人にうたれたうたか、はられたうたかとぞ、問たりけるとあるも、たうたかは、賜 [タ] びたかなり、なほ賜 [タ] を、多婢 [タビ] 多扶 [タブ] 多婆流 [タバル] 多辨 [タベ]、と云ること、これかれあり、四ノ巻に、幣者將賜 [ヌサハタバラム]、十四に、伊低兒多婆里爾 [イデコタバリニ]、十八に、己禮波多婆利奴 [コレハタバリヌ]、書紀雄略天皇ノ卷に、凡河内ノ直香賜、と云人ノ名ありて、註に、香賜、此云二舸□[手偏+施の旁]夫 [カタブ] 一とあり、さてつとめたふべしとは、保愛をくはへて、早く本復し給へ、といふなるべし、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「勤多扶倍思」(ツトメタブベシ) 舒明紀即位前紀に「故レ慎テ以テ自愛(ツトメヨ)矣」とある「自愛」が今の場合に適切である為に諸注に引用せられてゐるが、自愛を「ツトメ」とする訓注は存しないのであり、欽明紀 (五年二月) にも「戒 (ツトメヨ)」とあるが、それも傍訓にすぎず、集中にはこの他には「名に負ふ伴のを 己許呂都刀米輿 (ココロツトメヨ)」 (20・4466) とあるのみであるが、その用例と今の原文「勤」の文字とを照合すると、やはり勤とか勉とかいふ文字に相当する言葉である事が認められ、今の場合はその内容に自愛せよとか用心せよとかの意を含む事になると見るべきであらう。「たぶ」は「多婆利 (タバリ)」 (18・4133)、「多婢弖 (タビテ)」 (20・4455) などの例があり、四段に活用して、「賜ふ」又は「給ふ」の古語と見るべきである。ここは敬語の助動詞としての「給ふ」で、お大事になさいませの意となる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「勤多扶倍思」(ツトメタブベシ) 「勤」は新撰字鏡に「邵」に「勉也豆止牟」の注が見え、また「勉」に「勤也」の注もあるので「ツトム」と訓む。講義には、舒明紀の「自愛」を「ツトメヨ」と訓む例をあげ、ここの「トツメ」も自愛を意味するだろうと記している。「多扶 (タブ)」は敬語の「タマフ」の約。続紀宣命に「かたらひ宣り多布 (タブ) 言を聞くに」 (三十六詔) とあり、雄略九年紀の「凡河内直香賜」の「香賜」に「舸□[施の方が手偏]夫 (カタブ)」の訓注がある。ベシは勧誘の助動詞。大切になさって下さいよ、の意。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一首一考 | 注釈 | 【考】 私注に初二句を「ワガキキシ ミミニヨクニツ」と訓んで、「仲郎が『みやびをに吾はあり』といふのに対して『私はさきに君をおそのみやびをと申しましたが、なるほどいま仰せられると、それももつともで、君は評判の如くみやびをでいらつしやる』ととるべきで、此の歌では此の二句が主内容をなすものである。」と新見が述べられてゐる。しかしこの解釈は少し無理で、初二句は訓釈の條でも述べたやうに、下の句に対する修飾句とし、「ミミニヨクニテ」と訓んで、この作の主内容はやはり下の句にあると見るべきである。その「耳に好く似る」といふ内容については、金子氏の評釈に「初二句から考へれば成程、田主が一時脚気でも病んで困つてゐるといふ噂はありもしたらう。然しそれは何も常住の脚病といふのではなく、この時分にはもうピンピンしてゐたのだと見たい。只女郎が忍んで訪れた時に、田主は無精らしくおのが部屋から出て来ず、勝手に『任レ念就レ跡帰去也』で、一向構ひつけなかつた。その上『おその風流男』と嘲つてやると『宿かさず還ししわれぞ風流士』などと減らず口を叩くので、女郎は忌々しさに、一時の噂をこれ幸ひと利用して大いに誇張し、成程あの時出ていらつしやらなかつた事を思ふと、貴方は全く噂通りの足萎えなのですね、折角御療養なさるがよいと飜弄したのである。」とあり、新考の増訂本にも似た意味の事が加へられてゐるが、この想像があたつてゐやう。前二首の贈答に更にこの作を加へたのは蛇足であり、そこに女心があると云つたら失言にならうか。ともかく、それに男は答へてゐない。この勝負女の負である。なほこの「足」が歩く「あし」ではないといふうがつた説をどこかで見たやうに記憶するが、今思ひ出せない。これも蛇足であらうか。 [右依中郎足疾贈此歌問訊也] 説文に「問、訊也」 (二) とあり、また「訊、問也」 (三) とある。講義に二字で「とぶらふ」と訓まれてゐる。田主の名が史に見えず、この物語が作り物語めいてゐるので全註釈には「或ひは旅人の仮名であるかも知れない。」とある。巻五の松浦河に遊ぶ贈答歌の如きは明らかに作り物語と見るべきものであるが、これはそれ程でなく、実際の贈答歌に支那文学の影響をうけた脚色が加へられたものと見るべきであらう。なほ仮名だとすると「タヌシ」ではなく「タモリ」即ち「田守」即ち一本足のかかしといふ事になるといふ説がある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 129 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 本歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版](1980年9月)も併記する 【題詞】 大津皇子宮待石川女郎贈大伴宿禰宿奈麿歌一首 〔頭書〕元暦校本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、題詞ノ下ニ小字二行ニ次ノ文アリ。今元暦校本ニヨリテコレヲ揚げ他本ノ異ヲソノ後ニ注ス。 「女郎字曰山田郎女也宿奈麻呂宿祢者大納言兼大将軍卿之第三子也」。 細井本・大矢本・温故堂本「郎女」ノ右下ニ「ト」アリ「三」ノ下「之」アリ。 京都大学本「字」ノ右下赭「ヲ」アリ。「田」ノ右下ニ赭「ノ」アリ。「郎女」ノ右下ニ「ト」アリ。「三」ノ下「之」アリ。 西本願寺本、題詞ノ次行ニ小字二行ニ次ノ文アリ。 「女郎字曰山田ノ郎女ト也宿奈麿宿祢者大納言兼大将軍卿之第三子也」。 神田本、題詞ノ次行ニ大字ニ次ノ文アリ。 「女郎字曰山田郎女也宿(スク)奈麿宿祢者大納言兼大将軍卿之第三子也」。 天治本・神宮文庫本・細井本・陽明本、題詞ノ下ニ小字二行ノ次ノ文アリ。 天治本ニヨリテコレヲ揚ゲ、他本ノ異ヲソノ後ニ注ス。 「女郎字曰山田郎女也宿奈麻呂宿祢者大納言兼大将軍卿之第三子也」。 細井本、「祢」ヲ「称」ニ作ル。陽明本、「郎女」ヲ「女郎」トス。 〔本文〕津。元暦校本、右ニ朱「伴一本」アリ。西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「伴」。 待。元暦校本・古葉略類聚鈔・神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本・活字無訓本・天治本・神宮文庫本、「侍」。 (禰。細井本、「称」。宿禰の「禰」) 宿。古葉略類聚鈔・神田本・天治本・陽明本、ナシ。但、陽明本、「〇符」アリ。右ニ書ケリ。 麿。西本願寺本、「磨」ヲ直セリ。 歌。神田本、「謌」。 〔訓〕大津皇子宮待石川女郎。 西本願寺本・温故堂本、訓アリ、次ノ如シ。「大伴皇子(ミコ)ノ宮ノ侍(マカタチ)」。但、温故堂本「ミコ」ナシ。 細井本、訓アリ、次ノ如シ。「大津ノ皇子(ミコト)ノ宮(ミヤ)侍(マカタチ)石川ノ女郎」。 大矢本・京都大学本、訓アリ、次ノ如シ。「大伴ノ皇子ノ宮ノ侍(マカタチ)石川ノ女郎」。京都大学本、「皇子」ノ右ニ赭「ミコ」アリ。 天治本、訓アリ、次ノ如シ。 「大津ノ皇子宮待(ミコトノミヤマカタチ)石川ノ女郎贈大伴宿祢宿奈麿(スクナマロ)歌」。 〔諸説〕大津皇子宮待。代匠記初稿本、「待」ハ「侍」ニ作リ、「マカタチ」ト訓ズ。万葉考、六字衍トス。 【本文】 古之 嫗爾為而也 如此許 戀爾将沉 如手童兒 (イニシヘノ ヲウナニシテヤ カクハカリ コヒニシツマム タヽワラハコト) 〔頭書〕類聚古集、前行ニ「大津皇子宮侍石川女郎贈大伴宿祢奈麻呂歌 女郎字曰山田郎女宿奈丸者大納言兼大将軍卿第三子也」 右ニ墨「伴 一本」アリ。「祢」ヲ墨ニテ消セリ。「奈丸者」ノ三字ハ後ノ補筆ナリ。原字不明。 六帖、第二「いにしへのをんなにしてやかくはかり戀にしつまむてわらはのこと」。 〔本文〕許。温故堂本、「計」。 沉。類聚古集、「流」。 〔訓〕ヲウナニ。元暦校本・類聚古集、「□(判読不明下写真)むなに」。古葉略類聚鈔、「ヲムナニ」。神田本、「オンナニ」。西本願寺本、「オウナニ」。天治本、「ヲウナニ」。 コヒニ。古葉略略類聚鈔、ナシ。 シツマム。元暦校本、「しつめる」。「める」ノ右ニ朱「マム」アリ。細井本、「シツマン」。天治本、「しつめる」。 タヽワラハコト。元暦校本・類聚古集、「てわらはのこと」。古葉略類聚鈔・神田本、「テワラハノコト」。西本願寺本・大矢本・京都大学本、「タワハラノコト」。 大矢本・京都大学本、「タ」青。細井本・温故堂本、「タハラハノコト」。活字附訓本、「ヽ」ナシ。 天治本、「てわらはのこと」。 神宮文庫本・陽明本、「タハラハノコト」。神宮文庫本、「ハラハ」ハ磨リ消セル上ニ書ケリ。陽明本、「タ」青。 〔諸説〕イニシヘノ。童蒙抄、「トシヘニシ」。万葉考、「フリニシ」。 ヲウナ。代匠記精撰本、「オムナ」トモ訓ズ。万葉考、「オヨナ」。攷證、「オミナ」。 如手童兒 (タヽワラハコト)。仙覚抄、「タワラハノコト」。代匠記精撰本、「テワラハノコト」。 万葉集略解礼記、「手」ハ衍トス。又ハ「如手童兒」ハ「手童兒如」ノ誤カ。(古點)ヲ否トシテ「ワカキヽノ」トス。万葉集古義「アカキヽシ」。
『一云戀乎大爾忍金手武多和郎波乃如』 〔頭書〕元暦校本・類聚古集・古葉略類聚鈔・温故堂本、前ノ歌ノ本文ノ下ニ小字ニ書ケリ。 神田本・西本願寺本・細井本・大矢本・京都大学本、小字ニ書ケリ。 天治本・神宮文庫本、前ノウタノ本文ノ下ニ小字二行ニ書ケリ。 〔本文〕一。京都大学本、赭ノ合点アリ。 乎。元暦校本、「手」右ニ朱「乎」アリ。 大。神田本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「太」。天治本、コノ下ニ「巾」アリ。神宮文庫本、「太」。 爾。類聚古集、墨ニテ直セリ。原字「余」ナラン。 忍。元暦校本、「忽」。右ニ朱「忍」アリ。 金手。古葉略類聚鈔、「□□(判読不明下写真参照)」。 多。類聚古集・古葉略類聚鈔、ナシ。神田本、「手」。 和。類聚古集、「知」。 郎。元暦校本・類聚古集・古葉略類聚鈔・神田本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本・天治本、「良」。 如。類聚古集、「女」。古葉略類聚鈔、「や母」。 〔訓〕戀乎大爾忍金手武多和郎波乃如。 神田本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本、右ニ朱「コヒヲタニシノヒカ子テムタワラハノコト」アリ。 細井本、右ニ訓アリ。文同前。 神宮文庫本、右ニ「コヒヲタニシノヒカネテムタワラハノコト」 〔諸説〕一云。攷證、一云以下十六文字小字トス。 戀乎大爾。代匠記精撰本、「大」ハ「太」ノ誤。 多和郎波。代匠記精撰本、「郎」ハ「良」ノ誤。萬葉集美夫君志、「郎」ハ「良」ト通ニテ何レニテモ可トス。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「題詞」考 | 注釈 | 『大津皇子宮侍(マカダチ)石川女郎贈二大伴宿祢宿奈麻呂一歌一首』 この題詞の下に元暦校本以下の古写本には次の如き注がある。 [女郎字曰二山田郎女一也宿奈麻呂宿祢者大納言兼大将軍卿之第三子也] 「侍」に西本願寺本マカタチと訓をつけてゐる。古事記上巻に「従婢」、神代紀下に「侍者」、欽明紀に「従女」 (廿三年八月の條)、遊仙窟に「婢」などマカタチ又はマカダチの訓が附せられ、御巫本日本書紀私記には「侍者 末-加-太-知」とあつて、マカダチと訓むべきであらう。大津皇子の宮の侍女の意である。従つて石川女郎とあるは、「107」以下にある石川郎女と同人と見るべきであらう。「110」の題詞の注に「女郎字曰二大名兒一」 とあり、ここは右にあげたやうに「女郎字曰二山田郎女一」とあるので、別人のやうにも考へられるが、大名兒といふのは真間の手兒奈 (3・431)、末の珠名 (9・1738) などの手兒名や珠名と同じく、呼び名であり、山田郎女といふのは、大伴郎女をまた坂上郎女といふ (4・528左注参照) のと同じく、住んだ地名などによる通稱と見るべきであるから、石川郎女と山田郎女と大名兒とは別人とはならず、二ケ處の注も、前者は歌の句に対する説明としてなされたものであり、両者を区別する為のものではなく、むしろ題詞の大津皇子云々こそ両者同人たる事を示すものと見るべきである。なほこの題詞を、前につづく田主との贈答をした石川女郎と区別する為とする人もあるが、これも資料本にあつた題詞をそのまま採つたものとすれば別人とはならず、集の編者は同人と考へて並べ収めたと見ることが出来よう。 「宿奈麻呂」は右に引用の注に大納言兼大将軍の第三子とあつて、安麻呂 (101題詞の條参照) の子である。続紀和銅元年正月の條に従六位下より従五位下、五年正月従五位上、霊亀元年五月左衛士督、養老元年正月正五位下、三年七月「始置二按察使一」とある條に備後国守正五位上大伴宿禰宿奈麻呂をして安芸、周防ニ国を管せしむ、とあり、四年正月に正五位下より正五位上を授くとあるによると右の「正五位上」は正五位下の誤かと思はれる。神亀元年正月従四位下とあつて、それ以後の記事は見えない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「古之 嫗尓為而也」訓・注 | 代匠記 | 古之嫗爾爲而也如此許戀爾將沈如手童兒 [イニシヘノヲウナニシテヤカクハカリコヒニシツマムタワラハコト] 嫗、『六帖三、ヲムナ、』 如手童兒、『六帖、テワラハノゴト、仙覺抄云、タワラハノゴト、幽齋本同レ之、』 古ノ嫗と我身を云は、年のねびたるを卑下して云なり、嫗は上に和名を引ごとく老女之稱にて、和訓於無奈 [オムナ] なれば假名も別なり、枕草紙に、冷じき物をいへる中に、おうなのけさうと云ひ、源氏に、おうなになるまで、又人からやいかゞおはしましけん、おうなとつけて心にもいれず、と云へる如きは皆嫗なり、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉考 | 古之 [フリニシ]、 四言、齡 [ヨハヒ] のふりしなり、今本いにしへのと訓しは、此歌にかなはず、 嫗爾爲而也 [オヨナニシテヤ] 、 紀に老此云二於由ト一といひ、(卷九)意余斯遠波 [オヨシヲバ] と有は老 [オイ] しをばなり、是に依に嫗は於與奈 [オヨナ] と訓べし、此與 [ヨ] を伊乎 [イヲ] の約 [ツヾメ] とする時は、於伊乎美奈 [オイヲミナ] てふ言となればなり、和名抄に嫗 (於無奈) 老女之稱也と有は、例も見えず、言の意もおぼつかなし、思ふに此無は與を誤しにやあらん、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 古之 [フリニシ]。嫗爾爲而也 [オミナニシテヤ]。如此許 [カクバカリ]。戀爾將沈 [コヒニシヅマム]。如手童兒 [タワラハノゴト]。 古之は、フリニシと訓べし、布里 [フリ] は、古 [フル] びといふに同じ、(即チ、フルビは、フリと約(マ)るをもおもへ、) 爾は、過爾之 [スギニシ]、散爾家流 [チリニケル]、老爾多流 [オイニタル]、などいふ爾 [ニ] と同じくて、那爾奴 [ナニヌ] の活用辭なり、過 [スギ] を、過那牟 [スギナム]、過奴流 [スギヌル]、ともいふにて、其活用の趣をしるべく、餘も是に准へて、さとるべし、(然るを註者等、是等の爾 [ニ] の辭を、去 [イニ] の意とこゝろえて、古爾之 [フリニシ] は、古去 [フリイニ] し、過奴流 [スギヌル] は、過去 [スギイヌ] るの略言ぞと云るは、甚しき誤なり、熟々古言の樣を、味ひてさとるべし、) 之 [シ] は、過去しことをいふ辭なり、 嫗爾爲而也 [オミナニシテヤ] は、嫗を、オミナと訓は、(舊本に、ヲウナと訓るは、論に足ず、略解にオムナとよめるも、中古の音便言のまゝによめるなり、また岡部氏が、オヨナとよめるは、理なし、况 [マシ] て和名抄の於無奈 [オムナ] を、無は與 [ヨ] の誤にや、とさへ云るは、太 [イミ] じき謾ごとなり) 字鏡に、□[女偏+長]ハ於彌奈 [オミナ]、(□[女偏+長]ノ字は、字書に見あたらず、こは齡の長たる意もて、御國にて製れる字ならむ、) 續紀十三に、紀ノ朝臣意美那 [オミナ]、(こは婦人の名なり、) など見えたるに從レり、古事記傳に、抑々老女を、於彌那 [オミナ] と云は、少 [ワカ] きを、をみなと云と對ヘて、大と小とを以て、老と少とを、別てる稱なり、又伊邪那岐伊邪邪美などの、御名の例を思ふに、おきなおみなは、伎 [キ] と美 [ミ] とを以て、男女を別てる稱なるべし、さて和名抄に、説文 (ニ) 云、嫗ハ、老女之稱也、和名於無奈 [オムナ] と見え、又靈異記に、嫗ハ、於于那 [オウナ] など見えたるは、中古よりして、美 [ミ] を、音便に、牟 [ム] とも宇 [ウ] とも、云なせるものなりと云り、(猶甚委く論へり、披キ考フべし、 荒木田氏が、於無那 [オムナ] は、於伊袁美那 [オイヲミナ] なり、といへるは、用 [トル] に足 [タ] らず、) 也 [ヤ] は、將沈 [シヅマム] の下に、移して意得べし、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 古りにし 嫗にしてや かくばかり 戀に沈まむ た童の如 古之 [フリニシ] 嫗爾爲而也 [オムナニシテヤ] 如此許 [カクバカリ] 戀爾將沈 [コヒニシヅマム] 如手童兒 [タワラハノゴト] 古之嫗爾爲而也 [フリニシオムナニシテヤ] ――嫗は和名抄に嫗、於無奈、老女稱也とあり、字鏡に□[女偏+長]、於彌奈とある。オムナともオミナともよめる字であるが、暫くオムナとして置かう。古之嫗 [フリニシオムナ] は、年を取つて經驗ある老女の意。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「古之 嫗尓為而也」(フリニシオミナニシテヤ) 嫗は倭名抄 (一) に「説文云、於屢反、和名於無名、老女稱也」とあり、老女の意に用ゐられる。新撰字鏡 (三) には「□(女偏に長)」に「於弥奈 (オミナ)」とあり、霊異記 (中、第十六話) には「嫗」に「於于那 (オウナ)」とある。オミナがオムナとなり更にオウナとなつたものと思はれる。今は古きに従つてオミナと訓む。「古りにし」は年をあり経た意で、今めかしき事の反対で、老嫗の意を更に強めたものである。「や」は下の「沈まむ」にかかる疑問の係助詞で、詠歎の意のこめられたものである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「古之 嫗尓為而也」(フリニシオミナニシテヤ) 原文「古之」で、旧訓「イニシヘノ」であったのを、真淵は「齢のふりし也、今本いにしへのと訓しは此哥かなはず」と、「フリニシ」に改訓した。真淵の言う通り「イニシヘノ」では歌意にそぐわない。嫗は既出。霊異記中巻巻第十六話の嫗に「於于那」の訓法が見え、和名抄には「於無奈」とある。もと「オミナ」であって、それが「オムナ」となり、さらに「オウナ」となったのであろう (講義)。ここでは「オミナ」と訓む。老女の意。「シテヤ」の「ヤ」は疑問の助詞で下句にかかる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「戀尓将沈」訓・注 | 代匠記 | 戀ニ沈マムとは臥沈て泣なり、第四に、玉きぬの、さゐさゐ沈み家の妹に、物いはず來て思かねつも、とよめる沈に同じ、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「戀尓将沈」(コヒニシヅマム) 「恋に沈まむ」は、万葉集にこの一例のみの珍しい例。小島憲之『上代日本文学と中国文学』中巻 (917頁) に「『沈む』の例は、万葉集に於いては、『沈みにし妹が姿を』(2・229) の如く、水死など具体的なことにこの語を用ゐ、抽象的なものの例はこの『恋に沈む』が一例である。しかし「文選」に『思子沈心曲、長歎不能言』(劉公幹、贈徐幹一首)、『歓沈難尅興』(陸士衡、為顧彦先贈婦) とみえ、心情的なものに『沈』を用ゐた例があることがわかる。『恋に沈む』の如き表現も、中国的なものとわが国語『沈む』との交感によつて生れた新しい表現ではないか」と記す。恋の思いに溺れるのだろうかの意。注釈 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「如手童兒」訓・注 | 代匠記 | タワラハゴト、此點字に叶はず、注にタワラハノゴトとあれば、仙覺のタワラハノゴトと點ぜるは叶へども、六帖に依てテワラハノゴトとよむべし、其所以
[ユヘ] は、集中に異 [イ] を注する傍例、一句にても二三句にても、異あるをば注なし、異なきをば注せず、然れば仙覺の如くよまば、注には唯、一云戀乎太爾忍金手武と三四兩句の異をのみ注すべきに、三句の異を注せるにて六帖に依べしと申なり、稚子
[イトケナキコ ] を手兒 [テコ] と云へるを、多古 [タコ] とはよまざれば、テワラハ此に准ずべし、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 如手童兒 [タハラハノゴト] は、四ノ卷に、幼婦常言雲知久手小童人吠耳泣管 [タワヤメトイハクモシルクタワラハノネノミナキツヽ] 云々、契冲、手わらはとは、はゝめのとなどの、手をはなれぬをいふべしと云り、書紀に、童女 [ワラハメ] 、和名抄ニ云、禮記ニ云、童ハ、未レ冠之稱也、和名和良波 [ワラハ]、文選東京賦ノ註ニ云、娠子、娠子ノ讀、師説、和良波部 [ワラハベ]、字鏡ニ云、僮ハ、未レ冠人也、和良波 [ワラハ]、また□[女偏+兒]ハ、和良波 [ワラハ]、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 【釈】「如手童兒」(タワラハノゴト) タは接頭語。タワラはは幼童。ここは若い女をさして言つているであろう。年端も行かない女ならは戀に沈むのももつともであるが、自分のような年輩の女で、なおかつ戀に沈むものかというのである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「如手童兒」(タワラハノゴト) 「タワハラ」の「タ」は接頭語。形容詞・動詞に冠するものと異なり、名詞に冠したものには手の義が著しいと考えられる (講義)。「ワラハ」は新撰字鏡に「未冠之称也」とあるが、「タワラハ」は「ミドリコ (乳飲み子)」 や「ハフコ (平生)」に対し歩き始めた後のまだ母の手を離れぬ幼児を指すらしい。「タワハラノゴト」とは、「ただ泣くだけの童のように」 (窪田評釈) と解される。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 130 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版](1980年9月)も併記する 【題詞】 長皇子輿皇弟御歌一首 〔頭書〕京都大学本、肩ニ朱「天智天皇第四子」アリ。 〔本文〕輿。神田本、「興」。 皇 (皇弟の「皇」)。神田本、コノ下「子」アリ。天治本、コノ下ニ「〇符」アリ。右ニ「子 無或本」アリ。 弟。神田本、「苐」。 歌。神田本、「謌」。 〔訓〕輿。細井本、右下ニ「ル」アリ。温故堂本、右下ニ「フ」アリ。大矢本・京都大学本、右ニ「アタフル」アリ。京都大学本、「アタフ」ヲ赭ニテ消セリ。 神宮文庫本、訓アリ、次ノ如シ。「与皇弟 (アタフルスメイロトニ)」。 皇弟。細井本・西本願寺本・大矢本・京都大学本、右ニ「スメイロトニ」アリ。温故堂本、右ニ「スメイロト」アリ。 【本文】 丹生乃河 瀬者不渡而 由久□(筴に辶)久登 戀痛吾弟 乞通来禰 (ニフノカハセヲハワタラテエクユクトコヒイタムワカセコチカヨヒコ子) 〔頭書〕類聚古集、前行ニ「長皇子与皇弟御歌」。 天治本、訓ハ別行片仮字ニテ第三句マデ書ケリ。ソノ肩ニ「本マヽ」アリ。 〔本文〕丹。神田本、「舟」。 由。類聚古集、「曲」。 □(筴に辶)。元暦校本・類聚古集・古葉略類聚鈔・神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本・活字無訓本・天治本・神宮文庫本、「遊」。 戀。類聚古集、「慈」。 痛。古葉略類聚鈔、ナシ。 〔訓〕ニフノカハ。類聚古集、「にはのかは」。墨ニテ上ノ「は」ヲ消セリ。ソノ右ニ墨「ふ」アリ。 セヲハ。類聚古集、「セ」ナシ。墨ニテ右ニ書ケリ。訓ノ中此ノ字ニ當ル處ニ墨〇符アリ。 エクユクト。元暦校本・類聚古集、「ゆくゆくと」。古葉略類聚鈔・神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「ユクユクト」。 天治本、「ユク〃〃ト」。 コヒイタムワカセコチカヨヒコ子。元暦校本、以上十五字ナシ。別筆ニテ補ヘリ。類聚古集・古葉略類聚鈔・神田本、以上十五字ナシ。 西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本、以上十五字朱。 温故堂本・大矢本・京都大学本、「戀痛」ノ左ニ「コヒタミ」、「乞」ノ左ニ「コヒ」、「来」ノ左ニ「キ」アリ。 京都大学本、赭ニテ「コヒ」「キ」ヲ消セリ。 細井本、「コヒ」ヲ「コイ」トセリ。「乞」ノ左ニ「コヒイニ」アリ。「来」ノ左ニ「キイ」アリ。 [コチカヨヒコネ] 神宮文庫本、「乞」ノ左ニ「コヒ」アリ。「来」ノ左ニ「キ」アリ。 〔諸説〕セヲハワタラテ。代匠記初稿本、「セハワタラズテ」。 由久□(筴に辶)久登。代匠記初稿本、「□(筴に辶)」ハ「遊」ノ誤。 コヒイタム。童蒙抄、「コヒワフ」。万葉考、「コヒタム」。万葉集略解、「コヒタキ」。 ワカセ。代匠記初稿本、書入、「ワキモ」。万葉集古義、「アオト」。 コチカヨヒコ子。代匠記精撰本、「イデカヨヒコ子」カ。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「丹生河」考 | 注釈 | 【訓釈】「丹生乃河」(ニフノカハ) 丹生は丹砂を産出するところの意で、従つて丹生とか丹生川とかいふ名は諸方にあるわけであるが、ここはやはり吉野の丹生川であらう。丹生川は大和志 (吉野郡) に「源自二吉野山及赤瀧山一、経二河分、長瀬一、遶二丹生社前一、経二歴長谷、西山、貝原、小古田、河岸、城戸、河合、黒淵、大日川、加名生(カナフ)、魚梁瀬(ヤナセ)、和田、江出(ヅル)、老野等一、過二瀧村一、入二宇智郡一」とある。下市より約二里南に下市町字長谷に丹生川上神社があり、そのあたりでは今、黒瀧川と呼ばれてゐる。宇智郡に入つて南宇智村丹原に丹生川神社があり、その東を北流して、五條の南、霊安寺の西で吉野川の本流に合してゐる。右の丹生川上神社は明治四年に官幣大社に列せられたが、後に吉野川の上流川上村迫に丹生川上神社の奥宮と稱せられてゐた社が明治廿九年にまた官幣大社に列せられ、次で吉野川の支流高見川 (又小川ともいふ) の川上に大正十一年に官幣大社丹生川上神社が定められ、前者を上ノ社、後者を中ノ社と呼ばれ、はじめの丹生村の社を下ノ社と呼ばれるに至つてややこしくなつたが、古くから丹生川と呼ばれたのは右に述べたものと思はれる。しかしはじめに述べたやうに丹生川はあちこちにあり、神武紀に見える丹生川は宇陀郡と思はれ、今も宇陀郡榛原町雨師に式内丹生神社があり、今の場合も推定にとどまる (「南大和行脚覚書」 国語・国文第五巻第十号昭和十年十月参照)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「瀬者不渡而」訓・注 | 代匠記 | 丹生乃河瀬者不渡而由久□[(筴に辶)] 久登戀痛吾弟乞通來禰 [ニフノカハ セヲハワタラテ エクユクト コヒイタムワカセ コチカヨヒコ子] 丹生ノ川は、大和宇智郡にあり、丹生神社あり、專雨を祈る所なり、第二の句の點惡からねど字に叶はず、今按セハワタラズテと讀べし、これにて能く字に叶へり、此二句に、結句を合せて心得るに、皇女の宮は丹生川の彼方に有れば、えあひ給はぬ中を、やがて彼川を渡らぬに譬たまへるか、上の但馬ノ皇女の、朝川わたるとよませ給へるに注せしが如し、若は同じ都の内ながら、只相見ぬ中に譬出し給へるにや、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 童蒙抄 | 丹生乃河瀬者不渡而由久遊久登戀痛吾弟乞通來禰 にぶのかは、せはわたらずて、ゆくゆくと、こひわぶわがせ、こちかよひこね [瀬者不渡而] 古本印本等には、せをばわたらでとよめり。義は同じき事ながら、ずてといふことば古くいひ來りたる詞也。物がたりなどによりて、文字の通に瀬はわたらずてとよむ也。瀬をわたらずてとは、河をわたりては心もとなきほどに、わたらずにかち路より來り給へと也 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攷證 | 丹生乃河 [ニフノカハ]。瀬者不渡而 [セハワタラズテ・セヲバワタラデ]。由久遊久登 [ユクユクト]。戀 [コヒ]痛[タム・イタム]吾弟[ワガセ]。乞通來禰 [コチカヨヒコネ]。 瀬者不渡而 [セハワタラズテ・セヲバワタラデ] 舊訓、せをばわたらでとよめれど、者の一字を、をばとよむべきよしなし。今のごとくよむべし。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 丹生乃河 [ニフノカハ]。瀬者不渡而 [セハワタラズテ]。由久遊久登 [ユクユクト]。戀痛吾弟 [コヒタムアオト]。乞通來禰 [イデカヨヒコネ]。 瀬者不渡而 [セハワタラズテ] は、恐き河瀬を渡らば、そこなひもや侍らむ、瀬は渡らずして、來ませといふなり、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「瀬者不渡而」(セハワタラズテ) 作者が瀬を渡らずと解く説 (檜嬬手) と第五句へつづけて相手の動作と解く説 (古義) と次の句の序と見る説 (全註釈) とがある。この初二句は実景ではあるが、次の句の序と見るべきであらう。「て」でとめた序詞には、 まそ鏡手取持手(テニトリモチテ)-あさなあさな見む時さへや (11・2633) さされ石に駒を波佐世氐(ハサセテ)-心痛み吾が思ふ妹に (14・3542) なでしこが花等里母知弖(ハナトリモチテ)-うつらうつら見まくのほしき (廿・4449) など十数例がある。序としてのかかりについては次に述べる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「瀬者不渡而」(セハワタラズテ) 旧訓「セヲハワタラテ」とあったが、童蒙抄及び代匠記 (初稿本) に「セハワタラズテ」とする。川瀬は渡らないで、の意。どの句へかかるか、また、「渡らず」の主語は誰かなど、諸注の解釈は分かれている。童蒙抄は「河を渡りては心もとなきほどに、わたらずにかち路より来り給へと也」と相手 (弓削皇子) の動作として解したが、代匠記 (初稿本) には「川を渡らぬは、あははやとおもふ心のみありて、事のならぬにたとへていへり」と作者自身の行為の比喩としている。以後の注もそのいずれかによる。古義・古典大系・古典全集などが前者であり、攷証・講義・佐佐木評釈・全註釈・私注・澤瀉注釈・古典集成・講談社文庫など後者である。ただし、全註釈および澤瀉注釈では初二句を実景に即したものではあるが、次の「ゆくゆくと」にかかる序とみる。相手の行為とするか作者自身の動作と解するかは、「ゆくゆくと」と及び「恋痛」の把握の仕方による。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「由久遊久登」訓・注 | 代匠記 | ユクユクトとは、末に大舟のゆくらゆくらなどよめるに同じ、上の弓削ノ皇子の、大舟のはつる泊のたゆたひにと云御歌に付て注せり、思ふ心のはかゆかでのびのびなる意なり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 童蒙抄 | [由久遊久登] (ユクユクト) ゆるゆるとゝいふ義也。ゆくらかになどゝもいひて、いそがぬ事を云。事の急なる事を、ゆくりもなくと云も、ゆるやかになき不意の事を云也。いそぎて川をわたり給ふ事は、心もとなきほどに、河をわたらずに、ゆるゆると來り給へとの事也 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | 丹生乃河。瀬者不渡而。由久遊 [遊ヲ今篋ニ誤元ニ依テ改] 久登。戀痛吾弟。乞通來禰。 にふのかは。せはわたらずて。ゆくゆくと。こひたきわがせ。いでかよひこね。 ユクユクトは、物思ひに思ひたゆたふにて、卷十二、あまのかぢ音ゆくらかに、卷十三、大舟のゆくらゆくらになど有るに同じ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 由久遊久登 [ユクユクト] (遊ノ字舊本「□(筴に辶)」に誤、今は元暦本類聚抄拾穗本等に從つ、) は、次の戀痛 [コヒタム] へ、直につゞけては、聞べからず、尾句の上に、めぐらして意得べし、さて此言は、難 [ナヅ] みとゞこほることなく、するすると物する意を、いふことゝきこえたり、(これを集中に、海部之□[楫+戈]音湯鞍干 [アマノカヂノトユクラカニ]、あるは、大船之由久羅由久羅 [オホブネノユクラユクラ] などある、由久羅 [ユクラ] と同言にて、物思ひたゆたふを、由久由久登戀 [ユクユクトコフ]、といふよしに、心得たるは、うけがたし、其は言の似たるより、ふと同意ぞとおもひよれることなれど、よく味ふるときは、さては尾句、力ラなくきこえたれば、必ス此ノ一句は、下にうつして聞べきことなり、拾遺集に、菅家大臣、君が住宿のこずゑのゆくゆくとかくるゝまでにかへり見しはや、とあるも、するすると顧 [カヘリミ] し、といふなるべし、源氏物語賢木に、おとゞは、おもひのまゝに、こめたる所おはせぬ本性に、いとゞ老の御ひがみさへ、そひ給ヒにたれば、なにごとにかはとゞこほり給はむ、ゆくゆくと宮にもうれへ聞え給ふ、とあるゆくゆくも、ありのまゝに、するするといふ意にきこえたれば、同言にやあらむ、) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 丹生の川 瀬は渡らずて ゆくゆくと 戀ひたき吾がせ こち通ひ來ね 丹生乃河 [ニフノカハ] 瀬者不渡而 [セハワタラズテ] 由久遊久登 [ユクユクト] 戀痛吾弟 [コヒタキワガセ] 乞通來禰 [コチカヨヒコネ] 由久遊久登 [ユクユクト] ――この語の解種々あるが、源氏物語賢木の卷に、「何ごとにかはとどこほり給はむ。ゆくゆくと宮にもうれへ聞え給ふ」とあるによれば、滞なくすらすらとの意である。さうすればこの句は、乞通來禰 [コチカヨヒコネ] に續くものと見ねばならぬ。これを湯鞍干 [ユクラカニ] (三一七四)・大舟乃往良行羅二 [オホフネノユクラユクラニ] (三二七四) などと同じく見て、心の動搖する樣に解する説は採らない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 丹生乃河 [ニフノカハ] 瀬者不渡而 [セハワタラズテ] 由久遊久登 [ユクユクト] 戀痛吾弟 [コヒタシワオト] 乞通來祢 [イデカヨヒコネ] 由久遊久登 [ユクユクト] 他に用例は無いが、「大船乃 [オホフネノ] 由久良由久良爾 [ユクラユクラニ] 思多呉非爾 [シタゴヒニ] 伊都可聞許武等 [イツカモコムト] 」 (卷十七、三九六二) などの、ユクラユクラニと同語であろうと言われている。それによれば、大船の波のまにまに動搖するように、心の落ちつかず定まらないことをいう副詞と考えられる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攷證 | 由久遊久登 [ユクユクト] 代匠記に、ゆくゆくとは、第十二、十三などに、大舟のゆくらゆくらとよめる、おなじ。俗語に、ゆくりとしてといふも是也。ゆるゆるとと、つねにいふ心なり云々とあるにしたがひて、略解にも、物思ひにおもひたゆたふ也といへれど、これらあまりに思ひすぐしたる説也。拾遺集別に、贈太政大臣、君がすむ宿のこずゑの、ゆくゆくとかくるゝまでにかへり見しはや云々とあるは、菅家の御歌なれば、菅家は、この御歌の由久遊久等 [ユクユクト] を、行行とと心得給ひしと見えたり。これによりて、こゝをば、行々とと心得べし。まへに、丹生の川、瀬はわたらずてといひくだしたるにては、行々の意なるをしるべし。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「由久遊久登」(ユクユクト) 原文「遊」の字流布本に「□(筴に辶)」となつてゐるが、元暦本以下の諸本いづれも「遊」とあり、それにより「ユクユクト」と訓むべき事に問題ない。ただその解釈について代匠記に「大舟ノユクラユクラナドヨメルに同ジ」と云つて以来その説が多く行はれ、現在にも一部で認められてゐるが、「ユク」と「ユクラ」とは一字の相違ながら、「ユタ」と「タユタ」 (7・1352) と相似て相異なる例もあるやうに、むしろその相違にこそ注意すべきものであつて、これを無造作に混同すべきものではない。攷證、古義にその差別に注意したのは正しいが、拾遺集巻六、菅公の作、 君が住むやどの梢を行く行くとかくるるまでにかへりみしやは の「行く行くと」を例に引いたのは、「行きながら」の意であつて今の例にならず、古義に源氏物語 (賢木) に「おとどは、おもひのままに、こめたる所おはせぬ本性に、いとど老の御ひがみさへ、そひ給ひたれば、なにごとにかとどこほり給はむ、ゆくゆくと宮にもうれへ聞え給ふ」とあるを引いて、「ありのままに、するするといふ意に聞こえたれば同言にやあらむ」と云つたのは注意すべきである。精考に「後のものながら増鏡村時雨の章、後醍醐天皇の中宮御難産の條に『ただゆくゆくと水のみ出でさせて給ひて』とあるも、ただ水ばかりがスースーと出た意で、ここの語勢によく当たるやうに思ふ」とあるが、「ゆくゆく」を副詞として用ゐた例はなほ他にも多く、大日本国語辞典に宇津保物語、嵯峨院の巻「御腹はゆくゆくと高くなる」及び續詞花集の、 君なくてゆくゆくしげる庭草に鳴く蟲よりも我ぞ悲しき (巻九) 清原元輔 の例をあげてそこにあてられた「ずんずん」の訳語こそ、我が意を得たもので、私が今の句の訳語として考へたものもそれである。更に今の歌の場合に適切なものをあげれば、雅言集覧の廣足の増補にも入れられてゐる俊頼集の、 川の瀬のおちまふ水のゆくゆくと思ふ心を人にいはばや の如きは上二句が序になつてをり、「川の瀬」といふ言葉もあつて、或いはこの作者は萬葉の作を本歌としたものでないかとも考へられ、さうすればむしろここに俊頼の萬葉解釈が示されてゐるといふ事にもならう。ともかく「ゆくらゆくら」は、ものの動揺し、たゆたふ事であり、「ゆくゆく」はむしろそれとは対蹠的で、ものの進み、はやる事であるやうに見える。従つて諸注の多くに「ゆくらゆくら」の意に解しながら、次の句の修飾としたのは適切ではなく、又古義などは「ゆくゆく」と解きながら、第四句を飛ばして第五句へつづけたのも、例の萬葉の句の順序 (132、1・20、39参照) から云つてももの遠く、これはずんずんと思ひまさつてゆく意の副詞として、次の句の修飾と見て最も適切であらう。ただ第二句とのつづきは、右の俊頼集の場合同様、「行く」といふ本来の動詞としての意義によつてゐるものと見るべきである。さてその「行く」と上の「渡らず」といふ語との内容上の関係であるが、「渡らずてゆく」と云へば提に沿うてでも行くやうであるが、これは「川を渡らず」とあるのでなくて、「瀬は」とある事に注意を要するので、それについては精考に「一々河瀬を踏んで通ふなどは煩わはしく・・・瀬ぶみなどせず」と解かれてゐるやうに、川は渡るのであるが、瀬をさがし求めて渡るといふ事はしない、といふ意味で、思ひ余つては淵瀬の見さかひもなく、「刀根川の河瀬も知らずただわたり」 (14・3413) とあるやうに、がむしやらに直渡りに渡らうといふ意味で、「瀬は渡らずて」「ゆくゆく」とつづけたものであり、それをまたそのまま次の句を修飾する副詞としたと見るべきである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「由久遊久登」(ユクユクト) 代匠記・童蒙抄など「ゆくらゆくら」と同じとしたが (講義も同じ)、攷証に拾遺集の「君が住む宿のこずゑのゆくゆくとかくるるまでにかへり見しはや」 (菅原道真) を引いて「行行の意」とし、古義にも同歌と源氏物語 (賢木) の「ゆくゆくと宮にもうれへ聞え給ふ」の例をあげ「ありのままにするするといふ意」と推定した。その後、万葉集精考に増鏡 (村時雨)、注釈に宇津保物語 (嵯峨院巻) の例などあげられている。続詞花集の「君なくてゆくゆくしげる庭草に鳴く虫よりも我ぞ悲しき」 (清原元輔) の例も、「ずんずん」の意であって、この歌にふさわしいものであろうと注釈に説かれており、さらに、俊頼集の「川の瀬のおちまふ水のゆくゆくと思ふ心を人にいはばや」を、第二句まで「ゆくゆくと」の序になっている例として引かれているのも注目される。俊頼は長皇子の歌を本歌としたのではないかと推測され、彼の「ゆくゆくと」の解釈も見うると考えられる。こうした例から注釈は、「ゆくらゆくら」とはむしろ逆に、物事の進み、心のはやる意の副詞として「ゆくゆくと」を見るのである。第二句との続きは、「渡らずてゆく」であり、「ゆく」を掛詞として「ゆくゆくと」に転ずるのであり、「玉くしげ覆ふを安み開けていなば君が名はあれど吾が名し惜しも」 (2・93)、「かはづ鳴く六田の川の川柳のねもころ見れど飽かぬ川かも」 (9・1723) などと同様の序歌と考えられる。また「瀬は渡らずて」は、川を渡らないというのではなく、淵瀬を選ばずがむしゃらに直渡りに渡ることを意味するとも言う。これは詳しい説明で、従うべきものと思われる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「恋痛吾弟 (こひいたしわがせ)」訓・注 | 代匠記 | 戀イタムは、戀佗て心の痛むなり、ワガセとは、せは、男女に通ずる詞なり、此に弟の字をかけるは、端作に皇弟とあれば意を得て義訓せり、此卷下に至て、大來の皇女の、二上山をいもせと吾みむとよませ給へるには、弟の字も妹に用たり、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 童蒙抄 | 戀痛 古本印本等にはこひいたむとよめり。しかれどもことばつたなければ、痛はなやむ義也。よりてこひわぶとよむべし。わぶはなやむ事を云、こひしたひ給ふとの義也 吾弟 前にも注せるごとく、先を賞してせと云也 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | 丹生乃河。瀬者不渡而。由久遊【遊ヲ今篋ニ誤元ニ依テ改】久登。戀痛吾弟。乞通來禰。 にふのかは。せはわたらずて。ゆくゆくと。こひたきわがせ。いでかよひこね。 戀痛はいと戀しきを強く言ふ詞なり。愛るを愛痛 [メデタキ] と言ふが如し。ワガセは親しみ敬ふ言。實を以て弟の字を用ひたり。和名抄、備中賀夜郡弟翳勢庭妹 (爾比世) なども有り。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攷證 | 戀 [コヒ] 痛 [タム・イタム] 吾弟 [ワガセ]。 略解に、戀痛は、いと戀しきを、強くいふ詞也。愛するを、愛痛 [メデタキ] といふがごとし云々といへるは、誤れり。戀痛 [コヒタム] の、痛 [タム] は、借字にて、船を□[手偏に旁] 多武 [コギタム]、□[手偏+旁] 多味 [コギタミ] 【この事は上攷證一下四十五丁にいへり。】などいふ多武 [タム] と同じく、また、本集十一 [三丁] に、崗前多味足道乎 [ヲカノサキタミタルミチヲ] 云々ともありて、こは、集中囘轉などの字をも、よみて、ものなづみゆく意にいへり。されば、こひたむの、たむは、まへのゆくゆくとへかゝりて、戀になづみて、行たむ意也。吾弟 [ワガセ] の弟 [セ] は、上 [攷證一上三丁] にいへるがごとく、親しみ敬ふ意にて、男どもち、せといへり。この事は、下 [攷證三上十四丁] に、くはしくいふべし。こは、略解に、わがせは親しみ敬ふ言實を以、弟の字を用ひたり。和名抄、備中賀夜郡、弟翳 勢 庭妹 [爾比世] などもあり云々といへるがごとく、弟をせとのたまへる也。遊の字、印本□ (筴に辶) に誤れり。今拾穗本に依て改む。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 戀痛吾弟は、コヒタムアオトと訓べし、(略解に、戀痛を、コヒタキとよみて、めづるを、めで痛といふがごとく、いと戀しきを、強くいふ詞なり、と云るはわろし、戀多伎 [コヒタキ]
といふ詞、物に見えたることなし、) 吾弟は、(岡部氏が、舊本に從て、ワガセとよめるは、よしなし、) 阿我於登 [アガオト]、といふべきが如くなれども、吾カ君を、阿岐美
[アギミ] 、吾カ兄を、阿勢 [アセ]、ともいふ例によりて訓べし、(かく訓ときは、調もよくとゝのへり、) 十七に、波思伎余思奈弟乃美許等 [ハシキヨシナオトノミコト]、(九ノ卷に、箸向弟乃命
[ハシムカフオトノミコト ] とあり、弟は、いづれもオトと訓べし、)とあり、(兄を、阿勢 [アセ] とも奈勢 [ナセ] とも云、弟を、阿於登
[アオト] とも奈於登 [ナオト] とも、云しなり) かくてこの於登 [オト] と云言は、古事記上卷高比賣ノ命歌に、阿米那流夜淤登多邦婆多能
[アメナルヤオトタナバタノ] 云々と見えて、そのもとは、人を深く親睦 [シタシ] む稱なりしと見えたり、さて人の季ノ子は、殊更に父母に親愛るゝから、於登兒
[オトコ] と云より、後に兄弟の弟を、稱ことには定れるなるべし、(また催馬樂葦垣に、止々呂介留己乃以戸乃於止與女 [トゞロケルコノイヘノオトヨメ]
云々、我門に、美曾乃不乃安也女乃古保利乃大領乃末名牟須女止以戸於止牟須女止古曾伊波女 [ミソノフノアヤメノコホリノタイリヤウノマナムスメトイヘオトムスメトコソイハメ]、などある、於止與女
[オトヨメ]、於止牟須女 [オトムスメ] は、婦また女を、親睦みて云るか、さらばかの、淤登多那婆多 [オトタナバタ] の淤登 [オト] に同じ、されど此は、又實に弟婦
[オトヨメ] 弟女 [オトムスメ] を云るにもあらむか、ともおもはるれども、何とやらむ、さも聞えざるなり、 古事記傳、右の淤登多那婆多能 [オトタナバタノ] の歌の下に云ク、如此さまに云淤登 [オト] は、人の季子 [スヱノコ] を、淤登子 [オトコ ]と云、其ノ淤登 [オト] なり、さて季ノ子は、父母に殊 [コトニ] 愛 [ウツクシ] まるゝ物なる故に、それより點りて、必スしも季ノ子ならねども、賞愛まるる意にて、なべて美女などをも、淤登 [オト] 某とぞ云けむとあるは、本末をとりたがへたる説なるべし、又谷川ノ士清が、弟は、劣 [オトリ] 人の義ぞと云るは、例の末にのみつきていへる論なれば、云に足ぬひがことなり、) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 戀痛吾弟 [コヒタキワガセ] ――コヒタシワガセとよむ説もある。これは由久遊久登戀痛 [ユクユクトコヒタシ] と續くものと見るのだが、由久遊久は通ふにかゝつてゐるものと見て、それには從はない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 戀痛吾弟 [コヒタシワオト] コヒタシは、コヒイタシの約、戀のはなはだしいのをいう形容詞。「凡有者 [オホナラバ] 左毛右毛將レ爲乎 [カモカモセムヲ] 恐跡 [カシコミト] 振痛袖乎 [フリタキソデヲ] 忍而有香聞 [シノビテアルカモ]」 (卷六、九六五)。この歌の振痛シと同樣の語構成と見られる。イタシは詰つてタシと聞えるのだろう。その終止形。コヒタキとして連體形ともされる。ワオトは、皇帝を呼び懸けている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「戀痛吾弟」(コヒタキワガセ) この句以下の訓は元暦本には別筆で加へられ、西本願寺本などには朱筆で書かれてゐるから、古訓がなくて仙覚がはじめて点したものと思はれ、「コヒイタムワカセ」とある。その後、万葉考は原文「戀痛」の訓を「コヒタム」と改め、略解は「コヒタキ」とし、折口氏口訳、増訂本全註釈には「コヒタシ」とし、また「コヒイタキ」 (万葉集私注) などの訓もある。代匠記に「戀イタムハ、戀侘テ心ノ痛ムナリ」と解き、略解には「戀痛はいと戀しきを強くいふ詞也。愛るを愛痛 (メデタキ) といふが如し。」とあるが、要するに「痛」は痛快、通愛、痛感、などと用ゐられ、前にも「事痛有 (コチタクアリ)」 (114) の條で述べたやうに、事の甚だしく、切なる意で、「イタム」と訓めば動詞となり、「イタシ」と訓めば形容詞となるわけで、まづそのいづれであるかを考へるに、古義には「戀多伎 (コヒタキ) といふ詞、物に見えたることなし」と云つてゐるが、「コヒタム」といふ言葉も物に見えない事は同様である。共に用例はないが、「××たし」といふ形の形容詞は、右の「こちたし」をはじめ「うれたし」 (8・1507)、「めでたし」などの例から類推して、「こひたし」といふ形容詞が存在したと見る方が自然であらう。殊に「他言者 (ヒトコトハ) 真言痛成友 (マコトコチタクナリヌトモ)」 (12・2886)、「振痛袖乎 (フリタキソデヲ) 忍而有香聞 (6・965)」 などの用語及び用字例と較べて今もまた「コヒタキ」と訓むべき事がうなづかれよう。さて形容詞とすれば、次には終止か連体かといふ問題であるが、これはどちらにも訓み解く事が出来る。しかし終止とすれば所謂四句中間切のものとなり、その例は集中に廿余を数へるが、その大半は、 河の上のいつ藻の花のいつもいつも来益(キマセ) 吾背子(ワガセコ) 今ならずとも (4・491) 汝が母に嘖られ吾は行く青雲の伊氐来(イデコ) 和伎母兒(ワギモコ) 相見て行かむ (14・3519) 真木柱ほめて造れる殿のごと 已麻勢(イマセ) 波波刀自(ハハトジ) 面変りせず (廿・4342) の如き形のもので、動詞、助動詞の命令形で切り、その下にその語の対象を示す名詞が独立句として置かれてゐる。 ま菅よし宗我の河原に鳴く千鳥間無(マナシ) 吾背子(ワガセコ) 吾が恋ふらくは (12・3087) 形容詞の終止形で切れたものはこの一例のみである。もし今の「戀痛」を形容詞の終止形とするならば、その唯一例に準ずる事になるが、右の例は仮名書でなく終止と明示されてゐないに拘らず終止たる事が明瞭であるに反し、今の場合はさうでない事右に述べた如く、且、終止とする時には、 瀬は渡らずてゆくゆくと戀痛し 吾弟 となつて、その「て」「と」をうけた小きざみな調子が一首の姿を乱し、右にあげた四首の四句中間切のどの例と較べても、ゆきとほつた声調をなしてゐない事が認められる。もしこれを連体形として訓み、すぐ前にあつた作 (128) と並べると、 吾が聞きし耳によく似てあしかびの足痛(アシヒク)吾勢 つとめたぶべし (128) 丹生の河瀬はわたらずてゆくゆくと戀痛(コヒタキ)吾弟 こちかよひこね (130) 前者は動詞であり、後者は形容詞である相違はあるが、一首全体の姿が極めて相似た形のものとなり、はじめておちつきを得たものになる。即ちこれは終止として中間切と見るべきものでなくして、連体形として訓み解くべきものと考へる。 次に吾弟は旧訓ワガセとあり諸注多くそれに従つたが、古義に「アオト」とし全註釈に「ワオト」とした。「せ」は年齢にかかはらず男性を呼ぶ名 (1・2) であり、「おと」は性別にかかはらず年下の者を呼ぶ名 (題詞の條参照) であり、ここは年下の男性と思はれる場合であるから、「セ」と云つても「オト」と云つてもまちがひではない。ただわざわざ「弟」と書かれてゐるところよりすると、年下の意が主となつてゐて、文字通り「オト」と訓んだ方がよいやうに見える。集中の例では「弟乃命者 (オトノミコトハ)」 (9・1804)、「奈弟乃美許等 (ナオトノミコト)」 (17・3957) など「弟」は「オト」と訓む例で、「セ」と訓ませたところはないやうに思はれるからである。そこで弟をオトと訓むのが正しいやうに考へられるのであるが、「ア (ワ) オト」といふ言葉はものに見えない。即ち「吾」といふ代名詞と「弟」といふ名詞とを直接結びつけるといふ点に疑問があるのである。右に引用したやうに、「汝弟(ナオト)」と認むべき語があり、一方古事記に「阿勢 (アセ)」 (景行)、「阿世 (アセ)」 (雄略) とあつて、それを「吾兄 (アセ)」の意とすれば、当然「吾弟 (アオト)」といふ語もありさうに思はれるのであるが、古事記の「アセ」は「吾兄」の意とする確証なく、むしろ噺言葉とする説が有力であり、萬葉には「奈弟」の他に「奈勢 (ナセ)」 (14・3458)、「名兄 (ナセ)」 (16・3885)、「名姉 (ナネ)」 (4・724) の語はあつても「吾兄 (アセ)」「吾姉 (アネ)」などの語は見えない。これは当然の事であつて、「ナ」を汝の意とすれば、汝(ナ)と弟(オト)、兄(セ)、姉(ネ)とは同格の語であり、又「ナ」を単に愛稱としても、その「ナ」と「オト」、「セ」、「ネ」などとが直接結びつく事に不審はないが、「吾」の場合は「和我勢」 (1・19)、「我兄子乎 (ワガセコヲ)」 (12・2938) の如く、表記の有無にかかはらず、「が」の助詞を加へるのが例であり、「吾君」 (3・376) も「アガキミ」と訓むべきであり、「吾妹 (ワギモ)」の「ギ」は「ガイ」の合したものであつて、「が」が省略されたものではない。従つて「吾弟」を「ワ (ア) オト」と訓む事は異例であつて、もし「弟」の文字に即して訓めば、「ワガオト」と訓むべきである。単独母音節があるから字余りも許される。しかしそれまでにして「オト」の訓に執着するには及ばないと考へる。「せ」は「弟」を含む事はじめに述べた如く、「弟」を「セ」と訓む事は勿論妨げないのであるから、ここは訓としては「ワガセ」とし、意味としては「吾が弟」と解すればよいのである。右に弟をセと訓んだ例が無いやうに思はれると云つたけれども、「弟世」 (165) の用字例は、その條で述べるやうに、弟をセと訓む事を示したものとも見るべきものであり、今もそれと同じく、しひてむつかしく「ワオト」だの「ワガオト」だのといふまでもなく、古訓の「ワガセ」に帰ればようのである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「恋痛」(コヒイタキ) 原文「恋痛」を西本願寺本に「コヒイタム」と訓まれ、代匠記もそれによっていたが、略解に「コヒタキ」、折口口訳・全註釈には「コヒタシ」と訓んだ。「コヒタキ」は、「いと恋しきを強くいふ詞」で、「愛るを愛痛 (めでたき)といふが如」きであるとされるのであるが (略解)、講義には、このような「形容詞のあるべしとも思はれず」、又古来の文献にその証なしと、これを否定した。戦後の注釈書でも「コヒタキ」と訓むものがあるが、例のないのは欠点とされよう。私注・古典大系および古典全集に「コヒイタキ」あるいは「コヒイタシ」とするのは、その点を改めた訓と言える。古典大系の「965歌」の補注に「振り痛き袖をしのびてあるかも」の「フリイタキ」について次のように述べられているのが参考になろう。「フリイタキ」を「フリタキ」と訓むのが普通であるが、「希望を表わす・・・タシという語は、鎌倉時代以後に現れたもので、それ以前には例がない。それゆえここを、希望のタシとは解し難い。イタシという語は奈良時代では『コチタシ』などの形で他の語と複合するだけであるが (中略)、平安時代になると『埋れいたし』『屈しいたし』などの例があり、ウモレ・屈シを名詞のように見做して、ウモレルコト甚シ、屈スルコト甚シの意に使っている。これらは源氏物語の例であるが、こうした用法は、奈良時代にも行われ得たと思われるので、ここの振りイタキ袖を、振ルコト甚シの意と解し、いつも甚しく振る袖と解釈する」。130歌の「恋痛」を古典大系に「コヒイタキ」と訓んだのも同様な理由によると考えてよかろう。平安時代においても「~イタシ」の形になっているので、万葉集のこの歌においても「コヒタシ」より「コヒイタシ」の方が穏やかだろう。「コヒイタシ」の意味で「コヒタシ」もしくは「コヒタキ」と訓むのも誤りとは言えないと思われるが、ここでは約音としない形に従っておく。なお、「コヒイタシ」と終止形に読み、そこに区切りをおくと、句割れになる。注釈に記されているように、四句の中間切れの集中例二十余の大半は命令形で、その呼びかけられる対象を示す名詞を伴っている。形容詞の終止形は、「間無し吾が背子吾が恋ふらくは」 (12・3087) のみであるし、この130歌の場合より、句割れにも無理がない。「コヒイタシ・コヒイタキ」のいずれにも訓まれうるが、皇子の他の歌の作風から言えば (〔考〕参照) 「コヒイタキ」が穏やかではなかろうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「乞通来祢 (イデカヨヒコネ)」訓・注 | 代匠記 | コチカヨヒコネは、こなたへかよひ來よなり、今按、此集に乞の字をイデとよめり、いでは即物を乞詞なり、允恭紀云、且曰、壓乞戸母 [イデトジ]、其蘭 [アラヽキ] 一莖焉、『壓乞、此運二異提一、戸母、此ヲハ運二覩自 [トジト] 一、』云云、これらに依て今もイデと点ずべきか、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 童蒙抄 | 乞通來禰 [コチカヨヒコネ] こちは此方へといふ義也。此方と云ことを、こちと古くいひ來りて、源氏物語等にも多く見えたり。いでともよまんか、出るの意地。且通の字道と云字にて、こちもかちも同事なれば、歩道の意かちぢとよめる義もあらんか。此終の句末レ決也。先こち通ひこねとよみて、此方へかよひ來り給へとの事也。歌の意は河を渡り給ふてはあやうくおぼつかなき程に、急ぎ給はずとも、ゆるゆるとかちぢを通ひ來り給へと他。御兄弟むつまじき御間がら、かくこひしたひ給ふて、よみたまへるなるべし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | イデは字の如く物を乞ふ詞なり。允恭紀二年云云、謂二皇后一曰云云、壓乞戸母云云、註に壓乞此云二異提 [イデ]一戸母此云二覩自 [トジ]一と有り。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攷證 | 乞通來禰 [コチカヨヒコネ] 略解に、いでは、字のごとく、物を乞詞也。允恭紀二年云々、謂二皇后一曰云々、壓乞戸母云々。注に、壓乞此云二異堤 [イデ]一、戸母此云二覩自 [トジ]一とあり云々とて、いでかよひこねとよめりしは、いかゞ。舊訓のまゝ、こちとよむべし。そは本集七『六丁』に、吾勢子乎乞許世山登 [ワカセコヲコチコセヤマト] 云々とありて、また六『十二丁』七『十丁』十二『十五丁』などに、越乞 [ヲチコチ] とも、かきたるにても思ふべし。さて、こちといふも、ねがふ意、禰といふも、下知の詞にて、何とぞ、こなたへかよひこよかしといふ意也。さて一首の意は、丹生の川の、瀬をばわたらずして、行くとて、行道に戀なづみたり。わがせの君よ。何とぞ、こなたへかよひこよかしと也。今世、此方といふを、こちといふも、これらよりうつりしなるべし。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 乞通來禰 [イデカヨヒコネ]、(乞ノ字、類聚抄には与とかけり、望辭の己曾 [コソ] にも、與とも乞とも書れば、もとより通ハシ用たるか、) 乞 [イデ] は、物を乞ふ處に云り、七ノ卷に、吾勢子乎乞許世山登 [ワガセコヲイデコセヤマト] 云々、(これも吾カ夫子よ乞 [イデ] 來 [コ] よ、と云フ意のつゞけなり、然るをコチコセ山とよみて、此處 [コチ] へ來 [コ]、と云意とするは非なり、) 四ノ卷に、乞吾君人之中言聞超名湯目 [イデアギミヒトノナカコトキヽコスナユメ]、十二に、乞吾駒早去欲 [イデアガコマハヤクユキコソ]、十四に、伊低兒多婆里爾 [イデコタバリニ]、書紀允恭天皇ノ巻に、謂二皇后一曰、云々、壓乞戸母、云々、註に、壓乞、此云二異提 [イデト]一、戸母、此云二覩自 [トジト]一とあり、來禰 [コネ] は、來 [コ] よと乞望 [ネガ] へる辭なり、禰 [ネ] の望辭ノ例、一ノ巻ノ初に委ク云り、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 乞通來禰 [コチカヨヒコネ] ――イデカヨヒコネとコチカヨヒコネの兩訓がある。乞は乞吾君 [イデワキミ] (六六○)・乞如何 [イデイカニ] (二八八九)・乞吾駒 [イデワガコマ] (三一五四) に從へばイデであり、越乞爾 [ヲチコチニ] (九二〇)・乞許世山登 [コチコセヤマト] (一〇九七)・乞痛鴨 [コチタカルカモ] (二七六八) に從へばコチである。此處の意から推してコチとよむことにした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 乞通來祢 [イデカヨヒコネ] 乞はイデともコチとも讀まれ、いずれにても通ずる所である。イデは、さあと誘う語。「伊田何 [イデイカニ] 極太甚 [ココダハナハダ]」 (卷十一、二四〇〇) など使われている。「壓乞、此云二異提一」(允恭天皇紀)とあつて、強く乞う意である。コチは此方の義で、こちらへ通つていらつしやいの意。コネは動詞來に、希望の助詞ネの接續したもの。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「乞通來祢」(コチカヨヒコネ) 原文「乞」を旧訓に「コチ」とあつたのを、代匠記に「イデト点ズベキカ」と一説をあげてからそれに従ふ人々もある。「乞」を「イデ」と訓む事は前 (1・8) に述べたが、又「越乞 (ヲチコチ)」 (6・920、その他)、「乞許世山 (コチコセヤマ)」 (7・1097)、「乞痛鴨 (コチタカルカモ)」 (11・2768) など音読して「コチ」の仮名に借りた例がある。「コチ」と訓めば此方の意となる。今の場合は「いで」の意 (4・660参照) でも解く事は出来るが、「通ひ来ね」とあり、右に引いた「乞許世」も参照せられ、また初二句は序詞ではあるが、川に臨んでの実景とも思はれ、かたがた「コチ」とも訓み、此方へ通つていらつしやい、の意に解いた方が適切であらう。「ね」は希求の助詞 (1・1)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「乞通來祢」(イデカヨヒコネ) 原文「乞」を旧訓に「コチ」と訓んだが、代匠記 (初稿本) に「乞の字はいてともよめり」とし、「コチ・イデ」両案を併記。以後、諸注の訓も両説に分かれている。講義に「意はいづれにても通ずべきさまなるが『通来る』といふ語によくあはせむには『コチ』の方によるべきならむ」と言い、注釈に、「今の場合は『いで』の意 (4・660参照) でも解くことは出来るが、『通ひ来ね』とあり、右に引いた『乞許世 (コチコセ)』も参照せられ、また初二句は序詞ではあるが、川に臨んでの実景とも思われ、かたがた「コチ」と訓み、此方へ通つていらつしゃい、の意に解いた方が適切であらう。」と記しているように、「コチ説」を採用している注釈書でも、漠然とした理由を羅列するに過ぎない。従って私注のように「『乞』をコチと訓み、こちらへといふ意にすれば解りよいが、コチゴチ、ヲチコチの例はあつてもコチ独立の例がないし、歌調も俗に堕ちる」と、歌調によって「コチ」を否定し、「イデ」の訓によるものもあるわけである。全註釈に、両説を併記し、判断を保留しているのが、問題の難しさを象徴するであろう。「乞通来祢 (イデかよひこね)」と訓むか「乞通来祢 (コチかよひこね)」と訓むかは、「乞」を正訓字 (もしくは義訓字) として扱うか、音仮名 (二合仮名) として扱うかの相違である。乞のようにあまり多用されない音仮名の場合、これを正訓字や訓仮名の間に孤立的に使用することがないのが一般であって、そのことは『万葉表記論』の第三篇 (音訓交用表記の論) に詳述した通りである。問題の「乞」は、「吾弟」と「通」という訓字の間に挿まれており、「乞」も訓字として用いるならば問題ないが、音仮名「乞 (コチ)」として利用されていると考えるとすれば、例外的な用法に属する。万葉集内の「乞 (コチ)」の例は、すでに諸注に引かれているとおり、「吾勢子乎乞許世山登人者雖云」 (7・1097)、「白管乃知為等乞痛鴨」 (11・2768)、「越乞尓思自仁思有者」 (6・920)、「舟召音越乞所聞」 (7・1135)、「越乞兼而結鶴」 (12・2973) のように、音仮名の幾つか連続する中に使われている。一方、「乞吾君」 (4・660)、「乞如何」 (12・2889)、「乞吾駒」 (12・3154) のように訓字の連続の中では音仮名ではなく「イデ」の意味の訓字になる。有名な巻一の八番歌の「許藝乞菜」も「乞菜 (いでな)」は訓字の連続を成しており、孤立的に置かれていない。つまり「乞」は用例数こそ多くはないが、訓字としても音仮名としても使われているのであり、訓字集団の中では訓字として、音仮名の集団の中では音仮名として使用されていると言える。そこに誤読をさけるための周到な配慮を見ることができる。130歌の「乞」は、「吾弟」と「通」という訓字に挟まれた位置にある。音仮名として頻用されたものではないから (万葉集以外に仮名の用例を見ない)、訓字間に孤立的に用いて音仮名として読ませるようなことを万葉集の筆者はしなかったであろう。訓字の間に、訓字として用いたので、音で読まれようとは予想しなかったはずである。「イデカヨヒコネ」が正しい訓と思われる。「イデ」は、感動詞で、「イザ」に似るが、「イザ」が人を誘い、自分の意志を強調するためにのみ使われるのに対し、「イデ」は他人に対してある行為を乞い求める場合や、自分に対する問い掛けを表わす場合にも用いる。万葉集に「イザ」を「率」、「イデ」を「乞」と記す例が多いのは、そうした意味の差にもとづくと思われる。「通ひ来ね」の「ネ」は、希求の助詞。「ナム」よりも実現性の濃い行為について言う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 131 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版](1980年9月)も併記する 【題詞】 柿本朝臣人麿從石見國別妻上来時歌二首□[笄の竹冠が「八」]短歌 〔本文〕朝臣。京都大学本、ナシ。 歌。神田本」、「謌」。 □[笄の竹冠が八]。京都大学本、赭ノ合点アリ。 短歌。元暦校本・神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、二字小字ニ書ケリ。 〔訓〕京都大学本、赭訓アリ、次ノ如シ。「柿本ノ朝臣人麿從石見國別テ妻ニ上リ来ル時」。 西本願寺本、「見」ノ下ニ「ノ」アリ。 〔諸説〕短歌。攷證、「短歌」ノ下「四首」脱トス。 【本文 1】 石見乃海 角乃浦回乎 浦無等 人社見良目 滷 (イハミノウミ ツノヽウラワヲ ウラナミト ヒトコソミラメ カタ) (「校本萬葉集」では任意に分解説しているが、しているが、「新増補版」では、後段のように、二つに分けて載せている) 〔頭書〕元暦校本、別行平仮字ノ訓ナシ。漢字ノ右ニ朱片仮字ノ訓アリ、之ニテ校ス。處々ニ朱、墨ノ訓アリ、コレヲ記入ス。 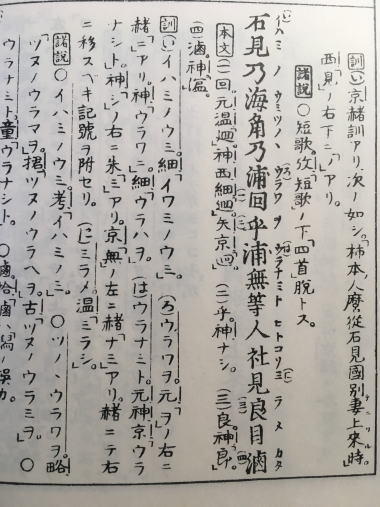 細井本、訓ヲ朱書セリ。 袖中抄第四、「石見ノ海角(ウミツノ)乃浦廻ヲウラナシト人コソミラメカタナシト人コソミラメ云々」。 〔本文〕回。元暦校本・温故堂本、「廻」。神田本・西本願寺本・細井本、「迴」。大矢本・京都大学本、「回」。 乎。神田本、ナシ。 良。神田本、「右写真参照」。 滷。神田本、「右写真参照」。 〔訓〕 イハミノウミ。細井本、「イワミノウミ」。 ウラワヲ。元暦校本、「ヲ」ノ右ニ赭「ニ」アリ。神田本、「ウラワニ」。細井本、「ウラハヲ」。 ウラナミト。元暦校本・神田本・京都大学本、「ウラナシト」。神田本、「シ」ノ右ニ朱「ミ」アリ。 京都大学本、「無」ノ左ニ赭「ナミ」アリ。赭ニテ右ニ移スベキ記号ヲ附セリ。 ミラメ。温故堂本、「ミラシ」。 〔諸説〕イハミノウミ。万葉考、「イハミノミ」。 ツノヽウラワヲ。万葉集略解、「ツヌノウラマヲ」。万葉集捃解、「ツヌノウラヘヲ」。 古義、「ツヌノウラミヲ」。 ウラナミト。童蒙抄、「ウラナシト」。 滷。拾遺集、「滷」ハ「潟」ノ誤カ。 【本文 2】 無等 [一云 礒無登] 人社見良目 能嘆八師 浦者無友(ナミト ヒトコソミラメ ヨシヱヤシ ウラハナクトモ) 〔本文〕無。神田本、「无」。 (一云の「無」)。元暦校本・神田本、「无」。 良。神田本、「右写真参照(本文1と同じ)」。 目。元暦校本、「自」。右ニ赭「目」アリ。 嘆。元暦校本・神田本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「咲」。 無。元暦校本、「无」。 友。元暦校本、ナシ。右ニ朱「□(友の『又』の右肩に『﹅』がある)」。 〔訓〕 ナミト。元暦校本・神田本・京都大学本、「ナシト」。 神田本、「シ」ノ右ニ朱「ミ」アリ。京都大学本、「無」ノ左ニ赭「ナミ」アリ。 礒無登。神田本・西本願寺本・細井本・大矢本・京都大学本、右ニ朱「イソナミト」アリ。温故堂本、右ニ朱「イソナシト」アリ。 ヨシヱヤシ。西本願寺本・細井本、「ヨシエヤシ」。 〔諸説〕ナミト。童蒙抄、「ナシト」。 能嘆八師。代匠記初稿本、「嘆」ハ「咲」ノ誤。 ウラハナクトモ。万葉集玉小琴、「ナケトモ」。万葉集捃解、「ナクトモ」ヲ可トス。 【本文 3】 縦畫屋師 滷者 [一云 礒者] 無鞆 鯨魚取 海邊乎指而(ヨシヱヤシ カタハナクトモ イサナトリ ウナヒヲサシテ) 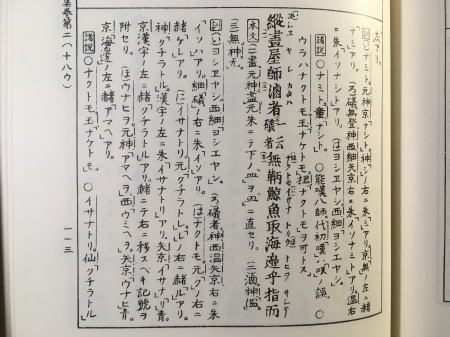 〔本文〕畫。元暦校本・神田本、「盡」。元暦校本、朱ニテ下ノ「皿」ヲ「右写真参照」ニ直セリ。 滷。神田本、「右写真参照」。 無。神田本、「无」。 〔訓〕 ヨシヱヤシ。西本願寺本・細井本、「ヨシエヤシ」。 礒者。神田本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本、右ニ朱「イソハ」アリ。 細井本、「礒」ノ右ニ朱「イソ」アリ。 ナクトモ。元暦校本、「ク」ノ右ニ赭「ケレ」アリ。 イサナトリ。元暦校本、「クチラトレ」。「レ」ノ右ニ赭「ル」アリ。 神田本、「クチラトル」。漢字ノ左ニ朱「イサナトリ」アリ。 大矢本・京都大学本、「イサナ」「リ」青。 京都大学本、漢字ノ左ニ赭「クチラトル」アリ。赭ニテ右ニ移スベキ記号ヲ附セリ。 ウナヒヲ。元暦校本・神田本、「アマヘヲ」。 西本願寺本、「ウミヘヲ」。 大矢本・京都大学本、「ウナヒ」青。京都大学本、「海邊」ノ左ニ赭「アマヘ」アリ。 〔諸説〕ナクトモ。万葉集玉小琴、「ナケトモ」。 イサナトリ。仙覚抄、「クチラトル」 (古点) ヲ否トシ「イサナトリ」トス。 ウナヒヲサシテ。仙覚抄、「アマヘヲサシテ」 (古点) ヲ否トシ「ウミヘヲサシテ」トス。 【本文 4】 和多豆乃 荒礒乃上尓 香青生 玉藻息津藻 朝(ニキタツノ アライソノウヘニ カアヲナル タマモキキツモ アサ) 〔本文〕息津。神田本、「自」。右ニ「息津」アリ。 〔訓〕 ニキタツノ。元暦校本・神田本、「ワタツミノ」。元暦校本、「タツ」ノ右ニ赭「キタ」アリ。神田本、「和」ノ左ニ朱「ニキ」アリ。 大矢本、「ニキ」ナシ。 京都大学本、「ニキ」青。漢字ノ左ニ赭「ワタ子/ツミノ/タツノ」アリ。赭ニテ「ワタツミノ」ヲ右ニ移スベキ記号ヲ附セリ。 カアヲナル。元暦校本、「アヲナル」ノ右ニ赭「アヲオフル」アリ。但、「ル」ハ明ナラズ。 オキツモ。元暦校本、「ヲチツモ」。「チ」ノ上ニ消セル痕アリ。細井本・温故堂本、「ヲキツモ」。 〔諸説〕ニキタツノ。仙覚抄、「ワタツミノ」 (古点) ヲ否トシ「ニギタツノ」ヲ可トス。万葉集玉小琴、「ワタツノ」。 アライソノ。代匠記精撰本、「アリソノ」トモ訓ズ。 香青生。万葉考、「生」ハ「在」ノ誤。 【本文 5】 羽振 風社依米 夕羽振流 浪社来縁 浪之共 彼(ハフル カセコソヨラメ ユフハフル ナミコソキヨレ ナミノムタ カ) 〔訓〕 ユフハフル。細井本、「イフハフル」。 ナミコソ。元暦校本、「ナミ」ノ右ニ赭字アレト不明。 キヨレ。細井本、「キヨル」。 ムタカヨリカクヨリ。元暦校本・神田本、「トモカシコモコヽモ」。元暦校本、「彼縁此依」ノ左ニ墨「カヨリカクヨリイ本」アリ。 神田本、「縁此依」ノ左ニ朱「ヨリカクヨリ」アリ。 西本願寺本・大矢本・・京都大学本、九字青。京都大学本、漢字ノ左ニ赭「トモカシコモコヽモ」アリ。 温故堂本、「ムタカヨソカクヨソ」。 〔諸説〕風社依米 (カセコソヨラメ)。万葉集略解、「カゼコソヨセメ」。万葉集古義、「依米」ハ「来米」ノ誤。訓、「カゼコソキヨセ」。 夕羽振流。万葉考、「流」ノ字衍トス。 ナミコソキヨレ。万葉集捃解、「ナミコソキヨセ」。 ナミノムタ。仙覚抄、「ナミノトモ」 (古点) ヲ否トシ「ナミノムタ」トス。 【本文 6】 縁此依 玉藻成 依宿之妹乎 [一云 □(右下写真参照)之伎余思 妹之手本乎] 露(ヨリカクヨリ タマモナス ヨリ子シイモヲ ツユ) 〔本文〕(此依の)依。神田本、ナシ。左ニ「縁」アリ。本文中「此玉」ノ間ニ「〇」符アリ。 □(右下写真参照)。元暦校本・神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本・活字無訓本・活字附訓本、「波」。 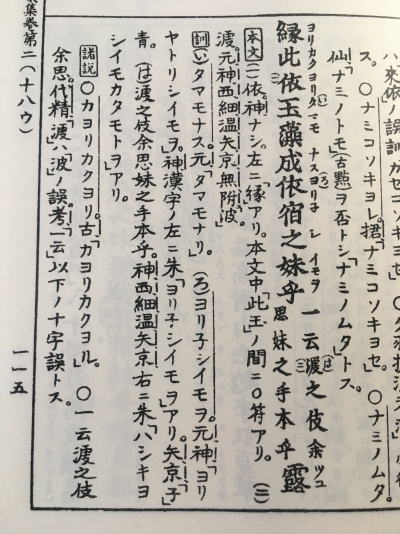 〔訓〕 タマモナス。元暦校本、「タマモナリ」。 〔訓〕 タマモナス。元暦校本、「タマモナリ」。ヨリ子シイモヲ。元暦校本・神田本、「ヨリヤトリシイモヲ」。 神田本、漢字ノ左ニ朱「ヨリ子シイモヲ」アリ。 大矢本・京都大学本、「子」青。 □(右写真参照)之伎余思 妹之手本乎。神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、 右ニ朱「ハシキヨシイモカタモトヲ」アリ。 〔諸説〕カヨリカクヨリ。万葉集古義、「カヨリカクヨル」。 一云 □(右写真参照)之伎余思。代匠記精撰本、「□」ハ「波」ノ誤。 万葉考、「一云」以下ノ十字誤トス。 【本文 7】 霜乃 □(右下写真参照)而之来者 此道乃 八十隈毎 萬段 顧為 (シモノ オキテシクレハ コノミチノ ヤソクニコトニ ヨロツタヒ カヘリミスレ) 〔本文〕乃。神田本、コノ下「□(右下写真参照)乃」アリ。 萬。細井本、「万」。 〔訓〕 シモノ。神田本、コノ下「ヲキ」アリ。 オキテシクレハ。元暦校本、「オキテコシハ」。 神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本、「ヲキテシクレハ」。 〔諸説〕ツユシモノ。代匠記精撰本、「ツユジモノ」。 【本文 8】 騰 彌遠爾 里者放奴 益高爾 山毛越来奴 夏草 (ト イヤトホニ サトハヌ マスタカニ ヤマモコエキヌ ナツクサ) 〔本文〕(放奴の)奴。大矢本、コノ下「益」アリ。但、消セリ。 〔訓〕 イヤトホニ。元暦校本・細井本、「イヤトヲニ」。 サトハヌ。元暦校本・神田本、「サトハハナレヌ」。神田本、「放」ノ左ニ朱「サカリ」アリ。 西本願寺本・細井本・大矢本・京都大学本、「サトハサカリヌイ」。 細井本、「放」ノ左ニ朱「ハナレイニ」アリ。大矢本・京都大学本、「サカリ」青。 京都大学本、「放」ノ左ニ赭「ハナレ」アリ。 温故堂本、「サトワカレヌ」。「放」ノ左ニ「ハナレ」アリ。 マスタカニ。京都大学本、赭ニテ「マス」ヲ消シテ右ニ「イヤ」ヲ書ケリ。 コエキヌ。細井本、「コヘキヌ」。 〔諸説〕里者放奴。童蒙抄、「サトハハナレヌ」ト訓ズルヲ否トシ「サトハサカリヌ」ト訓ズルヲ可トス。 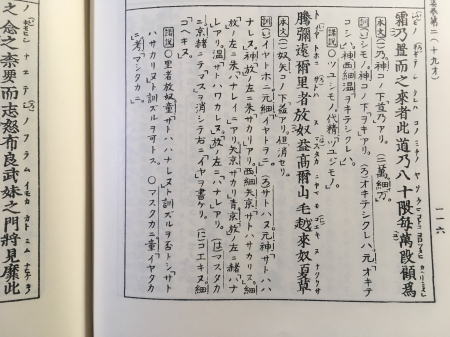 マスタカニ。童蒙抄、「イヤタカニ」。万葉考、「マシタカニ」。 【本文 9】之 念之奈要而 志怒布良武 妹之門将見 靡此山 (ノ オモヒシ ナエテシノフラム イモカカトミム ナヒケコノヤマ) 〔本文〕(念之の)之。元暦校本・神田本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「思」。 怒。西本願寺本、「奴」。 〔訓〕 オモヒシナエテ。元暦校本、「オモヒモナエテ」。「念思奈」ノ左ニ赭「オモホシナ」アリ。 神田本、「ヲモヒシナエテ」。 細井本、「ヲモイシナエテ」。 温故堂本、「ヲモヒシナヱテ」。 シノフラム。元暦校本、「シヌフラム」。「フラム」ノ右ニ赭「フラム」アリ。 〔諸説〕シノフラム。万葉考、「シヌブラム」。 [校本萬葉集新増補版]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「柿本朝臣人麻呂」万葉集注釈一考 | 注釈 | 「人麻呂」は既出 (1・29)。石見国滞在の事は史に見えない。人麻呂は石見国で死んでゐるらしい (222-225) ので、一度の旅行ではなくて、石見に滞在し、この上京以後にも再び石見に住んだのではないかと思はれる。即ち国府の役人として「掾目などのうちにありしならむか」といふ講義の説の如く、万葉考に「この度は朝集使にて、かりに上るなるべし、そは十一月一日の官会にあふなれば、石見などよりは、九月の末十月の初に並べし、仍て此哥に黄葉の落をいへり」といふ推定によるべきか。太政官式に「凡諸国考選ノ文及雑公文、附二朝集使一。十一月一日進二辨官一。云々」とあり、主計式上には調庸などの為に諸国より上京する往復の行程が記されてゐるが、石見国は「行程上廿九日。下十五日。」とある。この石見国で別れた妻といふのは、この歌につづいて載せられてゐる依羅娘子 (140) であらう。人麻呂には死んだ二人の妻 (207-216) があり、依羅娘子は人麻呂が死んだときに挽歌を詠んでゐるので、後の妻であることがわかる。代匠記や万葉考にはこの妻と依羅娘子とを別人と考へ、代匠記にはこの妻を初の妻とし、後に大和へ呼び寄せたが死別し、後依羅娘子を後妻としたと説き、考別記二「柿本朝臣人麻呂ガ妻」の條では二人の死別した妻と石見国で通ひ初し女と京で後に妻とした依羅娘子と四人の妻があつたと説いてゐる。私は三人の妻と考へるので、それらの妻についてはなほそれぞれの條で述べる。妻は倭名抄 (一) に白虎通云として「妻者斉也。輿レ夫斉レ躰也」とし、「和名米 (メ)」とある。それによつて嫡妻にのみ用ゐるべき字であるとも説かれてゐるが、古義に「古ヘは凡て嫡妻をはじめて、妾またかりに通婚せしをも、総ては米
(メ) と稱したことなれば、妻と書しこそ、古ヘのさまなれ」と云ひ、「ここなるは嫡妻にあらじ、こは石見国へまけられし間、彼ノ国にて、通ひ住し妻なりけむ」とあるに従ふべきである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「石見乃海 (いはみのうみ)」訓・注 | 万葉考 | 石見乃海 [イハミノウミ]、紀に、あふみのうみを、阿布彌能-彌 [ミ] とあれば、今もうみのうを略きよむなり、下もならへ、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 石見乃海は、イハミノミと訓べし、書紀神功皇后ノ卷ノ歌に、阿布瀰能瀰齊多能和多利珥 [アフミノミセタノワタリニ] (近江之海瀬田之渡爾なり、)とあり、石見の名ノ義は、字の如くなるか、又は石群 [イハムレ] の約りたるにてもあらむか、すべて此ノ國、唐の崎なる、かの大汝少彦名ノ二神の、おはしたる志都ノ岩屋、殊に岩多く群たる故にしか名におへるか小篠 [ヲサヽノ] 御野は、この國の海邊、おしなべて岩なれば、石海 [イハミノ] 國ならむと云るよし、斎藤ノ彦麻呂カ諸國名義考に云り、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「石見乃海」(イハミノウミ) 神功紀に、「阿布弥能弥(アフミノミ)」とあるにより考にイハミノミはと訓んで以来それに従ふ学者が多いが、集中の例では「伊豆乃宇美尓(イヅノウミニ)」 (14・3360)、「古之能宇美乃(コシノウミノ)」 (17・3959)、「奈呉能宇美能(ナゴノウミノ)」 (17・3989)、「布勢能宇弥尓(フセノウミニ)」 (17・3991) など、地名につづけて何々の海といふ場合、仮名書例は六音になつても、すべてウミとあるので、今もイハミノウミと訓む。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「石見乃海」(イハミノウミ) 旧訓「イハミノウミ」と訓まれていたのを真淵の考に「イハミノミ」と訂し、「紀にあふみのうみを、阿布弥能弥 (あふみのみ) とあれば、今もうみのうを略きよむ也、下もならへ」と記した。しかし、同じ考の次の「135歌」の冒頭「つのさはふ石見の海の」は、「イハミノウミノ」と略かずに訓まれていて、必ずしも「イハミノミ」に統一されていない。万葉集の仮名書に「古之能宇美乃」 (17・3959)、「奈呉能宇美能」 (17・3989) など字余りに「ウミ」と記されたものを見るし、「伊豆乃宇美」 (14・3360)、「駿河能宇美」 (14・3359) など「国名+ウミ」の形も見られる。後の例になるが、玉葉集の「名に高きいはみの海の沖つ波ちへにかくれぬ大和島根は」 (旅歌1179) も「イハミノウミ」となっている。しいて音を略して読まなければならぬ理由は認められない。石見の海は、「国府のあつた伊甘から都農、江西、江ノ川川口あたりまでの一帯の海のことで、つまり当時の国府の人々の頭に這入り易かつた範囲の海」 (評釈篇) と考えていい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「角乃浦廻 (つののうらみ)」訓・注 | 万葉考 | 角乃浦囘乎 [ツノヽウラワヲ]、和名抄に石見ノ國那賀ノ郡、都農 (都乃) とあり、こゝの海-方 [ベ] をいふべし 浦囘は浦のめぐりあたりをいふ、後世うらはと書は誤なり、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 角乃浦回乎、(回 (ノ) 字、拾穗本には廻と作り、) ツヌノウラミヲと訓べし、角は、和名抄に石見ノ國那賀ノ郡都農 (都乃 [ツノ] ) 郷あり、其ノ地の海邊なり、今も其ノ處を角津と呼よし、國人いへり、回をミと訓こと、上 (一卷) に委ク辨ヘ云り、(略解に、ウラマとよめるはわろし、また舊本に、ウラワとよめるなどは、云にも足ず) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「角乃浦廻」(ツノノウラミ) 原文「角」の文字は古事記では「木角宿祢者 木臣、(都奴臣、坂本臣之祖)」 (孝元記)、「高志前(コシノミチノクチ)之角鹿・・・今謂二都奴賀(ツヌガ)一謂也」 (仲哀記) などとあつて、ツヌと訓まれてゐるが、集中では「角松原 (ツノノマツバラ)」 (3・279) を又「都努乃松原 (ツノノマツバラ)」 (17・3899) と書き、「栲角乃 (タクヅノノ)」 (3・460) を又「多久頭怒能 (タクヅノノ)」 (20・4408) と書いて「ツノ」と訓まれてゐるから、今も「ツノ」と訓む。和名抄 (八)、石見那賀郡に都農がある。江川の河口の西南に今、都野津町 (江津市のうち) のあるあたりと思はれる。「浦み」の「み」は「島回」 (1・42) の「み」に同じ。浦回 (うらわ) の意。回、迴などの文字についても島回の條で述べた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「角乃浦廻」(ツノノウラミ) 「角」は「角松原」 (3・279) を「都努乃松原」 (17・3899) と記す例があり、「ツノ」と訓む。「努」は「ノ (甲)」の音をあらわす。和名抄の石見国那賀郡に都農とあるのは、今の江津市都野津町あたりと推測されていて、それと関係があるかと言う。浦廻は、旧訓「ウラワ」であったが、古義に「ウラミ」と改訓した。浦回とも書き、「礒浦箕」 (9・1671)、「礒乃浦廻」 (185、7・1155など)、「石浦廻」 (7・1301)、「礒之裏未」 (9・1799) などによって「ウラミ」と訓むことが察せられる。「ミ」は既出 (115歌参照)。「ミ (乙類)」で、曲りめぐる意の上二段動詞「ム」の連用形「ミ (乙類)」に語源が求められる。ある地形の部分を取り巻いている意で、その周辺の部分をあらわし、さらにその場所を漠然とさすに至ったものと言われる (時代別)。ここでは浦の湾曲したところを浦廻と言っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「浦無等 人社見良目 うらなしとひとこそみらめ)」訓・注 |
代匠記 | ウラナミト人コソミラメとは、能浦なしと、人こそみるらめなり、「る」もじなきは古語なり、和名云、四聲字苑云、浦、大川旁曲渚、船隱レ風所也、[傍古反、和名、宇良、] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | ○浦無等 [ウラナシト] (等ノ字拾穗本に登と作り、) は、よき浦なしと、といふなるべし、浦は、和名抄に四聲宇苑ニ云、浦ハ大川ノ旁曲渚、船隱レ風ニ所也、和名宇良 [ウラ] とあり、 ○人社見良目 [ヒトコソミラメ] は、他 [ヨノ] 人こそ、さは見らめ、よしやさはありともとの意なり、社 [コソ] は、他にむかへて、その物をとりわきて、たしかにいふ時の詞なり、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | ○浦無等 [ウラナシト] ――佳い浦が無いとの意。 ○人社見良目 [ヒトコソミラメ]――人こそ見るらめに同じで、見らめは古い格である。社をコソと訓むのは神社は人の祈願する所であるからで、乞の字をコソと訓むに同じである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 浦無等人社見良目 ウラナシトヒトコソミラメ。 社をコソと讀むのは、神社に對しては願望をするので、願望のコソに當て、轉じて係助詞にも使用するに至つたものとされている。ミラメは、「行來跡見良武 [ユキクトミラム]」 (巻一、五五) 參照。動詞見ルに、推量の助動詞ラムの接續したものである。ラムは動詞の終止形を受けるのを通例とするが、古くは上一段動詞に限り、ミラムの如き形を取るのである。その意は、世人は、浦無しと見もしようというにある。不定時の現在推量である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | 浦無しと よい浦がないと(代匠記)。人こそ見らめ 見らめは見るらめの古格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「浦無等 人社見良目」(ウラナシト ヒトコソミラメ) 浦無しと―「浦は裏(ウチ)にて汭江(イリエ)をいふ」と万葉考にあるやうに、「うら」「うち」同意の語で、汀が内へ入りこんで舟がかりするによいやうなところを云ひ、日本海に面したこのあたりの海岸は直線的で、所謂曲浦の趣に乏しい事を云つたものである。 人こそ見らめ―原文「社」は神社に祈願をかけるところより「乞」の字と同じく願望の意の「こそ」と訓み、更に係助詞の「こそ」にも用ゐたものである。その「こそ」をうけて推量の助動詞「らむ」が已然形「らめ」となつた。「らむ」は現在推量と云はれるものであるが、必ずしも厳密に現在その事があると推定される (1・4、40などの如き) 場合に限らない事、前 (1・55) に述べた。「見」と「らむ」との接続についてもそこで述べた。浦無しと世の人は見もしよう、といふのである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「浦無等 人社見良目」(ウラナシト ヒトコソミラメ) 「ウラ」は、海や湖の水際の陸の方に入りこんだところを言う。浦を新撰字鏡に「曲濱也」とし、万象名義に「水濱・水崖」と記すのは、右の「ウラ」に近い字義を思わせよう。「ウラナシト」は、よい浦が無いと、の意。「138歌」の或本歌では「津の浦を無み」となっており、巻十三にも「浦無みか 船のより来ぬ」 (3225) とあって、船着き場となるような良い浦がないことをあらわす。この「ウラナシ」も近い内容と見られる。澤瀉注釈には「日本海に面したこのあたりの海岸は直線的で、所謂曲浦の趣に乏しい事を云つたもの」と言う。「ヒトコソミラメ」の「ヒト」は、世間の人。「コソ・・・已然形」で、逆説。原文「コソ」を「社」と記す。「社(コソ)」は記紀の人名にも見え、広く使われたと見られる。神社に祈願をかけることから、希望の意の「コソ」をあらわし、さらに係助詞の「コソ」にも用いるようになったものか (注釈)。人麻呂歌集 (11・2359、13・3309) にも作歌 (138、3・239) にも用例がある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「滷無等(かたなしと)」訓・考 | 古義 | 滷無等 [カタナシト] は、おもしろき潟なしと、と云なるべし、舊本に一ニ云、磯無登とあり、滷は、和名抄に、文選海賦ニ云、海溟廣潟、師説ニ加大 [カタ]、字鏡に、灘ハ砂聚也、云々、又加太 [カタ]、また洲ハ洲渚ナリ、加太 [カタ] とあり、滷ノ字は、玉篇ニ云、滷ハ鹹水也とあり、いかゞにや、源ノ嚴水云ク、この滷 [カタ] は、鹽干潟にて、浦の汭江 [イリエ] など鹽干れば、深き處は、池などのやうに殘り、淺き處處、面白くあらはれ出て、めづらしければ、浦とむかへ云るなり、たひらかなるところの、唯一つらに、鹽の干たるは、何の見處かあらむ、出羽ノ國象潟、八郎潟など云る處は、鹽干潟にはあらねど、大海ちかき湖水にて、海とは、たゞ帶ばかりの濱を、隔たるのみにて、小き嶋などありていとめでたき處なり、この潟、越後あたりにも、こゝかしこに有といへり、岡部氏は、北海には鹽の滿干なき故、潟なきよしいへれど、出羽越後、すでに潟あれば、石見ノ國にも、いにしへは、かかる處を、潟といひけむを、角の浦に、かゝる潟のなかりければ、かくよまれしなるべし、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 滷無等 [カタナシト] ―― これも良き潟なしとの意。滷は干潟となる遠淺の海岸をいふ。北海は干滿の差が無いから、潟もないわけである。滷の字は潟に同じ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | 潟無しと 潟は干潟となるやうな遠淺の海岸。 なほ日本海岸に多い八郎潟、邑知潟、象潟などの潟で、一種の鹹湖をいふといふ説(講義)も注意すべきである。よい潟がないと。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「よしゑやし」訓・考 | 拾穂抄 | よしえやし 仙曰よしや也えの字下のしの字助語也見安云よしやよし也 袖中抄こそはといふ心也あらはあれと云心也 なといへるも此義に同 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | 能嘆八師は、よしやの古語なり、古事記上に、阿那邇夜志 [アナニヤシ] とあるは、日本紀の神代紀に、妍哉、此云二阿那而惠夜 [アナニエヤ] 一、とあるに同じ、然れば「あなにやし」の「し」は語の、助なり、又神武紀に、妍哉、此云二鞅奈珥夜 [アナニヤト] 一、とあれば、「あなにゑや」の「ゑ」も休め字なるを以て、今のよしゑやしの「ゑ」と「し」との二字助語なること准じて知べし、後に吉哉と書てよしゑやしとよめる此なり、「嘆」は上に注する如く咲の字の訛れるなり、咲は「ゑむ」とよむを下を略して用るは、諺に笑ふ顔のうるはしきをゑがほよしと云が如し、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉考 | 能咲八師 [ヨシヱヤシ]、假にゆるして縱 [ヨシ] やといふなり、咲と師は助辭、下も同じ、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | ヨシヱヤシは、ヨシヤと言ふにて、ヱとシは助辭なり。其の浦も滷も無くともよしや、我は愛る妹有りと言ふ心なるをここには言はず、次に句を隔てて依寢シ妹と言ふにて知らせたり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | ○能咲八師 [ヨシヱヤシ] (咲ノ字、舊本に嘆と作るは、誤なり、今は元暦本拾穂本等に從つ、古寫本に唉とあるも、咲の誤ならむ、) は、假リに縱 [ユル] す辭とて、よしやさはあれ、といふ意の古言なり、又四惠夜 [シヱヤ] とも、惠夜 [ヱヤ] とも云ヘり、師 [シ] は、助辭なり、(岡部氏が、咲をも、助辭といへるは、たがへり、) ○浦者無友 [ウラハナクトモ] は、よき浦は無とも、と云なり ○縱畫屋師 [ヨシヱヤシ] は、上に云るが如し、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 能咲八師 [ヨシエヤシ] ―― よしやといふに同じで、ヱとシとは詠嘆の助詞である。よしやは、たとひの意。 浦者無友 [ウラハナクトモ] ―― 無友は舊訓ナクトモであるのを、宣長はナケドモに改めた。併しここは已然形でなくともよい所であり、又卷十五に與之惠也之比等里奴流欲波安氣婆安氣奴等母 [ヨシエヤシヒトリヌルヨハアケバアケヌトモ] (三六六二) とあつて、ヨシヱヤシを、トモで受けてゐるから、これもナクトモがよからう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | (二句目の)縱畫屋師滷者無鞆 [ヨシヱヤシカタハナクトモ]。 上の二句に對して對句を成している。講義にここで段落であるように説いているのは誤りである。 一云礒者 [アルハイフ、イソハ]。 滷者に對する別傳である。この別傳は、上の一云礒無登とある別傳と同一の傳來であることが知られる。この傳來には、共に滷に代うるに礒とあつたので、照應をしている。かように一首の中には、同一の傳來による別傳が記入されているので、それらの一を採つて本文を改めるが如きことは、避けねばならぬことである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | よしゑやし よしゑは獨立して用ゐた例(二五三七)もあり、又「我はくるしゑ」 (天智紀) ともあり、ゑは感動の助詞。やしは「あなにやし」「はしきやし」のやしに同じ。 たとへ――であつてもの意。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「能咲八師・縦畫屋師」(ヨシヱヤシ) 「ゑ」も「やし」も詠歎の助詞。「よしゑ」 (11・2537) とも云ひ、単に「よし」 (10・2110) ともいふ。その「よし」には「縦」の字が当てられてゐる事が多く、その漢字の義と同じ意味に用ゐられてゐる。即ち、 馬買はば妹徒歩(かち)ならむ縦恵八子(よしゑやし)石は踏むとも吾は二人行かむ(13・3317) の如きは、たとひ何々しようとも、よしや何々であらうとも、などの意に用ゐられたものであり、 縦恵八師(よしゑやし)死なむよ吾妹生けりともかくのみこそ我が恋ひ渡りなめ(13・3298) の如きは「ゆるす」の意によるもので、本来ならばゆるす事でなく、それが望ましい事ではないが、事情がかうなつてる上は、力及ばず、もういつその事、と捨てばちな気持ちになる、さういふなげやりな「ゆるす」であつて、一言にいへば「ままよ」といふ事である。その場合だとそこで切れた形になる。今の場合もそれだと解釈されがちであるが、今は前者の場合であつて、よしや浦は無くとも・・・風こそよせめ、とつづいてゆくのである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「能咲八師 浦者無友 縦畫屋師 滷者 [一云 礒者] 無鞆 」(ヨシヱヤシ ウラハナクトモ ヨシヱヤシ カタハ [イソハ] ナクトモ) 「能咲八師」「縦畫屋師」は「ヨシヱヤシ」の仮名表記。「能」は「ヨク~ス」という可能の意に用いられることが多く、そこから「ヨシ」にも宛てられた。万葉集にも「玉津島能(ヨク)見ていませ」 (7・1215)、「能(ヨシ)野川いはとかしはと常磐なす吾は通はむ」 (7・1134、芳野作) などの例を見る。「咲」は「エム」意。その語幹「ヱ」の仮名として使ったもの。「縦」は、万象名義に、「子用反、恣・放・・・乱・緩」とあり、「ユルスコト、ハナスコト、ホシイママニスルコト」などを意味する。ここではどうあってもかまわないという、認容・放任の意の「ヨシ (副詞)」に宛てる。八(ヤ)・師(シ)・畫(ヱ)・屋(ヤ) は一字で一音ずつに宛てた仮名。「ヨシヱヤシ」の「ヱ・ヤ・シ」は助詞。逆説仮定条件の助詞「トモ」と呼応し、たとえ人の言う通りであろうともの意をあらわす。「滷は無くとも」まで、代匠記・講義などに第一段とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「鯨魚取(いさなとり)」訓・考 | 拾穂抄 | いさなとり 仙曰古点にくしらとると点其心あたらすいさなとりと和すへし 鯨魚取 [イサナトリ] 淡海 [アフミ] の海とも有近江の海にいかて鯨あるへき日本紀衣通姫の哥とこしへに君もあへやもいさなとり海のはまものよる時ときをいさなとりは魚とる儀也鯨をいさとよむ壹岐風土記云鯨伏 [イサ] 在二郡西ニ一昔者 [ムカシ] 鮨鰐 [ワニノウヲ] 追 [ヲフテ] レ鯨ヲ走リ來ル隠レ伏ス故ニ云二鯨伏ト一俗ニ云為伊佐 [ヰイサ] 畧注愚案童蒙抄ニ此衣通姫のいさな取を礒菜とり也さとそと五音相通する也とあり正説なるへしされはいさなとりは海の枕詞にて礒菜は近江にもあるへけれはいさなとり近江の海ともいふへし又釋日本紀衣通姫哥釋ニ曰ク謂フ二鯨取ト一異舎 [イサ] 者鯨也儺 [ナ] 者魚也言 [イフコヽロハ] 漁シテ取ル二鯨魚ヲ一也私案ニ欲スルレ謂ントレ海ト之發語也云々くしらとりの説不可捨 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 鯨魚取 [イサナトリ] は、海といはむ料 [ガネ] の枕詞なり、書紀允恭天皇ノ卷ノ歌に、等虚辭部邇枳彌母阿閇椰毛異舍儺等利宇彌能波摩毛能余留等枳等枳弘 [トコシヘニキミモアヘヤモイサナトリウミノハマモノヨルトキトキヲ] とあり、集中には往々見えたり、鯨魚は、伊佐邪 [イサナ] にて、即チ鯨 [クヂラ] の事なり、壹岐ノ國風土記、鯨伏ノ郷といふ、名の由縁を云るところに、鮫走來テ隱伏キ、故云二ニ鯨伏 [イサフシト] 一云々(俗云レ鯨爲二伊佐 [イサト] 一、)と見えたり、なほ鯨の事、品物考に云り、さて鯨魚を漁 [トル] 海、とつゞけたり、鯨魚等留 [イサナトル] といはずして、等利 [トリ] としも云るは、歌ひ絶て、次の句を歌ふ枕詞の一ツノ格にて、其ノこと上にも云り、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 鯨魚取 [イサナトリ] ―― 鯨を古名イサナと呼んだ。勇魚 [イサナ] の義であらう。鯨を捕へる海の意で枕詞として用ゐられる。この句から玉藻成 [タマモナス] までは、依宿之 [ヨリネシ] と言はむ爲の序詞。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 鯨魚取 イサナトリ。枕詞。鯨魚を取る義で、海に冠する。クジラをイサナということは、壹岐國風土記の逸文に「鯨伏、昔者鮨鰐追レ鯨、鯨走來隱伏、故云二鯨伏一。鰐竝鯨竝化二爲石一、相去一里。俗云レ鯨爲二伊佐一」(萬葉集註釋所引)とある。「異舍灘等利 [イサナトリ] 宇瀰能波麻毛能 [ウミノハマモノ]」(日本書紀允恭天皇紀)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「鯨魚取」(イサナトリ) 海、濱などの枕詞。允恭紀に「異舍儺等利宇彌能波摩毛能 (イサナトリ ウミノハマモノ)」と仮名書例があり、本集には「勇魚取 (イサナトリ)」 (138) ともある。仙覚抄に引用の壱岐国風土記に「鯨伏郷在二郡西一、昔者鮨鰐追レ鯨、鯨走來隱伏、故云二鯨伏一。鰐竝鯨竝化二爲石一、相去一里。俗云レ鯨爲二伊佐一」とあるによつて鯨魚を「いさな」といふ事がわかる。鯨魚を取る意として用ゐあっれた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「鯨魚取」(イサナトリ) 海・浜・灘などにかかる枕詞。「イサナ」は勇魚とも書かれ鯨を意味する。仙覚抄所引壱岐風土記に「俗云鯨爲伊佐」とある。その鯨を取る海の意で、海に関連する語を修飾する。なお、この枕詞は、万葉集以後は使われない (新続古今集神祇部の歌は、日本書紀歌謡を再録したものである)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「海邊乎指而(うみへをさして)」訓・考 | 代匠記 | ウナヒヲ指テとは、出立て舟に乘て來るなり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉考 | 海邊乎指而 [ウミベヲサシテ] 、 指て行なり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 海邊乎指而は、ウミヘヲサシテと訓べし、十八に、波萬部余里和我宇知由可波宇美邊欲利牟可倍母許奴可安麻能都里夫禰 [ハマヘヨリワガウチエカバウミベヨリムカヘモコヌカアマノツリフネ]、とあるは、これ海邊を、「ウミヘ」と訓べき、明 [サダ] かなる例證なり、又書紀竟宴ノ歌に、佐々奈美乃與須留宇美倍爾美夜波之女與與爾多江奴加支美加美乃知波 [サヽナミノヨスルウミベニミヤハジメヨヽニタエヌカキミガミノリハ]、(知は、利の誤といへり、)古今集に、めいじうといふ宇美邊 [ウミヘ] にて、土佐日記に、もし宇美弊 [ウミへ] にてよまゝしかば、などもあり、(然るを、是を舊訓によりて、註書どもにも、「ウナヒ」とよみ、又本居氏も、然訓べきよし、既くいはれたりといへども、必スさは訓まじき理あり、こはもしは、十四に、奈都蘇妣久宇奈比乎左之弖 [ナツソビクウナヒヲサシテ] 云々とある、宇奈比 [ウナヒ] を、海邊と心得たるより、しかよめるにやあらむ、かゆ宇奈比 [ウナヒ] は、攝津ノ國にも、兎原 [ウナヒ] てふ地ある如く、地ノ名にてこそあらめ、彼ノ歌の前後の次 [ナミ] も、皆地ノ名をよめるにても、しるべし、さて山備 [ヤマビ] 河備 [カハビ] 岡備 [ヲカビ] 濱備 [ハマビ] などいふ言のあれば、宇奈備 [ウナビ] ともいふべし、と思ふ人あるべけれども、もしその例によらば、宇美備 [ウミビ] とこそいはめ、宇奈原 [ウナバラ] などいふ奈 [ナ] は、之 [ノ] に通ふ言にて、海之 [ウノ] の意、海原を、宇乃波良 [ウノハラ] とも、假字書せるにてしるべし、さらばいかでか、海乃備 [ウノビ] 、と乃 [ノ] の言をおきては云べき、されば河乃備 [カハノビ] 、山刀傍 [ヤマノビ] 、など云ること、ひとつもなし、但し九ノ卷に、三諸之神邊山爾 [ミモロノカミナビヤマニ] 云々、とあれば、なほ邊を、「ナビ」と訓べからざるにあらず、と人皆思ふこともありなむ、余も、神邊と書ること、いと意得がてなりしを、よく思ふに、邊は、連ノ字の寫誤なるべく、おもひなりぬ、七ノ卷に、佐左浪乃連庫山爾 [ササナミノナミクラヤマニ] 云々、とも有を、考ヘ併セてしるべし、邊ノ字にては「ナビ」と訓べき理、あるべくもあらずなむ、) 指而 [サシテ] は、玉藻奧津藻 [タマモオキツモ] を、風浪の海邊を指て、來縁する意なり、(岡部氏が、作者の自ら指て行ク意に、解なせるは、大 [イミ] しき非なり、) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 海邊乎指而 ウミベヲサシテ。ウミベは海岸。海岸を目ざして海藻を寄せると、下文に續く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | 海邊をさして 古義に下の「風こそ依せめ」「浪こそ來縁せ」につづけるといふ説がよい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「海邊乎指而」(ウミベヲサシテ) 沖から海岸の方へ、の意で、下の藻が寄せるとつづく。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「海邊乎指而」(ウミヘヲサシテ) この句の掛かり方に問題があり、代匠記(精撰本) には「出立テ舟ニ乘テ來ルナリ」とし、万葉考には「指て行也」と解した。茂吉評釈も「海辺を通つて来て」と訳している。しかし、古義にはこの万葉考の説を「大(イミ)しき非なり」と否定し、「指而は玉藻奥津藻を風浪の海辺を指て来縁する意なり」と記した。作者が海辺をさしてゆくとは受け取り難いだろう。私注に「このサシテは明瞭でない語である。海べをさして行くの意味の行くが省略されて居ると見るのは分かりよいが、作者は海ぞひに行くので、それを海べをさしてとは言ふまいと思はれる上、前後の語調からもさうした省略があるとは考へられない。風、波が海べをさして寄るといふ説も、餘り句を距てすぎて居るやうに思はれる」と言うように問題のある句である。即ち「ウミベヲサシテ、カアヲオフル、タマモ云々と続けて解かうとするのである」というのも従えない。諸注の中にはこの部分の接続関係の不明な口訳文もあり、問題の深さを感じさせるのであるが、古義説を受ける形で古典全集や古典集成に「風こそ寄せめ」「波こそ来寄れ」に続くと注しているのが構文上もっとも妥当である。ただし、「風こそ寄せめ」の訓については後述。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「海辺乎指而」(ウミヘヲサシテ) この海辺は沖から海辺をさしていう。下の「風こそ寄せめ」「波こそ来寄れ」に続く。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「和多豆乃(にきたづの)」訓・注 | 拾穂抄 | にきたつ 伊予の熟田津にはあらし石見の角の浦を思ふ哥なれは也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉考 | 和多豆乃 [ニギタヅノ]、 今は此名なしといへり、されども國府より屋上まで行間、北の海方[ベ]にて、即そこの有さまを、ことばとしつる歌なるからは、和た津てふところ、その邊にありしなり、今濱田といふは、もしにぎたの轉にや、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉の小琴 | 和多豆乃、石見國那賀郡に、渡津村とてて海邊に今もあり、是也、此句四言に訓べし、多豆の二字を音に書たれば、和も字音に書ることしるし、然るににぎたづとしも訓るは、伊豫の熟田津のことを思ひて、ふと誤れるものなるを、今迄其誤を辨へたる人なし、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | 和多豆は宣長云、石見國那賀郡の海邊に渡津 [ワタヅ] 村とて今有り、ここなるべし。さればワタヅノと四言の句なり。或本の歌柔田津と書けるは、和多豆をニギタヅと訓み誤れるにつきて出來たる本なるべしと言へり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 和多豆乃、本居氏、石見ノ國那賀ノ郡の海邊に、渡津村とて今有リ、ここなるべし、されば和多豆乃 [ワタヅノ]、四言の句なり、或本の歌に、柔田津と書るは、和多豆を「ニキタヅ」 とよみ誤れるにつきて、出來たる本なるべしと云り、(にきたづといふ地は、今もなしと國 [クニ] 人も云り、) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 和多豆乃 [ワタヅノ] ――舊訓ニギタヅだが、玉の小琴に、石見國那賀郡の海邊に渡津村といふのが今もあると言つてから、ワタヅ説が有力になつた。次の或本の歌には柔田津とあるから、ニギタヅとよむのも捨つべきでないが、今、石見にその地名が無いから、暫くワタヅとよむことにする。渡津は江川の河口、都濃村の東北にある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 和多豆乃 ワタヅノ。ワタヅは渡津で、航海する船の發著地である。或る本の歌(一三八) のこの句に相當する處には、柔田津乃とあるので、ここをもニキタヅノと讀む説 (仙) があるが、その方はよい傳來でないから、これを證としないがよい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | 和多豆 [わたづ] 地名、今の那賀郡江津町渡津の地で、江川 [がうのがは] の河口の東岸、角の東に當る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「和多豆乃」(ニキタヅノ) 原文「和多豆」とあるので、「ワタヅ」と訓み渡津の意とし、都野津より更に一里余りも東にある江川の東岸の江津市渡津のことだとする説が多く行はれてゐるが、この歌の異伝である或本の歌 (138) には「柔田津」とある。それとこれとは同じもので「和」の字は「和細布 (ニキタヘ)」 (3・443)、「和海藻 (ニキメ)」 (16・3871) などのやうに、「ニキ」と訓ませるつもりで書いたものと思はれる。「和多豆 (ワタヅ)」を「ニキタヅ」と訓み誤つた為に「柔田津」と書くやうになつたと説く人々があるが、これはもつてまはつた解釈で、人麻呂は自作に推敲を加へ、いろいろに書きかへ、文字も自由にとりかへて用ゐたので、「屋上の山」(135) を又「室上山」とも書き、「勿散乱曾 (チリナマガヒソ)」 (137) を又「知里勿乱曾(チリナマガヒソ)」とも書いた如く、「和多豆」とも「柔田津」とも書いたので、「柔田津」とある事こそ「ニキタヅ」と訓む証と見るべきである。渡津では位置として不適当で、ここはまだ出発前、妻とむつみかはした時、そのより寝た地の事を云つてゐるのであるから、出発後、次の長歌にある渡(わたり)の山の付近の渡津を持ち出すのは早すぎるのである。ただその柔田津がどこかといふ事が不明であるが、「和田 (ニキタ)」とは「荒田」と対する言葉で、よく耕され土壌の肥えた豊穣な田の意味で、都野津付近にさうした田野があつて和田津と云つたと見ればよいであらう。普通名詞にも近い地名で、現に伊予にも同名の熟田津 (1・8) があつたのだが、それも今日知られなくなつてゐるやうに、この柔田津もその名が失はれたと見るべきである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「和多豆乃」(ワタヅノ) 「和多豆」は古訓に「ワタツミノ」とあったのを、仙覚が「ニキタツノ」と改訓した。代匠記・万葉考などそれによったが、宣長の「玉の小琴」に、「此句四言に訓べし、多豆の二字を音に書たれば、和も字音に書ることしるし、然るににぎたづとしも訓るは、伊豫の熟田津のことを思ひて、ふと誤れるものなるを、今迄其誤を辨へたる人なし」として、「ワタヅノ」と訓むべきことを提唱した。以後の諸注は、ニキタツ説「檜嬬手・攷證・美夫君志・注釈・古典大系・古典全集・古典集成など」、ワタツ説「古義・註疏・新考・講義・全註釈・評釈篇・佐佐木評釈・窪田評釈など」のいずれかによっている。前者を採る澤瀉注釈には、「この歌の異伝である或本の歌 (138) には『柔田津』とある。それとこれとは同じもので『和』」の字は『和細布 (ニキタヘ)』 (3・443)、『和海藻 (ニキメ)』 (16・3871) などのやうに、『ニキ』と訓ませるつもりで書いたものと思はれる。」と言う。「渡津では位置として不適当で、ここはまだ出発前、妻とむつみかはした時、そのより寝た地の事を云つてゐるのであるから、出発後、次の長歌にある渡(わたり)の山の付近の渡津を持ち出すのは早すぎるのである」とも記すのは、宣長が「和多豆」を「和多豆乃、石見國那賀郡に、渡津村とてて海邊に今もあり、是也」と断定したのに対する反論である。一方、後説による全註釈には、「或る本の歌(一三八) のこの句に相當する處には、柔田津乃とあるので、ここをもニキタヅノと讀む説 (仙) があるが、その方はよい傳來でないから、これを證としないがよい」と記している。問題は、「和多豆」の訓と、「或本の歌」(138) の「柔田津」との関係、及び現存する地名との関係の三点に絞られると思う。そのうち、現存の地名との関係については、「角の浦」にしても、「高角山」にしても確かなことが言えないのと同様に「渡津」を論拠として「和多津」の訓を決定することは、方法的に無理であろうと思われる。また、「或本歌」の「柔田津」によって、「和多豆」を「ニキタツ」と訓むことも、方法的に疑問を含む。人麻呂作歌の異伝については後述するが、「柔田津」と記す「138歌」が人麻呂の初案を示すとしても、また、後代の人々による伝承後の変化をあらわすとしても、一方の文字面から一方の訓を決定することは難しい。それを端的に示すのは「132歌」の「高角山」と「139歌」の「打歌山」の場合で、後者を前者にならって「タカツノヤマ」と訓み、「打」を「タ」、「歌」を「カ」の音仮名と考えて、「ツノ」に相当する文字の誤脱まで想定した万葉考の説の誤りであることは、現在では常識化している。「132歌」と「139歌」との関係が作者の推敲の結果であるか否かに関わりなく、「打歌山」は「ウツタノヤマ」と訓み、「高角山」とはいちおう切り離して考えられるべきである。そうした例に照らしても「和多豆」は「柔田津」と切り離して先入見なしに読み解かれなければならない。もし「和多豆」を普通の仮名書きの例として訓むなら、「ワタヅ」であって、「ニキタヅ」にはならないだろう。もちろん宣長の言うように「多豆」が音仮名だから同様に「和」も音仮名のはずだというような単純な理由ではない。万葉集における単語の交用表記からいって地名「ニキタツ」を「和多豆」と記したとは考え難いのである。音仮名頻度のきわめて高い「和」を「ニキ」と訓読させ、そのあとに「多豆」という音仮名を連続させるような、誤読の危険性の高い記し方を避けているのが、万葉集の筆録者たちの知恵である (詳細は『万葉表記論』第三篇「音訓交用表記の論」参照)。したがって、「ワタヅ」と訓むのがおそらくおそらく正しいと思われる。 宣長の言う渡津は、都野津の東北、江川を渡った対岸にあるが、それがここに言う「和多豆」であるかどうかは不明。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 【和多豆乃】(ニキタヅノ) 「和多豆(ニキタヅ)」は、地名か穏やかな津を言う普通名詞か不明。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「有礒乃上尓(ありそのうへに)」訓・考 | 代匠記 | 【和多豆乃荒礒乃上爾】「ニキタツノアライソノウヘニ」 ニギタヅノ荒礒ノ上ニ、熟田津は第一に出たり、荒磯はアリソともよめり、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 荒磯乃上爾 [アリソノウヘニ] は、藻を風浪の礒の上によせ來るよしなり、荒磯 [アリソ] は、(「アライソ」の、「ライ」を切れば、「リ」となる故に、「アリソ」と云、) 荒 [アラ] は、荒山 [アラヤマ ] 荒野 [アラヌ] などの荒 [アラ ] なり、礒は海濱 [ウミヘタ ] の石巖を云り、(玉篇云、□[山/欽]□[山/金]崎礒ハ、石巖也、とあり、) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 荒礒乃上爾 [アリソノウヘニ] ―― 荒磯は人げ疎き荒凉たる磯。波の荒きをいふのではない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 荒礒乃上尓 アリソノウヘニ。アリソは、アライソの約言。荒い礒で、浪や岩が大きく、豪壯の感を與える礒をいう。ウヘは、その上であるが、荒礒にというに同じ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | 荒磯(ありそ)の上に 荒い磯の上に、下に生ふるを補つて解する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「荒礒乃上尓」(アリソノウヘニ) 「古之能宇美乃 安里蘇乃奈美母 (コシノウミノ アリソノナミモ)」 (17・3959) などの仮名書例により「アリソ」と訓み、語意は荒礒の文字による。「荒礒(あらいそ)」をつづめて「アリソ」と云つたものと思はれる。現礒 (アライソ) の義と見る説もあるが、集中卅八例中「荒」又は「麁」の文字を用ゐたもの卅例、「有」「在」一例づつあるのみで他は仮名書である。特にこの語人麻呂及び人麻呂集に用例多く、十一例中、人麻呂集に「在衣邊 (アリソベ)」 (9・1689) の一例ある他はすべて「荒礒」とある。右の一例は「礒」も「衣」といふ借訓仮名である事が注意せられる。尚これらの「礒」の文字も右に述べたやうに「磯」の方が適切であるが、当時主として「礒」を当てたやうである。そして時に、 潮気立つ荒礒にはあれど行く水の過ぎにし妹が形見とぞ来し (9・1797)人麻呂集 ま草刈る荒野にはあれどもみち葉の過ぎにし君が形見とぞ来し (1・47)人麻呂 の「荒礒」「荒野」を較べる事によつて文字通り「荒礒」の義に用ゐた事がわかる。即ちこの「荒礒」は右に「礒なし」と云つた舟人たちに親しまれたよい礒でなくて、人々に忘れられたやうな荒礒の意である。ただかうして人麻呂たちの歌に「ありそ」の語がくりかへされてゐるうちに本来の「荒」の意が次第に失はれて単に「いそ」といふべきところにも「ありそ」といふ語が特に歌語として愛用されるに至つたと見る事も出来よう。さてその荒礒の上に藻が寄せるのである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「荒礒乃上尓」(アリソノウヘニ) 「荒礒」は「アリソ」と読む。荒い海岸の厳を意味する「アライソ」の約。集内に安里蘇・安利蘇などの仮名書き例がある。人麻呂集に「在衣 (アリソ)」(9・1689) という訓仮名表記も見え、約音化の早く行われていたことが知られる。「上に」は、「~ノホトリニ」の意。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「新全集」採用の「有」について | 新全集 | 【有礒乃上尓(ありそのうへに)】新全集凡例より 「新編日本古典文学全集」西本願寺本を底本とし、古写本の校合は、校本萬葉集によると共に、桂本・元暦校本・金澤本・紀州本・類聚古集・古葉略類聚鈔・神宮文庫本など複製本の備わっているものはこれについて再検証し、冷泉本・陽明本・近衛本・京都大学本は現物について確認することに努め、また検天治本や諸家に伝わる断簡類についても目に触れたものはすべて校勘に付し、誤りがないように配慮した。 [私が目にする諸本・諸注の範囲では、すべてが「荒」であり、「新全集」が採る「有」は、見当たらない。凡例を読む限り、どこかにその原点はあると思うのだが・・・] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「香青生(かあをくおふる)」訓・考 | 拾穂抄 | 香青 [カアヲ] なる かうはしくあをき也藻をほめていふ詞なるへし或説かは助字也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | 香青在 [カアヲナル] は、「か」も發語の詞なり、此集に黒きを「か」くろきともよめり、源氏に易さを「か」やすき、弱きを「か」よはき、よれるを「か」よれるなどあり、俗にも細きを「か」ほそきと云へり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉考 | 香青在 [カアヲナル]、香は發言にて、集中に、香黒キ髪、さいばりに、かよりあひなどいふ皆同じ、 「在」を今本「生」と有は、草の手より誤れるものなり、青に有てふ言をつゞめて、あをなると云に、在と書は例なり、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 香青生 [カアヲナル] とは、香 [カ] は、發言にて、集中に黒 [クロ] きを可黒 [カクロ] き、易きを可易 [カヤス] き縁會 [ヨリアヒ] を可縁 [カヨリ] あひ、細 [クハシ] きを可細 [カクハシ] き、(但し可細 [カクハシ] きの可 [カ] は、香 [カ] の細 [クハシ] きを云と、たゞ發言に云ると、二ツあり、) など云り、又よわきを、かよわきと云ることも、物語書に見えたり、みな同じことなり、生 [ナル] は、借リ字にて、爾有 [ナル] の意なり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 香青生 [カアヲナル] ―― 香は接頭語。さ青などいふも同じ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 香青生 カアヲナル。カは接頭語。色については、「蚊黒爲髪尾 [カグロシカミヲ]」(卷十六、三七九一) の例がある。次の句を修飾している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | か青なる かは接頭辭。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私注 | 【語釈】「香青生」(カアヲオフル) 青く生えて居る。「カ」は發語。此の句は「カアヲナル」と訓まれて「ナル」は「ニアル」の意、即ち「カアヲナル」は青い意と解かれて居た。然し「生」を「ニアル」の意としては借訓としても例がないし巻十三 (3291) の歌に「真木立山爾 青生 山菅之根乃」とある。「青生」は「アヲクオフル」と訓むべきであらうから、ここも「カ」が加はつただけで「カアヲクオフル」と訓まねばならぬ所であらう。ただ音数が多いから「高く知らす」を「タカシラス」と言ふ格で「アヲオフル」と訓むのである。又巻十四 (3488) の「於布之毛等」を生ふる楚の意と見れば「オフ」に四段の活用があつて、此の句も「カアヲオフ」と五音によめるかも知れないがそれは文法学者の説をまつことにした。尤も「オフル」といふ訓は元暦校本の代赭で既に見えて居るとのことである。或は生は「ムス」の訓も考へてみるべきかも知れぬ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「香青生」(カアヲナル) 「香青生」を旧訓に「カアヲナル」とする。元暦校本には「アヲナル」の右に「アヲオフル」ともある。「生」は「オフ・イク」に宛てられることも多い文字で、人麻呂歌集及び作歌にも「生刀毛無」 「上瀬尓生玉藻」など見えるが、「ナリ」とか「ナル」にあてた例は、見られない。万葉集内でもただ一例。巻十一に「潮満てば水沫に浮かぶまなごにも吾は生鹿恋ひは死なずて」(2734) の「生鹿」を「ナリシカ」 (注釈)・「ナレルカ」 (私注)・「ナリテシカ」 (桜楓本) と訓む説によれば、「ナリ」に宛てた例があることになる。「生」は玉篇佚文に「産地進也造也」とあり、また「凡生天地之間皆謂物也事也」ともある。日本語の「ナル」はあるものが変化して他の物になること、事が成就すること、生物が生じ、成長することをあらわすのであって、とくに最後の意味が、「生」の字義と重なるところをもつ。したがって「カアヲナル」を「香青生」と記すことは、あり得たものと考えられる。また巻十六に「人魂の佐青有君が」 (3889) という詞句があり、「サアヲナル」の語形も認められるから、「カアヲナル」も同様に扱われよう。問題は、人麻呂が「蚊青生」ではなく「香青生」と記したのはなぜかという点にあると思われるが、生命感あふれる藻のイメージを愛好した作者が、本来「香青有」と記すべきところを「香青生」とすることもあったのではなかろうか。人麻呂の文字遣いに細かい配慮を見る事は後にも記す通りで (210歌参照)、ここは岩礁に生えているものであることを文字によって示したと考えられよう。なお、毛利正守「万葉集・オモフの字余りと脱落」 (親和国文十七号) に字余り研究の立場から「カアオナル」と字余りでなく訓むむべきことを説いているのも参照される。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釈注 | 【注】「香青生」(カアクオフル) 「か青く」は青々と。「か」は接頭語。「巻五-804、か黒き髪」など。「生ふる」は根生えている意。この句、中に母音が二つあって字余りであることを免れる。ただし、旧訓は「香青生 (カアヲナル)」。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「玉藻息津藻(たまもおきつも)」訓・注 | 代匠記 | 玉モオキツモとは、玉もは藻をほめ、おきつ藻は、奥に有藻なり、共に藻の□[手偏+總の旁] 名にて、あながちに替らねど、かく重ねて云るは古歌の習なり、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉考 | 玉藻息津藻 [タマモオキツモ]、 同物を重ねいふはあやなすのみ、息は借字、澳なり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 玉藻息津藻 [タマモオキツモ] とは、息 [イキ] は借リ字にて、澳 [オキ] なり、玉藻は藻をほめていふ、澳津藻 [オキツモ] は、海ノ底に生たるをいふ、礒邊に生たるを、邊津藻といふに對ひたり、さてこれは、二ツ物にあらず、やがて澳津玉藻とも云るにてしるべし、一ツ物を、かく二樣にいひて、あやなしたるなり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 玉藻息津藻 タマモオキツモ。玉藻と沖の藻であるが、同物を語を變えて言つた。この句は、玉藻沖つ藻を呼びあげている。さてそれに風や浪が寄るというのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「玉藻息津藻」(タマモオキツモ) 「玉藻」は既出 (1・40)。「沖つ藻」は沖の藻。「沖つ玉藻」と云つても同じであるが、「横野の春野」 (10・1825)、「かくさふ浪の五百重浪」 (11・2437)、「い小竹(ささ)群竹」 (19・4291) などのやうにニ語にわけてくりかへし、歌詞としての調子を整へたもの。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「玉藻息津藻」(タマモオキツモ) 「玉藻」の「玉」は美称。「沖つ藻」は「沖の藻」。沖は万葉集では「奥」と記すのが普通。「息」を「オキ」に宛てたのは息長という固有名以外はこの石見相聞歌のみ。先の「生」と同じく視覚的に生命感を暗示する意図があったか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「玉藻息津藻」(タマモオキツモ) 玉藻と沖ツ藻とは、互いに同格をなし、寄セメには目的格、来寄レには主格として続く。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「朝羽振(あさはふる)」注 | 拾穂抄 | あさ羽ふる 見安云朝吹わたる風也愚案風は鳥の羽吹やうなれはしか云也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | [朝羽振、風コソヨラメ]とは、和名に、鳥の羽振に、□[者/羽]の字を出せり、はふくと云も同じ詞なり、風の海水をうちて吹來る音は、鳥の羽を打て振ふ樣なれば喩てかくいへり、郭璞が江賦に、宇宙澄□、八風不レ翔 [フカ]、此「翔」の字を用たるも此意なるべし、依らめは上の玉もの事なれば、風にこそよるらめと云るなり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉考 | 朝羽振 [アサハブル]、 一本この朝羽振より下四句は無て、明 [アケ] 來者、浪己 [コ] 曾來依 [キヨレ]、夕去者、風己曾來依とありて、浪之共とつづく、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | 朝ハフル云云、玉藻は朝夕の風浪こそ寄すべけれとなり。羽振は、風浪の立つを鳥の羽振に譬ふ。卷四、風を痛み其振 [イタフル] 浪の、卷十八、打羽振涙 [ハブキ] 鷄は鳴けども、古事記、爲釣乍打羽擧 [ハブキ] 來人、又天日矛の持來し寶に振浪 [ナミフル] 比禮、風振 [カゼフル] 比禮などと言ふ事も有り。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 朝羽振 [アサハフル]、夕羽振流 [ユフハフル]、(流ノ字は、衍文なるべし、) 羽 [ハ] は扇 [ハフ] る意の古言と見ゆ、(鳥の羽も、易 [ハフ] る意もて、負ヘる名なるべし、) 振は、起リ觸るを云、風浪などの、物に扇 [ハフ] り觸るを云なり、六ノ卷に、朝羽振浪之聲躁 [アサハフルナミノトサワギ]、十九に、三更而羽振鳴志藝 [サヨフケテハフリナクシギ]、又打羽振鷄者嶋等母 [ウチハフリカケハナクトモ]、古事記神武天皇ノ條に、爲釣乍羽擧來 [ツリシツヽハフリクル] 人、(これ等は、羽振といへる例なり、神代紀上に、素戔嗚ノ尊、云々、扇レ天ヲ扇レ國ヲ上二諸于天ニ一、とある扇をも、「ハフリ」 とよめる人あり、) また集中十一に、風緒痛甚振浪能 [カゼヲイタミイタフルナミノ]、十四に、奈美乃保能伊多夫良思毛與 [ナミノホノイタブラシモヨ]、十七に、宇知久知夫利乃之良奈美乃安里蘇爾與須流 [ウチクチブリノシラナミノアリソニヨスル]、相模ノ國風土記に、鎌倉ノ郡見越ノ崎、毎レ有二速浪一崩シキレ石ヲ、國人名二號伊曾布利 [イソブリト] 一、謂レ振ルヲレ石ニ也、土佐日記に、磯振 [イソブリ] の寄スる磯には年月のいつとも分ぬ雪のみぞ零、(これら、浪に振と云る例なり、風には、常に布久 [フク] といふも、布流 [フル] に同し、をもをも布久 [フク] と、布流 [フル] と、同言なるよしは、神代紀に其ノ證見えたるよりはじめて、往々 [コレカレ] 例多し、) などあり、(しかるを岡部氏が、風浪のたつを、鳥の羽振に譬ふと云るは、本末を取失ひたる論なり、鳥の羽も、扇 [ハフ] り飛 [トブ] 具なる故に、負る名にこそあれ、又十九に、打羽振 [ウチハフリ] とあるも、羽を振よしにはあらず、羽振 [フリ] は、たゞ扇り振よしなるをや、もし羽を振ル意ならむには、羽打振 [ハウチフリ] とこそ、いふべけれ、) 古事記(天之日矛が持來し、玉津寶の中、)に、振浪比禮 [ナミフルヒレ]、振風比禮 [カゼフルヒレ]、とも見えたり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 朝羽振 [アサハフル] ―― 羽振は風の起るをいふ。鳥の羽たたきによつて、風が起るから出た語だと言はれてゐる。朝羽振 [アサハフル] は朝吹く意で、下に風とつづいてゐる。次の夕羽振流 [ユフハフル] は浪に續いてゐるが、これは夕風につれて立つ浪の意である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 朝羽振 アサハフル。ハフルは、鳥の羽を振つて飛ぶ意。後の夕羽振流とあるを、ユフハフルと讀むのに照らして、アサハフルと讀んでいる。鳥の羽ぶきのように風の吹くを譬えたのである。類聚名義抄に、□[者/羽]にハフルの訓がある。この字は飛びのぼる意の字。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | 朝羽振る 羽振るは鳥の羽ばたきすることで、風の吹くのを譬へていふ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「風社依米(かぜこそよせめ)」訓・注 | 万葉考 | 風社依米 [カゼコソヨラメ]、夕羽振 [ユフハブル]、 【今本、(私注:「朝羽振」の「振」に対し)下の振の下に流と有は、上の例に違、理りもわろし、】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | 朝羽振。風社依米。夕羽振。浪社來縁。あさはふる。かぜこそよせめ。ゆふはふる。なみこそきよれ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 風社依米 [カゼコソキヨセ]、浪社來縁 [ナミコソキヨセ]は、次に載る或本のには、明來者浪己曾來依夕去者風己曾來依 [アケクレバナミコソキヨセユフサレバカゼコソキヨセ]、とあるによりて思ふに、依米は、もと來依と有しを顛置 [オキタガ] へ、また來を、米に誤りしなるべし、さらば來依來縁は、共に「キヨセ」 と訓べし、伎與勢 [キヨセ] は、來よすれの意なり、(即チ「スレ」 の切、「セ」 となるをも思フべし、) こは風浪の玉藻奧津藻を、令 [ス] 二來依 [キヨ] 一を云なり、(然るを舊本をはじめ、略解にも何にも來縁を、「キヨレ」 とよみたるは、いみじきひがことなり、さては風浪の、自ら來縁、といふ言となりて、玉藻息津藻といふこと、うきて聞ゆればなり、) 十三に、奧浪來因白珠 [オキツナミキヨスシラタマ] とあると同じ、(此をも、「キヨル」と訓るは、ひがことなり、かならず 「キヨス」 とよまでは、かなはぬことぞ、後撰集に、住吉の岸に來よする奧つなみ間なくかけてもおもほゆる哉、金葉集に、藻刈船今ぞ渚に來よすなる汀のたづの聲さわぐなり、これらも、來よすと云る例なり、) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 風社依米 カゼコソヨラメ。依米は、略解にヨセメと讀んでいる。依をヨスと讀むことは、「奧波 [オキツナミ] 依流荒礒之 [ヨスルアリソノ] 名告藻者 [ナノリソハ]」 (卷七、一三九五)、「汝乎曾母 [ナレヲゾモ] 吾丹依云 [ワレニヨストフ] 吾叫毛曾 [ワレヲモゾ] 汝丹依云 [ナレニヨストフ]」 (卷十三、三三〇五) 等、例が多い。ここはヨセメでよく通ずるが、動詞寄スは、下二段活であるから、下の浪社來縁の句については、ナミコソキヨスレと言わなければならず、それは極めて不調であつて、あり得べくも思われない。これは、上の玉藻沖つ藻の句は、玉藻沖つ藻を呼び懸けたもので、強いて言えば、玉藻沖つ藻あり、それに風や浪が寄るというのであろう。實際に歌い上げる場合には、そのあいだに若干の詞句が挿入されるから、格別不合理を感じないであろう。但し四段活の例もある。「妹慮豫嗣爾 [メロヨシニ]」(日本書紀三)、「都麻余之許西禰 [ヅマヨシコセネ]」(卷十四、三四五四) などそれで、人麻呂歌集所出の、「妻依來西尼 [ツマヨシコセネ]」(卷九、一六七九)も、上記の例によつてツマヨシコセネと讀まれるから、人麻呂の作品に、四段活に使われていたとしても不思議はない。ただ下のカヨリカクヨリに對しては、やはりヨラメとあるべきだろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | 風こそ依せめ 風が藻を海邊に向つて寄せるであらう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私注 | カゼコソヨラメ 「ヨセメ」と訓み風が藻を寄せるであらうとも取られて居るが、之は岩礁に生えて居る藻に風が波と共によるのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「風社依米」(カゼコソヨセメ) 原文「風社依米」とあつて旧訓に「カゼコソヨラメ」とあつたが略解が「カゼコソヨセメ」と改めた。今もなほ旧訓による人が多いのは次の対句を考へての事であるが、その事は次に述べるやうに語法としては別に考へてよく、ここは玉藻を風が寄せて来るのであるから「ヨセメ」と訓むべきである。講義に「依」は「ヨル」と訓む字だとあるが、「依」も「縁」も共に「ヨル」とも「ヨス」とも訓まれてゐる。「奥浪(オキツナミ) 依流荒礒之(ヨスルアリソノ)」 (7・1395) などとある。「め」は「こそ」をうけた「む」の已然形で、その「め」は「よしゑやし」の條で述べたやうに、上の「浦は無くとも」をうけてゐる (1・31参照)。上の「無くとも」のところで句を切つて「妻と共に住めば楽しいところだ」といふやうな意を補つて解釈する説が多く行はれてゐるが、それは当たらない。浦や潟は無くとも、美しい玉藻を朝風がよせよう、とその美しい眺めをたたへたのである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「朝羽振風社依米」(アサハフルカゼコソヨラメ) 旧訓「アサハフルカゼコソヨラメ」。古義に (私注:略解の間違いかと思う) 「ヨセメ」と改訓。「アサハフル」は、朝鳥の羽ばたくことを比喩としたもの、考に「羽振は風浪のたつを鳥の羽振に譬ふ」と言う。茂吉評釈に諸注の説を記した上で、古事記の「振浪(ナミフル)比礼、振風(カゼフル)比礼」 (中巻) の例などあげている。代匠記に「風ノ海水ヲウチテ吹来ル音ハ、鳥ノ羽ヲ打テ振フ様ナレバ喩テカクイヘリ」 (精撰本) と言ったのは、羽音を想像し、聴覚的イメージに限定したもので、茂吉もそれをうけて、「朝鳥の羽音の如く風が吹いて来よう」と訳している。窪田評釈にもほぼ同様な説明が見られる。風の場合は音表象が強く意識されたであろう。なお、「風社依米」を「カゼコソヨセメ」と訓み、「玉藻沖つ藻」を吹き寄せるだろうと訳している注釈書も少なくない (古典大系・古典全集・講談社文庫など)。拙著『校註古典叢書万葉集(一)』にも、「玉藻沖つ藻に」吹き寄る意味としながら「ヨセメ」と訓んだのであるが、「玉藻に」寄る意味ならば、「之は岩礁に生えて居る藻に風が波と共によるのである」として、「ヨラメ」の訓を採用している私注の訓の方が適切だろう。古義その他のように藻を吹き寄せるというのは、根無しの枯れた藻のような印象を与え、先の「和多豆の 荒礒の上に か青なる」という表現にもそぐわない。「寄らめ」と訓んで、藻に寄ると解したい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「羽振流 浪社来縁 (ゆふはふるなみこそきよれ)」訓・考 |
代匠記 | 夕羽振浪コソ來ヨレとは、此浪も風に依て立てば、夕はぶるといへり、浪こそ來よれといふ心上の如し、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉考 | 浪社來緑 [ナミコソキヨレ]、 玉藻は朝夕の風浪にこそよらめといふなり、 羽振は風浪のたつを鳥の羽振に譬ふ、(卷四) 風緒痛 [ヲイタミ]、甚振浪能 [イタブルナミノ] 、間無 [アヒダナク]、卷十八に、打羽振 [ブキ]、鷄 [カケ] 者鳴等母、猶此類あり、古事記に、(神武) 爲釣乍 [ツリシツヽ] 打羽擧 [ハブキ] 來 (ル) 人、また天日矛 [アマノヒボコ] が持來し寶に、振浪比禮 [ナミフルヒレ] 、振風 [カゼフル] 比禮などいふこともあり、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 夕羽振流浪社來緑 ユフハフルナミコソキヨレ。上の朝羽振風社依米に對して對句を成している。これも上の句と同樣に解すべきである。朝風、夕浪と分けて詠んでいるが、これも、ただ朝夕に風や浪が寄るというべきを、格調上分けたまでである。段落で、以上、第一段の第二節。目前の景によつて想を構えて、以下の、浪ノ共、玉藻ナスの二句を起す序としている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | 浪こそ來縁せ 浪が藻をよせて來る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「浪社來緑」(ナミコソキヨレ) 原文「來緑」を前の句と対して「キヨセ」と訓む説もあるが、浪が藻をよせる事を「来よす」とは云はない。「来よす」といふ言葉はあるが、それは、「白浪之 来縁島乃 荒礒尓毛 (シラナミノ キヨスルシマノ アリソニモ)」 (11・2733) の如く、自動詞で、浪そのものがよせてくるのであつて、「風こそよせめ」の「よせ」と同じものではない。ここはむしろ「キヨレ」と訓んで、前の句では風が藻をよせると云ひ、ここでは浪が寄つて来る意で、対句にはなつてゐるが、文としてははじめから前の句の終までで結ばれ、後の句は独立し、夕方に立つ浪が寄つて来る、と一旦そこで切れるが、その浪と共に、と下へつづいて序となつてゐる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「夕羽振流浪社來緑」(ユフハフルナニコソキヨレ) 「朝羽振る 風こそ寄らめ」と対句。夕鳥の羽ばたくように波が寄せて来るという意味。この場合は、視覚印象を含めて言うのだろう。西郷信綱『万葉私記』に、古事記見える「釣りしつつ打ち羽振り来る人」や、書紀の「押し羽振るうまし御神」などの例をあげ、神話的表現の詩的再生としてこの部分を評価している。おそらく人麻呂の脳裏には、文選行旅詩の「鱗鱗トシテタ雲起リ 猟猟トシテ暁風ハ遒カナリ、沙ヲ騰ゲテ黄霧ヲ鬱ニシ、浪ヲ翻シテ白鷗ヲ揚グ」 (還都道中作) などの叙景表現もあっただろう。神話的表現と中国詩の叙景表現との双方の影響を受けて、この対句は生み出されたものと思われる。なお、この二句に視覚的印象が強いとすれば、先の二句の聴覚的映像とを合わせ、視聴対をなすことになる。おそらく和歌における視聴対の最初の例であろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「夕羽振流浪社來緑」(ユフハフルナミコソキヨレ) 「波コソ」は、「波ニコソ」の意。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「浪之共 彼縁此依 (なみのむたかよりかくよる)」訓・注 |
註釈 | [浪之共 (なみのむた)] 浪之共 [ナミノムタ]、此句古點ニハ、ナミノトモト點ス。イマハナミノムタト點ス。トモトイフコトハヲ、古語ニハ、ムタトイフ也。トモトヨメリトモ、ソノ心オナシケレトモ、古語ニハ、ムタトイフ。日本記ニミヱタリ。此集ニモミヱタリ。古集ニムカヒテ、古語ヲソムクヘカラサレハ、ムタト點スル也。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拾穂抄 | 浪のむた 仙曰日本紀此集共の字をむたとよむ愚案波と共にの心也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | 浪ノムダカヨリカクヨリとは、「むた」 は「ともに」 と云古語なり、第十五に 、可是能牟多 [カセノムタ]、與世久流奈美爾 [ヨセクルナミニ]、また君我牟多 [キミガムタ]、由可麻之毛能乎 [ユカマシモノヲ]、など其外あまたよめり、依て古點は浪のともなりけるを、仙覺の改られたる由、彼抄に見えたり、尤叶へり、かよりかくよりは、此集に「と」 にかくにと云を、「か」 にかくにとあれば、「と よりかくよりなり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉考 | 浪之共 [ナミノムタ]、 浪のともにといふなり、(卷十一) 君我牟多 [キミカムタ]、由可麻之毛能乎 [ユカマシモノヲ]、その外にも多けれど、皆共 [トモ] の意なり、今物の彼此わかぬを、めたともみたともいふを、土左人はむたといふといへり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | 浪ノムタは、浪と共にと言ふなり。卷十五、君が牟多 [ムタ] ゆかましものを。其外にも多し、皆共の意なり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 浪之共 [ナミノムタ] は、契冲、浪と共になり、牟多 [ムタ] は、今の俗語に、めたと云にもかよひてきこゆることあり、ともにといふ詞の、古語なるべしと云り、十五に可是能牟多與世久流奈美爾 [カゼノムタヨセクルナミニ] 、又君我牟多由可麻之毛能乎 [キミガムタユカマシモノヲ] など、猶多し、 彼縁此依は、「カヨリカクヨル」 と訓べし、(しばらく、此處にて、絶て心得べし、こを「カヨリカクヨリ」 と訓て、妹がよることゝするは、ひがことなり、こは玉藻のよる事を云るなれば、必スかよりかくよる、とよむべきことなり、浪之共玉藻成此縁此依 [ナミノムタタマモナスカヨリカクヨリ]、と句を置かへて、聞べき處にもあらざればなり、と高橋ノ正元も云たりき、) さて此 [コ] は、とよりかうよるにて彼方此方 [カナタコナタ] に依る、といはむが如し、すべて、とにかくといふことを、古言には、可爾迦久 [カニカク] といへり、此下に、彼往此去 [カユキカクユキ]、三ノ卷に、左右將爲 [カモカクモセム]、四ノ卷に、云云意者不持 [カニカクニコヽロハモタズ]、又鹿□[者/火]藻闕二毛 [カニモカクニモ]、五ノ卷に可爾迦久爾 [カニカクニ]、十六に、左毛右毛 [カニモカクニモ] などあり、又五ノ卷に、可由既婆比等爾伊等波延可久由既婆比等爾邇久麻延 [カユケバヒトニイトハエカクユケバヒトニニクマエ]、古事記應神天皇ノ御歌に、迦母賀登和賀美斯古良迦久母賀登阿賀美斯古邇 [カモガトワガミシコラカクモガトアガミシコラ]、續紀十ノ卷に、加久耶答賜 [カクヤコタヘタマハム]、加耶答賜止 [カヤコタヘタマハムト] など、加 [か] と加久 [カク] と言を隔ても云り、但し續紀なるは、流布 [ヨニアル] 本に二ツながら、加久耶 [カクヤ] とあるは、つたなく聞ゆれば、一ツの久ノ字は、まぎれて入しなるべし、今は一本に從て引つ、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 彼縁此依 [カヨリカクヨリ] ―― 彼方に依り此方に依る意であるが、鹿煮藻闕二毛 [カニモカクニモ] (六二八) などの如く、カとカクとが連ねて用ゐられる習慣がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 浪之共 [ナミノムタ]。ムタは共の意の古語で、助詞ノもしくはガを受ける。「可是能牟多 [カゼノムタ] 與世久流奈美爾 [ヨセクルナミニ]」(卷十五、三六六一) の例がある。上の風コソ寄ラメの句を受けている。 彼縁此依 [カヨリカクヨリ]。カヨリカクヨル (古義)。カもカクも、それとさす體言である。カモカクモ、カニモカクニモ、カ行キカク行キなど、用例が廣い。ここは、あのようにもこのようにも寄るの意。下の寄リ宿シを修飾する。カヨリカクヨルと讀むのは、ただちに次の玉藻を修飾するとするのであるが、調子の上からは、カヨリカクヨリがすぐれている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | 浪の共 [ムタ] 浪と共に。 彼より此より 「か」「かく」は、「かにかくに」「かにもかくにも」の「か」「かく」に同じ。あちらによりこちらにより。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「浪之共 彼縁此依」(ナミノムタ カヨリカクヨル) 「むた」は「共」の字が用ゐられてゐるやうに、共に、の意。「可是能牟多 与世久流奈美尓 (カゼノムタ ヨセクルナミニ)」 (15・3661) の如き仮名書例がある。「彼より比よる」は浪のまにまにあちらへ靡きこちらへ靡く、と次の玉藻を修飾する。原文「此依」を「カクヨリ」と訓んでゐる書が多いが、それでは下の「より寝し」へかかる事になり、作者が浪と共にねることになつてあたらない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「浪之共 彼縁此依」(ナミノムタ カヨリカクヨル) 「共」は「~トトモニ」の意。旧訓「カヨリカクヨリ」であったのを、古義に「カヨリカクヨル」と訂した。以下の諸注も二説に分かれる。「カクヨル」と訓めば、次の玉藻の修飾語となり、「カクヨリ」ならば「寄り寝し」にかかることになる。茂吉評釈・佐佐木評釈・全註釈など後説によっているが、最近の注釈書の多くは前説を採る (注釈・窪田評釈・私注・古典大系・古典全集・古典集成など)。茂吉は「此句は下の妹の行為を表はさむための誘導表現である」と言い、全註釈には「調子の上からは、カヨリカクヨリがすぐれている」と記すが、いずれも理由は明確でない。それに対し、前説 (カクヨル) を採用するものは、「玉藻」に直接かかることを当然とし、「カクヨリ」では「より寝し」を修飾することになり、「作者が浪と共にねることになって」不適当だと言う。旧訓以来の伝統的な訓ではあるが、「カクヨリ」は文脈上ふさわしくないであろう。古義に「こをカヨリカクヨリと訓て、妹がよることとするはひがことなり。こは玉藻のよる事を云るなれば必かよりかくよるとよむべきことなり評と評したのが正しい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「浪之共 彼縁此依」(ナミノムタ カヨリカクヨル) 「か寄りかく寄る」-「カ・カク」はああ・こうの意の指示副詞。なよなよと揺れ動くさま。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「玉藻成 依宿之妹乎 (たまもなす よりねしいもを)」訓・考 |
拾穂抄 | 玉藻なすよりねし妹 藻は波とゝもにとよりかくよれはよりねしといはん枕詞に玉藻なすと云なすとは其物のやうなるとの詞也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | 玉モナス依ネシ妹ヲは、日本紀に如二五月蠅一とかきて、サバヘナスとよめれば、玉もの如く、こなたかなたより依合て寢しなり、後に玉藻なす靡かぬらむともよめり、これは、伊與の地について渡る舟の上に見る物に寄て云なり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | 玉モナスの成スは如くなり。ヨリネシイモヲは、玉藻の如く靡きあひ寢し妹をとなり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 玉藻成 [タマモナス] は、玉藻の如なり、如を成 [ナス] と云こと、既く一ノ卷に出づ十一に、敷栲之衣手離而玉藻成靡可宿濫和乎待難爾 [シキタヘノコロモテカレテタマモナスナビキカヌラムワヲマチカテニ]、 依宿之妹乎 [ヨリネシイモヲ] の下に、舊本に、一ニ云、波之伎余思 (波ノ字、舊本に□とあるは誤なり、今は古寫本拾穗本等によりつ、) 妹之手本乎、と註せり、(こは浪之共彼縁此依波之伎余思云々、と連くべくもなし、いかゞなり、かれ按フに、こは一本には、波之伎余思の上に、靡吾宿之、など云句のありしを、校合の時、ゆくりなく脱せしものなり、さらば玉藻成靡吾宿之波之伎余思云々、と連くべし、次に載る或本に、浪之共彼依此依玉藻成靡吾宿之敷妙之妹之手本乎、とあるを以、考ヘ知ルべし、) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 玉藻成 [タマモナス] ―― 玉藻の如くの意。依宿之妹 [ヨリネシイモ] の枕詞であるが、上に海に關して述べて來たのは、玉藻を言はむ爲であり、又玉藻は女のは女の柔い形容であるから、普通の枕詞とは違ふところがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 玉藻成 タマモナス。玉藻のようにある。上の玉藻沖ツ藻の句と照應している。 依宿之妹乎 ヨリネシイモヲ。寄り添い寢た妻をである。妹は女子の愛稱。妻というと客觀性が強くなるが、妹というと、三人稱に使用されても、その人を思う情味が感じられる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「玉藻成 依宿之妹乎」(タマモナス ヨリネシイモヲ) 「なす」は、-のやうに、の意。既出 (1・19)。「玉藻なす」までは「より寝し」の譬喩的な序。「より寝し妹」は寄り添うてねた妻。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「玉藻成 依宿之妹乎」(タマモナス ヨリネシイモヲ) 「玉藻ナス」は、玉藻のように、の意。「タマモナス」まで冒頭から二十三句は、「寄り寝し」にかかる比喩的な序。即境的な景物を提示し、それを人事に転換してゆくのが古代歌謡の技法であって、応神記の「いざ子ども 野蒜摘みに 蒜摘みに 我が行く道の 香妙し 花橘は上(ほ)つ枝は 鳥居枯らし 下づ枝は 人取り枯らし 三つ栗の 中つ枝の ほつもり あから嬢子を いざささば 良らしな」(四十三歌) にも見られる。前代の技法を人麻呂は新しい相聞長歌に利用したのである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「玉藻成 依宿之妹乎」(タマモナス ヨリネシイモヲ) 「玉藻なす」-冒頭からこの句まで「寄リ寝シ」を起こす序。石見の海岸の景を叙しながら残して来た妻の自分に従順であった妻のイメージを喚起する効果を果たしている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「[一云 波之伎余思 妹之手本乎 (はしきよし いもがたもとを)]」訓・考 |
代匠記 | 注に□ [右写真参照] 之伎余思とは、愛の字を「はしき」とよめり、此字を、「うるはし」 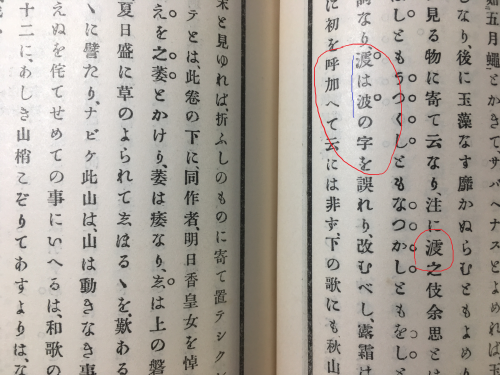 とも「うつくし」 とも「なつかし」 とも「をし」 ともよめり、はしきも、 とも「うつくし」 とも「なつかし」 とも「をし」 ともよめり、はしきも、それらにかよへる詞なり、□ [右写真参照] は波の字を誤れり、改むべし、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | 或本のハシキヨシは愛る詞。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 一云波之伎余思妹之手本乎 アルハイフ、ハシキヨシイモガタモトヲ。上の玉藻ナス寄リ宿シ妹ヲの句に對する別傳であるが、これでは、上の浪ノムタカ寄リカク寄リの句に、接續しない。本文の方が可である。ハシキヨシは、ハシキヤシともいう。ハシキは愛すべくある意の形容詞。ヤシは感動の助詞。タモトは手の上部、腕。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓注】「一云 波之伎余思 妹之手本乎」(ハシキヨシ イモガタモトヲ) 「はしき」は愛らしい意の形容詞「はし」の連体形。「よし」は「青丹よし」 (1・17) などの「よし」と同じく詠歎の助詞。「たもと」は今「袂」の字が用ゐられ、袖の下部、袋のやうになつてゐるところをいふやうであるが、萬葉では「袂」は「袖」と同じく「そで」であり (134参照)、「たもと」は「手本」と書かれてゐる場合が多く、手の本、即ち手首或は袖口のあたりをさしたもののやうである。従つて「袖まく」とも「たもとをまく」とも云はれてゐるが、「袖振る」「袖濡る」の例があつて「たもとを振る」「たもとをぬらす」の例がない所以もうなづくことが出来よう。 わが袖はたもととほりてぬれぬとも恋忘貝とらずは行かじ (15・3711) の如きは袖とたもとの区別を示す恰好の例である。一本にはこの二句が「玉藻なす 寄り寝し妹を」の代わりに用ゐられてあるといふ意味の注と見られるが、それでは上の句との続きが適切でない。これは或は一本には上二句の下にこの二句があり、くりかへしの対句をなしてゐたもので、「或書有二・・・句一」(13・3291) といふ風な注であるべきものを「一云」としてしまつたものかとも考へられる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「一云 波之伎余思 妹之手本乎」(ハシキヨシ イモガタモトヲ) 「ハシキ」はいとおしい、愛らしいの意の形容詞。同じくいとおしさを表わすものでも、「カナシ」が切なさを伴うのに対して、「ハシ」は讃美の情をともなうようだ。「ヨ・シ」は詠嘆の助詞。「ハシキヤシ」ともいう。「タモト」は、現在の「袂」というのと異なり、手首もしくは袖口のあたりを指す。この「一云」は、「玉藻なす 寄り寝し妹を」のかわりになる異伝を示したように受け取られるが、それでは「浪の共 か寄りかく寄る」とのつながりが不明確になるので、澤瀉注釈に「これは或は一本には上二句の下にこの二句があり、くりかへしの対句をなしてゐたもので、『或書有二・・・句一』(13・3291) といふ風な注であるべきものを『一云』としてしまつたものか」と言う。従うべき推定と思う。茂吉評釈に、「直接に妹をと云はずに、妹が袂と云ふのは間接的で、却つて続きが悪いやうである」とも記す。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「露霜乃(つゆしもの)」考 | 代匠記 | 露霜は、露と霜となり、露結て霜となる故に、霜に初を呼加へて云には非ず、下の歌にも、秋山に落るもみぢばとあれば、此時、九月の末と見ゆれば、折ふしのものに寄て置テシクレバとつゞけられたり、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉考 | 露霜乃 [ツユジモノ]、 冠辭、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 露霜乃 [ツユシモノ] は、露 [ツユ] と霜 [シモ] となり、共におくものなれば、置てしくれば、といはむ料なり、と契冲は云り、本居氏は、露霜は、みなたゞ露のことなり、されば七ノ卷十ノ卷などには、詠レ露ヲといへる歌によめり、そもそもたゞ露を、露霜といはむことは、いかにぞや聞ゆめれども、此ノ名によりて思ふに、志毛 [シモ] といふは、もとは露をもかねたる總名にて、其ノ中に、氷らであるを、都由志毛 [ツユシモ] といひ、省きて都由 [ツユ] とのみもいへるなり、そは都由 [ツユ] は、粒忌 [ツブユ] のよしにて、忌 [ユ] とは、清潔 [キヨラ] なるを云、雪 [ユキ] の由 [ユ] も同し、されば露霜とは、粒 [ツブ] たちて、清らなる志毛 [シモ] 、といふことなりといへり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 露霜乃 [ツユジモノ] ―― 置くの枕詞。露じ物で、露のやうな物の意である。秋の末に置く水霜を露霜といふのは、古意ではあるまい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 露霜乃 ツユジモノ。枕詞。置クに冠する。ツユジモは、露と霜とであるとする見解と、一種のものであるとする見解とがあるが、これはたとえば、山川の如き語について、山と川とも、また、山中の川とも解せられるようなもので、兩立し得る解である。ここは十月のはじめごろとする季節によつて、ツユジモとし、露からなかば、霜になつたものとすべきだろう。「烏玉之 [ヌバタマノ] 吾黒髪爾 [ワガクロカミニ] 落名積 [フリナヅム] 天之露霜 [アメノツユジモ] 取者消乍 [トレバケニツツ](卷七、一一一六)、「夢戀爾 [ツマゴヒニ] 鹿鳴山邊之 [カナクヤマベノ] 秋□[草冠/互]子者 [アキハギハ] 露霜寒 [ツユジモサムミ] 盛須疑由君 [サカリスギユク]」(卷八、一六〇〇) の如き例は、この用法である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | 露霜の 露や霜の如く。置くにかかる枕詞。露霜は、露のこと (宜長)、露の如き霜 (新解) ともいふ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「露霜乃」(ツユシモノ) 玉勝間 (十四) に「こは後の哥には、露と霜とのとによめども、萬葉なるは、みなただ露のと也」といひ、今も方言に秋の薄霜のことを「つゆじも」といふところ (信濃その他) があるので、露又は霜の一種と見る説があるが、やはり露や霜と見て不都合はない。露も霜も置くものとして、「置く」の枕詞とした (4・651参照)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「露霜乃」(ツユシモノ) 「ツユシモ」を仙覚は「露ノ霜ニ成程ナレバ露霜ト云。霜ニモ成ハテズ、猶露ニテ又露ニモアラヌ程ナリ」 (仙覚抄) と言い、契沖も「露霜ハ、今按、露ト霜トニハアラズ。露結テ霜トナル故ニ寒ク成行比ノ露ヲ霜ヲ呼加ヘテ云ナリ。其証ハ露霜トツヅケテヨメル歌アマタアル中ニ、第七ニ詠露ト題シテ天之露霜トヨミ、第十ニモ同題ニテ、露霜置寒毛時者成尓家類可聞トヨメリ。然レバ霜ヲ濁テヨミテ一種トスベシ」 (代匠記精撰本) と記す。宣長は「後の哥には、露と霜とのことによめども、萬葉なるは、みなただの露のこと也」 (玉の小琴) としており、たしかに「久方の天の露霜おきにけり家なる人も待ち恋ひぬらむ」 (4・651) のように露のことを言ったと見られる例もあるが、「秋されば置く露霜にあへずして都の山は色づきぬらむ」 (15・3699) のごとく露と霜の双方を言ったと思われる例もある。それぞれ歌に即して解されるべきであろう。この「露霜の」は、比喩的な枕詞として使われたもの。露や霜のおくことから、その露霜のようにあとに残して来たので、の意。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「置而之来者(おきてしくれば)」訓・考 | 略解 | オキテシ云云は、妹を捨て置くなり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 置而之來者 [オキテシクレバ] は、とゞめ置て來れば、といふなり、置 [オキ] はともに率て來ぬをいふ、倭乎置而 [ヤマトヲオキテ] の置に同し、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 置而之來者 オキテシクレバ。妹を置いて來ればで、シは強意の助詞。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「置而之來者」(オキテシクレバ) 「オク」は、「露・霜・雪」などについては、降りとどまる意味で、そのほか、物を置く意味にも、放っておくにも用い、「そらみつ 大和におきて」 (1・29) のように、あとに残す、あとにする意味にも使う。ここの「オク」は露霜の降りとどまる意と、あとに残す意との掛詞になっている。「シ」は強意の助詞。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「八十隈毎(やそくまごとに)」訓・注 | 古義 | 此道乃 [コノミチノ] 云々は、一ノ卷に、川隈之八十隈不落萬段顧爲乍 [カハクマノヤソクマオチズヨロヅタビカヘリミシツヽ]、とあるに同し、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 此道乃八十隈毎 コノミチノヤソクマゴトニ。今通行している道路なので、この道という。八十隈は、多數の曲りかどの隅。山路であつて、隈が多いのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「八十隈毎」(ヤソクマゴトニ) 「八十隈」は多くの曲り角。「クマ」については「115歌参照」。「ヤソ」は、数の多いことをあらわす。「八十島・八十伴の緒」などに同じ。「ゴトニ」は、すべての~においての意で、名詞に接続する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「萬段(よろづたび)」訓・考 | 注釈 | 【訓釈】「萬段」(ヨロヅタビ) 前に「よろづ度かへりみしつつ」 (1・79) の例があつた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「萬段」(ヨロヅタビ) 原文「萬段」の「段」を「タビ」と訓むことについて、小島憲之は、万象名義に「徒換反、椎物」とあるのを引いて、「段」には「断つ」「くぎる」「わかつ」などの意があり、その動作の何度となく繰返されるのが「萬段」であろうと言う (「万葉用字考証実例(一)」『万葉集研究』第二集)。また、唐招提寺所蔵の「古本令私記」の断簡 (営繕令) に一度一段の訓詁も見え、この「度」すなわち「段」は万葉の「萬段」に応用できるかもしれないと言う (同右、補注)。これによって「段=度」は一応の根拠が与えられたと見て良いであろうが、「度」と「段」と同じ訓詁をもつことについて他の確証が望まれると補記されている。あるいは「遍」を「ヘニ」に、「談」を「タミ」に宛てる例 (出雲風土記、出雲郡美談郷) が見られるように、段の音にも関連しているのであろうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「弥遠尓 里者放奴 (いやとほに さとはさかりぬ)」訓・注 |
略解 | 里ハサカリヌは、遠ざかると言ふに同じ。すべて行く道のさまを言ふ中に、別を悲しむ情あり。益高に、宣長云、すべて益はイヤと訓むべし。此卷の下に、こぞ見てし云云、あひ見し妹は益 [イヤ] 年さかる。卷七、さほ川に云云、益 [イヤ] 河のぼる。卷十二、ちかくあれば云云、こよひゆ戀の益 [イヤ] まさりなむ。これらイヤと訓めりと言へり。此益高には、マシタカニとても有るべけれど、イヤと訓まずしてかなはぬ所多し。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 彌遠爾 [イヤトホニ] 云々、廿ノ卷家持卿歌に、伊夜等保爾國乎伎波奈例伊夜多可爾山乎故要須疑 [イヤトホニクニヲキハナレイヤタガニヤマヲコエスギ] 云々とあり、 里者放奴 [サトハサカリヌ] は、已く里は遠く放り來ぬとなり、奴 [ヌ] は、已成 [オチヰ] の奴 [ヌ] なり、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 弥遠尓里者放奴 [イヤトホニサトハサカリヌ]。イヤトホニは、いよいよ遠くの意の副詞句。サトは、別れて來た妻の住んでいる里である。サカリは離れる意の動詞。句切。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「弥遠尓里者放奴」(イヤトホニサトハサカリヌ) いよいよ遠く、妻の住む里は離れた。「いや」は既出 (1・36)。「さかる」は古事記上巻「奥疏神」に注して「訓レ疏云二奢加留(サカル)一」とあり、「也麻等乎毛(ヤマトヲモ) 登保久左可里弖(トホクサカリテ)」 (15・3688) の仮名書例、「弥遠丹(イヤトホニ) 里離来奴(サトサカリキヌ)」 (13・3240) などの用字をも参照して、へだたり離れる意であることがわかる。この二句は次の二句と対句になつてゐる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「弥遠尓里者放奴」(イヤトホニサトハサカリヌ) 「弥」は「益」に通ずる。「イヤ」は単に「ヤ」と言う場合もあり、物の程度の盛んなことを表わす。「イヤトホニ」で、いよいよ遠く、の意。「里」は地方行政区画の称で、五十戸を一里とした。「放」は遠くはなれるの意。人麻呂作歌に「弥年離(イヤトシサカル)」 (211) を「弥年放(イヤトシサカル)」 (214) と記した例もあり、「サカル」と訓む。この二句、次の二句と対句をなす。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「益高尓(いやたかに)」訓・考 | 玉の小琴 | 益高爾、此類の益の字をますとも、ましとも訓るは皆誤也、いやと訓べし、益をいやと訓證例は、此卷〔四十丁〕に去年見而之、云々相見し妹は、益年さかる、七卷〔廿三丁〕に佐保川爾、云々益河のぼる、十二卷〔三十三丁〕近有ば、云々こよひゆ戀の、益まさりなむ、是等也、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 益高爾は、「イヤタカニ」 と訓べし、(本居氏、益は、すべて「イヤ」 と訓べし、此ノ卷ノに、あひみし妹は益年 [イヤトシ] さかる、七ノ卷に、益河 [イヤカハ] のぼる、十二に、こよひゆ戀の益 [イヤ] まさりなむ、これら「イヤ」
とよめり、と云り、略解にこの説をうけながら、此ノ益高は、ましたかとても有べしとて、しか訓たるは、いかにぞや、いみじきひがことゝ云べし、凡て益を、「シ」 と訓ときは必ス「マシテ」 云々、と而 [テ] の辭をおかずして、「マシ」 云々といふ例は、さらになきことなるをや、) 高とは、山の縁に云るにて、意は遠きよしなり、 山毛越來奴 [ヤマモコエキヌ] とは、毛 [モ] は上の者 [ハ] にむかへて云り、山をも、已 [ハヤ] く遠く越來りぬとなり、奴 [ヌ] は、已成 [オチヰ] の奴 [ヌ] なり、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 益高爾 [イヤタカニ] ―― マスタカニ・マシタカニの訓もあるが、益目頼染 [イヤメヅラシミ] (一九六)・益益南 [イヤマサリナム] (三一三五) などによれば、イヤタカニがよい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 益高尓山毛越來奴 イヤタカニヤマモコエキヌ。上のイヤ遠ニ里ハサカリヌの句と對句を成している。いよいよ高く山も越えて來たの意で、句切。以上第二段。作者が山路につき、妻の住む里から、遠ざかつたことを敍している。「道前 [チノクマ] 八十阿毎 [ヤソクマゴトニ] 嗟乍 [ナゲキツツ] 吾過往者 [ワガスギユケバ] 爾遠丹 [イヤトホニ] 里離來奴 [サトサカリキヌ] 禰高二 [イヤタカニ] 山文越來奴 [ヤマモコエキヌ]」(卷十三、三二四〇) の如き類型の句がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「益高尓山毛越來奴」(イヤタカニヤマモコエキヌ) 「益(イヤ)」は人麻呂歌集 (11・2426、2459)、人麻呂作歌 (131、138、196、214、3・239、261) に多い。巻二十の家持作歌に「伊夜等保尓 國乎伎波奈例 伊夜多可尓 山乎故要須疑 (イヤトホニ クニヲキハナレ イヤタカニ ヤマヲコエスギ) 」 (4398) とあるのや、巻十三に「弥遠丹 里離来奴 弥高二 山文越来奴」 (3240) とあるのは、この歌を踏まえたものであろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「夏草之 念思奈要而 (なつくさの おもひしなえて)」訓・考 |
拾穂抄 | おもひしなへて 妹もおもひしほれて我を忍ふらんと思ひやる心也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | 夏草ノ念シナエテとは、此卷の下に、同作者、明日香皇女を悼奉てよまれたる歌にも此詞あるに、「しなえ」 を「之萎」 とかけり、萎は痿なり、「し」 は上の磐之媛の御歌の石根しまきての「し」 の如し、夏日盛に草のよられてしほるゝを、歎ある人の物思ふ時、心もよはり身もうなだるゝに譬たり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | 夏草ノ枕詞。オモヒシナエテは、なよよかにうなだれて物思ふさまを言ふ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 夏草之 [ナツクサノ] は、之奈要 [シナエ] といはむ料における枕詞なり、 念之奈要而 [オモヒシナエテ] (之ノ字、拾穗本には思と作り、) は、念の切なるにつけて、うなだれしなえて、吾を慕ふらむ、と妹がさまを、おもひやりて云り、之奈要 [シナエ] は、うなだれ萎 [ナユ] るをいふ、次に載る或本には、思志萎而 [オモヒシナエテ] とあり、又集中に、夏草乃之奈要裏觸 [ナツクサノシナエウラブレ] 、君に戀之奈要裏觸 [コヒシナエウラブレ] などもあり、又三ノ卷に、眞木葉乃志奈布勢能山 [マキノハノシナフセノヤマ]、十ノ卷に、秋芽之四搓弖將有妹之光儀乎 [アキハギノシナヒテアラムイモガスガタヲ]、十三に、春山之四名比盛而 [ハルヤマノシナヒサカエテ]、廿ノ卷に、多知之奈布伎美我須我多乎 [タチシナフキミガスガタヲ]、などありて、之奈由 [シナユ]、之奈布 [シナフ]、同言なるが、夜伊由延 [ヤイユエ] にも、波比布幣 [ハヒフヘ] にも、もとより二樣に活用ク言なり、此 [コ] は上にも云り、(冠辭考の説は、これかれ誤多し、) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 夏草之 [ナツグサノ] ―― 夏の草は日に照らされて、萎えるものであるから、之奈要 [シナエ] の枕詞とする。 念之奈要而 [オモヒシナエテ] ―― 之奈要は萎えること。シは接頭語であらう。助詞のシではない。於君戀之奈要浦觸 [キミニコヒシナエウラブレ](二二九八) とある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 夏草之 ナツクサノ。枕詞。夏の草は、日に萎えるものであるから、次のシナエテに冠する。 念思奈要而 オモヒシナエテ。シナエテは、なえなえとしての意。「於レ君戀 [キミニコヒ] 之奈要浦觸 [シナエウラブレ]」(卷十、二二九八) 等の例に依り、シナユの語があることが知られる。下二段活。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | 夏草の 萎えにかかる枕詞。夏の草が日に當つて萎れるの意。思ひ萎えて 思ひ萎れて、物思ひに元氣もなくなつて。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「念思奈要而」(オモヒシナエテ) 原文「念思奈要而」とあるので、「シナエテ」の訓に疑問がもたたれるやうであるが、或本歌 (138) には「思志萎而 (オモヒシナエテ)」とあり、「於君戀(キミニコヒ) 之奈要浦觸(シナエウラブレ) 吾居者(ワガヲレバ)」 (10・2298) ともあつて「しなえ」の語があり、萎え萎えとしをれる意である事が察せられる。ヤ行下二段活用。「しなふ」 (3・291) とは別である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「夏草之 念思奈要而」(ナツクサノ オモヒシナエテ) 「夏草の」は比喩的な枕詞。「冠辞考」に「こは夏草はまだ弱ければ、なよよかにうなだれるるを、人の物おもひする時のさまにたとへたり」と言い、福井久蔵『枕詞の研究と釈義』に「暑熱の為めに草木の靡きしなびてあるを、思にあぐみたるに比」したものと説く。ただし、別稿 (「人麻呂の枕詞について」『万葉集研究』第一集) にも記したとおり、こうした説明には疑問が感ぜられる。万葉集内の「夏草」という語を拾ってみると、「夏草の茂きはあれど」 (9・1753)、「夏草の刈り掃へども」 (10・1984)、「夏草を腰になづみ」 (13・3295) のように、蓬々と生い茂った状態が歌われており、人麻呂作歌にも「夏草か繁くなりぬる」 (1・29或云) とある。こうした例から、当時の人々の「夏草」についての一般的なイメージを推測することができるであろう。このことは古今集以後においても変わらぬようで、「夏草の上は茂れる沼水の行く方のなきわが心かな」 (古今462)、「枯れはてむ後をば知らで夏草の深くも人の思ほゆるかな」 (古今686)、「人ごとは夏草の草の茂くとも君と我としたづさはりなば」 (拾遺629) など、夏草の茂りを詠むものは、きわめて多い。逆に、夏草のしおれるさまを歌ったものは見られない。万葉以後の枕詞を見ても、「夏草のかりそめにとて来しかども難波の浦に秋ぞくれぬる」 (新古今)、「夏草のしげき思は蚊やり火の下にのみこそもえ渡りけれ」 (新勅撰) など、やはり夏草の茂りや、それを刈ることに言い掛けた歌ばかりである。夏草がしおれるのは秋で、「吹くからに秋の草木のしをるればむべ山風をあらしといふらむ」 (古今249) の作は、広く知られている。こうしたことを踏まえて「夏草の思ひしなえて」を読むと、こんもりと生い茂った夏草が、秋になってしおれるように、しょんぼりとしている様子と解釈されるであろう。この長歌に即して言えば、「露霜の」などから推測されるように、歌われている季節は秋であり、共に過ごした夏の間、生き生きとよろこびにあふれていた状態と、今別れて来たのちに恐らくしょんぼりと生気を失っているであろう状態とが二重写しになって想像される。そういう特殊な効果を持った枕詞ではなかろうか。なお、「196歌〔注〕参照」。 「オモヒシナエテ」は、「君に恋ひ之奈要うらぶれ」 (10・2298)、「うちなげき 之奈要うらふれ しのひつつ」 (19・4166) などからわかるように、思ひわずらってうなだれしおれる状態を言う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「志怒布良武(しのふらむ)」訓・考 | 万葉考 | 志怒布良武 [シヌブラム]、妹之門將見 [イモガカドミム]、靡此山 [ナビケコノヤマ]、/ 古郷出てかへり見るほどの旅の情、誰もかくこそあれ、物の切なる時は、をさなき願ごとするを、それがまゝによめるは、まことのまことなり、後世人は此心を忘れて、巧みてのみ歌はよむからに、皆そらごとゝ成ぬ、さて (卷三) 靡 [ナビ] けと、人はふめども、かく依 [ヨレ] と、人は衝 [ツケ] ども、こゝろなき山の、奥磯 [オキソ] 山三野之 [ノ] 山とよめるは、いと古への歌なり、(卷五)「惡木 [アシキ] 山、ごずゑことごと、あすよりは、なびきたれこそ、妹があたり見ん」てふは、今をとれるか、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | シヌブは慕ふなり。シノブを古くシヌブと言へり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 志怒布良武 [シヌフラム] (怒ノ字拾穗本には奴と作り、) は、吾を慕ふらむ、と妹がさまを、推量りていへるなり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 志怒布良武 [シヌブラム] ―― 志怒布は思ひ出しなつかしがること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 志怒布良武 [シノフラム]。このシノフは、思慕する意に使用されている。別かれた後の妻の樣子を想像している句で、連體形である。布は、シノフの清音であつたことを語る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | 偲ふらむ 私を懷しく思つてゐるであらう。連體格で、妹にかかる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「志怒布良武 妹之門将見」(シノフラム イモガカドミム) 原文、西本願寺本に「志奴布」とあるが、元暦校本・紀州本・細井本に「志怒布」とあるのによる。「シノフ」は、既出の「忍 (シノブ)」 (129の一云) とは別語。「慕う・偲ぶ・賞美する」などの意の「志怒布」は「シノ(甲類)フ」であり、「こらえる・隠す」意の「忍ぶ」は「シノ(乙類)ブ」で、「ノ」の甲類・乙類の相違があり、「フ」の清濁も異なる。このニ語は、平安時代になると活用・意味が交錯するようになる。「ラム」は視界外の推量をあらわす。自分のことを恋い偲んでいるであろう妻の家の門を見たい、の意。この句「或本歌」 (138) には、「嘆くらむ角の里見む」となっている。妻の家から遠く離れ、もう家も見えなくなった地を焦点として詠まれているので、或本歌の歌句 (角の里見む) の方が自然のようであるが、それだけ常識的で、「妹が門見む」の強さに及ばない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「靡此山(なびけこのやま)」訓・注 | 拾穂抄 | なひけ此山 山もなひきかたよりて妹か門を見せよと也山をなひけといへる珎き詞とそ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | ナビケ此山は山は動きなき事のためしにもすなるを、そなたの方の見えぬを侘てせめての事にいへるは、和歌の習面白き物の妻を思ふ心あはれ深し、第十二に、あしき山梢こぞりてあすよりは、なびきたれこそ妹があたりみむ、十三にも、我かよひ路のおきそ山みのゝ山靡かすと人はつげども、かくよれと人はつげども、などよめるに心おなじ、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 童蒙抄 | 妹之門將見靡此山 童子門 なひけ此山とはいつれの山を指にや。山のなひくへきにあらぬを、なひけ此山とよめることは、あまりなることに聞え侍る。しかれとも人麻呂のの歌に、かくよむをよき事にするにや。 答 此山と指は、此道と上にいへると同しく、石見より登り來る道に有山を指て云へるとみるへし。反歌に高角山の名あれとも、此山は益高に山も越來ぬといへる、山々を指てみるへきなり。且なひけ此山といへるは、山のなひかぬことを、人麻呂おろかにてしらさるにはあらす。しかれとも妹をこひしたまふあまりに、山もなひきて妹か門をみせよとねかふ情は、切なる情の實なれは、是非をわきまへす、おろかによめる情の實なれは、これをよしとす、かの山の端にけていれすもあらなんとよめるも此情なり。戀歌哀傷述懷の歌には、皆此おもむきを實情とする也。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | ナビケ此山は、卷十三、靡けと人はふめども、かく依れと人は衝けども、心なき山のおきそ山、みぬの山といふに同じき意なり。切なる餘りにをさなく願ふ心を詠めり。卷十二、あしき山梢ことごとあすよりはなびきたれこそ妹が當り見むなど言ふも是をとれるか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 靡此山 [ナビケコノヤマ] は、山の障リて見せぬが、わびしければ、此ノ山靡けよ、と山に令せたるなり、これまことのこゝろなり、まことの歌なり、まことに山をも靡かしむる勢此ノ歌此ノ詞にあり、讀者かへすがへす味ヒ見べし、契冲、うごきなきものなるを、故郷の見えぬをわびて、せめての事にいふは、歌のならひおもしろきことなり、第十二に、あしき山木末こぞりてあすよりはなびきたれこそいもがあたり見む、第十三長歌の中に、わがかよひ道のおきそ山みのゝ山なびかすと人はふめどもかくよれと人はつけども、などもよめり云々、といへり、岡部氏云、古郷出て、かへりみるほどの旅情、誰もかくこそあれ、物の切なる時は、をさなき願ごとするを、それがまゝによめるは、まことのまこと也、後ノ世人は、此ノ心を忘れて、巧みてのみ歌はよむからに、皆そらごとゝ成ぬ、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 靡此山 ナビケコノヤマ。邪魔になるこの山に對して、靡き伏せと命じている。この山が無くば、妹の門が見えるだろうというのである。勿論それは構想であつて、山が無くても遠く來たので見えるわけは無いのだがそれを山に對してたいらになれと言う所に、妻を思う情があらわれている。「惡木山 [アシキヤマ] 木末悉 [コヌレコトゴト] 明日從者 [アスヨリハ] 靡有社 [ナビキタリコソ] 妹之當將v見 [イモガアタリミム]」(卷十二、三一五五) の歌は、類想の歌である。「靡得 [ナビケト] 人雖レ跡 [ヒトハフメドモ] 如此依等 [カクヨレト] 人雖レ衝 [ヒトハツケドモ] 無レ意 [ココロナキ] 山之 [ヤマノ] 奧礒山三野之山 [オキソヤマミノノヤマ]」(卷十三、三二四二) の歌は山を邪魔にしている。以上第三段、作者の希望を述べて力強く結んでいる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「靡此山」(ナビケコノヤマ) 既に超えて来た山に遮られて妹の門が見えないので、その山に靡けと云つたのである。山に靡けと云つた例は、「靡けと 人は踏めども かくよれと 人はつけども 心なき 山の おきそ山 み吉野の山」 (13・3242) の如きは人麻呂の作に先行するものかと思はれ、 あしき山木末(こぬれ)ことごと明日よりは靡きたりこそ妹があたり見む (12・3155) はそれに追随するものと云へよう。古今集には、 飽かなくにまだきも月のかくるるか山の端にげて入れずもあらむ (巻十七) 業平 があり、後世の俚謡にも、 山が高うてあの家(や)が見えぬ あの家可愛や山懀や とある。「山にくや」とため息をつくところ江戸の小唄らしく、「靡けこの山」と叫ぶところに萬葉のなげきがある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「靡此山」(ナビケコノヤマ) 「ナビ(甲類)ク」は、横に伏す意の動詞 (四段)。童蒙抄に「したひおもふ情の切なるあまりに、なびくべき山にはあらねど、なびけと下知したる也。業平の山の端にげていれずもあらなんといへる意と同じ雅情也」と言い、真淵は「物の切なる時は、をさなき願いごとをするを、それがままによめるはまことのまこと也。後世人は此心を忘れて、巧みてのみ哥はよむからに、皆そらごととなりぬ」 (考) と評している。茂吉評釈に、真淵は恐らく童蒙抄とは異なって、業平の歌と同列には置かなかったであろうと言い、「山の端逃げて」の句の遊戯的・間接的・弛緩的なるに反して、「靡けこの山」という句が、真率的・直接的・緊張的であることを悟入せねばならぬと記している。また大浜厳比古は、こうした烈しい表現を支えたエネルギーは何かという問いを発し、この一句こそ、前代の呪力文学の世界から精霊呪力を後退せしめ、現人神信仰によって、自然の神々を恐れぬ発想を可能とした人麻呂が、自然からの解放と禁忌をも破るほどの恋情の強さを表明したものにほかならないと言う (「叙景歌と人麻呂」万葉二十五号)。真淵のことばとともに、人麻呂のおかれた文学史的位置を考えさせる句と言える。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「靡此山」(ナビケコノヤマ) ナビクは横になること。山や海など人力で動かせない非情な存在に向かっての絶叫。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 132 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版](1980年9月)も併記する 【題詞】 反歌 〔本文〕 歌。元暦校本・神田本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本、コノ下「二首」二字アリ。 〔諸説〕 反歌。万葉集檜枛、「反歌」ハ「短歌」ノ誤。 【本文】 石見乃也 高角山之 木際従 我振袖乎 妹見都良武香 (イハミノヤ タカツノヤマノ コノマヨリ ワカフルソテヲ イモミツラムカ) 〔頭書〕 金澤本、コノ歌ノ本文マデ欠ケテ存セズ。訓ノミアリ。 類聚古集、前二行ニ「山反歌一首 人麿 [従石見国別妻]」アリ。 袖中抄、第四「石見ノヤ高角(タカツノ)山ノコノマヨリワカフルソテヲイモミツラムカ」 〔諸説〕 タカツノヤマノ。万葉考、「タカツノヤマノ」。 木際従 (コノマヨリ)。万葉考、一本ノ「従」ノ下「文」ヲ作ルヲ可トシ、「コノマユモ」ト訓ズ。古義、「従」ノ下「文」アルニヨラバ「コノマヨモ」ト訓ズ。
[校本萬葉集新増補版]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「代匠記」歌意考察 | 代匠記 | 石見乃也高角山之木際從我振袖乎妹見都良武香(イハミノヤタカツノヤマノコノマヨリワカフルソテヲイモミツラムカ) 拾遺には、石見なるたかまの山のと載らる (上述)、歌仙集の中の人麿集も如此あれば、若家集より撰て載らるゝ歟、家集は後人のしわざにて信じがたき物なり、此歌下の句を打返して、妹見つらむか我ふる袖をとなせば、意注を待ずして意明なりり、後鳥羽院御歌に、石見がた高角山に雲晴て、ひれふる嶺を出る月影、此御傳にや、八雲御抄にも、領巾を袖と思召けむ、猶今の歌を取らせ給ふに付ては、不審なる御歌なり、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「童蒙抄 [問答]」 | 童蒙抄 | 石見乃也高角山之木際從我振袖乎妹見都良武香 童子間 此歌は高角山の木際より、人丸の振袖を妹見つらんかとよめる歌にあらすや。しかれはなひけ此山とよめるも、此と指は高角山にあらすや。 後鳥羽院の御製にも、石見かた高角山に雲はれてひれふるみねを出る月影、とあれは、人麻呂わかれし妹を袖もてまねかれたるにや。妹かあたりもみん爲に、高角山に登りて、袖をふり給へるやうにきこえ侍るは如何。 答 反歌は長歌の意を三十一言にていひ述たるものなれは、長歌と同意趣なるを、長歌の意を得すして反歌のみをみては、歌の意見あやまることおほかるへし。おそらくは後鳥羽院も歌はたくひなき事なれとも、萬葉集はしろしめさす長歌の意もわきまへ給はすして、反歌のみを見たまひて、かの松浦さよひめかひれふりしたくひに、此反歌を心得させ給ひてや、此御製有なるへし。ひれと袖とも異也。此反歌は滿句の一躰にて、高角山に登りて人丸の旅行をしたふ妹より、木間よりみつらんとある歌也人丸袖ふり行をいもみつらんといひて、いかに高角山高くとも見えましきと、妹をいたはる心なるへし。長歌におもひしなえて吾をしぬふらん、妹か門を見むとおもへとも、山隔たりたれは、みるへくもあらぬによりて、此の山なひきて妹か門を見せよとねかひたる心に、なひけ此山とはよめり。然れとも此反歌のふる袖を、妹をまねく心にみることも害なかるへき歟。歌の意は人丸のふる袖を、高角山の木の間より妹みつらんかとよめるには決すへし。 童子問 後鳥羽院の御製は、新後拾遺集に載られたれは、先達も皆人丸の歌を心得違へられたるにや。且新後拾遺集には、高つの山を高間の山とあり。是もあやまりならんか。 答 後鳥羽院の御製をたれ有てあやまりとみんや。されは新後拾遺集に撰み入られたるもことわり也。袖とひれとの差別なとは、万葉集の古歌なとを見しりたる人にあらすは、おなしことのやうに心得違へらるへし。且高間の山とあるは傳寫の誤か。御製は高角山を角の字と間の字と字形相似たれは、うつしあやまれるにてもあらんか。又は万葉集に角字を間の字にかきあやまりたるを、後鳥羽院御覽ありて、高間の山となされたるか。いつれにても角の字の寫あやまりとみれは、御製の違にはなるましき也。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「石見乃也(いはみのや)」注 | 万葉考 | 石見乃也 [イハミノヤ]、 この也は與に通へり、上に籠毛與、吾者毛也などいふ皆同じ、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | この也は與に通へり。上に吾ハモヤなど言ふに同じ。木ノ間ヨリと言ふより次の四句を隔てて、妹見ツラ(108)ムカと續なり。人麻呂道に出でてかへり見して振る袖を、妹は高角山に登りて見返りつらむかとなり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攷證 | 石見乃也 [イハミノヤ] のやの、やは、地名の下へつけて、かろく添たる字にて、意なし。書紀繼禮紀に、阿符美能野 [アフミノヤ]、□[立心偏+豈]那能倭倶吾伊 [ケナノワクコイ] 云々。本集十四 [十八丁] に、美奈刀能也 [ミナトノヤ]、安之我奈可那流 [アシカナカナル] 云々。古今集大歌所に、あふみのや、かがみの山をたてたれば云々など見えたり。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 石見乃也 [イハミノヤ] 高角山之 [タカツヌヤマノ] 木際從 [コノマヨリ] 我振袖乎 [アガフルソデヲ] 妹見都良武香 [イモミツラムカ] 石見乃也 [イハミノヤ] の也 [ヤ] は、助辭にて、余 [ヨ] といはむが如し、七ノ卷に、淡海之哉八橋乃小竹乎 [アフミノヤヤハセノシヌヲ] 、書紀繼體天皇ノ卷ノ歌に、阿符美能野□[立心偏+豈] 那能倭倶吾何 [アフフミノヤケナノワクゴガ]、古今集に、淡海のや鏡の山を、十四に、美那刀能也安之我奈可那流 [ミナトノヤアシカナカナル] などあり、これら乃也 [ノヤ] と云る例なり、(岡部氏が、此を、籠母與 [モヨ]、吾者毛也 [モヤ]、などいふに同じ、と云るは、いさゝかたがへり、) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 石見乃也 [イハミノヤ] 高角山之 [タカツヌヤマノ] 木際從 [コノマヨリ] 我振袖乎 [ワガフルソデヲ] 味見都良武香 [イモミツラムカ] 石見乃也 [イハミノヤ] ―― 也 [ヤ] は輕く添へていふ歎辭である。近江のや鏡の山・ささなみや志賀の都などの、やに同じ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 石見乃也 [イハミノヤ] 高角山之 [タカツノヤマノ] 木際從 [コノマヨリ] 我振袖乎 [ワガフルソデヲ] 妹見都良武香 [イモミツラムカ] 石見乃也 [イハミノヤ] 「ヤ」は、感動の助詞であつて、意味にあつては、石見の高角山というに同じ。このヤの助詞ノに接續する例は、「阿符美能野 [アフミノヤ] □[立心偏+豈] 那能倭倶吾伊 [ケナノワクゴイ]」 (日本書紀九八、繼體天皇紀) の例がある。本集には、動詞助動詞の連體形に按績する例は多いが、助詞ノに接續する例は、(「淡海之哉 [アフミノヤ] 八橋乃小竹乎 [ヤバセノシノヲ]」 (卷七、-三五〇) の例があるだけである。「美奈刀能 [ミナトノ] 安之我奈可那流 [アシガナカナル] 多麻古須氣 [タマコスゲ]」 (卷十四、三四四五) の初句、美奈刀能の下に、仙覺本には也の字があるが、元暦校本等には無い。元來このヤは、歌いあげる時に、詞句の末につける感動の語から來たもので、琴歌譜の語中の歌詞を見ると、多數使用されており、しかもそれが別に歌詞として整理される場合には、大抵省路されて記録されない。ところが一句の音節數が固定するに及んで、五音もしくは七音の數に合わせるために、これが記録される場合を生ずる。この石見ノヤの如きもその一例であつて、歌われる歌に存する特有のものが、文筆作品としての記録形態を完成するために、使用されたものである。助詞ノに接續する場合は、その遊離性が強いために、廣く行われるに至らなかつたものであろう。なお、「吾はもや」のヤの如きも、同樣の經路により、發達したものと考えられる。萬葉後期においては、熟語的に使用されるもの以外には、かような形はほとんど行われなくなつた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | 石見のや高角 [たかつの] 山の木 [こ] の際 [ま] より我が振る袖を妹見つらむか 石見のや 「や」は調子をととのへる爲の助詞。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「石見乃也」(イハミノヤ) 「や」は詠歎の助詞。「近江のや矢橋(やはせ)の小竹(しの)」 (7・1350) の「や」と同じく、意味はその上の「の」から次の名詞へつづく。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「石見乃也」(イハミノヤ) 「ヤ」は間投助詞。琴歌譜の歌詞に多く見られ、元来歌謡をうたいあげる時に詞句の末に付ける感動の語から来たものと考えられる (全註釈)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「石見乃也」(イハミノヤ) 「ヤ」は連体格の下につく間投助詞。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「高角山(たかつのやま)」考 | 全注 | 【考】「高角山」(タカツノヤマ) 「見おさめ山の抒情」- 反歌の第一首目。「高角山」は、それを越えると妻の住んでいる里の見えなくなる、いわゆる「みおさめ山」なのであろう。那賀郡の嶋星山が高角山に相当すると言われるが (評釈篇)、断定はできない。と言うよりも、現実の地理に還元して考えることが、この歌の場合どれほどの意義を持つか疑わしいと思われる。 この第一反歌について、窪田空穂は、長歌の「妹が門見む 靡けこの山」よりも昂奮の度の高いものと記しているが (窪田評釈)、西郷信綱は逆に「たんに一首としてみれば、さして特色のない類型的なものにすぎない」 (私記) と言う。どちらもわたしには同調しがたい。〔注〕に触れた通り、長歌末尾の部分と同様の烈しい思いを歌ったのであって、評釈はあまり強く受けとめ過ぎ、私記は軽く見過ぎていよう。長歌末の抒情を別の形で歌い直したものであることは、反歌一首の形式の「或本歌」 (138、139) の場合にいっそう明らかなように思う。 【注】 長歌に「角の浦」とある、その角の里にある高い山の意味で作られた山名で、139歌の「打歌山」が本来の固有名かと推測される。「高角山」の方が角の里との関係がよく分かる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「高角山之(たかつのやまの)」訓・考 | 万葉考 | 高角山之 [タカツノヤマノ]、木際從文 [コノマユモ]、或本による、 是より次の一句を隔て、妹見つらんかとつゞけり、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攷證 | 石見乃也 [イハミノヤ] 高 [タカ] 角 [ツヌ・ツノ] 山之 [ヤマノ] 木際從 [コノマヨリ] 我振袖乎 [ワカフルソテヲ] 妹見都良武香 [イモミツラムカ] 高角山之 [タカツヌヤマノ] 高角山は、この外古書に見えざれば、郡は知ざれど、こゝに、かくよまれつるからは、國府のちかきあたりなるべし。下の或本歌には、打歌山とかけり。この事は、下にいふべし。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 高角山 [タカツヌヤマ] は、石見ノ國美濃ノ郡の山ノ名なり、今ノ俗に、高津と呼 [イフ] よし、國人いへり、此ノ地に、柿本大明神を鎭座 [イハヘ] りとぞ、(この歌を、拾遺集に、石見なるたかまの山とてあげしは、あまりかたはらいたくこそ、) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 高角山之 [タカツヌヤマノ] ―― 高角山は石見國美濃郡に、今、高津といふ所があつて、人麿を祀る社もあり、其處の山だらうと言はれてゐたが、その村は國府より遙か西方に當つて、都への歸路ではない。恐らく高角山は都農の附近の高い山の意で、都農の里は、人麿の妻の住んでゐた地であるから、その後方の山に違ない。今、島星山と稱するものが、それだと言はれてゐる。地圖參照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 高角山之 タカツノヤマノ。高角山は、角の里から上京の途上にある山で、角の地の山であるから角山といい、これに形容詞高を添えて高角山という。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | 高角山 角の義で、高は、高い山の意で添へたものと思はれ、また高角山ともいうたとも考へられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「高角山」(タカツノヤマ) 長歌の、津野の里にある山、高い山として高の語を加へたのであらう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「木際従(このまより)」訓・考 | 攷證 | 木際從 [コノマヨリ]。 この句をば、下へつけて、わがこゝにて振 [フル] 袖 [ソデ] を、高角山の木の間より、妹見つらんかと心得べし。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 木際從 [コノマヨリ] は從 [ヨリ] 二木間 [コノマ] 一なり、眞恒校本に、從、一本ニ、從文とあり、さらば「コノマヨモ」 と訓べし、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 木際從 [コノマヨリ] ―― この句は、第五句の妹見都良武香 [イモミツラムカ] につづくものと見る説が多かつたが、それでは句の續が穩やかでないから、我振袖乎 [ワガフルソテヲ] につづくものと見るがよい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 木際從 [コノマヨリ]。樹の間を通して、樹間から。木ノ間ヨリワガ振ル袖と次句に續くのであつて、見ツラムカに續くのではない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | 木の際より この句を五句「妹見つらむか」にかける説もあるが、直接下につづけ、木の間から我が振る袖をといふのが自然である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓注】「木際從」(コノマヨリ) 代匠記その他に「木の間より」を下の「妹見つらむか」につづけて解しようとする説もあつたが当たらない。長歌の歌意から考へてもその事は明らかであるが、萬葉の歌は出来るだけ句の順序のままに解くべき事、前 (1・39) にも述べた。また袖を振るといふ事は、前 (1・20) にもあつたやうに相手に対する意思表示であるから「どこそこからどこそこへ向かつて振る」といふ云ひ方があるわけで、 しろたへの袖はまよひぬ吾妹子が家当乎(イヘノアタリヲ) やまず振りしに (11・2609) の「家のあたりを」は「家のあたりへ向つて」の意であり、それに対して今は、「木の間よりわが振る」とあつて少しも不都合はないのである。なほこの事次にも述べる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「木際從」(コノマヨリ) 原文「木際従」。「際」は、玉篇佚文に、「邊也」とあり、そのあたりの意にも用いられたようだが、新撰字鏡には「子例反去間也方也接也」とも見える。ここでは「間」の意味で「木際」を「コノマ」と訓む。この句の掛かり方に問題があり、代匠記 (精撰本) に「此哥下ノ句ヲ打返して、妹見ツラムカ我フル袖ヲトナセは、注ヲ待スシテ意明ナリ」と言い、童蒙抄・考・略解・古義・檜嬬手なども「妹見つらむか」に掛かると見たが、井上新考に「此反歌は句のままに心得べし。即人麿が高角山の木間より袖を振りて見せしなり」と反対の説が出され、講義も「高角山も亦旅路のうちにあること著しく、又語のつづきも亦木際よりわがふる袖と直ちにつづくと見るが順当にして、他に之を否認すべき確証なき限りは穏かなる解し方とすべきものなりとす」と「我が振る袖」にそのまま掛かると見る説を支持した。茂吉評釈は、新考・講義の説を無理のないものとした上で、「地理的に云つても、角の里を立つてこの角の山の山腹を縫うて江川の岸に来るのだから、どうしてもさう解釈しないと道理に合はぬのである。これは私等同志も以前からさう解してゐたが、文献を諳んじてゐなかつたために実は契沖以来の第二説のあることを知らずにゐた有様であつた」とも言っている。地理的条件は確定しえないことなので除くとして、注釈に強調されているように「出来るだけ句の順序のままに解くべき」で「ワガフル」に掛かると考えられよう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「我振袖乎(わがふるそでを)」注 | 万葉考 | 我振袖乎 [ワガフルソデヲ]、妹見都良武香 [イモミツラムカ]、人まろ道に出て顧しつゝ振 [フル] そでを、妹は高角山にのぼりて、見おくりつらんかとなり、かく疑ふぞ情あり、 或本、初を石見爾有 [ナル]、末を吾袂振乎、妹見監 [ケン] 鴨と有、 〔私注:或本とは「拾遺集 1239」歌のことか〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攷證 | 我振袖乎 [ワカフルソテヲ]。妹見都良武香 [イモミツラムカ]。 袖を振は、人と別るゝ時、又はかなしき時、戀しきにたへずしてする、古しへのしわざなるべし。集中、人にわかるゝ所に、多くよめり。本集二【卅八丁】人麿妻死之後歌に、妹之名喚而袖曾振鶴 [イモカナヨビテソデヅフリツル] 云々。六【廿三丁】に、太宰師 [(マ)] 大伴卿上レ京時、娘子歌に、凡有者左毛右毛將爲乎 [オホナラバトモカモセムヲ]、恐跡振痛袖乎忍而有香聞 [カシコシトフリタキソデヲシヌヒテアルカモ] 云々。倭道者雲隱有 [ヤマトチハクモカクレタリ]、雖然余振袖乎無禮登母布奈 [シカレトモワカフルソテヲナカレトモフナ] 云々。七【四丁】に妹之當吾袖將振 [イモガアタリワカソテフラム]、木間從出來月爾雲莫棚引 [コノマヨリイテクルツキニクモナタナヒキ] 云々。十【廿六丁】に、汝戀妹命者 [ナカコフルイモノミコトハ]、飽足爾袖振所見都 [アクマテニソテフルミエツ]、及雲隱 [クモカクルマテ] 云々。十一【十二丁】に、袖振可見限吾雖有 [ソテフルヲミルヘキカキリワレハアレド]、其松枝隱在 [ソノマツカエニカクレタリケリ] 云々。高山岑行宍友衆袖不振來忘念勿云 [タカヤマノミネユクシヽノトモヲオホミソデフラスコシワスルトモフナ] 々などありて、猶いと多し。文選劉□[金+樂]擬古詩に、眇々陵二長道一、遙々行遠之、囘レ車背二京里一、揮レ手從レ此辭云々とあるも似たり。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 我振袖乎 [アガフルソデヲ] は、十一に袖振可見限吾雖有其松枝隱在 [ソデフルガミユベキカギリアレハアレドソノマツガエニカクリタリケリ] とあり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 我振袖乎 [ワガフルソデヲ]。 袖を振るは、合圖をするためであつて、この場合は、別れを惜しむために振る。袖は、手の部分を蔽うものであるから、畢竟手を振ることである。集中例は多い。別れに際して振ることをいうものに、「倭道者 [ヤマトヂハ] 雲隱有 [クモガクリタリ] 雖レ然 [シカレドモ] 余振袖乎 [ワガフルソデヲ] 無禮登母布奈 [ナメシトモフナ]」(卷六、九六六)、「汝戀 [ナガコフル] 妹命者 [イモノミコトハ] 飽足爾 [アクマデニ] 袖振所レ見都 [ソデフルミエツ] 及二雲隱 [クモガクルマデ]一」(卷十、二〇〇九) などがある |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「妹見都良武香(いもみつらむか)」考 | 全註釈 | 妹見都良武香 [イモミツラムカ]。 カは疑問の助詞。妹見ツを推量し、これを疑問としている法である。わが妻は見たであろうかと推量している。妹が木の間より見つらむかの意であるとする説は非である。語句の順序から見ても、それは穩當でない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「一首」考 | 古義 | 【歌ノ意】 歌ノ意は、妻が見むために、わが袖ふるふる來しを、そのふる袖を、石見の高角山の木間よりして、妹はそれと見つらむかとなり、四一二三五、と句を次第て意得べし、契冲、此ノ歌、人の心得あやまる歌なり、そのゆゑは、木ノ間より妹みつらむか、わがふる袖を、といふ意なれど、さいへば手つゝなれば、我ふる袖を、といふ句を、第四におかれたるゆゑに、第三の木のまより、といふに引つゞけて心得るゆゑに、かへざまになるなり、むかしもさりけるにや、後鳥羽ノ院の御製に、石見がた高角山に雪はれてひれふる峯を出る月影、今の人丸の歌は、わかれ來て、こなたより、わがふる袖を、故郷の高角山にのぼりて、見おこす妹が、木の間より見つらむか、とよまれたるを、さよひめならぬ人丸のひれを、高角山にふらせ賜へるは、袖とひれと物たがひて、男女たがひ所たがへり、いかめしき、御製なるにおどろきて、新後拾遺集に載られたれば、彼選者も、さこそこ心得られけめと云り、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 【評】 妻に別れて都農の里を離れ、山にさしかかつた時のことを述べたもので、もう逢はれぬと思ふにつけても、別を惜しんで高角山の木の間より我が袖を振つたのは、果して妻の目にとまつたであらうかと、今はそれが心にかかり出したのである。せめてあれでも妹の目に止まつて、彼の女の胸にやきつけられたならば、私は切めてそれで心を慰めよう。さてどうであつたらうと思ふのである。あはれな歌だ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 【評語】 道を行き進み、山を登りつつ、顧みがちに袖を振つた。山が邪魔になり、道の隈が重なつても、見えないと知りながら、妹を思つて袖を振つた心である。石見の國府から、實際袖を振るのが見える位置に、高角山を求めるのは間違いである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「我振袖乎 妹見都良武香」(ワガフルソデヲ イモミツラムカ) 万葉集の袖振りは、別離の場合にも、愛の表現にも、舞踏の型としても見られる。ここは別れを惜しんでのこと。「イモミツラムカ」の「カ」は疑問の助詞であるが、前の「123歌」の「掻きれつらむか」の「か」全に疑問の意が強かったのと比べると、妻に見えよとばかり袖を振る心の衝迫が強くあらわれている。長歌末尾の「靡けこの山」と同様の烈しい思いを、妹を主にして歌ったものである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 133 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版](1980年9月)も併記する 〔頭書〕 類聚古集、前行二「別妻人麿作反歌 集哥石見海」 古葉略類聚鈔、前行ニ「柿下朝臣人麿従石見国別妻上来時短哥」 【本文】 小竹之葉者 三山毛清爾 亂友 吾者妹思 別来禮婆 (サヽノハヽミヤマモサヤニミタレトモワレハイモオモフワカレキレハ) 〔本文〕 来。細井本、「未」。無訓本、「末」。 禮。古葉略類聚鈔、ナシ。 婆。類聚古集、「波」。 〔訓〕 サヽノハヽ。類聚古集、訓ノ右ニ朱「サノヽハヽ」アリ。 サヤニ。元暦校本、「そよに」。右ニ朱「サヤ或本」アリ。 ミタレトモ。元暦校本・金澤本・・類聚古集、「みたるとも」。古葉略類聚鈔・神田本・温故堂本、「ミタルトモ」。大矢本・京都大学本、「レ」青。 京都大学本、「亂」ノ左ニ赭「ミタレ」アリ。 ワレハイモオモフ。元暦校本、訓ノ左ニ赭「ワレハトモヲモフ」アリ。但、「モフ」ハ明ナラズ。金澤本、「われはいもをし」。古葉略類聚鈔・神田本、「ワレハイモヲシ」。 神田本、「妹思」ノ左ニ「イモヲモフ」アリ。細井本・温故堂本、「ワレハイモヲモフ」。 ワカレキレハ。元暦校本・金澤本・類聚古集、「わかれきぬれは」。古葉略類聚鈔・神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「ワカレキヌレハ」。 〔諸説〕 サヽノハヽ。代匠記精撰本、「サヽカハニ」カ。童蒙抄、「シヌノハハ」。略解、「サヽカハハ」トモ訓ズ。捃、「サヽノハハ」ヲ可トス。 ミタレトモ。仙覚抄、「ミタルトモ」 (古点) ヲ否トシ「ミタレトモ」トス。代匠記初稿本、「マガヘトモ」トモ訓ズ。 代匠記精撰本、「ワカルラム」「ミタルトモ」ヲ否トシ、「ミタレトモ」ヲ可トス。又ハ「マガヘトモ」トモ訓ズ。万葉考、「サワゲドモ」。檜、「サヤゲドモ」。 イモオモフ。童蒙抄、「イモシヌフ」。 ワカレキレハ。仙覚抄、「ワカレキヌレハ」。代匠記初稿本書入、「ワカレシクレハ」。
[校本萬葉集新増補版] 【本文】 小竹之葉者 三山毛清爾 亂友 吾者妹思 別来禮婆 (サヽノハヽミヤマモサヤニミタレトモワレハイモオモフワカレキレハ) 〔頭書〕 古今六帖、第四「篠の葉はみ山も余所にわかるらむ我は妹にし別れきぬれは」 夫木抄、第廿八「さゝのはゝみやまもさやにみたる共我はいも思ふわかれきぬれは」 新古今、九〇〇 [私注:新古今900 題しらず 人麻呂 「ささの葉はみ山もそよに亂るなりわれは妹思ふ別れ来ぬれば」] 〔本文〕 来。神宮文庫本、「未」。 〔訓〕 ミタレトモ。大矢本ハ「レ」青ナレド、近衛本、墨書セリ。 オモフ。神宮文庫本、「ヲモフ」。近衛本、「オモヒ」。 キレハ。神宮文庫本、「キヌレハ」。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「一首」考 | 拾穂抄 | さゝのはゝみ山もさやにみたれともわれはいもおもふわかれきぬれは 小竹之葉者三山毛清尓亂友吾者妹思別來礼婆 さゝの葉はみ山も 亂友仙曰古点みたるともと和ス みたれともと和スへし 祇曰此哥は妹に別て深山なとに旅の宿りして讀るなり 笹の葉はそよと打みたれてあれとも 我は只妹思ふと讀り 此哥末の集にみたるめりと入心は打亂て有をみるにも我は妹思ふと也 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | 小竹之葉者三山毛清爾亂友吾者妹思別來禮婆 [サヽノハヽミヤモサヤニミタレトモワレハイモオモフワカレキヌレハ] 歌の心は、み山は靜けきものなるに、さゝ原に風吹わたれば、其み山さへさわがしくみだるれども、我は狎にし故郷を別て來ぬれば、妻を思ふ意更に紛るゝ方なしとなり、第九に、高嶋のあと川なみはどよめども、吾は家思ふたぴねかなしみ、全此心なり、又源氏野分に、風さわぎ村雲まよふ夕にも、忘るゝまなく忘られぬ君、六帖にも清爾を「そよに」 とこそ改めつるを、後の人歌に、そよにさやぐと重てよまれたるは不審なり、又新古今に、腰の句を、亂なりと改られたるは、六義の興にして比の意に、彼み山を見れば、小竹原に風吹て亂る、此我妹を思ふ心も、古里を別きぬればさわぐごとそれが如しとにや、作者の意さには侍らざるべきにや、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 童蒙抄 | 童子又問 此反歌長歌の詞もみえす。自餘の反歌の例にもたかへるに似たり。しかれとも此歌人々に有て名歌とするは、いかなる所をさして稱美する歌にや。 答 よきうたかひなり。中古以來の歌人万葉集を見すしらさる故に、人丸の歌といへは、皆名歌と心得てみたりに稱美するのみにて、歌のよしあしをみわくる所へは及はす。人丸の歌とさへいへは後人のよみたる歌をもほめあけ、歌のきこゆきこえぬにも及はす、たゝほめにほめて、其實なき事ほのほのとあかしの浦の歌のたくひあまた有事也。此歌も長歌にあはせてみる所まてはいたらす、みたりによみなしたるとみゆるなり。此歌かなつけの如くによみては、反歌にもならす、歌といぶ所見えぬ也是古學をしらす、長歌にあはせて反歌をみるならひもしらすして、よみたかへたるものなり。 童子又問 此歌反歌にもならすと云へる所、もし海路の歌なるに、み山をよみたる所にてしか云へるにや。 答 いな、長歌に益高に山も越來ぬとあれは、その越行山をよめれは、山を詠るを反歌にならすといふへからす。凡反歌の長歌の言葉か、長歌の意をそむせて詠る例なし。此反歌にさゝの葉はみ山もさやになとゝいふ詞長歌に類せさるを云也。よりて僻案には小竹之葉者の五字をしぬの葉はとよむ也。これ長歌に、夏草のもひにしなえてしぬふらんといふ詞あれはしぬをよみ出て、下の句に吾者妹思と有にて、反歌にもなり歌にもなる也。小竹の二字を日本紀中にさゝと用ゐたる例もなし。皆しぬと用ゐたり。其證神代上云、篠小竹也、此云斯奴とあるをみてしるへし。此集の文字訓讀日本紀を本としてかけれは、日本紀を見ぬ人万葉集の文字をよむへからす。且清の字をさやとよみ來れり。尤清の字をさやかともさやけしともよむ、あまた例あれとも、小竹の二字をさゝとよまはさやともよむへし。小竹をしのはとよむときは、さやとよみては詞の義たかへり。よりて此清の字をすかとよむ證は、是も日本紀神代上に清地此云素鵝と訓注あれは也。且亂友をまかへともよむ意は、篠と管とは相似かよへは、篠の葉はみ山も管にまかへともといふを、衣の意にして、すかはきよき心なれとも、われは妹にわかれ來ぬれは、妹を思ふ心にきよからぬよし也。又案に清をすかとよますして、すゝしきを略してすゝとも用ゐたるか。すゝは薦にて、小竹と薦とは同類の竹と艸との異なる也。されはすゝ竹と云もの有。又しぬすすきといふ名あり。今此歌にては、しぬとすゝとを分て、しぬの葉はすゝにまかへともと云へるか。下の句は、とかくわれはいもしぬふとよますしては歌にあらす。小竹をよみ出して、下に妹しのふとあるにて、反歌ともなり歌といふもの也。しからすしてさゝの葉といひ、われは妹おもふとよみては、歌とみゆる所なし。歌は少詞のより所なくては、只平話のことになりて歌にならす。万葉集の文字よみたかへて歌を歌になさすしても、數百歳誤り來れるは、歌といふものをしらさる故也。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 歌ノ意は、狎々 [ナレナレ] し愛しき妹をとゞめ置て、別て來る道のさぶさぶしきに、まして御山は、よろづ物靜なるに、小竹原に風吹わたりて、佐夜佐夜 [サヤサヤ] と鳴さやげば、物おそろしくこゝろぼそくて、何事も忘るゝことわりなるに、吾はさらにまぎるゝ方なく、なほ妹を戀しくのみ、念ふとなり、源氏物語野分に、風さわざ村雲まよふ夕にも忘るゝまなくわすられぬ君、九ノ卷に、高島之阿渡河波者驟鞆吾者家思宿加奈之彌 [タカシマノアドカハナミハサワゲドモアレハイヘモフヤドリカナシミ]、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 【評】 笹の葉のさやさやと、山風に打ちそよぐ、淋しい路を辿りつつ、妻を思ふ若い旅人の情緒がか細く、か弱く、物哀げにあらはされてゐる。歌の調子も、笹の葉の戰ぎ鳴る旋律と一致してゐるやうな感がある。新古今に「ささの葉はみ山もそよに亂るなり我は妹思ふ別れ來ぬれば」として出てゐるのは、この歌が、かの繊細な新古今風に通ずるところがあつて、當時にも喜ばれたものであらう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 【評語】 滿山の小竹が秋風に鳴る中を、妻に別れて行く氣分がよく描かれている。諸種の訓法があるが、サを頭韻とする訓がすぐれているようだ。高宕な風格の出ている作品である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【考】「妻との別離を歌った最初の長歌」 妻との別離を長歌に歌ったわが国最初の作。巻一の軍王作歌 (5、6)、巻四の岡本天皇御製 (485~487) などは、いずれも制作年代に疑問があり、また別離を主題としたものでもない。ただし、この人麻呂作歌の制作時期は厳密には不明である。真淵の万葉考の『別記一』に、「柿本朝臣人麻呂」という項があり、そこには、
と記されている。それに従って晩年の作とするのが通説になっている。茂吉の『柿本人麿』総論篇に、これを景雲年中に降る作としたのは、巻二の亡妻挽歌 (207~212) を文武四年ごろとし、石見の別れの歌は「どうしてもそれ以後とせねばならぬ」と考えたからである。武田祐吉『国文学研究 柿本人麻呂攷』にもほぼ同様な説を見る。しかし真淵や茂吉などの想定とはまったく異なって、これを持統朝の初の作と考える説もある。契沖の代匠記に、
とあるのは、その早い例である。また神田秀夫『人麻呂歌集と人麿伝』には、人麻呂の九州行と関連ある作として持統七年ごろと推定している。真淵や茂吉の説とは、十数年の隔たりがある。 諸説のうちいずれが正しいか、判定は困難だが、人麻呂の長歌に付せられた「反歌」を仔細に見ると、持統五年以前には「反歌」と頭書し、同六年以後には「短歌」と記されていて、反歌の作法にも著しい変化が指摘されるので、そうした点から、持統朝前半とする契沖説に蓋然性が認められる。 なお、「131歌」の長歌の初案にはこの「小竹の葉は」の歌がなく、推敲の後に加えられたと考えられることや、人麻呂の伝記と作品との関係については、後に述べる (139歌の項および233歌の項参照)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「小竹之葉(ささのは)」訓・注 | 代匠記 | 小竹之葉者三山毛清爾亂友吾者妹思別來禮婆 [サヽノハヽミヤモサヤニミタレトモワレハイモオモフワカレキヌレハ] 發句はサヽガハニと和すべきか、第二十に、佐左賀波乃 [サヽガハノ]、佐也久志毛用阻 [サヤクシモヨニ] 云云、古歌の習、「の」 と云べき所を、多く「が」 といへば、何れにても有ぬべけれど、引る歌を證として驚かし申なり、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攷證 | 小竹之葉者 [サヽノハハ]。 古事記上卷に、訓二小竹一云二佐々一云々とありて、また書紀神功皇后元年紀に、小竹此云二之努一云々。本集一「八丁」に、しぬびつといふ所の借字にも、小竹櫃 [シヌビツ] と書たれば、小竹を、さゝとも、しぬともよむ也。されば、こゝは、舊訓のまゝに、さゝの葉はと訓べし。和名抄竹類に、蒋魴切韻云篠 「先鳥反、和名之乃、一云佐々、俗用二小竹二字一、謂二之佐々一」 細竹也云々とも見えたり。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 小竹之葉者は、「サヽガハハ」 と訓べし、廿ノ卷に、佐左賀波乃佐也久思毛用爾 [サヽガハノサヤクシモヨニ] とあり、なほ小竹を、佐々 [サヽ] と云る例、十九に、和我屋度能伊佐左村竹 [ワガヤドノイサヽムラタケ]、古事記允恭天皇ノ條ノ歌に、佐々婆爾宇都夜阿艮禮能 [サヽバニウツヤアラレノ] など、いと多し、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 【釈】「小竹之葉者」(ササノハハ) 小竹之葉者 [ササノハハ]。ササガハハ (代匠記)。小竹は、ササともシノとも讀むが、この歌では、ササと讀むがよい。小竹 [ささ]、サヤニ、騷 [さや] ゲドモと、サを頭韻としたために、全山ささと鳴る感じが出るのである。古事記上卷自註に、「訓二小竹一云二佐々一」とある。「佐左賀波乃 [ササガハノ] 佐也久志毛用爾 [サヤクシモヨニ ] 奈々弁加流 [ナナヘカル] 去呂毛爾麻世流 [コロモニマセル] 古侶賀波太波毛 [コロガハダハモ]」(卷二十、四四三一)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「小竹之葉者」(ササノハハ) 原文「小竹」は、「シノ」とも「ササ」とも訓まれる。古事記上巻の訓注に「訓二小竹一云佐々」と見え、神功紀には「小竹此云之努」とある。万葉集巻十一「朝柏閏八河邊之小竹之眼笑思而宿者」(2754) では、下句「しのひて寝れば」との関係から「シノ」と訓むことが明らかである。人麻呂歌集・人麻呂作歌では「細竹(シノ)」 (11・2478、略体歌) (7・1276、非略体歌)、「四能」 (1・45、作歌) とあって、「小竹(ササ)」と「細竹(シノ)」と区別されているように思われる。巻二十の防人歌に「佐左賀波乃佐也具志毛用」 (4431) とあるのは小竹の葉を「ササガハ」と言った例であるが、古今集に「笹の葉に置く霜よりも」 (恋二・563)、「笹の葉のさやぐ霜夜を」 (雑躰・1047) と見え、「ササノハ」が中央語として普通であったようだ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「三山毛清尓(みやまもさやに)」訓・考 | 代匠記 | ミヤマは直山にて、サヤニは山のさやぐと同じくさわぐなり、神代紀に聞喧擾之響焉、〔此云二佐椰霓利奈離 [サヤケリナリ] 一、〕又未平をもサヤゲリと訓ぜり、此皆さわぐなり、此集にもあまたあれば、煩はしければさのみは引ず、「わ」と「や」と同韻にて通ぜり、清の字は借てかけるなり、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉考 | 三山毛清爾 [ミヤマモサヤニ]、 三は眞 [マ] なり、清は借字、紀に、(神武)聞喧擾之響を、左揶霓利奈離 [サヤケリナリ] とよめる如く、嵐立て山の皆小篠 [ヲザヽ] の鳴さやぐなり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | サヤニは神武紀、聞喧擾之響を左椰霓利奈離 [サヤゲリナリ] と有る如く、小篠の風に鳴る音を言へり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攷證 | 三山毛清爾 [ミヤマモサヤニ]。 みやまの、みは、例のほむる詞にて、眞也。古事記下卷に、美夜麻賀久理弖云云と見えたり。深山の意とするは誤れり。清爾 [サヤニ] の、清 [サヤ] は、借字にて、小竹葉の、風などに、さやさやと鳴るをいへり。古事記中卷に、久毛多知和多理許能波佐夜藝奴 [クモタチワタリコノハサヤギヌ] 云々。書紀神武紀に、聞喧擾之響焉、此云二左佐椰霓利奈離 [サヤゲリナリ] 一云々。本集十〔卅八丁〕に、荻之葉左夜藝秋風之 [ヲキノハサヤキアキカセノ] 云々。二十〔四十二丁〕に、佐左賀波之佐也久志毛用爾 [サヽガハノサヤグシモヨニ] 云々などあるも、皆同じ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 三山毛清爾 [ミヤヤモサヤニ] とは、三 [ミ] は御 [ミ] なり、美稱なり、清 [サヤ] は、借リ字にて、佐夜佐夜 [サヤサヤ] と喧しく鳴リさわぐことなり、六ノ卷に、御山毛清落多藝都 [ミヤマモサヤニオチタキツ]、(これも清は借リ字にて、上に同し、) 又曾與 [ソヨ] ともいへり、(今の歌、新古今集には、そよにとて載たり、又同集に、君來ずば獨や宿なむ篠の葉の御山もそよにさやぐ霜夜を、ともあり、) 十ノ卷に、旗荒木未葉裳曾世爾 [ハタスヽキウラバモソヨニ]、(此ところ、舊本には、これかれ誤あり、) 十二に、布妙之枕毛衣世二嘆鶴鴨 [シキタヘノマクラモソヨニナゲキツルカモ]、新撰萬葉に、松葉牟曾與丹吹風者 [マツバモソヨニフクカゼハ] などあり、また古事記上卷に、水穂ノ國者、伊多久佐夜藝弖有祁理 [イタクサヤギテアリケリ]、また中卷神武天皇ノ條にも、此ノ詞あり、(其を書紀に、聞喧擾之響と書て此云二左椰霓利氣離 [サヤケリケリト] 一、氣を、舊本に奈に誤、) 又伊須氣余理比賣命ノ御歌に、加是布加牟登曾許能波佐夜牙流 [カゼフカムトソコノハサヤゲル]、古語拾遺に、阿那佐夜甜 [アナサヤケ]、(竹葉之聲也とあり、竹葉の觸あひて、さやさやと鳴が、聲のさやけく聞ゆる、と云より出たるなるべし、) 此ノ集十ノ卷に、荻之葉左夜藝秋風之吹來苗丹 [ヲギノハサヤギアキカゼノフキクルナベニ]、など用 [ハタラ] かしても云り、曾與具 [ソヨグ] と云ることは、後々彌多し、(新古今集に、篠の葉は御山もさやに打そよぎこぼれる霜を吹あらし哉、) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 三山毛清爾 [ミヤマモサヤニ] ―― 三山 [ミヤマ] の三 [ミ] は接頭語で意味はない。清爾 [サヤニ] はさやさやとの意で、清の字は借字である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 三山毛清尓 ミヤマモサヤニ。ミは接頭語。山を賞美して、山の山たる所をあらわす。いかにも山だという氣分でいる。サヤニは、音や色が他に紛れない狀態をいう副詞。ここに清爾の字を當て、他にも多く清の字を當てているのは、サヤが清明の意であるに由るものであろう。ここでは、次の句の騷ぐ狀態を、ミ山モサヤニと限定指向している。山もさやかに騷ぐというのである。「足引之 [アシヒキノ] 御山毛清 [ミヤマモサヤニ] 落多藝都 [オチタギツ] 芳野河之 [ヨシノノカハノ]」(卷六、九二〇) の、ミ山モサヤニと同樣の用法である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「三山毛清尓」(ミヤマモサヤニ) 「み」は接頭語。「さやに」はさらさらと音を立てること。さやさやの擬声語から「さやに」の副詞となり、次の句の「さやぐ」の動詞ともなり、「さやか」「さやけし」の副詞、形容詞ともなつたもので、類似の語「さわさわ」から「さわやか」「さわく」などの語が生まれ、「そよそよ」から「そよに」、「そよぐ」の語が生まれたのと似ている。そして「さやか」、「さやけし」に、「清・明」の字があてられるように、「さや」にも「清」の字があてられ、その字義にも用ゐられ、「清尓毛不見 (サヤニモミエズ)」 (135)、「佐夜尓美毛可母 (サヤニミモカモ)」 (廿・4423) の如きは共に「さやか」とほぼ同じ意に用ゐられたものであるが、今の場合は擬声語「さやさや」といふ語原的な意味に近く用ゐられたものである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「三山毛清尓」(ミヤマモサヤニ) 「ミ」は接頭語。美称と言われるが、意味論的にその発生が見直されるべきだと西郷信綱の私記 (十七頁) にいう。神や貴人に関することばに用いられることが多い。「ミ山」も元来、山の神に対する畏怖の気持ちのこもった言い方であったのであろう。「サヤニ」の原文「清尓」。巻六の「あしひきの 御山毛清 落ちたぎつ」 (920、金村) と同じく「サヤニ」 と訓む。人麻呂歌集に「吉野川音の清左(サヤケサ)」 (9・1724)、「三日月の清(サヤニモ)不見」 (11・2464)、「新治の今作る路 清(サヤカニモ)聞きてけるかも」 (12・2855) とある「サヤニ・サヤカニ」は、視覚的・聴覚的印象の明瞭なことをあらわす。「清」は、万象名義に「且盈反潔・・・澄・・・」などとあり、きよらかではっきりしている意味をあらわす文字。金村の「み山も清に落ちたぎつ」も滝の音の大きく明らかに聞こえることを言う。この人麻呂歌の場合、契沖の代匠記や真淵の万葉考のように「清」は「借字」で「ナリサヤグ」状態をあらわすと見るか、童蒙抄に「さやにはあきらかに也」とあるように、「清」を表意正訓字とするか、説が分かれている。あとの「乱」字の訓にもかかわるが、これを模倣した金村歌に正訓字として使われているように、人麻呂の場合も借訓とは言い切れまい。音を主とした擬声語的な「サヤニ」であったとしても、とくに「清」字を用いているのは、さわがしく厭われるのでない、清明的な印象を強めるためではなかったか。注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「三山毛清尓」(ミヤマモサヤニ) 「サヤニ」は、はっきりと、目にも鮮やかに、の意。ここは山道の笹原の風に吹かれて発する葉擦れの音、さやさや、をも写している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 【脚注】「三山毛清尓」(ミヤマモサヤニ) 「サヤニ」は「さやさや」という竹葉のそよぐ擬音。この音の印象から派生する「清く明るい」共感覚的視覚印象を、原文では「清」の文字をもって記してある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「乱友(さやげども)」訓・考 | 仙覚抄 | 小竹之葉者三山毛清尓亂友吾者妹思別來礼婆 [サヽノハハミヤマモサヤニミタレトモワレハイモオモフワカレキヌレハ] 此ノ歌ノ中ノ五字、古點ニハ、ミタルトモ和ス。イサヽカアヒカナハス。ミタレトモト和スヘシ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | 亂友は、六帖は一向に改たれば云に及ばず、古點は假令の意にて下句に叶はず、仙覺の今の点尤當れり、今按マガヘドモと和すべし、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 童蒙抄 | 童子問 仙覺抄は此歌の中の五文字古點にはみたるともと和す、いさゝか相叶はす。みたれともと和すへしとあり。古新いつれを是とせんや。 答 中五文字みたるともにてはてにをはかなはす。みたれとももことたらす。みたるれともならねはかなはす。されとみたるれともはことあまりてきゝやすからす。僻案にはまとへともと訓す。此集亂の字をまかふとよめる例すくなからす。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉考 | 亂友 [サワゲドモ]、 亂は驟なり、友は借字、(卷十) 高島の、阿渡 [アト] 河波は、驟 [サワゲ] ども、吾は家おもふ、別かなしみてふは、今をよみうつしたるなるべし、又(卷五) 松浦船、亂 [サワグ] ほり江とよみつ、さやぐはこゑ、さわぐはかたちなり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | 亂ドモをサワゲドモと訓むは、卷十二、松浦船亂ほり江の亂をサワグと訓みたるに同じ。越る山道のかしましきにも紛れず。吾は別れし妹を戀ふるとなり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攷證 | 亂 [マガヘ・ミダレ] 友 [トモ]。 舊訓、みだれどもと訓る、いと誤りなり。考に、さわげどもとよまれしも、いかゞ。亂は、本集此卷「廿丁」に、黄葉乃散之亂爾 [モミチハノチリノマガヒニ] 云々。八「卅八丁」に、秋芽之落之亂爾 [アキハキノチリノマガヒニ] 云々。十「十丁」に、散亂見人無二 [チリマガフラムミルヒトナシニ] 云々。十三「廿三丁」に、黄葉之散亂有 [モミチハノチリマガヒタル] 云々など、多くまがふとよめば、こゝもまがへどもと訓べし。小竹 [サヽ] の葉に、風などのふき、み山の物しづかなるも、さやさやと鳴さわぎて、物にまがへども、吾は愛する妹にわかれきぬれば、物にもまぎれず、こゝ一すぢに、妹をおもふとなり。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 亂友は、舊本に從て、「ミダレドモ」 と訓べし、(新古今集にも、み山もそよにみだれどもとて載たり、「サワゲドモ」、とよめるはわろし、) 今の心にていはゞ、みだるれども、といふべき如くなれども、如此 [カク] 云は、古言の格なり、古事記允恭天皇ノ條ノ歌に、加理許母能美陀禮嘆美陀禮 [カリコモノミダレバミダレ]、十二に、松浦舟亂穿江之 [マツラブネミダルホリエノ]、(岡部氏が、此ノ歌の亂をも、「サワグ」 とよみて、今を、「サワゲドモ」 、とよむ證とせるは、大しき非なり、三ノ卷ノ歌を以ても、必ス「ミダル」 とよむべきをしれ、) 三ノ卷に、苅薦乃亂出所見海人釣船 [カリコモノミダレイヅミユアマノツリブネ] などあり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檜嬬手 | 小竹之葉者 [サヽノハハ]、三山毛清爾 [ミヤマモサヤニ]、亂友 [サヤゲドモ]、吾者妹思 [アレハイモオモフ]、別來禮婆 [ワカレキヌレバ]。 「清爾」喧擾 [サヤゲ]の意なれども言のかよふまゝに、清 [サヤ] とは書ける也。六〔十二〕には、御山毛清落多藝都 [ミヤマモサヤニオチタギツ] とあり。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 亂友 [サヤゲドモ] ―― 亂の字、種々の訓があるが、上からの續き方では、サヤゲドモとよむのが一番よい。舊訓ミダレドモで、古義がこれに從つてゐるのは、諒解に苦しむ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 【釈】「亂友」(サヤゲドモ) 亂友 サヤゲドモ。ミダレドモ(舊訓)、マガヘドモ(代匠記一説、攷證)、サヤゲドモ(檜嬬手)等の諸訓がある。サヤゲドモと讀むのは、「佐左賀波乃 [ササガハノ] 佐也久志毛用爾 [サヤクシモヨニ]」(卷二十、四四三一) とある例による。この語は日本書紀神武天皇紀に「聞喧擾之響焉、此云二左揶霓利那離 [サヤゲリナリ]一」とあり、本集に「葦邊在 [アシベナル] 荻之葉左夜藝 [ヲギノハサヤギ] 」(卷十、二一三四) とあつて、喧擾の聲を立てるをいう。ドモは逆態前提法を示す助詞であるが、ここでは、小竹の葉は騷ぐけれども、それには拘わらずにの如き意味を成している。「タカシマノアトカハナミハサワケドモワレハ 家思 [イヘオモフ] 宿加奈之彌 [ヤドリカナシミ]」(卷九、一六九〇) の騷ケドモは、これと同樣の用法であり、一首の形も似ている歌である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「乱友」(サヤゲドモ) 原文に「乱友」とあり、旧訓に「ミダレドモ」とあつてそれに従ふ説も行はれてゐるが、それだと四段活用の已然形といふ事になり、「亂る」はもと四段活用であつた事は「みだりに」「みだり心地」などの語によつて察せられるが、萬葉には四段と認むべき仮名書例がなく、当時既に下二段活用になつてゐたと思はれるので、「ミダレドモ」の訓はとり難い。又金澤本等の古写本には「ミダルトモ」とありそれを支持する説もある。それだと下二段活用とも認められる事になり、又「とも」は長歌の「浦は無くとも」の如く現実にさうある場合にも用ゐるから、その訓は認められるやうに見えるが、「浦は無くとも」 (131) の場合でも一例をあげておいたやうに「とも」をうけては、 ・・・人さはに 入り居り登母(トモ)・・・撃ちてし夜麻牟(ヤマム)・・・(神武記) 七瀬の淀はよどむ等毛(トモ)吾はよどまず君をし麻多武(マタム) (5・860) の如く助動詞「む」で結ぶものが最も多く、 言とはぬ木にはあり等母(トモ)うるはしき君が手馴(タナ)れの琴にし安流倍志(アルベシ) (5・811) 我が背子し遂げむと言はば人言は繁くあり登毛(トモ)出でて相麻志呼(アハマシヲ) (4・539) の如く「べし」「ましを」などの語で受けるものなどがあるが、「妹思ふ」の如き動詞の終止形で止めたものの無いのは、それが必ずしも語法上不都合だといふのでは無いが、「とも」の語を受ける勢を成し得ないからだと思ふ。また『古径』一にも述べておいたやうに「亂る」といふ言葉は玉とか落葉とかバラバラに散乱するもの、髪とか柳とか細長く入り雑り乱れるものに用ゐられてゐて、枝ながらの竹の葉などには用ゐられてゐない事も、今の場合にはふさはしからぬやうに思はれる。また代匠記の一説として「マガヘドモ」の訓があり、それによられてゐる学者もあるが、「まがふ」の事は後 (137) にややくはしく述べるやうに、「亂」の文字に対する訓としては認められるけれども今の場合に適切な訓とは考へられない。「みだる」や「まがふ」はさうも訓めるといふ意味でしひて異を唱へたといふ感がせられるのであつて、ここは「葦邊在(アシベナル) 荻之葉左夜芸(ヲギノハサヤギ)」 (10・2134) 、「佐左賀波乃(ササガハノ) 佐也久志毛用尓(サヤグシモヨニ)」 (廿・4431) などの例によるべきであり、檜嬬手に「サヤゲドモ」と改めたのが正しいと考へる。後世の「そよぐ」に近く、音にも形にも用ゐられる。そのさわやかなさやぎにも心ひかれず、一心に妻を思ふといふのである。人麻呂の臨終の地と考へられる邑智町湯抱 (223参照) から大田へ出る三峡など身の丈に及ぶ大きな熊笹が茂つてゐるが、風に笹のよくそよぐ事を「けふはさやぎがよい」と今も土地の人はいふと、その湯抱の波多野虎雄氏から聞いた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「乱友」(ミダルトモ) 原文「乱友」を、元暦校本・金澤本・類聚古集・古葉略類聚鈔・紀州本・温故堂本などの古写本 (古点) に「みたるとも」と訓んだが、仙覚は「ミタレトモ」と改訓、代匠記に一案として「マガヘトモ」と訓む。万葉考に、これを「サワゲドモ」とし、檜嬬手では、「サヤゲドモ」と改めた。以後「ミダレドモ・ミダルトモ・サヤゲドモ・マガヘドモ」の四訓が行われている。澤瀉『古径』に、この問題を詳細に検討し、「サヤゲドモ」を採用する理由として、 ① 「乱る」は自動詞の場合は下二段活用で、四段活用の例は見られないから、「ミダレドモ」とは訓めない。 ② 「乱」を「サワグ」と訓みうる例がある。 ③ 「ミダル」は木の葉の場合の用例なく、葉の「ソヨグ」ことを「ミダル」というのはふさわしくない。 ④ 木の葉の場合は「サワグ」の例なく、すべて「サヤグ」である。 ⑤ 「サヤ」には清爽の意があり、「サワグ」も「サヤグ」も同様な語であるが、「ミヤマモサヤニ」という前句に続く場合は「サヤグ」の方がふさわしい。 ⑥ 「サヤグ」は聴覚を主とするが語源的に視覚を伴っているもので、この場合も、その意味で「サワグ」よりもふさわしい。 ⑦ 上代の歌にはとくに繰返しが多い。この歌もその例となるのではないか と、合わせて七項をあげている。確かに、万葉集に自動詞「ミダル」の四段活用はないようだし、記歌謡にも「美陀礼婆」 (80歌) があるから、人麻呂作歌の「ミダル」も下二段と考えられよう。「②」の「松浦舟乱穿江之水尾早」 (12・3173) の場合、注釈は「サワク」と訓む (全註釈・古典大系・古典全集など他の注釈書にも同訓が見られる)。「乱」を「サワク」「サヤグ」とよむ証はないと講義に記されているのは、右の「3173歌」の例によって、少なくとも疑わしいとせねばなるまい。「③」は『古径』にとくに強調されていることで、木の葉が枝ながら乱れるという例はなく、玉・刈薦・落花・雪・解衣などのように始めからバラバラに散乱しているものか、髪・柳・菅・藻などのように、糸様のものが入り雑り乱れる場合に限られるという。これも注目すべき調査であるが、柳や藻の乱れの詠まれていることは、「ササ」の葉の乱れという表現を全くありえないものとすることにはなるまいと思われる。「葉のソヨグことをミダルというのはふさわしくない」かもしれないが、枝ながら乱れるのである。「④」は、先に記した「②」の、乱を「サワク」と訓む例は「3173歌」に認められるにしても、それをさらに「サヤグ」という聴覚を主とした語 (語源はサヤサヤという擬声語) の表記に利用したと見るのであって、かなり苦しいと思われる。もちろん「葦原の中つ国は伊多久佐夜芸弖有那理」のような騒擾をあらわす場合もあるが、飽くまで聴覚を主とする語と考えられる。「ミダル」を、おもに視覚的印象中心の語とすれば、「サヤグ」は聴覚的印象を主とすると言えよう。『古径』に「サヤ」と類似した「ソヨ」の、万葉集では聴覚的内容に偏して使われていることをあげているのも、右を裏付ける。ただし、そうしたことが、「乱」を「サヤグ」と訓む証にはならない。「⑤ ⑥ ⑦」の三項も、同様に、「133歌」の「乱」を「サヤグ」と訓む確実な根拠となしえないことは、それぞれ明らかだろう。「①~⑦」の七項のうち、とくに注意されるのは、「① ② ③」の三項であり、注釈は「①」と「③」によって「ミダル」の訓をしりぞけたと言うことができる。しかし、注釈の否定した「ミダレドモ」は、「ミダル」の活用からいって成り立たないにしても、「ミダルトモ」と訓むとすれば、自動詞の活用 (下二段活用) にも抵触せず、「ミダル」の意味にもあまり支障を感じないように思われる。事実「ミダルトモ」は、金澤本・元暦校本・類聚古集・古葉類聚鈔・紀州本など古写本に広く見られるものであって、平安朝以後の人々の親しんだ訓と認められる。さらに、「ミダルトモ」と言うと、未来のことを仮定的に言う逆接の仮定条件を表わす語法のように思われがちであるが、既定の事実を認めながら表現する場合のあることは、 楽浪の志賀の 大わだ淀むとも昔の人にまたも逢はめやも (1・31) という人麻呂作歌によって確かめられる。同じことは、人麻呂歌集の、 高島の阿渡川波は騒鞆吾は家思ふ宿り悲しみ (9・1690) についても言えるだろう。右の第三句「騒鞆」も古写本 (藍紙本・伝壬生隆祐筆本・類聚古集・紀州本) には「サワクトモ」と訓まれており、西本願寺本では「サワケトモ」となっているが、「ケ」が青で、仙覚の改訓と知られる。古典大系にこれを「サワクトモ」と訓んだのは、右のような古訓を復活させたものと言えるのである。茂吉評釈に、
と言った上で、
と記しているのは、「ミダレドモ」による点は別にして、人麻呂作歌の混沌とした声調につき直観的な洞察を含んでいて注目されよう。私注の「山の風に靡く様が目にはつきり見えて笹の葉が吹き乱れて居るけれども」という大意にも視覚的印象を具体的に表現しており、「サヤゲドモ」では把えきれない感じのある人麻呂の詠風に迫ろうとしているのを見る。なお後考にまたねばならないが、「ミダルトモ」の訓に従っておきたい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「乱友」(さやげども) 「サヤグ」は「ソヨグ」と同じく顫動する意。ここは全山を蔽う笹の葉が乱れて鳴り響き、不気味な山中の感じを表す。しかし、逆接の「ども」がついて、それにもかかわらず一心不乱に妻を思う故に全然不安を覚えない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「別来礼婆(わかれきぬれば)」訓・注 | 全注 | 【注】「吾者妹思 別来礼婆」(ワレハイモオモフ ワカレキヌレバ) 見おさめの山を越え、別離の思いの決定的に深められたことを歌うのである。口語としてパラフレーズしてしまえば「わたしは妻のことをひたすらに思っている、別れて来たので」ということになるが、この単純な形に盛られた「尋常でない力」 (私記) に注目したい。作者の表現したかったのは、別れることによって始めて知った思慕の情の深さなのだろう。文選雑詩上に「不(レバ)二会(テ)遠(ク)別離(セ)一、安(ンゾ)知(ラム)レ慕(フコトヲ)二儔侶(ヲ)一」 (張茂先) とあるし、人麻呂が石見相聞歌の制作にあたり参考したと推測される陸機の「赴(ク)レ洛(ニ)詩」にも「感(ジテ)レ物(ニ)恋(ヒ)二堂室(ニ)一離思一(ニ)何(ゾ)深(キ)」とある。そうした中国詩から示唆を受けつつ、別れて後の深い思いを「吾は妹思ふ別れ来ぬれば」という句に託したのであろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻第二 134 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版](1980年9月)も併記する 【題詞】 或本反歌 〔本文〕 歌。神田本、「謌」。元暦校本・金澤本・神田本・西本願寺本・大矢本・京都大学本、コノ下ニ「曰」アリ。 〔諸説〕 或本反歌。古葉略類聚鈔、コノ題詞及ビ「石見爾有」ノ歌前ノ「石見乃也」ノ歌ノ次ニ移ス (拾本) ニ従ヒ、又小字トス。 【本文】 石見爾有 高角山乃 木間従文 吾袂振乎 妹見監鴨 (イハミナル タカツノヤマノ コノマニモ ワカソテフルヲ イモミケムカモ) 〔本文〕 文。金澤本、ナシ。類聚古集、「父」。 袂振。金澤本、「袖振」。類聚古集・神田本、「振袂」。神田本、訓ノ右ニ「袂(ソテ)振(フル)イ」アリ。 監。類聚古集、「濫」。 〔訓〕 イハミナル。金澤本、「いはみにある」。神田本・細井本、「イハミニアル」。神田本、漢字ノ左ニ「イハミナル」アリ。西本願寺本、「ナル」モト青。 大矢本・京都大学本、「ナル」青。京都大学本、赭ニテ「ナル」ヲ消セリ。「爾有」ノ左ニ赭「ニアル」アリ。 タカツノヤマノ。元暦校本、「たか」ノ右ニ赭「サカ」アリ。 コノマニモ。元暦校本・金澤本・類聚古集、「このまより」。神田本、「コマヨリモ」。「従文」ノ左ニ朱「ニモ」アリ。京都大学本、漢字ノ左ニ赭「コノマヨリ」アリ。 赭ニテ右ニ移スベキ記号ヲ附セリ。 ワカソテフルヲ。元暦校本・金澤本・類聚古集、「わかふるそてを」。神田本・温故堂本、「ワカフルソテヲ」。大矢本・京都大学本、「ソテフル」青。 イモミケムカモ。金澤本、「いもみつらんかも」。類聚古集、「いもみつらむか」。右ニ墨「或本イモミケムカモ」アリ。 神田本、「イモミラムカモ」。漢字ノ左ニ「イモミケムカモイ」アリ。細井本、「イモミケンカモ」。 〔諸説〕 コノマニモ。代匠記初稿本、「コノマユモ」。古義、「コノマヨモ」。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「或本反歌」考 | 童蒙抄 | 石見爾有高角山乃木間從文吾袂振乎妹見監鴨 童子問 此或本歌をあけたるは撰者の所爲歟。 答 古注者の所爲也。撰者の所爲ならねは、此卷も自餘の卷も低書しても有へき事なり。 童子又問 右の反歌はさのみたかへる所もみえさるを、何とて古注者書載られたるにや。 答 撰者ならは是非を一決して載らるへき事なれとも、注者の所見にしたかひてはと載へき事にてもあり。且或本とあれは、一本の万葉集ありとみえたれは、是非は後人にゆつりて、異本の歌載加へたるもたすけによらさるにはあらす。前後の歌いつれを是とせむは、見る人の知見に有へし。僻案には或本反歌を是とす。監の字は濫の誤りにても有へきか。監にても意に違ひ有へからねと、けんといふとらんといふとには、歌によりて少意たかへる也。 童子又問 前の反歌と、此反歌といつれを是といふへき所もなきに、後の反歌を是とすとはいかなる所にや。 答 中の五文字、前の歌にてはこのまよりとならてはよまれす。後の反歌にては、この間よりとはよまれす、このまゆもとよむ所に少たかひ有か。第一句石見爾有と云句にて、異義出來ましけれは也。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この「考」、「134」の注釈で載せている | 古義 | [或本歌一首并短歌。(138) 石見之海 [イハミノミ]。津乃浦乎 [ツヌノウラミヲ]。「無美」 浦無跡 [ウラナシト]。人社見良目 [ヒトコソミラメ]。滷無跡
[カタナシト]。人社見良目 [ヒトコソミラメ]。吉咲八師 [ヨシヱヤシ]。浦者雖無 [ウラハナクトモ]。縱惠夜思 [ヨシヱヤシ]。滷者雖無 [カタハナクトモ]。勇魚取
[イサナトリ]。海邊乎指而 [ウミヘヲサシテ]。柔田津乃 [ニギタヅノ]。荒礒之上爾 [アリソノウヘニ]。蚊青生 [カアヲナル]。玉藻息都藻
[タマモオキツモ]。明來者 [アケクレバ]。浪己曾來依 [ナミコソキヨセ ]。夕去者 [ユフサレバ]。風己曾來依 [カゼコソキヨセ]。浪之共
[ナミノムタ]。彼依此依 [カヨリカクヨル]。玉藻成 [タマモナス]。靡吾宿之 [ナビキアガネシ]。敷妙之 [シキタヘノ]。妹之手本乎 [イモガタモトヲ]。露霜乃
[ツユシモノ]。置而之來者 [オキテシクレバ]。此道之 [コノミチノ]。八十隈毎 [ヤソクマゴトニ]。萬段 [ヨロヅタビ]。顧雖爲 [カヘリミスレド]。彌遠爾
[イヤトホニ]。里放來奴 [サトサカリキヌ]。益高爾 [イヤタカニ]。山毛越來奴 [ヤマモコエキヌ]。早敷屋師 [ハシキヤシ]。吾嬬乃兒我 [アガツマノコガ]。夏草乃
[ナツクサノ]。思志萎而 [オモヒシナエテ]。將嘆 [ナゲクラム]。角里將見 [ツヌノサトミム]。靡此山 [ナビケコノヤマ]。] 津乃浦乎無美は、岡部氏、津能乃浦回乎 [ツノノウラマヲ] の、能と回とを落し、無美は、まぎれてこゝに入たるなり、と云るが如し、但シ角は、古くは都努 [ツヌ] とのみ云て、都乃 [ツノ] と云ることなければ、津野 [ツヌ] とか、(野も、努とのみ云り、) 津努 [ツヌ]とか、有しなるべし、浦回も、「ウラミ」 と訓べきこと、上に云る如し、目ノ字上なるは、拾穂本には米と作り、夜思の思ノ字拾穂本には之とあり、越ノ字拾穂本には超と作り、 [反歌。(139) 石見之海 [イハミノミ]。打歌山乃 [タカツヌヤマノ]。木際從 [コノマヨリ]。吾振袖乎 [アガフルソデヲ]。妹將見香 [イモミツラムカ]。] 石見之海と有はいかゞ、高角山とうけたれば、必ス海とはいふまじきをや、打歌山は、按フに、打歌は、竹綱の草書を見まがへて、寫し誤りたるにや、然有ば、「タカツヌヤマ」 と訓べし、竹は、集中に高島 [タカシマ] を、竹島 [タカシマ] とも書キ、書紀神代下卷に、竹屋 [タカヤ] てふ地ノ名を、高屋 [タカヤ] とも書り、鋼を、都農 [ツヌ] と訓ム由は、一ノ卷に、綱能浦 [ツヌノウラ] とある、其註を考ヘ見て知べし、又岡部氏は、打歌は、「タカ」 の假字にて、次に、角か津乃などの字、落しなるべしと云り、(津乃と云るはわろし、これも津野などゝこそありけめ、) 猶考フべし、(舊本に、「ウツタノヤマ」 とよめるは、さらによしなし、凡てこの或本ノ歌は長キ短キともに、甚く劣れり、 [右歌體雖レ同。句々相替。因レ此重載。] 上ノ件、舊本は、或本ノ反歌、石見爾有 [イハミナル] 云々は、小竹之葉者 [サヽガハハ] 云々の歌の次に入リ、或本ノ歌一首并短歌、と云よりこゝまで、秋山爾 [アキヤマニ] 云々、の歌の次に入りて、共に本章の列に載たり、今改めつ、且或本ノ歌は、拾穗本にも細書とせるに從つ、但し彼本には、石見乃海角乃 [イハミノミツヌノ] 云々の歌の次に、一ニ云、石見之海津乃云々とありて、石見乃也云々の次に、一ニ云、石見爾有云々、又云、石見之海打歌云々、と次順 [ツイデ] たり、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 石見なる 高角山の 木の間ゆも 吾が袖振るを 妹見けむかも 石見爾有 [イハミナル] 高角山乃 [タカツヌヤマノ] 木間從文 [コノマユモ] 吾袂振乎 [ワガソデフルヲ] 妹見監鴨 [イモミケムカモ] これは本文の歌と、殆ど意味にかはりはない。美夫君志に、「見監鴨の見監は過去なれば、此には叶はず」とあるが、これで少しも差支ない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 【評語】 後人傳承のあいだに轉訛を生じた歌と思われる。本文の歌に及ばない所以である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【考】 この作を伝誦の間に転訛したものと見る説もあるが、右に述べたやうに、むしろ「132歌」に達する迄の一つの習作と見るべきであらう。「131歌」と「138歌」との関係と同様と考へるのである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【考】 この歌、諸注に、意味はほとんど同じで、本文の詞句より劣ったものと評されているが、〔注〕に記したように、長歌とは異なる時を詠む反歌として作り直されたものとみられる。この「或る本の反歌」にも、「小竹の葉は」という「133歌」に相当する第二反歌は無かったと理解される (伊藤博「石見相聞歌の構造と形成」『万葉集の歌人と作品』上)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「尓有(にある→ なる)」訓・注 | 拾穂抄 | 一云いは見なるたかつの山の木のまにもわか袖ふるを妹見けんかも 石見尓有高角山乃木間從文吾袂振乎妹見監鴨 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | 石見爾有高角山乃木間從文吾袂振乎妹見監鴨 [イハミナルタカツノヤマノコノマユモワカソテフルヲイモミケムカモ] 石見爾有、〔官本亦云、イハミニアル、〕 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「石見尓有」(イハミナル) 原文「尓有」は「木路尓有云 (キヂニアリトイフ)」 (1・35)、「高尓有世婆 (タカニアリセバ)」 (9・1746) など「ニアリ」と訓まれる事は当然であり、「奈良尓安流伊毛我 (ナラニアルイモガ)」 (18・4107) の如き仮名書例もあるが、その一例の他には、殊に五言句には「ニアル」の仮名書字余り句がないので、今は「イハミナル」と訓む。(1・6参照)。石見の国にあるの意。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「石見尓有」(イハミナル) 前の「132歌」と異なって「イハミナル」とある。本文の「石見のや」にくらべて石見に対し親しみがこめられていないという評も見られるが (全註釈)、結句に「イモミケムカモ」とあるのと関連しており、石見の国を離れたところでの作として詠まれたものであろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「従文(ゆも)」訓・考 | 代匠記 | 今按 「從」 は 「ゆ」 ともよむべし、此集に「より」 を「ゆ」 とよめる所おほし、日本紀に神武天皇の御歌にもあり、古語なり、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攷證 | 木間從文 [コノマユモ]。 この間從文 [ユモ] の「從」は、よりの意、文 [モ] は助字也。書紀神武紀に、伊那瑳能椰摩能虚能莽由毛 [イナサノヤマノコノマユモ] 云々とあると同じ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 木間從文 コノマユモ。モは感動をあらわす助詞で、木の間を通してというに同じ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「從文」(ユモ) 神武紀に「伊那瑳能椰摩能(イナサノヤマノ) 虚能莽由毛(コノマユモ)」の例があり、木の間より、の意に詠歎の助詞「も」を添へたものである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「木間從文」(コノマユモ) 「132歌」には「コノマヨリ」とあった。「ユ」は「ヨリ」と同じ経由を示す助詞。「モ」は詠嘆の助詞。単に「ヨリ」というより、「ユモ」の方が強い。「コノマヨリワガフルソデヲ」は、現に袖を振っていることを想像させる表現であるが、「コノマユモワガソデフルヲ」には、やや後になってそのことを強調する気持ちがあらわれている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「木間從文」(コノマユモ) この「モ」は、並列を表す。妻の目に見えるはずもない遠い山中なのに袖を振ったことを示す。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「吾袂振乎(あがそでふるを)」考 | 攷證 | 袂振 [ソテフル]。 袂は、今は、たもとゝのみよめど、玉篇に、袂彌鋭切、袖也とありて、袖と同じ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 吾袂振乎 ワガソデフルヲ。これは動作が主になつている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 【吾袂振乎】(ワガソデフルヲ) 原文「袂」の文字を今「タモト」と訓むが、当時の「たもと」は今のたもとの意ではないこと前(131歌) に述べた如く、玉篇に「袂」に「袖也」とあり、新撰字鏡(四) にも「袂」に「曾弖(ソテ)」 と注し、類聚名義抄 (法、中) に至るつて「ソデとタモト」と両訓がある。今は袖と同様に用ゐたので、自分が袖を振るのを、の意。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「吾袂振乎」(ワガソデフルヲ) 原文の「袂」は、万象名義に「衣袖」とあって、袖に同じ。「132歌」には「吾が振る袖を」とあったし、あとの「139歌」にも同様な句が見える。この歌にのみ「吾が袖振るを」とあるのはなぜか、理由を考える必要があろう。後句に「見けむかも」と歌われているのと関連させて考えると、ここも「吾が振る袖」とは異なって、袖振りを過去のこととする意識から「吾が袖振るを」とせざるをえなかったものと思われる。「吾が〔袖振りし〕を」の意味である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文「妹見監鴨(いもみけむかも)」考 | 全註釈 | 妹見監鴨 イモミケムカモ。後になつてはたして見たであろうかと推量する語法を使つている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 【注】「妹見監鴨」(イモミケムカモ) この結句には、回想の意味が明らかである。つまり、「132・139歌」よりも、後の時に視座を移しての抒情と理解される。長歌末尾の「靡けこの山」から、さらに時を経過して歌っていることになる。一首の反歌のみ添える人麻呂作歌で、こうした歌い方は珍しい。後代の人の歌い変えとも、人麻呂の推敲とも説かれているが、後者であろう。そのことは、「139歌」の項に述べる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
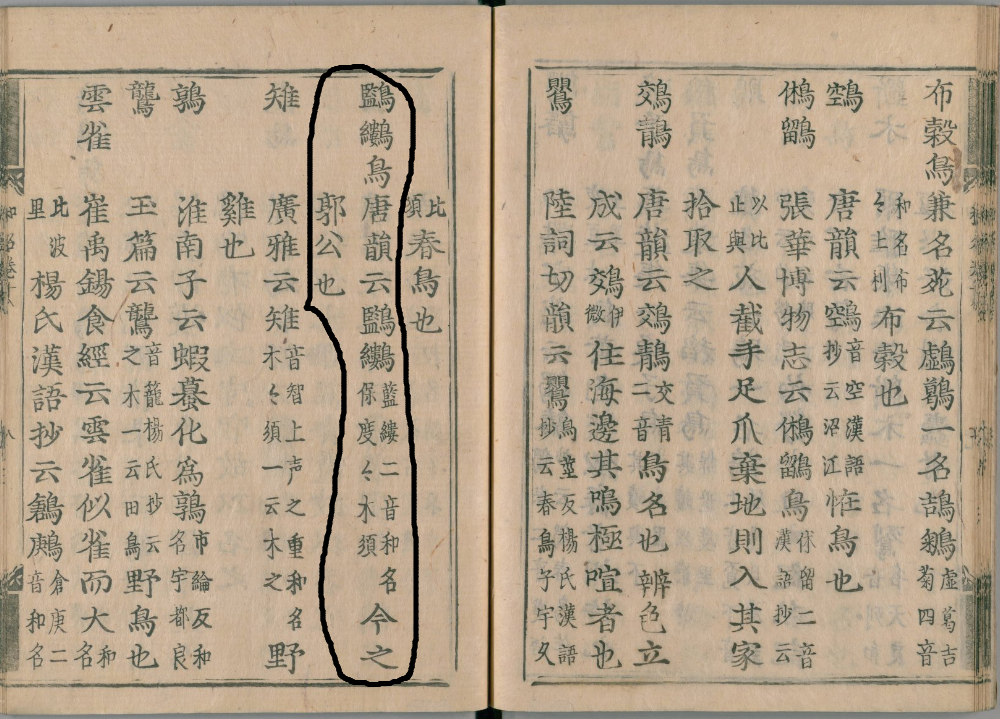
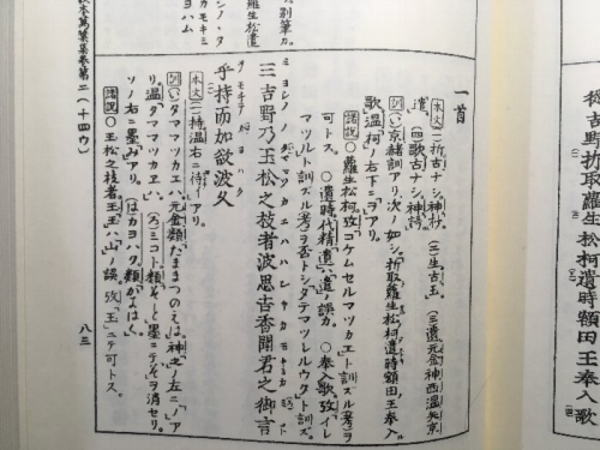
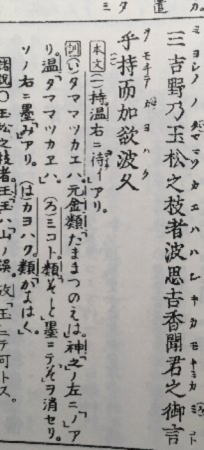
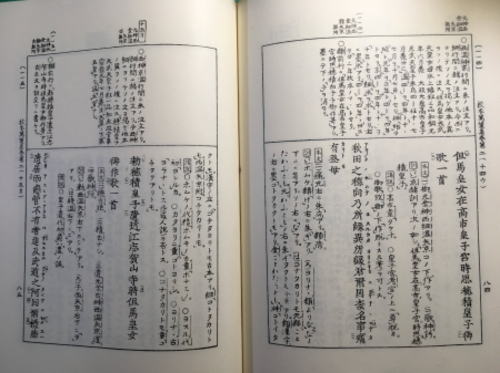
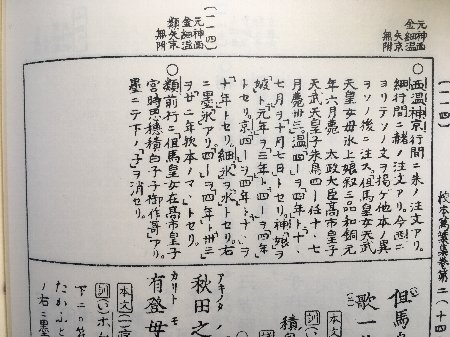
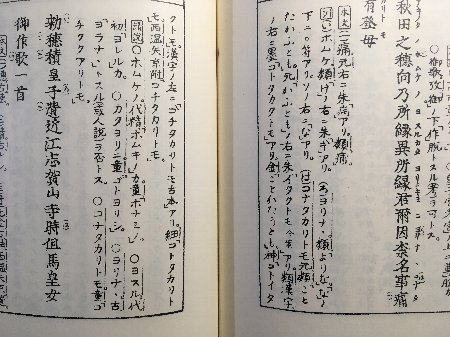
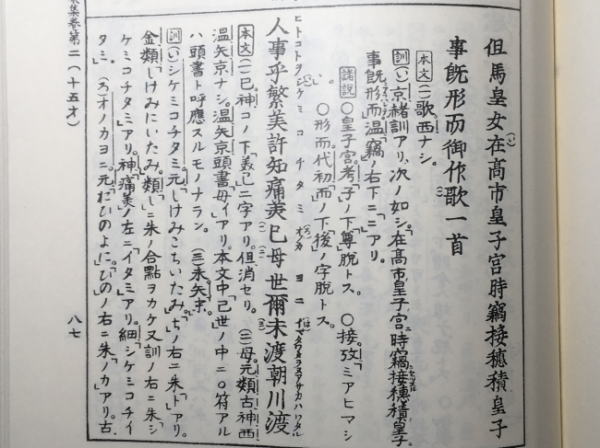
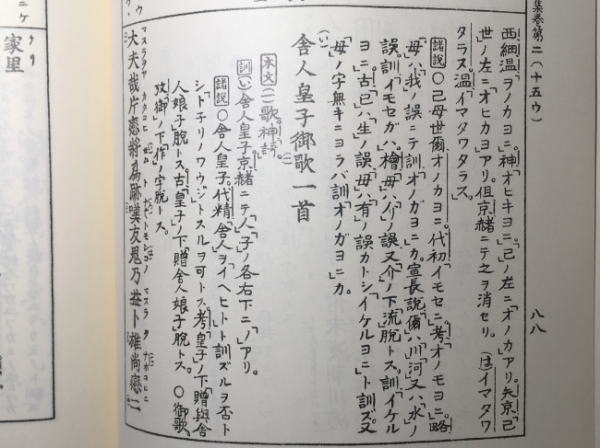
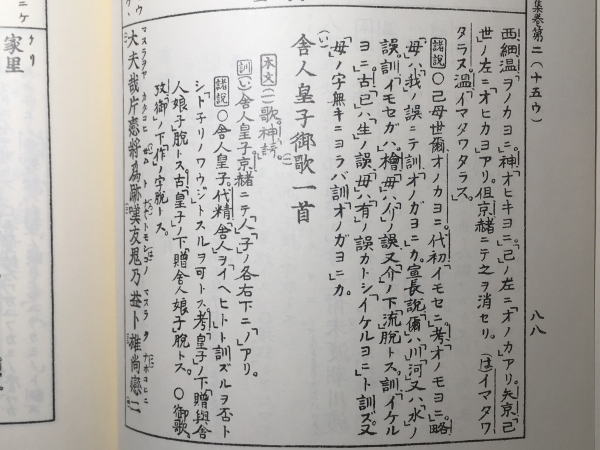
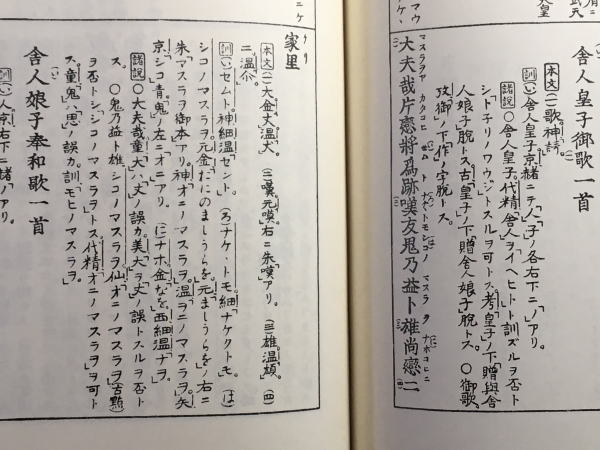
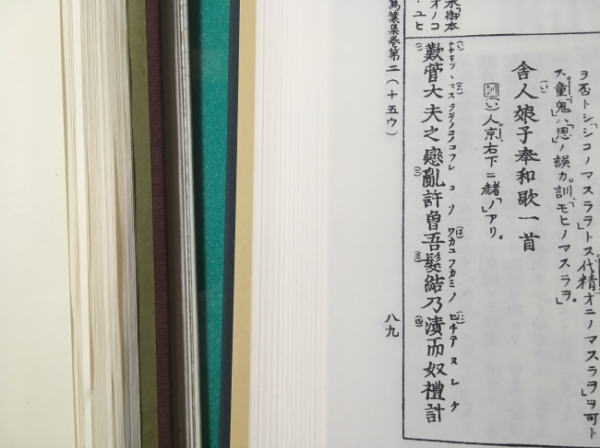
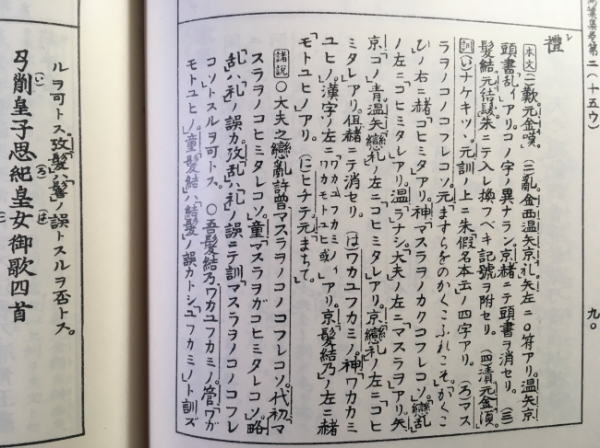
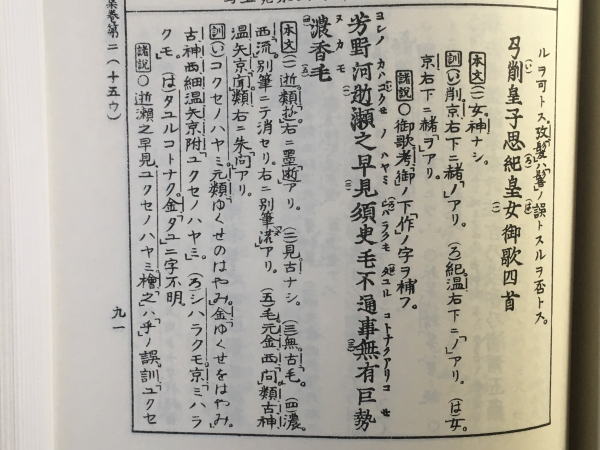
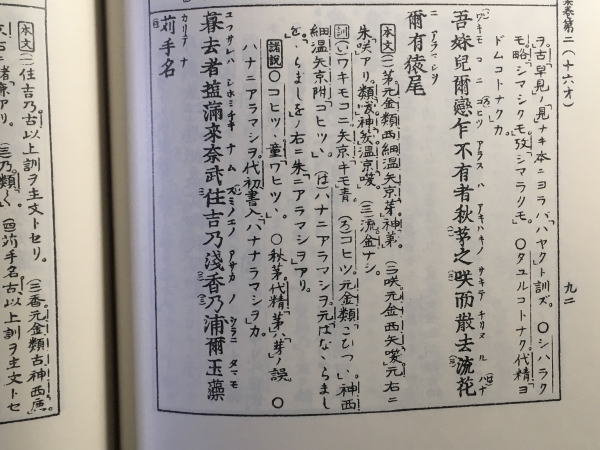
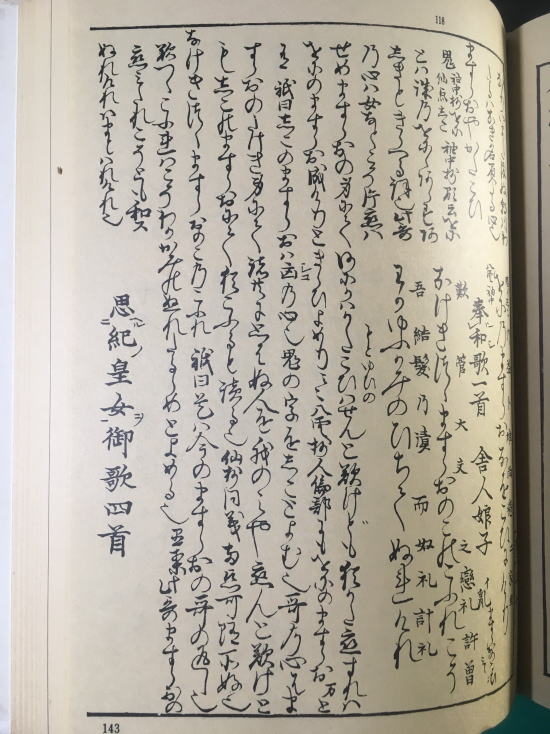
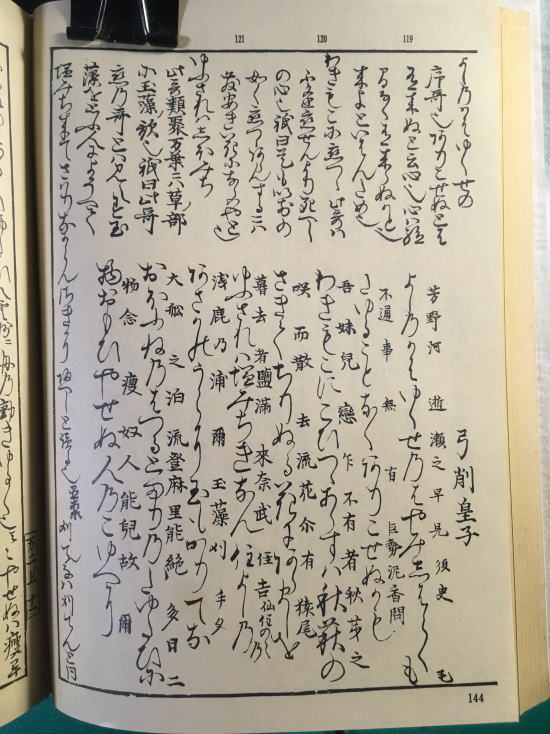
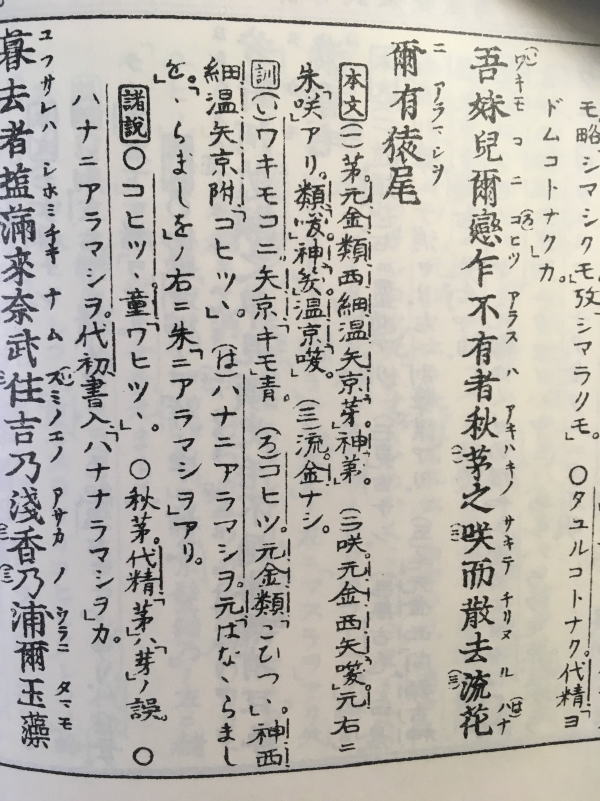 吾妹兒爾 戀乍不有者 秋芽之 咲而散去流 花爾有猿尾
吾妹兒爾 戀乍不有者 秋芽之 咲而散去流 花爾有猿尾