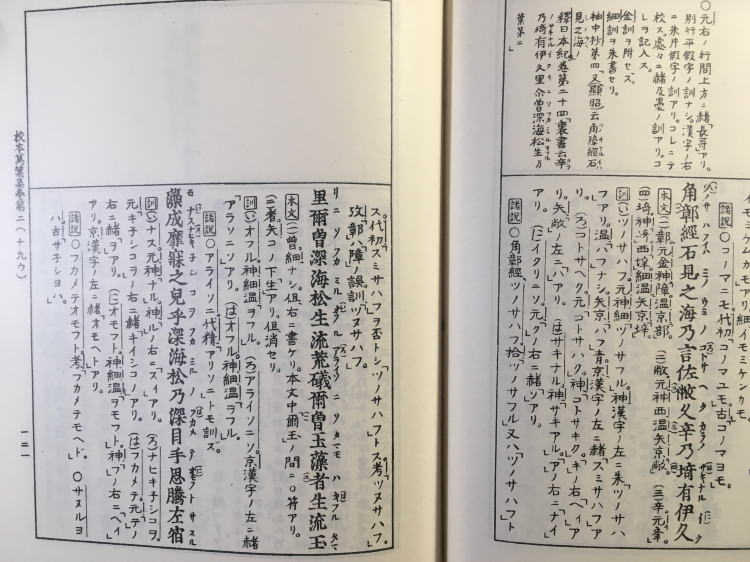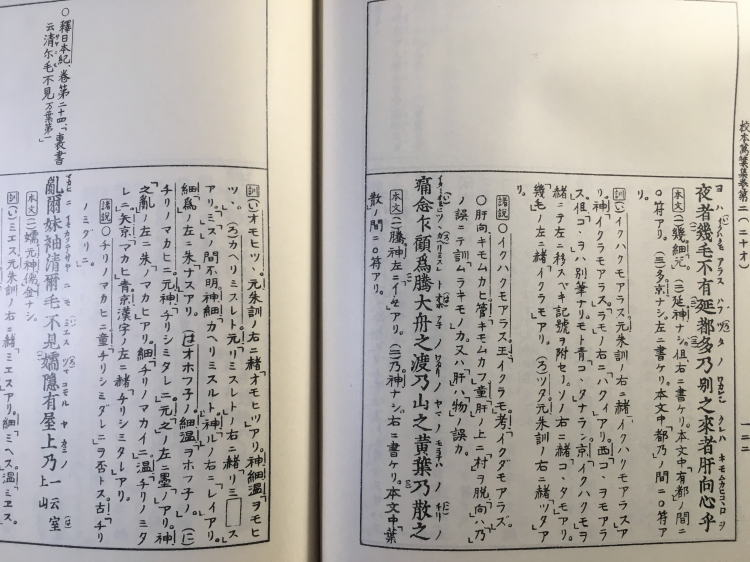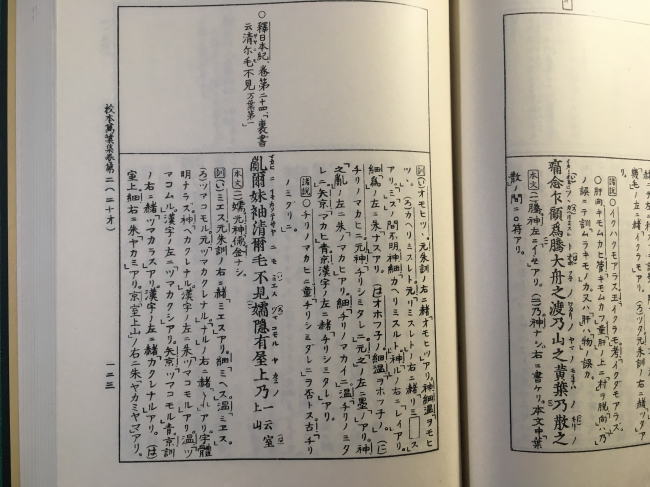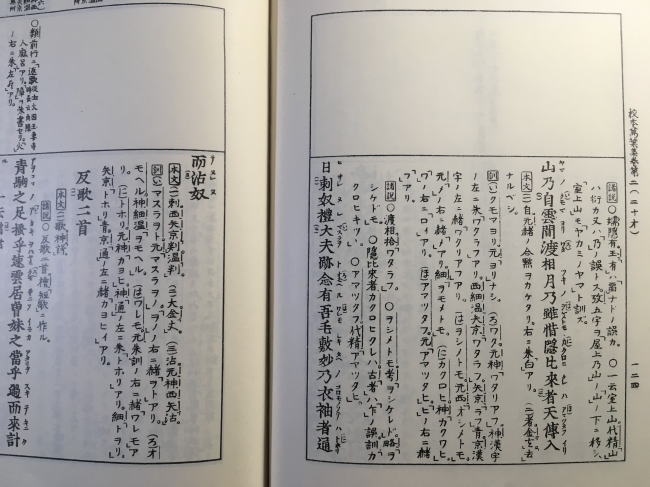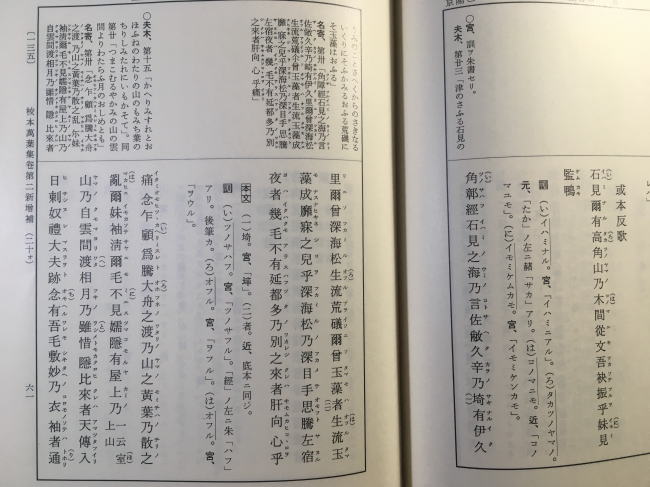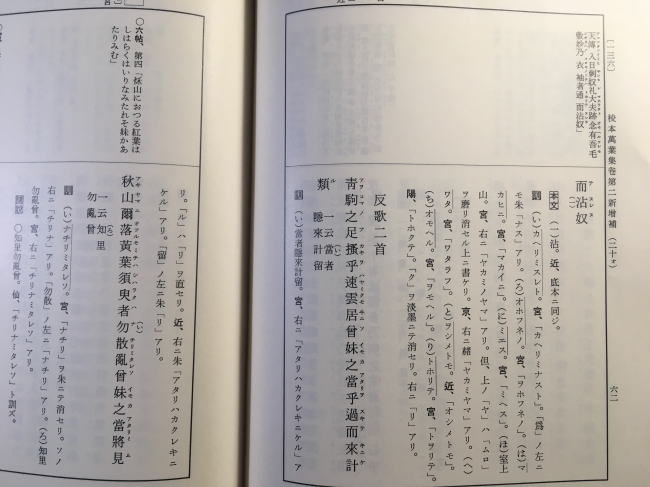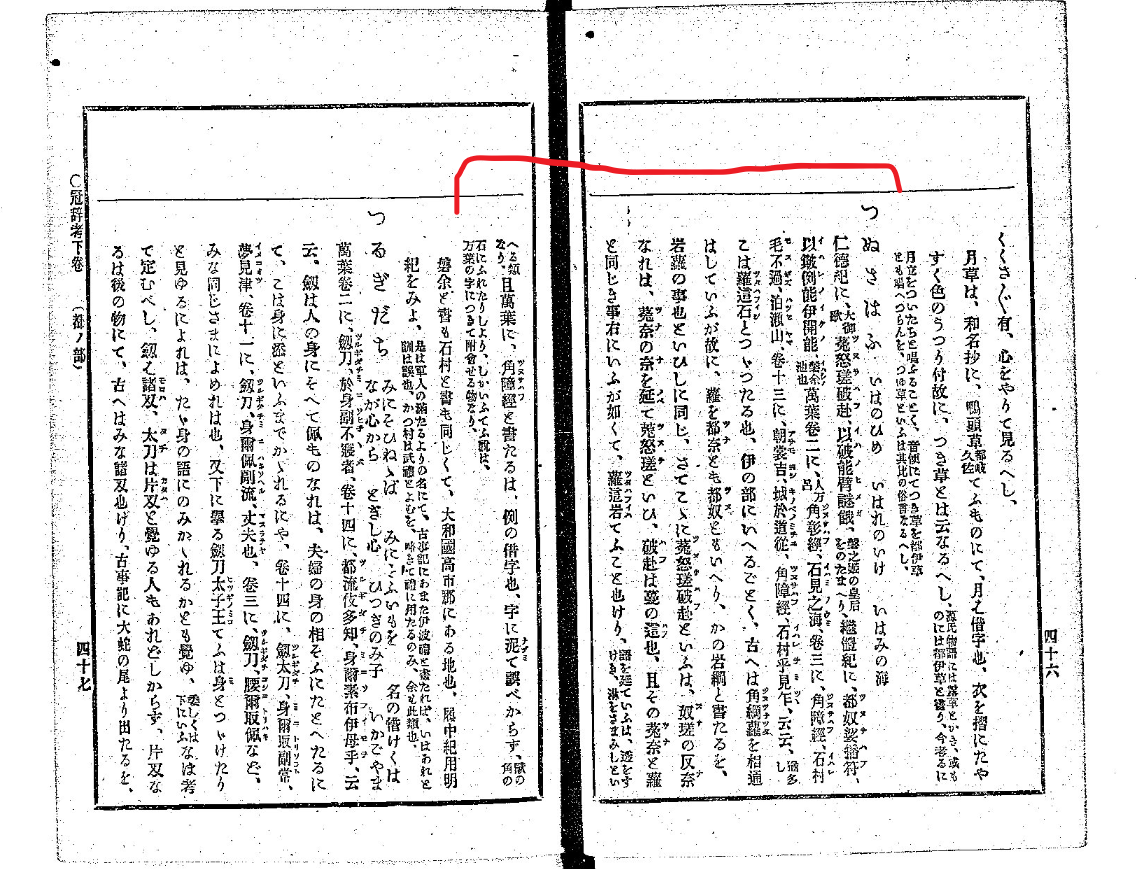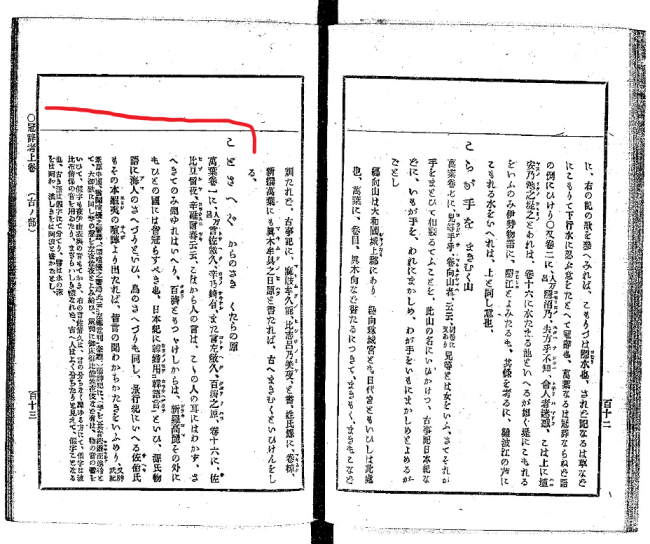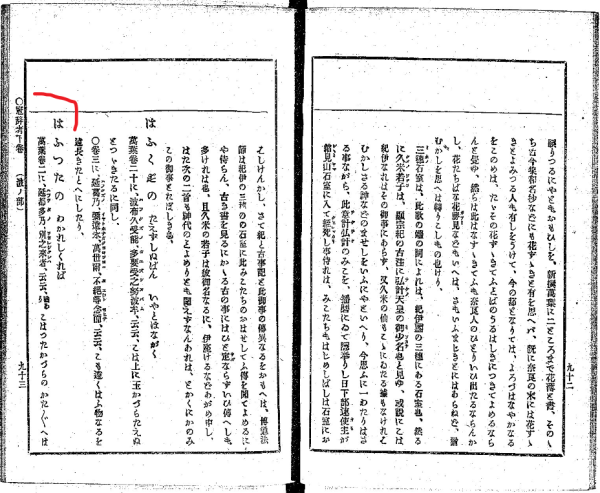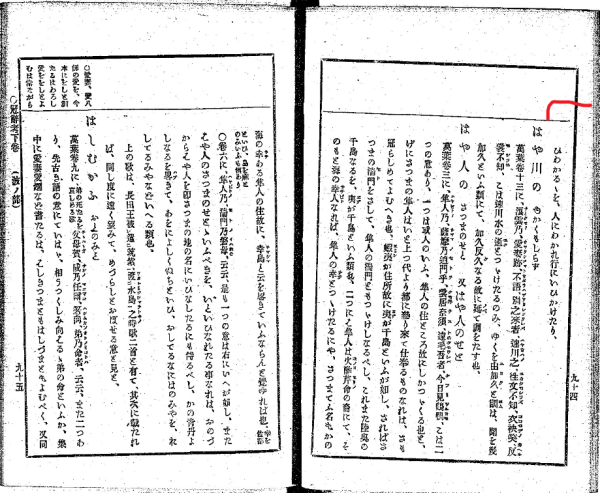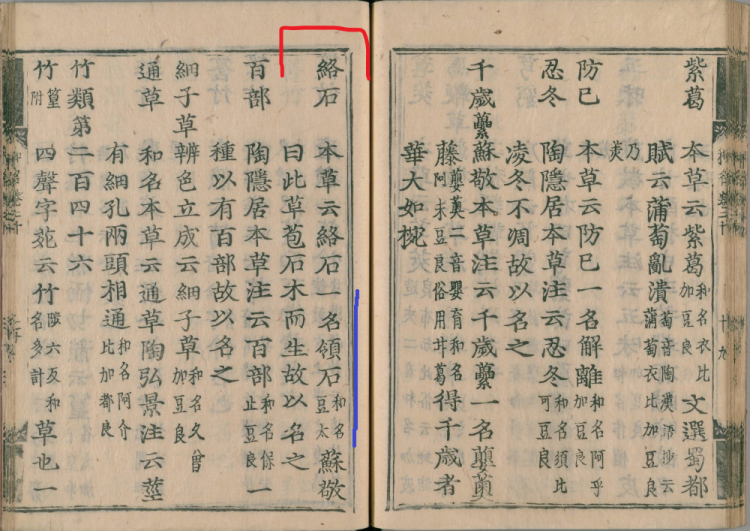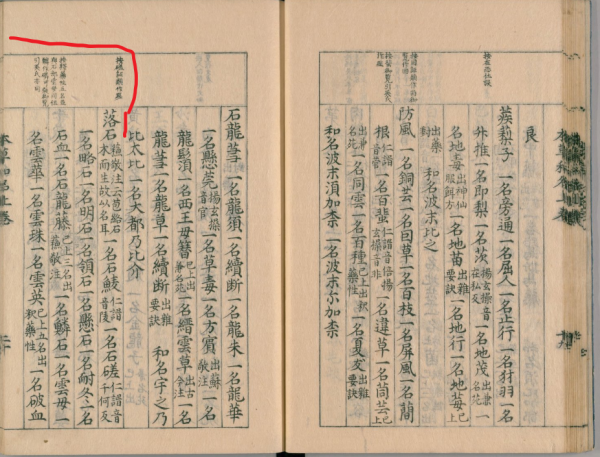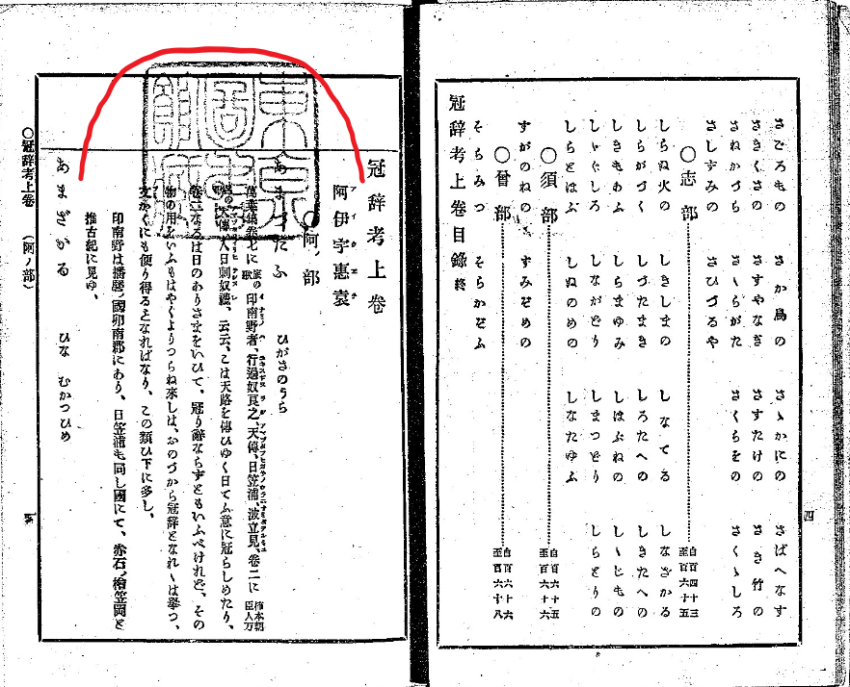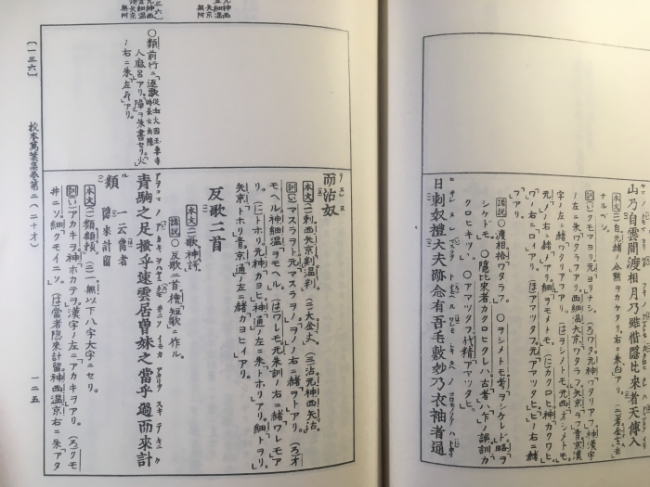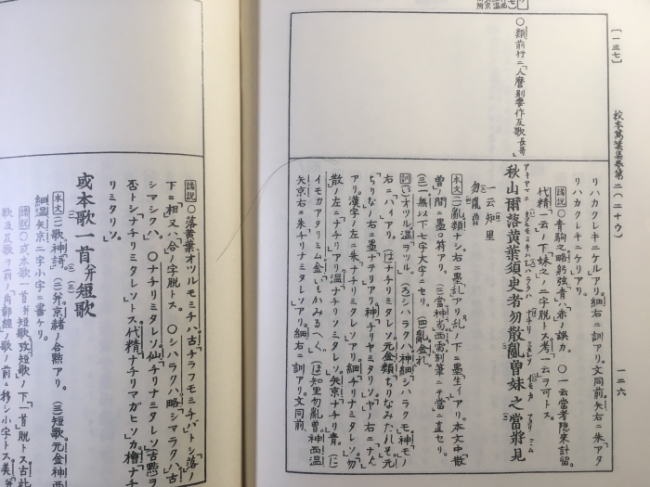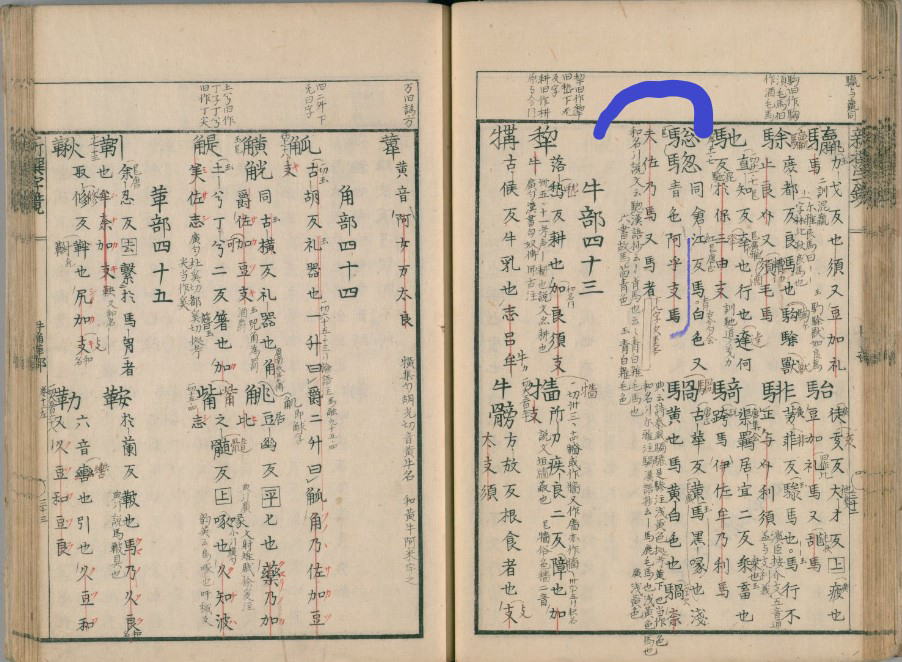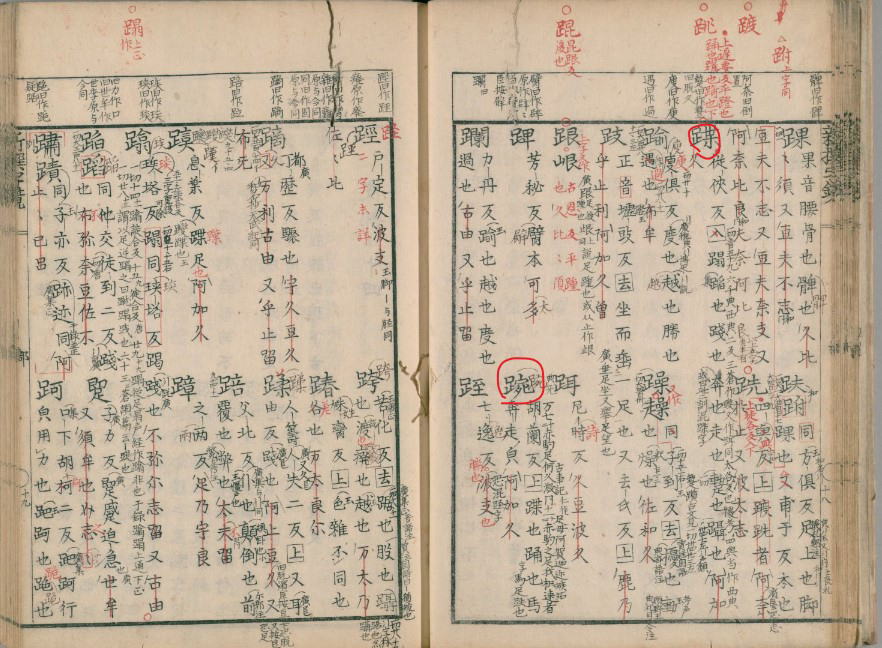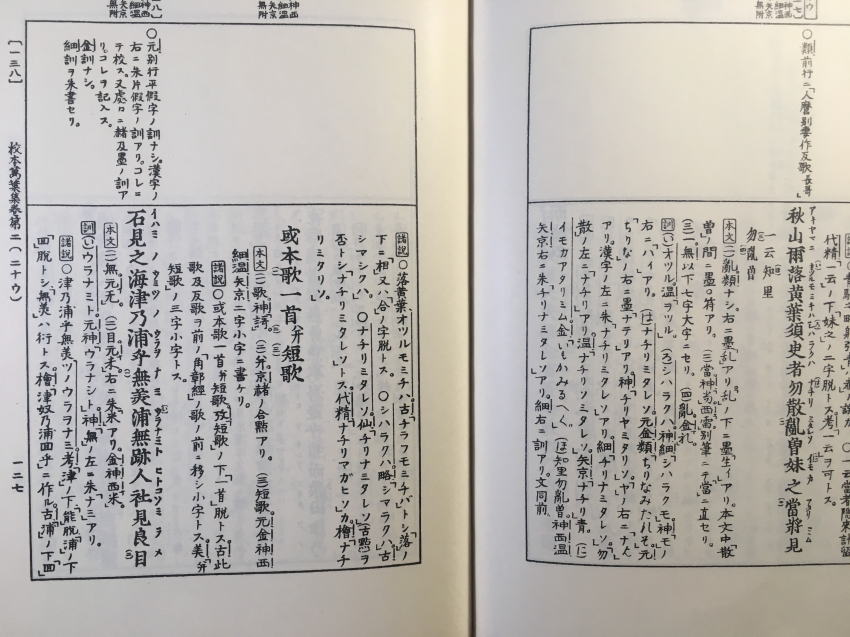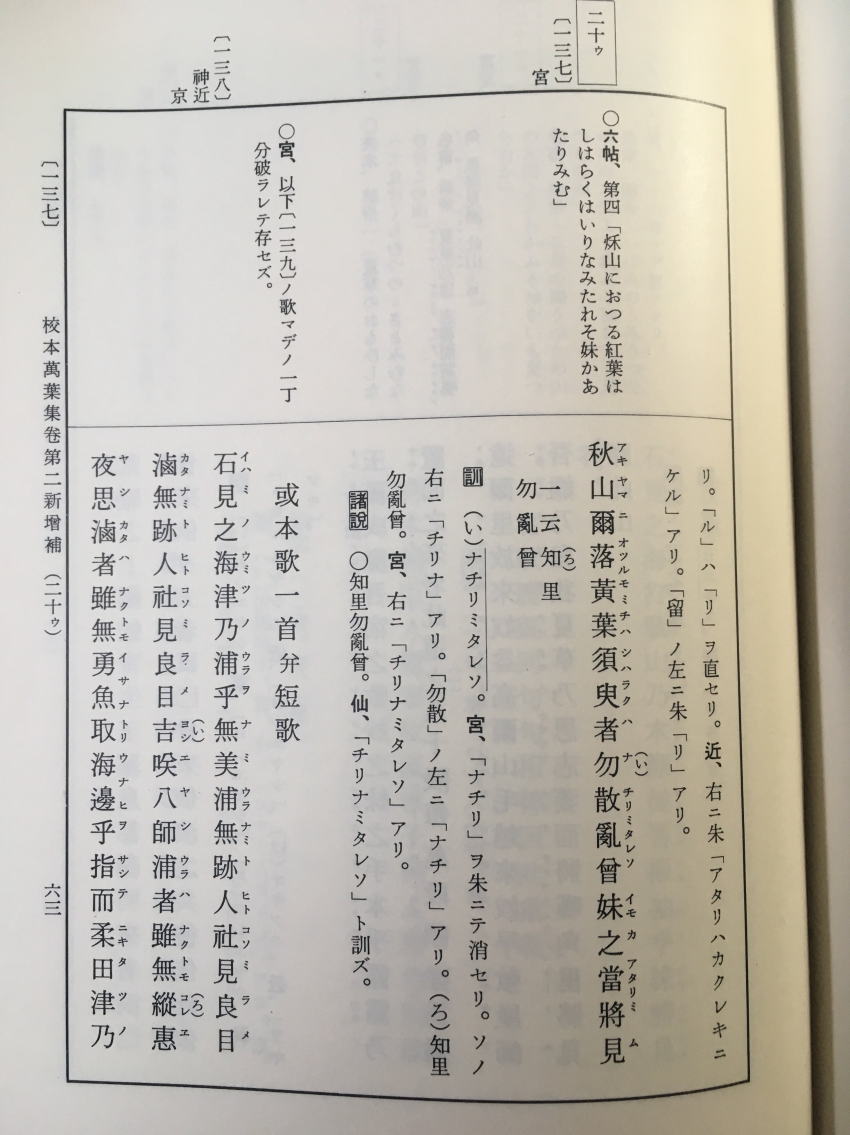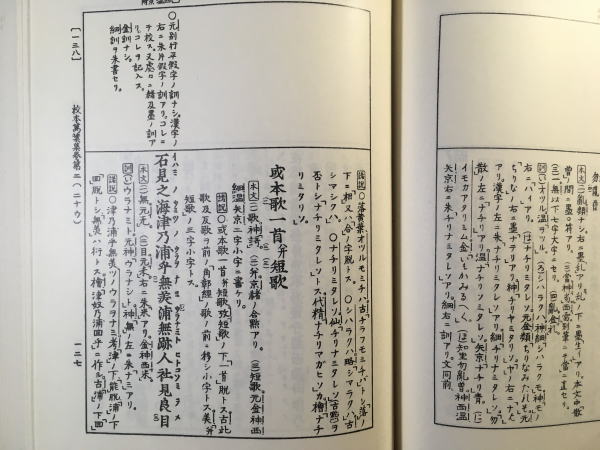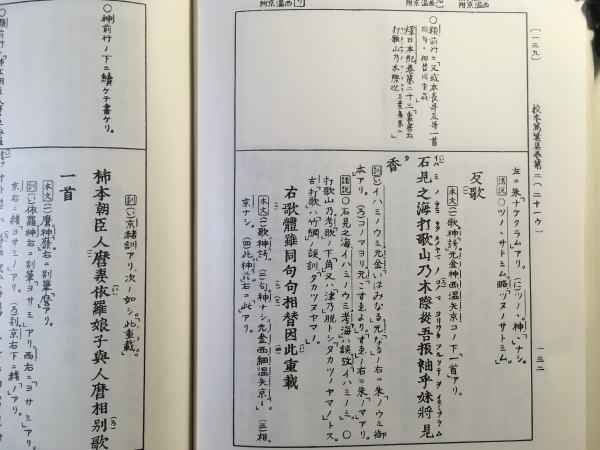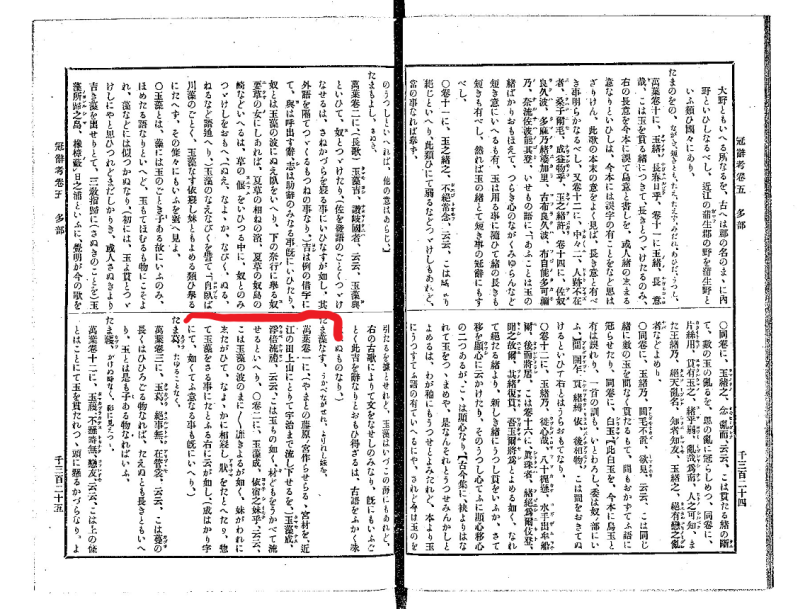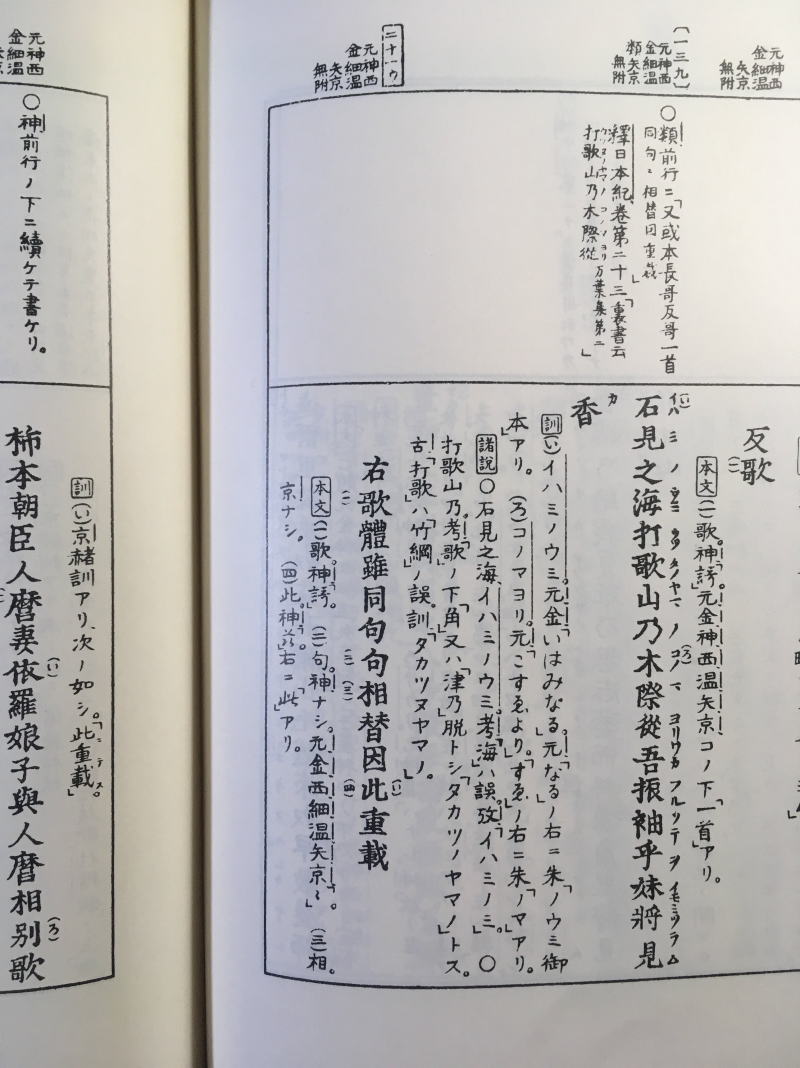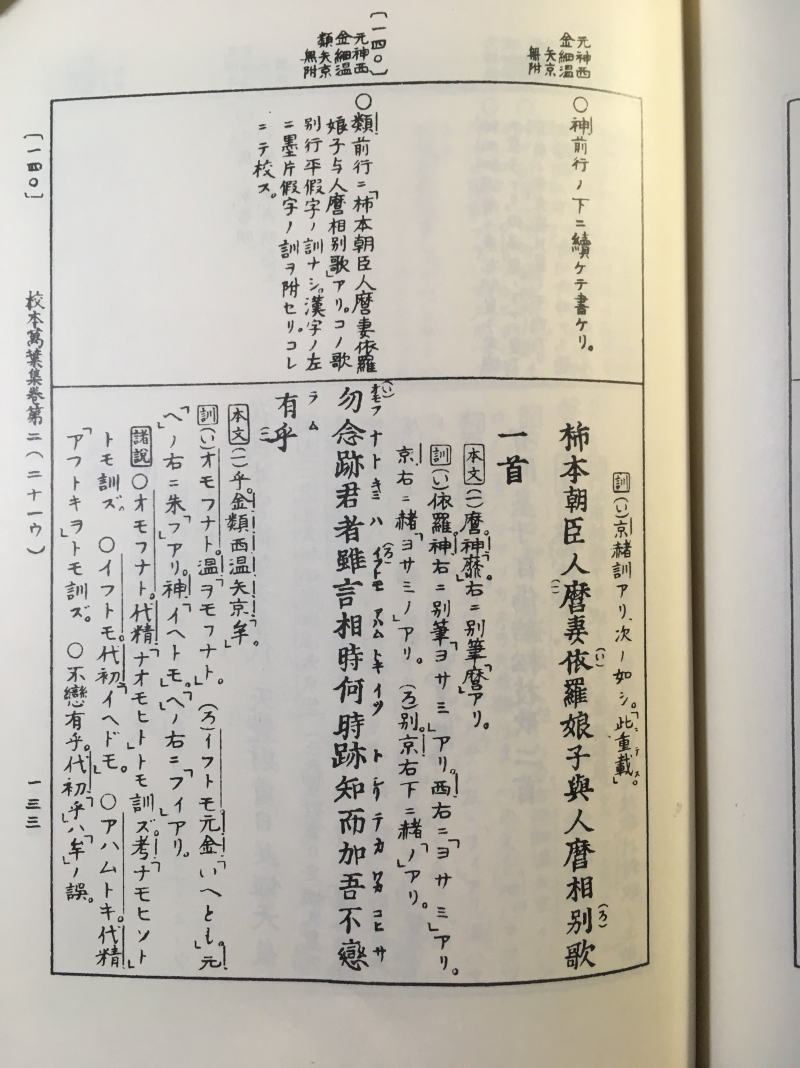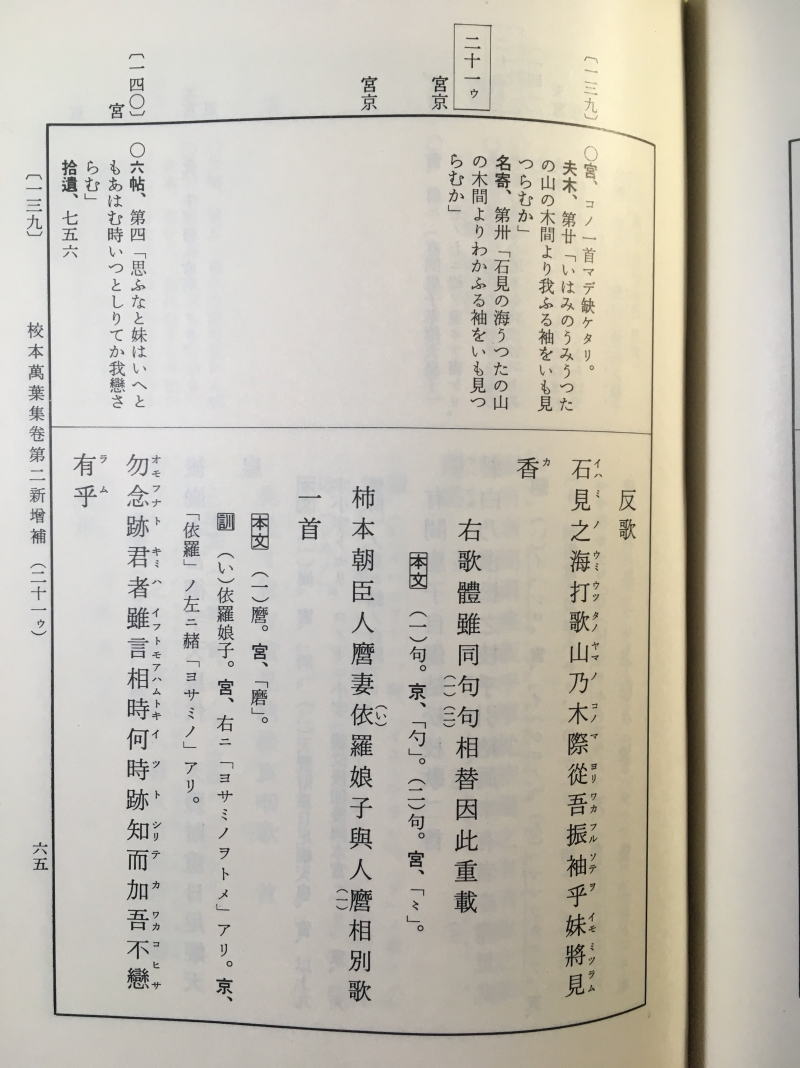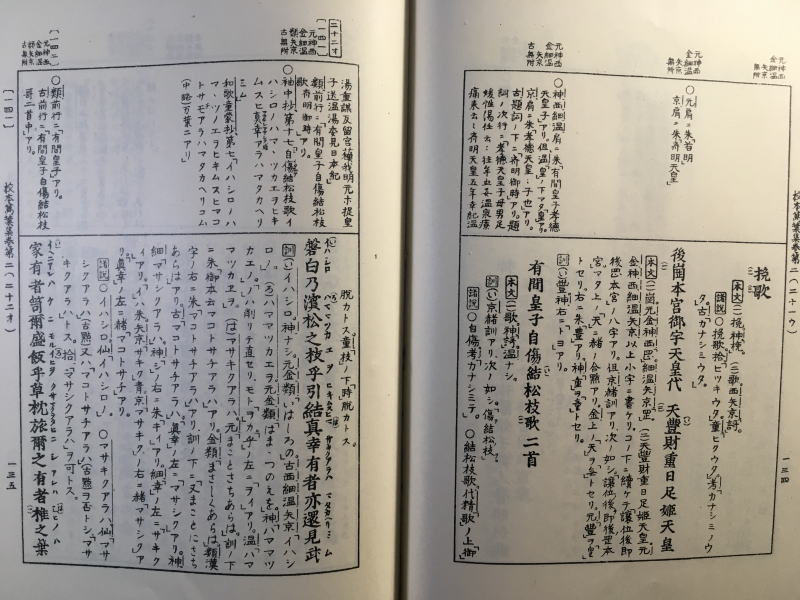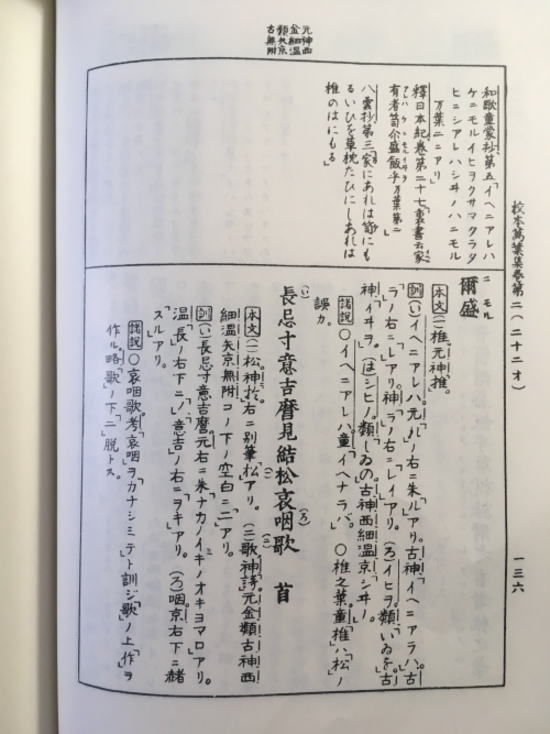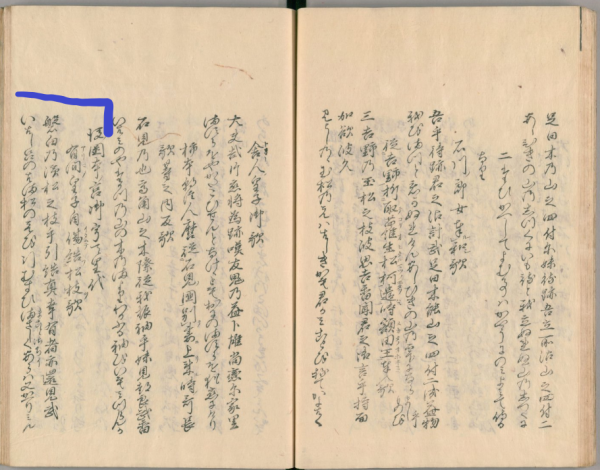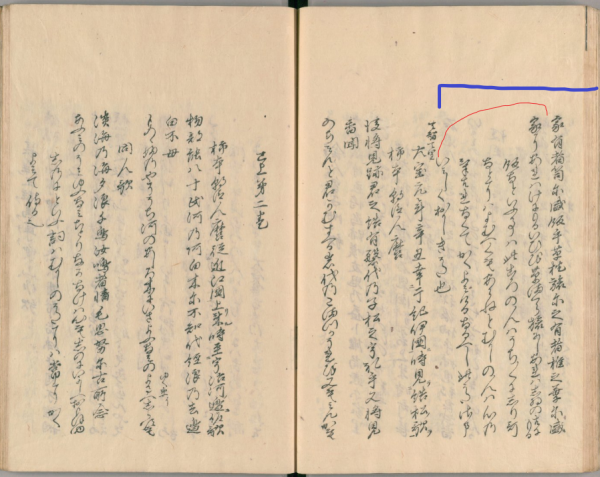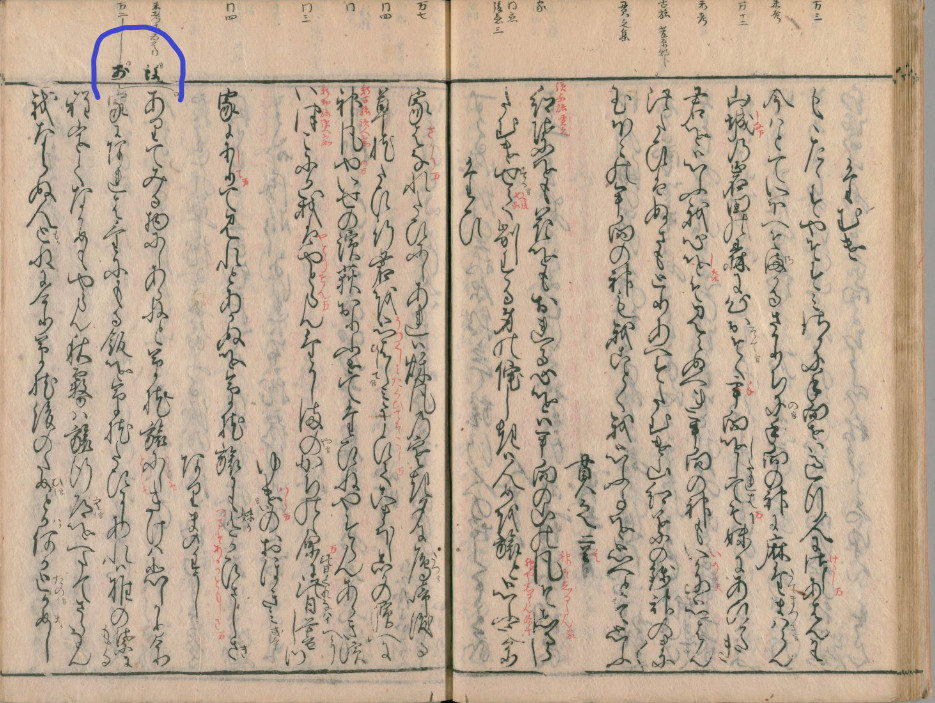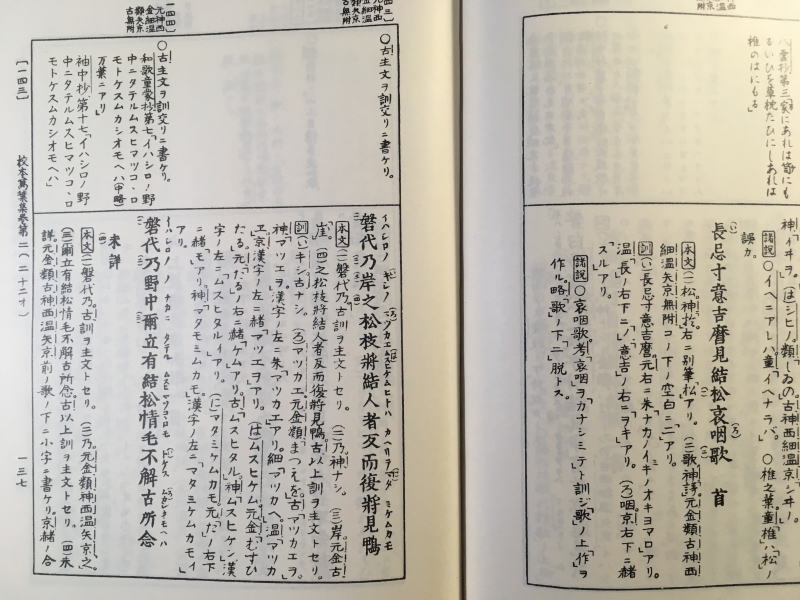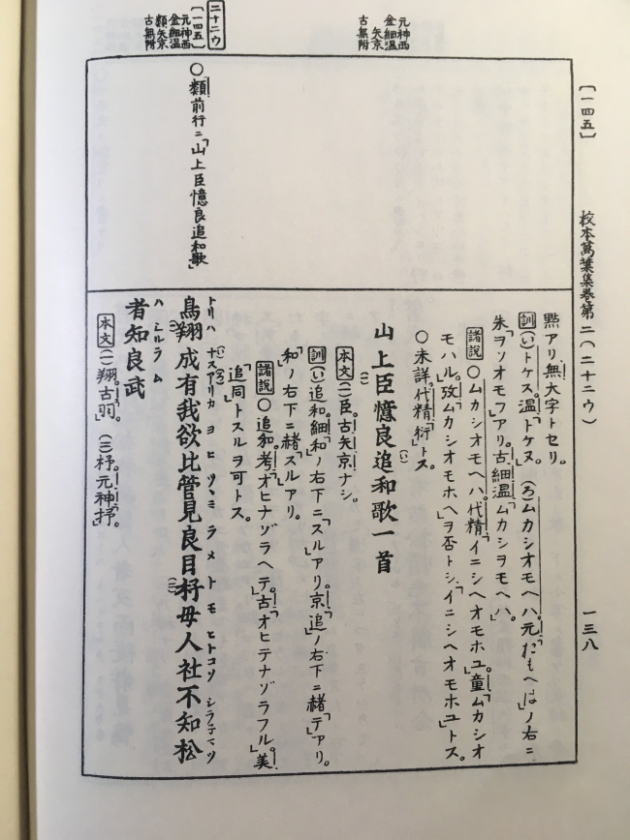| 歌番号 | 語句 | 諸注 | 諸注引用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巻二 135 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版] (1980年9月)も併記する <私注:長歌の場合、掲載が一句の途中で切れている> 〔頭書〕 元暦校本、右ノ行間上方ニ赭「長哥」アリ。別行平仮名字ノ訓ナシ。漢字ノ右ニ朱片仮字ノ訓アリ。コレニテ校ス。 處々ニ赭及墨ノ訓アリ。コレヲ記入ス。 金澤本、訓ヲ附セズ。 細井本、訓ヲ朱書セリ。 袖中抄、第四「又(顕昭)云 角障経石見之海(ツノサフル イハミノウミ)ノ」。 釈日本紀、巻第二十四「裏書云 辛乃埼有伊久里尓曽深海松生(カラノサキナルイクリニソフカミルヲフル)万葉第二」。 【本文】 角鄣經 石見之海乃 言佐敝久 辛乃埼有 伊久 (ツノサハフ イハミノウミノ コトサヘク カラノサキナル イク) 〔本文〕 鄣。元暦校本・金澤本・神田本、「障」。温故堂本・京都大学本、「部」。 敝。元暦校本・神田本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「敞」。 辛。元暦校本、「夆」 埼。神田本、「□[下写真参照]」。西本願寺本、「□[土偏に亠、下に羊]」。細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「□[土偏に辛]」。 〔訓〕 ツノサハフ。元暦校本・神田本・細井本、「ツノサフル」。神田本、漢字ノ左ニ朱「ツノサハフ」アリ。温故堂本、「ハフ」ナシ。 大矢本・京都大学本、「ハフ」青。京都大学本、漢字ノ左ニ赭「スミサハフ」アリ。 コトサヘク。元暦校本、「コトサハク」。神田本、「コトサキク」。「キ」ノ右「ヘイ」アリ。大矢本、「敞」ノ左ニ「ハ」アリ。 サキナル。神田本、「サキアル」。「ア」ノ右ニ「ナイ」アリ。 イクリニソ。元暦校本、「ク」ノ右ニ赭「ソ」アリ。 〔諸説〕 角鄣経、ツノサハフ。拾穂抄、「ツノサフル」又ハ「ツノサフ」トス。代匠記初稿本、「スミサハフ」ヲ否トシ「ツノサハフ」トス。万葉考、「ツヌサハフ」。 攷證、「鄣」ハ「障」ノ誤。訓、「ツヌサハフ」。
【本文】里爾曽 深海松生流 荒礒爾曽 玉藻者生流 玉 (リニソ フカミルオフル アライソニソ タマモハオフル タマ) 〔本文〕 曽(荒礒爾曽)。細井本、ナシ。但、右ニ書ケリ。本文中「爾玉」ノ間ニ「〇」符アリ。 者。大矢本、コノ下「生」アリ。但、消セリ。 〔訓〕 オフル。神田本・細井本・温故堂本、「ヲフル」。 アライソニソ。京都大学本、漢字ノ左ニ赭「アラソニソ」アリ。 オフル。神田本・細井本・温故堂本、「ヲフル」。 〔諸説〕 アライソニ。代匠記精撰本、「アリソニ」トモ訓ズ。 【本文】藻成 靡寐之兒乎 深海松乃 深目手思騰 左宿 ( モナスヒキ子シコヲ フカミルノ フカメテオモフト サヌル) 〔訓〕 ナス。元暦校本・神田本、「ナル」。神田本、「ル」ノ右ニ「スイ」アリ。 ナヒキ子シコヲ。元暦校本、「キ子シコヲ」ノ右ニ赭「キイシコノ」アリ。 フカメテ。元暦校本、「テ」ノ右ニ赭「ヲ」アリ。 オモフト。神田本・細井本・温故堂本、「ヲモフト」。神田本、「フ」ノ右ニ「ヘイ」アリ。京都大学本、漢字ノ左ニ赭「オモヘト」アリ。 〔諸説〕 フカメテオモフト。万葉考、「フカメテモヘド」。 ナヌルヨハ。古義、「サ子シヨハ」。 【本文】 夜者 幾毛不有 延都多乃 別之来者 肝向 心乎 (ヨハ イクハクモアラス ハフツタノ ワカレシクレハ キモムカヒ ココロヲ) 〔本文〕 幾。細井本、「□[下写真参照]」。 延。神田本、ナシ。伹、右ニ書ケリ。本文中「有都」ノ間ニ「〇」符アリ。 多。京都大学本、ナシ。左ニ書ケリ。本文中「都乃」ノ間ニ〇符アリ。 〔訓〕 イクハクモアラス。元暦校本、朱訓ノ右ニ赭、「イクハクモアラス」アリ。神田本、「イクラモアラス」。「ラモ」ノ右ニ「ハクイ」アリ。 西本願寺本、「コヽヲモアラス」。伹、「コヽヲ」ハ別筆ナリ。モト青「コヽタ」ナラン。 京都大学本、「イクハクモ」ヲ赭ニテ左ニ移スベキ記号ヲ附セリ。 ツタ。元暦校本、朱訓ノ右ニ赭「ツタ」アリ。 〔諸説〕 イクハクモアラス。玉小琴、「イクラモ」。万葉考、「イクダモアラズ」。 肝向、キモムカヒ。管見、「キモムカフ」。童蒙抄「肝」ノ上ニ「村」ヲ脱、「向」ハ「乃」ノ誤ニテ訓「ムラキモノ」カ。又ハ「肝」ハ「物」ノ誤カ。
【本文】 痛 念乍 顧為騰 大舟之 渡乃山之 黄葉乃 散之(イタミオモヒツヽカヘリミスレト オホフ子ノワタリノヤマノモミチハノ チリノ) 〔本文〕 騰。神田本、左ニ「□[上写真参照]」アリ。 乃。神田本、ナシ。右ニ書ケリ。本文中「葉散」ノ間ニ〇符アリ。 〔訓〕 オモヒツヽ。元暦校本、朱訓ノ右ニ赭「オモヒツ」アリ。神田本・細井本・温故堂本、「ヲモヒツゝ」。 カヘリミスレト。元暦校本、「リミスレト」ノ右ニ赭「リミ□ス」アリ。「ミ」「ス」ノ間不明。 神田本・細井本、「カヘリミスルト」。神田本、「ル」ノ右ニ「レイ」アリ。細井本、「為」ノ左ニ朱「ナス」アリ。 オホフ子ノ。細井本・温故堂本、「ヲホフ子ノ」。 チリノマカヒニ。元暦校本・神田本、「チリシミタレニ」。元暦校本、「之」ノ左ニ墨「ノ」アリ。 神田本、「之乱」ノ左ニ朱「ノマカヒ」アリ。細井本、「チリノマカヒニ」。 温故堂本、「チリノミタレニ」。 大矢本・京都大学本、「マカヒ」青。京都大学本、漢字ノ左ニ赭「チリシミタレ」アリ。 〔諸説〕 チリノマカヒニ。童蒙抄、「チリシミダレニ」ヲ否トス。古義、「チリノミダリニ」。 〔頭書〕 釈日本紀、巻第二十四、「裏書云清尓毛(サヤニモ)不見 万葉第一」 【本文】 亂爾 妹袖 清爾毛不見 嬬隠有 屋上乃 [一云 室上山] (マカヒニ イモカソテ サヤニモミエス ツマコモル ヤカミノ) 〔本文〕 嬬。元暦校本・神田本、「儒」。金澤本、ナシ。 〔訓〕 ミエス。元暦校本、朱訓ノ右ニ赭「ミエス」アリ。細井本、「ミヘス」。温故堂本、「ミヱス」。 ツマコモル。元暦校本、「ツマカクレナル」。「ナル」ノ右ニ赭「□[下写真参照]」アリ。字體明ナラズ。 神田本、「ヘカクレナル」。漢字ノ左ニ朱「ツマコモル」アリ。温故堂本、「ツマコムル」。漢字ノ左ニ「ツマカクシ」アリ。 大矢本・京都大学本、「ツマコモル」青。京都大学本、訓ノ右ニ赭「ツマカラス」アリ。漢字ノ左ニ赭「カクレナル」アリ。 室上。細井本、右ニ朱「ヤカミ」アリ。京都大学本、「室上山」ノ右ニ朱「ヤカミヤマ」アリ。 〔諸説〕 嬬隠有。玉小琴、「有」ハ「□[下写真参照]」ナドノ誤カ。 一云室上山。代匠記精撰本、「山」ハ衍カ又ハ「乃」ノ誤トス。攷證、五字ヲ「屋上乃山」ノ下ニ移シ、「室上山」モ「ヤカミノヤマ」ト訓ズ。
【本文】山乃 自雲間渡相月乃 雖惜 隠比来者 天傳 入 (ヤマノ クモマヨリ ワタツキノ ヲシメトモ カクロヒクレハ アマツタフ イリ) 〔本文〕 自。元暦校本、赭ノ合点ヲカケタリ。右ニ朱「白」アリ。 者。金澤本、「□[上写真参照]」。「去」ナルベシ。 〔訓〕 コモマヨリ。元暦校本、「ヨリ」ナシ。 ワタ。元暦校本・神田本、「ワタリアフ」。神田本、漢字ノ左ニ朱「ワタラフ」アリ。 西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「ワタラフ」。大矢本・京都大学本、「ラフ」青。京都大学本、漢字ノ左ニ赭「ワタリアフ」アリ。 ヲシメトモ。元暦校本・西本願寺本、「オシメトモ」。元暦校本、「メ」ノ右ニ赭「メ」アリ。細井本、「ヲモメトモ」。 カクロヒ。神田本、「カクワヒ」。「ワ」ノ右ニ「ロイ」アリ。 アマツタフ。元暦校本、「アマツタヒ」。「ヒ」ノ右ニ赭「フ」アリ。 〔諸説〕 渡相。拾穂抄、「ワタラフ」。 ヲシメトモ。万葉考、「ヲシケレド」。略解、「ヲシケドモ」。 隠比来者、カクロヒクレハ。古義、「者」ハ「乍」ノ誤。訓、「カクロヒキツゝ」。 アマツタフ。代匠記精撰本、「アマツタヒ」。 【本文】日刺奴礼 大夫跡 念有吾毛 敷妙乃 衣袖者 通而沾奴 (ヒサシヌレ マスラヲト オモヘルワレモ シキタヘノ コロモノソテハ トホリテヌレヌ) 〔本文〕 刺。西本願寺本・大矢本・京都大学本、「□[上写真参照]」。温故堂本、「判」。 大。金澤本、「丈」。 沾。元暦校本・神田本・西本願寺本・大矢本、「沽」。 〔訓〕 マスラヲト。元暦校本、「マスラヲノ」。「ヲノ」ノ右ニ赭「ヲト」アリ。 オモヘル。神田本・細井本・温故堂本、「ヲモヘル」。 ワレモ。元暦校本、朱訓ノ右ニ赭「ワレモ」アリ。 トホリ。元暦校本・神田本、「カヨヒ」。神田本、「通」ノ左ニ朱「トホリ」アリ。細井本、「トヲリ」。 大矢本・京都大学本、「トホリ」青。京都大学本、「通」ノ左ニ赭「カヨヒイ」アリ。 [校本萬葉集新増補版] 〔頭書〕 神宮文庫本、訓ヲ朱書セリ。 夫木抄、第廿三「津のさふる石見のうみのことさへくからのさきなるいくりにそふかみるおふる荒磯にそ玉藻はおふる」 名寄、第卅「角障經 石見之海乃 言佐敝久 辛乃埼有 伊久里尓曽 深海松生流 荒礒尓曽 玉藻者生流 玉藻成 靡寐之兒乎 深海松乃 深目手思騰 左宿夜者 幾毛不有 延都多乃 別之来者 肝向 心乎痛」 (ツノサフル イハミノウミノ コトサヘク カラノサキナル イクリニソ フカミルオフル アライソニソ タマモハオフル タマモナス ナヒキネシコヲ フカミルノ フカメテオモフト サヌルヨハ イクハクモアラス ハフツタノ ワカレシクレハ キモムカフ コヽロヲイタミ) 【本文】 角鄣經 石見之海乃 言佐敝久 辛乃埼有 伊久里尓曽 深海松生流 荒礒尓曽 玉藻者生流 玉藻成 靡寐之兒乎 深海松乃 深目手思騰 左宿夜者 幾毛不有 延都多乃 別之来者 肝向 心乎 (ツノサハフ イハミノウミノ コトサヘク カラノサキナル イクリニソ フカミルオフル アライソニソ タマモハオフル タマモナス ナヒキネシコヲ フカミルノ フカメテオモフト サヌルヨハ イクハクモアラス ハフツタノ ワカレシクレハ キモクカヒ コヽロヲ) 〔本文〕 埼。神宮文庫本、「□[土偏に辛]」。 者。近衛本、底本ニ同ジ。 〔訓〕 ツノサハフ。神宮文庫本、「ツノサフル」。「経」ノ左ニ朱「ハフ」アリ。後筆カ。 オフル。神宮文庫本、「ヲフル」。 (玉藻者生流の)オフル。神宮文庫本、「ヲウル」。 〔頭書〕 夫木抄、第十五「かへりみすれとおほふねのわたりの山のもみち葉のちりしみたれにいもかそて」。 同、第廿「つまこむるやかみの山の雲間よりわたらふ月のおしめとも」 名寄、第卅「念乍 顧為騰 大舟之 渡乃山之 黄葉乃 散之乱尓 妹袖 清爾毛不見 嬬隠有 屋上乃山乃 自雲間 渡相月乃 雖惜 隠比来者 天傳 入日刺奴礼 大夫跡 念有吾毛 敷妙乃 衣袖者 通而沾奴」 (オモヒツヽ カヘリミスレトニ オホフネノ ワタリノヤマノ モミチハノ チリノマカヒニ イモカソテ サヤニモミエス ツマコモル ヤカミノヤマノ コモマヨリ ワタラフツキノ オシメトモ カクロヒクレハ アマツタフ イリヒサシヌレ マスラヲト オモヘルワレモ シキタヘノ コロモノソテハ トホリテヌレヌ) 【本文】 痛 念乍 顧為騰 大舟之 渡乃山之 黄葉乃 散之亂爾 妹袖 清爾毛不見 嬬隠有 屋上乃 [一云 室上山] 山乃 自雲間 渡相月乃 雖惜 隠比来者 天傳 入日刺奴礼 大夫跡 念有吾毛 敷妙乃 衣袖者 通而沾奴 (イタミ オモヒツヽ カヘリミスレト オホフネノ ワタリノヤマノ モミチハノ チリノマカヒニ イモカソテ サヤニモミエス ツマコモル ヤカミノ [一云室上山] ヤマノ クモマヨリ ワタツキノ ヲシメトモ カクロヒクレハ アマツタフ イリヒサシヌレ マスラヲト オモヘルワレモ シキタヘノ コロモノソテハ トホリテヌレヌ) 〔本文〕 沾。近衛本、底本ニ同ジ。 〔訓〕 カヘリミスレト。神宮文庫本、「カヘリミナスト」。「為」ノ左ニモ朱「ナス」アリ。 オホフネノ。神宮文庫本、「ヲホフネノ」。 マカヒニ。神宮文庫本、「マカイニ」。 ミエス。神宮文庫本、「ミヘス」。 室上山。神宮文庫本、右ニ「ヤカミノヤマ」アリ。但、上ノ「ヤ」ハ「ムロ」を磨リ消セル上ニ書ケリ。京都大学本、右ニ赭「ヤカミヤマ」アリ。 ワタ。神宮文庫本、「ワタラフ」。 ヲシメトモ。近衛本、「オシメトモ」。 オモヘル。神宮文庫本、「ヲモヘル」。 トホリテ。神宮文庫本、「トヨリテ」。陽明本、「トホクテ」。「ク」を淡墨ニテ消セリ。右ニ「リ」アリ。
|
|||||||||
| 枕詞「つのさはふ」考 | 仙覚抄 | 角鄣經 [ツノサハフ]、石見之海乃 [イワミノウミノ]、言佐散久 [コトサヘク]、辛乃埼有 [カラノサキナル]、伊久里尓曾 [イクリニソ]云々。 ツノサハフトハ、ツノオホカルトイフ也。日本記ニハ、多ノ字ヲ、サハトヨム。ツノオホカリ、イハトツヽケムタメナリ。 |
||||||||||
| 拾穂抄 | つのさふる 類聚袖中抄等の点也日本紀十七ニ都奴沙府以波例能 [ツノサフイハレノ] とあるに随ふにや仙は日本紀十一ニ菟怒差破赴 [ツノサハフ] とあるに任てつのさはふと改む日本紀も兩様なれは兩点共に用へし釋ニ云角障 [ツノサウル] 也牛角堤を破るに岩のさはりし古事岩の枕詞と云々正説歟袖中には角と云所のみえぬ心と云仙抄は角多 [ヲヽキ] と注す由阿は□[羊+霊] 羊の角をふる儀と注皆如何。 | |||||||||||
| 代匠記 | 角鄣經石見之海乃言佐敝久辛乃埼有伊久里・・・ ツノサハフは石の枕詞、別に注す、 |
|||||||||||
| 童蒙抄 | 角障經石見之海乃 童子問 仙覺抄云、つのさはふとは、つのなほかるといふなり。日本紀には多の字をさはとよむ、おほかるいはとつゝけんため也とあり。岩には角の多きといはむもその理り有へきか。如何。 答 石には丸きも有、方も有て必しも角おほしといふへからす。僻案の義有。是も日本紀の歌の童子問に答へたれは、此集にてはいはす。万葉集は末なり、日本紀は本地。本に明らかなれは末おのつからまとはす。後世の學者皆本をしらすして、末を論する故に本にたかへは事明らかならす。よりて万葉集を明らかにせんには、古事紀日本紀の歌を明かにして、後万葉集にわたるへし。万葉集明らめて後、古今集を見れは疑なきを、後人は古今集を傳授を得されは、歌學の本明かならさるやうに心得て、万葉集をもみす。况や日本紀古事紀の歌には目をわたす事もなきをや。よりて万葉集の難義とする冠辭等、日本紀古事紀等にみたるは此集の問に答へす。日本紀古事紀等の童子問に答訖ぬ。 |
|||||||||||
| 万葉考 | 角障經 [ツヌサハフ]、 冠辭、 | |||||||||||
| 攷證 | 角障經 [ツヌサハフ]。 枕詞にて、冠辭考にくはし。角障經 [ツヌサハフ] とかけるは、借字にて、つぬ、つな、つたとかよふ故、蘿這石 [ツタハフイハ] とつゞけし也。さて、障の字、印本鄣に作れり。字書を考ふる 〔マヽ〕[障鄣]通ずる事なし。誤りなる事明らかなれば、本集三『廿一丁四十六丁』、十三『廿八丁廿九丁』などの例に依てあらたむ。
|
|||||||||||
| 古義 | 角鄣證 [ツヌサハフ] 角鄣經 [ツヌサハフ] は、石 [イハ] といはむ料の枕詞なり、書紀仁徳天皇繼體天皇ノ卷ノ歌、此ノ集三ノ卷十三ノ卷、其餘にも猶あり、皆石 [イハ] とつゞきたり、(冠辭考に、つたはふ石とつゞきたるなり、さて奴佐 [ヌサ] の反奈 [ナ] なれば、都奈 [ツナ] を延て、都奴佐 [ツヌサ] といひ、波布 [ハフ] は蔓の這なりと云り、されどつたを、つぬさといへりとは、おもはれず、) 荒木田氏が、絡石多蔓 [ツヌサハフ] と云るなるべし、と云るぞよろしかるべき、古ヘ格石 [ツタ] を、つなとも、つぬとも云たればなり、六ノ卷に、石綱 [イハツナ] とあるは契冲が石絡石 [イハツタ] なり、と云るを思ヒ合スべし、佐波波布 [サハハフ] は、佐波布 [サハフ] と切 [ツヾマ] れり、 |
|||||||||||
| 全釈 | 角鄣經 [ツヌサハフ] ―― 蔦多蔓 [ツヌサハフ] の意で、蔦かづらの類の、多く這ひまつはる石とづづく枕詞である。この他にこの語の解は多いが、採るべきものがない。この句から玉藻成までは靡くと言はむ爲の序詞。 | |||||||||||
| 全註釈 | 【釈】「角障經」(ツノサハフ) 角障經 ツノサハフ。枕詞。石に冠する。日本書紀に、「菟恕瑳破赴 [ツノサハフ] 以破能臂謎餓 [イハノヒメガ]」(五八、仁德天皇紀)、「都奴婆播符 [ツヌサハフ] 以簸例能伊開能 [イハレノイケノ]」(九七、繼體天皇紀) などあり、古い枕詞であることが知られる。語義は、冠辭考に、ツヌサはツナで、ツタの這うであるといい、荒木田久老はツヌはツタで、サハフはサハハフの約言であると云つている。しかしツヌサの語は無く、またサハハフの説も首肯されない。この枕詞は、集中五出しているが、いずれも角障經の文字を使用しており、他に明解が無いとせば、この字面は相當考慮されて然るべきである。すなわちツノは角であり、突出部を意味するものなるべく、サハフは、障ハフで、障フの連續狀態をあらわすものと解される。角が障害になる義で、石を修飾説明する枕詞になつているのであろう。 |
|||||||||||
| 評釈 | つのさはふ 石 [いは] の枕詞「いはれ」 にかけた例も卷三に見える。その語義については或は「つのさ」は「つな」 の延音で、「はふ」は蔓のはふ意 (考)、或はつたの多くはふ意 (槻落葉)、或は角 [つの] は物のかど、さはふは動詞さふの連續状態を表はす語で邪魔になるの意、即ち角角が邪魔になる意で石につづく (新解) 等諸説あつて一致しないが、「つの」 はつたの意とし、「さ」 は接頭辭、即ち、つたのはひまつはる石の意といふ説 (講義) が比較的穩かである。しかしこれもつのをつたとする點、なほ證に乏しい憾がある。 | |||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「角障經」(つのさはふ) 石にかかる枕詞。「菟恕瑳破赴 [ツノサハフ] 以破能臂謎餓 [イハノヒメガ]」 (仁徳紀)、「都奴婆播符 [ツヌサハフ] 以簸例能伊開能 [イハレノイケノ]」 (継体紀) などの古い例がある。冠辞考に「蘿這石 (ツタハフイハ)」 の義とし、「古へは角綱蘿 (ツヌツナツタ) を相通はしていふが故に、蘿を都奈 (ツナ) とも都怒 (ツヌ) ともいへり」と云ひ、久老は日本紀歌解槻乃落葉の「菟怒瑳破赴 (ツノサハフ)」 (仁徳紀) の條で「瑳破赴の瑳は、佐夜 (サヨ)、小男鹿 (サヲシカ) などいふ佐 (サ) にて助語とすべき歟。又は多延 (サハハフ) の約言にもやあらむ。」と云つてゐる。倭名抄 (十) に「本草云、絡石、一名領石」として「都太 (ツタ)」とある事などを考へると、右のニ家の説に従ふべきもののやうに見える。原文「角障」の角は古事記では「ヌ」の仮名であらはされ、萬葉では「ノ」の仮名であらはされた事前 (131) にも述べたが、右の書紀には「ツヌ」とも「ツノ」ともあるところを見ると「ツヌサハフ」が次第に「ツノサハフ」に轉じたものかと思はれる。「障」の字西本願寺本以後の諸本には「鄣」とあるが、金澤本その他の古写本は「障」であり、「障」の字は他にも多く、「鄣」は見えないので、通用の文字ではあるが、古写本によるべきである。「障る」の意で借訓の文字である。但、別に「あぢさはふ」 (196) といふ言葉があり、その「さはふ」と関係がありはしないかとも考へられ、そこに少し問題が残るやうにも思はれる。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】「角障經」(つのさはふ) 石見にかかる枕詞。日本書紀に「つのさはふ 磐の媛」 (仁徳紀)、「つぬさはふ 磐余」 (継体紀) の例がある。語義やかかり方は未詳。「ツノ」は日本紀歌解槻乃落葉に「ツタ」とし、「サハフ」は「サハハフ」で多く這う意との説も見られるが、全註釈に注意しているように、万葉集中の五例 (135、3・282、423、13・3324、3325) すべて「角障経」と書かれているのに意味があるかもしれない。紀歌謡のような古歌の場合は別として、人麻呂は古い枕詞に新しい解釈を施して使うことも多いので、ここの「ツノサハフ」も、その例とすれば、「角障経」という文字の通りに、角は萌え出した植物の芽、「サハフ」は「障フ」の再活用と解するのが正しいか。植物の芽の伸びるのを妨げる岩の意で、地名石見に冠したと見るのである。 |
|||||||||||
| 枕詞「ことさへく」考 | 仙覚抄 | 言佐敞久トハ、コトハノ、サヘラルヽ也。コトハノ、サタカニモキコヱヌ心也。 | ||||||||||
| 拾穂抄 | ことさへく 仙曰詞のさへらるゝ也詞のさたかにも聞えぬ也辛の崎をいはむとてをける也唐人の詞の聞知かたきによそふる也 | |||||||||||
| 代匠記 | 言サヘグは言のさはるなり、此もからの埼の枕詞なり、此には、「辛」 の字を書たれども、三韓の「韓」 の字の心になしてなり、日本紀に所々に、からの人の言を擧て、訛 [ヨコナマリ] て詳にしがたしと云ひ、敏達紀に韓婦 [カラメノコ]、用二韓語 [カラサヘツリヲ] 一、云云、此れ源氏に海人の物云をきゝ知らぬ事どもさへづりてと云ひ、孟子に、南蠻鴃 [ケキ] 舌之人など云へる心に、語をサヘヅルとは点ぜり、さればからの人の言は、こゝの人の耳にさはる心にかくはいへり、此卷の下に、ことさへぐくだらの原とあるも此心なり、 | |||||||||||
| 童蒙抄 | 童子問 仙覺抄云、言佐倣久とは言葉のさへらるゝ也。言葉のさたかにもきこえぬ心也。辛の埼は所の名なるへし。からのさきをいひ出んとて、ことさへくとは置る也。唐人のものいふ言葉のさきは、なにともきゝしりかたきによそふる也とあり。此説しかるへしや。 答 しかるへし。 |
|||||||||||
| 攷證 | 言佐敝久 [コトサヘク]。 枕詞にて、冠辭考にくはし。から人の言は、こゝの人の耳には、わかずさへぎてのみ聞ゆれば、ことさへぐ韓 [カラ] といふを、辛 [カラ] の埼とはつゞけしなり。また、ことさへぐ、百濟の原とつゞくるも意同じ。
|
|||||||||||
| 古義 | 言佐敝久 [コトサヘク] は、加羅 [カラ] の枕詞なり、此ノ下に、言左敝久百済之原從 [コトサヘククタラノハラヨ] とも見ゆ、此はすべて、異國人 [アダシクニビト] の言語 [モノイヒ] は、此方の人の耳には聞分がたく、喧響 [サヤギ] て聞ゆれば、言語 [コトバ] の喧響 [サヤ] ぐ韓 [カラ] 、また百濟 [クダラ] 、といふ意につゞけたり、十六に、佐比豆留夜辛碓爾舂 [サヒヅルヤカラウスニツキ] 、とよめるも、言語 [コトドヒ] の喧嘩 [サヒヅル] や韓 [カラ] といふにて、今と同意なり、さて左敝久 [サヘク] とは、鳥の囀 [サヘヅル] といふに同じくて、さわさわと喧響 [サヤメ] きて聞ゆるを云り、書紀に、韓婦 [カラメ] 用二韓語言 [カラサヘヅリテ] 一といひ、源氏物語赤石に、あやしき海土等 [アマドモ ]などの、高き人座する所とて、集り參りて、聞も知給はぬことゞもを、さへづりあへるも、いとめづらかなれど、得追もはらはず、玉葛に、いろあひこゝちよげに、聲いたうかれて、さへづり居たり、常夏に、御ゆるしだに侍らば、水をくみいたゞきても、つかうまつりなむ、といとよげに今少しさへづれば、浮船に、例のあらゝかなる、七八人をのこどもおほく、しなしなしからぬけはひさへづりつゝ、いりきたればなど、邊鄙人などの、ことにかしがましく、物いひさわぐさまに、多くいへり、又常陸風土記に、茨城ノ郡、古老曰、昔在二國巣 (俗語、都知久母 [ツチグモ]、又云、夜都賀波岐 [ヤツカハキ]、) 山之佐伯 [ヤマノサヘキ] 野之佐伯 [ヌノサヘキ] 一あるも、喧響 [サヤメ] く賊衆を謂りと見ゆ、又佐伯氏も、蝦夷の喧饗 [サヘキ] より出たるならむ、 | |||||||||||
| 全釈 | 言佐敝久 [コトサヘグ] ―― 韓の枕詞。言葉のさやぎ、喧しき韓人といふのである。 | |||||||||||
| 全註釈 | 言佐敝久 コトサヘク。枕詞。下に、「言左敝久 [コトサヘク] 百濟之原從 [クダラノハラユ]」(卷二、一九九) とあり、韓、百濟の枕詞となつている。コトは言語の義であり、サヘクは、從來騷ぐと同じで、言語の騷々しい意とされていた。しかしサヘクがサワクと同語であるといぅ證明は無い。むしろ、障フと關係あるものと見るべく、言語の通じない意を以つて、韓、百濟に冠するものと見るべきである。 | |||||||||||
| 評釈 | 言さへく さへくは強い意で語調に稜角のあるをいふとの新説 (新解) も出てゐるが、さへづると同じくしやべり方の騷々しい意で、外國人の言葉の意味が通ぜず、ただ喧しく聞える所から韓の枕詞となつたのであらう。 | |||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「言佐敝久」(ことさへく) 仙覚抄に「コトバノサヘラルヽ也、コトバノサダカニモキコヱヌ心也」とある。「さへく」は右にあげた「障る」、「障(さ)ふ」 (11・2380) などと同根の語であつて、田安宗武の摘要冠辞考に「ここの語はかしこに聞こえず、かしこの語はここに聞こえねばことばの間にものをへだてたることなるをもていへり」とあるやうに、日本人には唐人の言葉が通じないから、唐の枕詞とした。「サワク」とか「サヘヅル」とかと同語とするのはあたらない。「さへづる」は萬葉では「さひづる」であり、その「サヒ」○は「サヰ」 (1・42) と通じ、「サワ」とも「サワク」ともなつたので、それは別系の語である。「さひづらふ」 (7・1273)、「さひづるや」 (16・3886) 参照。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】「言佐敞久辛乃埼有」(ことさへく からのさきなる) 「コトサヘク」は「辛の埼」にかかる枕詞。原文「言佐敞久」の「敞」は、「シャウ」の音の文字であるが、奈良時代に「敝」と通用、「へ (甲)」の仮名として用いられた (古典大系本補注)。正倉院文書中の宣命草案に仮名用例を見るのであるが、両字の通用は中国に先例があるらしい (『金石異体字典』)。「コトサヘク」の「コト」は言葉。「サヘク」は仙覚抄に「コトバノサヘラルヽ也、コトバノサダカニモキコエヌ心也」と記すように、外国人のことばのはっきり聞きとりにくいこと。「カラ」 (朝鮮・中国などの外国) に冠する。「辛の埼」は、邇摩郡仁摩町宅野の海上にある韓島とする説 (古義・新講・全註釈など) や浜田市の北国府町の海岸唐鐘の浦の近くとする説 (茂吉雑纂)、江津市波子(ハシ)町の大崎鼻あたりとする説 (注釈) などがあるが、特定しうるかどうか、問題である。あえて定めずとも鑑賞には支障はない。 |
|||||||||||
| 新全集 | 【頭注】 カラ(韓)の枕詞。同じくカラにかかる枕詞に、「サヒヅルヤ」というのがあり、その「サヒヅル」は「サヘヅル」の古形、意味不明の言語を操ることを表す。この「サヘク」も「サヒヅル」と同源であろう。カラは古代朝鮮半島 (主として南部) の諸国の汎称。 |
|||||||||||
| 「からのさきなる」考 | 仙覚抄 | 辛乃埼有 [カラノサキナル] 辛乃埼ハ、所ノ名ナルヘシ。カラノサキヲ、イヒイテムトテ、コトサヘクトハヲケリ。唐人ノモノイフコトハノサキヲハ、ナニトモキヽシリカタキニヨソフル也。 |
||||||||||
| 攷證 | 辛乃崎有 [カラノサキナル]。 辛の埼、この外ものに見えず。郡しりがたし。猶たづぬべし。 |
|||||||||||
| 古義 | 辛乃崎 [カラノサキ] は、石見ノ國邇摩ノ郡|託農 [タクノ] 浦にありと國人云り、 | |||||||||||
| 全釈 | 辛乃埼有 [カラノサキナル] ―― 辛乃埼は「石見ノ國邇摩郡託農浦にありと國人云へり」と、古義に記してあるが、石見風土記に、「可良島秀二海中一、因レ之可良埼云。度半里」 とあつて、その島の對岸に當るのであらう。託農は即ち今の宅野村である。卷三の三五五の地圖參照。 | |||||||||||
| 全註釈 | 【釈】 辛乃埼有 カラノサキナル。島根縣邇摩郡宅野村の海上に辛島があり、それに對する海濱の岬角であろうという。 |
|||||||||||
| 評釈 | 【語】 韓の埼 石見風土記逸文に「可良島秀二海中一因レ之可良崎ト云フ 度リ半里」とある地で、渡津の東方十里許りの邇摩郡宅野村の海上にある辛島の出鼻をいふ(新講)。 |
|||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「辛乃埼」(からのさき) 邇摩郡仁摩町宅野の海上に韓島があり、それだとする説 (古義、新講、全註釈、その他) が最もひろく行はれてをり、豊田八十代氏の萬葉地理考には都野津の東北 (和木の海上) 「真島に対する岬崖あり、辛崎はこのあたりを指すか」とあり、齊藤茂吉氏は「辛乃埼考」 (『柿本人麿雑纂篇』) で濱田市の北国府町の海岸唐鐘 (タウガネ)の浦の「犬島、猫島、千畳敷、畳ヶ浦、赤鼻あたり一帯のうちの埼ではなからうか」とされた。宅野の韓島とするのは、齊藤氏も注意されてゐるやうに妻の住んだ里とはあまりにもかけ離れてゐて不適当である。後に出て来る渡りの山や屋上山よりも北にあり、道順から云つても逆である。これは前の津野や柔田津同様妻の里附近に求めるべきである。その点地理考の説の方がふさはしいが、これは単なる推定であつて何等証とすべきものがない。齋藤氏のは既に石見八重葎の中の小篠大記の説に見え、国府の近くであり、「唐」の名がついてゐて、いささか聴くべきものがあるが、今の「タウガネ」がもと「カラカネ」であつたとしても「からかね」は一語と見るべきものであり、「かね」が主体であつて、「から」はその修飾にすぎない。従つて「から」と「からかね」とを混同すべきものでない。これはむしと齋藤氏も引用せられてゐる 「安芸より石見を通過する道の記」 や槃游余録に見える唐山こそ注意すべきだと私は考へる。今その道の記を見ると (『鴨山考補註篇』二二一頁、『雑纂篇』四八七頁に引用せられたによる)、 高田山のすそへ下り、唐山 (入日のいとよく晴れたる時 頂より朝鮮の山々見ゆと云) などふりさけ見つゝ、都野津、加久志、江津を経て、玉江のわたしをこえ、・・・渡津村を過、海邊へいで・・・ とある。今これらの地名を今の名に直して逆にあげると、江津市渡津、江(ゴウ)川、喜久志、都野津、高田となつて、唐山の名は今残つてゐないが、高田の北の海岸に波子(ハシ)の町がある。国鐡都野津駅の次の駅である。その東北にある山ではないかと思はれ、その西北の麓が北に突出して、今大崎鼻と呼ばれてゐる。その名は殆ど普通名詞に近いものであり、このあたりには崎といはれるにふさはしいものがないので、右引用にあるやうに、そのうしろの山を唐山と呼び、その麓の出端(でばな)が唐の崎と呼ばれてゐたと考へる事は極めて自然な解釈ではなからうか。私は昨年 (卅ニ年) 十二月廿四日に、波子駅の東北、大崎鼻よりは東南にあたる、街道筋の江津市波子支所をたづねて聞いたが、唐山といふ名は今知る人がないやうであつた。しかし、私を大いに喜ばせた事は、唐山と私が推定した山の上に監視所が出来てをり、それは朝鮮よりの密輸船を監視するところであるといふ事実であつた。唐山といふ「名」は失はれてゐても、現に韓(から)通ひの船を見張る山であるといふ事は、唐山の実が尚存してゐるとも云へるのではなからうか。(一四五頁地図参照。) |
|||||||||||
| 全注 | 【注】「言佐敞久辛乃埼有」(ことさへく からのさきなる)、私注:前項「枕詞『ことさへく』考参照」 | |||||||||||
| 「いくり」考。 | 仙覚抄 | 伊久里尓曾 [イクリニソ]ト ハ、イハ發語ノ詞ハ、クリハ、石也。山陰道ノ風俗、石ヲハクリト云也。 | ||||||||||
| 拾穂抄 | いくり 仙曰いは發語の詞くりは石也山陰道の風俗石をくりと云也 | |||||||||||
| 代匠記 | イクリは仙覺抄に、「い」 は發語の詞、「くり」 は石なり、山陰 [セムオム] 道の風俗、石をば「くり」 と云なりといへり、今の世なべて「くり石」 と申は、ちひさきを申せば、「栗」 ばかりの石と云心にや、山陰道には大小を問ず皆「くり」 と云にこそ、今按、應神紀の御製に、由羅能斗能 [ユラノトノ]、斗那珂能異句離珥 [トナカノイクリニ] と遊ばされ、此集第六、赤人の歌にもよまれたれば、伊は發語の詞ならず、「くり」 は山陰道の風俗によらずして元來「いくり」 と云なるべし、又舊事紀第三云、櫛八玉 [クシヤタマノ] 神、化 [ナリテ] レ鵜入二海底ニ一咋 [クヒ] 二出底之埴一、作二天ノ八十毘良迦 [ヤソヒラカ] 一、云云、此を合せて思ふに、泥の黒きを□ [涅の下、土を工][クリ] と云へば、發語の詞を加て、「いくり」 と云にや、 | |||||||||||
| 童蒙抄 | 童子問 仙覺抄云、伊久里爾曾とは、いは發語の詞、くりは石なり。山陰道の風俗石をはくりと云也とあり。此説しかりや。 答 しかるへし。山陰道の風俗のみにもあらし。日本紀の歌にもいくりとよみたまへること也。古語也。 |
|||||||||||
| 万葉考 | 紀に (應神) 由蘿 [ユラ] のとの、となかの、異句離 [イクリ] にふれたつ、云云 (卷十五) 「わたのそこ、奥津伊久里 [オキツイクリ] に、あはび玉、さはにかづき出デ」などいへば、海の底の名をいくりと云り、さて必黒ければいくりといふか、 | |||||||||||
| 略解 | イクリ、應神紀、由羅のとのとなかの異句離《イクリ》云云、釋日本紀、句離謂v石也、異助語也と有り。 | |||||||||||
| 攷證 | 伊久里爾曾 [イクリニソ]。 古事記下卷に、由良能斗能斗那加能 [ユラノトノトナカノ]、伊久理爾布禮多都 [イクリニフレタツ]、那豆能紀能 [ナツノキノ] 云々。本集六〔十六丁〕に、淡路乃野島之海子乃 [アハチノヌシマノアマノ]、海底奧津伊久里二 [ワタノソコオキツイクリニ]、鰒珠左盤爾潜出 [アハヒタマサハニカヅキデ] 云云とありて、いくりは、海の石をいふ也。宣長云、くりといふにつきて、栗を思ひて、小 [チヒサ] き石をいふと云説は非也。海松 [ミル] の生とよめるにても、小きに限らぬ事をしるべし。又海の底なる石をいふと云も非也。古事記の歌も、底なる石にては叶はず。六巻の歌に、海底とよめるは、たゞ奧 [オキ] の枕詞にて、いくりへかゝれる言にはあらず。海底なるをも、又うへに出たるをもいひ、又小きをもいひ、大きなるをもいふ名也。云々といはれつるがごとし。又釋日本紀に、句離 [クリ] 謂レ石也、伊 [イ] 助語也云々。この説のごとく、くりは石のこと、いは發語なるべし。 |
|||||||||||
| 古義 | 伊久里 [イクリ] は、海中の石をいふべし、(袖中抄に、船路には、石をいくりと云り、としるせり、) 六ノ卷に海底奧津伊久利二鰒珠左盤爾潜出 [ワタノソコオキツイクリニアハビタマサハニカヅキデ]、また古事記仁徳天皇ノ條ノ歌に、由良能斗能斗那加能伊久理爾布禮多都 [ユラノトノトナカノイクリニフレタツ] 云々、此ノ歌書紀には、應神天皇ノ卷に出で、その釋に、異句離 [イクリハ] 句離 [クリハ] 謂レ石ヲ也、異ハ助語也と見ゆ、(異ハ助語と云こといかゞ、) 又十七に、伊毛我伊弊爾伊久理能母里乃 [イモガイヘニイクリノモリノ] とあり、(これも、海石 [イクリ] に由ありて負ヘる地ノ名か、) | |||||||||||
| 全釈 | 伊久里爾曾 [イクリニゾ] ―― 伊久里は海の石をいふ。釋日本紀に「句離 [クリ] 謂レ石也、伊ハ助語也」とあるによれば、伊は接頭語で、石をクリといふのである。今も日本海沿岸地方では海礁をグリといつてゐる。 | |||||||||||
| 全註釈 | 【釈】 伊久里尓曾 イクリニゾ。イクリは、海中の岩礁をいう。「由良熊斗能 [ユラノトノ] 斗那賀能 [トナカノ] 伊久理爾 [イクリニ] 布禮多都 [フレタツ] 那豆能紀能 [ナヅノキノ] 佐夜佐夜 [サヤサヤ]」(古事記七五)、「淡路乃 [アハヂノ] 野島之海子乃 [ノジマノアマノ] 海底 [ワタノソコ] 奧津伊久利二 [オキツイクリニ] 鰒珠 [アハビタマ] 左盤爾潜出 [サハニカヅキデ]」(卷六、九三三) など使用されている。「曉之 [アカトキノ] 寐覺爾聞者 [ネザメニキケバ] 海石之 [イクリノ] 鹽干乃共 [シホヒノムタ]」 (卷六、一〇六二) の海石もイクリと讀むべきであろう。海中の暗礁をいうとする説があるが、暗礁に限定しないでもよいのだろう。 |
|||||||||||
| 評釈 | 【語】 いくり 應神紀に「ゆらのとのと中のいくりに」とあるを釋日本紀に註して「句離謂レ石也 異助語也」とある。用例より推せば、海の石をいふらしい。 |
|||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「伊久里」(いくり) 海中の岩礁を云つたやうである。釈日本紀 (廿四) に「句離 [クリ] 謂レ石也、異 [イ] ハ助語也」とあり、講義に「日本地誌提要には長門より羽後までひろく日本海沿岸の地方の地勢用言に暗礁を『何繰』といへるもの頗る多し。これ恐らくは古言の残り伝はれるものなるべし」といひ、柳田、倉田両氏の分類漁村語彙にも「日本海岸の広い区域に亘つって、海中の隠れ岩をクリと謂ふ。越後の出雲崎附近にイスズグリ・シワナグリ・マクリ、能登高屋の嫁グリ一名磁石石、丹後与謝郡平田の沖の七つグリ、同竹野郡のササグリ等が、何れもよく知られて居る。又ヰクリといふ地名も若狭には有る。」とある。 由良の門(と)の 門中(となか)の 伊久理(イクリ)に ふれ立つ なづの木のさやさや (仁徳記) -淡路の 野島の海人の 海の底 沖つ海石(イクリ)に 鰒玉 さはに潜(かづ)き出- (6・933) の如き例がある。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】 「イクリ」は仁徳記の歌謡に、「由良の門(と)の 門中(となか)の 伊久理(イクリ)に ふれ立つ なづの木のさやさや」とあり、集内にも「-淡路の 野島の海人の 海の底 沖つ海石(イクリ)に 鰒玉 さはに潜(かづ)き出-」 (6・933) が見られる。これらの例から、海中深くの岩礁をさして「イクリ」と称したことが推定される。山田講義には、日本地誌提要を引き、長門から羽後までの日本海沿岸の地方の地勢用語に、暗礁を「~繰」といっている例が多いことを記す。 |
|||||||||||
| 新全集 | 【頭注】 海中の岩礁で漁場になっているところ。 |
|||||||||||
| 原文「深海松(ふかみる)」訓・注 | 代匠記 | 深海松は、延喜式の宮内に、志摩、〔深海松、〕又長海松と云も見え、又此集に俣海松 [マタミル] ともよめれば、此等は梅松の中の別名なり、 | ||||||||||
| 万葉考 | 深海松生流 [フカミルオフル]、 宮内式の諸國の貢に、深海松長海松の二つ有、深みるは海底に生るをいふ、 | |||||||||||
| 略解 | 深ミルは宮内式の諸國の貢物に、深海松長海松の二有り。海底に生るを深ミルと言ふか。 | |||||||||||
| 攷證 | 深海松生流 [フカミルオフル]。 本集六〔十八丁〕に、奧部庭深海松採 [オキヘニハフカミルトリ]、浦囘庭名告藻苅 [ウラワニハナノリソカリ] 云々。十三〔廿二丁〕に、朝名寸二來依深海松 [アサナギニキヨルフカミル] 云々。延喜宮内式、諸國例貢御贄に、志摩深海松云々とありて、海松は、和名抄海菜類に、崔禹錫食經云、水松、状如レ松而無レ葉〔和名美流〕揚氏漢語抄云海松〔和名上同俗用レ之〕云々と見えたり。 |
|||||||||||
| 古義 | 深海松 [フカミル] は、宮内式、諸國例貢御贄の中に、深海松 [フカミル] 長海松 [ナガミル] あり、猶品物解に云べし、 | |||||||||||
| 全註釈 | 【釈】 深海松生流 フカミルオフル。ミルは海松。倭名類聚鈔海菜類に「水松狀如レ松而無レ葉〔和名美流〕楊氏漢語抄云海松〔和名上同俗用之〕」とある。海中の深い處に生えるもので、深海松という。句切。下の深海松ノ深メテの句を引き起すためにこの句を出している。 |
|||||||||||
| 評釈 | 【語】 深みる 海草の名。長さ五六寸で紐のやうな形をし枝を食用に供する。 |
|||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】 新撰字鏡 (十二) に「海松」を「美留(ミル)」とし、倭名抄 (九) には「崖禹食経云、水松 美流、楊氏漢語抄云、海松、式又用レ之 状如レ松而無レ葉者也」とある。海松は海底の岩石などに附着して生ずる海藻、通常六七寸に達する。根元は一本であるが、順次叉状に分かれ總のやうな形をしてゐる。質は海綿を更に緻密にしたやうなもので濃緑うぃ呈する。古くは食用に供され、延喜式にはあちこちにその名が見える。紫菜(ノリ)と並べあげられてゐる。「深海松」は海底深く生えてゐる意であるが、宮内式には志摩の貢物として特に「深海松」とあり、民部式の安房の貢物には「長海松」とある。今はさしみのつま「鯛や鱸など白身のあらひなど」 に用ゐられる。上の句の「ぞ」を受けて「生ふる」と連体形で結び、次の「荒礒にぞ 玉藻は生ふる」と対句になり、その「玉藻は生ふる」はその下の「玉藻なす」につづいて、その生ふる玉藻のやうに、「靡き」とつづいて序となつてをり、対句が相前後して下へ序としてつづいてゐる形で、対句式の序と云はれるものである。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】 「ミル」は新撰字鏡に「海松」に「美留」と注する。漢名は「水松」で緑色藻類に属し、多く浅海の岩石に生ずるという。形は叉状に分枝し、若いものを食用とする (松田修「萬葉の植物」大成第八巻)。深海松は、とくに海底深くに生えるもの。 |
|||||||||||
| 原文「靡寐之兒乎 (なびきねしこを)」訓・注 |
拾穂抄 | なひきねしこ 石見の妻を云也前によりねし妹なと有と同心の詞也。 | ||||||||||
| 童蒙抄 | 童子問 此歌にては、靡寐之兒乎とあれは、妹のことにあらす。人丸の兒のことをよめるにや。 答 人丸妻も前妻後妻ありとみえ、子も有とは後々の歌にてしられたれとも、此長歌は兒息のことにはあらす。妹の事とみるへし。女のことを子とむかしはよむ、常のこと也、されは靡寐之兒は妹のことゝもしるへし。 |
|||||||||||
| 攷證 | 靡寐之兒乎 [ナヒキネシコヲ]。 靡ねしとは、なよゝかに、物のうちなびきたるやうに、そひふしたるをいふ。本集一〔廿一丁〕に、打靡寐毛宿良目八方 [ウチナヒキイモヌラメヤモ] 云々とあり。猶その所にいへり。兒とは、男女にかぎらず、人を愛し親しみ稱していふことにて、子と書も、同じ。古事記下卷に、阿理岐奴能美幣能古賀 [アリキヌノミヘノコガ] 云々とあるは、三重采女が、自ら三重の子といへり。また同卷に、本陀理斗良須古 [ホタリトラスコ] 云々とのたまへるは、袁杼比賣 [ヲドヒメ] をさしてのたまへる也。本集一〔七丁〕に、此岳爾菜採須兒 [コノヲカニコナツマスコ] 云々。四〔廿丁〕に、打日指宮爾行兒乎 [ウチヒサスミヤニユクコヲ] 云々、人之見兒乎吾四乏毛 [ヒトノミルコヲワレシトモシモ] 云々。五〔十八丁〕に、宇米我波奈知良須阿利許曾 [ウメカハナチラスアリコソ]、意母布故我多米 [オモフコカタメ] 云々。七〔四十二丁〕に、薦枕相卷之兒毛 [コモマクラアヒマキシコモ] 云々などありで、猶いと多し。これらみな、女を親しみ愛して、子とはいへる也。兒は、玉篇に子、咨似切、兒也愛也云々とありて、子兒通用して、文選褚淵碑文 注、引二孟子劉注一云、子通稱也云々。漢書武帝紀云、子者人之嘉稱也云々とあるにても思ふべし。さて、上〔攷證二上廿八丁〕にいへるがごとく、女の名の下に、兒 [コ] の字を付るも、これらよりおこれる事なり。また、男を稱して子といふ事は、下〔攷證〕にいふべし。 |
|||||||||||
| 新全集 | 【頭注】 自分の言う通りに横たわって寝た妻を。 |
|||||||||||
| 原文「左宿夜者 (さねしよは)」訓・考 旧訓「サヌルヨハ」 |
<旧訓> |
【拾穂抄】 つのさふる石見のうみのことさへくからのさきなるいくりにそふかみる生るあらいそにそ玉もはおふるたまもなすなひきねしこをふかみるのふかめて思ふとさぬるよはいくはくもあらすはふつたのわかれしくれはきもむかひ心をいたにおもひつゝかへり見すれとおほふねのわたりの山のもみちはのちりのまかひに妹か袖さやにも見えすつまこもる屋かみの山の雲間よりわたらふ月のおしめともかくろひくれはあまつたふいり日さしぬれますらおとおもへるわれもしきたへの衣の袖はとをりてぬれぬ寝 角障經(仙さはふ)石見之海乃言佐敝久辛乃埼有伊久里尓曽深海松生流荒礒尓曽玉藻者生流玉藻成靡寐之兒乎深海松乃深目手思騰左宿夜者幾(イいくた)毛不有延都多乃別之來者肝向(イむかふ)心乎痛念乍顧為騰大舟之渡乃山之黄葉乃散之亂尓妹袖清尓毛不見嬬隠有屋上乃 室上山 山乃自雲間渡相月乃雖惜隠比來者天傳入日刺奴礼大夫跡念有吾毛敷妙乃衣袖者通而沾奴 【代匠記】 角鄣經石見之海乃言佐敝久辛乃埼有伊久里爾曽深海松生流荒礒爾曾玉藻者生流玉藻成靡寐之兒乎深海松乃深目手思騰左宿夜者幾毛不有延都多乃別之來者肝何心乎痛念乍顧爲騰大舟之渡乃山之黄葉乃散之亂爾妹袖清爾毛不見嬬隱有屋上乃 [ツノサハフイハミノウミノコトサヘクカラノサキナルイクリニソフカミルオフルアライソニソタマモハオフルタマモナスナヒキネシコヲフカミルノフカメテオモフトサヌルヨハイクハクアラスハフツタノワカレシクレハキモムカヒコヽロヲイタミオモヒツヽカヘリミスレトオホフネノワタリノヤマノチリノマカヒニイモカソテサヤニモミエスツマコモルヤカミノ〔一云室上山〕山乃自雲間渡相月乃雖惜隱比來者天傳入日刺奴禮大夫跡念有吾毛敷妙乃衣袖者通而沾奴 ヤマノクモマヨリワタラフツキノヲシメトモカクロヒクレハアマツタフイリヒサシヌレマスラヲトオモヘルワレモシキタヘノコロモノソテハトホリテヌレヌ] 【略解】 角鄣經。石見之海乃。言佐敝久。辛乃埼有。伊久里爾曾。深海松生流。荒磯爾曾。玉藻者生流。玉藻成。靡寐之兒乎。深海松乃。深目手思騰。左宿夜者。幾毛不有。(109)延都多乃。別之來者。肝向。心乎痛。念乍。顧爲騰。大舟之。渡乃山之。黄葉乃。散之亂爾。妹袖。清爾毛不見。褄隱有。屋上乃(-云室上山)山乃。自雲間。渡相月乃。雖惜。隱比來者。天傳。入日刺奴禮。丈夫跡。念有吾毛。敷妙乃。衣袖者。通而沾奴。 つぬさはふ。いはみのうみの。ことさへぐ。からのさきなる。いくりにぞ。ふかみるおふる。ありそにぞ。たまもはおふる。たまもなす。なびきねしこを。ふかみるの。ふかめてもへど。さぬるよは。いくらもあらず。はふつたの。わかれしくれば。きもむかふ。こころをいたみ。おもひつつ。かへりみすれど。おほぶねの。わたりのやまの。もみぢばの。ちりのまがひに。いもがそで。さやにもみえず。つまごもる。やがみのやまの。くもまより。わたらふつきの。をしけども。かくろひくれば。あまづたふ。いりひさしぬれ。ますらをと。おもへるわれも。しきたへの。ころものそでは。とほりてぬれぬ。 【攷證】 角障經 [ツヌサハフ]。石見之海乃 [イハミノウミノ]。言佐敝久 [コトサヘク]。辛乃崎有 [カラノサキナル]。伊久里爾曾 [イクリニソ]。深海松生流 [フカミルオフル]。荒礒爾曾 [アリソニソ]。玉藻者生流 [タマモハオフル]。玉藻成 [タマモナス]。靡寐之兒乎 [ナビキネシコヲ]。深海松乃 [フカミルノ]。深目手 [フカメテ] 思 [モヘ・オモフ] 騰 [ト]》。左宿夜者 [サヌルヨハ]。幾 [イクダ・イクバク] 毛不有 [モアラス]。延都多乃 [ハフツタノ]。別之來者 [ワカレシクレバ]。肝 [キモ] 向 [ムカフ・ムカヒ]。心乎痛 [コヽロヲイタミ]。念乍 [オモヒツヽ]。顧爲騰 [カヘリミスレト]。大舟之 [オホフネノ]。渡乃山之 [ワタリノヤマノ]。黄葉乃 [モミチハノ]。散之亂爾 [チリノマカヒニ]。妹袖 [イモカソテ]。清爾毛不見 [サヤニモミエス]。嬬隱有 [ツマコモル]。屋上乃山 [ヤカミノヤマ]〔一云室上山。〕乃 [ノ]。自雲間 [クモマヨリ]。渡相月乃 [ワタラフツキノ]。雖惜 [オシケドモ・ヲシメトモ]。隱比來者 [カクロヒクレハ]。天傳 [アマツタフ]。入日刺奴禮 [イリヒサシヌレ]。大夫跡 [マスラヲト]。念有吾毛 [オモヘルワレモ]。敷妙乃 [シキタヘノ]。衣袖者 [コロモノソテハ]。通而沾奴 [トホリテヌレヌ]。 |
||||||||||
| 代匠記 | 深メテ思フトサヌル夜ハ、イクバクモアラズとは、餘に人目を忍び過し、又は後を頼過して逢夜の少き心なり、十一に、かくばかり戀む物ぞとおもはねば、妹が袂をまかぬ夜も有き、十四東歌に、梓弓未に玉まきかくすゝぞ、寢なゝ成にし奥をかぬかぬ、此奥は後の心なり、人に深くかくすとてぞ、ねず成し後も逢むと末かけてたのむまにと云るなり、今も此意なり、此に依て見れば、迎てすゑ置たる妻にはあらで、時々通ひすまれたるなるべし、 | |||||||||||
| 万葉考 | 此ぬる夜はいくばくもあらで、別るといふからは、こは國にてあひ初し妹と聞ゆ、依羅 [ヨサミノ] 娘子ならぬ事知べし、 | |||||||||||
| 略解 | サヌルのサは發語。ハフツタノ枕詞。別シクレバは、ぬる夜はいくばくも無くて別ると言へば、國にて逢ひ初めし妹と聞ゆ。依羅娘子ならぬ事明らけし。 | |||||||||||
| 攷證 | 左宿夜者 [サヌルヨハ]。 さぬる夜はの、さは、さよばひ、さわたる、さばしり、さとほみ、さをどるなどの類、發語にて、意なし。たゞぬる夜はといへる也。集中いと多し。 |
|||||||||||
| 古義 | 左宿夜者は、「サネシヨハ」 と訓べし、(略解などに、舊本に從て、「サヌルヨハ」 とよめるは、今少しわろし、) | |||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】 「さ」は接頭語。共に寝た夜は、の意。旧訓に「サヌルヨハ」とあつたのを古義に「サネシヨハ」と改めた。「佐祢斯欲能 伊久陀母阿羅祢婆 (サネシヨノ イクダモアラネバ)」 (5・804) の仮名書例がある。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】 原文「左宿夜」を旧訓「サヌルヨ」と訓んでいたが、古義に「サネシヨハと訓べし、略解などに旧本に従てサヌルヨハとよめるは今少しわろし」として改めた。「サネシヨハ」と訓むのは、「シ」を読み添えることになるが、人麻呂作歌には同様な読添例を「相シ日」 (209、219)、「妹結シ紐」 (3・251) など拾いうるから、ここも、「サネシヨハ」で差し支えないだろう。作歌中の「シ」 (過去) は、52例を数える。その大部分は、之・師・斯などの仮名で書かれており (45例)、無表記は七例に過ぎない。人麻呂歌集に比べると丹念に書かれていると言って良い。ただ右のような表記の略された例もあるのである。「之」を記さぬほうが、過去を現前のことのように想起している感じが強い。 |
|||||||||||
| 原文「幾毛不レ有 (いくだもあらず)」訓 |
<旧訓> | 〔拾穂抄〕幾(イいくた)毛不有 イクハクアラス 〔代匠記〕幾毛不有 イクハクアラス 〔万葉考〕幾毛不有 イクバクモアラズ 〔略解〕 幾毛不有 いくらもあらず |
||||||||||
| 攷證 | 幾 [イクダ・イクバク] 毛 [モ] 不有 [モアラズ]。 舊訓、いくばくとよめるも、宣長が、いくらもとよまれしもいかゞ。こゝは、いくだもあらずとよむべし。そは、本集五〔九丁〕に、左禰斯欲能伊久陀母阿羅禰婆 [サネシヨノイクダモアラネバ] 云々。十〔廿七丁〕に、左尼始而何太毛不在者 [サネソメテイクダモアラネハ] 云々などあるにても思ふべし。 |
|||||||||||
| 古義 | 幾毛不有は、「イクダモアラズ」 と訓べし、五ノ卷に佐禰斯欲能伊久陀母阿羅禰婆 [サネシヨノイクグモアラネバ]、十ノ卷に、左尼始而何太毛不在 [サネソメテイクダモアラズ]、などあり、又十七に、年月毛伊久良母阿良奴爾 [トシツキモイクラモアラヌニ] ともあり、(本居氏は、これによりて、今をも伊久良 [イクラ] と訓し、それもさることながら、こは許々陀 [コヽダ] を、後に許々良 [コヽラ] と云如く、やゝ奈良ノ朝の季つかたよりの、詞とこそ聞えたれ、) これは、吾カ家に迎へて、すゑ置たる妻にはあらで、朝集使などにて、石見ノ國へ下り居られしほど、時々かよひ住れし娘子なれば、幾 [イクダ] もあらずといへること、勿論 [サラ] なり、 | |||||||||||
| 全釈 | 幾毛不有 [イクダモアラズ] ―― イクダとよむがよい。卷五に左禰斯欲能伊久陀母阿蘇禰婆 [サネシヨノイクダモアラネバ](八〇四)とある。 | |||||||||||
| 全註釈 | 幾毛不有 [イクダモアラズ]。イクダは幾何の意。「佐禰斯欲能 [サネシヨノ] 伊久陀母阿羅禰婆 [イクダモアラネバ]」(卷五、八〇四)、「左尼始而 [サネソメテ] 何太毛不レ在者 [イクダモアラネバ]」(卷十、二〇二三) などある。また「年月毛 [トシツキモ] 伊久良母阿良奴爾 [イクラモアラヌニ]」(卷十七、三九六二) の如くイクラともいう。ここは古きに從つてイクダと讀む。ココダの如きも、本集ではココダであるが、後にはココラになつている。結婚して久しくないのであろう。 | |||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「いくだもあらず」 これも旧訓には「イクハクモアラス」とあつたが、攷證に上に引用の例や「左尼始而 何太毛不在者 (サネソメテ イクダモアラネバ)」(10・2023) により改めたによる。玉の小琴には「年月毛 伊久良母阿良奴尓 (トシツキモ イクラモアラヌニ)」(17・3962) の例により「イクラ」としてゐる。「いくばく」の意を「いくだ」とも「いくら」とも云つたと思はれるが、今は用例の古い方による。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】 「イクダモアラズ」の原文は「幾毛不有」で、旧訓「イクハクモアラス」であったのを、攷證に「イクダモアラズ」と改訓した。万葉考及び玉の小琴には「イクラモアラズ」としている。人麻呂歌集に「さねそめて何太毛不在者」(10・2023) とある。巻五の憶良の歌に、「佐禰斯欲能 [サネシヨノ] 伊久陀母阿羅禰婆 [イクダモアラネバ]」(卷五、八〇四) と見え、巻十七の家持作歌には「年月毛 伊久良母阿良奴尓 (トシツキモ イクラモアラヌニ)」 (3962) とあって、後者によって宣長は「イクラ」と訓んだのであるが、古義にこれを評して「それもさることながら、こは許々陀を、後に許々良と云う如く、やや奈良朝の季つかたよりの、詞とこそ聞こえたれ」と言う通りであろう。「イクダ」も「イクラ」も、それほどの意。 |
|||||||||||
| 枕詞「はふつたの」考 | 拾穂抄 | はふつたの 蔦ははひわかるゝかつらなれは別てといはん枕詞也別しのし助字 | ||||||||||
| 代匠記 | ハフツタノとは、蔦は末々にはひわかるゝ物なれば、別るとつゞけむ爲なり、後に至ても多し、 | |||||||||||
| 童蒙抄 | [延都多別之來者] 童子問 はふつたをいへる意如何。 答 異義なし。つたかつらは本は一つにて、末はかたかたにはひわかるゝものなれは、別るといふ冠辭におけるまて也。此集第九卷にも、蔓都多乃各各向向天雲乃別石徃者とあり。 |
|||||||||||
| 攷證 | [延都多乃 ハフツタノ] 枕詞にて、冠辭考にくはし。葛 [ツタ] の、かなたこなたへ、はひわかるゝがごとく、わかれしくればと、つゞけし也。さて、つたは、和名抄に、絡石をよみ、本草和名に落石をよめれど、一種をさしていへるにあらず。つたは、蔓草をすべいふ名也。この事は、冠辭考補遺にいふべし。
|
|||||||||||
| 古義 | 延都多乃 [ハフツタノ] は、別 [ワカレ] の枕詞なり、十三十七十九などにも見えたり、これは絡石 [ツタ] の、かたかたへ蔓ひ別るゝを人の別にいひつゞけたり、 | |||||||||||
| 全釈 | 延都多乃 [ハフツタノ] ―― 這ふ蔦の別るとつづく枕詞。蔦蔓のたぐひは、枝を分ちて延び行くものだからである。 | |||||||||||
| 全注 | 【注】 「ハフツタノ」は、別れに冠する比喩的な枕詞。冠辞考に「こはつたかづらのかたがたへはひわかるるを、人にわかれ行にいひかけたり」と説く。 |
|||||||||||
| 新全集 | 【頭注】 「別ル」の枕詞。ツタは秋に紅葉するぶどう科の蔓性落葉植物。その蔓が延びて分岐するところからかけた。 |
|||||||||||
| 「別れし来れば」考 | 攷證 | 別之來者 [ワカレシクレバ]。 考云、このぬる夜は、いくばくもあらで別るといふからは、こは國にてあひそめし妹と聞ゆ。依羅 [ヨサミ] 娘子ならぬ事しるべし。 |
||||||||||
| ミ語法「心を痛み」注 | (代匠記) | 肝向心ヲ痛ミとは、憂ある時に心と、肝との二つを痛ましむる心か、遊仙窟云、下官 [ヤツカレ] 當レ見二此詩一、心膽倶ニ碎ク、文選、歐陽建、臨終詩云、痛哭摧二心肝一、今按遊仙窟に、心肝恰欲レ摧とあるを心肝の二字を引合てキモと點じ、雄略紀に心府をコヽロキモと点ず、玉邊云、府聚也、かゝれば、心も肝も互に「こゝろ」 とも「きも」 とも云へば、大守の國府に居る時諸郡此に向ふやうに、あらゆるきも心を主として此に向ふ意にて、心肝相對するにはあらで、村肝の心とあまたよめるに同じかるべし、兩義何れにもあれ、肝向ヒと点ぜるは叶はず、向フと改むべし、古事記下、仁徳天皇の御歌末云、岐毛牟加布許々呂袁陀邇迦 [キモムカフコヽロヲタニカ]、阿比淤母波受阿良牟 [アヒオモハズアラム]、此を證とすべし、 | ||||||||||
| (童蒙抄) | [肝向心乎痛念乍] 童子問 肝向心といふ詞心得かたし。或説に物おもひなけく時、肝と心とのふたつの臓をいたましむると云心也。むかふは對樣の心也。肝に對する心と云也といへり。此説しかるへきや。 答 肝心ともつらねていへは、むかふといふ詞ならは、對ふ義とならては解へくもおほへす。もし向の字異訓あるか。異義有かうたかひ殘れり。僻案には心の冠辭を村肝のといへは、肝向は村肝の顛倒にて、向は村の字の誤りとおほゆる也。猶正本を得て疑を決すへし。心の臓、肝の臓等の説古義にはなきこと也。古語はむつかしき道理のおもしろきやうなることは一向みえす。皆誤字をしらすして牽強傅會の説出來るものなれは、肝は心に對といふ説も、古風の語意に異なれはうけられぬこと也。しる人しるへし。 |
|||||||||||
| (攷證) | 肝 [キモ] 向 [ムカフ・ムカヒ]。 枕詞なり。宣長云、かくつゞくる由は、まづ腹の中にある、いはゆる五臓六腑の類を、上代には、すべて皆きもと云し也。さて、腹の中に、多くのきもの相對 [ムカ] ひて集りありて、凝々 [コリコリ] しと云意に、こゝろとはつゞくる也云々といはれしがごとし。猶くはしくは、冠辭考補遺にいふべし。 心乎痛 [コヽロヲイタミ]。 心をいたみは、心も痛きまで、いたましみ思ひこむ意にて、こゝろをいたさに也。この事は、下〔攷證三下五十三丁〕にいふべし。このいたみといふ語は、句をへだてゝ、顧すれどといふへかけて心得べし。いたみ思ひつゝとはつゞかざる也。妹にわかれくれば、心をいたさに、妹を思ひつゝ、かへり見すれど、わたりの山の紅葉のちりまがふ故に、妹が袖のさやかに見えずときくべし。 |
|||||||||||
| (古義) | 肝向 [キモムカフ] は、心 [コヽロ] の枕詞なり、九ノ卷に、肝向心摧而 [キモムカフコヽロクダケテ]、古事記仁徳天皇ノ大御歌に、岐毛牟加布許々呂袁陀邇迦
[キモムカフコヽロヲダニカ]、などあり、伎毛 [キモ] とは、いはゆる五臓六腑の類を凡てみなしかいふ由、一ノ卷ノ上に委ク云るが如し、向 [ムカフ]
とは腹中に、多くの伎毛 [キモ] の相對ひて、集り在ルをいふべし、心 [コヽロ] とつゞくは、多くの伎毛 [キモ] の凝々 [コリコリ] し、といふ意にいひかけたり、許々呂
[コヽロ] は、許呂許呂 [コロコロ] にて、凝々 [コリコリ] なり、海菜の心太 [コヽロフト] も、凝る意の名、神代紀に、田心 [タゴリ]
姫、此ノ集廿ノ卷に、妹之心 [イモガコヽロ] を、以母加去々里 [イモガコヽリ]、とあるなどを以て、曉るべしと本居氏云り、今按フに、伎毛 [キモ]
といふも、凝物 [コリモノ] の義なるべし、(許理 [コリノ] 切伎 [キ]、毛能 [モノノ] 切毛 [モ]、) 心乎痛 [コヽロヲイタミ] は、心が痛さにの意なり、既く出ツ、 |
|||||||||||
| (全釈) | 肝向 [キモムカフ] ―― 「五臓六臓相向かひ集まりて、凝々 [コリコリ] すといふ意より、こりこりの約轉なる心につづく」と、宣長は言つてゐるが、肝心 [キモココロ] も失すなどと言つて、古昔は心も肝も同じ意に用ゐられてゐるので、要するに肝の向ひ合ふ間に、心があると考へたものとすべきであらう。村肝の心と同じやうな語法である。 | |||||||||||
| (全註釈) | 【釈】 肝向 キモムカフ。枕詞。古人は精神は腹中にあると信じていた。人の腹中には臓腑が澤山あつて相對している。臓腑はすべてキモだから、肝向フ心と續くのである。 心乎痛 ココロヲイタミ。心が痛くして。心が惱ましくて。 |
|||||||||||
| (評釈) | 【語】 肝向ふ 心の枕詞。内臓の多く集り凝々 [こりこり] する意でつづく(宣長)といふよりも、内臓が向ひあつて蟠つてゐるのを肝向ふといひ、心の働きは肝から起ると思つたから心の枕詞としたとする(新講)のが穩かな説である。「村肝の」(五)參照。 |
|||||||||||
| (注釈) | 【訓釈】 「岐毛牟加布許々呂袁陀邇迦 [キモムカフコヽロヲダニカ」 (仁徳記) の仮名書例がある。肝とは五臓の意で、五臓が群がり向ひあつてゐるので「群肝の」(1・5) とも、「肝向ふ」 とも云ひ、その肝はまた心の意にも用ゐたので、「心」 の枕詞とした。 心を痛み、既出 (1・5)。 |
|||||||||||
| (全注) | 【注】 「キモムカフ」は心に冠する枕詞。仁徳記に「岐毛牟加布許々呂袁陀邇迦」とある。原文の「肝」 は、五臓の意。人の腹中には五臓が群がり向き合っているところから、「ムラギモノ」 とも「キモムカフ」 とも言う。記伝に「腹中にある、いはゆる五臓六腑の類を、上代には凡て皆伎毛と云しなり。さて腹中に多くの、伎毛の相対ひて集り在りて凝々しと云意・・・」(三十六) とある。五臓は心の宿る所と考えられたので、心に冠する。 |
|||||||||||
| 新全集 | 【頭注】 心を痛み-「痛ミ」は「痛シ」のミ語法。「ミ語法+思フ」は、「~だと思う」の意。 |
|||||||||||
| 「渡乃山(わたりのやま)」考 | 仙覚抄 | ワタリノヤマ、ヤカミノ山、可考在所。 | ||||||||||
| 代匠記 | 此山何れの國に有と云事を知らず、 | |||||||||||
| 童蒙抄 | 童子問 渡乃山は何國に在山の名にや。 答 所見なし。しかれとも長歌の詞につきて見れは、石見國の山の名にあらすして聞えす。いかにとなれは、下の詞に妹袖清爾毛不見とあれは、石見國を離れて、はるかに行かすしては妹袖石見といふへからす。されは石見の國の山とす。 |
|||||||||||
| 万葉考 | 渡乃山之 [ワタリノヤマノ] 、 府より東北、今道八里の所に在と云り、妹か振袖の見えずと云にかなへり、 | |||||||||||
| 略解 | 渡ノ山は府より東北八里の所に在りと言へり。 | |||||||||||
| 攷證 | 渡乃山之 [ワタリノヤマノ]。 この外、古書に見えず。名寄にも、石見とせり。考に、府より東北、今道八里の所にありと云り。妹が振袖の見えずといふにかなへり云々といはれつ。 |
|||||||||||
| 古義 | 渡 [ワタリ] 乃山は、岡部氏、府より東北、今道八里の處に在ルよし云り、國人に聞に、邑知ノ郡今の渡リ村甘南寺の山、これなりと云り、 | |||||||||||
| 全釈 | 渡乃山之 [ワタリノヤマノ] ―― 渡津附近の山であらう。 | |||||||||||
| 全註釈 | 【釈】 渡乃山之 ワタリノヤマノ。ワタリは、此處から向こうへ渡れる處をいう。「見度 [ミワタセバ] 近渡乎 [チカキワタリヲ] 廻 [タモトホリ] 今哉來座 [イマヤキマスト] 戀居 [コヒツツゾヲル]」(卷十、二三七九)。渡りの山は、わが前に立つている山をいう。山の名とするは誤りである。 |
|||||||||||
| 評釈 | 【語】 渡の山 渡津の近傍の山であらうが、明らかでない。又或はこれは地名でなく目の前に立つてゐる山と解する説もある。 |
|||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】 江川の北に今、江津市渡津(ワタツ) がある。必ずしもそこと断定しなくとも、江川の渡し場近くの山と見ればよいであらう。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】 -渡の山について、真淵は「府より東北、今道八里の所に在と云り」(万葉考) と記し、古義にこれを受けて「国人に聞に、邑智郡今の渡リ村甘南寺の山、これなりと云り」と言ったが、檜嬬手に「それは安芸・備後の方へ出る間道にて、古代の駅路に非ず」と否定。「人麻呂大人此度の帰京、たとひ朝集使にまれ、任限にまれ、国府を立ちて、邇磨郡・安濃郡を歴て、出雲路の方へ出て上るべきなれば、今那賀郡江の河近辺に八神村あり。道のつづきに山も多かれば、此処とすべし」としている。茂吉総論篇には「石見国那賀郡渡津村の近くの山である」とし、石見国名跡考の「渡る處の近辺の山を大凡に詠みたるにて一箇の山には非ずと覚ゆ」という言葉を引く。渡津村付近と断定しうるかどうかは疑問であるが、岡熊臣の「人麻呂事績考辨」に「官人ハ間道ヲ経ベキニアラズ、必駅路ヲ通ルベシ。今那賀郡江ノ河辺ニ八神村アリ。若クハ此アタリヲ作給ヘルカ。故、古代ノ駅路ヲ考ルニ、出雲路ヨリ入来テ、波祢(ハネ)・託濃(タクノ)・樟通(クスミチ)・江東・江西・伊甘(イカン)トアレバ、人麻呂モ府ヨリ此駅路ヲ過玉ハムニ、マヅ伊甘ハ国府ノ近辺ニ式内伊甘ノ神社アリ、此アタリナルベシ。角ノ浦モ其アタリ遠カラズ。江西ハ江ノ川ノ西ナレバ今ノ郷田(コウタ)村ノアタリナラム。江東ハ川ノ東ナレバ今ノ大田村 (中略) 渡津村ノアタリナルベシ。八神村モ此アタリ遠カラズ」と記すように、上代の駅路に従っていると見るのが自然だろう。 |
|||||||||||
| 原文「散之乱 (ちりのまがひ)」訓・注 |
拾穂抄 | ちりのまかひ 散まきれに妹かみえぬ心也古今ニモ散のまかひにいへち忘て云々 | ||||||||||
| 童蒙抄 | 黄葉乃散之亂妹袖清毛不見 童子問 散之亂の三字を、ちりのまかひとよみ來れり。此訓しかるへきや。妹袖清爾毛不見の七字を、いもかそてさやにもみえすとよみ來れり。是もしからんや。 答 散之亂の三字は、ちりしみたれにても有へけれと、此詞古語とみえて、ありのまかひちりのまかひといふ事あれは誤訓にては有へからす。散を塵とかよはして、塵のまかひといふへし。塵にかよはさすして、飛散のことのみにしては、ちりのといひかたし。且下の七字の訓は、不所見とあらは、みえすとよむへけれとも、不見の二字なれは、僻案の訓には妹かそてさやかにもみすと爲也。 |
|||||||||||
| 万葉考 | まがふてふ言に亂と書る、下に多し、 | |||||||||||
| 攷證 | 散之亂爾 [チリノマガヒニ]。 まがひは、上にいへるごとく、まぎるゝ意にて、紅葉のちりまぎらかす故に、妹がふる袖の、さやかにも見えずと也。古今集春下に、よみ人しらず、このさとにたびねしぬべし、さくら花、ちりのまがひに家路わすれ(て脱カ)云々とよめるも、ちりのまぎれにの意也。 |
|||||||||||
| 古義 | 散之亂爾は、「チリノミダリニ」 と訓べし、 | |||||||||||
| 全釈 | 散之亂爾 [チリノマガヒニ] ―― チリノミダリニとよむ説もある。亂の字は、ミダリとよむのが普通であるが、中にはミダリでは意をなさぬ處もある。例へば、吾岳爾盛開有梅花遺有雪乎亂鶴鴨 [ワガヲカニサカリニサケルウメノハナノコレルユキニマガヘツルカモ] (一六四〇) の如きがそれである。して見れば無理にミダリに統一しようとするのはよくない。ここなどはマガヒとよむ方がよい。 | |||||||||||
| 全註釈 | 【釈】 黄葉乃散之亂尓 モミチバノチリノマガヒニ。チリノミタレニ(温)。散り亂れることをチリマガフという。マガフは、他物と紛れる意に使つているが、區別がつかないので、亂れるの意になるのだろう。「毛美知葉能 [モミチバノ] 知里熊麻河比波 [チリノマガヒハ]」(卷十五、三七〇〇)、「春花乃 [ハルバナノ] 知里能麻可比爾 [チリノマガヒニ] 」(卷十七、三九六三) などある。「秋□[草冠/互]之 [アキハギノ] 落乃亂爾 [チリノマガヒニ] 呼立而 [ヨビタテテ]」(卷八、一五五〇) は、ここと同樣の用字法である。この句は實景で、おりしも秋から冬へかけての頃であつたことを語つている。 |
|||||||||||
| 原文「妹袖(いもがそで)」注 | 古義 | 妹袖 [イモガソデ] は、妹が振ル袖なるべし、わかれ來て見えずなるまでは、猶門などに立て、妻が袖振しなるべし、さていとゞ遠放るまゝ、幽になれるに、まして黄葉の散亂などして、さやかに見えずなれるよしなり、 | ||||||||||
| 全註釈 | 【釈】 妹袖清尓毛不見 イモガソデサヤニモミズ。散り亂れる黄葉に紛れて、妻の袖を明瞭にも見ずの意で、下の惜シケドモ隱ラヒ來レバの句に接續する。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】 -「イモガソデ」については、講義に「妻の姿をさすものなるが、特に袖といへるは、上にもいへる如く、妻が別れを惜しみて袖を振りてあらむと想像して、さて、その袖が見えぬといへるなり」と注する。これを現実に妹の袖振る姿の見うる場所までのこととし、先の高角山の袖振り(133) 以前を歌ったと解する人もあるが (伊藤博『万葉集の歌人と作品 上』290頁)、神野志隆光「石見相聞歌」 (『万葉集を学ぶ』第二集) などの指摘するように、それは誤りであろう。人麻呂は見えぬ妹の袖を黄葉の散り交うなかに映像化しているのである。 |
|||||||||||
| 原文「清尓毛不レ見 (さやにもみえず)」考 |
攷證 | 清爾毛不見 [サヤニモミエズ]。 清爾 [サヤニ] のさやは、上〔攷證一下四十九丁〕にいへるがごとく、さは、上におきたる助字、やは、やけ、やかなどの、下の字を略けるにて、明らかなる意也。十四〔十一丁〕に、勢奈能我素低母佐夜爾布良思都 [セナノガソテモサヤニフラシツ] 云々。二十〔四十一丁〕に、伊波奈流伊毛波佐夜爾美毛可母 [イハナルイモハサヤニミモカモ] 云々。古今集大歌所に、かひがねをさやにも見しか云々とあるにてもおもふべし。 |
||||||||||
| 枕詞「嬬隠有(つまごもる)」考 | 代匠記 | ツマコモル屋上ノ山とそへたるは、人の妻は深き屋にすゑおく物なる故なり、第十二、妻こもるやのゝ神山とよめるも同じ心なり、凡家は南陽をうけて作る故に、女は北に陰の位に當て深く住めば、北堂北の方など云ことも有なり、或者に尋るに、備前赤坂ノ郡に、八上と云所有と申き、此に依て和名を考るに、げにも赤坂郡に宅 [ヤカ] 美あり、流布の本注を失へる故にえよまず侍りき、かゝれば備後備前海路の次なり、 | ||||||||||
| 攷證 | 嬬隱有 [ツマコモル]。 枕詞にて、冠辭考にくはし。古しへは、妻をおく屋をば、あらたに建などもして、つまごみにやへがきつくるなどいへれば、こゝも、妻の隱りゐる屋とつゞけしなり。さて宣長云、これをつまごもるとよむ事は、假字書の例あれば、うごかず。然るに、隱有と有の字をそへて書るは、いかゞ。有の字あれば、必らずこもれるとよむ例也。されば、有は留の字などの誤りにや云々。この説さる事也。猶可レ考。
|
|||||||||||
| 古義 | 嬬隱有 [ツマゴモル] は、屋 [ヤ] の枕詞なり、十卷にも、妻隱矢野神山 [ツマゴモルヤヌノカミヤマ] とあり、さてこれは、妻隱と書る字ノ意にて、妻を率 [ヰ] て隱 [コモ] る屋、といふ意につゞけたり、古事記須佐之男ノ命ノ御歌に、夜久毛多都伊豆毛夜幣賀岐都麻碁微爾夜幣賀岐都久流曾能夜幣賀岐袁 [ヤクモタツイヅモヤヘガキツマゴミニヤヘガキツクルソノヤヘガキヲ]、とよみ給へるを、合セ思フべし、又集中にも、妻屋 [ツマヤ] と多く見えたるも、妻隱る屋をいふ意なるを併セ考フべし、(契冲も、人のつまは、おくふかき屋にかくれゐて外の人にまみえぬものなれば、かくつゞくるなり、長流が、昔はつまやと云所を別に立置なり、今在郷にて、つのやと云は、遺風かと云り、と云たりき、今按フに、新婦 [ニヒヨメ] を、俗に新造 [シンザウ] といふも、古ヘ妻の住べき家を、新に造れるが故に、その心ばえを以て、後世まで新造と云り、このこと、既く伊勢氏四季草にもさだせり、蜷川殿中日記にも、御新造といふこと見えたりと云り、さてこの枕詞を、冠辭考に、手の端 [ツマ] にこもる箭、といふ意につゞけたり、と云るはいかにぞや、そもそもたゞに端 [ツマ] とのみにて、手の端 [ツマ] のことゝは、きこゆまじきがうへ、矢は、手挾 [タバサミ] と集中にも多くよみたる如く、手の端に隱る物に非ず、さて矢は物を射るこそ、其ノ主用にはありけれ、されば矢の意につゞけしならば、引放とか、何ぞさるべき詞の、あるべきことなるをや、書紀武烈天皇ノ卷影媛カ歌に、逗磨御暮屡嗚佐□嗚須擬 [ツマゴモルヲサホヲスギ]、とある嗚佐□ [ヲサホ] は、地ノ名ノの方も、枕詞よりのつゞきの方も、嗚 [ヲ] は、添たる詞のみにして、別に意なし、さてまくら詞よりつゞくよしは、佐□ [サホ] は、狹含 [サホ] の意なり、佐 [サ] は、狹 [セマ] く迫りたる意なるべし、又たゞ眞 [マ] といふに、通ふ言にてもあるぺし、凡ノ□ [ホ] と云詞は、含 [フヽ] まる意あることなり、さればこゝは、含まり隱りたる隱所 [カクレガ] の謂 [ヨシ] にして、所謂 [イハユル] 膳所 [クミド]、など云に同じ意ときこゆ、かれ妻を率て隱る、狹含 [サホ] とはつゞくなり、そもそもこの□ [ホ] の言は、集中に、保々麻流 [ホヽマル]、書紀ノ歌に、府保語茂利 [フホゴモリ] などある、保々 [ホヽ] 府保 [フホ] に通ひ、又陰處を、保登 [ホト] と云も、含處 [ホト] の意にて、同言なり、さて隱れる所を、保 [ホ] とのみ云るは、古事記倭建ノ命ノ御歌に、夜麻登波久爾能麻本呂波多々那豆久阿袁加伎夜麻碁母禮流夜麻登志宇流波斯 [ヤマトハクニノマホロハたヽナヅクアヲカキヤマゴモレルヤマトシウルハシ]、書紀には、麻本呂波 [マホロハ] を、摩倍羅摩 [マホラマ] と作り、私記に云、師説ニ謂二鳥乃和支之之太乃毛乎 [トリノワキノシタノケヲ]一、爲二倍羅摩 [ホラマト]一也、摩ハ謂三眞寶 [マホヲ]レ也、言ハ鳥ノ腋羽乃古止久 [ノゴトク] 掩藏之國也、案ニ ] 奧區也、と云るは、さることなり、又應神天皇ノ大御歌に、知婆能加豆怒乎美禮婆毛毛知□ [こざと+施の旁] 流夜邇波母美由久爾能富母美由 [チバノカヅヌヲミレバモモチタルヤニハモミユクニノホモミユ]、などある、久爾能麻本呂波 [クニノマホロハ]、また久爾能富 [クニノホ] も、國之含 [クニノホ] と云にて、國中の含 [フヽ] まり隱れる處を云ば、今と同じ、然るを、此等を國之秀 [クニノホ] といふ説は、いかゞなり、凡ソ秀 [ホ] と云詞は、物の灼 [シル] く、あらはれ出たるを云言なれば、夜麻登波 [ヤマトハ] 云々の御歌、青垣山隱有 [アヲカキヤヤゴモレル]、とあるにつゞきたれば、國の秀 [ホ] とは云べからず、又知婆能 [チバノ] 云々も、家庭 [ヤニハ] も所見 [ミユ] とあれば、國の秀出 [ヒデ] たる所の見ゆるは、のたまふまでもなければ、國の秀 [ホ] とはのたまふまじきなり、故レこれら、必ス國之含 [クニノホ] なるを辨ふべし、冠辭考に、この嗚佐□ [ヲサホ] とかゝれるも、小箭 [ヲサ] と云かけたるなるべし、といへるは、あらざること、上に云るが如し、) 本居氏ノ玉ノ小琴ニ云、是をつまごもるとよむことは、假字書の例あれば動かず、然るに隱有と、有ノ字をそへて書るはいかゞ、有ノ字あれば、こもれるとよむ例なり、されば有は、留ノ字などの誤にや、 | |||||||||||
| 全釈 | 嬬隱有 [ツマゴモル] ―― 屋の枕詞である。妻を迎ふる爲に屋を作り、その内に妻と籠るのである。この句から渡相月乃 [ワタラフツキノ] までは雖惜 [ヲシケドモ] といはむ爲の序詞。今、雲間を月が渡るのではない。 | |||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】 妻とこもる屋、の意で、屋上山にかけた枕詞。「嬬」の字、金澤本脱す。元暦校本・紀州本、「儒」に誤る。 |
|||||||||||
| 「屋上乃山・室上山」考 | 代匠記 | 一本の室上山、此山は何處と云ことをしらず、山の字は衍文か、さらずば乃の字なるべし、 | ||||||||||
| 童蒙抄 | 童子問 屋上の山並室上山何國に在山にや。 答 前の渡の山に准して、此山も石見國の山の名とす。 |
|||||||||||
| 万葉考 | 屋上乃山乃 [ヤガミノヤマノ]、 渡山と同じ程の所といへり、かゝれば和多つは、いよゝ府に近き事顯はなり、さて府を立て此山遠からぬ所に宿りてよめるならん、 | |||||||||||
| 略解 | 屋上の山も渡の山と同じ程の所と言へり。さて府を立ち去りて、此山遠からぬ所に宿りて詠めるなるべし。 | |||||||||||
| 攷證 | 屋上乃山 [ヤカミノヤマ] 冠辭考云 (上「つまごもる、参照」)、屋山 (マヽ) の山は、光仁紀和名抄等にも、因幡國に八上郡あるによりて、この人麿、石見より山陰道を經て上られしにやといふ人あり。道の事は、しか也。屋山 (マヽ) は、この歌によめる心も、詞も、妻に別れたる、其日より、其夜までの事也。然れば、因幡の八山 (マヽ) にはあらで、遠からぬ程の山ならん云々。この説當れり。さて、一云室上山の五字を、印本山の字の上に入たれど、集中の例によりて、山の字の下に入たり。この一書の室上も、訓は同じけれど、文字のかはれるによりて、あげたるなるべし。 |
|||||||||||
| 古義 | 屋上乃山乃 [ヤカミノヤマノ]、舊本一ニ云、室上山とあり、屋上 [ヤカミ] も、渡 [ワタリ] の山と同じほどの處に在リと云り、今國人に聞クに、渡リの山八上山、いづれも邑知ノ郡にて、矢上村といふに、今原山と呼 [イヘ] るがある、それ即チ八上山なり、かくてその原山の中に、布于山といふがありて、きはめたる高山なりといへり、それをおしこめて、古ヘは屋上の山といへることさらなり、さればさる高山なるによりて、その雲間を、月の渡るよしに云るなるべし、(水戸侯釋に、或者に尋るに、備前赤坂ノ郡に、八上と云所ありと云り、此に依て和名抄を考フるに、赤坂ノ郡に宅美あり、流布本には、註を失へる故に、えよまずありしを、或者の説に思ひ合すれば、宅美は、「ヤカミ」 なりとさだめ、あげつらひ賜へり、しかれども、「ヤカミ」 に、宅美の訓音の字を、用ひたりとせむこといかゞ、なほ國人にも問ひて、委しく正すべきことなり、其 [ソ] はいかにまれ、今の屋上山は、なほ渡ノ山に隣りたる、山なるべくこそ思はるれ、玉ノ小琴ニ云、屋上の山の、と切て、隱ひ來れば、と下へつゞくなり、惜けども、屋上の山の隱れて見えぬよしなり、さて雲間より渡らふ月の、と云二句は、たゞ雖惜 [ヲシケドモ] の序のみなり、わづかなる雲間を行間の月は、惜きよしの序なり、もし此ノ月を、此ノ時の實の景としては、入日刺 [イリヒサシ] ぬれといふにかなはず、このわたりまぎらはし、よくわきまふべしといへり、此ノ説おもしろし、かく見る時は、山乃 [ヤマノ] の詞を、姑く山我 [ヤマガ] にかへてきく時は、意明なり、かく我 [ガ] の意の所を、乃 [ノ] といへること、古語に多し、八卷に、霍公鳥音聞小野乃秋風芽開禮也聲之乏寸 [ホトヽギスコヱキクオヌノアキカゼニハギサキヌレヤコヱノトモシキ]、とあるも、小野我 [ヲヌガ] といふ意なり、この類多し、准へ知べし、さて此ノ説によるときは、屋上山を、府のあたりにありとせるなるべし、しかれども、府のあたりに、屋上山ありといふ證を出さゞれば、おぼつかなし、かくてこの詞つゞきを、今一たびうちかへして、味ヒ見るに、大舟之渡乃山之黄葉乃散之亂爾妹袖清爾毛不見 [オホブネノワタリノヤマノモミヂバノチリノミダリニイモガソデサヤニモミエズ]、とあるに對へて、嬬隱有屋上乃山乃自雲間渡相月乃雖惜隱比來者 [ツマゴモルヤカミノヤマノクモマヨリワタラフツキノヲシケドモカクロヒクレバ] と云るにて、各々六句づゝいへるに、前の大舟之云々の六句は、聞えたるまゝなるに、後の嬬隱有 [ツマゴモル] 云々の六句を、自雲間渡相月乃雖惜嬬隱有屋上乃山乃隱比來者 [クモマヨリワタラフツキノヲシケドモツマゴモルヤカミノヤマノカクロヒクレバ]、と句を置かへて、きかむこと快からず、すべて對句は、一ツがなだらかなれば、一ツもなだらかに云つらね、一ツを句を置かへて、きくべく巧ミたれば、一ツをも句を置かへて、きくべく巧て云つらぬること、古ヘの長歌のさだまりなればなり、さればなほ、嬬隱有 [ツマゴモル] 云々の六句も、聞えたるまゝにて、さて屋上山は、渡ノ山のあたりにありとせむこと、穩なるべし、さて其意は、なほ次々にいふべし、) | |||||||||||
| 全註釈 | 【釈】 屋上乃山乃 ヤカミノヤマノ。島根縣那賀郡淺利村附近の高仙 [タカセン] 山のことであるという。因幡の八上郡の山ともいうが、因幡と石見とのあいだには出雲の國があるので、遠すぎよう。 一云室上山 アルハイフ、ムロカミヤマノ。屋上乃山乃の句の別傳であろうが、その山は所在未詳である。 |
|||||||||||
| 評釈 | 【語】 屋上山 一に云ふ室上山と同じく、今那賀郡松川村大字八神の地の山(全釋)とも、今高仙山といひ同郡淺利村より十數町の山(日本地誌提要)ともいはれる。しかし室上山と屋上山と同じ山をさすかどうか明かでない。 |
|||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】 日本地誌提要に「高仙山〔又屋上山ト云那賀郡浅利村ヨリ十三町五間〕」とあるを講義に引いて「浅利村は渡津より東、山陰道の要路に当たれば、この邊に屋上山といふがある以上はそれなるべし」とあるによる。旧参謀本部の地図に「室神山或小富士」とあるものがそれである。「一云々室上山」とあるのでその室上即ち今の室神で、屋上は別にあるやうに考へられるかと思ふが、「室」の字はまた「ヤ」とも訓み得る字であり、その用例 (3・307-309) もある。人麻呂は前に和多豆とも柔田津とも書いたやうに、屋上とも室上とも書いたので、同じく「ヤガミ」であつたが、集の編纂者は室上を「ムロガミ」と訓み別の山と考へて注を入れたので、後には室上の字に引かれて「ムロガミ」とも呼ばれるやうになり、-スミノエが「住吉」の字によつて「スミヨシ」となつたやうに-文字もまた上を神とも書くやうになつたと見れば極めて自然に落ち着く事が出来る。それより南の江川の北岸の八神の地とする説 (地名辞書) や、更に遥かに南の邑智郡矢上村 (今、石見町のうち) とする説 (新講) などもあるが、位置から云つてもあたらない。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】「嬬ごもる屋上の山・一に云ふ、室上山」 -屋上の山は、代匠記に備前赤坂郡の八上を考え、万葉考には、前の渡の山と「同じ程の所」としているが、山田講義には、日本地誌提要の「高仙山〔又屋上山ト云那賀郡浅利村ヨリ十三町五間〕」を引き、「浅利村は渡津より東、山陰道の要路に当たれば、この邊に屋上山といふがある以上はそれなるべし」と言う。茂吉評釈には、「浅利の停車場に近付くころ、また過ぎてからも暫時のあひだ見える形の好い山で、次の句の月のことを参照すればこの山だらうといふ想像もつく」と記されている。浅利は、江津の東、都野津とは反対の側にあたる小駅である。澤瀉注釈には旧参謀本部の地図に「室神山或小富士」として高仙山が記入されていることを指摘し、「一云、室上山」という異伝は、屋上山と同じ山を室上山とも記したのを、集の編輯者は「ムロカミ」と訓み別の山と理解したのではなかろうかと推測している。澤瀉は、前の「和多豆」と「柔田津」も単なる表記の差異と見ているが、これは「一云」という異伝全体釈にかかわる問題として把えられねばならぬ側面を持つ。「柔田津 (ニキタツ)」と「和多豆 (ワタヅ)」が異なるように、「屋上 (ヤカミ)」と「室上 (ムロカミ)」と異なるとも考えられよう。 一に云ふ、室上山 この注は、本来「屋上乃山」の下に記入されるべきで「乃」の次に入れられているのは誤り。巻三に「三穂乃石室」 (307)、「常磐成石室」 (308)、「石室戸尓立在松樹」 (309) という「石室 (イハヤ)」 の例があり、「室」は「ヤ」と訓み、屋に等しいとも考えられるので室上山は「ヤカミノヤマ」と訓むべしとする攷證以来の説に賛同する注者もあるが (茂吉評釈・注釈など。講談社文庫は本来ヤカミを表記したものを編者が誤解したという)、石室は石造りのむろを意味する熟字で、それを邦語の「イハヤ」に宛てたのが「三穂乃石室」などの例であろう。人麻呂歌集に「新室」 (11・2351、2352) とあるのも「ニヒムロ」であって「ニヒヤ」ではない。万象名義には室を「舒逸反宮・由・巣容・舎」、屋を「於鹿反居・形・舎」と注されていて通ずるところなしとしないが、万葉集や古事記に「室」一字で「ヤ」に宛てた例を見ないのは、両字を別義と見ていたのであろう。「ムロ」は、四囲をきっちり囲んだ室で、自然の岩を利用したものが「イハヤ」である。その他山腹などを掘って作られたもの、壁を塗りこめた家などをも言うらしい。室上山は「ムロカミヤマ」であろう。「嬬隠有」との関係は、夫婦のこもる新室の意で「ムロ」に冠したと解される。武烈紀の「つまごもる 小佐保を過ぎ」の例は、掛かり方が不明。なお「一云」という異伝の扱い方については、138歌の條に補説する。 |
|||||||||||
| 原文「自雲間 渡相月乃 (くもまよりわたらふつきの)」注 |
拾穂抄 | わたらふ 渡相月の空をわたる事也とをる事也 | ||||||||||
| 代匠記 | クモマヨリ渡ラフ月とは.雲の絶間に見えて西に渡月なり、雲間の月としも云ことは、下の二句を云んが爲なり、 | |||||||||||
| 童蒙抄 | 渡相月乃 童子問 渡相月の三字を、わたらふつきとよみ來れり。此訓しかるへしや。 答 しかるへきか。うつらふ月ともよむへきか。月はうつりぬなとゝ、此集の歌にみえたる所あり。又夜わたるつきともよめはわたらふ月も難有ましき也。 |
|||||||||||
| 万葉考 | 自雲間 [クモマヨリ]、渡相月乃 [ワタラフツキノ]、 妹があたりの、山に隱る、惜さを、月の雲隱るに譬ふ、 | |||||||||||
| 略解 | ワタラフ月はカタブク月をいふ。妹が當りの山に隱るる惜しさを、月の雲隱るるに添へて言へるのみにて、此月は實の景物にあらず。屋上ノ山ノと切りて隱レ來レバと言ふへ續けて心得べし。 | |||||||||||
| 攷證 | 自雲間 [クモマヨリ]。 この自 [ヨリ] は、をの意にて、古事記上卷に、箸從 [ヨリ]二其河一流下云々とあるも、その河を流れ下る也。また本集八〔廿四丁〕に、霍公鳥從此間鳴渡 [ホトヽキスコヽユナキワタル] 云々とある從 [ユ] も、よりの略にて、こゝをの意也。古今集春下、詞書に、山川より花のながれけるを云々とある、よりもおなじ。 渡相月乃 [ワタラフツキノ]。 わたらふの、らふは、るを延 [ノベ] たるにて、らふの反、るなれば、わたる月といふ意也。本集十一〔九丁〕に、雲間從狹徑月乃 [クモマヨリサワタルツキノ] 云々とも見えたり。さて、夜わたる月、つきわたる、また郭公鴈などの鳴わたるなどいふも、みな過る意なると去意なるとの二つ也。そは、廣雅釋詁三に、渡ハ、過也云々。廣韻に、渡ハ、過也去也云々とあるにても思ふべし。ここなる渡相 [ワタラフ] 月は、ゆく月と心得べし。宣長云、屋上の山のと切て、隱 [カクロ] ひ來ればといふへつゞく也。 |
|||||||||||
| 古義 | 自雲間 [クモマヨリ] は、雲間をと云むが如し、こゝの自 [ヨリ] は、をと云に通へり、上に委ク云り、さて高き山は、常に雲居れば、その屋上山の雲間を、と云意なるべし、かくてわづがなる、雲の透間より見ゆる月影は、やがてまた雲に隱るれば、をしき謂
[ヨシ] にいひつゞけたるなり、さて次に、入日刺奴禮 [イリヒサシヌレ] とあれは、實にこの時、月を見ていへるにはあらじ、只雖惜 [ヲシケドモ]
といはむ爲の序のみに、其ノ地の山の月のさまを云て、設いでたることばなるべし、前に渡リの山の黄葉を云たれば、後には、屋上の山の月をやとひて、對偶
[タグヒ] をとゝのへたるなり、 渡相月乃 [ワタラフツキノ] は、渡る月之 [ツキノ] にて、高山の雲間を、歴わたり行ク月のよしなり、(略解に、わたらふ月は、かたふく月を云、と云るは、いみじきひがことなり、) 和多良布 [ワタラフ] は、和多留 [ワタル] の伸りたる言にて、霧相 [キラフ] 散相 [チラフ] などの如し、伸ていふは、その歴わたり行さまの、緩なるをいへる詞なり、さて以上四句は、雖惜 [ヲシケドモ] を云むための序なり、 |
|||||||||||
| 全註釈 | 【釈】 自雲間渡相月乃 クモマヨリワタラフツキノ。ワタラフは、渡ルの續いて行われるをいう。雲のあいだを渡る月で、たちまち隱れて見えなくなるので、次の惜シケドモ隱ラヒ來レバを引き起している。これは實景ではなかろう。以上、嬬ゴモル以下この句まで序詞。 |
|||||||||||
| 評釈 | 【語】 渡らふ月の 渡らふは、渡るに繼續を表はす「ふ」のついたもの。「の」は如くの意。雲間より以下は、次句惜しけどもの序。 |
|||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】 この「より」は「み井の上より」 (111) の「より」と同じく、「を」といふに近い。「渡らふ」の「ふ」は継続の意の助動詞 (1・5)。「妻ごもる」よりこの句まで四句は「惜し」にかかる序である。作者が通路の山の名を用ゐ、その山の雲間を渡る月の如く、と云つたので、月そのものを眼前にしての景と考へなくてよい。 二上に隠ろふ月の惜しけども妹がたもとを離(かか)るるこのころ (11・2668) の例もある。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】 雲間を経て大空を移り行く月のように、の意。「嬬ごもる」以下四句、次の「惜しけども 隠らひ来れば」にかかる比喩的な序詞。ヨリは経由を示す助詞。雲間ヨリは、雲間をというのに近い。ワタラフのフは、継続または反復をあらわす接尾語 (助動詞とする説もある)。ここでは、渡ってゆくことの時間的継続をあらわしている。宣長の玉の小琴に「屋上の山のと切て、隠らひくればと云へ続く也。惜しけども屋上の山の隠れて見えぬ由也。さて雲間より渡らふ月のと云二句は、只雖惜の序のみ也。纔なる雲間をゆく、間の月は惜きよしの序也。若此月を此時の実の景物としては、入日さしぬれと云に叶はず。此わたり紛はし、よく辨ふべし」と言い、佐佐木評釈にも「雲間より渡らふ月の」という二句を序とする解を見る。宣長説は実景か否かということと序の長さとに問題を含んでいるし、佐佐木説も二句のみを「惜しけども」にかかる序と考えている点が、「嬬ごもる」以下四句を序とする説 (評釈篇・全註釈・私注・古典大系・古典全集・古典集成・講談社文庫) と対立するのである。しかし宣長のように「惜しけども屋上の山の隠れて見えぬ由也」という解には従いかねるだろう。前の「妹が袖 清にも見えず」に対して「惜しけども 隠らひ来れば」があるのであって、隠れるのは妹の家のあたりでなければならない。また実景ならずとする説は、山田講義に「曇りたる夜に東より西に渡り行く月の偶雲間より見ゆるが、それも間もなくかくれ行くべきなれば、かくはいへるなり」と記すように、月の隠れるのを夜景と解し、「嬬ごもる」以下四句を非実景とするのである (評釈篇・全註釈・注釈など)。これを夜景と定めれば、講義のようにも解されるが、窪田評釈に「『嬬隠る』以下これまでの四句は、道行き体の風景としていっているもので、屋上の山の実景である」と記す通り、日の入り前の実景とも解されるだろう。夜ではないが、淡い月の仰がれるのを序としたものとして味わいうるのである。 |
|||||||||||
| 原文「雖惜(をしけども)」訓・考 | 代匠記 | [雖惜 ヲシメトモ] 雖惜はヲシケレドとも讀べし、 |
||||||||||
| 万葉考 | 雖惜 [ヲシケレド]、 | |||||||||||
| 攷證 | 雖惜 [ヲシケドモ]。 舊訓、をしめどもと訓るも、考にをしけれどゝよまれしも、いかゞ。をしけどもとよむべし。をしけどもは、をしけれどもの、れを略ける也。そは、木集五〔十丁〕に、伊能知遠志家騰 [イノチヲシケト] 云々。十一〔廿九丁〕に、隱經月之雖惜 [カクラフツキノヲシケドモ] 云々。十七〔廿三丁〕に、伊乃知乎之家騰 [イノチヲシケド] 云々など見えたり。また、四〔廿五丁〕に、遠鷄跡裳 [トホケドモ] 云々。十五〔卅一丁〕に、由吉余家杼 [ユキヨケト] 云々。十七〔卅三丁〕に、等保家騰母 [トホケドモ] 云々などあるも、みな同格の語にて、れを略ける也。 |
|||||||||||
| 古義 | 雖惜は、「ヲシケドモ」と訓て、をしけれども、といふ意になるは古言なり、さて妹が家の、あたりの遠く放り隱れ來ぬることの、惜くはわれどもの意なり、十一に、二上爾隱經月之雖惜妹之田本乎加流類比來 [フタガミニカクロフツキノヲシケドモイモガタモトヲカルルコノゴロ] とあり、 | |||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】 原文「雖惜」を旧訓にヲシメトモとし、万葉考にヲシケレドと改め、さらに略解にヲシケドモとした。形容詞の已然形は後世同様「由遊志計礼杼母 (ユユシケレドモ)」 (199) の如く「ケレ」といふ形もあるが、「遠鶏跡裳 (トホケドモ)」 (4・553)、「伊能知遠志家騰 (イノチヲシケド)」 (5・804)、「由惠波奈家杼母 (ユヱハナケドモ)」 (14・3421)、「奈良能於保知波 由吉余家杼 (ナラノオホチハ ユキヨケド)」 (15・3728) の如く、未然形と同様「ケ」の形が多く用ゐられてゐるので、今も略解の改訓によるべきものと思ふ。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】 原文「雖惜」は講義に詳述されているようにヲシケドモと訓む。
|
|||||||||||
| 原文「隠比(かくらひ)」訓・考 | 代匠記 | カクロヒクレバとは、故郷も妹が袖も隱るゝなり、此は別の悲を別來てよむ故に、經る所の次に寄て言を綴るなり、孟子のいはゆる志をむかへて見るべし、筌を忘ずして強て理窟を探らざれ、 | ||||||||||
| 古義 | 隱比來者 [カクロヒキツヽ] 隱比來者は、按フに、者ノ字は、乍の草書を誤寫せるなるべし、「カクロヒキツヽ」 とあるべし、隱比 [カクロヒ] は、加久理 [カクリ] の伸りたるにて、緩なるをいふ、その緩なるは、漸々に隱來るよしなり、 |
|||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】隱比來者 [カクラヒ] 「隠比」は「カクロヒ」と訓み来つてゐるが、「隠る」に「ふ」 (1・5) がつづく場合は未然形を受ける例である。しかし「ラフ」が「ロフ」となる例もあるので、「カクロヒ」とならないとは云へない。しかし「カクロヒ」の仮名書例がなく、「隠合時」 (10・1980) の例があり、「合」の文字の用ゐられてゐる事は、「左丹頬合 (サニツラフ)」 (12・3144) の用例から考へても「カクラフ」又は「コモラフ」と訓むべきものと思はれるので、今も「カクラヒ」と訓むべきだと考へる。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】隱比來者 [カクラヒ] 「隠比」は「カクラヒ」と訓む。巻三に「渡る日のかげも隠比」 (317)、巻十一に「二上に隠経月の惜しけども妹が手本を離るるこのころ」 (2668) の例がある。「カクラヒ」は「カクル」に継続の「フ」の連用形の接した形。注釈に「カクロフ」と訓めなくはないが、巻十に「霍公鳥 隠合時尓」 (1980) とあるのは、「左丹頬合 (サニツラフ)」 (12・3144) の例から考えても「コモラフ」と訓むべきであり、それと同様に「カクラフ」とすべきだろうと記しているのに従う。 |
|||||||||||
| 枕詞「天傳(あまづたふ)」訓・考 | 拾穂抄 | あまつたふは日の天をゆく事也 | ||||||||||
| 代匠記 | 天傳 [アマツタフ] 天傳入日サシヌレとは、日は天路を傳ひ行故にかくつゞく、下にも多し、第三には久方天傳來自 [ヒサカタノアマツタヒコシ]とのみもよめり、第七に天傳日笠浦 [アマツタフヒガサノウラ] とあるを六帖に「あまつたひ」 とよみたれば、今もしかよむべし、第三を以て證すれば、やがて日の名なり、さしぬればと云ざるは古語なり、加て意得べし、夕になれば彌陰氣に催されて、日比大丈夫と思あがりしかひなく離別の悲に袖をしぼるとなり、 |
|||||||||||
| (童蒙抄) | 雖惜隱比來者天傳入日刺奴禮 童子問 天傳入日刺奴禮の七字を、あまつたふいりひさしぬれと、よみ來りたれとも句意心得かたし。或説に日は大空を傳ひ行心地といひて、夕になれは陰氣に感し、心ほそくなるなる躰をいふといへり。しかりや。 答 上に、自雲間渡相月乃雖惜隱比來者といふ句に對する句なれは、先達よみ來れる訓にては義不レ通。訓の誤りなるへし。刺奴禮といふ詞もいはれす。句證も句例もなくて、みたりに訓すへきことにあらす。此七宇とかくに異訓有へし。 童子又問 先生賢按の訓はなき事にや。 答 なきにあらねとも、決めて僻案の訓を是ともおもはす。猶好訓有へしとおもへは、しはらくさしおく也。 童子強て請問 答 強て問にはもたしかたし。天傳はあめつたふにて、雨ふらんことを示したるを、あめつたふといふか。其證此集にあめつたふひかさのうらといふ句あり。日かさは日笠也。日の笠をきれは、必三日の内雨ふるしるしといひ傳へたれは、雨傳日笠の浦とつつけたるなるへし。是を句證として、此天も雨傳の借訓なるへし。入日の二字は、虹といふか。日を入る方は西なれは、入日とかきてにしと用ひたるか。これにてはしを濁りかたき故に、西にはあらすして入日の字の音を用ゐたるか。しからは入日にの音呉音なり。日ハシツにては漢音なれは、これをいかゝとおもふ也。されとしらじといふを、しらにと古語に用ゐたれは、入日をににと呉音に用ひて、虹にならんや。此所いまた決せぬか故に、的當の案訓ともおほえされはもらしかねたり。しかれとも、入日をいりひとよみては義かなはす。刺奴禮はさしやつれなるへし。されはあめつたふ虹さしやつれにては、句意もきこゆへし。奴はやつことよめは、奴禮はやつれなるへし。虻も常言にさすといへは、虹さしやつれといふに難有へからす。是僻案の一訓也。 童子又問 入日さしは、上の句に對して相叶ふ賢訓なるへし。しかれともやつれといふ詞いまた心得かたし。如何。 成る所也。人麻呂官位有人とみえす。しかるを正三位なとゝいへる妄説とるにたらす。古今集の長歌にも、身はしりなからとよめる家稱にて、無位無官の人とみえたり。もし有位ならは、至極下位の人なるへし。されは旅行のやつれをよめる歌、此集中に見えたれは、かれこれを相考へて此句を解るに、虹刺奴禮は旅行の荷刺やつれたるとよめるなるへしかくみれは、天曇り雨を傳ふ旅行に、荷おもくさしやつれたれは、丈夫とおもへる吾もと、下の句へ旅愁の涙、襟をひたす感慨きはまりなかるへし。此僻案歌をしる人にあらすしてはかたりかたし。 |
|||||||||||
| 攷證 | 天傳 [アマツタフ]。 枕詞にて、冠辭考にくはし。天路を傳ひゆく日とつゞけし也。下〔攷證三下卅丁〕をも考へ合すべし。
|
|||||||||||
| 古義 | 天傳 [アマヅタフ] は、日の枕詞なり、これは天路をつたひ行ク日、とかゝれるなり、(入日は、夕日にて、枕詞よりは、入り言には關らず、) | |||||||||||
| 全註釈 | 天傳 アマヅタフ。枕詞。天空を傳う意で日に冠する。假字書きの例は無く、皆、天傳と書いている。「天傳 [アマヅタフ] 日笠浦 [ヒガサノウラニ] 波立見 [ナミタテリミユ]」 (卷七、一一七八)。 | |||||||||||
| 全注 | 【注】天傳 [アマツタフ] 「アマツタフ」は大空を伝い渡る意で、入り日にかかる枕詞。「天傳」を代匠記に「アマツタヒ」と訓んだが (精撰本)、「天伝日笠の浦に波立てり見ゆ」 (7・1178)、「天伝日のくれぬいれば」 (13・3258)、「天伝日のくれゆけば」 (17・3895) という集内の例から「アマツタフ」が正しいと推測される。なお、「アマヅタフ」と濁音に訓む注釈書が多いが (万葉考・古義・略解・評釈篇・佐佐木評釈・全註釈・窪田評釈・注釈・私注・古典全集・古典集成など)、講義や古典大系のように清音にも訓みうる。「アマテラス」に「安麻泥良須 (アマデラス)」と濁音化した例を見るように、「天伝」も後には「アマヅタフ」と発音されるようになったかも知れないが、枕詞「天伝」のもっとも古い例として、清音のままとする。 |
|||||||||||
| 「入日さしぬれ」注 | 拾穂抄 | さしぬれ さしぬれはといふはの字を略せしなるへし此集に此てにをはおほし今はこのむましきにや | ||||||||||
| 万葉考 | 入日刺奴禮 [イリヒサシヌレ]、 夕べに成ていよゝ思ひまされり、 | |||||||||||
| 略解 | 入日サシヌレは、ヌレバのバを略けり、前にも此例出づ。夕べに成りて彌思ひまさるなり。 | |||||||||||
| 攷證 | 入日刺奴禮 [イリヒサシヌレ]。 上に、こそのかゝりなくして、れとうけたるは、集中長歌の一つの格也。そは、本集三〔五十四丁〕に、晩闇跡隱益奴禮 [ユフヤミトカクリマシヌレ] 云々。また〔五十八丁〕久堅乃天所知奴禮 [ヒサカタノアメシラシヌレ] 云々。五〔五丁〕に、宇知那比枳許夜斯努禮 [ウチナヒキコヤシヌレ] 云々などありて、集中いと多し。また、こそなくして、せとうけたるもあり。この事は、下〔攷證五下〕にいふべし。これらの、れ、せなどの下に、ばを加へて、れば、せばなどと見れば、よく聞ゆと、宣長いはれぬ。 |
|||||||||||
| 古義 | 入日刺奴禮 [イリヒサシヌレ] は、入日刺奴禮婆 [イリヒサシヌレバ] の意なり、一ノ卷營二藤原宮一役民ノ歌に、浮倍流禮 [ウカベナガセレ] とある下に委ク云り、入日 [イリヒ] は、夕日なり、上に出づ、さらぬだに、夕暮は物がなしきものなるに、かゝる別をさへしければ、いとゞ堪がたきよしなり、 | |||||||||||
| 全註釈 | 【釈】 入日刺奴禮 イリヒサシヌレ。入日がさしたからという意の條件法である。日が暮れて、入日のさしわたる頃となつたから。「あしひきの山邊をさして、夕闇と隱りましぬれ、言はむ術せむ術知らに」 (下略)(卷三、四六〇)、「ひさかたの天知らしぬれ、こいまろびひづち泣けども爲 [せ] む術 [すべ] も無し」 (同、四七五) など、この語法である。バを補つて、入日さしぬれば、知らしぬればというように解してよい。 |
|||||||||||
| 評釈 | 【語】 入日さしぬれ 入日がさして來たので。 | |||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】 入日さしぬれば、の意。「かくなれこそ」 (1・13)、「あまなれや」 (1・23)、「思ほしせめか」 (1・29) などは已然形に「こそ」「や」「か」の助詞がついて下へつづくものであるが、今のは已然形が条件法になつて直接下へつづくものである。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】 「イリヒサシヌレ」は、入日さしぬればの意。山田孝雄『奈良朝文法史』に「順続的確定条件をあらはすに用言の已然形を以て直にあらはし、接続助詞を伴はずしてあることあり」と述べるように、已然形を述語とする句の全体を後句相関させる一つの接続型式であり、両句の間には、前句が後句の原因理由にあたる意味関係の認められることが多いのである (山口堯二『古代接続法の研究』)。もっとも、因由性以外の意味関係のある例も見え、「さ婚ひに あり立たし 婚ひに あり通はせ 大刀が緒も 未だ解かずて・・・」 (記二歌) のように機縁性の関係を示す場合もある。「イリヒサシヌレ」の場合は、あとの「衣の袖は 通りて濡れぬ」の理由を示す。 |
|||||||||||
| 新大系 | 【脚注】 「入日さしぬれ」は、「入日さしぬれば」の意。「さてここの『奴礼』は已然形のままにて条件を示す古の語格の一にして、後世の語ならば、この下に『ば』を加へてさて下につづくるものなるが、ここはその『ば』なくして、しかも、下の語の条件となるなり」 (『講義』)。「大雪の乱れて来たれ」 (199)、「夕闇と隠りましぬれ」 (460)、「山隠しつれ心どもなし」 (471)、「ひさかたの天知らしぬれ」 (475)。 |
|||||||||||
| 新全集 | 【頭注】 入日さしぬれ-入日がさしたので、已然形で言い放つ法。上代語では、接続助詞「バ」がなくても已然形そのままの形で順接確定 (その大半理由格) を表すことがあった。→ 118「恋ふれこそ」。 |
|||||||||||
| 原文「大夫」異同(童蒙抄) | 童蒙抄 | 大夫跡念有吾毛 童子問 此歌にも大夫と有は誤字にや。 答 しかり丈夫に改むへし。 |
||||||||||
| 「敷妙乃 衣袖者 通而沾奴」考 | 仙覚 | 敷妙乃衣袖者通而沾 [シキタヘノコロモノソテハトホリヌレ] 奴。シキタヘトハ、ウチマカセテハ、枕ニコソイヒナラハシテハヘレトモ、此集ニハ、シキタヘノ衣、シキタヘノソテナトモヨメリ。シキトイフハ、シケシトイフコトハ、タトヘハホムルコトハナレハ、ツネニタヘナリトイハンコトハニハ、ナニコトモイハレヌヘキニヤ。タトヘハ、トコメツラナトイフカコトシ。裏書云、押紙云、私云、敷妙トイフハ、敷義歟。シケキ義不審、可決之。 | ||||||||||
| 拾穂抄 | しきたへ 奥儀抄にしく心云々此折此景に感涙深しと也 | |||||||||||
| 童蒙抄 | 敷妙乃衣袖者通行沾奴 童子又問 敷妙乃衣といふこと心得かたし。或説に敷妙の衣の袖とは、袖をは枕にして常にぬるものなれはいふとあり。衣をしくものにも有へからねは、此説も心得られす。如何。 答 よきうたかひ也。袖をは枕にして、常にぬるといふこともいはれす。たとへといふは、荒妙和妙なといひて衣服の名也。拷の宇を用ひ來れり。拷は楮の字の誤りとみえたれとも、今更改めかたけれは、楮の誤字としりて、舊きにしたかふて、私に改めぬを故實を守るとする也。伊弉册の册の宇の類也。南の字の誤りとしりなから、册の字を通用する也。さてしき拷と云は、しきは稱美の辭にて、只拷といふまてと心得へし。敷の字義にはよるへからす。是も僻案には敷妙とかきてうつたへとよむ也。うつは稱美の詞なれは、しき妙うつ妙おなしことといふへけれとも、しきたへといふかな書をみす。布たへと書たる所あれは、布の字はしきとは訓へけれともうつとはよみ難しと難する人あるへし。それはうつたへにあらす。あらたへとよむへき也。荒妙を布をいへは也。是一僻案也。 童子又問 布拷をあらたへとす。義讀にてさもよむへし。敷の字をうつとよみたる證例ありや。 答 あり。令集解神祇令に古訓みえたり。 童子又問 仙覺抄にはしきたへとは、うちまかせは枕にこそいひならはしてはへれとも、此集にはしきたへの衣、しきたへの袖なととよめり。しきといふは、しけしといふこと也。たとへはほむること也。なれはつねにたへなりといはん詞には、なに事もいはれぬへきにや。たとへはとこめつらなといふことしと云云とあり。これも誤りなるへきか。 答 しき妙の説先達の説々みなとるにたらす。只しきたへとよむ語例を求めて、可否をしるへし。かなつけの本にしたかひて古語有ときはむる事有へからす。うつたへといふ古語あまたあり。打酒打麻打ゆふその數つくしかたし。 |
|||||||||||
| 万葉考 | 敷妙乃 [シキタヘノ]、 冠辭、こは夜 [ヨル] のものをいふ辭にて、即宿りしての思ひをいへり、 衣袖者 [コロモノソデハ]、通而沾奴 [トホリテヌレヌ]、 卷十九に、潜□[盧+鳥][ウヲカフ] 歌とて、「吾妹子が、形見がてらと、紅の、八しほに染て、おこせたる、ころものすそも、通りてぬれぬ」 とよめるは、下にかさね着し紅衣と聞ゆ、然れば上より下のかさねかけてぬるゝといふめり、今も此如く下の袖までなみだにぬれとほりしなり、(卷十一)「吾袖は、多毛登等保里 [タモトトホリ] て、ぬれぬとも、戀忘貝、とらずばゆかじ」 といへるは、はた袖より臂のもとかけて、ぬれのぼるをいひて、今とはいささかことなり、 |
|||||||||||
| 略解 | 敷タヘノ枕詞、是は夜の物をいふ詞なり。ますらをと思ひ誇りて在りし吾も下に重ねし衣の袖まで涙に濡れ通りしとなり。 | |||||||||||
| 攷證 | 衣袖者 [コロモノソデハ]。通而沾奴 [トホリテヌレヌ]。 本集十〔十六丁〕に、春雨爾衣甚將通哉 [ハルサメニコロモハイタクトホラメヤ] 云々。十三〔十一丁〕に、吾衣袖裳通手沾沼 [ワカコロモテモトホリテヌレヌ] 云々。十五〔廿八丁〕に、和我袖波多毛登等保里弖奴禮奴等母 [ワカソテハタモトトホリテヌレヌトモ] 云々などありて、重ね著たる袖の、うらまで通りて、ぬれぬと也。 |
|||||||||||
| 古義 | 敷妙乃 [シキタヘノ]は、枕詞なり、既く出づ、 通而沾奴 [トホリテヌレヌ] は、袖の表より裏まで、濕達 [ヌレトホ] りぬとなり、十五に、和我袖波多毛登等保里弖奴禮奴等母 [ワガソデハタモトトホリテヌレヌトモ]、十九に、服之襴毛等寶利弖濃禮奴 [コロモノスソモトホリテヌレヌ] などあり、奴 [ヌ] は已成 [オチヰ] の奴 [ヌ] なり、 |
|||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】通而沾奴 [トホリテヌレヌ] 袖の中までも通つてぬれた、の意。前 (131) に引用した「和我袖波 多毛登等保里弖 奴礼奴等母 (ワガソデハ タモトトホリテ ヌレヌトモ)」(15・3711) の仮名書例もある。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】通而沾奴 [トホリテヌレヌ] 「シキタヘ」は敷物にする栲の意。「シキタヘノ」は衣にかかる枕詞。「トホリテヌレヌ」の原文「通而沾奴」の「沾」を、元暦校本・紀州本・西本願寺本・大矢本に「沽」とする。「沽」は新撰字鏡に「葛胡反買也洗也潔也」とあり、とあり、「沾」は「薄也益也為霑字也」と見えるもので、通用はしない。『金石異体字典』に、「沽」は「買」の異体字とする。文脈からいって、「沽」は誤写と考えられ、金澤本・温故堂本・京都大学本に「沾」とあるのによる。「ヌレル」の意。巻十五に「和我袖波多毛登(等保里弖)奴禮奴等母」 (3711)、巻十九に「服之襴毛(等寶利弖濃禮奴)」 (4156) とあり、「トホリテヌレヌ」と訓む。衣の袖は涙のために濡れとおった、の意。 |
|||||||||||
| 巻二 136 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版] (1980年9月)も併記する 【題詞】反歌二首 〔本文〕 歌。神田本、「謌」。 〔諸説〕 反歌二首。万葉集桧嬬手、「短歌」ニ作ル。 〔頭書〕 類聚古集、前行ニ「返歌 従出火因玉妻寺時長云角障 人麻呂」アリ。「障」ヲ朱書セリ。「火」ノ右ニ朱「左□[下写真参照]」アリ。 【本文】 青駒之 足掻乎速 雲居曽 妹之當乎 過而来計類 [一云 當者隠来計留] (アヲコマノ アカキヲハヤミ クモ井ニソ イモカアタリヲ スキテキニケル) 〔本文〕 類。類聚古集、「頼」。 一。活字無訓本、以下八字大字ニセリ。 〔訓〕 アカキヲ。神田本、「ホカテヲ」。漢字ノ左ニ「アカキヲ」アリ。 クモ井ニソ。細井本、「クモイニソ」。 當者隠来計留。神田本・西本願寺本・温故堂本・京都大学本、右ニ朱「アタリハカクレキニケル」アリ。細井本、右ニ訓アリ。文同前。 大矢本、右ニ朱「アタリハカクレキニケリ」アリ。 〔諸説〕 青駒之。略解、躬弦、「青」ハ「赤」ノ誤カ。 一云 當者隠来計留。代匠記精撰本、「一云」ノ下「妹之」ノ二字脱トス。万葉考、「一云」ヲ可トス。
[校本萬葉集新増補版] 【題詞】 反歌二首 【本文】 青駒之 足掻乎速 雲居曽 妹之當乎 過而来計類 [一云 當者隠来計留] (アヲコマノ アカキヲハヤミ クモヰニソ イモカアタリヲ スキテキニケル) 〔訓〕 當者隠来計留。神宮文庫本、右ニ「アタリハカクレキニケル」アリ。「ル」ハ「リ」ヲ直セリ。近衛本、右ニ朱「アタリハカクレキニケル」アリ。「留」ノ左ニ朱「リ」アリ。
|
|||||||||
| 原文「青駒之(あをこまが)」訓・考 | 拾穂抄 | あをこまのあかきをはやみ雲ゐにそいもかあたりをすきて來にける 一云あたりはかくれきにける あを駒のあかきを 青は馬の毛色也催馬楽にあをのまとりつなけと有白馬節會をあをむまといふは別儀也 |
||||||||||
| 代匠記 | 青駒之足掻乎速雲居曾妹之當乎過而來計類 [アヲコマノアカキヲハヤミクモヰニソイモカアタリヲスキテキニケル] 〔一云當者隱來計留〕 青駒は、和名云、説文云、□[馬+怱]〔音聰、漢語抄云□[馬+怱] 青馬也、〕青白雜毛馬也、 |
|||||||||||
| 童蒙抄 | 青駒之足掻守速雲居妹之當乎過而來計類〔一云當者 隱來計留〕 童子問 青駒をよみ出せる義は如何。 答 その時の駒青かりし故なるへし。赤駒とよめる歌もあり。黒駒とよめるもあれは、實にその時駿馬に乘たるをよめるなるへし。 |
|||||||||||
| 万葉考 | 青駒之 [アヲゴマノ]、 白馬なり、 | |||||||||||
| 攷證 | 青駒之 [アヲコマノ]。足掻乎速 [アカキヲハヤミ]。雲居曾 [クモヰニソ]。妹之當乎 [イモカアタリヲ]。過而來計類 [スキテキニケル]。〔一云。當者隱來計留。〕 青駒之 [アヲコマノ]。 和名抄牛馬類云、説文云□ [馬+怱]〔音聰、漢語抄云、聰青馬也、黄聰馬、葦花毛馬也。日本紀私記云、美太良乎乃宇萬。〕青白雜毛馬也云々とある、是にて、實に眞青 [マサヲ] なる毛の馬あるにあらず。本集十二〔廿八丁〕に、□[馬+総の旁] 馬とあるも、青き馬也。二十〔五十八丁〕に、水鳥乃可毛能羽能伊呂乃青馬乎 [ミツトリノカモノハノイロノアヲウマヲ] 云々などあるにても、白き馬にはあらで、青き馬なるをしるべし。猶くはしくは、古事記傳卷十八、玉勝間卷十三などに見えたれば、こゝに略す。 |
|||||||||||
| 古義 | 青駒之 [アヲコマガ]。足掻乎速 [アガキヲハヤミ]。雲居曾 [クモヰニソ]。妹之當乎 [イモガアタリヲ]。過而來計類 [スギテキニケル]。 青駒 [アヲコマ] は、略解に、躬弦云、青は赤の誤かと云り、是に依てなほ思ふに、七ノ卷に、赤駒足何久激 [アカコマガアガクタギチニ]、十一に、赤駒之足我枳速者 [アカコマアガキハヤケバ]、十四に、安可胡麻我安我伎乎波夜美 [アカコマガアガキヲハヤミ]、また其ノ餘四ノ卷に、赤駒之越馬柵乃 [アカコマノコユルウマセノ]、五ノ卷に、阿迦胡麻爾志都久良宇知意伎 [アカコマニシヅクラウチオキ]、十二に、赤駒射去羽計 [アカコマノイユキハバカル]、十三に、赤駒厩立 [アカコマノウマヤヲタテ]、十四に、安可胡麻我可度弖乎思都々 [アカコマガカドデヲシツヽ]、又安加胡麻乎宇知弖左乎妣吉 [アカコマヲウチテサヲビキ]、十九に、赤駒之腹婆布田爲乎 [アカコマノハラバフタヰヲ]、廿ノ卷に、阿加胡 [アカコ] 麻乎夜麻努爾 [マヲヤマヌニ] 波賀志 [ハカシ] など、赤駒 [アカコマ] と云る甚多くして、青駒 [アヲコマ] てふは集中に外に見えたることなく且青と赤とは、草書もやゝ似たれば、信に彼ノ説は、謂 [イハ] れたることにこそ、しかれども、廿ノ卷家持卿、七日侍宴の爲に作る歌に、水鳥乃可毛能羽能伊呂乃青馬乎 [ミヅトリノカモノハノイロノアヲウマヲ] ともありて、今のも、實に青毛の駒なりけむも知ねば、今は猶もとのまゝにて、「アヲコマ」 と訓てありつ、和名抄ニ、説文ニ云、□[馬+總の旁] ハ、漢語抄ニ云、□[馬+總の旁] ハ、青馬也、 |
|||||||||||
| 全釈 | 青駒之 [アヲゴマノ] ―― 和名抄に説文云、□[馬+總の旁] 音聰、漢語抄云、□[馬+總の旁] 青馬也、とあり、新撰字鏡にも□[馬+總の旁] 阿乎支馬とある。卷二十に水鳥乃可毛能羽能伊呂乃青馬乎 [ミヅトリノカモノハイロノアヲウマヲ](四四九四)とあるから、青毛の馬である。白馬ではない。安田躬弦が赤駒の誤かと言つた説は從ふべきでない。 | |||||||||||
| 全註釈 | 【釈】 青駒之 アヲゴマノ。アヲゴマは、倭名類聚鈔に□[馬+總の旁] を釋して、漢語抄に□[馬+總の旁] 青馬也とあるを引き、青白雜毛馬也とあるから、青と白とまじつた毛の馬をいう。白馬節會をアヲウマノセチヱというのは、平安時代以後のことであるが、その白馬も、本來は純白の馬ではなくて、青白い馬を見たものであろう。コマはもと小馬の義だが、コは愛稱の接頭語となつて、ちいさい意は無い。 |
|||||||||||
| 評釈 | 【語】 青駒 [あをごまの] 青毛の馬。白馬の節會をあをうまの節會というてゐるが、これももと青馬であつたのが、後、白馬に改められ、よび名のみ舊のままに殘つたらしいから、これを證として、ここを白馬と見るのは當らない。 |
|||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「あをこまの」 青駒-新撰字鏡 (五) に「驄□[馬+忽]」に「馬白色又青色」と注し、享和本 (上) には「阿乎支馬」とある。倭名抄 (七) に「漢語抄云、驄青馬也」とあり、説文 (十) には「驄、馬青白襍毛也」とあつて、我が国では青毛白毛の雑つたものを青馬といひ、後には白馬と書いて「アヲウマ」と云つたやうである。なほこの事は後 (廿・4494) に述べる。駒は倭名抄 (七) に「古萬(コマ)」と注し、「馬子也」とあるが、必ずしも子馬の義ではなく、小水葱(コナギ)、小菅(コスゲ)などの「こ」と同じく愛稱としての接頭語「こ」を加へたものと見るべきである。古今以後になると「馬 (うま)」の語は殆ど用ゐられず、いづれも「こま」となり、それが歌語となつた。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】「あをこまが」 原文「青駒之」を「アヲコマノ」と訓むのが通説だが「アヲコマガ」とする説も見られる。古典全集・古典集成などに「アヲコマガ」と訓むのは「赤駒我門出をしつつ出でかてにせしを見立てし家の子らはも」 (14・3534)、「さわたりの手児にい行き逢ひ赤駒我足掻を早み言問はず来ぬ」 (14・3540) などの例を考慮してのことと思われる。東歌の例ではあるが、「アカコマガアガキ」とあるのは注意すべきで、「ノ」と「ガ」の相違について山田孝雄の『奈良朝文法史』に、「ノ」は「下なる語に意義の主点を帰着せしむる如き関係」で下へ続けるのに対して、「ガ」は連体用法に立ちながらその受ける語に意義上の主点をおくと述べられているのが思い合わされる。抒情表現として軽視しえない問題がそこに含まれているのだろう。すなわち「赤駒が足掻き」と言えば、赤駒に意義上の重点が置かれるのに対して、「赤駒の足掻き」ならば、足掻きの方に重点が置かれる。従ってこの歌を「青駒が足掻きを早み」と訓むと「青駒」に重点が置かれ、自分の感情を後に残しつつ駒の早さを歎く意味が強められるようである。その方がふさわしいと思われるので、「アヲコマガ」と訓む説に従う。なお「アヲコマ」は、青馬に同じく、青毛の馬であり、白色と黒色の毛の入りまじった馬を言う。 |
|||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「あをこまが」 この「アヲ」は灰色をさすか。コマは乗用となる雄馬をいう。雌馬は一般に運搬・耕作などの雑役に用いられた。「ダマ (駄馬)、即ちザウヤク(雑役)牝馬。また荷物を負わせる家畜」(日葡辞書)。「ガ」は所有格。 |
|||||||||||
| 新大系 | 【脚注】「あをこまが」 倭名抄に「漢語抄云、驄、青馬也」。新撰字鏡 (享和本) に「驄□[馬+忽] 馬白色又青色、阿乎支(あをき)馬」とある。「青駒」とは灰色・白・葦毛などの馬をいうらしい。「こま」は、中世、特に牡馬を指していう場合がある。牝馬は「駄(だ)」「雑役(ざふやく)」などと呼ばれた。「ばびろにやの国に駒(こま)がいばえば、必ずこの国の雑役が胎むことがある」(天草本エソポ物語)。古代の「こま」も牡馬として理解し得る例がある。ここもその一つ。
|
|||||||||||
| 原文「足掻乎速 (あがきをはやみ)」注 |
拾穂抄 | あかきは馬の歩む足遣ひ也我心はさも急かねど馬の早くて妹があたりを遠く過こしと也 | ||||||||||
| 代匠記 | アガキは、文選東都賦云、「馬踠 二餘リノ足一、輸曰踠ハ屈也、言ハ馬之足力有レ餘、」異を注する中に、一云の下に妹之の二字脱たるべし、如此句を斷て注する例なし、 | |||||||||||
| 童蒙抄 | 童子問 あかきといふは、今俗に少童なとの走りまふを、あかきといふも同しきか。 答 しかるへし。踠の字を書へし。今足掻とかけるは、語義をかけるなるへし。 童子問 此反歌にてみれは、旅行馬にて人丸登り給へるか。しからは船中の作ともみるましきか。 答 いかにも此反歌によれは、陸を馬にて來れるとも見るに、其證なきにあらす。しかれとも熟田津なとの玉藻奧つ藻なとをよめるによれは、海路にあらすといひかたし。此旅行、馬にても歩行にても船にてもありたるともみるへし。その意をのへて、海路山路をよみ合せたるとみれは、いよいよ人丸の作首歌はれぬへし。今日長途の旅行には、舟にものり、馬にものり、歩行もする常の事也。されはその長途のさまさまにうつりかはる有さまを詠には、如レ此の一格ともすへき長歌短歌なるへし。 |
|||||||||||
| 万葉考 | 足掻乎速 [アガキヲハヤミ]、 馬は足して土をかくが如くあゆむをいふ、 | |||||||||||
| 略解 | アガキは、馬は足にて士をかくが如く歩めばしか言ふ。卷二、赤駒のあがき早くは雲ゐにも隱れ行かむを袖まけわがせと有り。躬弦云、ここも青は赤の誤りならむか。 | |||||||||||
| 攷證 | 足掻乎速 [アカキヲハヤミ]。 本集七〔十二丁〕に、赤駒足何久激 [アカコマノアカクソヽキニ] 云々。七〔十四丁〕に、赤駒之足我枳速者 [アカコマノアカキハヤクハ] 云々などありて、猶多し。こは、新撰字鏡に、踠 ハ 蹀也踊也、馬奔走貌、阿加久云々とありて、馬のありくかたち也。鳥の羽掻 [ハネカク] などいふもこれにおなじ。 |
|||||||||||
| 古義 | 足掻乎速 [アガキヲハヤミ]は、足掻 [アガキ]が速さにの意なり、足掻 [アガキ]は、古事記仁徳天皇ノ條に、大后石之日賣ノ命の、足母阿賀迦爾嫉妬
[アシモアガカニネタミタマヒキ]、(足掻貌 [アガクガニ]なり、)字鏡に、踠ハ、踝也踊也、馬奔走スル貌、阿加久 [アガク]、また蹀ハ、阿加久
[アガク] などあり、續古事談に、この馬たかくあがりて、おちたつほどに、前の足二ツをもて、この權ノ守が、左右の指貫のうへをふまへつ、權ノ守あわてさわぎて、西枕にたふれふして、足をあがけども、馬ふまへて、やゝ久しくのかず、などもあり、(足掻
[アガク]は、足ノ字を書る如く、足に限りていひ、手してするを手搖と云しを、後には轉りて、手足にかぎらず、動搖 [ウゴカ]しはたらかすをば、すべてあがくと云るなり、塵添埃嚢抄に、手足を「アガク」と云は、字には蹀とも踠とも書キ、文選に、馬踠 [アガク]二餘ノ足ヲ一とよめり、聖武天皇東大寺を建立して鎭守の爲八幡を勸請申されけるに、宇佐ノ宮より瑤の御輿にめし、儀衛を調へて御幸成けるが、已 [スデ] に法會始まる時、御前
[ミサキ] 見えければ、行基菩薩御幸遲しとて、門に立て、手を□[足+蝶の旁] [アガ]きて招かせ給ふ故に、彼ノ門を、手蹀 [テガイ]門と云、前なる路を、手蹀 [ガイ] 大路と云なりと見えたり、又うつほ物語國ゆづりの卷に、おほす、事平かにと、手をあがき祈り願立テさせ給ふなど、手をあがくといへること多き、皆それなり、)
|
|||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「あがきをはやみ」 「安可胡麻我 安我伎乎波夜美 (アカゴマガ アガキヲハヤミ)」(14・3540) の仮名書例がある。馬は足で掻くやうにするから馬の歩みを「足掻」といふ。その歩みが早くて、の意。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】 巻十四に「安可胡麻我 安我伎乎波夜美」(3450) とある。「アガキ」は、掻くようにして足を動かすことをいう。新撰字鏡に「馬奔歩貌、阿加久云々」とある。自分の乗った青の足が速くて、の意。 |
|||||||||||
| 新全集 | 【頭注】 馬が勇んで、前足で地面を掻くようにすること。 |
|||||||||||
| 「雲居曽(くもゐにそ)」注 | 万葉考 | 雲居曾 [クモヰニゾ]、 此言をかく遠き事にいふは轉じ用るなり、 | ||||||||||
| 攷證 | 〔攷證一下卅七丁〕にいへるごとく、雲居は、天をいひて、天は遠きものなれば、遠きたとへにいへるなり。 | |||||||||||
| 全釈 | 雲居曾 [クモヰニゾ] ―― 雲居は空、ここは空の如くに遠くの意。 | |||||||||||
| 全注 | 【注】 「クモヰ」は、「巻向の弓月が嶽に雲居立てるらし」 (7・1087) のように、雲そのものを指す場合もあるが、雲のかかっている所や雲のかかっているような遠隔の所をあらわすこともある。ここは、はるかに離れた場所を言う。 |
|||||||||||
| 原文「妹之當乎 (いもがあたりを)」訓・考 |
万葉考 | 妹之當乎 [イモガアタリヲ]、過而來計類 [スギテキニケル]、」 或本、妹之當者 [ハ]、隱 [カクレ] 來ニ計留、 これによらん歟、(卷四)「赤ごまの、あがきはやくば、雲ゐにも、隱往 [カクレユカン] ぞ、袖まけわぎも、」 | ||||||||||
| 全註釈 | 【釈】 妹之當乎 イモガアタリヲ。妻の住む家の附近を。 |
|||||||||||
| 原文「過而来計類 (すぎてきにける) 」訓・注 |
古義 | 過而來計類 [スギテキニケル]、舊本に、一ニ云、當者隱來計留と註せり、 | ||||||||||
| 全註釈 | 過而來計類 スギテキニケル。ゾを受けて、連體形で結んでいる。 | |||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】 「過ぐ」は通過の意味のみでなく、去る、後にするなどの意にも用ゐられる。ここは後者の意である。 |
|||||||||||
| 原文「一云 當者隠来計留 (あたりはかくりきにける)」考 |
全註釈 | 一云當者隱來計留 アルハイフ、アタリハカクリキニケル。本文の四句の後半からの別傳である。これに依れば、妹があたりは、雲居に隱れて來たということになる。 | ||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】 これは第四句の後半が一本にはかうあるといふのである。「隠る」は萬葉後期は下二段活用の例があるが、前期はまだ四段の例が多いから (1・17)、ここも四段に訓む。上の「ぞ」を受けて「ける」と結んだ。私注に「スギテキニケルが単純でよい。」とあるに同感であり、編者もその方をすぐれたものとして本文としたのであらう。 |
|||||||||||
| 全注 | 【考】 反歌の第一首目。長歌の終り近くの「嬬ごもる 屋上の山の 雲間より 渡らふ月の 惜しけども 隠らひ来れば」を受け、それを強調する内容の反歌である。長歌の方が抒情が露わで、「一に云ふ」の異伝もその詠み方に近いが、本文は「妹が当たりを過ぎて来にける」と、たんに行為を叙べるだけにとどめたために、感動が深くなった。異伝を、後の訛り伝とする説もあるが、作者の推敲前の形を示すものであろう。 |
|||||||||||
| 巻二 137 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版] (1980年9月)も併記する 〔頭書〕 類聚古集、前行ニ「人麿別妻作反歌 長哥」 【本文】 秋山爾 落黄葉 須臾者 勿散亂曽 妹之當将見 [一云 知里勿亂曽] (アキヤマニ オツルモミチハ シハラクハ ナチリミタレソ イモカアタリミム) 〔本文〕 亂。類聚古集、ナシ。右ニ墨「乱」アリ。「乱」ノ下ニ墨「生イ」アリ。本文中「散曽」ノ間ニ墨〇符アリ。 當。神田本、「□[下写真参照]」。西本願寺本、「雷」。別筆ニテ「當」ニ直セリ。 (一云の)一。無訓本、以下七字大字ニセリ。 (一云々の)亂。金澤本、「□[下写真参照]」。 〔訓〕 オツル。温故堂本、「ヲツル」。 シハラクハ。神田本・細井本、「シハラクモ」。神田本、「モ」ノ右ニ「ハイ」アリ。 ナチリミタレソ。元暦校本・金澤本・類聚古集、「ちりなみたれそ」。元暦校本、「ちりな」ノ右ニ墨「ナテリ」アリ。 神田本、「チリヤミタリソ」。「ヤ」ノ右ニ「ナ□[下写真参照]」アリ。漢字ノ左ニ朱「ナチリミタレソ」アリ。 細井本、「チリナミタレソ」。「勿散」ノ左ニ「ナチリ」アリ。温故堂本、「ナチリソミタレソ」。大矢本・京都大学本、「ナチリ」青。 イモカアタリミム。金澤本、「いもかみるへく」。 知里勿亂曽。神田本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本、右ニ朱「チリナミタレソ」アリ。細井本、右ニ訓アリ。文同前。 〔諸説〕 落黄葉、オツルモミチハ。万葉集古義、「チラフモミチバ」トシ「落」ノ下ニ「相」又ハ「合」ノ字脱トス。 シハラクハ。万葉集略解、「シマラクハ」。万葉集古義、「シマシクハ」。 ナチリミタレソ。仙覚抄、「チリナミタレソ」(古点)ヲ否トシ「ナチリミタレソ」トス。代匠記精撰本、「ナチリマガヒソ」カ。万葉集桧嬬手、「ナチリミタリソ」。
[校本萬葉集新増補版] 〔頭書〕 六帖、第四「□ (火+禾 [下写真参照]) 山におつる紅葉はしはらくはいりなみたれそ妹かあたりみむ」 【本文】 秋山爾 落黄葉 須臾者 勿散亂乱曽 妹之當将見 [一云 知里勿亂曽] (アキヤマニ オツルモミチハ シハラクハ ナチリミタレソ イモカアタリミム) 〔訓〕 ナチリミタレソ。神宮文庫本、「ナチリ」ヲ朱ニテ消セリ。ソノ右ニ「チリナ」アリ。「勿散」ノ左ニ「ナチリ」アリ。 知里勿亂曽。神宮文庫本、右ニ「チリナミタレソ」アリ。 〔諸説〕 知里勿亂曽。仙覚抄、「チリナミタレソ」ト訓ズ。
|
|||||||||
| 原文「落黄葉 (おつるもみちば)」訓・考 |
古義 | 落黄葉 [チラフモミチバ] 落黄葉は、「チラフモミチバ」と訓べし、十五に、錢美知婆能知良布山邊由 [モミチバノチラフヤマヘユ] と見えたり、さて知良布 [チラフ] は、即チ知流 [チル] の伸りたる言にて、伸云は、其ノ落ことの緩なるをいふ詞なり、さて落ノ字のみにて、知良布 [チラフ] と訓むこと、もとより難 [コト] はなけれども、集中に、知良布 [チラフ] と訓べきところに、散相 [チラフ] 散合 [チラフ] 、などゝ書たるをおもへば、もしはこゝも落の下に、相ノ字合ノ字などの、脱しにもあるべし、(略解などに、舊本の訓のまゝに「オツルモミチバ」とよみたれども、花黄葉の類の散を、オツルと云は、古言にあらざるをや、〉 |
||||||||||
| 全註釈 | 【釈】 秋山尓落黄葉 アキヤマニオツルモミチバ。黄葉の散るをオツということは、「和我世故我 [ワガセコガ] 之米家牟毛美知 [シメケムモミチ] 都知爾於知米也毛 [ツチニオチメヤモ]」(巻十九、四二二三) など例がある。この句、黄葉を呼び懸けている。古義には落をチラフと讀んでいるが、ここはフに相當する字が無いから、オツルとする。地上に落下する意である。 |
|||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「ちらふもみちば」 原文「落」を「オツル」と訓み来つたが、古義に「チラフ」と改め、「落」を「チラフ」と訓む事に難はないが、「散相(チラフ)」、「散合(チラフ)」などの例によりもしは「相」、「合」の字の脱したのか、と云ひ、花黄葉の散るを「オツル」といふは古言でもないと云つてゐる。それに対して講義には「本都延能(ホツエノ) 延能宇良婆波(エノウラバハ) 那加都延尓(ナカツエニ) 淤知布良婆閇(オチフラバヘ) 那加都延能(ナカツエノ) 延能宇良婆波(エノウラバハ) 斯毛都延尓(シモツエニ) 淤知布良婆閇(オチフラバヘ)」(雄略記) の例を引き、全註釈には「和我世故我(ワガセコガ) 之米家牟毛美知(シメケムモミチ) 都知尓於知米也母(ツチニオチメヤモ)」 (19・4223) の例を引いて、「オツル」でよいとある。しかしここに引かれた例は上の枝から「中つ枝に」落ち、中の枝から「下つ枝に」落ちるのであり、黄葉が枝から「土に」落ちるのである。「秋山に」落ちるのも同じだと見えるかと思ふが、大空から鳥が秋山に落ちるのならば同じだと云へるけれど、黄葉は秋山に落ちるのではない。黄葉は秋山にありて散るのである。だから右に引かれた例は今の場合にはあてはまらない。のみならず、「土に」であつても必ずしも「落ちる」には限らない。花黄葉に「落つ」と云つた仮名書例は右の一例の他に、 我が門の片山椿まこと汝我が手触れなな 都知尓於知母加毛(ツチニオチモカモ) (廿・4418) の一例-これも「土に」とある-があるのみである。しかもその落ちるものは椿である。椿は落椿と今の人もいふ如く、ポタリと土に落ちるものなのである。 やどなる桜の花は今もかも松風早み 地尓落良武(ツチニチルラム) (八・1458) 桜の花は「散る」のであつて、「土に」とあり「落」の文字が書かれてゐてもこれを「ツチニオツ」と訓む人は無い。又、 -百枝さし 生ふる橘 玉に貫く 五月を近み あえぬがに 花咲きにけり 朝に日に 出で見るごとに 息の緒に 我が思ふ妹に まそ鏡 清き月夜に ただ一目 見するまでには 散りこすな ゆめと言ひつつ ここだくも 我が守るものを うれたきや 醜霍公鳥 暁の うら悲しきに 追へど追へど なほし来鳴きて いたづらに 地尓令散者(ツチニチラセバ)- (八・1507) の「落」を「チリ」と訓む事も疑つた者なく、その反歌、 妹が見て後も鳴かなむ霍公鳥花橘を 地尓落津(ツチニチラシツ) (八・1509) の結句の訓も疑が無いであらう。 開(サク) 96、落(チル) 76、落(フル) 47、落(オツ) 25、 咲(サク) 70、散(チル) 75、零(フル) 154 この読例は概数ながら、その用例数を見ても「落」を「チル」と訓む事は十分認められるところであり、同じ作者の「黄葉之落去奈倍尓 (モミチバノチリヌルサベニ)」 (209) の例と較べても「アキヤマニ チラフモミチバ」の訓は動かない事が認められよう。ただ古義には誤字説が出てゐるが、助動詞の訓添の例は人麻呂の作には珍しい事ではなく、現に前の短歌にも「来計類(キニケル)」「来計留(キニケル)」の如く完了の助動詞「に」の表記は略されてゐるのであるから、今も継続の助動詞「ふ」が訓添になつてゐる事は十分認められるであらう。しかも古点に「オツルモミチバ」とあつて、古義以前に疑ふもののなかつた事は、継続の助動詞が早く忘れられ、 秋の月山べさやかに照せるはおつるもみちの數を見よとか (古今集巻五) 風吹けばおつるもみちの水きよみちらぬ影さへ底に見えつつ (同) の如き古今以後の用語に耳馴れた為と云へるであらう。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】「あきやまに おつるもみちば」 「落黄葉」を旧訓に「オツルモミチハ」と訓だが、古義に「チラフモミチバ」とし、「落」の字の下に「相」もしくは「合」の字が脱したものと見た。そして「花・黄葉の類の散るをオツルと云は古言にあらざるをや」と言っているが、講義にも引かれているように、雄略記の「上つ枝の末葉は 那加都延尓(ナカツエニ) 淤知布良婆閇(オチフラバヘ)」などの例もあって、黄葉を「チル」とも「オツ」とも表わしたと考えられる。「相」「合」の誤脱を考えるより「オツルモミチバ」と訓むのが適切だろう。注釈に古義の説を受け、記歌謡の例は、上の枝から中の枝に落ち、中の枝から下の枝に落ちるのであり、また、万葉集巻十九の「わが背子が標めけむもみち都知尓於知米也母」(4223) の場合は黄葉が枝から土に落ちるのであり、それに対してこの歌の場合は「黄葉は秋山にありて散るのである」から、同様の例とは見なしがたいとし、また継続の助動詞「フ」の訓添えは十分認められることとして、原文のまま「チラフモミチバ」と訓むべきことを述べている。これは古義説を修正したものとして注目されるが (私注・古典集成にも同訓を採用)、他の人麻呂作歌のなかでは「散相(チラフ)」 (1・36)、「渡相(ワタラフ)」(135)、「隠比(カクラヒ)」(135)、「流触経(ナガレフラバフ)」(194)、「靡相(ナビカヒ)」(194)、「靡相(ナビカヒ)」(196) というふうに継続の助動詞「フ」は文字に記されているのであり、ここだけ「散(チラフ)」と記したとは考え難い。「チラフ」とすれば古義のように脱字を認めざるをえないだろうし、誤脱を認めまいとすれば、「チラフ」とは訓めない。注釈に助動詞の訓み添えは珍しくないとして完了の助動詞「ニ」(来計類) の例をあげているのは、語の性格や前後の文字面の相違を無視したものと思われる。「オツルモミチバ」と訓み、秋山においてしきりに落ちる黄葉に呼び掛けたと解するのが妥当と思われる。 |
|||||||||||
| 原文「須臾者(しましくは)」訓・考 | 仙覚抄 | 秋山尓落黄葉須臾者勿散亂曾妹之當將見 [アキヤマニヲツルモミチハ シハラクハ ナチリミタレソイモカアタリミム] | ||||||||||
| 拾穂抄 | 秋山尓落黄葉須臾者勿散亂曽妹之當將見 知里勿亂曽 あき山におつるもみちは しはらくは なちりみたれそ妹かあたりみん 一云ちりなみたれそ |
|||||||||||
| 代匠記 | 秋山爾落黄葉須臾者勿散亂曾妹之當將見 [アキヤマニオツルモミチハ シハラクハ ナチリミタレソイモガアタリミム]〔一云知里勿亂曾〕 | |||||||||||
| 童蒙抄 | 童子問 須臾者をしはらくとよみ來れり。者の字をもとよむはものといふ訓故か。 答 しかり。しかれともこの歌にては、者をもとよむはよろしからす。はとよむへし。 |
|||||||||||
| 万葉考 | 落黄葉 [オツルモミヂバ]、須臾者 [シバラクハ]、勿散 [ナチリ]亂 [ミダリ・マガヒ] 曾 [ソ]、妹之當將見 [イモガアタリミム] | |||||||||||
| 略解 | 秋山爾。落黄葉。須臾者。勿散亂曾。妹之當見。一云知里勿 [チリナ] 亂曾 あきやまに。おつるもみぢば。しまらくは。なちりみだれそ。いもがあたりみむ。 集中暫の事を、シマラク、シマシクなど假字書あり。 |
|||||||||||
| 攷證 | 須臾者 [シマラクハ]。 舊訓、しばらくとあれど、しまらくとよむべし。そのよしは、上〔攷證二上卅八丁〕にいへり。 |
|||||||||||
| 古義 | 須臾者 [シマシクハ] 須臾者は、「シマシクバ」 と訓べし、上に出づ、 | |||||||||||
| 全釈 | 須臾者 [シマシクハ] ―― 須臾は之麻思久母 [シマシクモ](三六〇一) とも思麻良久波 [シマラクハ](三四七一) ともあるから、どちらでもよい。 | |||||||||||
| 全註釈 | 【釈】 須臾者 シマシクハ。シマシクは、文字通り寸時である。ちよつとの間は。 |
|||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「しましくは」 暫くは。既出 (119)。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】「しましくは」 「須臾」を「シマシ」と訓むことは、119歌参照。ここは「シマシク」。 |
|||||||||||
| 原文「勿散乱曽 (なちりまがひそ)」訓・考 |
仙覚抄 | 秋山尓落黄葉須臾者勿散亂曾妹之當將見 [アキヤマニヲツルモミチハシハラクハ ナチリミタレソ イモカアタリミム] 一云、知里勿礼曾 [チリナミタレソ]。 此歌第四句、古點ニハ、チリナミタレソト、點セリ。イマハ、ナチリミタレソト和ス、如ク二古點一、チリナミタレソトイフヘクハ、一云、知里勿亂曾ト注スヘカラス。シカレハ、麁 [ソ] 本ヲハ、ナチリミタレソトヨムヘキナリ。カハルコトナクハ、注ニ一云、チリナミタレソトイフヘカラサルカユヱ也。 |
||||||||||
| 代匠記 | 今按、是は渡の山のもみぢ葉の、散のまがひにと云をかへしてよまれたれば、第四の句ナチリマガヒソと和すべきにや、注可レ准レ之、 | |||||||||||
| 万葉考 | 勿散 [ナチリ]亂 [ミダリ・マガヒ]曾 [ソ] | |||||||||||
| 略解 | 勿散亂曾。なちりみだれそ。 ちり亂るる事なかれと言ふを、古くは斯く言へり。 |
|||||||||||
| 攷證 | 勿散 [ナチリ] 亂 [マカヒ・ミタレ] 曾 [ソ]。 舊訓、みだれそとあれど、まがひそとよむべし。そのよしは、上にいへり。一首の意明らけし。 |
|||||||||||
| 古義 | 勿散亂曾は、「ナチリミダリソ」 と訓べし、舊本に、一ニ云、知里勿亂曾、と註せり、 | |||||||||||
| 全釈 | 勿散亂曾 [ナチリミダレソ] ―― この句をナチリミダリソとよんだ、古義や美夫君志説は惡い。ミダリとなるのは四段活用で、他動詞である。 | |||||||||||
| 全註釈 | 【釈】 勿散亂曾 ナチリマガヒソ。ナは禁止の意の助詞。亂は、ミダレとも讀まれるが、この歌は長歌の句によつていると見られるので、そのチリノマガヒニを受けてナチリマガヒソと讀む。ソは助詞。句切。 |
|||||||||||
| 評釈 | 秋山に落つる黄葉 [もみぢば] 須臾 [しましく] はな散り亂れそ妹があたり見む (一に云ふ、散りな亂れそ) 【語】な散り亂れそ 散り亂れてはならない 【訓】な散り亂れそ 白文「勿散亂曾」で、舊訓「ナチリミダレソ」考「ナチリミダリソ」とある。亂るは四段活用の場合は他動詞、下二段の場合は、自動詞と考へられるので、舊訓による。 |
|||||||||||
| 注釈 |
【訓釈】「ちりなまがひそ」 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】「なちりまがひそ」 原文「勿散乱曽」を、元暦校本・金澤本・類聚古集に「ちりなミタレソ」と訓んでいるが、仙覚抄に「ナチリミタレソ」と改め、さらに代匠記(精撰本) に「ナチリマガヒソ」と改訓した。禁止の意味の「ナ」は人麻呂歌集・人麻呂作歌では「勿・莫」の文字によって表わしており、「莫謂花」「勿謂花」「草勿手折」「」「雲莫隠」などと記される。「勿・莫」のあとに来る動詞の動作を禁ずる意味で「ナ~ソ」と言われるのだが、「莫」字が常に「莫~」の形で使われるのに対し、「勿」字は「所知勿」とか、「忘念勿」「相与勿」の場合にも用いられていて、「勿謂花」「雲勿棚引」「草勿手折」などとあわせて「勿」の用法の幅広さを窺わせる。「勿謂」は「ナノリソ」、「草勿手折」は「クサナタヲリソ」であり、「忘念勿」は「ワスルトオモフナ」と訓むべきもの。つまり「勿」は日本語の語順によっていると判断される。従って「勿散乱曽」は「ナチリマガヒソ」と、「勿」を先ず訓むべきで、「勿散」を「チリナ」と訓む旧訓や、澤瀉注釈の訓は誤りと思われる。「乱」を「マガヒ」と訓むことは、135歌の〔注〕参照。「ナチリマガヒソ」で、散り乱れることなくあれ、の意。 |
|||||||||||
| 「一云知里勿乱曽」考 | 全注 | 【注】「一に云ふ ちりなまがひそ」 結句の異伝で、本文とは助詞「ナ」の位置が異なっている。本文の「ナチリマガヒソ」であると、「チリマガフ」が禁止される内容となり、異伝の「チリナマガヒソ」では、チルこと自体というより、マガフことが禁止の内容となるような感を与える。どちらにしても意味的には「かはることなし」(講義) と言えるのだろうが、本文の本文の方が強い印象を与えるようだ。 |
||||||||||
| 巻二 138 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版] (1980年9月)も併記する 或本歌一首并短歌 〔本文〕 歌。神田本、「謌」。 并。京都大学本、赭ノ合点アリ。 短歌。元暦校本・金澤本・神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本二字小字ニ書ケリ。 〔諸説〕 或本歌一首并短歌。攷證、「短歌」ノ下「一首」脱トス。古葉略類聚鈔、此歌及反歌ヲ前ノ「角鄣経」ノ歌ノ前ニ移シ小字トス。萬葉集美夫君志、「并短歌」ノ三字小字トス。 〔頭書〕 元暦校本、別行平仮字ノ訓ナシ。漢字ノ右ニ朱片仮字ノ訓アリ。コレニテ校ス。又處々ニ赭及墨ノ訓アリ。コレヲ記入ス。 金澤本、訓ナシ。 細井本、訓を朱書セリ。 【本文】 石見之海 津乃浦乎無美 浦無跡 人社見良目 (イハミノウミ ツノウラヲナミ ウラナミト ヒトコソミラメ) 〔本文〕 無。元暦校本、「无」。 目。元暦校本、「耒」。右ニ朱「米」アリ。金澤本・神田本・西本願寺本、「米」。 〔訓〕 ウラナミト。元暦校本・神田本、「ウラナシト」。神田本、「無」ノ左ニ朱「ナミ」アリ。 〔諸説〕 津乃浦乎無美「ツノウラヲナミ」。万葉考、「津」ノ下「能」脱、「浦」ノ下「回」脱トシ、「無美」ハ衍トス。萬葉集檜枛、「津奴乃浦回乎」ニ作ル。 古義、「浦」ノ下「回」脱、「無美」ハ衍トスルヲ可トシ、「津」ノ下「野」又ハ「努」脱トシ訓「ツヌノウラミヲ」トス。 【本文】 滷無跡 人社見良目 吉咲八師 浦者雖無 縦恵 (カタナミト ヒトコソミラメ ヨシエヤシ ウラハナクトモ コレヱ) 〔本文〕 滷。神田本、「□[下写真参照]」。 跡。神田本、ナシ。右ニ書ケリ。本文中「無人」ノ間ニ「〇」符アリ。 吉。金澤本、「□[下写真参照]」。 無。元暦校本、「无」。 〔訓〕 カタナミト。元暦校本・神田本、「カタナシト」。神田本、「シ」ノ右ニ朱「ミ」アリ。京都大学本、「無」ノ左ニ赭「ナシ」アリ。 ヨシエヤシ。元暦校本・神田本・西本願寺本・温故堂本・大矢本、「ヨシヱヤシ」。 ナクトモ。元暦校本、「ナケレ」。「レ」ノ下墨「ト」アリ。神田本、「ナケレトト」。「レ」ノ右ニ「トイ」アリ。漢字ノ左ニ朱「ナクトモ」アリ。 京都大学本、漢字ノ左ニ赭「ナケレト」アリ。 コレヱヤシ。元暦校本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「ヨシヱヤシ」。神田本、「ヨルニヤシ」ソノ右ニ「ヨシイヱイヤイ」アリ。 附訓本、「ヨシヱヤシ」。 【本文】 夜思 滷者雖無 勇魚取 海邊乎指而 柔田津乃 (ヤシ カタハナクトモ イサナトリ ウナヒヲサシテ ニキタツノ) 〔本文〕 滷。神田本、「□[下写真参照]」。 無。元暦校本、「无」。 柔。元暦校本、コノ下「木」アリ。 〔訓〕 ナクトモ。元暦校本・神田本、「ナケレト」。神田本、漢字ノ左ニ朱「ナクトモ」アリ。京都大学本、漢字ノ左ニ赭「ナケレト」アリ。赭ニテ右ニ移スベキヲ示セリ。 イサナトリ。元暦校本・神田本、「クチラトル」。神田本、漢字ノ左ニ朱「イサナトリ」アリ。温故堂本、「イサナトル」。西本願寺本・大矢本・京都大学本五字青。 京都大学本、漢字ノ左ニ赭「クチラトル」アリ。 ウナヒヲ。元暦校本、「アマヘヲ」。「アマ」ノ右ニ赭「ウミ」アリ。神田本・西本願寺本・温故堂本、「ウミヘヲ」。神田本、「ウミ」ノ右ニ「アマイ」アリ。 西本願寺本、「ウミ」モト青。大矢本・京都大学本、「ウナヒ」青。京都大学本、漢字ノ左ニ赭「ウミヘ/アマヘ」アリ。 ニキタツノ。元暦校本、「子キホタツノ」。「子キ」ノ右ニ赭「ニキ」アリ。神田本、「ニキ」ノ右ニ「子キイ」アリ。温故堂本、「マキタツノ」。 【本文】 荒礒之上爾 蚊青生 玉藻息都藻 明来者 浪巳 (アライソノウヘニ カアヲナル タマモオキツモ アケクレハ ナミコ) 〔本文〕 「」 荒。元暦校本、コノ下「木」アリ。但、朱ニテ消セリ。 蚊。元暦校本、右ニ朱「□□□□[下写真参照]」アリ。金澤本、「□[下写真参照]」。 〔訓〕 カアヲナル。元暦校本、「カアヲリオフル」。「リ」ノ右ニ赭「ヲ」、「オフル」ノ右ニ墨「ナル」アリ。神田本、「カアヲヲフル」。「アヲヲフル」ノ右ニ「アヲリイ」アリ。 漢字ノ左ニ朱「カアヲナル」アリ。大矢本・京都大学本、「ナル」青。 オキツモ。神田本・温故堂本、「ヲキツモ」。 【本文】 曽来依 夕去者 風巳曽来依 浪之共 彼依此依 (ソキヨレ ユフサレハ カセコソキヨレ ナミノムタ カヨリカクヨリ) 〔本文〕 浪。元暦校本、「海」。朱「浪」アリ。 彼依此依。元暦校本・神田本、「彼」ヲ「波」トセリ。「此依」ナシ。元暦校本、「波依」ヲ墨ニテ消セリ、右ニ墨「彼依此依イ」アリ。神田本、左ニ「此依」アリ。 元暦校本・神田本、本文中「依玉」ノ間ニ「〇」符アリ。 〔訓〕 ムタカヨリカクヨリ。元暦校本、「トモナミヨル」。「彼依」ノ左ニ墨「カヨリカクヨリ」アリ。神田本、「トモナミヨル」。漢字ノ左ニ朱「ムタカヨリカクヨリ」アリ。 西本願寺本、以上九字モト青。大矢本・京都大学本、以上九字青。京都大学本、「共」ノ左ニ赭「トモ」アリ。 〔諸説〕 風巳曽来依。攷證、「風社依米」(本歌)ノ誤。訓「カゼコソヨラメ」。 【本文】 玉藻成 靡吾宿之 敷妙之 妹之手本乎 露霜乃 (タマモナス ナヒキワカ子シ シキタヘノ イモカタモトヲ ツユシモノ) 〔本文〕 本。細井本、ナシ。右ニ書ケリ。本文中「手乎」ノ間ニ「〇」符アリ。 〔訓〕 ナス。元暦校本・神田本、「ナリ」。大矢本・京都大学本、「ス」青。京都大学本、「成」ノ左ニ赭「ナリ」アリ。 ナヒキワカ子シ。元暦校本、「ナヒキワレコヤトリシ」。「レ」ノ右ニ墨「カ」アリ。神田本、「ナヒキノワカレヤトリシ」。大矢本・京都大学本、「カ子」青。 京都大学本、「宿」ノ左ニ赭「ヤトリ」アリ。 【本文】 置而之来者 此道之 八十隈毎 萬段 顧雖為 弥 (オキテシクレハ コノミナノ ヤソクマコトニ ヨロツタヒ カヘリミスレト イヤ) 〔本文〕 萬。細井本、「万」。 彌。神田本、「□[下写真参照]」。 〔訓〕 オキテシ。神田本・西本願寺本・温故堂本、「ヲキテシ」。 コノミナノ。元暦校本・神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本・附訓本、「コノミチノ」。 ヨロツタヒ。元暦校本、「ヨロ」ノ右ニ赭「ヨロ」アリ。神田本、「ヨロツタカ」。「カ」ノ右ニ「ヒイ」アリ。 【本文】 遠爾 里放来奴 益高爾 山毛越来奴 早敷屋師 (トホニ サトサカリキヌ マスタカニ ヤマモコエキヌ ハシキヤシ) 〔本文〕 越。元暦校本・金澤本・神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「超」。 屋。神田本、コノ下「乃」アリ。 師。神田本、左ニ「イ□[下写真参照]」。 〔訓〕 トホニ。神田本・京都大学本、「トヲニ」。 サカリ。元暦校本・神田本・温故堂本、「ハナレ」。神田本、「放」ノ左ニ朱「サカリ」アリ。大矢本・京都大学本、青書セリ。京都大学本、「放」ノ左ニ赭「ハナレ」アリ。 マス。元暦校本・神田本、「イヤ」。元暦校本、「益」ノ左ニ墨「マス」アリ。大矢本・京都大学本、「ス」青。京都大学本、「益」ノ左ニ赭「イヤ」アリ。 コエキヌ。細井本、「コヘキヌ」。温故堂本、「コヱキヌ」。 ハシキヤシ。神田本、「サシキヤノシ」。 【本文】 吾嬬乃兒我 夏草乃 思志萎而 将嘆 角里将見 靡此山 (ワカツマノコカ ナツクサノ オモヒシナエテ ナケクラム ツノノサトミム ナヒケコノヤマ) 〔頭書〕 袖中抄、第二十「万葉長哥云ワカツマノコカ夏草ノ思志萎(オモヒシナエ)テナケヽトモトモヨメリ」 〔本文〕 吾嬬乃。神田本、ナシ、右ニ「吾嬬乃(ワカツマノ)イ」アリ。本文中「師兒」ノ間ニ「〇」符アリ。 嘆。細井本・無訓本、「咲」。 里。元暦校本、「黒」。左ニ朱「里」アリ。 〔訓〕 ワカツマノ。神田本、ナシ。本文の校異ヲ見ヨ。 オモヒシナエテ。元暦校本、「思志萎」ノ左ニ赭「オモホシナエ」アリ。神田本・温故堂本、「ヲモヒシナエテ」。細井本、「オモイシナエテ」。 ナケクラム。元暦校本・神田本、「ナケケトモ」。神田本、漢字ノ左ニ朱「ナケクラム」アリ。 ツノヽ。神田本、「ヽ」ナシ。 〔諸説〕 ツノヽサトミム。略解、「ツヌノサトミム」。
[校本萬葉集新増補版] 【頭書】 神宮文庫本、以下 〔139〕ノ歌マデノ一丁分破ラレテ存セズ。 【題詞】 或本歌一首 并短歌 【本文】 石見之海 津乃浦乎無美 浦無跡 人社見良目 滷無跡 人社見良目 吉咲八師 浦者雖無 縦恵夜思 滷者雖無 勇魚取 海邊乎指而 柔田津乃 荒礒之上爾 蚊青生 玉藻息都藻 明来者 浪巳曽来依 夕去者 風巳曽来依 浪之共 彼依此依 イハミノウミ ツノウラヲナミ ウラナミト ヒトコソミラメ カタナミト ヒトコソミラメ ヨシエヤシ ウラハナクトモ コレヱヤシ カタハナクトモ イサナトリ ウナヒヲサシテ ニキタツノ アライソノウヘニ カアヲナル タマモオキツモ アケクレハ ナミコソキヨレ ユフサレハ カセコソキヨレ ナミノムタ カヨリカクヨリ 〔訓〕 ヨシエヤシ。京都大学本、「ヨシヱヤシ」。 コレヱヤシ。神田本、「トヨルニヤシ」。近衛本、「ヨシエヤシ」。 オキツモ。近衛本、「ヲキツモ」。 【頭書】 夫木、第卅一「夏草のおもひなへてなけくらむつのゝさとみむなひけこの山」 名寄、第卅「夏草乃 思志萎而 将嘆 角里将見 靡此山(ナツクサノ オモヒシナヘテ ナケクラン ツノヽサトミン ナヒケコノヤマ) 上略」 【本文】 玉藻成 靡吾宿之 敷妙之 妹之手本乎 露霜乃 置而之来者 此道之 八十隈毎 萬段 顧雖為 彌遠爾 里放来奴 益高爾 山毛越来奴 早敷屋師 吾嬬乃兒我 夏草乃 思志萎而 将嘆 角里将見 靡此山 タマモナス ナヒキワカネシ シキタヘノ イモカタモトヲ ツユシモノ オキテシクレハ コノミナノ ヤソクマコトニ ヨロツタヒ カヘリミスレト イヤトホニ サトサカリキヌ マスタカニ ヤマモコエキヌ ハシキヤシ ワカツマノコカ ナツクサノ オモヒシナエテ ナケクラム ツノヽサトミム ナヒケコノヤマ 〔本文〕 (此道)之。京都大学本、「乃」。 〔訓〕 コエキヌ。近衛本、「コヱキヌ」。
|
|||||||||
| 「題詞」考 | 全註釈 | 【釋】或本歌 アルマキノウタ。前出の一三一の歌の別傳である。その歌は、本文中にも詞句の別傳を傳えていたから、併わせて三種の傳來があることになる。これは前掲の歌と、詞句の相違が相當に多いので、別掲したのであろう。 | ||||||||||
| 新全集 | 【頭注】 人麻呂の作品、特に長歌において、「或意は云ふ」または「一に云ふ」 と断って異文を示したものが多い。これらについて、人麻呂自身の初案と推敲の結果との違いとみる説と、人麻呂作品の伝誦過程において生じた訛伝とみる説とがある。山上憶良や大伴家持などの作品にもこの種の異文注記があるが、それらは大部分本人自記による初案とみてよいもののようである。人麻呂の歌にもその種の異文が大半を占めると思われるが、伝誦間に生じた訛伝と解すべきものが他の作者たちに比べて多いようである。この異文注記が量的に少ない場合は「29・38」などのように小字で書き入れるが、この歌のように異文が比較的に多く、句数の上でも一致せず、かつ他方の歌に既に異文が注記されている場合、「或本の歌」という題詞を付して別個の歌として扱っている。 |
|||||||||||
| 「津の浦をなみ」注 | 拾穂抄 | つの浦をなみ 浦なみと重ね詞にや但つの浦をなみはなんといふてにはの詞なるへし此哥前のなか哥と同し心なれは也 | ||||||||||
| 代匠記 | 此點の同異、今案の點等上の歌に准ず、第二の句津乃浦ヲナミは、上に角乃浦囘と云所の名にあらで.大舟などあまた泊る浦となる浦のなしと云心なるべし、若然らずばつの浦をなみと云こと不審なり、さきの如く先角浦と名をば定置て、よき浦なしと人こそ見らめとぞ有べき、さらずば、津乃浦無美、うらなみとと云べし、さるにても元來みづから能浦なしと見ば、人を待ずして浦はなけれど滷はなけれどと云べき理なれば、それもいはれず、津乃浦とかけるに付て思ふに、唯初に申つる義なるべし、其外は替れる義なし、 | |||||||||||
| 童蒙抄 | 石見之海津乃浦乎無美云云 童子問 此或本の歌と、前の歌とは大方おなし躰なれとも、いつれか是ならんや。 答 此反歌の角里將見と有は、前の歌にまされとも、妹之手本乎置而之來者といふは、前におとれる歟。 しかれとも此歌にては置をすておくと見るへからす。曉起て別し意にみるへし。兩首ともに好む所にしたかふへし。 |
|||||||||||
| 万葉考 | 石見之海、津乃浦乎無美、浦無跡、 こは津能乃浦囘 [ワ] 乎の能と囘を落し、無美はまぎれてこゝに入たるなり、此外いと誤多し、たまたま誤ならで異なるは、右の歌に註しつ、 |
|||||||||||
| 略解 | 石見之海。津乃浦乎無美。(是は津能乃浦囘乎の能と囘を脱し、無美は紛れて入たりと見ゆ)浦無跡。 | |||||||||||
| 攷證 | 津之浦乎 [ツノウラヲ]。 眞淵の説に、津能乃浦囘乎[ツノヽウラワヲ]の、能と囘を落し、無美は、まぎれてこゝに入たる也。其外、誤りいと多し。依て、この歌はとらず云々とあり。さもあるべし。 |
|||||||||||
| 全釈 | 津乃浦乎無美 [ツノウラヲナミ] ―― この句は津能乃浦回乎 [ツノノウラミヲ] の誤で、能の字脱ち、無美は衍であらうと考に見えるが、ツヌと言ふべき處であるから、能ではあるまい。 | |||||||||||
| 全註釈 | 【釈】 津乃浦乎無美 ツノウラヲナミ。前出の歌には角乃浦廻乎とあり、その方がよく通る。これはそれを訛傳したのであろう。これでは下の句との按續がわるい。これを誤字ありとする説があるが、かような形において傳えられたものと解すべきである。 |
|||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「つのうらをなみ」 前に津野の浦のあるところを単に津の浦とも云つたのであらう。しかしそこは浦といふ名に値しなく、入江になつてゐなくて、の意。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】 津は、普通名詞とすれば舟の泊まる所を言う。代匠記(精撰本)に「上ニ角乃浦回ト云所ノ名ニハアラテ、大舟ナトアマタ泊ル津トナル浦ノナシト云心ナルヘシ、然ラスハツノ浦ヲナミト云コト不審ナリ」と記されている通りであろう。考に「こは津能乃浦回乎の能と回を落し、無美はまぎれてここに入たる也」と言うのは、誤伝と判断したのであり、檜嬬手・古義・美夫君志などもこれに従っているが、講義に「この所いづれの本にも誤脱なし。而して、かく異なる点あればこそ、あげたるなるべければ、その『つのうら』といふ地知られずとも、かく異本にありといふことなれば改むるは強事なるべく、ただ疑はしきを闕くに止まるべきなり」と記すように、誤伝説には従えない。「131歌」の「角の浦廻を」のほうが、妻の住む角の里近くの海岸であることがわかり易い。「津の浦を無み」は、石見の海岸に船着き場となる良い浦のないことを全般的に言ったもので、次句と重複する。 |
|||||||||||
| 原文「海邊(うみへ)」訓・考 | 拾穂抄 | うなひ 海邊と書うみへとおなし又うみへとも讀へき歟 | ||||||||||
| 代匠記 | ウナヒヲサシテ | |||||||||||
| 攷證 | 海邊乎指而 [ウナヒヲサシテ] | |||||||||||
| 全釈 | 海邊乎指而 [ウミベヲサシテ] | |||||||||||
| 全註釈 | 海邊乎指而 [ウミベヲサシテ] | |||||||||||
| 評釈 | 海邊 [うみべ]を指して | |||||||||||
| 注釈 | 海邊乎指而 [ウミベヲサシテ] | |||||||||||
| 全注 | 海邊乎指而 [ウミヘヲサシテ] | |||||||||||
| 原文「柔田津(にきたつ)」訓・考 | 全釈 | 柔田津乃 [ニギタヅノ] ―― 本文に和多豆乃とあるので、これをワタヅとすれば、柔田津の傳はどうして出來たものか、頗る迷はざるを得ない。 | ||||||||||
| 全註釈 | 【釈】 柔田津乃 ニキタヅノ。前の歌では和多豆乃とあつた。此處に柔田津とあるのに依れば地名とすべきであろう。かの和多豆をもニキタヅと讀めというのは、この字面に依つているのである。しかし恐らくはもと和多豆乃とあつたものをニキタヅと讀み誤つて、この字面を生じたものであろう。 |
|||||||||||
| 評釈 | 【語】 柔田津 「一三一」に述べた如く、今石見に見當らぬ地名で、不明とする他はない。或は和多豆を夙く誤り訓んだものであららか。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】「柔田津の荒磯の上に」 原文「柔田津」は、「ニキタツ」と訓む。「131歌」本文の「和多豆」との関係について、新考に「柔田津は底本の和多豆に当たれり。されば底本の和多豆は之と相照してなほニギタヅとよむべきかといふにおそらくは和多豆をニギタヅと誤り訓みて柔田津と書きたるならむ」と言い、講義にも「和をニギとよむによりて巻一の地名に附会して後人の書き改めしものなるべくして人麿の原本にはあらざるべし」と推測している。「或本歌」の詞句を後人の変改と考えるわけで、評釈篇・窪田評釈にも、全註釈・私注などにも同様な説を見る。これらを伝誦説と名づけるなら、反対に作者の初案と考える推敲説もあって、澤瀉注釈・古典集成や、松田好夫『万葉研究 新見と実証』、伊藤博『万葉集の歌人と作品 上』などに見られる。曽倉岑「万葉集巻一・巻二における人麻呂歌の異伝」(国語と国文学昭和三十八年八月) に推敲・伝誦両説の根拠の薄弱なことを述べ、二歌の詞句の比較によって伝誦か推敲かを決定する方法について論じているのは、基本的な問題を引き出したものである。直観的な印象による判断でなく、詞句の比較検討をとおして、推敲・伝誦のいずれであるか考えられるべきである。このニキタツとワタヅとは、地名の相違であって、それ自体としては是非を決定する手掛かりにならない。が、後述するような他の詞句の比較から言って、異伝は推敲の過程を示すものとする説によるべきである。 |
|||||||||||
| 原文「玉藻息都藻 (たまもおきつも)」考 |
全注 | 【注】 原文「玉藻息都藻」。オキ (沖) を「息」の字によって記した例は、前の「131歌」とここ以外にない。作者人麻呂の意図的表記と考えられよう。 |
||||||||||
| 「明来者 浪己曽来依 夕去者 風己曽来依」考 |
拾穂抄 | 明くれは 夜明來れは也 | ||||||||||
| 攷證 | 明來者 [アケクレバ]。 本集六〔十一丁〕に、閲來者朝霧立 [アケクレバアサキリタチ]、夕去者川津鳴奈利 [ユフサレハカハツナクナリ] 云々。十〔十八丁〕に、明來者柘之左枝爾 [アケクレハツミノサエタニ]、暮去 [ユフサレハ]、小松之若未爾 [コマツカウレニ] 云々。十五〔十一丁〕に、由布佐禮婆安之敝爾佐和伎 [ユフサレハアシヘニサワキ]、安氣久禮婆於伎爾奈都佐布 [アケクレハオキニナツサフ] 云々などありて、集中猶いと多し。皆、夜があけつゞくればにて、あけゆけばなどいふに同じ。 風己曾來依 [カゼコソキヨレ]。 浪己曾來依 [ナミコツキヲレ] といふは、聞えたれ、風こそきよれといふは聞えず。風は、ふくとこそいへ、來依 [キヨル] とはいふべからず。こは、本歌に風社依米 [カセコソヨラメ] とあるを、誤りしなるべし。 |
|||||||||||
| 全註釈 | 【釈】 明來者浪己曾來依 アケクレバナミコソキヨレ。前の歌には、朝羽振風社依米とあつて、朝羽振は風を修飾していた。この傳來では、夜が明けて來ればと敍している。また浪が先になつている。 夕去者風己曾來依 ユフサレバカゼコソキヨレ。これも前の歌には、夕羽振流浪社來縁となつていた。 |
|||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】 前の歌では「朝羽振る風こそよせめ 夕羽振る浪こそ来よれ」とあるところで、こちらでは風と浪とが前後して、前に「よせめ」「来よれ」とあつたところが、こちらでは双方とも「来よれ」となつてゐる。前句「よせめ」であつてこそ、前に述べたやうにその上の玉藻おきつ藻をうけるのであるが、「来よれ」では「玉藻おきつ藻」が浮いたものになつてしまふ。又「風」が前に「浪」があつてこそ、次の「浪のむた」とのつづきも自然である。かうして前の方がよいわけであるが、これを伝誦の間に形が乱れたと考へるよりも、むしろこれが作者の言葉であつて、それに推敲を加へて語法を整へたものが前にかかげられたものと考へるべきだと私は信ずる。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】 朝・夕、浪・風を対照した二句対であるが、繰り返し的な性格が濃い。「131歌」の「朝羽振る風こそ寄らめ 夕羽振る波こそ来寄れ」に比べ、「平易に常識的になつてゐる」(評釈篇) とも評されるが、朝夕の自然の景を対句に詠む場合、奈良時代には「明けくれば 朝霧立ち 夕されば かはづ鳴くなへ」 (6・913)、「夕されば 芦辺に騒き 明けくれば 沖になづさふ」 (15・3625) など、繰り返し的な性格を薄め、朝夕のそれぞれに特有な景を選んで視覚と聴覚とを対照的に歌い込む対句を見るようになる。これは中国における六朝以後の対句技法の影響と思われるものであり、そうした対句の技法的深化の状況からいって、人麻呂の「131歌」の詞句を伝誦した奈良時代の人々が、「138歌」のような繰り返し的対句に歌い改めたとは考えにくい。その点も推敲説に利があろう。 |
|||||||||||
| 「玉藻成 靡吾宿之 敷妙之 妹之手本乎」考 |
拾穂抄 | 玉もなすなひき我ねし 玉もなすはなひきといはんとて也なひき我ねしは前のうたによりねしとあるに同しくよりなひきの儀也 | ||||||||||
| 攷證 | 敷妙之 [シキタヘノ]。 枕詞にて、冠辭考にくはし。上にもいへるがごとく、しきたへは、しげき栲といふことにて、袖、袂、衣、床、まくらなどつゞくを、こゝは、語を隔てゝ、妹之手本といふ、袂へつゞけしなり。枕詞の、語を隔てて下へつゞく例は、冠辭考補遺にいふべし。 妹之手本乎 [イモカタモトヲ]。 手本 [タモト] は、借字にて、袂なり。
|
|||||||||||
| 全註釈 | 【釈】 靡吾宿之 ナビキワガネシ。前の歌では、依宿之妹乎となつており、玉藻ナスは、妻の修飾になつていた。この傳來では、作者自身が靡いて寢たと言つている。しかし男子が靡キ宿シというのはおかしいことであり、また玉藻のように靡くということは、人麻呂の歌には常に婦人の上にいうことであつて、自分が靡いて寢たというのはまさしく傳え誤つたものと認められる。また下の句に對して靡キ吾ガ寢シ妹ガ手本ヲではよく續かないのである。 敷妙之妹之手本乎 シキタヘノイモガタモトヲ。この句は、前の歌には相當する句が無く、以上の四句を併せて玉藻成依宿之妹乎になつているのである。前の歌の歌詞中の一云に、波之伎余思妹之手本乎とあるは、この或る本の傳來と關係があるのであろう。 |
|||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「玉藻なす靡き吾がねししきたへの妹がたもとを」 この四句は前の「玉藻なすよりねし妹を」の二句に相当するところで、ここにもまた右に述べた事を認め得ると私は考へる。前にその二句の下の一云が二句のかはりではなくて、その句を加へた四句であらうと述べておいたが、 玉藻なす 靡き吾がねし しきたへの 妹がたもとを 玉藻なす よりねし妹を はしきよし 妹がたもとを 玉藻なす よりねし妹を かう三つ並べてみると再轉三變した人麻呂の修辭推敲のあとが辿られるのではないかと私は考へる。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】「玉藻なす靡きわが宿し敷妙の妹が手本を」 「131歌」の「玉藻なす 寄り寝し妹を」にくらべ、「敷妙の 妹が手本を」は冗長で、本文の簡浄さに及ばない。「131歌」の「一云」によると、「玉藻なす 寄り寝し妹を はしきよし 妹が手本を」という異伝もあったようだ。「或本歌」と「一云」のそれぞれを後代の伝誦による変化とする説もあるが、澤瀉注釈および伊藤博(『万葉集の歌人と作品 上』) によれば、「或本歌」の「玉藻なす 靡きわが宿し 敷妙の 妹が手本を」が初案で、「一云」の「玉藻なす 寄り寝し妹を はしきよし 妹が手本を」が再案、そして本文の「玉藻なす 寄り寝し妹を」が最終案であるという。 |
|||||||||||
| 「弥遠尓 里放来奴 益高尓 山毛超来奴」考 |
全註釈 | 【釈】 里放來奴 サトサカリキヌ。 前の歌には、里者放奴とあり、これもその方がよい。 |
||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「里放来奴」(さとさかりきぬ) 里をはなれて来た、の意で、次の「山も越え来ぬ」の対句としてはふさはしく整つてゐるやうであるが、語法が同じくりかへしになつてゐるところ初期歌謡の例に多い形で、それに推敲を加へ前の「里はさかりぬ」に改めたものと思はれる。「里は」と云へば里が主語となつて下の句と語法的に相対する事になるわけである。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】 「131歌」の本文「いや遠に 里は放りぬ いや高に 山も越え来ぬ」の方が、対句に変化がある。それを、平凡な繰り返し的対句から推敲を経て得られた形と見るか、本文から「或本歌」の形へ伝誦によって変化したと見るかで、説が分かれる。注釈に「語法が同じでくりかへしになつてゐるところ初期歌謡に例の多い形で、それに推敲を加へ前の『里はさかりぬ』に改めたものと思はれる。『里は』と云へば里が主語となつて下の句と語法的に相対する事になるわけである」と記す。 |
|||||||||||
| 「早敷屋師 吾嬬乃兒我 夏草乃 思志萎而 将レ嘆 」考 |
註釈 | 早敷屋師吾嬬乃兒我 [ハシキヤシワカツマノコカ] 云々。先達オホク女ヲハ、ハシキヤシトイフトイヘリ。今撿ルニ、ハシキヤシトイフハ、コトノハノシケキ義也。男トモ女トモ、トリワキテハイフヘカラス。 日本記卷第十七、男火迹天皇 [ヲホトノスメラミカト]〔繼躰天皇更ノ名ハ彦太尊〕七年九月、勾大兄 [マカリノオホヱノ] 皇子親 [ミツカラ] 娉 [メス・ムカヘ] 二春日ノ皇女ヲ一。於レ是月夜清談 [ツキノヨスカラニモノカタリシテ] 不レ覺 [オロカニ] 二天曉 [アケヌ]。斐然 [フミツクル・ウタツクル] 之藻忽 [ミヤヒニ] 形ス二於言ニ一。乃口唱 [クチツウタテ] 曰ク、野施摩倶你 [ヤシマクニ・八洲國]、都麼々祁□[加/可] 泥底 [ツママチカネテ] 播屡比能 [ハルヒ (春日)ノ]、□[加/可] 須我能倶你々 [カスカ(春日)ノクニニ]、倶婆施謎鳴 [クハシキメ (妙女)]、阿唎等枳々底 [アリトキヽテ]、與慮志繼鳴 [ヨロシキメ(宜女)、阿唎等枳々底 [アリトキヽテ]、莽紀佐倶 [マキ サク(割)]、避能伊陀圖嗚 [ヒノイタトヲ(檜板戸)、飫斯毘羅枳 [ヲシヒラキ(押開)、倭例以梨魔志 [ワレイリマシ(吾入座)、阿都圖唎 [アトトリ(跡取)、都磨怒唎絶 [絁]ィ)底 [ツマトリタエテ]、 魔倶羅圖唎 [マクラトリ(枕取)]、都磨怒唎絶底 [ツマトリ(妻取)タエテ]、伊慕我提嗚 [イモカテ(妹手)ヲ]、倭例你魔柯絶毎 [ワレニ マカタヱ(纒絶)]、倭我提嗚磨 [ワカ テ(手)ヲハ]、伊慕你魔柯絶毎 [イモニマカタヘ]、麼左棄逗羅 [マサカツラ]、多々企阿藏(叩朝)播利 [タヽキアサハリ]、矢自矩矢盧 [シヽクシロ(泪玉女粧)、于魔伊祢矢(今不寢)度你 [イマイネシトニ]、々播都等唎 [ニハツトリ(鷄)、柯稽播儺倶(掻羽鳴)儺梨 [カケハナクナリ]、奴都等梨 [トツトリ]、枳蟻矢播等余武 [キキシハトヨフ(雉呼)]、婆絶稽矩謨 [ハタヽキモ(絶)、伊麻娜以播嬬底 [イマタイハステ(未言)、阿開你啓梨倭蟻慕 [アケニケリワキモ(明吾妹)]。已上。コノウタノコヽロ、カナラスシモ女ヲイフヘシトモキコヱス。サレハ此集ノ歌ニハ、男ニモ女ニモ、乃至草木ニモアレ、水ノヲトニモアレ、コトノハノシケキニハミナヨメリ。又ハシキヤシトモ、ハシキヨシトモ、ハシケヤシトモカケル、オナシコトナルヘシ。今ノ第二卷ノ歌ニハ、ハシキヤシ、ワカツマノコカトツヽケタレハ、女トモイヒツヘシ。女ヲイフト尺スルハ、此歌ナトニヨリケルニヤ。シカレトモ男ニモヨメリトイフコトハ、第十六卷、竹取翁ニアヒヲ、九箇神女ヨメル歌ニハ、ハシキヤシオキナノウタニオホヽシキコヽノヽコラヤカマケテヲラムトヨメリ。第廿卷ニ、天平寶字二年二月於式部大 帥 [輔ィ] 中臣清麿朝臣家宴歌ニモ、ハシキヨシケフノアロシハイソマツノツネニイマサネイマモミルコトヽヨメリ。此歌ハ、作者、右中辨大伴宿祢家持也。コノ歌トモハ、男ヲヨメリ。又第七 [十ィ] 卷歌ニ、ハシキヤシワキヘノケモヽモトシケクハナノミサキテナラズアラメヤモトイヘリ。コノハシキヤシハ、モヽニヨソヘテヨメリ。又第十二卷歌ニ、イハヽシルタルミノミツノハシキヤシキミニコフラクワカ心カラ。コレハミツニヨソヘテ、ハシキヤシトヨメリ。シカレハカナラスシモ、女ヲハ、ハシキヤシトイフトハ尺シサタムヘカラサルヲヤ。 |
||||||||||
| 拾穂抄 | なつ草の思ひしなへて 夏草は照日にしほるれはしなへてといはん諷詞にをく也 | |||||||||||
| 攷證 | 早敷屋師 [ハシキヤシ]。 はしきやしの、しは、よしゑやしの、しと同じく、助字也。はしきは、愛 [ハシキ] にて、愛する意なれば、吾嬬の兒とはつゞけし也。屋 [ヤ] は、よに通ひて、そへたる語也。猶くはしくは、下〔攷證二下十二丁〕にいふべし。 吾嬬乃兒我 [ワカツマノコカ]。 わがつまのこがの、兒は、上に、靡寐之兒乎とある、兒と同じく、親しみ愛していへるなり。この事は上にいへり。 |
|||||||||||
| 全釈 | 早敷屋師 [ハシキヤシ] ―― 美 [ハ] しきやしで、ヤとシとは詠嘆の辭、ヨシヱヤシのヤシに同じ。ハシキは美しき、又は愛すべきの意。 | |||||||||||
| 全註釈 | 早敷屋師吾嬬乃兒我 ハシキヤシワガツマノコガ。 前の歌には、この句が無い。この或る本の傳來では、下が角ノ里見ムとあるので、この句のあるを要する。ハシキヤシは、愛すべきの意で、ヤシは感動の助詞。ツマノコは妻をいう。コは愛稱。「波之吉余之 [ハシキヨシ] 曾能都末能古等 [ソノツマノコト] 安沙余比爾 [アサヨヒニ] 惠美々惠末須毛 [ヱミミヱマズモ]」(卷十八、四一〇六)、「佐穗度 [サホワタリ] 吾家之上二 [ワギヘノウヘニ] 鳴鳥之 [ナクトリノ] 音夏可思吉 [コヱナツカシキ] 愛妻之兒 [ハシキツマノコ]」(卷四、六六三) など、用例がある。 將嘆 ナゲクラム。前の歌には、志恕布良武とあつた。シノフは内面的であり、ナゲクは外形にあらわれている。いずれでもよいが、シノフの方が奧行が深い。 |
|||||||||||
| 評釈 | 【語】 愛しきやし 愛らしい、いとほしいの意。「やし」は「よしゑやし」の「やし」に同じ。吾が嬬の兒 兒は愛稱。 |
|||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「はしきやし吾が妻の子が」 この二句は第二案以後には削られらもので、この「はしきやし」が第二案では「はしきよし 妹がたもと」へ移されたものである。「やし」は「よし」に同じ。「妻の子」の「子」は愛稱として用ゐられたもの。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】 本文では「はしきやし 吾が嬬の児が」の二句のかわりに「夏草の 思ひしなえて」が入り、「嘆くらむ 角の里見む」は「偲ぶふらむ 妹が門見む」になっている。「或本歌」の形が説明的で、感動の乏しいものであるのに対し、本文の「夏草の 思ひしなえて 偲ふらむ 妹が門見む」は、嘆いている妹に焦点を搾り、生き生きと映像化していて、末尾の「靡けこの山」という命令表現にも現実感を加えている。 |
|||||||||||
| 「角里将レ見 (つののさとみむ)」考 |
拾穂抄 | つのゝさと見ん 前には妹か門みんとあり角の里は即妹か里にや | ||||||||||
| 攷證 | 角里將見 [ツヌノサトミム]。 角里 [ツヌノサト] は、角浦 [ツヌノウラ] とある同所歟。高角山 [タカツヌヤマ] といふも、角といふからは、こゝによしありて聞ゆ。角浦、高角山など、同所ならば、まへの歌のおもむきにては、國府より、妻に別れて、上る道のほどと聞ゆるを、こゝに、かくよめるは、角里に妻を置たりと見ゆ。いづれを是とせん、とは思へど、おそらく、この歌の方誤りなるべし。 |
|||||||||||
| 全註釈 | 【釈】 角里將見 ツノノサトミム。前の歌には、妹之門將見とあつた。この歌では、上の、ハシキヤシワガ妻ノ兒ガの句があるから、角の里と言つている。これも妹ガ門の方が、欲する所が集中されていてよい。 |
|||||||||||
| 「或本歌」考 | 全註釈 | 【評語】 以上註釋の欄に記したように、前の歌の方がおおむね正説と認められる。傳承のあいだに訛傳を生じたものであろう。しかしこれに依つて、この歌が當時の人々のあいだに愛誦されたことが知られる。 |
||||||||||
| 評釈 | 【評】 前出の「一三一」の異傳であり、それと比べると、解り易くなつてゐるやうであるが、歌としては劣る。例へば「明け來れば」「夕されば」は「朝羽ふる」「夕羽ふる」に比して解りよいし、「一三一」で「玉藻なす寄り寢し妹を」とあつたのを「玉藻なす靡き吾がねし敷妙の妹が袂を」としたのは、詳しくはなつたが、簡潔な前者に劣り、「愛しきやし」云々の挿入も同樣である。特に「里は放りぬ」と「里放り來ぬ」との聲調の差、「妹が門見む」と「角の里見む」との感情の集中の差は、歌に志す者にとつてよく注意すべきところである。 |
|||||||||||
| 注釈 | 【考】 この作を初稿と見るべき事、訓釈の條でその一々の異同について述べた通りである。この作四十三句、その中より削り得る四句を削つて「131歌」の卅九句とし、「135歌」と同じ句数にして連作としての形を整へたものと考へられる。この作を伝誦の間に転訛したと見る説は右に述べた如く従ふ事は出来ない。人麻呂の時代とこの集の編纂の時代とは「転訛」が生ずる程に距つてもゐないのである。 |
|||||||||||
| 全注 | 【考】長歌一首の句数について 注釈に、この「或本歌」は四十三句であり、そこから四句を削って三十九句としたのが「131歌」であり、「135歌」と同句数の連作としたものと推定されている。 |
|||||||||||
| 新全集 | 【頭注】 人麻呂の作品、特に長歌において、「或本歌は云ふ」または「一に云ふ」と断って異文を示したものが多い。これらについて、人麻呂自身の初案と推敲の結果との違いとみる説と、人麻呂作品の伝誦過程において生じた訛伝とみる説がある。山上憶良や大伴家持などの作品にもこの種の異文注記があるが、それらは大部分本人自記による初案とみてよいもののようである。人麻呂の歌にもその種の異文が大半を占めると思われるが、伝誦間に生じた訛伝と解すべきものが他の作者たちに比べて多いようである。その異文注記が量的に少ない場合は「29歌」や「38歌」などのように小字で書き入れるが、この歌のように異文が比較的に多く、句数の上でも一致せず、かつ他方の歌に既に異文が注記されている場合、「或本の歌」という題詞を付して別個の歌として扱っている。 |
|||||||||||
| 巻二 139 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版] (1980年9月)も併記する 【題詞】反歌 〔本文〕 歌。神田本、「謌」。元暦校本・金澤本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本、コノ下「一首」アリ。 【頭注】 類聚古集、前行ニ「又或本長哥反哥一首同句々相替因此重載」。 釈日本紀巻第二十三「裏書云 打歌山乃木際従 (ウツタノヤマノコノマヨリ) 万葉集第二」 【本文】 石見之海 打歌山乃 木際従 吾振袖乎 妹将見香 (イハミノウミ ウツタノヤマノ コノマヨリ ワカフルソテヲ イモミツラムカ) 〔訓〕 イハミノウミ。元暦校本・金澤本、「いはみなる」。元暦校本、「なる」ノ右ニ朱「ノウミ御本」アリ。 コノマヨリ。元暦校本、「こすゑより」。「すゑ」ノ右ニ朱「ノマ」アリ。 〔諸説〕 石見之海、イハミノウミ。万葉考、「海」ハ誤。攷證、「イハミノミ」。 打歌山乃。万葉考、「歌」ノ下「角」又ハ「津乃」脱トシ「タカツノヤマノ」トス。古義、「打歌」ハ「竹綱」ノ誤。訓、「タカツヌヤマノ」。 【左注】右歌體雖同句句相替 因此重載 〔本文〕 歌。神田本、「謌」。 句。神田本、ナシ。元暦校本・金澤本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「々」。 相。京都大学本、ナシ。 此。神田本、「□[下写真参照]」。右ニ「此」アリ。 〔訓〕 此。京都大学本赭訓アリ、次ノ如シ。「此ニ重テ載ス」。
[校本萬葉集新増補版] 【題詞】反歌 【頭書】 神宮文庫本、コノ一首マデ缼ケタリ。 夫木和歌抄、第廿「いはみのうみうつたの山の木間より我ふる袖をいも見つらむか」。 歌枕名寄、第卅「石見の海うつたの山の木間よりわかふる袖をいも見つらむか」。 【本文】 石見之海 打歌山乃 木際従 吾振袖乎 妹将見香 (イハミノウミ ウツタノヤマノ コノマヨリ ワカフルソテヲ イモミツラムカ) 【左注】右歌體雖同句句相替 因此重載 〔本文〕 「句句」、最初の「句」。京都大学本、「勺」。 「句句」、二番目の「句」。神宮文庫本、「々」。 |
|||||||||
| 「前歌に問もらす」 | 童蒙抄 | 童子問 前歌に問をもらすは今問也。早敷屋師吾嬬乃兒我と云詞解かたし。嬬の冠辭か、仙覺抄云、早敷屋師吾嬬乃兒我云云、先達おほく女をははしきやしと云といへり。今撿るにはしきやしといふは、言のはのしけき義也。男とも女ともとりわきては云へからす。日本書紀卷第十七云、男大迹天皇云云婆絁稽矩謨伊麻娜以播□[歿の旁が需]庭阿開仁啓梨倭蟻慕巳上。此歌の心かならすしも女をいふへしともきこえす。されは此集の歌には、男にも女にも乃至草木にあれ、水の音にもあれ、言のはのしけきにはみなよめり。又はしきやしとも、はしきよしとも、はしてやしともかける、おなし由となるへし。今の第二卷の歌には、はしきやしわかつまのことゝつゝけたれは、女ともいひつへし。女をいふと釋するは、此歌なとによりけることにや。しかれとも男にもよめりと云事は、第十六卷竹取の翁にあひて、九ゲの神女のよめる歌には、はしきやしおきなのうたにおほしきこゝのゝこらやまけてをらんとよめり。第二十卷に.天平寶字二年二月於2式部大輔中臣清麻呂朝臣家1宴歌にも、はしきよしけふのあろしはいそまつのつねにいまさねいまもみることとよめり。此歌は作者右中辨大伴宿禰家持なり。この歌ともは、男をよめり。又第七卷の歌に、はしきやしわきへのけもももとしけく花のみさきてみならすあらめやもとよめり。このはしきやしは桃によそへて讀り又第十二卷の歌に、いはゝしるたるみの水のはしきやしきみにこふらくわか心から、これは水によそへてはしきやしとよめり。しかれはかならすしも女をはしきやしといふとは、釋し定むへからさるをやとあり。此説は男女草木につきて、はしきやしといふ證歌をあけたるまてにて、句意きこえす。いかに心得へきや。 答 此詞も本日本書紀の歌にみえたれは、かの童子問に答へてこゝにいはす。 |
||||||||||
| 原文「打歌山 (うつたのやま)」訓・考 |
拾穂抄 | (反歌「132・134歌」の次に併せて載せる) いは見のやたかつの 我はなつかしくてかへり見まねくといへとも里遠く山高くて見えす妹は我ふる袖を見つらんかさもあらしとの心也一云哥義同 |
||||||||||
| 童蒙抄 | 童子問 打歌山、或人の云長門國にありといへり。しかりや。 答 長門の國にも有歟。同名の所諸國におほければ、さも有へし。しかれとも石見之海打歌山乃木際從と、此人麻呂の歌にみゆるからは、石見の山の名とみるへし。同名有とても他國にては長歌にかなはす。只木際從吾振袖とつゝきたるを隔句とみすして、木際にて人麻呂の袖を振とみる誤より、打歌山も長門國に有といふ説出來たる歟。それも旅立の道海にうかはす、先角の山にてもあれ、打歌山にもあれ、越行時に人麻呂山上より袖を振て、まねかれたりといはゝ、いはれましきにもあらさるか。猶復案して決すへき歟。 復案 從吾振袖乎妹將見香、此歌前案に隔句の歌と見て、何國にてもあれ、旅行の路より人麻呂の袖を振たまへるを、角の山にまれ、人麻呂の妻の、木の間より見るらんかみえましきと歎く歌の意とみたれとも、隔句とみるもいかゝなれは、順句にみて木の間より人麻呂の袖を振たるに決すへし。しかれは後鳥羽院の御製も、さのみあやまりにあらさる歟。しかれとも此御製は松浦さよ姫のひれふりし山を、とりちかへたまへるより、石見かたとよみ給へるとみたれは、いつれにしても相違の事なり。ひれと袖とのたかひを、袖ふる峰と改めまほしきこと也○されは靡此山といふ句も、或本の歌にては、此山とは打歌山を指て見るへし。前の長歌にては高角山とみるへし。若打歌山は、高角山の一名か、然らはいつれにても相違有まし。人麻呂の袖ふりしと(488)みる復案の證は、前の反歌にも、小竹之葉者三山毛とよまれ、又高角山とよまれたれは、反歌皆山の歌也。是一證也。且或本歌にも、秋山に落黄葉の歌有。又或本の歌の反歌に、打歌山の歌あれは、船中の作にはあらさるとみえたり。是一證也。 |
|||||||||||
| 万葉考 | 【此初句、海と有も誤れり、】此打歌 [タカ] は假字にて、次に角か津乃 [ツノ] などの字落し事、上の反歌もて知べし、今本にうつたの山と訓しは人わらへなり、 | |||||||||||
| 略解 | この打歌山をウツタノヤマと假字つけたれど、いと由なし。打歌の下角の字の脱ちたるなるべし。然らば打歌はタカの假字書にて、タカツノヤマと訓むべきなり。初句石見の海と有るも誤れりと見ゆ。長歌短歌ともに或本は取られぬ事多し。 | |||||||||||
| 攷證 | 打歌山乃 [ウツタノヤマノ]。 考云、この打歌は、假字にて、次に、角か、津乃などの字落し事、上の反歌もてしるべし。今本に、うつたの山と訓しは、人わらへ也云々といはれつる、さもあるべし。 |
|||||||||||
| 全釈 | 石見之海 [イハミノミ] 打歌山乃 [タカツヌヤマノ] 木際從 [コノマヨリ] 吾振袖乎 [ワガフルソデヲ] 妹將見香 [イモミツラムカ] 打歌山乃 ―― この句は舊訓ウツタノヤマノであるが、頗る穩やかでない。考には打歌 [タカ] は假名で、次に角か津乃などが落ちたのであらうと言つてゐる。角の字を補ふのはよいやうだが、打の字はタとよんだ例がなく、歌もカとよんだものはない。哥を何哥毛 [ナニシカモ] (一四七五) とよんだのがあるのみである。恐らくは誤字であらう。古義の竹綱 [タカツヌ] 説はあまり物遠い。 |
|||||||||||
| 全註釈 | 【釈】(イハミノウミ。次の打歌山の所在を示している。しかし長歌の方は角ノ浦ミであるから石見の海と言つてよいのだが、打歌の山の所在を石見の海というのは無理である。) 打歌山乃 ウツタノヤマノ。地名であろうが所在未詳。しかし前出の高角山の誤傳と認められる。これも高角山とあつた高を打歌と書いたのから誤つたものであろう。 |
|||||||||||
| 評釈 | 石見 [いはみ] の海打歌 [うつた] の山の木 [こ] の際 [ま] より吾が振る袖を妹見つらむか 〔評〕 前出「一三二」の異傳であるが、初句「海」というて、二句「山」といふこともいかがである。誤傳であらう。 〔語〕 打歌の山 地名と思はれるが、よく分らぬ。次項參照。 〔訓〕 打歌の山 考は「打歌」をタカと訓み、下に角か津乃の脱といひ、古義はT竹綱《タカツヌ》山」の誤といつてゐるが、諸本異同なく、確證がない。暫く舊訓に從ふ。 |
|||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】 打歌山-「打歌」の二字を金澤本以来「ウツタ」と訓んでゐる。この二字に誤がなければ「ウツウタ」の約として「ウツタ」と訓むより致し方がないやうに思はれる。しかし「132歌」にも「134歌」にも「高角」とあり、今の長歌にも「角里」とあつて、当然タカツノとあるべきところである。そこで万葉考には「打歌(タカ)は仮字にて、次に角か津乃(ツノ)などの字落」ちたとしてをり、古義には「竹綱」の草書の誤かとしてゐる。「打」の字は「埿打(ヒヅチ)」 (194)、「亦打(マツチ)」 (1・55) など借訓の仮名には用ゐられてゐるが、音仮名の例は他にない。しかし「タ (ダは慣用音)」の音を借りたと見る事は出来る。「歌」も「歌方 (ウタカタ)」 (12・2896) の如き借訓の例のみであるが、「カ」の音を借りたと見る事は勿論認められるからやや見なれない感はあるが、万葉考の説によるべきかと思はれる。即ち人麻呂が最初の草稿にはかうした仮名書を用ゐたが、後には高角と改め、その方は正しく書き写されたが、草案の方はもともと乱れがちな走り書きであり、転写の間に脱字なども生じ、集の編纂者の手にはひつた時には既に「打歌」となつてゐたものと思はれる。若し「タカツノ」と訓まれる文字であつたらここにあげる必要はないわけで、左注にあるやうに、「句々相替」つてゐたればこそあげたので、編纂者にも疑問のままに収められたものと見るべきである。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】「打歌山乃 木際従」 (うつたのやまの このまより) (石見の海 「132歌」の「石見のや」、「134歌」の「石見なる」にくらべ、「石見の海」という第一句は次の句への続き具合が自然でない。「132」が原形で、伝誦の間に変形したとも考えられるが-真淵は「此初句、海と有も誤れり」と言い、以後の諸注にも、次の打歌山とのつながりを不審とするものが多い-、「打歌山」という地名の相違とともに人麻呂の初稿と考える説が有力((伊藤前掲書など)))。 「132歌」の「高角山」が「打歌の山」となっている。旧訓「ウツタノヤマ」とあったのを真淵は「此打歌(タカ)は仮字にて、次に角か津乃なとの字落し事、上の反哥もて知べし、今本にうつたの山と訓しは人わらへ也」として、「タカツノヤマ」の誤字と見、古義にも竹綱の草書の誤りかとする。以後誤字もしくは脱字を認める説が有力である。しかし、古典全集本頭注に「打の字は頂と同音でタの仮名とはなりえない」と記すように、タカを「打歌」と表記したとは認めがたい。篆隷万象名義 (巻二之一) にも新撰字鏡にも「打」を「丁洽反撃也」と注しているように、他・多などと同じ「タ」の仮名としたとは考えがたいのである。その上に写本からは想像しにくい脱字をも認めなければならないとすれば、「打歌(タカ)」という真淵説は捨てられるべきである。旧訓に「ウツタノヤマ」とあるのは、文字に即した訓であり、人麻呂歌集や人麻呂作歌に「ウツ」の借訓字「打」は他の例も見られるので固有名表記として、それほど珍奇な例ではないと思われる。「132歌」の「高角山」と同名であるべきだとする先入主から「打歌」が異常に見えるに過ぎない。ただしこの二つの山名のみを手掛かりとして、伝誦説・推敲説のいずれが正しいか、決定することはできない。 |
|||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「打歌の山」(うつたのやま) 島根県江津市の近くであろうが、所在未詳。一説にタカツノ山のタカを漢字音で「打歌」と記したものか、とする説がある。ただし、「打」は呉音「チャウ」、漢音「テイ」で、「タ・ダ」と発音するのは時代が下がった元代の中原音韻以降だといわれ、その可能性は少ない。今は「ウチウタ」の約音「ウツタ」と読んでおく。 |
|||||||||||
| 新大系 | 【脚注】「打歌の山」(うつたのやま) 「打歌の山」は所在未詳。『全註釈』の言う通り、「打歌山」の所在を「石見の海」と言うのは無理である。 |
|||||||||||
| 原文「妹将レ見香 (いもみつらむか)」訓・考 |
注釈 | 【訓釈】「妹将見香[聞]」(イモミツラムカ/イモミケムカモ) 原文「妹将見香」とあるを金澤本以後現代の諸家系に至るまで「イモミツラムカ」として異説を見ない。これは前の「妹見都良武香(イモミツラムカ)」(132) とあるによつたもので、論議の余地なきものと認められたのかと思ふが、講義には右 (132) の例により「姑く古来のままにす」とやや慎重な態度がとられてゐる。しかし「将見」は「ミム」と訓むのが通例であり、然らざれば「ミラム」とも訓む事右の長歌の「将嘆」でも察せられ、人麻呂作の「白水郎跡香将見 (アマトカミラム)」 (3・252) の例もある。けれども「ミツラム」と訓んだ例はないのみならず、すべて「将レ□」を「-ツラム」と訓んだ例集中に一例もない。尤も訓添は認められる事であり、「幾代将経 (イクヨヘヌラム)」 (3・355)、「将開可聞 (サキヌラムカモ)」 (8・1436) の如く「ヌラム」と訓んだと思はれる二例があるから「ツラム」と訓めないわけではない。しかし「ツラム」という訓添の唯一例を認める前に、もつと例のある訓み方を考へてみる必要がある。それは「ケム」と訓む例のある事で、すぐこの先に「将結 (ムスビケム)」 (143)、「復将見鴨 (マタミケムカモ)」 (143) と一首中に二つもあり、その先の「又将見香聞 (マタミケムカモ)」 (146) は「人麻呂歌集中出」と注のあるものであり、その他「将レ□」を「-ケム」と訓んだ例は「-ラム」と訓んだ例に次いで用例の多いものである。この事実に注意して前の或本反歌 (134) を見ると「妹将監鴨 (イモミケムカモ)」とある。この二つの事実は何を示すか。私は次のやうな二案を考へる事が出来るやうに思ふのである。その第一案は、この句はもと「妹将見香聞 (イモミケムカモ)」といふ風になつてゐたが、第二句同様脱字を生じたもので、その事は人麻呂が別に「妹見監鴨」と書いてゐる事によつてわかり、後人麻呂はその「けむかも」を「つらむか」 (132) に改めたと推定する事であり、第二案は人麻呂はもと「イモミケムカモ」と「イモミツラムカ」と二案をもつてゐたが、はじめ後者の表記として不用意に「妹将見香」と書いてみたが、「将見」では「ミケム」と訓まれる事に気づいて、「見監」と「見都良武」とに改めたと推定する事である。前者は (139) → (134) → (132) といふ事になり、後者は (139) → (132) といふ事になり、いづれにしても「妹将見香」は書式として不備又は不親切であり、これもまた第二句同様、(132) 或は (134) の草案たる事を示すものだと考へる。 |
||||||||||
| 全注 | 【注】「妹将見香」(いもみつらむか) 原文「妹将見香」。「将」を「ラム」と訓む例は、「将嘆」 (138)、「白水郎跡香将見」 (3・252) にもある。また、助動詞「ツ」の訓み添えは「夢見ツル」 (10・2241)、「妹名告ツ」 (11・2441)、「何此夜明テム鴨」 (11・2458)、「可見ツ限」 (11・2485)、「吾名謂ツ」 (11・2497)、「念不得ツ」 (11・2499)、「我謂ツル」 (11・2507)、「聞テケル鴨」 (12・2855) など、人麻呂歌集略体歌に多数見え、同じく非略体歌にも「揩テ者吉」(7・1281) のような例がある。人麻呂作歌には、この他に「ツ」の訓み添えは見られないが、ラムに「将」を宛て、「ミツラム」を「将見」と「ツ」を略して記すこのような書き方があってもおかしくはないであろう。澤瀉注釈には「将見」は「ミム」もしくは「ミラム」とは訓むが、「ミツラム」の例は、人麻呂作歌どころか集内に一つもないから、もっと別の訓み方を考えるべきだとして、「ミケムカモ」をあげ、「聞 (モ)」の誤脱とされている。これは一案であるが、人麻呂歌集・人麻呂作歌を通じて「将 (ケム)」の例は「146歌」の「又将見香聞」以外にないし、しかも「146歌」が本来人麻呂歌集の歌であったかどうかかなり疑わしいので (稲岡『万葉表記論』第一篇)、これを作歌の「将 (ケム)」を認容する手掛かりとはしがたいのである。 |
|||||||||||
| 「左注」考 | 童蒙抄 | 右歌亦雖同句句相替因此重載 童子問 右の注も前問の答に準ては、古注者の文なりとや。 答 しかり。 |
||||||||||
| 攷證 | 右歌體雖レ同。句々相替三。因レ此重載。 歌體。元暦本、體を躰に作れり。いづれにてもあるべし。 |
|||||||||||
| 全註釈 | 【釋】右 ミギハ。一三八、一三九の二首を指している。それを載せるについての説明である。 歌體 ウタノカタチ。體は、形體の意であろう。歌經標式には歌體三ありとして、求韵、査體、雜體の三を擧げている。 |
|||||||||||
| 「反歌三種」考 (万葉集全注) | 全注 | 【考】「三種の第一反歌」 第一反歌にあたる歌詞には三種あって、まず本文の132歌「石見のや高角山の木の間より我が振る袖を妹見つらむか」があり、次に「或本反歌」の134歌「石見なる高角山の木の間ゆも吾が袖振るを妹見けむかも」がある。さらに「或本歌」の反歌として139歌「石見の海打歌の山の木の間より吾が振る袖を妹見つらむか」を見るのであり、この三種の歌詞の関係が問題となる。本文132歌以外を後代の伝誦による変形とする説が真淵以来有力であったが、最近では、そうした伝誦説に疑問が持たれ、134→139→132の順序で作者の推敲が行われたとする説を見るようになった (松田好夫「人麻呂作品の形成」万葉二十五号、昭和三十二年五月)。さらに伊藤博『万葉集の歌人と作品』上巻では、「或本歌」を初稿とし、139→134→132の順序による推敲が推定されている。推敲か伝誦かの判断は難しいが、単純に口誦による流伝を想像し、「人麻呂のものは当時すでにかくの如くにして十二語ぐらゐの変形を以て流伝され、時には大衆向けに通俗化され、民謡化されつつあつたことを思ふと、人麻呂は当時、或は歿後になかなか有名であつただらうと想像することが出来る」というだけでは片付けられないのである。 |
||||||||||
| 巻二 140 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版] (1980年9月)も併記する 【頭注】 神田本、前行ノ下ニ続ケテ書ケリ。 【題詞】柿本朝臣人麿妻依羅娘子輿人麿相別歌一首 〔本文〕 麿。神田本、「□[下写真参照]。右ニ別筆「麿」アリ。 〔訓〕 依羅。神田本、右ニ別筆「ヨサミ」アリ。西本願寺本、右ニ「ヨサミ」アリ。京都大学本、右ニ赭「ヨサミノ」アリ。 別。京都大学本、右下ニ赭「ノ」アリ。 【頭注】 類聚古集、前行ニ「柿本朝臣人麿妻依羅娘子与人麿相別歌」アリ。コノ歌別行平仮字ノ訓ナシ。漢字ノ左ニ墨片仮字ノ訓ヲ附セリ。コレニテ校ス。 【本文】 勿念跡 君者雖言 相時 何時跡知而加 吾不戀有乎 (オモフナト キミハイフトモ アハムトキ イツトシリテカ ワカコヒサラム) 〔本文〕 乎。金澤本・類聚古集・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「牟」。 〔訓〕 オモフナト。温故堂本、「ヲモフナト」。 イフトモ。元暦校本・金澤本、「いへとも」。元暦校本、「へ」ノ右ニ朱「フ」アリ。神田本、「イヘトモ」。「ヘ」ノ右ニ「フイ」アリ。 〔諸説〕 オモフナト。代匠記精撰本、「ナオモヒト」トモ訓ズ。万葉考、「ナモヒソト」トモ訓ズ。 イフトモ。代匠記初稿本、「イヘドモ」。 アハムトキ。代匠記精撰本、「アフトキヲ」トモ訓ズ。 不戀有乎。代匠記初稿本、「乎」ハ「牟」ノ誤。
[校本萬葉集新増補版] 【題詞】柿本朝臣人麿妻依羅娘子輿人麿相別歌一首 〔本文〕 麿。神宮文庫本、「磨」。 〔訓〕 依羅娘子。神宮文庫本、右ニ「ヨサミノヲトメ」アリ。京都大学本、「依羅」ノ左ニ赭「ヨサミノ」アリ。 【頭書】 六帖、第四「思ふなと妹はいへともあはむ時いつとしりてか我戀さらむ」 拾遺集、七五六 【本文】 勿念跡 君者雖言 相時 何時跡知而加 吾不戀有乎 (オモフナト キミハイフトモ アハムトキ イツトシリテカ ワカコヒサラム)
|
|||||||||
| 「題詞」考 | 代匠記 | 勿念跡君者雖言相時何時跡如而加吾不戀有牟 [オモフナトキミハイフトモアハムトキイツトシリテカワカコヒサラム] 拾遺、家集、六帖、一同なる上、義尤然るべし、相時はアフトキヲともよむべし、終の乎の字は牟の字の誤れるなり、歌の心明なり、拾遺には此歌を人丸の歌として戀に載らる、似たる歌にて、第十二人丸集の歌に、後にあはむ吾 [ワレ] を戀なと妹はいへど、こふる間に年はへにつゝ、相聞なれば此レこそ叶ひ侍らめ、六帖に、別に入たるは得たるを、君を妹に改て此も人丸の歌とす、此等は家集に、さみの郎女相別侍ける時のと有を取用たるか、郎女にといはざれば、郎女が歌を書入たらむとも申なすべくや、 |
||||||||||
| 童蒙抄 | 柿本朝臣人麻呂妻依羅娘子與人麻呂相別歌一首 童子問 さきに人麻呂の妻に前妻後妻有よし命をうけ侍る。この依羅娘子は、前妻柿本人麻呂後妻か。此所に次てたれは、この別の時の歌なるへし。如何。 答 この依羅娘子は、前妻にはあらす。後妻とみるへし。前妻は石見國に在しを、後には大和國によひて、高市郡輕郷におかれたるとみえたり。すゑにいたりてみるへし。前妻の名はみえす。依羅子名はみえたり。今此別の歌は異時の歌なるへし。撰者類によりて此所へ撰み次てるなるへし。 |
|||||||||||
| 万葉考 | 柿本ノ朝臣人麻呂ガ妻 [メ] 依羅娘子 [ヨサミノイラツメ] 、與 [ト] 二人麻呂一相別ルヽ時作歌、 こは右の假 [カリ] に上りて又石見へ下る時、京に置たる妻のよめるなるべし、かのかりに上る時、石見の妹がよめる歌ならんと思ふ人のあるべけれど、さいひては前後かなはぬ事あり、別記の人まろの妻の條にいふ、〔拾遺歌集に、此歌を人まろとてのせしは、餘りしきひがことなり、人まろの歌の調は、他にまがふ事なきを、いかで分ざりけん、此端詞を見ざりしなり、〕 |
|||||||||||
| 略解 | 柿本朝臣人麻呂妻依羅娘子與二人麻呂一相別歌一首 これは人麻呂假に上りて、又石見へ下る時、京に置きたる妻の詠めるなり。 |
|||||||||||
| 攷證 | 與二人麿一相別。 考云、こは右の、假に上りて、又石見へ下る時、京に置たる妻のよめるなるべし。かの、かりに上る時、石見の妹がよめる歌ならんと思ふ人あるべけれど、さいひては、前後かなはぬ事あり云々。 |
|||||||||||
| 古義 | 柿本朝臣人麿妻依羅娘子 [カキノモトノアソミヒトマロガメヨサミノイラツメガ]。與 [ト] 二人麿 [ヒトマロ] 一相別歌一首 [ワカルヽウタヒトツ]。 依羅ノ娘子は、傳詳ならず、依羅は、氏なるべし此ノ氏は姓氏録などにも見ゆ、この娘子は、人麿の嫡妻なるべし、但し嫡妻に、前後二人ありと見えたり、前妻は、人麿に先だちてみまかれること、此ノ卷ノ未に見えたり、その姓氏は知がたし、この依羅氏は後妻にて、人麿の死に後れたること、又末に見ゆ、 相別は、人麿の假に上りて、又石見へ下る時などや、京に遺レ居る妻のよめるならむ、 |
|||||||||||
| 全釈 | 柿本朝臣人麿ノ妻依羅娘子 [ヨサミノイラツメ] 與二人麿一相別ルル歌一首 依羅娘子は依羅氏の人であらう。人麿の二度目の妻で大和に住んでゐた。この歌は人麿が再び石見へ赴かうとした時、別を惜しんでよんだものである。これを石見にゐる女とする説もあるが、それは誤である。二二四の題詞參照。 |
|||||||||||
| 全註釈 | 柿本朝臣人麻呂妻依羅娘子、與二人麻呂一相別歌一首 柿木の朝臣人麻呂が妻の依羅の娘子の、人麻呂と相別るる歌一首 【釋】 柿本朝臣人麻呂妻依羅娘子 カキノモトノアソミヒトマロガメノヨサミノヲトメ。依羅は氏であろう。配偶者があつても、娘子の文字を使用することは、「娘子臥聞二夫君之歌一」(卷十六、三八〇五題詞)、「時有二娘子一、夫君見レ棄、改二適他氏一也」(同、三八一五左註) など例が多い。若い婦人というだけで結婚していると結婚していないとに關しない。この人は、後に、「柿本朝臣人麻呂死時、妻依羅娘子作歌二首」(卷二、二二四題詞) とあつて、人麻呂の死んだ時に、歌を詠んでいるから、その後妻であることはあきらかである。石見の國にいた娘子で、人麻呂が上京に際して別れを悲しんで歌を詠んだのも、この人に對してであろう。その他いかなる人とも知られないが、京より伴ない下つたという徴證も無く、部内の娘子を娶つたのでもあろうかと考えられる。 |
|||||||||||
| 評釈 | 姉本朝臣人麻呂の妻依羅娘子 [よさみのをとめ]、人麻呂と相別るる歌一首 〔題〕 依羅は氏。依羅娘子は傳不詳。ここの歌の配列から見れば、石見國に殘して來た妻らしいが、下の「二二四」(138)に依つて、大和に住んでゐた妻といふ説もある。 |
|||||||||||
| 注釈 | 依羅は氏。和名抄河内丹比郡依羅を与左美[ヨサミ] (高) とあり、摂津住吉郡大羅を於保与左美[オホヨサミ] (高) とあつて、ヨセアミをつづめヨサミと云つた。依網とも書く。開化記に「依網之阿毘古」とある。新撰姓氏録に依羅宿禰 (摂津皇別) もあり、依羅連 (左京神別上、右京神別上、河内国諸蕃) もあり、最後のものは「百済国人素祢志夜麻美乃君(スネヤマミノキミ)之後也」とある。依羅娘子はその素姓を明らかにしない。娘子は既婚者にも用ゐる。「時有二娘子一。夫君見レ棄改二適他人一也」(16・3815左注) などともある。この娘子を右の石見での妻と別人とする説のあることは前 (131題詞の條) に述べたが、これは右の一連の作につづけて、云はば贈答の形で載せられてゐるので、人麻呂が別れを惜しんだその妻と見るのが自然であらう。 | |||||||||||
| 全注 | 〔依羅娘子という名称〕 万葉集一般の「〇〇娘子」からすれば、依羅氏出身の娘子か、依羅地方に住む娘子と理解される (神田秀夫『人麻呂歌集と人麻呂伝』、藤原芳男「万葉の郎女」万葉四十六号、小野寛「女郎と娘子」『論集上代文学』第三冊など)。依羅氏が山陰地方に住んだ形跡は古代文献の中に求められず、ほとんど河内・摂津・和泉の三国に集中しているし (大越寛文「柿本人麻呂終焉挽歌」『万葉集を学ぶ』第二集)、また依羅という地名も大和に近い河内・摂津か、三河国に求められる (和名抄に河内国丹比郡と参河国碧海郡に見え、また摂津国住吉郡には大羅の地名があり、於保依佐美と訓む)。日本書紀に見られる地名の依網 (崇神六十二年紀、仁徳四十三年九月紀、推古十五年紀、皇極元年五月紀) は、すべて河内の依羅で、河内志の「丹比郡池内池、在二池内村一。広三百余畝。或曰二依羅池一」の記事に合致する。右のような依羅氏及び依羅(依網)という地名のありようから、依羅娘子が元来石見出身の娘子であったとは考え難いであろう。依羅宿祢は新撰姓氏録摂津国皇別に日下部宿祢同祖、彦坐命之後也とあり、また依羅連は、同書河内国諸蕃に、百済国人素祢志夜麻美乃君之後也と記されていて、前記の地名に近いところを本貫とした氏族と知られる。依羅娘子の出身も、おそらく畿内であったのでないかと思われる。 〔石見相聞歌との関係〕 この「140歌」は、直前の長歌、すなわち人麻呂の石見相聞歌と、どのような関係にあるか。その点についても、説が分かれている。石見妻と依羅娘子を同一人と見るか、別人と見るかの問題とともに【考】の条に述べる。 【考】「依羅娘子は石見妻か」 この歌について、真淵は、 人麻呂カ妻依羅娘子与二人麻呂一別時ノ哥とて、思ふなと、君はいへども、あはん時、いつと知てか、吾こひざらん、とよみしは、載し次いでに依ば、かの石見にて別れしは即此娘子とすべきを、下に人まろの石見に在て身まからんずる時、しらずと妹が待つつあらんとよみ、そを聞てかの娘子、けふけふとわが待君とよみたるは、大和に在てよめるなれば、右の思ふなと君はいへどもてふは、石見にて別るるにはあらず、ここ朝集使にてかりにのぼりて、やがて又石見へ下る時、むかひめ依羅娘子は、本より京に留まりて在故にかくよみつらん、あはん時いつと知てかといふも、かりの別と聞えさる也 (別記二) と記している。真淵は、依羅娘子は石見妻と別人と考え、140歌を人麻呂の再び石見へ下ってゆく時に京に留まっていた娘子の詠んだものと推定したのである。攷證・略解。檜嬬手・古義・新考・私注など、みなこの説によっている。一方、山田講義には、 これは上の歌のつづきに置けるによりて、なほ石見国に留り残れる妻の歌とせざるべからず。按ずるに人麿には前に妻ありしがそれが身亡りしことはこの巻挽歌の中の長歌にて明らかなるが、「207歌」その下に人麿が石見国に在りて死に臨みし時に自ら傷(カナ)しみて作れる歌「223歌」の次に「人麿死時妻依羅娘子作歌」とあれば、依羅娘子とあるはその後の妻なること明らかなり。しかもこれの歌をば京に在りてよめりとするにて上の如き説も出でしなるべきが、そはその歌の解き方をさる意にとりなしたりしによることにて、その歌の趣にてはその墓地を明らかに見知りての詠と思はるれば、この依羅娘子が石見に在りしことを思ふべきなり。 と、同人説が説かれている。茂吉評釈にも、 角の里の人麿妻と依羅娘子は同一人で、「勿念ひと君は言へども」といふ依羅娘子は角の里にゐて、人麿の上来を名残惜しく思うて詠んだ歌とし、従つて、人麿の臨終に間に合はず、「今日今日と吾が待つ君は」 (巻二。224) と依羅娘子の咏んだのも、娘子は石見 (国府或は角の里) にゐて咏んだこととなり、私の「鴨山考」が成立つこととなるのである。万葉の編輯の具合も、「勿念ひと君は言へども」の歌を、人麿上来の歌の次に載せてゐるのは、その当時既に人々がさう思つてゐたやうに思へるのである。 とあるし、同様な考えは、窪田評釈・澤瀉注釈などにも見える。別人説と同人説と、二説が相譲らない形で現在に至っていると言ってよい。 茂吉の記しているとおり、巻二の最終編者やそれ以後の人たちは、人麻呂の石見妻と依羅娘子とを同人と考え、「140歌」を人麻呂の長歌と贈答の形で載せられていると見ていた可能性が強い。澤瀉注釈に「贈答の形で載せられてゐるので、人麻呂が別れを惜しんだ妻と見るのが自然であらう」とあるのは、そうした見方を端的に示している。 しかし「140歌」は、直前の人麻呂作歌と対をなすものだろうか。両歌の題詞を注意してみると、必ずしもそうは言えないように感ぜられる。たとえば「131歌」の題詞には単に「妻」と記されているのに、「140歌」の方には「妻依羅娘子」とあって、両者はむしろ別人として意識されていたのではないかと思われる。 臨終歌「223」のところでも触れるとおり、人麻呂の死後間もないころに、人麻呂と石見国の関係や、その死をめぐる伝承が生じていたらしい。巻二の編纂者は、人麻呂の晩年における石見赴任、上京、石見での客死などを伝記的事実と信じ、「223歌」の題詞に「在石見国臨死時」と記したものと思われる。 前にも掲げたが、茂吉の『柿本人麿』総論篇に、万葉集の記載を疑っていたら、人麻呂の伝記も作歌年次配列もとうてい成立しがたいであろうことが強調され、「鴨山考」の前提となる認容事項として次の三箇条があげられている。 (一)人麻呂が晩年石見国府の役人となっていたことを認めること。 (二)石見娘子、依羅娘子は同一人であり、かつ人麻呂没時に依羅娘子が石見にいたことを認めること。 (三)人麻呂が石見国で死んだことを認めること。 これは極めて慎重な用意と言うべきであるが、(三)は「在石見国臨死時自傷作歌」という題詞の記載に直結して認められるにしても、(一)や(二)が同様に認められるとは言えない。依羅娘子を石見妻と同人とする確証は求め難いし、むしろ別人と見る方が自然であることは、先に記したとおりである。また、人麻呂の石見赴任を晩年とすることも、確かな根拠があるわけではない。契沖の代匠記に持統朝の初年としているのが、かえって真相に近いかも知れない。詳細は、今後の検討に委ねなければならないが、作品の性格からいうと、石見相聞歌は持統朝前半と考えるべきものと思われる (稲岡『万葉集の作品と方法』第二章参照)。 人麻呂の石見赴任を伝記上の事実とするなら、持統朝前半以前のことであったろうし、依羅娘子の「140歌」は、その後の地方下向のさいに詠まれたものと考えられるのである。 |
|||||||||||
| 新大系 | 【脚注】 依羅娘子は、「224・225歌」の題詞に「柿本朝臣人麻呂の死にし時に、妻の依羅娘子の作りし歌二首」と見えるが、同一人か否かは確実でない。人麻呂の伝、また人麻呂の妻の問題は未解決である。 |
|||||||||||
| 原文「勿念跡 君者雖レ言」 訓・考 |
拾穂抄 | おもふなときみはいふともあはんときいつとしりてかわかこひさらん 勿念跡君者雖言相時何時跡知而加吾不戀有牟 おもふなと君はいふとも 祇曰一向に思ふなといふにあらすさのみ心をくたきては思ふなと慰めていへる也扨こそ君はいふとも知ぬ事となけく哥也 |
||||||||||
| 代匠記 | 〔訓〕 勿念跡君者雖言相時何時跡如而加吾不戀有牟 [オモフナトキミハイフトモアハムトキイツトシリテカワカコヒサラム] |
|||||||||||
| 童蒙抄 | 勿念跡君者雖言相時何時跡知而加吾不戀有乎 童子問 右の歌を、かなつけよみには、思ふなと君はいふ共あはむ時いつとしりてかわかこひさらんとあり。拾遺和歌集卷第十二戀二に、此歌を載られたるには、思ふなと君はいへとも逢時をいつとしりてか我か戀さらん、と有。何れのよみか是なるや 答 拾遺集の方是なり。雖言の二字をいふともいへとも、歌によりていつれをも用ゆへし。此歌にはいふともはあしゝ。且相時の二字をあはんときはよみかたし。あふ時をとよめるよろしき也。拾遺集の訓此歌に限りてはよろしけれとも、題しらす人まろとのせられたるは誤り也。すへて柿本の人まろの歌、拾遺集にあまた載られたれとも、皆よみたかへられたり。しかれは万葉集を見すして、かの時よみあやまりたる歌を、書のせたる物をや見たまひて、本集の万葉にはよらすして、後の書を證としてや書のせ給らんとそおしはからるゝ也。しからすは、いかてか拾遺集の誤り何故とはかりかたし。一首も人丸の歌をのせられたる中に、正しき事なし。皆たかへり。中にも此歌は人まろの歌にあらす。依羅娘子の人まろとわかれの時の歌と、題にもみえたるを、題しらすとのせられたるも誤りなるへし。只歌の詞につきて戀の歌と心得られて、戀の二に加へられたるなるへし。別の部に入て有へき事なり。これ万葉集の本書を見すして、妄りに載られたる事明けし。 |
|||||||||||
| 万葉考 | 〔訓〕 勿念跡 [オモフナト・ナモヒソト]、君者雖言 [キミハイヘドモ]、相時 [アハントキ]、何時跡知而加 [イツトシリテカ]、我不戀有牟 [ワガコヒザラム]、 |
|||||||||||
| 攷證 | 勿念跡 [オモフナト]。君者雖言 [キミハイヘトモ]。相時 [アハムトキ]。何時跡知而加 [イツトシリテカ]。吾不戀有牟 [ワカコヒサラム]。 勿念跡 [オモフナト]。今別るゝ、そのわかれを悲しび思ふなと也。 君者雖言 [キミハイヘドモ]。舊訓、君はいふともとあれど、いへどもと訓むべし。雖の字を、書るにてしるべし。一首の意明らけし。 |
|||||||||||
| 古義 | 勿念跡 [ナオモヒト]。君者雖言 [キミハイヘドモ]。相時 [アハムトキ]。何時跡知而加 [イツトシリテカ]。吾不戀有牟 [アガコヒザラム]。 勿念跡は、「ナオモヒト」と訓べし、(舊本に、「オモフナト」とよめるは、非なり、しかさまに云も、古言にあることなれど、さらば集中の例、念勿跡と書べきを、しからねば、さはよむべからず、又略解などに、「ナモヒソト」とよめる、此は又、大 [イミ] じきひがことなり、其ノ故は、凡て念 [オモフ] は、家念 [イヘモフ] 妹念 [イモモフ]、などやうに云時こそ、母比 [モヒ] 母布 [モフ] などもいへれ、かゝるところなどにて、念 [オモヒ] の於 [オ] を省きて、母比 [モヒ] 母布 [モフ] といふことは、さらになきことなるをや、)さて那於毛比曾 [ナオモヒソ] とあるべき處を、下の曾 [ソ] の辭無は、古き代の歌には、常多し、(然るを後々の歌どもには、下の曾 [ソ] は、なくてはあらぬことぞ、とのみ意得て、かへりて上の那 [ナ] をば、省きていはざるがまゝ聞ゆる、こはいみじきひがことぞかし、那 [ナ] はかならずなくては、聞えぬことなるをや、) |
|||||||||||
| 全釈 | 勿念跡 [ナオモヒト] 君者雖言 [キミハイヘドモ] 相時 [アハムトキ] 何時跡知而加 [イツトシリテカ] 吾不戀有牟 [ワガコヒザラム] 勿念跡 [ナオモヒト] ――] この句は舊訓オモフナト、考はナモヒソトであるが、代匠紀にナオモヒトとよんだのが良いやうである。勿の字は、不吹有勿勤 [フカザルナユメ] (七三)・妹森毛有勿久爾 [イモモアラナクニ] (七五)。置勿爾到 [オキナニイタリ] (三八八六) などの如く、ナとよむのが常である。ソを附する必要はない。 |
|||||||||||
| 全註釈 | 勿念跡 [ナオモヒト] 君者雖レ言 [キミハイヘドモ] 相時 [アハムトキ] 何時跡知而加 [イツトシリテカ] 吾不レ戀有牟 [ワガコヒザラム] 【釈】 勿念跡 ナオモヒト。ナが禁止の副詞。下に助詞ソが無くていうのは、古い形である。「木間從 [コノマヨリ] 出來月爾 [イデクルツキニ] 雲莫棚引 [クモナタナビキ]」(卷七、一〇八五)、「比可婆奴流奴留 [ヒカバヌルヌル] 安乎許等奈多延 [アヲコトナタエ]」(卷十四、三五〇一)。 |
|||||||||||
| 評釈 | 勿念 [なおも] ひと君は言 [い] へども逢はむ時いつと知りてか吾が戀ひざらむ 【語】 な念ひ 思ふな。上代では禁止の助詞の「な」は、必ずしも下に「そ」を伴はない。「ものな思ほし」(七七)參照。 |
|||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「な思ひと」 旧訓に「オモフナト」とあつたのを万葉考に「ナモヒソト」とも訓じ、古義には「ナオモヒト」と改め、「家念(イヘモフ)」、「妹念(イモモフ)」などのやうな時には「モヒ・モフ」などもいふが、かういふ場合には「オ」を省く例がないと云つてゐる。「な~そ」の「そ」を略する例「表者奈佐我利(ウヘハナサカリ)」(5・904) その他があるので、「ナオモヒト」と訓む。「オモフナト」とも訓んでさしつかへない (137参照) が、後にも引用するやうに「莫戀吾妹(ナコヒソワギモ)」(10・1895) の例により「ナオモヒト」がよいであらう。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】「な思ひと」 原文「勿念跡」。旧訓「オモフナト」であったが、代匠記精撰本に「勿念ハ、此集ノ傍例ニヨラハ、ナオモヒトモヨムヘシ。オモフナヽト云時ハ、多分勿トヤウニ下ニカケリ。」と記す。ただし、この部分は後に抹消されたようで、契沖に旧訓を訂するほどの自信はなかったらしい。真淵の万葉考では、左に一案として「ナモヒソト」と付訓されている。古義に「勿念跡は、那於毛比登と訓べし、旧本にオモフナトとよめるは非なり、しかさまに云こと古言にあることなれど、さらば集中の例、念勿跡と書べきを、然らねば、さはよむべからず、又略解などに、ナモヒソトとよめる、此は又大(イミ)じきひがことなり、其故は凡て念は家念妹念などのやうに云時こそ母-比母-布などもいへれ、かかるところなどに、念の於を省きて母-比母-布といふことは、さらになきことなるをや」と述べているのは詳細で、しかも問題点を確実に押さえたものである。前に「137歌」の「ナチリマガヒソ」について記したとおり、語序と表記の順序とが「勿」に関しては一致しており、「オモフナト」ならば「念勿跡」と書かれるはずである。注釈に「オモフナトとも訓んでさしつかへない」と付記しているのは蛇足であり、誤りである。 |
|||||||||||
| 新大系 | 【脚注】 この歌、拾遺集に「思ふなと君は言へども逢ふことをいつと知りてかわが恋ひざらむ」(恋二) という形で伝わる。第二句、イフトモと訓む説がある (新編日本古典文学全集)。 |
|||||||||||
| 新全集 | 【頭注】「な思ひそ」 「ナ~ソ(ネ)」は禁止の語法。優しくなだめすかすような語調であったと思われる。→ 「137 な散りまがひそ」 |
|||||||||||
| 原文「相時(あはむとき)」訓・考 | 全註釈 | 【釈】 相時 アハムトキ。別れに臨んで詠んでいるので、やがてまた逢うだろう時と言つている。 |
||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「逢はむ時」 「相時」とあるので代匠記に「アフトキヲトモヨムベシ」とある。「相時麻而波(アフトキマデハ)」(8・1526) の例もあつて「アフトキ」とも訓めるが、それは一年に一度は逢へるにきまつてゐるのであり、今は「安波牟日乎(アハムヒヲ) 其日等之良受(ソノヒトシラズ)」(15・3742) といふのと同じ心であり、その仮名書例や、人麻呂集の「及相日(アハムヒマデニ)」(12・2854) の表記に準じて「アハムトキ」と訓む。 |
|||||||||||
| 注釈 | 【注】「逢はむ時」 原文「相時」を、旧訓「アハムトキ」とし、江戸時代以降の諸注も多くこの訓によっているが、代匠記精撰本に「アフトキヲトモヨムヘシ」と注している。助詞「ヲ」の無表記例とともに、「貴在ム等」(167・人麻呂)、「為ム便」(196・213・人麻呂) など、推量の助動詞「ム」の訓添えも少なからず見られるのであり、訓添えの可能性はどちらにも認められる。ただ、のちに再会する時のことを、人麻呂歌集に「後ニモ相ム」(10・1895)、「相ム日待尓」(10・2012)、「及二相ム日一」(12・2854) などと歌い、「ム」を訓添えていること、そのほかにも「将レ相日のため」(12・3181)、「安波牟日のかたみにせよと」(15・3753)、「相日左右二」(12・3142) など例の多く見られることを通して、「アハムトキ」という旧訓の方がふさわしいと思われる。 |
|||||||||||
| 結句「牟」注 | 童蒙抄 | 童子又問 此歌の終に乎の字あり。しかるをよますして捨けるはいかゝ。 答 乎の字は誤字なるへし。牟の字に改むへし。有牟の二宇にて、さらんと上に不の字有故によまれたるなり。 |
||||||||||
| 略解 | 有乎は有牟の誤れる事明らけし。 | |||||||||||
| 古義 | 牟ノ字、舊本には、乎に誤れり、古寫本并人麿勘文に引るに從つ、 歌ノ意は、はやかへり上り來て相見むぞ、さばかり吾を慕ひて、物念をすることなかれ、と君は妾 [ワ] が心をなぐさめてはのたまへども、そのかへり上り來まさむ月日を、何時 [イツ] のことゝ知てかは、戀しく思はずにあるべき、となり、(拾遺集に、題不知、人まろとて、此ノ歌を載られたるは、あまりしき誤なり、彼ノ集の撰者は、此ノ題詞をだに見ざりしにや、いとかたはらいたし、) |
|||||||||||
| 巻二 141 | 部立「挽歌」訓・考 | 拾穂抄 | 挽 [ヒツキ] 歌 挽歌 八雲云俊頼抄ニ悲哥也云々古ノ挽哥 [ハンカ] は大略悲か非ルレ悲ニも有か愚案蒙求曰挽 [ヒク]レ柩 [ヒツキヲ] 者ノ歌 [ウタフ] レ之ヲ因テ呼テ為二挽歌ト一文選二十八李善註ニ斉 [セイ] 乃田横 [テンクハウ] 自殺 [ジサツ] せし時從者 [シヨウシヤ] 此哥をつくりて哀音 [アイイン] を寄 [ヨス] と云々然共此集にはひつきうたのみにはあらす |
|||||||||
| 代匠記 | 此義別に注す、後の集の哀傷なり | |||||||||||
| 万葉考 | 挽歌 [カナシミノウタ]。これを末に載て卷を結びたるにて、こは時代しられたる歌を撰集めし卷なるを知ぬ、〔挽歌の字は借て書のみ、字に泥ことなかれ、別記有、〕 | |||||||||||
| 略解 | 挽歌 柩を引く歌の名目を借りたるのみにて、後の集の哀傷なり。 | |||||||||||
| 攷證 | 挽歌。 挽歌は晋書樂志に、挽歌、出二于漢武帝役人之勞一、歌聲哀切、遂以爲二送終之禮一云々。崔豹古今注に、薤露蒿里、並喪歌也、出二田横門人一、横自殺、門人傷レ之、爲二之悲歌一、言人命如三薤上之露易二晞滅一也、亦謂人死魂魄歸二乎蒿里一、故有二二章一、至二孝武時一、李延年乃分爲二二曲一、薤露送二王公貴人一、蒿里送二士大夫庶人一、使二挽柩者歌一レ之、世呼爲二挽歌一云々とありて、古今注にいへるがごとく、もとは喪歌とも、悲歌ともいひしかば、此方の哀傷の歌に當れり。さてその歌の言の、あはれにはかなく悲しければ、柩 [ヒツギ] を挽 [ヒク] とき、うたはせしより、挽歌といへるなれば、その字を借用ひて、哀傷の歌をばのせし也。さて、左の山上臣憶良追和歌の左注に、右件歌等、雖レ不二挽レ柩之時所一レ作、唯擬二歌意一、故以載二于挽歌類一焉云々とあるは、本 [モト] のことをばしらずして、挽歌は柩を挽ときうたふ歌ぞとのみ、心得たる人のしわざにて、とるにたらず。また古事記中卷に、是四歌者、皆歌二其御葬一也、故至レ今、其歌者、歌二天皇之大御葬一也云々とあるにても、古くより、御葬に歌をうたひしをしるべし。 |
|||||||||||
| 古義 | 挽歌 [カナシミウタ] 挽歌は、字には泥 [ナヅマ] ずして、可那斯美 [カナシミ] 歌と稱 [イ] ふ、其は相聞と書るを、「シタシミウタ」 と稱 [イヘ] る類なり、さてこの部は、中古已來の歌集に、哀傷歌と云るに全ラ同し、挽歌の字の出處、且寧樂人の、此ノ熟字をとり出て、歌ノ部の名目にしたる謂など、委しく首ノ卷に云り、(舊本、此ノ下山上ノ臣憶良ノ追和歌の左註に、右件ノ歌等、雖レ不二挽柩之時一所レ作、唯擬二歌意一、故以戴二于挽歌類一焉といへるは、既く岡部氏もさだせし如く、徐にをさなき註にあらずや、此ノ集の挽歌と有ル部内には、いにしへの事をきき傳へしをも載つれば、たゞかなしみ歌てふことのみなるは著きを、挽歌の字に就て、今更に柩をひきひかぬなどいふべきことかは、 |
|||||||||||
| 全釈 | 挽歌 挽歌はバンカとよむ。葬送の際に歌ふ歌。挽の字を用ゐるのは、柩を載せた車を挽く意である。晋書に「挽歌出二于漢武帝、役人之勞一、歌聲哀切、遂以爲二送レ終之禮一」崔豹古今注「薤露蒿里、竝出二田横門人一、至二李延年一、乃分爲二兩曲一、薤露送二王公貴人一、蒿里送二士大夫庶人一、使二挽レ柩者歌一レ之、世亦呼爲二挽歌一」とあるから、彼土の熟語で、音讀したに相違ない。考はカナシミノウタとよみ、古義はカナシミウタとしたのは從はれぬ。ヒキウタの訓はありさうであるが、その確證を認め得ない。古今集以後の哀傷に相當するものである。 |
|||||||||||
| 全註釈 | 挽歌 【釋】挽歌 メニカ。雜歌、相聞に對する部類の一つで、人の死を傷む歌をいい、後世の歌集における哀傷歌に相當する。この名目は、漢籍に出ている。晉書の樂志に、「挽歌、出二于漢武帝役氏之勞一、歌聲哀切、遂以爲二送終之禮一。」崔豹の古今注に「薤露蒿里、竝喪歌也。出二田横門人一。横自殺、門人傷之、爲二之悲歌一言、人命如三薤上之露易二晞滅一也。亦謂、人死魂魄歸二乎蒿里一。故有二二章一。至二孝武時一、李延年乃分爲二二曲一、薤露送二王公貴人一、蒿里送二士大夫庶人一、使二挽レ柩者歌一レ之、世呼爲二挽歌一。」すなわち、挽歌は、柩車を挽く時の歌の義である。わが國にても遂葬の時に歌を歌つたことは、古事記中卷に、倭建 [やまとたける] の命の妃の歌を録して、「是四歌者、皆歌二其御葬一也。故至レ今、其歌者、歌二天皇之大御葬一也」とある。本集においては、これを廣義に取り、ただに送葬の時の歌のみならず、傷亡の歌は勿論、その後の追悼の歌に及び、またまさに死のうとする時の歌をも含めている。挽歌は、訓讀すればカナシミウタであろうが、音讀すれば、呉音に依らばメンカであるが、普通にバンカと讀んでいる。この卷のほかに、部類の標目としては、卷の三、七、九、十三、十四の諸卷に見えている。この標目も、多分柿本朝臣人麻呂歌集から出たものなるべく、人麻呂の作において、挽歌は格別に發達している。本集における部類の標目に、賀歌が無くして挽歌があるのも、さような特殊の關係から來ているものなるべく、當時の歌の分類の標目としてその必要が感じられたのであろう。 |
|||||||||||
| 評釈 | 挽歌 [ばにか] 〔分類〕 挽歌は、晉書、崔豹古今注等に出典があり、柩を挽く時の歌といふのが原義で、轉じて死喪に關する歌を廣くいふ。勅撰集の部立では哀傷に相當するが、哀傷の部には、直接死喪に關係がなく、單に無常感を歌つた歌などをも含めてをろ、もとより全く、一致するものではない。 |
|||||||||||
| 注釈 | 巻二を相聞と挽歌とにわかち、挽歌は文選の部立の名稱を用ゐたものである事既にはじめの相聞の條で述べた。挽歌の語については既に攷證に崔豹の古今注に「薤露蒿里、並喪歌也、出二田横門人一、横自殺、門人傷レ之、爲二之悲歌一、言人命如三薤上之露易二晞滅一也、亦謂人死魂魄歸二乎蒿里一、故有二二章一、至二孝武時一、李延年乃分爲二二曲一、薤露送二王公貴人一、蒿里送二士大夫庶人一、使二挽柩者歌一レ之、世呼爲二挽歌一云々」とあり、又晋書楽志に「挽歌、出二于漢武帝役人之勞一、歌聲哀切、遂以爲二送終之禮一云々」とあるを引き、「もとは喪歌とも、悲歌ともいひしかば、此方の哀傷の歌に当れり」と云つてゐるやうに、もとは柩を挽く時の歌の義であるが、後人が追悼の歌や或いは臨終の作などをもこの部立の中へ入れてゐる。雑歌、相聞同様音読すべきであらう。 | |||||||||||
| 全注 | 「歌」の字、西本願寺・大矢本・京都大学本に「謌」とあるが、元暦校本・金澤本・紀州本などに「歌」とあるのによる。 挽歌は、相聞・雑歌とならぶ三大部立の一。文選の部類の一であり、元来は口唱歌謡的なものを意味し、口唱性を持たない文学の場合は、むしろ「挽歌詩」というべきものであったが、歌謡性の挽歌と創作詩として作られた挽歌詩とを含め、一般に「挽歌」という総称が行われたのである(小島憲之『上代日本文学と中国文学』中)。そうした文選の部類名が利用されて、万葉の部立としての「挽歌」という名称ができたと見られる。もともと中国において葬儀のさいに柩を挽く者の歌った歌を意味したのであるが、万葉集では、臨死の歌、殯宮の儀礼における歌、亡き人をしのぶ哀傷の歌などを広く含んだ部立の名に用いられている。この「挽歌」と異なるものとして「葬歌」がある。古事記のヤマトタケルの物語中に見られる葬歌は、推古朝以後のある時期に天皇の大葬歌として作られたものと推測されるのであり (土橋寛『古代歌謡の世界』)、万葉の挽歌は、それと起源や性質を異にするもので、孝徳天皇大化五年三月造媛の死を悲しんで、皇太子中大兄に歌を献った野中川原史満の作などにその源を求めることができる。 |
|||||||||||
| 「後岡本宮」考 | 古義 | 後崗本宮御宇天皇代 [ノチノヲカモトノミヤニアメノシタシロシメシヽスメラミコトノミヨ]。 此標は、既く一ノ卷に出づ、齊明天皇の宮號なり、天皇代の下、舊本等に天豐財重日足姫ノ天皇とあるは、後人のしわざなること、既く云る如し、 |
||||||||||
| 全注 | 斉明天皇の宮。斉明二年紀に「是歳、飛鳥の岡本に更に宮地(みやどころ)を定む。(中略) 遂に宮室を起つ。天皇乃遷りたまふ。號(なづ) けて後飛鳥岡本宮と曰ふ」とある。舒明の皇居も同地であったので「後」を冠して区別したのである。岡本の地は現在のどの辺にあたるか確定せず、大字丘(大和志)・大字島庄付近(大和志料)・雷岡の東方(喜田貞吉) など諸説がある。 | |||||||||||
| 「題詞」考 有間皇子自傷結松枝歌二首 |
註釈 | 孝徳天皇御子、有間皇子ノ御哥也。齊明女帝ノ御時、蘇我赤兄ト心ヲ同クシテ、御門カタフケントセシカ紀伊國岩代ト云所ニアリテ、志ノトケカタカランコトヲ患テ、其所ニアル松ノ枝ヲ結テ手向トシテ、此哥ヲ讀置テ外ヘ出玉ヒテ、思フコトカナイナハ、松ノ枝ノ、トケサランサキニカヘリコンコトノ玉ヒシカトモ、事ナラスシテ、終ニ藤代坂ニテ殺サレ玉ヒシト也。故ニ結松ト云コト、事起リ有レ憚云々。 | ||||||||||
| 拾穂抄 | いはしろのはま松か枝 哥林良材云有馬皇子は孝徳天皇の御子也斉明の女帝の御時蘇我 [ソカ] の赤兄 [アカエ] と心を同くしてみかとをかたふけんとせしか紀伊国岩代に在て心さしのとけかたからん事を愁 [ウレ] へて其所の松か枝をむすひて手向として此哥をよむ其間に赤兄かかへり忠により有馬皇子の謀反あらはれて終に藤代坂にてころされ侍ると云々日本紀二十六ニ委仙曰此哥第四句古点にはまさしくあらはと点し或はまことさちあらはと点スあひかなはすまさきくあらはと和すへしまさきくといふはまことのさいはい也此集十七にまさきくもありたもとをりと云々愚案日本紀二ニ必當平安カナラスマサキクマシマサンとよめり然共此哥類聚萬葉童蒙抄袖中抄ことには俊成卿の古來風躰等にもまさしくと有近くは哥林良材にもまさしく也改てまさきくと和せん事如何又まさしくまさきく五音相通同義なるへし | |||||||||||
| 代匠記 | 孝徳紀云、立2二妃ヲ1、元妃阿倍ノ倉梯 [クラハシ] 麻呂大臣ノ女曰2小足媛 [ヲタラシヒメ]1生2有間ノ皇子1、齊明紀云、三年九月。有間ノ皇子性黠 [ヒトヽナリサトシ] 陽狂 [イツハリタワレテ] 云云。徃2牟婁ノ温湯ニ1僞v療 [ヲサムル]v病來讃 [ホメテ] 2國ノ體勢1曰纔 [ヒタスラ] 觀2彼ノ地1病自蠲消 [ノソコリヌト] 云云、天皇聞悦、思3欲徃觀2彼地1、四年冬十月庚述朔甲子、幸2紀温湯ニ1云云、十一月庚辰朔壬午、留守官蘇我ノ赤兄ノ臣語2有間皇子1曰、天皇所v治政事、有2三失1矣云云、有間ノ皇子乃知2赤兄之善1v己、而欣然報答之曰、吾年始可v用v兵時矣、甲申有間ノ皇子向2赤兄ノ家1登v樓而謀、夾膝 [オシマツキ ] 自斷、於v是知2相之不祥1倶盟而止、皇子歸而宿之、是夜半赤兄遣2物部朴 [エ] 井連鮪1率2造v宮丁 [ヨホロ] 1圍2有間ノ皇子於市經 [イチフノ] 家1、便遣2驛使1奏2天皇所1、戊子捉3有間ノ皇子與2守君大石、坂合部連藥、鹽屋連鯏魚1、送2紀温湯1、舎人新田部末麻呂從焉。於v皇太子親問テ2有間皇子ニ1曰、何故カ謀人 [ミカトカタフケントスル ]、答曰、天與2赤兄1知、吾全不v解、庚寅遣2丹比ノ小澤 [ヲサハノ] 連國襲1、絞 [クヒル] 2有間ノ皇子於藤白ノ坂1、是日斬2鹽屋連鯯 [コノシロ]、舎人新田部連末麻呂於藤白ノ坂1、鹽屋連鯯魚、臨v誅言、願ハ令3右ノ手作2國寶器1、流2守君大石於上毛野國ニ坂合部藥於尾張國1、此下の注に異設を擧る中に、皇子年始十九未v及v成v人と云へり、先達の設の中に日本紀を能考へざる事ある故に今引て始終を明せり、十一月九日補へられて牟漏ノ郡へおはしまし、十一日に藤白にて絞られたまへば、此は十日に帝の御許へおはする道に磐代を過とて、我運命いまだ盡ずして事の樣を申ひらき、其を聞召分て助け給ふ事もあらば、又歸て此松を見んと引結て讀せたまふなるべし、他の皇子に准ずるに、此皇子も御歌と云ふべきを、歌とのみあるは若脱たるか、罪有て經 [ワナカ] れ給ふ故なりといはゞ、大津皇子も御歌と云べからざるをや、 | |||||||||||
| 童蒙抄 | 童子問 有馬皇子はいつれの皇子そや。 答 孝徳天皇の皇子也。母は阿部倉梯麻呂大臣女小足媛也。くはしく日本書紀孝徳記にみえたり。齊明天皇四年に、謀反の事あらはれて、絞られ給ふ事日本紀をみて知るへし。 |
|||||||||||
| 万葉考 | 有間皇子 [アリマノミコ] 自傷 [カナシミテ] 結 [ムスビテ] 2松枝 [マツガエヲ] 1御作 [ヨミタマヘル] 歌、 紀に孝徳阿倍ノ倉梯麻呂ガ女、小足 [ヲタラシ] 媛ノ生2有馬皇子1と見ゆ、さて斉明天皇四年十月、天皇紀伊の牟漏 [ムロ] の湯へ幸ありし時、此皇子そむき給ふ事顯れしかば、かの紀伊へめしけるに、其國の岩代の濱にで御食 [ミヲシ] まゐる時、松が枝を結びて、吾この度幸 [サキ] くあらば、又かへり見んと契り給ひし御歌なり、かゝるに其明る日、藤代てふ所にて、命うしなひまゐらせつ、 | |||||||||||
| 略解 | 孝德紀、阿倍倉梯麻呂女小足媛、有馬皇子を生むと見ゆ。齊明天皇四年十月、天皇紀伊の牟漏の湯へ幸ありし時、此皇子叛き給ふ事顯れしかば、紀伊へ召しけるに、其國の岩代の濱にて御食 [ミヲシ] まゐる時、松が枝を結びて、吾此度幸くあらば又還り見むと契り給ひし御歌なり。其あくる日藤代にて命うしなひまゐらせつ。歌の上御の字を脱せり。 | |||||||||||
| 攷證 | 有間皇子。自傷結2松枝1御歌。二首。 有間皇子。 書紀孝徳紀に、妃阿部倉梯麿大臣女、曰2小足媛1、生2有間皇子1云々。齊明紀に、四年十一月、庚辰朔壬午、留守官蘇我赤見臣、語2有間皇子1曰、天皇所v治政事、有2三失1矣、大起2倉庫1、積2聚民財1、一也、長穿2渠水1、損2費公糧1、二也、於v舟載v石、運積爲v丘、三也、有間皇子、乃知2赤兄之善1v己、而欣然報答之、曰、吾年始可v用v兵時矣、甲申、有間皇子、向2赤兄家1、登v樓而謀、夾腰自斷、於v是、知2相之不詳1、倶盟而止、皇子歸而宿之、是夜半、赤兄遣2物部朴井連鮪1、率2造宮丁1、圍2有間皇子於市經家1、便遣2驛使1奏2天皇所1、戊子、捉3有間皇子與2守君大石坂部連藥、鹽屋連鯯魚1、送2紀温湯1、舎人新田部米麻呂從焉、於v是、皇太子親問2有間皇子1曰、何故謀反、答曰天與2赤兄1知、吾全不v解、庚寅、遣2丹比小澤連國襲1、絞2有間皇子於藤白坂1云々とあるがごとく、皇子の謀反あらはれ給ひて、天皇の紀温湯におはします御もとに、遣はされける道な 磐白にて、自傷給ひて、松枝を結び給ひし也。 自傷。 史記蘇秦傳に、出游數歳、大困而歸、兄弟嫂妹妻妾竊皆笑之、蘇秦聞之、而所自傷、乃閉v室不v出、出2其書1徧觀之云々とある、自傷と同じく、かなしむ意也。考に、かなしみてとよまれしもあたれり。 結2松枝1。 代匠記に、十一月十日に、磐代の濱をすぎ給ふとて、わが運命いまだ盡ずして、事の始終を申ひらき、それをきこしめしわけて、たすけたまはゞ、又かへりて、この松を見んと、神のたむけに、引むすびて、つゝがなからん事を、いのりて、よませ給へるなるべし云々といへるは、たがへり。松が枝を結び給ふは、御旅路なれば、道のしをりし給ひ、御よはひをちぎらせ給ふ心にて、何とぞ申ひらきて、かへりきて今一度この結びし松を見る事もがなとおぼして、結び給ふ也。すべて、しらぬ旅路などにては、木にまれ草にまれ、折かけ、又は結びなどして、道のしをりとする事、中古までのならはしにて、韻會栞字注に、謂隨所行林中、斫其枝爲道記識也云々とあるも、全くこゝのしをりとこそ聞ゆれ。さて本集、一〔十一丁〕に、君之齒母 [キミカヨモ] 吾代毛所知武 [ワカヨモシラム] 磐代乃岡之草根乎 [イハシロノヲカノクサネヲ]、去來結手名 [イサムスヒテナ] 云々。六〔四十一丁〕に、靈剋壽者不知 [タマキハルイノチハシラス]、松之枝結情者 [マツカエヲムスフココロハ]、長等曾念 [ナカクトソオモフ] 云々。七〔十五丁〕に、近江之海湖者八十 [アフミノミミナトハヤソチ]、何爾加君之舟泊草結兼 [イツクニカキミカフネハテクサムスヒケン] 云々。十二〔廿佐丁〕に、妹門去過不得而草結 [イモカヽトユキスキカネテクサムスフ]、風吹解勿 [カセフキトクナ]、又將顧 [マタカヘリミム] 云々。廿〔六十丁〕に、夜知久佐能波奈波宇都呂布 [ヤチクサノハナハウツロフ]、等伎波奈流麻都能左要太乎 [トキハナルマツノサエタヲ、和禮波牟須婆奈 [ワレハムスバナ] 云々などあるも、よはひをちぎり、またしるしにとて、木草をむする也。これらを見ても思ふべし。 御歌。 印本、御の字を脱せり。今集中の例によりて加ふ。 |
|||||||||||
| 古義 | 有間皇子自傷 [アリマノミコノカナシミマシテ] 結 [ムスビタマヘル] 2松枝 [マツガエヲ] 1御歌二首 [ミウタフタツ]。 有間ノ皇子は、孝徳天皇ノ紀に、立2二ノ妃ヲ1、元妃阿倍ノ倉梯麻呂ノ大臣ノ女ヲ曰2小足媛 [ヲタラシヒメト] 1、生2有間ノ皇子ヲ1と見ゆ、さて齊明天皇四年十月、天皇紀伊ノ湯に幸ありしほど、此ノ皇子謀反の事あらはれしかば、十一月九日捕へられて、紀伊ノ國へ送り奉り、十一日に藤白にて絞 [クビ] れ賜へば、此は十日に藤白に至ますほどに、彼ノ國岩代ノ濱を經まして、其ノ濱の松枝を結び、吾この度幸 [サキ] くてあらば、又かへりみむと、契り賜ひし御歌なり、齊明夫皇ノ紀ニ云、三年九月、有間ノ皇子、性黠 [サトク]、陽狂 [イツハリタブル] 云々、往2牟婁ノ温湯ニ1、僞 [マネシテ] v療ルv病ヲ、來讃2國體勢 [クニカタヲ] 1曰、纔ニ觀ニ2彼ノ地ヲ1、病自ラ蠲消 [ノソコリヌ] 云々、天皇聞シ悦ヒタマヒ、思2欲 [オモホス] 往觀 [ミソナハサムト] 1、四年冬十月庚戌朔甲子、幸2紀ノ温湯ニ1、十一月庚辰朔壬午、留守官蘇我ノ赤兄ノ臣、語リテ2有間ノ皇子ニ1曰、天皇ノ所治 [ノシラス] 政事有2三ノ失1矣、云々、有間ノ皇子、乃知2赤兄之善 [ウルハシキコトヲ] 1v己ニ、而欣然報答之曰 [ヨロコビコタヘタマハク]、吾年始テ可v用v兵ヲ時ナリ矣、甲申、有間之皇子、向2赤兄カ家ニ1、登テv樓ニ而謀、夾膝 [オシマツキ] 自ラ斷 [ヲレキ]、於是知2相之不祥 [アシキヲ] 1、倶ニ盟テ而止、皇子歸而宿之、是之夜半ニ赤兄、遺テ2物部之朴之井ノ連鮪ヲ1率テ2造v宮丁ヲ1、圍2有間ノ皇子ヲ於市經 [イチフノ] 家ニ1、便遣2驛使ヲ1、奏ス2天皇所 [オホミモトニ] 1、戊子、捉テ3有間ノ皇子、與ヲ2守ノ君大石、坂部ノ連藥、鹽屋ノ連鯯魚1、送 [オクリマヲス] 2紀ノ温湯ニ1、舍人新田部ノ米麻呂從 [ミトモツカヘタリ] 焉、於是皇太子 親 [ミヅカラ] 問2有間ノ皇子ニ1曰、何ノ故ニカ謀反 [ミカドカタブケントセシ] 答曰、天與2赤兄1知レリ、吾全 [カツテ] 不解 [シラズ] 、庚寅、遣丹比ノ小澤ノ連國襲ヲシテ、絞ラ有馬ノ皇子ヲ、於藤白ノ坂ニ、通證に、藤白ノ坂ハ、海部有田兩郡之堺也、今按ニ岩代屬2牟婁ノ郡ニ1、今有間ノ皇子ノ祠在リ焉とあり、 御ノ字、舊本に無は脱たるなり、例に依て補へり、 |
|||||||||||
| 全釈 | 有間皇子自ラ傷ミテ結ベル2松枝ヲ1歌二首 有間皇子は孝徳天皇の御子である。孝徳紀に、「妃阿部ノ倉梯麻呂ノ大臣ノ女曰2小足媛1、生2有間皇子1」とある。又齊明紀の四年十一月の條に、この皇子の謀反があらはれたことを記し、「於v是皇太子、親問2有間皇子1曰、何故謀反、答曰、天與2赤兄1知ル、吾全不v解、庚寅遣2丹比小澤連國襲1、絞2有間皇子於藤白坂1」とある。皇子の謀反あらはれ、折から天皇紀ノ温湯に行幸中であつたから、其處へお連れ申す道すがら、磐代で自ら傷んで、松の枝を結ばれたのである。 |
|||||||||||
| 全註釈 | 有間皇子、自傷結2松枝1歌二首 有間の皇子の、みづから傷みて松が枝を結ぶ歌二首 【釋】 有間皇子 アリマノミコ。孝德天皇の皇子。孝德天皇が崩じて齊明天皇重祚されるに及んで、その三年九月に、紀伊の國の牟婁の湯に往き、國の體勢を觀、わずかにその 地を觀るに病おのずから瘉えたと申したので、天皇悦んでその地を見ようとし、四年十月、紀の温湯に行幸あり、十一月、有間の皇子に謀反の企圖ありと聞いて召し寄せ、皇太子 (天智天皇) みずから問われた。皇子は行宮を出て京に上る途上、藤白の坂において縊り殺された。日本書紀によるに、有間の皇子は、十一月九日に捕えられて紀伊の國に送られ、皇太子の尋問を經て十五日に殺された。京から行宮まで、普通五六日の日程である。 自傷結松枝歌 ミヅカライタミテマツガエヲムスブウタ。 皇子が召されて牟婁の行宮に行く途上、磐白の地で詠んだ歌である。自傷とあるのは、この行、生還を期しがたい事情にあつたので、みずから哀傷されたのをいう。松が枝を結ぶことについては、古人は、結ぶことに信仰を有していたことが根柢になつている。そのことは、既に、「磐代乃 [イハシロノ] 岡之草根乎 [ヲカノクサネヲ] 去來結手名 [イザムスビテナ]」(卷一、一〇) の條に記した所である。松が枝を結ぶのは、まじないで、壽命を結び留めまた無事にその處に立ち還ろうとする心である。物を結ぶことは、わが魂を結び留めるという意味であつて、後にまた、結んだものにめぐりあう事ができるとしていた。これが松が枝を結ぶ、草を結ぶ、衣の紐を結ぶ、菅の根を結ぶ等の行事となつてあらわれている。中にも行人が松の枝や草葉を結ぶのは、これより先に旅行してもまた此處に無事に立ち歸るという意味があり、みずから祝うまじないである。有間の皇子に限らず何人でもする風習である。後世結び松をもつて不吉な事のように感じているのは、有間の皇子の故事があるからであつて、松を結ぶというその事自身には、さような不吉な内容は全然無く、松の木の性質上、むしろ將來を祝う氣もちがあることは、例歌に依つて知られる所である。 |
|||||||||||
| 評釈 | 有間皇子 [ありまのみこ]、自ら傷みて松が枝を結べる歌二首 〔題〕 有間皇子 孝徳天皇の皇子。齊明天皇の時、蘇我赤兄に謀られて、紀伊行幸の御留守中不軌を企てられたが、事あらはれて紀伊の牟婁の行宮に送られ、藤白 (今の海草郡内海村) で死を賜うた。御年十九。齊明天皇四年十一月のことである。結松は「一〇」參照。これは皇子が牟婁 (西牟婁郡湯崎) に送られる途中のことであらう。 |
|||||||||||
| 注釈 | 有間皇子、自傷結2松枝1歌二首 「有間皇子」は孝徳紀大化元年秋七月の條に「妃阿部倉梯麻呂大臣女曰2小足媛1、生2有間皇子1」とあつて孝徳天皇の皇子である。斉明紀三年の條に「有間皇子性黠 [サトシ] 陽狂 [イツハリタフレテ] 云云。徃2牟婁温湯1僞v療v病。來讃2國體勢1曰。纔觀2彼地1。病自蠲消 [ノソコリヌ] 云云、天皇聞悦、思2欲徃觀1」とあり、その翌四年冬十月十五日に紀の湯に行幸あり、留守官蘇我赤兄が皇子に天皇の政に三の失ある事を語つたので、皇子は赤兄が好意を寄せてゐると考へて謀反の決意を示され、十一月「甲申 (五日)、有間皇子、向2赤兄家1、登v樓而謀、夾膝 [オシマツキ] 自斷 [ヲレヌ]、於v是知2相之不祥1、倶盟而止。」皇子は帰られたが即夜、赤兄は人を遣して皇子の家を圍み、一方天皇の許へ注進、九日皇子を紀伊へ送る。皇太子親しく糾問。その帰途「庚寅 (十一日)、遣2丹比小澤連國襲1、絞2有馬皇子於藤白坂1」とある。今海南市の南より下津町橘本(キツモト)へ越える道を藤白峠といふ。その麓、藤白神社の少し南、峠道の側に大きな椿の木あり、石地蔵を祀る。そこを有間皇子の御墓の伝説地といふ。書紀に「或本云」として異伝を載せてゐる。その中に「方今皇子年始十九。未v及2成人1。可下至2成人1而待中其徳上云々」の語あり、御年十九といふ事がわかる。 松が枝を結ぶは前 (1・10) に草を結ぶとあつたのと同じく無事を祈る心である。 |
|||||||||||
| 全注 | 有間皇子、孝徳天皇の皇子。母は阿倍倉梯麻呂の女小足媛。孝徳天皇には皇后間人皇女、妃乳娘との間に子がなく、有間はただ一人の皇子であったらしい。生年は、斉明四年(658)十一月紀所引の「或本」に「皇子、年始めて十九」とあるのによれば、舒明十二年(640)となる。斉明三年九月紀に「有間皇子、性黠(さと)くして陽狂(うほりくるひ)すと、云々。牟婁温湯に往きて、病を療(をさ)むる偽(まね)して来、国の体勢(なり)を讃めて曰はく、『纔觀2彼地1。病自蠲消 [ノソコリヌ] 』と、云々」とあり、皇位継承の有力な候補者とみられていた皇子が狂人をよそおったことを伝えている。翌四年冬十一月三日、紀温湯行幸の留守の間に、蘇我赤兄は斉明天皇の失政を非難し、皇子の挙兵をうながした。同月五日、盟約を交わしたその日の夜、赤兄は突然市経(いちふ)の有間皇子の家に兵を遣し、皇子を捕えさせ、九日には紀温湯に護送させた。こうした赤兄の不可解な行動の背後には中大兄の指示があったとも、また、赤兄は途中から皇子を裏切るようになったのだとも言われている。十一日、皇子は藤白坂 (現在の海南市内海町藤白) で絞殺された。 | |||||||||||
| 「童蒙抄問答」 | 童蒙抄 | 童子又問 此歌の注を良材集云、右有間皇子は孝徳天皇の御子也。齊明女帝の御時蘇我赤兄と心を同しくして、御門かたふけせんとせしか、紀伊國岩代と云所にありて、心さしのとけかたからん事をうれへて、其所にありける松の枝をむすひて、手向として此歌を詠置て外へ出侍し、其間に赤兄かしかしかのよしを御門へ申侍しそのかへり忠により 有間皇子の謀反の事あらはれて、つひに藤白坂にしてころされ侍り、のちのちの人此松の事よめる歌おなしく、万葉集にのせ侍り。同岩代の野中にたてる結松心もとけぬむかしおもへは〔意吉麻呂〕。のちこんと君かむすへる岩代の小松のうれを又みけんかも人丸とあり。此注はたかひなく侍や。 答 此良材の御注、大概は日本書紀をもちて書たまへは、事の相違ひもなけれとも、万葉集の本文につきて賢按をもめくらし給ひたるとみゆるなり。文字の違ひもあれと、それは傳寫の誤りなるもはかりかたし。只万葉集につきて此歌をみれは、有間皇子はしめ紀伊國岩代と云所に有て、心さし逐けかたからん事をうれへて、其所にありける松の枝をむすひて、手向として此歌を讀置給ふには有へからす。いかにとなれは、此歌の前書と有間皇子自傷結松枝歌二首と有、自傷の二字につきておもへは謀叛の事あらはれて、赤兄に捉られて紀温湯に送られ給ふ時に、詠給へる歌なるへし。よりて自傷の二字も有か。此歌後の時の歌なれは、挽歌の中にも入たるなるへし。そのうへ二首の内後の歌も捉られておくられ給へる時なれは、笥に盛飯をも松の葉をしきておろそかなる飯をあたへたるにつきて、自傷の二字も有てよく相叶ふへし。しかるをたゝはしめ紀湯に陽狂の時の詠としては、此詠を追和する事もいかゝ。謀反の志をとけさせ給はぬをいたまは、謀反の意をたすくるにいたれは、ともに罪人といふへき難有へし。すてに謀反あらはれて捉られて死罪にきはまれるか故、自傷も有て若恩降を得て二度かへりみんことをねかひ給へる時の事ならは、意吉麿哀咽歌も罪なかるへし。且人丸の歌に、きはめて歌林良材に載られたる事は心得かたし。人麻呂歌集中に出と古注者の書たるは、必人麻呂の歌のみに有へからす。他人の歌も歌集の中に見えたるを注せるなるへし。人麻呂歌ならはこゝに人丸とこそ有へし。歌集中に出と有にて他人といふへし。良材集の歌にも文字のたかひかなのちかひあり。是は傳寫のあやまりも有へし。濱松ともよみ、岸の松とも野中と松とも詠むへき事なれは、しひて論するには及ふましきか。有間皇子此時捉れて送られ給ふ旅行なれは、自ら結ひ給ふ事はなるましきかとうたかふ人あれと、それは凡人にもあらす。いまた罪科さたまりたるにもあらす。赤兄か謀りことにて捉て送りたれは、兵卒に打圍まれて、行給ふとても小松の枝をむすひ給ふほとの事をゆるすましきにあらす。 |
||||||||||
| 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版] (1980年9月)も併記する 【部立】挽歌 〔本文〕 挽。神田本、「梚」。 歌。西本願寺本・大矢本・京都大学本、「謌」。 〔諸説〕 挽歌。拾遺集、「ヒツキウタ」。童蒙抄、「ヒクウタ」。万葉考、「カナシミノウタ」。古義、「カナシミウタ」。 【後崗本宮御宇天皇代 [天豊財重日足姫天皇]】 〔頭注〕 元暦校本、肩ニ朱「□[下写真参照]」。 京都大学本、肩ニ朱「」斉明天皇」。 〔本文〕 崗。元暦校本・金澤本・神田本・西本願寺本、「□[下写真参照]」。細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「罡」。 天豊財重日足姫天皇。元暦校本・金澤本・神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、 以上小字ニ書ケリ。コノ下ニ続ケテ「譲位後即後□[下写真参照]本宮」ノ八字アリ。 但、京都大学本、赭訓アリ、次ノ如シ。「譲位ノ後チ即後ノ罡本宮」。又上ノ「天」ニ赭ノ合点アリ。金澤本、上ノ「天」ヲ「□[下写真参照]」トセリ。 元暦校本、「豊」ヲ「□[下写真参照]」トセリ。右ニ朱「豊」アリ。神田本、「重」ヲ「童」トセリ。 〔訓〕 豊。右ニ「トヨ」アリ。 【題詞】有間皇子自傷結松枝歌二首 〔頭書〕 神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本、肩ニ朱「有間皇子孝徳天皇皇子」アリ。但、温故堂本、「皇」ノ下マタ「皇」アリ。京都大学本、肩ニ朱「孝徳天皇々子也」アリ。 古葉略類聚鈔、題詞ノ下ニ「斉明御時」アリ。 題詞ノ次行ニ「孝徳天皇子母男足媛性湯任云々往年出安温泉療痛来去々斉明天皇五年幸紀温湯重謀反留宮蘇我明元ホ捉皇子送温湯委見日本紀」 類聚古集、前行ニ「有間皇子自傷結松枝歌 斉明御時」アリ。 〔本文〕 歌。神田本、「謌」。温故堂本、ナシ。 〔訓〕 京都大学本、赭訓アリ、次ノ如シ。「傷テ結松ノ枝ヲ」。 〔諸説〕 自傷。万葉考、「カナシミテ」。 結松枝歌。代匠記精撰本、「歌」ノ上「御」脱カトス。童蒙抄、「枝」ノ下「時」脱カトス。 【本文】磐白乃 濱松之枝乎 引結 真幸有者 亦還見武 (イハシロ ハママツカエヲ ヒキムシヒ サキクアラハ マタカヘリミム) 〔頭書〕 袖中抄、第十七「自(ミ)傷(イタム)ヲ結松枝歌イハシロノハママツカエヲヒキムスヒ真幸(マサキシ/マサシク或)アラハマタカヘリミム」 和歌童蒙抄、第七「イハシロノハママツノエヲヒキムスヒマコトサモ(チ)アラハマタカヘリコム (中略) 万葉ニアリ」 〔訓〕 イハシロ。神田本、ナシ。元暦校本、金澤本・類聚古集、「いはしろの」。古葉略類聚鈔・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「イハシロノ」。 ハママツカエヲ。元暦校本・金澤本・類聚古集、「はまヽつのえを」。神田本、「ハママツカエノ」。「ノ」ハ削リテ直セリ。モト「ヲ」カ。「乎」ノ左ニ「ヲイ」アリ。 温故堂本、「ハママツカヱヲ」。 マサキクアラハ。元暦校本、「まことさちあらは」。訓ノ下ニ朱「御本云マコトサチアラハ」アリ。金澤本・類聚古集、「まさしくあらは」。 類聚古集、漢字ノ右ニ朱「マコトサチアラハ」アリ。訓ノ下ニ「又まことにさちあらは」アリ。 古葉略類聚、「マコトサチアラハ」。「真幸」ノ左ニ「マサシク」アリ。神田本・細井本、「マサシクアラハ」。神田本、「シ」ノ右ニ朱「キイ」アリ。 細井本、「幸」ノ左ニ「サキクイ」アリ。「イ」ハ朱。大矢本・京都大学本、「サキク」青。 京都大学本、「マサキク」ノ右ニ赭「マサシク」アリ。「真幸」ノ左ニ赭「マコトサチ」アリ。 〔諸説〕 イハシロ。仙覚抄、「イハシロノ」。 マサキクアラハ。仙覚抄、「マサシクアラハ」 (古点) 又ハ「マコトサチアラハ」 (古点) ヲ否トシ、「マサキクアラハ」トス。拾遺集」、「マサシクアラハ」ヲ可トス。
[校本萬葉集新増補版] 【部立】挽歌 〔本文〕 歌。神宮文庫本、「謌」柿本朝臣人麿妻依羅娘子輿人麿相別歌一首 挽歌。拾遺集、「ヒツキウタ」。童蒙抄、「ヒクウタ」。万葉考、「カナシミノウタ」。古義、「カナシミウ 【後崗本宮御宇天皇代 天豊財重日足姫天皇】 〔頭書〕元暦校本、朱頭書「下写真参照」アリ。 〔本文〕 崗。神宮文庫本、「岡」。 天豊財重日足姫天皇。神宮文庫本、以上九字小字トセリ。コノ下ニ小字「譲位後即後岡本宮」アリ。京都大学本、「天豊財」ノ肩ニ赭ノ合点アリ。 【題詞】有間皇子自傷結松枝歌二首 〔頭書〕神宮文庫本、肩ニ「有間皇子孝徳天皇子」アリ。朱ノ上ニ赭ヲ重ネテ書ケリ。 【本文】磐白乃 濱松之枝乎 引結 真幸有者 亦還見武 (イハシロ ハママツカエヲ ヒキムスヒ マサキクアラハ マタカヘリミム) 〔頭書〕 六帖、第五「岩代の濱松かえをひき結ひまさきくあらは又かへりみむ」 夫木抄、第廿九「いはしろのはま松か枝を引むすひまさしくあらは又かへりみむ」 名寄、第卅三「磐白乃 濱松之枝乎 引結 真幸有者 亦還見武 (イハシロノ ハママツカエヲ ヒキムスヒ マサキクアラハ マタカヘリミム)」 〔訓〕 イハシロ。神宮文庫本、「イハシロノ」。 ハママツカエヲ。天治本、「カ」ニ相当スル字小サク、「の」カ「□[下写真参照]」カ明ナラズ。近衛本、「ハママツカヱヲ」。 マサキクアラハ。天治本、「まさしくあらは」。漢字ノ右ニ墨「マコトサチアラハ或本」アリ。 神宮文庫本、「サキク」ヲ朱ニテ消セリ。「キ」ヲ更ニ消シ、右ニ「シ」ヲ書ケリ。コレモ朱ニテ消セリ。「幸」ノ左ニ「サキク」アリ。 カヘリミム。天治本、「ミ」蝕アリテ見エズ。
|
||||||||||
| 「磐白(いはしろ)」注 | 全註釈 | 【釈】磐白乃 イハシロノ。磐白は既出 (卷一、一〇)。和歌山縣日高郡の海岸の地名で、牟婁の温泉に赴く途中にある。 | ||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】 岩代は既に述べた (1・10)。その松の遺跡といはれるところにもと老松があつたやうであるが枯れ、その後また若松が植ゑられてゐたが、それも道路改修の為に移され、今徳富蘇峰氏撰する碑が立つてゐる。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】 岩代は今の和歌山県日高郡南部町で、紀の湯 (和歌山県西牟婁郡白浜町の湯崎温泉) から二十数キロの地。田辺湾をはさんで、対岸に紀の湯を望むことができる。藤白と紀の湯との中間にあり、作歌は往路のものか、復路のものか明らかでないが、歌の内容からいうと往路とするのがふさわしい。 |
|||||||||||
| 「引結(ひきむすび)」注 | 古義 | 引結 [ヒキムスビ] は、結び合することなり、引は手して物することにそへ云辭にて、取撫 [トリナテ] などいふ取に同じ、松カ枝を結びて契をかくること、一ノ卷中皇命ノ御歌に、君之齒母 [キミガヨモ] 云云、岡之草根乎去來結手名 [ヲカノクサネヲイザムスビテナ]、とある下に云るを合セ見べし、 | ||||||||||
| 全釈 | 濱松之枝乎引結 [ハママツガエヲヒキムスビ] ―― 濱の松の枝をわがねること。草木の枝を結ぶことは、記念として、又は、後會を期するやうな意味でやつた風俗らしい。既に卷一に磐代乃岡之草根乎去來結手名 [イハシロノヲカノクサネヲイザムスビテナ](一〇) とあつたが、その他卷六、靈剋壽者不知松之枝結情者長等曾念 [タマキハルイノチハシラズマツガエヲムスブココロハナガクトゾオモフ] (一〇四三)、卷二十に夜知久佐能波奈波宇都呂布等伎波奈流麻都能左要太乎和禮波牟須婆奈 [ヤチクサノハナハウツロフトキハナルマヅノサエダヲワレハムスバナ] (四五〇一) などがそれである。皇子は温湯にましました天皇にま見え給うて、謀反の辯解が出來て、再びこの地を過ぎむと思し召して、松の枝を結ばれたものである。 | |||||||||||
| 全註釈 | 【釈】 濱松之枝乎 ハママツガエヲ。濱邊の松が枝をで、前にも、「白浪乃 [シラナミノ] 濱松之枝乃 [ハママツガエノ]」(卷一、三四) の例がある。 引結 ヒキムスビ。松が枝を結ぶのであるから、その若い枝を結んだに相違なく、一四六の歌には、子松ガウレとある。一本の枝を輪に結ぶのか、二本の枝を合わせて結ぶのか不明である。また繩か緒の如き他物を以つて結ぶかとも考えられるが、衣の紐や草の葉などは、それ自身を結ぶものであろう。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】 「ヒキムスビ」は、今結んでいることをあらわす中止法。草や木の枝を結ぶのは、旅の安全を祈る鎮魂の習俗。巻一の中皇命の「君が代も我が代も知るや岩代の岡の草根をいざ結びてな」 (10) も、ほぼ同じ頃の作である。 |
|||||||||||
| 新全集 | 【頭注】 結ビ → 10(いざ結びてな)。古代人は紐のみならず木の枝や草の茎葉などを結ぶことによって何ものかと盟約し、何らかの願わしい事態が実現する事を期待し予祝いした。 |
|||||||||||
| 原文「真幸有者 (まさきくあらば)」訓・考 |
仙覚抄 | 磐白乃濱松之枝乎引結眞幸有者亦還見武 [イハシロノハママツカエヲヒキムスヒマサキクアラハマタカヘリミム] 此歌ノ第四句、古點ニハ、アルヒハ、マサシクアラハト點ス。アルヒハ、マコトサチアラハト點セリ。兩説トモニアヒカナワス。マサキクアラハト和スヘシ。マサキクトイフハ、眞幸 [マコトノサイワイ] 也。此集第七 [十七ィ] 卷、大伴宿祢池主歌詞中云、吉美賀多太可乎麻佐吉久毛安里多母等保利等 [キミカタタカヲマサキクモアリタモトオホリト] ト云々。第廿卷、追2痛防人 [サキモリノ] 悲別ノ之心ヲ1作歌詞中云、麻佐吉久母波夜久伊多里弖 [マサキクモハヤクイタリテ] 云々。作例如此。何ノ爲2不審ト1乎。 |
||||||||||
| 童蒙抄 | 童子問 仙覺抄云、此歌の第四句古點にはあるひはまさしくあらはと點し、あるひはまことさちあらはと點せり。兩説共に相かなはす。まさきくあらはと和すへし。まさきくといふは眞幸也。此集第十七卷、大伴宿禰池主歌詞中云、吉美賀多太乎麻佐吉久毛安里多母等保梨云云。第二十卷追痛防人悲別之心作歌詞中云、麻佐吉久母波夜久伊多里弖云云。作例如v此。何爲2不審1乎とあり。此訓はしかるへきや。 答 しかるへし。 |
|||||||||||
| 万葉考 | 濱松之枝乎 [ハママツガエヲ]、引結 [ヒキムスビ]、眞幸有者 [マサキクアラバ]、 幸 [サキ]くてふ事は既出、 | |||||||||||
| 攷證 | 眞幸有者 [マサキクアラハ]。 眞 [マ] さきくの、眞 [マ] は、添たる字にて、國のまほら、眞 [マ] かなし、眞 [マ] さやかなどいふ類の眞 [マ] 也。この類、猶多し。幸 [サキク] は、字のごとく、福 [サキハヒ] ありて、つゝがなくの意にて、こゝは、かの謀反の事を申ひらきて、つゝがなく幸ひにかへり來たらば、今この結びし松を、二たびかへり見んと也。さて、まさきくは、本集三〔廿二丁〕に、吾命之眞幸有者 [ワカイノチノマサキクアラハ]、亦毛將見 [マタモミム] 云々。又〔五十一丁〕に、 平間幸座與 [タヒラケクマサキクマセト]、天地乃神祇乞祷 [アメツチノカミニコヒノミ] 云々。十三〔十丁〕に、言幸眞福座跡 [コトサキクマサキクマセト]、恙無福座者 [ツヽミナクサキクイマセハ: 云々などありて、猶いと多し。 |
|||||||||||
| 古義 | 眞幸有者 [マサキクアラバ] とは、眞 [マ] は美稱にて平 [サキ] くあらばなり、十三にも、樂浪乃志我能韓埼幸有者又反見 [サヽナミノシガノカラサキサキクアラバマタカヘリミム] 云々とあり、 | |||||||||||
| 全註釈 | 【釈】 眞幸有者 マサキクアラバ。マは接頭語。サキクは、幸運にある意の形容詞。「吾命之 [ワガイノチシ] 眞幸有者 [マサキクアラバ] 亦毛將見 [マタモミム] 志賀乃大津爾 [シガノオホツニ] 縁流白浪 [ヨスルシラナミ]」(卷三、二八八) など使用され、また好去の文字をもマサキクと讀んでいる。「好去而 [マサキクテ] 亦還見六 [マタカヘリミム] 大夫乃 [マスラヲノ] 手二卷持在 [テニマキモテル] 鞆之浦廻乎 [トモノウラミヲ]」(卷七、一一八三)。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】 「マ」は接頭語。「サキク」は無事に、の意。旧訓「マサシクアラハ」あるいは「マコトサチアラハ」を仙覚抄に「マサキクアラハ」と改訓した。巻十七に「麻佐吉久登伊比氐之物乎」 (3958)、巻二十に「麻佐吉久母波夜久伊多里弖」 (4331) の仮名書があり、「マサキク」と訓む。「サキ・サキハヒ」などと関連のある語で、人間についてその無事を言うのが普通だが、「ささなみの志賀の辛崎幸くあれど」 (1・30) のように、自然について言うこともある。茂吉は「辛崎幸くあれど」を「特殊的」な例と見、「或は人麿が創めたもののやうな気もしてゐる」 (評釈篇) と記しているが、万葉集における用例や語義から考えて、始は自然・人事の双方にわたって使用され、後にもっぱら人事についてのみ使われるようになったと解する方が穏やかだろう。なお、この皇子の歌の「マサキクアラバ」について、中西進『万葉史の研究』には、「無事であったら」という諸注の解を不十分とし、直接には「結松の解けざる状態を仮定」しているのであって「必然的にその場合は命が無事だと言う結果を予想」するに過ぎないと言う。これは注意すべき指摘である。ただ松のことに限定するのは問題で、岩代の神および自然の栄えと、祈りを捧げる者の平安とは一体的に把握されるものとして、「マサキクアラバ」に歌いこまれていると考えるべきだろう。 |
|||||||||||
| 原文「亦還見武 (またかへりみむ)」訓・考 |
童蒙抄 | 童子又問 一條禅閤の歌林良材集岩代乃結松事の一條に此歌をあけられたるにも、第四句をまさしくあらはありて、第五句を又かへりこん「有馬皇子」とかき給へるも誤りにや。 答 誤り給へり。皆万葉集の本文によらすして、よみたかへたる歌のかなかきのみをみたまひて、みたりに万葉集とて引てのせられたるとみえたり。万葉集の本文につかすして歌をしらす、文字の訓の是非をもわきまへられす、末學の意と心得て注釋等をくはへられたる事、枚擧にいとまあらす。禅閤の博覽は更にいふへくもあらねとも、万葉集はうとくおはしけるやらん。万葉集の釋なとまゝなされたるをみるに、一つも是とみやる事なし。かな遣ひをも知り給はさるは、古學をしたはさる故なるへし |
||||||||||
| 全注 | 【注】 またふたたびこの松の枝をみよう、の意。「ミム」の「ム」を推量に解するか (佐佐木評釈・注釈・古典集成など)、意志的表現と解するか (窪田評釈・私注・古典大系・古典全集・私記など)、説が分かれている。真淵の万葉考に「松が枝を結びて、吾この度幸くあらば又まへり見んと契り給ひし御哥也」と注するのは、後者か。いずれであるか判断しがたい注も多く、私自身、前説によってこの歌を論じたこともあったが (有精堂『万葉集講座』第五巻)、「まさきくてまた還り見む大夫の手に巻き持てる鞆の浦回を」 (7・1183)、「白崎は幸く在りまて大船に真梶しじ貫きまた将願」 (9・1668)、「妹が門行き過ぎかねて草結ぶ風吹き解くなまた将願」 (12・3056) などは明らかに後者であり、皇子歌も同様に解するのが良いと思われる。 |
|||||||||||
| 「一首」評 (万葉集全釈・評釈万葉集) |
全釈 | 〔評〕 あはれな事件に伴なつた歌の故か、何となく悲しい感じを與へる作である。皇子への同情は、後の人をして多くの結松の歌をよましめた。それは次の數首のみではなく、萬葉以後にも澤山あるのである。 |
||||||||||
| 評釈 | 〔評〕 質朴で何の飾りもない言ひ方に、却つて切々たる哀感を感じさせる。三句でちよつと休止し、四句に又輕く抑揚を附してゐる調べにも、深い歎息を聞くやうに思はれる。また、結び松は、上古の信仰を物語つてゐるのであるが、磐代といふ地名から、堅く變らぬ石といふ聯想も動いたのであらうか。 |
|||||||||||
| 巻二 142 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版] (1980年9月)も併記する 【頭書】 類聚古集、前行ニ「有間皇子」アリ。 古葉略類聚鈔、前行ニ「有間皇子自傷結松枝哥二首中」アリ。 和歌童蒙抄、第五「イヘニアレハケニモルイヒヲクサマクラタヒニシアレハシヰノハニモル 万葉二ニアリ」 釈日本紀、巻二十七「裏書云家有者筍尓盛飯乎(イヘニアレハケニモルイヰヲ) 万葉第二」 八雲抄、第三「家にあれは筍(ケ)にもるいひを草枕たひにしあれは椎のはにもる」 【本文】家有者 笥爾盛飯乎 草枕 旅爾之有者 椎之葉爾盛 (イヘニアレハ ケニモルイヒヲ クサマクラ タヒニシアレハ シヒノハニモル) 〔本文〕 椎。元暦校本・神田本、「推」。 〔訓〕 イヘニアレハ。元暦校本、「れ」ノ右ニ朱「ル」アリ。古葉略類聚鈔・神田本、「イヘニアラハ」。古葉略類聚鈔、「ラ」ノ右ニ「レ」アリ。神田本、「ラ」ノ右ニ「レイ」アリ。 イヒヲ。類聚古集、「いゐを」。古葉略類聚鈔・神田本、「イヰヲ」。 シヒノ。類聚古集、「しゐの」。古葉略類聚鈔・神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本・京都大学本、「シヰノ」。 〔諸説〕 イヘニアレハ。童蒙抄、「イヘナラバ」。 椎之葉。童蒙抄、「椎」ハ「松」ノ誤カ。
[校本萬葉集新増補版] 【頭書】 六帖、第四「家にあれはけにもる飯を草枕たひにしあれは椎の葉にもる」(八雲、第三同 【本文】家有者 笥爾盛飯乎 草枕 旅爾之有者 椎之葉爾盛 (イヘニアレハ ケニモルイヒヲ クサマクラ タヒニシアレハ シヒノハニモル) 〔訓〕 イヘニアレハ。神田本、「イヱニアラハ」。「ラ」ノ右ニ「レイ」アリ。京都大学本、「レ」ハ磨リ消セル上ニ書ケリ。 シヒノ。神宮文庫本・近衛本、「シヰノ」。
|
|||||||||
| 原文「家有者 (いへにあれば)」訓・考 |
童蒙抄 | いへならば、けにもるいひを、くさまくら、旅にしあれば、しひのはにもる 家有者 例の約言家にあらばと云義也 |
||||||||||
| 全釈 | 家有者 [イヘニアレバ] ―― イヘニアラバとよむ説はよくない。旅爾之有者 [タビニシアレバ] に對して、これは、アレバといふべきである。 | |||||||||||
| 全註釈 | 【釈】 家有者 イヘニアレバ。家にいる時にはの意。既定の事實として已然形による。 |
|||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「いへにあれば」 古葉略類聚鈔 (1・18ウ) には「アラハ」とし右に「レ」とし、紀州本にも「ラ」として右に「レイ」とあつて、「アラバ」の訓もあつたやうである-童蒙抄には「イヘナラバ」とある-が、家にある時には、といふ既定の事実であるから「アレバ」でよい。「ニア」をつづめて「ナ」とする事も出来るが「ア」の母音を含む六音としてそのままにしてよい。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】「いへにあれば」 元暦校本・類聚古集・西本願寺本など、「イヘニアレバ」と訓む。古葉略類聚鈔に「アラハ」とし「ラ」の右に「レ」を記し、紀州本にも「ラ」とし右に「レ」を記している。家にいる時にはいつも、の意で、「イヘニアレバ」と訓むのが正しいであろう。 |
|||||||||||
| 「笥尓盛飯乎 (けにもるいひを)」考 |
仙覚抄 | 家有者笥尓盛飯乎草枕旅尓之有者椎之葉尓盛 [イヘニアレハケニモルイヒヲクサマクラタヒニシアレハシイノハニモル] ムカシハ飯ヲハ、笥ニモリケル也。イマモ勸學院ニハ、其儀ハヘルトカヤ。 |
||||||||||
| 拾穂抄 | いへにあれはけにもるいひを草枕たひにしあれはしゐのはにもる 家有者笥尓盛飯乎草枕旅尓之有者椎之葉尓盛 いへにあれはけにもる 仙曰むかしは飯を笥にもりける今も勧学院に其儀侍るとかや愚案日本紀云玉笥には飯さへもり玉もひに水さへもりと云々古來風躰云「飯なと云事哥に讀へくもあらねと昔の人は心け晴なくてかく讀けるなるへし此哥さまはいみしくおかしき哥也」云々此家にあれはの哥の事也
|
|||||||||||
| 代匠記 | 家有者笥爾盛飯乎草枕旅爾之有者椎之葉爾盛 [イヘニアレハケニモルイヒヲクサマクラタヒニシアレハシヒノハニモル] 笥は玉篇云、思吏切、竹作盛v飯方器也、和名云、禮記註云、笥〔思吏反、和名計〕盛v食器也、さらぬだに旅侘しきを、殊に謀反の事によりて捕はれて物部 [モノヽフ] の中に打圍まれておはします道なれば、萬引かへたる樣、笥にもる飯を椎の葉に盛とよませ給へるにこもれり、孝徳天皇の御子なれば、位に即かせたまふまでこそなくともさておはしまさば世に重んぜられておはすべきに、由なき事思ひ立給て刑戮の辱に遇たまふは不思儀の事なれど、此二首の御歌殘りて今の世の人まであまねく知參らするも、偏に此道の徳なり、端作の詞には此歌は叶はぬ樣なれど、初の歌を先として云へり、かゝる事あやしむべからず、 |
|||||||||||
| 童蒙抄 | 家有者笥爾盛飯乎草枕旅爾之有者椎之葉爾盛 [いへならば、けにもるいひを、くさまくら、旅にしあれば、しひのはにもる] 笥爾盛 飯物を盛るうつは物を笥と云也。仙覺はこれをくしげと心得たると見えたり。文永の頃迄は勸學院には此義ありと云て、笥は食物をもる物にはあらで、くしげの一種と見たるか。其意得がたし。もし笥の宇にくしげと後人點をつけたるか。其意心得難し。日本紀武烈卷、物部影妻が歌にも、玉笥には飯さへもりと有。和名鈔卷第十六云、笥、禮記注云、笥思吏反、和名計、盛v飯器也云々 |
|||||||||||
| 万葉考 | 家有者 [イヘニアレハ]、笥爾盛飯乎 [ケニモルイヒヲ]、 笥は和名抄にも介 [ケ] と訓つ、いと古への飯笥 [イヒゲ] は、藺 [ヰ] 竹などして作り、又木をわげたるも本よりならん、顯宗天皇紀、影姫が歌に、多摩該儞播
[タマケニハ]、伊比左倍母理 [イヒサヘモリ]、このたまけは丸笥 [ケ] なり、 鎮魂祭式に、飯笥一合、云云、即盛2藺笥 [ヰノケニ]1、 |
|||||||||||
| 略解 | 家有者。笥爾盛飯乎。草枕。旅爾之有者。椎乃葉爾盛。いへにあれば。けにもるいひを。くさまくら。たびにしあれば。しひのはにもる。 和名抄、笥和名計、盛v食器也。武烈紀影姫 [カゲヒメノ] 歌に、多摩該儞播伊比左倍母理 [タマケニハイヒサヘモリ]、此タマケは丸笥なり。鎭魂祭式に飯笥一合云云、即盛v笥など有り。今も檜の葉を折敷きて強飯を盛る事有るが如く、旅にてはそこに有りあふ椎の小枝を折敷きて盛りつらむ。椎は葉の細かに繁くて平かなれば假初に物を盛べき物なり。 |
|||||||||||
| 攷證 | 家有者 [イヘニアレハ]。笥爾盛飯乎 [ケニモルイヒヲ]。草枕 [クサマクラ]。旅爾之有者 [タヒニシアレハ]。椎之葉爾盛 [シヒノハニモル]。 笥爾盛飯乎 [ケニモルイヒヲ]。 笥は、和名抄木器類に、禮記注云笥〔思史反和名介〕盛v食器也云々とありて、玉篇に、笥盛v飯方器也云々、また書紀武烈紀に、□[木+(施の旁の也が巴)]摩該儞播伊比佐倍母理 [タマケニハイヒサヘモリ] 云々とある、たまけも、玉笥也。延喜四時祭式に、供御飯笥一合云々。齋宮式に、飯笥、藺笥各五合云々とあるにても、笥は飯を盛器なるをしるべし。 |
|||||||||||
| 古義 | 家有者 [イヘニアレバ]。笥爾盛飯乎 [ケニモルイヒヲ]。草枕 [クサマクラ]。旅爾之有者 [タビニシアレバ]。椎之葉爾盛 [シヒノハニモル。 笥爾盛飯乎 [ケニモルイヒヲ] とは、飯笥 [イヒケ] に盛リて食ふ飯をといふなり、和名抄に、禮記註ニ云、笥ハ盛v飯ヲ器也、和名計 [ケ]、字鏡に、箪ハ笥也、太加介 [タカケ]、武烈天皇ノ紀影姫ノ歌に、多麻該儞播伊比左倍母理 [タマケニハイヒサヘモリ]、(玉笥には飯さへ盛なり、玉は例の美稱なり、岡部氏が、丸笥なりと云るは、いみじき非なり、)神祇式鎭魂祭ノ條に、供御飯笥 [イヒケ].一合云々、右其ノ日、御巫於2宮齋院ニ1舂v稻ヲ云々、即盛2藺笥ニ1、齋宮式に、年料供物云々、飯笥藺笥各五合云云、造傭雜物云々、銀飯笥一合云々、板飯笥二合云々、内匠寮式に、銀器御飯笥 [オモノケ] 一合、(徑六寸深一寸七分、)夫木抄に、四方の海を一の笥 [ケ] して汲干む時にや我カ有なりも出べきなど見ゆ、土佐ノ國朝峯ノ神社にて、酒をのむ器を、けさかづきといへり、笥盃 [ケサカヅキ] なり、其ノ形今のもつさうの如くにして圓 [マロ] し、 |
|||||||||||
| 全釈 | 家有者 [イヘニアレバ] 笥爾盛飯乎 [ケニモルイヒヲ] 草枕 [クサマクラ] 旅爾之有者 [タビニシアレバ] 椎之葉爾盛 [シヒノハニモル 笥爾盛飯乎 [ケニモルイヒヲ] ―― 笥は器であるが、狹義では食器をいふ。和名抄に「禮記注云笥、『思吏反和名介』盛v食器也」とある。 |
|||||||||||
| 全註釈 | 家有者 [イヘニアレバ] 笥尓盛飯乎 [ケニモルイヒヲ] 草枕 [クサマクラ] 旅尓之有者 [タビニシアレバ] 椎之葉尓盛 [シヒノ] [ハニモル] 笥尓盛飯乎 ケニモルイヒヲ。笥は、玉篇に「笥、盛v飯方器也」とあり、倭名類聚鈔に、「禮記注云笥『思吏反和名介』盛v食器也」とある。笥に盛るを習とする飯をの意。當時の飯は、米を甑 [こしき] に入れて蒸したものである。 |
|||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】「笥に盛る飯」 笥は説文 (五) に「飯及衣之器也」とあり、玉篇には「盛飯方器也」とある。倭名抄 (四) に「禮記注云、笥 思史反、介 盛食器也」とある。「櫛笥 (クシゲ)」 (93)、「麻笥」 (13・3243) の語もあつて、説文に云つてゐるやうに、もとは食器に限らなかつたが、単に笥といへば食器特に飯を盛る器をさす事になつたものと思はれる。曲禮 (上) 「簟笥」の注に「簟圓笥方皆竹器」とあるが、我が国の笥(け)は質や形がさう限定されてゐなかつたものと思はれる。「藺笥(ヰケ)」 (四時祭式、齋宮式、その他)、「板笥(イタケ)」 (齋宮式、その他)、「銀飯笥(シロガネノイヒケ)」 (齋宮式、その他)、「圓笥(マロケ)」 (主計式) などの語が見える。「柁摩該你播(タマケニハ) 伊比左倍母理 (イヒサヘモリ)」 (武烈紀) は「玉笥には飯さへ盛り」でその玉は美稱である。飯は甑(こしき)で蒸したものである。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】「笥に盛る飯を」 笥は食器。万象名義 (巻四之二) に、「思史反盛食竹器」とあり、和名抄の木器の部にも「和名計、盛食器也」とあるように、多く竹製あるいは木製であったらしい。ただし内匠寮式銀器に「御飯笥一合」とも見え、銀製の物も使われていたことが分かる。武烈紀の影媛の歌に「拖摩該(タマケ)には飯さへ盛り」と歌われているのが今日の飯茶碗のようなものであったかどうか問題だが、この142歌の場合は一人分の飯を盛る茶碗の類と推測される (関根真隆『奈良朝食生活の研究』)。家では立派な笥に盛って食べる飯を、の意。 |
|||||||||||
| 新全集 | 【頭注】 「ケ」はすべて物を入れる容器をいう。ここは飯を盛る「飯笥(いいけ)」。「モヒ」が比較的に深く飲料水など液体をたたえるためのものであるのに対してこの方が浅かった。やがてそれに盛る食事を「ケ」、水を「モヒ」と称するに至る。 |
|||||||||||
| 新大系 | 【脚注】 名義抄に、「簟」の字を「イヒモルケ」と訓む。「イヒモルケ」が無いので、椎の葉を重ねて食器 (「け」) に代用したのである。 |
|||||||||||
| 「椎之葉尓盛 (しひのはにもる)」考 |
童蒙抄 | 『椎之葉爾盛 (しひのはにもる)』 上古は飲食物を旅行などにては、柏椎の葉にもりて食したることもあるべし。さまではあるまじけれど、此歌はたゞ旅のいぶせく、ものわびしき躰をよみ給ふ也。あながちそれと決したる事にはあらねど、とらはれ人となりての旅行なれば、いぶせさいはん方なき躰をよみたまへる也 |
||||||||||
| 万葉考 | 旅爾之有者 [タビニシアレバ]、椎之葉爾盛 [シヒノハニモル]、 今も檜の葉を折敷て、強飯を盛ことあるが如く、旅の行方 [ユクヘ] にては、そこに有あふ椎の小枝を折敷て盛つらん、椎は葉のこまかに繁くて平らかなれば、かりそめに物を盛べきものなり、さて有がまゝによみ給へれば、今唱ふるにすら思ひはかられて哀なり、 |
|||||||||||
| 攷證 | 椎之葉爾盛 [シヒノハニモル]。 椎は、新撰字鏡に、奈良乃木とよめり。されど、書紀神武紀に、椎根津彦 [シヒネツヒコ]〔椎此云辭□[田+比]とありて、和名抄菓類に、本草云椎子〔直追反和名之比〕云々とあれば、しひとよむべし。考云、今も、檜の、葉を折敷て、強飯を盛事あるがごとく、旅の行方にては、そこに有あふ椎の小枝を打敷て、盛つらん。椎は、葉のこまかに、しごく平らかなれば、かりそめに物を盛べきもの也。さてあるがまゝに、よみ給へれば、今唱ふるにすら、思ひはかられてあはれ也云々。 |
|||||||||||
| 古義 | 旅爾之有者 [タビニシアレバ]は、一ノ卷軍ノ王ノ歌に、草枕客爾之有者 [クサマクラタビニシアレバ] とあるに同じ、之 [シ] はその一すぢをとりたてゝ、おもく思はすせ處におく助辭なること、彼處に云るが如し、 椎之葉爾盛 [シヒノハニモル] は、旅にしあれば、其ノ地にありあふ椎ノ枝を折敷て、飯を盛しよしなり、椎は葉のこまかに繁くて平らかなれば、かりそめに飯など盛べきものなり、今も檜ノ葉を折敷て、強飯を盛事あるを思ふべし、さて尋常の旅ならば、皇子の御身として、さまでの事はあるべからぬを、此は謀反の事によりて捕はれて、物部の中に打圍まれておはする道なれば、萬ツ引かへたる樣、此ノ御一句にこもれり、 |
|||||||||||
| 全釈 | 椎之葉爾盛 [シヒノハニモル] ―― 椎の小枝を折つて飯を盛るのである。新考に椎の葉は細かにてふさはしからずと云つて、椎は楢とよむのだらうとあるが、一枚の葉に盛るのではなく、枝の上に載せるのだから、椎の葉でよいのである。 | |||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】 「椎」は旧訓「シヒ」とあり、神武紀に椎根津彦の注に「椎此云二辭□[毘の「田」が左の偏](シヒ)一」(即位前紀甲寅年) とあり、本草和名 (下) にも和名抄 (九) にも「椎子」に「之比」とあり、疑問はないやうであるが、椎の葉は小さく、その上に飯を盛る事に疑がもたれるので、講義には新撰字鏡 (七) に「椎」に「奈良の木也」とあり、又元明天皇陵を続紀に「椎山陵」 (養老五年十二月) とあり、延喜式には「奈保山東陵」とあつて「猶」の誤字とする説もあるが、その所在は奈良山であるから「椎」を「ナラ」と訓んだと思われ、今も「ナラ」と訓まれないのではなく、「楢の葉」ならば大きく、今も山人の握飯を包むに用ゐられるから似合はしい、といふ説を述べられた上で、「されど、今この歌は十月十一日の比によまれしなれば、楢の葉は直ちに得らるべくもあらねば、なほ常緑木の椎の方によるべくや。」とある。椎の葉の小さい事は認めながら既に万葉考に「今も檜の葉を折敷て、強飯を盛ことあるが如く、旅の行方 [ユクヘ] にては、そこに有あふ椎の小枝を折敷て盛つらん、椎は葉のこまかに繁くて平らかなれば、かりそめに物を盛べきもの也」とある。檜葉を用ゐる事は今も伊勢神宮で行はれてゐる事であり、神楽殿の御殿は今日ではお洗米に代へられたが、私が少年の頃にはそれらも強飯を円錐形に固めて檜葉の上に載せられたものであつた。「握飯(にぎりいひ)」の枕詞は常陸風土記にも見えて、旗に握飯を用ゐる事昔も今もかはらぬ事と見てよく、従つて葉は小さくとも枝ながら敷並べれば不都合はなく、ただ檜葉の方がより適当してゐる事は認められるが、現にありあはせたものをまにあはせに用ゐたと見ればよいであらう。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】 「椎」は神武紀に「椎此をば辭□[毘の「田」が左の偏](シヒ)と云ふ」の注があり、和名抄にも「直追反和名之比」と見える。新撰字鏡には「奈良乃木也」とあって、ナラの訓もあったことが知られるが、ここは書紀の注に従って「シヒ」と訓むべきだろう。「シイ」という呼び名は、普通スダジイ (一名ナガジイ) とツブラジイとを合わせて言ったものらしい (松田修『万葉植物新考』)。スダジイの方が実が長く、葉が広く、葉裏は淡褐色を帯びている。山田講義に、「椎は葉大さらぬものなれば、この上に飯を盛らむは如何にすべき事にか」と疑い、万葉考の「今も檜の葉を折敷て、強飯を盛ことあるが如く、旅の行方 [ユクヘ] にては、そこに有あふ椎の小枝を折敷て盛つらん、椎は葉のこまかに繁くて平らかなれば、かりそめに物を盛べきもの也」とあるのを引きながら、「椎」は「ナラ」とも訓みうるが、この歌は十月十一日のころによまれたものなので、楢の葉は直ちに得られるはずもなく、やはり常緑木の椎の方であろうと言っている。これはていねいな考察である。澤瀉注釈には、伊勢神宮神楽殿の御饌に強飯を固めて檜の葉に盛ったことを紹介し、葉は小さくとも枝ながら敷き並べたのであろうと推測する。なお、この飯を皇子の食事のためのものと見るか、神饌用と見るかに関しても、説の分かれがある。その点については、〔考〕の条に述べる。 |
|||||||||||
| 「一首考」 | 童蒙抄 | 此標題とは不v合歌也。結松枝歌二首とありて、此歌は難2心得1。もしくは標題の松枝の下に、時の字を脱したる歟。椎の字松の字の誤り歟。椎の字松にても、むすぶといふには不v合とも、松なればまだ縁あるか。時の字の脱ならば、二首と標せるもかなひ侍らんか。歌の意はたゞ旅行のいぶせく、あさましきありさまをよみ拾ふて、あはれによくきこえたる御詠也 | ||||||||||
| 古義 | 御歌ノ意は常さへあるに、いみじき御大事を、おもほしめしたち給ふ事あらはれて、趣かせ給ふ御旅中の、いともわびしく堪がたきさまをのたまへるにて、かくれたるすぢなし、契冲もいひし如く、此ノ二首の御歌に、その時 [ヲリ] の御心たましひとなりてやどれるにや、いと身にしみてかなしきことかぎりなし、さてこの一首は、結2松枝ヲ1といふにはかなはねども、はじめの御歌につけて、同時の御作にもあれば、結2松枝ヲ1歌二首とはいへるなり、 | |||||||||||
| 全釈 | 〔評〕 旅寢となれば物憂きにとは、近代までの言葉であつた。文字通りに草枕旅であつたのだから、飯を椎の葉に盛つて食べたのに僞はない。ましてこれは、囚はれの御身としての旅であるから、いろいろ悲しい考がお湧きになつたであらう。物あはれな調子が、人を動かさずには置かない作である。 |
|||||||||||
| 全註釈 | 【評語】 單なる旅の歌であるが、縁によつて併わせ掲げたものと見える。不自由がちな旅の生活をよく敍している。草枕の枕詞も非常によく利いている。シイの葉に盛るというのは、印象的な句であるが、ここでは路傍の樹葉を取つて飯を盛つたのであつて、實際のシイの葉であつてもなくてもどうでもよい。それを具體的にシイの葉と指摘したのが利いたのである。 |
|||||||||||
| 評釈 | 〔評〕 「旅にしあれば」とあるが、固より當時の旅、特に貴人の旅がすべてかうであつたわけではない。かかる特殊な時であつたからなのであらう。しかし、それについては何事も述べず、ただ單純に椎の葉に盛るといふに過ぎない。詠歎的な語は助詞だにもない。しかも哀感は身に染みて感ぜられる。味はへば味はふほど切實な作である。 |
|||||||||||
| 注釈 | 【考】 この歌は六帖 (四「旅」)に、 ありてみるものにしあらねど草枕旅にし聞けばかなしかりけり の歌の次に載せられて作者の名が無く、前の歌に「ありまのわうじ」とあるのは標注に注意してゐるやうに作者の記入を前後したものと思はれる。[古今和歌六帖、下写真] 勅撰集には採られてゐないが、俊成の「古来風体抄」には前の作と二首並べあげられて、[上項「笥尓盛飯乎 (拾穂抄)写真」参照] 飯などいふ事は、此ごろの人もうちうちにはしりたれど、歌などにはよむべくもあらねど、昔の人は心のけはれなくてかくよみけるなるべし。此歌、うたざまはいみじくをかしき歌也。 と注意してをり、「旅にしあれば椎の葉に」の語は近世の浄瑠璃、俳文その他の雑文に引用せられて、人口に膾炙せられるところとなつた。東京九段上の割烹阿家の女主人にして歌びとの高橋ひで子氏は大和宇智郡の出身であるが、郷里にあつた頃、米の粉を水にねつたものを、椎の葉にのせて、あちこちの道祖信に供へた事を覚えてをり、萬葉の「椎の葉に盛る」もさうした神へのお供と見られないかと述べられた事があつた。「家にあれば笥に盛る飯」とだけあるを直ちに神饌と見る事は少し無理であり、みづからの食事としてこそ「旅にしあれば」のあはれは切実に感じられよう。しかし、宇智は紀伊と境を接するところであり、その地に残るこの風習は右に述べた檜葉と共に参考にすべきものとして附記する事とした。
|
|||||||||||
| 全注 | 【考】「神饌説について」 この歌、普通は紀の湯へ護送される旅中のわびしい食事を詠むものと解されている。代匠記に「サラヌタニ旅ハ侘シキヲ、殊ニ謀反ノ事ニヨリテ捕ハレテ、物部ノ中ニ打囲マレテオハシマス道ナレハ、萬引カヘタル様笥ニモル飯ヲ椎ノ葉ニ盛トヨマセ給ヘルニコモレリ。」と言い、講義「事なくて家に在る時には然るべき飯笥に盛りて食すべき飯をば、今は旅にあれば、椎の葉に盛りて食するが悲しく物あはれなる事よとなり」と言う。ただし戦後になって、皇子の食事でなく、岩代の神への供え物として椎の葉に盛ったと見る神饌説が一部に唱えられた。そのもっとも早いものは高崎正秀「萬葉集の謎解き」 (文芸春秋昭和三十一年五月) である。その中に奈良では今でも小さな椎の葉に小量ずつお供物を盛り分けて神仏を巡拝してまわる風習のあることが紹介され、「家にをれば、立派なちゃんとした御器に盛つて、お供へするのだが、今は旅先のこと故、椎の葉に盛つて差上げます。どうぞ神様よ、御納受下さいませ」と「紀州磐代の道祖神の神前に供へて」旅路の安全と身の行く末を祈願した歌として詠まれるべきことが説かれている。奈良における習俗は歌人の高橋英子氏の語ったところと言う。この高崎説は、犬養孝『万葉の旅』には神饌を葉に盛る習俗として、岩代の地で「ヒトゲ」という米粉のだんごを二つ、かしの葉に重ねて氏神に捧げる例が紹介されている。 神饌説は、珍しい習俗と関連しているし、また、有間皇子の結び松の歌 (141歌) が岩代の神に対する祈りの歌ということもあって、たしかに興味深く聞かれるし、誰にでも理解され易いように思われる。高校の教科書などにも採用されている歌なので、教室で神饌説を通して皇子歌にはじめて接したという若い人達も少しずつ数を増やしているようだ。 しかし、高崎説は、正しいのであろうか。皇子歌の「笥に盛る飯」は、神に供える飯なのであろうか。 この「142歌」の形式は、「家にあれば・・・(A)・・・旅にしあれば・・・(B)・・・」であり、「AとB」との落差は大きさによって、旅先での悲嘆が強調されるところに特徴がある。わたしに疑問に思われるのは、道祖神に手向けをしつつ、それと対比的に「家にあれば・・・」と歌ったとする、神饌説におけるその発想自体と言ったら良かろうか。 高崎説によれば、この歌は家で神に供え物をする場合 (A) と、旅先で道祖神に手向けをする場合 (B) とを比較していることになるが、道祖神への手向けが、故郷の家における氏神への神饌の御器を想起させ、しかも習俗として特定された木の葉に盛っているにもかかわらず、その粗末さが嘆かれるというのは、この作品の内部からではなく、むしろ外側から強いて構えた発想で、リアリティを欠いたもののように思われる。端的に言って「葉に盛る」習俗が岩代なら岩代に固有のものであればあるだけ、(A)と(B)とを比較し対照して歌うこと自体その抒情的必然性を乏しくするだろう。 この歌は神饌を歌ったわけではなく、捕られて紀伊湯へ護送される途中の食事の有様を、家に居ての食事と対比しつつ淡々と詠じたものと考えられる。異常な迫力は、死を直視せねばならなかった皇子の立場の、おのずからなるあらわれであろう。茂吉秀歌に、 羇旅のの不自由を歌つてゐるやうな内容でありながら、さういふものと違つて感ぜねばならぬものを此歌は持つてゐるのはどうしてか。これは史実を願慮するからといふのみではなく、史実を念頭から去つても同じことである。これは皇子が、生死の問題に直面しつつ経験せられた現実を直にあらはしてゐるのが、やがて普通の羇旅とは違つたこととなつたのである。 とあるのは、彼の「写生」説に引きつけ過ぎているきらいはあるが、迫力の生ずる所以を説いたものである。 |
|||||||||||
| 巻二 143 | 「題詞」訓・考 | 童蒙抄 | 長忌寸意吉麿見結松哀咽歌二首 [ながのいみきおきまろ、むすびまつを見てかなしみむせぶうたふたくさ] 長忌寸意吉麿 系傳不v知。奧にいたりて與麻呂ともしるせり。標題に後崗本宮御宇としるしたれど、前二首計にて此歌已下は後の御代の歌なり。しかれども結松につきてよめる故、此次にのせたると見えたり |
|||||||||
| 万葉考 | 長忌寸意吉麻呂 [ナガノイミキオキマロ]、見テ2結松ヲ1哀咽 [カナシミテ] 作歌、 意吉麻呂は、文武天皇の御時の人にて、いと後の歌なれど、事の次でもてこゝには載しなり、下の人まろが死時の歌になぞらへてよめる丹治ノ眞人が歌を、其次に載たる類なり、眞人は人まろと同時なるやしらねど、擬歌などをならべ載たる例に取なり、 意寸麻呂の時代の事、此挽歌の條の別記をあはせ見るべし、 |
|||||||||||
| 略解 | 長忌寸意吉麻呂 [ナガノイミキオキマロ]見2結松1哀咽歌二首 今本二の字を脱せり。意吉麻呂は文武天皇の御時の人にて、後なれど、事の次でを以てここに載せたり。歌の上作の字有るべし。 |
|||||||||||
| 攷證 | 長忌寸意吉 [オキ] 麿。見2結松1哀咽歌。二首。 長忌寸意吉 [オキ] 麿。父祖官位、不v可v考。上〔攷證一下四十四丁〕に出たり。考云、意吉麿は、文武天皇の御時の人にて、いと後の歌なれど、事の次で、こゝには載し也。下の、人まろが死時の歌になぞらへてよめる、丹治眞人が歌を、其次に載たる類也 眞人は、人まろと同時なるやしらねど、擬歌などをならべ載たる例にとる也云々といはれつるがごとし。 哀咽。 哀は、かなしむ意、咽は、梁武帝七夕詩に怨咽雙念斷、悽悼兩情懸云々。陸雲書に、重惟痛恨言増哀咽云々。庾信麥積崕佛龕銘に、水聲幽咽、山勢崆□[山+囘]云々などあると同じくむせぶ意にて、哀 [カナシミ] にたへずして、むせぶをいふ也。考に、この二字をかなしみてとよまれしも當れり。 |
|||||||||||
| 古義 | 長忌寸意吉麻呂 [ナガノイミキオキマロガ]。見 [ミテ] 2結松 [ムスビマツヲ] 1哀咽 (作) 歌二首 [カナシミヨメルウタフタツ]。 意吉麻呂 [オキマロ] は、傳詳 [サダカ] ならず、一ノ卷に奧麻呂とあると同人なり、さてこは、文武天皇の御時の人にて、いと後の歌なれど、事の次もて、こゝには載しなり、さる例集中にいと多し、考へわたすべし、 作ノ字、舊本には脱せり、今補二ノ字、舊本には脱せり、今は拾穗本によりつ、 〔柿本ノ朝臣人麻呂ノ歌集ニ云。大寶元年辛丑。幸2于紀伊ノ國ニ1時。見2結松ヲ1作歌一首。〕 柿本云々の十字、舊本にはなし、元暦本官本古寫本等には、一首の下に、柿本朝臣人麻呂ノ歌集中世也と註せり、(但し拾穗本に、柿本朝臣人麻呂とのみ有はわろし、) 寶ノ字、舊本實と作るは、誤なること著し、今は古寫本人麻呂勘文等に据つ、 幸2于紀伊ノ國1 (于字、拾穗本にはなし、) は、續紀に、大寶元年九月丁亥、天皇幸2紀伊ノ國ニ1云々、とある度のことなるべし、なほ一ノ卷にも云り、 作ノ字、舊本に無は脱たるなり、今は官本に從つ、
|
|||||||||||
| 全釈 | 長忌寸意吉麿 [ナガノイミキノオキマロ]見テ2結松ヲ1哀咽セル歌二首 意吉麻呂は卷一の五七に奧麻呂とある人で、文武天皇の時の人であるが、結松に關した歌であるから、ここに載せたのである。 |
|||||||||||
| 全註釈 | 長忌寸意吉麻呂、見2結松1哀咽歌二首 長 [なが] の忌寸意吉麻呂 いみきおきまろ] の、結び松を見て哀咽 [あいえつ] せる歌二首 【釋】 長忌寸意吉麻呂 ナガノイミキオキマロ。既出 (卷一、五七)。卷の一には、名を奧麻呂としているが同人である。卷の一には大寶二年の歌があり、文武天皇時代の人である。即興の作に長じ、特殊の題材を歌にする手腕をもつている。この歌は何時の作であるか不明であるが、大寶元年の紀伊の國の行幸の時と假定すれば、有間の皇子の死後、四十三年後の作である。 見結松 ムスビマツヲミテ。當時、有間の皇子の結んだ松樹が現存していたものと見える。多分枝が結ばれたままに成長し、これは有間の皇子が結んだのだという傳説を生じたのであろう。事實としては、有間の皇子は、歸途此處を通過され、藤白の坂で殺されたのだから、多分結びを解いて無事を祝われたであろう。 哀咽歌 アイエツセルウタ。咽は、咽喉がつまつて聲の出ない狀をいう動詞。訓讀では、カナシミムセブウタと讀む。 |
|||||||||||
| 評釈 | 長忌寸意吉麻呂 [ながのいみきおきまろ]、結松を見て、哀咽 [かなし] める歌二首 〔題〕 長忌寸意青麻呂は、「五七」の奧麻呂と同人であらう。奥麿は有馬皇子より約五十年後の文武天皇の朝の人であるが、皇子の結ばれたといふ松を見て、往時を偲んで作つた歌であるから、便宜上、皇子の歌につづけて配列したものと思はれる。 |
|||||||||||
| 注釈 | 長忌寸意吉麻呂見2結松1哀咽歌二首 「長忌寸意吉麻呂」は既出 (1・57)。大宝元年に持統、文武両帝紀伊へ幸せられた折の作。巻一 (54-56) にはその名が見えないが、巻九に載せられたうち (1673) には左注にその名が見えるので、その折に供奉してこの作もなされたものかと思はれる。それだと斉明四年は四十三年前といふ事になる。有間皇子の結ばれた-或いはさう伝へる-松がそのままに残つてゐて、それを見て詠んだものである。 「哀咽」は陸雲與載季甫書に「重惟痛恨言增哀咽」などある語を用ゐたもので「アイエツセル」と音読したものであらう。 |
|||||||||||
| 全注 | 長忌寸意吉麻呂、結び松を見て哀(かな)しび咽(むせ)ぶ歌二首 長忌寸意吉麻呂 伝未詳。人麻呂と同時代から、やや後の時代にかけて活動した歌人で、難波・三河および紀伊行幸の旅の歌の他、巻十六に「詠物歌八首」も見え、人々のもとめに応じて即興的に作歌した、特異な才能が偲ばれる。 結び松を見て これは有間皇子歌に関わりのある松だろう。巻九に、「大宝元年辛丑冬十月、太上天皇大幸紀伊国時歌」という題詞で十三首の歌が載せられており、その中の一首 (1673) に、「右の一首は、山上憶良の類聚歌林に曰はく、長忌寸意吉麻呂の詔に応へてこの歌を作るといへり」の左注があり、意吉麻呂は大宝元年紀伊行幸に従駕しているので、その折、岩代の結び松を見ての作とも考えられる。 哀咽 哀しみのために咽喉がつまるの意。巻三の大伴旅人の歌に、「情咽都追涕之流」 (453) と見え、咽をムスと読むことがわかる。 |
|||||||||||
| 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版] (1980年9月)も併記する 【題詞】 長忌寸意吉麿見結松哀咽歌 首 〔本文〕 松。神田本、「□[下写真参照]」。右ニ別筆「松」アリ。 歌。神田本、「謌」。 元暦校本・金澤本・類聚古集・古葉略類聚鈔・神田本・西本願寺本・細井本・温故堂本・大矢本・京都大学本・無訓本・附訓本、コノ下ノ空白ニ「二」アリ。 〔訓〕 長忌寸意吉麿。元暦校本、右ニ朱「ナカノイミキノオキヨマロ」アリ。 温故堂本、「長」ノ右下ニ「ノ」、「意吉」ノ右ニ「ヲキ」アリ。 咽。京都大学本、右下ニ赭「スル」アリ。 〔諸説〕 哀咽歌。万葉考、「哀咽」ヲ「カナシミテ」ト訓ジ「歌」ノ上「作」ヲ作ル。略解、「歌」ノ下「ニ」脱トス。 【頭書】 古葉略類聚鈔、主文ヲ訓交リニ書ケリ。 【本文】 磐代乃 岸之松枝 将結 人者反而 復将見鴨 (イハシロノ キシノマツカエ ムスヒケム ヒトハカヘリテ マタミケムカモ) 〔本文〕 磐代乃。古葉略類聚鈔、訓ヲ主文トセリ。 乃。神田本、ナシ。 岸。元暦校本・金澤本・古葉略類聚鈔、「崖」。 之松枝 将結 人者反而 復将見鴨。古葉略類聚鈔、以上訓ヲ主文トセリ。 〔訓〕 キシ。古葉略類聚鈔、ナシ。 マツカエ。元暦校本・金澤本・類聚古集、「まつえを」。古葉略類聚鈔、「マツカエヲ」。神田本、「マツエヲ」。漢字ノ左ニ朱「マツカエ」アリ。細井本、「マツカヘ」。 温故堂本、「マツカヱ」。京都大学本、漢字ノ左ニ赭「マツエヲ」アリ。 ムスヒケム。元暦校本・金澤本、「むすひたる」。元暦校本、「たる」ノ右ニ赭「ケム」アリ。古葉略類聚鈔、「ムスヒタル」。 神田本、「ムスヒケン」。漢字ノ左ニ「ムスヒタルイ」 マタミケムカモ。元暦校本、「た」ノ右下ニ赭「モ」アリ。神田本、「マタモミムカモ」。漢字ノ左ニ「マタミケムカモイ」アリ。
[校本萬葉集新増補版] 【題詞】 長忌寸意吉麿見結松哀咽歌 首 〔本文〕 歌。神宮文庫本、コノ下ノ空白ニ「二」アリ。 【頭書】 六帖、第五「岩代の岸の松かえ結ひけむ人は返りて又もみむかも」 夫木、第廿六「岩代のきしの松かえむすひたり人はかへりて又みけむかも」 名寄、第卅三「いはしろのきしの松か枝むすひけむ人はかへりてまた見けむかも」 【本文】磐代乃 岸之松枝 将結 人者反而 復将見鴨 (イハシロノ キシノマツカエ ムスヒケム ヒトハカヘリテ マタミケムカモ) 〔本文〕 乃。大矢本・京都大学本、「之」。
|
||||||||||
| 「崖(きし)」訓・考 | 童蒙抄 | 磐代乃岸之松枝將結人者反而復將見鴨 [いはしろの、きしのまつがえ、むすびけん、ひとはかへりて、またみけんかも] 岸之松枝 有馬皇子の御歌には、濱松がえとあり。此處にはきしとあり。海邊の惣体を云たるものなり。次の歌には野中にともあり。これ岩代の濱の邊の惣てを云たる也 |
||||||||||
| 万葉考 | 岸之松枝 [キシノマツガエ]、〔濱とも岸とも野ともよめり、濱岸のべの野に立たる松としらる、〕 | |||||||||||
| 攷證 | 磐代乃 [イハシロノ]。岸之松枝 [キシノマツカエ]。 まへの御歌には、濱松之枝といひ、こゝには岸といひ、次のには、野中に立るといへり。この松は、野につゞきたる濱岸にありしなるべし。 |
|||||||||||
| 全釈 | 岸之松枝 [キシノマヅガエ] ―― の字、元暦校本その他に崖に作つてゐる。いづれでもよからう。 | |||||||||||
| 全註釈 | 崖之松枝 キシノマツガエ。 崖は、諸本に岸に作つている。崖は、元暦校本等による。崖は高地の端で切り取つたような地形をいう。肥前國風土記の古寫本等にこの字を岸の意味に用いている。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】 原文、西本願寺本には「岸之松枝」とあるが、元暦校本・金澤本・古葉略類聚鈔に「崖」としてゐる。和名抄に「崖岸、水辺曰涯、岐之、下同、涯陗而高曰岸」とあり、「キシ」と訓むことを知るが、万象名義には「崖」を「牛佳反高邊」 (巻第六之一)、「邊」を「補賢反近・垂・厓・方・偏・倚」 (巻第三之一) とする。「厓」は「五佳反水邊・方」 (巻第六之一) であり、水辺のきりたったところを意味する文字。邦語の「キシ」は、海や川の岸にも、がけにも用いる。 |
|||||||||||
| 新全集 | 【頭注】 崖の松が枝-今も岩代の有間皇子結び松の記念碑がある一帯は、海食崖をなしている。 |
|||||||||||
| 「一首考」 | 拾穂抄 | いはしろのきしの松か枝むすひけんひとはかへりてまた見けんかも 磐代乃岸之松枝將結人者反而復將見鴨 いはしろのきしの松か 彼真幸あらはまた歸りこんとよめるをうけて其皇子は又歸て此松を見しや否 [イナヤ] と也 【上、「題詞訓・考『古義』」参照】 |
||||||||||
| 代匠記 | 磐代乃岸之松枝將結人者反而復將見鴨 [イハシロノキシノマツカエムスヒケムヒトハカヘリテマタミケムカモ] 又見給はぬ事は知ながらかやうによむ事歌の習なり、たゞ又も見給はずといはんより悲しく聞ゆるなり、 |
|||||||||||
| 童蒙抄 | 磐代乃岸之松枝將結人者反而復將見鴨 いはしろの、きしのまつがえ、むすびけん、ひとはかへりて、またみけんかも 將結人者 皇子をさして云たる也。み命さきくましまさば又かへりみんと、誓ひ給ひて結べる松が枝は今猶存せるが、そのむすび給ひし人は、返りてみたまひしや、見もしたまはでくびれさせられたる事の、いたましきよとかなしみたる歌也。歌の意別の義なくきこえたる通也。 |
|||||||||||
| 攷證 | 磐代乃 [イハシロノ]。岸之松枝 [キシノマツカエ]。將結 [ムスヒケム]。人者反而 [ヒトハカヘリテ]。復將見鴨 [マタミケムカモ]。 復將見鴨 [マタミケムカモ]。 略解に、皇子の御魂の、結枝を、又見給ひけんかといふ也云々といへるは、たがへり。又みけんかもの、かもは、疑ひの、かの、下へ、もを添たるにて、本集此卷〔十九丁〕に、吾袂振乎妹見監鴨 [ワカソテフルヲイモミケムカモ] 云々。八〔五十五丁〕に、君之許遣者與曾倍弖牟可聞 [キミガリヤラハヨソヘテムカモ] 云々。十五〔二十二丁〕に、安伎波疑須々伎知里爾家武可聞 [アキハキスヽキチリニケムカモ] 云々などある、かもと同じく、こゝの意は、磐代の岸の松が枝を、結びけん君は、又かへりきて、二たびこの結びけん松を見けんか、いかにぞ。さる事もなく、やみ給ひしぞあはれなると、意をふくめたる也。 |
|||||||||||
| 古義 | 磐代乃 [イハシロノ]。岸之松枝 [キシノマツガエ]。將結 [ムスビケム]。人者反而 [ヒトハカヘリテ]。復將見鴨 [マタミケムカモ]。 歌ノ意は、皇子はじめこの松カ枝を結びつゝ、眞幸くあらばと契り給ひしを、又かへり見給ひけむか、とうたがひて、さていかさまにも、その皇子は、その時藤代にて、御命うしなはれ給ひしかば、ふたゝび反リ見し賜はずなりにけむを、その松のみ、今に枝の結ばれながら、その時の如くて有を見るがかなしき事となり、(略解に皇子の御魂の結ヒ松を又見給ひけむか、といふなりと云るはいみじき非なり、) |
|||||||||||
| 全釈 | 磐代の 岸の松が枝 結びけむ 人はかへりて また見けむかも 磐代乃 [イハシロノ] 岸之松枝 [キシノマツガエ] 將結 [ムスビケム] 人者反而 [ヒトハカヘリテ] 復將見鴨 [マタミケムカモ] 〔評〕 有間皇子が再び歸つて、結松を見られなかつたことは、承知してゐるのだが、復將見鴨 [マタミケムカモ] と疑ふやうに言つたのである。其處に餘情が籠つてゐる。略解に「皇子の御魂の、結枝を又見給ひけむかといふ也」とあるは、下の鳥翔成の歌から思ひ付いたのであらうが、非常な誤解である。 |
|||||||||||
| 全註釈 | 磐代の 崖の松が枝、結びけむ 人は還りて また見けむかも。 磐代乃 [イハシロノ] 崖之松枝 [キシノマツガエ] 將v結 [ムスビケム] 人者反而 [ヒトハカヘリテ] 復將v見鴨 [マタミケムカモ] 【評語】 この歌は、はたして結び松に驗あつて、有間の皇子がまた見たであろうかどうかということを、疑つている語調であるが、裏面には、二度と見ることを得なかつたことを思つてこれを悼んでいるものである。それを疑問の語であらわしたところに、無限の哀愁が生ずる。 |
|||||||||||
| 評釈 | 磐代 [いはしろ] の崖 [きし] の松が枝 [え] 結びけむ人はかへりて復 [また] 見けむかも 〔評〕 皇子が松を結んで祈られた甲斐はあつたかどうかと歌では疑つてゐるのであるが、奥麿はもとより皇子の最期については知つてゐたのである。それをかく「見けむかも」といつたところに哀愁がある。「けむ」を重ねてゐるのもよい。皇子の御作に比べては、動機、環境、すべて比較にならぬし、作品の價値も比較にならないが、これも惡い歌ではない。 |
|||||||||||
| 全注 | 【考】 題詞の所で述べたように、この作が大宝元年紀伊行幸時のものとすると、有間皇子の事件から四十三年後のこととなる。現代にたとえれば、ちょうど大戦の前を回想するほどの時の経過が考えられるが、おそらく意吉麻呂にとっては、昨日のことのように偲ばれたのであろう。結句の「マタミケムカモ」は、単に結び松を見た見ないにこだわっているのではなく、恙なくあったかどうかを歌っているわけで、作者が事件の顛末を承知しながら歌っているところに、皇子の死に寄せる同情の深さが感ぜられる。 なお、この作以後、「146歌」の「結び松を見る歌一首」まで、斉明朝の歌ではないが、関連する作として、有間皇子歌のあとに配列されたものと思われる。 |
|||||||||||
| 新大系 | 【脚注】 四十数年後、大宝元年(701)十月、持統・文武両帝の紀伊行幸に従い、この地を過ぎた作者の感慨である。→「1673左注」。長忌寸意吉(奥)麻呂は既出 (57)。 有間皇子は、十一月十日、「紀の湯」を出て、帰路、藤白坂で殺害された。岩代を通って、結び松に再会していたであろう。題詞の「哀咽」は漢語。「166左注」にも所見。 |
|||||||||||
| 巻二 144 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 129歌より、岩波書店校本萬葉集[新増補版] (1980年9月)も併記する 【頭書】 古葉略類聚鈔、主文ヲ訓交リニ書ケリ。 和歌童蒙抄、第七「イハシロノ野中ニタテルムスヒマツココロモトケスムカシオモヘハ(中略) 万葉ニアリ。」 袖中抄、第十七「イハシロノ野中ニタテルムスヒマツココロモトケスムカシオモヘハ」 【本文】磐代乃 野中爾立有 結松 情毛不解 古所念 未詳 (イハシロノ ノナカニタテル ムスヒマツ ココロモトケス ムカシオモヘハ) 〔本文〕 磐代乃。古葉略類聚鈔、訓ヲ主文トセリ。 乃。元暦校本・金澤本・類聚古集・神田本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本、「之」。 爾立有 結松 情毛不解 古所念。古葉略類聚鈔、以上訓ヲ主文トセリ。 未詳。元暦校本・金澤本・類聚古集・古葉略類聚鈔・神田本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本、前ノ歌ノ下ニ小字ニ書ケリ。 京都大学本、赭ノ合点アリ。無訓本、大字トセリ。 〔訓〕 トケス。温故堂本、「トケヌ」。 ムカシオモヘハ。元暦校本、「おもへは」ノ右ニ朱「ヲソオモフ」アリ。古葉略類聚鈔・細井本・温故堂本、「ムカシヲモヘハ」。 〔諸説〕 ムカシオモヘハ。代匠記精撰本、「イニシヘオモホユ」。童蒙抄、「ムカシオモハル」。攷證、「ムカシオモホヘ」ヲ否トシ、「イニシヘオモホユ」トス。 未詳。代匠記精撰本、「衍」トス。
[校本萬葉集新増補版] 【頭書】 六帖、第五「岩代の野中にたてる結ひ松心もとけす昔をそおもふ」 夫木、第廿九「岩代の野中にたてるむすひ松心もとけすむかしおもへは」 名寄、第卅三「磐代乃 野中爾立有 結松 情毛不解 古所念 (イハシロノ ノナカニタテル ムスヒマツ ココロモトケス ムカシオモヘハ)」 拾遺、八五四・一二五六 【本文】磐代乃 野中爾立有 結松 情毛不解 古所念 (イハシロノ ノナカニタテル ムスヒマツ ココロモトケス ムカシオモヘハ) 未詳 〔本文〕 乃。神宮文庫本、「之」。 未詳。神宮文庫本、朱ノ合点アリ。
|
|||||||||
| 「一首訓考」 | 拾穂抄 | いはしろの野中にたてる結ひ松こゝろもとけすむかしおもへは 磐代之野中尓立有結松情毛不解古所念 いはしろの野中に 彼隠謀有し皇子を心もとけすと讀にや此哥人丸集にあるを拾遺集戀四に入心もとけすと難面き人をいふやうなれは戀部に入歟 |
||||||||||
| 代匠記 | 磐代乃野中爾立有結松情毛不解古所念 [イハシロノノナカニタテルムスヒマツコヽロモトケスムカシオモヘハ] 未詳 結松を承て心モトケズといへるは題の哀咽なり、ムカシオモヘバの點、字に叶はず、六帖にはむかしをぞ思ふとあり、今按、イニシヘオモホユと和すべし、人丸集と云物に入たるを見て拾遺には載られたるか、注の未詳こそ又何故にいへるにかと詳ならね、衍文にや、若下の大寶元年の歌に作者なければ、そこより此にまじはり來れるか、 |
|||||||||||
| 童蒙抄 | 磐代乃野中爾立有結松情毛不解古所念 童子問 歌の意は明かなるへし。第五句所念の二字をむかしおもへはとよむこといかゝ。念者とも有へきに、所念とありてもおもへはとよむへきや。 答 是はてにをはをあはせてしかよみたるなるへし。所念の二字は、おもほゆとかおもはるとか、しのはるとかにて有へし。 |
|||||||||||
| 略解 | 磐代乃。野中爾立有。結松。情毛不解。古所念。 いはしろの。のなかにたてる。むすびまつ。こころもとけず。いにしへおもほゆ。 結ぶと言ふより解けずと言へり。此松結ばれながら生ひ立ちて、此時迄も有りしなるべし。 未詳 此二字紛入りたりと見ゆ。 |
|||||||||||
| 古義 | 乃ノ字、拾穗本には之と作り、 舊本此處に、未詳ノ二字あり、今は拾穗本になきによりつ、 (現存六帖に岩代の野中の松を吾と見よつれなき色にむすぼほれつゝ、今の歌によれり、) |
|||||||||||
| 評釈 | 磐代の野中に立てる結 [むす] び松 情 [こころ] も解けず古 [いにしへ] 念ほゆ 未だ詳ならず 〔評〕 結び松をうけて、「心も解けず」と縁語のやうにいつたのは巧みであるが、それが却つて一首の味はひを失はせ、前の歌の素直なのに及ばない。卷十六に、意吉麿が諸種の物を詠じた歌が「三八二四」以下數首ある。この作者はかういふ著しい一面があつたのであらう。 未だ詳ならず 題詞によればこれも意吉麿の歌であるが、それを疑つたのであらうか。梨壺の五人の註などであららか。 |
|||||||||||
| 注釈 | 【訓釈】いまだ詳かならず この注は何の事をさしたのかわからない。次に述べるやうに拾遺集には恋の部に入り作者も人麻呂となつてゐるので、童蒙抄には後人が拾遺集を見てそれらの点に不審をもつて傍注したのであらうと云つてゐる。未詳の文字は集中に散在し、前(1・7)にも述べたやうに、後人が加へたものと思はれる。 【考】 この作、拾遺集には巻十四 (恋四) と第十九 (雑恋) とに題知らず、人麿として出てゐる。共に結句は「昔おもへな」とある。柿本集にも結句同様であり、それによつたものと思はれる。古今六帖 (五) には「昔を恋ふ」と題した最初にあげられ、作者は無く、結句「むかしぞ思ふ」とある。早く作者や縁起を失つて恋の歌として伝誦せられたものと思うはれ、さうした中から、 岩代の野中に立てる村すすき松ふく風にむすぼほれつつ(夫木抄、十一「薄」) 順徳院 の如き作もなされたのであらう。袖中抄 (十七) にはこの作をあげて縁起を語り、夫木抄 (廿九「松」) には作者を意吉丸としたが、両書とも結句はなほ「むかしおもへば」とあつて、「イニシヘオモホユ」の訓は代匠記に至つてはじめて改められたものである。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】未だ詳らかならず 「未詳」の二字、元暦校本・金澤本・類聚古集・古葉略類聚・紀州本・西本願寺本・温故堂本・大矢本・京都大学本の諸本の歌の下に小字で記されている。代匠記 (精撰本) に「注ノ未詳コソ又何故ニイヘルニカト詳ナラネ、衍文ニヤ」とも、「下ノ大宝元年ノ哥ニ作者ナケレハソコヨリ此ニマシハリ来レルカ」とも言うが、疑問である。この歌は拾遺集に人麻呂作として載っており、そのために、作者について不審を抱いた後人の記入した注かという童蒙抄説が有力。巻一の額田王歌「秋の野のみ草刈り葺き・・・」 (七) の題詞下に「未詳」とあるのも同種で、作者に関する不審を表わした注と思われる。 【考】縁語的な照応 窪田評釈に「『結び』と『解け』という語の照応をねらっているのは、(中略) この歌を低調なものとしている。こうした語そのものの興味は、口承文学にあっては、伝統的な、根深いものとなっていたが、すでに個人的作風に移ったこの歌にあっては、文芸性の末梢的なものにすぎなくなり、作風とは矛盾するものとなったのである。」と言う。〔注〕にも触れたように、解けずにある松の枝を見て「情けも解けず」と詠まれたのであり、その第三句から第四句にかけての縁語的なことばの照応が作品を底の浅いものに感じさせている。 |
|||||||||||
| 「野中尓立有 結松 (のなかにたてるむすびまつ)」考 |
注釈 | 【訓釈】 結び松の遺跡と云はれるあたりの海岸が崖になつてゐる事、前 (1・10) にも述べたが、その上は今は田畑もつづいてゐて、野といはれるにもふさはしいところであるから、野中に立つとも云つたものと思はれる。結び松といへば当時それと知られてゐたのであらう。その結び松を眼前にして、結び松よ、と呼びかけたやうな形で、そしてその松のやうに、心もとつづけたのである。 |
||||||||||
| 全注 | 【注】 前歌に「岸の松が枝」とあったのと同じ松を指す。岸とも野中とも表現されるのは、実際の地勢が「キシ」とも野とも言いうる所であったためだろう。当時と現在とでは、地勢に変化のあったことを考慮しなければならないが、有間皇子の結び松の遺跡と言われるあたりは前方が崖になっているし、背後は野と言ってもさしつかえない所でもある。「結び松」は、枝を結んだ松を実際に見ての表現と考えられる。もちろん、皇子の結んだ時のままであったかどうか疑わしいが、あとの「情も解けず」から推測すると、意吉麻呂は、そのまま解けずにあるものと信じて詠んでいると思われる。 |
|||||||||||
| 「情毛不解(こころもとけず)」考 | 攷證 | 磐代乃 [イハシロノ]。野中爾立有 [ノナカニタテル]。結松 [ムスヒマツ]。情毛不解 [コヽロモトケスズ]。古所念 [イニシヘオモホユ・ムカシオモホヘ]。 情毛不解 [ココロモトケズ]。 こは、本集九〔二十二丁〕に、家如解而曾遊 [イヘノコトトケテソアソフ] 云々。十七〔十七丁〕に、餘呂豆代爾許己呂波刀氣底 [ヨロツヨニコヽロハトケテ]、和我世古我都美之乎見都追 [ワカセコカツミシヲミツツ]、志乃備加禰都母 [シノヒカネツモ] 云々。後撰集春下、兼輔朝臣、一夜のみねてしかへらば、ふちの花、心とけたるいろみせんやは云々。戀一、よみ人しらず、なきたむるたもとこほれるけさ見れば、心とけても君を思はず云々などあると同じくて、こゝの意は、かの結び松を見れば、いにしへ思ひ出られて、かなしさに心むすぼゝれて、そゞろにものかなしと也。考云、この松、結ばれながら、大木となりて、此時までもありけん。 |
||||||||||
| 古義 | 磐代乃 [イハシロノ]。野中爾立有 [ヌナカニタテル]。結松 [ムスビマツ]。情毛不解 [コヽロモトケズ]。古所念 [イニシヘオモホユ]。 情毛不解 [コヽロモトケズ]は、結ぼほれたるよしなり、不解 [トケズ]は結といふ縁によりて云るなり、此ノ松結ばれながら生立て、此時迄も有つらむ、 |
|||||||||||
| 全釈 | 磐代乃 [イハシロノ]。野中爾立有 [ヌナカニタテル]。結松 [ムスビマツ]。情毛不解 [コヽロモトケズ]。古所念 [イニシヘオモホユ]。 情毛不解 [ココロモトケズ] ―― 不解 [トケズ] は結ぶの縁語として用ゐられたもの。この句を美夫君志に「その結びし人の心の解けずぞありけむとなり」とあるのは誤である。下の古所念 [イニシヘオモホユ] にかかつてゐるのだから、この結松を見た作者自身の心が、解けないのである。 |
|||||||||||
| 全註釈 | 磐代乃 [イハシロノ] 野中爾立有 [ノナカニタテル] 結松 [ムスビマツ] 情毛不解 [ココロモトケズ] 古所念 [イニシヘオモホユ] 未詳 情毛不解 ココロモトケズ。松も結ばれたままであり、わが心も解けずにで、心の快活でないのをいう。 |
|||||||||||
| 評釈 | 〔語〕 情も解けず 結び松の結ばれたままになつてゐるのをうけて、解けずといつたもの。心の結ぼほれて晴々しないこと。 |
|||||||||||
| 全注 | 【注】 講義に「『結松』に対して『トケズ』といへるは一は詞の文(アヤ)なるが、一は結松の古結べるままに残れる故にいへるなり」と記しているのが、要を得た注である。「ココロモトケズ」は、心のうちとけず、結ぼれたままであることを表わす。 |
|||||||||||