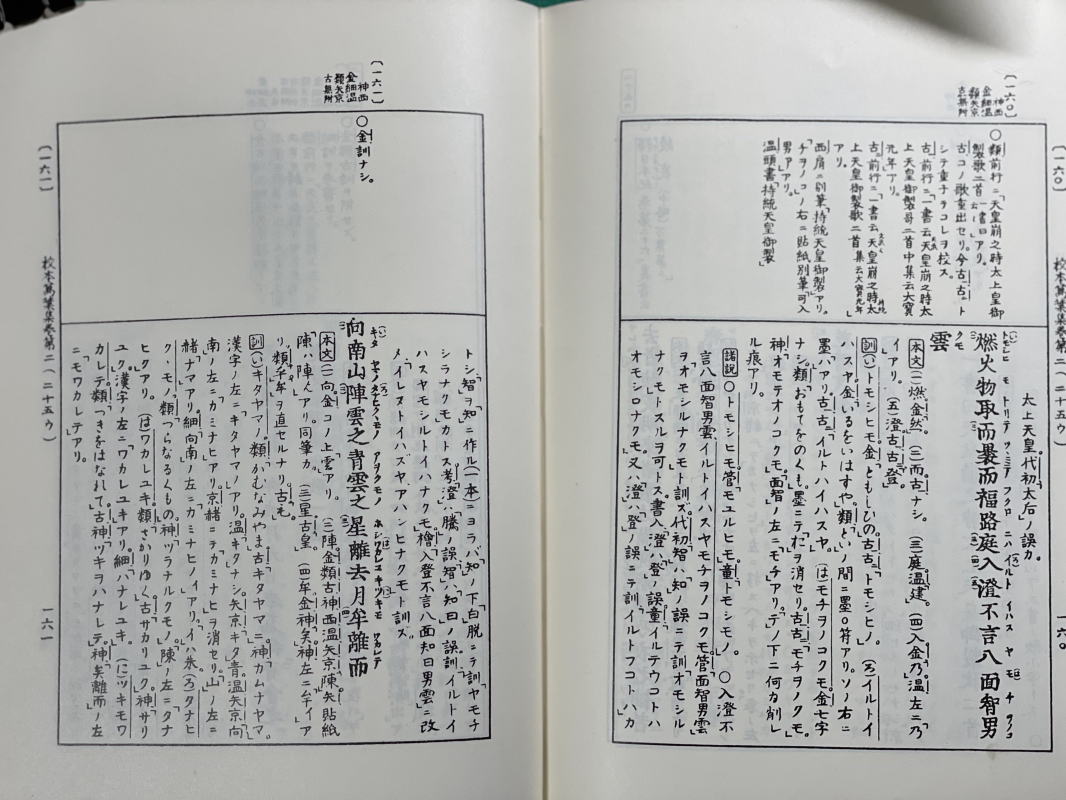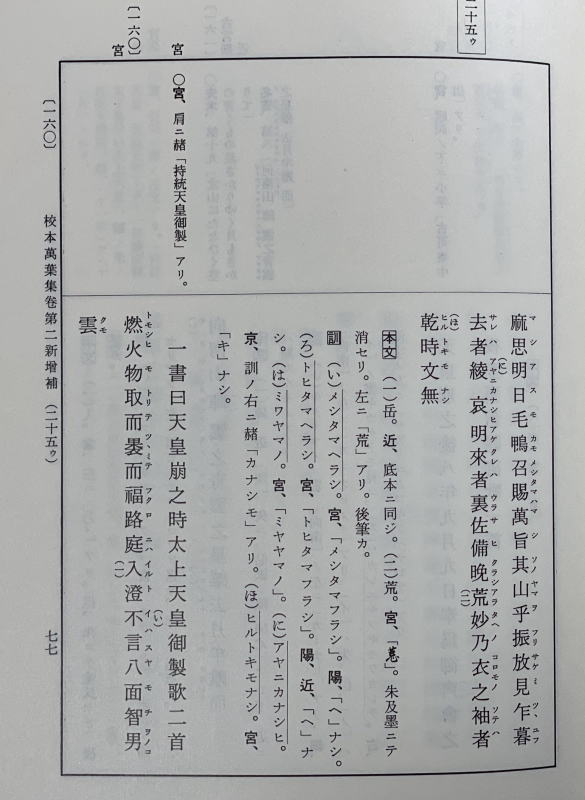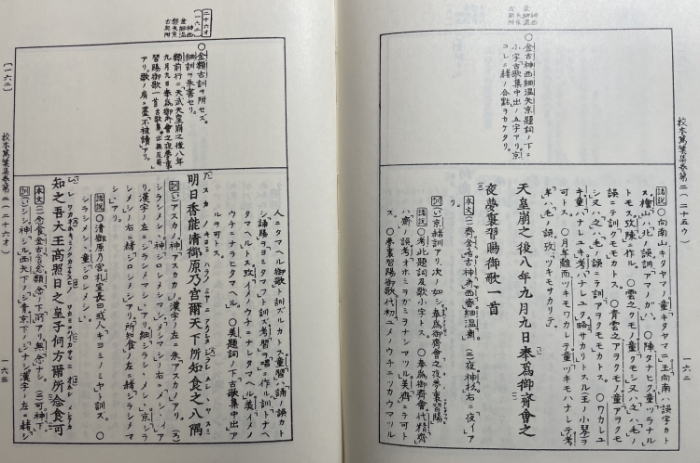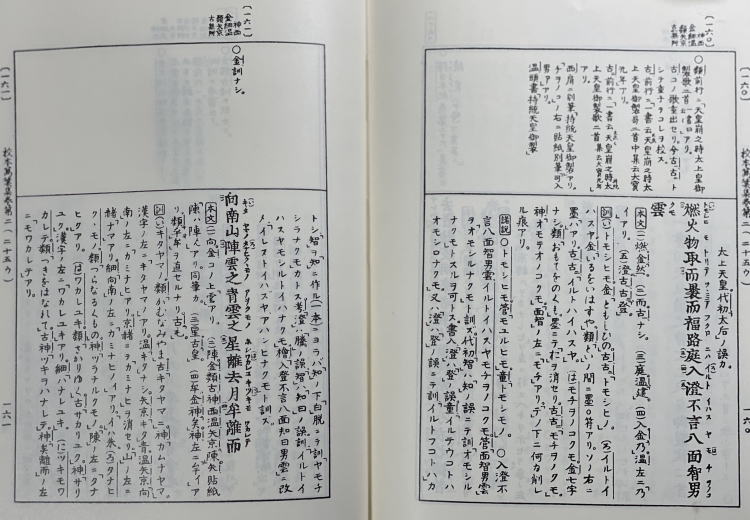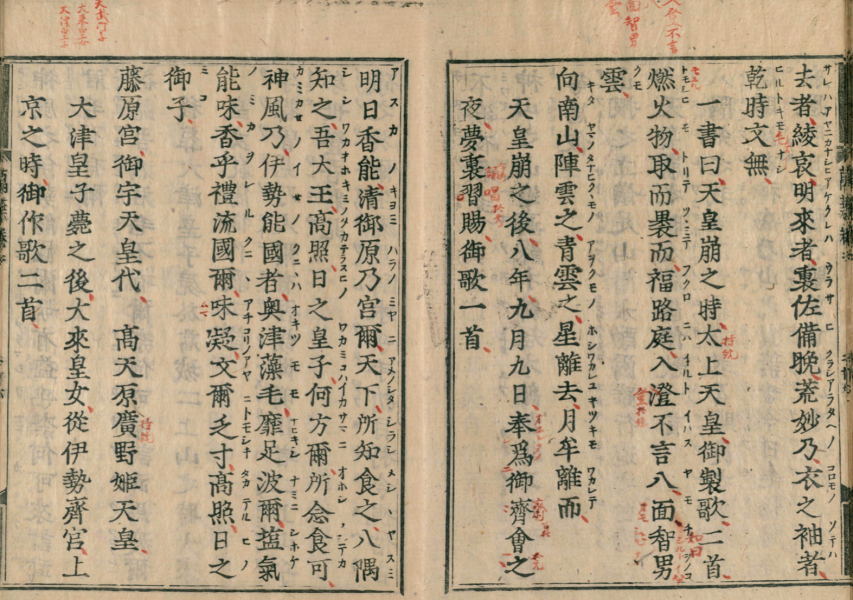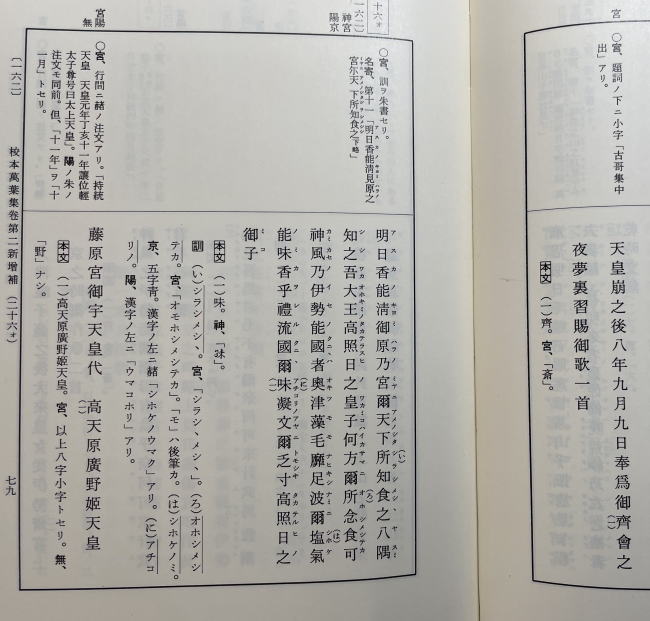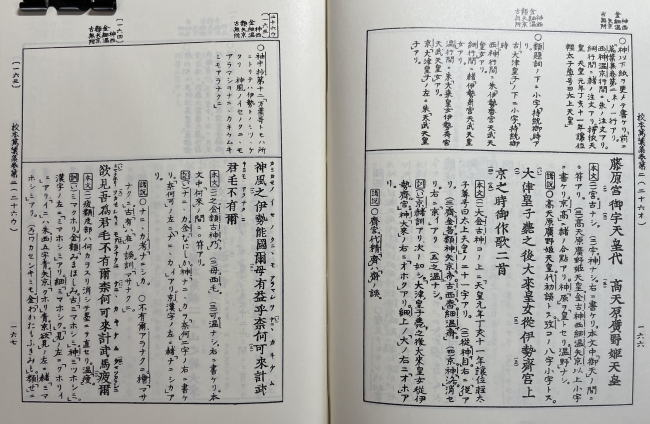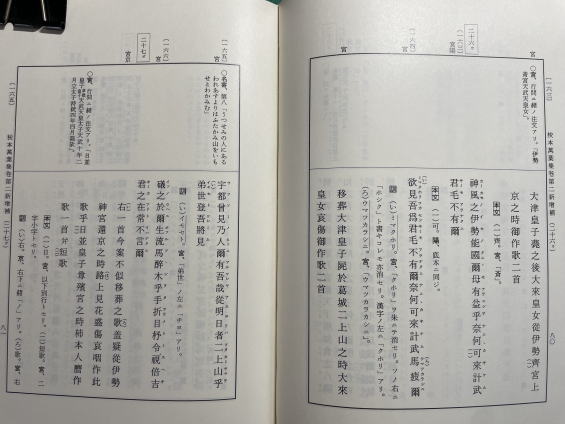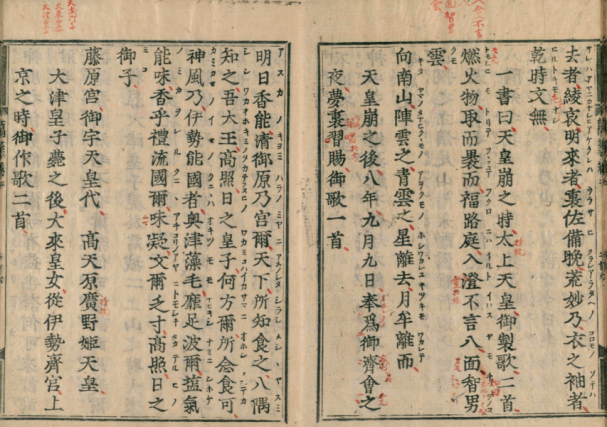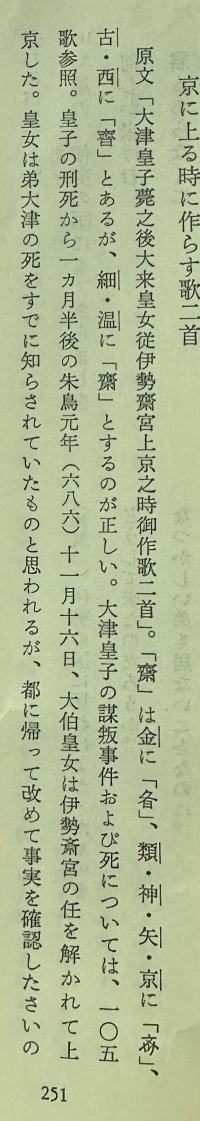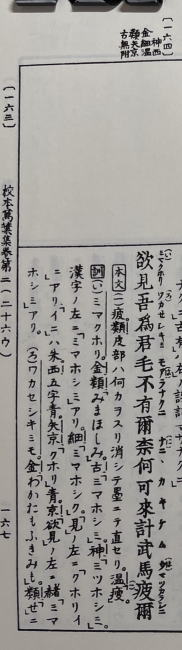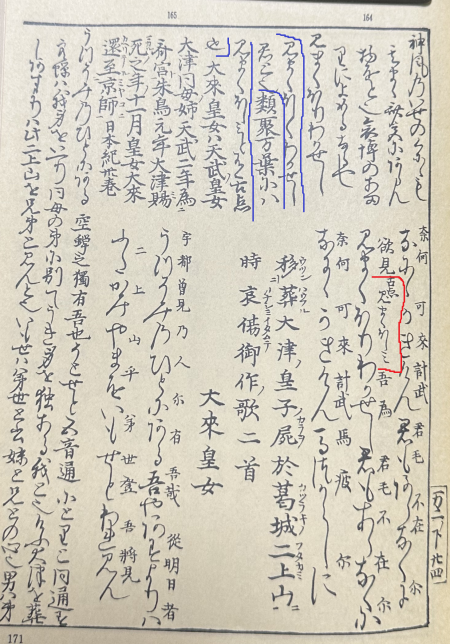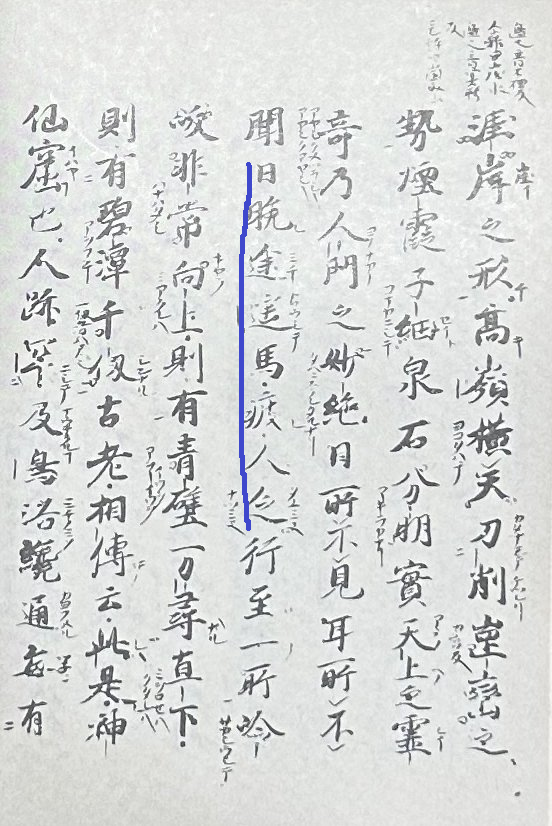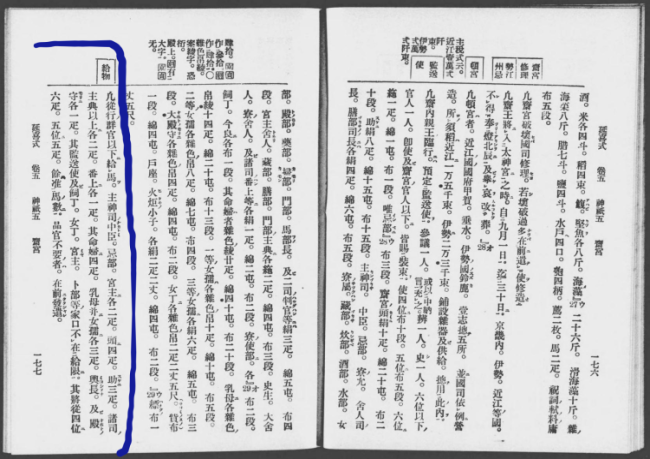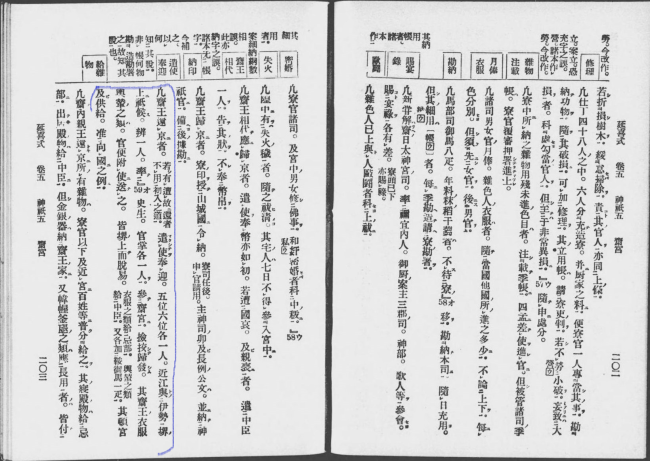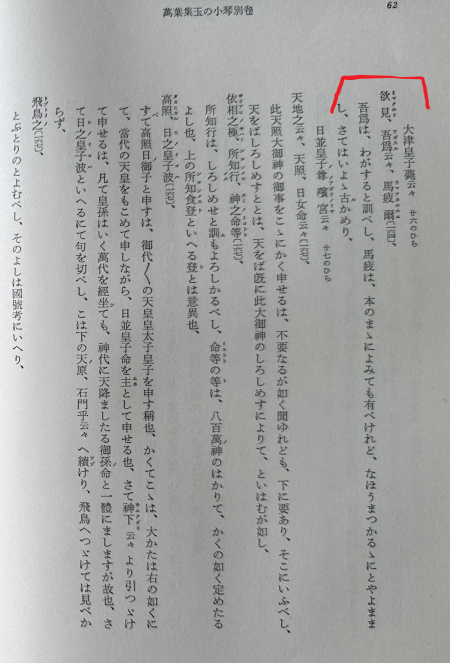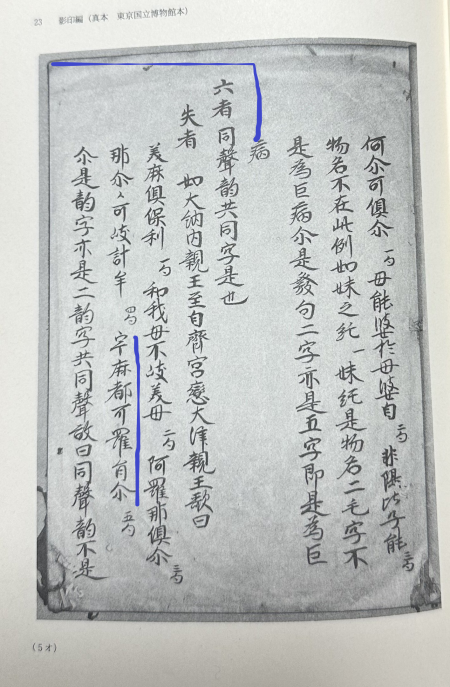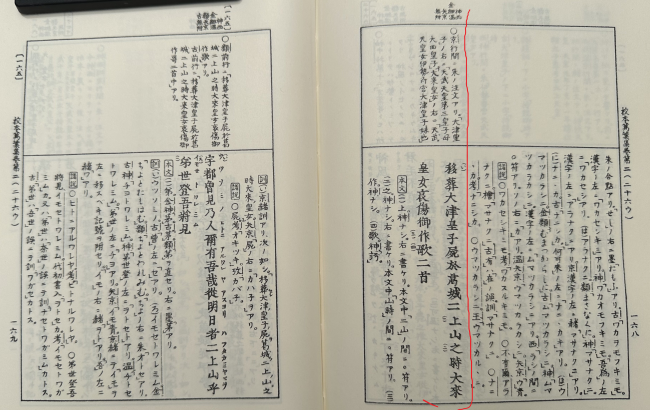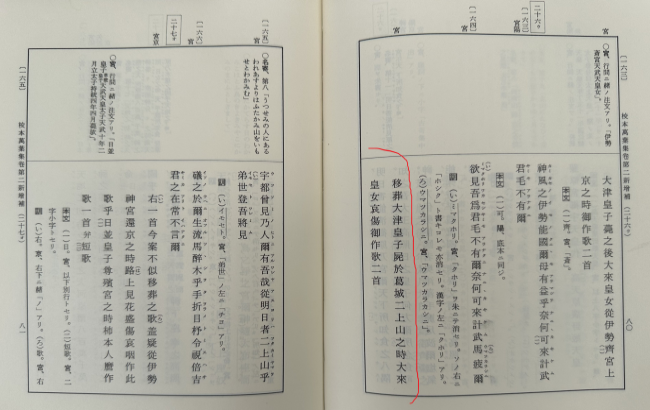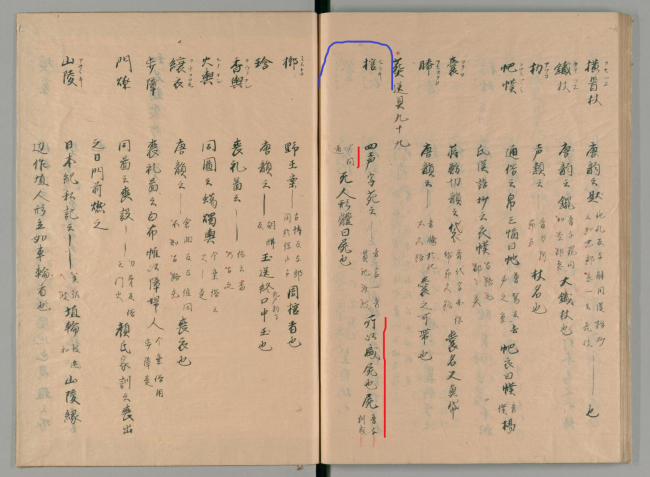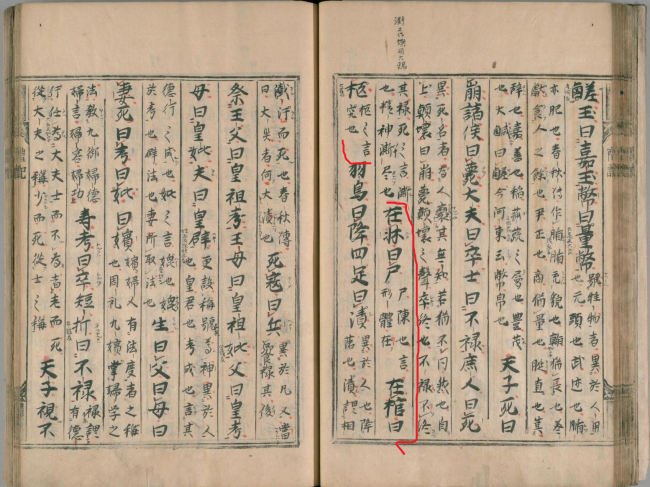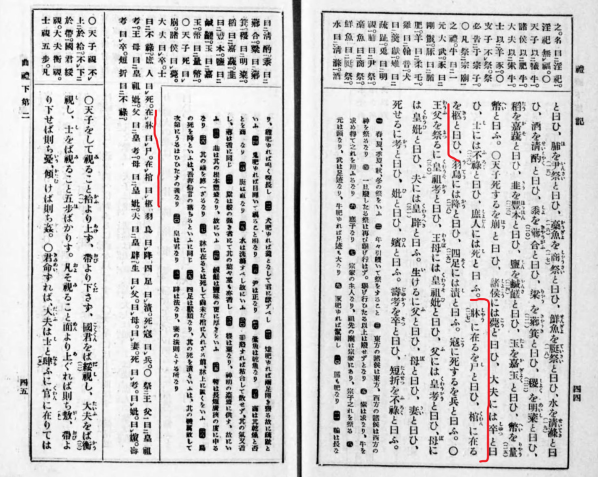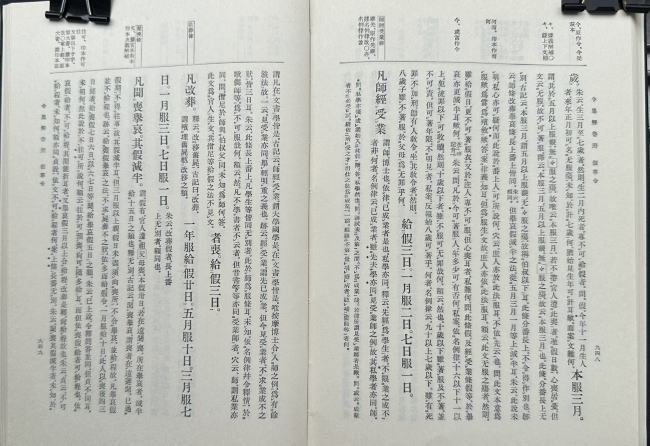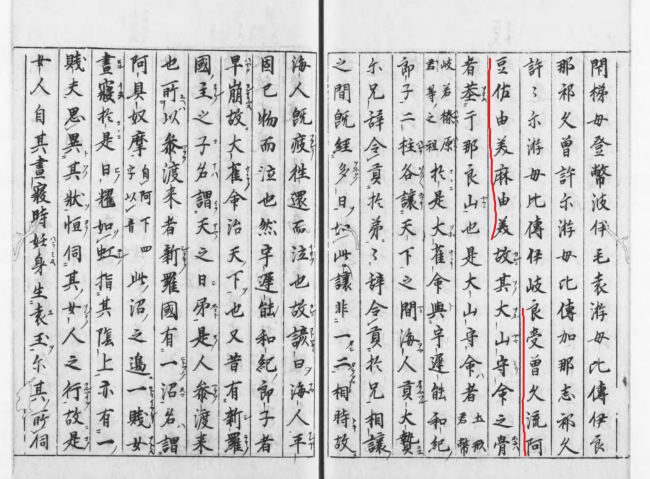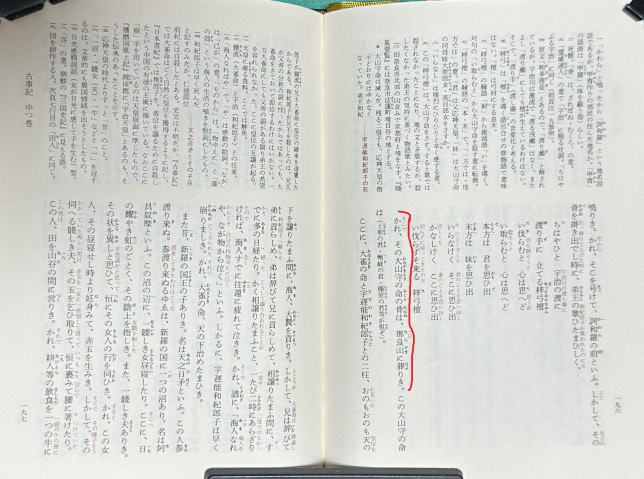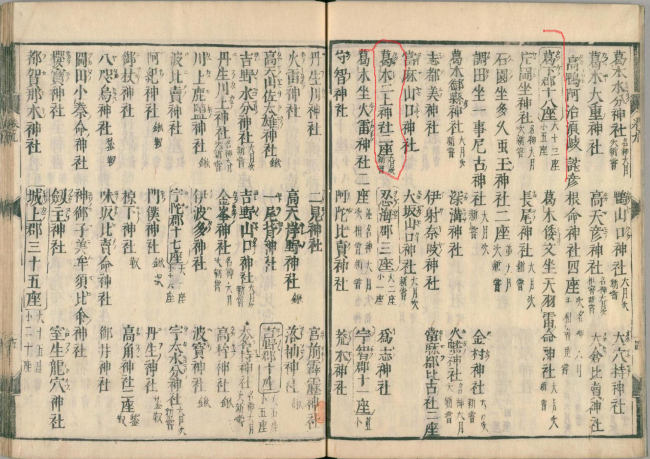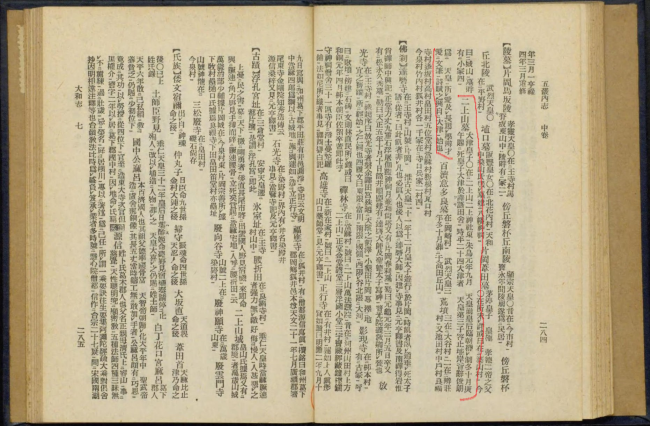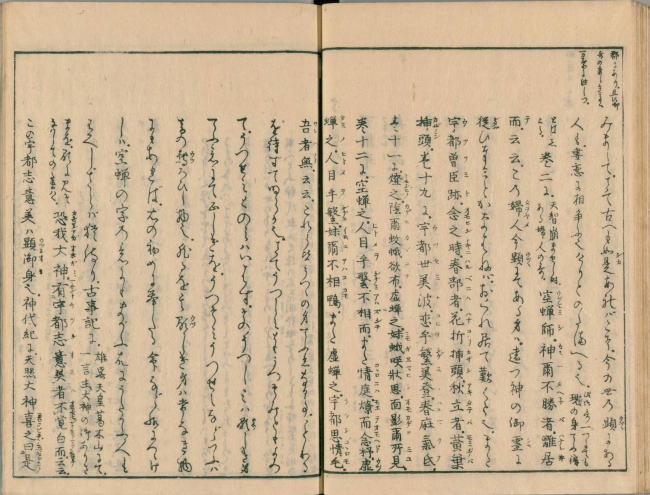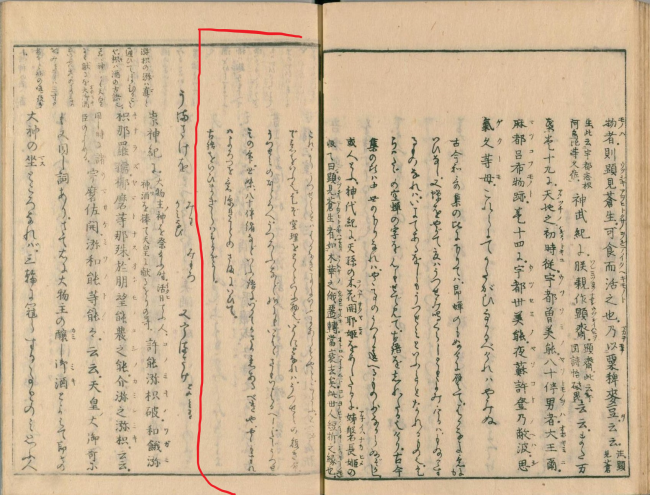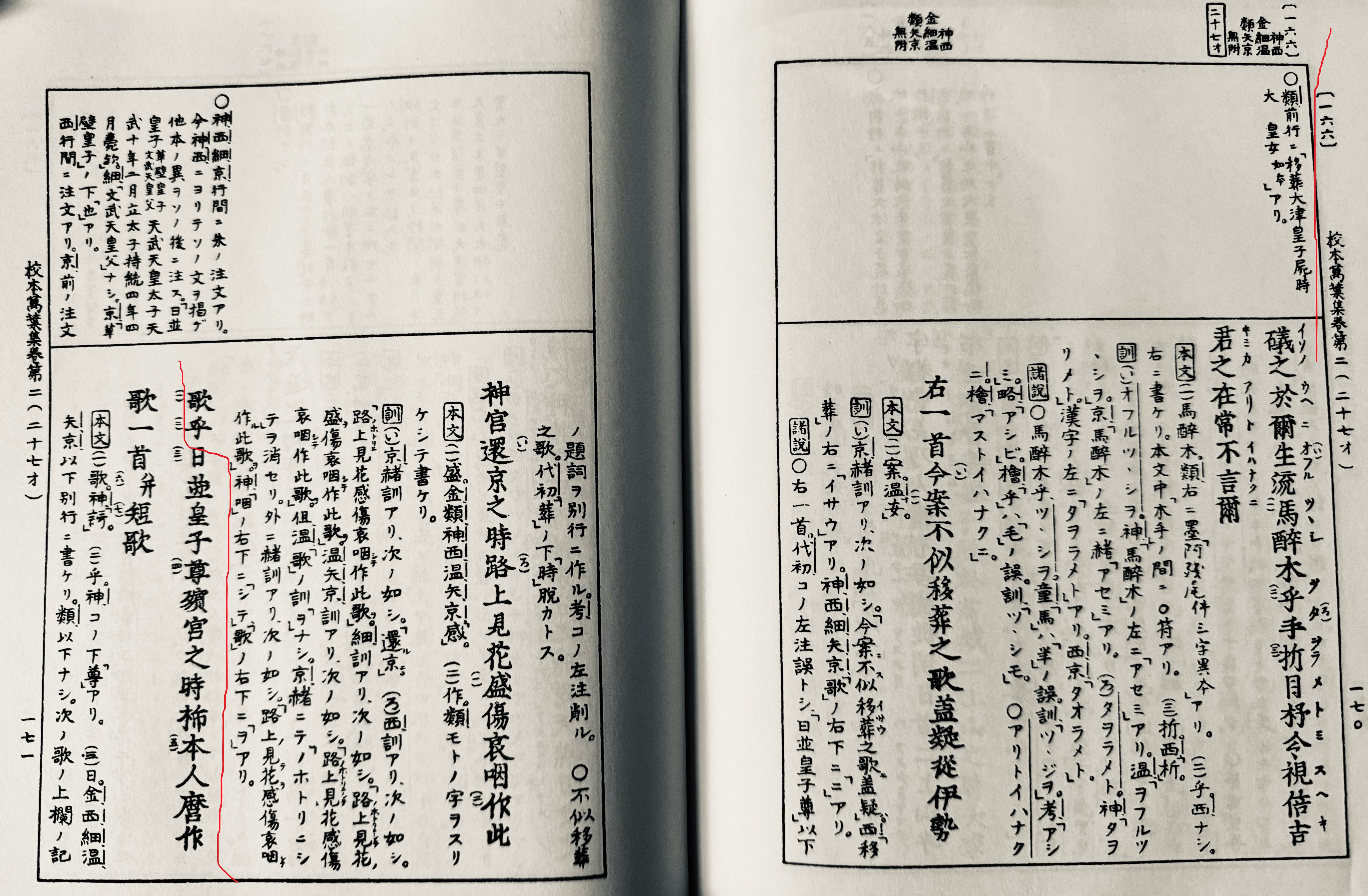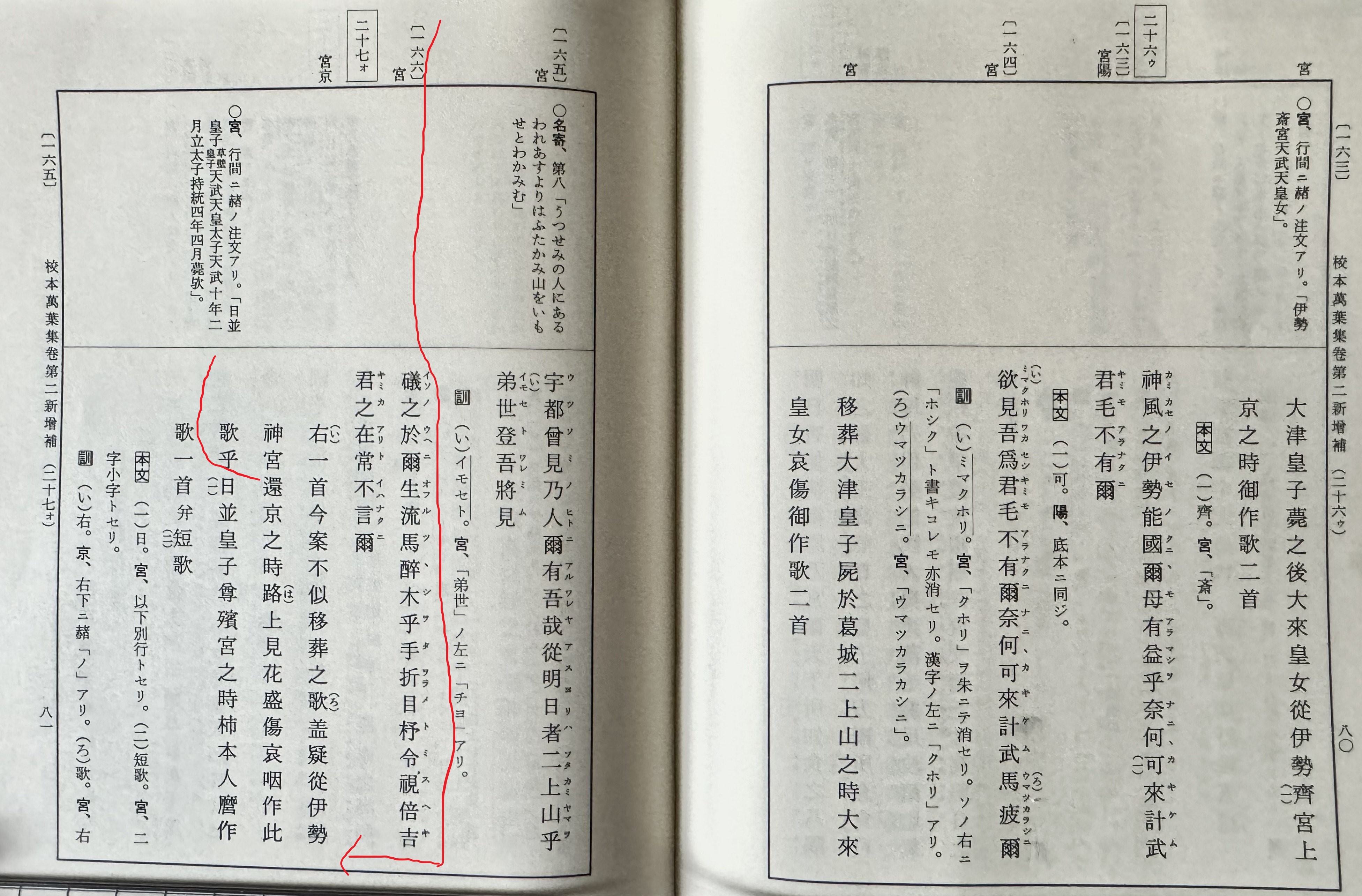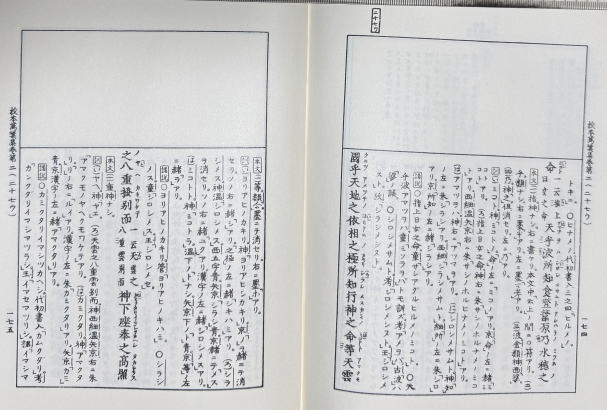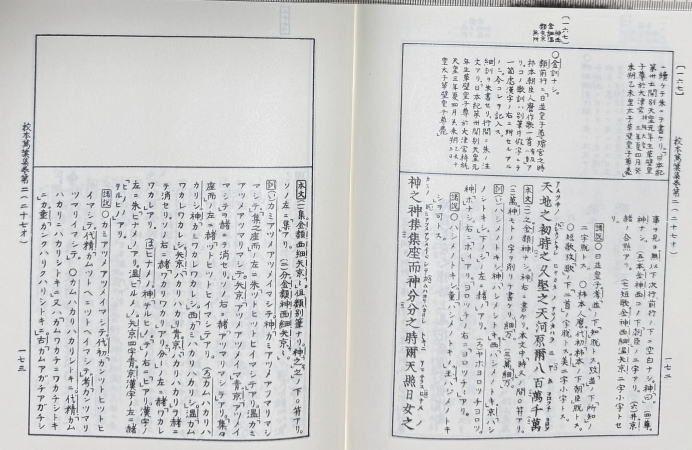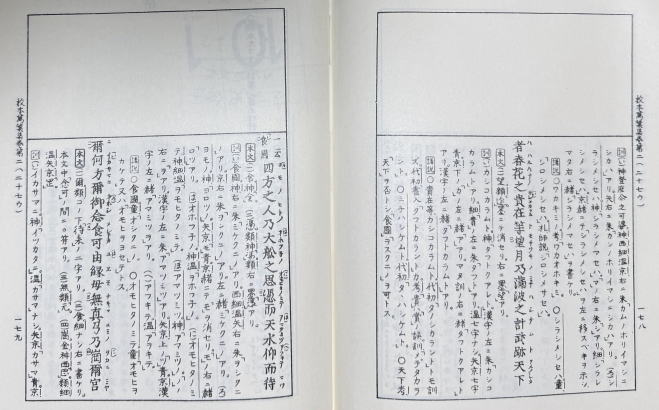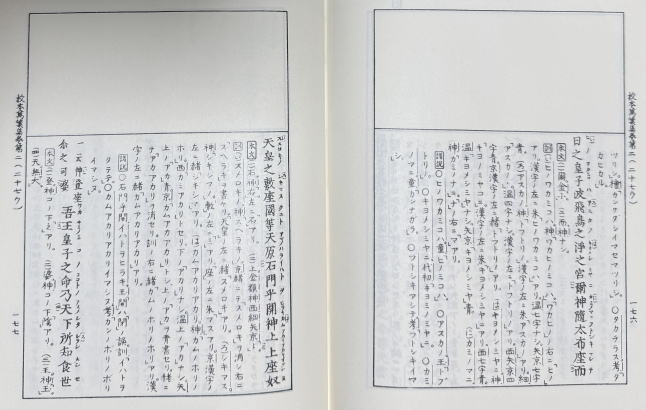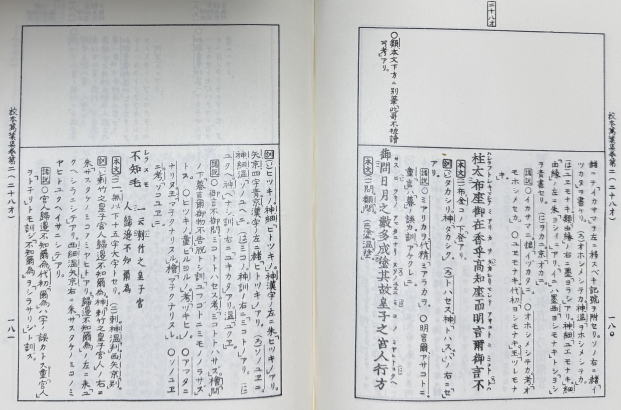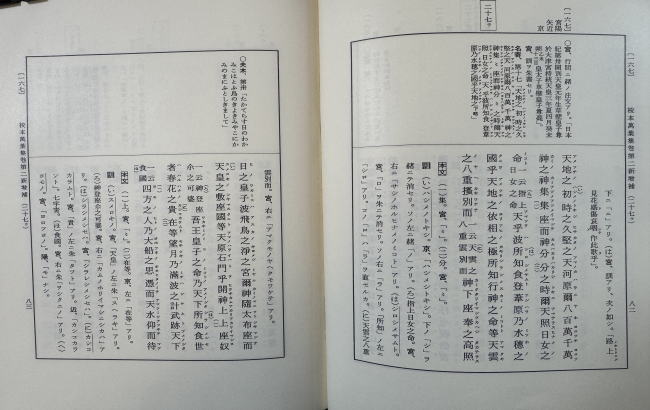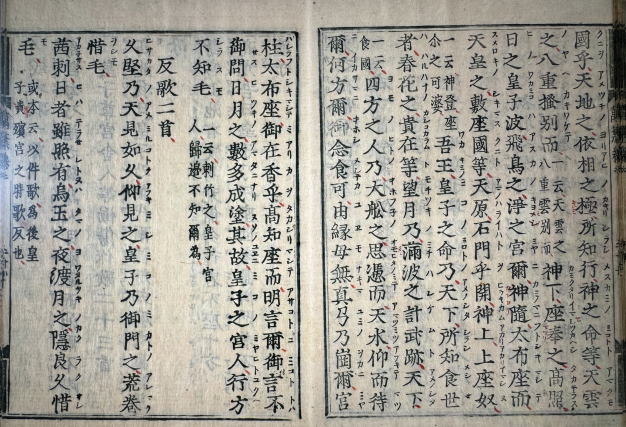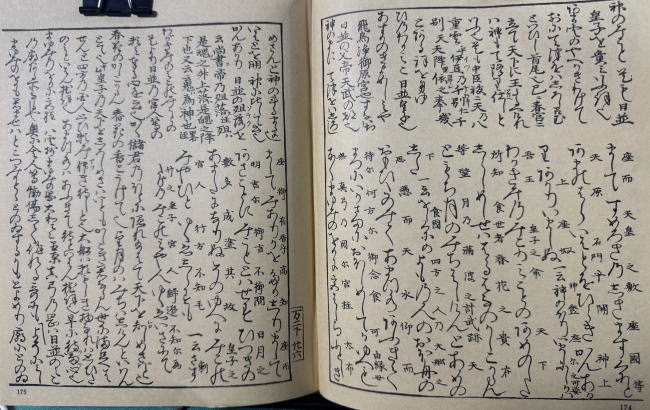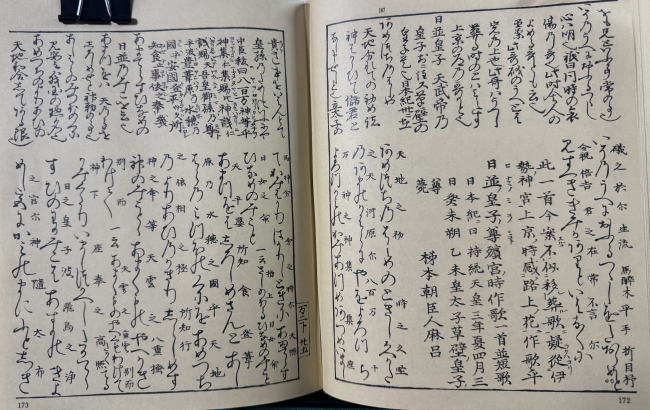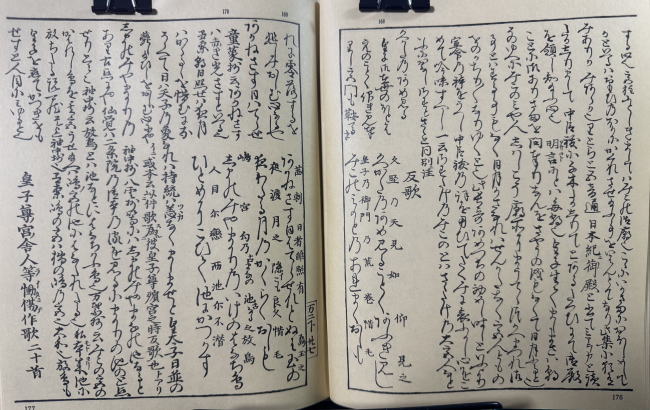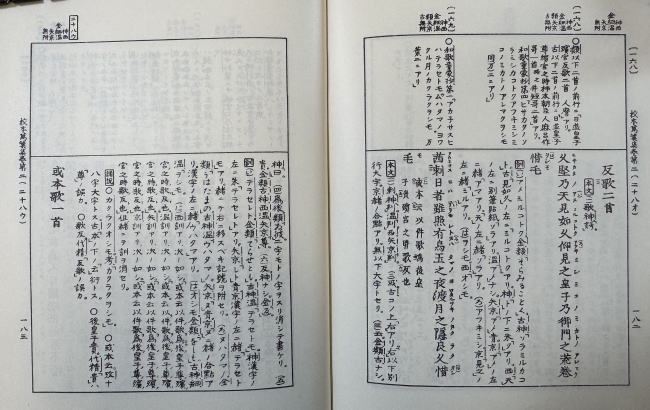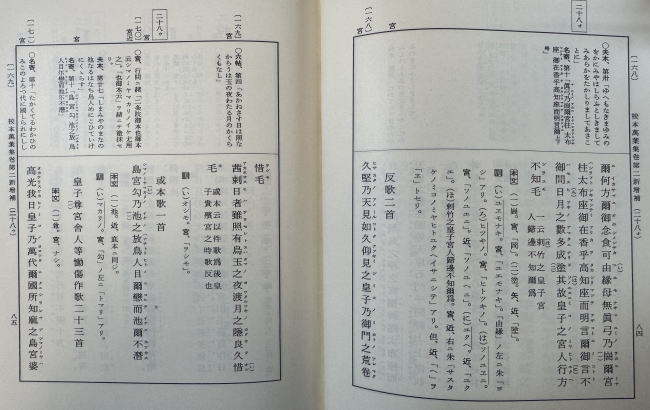| 歌番号 | 語句 | 諸注 | 諸注引用 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巻二160 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 校本萬葉集
|
||||||||||||||||||||||||||
| 活字附訓本 | 活字附訓本 | 活字附訓本 (国立国会図書館蔵書)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 諸注引用 | 註釈 | 燃火物取而褁而福路庭入澄不言八面智男雲《トモシヒモトリテツヽミテフクロニハイルトイハスヤモチヲノコクモ》 此歌ノ心ハ、葬礼ノナラヒ、フタヽヒモノヲアラタメ、モチヰルコトハ、イムヘキコトナレハ、死人ノマクラカミニ、トモシタル火ヲモチテ、葬所ニテモ、ヽチヰルヘキ也。サテトモシヒモ、トリテツヽミテ、フクロニハ、イルトイハスヤトヨメル也。モチヲノコクモトハ、モツヘキヲノコモ、キタルトイフ歟。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 管見 | もゆる火もとりてつゝみて これは火うちを、ものにつゝみて袋に入て持心なり。 おもしるなくも をもしるは、つねに相見る顔をいふ也。睦ましくむかへる人の、なくなれるをよめる心なり。面しる子らか見えぬ共よめり。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 拾穂抄 | 天皇崩時歌二首 太上天皇 ともしひもとりてつゝみてふくろにはいるといはすやおもしるなくも 燃火物取而裹而福路庭入登不言八面知(イもち)男(おのこ)雲(くも仙点) ともしひもとりて 火打を物に包て袋にいるゝ心也おもしるなくもとは常に顔見し人のなく成しと也おもしる子らか見えぬともよみし詞と同シ仙覺は結句をもちおのこくもと讀て死人の枕上の灯を葬所ニモ可用にこれを持へき男の來る心云々難用歟 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | 一書曰天皇崩之時太上天皇御製歌二首 此一書と云は、文武天皇崩御の後久しからずして或人の記し置るを取て撰者かくことわるか、さらねば右に太后と申たるは能叶へればさこそ書ぺけれ、 160 燃火物取而褁而福路庭入澄不言八面智男雲 《トモシヒモトリテツヽミテフクロニハイルトイハズヤモチヲノコクモ》 面智、【仙覺抄、智作v知、】 燃火物は、今按、モユル火モとよむべきか、結句はオモシルナクモとよむべし、第十二に、面知《オモシル》君が見えぬ此頃とも、又面知兒等《オモシルコラ》が見えぬ比かもとよめるは、面知とは常に相見馴る顔を云なり、幸に仙覺抄に智を知に作れり、此今按に付ても二義あるべし、一つには、如何なるもゆる火をも能方便してつゝみつれば、袋に入れても持と云に非ずや、寶壽がぎりましまして昇霞し給をば、冥使の來る時如何にも隱し奉るべき方なければ、明暮見馴奉し龍顔を今は見參らせぬが悲しき事とよませたまへるか、二つには、如何なるもゆる火も方便ある物は裹て袋に入るやうに威勢ましませし君も、無常のさそひ參らせて何所《イツチ》か率《ヰ》て奉けん、又も見えさせ給はずとや、燃る火を袋に入るといふ事物に見えたる事歟、諺などを讀せ給へる歟、後人當v考、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 童蒙抄 童子問 |
一書曰天皇崩之時太上天皇御製歌二首 童子問 此天皇崩はいづれの天皇ぞや。 答 天武天皇の崩也。 童子又問 天武天皇の時太上天皇はなし。いかなることぞや。 答 此疑問さるべき事也。太上天皇は持統天皇也。しからば大后とも書べきことなれども、此集最初の撰者の所爲にはあらず、後に再補の時加へ入たるなるべし。其證に一書曰と有を見るべし。太上天皇御在世の時、御名をしるすことを憚りて、太上天皇御製歌としるしおきたる書をその文のまゝに擧たるなるべし。古注者の補載と見るべし。 燃火物取而褁而福路庭入澄不言八面智男雲 童子問 仙覺注云、此歌の心は、葬禮のならひ二度物をあらため用ゐることはいむべき事なれば、死人の枕がみにともしたる火をもちて、葬所にてももちゐるべき也。さてともしびもとりてつゝみてふくろにはいるといはずやとよめる也。もちおのこくもとは、もつべきおのこもきたるといふ歟とあり。可v然ことともおぼえず。先生の賢按あらずや。 答 僻案の訓あり。然火物の三字をともしびもとよめるは、文字はさよむべきことなれども、下の詞にとりてつゝみてふくろに入るといふべからす。ともしびつゝまるゝものにあらず、袋に入らるべきことあらず。此三字は、僻案の訓にはともしものとよむ。火を燃す物なれば、火打つけ木などの物也。これは、旅行に必袋に入て持事也。日本武尊の東征の時、倭比賣命火打を入て御嚢を給へる事をしるべし。されば今天皇崩御の時、黄泉に徃給ふ旅用の物に、ともし物をも嚢に納て棺内に入ることを詠給ふなるべし。今の世の俗にも古にならふ人、棺内に品々の調度を納るがごとし。取而褁而、此四字一句にてとりてつゝみてと訓。福路庭、此三字一句ふくろにはと訓、入澄不言八、此五字一句、澄は登の字の誤りなるべし。此五字をいるといふことやと訓。入といふとは、いるちふともいるとふともいひて、いるといふの畧語也。さればいるといふことやは今初めてのことにあらず、いにしへよりともしものとりてつゝみて嚢には入るといふことあれば、いるとふことやと詠給へるなるべし。面智男雲、此四字一句にておもしらなくもと訓。言はおもしろくもなき義なり。 歌の惣意は、ともしものとりてつゝみて嚢に入るといふことは、世にまれなる物を乏物といふ也。めづらしき物は秘藏して、とりてつつむ上にも猶袋にも入るゝことなれば、それを兼て、さる事あるはおもしろき事にもすべけれど、黄泉の旅行にかゝることをし給ふは、おもしろからずと歎き給ふ御歌とみるべし。天皇行幸とても、供奉の人は燃火物を入る旅行と嚢は持べけれ、今天皇の獨黄泉の旅行に此嚢を奉ることを、大后の御意にかなしと思ひ給ふをかく詠給ふなるべし。 童子又問 面智男雲の四字は、もし面知呂男雲の五字にはあらずや。智の字しろと訓べきこといかゞに聞え侍る。知の字はしと音に用ゐたる例あまたみえ侍り。いかゞ。 答 さるべき一案なるべし。僻案には、智の字は知の誤字にて、下の日は男の字を傳寫混雜してあやまれるかとおもへば、四字一句としたり。其證は仙覺注釋の本には知に作りて智の字にあらず、知の字はしるとも、しらとも、しめとも相通はし通用ゐる例すくなからねば、直におもしろなくもと訓也。猶異本の證とすべき出來たらば、可不を決すべし。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 童蒙抄 | 燃火物取而褁而福路庭入澄不言八面智男雲 ともしもの、とりてつゝみて、ふくろには、いるてふことは、おもしろなくも 燃火物 古本印本の點ともしひもとあり。ともしびをつゝむべきやうやあらん。これは乏物といふ意にて、天皇の御秘藏なされし物を悉くおさめ入れて、送り奉るの義、今の世とてもある事也。かつ上古は火打などをも棺の内へ入たるごとくも聞ゆる也。やみぢに入るといふによりさだめて火打を入たる義もあるべし。さてこそとりてつゝみてふくろにはと下にあるなり。此ふくろは火打袋などを云たる義歟。生前の時の旅行には上代みな火打袋を持ちたる也。日本武尊の東征のとき倭姫命の被v遣し事など、古事記に見えたり。しかれば送葬のときの具にも此歌を以て見れば棺中へ被v入たるやうにも聞ゆる也。火打と珍物との事をかねて、ともしものとはよみたまへるなるべし 入澄不言八 古本印本共にいるといはずやとよめり。かくよみては歌の義いかんといへる事か聞き得がたく、又聞えたる釋もなく、下の句の意も歌詞とも聞えず。いかんとも心得がたき點なり。當家の傳には、いるてふことはとよむ意は、火打あるひは珍物寶物等をとりつゝみて、ふくろにいるゝといふことは、御葬のときのことなれば、面白からぬ物うき事の義といふの意にて、入てふことゝはとよむ也。澄の字は澂の字の俗字也。字書に澂、直貞切、音里、水靜而清、徐鉉曰、今俗作v澄非v是云々。しかれば澄不の二字の音を借訓に書たると見る也。尤此集中に此澄の字をてと用ひたる事此外に不v見ば、若し片の水を誤りて添へたる歟。しからばとふとよむべし。とふといふもちふといふ轉語にて、といふといふことを等布ともいふこと則ち此集第十四卷の歌に、からす等布おほをそ鳥とよめる歌ありて、此とふもからすといふおほをそとといふ義也。いづれにまれ澄不の二字はといふといふの義と見ゆる也 面智男雲 古本印本共にもちおとこくもとよめり。如v此の歌詞あらんや。しかれども仙覺律師の釋に、葬禮のならひ二たび物をあらため用ゐることを忌む事なれば、死人の枕上にともしたる火を以て葬所にて用ゐる故、それをもつべきをのこもきたるとの意歟と注せり。如v此釋しても全體の歌の意不v通也。よりて當家の傳はおもしろなくもよみて、全體の歌の意通する也。御葬送の時乏物どもをとりつゝみて、袋に入るゝといふ事は、おもしろからぬ物うき事と云の歌の意と聞ゆる也 智の字一本に知の宇に作れるもあり。因v茲則一僻案の釋あり。もし今の本の智の字知白の二字の合したる歟。なき本によりておもへば白の字を脱したる歟。智の字一字ならば、落すべき事にもあらねど、知白の二字故脱落あるまじきにもあらず。もしゝからば下の句の意別案あり。入澄不言八百知白男雲を、いるといふことのやもぢしらなくともいふ義ならんか。男雲とかきてなくもとよませる事は此集中數多也。やもぢはやみぢなり。ともし物とり包みてふくろに入といふことの、やみぢはいかやうのところぞ。したひ行たまひてしり給はんとの意歟。しらなんとはよもつくにゝ追ひ行て、そのみちをしり給はんとねがひたまふ意なり。御かなしみのあまり、やみぢをもしろしめしたきと、ねがひ給ふ義歟 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉考 | 燃火物《モユルヒモ》、取而裹而《トリテツヽミテ》、福路庭《フクロニハ》、 袋に者なり、 入澄《イルト》、 騰か、 不言八面《イハズヤモ》、 【八面をやものかなとせしは、(卷四)にもあり、】 知曰《シルトイハ》、 今本智と有は、知曰二字なるべし、 男雲《ナクモ》、 こは借字にて、無毛《ナクモ》の意なり、後世も火をくひ、火を蹈わざを爲といへば、其御時在し役ノ小角がともがらの、火を袋に包みなどする、恠き術《ワザ》する事有けん、さてさるあやしきわざをだにすめるに、崩ませし君に逢奉らん術を知といはぬが、かひなしと、御なげきの餘にの給へるなり、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | 一書曰。天皇崩之時太上天皇御製歌二首。 此太上は持統天皇に當れり。天武天皇崩りませし後、四年に即位、十一年八月御位を文武天皇に讓りたまひて後、太上と申奉る。天武崩りませる時、太上と書けるはひがごとなり。 燃火物。取而裹而。福路庭。入澄不言八面。智男雲、 もゆるひも。とりてつつみて。ふくろには。いるといはずやも。しるといはなくも。 智一本知に作る。今本イルトイハズヤ、モチヲノコクモと點あれど由なし。翁試みに言はれしは、澄は登の誤り、智は知曰二字ならむか。然らばイルトイハズヤモ、シルトイハナクモと訓むべし。是は後世火をくひ、火を踏むわざを爲なれば、其御時在りし役ノ小角か輩の、火を袋に包みなどする恠き術する事の有りけむ。さてさる怪きわざをだにするに、崩り給ひし君に逢ひ奉らむ術を知ると言はぬがかひなしとにや。契沖云、卷十二に、面知君が見えぬ此ごろとも詠みたれば、智は知の誤りにて、イルトイハズヤ、オモシルナクモと訓まむか。見なれ奉り給へる御面わの見え給はぬを戀奉り給へるなりと言へり。智を知に作れる本もあれば、面知とせむ方も然るべくも思はるれど、猶穩ならず。考ふべし。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 攷證 | 一書曰。天皇崩之時。太上天皇御製歌。二首。 この天皇の御時、太上天皇おはしまするなし。されば考るに、こは持統天皇を申すなり。この時持統天皇は、いまだ天武帝の皇后にておはしましゝ事、まへに太后とあるがごとし。さて太上天皇の尊號は、持統帝より、はじまりしかば、ことさらに太上天皇とは申すなり。されどこゝは天武帝崩じましゝ所なれば、太后とかくべきを、太上天皇と書しは、この一書の誤り也。 燃火物《モユルヒモ》。取而□而《トリテツメミテ》。福路庭《フクロニハ》。入澄不言八面《・イルトイハスヤモ》。智男雲《・チヲノコクモ》。 燃火物《モユルヒモ》。 舊訓、ともしびもとあれど、燃の字、ともし火とよまんいはれなし。こは長流がもゆるひもとよめるに、したがふべし。廣韻に、燃俗然字云々。説文に、然燒也云々とあり。又本集十一【四十二丁】に、燒乍毛居《モエツヽモヲル》云々。十二【廿一丁】に、燒流火氣能《モユルケフリノ》云々など、燒をもゆるとのみよめるにても、こゝももゆるとよむべきをしるるべし。 福路庭《フクロニハ》。 福《フク》路は、借字にて、嚢なり。古しへは、何事にも、袋《フクロ》を用ひしことと見えたり。そは、古事記上卷に、於2大穴牟遲神1、負v□[代/巾]《フクロ》爲2從者1、率往云々。書紀雄略紀に、二2分子孫1、一分賜2茅渟縣主1、爲2負v嚢者1云々。續日本紀に大寶元年十二月、戊申、賜2諸王卿□[代/巾]樣1云々。靈龜二年十月、禁武官人者朝服之袋儲而勿v著云々。本集四【五十三丁】に、生有代爾吾者未見《イケルヨニワレハマタミス》、事絶而如是※[立心偏+可]怜縫流嚢者《コトタエテカククオモシロクヌヘルフクロハ》云々。この外集中、はり袋、すり袋なども見えたり。催馬樂庭生に、見也比《□》止乃左久留不久呂乎於乃禮加介太利《ミヤヒトノサクルフクロヲオノレカケタリ》云々。靈異記中卷に、從2緋嚢1、出2一尺鑿1云々。清和實録貞觀十二年三月十六日紀に、納糒帶袋見えたり。この外とのいものゝふくろゑぶくろなどもいひ、猶諸書に見えたれどことごとくあぐるにいとまなし。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 〔一書ニ曰。天皇ノ崩之時《カムアガリマセルトキ》。太上天皇ノ御製歌《ミヨミマセルオホミウタ》二首。〕 太上天皇、契冲云、此ノ太上天皇おぼつかなし、天武ノ御時太上天皇なし、もし文武の朝の人のしるしをけるに、持統天皇の、御ことを申せる歟、それに打まかせて載たるにや、天皇に對する太上天皇なれば、あやまれりときこゆ、たとひ持統の御事ならば、さきのごごとく大后とこそ申べけれ、以下三首は、一書に載たることなれば、もとより、本章にはあらざるべし、故レ小字とす、 〔燃火物《モユルヒモ》。取而裹而《トリテツヽミテ》、福路庭《フクロニハ》。入澄不言八《イルトイハズヤ》。面智男雲。〕 澄ノ字、類聚抄官本拾穗本等には、登と作り、智ノ字、拾穗本并一本には、知と作り、御歌ノ意、解得難し、(岡部氏が云るは、福路庭《フクロニハ》は、袋に者なり、澄は騰か、智は知曰ノ二字なるべし、男雲は借リ字にて無毛《ナクモ》の意なり、されば第四五ノ句、イルトイハズヤモシルトイハナクモと訓べし、後ノ世も、火をくひ、火を蹈わざを爲といへば、其ノ御時在し、役ノ小角がともがらの、火を袋に包みなどする、恠き術する事有けむ、さてさるあやしきわざをだにすめるに、崩リませし君に、逢奉らむ術を知といはぬがかひなしと、御なげさの餘リに、のたまへるなりと云り、いかゞあらむ、契冲がいへりしは、智は知の字なるべし、イルトイハズヤオモシルナクモと訓むか、おもしるは、常にあひみる顔をいふことなり、第十二に、おもしる君がみえぬ此ごろとも、おもしるこらが見えぬ比かもともよめり、もゆる火だにも、方便をよくしつれば、ふくろに取いれてかくすを、寶壽かぎりましまして、とゞめ奉るべきよしなくて、見なれたてまつり給へる、御おもわの見えたまはぬを、こひ奉りたまへるなりと云り、これもいかゞなり、猶考フべし、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 檜嬬手 | 一書ニ曰フ、天皇ノ崩之時《カムアガリタマフトキ》、太上天皇ノ御製歌一首 燃火物《モユルヒモ》、取而褁而《トリテツヽミテ》、福路庭《フクロニハ》、入登不言八《イレヌトイハズヤ》、面知日男雲《アハンヒナクモ》。 〇「一書曰」此は文武天皇の朝の人の、記し置ける物の中より、其まゝに書き入れたる也。其の朝にては、持統天皇を太上天皇と稱《マヲ》しならはしけるまゝの言《コトバ》也。是を左右《トカウ》云ひて改むる人は書入れと云ふことを思はざる也。 〇「燃火物」此は、燒火の炎にて燃上ル火を云ふ也 〇「取而褁而」手に取て、絹紙などに包むなり。 〇「福路庭」帋にはなり。 〇「入登不言八」言《イフ》は例の添へ言にて納《イ》れずやは、納《イル》るではなきか、と云ふ意也。此は、文武天皇の朝には、然《サ》る幻術する者あるをきこしめして詔ふ詞也。文武紀二年七月乙丑ノ詔に、禁ス2博戯遊手之徒ヲ1其ノ居停ノ主人ハ亦與ニ居スルモノニ2同罪ニ」。同三年五月丁丑、役《エンノ》君|小角《ヲヅヌヲ》流ス2于伊豆ノ島ニ1初メ小角住ミ2於葛木山ニ1以テ2咒術ヲ1稱セラル。外從五位下|韓國連廣足《カラクニノムラジヒロタリ》師トスv焉ヲ。後害シ2其能ヲ1讒スルニ以テ2妖惑ヲ1。故ニ配セラル2遠處ニ1。世ニ相ヒ傳ヘテ云ハク小角能ク役2使シテ鬼神ヲ1汲ミv水ヲ採ラシムv薪ヲ若シ不レバv用ヒv命ヲ即以テv咒ヲ縛スv之ヲと見ゆ。されば此徒のさる咒術《ワザ》をなしゝ也。 〇「面知日男雲」今本、面智男雲とある、智は知日二字を一字に寫し誤りたる也。さて面知《オモヲシル》とは、逢見と云ふ意の義訓なれば、其の義を得て面知日男雲《アハムヒナクモ》と訓むべし。十二【二十五】水莖之崗乃田葛葉緒吹變面知兒等之不見比鴨《ミヅグキノヲカノクズハヲフキカヘシアヒミシコラガミエズコロカモ》とある、此の面知《アヒミシ》と合せて知るべし。 〇一首の意は、燃る火をだに、手に取りて包みて、袋に入るゝではなきか、然るに我がかくまで戀ひ奉る君に、又逢はん術のなき世にもあるかなとなり。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 口訳 | 天皇(天武)崩御の時、皇后(持統)の御歌 燃ゆる火もとりて包みて、袋には入ると言はずや。會はなくもあやし 燃ゆる火さへも、燈籠に包み込むことが、出來るといふではないか。さすれば、死んだ人の魂も、留めて置かれない筈はないのに、會はれないのは、どうも不思議だ。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 一書曰、天皇崩之時、太上天皇御製歌二首 天武天皇崩御の時、大后即ち持統天皇の御製である。太上天皇と記し奉つたのは、文武天皇の御代に誰かが記したものを、その儘ここに書き込んだのである。 燃ゆる火も 取りて包みて 袋には 入ると言はずやも 知ると言はなくも 燃火物《モユルヒモ》 取而褁而《トリテツツミテ》 福路庭《フクロニハ》 入澄不言八面《イルトイハズヤモ》 智男雲《シルトイハナクモ》 役ノ行者ノ術デハ、燃エテヰル火ヲ手ニ取ツテ、包ンデソレヲ袋ニ入レルト云フデハナイカ、ソノヤウナ不思議ナコトモ、出來ルモノヲ、御崩レ遊バシタ天子樣ニ御遭ヒ申ス術ヲ知ツテヰルト言ハナイヨ。知ツテヰサウナモノダニ。アアドウゾシテ御逢ヒ申シタイモノダ。 ○燃火物取而褁而《モユルヒモトリテツツミテ》――燃える火を、手に執り、紙などに包んで、袋に入れるといふ不思議な術が、役行者などによつて行はれてゐた話をお聞きになつて、お詠みになつたのであらう。 ○智男雲《シルトイハナクモ》――考に、智を知曰の二字にして、シルトイハナクモとよんだのに從ふ。面を五の句に入れて、オモシルナクモとよむのも、又、面知日としてアハムヒナクモとよむのも、面知因としてアフヨシナクモとよむ説も、賛成出來ない。面知をアフとよんだ例は一つもない。 〔評〕 珍らしい材料を取入れた歌である。かかる妖術さへ行はれる世に、神去り給うた御魂を、呼び返し得ぬとは悲しいことよと宣うたので、親しい者を亡つた人が、現代の醫學に呪の聲を發するのに、いくらか似通つた考へ方である。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 一書曰、天皇崩之時、太上天皇御製歌二首 一書に曰はく、天皇の崩りましし時に、太上天皇の御製の歌二首 【釋】一書曰 アルフミニイハク。同じ作歌事情にある歌を一書によつて擧げたのである。歌は全然別なのであるから、一書曰とするにも及ばないのであるが、一次の編纂の後に加えられたので、かような形を呈するに至つたのであろう。一書は何の書か不明である。 天皇崩之時 スメラミコトノカムサリマシシトキニ。天武天皇の崩御の時。 太上天皇 オホキスメラミコト。持統天皇。後に太上天皇にましましたのを、前に及ぼして書いている。 燃ゆる火も 取りて裹《つつ》みて 嚢《ふくろ》には 入ると言はずや。 面知《おもし》らなくも。 燃火物《モユルヒモ》 取而裹而《トリテツツミテ》 福路庭《フクロニハ》 入澄不v言八《イルトイハズヤ》 面智男雲《オモシラナクモ・モシルトイハナクモ》 【譯】燃える火も、取つて包んで、嚢には入れるというではないか。わかりかねることです。 【釋】燃火物 モユルヒモ。モユルヒは、火の特性を説明している。ただ火もでよいのだが、モユルを冠するので、その狀態が描寫されている。 取而裹而 トリテツツミテ。火を取つて包んでで、できかねることをいう。 福賂庭 フクロニハ。フクロは嚢。物を入れるために作つたもの。福路の二字は字音假字として使用されている。 入澄不言八面智男雲 イルトイハズヤオモシラナクモ。 イルナイハズヤモチヲノコクモ (西) オモシルナクモ (管) イルテウコトハオモシロナクモ (童) ―――――――――― 面智男雲《オモシルナクモ》 (代初) 入登不言八面知白男雲《イルトフコトヤモチシラナクモ》(童) 入騰不言八面知曰男雲《イルトイハズヤモシルトイハナクモ》(考) 入登不言八面知日雲《イルトイハズヤアハンヒナクモ》(檜) 澄は、トの假字に用いた例を見ない。古葉略類聚鈔には、この歌を重出しているが、そのいずれにも登に作つている。イルトイハズヤは、嚢には入れるといぅではないかの意で、句切。以上は火のようなものも、包んで嚢に入れるそうだの意で、不可能と思われることでもできるの譬喩に言つているらしい。次に五句は、考には、面を上の句につけ、智を知曰の誤として、シルトイハナクモと讀んでいる。これによれば、知るとは言わないことだの意になり、火でも嚢にはいるというのに、君の崩御のことは、了解に苦しむの意となる。原文のままならば、オモシラナクモと讀むほかは無い。オモシルは、集中、「如v神《カミノゴト》 所v聞瀧之《キコユルタキノ》 白浪乃《シラナミノ》 面知君之《オモシルキミガ》 不v所v見比日《ミエヌコノゴロ》」(卷十二、三〇一五)、「ミヅグキノヲカノクズハヲフキカヘシオモシルコラガミエヌコロカモ」(同、三〇六八)の用例があり、知り合いの意に使用されている。それでオモシラナクモは、親しみの無いことだ、了解し得ないことだの意になるのであろう。 【評語】上四句は、出來にくいことを言つているようで、興味をひく詞句であるが、五句に難關があり、十分に鑑賞されないのは惜しむべきである。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | 一書に曰く、天皇崩りましし時、太上天皇の御製の歌二首 燃ゆる火も取りて裹《つつ》みて袋には入ると言はずやも知るといはなくも 〔題〕 或書に載せてある歌を參考の爲に加へたもので、天皇は天武天皇、太上天皇は持統天皇。文武天皇の御代に記した書き方をそのまま轉載したのであらう。 〔譯〕 燃えてゐる火でさへも取つてつつんで、袋に入れるといふではないか。それであるのに、崩御をとどめ奉る術を、誰も知るとはいはないことである。 〔評〕 訓義上異説があいが、眞淵のいふやうに幻術の類を考へて、崩御をとどめまつる術のないことを歎いての御歌であらう。或は、靈の御行方を知るといはないとも解される。まことに特異な素材である。四、五句の間に省略が多く、四句に、「入るといはずやも」と反語的に強く述べ、五句に「言はなくも」と沈んだ語調となつてゐることは對比して、味はひが深い。 〔語〕 ○燃ゆる火も 以下は當時、役の小角など火を袋に裹みなどする不思議な術をする者があつたのをいふ(考)。 〔訓〕 ○四五句、白文「入登不言八面知曰男雲」で、「登」は古葉略類聚鈔による。他の諸本は「澄」に作る。「知曰」は諸本「智」とあり、このままでは解せられないので、代匠記、檜嬬手、新考は「面」以下を一句とし、上をイルトイハズヤとし、五句は代匠記「面智《オモシル》ナクモ」檜嬬手「南知日《アハムヒ》ナクモ」新考「面知因《アフヨシ》ナクモ」とし、考は「面」を四句につけ、「知曰《シルトイハ》ナクモ」と改めてゐる。暫く考により、後考を俟つこととしたい。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 一書曰天皇崩之時太上天皇御製歌二首 代匠記に「此一書ト云ハ、持統天皇御譲位ノ後或人ノ記シ置ルヲ取テ撰者カクコトワル歟。サラズバ右ニ太后ト申タルハ能叶ヘレバサコソ書ベケレ」と云つてるやうに、前の例によれば太后と書くべきであるが、一書にはこの御製が文武即位以後に記録せられ、巻一の多くの例のやうに太上天皇と書かれてゐたものと思はれる。 燃火物 取而褁而 福路庭 入澄不言八 面知日男雲 モユルヒモ トリテツツミテ フクロニハ イルトイハズヤ アハムヒヲクモ 燃ゆる火も 取りて包みて 袋には 入ると云はずや あはむ日招(を)くも 【口譯】 燃える火を取つて包んで袋に入るといふではないか。さういふ奇蹟が行はれるやうに、天皇にお逢ひ申す日を招き祈つてゐることよ。 【訓釈】 -燃ゆる火も取りて包みて- 「燃」の字、金澤本にのみ「然」とある。説文(十)に「然、燒也」とあり、廣韻(二)に「俗作レ燃」とあつて、後に火扁を加へたものであるが、今は他の諸本に「燃」とあるに従ふ。訓はすべてトモシとあつたが管見にモユルと改めたによる。「包み」の原文諸本いづれも「褁」とある。説文に「裏、纒也」とあつて、裏が正字であるが、龍龕手鑑(一)には褁を俗字とし、新撰字鏡(四)に裏褁の二字をあげて「豆々牟(ツツム)」とある。我が国では主として褁の字を用ゐたものと思はれる。燃ゆる火と云つたのは炭火のやうなものでなくて、炎を立てて燃えてゐるといふ意を強調する爲で、さういふ勢のある火でも取つて包みみて、と云つたのである。 -袋には入ると云はずやあはむ日招くも- 原文「福路」は字音仮名として用ゐたので、袋の意である。「澄」の字、古葉略類聚鈔にはこの歌二ヶ處(一・二〇ウ、四・七オ) に重出してゐるが、共に「登」とある。登であれば「と」の仮名として通例の事であるが、金澤本その他の諸本には「澄」とあつて、それをトと訓む事は異例である。「入るといはずや」は入れるといふではないか、の意。「や」は反語。この下、原文「面」の字をこの句につづけて考にはイルトイハズヤモと訓んでゐる。「吾戀目八面(ワレコヒメヤモ)」(十・二二五五) などのやうに、「八面(ヤモ)」の例はなほ他にもあり、さうすれば「も」は詠歎で、その訓釋も認められるが、その訓の決定は第五句の訓釋と共に考へねばならぬ。しかるにそれが古来の難訓となつてゐて、金澤本には「面智男雲」に相当するところは訓を缺き、類聚古集(十四・五) 「おもてをのくも」とし「お」を消し、紀州本「オモテオノコクモ」、古葉略類聚鈔「モチヲノクモ」、西本願寺本、その他「モチヲノコクモ」とあるが、いづれも何の事ともわからない。そこで以下にいささか小見を述べるが、まづこの問題には三つの考ふべき点がある。 その一つはどの字から第五句と見るべきかといふ事。 その二は「面智」又は「智」を何と訓むかといふ事。 その三は「男雲」を諸注にナクモと訓んでゐるがそれでよいかといふ事。 私はまづその三からはじめたいと思ふ。「男雲」をナクモと訓む事従来の諸注の殆どすべてに一致してゐるところであるが、これには二つの難がある。その一は木下正俊君によつて先般してきせられた。同君は「脣内韻尾の省略される場合」(萬葉 第十号、昭和廿九年一月) の稿の中で、「男」はナムであつて、これを単にナと訓むとすると脣内韻尾を省略する事になるが、そのM韻尾の省略される例は「情有南根畝(ココロアラナム)」(一・一八)、「神南備(カムナビ)」(九・一七七三) などの如く、下につづく音がM・Bなどの子音と重なる場合であつて、今の如くK音につづく例がない、と述べられてゐる。これは傾聴すべき説だと思ふ。即ち男雲をナクモと訓む事は文字の訓読例として認め難いといふ難である。次にかりにナクモと訓むとしてもその語義にまた難がある。その「なく」を「等伎乃之良奈久(トキノシラナク)」(十五・三七四九) などの打消の助動詞「ぬ」の所謂延言とするならば、「なくも」はそれに詠歎の「も」を添へた事になる。しかしさういふ例は存在しない。「不相毛恠(アハナクモアヤシ)」(十一・二六四二) の如きはあるが、それは今の場合と同じではない。「妹毛有勿久尓(イモモアラナクニ)」(一・七五) の如く「なくに」の結びは夥しくあるが、「なくも」の結びはない。それならば、「なく」を形容詞「無し」の連用形だとすればどうかといふに、これも「時友無雲戀度鴨(トキトモナクモコヒワタルカモ)」(十一・二七〇四) の如き例はあるが、詠歎の「も」で結ぶ場合に「なくも」とする事は不合理でもあり、用例もない。即ちいづれの義にとるも「なくも」の語は認め難い。かうした用字例からも用語例からもナクモと訓む事は成立しない。むしろ今迄不問に過されてゐた事が迂闊であつたといふべきである。 然らば何と訓むかといふに、「男」の字は仮名としては「男爲鳥(ヲシドリ)」(十一・二四九一)、「片思男責(カタモヒヲセム)」(四・七一九)、「海部尓有益男(アマニアラマシヲ)」(十一・二七四三) などすべてヲの仮名にのみ用ゐられてゐる字であるから「男雲」をヲクモと訓む事は極めて自然に認められるはずである。仮名用例としても、音訓混淆の仮名もありはするが、右に引用した「男爲(オシ)」、「男責(オセム)」、「益男(マシヲ)」がいづれも二字とも訓仮名である点から見てもわかるやうに、草仮名が発達して仮名字母の音訓混淆が気にならなくなつた平安朝以後の人々が考へるより以上に萬葉時代は仮名の音訓が区別されて用ゐられてゐた〔「多奈和丹」(四・六〇六) 参照〕ので「男雲」をナクモなどは訓まなかつたはずである。殊に次に引用するやうに、「名雲(ナクモ)」の例のある事と較べても、「男雲」はヲクモと訓む事は動かぬ事だと思ふ。また今の場合、上に音仮名の「福路(フクロ)」があり下に訓仮名の「男雲(ヲクモ)」があるといふ事もふさはしい対照をなした用字法と考へられる。かくの如く「男雲」をヲクモと訓む事は、今迄気づかなつた事がむしろ不思議にさへ思はれる程であるにかかはらず、その訓が諸家によつて用ゐられなかつたのは「をくも」の語意に思ひ至らなかつた爲であらうと思ふが、「をく」の語は、 (1) ・・・二上(ふたかみ)の 山飛び越えて 雲がくり 翔りいにきと 帰り来て しはぶれつぐれ 呼久余思乃(ヲクヨシノ) そこに無ければ 云ふすべの たどきを知らに 心には 火さへ燃えつつ 思ひ戀ひ 息づき餘り けだしくも あふことありやと・・・(大伴家持 十七・四〇一一) (2) ・・・月立ちし 日欲里乎伎都追(ヒヨリヲキツツ) うち偲ひて待てど来鳴かぬほととぎすかも(大伴家持 十九・四一九六) の「呼久(ヲク)」「乎伎(ヲキ)」とある「をく」であると私は考へる。即ちその「をく」は古事記上巻天孫降臨の條に「遠岐斯八尺勾璁(ヲキシヤサカノマガタマ)」とあり、神代紀上、天石窟戸の條の第一の一書に「奉招禱也(ヲキタテマツラム)」とあり、記伝(十五)に「凡て遠岐(ヲキ)とは、物を招キ寄セむとする事にて」とあるやうな意である事は、右の家持の長歌が逃した鷹を夢に見て詠んだ作であり、「呼久」の文字はヲクの仮名であると共に又「呼」の字義にもよつてゐると思はれる事を考へても、うなづけるやうに思ふ。なほ集中には、 (3) ・・・正月(むつき)立ち 春の来らばかくしこそ 烏梅乎乎利都々(ウメヲヲリツツ) 楽しきをへめ(大貮紀卿 五・八一五) の「乎利」が紀州本、無点本には「乎岐(ヲキ)」とあり、 (4) ・・・み冬つぎ 春は来れど梅の花 君にしあらねば 遠流人毛無之(ヲルヒトモナシ) (大伴書持 十七・三九〇一) の「遠流」が元暦本には「遠久(ヲク)」とあり、 (5) ・・・春のうちの 楽しきをへば 梅の花 手折乎伎都追(タヲリヲキツツ) 遊ぶにあるべし (大伴家持 十九・四一七四) の「乎伎」がある。(3) は天平二年大宰府にての梅花の宴の作であり、(4) も (5) もその折の作に追和したものであり、その (5) に「乎伎」の語があり、(4) にも元暦本には「遠久」とあり、(1) も紀州本などに「乎岐」とある事は十分注意に値する事である。全註釈には (3) を「乎伎」として「これは梅を招きつつで、梅花を賓遇する意になる。」とし、(4) (5) の例をあげて、「かくの如く」呼応するものがあり、原形は、乎岐、遠久であつたのを、この語を理解しない後人が、易きに就いて、折るとしたのであらう。」と述べられてゐる。大体この説に従ふべきもののやうに思はれるが、(3) と (4) とは作者を異にしてゐるので、なほ断定には慎重を期すべきものだとしても、(5) は (1) (2) と同じく家持の作であり、そこには「手折乎岐」とあつて、その「乎岐」が (3) のやうに「乎利」かと疑ふ余地はなく、殊に家持は憶良と同じく古語を好んで用ゐる癖があつたので、記紀や今の御作に見える「をく」の語を、 (1) (2) (5) でくりかへし用ゐたのであると断ずる事が出来る。いな、むしろ今の御作こそ家持の用語の出典となつたもので、それは、 かからむとかねて知りせば大御船泊てしとまりに標結はましを(額田王 二・一五一) が家持の、 かからむとかねて知りせば越の海の 荒磯の浪も見せましものを(十七・三九五九) となつたのと同じく、神去り給うた天皇を追慕された今の御作を愛誦してゐた家持が、その御作の中の「をく」の語を、逃れ去つた鷹を求める長歌の中に採り用ゐたといふべきであらう。かくの如く観ずれば、いよいよ「をく」の語がここにある事は動かし難い事実となる。さて「をく」の語が決定したとすれば、「をくも」はそれに詠歎の助詞「も」が添へられたもので、「他回来毛(タモトホリクモ)」(七・一二五六)、「飽田志付勿(アクタシツクモ)」(七・一二七七)、「鶯名雲(ウグヒスナクモ)」(十・一八二五) などの「来も」「著くも」「鳴くも」 の類である事はいふまでもない。 かうして「男雲」の訓義が解決せられたとすれば、それを生かすやうに第一第二の点を考察すればよいといふ事になる。 第一の問題は紀州本、西本願寺本など「面」を第五句に入れてイルトイハズヤと訓でゐたのであるが、考に至つて「面」を第四句に入れてイルトイハズヤモと改めたのである。この改訓は考に「智」を「知日」の語としてシルトイハナクモと訓む爲の処置によつたもので、結句を「知ると云はなくも」として「崩ませし君に逢奉らむ術を知といはぬがかなしと御なげきの餘にの給うへる也」と解し、今もそれに従ふ学者もあるが、右のやうな意を単に「知るといはなくも」と云つたと見る事は無理であるのみならず、ナクモの訓が右に述べたやうに既に否定されてゐるのだから考の案は成立せず、第一の問題も問題にならないやうなものであるが、「八面」をヤモと訓む事は、右に述べたやうにその一句としては十分認められるものだるが故に、第二の問題に入る前に一応考察しておく事も意味があらうと思ふ。イルトイハズヤモと八音に訓む事も中間に単独母音節があるから認められはするが、「妹尓不相而(イモニアハズシテ)」(一二五) の條で述べたやうに、類似の句が句の位置により七音ともなり八音ともなるのであつて、第四句には八音句が無いといふわけではないが、同じやうな句が結句に来る場合には八音となり第四句に来る場合は七音となるといふ事実の多い事は確実である。今問題にした「やも」の結びを例にしても、 楽浪の志賀の 大わだ淀むとも昔の人に亦母相目八毛(マタモアハメヤモ) (一・三一) 今日今日と我が待つ君は石川の峽に 交りて有登不言八方(アリトイハズヤモ) (二二四) こもりくの泊瀬娘子が手に巻ける玉は乱れて有不言八方(アリトイハズヤモ) (三・四二四) ま幸くて妹が斎はば沖つ波千重に立つとも佐波里安良米也母(サハリアラメヤモ) (十五・三五八三) 霍公鳥今鳴かずして明日越えむ山に鳴くとも之流思安良米夜母(シルシアラメヤモ) (十八・四〇五二) の如く字余りになつてゐる例が確実と認められるもののみでも十八例は数へられるが、それが全部結句の例のみであつて第四句のものは一例もないのである。その事を見ても今の場合しひてイルトイハズヤモと字余りにする事は異例であつてここはイルトイハズヤとあるが穏やかである。従つて「面」は第五句に入るべきであると認めてまづあやまりはあるまい。 そこで残された第二の問題の内「智」一字を考へる必要は必要はなくなり「面智」を何と訓むかといふ事が最後の問題となる。さて「面智」の二字として訓んだものに長流の管見があり、オモシルナクモとして「つねに相見る顔をいふ也。睦ましくむかへる人のなくなれるをよめる心なり。」と云ひ、私注これにより、全註釈にはオモシラナクモとして「親しみの無いことだ。了解し得ないことだ」と解されてゐるが、これらはいづれもナクモの訓の上に立つてゐるので、既にナクモが否定された以上これらの訓義は成立せず、オモシルにしろオモシラにしろナクモとつづくべきものではない。そこで出直して「をくも」の語がつづく可能性のある説を物色するに、ここに極めて適切な説が既に述べられてゐる事を見出す。それは檜嬬手に、「面智」の二字を「面知日」三字の語としてアハムヒと訓でゐる事である。即ち「さて面知(オモテシル)とは、逢見と云意の義訓なれば其の義を得て、面知日男雲(アハムヒナクモ)と訓むべし。」といひ、 水茎之(ミヅクキノ) 崗乃田葛葉緒(ヲカノクズハヲ) 吹變(フキカヘシ) 面知/兒等之(コラガ) 不見比鴨(ミエヌコロカモ) (十二・三〇六八) の第四句の「面知」をアヒミシと訓み、同じ著者の鐘のひびき巻二にも、 如神(カミノゴト) 所聞瀧之(キコユルタキノ) 白浪乃(シラナミノ) 面知/君之(キミガ) 不所見比日(ミエヌコノコロ) (十二・三〇一五) の「面知」をもアヒミシとし、 對面者 面隠流(オモカクサルル) 物柄尓(モノカラニ) 継而見巻能(ツギテミマクノ) 欲公毳(ホシキキミカモ) (十一・二五五四) の初句「對面者」をアヒミレバとし、それらを例として「面知」をアハムとしてゐる。右の引例の二つの「面知」をアヒミシと訓んだ事は従ひ難く、又ナクモととつづけた事も誤であるが、「面智」を「面知日」の三字の誤としてアハムヒと推定したのは卓見であると思ふ。「智」の文字はチの仮名には用ゐられてゐるが、この字を訓読した例は集中に一ケ所も無い。しかも右に述べたやうに「男雲」が借訓の文字である点からもその上の二字乃至三字はまた訓読されるべきが通例で、ここに「智(ち)」などといふ音仮名があるべきところではない。「知る」意ならば「知」の文字であるべきが集中の例である。しかも「をく」といふ動詞がつづくべき言葉ととして「知る」といふ風な動詞では落ち着かない。そこが名詞であれば最もよく落ち着く。即ち「面智」は「面知日」の誤であつて、「面知」を用言として訓読し、その下に「日」をつけて、何々する日を「をく」といふのであれば、用字としても集中の例に適ひ語意も徹る。その「何々する」を檜嬬手は「あはむ」と推定したのである。卓見と私が云つたのは右のやうな意味に於いてである。かうして前に引用した書紀の用字によりヲクに「招禱」の漢語をあてて「面知日男雲(アハムヒヲクモ)」の一句を解くと、今は亡き天皇に再び謁見せむ日を招禱することよ、といふ事になる。これで上下の語ははじめて契合すると云へるのではなからうか。ただここで念の爲に断つておかねばならぬ事は、右にも述べたやうに守部が例證とした二つの「面知」はアヒミシとは訓み難く、これは上の句の序よりのつづきから見て従来訓み来つたやうに文字のままオモシルと訓むべきものと考へられる事である。しかしその事は、「面知」をオモシルと訓めないといふ事ではない。たとへば「往来」は「往来跡見者(ユキクトミレバ)」(九・一八一〇) の如く、文字のままにユキクとも訓まれると共に、「鶯之(ウグヒスノ) 往来垣根乃(カヨフカキネノ)」(十・一九八八) の如くカヨフと義訓する例が多く、また「忘哉(ワスルヤト) 語(モノガタリシテ) 意遣(ココロヤリ)」(十二・二八四五) の如く「意遣」をココロヤリと訓んでゐるからそれと殆ど同じ「意追」の「追」も「おひやる」の義でココロヤリと訓めるやうであるが、「戀事(コフルコト) 意追不得(ナグサメカネテ)」(十一・二四一四) の如くナグサメと義訓してをるなど、「面知」もまた義訓してアフと訓む事は認められると私は考へる。新考の増訂本に「面知因男雲(アフヨシナクモ)」とされたのはナクモを生かさうとしての誤字説でではあるが、面知をアフとされたのは檜嬬手の説を肯定されたものである。 以上三つの問題を考察した結果、アハムヒヲクモと結句を訓む事とすれば、上四句は真淵の考に「後世も火をくひ、火を蹈むわざを爲といへば其御時在し役小角がともがらの火を袋に包みなどする、恠き術(ワザ)する事有けん」とあるやうに、さうした不可能と考へられる奇蹟も行ふ人があるといふではないか、との意味であつて、その奇蹟の実現を祈つて「逢はむ日招(を)くも」と結んではじめて首尾整ふと云へるのではなからうか。 【考】 右、結句の「逢はむ日」が誤字説の上に立つた義訓である点にいささか不安が残り、「をくも」程の不動性がなく、言葉としても「逢はむ日」よりももつと直接端的な言葉であつてほしいやうな気もせられるのであるが、今はこれ以上の案を得難いので檜嬬手の説に従つて後考を俟つ事とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 一書に曰く、天皇崩(かむあが)りましし時、太上天皇の御製歌(おほみうた)二首 〇原文「一書曰天皇崩之時太上天皇御製歌二首」。代匠記(初稿本)に「太上天皇」を「太后」の誤りとするが、改める必要はない。持統天皇を太上天皇と記すのは、文武朝で、この題詞はそのころ記されたものであることがわかる。「一書曰」という特異なかたちの題詞は前(一四八歌)にもあった。それも天智天皇を近江天皇と記しており、後代の資料から追補されたものであることを思わせるが、ここも同様な編纂上の事由によるのであろう。 燃ゆる火も 取りて包みて 袋には 入ると言はずや 逢はむ日招くも 燃火物《モユルヒモ》 取而褁而《トリテツツミテ》 福路庭《フクロニハ》 入澄不言八《イルトイハズヤ》 面知日男雲《アハムヒヲクモ》 【注】 〇燃ゆる火も- 原文「燃」を金澤本に「然」とする。「然」は「燃」に通ずる文字ではあるが(『金石異体字典』)、集内に通用の例を見ないので、類聚古集・古葉略類聚鈔・紀州本・西本願寺本などによって、「燃」とする。「物」はモの音仮名。燃えている火でさえも、の意。 〇取りて包みて- 原文「褁」は、新撰字鏡に「裏褁」を「苞也纏也豆々牟」と注しているように裏に通ずる文字。玉篇佚文にも「包也」とあってツツムと訓む。 〇袋には入ると言はずや- 「福路」はフクロの借音表記。「入澄」の「澄」は集内でこの一例のみ。古葉略類聚鈔には「登」とあるが、金澤本・紀州本・西本願寺本・類聚古集などによって澄としておく。古典大系補注に「澄の字は蒸韻に属する文字である。蒸韻の文字は隋唐の時代には、日本語のオ列乙類を表記するのに適しなかったが、やや古い時代の六朝の南方音ではオ列乙類を書くに適していた。・・・(中略)・・・澄のように舌音を頭子音に持つ文字は、音の変化が早いのが一般であるのに、澄だけが奈良朝でト乙類に用いられているのは、漢魏頃の古い字音が伝えられていたものであろう」という。イルトイハズヤは、入れると言うではないかの意。ズヤは、自分自身への問いかけを表す。 〇逢はむ日招くも- 原文「面知日男雲」は、金澤本・類聚古集・紀州本・西本願寺本・古葉略類聚鈔などすべての写本に「面智男雲」とあって、難訓の箇所。代匠記(オモシルナクモ)、童蒙抄(オモシロナクモ)、万葉考(シルトイハナクモ)、新考(アフヨシナクモ)、口訳(アハナクモアヤシ)、吉田増蔵:文学昭和八年四月(メニツカナクモ)、全註釈(オモシラナクモ)、注釈(アハムヒヲクモ)などの試訓がある。澤瀉注釈に、「面智」または「智」を如何に訓むか、「男雲」をナクモと訓むものが多いがそれで良いか、と問題点を搾っているのは、適切な処理である。男をナの仮名と見るのは、木下正俊「唇内韻尾の省略される場合」(万葉十号) に指摘するとおり、「畝南(ナモ)」(1・十八)、「南備(ナビ)」(9・一七七三) のように下接する音がMやBなどの子音である場合で、ナクモのようにK音の例はない。また、音訓交用表記という面から見ても、音仮名用例の乏しい「男」を「智(シル)」とか「日(ヒ)」(これは訓によって異なるが) と「雲(クモ)」の間に挿入して音仮名として訓ませようというのは万葉集および上代文献の中で異例の書き方である (稲岡『万葉表記論』第三篇)。「男」は澤瀉注釈に言うとおりヲの訓仮名と見るのが至当であろう。「男雲」をヲクモと訓み「招くも」と解した注釈の訓も至当なものと思う。「面智男雲」を結句の七音に宛て、「男雲」をヲクモとするなら、「面智」は四音に読まれなければならない。オモシルとかメニツクなどと訓む説は男雲(ヲクモ) には続かないので否定されようし、第一「面智」の二字の訓として無理が目立つ。そうした訓に比べると、檜嬬手に「面智」を「面知日」の誤りと考え、「面知とは、逢見と云意の義訓なれば其の義を得て、面知日男雲(アハムヒナクモ) と訓べし」 と記しているのは、優れた着想と言えよう。澤瀉注釈に檜嬬手の「面知日(アハムヒ)」と「男雲(ヲクモ)」を合わせ「逢はむ日招くも」という新訓を得て、「今は亡き天皇に再び謁見せむ日を招禱することよ」と解しているのは、檜嬬手説の修正案である。澤瀉氏自身が「逢はむ日」よりももっと直接端的な言葉であってほしいような気もすると付言しており、別訓もありうると思うが、現在考えられる最良の訓と思う。 【考】奇蹟の実現 結句の定訓を得ないので、歌意も十分につかみきれず、評価も注釈書によって異なるが、第四句までの内容から推察して、不思議な術を行う道士のように奇蹟を実現してほしいという願いを歌ったものと思われる。真淵の考に「後世も火をくひ、火を蹈わざを為といへば、其御時在し役ノ小角がともがらの、火を袋に包みなどする、恠き術する事有けん、さてさるあやしきわざをだにすめるに、崩ませし君に逢奉らん術を知といはぬがかひなし」とあるのは、結句をシルトイハナクモと訓む説によっている点に問題を残すが、さすがに歌の心をとらえたものと言える。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 一書曰、天皇崩之時、太上天皇御製歌二首 一書に曰く、天皇の崩(ほう)じたまひし時に、太上天皇(だいじやうてんわう)の御製(つく)りたまひし歌二首 燃火物 取而褁而 福路庭 入燈不言八面 智男雲 もゆるひも とりてつつみて ふくろには いるといはずやも 智男雲 【脚注】 結句「智男雲」は、解読不能。一首の歌意も把握し難い。「火を中に入れても燃えない袋」というような幻術でもあって、「それなのに崩御した天皇を蘇生させる術はないのか」と嘆いたのであろうか (万葉考)。第四句、「入ると」の「と」の原文は、諸本「澄」 に作る。「澄」では意味不通。「燈」に改める。古葉略類聚鈔の「登」を採ることも可能。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 一書曰、天皇崩之時、太上天皇御製歌二首 一書に曰く、天皇崩ります時に、太上天皇の製(つく)らす歌(みうた)二首 燃火物 取而褁而 福路庭 入燈不言八面 智男雲 もゆるひも とりてつつみて ふくろには いるといはずやも 智男雲 【頭注】 入るといはずやも-原文「入燈不言八面」の「澄」は音ヂヨウで助詞ト(乙)を表す文字として適当でない。登と同音の燈の誤りとみて意改する。以上四句は、不可能と思えることさえも可能とする不思議な方術さえあるというではないか、それなのに崩御した天皇を復活蘇生させることができなくて残念だという気持ちを表すのであろう。 智男雲-原文のまま。読み方不明。 頭注◆ この歌の上四句にに見られる奇蹟的な叙述については、漢代以来、中国に流入普及した西域・インドの幻術とのかかわりが考えられるかもしれない。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 結句諸説 | [註釈] モチヲノコクモトハ、モツヘキヲノコモ、キタルトイフ歟。 [管見] おもしるなくも をもしるは、つねに相見る顔をいふ也。睦ましくむかへる人の、なくなれるをよめる心なり。面しる子らか見えぬ共よめり。 [拾穂抄] おもしるなくも おもしるなくもとは常に顔見し人のなく成しと也おもしる子らか見えぬともよみし詞と同シ [代匠記] 結句はオモシルナクモとよむべし、第十二に、面知《オモシル》君が見えぬ此頃とも、又面知兒等《オモシルコラ》が見えぬ比かもとよめるは、面知とは常に相見馴る顔を云なり、幸に仙覺抄に智を知に作れり、此今按に付ても二義あるべし、一つには、如何なるもゆる火をも能方便してつゝみつれば、袋に入れても持と云に非ずや、寶壽がぎりましまして昇霞し給をば、冥使の來る時如何にも隱し奉るべき方なければ、明暮見馴奉し龍顔を今は見參らせぬが悲しき事とよませたまへるか、二つには、如何なるもゆる火も方便ある物は裹て袋に入るやうに威勢ましませし君も、無常のさそひ參らせて何所《イツチ》か率《ヰ》て奉けん、又も見えさせ給はずとや、燃る火を袋に入るといふ事物に見えたる事歟、諺などを讀せ給へる歟、後人當v考、 [童蒙抄] 面智男雲 古本印本共にもちおとこくもとよめり。如v此の歌詞あらんや。しかれども仙覺律師の釋に、葬禮のならひ二たび物をあらため用ゐることを忌む事なれば、死人の枕上にともしたる火を以て葬所にて用ゐる故、それをもつべきをのこもきたるとの意歟と注せり。如v此釋しても全體の歌の意不v通也。よりて當家の傳はおもしろなくもよみて、全體の歌の意通する也。御葬送の時乏物どもをとりつゝみて、袋に入るゝといふ事は、おもしろからぬ物うき事と云の歌の意と聞ゆる也 智の字一本に知の宇に作れるもあり。因v茲則一僻案の釋あり。もし今の本の智の字知白の二字の合したる歟。なき本によりておもへば白の字を脱したる歟。智の字一字ならば、落すべき事にもあらねど、知白の二字故脱落あるまじきにもあらず。もしゝからば下の句の意別案あり。入澄不言八百知白男雲を、いるといふことのやもぢしらなくともいふ義ならんか。男雲とかきてなくもとよませる事は此集中數多也。やもぢはやみぢなり。ともし物とり包みてふくろに入といふことの、やみぢはいかやうのところぞ。したひ行たまひてしり給はんとの意歟。しらなんとはよもつくにゝ追ひ行て、そのみちをしり給はんとねがひたまふ意なり。御かなしみのあまり、やみぢをもしろしめしたきと、ねがひ給ふ義歟 [万葉考] 不言八面《イハズヤモ》、 【八面をやものかなとせしは、(卷四)にもあり、】 知曰《シルトイハ》、 今本智と有は、知曰二字なるべし、 男雲《ナクモ》、 こは借字にて、無毛《ナクモ》の意なり、後世も火をくひ、火を蹈わざを爲といへば、其御時在し役ノ小角がともがらの、火を袋に包みなどする、恠き術《ワザ》する事有けん、さてさるあやしきわざをだにすめるに、崩ませし君に逢奉らん術を知といはぬが、かひなしと、御なげきの餘にの給へるなり、 [略解] 智一本知に作る。今本イルトイハズヤ、モチヲノコクモと點あれど由なし。翁試みに言はれしは、澄は登の誤り、智は知曰二字ならむか。然らばイルトイハズヤモ、シルトイハナクモと訓むべし。是は後世火をくひ、火を踏むわざを爲なれば、其御時在りし役ノ小角か輩の、火を袋に包みなどする恠き術する事の有りけむ。さてさる怪きわざをだにするに、崩り給ひし君に逢ひ奉らむ術を知ると言はぬがかひなしとにや。契沖云、卷十二に、面知君が見えぬ此ごろとも詠みたれば、智は知の誤りにて、イルトイハズヤ、オモシルナクモと訓まむか。見なれ奉り給へる御面わの見え給はぬを戀奉り給へるなりと言へり。智を知に作れる本もあれば、面知とせむ方も然るべくも思はるれど、猶穩ならず。考ふべし。 [古義] 入澄不言八《イルトイハズヤ》。面智男雲。智ノ字、拾穗本并一本には、知と作り、御歌ノ意、解得難し、(岡部氏が云るは、福路庭《フクロニハ》は、袋に者なり、澄は騰か、智は知曰ノ二字なるべし、男雲は借リ字にて無毛《ナクモ》の意なり、されば第四五ノ句、イルトイハズヤモシルトイハナクモと訓べし、後ノ世も、火をくひ、火を蹈わざを爲といへば、其ノ御時在し、役ノ小角がともがらの、火を袋に包みなどする、恠き術する事有けむ、さてさるあやしきわざをだにすめるに、崩リませし君に、逢奉らむ術を知といはぬがかひなしと、御なげさの餘リに、のたまへるなりと云り、いかゞあらむ、契冲がいへりしは、智は知の字なるべし、イルトイハズヤオモシルナクモと訓むか、おもしるは、常にあひみる顔をいふことなり、第十二に、おもしる君がみえぬ此ごろとも、おもしるこらが見えぬ比かもともよめり、もゆる火だにも、方便をよくしつれば、ふくろに取いれてかくすを、寶壽かぎりましまして、とゞめ奉るべきよしなくて、見なれたてまつり給へる、御おもわの見えたまはぬを、こひ奉りたまへるなりと云り、これもいかゞなり、猶考フべし、 [檜嬬手] 「面知日男雲」今本、面智男雲とある、智は知日二字を一字に寫し誤りたる也。さて面知《オモヲシル》とは、逢見と云ふ意の義訓なれば、其の義を得て面知日男雲《アハムヒナクモ》と訓むべし。十二【二十五】水莖之崗乃田葛葉緒吹變面知兒等之不見比鴨《ミヅグキノヲカノクズハヲフキカヘシアヒミシコラガミエズコロカモ》とある、此の面知《アヒミシ》と合せて知るべし。 [口訳万葉集] 袋には入ると言はずや。會はなくもあやし さすれば、死んだ人の魂も、留めて置かれない筈はないのに、會はれないのは、どうも不思議だ。 [全釈] 智男雲《シルトイハナクモ》――考に、智を知曰の二字にして、シルトイハナクモとよんだのに從ふ。面を五の句に入れて、オモシルナクモとよむのも、又、面知日としてアハムヒナクモとよむのも、面知因としてアフヨシナクモとよむ説も、賛成出來ない。面知をアフとよんだ例は一つもない。 [全註釈] 面智男雲《オモシラナクモ・モシルトイハナクモ》 次に五句は、考には、面を上の句につけ、智を知曰の誤として、シルトイハナクモと讀んでいる。これによれば、知るとは言わないことだの意になり、火でも嚢にはいるというのに、君の崩御のことは、了解に苦しむの意となる。原文のままならば、オモシラナクモと讀むほかは無い。オモシルは、集中、「如v神《カミノゴト》 所v聞瀧之《キコユルタキノ》 白浪乃《シラナミノ》 面知君之《オモシルキミガ》 不v所v見比日《ミエヌコノゴロ》」(卷十二、三〇一五)、「ミヅグキノヲカノクズハヲフキカヘシオモシルコラガミエヌコロカモ」(同、三〇六八)の用例があり、知り合いの意に使用されている。それでオモシラナクモは、親しみの無いことだ、了解し得ないことだの意になるのであろう。 [評釈] 四五句、白文「入登不言八面知曰男雲」で、「登」は古葉略類聚鈔による。他の諸本は「澄」に作る。「知曰」は諸本「智」とあり、このままでは解せられないので、代匠記、檜嬬手、新考は「面」以下を一句とし、上をイルトイハズヤとし、五句は代匠記「面智《オモシル》ナクモ」檜嬬手「南知日《アハムヒ》ナクモ」新考「面知因《アフヨシ》ナクモ」とし、考は「面」を四句につけ、「知曰《シルトイハ》ナクモ」と改めてゐる。暫く考により、後考を俟つこととしたい。 [注釈] 面知日男雲 アハムヒヲクモ 上記「注釈」詳細 [全注] 面知日男雲《アハムヒヲクモ》 逢はむ日招くも- 原文「面知日男雲」は、金澤本・類聚古集・紀州本・西本願寺本・古葉略類聚鈔などすべての写本に「面智男雲」とあって、難訓の箇所。代匠記(オモシルナクモ)、童蒙抄(オモシロナクモ)、万葉考(シルトイハナクモ)、新考(アフヨシナクモ)、口訳(アハナクモアヤシ)、吉田増蔵:文学昭和八年四月(メニツカナクモ)、全註釈(オモシラナクモ)、注釈(アハムヒヲクモ)などの試訓がある。澤瀉注釈に、「面智」または「智」を如何に訓むか、「男雲」をナクモと訓むものが多いがそれで良いか、と問題点を搾っているのは、適切な処理である。男をナの仮名と見るのは、木下正俊「唇内韻尾の省略される場合」(万葉十号) に指摘するとおり、「畝南(ナモ)」(1・十八)、「南備(ナビ)」(9・一七七三) のように下接する音がMやBなどの子音である場合で、ナクモのようにK音の例はない。また、音訓交用表記という面から見ても、音仮名用例の乏しい「男」を「智(シル)」とか「日(ヒ)」(これは訓によって異なるが) と「雲(クモ)」の間に挿入して音仮名として訓ませようというのは万葉集および上代文献の中で異例の書き方である (稲岡『万葉表記論』第三篇)。「男」は澤瀉注釈に言うとおりヲの訓仮名と見るのが至当であろう。「男雲」をヲクモと訓み「招くも」と解した注釈の訓も至当なものと思う。「面智男雲」を結句の七音に宛て、「男雲」をヲクモとするなら、「面智」は四音に読まれなければならない。オモシルとかメニツクなどと訓む説は男雲(ヲクモ) には続かないので否定されようし、第一「面智」の二字の訓として無理が目立つ。そうした訓に比べると、檜嬬手に「面智」を「面知日」の誤りと考え、「面知とは、逢見と云意の義訓なれば其の義を得て、面知日男雲(アハムヒナクモ) と訓べし」 と記しているのは、優れた着想と言えよう。澤瀉注釈に檜嬬手の「面知日(アハムヒ)」と「男雲(ヲクモ)」を合わせ「逢はむ日招くも」という新訓を得て、「今は亡き天皇に再び謁見せむ日を招禱することよ」と解しているのは、檜嬬手説の修正案である。澤瀉氏自身が「逢はむ日」よりももっと直接端的な言葉であってほしいような気もすると付言しており、別訓もありうると思うが、現在考えられる最良の訓と思う。 [新体系] 結句「智男雲」は、解読不能。一首の歌意も把握し難い。 [新全集] 智男雲-原文のまま。読み方不明。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 巻二161 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 校本萬葉集
|
||||||||||||||||||||||||||
| 活字附訓本 | 活字附訓本 | 活字附訓本 (国立国会図書館蔵書)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 諸注引用 | 拾穂抄 | きた山にたなひく雲の青くものほしわかれゆき月もわかれて 向南山(のイ) 陣雲之青雲之星離去月牟離而 きた山に(のイ) たなひく雲の 青雲たな引て星にも月にも別し心也帝の別によせて歎給心なるへし |
|||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | 向南山陣雲之青雲之星離去月牟離而《キタヤマノタナヒクヽモノアヲクモノホシワカレユキツキモワカレテ》 此御歌も亦解しがたし、北山よりたなびき出る雲間に星も月も雲に連て見ゆるが雲の消移り行まゝに星も月も雲に遠ざかる如く、萬の御名殘も月日を經て替り行く由などにや、六帖に雨ふれば北にたなびく白雲の云云、向南は義をもてかけり白からずと云が黒き義なるやうの心なり、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 童蒙抄 童子問 |
向南山陣雲之青雲之星離去月牟離而 童子問 此御製は仙覺注釋もなし。いかなる御製の意にや。 答 僻案兩義あり。先訓のまゝにて解すれば、向南山をきたやまと訓じて、群臣は天皇のしりへに位すれば、群臣の列陳する位を北山と比して、陳雲は列陳の雲客に比し、たなびく雲のと詠給ふなるべし。青雲之とは猶白雲といはんがごとし。今も白馬を青馬といひ、古語にも白といはむとて青雲の冠辭例有。されば御葬送群臣の服皆白きを用られたるによりて、青雲のと有歟、もし青は素の誤字にて、直にしら雲を傳寫□[言+爲]れる歟。いづれにても強て義に害有べからず。星離去は三台星も天皇にしたがひず離去、月卿も離去て從ひ奉らず、天宮に神あがりしたまふことを悲みたまひて詠させ給ふと見る也。此一義の僻案也。又一義の僻案には、向南山の三字をおほろやまと訓。いかにとなれば、天皇は南面の位なれば、天皇まします處大内山と稱すればすなはち皇居の地を指て、向南山と書て大内山と詠給へる歟、もしは此天皇の山陵大内山なれば、葬送奉る山陵を大内山と詠給ふるかなるべし。陳雲は陳列の雲客を比して、雲の上人の陳列して送り奉り、三台星月卿もしたがひ奉りしに、むなしく大内山に葬奉りては、陳列する事もなく、月も星も雲も皆とゞまらずしてわかれ去りて、獨天皇の尊骸を大内山にのこしおき奉りて退去することをなげき給ふ御製と見る也。青雲之三字、もし雲の字は字形相似たれば、霄の字の誤にあらずや。霄の字ならば青霄之三宇おほぞらのと訓て、星離去月牟離山と云、星と月とにかけ給へる冠句にしてみるべし。此兩義汝好む所にしたがふべし。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 童蒙抄 | 向南山陣雲之青雲之星離去月牟離而 北山に、たなびくゝもし、青ぐもし、ほしはなれゆき、月もはなれて 向南山 きた山と古點をなせる尤よき訓なり。又大内山とも訓すべきか。天子は南面してたゝせ給ひ、臣は後に從ふなれば向南山とは禁廷をさしていひし御詠と見えたれば、禁中を大内山ともいへば、直ちに禁中をさしてのたまひし歌の意にもきこゆる也 陣雲之 この陣の字つらなるともよむべき歟。諸司百官の禁庭につらなるの義をよそへたまふか。然れどもくもとある故、つらなるよりは古點の通たなびく雲しかるべからんか。好むところにしたかふべし。たなびくにてもつらなるにても意はおなじ事なるべし。雲之とある之の字を訓によまん事きゝよけれども、青雲のほしとつゞく事いかゞなり。此歌は月卿雲客の事をよそへよみ給ふ事なれば、青雲のほしとは、ほしにかぎるところいかゞ也。よりて助字に見てしとはよむなり。もしくは毛のあやまり歟。たなびく雲も青雲もとよみたまへるか、しかれば義安き也 星離去月牟離而 三公九卿月卿雲客悉くはなれ奉りて、行てかへらせ給はぬよみぢへ、天皇たゞ御ひとりいてますことの、果敢なくかなしき御事におぼしめす、かぎりなき御かなしみの御歌也 歌の意は右に釋するごとく、諸臣悉くはなれ奉り、かくれまします事を、いたみかなしませ給ふて、よませたまへるいともあはれなる御歌也 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉考 | 向南山《キタヤマニ》、陣雲之《タナビクモノ》、青雲之《アヲグモノ》、 青は白なり、さて雲の星をはなるとかゝる、 星離去《ホシハナレユク》、月毛《ツキモ》、 今本牟と有は誤、 離而《ハナレテ》、 后をも臣をもおきて神あがりませるを、月星にはなれて、よそに成行雲に譬給へり、さて此二首は、此大后の御歌のさまならず、から文學べる男のよみしにや、されども歌は端詞によりてとくなり、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | 向南山。陣雲之。青雲之。星離去。月牟離而。 きたやまに。たなびくくもの。あをぐもの。ほしはなれゆき。つきもはなれて。 星雲は白雲なり。さて雲の星を離ると懸かれり。牟は毛の誤りなるべし。是は后をも臣をも、おきて神あがりませるを、月星に放れて、よそに成り行く雲に譬へ給へりと翁言はれき。宣長云、星雲之星は青天に有る星なり。雲と星と離るるには有らず、二つの離はサカリと訓みて、月も星もうつり行くを云ふ。ほどふれば星月も次第に移りゆくを見給ひて、崩り給ふ月日の、ほど遠く成り行くを悲しみ給ふなりと言へり。是おだやかなり。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 攷證 | 向南山《キタヤマニ》。陣雲之《タナビククモノ》。青雲之《アヲクモノ》。星《ホシ》離《サカリ・ワカレ》去《ユキ》。月牟《ツキモ》離《サカリ・ワカレ》而《テ》。 -向南山《キタヤマニ》。 きた山とよむは、義訓也。名所にあらず。南に向ふは、北なれば、北方の山をのたまへり。顧瑛詩に、料應堂北梅花樹、今歳聞時向v南云々などあるにても、南に向ふは北なるをしるべし。 -陣雲之《タナヒククモノ》。 陳は、義訓なり。玉篇に、陳除珍切、列也布也云々と見えて、たなびくとは、本集三【卅二丁】に、白雲者行憚而棚引所見《シラクモハユキハヽカリテタナヒケルミユ》云々。四【五十一丁】に、春日山霞多奈引《カスカヤマカスミタナヒキ》云々。この外、集中いと多く、輕引、霏□[雨/微]、桁曳などの字をも、よみて、そらに物など引はへたらんやうに、引わたし覆《オホ》ふをいふこと也。されは、陳の字をかける也。さて古事記上卷に、八重多奈雲云々。本集八【五十五丁】に、棚霧合《タナキラヒ》云々。十三【廿四丁】に、柳雲利《タナクモリ》云々などある、たなも、たなびくといふと同じ。 -青雲之《アヲクモノ》。 宣長云、青雲といへる例は、祈年祭祝詞に、青雲能靄極《アヲクモノタナヒクキハミ》、白雲能墜坐向伏限《シラクモノオリヰムカフスカキリ》云々。萬葉十三【廿九丁】に、白雲之棚曳國之《シラクモノタナヒククニノ》、青雲之向伏國乃《アヲクモノムカフスクニノ》。十四【廿八丁】に、安乎久毛能伊氐來和伎母兒《アヲクモノイテコワキモコ》云々。十六【廿九丁】に、青雲乃田名引日須良霖曾保零《アヲクモノタナヒクヒスラコサメソホフル》。そもそも青色の雲は、なきものなれども、たゞ大|虚空《ソラ》の、蒼《アヲ》く見ゆるを、しかいふ也云々といはれつるがごとし。史記伯夷傳に、青雲之士云々。南史に、意在2青雲1云々。淮南子に、志屬2青雲1云々などあるも、みな虚空をさして、青雲とはいへる也。 -星《ホシ》離《サカリ・ワカレ》去《ユキ》。 宣長云、青雲之星は、青天にある星也。雲と星と、はなるゝにはあらず。二つの離は、さかりと訓て、月も星も、うつりゆくをいふ。ほどふれば星月も次第にうつりゆくを見たまひて、崩たまふ月日の、ほど遠くなりゆくを、かなしみ給ふ也云々といはれつるがごとく、王勃勝《(マヽ)》王閣詩に、物換星移幾度v秋云々。杜牧詩に、經2幾年月1換2幾星霜1云々などある、星の字も、年月の事なり。離を、さかりとよむ事は、上【攷證一上四十七丁】に見えたり。月牟《ツキム》の、牟は、毛の誤り也とて、考には月毛と直されたれど、牟《ム》と毛《モ》と音かよへば、牟を、もとよまん事論なし。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 〔向南山《キタヤマニ》。陣雲之《タナビククモノ》。青雲之星離去《アヲクモノホシサカリユキ》。月毛離而《ツキモサカリテ》〕 〇向南山《キタヤマ》は、北山《キタヤマ》なり、意を得て書る字なり、西渡《カタブク》丸雪《アラレ》青頭鷄《カモ》など書る類なり、 ○陣雲之《タナビククモノ》は、青雲をいはむためなり、さて青雲は、たゞ天《ソラ》のことにて、たなびくとはいふまじけれど、雲といへるちなみに、たなびく雲の云々、といひつらね給へるなり、 ○青雲之《アヲクモノ》云々、本居氏云、青雲之星は、青天にある星なり、雲と星とはなるゝにはあらず、二ツの離は、さかりと訓て、月も星もうつり行をいふ、ほどふれば、星月も次弟にうつりゆくを見賜ひて、崩給ふ月日のほど遠く成行を、悲み給ふなりと云り、(岡部氏が、后をも臣をもおきて、神あがりませるを、月星にはなれて、よそに成行雲に譬賜へり、と云るはいかゞ、) ○月毛離而《ツキモサカリテ》(毛ノ字、舊本には牟と作り、今は類聚抄に從つ、但し五ノ卷に、多布刀伎呂可儛《タフトキロカモ》、貞觀儀式宣制に、在牟可止奈无《アラムカトナモ》、新撰萬葉に、郁子牟鳴濫《ウベモナクラム》、また老牟不死手《オイモシナズテ》、また音丹佐牟幡似重鉇《コヱニサモハタニタルカナ》、また風牟間南《カゼモトハナム》、また松葉牟曾譽丹吹風者《マツハモソヨニフクカゼハ》、延喜六年書紀竟宴ノ歌に、無止女佐理世波《モトメサリセバ》、また爾己禮留多見无《ニゴレルタミモ》などあれば、儛無无牟を、毛に通用ることもありしなるべし、古代の平假名に、かならず毛なるべき所を、んとかける事多し、んは无のなだらかになれるにて、これも无を、毛に通ハシ用ひし、一ツの例なり、) は、月も遠ざかりてなり、月とは、月次の月をいふ、 ○御歌意は、崩御《カムアガリ》ましゝは、きのふ今日のことゝ思ふに、いつしか星うつり、月日も遠ざかりて、次第《ツギツギ》に久しく成行めれど、なほ哀悲の心は、うすらぐよしもなくて、いとゞ堪がたく思はるゝ、とのたまふにや、此ノ兩首、岡部氏もいへりし如く、口風いかさまにも、こちこちしく聞えたり、持統天皇の御製のふりにあらず、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 檜嬬手 | 向南北《アマノガハ》、陣雲之《タナビククモノ》、青雲之《アヲグモノ》、星離去《ホシサカリユク》、月毛離而《ツキモサカリテ》。 ●「向南北」今本北ヲ作リv山ニて、きたやまにと訓みたれど、二三句の蒼天を云へれば、山にたなびく雲にあらず。たとひ、此句向v南《ムカヒミルニ》として、よし野山とよむとも、山に棚引く雲としては、蒼天《アヲグモ》と云ふに續かず、句を妨げて害あり。故に古本又由阿本等に、向南北陣雲とある五字の意を、つらつら考るに、今俗に天漢《アマノカハ》と云ふもの、初めは東西に亘り、九十月より南北に向ひて、實に、一陣の雲とも云ふべきものなれば、初二句を合せて、あまのかはたなびくくもとはよみつ。漢國にて天漢・銀河など云ふも、即比事なるを、あまのかはと訓み來つるも、久しき事なりければ妨げなし ●「青雲之、星離去」蒼天の星と云ふにて、かの銀河と云ふものゝ白ケたるを、姑《シバラ》く陣雲《タナビククモ》とは云へど、實は蒼天の星群なれば、行道の轉じゆくを離《サカル》と云ふ也。さて蒼天を青雲と云ふは、蒼隈《アヲクマ》にて、空を累ねて遠く見る故に、蒼々と見ゆるなれば、隈《クマ》と云ふ。久萬《クマ》は古利《コリ》にて、氣の凝りたる也。祈年祭祝詞に、青雲能靄極《アヲクモノタナビクキハミ》十三【二十九】青雲之|向伏國乃《ムカブスクニノ》十六【二十九】伊夜彦《イヤヒコ》のおのれ神さび青雲の田多引日《タナビクヒ》すら、こさめそぼふる」此等皆晴天の空を云へり ●「月毛離而」こは空の月にはあらず。月次《ツキナミ》の月の遠ざかりて星の行道の轉じゆくよし也。按ふに此《コ》の間《ホド》は陰陽師の行はれそめつるさかりなりければ、彼の人死ねば、天の星となると云ふことを、女心に信じ給ひて御心あてに、御魂の星は此星ぞと、銀河の中に見とめて其夕べより慕ひましけんを、月比《ツキコロ》の經ゆくまゝに、其星の遠ざかりゆくを歎き給ふなるべし。是にて一首の意は察すべし。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 口訳 | 神南備《カムナビ》に天霧ひつゝ、青雲の星|離《サカ》り行き、月も離りて 神南備山に、眞黒に霧が棚引いて、その爲に、星も散り散りに、見えなくなり、月も遠く見えなくなつてしまつた。 (何ととりとめたことのない悲しみを、天體に託して歌はれたのである。) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 北山に たなびく雲の 青雲の 星さかりゆき 月もさかりて 向南山《キタヤマニ》 陣雲之《タナビククモノ》 青雲之《アヲクモノ》 星離去《ホシサカリユキ》 月牟離而《ツキモサカリテ》 天子樣ガ崩御ノ後、何時ノ間ニカ、(向南山陣雲之) 大空ノ星モ移リ行キ、月モ移ツテ行ツテ月日ガ大分經ツタ。シカシ私ノ胸ノ中ノ悲シサハ少シモ滅ジナイ。 ○向南山《キタヤマニ》――向南をキタとよむのは義訓である。北山は山の名ではない。 ○陣雲之《タナビククモノ》――陣は陳に作る本もある。この二字は常に相通じて用ゐられてゐるから、どちらでもよい。布列の意である。この句をツラナルクモノとよむ説があるが、雲に列なるといふのは、普通でないから、タナビクの方がよい。卷十六に青雲乃田名引日須良霖曾保零《アヲクモノタナビクヒスラコサメソボフル》(三八八三) とあるから、猶更である。陣の字は本集中他に見えぬ字である。陳はチの假名に用ゐられてゐる。上の二句は青雲之《アヲグモノ》の序詞。 ○青雲之《アヲグモノ》――青空説と白雲説と二つあつて、いづれとも決し難い。古事記に「青雲之白肩津《アヲクモノシラカタノツ》」として、白の枕詞に用ゐてあるのは、白は著《シル》しの意で青空の鮮かなことに言ひかけたのだと宣長は言つてゐる。祈年祭祝詞に「青雲能靄極白雲能墜坐向伏限《シラクモノタナビクキハミシラクモノオリヰムカブスカギリ》」とあり、卷十三には白雲之棚曳國之青雲之向伏國乃《シラクモノタナビククニノアヲクモノムカブスクニノ》(三三二九) とある。卷十四には安乎久毛能伊氐來和伎母兒安必見而由可武《アヲクモノイデコワギモコアヒミテユカム》(三五一九) といふやうな用例もある。これらから論ずれば、どちらにもなるので、新考の青雲はブリユーでなくペールであると言ふ説は、最も新説であらうが、卷十六の青雲乃田名引日須良霖曾保零《アヲグモノタナビクヒスラコサメソボフル》(三八八三) などは、どうしても、晴天でも小雨が降るといふ意でなければならぬと思ふ。もし、この青雲を、白雲の薄いペールの雲とするならば、さういふ雲を後世でも何とか呼んだであらうが、その所見が更に無い。又青雲を白い薄雲とするならば、快晴の場合は、古代人は何といつて、それを讃へたらう。これも一寸見當らぬやうである。天原雲無夕爾《アマノハラクモナキヨヒニ》(一七一二) といふやうな言ひ方もあるが、青雲のたなびく空といふ語が用ゐられるのが常であつたのではあるまいかと思はれる。扨この歌では青空にある星と下につづくのである。 ○星離去月牟離而《ホシサカリユキツキモサカリテ》――離をサカリとよむのは、一五〇に述べた通りだ。牟は毛の誤。正辭が牟をモとよむのだと言つたのは僻論であらう。本集には牟をモとよんだ例は他にない。星を新考に日毛の誤としたのはよくない。 〔評〕月日の經つのを月星の移るを以てあらはしたのは、純日本思想ではないやうだ。支那の陰陽説などの影響があるやうに思はれる。考にはこの二首は持統天皇の御製の風でなく、こちごちしい歌だといつてゐるのは、予も同感である。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 北山に たなびく雲の 青雲の 星|離《さか》り行き 月を離りて 向南山《キタヤマニ》 陳雲之《タナビククモノ》 青雲之《アヲグモノ》 星離去《ホシサカリユキ》 月矣離而《ツキヲサカリテ》 【譯】北山に續いている雲の青雲が、星を離れ行き、月をも離れて、大空に向かうことである。 【釋】 向南山 キタヤマニ。向南山は、義を以つて北山に當てる。天武天皇の明日香の眞神が原の山陵は、南面しており、南方からこれを見そなわして詠まれたのであろう。 陳雲之 タナビククモノ。陳は細井本に陣に作つている。陳陣は、もと同字であつて、義においては同じである。陳は玉篇に「列也、布也」とあるに依つて、雲についていうので、タナビクと讀むが、ツラナルとも讀まれる。意は御陵の山にたなびいている雲である。 青雲之 アヲグモノ。アヲグモは、青天をいう。 「アヲグモノタナビクハミシラクモノオリヰムカブスカギリ」(祈年祭祝詞)、 「シラクモノタナビククニノアヲグモノムカブスクニノ」(卷十三、三三二九)、 「アヲグモノタナビクヒラコサメソボフル」(卷十六、三八八三)などがある。 たなびく雲の青雲とは疊語で、同じ雲である。青雲ノ、下の句に對して主格を成している。 星離去月矣離而 ホシサカリユキツキヲサカリテ。 ホシサリユクツキヲハナレテ(神) ―――――――――― 星離去月乎離而《ホシサカリユクツキヲハナレテ》(類) 星離去月牟離而《ホシワカレユキツキモワカレテ》(西) 星離去月牟離而《ホシハナレユキツキモハナレテ》(童) 星離去月牟離而《ホシサカリユキツキモサカリテ》(玉) 日毛離去月毛離而《ヒモサカリユキツキモサカリテ》(新考) 星を離れてゆき、月を離れてというは、竝立の云い方で、星や月を離れてということになる。意は、青雲が星や月を離れて天空高く昇るというので、天皇の神靈についていうのであろう。但し訓解ともに諸説が多いのは、結局一通りでは解釋に苦しむからである。星を日毛の誤とする新考の説は、通りがよい。 【評梧】この歌、以上の如く解しておいたが、これも難解の歌で、正しい解釋を知らない。大陸思想の影響を容れているともいわれるが、それも確でない。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | 北山につらなる雲の青雲の星|離《さか》りゆき月も離《さか》りて 〔譯〕 北山に連なつてゐる青空の、星も移り、月も移つてゆく。 〔評〕 この歌も異説の多い歌であるが、右のやうに解いた。明け暮れ眺め給ふ北山、それも恐らく御陵の方角であらうが、そこに見られる星、月の移つたことを御覽になつての詠歎で、これをただ萬物の轉變したといふ概念的ないひ方と見るべきではなく、見るもの聞くものにつけて、御在世の時を懷しまれる御心持とし、大らかで美しい自然描寫で、「月も離りて」といひさしてをられる、深い歎きを味はひたいと思ふ。 〔語〕 ○北山 山の名ではない。北方の山の意。 ○青雲 白雲の義といふ説もあるが、「青雲のたなびく日すらこさめそぼ降る」(三八八三)などの用例から見て、青天、青空の義とする説に從ふ。 〔訓〕 ○北山 白文「向南山」で、檜嬬手は「向南北」の誤とし、「アマノガハ」と訓み、人が死ねば魂は星となるといふのを信じて、銀河の中の或星が、月の經つにつれて次第に動いて行くと解してゐるのは珍しい解ではあるが、從ひかねる。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 向南山 陳雲之 青雲之 星離去 月矣離而 キタヤマニ タナビククモノ アヲクモノ ホシハナレユキ ツキヲハナレテ 北山にたなびく雲の青雲の星離れゆき月を離れて 【口譯】 北山にたなびひてゐる雲の、その青雲が、星を離れて行き、月をも離れて-大空高く飛び去るやうに、我が大君の御霊は神去り給ううて-。 【訓釈】 -北山にたなびく雲の青雲の- 原文「向南山」を類聚古集(十四・六) にカムナミヤマとし、紀州本にカムナヤマとある他は諸本キタヤマと訓んでをる。向南風を北風といひ、山の南を山陽といふ事はわかるが、向南山といふ表現は少しおちつきかねるやうに見える。玉の小琴追考に「向南は誤字には有ざるか、こは山の名なるべき也。」といひ、恵岳の選要抄では北では月が見えないといふ理由で「明日香の都より南にあたる葛城山は南向にて南おもての山にて明日香のかたはうら也」と云つて、カツラキニと訓んでゐるが、その訓によつて金子氏は天武天皇、日並皇子の陵墓の方角の山としたなど、向南山をキタヤマと訓む事に不安をもつての事かとも考へられる。しかしこの用字については小島憲之君が「毛詩などにも見える如く南は明るい陽(ヤウ)を北は暗い陰(イン)を示し、顔延年の宋文皇帝元皇后哀策文(文選哀下) の中に、『南背2国門1、北首2山園1』と見えるのも単に対句としての南と北の対比だけではなく、北に陰を示してゐるのである。つまり『向南』は北であり、同時に北と対比の南をも出してハツキリ陰なる北を出して来たわけで」(「萬葉人の庖厨に漢籍あり」国語・国文 第廿二巻第七号、昭和廿八年七月) と述べられてゐるやうに、向南山と書いてキタヤマと訓ませ、どこにかかる雲も同じであるが、特に陰を示す北山にたなびく、と云つたのである。たなびくの原文流布本に「陣」とあるが、金澤本その他の写本多く、「陳」とある。玉篇に「陣」は「本作レ陳」とあり、「陳」 は「列也布也」 とあつてもと同字であり、金澤本・類聚古集等にはツラナル、古葉略類聚鈔(四・七オ)、西本願寺本その他にはタナビクとある。「蒙」(十二・三一八八) の字をもタナビクと訓むやうに、今も、「列なる」 の義をとつてタナビクと訓む。次に青雲であるが、宣長は青空の意と解き、それに従ふ人が多い。しかし吉井巖君は当時の支那の詩文に見える青雲が空でなくて雲である事を明らかにし、本集をはじめ我が国上代の例も雲と見るべく、今の例は難解であるが、この作には特に中国文学との関連が認められるのでやはり雲と思ふという説 (「青雲攷」萬葉 第五号、昭和廿七年十月) を発表されてゐる。たとへば、 白雲の たなびく国の 青雲の 向伏す国の 天雲の 下なる人は・・・(十三・三三二九) の白雲は雲で、青雲は空だとは考へられない事であり、 大君の命畏み 阿乎久牟(アヲクム)のたなびく山を越よて来のかむ(廿・四四〇三) の青雲(アヲクムは結句のコヨテキノカムがコエテキヌカモの訛りであるやうに、アヲクモの訛りとする) が、たなびく山といふのであるから青空でない事は、吉井君もあげてゐる「白雲のたなびく山を越えて来にけり」(三・二八七) などの例と較べても明らかである。 後のものではあるが、會丹集にも、 青雲や空にたなびき渡るらん照る日のえしもさやけからぬは といふのがあり、又三大実録、仁和元年七月の條に、 天有2青雲1、自2東北1卿竟2西南1。 とあるのも、文徳実録、天安二年六月の條に、 早旦有2白雲1、自レ艮亘レ坤、時人謂2之旗雲1。 とあるのと対照して青雲が雲である事を認むべきである。これらの例は吉井君も注意されてゐるところであるが、粂川定一氏は (『大成』訓詁篇上)、高句麗本紀第一東明王三年の條に青赤、百済本紀第二古尓王二十六年の條等にも青紫の雲の現はれてゐる事を注意し、石丸雄吉氏著『雲の気象学』に「国際十種雲級一覧表」の高層雲俗稱おぼろ雲の形態及特性として、「灰色又は淡藍色を呈する巻層雲の厚い雲である」とあるを引いて、広い意味の青といへるだらうとし、更に同書に古人の用ゐた雲の占、 雲青きはその月の内に大雨あり 四方に青白き雲あれば雨なり を引用されてゐる。私が少年の頃、伊勢で夕立ちなどのあと青空の見えそめたのを「青雲が出て来た」と祖母や母から聞かされた記憶があるので、青雲を青空とする解説を一概には斥け難いのではあるが、萬葉の青雲が雲であると断ずべき事は右の諸例で十分であると思はれ、殊に今の場合「北山にたなびく雲の」とあるのだから、もし強ひて青雲を青空とする爲には、全釈の如く「上の二句は青雲の序詞」 と見なければならない。しかしそれは無理な解釈であつて、金子氏が「上の句の調子は二句で切らず三句までいひ下した詞態と見るが自然であらう」といひ、井上氏が「キタ山ニツラナル青雲ノといふべきを調の爲に今の如く云へるにて」と云つて「日下江の入江の蓮花蓮」(雄略記) などの例をあげられてゐるやうに、第二句の雲と同じものと見るべきであり、吉井君の説の如く支那文学の影響による青雲であつて、青の色そのものにあまり深く拘泥するに及ばない。さてその青雲は主語であり、「の」 は主語につく助詞である。従来の諸説多くは青雲を青空と解してゐた爲に、「空の星」「空の月」と「の」 は所有格を示すものとなり、従つて次の星と月とが主語となつたのであるが、青雲が雲だとなると「雲の星」「雲の月」 とはなり得ないからである。その事更に次に述べる。 -星離れゆき月を離れて- 「月」 を原文金澤本と紀州本とには「月矣」とあるが、類聚古集・西本願寺本その他には「月牟」 とあり、紀州本も左には「牟イ」とある。古葉略類聚鈔のみは「月毛」とある。金澤本にはこの歌訓無く、類聚古集と紀州本とにはツキヲとあり、古葉略類聚鈔・西本願寺本その他の諸本はツキモとある。古葉略類聚鈔には左にツキヲともある。これらの文字と訓との處置を考へるに、 (一)現存古写本のうち時代の古いものに「矣」とあること。 (二)「矣」 「牟」 との字訓を比較するに、「匚」が 「□[上の一の下がしんにょう]」 になつたやうな例 (一〇〇) もあつて畫の多いものから少ないものへ誤写せられるとは限らないが、「□[狭の旁と刂]」が「□[叛の扁と刂]」 に誤る例 (十一・二五一三、その他) のやうなのが普通であり、今も「矣」 が 「牟」 に誤つたと見るのが自然であること。 (三)原文は「牟」(類聚古集)、「毛」 (古葉略類聚鈔) となつてゐるにかかはらずツキヲの訓の残されてゐること。 (四)ツキモの訓は原文「毛」となつてゐる古葉略類聚鈔にはじまること。 の四点が認められ、「矣」 から 「牟」 と誤り、又 「毛」 ともなつたので、原本は 「矣」 であつたと推定する事が出来る。従来の諸家は古写本を見ず又それを軽視してツキモの旧訓を正しいとする先入観に立つて 「矣」 を 「毛」 の誤としたり、牟にモの音ある事を述べ、 (字音辨證などに牟をモと訓む例もあげられてゐるが、少なくも萬葉には他に例なく、前に引用した 「阿乎久牟」 もムであつてモではない) などしたのは本来を誤つたものであつて、「矣」 を原本の文字としてヲと訓むべきである。さて 「月を」 といふ訓を決定したとすると当然上の 「星」 には助詞が添へられれてゐないが、意は 「を」 を加へて 「星を」 として解すべきものと認められ、 「星を」 「月を」 といふ事になれば、更に上の「青雲の」 は右に述べた 「青雲」 の解とこの 「月を」 の訓と上下より支え支へられて主語たる事がいよいよ明確に認められよう。そしてその事が確認せられれば更にまた第四句の 「去」 の訓が決定せられる事にならう。「去」 の字、類聚古集、古葉略類聚鈔、紀州本の三本にユクとあり、古葉略類聚鈔の左、及び西本願寺本以後の諸本にはユキとあり、諸家の説も二つに分かれてゐる。もし星が主語とすれば 「去」 はユクと訓んだ終止形と見る事が出来る。しかし右の如く 「青雲の」 が主語と確定すれば佐伯君が 「萬葉集の助詞二種」 で述べられてゐるやうに、 「が」 「の」 の助詞は終止形ではうけないのだから、もしユクと訓むとすれば、「息にわがする」 (十四・三五三九) の場合の如く今は四段であるから形は同じであるが、連体形といふ事になり、「星をはなれゆくよ」 の意になり、「月をはなれて」 はその副詞句をなすやうな形になる。しかしこの第四、五句は、第二句と第三句とのやうに、連疊の形をなしてゐるものと見るべきだと思ふ。さうだとすれば、佐伯君の例 (『萬葉語研究』五頁) にも見えるやうに、「水手(かこ)の声よび」 (十五・三六二二) とか 「戀の奴のつかみかかりて」 (十六・三八一六) とかの例により 「青雲の星ははなれゆき月をはなれて」とならざるを得ないのである。即ち第三句以下は青雲が星を離れゆき月を離れて-といふ事になり、従来顧られなかつた考の 「后をも臣をもおきて神あがりませるを、月星にはなれtよそに成行雲に譬給へり」 といふ説がうなづかれる事になり、全註釈に 「青雲が星や月を離れて天空高く昇るといふので、天皇の神霊に就いていふのであらう。」 といふ一寸見ると理解し難いやうな言葉にはつきり同感する事が出来る事になる。かうして宣長以来多く行はれてゐた星移り月替りといふ解釈は、一応誰しも考へるところではあるが、右の如く青雲が主語とわかれば当然否定さるべきものである。 我が面の忘れむしだは国はふり嶺に立つ雲を見つつ偲はせ(十四・三五一五) 春日なる御笠の山に居る雲を出で見るごとに君をしぞ思ふ(十二・三二〇九) 雲に人の面影を偲ぶ事は集中にいくつも見るところであり、 こもりくの初瀬の山の山の際にいさよふ雲は妹にかもあらむ(三・四二八) この雲は題詞に 「土形娘子火2葬泊瀬山1時」 とあつて、火葬の煙を雲と見たものであり、天子の火葬は持統天皇にはじまるのであるから、今はただ雲に神上がります天皇の御霊を偲ぶと見るべきものである。今日の天文の常識からは、雲は地球上のものであり、星とのへだたりは論外であるが、上代人が大空に立ち登る雲を見て、星や月をも凌いで、天上無限の彼方に消え去るものと考へる事もうなづける事ではなからうか。さう考へればその雲に神去り給ふ天皇の御霊を偲びつつ星を離れ行き月を離れて-といふ事は十分了解される事であらう。原文二つの 「離」 を類聚古集、紀州本には上をサカリと訓み、下をハナレと訓んでゐるが、他の諸本多く共にワカレと訓んでゐたのを玉の小琴にサカリと改めてよ諸注殆ど皆それに従ふに至つた。しかし 「離」 の字は集中の読例としてはサカリ、サカルと訓む事が多いやうであるが、語としてはハナルといふ言葉が日常に用ゐられてをり、離をむしろハナルと訓む方が穏当と認むべき例のある事既に (一五〇) 述べた如く、特に今の場合はそこで引用した「久毛婆奈礼 (クモバナレ)」(十五・三六九一) や仁徳紀の、 山和邊に西風吹きあげて玖毛婆那礼 (クモバナレ) や丹後風土記 (釋日本紀巻十二、雄略の條所引) の、 大和邊に風吹きあげて久母婆奈礼 (クモバナレ) の 「雲離れ」 の例と同じくハナレと訓むべきものと思はれる。宣長がサカリとしたのは星や月を歳月の意に解した爲で、それならば 「益年離 (イヤトシサカル)」 (二一四) を例としてサカリと訓む事認められるが、右の述べたやうに、雲や星を眼前に見る雲や星とすれば、右の 「雲離れ」 の例こそ最も適切なものと見るべきである。 【考】 この御作に支那文学の影響ある事は訓釋の條で述べた如くであるが、それは文字の表記や語句に認められる影響であつて、この一首を貫く作意と声調とはあくまでも我が上代ぶりの姿であり、同じ作者の 「春過ぎて」 (一・二八) と相通ずるものと考へてゐる。斎藤氏も 「自分は此歌を尊敬し愛誦してゐる。『春過ぎて夏来るらし』と殆ど同等ぐらゐの位置に置いてゐる。何か混沌の気があつて二二ヶ四と割切れないところに心を牽かれるのか、それよりももつと真実なものがこの歌にあるからであらう。」 (『秀歌』) と述べられてゐる。しかし、同氏の説は大体旧訓により旧説に立つての上の鑑賞であるが、私は右に解き来つたやうな訓釋の上に立つてこそその批評は適切を加へるのではないかと考へるのである。 雨降れば北にたなびくあま雲をきみによそへてながめつるかな(貫之集第九) の作が古今六帳 (一「雲」) には第三句 「白雲を」 として載せられ、代匠記にもそれが引用せられてをり、一つの参考となる歌であり、今の御作の影響も考へられないではないが、貫之集のものは 「こしのかたなる人にやる」 と詞書があつてその作意は全く別のものであると共に、今の御作の風格はかうした作と較べる事によつて一層その面目を発揮するであらう。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 向南山 陳雲之 青雲之 星離去 月矣離而 北山にたなびく雲の青雲の星離り行き月を離れて 向南山 (キタヤマニ) 陳雲之 (タナビククモノ) 青雲之 (アヲクモノ) 星離去 (ホシハナレユキ) 月矣離而 (ツキヲハナレテ) 【注】 〇北山に 原文 「向南山」。古葉略類聚鈔にキタヤマニ、金澤本にキタヤマノ、類聚古集にカムナヒヤマとする。代匠記にもキタヤマノと訓んだが、童蒙抄および万葉考にはキタヤマニとある。向南山をキタヤマと訓むことに疑義も出されてきたが、小島憲之 「万葉人の庖厨に漢籍あり」 (国語国文昭和二十八年七月) に、文学表現の上で 「向南」 としたのは崩御と関係があろうと述べて、「これは毛詩などにも見える如く、南はあかるい陽を示し、その反対に北は暗い陰を示す。顔延年、宋文元皇后哀策文 (文選五八) の中に『南背(ソムキ)2国門1,北首(ムカフ)2山園1』(寛文版訓) とみえ、葬車の悲しくみささぎに向ふ描写を述べてゐるのは、単に南と北との対比ばかりでなく、北に墓処としての陰を示してゐる『向南』は北であり、文字によつて北と反対の南を表し、陰なる北を明確に示す」 (『上代日本文学と中国文学』中巻に収載) と、漢籍に典拠のあることを指摘した。その後の注釈書も多くこの訓による。「陳雲」 「青雲」 などと共に漢籍を踏まえた表現であることは確かだろう。しかし右にあげられた哀策文の例が適当かどうか、問題は残る。作歌の場所について、武田全註釈に、「天武天皇の明日香真神が原の山陵は、南面しており、南方からこれを見そなわして詠まれたのであろう」 と言う。天武天皇の殯宮は、朱鳥元年九月十一日に 「南庭」 に設けられているが (書紀)、この歌の 「向南山」 はその殯宮の地を指すのでも、またそこから望んでのことでもなく、持統二年冬十一月に大内陵に葬った後、宮殿からごらんになって詠まれたとするのである。山田講義に 「按ずるに、こは恐らく南方よりその御陵所の方を眺めてよまれしならむ。山科(ママ)御陵の地勢よくこの語にあてはまれり。」 と記しているのは、武田説の先蹤である。なお、岸俊男 「古代(2)」 (『明日香村史』上巻) に「 向南山」をキタヤマと訓むことに疑問が記され、明日香の神南備山を言うのではなかろうかとされており、また講談社文庫本にも向南をキタと訓む点に疑義を提し、カムヤマの訓を付している。ただし、それらによってカムヤマあるいはカムナビ (口訳)・カムナビヤマなどと訓むとすれば、なおさら「向南山」 の文字面を離れると思われる。講義に、「『向南』二字を以て一語として『キタ』にあてたるにあらず、『向南山』三字を以て一語として直ちに『キタヤマ』の義に用ゐたるなるべし。南に向へる山は即ち北山に外ならざればなり」 と記すのが、簡潔に要点を押さえた発言と思われる。 〇たなびく雲の 原文 「陳雲」を細井本に 「陣雲」 とする。他の諸本に 「陳」 とあるのによるべきだろう。陳はもと陣と同字であり、玉篇に 「列也、布也」 とあり、万象名義にも 「列、故、処」 の注を見る。類聚古集・紀州本の付訓にツラナルクモノとあるのは、そうした陳の字義によるらしい。江戸時代以後の諸注の大部分がタナビクと訓むが (口訳にはアマギラヒツツとする)、その理由は、雲が連なると言った例がなく、タナビクの例は多く見られることにある。茂吉『秀歌』に、ツラナルと訓み、 「この方が型を破つて深みを増して居る」 と記しているが、やはりタナビクの方が穏やかだろう。周の廋信の擬詠懐二七首に 「陳雲平不動、秋蓬巻欲飛」 と見えるように、これも漢籍による文字で (小島前掲書)、「平不動」 の状態が邦語のタナビクに近いのであろう。ノは同格の助詞。 〇青雲の 青雲を、白雲と見る説 (万葉考・略解・新考など)、青空と見る説 (玉の小琴・古義・美夫君志・講義など)、彩旗と見る説 (野雁新考) などがあったが、雲と見るのが正しい (吉井巌「 青雲攷」万葉五号)。それも色のある雲であろう (小島前掲書)。ノは主格の助詞。 〇星離れゆき 原文 「星離去」 を旧訓ホシワカレユキと訓んだが、童蒙抄にハナレユキ、万葉考にハナレユクとし、宣長 (玉の小琴) は、サカリユキと改めた。上句の 「青雲の」 が主語で、「離去」 は述語であり、離は前 (一五〇歌) にサカリと訓む例があったが、ここは澤瀉注釈に記すように、「大和辺に西風(にし)吹きあげて玖毛婆那礼(クモバナレ)」 (仁徳紀歌謡) と同じく、ハナレユキと訓むのがふさわしい。 〇月を離れて 原文 「月矣離而」。「矣」 を西本願寺本・細井本・大矢本・京都大学本などに 「牟」 とするが、金澤本・紀州本には 「矣」 とあって、矣から牟へ誤写されたことが考えられる。「牟」 は、ムの音仮名として多用され、万葉集以外にも推古期遺文・大宝戸籍・養老戸籍・古事記・日本書紀・風土記などほとんどの上代文献に見うるものであるが、この歌にムでは合わない。また、モの用例は見られない (日本霊異記下巻第二十四に「儻、古戸牟良」の注があり、これをトモラと訓むという説もあるが、) これはトムラで、牟はムの仮名と考えられる。そうした点からも、金澤本・紀州本によって 「矣」 を原字とすべきである。青雲が、月を離れて、の意。 【考】 雲と天皇の霊 「向南山」が北山で、天武の大内陵のある所を指すとすれば、その上にかかる青雲の・星・月を離てゆくのに託して、天皇の霊の遠ざかりゆく悲しみを歌ったものと思われる。万葉考に 「后をも臣をもおきて神あがりませるを、月、星にはなれてよそに成行雲に譬給へり」 と言う。古代の人にとっては、立ちのぼる雲、霧・煙などは単なる自然現象ではなく、霊力を有するもの、ないし霊力や霊魂の発現し、活動する姿として観念されたのである。そのことは、古代説話・考古学的遺物・仏教美術などによって知ることができる (土橋寛『古代歌謡と儀礼の研究』)。天皇の霊の発現として青雲が見られているのであり、「星」・ 「月」 は臣・后とを象徴していると考えるべきであろう。北山を離れた雲は、星を離れ、月を離れて天高く上昇して行くのである。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 向南山 陳雲之 青雲之 星離去 月矣離而 キタヤマニ タナビククモノ アヲクモノ ホシハナレユク ツキヲハナレテ 北山にたなびく雲の青雲の星離れ行く月を離れて 【脚注】 初句の原文 「向南」、第二の原文 「陳雲」、第三句の原文 「青雲」 は、六朝時代の漢籍所見の語。歌の意味、特に下二句が分かりにくい。 「衆星は月をその主と為す」 (大樹緊那羅王所問経二) という。何か関係を求め得るであろうか。一応、右のように訓読・口語訳して、後考に俟つ。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 向南山 陳雲之 青雲之 星離去 月矣離而 キタヤマニ タナビククモノ アヲクモノ ホシハナレユキ ツキヲハナレテ 北山にたなびく雲の青雲の星離れ行き月を離れて 【頭注】 〇北山- 原文 「向南山」 の 「向南」 は南を向く意から北を表わした義訓。死者を北方に葬り、その首を北に向けるのは古代中国の習俗 (『礼記』檀弓下)。これによって書いたか。 〇青雲- 漢籍から借りた語。 〇星離れ行き月を離れて- 皇后や皇子から離れて天皇が崩じたことを、雲が星や月を離れて遠くへ去って行ったように述べた隠喩。この下に、行くことよ、の意が省かれている。なお、『文選』江賦に 「星離」 の語が見え、その 「離」 は、つらなる意と思われる。あるいはそれと関係があるか。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 巻二162 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | 校本萬葉集
|
||||||||||||||||||||||||||
| 活字附訓本 | 活字附訓本 | 活字附訓本 (国立国会図書館蔵書)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 清御原乃宮 | 注釈 | 天武天皇の皇居。 【澤瀉注釈巻一第二二より】 天武紀元年九月の條に 「庚子(十二日) 詣2于倭京1而御2嶋宮1。癸卯(十五日)自2嶋宮1移崗本宮1。是歳、營2宮室於岡本宮南1。即冬遷以居焉。是謂2飛鳥浄御原宮1。 」 とあつて、壬申の乱平ぎて大和へ帰られ、間もなく造営せられたところであり、前に述べた岡本宮の南にあたり、喜田貞吉博士が明日香村の飛鳥小学校の附近とせられたのに従ふべきものと思はれる。即ち雷岡の東である。高市村上居(ジヤウゴ) の地とする説はあたらない (『帝都』七六頁-七九頁参照)。古事記の序文には 「飛鳥清原大宮」 とある。元暦本には 「御」 の字がないが、右に朱筆で加へられてをり、元暦本書写の際に脱し、校合にあたり加へたものと思はれる。「宮」 の下、目録には 「御宇」 の二字あり、他の例によれば、あるべきところであるが、現存の諸本にはない。ただ元暦本には 「天武」 の二字があり、その右に赭で 「御宇」 とある。 「天武」 の文字は他の例にも違ひ、元暦本だけの異であるからまぎれ入つたものと思はれるが、 「御宇」 の二字も現存の諸本の書写せられた頃には既に脱してゐたものと考へられる。 「明日香浄御原宮」 は持統天皇八年まで皇居となつてゐたが、「浄御原宮 (御宇) 天皇代」 とは天武天皇の御代の意である。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 諸注引用 | 管見 | 鹽けのみかほれる國 鹽けとは、鹽のいげなり。鹽ぐもりとて、海のくもるをいふ。けふりに似たれは、かほれるとはいふ也。鹽けたつあら礒ともよめり。日本紀こ、伊弉諾尊曰、我所生之國、唯有朝霧而薫滿之哉とのたまふといへり。きりも、けふりににたれは、かくいへり。 味凝《アヂコリ》のあやにともしき よきことの集りよれるを、味凝といふ。あやは、にしきなとにをり付たる紋をいふ也。うつくしく目につける紋は、みたらぬ心にて、ともしきとはゆふ也。見《ミ》のともしき、聞《キヽ》のともしきとよあるも、見たらず聞たらず也。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 拾穂抄 | 天皇|崩後《カミサリテ》八年九月九日|奉為《ヲホンタメニセン》御齋會《ヲカミノ》夜ノ夢ノ裏《ウチニ》賜《タマフ》御歌一首 出2古歌ノ集ニ1 あすかのきよみはらのみやにあめの下しらしめしゝやすみしるわかおほきみの高てらす日のわかみこはいかさまにおほしめしてか神かせのいせのくにゝはおきつもゝなひきし波にしほけのみかをれるくにゝあちこりのあやにともしきたかてるひのみこ 明日香能清御原乃宮尓天下所知食之八隅知之吾大王高照 (たかてる) 日之皇子何方尓所念食可神風乃伊勢能國者奥津藻毛靡足波尓塩氣能美香乎礼流國尓味凝文尓乏寸高照日之御子 あすかのきよみはら 天武の宮古也 御齋會《ヲカミ》追善なり 高てらすひのわかみこ 天武帝をさして申也 しほけのみかをれる国 八雲御抄には |しほけのうまいかをれる《塩氣能美香乎礼流》国は伊勢国也云々是古点にや見安云しほけは塩のいき也愚案塩曇とて潮の燻薫る心也あちこりは美味の集る心也国をほむる詞也見安同義 あやにともしき あやにくに戀したふ心也 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | 天皇崩之後八年九月九日奉爲御齊會之夜夢裏習賜御歌一首 持統紀を考るに此事見えず、習賜とは帝の御夢ごゝに御みづから誦習したまふか、又賜の字の心を思ふに先帝の神靈の帝の御夢に入らせたまひて、此歌を奉られて誦習せしめ給へるか、第十六に夢裡作歌の注に云、右歌一首忌部首黒磨夢裡作2此戀歌1贈v友、覺而不誦習如v前、今の習賜此に同じ、齊は齋に作るべし、官本注して云、古歌集中出、 明日香能清御原乃宮爾天下所知食之八隅知之吾大王高照日之皇子何方爾所念食可神風乃伊勢能國者奥津藻毛靡足波爾鹽氣能味香乎禮流國爾味凝文爾乏寸高照日之御子 《アスカノキヨミハラノミヤニアメノシタシラシメシヽヤスミシシワカオホキミノタカテラスヒノワカミコハイカサマニオホシメシテカカミカセノイセノクニヽハオキツモモナヒキシナミニシホケノミカヲレルクニヽアチコリノアヤニトモシキタカテルヒノノミコ》 高照日之御子、【官本更點、云、タカテラスヒノミコ、】 靡足は今按ナミタルとも讀べし、塩氣ノミカヲレル國とは即上の伊勢なり、神代紀云、伊弉諾《イザナギノ》尊ノ曰、我|所v生《ウメル》之國ニハ唯有2朝霧1而薫滿之哉、神樂歌云、伊勢嶋や海人のとねらが燒|火《ホ》の氣、をけをけ、燒火の氣、いそらが崎にかほりあふ、をけをけ、此集第九人丸集歌云、鹽氣立荒礒《シホケタツアライソ》にはあれど云云、今案此下に落句あるべし、香乎禮流の乎は保なるべきを同韻なれば通せるか、若は草案にて矢錯せるか、味凝はあやと云んためなり、第六にもよめり、別に注す、高照罵は官本の又の点に上とおなじくタカテラスと和せるに從ふべし、此御歌も亦何事にかと心得がたし、今試に釋すべし、此は壬申の亂あるべき事を太神宮かねて遙に知食て御みづから天武天皇とならせ給ひ、或は末社の神等を降させ給て天皇となし參らせ給へるが、事成り世治て後誠に崩じ給ふにはあらで神靈の伊勢へ皈らせ給ふ意か、天武紀云、丙述旦於2朝明《アサケノ》郡ノ迹太川《トホカハ》邊1望2拜天照太神1、此卷の下に人丸高市ノ皇子ノ尊ノ殯宮を悼て作らるゝ歌に云云、此等にて知べし、其外古事記の序天武紀の神託卜筮等誠に天の縱《ユル》せる帝なれば、必ず神の化現なるべし、懷風藻の大友ノ皇ノ傳ノの皇子の夢を記せるこそ少天皇をほめ申さぬ意なれど、大友ノ皇子葛野ノ王の傳を殊にゆゝしく書て、撰集も寶字年中なれば、疑らくは彼時の文者淡海眞人三船の撰にて、先祖の事とて筆を振はれければ、家に深く藏されける故久しく世にも弘まらで、遙に後に出たるにや、凡不測なるを神と云へば、權迹を以て輙く論ずべからず、若事迹を堅く執せば、應神天皇|甘美《ウマシ》内宿禰讒を信じて武内宿禰を殺さんとし給へり、これ神の定給へる胎中天皇に叶はざるに似たり、神代も亦然り、儒道佛道などによらば違る事あるべし、水火相せまれば互に爭て婦姑の如くなれど、其牲天地に在て増減なし、唯凡慮を捨べし、かをれる國にと云下に句の脱たらむと申は、終りの二句は上の高照日のみこを再び云てほめ申詞にて、いかさまに思召てかと云より此方を收拾する詞なければなり、若はあやに乏しきと云所句絶にて、上を收拾して高照日のみこの一句を立て上を呼返して稱嘆し奉るか、後の人定むべし、天武の御歌にて御みづからかく勅すとも違べからず、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 童子問 | 天皇崩之後八年九月九日奉爲御齋會之夜夢裏習賜御歌一首 童子問 此歌の前がきの内、習の字心得られず。いかゞ。 答 疑問ことわりいやつこ也。習は誤字なるべし。賜の字もうたがひなきにあらず、異本を得て改正すべし。 明日香能清御原乃宮爾天下所知食之八隅知之吾大王高照日之皇子何方爾所念食可神風乃伊勢能國者奧津藻毛靡足波爾塩氣能味香乎禮流國爾味疑文爾乏寸高照日之御子 童子問 此御歌詞もいひたらぬ句のみおほく、意も得がたし。先生賢按義も訓も有にや。 答 此御歌には強て異訓有べくもみえず、異義の僻案もなし。只疑らくは、何方爾所念食可とある句の下に脱漏有て、崩御なりし句有べくみゆる也。しからずば只此何方爾所念食可といふに、崩御なりしことをこめてみるべし。夢裏の御歌なれば、詞もとゝのほらずいひかなへ給はぬことも有とみるべし。四言一句のあるも古語のまゝにて、しひて御詠の作骨有べからねば、大概歌の意きこえば可なるべし。 童子問 伊勢能國者の五字をいせのくににはとよみ來れり。國にはといへば、始終のてにをは聞得がたし。いかに。 答 いせのくにはとよむべし。六言にては、例の七言に口なれたれば、ことたらぬ故に、くにゝはとよみ來れるなるべし。疑問のごとく、國にはとよみては義かなはぬ也。 童子又問 靡足波爾、此四字なびきしなみにとよみ來れり。可v然や。 答 足はあしの訓を上略して用ゐたるといふべけれども、過去のし義かなひがたし。なびける波にとよむべし。足はたるとよむ下の言をとれるなるべし。 童子問 鹽氣能味、此四宇しほけのみとよみ來れり。かゝるべきや。 答 鹽氣と書て義訓有べき古語もなければ、先訓にまかすべし。しかれども氣を濁りて訓べき歟。俗言にもいげといふこと有。鹽のいげとみるべし。しからばもし鹽氣をゆげと訓て、ゆげのうまくとよむべき歟。 童子問 味疑文爾乏寸といふ句、其意得がたし。先生賢按の訓も義もあらずや。 答 これは僻案の訓義あり。味凝をあぢこりとよみ來る事義不v通、うまごりとこを濁てよむべし。うまとは古語に稱美の辭に用ゐる例すくなからねば也。こりはおりにて、文といはん冠辭にうま織の文とうけ給へる語なるべし。あやにともしきははなはだめづらしきと稱する詞にて、日を尊稱の辭なるべし。世に希有なるものはめづらしきと稱する古語なれば、此大王は日の神のみ子と稱し奉る意なるべし。されば歌の惣意は、清御原の宮に天下をしろしめしたる君の、いかさまに覺しめしてか、天下をしろしめさずして、天宮にはかへりたまふことぞといふ御歌とみる也。神風の伊勢國より下は日神の鎭座の御國なれば、皆日神のまします、國を尊稱したる詞にて、高照日のみこといひて、此日のみこいかさまにおぼしめしてか、伊勢の國にもましまさず、天宮には上り給ふ事ぞといふ御歌の意なるべしとみる也。此外に御意有ての御歌かはしらず、只御歌の詞にすがりてみずして、詞を添へ加へていはゞ、いかやうのことにもなりぬべけれど、古葉を釋するは只詞の有にしたがひて、牽強附會をさくるを正義の釋とす。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 童蒙抄 | 天皇崩之後八年九月九日奉爲御齊會之夜夢裡習賜御歌一首 すめらみこと、かみあがりたまふてのち、やとせながつき九日、おほんためのみをがみのよ、ゆめのうちによみ給ふみうたひとくさ 天皇 天武帝也 崩之後八年九月八日 日本紀卷第卅持統天皇七年九月丁亥朔云々、丙申爲2淨御原天皇1設2無遮大會於内裏1云々。此外八年九月に齊會を被v行し事紀に不v見。此時の御齊會のことなるべし。尤崩御の年より八年にあたる故、後八年としるせる歟。又九日とあれども持統紀を考ふれば、十日にあたるなり。しかれば九日夜のみゆめに見給ふを、九日としるせる歟。御忌日は九月九日也 御齊會之夜 饗僧拜佛誦經施物等を賜ふて佛事を被v行し義也 夢裏習賜 此習の字難2心得1。誦の誤りなるべし。よつてよみ給ふと點をなせり 明日香能淨御原乃宮爾天下所知食之八隅知之吾大王高照日之皇子何方爾所念食可神風乃伊勢能國者奧津藻毛靡足波爾鹽氣能味香乎禮流國爾味凝文爾乏寸高照日之御子 あすかの、きよみはらに、あめのした、しろしめしゝ、やすみしゝ、わがおほきみ、たかてらすひのみこ、いかさまに、おぼしめしてか、かみかぜの、いせのくには、おきつもゝ、なびきしなみに、けぶりのみ、かをれるくにゝ、うまごりの、あやにとぼしき、たかてるひのみこ 明日香能淨御原乃宮爾 天武天皇の御在世の皇居の地宮殿の義を云たる義也 高照日之皇子 前にも度々注せるごとく、天照大神より御正統のひつぎをうけ給ふすめらみこと故、直ちに日神のみこと云義也。此歌には別而日のみことなくてはかなふまじき御歌也 鹽氣能味 古本印本ともにしほけのみとよめり。しかれども鹽の氣のたつは、けむりのごとくなるものにて、水のけむりなどゝ古詠にもよめば、鹽氣の二字義則にけむりとはよむなり。波のたつときは煙のたつにひとしく見ゆれば、なびけるなみにけむりのみとつゞけたると見えたり 香乎禮流國爾 かをれるは薫る義也。今通例にはかほると書けども、薫るのかなはを也。かほるとほの字を書たる證明不v見。よつて當家の流にはをのかなを用ゐる也。はねる音の字のをほのうたがはしき假名は、ほの字を書くと云ひならはせり。不v合こと也。既に薫の字かなにほの字を書たる正記證明所見なく、既に此集如v此をの假名を用ゐたり 味凝文爾 うまこりとはあやといはんための冠辭にて、ほめたることば也。古本印本等にはあぢこりとよめり。あぢこりといふ義は何といふことわりにや心得がたし。當家の傳はうまこりとよむ、うまはほめたる義うま人のうましなどいふて稱美の詞也。こりはおりといふ義にて、うまおりの綾とうける冠詞也。あやとは感嘆したる詞あなと云も同事也 乏寸 は珍敷といふと同事にて、至つてほめたる詞也。如v此上より段々と、かをれる國にうまこりのあやにともしきと云下して、みな詞をながくほめたる義也 高照日之御子 天照大神の直にみことさしてのたまふたる義也。 この歌の意は、天武天皇のみたましゐ伊勢神宮にうつり入らせられ、直に日の神の御徳とひとしくならせ給ふゆゑ、あやにともしく見奉ることも、ならせられぬといふ義を御夢中によませ給ふ也。御夢の中の御うたなれば、始終の連續もあるまじき事なるに、しかもよくきこえて不思議なる御夢の歌也。かやうのこともありし故、御謚を天武とも奉2尊稱1られたると見えたり |
||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉考 | 天皇崩之後、八年九月九日ニ、奉v爲《ナシマツル》2御齋會《オホミヲガミヲ》1、之|夜《ヨ》、夢裏唱賜《イメノチニトナヘタマヘル》御歌、 此次に藤原宮御宇と標して、右同天皇崩ませる朱鳥元年十一月の歌を載、其次には同三年の歌有を、こゝに同八年の歌を載べきにあらず、且待統天皇の大御歌とせば、御製とも御夢とも有べし、かたがたいかなる野書をか裏書にしつらん、然るを後の心なしの、遂に本文にさへ書なせしものなり、【有馬ノ皇子の御歌の次に、いと後の追加を載しとは異にて、中々に同天皇の大御歌の年月の前後せるは、有まじき事なり、】 此御齋會の事は、紀に (持統) 二年二月の詔に、自v今以後、毎ニv取2國忌ノ日1、要須v齋也とあり、 明日香能、清御原乃宮爾、天ノ下、所知食之《シロシメシヽ》、八隅知之、吾大王、高|照《ヒカル》、日之皇子《ヒノミコ》、何方爾《イカサマニ》、所念食可《オモホシメセカ》、 神風乃、伊勢能國者、奥《オキ》津藻毛、靡足波爾《ナミタルナミニ》、鹽|氣能味《ゲノミ》、香乎禮流《カヲレル》國爾、 潮の滿る時くもるを、加乎留といふなり、冠辭の朝霞の下に委、 味凝《ウマゴリ》、 冠辭、 文爾乏寸《アヤニトモシキ》、高照日之|御子《ミコ》、 こは意得がたきを、強ていはゞ、天皇吉野より伊勢の國へ幸有て、桑名におはせし事を、さるたふとき大御身の、あら海べたにおはせしが、めづらかにかたじけなきよしか、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | 天皇崩之後八年九月九日奉v爲2御齋【齋ヲ今齊ニ誤】會1之夜夢裏習賜御歌一首 習は誦の誤りか。此次に藤原宮御宇と標して、右同天皇崩りませる朱鳥元年十一月の歌を載せ、其次に同三年の歌有るを、ここに同八年の歌載すべきに非ず。且持統天皇の御歌とせば御製と有るべし。かたがたいぶかしき由考に言へり。此御齋會の事、持統紀二年二月の詔に、自v今以後毎v取2國忌日1要須v齋也と有り。 明日香能。清御原乃。宮爾。天下。所知食之。八隅知之。吾大王。高照。日之皇子。何方爾。所念食可。神風乃。伊勢能國者。奧津藻毛。靡足波爾。鹽氣能味。香乎禮流國爾。味凝。文爾乏寸。高照日之御子。 あすかの。きよみはらの。みやに。あめのした。しろしめしし。やすみしし。わがおほきみ。たかひかる。ひのみこ。いかさまに。おもほしめせか。かむかぜの。いせのくには。おきつもも。なびきしなみに。しほげのみ。かをれるくにに。うまごり。あやにともしき。たかひかるひのみこ 靡足舊點にナビキシと有るからは、足をシの假字に用ひしか。又は之の誤りならむ。潮の滿る時くもるをカヲルと言ふ。神代紀に我所v生之國。唯有2朝霧1而薫滿之哉。又神樂歌に、いせじまやあまのとめらかたくほのけおけおけ、たくほのけいそらがさきにかをりあふおけおけ。又卷九に、鹽氣たつありそにはあれどなども詠めり。合せ考ふべし。冠辭考朝ガスミの條にも委し。味ゴリ枕詞。此歌いと心得がたし。強て言へば、天皇吉野より伊勢の國へ幸有りて、桑名におはせし事を、尊きおほむ身にて、荒海の邊におはせしが、めづらかに忝なき由か。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 攷證 | 天皇崩之後。八年九月九日。奉v爲2御齋會1之夜。夢裏習賜《イメノウチニナレタマヘル》御歌。一首。 崩之後八年。 天武天皇、朱鳥元年崩じ給ひしかば、後八年は持統天皇七年にあたれり。 九月九日。 持統紀云、七年九月、丙申、爲2清御原天皇1、設2無遮大會於内裏1云々とあり。この月、丁亥朔なれば、丙申は十日に當れり。さるをこゝには、九日とせり。いづれをか正しとせん。 御斎會。 齋會は、書紀敏達紀に、大會設v齋とはあれど、蘇我馬子宿禰の家にての事にて、臣家の齋會なり。推古紀に、十四年四月、壬辰、丈六銅像坐2於元興寺金堂1、即日設v齋於v是會集人衆、不v可2勝數1云々とあるも、元興寺の齋會なり。天武紀に、四年四月、戊寅、請2僧尼二千四百餘1、而大設v齋焉云々とある、宮中御齋會のはじめなり。持統紀に、二年二月乙巳、詔曰、自v今以後、毎v取2國忌日1、要v須v齋也云々と見えたり。後は、正月八日より十四日まで行はるゝよしなり。こははるかに後のことなり。 夢裏習賜《イメノウチニナレタマヘル》。 習賜は、目録になれたまふと訓るをよしとす。これを、考には、唱賜と直し、略解には、習は誦の誤かといへれど、いかが。漢書五行志、中之下に、習狎也とありて、狎は、なるゝ義なれば、こゝは、太后の御夢のうちに、天皇に親しく馴れ給ふさまを見たまひて、御いめの中ながら、この御歌をよませ給ふ也。さて、是は、天武帝崩給ひて後、八年にて持統帝七年の事なれば、この清御原宮御宇の條に、載べきにあらずとて、本文に略かれしかど、甚しき誤り也。年代はいかにまれ、こは、天武帝の御爲に、御齋會をまうけ給ひて、しかも多年を經ても、猶わすれかねさせ給ひて、御夢にさへ見奉りて、御歌をよませ給ふなれば、こゝに入べき事、論なきをや。また、こゝに、太后としるし奉らねど、こは、まへの天皇崩之時、太后御作歌とある端辭を、うけたるにて、御歌とさへあれば、太后の御歌なる事、明らけし。又代匠記に引る官に、小字にて、古歌集中出とあれど、集中の例、左注にあぐべきなれば、こゝにはとらず。 明日香能《アスカノ》。清御原乃宮爾《キヨミハラノミヤニ》。天下《アメノシタ》。所知食之《シラシメシシ》。八隅知之《ヤスミシシ》。吾大王《ワカオホキミ》。高《タカ》照《ヒカル・テラス》。日之皇子《ヒノミコ》。何方爾《イカサマニ》。所念食可《オモホシメセカ》。神《カム・カミ》風乃《カセノ》。伊勢能國者《イセノクニハ》。奧津藻毛《オキツモモ》。靡足波爾《ナヒキシナミニ》。鹽氣能味《シホケノミ》。香乎禮流國爾《カヲレルクニヽ》。味凝《ウマコリ》。文爾乏寸《アヤニトモシキ》。高《タカ》照《ヒカル・テラス》。日之御《ヒノミコ》。 高《タカ》照《ヒカル・テラス》日之《ヒノ》皇子《ミコ・ワカミコ》。 高照《タカヒカル》は、枕詞。日之皇子《ヒノミコ》とは、天皇は、日之神の御末ぞと申意也。この事上【攷證一下十九丁】にいへり。ここは、わが大王《オホキミ》は、日の神の御末ぞと申す意なり。 何方爾《イカサマニ》。所念食可《オモホシメセカ・オホシメシテカ》。 本集一【十七丁】に、何方御念食可《イカサマニオモホシメセカ》、天離夷者雖有《アマサカルヒナニハアレト》、石走淡海國乃《イハヽシノアフミノクニノ》、樂浪乃大津宮爾《サヽサミノオホツノミヤニ》、天下所知食兼《アメノシタシラシメシケム》云々ともありて、食可は、めせばかの意にて、可《カ》は、疑ひの辭なれば、右に引る一卷の歌にて、所知食兼《シラシメシケム》と結べり。さて、こゝはいかさまにおぼしめせばか、この伊勢の國には、おはしますらんとのたまふ也。 神風乃《カムカセノ》。 枕詞にて、冠辭考にくはし。上【攷證一下七十四丁】にも出たり。 靡足波爾《ナヒキシナミニ》。 靡足《ナヒキシ》は、波へもかゝりて、波の風にふきよせられなどするを、なびくといひて、藻も、波も、なびく也。本集二十【六十三丁】に、阿乎宇奈波良加是奈美奈妣伎《アヲウナハラカセナミナヒキ》、由久左久佐都々牟許等奈久《ユクサクサツヽムコトナク》、布禰波々夜家無《フネハヽヤケム》云々とあるにても、波のなびくといふをしるべし。さて、足をしの假字用ひしは、略訓也。割をき、石をし、市をちの假字に用ふるたぐひ多し。或人、九【十九丁】に、片足羽河《タダシハカハ》とあるを、ここの略訓の例に引たれど、あしの、あの字は、かたのたの字の引聲にこもりて、おのづからにはぶかるゝ格なれば、こゝの例にあらず。 鹽氣能味《シホケノミ》。香乎禮流國爾《カヲレルクニヽ》。 鹽氣は、鹽の氣也。本集九【卅二丁】に、鹽氣立荒礒丹者雖有《シホケタツアリソニハアレト》云々。能味《ノミ》はばかりの意。この伊勢の國は、鹽氣のみ立みちたる國なるを、いかにおぼしめしてか、この國にはおはすらんとの意也。香乎禮流《カヲレル》は、鹽氣のたちて、くもれるをいへり。書紀神代紀上、一書に、我所v生之國、唯有2朝霧1、而薫滿之哉、云々。神樂、弓立歌に、多久保乃計《タクホノケ》、以曾良加左支仁《イソラカサキニ》、加保利安不《カホリアフ》、於介於介《オケオケ》云々とあるは、こゝと同語なれど、假字たがへり、とあるにても思ふべし。さて、この所、必ず脱句あるべし。鹽氣能味香乎禮流國爾《シホケノミカヲレルクニニ》、味凝文爾乏寸《ウマコリノアヤニトモシキ》とはつづくべくもあらぬうへに、上に、何方爾所念食可《イカサマニオホシメセカ》とある、可もじの結びなし。されば、こゝに脱句ありて結び辭もうせしこと、明らけし。 味凝《ウマコリノ》。 枕詞にて、冠辭考にくはし。本集六【十一丁】に、味凍とかけるも、借字にて、美織《ウマクオリ》の綾とつづけしにて、くおの反、こなれば、うまごりとはいへりき。綾を詞のあやにとりなしてつづけし也。 文爾乏寸《アヤニトモシキ》。 文爾《アヤニ》は、借字にて、まへにいへるごとく、歎息の辭なり。乏寸《トモシキ》といふに、三つあり。一つは、めづらしと愛すると、一つは、うらやましき意なると、一つは、實に乏《トモシ》くまれなる意なると也。うらやましき意なるは、上【攷證一下四十一丁】ともしくまれなる意なるは、下【攷證三上五十七丁】にいへり。こゝなるは、めづらしと愛する意なる事、何にまれ、少くともしき物は、めづらしく思ふよりいへる也。そは、本集三【廿二丁】に、出來月乃光乏寸《イテクルツキノヒカリトモシキ》云々。四【廿丁】に、人之見兒乎青四乏毛《ヒトノミルユヲワレシトモシモ》云々。六【十一丁】に、味凍綾丹乏敷《ウマコリノアヤニトモシキ》云々。九【十五丁】に、吉野川音清左見二友敷《ヨシヌカハオトノサヤケサミルニトモシク》云々などありて、猶多し。さてこゝの意は、あやにともしくめづらしと思ひ奉る、日之皇子と、天皇をさして申給ふ也。この御歌一首は《(マヽ)》の意は、脱句あれば、解しがたし。また夢中の御詠なれば、おのづからにしどけなきにや。またこの天皇、はじめよし野に入せ給ひしが、吉野より伊勢國へ幸ありし事あるをおぼしいでゝ、よみ給へるにもあるべし。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 天皇ノ崩之《カムアガリマシヽ》後。八年九月九日|奉2爲《ツカヘマツレル》御齊會《ヲガミ》1之|夜《ヨ》。夢裏習賜御歌一首《イメニヨミタマヘルミウタヒトツ》。 此ノ條も、即右の一書の中なり、 ○八年は、朱鳥八年なるべし、此次に、藤原ノ宮ニ御宇シ天皇代と標して、朱鳥元年十一月の歌を載、其ノ次に、同三年の歌あれば、こゝに同八年の歌、載べきにあらざれども、此は右の一書に連ね載たるを、やがて其まゝ、此間《コヽ》にあげたるなり、 ○御齊會 (齊は、齋と通 (ハシ) 用ひたり、) は、持統天皇ノ紀に、朱鳥三年二月乙巳、詔曰、自v今以後、毎ニv取《アタル》2國忌ノ日ニ1、要《カナラス》須シv齋《ヲガミス》也と見ゆ、その行事は、大極殿にて、金光明經を讀誦《ヨマ》しめらるゝことゝ見えたり、金光明經は、即チ最勝王經なり、天武天皇ノ紀に、九年五月乙亥、勅云々、始テ設2金光明經ヲ于宮中ニ1と見えたる、是この會の起《ハジマリ》なり、又持統天皇ノ紀に、九年五月癸巳、以2金光明經一百部ヲ1、送2置諸国ニ1、必ス取テ2毎年正月上玄ヲ1讀之、其布施、以2當國ノ官物ヲ1宛之、とも見えたり、 ○習ノ字は、唱か誦かの誤か、又は唱の義にて古ヘ用ひし字にや、十六に、夢裡ニ作ル歌、荒城田乃《アラキダノ》云々、右ノ歌一首、忌部ノ首黒麻呂、夢ノ裡ニ作2此ノ戀歌ヲ1贈v友ニ覺テ而令2誦習1如v前ノ、と見えたればなり、 ○御歌とあるも、持統天皇のとせる、一書の説なるべし、 ○古寫本に、古歌集中に出とあり、 明日香能《アスカノ》。清御原乃宮爾《キヨミハラノミヤニ》。天下《アメノシタ》。所知食之《シロシメシシ》。八隅知之《ヤスミシシ》。吾大王《ワガオホキミ》。高照日之皇子《タカヒカルヒノミコ》。何方爾《イカサマニ》。所念食可《オモホシメセカ》。神風)乃《カムカゼノ》。伊勢能國者《イセノクニハ》。奧津藻毛《オキツモヽ》。靡足波爾《ナビカフナミニ》。鹽氣能味《シホケノミ》。香乎禮流國爾《カヲレルクニニ》。味凝《ウマコリ》。文爾乏寸《アヤニトモシキ》。高照日之御子《タカヒカルヒノミコ》。 〇奧津藻毛、とあるは疑はし、毛はもしは、之の誤などにはあらざるか、 ○靡足波爾は、足は合ノ字の誤なるべし、合の草書足と混易し、さらばナビカフナミニと訓べし、ナビカフは、ナビクの伸りたる言なり、下に、玉藻成彼依此依靡相之《タマモナスカヨリカクヨリナビカヒシ》、とあるに同じ、(ナビカヒ〔は、ナビキの伸りたるなり、岡部氏が、ナミタルとよめるはわろし、又略解に、舊點にナビキシとあるからは、足をシの假字に用ひしか、又は之の誤かと云れど、こゝはナビキシ、といふべき所にあらざるをや、) ○鹽氣能味《シホケノミ》(味ノ字拾穗本には美と作り、)は、九ノ卷に鹽氣立荒磯丹者雖在《シホケタツアリソニハアレド》、ともよめり、 ○香乎禮流《カヲレル》は、神代紀に、伊弉諾ノ尊曰、我カ所生之國《ウメリシクニ》、唯有朝霧而薫滿之哉《アサギリノミカヲリミテルカモ》、神樂歌弓立に、いせしまやあまのとねらがたくほのけをけをけ(本)たくほのけいそらがさきにかをりあふをけをけ(末、)十六に、香塗流《コリヌレル》云々、(皇極天皇ノ紀に、燒v香《コリヲ》、延喜式忌詞に、堂ヲ稱2香焼《コリタキト》1、)香をコリとよめるも、カヲリの切りたる言なり、 ○味凝《ウマコリ》は、まくら辭なり、六ノ卷にも、味凍綾丹乏敷《ウマコリアヤニトモシキ》と有リ、味凝味凍など書るは、皆借リ字にて、美織《ウマキオリ》の綾てふ語なり、と冠辭考に云るは、さることなり、宇麻《ウマ》とは、味飯《ウマイヒ》味酒《ウマサケ》など云る味なり、抑々|宇麻志《ウマシ》といふ言、後ノ世は、食フ物の味にのみかぎりて、いふ如なれゝど、古ヘはしからず、耳にも目にも心にも、すべてよしと思ふものには宇麻志《ウマシ》とは云るなり、故レ美織物《ヨキオリモノ》の謂《ヨシ》にて、宇麻許里《ウマコリ》とは云なりけり、(宇麻許里《ウマコリ》は、宇麻伎於里《ウマキオリ》の約なり、伎於《キオノ》切|許《コ》、) ○文爾乏寸《アヤニトモシキ》は、あやしきまでに、おむかしくめでたき謂なり、六ノ卷に、味凍《ウマコリ》云々、(上に引、)また芳野河之河瀬乃清乎見者《ヨシヌノカハノカハノセノキヨキヲミレバ》云々|毎見文丹乏《ミルゴトニアヤニトモシミ》、八ノ卷に、誰聞都從此間鳴渡鴈鳴乃《タレキヽツコヨナキワタルカリガネノ》、嬬呼音乃乏知左寸《ツマヨブコヱノトモシキマデニ》、九ノ卷に、妹當茂苅音夕霧《イモガアタリコロモカリガネユフギリニ》、來鳴而過去及乏《キナキテスギヌトモシキマデニ》、また、欲見來之久毛知久吉野川《ミマクホリコシクモシルクヨシヌガハ》、音清左見二友敷《オトノサヤケサミルニトモシキ》、十三に、五十串立神酒座奉神主部之《イクシタテミワスヱマツルカムヌシノ》、雲聚山蔭見者乏文《ウズノヤマカゲミレバトモシモ》、十七に伊美豆河泊美奈刀能須登利《イミヅカハミナトノストリ》云々|等母之伎爾美都追須疑由伎《トモシキニミツヽスギユキ》、また曾己乎之毛安夜爾登母志美之怒比都追安蘇夫佐香理乎《ソコヲシモアヤニトモシミシヌビツヽアソブサカリヲ》、廿ノ卷に、夜麻美禮婆見能等母之久《ヤマミレバミノトモシク》、可波美禮波見乃佐夜氣久《カハミレバミノサヤケク》などある、これら皆おむかしく、めでたく思ふを、等母志《トモシ》といへり、此外|乏《トモシ》と云言、集中に甚多し、その中に、或は羨き意、或は少き意などにも云り、本居氏云、乏ノ字を書は、不足《アカズ》思ふより轉れる、一ツの意にして、登母志《トモシ》てふ言の、本義《モトノコヽロ》には非ず、此ノ字に勿《ナ》泥《ナヅ》みそ、 ○御歌ノ意|了解《サトリ》がたし、さきに天武天皇、吉野より伊勢ノ國に幸して、桑名におはしましゝことを、かたじけなみして宣へるか、未タ詳ならず、本居氏云、こは御夢に見賜へる御歌なれば、もとより通《キコ》えぬことなるべし、されど語のつゞきなどは、うるはしき故、そのまゝにて載つらむ、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 檜嬬手 | 天皇崩マシテ之|後《ノチ》八年《ヤトセノ》九月九日、奉ルv爲シ2御齋會ヲ1之夜、夢裏《ミユメニ》唱賜《トナヘタマヘル》御歌《ミウタ》一首 明日香能《アスカノ》、清御原乃宮爾《キヨミハラノミヤニ》、天下《アメノシタ》、所知食之《シロシメシヽ》、八隅知之《ヤスミシシ》、吾大王《ワゴオホキミ》、高照《タカヒカル》、日之皇子《ヒノミコ》、何方爾《イカサマニ》、所念食可《オモホシメセカ》、神風乃《カムカゼノ》、伊勢能國者《イセノクニハ》、奥津藻毛《オキツモヽ》、靡留波爾《ナビケルナミニ》、鹽氣能味《シホゲノミ》、香乎禮流國爾《カヲレルクニニ》、味凝《ウマゴリノ》、文爾乏寸《アヤニトモンキ》、高照《タカヒカル》、日之御子《ヒノミコ》。 〇天武天皇崩リ坐して八年の正當の御忌日に、持統天皇御國忌の御爲に、御をがみゑをせさせ給へるに、其夜御夢によみ賜へる御製歌也。然るに、大后とも、天皇とも、御製歌とも記さゞるは、其世の人の私集に記したるまゝを書き入れたる也。此御齋會は、天武の御爲に始めさせ給へる也。持統二年二月乙己、詔シテ曰ハク自v今以後毎ニ取リテ2國忌ノ日1要《カナラズ》須v齋ル也とある、是也。今本に習賜のある習は唱ノ字を誤れる也。 〇「明香能」以下八句既にいくたびも出づ 〇「何方爾、所念食可」是も一ノ卷に出づ。可の言は下の香乎禮流國と云ふ迄に係れり。 〇「神風乃云云」此つゞきの事、言別《コトワキ》に論《アゲツラ》へり。さて端書に夢裏ニ唱ヘ賜フと在りて、此《コヽ》にかく詔へるは、御夢に天皇の御魂の入らせ賜ひて、吾が靈《ミタマ》は、伊勢ノ海の云々とやうに、告げ給ふと夢見させ給ひし也。此伊勢は志摩の事にて、持統天皇の志摩へ度々|行幸《イデマ》しけるも、此故也。又天武天皇御在世より、伊勢大神を甚《イタ》く尊信し給ひし事は紀にも見え神異例にも引きおけり。又志摩國に御ゆゑよし坐シて、朝夕の御饌《ミケ》を彼の國にめしける、集中にも歌多く見ゆ、かゝれば、大御魂の彼の國にあもりましける事もありけんかし 〇「鹽氣能味、香乎禮流國爾」氣《ケ》は字音にあらず。十六にも日異爾乾而《ヒノケニホシテ》とある異《ケ》にて、古言也。神代紀に唯朝霧而薫滿之哉《タヾアサギリノミカヲリミテルカモ》と、霧霞にもかをると云へること、これも道別に釋せり 〇「味凝、文爾乏寸」美織《ウマゴリ》の綾《アヤ》とかゝりて、文爾乏寸《アヤニトモシキ》は、あなうらやましき日之御子と詔ふ也。 〇一篇の惣意は、こよひ御をがみ會《ヱ》に、さ夜更けてまどろむ間《ホド》に、明けくれ慕ひ奉る夫《ツマ》の尊の夢に見えさせ給ひて、吾が御魂は伊勢ノ國にあり。其國はおきつ藻の靡ける波に、鹽氣のみかをれる國にて、おもしろき國なりと詔《ノタマ》はすに、あなうらやましや、高照る日の御子よと白すまではおぼえたり。その末は夢なれば、いかにありけんと云ふほどの事なれば、此大御歌の首尾せざるを、左右《トカク》云ふ説は、此夢裏の御唱へをよくもおもひやらぬなり。上の、大津ノ宮ノ夫人の御歌にも「吾戀ふる君ぞこぞの夜夢に見えつる」とあり。其歌は醒めて後、現にてよめる也。今此大御歌は、夢ながらよませ給へるなるぞかし。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 口訳 | 天皇崩ぜられた後、八年經て九月九日に御齋會のあつた晩に、夢の中に口吟《クチズサ》みなされた持統天皇の御製 飛鳥《アスカ》の淨見原《キヨミハラ》の宮に、天の下しろしめしゝ安治《ヤスミ》しゝわご大君、たかひかる日の御子。いかさまに思ほし召せか、かむかぜの伊勢の國は、沖つ藻も靡きたる浪に、鹽氣《シホケ》のみ馨れる國に、うまごりあやにともしき高光る日の御子 (これは夢の中の御歌であるし、殊には、神秘的な傳説を伴うたものであるから、幾分普通人の文章法と違うて、暗示的に出來てゐる爲、難解な點がないではない。)飛鳥の淨見个原の宮で天下を治めていらつしやつた天子即、日の神の御|裔《スエ》の我が天皇陛下は、どう御思ひなさつたのか、伊勢の國でいふと、大洋の藻が絡み合うて、寄せて來る浪の上に、汐の馨りの立つてゐる、さうした國へ出掛けた儘、御歸りにならない。無性に御會ひ申したい、立派な天皇陛下よ。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 天皇崩之後、八年九月九日奉ルv爲シ2御齊會1之夜、夢裏ニ習ヒ賜ヘル御歌一首 天武天皇崩御は、朱鳥元年であるから、後八年は持統天皇七年である。持統天皇紀に「七年九月丙申、爲2清御原天皇1設2無遮ノ大會於内裏1」とあるのが、即ちこの齊會であらう。齊は齋に通じて用ゐたもの。夢裏習賜は、夢の内に幾度か口吟み給うた歌の意である。習は繰返すこと。この題詞の下に「古歌集中出」の五字が古本にある。 明日香の 清御原の宮に 天の下 知ろしめしし やすみしし 吾大王 高照らす 日の皇子 いかさまに 思ほしめせか 神風の 伊勢の國は 沖つ藻も なみたる波に 鹽氣のみ 香れる國に 味凝《うまごり》 あやにともしき 高照らす 日の皇子 明日香能《アスカノ》 清御原乃宮爾《キヨミハラノミヤニ》 天下《アメノシタ》 所知食之《シロシメシシ》 八隅知之《ヤスミシシ》 吾大王《ワガオホキミ》 高照《タカテラス》 日之皇子《ヒノミコ》 何方爾《イカサマニ》 所念食可《オモホシメセカ》 神風乃《カムカゼノ》 伊勢能國者《イセノクニハ》 奧津藻毛《オキツモモ》 靡足波爾《ナミタルナミニ》 鹽氣能味《シホゲノミ》 香乎禮流國爾《カヲレルクニニ》 味凝《ウマゴリ》 文爾乏寸《アヤニトモシキ》 高照《タカテラス》 日之御《ヒノミコ》 飛鳥ノ淨見原ノ宮デ、天下ヲ御支配ナサツタ(八隅知之)私ノ天子樣(高照)天子樣ガ何ト思召シタカ(神風乃)伊勢國ハ、アノ沖ノ藻ガ靡イタ波ニ、潮ノ重吹《シブキ》バカリガ薫ツテヰル伊勢ノ國ニ、遙々御出デ下サツテ誠ニ(味凝)不思議ナ程珍ラシイ(高照)天子樣デヰラツシヤルヨ。 ○神風乃《カムカゼノ》――伊勢の枕詞。既出(八一)。 ○奧津藻毛《オキツモモ》――毛は乃の誤と古義にあるが、改める必要はあるまい。 ○靡足波爾《ナミタルナミニ》――足を留としてナビケル、合としてナビカフの訓もあるが、代匠記にナミタルとよんだのに從ふことにする。ナミタルは靡きたるの意。 ○鹽氣能味香乎禮流國爾《シホゲノミカヲレルクニニ》――鹽氣は海上にかかつた潮の氣でもやの如きをいふ。香乎禮流《カヲレル》は潮の香のするをいふ。 ○昧凝《ウマゴリ》――アヤの枕詞。味織《ウマオリ》の綾とつづくのだらうといふ。 ○文爾乏寸《アヤニトモシキ》――不思議に珍らしき意。この乏寸《トモシキ》は羨しい意ではない。 〔評〕 天武天皇が、伊勢の國におはしました御有樣を、ほめたたへたのである。この天武天皇の御英姿は、吉野から伊勢へ幸して、桑名にあらせられた時の事とする説もあるが、要するに、夢中伊勢の海岸に立たせられた御姿である。何處とか何時とか、定める必要はない。夢の中の御歌だから、通ぜぬも道理だと宣長は言つてゐるが、別に意味の不明なところも無く、普通の御歌である。但し挽歌といふ感じはしない。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 天皇崩之後、八年九月九日、奉爲御齋會之夜、夢裏習賜御歌一首 古歌集中出 天皇の崩《かむさ》りましし後、八年の九月九日に、奉爲《おほみため》にせし御齋會の夜に、夢の裏に習ひたまへる御歌一首 【古歌集の中に出づ。】 【釋】天皇崩之後 スメラミコトノカムサリタマヒシノチ。天武天皇の崩後。 八年九月九日 ヤトセノナガツキノココノカ。天武天皇は朱鳥元年の九月九日に崩御されたので、八年は、八年を經過したものとすれは、持統天皇の八年であり、九月九日はその御忌日である。 奉爲 オホミタメニセシ。奉爲は、漢籍から來た字面で、奉は敬意をあらわす。二字オホミタメと讀み、ニセシを讀み添える。天武天皇御冥福の御爲にの意である。 御齋會之歌 オホミヲガミノヨ。齋を設けて佛事を修するを齋會という。天武天皇の御冥福に資せんがために行われた御齋會の夜である。御齋會は、ゴサイヱともいう。 夢裏習賜御歌 イメノウチニナラヒタマヘルミウタ。習は、しばしば繰り返すをいう。夢の中にして自然に得させたまう御歌の義。この歌、作者を傳えないのは、夢中に得られた歌だからであつて、その夢の主は、持統太上天皇にましますであろう。御製といわないのは、夢裡に得られたからであつて、神佛のお告げというが如き信仰があるからである。夢のうちに歌をよむことは、本集では、「荒城田乃《アラキダノ》 子師田乃稻乎《シシダノイネヲ》」(卷十七、三八四八)の歌の左註に「右歌一首、忌部黒麻呂、夢裏作2此戀歌1、贈v友、覺而令2誦習1如v前」とある。 明日香の 清御原《きよみはら》の宮に 天の下 知らしめしし やすみしし わが大王 高照らす 日の皇子、 いかさまに 念ほしめせか、 神風の 伊勢の國は、 奧《おき》つ藻も 靡《な》みたる波に、 潮氣《しほけ》のみ 香《かを》れる國に、 味凝《うまごり》 あやにともしき 高照らす日の皇子。 明日香能《アスカノ》 清御原乃宮尓《キヨミハラノミヤニ》 天下《アメノシタ》 所v知食之《シラシメシシ》 八隅知之《ヤスミシシ》 吾《ワガ・ワゴ》大王《オホキミ》 高照《タカテラス》 日之皇子《ヒノミコ》 何方尓《イカサマニ》 所v念食可《オモホシメセカ》 神風乃《カムカゼノ》 伊勢能國者《イセノクニハ》 奧津藻毛《オキツモモ》 靡足波尓《ナミタルナミニ》 潮氣能味《シホケノミ》 香乎禮流國尓《カヲレルクニニ》 味凝《ウマコリ・アジコリ》 文尓乏寸《アヤニトモシキ》 高照《タカテラス》 日之御子《ヒノミコ》 【譯】明日香の清御原の宮で天下を知ろしめした、八方を知ろしめすわが大君、照り輝く日の御子樣は、どのように思しめされてか、神風の吹く伊勢の國は、沖の海藻も靡いている波に、潮の香の立ち昇る國に、まことに貴い照り輝く日の御子樣。 【構成】別に段落は無い。 【釋】 明日香能清御原乃宮尓 アスカノキヨミハラノミヤニ。天武天皇の皇居である。宮號によつて、その天皇をさす所をあきらかにするは古文の例である。 天下所知食之 アメノシタシラシメシシ。下のシは時の助動詞キの連體形。 八隅知之吾大王高照日之皇子 ヤスミシシワガオホキミタカテラスヒノミコ。ヒノミコは、既出。貴い御子の義に、日ノを冠するのだろう。「高光《タカヒカル》 日御朝庭《ヒノミカド》」(卷五、八九四)、「日之御調等《ヒノミツキト》」(卷六、九三三)。ここは天武天皇。以上天武天皇を呼び懸けている。 何方尓所念食可 イカサマニオモホシメセカ。近江の荒都を過ぎし時の歌(卷一、二九)に「何方《イカサマニ》 御念食可《オモホシメセカ》」とある。オモホシメセカは、オモホシメセバカの意で、疑問の條件法であるが、獨立句として插入されていて、結びが無い。意外の事だという感じをあらわすに使用する常用の句である。 伊勢能國者 イセノクニハ。下の句に對する主格の提示。 奧津藻毛 オキツモモ。海上の藻も。 靡足波尓 ナミタルナミニ。舊訓ナビキシナミニと讀んでいるが、足を助動詞シに當てた例は、他に無い。助詞シに當てた例も無い。「級照《シナテル》 片足羽河之《カタシハガハノ》」(卷九、一七四二)、「日倉足者《ヒグラシハ》 時常雖v鳴《トキトナケドモ》」(卷十、一九八二)の例は、上の音がア段の音で、アシのアを吸收したものと見られる。靡をナミと讀むのは、「旗須爲寸《ハタススキ》 四能乎押靡《シノヲオシナベ》」(卷一、四五)の如く、押靡と書いた例多く、それはオシナベと讀んでおり、下二段活と見られるが、四段活用としては「麻都能氣乃《マツノケノ》 奈美多流美禮婆《ナミタルミレバ》 伊波妣等乃《イハビトノ》 和例乎美於久流等《ワレヲミオクルト》 多々理之母己呂《タタリシモコロ》」(卷二十、四三七五)があり、この奈美多流は、普通に竝みたるの義として、解せられているが、歌意よりすれば、靡みたると解するを可とするようである。また足は、助動詞タルに使用することは多く、上の一五八にも使用している。歌意よりしても過去のこととするは無理であるから、かたがたナミタルナミニと讀むべきであつて、海上の藻の靡いている波にの意とすべきであろう。この句の意は、靡みたる波にてありの意で、下の鹽氣ノミカヲレルの句と對している。 鹽氣能味 シホケノミ。シホケは、潮の氣で、潮の發する氣をいう。ノミは、それの特にはなはだしく、他物無き狀をいう。「鹽氣立《シホケタツ》 荒礒丹者雖v在《アリソニハアレド》 往水之《ユクミヅノ》 過去妹之《スギニシイモガ》 方見等曾來《カタミトゾコシ》」(卷九、一七九七)。 香乎禮流國尓 カヲレルクニニ。カヲレルは、霧霞などの立ち煙るをいう。日本書紀神代の上に「伊弉諾尊曰我所v生之國、唯有2朝霧1而、薫滿之哉」とある。その國に、日の皇子はとつづく語法。 味凝 ウマコリ。枕詞、ウマキオリの約言で、上等の織物の義に、アヤ(綾)に懸かるのであろうとされているが、ウマオリ、ウマシオリならばともかく、ウマキオリの形が、古くあるようには思えない。「味凍《ウマコリ》 綾丹乏敷《アヤニトモシク》」(卷六、九一三)とも書かれていて、共にアヂコリとも讀まれる。倭名類聚鈔に、凝海藻にコルモハの訓があり、凝結のために使う海藻だろうから、ニコゴリのような食物があつて、それをウマコリと言い、驚嘆のアヤに冠したのだろう。もしくはコリは凍結で、アヂコリと讀んで、たくさんの氷の意か。 文尓乏寸 アヤニトモシキ。アヤニは驚嘆すべくある意の副詞。トモシキは、ここは賞美すべく慕わしい意に使用されている。 高照日之御子 タカテラスヒノミコ。上に提示した句を繰り返して結んでいる。 【評語】夢裡の歌であつて、言い足らない詞句のあるのはやむを得ない所である。沖ツ藻モ靡ミタル波ニ、また鹽氣ノミカヲレル國ニと言つて、その歸結をつけずに轉じているが如きはそれである。また歌いものとして傳えられていた歌の成句を使用することの多いのも、夢裡の歌である特色を備えている。これによつて内容が一層神秘になつている。高照ラス日ノ御子と伊勢の國との關係は明瞭でないが、天武天皇の神靈が伊勢の國に赴かれるように解せられ、その伊勢の國を稱える詞句に重點が置かれている。古事記の序文に、天武天皇の擧兵について、夢ノ歌ヲ聞キテ業ヲ纂ガムコトヲ想ホシとあり、前兆として夢の歌があつたと見られ、その歌は不明であるが、この歌に関係があるかも知れない。また作者は、天武天皇の擧兵の際、共に伊勢に赴かれた。そういうことも自然関係して來ているであろう。なお人が死んで、その靈が伊勢に赴くことは、後世の俚謠にその證があり、當時もそういう信仰があつたかも知れない。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | 天皇崩りましし後、八年九月九日|奉爲《おほみため》にせし御齋會《おほみをがみ》の夜、夢《いめ》の裏《うち》に習ひ賜へる御歌一首 明日香《あすか》の 清御原《きよみはら》の宮に 天《あめ》の下 知らしめしし やすみしし 吾|大王《おほきみ》 高照す 日の皇子《みこ》 いかさまに 念《おも》ほしめせか 神風《かむかぜ》の 伊勢の國は 奥《おき》つ藻も 靡《な》みたる波に 鹽氣《しほけ》のみ 香《かを》れる國に 味凝《うまこり》 あやにともしき 高照す 日の皇子 〔題〕 天武天皇崩御の後八年は持統天皇七年に當り、此の年の九月九日即ち天皇の御忌日に御齋會が行はれたのであつて、このことは紀にも見えてゐる。(但、紀は十日になつてゐる)夢の裏に習ひ賜ふとは、夢の中に覺え給ふの意と思はれる。 〔譯〕 明日香の清御原の宮に天下を治め給うた我が大君、日の皇子はどうお思ひになつたのか、伊勢の國の沖の藻も靡いてゐる波に、潮氣が一面に立ち霞んでゐる國に、まことに慕はしい日の皇子。 〔評〕 夢裏に習ひ賜へる歌であるからであらうか、「いかさまに念ほしめせか」の結びはなく、また、「伊勢の國は」から「日の皇子」への續きも不明で、中間にも、或は終にも脱漏かと見られる點がある。強ひて解すれば考のいふやうに、吉野より伊勢の國に入らせられた時、海濱に立ち給うた御姿を讃へたものと解せられる。いづれにしても句々莊重、端正な古調を存してをる。 〔語〕 ○明日香の清御原の宮 天武天皇の皇居。「二二」參照。 ○やすみしし 「五〇」參照。 ○いかさまに念ほしめせか、「二九」參照。 ○神風の 伊勢の枕詞。「八一」參照。 ○奥つ藻 「一三一」參照。 ○靡みたる波に 靡いてゐる波に。 ○香れる國 香るは香氣のたつとも解されるが、潮の香の立ち霞む意とみるのがよい。古くは香るを霞霧などの立ちこめる意にも用ゐてゐる。 ○味凝 あやの枕詞。うまく織りの略で、巧みに織つた綾とかかる。 ○あやにともしき あやは「一五九」參照。ともしきは、愛すべき、慕はしき。 〔訓〕 ○靡みたる波に 白文「靡足波爾」の「靡足」を「靡留《ナビケル》」(檜嬬手)、「廣合《ナビカフ》」(古義)等誤字とする説には從へない。また「足」をシの假字として、ナビキシナミニと訓む舊訓に從ふ註も多いが、代匠記ナミタルが穩かであらう。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 天皇崩之後八年九月九日奉爲御齋會之夜夢裏習賜御歌一首 古歌集中出 天武天皇の崩御は朱鳥元年九月九日である事は前 (一五九題詞) に述べた。それから八年は持統天皇七年にあたる。その七年九月の紀に 「丙申。爲2浄御原天皇1。設2無遮大會於内裏1。繫囚悉|原遣(ユルシヤル)。」 とあつて右の題詞と一致するやうであるが、丙申は十日であつて正忌日の翌日にあたる。そこで紀を誤記かとも見られてゐるが、私注には御斉會は次に持統紀二年の記事を引用するやうに恒例となつてゐたので紀には記さず、翌日の無遮大會のみを記したのだとして無遮大會は道俗男女貴賤上下をへだてることなく、普く来衆に施與するもので、斉會とは別であり、今の題詞により九日に御斉會が行はれ、紀により十日に無遮大會が行はれた事が知られると述べられてゐる。天武崩御の朱鳥元年十二月に無遮大會を大官、飛鳥、川原等の五寺で営み、翌持統元年九月 「庚午、設2無遮大會於京師諸寺1。辛来。設2斉於殯宮1。」 とあるは九日十日とつづいて斉會が行はれた事を示し、翌二年正月八日には 「設2無遮大會於薬師寺1。」 とあつて、その後四年二月に 「設2斉於内裡1。」 とあるだけで、例年の御斎會の記事は見えないので、私注の説によるべきであらう。 「奉爲」 の文字については山田孝雄博士に 「奉爲考」 (藝文 第十六巻第七号 大正十四年七月) がある。奉爲の文字は梁の石像銘に 「奉爲亡父亡母」 とあるがはじめで、本邦上代の金石文、日本書紀その他の上代文献に散見し、「おほんため」 と義訓すべきであるといふ。オホンは 「大御(オホミ)」 の訛つたもので、今はオホミタメノと訓む。 「斉會」 は敏達紀十三年の條に 「大會設斉(タイヱノヲカミス)」 とあるものがはじめであり、それは蘇我馬子の営んだものであるが、宮中の御斉會は天武紀四年に 「夏四月甲戌朔戊寅。請2儈尼二千四百餘1而|設斉焉(ニヲカミス)」とあるをはじめとされてゐる。儈尼を集めて読経供養するもので、持統紀二年二月の條に 「乙巳(十六日)。詔曰。自今以後。毎レ取2国忌日1。要須レ斉也」 とあり、後には毎年正月宮中で行はれるやうになつた。 「夢裏習賜(イメノウチニナラヒタマヘル)」 は夢の中で幾度もくりかへし自然に覚えられた、といふ意味であらう。夢裡作歌の例は巻十六 (三八四八) にもある。「御歌」 とのみあつて、作者を明記してないが、やはり持統天皇と見るべきであらう。「古歌集中出」 の注は版本には脱してゐる。 明日香能(アスカノ) 清御原乃宮尓(キヨミハラノミヤニ) 天下(アメノシタ) 所知食之(シラシメシシ) 八隅知之(ヤスミシシ) 吾大王(ワガオホキミ) 高照(タカテラス) 日之皇子(ヒノミコ) 何方尓(イカサマニ) 所念食可(オモヒシメセカ) 神風乃(カムカゼノ) 伊勢能國者(イセノクニハ) 奥津藻毛(オキツモノ) 靡足波尓(ナミタルナミニ) 塩氣能味(シホケノミ) 香乎礼流國尓(カヲレルクニニ) 味凝(ウマゴリ) 文尓乏寸(アヤニトモシキ) 高照(タカテラス) 日之御子(ヒノミコ) 明日香の 清御原の宮に 天の下 知らしめしし やすみしし 我が大君 高照らす 日の御子 いかさまに 思ほしめせか 神風の 伊勢の国は 沖つ藻も 靡みたる波に 潮気のみ 香れる国に 味凝り あやにともしき 高照らす 日の御子 【口釋】 飛鳥の浄御原の宮で天下をお治めになつた、八隅を知ろしめすわが大君、大空高く照らす日の皇子は、どのやうに思召せばか、神風の吹く伊勢の国は、沖の藻も靡いてゐる波に潮気のみ烟つてゐる国に、誠に慕はしい、大空高く照らす、我が日の皇子は-。 【訓釋】 飛鳥の浄御原の宮-既出(一・二二標題)。 天の下知らしめしし-既出(一・二九)。 八隅知し吾が大君-既出(一・三)。 高照らす日の皇子-既出(一・四五)。 いかさまに思ほしめせか-既出(一・二九)。「めせか」 はめせばか、の意で、その 「か」 は下にかかるわけであるが、この作では下が完全に結ばれてゐないので、従つてこの語に呼応するものが無くなつてゐる。 神風の-既出(一・八一)。枕詞。 沖つ藻も靡みたる波に-「沖つ藻」 は既出 (一三一)。靡みたるの原文 「靡足」 とあり、旧訓にナビキシ とあり、講義には仁賢紀に 「諱大脚。更名大爲」 とあり、顕宗紀 (前紀) に 「更名大石尊」 とある、いづれもオホシと訓む例をあげ、「脚」、「石」 をシの仮名に用ゐてゐるから 「足」 をシの仮名に用ゐた事を認められてゐるが、集中 「足」 の場合は 「片足羽河(カタシハガハ)」 (九・一七四二)、「荒足(アラシ)」 (七・一一〇一)、「痛足河(アナシガハ)」 (七・一〇八七) などいづれも上の音がア段である」場合に限られてゐるから、代匠記に 「ナミタルトモ読ベシ」 とあるに従ふべきであらう。「足」 をタルと訓んだ例は前 (一五八) にもある。ナミは靡きの意で、「靡け」 (他動詞) をナベ (一・一) とも云つたやうに、「靡き」 (自動詞) をナミとも云つたと思はれる。沖の藻も靡いてゐる波に、の意。 潮気のみかをれる国に-「潮気」 は潮の気で 「塩気立(シホケタツ) 荒磯丹者雖在(アリソニハアレド)」 (九・一七九七) ともある。「かをる」 は神代紀上の一書に大八洲国を生み更に諸神を生み給はむとするところに 「伊弉諾尊曰、我所レ生之国唯有2朝霧1而薫満之哉」 とあり、神楽歌の弓立歌に 「伊勢島の 海人の刀祢等が 焼く火(ほ)の気(け) おけおけ焚く火の気 磯良が崎に 加保(カホ)[乎(ヲ)利安不(リアフ) おけおけ]」 とあつて、香の薫るの意のみでなく、霧や火気の立ちこめるにも用ゐ、ここも藻の靡いてゐる波に潮気の立ち煙るばかりの土地に、の意である。 うまごり-枕詞。冠辭考に春満の説として 「美織(ウマオリ)の綾てふ語也」 とある。うまきおりの約と見るのである。「味凍(ウマコリ) 綾丹乏敷(アヤニトモシキ)」 (六・九一三) の例もある。 あやにともしき-「あやに」 は既出 (一五九)。「ともし」 は乏しの意から転じて羨しの意 (一・五三) にもなり、愛すべく、心惹かれる、などの意にも用ゐられる。今はその意である。「吉野川音のさやけさ見二友敷(ミルニトモシク)」 (九・一七二四)、「阿倍の田のもにゐる鶴(たづ)の等毛思吉伎美波(トモシキキミハ)あすさへもがも」 (十四・三五二三) などの例である。 高照らす日の皇子-前にある言葉がくりかへされた形で、それが結びになつてゐるやうであるが、実際は中断されてゐるのである。上に述べた 「思ほしめせか」 をうけるものではなく、「靡みたる波に」 や 「かをれる国に」 などの下にそれが省略されたと見る説が多いが、これはそこに意識的な省略があると見るよりは更に 「日の皇子は」 と下へつづくべきはずが中断されたもので、しかも日の皇子が上のくりかへしの形になつてゐるので結句のやうな体裁をなしてゐると見るべきであらう。 【考】 この御作の前半は訓釋の條で 「既出」 の語をくりかへしておいたが、それは必ずしもその語がこの御作の語に先行するといふ意味ではないにしても、さうした類似の語がこの御作の前後にくりかへされてゐるといふ事は、当時の常套語の羅列といふ事になつて夢の中で口ずさまれたといふ事もうなづかれよう。後半になつて作意らしいものが示されてゐるが、その伊勢の国が何の爲に持ち出されたか、天武天皇の神霊が伊勢の国へ赴かれたやうにも解されるが、それは挽歌といふ観念からさう思はれるのであつて、必ずしもさう解かねばならぬものではない。壬申の乱に天武天皇が伊勢を廻つて美濃へ入られ、作者たる皇后も同列して難澁せられた事は忘れ難き思出であり、また作者がこの作の前年に伊勢行幸をせられた事も新しい記憶であり、さうした新旧の記憶が夢の中に結びついて、「伊勢の国は...」 となり 「潮気のみかをれる」 といふやうな、うらさびた表現ともなつたのであるが、それが十分一首の歌としての構成を全くしないうちに御夢さめて、かうした未完成の形だけで残された、といふ風に見るべきではなからうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 天皇の崩りましし後の八年九月九日、奉爲 (おほみため) の御齋會 (ごさいゑ) の夜、夢のうちに習ひ賜ふ御歌一首 古歌集の中に出づ 〇原文 「天皇崩之後八年九月九日奉爲御齋會之夜夢裏習賜御歌一首」。「齋」 を金澤本に 「□ (夊の下に日)」、古葉略類聚鈔・紀州本に 「斉」、西本願寺本に 「齊」 とするが、細井本・温故堂本に 「齋」 とあるのが正しい。 〇斎会 僧を集めて斎食を施す法会。わが国では敏達天皇十三年 (五八四) に行われたのが最初らしい (『仏教語大辞典』)。天武四年四月紀に 「甲戌朔戊寅、請僧尼二千四百余而大設齋焉」と見える。また持統二年二月紀に 「乙巳、詔曰自今以後毎レ取2国忌日1、要須レ齋也」とあり、国忌のつまり先帝の崩御の日に齋 会をもよおすことが定められている。天武天皇の崩御は、朱鳥元年九月九日。この歌の題詞の 「九月九日奉為御齋 会之夜」 は、その国忌の夜のこと。 「奉為」 は山田孝雄 「奉為考」 (芸文大正十四年九月) によってオホンタメ (オホミタメ) と訓む。ここに 「八年九月九日」 とあるのは持統天皇七年にあたる。日本書紀持統七年九月九日の条には齋会の記事がなく、翌日に 「丙申 (十日)、為2浄御原天皇1、設2無遮大会於内裏1 」 と記されているので九日の誤記とする説もある (古典大系本書紀頭注)。しかし、国忌日の齋 会は持統二年二月の詔に明言されているとおり年毎に行われたと思われるの、以後記すところが全くない。ここの無遮大会は忌日の斎会と別に行われたものと考えるべきである、 (私注)。無遮大会とは、仏教において、国王が施主となって国内の僧尼貴賤一切の人々を制限なく供養し布施する大会をいう (『仏教語大辞典』)。 〇夢のうちに習ひ賜ふ 夢の中でくりかえし詠み覚えられた歌ということだろう。普通の夢ではなく、鎮魂のためにとくに夢を見ることが行われたか (一五〇参照)。作者を記していないが、「御歌」 とあり、大后 (持統天皇) 作歌と思われる。「古歌集」 は既出 (八九歌左注)。万葉集編纂のための資料となった歌集の一。編纂者および編纂年代など不詳であるが、持統・文武朝から奈良時代初期にかけての作歌を収めたものと推定される。 明日香能《アスカノ》 清御原乃宮尓《キヨミハラノミヤニ》 天下《アメノシタ》 所知食之《シラシメシシ》 八隅知之《ヤスミシシ》 吾大王《ワガオホキミ》 高照《タカテラス》 日之皇子《ヒノミコ》 何方尓《イカサマニ》 所念食可《オモホシメセカ》 神風乃《カムカゼノ》 伊勢能國者《イセノクニハ》 奧津藻毛《オキツモモ》 靡足波尓《ナミタルナミニ》 塩氣能味《シホケノミ》 香乎禮流國尓《カヲレルクニニ》 味凝《ウマコリ》 文尓乏寸《アヤニトモシキ》 高照《タカテラス》 日之御《ヒノミコ》 明日香の浄御原の宮で 天下をお治めになられた (やすみしし) わが大君 (高照らす) 日の皇子はどのようにお思いになられてか、 (神風の) 伊勢の国は沖つ藻も靡いている波の上に 潮の香ばかり立ちこめている国に (うまこり) むしょうに慕わしい (高照らす) 日の皇子。 【注】 〇 明日香の浄御原の宮に- 天武天皇の皇居。既出 (一五六歌の前の標参照)。 〇 天の下知らしめしし- 天下をお治めになった、の意。「天の下」 という語は上代文献に約四百例見えるが、ほとんどが天皇の統治を語る文脈にあらわれる。もと漢籍に見られる 「天下」 の意味・用法を取り入れ、地上の人間世界を天皇による統治という視点から包括的にとらえた呼び名と考えられる (遠山一郎「アメノシタの成立」国語国文昭和五十七年七月)。シラシメシシのシラは支配する意の動詞。次のシは尊敬の助動詞。メシシの最後のシは過去の助動詞キの連体形である。 〇 やすみししわが大君- 既出 (一五五歌、一五九歌など)。 〇 高照らす日の皇子- 天武・持統天皇とその皇子たち (孫にあたる軽皇子を言う場合もある) について、特に使われた讃称。この時期における日神崇拝と天皇即神観の高揚を背景として人麻呂の創造した称詞と推測される。この持統天皇の作歌や、巻一の藤原宮役民作歌・御井歌などにも見られるのは、それを襲用したものであろう。草壁皇子の舎人の歌や人麻呂作歌 (二三九) にタカヒカルヒノミコという表現を見るが、タカヒカルよりもタカテラスに敬意が深く、おそらく前者より後者の方が新しい形と思われる。ヒノミコの原義は、日神の子孫を意味したものか、日のように照り輝く御子の意であったか、容易に決し難いけれども (土橋寛『古代歌謡全注釈』)、タカテラスは日神 (天照大神) の高く照り輝きいます意で、直接には日にかかる語句であったと見られよう。もちろん大君の君臨統治を暗示するはたらきも持つ。 〇 いかさまに思ほしめせか- 原文 「何方尓所念食可」 の 「念食」 を金澤本・古葉略類聚鈔に 「食念」 とするのは誤り。「何方尓」 はイカサマニと訓む。何はイカ (ニ) であり、方は方向・方法・理由などをあらわすサマにあたる。メセカはメセバカに等しい。どのようにお考えになられたからか、の意。巻一の近江荒都歌 (1・二九) にも、このあとの日並皇子挽歌 (一六七) にも、「いかさまに思ほしめせか」 と見え、挽歌における常套表現と見られる。ここでは、皇居を去って伊勢国に行かれた天武天皇の心のはかり難いことを、どのようにお考えになられてかと嘆いているのである。 〇 神風の伊勢の国は- カムカゼノは、伊勢に冠する枕詞。伊勢は神のいる地で、常に風の烈しい所であるところから伊勢にかかるとも、神風を息吹(いぶき)とし、その古語 「息」 に繰り返しの意でかかるとも言うが、確かなことは分からない。記紀歌謡にも見えるので、古くから歌われたのであろう。古意はともかく、人麻呂の時代以後は、神風を吹かせ天武天皇の軍を御加護なされた神のいます伊勢という意識が強くあったと思われる (一九九歌参照)。この歌にも、そうした意識があろう。 〇 沖つ藻も靡みたる波に- 「沖つ藻」 は既出 (一三一歌)。「靡みたる」 の原文 「靡足」。ナミは、ここのみに見える。靡かせる意の動詞 (下二段活用) 「靡ぶ」 に対し、四段活用の自動詞「靡ぶ」 が想定されるし、バ行とマ行の音通ということでナム (連用形ナミ) という形も推定される。足は前 (一五八歌) にもあったように、存在の助動詞タルを表す借訓字。沖の藻もなびいている波の上に、の意。足をシの仮名としてナビキシと訓むのは、あとのシホケノミカヲレルとの対照から言って無理であろう。 〇 潮気のみかをれる国に- シホケは、人麻呂歌集に 「潮気立つ荒磯にはあれど行く水の過ぎにし妹が形見とぞ来し」 (9・一七九七) と見える。ケは、そのものの気配であり、潮の香を言う。カヲルは、霊異記上巻第五話に、「屍有異香而□[馛の旁が分]馥矣」 の[赤文字]に注して 「上音分、下音服□□□乎礼利」 とあり、欠字部分は 「二合可」 の三文字と推定されるので (古典大系霊異記頭注)、匂いのすること、香気を放つことを意味する動詞と考えられるが、神楽歌に 「伊勢志摩の 海人の刀祢らが 焼く火(ほ)の気(け) おけおけ 焼く火の気 磯良が崎に 加保利安不 おけおけ」(古典大系本神楽歌七五番歌) とあるのは、匂うというより、煙の立ちこめることを言う例。なお古典大系本には加保利安不となっているが (梁塵後抄による)、天理図書館蔵重種本では 「加緒利阿比多利」 とあって、古形を示す (白藤礼幸 「神楽歌語彙索引」『論集上代文学』第十二冊 )。一六二歌のカヲレルも、これと同じく潮気の立ちこめている状態をあらわすのであろう。なお、この句を受ける述語がなく、文が不完全なままに終わっている。折口口訳では、「さうした国へ出掛けた儘、御帰りにならない」 を補っている。 〇 うまこりあやにともしき- ウマコリはアヤニに冠する枕詞。ウマキオリすなわち立派な織物の意で綾にかかるとも (冠辞考に荷田春満の説としてあげる)、コリは朝鮮語で綾をあらわす語と同源とも (古典大系) いう。後者なら 「庭つ鳥 鶏」 「野つ鳥 雉」 などとひとしく類語反復型枕詞である。アヤニは駆出 (一五九歌)。トモシキは乏しい・少ない意から、転じて羨ましい、心が惹かれることをあらわす形容詞。ここでは、心惹かれる意。 【考】 夢の裏に詠みならった歌 冒頭の四句は音数も整わず、歌というよりむしろ散文の表現で、五句目の 「やすみしし」 以下が普通の長歌の形となっている。二十句から成り、その大部分を讃歌あるいは挽歌の慣用句が占めていると言ってよい。僅かに 「沖つ藻も 靡みたる波に 潮気のみ かをれる国に」 の四句が、他の歌には見られない特殊な伊勢の海の表現であるが、 「かをれる国に」 のあとに続くべき述語を欠いており、不安定で意味的に不完全な印象を与える。しかし夢裏に詠みならった歌として、それがかえってふさわしく、あわれ深くも感じさせよう。潮気の立ちこめる波の上に、「高照らす 日の皇子」 天武天皇の面影がおぼろに浮かんだところで、夢のとだえたように歌は終わっている。私注にはこれを 「崩御後の天皇の有様、即ち人の死後の生活を歌つて居るものと解すべきだ。」とし、「後のことではあるが関白道長が栄華を極めた晩年をただ後世のことのみ拘はつて、人間のなし得る善業といふ善業を積んで死んだ後、人の夢によつてやつと下品下生であつたことが分つたが、それでも浄土の中であると残つた者たちが喜び合つたといふ話がある。夢に死後があらはれるといふのは自然なことであり、時に思の外のこともあるものなのであらう。...十日に無遮大会が殊に天皇の為に設けられたのは、推測を加へるなら、九日の夜夢にあらはれた天皇のみ姿がいかにもあはれ深いので、その追善のためであつたのではあるまいか」 と想像している。 なお、この歌の 「夢」 は、魂鎮めのための夢占いのもので、その夢の収穫として一六二歌があったのだろうとも言われる (伊藤博「天智天皇を悼む歌」美夫君志十九号)。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 新体系 | 明日香能《アスカノ》 清御原乃宮尓《キヨミノミヤニ》 天下《アメノシタ》 所知食之《シラシメシシ》 八隅知之《ヤスミシシ》 吾大王《ワガオホキミ》 高照《タカテラス》 日之皇子《ヒノミコ》 何方尓《イカサマニ》 所念食可《オモホシメセカ》 神風乃《カムカゼノ》 伊勢能國者《イセノクニハ》 奧津藻毛《オキツモモ》 靡足波尓《ナミタルナミニ》 塩氣能味《シホケノミ》 香乎禮流國尓《カヲレルクニニ》 味凝《ウマコリ》 文尓乏寸《アヤニトモシキ》 高照《タカテラス》 日之御《ヒノミコ》 第二句の原文 「清御原乃宮尓」 は、キヨミハラノミヤニと訓まず、音数に合わせて 「キヨミノミヤニ」 と訓む。「浄之宮(きよみのみや) 」(一六七)。この歌は持統天皇の作と思われる。「夢の裏に」 歌を詠んだ例としては、巻十六に、忌部首(いむべのおびと)黒麻呂天の例 (三八四八) がある。何らかの啓示によるものであろう。歌の文脈が整っていないことも、夢中に得た作という事情に関わるか。-中略-「神風の伊勢の国は」という提示は唐突である。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 巻二163 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 | [校本萬葉集]
|
||||||||||||||||||||||||||
| 活字附訓本 | 活字附訓本 | 活字附訓本 (国立国会図書館蔵書)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 諸注引用 | 拾穂抄 | 藤原宮御宇 大津ノ皇子|薨《ミマカリテ》後|從《ヨリ》2伊勢ノ齋宮《イツキノミヤ》1上京ノ時ノ御作歌二首 大來皇女《ヲホクノヒメミコ》 大津皇子薨 持統天皇元年十一月三日依テ2謀反ニ1薨 かみかせのいせのくにゝもあらましをなにゝかきけん君もあらなくに 神風之伊勢能國尓毛有益乎奈何可來計武君毛不材尓 神風のいせのくにゝも 其まゝ齋宮にあらん物をと也哀悼のあまりによめるなるへし |
|||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | 藤原宮御宇天皇代 高天原廣野姫天皇 此注殊に誤れり、下に至て自から顯はるべし、 大津皇子薨之後大來皇女從伊勢齊宮上京之時御作歌 二首 持統紀云、朱鳥元年十一月丁酉朔壬子、奉2伊勢神宮1皇女大來還2至|京師《ミヤコニ》1、十四歳にて齋宮に立たまひ、十四年に當て還たまへり、文武紀云、大寶元年十二月乙丑、大伯《オホクノ》内親王薨ず、齊は齋に改むべし、 神風之伊勢能國爾母有益乎奈何可來計武君毛不有國爾《カミカセノイセノクニヽモアラマシヲナニヽカキケムキミモアラナクニ》 アラマシヲは、皈らずしてさて有まし物をと悔たまふなり、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 童子間 | 藤原宮御宇天皇代 大津皇子薨之後大來皇女從伊勢齋宮上京之時御作歌二首 童子問 大津皇子と大來皇女と兄弟にてましますや。 答 しかり。天武天皇のみこにて、同母の兄弟地。大來皇女は大津皇子の姉也、御母は大田皇女也。大田皇女は天智天皇の皇女也。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 童蒙抄 | 藤原宮宮御宇天皇代 高天原廣姫天皇 大津皇子薨之後大來皇女從伊勢齊宮上京之時御作歌二首 おほつのみこみまかれる後、おほきの皇女、いせのいつきのみやよりみやこにのぼり給ふときみつくりうたふたくさ 大津皇子 大來の皇女の事は前に審也 從伊勢齊宮上京之時 日本紀卷第卅持統紀云、朱鳥元年十一月丁酉朔壬子、幸2伊勢神祠1皇女大來還2至京師1云々 神風之伊勢能國爾母有益乎奈何可來計武君毛不有爾 かみかぜの、いせのくにゝも、あらましを、なにゝかきけん、君もあらなくに 此歌の意はきこえたる通也。此君とよみ給ふは大津皇子の事歟。また御父の親天武の御事をよませ給ふやわかちがたし。標題に大津皇子の事をあげたれば、皇子の事と見ゆれども、君とさし給ふことは前にもありといへども、このところにては、天武の御事ともきこゆる也 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉考 | 藤原ノ宮ニ御宇天皇代。 ○大津ノ皇子ノ薨之後《スギタマヘルノチ》、大來《オホクノ》皇女、 既出、 從2伊勢ノ齋ノ宮1上《ノボリタマフ》v京《ミヤコヘ》之時《トキ》、御作歌、 朱鳥元年十一月なり、 神風之《カミカゼノ》、 冠辭、 伊勢能國爾母《イセノクニニモ》、有益乎《アラマシヲ》、奈何可來計武《ナニシカキケム》、君毛不有爾《キミモアラナクニ》、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | 藤原宮御宇天皇代 高天原廣野姫天皇 [後に持統と申す] 大津皇子薨之後大來皇女從2伊勢齋宮1上京之時御作歌二首 朱鳥元年十一月なり。 神風之。伊勢能國爾母。有益乎。奈何可來計武。君毛不有國。 かむかぜの。いせのくににも。あらましを。なにしかきけむ。きみもあらなくに。 神カゼノ枕詞。君は大津皇子をさし給へり。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 攷證 | 藤原宮御宇天皇代。高天原廣野姫天皇。 天皇、御謚を持統と申す。 この宮の事は、上【攷證一上四十三丁】に出たり。高天原廣野姫天皇の九字、印本大字とす。今集中の例によりて、小字とせり。 大津皇子薨之後。大來《オホク》皇女。從2伊勢齋宮1上v京之時。御作歌。二首。 大津《オホツ》皇子薨。 天武帝の皇子也。朱鳥元年十月。薨給へり。上【攷證二上廿二丁】にもくはし。 大來《オホク》皇女。 天武帝の皇女、大津皇子同母の御姉なり。白鳳二年、齋宮になり給ひて、朱鳥元年十一月に、齋宮より、京にかへらせ給ひぬ。こは、大津皇子の御事によりてなるべし。この皇女、まへには、大伯皇女と見えたり。その所【攷證二上廿三丁】にくはし。 神風之《カムカセノ》。伊勢能國爾母《イセノクニニモ》。有益乎《アラマシヲ》。奈何可來計武《ナニシカキケム》。君毛不有爾《キミモアラナクニ》。 奈何《ナニシ》。 奈何は、集中、なぞ、などかなどもよめり。みな義訓なり。 君不有爾《キミモアラナクニ》。 君は、大津皇子をさしたまへり。一首の意明らけし。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 藤原宮御宇天皇代《フヂハラノミヤニアメノシタシロシメシヽスメラミコトノミヨ》。 此ノ標、既く一卷に出づ、 ○天皇代の下、舊本等に、高天ノ原廣野姫ノ天皇とあるは、後人のしわざなり、こは持統天皇文武天皇兩朝の標なるを、一御代のみの標と意得たる僻ことなり、 大津皇子薨之後。大來皇女。從2伊勢齊宮1上京之時。御作歌二首。 オホツノミコノスギマシシノチ オホクノヒメミコノ イセノイツキノミヤヨリ ノボリタマヘルトキ ヨミマセルミウタフタツ 〇大津ノ皇子ノ薨は、朱鳥元年十月二日に、皇子御謀叛のこと覺《アラ》はれて、同三日に、譯語田舍にして、御年二十四にて賜死《ウシナハレ》ましまししよし、書紀に見えて上に引り、 ○大來ノ皇女は、大津ノ皇子の御姉なり、この皇女の上京《ノボラ》せ給ふ事も、同じ元年十一月丁酉朔壬子、伊勢ノ神社に奉《ツカヘマツリ》しが、京師に還至しめ給ふよし、書紀を引て上に委ク云り、大來《オホク》、上には大伯《オホク》と作り、書紀にも二タ様に書たり、 ○伊勢ノ齊宮は、大御神につかへまつり給ふ皇女たちの、御身をさやめて、齋こもり給ふ宮をいふ、和名抄に、職員令ニ云、齋宮寮ハ、以豆岐乃美夜乃豆加佐《イツキノミヤノツカサ》とあり、下の歌に見えたる、齋宮《イハヒノミヤ》とは異なり、混ふべからず、猶委しくは、下にいふべし、 神風之《カムカゼノ》。伊勢能國爾母《イセノクニニモ》。有益乎《アラマシヲ》。奈何可来計武《ナニシカキケム》。君毛不在爾《キミモマサナクニ》。 ○之ノ字、類聚抄には乃と作り、○母ノ字、拾穗本には毛と作り、○有益乎《アラマシヲ》は、京師に還らずして、さてあらまし物をとなり、 ○君毛不在爾《キミモマサナクニ》(在ノ字、舊本には有と作り、今は拾穗本に從つ、)は、君もおはしまさぬことなるに、といふなり、君は大津ノ皇子をさし賜へり、 ○御歌ノ意かくれたるところなし、皇子のなほおはしますごとおもひていそぎ上り來しを、はや薨給ひぬるよ、とおどろきかなしみ給へるよしなり、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 檜嬬手 | 藤原ノ宮ニ御宇シヽ天皇ノ代、大津皇子ノ薨之後《スギタマヘルノチ》、大來《オホクノ》皇女、從リ2伊勢ノ齋宮1上リタマフv京ニ之時、御作歌二首、 神風之《カムカゼノ》、伊勢能國爾母《イセノクニニモ》、有益乎《アラマシヲ》、奈何可來計武《ナニシカキケム》、君毛不有爾《キミモマサナクニ》。 〇此の皇子・皇女は、御同母《ミハラカラ》にて、殊に御親しかりける故に、一卷にも、竊ニ下リ2伊勢ニ1給ひし事のあるなり。さて大來《オホク》の還り上り給ひしは、持統紀元年十一月の事、大津皇子の事顯はれて失はれ給ひしは、同年十月三日の事なりき。 〇御歌の意少しも隱れたる所なし。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 口訳 | 藤原ノ宮〔持統・文武〕の御代 大津皇子《オホツノミコ》薨ぜられて後、大伯皇女《オホクノヒメミコ》伊勢の齋宮《イツキノミヤ》から、都へ上られた時の御歌
かむかぜの伊勢の國にもあらましを。何しか來けむ。君もあらなくに こんなことなら、伊勢の國に居たはずだのに、どうして來たのであらう。壞しい弟の君も居られないのに。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 藤原宮御宇天皇代 高天原廣野姫天皇《タカマノハラヒロヌヒメノスメラミコト》 持統天皇の御代 大津皇子薨之後、大來《オホク》皇女、從2伊勢|齊宮《イツキノミヤ》1上京之時、御作歌二首
大津皇子は朱鳥元年十月二日謀叛のことあらはれ、三日、譯語田舍《ヲサダノイヘ》で殺され給うた。御年二十四。同元年十一月丁酉朔壬子伊勢より大來皇女都に還り拾ふ。大來は前に (一〇五歌) 大伯と記してあつた。齊は齋に通用せしめたもの。 神風の 伊勢の國にも あらましを なにしか來けむ 君も在らなくに 神風之 伊勢能國爾母 有益乎 奈何可來計武 君毛不有爾 カムカゼノ イセノクニニモ アラマシヲ ナニシカキケム キミモアラナクニ 私ハ、(神風之) 伊勢ノ國ニ居ルベキデアツタノニ、弟ノ君ガ御薨レナツタノニ、何シニ都ヘ上ツテ來タノデアラウ。薨クナラレタコトヲ知ラズニ來テ、悲シイコトデス。 ○君毛不有爾《キミモアラナクニ》――君は御弟大津皇子を指して言はれた。アラナクニを古義にマサナクニとよんでゐる。 〔評〕 皇子の薨去を全く御存じなく、御着京になつて始めて變事を聞かれ、驚愕と落膽とに洩らされた、嗟嘆の聲が、如何にも痛々しい。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 藤原宮御宇天皇代 讓2位輕太子1尊號曰2太上天皇1。 藤原の宮の天の下知らしめしし天皇の代 【高天の原廣野姫の天皇、天皇の元年は丁亥の年にして、十一年、位を輕の太子に讓りたまひ、尊號して太上天皇と曰す。】 【釋】 藤原宮御宇天皇代 フヂハラノミヤニアメノシタシラシメシシスメラミコトノミヨ。藤原の宮は、持統天皇文武天皇二代の宮室であるが、下の註は持統天皇のみを擧げている。實際は、二代にわたつて歌を載せており、終りの部分は寧樂の宮にはいつているものもあるかも知れない。 高天原廣野姫天皇 タカマノハラヒロノヒメノスメラミコト。持統天皇。以下の文は、巻の一、二八の歌の前にも、大同小異の文が載せてある。 大津皇子薨之後、大來皇女、從2伊勢齋宮1上v京之時、御作歌二首 大津の皇子の薨《かむさ》りたまひし後に、大來の皇女の、伊勢の齋の宮より京に上りたまひし時に、作りませる御歌二首 【釋】 大津皇子薨之後 オホツノミコノカムサリタマヒシノチニ。大津の皇子のことは、既出(巻二、一〇五)。その薨去に関することもそこに記した。 大來皇女 オホクノヒメミコ。大伯の皇女に同じ。既出(卷二、一〇五)。大津の皇子の同母の姉。 從伊勢齋宮上京之時 イセノイツキノミヤヨリミヤコニノボリタマヒシトキニ。伊勢の齋の宮は、皇大神宮に奉仕する皇女の宮殿をいう。三重縣多氣郡櫛田村にあつた。大來の皇女は、朱鳥元年十一月十六日に、伊勢の齋の宮から還京された。大津の皇子の死んだ十月三日から四十日ばかり後である。その頃に詠まれた歌である。 神風《かむかぜ》の 伊勢の國にも あらましを。いかにか來《き》けむ。 君もあらなくに。 神風乃《カムカゼノ》 伊勢能國尓母《イセノクニニモ》 有益乎《アラマシヲ》 奈何可來計武《イカニカキケム》 君毛不v有尓《キミモアラナクニ》 【譯】 伊勢の國におつたらよかつたものを。何しに來たことだろう。君もおいでにならないのに。 【釋】 神風乃 カムカゼノ。枕詞。既出。 伊勢能國尓母 イセノクニニモ。作者の齋宮の皇女としてましました伊勢の國のことを述べられている。その國から上京されたのである。 有益乎 アラマシヲ。マシは不可能の希望であるから、皇女は都に上られたが、伊勢の國にあつたならという意をあらわしている。ヲは感動の助詞。句切。 奈何可來計武 イカニカキケム。ナニニカキケム(舊訓)、ナニシカキケム(金)。歌經標式にも次の歌の同句にナニニカキケムとあるが、集中、奈何は多くイカニと讀むべき處に使用し、ナニと讀むべき例を見ない。「栲領巾乃《タクヒレノ》 懸卷欲寸《カケマクホシキ》 妹名乎《イモガナヲ》 此勢能山爾《コノセノヤマニ》 懸者奈何將v有《カケバイカニアラム》」 (卷三、二八五) の類である。ケムは、過去推量の助動詞。上り來た心を、自分ながら、いかにしてか來たことぞ、と悔いる心である。句切。 君毛不有尓 キミモアラナクニ。君は大津の皇子。アラナクはあらぬこと、ニは助詞。 【評語】 はるばると伊勢から上京したが愛弟の既に死んでいるくやしさがえがかれている。何だつて來たのだろうと悔む心が痛切に感じられる。この歌は、連作の第一首として、次の歌を呼び起す含みを存して、總括的に歌つているが、悲痛の情はよく出ている。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | 藤原宮御字天皇代 高天原廣野姫《たかまのはらひろのひめ》天皇 大津皇子薨りましし後、大來皇女《おほくのひめみこ》伊勢の齋宮《いつきのみや》より京に上《のぼ》りましし時、御作歌《つくりませるうた》二首 神風《かむかぜ》の伊勢の國にもあらましを奈何《いか》にか來《き》けむ君もあらなくに 〔代號〕持統天皇の御代。「二八」參照。〔題〕大津皇子 「一〇五」 參照。 〔譯〕こんなことならば、伊勢の國にそのまま居ればよかつたのに。どうしてこの京師に來たのであらうか。君もゐないことであるのに。 〔評)大和は都である。まして皇女にとつては家郷である。それであるのに、「伊勢の國にもあらましを」と歎ぜられた心は、強く我々の胸をうつ。皇女は皇子の薨後歸京せられたのである。「一〇五」「一〇六」 に見られる弟思ひの皇女の悲歎は如何ばかりであつたであらう。三句まで一息に述べて 「あらましを」 と嘆じ、次に 「奈何にか來けむ」 と反省の氣特を、最後に 「君もあらなくに」 と理由を説明してをられるが、それも單なる説明でなく、愬へるやうに、字餘りの句によつて結んであるのも、甚だ自然でをる。 〔語〕○あらましを もしかうと知つてゐたならば、伊勢の國にゐたであらうに。○奈何にか來けむ 何しに來たのであらうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 藤原宮御字天皇代 高天原廣野姫天皇 この標題は既出 (一・二八ノ前)。その條で注したやうに今の場合も古写本には更に「天皇元年丁亥十一年譲位軽太子尊號曰太上天皇」 と注してゐる。金澤本、紀州本には次の題詞のやうな形ですぐ題詞につづけられてをるが、西本願寺本などは標題の右に朱筆で書かれてをり、後の注記が題詞と一つになつたものと思はれる。 なほ紀州本はこの標題の右に 「萬葉集巻第二未」 とあつて、そこから別紙になつてゐる。紀州本は巻頭目録のはじめにも 「萬葉集巻第二本」 とあつて、今の 「未」 は 「末」 の誤で、この巻がもと二つに別けられてゐた事を示すものである。巻一に比して巻二の分量が多い爲に二つに分けたのであらうが、それが紀州本だけである事、本の方が目録を含めてのものである事、などから見てやゝ時代が下つて後になされたものと考へられる。 大津皇子薨之後大來皇女從2伊勢齊宮1上レ京之時御作歌二首 「大津皇子」 は既出 (一〇五)。「大来皇女」 は大伯皇女と同じくやはり同じところで述べた。斎宮の地は今多気郡斎明村の地で、近畿斎宮驛の東北に斎宮阯がある。持統紀朱鳥元年の條に 「十一月丁酉朔壬子 (十六日) 奉2伊勢神祠1皇女大来。還至2京師1」 とある。大津皇子の薨じた十月三日より四十日餘日後のことであり、その頃の御作と思はれる。 神風之 伊勢能國爾母 有益乎 奈何可來計武 君毛不有爾 カムカゼノ イセノクニニモ アラマシヲ ナニシカキケム キミモアラナクニ 【口譯】伊勢の国にもあらうものを、どうして来たのであらう。君もいらつしやらないに。 【訓譯】 神風の-枕詞。既出 (一・八一)。 あらましを-「まし」 は既出 (一・六七)。仮説の推量。今は都へ帰つたが、こんな事ならいつそ伊勢に居たならば、の意。 なにしか来けむ-「なにしか」 の原文 「奈何可」 とあり、金澤本にナニシカとある (この文字何かを消して書いたやうに見える) が、他の諸本にはナニニカとあつた (これには平仮名の「し」が重點になつたのかと思はれるふしもある) のを万葉考が再びナニシカに改め諸注多くそれに従ふに至つた。全註釈には奈何をナニと讀むべき例を見ないと云つてイカニカと讀まれてゐるが、「奈何爲二(ナニセムニ)」(四・七四八)、「奈何不来喧(ナニカキナカヌ)」(八・一四八七) など奈何をナ二と訓むべき例はいくつもある。「いかにか」 の語は 「家に行きて伊可尓可阿我世武(イカニカアガセム)」(五・七九五)、「春の柳と我がやどの梅の花とを伊可尓可和可武(イカニカワカム)」(五・八二六) などのやうに用ゐられてゐて、どのやうにか、とかどういふ風にか、とかの意味で、今の場合に適切ではない。「なにしか」 とか 「なにしかも」 とかいふ語は 「今更に何牡鹿将念(ナニシカオモハム)」 (一二・二九八九)、「奈尓之可母(ナニシカモ) 霧に立つべく歎きしまさむ」(十五・三五八一)、「なにしか人を思ひそめけむ」 (古今集、十二)、「なにしかも人を恨みむ」 (古今集、十九)、萬葉にも古今以後にもあつて、どうして、何の爲に、などの意で、反語的に用ゐられてをり、今の場合に適切である。シを訓添へる事は「奈何鴨(ナニシカモ) 目言をだにもここだ乏しいき」 (四・六八九)、「何哥毛(ナニシカモ) ここだく戀ふる」 (八・一四七五) などの例もあつて不審とすべきでない。「し」 は意味を強める助詞。何の爲に来たのであらう、の意。 君もあらなくに-「君」 は大津皇子。「あらなく」 は既出 (一・七五)。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 藤原宮御字天皇代 高天原廣野姫天皇 〇原文 「藤原宮御字天皇代」。「高天原廣野姫天皇」 は、金澤本、古葉略類聚鈔、紀州本、西本願寺本、細井本など小字。持統天皇を指す。金澤本・古葉略類聚鈔・紀州本などこの下に 「天皇元年丁亥十一年譲位軽太子尊号曰太上天皇」 の注がある。藤原宮については、一〇五歌標題参照。 大津皇子の薨(かむあが) りましし後に、大来皇女、伊勢の斎宮より京に上がる時に作らす歌二首
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 新体系 | 藤原宮 (ふじはらのみや) に宇御 (あめのしたをさ) めたまひし天皇 (すめらみこと) の代 (みよ) [高天原廣野姫天皇 (たかまのはらひろのひめのすめらみこと)。天皇の元年は丁亥 (ていがい)。十一年、軽太子 (かるのたいし) に譲位して、尊号して太上天皇と曰ふ] 藤原宮御宇天皇代 [高天原廣野姫天皇<天皇元年丁亥十一年譲位軽太子尊号曰太上天皇>] 大津皇子の薨 (こう) ぜし後に、大来皇女 (おほくのひめみこ) の、伊勢の斎宮 (いつきのみや) より京 (みやこ) に上りし時に御作りたまひし歌二首 大津皇子薨之後、大来皇女従伊勢齊宮上京之時御作歌二首 神風乃 伊勢能國尓母 有益乎 奈何可来計武 君毛不有尓 かむかぜの いせのくににも あらましを なにしかきけむ きみもあらなくに 【脚注】 大津皇子の謀反が発覚し、処刑されたのは朱鳥元年 (686) 十月三日。年二十四 (日本書紀・持統称制前紀)。→416。十一月十六日、「伊勢神祠に奉(つかへまつ)れる皇女大来、還りて京師に至る」 (同上)。天武天皇崩御による忌服のために離任と思われる。歌は、言々句々、大津皇子の死に対する深い悲しみが滲み出ている。「伊勢の国にもあらましをなにしか来けむ」 と悔み、「君もあらなくに」 と、弟君の死を如何ともし難い現実として痛嘆する。歌中に句切れのある 「なくに」 止めは逆接を表す (木下正俊『万葉集語法の研究』) が、それだけに詠嘆の念も深くこもる。大伯皇女は既出 (一〇五・一〇六)。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 藤原宮 (ふじはらのみや) に天の下治 (あめのしたをさ) めたまひし天皇 (てんわう) の代 (みよ) [高天原廣野姫天皇 (たかまのはらひろのひめ)、天皇の元年の丁亥 (ていがい)、十一年に位 (みくらゐ) を軽太子 (かるのひつぎのみこ) に譲り、尊号を太上天皇といふ] 藤原宮御宇天皇代 [高天原廣野姫天皇<天皇元年丁亥十一年譲位軽太子尊号曰太上天皇>] 大津皇子の薨 (こう) ぜし後に、大伯皇女 (おほくのひめみこ)、伊勢の斎宮 (いつきのみや) より京 (みやこ) に上る時に作らす歌二首 大津皇子薨之後、大来皇女従伊勢齊宮上京之時御作歌二首 神風乃 伊勢能國尓母 有益乎 奈何可来計武 君毛不有尓 かむかぜの いせのくににも あらましを なにしかきけむ きみもあらなくに 【頭注】 〇伊勢の国にもあらましを-アラマシヲは、いた方が良かったのに、の意。このモは 「妹が家も継ぎて見ましを」 (九一) のそれと同じく、反実仮想と呼応する用法。伊勢での暮らしもつらく悲しかったが、大津皇子のいない大和国にいるよりはよほどましだ、という気持ちを表す。 〇なにしか来けむ-ナニは理由を尋ねる疑問副詞。ここは自問。 〇君もあらなくに-大津皇子もこの世にいないのに。 ※藤原濱成『歌経標式』に 「大伯内親王、大津親王に恋ふる歌」 として、この歌の上三句が取り上げられている。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 巻二164 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 活字附訓本 | 活字附訓本 | 活字附訓本 (国立国会図書館蔵書)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 諸注引用 | 拾穂抄 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | 欲見吾爲君毛不有爾奈何可來計武馬疲爾 ミマクホリワカセシキミモアラナクニナニヽカキケムウマツカラシニ 詩云、陟 (ノホレハ) 2彼高岡1、我馬玄黄、遊仙窟云、日晩途遙、馬疲人乏 (タユミヌ)、 【筆者注】解釈に、二つの古典を引用している意味を、万葉時代のその文化的背景を考察していると思う。 詩云 ここで言う「詩」とは、 契沖は、「万葉集」を 「詩経」 に準ずるものとみなしている、と言われている (ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典より) 中国最古の詩集。前9世紀から前7世紀にかけての詩 305編を収める。伝承によれば,孔子が門人の教育のために編纂したもの。「風」「雅」「頌」に大別され,「風」はさらに 15の「国風」に分れて黄河沿いの国々の民謡を主とし,「雅」は「大雅」と「小雅」に分れ,周の朝廷の宴会に歌われたもので,建国伝説を詠んだ長編叙事詩を含む。「頌」は「周頌」「魯頌」「商頌」に分れ,祖先の廟前で奏せられた神楽 (かぐら) と考えられる。詩の形式は4言で1句,4句で1章となるのが基本。伝承されるうちに各学派がそれぞれのテキストにそれぞれの解釈をもつようになり,漢初には斉,魯,韓,毛の4家があったが,次第に毛家の伝えたいわゆる『毛詩』が他を圧倒するようになり,今日完全に伝えられている『詩経』は『毛詩』であるとされる。五経の一書。 その「詩経」の 「国風・卷耳」に収められる一節で、 陟彼高岡 我馬玄黄 険しい山に登ると、私の馬は疲れ果てた。 遊仙窟 「遊仙窟」 は、(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典より) 中国,初唐の文語中編小説。張さく (ちょうさく。 660頃~740頃) の著。1巻。勅命を奉じて旅に出た張生が,神仙の窟に迷い込み,崔十娘という美女と歓楽の一夜を過す物語を張生の一人称で綴ったもの。六朝駢文 (べんぶん) の華麗な文体を基調とし,応酬される詩や対話には韻文を用い,さらに民間の俗語もまじえ,多彩な文体で書かれている。本書は中国で失われて日本にのみ伝わったいわゆる佚存書の一つで,日本では山上憶良の『沈痾自哀文』に引用されるなど古くから広く愛読され,多くの写本,刊本が 14世紀以降出されている。 20世紀に入って中国に逆輸入された。
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 童蒙抄 | 欲見吾爲君毛不有爾奈何可來計武馬疲爾 みまゝくはり、わがせしきみも、あらなくに、なにゝかきけん、うまつからしに 欲見吾爲 大來の皇子のみまほしくおぼしめすきみもましまさぬに、何しに京へのぼり給ひしことぞと也。 これらの御うたをみても君とさし給ふは天武の御事のやうにきこえ侍る也。 御父のみことをおきて、大津のみこをかくまでしたひ給ふべき事にも不覺義也。歌の意はきこえたる通地 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉考 | 欲見 [ミマクホリ]、吾爲君毛 [ワガスルキミモ]、不有爾 [アラナクニ]、奈何可來計武 [ナニシカキケム]、馬疲爾 [ウマツカラシニ]、 同じさまにて、言を少しかへたるは、いにしへ有し一つのさまなり、打うたひたる時あはれなるべし、うまつからしは、ことわざの言なり、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | 欲見 吾爲君毛 不有爾 奈何可來計式 馬疲爾 みまくほり わがするきみも あらなくに なにしかきけむ うまつかるるに 是も上に同じさまにて、言を少し變へたるも、古しへ有りし一つの體なり。馬ツカルルニと言ひて、我心身をもそへ給へり。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 攷證 | 欲見 [ミマクホリ] 吾爲君毛 [ワカセシキミモ] 不有爾 [アラナクニ] 奈何可來計武 [ナニシカキケム] 馬疲爾 [ウマツカラシニ] 欲見 [ミマクホリ]。 字のごとく、見んと欲する也。本集三【四十二丁】に、朝爾食欲見其玉乎 [アサニケニミマクホリスルソノタマヲ] 云々。四【廿六丁】に、生日之爲社妹乎欲見爲禮 [イケルヒノタメコソイモヲミマクホリスレ] 云々などありて、猶いと多し。こゝは、わが見まくほりせし君もなうなくにと、上下して、心得べし。そは、七【十九丁】に、欲見吾爲里乃 [ミマクホリワカスルサトノ] 云々。また【廿六丁】見欲我爲苗 [ミマクホリワカスルナヘニ] 云々などあるもおなじ。 馬疲爾 [ウマツカラシニ]。 略解には、うまつかるゝにと訓れど、舊訓のまゝ、うまつからしにとよむべし。わが見んと思ふ君も、いまはおはさぬものを、何しにか來にけん。たゞ馬をつからすのみぞと也。疲 [ツカル] は、本集七【廿七丁】に、春日尚田立羸 [ハルヒスラタニタチツカル] 云々。十一【廿六丁】に、玉戈之道行疲 [タマホコノミチユキツカレ] 云々。靈異記中卷に、疲【都加禮爾弖】とありて、遊仙窟に、日晩途遙、馬疲人乏云々と見えたり。さて、こは、齋宮自ら、馬にのり給ふにはあらず。御供の人々の馬を、のたまふ也。そは、延喜齋宮式に、凡從行群官以下給レ馬、主神司中臣忌部宮主各二疋、頭四疋、助三疋、命婦四疋、乳母并女嬬各三疋、輿長及殿守各一疋。 -中略- 凡齋王、還レ涼者、其齋王衣服輿輦之類、官便附レ使送レ之、皆堺上而脱易【衣服之類、給2忌部1、輿輦之類、給2中臣1、又各加2鞍御馬一匹1】云々とあるにても、齋宮は御輿にて、從行の人は騎馬なるをしるべし。
【筆者注】万葉集における「疲」 万葉集で原文に「疲」の文字が使われているのは、意外にも二首しかなかった 本歌「164 馬疲爾 」 と 「巻11-2651(旧番号 2643) 玉戈之 道行疲 伊奈武思侶 敷而毛君乎 将見因母鴨」 この字を、ごく自然に「自動詞ラ行下二段 つかる」なのだと思い込んでいたが、実際に万葉の当時ではその訓は、一般的な訓みだったのかどうか、例が少ないように思う 平安時代初期 弘仁十三年 (822年ころ) に編された日本最古の仏教説話集「日本霊異記」、その中巻「第二十五」に、「其鬼走疲」を、 国会図書館本訓釈 疲 都加礼爾弖霊異記(810‐824)中「其の鬼、走り疲(ツカレニテ)」 〈国会図書館本訓釈 疲 都加礼爾弖〉」 とあり、「疲」の訓を、「都加礼爾弖 (つかれにて)」 としている |
||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 欲見 吾爲君毛 不在爾 奈何可來計武 馬疲爾 ミマクホリ アガスルキミモ マサナクニ ナニシカキケム ウマツカルヽニ 不在爾 [マサナクニ](在ノ字、舊本には有と作り、今は拾穗本に從つ、)は、おはしまさぬことなるに、といふなり、 ○馬疲爾(疲ノ)字、古寫本に痩と作るはわろし、)は、ウマツカルニと訓べし、 ○御歌ノ意、これもかくれたる所なし、相見まく欲する皇子も、はや薨給ひて、おはしまさぬことなるに、何の故に、馬の苦み疲るゝをもいとはで、いそぎ上り來つらむとなり、右と同じ様の歌に、少し換てよみ賜へり、さる例古ヘは多し、打連て誦ふるに、ことにあはれなるものなり、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 檜嬬手 | 欲見 吾君毛 不有爾 奈何可來計武 馬疲爾 ミマクホリ ワガスルキミモ マサナクニ ナニシカキケム ウマツカラシニ 〇「欲見、吾爲君毛」此二句は吾が見まくほりする君もといふ意なり。 〇「馬疲爾」毛詩ニ曰ハク、陟リ2彼高岡ニ1我馬玄黄ス。遊仙窟ニ云ハク、日曉ケ途遙ニシテ馬疲レ□ム。此御兄弟、詩賦を好み給へれば、これらを思したる歟。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 口訳 | 見まく欲 [ホ] り我がする君もあらなくに、何しか來けむ。馬疲るゝに 折角逢はうと思うてやつて來た方も、御いでゞないのにどうして、わざわざ馬が疲れるのにやつて來たのであらう。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 見まくほり 吾がする君も あらなくに 何しか來けむ 馬疲るるに 欲見 ミマクホリ] 吾爲君毛 [ワガスルキミモ] 不有爾 [アラナクニ] 奈何可來計武 [ナニシカキケム] 馬疲爾 [ウマツカルルニ] 逢ヒタイト私ガ思ツテヰル御方ハ、御薨去ナサレテ、コノ世ニハ御イデナサラナイノニ、何シニ私ハ、伊勢カラ遙々急イデ、馬ガ疲レルノモカマハズニ、都ニ上ツテ來タノデアラウ。 ○馬疲爾 [ウマツカルルニ] ―― 舊訓ウマツカラシニとあるが、疲らすと他動詞に見ては、歌品が下るやうに思はれる。ツカルルと言ふべきところである。 〔評〕 遙々の上京も、得たところは何もない。ただ徒に馬を疲勞せしめたのみであると嘆ぜられたので、哀調人を動かすものがある。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 見まく欲 [ほ] り わがする君も あらなくに。 いかにか來けむ 馬疲らしに。 欲レ見 [ミマクホリ] 吾爲君毛 [ワガスルキミモ] 不レ有尓 [アラナクニ] 奈何可來計武 [イカニカキケム] 馬疲尓 [ウマツカラシニ] 【譯】 見たいと思う君も、おいでにならないのに、何しに來たことでしょう。馬を疲れさせるだけだのに。 【釋】 欲見 ミマクホリ。ミマクは、見むことの意の體言、ホリは欲する意の動詞。假字書きの例に、「見麻久保里 [ミマクホリ] 念間爾 [オモフアヒダニ]」(卷十七、三九五七)、「見麻久保里 [ミマクホリ] 於毛比之奈倍爾 [オモヒシナヘニ]」(卷十八、四一二〇) がある。同型の語例には、「奈久許惠乎 [ナクコエヲ] 伎可麻久保理登 [キカマクホリト]」(卷十九、四二〇九)がある。 吾爲君毛 ワガスルキミモ。わが見まく欲りする君もの意であるが、句の都合に依つてかように置かれている。 奈何可來計武 イカニカキケム。前の歌と同じ位置に置いてある。句切。 馬疲尓 ウマツカラシニ。舊訓ウマツカラシニとあり、玉の小琴にウマツカルルニと讀み改めた。これは歌經標式に、宇麻都可羅旨尓とあるによつて、ウマツカラシニと讀むべきである。馬を疲らせることなるにの意である。齋宮の下向上京は、後世は輿に依られたが、當時は、馬上であつたのであろう。日本書紀、天武天皇の擧兵のために伊勢に赴かれた時の記事に「是日、發途入2東國1。事急不レ待レ駕而行之。□[脩の月が黒]遇2縣犬養連大伴鞍馬1、因以御駕。乃皇后載レ輿從之」とあり、また「到2川曲坂下1而日暮也。以2皇后疲1之、暫留レ輿而息」ともあり、この後の文は、鈴鹿の山道を越えられた際の記事である。輿によられたとしても、下司竝に荷駄に多數の馬を使用したであろう。
【評語】 この二首は、皇女が、弟の身の上を氣遣るつて京に上つたが、その效 [かい] の無かつたことを歌われている。連作であつて、同じ型を用いて、層を重ねて意味を強調して行く形になつている。殊にこの歌に、皇女御自身の疲勞を歌わないで、馬の上を憐まれているのは、皇女の御作としてふさわしい表現である。 【參考】別傳。 如大柄 (伯)内親王至v自2齋宮1戀2大津親王1歌曰、 美麻倶保利 [ミマクホリ] 一句 和我母不岐美母 [ワガモフキミモ] 二句 阿羅那倶尓 [アラナクニ] 三句 那尓々可岐計牟 [ナニニカキケム] 四句 宇麻都可羅旨尓 [ウマツカラシニ] 五句。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | 見まく欲[ほ] り吾がする君もあらなくに奈何 [いか] にか來けむ馬疲るるに 〔譯〕 私がお目にかかりたいと思ふ君もおいでにならないのに、何しに來たのであらうか。馬が疲れるばかりであるのに。 〔評〕 この歌では、前の歌の驚きと歎きは、やや形をかへて、投げだすやうなひびきを持つてゐる。はじめに、「見まく欲り吾がする君も」と一息にいつてしまひ、終に、馬が疲れるだけであるのにとはき出すやうに附加してをられる。怒りを交へた愚痴といつた感である。「君も在らなくに」の語は前の歌の繰返しであるが、やはり他とかへることのできぬ語である。なほ五句「ツカラシニ」と訓めば、疲れさせる爲であるのにと解されるが、それはあまりに作爲的で、率直な歎きとうけとれぬやうに思ふ。 〔語〕 ○見まく欲り吾がする 自分の見ようと欲する。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 欲見 {ミマクホリ] 吾爲君毛 [ワガスルキミモ] 不有爾 [アラナクニ] 奈何可來計武 [ナニシカキケム] 馬疲爾 [ウマツカルルニ] 見まくほり 吾がする君も あらなくに 何しか来けむ 馬疲るるに 【口譯】 逢はうと私の願つてゐる君もいらつしやらいに、何の爲に来たのであらう。いたづらに馬の疲れるばかりなのに。 【訓譯】 見まくほり吾がする君も-「見まく」 は見むこと。「まく」 は既出 (一〇三)。「ほり」 は既出 (一・一二)。欲する意の四段活用動詞で、それに 「す」 がついて 「欲りす」 となり、後に音便で 「欲す」 となり一語と考へられるやうになつたものである。今はその 「ほり」 と 「す」 との間に 「吾」 を入れたもので、「見まくほり吾が思ふ妹」 (十一・二七九三)、「見まくほり吾が待ち戀ひし」 (十・二一二四) と同じ用ゐざまである。即ちまだ 「ほり」 と 「す」 が一語と考へられず、「ほり」 が独立した単語であつた事が認められる。二句の意は吾が見まくほりする君も、であるが調の爲 「吾」 を中間に挿んだものである。 馬疲るるに-原文 「馬疲尓」 とあつて旧訓ウマツカラシニとあつたのを玉の小琴に、ツカルルと訓みたい、その方が古風だと云ひ、以後両説が行はれてゐる。前説をとるものには学者が多く、後説によるものには歌人が多い。万葉考に 「うまつからしはことわざの言也」 とあるは 「くたぶれまうけ」 などの類と見るので、馬つからしといふやうな言葉が常用されてゐたとすれば、それも一つの解釈にはなるが、略解には 「馬つかるるにといひて、我心身をもそへ給へり。」 とあつて、それだと馬も疲るるものを、といふ解釈になる。 「つかる」 の例は集中に 「道行疲(ミチユキツカレ)」 (十一・二六四三)、「手力労(タチカラツカレ)」 (七・一二八一)、「田立羸(タニタチツカル)」 (七・一二八五) があつて、「つからし」 の例は他にない。しかし今の作が歌経標式に採られたものに 「宇麻都可羅旨尓 (ウマツカラシニ)」 となつてゐるので、前に 「良人四来三」 (一・二七) を歌経標式に 「與岐比等與倶美 (ヨキヒトヨクミ)」 とあるによつてヨキヒトヨクミと訓んだのと同じ態度に従へば、今もツカラシニと訓むべきもののやうにも考へられる。しかし (一・二七) の場合はそのところで述べたやうに、種々の点からその事が認められるのであるが、今の場合にもそれが認められるか。歌経標式にはなほ問題があるにしても、ともかく萬葉集が家持の手を離れて後の最初の古訓と認める事の出来るものではある。しかし 「足何久激 (アガクタギチ/ソソキ)」 (七・一一四一) や 「石激 (イハハシル/ソソク)」 (八・一四一八) の 「激」 をソソキ、ソソクと訓む事が最も萬葉編纂時代に近い古訓であるとしても、古義や万葉考によつてタギチ、ハシルと改訓されたのを正しいと認むべきであると同様に、今の場合も歌経標式の古訓に盲従する事なくこの一首の作としての正訓を求めねばならない。従来の諸家多くこの訓の決定にあたつて 「疲らし」 と 「疲るる」 との語にのみ拘泥してゐるのは誤つてゐる。問題はむしろその下の助詞「に」にあると私は考へる。その事に多少説き及ぼしてゐるのは次田氏の新講のみである。同書にいふ、「『馬疲らしに』と訓んでは馬を疲れさせるのが目的のやうに聞こえて穏やかでない。小琴の訓に従つて、最後の『に』を『在らなくに』の『に』と同じ余情を表す助詞と見るのが妥当である。」 これは解決への正しい方角を示すものだと考へる。ただこれをもう少しはつきりさせる必要がある。「疲らし」 と 「疲るる」 とは自他を異にした動詞である爲にそれに拘はりがちなのであるが、かりにこれを一つの動詞にしてみるともう少しはつきりする。たとへば、 何しに来けむ吾妹子を見に 何しに来けむ吾妹の見るに 同じ 「見る」 につづく 「に」 であるが、前者は 「見る」 の連用形を受けて、下につづく語の目的を示す格助詞であり、後者は連体形をうけて下の語に対して逆接的な余情を含む詠歎の助詞である。「馬疲らしに」 は前者であり、「馬疲れるるに」 は後者である。これだけの手数をかけた上で、「馬疲らしに」 と訓む場合と 「馬疲るるに」 と訓む場合の一首の構成を見ると、前者は、 (一)見まくほり吾がする君もあらなくに馬疲らしに何しか来けむ といふ形になり、後者は、 (二)見まくほり吾がする君も「あらなくに」/「馬疲るるに」-何しか来けむ といふ形になる。これをこの前の歌の、 神風の「伊勢の国にもあらましを」/「君もあらなくに」-何しか来けむ と較べ、右の新講の説をも一度参照するならば、(一) と(二) といづれが適切な解釈になるか、いづれが散文的であり、いづれが歌品が高いか、いづれが 「神風の」 の作につづく連作としてふさはしいか、といふ事がはじめてはつきりと納得せられるのではなからうか。そして (一) の説に学者が多く (二) に歌人が多いと云つた事もはじめて理解せられるのではなからうか。即ち歌経標式の訓は古訓ではあるが、既に萬葉の作が散文化せられた姿を示すもので、玉の小琴の説こそまことに 「愈古るかめり」 (玉の小琴、追考/上の全註釈写真) といふ事になり、前に引用した 「石激(イハソソク)」 の古訓を 「石激(イハハシル)」 に改めた考の説とその功を同じくするものと云へよう。この馬については斎宮式に 「凡從行群官以下給レ馬、主神司中臣忌部宮主各二疋、頭四疋、助三疋、命婦四疋、乳母并女嬬各三疋、輿長及殿守各一疋」 とあり、又 「凡齋王、還レ涼者、[若有遭故還者。不用初入之道。] 遣使奉迎。・・・其齋王衣服、輿輦之類。官便附レ使送レ之、」 (上の項、攷證を参照) などとあるので、攷證に 「斎宮は御輿にて、従行の人は騎馬なるをしるべし」 と云つてゐる。この御作の頃、延喜式と同じとは云へないであらうが、お供の人が相当多くの馬を用ゐた事を認める事が出来よう。 【考】 前の作の結句が次の作では上三句に移され、しかも全体として構成を同じくした句法になつてゐる事訓釋の條で述べた如く、いかにも連作らしい形を整へてゐる。悲傷やまずの感がこの反復のすがたに遺憾なく示されてゐる。歌経標式に載せられた原文は、 美麻倶保利 [ミマクホリ] 和我母不岐美母 [ワガモフキミモ] 阿羅那倶尓 [アラナクニ] 那尓々可岐計牟 [ナニニカキケム] 宇麻都可羅旨尓 [ウマツカラシニ] とあつて第二句も 「我が思ふ君」 とかへられてゐる。「疲るるに」 が 「疲らしに」 になつた事は単なる動詞の自他の相違でない事は、訓釋の條で述べたが、その相違はまた (九一) の本文と一云との相違にも極めて似てゐる事が認められ、それと較べる事によつても 「疲るるに」 であるべき事がうなづかれるであらう。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 欲見 {ミマクホリ] 吾爲君毛 [ワガスルキミモ] 不有爾 [アラナクニ] 奈何可來計武 [ナニシカキケム] 馬疲爾 [ウマツカルルニ] 見まくほり 吾がする君も あらなくに 何しか来けむ 馬疲るるに 逢いたいと願っている君もいらっしゃらないのに、何の為に来たのであろうか。馬が疲れるばかりなのに。 【注】 〇 見まくほり 原文 「欲見」 を金澤本・類聚古集・古葉略類聚鈔・紀州本にミマホシミと訓んでいるが、西本願寺本にミマクホリとするのが正しい。巻二十に 「秋と言へば心そ痛きうたけに花になそへて見麻久保里香聞」 (四三〇七、家持) と見える。ミマクはミムコトの意。 〇 吾がする君も 旧訓にワガセシキミモとあったのを、万葉考にワガスルキミモと改訓した。セシと過去形にするよりもスルという現在形のほうが文字に即し、意味の上からも良い。 〇 あらなくに いないことなのに。前歌 (一六三歌) の結句をそのまま第三句に置いている。 〇 何しか来けむ 前歌の第四句と文字も全くひとしい。 〇 馬疲るるに 原文 「馬疲尓」 を旧訓にウマツカラシニと訓んでいたのを-代匠記・万葉考なども同訓。後者には 「うまつからしはことわざの言也」 とある。-玉の小琴にウマツカルルニと改訓、以後両訓が行われている。最近の注釈書では、秀歌・私注・古典大系・注釈・古典集成・講談社文庫本などツカルルニであり、窪田評釈・古典全集などがツカラシニの訓による。後説の理由として、この歌を歌経標式に 「美麻倶保利 [ミマクホリ] 和我母不岐美母 [ワガモフキミモ] 阿羅那倶尓 [アラナクニ] 那尓々可岐計牟 [ナニニカキケム] 宇麻都可羅旨尓 [ウマツカラシニ] 」 と記している事実があげられるが、歌経標式の訓は第二句・第四句にも相違を含み、かならずしも信頼しえない。また原文の 「馬疲尓」 は普通に訓めばウマツカルルニとなるはずだろう。ツカラシのシのような使役の意味の 「ス」 を無表記とした例は巻一・巻二に見当たらない。大伯皇女の歌でも、あとの一六六歌にはミスを 「令視」 としている。さらに意味の上から、古典全集のように 「馬を疲らせになのか」 と解するのは無理であろう。前歌の結句 「君もあらなくに」 が重い嘆きを示す逆接表現であったのと同じく、ここも 「馬が疲れるのに」 と解するほうが自然である。 【考】馬疲るるに 第四句までは、前歌と全く等しい内容である。「馬疲るるに」 という結句は、皇女の上京に馬が使われたこと、おそらく乗馬として使ったのであろうこと、急ぎの旅であったために大和に到着したときには馬もまた疲れ切った状態であったろうことなどを思わせる。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 新体系 | 見まく欲り 我がする君も あらなくに なにしか来けむ 馬疲るるに 欲見 {ミマクホリ] 吾為君毛 [アガスルキミモ] 不有爾 [アラナクニ] 奈何可來計武 [ナニシカキケム] 馬疲爾 [ウマツカルルニ] 逢いたいと私が切に思うあの方もいないのに、一体何のために来たのだろう、馬が疲れるだけなのに。 【脚注】 結句の訓みは、「馬疲るるに」 と 「馬疲らしに」 と、両説ある。歌経標式に 「大伯内親王斎宮より至り、大津親王に恋ひし歌」 として、この歌を引き、結句は 「うまつからしに (宇麻都可羅旨尓)」 とある。万葉集の原文 「馬疲尓」 は、この訓に拠る (『講義』、『全註釈』) か、あるいは 「馬つかるるに」 (玉の小琴、略解) の訓に拠るか。ここには後者の訓みを採用する。使役の 「し」 を補読する 「疲らし」 と訓むよりも、補読のない 「疲るる」 の方が自然であろう。「なにしか来けむ」 と第四句で切り、「馬疲るるに」 の結句で、自らの疲れと落胆を述べたと解される。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 見まく欲り 我がする君も あらなくに なにしか来けむ 馬疲るるに 欲見 {ミマクホリ] 吾為君毛 [アガスルキミモ] 不有爾 [アラナクニ] 奈何可來計武 [ナニシカキケム] 馬疲爾 [ウマツカルルニ] 逢いたいと 思うあの方も いないのに なんで来たのだろう 馬が疲れるだけなのに 【頭注】 見まく欲り我がする君も-見マクは見ムのク語法。ホリスは欲する意。 馬疲るるに-馬が疲れるだけなのに。 ※この歌、『歌経標式』では下二句が 「なににか来けむ馬疲らしに」 となっている。ナニニカはナニシカに対する中古語形。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 巻二165 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 活字附訓本 | 活字附訓本 | 活字附訓本 (国立国会図書館蔵書)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 諸注引用 | 拾穂抄 | 移2葬 [ウツシハウフル] 大津ノ皇子ノ屍 [カラヲ] 於葛城二上 [カツラキノフタカミ] 山ニ1時哀傷 [カナシミイタムテ] 御作ノ歌二首 大來皇女
うつそみのひとにある吾やあすよりはふたかみやまをいもせとわれ見ん 宇都曽見乃人尓有吾哉從明日者二上山乎弟世登吾將見 うつそみのひとにある 空蝉之獨有吾也そとせと五音通にとりと同通す 空蝉は我身をいへり同母の弟に別てうき身を独ある我と也 けふ大津を葬しあすよりは此二上山を兄弟と見んと也 いもせは弟世と書妹と兄との心也男は弟をも兄といふ事常の事也 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | 移葬大津皇子屍於葛城二上山之時大來皇女哀傷御作歌二首 日本紀には初何處に葬とも見えざれども、此によれば初葬りける處より二上山に移し葬らると見えたり、此事も亦紀には載られず、 宇都曾見乃人爾有吾哉從明日者二上山乎弟世登吾將見 ウツソミノヒトニアルワレヤアスヨリハフタカミヤマヲイモセトワレミム ウツソミはうつせみに同じ、此集いづれをも用たり、世とすること上の如し、 イモセは、いもは妹、せは兄なり、大津ノ皇子は、皇女には御弟なれど、せは女の男を呼詞なり、 歌の心は我はかひなくながらへて世上の人にてあるを、皇子の尸を移し葬らば、明日より、かけても思はぬ二上山をいもせと見む事よと嘆たまふなり、 二上は山二つ並たる故に、第七にも、紀路にこそ妹山有けれ葛戒の二上山も妹こそ有けれ、とよめり、さればせとみむとこそよみ給ふべけれど、 歌の習なれば大樣に廣くいもせとのたまへり、又オトセと云ふによらば弟を豈といふべき理はなけれど、せは唯男を貴て呼詞と意得れば、あすよこりや山を弟と見んとのたまふなり、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 童蒙抄 | 移葬大津皇子屍於葛城二上山之時大來皇女哀傷御作歌二首 おほつのみこのかばねを、かつらぎのふたかみやまにうつしはふむるとき、おほきのすめひめかなしみいたみたまふてみつくりうた二くさ 屍 和名抄云、屍 [音與レ尸同、訓或通] 死人形體曰レ屍。禮記曲禮云、在レ牀曰レ尸在レ棺曰レ柩。白虎通云、尸之爲レ言失也、陳也、失レ氣亡レ神形體独陳
宇都曾見乃人爾有吾哉從明日者二上山乎弟世登吾將見 うつそみの 人なるわれや あすよりは ふたかみやまを おとせとわれみん 宇都曾見 うつせみといふも同じ事にて、現の身といふこと也。第一卷にもくわしく注せり 人爾有吾哉 にあの約言なゝれば、なるわれやとはよむ也。意は皇女は現在の身なればと也。哉と云はわれはといふと同事也 二上山乎弟世登吾將見 過行たまふ弟のみ子を直に見給ふ事はもはやならねば、屍をおさめられたるふたかみ山を、おとゝのみこと見給はんと也。 おとせといふはおとうとゝいふと同事也。せとはすべて女子より男子をさしていふ古語也。なせとわれ見んとよみて同じからん 歌の意は、おなじはらからの、おとのみこうせ給ひわけてもいたましきありかたちにて、かくれ給ひ、ことさらに改葬までありて、いとゞ御なげきのあまりに、皇女はかく現在ましましても、過行たまふ弟のみこを直に見たまふ事ならねば、今よりしては御はか所の二上山をおとのみこと見給はんと、したひかなしみ給ふて、よみたまへる也 【童子間】 移葬大津皇子屍於葛城二止山之時大來皇女哀傷御作歌二首 宇都曾見乃人爾有吾哉從明日者二上山乎弟世登吾將見 童子問 宇都曾見は世の冠辭とのみ心得侍るに、人といふ冠辭にも用ゐるにや。 答 宇都曾見といふ辭必冠辭にあらず。第一卷に、中大兄三山歌に虚蝉毛嬬乎とも詠給ひて、今はうつゝの人うつゝの身ともいふ古語なり。 うつせみともうつそみとも、皆おなじこと也。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉考 | 移葬 (ウツシハフル) 大津ノ皇子ノ屍 (オキツキヲ)、於葛城ノ二上 (フタガミ) 山ニ之時 (トキ)、 こは葛下ノ郡の山のはてに、上とがりたる峯二つ並立て、よそめもまがはぬ山なり、下の卷にも出たり、 大來ノ皇女ノ哀傷 (カナシミテ) 御作 (ヨミタマフ)歌、 宇部曾見乃 (ウツソミノ)、人爾有吾我 (ヒトナルワレヤ)、顯 (ウツヽ) の身にて在吾哉なり、 從明日者 (アスヨリハ)、二上山乎 (フタガミヤマヲ)、弟世登吾將見 (イモセトワガミム)、」 今うつゝにて在るわれにして、言もとはぬ此山を、兄弟と見てやあらんずらんと歎き給ふなり、(卷八、詠山)「木路 (キヂ) にこそ、妹山ありとへ、三櫛上 (ミクシゲ) の、二上山も、妹こそ有けれ、」 只妹こそといふは、是はもと妹を葬し故か、(卷十四、挽歌)「うつせみの、世の事なれば、よそに見し、山をや今は、因處《ヨスガ》と思はん、」 本は男女の兄弟を、いもせといひしからは、こゝも今本の訓によりぬ、然れども右の卷八なるは、二上を妹とのみよみし如く、こゝも此山を弟として、なせと我見んとよみ給ふか、然らば奈世 (ナセ) と有しを、弟世に誤つらんか、古へ兄弟の長幼をいはず、女より男をばせといひし事別記にいふ、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | 移送大津皇子屍ヲ於葛城二上山之時大來皇女哀傷御作歌二首 二上山は葛下郡にあり。 宇都曾見乃 人爾有吾哉 從明日者 二上山乎 弟世登吾將見 うつそみの ひとなるわれや あすよりは ふたがみやまを いもせとわかみむ 今現にてある我にして、此山を兄弟と見てや有らむずらむと歎き給ふなり。卷七、木路にこそ妹山有りとへ三櫛上の二上山も妹こそ有りけれ。是はもと妹を葬りし故か。卷三、うつせみの世の事なればよそに見し山をや今はよすがと思はむと言ふも相似たり。もとは男女の兄弟をもイモセと言ひしなり。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 攷證 | 移葬大津皇子屍(ミカハネ) 於葛城二上山之時 大來皇女哀傷御作歌 二首 移葬。 假寧令集解に、改移舊屍、古記曰、改葬謂殯埋舊屍柩改移之類云々とあれば、移葬は改葬といふに同じく、今まで殯してありつるを、墓所に移し葬るをいへり。 屍(ミカバネ)。万葉考に、屍をおきつきとよまれしは、甚しき誤り也。屍は、禮記曲禮に、在牀曰屍、在棺曰柩云々とありて (筆者注、上記童蒙抄の写真参照)、屍は 人死していまだ柩にも入ざるをいへる事、古事記中卷に、大山守命之骨者、葬于那良山也云々とある、骨も、みかばねとよむべきにてもしるべし。
本集十八【廿一丁】に、海行者美都久屍 (ウミユカハミツクカハネ)、山行者草牟須屍 (ヤマユカハクサムスカハネ) 云々とも見えたり。 さて、おくつきは、墓の事なれば屍をよめるは誤り也。この事は、下 [攷證三] にいふべし。 葛城二上山。 いま葛城山は、大和國葛上郡、二上山は、葛下郡なり。葛城は、書紀神武紀に高尾張邑、有土蜘蛛、其爲人也、身短而手足長、與侏儒相類、皇軍結葛網、而掩襲殺之、因改號其邑、曰葛城云々とありて、いにしへは、葛上下二郡、おしなべて葛城とは云ひし也。和名抄國郡部に、大和國葛上 [加豆良岐乃加美] 葛下 [加豆良木乃之毛] 云々とありて、二郡とはわかれしかど、猶かつらぎといへり。されば、葛下郡の二上山をも、葛城二上とはいへる也。そは、延喜神名式に、大和國葛下郡、葛木二上神社云々とあるにても思ふべし。大和志に、葛下郡二上山墓在二上山、二上神社東云々と見えたり。猶この山は、集中の歌にも見えて、越中にも同名あり。 【以下国立国会図書館デジタルコレクション】
宇都曾見乃 (ウツソミノ) 人 (ヒト) 爾有 (ナル・ニアル) 吾哉 (ワレヤ) 從明日者 (アスヨリハ) 二上山乎 (フタカミヤマヲ) 弟世登吾將見 (イモセトワレミム) 宇都曾見乃 人爾有吾哉 宇都曾美は、現身 (ウツシミ) といふ意なる事、志 (シ) と曾 (ソ) と音かよへば也。これを、借字に、虚蝉 (ウツセミ)、空蝉 (ウツセミ) などかけるも、志 (シ) と世 (セ) と音かよひて、現身 (ウツシミ) なり。この事は、冠辭考、うつせみの條にくはし。さて、こゝの意は、己れは現 (ウツヽ) の身の人にはあれども、君を、二上山に葬りたるからは、明日よりは、その二上山を、いもせとは見んとなり。 弟世登吾將見 (イモセトワレミム)。 弟を、いもせとよむは、妹の意にて、義訓なり。兄弟夫婦、おしなべて、いもせとはいへり。そは、書紀仁賢紀、分注に、古者不言兄弟長幼、女以男稱兄 (セ)、男以女稱妹 (イモ) 云々とありて、いもせは、男女の稱にて、兄弟夫婦ともに、男は女を、いもといひ、女は男を、せといひしより、こゝは兄弟を、いもせとはいへる也。本集六〔卅二丁〕に、不言問木尚妹與兄有云乎 (モノイハヌキスライモトセアリトフヲ)、直獨子爾有之苦者 (タヾヒトリコニアルカクルシサ) 云々。十七〔廿三丁〕に、伊母毛勢母和可伎紀等毛波 (イモモセモワカキコトモハ) 云々。七〔十九丁〕に、人在者母之最愛子曾 (ヒトナラハハヽノマナコソ)、麻毛吉木川邊之妹與背之山 (アサモヨシキノカハノヘノイモトセノヤマ) 云々。後撰集雜三に、はらからの中にいかなる事かありけん、つねならぬさまに見え侍りければ、よみ人しらず、むつまじきいもせの山の中にさへへだつるくものはれずもあるかな云々。宗于集に、はらからなる人の、うらめしきことあるをりに、君とわがいもせの山も秋くればいろかはりぬるものにぞありける云々。これら、みな兄弟をいへり。夫婦をいへるは、やゝ後のことなり。
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 移葬 [ウツシハフリマツレル] 大津皇子屍 [オホツノミコノミカバネヲ]。於葛城二上山 [カヅラキノフタカミヤマニ] 之時 [トキ ]。大來皇女哀傷御作歌二首
[オホクノヒメミコノカナシミテヨミマセルミウタフタツ]。 移葬は、初何處に葬りしといふこと、書紀に見えざれども、此によれば、初葬ける地より、二上山に移し葬られしと見ゆ、二上山は、大和志に、在2葛下ノ郡當麻村ノ西北ニ1、半跨2河州ニ1、兩峯對、一ヲ曰2男ノ嶽ト1、一ヲ曰2女ノ嶽ト1、北ニ有小峯、呼2銀ノ峯ト1、南ニ有2瀑布1、高丈餘、有2古歌1と見えたり、七ノ卷に、木道爾社妹山有云櫛上 [キヂニコソイモヤマアリトイヘミクシゲノ] 、二上山母妹許曾有來 [フタガミヤマモイモコソアリケレ]、十ノ卷に、大坂乎吾越來者二上爾 [オホサカヲアガコエクレバフタガミニ]、黄葉流志具禮零乍 [モミチバナガルシグレフリツヽ]、十一に、二上爾隱經月之雖惜 [フタガミニカクラフツキノヲシケドモ] 云々などもあり、神名帳に、大和ノ國葛下ノ郡、葛木ノ二上ノ神社とあり、越中ノ國にも二上山ありて、集中に多くよめり、同名別地なり、 〇字都曾見乃 [ウツソミノ] 人爾有吾哉 [ヒトナルアレヤ] 從明日者 [アスヨリハ] 二上山乎 [フタガミヤマヲ] 弟世登吾將見 [ワガセトアガミム] 人爾有吾哉 [ヒトナルアレヤ] は、人にてある吾哉よいふなり、哉 [ヤ] は、將見 [ミム] の下にうつして意得べし、 ○弟世は、吾世とありしを、寫し誤れるにや、(大津ノ皇子は、大來ノ皇女の御弟なれば、弟とあるべしとおもひて、後人の改めたるものか、)さらばワガセと訓べし、(もとのまゝにて、イモセと訓たれども理なし、)仁賢天皇ノ紀に、古者不言兄弟長幼、女ハ以男ヲ稱兄ト、男ハ以女ヲ稱妹トと云る如く、姉より弟をさして、兄 [セ] と云ることも、古は常多かり ○御歌ノ意は、現にて在吾カ身にして、明日より後は、言も通はぬ二上山を、吾カ兄と見つゝあらむ歟、と歎き賜ふなり、三ノ卷(高橋ノ朝臣の、死妻を悲傷る歌)に、打背見乃世之事爾在者外爾見之 [ウツセミノヨノコトナレバヨソニミシ]、山矣耶今者因香跡思波牟 [ヤマヲヤイマハヨスカトオモハム、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 口訳 | 大津ノ皇子の亡骸 [ナキガラ] を、葛城の二上山 [フタカミヤマ] に移葬し奉つた時、大/伯 [クノ] 皇女の御歌。二首 うつそみの人なる我や、明日よりは、二上 [フタカミ] 山を阿弟 [イロセ] と我が見む 肉體を持つた人間である私として、大事の弟を葬つた山だから、明日からは、二上山をば兄弟 [キヤウダイ] と見ねばならぬのだらうか。(山嶽信仰に根ざしてゐる。) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 移2葬大津皇子屍ヲ於葛城ノ二上山1之時、大來皇女哀傷御作歌二首 移葬とは一度葬りて、更に移した意か。或は殯宮から移して葬つた意か。恐らく後者であらう。葛城二上山は、北葛城郡で河内の國境にあり。頂が二つに分れて雄嶽女嶽といふ。ここに挿入の寫眞は天香具山から西方を望んだもので、辰巳利文氏の撮影にかかる。同氏の大和萬葉古蹟寫眞解説によれば「左端前方の人家は磯城郡香久山村大字木之本で啼澤森はこの村落にある。そのすぐ後方に見えるのは高市郡鴨公村大字別所である。右端の人家は同じく鴨公村大字高殿である。このあたりが藤原宮址とされてゐる。今前方にひらけて見えるたんぼの大部分は宮地と見てさしつかへがなからうと思ふ。黒く小高い山が畝傍山で、山の右麓 (北) に見える茂みが神武帝陵である。遠景の山脈は葛城山で、その右端が二上山である。云々」とある。 うつそ身の 人なる吾や 明日よりは 二上山を いもせと吾が見む 宇都曾見乃 [ウツソミノ] 人爾有吾哉 [ヒトナルワレヤ] 從明日者 [アスヨリハ] 二上山乎 [フタカミヤマヲ] 弟世登吾將見 [イモセトワガミム] カウシテ現ノ身ヲ持ツテヰル人間デアリナガラ私ハ明日カラハ、私ノ弟ノ大津皇子ヲ葬ツタアノ二上山ヲ、兄弟ダト思ツテ私ハ見ヨウカ。悲シイコトニナリマシタ。 ○字都曾見乃 [ウツソミノ] ―― 現身 [ウツシミ] のに同じ。この世に肉體を持つてゐるの意。 ○弟世登吾將見――弟世は種々の訓があるが、イモセが無難であらう。弟をイモとよんだ例は他に見えないが、さうよんで差支ない文字であらう。イモセは兄弟の意。但しこれをイロセとよんで、同母弟の意に見られないこともない。 〔評〕 明日からは謠かに二上山を仰いで、亡き弟を思はうと言ふ御心が痛ましい。併し二上山の雙峰相並んでゐるのを、我ら姉弟の姿と思はうと宣つたのか、或は單に二上山を弟として眺めようと、仰せになつたのかといふ疑問が生ずる。イモセとよめば、前者の解が至當であらうし、又その方が哀情が深いやうに思はれる。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 移葬大津皇子屍於葛城二上山之時、大來皇女、哀傷御作歌二首 大津の皇子の屍 [かばね] を、葛城 [かづらき] の二上山に移 [うつ] し葬 [はふ] りし時に、大伯 [おほく] の皇女の、哀傷して作りませる御歌二首 【釋】移葬大津皇子屍於葛城二上山之時 オホツノミコノカバネヲカヅラキノフタガミヤマニウツシハフリシトキニ。 移葬は、屍柩を殯所から墓所に移し葬るをいう。假寧令の集解に、改葬を釋して「釋云、改2埋舊屍1。古記曰、改葬謂殯2埋舊屍柩1改移之類」(※上項「攷證 〔令集解巻第四十假寧令第二十五「凡改葬」〕参照) とある。これによれば、一旦葬つたものを移葬するのではないが、ここにいう所と違うだろう。屍は、日本靈異記訓釋に「屍骸、二合死ニカバネ」(中卷一條)とあるが、本集に三音に當てて書いている。葛城の二上山は、葛城山中の二上山で、大阪府と奈良縣との堺、大和川の南方にあり、二峰から成つている山である。その峰に近い處に大津の皇子の基と傳えるものがある。 うつそみの 人なる吾や、 明日よりは 二上山 [ふたがみやま] を兄弟 [いろせ] とわが見む。 宇都曾見乃 [ウツソミノ] 人尓有吾哉 [ヒトナルワレヤ] 從明日者 [アスヨリハ] 二上山乎 [フタガミヤマヲ] 弟世登吾將見 [イロセトワガミム] 【譯】生きているこの自分は、明日からは、あの二上山をわが親しい弟と見るのだろうか。 【釋】 宇都曾見乃 ウツソミノ。ウツソミは、ウツセミに同じ。もしこの語義が、ウツシオミの義であるならば、この方が原形ということになる。集中の用例は、「天地之 [アメツチノ] 初時從 [ハジメノトキユ] 宇都曾美能 [ウツソミノ] 八十伴男者 [ヤソトモノヲハ]」(卷十九、四二一四 ) の一例が大伴の家持の作である以外は、柿本の人麻呂の作品中に見られる。ここでは、この世の人である意に、次句の人を修飾している。 人尓有吾哉 ヒトナルワレヤ。ナルは、歴史的にはニアルである。ヤは疑問の係助詞。 從明日者 アスヨリハ。今日二上山に移葬したので、明日以後のことを言つている。 弟世登吾將見 イロセトワガミム。イロセは、同母の兄弟をいう語。古事記上卷、須佐 [すさ] の男 [お] の神の詞に、「吾者、天照大御神之伊呂勢者也」、中卷、神武天皇記に 「其伊呂兄五瀬命」とある。イロは、肉親を意味し、この語を使用した熟語には、イロハ (母)、イロネ (姉)、イロモ (妹) 等がある。セは、男性の稱である。上のもを受けて結んでいる句。 【評語】この歌は生ける身にして、かの山をわが弟と見ようか。さりとて山は物言わずつれないものをの意が含まれている。ウツソミノ人ナル吾の句には、生ける人としての自覺がよくあらわれている。何故皇子の屍を葛城の二上山の如き高處に葬つたかというに、その説明は無いが、皇子の神靈を畏怖したのではないかとも考えられる。高貴の人を高い山に葬ることは例があるが、それもその神靈を尊んでの事であつて、刑死した皇子に對しても特にそぅいう思想を生ずるに至つたのであろう。 【參考】同句、うつせみの人なる吾。 (上略)うつせみの人なる我や、何すとか一日一夜も、離 [さか] り居て嘆き戀ふらむ (下略)(卷八、一六二九) (上略)うつせみの世の人吾も、此處をしもあやに奇 [くす] しみ (下略)(卷十八、四一二五) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | 大津皇子の屍 [みかばね] を葛城 [かつらぎ] の二上山に移 [うつ] し葬 [はふ] りし時、大來皇女哀しみ傷みて御作歌 [つくりませるうた] 二首 うつそみの人なる吾や明日よりは二上山 [ふたかみやま] を弟世 [いろせ] と吾が見む 〔題〕 葛城は、今の葛城山かち金剛山、二上山あたりを廣くさしたのである。二上山は今北葛城郡で、河内との境、大和の西に聳えてゐる。皇子の御墓は今この雄岳の頂にある。移し葬るは、殯宮より墓所に屍を移し葬る意。 〔譯〕 この現世の人である私はまあ、明日からは二上山を兄弟と眺めることであらう。 〔評〕 「うつそみの人なる吾や」の嘆き聲は、前の歌に比して深く沈んだ歎きである。「吾や」と、下に「吾が見む」と重ねたのは、考へれば異樣であるが、「吾が見む」と、強くいはねばならぬ氣持なのであらう。二上山は名のごとく、雄岳、雌岳の二つの峯に分れ、大和平野からは、東の三輪山と共に、何處からも望まれる美しい山である。それだけに一層諦めようとしても諦めきれぬ思ひなのであらう。 〔語〕 ○うつそみ うつしをみの略で、現世の義、と大野晋氏の新説である。この世の意。 ○人なる吾や 「や」は感動の意。 ○兄弟 [いろせ] 同母の兄弟。ここは弟。 〔訓〕 ○弟世 代匠記「オトセ」考「イモセ」等何れもよくない。古事記素盞嗚命の御言葉に、「吾者天照大神之伊呂勢者也」とあり、又「其伊呂勢五瀬命」とあるから、いろせがよい。 国立国会図書館デジタルコレクション「古事記上巻素盞嗚命」 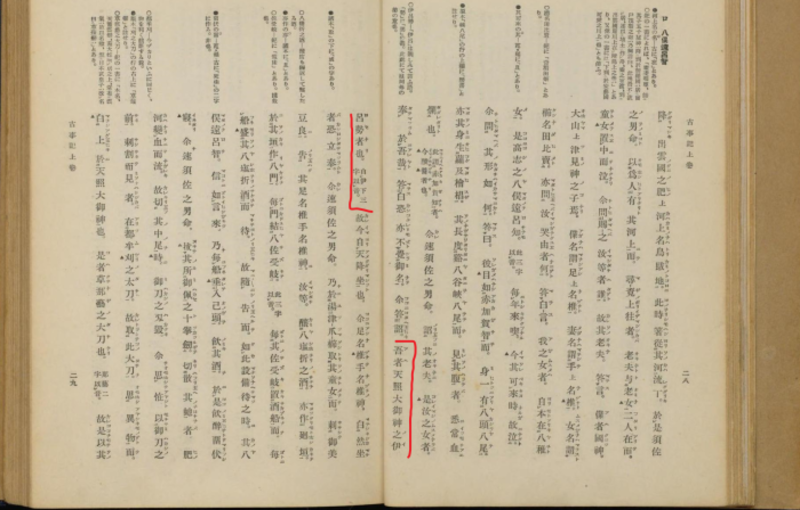 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 移葬大津皇子屍於葛城二上山之時大来皇女哀傷御作歌二首 仮寧令集解「改葬」の條に「釋云。改移奮屍。古記曰。改葬謂殯埋奮屍柩改移之類」とあるによつて攷證に「移葬は改葬といふに同じく、今まで殯してありつるを、墓所に移し葬るをいへり」とある。即ち今一旦葬つた墓所を他へ移す意でなく、殯宮より墓所に移す事をいふ。講義には「この移葬が喪のありしより多少の時日を経過することあり」として古京遺文に載せる船首王後墓誌には「殯亡於阿須迦天皇之末歳次辛丑十二月庚寅。故戊辰年十二月殯塟於松岳山上」とあり、伊福吉部臣徳足比賣墓誌には和銅元年秋七月一日に卒し三年「冬十月火葬即殯此處」とあり、石川朝臣年足墓誌には天平宝字六年の九月に薨じて十二月に葬るといふ例があげられてゐる。最初の例は講義に三年とあるは誤解で、舒明天皇十三年より天智七年まで廿七年を距ててゐる例である。 「屍」は霊異記(下、第一話) に「屍骸 二合死ニカハ子」とあつてシニカハネと訓んでゐるが、集中の例としては「海行者(ウミユカバ) 美都久屍(ミツクカバネ) 山行者(ヤマユカバ) 草牟須屍(クサムスカバネ)」(十八・4094) とあつて単にカバネと訓んだやうである。 「葛城二上山」は大和志葛下郡の條に「在當麻村西北半跨河州、兩峯相対一曰男嶽一曰女嶽云々」とある。大和と河内とを堺する葛城山脈は今、南につづくところを金剛山と呼び、北につづくものを二上山と呼んでゐるが、古くはすべてを葛城と呼んだので、「葛城の二上」と記したものである。金剛の最高峯一一一二米、葛城九五九米、二上四七四米。二上の南の峯を雌嶽と云ひ、北を雄嶽と云ふ。後者は前者より高く、その雄嶽の北端に大津皇子の御墓がある。登山道はやや急で、殊に道に迷へば難澁するところであるが、僅かの時間で登ることが出来、しかも眺望甚だ佳。大和、河内の両平野を見下ろす事が出来、又その両平野のいづこからも、遠くは難波の都あたりからも一見してその山と見放けられる山である。さほどの高さでなくて、しかも上からも下からもこんなに遠く見放けられる山は他にこのあたりには求め難い。さうした山の頂きに特にこの皇子の屍を葬つたといふ事は何を意味するか。同じく御謀反の故を以つて死の運命を辿られた有間皇子の御墓はただ伝説地といふものを伝へるのみ(141) であるに較べて、この大きな相違は考へられてよい問題であらう。 宇都曽見乃 人尓有吾哉 従明日者 二上山乎 弟世登吾将見(ウツソミノ ヒトニアルワレヤ アスヨリハ フタカミヤマヲ ナセトワガミム) うつそみの ひとにあるわれや あすよりは ふたかみやまを なせとわがみむ (金澤本) 【口譯】 この世の人である私は、マア、明日からは、あの二上山を弟の君と考へて眺めようか。 【訓譯】 うつそみの人にある吾や----「うつそみは」 は「うつせみ」(一・13) と同じ。「や」 は詠歎の意をもつた疑問の係助詞で、結句にかかる。この世の人である私は云々しようかナア、の意。 二上山を汝背と吾が見む----二上山は題詞の條で述べた。汝背の原文「弟世」 とある。金澤本などの古写本には「弟」 の字「苐」 とあり、チヨと訓でゐる。チと訓だのは「茅」 の字としての訓であるが、苐と茅の混同は時々あるにしても、ここは確実に「茅」 と認むべき文字はない。校本萬葉集に古葉略類聚鈔に「茅」 とあるやうに注されてゐるが、同書の複製本について見るとやはり「苐」 と認めた方がよく、そしてそれらの「苐」 はまた「弟」 の誤と認むべきであり、はやく類聚古集(十四・七六) には「苐」 を「弟」 と直されてをり、西本願寺本以後の諸本によつて「弟」 を正字と認める。さてその弟世を西本願寺本以後イモセと訓で、その旧訓による諸注もあるが、弟をイモと訓んだ例もなく、字義としても当たらず、「いもせ」 と云へば夫と妻、兄と妹、といふ事になつて歌意としてもふさはしくない。そこで「奈世(ナセ)」 の誤とする説(考) や「吾世(ワガセ) の誤とする説(古義) などもあるが、この作者にとつて大津皇子は全く文字通りの「弟」 であるのだからこれをみだりに誤字とすべきでない。そこで「弟世」 そのままにして訓むものに二説あり、ナセと訓むとイロセと訓むとである。前者は檜嬬手であり、後者は折口氏の口譯にはじめて見え、新訓、講義その他現在の諸注に多くその説が行はれてゐる。檜嬬手に「弟の字は實を以てかき、世を加へたるは那勢とよませんとなり」 とあるは注意すべき説である。ここに弟の字を用ゐる事は右に述べたやうに適切な用字であるが、この字はオトとも訓めるがセとも訓める。セと訓める例として檜嬬手には「吾弟(ワガセ)」 (130) の例があげられてゐるが、私もその條で述べたやうに弟をセと訓む事が出来る。ただ、両様に訓めるところからセと訓む事をたしかめる為に更に「世」の字を加へたので、それは「雖干跡不乾(ホセドカワカズ)」(七・1186) の「雖」 が意を示し、「跡」 が訓を示したのと同じで、重複した用字法と見る事が出来る。即ち「弟世」 意としては弟の義を示し、訓としてはセといふべき事を示したといふ事になるが、セとだけでは一句の調が整はない。そこで右に述べたやうにナセ、イロセの両説が生じたのでイロセは講義に古事記上巻素戔嗚尊が「吾者天照大御神之伊呂勢也」 とあると神武記に「其伊呂兄五瀬命」 とあるを引き、「こは古事記伝にいへる如く同母兄弟をいふ古語なれば、ここに適せるが故に、『弟世』を必ずかくよむべしといふ確證を見ざれど姑く之従ふ」 とあり、この説が有力になつたのであるが、「弟世」 の表記そのものにはただ「せ」 の意があるのみであるから、「清明」(一・15) をマサヤカと訓むマの訓添と同じく、イロもナも共に訓添である点は同様である。だからこの場合いづれが訓添として、より適切であるかを考へるべきであるが、「いろ何」 といふ例は右の「いろせ」 の他に古事記に「有二女。兄名縄伊呂泥(ハヘイロネ)・・・弟名縄伊呂杼(ハヘイロト)」(安寧記) とあり、和妙抄(一) にも「兄」 に「和名古乃加美(コノカミ)、日本紀私記云伊呂祢(イロネ)」 とあり、「妹」 に「和名以毛宇止(イモウト)、日本紀私記云以呂止(イロト)」 とあり、又古事記上巻に「其伊呂妹(イロモ)高比賣命」 あり、和妙抄(一) には「母」 に「和名波々、日本紀私記云、日本紀私記云、母、以路波(イロハ) とある。右の古事記の例で云へば、記伝の説のやうにも見えるが、「いろは」 の例などを考へると「いろ」 は愛稱と見る方があたつてゐるやうに思はれる。一方「なせ」 の「な」 は汝の意と思はれる事前(130) に述べた如くであるが、これも愛稱に近い用ゐざまである。さうだとすれば「いろせ」 も「なせ」 もほぼ同様に認められるものであるが、「いろ」 の方は、「いろせ」 をはじめ「いろも」 「いろと」「いろは」 など「いろ何」 の語が集中には一つも用ゐられてゐないに対して「な」 の方は既にあげたやうに「名兄(ナセ)」 (十六・3885)、「奈勢(ナセ)」(十四・3438) をはじめ「奈弟(ナオト)」(十七・3957)、「名姉(ナネ)」(四・724)、「那迩妹(ナニモ)」(古事記上巻) の如く用例が多く、又イロセと訓めば八音の句となり―「吾」 をアガと訓めば、字余り例の法則には叶ふからそれも認められないではないが、第二句にワレといひ、ここアガとしてしひて八音にしなくとも-、ナセと訓めば七音の句となつて音調も整ひ、イロの二音を加へるよりナの一音を加へた方が自然であり、二上山に相対した呼びかけとしても「なせ」 の方が表現の直接さが感ぜられる。以上二三の理由から今はナセと訓む事とした。右にも述べたやうに、既に二句で「吾」 といひ結句でまた「吾」 といふのは重複である。上に「吾や」 と云つてゐるのであるから下はただ「なせと見む」 でよいわけであるが、中間に句をへだててをり、「なせと見む」 とだけではおちつかぜ、詠歎の心を深める為に、もう一度「吾」 をくりかへしたものと思はれる。さて上の「や」 をうけた「見む」 であるからそれは連体形の結びであり、従つて「吾」 はワガと訓む(105参照)。幽明境を異にして、現実にあひ見る事が出来ないから御墓所となつた二上山」を弟の君と眺めようか、の意である。 【考】 二上山の二つの峯を我々兄弟と見ようとする解釈があるが、それは「弟世」 をイモセと訓での上であり、訓釋の條で述べたやうにその訓は無理であるからその解釈は成立たない。 昔こそ外(よそ) にも見しか吾妹子が奥津城(おくつき) と思へば愛(は) しき佐保山 (三・474)家持 も同想の歌である。但、今の御作の歌は深い。「や」 の助詞に悲痛な詠歎がこめられてゐる。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 大津皇子の屍(かばね)を葛城の二上山に移し葬る時に、大来皇女の哀しみ傷みて作らす歌二首 〇原文 「移葬大津皇子屍於葛城二上山之時大来皇女哀傷御作歌二首」。特に注意すべき文字の異同はない。屍は、死体・なきがらの意。巻十八に「海行者 美都久屍 山行者 草牟須屍」(四〇九四、家持) とあり、霊異記中巻の訓注に「屍骸 二合死ニカハ子」 と見える。名義抄に「屍」 をカバネと訓んでおり、ここもカバネが適切だろう。移葬は、殯宮から屍を移し埋葬することを言うが、大津の場合は、正式にモガリの儀礼を行うことなく、直ちに葬られたのであろう。 〇葛城二上山 奈良県北葛城郡当麻村の二上山(にじょうさん) を指す。北の雄岳、南の雌岳、二つの峰のあるところからの名で、大津皇子の墓所は雄岳山頂付近にある。皇子の墓地をなぜここに定めたのか、確かなことはわからないが、二上山をこの世とあの世の境の山として意識した持統天皇が、自分の最大の敵であった大津皇子の魂をこの世とあの世との間にとどめておこうとしたとも説かれている(田中日佐夫『二上山』)。 うつそみの 人なる吾や 明日よりは 二上山を いろせと吾(あ) が見む この世の人間であるわたくしは、明日からは あの二上山を弟として見ることでしょうか。 宇都曽見乃 人尓有吾哉 従明日者 二上山乎 弟世登吾将見(ウツソミノ ヒトナルワレヤ アスヨリハ フタカミヤマヲ イロセトアガミム) 【注】 〇うつそみの ウツソミはウツセミ(150歌に既出) の古形。この歌のほかには、人麻呂作歌(196、210の一云、212) とそれを模倣して古語を用いた家持の作歌(19・四二一四) にしか見られない。ウツソミ(ウツセミ) は現世の人を意味するが、現世の意で用いられることもある。ここは後者。 〇人なる吾や 旧訓ヒトニアルワレヤであったが、考にヒトナルワレヤと改訓。以後両訓が並存している。原文「人尓有吾哉」 を文字通りに読めばヒトニアルとなる。しかしナルを「有」 の一字であらわした「山跡有(ヤマトナル)大島嶺」 (91)、「辛乃埼有(サキナル)伊久里」(135)、「島宮上池有(ウヘノイケナル)放鳥」(172) もあり、記紀歌謡にも「我が御酒(みき)那良受」(記三九歌)、「尾津の埼那流一つ松」(記二九歌) と見えるので、那流・有・尓有を同じくナルに宛てた表記とも考えられる。ここでは後者により、前の134歌の例とともにナルと訓む。ナルは断定の助動詞。ワレヤのヤは疑問の係助詞で、結句の「イロセトアガミム」 までの文全体にかかる。 〇二上山をいろせと吾が見む イロセは原文「弟世」。弟を金澤本・紀州本に「苐」、古葉略類聚鈔には「茅」(これも苐か) とし、金澤本・類聚古集・古葉略類聚鈔などの付訓にチヨと見えるが、苐は弟の誤りであろう。西本願寺本以後の諸本に弟とするのによる。弟世の二字、西本願寺本にイモセと訓む。現代の注釈書や研究書でもこの訓によるものを見るが、(私注、市村宏『万葉集新論』など)、弟の字義および通常訓からいって、イモと訓むのは無理である。また檜嬬手には「弟の字は実を以てかき、世を加へたるは那勢とよませんとてなり」 とし、弟世(ナセ) と解する。これを受け、澤瀉注釈に「『弟世』は意としては弟の義を示し、訓としてはセといふべき事を示した。」 ものと言う。ナセ・イロセの両訓いずれも訓み添えを要するのであり、「イロ~」 は集中に一つも例が見えないのに対し「ナセ」 の例は多いから、ここも弟世(ナセ) と訓むべきだろうとしている。これも、慎重に考えられたものであるが問題を含む。詳細は別稿「『弟世』と『伊呂勢』-『世』字書添えの意義」(万葉五十九号) に譲が、この歌の表記者は「弟」一字ではイロトと読まれる可能性の多い点を考慮し、「世」 を書き添えたのであろう。ナセと訓ませるつもりであったとすれば、「弟」 一字でナオトと訓むことが一般に行われていたとしなければならない。注釈ではそれを認め、イロセ・ナセ両訓の可能性をほぼ対等のものとして論を進めているが、「弟」 一字をナオトと訓だ確かな例はないのである。ナセ・ナオトの場合は必ずナを仮名表記しているのも見逃せない。神代記の須佐之男命が足名椎・手名椎に名のる場面に「伊呂勢」 とあるのは、「伊呂弟」 ではイロトと訓まれる可能性が強いためセを仮名書きしたのであろう。「弟世」 イロセと訓ませるための「世」 の書き添えと見て良い。イロセは同母の兄弟の称である。イロセトアガミムは結句の字余りとなるが、句中に単独母音(ア) を含んでいて、七音句に準ずる。 【考】 移葬について 大津皇子の死を日本書紀は、「(朱鳥元年十月) 庚午(二日) に、皇子大津を訳語田の舎に賜死(みまからし) む。時に年二十四なり、妃皇女山辺、髪を被(くだしみだ) して徒跣(そあし) にして、奔(はし) り赴(ゆ) きて殉(ともにし) ぬ。見る者皆歔欷(なげ) く。」 と伝える。謀叛人として刑死させられたのであり、妃も殉死したという。この記事から皇子の殯宮の設けられたことを推定するのは困難だろう。移葬は、通常「改葬」 とひとしく「釈会。改移旧屍。古記曰。改葬謂殯埋旧屍柩改移之類」 (仮寧令集解、改葬) の意とされる。攷證に「移葬は改葬といふに同じく、今まで殯してありつるを、墓所に移し葬るをいへり」 と言い、注釈に「一旦葬つた墓所を他へ移す意でなく、殯宮より墓所に移す事をいふ」 と記しているのは、みなその意味のものであるが、ここも同様に理解することができるかどうか、問題であろう。ただ、このあとの歌(166) に、あしびの花を詠んでいるので、移葬を翌年(持統元年) 早春とすると、約二ヵ月の間、大津の屍がどこかに置かれてあったことは間違いない。その原葬地は、まったく分からない。 二上山を「弟世」と見ること 「弟世」 をイロセを訓むことは〔注〕に述べた。私注に「この歌の趣は葬つた二上山を弟の姿として、弟として見ると云ふのではなく、その二つ並んだのを妹背として見、背を失つて一人となつた心のよりどころとしようと云ふのであるから、やはりイモセと訓むべきであらう」 とするのは、イモセの訓を前提にした考説で従えない。弟を葬った二上山であるゆえに、明日からはその山を弟として見ようというので、それでこそ「うつそみの人なる吾や」 という冒頭の句が生きると思われる。この二句に、現(うつし) 身の自分と、あの世の皇子との距りが嘆かれているのである。注釈に「昔こそ外(よそ) にも見しか吾妹子が奥津城と思へば愛(は) しき佐保山」(3・四七四、家持) を同類の歌という。しかし断絶の嘆きの深さは、比較にならないようだ。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 大津皇子の屍(かばね)を葛城の二上山に移し葬(はぶ) りし時に、大来皇女の哀傷して御作(つく) りたまひし歌二首 うつそみの人なる我(われ) や明日よりは二上山(ふたがみやま) を弟(いろせ) と我(あ) が見む 移葬大津皇子屍於葛城二上山之時大来皇女哀傷御作歌二首 宇都曽見乃 人尓有吾哉 従明日者 二上山乎 弟世登吾将見(ウツソミノ ヒトナルワレヤ アスヨリハ フタガミヤマヲ イロセトアガミム) この世の人である私は、明日からは、二上山を弟として眺めることでしょうか。 【脚注】 二上山雄岳山頂に大津皇子の墓と伝えられる墳墓がある。処刑の地は、磐余(いわれ) の「訳語田(をさた) の宮」。その地の葬所から二上山へ移葬したのであろうか。罪人である以上、殯宮が設けられたかどうかも疑わしい。この題詞に「屍」 の語を用いていることも注意を要する。続日本紀は、長屋王について、「使いを遣はして長屋王・吉備内親王の屍を生駒山に葬らしむ」(天平元年二月十三日) と記す。罪死の人だったので「屍」 の字が使われたのであろう。「うつそみ」 は「うつせみ」 の古形(→196・2101云・213)。「いろせ」 は同母の兄弟を指す語。うつそみの人にある我れや明日よりは二上山を弟背と我が見む |
||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 大津皇子の屍(かばね)を葛城の二上山に移し葬(はぶ) る時に、大伯皇女の哀傷して作らす歌二首 うつそみの 人なる我(あれ) や 明日よりは 二上山(ふたがみやま)を 弟(いろせ) と我(あ) が見む 移葬大津皇子屍於葛城二上山之時大来皇女哀傷御作歌二首 宇都曽見乃 人尓有吾哉 従明日者 二上山乎 弟世登吾将見 (ウツソミノ ヒトナルアレヤ アスヨリハ フタガミヤマヲ イロセトアガミム) この世の 人であるわたしは 明日からは 二上山を 弟として眺めるのか 【頭注】 うつそみ-ウツセミ(13) に同じ。共にウツシ(現) + オミ(人) の約音形。このオミはヒトに同じ。「臣、ヒト」 (名義抄)。 弟-同母の兄弟。イロエ(同母兄)・イロネ(同母兄姉)・イロド(同母弟妹)・イロモ(同母妹) などの類似呼称がある。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 巻二166 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 活字附訓本 | 活字附訓本 | 活字附訓本 (国立国会図書館蔵書)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 諸注引用 | 拾穂抄 | いそのうへにおふるつゝしをたおらめど見すへききみかありといはなくに 礒之於尓生流馬酔木乎手折目杼令視倍吉君之在常不言尓 此一首今案スルニ不似移シ葬ル歌ニ疑ラクハ從 [ヨリ] 伊勢ノ神宮上京ノ時感シテ路上ノ花ニ作歌乎 いそのうへにおふるつゝし 心は明也祇曰同時の哀傷の哥也此時舎人のよめる哥とも云也 愚案此哥礒のうへとは岩の上也此哥はうつし葬る時のとはみえす上京の道の哥と也 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | 礒之於爾生流馬醉木乎手折目杼令視倍吉君之在常不言爾 [イソノウヘニオフルツヽシヲタヲラメトミスヘキキミカアリトイハナクニ] イソノ上は石の上なり、神功皇后紀に、登河中石上(ニ)、とあるをイソノウヘと点ぜり、大和の石上又同じ、於は上なり、文紀に憶良の氏/山上 [ヤマノウヘ]を山於 [ヤマノウヘ]とかけり、南京の法相宗の學者内典を讀時某においてを某のうへにと讀習へるは古風の故實なるべし、馬醉木は集中/數 [アマタ]あり、点今の如し、別の歌の馬醉木を六帖にもあせみとよめり、別に注す、歌の意明なり、此皇女の御歌、以前共に六首、何れも悲しきは、皆大津 (ノ)皇子によりて讀給ふ故なり、 右一首今案不似移葬之歌盖疑從伊勢神宮還京之時路上見花感傷哀咽作此歌乎 移葬の下に時の字脱たるべし、此注は撰者の誤なり、所謂智者千慮必有一失とは此事なり、皇女は十一月十六日に都へ皈たまへば、此は明る年の春花盛の比、皇子の尸を移葬に因て感じてよみ給ふなるべし、有間皇子の松枝を結歌二首の後の歌に准ずべし、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 萬葉集 童子間 |
礒之於爾生流馬醉木乎手折目杼令視倍吉君之在常不言爾 右一首今案不似移葬之歌盖疑從伊勢神宮還京之時路上見花盛傷哀咽作此歌乎 童子問 右二首の中一首はまことに移葬の時の歌とはみえがたければ、古注者の今案しかるべからずや。 答 いな、此者古注者の今案かへりて心得がたし。いかにとなれば、大來皇女の前の二首の御歌にて見れば、大津皇子の薨は上京ありて聞召たる御歌ときこゆる也。大津の皇子の薨は順死にあらざれば、大來皇女にはしらせまつらずして。京にかへし來させ給ふなるべし。さればにや右一首の下句、歸京有て聞しめされたる御詞ときこゆる也。且路上見花盛とあること、馬醉木の花の盛時節たがへり。馬醉木は花盛は春の末より夏にいたりて花咲也。大來皇女いせの齋宮より歸京は日本紀にみえて、朱鳥元年十一月丁酋朔壬子奉伊勢神祠皇女大來還至京師とあれば、いかゞとおぼゆる也。 童子又問 右の一首歸京路上の御歌ならずば、移葬の歌とはいかゞみるべきや。 答 葛城山に移葬とあれば、墓所に詣給ふ時馬醉木を見て詠給ふと見るかへりてむつかしからず。二首の内前の御歌はいまだ葬めざる時の御詠とみえて、明日よりはと句中にあり、後の御歌は移葬て墓所に詣給ふ路上の馬醉木の歌とみるべし。礒之於爾と有初五文字も、二上山中の石のへに生たるとみえたり。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 童蒙抄 | 磯之於爾生流馬醉木乎手折目杼令視倍吉君之在常不言爾 いそのうへに、おふるつゝじを、たをらめど、見すべききみの、ありといはなくに 礒之於爾 いしの上也。いそはいしといふ義也。水邊ならではなきものと心得たる人もあらんか。大なるたがひ也。石上ふるといふ地名にてもしるべき也。此いそのうへも、古注者もし海邊の事に心得たる歟。左注の趣心得がたき也 馬醉木 馬の字は羊の字のあやまりならんか。馬なればあせみ也。毒木のあせみを折て、見すべき君かとよみ給ふ事あるべからず。あせみを此集に馬醉木と書て、牛馬此葉を食めば忽醉花と云傳へたり。又羊躑躅と書て、いはつゝじとも、もちつゝじともよめり。羊此花を喰はゞ、躑躅して忽死と云義あり。是によりてつゝじをもあせみの例にて羊醉木と書きたるを、羊を誤りて馬に作れる歟。されば古本印本ともに點にはつゝじとよめり 右一首今案不似移葬之歌盖疑從伊勢神宮還京之時路上見花感傷哀咽作此歌乎 みぎのひとくさ、いまおもふに、はふりをうつすときのうたにゝず、けだしうたがふらくは、いせのかんのみやよりみやこにかへり給ふとき、みちのほとりのはなざかりなるを見て、いたみかなしみむせびてこのうたをつくれるか 是古注者の文なり。此注心得がたし。二首ともなるほど移葬の時の歌と見ゆる也。しかるを伊勢よりかへり上り給ふとき、路次の花盛を見てといへること大成不v考事也。大來皇女いせよりかへり登り給ふは十一月なり。則年月前に注せり。しかればつゝじの咲くべき時節にあらず。古注者如此見あやまりたるは、礒の於を海邊の事と見たる故なるべし |
||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉考 | 〇磯之於爾 [イソノウヘニ]、 古へは石をいそともいひしかば、此二上山の石 [イシ]むらの邊に生たるあしみをいふなり、ほとりの事をうへといふは常なり、磯と書しに惑ふ人あればいふ、 〇生流馬醉木乎 [オフルアシミヲ]、手折目杼 [タヲラメド]、 こは木瓜 [モケ]の花をいへり、三月の頃、野山につゝじとひとしく赤く咲めれば、庭にも植るものにて、池水の照までに咲るなど、集中に多くよめり、誤れる説あれば、冠辭考に委くいひつ、 〇令視倍吉君之 [ミスベキキミガ]、在常不言爾 [アリトイハナクニ]、 移はふりの日に、皇女もしたひ行給ふ道のべに、此花を見てよみ給へるものなり、上の歌に、あすよりはと有からは、他 [アダ]し日にあらず、さてかゝる時、皇子皇女にもそこへおはする事、紀にも集にも見ゆ、古への心ふかさしるべし、 ○今本是に注あれど、いとひがことなれば、こゝには捨て別記にことわりぬ、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | 礒之於爾。生流馬醉木乎。手折目杼。令視倍吉君之。在常不言爾。 いそのうへに。おふるあしびを。たをらめど。みすべききみが。ありといはなくに。 古へはただ石をイソとも言へば、此二上山の石有るあたりに生ひたるあしびを言ふなり。ホトリの事をウヘと言ふは常なり。卷十、かはづ鳴よしのの川の瀧上の馬醉之花云云と有るを、今本ツツジと訓む。六帖に此歌をアセミノ花とて載せたれば、古くはアセミと訓みしならむ。よりてここもアセミと訓むべけれど、卷七に安志妣成 [アシビナス]、卷廿に安之婢 [アシビ]と書けるをもて、ここはアシビと訓めり。六帖にアセミと有るは、音の通へばやや後にはしか唱へしなるべし。さてアセミは木瓜 [ボケ]の花なるべし。三月のころ野山に、躑躅とひとしく赤く咲くものにて、集中に多し。冠辭考、アシビナスの條に委し。からぶみに馬醉木と言へるは、こと物なるべく聞ゆれど、字に泥 [ナヅ]む事なかれ。此み歌も移葬の日に、皇女も慕ひ行きたまひて、此花を見て詠み給へるなり。古へはかかる時、皇子皇女もそこへおはする事、紀にも集にも見えたり。 左註は後人のしわざなるべし。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 攷證 | 礒之於爾 [イソノウヘニ]。生流馬醉木乎 [オフルツヽジヲ]。手折目杼 [タヲラメト]。令視倍吉君之 [ミスヘキキミカ]。在常不言爾 [アリトイハナクニ]。 礒之於爾 [イソノウヘニ]。 磯 [イソ]は借字にて、曾 [ソ]と志 [シ]と音かよへば、石なり。本集十一〔十二丁〕に、磯上立回香瀧 [イソノウヘニタチマフタキノ]云云。十二〔三丁に、磯上生小松 [イソノウヘニオフルコマツノ]云々などあるも、皆石なり。於 [ウヘ]は、三〔四十丁〕に、玉藻乃於丹獨宿名久二 [タマモノウヘニヒトリネナクニ]などもよみて、廣韻に、於居也とあれば、自らうへの意こもれり。 生 流馬醉木乎 [オフルツツシヲ]。 馬 醉木を、考には、あしびと訓て、本集二十〔六十二丁〕に、安之婢 [アシヒ]とあると、同物として、今いふ木瓜 [ホケ]なりといはれしは、誤れり。そのよしを、くはしくいはん。まづ、馬醉木は、本集八〔十五丁〕十三〔二丁〕などには、馬醉木とかき、十〔十丁十四丁十七丁〕には、馬醉花とかけり。いづれも、この集の外、漢土の書にも見ゆる事なし。これこの集の義訓に、まうけて、嶼る字なれば也。本集十に、馬醉花とかける、三首の歌は、六帖第六、あせみの條に載て、みなあせみと訓り。こは、天暦の御時、梨壺の五人に詔して、この集を讀解しめ給ひしをりの訓なるべけれど、其後、仙覺がつゝじと訓せしぞさる事なりける。そもそも、つゝじを、馬醉木と書たる事、この集の外は、ものに見えざれど、和名抄木類に、陶隱居本草注云、羊躑躅〔擲直二音、和名以波豆々之、一云毛知豆々之〕羊誤食之、躑躅燭而死、故以名之云々とありて、本はつゝじを、羊躑躅といひしかど、やがて、羊の字をはぶきて、躑躅とのみもいひし事、漢土の書にも多くありて、今もしか也。躑躅とは、一切經音義卷八、引字林て、躑躅□[足+主]足不進也云々。玉篇に、躑躅不能行云々とありて、ゆくことならざる意にて、羊の、つゝじを食へば、足すくみて、行ことならざる故に、つつじを、しか名づけしなれば、馬の醉 [ヱヘ]るも、足すくみて、行ざるもの故に、馬の醉 [ヱヘ]るは、躑躅する事、もとよりなれば、躑躅の意をとりて、つゝじに、馬醉木とはかける也。こは、謎 [ナゾ]のごとき、字の用ひざまなる事、集中、山下風を、あらしのかせとよみ、馬聲の二字を、いの假字とし、所聞多を、かしまとまみ、向南を、きたとよみ、八十一を、くゝとよみ、二五を、とをとよみ、十六を、しゝとよみ、義之を、てしとよめる類、かぞへがたし。この類としるべし。さで、馬醉木 [アシヒ]も、安之婢 [アシビ]も、前によめる所も、咲時も、大かたは同じければ、同物とせしも、ことわりなれど、上にいへるを見ても、同物ならぬをしるべし。(頭書、再考るに、馬醉木をつゝじとせしは非なりけり。大和本草本草啓蒙など□[木+浸の旁]木〔アセホ〕を當たるも非也。□[木+浸の旁]木は、食へば、馬の醉るもの故に、馬醉木の字にのみ付て、これを定めしなるべけれど、花小き白き花にて、房になりて咲て、正月の末にひらきて、見るにたらね花也。集中詠る所を、こゝにあげたれば、よくく考へて、これにならぬをしるべし。七〔十丁〕に、安志妣成榮君之 [アシヒナスサカエシキミカ]云々。八〔十五丁〕に、山毛爾咲有馬醉木乃 [ヤマモセニサケルアシヒノ]、不惡君乎何時 [ニクカラヌキミヲイツシカ]云々。十〔十四丁〕に、吾瀬子爾吾戀良久者 [ワカセコニワカコフラクハ]、奧山之馬醉花之今盛有 [オクヤマノアシヒノハナノイマサカリナリ]。また十七丁、春山之馬醉花之不惡 [ハルヤマノアシヒノハナノニクカラズ]云々。十三〔二丁〕に、本邊者馬醉木花開 [モトヘハアシヒハナサク]、末辺方椿花開 [スヱヘハツハキハナサク]云々。二十〔六十二丁〕に、乎之能須牟伎美我許乃之麻家布美禮姿安之婢乃波奈毛左伎爾家流可母 [ヲシノスムキミカコノシマケフミレハアシヒノハナモサキニケルカモ]。また伊氣美豆爾可氣左倍見要底 [イケミツニカケサヘミエテ]、佐岐爾保布安之婢乃波奈乎蘇弖爾古伎禮奈 [サキキニホフアシヒノハナヲソテニコキレナ]。また伊蘇可氣乃美由流伊氣美豆 [イソカケノミユルイケミツ]、底流麻□[泥/土]爾左家流安之婢乃知良麻久乎思母 [テルマテニサケルアシヒノチラマクヲシモ]などあるを、おしわたし考るに、あしびなす榮えし君とも、山も迫にさけるあしびとも、池水てるまでにともあれば、花やかに咲榮ゆるものとこそおもはるれ。今いふあせぼの如く、見るにもたらぬ花を、いかでか賞すべき。このあせぼといふ木、たまたま馬に毒する功ありとも、これとは定めがたき事、人に毒するもの一二種のみならねば、馬に毒するものもまた猶ありぬべきにてしるべし。されば、冠辭考にいはれたる如く、木瓜なるべし。木瓜の種類、いと多き中にも、しどみと云ふものぞ、古しへのあしびなるべき。これを、中古よりは、あせみといへり。しとせと通ずればなり。堀川百首に〔俊頼〕とりつなげ玉田横野のはなれごま、つゝじのけたにあせみはなさくとよまれたれど、かのあせぼは、正月末、二月のはじめに咲て、つゝじに先だつ事、一月あまり也。又夫木抄卷廿九に、〔光俊〕おそろしや、あせみの枝を折たきて、南にむかひいのるいのりはとよまれしは、人を呪咀する護摩には刺ある木をたきて、南に向ひて祈るよしなれば、今の木瓜よく當れり。されば、中古よりは、木瓜と定めしなれば、今もこれに從ふべし。) 在當不言爾 [アリトイハナクニ]。 このなくには、下へ意をふくめたるにて、一首の意は、今この二上山の、石の上に、生たるつゝじの花を、手をらめども、見すべき君が、ありともいはぬは、いとかなしと、悲しみ給へるなり。さて、考に、移はふりの日に、皇女もしたひゆきたまふ道のへに、この花を見て、よみ給へるもの也。上の歌に、あすよりはとあるからは、他 [アタ]し日にあらず。さて、かゝる時に、皇子、皇女も、そこへおはする事、紀にも、集にも、見ゆ。古への心ふかさしるべし云々といはれつるがごとくなれば、左注に、不似移葬之歌とあるは、非なり。 右一首。今案。不似移葬之歌。盖疑。從伊勢神宮還京之時。路上見花盛。傷哀咽作此歌乎。 右の左注は、誤りなる事、まへにいへるがごとし。哀咽は、かなしみむせぶ意なる事、上に見結松哀咽歌とある所にいへるがごとし。さて、次の日並知皇子云々の端辭を、印本、この左注につづけしるせり。今、活字本、古本などによりて、別行とす。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 磯之於爾 [イソノウヘニ]。生流馬醉木乎 [オフルアシビヲ]。手折目杼 [タヲラメド]。令視倍吉君之 [ミスベキキミガ]。在常不言爾 [マストイハナクニ]。
〇磯之於爾 [イソノウヘニ]は磯のあたりに、といふほどの意なり、於はウヘなり、集中にも木末之於 [コヌレガウヘ]など見え、續紀にも憶良が氏を、山/於 [ノウヘ]と書り、 ○馬醉木 [アシビ]は、今(ノ)世にあせぼといふ木なり、土左(ノ)國にては、今もあせびと云り、(岡部氏が、木瓜の事とせるは、いみじきしひほとなてり、)猶品物解に委しくいふ ○在常不言爾 [マストイハナクニ]は、おはしまさぬことなるに、といふ意なり、言 [イフ]の言は輕く見べし、 ○御歌(ノ)意は、磯のあたりに咲たる、馬醉木(ノ)花を、手折つべく思へども、今は見すべき君が、おはしまさぬことなるにとなり、移葬の日に、この皇女も、したひ行賜ふ道の川邊の磯などに、馬醉木の咲たるを見て、よみ給へるなり、 ○舊本こゝに、右一首、今案(ニ)、不似移葬時之歌、〔(時(ノ)字、舊本にはなし、官本にはあり、〕蓋疑、從伊勢神宮還京(ニ)之時、路上見花盛、傷哀咽作此歌乎、と註せるは、後(ノ)世のをこ人の書入(レ)なり、いかにとなれば、かの皇女は、十一月京に還り給へれば、いかでか、馬醉木(ノ)花の、盛なるよしあらむやは、故(レ)削去 [ステ]つ、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 口訳 | 石 [イソ]の上 [ウヘ]に生ふる馬醉木 [アシビ]を手折らめど、見すべき君がありと云はなくに 岩の邊に生えて居る馬醉木を折つても見ようが、併し見せたいと思ふ方は、生きてゐると云ふではなし、詰らぬことだ。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 磯の上に 生ふる馬醉木を 手折らめど 見すべき君が ありといはなくに 礒之於爾《イソノウヘニ》 生流馬醉木乎《オフルアシビヲ》 手折目杼《タヲラメド》 令視倍吉君之《ミスベキキミガ》 在常不言爾《アリトイハナクニ》 川ノ邊ノ〔四字傍線〕、岩ノ上ニ生エテヰル馬醉木ノ花ヲ、手折ラウト思フガ、コレヲ折ツテ歸ツテモ〔十字傍線〕、見セルベキ貴方ガ、コノ世ニ生キテ居ラレナイカラ悲シイ〔五字傍線〕。 ○礒之於爾《イソノウヘニ》――礒はイシと通ずる語で、凡て石の多い所、主に水邊の石崖などをいふ。ここは川の岸であらう。於は山於憶良《ヤマノウヘノオクラ》とある如く、ウヘとよむ字である。○生流馬醉木乎《オフルアシビヲ》――馬醉木は※[木+浸の旁]とも記す。石南科※[木+浸の旁]木屬の(183)常緑灌木で、樒・榊に類した葉である。花は白色又は僅かに淡紅色を帶びてゐるものもあり、壺状をなして、總状花序に排列し、早春より開く。花房は長くはないが、葉の上に蔽ふやうに澤山咲くので、誠に美觀である。萬葉人の愛した花だ。○在常不言爾《アリトイハナクニ》――不言《イハナク》は極めて輕く添へたもので、アラナクニとしても同じやうな意味である。 〔評〕 弟君への家苞に、この馬醉木を手折らうと思はれたので、御兄弟の親密さがよくあらはれてゐる。しかも見すべき弟君は既に亡しと、嘆かれた御心の悲しさが、思ひやられて哀切な歌である。 右一首、今案(ズルニ)不v似2移葬之歌(ニ)1盖(シ)疑(フラクハ)從2伊勢神宮1還(ル)v京之時、路上(ニ)見(テ)v花(ヲ)感傷(ミ)哀咽(シテ)作(ル)2此歌(ヲ)1乎 この註は後人のさかしらである。不似移葬之歌とあるのは、礒之於爾とあるのを御墓への道すがらとしては似合はぬと考へたものであらう。皇女の上京は十一月であるから馬醉木は未だ咲かぬ筈である。見花感傷の感は流布本は盛であるが、古本多く感であるから、それに從ふことにした。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 礒 [いそ]の上 [ウヘ]に 生ふる馬醉木 [アシビ]を 手折 [たを]らめど、 見すべき君が ありといはなくに。 礒之於尓 [イソノウヘニ] 生流馬醉木乎 [オフルアシビヲ] 手折目杼 [タヲラメド] 令視倍吉君之 [ミスベキキミガ] 在常不言尓 [アリトイハナクニ] 【譯】礒の上に生えているアシビを手折りもしようが、お目に懸くべき君が、この世にあると誰もいう人が無いことです。 【釋】礒之於尓 イソノウヘニ。イソは石の群りある處。ウヘは、その處。野の上などと同じ言い方で、礒ニ生フルアシビでよいのだが、所在を明確にするために、 礒の上と言つている。 生流馬醉木乎 オフルアシビヲ。アシビは、今いうアセボであるという。アセボは、シヤクナゲ科アセボ屬の常緑灌木で、春の初めに白い房形の垂り花をつける。 清楚な、どちらかというと寂しい氣味の花である。馬の毒で馬は食わないので馬醉木という。これをアシビと讀むのは、 「安志妣 [あしび]なす樂えし君」(卷七、一一二八)等があつて、安志妣すなわち馬醉木であるとするのであるが、「池水に影さへ見えて咲きにほふ安之婢の花」 (卷二十、四五一二)、「礒影の見ゆる池水照るまでに咲ける安之婢」(同、四五一三)の如く華やかなものとして、適切な歌もあつて、今日いうアセボでは、 適しない點がある。また早春の花とする證明もない。そこで美夫君志にはボケのこととしている。まず馬醉木とアシビと同物か異物かが問題になり、 次にそれがいずれにしても今日の何に相當するかが問題になる。馬醉木の字面は、馬の醉うことを意味するであろうが、これによれば赤い花であるかも知れない。 アセボは毒のある植物であるが、馬はこれを喰わないから、これによつて馬が醉うとする從來の解釋は成立しない。毒の有無には拘わらなくてよいのである。 しかし今明解を得ないから、訓は從來のものによる。 手折目杼 タヲラメド。タは接頭語。メドは、助動詞ムと、助詞ドと結合して、逆態條件法を作つている。手折りもしようがの意。 令視倍吉君之 ミスベキキミガ。ミスは、使役の語法。見しむべき。お見せすべき。君は大津の皇子。 在常不言尓 アリトイハナクニ。イハナクは、言わないこと、ニは助詞。誰も、君がありとは言わないことだの意。 【評語】花または自然の景色などを、人に見せたいという内容の歌は多いが、これほどに緊張した歌はすくない。事情が事情だからでもあるが、やはり作者の人がらに依る所が多い。この歌は、初二句の具體的な指摘が、非常に役立つている。 右一首、今案、不似移葬之歌。蓋疑從伊勢神宮還京之時、路上見花、感傷哀咽作此歌乎。 右の一首は、今案ふるに、葬を移す歌に似ず。けだし疑はくは、伊勢の神宮より京に還りし時、路上に花を見て、感傷/哀咽 [あいえつ]して、この歌を作りませるか。 【釋】今案 イマカムガフルニ。以下、編者の意見である。しかし、移葬の時が、たまたまアシビの花咲く頃であつて、それを眺めて詠まれたものとして、何の不都合も無い。アシビが何の木であるにしても、卷の八には春の部に入り、卷の十三にはツバキと組み合わされていて春咲く花木と考えられ、皇女の上京は、十一月であるから、季節から言つても、上京の時の作とは考えられない。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | 磯の上 [うへ]に生 [お]ふる馬醉木 [あしび]を手折 [たを]らめど見すべき君が在りと言はなくに 右の一首は、今案ふるに、葬を移す歌に似ず。蓋し疑はくは、伊勢の神宮より京に還りし時、路上に花を見て、感傷 [かな]しみ哀咽 [いた]みて此の歌を作りませるか。 〔譯〕 岩の上に生えてゐる馬醉木を折らうと思ふが、お目にかけたいと思ふ君が、この世においでになると誰も言はないことである。 〔評〕 左註に、作歌の動機を疑つてゐるが、二上山に移葬して後、山の馬醉木の花を見て詠まれたものと思はれる。 折に觸れ事に接してほとばしる悲しみは、愈々切なるものが感ぜられる。「在りといはなくに」の調べにも、深く長い吐息が思はれる。 大伯皇女の作は、技巧といふべきものはないが、すべておのづから流れる眞情が深い。 〔語〕 ○磯の上に 磯は岩の群つてゐるところ、上はほとりの意。 ○馬醉木 [あしび] あせび、あせみともいひ、常緑の灌木で、春の初、壺状の白或は淡紅色の花が房のやうに列つて咲く。葉に毒があつて、獣が食べない。奈良の春日大社の境内には特に多いが、大津皇子の墓邊にもあつたのである。 ○在りといはなくに いふは世人がいふの意。この世にいますとは誰もいはぬことよ。 〔左註〕 この歌は移葬の歌らしくないので、或は伊勢より京に還る途上の作かと疑つたのである。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 礒之於尓 生流馬酔木乎 手折目杼 令視倍吉君之 在常不言尓 [イソノウヘニ オフルアシビヲ タヲラメド ミスベキキミガ アリトイハナクニ] 磯の上に 生えてゐる馬酔木を手折りもしようけれど、それをお目にかけるべき君がいらっしやるとは云はないものを 【訓釋】 礒の上に――磯は既出(一三一)。前に述べた如く「礒」と「磯」とは別字であるが、萬葉では混同せられてゐる感があり、磯とあるべきところに礒の文字が用ゐられてゐるが、今のごときは礒の本義巌の意に用ゐられたものと思はれる。しかもかくの如き例と見るべき「伊蘇(イソ)のまゆたぎつ山川」(十五・三六一九) も題詞に「長門島船泊礒邊」とあり、「礒の上に根はふ室の木」(三・四四八) も鞆浦であり、「礒の上のつままを見れば」(十九・四一五九) も越中の海岸、澁渓埼の事であり、 礒の上に爪木折り焚き汝がためと我が潜き来し沖つ白珠 (七・一二〇三) の如きも海岸である事が明らかである。かうした用例から考へると巌の意に用ゐられてゐるものも、集中で「礒」とあるものは「いは」といふ場合には区別せられ、水辺の巌をさしたものかと思はれる。「於」を上の意に用ゐる事については代匠記に山上憶良を文武紀大宝元年正月の條に「山於憶良」とある事を引き「南京ノ法相宗ノ学者、内典ヲ讀時、某ニオイテヲ某ノウヘニト讀習ヘルハ古風ノ故實ナルベシ」と云ひ、山田孝雄博士は萬葉集訓義考三(『萬葉集考叢』所収「於をウヘとよむこと」) に上代文献や佛書、漢籍に於をウヘと訓む例をあげられてゐる。集中には「大殿於(オホトノノウヘニ)」(三・二六一)、「木末之於者(コヌレノウヘハ)」(七・一二六三) などがある。 馬酔木――紀州本と京大本とには左にアセミとあるが、旧訓いづれもツツシとあつたのを考にアシミとし、更に冠辭考にアシビと改めてより一般にそれによる事となつた。本草和名(上)には羊躑躅に「和名/以波都々之(イハツツシ)又/之呂都々(シロツツシ) 一名毛知都々之(モチツツシ)」とし「陶景注云、羊誤食躑躅而死故以名之」とあるので、講義に馬酔木の字面は漢土の書には見えず。羊躑躅と同じく馬も喰へば酔ふといふ推測によつたものであらうが、本邦の普通のつつじは食ふとも酔ひも死にもせず、羊躑躅に当たるものは黄色大輪の黄つつじであるが、これは外来の植物だらうとし、「今本集にある馬酔木は山野に自生したる様に美ゆれば、この羊躑躅にあらざるは明らかなりとす。さて本集巻十に馬酔木とかける三首の歌は古今六帖に『あせみ』の條にのせいづれも『あせみ』とよめり。されば馬酔木は『あせみ』といふ物にあたると平安朝頃の人には、思はれしこと明らかなり。然るに、萬葉集には仮名書に『あせみ』とせるものなくして、仮名書にせるには『あしび』とかけるもの屡美ゆ。」と、馬酔木をアシビと訓むべき事を述べられた。しかるに冠辭考には木瓜(モケ)の事とし、美夫君志別記には馬酔木はアセミと訓み、□[綅の糸偏が木偏] で、俗に云ふアセボであり、「安志妣」(七・一一二八)、「安之婢」(廿・四五一一) などアシビと仮名書のものは木瓜の事で、前者は自然の山樹として詠まれ、後者は庭中の趣であり、「磯かげの見ゆる池水照るまでに」とあつて紅色と思はれる木瓜であるといふ説がくはしく述べられてゐる。しかし既に益軒の大和本草(十二) に馬酔木にアセボノキと傍訓し、「葉ハ忍冬ノ葉ニ似タリ 又シキミノハニ似て細也 味苦ク澁ル 春ノ末青白花開テ下ニサガル 少黄色ヲ帯ブ 微毒アリ 馬此葉ヲクラヘバ死ス」とある。馬酔木がアシビで後にアセビともアセミともアセボとも転じたもので、山に自生もし、庭園にも植ゑたので、照るとかにほふとかいふ言葉は色とは無関係で白いものにもいふ例(十・一八五九、二三三五) があるから、木瓜といふ説は当たらない。今も奈良春日神社の境内から公園のあたりに三月の末、雪のやうに咲き乱れてゐる。萬葉古今動植正名に「鹿この葉を食へば不時に角落つ。鹿も之を知り近つきよらぬ故、人家庭園に多く栽うるは、鹿を防ぐの用なりといふ。」とある。 見すべき君がありといはなくに――その花を見せるべき君がこの世にありとは人が云はぬ事なるに、の意。「生けりとも吾によるべしと人云名国(ヒトノイハナクニ)」(十一・二三五五) の「云はなくに」と同じで、それには「人の」の主語があり、今はその主語が略された形で、誰もさういふ人はない、の意であるが、右の「人の云はなくに」に比して、主語の実在性が薄く、単に「あらなくに」の語意を強めたものになつてゐる。 【考】 誰も思ふやうな事をたくみを加へず素直に歌つたにとどまるやうであるが、纆綿たる真情の胸に迫る佳品である。 右一首今案不似移葬之歌 盖疑従伊勢神宮還京之時路上見花感傷哀咽作此歌乎 この注は例の編者の注と思はれるが、伊勢より帰京されたのは十一月であり、馬酔木の咲くのは春であつてあたらない。考に「移はふりの日に、皇女もしたひ行給ふ道のべに、此花を見てよみ給へるもの也、上の哥にあすよりはと有からは他(アダ)し日にあらず、さてかかる時皇子皇女もそこへおはする事、紀にも集にも見ゆ、古への心ふかさしるべし、」とある。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 礒之於尓之於尓 生流馬酔木乎 手折目杼 令視倍吉君之 在常不言尓 [イソノウヘニ オフルアシビヲ タヲラメド ミスベキキミガ アリトイハナクニ] 岩のほとりに生えている馬酔木を 手折ろうと思うけれど、見せるべき君はいらっしゃらないものを。 【注】 〇磯の上に―― 礒・磯の二字については、既述(一三一歌)。ここは原文「礒」で、海岸の岩の多い所を言うわけでなく、単に岩のほとりを言う。 〇生ふる馬酔木―― 原文「馬酔木」を、旧訓ツツシと訓んだが、考にアシミとし(冠辭考にアシビ)、略解にもアシビと改訓した。冠辭考には木瓜のことと考えられているが、松田修『万葉植物新考』によると、アシビは今アセビと呼んでいるもので(牧野『新日本植物図鑑』にアセビとある)、その名は「足しびれ」の略かともいう。本州・四国・九州の乾燥した山地にはえるツツジ科の常緑の低木で、早春枝の先に複総状花序を下垂し、多数のスズランのような白色つぼ状の花をひらく。地方によっていろいろな名があり、本草綱目啓蒙にも「□(綅の糸偏が木偏)アシミ万葉集 アセボ古今通名 馬酔木共同上 アセミ古歌仙台 アセビ枕草子土州 アセモ江戸 アセブ播州豊前 アシブ雲州」と記されている。また、金井紫雲『花と芸術』に、その称呼の地方による相異を「奈良付近から畿内一円にかけては『あせみ』『あしび』『あせぼ』『あしみ』など呼び、土佐付近では『あせび』関東では『あせも』播州や豊前では『あせず』伊勢では『ゑせび』筑前では『よしみ』或は『よしみしば』出雲では『あせぶ』備前では『やましば』安芸では『こまやしば』越前では『あせぼしば』その他沢山ある」と記している。万葉集にアシビの名だけ見えるのは、それが奈良付近から畿内一円にかけての呼名だったからで(松田前掲書)、馬酔木と書かれるのは、牛馬がその葉を食べると中毒を起こし、酔ったようになるからである。古今六帖「あせみ」の項に、巻十の三首が載せられているが、古今集以後の歌にはあまり見られない。 〇手折らめど―― 手折ろうと思うけれど、タヲルのタは接頭語。タムクなどのタと同じく、手の意が強く感じられる。 〇見すべき君がありと言はなくに―― 原文「不言尓」は、人麻呂歌集に「云名国」(11・二三五五) などとあるのと同様、イハナクニと訓む。歌中の句切れのない歌における結句のナクニ止めについては、九七歌参照。詠嘆終止であるが、逆説的な気息の感じられる場合もある(木下『万葉集語法の研究』)。ここも、言ワナイコトヨとか、君ガオイデニナラナイと言い切ってしまうのと、やや異なるように思われる。 【考】 〇作歌の時期 馬酔木の開化は早春で、持統元年正月にこの歌は詠まれたものと思われる。いったん皇子の屍を葬ったのち、後に移葬されたとすれば、もっと後、つまり持統二年か三年であってもかまわないことになるが、一六五歌の「明日よりは二上山をいろせと吾が見む」の嘆きを思い合わせると、皇子の死からまだ間もないころとするのが妥当であろう。代匠記に「朱鳥二年の春なるべし」とあるのは、持統元年のことと思われる。茂吉秀歌は、前歌(一六五歌) とあわせて「この二首は、前の御歌等に較べて、稱しつとりと底深くなつてゐるやうにおもへる。『何しか来けむ』といふやうな強い激越な調がなくなつて、『現身の人なる吾や』といつて、諦念の如き心境に入つたもののいひぶりであるが、併し二つとも優れてゐる」と言う。 〇仮託説について 大津皇子に関わる一連の歌を、大津皇子・大伯皇女の自作ではなく、後代の人の仮託の作ではないかという説が見られる。都倉義孝「大津皇子とその周辺」(有精堂『万葉集講座』第五巻) は「大津の歌はすべて仮託で、彼の歌は万葉人の幻想の中に生まれたというのが稿者の仮説である」として、大津皇子物語ともいうべき伝承が持統朝から奈良朝にかけて次第に悲劇的な趣向を強めつつ宮廷人の脳裏に形成されていったなかで仮託された可能性の大きいことをいっている。巻二の大伯皇女の挽歌四首は、「この緊迫したドラマチックな歌語りの締め括り、後日譚として位置づけられていた」とも記す。また、中西進「大津皇子の周辺」(『万葉集の言葉と心』)にも同様な方向の論を見るが、都倉論文の冒頭に言うように「その仮説が真相であることを論証する手だてを持ち合わせていない」現状である。皇子関係歌の配列に物語的構成を読み取り得ることは事実であるにしても、そこから直ちに仮託説を導くわけにはゆかないのであって、なお仮想あるいは空想の域にとどまると言わざるをえない。 〇大伯皇女と作歌 皇女の作歌六首(一〇五、一〇六、一六三~一六六) はいずれも抒情歌として質の高いものである。長年伊勢斎宮にあった皇女がどのようにしてかような新しい抒情歌を作りえたのか、が問題とされよう。まだ十分に議論が煮詰められていないが、「歌謡群にとりまかれていた当時の人は、特別の教養や修業なしでこの程度の歌は即座によめたのだろう」(私記一六三、一六四歌の項) と考えられるような歌謡的な調べを感じさせる一方で、内面化による緊迫感をも表現しえているわけで、作品の孕むそのような矛盾した性格の解明なしに後代の仮託か否かを論じてみても仕方がない。幼少の大伯皇女の周囲には言語教育担当者がいたはずであるし、斎宮としての生活の中で触れる祝詞・呪詞などが作歌の土壌となったことも疑えまいが(伊藤博『万葉集の歌人と作品 上』)、天皇の御杖代という公的な立場と、姉という私的な立場との矛盾した歴史的状況において、初めて私的な愛情が美しい歌に結晶する機会を持ったという西郷前掲書の説明は掘り下げて考えられるべきものだろう。 右の一首は、今案(かむが)ふるに移し葬る歌に似ず。けだし疑はくは、伊勢神宮より京に還る時に、路の上に花を見て感傷哀咽してこの歌を作るか。 〇原文 「右一首今案不似移葬之歌 盖疑従伊勢神宮還京之時路上見花感傷哀咽作此歌乎」。特に目立った写本間の異同はない。代匠記(初稿本)に、「移葬」の下に「時」脱かとするが、誤脱を考える必要はないようだ。 〇編者の誤解 この左注は、「磯の上に」とあるのを、海岸の作と見て記されたものと思われる。すでに多くの注釈書に指摘されているように、アシビは早春の花で、皇女の上京した十一月ではなく早春の移葬と作歌が考えられ、この注の筆者の勘違いは明らかである。また、アシビが海浜に生えるのでなく、乾燥した山地に生える常緑低木であることも考え合わせられよう。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 新大系 | 礒之於尓 生流馬酔木乎 手折目杼 令視倍吉君之 在常不言尓 [イソノウヘニ オフルアシビヲ タヲラメド ミスベキキミガ アリトイハナクニ] 右一首今案不似移葬之歌 盖疑従伊勢神宮還京之時路上見花感傷哀咽作此歌乎 岩のほとりに生えている馬酔木を手折りたいと思うが、見せてあげたいあなたがいるというのではないのに 右の一首は、今考えてみると、移葬の歌らしくない。あるいは、伊勢神宮から上京して来る時、路傍に花を見て、悲しみ咽び泣いて、この歌を作ったのだろうか。 「あしび」は早春に咲く。「移葬」の時期が早春であったとすれば、左注の言うような疑いは不要である。左注の筆者は、前年に「移葬」が行われたものと理解して、「あしび」の花に不審を感じたのであろう。大伯皇女の帰京は十一月十六日。左注筆者が、伊勢からの道中、「路上見花」とのみ書いて、特に花の名を明記しなかったことも、十一月の季に「あしびの花」は不適当と思ったためであろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 新全集 | 大伯皇女の帰京は十一月十六日(太陽暦の十二月九日)。あしびの開花期は一般に早春だが、花房は晩夏から伸び、日だまりでは十二月上旬頃咲くことも珍しくない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 巻二167 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 |
|
||||||||||||||||||||||||||
[校本萬葉集新増補版]
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 活字附訓本 | 活字附訓本 | 活字附訓本 (国立国会図書館蔵書)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 諸注引用 | 拾穂抄 | 日並皇子尊 [ヒナミノミコノミコト]殯宮ノ時作歌一首並短歌 日本紀ニ曰持統天皇三年夏四月三日癸未朔乙未皇太子草壁ノ皇子ノ尊薨 柿本朝臣人麻呂 日並皇子 天武帝の皇子前ニ注ス草壁の皇子是也日本紀卅ニ在 あめつちのはしめのときし久かたのあまのかはらにやをよろつちよろつかみのかみあつめあつめいましてかみはかりはかりしときにあまてらすひなめのみこと 一云さしのほるひなめのみこと あまつをはしろしめさんとあしはらのみつほのくにをあめつちのよりあひかきりしらしめす神のみことゝあまくものやへかきわけて 一云あまくものやへくもわけて かみくたりいましつかへしたかてらすひのわかみこはあすかのきよめし宮にかみのまにふとしきましてすめろきのしきますくにとあまのはらいはとをひらきかんあかりあかりいましぬ 一云神のほりいましにしかは わかきみのみこのみことのあめのしたしらしめしせははるはなのかしこからんともち月のみちはしけんとあめのした 一云をしくにの よもの人のおほ舟のおもひたのみてあまつ水あふきてまつにいかさまにおほしめしてかゆへもなくまゆみのをかに宮はしらふとしきましてみありかをたかしりましてあさことにみこととはせすひつきのあまたになりぬそのゆへにみこのみやひとゆくゑしらすも 一云さすたけのみこのみや人ゆくゑいさにて [天地之初時久堅之天河原尓八百萬千萬神之神集集座而神分分之時尓天照日女之命 指上日女之命 天乎婆所知食登葦原乃水穂之國乎天地之依相之極所知行神之命等天雲之八重掻別而 天雲之重雲別而 神下座奉之高照(たかくてる)日之皇子波飛鳥之浄之宮尓神随太布座而天皇之敷座國等天原石門乎開神上上座奴 神登座尓之可婆 吾王皇子之命天下所知食世者春花之貴在等望月乃満波之計武跡天下 食國 四方之人乃大船之思憑而天水仰而待尓何方尓御念食可由縁母無真弓乃岡尓宮柱太布座御在香乎高知座而明言尓御言不御問日月之數多成塗其故皇子之宮人行方不知毛 刺竹之皇子宮人歸邊不知尓為] あめつちのはしめ 天地分れての初め諸神はからひて儲君となし申せしと也立太子の貴き事をいはんとて皇孫のためしにいふにや中臣祓に曰/八百萬神等乎[ヤヲヨロツノカミタチヲ]神集仁集賜比[カミアツメニアツメタマヒ]神議仁議賜天[カミハカリニハカリタマヒテ]吾皇孫乃尊乎波[ワカスメミマノミコトヲハ]豊葦原[トヨアシハラ]乃/水穂[ミツホ]乃/國乎[クニヲ]安國/登[ト]平介久[タイラケク]所知食止[シロシメセト]事依[コトヨサシ]奉幾 あまてらすひなめの 日並のみこを云也 あまつをは 天の事をしろしめせと神勅の事也 あしはらのみつほのくに 見安云我国の惣名也 あめつちのよりあひの 天地和合してある限也 神のみこと 是も日並皇子を貴みいふ詞也 あま雲のやへかきわけて 前に天つをはしろし召むといひし首尾也巳ニ春宮ニ立て天下に王たるへけれは神も天降り仕[ツカヘ]しといふ也是も中臣祓ニ天乃八重雲乎/伊豆[イツ]乃/千別[チワキ]仁千別天天降里/依之[ヨサシ]奉幾とある詞を用ゆ ひのわかみこ 日並皇子也 あすかのきよめしみや 飛鳥浄御原宮也すなはち日並の父帝天武の都也 神のまに 天つをはしろしめさんと神の計るまゝに也 いはとを開 神に比して云也 かんあかり 日並の殂落[ソラク]を云尚書ニ帝乃殂落ス注殂ハ是魂ノ之舛上落ハ是魄ノ降下也又云魂ハ為v神也 わがきみのみこのみことの 是より日並の宮人等の頼み奉る心を云也かく儲君のほとに隠れ給はて天下を知[シロ]しめさばと也 春花のかしこからん 春花の香とうけて也望月のはみちはしけんといはんとて也此皇子の天下をしろしめさはいともかしこき君ならん世に満足はせんと四方の国人思ひ頼み仰[アフ]き待しと也大船は頼もしき物なれは思ひたのみといはん枕詞也あまつ水はあふきて待といはん枕詞也旱に待ツv雨ヲ心也 まゆみのをかに宮柱 八雲抄まゆみの岡大和云々愚案真弓の岡は日並のみこの廟ある所なるへし奧に舎人等慟傷して作れる哥にもよそにみしまゆみのをかも君ませはとこつみかとゝとのゐするかもとよめり廟にとのゐする心也宮柱ふとしきましてはみこの御廟也こゝにいかさまにおほしめしてかといへるはおもひのほかにかくれさせ給ふ事をいはんとてなり此集に猶有 みありか みあらか也りとらと五音通日本紀ニ御殿と書てミアラカと讀 たかしりまして 中臣祓に千木たかしりてとあるたくひにて御殿を領し知給ふ心也 明言[アサコト]にとは毎朝也皇子生てましまさは朝ことに御ありさまを問奉りなんをさやうの儀もなくて日月ふると也 そのゆへにみこのみや人 しはしこそ廟所にまうてゝつかへまつれ御事とはする事もなく日月かさなれはせんかたなく宮人とものをのかちりちりなりゆくと也此長哥あめつちの初めし時しといふより宣命の躰をうつし中臣祓の詞を用ひてたくみに哀ふかし心をこめて吟味すへし一云さすたけのみこのとはさゝたけの大宮人なといふにおなしさすとさゝと同別ニ注
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | 日並皇子尊殯宮之時柿本人磨作歌一首并短歌 此皇子薨じ給ふ年月等は後の注にあり、持統紀云、天命開別天皇元年、生草壁(ノ)皇子(ノ)尊於大津宮、かゝれば薨じ給ふ時二十八歳なり、草壁(ノ)皇子又の御名は今の如し、天武紀云、十年春二月庚子朔甲子、云云、是日立草壁(ノ)皇子(ノ)尊爲皇太子、因(テ)以令攝、萬機、續日本紀第一云、日並知(ノ)皇子(ノ)尊者、寶字三年有陟進崇尊號、稱岡宮御宇天皇也、又云、慶雲四年夏四月庚辰、以日並知(ノ)皇子(ノ)命薨日、始入國忌、此端作上の注に引つゞけたるは後人の誤なり、柿本の下に朝臣を脱せり、目録には尸あり、 天地之初時之久堅之天河原爾八百萬千萬神之神集集座而神分分之時爾天照日女之命 【一云指上日女之命】 [アメツチノハシメノトキシヒサカタノアマノカハラニヤホヨロツチヨロツカミノカミアツメアツメイマシテカムハカリハカリシトキニアマテラスヒナメノミコト] 天乎波所知食登葦原乃水穗之國乎天地之依相之極所知行神之命等天雲之八重掻別而 【一云天雲之八重雲別而】 [アマツヲハシロシメサムトアシハラノミツホノクニヲアメツチノヨリアヒノカキリシラシメスカミノミコトトアマクモノヤヘカキワケテ] 神下座奉之淨之宮爾神隨太布座而天皇之敷座國等天原石門乎開神上上座奴 【一云神登坐尓之可婆】 [カミクタリイマシツカヘシタカテラスヒノワカミコハアスカノキヨメシミヤニカミノマニフトシキマシテスメロキノシキマスクニトアマノハライハトヲヒラキカムアカリアカリイマシヌ] 吾王皇子之命乃天下所知食世者春花之貴在等望月乃滿波之計武跡天下 【一云食國】 [ワカキミノミコノミコトノアメノシタシラシメシセハハルハナノカシコカラムトモチツキノミチハシケムトアメノシタ] 四方之人乃大舩之思憑而天水仰而待爾何方爾御念食可由縁母無眞弓乃崗爾宮柱太布座御在香乎高知座而明言爾御言不御問日日月之數多成塗其故皇子之宮人行方不知毛 【一云刺竹之皇子宮人歸邊不知爾爲】 [ヨモノヒトノオホフネノオモヒタノミテアマツミツアフキテマツニイカサマニオホシメシテカユヱモナキマユミノヲカニミヤハシラフトシキマシテミアリカヲタカシリマシテアサコトニミコトトハセスヒツキノアマタニナリヌソコユヱニミコノミヤヒトユクヘシラスモ] 所知食登、【官本亦云、シラシメサムト、】 依相之極、【官本亦云、ヨリアヒシキハミ、】 所知行、【官本亦云、シロシメス、】 飛鳥之、【官本亦云、トフトリノ、】 天皇之、【官本亦云、スヘラキノ、】 神集集座而は、今按、神代紀に依て、カムツドヘニツドヘイマシテと和すべし、神分分之時爾もカムハカリニハカリシトキニとよむべし、舊事紀云、于時八百萬神、於天(ノ)八湍[ヤセノ]河(ノ)々原神會集而[カムツトヘニツトヘテ]議計[ハカラフ]其(ノ)可奉祈謝[コヒノミ]之/方[サマ]矣、今按、分の字、字書に別也判也とありて議也といはざれば、カムワカチニワカチシ時ニと點を改むべきか、但分別して議定すれば、任ては陶じ心か、アマテラスヒナメノミコトは、御名の日の字によりて初より後の神のみことと云までは日神に比し奉て申さるゝなり、御名を申ことは臣としては有まじき事なるを、日本紀には草壁(ノ)皇子とのみあれば、日並は御徳をほめ申謚にてやかくはよまれたるか、アマツヲバ、シロシメサントとは、神代紀云、伊弉諾[イザナギノ]尊/勅任[コトヨザシテ]三子曰、天照太神者、可以/御[シラス]高天之原也云云、これを借て用たれども、心は只天下なり、葦原ノミヅホノ國は別に注す、天地ノヨリアヒノカギリは、極はキハミとよむべし、天は地をつゝめば依相なり、神ノ命トとは此所に議り定給てと意を入てよむべし、天雲ノ八重掻別テ神下とは、皇子の生れ出させ給へるを、天照大神の皇孫を天降し奉らせ給へるに譬るなり、神代紀云、皇孫乃離天(ノ)磐座[イハクラヲ]、且排分天(ノ)八重雲稜威之道別[イツノチワケニ]道別而天降件於日向襲之/高千穂峯[タカチホタケニ]矣似合たる事を借て用られたれば、さきと今、事替りたれども意つゞけり、高テラス日ノ皇子は此亦日並の御事なり、飛鳥之、官本/更[マタノ]點にトブトリノと和したるは、ちはやぶるは、神の枕詞なる故意を得て賀茂の社などもつゞくるやうに、明日香の淨御原なれば此も苦かるべからねど、飛鳥をアスカとよむ上は今の點に隨ふべし、キヨメシ宮、此點は誤れり、キヨミノ宮と改むべし、御の字は、めでたき字なれば、てにをはに假て二字に足すか、淨見原ともかけり、今彼舊地の俗には淨御[キヨミ]の二字を音に呼て申とかや、天武天皇は申すに及ばず、持統天皇も此時はいまだ淨御宮にましましければ、我なくても世は安らかに治りぬべしと思召て再天へ歸らせ給ふと申しなす心なり、一本の異を注するに、カムノボリイマシニシカバとは、是にて末の收拾慥ならぬやうなれど、先是に我思ふやうと意ををへて、いかさまに思召てかを思召てやらんとなしてみれば、日月のあまたになりぬと束ねたる所までのつゞき、能意得らるゝなり、本文のまゝにてもいかさまに思召てと意得る事是に同じ、春花ノ貴在トとは日本紀に貴盛をタノシと訓じたれば、彼に依てタノシカラントと讀べきか、望月ノ滿ハシケムト、此をば第十三に高市(ノ)皇子の薨じ給へるを慟み奉る歌に、十五月之[モチツキノ]、多田波思家武登[タヽハシケント]、とよめるに合て、此をもタヾハシケムトとよむべきか、鹽時の湛へ、水の湛と云も、滿て動かぬをいへば、花の盛を見るやうにたのしく、十五夜の滿たゝへたるを見るごとく望足なむと思ふなり、日本紀に偉の字をタヽハシと讀たれど、それとは意かはれり、大舟ノ思タノミテとは此詞後もあまたあり、大舟はいかにも乘てたのもしき物なればなり、天ツ水仰テ待ニとは雨の事なり、景行紀云、山神之興雲/零[フラシム]水[アメヲ]日でりする時空を仰雲を望て皇子の天つ日繼知しめさむ事を天下の人民/何時[イツ]かと待つなり、文選相如難蜀(ノ)父老(ヲ)檄云、擧踵思慕(スルコト)若枯旱之望雨、所以モナキは、今按由縁は引合てヨシと點じ改むべし、下に舍人が歌の中にも、よしもなきさたのをかべとよめり、おはすべきよしもなき所へおはしますらんなり、マユミノ岡は延喜式諸陵式云、眞弓丘陵、【岡宮御宇天皇、在大和國高市郡、兆域東西二町、南北二町、陵戸六畑、】或者云、味橿岳の西一里許に越村あり、越村の南に眞口の村ありといへり、皇極紀云、二年九月丁巳朔丁亥、吉備嶋皇祖母命薨、乙末葬皇祖母命于檀弓崗、これも同所なり、續日本紀第二十六云、天平神護元年十月己末朔辛未、行幸紀伊國、云云、癸酉過檀山陵(ヲ)詔陪從(ノ)百官(ニ)悉令下馬、儀衛卷其旗幟、御在香[ミアリカ]は殿なり、古語拾遺云、古語正殿謂之/麁香[アラカ]、然ればミアラカヲと讀べきか、ありか、かくれが、すみかなど云を思ひ合すれば、かは所の心ある詞にや、アサゴトニ、ミコトトハセズは、あさは日の意にて日毎になり、とはせずはいはずと云古語なり、崇神紀に不言をマコトトハズと點ぜり、ことゝはぬ木すらなど下によめるも物いはぬ木なり、日毎に舍人等が、殯宮へ祇候すれども、昔に替て物をも仰られぬなり、ユクヘシラズモは、下にもゆくへをしらずとねりはまどふと有ごとく、假令ば、道ゆく人のしるべを失へるごとく迷ふてゆくへをしらぬなり、人丸の舍人にてよまれたるにはあらず、舍人は殊に朝夕馴つかふまつる故に、下にもかやうの事には多く舍人の歌をよめり、注のサス竹は、君とも宮とも云に置辭なり、別に注す、ヨルベシラニスはよるべしらでなり、しらずをしらにといふは古語なり、日本紀の歌にも續日本紀の宣命の詞にもあり、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 萬葉集 童子間 |
日並皇子尊殯宮之時柿本人麻呂作歌一首并短歌 天地之初時之久堅之天河原爾八百萬千萬神之神集集座而神分分之時爾天照日女之命〔一云指上日女之命〕天乎波所知食登葦原乃水穗之國乎天地之依相之極所知行神之命等天雲之八重掻別而〔一云天雲之八重雲別而〕神下座奉之高照日之皇子波飛鳥之淨之宮爾神隨太布座而天皇之敷座國等天原石門乎開神上上座奴〔一云神登座爾之可婆〕吾王皇之子命乃天下所知食世者春花之貴在等望月乃滿波之計武跡天下〔一云食國】四方之人乃大船之思憑而天水仰而待爾何方爾御念食可由縁母無眞弓乃崗爾宮柱太布座御在香乎高知座而明言爾御言不御間日月之數多成塗其故皇子之宮人行方不知毛〔一云刺竹之皇子宮人歸邊不知爾爲〕 童子問 此歌訓のあやまり有てか、義やすくきゝ得がたし。先、天地之初時之の六字、先訓にはあめつちのはじめしときしといへり。賢訓もおなじきや。 答 あめつちのはじまるときしとよむべし。 問 神集集座而の五字、先訓はかみあつめあつめいましてといへり。賢訓もおなじきや。 答 かみつどへつどへまさせてとよむべし。 問 神分分之時の五字、先訓かみはかりはかりしときのといへり。賢訓もおなじきや。 答 かみくまりくまりしときにとよむべし。 問 天照日女之命、此六字先訓はあまてらすひなめのみことゝいへり。いかゞ。 答 あまてらすひるめのみことゝよむべし。 問 一云指上日女之命、此六字をさしのぼるひなめのみことゝ先訓にいへり。いかゞ。 答 さしのぼるひるめのみことゝよむべし。 問 先訓の意は、天照日女之命は日並皇子尊のことゝきこゆる故に、あまてらす日なめのみことゝある天照の二字心得がたく、もし日といはん爲ばかりの冠辭に天照とあるやとうたがへり。今賢訓にあまてらすひるめのみこととあれば、此神號よみやすし。日女の二字をひなめとはよみがたし。かつ神分の二字もかみくまりとはよみやすく、かみはかりとはよみがたけれども、神集に集神議に議り給へるといふ古語は、神代の紀にもみえたる故に、さはよむことゝのみおもへるは、ならふて察せぬなるべし。しかれどもかみくまりひるめのみことゝよむ義を委曲に示し教へ給へ。 答 此歌は、人麻呂古書に據てよめるなるべし。日本紀古事記にはみえざれども、今の世に傳らざる神代の古事の書あまた有とみえたる事は、古記古語に明らか也。もし此歌の古事古記にみえずとても、日本紀の神代の古記にしたがひてかく詠めるとみても、其意たがふべからず。先天地之初時之とは、日月もいまだ位定り給はぬ時をいふべし。久堅之三字は天の冠辭也。天河原爾八百万千万神の神集は、古記の義釋に及ばず明か也。集座而、これをつどへまさせてとよむ義は、八百万の神みづから集ふにあらず、つどへまさする神有とみるべし。その神は天神也。その天神は伊弉諾册の二神に勅し給ひし天神也。神分分之時、これをかみくまりまりしときにといふ義は、日神月神蛭兒素盞嗚尊すべて八百万の神に、おのおのその所その物をつかさどりしるべきことをよさし給ひて、万神をくだしたまひしときに、天照日女尊には高天原をしらしめたまふよしをのべたる詞とみゆる也。天照の二也を一には指上とあれども、天照の二字まさるべし。 問 天乎波、此三字先訓にはあまつをはといへり。しかるべきや。 答 しかるべからす。いかにとなれば、天の字をあまつとよむ事その例すくなからねども、それは皆下にいふ言につゞくる時助語につといひて、天神をあまつかみ、天社をあまつやしろといふたぐひ也。只天のみをいふ時あまつと用ゐたる例なし。此一句は天をばといふ古語なれば、あめをばといふは害なし。しかれどもあめをばといへば四言にて、古風例あれども、柿本人麻呂は古語の四言をもはじめて五言に詠めることあれば、この天乎波の三字も、五言の一句に用ゐられたるなるべし。これを五言によまんに、みそらをばとよむべき歟。 問 柿本人麻呂古語の四言を五言によめるとは、何を證據としてさ云へるや。 答 此集卷第一に載たる人麻呂の歌に、そらにみつやまとをおきてといふ句あり。是を證としてはいふ也。古語はそらみつやまとの國とあるを、人麻呂の歌にはじめてそらにみつと、にの助言を加へて五言によめり。此例をもちてあめをばといへば四言なれば、みそらをばと五言に用ゐられたることゝは爲也。 問 五言の證は承侍る。天の字をそらと訓る古證もありや。 答 右の人麻呂の歌に證あり。そらにみつといふ句に天爾滿と三字をかける、是を證例とすべき也。 問 所知食登、此四字を先訓にはしらしめさんといへり。しかるべきや。 答 しろしめされとよむべし。 問 登と有てにをは心得がたし。いかなる義ぞや。 答 此登は上にかへりて心得るてにをはの登也。天照日女尊は天をしろしめされと、神分りしりたまへる由來を述られたる詞也。これまでは天照大神の天位をかけ給ふよしを述て、これより下は日女神の子孫として、此葦原國の君として天くだし給ふことを云へりとみるべし。 問 天地之依相之極、此七字を先訓にはあめつちのよりあひのかぎりといへり。或説に極ははて也、地のはては天とひとつによりあふ心也といへり。可然訓義にや。 答 依相之極四字、異訓有べき歟。先訓先義の説にても然るべし。 問 神之命等此四字、先訓にかみのみことゝいへり。可然や。 答 等の字はたちと訓ずへし。とゝのみ訓ては、天照日女命より天武天皇にうつることわり、ことたらぬに似たり。文字も上に登の字をかき、こゝに等の字を書かへられたるも意有べければ、おなじくとゝはよむべからず。神のみことたちとよみて、瓊々杵尊より天武天皇までの日神の子孫の神等を、此一句にこめて詠るとみるべし。 問 神下座奉之五字、先訓にかみくだりいましつかへしといへり。可然や。 答 これは先訓のまゝにてもしかるべし。しかれども奉之の二字はまつりとよむ方まさるべき歟。 問 高照日之皇子波、此七字をたかてらすひのわがみこはと先訓にいへり。可然や。 答 皇子の二字をわがみこと訓がたし。たゞみことよむべし。ひのみこ古語なり。それをわがの二言をそへては古語にならず。わがといふ義も證もなし。 問 飛鳥之淨之宮爾、此七字をあすかのゝきよめしみやにと先訓にいへり。 答 先訓しかるべからず。飛鳥之の三字をあすかのゝとはよみがたし。あすかのと四言によむべし。しかれどもこれも五言によまんには、之の字をなるとはよむべし。あすかなる意に飛鳥之とかける歟。此之の字一首にかぎらず、此集にのとのみよめば四言になり、なるとよめば五言になる句あまたあり。此歌の下にもあり。なるといふ詞にあるといふ三言を約したる古語にて、文字を用ゐば之の字相當ればなり。たとへば駿河之富士といふをするがなるふじといひて、するがにあるふじといふ義、あすかなるきよみが原もあすかにある淨見が原といふ義のたぐひをしるべし。且淨之宮をきよめし宮といふべからず。飛鳥も地名淨見も地名なれば、あすかなるきよみのみやにとよむべし。 問 神隨の二字をかみのまにと先訓にいへり。可然や。 答 しかるべからず。かみながらとよむべし。古語也。 問 太布座而此四字、ふとしきましてと先訓にいへり。可然や。 答 是は先訓もしかるべし。しかれども而の字はいともと訓まほしき也。しからばふとしきませどもと反語の詞によめば、義やすき也。 問 高照日之皇子と下にいへる天皇とは、おなじ帝を指にや。 答 ことなり。日之皇子は天武帝を稱、下の天皇は持統帝を稱なるべし。 問 神上々座奴此五字を、かみあがりあがりいましぬと先訓にあり。可然や。 答 しかるべし。天武天皇の崩御を神あがりといへる也。此神あがりし給ふは、持統帝に御世を傳へたまはんとてしかるよしをのべて、日並皇子の皇太子となり給ひ、終に天皇となり給ひ、天下をしろしめすべきことをいへり。 問 春花之貴在等此六字、先訓にはるはなのかしこからんといへり。しかるべしや。此句の意はいかなる義にや。 答 先訓しかるべし。かしこからんといはん爲の冠句に春花のとはかけり。香といはん冠なり。かしこからんとは、帝徳のすぐれてたつとからんことをかねておもふよし也。 問 望月乃滿波之計武跡此九字、先訓もちづきのみちはしけんとゝいへり。訓もしかるや。義はいかなるや。 答 先訓しかるべし。義は帝徳の天の下に滿をよばんと云義なるべし。 問 天下を一云食國とあるは、いづれかまさるべきや。 答 義おなじかるべし。しかれども上に天下の句あればこゝは食國のかたまさるべき歟。食國の二字をしくにと訓べし。 問 四方之人乃此五宇、先訓よものひとのといへり。六言なれば、これをも七言によまゝくほしき也。いかが。 答 七言によむべし。上の飛鳥之の三字をあすかなるとよむべしといひし所に、下の句にも之の字をなるとよむべき所有といひしは、此句の之の字なり。よもなるひとのとよめば七言になりて、之の字なるとよみて、よもにあるひとのといふ句義也。 問 大船之思憑而此六字を、先訓におほふねの思ひたのみてといへり。或説に大船はのる心のたのもしげ成ものなれば、かく云なりといへり。此訓も義もしかるべきことにや。 答 しかるべからず。たのむといはん冠辭にも、おもひといはん冠辭にも、大船といふべきことわりなし。思憑而の三字異訓有べし。いまだ的當とおもふ異訓の僻案なし。思の字は此集にさまざまに用ゐたれば、もしうらと用ゐたる歟。しからばうらたのみしてといふ句歟、うらにかゝりてなどゝよむ歟。憑の字は日本紀にもかゝると用ゐたる古訓おほければ、よるとかかゝるとかよむには、大船の冠辭もかなふべし。おもひたのむといふ冠辭には紆遠なるべし。猶後案に一決すべし。しばらく缺てさしおくべし。 問 天水仰而待爾此六字、先訓あまつみづあふぎてまつるといへり。或説に、義は天水は雨也。ひでりに雨のくだるを待心なりといへり。訓も義も可然歟。 答 天水の二字異訓あるべき歟。先訓にしたがひもすべし。皆これ日並尊の天下をしろしめさば、帝徳貴くみちをよぶべきことを萬民おもひをかけて、めぐみを天をあふぐごとくにあふぎのぞみてまちしに、いかにおぼしめしてか、天下をしろしめさずして、はやく薨給へることを下に述たり。 問 由縁母無、此四字をゆえもなくと先訓にいへり。可然や。或説にはよしもなくとよめり。可不いかゞ。 答 由縁を故と云義なればゆゑとかく也。縁の字は延のかななればかな違へば、これは義訓有べし。僻案にはよしもなくなどゝよむべき歟、はしもなくともよむべけれども、それは一字にても有べきを、由縁の二字あれば、よしもなくにても有べからず 問 一云刺竹之皇子宮人と有。皇子の冠辭に刺竹といへる義いかなることぞや。 答 此冠辭其義まちまちにして、いまだ一定正義を得ず。聖徳太子の御歌にもさゝ竹の君はやなぎと詠給ひ、さゝ竹の大宮人ともありて、天皇或は皇子或大宮人など、皆朝廷帝徳を稱するに竹を用ゐたる古語歟。しからずば箕といふものは竹を以てさしくみたる物故に、箕といふ冠辭にさゝ竹さす竹などゝいへる歟。よりてきみといふにもさゝ竹といひ、皇子といふにも刺竹といひ、宮といふにも刺竹といふにや。上古の冠辭の俗義によれば、箕の冠辭といはん古風にかなふべし。 問 歸邊不知爾爲、此六字を先訓ゆくへいさにしてといへり、しかるべきや。 答 義はさるべけれども、句例みえねば異訓有べし。不知爾の三字いかにと義訓すべき歟。しからば六字をゆくへいかなるとよむべくおぼゆる也。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 童蒙抄 | 日並皇子尊殯宮之時柿本人麻呂作歌一首並短歌 [ひなめしのみこの尊のもがりの宮のとき、かきのもとのひとまろつくるうたひとくさならびにみじかうた] 日並皇子尊 草壁皇子の事也。第一卷に注せり。持統紀云三年云々、夏四月云々、乙未皇太子草壁皇子尊薨云々。もがりのみやの事は、紀に不見故月日難考也 天地之初時之久竪之天河原爾八百萬干萬神之神集集座而神分分之時爾天照日女之命【一云指上日女之命】天乎波所知食登葦原乃水穂之國乎天地之依相之極所知行神之命等天雲之八重掻別而【一云天雲之八重雲別而】神下座奉之高照日之皇子波飛鳥之淨之宮爾神隨太布座而天皇之敷座國等天原石門乎開神上上座奴【一云神登座爾之可婆】吾王皇子之命乃天下所知食世者春花之貴在等望月乃滿波之計武等天下【一云食國】四方之人乃大船之思憑而天水仰而待爾何方爾御念食可由縁母無眞弓乃崗爾宮柱太布座御座香乎高知座而明言爾御言不御問日月之數多成塗其故皇子之宮人行方不知毛【一云刺竹之皇子宮人歸邊不知爾爲】 あめつちの、はじめのときの、ひさかたの、あまのかはらに、やほよろづ、ちよろづかみの、かみづとひ、つどひいまして、かむくばり、くばりしときに、あまてらす、ひなめのみこと【一云さしあぐるひるめのみこと】あまつをば、しろしめさむと、あしはらの、みづほのくにを、あめつちの、よりあひしかぎり、しろしめす、かみのみことゝ、あまぐもの、やへかきわけて【一云あまぐものやへくもわけて】かみくだり、いましつかへし、たかてらす、ひのみこは、あすかのきよめしみやに、かみながら、ふとしきまして、すめろぎの、しきますくにと、あまのはら、いはとをひらき、かみあがり、あがりいましぬ【一云かむのぼりいましにしかば】わがきみの、みこのみことの、あめのした、しろしめしせば、はるはなの、かしこからむと、もちづきの、みちはしけむと、あめのした【一云をしくにの】よもなるひとの、おほぶねの、おもひたのみて、あまつみづ、あふぎてまつに、いかさまに、おぼしめしてか、ゆゑもなき、まゆみのをかに、みやばしら、ふとしきまして、みあらかを、たかしりまして、あさごとに、みことゝはせず、よるひるの、あまたになりぬ、そのゆゑに、みこのみやびと、ゆくへしらずも【一云さすたけのみこのみやびとゆくへしらざりし】 初時之 天地開闢ありしはいつともしれず。そのはじめのときは遠くひさしき事なれば、ひさかたの天といはんとての序に、如此よみ出したるもの也 久堅之 これは古來より説々多し。しかれどもみな理屈の説にて難信用義也。先づ久かたとはあめあまといはん爲の冠辭にて、それよりうけて天象の物に直ちに久かたの月、ひかりなどともよみ來れり。あめの冠辭にひさかたとよむ義は、天はとこしなへにして天地ひらけわかれしとき、いつをはじめともしられず。初めより遠く久しきものなれば、久しき方といふ義に、あめ空などの冠辭にいへるものなり。堅といふ字は借訓にて字義の意にはあらず。堅のとつゞく義はならぬ也 天河原爾 上天の義をさして云。神代卷古語拾遺等に、天安川などしるされたるも同事也 八百萬干萬 數かぎりもなく、あまたの神たちをさしていふたる義なり 神集集座 神代下卷云、故高皇産靈尊召集八十諸神云々。延喜式祝詞部、高天原仁神集仁集賜比神議仁議云々 神分分之時爾 かんくばり、くばりし時にとよむべし。此意は天地山川萬物をつかさどりしろしめす神々を、それそれそこそこに八百萬千萬の神たちあつまりて、はかり從ひ給ひしと云義也。神代の卷等にては、伊弉二神のみことのりにては御子神々をそれそれにことよさゝしめ給ふとあるを、此歌にてもろもろもろの神たち寄集りてはかり給ふと也。神代上卷云、是共生日神號大日〇貴中略當早送于天而授以天上之事云々。此神くばりの事をいふたる也 天照日女之命 天照大神の義を云也。神代上卷、一書云、天照大日〓尊云々。しかれば日女の二字ひるめとよむべき也 一云指上日女之命 一本にはさしあぐるひるめの命とありしを、古注者書入れたる也。神代卷に天照大神を天柱をもてあめに送上と云ことあるによりて、さしあぐるひるめの命ともよめる歟 天乎波 古本印本にあまつをばとよめり。津の字なくても、訓義によりて例あれば苦しからず。みそらをばとよみても同事なれば、聞きよきかたにしたがふべし 所知食登 延喜式大殿祭祝詞云、 所知食 止、古語云、志呂志女須。 是迄天の事は天照大神の治めしろしめすとの事なり 葦原乃水穂之國乎 我國を稱讃したる國號なり。神代卷に委しき傳あることなれば、細注を憚る。先は我國の佳名と心得て、廣く及ぼしては一天地國土の義ともしるべし。日本紀且延喜式の祝詞の文等に多き言葉也 天地之依相之極 あめつちのよりあひしきはみとは、一天地國土のあらんはてかぎりまでと云義也。延喜式祝詞の文にあまたあり 所知行 國土の極まるはてまでをしろしめすとの事也 神之命等 天地國土の限をしろしめすことは、中々凡人の徳にてはならぬ義、神明の御徳を具へたまふて、をさめしろしめすといふ義、もつとも上天は天照大神しろしめし、國土のかぎりは瓊々杵の尊より已來、御代々の天皇をさして神の命とはよめる也 天雲之八重掻別而 幾重ものあまぐもゝかきわけて、はるかに遠き天より降臨ましませし事を述べたる也。神代卷且宣命祝詞等の詞に多き詞也 天下座奉之 天孫降臨の義を云て、天武帝迄の事をうけていひたるもの也。瓊々杵の命より、天武天皇迄の義を云ひたる事と見るべし 高照日之皇子 至つて尊稱して天子を直ちに日の皇子にして奉見べき事也。此高照は天武の御事とも見え、また日並皇子の御事とも見ゆる也。いづれに見ても同事の意なるべし 神隨 かみなるからにと云の義也。第一卷にも注せり 太布座而 第一卷に注せり。天子の天下を治め給ふ事の、大なる御徳の正しく確かなる事になぞらへて、ほめ奉りたる詞也。祝詞の文等に多き詞也 天皇之敷座國等 御代々の日嗣の皇子のしきをさめ給ふ國と、太布座而と上へかへりて見る意也。日並皇子の天皇となり給ふて、敷をさめ給ふ國なるにと云の意にも相通ふ也 天原石門乎開神上 是は天皇はもし日嗣のみ子にもあれ、かくれましましたる義を云ひたること也。天照大神のみたまの御座所は、高天原の岩屋戸也。そのみたまをうけつぎ給ふ日嗣の御子なれば、その本の御座所に歸り給ふ故、石門を開きとなり。上天歸天といふて上一人より下萬民までも、たましゐのかたちを離るれば、本の上天に歸る理、この歌にてもさとりしるべきこと也。此歌一首をもつて我國神道の教を解かんにはいかやうにもいひのべらるべけれども、歌は歌の道一筋の事に見るべし。歌の道をもて天下の治亂の事をとき、教へのことに解きなすは、かへつて道の妨げあるもの也 上 座奴 神あがりましましぬと、是迄にて天武帝の崩御の義をのべたるもの也。皇子のかくれたまふ事を述べたる義とも見ゆる也 一云神登座爾之可婆 一説には如v此あると也。此一説の趣をもつてみれば、天武帝の神あがり給ひたる事をいふ句にきこゆる也 吾王皇子之命乃 日並尊をさして也 貴在等 花の香とうけたる意也。かしこからんと云は、おそるゝ義をもいへども、こゝは花のうるはしくよからんといふの意にて、花の香とうけんためにかしこからんとはいふたるもの也 望月乃滿波之計武跡 もちづきは十五夜の月を云。その月のくもりなきごとく、あきらけき道をしきほどこされんと、天下の人のおもひをかけしといふ義をよそへてよめる也 天下 一云食國 意は同じき也。本文にてはあめのしたとよみ、一云の義にてはをしくにのと、のゝ字を添へてよむべき也 四方之人乃 是を古本印本共に、よもの人のと一字不足によめり。四言一句の例もあまたあれば難もなけれど、此集中に之の字をなるとよめばよく義通じ、又よまねばならぬ歌もありて、之の字はなるとよむべき也。にあるといふの義にて、此之の字を書たると見えたり。駿河なる、信濃なるなども、信濃にある、駿河にあるといふ義を約してなるとは云たるもの也。此處もよもなる人のとよめば、能く句意調ふ也 大 船之思憑而 此詞集中にあまたあり。古本印本等にも、おもひたのみてとよめり。大船はたのみあるものなる故にと云意にて、かくよめると云義なれども、たのみと云詞、船に縁なき詞なれば、何とも解しがたき也。日本紀神代上卷に顯神明之憑談、此六字をかんがゝりとよめる字訓あれば、憑の字かけてとか、かゝりてとかよむべき也。よつておもひをかけてとよむ也。船はかゝりかゝるといふことあれば也。又はおもひをよせてとよむ義もあらんか。依也託也といふ字義あれば、よせてもたのみと云義とおなじ意にて、あめの下の人おもひよりて、たのみにしてと云義也 天水 あまつみづとつと云言葉をそへてよむべし。天水とは、雨の事を云たるもの也 仰而待爾 旱魃に雨を乞ふ如くに、皇子の天下をしろしめさんときをまちしにと也。又下の眞弓の岡より歸らせ給ふを、待つなど云の意をもこめたるか 由縁母無 何のよしもなきまゆみのをかの、もがりのみやにとゞまりましますことを云也 宮柱太布座 皇子のもがりのみや故、當然稱美してよめる也 御在香乎 御座所の事也。御殿をさしてみありかと云也。古語拾遺延喜式祝詞の文に、御殿の古語を、みあらかといふ事見えたり 明言爾 朝毎といふ意也。言の字もしくは暮の字の誤り歟。夜はいね給ふなれば、仰ごとあるはあさことゝもいはるべけれど暮の字なれば、明くれにと云ていよいよ義やすき也 御言不御問 みことゝはせずとは何事をものたまはずと也。不御問の字みとはずともよむべけれど、句例なければ天子の御事には御の字を添へ用ゐる事常のことなれば、とはせずとよむ也 日月之數 ひるよるのと、義訓に句を調へてよむべし 數多成塗 あまたになりぬとは、日並皇子かくれまして、もがりのみやへいでませしよりかへらせ給はず、仰事とてもなくあまたの月日のへぬればと也 其故 月日のあまたふれども、みことも問はせずして、かくれさせ給ふ故、皇子に奉仕の宮人どもみな離散すると也 行方不知毛 日並皇子尊うせ給へば、奉仕の宮人ども、みなちりぢりにわかれさりて、行へもしられずなり行事の、あはれにあさましき事をよめる也 此歌の意は、天つちひらけわかれて、たかく遠くひろき天の河原に、八百萬の神たちあつまりまして、それぞれの神の御徳にしたがひて、つかさどり給ふ事を、ことよさし給ふて、そこそこにくばり給ふに、天照大神はみそらのことをしらしめ給へとの、神はかりごと定まりて、一天地國土の君とならしめ給ふ事をはじめて、其御徳を今上皇帝までも、うけつぎゆづらせ給ふ事の、萬國にすぐれて尊くもかしこき我本邦の神系たゞならぬ趣をいひのべ、一天四海の夷八蕃までも、我神國の神の命の御徳をもて、惠み治めさせ給ふ儀と尊稱し奉りて、神代のふみにしるされたる天孫降臨ましましてより、天武天皇まで神系たえず、神くだりいまし給ふ事をいひつゞけて、御代々のすめらぎは、すなはち御大祖の日の神のみ子と、尊みかしこみ奉る理りを示して、高照日の皇子とよみ給ふ。その御徳のことなる事は、神あがり給ふも日の神のみもとに歸りをさまり給ふといふ義を、石門をひらき、神上り上りいましぬとよみきりて、さて日並皇子の御存命ましまして、日嗣の御徳をうけつがせ給ひて、あめの下を治め給はゞ、春の花も香はしく、秋の月もさやかにあきらけき御代と、四方の國人もたのみをかけて待ち奉りしに、よしもなくかくれまして、眞弓の宮に移り給ひしより、歸らせ給ふこともなく、御言だにのたまひ仰せられず、あまたの月日のへぬれば、つかへまつりし宮人のみなちりぢりにわかれ行きて、いとあさましくあはれなる時のありさまを、かくつまびらかによめる也。何の事もなき事をかやうに連續分明によみつらねし事、まことに人丸の風骨ならではなりがたき事也 一云刺竹之皇子云々 例の古注者の一説也。古本には小字にて下に割書せり。尤可然也。さす竹の事説々有て、竹は君の徳に比し、天子皇子をさしていふたるものと云傳へたれど、すべて上代の冠辭さやうの理をつめて、重き事をいふたる義かつてなきこと也。みな後世入りほかなる説をもつていひまはしたること多し。此さす竹も箕といふ冠辞と見えたり。箕は竹にてさすものなれば、たゝみとうけるまでのことゝみゆる也。この後の歌はみな大みや人とあり。舍人壯士と云歌一首あり。これはとねりとよまんや。みやび人おのこともよむべきや。又うしかひわらはをもとねりといへば、このさす竹は別の意あらんか。まづさすたけとは箕の冠辭と見るべし。のちのちの集に入りたる歌には、さゝ竹ともよめり。しかれども本語はさす竹也。此集十五卷目の歌に、佐須太氣のと書きたれは、これを證とすべし 歸邊不知爾爲 古本印本ともに、不知爾爲の四字をいさにしてとも、しらずにしとも點をなせり。難心得點也。此四字は、しらざりしとよむべし。しらざりしはしらずありしと云の意也 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉考 | 日並知[ヒナメシノ]皇子(ノ)尊/殯[アガリノ]宮之時、 知は例に依て補、 【此集に葬の後にも殯の時とあるは、既葬奉ても、一周御はか仕へする間をば、殯といひしのみ、天皇の外は別に、殯宮をせられねばなり、】 柿本朝臣人麻呂(カ作歌、 此薨ましゝは、朱鳥三年四月なる事紀に見ゆ、紀に、草壁皇子尊と有は、此尊の今一つの御名なり、 天地之[アメツチノ]、初時之[ハシメノトキノ]、久竪之[ヒサカタノ]、天河原爾[アマノガハラニ]、 紀には天(ノ)安[ヤス]河原といへるを、こゝには安を略く、 八百萬[ヤホヨロヅ]、千萬神之[チヨロヅガミノ]、神集[カンツマリ]、々座而[ツマリイマシテ]、神分[カンハカリ]、分之時爾[ハカリシトキニ]、 天孫を、水穗の國に降しまゐらせんとての神/議[ハカリ]なれば、次の四句をおきて、葦原云云と云へかゝれり、さて次の四句の事は、右の神はかり有しよりも前の事なるを、言を略きて句をなすとて前後にいへり、 天照[アマテラス]、日女之命[ヒルメノミコト]、 一云、指上[サシノボル]日女之命、是も同御ことなり、 天乎波[アメヲバ]、 四言、天をば既に日女命の長くしろしめすべければ、天孫は、豐あし原の國を、つちと久しく知[シラ]さんものとて、降し奉り給ふとなり、 所知食登[シロシメシスト]、葦原乃[アシハラノ]、水穗之國乎[ミヅホノクニヲ]、 水は借字にて、稚々[ミヅミヅ]しき八束穗の事なり、 天地之[アメツチノ]、依相之極[ヨリアヒノキハミ]、 既天地の開分れしてふに對[ムカ]へて、又より合ん限りまでといひて、久しきためしにとりぬ、(卷四)にも此言あり、 所知行[シロシメス]、 宣命にも此三字をかくよみたり、 神之命等[カミノミコトト]、即天孫彦/火瓊々杵[ホノニヽギノ]命を申す、次の言は、神代紀祝詞などに同、 天雲之[アマグモノ]、八重掻別而[ヤヘカキワケテ]、 一云、天雲之、八重雲別而、 神下[カンクダリ]、座奉之[イマシマツラシ]、 一/段[キダ]なり、是まであめ御[ミ]まの御ことなり、【いましまつらしは、次に上いましぬといふに對[ムカ]ふ言なり、さてあがめことばのみぞ、】 高照[タカヒカル]、日之皇子波[ヒノミコハ]、 是よりは、上の天孫の日嗣の御孫の命、今の天皇(天武)を申せり、さてその天皇崩ましては、又天に歸り上りますよしをいはんとて、先天孫の天降ませし事をいへり、かゝる言の勢ひ此人のわざなり、 飛鳥之[アスカノ]、 四言、 淨之宮爾[キヨミノミヤニ]、 原を略けるは(卷十四)に、妹も吾も、清[キヨミ]之河のてふ類なり、 神隨[カンナガラ]、既出、 太布座而[フトシキマシテ]、 是まで四句は、天武天皇御代しらする間を申す、 天皇之[スメロギノ]、敷座國等[シキマスクニト]、 是より、崩ましては天を敷ます國として、上りますといへり、下に天所知流[アメシラシヌル]と書も薨ましての事なり、 天原[アマノハラ]、石門乎開[イハトヲヒラキ]、神上[カンノボリ]、上座奴[ノボリイマシヌ]、 二段なり、右には神下といひ、こゝに神上といへり、一云、神/登[ノボリ]、座爾之可婆[イマシニシカバ]、かく下へいひつゞけては、次の春花之云云に至てわろし、 吾王[ワガオホキミ]、皇子之命乃[ミコノミコトノ]、天下[アメノシタ]、所知食世者[シロシメシセバ]、 是より日並知皇子尊の御事、【古事記上に、天にても、領[シロ]しめすところを國といふ事と見ゆ、】 春花之[ハルバナノ、賞在等[メデタカラント]、 めでたきとは、何をもほむることなり、今本貴と有は、花にいふことばにあらず、 望月乃[モチヅキノ]、滿波之計武跡[タヽハシケムト] (卷三)何時可聞[イツシカモ]、日足座而[ヒタラシマシテ]、十五月之[モチヅキノ]、多田波志家武[タヽハシケム]と有は、こゝと同じ事なれば、今をもたゝはしとよみつ、湛[タヽヘ]るは滿る意にて、天の下に御惠のみち足[タリ]なんといふなり、【今本に、みちはしけんと訓しは、計武てふ辭にかなはず、此けんはたゞはしからんてふ意なり、冠辭考にはたらはしとも訓たれど、今に依べし、】 食國[ヲスクニノ]、 今本こゝも天(ノ)下と有は、よろしからねば、一本によりぬ、 四方之人乃[ヨモノヒトノ]、六言、 大船之[オホフネノ]、冠辭、 思馮而[オモヒタノミテ]、天水[アマツミヅ]、 水かれたる時に雨待如くてふなり、卷十八に家持ぬしもよみつ、 仰而待爾[アフギテマツニ]、何方爾[イカサマニ]、御念食可[オモホシメセカ]、由縁母無[ヨシモナキ]、 次の舍人の歌にも、所由無[ヨシモナキ]、佐太乃[サダノ]岡邊爾といへる、即同時同所の事なり、(卷十四)「よそに見し、山をや今は、因香[ヨスガ]と思はん、」卷十六に、「荒雄らが、余須可の山と見つゝしぬばん、」是らのよすがとよしと同し言なり、【由縁[ヨシ]も無[ナキ]は(卷三[今十三])挽歌に、津禮母無[ツレモナキ]、城[キノ]上(ノ)宮爾、大殿乎都可倍奉而と有に意も事も同じ、委は其歌にいふ、】 眞弓乃崗爾[マユミノヲカニ]、 此陵は式にも高市郡眞弓丘と見ゆ、 宮柱[ミヤバシラ]、太布座[フトシキイマシ]、御在香乎[ミアラカヲ]、 香は借字にて御在所[ミアラカ]なり、 高知座而[タカシリマシテ]、 知は敷なり、そのよし上に見ゆ、さて陵に高殿はあらねどかく云は文なり、 明言爾[アサコトニ]、 日毎てふ意なり、言は借字、 御言不御問[ミコトトハサズ]、 古へはものいふを、こととふ、ものいはぬを、ことゝはずといヘり、此次に、東の、たぎの御門に、さもらへど、きのふもけふふ、召こともなしといへると心同じ、 日月之[ツキヒノ]、四言、 數多成塗[アマタニナリヌ]、其故[ソコユユニ]、皇子之宮人[ミコノミヤビト]、行方不知毛[ユクヘシラズモ]、一云、刺竹之[サスタケノ]、皇子[ミコノ]宮人、歸邊不知爾爲[ユクヘシラニスル]、 これも異ならず、さて下の高市皇子尊の殯時、此人よめる長歌、その外此人の樣を集中にて見るに、春宮舍人にて此時もよめるなるべし、然ればこゝの宮人はもはら大舍人の事をいふなり、その舍人の輩この尊の過ましては、つく所なくて、思ひまどへること、まことにおしはかられて悲し、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | 日並皇子尊殯宮之時柿本朝臣人麻呂作歌一首并短歌 並の下知の字有るべし。朝臣の字を脱せり。目録に依りて補ふ。 此皇子朱鳥三年四月薨じましし事紀に見ゆ。草壁皇子尊とも申せり。天皇の外は殯宮をばせられねども、葬の後一周御墓仕へする間をば殯と言ひしと見ゆ。今本誤りて右の左註より、此端詞を書き續けたり。 天地之。初時之。久堅之。天河原爾。八百萬。千萬神之。神集。集座而。神分。分之時爾。天照。日女之命。[一云指上日女之命、]天乎波。所知食登。葦原乃。水穗之國乎。天地之。依相之極。所知行。神之命等。天雲之。八重掻別而。[-云天雲之、八重雲別而、]神下。座奉之。 あめつちの。はじめのときし。ひさかたの。あまのかはらに。やほよろづ。ちよろづかみの。かむつどひ。つどひいまして。かむはかり。はかりしときに。あまてらす。ひるめのみこと。あめをば。しろしめすと。あしはらの。みづほのくにを。あめつちの。よりあひのきはみ。しろしめす。かみのみことと。あまぐもの。やへかきわけて。かむくだり。いませまつりし。 久堅ノ、枕詞。紀に天の安河原と有るを安を略けり。八百萬千萬神ノ云云は、天孫を水穗の國へ降しまゐらせむとの神議[カムハカリ]なれば、天照の句以下四句を隔てて、葦原云云と言ふへかかれり。此四句の事は、右の神はかり有りしよりも前の事なるを、言を略きて句をなすとて前後に言へり。天テラス云云、一本のサシノボルも同じ事なり。天をば既に日女の命の長くしろしめせば、天孫は豐葦原の國を地と久しく知らさむものとて、降し奉り給ふとなり。水穗の水は借字にて、稚稚[ミヅミヅ]しき穗なり。天地ノヨリ相ノ極ミは、既に天地の開分れしと言ふに對へて、又依合はむ限までとなり。神ノ命ト云云、即ち天孫彦火瓊瓊杵命を申す。天雲ノ云云の詞は、神代紀祝詞など同じ古言なり。神下リイマセマツリシ、宣長云、卷十五、ひとぐににきみを伊麻勢弖と有るによりて、ここもイマセマツリシと訓むべし。イマセは令座の意なりと言ふによれり。ここにて一段にして、これまで天孫の御事なり。 高照。日之皇子波。飛鳥之。淨之宮爾。神隨。太布座而。天皇之。敷座國等。天原。石門乎開。神上。上座奴。[一云、神登座爾之可婆。] たかひかる。ひのみこは。あすかの。きよみのみやに。かむながら。ふとしきまして。すめろぎ[おほきみ]の。しきますくにと。あまのはら。いはとをひらき。かむあがり。あがりいましぬ。 タカヒカル云云、此日の皇子は日並知皇子尊を申すなり。此句にて暫く切りて、天原云云と言ふへ懸る。此國士は天皇の敷座國[シキマスクニ]なりとして、日並知尊は天へ上り給ふと言ひなしたり。此時天皇は持統天皇にて、淨御原宮におはしませり。是れ二段なり。開は閉の誤りにてタテテと訓むべし。卷三、豐國の鏡の山の石戸立[イハトタテ]隱れにけらしと有る類ひなりと、宣長説なり。一本の神ノボリ、イマシニシカバの方は、句つづきよからず。本文を用ふべし。 吾王。皇子之命乃。天下。所知食世者。春花之。貴在等。望月乃。滿波之計武跡。天下。[一云/食國[ヲスクニ]]四方之人之。大船之。思憑而。天水。仰而待爾。何方爾。御念食可。由縁母無。眞弓乃崗爾。宮柱。太布座。御在香乎。高知座而。明言爾。御言不御問。日月之。數多成塗。其故。皇子之宮人。行方不知毛。[一云、刺竹之[サスタケノ]、皇子宮人[ミコノミヤヒト]、歸邊不知爾爲[ヨルヘシラニシテ] わがおほきみ。みこのみことの。あめのした。しろしめしせば。はるはなの。たふとからむと。もちづきの。たたはしけむと。あめのした。よものひとの。おほぶねの。おもひたのみて。あまつみづ。あふぎてまつに。いかさまに。おもほしめせか。つれもなき。まゆみのをかに。みやはしら。ふとしきいまし。みあらかを。たかしりまして。あさごとに。みこととはさず。つきひの。まねくなりぬる。そこゆゑに。みこのみやびと。ゆくへしらずも。 吾王皇子ノミコト云云、ここも日並知尊の御事なり。春花ノ貴カラムとは則ちめでたきを言ひて褒むる詞なり。貴の字義に拘はる事莫かれと有る、宣長説に據るべし。望月ノ云云、卷十三もちづきの多田波思家武[タタハシケム]とあるによりて、契沖しか訓めり。湛ふるは則ち滿つる意にて、御惠の足らひなむと言ふなり。天ノ下或本のヲスグニ、いづれにても有るべし。食國はしろしめす國なり。大船ノ、枕詞。天ツ水は、水かれたる時に、雨を待ち乞ふ如くと言ふなり。由縁モナキは、三卷、都禮毛奈吉[ツレモナキ]さほの山べに、卷十三、津禮毛無城上宮爾由[ツレモナキキノヘノミヤニ]、是等によりて、ここもツレモナキと訓まむと宣長言へり。則ち故由も無き意なり。眞弓岡、式に高市郡眞弓丘陵見ゆ。宮柱云云、上に見ゆ。ここは陵にて宮殿は有らねど、常の御殿になぞらへ言へり。アサゴトニ、言は借字にて、日毎ニと言ふ意なり。ミコトトハサズ、古へもの言ふをコトトフ、モノイハヌをコトトハヌと言へり。數多成塗、マネクナリヌルと訓むこと、卷一に既に言へり。ミ子ノ宮人云云、一云、サスタケノミコノ宮人云云とあれど、數多ナリヌルと言ふより、ソコユヱニと續ける方まされれば一本はとらず。ここは御墓づかへの日數終りて退散を言へり。さて下の高市の皇子尊の殯の時、人麻呂の長歌などを見るに、春宮舎人にて此の時も詠まれしなるべし。然ればここの宮人の事を言ふなり。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 攷證 | 日並所知皇子尊。殯宮之時。柿本朝臣人麿作歌。一首。并短歌二首。 日並所知[ヒナメシノ]皇子尊。 文武天皇の御父、草壁皇子を申奉る。尊號を、岡宮天皇と申奉れり。そのよしは、上【攷證一下廿四丁】にいへり。さて、所知の二字、印本なし。今、上の元暦本によりて補ふ。續日本紀には、日並知皇子とあり。所の字は、そへたるのみ。上【攷證二上廿七丁】考へ合すべし。(頭書、再考、所知の二字なきをよしとす。そのよしは上【攷證二上廿七丁】にいへり。) 殯宮之時。 考云、この集に、葬の後にも、殯の時とあるは、既葬奉りても、一周、御はか仕へする間をば、殯といひしのみ。天皇の外は、別に殯宮をせられねば也云々といはれつれど、この歌にも、眞弓乃岡爾[マユミノヲカニ]、宮柱太布座[ミヤハシラフトシキマシ]云々とありて、下の、明日香皇女木〇[瓦+缶]殯宮歌にも、木〇[瓦+缶]宮乎、常宮跡定賜云々ともあれば、殯宮なしとはいひがたし。皇女すら、かくのごとし。まして、こゝは皇太子におはし奉れば、殯宮ありし事明らけし。今考ふるに、天皇は、さる事にて、皇子、皇女などは、別に殯宮をたてらるゝ事はなくて、御墓と定むべき所のかたはらに、殯宮をおかれし事とおぼゆ。そは、この歌、下の歌などを考へ合せて、しるべし。さて、書紀持統紀に、三年四月、乙未、皇太子草壁皇子尊薨云々と見えたり。 柿本朝臣人麿。 印本、朝臣の二字なし。集中の例、姓をしるせれば、目録によりて補ふ。また、麿を、丸に作れど、これも又目録によりてあらたむ。麿を、丸とかくは、やゝ後のことにて、古今集眞字序に、人丸とあるも、古本にも、人麿とせり。 二首。 この二字も、印本なし。集中の例によりて加ふ。 天地之[アメツチノ]。初時之[ハシメノトキシ]。久堅之[ヒサカタノ]。天河原爾[アマノガハラニ]。八百萬[ヤホヨロツ]。千萬神之[チヨロツガミノ]。神[カム]集[ツトヒ・アツメ]。集[ツトヒ・アツメ]座而[イマシテ]。神分[カムハカリ]。分之時爾[ハカリシトキニ]。天照[アマテラス]。日女之命[ヒルメノミコト]【一云。指上[サシノホル]。日女之命[ヒルメノミコト]。】天乎波[アメヲハ]。所知[シラシ]食[メヌ・メサム]登[ト]。葦原乃[アシハラノ]。水穗之國乎[ミツホノクニヲ]。天地之[アメツチノ]。依相之[ヨリアヒノ]極[キハミ・カキリ]。所知行[シラシメス]。神之命等[カミノミコトト]。天雲之[アマクモノ]。八重掻別而[ヤヘカキワケテ]。【一云。天雲之[アマクモノ]。八重雲別而[ヤヘクモワケテ]。】神下[カムクタリ]。座奉[イマセマツリ・イマシツカヘ]之[シ]。高[タカ]照[ヒカル・テラス]。日之皇子波[ヒノミコハ]。飛鳥之[アスカノ]。淨之[キヨミノ・キヨメシ]宮爾[ノミヤニ]。神髄[カムナカラ・カミノマニ]。太布座而[フトシキマシテ]。天皇之[スメロキノ]。敷座國等[シキマスクニト]。天原[アマノハラ]。石門乎開[イハトヲヒラキ]。神[カム・カミ]上[アカリ]。上[アカリ]座[イマシ・マシ]奴[ヌ]。【一云。神登[カムノホリ]。座爾之可婆[イマシニシカハ]。】吾王[ワカオホキミ]。皇子之命乃[ミコノミコトノ]。天下[アメノシタ]。所知食世者[シラシメシセハ]。春花之[ハルハナノ]。貴[タフト・カシコ]在等[カラムト]。望月乃[モチツキノ]。滿[タタ・ミチ]波之計武跡[ハシケムト]。天下[アメノシタ]【一云。食國[ヲスクニ]。】四方之人乃[ヨモノヒトノ]。大船之[オホフネノ]。思憑而[オモヒタノミテ]。天水[アマツミツ]。仰而待爾[アフキテマツニ]。何方爾[イカサマニ]。御念食可[オモホシメセカ・オホシメシテカ]。由縁[ツレ・ユヱ]母無[モナキ]。眞弓乃崗爾[マユミノヲカニ]。宮柱[ミヤハシラ]。太布座[フトシキマシ]。御[ミ]在[アラ・アリ]香乎[カヲ]。高知座而[タカシリマシテ]。明言爾[アサコトニ]。御言[ミコト]不御問[トハサス・トハセス]。日月之[ヒツキノ]。數多[マネク・アマタニ]成塗[ナリヌル]。其故[ソコユヱニ]。皇子之宮人[ミコノミヤヒト]。行方不知毛[ユクヘシラスモ]【一云。刺竹之[サスタケノ]。皇子宮人[ミコノミヤヒト]。歸邊不知爾爲[ユクヘシラニス]。】 初時之[ハシメノトキシ]。 考には、之を、のとよまれしかど、しとよむべし。このしは助字のみ。 天河原爾[アマノガハラニ]。 安之河をいへる也。古事記上卷に、是以八百萬神、於天安之河原[アメノヤスノカハラ]、神集而[カムツトヘトヘテ]云々とあり。集中七夕の歌に、天の川原、また天川、安の川原などいへるは、漢土にいへる天漢に、中國の古への、安の川原を、合せていへるなり。 八百萬[ヤホヨロツ]。千萬神之[チヨロツカミノ]。 八百[ヤホ]は、彌百[イヤホ]にで、數多きい[(マヽ)]ふ。こゝは何百萬、何千萬神といへる也。 神[カム]集集[ツトヒツトヒ・アツメアツメ]座而[イマシテ]。 舊訓、かむあつめ、あつめいましてとあるは、いふにもたらぬことにて、考に、かむづまり、つまりいまして、とよめるもいかゞ。古事記にも、上に引るごとくありて、大祓祝詞にも、高天原爾神留坐[タカマノハラニカムツマリマス]、皇親神漏岐神漏美乃命以弖[スメラカムツカムロキカムロミノミコトモチテ]、八百萬神等乎[ヤホヨロツノカミタチヲ]、神集々賜比[カムツトヘニツトヘタマヒ]、神議々腸氐[カムハカリニハカリタマヒテ]とあり。されば、かむつどひ、つどひいましてとよむべし。こゝは千萬神の自らつどひ給ふ也。(頭書、古事記上卷に、訓集云都度比[ツドヒ]。) 神分[カムハカリ]。分之時爾[ハカリシトキニ]。 分は、字鏡集に、はかるとよめり。古事記上卷に、八百萬神/議白之[ハカリテ]云々。大殿祭祝詞に、以/天津御量氐事問之[アマツミハカリモテコトヽヒシ]云々とありて、まへに引る大祓祝詞にも、神議賜[カムハカリ]と見えたり。こは、神たち、はからひ定めたまふをいへる也。 天照[アマテラス]。日女之命[ヒルメノミコト]。 書紀神代紀上に、生日神號大日〇貴、【大日〓貴、云於保比屡咩能武智、〇音力丁反、一書云、天照大神、一書云、天照大日〓尊、】此子光華明彩、照徹於六合之内云々とあり。これすなはち、日神にて、天照大神を申奉れり。 一云。指上[サシノホル]。日女之命[ヒルメノミコト]。 日月ともに、そらにさしのぼる故に、枕詞のごとく、さしのぼるひるめの命とつゞけし也。 天乎波[アメヲハ]。所知[シラシ]食[シメシヌ・メサム]登[ト]。 古事記上卷に、其頸珠之、玉緒毛由良邇、取由良迦志而、賜天照大御神而、詔之、汝命者、所知高天原矣、事依而賜也云々とあるごとく、天をば、天照大御神のしろしめせば、いへるなり。 葦原乃[アシハラノ]。水穗之國乎[ミツホノクニヲ]。 葦原[アシハラ]は、宣長云、葦原は、もと天つ神代に、高天原よりいへる號にして、この御國ながらいへる號にはあらず。さて、この號の意は、いといと上つ代には、四方の海べたは、ことごとく葦原にて、其中に國所はありて、上方より見下せば、葦原のめぐれる中に見えける故に、高天原より、かくは名づけたる也云々といはれつるがごとし。水穗國[ミツホノクニ]の、水は、借字にてみづみづしき意、穗[ホ]は、稻穗にて、中國は、稻の萬國にすぐれたる國なれば、ことさらに、みづ穗國とはいへる也。これらの事は、宣長が國號考にくはしくいへり。さて、こゝは、古事記上卷に、天照大御神之命以、豐葦原之千秋長五百秋之水穗國者、我御子正勝々速日天忍穗耳命之所知國、言因賜而、天降也云々とあるをとりて、よまれし也。 天地之[アメツチノ]。依相之極[ヨリアヒノキハミ]。 本集六【四十三丁】に、天地乃依會限[アメツチノヨリアヒノキハミ]、萬世丹榮將往迹[ヨロツヨニサカエユカムト]云々。十一【四十一丁】に、天地之依相極[アメツチノヨリアヒノキハミ]、玉緒之不絶常念妹之當見津[タマノヲノタエシトオモフイモカアタリミツ]云々などありて、また十一【九丁】に、天雲依相遠[アマクモノヨリアヒトホミ]云々なども見えたり。考に、すでに、天地の開わかれしてふにむかへて、又よりあはんかぎりまでといひて、久しきためしにとりぬ云々といはれつるがごとし。さて、極[キハミ]といふ言は、まりの反、みにて、きはまりてふ言にて、かぎりをいへり。本集四。(以下空白)(頭書、書紀神代紀下一書に寶祚之隆、當與天壌無窮者矣。) 神之命等[カミノミコトト]。 こは、彦火瓊々杵命[ヒコホノニヽキノミコト]を申奉れり。て[(マヽ)]等[ト]もじは神下[カムクタシ]といふへかゝりて、こゝの意はこの葦原の中國は、天神の御子の、しろしめすべき國ぞとて、天の八重雲を、かきわけて、くだし奉り給ふとなり。 天雲之[アマクモノ]。八重掻別而[ヤヘカキワケテ]。 古事記上卷に、押分天之八重多那雲而、伊都能知和岐知和岐弖[イツノチワキチワキテ]於天浮橋宇岐士摩理蘇理多々斯弖[ウキシマリソリタヽシテ]、天降坐于/竺紫日向之高千穗之久士布流多氣[ツクシノヒムカノタカチホノクシフルタケニ]云々。書紀神代紀下に、且排分天八重雲云々。大祓祝詞に、天之八重雲 乎、伊頭 乃 千別 爾 千別 弖 云々。本集十一【廿八丁】に、天雲之八重雲隱[アマクモノヤヘクモカクリ]云々などありで、八重[ヤヘ]の八は、例の彌の意にて、天の雲の、いくへともなく、重[カサ]なりたるを、かきわけ、天降し奉れりとなり。 神下[カムクタリ]。座奉之[イマセマツリシ・イマシツカヘシ]。 舊訓、かむくだりいましつかへしとあれど、さては、意聞えがたし。宣長云、十五卷【卅四丁】に、比等久爾々伎美乎伊麻勢弖[ヒトクニヽキミヲイマセテ]とあれば、いませまつりしとよむべし。いませは、令v坐の意也云々といはれしによるべし。意はまへにいへり。 日之皇子波[ヒノミコハ]。 賂解云、この日之皇子は、日並知皇子尊を申す也。この句にて、しばらく切て、天原云々といふへかゝる。この國土は、天皇の敷坐國也として、日並知尊は、天へ上り給ふといひなしたり。この時、天皇は持統天皇にて、淨御原宮におはしませり云々といへるがごとし。 飛鳥之[アスカノ]。淨之宮爾[キヨミノミヤニ]。 この天武帝の大宮なり。上【攷證一上卅六丁】にいへり。 神髄[カムナカラ・カミノマニ]。 かむながらと訓べし。神にましましまゝ[(マヽ)]にといへる意也。この事は、上【攷證一下八丁】にいへり。 太布座而[フトシキマシテ]。 太[フト]は、ものをほめていふ詞、布[シキ]は借字にて、知り領し給ふをいふ言にて、本集一【廿一丁】に、高照日之皇子[タカヒカルヒノミコ]、神長柄神佐備世須登[カムナカラカムサヒセスト]、太數爲京乎置而[フトシカスミヤコヲオキテ]云々ともありて、こは天武帝の御代しろしめすを申せり。さて、この事は、上【攷證一下十九丁】にいへり。 天皇[スメロキ]。 天皇は、集中すめろぎとも、おほきみとも訓たり。下【攷證三下四十五丁】考へ合すべし。 敷座國等[シキマスクニト]。 この國土は、天皇のしりまします國とて、日の皇子は、天をしらさんとて、こゝをさり給ひて、天にのぼり給ふと也。等[ト]もじに、心をつくべし。(頭書、しきますとは、知り領しますをいへる事。) 石門乎開[イハトヲヒラキ]。 古事記上卷に、天石屋戸。書紀神代紀下に、引開天磐戸とあるも、皆こゝに、石門とあると同じ。石[イハ]は、實の石にはあらで、たゞ堅固なる、たとへいへるにて、天之/石位[イハクラ]、天之/石靱[イハユキ]、天/磐船[イハフネ]などの類也。また、豐石窓[トヨイハマト]、櫛石窓[クシイハマト]などいふ、石[イハ]も同じ。こは天上にて、神のおはします所なれば、この皇子、薨じ給へるを、神上[カムアカリ]し給ふといへるに、かりに天原の石門を開て、のぼり給ふよしにいへる也。さて、この開の字を、宣長は、開は閇の誤りにて、たてとよむべし。三卷【四十五丁】に、豐國乃鏡山之石戸立[トヨクニノカゞミノヤマノイハトタテ]、隱爾計良思[コモリニケラシ]とある類也。開といふべきにあらず。石門を閇て、上るといひては、前後たがへるやうに思ふ人あるべけれど、神上は、隱れ給ふといふに同じ。天なる故に、上りとは申す也云々とて、開を閇に改められたり。こは、古事記、舊印本に、開天石屋戸而、刺許母理[サシコモリ]坐也とあるは、聞は閇の誤りにて、既に古本には、閇とある例ともすべけれど、書紀に、引開天磐戸云々。大祓祝詞に、天津神 波 天磐門 乎 押披 氐[オシヒラキテ]云々などありて、門は、出るにも、入るにも、開くべきものなれ、本のまゝに、開として、何のうたがはしき事かあらん。閇に改むるは、なかなかに誤りなるべし。 神[カム・カミ]上[アカリ]。 古事記、書紀など、崩をかむあがりとよめり。こゝも、崩給ふをいへるにて、天皇にまれ、皇子にまれ、崩じ給ふを、神となりて、天に上り給ふよしにいへる事は、集中、皇子たちの薨じ給ふにも、天[アメ]を所知[シラス]よしにいへるにても思ふべし。そは、本集此卷【卅六丁】三【五十八丁】五【四十丁】など考へ合せてしるべし。 上[アカリ]座[イマシ・マシ]奴[ヌ]。 天へ上り行[ユキ]ましぬと也。この座[イマシ]はつねの居る事を、座[イマス]といふとは、少しことかはりて、行ます事をいへる也。そは、古事記中卷に、佐々那美遲袁[ササナミヂヲ]、須久須久登和賀伊麻勢婆[スクスクトワカイマセハ]云々。本集三【卅八丁】に、好爲而伊麻世荒其路[ヨクシテイマセアラシソノミチ]云々。四【卅二丁】に、彌遠君之伊座者[イヤトホニキミカイマサハ]云々。十五【四丁】に、大船乎安流美爾伊多之伊麻須君[オホフネヲアルミニイタシイマスキミ]云々。また【五丁】多久夫須麻新羅邊伊麻須[タクフスマシラキヘイマス]云々。廿【四十四丁】に、安之我良乃夜敝也麻故要氐伊麻之奈婆[アシカラノヤヘヤマコエテイマシナバ]云々などあるに同じ。一云に、神登座爾之可婆[カムノホリイマシニシカハ]とありては、意聞えがたし。 吾王[ワカオホキミ]。皇子之命乃[ミコノミコトノ]。 こは、日並知皇子を申奉る也。すべて皇太子をば、日並皇子尊、高市皇子尊など、皇子の下へ、尊といふ字を付て、尊稱すれど、こゝに皇子之命とあるは、それとは別にて、妹の命、嬬の命、父の命、母の命など、たゞも[(マヽ)]命の字を付て、尊稱する詞なる事、本集三【五十七丁】安積皇子の薨時の歌も、吾王御子乃命[ワカオホキミミコノミコト]云々とあるにて、しるべし。此句よりは、日並知皇子の、天下をしろしめさば、めでたからんと思ふことのさまをいへり。 春花之[ハルハナノ]。 枕詞なれど、冠辭考にもらされたり。春の花は、めでたくうるはしきものなれば、貴[タフトシ]とは、つゞけしなり。之はごとくの意也。猶くはしくは、冠辭考補遺にいふべし。 貴[タフト・カシコ]在等[カラムト]。 古事記上卷に、益我王而甚/貴[タフトシ]云々。また、斯良多麻能伎美何余曾比斯多布斗久阿理祁理[シラタマノキミカヨソヒシタフトクアリケリ]云々。本集五【七丁】に、父母乎美禮婆多布斗斯[チチハハヲミレハタフトシ]云々。また【卅九丁】世人之貴慕[ヨノヒトノタフトミネカフ]云々。六【廿八丁】に、常磐爾座貴吾君[トキハニイマセタフトキワカキミ]云々。催馬樂安名尊歌に、安奈太不止、介不乃太不止左也[アナタフトケフノタフトサヤ]云々など見えたり。みなめでたくありがたきをいへり。宣長云、たふとからんとゝよむべし。たふときといふ言は、古へは、めでたき事にも多くいへり。貴の字に、かゝはりて、たゞこの字の意とのみ思ふべからず。この事、古事記傳にくはしくいへり。考に、貴とは、花にいふことばにあらずとて、賞の字に改められしは、中々にわろし云々といはれつるがごとし。さて、こゝの意は、わが皇子の命の、御代とならず(ばカ)、春の花のさきさかゆるがごとくめてたからんと、又望月のてりみちたるごとく、たゝはしけんと思ひしものをとなり。 望月乃[モチツキノ]。 枕詞にて、冠辭考にくはし。望月のごとく、滿はしけんとつゞけし也。 滿[タタ・ミチ]波之計武跡[ハシケムト]。 舊訓、みちはしけんとゝよめるは、いふにもたらぬ誤り也。本集十三【廿八丁】に十五月之多田波思家武登[モチツキノタタハシケムト]云々とあるによりて、たゝはしけんとゝよむべし。また十三【十一丁】に、天地丹思足椅[アメツチニオモヒタラハシ]云々。十九【四十一丁】に、韓國爾由伎多良波之氐[カラクニニユキタラハシテ]云々などもあれば、たらはしともよむべけれど、枕詞よりのつゞけざまを思ふに、猶たゝはしよむ[(マヽ)]むかたまされり。さて、こゝは、十五夜の月のごとく、足そなはりとゝのひなんといへる也。 大船之[オホフネノ]。 枕詞にて、冠辭考にくはし。こは海上にては、たゞ大船を、たのもしきものに思ひたのむものゆゑに、しかつゞけしなり。 思憑而[オモヒタノミテ]。 わが皇子の命の、天下をしろしめさば、めでたく滿しからんと、天下の四方の人の、思ひたのみ奉りて、あふぎてまち奉りしものを、いかにおぼしめしてか、かく早く、世をさり給ひけんとなり。 天水[アマツミツ]。仰而待爾[アフキテマツニ]。 天水[アマツミツ]は、雨なり。ひでりの時、天をあふぎて、雨を待ごとく、君が御代をまちしとなり。本集十八【卅二丁】、小旱歌に、彌騰里兒能知許布我其登久[ミトリコノチコフガコトク]、安麻都美豆安布藝弖曾麻都[アマツミツアフキテソマツ]云々と見えたり。又史記晋世家に、孤臣之仰v君、如百穀之望時雨云々ともあり。 何方爾[イカサマニ]。御念食可[オモホシメセカ]。 いかにおぼしめせはかの意にて、可は、ばかの意也。この事は、上【攷證一上四十七丁】にいへり。 由縁[ツレ・ユヱ]母無[モナキ]。 宣長云、三巻【五十四丁】に、何方爾念鷄目鴨[イカサマニオモヒケメカモ]、都禮毛奈吉佐保乃山邊爾[ツレモナキサホノヤマヘニ]云々。十三巻【廿九丁】に、何方御念食可[イカサマニオモホシメセカ]、津禮毛無城上宮爾[ツレモナキキノヘノミヤニ]、大殿乎都可倍奉而[オホトノヲツカヘマツリテ]云々。これらによるにこゝの由縁母無、また下【卅丁】なる所由無佐大乃岡邊爾[ツレモナキサタノヲカヘニ]云々などをも、つれもなきとよむべきこと也云々。この説によるべし。さて、これらの、つれもなきは、ゆかりもなきをいへるにて、また本集四【四十八丁】に、都禮毛無將有人乎[ツレモナクアルラムヒトヲ]云々。十【五十一丁】に、吾者物念都禮無物乎[ワレハモノオモフツレナキモノヲ]云々。十九【十九丁】に、都禮毛奈久可禮爾之妹乎[ツレモナクカレニシイモヲ]云々などあるは、今の世にもいふ所と同じく、心づよき意にて、つれなき人などもいひ、難面、強顔などの字をよむ意にて、こゝとは意たがへれども、もとは一つ語なり。 眞弓乃崗爾[マユミノヲカニ]。 延喜諸陵式に、眞弓丘陵、岡宮御宇天皇、在大和國高市郡、兆城東西二丁、南北二丁、陵戸六烟云々とあり。日並知皇子を追崇して、岡宮御宇天皇と申すよし、續日本紀、天平寶字二年八月戊申紀に見えたり。また續日本紀に、天平神護元年十月癸酉事駕過檀山陵、詔陪從百官、悉令下馬、儀衛卷其旗幟云々とあり。さて、この眞弓岡陵を、大和志に、皇極天皇の祖母の陵とするは誤れり。 御[ミ]在[アラ・アリ]香乎[カヲ]。 御在香は、御ありかの、りをらに通はしたるにて、すなはち宮殿なり。この事は、上【攷證一下廿七丁】にいへり。 高知座而[タカシリマシテ]。 本集一【十九丁】に、高殿乎高知座而[タカトノヲタカシリマシテ]云々。また【廿二丁】都宮者高所知武等[ミアラカハタカシルラムト]云々など見えて、殿を高く知り領しますなり。この事は、上【攷證一下九丁】にいへり。 明言爾[アサコトニ]。 代匠記に、明言爾[アサコトニ]には、朝毎になり。物のたまふ事は、朝にかぎらざれども、伺候する人は、ことに朝とくより、御あたりちかくはべりて、物仰らるゝ也云々とあるがごとし。明言は借字なり。 御言[ミコト]不御問[トハサス・トハセス]。 考云、古へは、ものいふをこととふ、ものいはぬを、ことゝはずといへり。この次に、東のたぎの御門にさもらへど、きのふもけふもめすこともなしといへると、心同じ云々といはれつるがごとく、言問はものいふこと也。そは、古事記中卷に、是御子、八拳〇[髟の下に耆]至于心前、眞事登波受[マコトトハズ]云々。本集四【廿一丁】に、明日去而於妹言問[アスユキテイモニコトトヒ]云々。また【卅三丁】外耳見管言將問縁乃無者[ヨソノミミツヽコトヽハムヨシノナケレハ]云々。また【五十七丁】事不問木尚[コトトハヌキスラ]云々。五【十一丁】に、許等々波奴樹爾波安里等母[コトヽハヌキニハアリトモ]云々などあるにても思ふべし。集中猶多し。 數多成塗[マネクナリヌル・アマタニナリヌ]。 宣長云、まねくなりぬると訓べし。まねくの事、一卷にいへるがごとし。塗、これをあまたになりぬと訓るはわろし。塗の字、ぬと訓べきよしなし云々といはれつるがごとし。猶上【攷證一下七十四丁】にくはし。 其故[ソコユヱニ]。 それゆゑにといふと同じ。すべて、中ごろよりの言に、それといふべきを、古くはそことのみいへり。そは、本集此卷下【卅一丁】に、所虚故名具鮫魚天氣留[ソコユヱニナクサメテケル]云々。三【五十六丁】に、曾許念爾〇[匈/月]己所痛[ソコモフニムネコソイタメ]云々。四【十七丁】に、彼所毛加人之吾乎事將成[ソコモカヒトノワヲコトナサム]云々などありて、集中猶多し。みな、それといふ意也。さて、この句は、明毎爾御言不問、日月之數多 (成脱カ) 塗といふをうけて、それゆゑに、しかじかといふ語を起すことば也。 皇子之宮人行方不知毛[ミコノミヤヒトユクヘシラスモ]。 皇子の宮人は、春宮傅よりはじめて、舍人、馬部などまで、春宮の官人をおしなべていふ事ながら、專ら、舍人をいふとおぼし。その舍人等が、御墓仕へする日數へて、それぞれ逸散するを、ゆくへしらずとはいへる也。考云、下の高市皇子尊の殯時、この人のよめる長歌その外、この人の樣を、集中にて見るに、春宮舍人にて、この時もよめるなるべし。然れば、こゝの宮人は、もはら大舍人の事をいふ也。その舍人の輩、この尊の返ましては、つく所なくて、思ひまどへること、まことにおしはかられてかなし云々。 一云。刺竹之[サスタケノ]。皇子宮人[ミコノミヤヒト]。歸邊不知爾爲[ユクヘシラニス]。 刺竹之[サスタケノ]は、枕詞に、冠辭考にくはしく解れしかど、あたれりともおぼえず。とにかくに、思ひ得る事なし。さて、これも意は、本書とかはる事なけれど、句のつゞき、本書のかたまされり。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 日並皇子尊殯宮之時《ヒナミノミコノミコトノアラキノミヤノトキ》。 柿本朝臣人麿作歌一首并短歌《カキノモトノアソミヒトマロガヨメルウタヒトツマタミジカウタ》。 日並皇子(ノ)尊(ノ)殯宮云々は、持統天皇(ノ)紀に、三年夏四月癸未朔乙未、皇太子草壁(ノ)皇子(ノ)尊薨、とある時のことなり、此(ノ)皇子(ハ)、天智天皇元年に生(レ)賜ひて、薨(キ)賜へる時は、二十八歳なり、日並(ノ)皇子は、草壁(ノ)皇子の更名《マタノミナ》、日並所知《ヒナミシラスノ》皇子と申しゝを、略(キ)申せるなり、既く委(ク)註り、さて本居氏、師の考には、天皇の餘は、別に殯(ノ)宮は立られず、これらは一周まで、御墓づかへする間を、凡て殯と云しなり、とあり、今按(フ)に、天皇のほかは、殯(ノ)宮無き證も見えず、又|正《マサ》しく、蘋(ノ)宮ありし證も見えねども、既に殯(ノ)宮之時とあるうへは、たとひ其(ノ)宮は立られずとも、殯(ノ)宮と云しことは、明らけし、孝徳天皇(ノ)紀の制に、凡王以下、及至2庶人(ニ)1、不v得v營v殯(ヲ)、とあるに依らば、皇子は殯せしなり、又此(ノ)制より前には、王以下も殯せしなるべし、さて右の如く、殯宮之時と云るは、御喪之時と云義にて、必(ス)しも、殯宮に坐ほどのみを云に非ず、故(レ)端に、右の如く標《アゲ》たる歌、いづれも、既に葬(リ)奉れる、後の事までをよめり、されば、師の一周までの間を云、といはれたるは、當れりと云り、皇子に殯(ノ)宮と云るは、此(ノ)下、高市(ノ)皇子(ノ)尊、城上(ノ)殯宮之時云々、明日香(ノ)皇女、木〇[瓦+缶](ノ)殯宮之時、云々などもあり、 ○朝臣の二字、舊本に脱たり、目録并類聚抄官本古寫本拾穗本人麻呂勘文等に依つ、 ○短歌の下、類聚抄に二首とあり 天地之《アメツチノ》。初時之《ハジメノトキシ》。久堅之《ヒサカタノ》。天河原爾《アマノガハラニ》。八百萬《ヤホヨロヅ》。千萬神之《チヨロヅカミノ》。神集《カムツドヒ》。集座而《ツドヒイマシテ》。神分《カムアガチ》。分之時爾《アガチシトキニ》。天照《アマテラス》。日女之命《ヒルメノミコト》。天乎波《アメヲバ》。所知食登《シロシメスト》。葦原乃《アシハラノ》。水穗之國乎《ミヅホノクニヲ》。天地之《アメツチノ》。依相之極《ヨリアヒノキハミ》。所知行《シロシメス》。神之命等《カミノミコトト》。天雲之《アマクモノ》。八重掻別而《ヤヘカキワケテ》。神下《カムクダリ》。座奉之《イマセマツリシ》。高照《タカヒカル》。日之皇子波《ヒノミコハ》。飛鳥之《アスカノ》。淨之宮爾《キヨミノミヤニ》。神髄《カムナガラ》。太布座而《フトシキマシテ》。天皇之《スメロギノ》。敷座國等《シキマスクニト》。天原《アマノハラ》。石門乎開《イハトヲヒラキ》。神上《カムノボリ》。上座奴《ノボリイマシヌ》。吾王《ワガオホキミ》。皇子之命乃《ミコノミコトノ》。天下《アメノシタ》。所知食世者《シロシメシセバ》。春花之《ハルハナノ》。貴在等《タフトカラムト》。望月乃《モチヅキノ》。滿波之計武跡《タヽハシケムト》。天下《アメノシタ》。四方之人乃《ヨモノヒトノ》。大船之《オホブネノ》。思憑而《オモヒタノミテ》。天水《アマツミヅ》。仰而待爾《アフギテマツニ》。何方爾《イカサマニ》。御念食可《オモホシメセカ》。由縁母無《ツレモナキ》。眞弓乃崗爾《マユミノヲカニ》。宮柱《ミヤバシラ》。太布座《フトシキイマシ》。御在香乎《ミアラカヲ》。高知座而《タカシリマシテ》。明言爾《アサゴトニ》。御言不御問《ミコトトハサズ》。日月之《ツキヒノ》。數多成塗《マネクナリヌレ》。其故《ソコユヱニ》。皇子之宮人《ミコノミヤヒト》。行方不知毛《ユクヘシラズモ》。 〇天地之初時之《アメツチノハジメノトキシ》は、古事記に、天地初發之時《アメツチノハジメノトキ》とあるは、實に天地初發の事を、いふことなるに、集中に、天地之初時《アメツチノハジメノトキ》とあるは、天地初發よりは、遙に後の事なれども、神代の上(ツ)世をば、大かたに天地之初、といへるなり、時之《トキシ》の之《シ》は、助辭なり、 ○久堅之《ヒサカタノ》は、枕詞なり、既く出づ、 ○天河原爾《アマノガハラニ》云云、古事記天降(ノ)條に、爾《コヽニ》高御座巣日(ノ)神、天照大御神之命以、於2天(ノ)安河之河原1、神2集(ヘ)八百萬神(ヲ)1集而、 思金神、令v思而詔(ク)、云々、大祓(ノ)詞に、高天原爾神留坐《タカマノハラニカムニツマリマス》、皇親神漏岐神漏美之命以氐《スメラガムツカムロギカムロミノミコトモチテ》、八百萬神等乎《ヤホヨロヅノカムタチヲ》、神集集賜神講議賜氐《カムツドヘツドヘタマヒカムハカリハカリタマヒテ》、我皇孫之命波《ワガスメミマノミコトハ》、豊葦原乃水穂之國乎《トヨアシハラノミヅホノクニヲ》、安國止平久知所食止《ヤスクニトタヒラケクシロシメセト》、事依奉岐《コトヨザシマツリキ》などあり、 ○千萬神之《チヨロヅカミノ》、六(ノ)卷に、千萬乃軍《チヨロヅノイクサ》ともあり、 ○神集は、カムツドヒと訓べし、古事記、及大祓(ノ)詞なるは、ツドヘなり、其は大命以令v集給ふよしなればなり(ツドヘは、ツドハセのハセを切(メ)て、ヘと云るなり、)此は神等の、自(ラ)集ひ給ふよしなれば、ツドヘとは訓べからず、 ○神分は、大祓(ノ)詞に、神議《カムハカリ》とあるによりて、むかしより、カムハカリと訓來れども、分(ノ)字に、議と通ふ義あることを未(タ)見ず、字書にも、分(ハ)別(ツ)也判(ツ)也賦(ル)也、など註して、賦は、班賦ともつらね云字なり、故(レ)案(フ)に、神分、云々は、カムアガチアガチシトキニ、と訓べきか、某々の神は、某々の地を所知《シロシ》めせ、と差班《サシアガ》ち配《クマ》り賜へるこゝろなり、六(ノ)卷藤原(ノ)宇合卿(ヲ)、遣2西海道(ノ)節度使1之時の歌に、山乃曾伎野之衣寸見世常件部乎班遣之《ヤマノソキヌノソキミヨトトモノベヲアガチツカハシ》云々、とある班に同じ、繼體天皇紀に、散2置《アガチオク》諸縣(ニ)1、續紀廿五詔に、天(ノ)下乃|諸國仁《クニクニニ》、書乎散天《フミヲアガチテ》、告知之米《ツゲシラシメ》、なほアガツの言は、神代紀に、廢渠槽、此云2秘波鵝都《ヒアガツト》1と見えたり、波は、阿(ノ)字の誤なり、(源氏物語澪標に、いとゞさびしく、こゝろぼそきことのみまさるに、さぶらふ人々も、やうやうあがれ行などして、とあるも、アガツといふと、アガルといふと、自他の差別あるのみにて、全(ラ)同言なり、) ○分之時爾《アガチシトキニ》、といふより、次の四句をおきて、葦原乃《アシハラノ》云云へかゝれり、そのゆゑは、これまでは、皇孫(ノ)命を、水穂(ノ)國に天降しまゐらせむとての、神議なればなり、 ○天照日女之命《アマテラスヒルメノミコト》云々、舊本に、一(ニ)云、指上日女之命《サシノボルヒルメノミコト》とあり、天照は、日といはむとての、枕詞におけるなるべし、指上とあるも、同じこゝろばえなり、神(ノ)等に枕詞をおくは、薦枕《コモマクラ》高御産栖日《タカミムスビノ》神、など云るこれなり、日女は、神代紀に、於是共生2日(ノ)神(ヲ)1、號2大日〓《オホヒルメノムヂト》1、一書(ニ)云(ク)、天照(ス)大日〓《オホヒルメノ》尊、此(ノ)子/光華明彩《ヒカリウルハシクマシテ》、照2徹《テリワタラセリ》於六合之内《アメツチニ》1、故(レ)二(ノ)神喜(ヒ)曰《タマハク》、吾思/雖《ドモ》v多《サハナレ》、未2有《マサズ》若此靈異之兒《カクバカリクシビナルミコハ》1、不v宜v久(ク)2留(メマツル)此(ノ)國(ニ)1、自當(トノリタマヒテ)3早送(リマヲス)2于天(ニ)1、而/授3以《ヨサシマツリキ》天上之事《アメノコトヲ》1、故(レ)以2天(ノ)柱1擧(マツリキ)於天上《アメニ》1、古事記に、此(ノ)時伊邪那岐(ノ)命、大歡喜詔《イタクヨロコバシテノリタマハク》、云々、賜(ヒテ)2天照大御神(ニ)1而/詔云《ノリタマハク》、汝命者《ナガミコトハ》、知2所《シラセト》高天(ノ)原(ヲ)1矣、事依而賜《コトヨザシテタマヒキ》也などあり天乎婆《アメヲバ》、(婆(ノ)字、舊本に波と作るはわろし、今は拾穗本に依つ、)乎婆《ヲバ》の辭、妙《ヨク》もいはれたるかな、 ○所知食登《シロシメスト》は、知しめすとての意なり、これまで四句の意は、天をば、日女(ノ)命の知しめすとて、それゆゑにといふほどの意なり、登《ト》はとての意なり、 ○葦原乃水穗之國乎《アシハラノミヅホノクニヲ》、名(ノ)義は、本居氏(ノ)國號考に委し、こゝは天(ノ)下をといふ意なり、 ○天地之依相之極《アメツチノヨリアヒノキハミ》は、天地の初て判《ワカレ》しといふに、對《ムカ》へたることにて、又寄(リ)合む限までと云(ヒ)て、久しき間のためしとせり、天地のあらむかぎり、と云意なり、天地の依(リ)相と云理は、さらになきことなれども、假に儲て、かくいへるが、おもしろき事なり、(契冲が天地の依相之極は、極めはてなり、地のはては、天とひとつによりあふ心なり、と云るはたがへり、)六(ノ)卷に、天地乃依會限萬世丹榮將往迹思煎石大宮尚矣《アメツチノヨリアヒノカギリヨロヅヨニサカヱユカムトオモヒニシオホミヤスラヲ》十一に、天地之依相極玉緒之《アメツチノヨリアヒノキハミタマノヲノ》、不絶常念妹之當見津《タエジトオモフイモガアタリミツ》、また天雲依相遠不相異手枕吾轉哉《アマクモノヨリアヒトホミアハズトモアタシタマクラアレマカメヤモ》ともあり、(天雲と云るは、少しいかゞなり、猶彼處にいふべし、) ○神之命等《カミノミコトヽ》は、即(チ)番能邇邇藝《ホノニヽギノ》命を指て申せるなり、等《ト》は、としての意なり、 ○天雲之八重掻別而《アマクモノヤヘカキワケテ》、舊本に、一(ニ)云、天雲之八重雲別而、と註《シル》せり、古事記に、故(レ)爾(ニ)詔2天津日子番能邇邇藝《アマツヒコホノニヽギノ》命(ニ)1而、離(レ)2天(ノ)之石位《イハクラヲ》1、押2分天(ノ)之/八重多那《ヤヘタナ》雲(ヲ)1而、伊都能知和岐知和岐弖《イツノチワキチワキテ》、於2天(ノ)浮橋1、宇岐士摩理蘇理多々斯弖《ウキシマリソリタヽシテ》、天2降坐《アモリマシキ》、于筑紫(ノ)日向(ノ)之高千穗(ノ)之、久士布流多氣《クシフルタケニ》1、書紀に、皇孫《スメミマ》乃離(リ)2天(ノ)磐座1、且つ排2分(ケ)天(ノ)八重雲(ヲ)1、稜威之道別道別而《イツノチワキチワキテ》、天2降《アモリマシキ》於日向(ノ)襲之高千穗(ノ)峯(ニ)1矣などあり、 ○神下《カムクダリ》は降臨《アマクダリ》賜ふことなり、 ○座奉之は、イマセマツリシと訓べし、奉v令v座しなり、(之《シ》は過去し方にいふ辭なり、)座《イマセ》は、五(ノ)卷に都加播佐禮麻加利伊麻勢《ツカハサレマカリイマセ》、十五に、比等久爾爾伎美乎伊麻勢弖《ヒトクニニキミヲイマセテ》、などある皆同し、さて發句より、此までの意を、つらねていはゞ天地の初發の時に天の河原に八百萬神等の集ひいまして神議し給ひし時に、既く天上をば、天照(ス)日女(ノ)命のしろしめす國ぞ、此(ノ)水穗(ノ)國を、皇孫(ノ)命の、天地と長(ク)久しく、しろしめすべき國ぞ、と定め賜ひて、天の八重雲を掻別て、天降し奉v令v座しなりと、まづ昔物語のごといひ置なり、かくて上に曾乃也何《ソノヤナニ》等の言無ければ、奉伎《マツリキ》といふこと、辭《テニヲハ》のとゝのひの正格《サダマリ》なれど、こゝは然《サ》云ては、宜しからざる所以《ユヱ》にわざと偏格《コトサマ》に、奉之《マツリシ》と云るなるべし、此(ノ)例、三(ノ)卷に、春霞春日里之殖子水葱《ハルカスミカスガノサトノウヱコナギ》、苗有跡云師柄者指爾家牟《ナヘナリトイヒシエハサシニケム》、(これも上に、曾乃也何《ソノヤナニ》等の言なければ、云伎《イヒキ》といふ、辭《テニヲハ》のとゝのひのさだまりなれど、さいひては宜しからぬゆゑに、云師《イヒシ》といへるならむ、)七(ノ)卷に、世間者信二代者不往有之《ヨノナカハマコトフタヨハユカザリシ》、過妹爾不相念者《スギニシイモニアハナクモヘバ》、〈これも上に、曾之也何《ソノヤナニ》等の言なければ、不有伎《ザリキ》といふ、辭のとゝのひのさだまりなれど、さいひては、宜しからぬゆゑに、不有之《ザリシ》といへるならむ、)十六に、家爾有之櫃爾鏁刺藏師戀乃奴之束見懸而《イヘニアリシヒツニクギサシヲサメテシコヒノヤツコノツカミカヽリテ》、(これも上に、曾乃也何《ソノヤナニ》等の言なければ、而伎《テキ》といふこと、辭のとゝのひのさだまりなれど、さいひては宜しからぬゆゑに、而師《テシ》と云るならむ、)又八(ノ)卷に、去年之春相有之君爾戀爾手師《コゾノハルアヘリシキミニコヒニテシ》、櫻花者迎來良之母《サクラバナハムカヘケラシモ》、(これも上に、さるべき言なければ、手伎《テキ》といふべきを、手師《テシ》とかへていへるか、但しこれは手伎《テキ》とありしを、寫し誤りたるにもあらむ、)又/古郷之奈良思之岳能霍公鳥《フルサトノナラシノヲカノホトヽギス》、言告遣之何如告寸八《コトヅケヤリシイカニツゲキヤ》、(これも上に、さるべき言なければ、遣伎《ヤリキ》といふべきを、遣之《ヤリシ》とかへていへるか、但し此(ノ)歌を、拾遺集に載たるには、言つげやりき、とあるを思へば、もとは、寸《キ》などの字なりしを、之《シ》に寫し誤りたるにもあらむ、)なほ余が、鍼嚢歌詞偏格(ノ)條に、委(ク)云るを披き考(ヘ)合(ス)べし、 ○高照日之皇子波《タカヒカルヒノミコハ》、こは天武天皇を指(シ)奉れるなり、(略解に、日之皇子は、日並知(ノ)皇子(ノ)尊を申すなり、此(ノ)句にて暫(ク)絶て、天原云々と云へかゝる、此(ノ)國土は、天皇の敷座國ぞとして、日並(ノ)皇子(ノ)尊は、天へのぼり賜ふ、と云なしたり、と云るは、いみじきひがことなり、さては下に、眞弓の崗爾宮柱太布座云々と云るにたちまちかけ合ざるは、いかにぞや、) ○淨之宮《キヨミノミヤ》は、明日香(ノ)清御原(ノ)宮なり、伎與美《キヨミ》とのみ云るは、三(ノ)卷に、妹毛吾毛清之河乃《イモヽアレモキヨミノカハノ》云々ともあり、 ○神隨《カムナガラ》は、神とましますが隨《マヽ》に、といふなり、既く出づ、 ○太布座而《フトシキマシテ》、これまで四句は、天武天皇の、御宇《アメノシタシロシメシ》し間を申せり、御徳澤《ミウツクシミ》の、またなく太く尊くましまして、天(ノ)下にしきほどこし給ふを、太布座《フトシキマス》といふ、 ○天皇之《スメロギノ》、これも天武天皇なり、(略解に、此(ノ)時天皇は、持統天皇にて、淨御原(ノ)宮におはしませりと云るは、まぎらはし、) ○敷座國等《シキマスクニト》は、崩(リ)ましては、又天(ノ)原を敷座國としてといふなり、崩(リ)ますを、天にのぼりますといふは、此(ノ)下、高市(ノ)皇子(ノ)命、城上の殯宮歌の、或書にも、我王者高日所知奴《ワガオホキミハタカヒシラシヌ》、ともありて、この現世《ウツシヨ》をすぎさり賜ふをば、皆天津宮にのぼり入せ給ふといへる事、此(ノ)上、結松の追和歌につきて、委(ク)論(ヒ)云り、 ○石門乎開《イハトヲヒラキ》は、天へ上り給ふとて、天の石門を開き、といひなしたり、(本居氏は、三(ノ)卷、豐國の鏡山之石戸立隱にけらし、とある歌によりて、開は、閇(ノ)字の誤とせられつれど、そは中々あしかりけり、いかにとなれば、こは此(ノ)國土より、高天(ノ)原にのぼり座といふから、石門を開(キ)と云るにて、猶常に、人の家に入にも、閇たる門を開(キ)て入て、さて後には、又開きし門を閇ると云如くなれば、彼(ノ)三(ノ)卷(ノ)歌とは、前後の違ありといふべし、故(レ)本居氏(ノ)説には、神上を、カムアガリとよみて、直に崩(ル)意に見つらめど、さにはあらず、次に猶いふべし、) ○神上上座奴、舊本に、一(ニ)云、神登座尓之可婆と註せり、こはわろし、神上は、カムノボリと訓べし、こゝは上に、天雲之《アマクモノ》云々/神下《カムクダリ》、とあるに對へて、天原《アマノハラ》云々|神上《カムノボリ》、と云なしたるにて、あらはに崩御と申さず、正しく、天にのぼりませしごとく云り、ときこえたればなり、(カムアガリ、とよまむはわろし、ノボリは、即(チ)クダリの對語なるにても考(フ)べし、さて一(ニ)云、神登とあるは、訓は同じけれど、異本に字面のたがへるがありしを、載しのみぞ、神上をば、カムアガリはとよむ故に、神登と一本にあるを、さらにあげしにはあらず、集中にさる例多し、ゆめまどふべからず、)奴《ヌ》は、已成《オチヰ》の奴《ヌ》なり、已く上り座しぬ、といふなり、さて上の高照《タカヒカル》云々、といふより、是までの意は、天武天皇は、淨御原(ノ)宮におはしまして、天下をしろしめしおはしましゝを、遂に天上をしろしめし、おはしますべき國ぞ、と御みづからおもほし立して、天の石門を押ひらきたまひて、神のぼりいましぬと云なり、さて吾王日並(ノ)皇子(ノ)尊の、天(ノ)下/所知食《シロシメシ》たらば云々、とつゞくなり、 ○吾王皇子之命乃《ワガオホキミミコノミコトノ》、これより初て、日並(ノ)皇子(ノ)尊を指奉れり、 ○天下知食世者《アメノシタシロシメセバ》は、御宇《アメノシタシロシメ》す代《ミヨ》になりせば、といふなり、 ○春花之《ハルハナノ》は、貴《タフト》といはむ料の枕詞なり、 ○貴在等《タフトカラムト》は、めでたからむとてといふ意なり、まづ多布等伎《タフトキ》といふ言は、めでたきことに云るなり、貴字の意にのみ見ては、こゝに春花之《ハルハナノ》と云るに叶はず、古事記上卷海宮(ノ)段に、豐玉毘賣(ノ)命の從婢の詞に、火遠理命をさして、甚麗壯夫《イトウルハシキヲトコマス》也、益(リ)2我(カ)王(ニモ)1而|甚貴《イトタフトシ》1と云る、其(ノ)傳に云(ク)、貴は、此(ノ)卷(ノ)末なる、豐玉毘賣(ノ)命(ノ)御歌に、期良多麻能伎美何余曾比斯多布斗久阿理祁理《シラタマノキミガヨソヒシタフトクアリケリ》、萬葉二に云々、催馬樂に安名多不止介不乃太不止左也《アナタフトケフノタフトサヤ》、などあると同じくて、美《メデタ》く好《ヨ》き意なり、是(レ)貴きの本義なり、太占《フトマニ》、太祝詞《フトノリト》、太幣《フトミテグラ》などの類の、太《フト》と同言にて、太布斗伎《タフトキ》は、太《フト》に多《タ》の添りたるなり後(ノ)世には音便に、多布斗《タフト》をば、とをとゝ呼《イフ》故に、異なるが如くなれども、古(ヘ)は、本(ノ)音のまゝに呼つれば、同しことなりと云り、今案(フ)に、三(ノ)卷大伴(ノ)卿讃v酒歌に、將言爲便將爲便不知極貴物者酒西有良之《イハムスベセムスベシラニキハマリテタフトキモノハサケニシアルラシ》、また倭姫(ノ)命(ノ)世記に、乙加豆知(ノ)命乎、汝國(ノ)名/何問賜《イカニトトヒタマヘバ》、白久《マヲサク》、意須比飯高《オスヒイヒタカノ》國止白而、進(リキ)2神田並神戸(ヲ)1、倭姫(ノ)命、飯高志止《イヒタカシト》白(ス)事、貴止《タフトシト》悦(ヒ)賜(ヒ)支《キ》、などある貴も、みなめでたき意なり、後世のごとく、貴尊などの字(ノ)意にのみあてゝは、通えがたきところ多からむ、 ○望月乃《モチヅキノ》は、枕詞なり、 ○滿波之計武跡は、契冲云、これをば、たゝはしけむとゝ訓べし、第十三に、十五月之多田波思家武登《モチヅキノタタハシケムト》とよめり、堪の字の心なり、潮などの、みちたゝへたるごとく、十五夜の月の、圓滿なるによせて、のぞみのたりて、かける事あらじ、と皆人の思ふなり、と云るがごとし、(但し、のぞみのたりて、云々と云る事、少しむづかしく聞ゆるなり、)天(ノ)下に、大御惠《オホミメグミ》の、普くみち足はしからむとて、と云る意なり、跡《ト》は二句ながら、とての跡《ト》なり、 ○天下《アメノシタ》、舊本に、一云、食國と註り、 ○匹方《ヨモ》は、四面《ヨモ》なり、 ○大船之《オホブネノ》は、枕詞なり、契冲云、大船のおもひ憑みてとは、大船は、のれる心の、たのもしげなる物なればなり、此(ノ)集に多き詞なり、和名集云、唐韻(ニ)云、舶、(傍陌(ノ)反、楊氏漢語抄(ニ)云、都具能布禰《ツクノフネ》、)海中(ノ)大船也、 ○天水《アマツミツ》は、日でりに水かれて、雨を仰(キ)待(ツ)意にいひて、枕詞とせり、十八に、安麻都美豆安布藝弖曾麻都《アマツミヅアフギテゾマツ》、(これは、直《タヾ》に雨を待(ツ)意なり、) ○御念食可《オモホシメセカ》は、御念《オモホ》しめせぼかの意なり、この句の下に、今一つ詞を加へて、何方爾御念食可云云《イカサマニオモホシメセカカク》ありけむ、と意得べし、(云云《カク》ありけむとは、薨まして、由縁母無眞弓乃崗爾《ツレモナキマユミノヲカニ》云々ありけむ、といふ意なり、御念食可由縁母無《オモホシメセカツレモナキ》、と直に續けては、可《カ》の言|結《トヂマ》らず)これ古歌の一(ノ)格なり、猶一(ノ)卷、近江(ノ)荒都(ノ)長歌の下に云るを、合(セ)考(フ)べし、さて吾王《ワカオホキミ》といふより、此(レ)までの意は、吾(ガ)王日並(ノ)皇子(ノ)尊の、天(ノ)下しろしめしたらば、國家も美《メデタ》く榮なむ、普き大御惠の、天(ノ)下に滿足はしてあらむと、四方八方の人の、ふかく思ひたのみて、仰ぎ待ほどに、いかやうにおぼしめせばか、かやうにならせ賜ひけむとなり、 ○由縁母無は、三(ノ)卷に、都禮毛奈古佐保乃山邊爾《ツレモナキサホノヤマヘニ》、十三に、津禮毛無城上宮爾《ツレモナキキノヘノミヤニ》、などあるによりて、こゝもツレモナキと訓べし、と本居氏云り、なほ三(ノ)卷、都禮毛奈吉《ツレモナキ》の註、考(ヘ)見べし、(源(ノ)嚴水云、略解に、ツレモナキは、ゆゑよしもなき意とあるは、あかぬこゝちすれば、もと連(ノ)字の意にて、ツレナキは、ともなひよる人もなき意なり、由縁の字も、よりたのむ意にて、書りとおぼゆ、) ○眞弓乃崗爾《マユミノヲカニ》、(崗(ノ)字、拾穗本には岡と作り、)諸陵式(ニ)云、眞弓(ノ)丘(ノ)陵、(岡(ノ)宮(ニ)御宇(シ)天皇、在2大和(ノ)國高市(ノ)郡(ニ)1、兆域東西二町南北二町、陵戸六烟、)續紀廿一に、廢帝、天平寶字二年八月戊申、勅(スラク)、日並知《ヒナミシラスノ》皇子(ノ)命、天(ノ)下未v稱2天皇(ト)1、追2崇尊號(ヲ)1、古今恆典(ナリ)、自v今以後、宜v奉v稱2岡宮(ニ)御宇(シ)天皇1、稱徳天皇、天平神護元年冬十月辛未、行2幸紀伊(ノ)國(ニ)1、發酉、過2檀山(ノ)陵(ヲ)1詔2陪從百官(ニ)1、悉令3下v馬、儀衛卷2其旗幟(ヲ)1、とあり、味橿丘の西一里許に越村あり、其(ノ)南に眞弓村といふありとぞ、 ○御在香乎《ミアラカヲ》、古事記に、御舍、書紀神代卷に、殿、神武天皇(ノ)卷に、大莊、崇神天皇(ノ)卷に、大殿など、皆ミアラカと訓り、古語拾遺に、瑞殿、古語/美豆能美阿良加《ミヅノミアラカ》、又建(テ)2都(ヲ)橿原(ニ)1、經2營帝宅1、仍令d天冨(ノ)命(ヲシテ)、率(テ)2手置帆負、彦狹知、二神之孫(ヲ)1、以2齋斧齋鉏1、始採2山材(ヲ)1構c立《ツクラ》正殿(ヲ)u、故其裔、今在2紀伊(ノ)國名草(ノ)郡御木麁香二郷(ニ)1、古語(ニ)、正殿、謂2之麁香(ト)1、採v材(ヲ)齋部(ノ)所v居謂2之(ヲ)御木(ト)1、造v殿(ヲ)齋部(ノ)所v居、謂2之麁香(ト)1、是其證也、また大殿祭(ノ)祝詞に、皇御孫之命乃《スメミマノミコトノ》、天之御翳日之御翳止《アメノミカゲヒノミカゲト》、造奉仕禮流《ツクリツカヘマツレル》、瑞之御殿《ミヅノミアラカ》、古語(ニ)云、阿良可《アラカ》、など見えたり、阿良《アラ》は、其(ノ)義いまだ考得ず、可《カ》は、所《カ》の意にても有べし、(唯し余が、一(ツ)の考あれば、こゝに擧(ク)、阿良可《アラカ》は、阿禮都伎所《アレツキカ》の約りたるにや、禮都伎《レツキ》を切(ム)れば、理《リ》となるを、その理《リ》を、良《ラ》に轉して、阿良可《アラカ》と云る歟、阿禮都伎《アレツキ》といふ言は、一(ノ)卷に、藤原之大宮都加倍安禮衝哉處女之友者《フヂハラノオホミヤツカヘアレツクヤヲトメガトモハ》、又六(ノ)卷長歌に、八千年爾安禮衝之乍天下所知食跡《ヤチトセニアレツカシツヽアメノシタシロシメサムト》云々とある、安禮都伎《アレツキ》にて、顯齋《アレツク》といふ古言なり、猶この言は、一(ノ)卷に委く註り、さらば、天皇を顯齋奉仕《アレツキツカヘマツ》る所の意にて、安良可《アラカ》とは云なるべし、但し阿良可《アラカ》は、常に御阿良可《ミアラカ》、と御の言をしもそへて云を、阿禮都久《アレツク》といふ時は、御阿禮都久《ミアレツク》、と御《ミ》の言を添ては、いふべからねば、猶別意ならむか、されども阿良可《アラカ》は、既く大殿の名目《ナ》となりたる上の事なれば、御《ミ》の言をそへむも、妨なかるべければ、右の意なるべくや、人考へ正してよ、岡部氏が、御在香《ミアラノカ》は、御在所《ミアリカ》なり、といへるは、いかにぞや、もし其(ノ)意ならむには、御麻斯可《ミマシカ》、とこそいふべけれ、あなかしこ、天皇の大坐坐大御舍《オホマシマスオホミヤ》をしも、皇威《イツ》を畏敬《カシコミ》し古(ヘ)人の意として、在所《アリカ》などゝは、いかでいはむや、又古事記傳に、阿良可《アラカ》は、在波可《アリハカ》にても有べし、波可《ハカ》は、いづこをはか、など云|波加《ハカ》にて、慥にそこと定まりたる處を云、理波《リハ》を切れば、良《ラ》なりとあるも、同じくあまなひがたき、ことにこそありけれ、) ○高知座而《タカシリマシテ》は、言の意は、既く出たる處に云つ、さて陵に、大殿はよしなけれど、凡て薨《スギマ》せしをも、薨賜ひしさまにいはず、大かた現世に、在坐《オマシマシ》給ふさまにいへれば、かく云るぞ、 ○明言爾《アサゴトニ》は、(言は借(リ)字、)毎《ゴト》v朝《アサ》になり、こゝにては、毎日といはむがごとし、 ○御言不御問《ミコトトハサズ》は、問《トフ》をとはす、告《ノル》をのらすといふは、あがめいふ時の詞なれば、トハサズとよませむとて、不御問と書り、知《シラ》すを御知《シラス》、見《メ》すを御見《メス》、など書る類なり、さてこゝは、下に、束乃多藝能御門爾雖伺侍《ヒムガシノタキノミカドニサモラヘド》、昨日毛今日毛召言毛無《キノフモケフモメスコトモナシ》、と云ると、心同じくて、物をも仰られず、と云意なり、物いふことを、問(フ)といふは、古語の常なり、言不問木尚《コトトハヌキスラ》、などよめるも、物いはぬといふ意なり、崇神天皇(ノ)紀に、不言を、マコトトハズとよめるをも思べし、 ○日月之は、ツキヒノと訓べし、日月と書るは、から國の熟字の隨《マヽ》を、用たるなれば、それには拘はらずして、古言のまゝに、ツキヒと訓は宇美可波《ウミカハ》を河海、欲流比流《ヨルヒル》を晝夜、と書たるが如し、此(ノ)下に、久堅之天所知流君故爾《ヒサカタノアメシラシヌルキミユヱニ》、日月毛不知戀渡鴨《ツキヒモシラニコヒワタルカモ》、とあるも同し、三(ノ)卷に、歳月日香《トシツキヒニカ》、四(ノ)卷に、白妙乃袖解更而遷來武《シロタヘノソデトキカヘテカヘリコム》、月日乎數而往而來猿尾《ツキヒヲヨミテユキテコマシヲ》、十(ノ)卷に、擇月日逢義之有者《ツキヒヱリアヒテシアレバ》、十五に、安良多麻能月日毛伎倍奴《アラタマノツキヒモキヘヌ》、十七に、草枕多妣伊爾之伎美我可敝里許武《クサマクラタビイニシキミガカヘリコム》、月日乎之良牟須邊能思良難久《ツキヒヲシラムスベノシラナク》、又/春花能宇都路布麻泥爾相見禰婆《ハルハナノウツロフマデニアヒミネバ》、月日餘美都追伊母麻都良牟曾《ツキヒヨミツヽイモマツラムソ》、十八に、月日余美都追《ツキヒヨミツヽ》、廿(ノ)卷に、月日餘美都々《ツキヒヨミツヽ》などあるは、みな古言のまゝに書たるなり、(これらは、月次《ツキナミ》日次《ヒナミ》の月日を云るなれば、から字《モシ》にはかゝはらず、都伎比《ツキヒ》といふが、定りたる言なること、古(ヘ)より後までもしかり、)又此(ノ)照す日月をば、なほ比都伎《ヒツキ》といひて、月次《ツキナミ》日次《ヒナミ》をいふ都伎比《ツキヒ》に分てるか、とおもふよしあり、(さるは月次日次をいふには、上に引ることく、月日と書たるが多きに、此てらす日月をいへるには、此(ノ)下に、天地日月與共《アメツチヒツキトトモニ》、五(ノ)卷に、許能提羅周日月能斯多波《コノテラスヒツキノシタハ》、又/日月波安可之等伊倍騰安我多米波照哉多麻波奴《ヒツキハアカシトイヘドアガタメハテリヤタマハヌ》、六(ノ)卷に、天地之遠我如日月之長我如《アメツチノトホキガゴトクヒツキノナガキガゴトク》、十三に、天地與日月共萬代爾母我《アメツチトヒツキトトモニヨロヅヨニモガ》、十九に、天地日月等登聞仁《アメツチヒツキトトモニ》、廿之卷に、天地乎弖良須日月能極奈久《アメツチヲテラスヒツキノキハミナク》など、いづれも日月とのみ書たれば、古(ヘ)より、これをば都伎比《ヒツキ》といへるか、但(シ)十三に、天有哉月日如吾思有《アメナルヤツキヒノゴトクアガモヘル》とあれば、なほいつれをも、都伎比《ツキヒ》といへるか、又は此(ノ)てらす日月をいふに、月日と書るは、たゞ一首なれば、月日とあるは、月日を、下上に誤寫せるにもあるべし、) ○數多成塗は、マネクナリヌレと訓べし、ヌレは、ヌレバの意なり、 ○皇子之宮人《ミコノミヤヒト》は、大舍人等《オホトネリドモ》のことなり、 ○行方不知毛《ユクヘシラズモ》、舊本に、一(ニ)云、刺竹之皇子宮人歸邊不知爾爲と註せり、(此(レ)は用べからず、數多成塗、といふよりのつゞきも、必(ズ)其故《ソコユヱ》とあるべく、はた不知爾爲《シラニスル》といふも、てにをはとゝのひがたければなり、)行かたもしらず、退き散ぬるは、さてもさてもかなしき事となり、毛《モ》は、歎息(ノ)辭なり、さて由縁母無《ツレモナキ》といふより此(レ)までの意は、よりたのみ賜ふべき人もなき、眞弓の崗に安定《シヅマリ》いまして、日毎に物を仰せらるゝこともなくて、月日の數《カズ》多《オホ》く積りぬれば、それ故に、親くめしつかはしゝ、大舍人のともゝ、行方しらず退《アガ》れ散ぬるが、さてもさても悲しやとなり、御墓づかへの日數終て、退散《アガル》さま、おもひやられ、あはれにかなし、下の高市(ノ)皇子(ノ)尊の殯宮の時、この朝臣の、長歌の反歌にも、去方乎不知舍人者迷惑《ユクヘヲシヲニトネリハマドウ》とあり、かくて其(ノ)長歌等を見るに、春宮(ノ)舍人にて、此時もよまれしなるべし、 ○歌(ノ)意は、天地の判れ始めて、高天(ノ)原に、事始めし給ひし時に、天の安(ノ)河原に、八百萬の神等の、神集ひいまして、神分し給ひしほど、已く天上を、天照大御神の、しろしめす國ぞ、此(ノ)天(ノ)下水穗(ノ)國を、皇孫|番能邇々藝《ホノニヽギノ》尊の、天地と長(ク)久しく、しろしめすべき國ぞと定め給ひて、天の八重雲を掻別て、天くだし座《イマ》せ奉りし、その大御裔孫《オホミスヱ》天武天皇は、明日香(ノ)清御原(ノ)宮にして、御宇《アメノシタシロシメシ》しを、つひに高天(ノ)原を、敷座(ス)國として上りましぬ、されば天つ日嗣の皇子、日並所知《ヒナミシラスノ》皇子(ノ)尊の、大御位に上りまし、天下しろしめす御代になりせば、國家も美《メデ》たく榮え、普き大御恩澤《オホミウツクシミ》は、天(ノ)下に、落るくまなく、滿足はしてあらむぞ、と四方八方の人の、ふかく思ひたのみて仰ぎ待しかひもなく、いかやうにおぼしめせばか、此(ノ)世をはやくさり座けむ、さてしも、よりたのみ給ふべき人さへもなき、檀(ノ)岡に宮柱太高敷(カ)して、安定座《シヅマリマシ》ませば、もとより親くしたがひ奉れる輩は、のこらず慕ひ行てさぶらへど、侍ふかひもなく、日ごとに物仰せらるゝこともなくて、たゞ哀しみ歎きてのみある間に、いつしかはやき月日のとゞまらずして、御墓づかへの日數も竟ぬれば、退散《アガル》とて人々別々に、行方もしらずなりぬるは、いともあはれにかなしくあさましくなげかしき事どもにぞ、ありけるとなり、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 口訳 | 日竝知皇子尊《ヒナメシノミコノミコト》を殯宮《アラキノミヤ》に移し奉つた時、柿本(ノ)人麻呂が作つた歌、並びに短歌。二首 天地《アメツチ》の始めの時し、ひさかたの天《アマ》の川原《ガハラ》に、八百萬千萬神《ヤホヨロヅチヨリヅガミノ》の、神集《カムツド》ひ集《つど》ひいまして、神謀《カムハカ》り計りし時に、天照す日〓女《ひるめ》の尊、天《アメ》をば知《シロ》しめすと、蘆原の瑞穗《ミヅホ》の國を、天地の寄り合ひの極み、知ろしめす神の尊と、天雲《アマグモ》の八/重《ヘ》掻き分けて神下《カムクダ》り坐《イマ》せ奉《マツ》りし、たかひかる日の御子は、飛鳥《アスカ》の淨見《キヨミ》个原に神ながら太敷《フトシ》き坐《マ》して、皇祖《スメロギ》の敷きます國と、天《アマ》の原《ハラ》磐戸《イハト》を開き、神/上《アガ》り上《アガ》り坐《イマ》しぬ。我《ワゴ》大君/皇子《ミコ》の尊の、天《アメ》の下|知《シロ》し召しせば、春花《ハルバナ》の尊《タフト》からむと、望月《モチヅキ》の圓滿《タヽハ》はしけむと、天の下/四方《ヨモ》の人のおほぶねの思ひ憑《タノ》みて、あまつみづ仰ぎて待つに、如何樣《イカサマ》に思ほしめせか、つれもなき檀《マユミ》の岡に、宮柱/太敷《フトシ》き坐《イマ》し、御家《ミアラカ》を高著《タカシ》りまして、朝毎に御言《ミコト》問はさず、月日の多《マネ》くなりぬる、其故《ソコユヱ》に皇子の宮人行/方《ヘ》知らずも 神代に歸つて考へるに、かの天地の始つた時、天の河原に、ある限りの神が集つて、それぞれ座に著かれて、評議のあつた時分に、天照皇大神が、御自身は、高天原を御治めになることを定め、日本の國をば、天と地との境目迄も、すつかり、治められる尊い方と御定めになつて、幾重にも重なり合うた雲を、かき分けて下しておよこしになつた、其日の神の御/裔《スヱ》なる天皇陛下は、飛鳥の淨見《キヨミ》个/原《ハラ》に、神樣其儘の御心で、御所を御建てになつて、其後、高天个原は、皇祖天照大神の、治めて入らつしやる國だから、といふので、高天个原へ通ふ岩戸を押し開けて、神樣としてお上りになつた。其で其御世嗣なる、私どもがお仕へ申して居る皇子《ミコ》樣が、世の中をお治めになる樣になれば、春咲く花のやうに、立派にあらうと思ひ、十五夜の月のやうに、十分であらう、と世の中の凡ての人たちが、大舟に乘つたやうな氣で、たよりにし、旱魃《ヒデリ》に雨を待つやうに、早く御位に即いて下さるやうに、と待つて居るのに、どんな風に御考へなさつたのか、あの寂しい檀《マユミ》の岡に御所の太い柱を御立てになり、御殿を高く御造りになつて、其處におちつき遊ばされ、以前は朝になれば、御側つきの者に、物を抑つしやつたが、此御所に御出でになつてからは、何も仰つしやらずに、日數が澤山たつたことのその爲に、御側仕への人は、用もなくなつて、皆何處へ行つてよいか、訣らずに迷うてゐることだ。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 日並皇子尊《ヒナメシノミコノミコト》殯宮《アラキノミヤ》之時、柿本朝臣人麿作歌一首並短歌 日並皇子尊は草壁皇太子。文武天皇の御父。朱鳥三年四月薨。御年二十八。殯宮之時は御喪の時といふ意である。元來殯は死して未だ葬らず、假に棺に斂めて賓客として待遇する意であるが、漢字本來の用法とは異つて本集では、葬り奉つた後、御墓所に奉仕する間を殯宮之時といふのである。 天地の 初の時し ひさかたの 天の河原に 八百萬 千萬神の 神集ひ 集ひいまして 神はかり はかりし時に 天照らす ひるめの尊 一云、さしのぼる 日女の命 天をば 知ろしめすと 葦原の 瑞穗の國を 天地の 依り合ひの極み 知ろしめす 神の命と 天雲の 八重かき別きて 一云、天雲の八重雲別きて 神下し いませまつりし 高照らす 日の皇子は 飛鳥の 淨みの宮に 神ながら 太敷きまして すめろぎの 敷きます國と 天の原 岩戸を開き 神上り 上りいましぬ 一云、神登りいましにしかば わが大王 皇子の命の 天の下 知ろしめしせば 春花の 貴からむと 望月の 滿《たた》はしけむと 天の下 一云、食す國 四方の人の 大船の 思ひ憑みて 天つ水 仰ぎて待つに いかさまに 思ほしめせか つれもなき 眞弓の岡に 宮柱 太敷きまし みあらかを 高知りまして 朝ごとに 御言問はさず 日月の まねくなりぬれ そこ故に 皇子の宮人 行方知らずも 一云、刺竹の 皇子の宮人 行方知らにす 天地之《アメツチノ》 初時之《ハジメノトキシ》 久堅之《ヒサカタノ》 天河原爾《アマノカハラニ》 八百萬《ヤホヨロヅ》 千萬神之《チヨロヅカミノ》 神集《カムツドヒ》 集座而《ツドヒイマシテ》 神分《カムハカリ》 分之時爾《ハカリシトキニ》 天照《アマテラス》 日女之命《ヒルメノミコト》【一云|指上《サシノボル》 日女之命《ヒルメノミコト》】 天乎波《アメヲバ》 所知食登《シロシメスト》 葦原乃《アシハラノ》 水穗之國乎《ミヅホノクニヲ》 天地之《アメツチノ》 依相之極《ヨリアヒノキハミ》 所知行《シロシメス》 神之命等《カミノミコトト》 天雲之《アマグモノ》 八重掻別而《ヤヘカキワケテ》 【一云|天雲之《アマグモノ》 八重雲別而《ヤヘクモワキテ》】 神下《カムクダシ》 座奉之《イマセマツリシ》 高照《タカテラス》 日之皇子波《ヒノミコハ》 飛鳥之《アスカノ》 淨之宮爾《キヨミノミヤニ》 神髄《カムナガラ》 太布座而《フトシキマシテ》 天皇之《スメロギノ》 敷座國等《シキマスクニト》 天原《アマノハラ》 石門乎開《イハトヲヒラキ》 神上《カムアガリ》 上座奴《アガリイマシヌ》【一云|神登《カムノボリ》 座爾之可婆《イマシニシカバ》】 吾王《ワガオホキミ》 皇子之命乃《ミコノミコトノ》 天下《アメノシタ》 所知食世者《シロシメシセバ》 春花之《ハルハナノ》 貴在等《タフトカラムト》 望月乃《モチヅキノ》 滿波之計武跡《タタハシケムト》 天下《アメノシタ》【一云|食國《ヲスクニ》】 四方之人乃《ヨモノヒトノ》 大船之《オホブネノ》 思憑而《オモヒタノミテ》 天水《アマツミヅ》 仰而待爾《アフギテマツニ》 何方爾《イカサマニ》 御念食可《オモホシメセカ》 由縁母無《ツレモナキ》 眞弓乃崗爾《マユミノヲカニ》 宮柱《ミヤバシラ》 太布座《フトシキマシ》 御在香乎《ミアラカヲ》 高知座而《タカシリマシテ》 明言爾《アサゴトニ》 御言不御問《ミコトトハサズ》 日月之《ヒツキノ》 數多成塗《マネクナリヌレ》 其故《ソコユヱニ》 皇子之宮人《ミコノミヤビト》 行方不知毛《ユクヘシラズモ》【一云|刺竹之《サスタケノ》 皇子宮人《ミコノミヤヒト》 歸邊不知爾爲《ユクヘシラニス》】 天地開闢ノ始ニ、(久堅之)天ノ安河原ニ數多ノ神樣達ガ御集リナサレテ、御相談遊バシタ時ニ、天照大御神、即チ〔二字傍線〕大日〓命ガ、天ヲ御支配ナサルノデ、葦原ノ水穗ノ國ヲ、天ト地トガ相合シテ一トナルヤウナ、極リノ無イ後ノ世マデモ、天地ノアラン限リ〔八字傍線〕、御支配ナサル神樣トシテ、皇孫瓊瓊杵命ヲ〔七字傍線〕、天ノ雲ノ、幾重ニモ重ツタ中ヲ押シ分ケテ、天降ラセ申シナサレタ。昔ハ斯樣ニシテ皇孫ガ天降リ遊バシタガ、天武天皇ト申ス〔昔ハ~傍線〕(高照)天子樣ガ飛鳥ノ淨御原ノ宮ニ、昔ノ神樣ノママニ、大キク御構ヘナサレテ、天下ヲ御治メナサレタガ、天ハ〔テ天~傍線〕天子樣ガ、御支配ナサル國ダトシテ、天ノ岩戸ヲ開イテ神樣トナツテ、天ヘ御上リナサレテ、天ヲ御支配〔九字傍線〕ナサレタ。天武天皇樣ハ御崩レ遊バシタ。斯クテ〔天武~傍線〕、私ガ御仕ヘシテヰル皇子ノ日並皇子ガ將來ハ天子トナツテ、コノ〔將來~傍線〕天下ヲ御支配遊バシタナラバ、サゾカシ、(春花之)結構ナコトデアラウ、又、(望月乃)、何モ缺ケルコトナク滿足デアラウトテ、天下ノ四方ノ人等ガ、擧ツテ〔三字傍線〕(大船之)當ニシテ思ツテ居テ、(天水)仰イデ、サウナルコトヲ〔七字傍線〕待ツテ居タノニ、日並皇子ハ〔五字傍線〕何ト思召シテカ、カヤウナ縁故ノナイ眞弓ノ岡ニ、宮ノ柱ヲ太ク御構ヘナサレテ、御殿ヲ高ク御作リナサレテ、御薨去遊バシテ眞弓ノ岡ヲ御墓トナサツタノデ〔御薨~傍線〕、毎朝毎朝何トモ〔三字傍線〕物モ仰セラレズ、月日バカリガ數多過ギマシタ。斯樣ニ御薨去ノ後、月日ガ多ク過ギタノデ、御墓ノ邊ニ仕ヘテヰタ〔十字傍線〕コノ皇子ノ御側付ノ人〔五字傍線〕タチモ、ドウシテヨイカ、途方ニクレテヰルヨ。 ○初時之《ハジメノトキシ》――之《シ》の宇無い本もある。 ○神分分之時爾《カムハカリハカリシトキニ》――分をハカルとよむのを疑つて、カムアガチ又はカムクバリなどの訓があるが、分の字美夫君志によれば、字鏡集にハカルとよんでゐるとあり、神集集賜比神議議賜氐《カムツドヒニツドヒタマヒカムハカリニハカリタマヒテ》、は古事記や祝詞の成語であるから、他によみ方はない。又、八百萬の神の集會で、神の知り給ふ所の、分配を議したことは無い。 ○天照日女之命《ァマテラスヒルメノミコト》――天照大御神を書紀に「生2日神1、號2大日〓貴《オホヒルメノムチ》1」とある。 ○葦原乃水穗之國乎《アシハラノミヅホノクニヲ》――古事記に、豐葦原之千秋長五百秋之水穗國《トヨアシハラノチアキノナガイホアキノミヅホノクニ》とあり。葦原に包まれた國で、みづみづしく稻穗の榮える國といふ意である。但し水穗を水田の穗と見る説もある。我が國の地味肥沃を賞めた稱呼である。 ○天地之依相之極《アメツチノヨリアヒノキハミ》――天地は元來一體であつたのが分離したのであるから、又何時か相合して一體となるものとして、その極限の際までの意。○神下座奉之《カムクダリイマセマツリシ》――神が下り給ふのであるから、神下りである。座奉之《イマセマツリシ》は、神下りをおさせ申したといふやうな意。これは皇孫瓊々杵尊を申し奉るのであるが、次への續きは、その御系統の天皇を申すのが常である。ここは次に高照日之皇子波《タカテヲスヒノミコハ》として、天武天皇を申してゐる。○天皇之敷座國等《スメロギノシキマスクニト》――天皇の支配し給ふ國なりとての意で、天皇の崩御を天を支配し給ふことと古代人は考へたのである。 ○石門(186)乎開神上上座奴《イハトヲヒラキカムアガリアガリイマシヌ》――天の石門を開けて、天上せられたといふので、これは天皇の崩御などについて、言ふ言葉である。○吾王皇子之命乃《ワガオホキミミコノミコトノ》――日並皇子を申し奉る。 ○春花之《ハルハナノ》――枕詞。春の花の榮えて美はしいのを貴しとつづけたのであらう。 ○望月乃《モチヅキノ》――滿月の如くの意。枕詞。 ○滿波之計武跡《タタハシケムト》――卷十三に十五月之多田波思家武登《モチヅキノタタハシケムト》(三三二四)とあるに同じく、たたはしくあらむとの意。たたはしは滿ちて缺けざること。 ○大船之《オホブネノ》――思憑而《オモヒタノミテ》の枕詞。大きい船に乘れば、心が安じて憑みとするからである。 ○天水《アマツミヅ》――雨のこと、仰而待爾《アフギテマツニ》の枕詞。空を仰ぎて雨を待つからである。 ○何方爾御念食可《イカサマニオモホシメセカ》――何と思召せばかの意。 ○由縁母無《ツレモナキ》――由縁は舊訓ユヱであるが、卷三に何方爾念鷄目鴨都禮毛奈吉佐保乃山邊爾《イカサマニオモヒケメカモツレモナキサホノヤマベニ》(四六○)・卷十三に何方御念食可津禮毛無城上宮爾《イカサマニオモホシメセカツレモナキキノヘノミヤニ》(三三二六)とあるからツレモナキがよい。縁故の無い意である。 ○眞弓乃岡爾《マユミノヲカニ》――高市郡坂合村大字眞弓にある岡。挿入した寫眞は、橘寺から西方を望んだ景で、遠景左方は金剛山、右方は葛城山。金剛山の前に見える丘陵の右が眞弓の丘で、左が佐田の丘である葛城山の前面に見える丘陵が、天武・持統兩帝の檜隈大内陵である。 ○御在香乎《ミアラカヲ》――御在處《ミアリカ》の意。宮殿。 ○高知座而《タカシリマシテ》――高く構へ給ひての意。 ○明言爾《アサゴトニ》――朝毎に。 ○御言不御問《ミコトトハサズ》――御言葉を宣はずの意。コトトフは物を言ふことである。 ○日月之《ヒツキノ》――考にツキヒノとよんであるが、文字通りがよからう。 ○數多成塗《マネクナリヌレ》――物の頻りなることをマネクといふ。ヌレはヌレバに同じ。 ○皇子之宮人行方不知毛《ミコノミヤビトユクヘシラズモ》――日並皇子の宮に奉仕した舍人どもは、途方にくれてゐるといふのである。 〔評〕 天地開闢から、天孫降臨へと説き起すのが、人麿の好んで用ゐた手法だ。さうして皇室の尊嚴を、口を極めてたたへてゐる。天皇の崩御を天原石門乎開神上上座奴《アマノハライハトヲヒラキカムアガリアガリイマシヌ》などと言つてゐるのは、實に神々しい表現法である。皇子の薨去を何方爾御念食可由縁無眞弓乃崗爾《イカサマニオモホシメセカツレモナキマユミノヲカニ》云々といぶかしげに言つて、露骨な述法を避けたのも巧みである。後の高市皇子尊城上殯宮之時の歌には及ばないが、典重の調に悲凉の氣を盛つた佳作である。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 日竝皇子尊殯宮之時、柿本朝臣人麻呂作歌一首 并2短歌1 日竝みし皇子の尊の殯《あらき》の宮の時に、柿本の朝臣人麻呂の作れる歌一首【短歌并はせたり。】 【釋】 日竝皇子尊 ヒナミシミコノミコト。既出(卷二、一一〇)。天武天皇の皇子、御母は皇后(持統天皇)。天武天皇の十年、皇太子となり、持統天皇の三年四月、薨去、御年二十八。 殯宮之時 アラキノミヤノトキ。人の死してまだ葬らない前に祭を行うを殯という。殯宮は、その祭を行う宮殿。皇子の御墓所は、奈良縣高市郡の眞弓の岡にあり、そこにまず宮殿を新設して殯を行われたのである。しかし本集では、墓前の祭をも殯というらしい。作者柿本の人麻呂は、皇子の生前、舍人として奉仕し、殯宮にも奉仕してこの歌を作つたと考えられる。 天地の 初めの時、 ひさかたの 天《あま》の河原に、 八百萬《やほよろづ》 千萬神《ちよろづがみ》の、 神集《かむつど》ひ 集《つど》ひいまして、 神分《かむわか》ち 分ちし時に、 天照らす 日女《ひるめ》の命《みこと》、【一は云ふ、さしのぼる日女の命。】 天をば 知らしめせと、 葦原の 瑞穗の國を、 天地の 寄り合ひの極《きは》み、 知らしめす 神の命《みこと》と、 天雲《あまぐも》の 八重かき別きて、【一は云ふ、天雲の八重雲別きて。】 神下《かむくだ》し 坐《いま》せまつりし 高照らす 日の皇子《みこ》は、 飛ぶ鳥の 淨《きよ》みの宮に 神《かむ》ながら 太敷《ふとし》きまして、 天皇《すめろき》の 敷きます國と、 天の原 石門《いはと》を開き 神上《かむあが》り 上り坐《いま》しぬ。【一は云ふ、神登りいましにしかば。】 わが大王 皇子の命の、 天の下 知らしめしせば、 春花の 貴からむと、 望月《もちづき》の 滿《たた》はしけむと、 天の下【一は云ふ、食す國の。】四方《よも》の人の、 大船の 思ひ憑《たの》みて、 天《あま》つ水 仰ぎて待つに、 いかさまに 念ほしめせか、 由縁《つれ》もなき 眞弓《まゆみ》の岡に、 宮柱 太敷きまし、 御殿《みあらか》を 高知りまして、 明言《あさごと》に 御言《みこと》問はさず、 日月《ひつき》の 數多《まね》くなりぬれ、 そこ故に 皇子の宮人 行く方知らずも。」【一は云ふ、さす竹の皇子の宮人、行く方知らにす。】 天地之《アメツチノ》 初時《ハジメノトキ》 久堅之《ヒサカタノ》 天河原尓《アマノガハラニ》 八百萬《ヤホヨロヅ》 千萬神之《チヨロヅガミノ》 神集《カムツドヒ》 集座而《ツドヒイマシテ》 神分《カムワカチ》 分之時尓《ワカチシトキニ》 天照《アマテラス》 日女之命《ヒルメノミコト》【一云指上日女之命】 天乎婆《アメヲバ》 所v知食登《シラシメセト》 葦原乃《アシハラノ》 水穗之國乎《ミヅホノクニヲ》 天地之《アメツチノ》 依相之極《ヨリアヒノキハミ》 所v知行《シラシメス》 神之命等《カミノミコトト》 天雲之《アマグモノ》 八重掻別而《ヤヘカキワキテ》【一云天雲之八重雲別而】 神下《カムクダシ》 座奉之《イマセマツリシ》 高照《タカテラス》 日之皇子波《ヒノミコハ》 飛鳥之《トブトリノ》 淨之宮尓《キヨミノミヤニ》 神隨《カムナガラ》 太布座而《フトシキマシテ》 天皇之《スメロキノ》 敷座國等《シキマスクニト》 天原《アマノハラ》 石門乎開《イハトヲヒラキ》 神上《カムアガリ》 上座奴《アガリイマシヌ》【一云、神登座尓之可婆】 吾王《ワガオホキミ》 皇子之命乃《ミコノミコトノ》 天下《アメノシタ》 所v知食世者《シラシメシセバ》 春花之《ハルバナノ》 貴在等《タフトカラムト》 望月乃《モチツキノ》 滿波之計武跡《タタハシケムト》 天下《アメノシタ》【一云、食國】 四方之人乃《ヨモノヒトノ》 大船之《オホブネノ》 思憑而《オモヒタノミテ》 天水《アマツミヅ》 仰而待尓《アフギテマツニ》 何方尓《イカサマニ》 御念食可《オモホシメセカ》 由縁母無《ツレモナキ》 眞弓乃岡尓《マユミノヲカニ》 宮柱《ミヤバシラ》 太布座《フトシキマシ》 御在香乎《ミアラカヲ》 高知座而《タカシリマシテ》 明言尓《アサゴトニ》 御言不2御問1《ミコトトハサズ》 日月之《ヒツキノ》 數多成塗《マネクナリヌレ》 其故《ソコユヱニ》 皇子之宮人《ミコノミヤビト》 行方不v知毛《ユクヘ》《シラズモ》【一云、刺竹之皇子宮人歸途不知尓爲】 【譯】 天地の開け始めたときに、高天の原の天の河原に、多數の神樣がお集まりになつて、方々の世界を分けた時に、天照らす大神は高天の原をば知ろしめせと定め、また葦原の瑞穗の國をば、天地が依り合つている限り永久に知ろしめす神樣として、天雲の八重を掻き分けてお下し申した輝く日の皇子樣は、飛ぶ鳥の淨みの宮に神にましますがままに御座遊ばされて、その後御歴代の天皇のまします國として、天の原の岩戸を押し開いてお登りになりました。かくてわが大君と仰ぐ皇子樣が、天下を御統治遊ばされましたなら、春の花のように貴いことでありましょうと、また秋の滿月のように滿ち足りてあるでしょうと、天下の四方の人々が大船のように頼みに思つて、天から降る雨露を仰ぐように仰いで待つていましたところ、どのようにお思いになつてか、縁故も無い眞弓の岡に宮柱をお建て遊ばされ、御殿を御建造遊ばされて、朝の御言葉をお下しにならず、過ぎ行く月日も多くなつて行きましたので、それゆえにわが皇子の宮の人々は、何とも途方に暮れていることであります。 【構成】 この歌は二段から成つている。初めから「神上り上り坐しぬ」まで第一段、天地開闢以來の事から敍し、天武天皇の上までを敍している。わが大君以下第二段、ここに草壁の皇子の薨去せられ御墓の前に殯宮を造つて、お祭り申し上げることを敍している。第二段に中心があり、第一段は準備的敍述である。 【釋】 天地之初時―- アメツチノハジメノトキ。アメツチは、天と地で、世界、宇宙の意をあらわす。元來アメに對しては、クニの語が對語として使用されていた。クニは、人文的な意味において地上をいう語であるが、大陸から天地の熟字が渡來するに及んで、物質的な意味に、アメツチの譯語が採擇された。その初めの時とは、宇宙の始期をいい、古事記の天地初發の時というのと同じである。 天河原尓―- アマノガハラニ。アマノガハラは、天上にあるという川の河原。古事記に安の河原という。 八百萬千萬神之―- ヤホヨロヅチヨロヅガミノ。ヤホヨロヅもチヨロヅも、極めて多數の義にいい、疊語を以つて表現している。「五百萬《イホヨロヅ》 千萬神之《チヨロヅガミノ》」(卷十三、三二二七)というも同じである。 神集集座而―- カムツドヒツドヒイマシテ。神の動作を述べる動詞に、カムの語をつけていうことは、續いて神分チ分チシ時ともいい、「神留坐」(祈年祭祝詞)、「神問【志爾】問志賜、神拂掃賜【比氐】(大祓の詞)など用例が多い。カムツドヒイマスとは、神の集合される意であつて、「是以、八百萬神、於2天安之河原1、神集々而【訓v集云2都度比1】」(古事記上卷)とあると同意である。 神分分之時尓―- カムワカチワカチシトキニ。カムハカリハカリシトキニ(舊訓)、カンクハリクハリシトキニ(童)、カムアガチアガチシトキニ(古義)等の諸訓がある。カムワカチワカチシトキニは、代匠記の一説である。分をハカルと讀むのは、議するの意によるものであるが、分をハカルと讀むのは無理であつて、ワカツと讀むことの正常なのに及ばない。ワカツとは、神々をそれぞれの國土に配分して領知せしめる義であつて、天地の初めに、かようなことがなされたことは、古事記日本書紀の記事には見えないが、古くはさような神話もあつたことと考えられる。その例證としては、日本書紀、垂仁天皇紀、一云に、「是時、倭大神、著2穗積臣遠祖大水口宿禰1而誨之曰、太初之時、期曰、天照大神、悉治2天原1、皇御孫尊、專治2葦原中國之八十魂神1、我親治2大地官1者、言已訖焉」とある。これは倭の大神の託宣の詞であるが、その内容は、よくこの人麻呂の歌にいう所と一致する。かような神話があつて、託宣の詞ともなつたものなるべく、この神話は、古事記日本書紀の結成に當つては、異端として削り去られたのであろぅ。柿本氏は、倭の大神を祭る大和神社の鎭座する處から遠くない地に住み、かような神話を傳えて、この歌ともなつたのであろう。この歌は、古事記日本書紀の成立以前に作られたので、かような傳えによつたと見るべく、すべて文字に表示されていることに基いて訓詁はなさるべきである。すなわち神々が天の河原に集合されて、領知すべき世界を分かつた時に、天照らす大神には高天の原、皇御孫の尊には葦原の水穗の國を配當されたというのである。 天照日女之命―- アマテラスヒルメノミコト。天照らす大神に同じ。日本書紀神代の上に、「於v是共生2日神1、號2大日〓貴1【大日〓貴、此云2於保比屢咩能武智1】」とあり、その一書に「天照天日〓尊」とある。日の女神の義である。 一云指上―- アルハイフ、サシノボル。サシノボルは枕詞。日に冠する。 天乎婆所知食登―- アメヲバシラシメセト。天照らす大神に、天を統治したまえと定められたの意。トは、上文を受けて、文を中止し、またの意に次の文につづく。 葦原乃水穗之國乎―- アシハラノミヅホノクニヲ。以下別の事になるから、句の上に、マタの如き語を補つて解すべきである。葦原の水穗の國は日本の別名で、古事記日本書紀にもしばしば見えている。古事記天孫降臨の段には「豐葦原之千秋長五百秋之水穗國」とあり、日本書紀神代の下には、これを漢譯して「葦原千五百秋之瑞穗國」とある。葦原とは、アシの自生している原野をいい、やがて開發して豐穣な美田とすべき素質の地であることを表示する。千秋の長五百秋、もしくは千五百秋とは、永久の年數をいい、秋とは穀物の成熟する季節であつて、これを以つて年の意味を表示する。水穗もしくは瑞穗とは、生々たる穀物の穗であり、それはイネを代表としてアワその他の穀物をも含んでいう。永久に穀物の生々として成熟する國の義である。これに葦原ノを冠するのは葦原の地で永久に穀物の成熟する國の意である。それを略して葦原の水穗の國というのである。契沖の萬葉代匠記には、「舊事記ヲ初テ及ヒ此集ニ至ルマテ、只、葦原瑞穗國ト云ヒ、此集第二ニハ、人麿歌ニ、葦原トモ云ハスシテ、水穗國トノミモヨマレタレハ、稻穗ニハアラス」とて、古く稻の穗について稱美する詞とされているのを否定し、葦原を美《ホ》めたので、アシの穗の瑞穗の國であるとしている。しかしなお穀物の穗についていうとすべきである。これは日本の國土をいい、その國土を知ろしめすために、天孫が降下されるとする思想である。 天地之依相之極―- アメツチノヨリアヒノキハミ。永久の意味を、具體的にあらわしていることは、「天地乃依會限《アメツチノヨリアヒノカギリ》 萬世丹《ヨロヅヨニ》 榮將v往迹《サカエユカムト》」(卷六、一〇四七)、「天地之《アメツチノ》 依相極《ヨリアヒノキハミ》 玉緒之《タマノヲノ》 不v絶常念《タエジトオモフ》 妹之當見津《イモガアタリミツ》」(卷十一、二七八七)などの例に徴してもあきらかである。語義については、一旦分かれた天地が、遠く久しい世のはてにふたたび合體しよう時までと解せられている。この語の參考としては、「轉雲乃《アマグモノ》 曾久敝能極《ソクヘノキハミ》(卷三、四二〇)の語があるが、これは天雲の退く方を限界とする意に解せられ、これに準じて考えるとすれば、天地の寄り合いを限界とする意に解すべきである。これを將來天地の寄り合うのを限界とする意に解しようとするは無理である。天地がたがいに寄り合つて、宇宙を構成している、その寄り合いの解けないあいだはの意とすべきである。 所知行―- シラシメス。この行の字の用法は古事記に、看行(中卷)、見行(下卷)、續日本紀に、所見行、所知行須などある例であつて、おこなう意に添えるといわれている。御統治になる意に、次の句の神の命を修飾する。 神之命等―- カミノミコトト。ミコトは尊稱。神樣として。 天雲之八重掻別而―- アマグモノヤヘカキワキテ。高天の原から葦原の水穗の國にお降りになる狀を説く。ヤヘは、天の雲の幾重ともなくかさなつているをいう。「押2分天之八重多那雲1而、伊都能知和岐知和岐弖、於2天津橋1、早岐士麻理蘇理多々斯弖、天2降坐于筑紫日向高千穗之久士布流多氣1」(古事記上卷)。「且排2分天八重雲1、稜威之道別道別而、天2降於日向襲之高千構峯1矣」(日本書紀、神代下)など傳えている。 天雲之八重雲別而―- アマグモノヤヘグモワキテ。本文の句と同じ意味を、語を變えて傳えている。 神下座奉之―- カムクダシイマセマツリシ。神々が、天孫をお降し申しての意。イマセは、敬語の使役法で、そうおさせ申すの意になる。高天の原からこの國に下したというのは、歴史的にいえば、天孫瓊々杵の尊であるが、下の句にこれを受けて、飛ブ鳥ノ淨ミノ宮ニ神ナガラ太敷キマシとあるによれば、その宮にましました方、すなわち天武天皇(もしくは日竝みし皇子の尊)ということになる。この國に御出現御降誕になつたことを、天から降られたという思想で表現しているのである。以上葦原ノ水穗ノ國からこの句まで、次の高照ラス日ノ皇子の修飾句になつている。 高照日之皇子波―- タカテラスヒノミコハ。この句は、天照ラス日女ノ命の句と竝んで、上の神分チ分チシ時ニを受けており、その意味でいえば、天孫の意になるが、それは思想としてであつて、實際的には、次の飛ぶ鳥の淨みの宮にいました方をさしている。文章の上からいえば、時代錯誤が行われている。 飛鳥之淨之宮尓―- トブトリノキヨミノミヤニ。トブトリノキヨミノミヤは、天武天皇の宮室である明日香の淨御原の宮である。日本書紀、天武天皇紀に、朱鳥元年七月の條に、「戊午、改v元曰2朱鳥元年1、仍名v宮曰2飛鳥淨御原宮1」とある。飛ぶ鳥の明日香といつた、その飛鳥の字を用いてただちにアスカの地名にも當て、本集にもアスカと讀むべきものがあるが、このあたりの歌中にはアスカの地名には、常に明日香とのみ書いているから、澤瀉博士の説によつて、トブトリノと讀むがよかろう。キヨミは淨み原のキヨミで體言になる。 神隨―- カムナガラ。既出(卷一、三八)。神なるがゆえに。 太布座而―- フトシキマシテ。既出(卷一、三六)。フトは雄大性を示す接頭語。シキは占有、領有の意の動詞。かく飛ぶ鳥の淨みの宮を御占有になるという敍述は、天武天皇の御事をいうと考えられる。この歌の主たる日竝みし皇子の歌について述べようとして、まず先帝の御上を敍したものである。但し卷の一、輕の皇子が安騎の野に出遊された時の歌に、太敷カス都ヲ置キとあるは、輕の皇子の事であるから、ここの太敷キマシテも、日竝みし皇子の尊に關することとしても解せられる。 天皇之―- スメロキノ。この天皇の語は、汎稱として使用せられ、主として、前の代の天皇をいう。 敷座國等―- シキマスクニト。領有せられる國として。クニは、高天の原をいう。トは、としての意。天皇は、統治の事終れば、天に還りたまうという思想である。 天原石門乎開―- アマノハライハトヲヒラキ。イハトは、堅固な門の義。イハは、岩石の義であるが、堅固の意に使われる。磐船などの例である。高天の原の入口に門戸ありとする思想である。日本書紀卷の二、神代の下、天孫降臨の章の第四の一書に、「引2開天磐戸1、排2分天八重雲1以奉v降之」とあるは、降下の記事であるが、磐戸を引きあけて降したとある。これは、墳墓の入口に岩を立てる風習と結合して、石門を開いて墳墓に入ることを、石門を開いて天に上るという形で表現するようになつたのである。そうして高天の原の入口に石門ありとする思想を生じたと見られる。 神上上座奴―- カムアガリアガリイマシヌ。神としての行動なので、神あがりという。アガリは天に昇る意。以上第一段、皇子の薨去のことを言おうとして、まず神話時代から説き起し、天武天皇の崩御にまで及んでいる。 神登座尓之可婆―- カムノボリイマシニシカバ。この別傳によれば、段落とならずに、以下の文に繼續することになる。この別傳では、上の高照らす日の皇子を以つて、日竝みし皇子の尊の事とする解釋は成立しない。これに依つても、第一段は、天武天皇の事を敍したとするを正解とすべきことが知られよう。 吾王皇子之命乃―- ワガオホキミミコノミコトノ。ワガオホキミは、皇子の命を修飾する。わが大君にまします皇子の命の意である。この皇子の命は、日竝みし皇子の尊をさす。 天下所知食世者―- アメノシタシラシメシセバ。天下を統治せられるとせばの意の假設條件法。皇子は皇太子であり、朱鳥元年九月天武天皇の崩御後即位せらるべきであつたが、その後四年目の四月に薨去されたのである。 春花之―- ハルバナノ。枕詞。譬喩によつて貴カラムを修飾している。春の花のように貴くあるだろうの意である。 貴在等―- タフトカラムト。天皇として仰ぐことが貴いだろうとの意で、下の思ヒ憑ミテに續く。 望月乃―- モチヅキノ。枕詞。十五夜の滿月のようにの意に、譬喩として、次の滿ハシに冠する。 滿波之計武跡―- タタハシケムト。タタハシは、滿ち足りてある意の形容詞で、動詞湛フから轉成したものである。靈異記に、偉にタタハシクの訓詁があり、本集に、「十五月之《モチヅキノ》多田波思家武登《タタハシケムト》」(卷十三、三三二四)の用例がある。タタハシケまでが形容詞で、シケは形容詞の活用形である。ムは助動詞。以上二句は、春花ノ貴カラムトの句と對句を成して、下の思ヒ憑ムに接續している。 食國―- ヲスクニノ。上の天ノ下の別傳である。御領土の意。本文の天ノ下の方が大きい。 四方之人乃―- ヨモノヒトノ。天下の諸方の人の意。 大船之―- オホブネノ。枕詞。大船は、安心せられ頼みになるので、憑ムに冠する。 思憑而―- オモヒタノミテ。心に信頼し思つて。 天水―- アマツミヅ。枕詞。天の水の義で、雨雪露の類をいい、その天から降るものなのにつけて、譬喩として仰グに冠する。「彌騰里兒能《ミドリゴノ》 知許布我其等久《チコフガゴトク》 安麻都美豆《アマツミヅ》 安布藝弖曾麻都《アフギテゾマヅ》」(卷十八、四一二二)。 仰而待尓―- アフギテマツニ。御即位になることを仰いで待つ所にの意。事實としては、天武天皇の崩後、適當の時期に、この皇子が即位せらるべきに定まつておつた。それが急速に運ばないで、母君なる皇后(持統天皇)が政務を見られたのは、大津の皇子の謀反があり、その他にも異腹の皇兄があつて、皇子の急速な即位を不便とする情勢にあつたものと考えられる。 何万尓御念食可―- イカサマニオモホシメセカ。既出(卷一、二九、卷二、一六二)。副詞句であるが、獨立句としての性質を感じて使用されたらしい。この句は、下の明言ニ御言問ハサズまでに懸かる。 由縁母無―- ツレモナキ。下に「所由無《ツレモナキ》 佐太乃岡邊爾《サダノヲカベニ》」(卷二、一八七)とあり、假字書きには、「都禮毛奈吉《ツレモナキ》 佐保乃山邊爾《サホノヤマベニ》」(卷三、四六〇)、「津禮毛無《ツレモナキ》 城上宮爾《キノヘノミヤニ》」(卷十三、三三二六)などある。ツレは、由縁、所由の文字通り、縁故、關係の義で、縁の無い、ゆかりの無いの意に、次の句の眞弓ノ岡を修飾する。由縁は、字に即してはヨシと讀まれる。 眞弓乃岡尓―- マユミノヲカニ。眞弓の岡は、奈良縣高市郡越智岡にあり、そこに皇子の墓が築かれているのであるが、この歌によれは、まずその地に殯宮が設けられたのである。 宮柱太布座―- ミヤバシラフトシキマシ。宮柱太シクとは、宮殿建造を壯大にするの意の熟語句。卷の一、三六參照。みずから宮殿を營まれる意に、敬語の助動詞マシを使用している。 御在香乎―- ミアラカヲ。ミアラカは、御在處の意で、宮殿をいう。ここは殯宮のこと。 高知座而―- タカシリマシテ。タカシリは、宮殿の高大を稱える動詞。宮殿を高々と御造營になる意である。この二句、上の宮柱太シキマシの句と對句になつている。 明言尓―- アサゴトニ。アサゴトニ(神)。 アラゴトニ(新考)。 明暮爾[アケクレニ](童) 明の字を朝の意に使つたのは、下に、「明者《アシタハ》」(卷二、二一七)の例がある。よつてこのままでアサゴトニと讀む。朝毎にの意であるとする説があるが、次に「御言不2御問1《ミコトトハサズ》」の句があるよりしてみれば、毎の意とせずして、言辭の義と解するを妥當とする。また原文のままにアカゴトニと讀むことも考えられる。アカは、曉《あかとき》、明星などのアカと同じく、明るい意であるが、明言と熟しては、明白な言語の意になるであろう。ニは、明言の性質にての意。しかし今、例のあるによることとする。御言不御問 ミコトトハサズ。御言を仰せられずの意。次の日月ノマネクナリヌレを修飾している。以上下のマネクナリヌレと共に上のオモホシメセカを受けている。 日月之―- ヒツキノ。この日月は、時間の上にいう日月である。 數多成塗―- マネクナリヌレ。マネクは度數の多いことをいう。ナリヌレは、ナリヌレバの意の條件法。段落ではない。 其故―- ソコヱニ。ソコは、その點の意に、上の句を受けている。「所虚故《ソコヱニ》 名具鮫兼天《ナグサメカネテ》」(卷二、一九四)などある。 皇子之宮人―- ミコノミヤビト。皇子の宮殿に奉仕していた人々。 行方不知毛―- ユクヘシラズモ。ユクヘは、行くべき方。それを知らないは、途方に暮れる意である。この種の用例としては、「埴安乃《ハニヤスノ》 池之堤之《イケノツツミノ》 隱沼乃《コモリヌノ》 去方乎不v知《ユクヘヲシラニ》 舍人者迷惑《トネリハマドフ》」(卷二、二〇一)などある。「物乃部能《モノノフノ》 八十氏河乃《ヤソウヂガハノ》 阿白木爾《アジロギニ》 不知代經浪乃《イサヨフナミノ》 去邊白不母《ユクヘシラズモ》」(卷三、二六四)の用例などは、これと違う用法で、形あるものについて言つている。モは感動の助詞。以上第二段、皇子の薨去を敍し、奉仕した人々の上に及んでいる。 刺竹―- サスタケノ。枕詞。宮、大宮に冠するが、その所以をあきらかにしない。假字書きのものの一例を除いては、皆サスタケに刺竹の文字を使用しているのは、その字義を感じて使用していたのであろう。以下は、本文のソコユヱニ以下の別傳である。「佐須陀氣能《サスダケノ》 枳瀰波夜那祇《キミハヤナキ》」(日本書紀一〇四)の例は、聖德太子の御歌と傳えるもので、君を修飾しているが、これを本義とすれば、ここも皇子、もしくは宮人に冠するものであろう。語意は、立ツ竹ノで、貴人の姿を竹にたとえるのだろうか。竹を貴人の譬喩に使うことは、ナヨ竹のトヲヨル皇子、ナヨ竹ノカグヤ姫などの例がある。 歸邊不知尓爲―- ユクヘシラニス。ニは、打消の助動詞ヌの連用形であるが、この形で副詞を構成している。「得難爾爲云《エガテニストフ》」(卷二、九五)などと同樣、動詞/爲《す》がこれを受けている。 【評語】 この歌は、神話時代から説き來つて雄大を極めている。人麻呂が皇子の薨去を悼む歌は、古代から説き起すを常としているが、これもその一である。これはこの皇子が皇太子として帝位に上るべき御方であつただけに、高天の原からお降りになつたお方である義をあきらかにしようとして、古來の傳えを歌つたものである。しかし先帝天武天皇が高天の原からお降りになつたことを説くあたりは、時代の混亂があり、詞句表現が不備であつて、豫備知識無しには思想を完全に解し得ないだろう。人がこの皇子に期待することが多かつたのに、これに添わなかつた有樣はよく描かれている。結末は、皇子の宮人の途方に暮れることを概括的に敍しており、作者としての感想は、むしろ反歌において現わされているのである。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | 日竝皇子尊《ひなみしのみこのみこと》の殯宮《あらきのみや》の時、柿本朝臣人麻呂の作れる歌一首并に短歌 天地《あめつち》の 初《はじめ》の時 久堅の 天《あま》の河原《かはら》に 八百萬《やほよろづ》 千萬神《ちよろづかみ》の 神集《かむつど》ひ 集《つど》ひ坐《いま》して 神分《かむあか》ち 分《あか》ちし時に 天照《あまて》らす 日下駄尊《ひるめのみこと》【一に云ふ、さしのぼる日女の命】 天《あめ》をば 知らしめすと 葦原の 水穗《みづほ》の國を 天地の 依《よ》り相《あ》ひの極《きはみ》 知らしめす 神の命《みこと》と 天雲《あまぐも》の 八重かき別きて【一に云ふ、天雲の八重雲別きて】 神下《かむくだ》し 坐《いま》せ奉《まつ》りし 高照らす 日の皇子《みこ》は 飛鳥《あすか》の 淨《きよ》みの宮《みや》に 神《かむ》ながら 太敷《ふとし》きまして 天皇《すめろき》の 敷きます國と 天《あま》の原 岩戸を開き 神上《かむあが》り 上《あが》り坐《いま》しぬ【一に云ふ、神登りいましにしかば】 わが大王《おほきみ》 皇子《みこ》の命《みこと》の 天《あめ》の下 知らしめしせば 春花《はるはな》の 貴《たふと》からむと 望月《もちづき》の 滿《たた》はしけむと 天《あめ》の下【一に云ふ、食す國】 四方の人の 大船《おほふね》の 思ひ憑《たの》みて 天《あま》つ水 仰ぎて待つに いかさまに 思ほしめせか 由縁《つれ》もなき 眞弓《まゆみ》の岡《をか》に 宮柱 太敷《ふとし》きまし 御殿《みあらか》を 高知りまして 朝ごとに 御言《みこと》問《と》はさず 日月《ひつき》の 數多《まね》くなりぬれ そこ故に 皇子《みこ》の宮人 行方《ゆくへ》知らずも【一に云ふ、さす竹の皇子の宮人ゆくへ知らにす】 〔題〕 曰竝皇子尊 草壁皇太子。「四九」參照。持統天皇三年四月御年二十八で薨ぜられた。 〔譯〕 天地の初めの時、天の河原に八百萬千萬の神々がお集りになつて、統治あそばす世界をお分ちになつた時に、天照大神は天をお治めになるとて、葦原の瑞穗の國を、天地の依り合つてゐる限り、永遠に治められる神として、幾重にも重なつてゐる天雲をかき分けて、この國土にお下しあそばされた皇孫の御裔たる日の皇子天武天皇は、飛鳥の淨みの宮にて御統治からせられ、その後、天の原の岩戸を開いてお上り遊ばされた。しかし、わが皇子の尊が天下をお治め遊ばしたならば、春の花のやうに貴くましますであらう、望月のやうに滿ち榮え給ふであらうと、天下四方の人々は頼みに思つて、旱天に雨を仰いで待つやうにお待ち申してをつたのに、どうお考へになつたのか、今まで何の縁故もない眞弓の岡に宮柱をしつかりとお建てになり、御殿を立派にお構へになつて、毎朝おかけ下さつた御言葉もお下しにならず、月日が長く經つた。その爲にお仕へ申してゐた宮人たちは、どうしてよいか、途方にくれてゐることである。 〔評〕 前半の「日の皇子」の解に異説があり、それに從つて多少明かでない點はあるが、もしこれを草壁の皇子のこととしては、「飛鳥の淨みの宮に云々」は勿論、後半の殯宮を作るあたりの記述と對して、同じ皇子の薨去を前後二樣に述べてゐることとなり、穩かでないから、前述のやうな解に從つて考へたい。さうして見ると、この歌は前半はここに直接關係のない天地開闢の大昔、八百萬の神々の會議と、天照大神が天上を支配あそばされたこと、次いで天孫降臨より、天武天皇の崩御といふ、悠久の時代から説き起して主題に入るといふ構成と考へられる。しかして、その言辭は莊重雄大である。さて次に、皇子の薨去を述ぶるに對しては、遠く凡慮の及ばぬ事としてゐる。又この段では、數おほい枕詞が悉く生き生きと精彩を放ち、調べのみではなく、内容に豐かさとうるほひとを與へてゐることを注意したい。なほ一首を通して、特に前半に於いては祝詞古事記などに類した言ひ方の多いことが認められる。例へば、大祓詞などの文章と比べ見る時、人麿の思想と手法が、遠く日本民族古來の宗教的口誦的なものにあることを知ることができるであらう。 〔語〕 ○天の河原 古事記に天の安の河原とあるのと同じ。○八百萬千萬神の 多くの神々が。○神/集《つど》ひ 神の動作であるから、上に神を冠したもので、集ひは集りの意。 ○神分ち分ちし時に 分《あか》つは分け配るの意。統治すべきところを、それぞれ分配せられた時。○ひるめの尊 天照大御神。 ○天をば知らしめすと 御自ら天をお治めなさるとて。○葦原の水穗の國 葦原の茂り、稻穗のよく熟る豐饒な國の意。 ○天地の依り相ひの極《きはみ》 天地開闢の時、分離した天地が再びより合ふ末の時、即ち天地の終の時までの意。 ○天雲の八重掻き別きて 幾重にも重なつた天雲をかきわけて。○神下し 天照大神が皇孫を此の國に下し給うたこと。 ○日の皇子 上からのつづきでは瓊瓊杵尊をさしまつることとなるが、省略があるのであつて、その御子孫たる日の皇子と解すべく、又ここでは特に天武天皇を申す。なほこれを日竝皇子の事とする説(代匠記)もあるが、次句の解その他から眞淵の説がよいと思はれる。 ○飛鳥の淨の宮 飛鳥淨御原の宮、天武天皇の皇居。「二二」參照。 ○すめろきの敷き坐す國と 天の原をも統治したまふ國とお考へになつて天に上りますとの意。天武天皇の崩御をかく申上げたもの。 ○吾が大王皇子の命 ここは日竝皇子の命。命は尊稱。父の命母の命などに同じ。○知らしめしせば お治めになつたならば。 ○春花の 春の花の榮え美しいが如く。「の」は、の如くの意。これを意味のない枕詞と解しては、歌の趣が缺けてしまふ。 ○望月の 滿月のやうに、滿ち足りてゐる譬。「の」は、の如くの意。○滿はしけむと 滿ち足りて缺けるところがないであらうと。 ○大船の 大船は航海するに心安く頼りとなるの意。○天つ水 仰ぎで待つにかかる枕詞。天つ水は雨。旱天に雨を仰ぎ待つの意。○つれもなき 何の縁故もない。 ○眞弓の岡 皇子の墓は、高市郡越智岡村大字森にある。○御あらか 「五〇」參照。 ○朝ごとに 毎日の意。伺候する人は早朝に參つて仰言を承つたので朝毎といふのである。○御言問はさず 何も仰せられず。 ○まねくなりぬれ 日數を重ねたので。まねくは數おほいの意。「八二」參照。○そこ故に それ故に。○皇子の宮人 皇子の宮に奉仕する人々。 ○行方知らずも どうしてよいか分らないことよ。 〔訓〕 ○初の時 白文「初時」は金澤本等による。通行本等の仙覺本には下に「之」があり、これにより「ハジメノトキシ」(舊訓、玉の小琴)、「ハジメノトキノ」(考)の二訓がある。 ○由縁もなき 白文「由縁母無」で、舊訓「ユヱモナキ」はよくない。考「ヨシモナキ」でもよいが、玉の小琴の訓による。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 巻二168 | 原文異同校本萬葉集 | 校本 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 活字附訓本 | 活字附訓本 | 活字附訓本(国立国会図書館蔵書)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 諸注引用 | 拾穂抄 | 久かたのあめ見ることくあふき見しみこのみかとのあれまくおしも 久堅乃天見如久仰見之皇子乃御門之荒卷惜毛 久かたのあめ見る 皇子御在世のほとは空のことく仰き見奉りし宮門も鞍馬まれに零落するを悲しみおしむ心なるへし |
|||||||||||||||||||||||||||
| 代匠記 | 反歌二首 久堅乃天見如久仰見之皇子乃御門之荒卷惜毛 [ヒサカタノアメミルゴトクアフキミシミコノミカトノアレマクヲシモ] 天見、【官本亦云、ソラミル】 歌の心明なり、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 童蒙抄 | 反歌二首 人丸の歌也 久堅乃天見如久仰見之皇子乃御門之荒卷惜毛 ひさかたの、あめみるごとく、あふぎみし、みこのみかどの、あれまくをしも 本歌に天水の仰て待にと云詞あり。よりて此反歌にも、天を見るごとく、仰見しと縁を引てよみたり。歌の意は、日つぎのみこなれば、天をあふぐことく尊みかしこみ奉りし、日並のみこかくれ給ひておはしまさねば、その宮殿宮門もあれはてんことのをしきと、かなしみいたみてよめる也。もといふはすべて嘆の詞をしきと云義を切にいひたる詞也 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 万葉考 | 反歌、 久堅乃、天見如久《アメミルゴトク》、仰見之《アフギミシ》、皇子乃御門之《ミコノミカドノ》、荒卷惜毛《アレマクヲシモ》、」 こは高市郡橘の島宮の御門なり、さて次の舍人等が歌どもにも、此御門の事のみを專らいひ、下の高市(ノ)皇子(ノ)尊の殯の時、人麻呂の御門の人とよみしをむかへみるに、人麻呂即舍人にて、その守る御門を申すなりけり、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 略解 | 反歌二首 久堅乃。天見如久。仰見之。皇子乃御門之。荒卷惜毛。 ひさかたの。あめみるごとく。あふぎみし。みこのみかどの。あれまくをしも。 これは島の宮の御門なり。次の舍人等の歌どもにも、此御門の事を專ら言ひ、下の高市皇子尊の殯の時、人麻呂の御門の人と詠みしを思ふに、人麻呂即ち舍人にて、其守る御門を申せしなるべし。アレマクヲシモは、アレムガ惜シキとなり。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 攷證 | 反歌二首 久堅乃《ヒサカタノ》。天見如久《アメミルコトク》。仰見之《アフキミシ》。皇子乃御門之《ミコノミカドノ》。荒卷惜毛《アレマクヲシモ》。 仰見之《アフキミシ》。 仰《アフク》は、すべて下より上を見る事なれば、下より、天皇、皇子などを見奉るにもいへり。御門などは、必らず、あふぎ見るものならねど、尊み敬ひて仰見之とはいへり。されば、天見如久《アメミルコトク》とは、たとへし也。まへに、天水仰而待爾《アマツミツアフキテマツニ》とあるをも思ふべし。 荒卷惜毛《アレマクヲシモ》。 荒《アレ》んはをLもにて、もは助字也。まくは、んといふ意にかよへり。上【攷證二上廿一丁】にいへり。考云、こは高市郡、橘の島宮御門なり。さて、次の舍人等が歌どもにも、この御門の事のみを、專らいひ、下の高市皇子尊の殯の時、人まろの、御門の人とよみしを、むかへ見るに、人まろ、即舍人にて、その守る御門を申すなりけり。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 古義 | 反歌二首《カヘシウタフタツ》。 二首の字、拾穗本にはなし、 久堅之《ヒサカタノ》。天見如久《アメミルゴトク》。仰見之《アフギミシ》。皇子乃御門之《ミコノミカドノ》。荒卷惜毛《アレマクヲシモ》。 〇久堅乃《ヒサカタノ》(堅(ノ)字、類聚抄には、方と作り、)は、天の枕詞なり、既くかたがたに見えたり、 ○天見如久《アメミルゴトク》云云は、三(ノ)卷長(ノ)皇子(ノ)遊2獵獵路(ノ)池(ニ)1之時、人麿(ノ)作歌に、久堅乃天見如久《ヒサカタノアメミルゴトク》、眞十鏡仰而雖見《マソカヾミアフギテミレド》、春草之益目頻四寸吾於冨吉美可聞《ハルクサノイヤメヅラシキワガオホキミカモ》、とあるに同し、 ○皇子乃御門之《ミコノミカドノ》、(之(ノ)字、拾穗本には、乃と作り、)岡部氏、こは高市(ノ)郡、橘の島(ノ)宮の御門なり、飛鳥の岡の里の東北五六町ばかりに、今も橘寺とてあり、ここぞ橘の島なるといへり、さて次下の、舍人等が歌どもにも、此(ノ)御門の事のみを、專らいひ、下の高市(ノ)皇子(ノ)尊の殯宮の時、此(ノ)朝臣の、御門の人とよまれしを、むかへ見るに、此(ノ)朝臣即(チ)舍人にて、その守りし御門を申せるなるべし、 ○荒卷惜毛《アレマクオシモ》は、荒行む事の、さても惜きよとなり、荒卷《アレマク》は、荒武《アレム》の伸りたる言なり、毛《モ》は、歎息の辭なり、 ○歌(ノ)意は、かくれたるところなし、 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 檜嬬手 | 反 歌 久堅乃《ヒサカタノ》、天見如久《アメミルゴトク》、仰見之《アフギミシ》、皇子乃御門之《ミコノミカドノ》、荒卷惜毛《アレマクヲシモ》。 ●「天見如久云々」天津日を仰ぎ見る如く仰ぎ貴み奉る日並知(ノ)尊の宮と云ふつゞき也。 ●「皇子乃御門之」御門と云ひて、宮殿の上になる事、朝廷をみかどゝ申すと同じ事也。此御門は島(ノ)宮の事なり、下の歌に出づ ●「荒卷惜毛」あれまくは將《マク》v荒《アレ》にて荒れんとするが惜しと云ふ也。さて其荒れは、宮殿のわろくなるのみにあらず。人の散りゆくを云ふなり。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 口訳 | ひさかたの天《アメ》見る如く、仰ぎ見し皇子《ミコ》の御門《ミカド》の荒れまく惜しも 御在世の時は、天を見るやうに尊み、ふり仰いで見た、皇子の御所の、荒れて行くのが殘り多いことだ。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全釈 | 反歌二首 ひさかたの 天見るごとく 仰ぎ見し 皇子の御門の 荒れまく惜しも 久堅乃《ヒサカタノ》 天見如久《アメミルゴトク》 仰見之《アフギミシ》 皇子乃御門之《ミコノミカドノ》 荒卷惜毛《アレマクヲシモ》 〇(久堅乃)空ヲ見ルヤウニ、私ドモガ仰イデ見タ日並皇子ノ御所ガ、皇子ガ御薨去遊バシタノデ、荒レルデアラウガ惜シイコトデアルヨ。 ○天見如久仰見之《アメミルゴトクアフギミシ》――皇子へかかるのである。日並皇子を尊んでかく申したのだ。 ○皇子乃御門《ミコノミカド》――日並皇子の御殿。今、高市郡高市村に大字島の庄があつて、そこがこの皇子の宮址だといはれてゐる。 〔評〕 皇子に對する敬意と思慕の情がよくあらはれてゐる。天見る如く仰ぐは、ふさはしい譬喩である。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全註釈 | 反歌二首 ひさかたの 天《あめ》見るごとく 仰ぎ見し 皇子《みこ》の御門《みかど》の 荒れまく惜しも。 久堅乃《ヒサカタノ》 天見如久《アメミルゴトク》 仰見之《アフギミシ》 皇子乃御門之《ミコノミカドノ》 荒卷惜毛《アレマクヲシモ》 【譯】かの大空を見るように仰いで見たわが皇子の御殿の、荒れようとするのが擁念である。 【釋】天見如久 アメミルゴトク。天を見るようにの意に、次の句を修飾している。 仰見之 アフギミシ。連體形の句で、次の句に接續している。宮殿の高大なのを感じさせている。 皇子乃御門之 ミコノミカドノ。ミカドは、宮殿の御門であり、これを以つて宮殿を象徴代表している。 荒卷惜毛 アレマクヲシモ。アレマクは荒れむこと。皇子ましまさずして、その宮殿の荒廢するを惜しんでいる。 【評語】 長歌の、天ツ水仰ギテ待ツニを受けて、しかも、御門を仰ぎ見る意に轉用している。その宮殿は、下の舍人等の歌には、橘ノ島ノ宮と歌つている。それらの舍人等の作の中にも、同じ思想の歌があつて、その宮殿に奉仕した人々の悲哀をよく語つている。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 評釈 | 反歌二首 ひさかたの天《あめ》見るごとく仰ぎ見し皇子《みこ》の御門《みかど》の荒れまく惜しも 〔譯〕 天を仰ぎ見るやうに仰ぎ見てゐたこの皇子の宮の荒れてゆくのは、惜しいことである。 〔評〕 長歌では、次第に流動し發展してゆく手法をとつたに對して、短歌では視點を集中し、具體的な素材を基としてゐることは、既に多くの長歌で認められてゐたところである。又この調べの大らかでたるみのない點も長歌にふさはしい。かやうに宮殿の荒れることを惜しんだ作の多いのは、上代人は死の穢を忌み、死者を出した住居は直ちに住み捨てて荒れるにまかせたからであるといふが、それをこの時代にまで及ぼしてよいかどうかは疑はしい。 〔語〕 ○皇子の御門 皇子の宮居。日竝皇子の宮は、今の高市郡高市村島の庄の地に在り、島宮といふ。なほ眞淵はこの御門を宮の御門と解し、人麿はその門を守る舎人の一人であつたといつてゐる。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | 反歌二首 久堅乃天見如久仰見之皇子乃御門之荒卷惜毛 [ひさかたの あめみるごとく あふぎみし みこのみかどの あれまくをしも] 【口譯】大空を仰ぎ見るやうに仰ぎ見た皇子の御殿の荒れるであろうことが惜しまれるよ 【訓釋】 ひさかたの――枕詞。既出(1・八二)。 天見る如く仰ぎ見し――天を金沢本その他の古本には「ソラ」とあるが、西本願寺本以下「アメ」とあるによる。天をソラと訓んだと思はれる例(1・二九) もあるが、長歌の「天乎婆」 の場合などと同じくアメと訓む。「天見る如く」は「仰ぎ見し」 の修飾。「君之御門乎(キミガミカドヲ) 如天(アメノゴト) 仰而見乍(アフギテミツツ)」(13・三三二四) ともある。その例でわかるやうに「仰ぎ見し」は次の句の「御門」にかかる。「ひさかたの 天見るごとく まそ鏡 仰ぎて見れど 春草の いやめづらしき 我が大君かも」(3・二三九) の例もあるので、次の「皇子」にかかるとする説もあるが、今の場合は先の例により御門までかかると見るべきである。仰ぎ見るのは皇子に対する敬意を含めてのものであるが、直接には宏壮な宮殿に対してのものである。 皇子の御門の荒れまく惜しも――御門は皇子の宮殿の門であるが、宮殿を代表するものとして宮殿全体をさす(1・五〇)。「まく」は「むこと」の意(一〇三)。「も」は詠歎の助詞。この宮殿は次々の歌に見える嶋宮である。その位置についてはその條で述べる。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 全注 | 反歌二首 久堅乃天見如久仰見之皇子乃御門之荒卷惜毛 [ひさかたの あめみるごとく あふぎみし みこのみかどの あれまくをしも] 【注】 〇天見る如く仰ぎ見し 長歌の「天つ水仰ぎて待つ」 を受け、天皇としての即位の待たれたことをこの上句は暗示するだろう。 〇皇子の御門 ミカドは、本来宮殿の門(ミは尊敬の接頭語) をあらわす語であったが、宮殿全体を示したり、朝廷や国家、さらに天皇をさしたりするようになった。ここは宮殿。 〇荒れまく惜しも アレマクは、荒れむことの意。あとの舎人等の歌の中に「高光る吾が日の皇子のいましせば島の御門は荒れざらましを」(一七三) などと歌われているのを見る。皇子薨去後いくばくもなく島の宮は荒廃して行ったらしい。ヲシは、手放しがたい、心残りである、いとしい、などの気持ちをあらわす。ここは、残念で痛ましい意であろう。「~ヲシモ」で終わる短歌は、集内に二十数例を数えるが、過ぎ行くものへの哀惜を、アレマクヲシモとかチラマクヲシモという形で歌ったのは、人麻呂が最初であったと思われる。モは詠嘆の終助詞。 【考】年次の明らかな人麻呂作として最初の作 〔注〕でも明らかなように即位のこともなく薨去された皇子の宮の荒れてゆくのを悲嘆した歌である。茂吉評釈に「長歌といひこの短歌といひ、既にかくの如くに完成せられてゐるのを見れば、この以前の人麻呂の作といふものを想像するのに興味を向けられがちである。そして、その対象は自然、人麻呂歌集出といふ歌に向けられるべきは先づ当然であらうか」と言う。人麻呂歌集歌を作歌より以前に作られたものとすれば、「旅なれば夜中をさして輝る月の高島山に隠らく惜しも」(9・一六九一)、「さをしかの心相思ふ秋萩のしぐれの降るに散らくし惜しも」(10・二〇九四)、「妻ごもる矢野の神山露霜ににほひそめたり散らまく惜しも」(10・二一七八) などがこの歌以前に作られていたことになる。舎人の「高光る吾が日の皇子のいましせば島の御門は荒れざらましを」(一七三) に比べて人麻呂の力量を感じさせる歌である。 |
||||||||||||||||||||||||||||