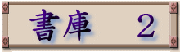| 掲載日:2002.05.11- | 巻九 相聞歌 1795 | たびびとのやどりせむのにしもふらばわがこはぐくめあめのたづむら | 遣唐使の母 |
| 掲載日:2002.05.12- | 巻二十 防人の歌 4444 | くさまくらたびのまるねのひもたえばあがてとつけろこれのはるもし | 椋椅部弟女 |
| 掲載日:2002.05.13- | 巻十五 遣新羅使 3637 | わがゆえにいもなげくらしかざはやのうらのおきべにきりたなびけり | 遣新羅使人 |
| 掲載日:2002.05.14- | 巻十二 寄物陳思 3111 | さひのくまひのくまがわにうまとどめうまにみずかへわれよそにみむ | 作者不詳 |
| 掲載日:2002.05.15- | 巻十 春雑歌 1828 | ふゆごもりはるさりくらしあしひきのやまにものにもうぐひすなくも | 出典未詳歌 |
| 掲載日:2002.05.17- | 巻十四 東歌 3365 | つくはねにゆきかもふらるいなをかもかなしきころがにのほさるかも | 作者不詳 |
| 掲載日:2002.05.28- | 巻三 雑歌 237 | いなといへどしふるしひのがしひかたりこのころきかずてわれおもひにけり | 持統(?文武)天皇 |
| 掲載日:2002.05.28- | 巻三 雑歌 238 | いなといへどかたれかたれとのらせこそしひはまをせしひかたりといふ | 安倍連志斐(?) |
| 掲載日:2002.05.30- | 巻十九 平穏を祈歌 4268 | あらたまのとしのをながくあがおもへるこらにおもふべきつきちかづきぬ | 藤原清河 |
| 掲載日:2002.06.09- | 巻第十六 由縁有る雑歌 3810 | みみなしのいけしうらめしわぎもこがきつつかづかばみずはかれなむ 一 | |
| 掲載日:2002.06.09- | 巻第十六 由縁有る雑歌 3811 | あしひきのやまかづらのこけふゆくとわれにつげせばかえりこましを 二 | |
| 掲載日:2002.06.09- | 巻第十六 由縁有る雑歌 3812 | あしひきのたまかずらのこけふのごといづれのくまをみつつきにけむ 三 |
どんなに栄光に満ちた遣唐使たちでも その苦難の船旅は 残ったものたちに憂いを与える 旅寝をする息子を想い 寒ければ...その羽根の下に包み込んでくれ 空を行く鶴に願いをなげる この年の遣唐使は二年後 五千巻の書籍と多くの仏像を招来した しかし... 一方でマレ−半島に漂着したものたち... 犠牲は大きい  |
掲載日:2002.05.11- たびびとのやどりせむのにしもふらばわがこはぐくめあめのたづむら 遣唐使の母 巻九 相聞歌 1795 天平五年(733)4月 遣唐使は難波の港を出港当時の世界でもっとも栄えた文明国唐 遣唐使の一員に選ばれることは おそらく最高の栄誉だろう しかしその道のりは 決して栄誉を担ったものたちの 姿ではなかったこのときの一行は 帰路暴風雨に遭い 四つの船は散り散りになって 中にはマレ−半島に漂着した船もあった 奈良県橿原図書館の「万葉集画撰」 野宿する少年の小屋に 三羽の鶴が舞い降りようとしている この作者の 愛しい息子を想わせる「画」... |
防人の妻の心情を こんにちまで伝え残す歌巻十四の「東歌」 巻二十の「防人の歌」 この時代の人々にとって 中央とは違う生活文化をもちながら 和歌という文化が育まれているのは 奇異に思えてならない 当時の言語はいったい どんな言葉で綴られていたのだろうそして中国文化の影響で 書籍が広くよみつがれだしたこの当時 市井の...普通の人々で和歌を階層とは...  |
掲載日:2002.05.12- くさまくらたびのまるねのひもたえばあがてとつけろこれのはるもし 椋椅部弟女 巻二十 防人の歌 4444 武蔵国の防人の妻の歌旅をすることは 歩くこと どこまでもどこまでも ただただ歩くこと どんなに丈夫な着物でも あちこちでのごろ寝には 相当傷んでくる旅のごろ寝の紐が切れたら この針を私の手と思って 縫って欲しいあなたとともに歩けなくとも 必要なときには いつも一緒にいます夫の赴任地に 心で同道する安心感 優しさの籠もった歌 |
天平八年(736)、当時の瀬戸内は 海路三十日と言われる このときの遣新羅使は、阿倍継麻呂当時の新羅は唐と親しく 日本など相手にしていなかった 当局ではなかなか会ってもらえず なんら成果もなく帰国する 一行の歌は巻十五にあるが 往路の歌140首に対して 帰路の歌は播磨灘家島付近の5首のみ その落胆振りが反映されている  |
掲載日:2002.05.13- わがゆえにいもなげくらしかざはやのうらのおきべにきりたなびけり 遣新羅使人 巻十五 遣新羅使 3637 嘆きは霧になる 妻の嘆きが霧になって この浦にたなびいている難波からの出立のとき 遣新羅使人の妻は 夫にことばを贈る瀬戸内の何処かで 霧が出たなら それは家で寂しく そして心配で嘆き哀しんでいる 自分の魂だと...霧にはいろいろなものが 浮かんでくる 自己の望むものが映る霧は妻の魂と知る |
 共に朝まで過ごした翌朝 妻が惜しみ慕う歌は多い万葉集の巻十一、十二の 正述心緒、寄物陳思歌は このような結婚した人の熱い想いが 青年の淡い恋に混じって 数多く見られる当時の女性の役割、存在 いや、神秘そのものを 男は尊び、畏れていたのだろう檜隈は奈良県高市郡明日香村の南部 |
掲載日:2002.05.14- さひのくまひのくまがわにうまとどめうまにみずかへわれよそにみむ 作者不詳 巻十二 寄物陳思 3111 万葉時代の、婚姻の実態を感じる 結婚した男女は 夜毎男が女のもとに通い 夜明けと共に 家を辞す馬に水を与えてくれ それが少しでも ほんの僅かないっときでも 男がそばにいることになるなら その、馬に水やる姿を 遠くからでも見ていたい女の家における 実質的な尊さを知るからこそ 男は決して 女を引き取りはしないしかし女の心は... この歌が語るもの... その心情は...今も不変だと思う |
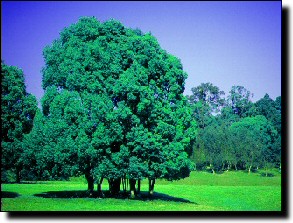 巻十は、人麻呂歌集、古歌集歌 そして出典未詳歌を集めている 雑歌、相聞歌を四季に分け この歌は「春雑歌・鳥を詠む」の一首 うぐいす、かっこうの歌が続く ただし、この地が独特の地である事を思えば 鳥の鳴き声も、また独特の意味を持つものと 感じてもいいと思う名もなき人の、春を謳歌する歌には違いないが四季の春もあれば 人が生を与えられて 初めて人生の春を実感する心の四季もあるはず 歌は、どのように自分が感じるか... 作者の意図に感動するもの そして自分を投影して感動するもの... 様々だと思う |
掲載日:2002.05.15- ふゆごもりはるさりくらしあしひきのやまにものにもうぐひすなくも 出典未詳歌 巻十 春雑歌 1828 甘橿丘から飛鳥を望む... この地が新しいこの国の 始まりとなった 壬申の乱を経て ここから飛鳥浄御原宮 そして藤原京へそれまでの豪族的な支配構造が 天皇中心の強権国家になったこの地あるものにとっては 大きな春の到来 しかしまたあるものにとっては 表に現れない 新たな権力の奪い合いが見えているはずそれを知らずか、あるいは知ってか それでも鶯の鳴く春を 謳歌するのどかな情景が それまでの歴史の中で 初めての春を 謳っているように感じる... |
 当時筑波山の東麓、今の石岡市に国庁があった 高橋虫麻呂は、そこに赴任していたと思われる 彼が残す多くの筑波山を中心とした歌は その風土風景を詠んでいる 筑波山は二つのピ−クがあり 東峰の女体山、西峰の男体山が それぞれ東西に大きな裾をひろげている 虫麻呂は、自己の心を 見せない人だと言われている 多くの作歌には、伝説などの物語の世界を 空想力を駆使してリアルに歌い上げている しかし、異郷の筑波でみせる虫麻呂の心情 この東歌のように、 彼は赴任地での古歌、伝承歌の採録に力を入れていたことだろう 高橋虫麻呂と言う ロマンティストが歌う万葉の歌の数々は 東国の風土に於いて より一層際立ってきたのだと思う |
掲載日:2002.05.17- つくはねにゆきかもふらるいなをかもかなしきころがにのほさるかも 作者不詳 巻十四 東歌 3365 筑波山は関東平野の東 常陸国(茨城県)に 綺麗な双耳峰を見せてくれる都を遥か遠くに離れ 国庁の役人として 日々を送る虫麻呂...筑波山から望む麓の景色は 彼にとって ふるさと龍田を想わせるのだろう心に想う娘が 寒さの中 布を乾すのを いとおしく見つめる |
掲載日:2002.05.28- いなといへどしふるしひのがしひかたりこのころきかずてわれおもひにけり 持統(?文武)天皇 巻三 雑歌 237 次の一首、志斐嫗との連歌律令体制化での最高権力者天皇 その天皇のそばに仕える 安倍連志斐(?)もう充分だ、たくさんだ といっても、いつも聞かされる しかしこのところ そんな語りもきかない天皇権力絶対の時代に おおらかな人間同士の 掛け合いがある |
掲載日:2002.05.28- いなといへどかたれかたれとのらせこそしひはまをせしひかたりといふ 安倍連志斐(?)巻三 雑歌 238 何を言われる いくらお断りしても 話せ話せと強くしいられ 仕方なくはなしているのに 「強い語り」とは...あまりでしょうこれが天皇と側近の 心を開いた 掛け合いに感じられて 今更ながらに 万葉集の幅の広さに驚く |
天平勝宝二年(750) 藤原仲麻呂(のちの恵美押勝)の 邸宅「田村第」にて 遣唐使一行の送別の宴が催されたこのときの大使、藤原清河は 入唐後、二度と日本の地を 踏むことはなかった  |
掲載日:2002.05.30- あらたまのとしのをながくあがおもへるこらにおもふべきつきちかづきぬ 藤原清河巻十九 平穏を祈歌 4268 長年ともに暮らし、想った妻と 恋懐かしむ月が...近づいた遣唐大使に任命された清河 時の実権者・仲麻呂の従兄弟に当たるが 入唐大使に任命され、送別の宴を 仲麻呂に催された その席での作歌清河は...自分の悲運を予感したのあろうか 後の生涯を想うと この一首は... とわの別れを 嘆くかのように切ない |
 巻第十六の「有由縁雑歌」には いわれを有する様々な歌が収録されている 昔物語風な男女の恋歌、民謡や伝説など... それぞれの歌の題詞が、歌のいわれを語る 「一人の女の身、滅やすきこと露の如し。 三人の雄の志、平しかたきこと石の如し。」 娘は、そう嘆いて池のほとりを彷徨い 水底に沈む |
掲載日:2002.06.09- みみなしのいけしうらめしわぎもこがきつつかづかばみずはかれなむ 一 あしひきのやまかづらのこけふゆくとわれにつげせばかえりこましを 二 あしひきのたまかずらのこけふのごといづれのくまをみつつきにけむ 三 巻第十六 由縁有る雑歌 3810、3811、3812 以前二人の若者に求愛され、その争いを悲しみ 山に入って自殺した「さくら児伝説」を掲載したが この三首は、そのときの若者の歌二首に続いて 収録されている 「かずら児伝説」と言われる三首 いづれも、当事者の三人がそれぞれ詠んだ歌かづらこ、と言う名の娘は やはりその争いを悲しみ、耳成山周辺の池に入水自殺をする 愛しいあの娘がやって来るというのなら 池の水よ、干上がってくれれば、良かったのに... おれにだけ、ほのめかしてくれれば... あなたの後を、追いかけて行きたい...死の国へ ・・・三様の気持ちの悲しみの叫び・・・ |
| |
|