| 俊頼髄脳 (としよりずいのう) | 平安時代 | 源俊頼(1055〜1129年) | 1111〜1115年頃成立 | 橋本不美男 校注・訳 | |
| 古来風躰抄 (こらいふうていしょう) | 鎌倉時代 | 藤原俊成(1114〜1204年) | 初撰本1197年・再選本1201年 | 有吉 保 校注・訳 | |
| 近代秀歌 (きんだいしゅうか) | 鎌倉時代 | 藤原定家(1162〜1241年) | 1209年、源実朝に進呈 | 藤平春男 校注・訳 | |
| 詠歌大概 (えいがのたいがい) | 鎌倉時代 | 藤原定家(1162〜1241年) | 1215〜1216、あるいは1221年頃成立 | 藤平春男 校注・訳 | |
| 毎月抄 (まいげつしょう) | 鎌倉時代 | 藤原定家(1162〜1241年) | 1219年成立 | 藤平春男 校注・訳 | |
| 国歌八論 (こっかはちろん) | 江戸時代 | 荷田在満(1706〜1751年) | 1742年成立 | 藤平春男 校注・訳 | |
| 歌意考 (かいこう) | 江戸時代 | 賀茂真淵(1697〜1769年) | 1764年成立 | 藤平春男 校注・訳 | |
| 新学異見 (にいまなびいけん) | 江戸時代 | 香川景樹(1768〜1843年) | 1811年成立 | 藤平春男 校注・訳 | |
| 各歌論書の掲載は、順次別頁に載せる。開始予定日は、2013年9月14日で、「ある日の万葉集」で、日々少しずつ紹介し、「歌論集書庫」にまとめる。 | |||||
| 歌学から歌論へ | 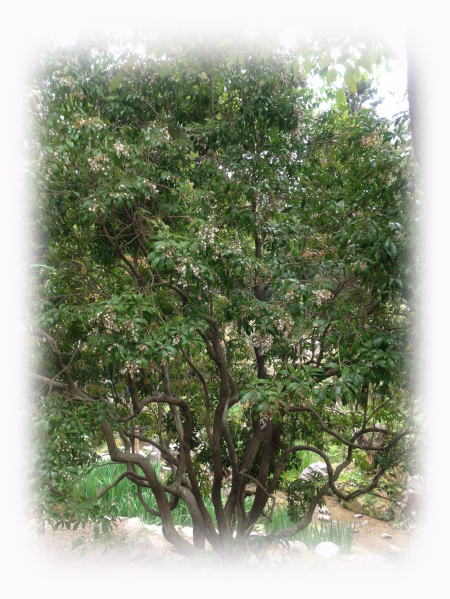 |
||||||||
| 歌論書といっても、平安時代までに成立した多くのものは、和歌の本質を論じたものは少なく、和歌に関する評論を含んだ作歌方法や教養に関する内容の方が主力であった。この史的展開については、本書の「解説」に述べられているとおりである。そして、本書に収載されている八作品がそれを証明してくれている。 | |||||||||
| 古典全般の教養的性格 | |||||||||
| 『俊頼髄脳』の項目だけをみてもわかるように、いわゆる歌学書で和歌に関する諸事が全体的に示されていて、事典的役目を果たしている。これは、和歌だけでなく、広く物語りなどをも理解するための立派な参考書である。四季の歌題や歌枕や異名などは、初心者の和歌詠作や教養に役立つし、秀歌例の場合でも、実例に立っての説明で鑑賞の基本を学ぶことができる。 歌論書・歌学書というと、その道の専門家が専門家に説くような感じがするが、もう少し時代の日常的な世界を反映していたことも確かであると思われるので、歌話の一つを示したい。 |
|||||||||
| 数奇的態度の世界 | |||||||||
| 『袋草紙』(藤原清輔著、平治元年<1159年>頃成立)に、 和歌は昔より師なし。而して能因、始めて長能伊賀守なりを師となす。当時肥後進士と云ひける時、物へ行く間、長能が宅の前にて車の輪を損じぬ。乃ち、車取りに遣す間、かの家に入りて始めて面会す。参仕の志有りといへども、自然に過ぐる間、幸ひかくの如き事有り。その由を談じて相互に契約す。能因云はく「和歌は何様(いかよう)に詠むべきにや」と。長能云はく、「山ふかみ落ちてつもれる紅葉葉のかわける上にしぐれ降るなり。かくのごとく詠むべし」と云はく。 とあり、また節信と能因の関係が、同書の別の所にもみえており、「長帯刀鹿矢(たちはきかごや)の節信は風流者であった。はじめて能因法師に会った時から互いに意気投合した。能因は『今日ご来訪くださった記念のお土産に見ていただきたい物があります』と言って、懐中から錦の小袋を取り出した。その中にかんなくずが一枚あり、彼は『私の大事な宝物です。長柄の橋を造った時のかんなくずです』と言って見せた。すると節信はたいそう喜び、彼も懐中から紙に包んだ物を取り出した。開けてみると干からびた蛙で、『これは井出の蛙でございます』と言った。お互いに感心しあって、おのおの懐中にして別れた」という雑談がある。 和歌を詠むことに対しての数奇的態度を示すものであったと思われる。能因法師が和歌を話題にする時は、うがいをしてから話をするなどの執心ぶりが『俊頼髄脳』にも揚げられている。 次に、歌論書として、正確に理解するために、著者の和歌活動も照らし合わせて考えるのも一つの方法であろう。 |
|||||||||
| 俊頼髄脳の背景 | |||||||||
| たとえば、源俊頼の歌合判として著名なものに、長治元年(1104年)五月二十六日「俊忠朝臣家歌合」がある。主催者の藤原俊忠は『古来風躰抄』の著者藤原俊成の父である。俊成の外祖母の妹の長子は、『讃岐典侍日記』の作者である。この歌合は、歌題十題で歌人十六人の十三番歌合で、さほど大きな歌合ではない。この歌合の判者俊頼の態度をみると、方人(かたうど・左右の対者の応援者)の発言が多いので、そのまとめ役的な態度であるが、古めかしい歌をさけ、文字続きのおかしさ、すべらかさを重視していて、『俊頼髄脳』の発言をよく反映している。 俊頼と俊忠は、堀河院歌壇の中心人物で、この歌壇で催された革新的事業が堀河百首(長治二年〜翌三年三月の間に奏覧)である。歌題百題からなり、応制百首のはじめとして、また組題百首として後世に多くの影響を与えた。この堀河百首の成立ののち、五、六年を経て『俊頼髄脳』は成立したのである。 |
|||||||||
| 俊成の革新的世界の背景 | |||||||||
| 藤原俊成の環境と和歌活動については、すでに多くの著作があり、その数の上からでも、俊頼の比ではない。「谷山茂著作集」(角川書店)の二巻「藤原俊成―人と作品―」の藤原俊成年譜が詳細で適確であるので参照されたい。 俊成は、歌風の時代的な相違を認識していたということで、俊成以前の歌論書とまったく異なっている。『古来風躰抄』の柿本人麻呂歌を評するところでも、「その時代の歌の『姿心』に適合しただけでなく、時代はさまざまに改まり、人の心も、歌の姿も、その折々によって変遷するものであるけれども、あの人麻呂の歌などは、上古・中古・今の末の世までを思い合わせているのだろうか...」と区別している。そうして、『万葉集』に続いて、『古今集』〜『千載集』の歌を選び説明するのである。 『古来風躰抄』を通読した時、俊成の理想としたとされる幽玄が秀歌評に現れぬことに不思議さを感じる人もあるかと思う。この幽玄についても、「谷山茂著作集」一巻に収載され、詳述されている。旧著『幽玄の研究』に比べて、大幅の補訂がなされており、用例を挙げて説明されている。俊成自身は幽玄という言葉にすがって特殊な様式を論じてはいない。『古来風躰抄』上巻の「なんとなく艶にもあはれにも」というように対立を絶したものである。しかし、幽玄という評語は、歌合の判詞では用いられており、その一例を示そう。
とある。俊成の「幽玄」は、「さびたり」(他に「優なり」「艶なり」「とほじろし」など)のように表現面から感じられる様式であるのに対して、歌の背後に或るものとの関係から生れる奥行きの深さや、複雑さである。 |
|||||||||
| 俊頼・俊成・定家と万葉集 | |||||||||
| 『古来風躰抄』の上巻は、序文を除いて『万葉集』によって占められている。和歌史的把握をする時に、その根源にあたる『万葉集』に多くを求めることは当然かもしれない。俊成は『万葉集時代考』(文治五年〜建久六年<1189〜1195年>)を著しているが、これは藤原良経の問いに応じて執筆されたとするもので、この本の奥書を信ずれば、初撰本『古来風躰抄』(建久八年)の直前ということになるが、俊成が『古来風躰抄』の抄出の際に依拠した『万葉集』は巻二十の巻末九十四首を欠く本かと推測されるが、初撰本『古来風躰抄』をみると、その読み方に苦心の跡が察せられる。良質の本文がなく、そのための苦心であったと推察できる。 『俊頼髄脳』の『万葉集』は、次点期のものであるが、前掲、俊忠家歌合の判で藤原仲実が、『万葉集』から証歌を示すと感心し、すぐに認めている点などから、『万葉集』にはあまり通じていなかったようである。 藤原定家は、建保元年(1213年)『万葉集』を藤原(飛鳥井)雅経に託して鎌倉幕府に届けたことが『吾妻鏡』によって知られるし、近年報告のあった広瀬本『万葉集』によって知られるごとく、整備された『万葉集』を書写、所持していたとみられる。 |
|||||||||
| 定家の歌論書と時代背景 |  |
||||||||
| 『近代秀歌』は、承元三年(1209年)八月十三日に定家が源実朝に遣送したものが初撰本である。この年、定家は『新古今集』の追加補訂の関係もあってか数度にわたって『新古今集』を書写している(五月十二日烏丸光栄本奥書、六月十九日柳願本奥書、七月一日正徹本奥書)。そうした中にあって、実朝は、七月、内藤知親を使となし、建永元年(1206年)の初学以後の歌三十首を選び合点を得るために定家に遣わし、六義風体のことを問うたことに答えたのが本書である。 実朝と定家の関係は、元久二年(1205年)九月二日の『吾妻鏡』の条にみえるごとく、内藤朝(知)親を通して『新古今集』が届けられていることでもわかる。『新古今集』は、これ以降、増補切継改訂期に移るのであるが、三月二十六日竟宴が行われ、形式上成立した。それから六ヶ月にも満たない時期で、後鳥羽院や撰者以外の所に渡った最初の写本とみられる本である。 『近代秀歌』は『新古今集』の撰者を務めて、当代の歌風を推し進めようと志向する態度の執筆であった。 父俊成と同じく史的展開を認識したうえで、従来の和歌史を批判し、紀貫之以降の和歌が余情妖艶の歌風を放捨した流れに立つことの批判である。そして、和歌再生の方法を説いたのである。秀歌例の多いことは、直接的な相手としては、源実朝であろう。父俊成の『古来風躰抄』が式子内親王のための執筆の直接的動機であったのとよく似ている。 『詠歌大概』は、承久三年(1221年)の承久の乱以降の著作とされている。定家はこの年六十歳である。この年以降、急激に古典書写で日を過ごすようになる。たとえば、『古今集』書写でみると、書写年次の明確なもの最低十四回の内十二回は六十を超えてからである。『後撰集』の場合も、十五回の大部分が六十歳を超えてからのものである。 たとえば、承久三年五月二十一日本(書陵部二十一代集)の奥書に 承久三年五月廿一日午前書之。 此集無尋常之本。為備後輩之所見、今日書写之。去六日書始之、同廿四日校了。以此本、重書写已四ヶ度。 一本進仁和寺宮 一本前摂政殿 一本付属嫡女 一本伝于嫡孫 三ヵ年間、凌老眼五度書之 とある。定家はこの前年の承久二年二月十三日、内裏和歌御会で詠んだ二首で後鳥羽院の勅勘を受け、その後の公の会に召すことを禁じられていた。そしてこの承久三年五月十四日には、承久の変が起き、七月十三日に後鳥羽院は隠岐に御遷幸という事件の最中にも、定家は『後撰集』を書写していたとみられる。 『詠歌大概』はこうした経験を経て晩年に達した時の、和歌的表現の原理と方法について述べたものである。前著の『近代秀歌』との大きな相違は、和歌史批判の論が欠けている点である。そして、新古今時代に盛行した「本歌取」方法について、さらに詳細に具体的に記している点である。本書も多くの例をあげているが、後鳥羽院の皇子梶井宮尊快法親王に献進するための著作とされることとかかわるものと思う。 『毎月抄』は、著者を定家とするか、偽書と考えるか決定できない。伝本上でみると、冷泉家系統本の為秀の時点で為家までさかのぼれることで上位にあり、その為家奥書の指示するものは定家の著とするのである。この為家本の奥書によれば、承久元年(1219年)七月に成立ということになる。真作・偽作の結論は出ていないが、論旨の中核部分は定家歌論として矛盾がないとみられる。 本書の注目すべき点は、『近代秀歌』や『詠歌大概』が主として説くところは詠歌技法論であった。それに対して、『毎月抄』は、様式分類としての十体論と、「有心体」を中心に詠歌態度論に重点を置いて述べているので、定家歌論としては、両者は相互補完的関係の中で把握することができる。 |
|||||||||
| 中世歌論書と定家仮託偽書 | |||||||||
| さらに、本書は、中世歌論書という角度でみるとき、いわゆる鵜鷺系偽書(桐火桶、愚秘抄、三五記)の一つとされる『愚見抄』(歌論書。著者・成立未詳。定家に仮託した偽書)は、『毎月抄』の十体に八体を加えて分類したり、十体の中で有心体を中心にみる点などに継承され、同じく偽書の『桐火桶』も『愚見抄』の一部を母胎として成ったものであり、同じく定家仮託偽書の『愚秘抄』も『毎月抄』を中心に引き、後世の正徹や心敬らによって定家歌論書の中核に据えられて大きな影響を与えた。また、定家仮託の偽書の歌論書『三五記』は、『毎月抄』の、批評眼の必要性の項目に見える歌論書『明月記』に見せかけたかという説がある。上巻に『毎月抄』の十体に二十体を加えた歌体論で、しかも有心体を中心とする点は、『毎月抄』を継承している。 定家歌論書のうち、『近代秀歌』も『詠歌大概』も説くところは、簡潔である。そして示めすところの例歌が多い。それに対して、『毎月抄』は、歌論書的スタイルで整っている。そうしたことが、前に掲げたような中世歌論書を生む母体となって、多くの影響を与えた点で注目される。そして、生れた鵜鷺系歌論書が藤原定家という巨大な名声を背景に次々に仮託偽書を生むことになった。この仮託偽書の浸透力に支えられて中世和歌の世界は展開したものであるとみられる。 この中世歌論書の世界は、やがて盛行する連歌論にも多く影響を与えることによって継承される。 |
|||||||||
| |
|||||||||