万葉集にはいまだに明らかになっていないことが多い。その成立事情や編纂目的などについても、古来様々な論議が繰り返され、時に既に決着がついたかのような説を成す者もなくはないが、外部は勿論、万葉内部にさえ確かな証拠といえるものはほとんどない。あらゆる意味において、万葉集はまだ多くの謎を秘めている。
早い話が、その書名の読み方も、実際はどうだったのか、確実なところは分っていない。普通には、ほとんどの人が「マンヨ-シュ-」と読むが、つい最近まで「マンニョ-シュ-」と唱える者も、かなりいた。こうした読み方は「因縁(いんねん)」「観音(くわんのん)」などと同じく連声と呼ばれる中世以来の読み癖によるもので、この他にも「三位(さんみ)」「陰陽師(おんみょうじ)」「雪隠(せっちん)」「屈惑(くったく)」などmやtの韻尾の場合についても似たようなことがあるが、主としてn韻尾を持つ字が上に、そしてア・ヤ・ワ行で始まる文字が下に来て塾合する場合に起こる日本語特有の現象、それが連声である。中古においても、それがなかったとはいえないが、奈良時代以前には、おそらくなかっただろう。今日、マンヨ-、マンニョ-のいずれを採るべきか、上代人はどう唱えていただろうか。それがわからないのである。
|
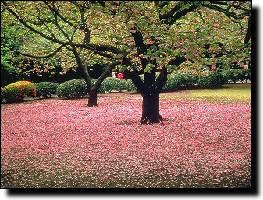 |