| 飛鳥坐神社歌碑 参道石段 |
 |
三諸者人之守山本辺者馬酔木花開
末辺方椿花開浦妙山曾泣児守山
みもろは ひとのもるやま もとへには あしびはなさき
すゑへには つばきはなさく うらぐはし やまそなく
こもるやま
作者未詳
万葉集巻第十三−3222(新編国歌大観3236)
|
一般的な訳 小学館日本古典文学全集に依る
三諸は、人が守っている山 本の辺りには、馬酔木の花が咲き 上の辺りには、椿の花が咲いている まことに見事な山だね 泣く子を守るように、人が守っているこの山は
|
三諸−ミムロとも。「三諸の神奈備」「神奈備の三諸」ともいい、本来、出雲系の神を祭る聖域カムナビと同格のように併記されることが多い。ただし、そのカムナビも時に原初的意義が忘れられることがあったが、ミモロはそれ以上に祭られる神を特定せず、国土神一般ないし氏神を祭る場として普通名詞的に用いることもあった。ここは飛鳥の神奈備をさしたものであろう。
人の守る山−この守ルは、番をする、大切にする、の意。
本辺には−ニハの訓、諸説あり。
末辺には−末辺は山頂付近。『古事記』下の歌謡(91)に「本にはい組み竹生ひ末辺にはたしみ竹生ひ」とある。
うらぐはし−心にしみ入るほどに美しい。ウラは心、クハシは繊細な美しさを表わす形容詞。風景を賛美する場合に用いる。
泣く子守る山−泣く子をあやすように優しく大切にするこの山は。 |
| 飛鳥寺 境内 |
 |
神岳に登って、山部赤人が作った歌一首
三諸乃 神名備山尓 五百枝刺 繁生有 都賀乃樹乃 弥継嗣尓 玉葛 絶事無 在管裳 不止将通 明日香能 舊京師者 山高三 河登保志呂之 春日者 山四見容之 秋夜者 河四清之 旦雲二 多頭羽乱 夕霧丹 河津者驟 毎見 哭耳所泣 古思者
みもろの かむなびやまに いほえさし しじにおひたる つがのきの いやつぎつぎに たまかづら たゆることなく ありつつも やまずかよはむ あすかの ふるきみやこは やまだかみ かはとほしろし はるのひは やましみがほし あきのよは かはしさやけし あさくもに たづはみだる ゆふぎりに かはづはさわく みるごとに ねのみしなかゆ いにしへおもへば
反歌
明日香河 川余藤不去 立霧乃 念應過 孤悲尓不有國
万葉集巻第三−324/5(新編国歌大観327/8)
|
324
神の宿る神奈備山 幾重も枝を広げながら 生い茂っている栂の木のように 絶えることなく通い続けたい明日香の古き都は 山高く 川は悠然と流れる 春の日には山に見入り 秋の夜には瀬音にやすらぐ 朝雲に鶴は乱れて舞い 夕霧に蛙は鳴きそろう そこに立ち見るたびに どうしようもなく泣けてしまう 古き時代に想いを寄せれば
325
明日香川に立ちこめる霧のように いつの間にか過ぎ行くような恋ではないのに |
| |
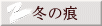 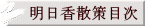 |
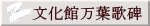 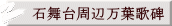 |