| 文化館万葉歌碑 |
| |
 |
変若水の瀬 (をちみづのせ)
天橋文長雲鴨高山文高雲鴨月夜見乃
持有越水伊取来而公奉而越得之旱物
あまばしも ながくもがも たかやまも たかぐもがも
つくよみの もてるをちみづ いとりきて
きみにまつりて をちえてしかも
作者未詳
万葉集巻第十三-3245(新編国歌大観3259) |
一般的な訳 小学館日本古典文学全集に依る
天の梯子の長いのがあればよい 高山のとびきり高いのがあればよい 月読おとこの持っている若水を 取って来て 君に捧げて若返っていただきたいものだ |
天橋も-天に上るための梯子。「モ」は希求表現や、~があればよいのに、の意の「マシヲ」などと呼応する用法。
長くもがも-「モガ(モ)」は希求の終助詞。天に届くほど長い梯子があったら月世界に行けるのに、という気持ちで言う。
月読-月の異名。「月読をとこ」とも
持てるをち水-「ヲチ水」は若返りの水。「ヲツ」は若返る意の上二段動詞。欠けてもまた満ちる月を、不死なるもの、永遠に若い男と解し、月にその不老の霊水があると考えて言う。
い取り来て-「イ」は接頭語。
をち得てしかも-原文は、底本など大部分の古写本に「越得之早物」とあるが、元暦校本に「越得之旱物」に作るによる。ただし、「テシカ(モ)」は話し手の願望を表すのが例で、他者に、~してあげたい、という場合には用いない点で疑問がある。 |
 |
蔭履む道 (かげふむみち)
片岡之此向峯椎蒔者今年夏之陰尓将化疑
かたをかの このむかつをに しひまかば ことしのなつの
かげにならむか
作者未詳
万葉集巻第七-1099(新編国歌大観1103) |
一般的な訳 小学館日本古典文学全集に依る
片岡山の この向こうの丘に 椎の実を蒔いたら 今年の夏の日
陰になるだろうか |
向つ峰-向こうに見える丘陵。ここは片岡山の東、奈良県北葛城郡上牧町の馬見丘陵をさすのだろう。なお同町の小字名に、向山・向城・小向など、遺称かと思われる地名が現存する。
陰にならむか-原文に「陰尓将比疑」とあるが、「比」は「化」の誤りとする『万葉集古義』の説による。「化」にはものの変化推移の意がある。春のうちから夏の炎暑を厭う趣だが、椎の実を植え付けてその緑陰を期待するというのは、誇張か、寓意があるか。
|
 |
常磐の広場 (ときわのひろば)
皆人乃寿毛吾母三吉野乃
多吉能床磐乃常有沼鴨
みなひとの いのちもわがも みよしのの たきのときはの
つねならぬかも
笠朝臣金村
万葉集巻第六-922(新編国歌大観927) |
一般的な訳 小学館日本古典文学全集に依る
皆の人の 命もわたしの命も み吉野の 滝の大岩のように
永久に変わらずあってほしいものだ |
皆人-原文底本などの仙覚本は「人皆」とあるが、元暦校本や類聚古集が「皆人」に創るのによる。ミナヒト・ヒトミナ両形あり、ミナヒト6、ヒトミナ11、そして、この歌のように写本間に異同があるもの3、という状態で、本文の決定は困難。→1482(皆人)・1738(人皆の)。
我がも-我ガ命モの意。ワガの下にあるべき名詞を省略した例に「幣は我がにはあらず」(神楽歌)のごときがある。また「我が命も常にあらぬか」(332)の例もあり、「常ならぬかも」の主格には「命」の語があるほうが自然。
常ならぬかも-「ツネ」は永久不変なもの。ヌカ(モ)は希求。 |
 |
風流士の道 (みやびおのみち)
春日在三笠乃山二月船出
遊士之飲酒坏尓陰尓所見管
かすがなる みかさのやまに つきのふねいづ
みやびをの のむさかづきに かげにみえつつ
作者不詳
万葉集巻第七-1295(新編国歌大観1299) |
一般的な訳 小学館日本古典文学全集に依る
春日の 三笠の山に 月の舟が出ている 風流士が 飲む酒杯に その影を映して |
月の舟-七夕の夜の月を舟にたとえた歌語的表現か。『懐風藻』所収の文武天皇詠月詩の「月舟は霧ノ渚ニ移リ、楓檝ハ霞ノ浜ニ浮ブ」などと類想。『新撰万葉集』の詩(215)にも「滝河浪ヲ起シテ月舟ヲ穿ツ」の句がある。
みやびを-風流を解する男子。官人たちをさすか。
※ 酒宴の席で詠まれた歌か。平城遷都後の作であろう。柿本人麻呂と「『人麻呂歌集』との関係はなお十分に明らかでないが、人麻呂に平城遷都後の作とみるべき確かな例がないと同様に、『人麻呂歌集』にも奈良朝の作は見当たらない。 |
 |
常世の海 (とこよのうみ)
伎弥乎麻都麻都良乃干良能越等売良波
等己与能久尓能阿麻越等売可忘
きみをまつ まつらのうらの をとめらは
とこよのくにの あまをとめかも
吉田連宜
万葉集巻第五-865(新編国歌大観869) |
一般的な訳 小学館日本古典文学全集に依る
(君を待つ) まつらの浦の 娘たちは 常世の国の
漁夫の娘ではないでしょうか
|
君を待つ-君の来訪を待っている、の意だが、第二句にかかる同音の枕詞の働きをも兼ねる。
常世の国-不老不死の仙郷。
|
| |
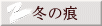 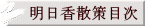 |
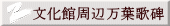 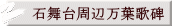 |