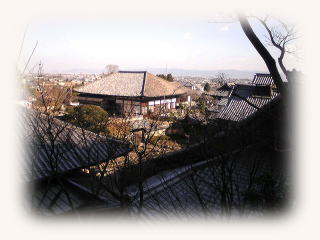| 高野山真言宗 別格本山 當麻寺(たいまでら) 大和十三佛霊場第六番 弥勒菩薩 大和七福八箇所第六十三番札所 関西花の寺第二十一番西南院 | |||||||||
| 縁起 | |||||||||
| 當麻寺が開創された際、役行者は金堂前(影向石)にて熊野権現を勧請し、その出現した場所に自身の道場を開いた。奈良時代には、當麻寺別当・実雅がその道場を住房とし、「中院」を開創。以来、中院は代々當麻寺別当(住職)の住房として受け継がれ、その後「中院御坊」と尊称された。これが現在の「中之坊」である。弘仁時代には、弘法大師が中之坊実弁を弟子として真言密教を伝え、以後、當麻寺は真言宗の霊場となった。 當麻寺には平安時代に四十余房、江戸時代にも三十一房の僧坊があったと記録されるが、中之房はこれらの筆頭寺院として、當麻寺内で最も古い由緒と高い寺格を伝えている。 庭園、書院、霊宝館などの数々の寺宝を残すほか、「導き観音」の信仰が篤い祈願所として、また写仏によって中将姫の教えを体感する霊場としても親しまれている。 |
|||||||||
| 大和三名園「香藕園(こうぐうえん)」名勝・史蹟 桃山時代 | |||||||||
| 中之坊庭園は、古くから大和三名園(竹林園、慈光院)と賞される池泉回遊式兼観賞式庭園。 鎌倉時代に起源を持ち、桃山時代に完成、さらに江戸初期に、後西天皇(第111代)を迎えるため片桐石州によって改修された。極端に低い土塀で二段構えとし、天平の三重塔が借景として映え、心宇池にその影を落とす。その歴史の重みと四季を通じた景観の美しさから、昭和九年に史蹟と名勝の保存指定を受ける。大和屈指の名園である。 |
|||||||||
| 書院・茶室 重要文化財 桃山―江戸初期 | |||||||||
| 後西天皇をお迎えした中之坊書院は、こけら葺きの情緒豊かな建築で、「御幸の間」、「鷺の間」、「鶴の間」などからなる。張壁、襖絵は、江戸初期の大家・曽我二直庵の筆になる楼閣、山水、花鳥の名画である。(子・辰・申年の秋に特別公開) 茶室「丸窓席」は、片桐石州が庭園の整備と共に造築したもので、大胆な大円窓が見事な四畳半の茶室。 茶室「知足庵」は、一対一で客人をもてなすのに石州が特に好んだとされる二畳中板の名席である。 |
 |
||||||||
| ぼたん園(花庭園) | |||||||||
|
有名な當麻のぼたんは、例年4月下旬から5月上旬頃にかけて色とりどりの大輪の花を咲かせる。その他、多種にわたる花々が、四季を通じて参詣者の目を楽しませてくれる。 |
|||||||||