秋篠寺小誌・尊像略記より
奈良時代末期宝亀七年(776)、光仁天皇の勅願により地を平城宮大極殿西北の高台に占め、薬師如来を本尊と拝し僧正善珠大徳の開基になる当寺造営は、次代桓武天皇の勅旨に引き継がれ平安遷都とほぼ時を同じくしてその完成を見、爾来、殊に承和初年常暁律師により大元帥御修法の伝来されて以後、大元帥明王影現の霊地たる由緒を以って歴朝の尊願を重ね真言密教道場として隆盛を極めるも、保延元年(1135)一山兵火に罹り僅かに講堂他数棟を残すのみにて金堂東西両塔等主要伽藍の大部分を焼失し、その面影は現今もなお林中に点在する数多の礎石及び境内各処よろ出土する古瓦等に偲ぶ外なく、更に鎌倉時代以降、現本堂の改修をはじめ諸尊像の修補、南大門の再興等室町桃山各時代に亘る復興造営の甲斐も空しく、明治初年廃仏棄釈の嵐は十指に余る諸院諸坊とともに寺域の大半を奪い、自然のままに繁る樹林の中に千古の歴史を秘めて佇む現在の姿を呈するに至っている。
当寺草創に関しては一面、宝亀以前当時秋篠朝臣の所領であったと思われる当地に既に秋篠氏の氏寺として営まれていた一寺院があり、後に光仁天皇が善珠僧正を招じて勅願寺に変えられたと見る説もあり、詳しくは今後の研究を待つ外ないが、当寺の名称の起こりを解明する一見解として留意すべきである。 |
 |
なお宗派は当初の法相宗より平安時代以後真言宗に転じ、明治初年浄土宗に属するも、昭和二十四年以降単立宗教法人として既成の如何なる宗派宗旨にも偏することなく仏教二千五百年の伝統に立脚して新時代に在るべき人間の姿を築かんとするものである。
|
本 堂
当寺創建当初講堂として建立されたが金堂の焼失以後鎌倉時代に大修理を受け、以来本堂と呼ばれてきたもの。事実上鎌倉時代の建築と考えるべきであるが様式的に奈良時代建築の伝統を生かし単純素朴の中にも均整と落ち着きを見せる純和様建築として注目される。桁行17.45米(五間)、梁間12.12米(四間)、軒高3.78米、軒出2.29米。
実際に本堂の中に入ると、外観から察するように、小ぢんまりとした空間だった。当寺本尊の薬師如来は、他で見る薬師如来よりも、気持ちが和らいで見える。印象に残ったのは、十二神将だ。如来像の左右に六体ずつが分かれている。その愛嬌のあるポーズが、何ともいえない。薬師如来の眷属として、浄土、衆生を護る十二の夜叉。その威嚇するような表情にも、おどけた格好に、親しみを抱いてしまう。信仰のある人には、お叱りを受けるだろうが、信仰心というのは、畏怖の念を持つのと同時に、やはり身近な親しみを必要とするのではないだろうか。
もっとも、注目されるのが、当寺にしか現存しない伎芸天だ。
伎芸天
頭部乾漆天平時代、体部寄木鎌倉時代、極彩色立像。密教経典「摩醯首羅大自在天王神通化生伎芸天女念誦法」などによって造顕され、経意によれば大自在天の髪際から化生せられた天女で、衆生の吉祥と芸能を主宰し諸伎諸芸の祈願を納受したまうと説かれている。古くは各地に於いても信仰されたと思われるが現在では他に全くその違例を見ず我国唯一の伎芸天像である。当寺帝釈天像及び梵天像、救脱菩薩像の三体と同様最初天平時代に造顕され、後災禍のため御胴体以下を破損し鎌倉時代に至って体部が木彫で補われたものと考えられ、これら四体の像はいずれも頭部のみ当初のままの乾漆造で体部は寄木造である。現在鬘部の宝冠及び両肩より垂れる天衣の一部が欠失し単純な形であるが、時代を隔ててなお保たれる調和と写実的作風は限りない人間味を湛え古くより美術家文芸家等の間にも広く讃仰者を集めている。
今にも舞いだしそうな雰囲気を漂わせている。ちょっと顔をかしげての憂いのある表情も素敵だった。一見して、像全体がちぐはぐに感じられたのは、解説にもあるように、体部が寄木造だから、そう感じたのだろう。それでも、頭部に見る表情の無限の美しさは、はかりしれない。そして、指先まで魂があるかのような造りが一層、優美に感じさせる。
|
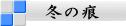 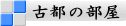 |