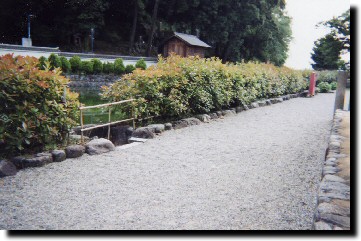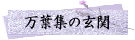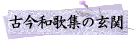|
古今和歌集へのアクセス (2004年5月31日記)
|
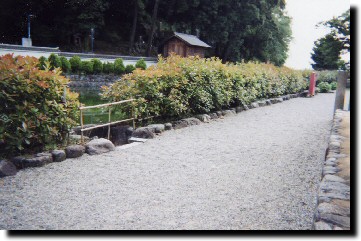
|
|
|
|
|
|
|
|
|
もう一つのサイトに、万葉集を中心とした私の思い入れを書いている。そもそものHP作成スタートのテーマは「万葉集」だったので、今でもやはり中心にしたいと思っている。
|
|
しかし、このところのアクセス状況を見ていると、はるかに併設の「古今和歌集」に集中している。「古今和歌集」がらみで検索すると、何とか私のサイトに到達するようだ。せっかく苦労して訪れたみなさんには申し訳ないと、思い始めた。というのも、そのサイトでは、どうしても「万葉集」に力が入ってしまって、「古今和歌集」は、それほど熱心ではなかった。勿論、万葉集に限らず、古今集にしても、歌論を語れるほどの知識もないが、自分の思い入れがストレートに表現できる「万葉集」にくらべ、「古今和歌集」は、どうしても構えてしまう。
|
|
併設した意味にしても、単純なものだ。「古今和歌集」編纂の意図が、ほぼ200年前に詠まれた歌を中心にした「万葉集」を意識しているからに他ならない。当時漢詩文隆盛の中で、初めて「やまとうた」を編纂できる勅命を受けたときの選者たちが、どれほど「万葉集」以来の和歌集を選べる喜びを感じ得たことか。その気持ちが、私なりに微笑ましく思えて、「古今和歌集」のページを設けることにした。
日本最初の勅撰歌集が、万葉集を意識し、その巻数をも万葉集に倣うように20巻としている。
|
だから、私にとっては、「古今和歌集」は、歳の離れた兄を慕っている「弟」のように思えてならなかった。
そう書けば、間違いなく専門家の方々から批判を受けると思う。しかし、そもそも歌の解釈は、専門家諸氏の解釈に合わせる必要はないだろう。その歌によって、自分が受けた影響が事実であり、それが必ずしも専門家の解釈とは一致するとは限らない。作者の意図を汲み取る必要も確かにある。それも大切だと思う。と、同時に、その歌を自分が気に入る何かが存在するはずで、それは個々の環境や心情に絡めて解釈してもいい。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
私にとって、「万葉集」も、「古今和歌集」も、あるいは他の歌集にしても、率直に私に語りかけ、そして常に私の心に響いているからこそ、いつまでも、いつまでも読み続けていけるのだと思う。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
これまでは、と言っても私がHPから離れる前までだから、もう1年半ほどになるが、「万葉集」のページと違って、「古今和歌集」のページは、原則として歌番号順に掲載していた。別に深い意味はないけれど、敢えて言えば、毎回歌を選ぶ手間を惜しんだといえる。それは、実に「古今和歌集」の愛好家の人たちには不遜な言い方だったと思う。「万葉集」の片手間の作業、といっているのに等しいことになるのだから。
|
「古今和歌集」にも、「万葉集」に劣らず直截てきで、熱情的な歌が多い。
|
|
特に、巻第十二 恋歌二 歌番号615
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
いのちやはなんぞはつゆのあだものをあうにしかへばおしからなくに とものり
命やは何ぞは 露のあだものを あふにしかへば惜しからなくに
|
|
|
|
|
この歌など、冷静に読んでもいいだろうし、私だったら
俺の命なんぞ、お前に逢えることと引き換えならば、いくらでもくれてやる!
と、なってしまう。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
専門家諸氏には、そんな言い方はないだろう、と言われそうだし、「露のあだもの」って何だい?とも訊かれそうだ。
|
|
しかし、そんな説明をする必要など、この歌の意からすると、まったく必要がないと私は思う。「俺の命なんて、露みたいに取るに足らないものだから...」。そんな前置きしなくても、「露のあだもの」という語句によって、私は、あんな語調のいい方に素直になれる。その語調をリードしているのが、私にとっては「露のあだもの」になる。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
この歌を引き合いに出した意味は、その私的解釈ではなく、この歌番号615というのを考えたかったから。
|
|
私の従来のスタイルでいけば、615番目に取り上げる歌ということになる。それは、本当は一番読みたい歌であるにもかかわらず、この先何年もかかってしまう。そのもどかしさもあった。では、何故そんな意にそぐわない原則を設けたのか、ということになり、その答えは、やはり片手間の作業だった、ということになってしまう。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内容はともかく、せっかく多くの人が「古今和歌集」に惹かれて、不本意にも私のサイトにやってきたとしても、せめて少しは微笑んで欲しいとの願いから、また書き始めていこうかと思っている。そして、原則を取っ払って、自分でその時の気持ちに合った、あるいは取り上げたい歌を、日ごとに追いかけて行きたい。
勿論、これをきっかけに、「万葉集」も再開していこう。
|
|
放りっぱなしのサイトに訪れてこられた人たちに、申し訳ない気持ちでいっぱいだった。それでも作成当時の意気込みが戻ってこなかったけれど、ようやく今、その勢いが甦ってきたように思う。
|
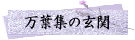 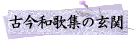 |
|
|